空き家の冒険
一八九四年春、ロンドン中が注目し、上流社会を震撼させた事件が起きた。名士ロナルド・アデア卿が、極めて異常かつ不可解な状況下で殺害されたのである。事件の詳細は警察の捜査によってすでに公にされているが、その多くは当時伏せられていた。というのも、検察側にとって状況証拠はあまりにも圧倒的で、すべての事実を法廷に持ち出す必要すらなかったからだ。十年近くが経過した今、ようやく私は、この驚くべき事件の全体像を完成させる「失われた環」を語ることを許された。事件そのものも興味深かったが、私にとってはその後に起きた信じがたい出来事に比べれば、取るに足らないものであった。それは、私の波乱に満ちた人生においても、最大級の衝撃と驚きをもたらしたのだ。長い歳月を経た今でさえ、そのことを思うと胸が震え、私の心を完全に呑み込んだ、あの突然の歓喜、驚愕、そして信じ難いという感情の洪水が再び押し寄せてくる。これまで私が折に触れて書き記してきた、ある非凡な人物の思考と行動に興味を示してくださった読者の皆様に申し上げておきたい。私がこの知識を分かち合わなかったことを、どうかお許しいただきたい。もし彼自身の口から発せられた厳格な禁止令がなければ、それを伝えることが私の第一の義務であると考えていたはずだからだ。その禁止が解かれたのは、つい先月の三日のことである。
ご想像の通り、シャーロック・ホームズとの親密な交友は、私に犯罪への深い関心を抱かせた。彼が姿を消した後も、世間を騒がせる様々な難事件の記事を注意深く読み漁ることを怠らなかった。それどころか、一度ならず、自分自身の知的好奇心を満たすため、彼の捜査手法を模倣して事件の解決を試みたことさえある。もっとも、その成果は芳しいものではなかったが。しかし、このロナルド・アデアの悲劇ほど私の心を捉えた事件はなかった。検死審問の証言を読み、氏名不詳の人物による計画的殺人と結論付けられたのを知ったとき、私はシャーロック・ホームズの死によって社会が被った損失の大きさを、かつてないほど痛感した。この奇妙な事件には、彼ならば間違いなく特別な興味をそそられたであろう点がいくつもあった。警察の努力も、ヨーロッパ随一の犯罪捜査専門家である彼の、鍛え抜かれた観察眼と鋭敏な頭脳によって補完され、いや、おそらくは先取りされていたに違いない。私は一日中、往診の馬車に揺られながらこの事件について考え続けたが、納得のいく説明は見出せなかった。繰り返しになるのを承知で、検死審問が終わった時点で公になっていた事実を、ここに要約しておこう。
ロナルド・アデア卿は、当時オーストラリア植民地総督であったメイヌース伯爵の次男であった。アデア卿の母は白内障の手術を受けるためにオーストラリアから帰国しており、息子のロナルド、娘のヒルダと共にパーク・レーン四二七番地に暮らしていた。この青年は上流社会に身を置き、知る限り敵はおらず、これといった悪癖もなかった。カーステアズのイーディス・ウッドリー嬢と婚約していたが、数ヶ月前に双方合意の上で解消しており、それが深い心の傷を残した形跡もなかった。それ以外では、彼の生活は穏やかで型にはまったもので、物静かな性格で感情を表に出すことも少なかった。しかし、こののんびりとした若い貴族に、死は一八九四年三月三十日の夜、十時から十一時二十分の間に、最も奇妙で予期せぬ形で訪れたのである。
ロナルド・アデアはカード遊びを好み、常にプレイしていたが、身を滅ぼすほどの大きな賭けはしなかった。彼はボールドウィン、キャヴェンディッシュ、バガテルという三つのカードクラブの会員だった。事件当日の夕食後、彼はバガテル・クラブでホイストを一勝負していたことがわかっている。午後の部にも参加していた。一緒にプレイしたマレー氏、ジョン・ハーディ卿、モラン大佐の証言によれば、ゲームはホイストで、カードの出方はほぼ互角だったという。アデアは五ポンドほど負けたかもしれないが、それ以上ではなかった。彼の財産は相当なものであり、その程度の損失が彼に影響を与えるはずもなかった。彼はほぼ毎日どこかのクラブでプレイしていたが、慎重なプレイヤーで、たいていは勝ち越して席を立つのが常だった。証言によれば、数週間前にはモラン大佐と組んで、ゴッドフリー・ミルナーとバルモラル卿から一度の勝負で四百二十ポンドもの大金を手に入れていたという。以上が、検死審問で明らかになった彼の最近の動向である。
犯行の夜、彼はちょうど十時にクラブから帰宅した。母親と妹は親戚の家で夜を過ごすため外出中だった。メイドの証言では、彼が二階の、普段は居間として使っている表の部屋に入る音を聞いたという。メイドはそこに暖炉の火を熾していたが、煙がひどかったため窓を開けておいた。十一時二十分、メイヌース夫人と娘が帰宅するまで、部屋からは何の物音も聞こえなかった。おやすみの挨拶をしようと、夫人が息子の部屋に入ろうとした。ドアは内側から鍵がかけられており、呼びかけにもノックにも応答はなかった。助けを呼んでドアをこじ開けると、哀れな若者はテーブルのそばに倒れていた。頭部は炸裂するリボルバー弾によって無残に破壊されていたが、室内にはいかなる種類の武器も見当たらなかった。テーブルの上には十ポンド紙幣が二枚と、金貨銀貨合わせて十七ポンド十シリングが、金額ごとに小さな山に分けて置かれていた。また、一枚の紙にはいくつかの数字とクラブ仲間の名前が記されており、死ぬ直前にカードの勝ち負けを計算しようとしていたのではないかと推測された。
状況を詳細に調べれば調べるほど、事件は複雑さを増すばかりだった。第一に、若者がなぜ内側からドアに鍵をかけたのか、その理由が説明できなかった。犯人がそうして、その後窓から逃げた可能性も考えられた。しかし、窓から地面までの高さは少なくとも二十フィート[訳注: 約6メートル]あり、下には満開のクロッカスの花壇が広がっていた。花も土も荒らされた形跡はなく、家と道路を隔てる細い芝生の上にも足跡はなかった。とすれば、ドアに鍵をかけたのは若者自身ということになる。だが、一体どうやって殺されたのか? 痕跡を残さずに窓まで登れる者などいるはずがない。仮に誰かが窓越しに発砲したとすれば、リボルバーでこれほど致命的な傷を負わせることができるとは、よほどの射撃の名手に違いない。それに、パーク・レーンは人通りの多い大通りで、家から百ヤードも離れていない場所に辻馬車の乗り場がある。誰も銃声を聞いていないのだ。にもかかわらず、そこには死体があり、弾頭が潰れてきのこ状になるソフトノーズ弾特有の形状をしたリボルバー弾があった。それが、即死は免れない傷をもたらしたのである。これがパーク・レーン事件の謎の全貌であり、動機が全く見当たらないことで、事態はさらに複雑になっていた。先にも述べた通り、若きアデアには敵らしい敵もおらず、部屋の金品や貴重品が持ち去られた形跡もなかったからだ。
私は一日中、これらの事実を頭の中で反芻し、すべてを矛盾なく説明できる理論を打ち立てようと試みた。そして、亡き友がすべての捜査の出発点だと断言していた「最も抵抗の少ない線」を見つけ出そうとした。正直に言って、ほとんど進展はなかった。夕方、公園を散策し、六時ごろにパーク・レーンのオックスフォード・ストリート側のはずれにたどり着いた。舗道には浮浪者の一団がいて、皆が一つの窓を見上げていた。それが私が見に来た家だと教えてくれた。色眼鏡をかけた背の高い痩せた男が、私服刑事だと私は強く疑ったが、何やら持論を指し示しながら説明しており、他の者たちは彼の話を聞こうと周りに群がっていた。私はできるだけ彼に近づいたが、その見解は馬鹿げているとしか思えず、うんざりして再びその場を離れた。その時、私の後ろにいた、背の曲がった年老いた男にぶつかってしまい、彼が抱えていた数冊の本を地面に落としてしまった。本を拾い上げながら、そのうちの一冊のタイトルが『樹木崇拝の起源』であったことを覚えている。この男は、商売か趣味か、いずれにせよ珍しい本を集めている哀れな愛書家に違いない、と私は思った。私はこの不慮の事故を詫びようとしたが、私が不運にも手荒く扱ってしまった本は、持ち主の目には非常に貴重な品であることは明らかだった。彼は軽蔑の唸り声をあげると踵を返し、その曲がった背中と白いもみあげが人込みの中に消えていくのが見えた。
パーク・レーン四二七番地の観察は、私が興味を抱いていた問題の解明にはほとんど役立たなかった。家は低い壁と柵で通りから隔てられており、その高さは全体で五フィートもなかった。したがって、誰かが庭に侵入するのは極めて容易だったが、窓にたどり着くのは全く不可能だった。雨樋もなければ、どんなに身軽な男でもよじ登る助けになるようなものは何もなかったからだ。ますます謎は深まるばかりで、私はケンジントンへの帰路についた。書斎に入って五分も経たないうちに、メイドが入ってきて、面会を求める人がいると告げた。驚いたことに、それは他ならぬ、あの奇妙な年老いた本の収集家だった。白髪の額縁からのぞく鋭く皺だらけの顔、そして少なくとも一ダースはある貴重な本を右脇にしっかりと抱えていた。
「お会いできて驚かれたでしょうな」と、彼は奇妙なしゃがれ声で言った。
私はそれを認めた。
「いやはや、わしにも良心というものがありましてな。あなた様がこの家に入られるのを偶然お見かけし、後からよろよろとついてきたのですが、こう思ったのです。あの親切な紳士のところへちょっと立ち寄って、先ほどの無礼な態度は悪気があったわけではないこと、そして本を拾ってくださって大変感謝していることをお伝えしよう、と。」
「些細なことを気にしすぎですよ」と私は言った。「失礼ですが、どうして私が誰だかお分かりになったのですか?」
「ええ、旦那様、もし差し出がましくなければ、わしはご近所さんでしてな。チャーチ・ストリートの角に小さな本屋を構えております。いつでもお越しくだされば、これほど嬉しいことはございません。ひょっとして、旦那様も収集家でいらっしゃいますかな。ここに『英国の鳥類』、『カトゥルス』、『聖なる戦い』――どれも掘り出し物ですぞ。この五冊があれば、そちらの二段目の棚の隙間がちょうど埋まります。見栄えがよろしくないでしょう、旦那様?」
私は後ろの飾り棚を見るために首を動かした。そして再び向き直った時、書斎のテーブルの向こうに、シャーロック・ホームズが微笑みながら立っていた。私は立ち上がり、全くの驚愕のうちに数秒間彼を見つめた。そして、生まれて初めて、そして後にも先にもないことだが、私は気を失ってしまったようだ。確かに灰色の霧が目の前で渦を巻き、それが晴れると、襟元が緩められ、ブランデーの痺れるような後味が口に残っていた。ホームズが私の椅子にかがみ込み、フラスコを手にしていた。
「ワトソン君」懐かしい声が言った。「本当に申し訳ない。君がこれほど動揺するとは、思いもしなかった。」
私は彼の両腕を掴んだ。
「ホームズ!」と私は叫んだ。「本当に君なのか? 本当に生きているのか? あの恐ろしい奈落の底から、這い上がることができたというのか?」
「待ってくれ」と彼は言った。「本当に、話ができる状態かね? 私の不必要に芝居がかった再登場で、君に深刻なショックを与えてしまったようだ。」
「大丈夫だ。だが、本当に、ホームズ、自分の目が信じられない。ああ、なんてことだ! 君が――他の誰でもない君が――私の書斎に立っているなんて。」
私は再び彼の袖を掴み、その下の細く、筋張った腕を感じた。「なるほど、幽霊ではないらしいな」と私は言った。「親友よ、君に会えて本当に嬉しい。座ってくれ。そして、あの恐ろしい裂け目からどうやって生還したのか、話してくれ。」
彼は私の向かいに座り、昔ながらの無頓着な様子で煙草に火をつけた。古本屋の着古したフロックコートを着ていたが、その人物の残りの部分は、白髪の山と古い本となってテーブルの上に置かれていた。ホームズは以前よりもさらに痩せ、鋭さを増していたが、その鷲鼻の顔には死人のような蒼白さが浮かんでおり、最近の生活が健康的なものではなかったことを物語っていた。
「体を伸ばせて嬉しいよ、ワトソン」と彼は言った。「背の高い男が何時間も続けて身長を一フィートも縮めなければならないのは、冗談ではないからな。さて、親友よ、説明のことだが、もし君の協力を得られるなら、我々の前には困難で危険な一夜の仕事が待ち構えている。その仕事が終わってから、状況のすべてを話した方が良いかもしれない。」
「好奇心でいっぱいだ。今すぐ聞きたい。」
「今夜、私と来てくれるかね?」
「いつでも、どこへでも。」
「まさに昔のようだ。出かける前に、軽く夕食をとる時間はあるだろう。さて、あの裂け目のことだ。そこから抜け出すのは、さして難しいことではなかった。理由は至って簡単、私はそもそも中に落ちてなどいなかったのだから。」
「落ちていなかった?」
「そうだ、ワトソン。私は決して落ちてはいない。君への書き置きは、全くの真筆だ。今は亡きモリアーティ教授の、どこか不吉な姿が安全へと続く細い小道に立ちはだかっているのを見たとき、私は自分のキャリアもこれで終わりかと、ほとんど疑わなかった。彼の灰色の瞳に、非情な決意を読み取った。そこで、彼と二言三言言葉を交わし、君が後に受け取ることになる短い手紙を書く許可を、丁重に得たのだ。私はそれを煙草入れとステッキと共に残し、小道を進んだ。モリアーティは私のすぐ後ろについてきた。道の終点に着いたとき、私は追い詰められた。彼は武器を抜かなかったが、私に突進し、その長い腕で私を抱きしめた。彼は自分のゲームが終わったことを悟り、ただ私に復讐することだけを望んでいた。我々は二人、滝の縁でよろめいた。しかし、私にはバリツ、つまり日本の武術の心得が多少あってね。これが一度ならず役に立っている。私は彼の掴みからするりと抜け出し、彼は恐ろしい叫び声をあげて数秒間狂ったように足をばたつかせ、両手で空を掻いた。だが、どんなにもがいても体勢を立て直すことはできず、そのまま落ちていった。崖の縁から顔を乗り出して、彼が遥か下まで落ちていくのを見届けた。そして岩にぶつかり、跳ね返って水飛沫をあげて水中に消えた。」
私は驚愕しながら、ホームズが煙草をふかす合間に語るその説明に耳を傾けた。
「だが、足跡は!」と私は叫んだ。「私はこの目で見たんだ。二人の足跡が小道を進み、誰も戻ってこなかったのを。」
「こういうことだ。教授が姿を消した瞬間、運命が私に実に類稀な好機を与えてくれたことに気づいた。私の死を誓った男は、モリアーティだけではないと知っていた。少なくとも他に三人はいて、彼らの私への復讐心は、リーダーの死によって増すばかりだろう。彼らは皆、極めて危険な男たちだ。いずれ誰かにやられるに違いない。一方で、もし世間が私の死を確信すれば、彼らは油断し、大胆になるだろう。やがて尻尾を出し、遅かれ早かれ、私は彼らを滅ぼすことができる。その時こそ、私がまだこの世にいることを公表する時だ。脳の働きというのは実に速いもので、モリアーティ教授がライヘンバッハの滝の底に到達する前に、私はこのすべてを考え抜いていたと思う。
私は立ち上がり、背後の岩壁を調べた。君の picturesque [訳注: 絵のように美しい、ここでは「生き生きとした」の意]な事件の記述は、数ヶ月後に大いなる興味を持って読んだが、そこでは壁は切り立っていると断言されていたね。それは文字通り真実ではなかった。いくつかの小さな足場があり、岩棚の気配もあった。崖はあまりに高く、すべてを登り切るのは明らかに不可能だったし、濡れた小道を通って足跡を残さずに進むのも同様に不可能だった。確かに、これまでも何度かやったように、ブーツを逆さまに履くこともできたかもしれないが、一方向に三組の足跡があれば、間違いなく偽装を疑われただろう。総合的に考えて、登るリスクを冒すのが最善だった。楽しい仕事ではなかったよ、ワトソン。滝が足元で轟音を立てていた。私は空想的な人間ではないが、誓って言う。奈落の底からモリアーティが私に向かって叫ぶ声が聞こえるようだった。一度のミスが命取りになる。草の塊が手から抜け落ちたり、濡れた岩の刻み目で足が滑ったりするたびに、もう駄目だと思ったことは一度ならずあった。だが、私は必死に登り続け、ついに数フィートの深さがあり、柔らかな緑の苔で覆われた岩棚にたどり着いた。そこでは人目につかずに、完璧な安らぎの中で横になることができた。私がそこに体を伸ばしていた時、君、親愛なるワトソン、そして君の同行者たちは、私の死の状況を、最も同情的かつ非効率的なやり方で調査していたのだ。
ついに、君たち全員が不可避かつ完全に誤った結論に達し、ホテルへと引き上げていった後、私は一人残された。これで私の冒険も終わりだと思っていたが、全く予期せぬ出来事が、まだ驚きが待ち受けていることを私に示した。巨大な岩が上から落下し、私のそばを轟音を立てて通り過ぎ、小道にぶつかり、裂け目へと跳ね返っていった。一瞬、事故だと思ったが、その直後、見上げると、暗くなりゆく空を背景に男の頭が見え、別の石が私が横たわっていたまさにその岩棚、私の頭から一フィートと離れていない場所を直撃した。もちろん、これが意味するところは明らかだった。モリアーティは一人ではなかった。共犯者が――そしてその一瞥だけで、その共犯者がいかに危険な男であるかがわかった――教授が私を襲っている間、見張りをしていたのだ。遠くから、私には見えずに、彼は友人の死と私の脱出を目撃していた。彼は待ち、そして崖の上まで回り道をして、同志が失敗したことを成し遂げようとしたのだ。
考えるのに長くはかからなかった、ワトソン。再びあの険しい顔が崖の上からのぞき、それが次の石の前触れだとわかった。私は小道へと這い降りた。冷静な状態ではできなかっただろう。登るよりも百倍は難しかった。だが、危険を考える暇はなかった。岩棚の縁から両手でぶら下がっていると、別の石が私のそばを唸りながら通り過ぎていったからだ。途中で滑り落ちたが、神の恵みか、私は傷だらけで血を流しながらも、小道に着地した。私は踵を返し、暗闇の中、山々を十マイル走り抜け、一週間後にはフィレンツェにいた。世界中の誰も私の行方を知らないという確信と共に。
私のただ一人の腹心は、兄のマイクロフトだった。君には何度も謝らなければならない、ワトソン。だが、私が死んだと思わせることが何よりも重要だったのだ。そして、もし君自身がそれを真実だと思っていなければ、あれほど説得力のある私の悲劇的な最期の記事を書くことはできなかっただろう。この三年間、何度君にペンを取ろうとしたことか。だが、その度に、君の私に対する愛情が、私の秘密を漏らすような軽率な行動に君を誘惑するのではないかと恐れた。そのために、今夜君が私の本をひっくり返した時、私は君から背を向けた。あの時私は危険に晒されており、君が驚きや感情を表に出せば、私の正体に注意が向けられ、最も嘆かわしく、取り返しのつかない結果につながったかもしれない。マイクロフトについては、必要な資金を得るために彼に打ち明けざるを得なかった。ロンドンでの事態の推移は、私が期待したほどうまくはいかなかった。モリアーティ一味の裁判で、最も危険なメンバーのうちの二人、私自身の最も執念深い敵が、自由の身となってしまったからだ。そこで私は二年間チベットを旅し、ラサを訪れたり、ダライ・ラマと数日を過ごしたりして楽しんだ。シガーソンという名のノルウェー人による驚くべき探検について読んだことがあるかもしれないが、君の友人の消息を受け取っているとは、夢にも思わなかっただろう。その後、ペルシャを抜け、メッカに立ち寄り、ハルツームでカリフと短いが興味深い会見を行った。その成果は外務省に伝えてある。フランスに戻ると、数ヶ月間、南フランスのモンペリエにある研究所でコールタール誘導体の研究に没頭した。これを満足のいく形で終え、ロンドンに残る敵が一人だけになったことを知ると、私は帰国しようとしていた。その矢先、私の行動を早めたのが、この非常に注目すべきパーク・レーン事件のニュースだった。それは事件そのものの魅力で私を惹きつけただけでなく、個人的に極めて特殊な機会を提供してくれるように思えた。私はすぐにロンドンへ渡り、自らベイカー街を訪ね、ハドソン夫人を激しいヒステリーに陥らせ、そしてマイクロフトが私の部屋と書類を寸分違わず昔のままに保存してくれていたことを見出した。そうして、親愛なるワトソン、今日の二時に、私は自分の古い部屋の、古い肘掛け椅子に座っている自分に気づいた。そして、彼が何度もその身で飾ってくれたもう一方の椅子に、旧友ワトソンの姿を見ることができればと、ただ願っていたのだ。」
これが、その四月の夜に私が聞いた驚くべき物語のすべてであった。もし、二度と見ることはないと思っていた、その背の高い、引き締まった姿と、鋭く、情熱的な顔を実際に目にしていなければ、到底信じがたい話だっただろう。彼は何らかの方法で私の身に起きた悲しい死別を知ったようで、その同情は言葉よりも態度に表れていた。「仕事は悲しみに対する最良の解毒剤だよ、ワトソン君」と彼は言った。「そして今夜、我々二人でやるべき仕事がある。もしそれを成功させることができれば、それだけでこの地球上での人間の人生を正当化するに足るものだ。」
私がもっと話してくれと頼んでも無駄だった。「朝になる前に、十分に聞くし、見ることになるさ」と彼は答えた。「我々には話し合うべき過去の三年がある。九時半まではそれで十分だろう。その時間になったら、空き家の注目すべき冒険に出発する。」
その時間、私が彼の隣で辻馬車に乗り、ポケットにリボルバーを忍ばせ、心に冒険のスリルを感じていた時、まさしく昔のようだった。ホームズは冷たく、厳しく、そして沈黙していた。街灯の光が彼の厳格な顔つきを照らすと、眉が思索に沈み、薄い唇が固く結ばれているのが見えた。犯罪の都ロンドンの暗いジャングルで、我々がこれからどんな猛獣を狩ろうとしているのかはわからなかったが、この名人猟師の様子から、その冒険が極めて重大なものであることは確かだった。そして、時折彼の禁欲的な憂鬱を破って浮かぶ皮肉な笑みは、我々の探求の対象にとって、良からぬ前兆であった。
私たちはベイカー街に向かっているのだと思っていたが、ホームズはキャヴェンディッシュ・スクエアの角で馬車を止めた。彼が降りる際、左右を鋭く見渡し、その後のすべての街角で、尾行されていないことを確認するために最大限の注意を払っていることに気づいた。私たちのルートは確かに奇妙なものだった。ホームズのロンドンの裏道に関する知識は並外れており、この時も彼は、私がその存在すら知らなかった厩舎や馬小屋の入り組んだ網の目を、確信に満ちた足取りで素早く通り抜けていった。やがて私たちは、古く陰気な家々が並ぶ小さな道に出た。そこからマンチェスター・ストリートを経て、ブランドフォード・ストリートへと至った。ここで彼は素早く狭い通路に曲がり、木の門を抜けて寂れた庭に入ると、鍵で家の裏口を開けた。私たちは共に入り、彼は背後で扉を閉めた。
そこは真っ暗だったが、空き家であることは明らかだった。剥き出しの床板の上を歩くと、足音がきしんだり、パキパキと鳴ったりした。伸ばした手は、壁紙がリボンのように垂れ下がっている壁に触れた。ホームズの冷たい、細い指が私の手首を掴み、長い廊下を前へと導いた。やがて、ドアの上の薄汚れた欄間窓がぼんやりと見えてきた。ここでホームズは突然右に曲がり、私たちは広く、四角い、何もない部屋に入った。隅は深い影に覆われていたが、中央は向こうの通りの明かりでかすかに照らされていた。近くにランプはなく、窓は埃で厚く覆われていたため、お互いの姿をかろうじて見分けられる程度だった。友は私の肩に手を置き、唇を私の耳に近づけた。
「どこにいるか、わかるかね?」と彼は囁いた。
「間違いなくベイカー街だ」と私は薄暗い窓を凝視しながら答えた。
「その通り。我々はカムデン・ハウスにいる。我々の古い下宿の真向かいに立つ建物だ。」
「だが、なぜここに?」
「あの絵になる建物を、実に素晴らしい眺めから見渡せるからだ。申し訳ないが、ワトソン君、もう少し窓に近づいて、決して姿を見せないように細心の注意を払い、そして我々の古い部屋を見上げてくれないか。君のささやかなおとぎ話の数々の出発点となった場所を。私の三年間の不在が、君を驚かせる力を完全に奪ってしまったかどうか、試してみようじゃないか。」
私はそっと前に進み、見慣れた窓の向こうを見やった。その窓に目が留まった瞬間、私は息を呑み、驚きの声をあげた。ブラインドが下ろされ、部屋には強い光が灯っていた。中に椅子に座っている男の影が、くっきりとした黒い輪郭で、窓という光るスクリーンに投げかけられていた。頭の構え、肩の角張り、顔立ちの鋭さ、見間違えるはずもなかった。顔は半ばこちらを向いており、その効果は、我々の祖父母が額に入れるのを好んだ黒いシルエット画のようだった。それはホームズの完璧な再現だった。あまりの驚きに、私は手を伸ばし、男自身が私の隣に立っていることを確かめようとした。彼は声を殺して笑い、身を震わせていた。
「どうだね?」と彼は言った。
「なんてことだ!」と私は叫んだ。「素晴らしい。」
「我が才気、齢に衰えず、型に嵌まらず、といったところかな」と彼は言った。その声には、芸術家が自らの創造物に対して抱く喜びと誇りが聞き取れた。「実に、私によく似ているだろう?」
「君自身だと誓ってもいいくらいだ。」
「この出来栄えは、グルノーブルのオスカー・ムニエール氏の手柄だ。彼は数日をかけて型取りをしてくれた。蝋でできた胸像だよ。残りは、今日の午後ベイカー街を訪れた際に、私自身が手配した。」
「だが、なぜ?」
「なぜなら、ワトソン君、私が別の場所にいる時に、ある特定の人物たちに私がそこにいると思わせたい、極めて強い理由があったからだ。」
「そして、部屋が見張られていると思ったのか?」
「見張られていると『知っていた』のだ。」
「誰に?」
「私の古い敵たちにだよ、ワトソン。そのリーダーがライヘンバッハの滝に眠る、あの charming [訳注: 魅力的な、ここでは皮肉] な連中にだ。忘れてはならない、私がまだ生きていることを知っていたのは、彼ら、そして彼らだけだった。遅かれ早かれ、彼らは私が自分の部屋に戻ってくると信じていた。彼らは絶えず部屋を監視し、そして今朝、私が到着するのを見たのだ。」
「どうしてわかるんだ?」
「窓から外をちらりと見たとき、彼らの見張りを認識したからだ。パーカーという名前の、まあ無害な男で、絞殺を稼業とし、ジューズ・ハープ[訳注: 口琴]の見事な演奏家だ。彼のことなどどうでもいい。だが、私が大いに気にかけたのは、彼の背後にいる、はるかに手強い人物、モリアーティの親友、崖の上から岩を落とした男、ロンドンで最も狡猾で危険な犯罪者だ。今夜、私を追っているのはその男だ、ワトソン。そして、我々が『彼』を追っていることに、その男は全く気づいていない。」
友の計画が、徐々に明らかになってきた。この都合の良い隠れ家から、監視する者たちが監視され、追跡する者たちが追跡されていた。あそこの角ばった影は餌であり、我々は狩人だった。我々は闇の中で静かに共に立ち、目の前を行き交う人々の急ぎ足の姿を見守った。ホームズは沈黙し、身じろぎもしなかった。しかし、彼が鋭く警戒し、その目が通行人の流れにじっと注がれていることはわかった。寒々しく、風の強い夜で、長い通りを風が鋭く吹き抜けていた。多くの人々が行き交い、そのほとんどはコートや襟巻きに身を包んでいた。一度か二度、同じ人物を前に見たような気がした。特に、通りの少し先にある家の戸口で風を避けているように見える二人の男が気になった。私は友の注意を彼らに引こうとしたが、彼は少し焦れたように声を漏らし、通りを見つめ続けた。彼は何度も足をそわそわさせ、壁を指で素早く叩いていた。彼が不安になり、計画が必ずしも望み通りに進んでいないことは明らかだった。ついに、真夜中が近づき、通りから徐々に人影が消えると、彼は抑えきれない動揺の中で部屋を行ったり来たりし始めた。私が何か言おうとした時、ふと明かりの灯る窓に目を上げ、またしても以前とほとんど同じくらいの驚きを経験した。私はホームズの腕を掴み、上を指さした。
「影が動いたぞ!」と私は叫んだ。
確かに、もはや横顔ではなく、背中が我々の方を向いていた。
三年という月日は、彼の気性の荒々しさや、自分より劣る知性に対する焦燥感を和らげることはなかったようだ。
「もちろん動いたさ」と彼は言った。「私がそんな滑稽なへまをやらかす間抜けだとでも思うのか、ワトソン。あからさまな偽物を立てて、ヨーロッパで最も抜け目のない連中がそれに騙されると期待するような。我々がこの部屋に来て二時間、ハドソン夫人はあの人形を八回、つまり十五分に一度、動かしている。彼女は前から操作する。そうすれば彼女自身の影が見えることはない。……ああ!」
彼は鋭く、興奮した様子で息を吸い込んだ。薄明かりの中、彼の頭が前に突き出され、その全身が緊張で硬直しているのが見えた。外の通りは完全に人気がなかった。あの二人の男はまだ戸口にうずくまっているのかもしれないが、もはや私には見えなかった。すべてが静かで暗く、ただ我々の正面にある鮮やかな黄色のスクリーンと、その中央に浮かび上がる黒い人影だけがそこにあった。完全な静寂の中、再び、あの細く、息の漏れるような音が聞こえた。それは激しく抑えられた興奮を物語っていた。一瞬後、彼は私を部屋の最も暗い隅へと引き戻し、私は彼の警告する手が私の唇に置かれるのを感じた。私を掴む指は震えていた。これほど友が動揺しているのを見たことはなかった。にもかかわらず、暗い通りは依然として寂しく、静まり返ったまま我々の前に広がっていた。
だが突然、彼のより鋭敏な感覚がすでに捉えていたものに、私も気づいた。低く、忍び寄るような音が私の耳に届いた。ベイカー街の方向からではなく、我々が隠れているまさにこの家の裏手からだった。ドアが開き、閉まった。一瞬後、廊下を足音が忍び寄ってきた。音を立てないように意図された足音だったが、がらんとした家の中ではっきりと反響した。ホームズは壁際に身をかがめ、私もそれに倣い、リボルバーの柄を握りしめた。暗闇を透かして見ると、ぼんやりとした男の輪郭が見えた。開いたドアの暗さよりもさらに黒い影だった。彼は一瞬立ち止まり、それから身をかがめ、威嚇するように部屋へと忍び込んできた。この不吉な人影は、我々から三ヤードも離れていない場所にいた。私は彼の飛びかかりに備えて身構えたが、その時、彼が我々の存在に全く気づいていないことを悟った。彼は我々のすぐそばを通り過ぎ、窓辺に忍び寄り、非常に静かに、音を立てずに窓を半フィートほど持ち上げた。彼がこの開口部の高さまで身をかがめると、もはや埃っぽいガラスで遮られることのなくなった街の光が、彼の顔をまともに照らした。男は興奮のあまり我を忘れているようだった。両目は星のように輝き、顔の筋肉は痙攣していた。彼は年配の男で、細く突き出た鼻、高く禿げ上がった額、そして巨大な灰色の口髭を持っていた。シルクハットは後頭部に押しやられ、開いたオーバーコートから夜会服のシャツの胸元が覗いていた。顔はやつれて浅黒く、深く、獰猛な皺が刻まれていた。手には杖のようなものを持っていたが、それを床に置くと、金属的な音が響いた。それからオーバーコートのポケットからずっしりとした物を取り出し、何かの作業に没頭した。その作業は、バネかボルトが所定の位置にはまるような、カチッという鋭く大きな音で終わった。床に膝をついたまま、彼は身を屈め、全体重と力を込めて何かのレバーを操作した。その結果、長く、回転するような、軋むような音が響き、再び力強いカチッという音で終わった。それから彼は体を起こし、私は彼が手にしているものが、奇妙な形をした銃床を持つ一種の銃であることを見て取った。彼は銃尾を開き、何かを込め、遊底を閉じた。そして、身をかがめ、銃身の先端を開いた窓の縁に乗せた。彼の長い口髭が銃床の上に垂れ、目が照準を覗き込むとキラリと光るのが見えた。彼が銃床を肩にしっかりと当てると、満足のため息がかすかに聞こえた。そして、あの驚くべき標的、黄色い背景の黒い人影が、彼の照星の先にくっきりと立っていた。一瞬、彼は硬直し、身じろぎもしなかった。そして、彼の指が引き金にかかった。奇妙な、甲高い風切り音、そして長く尾を引くガラスの砕ける銀色の響き。その瞬間、ホームズは虎のように狙撃手の背中に飛びかかり、彼をうつ伏せに叩きつけた。男はすぐに起き上がり、痙攣的な力でホームズの喉を掴んだが、私はリボルバーの銃床で彼の頭を殴りつけ、彼は再び床に倒れた。私は彼の上に覆いかぶさり、私が彼を押さえつけている間に、友が鋭く笛を吹いた。舗道に駆け足の音が響き、制服警官二人と私服刑事一人が正面玄関から部屋に駆け込んできた。
「君か、レストレード?」とホームズが言った。
「はい、ホームズさん。この仕事は私が引き受けました。ロンドンにお戻りになられて、何よりです。」
「君には少し非公式な助けが必要だと思ったものでね。一年で三件の未解決殺人事件はいただけない、レストレード。だが、モーズリーの謎は、君のいつもの――つまり、まあまあうまく処理したじゃないか。」
私たちは皆立ち上がっていた。捕虜は荒い息をつき、その両脇を屈強な警官が固めていた。すでに通りには数人の野次馬が集まり始めていた。ホームズは窓に歩み寄り、窓を閉め、ブラインドを下ろした。レストレードが二本の蝋燭を取り出し、警官たちはカンテラの覆いを外した。私はようやく、我々の捕虜をじっくりと見ることができた。
我々に向けられたのは、途方もなく精力的でありながら、同時に不吉な顔だった。上半分は哲学者の額、下半分は快楽主義者の顎を持ち、この男は善悪いずれにも大きな素質を持って生まれてきたに違いない。しかし、その冷酷な青い目と、垂れ下がった皮肉なまぶた、獰猛で攻撃的な鼻、そして威圧的で深く皺の刻まれた額を見れば、自然が発する最も明白な危険信号を読み取らずにはいられなかった。彼は我々の誰にも目もくれず、その目は憎しみと驚きが等しく入り混じった表情で、ホームズの顔に釘付けになっていた。「悪魔め!」と彼は呟き続けた。「抜け目のない、賢い悪魔め!」
「やあ、大佐!」とホームズは、乱れた襟を直しながら言った。「『旅の終わりは恋人たちの出会い』と、古い芝居にもある。あなたにお目にかかるのは、ライヘンバッハの滝の上の岩棚で私が横たわっていた時、あのようなご親切をいただいて以来ではないかと思いますな。」
大佐は、まるで夢うつつの人のように、まだ友を見つめていた。「狡猾な、狡猾な悪魔め!」と、彼が言えたのはそれだけだった。
「まだ紹介していませんでしたな」とホームズは言った。「こちらが、皆さん、セバスチャン・モラン大佐です。かつて女王陛下のインド陸軍に所属し、我が東方帝国が生んだ最高の大型獣猟師です。私の記憶が正しければ、大佐、あなたの虎の猟果は未だに破られていないのでは?」
獰猛な老人は何も言わず、ただ仲間を睨みつけていた。その野蛮な目と逆立った口髭は、驚くほど虎そのものに似ていた。
「私のごく単純な策略が、あなたのような年老いた『シカリ』[訳注: インドの狩人]を欺くことができたとは、驚きですな」とホームズは言った。「あなたにはお馴染みの手口でしょう。木の下に子ヤギを繋ぎ、その上でライフルを構えて待ち、餌が虎を誘き出すのを待つ。この空き家が私の木で、あなたが私の虎だ。万一、虎が複数現れた場合に備えて、あるいは、ご自身の狙いが外れるというあり得ない事態を想定して、予備の銃を用意していたのかもしれませんな。ここにいる彼らが」と彼は周りを指した。「私の予備の銃です。全く同じ構図です。」
モラン大佐は怒りの唸り声をあげて前に飛び出したが、警官たちが彼を引き戻した。その顔に浮かんだ憤怒は、見るもおぞましいものだった。
「白状しますが、一つだけあなたに驚かされました」とホームズは言った。「あなたがご自身でこの空き家と、この都合の良い正面の窓を利用するとは、予想していませんでした。私は、あなたが路上から行動するものと想像していました。そこでは友人のレストレードとその陽気な部下たちがあなたを待ち構えていたのですがね。その一点を除けば、すべては私の予想通りに進みました。」
モラン大佐は公式の刑事の方を向いた。
「私を逮捕する正当な理由があるかないかは別として」と彼は言った。「少なくとも、この人物の嘲りを受けるいわれはないはずだ。私が法の手に落ちた以上、物事は法に則って進めてもらいたい。」
「まあ、もっともな言い分だ」とレストレードは言った。「行く前に、何か他に言うことはありますか、ホームズさん?」
ホームズは床から強力な空気銃を拾い上げ、その仕組みを調べていた。
「見事で、他に類を見ない武器だ」と彼は言った。「音もなく、凄まじい威力を持つ。これを故モリアーティ教授の注文で製作した盲目のドイツ人機械工、フォン・ヘルダーを知っている。長年、その存在は承知していたが、実際に手にする機会はこれまでなかった。レストレード、君の特別な注意を喚起しておく。これに合う弾丸も同様にな。」
「その点は我々にお任せください、ホームズさん」とレストレードは言い、一行はドアの方へ移動した。「他に何か?」
「ただ、何の容疑で起訴するつもりか、尋ねたいだけだ。」
「何の容疑、ですか? それはもちろん、シャーロック・ホームズ氏に対する殺人未遂ですよ。」
「そうではない、レストレード。私はこの件で一切法廷に出るつもりはない。君に、そして君だけに、この見事な逮捕の手柄は帰するべきだ。そうだ、レストレード、おめでとう! 君のいつもの、狡猾さと大胆さの幸福な混合によって、彼を捕らえたのだ。」
「彼を! 誰を捕まえたんです、ホームズさん?」
「警察が総力をあげて探し求めていた男――先月三十日、パーク・レーン四二七番地の二階表の開いた窓から、空気銃で炸裂弾を発射し、ロナルド・アデア卿を射殺した、セバスチャン・モラン大佐だ。それが容疑だ、レストレード。さて、ワトソン、もし割れた窓からの隙間風に耐えられるなら、私の書斎で三十分ほど葉巻でも燻らせれば、何か有益な楽しみが得られると思うがね。」
私たちの古い下宿は、マイクロフト・ホームズの監督と、ハドソン夫人の直接的な世話によって、変わらぬままに残されていた。中に入ると、確かに、見慣れないほど整頓されてはいたが、昔ながらの目印はすべて元の場所にあった。化学実験のコーナーと、酸で染みのついた松材のテーブル。棚には、多くの同胞市民が焼き払ってしまいたいと願うであろう、恐るべきスクラップブックと参考書の列。図表、ヴァイオリンケース、パイプ置き――タバコ入れにしていたペルシャスリッパさえも――部屋を見渡すと、すべてが目に飛び込んできた。部屋には二人の住人がいた。一人は、私たちが入ってくるとにこやかに迎えてくれたハドソン夫人。もう一人は、今宵の冒険でかくも重要な役割を果たした、奇妙な偽物だった。それは友を模した蝋色の模型で、実に見事に作られており、完璧な複製品だった。小さな台座テーブルの上に置かれ、ホームズの古いガウンが巧みにかけられていたため、通りからの錯覚は全く完璧だった。
「万事、注意は払ってくださいましたね、ハドソン夫人?」とホームズが言った。
「はい、旦那様。おっしゃられた通り、膝をついてやりましたとも。」
「素晴らしい。見事にやり遂げてくれましたな。弾がどこへ行ったか、ご覧になりましたか?」
「はい、旦那様。残念ながら、あなたの美しい胸像を台無しにしてしまったようです。頭をまっすぐ突き抜けて、壁でぺしゃんこになっていましたから。カーペットから拾い上げました。これです!」
ホームズはそれを私に差し出した。「柔らかいリボルバー弾だ、わかるだろう、ワトソン。これには天才的なひらめきがある。空気銃からこんなものが発射されるとは、誰が予想するだろう? 結構ですよ、ハドソン夫人。ご協力に感謝します。さて、ワトソン、もう一度君の古い席に座ってくれたまえ。君と議論したい点がいくつかあるんだ。」
彼は古びたフロックコートを脱ぎ捨て、今や、自分の肖像から取った鼠色のガウンをまとった、昔ながらのホームズだった。
「あの老練な『シカリ』の神経は衰えていないし、その眼光も鋭さを失っていない」と彼は、自分の胸像の砕けた額を検分しながら、笑って言った。
「後頭部のど真ん中、脳天をまっすぐ貫いている。彼はインド一の射撃手だったし、ロンドンでも彼に匹敵する者はほとんどいないだろう。その名前を聞いたことはあるかね?」
「いや、ない。」
「ふむ、名声とはそんなものか! だが、私の記憶が正しければ、君は一世紀に一人の偉大な頭脳を持っていたジェームズ・モリアーティ教授の名前も知らなかったはずだ。棚から私の人物伝索引を取ってくれたまえ。」
彼は椅子に深くもたれかかり、葉巻から大きな煙の雲を吐き出しながら、気だるそうにページをめくった。
「私のMのコレクションは素晴らしいものだ」と彼は言った。「モリアーティ自身がいるだけで、どの文字も輝かしいものになる。ここには毒殺者のモーガン、忌まわしい記憶のメリデュー、チャリング・クロス駅の待合室で私の左の犬歯をへし折ったマシューズ、そして最後に、今夜の我々の友人がいる。」
彼はその本を差し出し、私は読んだ。
モラン、セバスチャン、大佐。無職。元第1バンガロール工兵隊所属。1840年、ロンドン生まれ。オーガスタス・モラン卿(C.B.、元駐ペルシャ英国公使)の息子。イートン校及びオックスフォード大学卒業。ジョワキ遠征、アフガン戦争、チャラシアブ(殊勲者公式報告書に記載)、シェルプール、カブールに従軍。著書に『西ヒマラヤの大型獣』(1881年)、『ジャングルでの三ヶ月』(1884年)。住所:コンジット・ストリート。所属クラブ:アングロ・インディアン、タンカーヴィル、バガテル・カード・クラブ。
欄外には、ホームズの正確な筆跡でこう書かれていた。
ロンドンで二番目に危険な男。
「これは驚きだ」と私は本を返しながら言った。「この男の経歴は、名誉ある軍人のものだ。」
「その通りだ」とホームズは答えた。「ある時点までは、彼は順調だった。彼は常に鉄の神経を持つ男で、手負いの人食い虎を追って排水溝に這って入った話は、今でもインドで語り継がれている。ある種の木はな、ワトソン、一定の高さまで成長すると、突然、見苦しい奇形を発達させることがある。人間にもしばしば見られることだ。私には一つの持論がある。個人はその成長において、自らの祖先の全過程を体現しており、そのような善悪への突然の転換は、その血統に入り込んだ何らかの強い影響力を示すのだと。その人物は、いわば、自身の家族の歴史の縮図となるのだ。」
「それは少々、空想的に過ぎるのではないか。」
「まあ、固執はしない。原因が何であれ、モラン大佐は道を踏み外し始めた。公のスキャンダルはなかったものの、彼はインドに居づらくなった。彼は退役し、ロンドンに来て、再び悪名を馳せた。この時期に、彼はモリアーティ教授に見出され、しばらくの間、教授の参謀長を務めた。モリアーティは彼に惜しみなく金を与え、並の犯罪者では到底請け負えないような、一、二の非常に高度な仕事にのみ彼を使った。君は一八八七年のローダーのスチュワート夫人殺害事件を覚えているかもしれない。いや? まあ、私はモランがその黒幕だと確信しているが、何も証明できなかった。大佐は実に巧みに隠れていたため、モリアーティ一味が壊滅した時でさえ、我々は彼を罪に問うことができなかった。あの時、私が君の部屋を訪ねた際、空気銃を恐れて鎧戸を閉めたのを覚えているかね? 君は間違いなく、私の空想だと思っただろう。私は自分のしていることを正確にわかっていた。この驚くべき銃の存在を知っていたし、世界最高の射撃手の一人がその背後にいることも知っていたからだ。我々がスイスにいた時、彼はモリアーティと共に我々を追跡し、ライヘンバッハの岩棚で私にあの悪夢の五分間を与えたのは、間違いなく彼だ。」
「私がフランスに滞在していた間、新聞をいくらか注意深く読んでいたとお思いでしょう。もちろん、奴を捕らえる機会を虎視眈々と狙ってね。奴がロンドンで自由でいる限り、私の命などあってなきがごとしだった。昼も夜もその影が私に付きまとい、遅かれ早かれ奴に好機が訪れたはずだ。私に何ができただろう? 見つけ次第射殺するわけにもいかない。それでは私が被告席に立つことになる。治安判事に訴えても無駄だ。彼らにとっては荒唐無稽な疑いにしか聞こえない話に、介入などできはしない。だから私は何もできなかった。だが、犯罪ニュースには目を光らせていた。いずれ奴を捕まえられると知っていたからな。そこへ、このロナルド・アデアの死が報じられた。ついに私の機会が来たのだ。私が知っていることを考えれば、モラン大佐がやったのは確実ではないか? 彼は若者とカードをし、クラブから家まで後をつけ、開いた窓から彼を撃った。疑いの余地はない。あの弾丸だけで、奴の首に縄をかけるには十分だ。私はすぐにこちらへ渡った。歩哨に姿を見られたが、それは承知の上だ。彼が私の存在を大佐に報告するだろうと踏んでいた。私の突然の帰還を、奴が自身の犯罪と結びつけないはずがない。そして、ひどく狼狽するだろう。奴は私を即座に始末しようと試み、そのためにあの殺しの武器を持ち出すに違いないと確信していた。私は窓辺に絶好の的を残し、警察には必要になるかもしれないと警告しておいた――ところでワトソン、君があの戸口に潜む彼らの存在を見抜いたのは、実に的確だった――そして、観察に最適と思われる場所に陣取った。まさか奴が攻撃のために同じ場所を選ぶとは夢にも思わなかったがね。さあ、ワトソン、他に何か説明すべきことは残っているかね?」
「ええ」と私は言った。「モラン大佐がロナルド・アデア氏を殺害した動機が、まだはっきりしません。」
「ああ! ワトソン、そこからは推測の領域に入る。最も論理的な頭脳でさえ誤りを犯しかねない世界だ。現在の証拠から誰もが自らの仮説を立てることができ、君のものが私のものと同じくらい正しい可能性はある。」
「では、あなたは仮説を立てたのですね?」
「事実を説明するのはさほど難しくないと思う。証拠によれば、モラン大佐と若きアデアは、二人でかなりの額の金を勝ち取っていた。さて、モランがイカサマをしていたのは間違いない――それは私もずっと前から気づいていた。思うに、殺害の当日、アデアはモランがイカサマをしていることに気づいたのだ。おそらく彼は内密にモランと話し、自発的にクラブを脱会して二度とカードをしないと約束しない限り、不正を暴露すると脅したのだろう。アデアのような若者が、自分よりずっと年長の著名な人物をいきなり暴露して、醜聞を立てるとは考えにくい。おそらく私が示唆したように行動したのだろう。クラブからの追放は、不正なカードの儲けで生計を立てていたモランにとって破滅を意味する。それゆえ彼はアデアを殺害した。その時、アデアは、パートナーの不正によって得た利益を受け取るわけにはいかないから、いくら返すべきかを計算しようとしていたのだろう。彼は婦人たちに不意に入ってこられ、名前と硬貨で何をしているのかと問い詰められるのを恐れて、ドアに鍵をかけた。これでどうだろう?」
「あなたが真実を言い当てたに違いありません。」
「それは裁判で証明されるか、あるいは覆されるかだろう。いずれにせよ、モラン大佐が我々を悩ますことはもうない。フォン・ヘルダーの有名な空気銃はスコットランドヤード博物館の展示を飾り、そして再び、シャーロック・ホームズ氏は、ロンドンの複雑な生活がかくも豊かに提供してくれる興味深い小問題の数々を調べることに、その人生を捧げられるようになるのだ。」
ノーウッドの建築業者
「犯罪専門家の観点から言わせてもらうと」とシャーロック・ホームズ氏は言った。「惜しまれつつ亡くなったモリアーティ教授の死後、ロンドンは実に面白味のない街になってしまった。」
「あなたに同意する善良な市民は、そう多くはないと思いますがね」と私は答えた。
「まあ、まあ、自己中心的ではいけないな」彼はそう言って微笑み、朝食のテーブルから椅子を引いた。「社会全体が得をしたのは確かで、誰も損はしていない。職を失った哀れな専門家を除いてはね。あの男が暗躍していた頃は、朝刊は無限の可能性を秘めていた。ほんの些細な痕跡、ワトソン、ごく微かな兆候に過ぎないことが多かった。それでも、あの巨大で邪悪な頭脳がそこにいると私に告げるには十分だった。まるで、巣の縁の最も穏やかな震えが、中心に潜む醜悪な蜘蛛を思い起こさせるようにね。こそ泥、理不尽な暴行、目的のない凶行――手がかりを握る者にとっては、すべてがひとつの繋がりを持った全体像として解き明かされる。高等犯罪の世界を科学的に研究する者にとって、ヨーロッパのどの首都も、当時のロンドンが持っていたほどの利点は提供してくれなかった。だが、今は――」彼は肩をすくめ、自らが作り出すのに大いに貢献した現状を、ユーモラスに嘆いてみせた。
私が話しているこの頃、ホームズが戻ってきて数ヶ月が経っており、私は彼の依頼で開業医を売り払い、再びベーカー街の古い部屋を共有するために戻っていた。ヴァーナーという名の若い医師が、私のケンジントンでのささやかな診療所を買い取ってくれたのだが、私が思い切って提示した最高額を、驚くほどあっさりと受け入れた――この出来事は数年後にようやく説明がついた。ヴァーナーがホームズの遠縁であり、金を工面したのは実のところ我が友人だったと知ったのだ。
我々の共同生活の数ヶ月は、彼が述べたほど平穏無事だったわけではない。私の記録を見返すと、この期間には元大統領ムリリョの書類事件や、我々二人の命を危うくしかけたオランダの蒸気船「フリースランド号」の衝撃的な事件も含まれている。しかし、彼の冷徹で誇り高い性質は、世間の称賛といったものを常に嫌い、彼自身やその手法、成功について一切口外しないよう、私に最も厳格な口止めをしていた――この禁止令が、先に説明した通り、今ようやく解かれたのである。
シャーロック・ホームズ氏は、気まぐれな抗議の後、椅子にもたれかかり、ゆったりと朝刊を広げていた。その時、玄関のベルがけたたましく鳴り響き、すぐさま、誰かが拳で外扉を叩いているかのような、空ろな太鼓のような音が続いて、我々の注意を引いた。扉が開くと、ホールになだれ込むような騒々しい音がし、階段を駆け上がる素早い足音が響き、その一瞬後、血走った目をした狂乱状態の若い男が、蒼白で、髪を振り乱し、息を切らしながら部屋に飛び込んできた。彼は我々を交互に見たが、我々の探るような視線の下で、この無作法な登場について何らかの謝罪が必要だと気づいたようだった。
「申し訳ありません、ホームズさん」と彼は叫んだ。「どうかお許しください。私はほとんど正気を失っているのです。ホームズさん、私は不幸なジョン・ヘクター・マクファーレンと申します。」
彼はその名前だけで、訪問の理由もその無礼なやり方も説明できるかのように告げたが、我が友人の無表情な顔から察するに、彼にとっても私と同じく、何の意味もなさない名前らしかった。
「煙草をどうぞ、マクファーレンさん」と彼は言い、シガレットケースを押しやった。「そのご様子では、友人のワトソン博士なら鎮静剤を処方するに違いありません。ここ数日、ひどく暑かったですからな。さて、少し落ち着かれたようでしたら、そちらの椅子にお座りになり、あなたがどなたで、何をお望みなのか、ごくゆっくりと静かにお話し願いたい。名前をおっしゃいましたが、私が知っているかのように聞こえました。しかし断言しますが、あなたが独身で、弁護士で、フリーメイソンで、喘息持ちであるという明白な事実以外、私はあなたのことを何一つ存じ上げません。」
友人のやり方に慣れ親しんでいた私には、彼の推論を追うのは難しくなく、身なりの乱れ、法律書類の束、時計の飾り、そしてそれらを彼に気づかせた呼吸の様子を観察することができた。しかし、我々の依頼人は驚愕して目を丸くしていた。
「はい、そのすべてが私です、ホームズさん。そしてそれに加え、今このロンドンで最も不運な男です。どうか、どうか見捨てないでください、ホームズさん! もし私が話を終える前に逮捕に来たら、時間を稼いでください。私が真実のすべてを話せるように。あなたが外で私のために動いてくれると知っていれば、私は喜んで牢獄へ行けます。」
「逮捕ですと!」とホームズは言った。「これは実に喜ば――実に興味深い。何の容疑で逮捕されるとお思いで?」
「ロウアー・ノーウッドのジョナス・オールドエーカー氏殺害の容疑です。」
我が友人の表情豊かな顔には同情の色が浮かんだが、恐らくそれは満足感と全く無縁ではなかっただろう。
「やれやれ」と彼は言った。「ちょうど今朝食の席で、友人のワトソン博士に、新聞から扇情的な事件が消えてしまったと話していたところだったのに。」
我々の訪問者は震える手を伸ばし、まだホームズの膝の上にあったデイリー・テレグラフ紙を拾い上げた。
「これをご覧になっていれば、私が今朝ここへ参りました用向きが一目でご理解いただけたはずです。私の名と不幸が、今や誰の口にも上っているような気がしてなりません。」
彼は紙面をめくり、中央のページを見せた。「ここにあります。失礼して、読み上げさせていただきます。これを、ホームズさん。見出しはこうです。『ロウアー・ノーウッドの謎めいた事件。著名な建築業者の失踪。殺人と放火の疑い。犯人への手がかり』。これが彼らが既に追っている手がかりなのです、ホームズさん。そして、それが間違いなく私に繋がることを私は知っています。私はロンドン・ブリッジ駅から尾行されてきました。逮捕状を待っているだけなのは確かです。母の心を打ち砕いてしまう――母の心を!」
彼は不安のあまり両手をもみしだき、椅子の上で体を前後に揺すった。
私は、この暴力犯罪の実行者として告発されている男を興味深く見つめた。彼は亜麻色の髪で、色褪せたネガ写真のような、どこか頼りなげな美男子だった。怯えた青い瞳に、髭をきれいに剃った顔、そして弱々しく繊細な口元。年齢は二十七歳ほどだろうか、服装と物腰は紳士のそれだった。薄手の夏用オーバーコートのポケットからは、彼の職業を物語る、裏書きされた書類の束が突き出ていた。
「我々は与えられた時間を使わねばなりません」とホームズは言った。「ワトソン、すまないが、その新聞を取って問題の段落を読んでくれないか?」
依頼人が引用した力強い見出しの下に、私は次のような暗示的な記事を読み上げた。
「昨夜遅く、あるいは今朝未明、ロウアー・ノーウッドにおいて、深刻な犯罪を示唆すると思われる事件が発生した。ジョナス・オールドエーカー氏は同地区の著名な住人で、長年にわたり建築業者として事業を営んできた。オールドエーカー氏は五十二歳の独身で、ディープ・ディーン・ハウスという名の屋敷の、サイデナム側の端に住んでいる。彼は奇矯な習慣を持つ、秘密主義で隠遁的な人物として知られていた。ここ数年は事業から事実上引退しており、相当な富を築いたと言われている。しかし、家の裏手には小さな材木置き場が今も存在し、昨夜十二時頃、その積荷の一つが燃えているとの通報があった。消防隊はすぐに現場に駆けつけたが、乾燥した木材は激しく燃え盛り、積荷が完全に燃え尽きるまで鎮火することは不可能だった。ここまでは普通の事故のように見えたが、新たな兆候が深刻な犯罪を指し示しているようだ。火災現場に家主の姿がないことに驚きの声が上がり、調査が行われた結果、彼が家から姿を消していることが判明した。彼の部屋を調べたところ、ベッドには寝た形跡がなく、室内にあった金庫は開いており、多数の重要書類が部屋中に散乱し、そして最後に、殺人を伴う争いの痕跡があった。室内からはわずかな血痕が発見され、また、樫のウォーキング・ステッキにも柄の部分に血の染みが認められた。ジョナス・オールドエーカー氏がその夜、寝室に遅い訪問者を迎えていたことが知られており、発見されたステッキは、この人物のものであると特定されている。この人物とは、ロンドンの若い弁護士ジョン・ヘクター・マクファーレン氏で、グレシャム・ビルディング四二六号のグラハム&マクファーレン事務所のジュニア・パートナーである。警察は、犯行の極めて有力な動機となる証拠を確保していると考えており、総じて、扇情的な展開が続くことは疑いない。
続報――本紙が印刷に入る時点で、ジョン・ヘクター・マクファーレン氏がジョナス・オールドエーカー氏殺害の容疑で実際に逮捕されたとの噂が流れている。少なくとも逮捕状が発行されたことは確かである。ノーウッドでの捜査には、さらなる不吉な進展があった。不運な建築業者の部屋にあった争いの痕跡に加え、現在では、寝室(一階にある)のフランス窓が開け放たれていたこと、何かかさばる物体が材木の山まで引きずられたような跡があったこと、そして最後に、燃え残った炭の灰の中から焼死体の一部が発見されたと断定されている。警察の説によれば、極めて扇情的な犯罪が行われたもので、被害者は自室で棍棒で殴り殺され、書類を荒らされた後、死体は材木の山まで引きずられ、そこに火が放たれて犯行の痕跡すべてを隠蔽しようとしたというものである。犯罪捜査の指揮は、スコットランドヤードのレストレード警部の経験豊富な手に委ねられており、彼はいつもの精力と明敏さで手がかりを追っている。」
シャーロック・ホームズは目を閉じ、指先を合わせながら、この注目すべき記事に耳を傾けていた。
「この事件には確かに興味深い点がいくつかある」と彼は気だるげな口調で言った。「まずお伺いしたいのですが、マクファーレンさん、あなたの逮捕を正当化するのに十分な証拠があるように思えるのに、どうしてあなたはまだ自由の身なのですか?」
「私はブラックヒースのトリントン・ロッジに両親と住んでいます、ホームズさん。ですが昨夜は、ジョナス・オールドエーカー氏と非常に遅くまで仕事があったため、ノーウッドのホテルに泊まり、そこから事務所へ向かいました。この事件については、電車に乗るまで何も知らず、そこで今お聞きになった記事を読んだのです。私はすぐさま自分の置かれた恐ろしい危険を悟り、この事件をあなたのお力に委ねようと急いできたのです。市の事務所か自宅にいれば、間違いなく逮捕されていたでしょう。ロンドン・ブリッジ駅から男が後をつけてきましたし、きっと――ああ、神様! あれは何です?」
それは玄関のベルの鋭い音で、すぐさま階段を上る重い足音が続いた。一瞬の後、我々の旧友レストレードが戸口に現れた。彼の肩越しに、制服警官が一人か二人、外にいるのがちらりと見えた。
「ジョン・ヘクター・マクファーレンさんですね?」とレストレードは言った。
我々の不運な依頼人は、死人のような顔で立ち上がった。
「ロウアー・ノーウッドのジョナス・オールドエーカー氏を故意に殺害した容疑で、あなたを逮捕します。」
マクファーレンは絶望の身振りで我々の方を向き、打ちひしがれた者のように再び椅子に崩れ落ちた。
「少し待ってください、レストレード」とホームズは言った。「三十分の遅れがあなたに影響するわけでもあるまい。この紳士は、事件を解明する助けになるかもしれない、この非常に興味深い出来事のあらましを、我々に話そうとしていたところなのです。」
「事件の解明に困難はないと思いますがね」とレストレードは険しい顔で言った。
「それでも、差し支えなければ、ぜひ彼の話を聞いてみたいのですが。」
「まあ、ホームズさん、あなたのお願いを断るのは難しい。過去に一度ならず警察の役に立ってくれましたし、スコットランドヤードはあなたに恩がありますからな」とレストレードは言った。「しかし、私は被疑者と共にいなければなりませんし、彼が話すことはすべて、彼に不利な証拠として扱われると警告する義務があります。」
「望むところです」と我々の依頼人は言った。「私が望むのは、あなたが絶対的な真実を聞き、認めてくださることだけです。」
レストレードは腕時計を見た。「三十分だけ時間を差し上げましょう」と彼は言った。
「まず説明しなければなりませんが」とマクファーレンは話し始めた。「私はジョナス・オールドエーカー氏のことを何も知りませんでした。彼の名前には聞き覚えがありましたが、それは何年も前に両親が彼と知り合いだったからで、その後は疎遠になっていました。ですから、昨日の午後三時頃、彼が市の私の事務所に歩いて入ってきた時は、非常に驚きました。しかし、彼が訪問の目的を告げた時には、さらに驚愕しました。彼は手に、走り書きで埋め尽くされたノート数枚を持っていました――これがそうです――そして、それを私の机の上に置いたのです。」
「『これが私の遺言書だ』と彼は言いました。『マクファーレンさん、これを正式な法律の形に整えてもらいたい。君がそうしている間、私はここに座っていよう』。」
「私はそれを書き写し始めました。そして、いくつかの留保はあるものの、彼が全財産を私に残すと知った時の私の驚きを想像してみてください。彼は白目の、イタチのような奇妙な小男で、顔を上げると、彼の鋭い灰色の目が面白がったような表情で私をじっと見つめていました。遺言書の内容を読みながら、自分の目を信じることができませんでした。しかし彼は、自分は独身で生きている親戚もほとんどおらず、若い頃に私の両親を知っており、私のことは非常に立派な若者だと常に聞いていたので、自分の金がふさわしい者の手に渡ると確信している、と説明しました。もちろん、私にできたのは、どもりながら感謝を述べることだけでした。遺言書は正式に完成し、署名され、私の書記が証人となりました。これがその青い紙の遺言書で、こちらの紙切れは、説明した通り、その下書きです。それからジョナス・オールドエーカー氏は、私が目を通して理解しておくべき多数の書類――建築賃貸契約書、権利証書、抵当証書、株券など――があることを私に告げました。彼は、すべてが片付くまで安心できないと言い、その夜、遺言書を持ってノーウッドの彼の家に来て、事を運んでほしいと懇願したのです。『いいかね、君、すべてが片付くまで、この件についてはご両親には一言も話してはいけない。これは彼らへのちょっとしたサプライズにしておこう』。彼はこの点を非常に強く主張し、私に固く約束させました。」
「ホームズさん、ご想像がつくでしょうが、私に彼の頼みを断る気などありませんでした。彼は私の恩人であり、私の望みは彼の願いを一つ残らず実行することだけでした。そこで私は家に電報を打ち、重要な用件があり、何時に帰れるか分からないと伝えました。オールドエーカー氏は、九時に夕食を共にしたいと言っていました。その時間より前には帰宅しないかもしれないとのことでした。しかし、彼の家を見つけるのに少し手間取り、着いたのは九時半近くになっていました。彼に会うと――」
「少し待ってください!」とホームズが言った。「ドアを開けたのは誰です?」
「中年の女性で、おそらく家政婦だったと思います。」
「そして、あなたの名前を告げたのも彼女ですね?」
「その通りです」とマクファーレンは言った。
「どうぞ、続けてください。」
マクファーレンは湿った額を拭い、話を続けた。
「私はその女性に居間へ通され、そこには質素な夕食が用意されていました。その後、ジョナス・オールドエーカー氏は私を寝室に案内しました。そこには重々しい金庫が立っていました。彼はそれを開け、大量の書類を取り出し、我々は一緒にそれに目を通しました。終わったのは十一時から十二時の間でした。彼は家政婦を起こしてはいけないと言いました。彼は私を、ずっと開け放たれていた彼自身のフランス窓から送り出してくれたのです。」
「ブラインドは下りていましたか?」とホームズが尋ねた。
「確かではありませんが、半分だけ下りていたと思います。ええ、彼が窓を大きく開けるためにそれを引き上げたのを覚えています。私のステッキが見当たらなかったのですが、彼は『構わんよ、君。これから君とはしょっちゅう会うことになるだろうからね。君が取りに戻ってくるまで、ステッキは預かっておこう』と言いました。私は彼をそこに残しました。金庫は開いたままで、書類は束になってテーブルの上にありました。あまりに遅かったのでブラックヒースには帰れず、アナリー・アームズで一晩を過ごし、朝、この恐ろしい事件について読むまで、何も知らなかったのです。」
「他に何かお聞きになりたいことは、ホームズさん?」とレストレードが言った。この注目すべき説明の間に、彼の眉は一度ならず吊り上がっていた。
「ブラックヒースへ行くまでは、ありません。」
「ノーウッドのことでしょう」とレストレードは言った。
「ああ、そうですな。疑いなく、そう言うつもりだったのでしょう」とホームズは謎めいた笑みを浮かべて言った。レストレードは、認めたくはないだろうが数々の経験から、この頭脳が自分には impenetrable なものを切り裂くことができると学んでいた。私は彼が我が友人をいぶかしげに見つめるのを見た。
「近いうちに、あなたと一言お話ししたいのですが、シャーロック・ホームズさん」と彼は言った。「さて、マクファーレンさん、私の部下が二人、ドアのところにいます。四輪馬車も待たせてあります。」
哀れな若者は立ち上がり、我々に最後の懇願するような一瞥を投げかけて部屋から出て行った。警官たちが彼を馬車へ連行したが、レストレードは残った。
ホームズは遺言書の下書きとなったページを拾い上げ、顔にこの上ない興味を浮かべてそれらを眺めていた。
「この文書にはいくつか興味深い点がありますな、レストレード?」と彼は言い、それを押しやった。
警官は当惑した表情でそれらを見た。
「最初の数行と、二ページ目の中程、それから最後のほうの一、二行は読めます。印刷のように鮮明です」と彼は言った。「しかし、その間の文字はひどく悪筆で、三箇所ほど全く読めないところがあります。」
「それをどう解釈しますか?」とホームズは言った。
「さて、あなたはどう解釈します?」
「電車の中で書かれたものだということです。綺麗な文字は駅を表し、汚い文字は走行中、そして非常に汚い文字はポイントを通過している時を示している。科学的な専門家なら、これが郊外の路線で書かれたものだと即座に断定するでしょう。大都市の近郊でなければ、これほど短い間隔でポイントが連続することはないからです。彼の全行程が遺言書の作成に費やされたと仮定すれば、その電車はノーウッドとロンドン・ブリッジの間で一度しか停車しない急行だったことになります。」
レストレードは笑い出した。
「あなたの理論が始まると、私にはとても敵いませんよ、ホームズさん」と彼は言った。「これが事件とどう関係するというのです?」
「まあ、若者の話が、遺言書が昨日ジョナス・オールドエーカーによって移動中に作成されたという点まで裏付けられたということです。奇妙ではありませんか? これほど重要な文書を、これほど行き当たりばったりな方法で作成するとは。彼はそれが実質的に重要になるとは考えていなかったことを示唆しています。もし人が、決して効力を持たせるつもりのない遺言書を作成するとしたら、このようにするかもしれません。」
「まあ、彼は同時に自分自身の死亡診断書を作成したわけですがね」とレストレードは言った。
「ほう、そうお考えですか?」
「あなたは違うと?」
「まあ、十分にあり得ることですが、私にはまだ事件がはっきりしません。」
「はっきりしない? これで明確でなければ、一体何が明確だと言うんです? ここに一人の若者がいる。ある年上の男が死ねば、自分が財産を相続することになると突然知る。彼はどうします? 誰にも何も言わず、しかし、その夜、何らかの口実で依頼人に会いに行く手はずを整える。家の中にいる唯一の他人が寝静まるのを待ち、そして男の部屋という密室で彼を殺害し、その死体を材木の山で焼き、近所のホテルへ立ち去る。部屋の血痕もステッキの血痕もごくわずかだ。おそらく彼は自分の犯行を血の流れないものだと考え、もし死体が燃え尽きれば、死亡方法の痕跡――何らかの理由で、彼を指し示すに違いない痕跡――をすべて隠せると期待したのだろう。これらすべてが明白ではないですか?」
「私には、レストレード君、少々明白すぎるように思えるのですがね」とホームズは言った。「あなたは他の偉大な資質に想像力を加えてはいないが、もし一瞬でもこの若者の立場に身を置いてみたら、遺言書が作成されたまさにその夜に犯行に及ぶだろうか? 二つの出来事をこれほど密接に関連付けるのは、危険だとは思わないかね? それに、あなたが家の中にいることが知られていて、使用人があなたを中に入れた時に、わざわざその機会を選ぶだろうか? そして最後に、死体を隠すために多大な労力を払いながら、自分が犯人であるという証拠として自分のステッキを残していくかね? 認めなさい、レストレード、これらすべては非常にあり得ないことだ。」
「ステッキについては、ホームズさん、あなたもご存知の通り、犯人はしばしば動転して、冷静な人間なら避けるようなことをするものです。おそらく部屋に戻るのが怖かったのでしょう。事実に合う別の説を聞かせてください。」
「半ダースほどなら、いとも簡単に提供できますよ」とホームズは言った。「例えば、ここに、非常にあり得そうで、しかも蓋然性の高い説がある。無料で差し上げましょう。年配の男が、明らかに価値のある書類を見せている。通りすがりの浮浪者が、ブラインドが半分しか下りていない窓からそれを見る。弁護士は退場。浮浪者が入場! 彼はそこにあったステッキを掴み、オールドエーカーを殺害し、死体を焼いた後に立ち去る。」
「なぜ浮浪者が死体を焼く必要が?」
「そのことなら、なぜマクファーレンが?」
「何かの証拠を隠すためでしょう。」
「おそらく浮浪者は、そもそも殺人があったこと自体を隠したかったのかもしれません。」
「ではなぜ浮浪者は何も盗まなかったのですか?」
「それらが彼には換金できない書類だったからです。」
レストレードは首を振ったが、その態度は以前ほど絶対的な確信に満ちているようには見えなかった。
「まあ、シャーロック・ホームズさん、あなたはあなたの浮浪者を探すがいい。あなたが見つけている間、我々は我々の男を押さえておきます。どちらが正しいかは、いずれ分かるでしょう。この点をよく考えてください、ホームズさん。我々が知る限り、書類は一つも持ち去られていない。そして、被疑者はこの世で唯一、それらを持ち去る理由がない男なのです。彼は法定相続人であり、いずれにせよそれらを手に入れることになるのですから。」
我が友人はこの言葉に衝撃を受けたようだった。
「証拠がある意味であなたの説を非常に強く支持していることを否定するつもりはありません」と彼は言った。「ただ、他の説も可能だと指摘したいだけです。あなたがおっしゃる通り、未来が決定するでしょう。ではまた! おそらく今日中にノーウッドに立ち寄って、あなたの進捗を拝見しますよ。」
刑事が去ると、我が友人は立ち上がり、気の合う仕事が待っている男のきびきびとした様子で、その日の仕事の準備を始めた。
「私の最初の動きは、ワトソン」と彼はフロックコートに慌ただしく袖を通しながら言った。「言ったように、ブラックヒースの方向でなければならない。」
「ノーウッドではないのですか?」
「なぜなら、この事件には一つの奇妙な出来事が、もう一つの奇妙な出来事のすぐ後に続いているからだ。警察は二番目の出来事に注意を集中するという過ちを犯している。それが実際に犯罪であるという理由だけでね。しかし、私には、この事件にアプローチする論理的な方法は、最初の出来事――かくも突然に、かくも予期せぬ相続人に対して作られた、あの奇妙な遺言書――に光を当てることから始めるのが明白だ。それが後に続いたことを単純化する助けになるかもしれない。いや、君、君の助けは借りられないと思う。危険の見込みはない。さもなければ、君なしで出かけるなど夢にも思わない。夕方会う時には、私の保護を求めてきたこの不運な若者のために、何かできたと報告できることを願っている。」
友人が戻ったのは遅い時間だった。彼のやつれて不安げな顔を一目見て、出発の際に抱いていた高い希望が満たされなかったことが分かった。彼は一時間ほどヴァイオリンを単調に弾き続け、自身の乱れた精神をなだめようと努めていた。やがて彼は楽器を投げ捨て、自らの不首尾についての詳細な報告に没頭した。
「すべてがうまくいかない、ワトソン――これ以上ないほどにだ。レストレードの前では平静を装っていたが、誓って言う、今回ばかりはあの男が正しい道を進んでいて、我々が間違っていると信じている。私の直感はすべて一方を指し、事実はすべて他方を指している。そして、英国の陪審員が、レストレードの事実よりも私の理論を優先するほどの知性にまだ達していないことを、私は大いに恐れている。」
「ブラックヒースへは行ったのですか?」
「ああ、ワトソン、行ってきた。そして、亡きオールドエーカーがかなりの悪党だったことをすぐに見抜いたよ。父親は息子を探しに出かけていた。母親は家にいた――小柄で、ふわふわした、青い目をした人で、恐怖と憤りで震えていた。もちろん、彼女は息子の有罪の可能性すら認めようとはしなかった。しかし、オールドエーカーの運命について驚きも後悔も表明しなかった。それどころか、彼女は彼について非常に辛辣に語ったので、無意識のうちに警察の主張をかなり強化してしまっていた。当然、もし息子が彼女がその男についてこのように話すのを聞いていれば、憎悪と暴力へと彼を駆り立てたことだろう。『彼は人間というより、悪意に満ちた狡猾な猿のようでした』と彼女は言った。『若い頃からずっとそうでしたわ』。」
「『その頃、彼をご存知だったのですか?』と私は尋ねた。」
「『ええ、よく知っていました。実を言うと、昔の求婚者でしたの。彼から背を向け、たとえ貧しくともより良い男性と結婚する分別があって、本当に良かったと思います。彼と婚約していた時、彼が鳥小屋に猫を放ったという衝撃的な話を聞きました。その残忍な残酷さにひどく恐ろしくなり、彼とはもう一切関わりを持たないことにしたのです』。彼女は整理だんすをかき回し、やがてナイフで無残に傷つけられ、切り刻まれた女性の写真を取り出した。『これは私自身の写真です』と彼女は言った。『彼は私の結婚式の朝、彼の呪いと共に、この状態で私に送りつけてきたのです』。」
「『なるほど』と私は言った。『しかし、少なくとも彼は今ではあなたを許したようですな。全財産をあなたの息子さんに残したのですから』。」
「『息子も私も、ジョナス・オールドエーカーから、生きていようと死んでいようと、何も欲しくありません!』と彼女は、しかるべき気概をもって叫んだ。『天には神様がいらっしゃいます、ホームズさん。そして、あの邪悪な男を罰したその同じ神様が、ご自身の良い時に、私の息子の手が彼の血で汚れていないことを示してくださるでしょう』。」
「まあ、いくつか手がかりを試してみたが、我々の仮説を助けるものは何も得られず、むしろ不利になる点がいくつかあった。ついに諦めて、ノーウッドへ向かった。」
「このディープ・ディーン・ハウスという場所は、けばけばしい煉瓦造りの大きな近代的な別荘で、自身の敷地の奥に建っており、正面には月桂樹の茂みのある芝生がある。右手の、道路から少し離れたところに、火事の現場となった材木置き場があった。これが私の手帳のページに描いた大まかな見取り図だ。左側のこの窓が、オールドエーカーの部屋に通じる窓だ。道路から中を覗けるのが分かるだろう。それが今日得られた唯一の慰めのようなものだ。レストレードはいなかったが、彼の巡査部長が案内役を務めてくれた。彼らはちょうど大きな宝の山を見つけたところだった。午前中を費やして燃えた材木の山の灰をかき回し、炭化した有機物の残骸の他に、変色した金属の円盤をいくつか確保していた。注意深く調べてみると、それらがズボンのボタンであることは疑いようもなかった。そのうちの一つには、オールドエーカーの仕立屋である『ハイアムズ』の名が記されていることさえ見分けることができた。それから私は芝生を非常に念入りに調べ、痕跡を探したが、この干ばつですべてが鉄のように硬くなっていた。何か物体か包みが、材木の山と一直線上にある低いイボタの生け垣を通り抜けて引きずられたこと以外、何も見られなかった。もちろん、これらすべては公式の説と一致する。八月の太陽を背に芝生を這い回ったが、一時間経っても以前より賢くはなっていなかった。」
「さて、この失敗の後、私は寝室に入ってそこも調べた。血痕は非常にわずかで、単なる擦り跡や変色だったが、間違いなく新しいものだった。ステッキは取り除かれていたが、そこにも痕跡はわずかだった。ステッキが我々の依頼人のものであることに疑いはない。彼も認めている。両者の足跡はカーペット上に見分けることができたが、第三者のものはなく、これもまた相手側に有利な材料だ。彼らは常に得点を重ねているのに、我々は足踏み状態だった。」
「ほんのわずかな希望の光を得たが――それでも何にもならなかった。金庫の中身を調べた。そのほとんどは取り出されてテーブルの上に置かれていた。書類は封筒に封入されており、そのうちの一、二通は警察によって開封されていた。私が判断する限り、それらは大して価値のあるものではなく、銀行の通帳もオールドエーカー氏がそれほど裕福な状況にあったとは示していなかった。しかし、私にはすべての書類がそこにあるわけではないように思えた。いくつかの証書――おそらくより価値のあるものだろう――への言及があったが、それらを見つけることはできなかった。もちろん、これを明確に証明できれば、レストレードの主張を彼自身に突き返すことになる。まもなく相続すると分かっているものを、誰が盗むだろうか?」
「最後に、他のすべての隠れ家を探し尽くし、何の手がかりも得られなかったので、家政婦で運試しをしてみた。レキシントン夫人というのが彼女の名前だ――小柄で、色黒で、無口な人物で、疑り深く横目で見る。彼女は話そうとすれば何か話せるはずだ――私はそう確信している。しかし、彼女は蝋のように口が堅かった。ええ、彼女がマクファーレン氏を中に入れたのは九時半だった。そうする前に自分の手が萎びてしまえばよかったのに、と。彼女が寝たのは十時半。彼女の部屋は家の反対側にあり、何が起こったのか何も聞こえなかった。マクファーレン氏は帽子を、そして彼女の記憶ではステッキもホールに置いていった。火事の警報で目が覚めた。彼女の哀れな、愛しいご主人は間違いなく殺害された。彼に敵はいたか? まあ、誰にでも敵はいるものだが、オールドエーカー氏はあまり人付き合いをせず、仕事上でしか人に会わなかった。彼女はボタンを見て、それが昨夜彼が着ていた服のものだと確信している。材木の山は非常に乾燥していた。一ヶ月も雨が降っていなかったからだ。それは火口のように燃え、彼女が現場に着いた時には、炎しか見えなかった。彼女も消防士たちも皆、その中から肉の焼ける匂いを嗅いだ。書類のことも、オールドエーカー氏の私的な事情も何も知らない。」
「というわけで、ワトソン、これが私の失敗報告だ。だが、それでも――それでも――」彼は確信の発作に駆られて細い手を握りしめた。「私はすべてが間違っていると知っている。骨の髄までそう感じる。まだ表に出てきていない何かがある。そして、あの家政婦はそれを知っている。彼女の目には、罪の意識を持つ者だけが浮かべる、不機嫌な反抗の色があった。しかし、これ以上話しても仕方がない、ワトソン。何か幸運な偶然が我々に舞い込んでこない限り、ノーウッド失踪事件は、我慢強い大衆が遅かれ早かれ耐えなければならなくなると私が見越している、我々の成功の年代記には名を連ねないだろうと恐れている。」
「しかし」と私は言った。「あの男の外見は、どんな陪審員にも有利に働くでしょう?」
「それは危険な議論だ、ワトソン。八十七年に我々に無罪放免を求めてきた、あの恐ろしい殺人鬼、バート・スティーヴンスを覚えているかね? あれほど温和な物腰の、日曜学校に通うような好青年が他にいただろうか?」
「それは本当です。」
「我々が代わりの説を立証することに成功しない限り、この男は破滅だ。現在彼に対して提示されうる事件に、ほとんど欠点を見つけることはできない。そして、その後の捜査はすべてそれを強化するのに役立っている。ところで、あの書類について一つ奇妙な小さな点がある。それが調査の出発点になるかもしれない。銀行の通帳を調べてみると、残高が少ないのは、主に昨年一年間にコーネリアス氏宛てに振り出された多額の小切手のためだと分かった。引退した建築業者が、これほど多額の取引をするこのコーネリアス氏とは何者なのか、興味をそそられることは認めよう。彼がこの事件に関与している可能性はあるだろうか? コーネリアスは仲買人かもしれないが、これらの多額の支払いに対応する株券は見つかっていない。他に手がかりがない以上、私の調査は今、これらの小切手を現金化した紳士について銀行で尋ねる方向へ進まざるを得ない。しかし、君、恐れているのは、我々の事件が、レストレードが我々の依頼人を絞首刑にして、不名誉な結末を迎えることだ。それは間違いなくスコットランドヤードの勝利となるだろう。」
その夜、シャーロック・ホームズがどれほど眠ったかは分からないが、私が朝食に下りていくと、彼は青白く憔悴し、明るい瞳は周りの隈のせいで一層輝いて見えた。彼の椅子の周りのカーペットには、吸い殻と朝刊の早版が散乱していた。開かれた電報がテーブルの上に置かれていた。
「これをどう思う、ワトソン?」と彼は尋ね、それを投げ越した。
それはノーウッドからで、次のように書かれていた。
重要なる新証拠入手。マクファーレンの有罪、確定的に立証さる。事件より手を引くことを勧告す。――レストレード。
「これは深刻そうですね」と私は言った。
「レストレードのささやかな勝ち鬨だよ」とホームズは苦々しい笑みを浮かべて答えた。「だが、事件を放棄するのはまだ早計かもしれん。結局のところ、重要な新証拠というのは諸刃の剣で、レストレードが想像するのとは全く違う方向を切り裂く可能性もある。朝食を済ませたまえ、ワトソン。二人で出かけて、何ができるか見てみよう。今日は君の同伴と精神的な支えが必要になりそうだ。」
我が友人は自身では朝食をとらなかった。彼の特異な性質の一つで、最も緊張が高まった時には一切の食事を許さず、純粋な栄養失調で倒れるまでその鉄のような体力に頼るのを私は知っていた。「今は消化にエネルギーと神経力を割く余裕がない」と、私の医学的な忠告に対して彼は言うのだった。だから、今朝彼が手つかずの食事を後に残し、私と共にノーウッドへ出発したことに驚きはなかった。ディープ・ディーン・ハウスの周りには、野次馬の群れがまだ集まっていた。それは私が想像していた通りの郊外の別荘だった。門の内側でレストレードが我々を迎えた。彼の顔は勝利に紅潮し、その態度はひどく勝ち誇っていた。
「さて、ホームズさん、もう我々が間違っていると証明しましたか? あなたの浮浪者は見つかりましたかな?」と彼は叫んだ。
「私は何の結論にも達していません」と我が友人は答えた。
「しかし、我々は昨日結論を出し、そして今、それが正しいと証明された。ですから、今回は我々があなたより少し先を行っていたと認めざるを得ませんな、ホームズさん。」
「確かに、何か尋常ならざることが起こったという様子ですな」とホームズは言った。
レストレードは声高に笑った。
「あなたも我々と同様、負けるのはお嫌いでしょう」と彼は言った。「人間、いつも自分の思い通りにはいかないものですな、ワトソン博士? こちらへどうぞ、紳士諸君。ジョン・マクファーレンがこの罪を犯したのだと、きっぱりとご納得させられると思いますよ。」
彼は我々を廊下を通って、その先の暗いホールへと案内した。
「若いマクファーレンが犯行後に帽子を取りに出てきたのは、ここに違いありません」と彼は言った。「さあ、これを見てください。」
彼は芝居がかった素早さでマッチを擦り、その光で白塗りの壁の血の染みを照らし出した。彼がマッチを近づけると、それが単なる染み以上のものであることが分かった。それは、はっきりと印された親指の指紋だった。
「それを拡大鏡でご覧なさい、ホームズさん。」
「ああ、そうさせてもらおう。」
「二つとして同じ指紋はないことはご存知でしょう?」
「その種のことは耳にしたことがあります。」
「では、その指紋を、今朝私の命令で採取した、若いマクファーレンの右手の親指の蝋の型と比べていただけますかな?」
彼が蝋の型を血の染みに近づけると、二つが間違いなく同じ親指のものであることを見るのに、拡大鏡は必要なかった。我々の不運な依頼人が破滅したことは、私には明白だった。
「これで決まりだ」とレストレードは言った。
「ええ、これで決まりです」と私は思わず同調した。
「決まりだ」とホームズは言った。
彼の口調に何か引っかかるものを感じ、私は彼の方を振り向いた。彼の顔には異常な変化が起こっていた。内なる愉快さで顔が歪んでいる。二つの目が星のように輝いていた。私には、彼が痙攣的な笑いの発作を必死に抑えようとしているように見えた。
「やれやれ! これはこれは!」と彼はついに言った。「さて、誰がこんなことを考えついたものか。そして、見かけがいかに当てにならないことか! 見たところ、あんなに好青年なのに! 我々自身の判断を信じてはいけないという教訓ですな、レストレード君?」
「ええ、我々の中には少々自信過剰になりすぎる傾向がある者もいますからな、ホームズさん」とレストレードは言った。その男の無礼さは腹立たしかったが、我々はそれに腹を立てることはできなかった。
「この若者が、帽子を掛け釘から取る際に、右手の親指を壁に押し付けたとは、何と天の助けか! 考えてみれば、実に自然な行動でもある。」
ホームズは表面上は冷静だったが、話しながら彼の全身は抑えられた興奮で身もだえした。
「ところで、レストレード、この注目すべき発見をしたのは誰かね?」
「家政婦のレキシントン夫人が、夜警の巡査に注意を促したのです。」
「夜警の巡査はどこにいた?」
「彼は犯行が行われた寝室で、何物にも触れられないように見張りを続けていました。」
「しかし、なぜ警察は昨日この跡を見なかったのかね?」
「まあ、ホールを念入りに調べる特別な理由はありませんでしたから。それに、ご覧の通り、あまり目立つ場所でもありません。」
「いや、いや――もちろんそうだろう。この跡が昨日からそこにあったことに疑いはないのだろうな?」
レストレードは、まるでホームズが正気を失ったのではないかと思うような目で彼を見た。私自身も、彼の陽気な態度と、やや突飛な発言に驚いたことを告白する。
「マクファーレンが自分に不利な証拠を強化するために、真夜中に牢獄から抜け出したとでもお考えかどうかは知りませんが」とレストレードは言った。「それが彼の親指の跡でないとでも言うなら、世界のどの専門家にでも判断を委ねますよ。」
「それは紛れもなく彼の親指の跡だ。」
「では、それで十分だ」とレストレードは言った。「私は実践的な人間です、ホームズさん。証拠が手に入れば、結論を出す。何か言いたいことがあれば、私は居間で報告書を書いていますから。」
ホームズは平静を取り戻していたが、その表情にはまだ面白がるような光がちらついているように私には見えた。
「やれやれ、これは非常に悲しい展開だ、ワトソン、そうではないかね?」と彼は言った。「だが、これには奇妙な点があり、我々の依頼人にいくらかの希望を与えてくれる。」
「それを聞いて嬉しいです」と私は心から言った。「もう彼も終わりかと心配していました。」
「そこまで言うつもりはないよ、ワトソン。実のところ、我々の友人があれほど重要視しているこの証拠には、一つ実に深刻な欠陥があるのだ。」
「本当ですか、ホームズ! それは何です?」
「これだけだ。私が昨日ホールを調べた時、あの跡はそこになかったと知っているということだ。さて、ワトソン、少し陽の光の中を散歩しようじゃないか。」
混乱した頭脳、しかし心にはいくらかの希望の温もりが戻りつつある中で、私は友人に伴われて庭を一周した。ホームズは家の各面を順番に、大きな関心を持って調べた。それから彼は中へ案内し、地下室から屋根裏まで建物全体をくまなく見て回った。ほとんどの部屋は家具がなかったが、それでもホームズはそれらすべてを詳細に調査した。最後に、三つの空き寝室の外を通る最上階の廊下で、彼は再び愉快さの発作に襲われた。
「この事件には実にユニークな特徴がいくつかあるな、ワトソン」と彼は言った。「そろそろ我々の友人レストレードを我々の信頼の輪に加える時が来たと思う。彼は我々を相手に少しばかり笑ったのだから、もし私のこの問題の読みが正しければ、我々も彼に同じことをしてやれるかもしれん。そうだ、そうだ、どうアプローチすべきか見えてきたぞ。」
スコットランドヤードの警部はまだ客間で報告書を書いていたが、ホームズが彼を遮った。
「この事件の報告書を書いていらっしゃると伺いましたが」と彼は言った。
「その通りだ。」
「少し早計だとは思いませんか? どうもあなたの証拠は完全ではないように思えるのですが。」
レストレードは友人のことをよく知っていたので、彼の言葉を無視することはできなかった。彼はペンを置き、いぶかしげに彼を見た。
「どういう意味です、ホームズさん?」
「ただ、あなた方がまだ会っていない重要な証人がいる、ということです。」
「その証人を連れてこられるかね?」
「できると思います。」
「ならば、そうしたまえ。」
「最善を尽くしましょう。巡査は何人いますか?」
「呼べばすぐに来られる者が三人おります。」
「素晴らしい!」ホームズは言った。「失礼ながら、彼らはみな大柄で屈強、そして声の大きい男たちですかな?」
「間違いなくそうでしょうが、声の大きさがこの件と何の関係があるのか、皆目見当もつきませんな。」
「それについては、いずれお分かりいただけるでしょう。他にも一、二の事柄と共にな」ホームズは言った。「どうか部下の方々をお呼びください。やってみせましょう。」
五分後、三人の警官がホールに集合した。
「離れに、かなりの量の藁があるはずです」ホームズは言った。「そのうち二束を運び込んできてください。私が求める証人をあぶり出すのに、大いに役立つはずです。どうもありがとう。ワトソン君、君はポケットにマッチを持っているだろう。さあ、レストレード君、皆さんも私と一緒に最上階の踊り場までお付き合い願いたい。」
前にも述べたように、そこには広い廊下があり、三つの空き部屋の前を走っていた。その廊下の端に、我々はシャーロック・ホームズによって整列させられた。巡査たちはにやにや笑い、レストレードは驚きと期待、そして嘲りが入り混じった表情で我が友を見つめている。ホームズは手品を披露する奇術師のような面持ちで我々の前に立っていた。
「恐縮ですが、巡査殿の一人にバケツ二杯の水を持ってきてもらえませんか? 藁はこちらの床に、両側の壁から離して置いてください。さて、これで準備万端でしょう。」
レストレードの顔が怒りで赤くなってきた。「我々をからかっているのか、シャーロック・ホームズ君」彼は言った。「何か知っているのなら、こんな馬鹿げた真似をせずとも、口で言えるはずだ。」
「保証しますよ、レストレード君。私のやる事なす事すべてに、ちゃんとした理由があるのです。数時間前、形勢があなたに有利に見えた時、少し私をからかいましたね。ですから、今度は私が少々芝居がかった演出をするのをお許しいただきたい。ワトソン君、その窓を開けて、藁の端にマッチで火をつけてくれないか。」
私はその通りにした。隙間風にあおられて灰色の煙が渦を巻いて廊下を流れ、乾いた藁がパチパチと音を立てて燃え上がった。
「さあ、レストレード君、君のためにこの証人を見つけ出せるかどうか、試してみましょう。皆さん、ご一緒に『火事だ!』と叫んでいただけますかな? では、一、二、三――」
「火事だ!」我々は一斉に叫んだ。
「ありがとう。もう一度お願いします。」
「火事だ!」
「紳士諸君、もう一度だけ、全員で。」
「火事だ!」
その叫び声は、ノーウッド中に響き渡ったに違いない。
その声が消えやらぬうちに、驚くべきことが起こった。廊下の突き当たりにある、ただの壁としか見えなかった場所から突然ドアが開き、穴から飛び出す兎のごとく、しなびた小男が飛び出してきたのだ。
「見事!」ホームズは落ち着き払って言った。「ワトソン君、藁にバケツの水を。それで十分だ! レストレード君、君の捜していた最重要行方不明証人、ジョナス・オールドエーカー氏をご紹介しよう。」
刑事はあっけにとられて、その新参者を凝視した。当人は廊下の明るい光に目をしばたたかせ、我々とくすぶる火を交互に見ている。それは実に不快な顔つきだった――狡猾で、邪悪で、悪意に満ち、落ち着きのない薄灰色の目と白い睫毛を持っていた。
「これは一体どういうことだ?」レストレードがようやく口を開いた。「今まで何をしていたんだ、ええ?」
オールドエーカーは、怒り狂う刑事の真っ赤な顔から身をすくめ、不安げな笑いを漏らした。
「私は何も悪いことはしておりません。」
「悪いことだと? お前は罪なき男を絞首台に送ろうと全力を尽くしたんだぞ。ここにこの紳士がいなければ、お前の企みは成功していたかもしれんのだ。」
その哀れな男はしくしくと泣き始めた。
「本当です、旦那様。ただの悪戯だったのです。」
「ほう! 悪戯だと? 笑っていられるのは今のうちだけだと請け合おう。こいつを階下へ連れて行け。私が戻るまで居間に閉じ込めておけ。ホームズ君」二人が去った後、彼は続けた。「巡査たちの前では言えなかったが、ワトソン博士の前だから言わせてもらう。どうやってやり遂げたのかは謎だが、これは君の仕事の中でも最高に鮮やかな手際だ。君は無実の男の命を救い、警察の面目を丸潰れにするはずだった重大な不祥事を防いでくれた。」
ホームズは微笑み、レストレードの肩を叩いた。
「面目丸潰れどころか、君の評判は大いに高まることでしょう。君が書いていた報告書に少し手心を加えれば、レストレード警部の目を欺くのがいかに困難か、皆が理解するはずです。」
「それで、君の名前は出したくないと?」
「全く。仕事そのものが報酬ですから。まあ、いずれ遠い未来に、私の熱心な歴史家が再び原稿用紙を広げることを許した暁には、私も名誉を得ることになるかもしれませんがね――なあ、ワトソン君? さて、この鼠がどこに潜んでいたか、見てみましょう。」
廊下の突き当たりから六フィートのところに、漆喰塗りの木舞壁の間仕切りが設けられ、その中に巧妙に隠し扉が作られていた。内部は軒下の隙間から光が差し込んでいる。いくつかの家具と食料、水が備えられ、多数の書物や書類と共に置かれていた。
「建築業者であることの利点ですな」我々が出てくると、ホームズは言った。「共犯者なしで、自分だけの小さな隠れ家をしつらえることができた。もちろん、あの貴重な家政婦は別ですが。レストレード君、彼女もすぐに袋の鼠にすることをお勧めしますよ。」
「君の助言に従おう。しかし、どうやってこの場所を知ったんだ、ホームズ君?」
「あの男はこの家の中に隠れていると確信していました。ある廊下を歩測してみると、階下の対応する廊下より六フィート短い。これで、彼の居場所はほぼ明らかでした。火事の警報を前にして、静かに寝ていられるほどの度胸はないだろうと考えたのです。もちろん、乗り込んで捕らえることもできましたが、彼自身に正体を現させる方が面白い。それに、今朝の君のからかいに対し、少しばかり煙に巻くくらいの借りは返しておかないとね、レストレード君。」
「うむ、確かにそれで貸し借りはなしだ。しかし、そもそもどうして彼が家の中にいると分かったんだ?」
「拇印ですよ、レストレード君。君はあれが決定的な証拠だと言った。その通り、全く違う意味で決定的だったのです。私は、それが前日にはなかったことを知っていました。ご存じの通り、私は細部に多大な注意を払う質でしてね、ホールを調べた時、壁には何もないことを確認していたのです。したがって、それは夜の間に付けられたものだ。」
「しかし、どうやって?」
「ごく簡単なことです。書類に封をする際、ジョナス・オールドエーカーはマクファーレンに、柔らかい蝋の上に親指を押しつけて封印の一つを確実にするよう頼んだ。あまりに素早く、自然に行われたので、おそらく若者自身も覚えていないでしょう。おそらくは偶然の出来事で、オールドエーカー自身もそれをどう使うかなど考えていなかった。しかし、あの隠れ家で事件について思いを巡らすうち、その拇印を使えばマクファーレンにとってどれほど決定的な証拠を作り出せるか、突如として閃いたのです。彼にとって、封蝋から蝋の型を取り、針で刺して得られるだけの血で湿らせ、夜の間に自分か家政婦の手で壁に印を付けることなど、赤子の手をひねるようなものでした。彼が隠れ家に持ち込んだ書類を調べれば、その拇印のついた封蝋が見つかることに賭けてもいい。」
「素晴らしい!」レストレードは言った。「素晴らしい! 君が言うように、全てが水晶のように明らかだ。しかし、この手の込んだ欺瞞の目的は何なんだ、ホームズ君?」
刑事の横柄な態度が、突如として教師に質問する子供のようになったのを見るのは、私にとって愉快な光景だった。
「ふむ、それを説明するのはさほど難しくはないでしょう。今、階下で我々を待っている紳士は、非常に陰険で、悪意に満ちた、執念深い人物です。彼がかつてマクファーレンの母親に求婚を断られたことを知っていますか? 知らない! だから言ったでしょう、まずブラックヒースへ、それからノーウッドへ行くべきだったと。さて、彼に言わせればこの屈辱が、彼の邪悪で策略に満ちた脳裏に深く刻み込まれ、生涯を通じて復讐を渇望しながらも、その機会を得られずにいた。ここ一、二年、彼の身辺では物事がうまくいかなくなり――秘密の投機だと思いますが――彼は窮地に陥った。そこで債権者を騙すことを決意し、その目的で、あるコーネリアス氏という人物に多額の小切手を支払っている。これは、思うに、彼自身の別名でしょう。まだこの小切手を追跡してはいませんが、オールドエーカーが時折二重生活を送っていたどこかの地方の町で、その名前で銀行に預けられたに違いありません。彼は完全に名前を変え、この金を引き出して姿をくらまし、どこか別の場所で人生をやり直すつもりだったのです。」
「なるほど、ありそうな話だ。」
「そして彼は閃いたのでしょう。失踪するにあたり、追跡を完全に振り切り、同時に、かつての恋人の一人息子に殺されたという印象を与えることができれば、彼女に対して十分かつ決定的な復讐を果たせる、と。それは悪事の傑作であり、彼は名人のごとくそれを実行した。犯行に明白な動機を与える遺言書のアイデア、両親に知られていない秘密の訪問、杖の保持、血痕、そして薪の山にあった動物の残骸とボタン、すべてが見事でした。数時間前には、私にも到底逃れられない網のように思えた。しかし、彼には芸術家の持つ至高の才能、すなわち引き際を知るという知識が欠けていた。彼はすでに完璧なものをさらに良くしようと望み――不運な犠牲者の首にかかる縄をさらにきつく締めようとして――全てを台無しにしたのです。降りましょう、レストレード君。彼に一、二、尋ねたいことがある。」
その悪意に満ちた男は、自宅の居間で、両脇を警官に固められて座っていた。
「悪戯だったんです、旦那様――ただの悪戯で、それ以上のものではありません」彼は絶え間なく泣き言を言った。「本当です、旦那様。私はただ、自分が失踪したらどうなるか、その反応が見たくて身を隠しただけなのです。まさか私が、哀れなマクファーレン青年に何か危害が及ぶのを許したなどと、そんな非道な想像はなさらないでしょう。」
「それは陪審が決めることだ」レストレードは言った。「いずれにせよ、殺人未遂でなくとも、共謀罪で貴様を起訴することになるだろう。」
「そして、あなたの債権者たちはコーネリアス氏の銀行口座を差し押さえることになるでしょうな」ホームズは言った。
小男はびくりとし、悪意に満ちた目を我が友に向けた。
「ずいぶんと世話になったな」彼は言った。「この借りは、いつか必ず返す。」
ホームズは寛大に微笑んだ。
「思うに、今後数年間は、あなたの時間は非常に多忙なものになるでしょう」彼は言った。「ところで、薪の山に入れたのは、あなたの古いズボンの他に何でしたかな? 死んだ犬か、兎か、それとも何か? 教えてくれないのですか? やれやれ、何とも不親切な! まあ、おそらく兎二羽もいれば、血痕と焼け焦げた灰の両方の説明がつきますな。ワトソン君、いつかこの事件を記録するなら、兎で辻褄を合わせるといい。」
踊る人形
ホームズは何時間も黙って椅子に座り、その細長い背を丸めて化学実験用の容器を覗き込んでいた。その中では、ひときわ悪臭を放つ物質が調合されているところだった。頭を胸にうずめるようにしているその姿は、私から見れば、鈍い灰色の羽毛と黒い冠羽を持つ、奇妙でひょろりとした鳥のようだった。
「それで、ワトソン君」彼は唐突に言った。「南アフリカの証券には投資しないことにしたのかね?」
私は驚きのあまり、飛び上がらんばかりだった。ホームズの奇妙な能力には慣れっこになっていたが、私の最も内密な思考にこうも突然踏み込んでこられると、全く説明がつかない。
「一体全体、どうしてそんなことが分かるんだ?」と私は尋ねた。
彼は湯気の立つ試験管を手に、丸椅子の上でくるりとこちらを向いた。その窪んだ目には、面白がるような光が宿っていた。
「さあ、ワトソン君、完全に度肝を抜かれたと白状したまえ。」
「その通りだ。」
「その旨、一筆書かせるべきだったな。」
「なぜ?」
「なぜなら、五分後には君が『何とも馬鹿馬鹿しいほど単純だ』と言うだろうからだ。」
「そんなことは決して言うものか。」
「いいかね、ワトソン君」――彼は試験管をラックに立て、教壇に立つ教授が学生に講義するかのような口調で話し始めた――「一つ一つが前の事柄に依存し、それぞれが単純な推論を連続して組み立てることは、実のところ難しくはない。そうした後、中間の推論をすべて取り払い、聴衆に出発点と結論だけを示せば、驚くべき、もっとも、それは見かけ倒しかもしれないが、効果を生み出すことができる。さて、君の左手の人差し指と親指の間の窪みを観察すれば、君がそのなけなしの資本を金鉱に投資するつもりはないと確信するのは、さして難しいことではなかった。」
「何の繋がりも見えないが。」
「まあ、そうだろう。だが、すぐに密接な繋がりを示してやろう。この極めて単純な連鎖の、失われた環はこうだ。一、昨夜クラブから帰宅した時、君の左手の人差し指と親指の間にチョークがついていた。二、君がチョークをそこにつけるのは、ビリヤードでキューを安定させる時だ。三、君はサーストンと以外ではビリヤードをしない。四、四週間前、君は私に、サーストンが南アフリカの不動産に関するオプション権を持っており、それが一ヶ月で失効するため、君にも共同出資を望んでいると話した。五、君の小切手帳は私の引き出しに鍵をかけてしまってあり、君は鍵を要求していない。六、よって、君はそのような形で金を投資するつもりはない。」
「何とも馬鹿馬鹿しいほど単純だ!」私は叫んだ。
「その通り!」彼は少しむっとして言った。「どんな問題も、一度説明されてしまえば子供だましになるものだ。ここに未解決の問題がある。どうだね、ワトソン君、これをどう解くか見てみようじゃないか。」
彼はテーブルに一枚の紙を投げつけ、再び化学分析へと向き直った。
私は紙の上に描かれた馬鹿げた象形文字を、驚きをもって見つめた。
「なんだ、ホームズ、これは子供の落書きじゃないか」私は叫んだ。
「ほう、君はそう思うかね!」
「でなければ、一体何だというんだ?」
「それこそ、ノーフォーク州ライディング・ソープ・マナーのヒルトン・キュービット氏が知りたくてたまらないことなのだよ。この小さな謎は朝一番の郵便で届き、彼は次の列車でこちらへ向かうことになっている。ほら、ベルが鳴ったぞ、ワトソン君。彼が来たとしても、さほど驚きはしないな。」
階段を上がる重い足音が聞こえ、その直後、背の高い、血色の良い、髭をきれいに剃った紳士が入ってきた。その澄んだ瞳と紅潮した頬は、ベーカー街の霧とは無縁の生活を物語っていた。彼は部屋に入ると同時に、イングランド東海岸の力強く、清々しく、身の引き締まるような空気を運んできたかのようだった。我々一人一人と握手を交わし、腰を下ろそうとした時、彼の視線は、私が先ほどまで調べてテーブルに置いたままにしていた、奇妙な印のついた紙に留まった。
「さて、ホームズさん、これをどう思われますかな?」彼は叫んだ。「あなたが奇妙な謎を好むと伺いましたが、これ以上に奇妙なものはないでしょう。私が来る前に研究する時間があるようにと、先にこの紙をお送りしたのです。」
「確かに、なかなかに奇妙な代物ですな」ホームズは言った。「一見したところ、子供の悪戯のように見えます。紙の上に描かれた、いくつもの馬鹿げた小人が踊っている。なぜ、このような奇怪なものを重要視されるのですか?」
「私なら、決して。しかし、妻がそうなんです。彼女は死ぬほど怖がっている。口には出しませんが、その目には恐怖が浮かんでいます。だからこそ、私はこの件の真相を突き止めたいのです。」
ホームズは紙を掲げ、太陽の光がさんさんと当たるようにした。それはノートから破り取られた一枚だった。印は鉛筆で書かれており、次のようにならんでいた。

ホームズはしばらくそれを吟味し、それから注意深く折りたたんで手帳にしまった。
「これは実に興味深く、また類を見ない事件になりそうですな」彼は言った。「キュービットさん、お手紙でいくつか詳細を伺いましたが、我が友ワトソン博士のためにも、もう一度すべてをお話しいただけると大変ありがたい。」
「私は話がうまくないもので」我らが依頼人は、その大きく力強い手を神経質に組んだり解いたりしながら言った。「分かりにくいところがあれば、何でもお尋ねください。話は去年の結婚の時から始めますが、まず申し上げておきたいのは、私は富豪ではありませんが、我が一族は五世紀にわたってライディング・ソープに住んでおり、ノーフォーク州でこれ以上知られた家はないということです。去年、私は女王陛下の祝典のためにロンドンへ上り、ラッセル・スクエアの下宿に滞在しました。というのも、我々の教区の牧師であるパーカー師がそこに泊まっていたからです。そこにアメリカ人の若い女性がおりまして――パトリックという名でした――エルシー・パトリック。どういうわけか我々は親しくなり、一ヶ月も経たないうちに、私はこれ以上ないほど恋に落ちていました。我々は登記所でささやかに結婚し、夫婦としてノーフォークへ戻ったのです。由緒ある旧家の男が、妻の過去も身内も何も知らずにこんな風に結婚するなんて、狂気の沙汰だと思われるでしょう、ホームズさん。しかし、もし彼女に会い、彼女を知っていただければ、ご理解いただけるはずです。」
「エルシーは、そのことについて非常に正直でした。もし私が望むなら、この話から手を引く機会をいくらでも与えてくれたと言っても過言ではありません。『私の人生には、とても不愉快な関わりがありました』と彼女は言いました。『そのことは全て忘れたいのです。過去については二度と触れたくありません。私にとって、とても辛いことですから。もし私をめとってくださるなら、ヒルトン、あなたは個人的に恥じるべきことは何もない女を妻にすることになります。でも、それについては私の言葉を信じていただくしかなく、私があなたのものになるまでの過去については、沈黙を許していただかなければなりません。もしこの条件が厳しすぎるのでしたら、どうぞノーフォークへお帰りになって、私をあなたが見つけた孤独な生活の中に置いていってください』。結婚式の前日に、彼女はまさにそう私に言ったのです。私は彼女の条件で彼女を受け入れることに満足していると告げ、そしてその言葉を守ってきました。」
「さて、結婚して一年、我々はとても幸せに暮らしてきました。しかし、一ヶ月ほど前、六月の終わりに、初めて不穏な兆候が見られたのです。ある日、妻がアメリカから手紙を受け取りました。アメリカの切手が見えました。彼女は死人のように真っ青になり、手紙を読むと、それを暖炉に投げ込みました。彼女はその後そのことに一切触れず、私も何も言いませんでした。約束は約束ですから。しかし、その瞬間から彼女に心休まる時はないのです。いつも顔には恐怖の色が浮かんでいます――何かを待ち、予期しているかのような表情です。私を信頼してくれればいいのですが。私が彼女の一番の味方だと分かるはずです。しかし、彼女が口を開くまでは、私には何も言えません。誤解しないでいただきたいのですが、ホームズさん、彼女は正直な女性です。過去にどんな問題があったにせよ、それは彼女の落ち度ではありません。私はただのノーフォークの田舎郷士にすぎませんが、イングランド広しといえども、私ほど家の名誉を重んじる男はおりません。彼女はそれをよく知っていますし、結婚する前から知っていました。彼女が家の名誉を汚すようなことは決してしない――それだけは確信しています。」
「さて、ここからが私の話の奇妙な部分です。一週間ほど前――先週の火曜日のことでした――窓の桟の一つに、この紙にあるような、馬鹿げた小さな踊る人形がいくつも描かれているのを見つけました。チョークで走り書きされていたのです。私は馬丁の少年が描いたのだと思いましたが、その子は全く知らないと誓って言いました。いずれにせよ、夜の間に現れたものです。私はそれを洗い落とさせ、後になってから妻にそのことを話しました。驚いたことに、彼女はそれを非常に深刻に受け止め、もしまた現れたら見せてほしいと私に懇願しました。一週間は何も起こりませんでしたが、昨日の朝、庭の日時計の上にこの紙が置かれているのを見つけたのです。それをエルシーに見せると、彼女は気を失って倒れてしまいました。それ以来、彼女は夢遊病者のように、半分呆然とし、目には常に恐怖が潜んでいます。その時です、私があなたに手紙を書き、この紙を送ったのは。警察に持ち込めるような話ではありません。笑われるのが関の山でしょう。しかし、あなたならどうすべきか教えてくださるはずだ。私は金持ちではありませんが、もし私の可愛い妻に危険が迫っているのなら、最後の一銭まで使って彼女を守ります。」
古きイングランドの大地に根ざしたこの男は、実に立派な人物だった――素朴で、実直で、穏やかで、その大きく真摯な青い瞳と、広く整った顔立ちをしていた。妻への愛と彼女への信頼が、その表情に輝いていた。ホームズは彼の話を最大限の注意を払って聞き、そして今、しばらくの間、沈黙と思考に沈んでいた。
「キュービットさん」彼はついに口を開いた。「最善の策は、奥様に直接訴えかけ、その秘密を分かち合ってくれるよう頼むことだとは思いませんか?」
ヒルトン・キュービットは、そのがっしりとした頭を横に振った。
「約束は約束です、ホームズさん。もしエルシーが話したいと思えば、そうするでしょう。そうでなければ、私が彼女の信頼を無理強いするべきではない。しかし、私には私自身のやり方で行動する権利がある――そして、そうするつもりです。」
「ならば、私も心からお力になりましょう。まず第一に、ご近所で見慣れない人物が目撃されたという話はありますか?」
「いいえ。」
「非常に静かな場所だとお見受けしますが。見慣れない顔があれば、噂になりますか?」
「すぐ近所であれば、はい。しかし、さほど遠くないところに、いくつかの小さな保養地があります。それに、農家は下宿人も受け入れていますから。」
「この象形文字には、明らかに意味がある。もしそれが全くの気まぐれなものであれば、我々には解読不可能かもしれません。しかし、もし体系的なものであれば、必ずや真相を突き止められるでしょう。ですが、この特定のサンプルはあまりに短すぎて、何もできません。そして、あなたがもたらしてくれた事実もあまりに漠然としていて、調査の足がかりがない。私の提案はこうです。ノーフォークへお帰りになり、鋭く見張りを続け、新たに出現する踊る人形があれば、その正確な写しを取ってください。窓の桟にチョークで描かれたものの写しがないのが、実に残念でなりません。近所の見知らぬ人物についても、慎重に聞き込みをしてください。新たな証拠が集まったら、また私のところへお越しください。それが、ヒルトン・キュービットさん、私があなたにできる最善の助言です。もし何か急を要する新たな展開があれば、いつでもノーフォークのご自宅へ駆けつけます。」
この面会は、シャーロック・ホームズを深く物思いに沈ませた。続く数日間、彼が手帳からその紙片を取り出し、そこに記された奇妙な図形を長く熱心に見つめるのを、私は何度か目にした。しかし、彼がその件について言及することはなく、二週間ほど経ったある日の午後まで時は流れた。私が外出しようとすると、彼が私を呼び止めた。
「ここにいた方がいい、ワトソン君。」
「なぜ?」
「今朝、ヒルトン・キュービットから電報を受け取ったのだ。踊る人形のヒルトン・キュービットを覚えているかね? 彼は一時二十分にリバプール・ストリート駅に着くことになっている。いつここに現れてもおかしくない。電報から察するに、何か重要な新しい出来事があったようだ。」
我々は長く待つ必要はなかった。ノーフォークの郷士は、辻馬車が運べる限りの速さで駅から直行してきた。彼は疲れ切った目と、しわの寄った額で、心配と落胆の表情を浮かべていた。
「この一件は、私の神経をすり減らしています、ホームズさん」彼は疲れ果てた男のように肘掛け椅子に沈み込みながら言った。「見えない、知らない連中に囲まれ、何らかの企みを持たれていると感じるだけでも十分悪い。しかし、それに加えて、それが妻をじわじわと殺していると分かれば、生身の人間が耐えられる限度を超えてしまいます。彼女はそれで衰弱していく――まさに私の目の前で衰弱していくのです。」
「彼女はまだ何も?」
「いいえ、ホームズさん、まだです。ですが、哀れな彼女が話したがっているのに、どうしても一歩を踏み出せない、という時が何度かありました。私も助けようとしましたが、おそらく不器用で、彼女を怖がらせてしまったのでしょう。彼女は私の旧家や、州での評判、そして我々の汚れなき名誉への誇りについて語り、いつも核心に近づいていると感じるのですが、どういうわけか、そこへ至る前に話が逸れてしまうのです。」
「しかし、ご自身で何か発見は?」
「かなりのことを、ホームズさん。調べていただくために、新しい踊る人形の絵をいくつか持ってきました。そして、さらに重要なことに、私はその男を見ました。」
「何と、それを描いている男を?」
「はい、彼が描いているところを。しかし、順を追って全てお話ししましょう。あなたを訪ねた後、私が戻って翌朝一番に目にしたのは、新しい踊る人形の群れでした。正面の窓から丸見えの、芝生の脇に立つ道具小屋の黒い木製のドアに、チョークで描かれていたのです。正確な写しを取りました。これがそうです。」
彼は紙を広げ、テーブルの上に置いた。これがその象形文字の写しである。

「素晴らしい!」ホームズは言った。「素晴らしい! どうぞ続けてください。」
「写しを取った後、私はその印を消し去りましたが、二日後の朝、また新たなものが現れました。その写しがここにあります。」

ホームズは手をこすり合わせ、喜びのあまりくすくすと笑った。
「我々の資料は急速に蓄積されていますな」彼は言った。
「三日後、紙に走り書きされた伝言が、日時計の上の小石の下に置かれていました。これがそうです。ご覧の通り、文字は最後のものと全く同じです。その後、私は待ち伏せを決意し、リボルバーを取り出して書斎で夜を明かしました。書斎からは芝生と庭が見渡せます。午前二時頃、外の月明かりを除いては全てが闇に包まれる中、私が窓辺に座っていると、背後に足音が聞こえ、そこにいたのは寝間着姿の妻でした。彼女は私に寝室へ来るよう懇願しました。私は、我々にこんな馬鹿げた悪戯をするのが誰なのか確かめたいのだと、率直に告げました。彼女は、それは無意味な悪戯で、気にする必要はないと答えました。」
「『本当に気になるのなら、ヒルトン、二人で旅行にでも出て、この厄介事を避けましょう』。」
「『何だと、悪戯者のせいで自分の家から追い出されるというのか?』私は言いました。『そんなことをしたら、州中の笑いものになるぞ』。」
「『とにかく、寝室へいらして』と彼女は言いました。『朝になったら話し合いましょう』。」
「突然、彼女が話している最中に、月明かりの中でその白い顔がさらに青ざめるのが見え、私の肩を掴む手に力がこもりました。道具小屋の影で何かが動いていたのです。私は、角を這うように回り込み、ドアの前にうずくまる、黒く忍び寄る人影を見ました。ピストルを掴んで飛び出そうとしたところ、妻が私の体に腕を回し、痙攣するような力で私を抱きしめました。私は彼女を振りほどこうとしましたが、彼女は必死にしがみついてきました。ようやく自由になったものの、私がドアを開けて小屋にたどり着いた時には、そいつはもういなくなっていました。しかし、存在の痕跡は残していきました。ドアには、すでに二度現れたのと同じ、私がこの紙に写した踊る人形の配列が描かれていたのです。敷地中を走り回りましたが、男の他の痕跡はどこにもありませんでした。それなのに、驚くべきことに、そいつはずっとそこにいたに違いないのです。というのも、朝になって再びドアを調べると、私がすでに見たいくつかの絵の下に、さらに絵を走り書きしていたのですから。」
「その新しい絵はお持ちですか?」
「はい、非常に短いものですが、写しを取りました。これがそうです。」
彼は再び紙を取り出した。新しい踊りは、このような形だった。
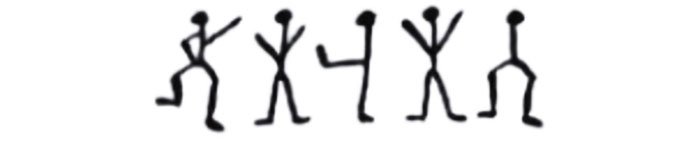
「教えてください」ホームズは言った――その目から、彼が非常に興奮しているのが見て取れた――「これは最初のものへの単なる追加でしたか、それとも全く別個のものに見えましたか?」
「ドアの別の羽目板にありました。」
「素晴らしい! これは我々の目的のために、何よりも重要なものです。希望が湧いてきました。さて、ヒルトン・キュービットさん、非常に興味深いお話を続けてください。」
「もうお話しすることはありません、ホームズさん。ただ、あの夜、こそこそする悪党を捕まえられたかもしれないのに、私を引き留めた妻に腹を立てたことくらいです。彼女は、私が危害を加えられるのを恐れたと言いました。一瞬、彼女が本当に恐れていたのは、彼が危害を加えられることではないか、という考えが頭をよぎりました。というのも、彼女がこの男が誰で、これらの奇妙な合図が何を意味するのかを知っていることは疑いようがなかったからです。しかし、ホームズさん、妻の声には、そしてその目には、疑いを差し挟むことを許さない何かがあり、彼女が心から案じていたのは、まさしく私自身の安全だったと確信しています。これが事件の全てです。さて、どうすべきか、あなたのアドバイスをいただきたい。私自身の考えとしては、農場の若者を六人ほど茂みに潜ませておき、この男が再び現れたら、二度と我々に手出しできないよう、こてんぱんに打ちのめしてやりたいのですが。」
「恐れながら、そのような単純な治療法で済むには、事件は深すぎます」ホームズは言った。「ロンドンにはどのくらい滞在できますか?」
「今日中に戻らねばなりません。妻を一晩中一人にしておくわけにはいきません。彼女は非常に神経質になっており、戻ってきてほしいと懇願しているのです。」
「おっしゃる通りでしょう。しかし、もし滞在していただけたなら、一、二日中にご一緒にお戻りできたかもしれません。とりあえず、これらの紙を私に預けていってください。近いうちにあなたを訪ね、この事件に何らかの光を当てることができる可能性は高いと思います。」
シャーロック・ホームズは、依頼人が我々の元を去るまで、冷静で専門家らしい態度を崩さなかった。もっとも、彼をよく知る私には、彼が深く興奮しているのが容易に見て取れた。ヒルトン・キュービットの広い背中がドアの向こうに消えた瞬間、我が友はテーブルに駆け寄り、踊る人形の描かれた紙片を全て目の前に並べ、複雑で緻密な計算に没頭した。二時間もの間、私は彼が次から次へと紙を数字と文字で埋めていくのを眺めていた。彼は作業に完全に没頭し、私の存在を明らかに忘れていた。時には進展があり、仕事中に口笛を吹いたり歌ったりしたかと思えば、時には行き詰まり、眉間にしわを寄せ、うつろな目で長時間座り込むこともあった。ついに彼は満足の叫びをあげて椅子から飛び上がり、両手をこすり合わせながら部屋を行き来した。それから、電信用の用紙に長い電文を書いた。「これに対する返事が私の期待通りなら、君のコレクションに加えるにふさわしい、実に見事な事件が手に入ることになるぞ、ワトソン君」彼は言った。「明日にはノーフォークへ下り、我らが友に、彼の悩みの種の秘密について、非常に明確な知らせを届けられるだろう。」
正直に言うと、私は好奇心でいっぱいだったが、ホームズが自分のタイミングとやり方で真相を明かすのを好むことを知っていたので、彼が私を信頼して打ち明けてくれる時が来るまで待つことにした。
しかし、その返信電報は遅れ、焦燥の二日間が続いた。その間、ホームズはベルが鳴るたびに耳をそばだてた。二日目の夕方、ヒルトン・キュービットから手紙が届いた。彼の周りでは全てが静かだったが、その朝、日時計の台座に長い文が現れたという。彼はその写しを同封しており、ここに再現する。

ホームズはこの奇怪なフリーズ[訳注:帯状の装飾]に数分間かがみ込んでいたが、突然、驚きと狼狽の叫びと共に飛び上がった。その顔は不安でやつれていた。
「この事件をここまで放置しすぎた」彼は言った。「今夜、ノース・ウォルシャム行きの列車はあるか?」
私は時刻表を調べた。最終列車は出たばかりだった。
「ならば、朝食を早めにとり、朝一番の列車に乗る」ホームズは言った。「我々の存在が緊急に必要とされている。ああ! 待ち望んでいた電報だ。ハドソン夫人、少々お待ちを、返信がいるかもしれません。いや、全く予想通りだ。このメッセージは、ヒルトン・キュービットに事態を知らせるのに一刻の猶予も許されないことを、さらに決定的にした。我らが素朴なノーフォークの郷士は、奇妙で危険な蜘蛛の巣に絡めとられているのだ。」
そして、まさにその通りとなった。私にはただ子供じみて奇怪に思えた物語の暗い結末に差し掛かる今、私は再び、当時私を満たした狼狽と恐怖を味わっている。読者の皆様にもっと明るい結末を伝えられればと願うが、これらは事実の記録であり、数日の間ライディング・ソープ・マナーの名をイングランド中に知らしめた奇妙な一連の出来事を、その暗い危機的結末まで、私は追わねばならない。
我々がノース・ウォルシャムで列車を降り、目的地を口にするや否や、駅長が駆け寄ってきた。「ロンドンから来られた刑事さん方ですな?」と彼は言った。
ホームズの顔に苛立ちの色がよぎった。
「なぜそう思われる?」
「ノリッジからマーティン警部が通られたばかりですので。しかし、あるいは外科医の先生方か。奥様はまだ亡くなってはおられません――少なくとも最後の報告では。まだ助かるかもしれませんな――もっとも、絞首台行きかもしれませんが。」
ホームズの額は不安で曇っていた。
「我々はライディング・ソープ・マナーへ向かうところだ」彼は言った。「しかし、そこで何が起こったのかは何も聞いていない。」
「恐ろしい事件です」駅長は言った。「ヒルトン・キュービット氏と奥様、お二人とも撃たれたのです。奥様が旦那様を撃ち、それからご自分を――使用人たちはそう言っているそうです。旦那様は亡くなられ、奥様の命も絶望的だと。やれやれ、ノーフォーク州で最も古い家柄の一つで、最も尊敬されていたご一家だったのに。」
ホームズは一言も発さず馬車に急ぎ、七マイルの長い道のりの間、一度も口を開かなかった。彼がこれほどまでに打ちのめされているのを見るのは、滅多にないことだった。ロンドンからの道中ずっと彼は落ち着かず、朝刊を不安げな注意を払ってめくっているのには気づいていたが、今や最悪の恐怖が突然現実のものとなり、彼は茫然自失の憂鬱に沈んでいた。彼は座席に背をもたせ、暗い思索にふけっていた。しかし、我々の周りには興味を引くものが多くあった。我々はイングランドでも類を見ないほど特異な田園地帯を通り抜けていたのだ。まばらに点在するコテージが今日の人口を表している一方で、あたり一面、巨大な四角い塔を持つ教会が平坦な緑の風景から突き出ており、古きイースト・アングリアの栄光と繁栄を物語っていた。やがて、ドイツ海[訳注:現在の北海]の紫色の縁がノーフォーク海岸の緑の縁の上に現れ、御者が鞭で木立から突き出た二つの古い煉瓦と木材の切妻を指さした。「あれがライディング・ソープ・マナーです」と彼は言った。
我々がポルティコのある正面玄関に馬車を寄せると、その前、テニスの芝生の脇に、我々にとって奇妙な関わりを持つ黒い道具小屋と台座付きの日時計があるのが見えた。きびきびとして抜け目のない態度の、口髭に蝋を塗った小粋な小男が、ちょうど高いドッグカートから降りたところだった。彼はノーフォーク警察のマーティン警部と名乗り、我が友の名を聞くと、かなり驚いた様子だった。
「これは、ホームズさん、犯行は今朝の三時に起こったばかりです。どうやってロンドンでそれを聞きつけ、私と同じくらい早く現場に着くことができたのですか?」
「予期していたのです。防ぐ望みを抱いて来ました。」
「では、我々の知らない重要な証拠をお持ちに違いない。お二人は大変仲睦まじいご夫婦だったと聞いておりますから。」
「私が持っているのは、踊る人形の証拠だけです」ホームズは言った。「その件は後ほどご説明します。今は、この悲劇を防ぐには遅すぎた以上、私の持つ知識を用いて、正義がなされることを確実にしたいと強く願っています。捜査に協力させていただけますか、それとも、私が独立して行動するのを望まれますか?」
「ご一緒に行動できるとあれば、光栄の至りです、ホームズさん」警部は真剣に言った。
「では、一刻の無駄もなく、証言を聞き、現場を調べさせていただきたい。」
マーティン警部は、我が友に彼自身のやり方で事を進めさせるという分別を持ち合わせており、その結果を注意深く記録することに満足していた。地元の外科医である白髪の老人が、ちょうどヒルトン・キュービット夫人の部屋から降りてきたところで、彼女の傷は重いが、必ずしも致命的ではないと報告した。弾丸は脳の前部を貫通しており、意識を取り戻すまでにはしばらく時間がかかるだろうとのことだった。彼女が撃たれたのか、自ら撃ったのかという問いに対しては、彼は断定的な意見を述べることを避けた。確かに、弾丸は至近距離から発射されていた。部屋で見つかったピストルは一丁のみで、そのうち二発が発射済みだった。ヒルトン・キュービット氏は心臓を撃ち抜かれていた。彼が彼女を撃ち、その後自分を撃ったとも、あるいは彼女が犯人だったとも考えられた。というのも、リボルバーは二人のちょうど中間の床に落ちていたからだ。
「彼は動かされましたか?」ホームズが尋ねた。
「奥様以外は何も動かしておりません。負傷した彼女を床に寝かせておくわけにはいきませんでしたから。」
「こちらにはどのくらい?」
「四時からです。」
「他には?」
「ええ、ここにいる巡査です。」
「そして、何も触っていないと?」
「何も。」
「非常に慎重に行動された。誰があなたを呼んだのですか?」
「メイドのサンダースです。」
「警報を鳴らしたのは彼女ですか?」
「彼女と、料理人のキング夫人です。」
「彼女たちは今どこに?」
「台所だと思います。」
「では、すぐに彼女たちの話を聞くのがよさそうだ。」
樫の板張りと高い窓のある古いホールは、捜査法廷と化していた。ホームズは大きな古風な椅子に座り、そのやつれた顔から、冷徹な目が光っていた。その目には、救うことのできなかった依頼人がついに報われるまで、この探求に生涯を捧げるという固い決意が読み取れた。小粋なマーティン警部、白髪頭の田舎医者、私、そして朴訥な村の警官が、その奇妙な一同の残りのメンバーだった。
二人の女性は、自分たちの話を十分に明確に語った。彼女たちは爆発音で眠りから覚め、その一分後には二発目の音が続いた。二人は隣接する部屋で寝ており、キング夫人がサンダースの部屋に駆け込んだ。一緒に階段を降りた。書斎のドアは開いており、テーブルの上では蝋燭が燃えていた。主人は部屋の中央でうつ伏せに倒れていた。完全に絶命していた。窓の近くでは奥様がうずくまり、頭を壁にもたせかけていた。彼女はひどい傷を負っており、顔の片側は血で赤く染まっていた。息は荒かったが、何も話すことはできなかった。廊下も部屋も、煙と火薬の匂いで満ちていた。窓は確かに閉まっており、内側から鍵がかかっていた。二人の女性はこの点について断言した。彼女たちはすぐに医者と巡査を呼びにやった。それから、馬丁と馬丁の少年の助けを借りて、負傷した女主人を彼女の部屋へ運んだ。彼女も夫もベッドにいた。彼女はドレスを、彼は寝間着の上にガウンを着ていた。書斎では何も動かされていなかった。彼女たちの知る限り、夫婦喧嘩など一度もなかった。いつも大変仲睦まじい夫婦だと見ていた。
これらが使用人たちの証言の要点だった。マーティン警部の質問に対し、彼女たちは全てのドアが内側から施錠されており、誰も家から逃げ出すことはできなかったと明言した。ホームズの質問に対しては、二人とも最上階の自分たちの部屋から飛び出した瞬間から火薬の匂いに気づいたと記憶していた。「その事実を、あなたの注意に強く喚起しておきます」ホームズは同業者に言った。「そして今、我々はこの部屋を徹底的に調査する態勢が整ったと思います。」
書斎は小さな部屋で、三方を本棚に囲まれ、庭に面した普通の窓に向かって書き物机が置かれていた。我々の最初の注意は、不運な郷士の遺体に向けられた。その巨体は部屋を横切るように伸びていた。着衣の乱れは、彼が急いで眠りから覚まされたことを示していた。弾丸は正面から撃ち込まれ、心臓を貫通した後、体内に留まっていた。彼の死は間違いなく即死で、苦痛はなかっただろう。ガウンにも手にも、火薬の痕はなかった。田舎の外科医によれば、夫人には顔に汚れがあったが、手にはなかったという。
「後者の不在は何も意味しませんが、その存在は全てを意味するかもしれません」ホームズは言った。「質の悪い薬莢から火薬が後方に噴出しない限り、痕跡を残さずに何発も撃つことは可能です。キュービット氏のご遺体は、もう動かしていただいて結構でしょう。博士、奥様を傷つけた弾丸はまだ回収されていないのですね?」
「それが可能になるまでには、大手術が必要になります。しかし、リボルバーにはまだ四発の弾が残っています。二発が発射され、二つの傷がつけられた。ですから、弾丸は一つ一つ説明がつきます。」
「そう思われますな」ホームズは言った。「では、明らかに窓の縁に当たった弾丸についても説明できますかな?」
彼は突然振り返り、その細長い指は、窓枠の下部から一インチほど上の、下の窓框を貫通した穴を指していた。
「何と!」警部は叫んだ。「一体どうやってそれを見つけたのですか?」
「探したからです。」
「素晴らしい!」田舎医者は言った。「まさしくその通りですな。では、三発目が撃たれ、したがって第三の人物がいたに違いない。しかし、それは誰で、どうやって逃げたというのでしょう?」
「それこそが、我々が今まさに解決しようとしている問題です」シャーロック・ホームズは言った。「マーティン警部、使用人たちが部屋を出るとすぐに火薬の匂いに気づいたと言った時、私がその点は非常に重要だと述べたのを覚えていますか?」
「はい、警部。しかし、正直に申し上げると、完全には理解しておりませんでした。」
「それは、発砲の際、部屋のドアだけでなく窓も開いていたことを示唆しています。さもなければ、火薬の煙がこれほど急速に家中に広がるはずがない。そのためには、部屋に隙間風が必要だったのです。しかし、ドアも窓も、ごく短い時間しか開いていなかった。」
「どうやってそれを証明するのですか?」
「蝋燭の蝋が流れていなかったからです。」
「見事だ!」警部は叫んだ。「見事だ!」
「悲劇の際に窓が開いていたと確信し、私は、この事件には第三の人物が関与しており、その人物がこの開口部の外に立ってそこから発砲したのではないかと考えました。この人物に向けられた弾は、窓框に当たる可能性がある。私は探し、そして、案の定、弾痕があったのです!」
「しかし、どうして窓が閉められ、鍵がかかっていたのですか?」
「女性の最初の本能は、窓を閉めて鍵をかけることでしょう。しかし、おや! これは?」
それは、書斎のテーブルの上に置かれていた婦人用のハンドバッグだった――クロコダイル革と銀でできた、小粋な小さなハンドバッグだ。ホームズはそれを開け、中身をぶちまけた。そこには、輪ゴムで束ねられたイングランド銀行の五十ポンド紙幣が二十枚あった――それ以外には何もなかった。
「これは保管しておかねばなりません。裁判で重要になるでしょうから」ホームズは、バッグとその中身を警部に手渡しながら言った。「さて、この第三の弾丸に光を当てる必要があります。木材の裂け方からして、明らかに部屋の中から発射されたものです。料理人のキング夫人にもう一度会いたい。キング夫人、あなたは大きな爆発音で目が覚めたと言いましたね。そう言った時、それは二発目よりも大きく聞こえたという意味でしたか?」
「さあ、旦那様、眠りから覚まされたものですから、判断は難しいですが。しかし、とても大きく聞こえたように思います。」
「それが、ほぼ同時に発射された二発の銃声だったとは思いませんか?」
「それは何とも申し上げられません、旦那様。」
「私は、疑いなくそうだったと信じています。マーティン警部、この部屋が我々に教えてくれることは、もう全て尽くしたと思います。もしよろしければ、私と一緒に外を回っていただければ、庭がどのような新しい証拠を提供してくれるか、見ることができるでしょう。」
書斎の窓際まで花壇が続いており、我々はそこへ近づくと、みな一様に驚きの声を上げた。花は踏みつけられ、柔らかな土には足跡が無数に残されていた。大きく、男性的で、奇妙なほど長く鋭い爪先を持つ足跡だ。ホームズは、さながら傷ついた鳥を追う猟犬のごとく、草葉のあいだを嗅ぎまわった。やがて満足げな声を上げると、身をかがめ、小さな真鍮の円筒を拾い上げた。
「思った通りだ」と彼は言った。「リボルバーには排莢装置が付いていた。これが三発目の薬莢だ。マーティン警部、これで事件はほぼ解明したと言っていいでしょうな。」
田舎の警部は、ホームズの迅速かつ見事な捜査の進展に、ただただ驚愕の表情を浮かべていた。最初は自らの立場を主張しようとする気配も見せたが、今や感嘆の念に打ちのめされ、ホームズが導くところへ疑問も挟まず従う覚悟ができていた。
「誰を疑っておられるのですか?」と彼は尋ねた。
「それは後ほど。この問題には、まだ君に説明できていない点がいくつかある。ここまで来た以上、私自身の方針で事を進め、その上で一切をすっきりと解明するのが最善だろう。」
「お望みのままに、ホームズさん。犯人さえ捕まれば、それで結構です。」
「なにも勿体ぶるつもりはない。だが、事を進めている最中に、込み入った説明を長々とするわけにはいかないのだ。この事件の糸は、すべて私の手の中にある。たとえ奥方が意識を取り戻さなかったとしても、我々は昨夜の出来事を再現し、正義が為されることを請け合うことができる。まず第一に、この近所に『エルリッジ』という名の宿屋があるかどうか知りたい。」
使用人たちに尋問したが、誰もそのような場所は聞いたことがないという。厩番の少年が、イースト・ラストンの方角へ数マイル行ったところに、その名の農夫が住んでいることを思い出し、一筋の光を投げかけた。
「それは人里離れた農場かね?」
「ええ、大変な辺鄙なところに。」
「おそらく、昨夜ここで起きたことは、まだ耳にしていないだろうな?」
「たぶん、そうだと思います。」
ホームズはしばし考え込み、やがてその顔に奇妙な笑みが浮かんだ。
「馬に鞍を置け、坊主」と彼は言った。「エルリッジ農場まで手紙を届けてもらいたい。」
彼はポケットから、踊る人形が描かれた紙片を何枚か取り出した。それを目の前に広げ、書斎のテーブルでしばらく作業を続けた。やがて少年に手紙を手渡し、宛名の人に直接渡すこと、そしていかなる質問にも一切答えてはならないと指示した。手紙の表書きは、ホームズの常の几帳面な筆跡とは似ても似つかぬ、乱れた不規則な文字で書かれていた。宛名は、ノーフォーク州、イースト・ラストン、エルリッジ農場、エイブ・スレイニー氏となっていた。
「警部」とホームズは言った。「護衛を要請する電報を打っておいた方がよろしいでしょう。もし私の計算が正しければ、郡の刑務所へ移送するには、ことのほか危険な囚人を相手にすることになるかもしれませんからな。この手紙を届ける少年が、君の電報も打ってくれるでしょう。ワトソン、午後に町へ出る汽車があるなら、それに乗るのが得策だろう。終えねばならぬ興味深い化学分析が残っているし、この捜査も急速に終結へ向かっている。」
若者が手紙を携えて出発すると、シャーロック・ホームズは使用人たちに指示を与えた。もしヒルトン・キュービット夫人を訪ねてくる客があっても、夫人の容態については一切知らせず、すぐに客間へ通すように、と。彼はこの点を最大限の真剣さをもって彼らに徹底させた。そして最後に、「もう我々の出る幕はない。何が待ち受けているか、時が来るまでせいぜい時間を潰すとしよう」と言いながら、我々を客間へと案内した。医者は患者のもとへ帰ってしまい、残ったのは警部と私だけだった。
「一時間ほど、興味深く有益な時間を過ごす手助けができると思う」とホームズは言い、椅子をテーブルに引き寄せ、目の前に踊る人形の奇妙な絵が記録された様々な紙を広げた。「さて、友人のワトソン。君の生来の好奇心をこれほど長く満たさずにいた償いは、何としてもせねばなるまい。警部にとっては、この事件全体が、職業上の注目すべき研究対象となるやもしれん。まずは、ヒルトン・キュービット氏が以前ベーカー街で私に相談した際の、興味深い経緯からお話ししよう。」
それから彼は、すでに記録されている事実を簡潔に要約した。「私の目の前にあるのが、この奇妙な代物だ。もしこれがあれほど恐ろしい悲劇の前触れでなかったなら、一笑に付したかもしれん。私はあらゆる暗号に精通しているつもりでね。この分野に関しては、百六十種の暗号を分析したささやかな論文を著したこともある。だが、告白すると、これはまったく新しい形式だ。この体系を考案した者の狙いは、これらの記号がメッセージを伝えていることを隠し、単なる子供の気まぐれな落書きだと思わせることにあったようだ。」
「しかし、ひとたびこれらの記号が文字を表していると見抜き、あらゆる暗号解読の指針となる法則を当てはめてみれば、解読は存外容易だった。最初に私に示されたメッセージはあまりに短く、『XXX』という記号がEを表す、とある程度の確信をもって言うのが精一杯だった。ご存知の通り、Eは英語のアルファベットで最も頻繁に使われる文字で、その出現率は非常に高いため、短い文章でさえ最も多く見られることが期待できる。最初のメッセージの十五の記号のうち、四つが同じだった。ゆえに、これをEと見なすのは妥当だった。確かに、ある場合は人形が旗を持ち、ある場合は持っていなかったが、旗の配置からして、文章を単語に区切るために使われている可能性が高かった。私はこれを仮説として受け入れ、Eが次の記号で表されると書き留めた。」

「だが、ここからが調査の真の難関だった。Eに次いで出現頻度の高い英語の文字の順序は、決して明確ではない。印刷物一枚の平均で見られる優位性も、短い一文では逆転しうる。大雑把に言えば、T、A、O、I、N、S、H、R、D、Lの順に出現するが、T、A、O、Iはほぼ同率で、意味が通じるまで各組み合わせを試すのは果てしない作業になる。そこで私は、新たな材料を待つことにした。ヒルトン・キュービット氏との二度目の面談で、彼はさらに二つの短い文と、一つのメッセージを提供してくれた。これは旗がないことから、単一の単語であると思われた。これがその記号だ。さて、この単一の単語には、五文字の単語の二番目と四番目に、すでに解明済みのEが二つ来ている。考えられるのは『sever(断つ)』、『lever(てこ)』、あるいは『never(決して)』。懇願に対する返事だとすれば、最後の『never』が最も可能性が高いのは論を俟たないだろうし、状況からしても、夫人が書いた返信であると示唆されていた。これを正しいと仮定すれば、我々はこれらの記号がそれぞれN、V、Rを表すと言えるようになる。」
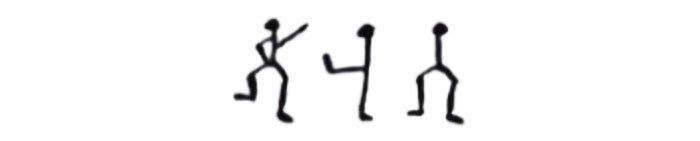
「それでもまだ、私はかなりの困難に直面していた。だが、幸運なひらめきが、さらにいくつかの文字を解き明かす鍵を与えてくれた。もしこれらの懇願が、私の予想通り、夫人の若き日をよく知る人物からのものだとしたら、三文字を間に挟んで二つのEを含む組み合わせは、まさしく『ELSIE(エルシー)』という名前を表している可能性が非常に高い。調べてみると、そのような組み合わせが、三度繰り返されたメッセージの末尾を形成していることがわかった。間違いなく、エルシーへの何らかの懇願だ。こうして私はL、S、Iを手に入れた。しかし、それはどんな懇願だったのか? 『Elsie』の前の単語はわずか四文字で、Eで終わっている。間違いなく『COME(来い)』に違いない。Eで終わる他の四文字単語をすべて試したが、この状況に合うものは見つからなかった。こうして私はC、O、Mを手に入れ、最初のメッセージに再び挑むことができるようになった。単語に区切り、まだ未知の記号には点を打っていく。すると、このようになった。」
.M .ERE ..E SL.NE.
「さて、最初の文字はA以外にありえない。これは極めて有用な発見だ。この短い文の中に三度も現れるのだから。そして二番目の単語にはHも明らかに見える。するとこうなる。」
AM HERE A.E SLANE.
あるいは、名前の明白な空欄を埋めれば、こうだ。
AM HERE ABE SLANEY. (俺はここにいる、エイブ・スレイニー)
これで非常に多くの文字が判明したため、かなりの自信をもって二番目のメッセージに取り掛かることができた。解読すると、このようになった。
A. ELRI. ES.
ここでは、欠けている文字にTとGを当てはめ、これが書き手の滞在している家か宿屋の名前だと仮定する以外に、意味をなす方法はなかった。」
マーティン警部と私は、友人がいかにして我々の困難を完全に掌握するに至ったか、その詳細かつ明快な説明に、最大限の興味をもって聞き入っていた。
「それで、どうされたのですか?」と警部が尋ねた。
「このエイブ・スレイニーがアメリカ人であると考える理由は十分にあった。エイブはアメリカ式の短縮形であり、アメリカからの手紙がすべての騒動の発端だったからだ。また、この件には何らかの犯罪がらみの秘密があると考える根拠も十分にあった。夫人が過去についてほのめかしたこと、夫に真相を打ち明けるのを拒んだこと、その両方がその方向を示していた。そこで私は、ニューヨーク市警の友人、ウィルソン・ハーグリーヴに電報を打った。彼はロンドンの犯罪に関する私の知識を、一度ならず利用したことがある。エイブ・スレイニーという名前に聞き覚えがあるかと尋ねたのだ。これが彼の返事だ。『シカゴで最も危険な悪党』。彼の返事を受け取ったまさにその晩、ヒルトン・キュービット氏がスレイニーからの最後のメッセージを送ってきた。既知の文字で解読すると、このようになった。」
ELSIE .RE.ARE TO MEET THY GO. (エルシー、汝の神に会う準備をせよ)
PとDを加えることでメッセージは完成し、この悪党が説得から脅迫へと手段を移行させたことがわかった。そしてシカゴの悪党に関する私の知識から、彼がその言葉を極めて迅速に行動に移すであろうと予期した。私は直ちに友であり同僚であるワトソン博士と共にノーフォークへやってきた。だが、不幸にも、最悪の事態がすでに起きた後だった。」
「あなたのような方と事件をご一緒できるとは、光栄の至りです」と警部は熱を込めて言った。「しかし、率直に申し上げることをお許しください。あなたはご自身にのみ責任を負えばよいが、私は上司に報告する義務があります。もしエルリッジに住むこのエイブ・スレイニーが真犯人であり、私がここに座っている間に逃亡でもしたら、私は間違いなく深刻な窮地に陥るでしょう。」
「ご心配には及びません。彼は逃げようとはしないでしょう。」
「なぜそうお分かりに?」
「逃亡は罪を認めることだからです。」
「では、逮捕しに行きましょう。」
「彼がここに来るのを、今か今かと待っているところです。」
「しかし、なぜ彼が来るのですか?」
「私が手紙を書いて、来るように頼んだからです。」
「信じられません、ホームズさん! なぜあなたが頼んだからといって、彼が来るのですか? そんな要求は、むしろ彼の疑念を掻き立て、逃亡させる原因になるのではありませんか?」
「手紙の書き方には、それなりの工夫をしたつもりです」とシャーロック・ホームズは言った。「事実、私の見込み違いでなければ、ほら、ご本人が私道を通ってこちらへやって来ましたよ。」
一人の男が、玄関へと続く小道を大股で歩いてきた。背が高く、ハンサムで、日に焼けた浅黒い男だった。灰色のフランネルのスーツにパナマ帽をかぶり、剛毛の黒い髭を生やし、大きく攻撃的な鷲鼻で、歩きながらステッキを振り回している。まるで自分の土地であるかのように道を闊歩し、やがて彼の鳴らす、自信に満ちたけたたましいベルの音が聞こえてきた。
「諸君」とホームズは静かに言った。「我々はドアの陰に陣取るのが最善だろう。ああいう輩を相手にするには、あらゆる警戒が必要だ。警部、手錠のご用意を。話は私に任せていただきたい。」
我々は一分間、沈黙のうちに待った――決して忘れられない、そんな一分間だった。やがてドアが開き、男が足を踏み入れた。その瞬間、ホームズは男の頭にピストルを突きつけ、マーティン警部がその両手首に手錠をかけた。すべてがあまりに素早く、鮮やかに行われたため、男は襲われたと気づく前に無力化されていた。彼は燃えるような黒い瞳で、我々一人一人を睨みつけた。それから、苦々しい笑いを 터뜨けた。
「よう、旦那方。今回はまんまと一杯食わされたようだ。とんでもない奴にぶち当たっちまったらしいな。だが、俺はヒルトン・キュービット夫人からの手紙に応じてここに来たんだ。まさか、あの人がこの件に関わってるなんて言わねえだろうな? 俺を罠にかける手助けをしたなんて、言わねえだろうな?」
「ヒルトン・キュービット夫人は重傷を負い、生死の境をさまよっておられる。」
男は悲痛な叫び声を上げた。その声は家中に響き渡った。
「気でも狂ったのか!」と彼は獰猛に叫んだ。「怪我をしたのは奴の方だ、あの人じゃねえ。誰が可愛いエルシーを傷つけるってんだ? 脅しはしたかもしれん――神よ、お許しを! ――だが、あの人の綺麗な髪の一筋だって、俺は触れやしねえ。取り消せ! あの人は無事だと言え!」
「彼女は、亡くなった夫の傍らで、ひどく傷ついた状態で見つかりました。」
彼は深いうめき声とともに長椅子に沈み込み、手錠をかけられた両手で顔を覆った。五分間、彼は沈黙していた。やがて再び顔を上げ、絶望からくる冷たい落ち着き払った声で話し始めた。
「旦那方に隠すことは何もねえ」と彼は言った。「俺が奴を撃ったとしても、奴も俺を撃った。それなら殺しじゃねえ。だが、俺があの女を傷つけられたと思うなら、あんた方は俺のことも、あの人のことも、何もわかっちゃいねえ。言っておくが、この世に俺ほどあの人を愛した男はいねえんだ。俺にはあの人を得る権利があった。何年も前に、俺と誓い合った仲だ。どこの馬の骨とも知れねえイギリス人が、俺たちの間に割り込んできやがった。俺にこそ、あの人に対する第一の権利があったんだ。俺はただ、自分のものを取り戻そうとしていただけだ。」
「彼女は、君という人間の正体を知った時、君の影響下から逃れたのだ」とホームズは厳しく言った。「彼女は君を避けるためにアメリカから逃げ、イギリスで高潔な紳士と結婚した。君は彼女を追い詰め、追いかけ、彼女の人生を惨めなものにした。彼女が愛し、尊敬していた夫を捨てさせ、彼女が恐れ、憎んでいた君と共に逃げるように仕向けるために。そして君は、高潔な男を死に追いやり、その妻を自殺にまで追い込んだ。これが、この件における君の所業だ、エイブ・スレイニー君。法廷でその罪を償うことになるだろう。」
「エルシーが死んじまったら、俺がどうなろうと知ったこっちゃねえ」とアメリカ人は言った。彼は片手を開き、掌の中でくしゃくしゃになった手紙を見た。「おい、旦那!」と彼は目に疑いの光を浮かべて叫んだ。「これで俺を脅そうって魂胆じゃねえだろうな? もしあの人があんたの言う通りひどい怪我をしてるんなら、この手紙を書いたのは一体誰なんだ?」
彼はそれをテーブルの上に投げつけた。
「私が書いた。君をここへおびき寄せるためにな。」
「あんたが書いた? 『ジョイント』の仲間以外に、踊る人形の秘密を知る者なんざ、この世にいるはずがねえ。どうしてあんたがこれを書けたんだ?」
「人が創り出せるものならば、人が解き明かせぬはずはない」とホームズは言った。「君をノリッジへ護送する馬車が来る。だがそれまでの間、君がもたらした損害を、わずかながら償う時間がある。ヒルトン・キュービット夫人自身が、夫殺しの重大な嫌疑をかけられていたことを知っているかね? 私がここに居合わせ、たまたま持ち合わせていた知識があったからこそ、彼女は告発を免れたのだ。君が彼女にしてやれる最低限のことは、彼女があの悲劇的な結末に、直接的にも間接的にも、一切関与していなかったことを、世間に明らかにすることだ。」
「望むところだ」とアメリカ人は言った。「俺にとって一番いいのは、洗いざらい真実をぶちまけることだろうからな。」
「警告しておくが、その証言は君に不利に使われることになるぞ」と警部は、英国の刑事法の見事な公正さをもって叫んだ。
スレイニーは肩をすくめた。
「上等だ」と彼は言った。「まず第一に、旦那方に分かっておいてもらいたいのは、俺はこの女性を子供の頃から知ってるってことだ。シカゴに俺たち七人の仲間がいて、エルシーの親父が『ジョイント』のボスだった。抜け目のない男だったよ、パトリックの爺さんは。あの暗号を考え出したのも、親父だ。鍵を知らなきゃ、ただの子供の落書きにしか見えねえ。まあ、エルシーも俺たちのやり方を少しは学んだが、この商売には耐えられなかった。それに、あいつは自分で稼いだ真っ当な金をいくらか持ってたんで、俺たちを出し抜いてロンドンへ高飛びしちまった。俺と婚約してたし、俺が別の仕事に就いてりゃ結婚してくれたと思う。だが、あいつは裏稼業には一切関わりたがらなかった。このイギリス人と結婚してから、ようやく居場所を突き止めたんだ。手紙を書いたが、返事はなかった。その後、俺はこっちへ渡ってきて、手紙が駄目なら、あいつが読める場所にメッセージを置いた。」
「ここへ来て、もう一月になる。俺はあの農場に住んでた。階下の部屋を借りて、毎晩誰にも知られずに出入りできた。あらゆる手を使ってエルシーを連れ出そうとした。メッセージを読んでいるのは分かってた。一度、メッセージの下に返事を書いてきたからな。それから俺はかっとなって、脅し始めた。するとあいつから手紙が来た。どうか立ち去ってくれ、もし夫に醜聞が降りかかるようなことがあれば、悲しみで胸が張り裂けてしまう、と。夫が眠りにつく午前三時に降りてきて、書斎の端の窓越しに話をするから、その後は平穏な生活を送らせてほしい、と書いてあった。あいつは降りてきて、金を持っていた。俺を買収して追い払おうとしたんだ。それで俺は逆上し、あいつの腕を掴んで窓から引きずり出そうとした。その瞬間、夫がリボルバーを手に飛び込んできた。エルシーは床に崩れ落ち、俺たちは向かい合った。俺も銃を持ってたんで、それを突きつけて奴を脅し、逃げようとした。奴が撃ったが、弾は外れた。俺もほとんど同時に引き金を引いた。奴はばったり倒れた。俺は庭を横切って逃げたが、その時、背後で窓が閉まる音が聞こえた。これが神に誓って真実だ、旦那方、一言一句違わねえ。その後、あの小僧が手紙を持って馬でやって来るまで、俺は何一つ知らなかった。その手紙のせいで、俺はまんまとカモみたいにここへやって来て、あんた方の手に落ちたってわけだ。」
アメリカ人が話している間に、一台の馬車が到着していた。中には制服警官が二人座っている。マーティン警部は立ち上がり、囚人の肩に手を置いた。
「行く時間だ。」
「先に彼女に会えないか?」
「いや、意識がない。シャーロック・ホームズさん、またいつか重要事件を担当する際には、あなたという幸運が私の傍らにあることを願うばかりです。」
我々は窓際に立ち、馬車が走り去るのを見送った。振り返った時、囚人がテーブルに投げた紙の塊が目に留まった。ホームズが彼をおびき寄せた手紙だった。
「読んでみたまえ、ワトソン」と彼は微笑みながら言った。
そこには言葉はなく、ただこの短い踊る人形の列があるだけだった。

「私が説明した暗号を使えば」とホームズは言った。「これが単に『すぐにここへ来い』という意味だとわかるだろう。彼がこの誘いを断るはずはないと確信していた。夫人以外から来たとは、到底想像できないだろうからな。というわけで、親愛なるワトソン、我々はついに、これまで悪の手先となることの多かった踊る人形を、善のために役立てることができた。君の手帳に何か珍しい話題を提供するという約束も、これで果たせただろう。汽車は三時四十分だ。夕食までにはベーカー街に戻れるだろう。」
結びの言葉を一つだけ。アメリカ人、エイブ・スレイニーはノリッジの冬期巡回裁判で死刑を宣告されたが、情状酌量の余地があったこと、そしてヒルトン・キュービットが先に発砲したことが確実であったことから、その刑は懲役に減刑された。ヒルトン・キュービット夫人については、私が知る限り、完全に回復し、今も未亡人として、貧しい人々の世話と夫の遺産の管理にその全生涯を捧げていると聞いている。
孤独なサイクリストの冒険
一八九四年から一九〇一年までの間、シャーロック・ホームズ氏は多忙を極めた。この八年間に、彼が相談を受けなかった難事件は公的なものには一つとしてなく、また私的な事件においても、その中には最も複雑で異常な性質を持つものも含まれていたが、何百という事件で彼は重要な役割を果たしたと言って差し支えない。この長きにわたる絶え間ない仕事の結果、多くの目覚ましい成功と、いくつかの避けられない失敗が生まれた。私はこれらすべての事件について極めて詳細な記録を保存しており、またその多くに私自身が個人的に関わっていたため、どれを選んで世に公表すべきかを知るのは容易なことではないと想像されるだろう。しかしながら、私は以前からの流儀を守り、犯罪の残虐性よりもむしろ解決の巧妙さと劇的な質によってその興味が引き出される事件を優先することにしたい。この理由から、私は今、読者の前に、チャーリントンの孤独なサイクリスト、ミス・ヴァイオレット・スミスにまつわる事実と、我々の調査が予期せぬ悲劇に終わった奇妙な結末を提示しようと思う。確かに、この一件は、我が友がその名を知らしめた能力の目覚ましい実例を示すには至らなかった。しかし、この事件にはいくつかの点があり、私がこれらの小物語の材料を収集する長大な犯罪記録の中でも、際立った存在となっている。
一八九五年の手帳をひもとくと、我々が初めてミス・ヴァイオレット・スミスのことを耳にしたのは、四月二十三日の土曜日であったことがわかる。彼女の訪問は、記憶によれば、ホームズにとっては極めて歓迎されざるものだった。というのも、彼はその時、著名なタバコ王ジョン・ヴィンセント・ハーデンが受けていた奇妙な迫害に関する、非常に難解で複雑な問題に没頭していたからだ。何よりも思考の精密さと集中を愛する我が友は、手中の問題から注意をそらすものを何であれ嫌った。しかし、彼の性分にそぐわない無情さでもってしなければ、夕刻遅くにベーカー街に現れ、彼の助けと助言を懇願した、背が高く、優雅で、女王のような気品を持つ、若く美しい女性の話を聞くのを断ることは不可能だった。彼の時間はすでに完全に埋まっていると説いても無駄だった。その若い淑女は自分の話を語る決意で来ており、それを終えるまで、力ずくでなければ彼女を部屋から追い出すことはできないのが明らかだった。諦めたような様子と、やや疲れた笑みを浮かべ、ホームズはその美しい侵入者に席を勧め、何に悩んでいるのかを我々に知らせるよう促した。
「少なくとも、ご健康の問題ではなさそうですな」と彼は言い、その鋭い目が彼女をざっと見渡した。「あれほど熱心な自転車乗りなら、活力に満ち溢れているに違いない。」
彼女は驚いて自分の足元に視線を落とした。私は、ペダルの縁との摩擦によって、靴底の側面がわずかにすり減っているのに気づいた。
「はい、よく自転車に乗ります、ホームズさん。そしてそれが、今日あなたを訪ねたことと関係があるのです。」
我が友は、淑女の手袋をはめていない手を取り、科学者が標本に示すような綿密な注意と、ごくわずかな感傷をもってそれを調べた。
「お許しください。これが私の仕事なものですから」と彼は言いながら、その手を離した。「危うく、あなたがタイプライターを打つ方だと誤解するところでした。もちろん、音楽であることは明白です。ワトソン、ほら、両方の職業に共通する、へら状の指先がわかるかね? しかし、そのお顔には霊妙な雰囲気がある」――彼女は穏やかに顔を光の方へ向けた――「タイプライターでは生まれ得ないものです。このご婦人は音楽家ですな。」
「はい、ホームズさん。音楽を教えております。」
「田舎で、でしょうな。その顔色から察するに。」
「はい、サリー州の境、ファーナムの近くです。」
「美しい土地で、最も興味深い逸話に満ちています。覚えているかね、ワトソン。我々が偽造犯のアーチー・スタンフォードを捕らえたのは、あの近くだった。さて、ミス・ヴァイオレット、サリー州の境、ファーナムの近くで、あなたに何が起こったのですかな?」
その若い淑女は、非常に明瞭かつ落ち着いた様子で、次のような奇妙な話を始めた。
「父は亡くなりました、ホームズさん。旧インペリアル劇場のオーケストラを指揮していた、ジェイムズ・スミスです。母と私は、二十五年前にアフリカへ渡り、それ以来一度も便りのなかったラルフ・スミスという叔父を除いて、この世に身寄りがなくなりました。父が亡くなった時、私たちは大変貧しい暮らしをしておりましたが、ある日、『タイムズ』紙に私たちの居場所を尋ねる広告が出ていると知らされました。誰かが私たちに財産を残してくれたのだと思い、どれほど興奮したかお分かりになるでしょう。私たちはすぐに、新聞に名前が載っていた弁護士のもとへ向かいました。そこで、南アフリカから一時帰国していたカラザーズ氏とウッドリー氏という二人の紳士にお会いしました。彼らが言うには、私の叔父は彼らの友人で、数ヶ月前にヨハネスブルグで極貧のうちに亡くなり、最後の息で、親戚を探し出し、不自由がないか確かめてほしいと頼んだとのことでした。生きている間は私たちのことなど気にもかけなかったラルフ叔父が、死んでから私たちのことをそんなに気にかけるなんて奇妙に思えましたが、カラザーズ氏が説明するには、叔父は兄の死をちょうど耳にしたばかりで、私たちの運命に責任を感じたからだということでした。」
「失礼」とホームズは言った。「その面会はいつのことですかな?」
「去年の十二月です――四ヶ月前になります。」
「どうぞ、続けてください。」
「ウッドリー氏という方は、私には大変不快な人物に思えました。しょっちゅう私に色目を使ってくるのです――品がなく、顔はむくみ、赤髭を生やした若い男で、髪を額の両脇に撫でつけていました。本当に嫌な人だと思いましたし、シリルが私にそんな人と知り合ってほしくないだろうと確信していました。」
「おお、シリルというのが彼のお名前ですな!」とホームズは微笑んだ。
若い淑女は顔を赤らめ、笑った。
「はい、ホームズさん。シリル・モートンと申します。電気技師で、夏の終わりには結婚する予定です。まあ、どうして彼の話などしてしまったのでしょう。私が申し上げたかったのは、ウッドリー氏は本当に不快でしたが、ずっと年上のカラザーズ氏の方は、より好感が持てたということです。彼は浅黒く、血色が悪く、髭をきれいに剃り、無口な方でしたが、礼儀正しく、笑みは pleasant でした。彼は私たちの暮らし向きを尋ね、私たちが大変貧しいと知ると、彼の十歳になる一人娘に音楽を教えに来ないかと提案しました。母を残していくのは気が進まないと申しますと、毎週末に実家へ帰ればいいと提案してくださり、年に百ポンドという、間違いなく破格の給料を提示してくださいました。それで結局お受けすることになり、ファーナムから六マイルほど離れたチルターン・グランジへ参りました。カラザーズ氏はやもめでしたが、ディクソン夫人という、大変きちんとした年配の女性を家政婦として雇い、家事を任せていらっしゃいました。お子さんは可愛らしく、すべてが順調に思えました。カラザーズ氏はとても親切で音楽好きで、私たちは毎晩とても楽しい時を過ごしました。毎週末、私は町の母のもとへ帰っておりました。」
「私の幸せに最初の影が差したのは、あの赤髭のウッドリー氏がやって来た時です。一週間の滞在でしたが、ああ、私には三ヶ月にも感じられました。彼は恐ろしい人で、他の誰に対しても横暴でしたが、私に対してはそれ以上にひどいものでした。私に下品な求愛をし、自分の富を自慢し、もし結婚すればロンドンで一番のダイヤモンドをやると言い、そしてついに、私が彼を相手にしなくなると、ある日の夕食後、私を腕の中に捕らえたのです――彼は恐ろしく力が強かった――そして、キスするまで離さないと誓いました。カラザーズ氏が入ってきて彼を私から引き離すと、彼は自分の主人に殴りかかり、彼を打ち倒して顔に切り傷を負わせました。ご想像の通り、それで彼の滞在は終わりました。翌日、カラザーズ氏は私に謝罪し、二度とあのような侮辱に遭わせることはないと請け合ってくださいました。それ以来、ウッドリー氏には会っておりません。」
「そして今、ホームズさん、ついに、今日あなたにご助言をいただきたく参りました特別な事柄についてお話しします。毎週土曜の午前、私は自転車に乗ってファーナム駅へ行き、十二時二十二分発の町へ向かう汽車に乗ります。チルターン・グランジからの道は人通りがなく、ある地点では特にそうです。というのも、一マイル以上にわたって、片側はチャーリントン・ヒース、もう片側はチャーリントン・ホールの周りに広がる森に挟まれているからです。これほど寂しい道はどこを探しても見つからないでしょうし、クルックスベリー・ヒルの近くの幹線道路に出るまでは、荷馬車一台、農夫一人に会うことさえ稀です。二週間前、この場所を通りかかった時、ふと肩越しに振り返ると、二百ヤードほど後ろに、同じく自転車に乗った一人の男がいるのが見えました。中年の男のようで、短い黒髭を生やしていました。ファーナムに着く前にもう一度振り返りましたが、男は消えていたので、それ以上は気にしませんでした。しかし、月曜日に戻ってきた時、同じ道の同じ区間で同じ男を見たのですから、どれほど驚いたかお分かりになるでしょう、ホームズさん。その出来事が、次の土曜日と月曜日にも、まったく同じように繰り返された時、私の驚きは増しました。彼はいつも一定の距離を保ち、私にちょっかいを出すようなことは一切ありませんでしたが、それでも、実に奇妙なことでした。そのことをカラザーズ氏に話しますと、彼は私の話に興味を示したようで、馬と軽馬車を注文したので、今後はこの寂しい道を一人で通ることはなくなるだろうと言ってくださいました。」
「馬と軽馬車は今週届くはずでしたが、何らかの理由で納品されず、また自転車で駅まで行かなければなりませんでした。それが今朝のことです。チャーリントン・ヒースに来た時、私が注意深く見回したことはお察しいただけるでしょう。すると案の定、あの男がいたのです。二週間前とまったく同じように。彼はいつも遠くにいるので、顔をはっきりと見ることはできませんでしたが、間違いなく私の知らない誰かでした。黒っぽいスーツに布製の帽子をかぶっていました。彼の顔について唯一はっきりと見えたのは、黒い髭だけです。今日は怖くはありませんでしたが、好奇心でいっぱいになり、彼が誰で、何を望んでいるのかを突き止めようと決心しました。私は自転車の速度を落としましたが、彼も速度を落としました。それから完全に止まりましたが、彼も止まりました。そこで、彼を罠にかけることにしました。道に急なカーブがあり、私はそこを全速力で曲がり、そして止まって待ったのです。彼が止まる間もなくカーブを曲がりきって、私の前を通り過ぎるだろうと期待して。しかし、彼は現れませんでした。そこで私は引き返し、角の向こうを覗き込みました。一マイル先まで道が見えましたが、彼はそこにいませんでした。さらに不思議なことに、その地点には彼が曲がれるような脇道は一本もなかったのです。」
ホームズはくすくす笑い、両手をこすり合わせた。「この事件は確かに、独特の様相を呈していますな」と彼は言った。「あなたが角を曲がってから、道に誰もいないと気づくまで、どれくらいの時間が経ちましたか?」
「二、三分です。」
「では、彼は道を後戻りしたはずはない。そして脇道もないとおっしゃる?」
「ありません。」
「とすれば、彼は間違いなく、道のどちらかにある小道に入ったのでしょう。」
「ヒース側ではありえません。もしそうなら、私に見えたはずです。」
「つまり、消去法によって、彼はチャーリントン・ホールの方へ向かったという事実に行き着きます。私の理解では、ホールは道の片側に、自身の敷地内に建っているのですね。他に何か?」
「何もありません、ホームズさん。ただ、あまりに不可解で、あなたにお会いしてご助言をいただくまでは、心が休まらないと感じたのです。」
ホームズはしばらく黙って座っていた。
「婚約者の方はどちらに?」と彼はついに尋ねた。
「コヴェントリーのミッドランド電気会社におります。」
「彼があなたを驚かせようと、突然訪ねてきたということは?」
「まあ、ホームズさん! まるで私が彼を見分けられないとでもおっしゃるように!」
「他にあなたを慕う方は?」
「シリルを知る前には何人か。」
「それ以降は?」
「あの恐ろしいウッドリーという男がいました。もし彼を求愛者と呼べるのでしたら。」
「他には誰も?」
我々の美しい依頼人は、少し戸惑ったようだった。
「それはどなたですかな?」とホームズは尋ねた。
「ああ、単なる私の思い過ごしかもしれませんが、時々、私の雇い主であるカラザーズ氏が、私に大変な興味を抱いていらっしゃるように感じることがあります。私たちは一緒に過ごすことが多いのです。夜には私が彼の伴奏をします。彼は何もおっしゃいません。完璧な紳士です。でも、女にはわかるものです。」
「はあ!」
ホームズは真剣な表情になった。「彼の生業は?」
「裕福な方です。」
「馬車も馬も持たずに?」
「まあ、少なくとも、かなり裕福ではあります。でも、週に二、三度、シティへ出かけています。南アフリカの金鉱株に深く関心をお持ちのようです。」
「何か新しい進展があれば、知らせてください、ミス・スミス。今は大変忙しいのですが、あなたの事件についていくつか調査する時間を見つけましょう。それまでの間、私に知らせずに行動を起こさないでください。さようなら。あなたから良い知らせだけが届くことを願っております。」
「あれほどの娘に言い寄る男がいるのは、いわば自然の摂理というものだ」とホームズは、瞑想にふけるようにパイプをふかしながら言った。「だが、選りによって、人里離れた田舎道で自転車に乗って、というのはいただけないな。間違いなく、何かを隠している恋人だろう。しかし、この事件には奇妙で示唆に富む点がある、ワトソン。」
「彼があの地点にだけ現れるということですか?」
「その通り。我々がまずすべきは、チャーリントン・ホールの住人が誰なのかを突き止めることだ。それから、カラザーズとウッドリーの関係はどうだ? あれほどタイプの違う男に見えるのに。なぜ二人とも、ラルフ・スミスの親戚探しにそれほど熱心だったのか? もう一点。家庭教師に市場価格の倍の給料を払いながら、駅から六マイルも離れているのに馬を一頭も飼っていないとは、一体どんな家庭なのだ? 妙だ、ワトソン――実に妙だ!」
「あなたが行かれるのですか?」
「いや、君が行くのだよ、ワトソン君。これは些細な痴話かもしれんし、そのために他の重要な研究を中断するわけにはいかない。月曜に、君は早めにファーナムへ着き、チャーリントン・ヒースの近くに身を隠し、これらの事実を君自身の目で確かめ、君自身の判断で行動するのだ。それから、ホールの住人について調べた上で、私のところへ戻って報告してくれたまえ。さて、ワトソン、我々が解決への確かな足がかりをいくつか得るまで、この件についてはもう一言も口にしてはならん。」
依頼人の女性から、月曜にはウォータールーを九時五十分に出る汽車で帰ると聞いていたので、私は早めに出発し、九時十三分の汽車に乗った。ファーナム駅でチャーリントン・ヒースへの道を尋ねるのに苦労はなかった。その若い淑女の冒険の舞台を間違うはずはなかった。道は片側が開けたヒース、もう片側は見事な木々が点在する公園を囲む古いイチイの生け垣の間を走っているからだ。苔むした石造りの正門があり、両側の門柱の上には朽ちかけた紋章が飾られていたが、この中央の車道の他に、生け垣に切れ目があり、そこを通る小道がいくつかあることに気づいた。屋敷は道からは見えなかったが、周囲のすべてが陰鬱と荒廃を物語っていた。
ヒースは黄金色に咲き誇るハリエニシダの茂みに覆われ、明るい春の日差しを浴びて見事に輝いていた。私はその茂みの一つを背に陣取り、ホールの門と、その両側に長く伸びる道を一望できるようにした。私が来た時には人気がなかったが、今、私が来たのとは反対方向から自転車が一台下ってくるのが見えた。黒っぽいスーツを着ており、黒い髭を生やしているのがわかった。チャーリントンの敷地の端に着くと、彼は自転車から飛び降り、それを引いて生け垣の切れ目を抜け、私の視界から消えた。
十五分ほど経って、二台目の自転車が現れた。今度は駅から来た若い淑女だった。彼女がチャーリントンの生け垣にさしかかった時、あたりを見回すのが見えた。その直後、男が隠れ場所から現れ、自転車に飛び乗って彼女を追った。広大な風景の中で動いているのはその二人だけだった。自転車に背筋を伸ばして座る優雅な少女と、その後ろでハンドルバーに低く身をかがめ、その一挙手一投足に奇妙なほどこそこそした様子を漂わせる男。彼女は彼を振り返り、速度を落とした。彼も速度を落とした。彼女は止まった。彼もすぐに止まり、二百ヤードの距離を保った。彼女の次の動きは、予想外であると同時に、実に気丈なものだった。彼女は突然車輪をくるりと回し、彼に向かってまっすぐ突進したのだ。しかし、彼も彼女と同じくらい素早く、必死に逃げ出した。やがて彼女は再び道を戻ってきた。頭を誇らしげに上げ、無言の付き人にはこれ以上関心を払う気はないという態度だった。彼も向きを変え、道のカーブが彼らを私の視界から隠すまで、依然として距離を保っていた。
私は隠れ場所に留まっていたが、それは正解だった。やがて男が再び現れ、ゆっくりと自転車を漕いで戻ってきた。彼はホールの門を入り、自転車から降りた。数分間、彼が木々の間に立っているのが見えた。両手を上げ、ネクタイを直しているようだった。それから彼は自転車に乗り、私から遠ざかるように車道を通ってホールの方へ走り去った。私はヒースを横切り、木々の間から覗き込んだ。遠くに、チューダー様式の煙突が突き出た古い灰色の建物が垣間見えたが、車道は鬱蒼とした茂みの中を通っており、男の姿はそれ以上見えなかった。
しかし、私としては、午前中の仕事としてはまずまずの成果を上げたと感じ、意気揚々とファーナムへ歩いて戻った。地元の不動産業者はチャーリントン・ホールについて何も知らず、ポール・モールの有名な会社を紹介してくれた。帰り道にそこに立ち寄り、担当者から丁重な応対を受けた。いや、チャーリントン・ホールを夏の間借りることはできないとのこと。ほんの少し遅かった。一ヶ月ほど前に貸し出されたばかりだという。テナントの名前はウィリアムソン氏。きちんとした年配の紳士だそうだ。丁寧な口調の担当者は、顧客の事情は話せる事柄ではないので、それ以上は申し上げられないと恐縮していた。
シャーロック・ホームズは、その晩、私が提出できた長い報告に注意深く耳を傾けたが、私が期待し、評価してほしかった、あの簡潔な賞賛の言葉は引き出せなかった。それどころか、彼の厳格な顔はいつも以上に険しく、私のしたこと、そしてしなかったことについて、次のようにコメントした。
「君の隠れ場所は、実にまずかったな、ワトソン君。生け垣の向こうにいるべきだった。そうすれば、この興味深い人物を間近で見られただろうに。現状では、君は何百ヤードも離れていて、ミス・スミスよりも情報が少ないくらいだ。彼女はあの男を知らないと思っているが、私は知っていると確信している。でなければ、なぜ彼は、彼女に顔を見られるほど近づかれるのを、あれほど必死に嫌がるのか? 君は彼がハンドルバーに身をかがめていたと描写している。これもまた、顔を隠すためだ。君は実に、ひどい失態を演じたものだ。彼は屋敷に戻った。そして君は彼が誰なのか突き止めたい。それでロンドンの不動産業者へ行くとは!」
「では、どうすればよかったのですか?」
私はいくらか熱を帯びて叫んだ。
「最寄りのパブに行くべきだった。そこが田舎の噂話の中心地だ。主人から下働きに至るまで、あらゆる名前を教えてくれただろう。ウィリアムソン? 私の頭には何も浮かばない。もし彼が年配の男なら、あの若い淑女の運動能力あふれる追跡から疾走して逃げる、活動的なサイクリストではありえない。君の遠征で我々は何を得たかね? あの少女の話が真実だという知識。それは一度も疑ったことはない。サイクリストとホールの間に繋がりがあること。それも疑ったことはない。ホールがウィリアムソンに貸されていること。それがわかって、誰が得をする? まあ、まあ、そんなに落ち込んだ顔をしないでくれたまえ、君。来週の土曜日までは、我々にできることはほとんどない。その間に、私自身が一つ二つ、調査をしてみるかもしれん。」
翌朝、ミス・スミスから手紙が届いた。私が目撃したのと全く同じ出来事を簡潔かつ正確に詳述していたが、手紙の核心は追伸にあった。
ホームズさん、私の秘密をお守りくださると信じておりますが、ここでの私の立場が難しくなっております。雇い主から結婚を申し込まれたのです。彼のお気持ちは大変深く、誠実なものだと確信しております。しかし同時に、私の約束はもちろん、別の方に交わしております。彼は私の断りを非常に真剣に、しかしとても優しく受け止めてくださいました。ですが、状況が少々気まずいものになっていることは、お分かりいただけるかと存じます。
「我々の若い友人も、厄介な事態に巻き込まれつつあるようだ」とホームズは、手紙を読み終えると、思案深げに言った。「この事件は確かに、当初考えていたよりも興味深い様相を呈し、発展の可能性を秘めている。田舎で静かで平穏な一日を過ごすのも悪くない。今日の午後、出かけて行って、私が立てたいくつかの仮説を試してみる気になった。」
ホームズの田舎での静かな一日は、奇妙な結末を迎えた。彼は夕方遅くにベーカー街に到着したが、唇は切れ、額には変色したこぶができており、およそ自らがスコットランド・ヤードの捜査対象にふさわしいような、荒れた雰囲気を漂わせていた。彼は自らの冒険に大いに面白がり、それを語りながら心から笑った。
「私はあまり体を動かす機会がないから、これはいつも楽しみでね」と彼は言った。「ご存知の通り、私は古き良き英国のスポーツであるボクシングに、いくらかの心得がある。時として、それが役に立つ。例えば今日などは、それがなければ非常に不名誉な目に遭っていただろう。」
私は彼に何があったのか話してほしいと頼んだ。
「君にも勧めた、あの田舎のパブを見つけてね。そこで慎重に聞き込みをした。私はバーにいて、おしゃべりな主人が、私が欲しい情報をすべて提供してくれた。ウィリアムソンは白髭の男で、ホールの少数の使用人たちとひっそり暮らしている。彼が聖職者である、あるいはあったという噂があるが、ホールでの短い滞在中に起きたいくつかの出来事は、私には特に聖職者らしからぬものに思えた。すでに聖職者斡旋所でいくつか調査をしたが、確かにその名の聖職者がおり、その経歴は著しく暗いものだったという。主人はさらに、ホールにはたいてい週末に客が訪れる――『たちの悪い連中ですよ、旦那』――特に、赤髭のウッドリー氏という紳士はいつも来ている、と教えてくれた。そこまで話が進んだ時、誰あろう、その紳士本人が入ってきたではないか。彼は酒場でビールを飲んでいて、会話をすべて聞いていたのだ。俺は何者だ? 何が望みだ? 質問してどういうつもりだ? 彼は実に口達者で、その形容詞は非常に力強かった。罵詈雑言の締めくくりに、悪意に満ちた裏拳を繰り出してきたが、私はそれを完全には避けきれなかった。その後の数分間は、実に楽しいものだった。がむしゃらに殴りかかってくる無頼漢に、鮮やかな左ストレートを叩き込んでやったというわけさ。結果はご覧の通り。ウッドリー氏は荷馬車で家路についた。こうして私の田舎への小旅行は終わった。そして告白せねばなるまいが、いかに楽しかったとはいえ、サリー州の境での私の一日は、君のそれと比べて、さほど有益であったとは言えないな。」
木曜日には、我々の依頼人からまた別の手紙が届いた。
ホームズさん、私がカラザーズ氏のもとを辞めることになったと聞いても、驚きにはならないでしょうね。これほどの高給でも、今の不快な状況に耐えることはできません。土曜日に町へ出て、もう戻るつもりはありません。カラザーズ氏が馬車を用意してくださったので、寂しい道での危険も――もし本当に危険があったとしての話ですが――もうありませんわ。 私が辞めることにした特別な理由ですが、それは単にカラザーズ氏との気まずい関係だけではありません。あの忌まわしい男、ウッドリー氏が再び現れたのです。あの男はいつも醜悪でしたが、今は輪をかけて恐ろしい姿になっています。どうやら事故に遭ったらしく、ひどく顔かたちが崩れているのです。窓からその姿を見かけましたが、幸いにも顔を合わせることはありませんでした。彼はカラザーズ氏と長いこと話し込んでいて、その後、氏はひどく興奮しているようでした。ウッドリーはここに泊まったわけではないのに、今朝また茂みのあたりをこそこそ嗅ぎ回っているのを見かけましたから、この近所に滞在しているに違いありません。あんな男がうろついているくらいなら、獰猛な野生動物が放し飼いにされている方がまだましです。言葉にできないほど、あの男を憎み、恐れています。どうしてカラザーズ氏はあのような生き物を一瞬たりとも我慢できるのでしょう? ともかく、私の悩みも土曜日にはすべて終わるのですわ。
「そう願いたいものだ、ワトソン、心からそう願うよ」ホームズは重々しく言った。「あのうら若き女性の周りでは、何か深い陰謀が渦巻いている。我々には、彼女が最後の道のりで誰にも手出しされないよう見届ける義務がある。ワトソン、土曜の朝に一緒に駆けつけて、この奇妙で込み入った調査が不測の結末を迎えないように、我々は時間を割かねばならんと思う。」
実を言うと、私はこれまでこの事件をさほど深刻に捉えていなかった。危険というよりは、むしろグロテスクで奇怪な事件に思えたのだ。男が大変な美人の後をつけ狙うなど、聞いたこともない話ではない。しかも、声をかける勇気すらないどころか、彼女が近づくと逃げ出すほどの小心者とあっては、手ごわい襲撃者とは到底言えなかった。ごろつきのウッドリーは全くの別人種だが、一度を除いて依頼人に手出しはしておらず、今またカラザーズの家を訪れても彼女の前に姿を現してはいない。自転車の男は、間違いなく酒場の主人が話していた屋敷での週末パーティーの客なのだろうが、その正体も目的も、依然として謎に包まれたままだった。だが、ホームズの厳しい態度と、部屋を出る前にリボルバーをポケットに滑り込ませたという事実が、この奇妙な一連の出来事の裏には悲劇が潜んでいるのかもしれない、という予感を私に抱かせたのである。
雨の夜が明けると、輝かしい朝が訪れた。ヒースに覆われた田園地帯は、花咲くハリエニシダの茂みが燃えるように輝き、ロンドンのくすんだ褐色や灰色に見飽きた目には、いっそう美しく映った。ホームズと私は広々とした砂の道を歩きながら、新鮮な朝の空気を吸い込み、鳥のさえずりと春の息吹に心を躍らせた。クルックスベリー・ヒルの肩に当たる道の登り坂からは、古木のオークの森の中から威圧的にそびえ立つ屋敷が見えた。そのオークは、いかに古かろうと、取り囲む建物よりはまだ若かった。ホームズは、ヒースの茶色と芽吹き始めた森の緑との間を、赤みがかった黄色の帯となってうねる長い道を指さした。はるか遠くに、黒い点となってこちらへ向かってくる乗り物が見える。ホームズは焦れたように声を上げた。
「三十分の余裕を見ておいたんだが」と彼が言った。「あれが彼女の馬車だとすれば、早いほうの列車に乗るつもりだな。まずいぞ、ワトソン。我々が追いつく前に、彼女はチャーリントンを過ぎてしまう。」
坂を越えた途端、乗り物は見えなくなった。しかし、我々はひたすら足を速めた。そのペースたるや、座ってばかりの私の生活が祟り、私は遅れざるを得なかった。だがホームズは、有り余る神経エネルギーを自在に引き出せるせいか、常日頃から鍛えられている。その弾むような足取りは少しも衰えることなく進み、やがて私の百ヤードほど先で、突如として立ち止まった。そして、悲嘆と絶望の身振りで手を振り上げるのが見えた。時を同じくして、空のドッグカートが道のカーブから現れ、馬は駆け足で、手綱を引きずりながら、けたたましくこちらへ向かってきた。
「手遅れだ、ワトソン、手遅れだ!」私が息を切らして駆け寄ると、ホームズが叫んだ。「早い列車を計算に入れていなかったとは、なんたる失態だ! これは誘拐だ、ワトソン――誘拐だ! 殺人か! いや、何が起きたか神のみぞ知る! 道を塞げ! 馬を止めろ! そうだ、よし。さあ、飛び乗れ。この私の失態が招いた結果を、取り返せるかどうか試してみよう。」
我々はドッグカートに飛び乗った。ホームズは馬の向きを変えさせると、鋭く鞭を入れ、我々は来た道を飛ぶように引き返した。カーブを曲がると、屋敷とヒースの間の道がすべて見渡せた。私はホームズの腕を掴んだ。
「あの男だ!」私は息を呑んだ。
一人きりの自転車乗りがこちらへ向かってくる。頭を下げ、肩を丸め、ありったけの力をペダルに込めている。まるで競走選手のように飛ばしていた。突然、彼は髭面の顔を上げ、我々が間近にいるのを見ると、自転車から飛び降りて急停止した。その石炭のように黒い髭は、蒼白な顔と奇妙な対照をなし、目は熱でもあるかのように爛々と輝いていた。彼は我々とドッグカートを睨みつけた。やがて、その顔に驚愕の色が浮かんだ。
「おい! 止まれ!」彼は自転車で我々の道を塞ぎながら叫んだ。「そのドッグカートはどこで手に入れた? 止めろ、おい!」男はサイドポケットからピストルを引き抜きながら怒鳴った。「止めろと言っているんだ! さもないと、畜生、馬に弾丸をぶち込むぞ!」
ホームズは手綱を私の膝に放り投げ、荷車から飛び降りた。
「あなたに会いたかった。ミス・ヴァイオレット・スミスはどこです?」と、彼はいつものように素早く、明瞭な口調で言った。
「こっちが聞きたいくらいだ。あんたたちは彼女のドッグカートに乗っている。どこにいるか知っているはずだろう。」
「道でこのドッグカートを見つけました。誰も乗っていなかったのです。お嬢さんを助けるために引き返してきたところです。」
「なんてことだ! なんてことだ! どうすればいいんだ?」見知らぬ男は、絶望のあまり錯乱したように叫んだ。「奴らにやられたんだ。あの地獄の猟犬ウッドリーと、悪党牧師に。さあ、来てくれ、もし本当に彼女の味方なら。力を貸してくれ。チャーリントンの森で俺が骸を晒すことになっても、必ず彼女を救い出す。」
彼はピストルを手に、取り乱した様子で生け垣の切れ目へと走った。ホームズがその後を追い、私は馬を道端で草を食ませておいて、ホームズに続いた。
「ここを抜けていったな」彼はぬかるんだ小道の数人の足跡を指して言った。「おい! ちょっと待て! 茂みの中にいるのは誰だ?」
それは十七歳くらいの若者で、馬丁のような服装をし、革のズボンに脚絆をつけていた。仰向けに倒れ、膝を立て、頭にはひどい切り傷を負っている。意識はなかったが、息はあった。傷を一目見て、骨には達していないことがわかった。
「馬丁のピーターだ」と見知らぬ男が叫んだ。「彼女の馬車を御していたんだ。あの獣どもが引きずり下ろして、棍棒で殴りつけたんだ。放っておけ。どうせ助けてやれん。だが、彼女だけは、女に降りかかる最悪の運命から救い出せるかもしれん。」
我々は木々の間を縫う小道を夢中で駆け下りた。屋敷を囲む植え込みにたどり着いたとき、ホームズが足を止めた。
「屋敷へは行っていない。足跡は左だ――ここ、月桂樹の茂みのそばだ。ああ! やはりな。」
彼がそう言った瞬間、女の甲高い悲鳴――恐怖に狂ったような震えを伴う悲鳴――が、我々の目の前の緑濃い茂みからほとばしった。その叫びは、最も高い音のところで、喉を詰まらせるような音とともに、唐突に途絶えた。
「こっちだ! こっちだ! ボウリング場にいる!」見知らぬ男は茂みを突っ切って叫んだ。「ああ、卑怯な犬どもめ! ついてきてくれ、諸君! 遅かった! 手遅れだ! ちくしょうめ!」
我々が突然飛び出した先は、古木に囲まれた美しい芝生の空き地だった。その向こう側、巨大なオークの木陰に、三人の奇妙な一団が立っていた。一人は女性、我々の依頼人だ。ぐったりと気を失いかけ、口にはハンカチが巻かれている。その向かいには、残忍で厚かましい顔つきの、赤髭の若い男が立っていた。脚絆をつけた両足を大きく開き、片腕を腰に当て、もう一方の手では乗馬鞭を振り回し、その全身から勝ち誇った虚勢がにじみ出ている。二人の間には、灰色の髭を生やした年配の男がいた。明るい色のツイードスーツの上に短いサープリス[訳注:聖職者が着る白い上衣]を羽織っており、どうやら結婚の儀式を終えたばかりのようだ。我々が現れると祈祷書をポケットにしまい、陽気な祝福の意を込めて、不吉な花婿の背中を叩いた。
「結婚させられたんだ!」私は息を呑んだ。
「行くぞ!」我々の案内役が叫んだ。「行くぞ!」
彼は空き地を突っ切って駆け出した。ホームズと私もその後に続く。我々が近づくと、女性はよろめき、支えを求めて木の幹にもたれかかった。元聖職者のウィリアムソンは、からかうような丁寧さで我々に一礼し、ごろつきのウッドリーは、残忍で得意満面の笑い声を上げながら進み出た。
「髭は取っていいぜ、ボブ」と彼が言った。「お前のことなんざお見通しさ。まあ、お前とお仲間さんは、ちょうどいいところに来てくれたもんだ。ウッドリー夫人を紹介できるってもんだからな。」
我々の案内役の返答は、実に奇妙なものだった。彼は変装に使っていた黒い髭をひったくって地面に投げ捨てた。その下から現れたのは、青白く、髭をきれいに剃った面長の顔だった。そしてリボルバーを抜き放つと、危険な乗馬鞭を振り回しながら迫ってくる若いならず者に狙いを定めた。
「そうだ」我々の味方は言った。「俺はボブ・カラザーズだ。この女性の名誉は、たとえ絞首刑になろうとも、俺が取り戻す。彼女に手を出したらどうなるか、言っておいたはずだ。神に誓って、言ったことは実行させてもらう。」
「手遅れだ。こいつは俺の女房だ。」
「いや、お前の未亡人になる。」
彼のピストルが火を噴き、ウッドリーのベストの胸から血が噴き出すのが見えた。男は悲鳴を上げて一回転し、仰向けに倒れた。その醜い赤ら顔は、見る間に恐ろしいまだら模様の蒼白さに変わった。まだサープリスを着たままの老人は、私がかつて聞いたこともないような汚い罵詈雑言を立て続けに吐き出し、自らもリボルバーを抜いた。だが、それを構えるよりも早く、ホームズの銃口が彼に向けられていた。
「そこまでだ」友人は冷ややかに言った。「ピストルを捨てろ! ワトソン、それを拾え! 奴の頭に突きつけろ。ありがとう。君、カラザーズ、そのリボルバーをよこせ。これ以上の暴力は許さん。さあ、渡すんだ!」
「いったい、あんたは何者だ?」
「私の名はシャーロック・ホームズ。」
「なんてことだ!」
「私の名を聞いたことがあるようだね。警察が到着するまで、私がその代理を務める。おい、君!」彼は空き地の端に現れた、怯えた様子の馬丁に叫んだ。「こっちへ来い。このメモを持って、馬を飛ばせるだけ飛ばしてファナムへ行くんだ。」
彼は手帳の一葉に数語を走り書きした。「警察署の警視に渡せ。彼が来るまで、全員、私が身柄を預かる。」
ホームズの力強く、威厳に満ちた個性は、この悲劇的な場面を完全に支配し、誰もが皆、彼の手の中の人形と化した。ウィリアムソンとカラザーズは、いつの間にか負傷したウッドリーを家の中へ運んでおり、私は怯える娘に腕を貸した。負傷者はベッドに寝かされ、ホームズの頼みで私が診察した。そして、古いタペストリーが掛かった食堂で二人の囚人を前に座る彼の元へ、報告を届けた。
「命に別状はありません」と私は言った。
「何だと!」カラザーズは椅子から飛び上がって叫んだ。「今すぐ二階へ行って、とどめを刺してやる。あの天使のような女性が、生涯、〝唸り屋ジャック〟ウッドリーに縛り付けられると言うのか?」
「その心配は無用だ」とホームズは言った。「いかなる状況下でも、彼女が彼の妻になることはない。それには、実に確かな理由が二つある。第一に、ウィリアムソン氏に結婚式を執り行う資格があるかどうか、大いに疑問の余地がある。」
「私は叙階されている!」と老悪党が叫んだ。
「そして聖職も剥奪されている。」
「一度聖職者になれば、永久に聖職者だ。」
「そうは思わんがね。許可証はどうだ?」
「結婚許可証は持っている。このポケットに。」
「ならば、それは詐術で手に入れたものだろう。しかし、いずれにせよ、強制された結婚は結婚ではない。だが、きわめて重大な重罪ではある。じきに思い知ることになるだろう。私の見込み違いでなければ、今後十年ほど、その点をじっくり考える時間ができるはずだ。君、カラザーズ、君はピストルをポケットに入れたままにしておくべきだったな。」
「私もそう思い始めています、ホームズさん。ですが、あの子を守るために私がどれほど用心してきたか――私は彼女を愛していたのです、ホームズさん。生まれて初めて愛というものを知りました――その彼女が、南アフリカで最も残忍なごろつきの手に落ちたと考えただけで、気が狂いそうになりました。キンバリーからヨハネスブルグに至るまで、その名を聞けば誰もが震え上がるほどの恐怖の代名詞なのですから。信じられないでしょうが、ホームズさん、あの子を雇ってからというもの、あの悪党どもが潜んでいると知っていたこの家の前を彼女が通る時は、一度たりとも、無事を確認するために自転車で後をつけない日はありませんでした。彼女は善良で気位の高い娘ですから、私が田舎道を尾行していると知ったら、長くは私の元にいてくれなかったでしょう。だから、気づかれないように距離を置き、髭をつけて変装していたのです。」
「なぜ危険を教えてあげなかったのですか?」
「それをすれば、やはり彼女は私のもとを去ってしまったでしょう。それには耐えられなかった。たとえ彼女が私を愛してくれなくとも、家の中で彼女の可憐な姿を見かけ、その声を聞くだけで、私にとっては大きな意味があったのです。」
「ふむ」と私は言った。「カラザーズさん、あなたはそれを愛と呼ぶが、私に言わせれば自己満足ですな。」
「あるいは、その二つは表裏一体なのかもしれません。いずれにせよ、彼女を行かせるわけにはいかなかった。それに、これだけの連中がうろついているのですから、近くに誰かが見守っている方が彼女のためにも良かったのです。そして、電報が届いたとき、奴らが必ず動くと確信しました。」
「何の電報です?」
カラザーズはポケットから電報を取り出した。
「これです」と彼は言った。
それは短く、簡潔だった。
老人は死んだ。
「ふむ!」とホームズは言った。「事の運びが見えてきたようだ。そして、君が言うように、この知らせが連中を最後の行動に駆り立てたであろうことも理解できる。だが、待っている間、話せることを話してくれたまえ。」
サープリスを着た老悪党が、汚い言葉を立て続けに吐き出した。
「ちくしょう!」と彼は言った。「もし俺たちのことを喋ったら、ボブ・カラザーズ、ジャック・ウッドリーにしてやったのと同じ目にあわせてやる。女のことなら好きなだけ泣き言をほざいてろ、そいつはお前自身の問題だ。だが、この私服警官に仲間を売るような真似をしたら、てめえの人生で最悪の一日になると思え。」
「聖職者殿、そう興奮なさらずに」ホームズは煙草に火をつけながら言った。「あなた方に対する嫌疑は十分に明白で、私が聞きたいのは、個人的な好奇心を満たすための些細な詳細だけだ。しかし、もし話しにくいというのであれば、私が話そう。そうすれば、秘密を守り通す望みがどれほどあるか、わかるだろう。第一に、この企てのために南アフリカから来たのは三人――君、ウィリアムソン、君、カラザーズ、そしてウッドリーだ。」
「嘘っぱちその一だ」と老人が言った。「こいつらのどちらにも二ヶ月前まで会ったこともないし、アフリカなんぞ生まれてこのかた行ったこともない。そのパイプにでも詰めて吸うがいいさ、お節介ホームズさんよ!」
「彼の言うことは本当です」とカラザーズが言った。
「なるほど、では二人で来たのだな。聖職者殿は我らが国産品というわけだ。君たちは南アフリカでラルフ・スミスと知り合いだった。彼が長くは生きられないと信じるに足る理由があった。そして、彼の姪が財産を相続することを知った。どうだね――え?」
カラザーズは頷き、ウィリアムソンは悪態をついた。
「彼女が最近親者であることは疑いなく、そして君たちは、あの老人が遺言書を作らないことも承知していた。」
「読み書きができませんでしたから」とカラザーズは言った。
「そこで君たち二人は渡英し、娘を探し出した。計画は、一人が彼女と結婚し、もう一人が略奪品の分け前にあずかるというものだった。何らかの理由で、ウッドリーが夫役に選ばれた。それはなぜだ?」
「船旅の途中で、彼女を賭けてカードをやったんです。奴が勝ちました。」
「なるほど。君は若いご婦人を雇い入れ、そこでウッドリーが求婚する手はずだった。だが彼女は、彼が酔いどれの獣であることを見抜き、全く相手にしなかった。その一方で、君自身が彼女に恋をしてしまったことで、計画は少々狂った。このごろつきが彼女を所有するという考えに、もはや耐えられなくなったのだな?」
「ええ、誓って、耐えられませんでした!」
「君たちの間にいさかいが起きた。彼は激怒して君のもとを去り、君とは別に、独自の計画を立て始めた。」
「どうやらウィリアムソン、我々がこの紳士に話せることは、あまり残っていないようだ」カラザーズは苦笑いを浮かべて叫んだ。「ええ、我々は喧嘩し、奴に殴り倒されました。まあ、その点ではおあいこですがね。それから奴を見失いました。その頃に、ここの追放された神父と手を組んだのです。二人が、彼女が駅へ行くのに通らなければならない道沿いのこの場所で、一緒に暮らし始めたことを突き止めました。それからは彼女から目を離しませんでした。何か悪魔的な企みがあると感じていたからです。連中が何を企んでいるか知りたくて、時々様子を窺っていました。二日前、ウッドリーが私の家へこの電報を持ってきました。ラルフ・スミスが死んだことを示すものです。彼は私に、約束を守るかと尋ねました。私は断りました。では自分で彼女と結婚して、分け前をよこせと。私は喜んでそうするが、彼女が私を受け入れないだろうと答えました。すると奴は言ったのです。『まず結婚させちまおう。一、二週間もすれば、あいつも少しは物事の見方が変わるだろう』と。私は暴力には一切関わらないと断りました。すると奴は、いつもの口汚い悪党らしく、悪態をつきながら去っていき、それでも彼女を手に入れてやると誓っていました。彼女はこの週末に私のもとを去る予定で、駅まで送る馬車も用意していましたが、どうにも胸騒ぎがして、自転車で後を追ったのです。しかし彼女は先に出てしまい、私が追いつく前に、悪事はなされてしまいました。私が最初に事態を知ったのは、お二人が彼女のドッグカートで引き返してくるのを見たときです。」
ホームズは立ち上がり、吸いさしの煙草を暖炉に投げ入れた。「私はひどく鈍かったようだ、ワトソン」と彼は言った。「君が報告書で、自転車乗りが茂みの中でネクタイを直しているように見えたと書いたとき、それだけで全てを悟るべきだった。とはいえ、我々は奇妙で、いくつかの点では類を見ない事件を解決したことを、互いに祝福すべきだろう。私道に郡警察の三人が見える。そして、あの若い馬丁が彼らに遅れずについてこられるのを見て嬉しく思う。どうやら、彼も、そして興味深い花婿も、今朝の冒険で永続的な傷を負うことはなさそうだ。ワトソン、君は医者として、ミス・スミスの様子を見てきてくれないか。もし十分に回復しているようなら、我々が喜んで彼女を母親の家まで護衛すると伝えてくれ。もし回復が思わしくないようなら、ミッドランドにいる若い電気技師に電報を打つつもりだと匂わせれば、おそらく完治するだろう。カラザーズさん、あなたについては、邪悪な企てに加担した罪を償うために、できる限りのことをしたと思う。これが私の名刺です。もし私の証言があなたの裁判で助けになるのであれば、いつでもお力になります。」
我々の絶え間ない活動の渦の中では、読者もおそらくお気づきのように、物語を締めくくり、好奇心旺盛な方々が期待するであろう最後の詳細を記すことは、しばしば困難であった。一つの事件は次の事件への序曲であり、危機が一度去れば、登場人物たちは我々の多忙な生活から永遠に姿を消してしまう。しかし、この事件を扱った私の原稿の最後に、短いメモを見つけた。そこには、ミス・ヴァイオレット・スミスが確かに莫大な財産を相続し、現在はウェストミンスターの有名な電気会社モートン&ケネディの上級共同経営者であるシリル・モートンの妻となっていることが記録されている。ウィリアムソンとウッドリーは共に誘拐と暴行で裁判にかけられ、前者は懲役七年、後者は十年を言い渡された。カラザーズの運命については記録がないが、ウッドリーが最も危険なごろつきとして悪名高かったことから、彼の暴行は法廷でさほど重く見なされなかったと確信している。そして、正義の要求を満たすには、数ヶ月で十分だったと思う。
プライオリ学校の冒険
ベーカー街の我々の小さな舞台では、これまでにも数々の劇的な登場と退場があったが、ソーニークロフト・ハクスタブル文学修士、哲学博士、その他諸々の初登場ほど、突然で衝撃的なものは記憶にない。彼の学術的な肩書きの重みを支えるには小さすぎるように思える名刺が、数秒先んじて届けられ、次いで本人が入ってきた――その体躯は大きく、態度は尊大で、物腰は威厳に満ち、まさに冷静沈着と重厚さの化身であった。ところが、彼の最初の行動は、ドアが背後で閉まるや否や、テーブルによろめきかかり、そこから床に滑り落ちることだった。そして、その堂々たる姿は、我々の熊皮の暖炉用敷物の上に、人事不省で打ちのめされていたのである。
我々は跳び起き、しばし声もなく、この巨大な難破船の残骸を呆然と見つめた。それは、人生という大海原のはるか彼方で、突然の致命的な嵐に見舞われたことを物語っていた。やがてホームズが彼の頭にクッションを、私が彼の唇にブランデーを急いで運んだ。その重々しい白い顔には苦悩の皺が刻まれ、閉じた目の下のたるんだ袋は鉛色をしていた。締まりのない口は悲しげに口角が下がり、幾重にも重なる顎には無精髭が生えている。襟とシャツには長旅の垢が染みつき、形の良い頭からは手入れのされていない髪が逆立っていた。我々の前に横たわっていたのは、ひどく打ちのめされた男だった。
「どうだ、ワトソン?」とホームズが尋ねた。
「完全な衰弱です――おそらくは単なる空腹と疲労でしょう」私は、生命の流れが細々と弱く滴る、糸のような脈に指を当てながら言った。
「イングランド北部のマックルトンからの往復切符だ」ホームズは時計のポケットからそれを取り出しながら言った。「まだ十二時にもなっていない。ずいぶん早くに出発したに違いない。」
皺の寄ったまぶたが震え始め、やがて虚ろな灰色の両目が我々を見上げた。次の瞬間、男はよろよろと立ち上がり、顔を羞恥で真っ赤に染めた。
「この様な醜態をお許しください、ホームズさん。少々、神経が昂ぶっておりまして。ありがとうございます、もし牛乳を一杯とビスケットをいただければ、きっと回復するでしょう。私が自ら参りましたのは、ホームズさん、あなたに必ずや私と同行していただくためです。電報では、この事件の絶対的な緊急性をご納得いただけないのではないかと案じました。」
「すっかり回復なさってから――」
「もう大丈夫です。どうしてこれほど衰弱してしまったのか、自分でもわかりません。ホームズさん、次の汽車で私と一緒にマックルトンへ来ていただきたいのです。」
友人は首を横に振った。
「同僚のワトソン博士も証言してくれるでしょうが、我々は現在、非常に多忙です。フェラーズ文書の事件で拘束されていますし、アバガヴェニー殺人事件の公判も迫っている。よほど重要な問題でなければ、今の私をロンドンから呼び出すことはできません。」
「重要ですと!」来客は両手を振り上げた。「ホルダーネス公爵のただ一人のご子息が誘拐されたという話を、何もお聞きになっていないのですか?」
「何ですと! あの元大臣の?」
「その通りです。我々は新聞沙汰になるのを避けようと努めてきましたが、昨夜の『グローブ』紙に何やら噂が載りまして。あなたのお耳にも入っているかと思ったのですが。」
ホームズは長く細い腕をさっと伸ばし、参考資料用の百科事典から「H」の巻を抜き出した。
「『ホルダーネス、第六代公爵、ガーター勲爵士、枢密顧問官』――アルファベットの半分はありそうだ! 『ビヴァリー男爵、カーストン伯爵』――やれやれ、なんという肩書きの数だ! 『一九〇〇年よりハラムシャー州統監。一八八八年、サー・チャールズ・アップルドアの娘、イーディスと結婚。相続人にして唯一の子、ソルタイア卿。約二十五万エーカーの土地を所有。ランカシャーとウェールズに鉱物資源。住所:カールトン・ハウス・テラス、ハラムシャー州ホルダーネス・ホール、ウェールズ、バンゴール、カーストン城。一八七二年、海軍卿、国務長官――』ふむ、ふむ、この人物は間違いなく、英国臣民の中でも最高峰の一人だな!」
「最高峰、そしておそらくは最も裕福な。ホームズさん、あなたが仕事上の事柄において非常に高い志を持ち、仕事そのもののために働く覚悟がおありなのは承知しております。しかしながら、申し上げておきますと、公爵閣下はすでにご子息の居場所を突き止めた者に五千ポンドの小切手を、そして犯人を特定した者にはさらに千ポンドを渡すと内々に表明されております。」
「破格の申し出ですな」とホームズは言った。「ワトソン、我々はハクスタブル博士と共にイングランド北部へ戻ることにしよう。さて、ハクスタブル博士、その牛乳を飲み干されたら、何が起きたのか、いつ起きたのか、どのように起きたのか、そして最後に、マックルトン近郊のプライオリ学校のソーニークロフト・ハクスタブル博士が、この件とどう関わっているのか、なぜ事件から三日も経って――その顎の様子が日付を物語っていますが――私のささやかな助力を請いに来られたのか、親切に教えていただきたい。」
来客は牛乳とビスケットを食べ終えた。その目には光が、頬には血色が戻り、彼は大いなる気力と明晰さをもって状況を説明し始めた。
「まず申し上げておきますと、諸君、プライオリは私が創設し、校長を務める予備学校です。『ホラティウスに関するハクスタブルの寸見』という本で、私の名を思い出される方もおられるかもしれません。プライオリは、例外なく、イングランドで最も優秀かつ選りすぐりの予備学校です。レヴァーストーク卿、ブラックウォーター伯爵、サー・キャスカート・ソームズ――皆様、ご子息を私に託してくださいました。しかし、我が校がその頂点に達したと感じたのは、数週間前、ホルダーネス公爵が秘書のジェイムズ・ワイルダー氏を遣わし、ご子息で唯一の相続人である十歳の若きソルタイア卿を、私の保護下に置くとの知らせを受けたときでした。これが私の人生で最も打ちのめされる不幸の前触れになろうとは、夢にも思いませんでした。
夏学期の始まりである五月一日に、その少年はやって来ました。彼は魅力的な若者で、すぐに我々のやり方に馴染みました。お話ししてもよろしいでしょう――無分別ではないと信じますが、このような場合に中途半端な信頼は馬鹿げていますから――彼は家庭で必ずしも幸福ではありませんでした。公爵の結婚生活が平穏でなかったことは公然の秘密であり、その問題は双方合意の上での別居という形で終わり、公爵夫人は南フランスに居を構えました。これはごく最近のことで、少年の心情は強く母親に寄り添っていたことが知られています。ホルダーネス・ホールから母が去った後、彼はふさぎ込んでおり、公爵が彼を私の学校へ送ることを望んだのはそのためでした。二週間もすれば、少年はすっかり我々に打ち解け、見たところ、この上なく幸せそうでした。
彼が最後に目撃されたのは、五月十三日の夜――つまり、先週の月曜の夜です。彼の部屋は二階にあり、二人の少年が眠る、より大きな別の部屋を通って入るようになっていました。この二人の少年は何も見聞きしておらず、したがって、若きソルタイア卿がその通路を通って外に出なかったことは確かです。彼の部屋の窓は開いており、地面まで続く丈夫な蔦の蔓がありました。下に足跡は確認できませんでしたが、これが唯一可能な出口であることは間違いありません。
彼の不在が発覚したのは、火曜の朝七時でした。ベッドには寝た形跡がありました。彼は出かける前に、いつもの学校の制服である黒のイートンジャケットと濃い灰色のズボンをきちんと着込んでいました。誰かが部屋に侵入した形跡はなく、叫び声や争う物音があれば、隣室の年長の少年であるカウンタ――が非常に眠りの浅い子なので、間違いなく聞こえたはずです。
ソルタイア卿の失踪が判明したとき、私は直ちに学校中の全員――生徒、教師、使用人――の点呼を取りました。その時になって初めて、ソルタイア卿が一人で逃げたのではないことが判明したのです。ドイツ語教師のハイデガーがいなくなっていました。彼の部屋は二階の建物の反対側の端にあり、ソルタイア卿の部屋と同じ方角を向いていました。彼のベッドにも寝た形跡がありましたが、シャツと靴下が床に落ちていたことから、どうやら服を完全には着ずに去ったようです。彼も間違いなく蔦を伝って降りたのでしょう。芝生に着地した際にできた、彼の足跡を確認できました。彼の自転車は、この芝生の横にある小さな物置に保管されていましたが、それもなくなっていました。
彼は二年間私のもとで働き、最上の推薦状を持っていましたが、無口で気難しい男で、教師にも生徒にもあまり人気がありませんでした。逃亡者たちの痕跡は一切見つからず、今や木曜の朝になっても、我々は火曜の時と同じく、何もわかっていません。もちろん、直ちにホルダーネス・ホールへ問い合わせはしました。ほんの数マイルしか離れていないので、急にホームシックにでもなって父親のもとへ帰ったのかと思ったのですが、何の音沙汰もありませんでした。公爵はひどく動揺しておられ、私に至っては、この心労と責任感から神経衰弱に陥っている様を、あなた方ご自身でご覧になった通りです。ホームズさん、もしあなたがその全能力を発揮されるのであれば、今こそそうしていただきたい。あなたの生涯において、これほどそれに値する事件はないでしょうから。」
シャーロック・ホームズは、不幸な校長の陳述に最大限の注意を払って耳を傾けていた。引き結ばれた眉と、その間に刻まれた深い皺は、彼が集中するよう促されるまでもなく、この問題に全神経を注いでいることを示していた。それは、関わる利害の巨大さはさておき、複雑で異常なものを愛する彼の性質に、直接訴えかけるものだったに違いない。彼は今、手帳を取り出し、一つ二つメモを書き留めた。
「もっと早く私のところへ来なかったのは、ひどい怠慢ですな」彼は厳しく言った。「あなたは、私の調査に非常に深刻なハンデを負わせた。例えば、この蔦と芝生が、専門の観察者にとって何ももたらさなかったとは考えられない。」
「私に非はありません、ホームズさん。公爵閣下が、いかなる公のスキャンダルも避けたいと強く望まれたのです。家庭内の不幸が世間の目に晒されることを恐れておられるのです。その種のことを極度に嫌悪しておられます。」
「しかし、何らかの公式な捜査は行われたのでしょう?」
「ええ、行われました。そして、それはきわめて残念な結果に終わりました。少年と若い男が近隣の駅から早朝の列車で去るのが目撃されたとの情報があり、それが有力な手がかりかと思われました。しかし、昨夜になってようやく、その二人組がリバプールで発見されたとの知らせがあり、この件とは全く無関係であることが判明したのです。その時でした。絶望と失望の中、眠れぬ夜を過ごした後、私は始発の列車で直接あなたの元へ来たのです。」
「その偽の手がかりを追っている間、地元の捜査は手薄になったと推察しますが?」
「完全に中断されていました。」
「つまり三日間が無駄になったわけだ。この事件は、実に嘆かわしい扱われ方をしてきた。」
「それは感じておりますし、認めます。」
「しかし、この問題は最終的に解決可能であるはずだ。喜んで調査いたしましょう。失踪した少年と、このドイツ語教師との間に、何らかの繋がりを見つけることはできましたか?」
「全くありません。」
「彼はその教師のクラスにいましたか?」
「いいえ。私の知る限り、一言も言葉を交わしたことはありません。」
「それは確かに、非常に奇妙だ。少年は自転車を持っていましたか?」
「いいえ。」
「他に無くなった自転車は?」
「ありません。」
「それは確かですか?」
「間違いありません。」
「ふむ、では、まさか、このドイツ人が真夜中に自転車に乗り、少年を腕に抱えて走り去ったと本気で示唆するつもりではありますまいな?」
「もちろん、そんなことはありません。」
「では、あなたの心の中にある説は?」
「自転車は目くらましだったのかもしれません。どこかに隠しておいて、二人は徒歩で去ったのかも。」
「なるほど。しかし、少々馬鹿げた目くらましだとは思いませんか? その物置には他に自転車はありましたか?」
「数台ありました。」
「もし彼らが自転車で逃げたという印象を与えたかったのなら、二台隠したのではないでしょうか?」
「そうでしょうな。」
「もちろん、そうするはずだ。目くらまし説は成り立たない。しかし、この出来事は調査の素晴らしい出発点だ。何しろ、自転車は隠したり破壊したりするのが簡単なものではない。もう一つ質問です。彼が失踪する前日、誰か少年に会いに来ましたか?」
「いいえ。」
「手紙は受け取りましたか?」
「はい、一通。」
「誰から?」
「父親からです。」
「あなたは生徒の手紙を開封するのですか?」
「いいえ。」
「なぜ父親からだとわかったのですか?」
「封筒に紋章があり、公爵独特の硬い筆跡で宛名が書かれていました。それに、公爵も手紙を書いたことを覚えておられます。」
「その前に手紙を受け取ったのはいつでしたか?」
「数日間ありませんでした。」
「フランスからの手紙は?」
「いいえ、一度も。」
「私の質問の意図は、もちろんおわかりでしょう。少年は力ずくで連れ去られたか、自らの意志で去ったかのどちらかだ。後者の場合、これほど若い子がそのようなことをするには、外部からの何らかの働きかけが必要だったと考えるのが自然です。もし訪問者がいなかったのなら、その働きかけは手紙で来たに違いない。ゆえに、私は彼の手紙のやり取りの相手を見つけ出そうとしているのです。」
「残念ながら、あまりお力になれそうにありません。私の知る限り、彼の手紙の相手は、彼自身の父親だけでした。」
「失踪したまさにその日に、彼に手紙を書いた父親が、ですね。父と子の関係は非常に友好的でしたか?」
「公爵閣下は、誰に対してもあまり友好的ではありません。国家の重大な問題に没頭しておられ、普通の感情にはやや疎い方です。しかし、彼なりに、常に少年には親切でした。」
「しかし、後者の心情は母親の方にあったと?」
「はい。」
「彼はそう言いましたか?」
「いいえ。」
「では、公爵が?」
「とんでもない!」
「では、どうしてご存じなのですか?」
「公爵閣下の秘書であるジェイムズ・ワイルダー氏と、内々にお話をする機会がありまして。ソルタイア卿の気持ちについて教えてくれたのは彼です。」
「なるほど。ところで、その公爵の最後の手紙ですが――彼がいなくなった後、少年の部屋で見つかりましたか?」
「いいえ、彼はそれを持って行きました。ホームズさん、そろそろユーストン駅へ向かう時間かと。」
「四輪馬車を呼びましょう。十五分もすれば、お役に立てます。もしご自宅に電報を打たれるのでしたら、ハクスタブルさん、あなたの近所の人々には、捜査はまだリバプールか、あるいはその偽の手がかりがあなた方を導いたどこか別の場所で続いていると思わせておくのが賢明でしょう。その間に、私はあなたの足元で、少し静かに仕事をします。おそらく、匂いはそれほど冷めてはいないでしょうから、ワトソンと私のような二匹の老練な猟犬なら、その痕跡を嗅ぎつけられるかもしれません。」
その晩、我々はハクスタブル博士の有名な学校が位置する、ピーク地方の冷たく爽やかな大気の中にいた。我々が到着したときには、すでに暗くなっていた。ホールのテーブルに名刺が置かれており、執事が主人に何かをささやくと、彼は重々しい顔の隅々まで動揺を浮かべて我々の方を向いた。
「公爵がお見えです」と彼は言った。「公爵とワイルダー氏が書斎におられます。さあ、諸君、ご紹介しましょう。」
私はもちろん、かの有名な政治家の肖像画には馴染みがあったが、本人自身はその絵姿とは大きく異なっていた。彼は背が高く堂々とした人物で、非の打ちどころのない服装をし、引き締まった痩せた顔には、グロテスクなまでに湾曲した長い鼻がついていた。その顔色は死人のような蒼白さで、長く先細りになった鮮やかな赤髭との対比で一層際立っていた。その髭は白いベストの上に流れ落ち、その縁からは時計の鎖がきらめいている。そのような堂々たる人物が、ハクスタブル博士の暖炉の敷物の中央から、石のように冷たい視線で我々を見つめていた。彼の傍らには非常に若い男が立っており、私は彼が私設秘書のワイルダーであると理解した。彼は小柄で、神経質そうで、利口そうな水色の目と表情豊かな顔立ちで機敏に見えた。会話の口火を切ったのは、鋭く断定的な口調で、彼の方だった。
「今朝お電話しましたが、ハクスタブル博士、あなたがロンドンへ出発されるのを止めるには遅すぎました。あなたの目的が、シャーロック・ホームズ氏にこの事件の指揮を依頼することだと知りました。公爵閣下は、ハクスタブル博士、あなたがご相談もなくそのような措置を取られたことに驚いておられます。」
「警察が失敗したと知ったとき――」
「公爵閣下は、警察が失敗したとは全く確信しておられません。」
「しかし、ワイルダーさん、確かに――」
「ご存じの通り、ハクスタブル博士、公爵閣下は公のスキャンダルを避けることを特に望んでおられます。ごく少数の人々だけを信頼することをお好みになるのです。」
「その問題は簡単に解決できます」と、打ちのめされた博士は言った。「シャーロック・ホームズ氏は明日の朝の汽車でロンドンへお戻りになれます。」
「それはどうでしょうかな、博士、それはどうでしょう」とホームズは、この上なく穏やかな声で言った。「この北国の空気は活力を与えてくれますし、快適です。ですから、数日間、あなた方の荒野で過ごし、できる限り心を占めることにしようかと考えております。私があなたの屋根の下に宿るか、村の宿屋に泊まるかは、もちろん、あなたがお決めになることです。」
気の毒な博士が、ためらいの極致にいるのが見て取れた。その彼を救ったのは、赤髭の公爵の深々と響く声だった。その声は、まるでディナーのゴングのように鳴り響いた。
「ワイルダー君に同意するよ、ハクスタブル博士。私に相談するのが賢明だったろう。しかし、ホームズ氏がすでに君の信頼を得ている以上、我々が彼の助力を利用しないのは、実に馬鹿げたことだ。宿屋へ行くどころか、ホームズさん、よろしければホルダーネス・ホールに来て、私と共に滞在していただきたい。」
「閣下、ありがとうございます。調査の目的のためには、私はこの謎の現場に留まる方が賢明かと存じます。」
「お好きなように、ホームズさん。ワイルダー君か私が提供できる情報は、もちろん、いつでもご自由にお使いください。」
「おそらく、ホールでお目にかかる必要が出てくるでしょう」とホームズは言った。「ただ今お伺いしたいのは、閣下、ご子息の謎の失踪について、ご自身の中で何らかの説明はおつきになりましたか?」
「いいえ、ついておりません。」
「お辛いことに触れるのをお許しいただきたいのですが、他に選択肢がありません。公爵夫人がこの件に関与しているとお考えですか?」
偉大な大臣は、目に見えてためらいを見せた。
「そうは思いません」と、彼はようやく言った。
「もう一つの最も明白な説明は、身代金目的で子供が誘拐されたというものです。その種の要求は受けておられませんか?」
「いいえ。」
「もう一つ質問です、閣下。この事件が起こった日に、ご子息に手紙をお書きになったと伺っておりますが。」
「いや、書いたのはその前日だ。」
「その通りです。しかし、彼がそれを受け取ったのはその日ですね?」
「はい。」
「あなたの手紙の中に、彼の心を乱したり、そのような行動を促したりするような内容はありましたか?」
「いいえ、断じてありません。」
「その手紙はご自身で投函されましたか?」
貴族の返答は、秘書によって遮られた。彼はいくらか熱を帯びて口を挟んだ。
「公爵閣下はご自身で手紙を投函される習慣はございません」と彼は言った。「この手紙は他の手紙と共に書斎のテーブルに置かれ、私自身が郵便袋に入れました。」
「その中に確かにこの一通があったと?」
「はい、確認いたしました。」
「その日、閣下は何通の手紙をお書きになりましたか?」
「二十通か三十通だ。私は多くの手紙をやり取りする。しかし、これは少々的外れではないかね?」
「完全に、というわけではありません」とホームズは言った。
「私としては」と公爵は続けた。「警察には南フランスに注意を向けるよう助言した。すでに述べたように、公爵夫人がこのような凶悪な行為を助長するとは信じていないが、あの子はきわめてひねくれた考えを持っており、このドイツ人に助けられ、そそのかされて、彼女のもとへ逃げた可能性はある。ハクスタブル博士、我々はもうホールへ戻ることにしよう。」
ホームズが他にも尋ねたい質問があったのは見て取れたが、貴族のぶっきらぼうな態度は、面会が終わりであることを示していた。彼の極度に貴族的な性質にとって、見知らぬ者と内々の家庭の事情を議論することは、この上なく不快であり、新たな質問が一つ投げかけられるごとに、彼の公爵家の歴史の、慎重に影に隠された隅々に、より厳しい光が当てられるのを恐れているのは明らかだった。
貴族とその秘書が去ると、友人はすぐに、彼特有の熱意をもって調査に乗り出した。
少年の部屋は注意深く調べられたが、彼が窓からしか逃げられなかったという絶対的な確信以外、何ももたらさなかった。ドイツ語教師の部屋と所持品からも、それ以上の手がかりは得られなかった。彼の場合、蔦の蔓が体重でちぎれており、我々はランタンの光で、芝生に彼のかかとが落ちた跡を見た。短く刈られた緑の芝生に残されたその一つのくぼみが、この不可解な夜逃げの唯一の物的な証人だった。
シャーロック・ホームズは一人で家を出て、十一時過ぎにようやく戻ってきた。彼は近隣の大縮尺の地図を手に入れており、それを私の部屋へ持ち込むと、ベッドの上に広げ、その真ん中にランプを据えた。そして、その上で煙草をふかし始め、時折、煙を吐き出すパイプの琥珀色の吸い口で、興味深い地点を指し示した。
「この事件、ますます面白くなってきたぞ、ワトソン」と彼は言った。「確かに関連していくつか興味深い点がある。この初期段階で、君には我々の調査に大いに関わってくるかもしれない、これらの地理的特徴を理解してもらいたい。」
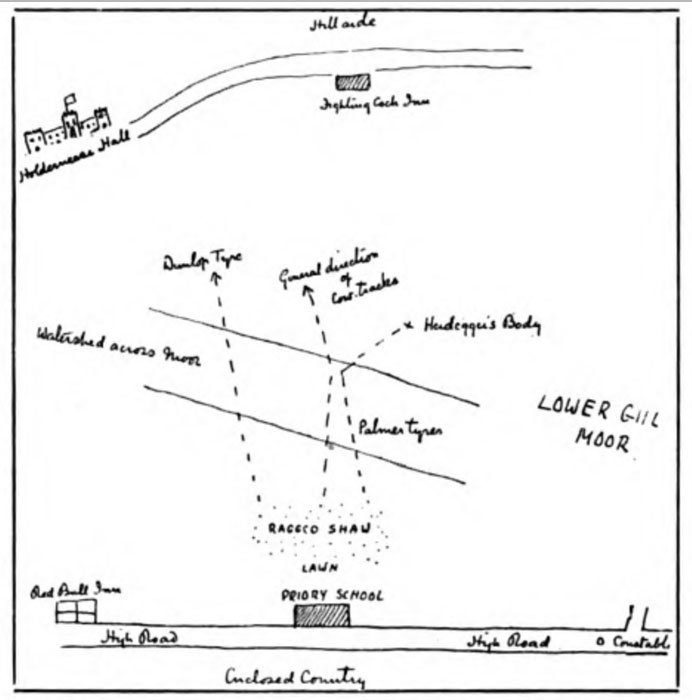
ホームズによる学校周辺の地図
「この地図を見ろ。この黒い四角がプライオリ学校だ。ここにピンを刺しておこう。さて、この線が主要道路だ。学校の前を東西に走っているのがわかるだろう。そして、どちらの方向へも一マイルは脇道がないこともわかる。もしこの二人が道路を通って去ったとすれば、それはこの道だ。」
「その通りです。」
「実に奇妙で幸運な偶然により、我々はある程度、問題の夜にこの道を通ったものを確認することができる。この地点、今私のパイプが置かれている場所に、郡の巡査が十二時から六時まで勤務していた。ご覧の通り、東側で最初の交差点だ。この男は、一瞬たりとも持ち場を離れなかったと断言しており、少年も男も、見られずにそちらへ行くことはできなかったと確信している。今夜、この警官と話したが、彼は完全に信頼できる人物のように思える。これで東側は塞がれた。次に、もう一方を処理しなければならない。ここには『赤牛亭』という宿屋があり、その女将が病気だった。彼女はマックルトンに医者を呼びにやったが、別の患者のところで不在だったため、医者が到着したのは朝になってからだった。宿屋の人々は、彼の到着を待って一晩中起きており、誰かしらが常に道に目を光らせていたようだ。彼らは誰も通らなかったと断言している。もし彼らの証言が確かであれば、我々は幸運にも西側を塞ぐことができ、逃亡者たちが全く道路を使わなかったと言うこともできるわけだ。」
「しかし、自転車は?」と私は反論した。
「その通り。自転車の話はいずれまた。推理を続けよう。もし彼らが街道を通らなかったとすれば、校舎の北側か南側の土地を横切ったに違いない。これは確実だ。では、両者を比較検討してみよう。校舎の南側は、君も見た通り、石垣で細かく区切られた広大な耕作地が広がっている。あそこを自転車で走るのは不可能だと私も認めよう。この線は消せる。となると、北側だ。ここには『ラギッド・ショー』と記された雑木林があり、その向こうには広大なロウアー・ギル・ムーアが広がっている。十マイルにわたって緩やかに上っていく起伏のある荒野だ。この荒野の片隅に、ホルダーネス公爵邸がある。街道を行けば十マイルだが、荒野を突っ切ればわずか六マイルだ。ここは実に寂寥とした平原でね。荒野の農夫が小さな土地で羊や牛を飼っているのがちらほらいるくらいだ。それ以外は、チェスターフィールドの街道に出るまで、チドリやダイシャクシギくらいしか住人はいない。ほら、教会が一軒、家が数軒、そして宿屋が一軒。その先は険しい丘陵地帯だ。我々が追うべきは、間違いなくこの北の方面だろう。」
「しかし、自転車は?」私は食い下がった。
「まあ、まあ!」ホームズは焦れたように言った。「腕のいい乗り手なら街道など必要ない。荒野には小道が縦横に走っているし、月は満月だった。おや! これは一体?」
激しくドアをノックする音が響き、その直後、ハクスタブル博士が部屋に飛び込んできた。その手には、白い山形の模様が入った青いクリケット帽が握られていた。
「ついに手がかりが!」彼は叫んだ。「ありがたい! やっとあの子の足取りが掴めました! これはあの子の帽子です。」
「どこで見つかったのですか?」
「荒野で野営していたジプシーの馬車の中から。彼らは火曜日に立ち去りました。今日、警察が彼らを突き止め、幌馬車を調べたところ、これが見つかったのです。」
「彼らは何と?」
「はぐらかして嘘を……火曜の朝に荒野で拾ったなどと。あの子の居場所を知っているに違いありません、あの悪党どもめ! 幸い、全員拘束されています。法の裁きを恐れるか、公爵の懸賞金に目が眩むか、いずれにせよ知っていることを洗いざらい吐くでしょう。」
「ひとまず、順調だな」博士がようやく部屋を出て行くと、ホームズは言った。「少なくとも、ロウアー・ギル・ムーアの方面に望みを託すべきだという私の説を裏付けている。警察は、このジプシーたちを逮捕した以外、地元では何もしていない。見てくれ、ワトソン! 荒野を横切る水路がある。地図にも記されているだろう。所々、沼地に広がっている。特にホルダーネス公爵邸と学校の間がそうだ。これだけ乾燥した天候では、他で足跡を探すのは無駄骨だが、あの場所なら何らかの痕跡が残っている可能性は十分にある。明日の朝早くに起こすから、君と私でこの謎に一筋の光を投げかけられるか試してみようじゃないか。」
夜が明け始めた頃、目を覚ますと、ベッドの脇にホームズの細長い姿があった。彼はすっかり身支度を整えており、どうやら既に外へ出ていたらしい。
「芝生と自転車置き場は調べてきた」と彼は言った。「ラギッド・ショーも一通り見てきた。さあ、ワトソン、隣の部屋にココアの用意ができている。急いでくれ。今日はとてつもない一日になるぞ。」
彼の目は輝き、頬は、眼前に仕事が広がるのを見た名工の高揚感で紅潮していた。この活動的で鋭敏な男は、ベーカー街の内省的で青白い夢想家とはまるで別人だった。神経質なエネルギーに満ちたそのしなやかな姿を見つめながら、我々を待ち受けているのはまさしく骨の折れる一日になるだろうと感じた。
しかし、その幕開けは、この上なく深い失望だった。我々は大きな期待を胸に、無数の羊の小道が交差する、赤褐色の泥炭質の荒野を横切り、我々とホルダーネス邸を隔てる沼地を示す、幅の広い薄緑色の帯状の場所までやって来た。もし少年が家路を辿ったのであれば、必ずここを通過したはずであり、痕跡を残さずに通ることはできないはずだった。だが、彼やドイツ人教師の気配はどこにもなかった。友は顔を曇らせ、苔むした地面についた泥の染み一つひとつを熱心に観察しながら、沼地の縁を大股で歩いた。羊の足跡は無数にあり、数マイル下った場所には牛が残した足跡もあった。それだけだった。
「ひとつ目の誤算だな」ホームズは、起伏の続く荒野を陰鬱な表情で見渡しながら言った。「あちらの方にもう一つ沼地があり、その間に狭い通路がある。おや! おやおや! これは一体何だ?」
我々は、黒いリボンのような細い小道に行き当たった。その真ん中のぬかるんだ土の上に、自転車の轍がはっきりと残っていた。
「やったぞ!」私は叫んだ。「見つけた!」
しかしホームズは首を振り、その表情は喜びに満ちているというより、むしろ当惑と期待が入り混じっていた。
「自転車には違いないが、あの自転車ではない」と彼は言った。「私は四十二種類のタイヤ痕を見分けることができる。君にも分かるだろうが、これはダンロップ社製で、外側のカバーに継ぎ当てがある。ハイデガーのタイヤはパーマー社製で、縦縞の跡が残る。数学教師のアヴェリング氏がその点を断言していた。したがって、これはハイデガーの轍ではない。」
「では、少年の?」
「彼が自転車を所有していたと証明できれば、その可能性もある。だが、それは全くできていない。この轍は、見ての通り、学校の方角から来た乗り手によってつけられたものだ。」
「あるいは、学校へ向かっていたのでは?」
「いや、いや、ワトソン君。より深く沈んでいるのは、当然、体重がかかる後輪の跡だ。後輪が前輪の浅い跡を横切って消している箇所がいくつか見受けられる。間違いなく学校から遠ざかる方向へ向かっている。我々の捜査に関係があるかないか分からんが、先に進む前に、これを逆方向に辿ってみよう。」
我々はその通りにしたが、数百ヤード進んだところで沼地を抜け、轍を見失った。小道を逆に戻り、泉が横切っている別の場所を見つけた。そこには再び自転車の跡があったが、牛の蹄でほとんど消えかかっていた。その先には何の痕跡もなかったが、小道は学校の裏手にあるラギッド・ショーの森へとまっすぐ続いていた。自転車はその森から出てきたに違いない。ホームズは丸石に腰を下ろし、両手で顎を支えた。私が煙草を二本吸い終わるまで、彼は身動き一つしなかった。
「ふむ、ふむ」と、彼はついに口を開いた。「もちろん、狡猾な男なら、見慣れない轍を残すために自転車のタイヤを交換することも考えられる。そんな発想ができる犯罪者なら、私も相手にする甲斐があるというものだ。この問題は保留にして、再び沼地に戻ろう。まだ調べていない場所が多く残っている。」
我々はぬかるんだ沼地の縁を系統的に調査し続けた。そして間もなく、我々の粘り強さは見事に報われた。沼地の低い部分を横切るように、ぬかるんだ小道が伸びていた。ホームズはそれに近づきながら歓喜の声を上げた。その中央には、細い電信線を束ねたような轍が続いていた。パーマー社のタイヤだ。
「ハイデガー先生に間違いない!」ホームズは得意満面に叫んだ。「私の推理はなかなか的を射ていたようだ、ワトソン君。」
「お見事です。」
「だが、まだ先は長い。小道を外れて歩いてくれ。さあ、跡を追おう。あまり遠くまでは続かないだろうが。」
しかし、進むにつれて、この辺りの荒野はぬかるみが多く、轍を頻繁に見失いはしたものの、その都度なんとか再び見つけ出すことができた。
「気づいたかね」とホームズが言った。「乗り手は今、間違いなくペースを上げている。疑いの余地はない。この轍を見てみろ、両方のタイヤがはっきり見える。前輪も後輪も同じ深さだ。これは、乗り手が全力疾走する時のように、ハンドルバーに体重をかけていることを意味する。何ということだ! 転倒している。」
轍の上には、数ヤードにわたって幅の広い不規則な擦り跡が残っていた。それから数個の足跡があり、再びタイヤ痕が現れた。
「横滑りしたのでしょう」と私は言った。
ホームズは、花の咲いたハリエニシダのしなびた枝を掲げた。見ると、黄色い花が無残にも深紅に染まっているではないか。私は恐怖に慄いた。小道の上にも、ヒースの茂みの中にも、凝固した血の黒い染みがあった。
「まずい!」とホームズは言った。「まずいぞ! 下がっていろ、ワトソン! 無駄な足跡はつけるな! ここから何が読み取れる? 彼は負傷して倒れ、立ち上がり、再び自転車に乗り、進んだ。だが、他に轍はない。この脇道には牛の足跡が。まさか雄牛に突かれたわけではあるまい。あり得ん! しかし、他の誰かの痕跡は見当たらない。先を急ぐぞ、ワトソン。轍に加えて血痕まであるのだ。もはや見失うことはないはずだ。」
我々の捜索はそれほど長くはかからなかった。湿って光る小道の上で、タイヤの轍が奇怪な曲線を描き始めた。ふと前方を見ると、鬱蒼と茂るハリエニシダの茂みの中から金属のきらめきが目に飛び込んできた。そこから我々は一台の自転車を引きずり出した。パーマー社のタイヤ、片方のペダルは曲がり、車体の前面はおびただしい血でべっとりと汚れていた。茂みの向こう側からは靴が突き出ていた。駆け寄ってみると、そこには不運な乗り手が横たわっていた。背の高い、豊かな髭をたくわえた男で、眼鏡をかけていたが、片方のレンズは砕け散っていた。死因は頭部への凄まじい一撃で、頭蓋骨の一部が陥没していた。このような重傷を負いながら走り続けたとは、彼の生命力と勇気のほどが窺える。彼は靴を履いていたが靴下はなく、開いたコートの下からは寝間着が覗いていた。間違いなく、ドイツ人教師だった。
ホームズは丁重に遺体を裏返し、細心の注意を払って検分した。それからしばらく深い思索に耽っていたが、その険しい眉から、この忌まわしい発見が捜査を大きく前進させたとは考えていないことが見て取れた。
「どうしたものか、少し判断に迷うな、ワトソン」と、彼はついに言った。「私としては、このまま捜査を続けたい。すでに多くの時間を失っており、一時間たりとも無駄にはできない。だがその一方で、この発見を警察に知らせ、この哀れな男の遺体を手配する義務もある。」
「私がメモを届けに戻りましょうか。」
「だが、君の協力が必要だ。少し待て! あそこで泥炭を掘っている男がいる。彼をここに連れてきてくれ。警察への案内を頼めるだろう。」
私はその農夫を連れてくると、ホームズは怯える男にハクスタブル博士宛のメモを託して行かせた。
「さて、ワトソン」と彼は言った。「今朝、我々は二つの手がかりを得た。一つはパーマー社のタイヤを履いた自転車で、それが何をもたらしたかは見た通りだ。もう一つは、継ぎ当てのあるダンロップのタイヤを履いた自転車。そちらを調べる前に、我々が既に知っていることを整理し、最大限に活用しよう。そして、本質的なことと偶発的なこととを切り分けるのだ。」
「まず第一に、少年が間違いなく自らの意志で去ったということを君に強調しておきたい。彼は窓から降り、一人か、あるいは誰かと一緒に出て行った。これは確かだ。」
私は同意した。
「さて、今度はこの不運なドイツ人教師に目を向けよう。少年は逃げ出す時、完全に服を着ていた。つまり、自分の行動を予期していたわけだ。だが、ドイツ人教師は靴下も履いていなかった。彼が行動を起こしたのは、間違いなく非常に急だった。」
「間違いありません。」
「なぜ彼は出て行ったのか? 寝室の窓から少年が逃げるのを見て、彼を追いかけて連れ戻そうとしたからだ。彼は自転車を掴み、少年を追跡し、その追跡のさなかに死を迎えた。」
「そのように思えます。」
「ここからが私の議論の核心だ。小さな少年を追う男の自然な行動は、走って後を追うことだろう。追いつけると分かっているからだ。だが、ドイツ人教師はそうしなかった。彼は自転車に目を向けた。聞くところによれば、彼は優れた自転車乗りだったという。少年が何か素早い逃走手段を持っているのを見なければ、彼はそうはしなかったはずだ。」
「もう一台の自転車ですね。」
「再現を続けよう。彼は学校から五マイルの地点で死を迎える。いいか、弾丸ではない。少年でも撃てなくはない弾丸ではなく、屈強な腕による残忍な一撃によってだ。とすれば、少年には逃走の供がいた。そして、その逃走は迅速だった。熟練の自転車乗りが追いつくのに五マイルもかかったのだから。しかし、我々は悲劇の現場周辺の地面を調査した。何が見つかった? 牛の足跡がいくつか、それだけだ。私は広範囲をぐるりと見回したが、五十ヤード以内に小道はない。もう一人の自転車乗りが実際の殺害に関与したとは考えられないし、人間の足跡もなかった。」
「ホームズ」私は叫んだ。「そんなことは不可能です。」
「素晴らしい!」と彼は言った。「実に明快な指摘だ。私の述べた通りでは不可能だ。したがって、私はどこかで述べ方を間違えたに違いない。しかし、君も自分の目で見たはずだ。何か誤りを示唆できるかね?」
「転倒して頭蓋骨を骨折したとは考えられませんか?」
「沼地でかね、ワトソン君?」
「お手上げです。」
「まあ、まあ、我々はもっと厄介な問題を解決してきたじゃないか。少なくとも材料は豊富にある、あとはそれをどう使うかだ。さあ、パーマーの線は尽きた。継ぎ当てのあるダンロップが我々に何をもたらしてくれるか、見てみようじゃないか。」
我々はその轍を拾い、しばらく追跡したが、やがて荒野はヒースの茂る長いカーブを描く上り坂となり、水路を後にした。もはや轍からこれ以上の助けは望めなかった。ダンロップのタイヤ痕が最後に確認できた地点からは、数マイル左手にそびえ立つホルダーネス公爵邸の壮麗な塔へ向かったとも、眼前に横たわるチェスターフィールド街道沿いの、低く灰色がかった村へ向かったとも考えられた。
扉の上に闘鶏の看板を掲げた、陰気でみすぼらしい宿屋に近づいた時、ホームズが突然うめき声を上げ、倒れそうになるのをこらえるように私の肩を掴んだ。彼は足首をひどく捻挫し、動けなくなるほどだった。彼は困難な様子でびっこを引きながらドアまで進んだ。そこでは、ずんぐりした色黒の初老の男が黒い陶製のパイプをふかしていた。
「ごきげんよう、ルーベン・ヘイズさん」とホームズは言った。
「あんたは誰だ、どうして俺の名前を知ってる?」田舎男は、狡猾そうな目を疑わしげに光らせて答えた。
「なに、頭の上の看板に書いてありますから。ご自分の家の主人であることは一目瞭然です。ところで、馬小屋に馬車のようなものはありませんかね?」
「ないね。」
「足を地面につけるのもやっとでして。」
「じゃあ、つけなきゃいい。」
「しかし、歩けません。」
「なら、片足で跳べばいい。」
ルーベン・ヘイズ氏の態度は愛想の欠片もなかったが、ホームズは見事な上機嫌でそれを受け流した。
「まあ、聞いてください」と彼は言った。「これは実に厄介な状況でしてね。どうやって進むかは問いません。」
「俺も問わんね」と不機嫌な主人は言った。
「非常に重要な用件なのです。自転車を貸していただけるなら、一ソブリン差し上げましょう。」
主人はぴくりと耳を動かした。
「どこへ行きたいんだ?」
「ホルダーネス公爵邸へ。」
「公爵様のお仲間かい?」主人は我々の泥まみれの服を皮肉な目つきで眺めながら言った。
ホームズは人の好さそうな笑みを浮かべた。
「いずれにせよ、我々に会えば喜んでくださるでしょう。」
「なぜだ?」
「行方不明の御子息の知らせを持ってきましたから。」
主人は明らかにぎくりとした。
「なんだって、足取りが分かったのか?」
「リヴァプールで目撃情報があったそうです。今にも見つかるでしょう。」
再び、無精髭の生えた重々しい顔にさっと変化がよぎった。彼の態度は、突然愛想が良くなった。
「俺は、たいていの人間より公爵様の幸運を願う筋合いはないんだ」と彼は言った。「昔、そこのお抱え御者の頭だったんだが、ひどい仕打ちを受けたもんでね。嘘つきの穀物商の言葉を鵜呑みにして、推薦状もなしに俺をクビにしたのはあの人だ。だが、若君がリヴァプールで見つかったと聞いて嬉しいよ。屋敷まで知らせを届ける手伝いをしよう。」
「ありがとうございます」とホームズは言った。「まずは食事をいただきましょう。それから自転車を持ってきてください。」
「自転車はない。」
ホームズは一ソブリン金貨を掲げた。
「だから、ないと言ってるだろう。屋敷までなら馬を二頭貸してやる。」
「まあ、まあ」とホームズは言った。「食事を済ませてから話しましょう。」
石畳の台所に二人きりになると、捻挫したはずの足首が驚くほど急速に回復した。日も暮れかかり、我々は早朝から何も口にしていなかったので、食事にしばらく時間をかけた。ホームズは物思いに沈み、一度か二度、窓辺へ歩み寄っては真剣な眼差しで外を見つめた。窓はみすぼらしい中庭に面していた。遠い隅には鍛冶場があり、煤けた少年が働いている。反対側には馬小屋があった。そんな風に何度か窓辺に行った後、ホームズが再び席に着いたかと思うと、突然、大声で叫びながら椅子から飛び上がった。
「まさしく! ワトソン、分かったぞ!」彼は叫んだ。「そうだ、そうに違いない。ワトソン、今日、牛の足跡を見たのを覚えているか?」
「ええ、何度か。」
「どこで?」
「そうですね、至る所で。沼地にも、小道にも、そして気の毒なハイデガーが死んだ場所の近くにもありました。」
「その通り。では、ワトソン、荒野で牛を何頭見た?」
「一頭も見ていないと思いますが。」
「奇妙だ、ワトソン。我々の通った道筋にはずっと足跡があったのに、荒野全体で牛を一頭も見かけないとは。実に奇妙だとは思わんかね、ワトソン?」
「ええ、奇妙です。」
「さあ、ワトソン、よく思い出してみるんだ。小道にあったあの足跡を思い浮かべられるか?」
「ええ、できます。」
「足跡が、時にはこんな風だったのを思い出せるかね、ワトソン」――彼はパンくずをいくつか並べてみせた――「:::::」――「そして時にはこう」――「:.:.:.:.」――「そして時折こうだ」――「.・.・.・」。「思い出せるかね?」
「いいえ、思い出せません。」
「だが、私にはできる。断言してもいい。まあ、後でゆっくり戻って確認しよう。結論を導き出せなかったとは、私もなんて目が節穴だったんだ。」
「それで、あなたの結論は?」
「並足も、駆け足も、襲歩もできる、実に驚くべき牛だということさ。何ということだ、ワトソン! こんな目くらましを考えつくとは、田舎の宿屋の主人の知恵ではないぞ。鍛冶場の少年以外、人けはないようだ。こっそり抜け出して、何が見えるか確かめてみよう。」
今にも崩れそうな馬小屋には、毛並みの荒い、手入れのされていない馬が二頭いた。ホームズはそのうちの一頭の後ろ脚を持ち上げ、大声で笑った。
「古い蹄鉄だが、打ったのは新しい。古い蹄鉄に、新しい釘。この事件は古典的名作になるぞ。さあ、鍛冶場へ行こう。」
少年は我々に構わず仕事を続けていた。私は、ホームズの目が床に散らばった鉄屑や木屑の間を右へ左へと素早く動くのを見た。しかし突然、我々の背後に足音が聞こえた。宿屋の主人だった。太い眉は獰猛な目の上に吊り上がり、浅黒い顔は激情に歪んでいた。手には先端に金属のついた短い杖を握り、あまりに威嚇的な様子で進んでくるので、ポケットの拳銃の感触が心底ありがたかった。
「このスパイどもめ!」男は叫んだ。「そこで何をしている!」
「おやおや、ルーベン・ヘイズさん」ホームズは冷静に言った。「まるで我々に何か見つけられるのを恐れているように見えますな。」
男は必死の努力で自分を取り繕い、引き結んでいた口元を歪めて作り笑いを浮かべた。それは、彼のしかめ面よりもなお不気味だった。
「俺の鍛冶場で何を見つけようとあんたらの勝手だ」と彼は言った。「だがな、旦那、俺の場所に勝手に嗅ぎ回られるのは気に入らねえ。とっとと勘定を済ませて出て行ってくれる方が、こっちもありがたいんだ。」
「分かりましたよ、ヘイズさん。悪気はありません」とホームズは言った。「あなたの馬を拝見していましたが、やはり歩くことにします。それほど遠くはないでしょうから。」
「屋敷の門まで二マイルもない。左の道だ。」
彼は我々がその敷地を出るまで、不機嫌な目つきで見送っていた。
我々は道をそれほど進まなかった。カーブで宿屋の主人の視界から隠れた途端、ホームズが立ち止まったからだ。
「子供の遊びで言う『熱い』状態だったな、あの宿屋では」と彼は言った。「ここから一歩離れるごとに『冷たく』なっていくようだ。いや、いや、とても離れるわけにはいかない。」
「確信しました」と私は言った。「あのルーベン・ヘイズは全てを知っています。あれほど分かりやすい悪党は見たことがありません。」
「ほう! 君にはそう映ったかね? 馬がいて、鍛冶場がある。ああ、実に興味深い場所だ、この『闘鶏亭』は。目立たないように、もう一度見てみることにしよう。」
灰色の石灰岩の巨石が点在する、長く続く丘の斜面が我々の背後に広がっていた。我々は道を外れ、丘を登っていた。その時、ホルダーネス公爵邸の方角に目をやると、一台の自転車が猛スピードでやってくるのが見えた。
「伏せろ、ワトソン!」ホームズは私の肩に重い手を置きながら叫んだ。我々が身を隠すか隠さないかのうちに、男は道を飛ぶように通り過ぎていった。舞い上がる砂埃の中、私は青ざめ、動揺した顔を垣間見た。その顔のあらゆる線に恐怖が刻まれ、口は開き、目は狂ったように前方を凝視していた。それは、昨夜見た小粋なジェイムズ・ワイルダー氏の、どこか奇怪な風刺画のようだった。
「公爵の秘書だ!」ホームズは叫んだ。「来い、ワトソン。彼が何をするか見てみよう。」
我々は岩から岩へと這うように進み、数分後には宿屋の正面玄関が見える場所までたどり着いた。ワイルダーの自転車がその脇の壁に立てかけられていた。家の周りには人影はなく、窓に顔が覗くこともなかった。ホルダーネス公爵邸の高い塔の向こうに太陽が沈むと、ゆっくりと黄昏が忍び寄ってきた。そして、薄闇の中、宿屋の馬小屋の庭で二輪馬車の両側のランプが灯るのが見え、間もなく蹄の音が響き渡ると、馬車は街道へ躍り出て、チェスターフィールドの方角へ猛烈な速さで走り去っていった。
「あれをどう思う、ワトソン?」ホームズは囁いた。
「逃亡のように見えます。」
「私が見た限りでは、軽装馬車に男が一人。まあ、ジェイムズ・ワイルダー氏ではなかったことは確かだ。ほら、彼がドアのところにいる。」
暗闇から赤い四角い光が浮かび上がった。その中央に、秘書の黒い人影があった。彼は頭を突き出し、夜の闇を覗き込んでいる。誰かを待っているのは明らかだった。やがて、街道に足音が聞こえ、光を背に第二の人影が一瞬見えたかと思うと、ドアが閉まり、再び全てが闇に包まれた。五分後、二階の部屋にランプが灯された。
「『闘鶏亭』は、どうやら奇妙な客筋を相手にしているようだ」とホームズは言った。
「酒場は反対側です。」
「その通り。いわば、内々の客というわけだ。さて、ジェイムズ・ワイルダー氏は一体全体、夜更けにあの巣窟で何をしているのか。そして、彼に会いに来た連れとは誰なのか? 来い、ワトソン、ここはひとつ危険を冒して、もう少し詳しく調べてみる必要がある。」
我々は二人でこっそりと道へ下り、忍び足で宿屋のドアまで渡った。自転車はまだ壁に立てかけられたままだった。ホームズがマッチを擦って後輪にかざすと、継ぎ当てのあるダンロップのタイヤに光が当たり、彼がくすくすと笑うのが聞こえた。我々の頭上には、明かりの灯った窓があった。
「あれを覗かねばならん、ワトソン。君が背をかがめて壁に手をついてくれれば、私なら何とかなると思う。」
次の瞬間、彼の足は私の肩の上にあったが、登りきるか登りきらないかのうちに、彼は再び降りてきた。
「さあ、友よ」と彼は言った。「今日一日の仕事はもう十分だ。得られるものは全て得たと思う。学校までは長い道のりだ、早く出発するに越したことはない。」
疲れる荒野の道のりを歩いている間、彼はほとんど口を開かなかった。学校に着いても中には入らず、マックルトン駅へ向かい、そこからいくつかの電報を打った。夜遅く、教師の死という悲劇に打ちのめされたハクスタブル博士を彼が慰めているのが聞こえ、さらに後になって、彼は朝出発した時と同じように鋭敏で活力に満ちた様子で私の部屋に入ってきた。「万事順調だ、友よ」と彼は言った。「明日の夕方までには、我々がこの謎の真相にたどり着くことを約束しよう。」
翌朝十一時、友と私はホルダーネス公爵邸の有名なイチイの並木道を歩いていた。我々は壮麗なエリザベス朝様式の玄関を通り、公爵閣下の書斎へと案内された。そこにはジェイムズ・ワイルダー氏がいた。物静かで丁寧な態度だったが、その挙動不審な目つきと引きつった顔つきには、昨夜の狂乱的な恐怖の痕跡がまだ潜んでいた。
「閣下にお会いに? 申し訳ありませんが、実は公爵はひどくご気分が優れないのです。悲劇的な知らせに大変動揺されておりまして。昨日の午後、ハクスタブル博士から電報を受け取り、あなた方の発見を知りました。」
「公爵にお会いしなければなりません、ワイルダーさん。」
「しかし、閣下はお部屋に。」
「では、お部屋まで伺います。」
「寝台におられるかと。」
「そこでお会いします。」
ホームズの冷徹で断固とした態度に、秘書は言い争っても無駄だと悟った。
「かしこまりました、ホームズさん。閣下にお伝えします。」
一時間ほど待たされた後、大貴族が現れた。その顔は以前にも増して死人のように青ざめ、肩は丸まり、私には前日の朝よりもずっと老け込んだように見えた。彼は荘重な礼儀正しさで我々に挨拶し、机に着席した。その赤い髭がテーブルの上に流れ落ちていた。
「さて、ホームズさん?」と彼は言った。
しかし、友の目は主人の椅子のそばに立つ秘書に注がれていた。
「閣下、ワイルダーさんがご不在の方が、もっと自由に話せるかと存じます。」
男は一層青ざめ、ホームズに悪意のこもった視線を投げかけた。
「閣下がそうお望みなら――」
「ああ、そうだ、下がってくれ。さて、ホームズさん、話とは何だ?」
友は、退室する秘書の後ろでドアが閉まるのを待った。
「実は、閣下」と彼は言った。「同僚のワトソン博士と私は、この事件に懸賞金がかけられているとハクスタブル博士から伺っております。閣下ご自身の口から、それを確かめさせていただきたい。」
「その通りだ、ホームズさん。」
「私の聞き及んだところが正しければ、御子息の居場所を知らせた者に五千ポンド、ということでよろしいですかな?」
「その通りだ。」
「そして、彼を監禁している人物の名を告げた者には、さらに千ポンド?」
「その通り。」
「後者の項目には、疑いなく、彼を連れ去った者だけでなく、彼を現在の状況に置き続けることを共謀している者も含まれますな?」
「そうだ、そうだ!」公爵は焦れたように叫んだ。「仕事を見事にやり遂げたなら、シャーロック・ホームズさん、待遇に不満を漏らすことにはならんはずだ。」
友は、彼の質素な趣味を知っている私には驚きだったが、貪欲そうな様子でその細い両手をこすり合わせた。
「テーブルの上に閣下の小切手帳が見えるようですが」と彼は言った。「六千ポンドの小切手を一枚、私宛に振り出していただけるとありがたい。横線を引いていただけると、なおよろしいかと。私の取引銀行は、首都州銀行オックスフォード街支店です。」
閣下は椅子に厳格に背筋を伸ばして座り、石のような表情で友を見つめた。
「冗談かね、ホームズさん? 冗談を言うような話題ではあるまい。」
「とんでもない、閣下。これほど真剣なことは生涯ございません。」
「では、どういう意味だ?」
「私が懸賞金を得る資格がある、という意味です。御子息の居場所は存じておりますし、彼を拘束している者についても、少なくとも一部は存じております。」
公爵の髭は、その死人のように白い顔を背景に、これまで以上に攻撃的な赤色を帯びていた。
「どこにいる?」彼は喘ぐように言った。
「あなたの屋敷の門から二マイルほどの『闘鶏亭』という宿屋に。少なくとも、昨夜までは。」
公爵は椅子に崩れ落ちた。
「そして、誰を告発するのか?」
シャーロック・ホームズの答えは驚くべきものだった。彼は素早く前に進み出て、公爵の肩に触れた。
「私が告発するのは、あなたです」と彼は言った。「さて、閣下、例の小切手をお願いします。」
飛び上がって、奈落の底に沈む者のように両手で虚空を掻きむしった公爵の姿を、私は決して忘れまい。それから、貴族としての並外れた自制心で、彼は再び腰を下ろし、両手で顔を覆った。彼が口を開くまで、数分の時が流れた。
「どこまで知っている?」彼はついに、顔を上げずに尋ねた。
「昨夜、お二人が一緒にいるのを見ました。」
「君の友人の他に、誰か知っている者は?」
「誰にも話しておりません。」
公爵は震える指でペンを取り、小切手帳を開いた。
「約束は守ろう、ホームズさん。君が得た情報が私にとってどれほど歓迎されざるものであろうと、小切手を書こう。最初に懸賞金を申し出た時、事態がこのような展開になるとは夢にも思わなかった。しかし、君と君の友人は、分別のある人間だろうな、ホームズさん?」
「閣下のおっしゃることがよく分かりかねます。」
「はっきり言わねばならんな、ホームズさん。この一件を知っているのが君たち二人だけなら、これ以上話が広まる理由はない。私が君に支払うべきは、一万二千ポンドということになるのではないかね?」
しかし、ホームズは微笑んで首を振った。
「恐れながら閣下、事はそう簡単には収まりそうにありません。あの教師の死の説明がついておりません。」
「だが、ジェイムズは何も知らなかった。彼にその責任を問うことはできまい。あれは、彼が不運にも雇ってしまった、あの残忍な悪党の仕業だ。」
「閣下、私はこう考えざるを得ません。ある人間が犯罪に手を染めた時、そこから派生するいかなる犯罪に対しても、道義的な責任を負うと。」
「道義的には、ホームズさん。君の言う通りだろう。だが、法の目から見れば違うはずだ。その場におらず、君と同じくらいその行為を憎み、忌み嫌っている殺人罪で、人間が断罪されることはない。それを聞いた途端、彼は恐怖と悔恨に満たされ、私に全てを告白した。そして、一刻の猶予もなく殺人者と完全に手を切った。おお、ホームズさん、彼を救ってくれ――彼を救ってくれ! 君に彼を救ってもらわねばならんのだ!」
公爵は最後の自制心をかなぐり捨て、引きつった顔で部屋を歩き回り、握りしめた拳を空中で振り回していた。やがて彼は自分を取り戻し、再び机に着席した。「誰にも話す前にここへ来てくれた君の行動に感謝する」と彼は言った。「少なくとも、この忌まわしい醜聞をどこまで小さくできるか、相談することはできるだろう。」
「その通りです」とホームズは言った。「閣下、それは我々が互いに全てを包み隠さず話すことによってのみ可能だと思います。私は力の及ぶ限り閣下をお助けするつもりですが、そのためには、事の次第を細部まで理解せねばなりません。閣下のお言葉がジェイムズ・ワイルダー氏に向けられたものであり、彼が殺人者ではないことは承知しております。」
「ああ、殺人者は逃亡した。」
シャーロック・ホームズは控えめに微笑んだ。
「閣下は、私のささやかな評判をほとんどお聞きになったことがないようですな。さもなくば、私から逃げ切ることがそれほど容易だとはお考えにならないでしょう。ルーベン・ヘイズ氏は昨夜十一時、私の情報に基づき、チェスターフィールドで逮捕されました。今朝、学校を出る前に、地元警察の署長から電報を受け取っております。」
公爵は椅子に背をもたせ、驚愕の表情で友を見つめた。
「君はほとんど人間離れした力を持っているようだ」と彼は言った。「ルーベン・ヘイズが捕まったと? ジェイムズの運命に影響しないのであれば、それを聞いて実に嬉しい。」
「あなたの秘書のですか?」
「いや、我が息子のだ。」
今度はホームズが驚く番だった。
「告白しますが、それは全くの初耳です、閣下。どうか、もっと詳しくお話しください。」
「君には何も隠すまい。君の言う通り、完全な率直さこそが、たとえ私にとってどれほど辛いものであろうと、ジェイムズの愚かさと嫉妬が我々を陥れたこの絶望的な状況における最善の策だろう。私がまだ若かった頃、ホームズさん、生涯に一度きりの恋をした。私はその女性に結婚を申し込んだが、彼女は、そのような結婚は私のキャリアを傷つけるだろうという理由で断った。もし彼女が生きていれば、私は決して他の誰とも結婚しなかっただろう。彼女は亡くなり、この一人の子供を残した。私は彼女のために、その子を慈しみ、育ててきた。世間に対して父であることを認めることはできなかったが、最高の教育を与え、成人してからは私のそばに置いた。彼は私の秘密を察し、それ以来、私に対する自分の権利と、私にとって忌まわしい醜聞を引き起こす力とを盾に、つけあがってきた。彼の存在は、私の不幸な結婚生活の一因でもあった。何よりも、彼は私の若い嫡出の跡継ぎを、最初から執拗な憎しみで憎んでいた。このような状況下で、なぜ私がジェイムズを屋敷に置き続けたのか、君は疑問に思うだろう。答えは、彼の顔に彼の母親の面影を見出し、その愛しい人のために、私の忍耐には際限がなかったからだ。彼女の愛らしい仕草の数々も――彼がそれを思い出させないものは一つもなかった。私は彼を追い出すことなどできなかった。だが、彼がアーサー――すなわちソルタイア卿――に危害を加えることをあまりに恐れたため、安全のためにハクスタブル博士の学校へやったのだ。
「ジェイムズがこのヘイズという男と接触するようになったのは、男が私の借地人で、ジェイムズが代理人を務めていたからだ。男は最初から悪党だったが、どういうわけか、ジェイムズは彼と親密になった。彼は昔から下賤な仲間を好む傾向があった。ジェイムズがソルタイア卿を誘拐しようと決心した時、彼が頼ったのがこの男だった。私が最後の日、アーサーに手紙を書いたのを覚えているかね。さて、ジェイムズはその手紙を開封し、学校の近くにあるラギッド・ショーという小さな森で会うようアーサーに求めるメモを差し込んだ。彼は公爵夫人の名を使い、そのようにして少年を来させた。その晩、ジェイムズは自転車でやってきて――これは彼自身が私に告白したことだ――森で会ったアーサーに、母親が会いたがっていること、荒野で待っていること、そして真夜中に森に戻ってくれば、馬を連れた男がいて、母親のところへ連れて行ってくれるだろうと告げた。哀れなアーサーは罠にかかった。彼は約束の場所へ行き、手綱を引かれたポニーと一緒のヘイズという男を見つけた。アーサーは馬に乗り、二人は共に出発した。どうやら――これはジェイムズも昨日聞いたことだが――彼らは追跡され、ヘイズが追跡者を杖で殴り、その男は傷がもとで死んだらしい。ヘイズはアーサーを自分の宿屋『闘鶏亭』へ連れて行き、二階の部屋に閉じ込めた。世話をしたのはヘイズ夫人で、彼女は親切な女だが、残忍な夫の完全な支配下にあった。
「さて、ホームズさん、これが二日前に私が君に初めて会った時の状況だ。私は君と同じくらい、真相については何も知らなかった。ジェイムズがなぜこのような行為に及んだのか、その動機を君は問うだろう。答えは、彼が私の跡継ぎに抱いていた憎しみには、理不尽で狂信的な部分が多々あったということだ。彼の考えでは、自分こそが私の全財産の相続人であるべきで、それを不可能にする社会の法を深く恨んでいた。同時に、彼には明確な動機もあった。彼は私が限嗣相続を廃止することを熱望しており、私にはそれが可能だと考えていた。彼は私と取引をするつもりだったのだ。もし私が限嗣相続を廃止すればアーサーを返し、そうすれば遺言によって財産が彼に残される可能性が生まれると。彼は、私が決して自ら警察の助けを借りて彼を追及することはないとよく知っていた。彼は私にそのような取引を提案するつもりだっただろうが、実際にはしなかった。事態の展開が彼にとってあまりに速く、計画を実行に移す時間がなかったのだ。
「彼の邪悪な計画を全て破綻させたのは、君がこのハイデガーという男の死体を発見したことだった。ジェイムズはその知らせに恐怖に襲われた。それは昨日、我々がこの書斎で共に座っている時に届いた。ハクスタブル博士が電報を送ってきたのだ。ジェイムズは悲嘆と動揺にあまりに打ちのめされていたので、私の疑念――それは完全には消えていなかったが――は即座に確信へと変わり、私は彼にその行為を問い詰めた。彼は完全に自発的な告白をした。それから、哀れな共犯者に罪深い命を救う機会を与えるため、あと三日間秘密を守ってくれるよう私に懇願した。私は――これまで常にそうしてきたように――彼の祈りに屈し、ジェイムズは即座に『闘鶏亭』へ急ぎ、ヘイズに警告し、逃亡の手段を与えた。私が日中にそこへ行けば憶測を呼ぶだろうから行けなかったが、夜になるとすぐに、愛しいアーサーに会うために急いだ。彼は無事で元気だったが、目撃した恐ろしい出来事に言葉にできないほど怯えていた。私は約束を尊重し、大いに不本意ながら、彼を三日間そこに、ヘイズ夫人の世話の下に置くことに同意した。彼の居場所を警察に知らせることは、同時に殺人者が誰であるかを告げることなしには不可能であり、その殺人者を罰することが、私の不運なジェイムズを破滅させることなしにどうして可能か、私には分からなかったからだ。君は率直さを求めた、ホームズさん。私はその言葉通り、今や一切の回りくどい言い方や隠し立てをせずに全てを話した。今度は君が私に対して同じように率直であってくれ。」
「そうしましょう」とホームズは言った。「まず第一に、閣下、あなたは法的に見て極めて深刻な立場に身を置かれたことをお伝えせねばなりません。あなたは重罪を黙認し、殺人者の逃亡を幇助した。ジェイムズ・ワイルダーが共犯者の逃亡を助けるために持っていった金銭が、閣下の財布から出たものであることは疑いようがありませんからな。」
公爵は同意して頭を下げた。
「これは、実に深刻な問題です。私の意見では、さらに罪深いのは、閣下の年少の御子息に対する態度です。あなたはこの巣窟に彼を三日間も放置した。」
「厳粛な約束の下に――」
「このような連中にとって、約束とは何ですか? 彼が再び連れ去られないという保証はどこにもない。罪ある年長の息子の機嫌を取るために、あなたは罪なき年少の息子を、差し迫った不必要な危険に晒した。全くもって正当化できない行為です。」
誇り高きホルダーネスの主は、自らの公爵邸でこのように叱責されることには慣れていなかった。血がその高い額に上ったが、良心が彼を沈黙させた。
「お助けしましょう。ただし、条件が一つだけあります。従僕を呼び鈴で呼び、私に好きなように命令を出させてください。」
一言もなく、公爵は電鈴を押した。使用人が入ってきた。
「喜んで聞きたまえ」とホームズは言った。「若様が見つかった。公爵のご意向により、馬車を直ちに『闘鶏亭』へ向かわせ、ソルタイア卿をお連れするように。」
「さて」喜びに沸く従僕が姿を消すと、ホームズは言った。「未来を確保したからには、過去に対してはより寛大になれる。私は公的な立場にはなく、正義の目的が果たされる限り、私が知る全てを暴露する理由はありません。ヘイズについては、何も言うことはない。絞首台が彼を待っており、私は彼をそこから救うために何もしないでしょう。彼が何を漏らすかは分かりませんが、閣下なら、沈黙することが彼の利益になると彼に理解させることができるに違いありません。警察の見地からすれば、彼は身代金目的で少年を誘拐したことになるでしょう。彼らが自らそれ以上のことを見つけ出さない限り、私がより広い視点を持つよう促す理由はありません。しかし、閣下には警告しておきます。ジェイムズ・ワイルダー氏が今後もあなたのお屋敷に留まることは、不幸を招くだけです。」
「それは理解している、ホームズさん。そして、彼が永久に私の元を去り、オーストラリアで一旗揚げに行くことは既に決まっている。」
「それならば、閣下、ご自身の結婚生活におけるいかなる不幸も彼の存在が原因であったと述べられたからには、公爵夫人にできる限りの償いをし、不幸にも中断されてしまった関係を再開するよう努められることをお勧めします。」
「それも手配済みだ、ホームズさん。今朝、公爵夫人に手紙を書いた。」
「それならば」ホームズは立ち上がりながら言った。「友と私は、この北へのささやかな訪問から得られたいくつかの実に喜ばしい結果を祝うことができると思います。もう一つ、解明したい小さな点があります。このヘイズという男は、牛の足跡を偽装する蹄鉄を馬に履かせていました。このような並外れた工夫を、彼はワイルダー氏から学んだのでしょうか?」
公爵は、顔に強い驚きの表情を浮かべ、一瞬考え込んだ。それからドアを開け、我々を博物館のように設えられた広い部屋へ案内した。彼は隅にあるガラスケースへ先導し、その銘板を指さした。
「この蹄鉄は」とそこにはあった。「ホルダーネス・ホールの堀から発掘されたものである。馬に使用されるものだが、下部は鉄製の割れた蹄の形をしており、追っ手を欺くためのものである。中世の略奪を事としたホルダーネスの男爵たちの所有物であったと推定される。」
ホームズはケースを開け、指を湿らせて蹄鉄に沿って滑らせた。彼の皮膚には、新しい泥の薄い膜が残った。
「ありがとうございます」彼はガラスを元に戻しながら言った。「これは、私が北部で見た中で二番目に興味深い品です。」
「では、一番目は?」
ホームズは小切手を折りたたみ、注意深く手帳にしまった。「私は貧しい男ですから」彼はそれを愛おしそうに叩き、内ポケットの奥深くへと押し込みながら言った。
黒ピーターの冒険
一八九五年の友人ほど、心身ともに絶好調だった彼を私は知らない。高まる名声は膨大な依頼をもたらし、ベーカー街の我々の質素な玄関をまたいだ高名な依頼人たちの正体をほのめかすことすら、私の軽率のそしりを免れないだろう。しかし、ホームズは、全ての偉大な芸術家がそうであるように、自らの芸術のために生きていた。ホルダーネス公爵の事件を除けば、彼がその計り知れない貢献に対して多額の報酬を要求するのを、私は滅多に見たことがない。彼はそれほど世俗に疎い――あるいは気まぐれ――であり、問題が彼の共感を呼ばない場合には、権力者や富豪からの助力を頻繁に断る一方で、その事件が彼の想像力をかき立て、彼の創意工夫に挑戦するような、奇妙で劇的な性質を呈している場合には、名もない依頼人のために何週間も没頭することもあった。
この記念すべき一八九五年には、奇妙で脈絡のない一連の事件が彼の注意を引いていた。ローマ教皇聖下ご自身のたっての願いで遂行された、トスカ枢機卿の急死に関する有名な調査から、ロンドンのイーストエンドから一つの悪の巣を取り除いた、悪名高きカナリア調教師ウィルソンの逮捕に至るまで、その範囲は多岐にわたった。これら二つの有名な事件に引き続いて起こったのが、ウッドマンズ・リーの悲劇であり、ピーター・ケアリー船長の死を取り巻く、極めて不可解な状況であった。シャーロック・ホームズ氏の業績の記録は、この実に稀有な事件の記述を抜きにしては完結しないだろう。
七月の第一週、友人は我々の下宿を頻繁に、そして長時間留守にしていたので、何か事件を手がけていることは分かっていた。その間、何人かの人相の悪い男たちが訪ねてきては「バジル船長」を尋ねていったことから、ホームズが数多ある変装と偽名の一つを使い、その恐るべき正体を隠してどこかで活動しているのだと察しがついた。彼はロンドンの各所に少なくとも五つの小さな隠れ家を持っており、そこで自在に人格を変えることができたのだ。彼は自分の仕事について何も語らず、私も無理に聞き出すような真似はしなかった。彼が捜査の方向性について私に示してくれた最初の明確な兆候は、実に突拍子もないものだった。彼は朝食前に出かけており、私が食事を始めようと席に着いたところへ、帽子をかぶったまま大股で部屋に入ってきた。その脇には、傘のように巨大な銛が挟まれていた。
「なんてことだ、ホームズ!」私は叫んだ。「まさか、そんな物を持ってロンドンを歩き回っていたわけではあるまいな?」
「肉屋まで馬車で行って、帰ってきたところだ。」
「肉屋へ?」
「おかげで食欲も旺盛だ。朝食前の運動がいかに価値あるものか、これに異論はあるまい、ワトソン君。だが、賭けてもいいが、私がどんな運動をしてきたか、君には当てられまいよ。」
「当てようとも思わんよ。」
彼はコーヒーを注ぎながら、くすくすと笑った。「もし君がアラーダイスの店の裏手を見ることができたなら、天井の鉤から吊るされた豚の死骸と、シャツ一枚でその豚にこの武器を猛然と突き立てている紳士の姿を目にしただろう。その精力的な人物こそが私で、いかなる腕力をもってしても、一撃で豚を串刺しにすることは不可能だと確信したところだ。君も試してみるかね?」
「とんでもない。しかし、なぜそんなことを?」
「ウッドマンズ・リーの謎に間接的な関わりがあると思えたからだ。おお、ホプキンス君、昨夜電報を受け取った。君が来るのを待っていたよ。さあ、一緒にどうかね。」
我々の訪問者は三十歳ほどの、極めて敏腕そうな男だった。落ち着いたツイードのスーツを着ていたが、制服に慣れた者特有の、背筋の伸びた立ち居振る舞いは隠せない。私はすぐに彼がスタンリー・ホプキンス、若き警部だと分かった。ホームズがその将来に大きな期待を寄せている人物であり、一方の彼もまた、この高名な素人探偵の科学的手法に対し、弟子のような称賛と尊敬の念を公言していた。ホプキンスの額には憂色が浮かび、深い落胆の様子で腰を下ろした。
「いえ、結構です。こちらへ来る前に済ませました。昨日は報告のために上京し、そのまま市内に泊まりましたので。」
「それで、報告の内容は?」
「失敗です、完全な失敗です。」
「進展なしかね?」
「皆無です。」
「ほう! それは私が一肌脱がねばなるまいな。」
「ぜひ、お願いしたいのです、ホームズさん。私にとって初めての大きな好機なのですが、すっかりお手上げでして。どうか、現場へ来て力を貸してください。」
「まあ、まあ、ちょうど私も、検死審問の報告書も含め、入手可能な証拠はすべて、いくらか注意深く目を通したところだ。ところで、犯行現場で見つかったあの煙草入れをどう思うかね? 何か手がかりはなかったか?」
ホプキンスは驚いた顔をした。「あれは被害者本人の煙草入れですよ。内側にイニシャルが入っていましたし。アザラシの皮製で、彼も古参の猟師でしたから。」
「だが、パイプがなかった。」
「ええ、パイプは見つかりませんでした。実際、彼はほとんど煙草を吸わなかったようですが、友人のためにいくらか持っていたのかもしれません。」
「なるほど。私がこの事件を担当していたなら、そこを捜査の出発点にしただろうと思って言ってみただけだ。ともあれ、友人のワトソン博士はこの件について何も知らないし、私としても事件の経緯をもう一度聞いても損はない。要点だけでいい、かいつまんで話してくれたまえ。」
スタンリー・ホプキンスはポケットから一枚の紙片を取り出した。「ここに、故人ピーター・ケアリー船長の経歴をまとめた日付があります。一八四五年生まれの五十歳。極めて大胆かつ有能なアザラシ・鯨猟師でした。一八八三年にはダンディー船籍の蒸気猟船シー・ユニコーン号を指揮しています。その頃、立て続けに航海を成功させ、翌一八八四年に引退。その後数年間は旅をしていましたが、最終的にサセックス州フォレスト・ロウ近郊のウッドマンズ・リーと呼ばれる小さな土地を購入しました。そこに六年間住み、そしてちょうど一週間前の今日、そこで亡くなりました。」
「この男には実に奇妙な点がありました。普段の生活では厳格なピューリタンで、無口で陰鬱な男でした。家族は妻と二十歳の娘、それに二人の女中です。この女中たちはひっきりなしに入れ替わっていました。決して楽しい職場ではなく、時には耐え難い状況になることもあったからです。男は時折大酒を飲み、ひとたび酒乱になると、まさに悪魔そのものでした。真夜中に妻と娘を家から叩き出し、屋敷の門の外の村中が彼女たちの悲鳴で目を覚ますまで、庭中を引きずり回して鞭打ったこともあったそうです。」
「一度、彼の素行を諫めようと訪ねてきた老牧師に凶暴な暴行を働き、召喚されたこともあります。要するに、ホームズさん、ピーター・ケアリーほどの危険人物を見つけるのは至難の業でしょう。船を指揮していた頃も同じ性格だったと聞いています。仲間内では『ブラック・ピーター』として知られており、その名は日焼けした顔立ちや巨大な髭の色だけでなく、周囲の者すべてを恐怖に陥れたその気性からつけられたものでした。言うまでもなく、彼は近隣の誰からも忌み嫌われ、避けられていましたし、その悲惨な最期を悼む言葉は一言も耳にしていません。」
「検死審問の記録で、男の小屋についてはお読みになったでしょう、ホームズさん。ですが、こちらのご友人はご存じないかもしれません。彼は母屋から数百ヤード離れた場所に木造の離れを建て、常にそこを『船室』と呼んでいました。そして毎晩そこで寝ていたのです。十六フィート×十フィートほどの、一部屋だけの小さな小屋でした。鍵は自分で持ち、寝床も自分で整え、掃除も自分でこなし、自分以外の者が敷居をまたぐことを許しませんでした。両側に小さな窓がありましたが、カーテンで覆われ、開けられることはありませんでした。窓の一つは街道に面しており、夜、そこに明かりが灯ると、人々は互いにそれを指さし、ブラック・ピーターが中で何をしているのかと噂したものです。その窓こそが、ホームズさん、検死審問で得られた数少ない確かな証拠の一つをもたらしてくれたのです。」
「ご記憶でしょうが、スレーターという石工が、殺人の二日前の午前一時頃、フォレスト・ロウから歩いてきて、屋敷の敷地を通り過ぎる際に立ち止まり、木々の間にまだ輝いている四角い光を見ました。彼は、ブラインドに男の横顔の影がはっきりと見え、その影は彼がよく知るピーター・ケアリーのものでは断じてなかったと断言しています。髭のある男でしたが、その髭は短く、船長のそれとは全く違う形で前方に突き出ていた、と。そう彼は証言していますが、酒場で二時間過ごした後でしたし、道から窓まではかなりの距離があります。それに、これは月曜日の話で、犯行は水曜日に行われました。」
「火曜日、ピーター・ケアリーは最悪の機嫌で、酒で顔を赤らめ、危険な野獣のように荒れ狂っていました。彼は家の中をうろつき、女たちは彼の足音を聞くと逃げ出しました。夜遅く、彼は自分の小屋へ下りていきました。翌朝二時頃、窓を開けて寝ていた娘が、その方角から恐ろしい絶叫を聞きましたが、彼が酔って大声でわめくのは珍しいことではなかったので、誰も気に留めませんでした。七時に起きた女中の一人が小屋のドアが開いているのに気づきましたが、男が与える恐怖はあまりに大きく、誰かが勇気を出して彼の様子を見に行くまで正午になっていました。開いたドアから中を覗き込んだ彼女たちは、ある光景を目にし、真っ青な顔で村へ飛んで逃げ帰りました。一時間以内に、私は現場に到着し、事件を引き継ぎました。」
「さて、私はご存じの通り、かなり肝が据わっている方ですが、ホームズさん、誓って言いますが、あの小さな小屋に頭を入れたときは震えが来ました。ハエやアオバエの羽音でオルガンのように唸りをあげ、床も壁もまるで屠殺場のようでした。彼はそこを船室と呼んでいましたが、まさに船室そのもので、船の中にいるかと錯覚するほどでした。一方の端には寝台、船員用の行李箱、地図に海図、シー・ユニコーン号の絵、棚には航海日誌がずらりと並び、すべてが船長室にあるべきものそのままです。そして、その中央に、男本人がいました。その顔は苦悶する亡霊のように歪み、まだらの巨大な髭は断末魔の苦しみで逆立っていました。その広い胸を鋼鉄の銛が貫き、背後の壁板に深く突き刺さっていたのです。彼は標本箱の甲虫のように壁に磔にされていました。もちろん、完全に絶命しており、あの最後の断末魔の叫びをあげた瞬間に息絶えたのでしょう。」
「あなたの手法は存じていますので、それを応用しました。何一つ動かすことを許さず、屋外の地面と室内の床を最も注意深く調べました。足跡はありませんでした。」
「君には見えなかった、という意味かね?」
「断言しますが、ありませんでした。」
「お人好しなホプキンス君、私は多くの犯罪を捜査してきたが、空飛ぶ生き物によって犯された事件にはまだ一度も出くわしたことがない。犯人が二本の足で立っている限り、科学的な探求者が見つけ出せる、何らかの窪み、擦り傷、些細な位置のずれが必ず存在するはずだ。この血まみれの部屋に、我々の助けとなる痕跡が何一つなかったとは信じがたい。だが、検死審問によれば、君が見落とさなかった物がいくつかあったようだね?」
若き警部は友人の皮肉な言葉に顔をしかめた。「あの時、あなたをお呼びしなかった私が馬鹿でした、ホームズさん。しかし、今さら悔やんでも仕方がありません。ええ、部屋には特に注意を要する物がいくつかありました。一つは犯行に使われた銛です。壁の棚からひったくられたものでした。そこには他に二本が残っており、三本目の場所が空になっていました。柄には『SS. シー・ユニコーン号、ダンディー』と刻まれています。このことから、犯行は激情に駆られた瞬間的なもので、殺人者は手近にあった最初の武器を掴んだものと思われます。犯行時刻が午前二時であるにもかかわらず、ピーター・ケアリーが普段着のままだったことは、彼が殺人者と会う約束をしていたことを示唆しており、テーブルの上にラム酒の瓶と汚れたグラスが二つあったこともそれを裏付けています。」
「うむ」とホームズは言った。「どちらの推論も妥当だろう。部屋にラム酒以外の蒸留酒はあったかね?」
「ええ、船員用の行李箱の上に、ブランデーとウィスキーが入ったタンタロス[訳注: 鍵付きの酒瓶置き]がありました。しかし、デキャンタは満たされており、使われた形跡はなかったので、我々にとっては重要ではありません。」
「それでも、それがそこにあったことには意味がある」とホームズは言った。「ともかく、君が事件に関係があると思う物について、もう少し聞かせてもらおう。」
「テーブルの上にはこの煙草入れが。」
「テーブルのどのあたりに?」
「真ん中にありました。粗いアザラシの皮でできており、毛足の短いもので、革紐で縛るようになっていました。内側の折り返し部分に『P.C.』と。中には半オンスほどの船員用の強い煙草が入っていました。」
「素晴らしい! 他には?」
スタンリー・ホプキンスはポケットからくすんだ色の表紙の手帳を取り出した。外側はざらざらで擦り切れ、ページは変色していた。最初のページには「J.H.N.」というイニシャルと「一八八三」という年号が書かれていた。
ホームズはそれをテーブルの上に置き、いつものように微細な観察を始めた。ホプキンスと私は、それぞれの肩越しに覗き込んだ。二ページ目には「C.P.R.」という印刷された文字があり、その後に何枚もの数字の羅列が続いた。別の見出しには「アルゼンチン」、また別の見出しには「コスタリカ」、「サンパウロ」とあり、それぞれの後には記号と数字のページが続いていた。
「これをどう見るかね?」とホームズが尋ねた。
「証券取引所の有価証券のリストのようです。『J.H.N.』は仲買人のイニシャルで、『C.P.R.』はその顧客かもしれません。」
「カナダ太平洋鉄道で考えてみたまえ」とホームズは言った。
スタンリー・ホプキンスは歯の間から悪態をつき、握りこぶしで自分の腿を叩いた。「なんて馬鹿だったんだ!」と彼は叫んだ。「もちろん、あなたの言う通りです。となると、解くべきは『J.H.N.』というイニシャルだけだ。すでに古い証券取引所の名簿は調べましたが、一八八三年当時、会員にも場外仲買人にも、このイニシャルに該当する者はいませんでした。しかし、これが私が握っている最も重要な手がかりだと感じています。ホームズさん、このイニシャルがその場にいた第二の人物、言い換えれば殺人者のものである可能性は認めていただけるでしょう。また、大量の有価証券に関する書類が事件に絡んできたことで、初めて犯行の動機について何らかの示唆が得られたとも言えます。」
シャーロック・ホームズの顔には、この新たな展開に完全に意表を突かれた様子が浮かんでいた。「君の二つの指摘は認めざるを得ない」と彼は言った。「正直に言うと、検死審問には出てこなかったこの手帳は、私が抱いていた見解を修正させるものだ。私が立てていた犯行の理論には、この手帳の入る余地がない。ここに記載されている有価証券の追跡は試みたのかね?」
「現在、各事務所に問い合わせていますが、これらの南米企業の完全な株主名簿は南米にあり、株を追跡できるようになるまで数週間はかかると思われます。」
ホームズは拡大鏡で手帳の表紙を調べていた。「ここに確かに変色があるな」と彼は言った。
「ええ、血痕です。床から拾ったと申し上げたはずですが。」
「血痕は上側だったか、下側だったか?」
「床板に接していた側です。」
「となれば、もちろん、この手帳が犯行後に落とされたことの証明になる。」
「その通りです、ホームズさん。その点は私も認識しており、殺人者が慌てて逃げる際に落としたものと推測しました。ドアの近くに落ちていました。」
「これらの有価証券は、故人の遺品からは見つかっていないのだろうな?」
「はい、ありません。」
「強盗を疑う理由は何かあるかね?」
「いえ。何も物色された形跡はありません。」
「なるほど、実に興味深い事件だ。それから、ナイフがあったな?」
「鞘に収まったままの鞘付きナイフです。故人の足元に落ちていました。ケアリー夫人が夫の物だと確認しています。」
ホームズはしばらく物思いに沈んでいた。「ふむ」と彼はついに口を開いた。「やはり、私が出向いてその目で確かめる必要がありそうだな。」
スタンリー・ホプキンスは喜びの声を上げた。「ありがとうございます。これで本当に肩の荷が下ります。」
ホームズは警部に向かって指を振った。「一週間前ならもっと楽な仕事だったろうがな」と彼は言った。「だが、今からでも私の訪問が全くの無駄骨に終わるとは限らない。ワトソン、もし時間があるなら、君も一緒に来てくれると嬉しい。ホプキンス君、四輪馬車を呼んでくれたまえ。十五分もすればフォレスト・ロウへ出発できるだろう。」
小さな田舎駅で降りた我々は、かつてサクソン人の侵略者を長らく食い止めた大森林の一部であった広大な森の残骸を、数マイルにわたって馬車で進んだ。それは六十年間、英国の砦となった難攻不落の「ウィールド」[訳注: イングランド南東部の森林地帯]である。この地は国内初の製鉄所の所在地であったため、広大な区域が伐採され、木々は鉱石を溶かすために切り倒された。今では北部のより豊かな鉱山地帯がその産業を吸収し、荒廃した木立と大地に残る巨大な傷跡だけが、過去の営みを物語っている。丘の緑の斜面にある開拓地に、長く低い石造りの家が建っていた。野原を貫く曲がりくねった私道がそこへ続いている。道に近く、三方を茂みに囲まれた小さな離れがあり、一つの窓とドアが我々のほうを向いていた。そこが殺人の現場だった。
スタンリー・ホプキンスはまず我々を母屋へ案内し、そこで殺された男の未亡人である、憔悴しきった白髪の女性に引き合わせた。その痩せこけ、深く皺の刻まれた顔と、赤く縁どられた瞳の奥に宿る怯えたような眼差しは、彼女が耐え忍んできた長年の苦難と虐待を物語っていた。彼女のそばには娘がいた。青白い顔をした金髪の少女で、父親が死んで嬉しい、彼を打ち倒した手に祝福あれ、と語るとき、その瞳は我々に挑戦的な炎を燃やしていた。ブラック・ピーター・ケアリーが築き上げたのは、実に恐ろしい家庭であった。再び陽光の下に出て、故人の足によって踏み固められた野原の小道を進むとき、我々は安堵の念を覚えた。
離れは、木の壁にこけら葺きの屋根という、ごく簡素な建物だった。ドアの横に一つ、奥の側にもう一つ窓がある。スタンリー・ホプキンスがポケットから鍵を取り出し、錠前にかがみこんだとき、彼は注意と驚きの表情を浮かべて動きを止めた。「誰かがこじ開けようとしています」と彼は言った。
その事実に疑いの余地はなかった。木部が削られ、その傷はペンキを通して白く見え、まるでたった今つけられたかのようだった。ホームズは窓を調べていた。「ここも誰かがこじ開けようとしたようだ。何者かは侵入に失敗したらしい。よほど腕の悪い泥棒に違いない。」
「これは実に奇妙です」と警部は言った。「昨日の夕方には、この傷はなかったと断言できます。」
「村の好奇心旺盛な者かもしれませんね」と私は提案した。
「その可能性は低いでしょう。村人でこの敷地に足を踏み入れる勇気のある者はほとんどいません。ましてや、小屋に押し入ろうとするなど。どう思われますか、ホームズさん?」
「運が我々に味方してくれていると思う。」
「その人物がまた来ると?」
「その可能性は非常に高い。彼はドアが開いているものと期待して来た。ごく小さなペンナイフの刃で入ろうとしたが、うまくいかなかった。さて、彼はどうするだろう?」
「もっと役に立つ道具を持って、次の夜にまた来るでしょう。」
「その通りだ。我々がそこで彼を待ち受けなければ、我々の落ち度ということになる。とりあえず、小屋の中を見せてくれたまえ。」
惨劇の痕跡は取り除かれていたが、小さな部屋の中の家具は犯行の夜のまま残されていた。二時間もの間、ホームズは凄まじい集中力で一つ一つの物を順に調べたが、その顔は探求が実を結んでいないことを示していた。その忍耐強い調査の中で、彼が一度だけ立ち止まった。「この棚から何か動かしたかね、ホプキンス君?」
「いえ、何も動かしていません。」
「何かが持ち去られている。棚のこの隅だけ、他よりも埃が少ない。横倒しに置かれた本だったかもしれない。箱だったかもしれない。まあいい、これ以上は何もできん。美しい森を散歩しようじゃないか、ワトソン。数時間、鳥や花と戯れよう。後でまたここで会おう、ホプキンス君。そして、夜中に訪れた紳士と、もう少し間近で対面できるか試してみよう。」
我々がささやかな待ち伏せ態勢を整えたのは、十一時を過ぎた頃だった。ホプキンスは小屋のドアを開けたままにしておくことを主張したが、ホームズはそれでは侵入者の疑いを招くと考えた。錠は極めて単純なもので、丈夫な刃物さえあれば押し戻すことができる。ホームズはまた、小屋の中ではなく、外の、奥の窓の周りに生えている茂みの中で待つことを提案した。そうすれば、もし男が明かりを灯せば監視できるし、この忍びやかな夜の訪問の目的も分かるというわけだ。
それは長く陰鬱な張り込みだったが、水辺に身を潜め、喉の渇いた猛獣の到来を待つ狩人が感じるようなスリルを伴っていた。闇の中から我々に忍び寄ってくるのは、いかなる獰猛な生き物なのか。牙と爪を閃かせて激しく戦わねば捕らえられない、凶暴な犯罪の虎か。それとも、弱く無防備な者にとってのみ危険な、こそこそと忍び寄るジャッカルの類か。
我々は完全な沈黙の中、茂みに身をかがめ、来るべきものを待ち受けた。最初は、遅れて帰る村人の足音や村から聞こえる声が張り込みの緊張を和らげてくれたが、それらの物音も一つ、また一つと消え、我々の上には完全な静寂が訪れた。ただ、夜の進行を告げる遠くの教会の鐘の音と、我々を覆う葉叢に降り注ぐ霧雨の囁きだけが聞こえていた。
二時半を告げる鐘が鳴り、夜明け前の最も暗い時間帯になったとき、門の方角から低くも鋭いカチリという音がして、我々は皆、はっとした。誰かが私道に入ってきたのだ。再び長い沈黙が続き、空振りだったかと私が思い始めたとき、小屋の向こう側から忍び足が聞こえ、一瞬後、金属が擦れるカチャカチャという音がした。男は錠をこじ開けようとしている。今度は腕が上がったか、道具が良くなったか、突然パチンという音と蝶番のきしむ音がした。そしてマッチが擦られ、次の瞬間、蝋燭の安定した光が小屋の内部を満たした。薄いカーテン越しに、我々の視線は中の光景に釘付けになった。
夜の訪問者は、華奢で痩せた若者で、黒い口髭がその死人のような顔の青白さを際立たせていた。年は二十歳を少し超えたくらいだろう。あれほど哀れなほど怯えている人間を私は見たことがない。歯がカチカチと鳴るのが見え、全身のあらゆる部分が震えていた。服装は紳士のもので、ノーフォーク・ジャケットとニッカーボッカーズを身につけ、頭には布製の帽子をかぶっていた。我々は彼が怯えた目で辺りを見回すのを見守った。やがて彼は蝋燭の燃えさしをテーブルに置き、隅の方へ姿を消した。彼が戻ってきたとき、手には大きな本、棚に並んでいた航海日誌の一冊があった。テーブルに寄りかかり、彼は目当ての項目を見つけるまで、その本のページを素早くめくった。そして、握りしめた拳で怒りの仕草を見せると、本を閉じ、隅に戻し、明かりを消した。彼が小屋を出ようと振り返るか振り返らないかのうちに、ホプキンスの手がその男の襟首を掴んだ。捕まったと悟った彼の、恐怖に引きつった息をのむ音が聞こえた。蝋燭が再び灯されると、そこには我々の哀れな捕虜が、刑事の腕の中で震え、うずくまっていた。彼は船員用の行李箱の上に崩れ落ち、助けを求めるように我々一人一人の顔を見つめた。
「さて、君」とスタンリー・ホプキンスが言った。「何者だね、そしてここで何をしていた?」
男は気を取り直し、平静を装おうと努めながら我々に向き直った。「刑事さんでしょう?」と彼は言った。「ピーター・ケアリー船長の死に関係しているとお思いでしょうが、誓って言いますが、私は無実です。」
「それは追々分かることだ」とホプキンスは言った。「まず、名前は?」
「ジョン・ホプリー・ネリガンです。」
ホームズとホプキンスが素早く視線を交わすのが見えた。「ここで何をしていた?」
「内密にお話しできますか?」
「いや、断じてならん。」
「なぜ、あなた方に話さねばならないのですか?」
「答えなければ、裁判で不利になるかもしれんぞ。」
若者は顔をしかめた。「分かりました、お話しします」と彼は言った。「話さない理由もありません。しかし、あの古い醜聞がまた蒸し返されるかと思うと……。ドーソン・アンド・ネリガンという名をお聞きになったことは?」
ホプキンスの顔から、彼が聞いたことがないのは明らかだったが、ホームズは鋭い興味を示した。「西部の銀行家のことだな」と彼は言った。「百万ポンドの負債で倒産し、コーンウォール州の半数の名家を破産させ、ネリガンは姿を消した。」
「その通りです。ネリガンは私の父です。」
ようやく確かな情報が得られたが、それでも、失踪した銀行家と、自らの銛で壁に磔にされたピーター・ケアリー船長との間には、大きな隔たりがあるように思えた。我々は皆、若者の言葉に熱心に耳を傾けた。
「本当に関わっていたのは父でした。ドーソンはすでに引退していました。私は当時まだ十歳でしたが、その全ての恥辱と恐怖を感じるには十分な年齢でした。父が全ての有価証券を盗んで逃げた、とずっと言われてきましたが、それは真実ではありません。父は、それらを現金化する時間さえあれば、すべてがうまく行き、すべての債権者に全額返済できると信じていました。彼は逮捕状が出る直前に、自分の小さなヨットでノルウェーへ向けて出発しました。母に別れを告げた最後の夜のことを覚えています。父は、持ち出す有価証券のリストを我々に残し、必ず名誉を回復して戻ってくると、そして父を信じた者は誰一人として損はさせないと誓いました。しかし、その後、父からの便りは一切ありませんでした。ヨットも父も、完全に姿を消したのです。母と私は、父もヨットも、そして彼が持ち去った有価証券も、海の底に沈んだのだと信じていました。しかし、我々には実業家の忠実な友人がおり、彼が少し前に、父が持っていた有価証券の一部がロンドン市場に再び現れたことを発見したのです。我々の驚きはご想像いただけるでしょう。私は何ヶ月もかけてそれらを追跡し、多くの疑念と困難の末、ついに最初の売り手がこの小屋の所有者、ピーター・ケアリー船長であったことを突き止めたのです。」
「当然、私はその男についていくつか調査をしました。そして、父がノルウェーへ渡っていたまさにその時期に、北極海から帰還する予定の捕鯨船を彼が指揮していたことが分かりました。その年の秋は荒れ模様で、南からの強風が長く続きました。父のヨットは北へ流され、そこでピーター・ケアリー船長の船と遭遇したのかもしれません。もしそうなら、父はどうなったのか? いずれにせよ、ピーター・ケアリーの証言から、これらの有価証券がどのように市場に出たかを証明できれば、父がそれらを売ったのではなく、持ち出した際に私的な利益を考えていなかったことの証明になるのです。」
「私は船長に会うつもりでサセックスへやって来ましたが、まさにその時、彼の悲惨な死が起こりました。検死審問で彼の船室の説明を読み、そこに彼の船の古い航海日誌が保管されていると書かれていました。もしシー・ユニコーン号の船上で一八八三年八月に何が起こったかを見ることができれば、父の運命の謎を解き明かせるかもしれない、と閃いたのです。昨夜、その航海日誌を手に入れようとしましたが、ドアを開けることができませんでした。今夜、再び試みて成功しましたが、その月の記述があるページが本から引き裂かれていることに気づきました。そしてその瞬間、あなた方の捕虜となったわけです。」
「それで全部かね?」とホプキンスが尋ねた。
「はい、全部です。」
そう言うと、彼の視線が泳いだ。「他に我々に話すことはないのか?」
彼はためらった。「いえ、何もありません。」
「昨夜より前に、ここへは来ていないのか?」
「いいえ。」
「では、これはどう説明する?」ホプキンスは叫び、決定的な証拠となる手帳を掲げた。最初のページには我々の捕虜のイニシャルが、そして表紙には血痕が付着していた。
哀れな男は崩れ落ちた。彼は両手で顔を覆い、全身を震わせた。「どこでそれを?」と彼はうめいた。「知りませんでした。ホテルで失くしたのだとばかり……」
「もうたくさんだ」とホプキンスは厳しく言った。「他に言うことがあるなら、法廷で言うがいい。今から私と一緒に警察署まで歩いてもらう。さて、ホームズさん、あなたとご友人がわざわざ助けに来てくださり、大変感謝しています。結果的にはあなた方のお力は不要で、私一人でもこの事件を成功裏に解決できたでしょうが、それでも感謝はしています。ブランブルタイ・ホテルに部屋を予約してありますので、皆で村まで歩いて下りましょう。」
「さて、ワトソン、どう思うかね?」翌朝、帰路の途中でホームズが尋ねた。
「君が満足していないのは見て取れるよ。」
「いやいや、ワトソン君、私は完全に満足している。だが同時に、スタンリー・ホプキンスの手法は感心できんな。スタンリー・ホプキンスにはがっかりした。彼にはもっと期待していたのだが。常に別の可能性を探り、それに備えるべきだ。それが犯罪捜査の第一の鉄則なのだよ。」
「では、別の可能性とは何だ?」
「私自身が追ってきた捜査線だ。何ももたらさないかもしれん。それは分からん。だが、少なくとも最後まで追ってみるつもりだ。」
ベーカー街では、いくつかの手紙がホームズを待っていた。彼はそのうちの一通をひったくるように手に取り、封を切ると、勝ち誇ったようにくすくすと笑い出した。「素晴らしいぞ、ワトソン! 別の可能性が展開してきた。電報用紙はあるかね? 私に代わって二通ほど打ってくれたまえ。『サムナー、船荷代理店、ラトクリフ・ハイウェイ。明日午前十時着で三名よこされたし。――バジル』。この界隈での私の名だ。もう一通は、『スタンリー・ホプキンス警部、ブリクストン、ロード街四十六番地。明日九時半、朝食に来られたし。重要。来られぬ場合は電報を。――シャーロック・ホームズ』。さあ、ワトソン、この忌々しい事件に十日間も悩まされてきた。これにて、私の前から完全に追放する。明日には、永久にこの事件の結末を聞くことができるだろう。」
指定された時刻きっかりにスタンリー・ホプキンス警部が現れ、我々はハドソン夫人が用意してくれた素晴らしい朝食の席に共についた。若き刑事は自らの成功に上機嫌だった。
「君の出した結論が正しいと、本気で思っているのかね?」とホームズが尋ねた。
「これ以上完璧な事件があるとは思えません。」
「私には決定的とは思えなかったがね。」
「驚きました、ホームズさん。これ以上何を求めるというのです?」
「君の説明は、あらゆる点を網羅しているかね?」
「もちろんです。若きネリガンは犯行当日にブランブルタイ・ホテルに到着しています。ゴルフをするという口実で。彼の部屋は一階にあり、好きな時に外出できました。その夜、彼はウッドマンズ・リーへ下り、小屋でピーター・ケアリーに会い、口論の末、銛で彼を殺害した。そして、自らの所業に恐れおののき、小屋から逃げ出しました。その際、ピーター・ケアリーに様々な有価証券について尋ねるために持参した手帳を落としたのです。お気づきかもしれませんが、いくつかにはチェック印がつけられ、その他――大多数――にはついていません。チェックのついたものはロンドン市場で追跡できましたが、残りは恐らくまだケアリーが所持しており、若きネリガンは、自身の供述によれば、父親の債権者に対して正しい行いをするためにそれらを取り戻そうと必死だったのです。逃走後、彼はしばらく小屋に近づく勇気がありませんでしたが、ついに必要な情報を得るために無理を押してそうした。どうです、すべて単純明快でしょう?」
ホームズは微笑んで首を振った。「私には一つだけ欠点があるように思える、ホプキンス君。それは、本質的に不可能だということだ。君は銛を人体に突き通すことを試したことがあるかね? ない? ち、ち、君、そういった細部にこそ注意を払わねばならんよ。友人のワトソンが証言してくれるだろうが、私は丸一日午前中をその練習に費やした。それは容易なことではなく、強く、熟練した腕を必要とする。しかし、この一撃は、武器の先端が壁に深くめり込むほどの猛烈な力で加えられている。この血の気の少ない若者に、これほど恐ろしい一撃が可能だと想像できるかね? 彼が真夜中にブラック・ピーターとラムの水割りを酌み交わした男かね? 二日前にブラインドに映った横顔は彼だったのかね? いや、いや、ホプキンス君、我々が探すべきは、別のもっと手ごわい人物なのだ。」
ホームズの言葉の間、刑事の顔はどんどん曇っていった。彼の希望も野心も、すべてが目の前で崩れ去っていく。しかし、彼は抵抗もせずに自分の立場を放棄するつもりはなかった。「ネリガンがあの夜、現場にいたことは否定できないでしょう、ホームズさん。あの手帳がそれを証明します。たとえあなたが穴を見つけ出せたとしても、陪審員を満足させるには十分な証拠があると自負しています。それに、ホームズさん、私は私の男を捕まえたのです。あなたの言うその恐るべき人物とやらは、どこにいるのですか?」
「どうやら、階段にいるようだ」とホームズは静かに言った。「ワトソン、そのリボルバーを手の届くところに置いておいた方がいいだろう」彼は立ち上がり、書き付けた紙をサイドテーブルに置いた。「さあ、準備は整った」と彼は言った。
外で何やらしゃがれた声の話し声がしていたが、やがてハドソン夫人がドアを開け、三人の男がバジル船長を訪ねてきたと告げた。「一人ずつ入れてくれ」とホームズは言った。
最初に入ってきたのは、リンゴのように赤ら顔で、ふわふわした白いもみあげを持つ、小柄な男だった。ホームズはポケットから手紙を取り出した。「名前は?」と彼は尋ねた。「ジェームズ・ランカスターです」「申し訳ない、ランカスター。船員の口は埋まってしまった。手間賃に半ソブリン金貨をやろう。この部屋に入って、数分待っていてくれ。」
二人目の男は、ひょろ長く干からびたような男で、まっすぐな髪と土気色の頬をしていた。名前はヒュー・パティンス。彼も同様に断られ、半ソブリン金貨を受け取り、待つように命じられた。
三人目の応募者は、際立った風貌の男だった。獰猛なブルドッグのような顔が、もつれた髪と髭に縁取られ、太くふさふさした、垂れ下がった眉の下から、二つの大胆な黒い瞳が光っていた。彼は敬礼し、船乗りらしく、帽子を手にくるくると回しながら立っていた。「名前は?」とホームズが尋ねた。「パトリック・カーンズ」「銛打ちか?」「はい。二十六回の航海経験があります」「ダンディーの出身だろうな?」「はい」「探検船にすぐ乗り込めるか?」「はい」「賃金は?」「月八ポンドです」「すぐにでも出発できるか?」「船具一式が手に入り次第」「身分証明書は持っているか?」「はい。」
彼はポケットから、擦り切れて油じみた書類の束を取り出した。ホームズはそれにざっと目を通し、返した。「君こそが私が求めていた男だ」と彼は言った。「サイドテーブルに契約書がある。それに署名すれば、すべて決まりだ。」
船乗りはよろめきながら部屋を横切り、ペンを取った。「ここに署名すればいいのか?」と彼はテーブルにかがみ込みながら尋ねた。ホームズは彼の肩越しにかがみ込み、両手を彼の首に回した。「これでいい」と彼は言った。
鋼鉄のカチリという音と、怒り狂った雄牛のような咆哮が聞こえた。次の瞬間、ホームズと船乗りは床の上で一緒に転げ回っていた。男は巨大な力の持ち主で、ホームズが巧みに手首にはめた手錠があったにもかかわらず、もしホプキンスと私が助けに駆けつけなければ、あっという間に友人を打ち負かしていただろう。私がリボルバーの冷たい銃口を彼のこめかみに押し付けたとき、ようやく彼は抵抗が無駄だと悟った。我々は彼の足首を紐で縛り、息を切らしながら格闘から立ち上がった。
「本当に申し訳ない、ホプキンス君」とシャーロック・ホームズは言った。「スクランブルエッグが冷めてしまったようだ。しかし、君が事件を見事な結末に導いたと思えば、残りの朝食も一層美味しく味わえるだろう?」
スタンリー・ホプキンスは驚きのあまり言葉を失っていた。「何と言っていいか分かりません、ホームズさん」と彼はついに、顔を真っ赤にして口走った。「私は最初から馬鹿な真似をしていたようです。今、分かりました。決して忘れるべきではなかったことを。私は弟子で、あなたは師匠だということを。今でさえ、あなたが何をしたかは分かりますが、どうやってそれを成し遂げたのか、それが何を意味するのか、さっぱり分かりません。」
「まあ、まあ」とホームズは機嫌よく言った。「我々は皆、経験から学ぶものだ。そして、君が今回得た教訓は、決して別の可能性を見失ってはならないということだ。君は若きネリガンに夢中になるあまり、ピーター・ケアリーの真の殺人者であるパトリック・カーンズに思いを馳せる余裕がなかったのだ。」
船乗りのしゃがれた声が我々の会話に割り込んできた。「おい、旦那」と彼は言った。「こんな風に手荒に扱われることに文句は言わねえが、物事は正しく呼んでもらいてえな。あんたは俺がピーター・ケアリーを殺害したと言うが、俺はピーター・ケアリーを殺したんだ。そこには天と地ほどの差がある。俺の言うことを信じねえかもしれん。ただの作り話だと思ってるかもしれんがな。」
「とんでもない」とホームズは言った。「君の言い分を聞こうじゃないか。」
「すぐに話せる。そして、神に誓って、一言一句真実だ。俺はブラック・ピーターを知っていた。あいつがナイフを抜いたとき、俺はすかさず銛を叩き込んでやった。やられるか、やるか、だったからな。そうやってあいつは死んだ。それを殺人と呼ぶなら好きにしろ。どっちにしろ、ブラック・ピーターのナイフで心臓を抉られるよりは、首に縄をかけられて死ぬ方がましだ。」
「どうしてそこへ?」とホームズが尋ねた。
「最初から話してやる。少し体を起こさせてくれ、話しやすいように。あれは八三年のことだ。その年の八月。ピーター・ケアリーはシー・ユニコーン号の船長で、俺は予備の銛打ちだった。俺たちは流氷帯を抜けて帰路についていた。逆風と一週間の南からの強風に吹かれながらな。その時、北へ流された小さな船を拾ったんだ。乗っていたのは一人、陸の人間だった。船員たちは船が沈むと思って、救命ボートでノルウェーの海岸を目指したらしい。たぶん全員溺れ死んだだろう。まあ、俺たちはその男を船に乗せ、そいつと船長は船室で長いこと話し込んでいた。そいつと一緒に引き上げた荷物は、ブリキの箱が一つだけ。俺の知る限り、男の名前は一度も口にされなかった。そして二日目の夜、そいつはまるで初めからいなかったかのように姿を消した。荒天の中、身を投げたか、海に落ちたかしたと公表された。だが、そいつに何が起こったか知っていたのは一人だけ、この俺だ。この目で見たんだ。暗い夜の真夜中の見張り当番の時、シェトランド諸島の灯りを見る二日前に、船長がそいつの踵を持ち上げて手すりの向こうへ放り込むのをな。まあ、俺はそのことを胸にしまい、どうなるか様子を見ていた。スコットランドに戻ると、その件は簡単に揉み消され、誰も何も聞かなかった。見知らぬ男が事故で死に、誰も詮索しようとはしなかった。その後すぐにピーター・ケアリーは船を降り、俺があいつの居場所を見つけるまでには長い年月がかかった。あいつがあのブリキの箱の中身のためにやったんだろうと、そして今なら俺の口を塞ぐために大金を払えるだろうと、そう踏んでいた。ロンドンであいつに会ったという船乗りから居場所を突き止め、脅しに行ったんだ。最初の夜、あいつはかなり分別があって、俺が一生海に出なくてもいいだけの金をくれると言った。二日後の夜にすべて決着をつけることになっていた。だが、行ってみると、あいつはべろべろに酔っぱらって、ひどい機嫌だった。俺たちは腰を下ろして酒を飲み、昔話に花を咲かせたが、あいつが飲めば飲むほど、その顔つきが気に入らなくなってきた。壁の銛が目に入り、事が終わるまでに必要になるかもしれんと思った。そしてついにあいつが俺に食ってかかってきた。唾を吐き、罵り、目には殺意を浮かべ、手には大きな折りたたみナイフを握っていた。あいつが鞘からナイフを抜く暇もなかった。俺の銛が奴を貫いていた。ちくしょう! なんて叫び声だったか! 今でもあの顔がちらついて眠れやしねえ。俺はそこに立っていた。あいつの血が周りに飛び散る中でな。しばらく待ったが、静かになったので、もう一度気を取り直した。見回すと、棚の上にブリキの箱があった。どっちにしろ、ピーター・ケアリーと同じくらい、俺にも権利がある。だから、それを持って小屋を出た。馬鹿なことに、煙草入れをテーブルの上に忘れてきちまった。」
「さて、ここからがこの話で一番奇妙な部分だ。小屋の外に出るか出ないかのうちに、誰かが来るのが聞こえて、茂みに隠れた。一人の男がこそこそとやって来て、小屋に入り、幽霊でも見たかのような叫び声をあげると、姿が見えなくなるまで必死に走り去った。そいつが誰で、何が目的だったのかは、俺にはさっぱり分からん。俺はと言えば、十マイル歩き、タンブリッジ・ウェルズで列車に乗り、そうしてロンドンに着いた。誰にも気づかれずにだ。」
「まあ、箱を調べてみると、金は入っておらず、俺にはとても売る勇気のない書類ばかりだった。ブラック・ピーターという金のなる木を失い、一シリングも持たずにロンドンで立ち往生だ。残されたのは自分の腕だけ。銛打ち募集、高給、という広告を見て、船荷代理店に行ったら、ここへ送られたというわけだ。俺が知っているのはそれだけだ。そしてもう一度言うが、もし俺がブラック・ピーターを殺したのなら、法律は俺に感謝すべきだ。麻の縄の代金を節約してやったんだからな。」
「非常に明快な供述だ」とホームズは立ち上がり、パイプに火をつけながら言った。「ホプキンス君、一刻も早く君の囚人を安全な場所へ移送すべきだろう。この部屋は独房には向いていないし、パトリック・カーンズ氏は我々の絨毯を少々占領しすぎている。」
「ホームズさん」とホプキンスは言った。「感謝の言葉もありません。今になっても、どうやってこの結果にたどり着いたのか理解できません。」
「単に、最初から正しい手がかりを得るという幸運に恵まれただけだ。もし私がこの手帳のことを知っていたら、君のように思考を惑わされていた可能性は十分にある。だが、私が聞いたことはすべて、一つの方向を指し示していた。驚異的な腕力、銛を扱う技術、ラムの水割り、粗い煙草の入ったアザラシの皮の煙草入れ――これらすべてが、船乗り、それも捕鯨船員を指していた。煙草入れの『P.C.』というイニシャルは偶然の一致であり、ピーター・ケアリーのものではないと確信していた。彼は滅多に煙草を吸わず、小屋にパイプもなかったからだ。私が小屋にウィスキーとブランデーがあったか尋ねたのを覚えているかね。君はあったと言った。他の酒が手に入るのに、わざわざラムを飲む陸の人間がどれだけいるだろうか? そうだ、私は船乗りに違いないと確信していたのだ。」
「それで、どうやって彼を見つけたのですか?」
「君、問題は極めて単純なものになっていたのだ。もし船乗りだとすれば、それはシー・ユニコーン号で彼と共にいた船乗りにしかあり得ない。私の知る限り、彼は他の船には乗っていなかった。私は三日間かけてダンディーに電報を打ち続け、その結果、一八八三年のシー・ユニコーン号の乗組員の名簿を手に入れた。銛打ちの中にパトリック・カーンズの名を見つけたとき、私の調査は終わりに近づいていた。男はおそらくロンドンにおり、しばらく国を離れたいと望んでいるだろうと推論した。そこで私は数日間イースト・エンドで過ごし、北極探検を計画し、バジル船長の下で働く銛打ちに魅力的な条件を提示した。そして、この結果というわけだ!」
「素晴らしい!」とホプキンスは叫んだ。「素晴らしい!」
「若きネリガンをできるだけ早く釈放しなければならん」とホームズは言った。「正直なところ、君は彼に謝罪すべきだと思う。ブリキの箱は彼に返さねばならないが、もちろん、ピーター・ケアリーが売却した有価証券は永遠に失われた。さあ、馬車が来たぞ、ホプキンス君。君の男を連れて行くがいい。もし裁判で私が必要なら、私とワトソンの住所はノルウェーのどこかになるだろう。詳細は後で送る。」
チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートンの冒険
私が語ろうとする出来事が起こってから、すでに幾年もの歳月が流れた。それでもなお、この件に触れることにはためらいを覚える。長い間、たとえ最大限の思慮深さと慎重さをもってしても、事実を公にすることは不可能であった。しかし今、主要な関係者はもはや人の法の及ばぬところにあり、しかるべき抑制を加えれば、誰一人傷つけることなくこの物語を語ることができるだろう。これは、シャーロック・ホームズ氏と私自身の経歴において、絶対的に比類なき経験を記録したものである。読者諸賢におかれては、実際の出来事を特定されかねない日付やその他の事実を私が伏せることを、どうかご容赦願いたい。
ある凍てつくような寒い冬の夜、ホームズと私はいつものように夕刻の散歩から戻ってきた。時刻は六時ごろだった。ホームズがランプの芯をかき立てると、その光がテーブルの上の名刺を照らし出した。彼はそれに一瞥をくれると、吐き捨てるような声をあげ、床に叩きつけた。私がそれを拾い上げて読むと、こうあった。
チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートン アップルドア・タワーズ ハムステッド在
代理人
「何者です?」と私は尋ねた。
「ロンドン一の悪党だよ」ホームズはそう答え、暖炉の前に腰を下ろして足を伸ばした。「カードの裏には何か書いてあるかね?」
私はそれを裏返した。
「『六時半に伺います――C・A・M』とあります。」
「ふん! そろそろ時間だな。ワトソン、君は動物園で蛇の前に立った時、あのぬらりぬらりと這い、毒々しい生き物どもを見た時に、ぞっとするような、身の縮むような感覚を覚えたことはないかね? 奴らの殺意に満ちた目、邪悪で平たい顔。そう、ミルヴァートンという男は私にそんな印象を与えるのだ。私はこれまで五十人もの殺人犯と渡り合ってきたが、その中でも最悪の輩でさえ、この男に覚えるほどの嫌悪感を抱かせたことはない。それなのに、奴との取引から逃れるわけにはいかんのだ。いや、実のところ、奴は私の招待でここへ来る。」
「しかし、一体何者なのです?」
「教えてやろう、ワトソン。奴こそは恐喝王の中の帝王だ。その秘密と評判がミルヴァートンの手に落ちた人間、特に女性には、神の救いを祈るほかあるまい! 奴は微笑みを浮かべ、大理石の心臓で、獲物が干上がるまでどこまでも搾り尽くす。その道にかけては天才で、もっとまともな商売をしていれば名を成しただろうに。奴の手口はこうだ。富と地位ある人々を窮地に陥れる手紙に高額を支払う用意があると、それとなく知らしめておく。品物は、裏切り者の従僕やメイドからだけでなく、人を信じやすい女性の信頼と愛情を勝ち得た、紳士然とした悪党どもからも頻繁に手に入れる。支払いは気前がいい。私が知る限りでは、たった二行の手紙のために従僕へ七百ポンドを支払い、その結果、ある貴族一家が破滅した。市場に出回るものはすべてミルヴァートンの元へ流れ、この大都市で奴の名を聞いて青ざめる者は何百人といる。奴の魔手がいつどこに伸びるか、誰にも分からん。なにしろ、その日暮らしの仕事をするにはあまりに裕福で、あまりに狡猾なのだ。奴は何年も切り札を温存し、賭け金が最も高くなった瞬間にそれを切るだろう。私は奴をロンドン一の悪党だと言ったが、君に問いたい。かっとなって仲間を殴り殺すような無頼漢と、膨れ上がった懐をさらに肥やすため、冷徹な計算のもと、悠然と人の魂を苛み、神経を締め上げるこの男と、一体どちらが悪だと言えるだろうか?」
これほど友人が感情を激して語るのを、私はめったに聞いたことがなかった。
「しかし、」と私は言った。「そんな輩なら、当然、法の裁きを受けるはずでは?」
「建前上は、間違いなく。だが現実には不可能だ。例えば、ある女性が奴を数ヶ月投獄させることで、自分自身の破滅がすぐさま訪れるとしたら、何になる? 奴の犠牲者は反撃する勇気を持てない。もし奴が潔白な人間を脅迫することがあれば、その時こそ捕えられるだろうが、奴は悪魔のように狡猾だ。いや、いや、奴と戦うには別の方法を見つけなければならん。」
「それで、なぜ彼がここに?」
「ある高貴な依頼人が、その痛ましい事件を私の手に委ねてくださったからだ。昨シーズンの社交界で最も美しいと謳われた、レディ・エヴァ・ブラックウェルだ。彼女は二週間後にドーヴァーコート伯爵と結婚することになっている。この悪魔は、彼女が書いた数通の不用意な手紙を握っている――不用意な、だ、ワトソン、それ以上のものじゃない――田舎のしがない若き地主に宛てたものだ。だが、婚約を破談にするには十分すぎる。ミルヴァートンは、大金が支払われなければ、その手紙を伯爵に送りつけるつもりなのだ。私は奴と会い、できる限りの条件で交渉するよう依頼されている。」
その瞬間、下の通りで馬車の立てる騒々しい音がした。見下ろすと、一対の見事な栗毛馬に引かせた壮麗な馬車が停まっており、その艶やかな臀部にきらびやかなランプの光が反射していた。従僕がドアを開け、アストラカン[訳注:子羊の毛皮]の毛深いオーバーを着た、小柄で恰幅のいい男が降り立った。一分後、男は部屋にいた。
チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートンは五十がらみの男で、大きく知的な頭、丸々とした髭のない顔、常に凍りついたような微笑みを浮かべ、幅広の金縁眼鏡の奥からは二つの鋭い灰色の目が爛々と輝いていた。その風貌にはどこかピクウィック氏[訳注:ディケンズの小説の登場人物]のような人の良さが漂っていたが、それもただ、張り付いた笑みの不誠実さと、落ち着きなく人を射抜くような目の硬い輝きによって損なわれていた。彼の声は、その顔つきと同じく滑らかで物腰が柔らかかった。ふっくらとした小さな手を差し伸べながら近づき、最初の訪問で我々と会えなかったことを残念に思うと囁いた。ホームズはその差し出された手を無視し、花崗岩のような顔で彼を見据えた。ミルヴァートンの笑みはさらに広がり、彼は肩をすくめ、オーバーを脱ぐと、念入りにそれを椅子の背にかけ、そして腰を下ろした。
「こちらの紳士は?」と彼は言い、私の方へ手を振った。「ご同席は賢明ですかな? よろしいので?」
「ワトソン博士は私の友人で、相棒です。」
「それは結構、ホームズさん。私が異を唱えたのは、ただあなたの依頼人の利益を考えてのこと。なにしろ、非常に繊細な問題ですので――」
「ワトソン博士は既に事情を聞いています。」
「では、仕事の話に入りましょう。あなたはレディ・エヴァの代理人だとか。私の条件を受け入れる権限はお持ちですかな?」
「あなたの条件とは?」
「七千ポンド。」
「さもなくば?」
「おやおや、口にするのも心苦しいのですが、十四日までにお支払いがなければ、十八日の結婚式は間違いなく執り行われないでしょうな。」
彼の我慢ならない笑みは、これまで以上に独り善がりな色を深めていた。
ホームズはしばし考え込んだ。
「どうやらあなたは、」と彼はついに口を開いた。「物事を楽観視しすぎているようだ。私はもちろん、それらの手紙の内容は熟知している。私の依頼人は、私が助言することなら何でもするだろう。私は彼女に、未来の夫にすべてを打ち明け、彼の寛大さにすがるよう勧めるつもりだ。」
ミルヴァートンはくすくす笑った。
「あなたは伯爵というお方をまるでご存じないようだ」と彼は言った。
ホームズの当惑した表情から、彼が伯爵をよく知っていることは私にも明らかだった。
「手紙に何の害があるというのだ?」と彼は尋ねた。
「活き活きとしていますよ――実に活き活きと」ミルヴァートンは答えた。「ご婦人は実に魅力的な書き手でいらっしゃる。しかし、ドーヴァーコート伯爵がお気に召さないことは請け合います。もっとも、あなたがそうお考えでないなら、その話はそこまでにしておきましょう。これは純粋に商談です。もし、それらの手紙が伯爵の手に渡ることが依頼人の最善の利益になるとお考えなら、それらを取り戻すためにかくも大金を支払うのは、実に馬鹿げたことでしょうな。」
彼は立ち上がり、アストラカンのコートを掴んだ。
ホームズは怒りと屈辱で顔が青ざめていた。
「少し待て」と彼は言った。「性急すぎる。これほど繊細な問題だ、我々はスキャンダルを避けるためにあらゆる努力をすべきだろう。」
ミルヴァートンは再び椅子に身を沈めた。
「あなたならそうお考えになると確信しておりました」と彼は喉を鳴らした。
「同時に、」ホームズは続けた。「レディ・エヴァは裕福な女性ではない。断言するが、二千ポンドですら彼女の財産には大きな負担であり、あなたが提示した金額は到底支払えるものではない。ゆえに、要求を穏当なものにしていただきたい。私が提示する金額で手紙を返してほしい。これ以上は出せないと、断言する。」
ミルヴァートンの笑みはさらに広がり、その目は愉快そうにきらめいた。
「ご婦人の財産について、あなたのおっしゃることが真実であることは承知しております」と彼は言った。「しかし同時に、ご婦人の結婚という機会は、ご友人やご親戚が彼女のために少々骨を折るのに、まことにふさわしい時であるとお認めになるでしょう。彼らは気の利いた結婚祝いに頭を悩ませているかもしれません。このささやかな手紙の束が、ロンドン中の燭台やバター皿をすべて合わせたよりも、大きな喜びをもたらすことを保証いたしましょう。」
「不可能だ」とホームズは言った。
「おやおや、まあまあ、なんとお気の毒な!」ミルヴァートンは分厚い手帳を取り出しながら叫んだ。「ご婦人方が努力をなさらないのは、どうにも賢明ではないと思わざるを得ませんな。これをご覧なさい!」
彼は紋章の入った封筒に入った小さな手紙を掲げた。「これは――まあ、明日の朝まではお名前を明かすのはフェアではありますまい。しかし、その時刻にはご婦人の夫君の手に渡っていることでしょう。すべては、彼女がダイヤモンドを模造品に替えれば手に入るような、はした金を用意しないからです。実に残念なことです! さて、あなたはマイルズ令嬢とドーキング大佐の婚約が突然破談になったのを覚えておいでかな? 結婚式のわずか二日前に、『モーニング・ポスト』紙に、すべてが取りやめになったという短い記事が載った。なぜか? ほとんど信じられないことですが、わずか千二百ポンドという馬鹿げた金額で、すべての問題は解決したのです。哀れだとは思いませんか? そして今、ここにいる分別あるあなたが、依頼人の未来と名誉がかかっているというのに、条件をめぐってぐずぐずしている。驚きましたよ、ホームズさん。」
「私の言っていることは真実だ」ホームズは答えた。「その金は用意できない。この女性の人生を破滅させてもあなたに何の得にもならないのだから、私が提示する相当額を受け取る方が、あなたにとっても良いはずだ。」
「そこがあなたの間違いです、ホームズさん。暴露は間接的にかなりの利益を私にもたらす。私には、熟しつつある同様の案件が八件から十件あります。もし、私がレディ・エヴァを厳しい見せしめにしたという噂が彼らの間に広まれば、彼らは皆、ずっと物分かりが良くなるでしょう。お分かりかな?」
ホームズは椅子から跳ね上がった。
「奴の後ろへ回れ、ワトソン! 逃がすな! さあ、旦那、その手帳の中身を拝見しようじゃないか。」
ミルヴァートンは鼠のように素早く部屋の隅へ滑り、壁を背にして立った。
「ホームズさん、ホームズさん」彼はコートの前を翻し、内ポケットから突き出た大型リボルバーの銃把を見せつけながら言った。「あなたが何か独創的なことをしてくれると期待していましたよ。こんなことは何度もやられましたが、それで何か良いことがありましたかな? 私は全身武装していると請け合います。そして、法が私を支持することを知っていますから、武器を使う準備は万端です。それに、私が手紙をここに手帳に入れて持ってくるなどというあなたの憶測は、全くの見当違い。そんな愚かなことはしませんよ。さて、紳士諸君、私は今夜、あと一、二件面会の予定がありましてね。ハムステッドまでは長旅なもので。」
彼は一歩前に出てコートを手に取り、リボルバーに手をかけ、ドアに向かった。私は椅子を手に取ったが、ホームズが首を振り、私はそれを再び置いた。お辞儀をし、微笑み、目をきらめかせ、ミルヴァートンは部屋を出て行った。数瞬後、馬車のドアがばたんと閉まる音と、彼が走り去る車輪の音が聞こえた。
ホームズは暖炉のそばで身じろぎもせず座っていた。両手をズボンのポケットに深く突っ込み、顎を胸に沈め、その目は燃え盛る熾火に注がれていた。半時間、彼は静寂の中にあった。そして、決心した人間の仕草で、彼はすっくと立ち上がり、寝室へと入っていった。しばらくして、やぎ髭を生やし、ふてぶてしい態度の、いなせな若き職人が、ランプでクレーパイプに火をつけ、通りへと降りていった。「しばらくしたら戻る、ワトソン」と彼は言い、夜の闇に消えた。彼がチャールズ・オーガスタス・ミルヴァートンに対する作戦を開始したのだと私は理解したが、その作戦がこれほど奇妙な形をとることになろうとは、夢にも思わなかった。
数日間、ホームズはこのいでたちで時間を問わず出入りしていたが、ハムステッドで時間を過ごしており、それは無駄ではなかった、という言葉以外、彼が何をしているのか私は何も知らなかった。しかしついに、風が窓に叫び声をあげてがなり立てる、荒れ狂う嵐の夜、彼は最後の遠征から戻り、変装を解くと暖炉の前に座り、彼独特の静かな内なる笑い方で心から笑った。
「君は私を結婚するような男だとは思わんだろう、ワトソン?」
「ええ、まさか!」
「私が婚約したと聞けば、興味を持つだろうね。」
「おやおや、君! おめで――」
「ミルヴァートンのメイドとだ。」
「なんてことだ、ホームズ!」
「情報が欲しかったのだよ、ワトソン。」
「いくらなんでもやりすぎでは?」
「最も必要な手段だった。私はエスコットという名で、羽振りのいい配管工だ。毎晩彼女と散歩し、話をした。やれやれ、あの会話ときたら! しかし、欲しいものはすべて手に入れた。私はミルヴァートンの家を、自分の掌を見るように知っている。」
「しかし、その娘さんは、ホームズ?」
彼は肩をすくめた。
「仕方ないことだ、ワトソン君。これほどのものが賭けられているのだから、手持ちのカードは最善の方法で切らねばならん。しかし、喜ばしいことに、私には憎き恋敵がいてね、私が背を向けた途端、間違いなく私を追い出すだろう。なんという素晴らしい夜だろう!」
「この天気がお好きなのですか?」
「私の目的に合っている。ワトソン、私は今夜、ミルヴァートンの家に押し入るつもりだ。」
私は息を呑み、その言葉に肌が粟立った。それは、凝縮された決意の響きをもって、ゆっくりと発せられた。夜の稲妻が荒々しい風景の細部までを一瞬にして映し出すように、一瞥にして、私はその行動がもたらしうるあらゆる結果を見たように思えた――発覚、逮捕、取り返しのつかない失敗と不名誉に終わる輝かしい経歴、そして友人自身が、あの忌まわしいミルヴァートンのなすがままになる姿。
「頼むから、ホームズ、自分が何をしているのか考えてくれ」と私は叫んだ。
「君、あらゆることを考慮したよ。私は決して行動を急いだりしないし、他に可能な手立てがあれば、これほど強引で、実に危険な手段はとらない。問題をはっきりと、公平に見てみよう。君も、この行動が法的には犯罪であっても、道徳的には正当化されると認めるだろう。彼の家に押し入るのは、彼の懐中手帳を力ずくで奪うのと大差ない――君も私に手を貸すつもりだった行動だ。」
私は頭の中でそのことを考えた。
「ええ、」と私は言った。「我々の目的が、違法な目的に使われるもの以外は何も取らないという限り、道徳的には正当化されます。」
「その通り。道徳的に正当化される以上、私が考慮すべきは個人的な危険の問題だけだ。一人のご婦人が絶望的な助けを必要としている時に、紳士たるもの、これを大げさに考えるべきではあるまい。」
「あなたは非常にまずい立場に立たされる。」
「まあ、それも危険の一部だ。これらの手紙を取り戻すには、他に可能な方法がない。不幸なご婦人には金がなく、打ち明けられる身内もいない。明日は猶予の最終日だ。今夜我々が手紙を手に入れなければ、あの悪党は言葉通り、彼女を破滅させるだろう。したがって、私は依頼人を見捨てるか、この最後の切り札を切るか、どちらかを選ばねばならん。ここだけの話だが、ワトソン、これはあのミルヴァートンという男と私の、丁々発止の勝負なのだ。君も見た通り、緒戦は奴に分があったが、私の自尊心と評判にかけて、決着をつけなければならん。」
「まあ、気は進みませんが、そうしなければならないのでしょう」と私は言った。「いつ出発しますか?」
「君は来ない。」
「それなら、あなたも行かない」と私は言った。「名誉にかけて誓います――生涯一度も破ったことはありません――もしあなたが私をこの冒険に加えてくれないなら、私はまっすぐ馬車で警察署へ行き、あなたを密告します。」
「君は助けにならん。」
「どうしてそれが分かるのです? 何が起こるか分かりませんよ。とにかく、私の決心は固い。あなた以外にも自尊心を持ち、評判さえ気にする人間はいるのです。」
ホームズは迷惑そうな顔をしたが、やがて眉が晴れ、私の肩を叩いた。
「よし、よし、君、そうしよう。我々は何年もこの部屋を共にしてきたのだ、同じ独房を共にすることになって終わるのも一興だろう。知っているかね、ワトソン、君に白状してもいいが、私は常々、自分は極めて有能な犯罪者になれただろうという考えを持っていた。これはその方面での、私の一生の好機だ。これを見ろ!」
彼は引き出しからこぎれいな小さな革ケースを取り出し、それを開くと、数々の輝く道具を見せた。「これは一級品の最新式夜盗道具一式だ。ニッケルめっきのバール、ダイヤモンドの刃先を持つガラス切り、自在鍵、そして文明の進歩が要求するあらゆる最新の改良が施されている。ここには、私の遮光ランタンもある。すべて準備万端だ。音のしない靴は持っているかね?」
「ゴム底のテニスシューズがあります。」
「素晴らしい! マスクは?」
「黒い絹で二つ作れます。」
「君にはこの種のことに強い天賦の才があるようだ。結構、マスクを作ってくれたまえ。出発前に冷たい夜食をとろう。今は九時半。十一時にチャーチ・ロウまで馬車で行く。そこからアップルドア・タワーズまでは歩いて十五分だ。真夜中前には仕事にかかれるだろう。ミルヴァートンは眠りが深く、十時半きっかりに就寝する。運が良ければ、二時までにはレディ・エヴァの手紙をポケットにここへ戻ってこられるはずだ。」
ホームズと私は夜会服に着替えた。芝居帰りの二人組に見えるようにするためだ。オックスフォード街で辻馬車を拾い、ハムステッドのある住所まで行った。ここで馬車を降り、極寒で風が身を刺すようだったので、外套のボタンをきっちり留め、我々はヒースの縁に沿って歩いた。
「繊細な扱いを要する仕事だ」とホームズは言った。「これらの文書は奴の書斎にある金庫に保管されている。そしてその書斎は寝室の前室だ。一方で、贅沢をしているああいう小柄な肥満体の男どもが皆そうであるように、奴は多血質で眠りが深い。アガサ――私の婚約者だ――が言うには、旦那様を起こすのは不可能だというのが使用人部屋の冗談だそうだ。奴には彼の利益に忠実な秘書がいて、一日中書斎から動かない。だから我々は夜に行く。それから、庭をうろつくたちの悪い犬がいる。ここ二晩、私は遅くにアガサと会い、彼女がその獣を閉じ込めて、私が自由に動けるようにしてくれている。これがその家だ、敷地内にあるこの大きなやつだ。門を通り――さあ、右手の月桂樹の中へ。ここでマスクを着けよう。見ろ、どの窓にも明かりのちらつき一つない。すべて順調だ。」
黒い絹の覆面で、我々はロンドンで最も凶悪な二人組の姿となり、静かで陰鬱な家へと忍び寄った。タイル張りのベランダのようなものが家の一面に沿って伸びており、そこにはいくつかの窓と二つのドアが並んでいた。
「あれが奴の寝室だ」ホームズは囁いた。「このドアは書斎に直結している。我々には好都合だが、施錠されている上に閂もかかっている。入るのに音を立てすぎるだろう。こちらへ回れ。客間につながる温室がある。」
そこは施錠されていたが、ホームズはガラスを円形に切り抜き、内側から鍵を回した。一瞬の後、彼は我々の後ろでドアを閉め、我々は法の目から見れば重罪人となった。温室の濃く暖かい空気と、異国の植物のむせ返るような芳香が、我々の喉をついた。彼は暗闇で私の手を取り、顔をかすめる茂みの土手を素早く通り抜けて導いた。ホームズには、注意深く培われた、暗闇で物を見る驚くべき能力があった。片手で私の手を握ったまま、彼はドアを開け、私は葉巻が吸われてからさほど時間の経っていない大きな部屋に入ったことをぼんやりと意識した。彼は家具の間を手探りで進み、もう一つのドアを開け、我々の後ろでそれを閉じた。手を伸ばすと、壁にかかったいくつかのコートに触れ、自分が廊下にいることを理解した。我々はそこを進み、ホームズは右手側のドアを非常に静かに開けた。何かが我々に飛びかかってきて、私の心臓は口から飛び出しそうになったが、それが猫だと気づいた時には笑い出しそうになった。この新しい部屋では暖炉が燃えており、再び空気はタバコの煙で重かった。ホームズはつま先立ちで入り、私が続くのを待ってから、非常に静かにドアを閉めた。我々はミルヴァートンの書斎におり、向こう側の垂れ幕が彼の寝室への入り口を示していた。
暖炉の火はよく燃えており、部屋はそれで照らされていた。ドアの近くに電灯のスイッチの輝きが見えたが、たとえ安全だったとしても、それをつける必要はなかった。暖炉の一方の側には、我々が外から見た出窓を覆う重いカーテンがあった。もう一方の側には、ベランダに通じるドアがあった。中央には机が置かれ、光沢のある赤い革の回転椅子があった。向かいには大きな書棚があり、その上にはアテナの胸像が置かれていた。書棚と壁の間の隅には、背の高い緑色の金庫が立っており、その表面の磨かれた真鍮の取っ手に暖炉の火が反射していた。ホームズは忍び寄ってそれを見た。それから彼は寝室のドアに這い寄り、頭を傾けて熱心に耳を澄ませた。中からは何の音もしなかった。その間、私は外のドアを通って退路を確保するのが賢明だろうと思い、それを調べた。驚いたことに、それは施錠もされていなければ、閂もかかっていなかった。私はホームズの腕に触れ、彼は覆面顔をそちらに向けた。彼がぎくりとするのが見え、明らかに私と同じくらい驚いていた。
「気に入らんな」と彼は私の耳元に唇を寄せて囁いた。「どうも腑に落ちん。いずれにせよ、ぐずぐずしている時間はない。」
「何か手伝えることは?」
「ああ、ドアのそばに立っていてくれ。誰かが来るのが聞こえたら、内側から閂をかけろ。そうすれば我々は来た道から逃げられる。もし向こうから来たら、仕事が終わっていればドアから出られるし、まだならこの窓のカーテンの陰に隠れられる。分かったか?」
私は頷き、ドアのそばに立った。最初の恐怖心は消え去り、法の守護者であった時よりも、その破壊者となった今の方が、より鋭い興奮に身を震わせていた。我々の使命の高い目的、それが私心なく騎士道的なものであるという意識、敵の卑劣な性格、そのすべてが冒険の興趣を増した。罪悪感を感じるどころか、私は我々の危険を喜び、高揚していた。感嘆の輝きをもって、私はホームズが道具のケースを広げ、繊細な手術を行う外科医の冷静で科学的な正確さで道具を選ぶのを眺めていた。金庫破りが彼の特別な趣味であることを私は知っており、多くの麗しいご婦人方の評判をその顎に収めているこの緑と金の怪物、この竜と対峙することが、彼にどれほどの喜びを与えているかを理解した。夜会服の袖口をまくり上げ――彼はオーバーを椅子に置いていた――ホームズは二本のドリル、バール、そしていくつかの合鍵を並べた。私は中央のドアのそばに立ち、他のドアそれぞれに目を配り、いかなる緊急事態にも備えていたが、実際のところ、もし邪魔が入ったらどうすべきか、私の計画はやや漠然としていた。半時間、ホームズは集中して作業を続けた。一つの道具を置き、別のを手に取り、それぞれを熟練した職人の力強さと繊細さで扱った。ついにカチリという音が聞こえ、幅広の緑の扉が開き、中にはそれぞれが結ばれ、封印され、銘が記されたたくさんの紙包みが見えた。ホームズは一つを取り出したが、揺らめく暖炉の火では読むのが難しく、彼は小さな遮光ランタンを取り出した。ミルヴァートンが隣の部屋にいる状況で、電灯をつけるのはあまりに危険だったからだ。突然、彼が立ち止まり、熱心に耳を澄ますのが見えた。そして一瞬のうちに、彼は金庫の扉をばたんと閉め、コートを拾い上げ、道具をポケットに詰め込み、窓のカーテンの後ろに飛び込み、私にも同じようにするよう合図した。
私が彼の隣に加わった時になって初めて、彼の鋭敏な感覚を警戒させたものが何であったかを聞き取った。家の中のどこかで物音がしたのだ。遠くでドアがばたんと閉まる音。それから、不明瞭で鈍いざわめきが、急速に近づいてくる重い足音の規則的な響きに変わった。彼らは部屋の外の廊下にいた。ドアの前で立ち止まった。ドアが開いた。電灯がつけられる鋭いカチッという音がした。ドアが再び閉まり、強い葉巻の刺激的な臭いが我々の鼻をついた。それから足音は、我々から数ヤードの範囲で、行ったり来たり、行ったり来たりを続けた。ついに椅子がきしむ音がし、足音は止んだ。それから鍵が錠の中でカチリと鳴り、紙が擦れる音が聞こえた。
それまで私は外を見る勇気がなかったが、今、私は目の前のカーテンの隙間をそっと広げ、覗き見た。ホームズの肩が私の肩に押し付けられる感触から、彼も私と同じものを観察していることが分かった。我々の真正面、ほとんど手の届くところに、ミルヴァートンの幅広く丸い背中があった。我々が彼の動きを完全に見誤っていたことは明らかだった。彼は寝室にはおらず、我々が見えなかった家の別棟にある喫煙室かビリヤード室で起きていたのだ。その広く、白髪交じりの頭、輝く禿げ上がった部分が、我々の視界のすぐ手前にあった。彼は赤い革張りの椅子に深くもたれかかり、足を伸ばし、長い黒い葉巻が口から斜めに突き出ていた。彼はクラレット色の、黒いベルベットの襟がついた、半軍服風の喫煙ジャケットを着ていた。手には長い法律文書を持ち、それを怠惰な様子で読みながら、唇からタバコの煙の輪を吹いていた。その落ち着いた態度とくつろいだ様子からは、すぐに立ち去る気配はなかった。
ホームズの手が私の手の中に忍び込み、状況は彼の掌握下にあり、心は穏やかだとでも言うように、安心させるように握るのを感じた。彼が、私の位置からはあまりにも明白なこと――金庫の扉が不完全に閉まっており、ミルヴァートンがいつでもそれに気づくかもしれないこと――を見ていたかどうかは分からなかった。私自身の心の中では、もし彼の視線の硬さから、彼がそれに気づいたと確信したら、すぐに飛び出し、私の外套を彼の頭にかぶせ、彼を羽交い締めにし、後はホームズに任せようと決めていた。しかしミルヴァートンは決して顔を上げなかった。彼は手の中の書類に気だるそうに興味を示し、弁護士の議論を追いながら、次々とページをめくっていた。少なくとも、書類と葉巻を終えれば彼は自室に行くだろう、と私は思った。しかし、彼がどちらかを終える前に、我々の思考を全く別の方向へ転換させる驚くべき展開が起こった。
ミルヴァートンが時計を見るのを、私は何度か観察した。一度は立ち上がっては、焦れたような仕草で再び座り込んだこともあった。しかし、彼がこんな奇妙な時間に約束をしているかもしれないという考えは、外のベランダからかすかな音が私の耳に届くまで、思いつきもしなかった。ミルヴァートンは書類を落とし、椅子に座ったまま硬直した。音は繰り返され、それからドアを優しく叩く音がした。ミルヴァートンは立ち上がってそれを開けた。
「やあ」と彼はぶっきらぼうに言った。「三十分近く遅刻だぞ。」
これが、施錠されていなかったドアと、ミルヴァートンの夜番の説明だったのだ。女性のドレスが優しく擦れる音がした。ミルヴァートンの顔が我々の方を向いた時、私はカーテンの隙間を閉じていたが、今、非常に注意深く再びそれを開けることにした。彼は席に戻っており、葉巻は依然として口の端から傲慢な角度で突き出ていた。彼の正面、電灯の眩しい光の中に、背の高い、ほっそりとした黒髪の女性が立っていた。顔にはベールをかけ、顎の周りにはマントを引き寄せている。彼女の息は速く、荒く、しなやかな体の隅々までが強い感情に震えていた。
「さて、」とミルヴァートンは言った。「君のせいで良い夜の休息を失ったよ、お嬢さん。それだけの価値があることを願うね。他の時間には来られなかったのかね?」
女性は首を振った。
「まあ、来られなかったのなら仕方ない。伯爵夫人が厳しい女主人なら、今が彼女に一矢報いるチャンスだ。おや、お嬢さん、何に震えているんだ? そうだ。落ち着きたまえ。さて、仕事に取り掛かろうじゃないか。」
彼は机の引き出しから手帳を取り出した。「君は、ダルベール伯爵夫人を窮地に陥れる手紙を五通持っていると言う。君はそれを売りたい。私はそれを買いたい。ここまではいい。あとは値段を決めるだけだ。もちろん、手紙を検分させてもらいたい。もしそれが本当に上物なら――なんてことだ、君か!」
女性は一言も発さず、ベールを上げ、顎からマントを落とした。ミルヴァートンの前に現れたのは、暗く、整った、はっきりとした顔立ちだった――鷲鼻、硬くきらめく目を縁取る力強い黒い眉、そして危険な笑みを浮かべた、まっすぐな薄い唇の口。
「私よ」と彼女は言った。「あなたのせいで人生を滅茶苦茶にされた女よ。」
ミルヴァートンは笑ったが、その声には恐怖が震えていた。「君は実に頑固だったからな」と彼は言った。「なぜ私をそこまで追い詰めたのだ? 保証するが、私は自分から蠅一匹傷つけたりはしない。だが、誰にでも仕事というものがある。私に何ができた? 私は君が払える範囲の値段をつけた。君が払わなかったのだ。」
「それであなたは手紙を私の夫に送った。そして彼は――かつて生きた中で最も高潔な紳士、私がその靴紐を結ぶ資格すらなかったほどの男――彼はその勇敢な心を打ち砕かれて死んだ。覚えているでしょう、あの最後の夜、私がこのドアを通って来た時、慈悲を乞い、祈ったのを。あなたは私の顔を見て笑った。今笑おうとしているようにね。ただ、あなたの臆病な心が唇の震えを止められないだけ。そう、あなたは二度とここで私に会うとは思わなかったでしょうね。でも、あの夜が私に教えてくれたのよ。どうすればあなたと顔と顔を合わせて、二人きりで会えるかをね。さあ、チャールズ・ミルヴァートン、何か言うことはある?」
「私を脅せるとは思うな」と彼は立ち上がりながら言った。「声を上げさえすれば、使用人を呼んで君を逮捕させることだってできる。だが、君の当然の怒りには酌量しよう。来たようにすぐ部屋を出て行け。そうすればこれ以上は何も言わん。」
女性は手を胸にしまい込み、その薄い唇には同じ死のような笑みを浮かべて立っていた。
「あなたはもう、私の人生を滅茶苦茶にしたように、誰の人生も滅茶苦茶にはさせない。私の心を締め上げたように、もう誰の心も締め上げさせない。私はこの世から毒物を排除する。くらえ、この犬め! ――これでも! ――これでも! ――これでも!」
彼女は小さなきらめくリボルバーを引き抜き、ミルヴァートンのシャツの胸元から二フィートと離れていない銃口から、弾倉を次々と彼の体に撃ち込んだ。彼は身をすくめ、そしてテーブルの上に前のめりに倒れ、激しく咳き込みながら書類をかきむしった。それからよろめきながら立ち上がり、もう一発撃たれ、床に転がった。「やられた」と彼は叫び、動かなくなった。女性は彼をじっと見つめ、その仰向けの顔に踵をすりつけた。彼女は再び見たが、音も動きもなかった。鋭い衣擦れの音が聞こえ、夜の空気が熱のこもった部屋に吹き込み、復讐者は去った。
我々が介入したとしても、男をその運命から救うことはできなかっただろう。しかし、女がミルヴァートンの縮こまる体に次々と弾丸を撃ち込むのを見て、私が飛び出そうとした時、ホームズの冷たく強い手が私の手首を掴むのを感じた。私はその固く、制止する握りのすべての論理を理解した――これは我々の関知することではない、悪党に正義が下ったのだ、我々には我々の義務と目的があり、それを見失ってはならないのだ、と。しかし、女が部屋から駆け出すやいなや、ホームズは素早く静かな足取りで、もう一方のドアのところへ行っていた。彼は錠に鍵を回した。それと同時に、家の中で声が聞こえ、慌ただしい足音がした。リボルバーの銃声が家中の者を起こしたのだ。完璧な冷静さで、ホームズは金庫へ滑るように移動し、両腕に手紙の束を抱え、それらをすべて暖炉に注ぎ込んだ。彼はそれを何度も何度も繰り返し、金庫は空になった。誰かがドアの取っ手を回し、外からドアを叩いた。ホームズは素早くあたりを見回した。ミルヴァートンにとって死の使者となった手紙が、彼の血でまだらになり、テーブルの上に横たわっていた。ホームズはそれを燃え盛る書類の中に放り込んだ。それから彼は外のドアから鍵を抜き、私の後を追って通り抜け、外側から施錠した。「こっちだ、ワトソン」と彼は言った。「この方向なら庭の壁を乗り越えられる。」
これほど早く警報が広がるとは信じられなかった。振り返ると、巨大な家は一面の光の洪水だった。正面玄関は開け放たれ、人影が私道を駆け下りてくる。庭全体が人でごった返しており、我々がベランダから現れると、一人の男が狩りの雄叫びを上げ、我々のすぐ後を追ってきた。ホームズは敷地を完璧に知っているようで、彼は小さな木々の植え込みを素早く縫って進み、私は彼のすぐ後を追い、先頭の追跡者は我々の後ろで息を切らしていた。我々の行く手を阻んだのは六フィートの壁だったが、彼はそのてっぺんに飛び乗り、越えた。私が同じようにした時、後ろの男の手が私の足首を掴むのを感じたが、私は蹴って自由になり、草の生えた笠石をよじ登った。私は茂みの中に顔から落ちたが、ホームズは一瞬で私を立たせ、二人で広大なハムステッド・ヒースを駆け抜けた。我々は二マイルほど走っただろうか、ついにホームズが立ち止まり、熱心に耳を澄ませた。我々の後ろは完全な静寂だった。我々は追跡者を振り切り、安全だった。
私が記録したこの驚くべき体験の翌日、我々が朝食を終え、朝のパイプを燻らせていると、スコットランド・ヤードのレストレード氏が、非常に厳粛で印象的な様子で、我々の質素な居間に案内されてきた。
「おはようございます、ホームズさん」と彼は言った。「おはようございます。今、大変お忙しいでしょうか?」
「あなたのお話を聞く時間くらいはありますよ。」
「もし、特に何も手持ちの事件がなければ、ハムステッドで昨夜起こったばかりの、実に驚くべき事件で我々を助けていただけないかと思いましてね。」
「おや!」とホームズは言った。「それは何です?」
「殺人です――非常に劇的で驚くべき殺人。あなたがこういうものにどれほど熱心か存じておりますので、アップルドア・タワーズまで足を運んでいただき、あなたのご助言を賜れれば、大変ありがたいのですが。これはありふれた犯罪ではありません。我々はこのミルヴァートン氏にしばらく目をつけておりまして、ここだけの話、彼は少々悪党でした。彼は脅迫目的で使う書類を所持していたことが知られています。これらの書類は殺人犯によってすべて焼かれました。価値のある品は何も盗まれていません。犯人たちは社会的地位の高い人物で、その唯一の目的は社会的な暴露を防ぐことだったのでしょう。」
「犯人たち?」とホームズは言った。「複数ですか?」
「ええ、二人いました。彼らは現行犯で捕まるところでした。足跡があり、人相書きもあります。彼らを追跡できる確率は十中八九です。最初の男は少々すばしっこかったですが、二人目は下働きの庭師に捕まり、もみ合った末にようやく逃げました。中肉中背で、がっしりした体つきの男――角張った顎、太い首、口髭、目にはマスクをしていたそうです。」
「それはかなり曖昧ですな」とシャーロック・ホームズは言った。「おや、それはまるでワトソンの人相書きのようだ!」
「本当ですね」と警部は面白そうに言った。「ワトソンさんの人相書きのようかもしれません。」
「さて、残念ながらお力にはなれませんな、レストレード君」とホームズは言った。「実のところ、私はこのミルヴァートンという男を知っており、彼をロンドンで最も危険な男の一人だと考えていました。そして、法が触れることのできない犯罪というものがあり、それゆえに、ある程度は私的な復讐が正当化されると考えています。いえ、議論しても無駄です。私の心は決まっています。私の同情は被害者よりもむしろ犯人たちにあり、この事件は扱いません。」
ホームズは我々が目撃した悲劇について、私に一言も語らなかった。しかし、その朝ずっと、彼が最も物思いにふける気分にあることに私は気づいていた。そして、その虚ろな目と上の空の様子から、何かを記憶から呼び起こそうと努めている男の印象を私に与えた。我々が昼食の最中だった時、彼は突然跳ねるように立ち上がった。「そうだ、ワトソン、分かったぞ!」と彼は叫んだ。「帽子を取れ! 私と来い!」
彼は全速力でベーカー街を下り、オックスフォード街に沿って走り、我々はほとんどリージェント・サーカスに到達した。ここの左手側に、当代の名士や美女の写真で満たされたショーウィンドウがある。ホームズの目はその中の一枚に釘付けになり、彼の視線を追うと、私は宮廷服をまとい、高貴な頭に高いダイヤモンドのティアラをつけた、威厳と気品のあるご婦人の写真を見た。私はその優美にカーブした鼻を、際立った眉を、まっすぐな口を、そしてその下にある力強い小さな顎を見た。そして、彼女の夫であった偉大な貴族であり政治家の、由緒ある称号を読んだ時、私は息を呑んだ。私の目はホームズの目と合い、彼はショーウィンドウから離れる我々に、唇に指を当てた。
六つのナポレオン
スコットランド・ヤードのレストレード氏が夕刻に我々のもとをふらりと訪れるのは、そう珍しいことではなかった。そしてシャーロック・ホームズにとって彼の訪問は歓迎すべきものだった。なぜなら、それによって彼は警察本部で起こっているすべてのことと接触を保つことができたからだ。レストレードがもたらすニュースの見返りとして、ホームズは常に、その刑事が従事しているいかなる事件の詳細にも注意深く耳を傾ける準備ができており、時折、積極的に干渉することなく、自身の広大な知識と経験から引き出したヒントや示唆を与えることができた。
この特定の夜、レストレードは天気と新聞について話した。それから彼は黙り込み、思案顔で葉巻をふかしていた。ホームズは鋭く彼を見た。
「何か注目すべき事件でも?」と彼は尋ねた。
「いえいえ、ホームズさん――特にこれといったものは。」
「では、それについて話したまえ。」
レストレードは笑った。
「まあ、ホームズさん、何か気になることがあるのを否定しても仕方ありません。ですが、あまりに馬鹿げた話なので、あなたを煩わせるのをためらったのです。一方で、些細ではありますが、間違いなく奇妙な事件でして、あなたが常軌を逸したものすべてに興味をお持ちなのは存じております。しかし、私の意見では、これは我々の分野というより、ワトソン博士の分野に属するものでしょう。」
「病気かね?」と私は言った。
「いずれにせよ、狂気です。それも奇妙な狂気。このご時世に、ナポレオン一世を憎むあまり、目にする彼の像なら何でも壊してしまうような人間がいるとは、お思いにならないでしょう。」
ホームズは椅子に深くもたれかかった。
「それは私の仕事ではないな」と彼は言った。
「その通り。私もそう言いました。しかし、その男が自分のものではない像を壊すために強盗を働くとなると、話は医者から警察官へと移ってきます。」
ホームズは再び身を起こした。
「強盗! それは面白くなってきた。詳細を聞かせてもらおう。」
レストレードは官給の手帳を取り出し、そのページから記憶を新たにした。
「最初の事件が報告されたのは四日前です」と彼は言った。「ケニントン・ロードで絵画や彫像を売る店を構える、モース・ハドソンという男の店でした。助手が店の正面を少し離れた隙に、ガシャンという音が聞こえ、急いで戻ると、カウンターに他の美術品と共に置かれていたナポレオンの石膏像が、粉々に砕け散っていました。彼は通りに飛び出しましたが、何人かの通行人が男が店から走り去るのを見たと証言したものの、誰一人見つけることも、その悪党を特定する手がかりを得ることもできませんでした。これは時折起こる、無意味なフーリガン行為の一つと思われ、担当巡査にはそのように報告されました。石膏像は数シリング以上の価値はなく、事件全体が特別な捜査をするにはあまりに子供じみているように思われました。」
「しかし、二番目の事件はより深刻で、またより奇妙でした。それは昨夜起こったばかりです。」
「ケニントン・ロードで、モース・ハドソンの店から数百ヤードと離れていない場所に、バーニコット医師という名の高名な開業医が住んでいます。彼はテムズ川南岸で最大級の診療所を構えています。彼の住居兼主診察室はケニントン・ロードにありますが、二マイル離れたロウアー・ブリクストン・ロードに分院と薬局を持っています。このバーニコット医師はナポレオンの熱狂的な崇拝者で、彼の家はフランス皇帝に関する本や絵画、遺物で満ちています。少し前に彼はモース・ハドソンから、フランスの彫刻家ドゥヴィーヌによる有名なナポレオンの頭部の石膏像を、二つ複製で購入しました。一つはケニントン・ロードの家の玄関ホールに、もう一つはロウアー・ブリクストンの分院の暖炉の上に置きました。さて、今朝バーニコット医師が階下に降りてきたところ、夜の間に家に強盗が入っていたことに驚きましたが、盗まれたものは玄関ホールの石膏の頭部だけでした。それは外に持ち出され、庭の壁に激しく叩きつけられており、その下で粉々になった破片が発見されました。」
ホームズは両手をこすり合わせた。
「これは確かに非常に斬新だ」と彼は言った。
「お気に召すかと思いました。しかし、まだ終わりではありません。バーニコット医師は十二時に分院へ行くことになっており、そこへ到着した時の彼の驚きようはご想像いただけるでしょう。窓が夜の間に開けられ、二つ目の胸像の破片が部屋中に散らばっていたのです。それは置かれていた場所で粉々に砕かれていました。どちらの事件でも、この悪戯を働いた犯人あるいは狂人につながる手がかりは何もありませんでした。さて、ホームズさん、これで事実はすべてです。」
「それは奇妙、いや、奇怪とさえ言える」とホームズは言った。「バーニコット医師の部屋で壊された二つの胸像は、モース・ハドソンの店で破壊されたものと全く同じ複製品だったのか、伺ってもいいかね?」
「同じ鋳型から取られたものです。」
「その事実は、像を壊す男がナポレオンへの一般的な憎悪に影響されているという説に反するはずだ。ロンドンに偉大な皇帝の像が何百と存在するであろうことを考えれば、無差別に偶像を破壊する者が、偶然にも同じ胸像の三つの複製から始めるというような偶然は、考えにくい。」
「ええ、私もあなたと同じように考えました」とレストレードは言った。「しかし一方で、このモース・ハドソンはロンドンのその地域で胸像を扱う商人であり、この三つが何年もの間、彼の店にあった唯一のものでした。ですから、あなたがおっしゃるように、ロンドンには何百もの像がありますが、この三つがその地区では唯一のものだった可能性は非常に高い。したがって、地元の狂信者がそれらから始めたのでしょう。どう思われますか、ワトソン博士?」
「単一狂の可能性に限界はありません」と私は答えた。「現代フランスの心理学者が『イデー・フィクス』[訳注:固定観念]と呼ぶ状態があります。それは些細な性質のものでありながら、他のすべての点では完全な正気を伴うことがあります。ナポレオンについて深く読んだ男、あるいは大戦を通じて何らかの世襲的な家の損害を受けた男が、そのような『イデー・フィクス』を形成し、その影響下でどんな奇怪な暴挙も可能になることは、考えられないことではありません。」
「それでは駄目だ、ワトソン君」とホームズは首を振りながら言った。「なぜなら、いかなる『イデー・フィクス』も、君の興味深い単一狂患者に、これらの胸像がどこに置かれているかを見つけ出させはしないからだ。」
「では、あなたはどのように説明しますか?」
「説明しようとはしない。ただ、その紳士の奇行にはある種の方法論があることだけを指摘しておこう。例えば、バーニコット医師の玄関ホールでは、物音が家族を起こす可能性があったため、胸像は壊される前に外に持ち出された。一方、分院では、警報の危険が少なかったため、置かれた場所で粉々にされた。この事件は馬鹿げたほど些細に見えるが、私の最も古典的な事件のいくつかが、最も見込みのない始まり方をしたことを思い返すと、些細なことと呼ぶ勇気はない。覚えているだろう、ワトソン、アバネッティ家の恐ろしい事件が最初に私の注意を引いたのは、暑い日にパセリがバターにどれだけ深く沈んでいたか、ということだった。だから、君の三つの壊れた胸像を笑うわけにはいかんのだよ、レストレード君。そして、これほど奇妙な一連の出来事に何か新たな進展があれば、ぜひ聞かせてもらいたい。」
我が友が待ち望んでいた事件の進展は、彼の想像をはるかに超え、迅速かつ悲劇的な形で訪れた。翌朝、私がまだ自室で身支度を整えていると、ドアを叩く音がしてホームズが入ってきた。その手には電報が握られていた。彼はそれを読み上げた。
「ケンジントン、ピット街一三一番地へ、至急来られたし。――レストレード。」
「いったい、何事かね?」と私は尋ねた。
「分からん――何が起きてもおかしくない。だが、どうやらあの石膏像事件の続報らしい。だとすれば、我らが石膏像破壊犯はロンドンの別の地区で活動を始めたということだ。ワトソン、テーブルにコーヒーがある。馬車は玄関で待たせてあるぞ。」
三十分後、我々はピット街に到着した。ロンドンの活気あふれる喧騒のすぐ脇にある、静かな袋小路のような場所だ。一三一番地は、どれもこれも胸を張るでもなく、いかにも堅実で、およそロマンとは無縁の家が立ち並ぶ一角にあった。馬車が乗りつけると、家の前の鉄柵に沿って野次馬がずらりと並んでいるのが見えた。ホームズは口笛を吹いた。
「おやおや! これは少なくとも殺人未遂だな。それくらいでなければ、ロンドンの使い走りの少年たちを引きつけられはしない。あの男の丸まった肩と伸びきった首を見れば、暴力沙汰があったのは明らかだ。ワトソン、これはどうだ? 一番上の段は洗い流されているが、他は乾いている。足跡は、まあ、十分すぎるほどだ! よしよし、レストレードが表の窓際にいる。すぐにすべてが分かるだろう。」
警部は非常に険しい顔で我々を迎え、居間へと案内した。そこでは、ひどく身なりの乱れた初老の紳士が、フランネルのガウンを羽織り、興奮した様子で部屋を行ったり来たりしていた。彼はこの家の主人――セントラル・プレス・シンジケートのホレス・ハーカー氏として紹介された。
「またナポレオン像の件です」とレストレードは言った。「昨夜、ホームズさん、あなたはこの事件に興味を示しておられたようでしたからね。事態がはるかに深刻な局面を迎えた今、立ち会っていただければお喜びになるかと思いまして。」
「それで、どう深刻になったのかね?」
「殺人です。ハーカーさん、こちらの紳士方に何があったのか、詳しくお話しいただけますかな?」
ガウン姿の男は、この上なく憂鬱な顔で我々の方を向いた。
「まったく奇妙な話です」と彼は言った。「私は生涯、他人のニュースばかり集めてきたというのに、いざ本物のニュースが我が身に降りかかってくると、混乱し、動揺するばかりで、二言三言もまともに話せない。もし私がジャーナリストとしてここに来たなら、自分自身に取材して、どの夕刊紙にも二段抜きの大見出しで記事を載せられたでしょうに。現状は、入れ替わり立ち替わりやってくる人々に同じ話を繰り返し、貴重なネタを無料で提供しているだけで、自分では何の役にも立てられない。しかし、シャーロック・ホームズさん、あなたのお名前はかねがね伺っております。この奇妙な事件を解明してくださるなら、私が話す手間も報われるというものです。」
ホームズは腰を下ろし、耳を傾けた。
「すべては、四ヶ月ほど前にこの部屋のために買った、あのナポレオンの胸像を中心に起こったようです。ハイ・ストリート駅から二軒隣のハーディング兄弟商会で安く手に入れたものです。私のジャーナリストとしての仕事は夜に行うことが多く、明け方まで筆を執ることも珍しくありません。今日もそうでした。三時頃、家の最上階の奥にある書斎に座っていると、階下で何やら物音が聞こえた気がしました。耳を澄ましましたが、二度目はなく、外の音だろうと結論づけました。ところが、その五分後、突如として恐ろしい叫び声が響き渡ったのです――ホームズさん、あれほどおぞましい音は聞いたことがありません。生涯、耳から離れないでしょう。私は一、二分、恐怖で凍りついていました。それから火かき棒を掴んで階下へ向かいました。この部屋に入ると、窓が大きく開け放たれており、暖炉の上から胸像がなくなっていることにすぐ気づきました。なぜ泥棒がそんなものを盗むのか、私にはさっぱり理解できません。ただの石膏像で、何の価値もない代物ですから。
「ご覧になれば分かりますが、あの開いた窓から出れば、大股で玄関の階段まで届きます。泥棒は明らかにそうしたのでしょう。そこで私は回り込んでドアを開けました。暗闇に足を踏み出した途端、そこに横たわっていた死体に躓きそうになりました。明かりを取りに戻ると、哀れな男が、喉を大きく切り裂かれ、あたり一面血の海と化していました。彼は仰向けに倒れ、膝を立て、口を恐ろしく開けていた。きっと夢に出てくるでしょう。私は警察の笛を吹くのがやっとで、そのまま気を失ったに違いありません。次に気づいた時には、玄関ホールで警官が私を見下ろしていました。」
「それで、殺された男は誰だったのかね?」とホームズが尋ねた。
「身元を示すものは何もありません」とレストレードは言った。「遺体は死体安置所で見られますが、今のところ何も分かっていません。背の高い、日焼けした、非常に屈強な男で、三十歳そこそこでしょう。身なりは貧しいですが、労働者というわけでもなさそうです。彼のそばの血溜まりには、角の柄の折りたたみナイフが落ちていました。凶器なのか、それとも被害者の所持品なのかは分かりません。衣服に名前はなく、ポケットにはリンゴ一個、紐数本、一シリングのロンドン地図、そして一枚の写真が入っていただけです。これがその写真です。」
それは明らかに小型カメラで撮られたスナップ写真だった。写っているのは、用心深く、鋭い顔つきをした猿のような男で、太い眉と、ヒヒの口吻のように突き出た非常に特徴的な顎を持っていた。
「それで、胸像はどうなったのかね?」とホームズは、その写真を注意深く吟味した後に尋ねた。
「あなたが来られる直前に知らせがありました。カムデン・ハウス・ロードにある空き家の前庭で見つかったそうです。粉々に砕かれていたと。今から見に行くところですが、ご一緒にどうですかな?」
「もちろんだ。その前に、少しあたりを調べておきたい。」
彼は絨毯と窓を調べた。「犯人はよほど足が長いか、さもなくば非常に身軽な男だ」と彼は言った。「下に地下室への入り口があることを考えると、あの窓枠に手をかけ、窓を開けるのは並大抵のことではない。戻るのは比較的簡単だったろうが。ハーカーさん、我々と一緒に、あなたの胸像の残骸を見に行かれますかな?」
意気消沈したジャーナリストは、書き物机に腰を下ろしていた。
「何とか記事にしなければなりません」と彼は言った。「もっとも、夕刊の第一版はとっくに詳細を報じて出回っていることでしょう。まったく、ついていない! ドンカスターで観覧席が崩落した時のことを覚えておいでですか? あの時、私はその観覧席にいた唯一のジャーナリストだったのに、私の新聞だけがその記事を載せられなかった。あまりの衝撃で筆が執れなかったのです。そして今度は、我が家の玄関先で起きた殺人事件の記事でさえ、出し遅れることになるのでしょう。」
我々が部屋を出る時、彼のペンが原稿用紙の上を甲高く走る音が聞こえてきた。
胸像の破片が見つかった場所は、わずか数百ヤードしか離れていなかった。我々は初めて、かの偉大な皇帝の姿を目にした。何者かの心に、これほど狂乱的で破壊的な憎悪を掻き立てたと思われるその姿を。それは粉々の破片となって、草の上に散らばっていた。ホームズはいくつかの破片を拾い上げ、注意深く調べた。その真剣な表情と的を射た仕草から、彼がついに手がかりを掴んだのだと私は確信した。
「どうです?」とレストレードが尋ねた。
ホームズは肩をすくめた。
「まだ先は長い」と彼は言った。「だが――だがしかし――まあ、いくつか示唆に富む事実はある。この奇妙な犯罪者の目には、この取るに足らない胸像を手に入れることが、人間の命よりも価値があった。それが一点。それから、もし壊すことだけが目的なら、家の中や、家のすぐ外で壊さなかったという奇妙な事実がある。」
「あの男と鉢合わせして、動転し、慌てふためいたのでしょう。自分が何をしているのか、分からなくなっていたに違いありません。」
「まあ、それも尤もだ。だが、君には特にこの家の位置に注意を払ってもらいたい。胸像が破壊された、この庭のある家の位置にだ。」
レストレードはあたりを見回した。
「空き家でしたから、庭で邪魔されることはないと分かっていたのでしょう。」
「そうだ。だが、通りのもっと先にもう一軒、空き家がある。ここに来る前に必ず通ったはずだ。運ぶ距離が長くなるほど誰かに会う危険が増すのは明らかなのに、なぜそこで壊さなかったのか?」
「降参です」とレストレードは言った。
ホームズは我々の頭上にある街灯を指さした。
「ここでは自分のしていることが見えたが、あそこでは見えなかった。それが理由だ。」
「なんと! その通りですな」と警部は言った。「そういえば、バーニコット医師の胸像も、彼の赤いランプからさほど遠くない場所で壊されていました。さて、ホームズさん、その事実をどう扱えばいいのでしょう?」
「記憶し、記録しておくことだ。後になって、これと関連する何かが現れるかもしれん。レストレード、君はこれからどうするつもりかね?」
「私の考えでは、最も現実的な方法は死者の身元を特定することです。それはさほど難しくないはず。彼が誰で、仲間が誰か分かれば、昨夜ピット街で何をしていたのか、そしてホレス・ハーカー氏の玄関先で彼に会い、殺したのは誰なのかを知る上で、良いとっかかりになるでしょう。そうは思いませんか?」
「確かにそうだろう。だが、私ならそのようには事件に臨まない。」
「では、どうなさるのです?」
「ああ、私のやり方で君を惑わすわけにはいかない。君は君のやり方で、私は私のやり方で進めるのがよかろう。後で情報を突き合わせれば、互いに補い合えるはずだ。」
「分かりました」とレストレードは言った。
「もしピット街に戻るなら、ホレス・ハーカー氏に会うといい。私からの伝言として、私の考えは完全に固まった、昨夜彼の家にいたのは、ナポレオンに憑かれた危険な殺人狂に違いない、と伝えてくれ。彼の記事の役に立つだろう。」
レストレードは目を丸くした。
「本気でそう信じているのですか?」
ホームズは微笑んだ。
「そう見えないかね? まあ、そうではないかもしれん。だが、ホレス・ハーカー氏とセントラル・プレス・シンジケートの購読者たちの興味を引くことは間違いない。さて、ワトソン、今日は長く、少々複雑な一日になりそうだ。レストレード、もし都合がつけば、今夜六時にベーカー街で会いたい。それまで、この死者のポケットから見つかった写真は預かっておこう。もし私の推理が正しければ、今夜、ちょっとした遠征に君の同行と助力を請わねばならなくなるかもしれん。では、また後で。幸運を祈る!」
シャーロック・ホームズと私は共にハイ・ストリートを歩き、胸像が購入されたハーディング兄弟商会に立ち寄った。若い店員が言うには、ハーディング氏は午後まで不在で、自分は新入りなので何も情報を提供できないとのことだった。ホームズの顔には失望と苛立ちが浮かんだ。
「まあ、まあ、すべてが我々の思い通りに進むわけではないさ、ワトソン」と、彼はついに言った。「ハーディング氏が午後まで戻らないのなら、また出直すしかない。君も察しているだろうが、私はこれらの胸像の出所を突き止め、その数奇な運命を説明しうる何か特別な事情がないか探ろうとしているのだ。次はケニントン・ロードのモース・ハドソン氏の所へ向かい、彼が何か手がかりを与えてくれるか見てみよう。」
馬車で一時間ほど行くと、その画商の店に着いた。彼は小柄で恰幅が良く、赤ら顔で、癇癪持ちな男だった。
「ええ、そうですとも。この私の店のカウンターの上で、ですよ」と彼は言った。「一体何のために税金を払っているのか分かったものじゃない。どんなならず者でも店に入り込んできて品物を壊していく。そうです、バーニコット医師に二つの像を売ったのは私です。とんでもないことです! ニヒリストの陰謀ですよ、きっと。無政府主義者でもなけりゃ、像を壊して回るなんて真似はしません。赤色共和主義者――私は連中をそう呼んでます。どこから像を仕入れたか? それが何の関係があるんですか。まあ、どうしても知りたいというなら、ステップニーのチャーチ街にあるゲルダ――商会から仕入れました。業界では名の知れた店で、もう二十年になります。いくつ持っていたか? 三つです――二つと一つで三つ――バーニコット医師のが二つと、白昼堂々このカウンターで壊されたのが一つ。この写真を知っているか? いや、知りませんな。……いや、待てよ、知っている。これはベッポじゃないか。イタリア人の出来高払いの職人で、店で重宝していました。彫り物もできるし、金箔を貼ったり、額縁を作ったり、雑用もこなしました。あの男は先週辞めて、それ以来音沙汰なしです。どこから来て、どこへ行ったのかも知りません。ここにいた間は、特に問題はありませんでした。胸像が壊される二日前にいなくなりました。」
「さて、モース・ハドソンから得られるのは、まあ、これくらいが妥当なところだろう」と、店を出ながらホームズは言った。「ケニントンとケンジントンの両方に、このベッポという共通項が見つかった。十マイル馬車を走らせた甲斐はあったというものだ。さあ、ワトソン、胸像の源流、ステップニーのゲルダ――商会へ向かおう。あそこで何か手がかりが得られなければ、それこそ驚きだ。」
我々は立て続けに、洒落たロンドン、ホテルのロンドン、劇場のロンドン、文士のロンドン、商業のロンドン、そして最後に、港湾のロンドンを通り抜け、ついに十万の魂が住まう川沿いの街へとたどり着いた。そこでは安アパートが密集し、ヨーロッパ中から追いやられた者たちの熱気と悪臭が立ち込めていた。かつては裕福なシティの商人たちの住居であった広々とした大通りに、我々が探していた彫刻製作所はあった。外には記念碑的な石造物で埋め尽くされた広大な庭があり、中には五十人ほどの職人たちが彫刻や型取りをしている広い部屋があった。支配人は金髪の大きなドイツ人で、我々を丁重に迎え、ホームズのすべての質問に明快に答えてくれた。帳簿を調べると、ドヴィーヌ作のナポレオン頭部の大理石像から何百もの石膏像が作られたこと、しかし一年ほど前にモース・ハドソンに送られた三つは六つ一組の半数で、残りの三つはケンジントンのハーディング兄弟商会に送られたことが分かった。その六つが他の石膏像と異なる理由はなく、誰かがそれを破壊しようと望む理由など考えもつかないと、彼はその考えを一笑に付した。卸値は六シリングだが、小売業者は十二シリングかそれ以上で売るだろうとのことだった。石膏像は顔の両側から取った二つの型で作られ、その二つの横顔の石膏を合わせて完全な胸像にする。作業は通常、我々がいたこの部屋でイタリア人によって行われる。完成した胸像は、乾燥させるために廊下のテーブルに置かれ、その後保管される。彼が話せるのはそれだけだった。
しかし、写真を見せると、支配人は驚くべき反応を示した。彼の顔は怒りで紅潮し、その青いチュートン人の瞳の上で眉が険しく寄せられた。
「ああ、この悪党め!」と彼は叫んだ。「ええ、いかにも、よく知っております。うちは昔から評判の良い工場でして、警察沙汰になったのは、後にも先にもこの男の件だけです。もう一年以上前のことになります。通りで別のイタリア人をナイフで刺し、警察に追われてこの工場に逃げ込んできて、ここで捕まったのです。ベッポという名でした――苗字は知りませんが。あんな人相の男を雇った私が馬鹿でした。しかし、腕は良かった――最高の職人の一人でしたよ。」
「それで、どうなったのですか?」
「刺された男は一命を取り留め、ベッポは一年で済みました。もう出所しているはずですが、ここに顔を出す度胸はないでしょう。彼の従兄弟がここで働いていますから、居場所を教えてくれるかもしれません。」
「いや、いや」とホームズは叫んだ。「従兄弟には一言も――一言も漏らさないでいただきたい。これは非常に重要な問題で、調べを進めるほどに、その重要性が増してくる。あなたが帳簿でその石膏像の販売に言及された時、日付が去年の六月三日であることに気づきました。ベッポが逮捕された日を教えていただけますかな?」
「給与台帳を見れば、おおよそ分かります」と支配人は答えた。「ええ」と彼はページをいくつかめくった後で続けた。「彼への最後の支払いは五月二十日です。」
「ありがとう」とホームズは言った。「これ以上、あなたのお時間とご忍耐を煩わせる必要はなさそうだ。」
我々の調査については口外せぬよう、最後にもう一度念を押し、我々は再び西へと顔を向けた。
午後もだいぶ更けてから、我々はレストランでようやく慌ただしい昼食にありついた。入り口のニュース速報には「ケンジントンの凶行。狂人による殺人」とあり、新聞の内容は、ホレス・ハーカー氏が結局のところ記事を掲載できたことを示していた。事件の全容が、非常に扇情的で華美な筆致で二段にわたって書かれていた。ホームズはそれを薬味立てに立てかけ、食事をしながら読んだ。一度か二度、彼はくすりと笑った。
「これは上出来だ、ワトソン」と彼は言った。「これを聞いてみたまえ。
『この事件に関して、意見の相違があり得ないことを知るのは喜ばしい。というのも、警察の中でも最も経験豊富なレストレード警部と、著名な探偵顧問シャーロック・ホームズ氏が、かくも悲劇的な結末を迎えたこの奇怪な一連の事件は、計画的な犯罪というよりはむしろ狂気に起因するものである、との結論にそれぞれ達したからである。精神の錯乱以外に、これらの事実を説明することはできない。』
「新聞とは、ワトソン、使い方さえ知っていれば、実に価値ある機関だ。さて、食事が済んだなら、ケンジントンへ戻ってハーディング兄弟商会の支配人がこの件について何と言うか聞いてみよう。」
その大商店の創設者は、活発で歯切れのいい小柄な人物で、身なりが良く、機敏で、頭脳明晰、弁も立つ男だった。
「ええ、旦那、夕刊の記事はもう読みましたよ。ホレス・ハーカー氏はうちのお得意様です。数ヶ月前にあの胸像を納めました。あの手の胸像はステップニーのゲルダ――商会から三つ注文しましてね。もう全部売れました。誰に、ですって? ああ、販売台帳を見ればすぐにお教えできますよ。ええ、ここに記録があります。一つはご覧の通りハーカー氏に、一つはチジックのラバーナム・ヴェイル、ラバーナム・ロッジのジョサイア・ブラウン氏に、そしてもう一つはレディングのロウワー・グローヴ・ロードのサンデフォード氏に。いえ、写真でお見せになったこの顔は見たことがありません。一度見たら忘れられないでしょうな、これほど醜い顔は滅多にありませんから。従業員にイタリア人はいるか? ええ、職人や清掃員の中に何人かおります。彼らがその気になれば、販売台帳を盗み見ることもできるでしょう。あの台帳を特に見張っている理由はありませんからな。いやはや、実に奇妙な事件です。もし調査で何か分かりましたら、ぜひ教えていただきたいものです。」
ハーディング氏が証言している間、ホームズはいくつかのメモを取っていた。事態の展開に彼がすっかり満足しているのが見て取れた。しかし彼は、急がなければレストレードとの約束に遅れる、とだけ言うと、それ以上は何も言わなかった。案の定、我々がベーカー街に着いた時には警部はすでに到着しており、焦燥に駆られて部屋を行ったり来たりしていた。その得意げな様子から、彼の一日の働きが無駄ではなかったことがうかがえた。
「どうですかな?」と彼は尋ねた。「何か収穫はありましたか、ホームズさん?」
「非常に忙しい一日だったが、まったくの無駄骨というわけでもなかった」と友は説明した。「小売業者と卸売業者の両方に会ってきた。今や、どの胸像もその出所から追跡できる。」
「胸像、ですか」とレストレードは叫んだ。「まあ、まあ、シャーロック・ホームズさん、あなたにはあなたのやり方があるのでしょうし、それに口を挟むつもりはありませんが、私の方があなたより良い仕事をしたと思いますよ。私は死体の身元を突き止めました。」
「ほう、それは本当かね?」
「そして、犯行の動機も。」
「素晴らしい!」
「サフラン・ヒルとイタリア人街を専門とする警部がいましてね。さて、この死体は首にカトリックの紋章を下げており、その肌の色と合わせて、南の出身ではないかと考えました。ヒル警部は彼を一目見るなり、誰だか分かりました。名はピエトロ・ヴェヌッチ、ナポリ出身で、ロンドンでも指折りの殺し屋です。彼はマフィアと繋がりがあります。ご存知の通り、殺人によってその掟を執行する秘密結社です。さあ、これで事件がどう解明され始めるかお分かりでしょう。もう一人の男も恐らくイタリア人で、マフィアの一員です。彼は何らかの形で掟を破った。ピエトロがその追跡に差し向けられた。おそらく、ポケットから見つかった写真は、人違いで刺してしまわないように、その男自身の写真でしょう。彼は男を追い、家に入るのを見届け、外で待ち伏せる。そして揉み合いの末、自らが致命傷を負った。どうですかな、シャーロック・ホームズさん?」
ホームズは賛同するように手を叩いた。
「見事だ、レストレード、見事だ!」と彼は叫んだ。「だが、胸像の破壊についての君の説明が今ひとつ分からなかったな。」
「胸像! あなたはいつまでその胸像にこだわっているのですか。結局のところ、それは取るに足らないことでしょう。せいぜい軽窃盗で、懲役六ヶ月がいいところだ。我々が本当に捜査しているのは殺人事件であり、私はその糸をすべて手中に収めつつあるのですよ。」
「それで、次の段階は?」
「至って簡単です。ヒルと一緒にイタリア人街へ行き、写真の男を見つけ出し、殺人容疑で逮捕する。ご一緒に行きますかな?」
「いや、やめておこう。我々の目的はもっと簡単な方法で達成できると思う。確かなことは言えんがね、何しろすべては――そう、すべては我々の力の及ばない要因次第なのだから。だが、大いに期待している――実際のところ、賭け率はちょうど二対一だ――もし今夜、我々と一緒に来てくれるなら、君が奴を捕らえる手助けができるだろう。」
「イタリア人街で?」
「いや、チジックの方が奴を見つけるには有望な場所だと思う。レストレード、もし今夜私とチジックに来てくれるなら、明日は君とイタリア人街へ行くことを約束しよう。遅れても何の支障もないはずだ。さて、これから数時間、我々は皆、睡眠を取るのがよかろう。出発は十一時より前にはならんだろうし、朝までに戻れる見込みも薄い。レストレード、夕食を共にし、出発の時間までソファで休んでくれたまえ。その間に、ワトソン、至急便の配達人を呼んでくれるとありがたい。手紙を送らねばならんのだが、すぐに届ける必要があるのだ。」
ホームズは夕べを、物置部屋の一つに詰め込まれた古い日刊紙のファイルを漁って過ごした。やがて彼が降りてきた時、その目には勝利の色が浮かんでいたが、調査の結果については我々のどちらにも何も語らなかった。私自身は、彼がこの複雑な事件の様々な紆余曲折をたどった手法を一歩一歩追っていた。我々が到達するであろう目標はまだ見えなかったが、ホームズがこの奇怪な犯罪者が残る二つの胸像に手を出すと予期していることははっきりと理解していた。そのうちの一つは、確かチジックにあったはずだ。我々の旅の目的が、彼を現行犯で捕らえることにあるのは疑いようもなかった。そして私は、友人が夕刊紙に偽の手がかりを紛れ込ませ、犯人に自分の計画を罰せられることなく続けられると思わせた、その狡猾さに感心せずにはいられなかった。ホームズが私にリボルバーを持っていくよう勧めた時も、驚きはしなかった。彼自身は、お気に入りの武器である、弾を込めた猟鞭を手に取っていた。
十一時に四輪馬車が玄関に到着し、我々はそれに乗ってハマースミス橋の向こう側のある地点まで向かった。そこで御者に待つよう指示した。少し歩くと、それぞれが庭を持つ快適な家々が並ぶ、人里離れた道に出た。街灯の光の中、我々はそのうちの一軒の門柱に「ラバーナム・ヴィラ」と書かれているのを読み取った。住人は明らかに就寝しており、玄関ドアの上の欄間窓から庭の小道にぼんやりとした円い光が一つ落ちている以外は、あたりは真っ暗だった。敷地と道を隔てる木の柵が内側に濃い黒い影を落としており、我々はそこに身をかがめた。
「長い待ち時間になりそうだ」とホームズは囁いた。「雨が降っていないのを幸運に感謝せねばな。時間潰しに煙草を吸うことすらできそうにない。しかし、我々の労が報われる可能性は二対一だ。」
しかし、我々の見張りはホームズが恐れていたほど長くはならず、非常に突然で奇妙な形で終わりを告げた。一瞬のうちに、何の物音もなく、庭の門が開き、猿のようにしなやかで素早い黒い人影が庭の小道を駆け上がった。我々はそれがドアの上から投げかけられる光をかすめ、家の黒い影に消えるのを見た。長い沈黙が続き、その間我々は息を殺していた。やがて、ごくかすかなきしむ音が耳に届いた。窓が開けられているのだ。音は止み、再び長い静寂が訪れた。男は家の中へ侵入している。部屋の中で、目隠しランタンの光が突然きらめくのが見えた。彼が探しているものは明らかにそこにはなく、再び別の窓のブラインド越しに、そしてまた別の窓から光が漏れた。
「開いた窓へ行こう。奴が這い出てくるところを捕まえるんだ」とレストレードが囁いた。
しかし、我々が動く前に、男は再び姿を現した。揺らめく光の中に彼が出てきた時、我々は彼が何か白いものを脇に抱えているのを見た。彼は用心深くあたりを見回した。人気のない通りの静けさに安心したのだろう。我々に背を向け、彼は荷物を下に置いた。次の瞬間、鋭く叩く音に続いて、ガチャン、ガラガラという音が響いた。男は自分のしていることにあまりに夢中で、我々が芝生を忍び足で横切る音に気づかなかった。虎のように飛びかかり、ホームズが彼の背中に乗った。その一瞬後、レストレードと私が彼を両手首で押さえつけ、手錠がかけられた。彼をひっくり返すと、身をよじり、怒りに満ちた表情をした、醜い、土気色の顔が我々を睨みつけていた。我々が捕らえたのが、まさしく写真の男だと分かった。
しかし、ホームズが注意を向けていたのは、我々の捕虜ではなかった。玄関の階段にしゃがみ込み、彼は男が家から持ち出したものを、この上なく注意深く調べていた。それはナポレオンの胸像で、今朝我々が見たものとそっくりで、同じように粉々に砕かれていた。ホームズは一つ一つの破片を慎重に光にかざしたが、他のどの石膏の破片とも何ら変わりはなかった。彼が調査を終えたちょうどその時、玄関の明かりがぱっとつき、ドアが開き、家の主人が姿を現した。シャツとズボン姿の、陽気で丸々とした人物だった。
「ジョサイア・ブラウン氏ですな?」とホームズは言った。
「はい、その通りです。そしてあなたは、間違いなくシャーロック・ホームズさんですな? 至急便で送っていただいた手紙を受け取り、言われた通りにしました。内側からすべてのドアに鍵をかけ、事の成り行きを待っていたのです。いやはや、この悪党を捕まえていただいて、実に嬉しい。紳士方、どうぞ中へ入って、何か召し上がってください。」
しかし、レストレードは男を安全な場所へ連行することを急いでいたので、数分後には我々の馬車が呼ばれ、四人全員でロンドンへ向かう道中にあった。捕虜は一言も発しようとせず、もつれた髪の影から我々を睨みつけていた。一度、私の手が彼の届く範囲にあるように見えた時、彼は飢えた狼のようにそれに噛みつこうとした。警察署にしばらく滞在し、彼の衣服を調べたところ、数シリングと長い鞘付きナイフ以外は何も出てこなかったことを知った。ナイフの柄には、新しい血痕が多量に付着していた。
「結構です」と、別れ際にレストレードは言った。「ヒルはこの手の連中をすべて知っていますから、彼の名前もすぐに分かるでしょう。私のマフィア説がうまくいくことがお分かりになるはずです。しかし、ホームズさん、彼を捕らえてくださったその手際の良さには、実に感謝しております。まだ、すべてを理解したわけではありませんが。」
「説明するには、少々時間が遅すぎるようだ」とホームズは言った。「それに、まだ片付いていない詳細が一つ二つある。これは最後まで解明する価値のある事件の一つだ。もし明日、もう一度六時に私の部屋に来てくれるなら、君が今でさえこの事件の全貌を把握していないことを示せると思う。この事件には、犯罪史上、まったく類を見ないいくつかの特徴があるのだ。ワトソン、もし私が君に私のささやかな事件をこれ以上記録することを許すなら、君はナポレオン胸像の奇妙な冒険の記述によって、そのページを活気づけることになると予見するよ。」
翌日の夕方、我々が再び会った時、レストレードは我々の捕虜に関する多くの情報を携えていた。彼の名はベッポ、苗字は不明。イタリア人社会では名の知れたろくでなしだった。かつては腕の良い彫刻家で、堅実な生活を送っていたが、悪の道に走り、すでに二度投獄されていた――一度は軽窃盗で、もう一度は、我々がすでに聞いていたように、同国人を刺した罪で。彼は英語を完璧に話すことができた。胸像を破壊した理由は依然として不明で、その件に関するいかなる質問にも答えることを拒否したが、警察は、彼がゲルダ――商会でこの種の仕事に従事していたことから、これらの胸像が彼自身の手で作られた可能性が非常に高いことを突き止めていた。これらの情報のほとんどは我々がすでに知っていたことだったが、ホームズは礼儀正しく耳を傾けていた。しかし、彼をよく知る私には、彼の心がどこか別の場所にあるのがはっきりと分かり、彼がいつも被っている仮面の下に、不安と期待が入り混じった感情を読み取った。やがて彼は椅子から身を乗り出し、目を輝かせた。玄関のベルが鳴ったのだ。一分後、階段を上る足音が聞こえ、白髪交じりのもみあげを生やした赤ら顔の初老の男が案内されて入ってきた。右手には古風な旅行鞄を提げ、それをテーブルの上に置いた。
「シャーロック・ホームズさんはこちらにおられますか?」
友はお辞儀をして微笑んだ。「レディングのサンデフォード氏ですな?」と彼は言った。
「はい、旦那。少々遅れてしまい申し訳ありません、電車の都合が悪くて。あなたが私にお書きになったのは、私が所有している胸像の件ですな。」
「その通りです。」
「お手紙はここに。あなたはこう書かれていました、『ドヴィーヌ作ナポレオンの複製を手に入れたく、貴殿が所蔵されているものに十ポンドをお支払いする用意があります』と。間違いありませんかな?」
「もちろんです。」
「お手紙には大変驚きました。どうして私がそのようなものを持っているとお知りになったのか、想像もつきませんでしたから。」
「驚かれたのも無理はありませんが、説明は至って簡単です。ハーディング兄弟商会のハーディング氏が、最後の一個をあなたに売ったと言い、あなたの住所を教えてくれたのです。」
「ああ、そういうことでしたか。私がいくらで買ったか、彼は言いましたかな?」
「いいえ、言いませんでした。」
「さて、私は正直者です、さほど裕福ではありませんがね。あの胸像には十五シリングしか払っておりません。あなたから十ポンドをいただく前に、そのことをお伝えすべきだと思いました。」
「その誠実さには敬意を表します、サンデフォードさん。しかし、私が提示した価格ですから、そのつもりでおります。」
「いやはや、ホームズさん、実に気前がいい。おっしゃる通り、胸像は持ってまいりました。これがそうです!」
彼は鞄を開け、ついに我々は、これまで何度も断片で見てきたあの胸像の完全な姿が、テーブルの上に置かれるのを目にした。
ホームズはポケットから一枚の書類を取り出し、十ポンド紙幣をテーブルの上に置いた。
「サンデフォードさん、この証人たちの前で、この書類に署名をいただけますかな。これは単に、あなたがこの胸像に関してこれまで持っていたあらゆる権利を私に譲渡するというものです。ご存知の通り、私は几帳面な男でして、後々どのような事態になるか分かりませんからな。ありがとうございます、サンデフォードさん。こちらがお金です。どうぞ良い夜を。」
我々の訪問者が姿を消すと、シャーロック・ホームズの動きは我々の注意を釘付けにした。彼はまず、引き出しから清潔な白い布を取り出し、テーブルの上に広げた。次に、新しく手に入れた胸像を布の中央に置いた。最後に、彼は猟鞭を手に取り、ナポレオンの頭頂部を鋭く一撃した。像は粉々に砕け散り、ホームズは砕けた残骸に熱心に身をかがめた。次の瞬間、彼は勝利の雄叫びを上げ、一つの破片を掲げた。その中には、プディングの中のプラムのように、丸くて黒い物体が埋め込まれていた。
「紳士諸君」と彼は叫んだ。「かの有名な、ボルジア家の黒真珠を紹介しよう。」
レストレードと私は一瞬黙り込んでいたが、やがて、まるで巧みに作られた芝居のクライマックスのように、二人とも思わず拍手を送った。ホームズの青白い頬に血の気が差し、彼は観客の賞賛を受ける名劇作家のように我々にお辞儀をした。このような瞬間、彼は一瞬、推理機械であることをやめ、賞賛と喝采を愛する人間的な一面をのぞかせるのだった。大衆的な名声には軽蔑をもって背を向ける、あの類まれな誇り高く控えめな性格も、友人からの自発的な驚嘆と賛辞には、心の奥底まで動かされることがあったのだ。
「そうだ、諸君」と彼は言った。「これは現存する世界で最も有名な真珠だ。そして幸運にも、一連の帰納的推理によって、それが失われたデーカー・ホテルのコロンナ公の寝室から、ステップニーのゲルダ――商会で製造された六つのナポレオン胸像の最後の一つである、この内部まで、その行方を突き止めることができた。レストレード、君も覚えているだろう、この貴重な宝石の失踪が巻き起こした大騒ぎと、それを取り戻そうとしたロンドン警視庁の空しい努力を。私自身もこの事件について相談を受けたが、何の手がかりも得られなかった。嫌疑はイタリア人である王女の侍女にかかり、彼女にはロンドンに兄がいることが証明されたが、我々は二人の間の繋がりを突き止めることができなかった。侍女の名はルクレツィア・ヴェヌッチ。そして、二日前に殺されたこのピエトロがその兄であったことは、私の心に疑いの余地はない。古い新聞のファイルを調べてみたところ、真珠の失踪は、ベッポが何らかの暴力犯罪で逮捕されるちょうど二日前のことだった――その逮捕劇は、まさにこれらの胸像が作られていた瞬間に、ゲルダ――商会の工場で起こったのだ。これで君たちにも事件の連なりがはっきりと見えただろう。もちろん、君たちが見ているのは、私に提示された順序とは逆の順序だがね。ベッポは真珠を所持していた。彼はピエトロからそれを盗んだのかもしれないし、ピエトロの共犯者だったのかもしれないし、ピエトロと彼の妹の仲介人だったのかもしれない。どれが正しい解決策であるかは、我々にとって重要ではない。
「重要な事実は、彼が真珠を持っていたということであり、それを身につけていたその瞬間に、彼は警察に追われていたのだ。彼は自分の働く工場へ向かい、この莫大な価値のある獲物を隠すのに数分しかないことを知っていた。さもなければ、身体検査で発見されてしまうだろう。廊下では六つのナポレオンの石膏像が乾かされていた。そのうちの一つはまだ柔らかかった。腕の良い職人であるベッポは、瞬時に湿った石膏に小さな穴を開け、真珠を落とし込み、数回触れて再び穴を塞いだ。見事な隠し場所だった。誰も見つけることはできまい。しかし、ベッポは一年間の禁固刑を宣告され、その間に六つの胸像はロンドン中に散らばってしまった。彼はどれに自分の宝物が入っているか分からなかった。壊してみるしか確かめる方法はなかった。振ってみても何も分からないだろう。石膏が湿っていたので、真珠はそれに付着する可能性が高かったからだ――実際、そうなっていた。ベッポは絶望せず、かなりの創意工夫と忍耐力で捜索を行った。ゲルダ――で働く従兄弟を通じて、胸像を購入した小売店を突き止めた。彼はモース・ハドソンの下で職を見つけ、その方法で三つを追跡した。真珠はそこにはなかった。次に、あるイタリア人従業員の助けを借りて、残りの三つの胸像の行き先を突き止めることに成功した。一つ目はハーカーの所にあった。そこで彼は共犯者に追われ、その共犯者は真珠を失った責任をベッポに問い、その後の乱闘で彼を刺したのだ。」
「もし彼が共犯者だったのなら、なぜ彼の写真を持っていたのだろう?」と私は尋ねた。
「第三者に彼のことを尋ねたい場合に、彼を追跡する手段としてだ。それが明白な理由だ。さて、殺人事件の後、私はベッポがおそらく行動を遅らせるよりも急ぐだろうと計算した。彼は警察が自分の秘密を読み解くことを恐れ、彼らに先を越される前に急いだのだ。もちろん、彼がハーカーの胸像から真珠を見つけなかったとは断言できなかった。それが真珠であるとさえ、確信していたわけではなかった。しかし、彼が何かを探していることは私には明らかだった。なぜなら、彼は他の家を通り過ぎて胸像を運び、ランプが見下ろす庭でそれを壊したからだ。ハーカーの胸像は三つのうちの一つだったので、私が君に言った通り、真珠がその中にある確率は二対一で低かった。残るは二つの胸像で、彼がまずロンドンのものに向かうのは明らかだった。私は第二の悲劇を避けるために家の住人に警告し、我々はそこへ向かい、最高の結果を得た。その時までには、もちろん、我々が追っているのがボルジア家の真珠であることは確信していた。殺された男の名前が、一つの事件ともう一つの事件を結びつけたのだ。残るはただ一つの胸像――レディングのもの――であり、真珠はそこにあるに違いなかった。私は君たちの目の前で所有者からそれを買い取り――そして、それはそこにある。」
我々は一瞬、黙り込んで座っていた。
「いやはや」とレストレードは言った。「ホームズさん、あなたが多くの事件を扱われるのを見てきましたが、これほど見事な手際の事件は知りませんな。スコットランド・ヤードでは、あなたに嫉妬などしていませんよ。いえ、旦那、我々はあなたを非常に誇りに思っています。もし明日お越しいただければ、最年長の警部から一番若い巡査に至るまで、喜んであなたと握手をしない者はいませんでしょう。」
「ありがとう!」とホームズは言った。「ありがとう!」そして彼が顔を背けた時、私には、彼がこれまで見たことのないほど、より柔らかな人間の感情に心を動かされているように見えた。一瞬後、彼は再び冷徹で現実的な思考家に戻っていた。「真珠を金庫に入れろ、ワトソン」と彼は言った。「そして、コンク・シングルトン偽造事件の書類を出してくれ。さようなら、レストレード。もし何か小さな問題が君のところに舞い込んできたら、私にできることなら、その解決に向けて一つ二つヒントを与えよう。」
第二章 三人の学生
九十五年のこと、いくつかの事情が重なり――その詳細に立ち入る必要はあるまい――シャーロック・ホームズ氏と私は、我が国屈指の大学町の一つで数週間を過ごすことになった。これから語る、ささやかだが教訓に富む冒険が我々の身に降りかかったのは、その滞在中のことであった。読者が大学や犯人を正確に特定するのに役立つような詳細を記すことが、いかに無分別で不快なことであるかは、言うまでもないだろう。かくも痛ましい醜聞は、静かに忘れ去られるのがふさわしい。しかし、事件そのものは、我が友が際立っていた資質の一端を明らかにするものであるから、しかるべき配慮をもって記述してもよかろう。この記述においては、事件を特定の場所に限定したり、関係者への手がかりを与えたりするような表現は、極力避けるよう努める所存である。
当時、我々は家具付きの下宿に滞在しており、その近くの図書館でシャーロック・ホームズは初期イングランドの勅許状に関する骨の折れる研究に没頭していた――その研究は実に目覚ましい成果をもたらし、いずれ私の物語の一つとなるかもしれない。ある晩、我々が知人である聖ルークス・カレッジのチューター兼講師、ヒルトン・ソームズ氏の訪問を受けたのは、ここでのことであった。ソームズ氏は背が高く、痩身で、神経質で興奮しやすい気性の持ち主だった。彼の落ち着きのない態度は常々承知していたが、この時に限っては、何か尋常ならざる事態が起こったことが明らかなほど、抑えがたい動揺を見せていた。
「ホームズさん、あなたの貴重な時間を数時間ほどお分けいただけないでしょうか。聖ルークスで非常に痛ましい事件が起こりまして、本当に、あなたがこの町におられるという幸運がなければ、私はどうしてよいか途方に暮れていたことでしょう。」
「今は非常に忙しいので、邪魔はされたくない」と友は答えた。「警察の助けを呼ぶ方を強く勧めたい。」
「いえ、いえ、とんでもない。そのような手段は全く不可能です。一度法に訴えれば、もはや止めることはできません。そしてこれは、大学の名誉のためにも、醜聞を避けることが何よりも肝要な事件の一つなのです。あなたの思慮深さは、その能力と同様によく知られております。あなたこそが、世界で唯一私を助けることのできるお方です。どうか、ホームズさん、お力をお貸しください。」
ベーカー街の居心地の良い環境を奪われて以来、友の機嫌は良くなっていなかった。スクラップブックも、化学薬品も、家庭的な散らかり具合もない彼は、不機嫌な男だった。彼は不承不承といった体で肩をすくめ、その間に我々の訪問者は、早口で、興奮した身振りを交えながら、堰を切ったように自分の話を語り出した。
「ご説明しなければなりませんが、ホームズさん、明日はフォーテスキュー奨学金試験の初日なのです。私は試験官の一人です。私の担当科目はギリシャ語で、最初の試験は、受験生が見たことのないギリシャ語の長文翻訳で構成されています。この文章は試験問題用紙に印刷されており、もし受験生が事前に準備できれば、それは当然、計り知れない利点となります。このため、問題用紙は厳重に秘密にされているのです。
「今日、三時頃、この問題用紙の校正刷りが印刷所から届きました。課題はトゥキュディデスの一章の半分です。本文は絶対に正確でなければならないので、私はそれを注意深く読み通さなければなりませんでした。四時半になっても、私の作業はまだ終わっていませんでした。しかし、友人の部屋でお茶を飲む約束をしていたので、私は校正刷りを机の上に置いたままにしました。一時間以上、部屋を留守にしました。
「ご存知でしょうが、ホームズさん、我々のカレッジのドアは二重になっておりまして、内側には緑色のラシャ張りのドア、外側には重い樫のドアがあります。外側のドアに近づいた時、鍵が差し込まれているのを見て驚きました。一瞬、自分の鍵を置き忘れたのかと思いましたが、ポケットを探ると、ちゃんと入っていました。私が知る限り、存在する合鍵は、私の使用人であるバニスターが持つものだけです。彼は十年もの間、私の部屋の世話をしており、その誠実さは全く疑う余地がありません。調べてみると、鍵は確かに彼のもので、彼がお茶は必要かと尋ねるために私の部屋に入り、出る際に非常に不注意にも鍵をドアに差しっぱなしにしていったことが分かりました。彼が私の部屋を訪れたのは、私が部屋を出てからほんの数分以内のことだったに違いありません。鍵を忘れたことは、他の日であれば大した問題にはならなかったでしょうが、この日に限って、それは最も嘆かわしい結果を生み出してしまったのです。
「机に目をやった瞬間、誰かが私の書類を漁ったことに気づきました。校正刷りは三枚の長い紙片でした。私はそれらをすべてまとめて置いておきました。ところが、戻ってみると、一枚は床に落ち、一枚は窓際のサイドテーブルの上にあり、三枚目だけが私が置いた場所にあったのです。」
ホームズが初めて身じろぎした。
「最初のページは床に、二枚目は窓際に、三枚目はあなたが置いた場所に」と彼は言った。
「その通りです、ホームズさん。驚きました。どうしてそんなことがお分かりに?」
「どうぞ、その非常に興味深い話を続けてください。」
「一瞬、バニスターが私の書類を検めるという、許しがたい無礼を働いたのかと思いました。しかし、彼は真剣そのものの様子で否定しましたし、彼の言葉が真実であることは私も確信しております。となると、別の可能性としては、通りがかった何者かがドアに鍵が刺さっているのを見つけ、私が外出中であることを知って、書類を盗み見るために入ったということになります。奨学金は非常に高額なものですから、大金が絡んでいるのです。 unscrupulous [訳注:良心のかけらもない、の意]な人間であれば、仲間を出し抜くために危険を冒すことも十分に考えられます。」
「バニスターはこの一件でひどく動揺していました。書類が間違いなく不正に触られたとわかったとき、彼は卒倒しかけたほどです。私は彼にブランデーを少し飲ませ、椅子にぐったりと座らせておいて、部屋をくまなく調べました。すぐに、侵入者が散らかった書類以外にもその存在の痕跡を残していることに気づきました。窓際のテーブルには、削られた鉛筆の削りかすがいくつか落ちていました。折れた芯の先もそこにありました。どうやら、その悪党は大急ぎで書類を書き写し、鉛筆を折ってしまったため、新しい芯を削り出さざるを得なかったようです。」
「素晴らしい!」事件に没頭するにつれて上機嫌を取り戻したホームズが言った。「幸運が君の味方をしたようだ。」
「それだけではありません。私には赤い革張りの立派な天板を持つ、新しい書斎机があるのですが、バニスターも私も、それが滑らかで染みひとつなかったと誓って言えます。ところが今見ると、そこに長さ三インチほどのくっきりとした切り傷が――ただの引っ掻き傷ではなく、まさしく切り傷です。それだけでなく、テーブルの上には、おが屑のようなものが混じった、黒い練り物か粘土のような小さな塊が見つかりました。これらの痕跡は、書類を漁った男が残したものだと確信しています。足跡はなく、彼の正体を示す他の証拠もありません。途方に暮れていたところ、ふと幸運にもあなたが町におられることを思い出し、この件をあなたのお力にすがるべく、まっすぐこちらへ参った次第です。どうかお助けください、ホームズさん。私の窮状はお分かりでしょう。犯人を見つけるか、さもなくば新しい問題が準備されるまで試験を延期しなければなりません。そして、それは説明なしには行えませんから、大学だけでなく学寮全体に暗い影を落とす、忌まわしい醜聞が巻き起こるでしょう。何よりも、この問題を静かに、内密に解決したいのです。」
「喜んで調査し、できる限りの助言を差し上げましょう」ホームズは立ち上がってオーバーコートを羽織りながら言った。「この事件、まったく興味がないわけでもない。書類が届いてから、あなたの部屋に誰か訪ねてきましたか?」
「はい、同じ階に住むインド人の学生、ドーラット・ラス君が、試験についていくつか詳細を尋ねに来ました。」
「彼もその試験を受けるのかね?」
「はい。」
「そのとき、書類はあなたのテーブルの上に?」
「私の記憶では、丸めてあったはずです。」
「だが、校正刷りだと見分けがつく可能性は?」
「ありえます。」
「他に部屋には誰も?」
「いいえ。」
「この校正刷りがそこにあることを知っていた者は?」
「印刷業者以外には誰も。」
「そのバニスターという男は知っていたかね?」
「いいえ、まさか。誰も知りませんでした。」
「バニスターは今どこに?」
「彼はひどく気分を悪くしておりまして、可哀想に。椅子にぐったりしたまま置いてきました。あなたのもとへ急いでおりましたので。」
「部屋のドアは開けたままに?」
「いえ、まず書類を鍵のかかる場所へしまいました。」
「となると、こういうことになりますな、ソームズさん。インド人の学生がその巻物を校正刷りだと認識しなかった限り、書類に手を出した男は、それがそこにあるとは知らずに、偶然見つけたということになる。」
「私にはそう思えます。」
ホームズは謎めいた笑みを浮かべた。
「よろしい」と彼は言った。「では、行ってみましょう。君の出る幕はないぞ、ワトソン――頭脳の事件だ、腕力沙汰ではない。まあいい、来たければ来たまえ。さあ、ソームズさん――ご案内を!」
我々の依頼人の居間は、長く低い格子窓によって、古色蒼然たる学寮の、苔むした中庭に面していた。ゴシック様式のアーチ型のドアが、すり減った石の階段へと続いている。一階が講師の部屋。その上には三人の学生が、各階に一人ずつ住んでいる。我々が問題の現場に到着したときには、すでに黄昏時だった。ホームズは立ち止まり、窓を熱心に見つめた。それから彼は窓に近づき、つま先立ちになって首を伸ばし、部屋の中を覗き込んだ。
「ドアから入ったに違いありません。窓ガラス一枚分の開口部以外に、入れる場所はありませんから」と、我々の博識な案内人は言った。
「おやおや!」ホームズはそう言うと、我々の同行人をちらりと見て、奇妙な笑みを浮かべた。「さて、ここで学ぶべきことがないのなら、中に入った方がよさそうだ。」
講師は外側のドアの鍵を開け、我々を部屋へと招き入れた。ホームズがカーペットを調べている間、我々は入り口に立っていた。
「残念ながら、ここには何の痕跡もなさそうだ」と彼は言った。「これほど乾いた日に何かを期待する方が無理だろう。あなたの使用人はすっかり回復したようだ。椅子に残してきたと言いましたね。どの椅子ですかな?」
「あそこの窓際の。」
「なるほど。この小さなテーブルの近くか。もう入ってきてもいいですよ。カーペットの調査は終わった。まずはこの小さなテーブルから見ていこう。もちろん、何が起こったかは明白だ。男は部屋に入り、中央のテーブルから一枚ずつ書類を取った。そして窓際のテーブルへ運んだ。そこからなら、あなたが中庭を横切って来るのが見え、逃げおおせると考えたからだ。」
「実を言うと、それは無理なのです」とソームズは言った。「私は脇のドアから入りましたから。」
「ああ、それは好都合だ! まあいずれにせよ、男はそう考えていた。三枚の紙片を見せてくれたまえ。指紋は――ないな! さて、彼はまずこの一枚を運び、それを書き写した。あらゆる省略形を使ったとして、どれくらいの時間がかかるだろうか? 十五分は下らない。それからそれを放り出し、次の一枚を掴んだ。その最中に、あなたの帰宅が彼を非常に慌ただしい退却へと追い込んだ――きわめて慌てていた。自分がここにいたことを知らせてしまう書類を元に戻す時間すらなかったほどだ。外のドアを入ったとき、階段を駆け足で下りてくる音には気づかなかったかね?」
「いいえ、気づいたとは言えません。」
「さて、彼は猛烈な勢いで書いたため鉛筆を折り、ご指摘の通り、再び削らざるを得なかった。これは興味深いぞ、ワトソン。この鉛筆はありふれたものではない。通常より太く、芯は柔らかい。外側の色はダークブルーで、製造者名は銀色の文字で印刷されている。そして残っている部分はわずか一インチ半ほどだ。そのような鉛筆を探しなさい、ソームズさん。そうすれば犯人は見つかります。おまけに、彼が大きくて非常に刃の鈍いナイフを持っていると付け加えておけば、さらに手がかりが増えるだろう。」
ソームズ氏はこの情報の洪水にやや圧倒された様子だった。「他の点は理解できます」と彼は言った。「しかし、実のところ、長さのことになりますと――」
ホームズは、NNという文字と、その後に何もない木の部分が続く小さな削りかすを差し出した。
「お分かりかな?」
「いえ、恐れながら、今のでもまだ――」
「ワトソン、私はいつも君を不当に評価していたようだ。君以外にもいるとはな。このNNとは何だろう? 単語の末尾だ。ヨハン・ファーバーというのが最も一般的な製造者名であることはご存知だろう。ヨハンの後に続く部分と、この鉛筆の残りの部分がちょうど同じ長さだということは、明白ではないかね?」
彼は小さなテーブルを横にし、電灯の光にかざした。「彼が書いた紙が薄ければ、この磨かれた表面に何らかの痕跡が残っているかと期待したのだが。いや、何も見えない。ここでこれ以上学ぶことはないと思う。さて、中央のテーブルだ。この小さな塊が、おそらくあなたがおっしゃっていた黒い練り物だろう。大まかにピラミッド形で、中が窪んでいるのがわかる。おっしゃる通り、おが屑の粒が入っているようだ。おやおや、これは非常に興味深い。そして切り傷――まさしく引き裂かれた跡だ。細い引っ掻き傷から始まり、ギザギザの穴で終わっている。この事件に私の注意を向けてくださったこと、深く感謝しますよ、ソームズさん。そちらのドアはどこへ?」
「私の寝室です。」
「この騒ぎの後、入られましたか?」
「いいえ、まっすぐあなたのもとへ参りました。」
「少し拝見したい。なんと趣のある、古風な部屋だ! 床を調べるまで、少々お待ちいただけますかな。いや、何も見えない。このカーテンはどうだろう? この後ろに服を掛けているのですね。もし誰かがこの部屋に隠れることを強いられたなら、ベッドは低すぎ、洋服箪笥は浅すぎるから、ここに隠れるしかない。誰もいませんかな?」
ホームズがカーテンを引いたとき、彼の態度のわずかな硬直と警戒心から、彼が不測の事態に備えていることがわかった。実際のところ、引かれたカーテンの向こうには、杭の列から吊るされた三、四着の服以外、何もなかった。ホームズは背を向け、不意に床にかがみ込んだ。
「おや! これは何だ?」と彼は言った。
それは黒いパテのようなものでできた小さなピラミッドで、書斎のテーブルにあったものと寸分たがわなかった。ホームズはそれを開いた手のひらに乗せ、電灯の眩い光にさらした。
「あなたの訪問者は、居間だけでなく寝室にも痕跡を残していったようですな、ソームズさん。」
「そこで何をしようとしたのでしょう?」
「十分に明白だと思う。あなたは予期せぬ道から戻ってきた。だから彼は、あなたがドアのすぐそばに来るまで何の警告も受けなかった。彼に何ができただろう? 彼は自分の存在を裏切るものすべてを掴み、身を隠すためにあなたの寝室へ駆け込んだのだ。」
「なんてことだ、ホームズさん。まさか、私がこの部屋でバニスターと話している間ずっと、気づきさえすれば犯人は袋の鼠だったとでもおっしゃるのですか?」
「私はそう読む。」
「確かに、別の可能性もあります、ホームズさん。私の寝室の窓をご覧になったかどうかわかりませんが。」
「格子窓、鉛の枠組み、三つの独立した窓、一つは蝶番で開き、人が通れるほど大きい。」
「その通りです。そして、その窓は中庭の隅に面しており、部分的に見えにくくなっています。男はそこから侵入し、寝室を通り抜ける際に痕跡を残し、最後にドアが開いているのを見つけて、そちらから逃げたのかもしれません。」
ホームズは焦れたように首を振った。
「現実的に考えましょう」と彼は言った。「この階段を使う学生は三人いて、あなたのドアの前を通りかかるのが常だ、と理解してよろしいですかな?」
「はい、その通りです。」
「そして、彼らは全員この試験を受けるのですか?」
「はい。」
「彼らのうち誰か一人を、他の者より疑う理由はありますか?」
ソームズはためらった。
「非常にデリケートな問題です」と彼は言った。「証拠もないのに、人を疑うのは気が進みませんからな。」
「その疑いとやらを聞きましょう。証拠は私が探します。」
「では、手短に、これらの部屋に住む三人の男の人物像をお話ししましょう。三人のうち一番下の階にいるのはギルクリストで、優秀な学者であり運動選手です。学寮のラグビーチームとクリケットチームでプレーし、ハードルと走り幅跳びでブルー[訳注:オックスフォード大学またはケンブリッジ大学の代表選手に与えられる称号]を取りました。立派な、男らしい青年です。彼の父親は悪名高いサー・ジェイベズ・ギルクリストで、競馬で身を滅ぼしました。私の教え子は非常に貧しい生活を強いられていますが、勤勉で働き者です。彼はきっと成功するでしょう。」
「二階にはインド人のドーラット・ラスが住んでいます。彼は物静かで、何を考えているかわからない男です。多くのインド人がそうであるように。ギリシャ語が苦手科目ではありますが、学業はよくできます。堅実で几帳面です。」
「最上階はマイルズ・マクラーレンの部屋です。やる気になれば素晴らしい才能を発揮する男で――大学でも指折りの知性の持ち主です。しかし、気まぐれで、自堕落で、無節操です。一年生のときには、カード賭博の醜聞で放校寸前になりました。今学期はずっと怠けていましたから、試験を恐れおののいて待っているに違いありません。」
「では、あなたが疑っているのは彼ですか?」
「そこまで断言する勇気はありません。しかし、三人の中では、彼が最も『ありえなくはない』人物でしょう。」
「その通り。さて、ソームズさん、あなたの使用人、バニスターに会わせていただきましょう。」
彼は小柄で、青白い顔をし、髭をきれいに剃り、ごま塩頭の五十がらみの男だった。彼の静かな生活のルーティンが突然乱されたことに、まだ苦しんでいるようだった。そのふっくらとした顔は神経質にひきつり、指は絶えず動き回っていた。
「我々はこの不幸な事件を調査しているのだ、バニスター」と彼の主人が言った。
「はい、旦那様。」
「聞いているぞ」とホームズが言った。「君はドアに鍵を差しっぱなしにしたそうだな?」
「はい、旦那様。」
「中にあの書類があったまさにその日にそんなことをするとは、実に奇妙だとは思わんかね?」
「まことに不運でございました。ですが、他の時にも時折、同じことをしてしまったことがございます。」
「いつ部屋に入ったのかね?」
「四時半ごろでございます。ソームズ様のティータイムでございますので。」
「どれくらい滞在した?」
「旦那様がご不在とわかりまして、すぐに引き下がりました。」
「テーブルの上の書類は見たかね?」
「いいえ、旦那様――断じて見ておりません。」
「どうしてドアに鍵を置き忘れたのかね?」
「紅茶盆を手に持っておりました。後で鍵を取りに戻ろうと思いました。それから、忘れてしまったのです。」
「外のドアはスプリング錠かね?」
「いいえ、旦那様。」
「では、ずっと開いていたわけだ?」
「はい、旦那様。」
「部屋にいた者は誰でも外へ出られた?」
「はい、旦那様。」
「ソームズさんが戻って君を呼んだとき、君はひどく動揺していたそうだな?」
「はい、旦那様。私がここにお仕えして長年になりますが、このようなことは一度もございませんでした。卒倒しかけました、旦那様。」
「そう聞いている。気分が悪くなり始めたとき、どこにいたのかね?」
「どこに、でございますか? ええと、ここで、ドアの近くでございます。」
「それは奇妙だ。君が座ったのは、あそこの隅の近くの椅子だ。なぜ他の椅子を通り過ぎたのかね?」
「存じません、旦那様。どこに座ろうと私には関係ございませんでした。」
「彼はあまり覚えていないのだと思います、ホームズさん。ひどい顔色でした――まったくの死人のようでした。」
「主人が去った後もここにいたのかね?」
「ほんの一分かそこらです。それからドアに鍵をかけて自分の部屋へ行きました。」
「誰を疑っている?」
「ああ、私などが口にできることではございません、旦那様。この大学に、そのような行いから利を得ようとする紳士がいるとは信じられません。ええ、旦那様、私は信じません。」
「ありがとう、それで結構」とホームズは言った。「ああ、もう一つ。君がお世話をしている三人の紳士の誰かに、何か異変があったことを話したかね?」
「いいえ、旦那様――一言も。」
「彼らの誰かを見かけたかね?」
「いいえ、旦那様。」
「よろしい。さて、ソームズさん、よろしければ中庭を散歩しましょう。」
集まり始めた闇の中、我々の上に三つの黄色い光の四角が輝いていた。
「三羽の鳥は皆、巣に戻っているようですな」ホームズは見上げて言った。「おや! あれは何だ? 一羽は随分と落ち着かないようだ。」
インド人学生だった。彼の黒いシルエットが不意にブラインドに現れた。彼は部屋の中を足早に行ったり来たりしていた。
「彼ら一人一人を覗いてみたいものだ」とホームズは言った。「可能だろうか?」
「お安い御用です」とソームズは答えた。「この一続きの部屋は学寮の中でも最も古いもので、見学者が見て回るのも珍しいことではありません。さあ、私が直々にご案内しましょう。」
「名前は伏せてください!」我々がギルクリストのドアをノックしたとき、ホームズは言った。背の高い、亜麻色の髪をした、ほっそりとした若者がドアを開け、我々の用件を理解すると歓迎してくれた。中には実に興味深い中世の家庭建築の断片がいくつかあった。ホームズはその一つにすっかり魅了され、手帳にスケッチすると言い張り、鉛筆を折り、我々のホストから一本借り、最後には自分の鉛筆を削るためにナイフまで借りた。同じ奇妙な偶然がインド人の部屋でも起こった――彼は物静かで小柄な、鷲鼻の男で、我々を訝しげに見ており、ホームズの建築学研究が終わったときには明らかにほっとしていた。どちらの場合も、ホームズが探していた手がかりを見つけたようには私には見えなかった。三番目の訪問だけが、不首尾に終わった。我々がノックしても外のドアは開かず、その向こうから聞こえてきたのは、罵詈雑言の洪水だけだった。「誰だか知らんが、とっとと失せろ!」と怒声が轟いた。「明日は試験なんだ。誰にも邪魔はさせん。」
「無礼な男だ」我々の案内人は、階段を下りながら怒りで顔を赤らめて言った。「もちろん、ノックしているのが私だとは気づかなかったのでしょうが、それにしても彼の態度は非常に無作法ですし、実のところ、この状況下ではむしろ疑わしい。」
ホームズの反応は奇妙なものだった。
「彼の正確な身長を教えていただけますかな?」と彼は尋ねた。
「実のところ、ホームズさん、はっきりとは申し上げられません。インド人よりは高く、ギルクリストほど高くはない。おそらく五フィート六インチといったところでしょう。」
「それは非常に重要です」とホームズは言った。「では、ソームズさん、今夜はこれでおやすみなさい。」
我々の案内人は、驚きと狼狽のあまり大声で叫んだ。「なんてことだ、ホームズさん、まさかこんな唐突に私を見捨てるおつもりではありますまい! あなたは状況を理解しておられないようだ。明日は試験なのです。今夜中に何らかの断固たる行動を取らねばなりません。答案の一枚でも不正に閲覧されたとあっては、試験を実施するわけにはいきません。この事態に立ち向かわねばならないのです。」
「現状のままにしておかねばなりません。明日の朝早くに立ち寄り、この件について話し合いましょう。その時には、何らかの行動方針を示すことができるかもしれません。それまでの間、何も変えてはなりません――何一つ。」
「承知いたしました、ホームズさん。」
「どうぞご安心ください。あなたの難局から抜け出す道は必ず見つかります。この黒い粘土と、鉛筆の削りかすは私が預かります。では、さようなら。」
我々が中庭の暗闇に出たとき、再び窓を見上げた。インド人はまだ部屋を歩き回っていた。他の二人は見えなかった。
「さて、ワトソン、どう思うかね?」
大通りに出たとき、ホームズは尋ねた。「さながら、ちょっとした室内ゲーム――三枚札当てのようなものではないかね? そこに三人の男がいる。犯人はそのうちの一人だ。さあ、選んでくれたまえ。君は誰だと思う?」
「一番上の階の口汚い男だ。前科が一番悪い。だが、あのインド人も油断ならない男だった。なぜずっと部屋を歩き回っているのだろう?」
「それには何の意味もない。何かを暗記しようとするとき、多くの者がそうするものだ。」
「彼は奇妙な目で我々を見ていた。」
「君だってそうするだろう。翌日に試験を控え、一瞬一瞬が貴重なときに、見知らぬ連中がどやどやと押しかけてきたらな。いや、それには何の意味もない。鉛筆もナイフも――すべて申し分なかった。だが、あの男が私を悩ませる。」
「誰が?」
「なぜかね、使用人のバニスターだ。この件で彼の狙いは何だ?」
「私には、まったくもって正直な男という印象だったが。」
「私にもそうだ。そこが悩ましいところだ。なぜ、まったくもって正直な男が――まあいい、ここに大きな文房具店がある。ここで我々の調査を始めよう。」
町には名の知れた文房具店が四軒しかなかった。ホームズはそれぞれの店で鉛筆の削りかすを取り出し、同じものを高値で買い求めようとした。どの店も、取り寄せは可能だが、通常サイズの鉛筆ではなく、在庫として置いていることは稀だという点で意見が一致した。友人は失敗に落胆した様子もなく、半ばユーモラスな諦めの表情で肩をすくめた。
「無駄足だったな、ワトソン君。これこそが最良かつ唯一の決定的な手がかりだったのに、空振りに終わった。だが、実のところ、それがなくても十分な事件を組み立てられると、私はほとんど疑っていない。おやまあ! もう九時近い。女将は七時半にグリーンピースだと口やかましく言っていた。君の止めどない煙草と、不規則な食事のせいで、いずれ立ち退き勧告を受け、私もその没落の巻き添えを食うことになるだろう――もっとも、神経質な講師と、不注意な使用人と、三人の進取の気性に富んだ学生の問題を解決するまでは、だがね。」
ホームズはその日、その件についてそれ以上言及しなかったが、遅い夕食の後、長い間物思いに沈んでいた。朝八時、私が身支度を終えたちょうどその時、彼が私の部屋に入ってきた。
「さて、ワトソン」と彼は言った。「そろそろ聖ルカ学寮へ行く時間だ。朝食は抜きでいけるかね?」
「もちろん。」
「我々が何か確かなことを伝えるまで、ソームズはひどくやきもきしているだろう。」
「何か確かなことを伝える当てがあるのか?」
「あると思う。」
「結論が出たのか?」
「ああ、ワトソン君、私は謎を解いた。」
「しかし、どんな新しい証拠を手に入れたんだ?」
「はっは! 伊達に朝の六時という非常識な時間に叩き起きたわけではない。二時間の重労働をこなし、少なくとも五マイルは歩き、その成果も手に入れた。これを見たまえ!」
彼は手を差し出した。その手のひらには、黒い練り物のような粘土でできた小さなピラミッドが三つあった。
「おや、ホームズ、昨日は二つしか持っていなかったじゃないか。」
「そして今朝、もう一つ手に入れた。三つ目が出てきた場所が、一つ目と二つ目の源でもあると考えるのが妥当な推論だろう。どうだね、ワトソン? さて、行こう。友人のソームズを苦痛から解放してやろう。」
不幸な講師は、我々が彼の部屋を訪ねたとき、確かに哀れむべき動揺状態にあった。数時間後には試験が始まるというのに、彼は事実を公表するか、それとも罪人が高額な奨学金をかけて競争するのを許すかというジレンマに陥ったままだった。彼は精神的な動揺のあまり、じっと立っていることさえできず、両手を熱心に差し出してホームズの方へ駆け寄ってきた。
「ああ、来てくださってよかった! 絶望して諦めてしまわれたのかと案じておりました。私はどうすればよいのでしょう? 試験は続行すべきでしょうか?」
「はい、ぜひとも続行させてください。」
「しかし、この悪党は? ――」
「彼は競争に参加させません。」
「ご存知なのですか?」
「そう思う。この件を公にしたくないのであれば、我々自身に一定の権限を与え、小さな私設の軍法会議を開く必要がある。あなたはそこへ、どうぞ、ソームズさん! ワトソン、君はここに! 私は真ん中の肘掛け椅子に座ろう。これで、罪ある者の胸に恐怖を刻み込むには十分な威厳が備わったことだろう。どうぞベルを鳴らしてください!」
バニスターが入り、我々の裁判官然とした様子に、明らかに驚きと恐れをなして後ずさった。
「ドアを閉めてくれたまえ」とホームズは言った。「さて、バニスター、昨日の出来事について真実を話してもらおうか。」
男は髪の生え際まで真っ青になった。
「すべてお話しいたしました、旦那様。」
「付け加えることはないかね?」
「何もございません、旦那様。」
「では、私からいくつか示唆させてもらおう。昨日、君があの椅子に座ったのは、誰が部屋にいたかを示すであろう何らかの物体を隠すためではなかったかね?」
バニスターの顔は死人のようだった。
「いいえ、旦那様、決して。」
「ただの示唆にすぎん」ホームズはにこやかに言った。「率直に認めよう、私にそれを証明することはできない。だが、ソームズさんが背を向けた途端、君が寝室に隠れていた男を解放したというのは、十分にありそうな話だ。」
バニスターは乾いた唇を舐めた。
「男などおりませんでした、旦那様。」
「ああ、それは残念だ、バニスター。今まで君は真実を語っていたのかもしれないが、今、君が嘘をついたことがわかった。」
男の顔は、不機嫌な反抗心で固まった。
「男などおりませんでした、旦那様。」
「さあ、さあ、バニスター!」
「いいえ、旦那様、誰もおりませんでした。」
「その場合、君からはこれ以上の情報は得られそうにないな。部屋に残っていてくれるかね? そこの寝室のドアの近くに立っていてくれたまえ。さて、ソームズさん、大変恐縮ですが、若いギルクリスト君の部屋へ行って、あなたの部屋まで降りてくるよう頼んでいただけますかな。」
一瞬の後、講師は学生を連れて戻ってきた。彼は背が高く、しなやかで、機敏な、素晴らしい体格の男で、弾むような足取りと、快活で屈託のない顔をしていた。彼の不安げな青い瞳が我々一人一人をちらりと見て、最後に遠い隅にいるバニスターの上に、茫然自失とした表情で留まった。
「ドアを閉めてください」とホームズは言った。「さて、ギルクリスト君、ここには我々しかいない。我々の間で交わされる言葉が外に漏れる心配は一切ない。我々は完全に率直に話し合うことができる。知りたいのだ、ギルクリスト君。君のような名誉ある人間が、どうして昨日のような行為に及んでしまったのかを。」
不幸な若者はよろめき後ずさり、恐怖と非難に満ちた視線をバニスターに投げかけた。
「いえ、いえ、ギルクリスト様、私は一言も――決して一言も申し上げておりません!」と使用人は叫んだ。
「いや、だが今、言った」とホームズは言った。「さて、君、バニスターの言葉の後では、君の立場が絶望的であること、そして唯一の活路が率直な告白にあることはわかるはずだ。」
一瞬、ギルクリストは手を上げて、歪む顔を抑えようとした。次の瞬間には、彼はテーブルのそばに膝から崩れ落ち、両手で顔を覆い、激しい嗚咽の嵐をほとばしらせていた。
「まあまあ」ホームズは優しく言った。「過ちは人の常だ。少なくとも、君を冷酷な犯罪者だと責める者は誰もいないだろう。私がソームズさんに何が起こったかを話し、君が間違っている箇所を訂正する方が、君にとっては楽かもしれない。そうしようか? まあいい、答えるに及ばん。聞きなさい、そして私が君に不当な扱いをしないことを見ていてくれたまえ。」
「あなたが、バニスターですら書類が部屋にあることを知るはずがなかった、と私におっしゃった瞬間から、ソームズさん、この事件は私の心の中で明確な形を取り始めました。印刷業者はもちろん、除外できます。彼は自分の事務所で書類を検めることができる。インド人学生も、私は問題にしなかった。もし校正刷りが巻物になっていれば、彼がそれが何であるかを知ることは不可能だからです。一方で、男が大胆にも部屋に侵入し、偶然にもまさにその日に書類がテーブルの上にあったというのは、考えられない偶然に思えました。私はその可能性を退けました。侵入した男は、書類がそこにあることを知っていたのです。どうやって知ったのか?」
「あなたの部屋に近づいたとき、私は窓を調べました。あなたは、私が白昼堂々、向かいの部屋のすべての目がある中で、誰かが窓をこじ開けて侵入した可能性を考えているのだと思われて、私を面白がらせてくれました。そのような考えは馬鹿げています。私が測っていたのは、通りすがりに中央のテーブルにどんな書類が置いてあるかを見るには、どれほどの身長が必要かということです。私の身長は六フィートですが、それでも努力してやっとできるくらいです。それ以下の身長の者にはチャンスはないでしょう。すでにお分かりの通り、私には、あなたの三人の学生のうち一人が並外れた長身の男であれば、その男が三人の中で最も監視する価値がある、と考える理由があったのです。」
「部屋に入り、私は脇のテーブルからの示唆について、あなたに打ち明けました。中央のテーブルからは何も得られませんでしたが、あなたがギルクリストの人物描写の中で、彼が走り幅跳びの選手であると述べたとき、すべてが一瞬のうちに私の頭に浮かびました。あとは、いくつかの裏付けとなる証拠が必要なだけでしたが、それもすぐに手に入れることができました。」
「起こったことはこうです。この若者は午後を運動場で過ごし、そこで跳躍の練習をしていました。彼は跳躍用の靴を持って帰りましたが、ご存知の通り、その靴にはいくつかの鋭いスパイクがついています。あなたの窓を通り過ぎたとき、彼はその長身のおかげで、あなたのテーブルの上にあるこれらの校正刷りを見て、それが何であるかを推測しました。もし、あなたのドアを通り過ぎたときに、あなたの使用人の不注意で置き忘れられた鍵に気づかなければ、何事もなかったでしょう。突然の衝動に駆られ、彼は中に入り、それが本当に校正刷りであるか確かめようとしました。質問をしに立ち寄っただけだ、といつでも言い訳ができるので、危険な行為ではありませんでした。」
「さて、それが本当に校正刷りだとわかったとき、彼は誘惑に負けたのです。彼は靴をテーブルの上に置きました。窓際のあの椅子に置いたのは何でしたかな?」
「手袋です」と若者は言った。
ホームズは勝ち誇ったようにバニスターを見た。「彼は椅子に手袋を置き、一枚ずつ校正刷りを取って書き写し始めた。彼は講師が正門から戻ってくると考え、そうすれば彼を見ることができると思っていました。我々が知るように、彼は脇の門から戻ってきた。突然、彼はドアのすぐそばで講師の足音を聞きました。逃げ場はありません。彼は手袋を忘れましたが、靴を掴んで寝室に飛び込みました。あのテーブルの傷が、片側では浅く、寝室のドアの方向に向かって深くなっていることにお気づきでしょう。それ自体が、靴がその方向に引きずられ、犯人がそこに逃げ込んだことを示すのに十分です。スパイクの周りの土がテーブルの上に残され、二つ目の塊が寝室で剥がれ落ちました。付け加えるなら、私は今朝、運動場まで歩いて行き、跳躍用の砂場に粘着質の黒い粘土が使われているのを確認し、その見本と、選手が滑るのを防ぐために撒かれている細かいなめし革の屑かおが屑をいくつか持ち帰りました。私は真実を語りましたかな、ギルクリスト君?」
学生は身を起こし、まっすぐに立った。
「はい、旦那様、その通りです」と彼は言った。
「なんてことだ! 付け加えることは何もないのか?」とソームズは叫んだ。
「はい、旦那様、ございます。ですが、この不名誉な暴露の衝撃で、私は混乱しております。ここに手紙があります、ソームズ先生。今朝早く、眠れぬ夜の最中にあなたに宛てて書いたものです。私の罪が露見したことを知る前のことでした。これです、先生。ご覧になればお分かりの通り、私はこう書いております。『私は試験を受けるのをやめる決心をしました。ローデシア警察の士官の職を提示されており、直ちに南アフリカへ発ちます』と。」
「君が不正な利益を得るつもりがなかったと聞いて、私は実に嬉しい」とソームズは言った。「しかし、なぜ決心を変えたのかね?」
ギルクリストはバニスターを指さした。
「私を正しい道に導いてくれたのは、この男です」と彼は言った。
「さあ、バニスター」とホームズは言った。「私が言ったことから、君だけがこの若者を外に出すことができたのは明らかだろう。君は部屋に残され、外に出るときにドアに鍵をかけたはずだからな。彼があの窓から逃げるというのは、信じがたい。この謎の最後の点を解き明かし、君の行動の理由を話してはくれんかね?」
「ご存知でありさえすれば、ごく単純なことでございました、旦那様。しかし、いかにご賢明なあなた様でも、ご存知のはずがございません。かつて、私はこの若様の父君、旧サー・ジェイベズ・ギルクリスト様にお仕えする執事でございました。旦那様が破産されたとき、私は学寮に使用人として参りましたが、たとえ世間から見放されても、昔の主人のことを忘れたことはございません。昔の日々のために、私はできる限りそのご子息を見守ってまいりました。さて、旦那様、昨日、騒ぎが起きてこの部屋に入りましたとき、私が真っ先に目にしたのは、あの椅子の上に置かれたギルクリスト様のなめし革の手袋でございました。私はその手袋をよく存じておりましたし、その意味するところも理解いたしました。もしソームズ様がそれをご覧になれば、万事休すです。私はあの椅子にどっかと腰を下ろし、ソームズ様があなた様を呼びに行かれるまで、てこでも動きませんでした。それから、私が膝の上であやしたこともある、哀れな若様が出てきて、すべてを私に告白したのです。私が彼を救うのが自然ではございませんでしょうか、旦那様。そしてまた、亡き父君がなさったであろうようにお話しし、そのような行いから利を得ることはできないのだと彼に理解させようと努めるのも、自然なことではございませんでしょうか? 私を責めることがおできになりますか、旦那様?」
「いや、断じてできん」ホームズは心からそう言うと、勢いよく立ち上がった。「さて、ソームズさん、あなたの小さな問題は解決したと思いますし、我々の朝食が家で待っています。行こう、ワトソン! 君については、ローデシアで輝かしい未来が待っていることを信じている。一度は地に落ちた。だがこれから、どれほど高く飛翔できるか、見せてもらおうではないか。」
黄金の鼻眼鏡の冒険
一八九四年の我々の業績を収めた、分厚い三冊の手稿に目を通すとき、告白するが、これほど豊富な題材の中から、それ自体が最も興味深く、同時に、我が友人がその名を知られる所以となった特異な能力を最もよく示すのに資する事件を選び出すのは、私にとって非常に困難なことである。ページをめくると、赤蛭の忌まわしい物語や、銀行家クロスビーの惨死事件に関する私の覚え書きが目に入る。ここにはまた、アデルトン悲劇の記述や、古代ブリテンの古墳の奇妙な内容物も見つかる。名高いスミス=モーティマー相続事件もこの時期のものであり、大通りで暗殺を犯したユレの追跡と逮捕も同様である――この功績により、ホームズはフランス大統領からの感謝の自筆書簡とレジオンドヌール勲章を勝ち取った。これらのいずれもが物語となるだろうが、総じて、ヨクスリー・オールド・プレイスの挿話ほど多くの奇妙な興味深い点を兼ね備えたものはない、と私は思う。この事件には、若きウィロビー・スミスの痛ましい死だけでなく、その後の展開が含まれており、それらが犯罪の原因に実に奇妙な光を投げかけたのである。
それは十一月の終わり近く、荒れ狂う嵐の夜だった。ホームズと私は夕方からずっと無言で座っていた。彼は強力なレンズを使ってパリンプセスト[訳注:羊皮紙などに書かれた文字を消し、その上に別の文字を記したもの]の元の碑文の残骸を解読することに没頭し、私は最近の外科に関する論文に深く沈潜していた。外では風がベーカー街を唸りながら吹き下ろし、雨が激しく窓を叩いていた。街のまっただ中、我々の周囲十マイル四方に人間の手による創造物が広がっているこの場所で、自然の鉄の掌握を感じ、巨大で根源的な力の前には、ロンドン全土といえども野に点在するモグラ塚に過ぎないことを意識させられるのは、奇妙なことだった。私は窓辺へ歩み寄り、人気のない通りを見下ろした。時折灯るランプが、ぬかるんだ道と光る敷石の広がりを照らしていた。一台の辻馬車が、オックスフォード・ストリートの端から水しぶきを上げて進んできていた。
「さて、ワトソン、今夜は外に出なくて済んで幸いだったな」ホームズはレンズを脇に置き、パリンプセストを巻きながら言った。「一回の作業としては十分だ。目にこたえる仕事だよ。私が解読できた限りでは、十五世紀後半に遡る修道院の会計記録以上の刺激的なものではないようだ。おや! おやおや! おやおや! 何事だ?」
風の単調な唸りの中に、馬の蹄の音が響き、縁石にこすれる車輪の長い軋む音が聞こえてきた。私が見た辻馬車が、我々のドアの前で止まったのだ。
「一体何の用だろう?」
男が馬車から降りてきたとき、私は思わず声を上げた。
「用? 我々に用があるのだ。そして我々には、気の毒なワトソン君、オーバーコートにネクタイ、それにゴム長靴と、人類がこの悪天候と戦うために発明したあらゆるものが必要になる。だが、待て! 馬車がまた走り去った! まだ望みはある。我々を連れ出すつもりなら、待たせておいたはずだ。駆け下りてドアを開けてくれたまえ、善良な人々は皆とっくに寝ている時間だからな。」
玄関ホールのランプの光が真夜中の訪問者に落ちたとき、彼が誰であるかを認識するのは難しくなかった。若きスタンリー・ホプキンス、将来有望な刑事で、ホームズがそのキャリアに何度か非常に実際的な関心を示してきた人物だった。
「彼はいるか?」と彼は熱心に尋ねた。
「上がってきなさい、君」と上からホームズの声がした。「こんな夜に、我々に何か良からぬ企みでもお持ちではないでしょうな。」
刑事は階段を上り、我々のランプの光が彼の光る防水外套を照らした。私がそれを脱がせるのを手伝っている間に、ホームズは暖炉の薪から炎をたたき起こした。
「さあ、ホプキンス君、もっと寄って足を温めたまえ」と彼は言った。「葉巻をどうぞ。それから博士が、お湯とレモンを調合した処方箋をお持ちだ。こんな夜には良い薬になる。こんな嵐の中、君を外に連れ出したからには、何か重要なことに違いない。」
「まったくです、ホームズさん。午後は大忙しでしたよ、請け合います。最新版の新聞でヨクスリー事件について何かご覧になりましたか?」
「今日、私は十五世紀より新しいものは何も見ていない。」
「まあ、ほんの短い記事で、しかも全部間違っていましたから、何も見逃してはいませんよ。私は少しもぐずぐずしていません。ケント州の、チャタムから七マイル、鉄道線路から三マイルのところです。三時十五分に電報で呼ばれ、五時にヨクスリー・オールド・プレイスに着き、調査を行い、最終列車でチャリング・クロスに戻り、辻馬車でまっすぐあなたのもとへ。」
「つまり、事件がはっきりしないということだろうな?」
「つまり、事件の糸口がまったく掴めないということです。私が見る限り、これまで扱った中でも最も錯綜した事件です。それなのに、最初はあまりに単純で間違うはずがないと思えたのですが。動機がないのです、ホームズさん。それが私を悩ませている――動機が掴めない。一人の男が死んでいる――それは否定しようがありません――しかし、私が見る限り、誰かが彼に危害を加えたいと思う理由が、この世に一つも見当たらないのです。」
ホームズは葉巻に火をつけ、椅子に深くもたれかかった。
「聞かせてもらおう」と彼は言った。
「事実はかなりはっきりさせてきました」とスタンリー・ホプキンスは言った。「今知りたいのは、それらすべてが何を意味するのか、ということです。私が解明できた限りの話は、こうです。数年前、この田舎の邸宅、ヨクスリー・オールド・プレイスを、コーラム教授と名乗る年配の男性が借りました。彼は病弱で、半ば寝たきり、残りの半ばは杖をついて家の中をよろよろと歩くか、庭師に浴用車椅子を押されて敷地内を移動していました。彼を訪ねてくる数少ない隣人からは好かれており、地元では非常に学識のある人物として評判です。彼の家には、年配の家政婦マーカー夫人と、メイドのスーザン・タールトンがいました。この二人は彼が越してきて以来ずっと一緒に働いており、非常に品行方正な女性のようです。教授は学術書を執筆しており、約一年前に秘書を雇う必要が生じました。最初に試した二人はうまくいきませんでしたが、三人目のウィロビー・スミス氏は、大学を出たばかりの非常に若い男性で、雇い主が求めていた通りの人物だったようです。彼の仕事は、午前中ずっと教授の口述筆記をすることで、夕方は通常、翌日の仕事に関係する参考文献や一節を探すのに費やしていました。このウィロビー・スミスには、アッピンガム校の少年時代にも、ケンブリッジ大学の青年時代にも、何一つ非難されるような点はありません。私は彼の推薦状を見ましたが、最初から礼儀正しく、物静かで、勤勉な青年で、弱点などまったくない人物です。それなのに、この若者が今朝、教授の書斎で、殺人としか考えられない状況下で死を迎えたのです。」
風が窓に唸り声をあげ、金切り声を上げた。ホームズと私は暖炉に身を寄せ合い、若い警部はゆっくりと、一点一点、彼の奇妙な物語を展開していった。
「イングランド中を探しても」と彼は言った。「これほど自己完結し、外部からの影響を受けない家庭は見つからないでしょう。何週間も過ぎ、庭の門から一歩も出ないこともしばしばでした。教授は仕事に没頭し、それ以外のことには存在しませんでした。若いスミスは近所に知り合いもおらず、雇い主とほとんど同じように暮らしていました。二人の女性も家から出る用事はありませんでした。浴用車椅子を押す庭師のモーティマーは、陸軍の恩給生活者で――クリミア戦争に従軍した、品行方正な老人です。彼は家に住んでおらず、庭の反対側にある三部屋のコテージに住んでいます。ヨクスリー・オールド・プレイスの敷地内で見かけるのは、これらの人々だけです。同時に、庭の門はロンドンからチャタムへ向かう主要道路から百ヤードのところにあります。掛け金で開くようになっており、誰でも歩いて入るのを妨げるものはありません。」
「さて、スーザン・タールトンの証言をお話しします。彼女がこの件について何か確かなことを言える唯一の人物です。午前中、十一時から十二時の間のことでした。彼女はその時、二階の正面の寝室でカーテンを掛ける作業をしていました。コーラム教授はまだベッドの中でした。天気が悪い日は、正午前に起きることはめったにないからです。家政婦は家の裏手で何かの仕事に忙しくしていました。ウィロビー・スミスは自分の寝室におり、そこを居間として使っていましたが、メイドはその時、彼が廊下を通り、彼女の真下にある書斎へ下りていくのを耳にしました。彼女は彼を見てはいませんが、彼の素早く、しっかりした足音に聞き間違えるはずがないと言っています。彼女は書斎のドアが閉まる音は聞いていませんが、一分かそこらして、階下の部屋で恐ろしい叫び声がしました。それは荒々しく、しわがれた悲鳴で、あまりに奇妙で不自然だったため、男のものか女のものか判別できなかったそうです。それと同時に、古い家を揺るがす重いどすんという音がし、それからすべてが静まり返りました。メイドは一瞬石のように固まっていましたが、やがて勇気を取り戻し、階下へ駆け下りました。書斎のドアは閉まっており、彼女はそれを開けました。中では、若いウィロビー・スミス氏が床に伸びていました。最初、彼女は怪我を見つけられませんでしたが、彼を起こそうとしたとき、彼の首の下側から血が流れ出ているのに気づきました。それは非常に小さいながらも非常に深い傷で、頸動脈を切断していました。傷を負わせた凶器は、彼のそばのカーペットの上に落ちていました。それは、古い様式の書斎机によく見られる、象牙の柄と硬い刃を持つ、封蝋用の小さなナイフの一つでした。教授自身の机の付属品の一部でした。」
「最初、メイドは若いスミスはすでに死んでいると思いましたが、カラフから水を彼の額にかけたところ、彼は一瞬目を開きました。『教授』、彼はそう呟きました――『あれは彼女だった』と。メイドは、それがまさしくその言葉であったと誓う覚悟です。彼は必死に何か他のことを言おうとし、右手を宙に掲げました。それから彼は後ろに倒れ、息絶えました。」
「その間に家政婦も現場に到着しましたが、彼女は若者の最期の言葉を聞き逃してしまいました。スーザンを遺体とともに残し、彼女は教授の部屋へ急ぎました。彼はベッドに起き上がっており、ひどく動揺していました。何か恐ろしいことが起こったと確信するのに十分な音を聞いていたからです。マーカー夫人は、教授がまだ寝間着のままであったと誓う覚悟です。実際、十二時に来るよう命じられていたモーティマーの助けなしに、彼が服を着ることは不可能でした。教授は遠くの叫び声を聞いたと断言していますが、それ以上のことは何も知らないと言います。彼は若者の最期の言葉、『教授――あれは彼女だった』について何の説明もできず、それが譫言の産物だろうと想像しています。彼は、ウィロビー・スミスにはこの世に敵など一人もいなかったと信じており、犯罪の理由を挙げることもできません。彼の最初の行動は、庭師のモーティマーを地元の警察に遣わすことでした。少しして、警察署長が私を呼び寄せました。私が到着するまで何も動かされておらず、家へ通じる小道を誰も歩かないよう、厳命が下されていました。あなたの理論を実践に移す絶好の機会でしたよ、シャーロック・ホームズさん。本当に、何も不足はありませんでした。」
「シャーロック・ホームズ氏を除いては、だがね」友人はやや苦々しい笑みを浮かべて言った。「さて、聞かせてもらおう。君はどんな仕事をしたのかね?」
「まず最初に、ホームズさん、この大まかな見取り図に目を通していただきたい。これで教授の書斎の位置と、事件の様々な点の全体像が掴めるでしょう。私の調査を追う助けになるはずです。」
彼は私がここに再現する大まかな図面を広げ、ホームズの膝の上に置いた。私は立ち上がり、ホームズの後ろに立って、彼の肩越しにそれを研究した。
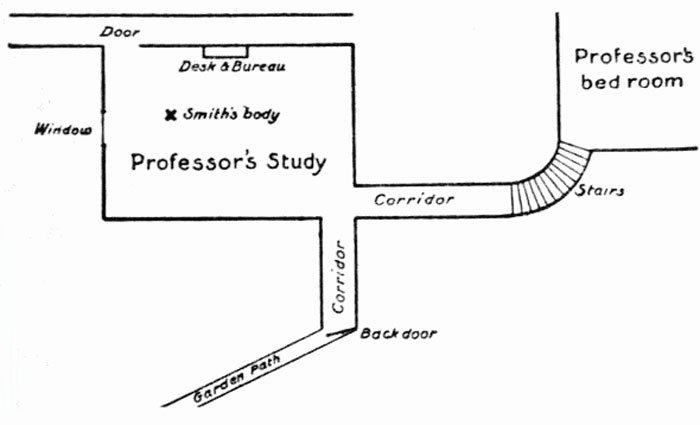
「もちろん、非常に大雑把なもので、私が重要だと考える点だけを扱っています。残りはすべて、後でご自身でご覧になるでしょう。さて、まず第一に、暗殺者が家に入ったと仮定して、彼あるいは彼女はどうやって入ったのか? 間違いなく、庭の小道と裏口を通ってです。そこから書斎へ直接アクセスできます。他のどの方法も、非常に複雑だったでしょう。逃走も同じ経路で行われたに違いありません。というのも、部屋の他の二つの出口のうち、一つはスーザンが階下へ駆け下りたときに塞がれ、もう一つはまっすぐ教授の寝室に通じているからです。したがって、私はすぐに庭の小道に注意を向けました。そこは最近の雨でぬかるんでおり、間違いなくどんな足跡も示すはずでした。」
「私の調査でわかったのは、相手が用心深く、手練れの犯罪者だということです。小道には足跡ひとつ見当たりませんでした。しかし、誰かが小道の脇にある芝生の縁を歩いたことは疑いようがありません。足跡を残すのを避けるためでしょう。はっきりとした足跡の類いは何も見つけられませんでしたが、芝生は踏みつけられており、間違いなく誰かが通ったのです。庭師も他の誰もその朝はそこへは行っておらず、雨は夜中に降り始めたばかりでしたから、それは殺人犯以外にありえません。」
「少し待ってくれ」とホームズが言った。「その小道はどこへ続いている?」
「街道へ。」
「長さは?」
「百ヤードほどです。」
「小道が門を抜ける地点なら、さすがに足跡を拾えたのではないか?」
「残念ながら、その地点はタイル張りでした。」
「では、街道そのものは?」
「いえ、そこは一面ぬかるみで、踏み荒らされていました。」
「ちぇっ、ちぇっ! では、その芝生の上の足跡は、来たものか、去ったものか?」
「判別不能でした。輪郭がまったくありませんでしたから。」
「足の大きさは?」
「見分けがつきませんでした。」
ホームズは苛立たしげに声を漏らした。
「それからずっと、土砂降りの雨にハリケーンのような風が吹き荒れている」と彼は言った。「今となっては、あの判読不能な古文書を読むより難しいだろう。まあ、仕方がない。それで、ホプキンス君、結局何も確証が得られなかったと確信した後、君はどうしたんだね?」
「いえ、多くのことを確信したと思いますよ、ホームズさん。誰かが外部から用心深く家に侵入したことはわかりました。次に廊下を調べました。そこはココナッツ繊維のマットが敷かれており、いかなる痕跡も残っていません。それで書斎自体に入りました。そこは殺風景な部屋です。主な家具は、固定式の整理箪笥がついた大きな書斎机です。この整理箪笥は二列の引き出しになっており、中央に小さな戸棚があります。引き出しは開いていて、戸棚には鍵がかかっていました。引き出しは常に開け放しだったようで、価値のあるものは何も入っていませんでした。戸棚には重要な書類がいくつかありましたが、こじ開けられた形跡はなく、教授も何もなくなってはいないと断言しています。盗み目的の犯行でないことは確かです。」
「次に、若者の遺体です。整理箪笥の近く、その図に印したように、すぐ左側で発見されました。刺し傷は首の右側にあり、後ろから前へと刺されていました。ですから、自殺である可能性はほとんどありません。」
「ナイフの上に倒れでもしない限りはな」とホームズが言った。
「その通りです。その考えも頭をよぎりました。しかし、ナイフは遺体から数フィート離れた場所で見つかっており、それも考えにくい。それに、もちろん、男自身の最期の言葉があります。そして最後に、これが極めて重要な証拠品で、亡くなった男の右手に握られていたものです。」
ポケットから、スタンリー・ホプキンスは小さな紙包みを取り出した。それを広げると、金縁の鼻眼鏡が現れた。その端からは、二本にちぎれた黒い絹の紐が垂れ下がっていた。「ウィロビー・スミスは非常に視力が良かった」と彼は付け加えた。「これが暗殺者の顔か、あるいは身につけていたものからひったくられたものであることは疑いようがありません。」
シャーロック・ホームズはその眼鏡を手に取り、この上ない注意と興味を払って調べ始めた。鼻にかけ、それを通して読もうと試み、窓辺へ行ってそれで通りを眺め、ランプの光をいっぱいに浴びせて微に入り細を穿つように観察し、そしてついに、くすりと笑ってテーブルに着くと、紙片に数行書きつけ、それをスタンリー・ホプキンスの方へ放り投げた。
「私にできるのはここまでだ」と彼は言った。「多少は役に立つかもしれん。」
驚いた刑事は、そのメモを声に出して読み上げた。そこには次のように書かれていた。
「求む、品行方正、貴婦人のごとき装いの女性。
鼻は際立って太く、両目はその鼻の両脇に寄りついている。
額にはしわが寄り、探るような目つきで、おそらく猫背であろう。
過去数ヶ月の間に、少なくとも二度、眼鏡屋を訪れた形跡あり。
眼鏡は度が非常に強く、眼鏡屋の数もさほど多くないため、
身元を突き止めるのは困難ではないはず。」
ホプキンスの驚愕の表情――それは私の顔にも映っていたに違いない――を見て、ホームズは微笑んだ。「私の推理など、単純そのものだろう」と彼は言った。「眼鏡ほど、見事な推理の場を提供してくれる品物はそうそうあるまい。特にこれほど特徴的なものであればなおさらだ。これが女性のものであると推測したのは、その繊細な作りから、そしてもちろん、亡くなった男の最期の言葉からだ。洗練され、身なりの良い人物であるという点については、ご覧の通り、純金で見事に縁取られている。このような眼鏡をかける者が、他の点でだらしないとは考えられない。鼻当てが君の鼻には広すぎることがわかるだろう。これは、その婦人の鼻の付け根が非常に広いことを示している。この種の鼻は通常、短く無骨なものだが、例外も十分にあるので、独断で決めつけたり、私の人物描写でこの点を強調したりすることは控えた。私自身の顔は細面だが、それでもこの眼鏡の中心、あるいはその近くに自分の目を合わせることができない。したがって、その婦人の目は鼻の両脇に非常に近い位置にある。ワトソン、わかるだろうが、この眼鏡は凹レンズで、度が並外れて強い。生涯を通じてこれほど極端に視界が狭められてきた婦人には、額や瞼、肩などに、そうした視力に特有の身体的特徴が必ず現れるものだ。」
「ああ」と私は言った。「君の論拠は一つ一つ追える。だが、告白すると、どうやって眼鏡屋への二度の訪問にたどり着いたのかが理解できない。」
ホームズは眼鏡を手に取った。
「わかるだろう」と彼は言った。「鼻当てには、鼻への圧迫を和らげるために、コルクの小さな帯が裏打ちされている。片方は変色し、わずかにすり減っているが、もう片方は新しい。明らかに、片方が取れて交換されたのだ。古い方も、ここ数ヶ月以内につけられたものだと判断する。両者は寸分違わず一致しているから、婦人は二度目も同じ店へ行ったのだろう。」
「これは驚いた、素晴らしい!」ホプキンスは感嘆の声を上げた。「これだけの証拠を手にしながら、全く気づかなかったとは! もっとも、ロンドンの眼鏡屋を片っ端から回るつもりではいましたが。」
「無論、そうしただろう。ところで、この事件について他に何か話すことはあるかね?」
「何もありません、ホームズさん。今やあなたは私と同じくらい――おそらくはそれ以上に――ご存知のはずです。田舎道や駅で見かけられた不審者がいないか調査させましたが、何の報告もありません。私を悩ませているのは、この犯罪に動機が全く見当たらないことです。誰一人として、動機の影すら示唆できないのです。」
「ああ! その点ではお力にはなれんな。だが、明日我々にも来てほしいのだろう?」
「もしご迷惑でなければ、ホームズさん。チャリング・クロスからチャタム行きの列車が朝六時にあります。八時から九時の間にヨクスリー・オールド・プレイスに着けるはずです。」
「では、それに乗ろう。君の事件には確かに非常に興味深い点がいくつかある。喜んで調査させてもらうよ。さて、もうすぐ一時だ。数時間でも眠っておくのが賢明だろう。君は暖炉の前のソファで何とかなるだろう。出発前に、私がアルコールランプを灯してコーヒーの一杯でも淹れてやろう。」
翌日には嵐は過ぎ去っていたが、我々が旅立ったのは、身を切るように寒い朝だった。テムズ川の荒涼とした湿地帯と、長くよどんだ川の流れの上に、冷たい冬の太陽が昇るのを見た。その光景は、我々の経歴の初期にアンダマン島の男を追跡した日々を、私にいつまでも思い起こさせるだろう。長く疲れる旅の後、我々はチャタムから数マイル離れた小さな駅で降りた。地元の宿屋で馬車に馬がつながれる間、我々は急いで朝食をかき込み、ついにヨクスリー・オールド・プレイスに到着したときには、すっかり仕事の準備が整っていた。庭の門で一人の巡査が我々を迎えた。
「やあ、ウィルソン、何かニュースは?」
「いえ、何もありません。」
「不審者を見たという報告は?」
「ありません。駅の者たちは、昨日、不審な者が来たり去ったりしたことはないと断言しています。」
「宿屋や下宿屋の調査はさせたか?」
「はい。身元が確認できない者はおりません。」
「まあ、チャタムまでは歩ける距離だ。誰かがそこに滞在したり、気づかれずに列車に乗ったりすることも可能だろう。これが例の庭の小道です、ホームズさん。昨日、ここに足跡はなかったと誓って言えます。」
「芝生の上の足跡はどちら側にあった?」
「こちら側です。小道と花壇の間の、この狭い芝生の縁です。今はもう痕跡は見えませんが、その時ははっきりとわかりました。」
「うん、うん。誰かが通ったな」ホームズは芝生の縁にかがみ込みながら言った。「我らが貴婦人は、慎重に足を選んで歩かねばならなかったはずだ。片側では小道に足跡を残してしまうし、もう片側では柔らかな花壇に、もっとはっきりとした足跡をつけてしまうのだからな。」
「ええ、相当に肝の据わった女に違いありません。」
ホームズの顔に鋭い表情がよぎるのを私は見た。
「彼女はこの道を戻ってきたに違いないと言ったな?」
「はい、他に道はありません。」
「この芝生の細長い部分を?」
「その通りです、ホームズさん。」
「ふむ! これは実に大した芸当だ――実に大した。さて、小道はもう調べ尽くしたようだ。先へ進もう。この庭の扉は普段は開いているのだろう? ならば、この訪問者はただ入ってくればよかったわけだ。殺意はなかったのだろう。さもなければ、書斎机からこのナイフを拾い上げるのではなく、何らかの武器を用意してきたはずだ。彼女はこの廊下を進み、ココナッツ繊維のマットには何の痕跡も残さなかった。そして、この書斎にたどり着いた。彼女はどれくらいここにいたのか? 判断する術はない。」
「ほんの数分でしょう。言い忘れましたが、家政婦のマーカー夫人が、その少し前に部屋の片付けに入っていたのです――彼女の言うには、十五分ほど前だと。」
「なるほど、それで時間の上限がわかる。我らが貴婦人はこの部屋に入り、何をしたか? 書斎机へ向かった。何のために? 引き出しの中の物ではない。取るに足るものがあったなら、当然鍵がかかっているはずだ。いや、あの木製の整理箪笥の中の何かが目的だった。おや! その表面にある傷は何だ? ワトソン、マッチをかざしてくれ。なぜこれを言わなかったんだ、ホプキンス君?」
彼が調べていた傷は、鍵穴の右側の真鍮の金具から始まり、約四インチにわたって伸び、表面のニスを削り取っていた。
「気づいてはいましたが、ホームズさん、鍵穴の周りには傷はつきものですから。」
「これは新しい、ごく最近のものだ。削れた部分の真鍮が光っているのを見たまえ。古い傷なら表面と同じ色になっているはずだ。私のレンズで見てみろ。ニスも、まるで畑の畝の両脇にある土のようだ。マーカー夫人はいるかね?」
悲しげな顔をした年配の女性が部屋に入ってきた。
「昨日の朝、この整理箪笥のほこりを払いましたか?」
「はい。」
「この傷に気づきましたか?」
「いいえ、気づきませんでした。」
「気づかなかったでしょうとも。ほこり払いを使えば、このニスの削りかすは掃き飛ばされてしまうはずですからな。この整理箪笥の鍵は誰が?」
「教授が時計の鎖につけておられます。」
「単純な鍵かね?」
「いいえ、チャブ式の鍵です。」
「よろしい。マーカー夫人、下がって結構だ。さて、少し進展があったな。我らが貴婦人は部屋に入り、整理箪笥へ進み、それを開けるか、開けようと試みた。彼女がそうしている最中に、若きウィロビー・スミスが部屋に入ってきた。慌てて鍵を引き抜こうとした彼女は、扉にこの傷をつけた。彼は彼女を掴み、彼女は手近にあった物――たまたまこのナイフだった――をひっつかみ、彼に手を離させようと切りつけた。その一撃が致命傷となった。彼は倒れ、彼女は目的の物を手に入れたか、あるいは手に入れずにか、逃走した。メイドのスーザンはいるかね? スーザン、君が叫び声を聞いた後、誰かがその扉から逃げ去ることは可能だったかね?」
「いいえ、不可能です。私が階段を降りる前に、廊下にいれば誰でも見えたはずです。それに、扉は決して開いていません。開けば聞こえたはずですから。」
「これでこの出口は除外された。ならば、婦人は来た道を戻ったに違いない。このもう一つの廊下は教授の部屋にしか通じていないと聞いている。そちらに出口はないのか?」
「ありません。」
「そこを下って、教授にお目にかかるとしよう。おや、ホプキンス君! これは非常に重要だ、実に重要だぞ。教授の廊下もココナッツ繊維のマットが敷かれている。」
「ええ、それが何か?」
「この事件との関連がわからないかね? まあいい。無理強いはすまい。おそらく私が間違っているのだろう。だが、私には何かを示唆しているように思える。私と一緒に行って、紹介してくれたまえ。」
我々は廊下を進んだ。庭へ続く廊下と同じ長さだった。突き当たりには短い階段があり、その先は扉になっていた。我々の案内人がノックし、そして教授の寝室へと我々を招き入れた。
それは非常に広い部屋で、無数の書物が壁を埋め尽くしていた。本は棚からあふれ出し、隅に山と積まれ、あるいは書棚の足元にぐるりと積み上げられていた。ベッドは部屋の中央にあり、その中には、枕で体を支えられた家の主がいた。これほど印象的な人物を見たことは滅多にない。こちらに向けられたのは、痩せこけた鷲鼻の顔で、深くくぼんだ眼窩に、垂れ下がったふさふさの眉の下から突き刺すような黒い目が潜んでいた。髪と髭は白かったが、髭だけは口の周りが奇妙に黄色く染まっていた。もつれた白い毛の中から煙草が赤く光り、部屋の空気は古くなった煙草の煙でむせ返っていた。彼がホームズに手を差し出したとき、その手もまたニコチンで黄色く染まっているのに私は気づいた。
「喫煙家でいらっしゃいますかな、ホームズさん?」と彼は、奇妙に気取ったアクセントのある、選び抜かれた英語で話しかけた。「どうぞ一本。あなたもいかがですかな? お勧めできますよ。アレクサンドリアのイオニデスに特別に作らせているものですから。一度に千本送ってよこすのですが、嘆かわしいことに、二週間ごとに新しい供給を手配せねばならんのです。いけませんな、実にいけません。ですが、老人には楽しみが少ない。煙草と私の研究――私に残されたのはそれだけです。」
ホームズは煙草に火をつけ、部屋中に素早く視線を走らせていた。
「煙草と私の研究、しかし今や煙草だけだ」と老人は叫んだ。「ああ! なんという致命的な邪魔が入ったことか! このような恐ろしい惨事を誰が予見できたでしょう? あれほど立派な若者だったのに! 断言しますが、数ヶ月の訓練の後、彼は素晴らしい助手でした。この件についてどうお考えですかな、ホームズさん?」
「まだ結論は出ていません。」
「我々にとって全てが闇の中であるこの事件に、あなたが光を投げかけてくださるなら、実に恩に着ます。私のような哀れな本の虫で病人には、このような打撃は身動きがとれなくなるほどです。思考能力を失ってしまったかのようです。しかし、あなたは行動の人――実務の人だ。それはあなたの日常生活の一部。いかなる緊急事態においても、あなたは平静を保つことができる。我々は実に幸運だ、あなたを味方に得て。」
老教授が話している間、ホームズは部屋の片側を行ったり来たりしていた。彼が並外れた速さで煙草を吸っているのを私は見ていた。彼が我々の主人の好む、新鮮なアレクサンドリア煙草を気に入ったのは明らかだった。
「ええ、実に打ちのめされるような打撃です」と老人は言った。「あれが私の畢生の大作――向こうのサイドテーブルにある書類の山です。シリアとエジプトのコプト修道院で発見された文書の分析で、啓示宗教のまさに根幹を深くえぐる研究になるでしょう。弱ったこの体では、助手を奪われた今、それを完成させられるかどうか……。おやまあ! ホームズさん、なんと、あなたは私自身よりも速い喫煙家ですな。」
ホームズは微笑んだ。
「私は目利きなものでして」と彼は言い、箱からもう一本――四本目――の煙草を取り出し、吸い終えた煙草の吸い殻から火をつけた。「コーラム教授、あなたに長々と尋問するようなご迷惑はおかけしません。犯行時刻にはベッドにおられたようですし、何もご存知ないでしょうから。ただこれだけお尋ねしたい。あの哀れな若者が最期に言った『教授――あれは彼女だった』という言葉は、どういう意味だったとお考えですかな?」
教授は首を振った。
「スーザンは田舎娘です」と彼は言った。「ご存知でしょう、あの階級の信じがたいほどの愚かさを。おそらく、あの哀れな若者は、何か支離滅裂なうわ言を口走り、彼女がそれをこの無意味な伝言に捻じ曲げたのでしょう。」
「なるほど。あなたご自身は、この悲劇について何の説明もお持ちでないと?」
「おそらくは事故、あるいは――ここだけの話ですが――自殺。若者には隠れた悩みがあるものです。我々が全く知らなかった、恋の悩みか何かでしょう。殺人よりは、その方がよほどありそうな推測です。」
「しかし、あの眼鏡は?」
「ああ! 私はただの学者――夢見る人間にすぎません。人生の現実的なことは説明できません。しかしそれでも、友よ、恋の証は奇妙な形を取ることもあると我々は知っています。どうぞ、もう一本お吸いなさい。それをそれほどまでに味わってくれる人を見るのは喜びです。扇子、手袋、眼鏡――男が自らの命を絶つとき、どんな品が形見として持ち運ばれ、大切にされるか、誰にもわかりません。この紳士は芝生の上の足跡について話しておられますが、結局のところ、そういった点では間違いやすいものです。ナイフについては、あの不運な男が倒れる際に遠くへ投げ出されたのかもしれません。私は子供のように語っているのかもしれませんが、私には、ウィロビー・スミスは自らの手で運命をたどったように思えるのです。」
ホームズは、こうして提示された説に心を打たれたようだった。彼はしばらくの間、考えに沈み、次から次へと煙草を吸いながら行ったり来たりを続けた。
「教えてください、コーラム教授」と、彼はついに言った。「あの整理箪笥の戸棚には何が?」
「泥棒の助けになるようなものは何も。家族の書類、亡き妻からの手紙、私に名誉を与えてくれた大学からの卒業証書。ここに鍵があります。ご自身でご覧になってください。」
ホームズは鍵を拾い上げ、一瞬それを見てから、彼に返した。
「いえ、私の助けになるとは思えませんな」と彼は言った。「静かにあなたの庭へ下りて、頭の中で事件全体をじっくり考えたいと思います。あなたが提示された自殺説には、一理ある。お邪魔したことをお詫び申し上げます、コーラム教授。昼食後まではご迷惑をおかけしないと約束します。二時にまた参りまして、その間に何か進展があればご報告いたします。」
ホームズは奇妙に上の空で、我々はしばらく黙って庭の小道を行ったり来たりした。
「何か手がかりは?」
と、ついに私が尋ねた。
「私が吸ったあの煙草次第だ」と彼は言った。「全くの見当違いという可能性もある。煙草がそれを教えてくれるだろう。」
「親愛なるホームズ」と私は叫んだ。「一体どうやって――」
「まあ、まあ、君も自分の目で確かめることになるだろう。そうでなくても、何の害もない。もちろん、我々には常に眼鏡屋という手がかりが残されているが、近道ができるならそれに越したことはない。ああ、善良なマーカー夫人が来た! 彼女と五分ほど有益な会話を楽しもうじゃないか。」
以前にも述べたかもしれないが、ホームズは、その気になれば、女性に対して独特の愛想の良さを発揮し、いともたやすく彼女たちと信頼関係を築くことができた。彼が口にした時間の半分も経たないうちに、彼は家政婦の好意を勝ち取り、まるで長年の知り合いのように彼女と談笑していた。
「ええ、ホームズさん、おっしゃる通りです。あの方は本当にひどい量の煙草をお吸いになります。一日中、時には一晩中です。朝、あのお部屋を見たことがありますが――まあ、ロンドンの霧かと思うほどでしたわ。お気の毒なスミスさんは、彼も喫煙家でしたが、教授ほどひどくはありませんでした。彼の健康――まあ、喫煙で良くなったか悪くなったかは、私にはわかりませんが。」
「ああ!」とホームズが言った。「しかし、食欲は減退させる。」
「さあ、それはどうでしょう。」
「教授はほとんど何も召し上がらないのでしょう?」
「まあ、気まぐれな方ですわ。それは確かです。」
「私が賭けてもいいが、今朝は朝食を摂らず、私が見たあれだけの煙草を吸った後では、昼食にも手をつけないだろう。」
「あら、それは外れですわ。何を隠そう、今朝は驚くほどたくさんの朝食を召し上がりました。あんなに見事に召し上がったのはいつ以来か思い出せないくらいです。それに、昼食にはカツレツの立派な一皿をご注文になっています。私自身も驚いているんです。昨日、あの部屋に入って、スミスさんが床に倒れているのを見てからというもの、食べ物を見るのも嫌でしたから。まあ、世の中には色々な人がいるものですわね。教授は食欲をなくしたりはなさらなかったようです。」
我々は午前中を庭でぶらぶらして過ごした。スタンリー・ホプキンスは村へ下り、前日の朝に何人かの子供たちがチャタム街道で見かけたという奇妙な女の噂を調べていた。友人に至っては、いつもの活力がすっかり失せてしまったようだった。彼がこれほど気の抜けたやり方で事件を扱うのを、私は見たことがなかった。ホプキンスが持ち帰ったニュース――子供たちを見つけ出し、彼らが間違いなくホームズの描写と完全に一致する女性を目撃し、その女性が眼鏡か鼻眼鏡をかけていたという知らせでさえ――も、彼の鋭い興味の兆候を少しも引き出すことはできなかった。彼がより注意を払ったのは、昼食の給仕をしたスーザンが、スミス氏は昨日の午前中に散歩に出ており、悲劇が起こる三十分前に戻ったばかりだと信じている、と自ら情報を提供したときだった。私自身にはこの出来事の重要性はわからなかったが、ホームズがそれを脳内に形成した全体的な計画に織り込んでいることははっきりと見て取れた。突然、彼は椅子から跳ね上がり、時計に目をやった。「二時だ、諸君」と彼は言った。「我々は上へ行って、我らが友、教授と決着をつけなければならん。」
老人はちょうど昼食を終えたところで、空になった皿は、家政婦が請け合った彼の旺盛な食欲を確かに証明していた。白い髪を振り乱し、爛々とした目を我々に向けた彼は、実に不気味な姿だった。口にはいつもの煙草がくすぶっていた。彼は服を着て、暖炉のそばの肘掛け椅子に腰掛けていた。
「さて、ホームズさん、この謎はもう解けましたかな?」
彼はそばのテーブルに置いてあった大きな煙草の缶を、私の友人の方へ押しやった。ホームズも同時に手を伸ばし、二人の間でその箱はテーブルの端からひっくり返ってしまった。一、二分、我々は皆、床にひざまずき、とんでもない場所から散らばった煙草を拾い集めた。再び立ち上がったとき、私はホームズの目が輝き、頬が紅潮しているのに気づいた。危機的状況においてのみ、私はそうした戦いの合図が掲げられるのを見てきた。
「ええ」と彼は言った。「解きました。」
スタンリー・ホプキンスと私は驚愕して彼を見つめた。老教授の痩せこけた顔に、嘲笑のようなものがかすかに震えた。
「ほう! 庭で?」
「いえ、ここで。」
「ここで! いつ?」
「たった今。」
「まさかご冗談でしょう、ミスター・シャーロック・ホームズ。言わせてもらいますが、これはそのようなやり方で扱われるにはあまりにも深刻な問題ですよ。」
「私は私の鎖の輪を一つ一つ鍛え、試しました、コーラム教授。そしてそれが頑丈であると確信しています。あなたの動機が何であるか、あるいはこの奇妙な事件であなたがどのような役割を果たしているのか、私にはまだ言えません。数分後には、おそらくあなたの口から直接それを聞くことになるでしょう。それまでの間、あなたの利益のために、過去に起こったことを再現しましょう。そうすれば、私がまだ必要としている情報が何か、あなたにもおわかりになるでしょう。」
「昨日、一人の婦人があなたの書斎に入った。彼女はあなたの整理箪笥にある特定の書類を手に入れるつもりでやって来た。彼女は自分の鍵を持っていた。私はあなたの鍵を調べる機会がありましたが、ニスにつけられたあの傷がつけたであろう、わずかな変色を見つけることはできませんでした。したがって、あなたは共犯者ではなかった。そして、証拠を読む限り、彼女はあなたの知らないうちに、あなたから盗みを働くために来たのです。」
教授は唇から煙の雲を吐き出した。「これは実に興味深く、ためになりますな」と彼は言った。「他に何か付け加えることは? まさか、その婦人をそこまで追跡したからには、彼女がどうなったかも言えるのでしょうな。」
「そう努めましょう。第一に、彼女はあなたの秘書に捕まり、逃れるために彼を刺した。この惨事は、不幸な事故であったと私は考えたい。なぜなら、その婦人がそれほど grievous な傷を負わせる意図はなかったと確信しているからです。暗殺者は非武装で現れたりはしない。自らが犯したことに horrified し、彼女は悲劇の現場から必死に逃げ出した。彼女にとって不幸だったのは、もみ合いの中で眼鏡をなくしてしまったことだ。そして、彼女は極度の近眼だったため、眼鏡なしでは全く無力だった。彼女は廊下を駆け下りたが、それは自分が来た廊下だと思い込んでいた――どちらもココナッツ繊維のマットが敷かれていたからだ――そして、手遅れになって初めて、自分が間違った通路を進み、退路が断たれたことに気づいた。彼女はどうすべきだったか? 戻ることはできない。その場に留まることもできない。進むしかない。彼女は進んだ。階段を上り、扉を押し開け、そしてあなたの部屋にたどり着いたのです。」
老人は口を開けたまま、呆然とホームズを見つめていた。その表情豊かな顔には、驚愕と恐怖が刻み込まれていた。今、彼は努力して肩をすくめ、不誠実な笑いを 터뜨렸다。
「全て結構ですな、ホームズさん」と彼は言った。「しかし、あなたの見事な理論には一つ小さな欠点がある。私自身が部屋におり、一日中そこを離れなかったのです。」
「それは承知しています、コーラム教授。」
「ではあなたは、私がそのベッドに横たわっていて、女性が私の部屋に入ってきたことに気づかなかったとでも言うのですか?」
「そんなことは言っていない。あなたは気づいていた。彼女と話した。彼女が誰だか分かった。そして、彼女が逃げるのを手助けした。」
再び教授は甲高い笑い声を上げた。彼は立ち上がり、その目は燃えさしのように輝いていた。
「気でも狂ったか!」と彼は叫んだ。「正気とは思えんことを言っている。私が彼女の逃亡を助けた? 彼女は今どこにいる?」
「そこにいます」とホームズは言い、部屋の隅にある高い書棚を指さした。
老人が両腕を振り上げるのが見えた。恐ろしい痙攣が彼の険しい顔を走り、彼は椅子に倒れ込んだ。その瞬間、ホームズが指さした書棚が蝶番でぐるりと回転し、一人の女性が部屋に飛び出してきた。「あなたの言う通りよ!」彼女は奇妙な外国訛りの声で叫んだ。「あなたの言う通り! 私はここにいるわ。」
彼女は隠れ家の壁から落ちてきた埃で茶色くなり、蜘蛛の巣をまとっていた。顔もまた汚れで筋がついており、どう見ても美人とは言えなかった。ホームズが見抜いた通りの身体的特徴に加えて、長く頑固そうな顎をしていたからだ。生来の目の悪さと、暗闇から明るい場所へ出た変化とで、彼女は呆然と立ち尽くし、我々が誰でどこにいるのかを見ようと瞬きを繰り返していた。しかし、これら全ての不利な点にもかかわらず、その女性の立ち居振る舞いにはある種の気高さがあった――挑戦的な顎と高く掲げられた頭には勇敢さがあり、尊敬と賞賛の念を抱かせずにはいられなかった。
スタンリー・ホプキンスは彼女の腕に手をかけ、囚人として確保しようとしたが、彼女は穏やかに、しかし服従を強いる抗いがたい威厳をもって彼を払いのけた。老人は顔をひきつらせながら椅子に身を預け、物思いに沈んだ目で彼女を見つめていた。
「ええ、私はあなたの囚人です」と彼女は言った。「立っていた場所から全て聞こえました。あなたが真実を知ったこともわかっています。全てを告白します。あの若者を殺したのは私です。でも、あなたは正しい――あれは事故だったと言ったあなたは。私が手にしていたのがナイフだとは知りもしませんでした。絶望の中で、テーブルから何かをひっつかみ、彼に放してもらおうと打ちつけたのです。これは真実です。」
「マダム」とホームズは言った。「それが真実であると確信しています。あなたはひどく具合が悪いようだ。」
彼女は恐ろしい顔色に変わっていた。顔の黒い埃の筋の下で、それは一層不気味に見えた。彼女はベッドの脇に腰を下ろし、それから話を続けた。
「ここにいられる時間はわずかです」と彼女は言った。「でも、あなた方には真実の全てを知っていただきたい。私はこの男の妻です。彼はイギリス人ではありません。ロシア人です。彼の名前は言いません。」
初めて老人が身じろぎした。「神のご加護を、アンナ!」彼は叫んだ。「神のご加護を!」
彼女は深い侮蔑の眼差しを彼に向けた。「なぜそんなに、あなたのその惨めな人生にしがみつくのですか、セルギウス?」と彼女は言った。「それは多くの者に害をなし、誰にも――あなた自身にさえも――善をもたらさなかった。しかし、神の時が来る前に、そのか細い糸を断ち切るのは私の役目ではない。この呪われた家の敷居をまたいで以来、私の魂にはすでに十分な罪が重なっています。でも、話さなければ、手遅れになってしまう。」
「申しましたように、紳士方、私はこの男の妻です。私たちが結婚したとき、彼は五十歳、私は二十歳の愚かな娘でした。ロシアのある都市、大学でのことでした――場所は言いません。」
「神のご加護を、アンナ!」老人は再びつぶやいた。
「私たちは改革者――革命家――ニヒリストでした、おわかりでしょう。彼と私、そして多くの仲間が。やがて困難な時代が訪れ、警察官が殺され、多くが逮捕され、証拠が求められました。そして、自らの命を救い、莫大な報酬を得るために、私の夫は自分の妻と仲間を裏切ったのです。ええ、私たちは皆、彼の告白によって逮捕されました。絞首台へ送られた者もいれば、シベリアへ送られた者もいました。私は後者の一人でしたが、終身刑ではありませんでした。夫は不正に得た金を持ってイギリスへ渡り、それ以来、静かに暮らしてきました。もし同志会が彼の居場所を知れば、一週間も経たずに正義が執行されることをよく知っていたからです。」
老人は震える手を伸ばし、煙草を一本取った。「私はお前のなすがままだよ、アンナ」と彼は言った。「お前はいつでも私に優しかった。」
「まだ彼の悪辣さの極みを話していません」と彼女は言った。「結社の仲間の中に、私の心の友が一人いました。彼は高潔で、無私で、愛情深い――私の夫とは正反対の人間でした。彼は暴力を憎んでいました。私たちは皆、有罪でした――それが罪ならば。しかし彼は違った。彼は永遠に、そのような道から我々を思いとどまらせようと手紙を書いていました。これらの手紙は彼を救ったはずです。私の日記も同様に。そこには日々、彼に対する私の感情と、私たち一人一人が取った見解が記されていました。私の夫はその日記と手紙の両方を見つけ、保管しました。彼はそれを隠し、あの若者の命を偽証によって奪おうと必死でした。これには失敗しましたが、アレクシスは囚人としてシベリアへ送られ、今、この瞬間も、塩の鉱山で働いています。それを考えなさい、この悪党、この悪党め! ――今、今、この瞬間に、アレクシスが、あなたがその名を口にする資格もない男が、奴隷のように働き、生きているというのに、私はあなたの命をこの手に握りながら、あなたを行かせるのです。」
「お前はいつでも高潔な女だった、アンナ」老人は煙草をふかしながら言った。
彼女は立ち上がったが、苦痛の小さな叫びとともに再び倒れ込んだ。
「終わりにしなければ」と彼女は言った。「刑期が終わったとき、私は日記と手紙を取り戻す決心をしました。それらをロシア政府に送れば、友の釈放が叶うからです。夫がイギリスに来たことは知っていました。数ヶ月の捜索の末、彼の居場所を突き止めました。彼がまだ日記を持っていることも知っていました。シベリアにいた頃、一度彼から手紙をもらい、私を非難し、そのページからいくつかの文章を引用していたからです。しかし、彼の執念深い性格からして、自らの意志でそれを私に渡すことは決してないと確信していました。自分で手に入れなければならなかった。この目的のために、私は私立探偵事務所から代理人を雇いました。彼は秘書として夫の家に入り込みました――それはあなたの二人目の秘書でしたよ、セルギウス、あなたを急に去っていったあの男です。彼は書類が戸棚に保管されていることを見つけ、鍵の型を取りました。彼はそれ以上は進もうとしませんでした。彼は私に家の見取り図を渡し、午前中は秘書がこちらで雇われているため、書斎はいつも空だと教えてくれました。そしてついに私は勇気を振り絞り、自分で書類を手に入れるためにやって来たのです。成功はしましたが、何という代償を払ったことでしょう!」
「ちょうど書類を手に入れ、戸棚に鍵をかけているとき、あの若者が私を捕まえました。私はその朝、すでに彼に会っていました。道で彼に会い、コーラム教授がどこに住んでいるか尋ねたのです。彼が教授に雇われているとは知らずに。」
「その通り! その通りだ!」とホームズが言った。「秘書は戻ってきて、雇い主に会った女性のことを話した。そして、最後の息で、それは彼女だ――彼がたった今、教授と話していたその彼女だ――という伝言を送ろうとしたのだ。」
「私に話をさせて」と女性は命令的な声で言った。その顔は苦痛に歪んだようだった。「彼が倒れたとき、私は部屋から飛び出し、間違った扉を選び、夫の部屋に入ってしまいました。彼は私を引き渡すと言いました。私は彼に、もしそうすれば、彼の命は私の手の中にあると示しました。彼が私を法に引き渡せば、私は彼を同志会に引き渡せる。自分のために生きたいからではなく、自分の目的を達成したかったからです。彼は私が言ったことを実行すると知っていました――彼自身の運命が私の運命と結びついていることを。その理由、そしてそれ以外の理由でなく、彼は私をかくまったのです。彼は私をあの暗い隠れ場所に押し込みました――彼だけが知る、昔の時代の遺物です。彼は自分の部屋で食事をとり、それで私に食事の一部を与えることができました。警察が家を去ったら、私が夜中にこっそり抜け出し、二度と戻らないという約束でした。しかし、どういうわけか、あなたは私たちの計画を読み解いてしまった。」
彼女はドレスの胸元から小さな包みを引き裂くように取り出した。「これが私の最後の言葉です」と彼女は言った。「ここにアレクシスを救う包みがあります。あなたの名誉と、あなたの正義への愛にこれを託します。受け取って! ロシア大使館に届けてください。さあ、私は自分の義務を果たしました、そして――」
「止めろ!」ホームズが叫んだ。彼は部屋を横切って跳び、彼女の手から小さな薬瓶をひったくった。
「遅すぎた!」彼女はベッドに倒れ込みながら言った。「遅すぎた! 隠れ家を出る前に毒を飲んだわ。頭がくらくらする! もう行くわ! お願いします、あの包みを忘れないで。」
「単純な事件だが、いくつかの点では教訓的だったな」と、町へ戻る道すがらホームズは言った。「最初から鼻眼鏡にかかっていた。亡くなった男が幸運にもこれを掴んでいなければ、我々が解決にたどり着けたかどうかは定かではない。眼鏡の度の強さから、持ち主はそれを奪われたとき、ひどく目が見えず、無力になるに違いないことは明らかだった。君が私に、彼女が一度も足を踏み外さずに狭い芝生の縁を歩いたと信じるよう求めたとき、私が、それは注目すべき芸当だと言ったのを覚えているだろう。私の心の中では、それは不可能な芸当だと断定していた。彼女が二つ目の眼鏡を持っていたという、ありそうもない場合を除いてはな。したがって、私は彼女が家の中に留まったという仮説を真剣に検討せざるを得なかった。二つの廊下が似ていることに気づくと、彼女がそのような間違いを犯すのは非常に容易であったことが明らかになり、その場合、彼女が教授の部屋に入ったに違いないことは明白だった。だから私は、この仮説を裏付けるものすべてに鋭く警戒し、隠れ場所のようなものがないか部屋を狭く調べた。絨毯は途切れなく、しっかりと釘で留められているようだったので、落とし戸という考えは捨てた。本棚の裏に隠し部屋がある可能性は十分にあった。ご存知の通り、そうした仕掛けは古い書斎にはよくあるものだ。私は、他の場所では本が床に山積みになっているのに、一つだけ書棚がすっきりと片付けられていることに気づいた。ならば、これが扉かもしれない。私を導くような印は見えなかったが、絨毯はくすんだ茶色で、調査には非常に都合が良かった。そこで私は、あの素晴らしい煙草を大量に吸い、疑わしい書棚の前の空間全体に灰を落とした。単純な仕掛けだが、非常に効果的だった。それから階下へ行き、君の目の前で、ワトソン、君には私の発言の意図はわからなかっただろうが、コーラム教授の食事の量が増えていることを確かめた――二人分の食事を供給しているのだから、当然のことだ。それから我々は再び部屋へ上り、煙草の箱をひっくり返すことで、床の様子を非常によく見ることができ、煙草の灰の上の足跡から、我々が留守の間に囚人が隠れ家から出てきたことをはっきりと見ることができたのだ。さて、ホプキンス君、チャリング・クロスに着いた。君の事件を見事に解決に導いたことを祝福するよ。君は本部へ向かうのだろう。私は、ワトソン、君と二人でロシア大使館へ馬車で行こうと思う。」
スリークォーター失踪
ベイカー街で我々が奇妙な電報を受け取るのは、かなり慣れたことだったが、七、八年前のある陰鬱な二月の朝に届き、シャーロック・ホームズ氏を十五分間も当惑させた一通の電報は、特に記憶に残っている。それは彼宛で、次のような文面だった。
お待ちを乞う。恐るべき不運。ライトウィング・スリークォーター行方不明、明日の試合に不可欠。オーバートン。
「ストランドの消印、発送は十時三十六分」ホームズは何度もそれを読み返しながら言った。「オーバートン氏はこれを送ったとき、相当興奮していたようだ。その結果、少々支離滅裂になっている。まあ、いい。私が『タイムズ』紙に目を通す頃には、彼もここに来るだろう。そうすれば全てがわかる。この停滞した日々には、どんな些細な問題でも歓迎だ。」
実際、我々の仕事はひどく閑散としており、私はそうした無為の期間を恐れるようになっていた。というのも、私の友人の頭脳は異常なほど活発で、取り組むべき材料なしに放置するのは危険だと、経験から知っていたからだ。長年かけて、私は彼の輝かしい経歴を危うくしかけた薬物への耽溺から、徐々に彼を遠ざけてきた。今では、通常の状況下では彼がもはやその人工的な刺激を渇望しないことを知っていたが、その悪魔は死んだのではなく眠っているだけであり、その眠りが浅く、目覚めが近いことも承知していた。仕事のない時期に、ホームズの禁欲的な顔にやつれた表情が浮かび、深く窪んだ不可解な目が物思いに沈むのを見てきたからだ。したがって、私はこのオーバートン氏が誰であれ、彼に感謝した。彼が謎めいたメッセージを携えてやって来て、友にとって彼の波乱万丈な人生のどんな嵐よりも大きな危険をもたらす、その危険な静寂を破ってくれたのだから。
我々の予想通り、電報の送り主はすぐにその後を追って現れた。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジのシリル・オーバートン氏の名刺が、体重十六ストーン、筋骨隆々たる巨大な若者の到着を告げた。彼はその広い肩で戸口をふさぎ、不安でやつれた端正な顔で、我々を一人ずつ見比べた。
「シャーロック・ホームズさんですか?」
私の友人はお辞儀をした。
「スコットランド・ヤードへ行ってきました、ホームズさん。スタンリー・ホプキンス警部に会いました。彼があなたに会うようにと勧めてくれたのです。彼が見る限り、この事件は正規の警察よりも、あなたの専門分野に近いだろうと。」
「どうぞお座りになって、何があったのかお話しください。」
「ひどいんです、ホームズさん――全くもってひどい! 髪が白くならないのが不思議なくらいです。ゴドフリー・スタントン――もちろん、彼のことはお聞きになったことがあるでしょう? 彼はまさにチーム全体の要なんです。フォワードを二人欠いても、スリークォーターラインにゴドフリーがいてほしい。パスにしろ、タックルにしろ、ドリブルにしろ、彼に敵う者はいません。それに、頭も切れるし、我々全員をまとめ上げることができる。どうすればいいんです? それをあなたにお聞きしたいんです、ホームズさん。第一控えのムーアハウスがいますが、彼はハーフとして訓練されていて、タッチライン際にとどまらず、いつもスクラムの方へ寄ってしまう。プレースキックは見事ですが、それも本当ですが、判断力がないし、全力疾走もからっきしだ。オックスフォードの俊足、モートンやジョンソンなら、彼の周りを軽々と走り回れるでしょう。スティーブンソンは足は速いが、二十五ヤードラインからドロップキックができない。パントもドロップキックもできないスリークォーターなんて、足の速さだけではポジションに値しません。いえ、ホームズさん、あなたがゴドフリー・スタントンを見つける手助けをしてくれない限り、我々はおしまいです。」
私の友人は、この長い演説に面白そうに、そして驚きながら耳を傾けていた。その演説は並外れた気迫と熱意をもってほとばしり、話の要点ごとに、たくましい手が話者の膝を叩いて強調された。我々の訪問者が黙ると、ホームズは手を伸ばし、彼の雑記帳の「S」の文字の巻を取り出した。今回ばかりは、その雑多な情報の宝庫を掘っても空振りだった。
「アーサー・H・スタントン、新進気鋭の若き偽造犯」と彼は言った。「それからヘンリー・スタントン、私が絞首刑にするのを手伝った男もいたが、ゴドフリー・スタントンは初耳だ。」
今度は我々の訪問者が驚く番だった。
「なんと、ホームズさん、あなたは何でもご存知だと思っていました」と彼は言った。「では、もしゴドフリー・スタントンのことを聞いたことがないのなら、シリル・オーバートンのこともご存知ないのでしょうね?」
ホームズは愛想よく首を振った。
「なんてこった!」とそのアスリートは叫んだ。「私は対ウェールズ戦のイングランド代表第一控えで、今年は大学代表チームのキャプテンを務めたんですよ。でも、そんなことはどうでもいい! イングランドに、ケンブリッジ、ブラックヒース、そして五度の国際試合に出場した名スリークォーター、ゴドフリー・スタントンを知らない人間がいるなんて思いもしませんでした。全く、ホームズさん、一体どこで暮らしてきたんですか?」
ホームズは、その若い巨人の無邪気な驚きに笑った。
「あなたは私とは違う世界――より甘美で、より健全な世界の住人なのですよ、オーバートンさん。私の活動範囲は社会の多くの分野に及んでいますが、幸いなことに、イングランドで最も素晴らしく、最も健全なものであるアマチュアスポーツには、決して及んでいません。しかし、今朝のあなたの思いがけない訪問は、新鮮な空気とフェアプレーの世界にさえ、私のなすべき仕事があるかもしれないことを示してくれました。ですから、さあ、どうぞお座りになって、ゆっくりと、静かに、一体何が起こったのか、そして私がどのようにあなたのお手伝いをすればよいのかを、正確にお話しください。」
若きオーバートンの顔は、頭脳よりも筋肉を使うことに慣れている男の、困惑した表情を浮かべた。しかし、徐々に、彼の物語から私が省略するであろう多くの繰り返しや不明瞭な点を交えながら、彼はその奇妙な話を我々の前に広げた。
「こういうことなのです、ホームズさん。申し上げた通り、私はケンブリッジ大学ラグビーチームのキャプテンでして、ゴドフリー・ストーントンは我がチームのエースです。明日、我々はオックスフォードと対戦します。昨日、全員でこちらへ来て、ベントレー私設ホテルに落ち着きました。十時に私が見回ったところ、皆すでに寝床についていました。チームを最高の状態に保つには、厳しいトレーニングと十分な睡眠が不可欠だと信じていますからね。ゴドフリーが部屋に入る前に、二言三言話したのですが、顔色が悪く、何か悩んでいる様子でした。どうしたのかと尋ねると、大丈夫だ、少し頭痛がするだけだと言うのです。私はおやすみと声をかけて、彼と別れました。その三十分後、ポーターが言うには、髭を生やした人相の悪い男が、ゴドフリー宛の手紙を持って訪ねてきたそうです。彼はまだ寝ておらず、手紙は彼の部屋に届けられました。ゴドフリーはそれを読むと、まるで斧で殴られたかのように椅子に崩れ落ちたそうです。ポーターはあまりに驚いて私を呼びに行こうとしましたが、ゴドフリーがそれを止め、水を一杯飲むと、どうにか落ち着きを取り戻しました。それから階下へ降り、ホールで待っていた男と少し言葉を交わし、二人で連れ立って出て行ったのです。ポーターが最後に二人を見たときには、まるで駆け出すような勢いで、ストランド街の方へ向かっていたとのことでした。今朝、ゴドフリーの部屋はもぬけの殻で、ベッドには寝た形跡もなく、持ち物はすべて昨夜私が見たときのままでした。彼はあの見知らぬ男と、何の前触れもなく姿を消し、それ以来、何の音沙汰もありません。もう二度と戻ってこないような気がするのです。ゴドフリーは骨の髄からのスポーツマンです。彼ほどの男が、トレーニングを放り出し、キャプテンである私を裏切るような真似をするからには、よほど抗いがたい事情があったに違いありません。ええ、もう永遠に帰ってこない、二度と会えない、そんな気がしてならないのです。」
シャーロック・ホームズは、この奇妙な物語に深く耳を傾けていた。
「それで、あなたはどうしたのかね」と彼は尋ねた。
「ケンブリッジに電報を打ち、何か彼の消息が伝わっていないか確認しました。返事が来ましたが、誰も彼を見ていないとのことです。」
「ケンブリッジに戻れた可能性は?」
「ええ、十一時十五分発の夜行列車があります。」
「だが、あなたの知る限り、彼はそれに乗らなかったと?」
「はい、目撃されていません。」
「次にどうしたのかね。」
「マウント・ジェイムズ卿に電報を打ちました。」
「なぜマウント・ジェイムズ卿に?」
「ゴドフリーは孤児でして、マウント・ジェイムズ卿が一番近い親戚なのです。叔父にあたる方だったと思います。」
「なるほど。それは新たな光を投げかけるな。マウント・ジェイムズ卿は英国でも指折りの富豪だ。」
「ゴドフリーもそう言っていました。」
「そして、ご友人は近しい親戚だと?」
「ええ、彼が相続人です。あの爺さんはもう八十に近く、その上、全身痛風まみれだとか。指の関節でビリヤードのキューにチョークを塗れる、なんて言われるほどです。絶対的なけちん坊で、ゴドフリーに一シリングたりとも渡したことはありませんが、いずれはすべて彼のものになるはずです。」
「マウント・ジェイムズ卿から返事は?」
「ありません。」
「ご友人がマウント・ジェイムズ卿のもとへ行く動機は何だろうか。」
「実は、昨夜、彼は何かを心配していました。もし金銭絡みのことだとしたら、莫大な資産を持つ一番近い親戚を頼った可能性はあります。もっとも、噂に聞く限りでは、金を得られる見込みはほとんどないでしょうが。ゴドフリーはあの老人を好いていませんでした。よほどのことがなければ、自分から行くはずがありません。」
「ふむ、それはすぐにわかることだ。もしご友人が親戚のマウント・ジェイムズ卿のもとへ向かったのだとすれば、今度は、あのような夜更けに人相の悪い男が訪ねてきたこと、そしてその男の来訪が引き起こした動揺を説明せねばならなくなる。」
シリル・モートンは両手で頭を抱えた。「さっぱりわかりません」と彼は言った。
「まあ、よろしい。今日は一日空いているから、喜んでこの件を調べさせてもらおう」とホームズは言った。「あなたには、この若き紳士のことはひとまず置いて、試合の準備を進めることを強くお勧めする。あなたがおっしゃる通り、彼をあのような形で引き離したのは、何か抗いがたい事情があったに違いない。そして、同じ事情が彼を今も引き留めている可能性が高い。一緒にホテルへ足を運び、ポーターが何か新しい手がかりを与えてくれるか見てみようじゃないか。」
シャーロック・ホームズは、身分の低い証人を安心させる術にかけては名人であった。ゴドフリー・ストーントンの残された部屋という私的な空間で、彼はすぐさまポーターから聞き出せることのすべてを引き出した。昨夜の訪問者は紳士でもなければ、労働者でもなかった。ポーターが言うところの「どこにでもいそうな男」で、五十がらみ、ごま塩の髭を生やし、顔色が悪く、地味な服装をしていたという。男自身も動揺しているように見えた。ポーターは、男が手紙を差し出したとき、その手が震えているのに気づいていた。ゴドフリー・ストーントンはその手紙をポケットにねじ込んだ。ストーントンはホールで男と握手はしなかった。二言三言言葉を交わしたが、ポーターが聞き取れたのは「時間」という一言だけだった。
それから二人は、話にあった通り、急ぎ足で立ち去った。ホールの時計はちょうど十時半を指していた。
「さて」とホームズは言い、ストーントンのベッドに腰を下ろした。「あなたは昼番のポーターだね?」
「はい、旦那様。私は十一時で勤務を終えます。」
「夜番のポーターは何も見ていないのだろうね?」
「はい、観劇帰りの一団が遅くに戻ってきただけで、他には誰も。」
「昨日は一日中、勤務だったのかね?」
「はい、旦那様。」
「ストーントン氏に何か伝言を届けたかね?」
「はい、電報を一通。」
「ほう! それは興味深い。何時ごろかね?」
「六時ごろです。」
「それを受け取ったとき、ストーントン氏はどこにいた?」
「ここの部屋です。」
「彼がそれを開封したとき、君はそばにいたのかね?」
「はい、返信があるかどうか確認するため、お待ちしておりました。」
「で、あったのかね?」
「はい、旦那様。彼は返信を書いておられました。」
「君がそれを持って行ったのか?」
「いいえ、ご自身で持って行かれました。」
「だが、君の目の前で書いたと。」
「はい、旦那様。私はドアのそばに立っておりまして、彼はあのテーブルで背を向けておられました。書き終えると、『ポーター、結構だ。これは自分で持って行く』とおっしゃいました。」
「何で書いたのかね?」
「ペンでございます。」
「電報用紙は、このテーブルの上にあるものかね?」
「はい、一番上のものです。」
ホームズは立ち上がった。用紙を手に取ると窓際へ運び、一番上にあったものを注意深く調べた。
「鉛筆で書かなかったのが残念だ」と彼は言い、がっかりしたように肩をすくめ、用紙を投げ捨てた。「君もよく知っているだろう、ワトソン。筆圧は通常、下の紙にまで写るものだ。この事実が、どれほど多くの幸せな結婚生活を破綻させてきたことか。しかし、ここには何の痕跡も見当たらない。だが幸いなことに、彼は先の太い羽根ペンで書いたようだ。この吸い取り紙に何らかの跡が残っていることは間違いないだろう。ああ、そうだ、まさしくこれだ!」
彼は吸い取り紙の一片をちぎり取り、我々に次のような象形文字のようなものを見せた。
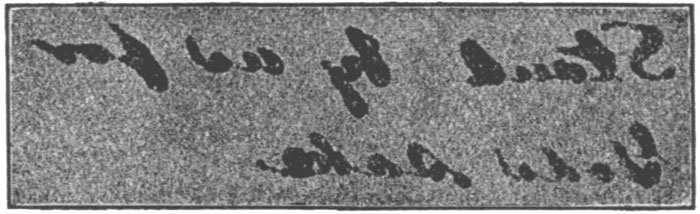
シリル・モートンはひどく興奮した。「鏡に映してください!」と彼は叫んだ。
「その必要はない」とホームズは言った。「紙が薄いから、裏返せばメッセージが読める。ほら、これだ。」
彼はそれを裏返し、我々は読んだ。

「つまり、これがゴドフリー・ストーントンが失踪する数時間前に打った電報の末尾というわけだ。少なくとも六つの単語が欠けているが、残された部分――『頼む、我々を助けてくれ!』――は、この若者が恐るべき危険の接近を察知し、誰かに助けを求めていたことを証明している。『我々を』だ、いいかね! もう一人、関わっている人物がいる。それは、あの顔色が悪く、神経質そうだった髭の男以外に考えられまい。では、ゴドフリー・ストーントンと髭の男の関係は何か? そして、差し迫った危険に対して二人が助けを求めた第三の存在とは何者か? 我々の捜査はすでにそこまで絞り込めた。」
「あとは、その電報が誰に宛てられたものかを見つけ出すだけですね」と私は提案した。
「その通りだ、ワトソン君。君の考察は実に深遠だが、残念ながら私もすでに思いついていたよ。だが、君も気づいているかもしれないが、他人の電報の控えを見せろと言っても、役所の人間が素直に応じてくれるとは限らない。こういうことには、お役所仕事がつきものだからな。しかし、少しばかりの繊細さと手際よさがあれば、目的は達成できると確信している。それまでの間、モートンさん、あなたに同席していただき、このテーブルに残された書類を調べさせてもらいたい。」
そこには多数の手紙、請求書、手帳があり、ホームズは素早く神経質な指つきと、鋭く突き刺すような眼差しで、それらをめくり、調べていった。「ここには何もないな」と彼はついに言った。「ところで、ご友人は健康な若者だったのだろうね? どこか悪いところは?」
「ぴんぴんしていますよ。」
「病気をしたことは?」
「一日もありません。咳で寝込んだことと、一度膝の皿を脱臼したことはありますが、たいしたことではありませんでした。」
「おそらく、君が思うほど丈夫ではなかったのかもしれないな。何か秘密の悩みを抱えていたのではないかと思う。君の許可が得られるなら、今後の捜査に関係してくるかもしれないので、この書類を二、三枚、ポケットに入れさせてもらおう。」
「待て、待て!」と甲高い不満げな声がし、我々が見上げると、戸口に奇妙な小柄な老人が、体をぴくぴくさせながら立っていた。錆びたような黒い服に、つばのやたらと広いシルクハット、そしてだらりとした白いネクタイという出で立ちで、全体として、ひどく田舎じみた牧師か、葬儀屋の無言の先導役といった印象だった。しかし、そのみすぼらしく、滑稽でさえある見た目にもかかわらず、彼の声は鋭く割れており、その態度は人を惹きつける素早い激しさを持っていた。
「あんたは誰だね、どういう権利でこの紳士の書類に触れているのかね?」と彼は尋ねた。
「私は私立探偵で、彼の失踪の謎を解明しようとしているところです。」
「ほう、そうかね? で、誰に頼まれたんだ、え?」
「こちらの紳士、ストーントン氏のご友人ですが、スコットランドヤードから私を紹介されたのです。」
「あんたは誰だね?」
「シリル・モートンです。」
「では、私に電報を打ったのはあんただな。私の名はマウント・ジェイムズ卿。ベイズウォーター行きのバスで、できる限り急いで来た。それで、探偵を雇ったと?」
「はい。」
「費用を払う用意はあるのかね?」
「友人のゴドフリーが見つかれば、彼が支払うことに何の疑いもありません。」
「だが、もし見つからなかったらどうする、え? それに答えろ!」
「その場合は、もちろんご家族が――」
「とんでもない!」と小男は金切り声をあげた。「私から一銭たりとも期待するな――一銭たりともだ! わかったかね、探偵さん! この若者の身内は私だけだが、言っておくが私に責任はない。彼に何か期待されるものがあるとすれば、それは私がこれまで金を無駄遣いしてこなかったからであって、今さらそれを始めるつもりはない。あんたが勝手にいじくっているあの書類だが、もしその中に何か価値のあるものがあった場合、あんたはその扱いについて厳しく責任を問われることになるぞ。」
「承知いたしました」とシャーロック・ホームズは言った。「ところで、この若者の失踪について、ご自身で何かご意見はおありですか?」
「ないね。あいつも自分の面倒くらい見られる図体と歳だ。もし馬鹿な真似をして姿をくらましたのなら、それを探し出す責任など、私は断固として負うつもりはない。」
「あなたのお立場はよくわかります」とホームズは、目にいたずらっぽい輝きを浮かべて言った。「おそらく、あなたは私の立場をあまりご理解いただけていないようだ。ゴドフリー・ストーントン氏は貧しい人物だったようです。もし彼が誘拐されたのだとしても、彼自身が持つ何かのためではありえない。あなたの富の噂は世に知れ渡っております、マウント・ジェイムズ卿。強盗団が、あなたの屋敷や、習慣や、財宝に関する情報を甥御さんから聞き出すために、彼を確保したという可能性は十分考えられます。」
我々の不愉快な小柄な訪問者の顔は、ネクタイのように真っ白になった。
「なんと、まあ! なんということを! そんな悪逆非道なことを考えもしなかった! 世の中には、なんと非道な悪党がいることか! だが、ゴドフリーは良い子だ――忠実な子だ。年老いた叔父を裏切るようなことは決してしないだろう。今晩のうちに、銀食器は銀行に移しておこう。それまでの間、どうか全力を尽くしてください、探偵さん! 彼を無事に取り戻すため、隅から隅まで探していただくようお願いします。金については、まあ、5ポンドか、まあ10ポンドくらいなら、いつでも私を頼ってくれて構わん。」
いくぶん懲りた様子ではあったが、この高貴なる守銭奴は、甥の私生活についてはほとんど知らなかったため、我々の助けになるような情報は何も提供できなかった。我々の唯一の手がかりは、途切れた電報であり、ホームズはその写しを手に、彼の連鎖の第二の環を探しに出かけた。我々はマウント・ジェイムズ卿を振り切り、モートンは彼らに降りかかった不運について、チームの他のメンバーと相談するために去った。
ホテルから少し離れたところに電信局があった。我々はその外で立ち止まった。
「試す価値はある、ワトソン」とホームズは言った。「もちろん、令状があれば控えを見せるよう要求できるが、まだその段階ではない。こんなに忙しい場所で顔など覚えていないだろう。ひとつ、賭けてみよう。」
「お忙しいところ申し訳ありません」と、彼は格子窓の向こうの若い女性に、極めて人好きのする態度で言った。「昨日送った電報のことで、少し手違いがありまして。返事が来ず、どうやら最後に自分の名前を書き忘れたのではないかと心配しているのです。そうなっていたか、教えていただけませんか?」
若い女性は控えの束をめくった。
「何時ごろでしたか?」と彼女は尋ねた。
「六時過ぎです。」
「どなた宛てでしたか?」
ホームズは指を唇に当て、私をちらりと見た。「最後の言葉は『頼む』でした」と彼は内緒話のように囁いた。「返事が来ないので、とても心配しているのです。」
若い女性は用紙の一枚を抜き出した。
「これですね。お名前はありません」と彼女は言い、それをカウンターの上で伸ばした。
「ああ、それで返事が来なかったのですね、もちろん」とホームズは言った。「やれやれ、なんて馬鹿なことをしてしまったんだろう! では、お嬢さん、ごきげんよう。おかげで安心しました。どうもありがとう。」
再び通りに出ると、彼はくすくす笑いながら両手をこすり合わせた。
「それで?」と私は尋ねた。
「順調だ、ワトソン君、順調だ。あの電報をちらりと見るために七つも違う策略を考えていたが、まさか最初の一手で成功するとは思ってもみなかった。」
「で、何を得たのですか?」
「我々の捜査の出発点だ。」
彼は辻馬車を呼び止めた。「キングス・クロス駅へ」と彼は言った。
「旅に出るのですか?」
「ああ、一緒にケンブリッジまで足を延ばさねばなるまい。すべての兆候が、その方向を指し示しているように思える。」
「教えてください」と、グレイズ・イン・ロードを馬車ががたごとと進む中で私は尋ねた。「失踪の原因について、もう何か見当はついているのですか? これまでの我々の事件の中でも、これほど動機が不明瞭なものはなかったように思います。まさか、本当に裕福な叔父の情報を吐かせるために誘拐されたなどと考えているわけではないでしょう?」
「告白するが、ワトソン君、それはあまりありそうな説明だとは思えない。だが、あの極めて不愉快なご老人の興味を最も引きそうな説明だとは思ったのだ。」
「確かにその通りでした。しかし、他にどんな可能性があるのですか?」
「いくつか挙げられる。この重要な試合の前夜にこの事件が起こり、しかもチームの成功に不可欠と思われる唯一の選手が巻き込まれているというのは、奇妙で示唆に富んでいると認めざるを得ないだろう。もちろん、偶然かもしれないが、興味深い。アマチュアスポーツに賭け事はないが、一般大衆の間ではかなりの賭けが行われている。競馬場の悪党どもが競走馬に手を出すように、誰かが選手に手を出してもおかしくはない。これが一つの説明だ。二つ目の非常に明白な可能性は、この若者が、現在の暮らし向きは質素であっても、実際には広大な財産の相続人であるということだ。身代金目的で彼を拘束する計画が練られたとしても不思議ではない。」
「それらの説では、電報のことが説明できません。」
「その通りだ、ワトソン。電報は依然として、我々が扱える唯一の確固たる事実であり、そこから注意をそらしてはならない。この電報の目的を明らかにするために、我々は今ケンブリッジへ向かっているのだ。我々の捜査の道筋は今のところ不明瞭だが、夕方までにはそれを解明するか、あるいはかなりの進展を遂げていなければ、私はひどく驚くだろう。」
我々がその古い大学都市に着いたときには、すでに日は暮れていた。ホームズは駅で辻馬車を拾い、レズリー・アームストロング博士の家へ向かうよう命じた。数分後、我々は最も賑やかな大通りにある大きな邸宅の前で停まった。中に通され、長い間待たされた後、ようやく診察室へ入ることを許されると、そこには机の後ろに腰掛けた博士がいた。
レズリー・アームストロングという名を知らなかったという事実が、私がどれほど医業から遠ざかっていたかを物語っている。今では、彼が大学の医学部の重鎮の一人であるだけでなく、科学の複数の分野でヨーロッパ中に名を知られた思想家であることを知っている。しかし、その輝かしい経歴を知らずとも、その男を一目見ただけで感銘を受けずにはいられなかっただろう。四角くがっしりとした顔、ふさふさした眉の下で物思いに沈む目、そして花崗岩を彫ったような頑固そうな顎。深い人格の持ち主、鋭敏な精神の持ち主、厳格で、禁欲的で、自制的で、恐るべき人物――それが私の読んだレズリー・アームストロング博士の姿だった。彼は私の友人の名刺を手に持ち、その険しい顔つきには、あまり喜ばしいとは言えない表情で顔を上げた。
「シャーロック・ホームズさん、お名前はかねがね。そして、あなたの職業も存じ上げております――私が決して感心しない職業の一つですがね。」
「その点では、博士、あなたは国中の犯罪者と意見が一致しますな」と私の友人は静かに言った。
「あなたの努力が犯罪の抑制に向けられている限り、それは社会の良識あるすべての構成員の支持を得るべきでしょう。もっとも、その目的のためには公的な機関で十分事足りると私は確信しておりますが。あなたの職業が批判にさらされやすいのは、個人の秘密に首を突っ込み、隠しておくべき家庭内の問題をほじくり返し、そしてついでに、あなた自身よりも忙しい人間の時間を無駄にするときです。例えば、現に今、私はあなたと会話する代わりに、論文を執筆しているべきなのです。」
「ごもっともです、博士。しかし、その会話が論文よりも重要だとわかるかもしれません。ついでに申し上げておきますと、我々はあなたが正当にも非難なさるのとは逆のことをしておりまして、事件が公的な警察の手に渡れば必然的に起こるであろう、私的な事柄が公になるのを防ごうと努めているのです。私を、国の正規軍に先んじて進む、非正規の先遣隊とでもお考えください。私は、ゴドフリー・ストーントン氏についてお尋ねしに来ました。」
「彼がどうかしたのかね?」
「ご存じでしょう?」
「彼は私の親しい友人だ。」
「彼が姿を消したことはご承知ですか?」
「ほう、なるほど!」
博士のごつごつした顔つきに、表情の変化はなかった。
「昨夜、ホテルを出たきり、消息がありません。」
「いずれ戻ってくるだろう。」
「明日は大学対抗のフットボールの試合です。」
「あのような子供じみた遊びには、何の共感も覚えん。若者の運命には深く関心がある。彼を知り、好ましく思っているからだ。フットボールの試合など、私の関心の範疇にはまったくない。」
「では、ストーントン氏の運命を調査する私に、ご同情を願います。彼がどこにいるかご存じですか?」
「知るわけがない。」
「昨日から彼に会っていないと?」
「ああ、会っていない。」
「ストーントン氏は健康な男でしたか?」
「もちろんだ。」
「彼が病気だったことは?」
「一度もない。」
ホームズは博士の目の前にさっと一枚の紙を突きつけた。「では、おそらくこれを説明していただけるでしょう。先月、ケンブリッジのレズリー・アームストロング博士に対し、ゴドフリー・ストーントン氏によって支払われた、十三ギニーの領収書付き請求書です。彼の机の上の書類の中から見つけ出しました。」
博士は怒りで顔を赤らめた。
「あなたに説明する義理があるとは思えませんがね、ホームズさん。」
ホームズは請求書を手帳に戻した。「公の場で説明する方がお望みなら、遅かれ早かれそうなるでしょう」と彼は言った。「私はすでに申し上げたはずです。他人が公表せざるを得ないことを、私はもみ消すことができると。私にすべてを打ち明ける方が、賢明な判断だと思いますがね。」
「何も知らん。」
「ロンドンにいるストーントン氏から連絡はありましたか?」
「あるわけがない。」
「やれやれ、また郵便局の仕業か!」ホームズはうんざりしたようにため息をついた。「昨夜の六時十五分、ゴドフリー・ストーントン氏から、あなた宛に非常に緊急の電報がロンドンから発信されています。彼の失踪と間違いなく関連のある電報です。それなのに、あなたは受け取っていない。これは実に怠慢だ。これからこちらの郵便局へ行って、苦情を申し立てることにします。」
レズリー・アームストロング博士は机の後ろから跳ね起き、その浅黒い顔は怒りで真紅に染まっていた。
「私の家から出て行ってもらおうか」と彼は言った。「あなたの雇い主、マウント・ジェイムズ卿に伝えたまえ。彼とも、彼の手下とも、一切関わりたくないと。さあ、もう一言も口を開くな!」
彼は猛烈にベルを鳴らした。「ジョン、この方々をお通ししろ!」
尊大な執事が我々を厳しく戸口へと案内し、我々は通りに放り出された。ホームズは爆笑した。
「レズリー・アームストロング博士は、確かに気骨のある人物だ」と彼は言った。「もし彼がその才能をそちらの道に向ければ、かの高名なモリアーティが残した空白を埋めるのに、あれほどふさわしい男は見たことがない。さて、哀れなワトソン君、我々はこのつれない町で、途方に暮れ、友もなく立ち往生だ。事件を投げ出さずにここを去ることはできん。アームストロングの家の真向かいにあるこの小さな宿は、我々の目的に実に都合がいい。君が表側の部屋を取り、一晩の必需品を買いそろえてくれるなら、私には少しばかり調査をする時間があるだろう。」
しかし、この「少しばかりの調査」は、ホームズが想像していたよりも長引くことになった。彼が宿に戻ってきたのは、九時近くなってからだった。彼は青ざめ、意気消沈し、埃にまみれ、空腹と疲労で疲れ果てていた。テーブルには冷たい夕食が用意されており、腹を満たし、パイプに火をつけると、彼は物事がうまくいかないときに自然と見せる、半ば滑稽で、まったくもって哲学的な見方をする準備ができていた。馬車の車輪の音がして、彼は立ち上がり、窓の外をちらりと見た。ガス灯の光の下、博士の家の前に、二頭立ての灰色の馬が引くブローアム型馬車が停まっていた。
「三時間も留守だった」とホームズは言った。「六時半に出発して、今戻ってきた。半径十マイルか十二マイルの範囲ということになる。これを一日に一回、時には二回やっている。」
「開業医にとっては珍しいことではありません。」
「だが、アームストロングは実質的には開業医ではない。彼は講師であり、顧問医だが、執筆活動の邪魔になる一般診療には関心がない。ではなぜ、彼にとってひどく煩わしいに違いない、こうした長旅をするのか。そして、彼が訪ねているのは誰なのか?」
「彼の御者なら――」
「ワトソン君、私が最初に当たったのが彼だと疑うかね? それが彼自身の生来の邪悪さから来たのか、主人の指図によるものかは知らんが、彼は無礼にも私に犬をけしかけた。しかし、犬も男も私のステッキの様子が気に入らなかったとみえ、その件は立ち消えになった。その後、関係は険悪になり、それ以上の聞き込みは問題外だ。私が得た情報はすべて、我々の宿の中庭にいた気さくな地元民からだ。博士の習慣と、日々の往診について教えてくれたのは彼だ。その瞬間、彼の言葉を裏付けるかのように、馬車が戸口に回ってきた。」
「後を追えなかったのですか?」
「素晴らしい、ワトソン! 今夜の君は冴えているな! その考えは私の頭をよぎったよ。君も気づいたかもしれないが、我々の宿の隣に自転車屋がある。私はそこに駆け込み、自転車を借り、馬車が完全に見えなくなる前に出発することができた。すぐに追いつき、それから百ヤードほどの慎重な距離を保ちながら、町を出るまでその灯りを追った。田舎道に十分入ったところで、少々屈辱的な出来事が起こった。馬車が停まり、博士が降りて、私が同じく停止していた場所まで素早く歩み寄り、道が狭いので、自分の馬車が私の自転車の通行を妨げていないか心配だと、見事なまでに皮肉たっぷりな口調で言ったのだ。その言い方ほど見事なものはなかっただろう。私はすぐに馬車を追い越し、主要な道を走り続け、数マイル進んだところで、馬車が通り過ぎるか見るために都合の良い場所で停止した。しかし、その気配はなく、どうやら私が見かけた幾つかの脇道の一つに曲がったことが明らかになった。私は引き返したが、やはり馬車は見当たらず、そして今、君が見る通り、私の後を追うように戻ってきたというわけだ。もちろん、当初はこれらの往診とゴドフリー・ストーントンの失踪を結びつける特別な理由はなく、ただアームストロング博士に関わることはすべて、現時点では我々にとって興味深いという一般的な理由から調査する気になっただけだ。だが、今や彼がこれらの外出で自分を追う者に対してこれほど鋭い監視の目を光らせているとわかると、この件はより重要性を増してくる。真相を明らかにするまで、私は満足できないだろう。」
「明日、後をつけましょう。」
「できるかね? 君が思うほど簡単ではない。君はケンブリッジシャーの景色に馴染みがないだろう? 隠れるのに適した土地ではないのだ。今夜私が通ってきたこの辺りの土地は、君の手のひらのように平らで何もない。そして、我々が追っている男は、今夜はっきりと示したように、馬鹿ではない。ロンドンでの新たな進展があればこの住所に知らせるよう、モートンに電報を打っておいた。それまでの間は、アームストロング博士に集中するしかない。彼の名前は、電信局の親切な若い女性が、ストーントンの緊急電報の控えで読ませてくれたのだ。彼は若者の居場所を知っている――それは私が誓ってもいい。そして、彼が知っているのなら、我々がそれを突き止められないのは、我々自身の落ち度ということになる。現状では、彼に一枚上手を行かれていることは認めざるを得ない。そして、君も知っての通り、ワトソン、このままゲームを終わらせるのは私の流儀ではない。」
しかし、翌日になっても、我々は謎の解決に一歩も近づけなかった。朝食の後、一通のメモが手渡され、ホームズはそれを微笑みながら私に渡した。
拝啓[と、そこにはあった]――あなたの時間は、私の後をつけ回すことで
無駄に費やされていると断言できます。昨夜お気づきの通り、私のブロ
ーアム型馬車には後部窓がついております。もし出発点に戻るだけの二
十マイルのドライブをご所望でしたら、ただ私の後をついてくればよい
のです。それまでの間、私をいくら監視しても、ゴドフリー・ストーント
ン氏の助けには一切ならないことをお伝えしておきます。そして、あの
紳士にしてやれる最善のことは、ただちにロンドンへ戻り、彼を追跡で
きないと雇い主に報告することだと確信しております。あなたのケンブ
リッジでの時間は、間違いなく無駄になるでしょう。
敬具
レズリー・アームストロング
「率直で、正直な敵だな、あの博士は」とホームズは言った。「ふむ、彼は私の好奇心をかき立てる。彼のもとを去る前に、どうしても真相を知らねばならん。」
「彼の馬車が戸口にいますよ」と私は言った。「今、乗り込むところです。そのとき、彼が我々の窓をちらりと見上げるのを見ました。私が自転車で運試しをしてみましょうか?」
「いや、いや、ワトソン君! 君の天賦の才覚には敬意を表するが、君ではあの博士の相手は務まらないだろう。おそらく、私自身の単独調査によって目的を達成できると思う。眠たいような田舎に、詮索好きなよそ者が二人も現れれば、私が好む以上に噂が立つだろうから、君は君自身の思うように過ごしてもらうしかない。この由緒ある街には、君を楽しませる見どころもあるだろう。夕方までには、もっと良い報告を持って帰れることを期待している。」
しかし、またしても、私の友人は期待を裏切られる運命にあった。彼は夜になって、疲れ果て、何の成果もなく戻ってきた。
「今日は空振りだったよ、ワトソン。博士の向かう大まかな方角を掴んで、一日かけてケンブリッジのそちら側にある村々をすべて訪ね、酒場の主人や他の地元の情報屋たちと情報を交換した。かなりの範囲を回った。チェスタートン、ヒストン、ウォータービーチ、オーキントン、それぞれを調査したが、どれも期待外れだった。あんな眠たいような田舎村で、二頭立てのブローアム型馬車が毎日現れれば、見過ごされるはずがない。またしても博士に一本取られたな。私に電報は来ているかね?」
「ええ、私が開封しました。これです。」
『トリニティ・カレッジ、ジェレミー・ディクソンよりポンペイを求めよ。』
「意味がわかりません。」
「ああ、これは実に明快だ。我らが友モートンからのもので、私の質問に対する返事だ。ジェレミー・ディクソン氏にちょっとメモを送れば、我々の運も向いてくるに違いない。ところで、試合の知らせは何かあったかね?」
「はい、地元の夕刊の最終版に素晴らしい記事が載っていました。オックスフォードが一点と二トライで勝利したそうです。記事の最後の数文はこうです。」
『ライト・ブルーズ[訳注:ケンブリッジ大学のチームカラー]の敗北は、不運にも欠場した国際級の名選手、ゴドフリー・ストーントンの不在にすべて起因すると言えよう。彼の不在は試合のあらゆる瞬間に感じられた。スリークォーター・ラインの連携不足と、攻撃・防御両面での弱さは、重く勤勉なフォワード陣の努力を帳消しにする以上のものだった。』
「では、我らが友モートンの予感が的中したわけだ」とホームズは言った。「個人的にはアームストロング博士に同意で、フットボールは私の関心の範疇にはない。今夜は早く寝よう、ワトソン。明日は波乱の一日になりそうな予感がする。」
翌朝、ホームズを一目見て、私はぞっとした。彼は暖炉のそばに座り、小さな皮下注射器を手にしていたからだ。私はその器具を、彼の唯一の弱点と結びつけて考えていた。それが彼の手の中で煌めくのを見たとき、最悪の事態を恐れた。彼は私の狼狽した表情を見て笑い、それをテーブルの上に置いた。
「いや、いや、君、心配するには及ばん。今回は悪の道具ではなく、むしろ我々の謎を解く鍵となるだろう。この注射器に、私はすべての望みを託している。たった今、小さな偵察から戻ったところで、すべて順調だ。しっかり朝食を摂りたまえ、ワトソン。今日はアームストロング博士の跡を追うつもりだ。そして一度追跡を始めたら、彼の巣穴まで追い詰めるまで、休息も食事もとるつもりはない。」
「それなら」と私は言った。「朝食は携帯した方がよさそうです。彼は早くも出かけるようですから。彼の馬車が戸口に。」
「構わん。行かせたまえ。私に追えない場所へ行けるなら、大した腕利きだ。食事が済んだら、階下へ来てくれたまえ。これから我々が取り組む仕事において、非常に高名な専門家である探偵を紹介しよう。」
我々が階下に降りると、私はホームズについて馬小屋の庭へ入った。彼は個別の馬房の扉を開け、中からずんぐりして、耳の垂れた、白と黄褐色のまだら模様の犬を連れ出した。ビーグルとフォックスハウンドの中間のような犬だった。
「ポンペイを紹介しよう」と彼は言った。「ポンペイは地元のドラッグハウンド[訳注:人工的な臭いを追う猟犬]の誇りだ。その体つきが示すように、決して足は速くないが、臭いを追わせれば実に忠実な猟犬だ。さて、ポンペイ、お前は速くはないかもしれんが、二人のロンドンから来た中年の紳士には速すぎるだろうから、失礼してこの革のリードをお前の首輪につけさせてもらうよ。さあ、坊や、行こう。お前の腕を見せてくれ。」
彼は犬を博士の家の戸口まで連れて行った。犬は一瞬あたりをくんくんと嗅ぎ、それから興奮した鋭い鳴き声をあげると、通りを駆け出し、もっと速く行こうとリードをぐいぐいと引っ張った。三十分もすると、我々は町を抜け、田舎道を急いでいた。
「何をしたのです、ホームズ?」と私は尋ねた。
「古臭いが由緒ある手口だ。だが時には役に立つ。今朝、博士の庭に入り込み、注射器一杯のアニスの実の油を後輪に吹きかけておいたのだ。ドラッグハウンドなら、ここからジョン・オ・グローツ[訳注:スコットランド北東端の村]までアニスの実の臭いを追うだろう。我らが友アームストロングは、ケム川を渡ってでも行かない限り、ポンペイを振り切ることはできまい。おお、あの狡猾な奴め! こうやって、前の晩は私をまいたのだな。」
犬は突然、主要な道から草の生い茂る小道へと入っていった。半マイルほど行くと、そこは別の広い道に出て、跡は我々がちょうど出てきた町の方向へ、右に急カーブしていた。道は町の南側を大きく迂回し、我々が出発したのとは反対の方向へと続いていた。
「この回り道は、完全に我々のためのものだったというわけか?」とホームズは言った。「あの村人たちに聞き込みをしても、何も得られなかったわけだ。博士は徹底的に策を弄したな。これほど手の込んだ欺瞞の理由を知りたいものだ。我々の右手がトランピントンの村のはずだ。そして、なんと! 角からブローアム型馬車がやってくる。急げ、ワトソン――急がないと見つかるぞ!」
彼は門を飛び越えて野原に入り、嫌がるポンペイを引っ張っていった。我々が生け垣の陰に隠れるか隠れないかのうちに、馬車ががたごとと通り過ぎた。中にいるアームストロング博士の姿がちらりと見えた。肩を落とし、両手で頭を抱え、苦悩そのものの姿だった。私の友人の、より一層険しい顔つきから、彼もそれを見たことがわかった。
「我々の探求は、何か暗い結末を迎えそうだ」と彼は言った。「それを知るまで、長くはかからないだろう。来い、ポンペイ! ああ、野原の中のあの小屋だ!」
我々が旅の終わりに着いたことは、疑いようもなかった。ポンペイは門の外で走り回り、しきりにくんくんと鳴いていた。そこにはまだブローアム型馬車の車輪の跡が見えた。一本の小道が、その寂しい小屋へと続いていた。ホームズは犬を生け垣に繋ぎ、我々は先を急いだ。私の友人は小さな田舎風のドアをノックし、返事がなかったのでもう一度ノックした。しかし、小屋は無人ではなかった。低い音が我々の耳に届いたからだ――それは、言いようもなく物悲しい、苦悩と絶望のうめき声のようなものだった。ホームズはためらって立ち止まり、それから、今しがた通ってきた道を振り返った。一台のブローアム型馬車が下ってくるところで、あの灰色の馬たちを見間違えるはずはなかった。
「なんと、博士が戻ってくるぞ!」とホームズは叫んだ。「これで決まりだ。彼が来る前に、これが何を意味するのか確かめねばならん。」
彼はドアを開け、我々は玄関ホールに足を踏み入れた。うなるような音は我々の耳にますます大きく響き、やがて一つの長く深い、苦悶の嘆きとなった。それは階上から聞こえてきた。ホームズは駆け上がり、私もそれに続いた。彼は半開きのドアを押し開け、我々二人は目の前の光景に愕然として立ち尽くした。
若く美しい女性が、ベッドの上に横たわり、死んでいた。その穏やかで青白い顔は、薄暗く大きく見開かれた青い瞳で、もつれた豊かな金髪の中から上方を見つめていた。ベッドの足元には、半ば座り、半ばひざまずき、衣服に顔をうずめた若い男がおり、その体は嗚咽で震えていた。彼はあまりに深い悲しみに打ちひしがれていたため、ホームズがその肩に手を置くまで、顔を上げることはなかった。
「あなたがゴドフリー・ストーントン氏ですか?」
「そうだ、そうだ、私だ――だが、もう遅い。彼女は死んだ。」
男はひどく呆然としており、我々が彼の助けに遣わされた医者以外の何者かであると理解させることができなかった。ホームズが慰めの言葉をかけ、彼の突然の失踪が友人たちに引き起こした心配を説明しようと努めていると、階段に足音がし、ドアのところに、アームストロング博士の重々しく、厳しく、問い詰めるような顔が現れた。
「さて、諸君」と彼は言った。「目的は達したようだな。そして、実にデリケートな瞬間を選んで侵入してくれたものだ。死を前にして口論はしたくないが、私がもっと若ければ、君たちの言語道断な振る舞いは、ただでは済まなかったと断言しておく。」
「失礼、アームストロング博士。少々誤解があるようです」と私の友人は威厳をもって言った。「もし我々と一緒に階下へ降りていただければ、この悲惨な出来事について、互いに何か光を当てることができるかもしれません。」
一分後、険しい顔の博士と我々は、階下の居間にいた。
「それで、どうだね?」と彼は言った。
「まず第一に、ご理解いただきたいのですが、私はマウント・ジェイムズ卿に雇われているわけではありません。そして、この件に関する私の同情は、完全にあの貴族に反するものです。人が行方不明になったとき、その運命を突き止めるのが私の務めですが、それを果たした以上、私に関する限り、この件は終わりです。そして、犯罪性がない限り、私は私的な醜聞を公にするよりも、むしろそれを隠すことに熱心なのです。もし、私の想像通り、この件に法の侵害がないのであれば、私の分別と、事実を新聞沙汰にしないための協力に、絶対的に信頼していただいて結構です。」
アームストロング博士は素早く一歩前に出て、ホームズの手を固く握った。
「あなたは立派な方だ」と彼は言った。「私はあなたを誤解していた。哀れなストーントンをこの窮状に一人残していくことに良心の呵責を覚え、馬車を引き返させたことで、あなたと知り合えたことを天に感謝する。あなたがこれだけご存じなら、状況は実に簡単に説明できます。一年前、ゴドフリー・ストーントンはしばらくロンドンに下宿し、家主の娘に情熱的な恋をして、結婚しました。彼女は美しいだけでなく善良で、善良なだけでなく聡明でした。誰もそのような妻を恥じる必要はありません。しかし、ゴドフリーはあの偏屈な老貴族の相続人であり、彼の結婚の知らせが、彼の相続権の終わりを意味することは間違いありませんでした。私はあの若者をよく知っており、彼の多くの優れた資質ゆえに彼を愛していました。物事を穏便に済ませるため、私はできる限りの手助けをしました。我々は、このことを誰にも知られないよう、最善を尽くしました。というのも、一度そのような噂が広まれば、誰もがそれを耳にするまで時間はかからないからです。この人里離れた小屋と彼自身の分別のおかげで、ゴドフリーはこれまで成功してきました。彼らの秘密は、私と、現在トランピントンに助けを求めに行っている一人の優秀な使用人以外、誰も知りませんでした。しかし、ついに、彼の妻が危険な病に倒れるという、恐ろしい打撃が訪れました。それは最も悪性の肺病でした。哀れな若者は悲しみで半狂乱でしたが、それでもこの試合のためにロンドンへ行かねばなりませんでした。秘密を暴露するような説明なしに、試合を欠場することはできなかったのです。私は電報で彼を元気づけようとし、彼は返信で、できる限りのことをしてほしいと懇願してきました。これが、あなたがどういうわけか不可解な方法でご覧になった電報です。私は彼に危険がどれほど切迫しているかは伝えませんでした。彼がここにいても何の役にも立たないとわかっていたからです。しかし、私は真実を娘の父親に送り、彼は非常に軽率にもそれをゴドフリーに伝えてしまいました。その結果、彼は半狂乱の状態でまっすぐここへやって来て、今朝、死が彼女の苦しみに終止符を打つまで、彼女のベッドの足元でひざまずいたまま、同じ状態であり続けました。以上です、ホームズさん。あなたの、そしてご友人の分別に頼れると確信しております。」
ホームズは博士の手を握った。
「行こう、ワトソン」と彼は言い、我々はその悲しみの家から、冬の日の青白い日差しの中へと出て行った。
アベイ・グランジの冒険
一八九七年の冬の終わり、ひどく寒く霜の降りた朝のことだった。肩を揺すられて、私は目を覚ました。ホームズだった。彼の手にした蝋燭が、その熱心な、かがみ込んだ顔を照らし出し、何かただならぬことが起きたのだと一目でわかった。
「来い、ワトソン、来い!」と彼は叫んだ。「事件だぞ。何も言うな! 服を着て、来るんだ!」
十分後、我々二人は辻馬車に乗り込み、チャリング・クロス駅へ向かう静かな通りをがたごとと走っていた。冬の夜明けの最初の微かな光が現れ始め、時折通り過ぎる早起きの労働者の姿が、乳白色に煙るロンドンの煤煙の中、ぼんやりと不鮮明に見えた。ホームズは黙って厚いコートに身をうずめ、私もそれに倣った。空気はひどく冷たく、我々は二人ともまだ朝食を摂っていなかったからだ。
駅で熱い紅茶を飲み、ケント行きの列車に席を取るまで、我々は十分に体が温まらなかった。彼が話し、私が聞くには、それが必要だった。ホームズはポケットからメモを取り出し、読み上げた。
ケント州マーシャム、アベイ・グランジにて、午前三時三十分
親愛なるホームズ殿
非常に注目すべき事件となりそうな件で、至急のご助力をお願いできれば幸
いです。まさにあなた向きの事件です。ご婦人を解放することを除き、す
べて私が見つけたままの状態にしておくよう取り計らいます。しかし、ユ
ースタス卿をこのままにしておくのが難しいため、一刻も早くお越しくだ
さるようお願いします。
敬具
スタンリー・ホプキンス
「ホプキンスが私を呼んだのはこれで七度目だが、その都度、彼の要請は完全に正当なものだった」とホームズは言った。「彼の事件はすべて、君のコレクションに収められていると思う。そして、認めねばならんが、ワトソン、君にはある種の選択眼がある。それが、君の物語の中で私が嘆かわしく思う多くの点を補って余りある。すべてを科学的な演習としてではなく、物語の観点から見るという君の致命的な癖が、有益で、古典的でさえあり得た一連の論証を台無しにしてしまっている。君は、読者を興奮させるかもしれないが、到底教えることのできない扇情的な細部にこだわるあまり、極めて緻密で繊細な仕事をないがしろにするのだ。」
「では、ご自分で書かれたらどうです?」と私は、いくらか苦々しさを込めて言った。
「書くとも、ワトソン君、書くとも。ご存じの通り、今はかなり忙しいが、私の晩年は、探偵術のすべてを一巻に集約した教科書の執筆に捧げるつもりだ。今回の調査は、殺人事件のようだ。」
「では、このユースタス卿は死んでいると?」
「そうだろうな。ホプキンスの筆跡にはかなりの動揺が見られるが、彼は感情的な男ではない。ああ、暴力沙汰があり、遺体は我々の検分のために残されていると推測する。単なる自殺であれば、彼が私を呼び出すことはなかっただろう。ご婦人の解放については、悲劇の間、彼女は自室に閉じ込められていたようだ。我々は上流階級の事件を扱っているぞ、ワトソン。ぱりぱりした便箋、『E.B.』のモノグラム、紋章、絵になるような住所。友人のホプキンスは、その評判に違わぬ働きをしてくれるだろう。そして、我々は興味深い朝を迎えることになるだろう。犯行は昨夜十二時より前だ。」
「どうしてそんなことがわかるのです?」
「列車の時刻を調べ、時間を計算したからだ。地元の警察が呼ばれ、彼らがスコットランドヤードに連絡し、ホプキンスが出向き、そして彼が私に連絡する。それだけで、一晩がかりの仕事になる。さて、チズルハースト駅に着いた。間もなく、我々の疑問も晴れるだろう。」
狭い田舎道を二マイルほど走ると、公園の門に着いた。門は、やつれた顔に何か大きな災厄の影を映した、年老いた門番が開けてくれた。並木道は、古いニレの木々の間を抜け、壮大な公園を貫き、正面にパラディオ様式の柱が立つ、低く広がった邸宅で行き着いた。中央部分は明らかに古く、蔦に覆われていたが、大きな窓は近代的な改築が施されたことを示しており、邸宅の一翼はまったく新しいもののように見えた。開け放たれた戸口で我々を迎えたのは、若々しい姿と、機敏で熱心な顔つきのスタンリー・ホプキンス警部だった。
「よくお越しくださいました、ホームズさん。ワトソン博士も。ですが、実を言うと、もし時間を巻き戻せるなら、わざわざお呼び立てはしませんでした。というのも、夫人が意識を取り戻されてから、事件についてあまりにも明快な証言をなさったので、我々がすべきことはほとんど残されていないのです。ルイシャムの強盗団をご記憶ですか?」
「何、あのランダル一家かね?」
「その通りです。父親と二人の息子。連中の仕業です。疑いの余地はありません。二週間前にシドナムで一件仕事をやり、その姿を目撃され、人相も割れています。これほど早く、これほど近くで次の犯行に及ぶとは、なかなかの度胸ですが、間違いなく奴らです。今回は絞首刑ものの事件ですな。」
「では、ユースタス卿は亡くなられたのか?」
「はい。ご自身の火かき棒で頭を殴りつけられました。」
「ユースタス・ブラックンストール卿、と馬車の御者が申しておりましたが。」
「その通りです。ケント州でも指折りの富豪でして……ブラックンストール夫人は朝の間にいらっしゃいます。お気の毒に、夫人は実に恐ろしい目に遭われました。最初にお会いしたときは、半死半生といったご様子でした。まずは夫人にお会いになって、事の次第をお聞きになるのがよろしいでしょう。その後、一緒に食堂を調べましょう。」
ブラックンストール夫人は、ただならぬ人物であった。あれほど優美な姿態、女性らしい物腰、そして美しい顔立ちの女性は滅多にお目にかかれるものではない。彼女はブロンドで、金色の髪に青い瞳を持ち、近頃の出来事がなければ、その髪の色にふさわしい完璧な肌の色艶だったろうに、今はやつれて憔悴しきっていた。彼女の苦しみは精神的なものだけでなく、肉体的にも及んでいた。片方の目の上には、見るもおぞましい、赤紫色に腫れ上がった瘤があり、背の高い、厳格そうなメイドが、酢と水で甲斐甲斐しく冷やしていた。夫人は長椅子にぐったりと身を横たえていたが、我々が入室したときの素早く鋭い眼差しと、その美しい顔立ちに浮かんだ油断のない表情は、彼女の知性も勇気も、この恐ろしい体験によって少しも揺らいでいないことを示していた。彼女は青と銀のゆったりとした部屋着に身を包んでいたが、その傍らの長椅子には、黒いスパンコールで覆われた夜会服が置かれていた。
「起こったことはすべてお話ししましたわ、ホプキンスさん」彼女は疲れたように言った。「代わりに説明していただけませんか? ……まあ、必要だとお思いなら、この紳士方に何があったかお話しします。お二人はもう食堂には?」
「まず奥様のお話を伺うのがよろしいかと思いまして。」
「早く事を済ませていただけると助かりますわ。あの人がまだあそこに横たわっていると思うと、ぞっとしますもの。」
彼女は身震いし、両手で顔を覆った。その拍子に、ゆったりとした部屋着の袖が滑り落ち、前腕が現れた。ホームズが驚きの声をあげた。
「他にも怪我を! マダム、これは?」
その白く丸い腕に、二つの鮮やかな赤い斑点が浮かび上がっていた。彼女は慌ててそれを隠した。
「何でもありません。今夜のこの忌まわしい出来事とは何の関係もありませんわ。あなたとご友人がお掛けくだされば、お話しできることはすべてお話しします。」
「私はユースタス・ブラックンストール卿の妻です。結婚して一年ほどになります。私たちの結婚が幸せなものではなかったと隠そうとしても、無駄でしょうね。たとえ私が否定しようとも、ご近所の誰もがそうお話しするでしょうから。もしかしたら、私にもいくらか非があったのかもしれません。私は南オーストラリアの、もっと自由で因習にとらわれない雰囲気の中で育ちましたから、この英国の暮らしは、その作法や堅苦しさがどうにも性に合わないのです。ですが、主な原因は、誰の目にも明らかな一つの事実にあります。それは、ユースタス卿が根っからの大酒飲みだったということです。あのような方と一時間も一緒にいることすら不愉快です。繊細で気性の激しい女が、昼も夜も彼に縛りつけられることが何を意味するか、ご想像いただけますか? このような結婚に縛られるなど、神への冒涜であり、犯罪であり、極悪非道です。あなた方のこの忌まわしい法律は、この国に呪いをもたらすでしょう。神がこのような邪悪が続くのをお許しになるはずがありません。」
一瞬、彼女は身を起こした。頬は紅潮し、額の痛ましい傷の下で瞳が燃え盛っていた。すると、厳格そうなメイドの力強くも優しい手が、夫人の頭をクッションへと引き戻し、荒々しい怒りは、激情のすすり泣きへと消えていった。やがて彼女は続けた。
「昨夜のことをお話しします。ご存じかもしれませんが、この屋敷では使用人たちは皆、新しい翼棟で寝ています。この中央の棟は居住区画で、後ろに台所、その上に私たちの寝室があります。私のメイドのテレサは、私の部屋の真上で寝ています。他には誰もおりませんし、遠い翼棟にいる者たちには、どんな物音も聞こえません。強盗たちはそのことをよく知っていたに違いありません。でなければ、あのような真似はしなかったでしょう。」
「ユースタス卿は十時半頃に寝室へ引き上げました。使用人たちもすでに自分たちの部屋に戻っていました。起きていたのは私のメイドだけで、彼女は私がお呼びするまで、屋敷の一番上にある自室におりました。私は十一時過ぎまでこの部屋で本に没頭していました。それから、階上に上がる前に、すべて異常がないか見回って歩きました。いつも私が自分でやることにしていましたの。先ほども申しましたように、ユースタス卿は必ずしも頼りになる方ではありませんでしたから。台所、執事の食料品室、銃器室、ビリヤード室、客間、そして最後に食堂へ入りました。厚いカーテンで覆われた窓に近づいたとき、突然、顔に風を感じ、窓が開いていることに気づきました。カーテンをさっと払いのけると、ちょうど部屋に足を踏み入れたばかりの、肩幅の広い年配の男と顔を合わせました。窓はフランス窓で、実際には芝生に通じる扉になっています。私は寝室用の蝋燭を手に灯しておりましたが、その光で、最初の男の後ろに、さらに二人、部屋に入ろうとしているのが見えました。私は後ずさりましたが、男は一瞬のうちに私に襲いかかりました。まず手首を、次に喉をつかまれました。悲鳴をあげようと口を開きましたが、男は拳で私の目の上を獰猛に殴りつけ、私は地面に倒れました。数分間、意識を失っていたに違いありません。気がつくと、彼らはベルの紐を引きちぎり、食堂のテーブルの端にある樫の椅子に私をしっかりと縛りつけていました。あまりに固く縛られていたので身動き一つできず、口にはハンカチを詰められていたので、声を出すこともできませんでした。その時です、不運にも夫が部屋に入ってきたのは。何か怪しい物音を聞きつけ、彼が見出したような光景を予期して準備してきたのでしょう。寝間着のシャツとズボンという姿で、お気に入りのブラックソーンの棍棒を手にしていました。彼は強盗たちに突進しましたが、別の一人――年配の男でした――が、身をかがめ、暖炉から火かき棒を拾い上げ、通り過ぎる夫に恐ろしい一撃を食らわせました。夫は呻き声をあげて倒れ、二度と動きませんでした。私は再び気を失いましたが、これもまた、ほんの数分間のことだったに違いありません。目を開けると、彼らはサイドボードから銀食器を集めているところでした。そして、そこにあったワインの瓶を抜いていました。三人ともグラスを手に持っていました。すでにお話ししましたかしら、一人は年配で髭を生やし、他の二人は若く、髭のない若者だったと。まるで父親と二人の息子のようでした。彼らは囁き声で話していました。それからこちらへ来て、私がしっかりと縛られていることを確かめました。最後に、彼らは窓を閉めて立ち去りました。口が自由になるまで、十五分はかかりました。自由になると、私の悲鳴でメイドが助けに駆けつけてくれました。他の使用人たちもすぐに騒ぎに気づき、私たちは地元の警察に連絡しました。警察はすぐにロンドンと連絡を取りました。本当に、私が申し上げられるのはこれだけです、紳士方。この辛い話をもう一度繰り返す必要がないことを願っております。」
「何か質問は、ホームズさん?」とホプキンスが尋ねた。
「ブラックンストール夫人の忍耐と時間をこれ以上奪うつもりはありません」とホームズは言った。「食堂に入る前に、あなたの経験をお聞かせ願いたい。」
彼はメイドに目を向けた。
「あたしは、あの男たちが家に入る前から見ていましたよ」と彼女は言った。「寝室の窓辺に座っていると、月明かりの中、向こうのロッジの門のそばに三人の男がいるのが見えましたが、その時は何も気にしませんでした。それから一時間以上経って、奥様の悲鳴が聞こえたんです。駆け下りてみると、可哀想なお方は、おっしゃる通り、あの状態で、旦那様は床の上、部屋中に血と脳漿をぶちまけて。女が正気を失うには十分な光景でしたよ。あんなふうに縛られて、ドレスにまで旦那様の血がかかって。でも、奥様は決して勇気を失うことはありませんでした。アデレードのメアリー・フレイザー嬢は昔から勇気のあるお方でしたし、アビイ屋敷のブラックンストール夫人となっても、その性根は少しも変わりません。紳士方、もう十分お尋ねになったでしょう。奥様はこれから、昔からのテレサと一緒にご自分の部屋へお戻りになり、どうしても必要な休息をお取りになります。」
母親のような優しさで、その痩身の女性は女主人の肩に腕を回し、部屋から連れ出した。
「彼女は夫人の生涯の付き人です」とホプキ-ンスは言った。「赤ん坊の頃から乳母として仕え、十八ヶ月前にオーストラリアから初めてイングランドに来たときも一緒でした。テレサ・ライトというのが彼女の名前で、近頃ではなかなか見つからないタイプのメイドです。こちらへどうぞ、ホームズさん!」
ホームズの表情豊かな顔から、鋭い興味の光が消え失せていた。謎が解けてしまえば、この事件の魅力もすべて失われたのだと私にはわかった。まだ犯人逮捕という仕事は残っているが、そんなありふれた悪党どもに手を汚すなど、彼がすることだろうか? 難解な分野の碩学が、はしかの診断に呼び出されたと知ったときのような、そんな苛立ちが友の目に見て取れた。しかし、アビイ屋敷の食堂の光景は、彼の注意を引きつけ、薄れかけていた興味を呼び覚ますには十分なほど異様であった。
そこは非常に広く天井の高い部屋で、彫刻の施された樫の天井に、樫材の羽目板、そして壁には鹿の頭の剥製や古い武器が見事に飾られていた。扉から一番遠い突き当たりには、我々が聞いていた背の高いフランス窓があった。右手にある三つの小さな窓から、冷たい冬の日差しが部屋に差し込んでいた。左手には大きく深い暖炉があり、その上には重厚な樫のマントルピースが張り出していた。暖炉のそばには、肘掛けと足元の横木がついた、どっしりとした樫の椅子があった。その開いた木組みの間を、深紅の紐が縫うように通され、両端が下の横木に結びつけられていた。夫人を解放する際に紐は外されたが、結び目はそのまま残っていた。これらの細部は後になって我々の注意を引いたにすぎない。というのも、我々の思考は、暖炉の前に敷かれた虎皮の絨毯の上に横たわる、恐るべき物体に完全に心を奪われていたからだ。
それは、四十歳ほどの、背が高く、がっしりとした体格の男の死体だった。仰向けに横たわり、顔は上を向き、短い黒髭の間から白い歯が覗き、まるで不気味に笑っているようだった。握りしめられた両手は頭上に掲げられ、その上に重いブラックソーンの杖が横たわっていた。その浅黒く、整った鷲鼻の顔立ちは、執念深い憎悪の痙攣に歪み、その死に顔を恐ろしく悪魔的な表情に固まらせていた。警報が鳴ったとき、彼はベッドにいたに違いない。気取った刺繍入りの寝間着を身につけ、ズボンからは素足が突き出ていた。頭部はひどく損傷しており、部屋全体が、彼を打ち倒した一撃の残忍な獰猛さを物語っていた。傍らには、衝撃で湾曲した重い火かき棒が転がっていた。ホームズは、その火かき棒と、それがもたらした、言葉では言い表せない惨状の両方を検分した。
「このランダル家の親父というのは、相当な力自慢に違いない」と彼は言った。
「ええ」とホプキンスは言った。「その男については多少記録がありますが、かなりの荒くれ者です。」
「捕らえるのに苦労はなさそうだ。」
「まったく。我々は奴をずっと探しておりまして、アメリカへ逃げたという話もありました。一味がここにいるとわかった以上、どうやっても逃げられません。すでにすべての港に手配済みで、今夜までには懸賞金もかけられます。解せないのは、夫人が奴らの人相を証言できるとわかっていながら、そして我々がその人相から奴らを特定しないはずがないとわかっていながら、どうして連中がこんな無茶な真似をしたかです。」
「その通りだ。ブラックンストール夫人も口封じするのが当然と考えるだろう。」
「夫人が気絶から回復したことに気づかなかったのかもしれません」と私は提案した。
「それはあり得るな。意識がないように見えれば、命までは取らないだろう。この気の毒な男についてはどうだね、ホプキンス君? 彼については、いくつか奇妙な噂を耳にしたことがあるが。」
「素面のときは気のいい男でしたが、酔うと、というよりは半ば酔うと、まったくの悪魔でした。完全に酔いつぶれることは滅多になかったのですがね。そういうときは悪魔が乗り移ったようで、何をしでかすかわかりませんでした。聞くところによると、その富と爵位にもかかわらず、一度ならず、我々の厄介になりかけたことがあります。犬に石油を浴びせて火をつけたという醜聞がありまして――しかも、悪いことに、奥様の犬だったのです――それはもみ消すのに一苦労しました。それから、あのメイドのテレサ・ライトにデカンタを投げつけたことも。あれも問題になりました。総じて、そしてここだけの話ですが、彼がいなくなって、この家も明るくなるでしょう。今は何をご覧になっているんですか?」
ホームズは膝をつき、夫人が縛られていた赤い紐の結び目を細心の注意を払って調べていた。それから、強盗が引きちぎった際に切れた、ほつれた端を念入りに検分した。
「これを引きちぎったとき、台所のベルはけたたましく鳴ったはずだ」と彼は言った。
「誰にも聞こえませんよ。台所は家のちょうど裏手にありますから。」
「強盗はどうして誰にも聞こえないと知っていた? どうしてあんな無謀なやり方でベルの紐を引っ張るような真似ができた?」
「その通りです、ホームズさん、その通り。私が何度も自問自答した、まさにその疑問です。この男がこの家とその習慣を知っていたに違いないことは疑いようがありません。使用人たちが皆、比較的に早い時間に寝てしまうこと、そして台所のベルが鳴っても誰にも聞こえるはずがないことを完全に理解していたに違いありません。したがって、彼は使用人の誰かと緊密に結託していたはずです。それは明らかでしょう。しかし、使用人は八人いますが、いずれも素行は良好です。」
「他の条件が同じなら」とホームズは言った。「主人がデカンタを投げつけた相手を疑うのが筋だろうな。だが、それでは、この女が献身的に仕えているように見える女主人への裏切りを伴うことになる。まあ、いい。それは些細な点だ。ランダルを捕まえれば、共犯者を確保するのも難しくはないだろう。夫人の話は、我々が目の当たりにしているあらゆる細部によって、裏付けを必要とするならば、確かに裏付けられているようだ。」
彼はフランス窓へ歩み寄り、それを開け放った。「ここには何の痕跡もないが、地面は鉄のように固いから、期待はできないだろう。マントルピースの上のこの蝋燭に火が灯されていたようだね。」
「ええ、その光と奥様の寝室の蝋燭の光で、強盗たちはあたりを見回したのです。」
「それで、何を盗んだのだね?」
「大したものは盗んでいません。サイドボードから銀食器を六点ほどです。ブラックンストール夫人は、ユースタス卿の死に動転して、そうでなければしたであろう家捜しをしなかったのだろうと考えておられます。」
「なるほど、それは本当だろう。だが、それでもワインをいくらか飲んだと聞いているが。」
「神経を落ち着かせるためでしょう。」
「その通り。サイドボードの上のこの三つのグラスは、手つかずだったのだろう?」
「ええ、瓶も連中が残していったままです。」
「見てみよう。おや、おやおや! これは一体?」
三つのグラスは一箇所にまとめられており、いずれもワインの色がついていたが、そのうちの一つにはワインの澱が溜まっていた。瓶はそのそばにあり、三分の二ほど残っていた。そしてその横には、深く染みのついた長いコルクが転がっていた。その様子と瓶の上の埃から、殺人者たちが楽しんだのが、ありふれた年代物ではないことがわかった。
ホームズの態度に変化が現れた。気だるげな表情は消え、その鋭く窪んだ瞳に、再び油断のない興味の光が宿るのを私は見た。彼はコルクを拾い上げ、詳細に調べた。
「どうやって抜いたのだね?」と彼は尋ねた。
ホプキンスは半開きになった引き出しを指差した。中にはテーブルリネンと大きなコルク抜きが入っていた。
「ブラックンストール夫人は、そのコルク抜きが使われたと言っていたかね?」
「いいえ、ご記憶でしょうが、瓶が開けられた瞬間、夫人は意識を失っておられました。」
「その通り。実を言うと、そのコルク抜きは使われていない。この瓶はポケット・スクリューで開けられた。おそらくナイフに内蔵されている、長さ一インチ半にも満たないものだろう。コルクの頭をよく見ればわかるが、コルクが抜けるまでに、スクリューは三度もねじ込まれている。貫通はしていない。この長いスクリューなら、一度で貫通させ、一気に引き抜いただろう。この男を捕まえたら、こういう多機能ナイフを所持していることがわかるはずだ。」
「素晴らしい!」とホプキンスは言った。
「しかし、このグラスには正直、困惑させられる。ブラックンストール夫人は、三人の男が飲んでいるのを実際に見た、そうだな?」
「ええ、その点ははっきりしていました。」
「ならば、それで終わりだ。これ以上、何を言うことがある? それでも、認めざるを得ないだろう、この三つのグラスは実に奇妙だ、ホプキンス君。何? 何も奇妙なことはないと? まあ、いいだろう。おそらく、私自身のような特別な知識と能力を持つ人間は、もっと単純な説明が手近にあるときでも、複雑な説明を求めたがる傾向があるのかもしれない。もちろん、グラスのことは単なる偶然に違いない。では、ごきげんよう、ホプキンス君。私がお役に立てることは何もないようだ。君の事件は非常に明快なように見える。ランダルが逮捕されたとき、そして何か進展があったときには知らせてくれたまえ。君の成功を近いうちに祝えることを願っているよ。さあ、ワトソン、我々は家でもっと有意義に時間を使えると思うよ。」
帰りの道中、ホームズが何か観察したことにひどく当惑しているのが、その顔から見て取れた。時折、彼は無理にその印象を振り払い、あたかも事件は解決したかのように話すのだが、すぐにまた疑念が彼を覆い、寄せられた眉と上の空の瞳は、彼の思考が再び、あの真夜中の悲劇が演じられたアビイ屋敷の大きな食堂へと戻っていることを示していた。ついに、突然の衝動に駆られ、我々の乗った列車が郊外の駅を這うように出て行こうとしたまさにその時、彼はプラットフォームに飛び降り、私のことも引きずり出した。
「すまない、我が友よ」カーブの向こうに我々の列車の後部車両が消えていくのを見ながら、彼は言った。「単なる気まぐれに見えるかもしれないことの犠牲にして申し訳ない。だが、誓って言うが、ワトソン、私はこの事件をこのままの状態にしておくことなど、到底できないのだ。私の持つあらゆる本能が、それに反して叫んでいる。これは間違っている――すべてが間違っている――断言するが、あれは間違っている。それなのに、夫人の話は完璧で、メイドの裏付けも十分、細部もかなり正確だった。それに対して、私に何が突きつけられる? 三つのワイングラス、それだけだ。だが、もし私が物事を鵜呑みにせず、もし我々がこの事件に白紙の状態から取り組み、出来合いの話に判断を歪められることがなかったなら、もっと確かな手がかりを見つけられたのではないだろうか? もちろん、見つけられたはずだ。チズルハースト行きの列車が来るまで、このベンチに座ってくれ、ワトソン。君に証拠を提示させてほしい。そして、まず第一に、メイドや女主人が言ったことは何であれ、必ずしも真実であるという考えを、君の心から捨て去るよう懇願する。あの夫人の魅力的な人柄に、我々の判断を歪められてはならないのだ。」
「確かに、彼女の話には、もし我々が冷静に見れば、疑念を抱かせるような細部がある。あの強盗どもは二週間前にシドナムで相当な獲物を手に入れた。彼らに関するいくらかの記述と人相書きは新聞にも載っており、架空の強盗が役割を演じる物語をでっち上げたい者なら、当然思いつくことだろう。実際のところ、大きな仕事を成功させた強盗というのは、通例、新たな危険な企てに乗り出すことなく、その収益を平和に静かに楽しむことを何より喜ぶものだ。また、強盗がこれほど早い時間に活動するのは異例であり、強盗が女性の悲鳴を防ぐために殴りつけるのも異例だ。そんなことをすれば、かえって悲鳴を上げさせる確実な方法だと考えられるからだ。人数が一人を制圧するのに十分な場合に殺人を犯すのも異例であり、もっと多くのものが手の届くところにあるのに、限られた略奪品で満足するのも異例だ。そして最後に言わせてもらえば、そのような男たちが瓶を半分空けて残していくのは、非常に異例だと言えるだろう。これら数々の異例な点は、君にはどう映るかね、ワトソン?」
「それらが積み重なると、確かに相当なものになりますね。しかし、一つ一つはそれ自体、十分にあり得ることです。私にとって最も異例に思えるのは、夫人が椅子に縛りつけられていたことです。」
「うむ、その点については、私もそれほど明確ではない、ワトソン。というのも、彼らは彼女を殺すか、あるいは彼女がすぐに逃走を知らせることができないように確保するかしなければならなかったのは明らかだからだ。だが、いずれにせよ、私は示しただろう、夫人の話にはある種のあり得なさの要素があるということを。そして今、それに加えて、ワイングラスの件が浮かび上がってきた。」
「ワイングラスがどうしたのです?」
「心の目で見ることができるかね?」
「はっきりと見えます。」
「三人の男がそこから飲んだと我々は聞かされている。それはありそうなことだと思うかね?」
「なぜです? どのグラスにもワインが入っていました。」
「その通り。だが、澱があったのは一つのグラスだけだった。君もその事実に気づいたはずだ。それは君の心に何を暗示する?」
「最後に注がれたグラスに、最も澱が溜まりやすいでしょう。」
「全く違う。瓶は澱でいっぱいだった。最初の二つのグラスが澄んでいて、三つ目のグラスにだけ澱が大量に入っているなど、考えられない。考えられる説明は二つ、二つだけだ。一つは、二杯目のグラスが注がれた後、瓶が激しく揺さぶられ、その結果、三杯目のグラスに澱が入ったというもの。それはありそうにない。いや、いや、私は自分が正しいと確信している。」
「では、どうお考えなのです?」
「使われたのは二つのグラスだけで、両方の残りが三つ目のグラスに注がれたのだ。三人がここにいたという偽の印象を与えるためにね。そうすれば、すべての澱は最後のグラスに集まるだろう、そうではないかね? そうだ、私はこれが真実だと確信している。だが、もし私がこの一つの小さな現象の真の説明にたどり着いたとすれば、その瞬間、この事件は平凡なものから極めて注目すべきものへと昇華する。なぜなら、それはブラックンストール夫人と彼女のメイドが我々に意図的に嘘をついたこと、彼女たちの話は一言も信じられないこと、彼女たちには真犯人を庇う非常に強い理由があること、そして我々は彼女たちの助けを一切借りずに、我々自身で事件を構築しなければならないことを意味するからだ。それが今、我々の前に横たわる使命だ。そして、ほら、ワトソン、シドナム行きの列車が来た。」
我々が戻ると、アビイ屋敷の住人たちは大いに驚いたが、シャーロック・ホームズは、スタンリー・ホプキンスが本部に報告に出かけたことを知ると、食堂を占拠し、内側から扉に鍵をかけ、二時間にわたって、彼の見事な推理の殿堂が築き上げられる堅固な基礎をなす、あの緻密で骨の折れる調査の一つに没頭した。教授の実演を観察する熱心な学生のように隅に座り、私はその驚くべき探求の一挙手一投足を見守った。窓、カーテン、絨毯、椅子、ロープ――それぞれが順番に詳細に調べられ、しかるべく熟考された。不運な準男爵の遺体は運び出されていたが、それ以外はすべて、我々が朝に見たままであった。ついに、驚いたことに、ホームズは巨大なマントルピースの上に登った。彼の頭上はるか高くに、まだワイヤーに繋がったままの数インチの赤い紐がぶら下がっていた。長い間、彼はそれをじっと見上げていたが、やがてそれに近づこうとして、壁の木製の棚受けに膝を乗せた。これで彼のてはロープの切れた端から数インチのところまで届いたが、彼の注意を引いたのは、ロープそのものよりも、むしろ棚受け自体であるように思われた。ついに、彼は満足の声をあげて飛び降りた。
「すべてわかったぞ、ワトソン」と彼は言った。「事件は解決だ――我々のコレクションの中でも最も注目すべき事件の一つだ。しかし、やれやれ、私は何と頭の回転が鈍かったことか。そして、生涯の不覚を犯すところだったとは! 今、いくつか欠けている環はあるものの、私の鎖はほぼ完成したと思う。」
「犯人たちは捕らえたのですか?」
「犯人だ、ワトソン、犯人。一人だけだが、非常に手強い人物だ。ライオンのように強く――あの火かき棒を曲げた一撃を見ろ! 身長は六フィート三インチ、リスのように敏捷で、指先は器用、そして最後に、驚くほど頭が切れる。この巧妙な話はすべて彼の創作なのだからな。そうだ、ワトソン、我々は実に驚くべき個人の仕業に遭遇したのだ。それなのに、あのベルの紐に、彼は我々が疑う余地のない手がかりを残してくれていたのだ。」
「手がかりはどこに?」
「いいかね、もし君がベルの紐を引きちぎるとしたら、ワトソン、どこで切れると思う? 当然、ワイヤーに繋がっている箇所だろう。なぜ、この紐のように、上から三インチのところで切れるのだ?」
「そこが擦り切れていたからでは?」
「その通り。我々が調べられるこちらの端は、擦り切れている。彼は抜け目なく、ナイフでそうしたのだ。だが、もう一方の端は擦り切れていない。ここからでは見えないが、マントルピースの上にいれば、擦り切れた跡が全くなく、きれいに断ち切られているのがわかる。何が起こったか再現できる。男はロープが必要だった。ベルを鳴らして警報を鳴らす恐れがあるので、引きちぎることはしなかった。では、どうしたか? 彼はマントルピースに飛び乗り、完全には届かなかったので、棚受けに膝を置いた――埃の中にその跡が見えるだろう――そうしてナイフを紐に当てたのだ。私はその場所に少なくとも三インチは届かなかった。そこから推測するに、彼は私より少なくとも三インチは背が高い男だ。あの樫の椅子の座面にある染みを見ろ! あれは何だ?」
「血です。」
「間違いなく血だ。これだけで、夫人の話は成り立たなくなる。もし犯行時に彼女が椅子に座っていたのなら、どうしてその染みができる? いや、違う。彼女は夫が死んだ後に椅子に座らされたのだ。あの黒いドレスにも、これに対応する染みがあるに違いない。我々はまだワーテルローの敗北を喫したわけではない、ワトソン。だが、これは我々のマレンゴだ。敗北に始まり勝利に終わるからな。さて、乳母のテレサと少し話がしたい。我々が望む情報を得るためには、しばらく慎重に行動しなければならない。」
この厳格なオーストラリア人の乳母は、興味深い人物だった――無口で、疑り深く、無愛想で、ホームズの快活な態度と、彼女の言うことすべてを率直に受け入れる姿勢が、彼女を打ち解けさせ、相応の愛想の良さを引き出すまでには、しばらく時間がかかった。彼女は亡くなった雇い主への憎しみを隠そうともしなかった。
「はい、旦那様が私にデカンタを投げつけたのは本当です。旦那様が奥様を罵るのを聞いて、もし奥様のお兄様がここにいたら、そんな口はきけなかったでしょうに、と言ってやったんです。その時に、投げつけてきたんですよ。私の可愛い小鳥さんにさえ手を出さなければ、十個でも二十個でも投げつければよかったんです。旦那様はいつも奥様を虐げていましたが、奥様は気位が高くて不平一つおっしゃいませんでした。旦那様が奥様にしたことのすべてを、私にさえ話してはくださいません。今朝、あなた方がご覧になった腕のあの痣についても、決して話されませんでしたが、あれが帽子のピンで突かれたものだということは、私にはよくわかっています。あの狡猾な悪魔め――亡くなった方をこんな風に言うなんて、神様お許しください! でも、あの人は悪魔でした。もし地上を歩く悪魔がいるとしたら、まさにあの人です。最初にお会いしたときは、蜜のように甘い方でしたのに――たった十八ヶ月前ですが、二人ともまるで十八年も経ったように感じています。奥様はロンドンに着いたばかりでした。ええ、初めての船旅で、それまで家を離れたことはありませんでした。旦那様は、その爵位とお金と、偽りのロンドンのやり方で奥様を射止めたのです。もし奥様が過ちを犯したのだとしたら、その償いはなさいました。これほど償った女はいないでしょう。いつお会いしたかですか? 到着してすぐのことでしたよ。私たちが着いたのが六月で、お会いしたのは七月。結婚されたのは去年の正月です。ええ、奥様はまた朝の間にいらっしゃいます。きっとお会いになるでしょう。でも、あまり無理をおさせにならないでください。あの方は、生身の人間が耐えられる限りの苦しみを味わってこられたのですから。」
ブラックンストール夫人は同じ長椅子に横たわっていたが、以前よりは顔色が良かった。メイドも我々と一緒に入室し、再び女主人の額の痣を湿布し始めた。
「また私を尋問しにおいでになったのではないといいのですが」と夫人は言った。
「いいえ」ホームズは、この上なく優しい声で答えた。「不必要なご面倒はおかけしません、ブラックンストール夫人。私の望みはただ、あなたのお気持ちを楽にすることだけです。あなたが大変な苦労をなさった女性であると、私は確信しておりますから。もし私を友として扱い、信頼してくださるなら、私がその信頼に応える人間であることがおわかりになるでしょう。」
「私にどうしろとおっしゃるの?」
「真実をお話しください。」
「ホームズさん!」
「いえ、いえ、ブラックンストール夫人――無駄です。私が多少なりとも評判を得ていることは、お聞き及びかもしれません。そのすべてを賭けて断言しますが、あなたの話は完全な作り話です。」
女主人とメイドは二人とも、青ざめた顔と怯えた目でホームズを見つめていた。
「なんて無礼な方でしょう!」とテレサが叫んだ。「奥様が嘘をおつきになったとでも言うのですか?」
ホームズは椅子から立ち上がった。
「私に話すことは何もありませんか?」
「すべてお話ししました。」
「もう一度お考えください、ブラックンストール夫人。率直になる方が、よろしいのでは?」
一瞬、彼女の美しい顔にためらいの色が浮かんだ。だが、何か新たな強い考えが、その顔を仮面のように固くさせた。
「知っていることはすべてお話ししました。」
ホームズは帽子を取り、肩をすくめた。「残念です」と彼は言い、それ以上何も言わずに、我々は部屋と家を後にした。公園には池があり、友はそちらへ足を向けた。池は凍っていたが、一羽の孤独な白鳥のために、一つだけ穴が開けられていた。ホームズはそれをじっと見つめ、それからロッジの門へと通り過ぎた。そこで彼はスタンリー・ホプキンス宛の短いメモを走り書きし、門番に預けた。
「当たるも八卦、当たらぬも八卦だが、友人ホプキンスのために何かしてやらねばならん。この二度目の訪問を正当化するためにもね」と彼は言った。「まだ彼を完全に信用するわけにはいかない。我々の次の活動舞台は、アデレード=サウサンプトン汽船会社の海運事務所にすべきだと思う。私の記憶が正しければ、ポールモールの端にある。南オーストラリアとイングランドを結ぶ蒸気船の航路はもう一つあるが、まずは大物を狙ってみよう。」
ホームズが支配人に名刺を渡すと、即座の対応が保証され、彼は必要な情報をすべて手に入れるのに時間はかからなかった。九五年の六月に、彼らの航路で母港に到着したのは一隻のみ。それは彼らの最大かつ最高の船、ロック・オブ・ジブラルタル号だった。乗客名簿を調べると、アデレードのフレイザー嬢がメイドと共にその船で航海していたことがわかった。船は現在、オーストラリアへ向かう途中で、スエズ運河の南のどこかにいる。士官は一人の例外を除いて九五年と同じだった。一等航海士のジャック・クロッカー氏は船長に昇進し、二日後にサウサンプトンから出航する新造船バス・ロック号の指揮を執ることになっていた。彼はシドナムに住んでいるが、もし我々が待つつもりなら、その朝、指示を受けに事務所に来る可能性が高いとのことだった。
いや、ホームズ氏は彼に会う気はなく、彼の経歴と人物像についてもっと知りたいとのことだった。
彼の経歴は素晴らしかった。船団に彼に匹敵する士官はいなかった。人物像については、勤務中は信頼できるが、船の甲板を離れると、荒々しく向こう見ずな男――頭に血が上りやすく、興奮しやすいが、忠実で、正直で、心優しい。それがホームズがアデレード=サウサンプトン汽船会社の事務所を後にする際に得た情報の要点だった。そこから彼はスコットランド・ヤードへ馬車を走らせたが、中には入らず、眉をひそめて馬車の中に座り、深い思索に沈んでいた。ついに彼はチャリング・クロス電信局へ回り、電報を打ち、そしてようやく、我々は再びベーカー街へと向かった。
「いや、私にはできなかった、ワトソン」我々の部屋に戻りながら、彼は言った。「一度あの令状が発行されれば、地球上の何ものも彼を救うことはできない。私の経歴の中で一度や二度、私は犯人を発見することによって、その犯人が犯した罪よりも、はるかに現実的な害をもたらしたと感じることがある。私は今、慎重さを学んだ。私は英国の法律を欺くことはあっても、自分の良心を欺くことはしたくない。行動を起こす前にもう少し知っておこう。」
夕方になる前に、スタンリー・ホプキンス警部が訪ねてきた。彼のほうは、あまりうまくいっていないようだった。
「あなたは魔法使いだと思いますよ、ホームズさん。本当に時々、あなたには人間離れした力があるのではないかと思うことがあります。さて、一体どうやって、盗まれた銀食器があの池の底にあるとわかったのですか?」
「知らなかったさ。」
「しかし、私に調べるように言ったではありませんか。」
「では、見つかったのかね?」
「ええ、見つかりました。」
「お役に立てたのなら、非常に嬉しい。」
「しかし、助けにはなっていません。あなたは事件をはるかに難しくしてくれました。銀食器を盗んでおきながら、それを一番近くの池に投げ込むなんて、一体どんな強盗です?」
「確かに、やや風変わりな行動だったな。私はただ、もし銀食器がそれを欲しくない人物――いわば、偽装のためにそれを取った人物――によって持ち去られたのだとしたら、彼らは当然それを処分したがるだろう、という考えに基づいただけだ。」
「しかし、なぜそのような考えがあなたの頭をよぎったのですか?」
「まあ、可能性はあると思ったのだ。フランス窓から外へ出たとき、氷に一つ、誘うような小さな穴の開いた池が、ちょうど彼らの鼻先にあった。これ以上の隠し場所があるかね?」
「ああ、隠し場所――その方がいいですね!」とスタンリー・ホプキンスは叫んだ。「ええ、ええ、すべてわかりました! 時間は早く、道には人がいた。銀食器を持っているところを見られるのを恐れた彼らは、それを池に沈め、人通りがなくなったら取りに戻るつもりだった。素晴らしい、ホームズさん――あなたの偽装という考えより、その方がずっといい。」
「その通り、君は見事な説を立てた。私自身の考えはまったくの突飛なものだったに違いないが、それが銀食器の発見に繋がったことは認めざるを得ないだろう。」
「ええ、そうです、そうです。すべてあなたのお手柄です。しかし、私はひどい痛手を負いました。」
「痛手?」
「ええ、ホームズさん。ランダル一味は、今朝、ニューヨークで逮捕されました。」
「やれやれ、ホプキンス君! それは確かに、彼らが昨夜ケントで殺人を犯したという君の説とは、かなり食い違うな。」
「致命的です、ホームズさん――まったくもって致命的です。しかし、ランダル一家以外にも三人組のギャングはいますし、あるいは警察がこれまで聞いたことのない新しいギャングかもしれません。」
「その通り、十分にあり得ることだ。何、もう行くのかね?」
「ええ、ホームズさん、この事件の真相を突き止めるまで、私に休みはありません。何かヒントをいただけませんか?」
「一つ与えたはずだが。」
「どちらのです?」
「まあ、偽装を提案した。」
「しかし、なぜです、ホームズさん、なぜ?」
「ああ、それが問題なのだ、もちろん。だが、その考えを君の心に留めておくことを勧める。もしかしたら、何か意味があるかもしれないと気づくかもしれない。夕食はとらないのかね? では、さようなら。どうなったか知らせてくれたまえ。」
夕食が終わり、テーブルが片付けられてから、ホームズは再びその件に言及した。彼はパイプに火をつけ、スリッパを履いた足を陽気な暖炉の炎にかざしていた。突然、彼は時計を見た。
「事態が進展しそうだ、ワトソン。」
「いつです?」
「今――数分以内に。先ほど、私がスタンリー・ホプキンスにかなりひどい態度をとったと君は思っただろう?」
「あなたの判断を信頼しています。」
「非常に分別のある返事だ、ワトソン。こう考えなければならない。私が知っていることは非公式なものであり、彼が知っていることは公式なものだ。私には私的な判断を下す権利があるが、彼にはない。彼はすべてを公にしなければならず、さもなければ職務への裏切り者となる。疑わしい事件で、彼をそのような辛い立場に置きたくはない。だから、私自身の心がこの件について明確になるまで、私の情報は保留にするのだ。」
「しかし、それはいつになるのですか?」
「時は来た。君は今、注目すべき小劇の最終場面に立ち会うことになる。」
階段に物音がし、我々の部屋のドアが開けられ、これ以上ないほど見事な男ぶりの男が入ってきた。彼は非常に背の高い若者で、金色の口髭を生やし、青い瞳を持ち、その肌は熱帯の太陽に焼かれ、弾むような足取りは、その巨大な体躯が頑健であると同時に敏捷であることを示していた。彼は背後でドアを閉め、それから拳を握りしめ、胸を波打たせ、こみ上げる感情を必死に抑えながら立っていた。
「お掛けなさい、クロッカー船長。私の電報は受け取られましたかな?」
我々の訪問者は肘掛け椅子に沈み込み、我々二人を交互に、探るような目で見た。
「あなたの電報は受け取りました。そして、あなたが指定した時間に来ました。あなたが事務所までおいでになったと聞きました。あなたからは逃げられない。最悪の事態を聞かせてください。私をどうするつもりですか? 逮捕するのですか? はっきり言ってください! 猫が鼠をいたぶるように、そこに座って私をもてあそぶのはやめていただきたい。」
「彼に葉巻を」とホームズは言った。「それを噛んでください、クロッカー船長。そして、神経を昂らせないように。もし私があなたをありふれた犯罪者だと思っていたら、こうして一緒に煙草を吸ってなどいませんよ。それは確かです。私に率直に話してくだされば、何か良い方向に進むかもしれません。私と駆け引きをするつもりなら、あなたを叩き潰します。」
「私にどうしろとおっしゃるのですか?」
「昨夜、アビイ屋敷で起こったことのすべてを、ありのままに話していただきたい――ありのままの話を、ですよ。何も付け加えず、何も省かずに。私はすでに多くのことを知っています。もしあなたが少しでも筋を外れたことを言えば、私はこの窓から警察の笛を吹き、この事件は永遠に私の手から離れます。」
船乗りは少し考えた。それから、日に焼けた大きな手で自分の脚を叩いた。
「賭けてみよう」と彼は叫んだ。「あなたは約束を守る、信頼できるお方だと信じます。そして、すべてをお話しします。しかし、一つだけ最初に言わせていただきたい。私に関する限り、私は何も後悔していませんし、何も恐れていません。そして、もう一度同じことをするでしょうし、その仕事を誇りに思うでしょう。あの人でなしめ、猫のように九つの命があったとしても、そのすべてを俺が奪ってやっただろうさ! しかし、問題はあのレディ、メアリー――メアリー・フレイザーです。あの呪われた名前で彼女を呼ぶことなど、決してありません。彼女を厄介事に巻き込むことを考えると、彼女の愛しい顔にほんの一つの微笑みをもたらすためなら、この命さえ投げ出すというのに、そう思うと、心が張り裂けそうです。それでも――それでも――私にこれ以上の何ができたでしょうか? 私の話をします、紳士方。そして、男として、私にこれ以上の何ができたか、お尋ねしたい。」
「少し遡らなければなりません。あなた方はすべてをご存じのようですから、私が彼女に会ったのが、彼女が乗客で、私がロック・オブ・ジブラルタル号の一等航海士だったときだということもご存じでしょう。彼女に会った最初の日から、彼女は私にとって唯一の女性でした。その航海の毎日、私は彼女をより深く愛し、それ以来、幾度となく、夜警の闇の中でひざまずき、彼女の愛しい足が踏んだと知っていたあの船の甲板にキスをしました。彼女は私と婚約したことはありません。彼女は、女性が男性に接する限り、この上なく公平に私に接してくれました。不満を言うつもりはありません。すべては私の一方的な愛であり、彼女の側はすべて、良き仲間意識と友情でした。我々が別れたとき、彼女は自由な女性でしたが、私は二度と自由な男にはなれませんでした。」
「次に海から戻ったとき、彼女の結婚を知りました。まあ、彼女が好きな人と結婚して、何が悪いでしょう? 爵位と金――彼女以上にそれをうまく身につけられる人がいるでしょうか? 彼女は、美しく、優雅なすべてのもののために生まれてきたのです。私は彼女の結婚を悲しみませんでした。そんな自己中心的な人間ではありません。ただ、幸運が彼女の元に訪れたこと、そして彼女が無一文の船乗りのために身を投げ出さなかったことを喜んだだけです。それが、私がメアリー・フレイザーを愛したやり方です。」
「さて、二度と彼女に会うことはないと思っていましたが、前回の航海で私は昇進し、新しい船はまだ進水していなかったので、シドナムの実家で数ヶ月待たなければなりませんでした。ある日、田舎道で、彼女の昔からのメイド、テレサ・ライトに会いました。彼女は、彼女のこと、彼のこと、すべてのことを私に話してくれました。紳士方、私はほとんど気が狂いそうになりました。この酔いどれのろくでなしが、彼女の靴を舐める資格もないくせに、彼女に手を上げようなどとは! 私は再びテレサに会いました。そして、メアリー自身に会いました――そして、また会いました。すると、彼女はもう私に会ってくれなくなりました。しかし、先日、一週間以内に航海に出発するようにとの通知を受け、私は出発する前に一度彼女に会おうと決心しました。テレサはいつも私の味方でした。彼女はメアリーを愛し、この悪党を私と同じくらい憎んでいたからです。彼女から、家の様子を教わりました。メアリーは階下の自分の小さな部屋で、夜遅くまで読書をする習慣がありました。昨夜、私はそこへ忍び寄り、窓を引っ掻きました。最初は、彼女は私に窓を開けてくれませんでしたが、心の中では、今では彼女も私を愛していることを私は知っています。そして、彼女は凍える夜の中に私を放っておくことはできませんでした。彼女は私に、大きな正面の窓に回るようにと囁きました。行ってみると、窓は私のために開けられており、食堂に入ることができました。再び彼女自身の口から、私の血を沸騰させるようなことを聞き、そして再び、私が愛する女性を虐待するこの獣を呪いました。さて、紳士方、私は彼女と一緒に窓の内側に立っていました。全くの無実で、神に誓って、その時、彼が狂人のように部屋に駆け込んできて、男が女に使える最も下劣な名前で彼女を呼び、手に持っていた杖で彼女の顔を殴りつけました。私は火かき棒に飛びつき、我々の間では正々堂々の戦いでした。ここを見てください、私の腕に、彼の最初の一撃が落ちたところです。それから私の番になり、私は彼を腐ったカボチャのように突き通しました。私が後悔したと思いますか? まさか! 彼の命か私の命かでしたが、それ以上に、彼の命か彼女の命かでした。どうして彼女をこの狂人の力の中に残しておくことができたでしょうか? そうやって私は彼を殺したのです。私は間違っていましたか? では、もしあなた方が私の立場だったら、どちらの紳士もどうしたでしょう?」
「彼が彼女を殴ったとき、彼女は悲鳴をあげ、それで上の部屋から年老いたテレサが下りてきました。サイドボードにワインの瓶があり、私はそれを開けて、ショックで半死半生だったメアリーの唇の間に少し注ぎました。それから私自身も一口飲みました。テレサは氷のように冷静で、あれは私の計画であると同時に、彼女の計画でもありました。強盗がやったように見せかけなければなりませんでした。私がよじ登ってベルの紐を切っている間、テレサは女主人に我々の話を繰り返し言い聞かせていました。それから私は彼女を椅子に縛りつけ、紐の端をほつれさせて自然に見せかけました。さもなければ、一体どうやって強盗がそこまで登って切ったのか、彼らは不思議に思うでしょうから。それから、強盗の考えを徹底させるために、銀の皿や壺をいくつか集め、私が十五分の猶予を得たところで警報を鳴らすようにと命令して、そこを離れました。銀食器は池に投げ込み、シドナムへ向かいました。人生で一度、本当に良い夜の仕事をしたという気分でした。そして、それが真実であり、すべてです、ホームズさん。この首が飛ぶことになっても。」
ホームズはしばらく黙って煙草を吸っていた。それから部屋を横切り、我々の訪問者の手を握った。
「私もそう思う」と彼は言った。「一言一句すべて真実だとわかっている。君が話したことで、私が知らなかったことはほとんどないからな。軽業師か船乗りでなければ、あの棚受けからベルの紐には届かないし、船乗りでなければ、紐を椅子に結びつけたあの結び方はできない。このご婦人が船乗りと接触したのは一度きり、それは彼女の航海の時だ。そして、それは彼女自身の階級の誰かだ。なぜなら、彼女は彼を必死に庇おうとしており、それによって彼女が彼を愛していることを示しているからだ。一度正しい道を歩み始めれば、君にたどり着くのがいかに容易だったか、わかるだろう。」
「警察が我々の小細工を見破れるはずがないと思っていました。」
「警察は気づいていない。そして、私の信じる限り、これからも気づくことはないだろう。さて、クロッカー船長、よく聞きたまえ。これは極めて深刻な問題だ。無論、あなたが耐え難いほどの挑発を受けた末の行動であったことは認めるつもりだ。自己防衛のためであったとすれば、あなたの行動は正当と認められる可能性も十分にある。だが、それを決めるのは英国の陪審員だ。それまでの間、私はあなたに深く同情している。もしあなたが二十四時間以内に姿を消すというのなら、誰も邪魔はしないと約束しよう。」
「そうなれば、すべてが明るみに出るのでは?」
「無論、明るみに出る。」
船乗りは怒りで顔を紅潮させた。
「男に対して、それがどういう提案だ? 法律の心得なら、私にも多少はある。メアリーが共犯者として扱われることくらいわかる。私がこそこそと逃げ出し、彼女一人に罪を償わせるとでもお思いか? とんでもない。奴らの好きにさせるがいい。だが、お願いだ、ホームズさん。どうか、哀れなメアリーを法廷に立たせずに済む方法を見つけてくれ。」
ホームズは再び、船乗りに手を差し出した。
「君を試しただけだ。君はいつ試しても本物だな。よろしい、私が引き受ける責任は重大だが、ホプキンスには見事なヒントを与えておいた。彼がそれを活かせなければ、私にできることはもうない。いいかね、クロッカー船長。これは正式な法に則ってやろう。君は被告人だ。ワトソン、君は英国の陪審員だ。君ほどその役柄にふさわしい男には会ったことがない。そして私が、裁判官だ。さて、陪審員の諸君、証言は聞いたな。被告人は有罪かね、無罪かね?」
「無罪です、裁判長殿」と私は答えた。
「『民の声は神の声』だ。クロッカー船長、君は無罪放免とする。法が他の誰かを犠牲者として見つけ出さない限り、君は私から追及されることはない。一年後にこのご婦人のもとへ戻りたまえ。そして、二人の未来が、我々が今宵下したこの裁きを正当化してくれることを願っている!」
第二の染み
私は、「アベイ農園」の事件を最後に、我が友シャーロック・ホームズ氏の功績を世に発表するのは打ち止めにするつもりでいた。この決意は、題材に事欠いたからではない。未だかつて一度も言及したことのない事件の記録が、何百と手元にあるのだから。また、この非凡な人物の特異な個性と類まれな手法に対する読者の興味が薄れたわけでもない。真の理由は、ホームズ氏自身が、自らの経験談をこれ以上公表することに難色を示したことにある。彼が現役で探偵業を営んでいた頃は、その成功の記録は彼にとって実用的な価値があった。しかし、ロンドンから完全に引退し、サセックス丘陵で研究と養蜂に身を投じて以来、名声がかえって彼を苛むようになり、この件に関する彼の願いは厳格に守られるべきだと、断固として要求してきたのだ。私がついに彼の承諾を得るに至ったのは、ひとえに、「第二の染み」の事件はいずれ機が熟したときに発表すると約束してしまったと彼に訴え、また、この長きにわたる一連の物語の締めくくりとして、彼がかつて手掛けた中で最も重要な国際的事件こそがふさわしいと指摘したからに他ならない。かくして、細心の注意を払って記述した事件の記録が、ようやく世に出されることになったのである。もしこの物語を語るにあたり、私がいくつかの細部を曖昧にしているように見えたとしても、読者の皆様には、私が口を閉ざすのには十分な理由があることを、容易にご理解いただけることだろう。
それは、年も、いや年代すらも伏せておくべき、ある秋の火曜日の朝のことだった。我々は、ベーカー街の質素な部屋の壁の内側に、ヨーロッパにその名を轟かす二人の訪問者を迎えていた。一人は、厳格で、鼻が高く、鷲のような鋭い目を持ち、人を圧する風格を備えた人物――二度にわたり英国首相を務めた、かの高名なベリンジャー卿その人であった。もう一人は、浅黒く、彫りの深い顔立ちで、優雅な物腰の、まだ壮年には至らぬ男。心身ともにあらゆる美質に恵まれたこの人物は、欧州担当大臣にして、この国で最も将来を嘱望される政治家、トレローニー・ホープ閣下であった。二人は、我々の書類が散らかった長椅子に並んで腰掛けていたが、そのやつれ、思い詰めた表情から、彼らをここまで運んできたのが、この上なく緊急を要する案件であることは一目瞭然だった。首相の、青い血管が浮き出た細い両手は、象牙の柄の傘の頭を固く握りしめ、その痩せこけた禁欲的な顔は、陰鬱な面持ちでホームズと私を交互に見ていた。欧州担当大臣は、神経質に口髭をいじり、時計の鎖の飾りを落ち着きなくもてあそんでいた。
「私が紛失に気づきましたのは、ホームズさん、今朝の八時でして、ただちに総理大臣にご報告いたしました。お二人で伺ってはどうかと提案されたのは、総理です。」
「警察には知らせましたか?」
「いいや」と、首相がその有名な素早くきっぱりとした口調で言った。「知らせてはいないし、知らせることも不可能だ。警察に知らせるということは、結局のところ、大衆に知らせるのと同じことになる。それこそ、我々が何としても避けたい事態なのだ。」
「それはなぜですかな、閣下?」
「問題の文書が、あまりにも重大な重要性を持つからだ。それが公になれば、極めて容易に――いや、ほぼ間違いなくと言ってもいい――ヨーロッパ全土を巻き込む、この上なく深刻な紛糾を招くことになるだろう。この一件が平和をもたらすか戦争を招くか、その分水嶺にあると言っても過言ではない。最大限の秘密保持のもとに回収できないのであれば、いっそ回収できない方がましですらある。なぜなら、それを手に入れた者たちが狙っているのは、その内容が世間に知れ渡ること、ただそれだけなのだから。」
「なるほど。さて、トレローニー・ホープさん、その文書がどのような状況で消えたのか、正確にお話し願えませんか。」
「それは、ごく簡単にご説明できます、ホームズさん。その書簡は――ある外国の君主からのものでした――六日前に受け取りました。あまりに重要なので、金庫にしまいっぱなしにはせず、毎晩ホワイトホール・テラスの自邸に持ち帰り、寝室の鍵付きの書類箱に保管しておりました。昨夜もそこにありました。それは確かです。夕食のために着替えている最中、実際に箱を開けて、中に文書があるのを確認しましたから。それが、今朝にはなくなっていたのです。書類箱は一晩中、化粧台の鏡の横にありました。私は眠りが浅い方ですし、妻も同様です。我々は二人とも、夜中に誰も部屋に入ってこなかったと誓って言えます。それなのに、繰り返しますが、書類は消えてしまったのです。」
「夕食は何時でしたか?」
「七時半です。」
「就寝されるまで、どのくらいの時間がありましたか?」
「妻は観劇に出かけておりました。私は彼女の帰りを待っていました。我々が部屋に戻ったのは十一時半でした。」
「では、四時間もの間、書類箱は無防備なままだったと?」
「あの部屋への立ち入りは、朝のメイドと、日中の私の従者か妻の侍女以外には、一切許されておりません。二人とも、我々に長く仕えている信頼できる使用人です。それに、どちらも、私の書類箱に通常の省庁の書類以上の価値あるものが入っているなど、知る由もありません。」
「その書簡の存在を知っていたのは誰です?」
「家の中には誰もいません。」
「奥様はご存じだったのでは?」
「いえ。今朝、書類がないことに気づくまで、妻には何も話しておりませんでした。」
首相は賛同するように頷いた。
「あなたの公務に対する意識の高さは、かねてより存じておりました」と彼は言った。「これほど重要な機密となれば、いかなる親密な家庭の絆よりも優先されるものと確信しておりました。」
欧州担当大臣は一礼した。
「お褒めに預かり光栄です、閣下。今朝まで、この件については妻に一言も漏らしておりません。」
「奥様が察することは?」
「いえ、ホームズさん、妻には察しようがありません――誰にも、察することなどできなかったはずです。」
「これまでに、何か書類をなくされたことは?」
「ありません。」
「英国で、この書簡の存在を知っていたのは誰です?」
「昨日、閣僚全員に知らされましたが、いかなる閣議にも伴う守秘義務の誓いは、総理大臣による厳粛な警告によって、さらに重いものとなっておりました。なんということだ、ほんの数時間のうちに、この私がそれを失ってしまうとは!」
彼の端正な顔は絶望の発作に歪み、両手で髪をかきむしった。その一瞬、我々は衝動的で、情熱的で、極めて鋭敏な、素のままの男の姿を垣間見た。次の瞬間には、貴族的な仮面が再びその顔を覆い、穏やかな声が戻っていた。「閣僚の他には、二、三人、省庁の役人が書簡の存在を知っています。英国では、それ以外には誰もおりません、ホームズさん、断言します。」
「しかし、国外では?」
「国外では、それを書いた当人以外、誰も見ていないと信じています。彼の閣僚たち――通常の公式ルートは使われていないと確信しております。」
ホームズはしばし考え込んでいた。
「さて、閣下、もう少し詳しくお尋ねしなければなりません。その文書とは一体何なのか、そしてなぜその消失がそれほど重大な結果を招くのか?」
二人の政治家は素早く視線を交わし、首相の毛深い眉が顰められた。
「ホームズさん、封筒は薄青色の細長いものです。赤い封蝋には、しゃがむ獅子の紋章が押されている。宛名は、大きく、力強い筆跡で――」
「恐れ入りますが、閣下」とホームズは言った。「それらの詳細は興味深く、実に不可欠なものではありますが、私の調査はもっと物事の根幹に迫らねばなりません。その書簡の内容は何だったのですか?」
「それは国家の最重要機密であり、恐縮ながら、お話しすることはできませんし、その必要性も認められません。もし、あなたが持つと言われる力をもって、私が述べたような封筒を中身ごと見つけ出すことができれば、あなたは国に大いに貢献したことになり、我々の力の及ぶ限りのいかなる報酬も得ることになるでしょう。」
シャーロック・ホームズは微笑みながら立ち上がった。
「お二方はこの国で最も多忙な方々だ」と彼は言った。「そして私自身も、ささやかながら、多くの依頼を抱えている。誠に残念ながら、この件ではお力になれそうにない。これ以上面会を続けても、時間の無駄というものでしょう。」
首相は、閣議すら震え上がらせたという、その奥深い目の鋭く獰猛な輝きとともに、勢いよく立ち上がった。「私は慣れていないのだ、君」と彼は口火を切ったが、怒りを抑えて再び腰を下ろした。一分かそれ以上、我々は皆、沈黙の中に座っていた。やがて、老政治家は肩をすくめた。
「あなたの条件を受け入れましょう、ホームズさん。間違いなく、あなたが正しい。我々が全幅の信頼を置かずに、あなたに行動を期待するのは理不尽というものだ。」
「私も同感です」と若い方の政治家が言った。
「では、お話ししましょう。あなたと、あなたの同僚であるワトソン博士の名誉に、全面的に信頼を寄せて。あなたの愛国心にも訴えかけたい。この国にとって、この一件が公になること以上の不幸は想像もできないからです。」
「我々を信頼していただいて結構です。」
「その書簡は、この国の最近の植民地政策の進展に腹を立てた、ある外国の君主からのものだ。急いで書かれたものであり、完全に彼個人の責任においてのものである。調査によれば、彼の閣僚たちはこの件について何も知らない。同時に、それは極めて不適切な表現で書かれており、中のいくつかの文言はあまりに挑発的な性質を持つため、公表されれば、間違いなくこの国に極めて危険な感情を引き起こすことになるだろう。それほどの騒動になるでしょう、閣下。その書簡が公表されてから一週間以内に、この国は大きな戦争に巻き込まれることになると断言しても憚らない。」
ホームズは紙片に名前を書き、首相に手渡した。
「その通り。彼だ。そして、この書簡――一千ミリオンの支出と十万人の命を意味しかねないこの書簡が――このような不可解な形で失われてしまったのだ。」
「送り主には知らせましたか?」
「はい、暗号電報を送りました。」
「あるいは、彼が書簡の公表を望んでいるのでは?」
「いいえ。我々には、彼がすでに、自分が無分別で短気な行動をとったと理解していると信じるに足る、強い理由があります。もしこの書簡が公になれば、我々にとってよりも、彼と彼の国にとって、より大きな打撃となるでしょう。」
「もしそうなら、書簡が公になることで誰が得をするのですか? なぜ誰かがそれを盗み、公表しようと望むのでしょうか?」
「そこから先は、ホームズさん、高度な国際政治の領域に入ります。しかし、ヨーロッパの情勢を考えれば、その動機を理解するのは難しくないでしょう。ヨーロッパ全土が、いわば武装した野営地なのだ。二つの同盟があり、軍事力の均衡を保っている。その天秤を握っているのが大英帝国だ。もし英国が一方の同盟と戦争に引きずり込まれれば、もう一方の同盟は、戦争に参加するしないにかかわらず、覇権を確立することになる。お分かりかな?」
「非常によくわかります。とすると、この君主の敵が、この書簡を確保し公表することで、彼の国と我々の国との間に亀裂を生じさせることが利益になる、というわけですな?」
「その通りです。」
「そして、この文書が敵の手に渡った場合、誰に送られることになるでしょうか?」
「ヨーロッパの主要な外務省のいずれかでしょう。おそらく今この瞬間も、蒸気の力が及ぶ限りの速さで、そこへ向かっている最中です。」
トレローニー・ホープ氏は胸に頭をうなだれ、呻き声を上げた。首相は彼の肩に優しく手を置いた。
「君の不運だ、友よ。誰も君を責めることはできない。君が怠った予防策など何一つない。さて、ホームズさん、これで事実関係はすべてお分かりいただけたはずだ。どのような方策をお勧めになりますか?」
ホームズは悲しげに首を振った。
「閣下は、この文書が回収されなければ戦争になるとお考えですか?」
「その可能性は非常に高いと思う。」
「では、閣下、戦争の準備をなさいますよう。」
「それは厳しいお言葉ですな、ホームズさん。」
「事実を考えてみてください。夜の十一時半以降に盗まれたとは考えられません。その時間から紛失が発覚するまで、ホープ氏と奥様は二人とも部屋におられたと聞いておりますから。とすれば、盗まれたのは昨夜の七時半から十一時半の間、おそらくは早い時間帯でしょう。犯人はそれがそこにあることを明らかに知っていたのですから、当然できるだけ早く手に入れようとするはずです。さて、閣下、これほど重要な文書がその時間に盗まれたとして、今頃どこにあるでしょう? 誰もそれを手元に置いておく理由はありません。必要とする者たちの手に、素早く渡されているはずです。今からそれを追い越したり、追跡したりする機会が我々にあるでしょうか? もはや我々の手の届かぬところにあります。」
首相は長椅子から立ち上がった。
「あなたの言うことは全く論理的だ、ホームズさん。この件は、もはや我々の手には負えないと感じる。」
「議論のために、仮に文書がメイドか従者によって盗まれたと仮定しましょう――」
「二人とも古くからの、信頼のおける使用人です。」
「お話によれば、お部屋は二階にあり、外部からの侵入口はなく、内部からも誰にも気づかれずに上階へ行くことはできないとのこと。とすれば、それを盗んだのは家の中の誰かに違いありません。泥棒はそれを誰に渡すでしょうか? 何人かいる国際的なスパイや秘密諜報員の誰かでしょう。その名前は私にはそこそこ馴染みがあります。その道の第一人者と言える者が三名いる。私はまず、彼ら一人一人が持ち場にいるかどうかを確かめることから調査を始めましょう。もし一人でも姿を消していれば――特に昨夜から行方が分からなくなっていれば――文書がどこへ行ったかについて、何らかの手がかりが得られるでしょう。」
「なぜ姿を消す必要があるのですか?」と欧州担当大臣が尋ねた。「彼は書簡をロンドンの大使館に持ち込む可能性も十分にあるでしょう。」
「そうは思いませんね。これらの諜報員は独立して活動しており、大使館との関係はしばしば緊張しています。」
首相は同意して頷いた。
「あなたの言う通りだろう、ホームズさん。彼はそれほど価値のある獲物を、自らの手で本部に届けるだろう。あなたの行動方針は素晴らしいと思う。一方、ホープ、我々はこの一つの不運のために、他のすべての職務を疎かにするわけにはいかない。日中に何か新しい進展があれば、あなたにご連絡する。そして、あなたの方でも、調査の結果を我々に知らせてくれるに違いない。」
二人の政治家は一礼し、厳粛な面持ちで部屋を後にした。
高名な訪問者たちが去った後、ホームズは黙ってパイプに火をつけ、しばらくの間、深い思索に沈んでいた。私は朝刊を開き、昨夜ロンドンで起きた sensational な犯罪記事に没頭していた。その時、友人が叫び声を上げ、すっくと立ち上がると、パイプを暖炉のマントルピースの上に置いた。
「そうだ」と彼は言った。「これ以上のやり方はない。状況は絶望的だが、望みがないわけではない。今からでも、誰がそれを盗ったか確信できれば、まだ犯人の手から離れていない可能性は十分にある。結局のところ、こいつらにとっては金の問題だ。そして私の背後には大英帝国の国庫がある。市場に出ているなら私が買う――たとえ所得税がもう一ペニー上がることになってもだ。奴が、向こう側で運試しをする前に、こちら側からどんな値が付くか様子を見るために、それを手元に留めておくことも考えられる。これほど大胆な勝負ができるのは、あの三人しかいない――オーベルシュタイン、ラ・ロティエール、そしてエドゥアルド・ルーカスだ。一人一人に会ってみよう。」
私は朝刊に目をやった。
「ゴドルフィン街のエドゥアルド・ルーカスですか?」
「そうだ。」
「彼には会えませんよ。」
「なぜだ?」
「昨夜、自宅で殺害されました。」
友人は、我々の冒険の中で実に頻繁に私を驚かせてきたが、今度は自分が彼を完全に驚かせることができたのだと気づいたとき、私は高揚感を覚えた。彼は驚愕して私を見つめ、それから私の手から新聞をひったくった。彼が椅子から立ち上がった時に私が読んでいたのは、この一節だった。
ウェストミンスターで殺人事件
昨夜、ゴドルフィン街十六番地で、謎めいた性格の犯罪が発生した。現場は、
テムズ川とウェストミンスター寺院に挟まれ、国会議事堂の巨大な塔の影と
も言える場所にある、十八世紀に建てられた古風で閑静な家々が並ぶ一角で
ある。この小ぢんまりとしながらも高級な邸宅には、数年前からエドゥアル
ド・ルーカス氏が住んでいた。氏はその魅力的な人柄と、国内屈指のアマ
チュア・テノール歌手であるという当然の評価によって、社交界で広く知ら
れていた。ルーカス氏は三十四歳の未婚で、その邸宅には年配の家政婦プリ
ングル夫人と、従者のミットンがいた。家政婦は早くに就寝し、家の最上階
で眠っていた。従者はその夜、ハマースミスの友人を訪ねて外出中であった。
十時以降、ルーカス氏は一人で家にいた。その間に何が起こったかはまだ明
らかになっていないが、十二時十五分前、ゴドルフィン街を巡回中のバレッ
ト巡査が、十六番地のドアが半開きになっていることに気づいた。ノックし
たが返事はなかった。表の部屋に明かりが見えたため、彼は通路に進み、再
びノックしたが、やはり応答はなかった。そこで彼はドアを押し開けて中に
入った。部屋はひどい混乱状態で、家具はすべて一方に押しやられ、椅子が
一脚、中央にひっくり返っていた。その椅子のそばに、片方の脚をまだ掴ん
だまま、この家の不幸な住人が倒れていた。彼は心臓を刺されており、即死
だったに違いない。犯行に使われたナイフは、壁の一つを飾っていた東洋の
武器の飾り額から引き抜かれた、湾曲したインドの短剣であった。部屋の貴
重品を運び出そうとした形跡がないことから、強盗が犯行の動機とは思われ
ない。エドゥアルド・ルーカス氏は非常に有名で人気があったため、その暴
力的で謎に満ちた死は、広範な友人たちの間で痛ましい関心と深い同情を呼
び起こすであろう。
「さて、ワトソン、これをどう思うかね?」と、長い沈黙の後、ホームズが尋ねた。
「驚くべき偶然の一致ですね。」
「偶然の一致だと! 我々がこの劇の演者として名前を挙げた三人のうちの一人が、まさにその劇が演じられていたと我々が知っている、まさにその時間帯に、非業の死を遂げているのだ。それが偶然である確率は、天文学的に低い。どんな数字を使っても表現できまい。いや、ワトソン君、二つの出来事は繋がっている――繋がっていなければならない。我々の仕事は、その繋がりを見つけ出すことだ。」
「しかし、そうなると、もう公式の警察がすべてを知っているはずでは。」
「とんでもない。彼らが知っているのは、ゴドルフィン街で見たことすべてだ。彼らはホワイトホール・テラスのことは何も知らない――そしてこれからも知ることはない。両方の出来事を知り、その関係を追跡できるのは、我々だけなのだ。いずれにせよ、私の疑いをルーカスに向けさせたであろう、明白な点が一つある。ウェストミンスターのゴドルフィン街は、ホワイトホール・テラスから歩いてほんの数分の距離だ。私が名前を挙げた他の秘密諜報員たちは、ウェストエンドの最も外れに住んでいる。したがって、ルーカスの方が他の者たちよりも、欧州担当大臣の家と接触したり、連絡を受け取ったりするのが容易だった――些細なことだが、出来事が数時間に圧縮されている場合、これが決定的に重要になるやもしれない。おや! これは一体何だ?」
ハドソン夫人が、婦人の名刺を盆に載せて現れた。ホームズはそれに目をやり、眉を上げると、私に手渡した。
「レディ・ヒルダ・トレローニー・ホープに、どうぞお上がりいただくようお伝えしてくれ」と彼は言った。
その一瞬後、その朝すでに高名な人々で彩られた我々の質素な部屋は、ロンドンで最も美しい女性の入場によって、さらなる栄誉に浴することになった。ベルミンスター公爵の末娘の美しさについてはしばしば耳にしていたが、いかなる描写も、いかなる色褪せた写真の熟視も、その絶妙な顔立ちが持つ、繊細で奥ゆかしい魅力と美しい色彩に対する心の準備をさせてはくれなかった。しかし、その秋の朝に我々が目にした彼女の姿は、その美しさが観察者に最初に印象づけるものではなかっただろう。頬は愛らしいが、感情の昂ぶりで青ざめ、目は輝いているが、それは熱に浮かされた輝きであり、感じやすい口元は、自制しようと固く引き結ばれていた。我々の美しい訪問者が、開いたドアの枠の中に一瞬たたずんだとき、目に飛び込んできたのは美しさではなく――恐怖であった。
「夫は、こちらに参りましたでしょうか、ホームズさん?」
「はい、奥様、いらっしゃいました。」
「ホームズさん、お願いです。私がここに来たことは、夫に言わないでください。」
ホームズは冷ややかに一礼し、婦人に椅子を勧めた。
「奥様は私を非常に微妙な立場にお置きになります。どうぞお掛けになって、ご用件をお話しください。しかし、無条件の約束はできかねます。」
彼女は部屋を横切り、窓に背を向けて腰を下ろした。それは女王のような存在感だった――背が高く、優雅で、そして強烈に女性的であった。「ホームズさん」と彼女は言った――そして、その白い手袋をはめた両手は、話しながら握り締められたり、開かれたりした――「率直にお話しします。そうすれば、あなたからも率直なお返事がいただけるかと期待して。夫と私の間には、一つのことを除いて、すべての事柄において完全な信頼関係があります。その一つとは、政治です。これに関しては、彼の唇は固く閉ざされています。何も話してはくれません。さて、昨夜、我が家で実に嘆かわしい出来事があったことは存じております。書類が一つなくなったことも。しかし、事が政治に関わるため、夫は私にすべてを打ち明けてはくれないのです。ですが、私にとって、この事態を完全に理解することは、不可欠――絶対に不可欠なのです。あなただけが、あの政治家たちを除けば、真実を知る唯一の人物です。ですから、ホームズさん、どうかお願いです。何が起こったのか、そしてそれがどういう結果を招くのか、正確に教えてください。すべてを、ホームズさん。依頼人の利益を思うあまり、口を閉ざすなどということはなさらないでください。保証いたしますが、彼の利益は、もし彼がそれに気づいてさえくれれば、私にすべてを打ち明けることによってこそ、最もよく守られるのですから。盗まれたのは、何という書類だったのですか?」
「奥様、あなたがお尋ねのことは、実に不可能なことです。」
彼女は呻き、両手で顔を覆った。
「お分かりになるはずです、奥様。もしご主人が、この件についてあなたに何も知らせないのが賢明だとお考えなら、職業上の守秘義務の誓いのもとに真実を知ったに過ぎない私が、彼が伏せていることをお話しするべきでしょうか? それを求めるのは公正ではありません。あなたが尋ねるべきは、彼自身です。」
「彼には尋ねました。最後の頼みの綱として、あなたのもとへ参りました。ですが、ホームズさん、何か具体的なことをお話しいただかなくとも、一点だけお教えいただければ、大変な助けになります。」
「何でしょう、奥様?」
「この一件で、夫の政治家としてのキャリアが傷つく可能性はありますか?」
「そうですね、奥様、もしこれが正しく解決されなければ、確かに非常に不幸な影響を及ぼすかもしれません。」
「ああ!」
彼女は、疑念が晴れた者のように、鋭く息を吸い込んだ。
「もう一つだけ、質問を、ホームズさん。この災難の最初の衝撃の中で夫が漏らした言葉から、この文書の紛失によって、恐ろしい公的な結果が生じかねないと理解しました。」
「もし彼がそう言ったのであれば、私がそれを否定することはできません。」
「それは、どのような性質のものですか?」
「いえ、奥様、そこでもまた、私がお答えできる範囲を超えたことをお尋ねです。」
「では、これ以上お時間は取らせません。ホームズさん、あなたがもっと自由にお話しになるのを拒まれたことを、責めるつもりはございません。そして、あなたの方でも、私が夫の不安を、彼の意志に反してでも分かち合いたいと願うことを、悪くはお思いにならないと確信しております。もう一度、私の訪問については何もおっしゃらないでくださいと、お願いいたします。」
彼女はドアのところから我々を振り返った。そして私は、その美しい、何かに取り憑かれたような顔、怯えた目、引き結ばれた口元の最後の印象を焼き付けた。そして彼女は去っていった。
「さて、ワトソン、麗しの女性は君の専門分野だ」と、次第に遠ざかるサラサラという衣擦れの音が、玄関のドアがバタンと閉まる音に変わって消えたとき、ホームズは微笑みながら言った。「あの美しいご婦人の狙いは何だったのかね? 本当は何が欲しかったのだ?」
「彼女自身の言葉は明快ですし、その不安もごく自然なものだと思いますが。」
「ふむ! 彼女の様子を考えてみろ、ワトソン――あの態度、抑えられた興奮、落ち着きのなさ、質問を執拗に繰り返す粘り強さ。彼女が、軽々しく感情を表に出さない階級の出身であることを忘れるな。」
「確かに、ひどく動揺していました。」
「彼女が、夫のためには自分がすべてを知ることが最善だと、奇妙なほど真剣に我々に断言したことも思い出せ。あれは何を意味していたのだ? そして気づいたに違いない、ワトソン、彼女がどうやって光を背にするように立ち回ったかを。我々に自分の表情を読まれたくなかったのだ。」
「ええ、部屋で唯一その位置にある椅子を選びました。」
「だが、女性の動機というのは、実に不可解なものだ。同じ理由で私が疑ったマーゲートの女性を覚えているかね。鼻におしろいがついていない――それが正しい解決策だと判明した。このような流砂の上に、どうやって確固たるものを築けるというのか? 彼女たちの最も些細な行動が千金の意味を持つこともあれば、最も突飛な振る舞いがヘアピン一本やカール用こて一つに起因することもある。では、ワトソン、失敬。」
「お出かけですか?」
「ああ、午前中はゴドルフィン街で、いつもの役所の友人たちと時間を潰してくる。我々の問題の解決はエドゥアルド・ルーカスにある。もっとも、それがどんな形をとるのか、見当もつかないがね。事実を得る前に理論を立てるのは、致命的な過ちだ。君はここで見張り番を頼む、ワトソン君。新たな訪問者があれば応対してくれ。もしできれば、昼食には合流する。」
その日も、次の日も、そのまた次の日も、ホームズは彼の友人が「無口」と評し、他の者なら「不機嫌」と呼ぶであろう雰囲気の中にいた。彼は駆け出しては駆け込み、絶え間なく煙草を吸い、ヴァイオリンで断片的な曲を奏で、物思いに沈み、不規則な時間にサンドイッチを貪り、私が投げかける何気ない質問にもほとんど答えなかった。彼自身、あるいは彼の探求が、うまくいっていないことは私にも明らかだった。彼は事件について何も語ろうとせず、私が検死審問の詳細や、故人の従者ジョン・ミットンの逮捕とそれに続く釈放を知ったのは、新聞からだった。検視官の陪審は、当然ながら「故意による殺人」との評決を下したが、犯人は依然として不明のままだった。動機も示唆されなかった。部屋は価値ある品々で満ちていたが、何も盗まれてはいなかった。死者の書類には手がつけられていなかった。それらは注意深く調べられ、彼が国際政治の熱心な研究者であり、精力的な情報通であり、卓越した言語学者であり、そして疲れを知らない手紙の書き手であったことが示された。彼はいくつかの国の指導的な政治家たちと親密な関係にあった。しかし、彼の引き出しを満たしていた書類の中から、 sensational なものは何も発見されなかった。女性関係については、多岐にわたるが表面的であったようだ。彼は女性の中に多くの知人を持っていたが、友人はほとんどおらず、愛する者もいなかった。彼の習慣は規則正しく、その振る舞いは穏やかだった。彼の死は完全な謎であり、今後もそうあり続ける可能性が高かった。
従者ジョン・ミットンの逮捕については、全くの無策でいるよりはましだという、窮余の一策であった。しかし、彼に対する容疑を維持することはできなかった。彼はその夜、ハマースミスの友人を訪れていた。アリバイは完璧だった。確かに、彼が家路についた時間は、犯行が発見される前にウェストミンスターに到着しているべき時間ではあったが、夜の天気が良かったことを考えれば、途中まで歩いたという彼自身の説明は十分にあり得ることのように思われた。彼が実際に到着したのは十二時で、予期せぬ悲劇に打ちのめされているように見えた。彼は常に主人と良好な関係にあった。死者の所持品のうちいくつかが――特に小さな剃刀のケースが――従者の箱の中から見つかったが、彼はそれらが故人からの贈り物であったと説明し、家政婦もその話を裏付けることができた。ミットンはルーカスに三年仕えていた。注目すべきは、ルーカスが大陸へ行く際にミットンを同行させなかったことだ。彼は時に三ヶ月もの間パリを訪れることがあったが、ミットンはゴドルフィン街の家の留守を任されていた。家政婦については、犯行の夜、何も物音を聞いていなかった。もし主人が訪問者を迎えたとすれば、彼自身が招き入れたのであろう。
かくして三日の朝が過ぎても、私が新聞で追う限り、謎は謎のままであった。もしホームズがそれ以上を知っていたとしても、彼はそれを胸に秘めていたが、レストレード警部がこの事件で彼に内密に協力を求めていると話してくれたので、彼があらゆる進展と密接に連絡を取り合っていることはわかっていた。四日目、パリから長い電報が届き、それがすべての疑問を解決するように思われた。
パリ警察によってなされた発見は(とデイリー・テレグラフ紙は報じた)、
先週月曜日の夜、ウェストミンスターのゴドルフィン街で非業の死を遂げた
エドゥアルド・ルーカス氏の悲劇的な運命を覆っていたヴェールを剥がしつ
つある。読者の皆様もご記憶のことと思うが、故人は自室で刺殺されている
のが発見され、その従者にいくらかの嫌疑がかけられたものの、アリバイに
よってその線は立ち消えとなっていた。昨日、アンリ・フールネー夫人とし
て知られ、オーステルリッツ通りに小さな別荘を構える女性が、使用人たち
によって精神に異常をきたしていると当局に通報された。診察の結果、彼女
は確かに危険かつ永続的な形の躁病を発症していることが判明した。調査の
結果、警察は、アンリ・フールネー夫人がロンドンへの旅行から戻ったのが
先週の火曜日であること、そして彼女をウェストミンスターの犯罪と結びつ
ける証拠があることを発見した。写真の比較により、アンリ・フールネー氏
とエドゥアルド・ルーカス氏が実は同一人物であり、故人が何らかの理由で
ロンドンとパリで二重生活を送っていたことが決定的に証明された。フール
ネー夫人はクレオール出身で、極めて興奮しやすい性質であり、過去にも狂
乱に等しい嫉妬の発作に苦しんだことがある。ロンドンでこれほどのセン
セーションを巻き起こした恐ろしい犯罪は、そうした発作の一つの中で犯さ
れたものと推測される。月曜の夜の彼女の足取りはまだ追跡できていないが、
彼女と見られる女性が、火曜の朝、チャリング・クロス駅で、その錯乱した
様子と激しい身振りによって多くの注目を集めたことは間違いない。したが
って、犯罪は精神異常の状態で犯されたか、あるいはその直後の影響によっ
て、この不幸な女性が正気を失ったかのいずれかであろう。現在、彼女は過
去について筋の通った説明をすることができず、医師たちも彼女の理性が回
復する見込みはないとしている。フールネー夫人と思われる女性が、月曜の
夜、数時間にわたってゴドルフィン街の家を見張っていたのが目撃されたと
いう証言もある。
「これをどう思う、ホームズ?」
彼が朝食を終える間、私はその記事を声に出して読んでやった。
「ワトソン君」と、彼はテーブルから立ち上がって部屋を行き来しながら言った。「君は実に辛抱強いが、この三日間、私が何も話さなかったのは、話すことが何もなかったからだ。今でさえ、このパリからの報告は、我々の助けにはほとんどならない。」
「確かに、あの男の死に関しては最終的な結論でしょう。」
「あの男の死など、些細な出来事――取るに足らないエピソードに過ぎない。我々の真の任務、すなわち、この文書を追跡し、ヨーロッパの破局を救うという任務に比べればな。この三日間で起こった唯一の重要なことは、何も起こらなかったということだ。私は政府からほぼ一時間ごとに報告を受けているが、ヨーロッパのどこにも騒動の兆しがないことは確かだ。さて、もしこの書簡が世に出回っているとしたら――いや、出回っているはずがない――しかし、出回っていないとすれば、どこにあるのだ? 誰が持っている? なぜそれは表に出されない? その疑問が、金槌のように私の脳を打ち続ける。ルーカスが、書簡が消えたその夜に死んだのは、果たして偶然だったのか? 書簡は彼の手に渡ったのか? もしそうなら、なぜ彼の書類の中にない? あの狂った妻が、それを持って行ったのか? もしそうなら、それはパリの彼女の家にあるのか? フランス警察に疑われることなく、どうやってそれを探せというのだ? これはな、ワトソン君、法が我々にとって、犯罪者と同じくらい危険な事件なのだ。あらゆる者が我々に敵対している。それでいて、かかっている利害は巨大だ。もし私がこれを成功裏に終結させることができれば、それは間違いなく私のキャリアの栄光の頂点を飾るものとなるだろう。ああ、前線からの最新情報が来たぞ!」
彼は手渡されたメモにさっと目を通した。「おや! レストレードが何か興味深いことを見つけたようだ。帽子をかぶれ、ワトソン。一緒にウェストミンスターまで散歩と行こう。」
私がその犯行現場を訪れるのは初めてだった――背が高く、薄汚れた、幅の狭い家で、それが生まれた世紀のように、堅苦しく、形式ばっていて、頑丈だった。レストレードのブルドッグのような顔つきが、正面の窓から我々を覗き見ており、大柄な巡査がドアを開けて我々を中に通すと、彼は暖かく我々を迎えた。我々が通された部屋は、犯行が行われたその部屋だったが、今ではその痕跡は、カーペットの上の醜い、不規則な染み以外には何も残っていなかった。このカーペットは部屋の中央に敷かれた小さな四角い粗織りの敷物で、その周りには、磨き上げられた四角いブロック状の、美しく古風な木製の床が広がっていた。暖炉の上には見事な武器の飾り額があり、そのうちの一つが、あの悲劇の夜に使われたものだった。窓際には豪華な書き物机があり、絵画、敷物、壁掛けといった部屋の細部に至るまで、すべてが女性的と言えるほど贅沢な趣味を物語っていた。
「パリのニュースは見たかね?」とレストレードが尋ねた。
ホームズは頷いた。
「フランスの友人たちは、どうやら今回は的を射たようだな。間違いなく、彼らの言う通りだろう。彼女がドアをノックした――抜き打ちの訪問だろうな、彼は自分の生活を、水も漏らさぬほど厳密に区別していたからな――彼は彼女を中に入れた、路上に放っておくわけにもいかなかったのだろう。彼女は彼をどうやって突き止めたかを話し、彼を非難した。一つが次を呼び、そしてあの短剣がすぐそこにあったものだから、結末はすぐにやって来た。だが、一瞬の出来事ではなかった。これらの椅子はあちらの隅にすべて押しやられていたし、彼は一脚を手にしていた。まるで彼女をそれで押しとどめようとしたかのように。我々には、まるで見てきたかのようにすべてがはっきりしている。」
ホームズは眉を上げた。
「それでも、私を呼ばれたのですか?」
「ああ、そうだ、それはまた別の話だ――ほんの些細なことだが、あんたが興味を持つような類のことだ――奇妙で、まあ、風変わりとでも言うかな。本筋とは何の関係もない――見たところ、あり得ない。」
「それは、一体何です?」
「まあ、ご存知の通り、この手の犯罪の後では、我々は物を元の位置に保つよう、非常に注意を払う。何も動かされていない。担当官が昼夜ここにいる。今朝、男が埋葬され、調査も終わったので――この部屋に関する限りはだが――少し片付けてもいいだろうと思った。このカーペットだ。ご覧の通り、これは固定されておらず、ただ敷いてあるだけだ。我々はこれを持ち上げる必要があった。すると見つけたんだ――」
「ええ? 見つけたのですか――」
ホームズの顔が不安でこわばった。
「まあ、あんたが百年考えても、我々が何を見つけたか、決して当てられないだろうな。カーペットの上の染みが見えるだろう? かなりの量が染み通ったに違いない、そうだろう?」
「間違いなく、そうでしょう。」
「さて、驚くだろうが、それに対応する染みが、白い木製の床にはないんだ。」
「染みがない! しかし、あるはず――」
「ああ、そう言うだろうな。だが、事実として、ないんだ。」
彼はカーペットの角を手に取り、それをめくって、確かに彼の言う通りであることを示した。
「しかし、裏側は表側と同じくらい染みている。跡が残っているはずだ。」
レストレードは、有名な専門家を困らせたことに満足して、くすくすと笑った。
「さて、説明を見せてやろう。二つ目の染みがあるんだが、それはもう一方とは対応していない。ご自分で確かめてみろ。」
そう言うと、彼はカーペットの別の部分をめくった。すると、そこには確かに、古風な床の四角い白い板の上に、大きな深紅の染みが広がっていた。「これをどう思いますかな、ホームズさん?」
「なぜ、簡単なことですよ。二つの染みは対応していた。しかし、カーペットが向きを変えられたのです。正方形で固定されていなかったから、簡単にできたでしょう。」
「スコットランドヤードは、カーペットが向きを変えられたなんてことをあんたに教えてもらう必要はないんだ、ホームズさん。それは明白だ、染みは互いの上に重なる――この向きに敷けばな。だが、私が知りたいのは、誰がカーペットを動かしたのか、そしてなぜだ?」
ホームズの硬直した顔から、彼が内なる興奮で震えているのが見て取れた。
「いいですか、レストレード」と彼は言った。「通路にいるあの巡査が、ずっとこの場所の責任者だったのですか?」
「ああ、そうだ。」
「では、私のアドバイスを聞きなさい。彼を注意深く尋問するのです。我々の前でやってはいけない。我々はここで待ちます。あなたは彼を奥の部屋に連れて行く。一人の方が、彼から自白を引き出しやすいでしょう。なぜ人を中に入れ、この部屋に一人で残しておくなどという大胆なことをしたのか、彼に尋ねなさい。やったかどうかを尋ねてはいけない。やったと決めつけてかかるのです。誰かがここに来たことを知っていると彼に告げる。彼を追い詰める。完全な自白だけが、許しを得る唯一の道だと彼に言うのです。私が言う通りにやりなさい!」
「ちくしょう、もしあいつが知っているなら、吐かせてやる!」とレストレードは叫んだ。彼は廊下に飛び出し、数瞬後、彼の威圧的な声が奥の部屋から聞こえてきた。
「今だ、ワトソン、今だ!」とホームズが狂気じみた熱意で叫んだ。あの無気力な態度の背後に隠されていた、悪魔的なまでの力が、エネルギーの発作となって爆発した。彼は床から敷物を引き剥がし、瞬く間に四つん這いになって、その下の木製の四角い板の一つ一つを爪で引っ掻いた。彼がその端に爪を食い込ませると、一つが横に回転した。それは箱の蓋のように蝶番で後ろに開いた。その下に、小さな黒い空洞が現れた。ホームズは熱心な手をそこに突っ込み、苦々しい怒りと失望の唸り声とともに引き抜いた。それは空だった。
「急げ、ワトソン、急げ! 元に戻すんだ!」
木製の蓋は元に戻され、敷物がまっすぐに引き直されたちょうどその時、レストレードの声が通路で聞こえた。彼が見つけたのは、暖炉のマントルピースに気だるそうに寄りかかり、諦めと忍耐の表情を浮かべ、抑えきれないあくびを隠そうと努めているホームズの姿だった。
「お待たせして申し訳ない、ホームズさん。この一件にはすっかり退屈されているようだな。さて、あいつは白状したよ。こっちへ入れ、マクファーソン。この紳士方に、君の実に許しがたい行いを聞いてもらえ。」
大柄な巡査は、ひどくうろたえ、悔恨の念に駆られながら、部屋にそろそろと入ってきた。
「悪気はなかったんです、本当に。昨夜、若い女がドアのところに来まして――家を間違えた、と。それで、話をするうちに。一日中ここで勤務していると、寂しいものでして。」
「それで、どうなった?」
「犯罪が行われた場所を見たがったんです――新聞で読んだ、と。とてもきちんとした、話し方の丁寧な若い女性でしたので、覗かせるくらいなら害はないだろうと。カーペットの上のあの染みを見た途端、彼女は床に倒れ込み、死んだように横たわってしまいました。私は奥へ走って水を持ってきましたが、彼女を意識に戻すことはできませんでした。それで、角の『アイヴィー・プラント』亭へブランデーを買いに行ったのですが、戻ってきた時には、若い女は回復して、いなくなっていました――恥ずかしかったのでしょう、私に顔を合わせる勇気がなかったのだと思います。」
「あの敷物を動かしたことについてはどうだ?」
「ええ、まあ、私が戻ってきた時には、確かに少し乱れていました。ほら、彼女がその上に倒れましたし、ここは磨かれた床で、それを固定するものが何もないですから。後で私がまっすぐに直しました。」
「私を騙すことはできないという教訓になったな、マクファーソン巡査」とレストレードは威厳を込めて言った。「君は、自分の職務怠慢が決して発覚しないと思ったに違いない。だが、あの敷物を一目見ただけで、誰かが部屋に入ったと確信するのに十分だった。幸運だったな、君。何もなくなっていなかったからいいものの、そうでなければ、とんだ窮地に立たされることになっただろう。こんな些細なことでお呼び立てして申し訳ありませんでした、ホームズさん。ただ、二つ目の染みが一つ目と対応していないという点が、あなたの興味を引くかと思いましてね。」
「確かに、非常に興味深かった。この女性がここに来たのは一度だけかね、巡査?」
「はい、一度だけです。」
「誰だったんだ?」
「名前は知りません。タイプライターの募集広告に応募してきて、番号を間違えたと――とても感じのいい、上品な若い女性でした。」
「背は高いか? 美人か?」
「ええ、すらりとした若い女性でした。美人と言えるかもしれません。人によっては、大変な美人だと言うでしょう。『ああ、お巡りさん、どうかちょっと覗かせてください!』と彼女は言いました。何と言いますか、可愛らしく、甘えるような仕草でして、ドアから頭を覗かせるくらいなら害はないだろうと思ったのです。」
「服装は?」
「地味でした――足元まである長いマントを着ていました。」
「何時頃だった?」
「ちょうど日が暮れかかった頃です。私がブランデーを持って戻ってきた時には、街灯が灯されていました。」
「結構」とホームズは言った。「行こう、ワトソン。我々には、他にもっと重要な仕事があるようだ。」
我々が家を出る時、レストレードは表の部屋に残り、悔い改めた巡査がドアを開けて我々を見送った。ホームズは玄関の段の上で振り返り、手に何かを掲げてみせた。巡査は食い入るように見つめた。
「なんてこった!」と彼は叫び、顔には驚愕の色が浮かんだ。ホームズは唇に指を当て、それを胸ポケットに戻すと、我々が通りを下っていくにつれて、大声で笑い出した。「素晴らしい!」と彼は言った。「さあ、友よ、ワトソン。最終幕の幕が上がる。君も聞いて安心するだろうが、戦争は起こらない。トレローニー・ホープ閣下の輝かしいキャリアに傷がつくこともない。無分別な君主がその無分別さの罰を受けることもない。首相がヨーロッパの紛糾に対処する必要もなくなる。そして、我々が少々機転を利かせてうまく立ち回れば、誰もびた一文損をすることなく、実に厄介な事態になりかねなかったこの一件を収めることができる。」
私の心は、この並外れた男への賞賛で満たされた。
「解決したのですね!」と私は叫んだ。
「ほとんどな、ワトソン。まだ暗闇に包まれた点がいくつかある。しかし、我々はこれだけのものを手に入れたのだから、残りを手に入れられないとしたら、それは我々自身の落ち度だ。ホワイトホール・テラスへ直行し、事態を決着させよう。」
我々が欧州担当大臣の邸宅に到着した時、シャーロック・ホームズが面会を求めたのは、レディ・ヒルダ・トレローニー・ホープであった。我々は朝の間に通された。
「ホームズさん!」とご婦人は言った。その顔は憤慨で紅潮していた。「これは、あまりに不公平で、思いやりのない振る舞いですわ。私があなたを訪問したことは、夫が私が彼の仕事に立ち入っていると思うことのないよう、秘密にしておきたかったと、ご説明したはずです。それなのに、あなたはこうしてここへいらっしゃることで私を窮地に陥れ、我々の間に仕事上の関係があることをお示しになる。」
「残念ながら、奥様、私には他に選択肢がございませんでした。私は、この極めて重要な書類を回収するよう依頼されております。つきましては、奥様、それを私の手にお渡しくださいますよう、お願い申し上げます。」
ご婦人はさっと立ち上がった。その美しい顔から、一瞬にして血の気が引いた。その目は虚ろになり――よろめいた――私は、彼女が卒倒するかと思った。しかし、壮絶な努力で彼女は衝撃から立ち直り、この上ない驚きと憤りが、他のあらゆる表情をその顔から追い払った。
「わ、私を侮辱なさるのですね、ホームズさん。」
「まあまあ、奥様。無駄なことです。手紙をお渡しなさい。」
彼女は呼び鈴へと駆け寄った。
「執事に表へご案内させますわ。」
「呼び鈴は鳴らさぬように、レディ・ヒルダ。もし鳴らせば、醜聞沙汰を避けようという私の懸命な努力がすべて水泡に帰します。手紙を渡していただければ、すべては丸く収まるのです。私にご協力いただけるなら、万事うまく取り計らいましょう。もし刃向かうというのであれば、私はあなたの所業を白日の下に晒さねばなりません。」
彼女は女王のごとき気品で、敢然と立ち向かった。その目は、あたかも彼の魂の奥底まで読み取ろうとするかのように、ホームズに注がれている。手は呼び鈴にかかっていたが、鳴らすことはためらっていた。
「私を怖がらせようというのですね。このような場所に乗り込んできて、女一人を脅しつけるなんて、紳士のなさることではありませんわ、ホームズさん。何かご存じだと仰る。いったい何をご存じなのです?」
「どうぞお座りください、奥様。もし倒れでもしたら、お怪我をなさいます。お座りになるまで、私は何も話しません。……ありがとうございます。」
「五分だけ差し上げますわ、ホームズさん。」
「一分で十分です、レディ・ヒルダ。あなたがエドゥアルド・ルーカスを訪ねたことも、彼に例の文書を渡したことも、昨夜、見事な手口で部屋に忍び込み、絨毯の下の隠し場所から手紙を持ち去ったことも、すべて承知しております。」
彼女は色を失った顔で彼を見つめ、二度、息を呑んでから、ようやく口を開いた。
「あなた、どうかしてるわ、ホームズさん……どうかしてる!」と、彼女はついに叫んだ。
彼はポケットから小さなボール紙の切れ端を取り出した。それはある肖像画から切り抜かれた、女性の顔であった。
「役に立つかと思い、持ち歩いておりました。警官はこれに見覚えがあるとのことです。」
彼女は息を呑み、椅子にぐったりと身を預けた。
「さあ、レディ・ヒルダ。手紙はお持ちのはず。まだ取り返しはつきます。あなたを苦境に陥れたいわけではないのです。私の務めは、失われた手紙をご主人の元へお返しすること。それで終わりです。私の忠告をお聞き入れになり、正直にお話しください。それが唯一の道です。」
彼女の気概は見事なものであった。この期に及んでも、まだ敗北を認めようとはしない。
「もう一度申し上げますわ、ホームズさん。あなたは馬鹿げた幻想に囚われているのです。」
ホームズは椅子から立ち上がった。
「お気の毒です、レディ・ヒルダ。私はあなたのために最善を尽くしましたが、すべては無駄だったようですな。」
彼は呼び鈴を鳴らした。執事が入ってくる。
「トレローニー・ホープ氏はおいでかな?」
「旦那様は、一時十五分前にはお戻りになります。」
ホームズは腕時計に目をやった。
「まだ十五分あるな」と彼は言った。「よろしい、待たせてもらおう。」
執事が背後の扉を閉めるか閉めないかのうちに、レディ・ヒルダはホームズの足元にひざまずき、両手を差し伸べ、その美しい顔を涙に濡らしながら見上げていた。
「ああ、お許しください、ホームズさん! どうかお許しを!」彼女は狂おしいほどの嘆願の声で懇願した。「お願いです、あの方には言わないで! 心から愛しているのです! あの方の人生に一片の影も落としたくない。こんなことが知れたら、あの方の気高い心は打ち砕かれてしまうでしょう。」
ホームズは夫人を立たせた。「奥様、土壇場で正気を取り戻してくださり、感謝します! 一刻の猶予もありません。手紙はどこです?」
彼女は書き物机へ駆け寄ると、鍵を開け、長い青い封筒を引き出した。
「ここにあります、ホームズさん。ああ、こんなもの、決して目にしなければよかった!」
「どうやってこれを戻すか……」ホームズは呟いた。「急いで、早く、何か方法を考えなくては! 書類箱はどこに?」
「まだ寝室に。」
「なんと幸運な! 急いで、奥様、それをお持ちください!」
一瞬の後、彼女は平たい赤い箱を手に現れた。
「以前はどうやって開けたのです? 合鍵をお持ちか? そう、もちろんお持ちのはずだ。開けてください!」
レディ・ヒルダは胸元から小さな鍵を取り出した。箱は音を立てて開く。中には書類が詰め込まれていた。ホームズはその青い封筒を書類の束の奥深く、別の文書の間にぐいと差し込んだ。箱は閉じられ、鍵がかけられ、寝室へと戻された。
「これで、あの方をお迎えする準備はできました」とホームズは言った。「まだ十分あります。私はあなたを庇うために、相当な無理をしています、レディ・ヒルダ。その代わり、この時間を使って、この奇妙な事件の真相をありのままにお話しいただきたい。」
「ホームズさん、すべてお話ししますわ」と夫人は叫んだ。「ああ、ホームズさん、あの方にほんの一瞬でも悲しい思いをさせるくらいなら、私はこの右腕を切り落としますわ! ロンドンのどんな女も、私ほど夫を愛してはおりません。それなのに、もし私のしたこと――いえ、せざるを得なかったことを知ったら……あの方は決して私を許さないでしょう。ご自身の名誉を何よりも重んじる方ですから、他人の過ちを忘れも赦しもしないはず。助けてください、ホームズさん! 私の幸せが、あの方の幸せが、私たちの人生そのものが懸かっているのです!」
「急いで、奥様、時間がありません!」
「あれは私の手紙でしたの、ホームズさん。結婚前に書いた、分別を欠いた手紙……愚かで、衝動的で、恋に夢中な娘が書いた手紙です。悪気はなかった。けれど、あの方ならきっと罪深いことだとお思いになるでしょう。もしあの方がその手紙を読んだなら、信頼は永遠に失われてしまったはずです。書いたのは何年も前のこと。すべては忘れ去られたことだと思っておりました。ところが、ついにあのルーカスという男から連絡があり、手紙が彼の手に渡ったこと、そして夫に見せると脅してきたのです。私は慈悲を乞いました。すると彼は、夫の書類箱にある、彼が指定するある文書を持ってくれば、私の手紙を返すと申しました。彼には役所に内通者がいて、その存在を教えたのでしょう。夫に害が及ぶことはないと、彼は請け合いました。私の身にもなってください、ホームズさん! 私にどうしろと仰るのです?」
「ご主人にすべてを打ち明けるべきでしたな。」
「できませんでした、ホームズさん、とてもできませんでしたわ! 一方には確実な破滅が、もう一方には、夫の書類を盗むという恐ろしい行いがありましたが、政治のことなど私にはその重大さが理解できず、一方で愛と信頼の問題は、あまりにも明白でした。私はやってしまったのです、ホームズさん! 夫の鍵の型を取り、あのルーカスという男に合鍵を作らせました。そして書類箱を開け、文書を持ち出し、ゴドルフィン街へ運んだのです。」
「そこで何が起こりましたかな、奥様?」
「約束通りにドアを叩くと、ルーカスが出てきました。私は彼の部屋へ入りましたが、あの男と二人きりになるのが怖かったので、玄関のドアは少し開けたままにしておきました。部屋に入る時、外に女が一人いたのを覚えています。用件はすぐに済みました。彼は私の手紙を机の上に置いており、私は彼に文書を渡しました。そして彼が私に手紙を返してくれた、その瞬間です。ドアの方で物音がしました。廊下に足音が聞こえたのです。ルーカスは素早く敷物の一部をめくり上げ、文書をそこにある隠し場所に押し込み、元に戻しました。」
「その後に起こったことは、まるで恐ろしい夢のようです。私の目に焼き付いているのは、ある女の暗く、狂乱した顔。そしてフランス語でこう叫ぶ声です。『待った甲斐があったわ。とうとう見つけた、この女と一緒にいるところを!』と。激しい揉み合いが始まりました。彼が椅子を手にし、女の手にはナイフが光っているのが見えました。私はその恐ろしい光景から逃げ出し、家から走り去りました。そして翌朝の新聞で、ようやくあの惨たらしい結末を知ったのです。その夜は幸せでした。手紙を取り戻し、未来に何が待ち受けているか、まだ知らなかったのですから。」
「一つの悩みが別の悩みに変わっただけだと気づいたのは、翌朝のことでした。書類を失った夫の苦悩は、私の心を抉りました。今すぐにでも彼の足元にひざまずき、自分のしたことを告白したい衝動を抑えるのがやっとでした。しかし、そうすれば過去の過ちを告白することにもなる。私がその朝あなたのもとを訪れたのは、自分の犯した罪の重大さをはっきりと理解するためでした。それを悟った瞬間から、私の心はただ一つ、夫の書類を取り戻すことだけに向かいました。あの恐ろしい女が部屋に入ってくる前に隠されたのですから、手紙はルーカスが置いた場所にまだあるはず。もし彼女が現れなければ、私には隠し場所がどこかも分からなかったでしょう。どうやって部屋に入るか? 二日間、その場所を見張りましたが、ドアは決して開け放たれることはありませんでした。昨夜、最後の試みに出たのです。何をし、どうやって成功したかは、もうご存じの通りです。私は書類を持ち帰りましたが、夫に罪を告白せずにそれを返す方法が見当たらず、いっそ燃やしてしまおうかと考えておりました。まあ、階段を上ってくるあの方の足音が!」
欧州大臣が興奮した面持ちで部屋に飛び込んできた。「何か知らせは、ホームズさん、何か知らせは?」と彼は叫んだ。
「いくつか希望が見えてきました。」
「ああ、ありがたい!」
彼の顔がぱっと輝いた。「首相が昼食に来られている。君の希望を伝えてもいいかね? 鋼の神経を持つあの方ですら、この恐ろしい事件以来、ほとんど眠れていないのだ。ジェイコブス、首相にこちらへお越しいただくよう頼んでくれ。君については、すまないが、これは政治の話だ。数分で食堂で合流しよう。」
首相の態度は落ち着いていたが、その目の輝きや、骨張った手の微かな震えから、若い同僚の興奮を分かち合っているのが見て取れた。
「何か報告があるとのことですな、ホームズさん?」
「今のところ、あくまで消極的な報告ですが」と友は答えた。「ありとあらゆる可能性を調べましたが、懸念されるような危険はもはやないと確信しております。」
「しかし、それだけでは不十分だ、ホームズさん。我々はいつまでもこのような火山の火口で暮らすわけにはいかん。何か明確なものが必要なのだ。」
「それを手に入れる望みはあります。だからこそ、私はここにいるのです。この件を考えれば考えるほど、手紙はこの家から一歩も出ていないという確信が深まります。」
「ホームズさん!」
「もし外に出ていれば、今頃とっくに公になっているはずです。」
「しかし、なぜ誰かがそれを盗んでおきながら、自分の家に保管しておく必要があるのです?」
「私は、そもそも誰かが盗んだとすら確信しておりません。」
「では、どうやって書類箱からなくなったというのです?」
「私は、そもそも書類箱から出たことすら疑わしいと考えています。」
「ホームズさん、このような冗談は時と場合をわきまえていただきたい。箱からなくなったのは私が保証します。」
「火曜の朝以来、箱の中を調べましたかな?」
「いいや。その必要はなかった。」
「ひょっとすると、見落とされたのかもしれません。」
「あり得ない、絶対に。」
「しかし、私にはそうは思えません。そういうことは時々起こるものです。中には他の書類もあるのでしょう。そう、それらに紛れ込んでしまったのかもしれません。」
「一番上にあったのだ。」
「誰かが箱を揺すって、場所が変わったのかもしれません。」
「いやいや、私は中身をすべて出したのだ。」
「まあ、ホープ君、それはすぐにわかることだろう」と首相が言った。「書類箱を持ってこさせたまえ。」
大臣は呼び鈴を鳴らした。
「ジェイコブス、私の書類箱を持ってきてくれ。まったく馬鹿げた時間の無駄だが、それでも君が納得しないというなら、そうしよう。ありがとう、ジェイコブス、ここに置いてくれ。鍵はいつも時計の鎖につけてある。ほら、これが書類だ。メロウ卿からの手紙、チャールズ・ハーディ卿からの報告書、ベオグラードからの覚書、ロシア・ドイツ間の穀物関税に関するメモ、マドリードからの書簡、フラワーズ卿からの覚え書き……おお、神よ! これは……ベリンジャー卿! ベリンジャー卿からの手紙じゃないか!」
首相は彼のその手から青い封筒をひったくった。
「そうだ、これだ――そして手紙は封も切られていない。ホープ君、おめでとう。」
「ありがとう! ありがとうございます! これで肩の荷が下りました。しかし、信じられない――あり得ないことだ。ホームズさん、あなたは魔法使いだ、魔術師だ! なぜここにあるとわかったのです?」
「それが他のどこにもないとわかっていましたから。」
「自分の目が信じられん!」
彼は狂ったようにドアへ走った。「妻はどこだ? すべてうまくいったと伝えなければ。ヒルダ! ヒルダ!」階段で彼が叫ぶ声が聞こえた。
首相は目を輝かせながらホームズを見た。
「さあ、ホームズさん」と彼は言った。「これは見た目以上に何か裏がある。手紙は一体どうやって箱の中に戻ったのですかな?」
ホームズは、その鋭い慧眼の詮索から逃れるように微笑みながら顔をそむけた。
「我々にも、外交上の秘密というものがありましてな」彼はそう言うと帽子を手に取り、ドアへと向かった。
THE END

