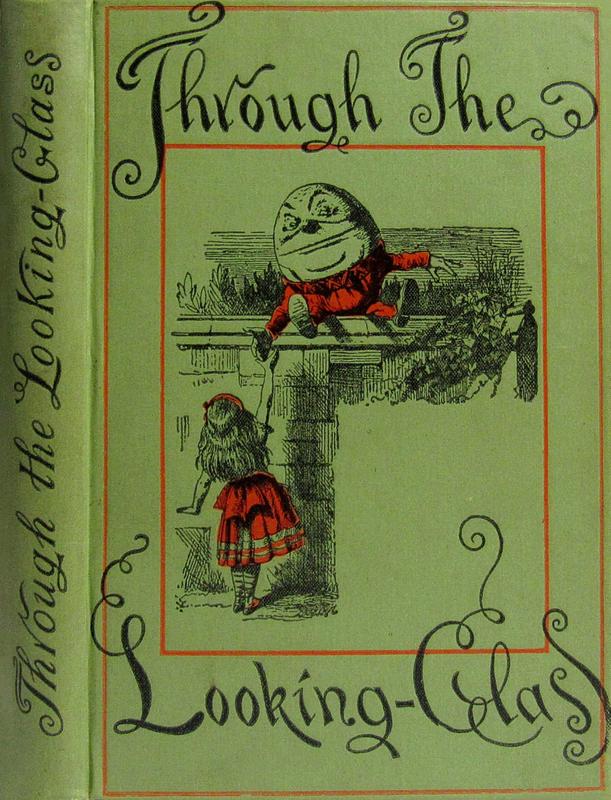
そしてアリスがそこで見つけたもの
ルイス・キャロル作
第一章 鏡の国のおうち
一つだけ確かなことがありました。それは、この件に白い子猫は一切関わっていない、ということです。すべては黒い子猫のせいでした。というのも、白い子猫はこの十五分間、ずっと親猫に顔を洗われていたのですから(しかも、それを考えればまあまあ我慢していました)。ですから、ご覧の通り、このいたずらに加担できるはずがなかったのです。
ダイナが自分の子供たちの顔を洗うやり方はこうでした。まず、片方の前足でかわいそうな子猫の耳を押さえつけ、それからもう片方の前足で、鼻から始めて毛並みに逆らうように、顔中をごしごしこするのです。そして今、申し上げた通り、ダイナは白い子猫に懸命に取りかかっていました。子猫はじっと横たわり、喉を鳴らそうとしていました――きっと、すべては自分のためになることだと感じていたのでしょう。
しかし、黒い子猫は午後早くに洗い終わっていました。ですから、アリスが大きな肘掛け椅子の隅に丸まって座り、半分独り言を言い、半分眠っている間に、子猫はアリスが巻こうとしていた毛糸玉で大はしゃぎの遊びを繰り広げていたのです。毛糸玉をあちこちに転がし、とうとう全部ほどいてしまいました。そしてそれは、炉辺の敷物の上に広がり、結び目ともつれの塊になっていて、その真ん中で子猫が自分のしっぽを追いかけて走り回っていたのでした。
「あら、なんていたずらっ子なの!」とアリスは叫び、子猫をひょいと抱き上げ、お仕置きされていると分からせるために、軽くキスをしてやりました。「本当に、ダイナがもっとちゃんとお行儀を教えるべきだったわ! ダイナ、あなたはそうすべきだったのよ、わかっているでしょう!」と彼女は付け加え、親猫を咎めるように見つめ、できるだけ不機嫌そうな声で言いました。それから彼女は急いで肘掛け椅子によじ登り、子猫と毛糸を一緒に持って、再び毛糸玉を巻き始めました。しかし、ずっとおしゃべりをしていたので、なかなかはかどりませんでした。時には子猫に、時には自分自身に話しかけていたのです。キティはアリスの膝の上でとてもおすましして座り、毛糸が巻かれていくのを見ているふりをしながら、時々片方の前足を伸ばしてそっと毛糸玉に触れました。まるで、もし許されるなら、手伝えたら嬉しいとでも言うかのようでした。
「キティ、明日が何の日か知ってる?」とアリスは話し始めました。「もし私と一緒に窓のところにいたら、当てられたでしょうね。でもダイナがあなたをきれいにしていたから、無理だったわ。男の子たちがかがり火のための枝を集めているのを見ていたの。たくさんの枝がいるのよ、キティ! ただ、とても寒くなって、雪も降ってきたから、やめなければならなかったの。気にしないで、キティ、明日かがり火を見に行きましょうね。」ここでアリスは、どんなふうに見えるか確かめようと、毛糸を二、三回キティの首に巻きつけました。これがひと騒動になり、毛糸玉は床に転がり落ち、何ヤードも何ヤードもまたほどけてしまったのです。
「あのね、私、とっても怒ったのよ、キティ」と、彼らが心地よく座り直すとすぐにアリスは続けました。「あなたがしでかしたいたずらを全部見たとき、もう少しで窓を開けて、あなたを雪の中に放り出すところだったんだから! あなたはそれに値したわ、このいたずら好きの可愛い子! 何か言い分はある? さあ、口をはさまないで!」と彼女は指を一本立てて続けました。「あなたの悪いところを全部教えてあげるわ。第一に、今朝ダイナがあなたの顔を洗っている間に二回も鳴いたこと。さあ、否定できないでしょう、キティ。私、聞いたんだから! 何て言ったの?」(子猫が話しているふりをして。)「ダイナの前足が目に入ったですって? まあ、それはあなたのせいでしょ、目を開けていたからよ。もしぎゅっと閉じていたら、そんなことにはならなかったわ。さあ、もう言い訳はしないで、聞きなさい! 第二に、私がスノードロップの前にミルクの受け皿を置いたとたんに、あなたがしっぽを引っ張ったこと! 何ですって、喉が渇いていたの? スノードロップだって喉が渇いていなかったとどうしてわかるの? さあ、第三に、私が見ていない間に、毛糸を全部ほどいたこと!
「これで悪いことは三つよ、キティ。そしてあなたはまだどれ一つ罰せられていないわ。あなたへのお仕置きは全部、来週の水曜日のために取っておくことにするわ。もし、私へのお仕置きが全部取っておかれたとしたら、どうなるかしら!」と彼女は子猫よりも自分自身に言い聞かせるように続けました。「一年の終わりには、どうなっちゃうのかしら? その日が来たら、私は刑務所に送られるんでしょうね、きっと。あるいは――そうね――もし一つのお仕置きが夕食抜きだとしたら、その惨めな日が来たとき、私は一度に五十回も夕食を抜かなければならなくなるわ! まあ、それくらいならあまり気にしないけど! 食べるくらいなら、いっそ食べないほうがずっとましだわ!
「窓ガラスに雪が当たる音が聞こえる、キティ? なんて素敵で柔らかい音なんでしょう! まるで誰かが外から窓中にキスをしているみたい。雪は木や野原が好きなのかしら、あんなに優しくキスをするなんて。そしてね、白い掛け布団で、みんなを暖かく覆ってあげるの。そしてたぶん、『おやすみ、可愛い子たち、夏がまた来るまでね』って言うのよ。そして夏に目を覚ますと、キティ、みんな緑色の服を着て、風が吹くたびに踊りだすの――ああ、とってもきれい!」とアリスは叫び、毛糸玉を落として手を叩きました。「そして、それが本当だったらどんなにいいかしら! 秋になって葉っぱが茶色くなると、森は眠そうに見えるもの、きっとそうよ。
「キティ、チェスはできる? さあ、笑わないで、あなた。真面目に聞いているのよ。だって、さっき私たちが遊んでいたとき、あなたはまるで分かっているかのように見ていたもの。そして私が『チェック!』[訳注:チェスで「王手」のこと]って言ったら、あなたは喉を鳴らしたわ! まあ、あれは素敵なチェックだったわ、キティ。本当に、あの意地悪なナイトが私の駒の中にくねくねと下りてこなければ、私が勝っていたかもしれないのに。キティ、あなた、ごっこ遊びをしましょう――」そしてここで、アリスが彼女のお気に入りの言葉「ごっこ遊びをしましょう」で始める話を、半分でもお伝えできたらと思うのです。彼女はつい昨日も、お姉さんとかなり長いこと口論をしたばかりでした――すべてはアリスが「私たちが王様と女王様ごっこをしましょう」と始めたせいでした。そして、何事もきっちりしているのが好きなお姉さんは、二人しかいないのだから無理だと主張し、アリスはとうとう「じゃあ、あなたがその一人になって、私が残りの全部になるわ」と言うしかなくなったのです。そして一度は、年取った乳母の耳元で突然「乳母さん! 私がお腹をすかせたハイエナで、あなたが骨っていうごっこ遊びをしましょうよ」と叫んで、本気で怖がらせたこともありました。
しかし、話がアリスの子猫への言葉から逸れてしまいました。「あなたが赤の女王ごっこをするのよ、キティ! あのね、もしあなたがきちんと座って腕を組んだら、そっくりに見えると思うわ。さあ、やってみて、お願いだから!」そしてアリスはテーブルから赤の女王を取り上げ、子猫が真似をするためのお手本としてその前に立てました。しかし、それはうまくいきませんでした。主な理由は、アリスが言うには、子猫がきちんと腕を組もうとしなかったからだそうです。そこで、罰として、彼女は子猫を鏡の前に持ち上げ、どれほど不機嫌な顔をしているか見せつけました。「そして、すぐにいい子にしないなら」と彼女は付け加えました。「あなたを鏡の国のおうちに入れてしまうわよ。それ、どう思う?」
「さあ、キティ、ちゃんと聞いてて、そんなにおしゃべりしないでくれたら、鏡の国のおうちについての私の考えを全部教えてあげるわ。まず、鏡を通して見える部屋があるでしょう。あれは私たちの応接間とそっくりなの、ただ物が左右反対になっているだけ。椅子の上に登れば全部見えるわ。暖炉の後ろの部分だけを除いてね。ああ! あの部分が見られたらどんなにいいかしら! 冬に火を焚いているのか、すごく知りたいの。絶対にわからないのよ、私たちの暖炉から煙が出ない限りはね。そうすれば、あの部屋にも煙が立ち上るんだけど、でもそれはただの見せかけかもしれないわ、火があるように見せかけるためだけのね。それから、本は私たちの本と少し似ているけど、文字が逆さまに書いてあるの。それは知ってるわ。だって、私たちの本を鏡にかざしてみたら、向こうの部屋でも本をかざしてきたもの。
「鏡の国のおうちに住むのはどう、キティ? あそこではミルクをもらえるのかしら? もしかしたら鏡の国の牛乳は飲んでもおいしくないかも――でも、ああ、キティ! 今度は廊下の話よ。私たちの応接間のドアを大きく開けておくと、鏡の国のおうちの廊下がほんのちょっぴり見えるの。見える限りでは私たちの廊下とそっくりだけど、その先は全然違うかもしれないじゃない。ああ、キティ! 鏡の国のおうちに通り抜けられたら、どんなに素敵でしょう! きっと、ああ! とってもきれいなものがあるに違いないわ! どうにかして通り抜けられる方法があるってことにしましょうよ、キティ。鏡がガーゼみたいに柔らかくなって、通り抜けられるってことにしましょう。あら、なんだか霧みたいになってきたわ、本当に! これなら簡単に通り抜けられそう――」彼女はこう言いながらマントルピースの上にいましたが、どうやってそこにたどり着いたのか、自分でもほとんど分かっていませんでした。そして確かに、鏡は明るい銀色の霧のように、溶け始めていました。
次の瞬間、アリスは鏡を通り抜け、鏡の国の部屋に軽やかに飛び降りました。彼女が真っ先にしたことは、暖炉に火があるかどうか見ることでした。そして、自分が残してきた暖炉と同じくらい明るくぱちぱちと燃えている本物の火を見つけて、すっかり嬉しくなりました。「それなら、ここも前のお部屋と同じくらい暖かいわね」とアリスは思いました。「ううん、むしろもっと暖かいわ。だって、ここには火のそばから離れなさいって叱る人が誰もいないもの。ああ、みんなが鏡を通してここの私を見て、手が出せないってなったら、なんて面白いでしょう!」
それから彼女は周りを見回し始め、元の部屋から見えていたものはごくありふれていて面白みがないのに、それ以外のものはすべて全く違っていることに気づきました。例えば、暖炉の隣の壁にかかった絵はどれも生きているようで、マントルピースの上の時計(鏡の中では裏側しか見えませんよね)には、小さなおじいさんの顔がついていて、彼女ににっこり笑いかけていました。
「この部屋はあっちほど片付いていないのね」とアリスは独り言を言いました。暖炉の燃え殻の中にチェスの駒がいくつか落ちているのに気づいたのです。しかし次の瞬間、小さく「あら!」と驚きの声をあげると、彼女は四つん這いになってそれらをじっと見つめていました。チェスの駒たちが、二人一組で歩き回っていたのです!
「ここに赤の王様と赤の女王様がいるわ」とアリスは言いました(駒たちを怖がらせないように、ささやき声で)。「そして、あそこには白の王様と白の女王様がシャベルの縁に座っているわ。こっちでは二つのお城が腕を組んで歩いている。私の声は聞こえないと思うわ」と彼女は頭をさらに近づけながら続けました。「それに、私のことも見えないはずよ。なんだか、私、透明人間になったみたい――」
その時、アリスの後ろのテーブルの上で何かがキーキーと鳴き始め、彼女が振り向くと、ちょうど白のポーン(歩兵)の一人が転がって足をばたつかせ始めるところでした。彼女は次に何が起こるのか、大変な好奇心をもってそれを見つめました。
「我が子の声ですわ!」と白の女王が叫び、王様をかすめて突進しました。その勢いがあまりに激しかったので、王様を灰の中に突き倒してしまいました。「私の大事なリリー! 私の気高き子猫ちゃん!」そして女王は必死に暖炉の柵の側面をよじ登り始めました。
「気高きだなんて、ばかな!」と王様は言いました。転んだ拍子にぶつけた鼻をこすりながら。彼が女王に少し腹を立てるのももっともでした。頭のてっぺんから足の先まで灰まみれだったのですから。
アリスはとても役に立ちたいと思いました。そして、かわいそうなリリーが金切り声をあげてひきつけを起こしそうだったので、急いで女王を拾い上げ、騒がしい小さな娘の隣のテーブルの上に置いてあげました。
女王ははっと息をのみ、座り込みました。空中を素早く移動したせいで、すっかり息が切れてしまい、一、二分というもの、ただ黙って小さなリリーを抱きしめることしかできませんでした。少し息が整うとすぐ、彼女は灰の中で不機服そうに座っている白の王様に向かって叫びました。「火山に気をつけて!」
「何の火山かね?」と王様は言い、心配そうに暖炉の火を見上げました。まるで火山を見つけるならそこが一番ありそうな場所だとでも思ったかのようでした。
「私を――吹き――飛ばしたのよ」と女王はぜいぜい言いながら答えました。まだ少し息が切れていたのです。「あなたも――いつもの道順で――上がってくるのですよ。吹き飛ばされないようにね!」
アリスは、白の王様が暖炉の格子の桟を一段一段ゆっくりと苦労して登っていくのを見ていましたが、とうとう言いました。「あら、そんな調子じゃ、テーブルに着くまで何時間もかかってしまいますわ。私が手伝ってさしあげたほうがずっといいでしょう?」しかし王様はその問いかけに全く気づきませんでした。彼にはアリスの声も聞こえず、姿も見えないことは明らかでした。
そこでアリスは王様をとても優しく拾い上げ、女王を持ち上げた時よりもゆっくりと運びました。息を切らさせないようにするためです。しかし、テーブルに置く前に、少しほこりを払ってあげたほうがいいかもしれないと思いました。あまりにも灰まみれだったのです。
彼女は後になって、生まれてこのかた、王様が見せたような顔は一度も見たことがないと言いました。目に見えない手に空中で持たれ、ほこりを払われていると気づいた時の王様の顔です。彼はあまりに驚いて叫び声をあげることもできませんでしたが、その目と口はどんどん大きく、そしてどんどん丸くなっていき、とうとうアリスの手が笑いで震え、もう少しで床に落としてしまうところでした。
「ああ! おねがいだからそんな顔をしないで、あなた!」と彼女は叫びました。王様に自分の声が聞こえないことをすっかり忘れて。「あなたが笑わせるから、ちゃんと持っていられないじゃない! それに、そんなに口を大きく開けていないで! 灰が全部入ってしまうわ――ほら、これで十分きれいになったと思うわ!」と彼女は付け加え、王様の髪をなでつけ、女王の近くのテーブルに置いてあげました。
王様はすぐに仰向けに倒れ、ぴくりとも動かなくなりました。アリスは自分のしたことに少し驚き、彼にかける水がないか部屋中を探し回りました。しかし、インクの瓶しか見つからず、それを持って戻ってくると、王様は回復しており、女王と二人、おびえたようなささやき声で話していました――あまりに声が小さかったので、アリスには何を言っているのかほとんど聞き取れませんでした。
王様はこう言っていました。「誓って言うが、愛しいお前、わしはヒゲの先まで冷たくなったぞ!」
それに対して女王はこう答えました。「あなたにヒゲなんてありませんわ。」
「あの瞬間の恐怖は」と王様は続けました。「わしは決して、決して忘れまいぞ!」
「いいえ、お忘れになりますわ」と女王は言いました。「そのことを覚え書きにしておかなければね。」
アリスが大変興味深げに見ていると、王様はポケットから巨大な手帳を取り出し、何かを書き始めました。ふとある考えがアリスに浮かび、彼女は王様の肩越しに伸びていた鉛筆の端をつかみ、彼のために書き始めました。
哀れな王様は困惑し、不幸そうな顔をして、何も言わずにしばらく鉛筆と格闘しました。しかしアリスの方が力が強く、とうとう王様は息を切らしながら言いました。「愛しいお前! 本当にもっと細い鉛筆を手に入れねばならん。これは少しも言うことをきかん。わしが意図しないようなことばかり書くのだ――」
「どのようなことですの?」と女王は言い、手帳を覗き込みました(そこにはアリスが「白の騎士が火かき棒を滑り降りている。とても危なっかしい」と書き込んでいました)。「それはあなたのお気持ちの覚え書きではありませんわ!」
テーブルの上のアリスの近くに本が置いてありました。彼女は白の王様を見守りながら(まだ少し彼のことが心配で、また気絶した場合に備えてインクをすぐかけられるようにしていました)、読める部分はないかとページをめくりました。「――だって、私の知らない言葉で書いてあるんだもの」と彼女は独り言を言いました。
それはこんなふうでした。
.YKCOWREBBAJ
sevot yhtils eht dna, gillirb sawT’
ebaw eht ni elbmig dna eryg diD
,sevogorob eht erew ysmim llA
.ebargtuo shtar emom eht dnA
彼女はしばらくこれに頭を悩ませましたが、とうとう名案がひらめきました。「あら、もちろん、これは鏡の国の本なのよ! それで、これを鏡にかざせば、文字がまた正しい向きになるんだわ。」
これがアリスの読んだ詩でした。
ジャバウォッキー
ブリリグの刻、ぬらやかなトーヴたち
ワベの中でジャイアし、ジンブルする。
ボロゴーヴはみなミムジイ、
そしてモームなラースがアウトグレイブする。
「ジャバウォックに気をつけよ、我が子よ!
噛みつく顎、捕らえる鉤爪!
ジャブジャブ鳥に用心し、かのフューミアスな
バンダースナッチを避けるのだ!」
彼はヴォーパルの剣を手に取り、
長きにわたりマンクスサムな敵を探し求めた――
やがてタムタムの木のそばで休み、
しばし物思いにふけりて立ちつくす。
彼がアフィッシュな思いに沈み佇むとき、
炎の眼持つジャバウォックが、
タルジイの森をヒューヒューと通り抜け、
ブクブクと音を立ててやってきた!
一、二! 一、二! そしてズバッズバッ!
ヴォーパルの刃がスニッカースナックと閃いた!
彼はそれを死なせておき、その首を手に、
意気揚々とギャランフィングして帰っていった。
「そして汝はジャバウォックを討ち取ったか?
我が腕の中へ来たれ、我が輝く少年よ!
おお、フラブジャスな日よ! カルー! カレイ!」
彼は喜びにチョートルした。
ブリリグの刻、ぬらやかなトーヴたち
ワベの中でジャイアし、ジンブルする。
ボロゴーヴはみなミムジイ、
そしてモームなラースがアウトグレイブする。
「とてもきれいみたいね」と彼女は読み終えて言いました。「でも、理解するのはちょっと難しいわ!」(ご覧の通り、彼女は全く意味が分からないということを、自分自身にさえ認めたくなかったのです。)「なんだか頭の中にいろんな考えが浮かんでくるみたい――ただ、それが何なのかはっきりとは分からないの! でも、誰かが何かを殺したことは確かね、とにかく――」
「でも、ああ!」とアリスはふと立ち上がって思いました。「急がないと、おうちの残りの部分がどんなふうか見る前に、鏡を通り抜けて帰らなくちゃいけなくなるわ! まずはお庭を見てみましょう!」彼女は一瞬で部屋を出て、階段を駆け下りました――というか、正確には走ったのではなく、アリスが独り言で言ったように、階段を速く楽に下りるための、彼女の新しい発明でした。彼女はただ指先を手すりに置いたまま、足で階段に触れることさえなく、ふわりと優雅に下りていきました。それからホールをふわりと通り抜け、そのままドアからまっすぐ外に出てしまうところでしたが、ドアの柱につかまらなかったら、そうなっていたでしょう。空中をそんなにたくさん浮遊したので少しめまいがして、再び普通に歩けるようになったことをむしろ嬉しく思いました。
第二章 生きた花のお庭
「あの丘のてっぺんまで行けたら、お庭がもっとよく見えるはずだわ」とアリスは独り言を言いました。「そして、ここにまっすぐそこへ続く小道がある――少なくとも、いいえ、そうじゃないわ――」(小道に沿って数ヤード進み、何度か急な角を曲がった後で)「でも、最後にはたどり着くでしょう。でも、なんて奇妙に曲がりくねっているのかしら! 小道というよりコルク抜きみたい! さて、この角を曲がれば丘へ行けるはず――いいえ、行けないわ! これはまっすぐおうちに戻ってしまう! それじゃあ、反対側を試してみましょう。」
そして彼女はその通りにしました。あちこちさまよい、次から次へと角を曲がってみましたが、何をしてもいつもおうちに戻ってきてしまうのです。実際、一度、いつもより少し速く角を曲がったときには、止まる前におうちにぶつかってしまいました。
「話しても無駄よ」とアリスはおうちを見上げ、まるでおうちが自分と議論しているかのように装って言いました。「まだ中には入らないわ。入ったらまた鏡を通り抜けて――元の部屋に戻らなくちゃいけなくなるって知ってるもの。そしたら私の冒険も全部おしまいよ!」
そこで、きっぱりとおうちに背を向けて、彼女は再び小道を進み始めました。丘に着くまでまっすぐ進み続けると心に決めて。数分間はすべて順調で、彼女がちょうど「今度こそ本当にやり遂げるわ――」と言ったとき、小道が突然ぐにゃりと曲がって、身震いし(と彼女は後で説明しました)、次の瞬間、彼女は実際にドアから中へ入っていく自分に気づきました。
「ああ、ひどすぎるわ!」と彼女は叫びました。「こんなに邪魔になるおうち、見たことないわ! 絶対に!」
しかし、丘はすぐそこに見えていましたから、もう一度始めるしかありませんでした。今度は大きな花壇に出くわしました。そこにはヒナギクの縁取りがあり、真ん中には柳の木が生えていました。
「ああ、オニユリさん」とアリスは、風に優雅に揺れている一本に話しかけました。「あなたが話せたらいいのに!」
「話せますとも」とオニユリは言いました。「話す価値のある相手がいるときにはね。」
アリスはあまりに驚いて、一分間も口がきけませんでした。すっかり息をのんでしまったようでした。やがて、オニユリがただ揺れ続けているだけだったので、彼女は再び、臆病な声で――ほとんどささやき声で――話しました。「それで、すべてのお花が話せるのですか?」
「あなたと同じくらい上手にね」とオニユリは言いました。「それに、ずっと大きな声で。」
「私たちから話しかけるのは礼儀に反しますからね」とバラが言いました。「それで、いつあなたが話しかけてくれるのかしらと、本当に不思議に思っていたところよ! 自分にこう言ったの。『あのお顔にはそれなりに分別がありそうだわ、利口そうではないけれど!』それでも、あなたはちゃんとした色をしているし、それはとても大事なことよ。」
「色のことなんて気にしないわ」とオニユリが言いました。「あの子の花びらがもう少しだけカールしていれば、申し分ないのだけれど。」
アリスは批評されるのが好きではなかったので、質問を始めました。「ここに植えられていて、誰も世話をしてくれる人がいなくて、時々怖くなったりしませんか?」
「真ん中に木があるじゃない」とバラは言いました。「他に何のためにあるというの?」
「でも、もし何か危険が迫ったら、木に何ができるのですか?」とアリスは尋ねました。
「『バウワウ!』って言うのよ!」と一輪のヒナギクが叫びました。「だから枝は『バウ』って呼ばれるのよ!」[訳注:英語の bough(大枝)と犬の鳴き声 bow-wow をかけた駄洒落。]
「それも知らなかったの?」と別のヒナギクが叫び、するとみんなが一斉に叫び始め、あたりは甲高い小さな声でいっぱいになったようでした。「みんな、静かになさい!」とオニユリが叫び、興奮で震えながら、情熱的に体を左右に揺らしました。「私が手を出せないと知っているのよ!」と、震える頭をアリスの方へ傾けながら、ぜいぜい言いました。「でなければ、あんな真似はできないはずよ!」
「気にしないで!」アリスはなだめるような口調で言い、ちょうどまた騒ぎ始めたヒナギクたちにかがみこむと、ささやきました。「もしお口を閉じていないなら、あなたたちを摘んでしまうわよ!」
一瞬で静かになり、ピンクのヒナギクのいくつかが白くなりました。
「それでいいのよ!」とオニユリは言いました。「ヒナギクが一番始末に負えないわ。一輪が話し始めると、みんな一斉に始めるんだから。あの子たちのやり方を聞いていると、こっちがしおれてしまうわ!」
「どうして皆さんはそんなに素敵にお話ができるのですか?」とアリスはお世辞を言って機嫌を直してもらおうと思いながら言いました。「私はこれまでたくさんの庭に行ったことがありますけど、どのお花も話せませんでしたわ。」
「手を下ろして、地面を触ってみなさい」とオニユリは言いました。「そうすれば理由がわかるわ。」
アリスはそうしました。「とても硬いわ」と彼女は言いました。「でも、それがこれと何の関係があるのか分かりません。」
「ほとんどの庭ではね」とオニユリは言いました。「花壇を柔らかくしすぎるの。だからお花たちはいつも眠っているのよ。」
これはとてももっともな理由に聞こえ、アリスはそれを知ってすっかり嬉しくなりました。「そんなこと、今まで考えたこともなかったわ!」と彼女は言いました。
「私の意見では、あなたは全く何も考えないのよ」とバラが、かなり厳しい口調で言いました。
「あんなに間抜けそうな顔をした人は見たことがないわ」とスミレが言いました。あまりに突然だったので、アリスは本当に飛び上がりました。それまで一言も話していなかったのですから。
「お黙りなさい!」とオニユリが叫びました。「まるであなたが誰かを見たことがあるみたいに! あなたは葉っぱの下に頭を隠して、そこでいびきをかいているだけじゃないの。世の中で何が起こっているかなんて、まるでつぼみみたいに何も知らないくせに!」
「このお庭には私の他にまだ人がいますか?」とアリスは、バラの最後の言葉を気にしないことにして言いました。
「この庭には、あなたのように動き回れる花がもう一つあるわ」とバラは言いました。「どうやってそうするのかしら――」(「あなたはいつも不思議に思ってばかりね」とオニユリが言いました)「でも、その子はあなたよりずっとふさふさしているわ。」
「私に似ていますか?」とアリスは熱心に尋ねました。というのも、「庭のどこかに、もう一人小さな女の子がいるんだわ!」という考えが心をよぎったからです。
「そうね、あなたと同じ不格好な形をしているわ」とバラは言いました。「でも、もっと赤くて――花びらはもっと短いと思うわ。」
「あの子の花びらは、ダリアみたいにきっちりまとまっているのよ」とオニユリが口をはさみました。「あなたみたいに、めちゃくちゃに散らかってはいないわ。」
「でも、それはあなたのせいじゃないわ」とバラは親切に付け加えました。「あなたはしおれ始めているのよ、わかるでしょう。そうすると、花びらが少しだらしなくなるのは仕方がないことなの。」
アリスはこの考えが全く気に入りませんでした。そこで、話題を変えるために、「その子は時々ここに来るのですか?」と尋ねました。
「じきに会えるでしょうよ」とバラは言いました。「あの子はとげのある種類なの。」
「どこにとげを生やしているのですか?」とアリスはいくらか好奇心をもって尋ねました。
「もちろん、頭の周り中に決まっているじゃない」とバラは答えました。「あなたもいくつか持っていないのかしらと不思議に思っていたところよ。それが普通の決まりだと思っていたわ。」
「あの子が来るわ!」とヒエンソウが叫びました。「足音が聞こえる、砂利道を、トントン、トントンって!」
アリスは熱心に周りを見回し、それが赤の女王であることに気づきました。「ずいぶん大きくなったわ!」というのが彼女の最初の感想でした。確かにその通りでした。アリスが最初に灰の中で彼女を見つけたとき、彼女はわずか三インチの高さしかありませんでした――そして今ここにいる彼女は、アリス自身より頭半分も背が高かったのです!
「新鮮な空気のおかげよ」とバラは言いました。「ここの空気は素晴らしく良いもの。」
「会いに行ってみようかしら」とアリスは言いました。というのも、花たちも十分に面白かったのですが、本物の女王様とお話をするほうがずっと素敵だろうと感じたからです。
「そんなこと、絶対にできませんわ」とバラは言いました。「私なら反対方向に歩くことをお勧めします。」
これはアリスにはばかげたことに聞こえたので、彼女は何も言わず、すぐに赤の女王の方へ出発しました。驚いたことに、彼女は一瞬で女王を見失い、再び正面玄関から入っていく自分に気づきました。
少し腹を立てて、彼女は引き返し、女王をあちこち探した後(とうとう遠くに見つけ出しました)、今度は反対方向に歩くという計画を試してみようと思いました。
それは見事に成功しました。一分も歩かないうちに、彼女は赤の女王と顔を合わせ、ずっと目指していた丘もすぐそこに見えました。
「どこから来たのです?」と赤の女王は言いました。「そしてどこへ行くの? 顔を上げて、丁寧にお話しなさい。そして、いつも指をもじもじさせるのはやめなさい。」
アリスはこれらの指示すべてに従い、できるだけ上手に、道に迷ったのだと説明しました。
「あなたの道というのが何を意味するのか分かりませんわ」と女王は言いました。「このあたりの道はすべてわたくしのものですからね。でも、そもそもなぜここへ出てきたのです?」と彼女はより親切な口調で付け加えました。「何を言うか考えている間にお辞儀をなさい、時間の節約になりますわ。」
アリスはこれに少し驚きましたが、女王をあまりに畏れていたので、それを疑うことはできませんでした。「おうちに帰ったら試してみよう」と彼女は独り言を思いました。「次に夕食に少し遅れたときにね。」
「もうあなたが答える時間ですわ」と女王は時計を見ながら言いました。「話すときは口をもう少し大きく開けて、そして常に『陛下』と言いなさい。」
「私はただ、お庭がどんなものか見てみたかっただけです、陛下――」
「よろしい」と女王は言い、アリスの頭を撫でました。アリスはそれが全く気に入りませんでした。「もっとも、あなたが『庭』とおっしゃいますが――わたくしが見てきた庭に比べれば、こんなものは荒れ地も同然ですわ。」
アリスはあえてその点について議論しようとはせず、続けました。「――そして、あの丘のてっぺんまでの道を見つけようと思ったのです――」
「あなたが『丘』とおっしゃいますが」と女王がさえぎりました。「わたくしなら、あなたがそれを谷と呼ぶであろう丘をお見せできますわ。」
「いいえ、そんなことはありませんわ」とアリスは、とうとう反論せずにはいられなくなって言いました。「丘が谷になるなんてありえませんわ、ご存じでしょう。そんなのでたらめですもの――」
赤の女王は首を振りました。「お好きなら『でたらめ』と呼んでもよろしいですが」と彼女は言いました。「わたくしが聞いてきたでたらめに比べれば、そんなものは辞書のように筋が通っていますわ!」
アリスは再びお辞儀をしました。女王の口調から、彼女が少し気分を害したのではないかと心配になったからです。そして、彼女たちは小さな丘のてっぺんに着くまで、黙って歩き続けました。
数分間、アリスは何も言わずに立ち、国中をあらゆる方向に見渡していました――そして、それは実に奇妙な国でした。たくさんの小さな小川がまっすぐに国を横切って端から端まで流れており、その間の地面は、小川から小川まで続くたくさんの小さな緑の生け垣によって、四角いマス目に区切られていました。
「まるで大きなチェス盤みたいに区切られているわ!」とアリスはとうとう言いました。「どこかに動いている駒がいるはずだわ――そして、本当にいるわ!」と彼女は喜びの声をあげ、興奮で心臓がどきどきし始めました。「これは壮大なチェスのゲームが繰り広げられているのよ――全世界でね。もしここが本当に世界なら、だけど。ああ、なんて面白いのかしら! 私もその一人だったらどんなにいいでしょう! 仲間に入れるなら、ポーンでも構わないわ。もちろん、一番なりたいのは女王様だけど。」
彼女はこう言いながら、本物の女王を少し恥ずかしそうにちらりと見ましたが、連れの女王はただ楽しそうに微笑み、「それは簡単ですわ。リリーはまだ遊ぶには若すぎるから、あなたが白の女王のポーンになればいいのよ。それに、あなたは最初から二番目のマスにいるわ。八番目のマスに着けば、あなたは女王様になるのよ――」ちょうどその瞬間、どういうわけか、彼女たちは走り始めました。
アリスは後になって考えてみても、どうして走り始めたのか、全く理解できませんでした。彼女が覚えているのは、手をつないで走っていて、女王があまりに速いので、ついていくのがやっとだったことだけです。それでも女王は「もっと速く! もっと速く!」と叫び続けましたが、アリスはもうそれ以上速く走れないと感じていました。それを言う息も残っていませんでしたが。
このことで最も奇妙だったのは、木々や周りの他のものが全く場所を変えなかったことです。どんなに速く走っても、何も通り過ぎることがないように思えました。「もしかして、すべてのものが私たちと一緒に動いているのかしら?」と、かわいそうな、途方に暮れたアリスは思いました。そして女王は彼女の考えを察したかのように叫びました。「もっと速く! 話そうとしないで!」
アリスにそんな気は少しもありませんでした。あまりに息が切れて、もう二度と話すことなどできないだろうと感じていました。それでも女王は「もっと速く! もっと速く!」と叫び、彼女を引っ張っていきました。「もうすぐ着きますか?」とアリスはとうとう何とか息を切らしながら言いました。
「もうすぐですって!」と女王は繰り返しました。「あら、十分前に通り過ぎましたわよ! もっと速く!」そして彼女たちはしばらく黙って走り続けました。アリスの耳元で風がヒューヒューと鳴り、髪が頭から吹き飛ばされそうだと彼女は思いました。
「さあ! さあ!」と女王が叫びました。「もっと速く! もっと速く!」そして彼女たちはあまりに速く進んだので、とうとう空中を滑るように、ほとんど足が地面に触れないほどになりました。そして突然、アリスがすっかり疲れ果てたちょうどその時、彼女たちは立ち止まり、気づくと彼女は地面に座り込み、息も絶え絶えで、めまいがしていました。
女王は彼女を木にもたれさせ、親切に言いました。「今は少し休んでもよろしいわ。」
アリスは大変驚いて周りを見回しました。「あら、まあ、私たち、ずっとこの木の下にいたみたい! すべてが元のままよ!」
「もちろんそうですわ」と女王は言いました。「そうでなくてどうなるというの?」
「ええと、私たちの国では」とアリスは、まだ少し息を切らしながら言いました。「私たちが今したように、長い間とても速く走ったら、普通はどこか別の場所に着くものなのです。」
「のろまな国ですこと!」と女王は言いました。「さあ、ここではね、ご覧なさい、同じ場所にとどまるためには、あなたにできる全力で走らなければならないの。どこか別の場所へ行きたいなら、少なくともその倍の速さで走らなくては!」
「試したくはありませんわ、どうか!」とアリスは言いました。「私はここにいるだけで十分満足です。ただ、とても暑くて喉が渇いているだけです!」
「あなたが何を欲しがっているか分かりますわ!」と女王は機嫌よく言い、ポケットから小さな箱を取り出しました。「ビスケットはいかが?」
アリスは、全く欲しいものではありませんでしたが、「いいえ」と言うのは失礼だろうと思いました。そこでそれを受け取り、できるだけ食べました。それはとても乾いていて、彼女は生まれてこのかた、こんなに喉が詰まりそうになったことはないと思いました。
「あなたが元気を取り戻している間に」と女王は言いました。「わたくしは寸法を測りますわ」そして彼女はインチで目盛りがついたリボンをポケットから取り出し、地面を測り始め、あちこちに小さな杭を打ち込みました。
「二ヤード先で」と彼女は距離を示すために杭を打ち込みながら言いました。「あなたに指示を与えますわ。もう一枚ビスケットはいかが?」
「いいえ、結構です」とアリスは言いました。「一枚で十分です!」
「喉の渇きは癒えましたかしら?」と女王は言いました。
アリスはこれに何と答えてよいか分かりませんでしたが、幸いにも女王は答えを待たずに続けました。「三ヤード先で、それを繰り返しますわ。あなたが忘れないようにね。四ヤード先で、さよならを言います。そして五ヤード先で、わたくしは行きますわ!」
彼女はこの時までにすべての杭を打ち終えていました。アリスが大変興味深げに見ていると、彼女は木に戻り、それからゆっくりと列を歩き始めました。
二ヤード目の杭で彼女はくるりと向きを変え、言いました。「ポーンは最初の一手で二マス進むのよ、ご存じでしょう。だからあなたはとても速く三番目のマスを通り抜けるでしょう。鉄道で、かしらね。そしてあっという間に四番目のマスに着くわ。さて、そのマスはトゥイードルダムとトゥイードルディーのものよ。五番目はほとんど水。六番目はハンプティ・ダンプティのもの。でも、何も感想はないの?」
「わ、私は――その時、何か言わなければいけないとは知りませんでした」とアリスは口ごもりました。
「あなたは『こんなにいろいろ教えていただいて、ご親切にどうもありがとうございます』と言うべきでしたわ。でもまあ、言ったことにしておきましょう。七番目のマスはすべて森よ。でも、騎士の一人が道を教えてくれるでしょう。そして八番目のマスでは、私たちは一緒に女王様になって、ごちそうと楽しみがいっぱいよ!」アリスは立ち上がってお辞儀をし、再び座りました。
次の杭で女王は再び向きを変え、今度はこう言いました。「英語で何というか思いつかないときはフランス語で話しなさい。歩くときはつま先を外側に向けなさい。そして、自分が誰であるかを忘れずに!」彼女は今度はアリスがお辞儀をするのを待たずに、さっさと次の杭へ歩いていき、そこで一瞬振り向いて「さようなら」と言い、それから最後の杭へと急ぎました。
どうしてそうなったのか、アリスには全く分かりませんでしたが、ちょうど彼女が最後の杭に着いたとたん、女王はいなくなっていました。彼女が空気の中に消えたのか、それとも森の中へ素早く走り去ったのか(「そして彼女はとても速く走れるんだわ!」とアリスは思いました)、推測する術はありませんでしたが、彼女はいなくなり、アリスは自分がポーンであること、そしてもうすぐ自分が動く番になることを思い出し始めました。
第三章 鏡の国の虫たち
もちろん、最初にすべきことは、これから旅する国を壮大に測量することでした。「なんだか地理を習うのととても似ているわ」とアリスは、もう少し遠くまで見えないかと期待してつま先立ちになりながら思いました。「主要な川――一つもないわ。主要な山――私がいるのが唯一の山だけど、名前はないみたい。主要な町――あら、あそこにいる、蜜を作っている生き物は何かしら? ハチのはずがないわ。一マイルも離れたところにいるハチなんて、誰も見たことがないもの、ご存じでしょう――」そしてしばらくの間、彼女は黙って立ち、そのうちの一匹が花々の間で忙しそうに動き回り、口吻を花に突き刺しているのを見ていました。「まるで普通のハチみたいだわ」とアリスは思いました。
しかし、これは普通のハチとは全く違うものでした。実際にはゾウだったのです。アリスはすぐにそれに気づきましたが、最初はその考えにすっかり息をのんでしまいました。「そして、なんて巨大な花々なんでしょう!」というのが彼女の次の考えでした。「屋根を取り払って茎をつけたコテージみたいだわ。そして、どれほどの量の蜜を作るのかしら! 下りて行って――いいえ、まだやめておきましょう」と彼女は、丘を駆け下り始めようとした自分を制し、突然内気になったことへの言い訳を探そうとしながら続けました。「あの子たちを追い払うための長い枝もなしに、あの中へ下りていくなんて絶対だめだわ。そして、散歩はどうだったって聞かれたら、なんて面白いでしょう。こう言うのよ――『ああ、まあまあ楽しかったわ――』」(ここでお得意の、軽く頭をかしげる仕草)「『ただ、とてもほこりっぽくて暑かったし、ゾウたちがとてもうるさかったの!』。」
「反対側を下りてみましょう」と彼女は少し間を置いて言いました。「そして、もしかしたら後でゾウたちを訪ねるかもしれないわ。それに、三番目のマスにどうしても入りたいんだもの!」
そこで、この言い訳とともに彼女は丘を駆け下り、六つの小さな小川の最初の一つを飛び越えました。
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
「切符を拝見!」と車掌が言い、窓から頭を突き出しました。一瞬のうちに、誰もが切符を差し出しました。切符は人々とほぼ同じ大きさで、客車をすっかり満たしているように見えました。
「さあ! 切符を見せなさい、お嬢さん!」と車掌はアリスを怒ったように見ながら続けました。そしてたくさんの声が一斉に言いました(「まるで歌のコーラスみたいだわ」とアリスは思いました)。「あの方を待たせるな、お嬢さん! なあに、あの方の時間は一分千ポンドの価値があるんだぞ!」
「申し訳ありませんが、持っていません」とアリスは怯えた声で言いました。「私が来たところには切符売り場がありませんでした」そして再び声のコーラスが続きました。「彼女が来たところには切符売り場の場所がなかったんだ。そこの土地は一インチ千ポンドの価値があるんだ!」
「言い訳をするな」と車掌は言いました。「機関士から買うべきだったんだ」そしてもう一度、声のコーラスが続きました。「機関を動かす男だよ。なあに、煙だけでも一吹き千ポンドの価値があるんだ!」
アリスは独り言を思いました。「それじゃあ、話しても無駄ね」彼女が話さなかったので、今度は声は加わりませんでしたが、大変驚いたことに、みんながコーラスで考えたのです(コーラスで考えるというのがどういう意味か、皆さんが理解してくださるといいのですが――実を言うと、私には分からないのです)。「何も言わないのが一番だ。言葉は一言千ポンドの価値があるのだから!」
「今夜は千ポンドの夢を見るわ、きっとそうよ!」とアリスは思いました。
この間ずっと、車掌は彼女を見ていました。最初は望遠鏡で、次に顕微鏡で、そしてオペラグラスで。最後に彼は言いました。「あなたは進行方向と逆向きに進んでいますね」そして窓を閉めて去って行きました。
「こんなに幼い子供なら」と彼女の向かいに座っていた紳士(彼は白い紙の服を着ていました)が言いました。「たとえ自分の名前を知らなくても、どちらへ向かっているかは知っているべきですよ!」
白い服の紳士の隣に座っていたヤギが、目を閉じて大声で言いました。「たとえアルファベットを知らなくても、切符売り場への道は知っているべきだ!」
ヤギの隣には甲虫が座っていました(それは全くもって奇妙な乗客で満員の客車でした)。そして、全員が順番に話すのが決まりのようだったので、彼はこう続けました。「彼女はここから手荷物として戻らなければならなくなるだろう!」
アリスには甲虫の向こうに誰が座っているのか見えませんでしたが、しゃがれた声が次に話しました。「機関車を交換――」とその声は言い、そこでやめざるを得ませんでした。
「馬みたいに聞こえるわ」とアリスは独り言を思いました。すると、彼女の耳元で、非常に小さな声が言いました。「それについてジョークが言えますね。『馬』と『声が嗄れた』[訳注:英語の horse と hoarse は同じ発音]で何か、ご存じでしょう。」
それから、遠くでとても優しい声が言いました。「彼女には『乙女、取り扱い注意』と札をつけなければなりませんね、ご存じでしょう――」
そしてその後、他の声が続きました(「この客車にはなんてたくさんの人がいるのかしら!」とアリスは思いました)。「彼女は頭がついているから、郵便で送らなければ――」「電報でメッセージとして送らなければ――」「残りの道は自分で列車を引かなければ――」などなど。
しかし、白い紙の服を着た紳士が身を乗り出し、彼女の耳にささやきました。「みんなが何を言おうと気にしないで、お嬢さん。列車が止まるたびに往復切符を買いなさい。」
「絶対に嫌ですわ!」とアリスは少し苛立って言いました。「私はこの鉄道の旅とは全く関係ないんですもの。さっきまで森にいたんです。そして、そこへ戻れたらいいのにって思っています。」
「それについてジョークが言えますね」と小さな声が彼女の耳元で言いました。「『できればそうしたいでしょうね』[訳注:英語の would(~したいだろう)と wood(森)をかけた駄洒落]で何か、ご存じでしょう。」
「そんなにからかわないで」とアリスは、声の主がどこにいるのか見つけようとしましたが無駄でした。「そんなにジョークを言ってもらいたいなら、どうしてご自分で言わないのですか?」
その小さな声は深くため息をつきました。明らかにとても不幸なようでした。アリスはそれを慰めるために何か同情的なことを言ったでしょう。「もし、他の人たちみたいにため息をついてくれたら!」と彼女は思いました。しかし、これはあまりにも驚くほど小さなため息だったので、もしそれが彼女の耳のすぐそばでなければ、全く聞こえなかったでしょう。その結果、彼女の耳はとてもくすぐったくなり、かわいそうな小さな生き物の不幸からすっかり気をそらされてしまいました。
「あなたが友達であることは知っています」とその小さな声は続けました。「親愛なる友、そして旧友です。そして、たとえ私が虫であっても、あなたは私を傷つけないでしょう。」
「どんな種類の虫ですか?」とアリスは少し心配そうに尋ねました。彼女が本当に知りたかったのは、それが刺すかどうかということでしたが、それを尋ねるのはあまり礼儀正しい質問ではないだろうと思いました。
「えっ、ではあなたは――」と小さな声が言い始めたとき、それは機関車からの甲高い悲鳴にかき消され、誰もが驚いて飛び上がりました。アリスもその一人でした。
窓から頭を出していた馬が、静かにそれを引っ込めて言いました。「ただの小川を飛び越えるだけですよ」誰もがこれで満足したようでしたが、アリスは列車が飛び跳ねるという考えに少し不安を感じました。「でも、これで四番目のマスに入れるわ、それは少しは慰めになるわね!」と彼女は独り言を言いました。次の瞬間、彼女は客車がまっすぐ空中に上がるのを感じ、恐怖のあまり、一番近くにあったもの、たまたまそれはヤギのひげでしたが、それにつかまりました。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ところが、そのあごひげは彼女が触れると溶けるように消えてしまい、気がつくとアリスは木の下に静かに座っていました――そしてブヨ(それが彼女が話していた虫だったのでした)が、ちょうど彼女の頭上の小枝でバランスをとりながら、その羽で彼女をあおいでいたのです。
それは確かにとても大きなブヨでした。「ニワトリくらいの大きさだわ」とアリスは思いました。それでも、あれほど長く一緒に話した後では、怖さは感じませんでした。
「――では、あなたは昆虫がみんな好きというわけではないのですね?」とブヨは、何事もなかったかのように静かに続けました。
「お話ができる昆虫は好きですわ」とアリスは言いました。「わたくしのいた所では、お話をする昆虫なんて一匹もいませんもの。」
「あなたのいた所では、どのような昆虫を喜ばれるのですか?」とブヨは尋ねました。
「わたくし、昆虫を喜んだりはしませんの」とアリスは説明しました。「どちらかというと怖いですから――少なくとも大きい種類は。でも、いくつか名前は言えますわ。」
「もちろん、その名前で呼ばれれば返事をしますよね?」とブヨは無頓着に言いました。
「そんなことするなんて、聞いたことがありませんわ。」
「名前で呼ばれても返事をしないのなら、名前がある意味はなんなのです?」とブヨは言いました。
「彼らにとっては意味はありませんわ」とアリスは言いました。「でも、名前をつけた人たちには役立つのでしょうね。そうでなければ、なぜ物には名前があるのかしら?」
「さあ、何とも言えませんね」とブヨは答えました。「この先、あそこの森の中では、彼らには名前がありません――とにかく、昆虫のリストを続けてください。時間を無駄にしていますよ。」
「ええと、アブがいますわ」アリスは指で名前を数えながら始めました。
「よろしい」とブヨは言いました。「あの茂みの中ほどに、よく見れば木馬バエがいますよ。全体が木でできていて、枝から枝へと揺れながら移動するのです。」
「何を食べて生きているのですか?」アリスは大変な好奇心をもって尋ねました。
「樹液とおがくずですよ」とブヨは言いました。「リストを続けてください。」
アリスは木馬バエを大変興味深げに見上げ、きっと塗り直されたばかりに違いないと思いました。とても鮮やかで、べたべたして見えたからです。そして彼女は続けました。
「それから、トンボがいますわ。」
「あなたの頭上の枝を見てごらんなさい」とブヨは言いました。「そこにはスナップドラゴンフライがいますよ。体はプラムプディングで、羽はヒイラギの葉、そして頭はブランデーで燃えるレーズンでできています。」
「そして、それは何を食べて生きているのですか?」
「フラーマリーとミンスパイです」とブヨは答えました。「そしてクリスマスボックスの中に巣を作るのです。」
「それから、チョウがいますわ」とアリスは続けました。頭が燃えているその昆虫をよく見た後で、こう独り言を思っていました。「昆虫がロウソクに飛び込むのがあんなに好きなのは、スナップドラゴンフライになりたいからなのかしら!」
「あなたの足元を這っていますよ」とブヨが言いました(アリスは少し驚いて足を引っこめました)。「パンとバターフライが観察できます。その羽は薄切りのパンとバターで、体はパンの耳、そして頭は角砂糖です。」
「そして、それは何を食べて生きているのですか?」
「クリーム入りの薄い紅茶です。」
新たな難問がアリスの頭に浮かびました。「もしそれが見つけられなかったらどうなるのかしら?」と彼女は提案しました。
「もちろん、死んでしまいますよ。」
「でも、そんなことはしょっちゅう起こるに違いありませんわ」アリスは考え深げに言いました。
「いつも起こります」とブヨは言いました。
この後、アリスは一、二分、考え込んで黙っていました。その間、ブヨは彼女の頭の周りをぶんぶん飛び回って楽しんでいました。やがて再び止まると、こう言いました。「あなたは自分の名前を失いたくはないでしょうね?」
「ええ、もちろん」アリスは少し心配そうに言いました。
「それでも、どうでしょうね」とブヨは無頓着な口調で続けました。「もし名前なしで家に帰ることができたら、どんなに便利か考えてもごらんなさい! 例えば、家庭教師があなたをお稽古に呼びたいとき、『こっちへいらっしゃい――』と呼びかけ、そこでやめざるを得なくなるでしょう。だって呼ぶべき名前がないのですから。そしてもちろん、あなたは行かなくて済むわけです、ね?」
「そんなの絶対にだめですわ、きっと」とアリスは言いました。「家庭教師がそんな理由でお稽古を免除してくれるなんて、思いもしませんわ。もしわたくしの名前を思い出せなかったら、使用人たちみたいに『お嬢様!』と呼ぶでしょうね。」
「ふむ、もしあちらが『ミス』と言って、それ以上何も言わなかったら」とブヨは言いました。「もちろん君はお稽古を『ミス』するわけだね。これはジョークだよ。君が言ってくれればよかったのに。」
「どうしてわたくしが言えばよかったなんて思うのですか?」アリスは尋ねました。「とてもつまらないジョークですわ。」
しかし、ブヨはただ深くため息をつくだけで、その頬を二つの大きな涙が伝い落ちてきました。
「そんなに悲しくなるのなら、ジョークなんて言うべきではありませんわ」とアリスは言いました。
すると、またあの憂鬱な小さいため息が一つ聞こえました。そして今度は、哀れなブヨは本当にため息とともに消えてしまったようでした。アリスが見上げると、小枝の上には何一つ見当たらなかったのです。そして、あまりに長くじっと座っていたのですっかり肌寒くなってきたので、彼女は立ち上がって歩き出しました。
彼女はすぐに開けた野原に出ました。その向こう側には森がありました。それは先ほどの森よりもずっと暗く見え、アリスはそこに入るのが少し怖くなりました。しかし、考え直して、進む決心をしました。「だって、絶対に引き返したりはしないわ」と彼女は心の中で思いました。そして、これが第八マスへ行く唯一の道だったのです。
「ここがきっと、物には名前がないという森なのね」と彼女は考え深げに独り言を言いました。「中に入ったら、わたくしの名前はどうなるのかしら? 全然失いたくはないわ――だって、そしたら別の名前をつけられることになるでしょうし、それはほとんど間違いなく醜い名前になるわ。でも、そうしたら、わたくしの元の名前を持っていった生き物を見つけようとするのが楽しみになるかも! ほら、まるで広告みたいにね、人々が犬を失くしたときの――『「ダッシュ」という名前にて応答。真鍮の首輪を着用』――会うものすべてに『アリス』って呼びかけて、そのうちの一匹が返事をするなんて想像してみて! もっとも、もし賢ければ、彼らは全然返事をしないでしょうけど。」
彼女はこんなふうにぶつぶつ言いながら歩いているうちに、森に着きました。そこはとても涼しくて日陰になっていました。「まあ、とにかくこれは大きな慰めだわ」と彼女は木々の下へ足を踏み入れながら言いました。「あんなに暑かった後で、――の中に入るなんて、――何の中へ?」彼女は言葉が思い浮かばないことに少し驚いて続けました。「つまり、――の下へ、――の下へ、――これの下へ入るってことよ、ね!」と木の幹に手を置きました。「これはいったい自分を何と呼ぶのかしら? きっと名前がないんだわ――あら、本当にそうよ!」
彼女は一分ほど黙って考え込んでいましたが、やがて突然また話し始めました。「じゃあ、本当に起こってしまったのね、結局! それで、今、わたくしは誰? 思い出すわ、もしできるなら! 絶対にやってみせるわ!」しかし、決意を固めてもあまり役には立たず、ずいぶん頭を悩ませた後で彼女が言えたのは、「エ、確かエで始まるはず!」ということだけでした。
ちょうどその時、一頭の子鹿がぶらぶらと通りかかりました。それは大きく優しい目でアリスを見ましたが、少しも怖がっているようには見えませんでした。「こっちへ! こっちへ!」アリスは手を差し出して、それを撫でようとしながら言いました。しかし、子鹿は少し後ろに下がっただけで、またアリスを見つめて立っていました。
「あなたの名前は何て言うの?」と子鹿はついに言いました。なんて柔らかく甘い声でしょう!
「わかればいいのに!」と哀れなアリスは思いました。彼女は、少し悲しそうに答えました。「今は、何でもないの。」
「もう一度考えてみて」と子鹿は言いました。「それではだめだよ。」
アリスは考えましたが、何も思いつきませんでした。「お願い、あなたの名前を教えてくださらない?」と彼女はおずおずと言いました。「それが少しは助けになるかもしれません。」
「もう少し先へ行ったら教えてあげるよ」と子鹿は言いました。「ここでは思い出せないんだ。」
そこで彼らは一緒に森を歩きました。アリスは子鹿の柔らかい首に愛情を込めて腕を回し、やがて別の開けた野原に出ました。するとそこで、子鹿は突然空中に跳ね上がり、アリスの腕から自由になりました。「ぼくは子鹿だよ!」とそれは喜びの声で叫びました。「そして、まあ! 君は人間の子供だね!」その美しい茶色の目に突然警戒の色が浮かび、次の瞬間には全速力で走り去ってしまいました。
アリスはそれを見送りながら立っていました。あんなに愛らしい小さな旅の道連れを突然失った悔しさで、泣き出しそうでした。「でも、これで自分の名前がわかったわ」と彼女は言いました。「それはいくらか慰めになるわ。アリス――アリス――もう忘れないわ。さてと、これらの道しるべのどれに従うべきかしら?」
それは答えるのにさほど難しくない質問でした。森を通る道は一本しかなく、二つの道しるべは両方ともその道に沿って指し示していたからです。「道が分かれて、違う方向を指したときに決めることにするわ」とアリスは独り言を言いました。
しかし、そんなことは起こりそうにありませんでした。彼女はずっとずっと進みましたが、道が分かれるところには必ず同じ方向を指す二つの道しるべがあり、一つには「トゥイードルダムの家へ」、もう一つには「トゥイードルディーの家へ」と書かれていました。
「きっと、」とアリスはついに言いました。「二人は同じ家に住んでいるんだわ! どうして今まで気づかなかったのかしら――でも、長くは滞在できないわ。『こんにちは』って挨拶して、森から出る道を尋ねるだけにするわ。暗くなる前に第八マスに着ければいいのだけれど!」そうして彼女は独り言を言いながらぶらぶらと歩いていき、やがて急な角を曲がったところで、二人の太った小男にばったり出くわしました。あまりに突然だったので、思わず後ずさりしましたが、次の瞬間には気を取り直し、彼らがそうに違いないと確信しました。
第四章 トゥイードルダムとトゥイードルディー
彼らは木の下に立っており、それぞれがもう一方の首に腕を回していました。アリスはどちらがどちらかすぐに分かりました。なぜなら、片方の襟には「ダム」と刺繍されており、もう片方には「ディー」とあったからです。「きっと襟の後ろ側には、それぞれ『トゥイードル』と書いてあるのね」と彼女は独り言を言いました。
彼らはあまりにじっと立っていたので、彼女は彼らが生きていることをすっかり忘れてしまい、それぞれの襟の後ろに「トゥイードル」という言葉が書かれているか見ようと辺りを見回していたところ、「ダム」と印のついた方から声がして、はっとしました。
「わしらを蝋人形だと思うなら」と彼は言いました。「金を払うべきだぞ、いいな。蝋人形はただで見るために作られたんじゃない、ぜったいにな!」
「その逆なり」と「ディー」と印のついた方が付け加えました。「わしらが生きていると思うなら、話しかけるべきだ。」
「本当にごめんなさい」というのがアリスに言えるすべてでした。というのも、古い歌の言葉が時計の刻む音のように頭の中で鳴り響いていて、それを声に出して言わずにはいられなかったからです。
「トゥイードルダムとトゥイードルディー けんかをすることに決めた トゥイードルダム言うことにゃ、トゥイードルディーが 大事な新品ガラガラ壊したと。 そこへ飛んできた大きなカラス タールの樽ほど真っ黒け 二人の勇者を驚かせ すっかりけんかを忘れさせた。」
「君が何を考えているか知ってるぞ」とトゥイードルダムは言いました。「だが、そうじゃない、ぜったいにな。」
「その逆なり」とトゥイードルディーは続けました。「もしそうなら、そうかもしれない。そして、もしそうだったなら、そうだろう。だが、そうではないのだから、そうではない。これぞ論理学だ。」
「わたくしが考えておりましたのは」とアリスはとても丁寧に言いました。「この森から出る一番良い道はどちらかしら、ということですの。とても暗くなってきましたし。教えていただけますか、お願いです。」
しかし、小男たちはただお互いを見つめてにやりと笑うだけでした。
彼らはまるで二人の大きな男子生徒そっくりに見えたので、アリスは思わずトゥイードルダムに指をさして、「一番の子!」と言いました。
「ぜったいに違う!」とトゥイードルダムはきびきびと叫び、ぱちんと口を閉じました。
「次の子!」とアリスはトゥイードルディーに移りながら言いましたが、彼が「その逆なり!」と叫ぶだけだろうと確信しており、そしてその通りになりました。
「君は間違っている!」とトゥイードルダムは叫びました。「訪問で最初にやることは、『ごきげんよう』と言って握手をすることだ!」そしてここで二人の兄弟は互いに抱き合い、それから空いている二つの手を差し出して、彼女と握手をしようとしました。
アリスはどちらか一方と先に握手をするのが好きではありませんでした。もう一方の気持ちを傷つけるのを恐れたからです。そこで、この難局を乗り切る最善の方法として、彼女は両方の手を一度につかみました。次の瞬間、彼らは輪になって踊っていました。これはごく自然なことに思えました(と彼女は後で思い出しました)。そして音楽が流れてきても驚きさえしませんでした。それは彼らが踊っている木の下から聞こえてくるようで、それは(彼女が何とか聞き分けたところでは)枝と枝がこすれ合って、まるでバイオリンと弓のように奏でられていたのです。
「でも、確かにおかしかったわ」(とアリスは後で、このすべてのいきさつを姉に話していたとき言いました)「気がついたら『くわの木の周りをまわろうよ』を歌っていたんですもの。いつ歌い始めたのか分からないけど、なんだかずーっと長い間歌っていたような気がしたの!」
他の二人の踊り手は太っていて、すぐに息が切れました。「一回のダンスには四周で十分だ」とトゥイードルダムはぜいぜい言いながら言いました。そして彼らは始めたときと同じくらい突然に踊るのをやめました。音楽も同時に止まりました。
それから彼らはアリスの手を放し、一分ほど彼女を見つめて立っていました。少し気まずい沈黙がありました。アリスは、たった今一緒に踊ったばかりの人々とどう会話を始めたらよいか分からなかったからです。「今『ごきげんよう』なんて言ってもだめだわ」と彼女は独り言を言いました。「なんだかもう、その段階は通り越してしまったみたい!」
「あまりお疲れではないとよろしいのですが?」と彼女はついに言いました。
「ぜったいに。そして、お尋ねいただきとてもありがとうございます」とトゥイードルダムは言いました。
「たいへん恐縮です!」とトゥイードルディーが付け加えました。「詩はお好きですか?」
「は、はい、まあまあ――いくつかの詩は」とアリスはためらいがちに言いました。「森から出る道はどちらか教えていただけますか?」
「彼女に何を暗唱してやろうか?」とトゥイードルディーは、アリスの質問には気づかず、大きな真剣な目でトゥイードルダムを見回しながら言いました。
「『セイウチと大工』が一番長いぞ」とトゥイードルダムは答え、兄弟を愛情込めて抱きしめました。
トゥイードルディーは即座に始めました。
「太陽は輝いていた――」
ここでアリスは思い切って彼をさえぎりました。「もしとても長いのでしたら」と彼女はできるだけ丁寧に言いました。「先にどちらの道か教えていただけませんか――」
トゥイードルディーは優しく微笑み、再び始めました。
「太陽は海の上で輝いていた 力の限りを尽くして輝き 彼は懸命に努力していた 波を滑らかに、そして明るくしようと―― そしてこれは奇妙なことだった、なぜならそれは 真夜中のことだったから。 月は不機嫌そうに輝いていた なぜなら彼女は太陽が そこにいる資格はないと思ったから 一日が終わった後に―― 『彼はずいぶん失礼だわ』と彼女は言った 『やってきて楽しみを台無しにするなんて!』 海はこれ以上ないほど濡れていた 砂はこれ以上ないほど乾いていた。 雲一つ見えなかった、なぜなら 空に雲はなかったから。 頭上を飛ぶ鳥はいなかった―― 飛ぶべき鳥がいなかったから。 セイウチと大工は すぐそばを歩いていた。 彼らは何よりも激しく泣いた、見て こんなにも大量の砂を。 『これが片付けられさえすれば。』 彼らは言った、『素晴らしいだろうに!』 『もし七人のメイドが七つのモップで 半年間掃いたなら、 君は思うかね』とセイウチは言った 『きれいにできると?』 『疑わしいね』と大工は言った そして苦い涙を流した。 『おおカキたちよ、我らと歩こう!』 セイウチは懇願した。 『楽しい散歩、楽しいおしゃべり、 塩辛い浜辺に沿って。 我らは四人以上は連れていけない、 それぞれに手を貸すために。』 一番年上のカキは彼を見た。 しかし一言も言わなかった。 一番年上のカキは片目をつむり、 重い頭を振った―― 言わんとすることは、彼は選びたくない カキの寝床を離れることを。 しかし四匹の若いカキが急いでやってきた ごちそうを心待ちにして。 彼らのコートはブラシがかけられ、顔は洗われ、 靴はきれいでこざっぱり―― そしてこれは奇妙なことだった、なぜなら、ご存知の通り、 彼らには足がなかったから。 さらに四匹のカキが彼らに続いた そしてまたさらに四匹。 そして次から次へと彼らはやってきた、ついに もっと、もっと、もっと―― 皆、泡立つ波を飛び跳ね 岸へと這い上がった。 セイウチと大工は 一マイルほど歩いた そして彼らは岩の上で休んだ 都合よく低い岩の上で。 そして小さなカキたちは皆立って 一列に並んで待っていた。 『時は来たれり』とセイウチは言った 『多くのことを語る時が。 靴について――船について――封蝋について―― キャベツについて――王様について―― そしてなぜ海は煮え立つほど熱いのか―― そしてブタに羽があるかどうかについて。』 『でも少し待って』とカキたちは叫んだ 『おしゃべりをする前に。 わたしたちの何人かは息が切れていて そしてわたしたちは皆太っているから!』 『急ぐことはない!』と大工は言った。 彼らはそれに大いに感謝した。 『パンを一斤』とセイウチは言った 『それが我らに主に必要なものだ。 コショウと酢もまた 実に結構なものだ―― さて、もし準備ができたなら、親愛なるカキたちよ 食事を始めよう。』 『でもわたしたちを食べるのはなしよ!』とカキたちは叫んだ 少し青ざめて、 『こんな親切を受けた後で、そんなことをするのは 陰気なことでしょう!』 『夜は素晴らしい』とセイウチは言った 『景色を称賛するかね? 『来てくれて本当に親切だった! そして君たちはとても素敵だ!』 大工は何も言わず、ただ 『もう一切れ切ってくれ。 君がそんなに耳が遠くなければいいのだが―― 二度も頼まなければならなかった!』 『恥ずかしいことのようだ』とセイウチは言った 『彼らにこんな策略を弄するとは、 あんなに遠くまで連れ出して あんなに速く歩かせた後で!』 大工は何も言わず、ただ 『バターが厚く塗りすぎだ!』 『君たちのために泣いている』とセイウチは言った。 『深く同情するよ。』 すすり泣きと涙とともに彼は選び出した 一番大きなサイズのものを。 ポケットのハンカチをかざしながら 涙あふれる目の前に。 『おおカキたちよ』と大工は言った。 『楽しいお散歩だったね! また家までとことこ帰ろうか?』 しかし返事はなかった―― そしてそれはほとんど奇妙なことではなかった、なぜなら 彼らは一匹残らず食べてしまったから。」 「わたくしはセイウチが一番好きですわ」とアリスは言いました。「だって、ほら、彼はかわいそうなカキたちに少し気の毒に思っていましたから。」
「でも、彼は大工よりたくさん食べたぞ」とトゥイードルディーは言いました。「ほら、彼はハンカチを前にかざしていたから、大工は彼がいくつ取ったか数えられなかったんだ。その逆なり。」
「それは意地悪ですわ!」アリスは憤慨して言いました。「それなら、大工が一番好きです――もし彼がセイウチほどたくさん食べなかったのであれば。」
「でも彼は取れるだけ食べたんだ」とトゥイードルダムは言いました。
これは難問でした。一呼吸おいて、アリスは始めました。「まあ! 二人ともとても不愉快な人たちでしたわ――」ここで彼女は、近くの森で大きな蒸気機関車がふうふう言うような音が聞こえて、ぎょっとして口をつぐみました。もっとも、それは野生の獣である可能性の方が高いと彼女は恐れました。「この辺りにライオンやトラはいますか?」彼女はおずおずと尋ねました。
「赤の王様がいびきをかいているだけだよ」とトゥイードルディーは言いました。
「見においでよ!」と兄弟は叫び、それぞれアリスの手を片方ずつ取って、王様が眠っている場所まで彼女を連れて行きました。
「すてきな光景だろう?」とトゥイードルダムは言いました。
アリスは正直にそうだとは言えませんでした。彼はふさのついた背の高い赤いナイトキャップをかぶり、だらしのない山のように丸まって横たわり、大きないびきをかいていました――トゥイードルダムが言うには、「頭が吹き飛ぶほど」のいびきでした。
「湿った草の上に寝ていて、風邪をひくんじゃないかしら」と、とても思いやりのある小さな女の子であるアリスは言いました。
「彼は今、夢を見ているんだ」とトゥイードルディーは言いました。「そして、何について夢を見ていると思う?」
アリスは「そんなの誰も当てられませんわ」と言いました。
「なんと、君についてさ!」とトゥイードルディーは勝ち誇ったように手を叩いて叫びました。「そして、もし彼が君の夢を見るのをやめたら、君はどこにいると思う?」
「もちろん、今いる場所にいるに決まってますわ」とアリスは言いました。
「君じゃないね!」とトゥイードルディーは軽蔑的に言い返しました。「君はどこにもいなくなる。だって、君は彼の夢の中のただの何かでしかないんだから!」
「もしそこの王様が目を覚ましたら」とトゥイードルダムが付け加えました。「君は消えちまう――ばん! ――まるでロウソクみたいにさ!」
「そんなことありません!」アリスは憤慨して叫びました。「それに、もしわたくしが彼の夢の中のただの何かだとしたら、あなたたちはいったい何なんですの、お聞きしたいわ?」
「同じく」とトゥイードルダムは言いました。
「同じく、同じく」とトゥイードルディーは叫びました。
彼はあまりに大声で叫んだので、アリスは思わず言わずにはいられませんでした。「しーっ! そんなに大きな音を立てたら、王様を起こしてしまいますわよ、きっと。」
「まあ、君が彼を起こすことについて話しても無駄だよ」とトゥイードルダムは言いました。「君は彼の夢の中の物の一つに過ぎないんだから。君は自分が本物じゃないってことをよく知っているだろう。」
「わたくしは本物です!」とアリスは言って泣き始めました。
「泣いたって少しも本物にはなれないよ」とトゥイードルディーは言いました。「泣くことなんて何もない。」
「もしわたくしが本物じゃなかったら」とアリスは言いました――涙を通して半ば笑いながら、すべてがあまりにばかばかしく思えたので――「泣くことなんてできないはずですわ。」
「まさかそれが本物の涙だとでも思っているんじゃないだろうね?」とトゥイードルダムは大変軽蔑した口調で割り込みました。
「この人たちが馬鹿げたことを言っているのは分かっているわ」とアリスは独り言を思いました。「そして、そのことで泣くなんて愚かだわ」そこで彼女は涙をぬぐい、できるだけ陽気に続けました。「とにかく、森から出た方がよさそうですわ、本当にとても暗くなってきましたもの。雨が降ると思いますか?」
トゥイードルダムは自分と兄弟の上に大きな傘を広げ、その中を見上げました。「いや、降るとは思わないね」と彼は言いました。「少なくとも――この下ではね。ぜったいに。」
「でも、外では降るかもしれませんわ?」
「降るかもしれない――もしそうしたいならね」とトゥイードルディーは言いました。「我々に異論はない。その逆なり。」
「自分勝手な人たち!」とアリスは思い、ちょうど「おやすみなさい」と言って彼らを置いていこうとしたとき、トゥイードルダムが傘の下から飛び出して、彼女の手首をつかみました。
「あれが見えるか?」と彼は、激情でむせぶような声で言いました。そして彼の目は一瞬にして大きく黄色くなり、震える指で木の下に横たわる小さな白いものを指さしました。
「ただのガラガラですわ」とアリスは、その小さな白いものを注意深く調べた後で言いました。「ガラガラヘビじゃないですよ、ね」と彼女は、彼が怖がっているのだと思って急いで付け加えました。「ただの古いガラガラ――すっかり古くて壊れていますわ。」
「そうだと分かっていた!」とトゥイードルダムは叫び、乱暴に足を踏み鳴らし、髪をかきむしり始めました。「もちろん、壊れている!」ここで彼はトゥイードルディーを見ました。すると彼はすぐに地面に座り込み、傘の下に隠れようとしました。
アリスは彼のアームに手を置き、なだめるような口調で言いました。「古いガラガラのことで、そんなに怒る必要はありませんわ。」
「でも古くないんだ!」とトゥイードルダムは、これまで以上の激怒で叫びました。「新しいんだ、言っておくが――昨日買ったんだ――僕の素敵な新しいガラガラが!」そして彼の声は完全な金切り声になりました。
この間ずっと、トゥイードルディーは自分ごと傘を畳もうと必死でした。それはあまりに奇妙なことだったので、アリスの注意は怒れる兄弟からすっかりそれてしまいました。しかし、彼は完全には成功せず、結局、傘にくるまって転がり、頭だけが出ている状態になりました。そして彼はそこに横たわり、口と大きな目を開けたり閉じたりしていました――「何よりも魚にそっくりだわ」とアリスは思いました。
「もちろん、戦いをすることに同意するよな?」とトゥイードルダムは、より落ち着いた口調で言いました。
「そうだろうな」ともう一方が不機嫌そうに答え、傘から這い出しました。「ただ、彼女に着付けを手伝ってもらわなきゃな、いいか。」
そこで二人の兄弟は手を取り合って森の中へ行き、一分後には腕いっぱいの物――枕、毛布、暖炉の敷物、テーブルクロス、皿の蓋、石炭入れなど――を抱えて戻ってきました。「ピンで留めたり、ひもを結んだりするのが得意だといいんだが?」とトゥイードルダムは言いました。「これらの物はどれもこれも、どうにかして身につけなきゃならんのだ。」
アリスは後になって、生まれてこのかた、何事につけてもこれほどの大騒ぎは見たことがないと言いました――あの二人のてんてこ舞いの様子――そして彼らが身につけた物の量――そしてひもを結んだりボタンを留めたりするのに彼女にかけた手間――「本当に、準備が終わる頃には、何よりも古い服の束みたいになるわ!」と彼女は独り言を言いながら、トゥイードルディーの首の周りに枕を配置しました。「彼の言うことには、『首が切り落とされないようにするため』だそうです。」
「ご存知でしょうが」と彼は非常に真面目な口調で付け加えました。「戦いで起こりうる最も深刻なことの一つは――首を切り落とされることなのです。」
アリスは声を出して笑いましたが、彼の気持ちを傷つけるのを恐れて、何とかそれを咳に変えました。
「僕はとても青ざめて見えるかい?」とトゥイードルダムが、ヘルメットを結んでもらいにやって来て言いました。(彼はそれをヘルメットと呼んでいましたが、確かにそれはソースパンにずっとよく似ていました)
「ええと――はい――少し」とアリスは優しく答えました。
「僕は普段はとても勇敢なんだ」と彼は低い声で続けました。「ただ、今日はたまたま頭痛がするんだ。」
「そして僕は歯が痛いんだ!」と、その言葉を耳にしたトゥイードルディーが言いました。「僕の方が君よりずっとひどい状態だよ!」
「それなら、今日は戦わない方がいいですわ」とアリスは、和解させる良い機会だと思って言いました。
「少しは戦わなくちゃならんが、長く続ける気はない」とトゥイードルダムは言いました。「今は何時だ?」
トゥイードルディーは自分の時計を見て、「四時半だ」と言いました。
「六時まで戦って、それから夕食にしよう」とトゥイードルダムは言いました。
「分かった」ともう一方が、やや悲しそうに言いました。「そして彼女が僕らを見ていてくれる――ただ、あまり近くに来ない方がいいぞ」と彼は付け加えました。「僕は本当に興奮すると、見えるものは何でもたいてい殴っちまうんだ。」
「そして僕は手の届くものは何でも殴る」とトゥイードルダムは叫びました。「それが見えるか見えないかにかかわらずね!」
アリスは笑いました。「きっと木をかなり頻繁に殴ることになるでしょうね」と彼女は言いました。
トゥイードルダムは満足げな笑みを浮かべて周りを見回しました。「思うに」と彼は言いました。「僕らが終わる頃には、この辺り一帯、立っている木は一本も残らないだろうよ!」
「そして、すべてはガラガラ一つのために!」とアリスは、彼らがそんな些細なことで戦うのを少しでも恥じてくれることを願いながら言いました。
「新しいものでなかったら、それほど気にしなかったんだがな」とトゥイードルダムは言いました。
「あの巨大なカラスが来てくれればいいのに!」とアリスは思いました。
「剣は一本しかないからな」とトゥイードルダムは兄弟に言いました。「だが、君は傘を使えるぞ――あれも同じくらい鋭い。ただ、早く始めないとな。できる限り暗くなってきている。」
「そして、もっと暗く」とトゥイードルディーは言いました。
あまりに急に暗くなってきたので、アリスは雷雨が来るに違いないと思いました。「なんて厚い黒雲かしら!」と彼女は言いました。「そしてなんて速く来るんでしょう! あら、まあ、羽がついているみたいだわ!」
「カラスだ!」とトゥイードルダムは甲高い警戒の声で叫びました。そして二人の兄弟は踵を返し、一瞬のうちに姿を消しました。
アリスは少し森の中へ走り、大きな木の下で立ち止まりました。「ここなら絶対に来られないわ」と彼女は思いました。「木々の間に体を押し込むには大きすぎるもの。でも、あんなに羽ばたかなければいいのに――森の中にまるでハリケーンを起こしているみたい――あら、誰かのショールが吹き飛ばされているわ!」
第五章 羊毛と水
彼女はそう言いながらショールを捕まえ、持ち主を探してあたりを見回しました。次の瞬間、白の女王が、まるで飛んでいるかのように両腕を大きく広げ、森の中を夢中で走ってきました。アリスはとても丁寧にも、ショールを持って彼女を迎えに行きました。
「ちょうど通りかかってよかったですわ」とアリスは、彼女が再びショールを羽織るのを手伝いながら言いました。
白の女王はただ、途方に暮れた怯えたような様子で彼女を見つめ、「バターつきパン、バターつきパン」と聞こえるようなことを小声で自分に繰り返し言い続けるばかりでした。アリスは、もし会話をするつもりなら、自分が何とかしなければならないと感じました。そこで彼女は、ややおずおずと始めました。「わたくしが今お話しておりますのは、白の女王様でいらっしゃいますか?」
「ええ、まあ、それを『お召しになる』[訳注:原文では「話しかける(addressing)」と「服を着る(a-dressing)」の言葉遊び]というのならね」と女王は言いました。「わたくしの考えでは、そういうものでは全くありませんが。」
アリスは、会話のまさに始まりで議論をするのはまずいだろうと考え、微笑んで言いました。「もし陛下が正しい始め方を教えてくださるのでしたら、わたくし、できる限りうまくやってみますわ。」
「でも、わたくしは全くやってほしくないのです!」と哀れな女王はうめきました。「この二時間、ずっと自分で服を着ておりましたのよ。」
アリスには、誰か他の人に着せてもらった方がずっとよかっただろうと思えました。彼女はひどくだらしなかったからです。「一つ一つのものが全部曲がっているわ」とアリスは独り言を思いました。「それに、ピンだらけだわ! ――ショールをまっすぐにしてさしあげましょうか?」と彼女は声に出して付け加えました。
「これに何が起こったのか分からないのです!」と女王は憂鬱な声で言いました。「機嫌が悪いのだと思いますわ。ここにピンで留め、あそこにピンで留めましたが、どうしても気に入ってくれないのです!」
「片側だけにピンで留めては、まっすぐになるはずがありませんわ」とアリスは、優しく直してあげながら言いました。「それに、まあ、なんてひどい髪の状態でしょう!」
「ブラシが絡まってしまったのです!」と女王はため息をついて言いました。「そして昨日は櫛をなくしました。」
アリスは注意深くブラシを外し、髪を整えるのに最善を尽くしました。「さあ、これでいくぶん見栄えがよくなりましたわ!」と彼女は、ピンのほとんどを付け直した後で言いました。「でも、本当に侍女を一人お持ちになるべきですわ!」
「喜んであなたを雇いますわ!」と女王は言いました。「週に二ペンス、そして一日おきにジャムを。」
アリスは思わず笑ってしまい、こう言いました。「わたくしを雇っていただきたいわけではありませんの――それにジャムは別に好きではありませんし。」
「とてもおいしいジャムですわよ」と女王は言いました。
「まあ、とにかく今日はいりませんわ。」
「もし欲しくても手に入りませんわよ」と女王は言いました。「ルールは、明日のジャムと昨日のジャム――でも今日のジャムは決してない、ですの。」
「いつかは『今日のジャム』になるはずですわ」とアリスは反論しました。
「いいえ、なりません」と女王は言いました。「一日おきのジャムですもの。今日はどの一日おきの日でもありませんでしょう。」
「おっしゃることが分かりませんわ」とアリスは言いました。「ひどく混乱します!」
「それが後ろ向きに生きるということの効果ですわ」と女王は親切に言いました。「最初はいつも少しめまいがするものですけれど――」
「後ろ向きに生きるですって!」アリスは大変驚いて繰り返しました。「そんなこと、聞いたこともありませんわ!」
「――でも、それには一つ大きな利点がありますの。記憶が両方向に働くのです。」
「わたくしの記憶は片方にしか働きませんわ、きっと」とアリスは言いました。「起こる前のことは思い出せませんもの。」
「後ろ向きにしか働かない記憶なんて、つまらないものですわ」と女王は言いました。
「あなたはどのようなことを一番よく覚えているのですか?」アリスは思い切って尋ねてみました。
「あら、来週の次の週に起こったこととかですわ」と女王は無頓着な口調で答えました。「例えば、今」と彼女は言いながら、指に大きな絆創膏を貼り付けました。「王様の使者がおります。彼は今、罰せられて牢屋におりますの。そして裁判は来週の水曜日まで始まってもいないのです。そしてもちろん、犯罪は一番最後に起こるのです。」
「もし彼がその犯罪を犯さなかったらどうなるのですか?」とアリスは言いました。
「その方がずっとよいでしょう、そう思いません?」と女王は、リボンの切れ端で指に絆創膏を巻きつけながら言いました。
アリスはそれを否定できないと感じました。「もちろん、その方がずっとよいですわ」と彼女は言いました。「でも、彼が罰せられることがずっとよいということにはなりませんわ。」
「そこがあなたは間違っていますわ、とにかく」と女王は言いました。「あなたは罰せられたことがありますか?」
「過ちを犯したときだけですわ」とアリスは言いました。
「そして、それであなたはすっかりよくなったのよ、分かっていますわ!」と女王は勝ち誇ったように言いました。
「はい、でもそのときは、罰せられる原因になったことをしてしまった後ですわ」とアリスは言いました。「それが全く違うのです。」
「でも、もしあなたがそれをしていなかったら」と女王は言いました。「それはもっとよかったでしょう。もっと、もっと、もっと!」彼女の声は「もっと」と言うたびに高くなり、最後にはほとんど金切り声になりました。
アリスがちょうど「どこかに間違いがありますわ――」と言い始めたとき、女王がものすごく大きな声で叫び始めたので、彼女は文を言い終えることができませんでした。「ああ、ああ、ああ!」と女王は、まるで手を振り払いたいかのように手を振りながら叫びました。「指から血が! ああ、ああ、ああ、ああ!」
彼女の叫び声は蒸気機関車の汽笛とそっくりだったので、アリスは両手で耳をふさがなければなりませんでした。
「どうしたのですか?」と彼女は、声が届く機会ができた途端に言いました。「指を刺したのですか?」
「まだ刺していませんわ」と女王は言いました。「でも、もうすぐ――ああ、ああ、ああ!」
「いつ刺す予定なのですか?」アリスは、笑いたくてたまらない気持ちで尋ねました。
「ショールをまた留めるときですわ」と哀れな女王はうめきました。「ブローチがすぐに外れてしまうのです。ああ、ああ!」彼女がそう言ったとたん、ブローチがぱっと開き、女王はそれを必死でつかんで、再び留めようとしました。
「気をつけて!」とアリスは叫びました。「全部曲がって持っていますわ!」そして彼女はブローチをつかみましたが、遅すぎました。ピンが滑り、女王は指を刺してしまったのです。
「これで血が出たわけがお分かりでしょう」と彼女はアリスに微笑みかけました。「これで、ここでは物事がどう起こるか理解できたでしょう。」
「でも、どうして今は叫ばないのですか?」アリスは、再び耳をふさぐ準備をしながら尋ねました。
「あら、叫ぶのはもう全部済ませましたもの」と女王は言いました。「もう一度全部やり直して、何の得があるというの?」
この頃には明るくなってきました。「カラスは飛んでいってしまったに違いありませんわ」とアリスは言いました。「いなくなってとても嬉しいです。夜が来るのかと思いましたわ。」
「わたくしも喜べたらいいのに!」と女王は言いました。「ただ、そのルールがどうしても思い出せないのです。あなたはこの森に住んで、好きなときに喜べて、とても幸せに違いありませんわね!」
「ただ、ここはとても寂しいのです!」とアリスは憂鬱な声で言いました。そして、自分の孤独を思ったとたん、二つの大きな涙が頬を伝い落ちました。
「ああ、そんなふうに続けないで!」と哀れな女王は、絶望して両手をもみながら叫びました。「あなたがどれほど大きな娘か考えなさい。今日どれほど長い道のりを来たか考えなさい。今が何時か考えなさい。何でもいいから考えなさい、ただ泣かないで!」
アリスは涙のさなかにあっても、これには思わず笑ってしまいました。「物事を考えることで、泣くのを我慢できるのですか?」と彼女は尋ねました。
「それがやり方ですわ」と女王はきっぱりと言いました。「誰も一度に二つのことはできませんでしょう。まずあなたの年齢から考えましょう――あなたは何歳?」
「ちょうど七歳半ですわ。」
「『ちょうど』なんて言う必要はありませんわ」と女王は言いました。「それがなくても信じられますから。さあ、今度はわたくしがあなたに信じることを差し上げましょう。わたくしはちょうど百一歳と五ヶ月と一日ですの。」
「そんなこと信じられませんわ!」とアリスは言いました。
「信じられない?」と女王は哀れむような口調で言いました。「もう一度やってみなさい。深く息を吸って、目を閉じるのよ。」
アリスは笑いました。「やっても無駄ですわ」と彼女は言いました。「不可能なことは信じられませんもの。」
「あなた、あまり練習を積んでいないのでしょうね」と女王は言いました。「わたくしがあなたの年の頃は、いつも一日に三十分はそれをやりましたわ。あら、朝食前に六つもの不可能なことを信じたことだってありますのよ。あら、またショールが!」
彼女がそう言ったとたんブローチが外れ、突然の突風が女王のショールを小川の向こうへ吹き飛ばしました。女王は再び腕を広げ、それを追いかけて飛び、今度は自分で捕まえることに成功しました。「捕まえましたわ!」と彼女は勝ち誇った声で叫びました。「さあ、わたくしが一人でまたピンで留めるのをご覧なさい!」
「では、指はもうよろしいのですか?」アリスは、女王の後を追って小川を渡りながら、とても丁寧に言いました。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 「ああ、ずっとよくなりましたわ!」と女王は叫び、続けるうちに声は金切り声になりました。「ずーっとよくなりました! よくなりました! よーくなーりーまーしーた! めーえーえー!」最後の言葉は長い鳴き声で終わり、あまりにヒツジのようだったのでアリスはすっかり驚いてしまいました。
彼女が女王を見ると、女王は突然羊毛にくるまってしまったように見えました。アリスは目をこすり、もう一度見ました。何が起こったのか全く分かりませんでした。自分は店にいるのでしょうか? そして、あれは本当に――本当にカウンターの向こう側に座っているのはヒツジなのでしょうか? いくらこすっても、それ以上のことは分かりませんでした。彼女は小さな暗い店の中で、カウンターに肘をついて寄りかかっており、その向かいには古いヒツジが肘掛け椅子に座って編み物をしていて、時々やめては大きな眼鏡越しに彼女を見ていたのです。
「何をお買いになりたいのかね?」とヒツジは、編み物から一瞬顔を上げて、ついに言いました。
「まだよく分かりませんの」とアリスはとても優しく言いました。「もしよろしければ、まず周りを全部見てみたいのですけれど。」
「前と両側なら見てもいいよ」とヒツジは言いました。「でも周り全部は見られないね――後頭部に目でもついてない限りは。」
しかし、たまたまアリスにはそれがなかったので、彼女は向きを変えながら、棚に近づくたびにそれを見ることで満足しました。
店はありとあらゆる珍しいものでいっぱいのようでした――しかし、一番奇妙だったのは、彼女がどの棚に何があるか正確に見極めようとじっと見つめると、その特定の棚はいつも決まって空っぽで、その周りの他の棚はこれでもかというほどぎっしり詰まっていることでした。
「ここでは物が動き回るのね!」と彼女はついに嘆くような声で言いました。一分ほど、ある時は人形のように、またある時は裁縫箱のように見え、いつも彼女が見ている棚のすぐ上の棚にある、大きくて輝くものをむなしく追いかけた後のことでした。「そして、これが一番腹立たしいわ――でもね、こうしましょう――」と彼女は、突然の思いつきで付け加えました。「一番上の棚まで追いかけるわ。天井を通り抜けるのは、さすがに困るでしょう!」
しかし、この計画さえも失敗しました。その「もの」は、まるで慣れっこであるかのように、ごく静かに天井を通り抜けていきました。
「お前さんは子供なのか、それとも独楽なのかね?」とヒツジは、別の編み針を取り上げながら言いました。「そんなふうにぐるぐる回っていると、じきにめまいがしてくるよ」彼女は今や十四組の編み針で同時に編んでおり、アリスは大変驚いて彼女を見ずにはいられませんでした。
「どうやってあんなにたくさんで編めるのかしら?」と途方に暮れた子供は独り言を思いました。「毎分毎分、ますますヤマアラシみたいになっていくわ!」
「ボートは漕げるかい?」とヒツジは、そう言いながら彼女に一組の編み針を渡して尋ねました。
「はい、少しなら――でも陸の上では――それに編み針では――」とアリスが言いかけたとき、突然編み針は彼女の手の中でオールに変わり、気がつくと彼女は小さなボートに乗って、土手の間を滑るように進んでいました。ですから、彼女にできることは最善を尽くすことだけでした。
「フェザー!」とヒツジは、別の編み針を取り上げながら叫びました。
これは何の返事も必要としない言葉のようだったので、アリスは何も言わず、ただ漕ぎ続けました。水には何かとても奇妙なところがある、と彼女は思いました。時々オールが水中で引っかかり、なかなか抜け出せなくなるのです。
「フェザー! フェザー!」とヒツジは、さらに編み針を取りながら再び叫びました。「すぐにカニを捕まえる[訳注:ボート用語で、オールを失敗すること]ことになるよ。」
「まあ、かわいいカニさん!」とアリスは思いました。「それはいいわ。」
「『フェザー』と言ったのが聞こえなかったのかい?」とヒツジは、編み針の束を手に取って怒ったように叫びました。
「ええ、聞こえましたわ」とアリスは言いました。「とても何度も――そしてとても大きな声で。お願いです、カニはどこにいるのですか?」
「水の中に決まっているだろう!」とヒツジは、両手がふさがっていたので、編み針の何本かを髪に突き刺しながら言いました。「フェザーだと言ってるんだ!」
「どうしてそんなに何度も『フェザー』と言うのですか?」アリスは、ややいらいらしてついに尋ねました。「わたくしは鳥ではありませんわ!」
「お前さんは鳥だよ」とヒツジは言いました。「お前さんは小さなガチョウ[訳注:おばかさん、という意味もある]さんさ。」
これにアリスは少し気分を害したので、一、二分、会話はありませんでした。その間、ボートは穏やかに進み、時には雑草の茂み(これがオールを水中でこれまで以上にひどく引っかからせました)の中を、また時には木々の下を、しかし常に見下ろすようにそびえる同じ高い川岸とともに進みました。
「あら、お願いです! 香りのよいショウブがありますわ!」アリスは突然の喜びに満ちて叫びました。「本当にありますわ――それになんてきれいなんでしょう!」
「それについてわしに『お願い』する必要はないよ」とヒツジは、編み物から顔も上げずに言いました。「わしがそこに置いたわけでもないし、取り去るつもりもないからね。」
「いいえ、でも、つまり――お願いです、待って少し摘んでもよろしいでしょうか?」とアリスは懇願しました。「もしボートを少し止めるのがお嫌でなければ。」
「どうやってわしが止めるんだい?」とヒツジは言いました。「お前さんが漕ぐのをやめれば、ひとりでに止まるだろうよ。」
ですから、ボートは流れのなすがままに任され、やがてそよぐイグサの茂みの中へと静かに滑り込んでいきました。そして、小さな袖は丁寧にまくり上げられ、小さな両腕は肘まで深く水に浸されました。イグサをできるだけ根元の方から折るためです。しばらくの間、アリスはボートの縁から身を乗り出し、からまった髪の毛先を水につけながら、ヒツジのことや編み物のことをすっかり忘れていました。輝く熱心な目で、愛らしい香りのするイグサの束を次から次へと掴んでいたのです。
「ボートがひっくり返らなきゃいいけど!」と彼女は独り言を言いました。「あら、なんて素敵な一本でしょう! でも、ちょっと届かなかったわ」。そして、ボートが通り過ぎる間にたくさんの美しいイグサを摘むことはできたものの、いつももっと素敵な一本が決して手の届かないところにあるというのは、確かになんとも腹立たしいことのように思えました(「まるでわざとみたい」と彼女は思いました)。
「一番きれいなのは、いつももっと遠くにあるのね!」と彼女はついに言いました。あまりにも遠くに生えているイグサの頑固さにため息をつきながら、頬を赤らめ、髪と手をびしょ濡れにして、よじ登るように自分の場所に戻り、見つけたばかりの宝物を並べ始めました。
そのイグサが、摘んだ瞬間から色あせ始め、香りも美しさもすべて失っていくことなど、そのときのアリスにとって何の問題だったでしょう? 本物の香りのよいイグサでさえ、ご存知の通り、ほんのわずかな時間しかもちません。そしてこれらは夢のイグサだったので、彼女の足元に山と積まれると、ほとんど雪のように溶けていってしまいました。しかし、アリスはほとんどそれに気づきませんでした。考えるべき不思議なことが、他にたくさんあったのです。
それほど進まないうちに、オールの一枚が水の中で動かなくなり、どうしても抜けなくなってしまいました(とアリスは後で説明しました)。その結果、オールの柄が彼女の顎の下に引っかかり、哀れなアリスの「あら、あら、あら!」という一連の小さな叫び声もむなしく、彼女は座席からまっすぐに払いのけられ、イグサの山の中へと落ちてしまいました。
しかし、彼女は怪我をせず、すぐに起き上がりました。ヒツジはその間ずっと、何事もなかったかのように編み物を続けていました。「見事なカニを捕まえましたね!」と、アリスがボートの中にまだいることに大いに安堵して自分の場所に戻ると、ヒツジは言いました。
「そうですか? わたしには見えませんでしたけど」とアリスは言い、用心深くボートの縁から暗い水の中を覗き込みました。「逃げなければよかったのに。小さなカニを一匹、お家に持って帰りたかったわ!」しかし、ヒツジは軽蔑するように笑うだけで、編み物を続けました。
「ここにはカニがたくさんいるのですか?」とアリスは言いました。
「カニも、ありとあらゆるものもいますよ」とヒツジは言いました。「選び放題です。ただ、心を決めなさい。さあ、何が買いたいのですか?」
「買うですって!」アリスは半分驚き、半分おびえたような口調で繰り返しました。というのも、オールも、ボートも、川も、一瞬のうちにすべて消え去り、彼女はまたあの小さな暗い店の中に戻っていたのです。
「卵を一つ買いたいのですが、お願いします」と彼女は恐る恐る言いました。「おいくらで売っているのですか?」
「一つなら5ペンスとファージング、二つなら2ペンスです」とヒツジは答えました。
「では、二つの方が一つより安いのですか?」アリスは驚いた口調で言い、財布を取り出しました。
「ただし、二つ買うなら、両方とも食べなくてはなりませんよ」とヒツジは言いました。
「では、一ついただきます」とアリスは言い、カウンターにお金を置きました。「だって、あまり美味しくないかもしれないでしょう」と心の中で思ったからです。
ヒツジはお金を受け取ると、箱にしまいました。それから「私は人の手に物を直接渡したりはしません。そんなことは決してしませんよ。ご自分で取らなくては」と言いました。そしてそう言うと、店のもう一方の端へ行き、棚の上に卵をまっすぐに立てました。
「どうしてそんなことしないのかしら?」とアリスは思いました。店の奥の方はとても暗かったので、テーブルや椅子の間を手探りで進みながら。「卵は、私が近づけば近づくほど遠ざかっていくみたい。ええと、これは椅子かしら? まあ、枝がついているわ! こんなところに木が生えているなんて、なんて変なのかしら! それに、本当に小さな小川まであるわ! もう、今まで見た中で一番奇妙なお店だわ!」
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * そうして彼女は歩き続け、一歩ごとにますます不思議に思いました。というのも、彼女が近づくと、すべてのものがその瞬間に木に変わってしまうのです。そして、卵も同じようになるだろうとすっかり予想していました。
第六章 ハンプティ・ダンプティ
しかし、卵はただ大きくなるばかりで、ますます人間らしくなっていきました。数ヤードの距離まで来ると、それには目と鼻と口があるのが見えました。そして、すぐそばまで来ると、それがまぎれもなくハンプティ・ダンプティ自身であることがはっきりとわかりました。「他の誰かであるはずがないわ!」と彼女は独り言を言いました。「彼の名前が顔中に書いてあるかのように、確信できるわ」。
あの巨大な顔になら、百回だって楽に書けたことでしょう。ハンプティ・ダンプティは、高い塀の上で、トルコ人のように足を組んで座っていました。その塀はあまりにも狭かったので、どうやってバランスを保っているのかとアリスはすっかり不思議に思いました。そして、彼の目は反対方向をじっと見つめていて、彼女には少しも気づかない様子だったので、アリスはきっと彼は結局のところ、ぬいぐるみか何かなのだろうと思いました。
「それに、なんて卵にそっくりなのかしら!」と彼女は声に出して言いました。いつ彼が落ちてきてもいいように、両手を構えながら立っていました。
「実に腹立たしい」とハンプティ・ダンプティは長い沈黙の後、アリスから目をそらしたまま言いました。「卵と呼ばれるとは――実に!。」
「卵のように見えると申し上げたのです、あなた」とアリスは優しく説明しました。「それに、とてもきれいな卵もありますでしょう」と、自分の発言を一種の褒め言葉に変えようと期待して付け加えました。
「世の中には」とハンプティ・ダンプティはいつものように彼女から目をそらして言いました。「赤ん坊ほどの分別もない者もおる!」
アリスはこれに何と答えてよいかわかりませんでした。これは会話とはまったく違う、と彼女は思いました。彼は決して彼女には何も言わなかったからです。実際、彼の最後の言葉は明らかに木に向けられたものでした。そこで彼女は立ち尽くし、静かに自分に言い聞かせるように繰り返しました。
「ハンプティ・ダンプティが塀の上 ハンプティ・ダンプティが落っこちた 王様の馬と家来をぜんぶ集めても ハンプティ・ダンプティを元に戻せなかった。」
「最後の行は詩にしては長すぎるわね」と彼女は、ハンプティ・ダンプティに聞こえるのを忘れて、ほとんど声に出して付け加えました。
「そこでそんなふうに独り言をぶつぶつ言っているでない」とハンプティ・ダンプティは、初めて彼女を見て言いました。「それより、お前の名前と用件を言え」。
「私の名前はアリスと申しますが――」
「ずいぶん馬鹿げた名前だな!」とハンプティ・ダンプティは焦れたように遮りました。「どういう意味だ?」
「名前に何か意味がなければならないのですか?」とアリスは疑わしげに尋ねました。
「もちろん、なければならん」とハンプティ・ダンプティは短く笑って言いました。「わしの名前はわしの形を意味しておる――しかも、なかなかの見事な形だ。お前のような名前では、ほとんどどんな形にでもなれてしまうだろうな」。
「なぜこんなところに一人きりで座っているのですか?」とアリスは、議論を始めたくなかったので言いました。
「なぜって、わしと一緒に誰もいないからだ!」とハンプティ・ダンプティは叫びました。「わしがその答えを知らないとでも思ったか? 別のを訊け」。
「地面に降りた方が安全だとは思いませんか?」とアリスは続けました。別のなぞなぞを出すつもりはなく、ただ、その奇妙な生き物への親切な心配からでした。「その塀はとても狭いですよ!」
「お前はとんでもなく簡単ななぞなぞを訊くな!」とハンプティ・ダンプティは唸るように言いました。「もちろん、そうは思わん! なぜなら、もし万が一わしが落ちたとしても――まあ、その可能性はないが――しかし、もし落ちたとしたら――」ここで彼は唇をすぼめ、あまりに厳粛で威厳のある表情をしたので、アリスは笑いをこらえるのがやっとでした。「もしわしが落ちたら」と彼は続けました。「王様が約束してくださったのだ――ご自身の口で――その、その――」
「王様の馬と家来をぜんぶ送ってくださると」とアリスは、やや賢明とは言えない口出しをしました。
「今のはひどすぎるぞ!」とハンプティ・ダンプティは突然かんしゃくを起こして叫びました。「お前はドアで――あるいは木の後ろで――あるいは煙突の下で――聞き耳を立てていたに違いない! でなければ、それを知っているはずがない!」
「そんなことはしておりません、本当に!」とアリスはとても優しく言いました。「本に書いてあるのです」。
「ああ、そうか! そういうことは本に書くかもしれんな」とハンプティ・ダンプティは落ち着いた口調で言いました。「お前たちがイギリスの歴史と呼ぶのはそういうものだ。さて、わしをよく見ろ! わしは王様と話したことのある者だぞ、このわしがな。お前は二度とこのような者には会えまい。そして、わしが威張っていないことを示すために、握手をしてやってもよいぞ!」そして彼は、身を乗り出し(その拍子に塀から落ちそうになりながら)、アリスに手を差し伸べながら、ほとんど耳から耳まで届くほどにっこり笑いました。彼女はそれを受け取りながら、少し心配そうに彼を見守りました。「もしこれ以上笑ったら、口の端が後ろでくっついてしまうかもしれないわ」と彼女は思いました。「そしたら、彼の頭がどうなるかわからないわ! きっと取れてしまうでしょうね!」
「そうだ、王様の馬と家来をぜんぶだ」とハンプティ・ダンプティは続けました。「彼らは一分もたたずにわしを拾い上げてくれるだろう、彼らがな! しかし、この会話は少し早すぎる。一つ前の発言に戻ろう」。
「申し訳ありませんが、よく覚えておりません」とアリスはとても丁寧に言いました。
「その場合は、最初からやり直そう」とハンプティ・ダンプティは言いました。「そして、今度はわしが主題を選ぶ番だ――」(「まるでゲームみたいに話すのね!」とアリスは思いました。)「では、お前に質問だ。お前は何歳だと言ったかな?」
アリスは少し計算して、「7歳と6ヶ月です」と言いました。
「間違いだ!」とハンプティ・ダンプティは勝ち誇ったように叫びました。「お前はそんな言葉は一言も言っておらん!」
「わたしは、『あなたは何歳ですか?』という意味だと思いました」とアリスは説明しました。
「もしわしがそう言いたかったなら、そう言っていたはずだ」とハンプティ・ダンプティは言いました。
アリスはまた議論を始めたくなかったので、何も言いませんでした。
「7歳と6ヶ月か!」とハンプティ・ダンプティは考え深げに繰り返しました。「居心地の悪い年頃だな。今、もしお前がわしの助言を求めていたなら、わしは『7歳でやめておけ』と言っただろうが――もう手遅れだ」。
「わたしは成長について助言を求めたことなんてありません」とアリスは憤慨して言いました。
「プライドが高すぎるのか?」と相手は尋ねました。
アリスはこの指摘にさらに憤慨しました。「つまり」と彼女は言いました。「人は年を取るのを止められないということです」。
「一人では無理かもしれんが」とハンプティ・ダンプティは言いました。「二人ならできる。適切な手助けがあれば、お前は7歳でやめられたかもしれんのだ」。
「なんてきれいなベルトを締めているのでしょう!」とアリスは突然言いました。
(年齢の話はもう十分だ、と彼女は思いました。そして、もし本当に交代で主題を選ぶのなら、今度は彼女の番でした。)「少なくとも」と彼女は考え直して訂正しました。「きれいなネクタイ、と言うべきでした――いいえ、ベルトです、つまり――申し訳ありません!」と彼女はうろたえて付け加えました。ハンプティ・ダンプティはすっかり気分を害したように見え、彼女はその主題を選ばなければよかったと後悔し始めました。「どっちが首で、どっちが腰なのかさえわかれば」と彼女は心の中で思いました。
明らかにハンプティ・ダンプティは非常に怒っていましたが、一、二分は何も言いませんでした。彼が再び口を開いたとき、それは低いうなり声でした。
「それは――実に――腹立たしい――ことだ」と彼はついに言いました。「人がネクタイとベルトの区別もつかないとは!」
「私がとても無知なのはわかっています」とアリスは、ハンプティ・ダンプティの機嫌が直るほど謙虚な口調で言いました。
「それはネクタイだ、小娘。そして、お前が言うように、美しいものだ。白の王様と女王様からの贈り物なのだ。さあ、どうだ!」
「本当にですか?」とアリスは、結局は良い主題を選んでいたのだとわかって、すっかり嬉しくなって言いました。
「彼らがわしにくれたのだ」とハンプティ・ダンプティは片膝をもう一方の膝の上で組み、その周りで両手を組んで、考え深げに続けました。「彼らがわしにくれたのだ――誕生日じゃない日のプレゼントとしてな」。
「失礼ですが?」とアリスは困惑した様子で言いました。
「気分を害してはいないぞ」とハンプティ・ダンプティは言いました。
「つまり、誕生日じゃない日のプレゼントって何ですか?」
「誕生日じゃないときにもらうプレゼントのことだ、もちろん」。
アリスは少し考えました。「私は誕生日のプレゼントの方が好きです」と彼女はついに言いました。
「お前は何を言っているのかわかっておらん!」とハンプティ・ダンプティは叫びました。「一年は何日ある?」
「365日です」とアリスは言いました。
「そして、お前には誕生日がいくつある?」
「一つです」。
「そして、365から1を引くと、何が残る?」
「もちろん、364です」。
ハンプティ・ダンプティは疑わしそうな顔をしました。「それは紙の上でやってもらいたいものだ」と彼は言いました。
アリスは微笑まずにはいられませんでした。彼女は手帳を取り出し、彼のために計算をしました。
365
- 1
____
364
___
ハンプティ・ダンプティはその本を受け取り、注意深く見ました。「それは正しくできているようだな――」と彼は始めました。
「逆さまに持っていますよ!」とアリスは口を挟みました。
「確かにそうだった!」とハンプティ・ダンプティは、彼女が本を正しい向きにしてあげると、陽気に言いました。「少し奇妙に見えると思ったのだ。言っていたように、それは正しくできているようだ――今はじっくり見直す時間はないが――そして、それはお前が誕生日じゃない日のプレゼントをもらえる日が364日あることを示している――」
「確かにそうですわ」とアリスは言いました。
「そして、誕生日のプレゼントはたった一日だけだ、わかるかね。どうだ、見事だろう!」
「『見事』というのがどういう意味かわかりません」とアリスは言いました。
ハンプティ・ダンプティは軽蔑するように微笑みました。「もちろん、わかるわけがない――わしが教えるまではな。わしが言いたかったのは、『お前にとって、見事な、ぐうの音も出ない議論だ!』ということだ!」
「でも、『見事』は『見事な、ぐうの音も出ない議論』という意味ではありません」とアリスは反論しました。
「わしが言葉を使うとき」とハンプティ・ダンプティはかなり軽蔑した口調で言いました。「それは、わしが選んだ通りの意味になるのだ――それ以上でも、それ以下でもない」。
「問題は」とアリスは言いました。「言葉にそんなにたくさんの違う意味を持たせることができるかどうかです」。
「問題は」とハンプティ・ダンプティは言いました。「どちらが主人かということだ――それだけだ」。
アリスはあまりに混乱して何も言えなかったので、一分ほどしてハンプティ・ダンプティが再び話し始めました。「やつらは気難しいところがある、一部のやつらはな――特に動詞は一番プライドが高い――形容詞はどうにでもなるが、動詞はそうはいかん――しかし、わしはそいつら全部を操れる! 不可侵入性! それがわしの言うことだ!」
「教えていただけますか」とアリスは言いました。「それがどういう意味か」。
「今のお前は道理のわかる子供のように話すな」とハンプティ・ダンプティは、とても満足そうに言いました。「わしが『不可侵入性』で言いたかったのは、その主題はもう十分だということ、そして、お前が次に何をするつもりか言ってくれた方がちょうどいいだろうということだ。まさか、残りの人生ずっとここにいるつもりではあるまい」。
「一つの言葉に持たせるには、ずいぶんたくさんの意味ですね」とアリスは考え深げな口調で言いました。
「わしが言葉にそんなふうにたくさんの仕事をさせるときは」とハンプティ・ダンプティは言いました。「いつも特別手当を払ってやるのだ」。
「まあ!」とアリスは言いました。彼女はあまりに混乱していて、他の言葉を発することができませんでした。
「ああ、土曜の夜にやつらがわしの周りに集まってくるのを見るべきだな」とハンプティ・ダンプティは、厳かに頭を左右に振りながら続けました。「給料をもらうためにな、わかるかね」。
(アリスは彼が何で支払うのかをあえて尋ねなかったので、ご覧の通り、私にもお伝えすることができません。)
「あなたは言葉を説明するのがとてもお上手なようですね」とアリスは言いました。「『ジャバウォックの詩』という詩の意味を親切に教えていただけませんか?」
「聞かせてもらおう」とハンプティ・ダンプティは言いました。「わしはこれまでに作られたすべての詩を説明できる――それに、まだ作られていない詩のかなりの数もな」。
これはとても希望が持てるように聞こえたので、アリスは最初の節を繰り返しました。
ブリリッグの時間、ヌルヌルしたトーヴが ウェイブの中でジャイアし、ジンブルしていた。 ミムジーだったのはボロゴーヴたち、 そして故郷を離れたラスがアウトグレイブしていた。[訳注: 原文の雰囲気を残すため、固有名詞的な単語はカタカナ表記としました。]
「始めるにはそれで十分だ」とハンプティ・ダンプティは遮りました。「そこには難しい言葉がたくさんある。『ブリリッグ』とは午後の4時――夕食のものを焼き(broiling)始める時間のことだ」。
「それはとてもしっくりきますわ」とアリスは言いました。「では、『スライシー』は?」
「うむ、『スライシー』は『しなやか(lithe)でぬるぬる(slimy)』という意味だ。『しなやか』というのは『活発』と同じことだ。わかるかね、これはかばん語のようなものだ――一つの言葉に二つの意味が詰め込まれているのだ」。
「今わかりました」とアリスは考え深げに言いました。「では、『トーヴ』とは何ですか?」
「うむ、『トーヴ』はアナグマのようなものだ――トカゲのようなものでもあり――コルク抜きのようなものでもある」。
「それはとても奇妙な見た目の生き物に違いありませんね」。
「その通りだ」とハンプティ・ダンプティは言いました。「それに、日時計の下に巣を作る――それに、チーズを食べて生きている」。
「では、『ジャイアする』と『ジンブルする』とは?」
「『ジャイアする』とは、ジャイロスコープのようにぐるぐる回ることだ。『ジンブルする』とは、錐のように穴を開けることだ」。
「そして、『ウェイブ』は日時計の周りの芝生のことでしょうね?」とアリスは、自分の創意工夫に驚きながら言いました。
「もちろんそうだ。それが『ウェイブ』と呼ばれるのは、わかるかね、その前方に長く、そしてその後方にも長く続いているからだ――」
「そして、両側にもずっと向こうまで」とアリスは付け加えました。
「まさしくその通り。さて、では、『ミムジー』は『薄っぺら(flimsy)でみじめ(miserable)』だ(これもお前にとってのかばん語だな)。そして、『ボロゴーヴ』は、羽が四方八方に突き出た、みすぼらしい痩せた鳥だ――生きたモップのようなものだな」。
「では、『モーム・ラス』は?」とアリスは言いました。「ずいぶんお手間をおかけしているようで申し訳ありません」。
「うむ、『ラス』は一種の緑色の子豚だ。だが、『モーム』については確信がない。思うに、『from home(家から)』の短縮形で――道に迷ったという意味だろうな、わかるかね」。
「では、『アウトグレイブする』とはどういう意味ですか?」
「うむ、『アウトグレイビング』は、ほえるのと口笛の中間のようなもので、間にくしゃみのようなものが入る。しかし、いずれその音を聞くことになるだろう、たぶん――向こうの森の中でな――そして、一度聞けばすっかり満足するだろう。誰がそんな難しいものを全部お前に繰り返して聞かせたのだ?」
「本で読みました」とアリスは言いました。「でも、もっとずっと簡単な詩を、誰だったか――トゥイードルディーだったと思いますが、暗唱してもらいました」。
「詩について言えばだな」とハンプティ・ダンプティは、その大きな片手を伸ばしながら言いました。「わしは、その気になれば他の連中と同じくらい詩を暗唱できるのだぞ――」
「まあ、その気になる必要はありませんわ!」とアリスは、彼が始めるのを止めさせようと期待して、急いで言いました。
「わしがこれから暗唱する詩は」と彼は彼女の言葉に気づかずに続けました。「まったくお前の楽しみのために書かれたものだ」。
アリスは、それならば本当に聞くべきだと感じ、腰を下ろして、やや悲しげに「ありがとうございます」と言いました。
「冬になり、野が白いとき、 私はこの歌を、あなたの喜びのために歌う――
ただ、私は歌わんがな」と彼は説明として付け加えました。
「歌っていないのはわかります」とアリスは言いました。
「わしが歌っているかいないか見えるというのなら、お前はたいていの者より目がいいな」とハンプティ・ダンプティは厳しく言いました。アリスは黙っていました。
「春になり、森が緑になるとき、 私が何を言いたいか、伝えようとしよう。」
「どうもありがとうございます」とアリスは言いました。
「夏になり、日が長いとき、 たぶんあなたはその歌を理解するだろう。 秋になり、葉が茶色になるとき、 ペンとインクを取り、それを書き留めなさい。」
「もしそんなに長く覚えていられたら、そうします」とアリスは言いました。
「そんなふうに口答えを続ける必要はない」とハンプティ・ダンプティは言いました。「分別がないし、わしの邪魔になる」。
「私は魚に伝言を送った 私は彼らに言った『これが私の願いだ』と。 海の小さな魚たちは、 私に返事を送り返してきた。 小さな魚たちの返事はこうだった 『それはできません、あなた。なぜなら――』。」
「申し訳ありませんが、よくわかりません」とアリスは言いました。
「先へ進むともっと簡単になる」とハンプティ・ダンプティは答えました。
「私は再び彼らに伝言を送って言った 『従う方が良いだろう』と。 魚たちはにやりと笑って答えた 『おや、なんてご機嫌ななめなんだ!』 私は一度言った、二度言った 彼らは助言に耳を貸さなかった。 私は大きくて新しいやかを取った、 私がなすべき行いにふさわしいものを。 私の心は跳ね、私の心はどきどきした 私はポンプでやかんを満たした。 すると誰かが私のところへ来て言った 『小さな魚たちは寝ていますよ。』 私は彼に言った、はっきりと言った 『では、もう一度彼らを起こさなければならない。』 私はとても大きな声ではっきりと言った 私は行って彼の耳元で叫んだ。」
ハンプティ・ダンプティはこの節を繰り返すとき、ほとんど叫び声に近い声を出したので、アリスは身震いしながら思いました。「何があっても、わたしがあの伝言係にはなりたくないわ!」
「しかし彼はとても頑固で高慢だった 彼は言った『そんなに大声で叫ぶ必要はない!』と そして彼はとても高慢で頑固だった 彼は言った『私が行って彼らを起こそう、もし――』 私は棚からコルク抜きを取った 私は自分で彼らを起こしに行った。 そしてドアに鍵がかかっているとわかったとき、 私は引いたり押したり蹴ったり叩いたりした。 そしてドアが閉まっているとわかったとき、 私は取っ手を回そうとした、しかし――」
長い沈黙がありました。
「それで全部ですか?」とアリスは恐る恐る尋ねました。
「それで全部だ」とハンプティ・ダンプティは言いました。「さようなら」。
これはやや突然だ、とアリスは思いました。しかし、もう行くべきだという非常に強い示唆を受けた後では、とどまるのは失礼だろうと感じました。そこで彼女は立ち上がり、手を差し出しました。「さようなら、またお会いするまで!」と彼女はできるだけ陽気に言いました。
「もし会ったとしても、お前のことはわからないだろうな」とハンプティ・ダンプティは不満そうな口調で答え、指の一本を握手のために差し出しました。「お前は他の人間とそっくりだからな」。
「一般的には、顔で判断するものですけど」とアリスは考え深げな口調で言いました。
「それこそわしが不満に思っていることだ」とハンプティ・ダンプティは言いました。「お前の顔は誰もが持っているのと同じだ――二つの目、こんなふうに――」(親指で空中にその場所を示しながら)「真ん中に鼻、下に口。いつも同じだ。今、もしお前の二つの目が鼻の同じ側にあったり――あるいは口が一番上にあったりすれば――それはいくらか助けになるのだがな」。
「それは素敵に見えないでしょうね」とアリスは反対しました。しかし、ハンプティ・ダンプティはただ目を閉じて、「試してみるまで待て」と言いました。
アリスは彼がまた話すかどうか一分ほど待ちましたが、彼は決して目を開けたり、それ以上彼女に注意を払ったりしなかったので、彼女はもう一度「さようなら!」と言いました。そして、これにも返事がなかったので、静かに歩き去りました。しかし、歩きながら独り言を言わずにはいられませんでした。「今まで会った中で、いちばん不愉快な――」(彼女はこれを声に出して繰り返しました。そんな長い言葉を言えるのは大きな慰めだったので)「今まで会った中で、いちばん不愉快な人たちの中で――」彼女がその文を終えることはありませんでした。というのも、その瞬間、大きな衝突音が森の端から端までを揺るがしたからです。
第七章 ライオンとユニコーン
次の瞬間、兵士たちが森を駆け抜けてきました。最初は二人、三人、それから十人、二十人とまとまって、そして最後には森全体を埋め尽くすかのような大群になりました。アリスは轢かれるのを恐れて木の後ろに隠れ、彼らが通り過ぎるのを見ていました。
彼女は、これまでの人生で、これほど足元のおぼつかない兵士たちを見たことがないと思いました。彼らはいつも何やかやにつまずいており、一人が倒れると、必ずさらに数人がその上に倒れ込むので、地面はすぐに小さな人の山で覆われました。
次に馬がやって来ました。四本足なので、歩兵よりはいくぶんましでしたが、それでも時々つまずいていました。そして、馬がつまずくと、乗り手は即座に落馬するというのが、決まった規則のようでした。混乱は刻一刻とひどくなり、アリスは森を抜けて開けた場所に出られたことをとても喜びました。そこには白の王が地面に座り、熱心に手帳に何かを書き込んでいました。
「みんな送り出したぞ!」と王はアリスを見て、喜びの調子で叫びました。「森を通ってきたとき、兵士たちに会わなかったかね、お嬢さん?」
「はい、会いました」とアリスは言いました。「数千人はいたと思います」。
「四千二百七人、それが正確な数だ」と王は手帳を参照しながら言いました。「馬は全部は送れなかったのだよ、わかるかね、二頭はゲームで必要だからな。それに、二人の伝令も送っていない。彼らは二人とも町へ行ってしまった。ちょっと道をよく見て、どちらかが見えるか教えてくれないか」。
「道には誰も見えません」とアリスは言いました。
「わしにもそんな目があったらなあ」と王は不機嫌な口調で言いました。「『誰でもないさん』が見えるとは! しかもあんなに遠くから! いやはや、この明るさでは、本物の人間を見るのがわしには精一杯だというのに!」
この言葉はすべてアリスには通じませんでした。彼女はまだ片手で目を覆い、道を熱心に見つめていました。「今、誰か見えます!」と彼女はついに叫びました。「でも、とてもゆっくり来ています――それに、なんて奇妙な格好をするんでしょう!」(というのも、その伝令はやって来る間、ずっと飛び跳ねたり、ウナギのように身をくねらせたりしており、その大きな両手は扇のように左右に広げられていたからです。)
「いや、そんなことはない」と王は言いました。「彼はアングロサクソン風の伝令で――あれはアングロサクソン風の身振りなのだ。彼は嬉しいときにしか、あれはやらない。彼の名前はハイガだ」(彼は「mayor」と韻を踏むように発音しました。)
「わたしの愛する人はHで始まる」とアリスは思わず口ずさみ始めました。「なぜなら彼は幸せ(Happy)だから。わたしが彼を憎むのはHで始まる、なぜなら彼は醜い(Hideous)から。わたしが彼に食べさせたのは――ええと――ええと――ハムサンドイッチ(Ham-sandwiches)と干し草(Hay)。彼の名前はハイガで、彼が住んでいるのは――」
「彼は丘(Hill)の上に住んでいる」と王は、自分がゲームに参加しているとは微塵も思わずに、あっさりと述べました。その間、アリスはまだHで始まる町の名前をためらっていました。「もう一人の伝令はハッタという。二人いなければならんのだ、わかるかね――来たり行ったりするために。一人は来るため、もう一人は行くためだ」。
「失礼ですが?」とアリスは言いました。
「物乞い(beg)をするのは上品ではないぞ」と王は言いました。
「ただ、理解できなかったと申し上げただけです」とアリスは言いました。「なぜ一人は来るためで、一人は行くためなのですか?」
「言わなかったかね?」と王は焦れたように繰り返しました。「二人いなければならんのだ――取ってきたり運んだりするために。一人は取ってくるため、もう一人は運ぶためだ」。
その瞬間、伝令が到着しました。彼は息が切れすぎて一言も話せず、ただ両手を振り回し、哀れな王に向かってこの上なく恐ろしい顔をするばかりでした。
「このお嬢さんはあなたをHで愛しているそうだよ」と王は、伝令の注意を自分からそらすことを期待してアリスを紹介しましたが――無駄でした――アングロサクソン風の身振りは刻一刻と奇妙さを増し、その大きな目は左右に激しく動いていました。
「お前はわしを怖がらせる!」と王は言いました。「気分が悪い――ハムサンドイッチを一つくれ!」
すると、アリスがとても面白がったことに、伝令は首から下げた袋を開け、王にサンドイッチを手渡しました。王はそれをがつがつとむさぼり食いました。
「もう一つサンドイッチを!」と王は言いました。
「もう干し草しか残っていません」と伝令は袋の中を覗き込みながら言いました。
「では、干し草を」と王はかすかなささやき声でつぶやきました。
アリスは、それが王をずいぶん元気にしたのを見て喜びました。「気分が悪いときは、干し草を食べるにまさるものはないな」と彼はアリスに、もぐもぐと食べながら言いました。
「冷たい水をかける方が良いと思いますけど」とアリスは提案しました。「あるいは、気付け薬とか」。
「何もより良いものはないとは言っていない」と王は答えました。「それにまさるものはないと言ったのだ」。これにはアリスもあえて反論しませんでした。
「道で誰とすれ違ったかね?」と王は、もう少し干し草をもらおうと伝令に手を差し伸べながら続けました。
「誰とも(Nobody)」と伝令は言いました。
「その通りだ」と王は言いました。「このお嬢さんも彼を見た。だからもちろん、『誰でもないさん』はお前より歩くのが遅いのだな」。
「最善は尽くしています」と伝令は不機嫌な口調で言いました。「確かに、私よりずっと速く歩く人なんていませんよ!」
「そんなことはありえん」と王は言いました。「さもなければ、彼の方が先にここに着いていたはずだ。しかし、もう息も整ったことだろうから、町で何が起こったか話してくれてもよいぞ」。
「ささやきます」と伝令は言い、両手をトランペットの形にして口に当て、王の耳に近づくように身をかがめました。アリスは、自分もそのニュースを聞きたかったので、残念に思いました。しかし、ささやく代わりに、彼はただ声の限りに叫びました。「またやってます!」
「それをささやきと呼ぶのか!」と哀れな王は叫び、飛び上がって身を震わせました。「もう一度そんなことをしたら、お前にバターを塗ってやるぞ! 地震のように頭の中を突き抜けていったわ!」
「ずいぶん小さな地震でないといけませんわね!」とアリスは思いました。「誰がまたやっているのですか?」と彼女は思い切って尋ねました。
「もちろん、ライオンとユニコーンだ」と王は言いました。
「王冠をかけて戦っているのですか?」
「そうだ、その通り」と王は言いました。「そして、この冗談の面白いところは、それがずっとわしの王冠だということだ! 走って見に行こう」。そして彼らは小走りに駆け出しました。アリスは走りながら、古い歌の言葉を自分に言い聞かせるように繰り返しました。
「ライオンとユニコーンが王冠かけて戦ってた ライオンはユニコーンを町中打ち負かした ある者は白パンを、ある者は黒パンをあげた ある者はプラムケーキをあげて町から太鼓で追い出した。」
「勝った――方が――王冠を――もらえるのですか?」と彼女は、走ってすっかり息が切れていたので、できる限り尋ねました。
「とんでもない!」と王は言いました。「なんて考えだ!」
「恐れ入りますが」とアリスは、もう少し走ってから、息を切らしながら言いました。「少し――止まって――息を――整えさせていただけませんか?」
「わしは十分に親切(good)だが」と王は言いました。「ただ、十分に強くないのだ。わかるかね、一分というのは恐ろしく速く過ぎ去る。バンダースナッチを止めようとするようなものだ!」
アリスにはもう話す息も残っていなかったので、彼らは黙って小走りを続け、やがて大群衆が見えてきました。その真ん中で、ライオンとユニコーンが戦っていました。彼らはひどい砂埃の中にいたので、最初はアリスにはどちらがどちらか見分けがつきませんでした。しかし、すぐにユニコーンの角で見分けることができるようになりました。
彼らは、もう一人の伝令であるハッタが立って戦いを見ている場所のすぐ近くに陣取りました。ハッタは片手に紅茶のカップを、もう片手にパンとバターを持っていました。
「彼は刑務所から出たばかりで、送り込まれたときはまだ紅茶を飲み終えていなかったんだ」とハイガはアリスにささやきました。「それに、あそこではカキの殻しかもらえないからね――だから、とてもお腹が空いて喉が渇いているんだよ。元気かい、坊や?」と彼は続け、ハッタの首に親しげに腕を回しました。
ハッタは振り返ってうなずき、パンとバターを食べ続けました。
「刑務所では幸せだったかい、坊や?」とハイガは言いました。
ハッタはもう一度振り返り、今度は一、二滴の涙が頬を伝いました。しかし、一言も口にしようとはしませんでした。
「話せ、話せないのか!」とハイガは焦れたように叫びました。しかし、ハッタはただもぐもぐと食べ続け、紅茶をさらに飲みました。
「話せ、話さないのか!」と王は叫びました。「戦いの進み具合はどうだ?」
ハッタは必死の努力をして、大きなパンとバターのかけらを飲み込みました。「とてもうまく進んでいます」と彼は詰まった声で言いました。「それぞれ、八十七回ほど倒れています」。
「では、そろそろ白パンと黒パンを持ってくる頃でしょうか?」とアリスは思い切って言ってみました。
「もう彼らのために用意されていますよ」とハッタは言いました。「私が今食べているのが、その一部です」。
そのとき、戦いに小休止があり、ライオンとユニコーンは息を切らしながら座り込み、王が「休憩10分!」と叫びました。ハイガとハッタはすぐに仕事に取りかかり、白パンと黒パンの粗末な盆を運びました。アリスは味見に一切れ取りましたが、とてもパサパサしていました。
「今日はもうこれ以上戦わないだろう」と王はハッタに言いました。「行って、太鼓を始めるよう命じてこい」。そしてハッタはバッタのように跳ねながら去って行きました。
一、二分、アリスは黙って立ち、彼を見つめていました。突然、彼女の顔が輝きました。「見て、見て!」と彼女は熱心に指差しながら叫びました。「白の女王様が野原を横切って走っています! あちらの森から飛ぶように出てきました――女王様ってなんて足が速いんでしょう!」
「間違いなく、敵が追いかけているのだ」と王は、振り返りもせずに言いました。「あの森は敵でいっぱいだからな」。
「でも、助けに走っていかないのですか?」とアリスは、彼があまりに平然としているのにとても驚いて尋ねました。
「無駄だ、無駄だ!」と王は言いました。「彼女は恐ろしく速く走る。バンダースナッチを捕まえようとするようなものだ! だが、君が望むなら、彼女についてメモを取っておこう――彼女は心優しく良い人なのだ」と彼は手帳を開きながら、静かに独り言を繰り返しました。「『creature』の綴りは『e』が二つだったかな?」
その瞬間、ユニコーンがポケットに両手を突っ込んで、彼らのそばをぶらぶらと通り過ぎました。「今回はわしの方が優勢だったかな?」と彼は王に、通り過ぎながらちらりと見て言いました。
「少し――少しな」と王は、やや神経質に答えました。「角で彼を突き刺すべきではなかったぞ、わかるかね」。
「彼を傷つけはしなかった」とユニコーンは無頓着に言い、そのまま行こうとしましたが、そのとき偶然アリスに目が留まりました。彼はかなり素早く振り返り、しばらくの間、この上ない嫌悪感をたたえた表情で彼女を見ていました。
「これ――は――何だ?」と彼はついに言いました。
「これは子供です!」とハイガは、アリスの前に出て彼女を紹介し、アングロサクソン風の身振りで彼女に向かって両手を広げながら、熱心に答えました。「今日見つけたばかりです。等身大で、二倍自然です!」
「わしはてっきり、あれらは架空の怪物だと思っていた!」とユニコーンは言いました。「生きているのか?」
「話せます」とハイガは厳粛に言いました。
ユニコーンは夢見るようにアリスを見て、「話せ、子供」と言いました。
アリスは話し始めると、唇が思わず微笑みの形に歪むのを止められませんでした。「ご存知ですか、わたしもいつもユニコーンは架空の怪物だと思っていましたの! 生きているのは一度も見たことがありませんでした!」
「さて、こうしてお互いに会ったからには」とユニコーンは言いました。「君がわしを信じるなら、わしも君を信じよう。これで取引成立かな?」
「はい、よろしければ」とアリスは言いました。
「さあ、プラムケーキを持ってこい、おじいさん!」とユニコーンは、彼女から王の方へ向き直って続けました。「お前の黒パンなんぞ、わしはいらん!」
「もちろんだ――もちろんだとも!」と王はつぶやき、ハイガに手招きしました。「袋を開けろ!」と彼はささやきました。「早く! そっちじゃない――そっちは干し草でいっぱいだ!」
ハイガは袋から大きなケーキを取り出し、皿と切り分け用のナイフを取り出す間、アリスに持たせました。それらがどうやってすべて袋から出てきたのか、アリスには見当もつきませんでした。まるで手品のようだ、と彼女は思いました。
この間にライオンも加わっていました。彼はとても疲れて眠そうで、目は半分閉じていました。「これは何だ!」と彼は、アリスを怠惰そうにまばたきしながら、大きな鐘の響きのように聞こえる、深くうつろな声で言いました。
「ああ、さて、これは何でしょう?」とユニコーンは熱心に叫びました。「決して当てられませんよ! 私にもわかりませんでしたから」。
ライオンはうんざりした様子でアリスを見ました。「お前は動物か――植物か――それとも鉱物か?」と彼は、一言おきにあくびをしながら言いました。
「これは架空の怪物です!」とユニコーンは、アリスが答える前に叫びました。
「では、プラムケーキを回せ、怪物」とライオンは言い、横になって顎を前足の上に乗せました。「そして、二人とも座れ」(王とユニコーンに向かって)「ケーキは公平に分けるんだぞ、いいな!」
王は明らかに、二匹の大きな生き物の間に座らなければならないことに非常に居心地悪そうでしたが、彼のための他の場所はありませんでした。
「今なら、王冠をかけてどんな戦いができることか!」とユニコーンは、哀れな王があまりに震えるので頭から落ちそうになっている王冠を、ずる賢そうに見上げながら言いました。
「わしが楽に勝つだろう」とライオンは言いました。
「それはどうかな」とユニコーンは言いました。
「何を、わしがお前を町中打ち負かしたではないか、このひよっこめ!」とライオンは、言いながら半ば起き上がり、怒って答えました。
ここで王が、喧嘩が続くのを防ぐために割って入りました。彼は非常に神経質になっており、声はすっかり震えていました。「町中だと?」と彼は言いました。「それはずいぶん長い道のりだ。古い橋を通ったのか、それとも市場を通ったのか? 古い橋からだと一番良い景色が見えるぞ」。
「知るもんか」とライオンは、再び横になりながらうなりました。「砂埃がひどくて何も見えなかった。あの怪物は、ケーキを切るのにずいぶん時間がかかっているな!」
アリスは小さな小川の土手に腰を下ろし、大きな皿を膝に乗せ、ナイフでせっせと切り分けていました。「とても腹立たしいですわ!」と彼女はライオンに答えて言いました(彼女は「怪物」と呼ばれるのにすっかり慣れてきていました)。「もう何切れか切ったのに、いつもまたくっついてしまうんです!」
「君は鏡の国のケーキの扱い方を知らないのだな」とユニコーンは言いました。「先に回して、後から切るんだ」。
これは馬鹿げたことに聞こえましたが、アリスはとても素直に立ち上がり、皿を回して運びました。すると、彼女がそうするうちにケーキは三つに分かれました。「さあ、切り分けろ」とライオンは、彼女が空の皿を持って自分の場所に戻ると言いました。
「おい、これは不公平だぞ!」とユニコーンは叫びました。アリスがナイフを手に持ち、どうやって始めたらよいかとても困惑して座っていると。「怪物はわしよりライオンに二倍も多くやった!」
「とにかく、自分の分は取っていない」とライオンは言いました。「プラムケーキは好きか、怪物?」
しかし、アリスが彼に答える前に、太鼓が鳴り始めました。
どこからその音が来るのか、彼女にはわかりませんでした。空気はそれで満ちているようで、頭の中をがんがんと鳴り響き、すっかり耳が聞こえなくなったように感じました。彼女は恐怖に駆られて飛び上がり、小さな小川を飛び越えました。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * そして、ライオンとユニコーンが、ごちそうを中断されて怒った顔で立ち上がるのをちょうど見たかと思うと、彼女は膝から崩れ落ち、両手で耳を覆い、その恐ろしい騒音を必死に遮ろうとしました。
「もしあれで『町から太鼓で追い出せ』ないなら」と彼女は独り言を思いました。「何があっても無理でしょうね!」
第八章 「わたくし自身の発明。」
しばらくすると、騒音は次第に消えていくように思え、やがて完全な静寂が訪れました。アリスは少し不安になって頭を上げました。誰の姿も見えず、彼女が最初に思ったのは、ライオンとユニコーンと、あの奇妙なアングロサクソン風の伝令たちの夢を見ていたに違いないということでした。しかし、足元にはまだ、プラムケーキを切ろうとした大きな皿が横たわっていました。「だから、やっぱり夢を見ていたわけじゃなかったのね」と彼女は独り言を言いました。「でなければ――でなければ、わたしたちみんなが同じ夢の一部なのかしら。でも、どうか赤の王様の夢じゃなくて、わたしの夢でありますように! 他の人の夢に属するなんて嫌だわ」と彼女は、やや不満げな口調で続けました。「行って彼を起こして、何が起こるか見てみたい気もするわ!」
その瞬間、彼女の考えは「おーい! おーい! 王手!」という大きな叫び声によって中断されました。そして、深紅の鎧に身を包んだ騎士が、大きなこん棒を振り回しながら、彼女に向かって馬を飛ばしてきました。彼が彼女にたどり着いたちょうどその時、馬は突然止まりました。「お前は私の捕虜だ!」と騎士は、馬から転げ落ちながら叫びました。
驚きはしましたが、その瞬間、アリスは自分自身よりも彼のことを心配し、彼が再び馬に乗るのをいくらか不安げに見守っていました。彼が快適に鞍に収まると、彼は再び始めました。「お前は私の――」しかし、ここで別の声が割り込みました。「おーい! おーい! 王手!」アリスは新たな敵に、いくらか驚いてあたりを見回しました。
今度は白の騎士でした。彼はアリスのそばに馬を寄せ、赤の騎士がしたのとまったく同じように馬から転げ落ちました。それから彼は再び馬に乗り、二人の騎士はしばらくの間、何も言わずに互いを見つめて座っていました。アリスはいくらか困惑しながら、一人からもう一人へと目をやりました。
「彼女は私の捕虜だ、わかるかね!」と赤の騎士がついに言いました。
「ええ、しかし、それから私が来て彼女を救出したのです!」と白の騎士が答えました。
「では、彼女をかけて戦わねばならんな」と赤の騎士は言い、兜(鞍からぶら下がっており、馬の頭のような形をしていました)を取り上げてかぶりました。
「もちろん、戦いの規則は守るのでしょうな?」と白の騎士は、自分も兜をかぶりながら言いました。
「私はいつもそうしている」と赤の騎士は言い、二人はアリスがその打撃を避けるために木の後ろに隠れるほどの猛烈さで、互いに打ち合い始めました。
「さて、戦いの規則とは何かしら」と彼女は、隠れ場所から恐る恐る覗き見しながら、戦いを見つめて独り言を言いました。「一つの規則は、もし一人の騎士がもう一人を打つと、彼を馬から叩き落とし、もし外すと、自分自身が転げ落ちる、ということらしいわ――そしてもう一つの規則は、まるでパンチとジュディの人形のように、腕でこん棒を抱えることらしいわ――転げ落ちるとき、なんて大きな音を立てるんでしょう! まるで暖炉の火かき道具一式がフェンダーに落ちたみたい! そして馬たちはなんて静かなんでしょう! まるでテーブルでもあるかのように、乗り降りさせているわ!」
アリスが気づかなかったもう一つの戦いの規則は、彼らがいつも頭から落ちるということらしく、戦いは二人がこの方法で並んで落ちることで終わりました。彼らが再び起き上がると、握手を交わし、それから赤の騎士は馬に乗って走り去りました。
「輝かしい勝利でしたな、そうでしょう?」と白の騎士は、息を切らしながら近づいてきて言いました。
「わかりません」とアリスは疑わしげに言いました。「私は誰の捕虜にもなりたくありません。私は女王様になりたいのです」。
「次の小川を渡れば、そうなりますよ」と白の騎士は言いました。「森の終わりまで安全にお送りしましょう――そして、わたくしは戻らねばなりません、ご存知の通り。それがわたくしのコマの動きの終わりですからな」。
「どうもありがとうございます」とアリスは言いました。「ヘルメットを脱ぐのをお手伝いしましょうか?」 どうやら騎士が一人で脱ぐのは無理なようでしたが、それでもアリスはなんとか揺さぶって、とうとう脱がせてあげることができました。
「これでようやく息がしやすくなった」と騎士は言って、両手でもじゃもじゃの髪をかきあげ、その優しい顔と大きくて穏やかな瞳をアリスに向けました。アリスは、生まれてこのかた、これほど奇妙な格好の兵隊さんを見たことがないと思いました。
騎士はブリキの鎧を着ていましたが、どうにも体に合っていないようでした。そして、肩からは奇妙な形をした小さな木箱を、逆さまに、しかも蓋が開いたままでぶら下げていました。アリスは大変な好奇心でそれを見つめました。
「私の小箱を感心して見ているようだね」と騎士は親しげな口調で言いました。「これは私自身の発明品でね、服やサンドイッチを入れておくためのものだ。わかるだろう、逆さまに運んでいるのは、雨が入らないようにするためさ。」
「でも、中の物が外に出てしまいますわ」アリスはそっと指摘しました。「蓋が開いているのはご存知ですか?」
「知らなかった」と騎士は言い、その顔に悔しそうな色がよぎりました。「では、中の物はみんな落ちてしまったに違いない! それではこの箱も役に立たない」 彼はそう言うと箱を外し、茂みの中に投げ込もうとしましたが、ふと何か思いついたようで、丁寧に木の枝にかけました。「なぜ私がそうしたか、わかるかね?」と彼はアリスに言いました。
アリスは首を横に振りました。
「ミツバチが巣を作ってくれるかもしれないと期待してね。そうすればハチミツが手に入る。」
「でも、鞍にはハチの巣箱か、それに似たようなものがくくりつけてありますわ」とアリスは言いました。
「ああ、あれはとても良い巣箱だよ」と騎士は不満げな声で言いました。「最高級の品だ。だが、まだ一匹もハチが近寄ってこない。そしてもう一つはネズミ捕りだ。思うに、ネズミがハチを追い払っているか、あるいはハチがネズミを追い払っているのだろう。どちらかはわからんがね。」
「ネズミ捕りは何のためかしらと思っていました」とアリスは言いました。「馬の背中にネズミがいるなんて、あまりありそうもないですもの。」
「あまりありそうもない、かもしれん」と騎士は言いました。「だが、もし万が一来たら、そこら中を走り回られるのはごめんだからね。」
「わかるだろう」としばらくして彼は続けました。「何にでも備えておくのが一番なんだ。馬が足首にたくさんの足輪をつけているのも、そのためだよ。」
「でも、あれは何のためなのですか?」アリスは大変な好奇心を込めた声で尋ねました。
「サメに噛まれるのを防ぐためだ」と騎士は答えました。「私自身の発明品だよ。さて、乗るのを手伝ってくれ。森の終わりまで一緒に行こう。そのお皿は何のためだ?」
「プラムケーキ用ですわ」とアリスは言いました。
「一緒に持っていった方がいい」と騎士は言いました。「もしプラムケーキを見つけたら重宝するだろう。この袋に入れるのを手伝ってくれ。」
これにはとても長い時間がかかりました。アリスがとても慎重に袋の口を開けていたにもかかわらず、騎士がお皿を入れるのがあまりに不器用だったからです。最初の二、三回は、お皿の代わりに彼自身が袋に落ちてしまいました。「わかるだろう、かなりきついんだ」と、やっとのことで入れ終えたときに彼は言いました。「袋の中に燭台がたくさん入っているからね」そして彼はそれを鞍にぶら下げました。鞍にはすでにニンジンの束やら火かき棒やら、その他たくさんの物が積まれていました。
「髪はしっかり留めてあるかね?」出発しながら彼は続けました。
「ええ、いつものように」アリスは微笑んで言いました。
「それではほとんど不十分だ」と彼は心配そうに言いました。「わかるだろう、ここの風はとても強いんだ。スープと同じくらい強い。」
「髪が吹き飛ばされないようにする方法を発明なさいましたか?」アリスは尋ねました。
「まだだ」と騎士は言いました。「だが、抜け落ちるのを防ぐ方法は発明したよ。」
「ぜひお聞きしたいですわ。」
「まず、まっすぐな棒を一本用意する」と騎士は言いました。「それから髪を、果樹のようにその棒に這い上がらせるんだ。さて、髪が抜け落ちる理由は、下に垂れ下がっているからだ。物は決して上には落ちないからね、わかるだろう。これは私自身の発明した方法だ。よかったら試してみるといい。」
あまり快適な方法には聞こえないな、とアリスは思いました。そして数分間、その考えに頭を悩ませながら黙って歩き続け、時々立ち止まっては可哀想な騎士を手伝いました。彼は確かに乗馬が上手ではありませんでした。
馬が止まると(それはとても頻繁にありました)、彼は前に落馬し、再び動き出すと(それはたいていかなり突然でした)、彼は後ろに落馬しました。それ以外ではかなりうまく乗っていましたが、時々横に落馬する癖がありました。そして、たいていアリスが歩いている側に落ちるので、彼女はすぐに、馬のすぐそばを歩かないのが一番だと気づきました。
「あまり乗馬の練習をなさっていないのではありませんか」と、彼が五度目に落馬したのを助け起こしながら、彼女は思い切って言ってみました。
騎士はその言葉にとても驚き、少し気分を害したようでした。「なぜそう言うのかね?」と彼は尋ねました。鞍によじ登りながら、反対側に落ちないように片手でアリスの髪を掴んでいます。
「だって、たくさん練習した人は、そんなに頻繁に落馬しませんもの。」
「私は十分練習した」と騎士はとても真面目な顔で言いました。「十分すぎるほど練習したとも!」
アリスは「まあ、そうですの?」と言うより他に良い言葉が思いつきませんでしたが、できるだけ心を込めてそう言いました。その後、彼らはしばらく黙って進みました。騎士は目を閉じて何やらぶつぶつ独り言を言い、アリスは次の落馬はいつかと心配そうに見守っていました。
「乗馬の極意とは」と騎士は突然大声で話し始め、右腕を振り回しました。「つまり、保つことだ……」ここで文は始まったのと同じくらい突然終わり、騎士はアリスが歩いていた道の真ん中に、頭からまっさかさまに落ちました。今度はアリスもすっかり怯えてしまい、彼を助け起こしながら心配そうな声で言いました。「骨が折れていないといいのですが。」
「言うほどのことはない」と騎士は、二、三本折れても気にもしないかのように言いました。「乗馬の極意とは、先ほども言ったが、適切にバランスを保つことだ。このように、だね……」
彼は手綱を放し、アリスに意味をわからせようと両腕を広げました。そして今度は、馬の足元に仰向けにばったりと倒れました。
「十分練習したんだ!」アリスが彼を再び立たせている間中、彼は繰り返し続けました。「十分練習したとも!」
「あまりにも馬鹿げていますわ!」とアリスは今度こそ我慢の限界に達して叫びました。「あなたは車輪のついた木馬に乗るべきです、本当に!」
「その種のは滑らかに進むのかね?」と騎士は大変興味深そうな声で尋ね、また落馬する寸前で、馬の首に両腕を回してしがみつきました。
「生きている馬よりずっと滑らかですわ」とアリスは、こらえようとしてもこらえきれず、きゃっと笑い声をあげて言いました。
「一つ手に入れよう」と騎士は考え深げに独り言を言いました。「一つか二つ、いや、いくつか。」
この後、短い沈黙があり、それから騎士はまた話し始めました。「私は物事を発明するのが得意でね。さて、さっき君が私を助け起こした時、私が少々物思いにふけった顔をしていたのに気づいたかね?」
「ええ、少し真剣なご様子でしたわ」とアリスは言いました。
「うむ、ちょうどその時、門を乗り越える新しい方法を発明していたのだ。聞きたいかね?」
「ええ、ぜひ」とアリスは丁寧に言いました。
「どうやってそれを思いついたか話そう」と騎士は言いました。「私はこう自問したのだ、『唯一の難点は足だ。頭はもう十分高い』と。さて、まず門の一番上に頭を置く。それから逆立ちをする。そうすれば足は十分高くなるだろう。そして、乗り越えられる、というわけだ。」
「ええ、それができれば乗り越えられるでしょうけど」とアリスは考え深げに言いました。「でも、それはかなり難しくはありませんか?」
「まだ試していないのだ」と騎士は真面目な顔で言いました。「だから確かなことは言えんが、おそらく少しは難しいだろうな。」
彼がその考えにとても悔しそうな顔をしたので、アリスは急いで話題を変えました。「なんて珍しいヘルメットをお持ちなんでしょう!」と彼女は明るく言いました。「それもあなたの発明品ですか?」
騎士は鞍からぶら下がっている自分のヘルメットを誇らしげに見下ろしました。「そうだ」と彼は言いました。「だが、あれより良いものを発明した。砂糖の塊みたいな形のやつだ。あれを被っていた頃は、馬から落ちても、ヘルメットがすぐに地面についた。だから、落ちる距離はほんのわずかだったのだ。だが、確かに、その中に落ちてしまう危険はあった。一度そうなったことがあってね。最悪なことに、私が抜け出す前に、もう一人の白の騎士がやって来てそれを被ってしまったのだ。自分のヘルメットだと思ったらしい。」
騎士があまりに真剣な顔でその話をするので、アリスは笑う気になれませんでした。「きっと彼を傷つけてしまったでしょうね」と彼女は震える声で言いました。「彼の頭の上に乗っていたのですから。」
「もちろん、蹴らなければならなかった」と騎士は非常に真面目に言いました。「それで彼は再びヘルメットを脱いだが、私を出すのに何時間もかかった。私はもう、稲妻みたいに……みたいに、しっかりハマってしまってね。」
「でも、それは違う種類の『しっかり』ですわ」とアリスは反論しました。[訳注:「fast」には「速い」と「固くくっついている」という意味がある]
騎士は首を振りました。「私にとっては、ありとあらゆる種類の『しっかり』でしたとも!」と彼は言いました。これを言うと彼は興奮して両手を上げ、即座に鞍から転げ落ち、深い溝にまっさかさまに落ちていきました。
アリスは溝のそばに駆け寄って彼を探しました。しばらくの間はうまく乗っていたので、この落馬にはかなり驚き、今度こそ本当に怪我をしたのではないかと心配しました。しかし、彼の足の裏しか見えませんでしたが、いつもの口調で話し続けているのが聞こえて、とても安心しました。「ありとあらゆる種類の『しっかり』だ」と彼は繰り返しました。「それにしても、他人のヘルメットを被るとは不注意な男だ。しかも、持ち主が中に入っているというのに。」
「どうしてそんなに平気で、逆さまのままお話ができるのですか?」アリスは、彼の足を引っ張って溝から引きずり出し、土手の上にぐったりと横たえながら尋ねました。
騎士はその質問に驚いたようでした。「私の体がどこにあろうと、何の問題があるかね?」と彼は言いました。「私の心は同じように働き続ける。実際、頭が下になればなるほど、私はどんどん新しいものを発明するのだ。」
「さて、私がこれまでやったこの種のことで最も賢いことと言えば」としばらくして彼は続けました。「肉料理のコースの間に新しいプディングを発明したことだ。」
「次のコースのために調理が間に合うようにですか?」とアリスは言いました。「いや、次のコースではない」と騎士はゆっくりと考え深げな声で言いました。「いや、断じて次のコースではない。」
「では、次の日ということになりますわね。一つの夕食でプディングのコースが二つあるなんてことはないでしょうし。」
「いや、次の日でもない」と騎士は前と同じように繰り返しました。「次の日でもない。実を言うと」と彼はうつむき、声がどんどん低くなりながら続けました。「あのプディングが調理されたとは到底思えん! 実を言うと、あのプディングが今後調理されるとも思えんのだ! それでも、発明するにはとても賢いプディングだったのだが。」
「何でできているつもりだったのですか?」アリスは彼を元気づけようと尋ねました。可哀想な騎士は、そのことでかなり落ち込んでいるように見えたからです。
「吸い取り紙から始まった」と騎士はうめきながら答えました。
「それはあまり美味しくなさそうですわね……」
「それだけでは美味しくない」と彼はかなり熱心に割り込みました。「だが、他のものと混ぜるとどれほど違うか、君には想像もつかないだろう。火薬や封蝋のようなものとだ。そして、ここでお別れしなければならない」彼らはちょうど森の終わりに着いたところでした。
アリスは困惑した表情をするしかありませんでした。プディングのことを考えていたのです。
「悲しんでいるようだね」と騎士は心配そうな声で言いました。「君を慰めるために歌を歌ってあげよう。」
「とても長いのですか?」とアリスは尋ねました。その日はもうたくさんの詩を聞いていたからです。
「長いよ」と騎士は言いました。「だが、とても、とても美しい。私が歌うのを聞いた者は皆、目に涙を浮かべるか、さもなければ……」
「さもなければ何ですの?」とアリスは言いました。騎士が急に黙り込んだからです。
「さもなければそうならない、というわけだ。歌の名前は『タラの目』と呼ばれている。」
「あら、それが歌の名前なのですか?」アリスは興味を持とうとしながら言いました。
「いや、わかっていないね」と騎士は少し腹立たしげに言いました。「それは名前がそう呼ばれているだけだ。本当の名前は『歳とった歳とった男』なのだ。」
「では、『それが歌の呼ばれ方ですのね』と言うべきでしたか?」アリスは言い直しました。
「いや、そうではない。それは全く別のことだ! 歌は『方策』と呼ばれている。だが、それはただそう呼ばれているだけだ、わかるだろう!」
「では、一体その歌は何なのですか?」とアリスは言いました。この時までにはすっかり混乱していました。
「ちょうどそれを話そうとしていたところだ」と騎士は言いました。「歌は本当は『門に腰掛けて』というのだ。そして曲は私自身の発明だ。」
そう言うと、彼は馬を止め、手綱を首に垂らしました。それから、片手でゆっくりと拍子を取り、まるで自分の歌の音楽を楽しんでいるかのように、その優しくもおかしな顔に微かな笑みを浮かべながら、歌い始めました。
アリスが鏡の国を旅する中で見たあらゆる不思議なことの中で、これこそが彼女がいつも最も鮮明に記憶しているものでした。何年も後になっても、彼女はその光景全体を、まるで昨日のことであったかのように思い出すことができました。騎士の穏やかな青い瞳と親切な微笑み、彼の髪を通してきらめく夕日、そして彼女を眩惑するほどの輝きで彼の鎧を照らす光、手綱を首にだらりと垂らし、足元の草を食みながら静かに動き回る馬、そして背後にある森の黒い影。これらすべてを彼女は一枚の絵のように心に焼き付けました。片手で目を覆い、木に寄りかかりながら、その奇妙な二人組を見つめ、半ば夢うつつで、その歌の物悲しい音楽に耳を傾けていました。
「でも、この曲は彼自身の発明じゃないわ」と彼女は独り言を言いました。「これは『我が全てを汝に捧ぐ』だわ」彼女は立って注意深く耳を傾けましたが、目に涙は浮かびませんでした。
「話せることはすべて話そう。 語るべきことはほとんどないが。 私は見た、歳とった歳とった男を、 門に腰掛けているのを。 『あなたは何者です、お爺さん?』私は言った、 『そして、どうやって暮らしているのです?』 すると彼の答えは私の頭をすり抜けていった まるで篩を通り抜ける水のように。 彼は言った『私は蝶を探している 麦畑で眠る蝶を。 それをマトンパイにして、 通りで売るのだ。 男たちに売るのだ』と彼は言った、 『荒れた海を航海する男たちに。 そうやって私はパンを得るのだ、 ほんのわずかなものだがね。』 しかし私はある計画を考えていた 自分の頬ひげを緑に染める計画を、 そしていつもとても大きな扇子を使うので それが見えないようにする計画を。 だから、返事のしようもなかったので その老人が言ったことに、 私は叫んだ、『さあ、どうやって暮らしているか教えてくれ!』 そして彼の頭をどついた。 彼の穏やかな口調は話を続けた。 彼は言った『私は自分の道を行く、 そして山の小川を見つけると、 それに火をつけるのだ。 そこから彼らはある物を作る、彼らが呼ぶところの ローランズ・マカッサル・オイルを。 だが、二ペンス半が全てだ 私の労苦に対して彼らがくれるのは。』 しかし私はある方法を考えていた バター生地で自分を養う方法を、 そうして毎日毎日 少しずつ太っていく方法を。 私は彼を左右によく揺さぶった、 彼の顔が青くなるまで。 『さあ、どうやって暮らしているか教えてくれ』私は叫んだ、 『そして何をしているのかを!』 彼は言った『私はタラの目を探す 明るいヒースの茂みの中で、 そしてそれをチョッキのボタンに仕立てるのだ 静かな夜に。 そしてこれらを私は金では売らない あるいは銀色に輝く硬貨でも。 だが銅の半ペニーのためなら、 それで九つ買えるだろう。 『私は時々バター付きロールパンを掘り、 あるいはカニのために鳥もちの枝を仕掛ける。 私は時々草の生えた小丘を探す 辻馬車の車輪のために。 そしてそれが方法なのだ』(彼はウィンクした) 『私が富を得る方法は。 そして喜んで飲み干しましょう 閣下の高貴なるご健康を。』 私はその時彼の話を聞いた、ちょうど 私の計画が完成したところだったので。 メナイ橋を錆から守るために ワインで煮るという計画が。 私は彼に大いに感謝した、私に教えてくれたことを 彼が富を得る方法を、 しかし主に、彼が願ってくれたことに対して 私の高貴なる健康を祝して飲みたいと。 そして今、もし偶然にも私が 指をにかわの中に入れてしまったり あるいは狂ったように右足を 左の靴に押し込んだり、 あるいはもし私のつま先の上に落としたりしたら とても重い重りを、 私は泣く、それは私に思い出させるから、 私がかつて知っていたあの老人のことを。 その眼差しは穏やかで、その話し方はゆっくりで、 その髪は雪よりも白く、 その顔はカラスによく似て、 燃え殻のような目で、一面に輝き、 その悲しみに取り乱しているように見え、 その体を前後に揺らし、 もぐもぐと低くつぶやき、 まるで口がパン生地でいっぱいのようで、 水牛のように鼻を鳴らした、 あの夏の夕べ、遠い昔の、 門に腰掛けていたのを。」
騎士がバラードの最後の言葉を歌い終えると、彼は手綱を引き寄せ、来た道を戻るように馬の頭を向けました。「君はもうほんの数ヤード行くだけだ」と彼は言いました。「丘を下り、あの小さな小川を渡れば、君は女王になる。だが、先ずは私を見送ってくれるだろう?」と彼は、アリスが指さす方向に熱心な眼差しで向きを変えた時に付け加えました。「長くはかからない。私が道のあの曲がり角に着いたら、待っていてハンカチを振ってくれるかね? それが励みになると思うんだ、わかるだろう。」
「もちろん、お待ちしますわ」とアリスは言いました。「そして、こんなに遠くまで来てくださって、本当にありがとうございます。歌も、とても気に入りました。」
「そうだといいのだが」と騎士は疑わしげに言いました。「だが、私が思っていたほどは泣かなかったな。」
そうして二人は握手をし、それから騎士はゆっくりと森の中へ馬を進めていきました。「彼を見送るのに、そう長くはかからないでしょうね」とアリスは、彼を見守りながら独り言を言いました。「ほら、行ったわ! いつものように頭からまっさかさま! でも、かなり簡単にまた馬に乗るわね。馬の周りにあんなにたくさんの物をぶら下げているおかげだわ」アリスはそう独り言を言い続けながら、馬がのんびりと道を進み、騎士がまず片側に、次に反対側にと落馬するのを見ていました。四、五回落馬した後、彼は曲がり角にたどり着き、そこでアリスは彼にハンカチを振って、彼が見えなくなるまで待ちました。
「励みになったといいのだけれど」と彼女は丘を駆け下りながら言いました。「そして、いよいよ最後の小川を渡って女王になるのね! なんて素敵な響きかしら!」ほんの数歩で彼女は小川のほとりに着きました。「とうとう第八マスだわ!」と彼女は向こう岸へ跳び越えながら叫びました。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * そして、苔のように柔らかい芝生の上に身を投げ出して休みました。そこには小さな花壇が点在していました。「ああ、ここに来られてなんて嬉しいんでしょう! それに、頭の上のこれは何かしら?」と彼女は、何かとても重く、頭の周りにぴったりとはまっているものに手をやりながら、狼狽した声で叫びました。
「でも、どうして私が気づかないうちにこんなものがここにあるのかしら?」と彼女は独り言を言いながら、それを持ち上げて膝の上に置き、一体何なのか確かめようとしました。
それは金の王冠でした。
第九章 女王アリス
「まあ、これは素晴らしいわ!」とアリスは言いました。「こんなに早く女王になれるなんて思ってもみませんでした。そして陛下、申し上げますが」と彼女は厳しい口調で続けました(彼女は自分を叱るのがどちらかというと好きなのです)。「そんな風に芝生の上でだらだらしているなんて、決して許されませんよ! 女王は威厳を持たなければならないのですからね!」
そこで彼女は立ち上がって歩き回りました。最初は王冠が落ちるのではないかと心配で、少々ぎこちない歩き方でした。しかし、誰も見ていないという考えに慰められました。「それに、もし私が本当に女王なら」と彼女は再び座りながら言いました。「そのうち、うまく扱えるようになるでしょう。」
何もかもがあまりに奇妙に起こるので、彼女は赤の女王と白の女王が自分のすぐそばに、それぞれ両側に座っているのを見つけても、少しも驚きませんでした。彼女は二人がどうやってそこに来たのかとても尋ねてみたかったのですが、それでは少々失礼にあたるのではないかと恐れました。しかし、ゲームが終わったかどうか尋ねるくらいなら差し支えないだろうと彼女は思いました。「あの、教えていただけますか……」と彼女は、おずおずと赤の女王を見ながら話し始めました。
「話しかけられた時だけ話しなさい!」と女王は鋭く彼女を遮りました。
「でも、もし皆がそのルールに従って」と、いつでもちょっとした議論の用意があるアリスは言いました。「そして、あなたが話しかけられた時だけ話して、相手もいつもあなたが話し始めるのを待っていたら、誰も何も言えなくなってしまいますわ、だから……」
「馬鹿馬鹿しい!」と女王は叫びました。「なぜわからないのかね、おチビさん……」ここで彼女は眉をひそめて言葉を切り、一分ほど考えた後、突然会話の話題を変えました。「『もし私が本当に女王なら』とはどういう意味だ? 自分をそう呼ぶ権利がどこにある? しかるべき試験に合格するまでは、女王にはなれないのだよ。そして、それを始めるのは早ければ早いほど良い。」
「私はただ『もし』と言っただけです!」と可哀想なアリスは哀れな声で訴えました。
二人の女王は顔を見合わせ、赤の女王は少し身震いしながら言いました。「この子はただ『もし』と言っただけだと申しておりますが……」
「でも、あの子はそれよりずっと多くのことを言いましたわ!」と白の女王は両手を絞りながら嘆きました。「ああ、それよりずっとずっと多くのことを!」
「その通りだ、わかっているだろう」と赤の女王はアリスに言いました。「常に真実を語り、話す前に考え、そして後でそれを書き留めることだ。」
「私は決してそんなつもりでは……」とアリスは言いかけましたが、赤の女王がじれったそうに遮りました。
「それこそ私が文句を言っていることだ! つもりであるべきだったのだ! 意味のない子供に何の使い道があると思う? 冗談でさえ何かしらの意味があるべきだ。そして子供は冗談より重要だろう、そう願いたいね。両手で試したところで、それを否定することはできまい。」
「私は手で物事を否定したりしませんわ」とアリスは反論しました。
「誰も君がそうしたとは言っておらん」と赤の女王は言いました。「試したとしてもできないと言ったのだ。」
「この子はそういう気分なのですわ」と白の女王は言いました。「何かを否定したいのだけれど、何を否定すればいいのかわからないのです!」
「意地悪で、たちの悪い気性だ」と赤の女王は述べました。そして、一、二分、気まずい沈黙が続きました。
赤の女王が白の女王に言うことで沈黙を破りました。「今日の午後、アリスの晩餐会にあなたをご招待します。」
白の女王は弱々しく微笑んで言いました。「そして私もあなたをご招待しますわ。」
「私がパーティーを開くことになっているなんて知りませんでしたわ」とアリスは言いました。「でも、もし開くのでしたら、招待客は私が招くべきだと思います。」
「我々はお前にそうする機会を与えたのだ」と赤の女王は述べました。「だが、お前はまだ行儀作法の授業をあまり受けていないのだろう?」
「行儀作法は授業では教わりませんわ」とアリスは言いました。「授業では計算とか、そういうことを教わります。」
「では足し算はできますの?」と白の女王が尋ねました。「一足す一足す一足す一足す一足す一足す一足す一足す一足す一はいくつ?」
「わかりません」とアリスは言いました。「途中でわからなくなりました。」
「この子は足し算ができない」と赤の女王が割り込みました。「引き算はできるか? 八から九を引け。」
「八から九は引けませんわ、ご存知でしょう」とアリスはすぐに答えました。「でも……」
「この子は引き算ができませんわ」と白の女王は言いました。「割り算はできますの? パンをナイフで割る。その答えは何です?」
「おそらく……」とアリスが言いかけると、赤の女王が代わりに答えました。「バター付きパンに決まっている。別の引き算の問題を試してみよう。犬から骨を取る。何が残る?」
アリスは考えました。「骨は残らないでしょうね、もちろん、私が取ってしまったら。犬も残らないでしょう、私に噛みつきに来るでしょうから。そして、きっと私も残らないでしょう!」
「では、何も残らないと思うかね?」と赤の女王は言いました。
「それが答えだと思います。」
「間違いだ、いつものことだが」と赤の女王は言いました。「犬の癇癪が残る。」
「でも、どうして……」
「なぜって、ほら!」と赤の女王は叫びました。「犬は癇癪を失うだろう?」[訳注:「lose one's temper」は「癇癪を起す」という意味の熟語]
「たぶんそうでしょうね」とアリスは慎重に答えました。
「ならば犬が去れば、その癇癪は残るのだ!」と女王は勝ち誇って叫びました。
アリスはできるだけ真面目な顔で言いました。「別々の道を行くかもしれませんわ」しかし、心の中では「なんてひどい馬鹿げた話をしているのかしら!」と思わずにはいられませんでした。
「この子は計算が全然できない!」と女王たちは声をそろえて、大いに強調して言いました。
「あなたは計算ができますの?」とアリスは、あまりに粗探しをされるのが嫌で、突然白の女王の方を向いて言いました。
女王は息をのみ、目を閉じました。「足し算ならできますわ、時間をいただければ。でも引き算は、どんな状況でもできませんの!」
「もちろん、ABCは知っているだろうね?」と赤の女王が言いました。
「ええ、もちろん知っています」とアリスは言いました。
「私もですわ」と白の女王がささやきました。「一緒に何度も唱えましょうね、あなた。そして秘密を教えてあげますわ。私は一文字の単語が読めるのです! それって素敵でしょう! でも、がっかりしないで。あなたもそのうちできるようになりますから。」
ここで赤の女王が再び始めました。「役に立つ質問に答えられるかね?」と彼女は言いました。「パンはどうやって作られる?」
「それは知っています!」とアリスは熱心に叫びました。「フラワーをいくつか取ってきて……」
「そのフラワー(お花)はどこで摘むのですか?」と白の女王が尋ねました。「お庭で、それとも生け垣で?」[訳注:英語では小麦粉(flour)と花(flower)は同じ発音]
「いえ、摘むのではなくて」とアリスは説明しました。「挽くんです……」
「何エーカーの土地(グラウンド)を?」と白の女王は言いました。「そんなにたくさんのことを省略してはいけませんわ」[訳注:英語では「ground」は「挽かれた」と「地面」の両方の意味を持つ]
「あの子の頭を扇いで!」と赤の女王が心配そうに割り込みました。「そんなに考えたら熱が出ますよ」そこで二人は葉の束で彼女を扇ぎ始め、髪がひどく乱れるので、アリスがやめてくれるよう頼まなければならないほどでした。
「これでまた大丈夫だ」と赤の女王は言いました。「外国語は知っているかね? 『フィドル・ディ・ディー』のフランス語は何だ?」
「『フィドル・ディ・ディー』は英語ではありませんわ」とアリスは真面目に答えました。
「誰が英語だと言った?」と赤の女王は言いました。
アリスは今度こそこの難局を切り抜ける方法を見つけたと思いました。「『フィドル・ディ・ディー』がどこの国の言葉か教えてくだされば、そのフランス語をお教えしますわ!」と彼女は勝ち誇って叫びました。
しかし、赤の女王は少々堅苦しく背筋を伸ばし、「女王は取引などしない」と言いました。
「女王が質問なんてしなければいいのに」とアリスは心の中で思いました。
「喧嘩はやめましょうよ」と白の女王が心配そうな声で言いました。「稲妻の原因は何ですの?」
「稲妻の原因は」とアリスは、これには बिल्कुल自信があったので、きっぱりと言いました。「雷です。いえ、いえ!」と彼女は慌てて訂正しました。「反対の意味でした。」
「訂正するには遅すぎる」と赤の女王は言いました。「一度言ってしまったことは、それで決まりだ。結果は受け入れなければならん。」
「それで思い出しましたわ」と白の女王は、うつむいて神経質に両手を組んだりほどいたりしながら言いました。「先週の火曜日に、それはひどい雷雨があったのです。つまり、先週の一連の火曜日のうちの一つですけれどね。」
アリスは困惑しました。「私たちの国では」と彼女は述べました。「一日に一回しか曜日がありませんわ。」
赤の女王は言いました。「それは貧弱で薄っぺらなやり方だ。さて、ここでは、たいてい昼と夜が一度に二つか三つあるし、冬には五晩まとめて過ごすこともある。暖かいためだよ、わかるだろう。」
「では、五晩は一晩より暖かいのですか?」アリスは思い切って尋ねてみました。
「もちろん、五倍暖かい。」
「でも、同じ理屈なら、五倍寒いはずですわ。」
「その通り!」と赤の女王は叫びました。「五倍暖かく、そして五倍寒い。ちょうど私が君より五倍金持ちで、そして五倍賢いのと同じようにね!」
アリスはため息をついて諦めました。「まるで答えのないなぞなぞみたいだわ!」と彼女は思いました。
「ハンプティ・ダンプティもそれを見ていましたわ」と白の女王は、まるで独り言のように低い声で続けました。「彼はコルク抜きを手に戸口へやって来ました……」
「何が望みだったのだ?」と赤の女王が言いました。
「彼は中に入ると言いましたの」と白の女王は続けました。「カバを探していたからですって。さて、たまたま、その朝は家にはそんなものはありませんでしたの。」
「普段はいるのですか?」アリスは驚いた声で尋ねました。
「ええ、木曜日だけですわ」と女王は言いました。
「彼が何のために来たか知っていますわ」とアリスは言いました。「魚を罰したかったのよ、だって……」
ここで白の女王が再び始めました。「それはひどい雷雨でしたの、想像もつかないでしょうけど!」(「この子には絶対無理よ、わかるでしょ」と赤の女王が言いました。)「そして屋根の一部が吹き飛んで、ものすごい量の雷が入り込んできたのです。そして大きな塊になって部屋中を転がり回り、テーブルや物をひっくり返して、私はあまりに怖くて、自分の名前も思い出せませんでしたの!」
アリスは心の中で思いました。「事故の真っ最中に自分の名前を思い出そうなんて、私なら絶対しないわ! 何の役に立つのかしら?」しかし、可哀想な女王の気持ちを傷つけるのを恐れて、これは声に出しては言いませんでした。
「陛下、この子をお許しください」と赤の女王は、白の女王の手の一つを自分の手に取り、優しく撫でながらアリスに言いました。「この子は悪気はないのですが、概して、馬鹿なことを言わずにはいられないのです。」
白の女王がおずおずとアリスを見ると、アリスは何か親切なことを言うべきだと感じましたが、その瞬間には本当に何も思いつきませんでした。
「この子はきちんとしつけられたことがないのです」と赤の女王は続けました。「でも、気立てが良いのには驚かされます! 頭を撫でてあげなさい、どれほど喜ぶか見てごらんなさい!」しかし、アリスにはそこまでする勇気はありませんでした。
「少しの親切と、髪を紙で巻いてあげれば、この子は見違えるようになりますわ。」
白の女王は深いため息をつき、アリスの肩に頭を乗せました。「私、とても眠たいのです」と彼女は嘆きました。
「お疲れなのね、可哀想に!」と赤の女王は言いました。「髪を撫でてあげて、あなたのナイトキャップを貸してあげて、そして心安らぐ子守唄を歌ってあげなさい。」
「ナイトキャップは持っていませんわ」とアリスは、最初の指示に従おうとしながら言いました。「それに、心安らぐ子守唄も知りません。」
「では私が自分でやらなければなりませんね」と赤の女王は言って、歌い始めました。
「ねんねしな、お嬢さん、アリスの膝で! ごちそうができるまで、お昼寝の時間よ。 ごちそうが終わったら、舞踏会に行きましょう、 赤の女王、白の女王、アリス、そしてみんなで!
「さあ、歌詞はわかったでしょう」と彼女は、アリスのもう片方の肩に頭を乗せながら付け加えました。「今度は私に歌ってちょうだい。私も眠くなってきたわ」次の瞬間には、両方の女王はぐっすりと眠り込み、大きないびきをかいていました。
「どうしたらいいのかしら?」とアリスは、まず一つの丸い頭が、次に別の頭が、彼女の肩から転がり落ち、重い塊のように膝の上に横たわるのを見て、大いに当惑して叫びました。「一度に二人の眠っている女王の世話をしなければならなかったなんて、これまで一度もなかったと思うわ! いいえ、イギリスの歴史の中でも、そんなことはあり得なかったわ。だって、一度に一人しか女王はいなかったんですもの。目を覚ましてちょうだい、この重たい人たち!」と彼女はじれったい声で続けましたが、穏やかないびき以外の返事はありませんでした。
いびきは分ごとにますますはっきりとし、だんだん曲のように聞こえてきました。とうとう彼女は言葉さえ聞き取れるようになり、あまりに熱心に耳を傾けていたので、二つの大きな頭が膝から消えた時も、ほとんど気づきませんでした。
彼女はアーチ型の戸口の前に立っていました。その上には大きな文字で「女王アリス」と書かれており、アーチの両側にはベルの取っ手がありました。一つには「訪問者用ベル」、もう一つには「使用人用ベル」と記されていました。
「歌が終わるまで待とう」とアリスは思いました。「それから鳴らそう。でも、どっちのベルを鳴らさなければならないのかしら?」と彼女は、その名前にとても戸惑いながら続けました。「私は訪問者でもないし、使用人でもないわ。『女王』と書かれたベルがあるべきなのに。」
ちょうどその時、ドアが少し開き、長いくちばしを持つ生き物が一瞬頭を突き出して「来週の次の週まで入場禁止!」と言い、再びドアをバタンと閉めました。
アリスは長い間ノックしたりベルを鳴らしたりしましたが、無駄でした。しかし、ついに、木の下に座っていた非常に年老いたカエルが立ち上がり、ゆっくりと彼女の方へよろよろと歩いてきました。彼は鮮やかな黄色い服を着て、巨大なブーツを履いていました。
「今度は何だね?」とカエルは深いしわがれ声でささやきました。
アリスは振り向き、誰にでも文句を言う準備ができていました。「ドアに応対するのが仕事の使用人はどこにいるの?」と彼女は怒って言い始めました。
「どのドアだね?」とカエルは言いました。
アリスは、彼のゆっくりとした話し方にいら立って、ほとんど足を踏み鳴らしそうになりました。「このドアに決まっているでしょう!」
カエルは大きな鈍い目でドアをしばらく見つめました。それから近づいて親指でこすり、まるでペンキが剥げるかどうか試しているかのようでした。それからアリスを見ました。
「ドアに応対する?」と彼は言いました。「ドアが何を尋ねてきたんだい?」彼はあまりにしわがれ声だったので、アリスにはほとんど聞こえませんでした。
「どういう意味かわかりませんわ」と彼女は言いました。
「わしは英語を話しているだろう?」とカエルは続けました。「それとも耳が聞こえんのか? ドアがお前に何を尋ねたんだ?」
「何も!」とアリスはじれったそうに言いました。「私はノックしていたのよ!」
「そんなことはするべきじゃない、するべきじゃない」とカエルはつぶやきました。「ドアをいらいらさせるからね」それから彼は近づいて、大きな足の一つでドアを蹴りました。「そいつを放っておけ」と彼は、木の方へよろよろと戻りながら、息を切らして言いました。「そうすれば、そいつもお前を放っておいてくれる、わかるだろう。」
その瞬間、ドアが勢いよく開かれ、甲高い声が歌うのが聞こえました。
「鏡の国の世界にアリスは言った、 『手には王笏、頭には王冠。 鏡の国の生き物たちよ、何者であれ、 赤の女王、白の女王、そして私と食事に来なさい』。」
そして何百もの声が合唱に加わりました。
「さあ、グラスをできるだけ早く満たし、 テーブルにボタンとふすまを振りかけよ。 コーヒーに猫を、紅茶にネズミを入れ、 女王アリスを三十回かける三で歓迎せよ!」
それから混乱した歓声が続き、アリスは心の中で思いました。「三十回かける三は九十だわ。誰か数えているのかしら?」一分後には再び静寂が訪れ、同じ甲高い声が別の節を歌いました。
「『おお、鏡の国の生き物たちよ』とアリスは言った、『近くに来なさい! 私を見るは名誉、聞くは恩恵。 夕食と紅茶を共にするは高き特権、 赤の女王、白の女王、そして私と!』。」
それから再び合唱が始まりました。
「さあ、グラスを糖蜜とインクで満たせ、 あるいは他に飲むのに楽しいものなら何でも。 サイダーに砂を、ワインに羊毛を混ぜ、 女王アリスを九十回かける九で歓迎せよ!」
「九十回かける九!」とアリスは絶望して繰り返しました。「ああ、そんなの終わりっこないわ! すぐに入った方がいいわ」そして、彼女が現れた瞬間、あたりは静まり返りました。
アリスは大きなホールを歩きながら、神経質にテーブルに沿って目をやり、あらゆる種類の五十人ほどの客がいることに気づきました。動物もいれば、鳥もいて、中には花さえも数輪いました。「招待されるのを待たずに来てくれてよかったわ」と彼女は思いました。「誰を招待するのが正しい人たちなのか、私には到底わからなかったでしょうから!」
テーブルの上座には三つの椅子がありました。赤と白の女王はすでにそのうちの二つに座っていましたが、真ん中の一つは空いていました。アリスはそこに座りましたが、沈黙の中で少々居心地が悪く、誰かが話してくれるのを待ち望んでいました。
ついに赤の女王が話し始めました。「スープと魚は逃したな」と彼女は言いました。「肉の盛り合わせを出しなさい!」そして給仕たちが羊のもも肉をアリスの前に置きました。アリスは、これまで肉の塊を切り分けたことがなかったので、少々心配そうにそれを見つめました。
「少し恥ずかしそうだね。その羊のもも肉に紹介しよう」と赤の女王は言いました。「アリス、もも肉。もも肉、アリス」羊のもも肉は皿の中で立ち上がり、アリスに小さくお辞儀をしました。アリスも、怖がっていいのか面白がっていいのかわからずに、お辞儀を返しました。
「一切れ差し上げてもよろしいですか?」と彼女は、ナイフとフォークを取り上げ、一方の女王からもう一方の女王へと目をやりながら言いました。
「とんでもない」と赤の女王はきっぱりと言いました。「紹介された相手を切り分けるのはエチケット違反だ。肉の盛り合わせを下げなさい!」そして給仕たちはそれを運び去り、代わりに大きなプラムプディングを持ってきました。
「プディングには紹介されたくありませんわ、お願いですから」とアリスは少し慌てて言いました。「さもないと、私たちは全く夕食にありつけなくなってしまいます。少し差し上げてもよろしいですか?」
しかし、赤の女王は不機嫌な顔をして、「プディング、アリス。アリス、プディング。プディングを下げなさい!」とうなりました。そして給仕たちはそれをあまりに素早く運び去ったので、アリスはそのお辞儀を返すことができませんでした。
しかし、アリスは赤の女王だけが命令を出すべき理由がわからないと思い、試しに「給仕さん! プディングを戻して!」と叫んでみました。すると、まるで手品のように、それは一瞬で再びそこにありました。それはとても大きかったので、彼女は羊のもも肉の時と同じように、それに対して少し内気にならずにはいられませんでした。しかし、彼女は大変な努力で内気さを克服し、一切れ切り分けて赤の女王に手渡しました。
「なんて無礼な!」とプディングは言いました。「もし私がお前から一切れ切り取ったら、お前はどう思うかね、この生き物め!」
それは分厚く、脂っこいような声で話し、アリスは返事の言葉もありませんでした。ただ座ってそれを見つめ、息をのむことしかできませんでした。
「何か言いなさい」と赤の女王は言いました。「会話をすべてプディングに任せるなんて馬鹿げている!」
「ご存知かしら、今日、私はものすごい量の詩を暗唱してもらったんです」とアリスは話し始めましたが、唇を開いた瞬間にあたりが静まり返り、すべての目が自分に注がれていることに気づいて、少し怖くなりました。「そして、とても奇妙なことだと思うのですが、どの詩も何らかの形で魚についてのものだったんです。このあたりでは、どうして皆そんなに魚が好きなのでしょう?」
彼女は赤の女王に話しかけましたが、女王の答えは少し的を外れていました。「魚についてだが」と彼女は、非常にゆっくりと厳粛に、アリスの耳に口を近づけて言いました。「白の女王陛下は素敵ななぞなぞを知っておられる。すべて詩で、すべて魚についてのものだ。暗唱させようか?」
「赤の女王陛下がそれを口にしてくださるとは、とても親切ですわ」と白の女王は、鳩の鳴き声のような声でアリスのもう片方の耳にささやきました。「それはなんて素敵なおもてなしでしょう! よろしいかしら?」
「ええ、お願いします」とアリスは非常に丁寧に言いました。
白の女王は喜んで笑い、アリスの頬を撫でました。それから彼女は始めました。
「『まず、魚を捕まえねばならぬ。』 それは簡単。赤ん坊でも捕まえられたと思う。 『次に、魚を買わねばならぬ。』 それは簡単。一ペニーで買えたと思う。 『さあ、私に魚を料理して!』 それは簡単、一分もかからないでしょう。 『皿の上に置いておいて!』 それは簡単、もうすでに入っているのだから。 『ここへ持ってきて! 夕食にさせて!』 そんな皿をテーブルに置くのは簡単だ。 『皿の蓋を取って!』 ああ、それはとても難しくて、私には無理そうだわ! なぜなら、にかわのようにくっついているから。 蓋を皿にくっつけている、真ん中に横たわりながら。 どちらがやりやすいでしょう、 魚の皿の蓋を取るか、なぞなぞの蓋を取るか?」
「一分考えて、それから当てなさい」と赤の女王は言いました。「その間に、我々は君の健康を祝して乾杯しよう。女王アリスの健康を!」と彼女は声を張り上げて叫び、すべての客がすぐにそれを飲み始めましたが、そのやり方は非常に奇妙でした。ある者たちはグラスを消火器のように頭にかぶり、顔を伝い落ちるものをすべて飲みました。またある者たちはデキャンタをひっくり返し、テーブルの縁から流れ落ちるワインを飲みました。そして三人の客(カンガルーのように見えました)は、ローストマトンの皿に這い上がり、熱心に肉汁をすすり始めました。「まるで餌箱の中の豚みたいだわ!」とアリスは思いました。
「きちんとしたスピーチでお礼を言うべきだ」と赤の女王は、アリスを見ながら眉をひそめて言いました。
「我々が支えてあげなければなりませんわね」と白の女王は、アリスが非常に素直に、しかし少し怖がりながら立ち上がろうとすると、ささやきました。
「どうもありがとうございます」と彼女はささやき返しました。「でも、私一人で十分うまくやれますわ。」
「それは全くもってふさわしくない」と赤の女王はきっぱりと言いました。そこでアリスは、潔くそれを受け入れようとしました。
(「それに、二人ともすごく押すのよ!」と彼女は後で、姉に祝宴の顛末を話したときに言いました。「私をぺちゃんこに押しつぶしたいのかと思ったくらいよ!」)
実際、彼女がスピーチをする間、その場にとどまるのはかなり困難でした。二人の女王が両側から彼女を押すので、彼女はほとんど宙に浮きそうになりました。「私は感謝を申し上げるために立ち上がります……」とアリスは話し始めました。そして、話しながら実際に数インチ立ち上がりましたが、テーブルの縁を掴んで、なんとか自分を引き下ろしました。
「気をつけて!」と白の女王は、両手でアリスの髪を掴みながら叫びました。「何かが起ころうとしていますわ!」
そしてその時(アリスが後で説明したところによると)、あらゆる種類のことが一瞬のうちに起こりました。ろうそくはすべて天井まで伸び、まるでてっぺんに花火がついたイグサの茂みのようになりました。瓶に至っては、それぞれ一組の皿を取り、それを急いで翼として取り付け、フォークを足にして、あらゆる方向に飛び回りました。「そして、とても鳥に似ているわ」とアリスは、始まりつつあるひどい混乱の中で、できるだけ冷静に思いました。
その時、アリスはすぐそばでしわがれた笑い声がするのを聞き、白の女王に何があったのかと振り返りました。しかし、女王様がいるはずの椅子に座っていたのは、なんと羊の脚肉でした。「ここにいるわよ!」とスープの蓋付き鉢から声が聞こえ、アリスが再びそちらを向くと、ちょうど女王様が人の良さそうな広い顔で、鉢の縁から一瞬ニヤリと笑いかけるのが見え、次の瞬間にはスープの中へ消えてしまいました。
一刻の猶予もありませんでした。すでに何人かのお客はお皿の中に寝そべっていますし、スープ用のおたまがテーブルの上をアリスの椅子に向かって歩いてきて、邪魔だからどくようにといらいらした様子で手招きをしていました。
「もう我慢できないわ!」アリスはそう叫ぶと、飛び上がって両手でテーブルクロスを掴みました。ぐいっと一回引っぱると、お皿も、大皿も、お客も、ろうそくも、何もかもがガラガラと音を立てて床にひとまとめに崩れ落ちました。
「それからあなたは」と、アリスは続けました。この騒ぎはすべてこの人のせいだと思っていた赤の女王に、猛然と向き直ったのです。しかし、女王はもうアリスの隣にはいませんでした。女王は突然、小さな人形くらいの大きさに縮んでしまい、今やテーブルの上で、後ろに引きずっている自分のショールを追いかけて、楽しそうにくるくると走り回っていたのです。
他の時であれば、アリスはこれを見て驚いたことでしょう。しかし、今の彼女はあまりに興奮していて、今さら何が起きても驚きはしませんでした。「あなたのことよ」とアリスは繰り返し、ちょうどテーブルに落ちてきた瓶を飛び越えようとしていたその小さな生き物を捕まえると、言いました。「あなたを揺すって子猫にしてやるわ、絶対よ!」
第十章 揺さぶること
アリスはそう言いながら女王をテーブルからつまみ上げると、力いっぱい前後に揺さぶりました。
赤の女王はまったく抵抗しませんでした。ただ、その顔はとても小さくなり、目は大きくて緑色になりました。そして、アリスが揺さぶり続けるにつれて、女王はどんどん背が低く――そして太く――そして柔らかく――そして丸く――なっていき――
第十一章 目覚め
――そしてとうとう、それは本当に子猫になってしまったのです。
第十二章 夢を見ていたのは誰?
「女王様、そんなに大きな音で喉を鳴らしてはいけませんわ」アリスは目をこすりながら、敬意を払いつつも、いくらか厳しい口調で子猫に言いました。「せっかくの、ああ! なんて素敵な夢だったのに、起こしてしまったじゃないの! それにね、キティ、あなたはずっと私と一緒だったのよ――鏡の国の世界をずっと。知ってた、ねえ?」
子猫にはとても厄介な癖があります(アリスはかつてそう言ったことがありました)。何を話しかけても、いつも喉を鳴らすのです。「『はい』の代わりにゴロゴロ鳴いて、『いいえ』の代わりにニャアと鳴くとか、何かそういう決まりがあればいいのに」と彼女は言いました。「そうすれば会話が続けられるじゃない! でも、いつも同じことしか言わない相手と、どうやってお話ができるっていうの?」
この時も、子猫はただゴロゴロと喉を鳴らすだけで、それが「はい」なのか「いいえ」なのか、見当もつきませんでした。
そこでアリスは、テーブルの上のチェスの駒の中から赤の女王を見つけ出しました。それから暖炉の前の敷物の上にひざまずき、子猫と女王を向かい合わせに置きました。「さあ、キティ!」アリスは勝ち誇ったように手を叩いて叫びました。「あなたがこれに変身したって、白状なさい!」
(「でも、ちっとも見ようとしないの」と、後でお姉さんにこのことを説明した時、アリスは言いました。「顔をそむけて、見えないふりをするのよ。でも、少し恥ずかしそうにしていたから、やっぱりあれは赤の女王だったに違いないと思うわ」)
「もうちょっと背筋を伸ばして座りなさいな!」アリスは楽しそうに笑いながら叫びました。「何を――何をゴロゴロ鳴こうか考えている間に、お辞儀をするのよ。時間の節約になるわ、忘れないで!」そう言ってアリスはその子猫を抱き上げると、小さなキスを一つしました。「赤の女王だった記念にね。」
「スノードロップ、いい子ね!」アリスは肩越しに白い子猫を見ながら続けました。その子はまだ辛抱強くダイナに体をきれいにしてもらっているところでした。「ダイナはいつになったら、白の女王陛下のお世話を終えるのかしら? 夢の中であなたがそんなにだらしなかったのは、きっとそのせいね――ダイナ! あなたが洗っているのが白の女王だって分かってるの? まったく、なんて失礼なのかしら!
「それで、ダイナは何になったのかしら?」アリスは子猫たちを眺めながら、片肘を敷物につき、手のひらに顎を乗せてくつろぎながら、ぺちゃくちゃと喋り続けました。「教えて、ダイナ、あなたはハンプティ・ダンプティになったの? きっとそうだと思うわ――でも、まだお友達には言わない方がいいわよ、確信がないから。
「ところでキティ、もしあなたが本当に夢の中で私と一緒にいたら、一つだけ絶対に楽しめたことがあったのよ――お魚のことばかりの詩を、たくさん聞かせてもらったの! 明日の朝は、とっておきのごちそうよ。あなたが朝ごはんを食べている間ずっと、『セイウチと大工』を暗唱してあげるわ。そうすれば、それをカキだと思えるでしょ、ね!
「さてキティ、この夢を全部見ていたのが誰だったのか、考えてみましょう。これは真剣な問題なのよ、あなた。そんな風に自分の前足をなめ続けるのはやめなさい――まるで今朝ダイナが洗ってくれなかったみたいじゃない! いいこと、キティ、それは私か、あるいは赤の王様のどちらかだったに違いないの。もちろん、王様は私の夢の一部だったわ――でも、私も王様の夢の一部だったのよ!赤の王様だったのかしら、キティ? あなたは王様の奥さんだったんだから、知っているはずよ――ああ、キティ、決着をつけるのを手伝ってちょうだい! 前足は後でも大丈夫でしょうに!」しかし、このいじわるな子猫はもう片方の前足をなめ始め、その質問が聞こえなかったふりをしました。
あなたは、どちらだったと思いますか?
陽の射す空の下、一艘のボートが、 夢見るようにゆっくりと進む 七月の夕暮れに――
寄り添う三人の子供たち、 熱心な瞳と素直な耳で、 素朴な物語に喜んで耳を傾ける――
あの陽の射す空は遠く色あせ、 こだまは消え、思い出は死に絶える。 秋の霜が七月を葬り去った。
それでも彼女は幻のように私を訪れる、 アリスは空の下を歩む 覚めた目には決して見えぬ空の下を。
また子供たちが、物語を聞きに、 熱心な瞳と素直な耳で、 愛おしそうに寄り添うだろう。
不思議の国に彼らは横たわり、 日々が過ぎゆくままに夢を見る、 夏が過ぎゆくままに夢を見る。
永久に流れを下りながら―― 黄金の輝きの中を漂いながら―― 人生、それは夢以外の何であろうか?
おしまい

