S.L.O.へ。古典を愛するその趣味に合わせて物語を構想した、アメリカの紳士である彼に。共に過ごした数々の楽しい時間のお礼として、心からの友情を込めて、親愛なる友人、著者より本書を捧ぐ。
購入をためらう読者へ
船乗りの歌にのせた船乗りの話、 嵐と冒険、熱さと寒さ、 スクーナー船、島々、置き去りにされた船乗りたち、 海賊どもに、埋められた黄金、 そして古き良きロマンのすべてを、昔ながらの語り口で語り直したものが、 かつての私を喜ばせたように、今の賢い若者たちを喜ばせることができるなら――
――いざ、物語の世界へ! もしそうでなく、もし勤勉な若者がもはや求めぬなら、 古き日の渇望を忘れ、キングストンや、勇ましきバランタイン、 森と波のクーパーを手に取らぬなら―― それもまたよし! ならば私も、我が海賊たちも、 彼らとその作品が眠る墓を共にしようではないか!
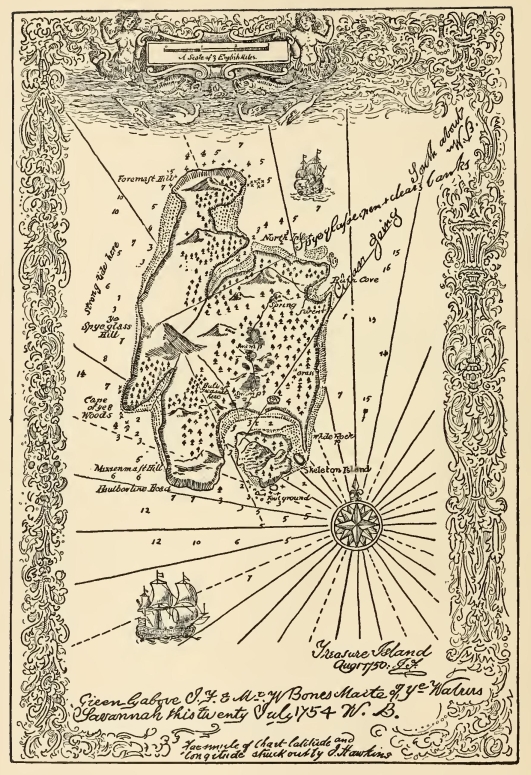
第一部 年老いた海賊
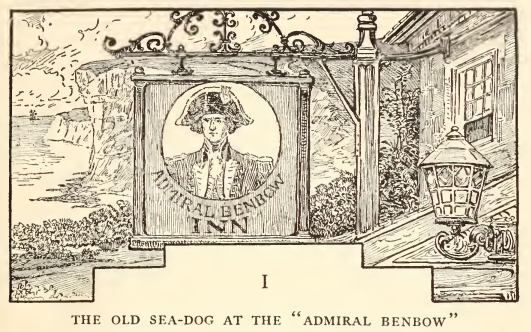
第一章 年老いた船乗り、「ベンボー提督亭」に現る
トレローニー郷士、ライブシー博士、そして紳士方が、私に宝島についての一部始終を書き記すよう求められた。島の場所を除いては、何一つ隠すことなく。島の場所を伏せるのは、未だ引き上げられていない宝がそこに眠っているからに他ならない。私は、神の恵み深き西暦一七――年にペンを取り、父が「ベンボー提督亭」を営んでいたあの頃、そして、顔に刀傷のある日に焼けた年老いた船乗りが、初めて我々の宿に腰を落ち着けたあの時に、立ち返ることにする。
昨日のことのように思い出せる。彼が宿の戸口へと重い足取りでやってきた時のことを。船乗り用の衣装箱を手押し車に乗せ、その後ろから引かせていた。背が高く、がっしりとして、ずんぐりとした、日に焼けて木の実のような色をした男。タールを塗ったおさげ髪は、汚れた青い上着の肩越しに垂れ、手は荒れて傷だらけ、爪は黒く割れていた。そして頬を横切る一本の刀傷は、薄汚れた、鉛のような白さだった。入り江を見回し、口笛を吹いていた姿を覚えている。そして、その後何度も歌うことになる、あの古い船乗りの歌をうたい始めた。
「死人の箱に十五人――ヨーホーホー、ラム酒の瓶!」
その声は、キャプスタン・バー[訳注:錨を巻き上げる装置のハンドル]を回すうちに調子が整い、そして壊れてしまったかのような、甲高く、古びて、震える声だった。それから、てこ棒のような棒切れで戸を叩いた。父が顔を出すと、無遠慮にラム酒を一杯注文した。運ばれてきたそれを、彼は鑑定家のようにゆっくりと味わい、なおも崖や我々の宿の看板を見上げていた。
「ここは都合のいい入り江だな」と、彼はやがて言った。「それに、気持ちのいい場所にある酒場だ。客は多いのか、おい。」
父は、客はほとんどいない、それが残念なところだと答えた。
「よろしい」と彼は言った。「なら、ここは俺の寝床だ。おい、そこのお前」手押し車を引いてきた男に彼は叫んだ。「こっちへ寄せて、箱を運び込むのを手伝え。しばらくここに厄介になる」彼は続けた。「俺は単純な男でな。ラム酒とベーコンエッグがあればいい。あとは、あそこの岬から船を見張れればな。俺の名前か? 船長とでも呼んでくれ。おっと、お前さんが何を考えてるか分かるぞ――ほらよ」。そう言って、彼は三、四枚の金貨を敷居に投げ捨てた。「これが無くなる頃に教えてくれりゃいい」と、司令官のような険しい顔つきで言った。
実際、彼の身なりはみすぼらしく、言葉遣いは粗野だったが、平の水夫といった風情は微塵もなく、むしろ服従されるか殴りつけるかに慣れた一等航海士か船長のように見えた。手押し車を引いてきた男の話では、彼は前の朝、「ロイヤル・ジョージ号」で郵便馬車を降り、沿岸にどんな宿があるか尋ね、我々の宿の評判が良かったのか、あるいは人里離れていると聞いて、滞在先に選んだのだろうということだった。我々がこの客について知ることができたのは、それだけだった。
普段は非常に無口な男だった。日中は真鍮の望遠鏡を手に、入り江や崖のあたりをうろつき、夜はずっと談話室の暖炉脇の隅に座り、非常に濃いラムの水割りを飲んでいた。話しかけられてもほとんど口を利かず、ただ突然、険しい顔つきでこちらを見上げ、霧笛のように鼻を鳴らすだけだった。我々も、宿に出入りする人々も、すぐに彼をそっとしておくことを学んだ。散歩から戻ると毎日、船乗りが道を通らなかったかと尋ねるのだった。最初は、同業者に会いたいのだろうと思っていたが、やがて彼らを避けたいのだと気づき始めた。船乗りが「ベンボー提督亭」に泊まることがあると(ブリストルへ向かう海岸沿いの道を行く者が時々いた)、彼は談話室に入る前に、カーテンのかかったドアから中を覗き込み、そういう客がいる間は、必ず鼠のように静かにしていた。少なくとも私にとっては、その理由は明白だった。というのも、私はある意味、彼の不安を共有していたからだ。「一本足の船乗り」に目を光らせ、現れたらすぐに知らせてくれれば、毎月一日に銀貨四ペンスをやると、ある日彼は私を脇に呼んで約束したのだった。月の初めが来て給金を催促すると、鼻を鳴らして私を睨みつけるだけのこともしばしばだったが、一週間も経たないうちに考え直し、四ペンス銀貨をくれ、そして「一本足の船乗り」を見張るよう、改めて命令を繰り返すのが常だった。
その人物がどれほど私の夢に取り憑いたか、語るまでもないだろう。風が家の四隅を揺さぶり、波が入り江に沿って崖に轟音を立てて打ち寄せる嵐の夜、私は千の姿、千の悪魔のような表情をした彼を見た。ある時は膝から、ある時は股から足が切り落とされている。またある時は、体の真ん中に一本足だけが生えた、奇怪な化け物だった。彼が跳び、走り、生け垣や溝を越えて私を追いかけてくるのは、最悪の悪夢だった。結局のところ、私はこの忌まわしい空想の形で、月々の四ペンス銀貨のために、かなり高い代償を払っていたのだ。
しかし、一本足の船乗りのことをあれほど恐れていたにもかかわらず、船長自身に対する私の恐怖は、彼を知る他の誰よりもずっと小さかった。ラムの水割りを、彼の頭が許す以上に飲む夜があった。そんな時は、座って邪悪で荒々しい古い船乗りの歌を、誰に気兼ねすることもなく歌うこともあれば、全員に酒を奢り、震え上がる客たちに無理やり自分の話を聞かせたり、歌の合唱をさせたりすることもあった。「ヨーホーホー、ラム酒の瓶!」という歌声で家が揺れるのを、私は何度も聞いた。近所の人々は皆、殺される恐怖から必死で加わり、咎められないようにと互いに負けじと大声で歌うのだった。というのも、こういう発作を起こした時の彼は、手がつけられないほど横暴な仲間だったからだ。静かにさせようとテーブルを平手で叩き、質問一つで、あるいは時には質問がないというだけで、話を聞いていないと判断して激怒した。そして、彼自身が酔って眠くなり、よろよろとベッドに向かうまで、誰一人として宿を出ることを許さなかった。
彼が語る物語が、人々を最も怖がらせた。絞首刑、板歩きの刑、海上の嵐、ドライ・トートゥガス諸島、そしてスペイン領の海での蛮行や場所についての、恐ろしい物語だった。彼の話によれば、彼は神が海上に存在を許した中でも最も邪悪な人間たちの間で生涯を過ごしてきたに違いなく、その物語を語る言葉遣いは、彼が描写する犯罪と同じくらい、我々素朴な田舎の人々を震撼させた。父はいつも、こんな横暴な扱いを受け、こき下ろされ、震えながらベッドに送られるのでは、客足がすぐに遠のき、宿は潰れてしまうだろうと言っていた。しかし、私は彼の存在が我々にとって良い影響をもたらしたと本気で信じている。人々はその時は怯えたが、後から振り返ると、むしろそれを好んでいた。静かな田舎の生活における、素晴らしい刺激だったのだ。中には、彼を「本物の海の男」だの「生粋の古参水兵」だのと呼んで賞賛するふりをする若者の一団さえいて、ああいう男こそがイングランドを海で恐れられる存在にしたのだと言っていた。
ある意味で、彼は確かに我々を破滅させようとしていた。何週間も、しまいには何ヶ月も滞在し続けたので、金はとっくに尽きてしまったのに、父はそれでもなお、もっと払うようにと強く言う勇気を持ち合わせていなかったのだ。父がそのことに触れると、船長は轟音と言ってもいいほど大きな音で鼻を鳴らし、哀れな父を部屋から睨み出した。そんな仕打ちの後で、父が両手を揉みしだいているのを私は見たことがある。彼が耐えていた苛立ちと恐怖が、その若くしての不幸な死を大いに早めたに違いない。
我々のところにいる間、船長は行商人から靴下を数足買った以外、服装を一切変えなかった。帽子の三角の一角が垂れ下がってしまったが、風が吹くとひどく邪魔になるにもかかわらず、その日からずっとそのままにしていた。彼が二階の自室で自分で繕っていた上着の様子を覚えている。それは終わりの頃には、継ぎはぎだらけになっていた。手紙を書くことも受け取ることもなく、近所の人々以外とは誰とも話さなかったし、その近所の人々とでさえ、ほとんどはラムに酔っている時だけだった。例の大きな衣装箱は、我々の誰もが開いているのを見たことがなかった。
彼が逆らわれたのは一度きりだった。それは終わりの頃、哀れな父が、やがてその命を奪うことになる病で衰弱しきっていた時のことだ。ある日の午後遅く、ライブシー博士が患者を診に来て、母の作った夕食を少し食べ、馬が村から下りてくるまでの間、パイプをふかしに談話室へ入った。我々の古いベンボー亭には馬小屋がなかったのだ。私は博士の後について入り、その対比を観察したのを覚えている。雪のように白いかつらをつけ、輝く黒い瞳を持ち、物腰の柔らかな、こざっぱりとした快活な博士と、無骨な田舎の人々、そして何よりも、ラムに酔い潰れ、テーブルに腕を突っ伏している、我らが海賊の、あの汚らしく、重々しく、目の濁った案山子との対比だ。突然、彼が――つまり船長が――例の終わりのない歌を歌い始めた。
「死人の箱に十五人――ヨーホーホー、ラム酒の瓶! 酒と悪魔が残りを片付けた――ヨーホーホー、ラム酒の瓶!」
最初、私は「死人の箱」とは、二階の表の部屋にある彼のあの大きな箱のことだと思い、その考えは悪夢の中で一本足の船乗りの姿と混じり合っていた。しかし、この頃には我々は皆、その歌に特に注意を払うことはとっくになくなっていた。その夜、歌が耳新しかったのはライブシー博士だけで、博士にはそれが心地よいものではなかったのが見て取れた。リウマチの新治療法について庭師のテイラー爺さんと話を続ける前に、一瞬、実に腹立たしげに見上げたからだ。その間、船長は自らの歌で次第に上機嫌になり、ついに我々が皆「静粛に」の合図だと知っているやり方で、目の前のテーブルを手で叩いた。ライブシー博士以外の声は即座に止んだ。博士は以前と変わらず、はっきりと優しい口調で話し続け、一言二言の間にきびきびとパイプを吸っていた。船長はしばらく彼を睨みつけ、再び手を叩き、さらにきつく睨みつけ、そしてついに、下劣で低い悪態をついた。「甲板の下は静かにしろ!」
「私に言っておられるのかね?」と博士は言った。ごろつきが、もう一つ悪態をつきながら、そうだと言うと、「あなたに言いたいことは一つだけだ」と博士は答えた。「ラムを飲み続けるなら、世間は近いうちに、非常に汚らわしい悪党一人と縁が切れることになるだろう!」
老人の怒りは凄まじかった。彼は跳ね起き、船乗り用の折りたたみナイフを抜いて開き、開いたまま手のひらの上でバランスを取りながら、博士を壁に串刺しにしてやると脅した。
博士は微動だにしなかった。彼は以前と同じように、肩越しに、同じ声の調子で、部屋中の皆に聞こえるようにやや高い声で、しかし完璧に落ち着き払って、彼に話しかけた。「そのナイフを今すぐポケットにしまわないなら、我が名誉にかけて約束しよう。君は次の巡回裁判で絞首刑になる。」

それから二人の間で睨み合いが続いたが、すぐに船長の方が折れ、武器をしまい、打ち負かされた犬のようにうなりながら席に戻った。
「さて、君」と博士は続けた。「私の管轄区にこのような男がいると知ったからには、昼も夜も君を見張っていると思っていい。私は医者であるだけでなく、治安判事でもあるのだ。君に対する苦情が少しでも私の耳に入れば、たとえ今夜のような無礼な振る舞い一つであっても、君を追い詰め、ここから追い出すための効果的な手段を講じる。それで十分だろう。」
まもなく、ライブシー博士の馬が戸口にやって来て、彼は馬に乗って去っていった。しかし船長は、その晩も、そしてその後何晩も、おとなしくしていた。

第二章 黒犬、現れそして消える
これからさほど経たないうちに、謎めいた出来事の第一弾が起こった。それは結局、我々を船長から解放することになったが、これからご覧いただくように、彼の厄介事から解放されたわけではなかった。それは長く厳しい霜と激しい嵐を伴う、凍えるように寒い冬だった。そして、哀れな父が春を見ることはまずないだろうということは、最初から明らかだった。父は日ごとに衰弱し、母と私は宿の切り盛りをすべて背負い込み、不愉快な客にあまり構っていられないほど忙しかった。
一月のある朝、非常に早い時間だった。身を切るような、霜の降りる朝で、入り江は白霜で一面灰色になり、さざ波が静かに石に打ち寄せ、太陽はまだ低く、丘の頂を照らし、はるか沖まで輝いているだけだった。船長はいつもより早く起き、浜辺へと下りていった。古い青い上着の広い裾の下でカトラスを揺らし、真鍮の望遠鏡を脇に抱え、帽子を後ろに傾けていた。彼が闊歩していくと、その吐く息が煙のように後に残り、大きな岩を曲がる彼から聞こえた最後の音は、まるでまだライブシー博士のことで頭がいっぱいであるかのような、憤慨した大きな鼻息だったのを覚えている。
さて、母は二階で父の看病をしており、私は船長が戻ってくるのに備えて朝食のテーブルを準備していた。その時、談話室のドアが開き、一人の男が入ってきた。これまで一度も目にしたことのない男だった。青白く、獣脂のような顔色をした男で、左手の指が二本欠けていた。カトラスを身につけてはいたが、とても戦士には見えなかった。私はいつも一本足であれ二本足であれ、船乗りに目を光らせていたが、この男には戸惑ったのを覚えている。船乗りらしくはないが、どこか海の香りがした。
ご用件は何かと尋ねると、ラムを飲みたいとのことだった。私がそれを取りに部屋を出ようとすると、彼はテーブルに腰を下ろし、近くに来るよう手招きした。私はナプキンを手にしたまま、その場で立ち止まった。
「こっちへ来な、坊主」と彼は言った。「もっと近くへ。」
私は一歩近づいた。
「このテーブルは、俺の相棒ビルのためのものかい?」彼はにやりと笑うような表情で尋ねた。
私は彼の相棒のビルという人は知らない、これは我々の家に滞在している、我々が船長と呼んでいる人のためのものだと答えた。
「まあな」と彼は言った。「俺の相棒ビルは、船長と呼ばれていてもおかしくはない。頬に傷があって、実に愉快な男だ、特に酒が入るとな、俺の相棒ビルは。まあ、議論のために、あんたんとこの船長には頬に傷がある、ということにしておこうか。それに、よければ、その頬は右側だということにしておこう。ああ、そうだ! 言った通りだろ。さて、俺の相棒ビルはこの家にいるのか?」
散歩に出ていると答えた。
「どっちだ、坊主? どっちへ行った?」
私が岩を指さし、船長が戻ってきそうなこと、どれくらいで戻るかを教え、その他いくつかの質問に答えると、「ああ」と彼は言った。「こいつは、俺の相棒ビルにとって、酒よりもいい土産になるだろうよ。」
その言葉を口にした時の彼の表情は、決して愉快なものではなく、たとえ彼が本気で言っていたとしても、この見知らぬ男は勘違いしているのだろうと私が考えるだけの理由はあった。しかし、それは私の知ったことではない、と私は思った。それに、どうしていいか分からなかった。見知らぬ男は宿の戸口のすぐ内側をうろつき、鼠を待つ猫のように角から覗き込んでいた。一度、私自身が道に出てみたが、彼はすぐに私を呼び戻した。そして、彼の気にいるほど素早く従わなかったので、その獣脂のような顔が恐ろしく豹変し、私が飛び上がるほどの悪態をついて中に入るよう命じた。私が戻るとすぐに、彼は元の態度に戻り、媚びるようでもあり、嘲るようでもある半々の態度で、私の肩を叩き、私は良い子だ、すっかり気に入ったと言った。「俺にも息子がいてな」と彼は言った。「お前さんと瓜二つで、俺の自慢の種だ。だがな、坊主どもにとって大事なのは規律だ――規律だよ。さて、もしお前さんがビルと一緒に航海していたら、二度も話しかけられるまでそこに突っ立ってはいなかっただろう――お前さんならな。それはビルのやり方じゃなかったし、彼と航海した奴らのやり方でもなかった。おっと、案の定、俺の相棒ビルが来たぞ、腕に望遠鏡を抱えてやがる、まったく、あいつめ。お前さんと俺は、談話室に戻って、ドアの後ろに隠れて、ビルをちょっと驚かせてやろうぜ――まったく、もう一度言ってやる、あいつめ。」
そう言うと、見知らぬ男は私と一緒に談話室へと後ずさり、私を自分の後ろの隅に押しやったので、我々は二人とも開いたドアに隠れる形になった。ご想像の通り、私は非常に不安で怯えていたが、見知らぬ男自身も明らかに怖がっている様子を見て、恐怖はさらに増した。彼はカトラスの柄を握りやすいようにし、鞘の中で刃を緩めた。そして、我々が待っている間ずっと、喉に塊が詰まったような感じで唾を飲み込み続けていた。
ついに船長が大股で入ってきて、右も左も見ずに後ろのドアをバタンと閉め、まっすぐ部屋を横切って朝食が待っている場所へと向かった。
「ビル」と見知らぬ男が言った。声は、大胆で大きくしようと努めているように私には思えた。
船長は踵を返して我々と向き合った。顔からは血の気が引き、鼻さえも青ざめていた。幽霊か、悪魔か、あるいはそれ以上に悪いものを見た男のようだった。そして、本当に、一瞬のうちに彼がそれほど老い、病んだように見えたのが気の毒に思えた。
「おい、ビル、俺だよ。古い船仲間が分からないのか、ビル、まさか」と見知らぬ男は言った。
船長は息を呑んだようだった。
「黒犬!」と彼は言った。
「いかにも」と相手は答え、いくらか落ち着きを取り戻した。「いつもの黒犬さ。『ベンボー提督亭』に、古い船仲間のビリーに会いに来たんだ。ああ、ビル、ビル、俺たちがこの二本の爪を失ってから、ずいぶんと色々なことがあったもんだな」そう言って、彼は傷ついた手を持ち上げた。
「おい、聞け」と船長は言った。「お前は俺を突き止めた。俺はここにいる。よし、それなら言え。何の用だ?」
「それでこそビルだ」と黒犬は答えた。「その通りだよ、ビリー。俺はこの可愛い坊主からラム酒を一杯もらおう。すっかり気に入っちまったんでな。それで、よければ腰を下ろして、腹を割って話そうじゃないか、古い船仲間みたいに。」
私がラム酒を持って戻ると、二人はすでに船長の朝食テーブルの両側に座っていた。黒犬はドアの隣に、古い船仲間と、そして私が思うに、逃げ道とに片目を向けられるように横向きに座っていた。
彼は私に出て行って、ドアを大きく開けたままにしておくよう命じた。「鍵穴から覗かれるのはごめんだぜ、坊主」と彼は言った。私は二人を残して、バーへと引き下がった。
しばらくの間、私は確かに聞き耳を立てていたが、低いざわめきしか聞こえなかった。しかし、やがて声が大きくなり始め、船長の発する言葉が、ほとんどは悪態だったが、一言二言聞き取れるようになった。
「駄目だ、駄目だ、駄目だ、駄目だ! これでしまいだ!」と彼は一度叫んだ。そして再び、「絞首刑になるなら、全員まとめてだ!」と。

その時、突然、すさまじい悪態と物音の爆発があった。椅子とテーブルが一塊になって倒れ、鋼のぶつかる音が続き、そして苦痛の叫び声。次の瞬間、私は黒犬が全力で逃げ出し、船長が猛然と追いかけるのを見た。二人ともカトラスを抜いており、黒犬は左肩から血を流していた。ちょうど戸口で、船長は逃亡者めがけて最後の一撃を放った。もし我々の大きな「ベンボー提督亭」の看板に阻まれていなければ、間違いなく背骨まで真っ二つになっていただろう。その傷跡は、今でも看板の枠の下側に見ることができる。
その一撃が戦いの終わりだった。道に出ると、黒犬は傷にもかかわらず、驚くほど見事な足さばきを見せ、半分のうちに丘の向こうへと消えていった。船長はと言えば、呆然とした男のように看板をじっと見つめていた。それから彼は何度か手で目をこすり、ついに家の中へと引き返した。
「ジム」と彼は言った。「ラム酒だ」。そう言うと、彼は少しよろめき、片手で壁に寄りかかった。
「怪我をしたんですか?」と私は叫んだ。
「ラム酒だ」と彼は繰り返した。「ここから出なければならん。ラムだ! ラム酒を!」
私はそれを取りに走ったが、起こったことすべてにすっかり動転しており、グラスを一つ割り、蛇口を汚してしまった。まだ私がもたもたしている間に、談話室で大きな物音が聞こえ、駆け込むと、船長が床に大の字になって倒れているのが見えた。同時に、叫び声と争いに驚いた母が、私を助けようと階段を駆け下りてきた。二人で彼の頭を持ち上げた。彼は非常に大きく苦しそうに息をしていたが、目は閉じられ、顔色は恐ろしい色だった。
「まあ、なんてことでしょう」と母は叫んだ。「この家の恥だわ! それに、あなたのお父様も病気なのに!」
その間、我々は船長を助けるためにどうすればいいか全く分からず、彼が見知らぬ男との乱闘で致命傷を負ったのだということ以外、何も考えられなかった。確かにラム酒を持ってきて、彼の喉に流し込もうとしたが、歯は固く食いしばられ、顎は鉄のように強かった。ドアが開き、ライブシー博士が父の往診に来てくれた時は、本当にほっとした。
「ああ、先生」と我々は叫んだ。「どうしたらいいでしょう? どこを怪我しているんですか?」
「怪我? 馬鹿なことを!」と博士は言った。「君たちと同じで、どこも怪我などしていない。この男は脳卒中を起こしたのだ、私が警告した通りに。さて、ホーキンズ夫人、あなたはすぐに二階の旦那さんのところへ行って、できればこのことは何も話さないでください。私はと言えば、この三重に価値のない男の命を救うために最善を尽くさねばならん。ジム、洗面器を持ってきてくれ。」
私が洗面器を持って戻ると、博士はすでに船長の袖を切り裂き、その筋骨たくましい腕を露出させていた。いくつかの場所に刺青があった。「幸運を」「順風満帆」「ビリー・ボーンズのお気に入り」といった言葉が、前腕に非常に丁寧かつ鮮明に彫られていた。そして肩の近くには、絞首台とそこから吊るされた男の絵があった。私が見るに、非常に生き生きと描かれていた。
「予言的だな」と博士は、その絵を指で触れながら言った。「さて、ビリー・ボーンズ君、それが君の名前なら、君の血の色を見てやろう。ジム」と彼は言った。「血は怖いかね?」
「いいえ、先生」と私は答えた。
「よろしい」と彼は言った。「では、洗面器を持っていなさい」。そう言って、彼はメスを取り、静脈を切開した。
大量の血が抜かれ、やがて船長は目を開け、ぼんやりと周りを見回した。最初に博士を認め、紛れもない不快な表情を浮かべた。次に彼の視線は私に落ち、ほっとしたように見えた。しかし、突然彼の顔色が変わ り、起き上がろうとしながら叫んだ。「黒犬はどこだ?」
「ここに黒犬はいない」と博士は言った。「君の背中にいる奴は別だがな[訳注:英語でblack dogは憂鬱や気分の落ち込みを意味することがある]。君はラムを飲み、脳卒中を起こした。私が言った通りにだ。そして私は今、全く不本意ながら、君を墓場から頭から引きずり出したところだ。さて、ボーンズ君――」
「それは俺の名前じゃない」と彼は遮った。
「どうでもいいことだ」と博士は答えた。「それは私の知っている海賊の名前でね。手っ取り早いからそう呼んでいるだけだ。君に言いたいことはこうだ。ラム一杯で死ぬことはないだろうが、一杯飲めば二杯、三杯と飲むことになる。そして、きっぱりやめなければ、私のカツラを賭けてもいい、君は死ぬ――分かるかね? ――死んで、聖書に出てくる男のように、自分が行くべき場所へ行くのだ。さあ、努力したまえ。一度だけ、君がベッドに行くのを手伝ってやろう。」
我々二人で、大いに骨を折って、なんとか彼を二階に運び上げ、ベッドに寝かせた。彼の頭は枕の上にがっくりと落ち、まるで気を失いかけているかのようだった。
「いいかね」と博士は言った。「私は良心にかけて言っておく――君にとってラムという名は、死を意味する。」
そう言うと、彼は私の腕を取り、父を診るために去っていった。
「大したことではない」とドアを閉めるとすぐに彼は言った。「しばらく彼を静かにさせておくのに十分な血は抜いた。一週間はいるべき場所に寝かせておくべきだ。それが彼にとっても、君たちにとっても最善だ。しかし、もう一度発作が起きたら、それで終わりだろう。」

第三章 黒丸
正午ごろ、私は冷たい飲み物と薬を持って船長の部屋のドアの前に立ち寄った。彼は我々が残していった時とほとんど同じ状態で横たわっていたが、体は少しだけ起こしており、弱っていると同時に興奮しているように見えた。
「ジム」と彼は言った。「ここにいる奴らの中で、お前さんだけがまともだ。それに、俺がいつもお前さんに良くしてやったのは分かっているだろう。毎月必ず、お前さん自身のために銀貨四ペンスをやってきた。そして今、見ての通りだ、相棒、俺はすっかり弱っちまって、誰にも見捨てられた。なあジム、ラムを一杯持ってきてくれ、頼むよ、相棒。」
「先生は――」と私は言いかけた。
しかし、彼は弱々しいながらも心のこもった声で、医者を罵り始めた。「医者なんてのは、みんなろくでなしだ」と彼は言った。「それに、あの医者に、船乗りの何が分かるってんだ? 俺はピッチのように熱い場所にいたこともあるし、黄熱病で仲間がばたばた倒れていくのも見てきた。地震で聖なる大地が海のように揺れるのもな――あの医者にそんな土地の何が分かる? ――それでも俺はラムで生き延びてきたんだ。ラムは俺にとって肉であり、飲み物であり、男であり、女房だった。もし今、ラムが飲めないなら、俺は風下の海岸に打ち上げられた哀れな老いぼれの船だ。俺の血はお前さんと、あのろくでなしの医者のせいだぞ、ジム」。そして彼はしばらく悪態をつき続けた。「見ろ、ジム、俺の指がどう震えるか」と彼は懇願するような口調で続けた。「じっとしていられないんだ、俺は。この聖なる日に一滴も飲んでいない。あの医者は馬鹿だ、言っておく。もしラムを一杯やらなきゃ、俺は幻覚を見るぞ。もういくつか見ちまった。あそこの隅に、お前さんの後ろに、フリントの爺さんがいるのが見えた。印刷物みたいにはっきりとだ。もし俺が幻覚を見始めたら、荒っぽい人生を送ってきた男だ、大暴れしてやるぞ。お前さんの医者自身が、一杯くらいなら害はないと言ったじゃないか。一杯くれたら、金貨一枚やるぞ、ジム。」
彼はますます興奮していき、そのことが私を不安にさせた。その日、父は非常に衰弱しており、静けさが必要だったからだ。それに、今彼に引用された医者の言葉に安心し、賄賂の申し出にはむしろ腹が立った。
「あなたのお金はいりません」と私は言った。「父に借りている分だけで結構です。一杯だけ持ってきます。それ以上は駄目です。」
私がそれを持っていくと、彼は貪るようにそれをつかみ、一気に飲み干した。
「ああ、ああ」と彼は言った。「こいつは少しはましになった、確かにな。さて、相棒、あの医者は俺がこの古い寝床にどれくらい寝てなきゃならんと言ってた?」
「少なくとも一週間です」と私は答えた。
「何だと!」と彼は叫んだ。「一週間! そんなことはできん。それまでに奴らは俺に黒丸を渡すだろう。あののろまどもは、この聖なる瞬間にも俺の風向きをうかがっている。手に入れたものも守れず、他人のものを欲しがるような連中だ。それが船乗りらしい振る舞いか、教えてもらいたいもんだ。だが俺は倹約家だ。俺の金を無駄にしたことも、失ったこともない。奴らをもう一度出し抜いてやる。奴らなんぞ怖くない。もう一段帆を広げて、また奴らを欺いてやる。」
こう話しながら、彼は非常に困難な様子でベッドから起き上がった。私の肩を、思わず叫び出しそうになるほど強く掴み、足をまるで重りのように動かしていた。その言葉は、意味の上では意気軒昂だったが、それが発せられた声の弱々しさとは悲しいほど対照的だった。ベッドの縁に座ったところで、彼は言葉を止めた。
「あの医者にやられた」と彼はつぶやいた。「耳鳴りがする。寝かせてくれ。」
私がどうにか助ける前に、彼は再び元の場所へと倒れ込み、しばらく黙って横たわっていた。
「ジム」と彼はやがて言った。「今日、あの船乗りを見たか?」
「黒犬ですか?」と私は尋ねた。
「ああ! 黒犬だ」と彼は言った。「あいつは悪党だが、奴を仕向けたもっと悪い奴がいる。さて、もし俺がどうにも逃げられなくて、奴らが俺に黒丸を渡したら、いいか、奴らが狙っているのは俺の古い衣装箱だ。お前は馬に乗れ――乗れるだろ? よし、それなら馬に乗って、――そうだな、そうだ! ――あの忌々しい医者のところへ行って、総員招集をかけろと伝えろ――治安判事とかそういう連中をだ。そうすれば奴は『ベンボー提督亭』に乗り込んでくるだろう――フリントの昔の乗組員どもが、男も小僧も、残っている全員がな。俺は一等航海士だった、フリントの爺さんの一等航海士で、場所を知っているのは俺だけだ。サバンナで、爺さんが死にかけている時に、それを俺にくれたんだ。ちょうど今の俺みたいにな。だが、奴らが俺に黒丸を渡すか、お前さんがあの黒犬か、あるいは一本足の船乗りをもう一度見るまでは、告げ口するんじゃないぞ、ジム――特にあいつにはな。」
「でも、黒丸って何なんですか、船長?」と私は尋ねた。
「召喚状だ、相棒。もし奴らがそれを持って来たら教えてやる。だが、お前さんは目を光らせておけ、ジム。そうすれば分け前は平等だ、名誉にかけて。」
彼はもう少しうわ言を言っていたが、声はどんどん弱々しくなっていった。しかし、私が薬を渡すとすぐに、彼は「船乗りがこれほど薬を必要としたことはない」と言いながら子供のようにおとなしく飲み、やがて気を失ったかのような重い眠りに落ちたので、私は彼をそのままにしておいた。もしすべてが順調に進んでいたら、私はどうしていただろうか。分からない。おそらく、私は医者にすべてを話していただろう。船長が告白を後悔して私を始末するのではないかと、死ぬほど怖かったからだ。しかし、事態は思わぬ方向に進み、その晩、哀れな父が突然亡くなったことで、他のことはすべて脇に追いやられた。当然の悲しみ、近所の人々の弔問、葬儀の手配、そしてその間も続けなければならない宿の仕事で、私は船長のことを考える暇も、ましてや彼を恐れる暇もほとんどなかった。
翌朝、彼は確かに階下に下りてきて、いつも通り食事をとった。量は少なかったが、ラムはいつもより多かったのではないかと思う。バーから自分で注ぎ、顔をしかめて鼻を鳴らしていたので、誰も彼に逆らおうとはしなかった。葬儀の前夜、彼はいつものように酔っぱらっていた。そして、喪に服している家で、彼があの醜い古い船乗りの歌を歌い続けるのを聞くのは、衝撃的だった。しかし、彼は弱っていたものの、我々は皆、彼を死ぬほど恐れていたし、医者は何マイルも離れた場所での急患で突然呼び出され、父の死後、家の近くに来ることはなかった。船長は弱っていたと言ったが、実際、彼は体力を取り戻すどころか、むしろ弱っていくように見えた。彼は階段を上り下りし、談話室からバーへと行き来し、時には戸口から鼻を出して海の匂いを嗅いだ。移動する時は壁に掴まって体を支え、険しい山を登る人のように、速く苦しそうな呼吸をしていた。彼は特に私に話しかけることはなく、自分の打ち明け話をすっかり忘れてしまったのだと私は信じている。しかし、彼の気性はより移り気になり、体の弱さを考慮に入れても、以前よりも暴力的になっていた。酔うとカトラスを抜き、むき出しのままテーブルの前に置くという、不穏な癖がついていた。しかし、それでも彼は以前ほど人々に構わなくなり、自分の考えに閉じこもり、やや心ここにあらずといった様子だった。例えば一度、我々が非常に驚いたことに、彼は別の曲を口ずさみ始めた。それは、海に出る前に若い頃に覚えたに違いない、田舎の恋の歌のようなものだった。
そんな風に日々は過ぎていった。葬儀の翌日、凍えるような霧の深い、霜の降りる午後三時ごろ、私が戸口に立ち、父のことを悲しい思いで考えていた時、道に沿って誰かがゆっくりと近づいてくるのが見えた。彼は明らかに盲目だった。杖で前を叩き、目と鼻を覆う大きな緑色の目隠しをしていた。そして、老いか弱さのためか、背中が丸まっており、フードのついた巨大な古ぼけた海用のマントを着ていたため、まるで奇形のように見えた。人生でこれほど恐ろしい姿をした人物を見たことはなかった。彼は宿から少し離れたところで立ち止まり、奇妙な節回しの声で、目の前の空間に向かって呼びかけた。「どなたか親切な方、哀れな盲目の男に教えてはいただけませんか。祖国イングランドを慈悲深く守るために、尊い視力を失ったこの男が――そしてジョージ王に神のご加護を! ――今、この国のどこに、どのあたりにいるのかを。」
「ここは『ベンボー提督亭』です、ブラック・ヒル・コーブの」と私は言った。
「声が聞こえる」と彼は言った。「若い声だ。手を貸してはくれんかね、親切な若き友よ、そして中へ案内してくれ。」
私が手を差し出すと、その恐ろしく、物腰の柔らかい、目の見えない生き物は、万力のように一瞬で私の手を握りしめた。私はあまりに驚いて身を引こうともがいたが、盲目の男は腕の一振りで私をぐいと引き寄せた。
「さあ、小僧」と彼は言った。「船長のところへ連れて行け。」
「だめです」と私は言った。「本当に、私にはできません。」
「ほう」と彼は嘲笑した。「そうかい! まっすぐ連れて行け。さもないと腕をへし折るぞ。」
そう言うと、彼は私の腕をぐいと捻り、私は思わず叫び声を上げた。
「あなたのためを思って言っているんです。船長は以前の船長とは違います。カトラスを抜いて座っているんです。別の紳士が――」
「さあ、歩け」と彼は遮った。私はあの盲目の男の声ほど、残酷で、冷たく、醜い声を聞いたことがなかった。その声は痛み以上に私を萎縮させ、私はすぐに彼に従い始めた。まっすぐ戸口を入り、談話室へと向かった。そこでは、病気の年老いた我らが海賊が、ラムに酔ってぼんやりと座っていた。盲目の男は私にぴったりと寄り添い、鉄のような片手で私を掴み、私が支えきれないほどの体重をかけてきた。「彼のところまでまっすぐ連れて行け。そして俺が見えたら、『ビル、友達が来たぞ』と叫べ。そうしないなら、こうしてやる」そう言って、彼は私をぐいと捻り、私は気を失うかと思った。あれやこれやで、私は盲目の物乞いを心底恐れ、船長への恐怖を忘れてしまった。談話室のドアを開けると、私は震える声で、彼に命じられた言葉を叫んだ。
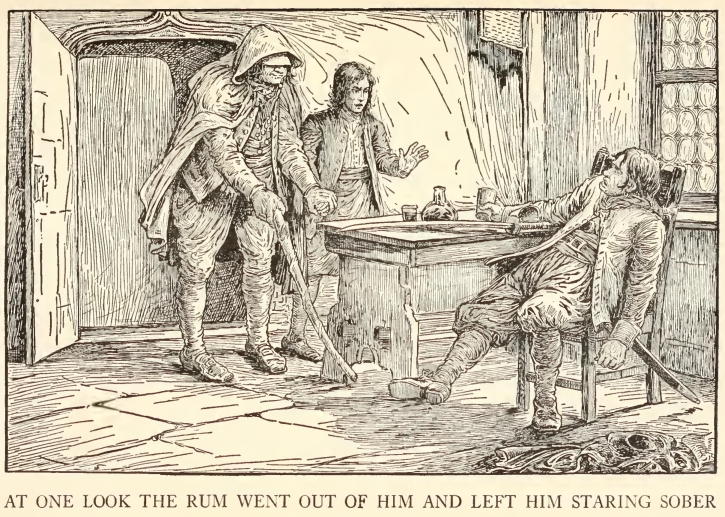
哀れな船長は目を上げた。一目見るなり、ラムの酔いは吹き飛び、彼はしらふのまま呆然と見つめていた。その顔の表情は、恐怖というよりは、むしろ死病にかかった者のそれだった。彼は立ち上がろうとしたが、体にそれだけの力が残っていたとは思えない。
「ビル、そこに座っていろ」と物乞いは言った。「俺には見えんが、指一本動かせば聞こえる。用件は用件だ。左手を出せ。小僧、奴の左手首を掴んで、俺の右手の近くへ持ってこい。」
我々は二人とも、言われた通りに忠実に従った。そして私は、彼が杖を持っていた手の中から何かを船長の手のひらに移すのを見た。船長の手は、即座にそれを握りしめた。
「これで用は済んだ」と盲目の男は言った。その言葉と共に、彼は突然私を放し、信じられないほどの正確さと素早さで、談話室から道へと飛び出した。私がまだ呆然と立ち尽くしている間、彼の杖がコツ、コツ、コツと遠ざかっていく音が聞こえた。
私も船長も、我に返るまでにしばらくかかった。しかし、やがてほぼ同時に、私はまだ握っていた彼の手首を放し、彼は手を引き寄せて手のひらを鋭く見つめた。
「十時だ!」と彼は叫んだ。「六時間。まだ間に合う」。そう言って彼は跳ね起きた。
そうしたまさにその時、彼はよろめき、手を喉に当て、一瞬ふらついたかと思うと、奇妙な音を立てて、床にまっすぐ顔から倒れ込んだ。
私はすぐに駆け寄り、母を呼んだ。しかし、急いでもすべては無駄だった。船長は、雷のような脳卒中に襲われ、即死していた。不思議なことだが、私は確かにあの男が好きではなかった。最近は気の毒に思い始めてはいたが、彼が死んだのを見ると、わっと泣き出してしまった。それは私が知る二度目の死であり、最初の死の悲しみは、まだ私の心に生々しく残っていた。

第四章 衣装箱
私はもちろん、知っていることすべてを母に話すのに時間を無駄にはしなかった。もっと早く話すべきだったのかもしれない。そして我々は、自分たちが困難で危険な状況にあることにすぐに気づいた。あの男の金の一部――もし持っていたらの話だが――は、確かに我々に支払われるべきものだった。しかし、船長の船仲間たち、とりわけ私が目にした黒犬と盲目の物乞いの二人が、死んだ男の借金の支払いのために自分たちの獲物を手放すとは到底思えなかった。すぐに馬に乗ってライブシー博士のところへ行けという船長の命令に従えば、母を一人で無防備なまま残すことになり、それは考えられなかった。実際、我々のどちらかがこれ以上家にいることは不可能に思えた。台所の暖炉で石炭が崩れる音も、時計の時を刻む音さえもが、我々を不安にさせた。耳には、近所のあちこちから足音が近づいてくるように聞こえた。談話室の床に横たわる船長の死体と、あの忌まわしい盲目の物乞いが近くをうろつき、戻ってくる準備をしているという考えとの間で、ことわざに言うように、恐怖で肌が粟立つ瞬間があった。何かを早急に決めなければならず、我々はついに、一緒に隣の村へ助けを求めに行くことにした。言うが早いか、我々は頭も覆わず、暮れなずむ夕闇と凍える霧の中へとすぐに駆け出した。
その村は、見えないものの、次の入り江の向こう側、数百ヤードも離れていない場所にあった。そして、私を大いに勇気づけたのは、それが盲目の男が現れた方向とは反対で、彼がおそらく戻っていったであろう方向とも逆だったことだ。道中、我々は時々立ち止まって互いにしがみつき、耳を澄ませたが、時間はさほどかからなかった。しかし、異常な音は何も聞こえなかった――ただ、さざ波の低い音と、森の住人たちの鳴き声だけだった。
村に着いた時にはすでにろうそくの明かりが灯っており、家々の戸口や窓から漏れる黄色い光を見て、どれほど元気づけられたか、決して忘れないだろう。しかし、それが結局、その場所で得られそうな助けの最良の部分だったことが判明した。というのも――男なら恥を知れと思うだろうが――誰一人として、我々と一緒に「ベンボー提督亭」に戻ることに同意してくれる者はいなかったのだ。我々の苦境を語れば語るほど、男も女も子供も、ますます家の安全な場所に固執した。フリント船長の名前は、私には聞き慣れないものだったが、そこにいた何人かにはよく知られており、大きな恐怖をもたらした。それに、「ベンボー提督亭」の向こう側で野良仕事をしていた男たちの中には、道で何人かの見知らぬ男たちを見かけ、密輸業者だと思って逃げ出したことを思い出した者もいた。そして、少なくとも一人は、我々が「キットの穴」と呼ぶ場所で小さなラガー船を見たという。そもそも、船長の仲間であるというだけで、彼らを死ぬほど怖がらせるには十分だったのだ。そして、かいつまんで言えば、別の方向にあるライブシー博士のところまで馬を走らせる気のある者は何人かいたが、宿を守るのを手伝ってくれる者は一人もいなかった。
臆病は伝染すると言う。しかし一方で、議論は人を大いに勇気づけるものでもある。そして、それぞれが言い分を述べた後、母が彼らに向かって演説した。父を亡くした息子のものになるべき金を失うつもりはない、と彼女は宣言した。「もし、あなた方の誰も勇気がないのなら」と彼女は言った。「ジムと私にはあります。来た道を、私たちは戻ります。あなたたち、図体ばかり大きくて、臆病な男たちには感謝などしません。たとえ死ぬことになっても、あの箱を開けてみせます。それからクロスリーさん、その袋をお借りします。私たちの正当なお金を持って帰るために。」
もちろん、私は母と一緒に行くと言ったし、もちろん、皆が我々の無謀さに声を上げたが、それでもなお、我々と一緒に行こうとする男は一人もいなかった。彼らがしてくれたのは、襲われた場合に備えて装填済みのピストルを私に渡し、我々が戻る途中で追跡された場合に備えて鞍をつけた馬を用意しておくと約束することだけだった。そして、一人の若者が武装した助けを求めて、博士のところへ先行することになった。
この危険な冒険に、我々二人が寒い夜の中へと出発した時、私の心臓は高鳴っていた。満月が昇り始め、霧の上端から赤みがかって覗いており、それが我々の足を急がせた。我々が再び外に出る前に、あたりが昼間のように明るくなり、我々の出発が見張りの目に晒されることは明らかだったからだ。我々は生け垣に沿って、音を立てずに素早く滑るように進んだ。恐怖を増すようなものを見たり聞いたりすることはなく、ほっとしたことに、「ベンボー提督亭」のドアが我々の後ろで閉まった。
私はすぐに閂をかけ、我々は暗闇の中で、死んだ船長の体と共に家に二人きりで、しばらく息を切らして立っていた。それから母がバーでろうそくを手に入れ、互いの手を握り合いながら、談話室へと進んだ。彼は我々が残した時のまま、仰向けに、目を開き、片腕を伸ばして横たわっていた。
「ブラインドを下ろして、ジム」と母はささやいた。「外から見張っているかもしれないわ。さあ」私がそうすると、彼女は言った。「あれから鍵を取らなくちゃ。でも、誰がそれに触るっていうの!」彼女はその言葉を口にしながら、むせび泣くようだった。
すぐに私はひざまずいた。彼の手のすぐそばの床に、片面が黒く塗られた小さな丸い紙切れが落ちていた。これが「黒丸」に違いない。拾い上げてみると、裏側には実に丁寧で読みやすい字で、短い伝言が記されていた。「今夜十時までだ。」
「十時までだったんだ、母さん」私がそう言ったのと、古時計が時を打ち始めたのは同時だった。突然の音に私たちは心臓が飛び出るほど驚いたが、まだ六時だとわかり、ほっとした。
「さあ、ジム」と母が言った。「鍵よ。」
私は船長のポケットを次から次へと探った。いくつかの小銭、指貫、糸と太い針、端をかじられた葉巻、柄の曲がった鞘付きナイフ、懐中方位磁石、そして火口箱。それしか入っておらず、私は絶望的な気分になった。
「首に下げているんじゃないかしら」と母が言った。
強い嫌悪感を押し殺して、彼のシャツの襟元を引き裂くと、案の定、タールで汚れた紐が下がっていた。それを船長自身のナイフで切り取ると、鍵が見つかった。この勝利に私たちは希望に満ち、すぐさま二階へ駆け上がった。彼が長く寝泊まりし、到着した日からずっと例の箱が置かれているあの小部屋へ。
外見はどこにでもある船乗りの箱で、天板には熱した鉄ごてで頭文字「B」が焼き付けてあり、角は長年の手荒い扱いでいくらか潰れ、欠けていた。
「鍵をちょうだい」と母が言った。錠はひどく固かったが、母は瞬く間に鍵を回し、蓋を跳ね上げた。
中からはタバコとタールの強い匂いが立ち上ったが、一番上には丁寧にブラシがかけられ、折り畳まれた上等な服が一着あるだけだった。母によれば、一度も袖を通したことのない服らしかった。その下から、がらくたが次々と現れた。四分儀、ブリキのジョッキ、数本の棒状タバコ、見事なピストルが二丁、銀の延べ棒、古いスペイン製の懐中時計、その他ほとんど価値のない異国製の装身具、真鍮張りのコンパス一組、そして五つか六つの奇妙な西インド諸島の貝殻。なぜ彼が、罪を犯し、追われる放浪の人生で、こんな貝殻を持ち歩いていたのか、後になって私は何度も不思議に思ったものだ。
その時点では、銀の延べ棒と装身具以外に価値のあるものは見つからなかったが、どちらも私たちの目当てではなかった。その下には古いボート・クロークがあり、幾多の港の砂州で潮を浴びたのか、白く塩を吹いていた。母が焦れたようにそれを引き上げると、箱の底に最後の品々が姿を現した。油布で包まれた書類らしき束と、触れるとジャラリと金の音を立てるズック袋だった。
「あの悪党どもに、あたしが正直者だってことを見せてやるわ」と母は言った。「宿代はきっちりいただく。でも一銭たりとも余分には取らない。クロッスリー奥さんの袋を持っててちょうだい」。そう言うと母は、船長のツケの分だけ、船乗りの袋から私が持っている袋へと金貨を数え始めた。

それは長く骨の折れる作業だった。金貨はありとあらゆる国のもので、大きさもまちまちだったからだ。ダブロン金貨、ルイ金貨、ギニー金貨、八レアル銀貨、その他名前も知らない硬貨がごちゃ混ぜになっていた。その中でもギニー金貨は最も少なく、母が勘定できるのはこの硬貨だけだった。
半分ほど数え終えたとき、私ははっとして母の腕を押さえた。凍てつく静かな空気の中、心臓が口から飛び出そうな音が聞こえたのだ。凍った道を叩く、あの盲人の杖の音だった。私たちが息を殺している間にも、音はどんどん近づいてくる。やがて宿の扉を鋭く叩く音がし、ドアノブが回され、忌まわしい男が入ろうとしてかんぬきがガタガタと鳴るのが聞こえた。そして、内も外も長い沈黙に包まれた。ようやく杖の音が再び始まり、そして、言葉にできないほどの喜びと安堵の中、音はゆっくりと遠ざかり、やがて聞こえなくなった。
「母さん」と私は言った。「全部持って、早く行こう」。かんぬきが下りているのは怪しまれるに決まっている。そうなれば奴らが蜂の巣をつついたように押し寄せてくるだろう。かんぬきをかけておいてどれほど良かったか、あの恐ろしい盲人に出会ったことのない者にはわかるまい。
しかし母は、怯えきってはいたものの、宿代より一銭でも多く取ることを承知せず、かといってそれより少なく取ることも頑として受け入れなかった。まだ七時にもなっていない、時間はたっぷりある、自分には正当な権利があるのだからきっちり貰う、と母は言う。そうして私と言い争っていると、丘の向こうから低く短い口笛が聞こえてきた。それは、私たち二人にとって十分すぎる合図だった。
「今ある分だけいただくわ」母は飛び上がった。
「じゃあ僕は、勘定の足しにこれを」と、私は油布の包みを拾い上げた。
次の瞬間、私たちは空の箱のそばに蝋燭を残し、手探りで階段を下りていた。そしてさらに次の瞬間には、扉を開け、全力で逃げ出していた。まさに間一髪だった。霧は急速に晴れつつあり、両側の高台にはすでに月が煌々と輝いていた。ただ、谷間の底と宿屋の扉の周りだけが、薄いヴェールに覆われ、私たちの逃走の第一歩を隠してくれていた。村までの道のりの半分にも満たない、丘の麓を少し過ぎたあたりで、私たちは月光の下に姿を晒さねばならないだろう。それだけではなかった。複数の人間が走ってくる足音がすでに耳に届き、振り返ると、揺れ動く光が急速に近づいてくるのが見えた。誰かが提灯を持っているのだ。
「ジム」母が突然言った。「お金を持って、先にお逃げ。あたし、もう倒れそう。」
これで二人ともおしまいだ、と私は思った。近所の人々の臆病さをどれほど呪ったことか。哀れな母の、その正直さと欲深さ、さっきまでの無謀さと今の弱さをどれほど責めたことか。幸いにも、私たちは小さな橋のたもとにいた。よろめく母を土手際まで支えていくと、案の定、母はため息をついて私の肩に崩れ落ちた。どうやってそんな力が出たのか自分でもわからないし、かなり手荒だったとは思うが、なんとか母を土手の下、橋のアーチの陰まで引きずり込んだ。橋桁が低く、這って進むのがやっとだったので、それ以上は動かせなかった。私たちはそこでじっとしているしかなかった。母はほとんど無防備に体を晒し、二人とも宿屋から声が聞こえるほどの距離にいた。

第五章 盲人の最期
ある意味で、私の好奇心は恐怖に勝っていた。じっとしていることなどできず、再び土手を這い上がり、エニシダの茂みに頭を隠して、宿の前の道を見渡せる場所を確保した。場所を定めた途端、敵が現れ始めた。七、八人、いずれも必死の形相で走ってくる。足音はばらばらで、提灯を持った男が数歩先を行っていた。三人の男が手を取り合って走っていた。霧ごしにも、その真ん中にいるのがあの盲目の物乞いだとわかった。次の瞬間、彼の声が私の推測が正しいことを証明した。
「ドアをぶち破れ!」と彼が叫んだ。
「へい、へい、親分!」と二、三人が応え、「ベンボー提督亭」に殺到した。提灯持ちもそれに続く。そして彼らが立ち止まり、ひそひそと何かを話しているのが聞こえた。ドアが開いていることに驚いたようだった。しかし、その静寂は短かった。盲人が再び命令を下したのだ。その声は先ほどより大きく、甲高くなっていた。焦りと怒りに燃えているかのようだった。
「入れ、入れ、中へ入れ!」と彼は叫び、ぐずぐずしている部下たちを罵った。
四、五人がすぐに従い、二人だけが恐ろしい物乞いとともに道に残った。一瞬の間があり、驚きの叫び声が聞こえ、そして家の中から「ビルが死んでるぞ」と叫ぶ声がした。
しかし盲人は、またしても彼らの遅さを罵った。
「この腰抜けども、何人かそいつを調べろ。残りは二階だ、箱を探せ」と彼は叫んだ。
古い階段をドタドタと駆け上がる音が聞こえ、家全体が揺れているようだった。その直後、新たな驚きの声が上がった。船長の部屋の窓が、ガラスの割れる音とともに乱暴に開け放たれ、一人の男が月光の中に上半身を乗り出し、下の道にいる盲目の物乞いに向かって叫んだ。
「ピュー」と男は叫んだ。「先を越されたぜ。誰かが箱の中身をひっくり返していやがる。」
「そいつはあるのか?」とピューが怒鳴った。
「金ならある。」
盲人は金を罵った。
「フリントの拳のことだ」と彼は叫んだ。
「どこにも見当たらねえ」と男は答えた。
「おい、下にいるやつ、ビルは持っているか?」と盲人が再び叫んだ。
すると、おそらく下に残って船長の体を調べていたであろうもう一人の男が、宿屋の戸口に現れた。「ビルはもう調べられた後だ」と彼は言った。「何も残っちゃいねえ。」
「宿屋の連中の仕業だ。あの小僧だ。奴の目玉をえぐり出しておくんだった!」と盲人のピューが叫んだ。「さっきまではいたはずだ。俺が試したときはドアにかんぬきがかかっていた。散れ、野郎ども、奴らを見つけ出せ。」
「確かに、明かりをここに置いていったぜ」と窓の男が言った。
「散って奴らを探せ! 家を隅々までひっくり返せ!」ピューは杖で道を叩きながら、繰り返し叫んだ。
それから宿中で大騒ぎが始まった。重い足音が走り回り、家具がひっくり返され、ドアが蹴破られ、その音は岩壁にまで反響した。やがて男たちが一人、また一人と道に出てきて、我々がどこにも見つからないと報告した。そして、死んだ船長の金の前で私と母を脅かしたのと同じ口笛が、再び夜の闇にはっきりと響いた。ただし、今度は二度繰り返された。私はそれを、いわば盲人が襲撃のために部下を呼び集める合図だと思っていたが、そうではなかった。村の方角の丘の中腹からの合図であり、海賊たちの様子からして、危険の接近を知らせる警告だったのだ。
「またダークだ」と一人が言った。「二回だ! ずらかるぞ、お前ら。」
「ずらかるだと、この腰抜けが!」とピューが叫んだ。「ダークは最初から馬鹿で臆病者だ。あんな奴の言うことなど気にするな。奴らはすぐ近くだ、遠くへは行けん。もう手に入れたも同然だ。散って探せ、この犬どもめ! ああ、ちくしょう」と彼は叫んだ。「俺に目さえあれば!」
この訴えはいくらか効果があったようで、二人の男が材木のあたりをあちこち探し始めたが、私の目には、それは気のない様子で、常に自分の身の危険を気にしているように見えた。残りの者たちは道の上で決心がつかずに突っ立っていた。
「何千ポンドもの大金が目の前にあるというのに、この馬鹿どもはぐずぐずしおって! そいつを見つけさえすれば王様のように金持ちになれるんだぞ。ここにあるとわかっていながら、こそこそ突っ立っているだけか。お前らの中にはビルに立ち向かう勇気のあった奴は一人もいなかった。だが俺はやったんだぞ、この盲目の俺がな! それなのにお前らのせいでこの好機を逃すというのか! 馬車を乗り回せるはずの俺が、ラム酒をせびる哀れな這いずり回る乞食になれというのか! ビスケットの中のゾウムシほどの度胸でもあれば、まだ奴らを捕まえられるはずだ。」
「ちくしょう、ピュー、ダブロン金貨は手に入れたじゃねえか!」と一人が不平を言った。
「例のブツはどこかに隠したのかもしれん」と別の男が言った。「ギニー金貨[訳注:ジョージ王の肖像が描かれていたためこう呼ばれる]を持って、ここでわめくのはやめろ、ピュー。」
まさに「わめく」という言葉がぴったりだった。これらの反論にピューの怒りは頂点に達し、ついに激情が理性を完全に圧倒した。彼は盲目のまま手当たり次第に部下たちを打ち、その杖は一人ならず重い音を立てて当たった。
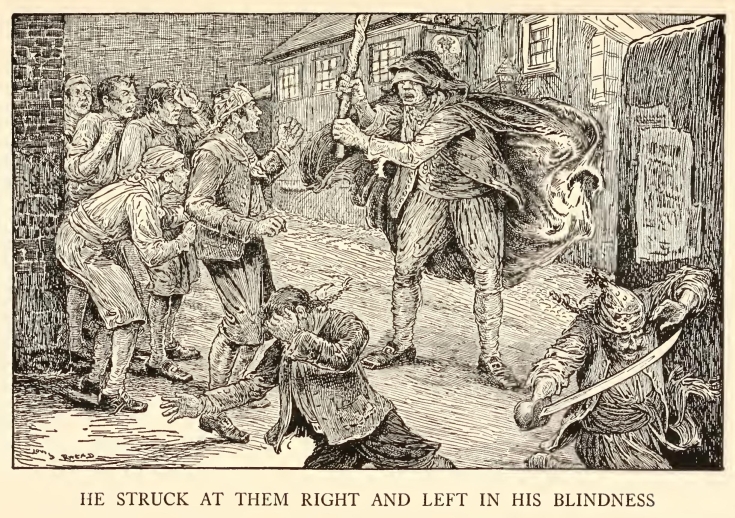
今度は部下たちが、この盲目の悪党を罵り返し、恐ろしい言葉で脅し、杖を掴んで彼の手から奪い取ろうとしたが無駄だった。
この仲間割れが私たちを救った。彼らがまだ言い争っている最中に、村の方角の丘の上から別の音が聞こえてきたのだ。馬が疾走してくる蹄の音だった。ほぼ同時に、生け垣の方からピストルの閃光と発砲音が響いた。それが最後の危険信号だったのは明らかで、海賊たちは一斉に踵を返し、四方八方に散っていった。一人は入り江に沿って海へ、一人は丘を斜めに横切って、という具合に。半分のうちに、ピューを除いて彼らの姿は影も形もなくなった。彼らがピューを見捨てたのは、純粋なパニックからか、あるいは彼の悪態や暴力への復讐か、私にはわからない。しかし彼は一人取り残され、狂乱状態で道をあちこち杖で叩き、手探りで仲間を呼び続けていた。ついに彼は道を間違え、私のすぐそばを通り過ぎ、村の方へと数歩走った。「ジョニー、黒犬、ダーク」などと仲間たちの名前を叫びながら。「おい、この老いぼれのピューを置いていかないでくれ、仲間だろ、このピューを!」
その時、馬の蹄の音が丘の頂上に達し、四、五人の騎手が月光の中に姿を現し、全速力で坂を駆け下りてきた。
これを見てピューは自分の過ちに気づき、悲鳴を上げて向きを変え、溝に向かってまっすぐ走って転がり落ちた。しかし彼は一瞬で立ち上がり、今や完全に方向感覚を失って、迫りくる馬群の先頭の馬の真下へと突進した。
騎手は彼を助けようとしたが、無駄だった。夜の闇に甲高い叫び声を響かせ、ピューは倒れた。四本の蹄が彼を踏みつけ、蹴散らして通り過ぎた。彼は横向きに倒れ、やがてうつ伏せに崩れると、二度と動かなかった。
私は飛び上がって騎手たちに声をかけた。彼らはこの事故に肝を冷やし、ちょうど馬を止めるところだった。すぐに彼らの正体がわかった。一人、他の者たちから遅れて走っていたのは、村からライブシー先生のところへ使いに行った少年だった。残りは税関吏で、少年が途中で出会い、機転を利かせて一緒に戻ってきたのだった。キットの入り江に停泊していた小型帆船の情報がダンス治安官の耳に入り、その夜、我々のいる方角へ彼を向かわせたのだ。この偶然のおかげで、母と私は死を免れたのである。
ピューは死んでいた。完全に息絶えていた。母の方は、村まで運んで冷たい水と気付け薬を嗅がせるとすぐに意識を取り戻し、恐怖に震えてはいたものの、別状はなかった。ただ、宿代の残りをしきりに嘆いてはいたが。その間、治安官はできる限りの速さでキットの入り江へと馬を走らせた。しかし部下たちは馬から降り、馬を引いたり、時には支えたりしながら、常に伏兵を警戒して谷間を手探りで下りていかねばならなかった。そのため、彼らが入り江に着いたときには、小型帆船はすでに出航していたのも無理はなかった。まだ岸の近くではあったが。治安官が船に呼びかけると、声が返ってきた。「月明かりから出ろ、さもないと鉛玉を食らうぞ」。同時に、弾丸が彼の腕のすぐそばをかすめていった。まもなく、船は岬を回り、姿を消した。ダンス氏は、彼自身の言葉を借りれば「陸に上がった魚のように」そこに立ち尽くし、B――の町へ部下を一人派遣してカッター船に警告するのが精一杯だった。「もっとも」と彼は言った。「そんなものは気休めにしかならん。奴らはまんまと逃げおおせた。これで一件落着だ。ただ」と彼は付け加えた。「ピューの旦那の鼻を明かせたのは愉快だったがね」。この時までに、彼は私の話を聞いていたのだ。
私は彼と一緒に「ベンボー提督亭」に戻った。家の中の惨状は想像を絶するものだった。私と母を血眼になって探すうちに、連中は時計さえもなぎ倒していた。実際に盗られたものは船長の金袋とレジの小銭だけだったが、私たちが破産したことは一目でわかった。ダンス氏には状況がまったく理解できなかった。
「金は奴らが持っていったんだろう? ではホーキンズ君、一体全体、奴らは何を探していたんだ? もっと金か、そうかね?」
「いえ、お金ではないと思います」と私は答えた。「実を言うと、その品物は僕が胸のポケットに持っているはずです。そして、正直に申し上げますと、これを安全な場所に預けたいのです。」
「もちろんだ、少年。その通りだ」と彼は言った。「よければ私が預かろう。」
「できれば、ライブシー先生に……」と私は言いかけた。
「その通りだ」と彼は陽気に遮った。「まったくもってその通り。あの方は紳士であり、治安判事でもある。そういえば、私もあの方か郷士殿のところへ馬を走らせて報告せねばならん。結局のところ、ピューの旦那は死んだ。残念だとは思わんが、死んだことには変わりない。そうなると、連中は国王陛下の税関吏に罪をなすりつけようとするだろうからな。そうだ、ホーキンズ君、よかったら君も一緒に連れて行ってやろう。」
私はその申し出に心から感謝し、馬のいる村まで一緒に歩いて戻った。私が母に目的を告げる頃には、一行は皆、馬上の人となっていた。
「ドッガー」とダンス氏が言った。「お前の馬は良い馬だ。この子を後ろに乗せてやれ。」
ドッガーのベルトにしがみついて私が馬にまたがると、治安官が号令をかけ、一行は弾むような速足でライブシー先生の家へと向かった。
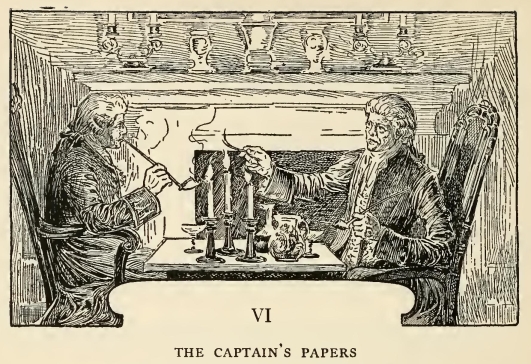
第六章 船長の書類
私たちは道中ずっと馬を飛ばし、ライブシー先生の家の前に着いた。家の正面は真っ暗だった。
ダンス氏に飛び降りてドアを叩くように言われ、ドッガーが鐙に足をかけるのを手伝ってくれた。ドアはほとんどすぐに女中が開けてくれた。
「ライブシー先生はいらっしゃいますか?」と私は尋ねた。
いいえ、と彼女は答えた。午後に一度お戻りになりましたが、郷士様のお屋敷へ夕食と夜を過ごしにお出かけになりました、と。
「ではそちらへ向かうとしよう、諸君」とダンス氏が言った。
今度は距離が短かったので、私は馬には乗らず、ドッガーの鐙革につかまって走った。門番小屋の門をくぐり、葉の落ちた、月明かりに照らされた長い並木道を抜けると、両側に広大な古い庭園を見下ろす白亜の屋敷が見えてきた。ここでダンス氏は馬から降り、私を連れて、一言断ると家の中へ通された。
召使いは私たちをマット敷きの廊下へと案内し、その突き当たりにある大きな書斎へと通してくれた。そこは壁一面に本棚が並び、その上には胸像が置かれていた。郷士殿とライブシー先生は、明るく燃える暖炉を挟んで両側に座り、パイプを手にしていた。
郷士殿をこんなに間近で見たのは初めてだった。身長は六フィートを超す長身で、それにふさわしく肩幅も広く、顔つきは無骨で飾り気がなかった。長旅で日に焼け、赤らみ、深いしわが刻まれている。眉は非常に黒く、よく動いた。それが彼に、気難しそうというよりは、短気で誇り高いといった印象を与えていた。
「入れ、ダンス君」と彼は、実に堂々と、そして少し見下したように言った。
「こんばんは、ダンス君」と先生は頷きながら言った。「そして、こんばんは、ジム君。何の用かね?」
治安官は背筋を伸ばして直立し、暗唱でもするかのように事の次第を語った。二人の紳士が身を乗り出し、顔を見合わせ、驚きと興味のあまりパイプを吸うのも忘れている様子は、実に見ものだった。母が宿屋へ引き返した話を聞くと、ライブシー先生は思わず自分の腿を叩き、郷士殿は「ブラボー!」と叫んで、長いパイプを暖炉の格子にぶつけて折ってしまった。話が終わるずっと前から、トレローニー郷士(ご記憶だろうが、それが郷士殿の名前だ)は席を立ち、部屋の中を大股で歩き回っていた。先生の方は、話をよく聞こうとでもいうように、白粉をはたいたかつらを外し、短く刈り込んだ黒髪の頭を晒して座っていたが、その姿は実におかしなものだった。
やがてダンス氏が話を終えた。「ダンス君」と郷士殿が言った。「君は実に立派な男だ。そして、あの真っ黒で極悪非道なならず者を馬で轢き殺したことについては、ゴキブリを踏み潰すのと同じく、美徳の行いと見なすぞ、君。このホーキンズ少年は切り札のようだ。ホーキンズ君、そこのベルを鳴らしてくれたまえ。ダンス君にエールを一杯やらねば。」
「それで、ジム君」と先生が言った。「君が、奴らが探していた物を持っているのだね?」
「はい、これです」と言って、私は油布の包みを彼に渡した。
先生はそれを隅々まで眺め、指がそれを開きたくてうずうずしているようだったが、そうはせず、静かに上着のポケットにしまった。
「郷士殿」と先生は言った。「ダンス君はエールを飲み終えたら、無論、国王陛下の公務に戻らねばなりません。しかし、ジム・ホーキンズ君は今夜、私の家に泊めていくつもりです。そして、もしよろしければ、冷たいパイを持ってこさせて、彼に夕食をとらせてはいかがでしょう。」
「君の好きなようにしたまえ、ライブシー」と郷士殿は言った。「ホーキンズ君は冷たいパイ以上のものに値する働きをした。」
そこで大きな鳩のパイが運ばれてきてサイドテーブルに置かれ、私は腹一杯の夕食にありついた。腹ペコだったのだ。その間、ダンス氏はさらに称賛の言葉を浴び、やがて退出していった。
「さて、郷士殿」と先生が言った。
「さて、ライブシー」と郷士殿が同じ息で言った。
「一人ずつ、一人ずつ」とライブシー先生は笑った。「このフリントという男のことはお聞き及びでしょうな?」
「聞いたことがあるか、だと!」と郷士殿は叫んだ。「聞いたことがあるか、ですと! 奴は海に出た中でも最も血に飢えた海賊でしたぞ。黒髭など、フリントに比べれば赤子同然だ。スペイン人どもは奴を途方もなく恐れていて、申し上げますが、私は時々、奴が英国人であることを誇りに思ったほどです。この目で奴の船の帆をトリニダード沖で見たことがあります。私が乗っていた船の、ラム酒樽から生まれたような臆病者の船長は、引き返しましたぞ。引き返したのです、ポート・オブ・スペインへと!」
「ふむ、私もイギリスで彼の噂は聞いたことがあります」と先生は言った。「しかし問題は、彼が金を持っていたかどうかです。」
「金!」と郷士殿は叫んだ。「話を聞いていなかったのですか? あの悪党どもが金以外の何を狙うというのです? 金以外の何を気にかけるというのです? 金のためでなければ、あのろくでなしどもが命を懸けるものがありますか?」
「それはすぐにわかるでしょう」と先生は答えた。「しかし、あなたはあまりに血の気が多くて大声で叫ぶものだから、私が口を挟む隙がない。私が知りたいのはこれです。仮に、私のこのポケットに、フリントが財宝を埋めた場所への手がかりがあったとして、その財宝はかなりの額になるのでしょうか?」
「額、ですと!」と郷士殿は叫んだ。「こうなりますぞ。もし我々がその手がかりとやらを手に入れたなら、私はブリストルの港で船を仕立て、あなたとホーキンズ君を乗せていく。そして一年かかろうとも、その財宝を手に入れてみせます。」
「よろしい」と先生は言った。「では、ジム君がよければ、包みを開けましょう」。そして彼はそれを目の前のテーブルに置いた。
包みは縫い合わされており、先生は道具箱を取り出して医療用のはさみで縫い目を切らねばならなかった。中には二つのものが入っていた。一冊の本と、封をされた一枚の紙だ。
「まず、本から見てみましょう」と先生は言った。
郷士殿と私は、先生が本を開くのを肩越しに覗き込んでいた。ライブシー先生が、食事をしていたサイドテーブルからこちらへ来て、探索の楽しみを分かち合おうと親切に合図してくれたのだ。最初のページには、ペンを持った人間が退屈しのぎか練習で書いたような、走り書きがいくつかあるだけだった。一つは入れ墨と同じ「ビリー・ボーンズのお気に入り」。それから「航海士、W・ボーンズ氏」、「ラムはもうごめんだ」、「パーム・キー沖で奴はそれを手に入れた」、その他、ほとんどが単語で意味の通らない断片的な言葉がいくつかあった。いったい誰が「それを手に入れた」のか、そして彼が手に入れた「それ」とは何なのか、私は不思議に思わずにはいられなかった。背中にナイフでも突き立てられたのかもしれない。
「ここには大した情報はないようですな」とライブシー先生はページをめくりながら言った。
次の十数ページは、奇妙な記録で埋め尽くされていた。行の一方には日付、もう一方には金額が記されており、普通の帳簿のようだったが、説明書きの代わりに、二つの間には様々な数の十字が記されているだけだった。例えば、一七四五年六月十二日には、七十ポンドという金額が誰かに支払われるべきであったようだが、その理由を説明するものは六つの十字だけだった。いくつかの場合には、確かに「カラカス沖」のように地名が書き加えられていたり、「六十二度十七分二十秒、十九度二分四十秒」のように緯度経度が記されているだけだったりした。
記録は二十年近くに及び、個々の金額は時とともに大きくなっていた。そして最後には、五、六度計算を間違えた末に総額が算出され、「ボーンズ、奴の山分け分」という言葉が書き添えられていた。
「これではさっぱり意味がわかりませんな」とライブシー先生は言った。
「真昼の太陽のように明白ですぞ」と郷士殿は叫んだ。「これはあの腹黒い犬畜生の帳簿です。この十字は、奴らが沈めたか略奪した船や町の名を表している。金額はあの悪党の分け前で、曖昧さを恐れた場合には、ご覧の通り、より明確なことを書き加えている。『カラカス沖』、ほら、ここで不運な船が襲われたのです。その船に乗っていた哀れな魂に神の御加護を。とうの昔に海の藻屑でしょうがな。」
「その通り!」と先生は言った。「旅慣れた方は違いますな。その通り! そしてご覧なさい、彼の地位が上がるにつれて金額も増えている。」
その本には他に、終わりの方の白紙のページにいくつかの場所の方位が記されているのと、フランス、イギリス、スペインの通貨を共通の価値に換算するための表があるくらいだった。
「抜け目のない男だ!」と先生は叫んだ。「騙されるような男ではなかったようですな。」
「そして今度は」と郷士殿が言った。「もう一つの方を。」
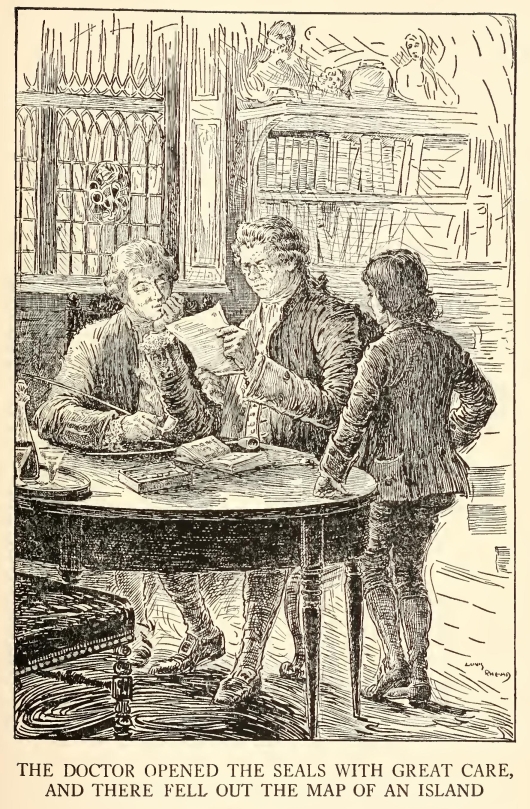
紙は数か所、封蝋の代わりに指貫で封がしてあった。おそらく、私が船長のポケットで見つけたあの指貫だろう。先生が慎重に封を開けると、中から一枚の地図が滑り落ちた。ある島の地図で、緯度経度、水深、丘や湾や入り江の名前など、船を安全に停泊させるために必要なあらゆる詳細が記されていた。島の大きさは長さ約九マイル、幅五マイル。形は、言うなれば、でっぷりとした竜が立ち上がったような姿で、陸に囲まれた立派な港が二つあり、中央には「遠眼鏡山」と記された丘があった。後から書き加えられたものがいくつかあったが、何よりも目立ったのは、赤いインクで書かれた三つの十字だった。二つは島の北部に、一つは南西部に。そして最後の十字のそばには、同じ赤いインクで、船長の震えるような字とは全く違う、小さく整った文字でこう書かれていた。「財宝の大部分はここに。」
裏には同じ筆跡で、さらなる情報が記されていた。
高い木、遠眼鏡山の肩、北北東よりやや北へ。
骸骨島、東南東微東。
十フィート。
銀の延べ棒は北の隠し場所にある。東の小山の尾根筋をたどり、顔のある黒い岩から南へ十ファゾム。
武器は砂丘にあり、見つけやすい。北の入り江の岬の北端、東より四分の一北。
J.F.
書かれていたのはそれだけだった。短く、私には意味不明だったが、郷士殿とライブシー先生を歓喜で満たすには十分だった。
「ライブシー」と郷士殿が言った。「君はこんなつまらん医者の仕事は即刻やめるんだ。私は明日ブリストルへ発つ。三週間もすれば、いや三週間! 二週間だ、十日で! 最高の船と、イギリスで選りすぐりの船員を手に入れてみせるぞ。ホーキンズ君は給仕係として来てもらおう。君は立派な給仕係になるぞ、ホーキンズ君。君、ライブシーは船医、私は提督だ。レッドルースとジョイスとハンターも連れて行く。順風に恵まれ、航海は素早く、場所を見つけるのに何の苦労もないだろう。そして手に入れた金で、食って、転げ回って、水切りでもして、未来永劫遊び暮らすのだ。」
「トレローニー」と先生が言った。「あなたと一緒に行きましょう。そして私が保証しますが、ジム君も行きます。この事業の誉れとなるでしょう。ただ一人、私が恐れている男がいます。」
「それは誰ですかな?」と郷士殿は叫んだ。「その犬の名を言いたまえ!」
「あなたです」と先生は答えた。「あなたはおしゃべりが過ぎる。この書類のことを知っているのは我々だけではない。今夜宿屋を襲った連中、あれは間違いなく大胆で命知らずの輩だ。そして船に残っていた者たち、さらに言えば、近くにいるであろう他の仲間たちも、皆、何が何でもあの金を手に入れようと躍起になっている。船出するまでは、我々は誰も一人で行動してはならない。ジム君と私は当分一緒に行動します。あなたはブリストルへ行く際、ジョイスとハンターを連れて行きなさい。そして、最初から最後まで、我々の誰も、見つけたものについて一言も漏らしてはなりません。」
「ライブシー」と郷士殿は答えた。「君の言うことはいつも正しい。私は墓場のように口を閉ざそう。」
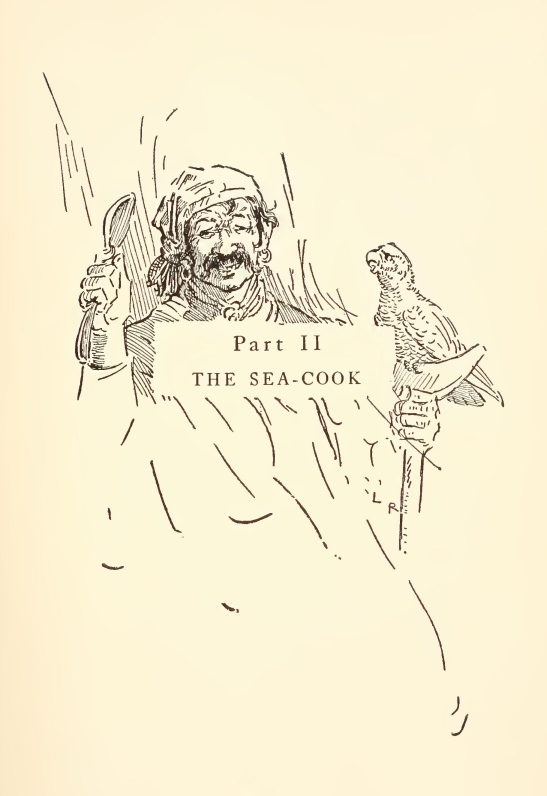
第二部 海のコック
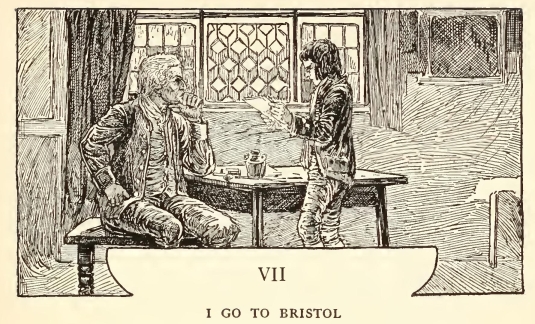
第七章 ブリストルへ
船出の準備が整うまでには、郷士殿が想像していたよりも長い時間がかかった。そして、最初の計画はどれ一つとして、ライブシー先生が私をそばに置いておくという計画でさえ、思い通りには進まなかった。先生は自分の診療所を引き継ぐ医者を探しにロンドンへ行かねばならなくなり、郷士殿はブリストルで多忙を極め、私はといえば、年老いた森番のレッドルースの世話になりながら、ほとんど囚人のように屋敷で暮らしていた。しかし心は海の夢と、見知らぬ島や冒険への甘美な期待で満ち溢れていた。私は何時間も地図に見入り、その細部をすべて記憶に焼き付けた。家政婦の部屋の暖炉のそばに座り、私は想像の中で、ありとあらゆる方角からあの島に近づいた。島の隅々まで探検し、遠眼鏡山と呼ばれるあの高い丘に千回も登り、その頂上から、刻々と変わる素晴らしい眺めを楽しんだ。時には島が野蛮人で溢れ、彼らと戦い、またある時には私たちを狩る危険な動物でいっぱいになった。しかし、どんな空想の中でも、私たちの実際の冒険ほど奇妙で悲劇的な出来事は思い浮かばなかった。
そうして数週間が過ぎたある晴れた日、ライブシー先生宛に一通の手紙が届いた。そこには「ご不在の場合は、トム・レッドルースまたは若きホーキンズが開封のこと」と追記されていた。この命令に従い、私たちは、いや、むしろ私が、以下の重要な知らせを見つけた。森番は活字以外のものを読むのは苦手だったのだ。
ブリストル、「古い錨亭」にて、一七――年三月一日
親愛なるライブシーへ
君が屋敷にいるのか、まだロンドンにいるのかわからんので、この手紙を両方の場所へ送る。
船は購入し、艤装も済んだ。すでに出航準備を整え、碇を下ろしている。これほど見事なスクーナーは想像もできまい。子供でも操縦できそうな船だ。二百トン、船名はヒスパニオーラ号。
旧友のブランディ氏を通して手に入れたのだが、彼は終始、驚くべき切り札となってくれた。この見上げた男は文字通り私のために身を粉にして働き、そして、我々が目指す港のことを、つまり財宝のことを聞きつけるや、ブリストルの誰もがそうだったと言っていい。
「レッドルースさん」私は手紙を読むのを中断して言った。「ライブシー先生はこれを快く思わないでしょう。郷士様は、結局、喋ってしまったんですね。」
「まあ、誰にそれ以上の権利があるってんだ?」と森番は唸った。「郷士様がライブシー先生のために口を利いちゃいけねえなんて、おかしな話だぜ。」
そこで私は口を挟むのをやめ、まっすぐ読み進めた。
ブランディ氏自身がヒスパニオーラ号を見つけ、実に見事な手腕で、ただ同然の値段で手に入れてくれた。ブリストルにはブランディ氏に対して途方もない偏見を抱く連中がいる。彼らは、この正直者が金のためなら何でもするとか、ヒスパニオーラ号は元々彼のもので、法外な値段で私に売りつけただのと言いふらしている。全くもって見え透いた中傷だ。しかし、彼らの誰一人として、この船の素晴らしさを否定する勇気はない。
ここまでは順調だった。作業員たち、つまり索具職人やら何やらが、実にいらいらするほど仕事が遅かったのは確かだが、それも時が解決してくれた。私を悩ませたのは船員だった。
原住民や海賊、あるいは憎きフランス人に備え、二十人ほどの男が欲しかったのだが、半ダースを見つけるのさえ悪魔のように骨が折れた。そんな時、実に驚くべき幸運が、私が必要としていたまさにその男を連れてきてくれたのだ。
私が波止場に立っていると、全くの偶然から、彼と話すことになった。聞けば、彼は年老いた船乗りで、酒場を経営し、ブリストルの船乗りは皆知っているとのこと。陸で健康を損ね、再び海へ出るためにコックの良い仕事を探していると言う。その朝は、潮の香りを嗅ぎにびっこを引きながらここまで来たのだと。
私は途方もなく心を動かされた。君もそうだったろう。そして純粋な同情から、その場で彼を船のコックとして雇った。ロング・ジョン・シルバーという名で、片足を失っている。しかし私はそれを推薦状と見なした。不滅のホーク提督のもと、国のために戦って失ったのだからな。彼には恩給がないのだ、ライブシー。我々が生きるこの忌まわしい時代を想像してみたまえ!
さて、私は一人のコックを見つけただけだと思っていたが、それは船員一同を発見したも同然だった。シルバーと私とで、数日のうちに、想像を絶するほど屈強な古参の船乗りたちの一団を集めることができた。見た目は良くないが、その顔つきからして、実に不屈の精神を持つ連中だ。断言するが、我々はフリゲート艦とだって戦えるぞ。
ロング・ジョンは、私がすでに雇っていた六、七人のうち二人を追い払ってさえくれた。彼らは、重要な冒険において我々が恐れねばならない、まさにあの手の陸の若造どもだと、彼は一瞬で見抜いたのだ。
私は最高の健康と気分だ。牛のように食い、木のように眠る。しかし、我が古参の船乗りたちがキャプスタンの周りを歩き回る足音を聞くまでは、一瞬たりとも心は休まらない。いざ海へ! 財宝なんぞくそくらえだ! 私の頭を狂わせたのは、海の栄光なのだ。さあ、ライブシー、すぐに来てくれ。私を尊敬するなら、一時間たりとも無駄にするな。
若きホーキンズ君は、レッドルースを護衛につけて、すぐに母親に会いに行かせたまえ。そして二人とも、全速力でブリストルへ来るように。
ジョン・トレローニー
追伸 ―― ブランディ氏が、我々が八月末までに戻らねば僚船を送ってくれることになっているのだが、その彼が航海長に素晴らしい男を見つけてくれたことを言い忘れていた。堅物なのが残念だが、他の点では宝のような男だ。ロング・ジョン・シルバーは、アローという名の、非常に有能な男を航海士として発掘してくれた。水夫長もいるのだぞ、ライブシー。だから、この素晴らしきヒスパニオーラ号では、万事、軍艦流に進められるだろう。
シルバーが資産家だということも言い忘れていた。彼が銀行口座を持ち、一度も当座貸越をしたことがないのを、私は自分の目で確かめている。彼は妻に宿屋の経営を任せている。そして彼女が有色人種の女性であることから、君と私のような年老いた独身者が、彼を再び放浪の旅へと駆り立てているのは、健康と同じくらい、その妻の存在もあるのではないかと推測するのも許されるだろう。
J. T.
再追伸 ―― ホーキンズ君は母君のもとで一晩過ごしてよろしい。
J. T.
この手紙が私をどれほどの興奮に陥れたか、想像がつくだろう。私は嬉しさのあまり、半ば我を忘れていた。そして、もし私が誰かを軽蔑したことがあるとすれば、それはぶつぶつと不平を言い、嘆くことしかできない年老いたトム・レッドルースだった。下っ端の森番たちなら誰でも喜んで彼と代わっただろうが、それは郷士殿のお気に召さなかった。そして郷士殿の意向は、彼らの間では法律のようなものだった。年老いたレッドルース以外には、不平を言うことさえも敢えてする者はいなかった。
翌朝、彼と私は徒歩で「ベンボー提督亭」へと向かった。そこで私は、母が元気でいるのを見て安心した。長い間、あれほどの厄介の種だった船長は、悪人が騒ぎを起こすことのない場所へと旅立っていた。郷士様がすべてを修理させ、客間と看板を塗り直し、いくつか家具も追加してくれていた。中でも、酒場の母のために美しい肘掛け椅子が用意されていた。私が留守の間、人手に困らないようにと、見習いの少年も見つけてくれていた。
その少年を見て、私は初めて自分の状況を理解した。その瞬間まで、私は目の前の冒険のことばかり考え、後にする家のことなど全く頭になかった。しかし今、私の代わりに母のそばにいるこの不器用な見知らぬ少年を見て、私は初めて涙がこみ上げてきた。私はこの少年につらく当たったと思う。彼は仕事に不慣れだったので、私が間違いを正したり、やり込めたりする機会はいくらでもあり、私はためらうことなくそれを利用したのだ。

夜が明け、翌日の昼食後、レッドルースと私は再び道を歩き始めた。私は母に、そして生まれた時から住んでいた入り江に、そして愛する古き「ベンボー提督亭」に別れを告げた。もっとも、塗り直されてからは、それほど愛着はなくなっていたが。最後に心に浮かんだのは、三角帽をかぶり、刀傷のある頬をし、古い真鍮の望遠鏡を持って、何度も浜辺を闊歩していたあの船長のことだった。次の瞬間、私たちは角を曲がり、私の家は見えなくなった。
夕暮れ時、荒野の「ロイヤル・ジョージ亭」で郵便馬車が私たちを拾った。私はレッドルースと太った老紳士の間に挟まれていた。速い動きと冷たい夜気にもかかわらず、私は最初からうとうとし、そして駅馬車区間を次から次へと、丘を上り谷を下る間、丸太のように眠りこけていたに違いない。ついに脇腹を突かれて目を覚ますと、私たちは街路に面した大きな建物の前で止まっており、夜はとっくに明けていた。
「どこですか?」と私は尋ねた。
「ブリストルだ」とトムは言った。「降りろ。」
トレローニー郷士は、スクーナーの作業を監督するため、波止場のずっと奥にある宿屋に滞在していた。私たちはそこまで歩いていかねばならなかった。道は、私にとってこの上ない喜びだったが、埠頭に沿っており、あらゆる大きさ、帆装、国籍の無数の船が並んでいた。ある船では船乗りたちが歌いながら仕事をし、別の船では男たちが私の頭上はるか高く、蜘蛛の糸ほどにしか見えない綱にぶら下がっていた。私は生涯、海岸で暮らしてきたが、それまで海に近づいたことなど一度もなかったように思えた。タールと塩の匂いは新鮮だった。遠い大洋を渡ってきたであろう、実に素晴らしい船首像を見た。それに、耳に輪をはめ、髭を巻き毛にし、タールで固めたお下げ髪をし、威張って不器用に歩く多くの老船乗りたちも見た。もし同じ数の王様や大司教を見たとしても、これほど嬉しくはなかっただろう。
そして私自身が海へ出るのだ。スクーナー船で、笛を吹く水夫長と、お下げ髪で歌う船乗りたちと一緒に。未知の島を目指し、埋められた財宝を探しに、海へ!
私がまだこの楽しい夢の中にいると、私たちは突然大きな宿屋の前に出て、トレローニー郷士に出会った。彼は丈夫な青い布地の服を着て、すっかり海軍士官のような出で立ちで、顔に笑みを浮かべ、見事な船乗り歩きを真似しながら、戸口から出てきたところだった。
「来たか!」と彼は叫んだ。「先生も昨夜ロンドンから到着した。ブラボー! これで乗組員は全員揃った!」
「ああ、郷士様」と私は叫んだ。「いつ出航するんですか?」
「出航だと!」と彼は言った。「明日だ!」
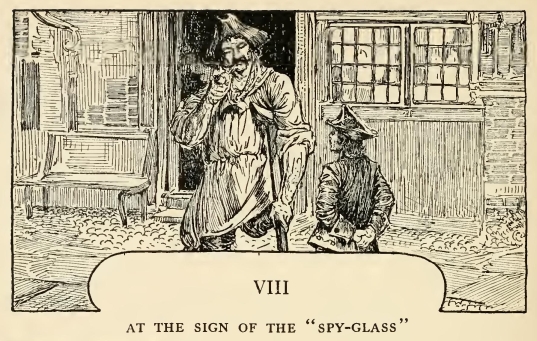
第八章 「遠眼鏡屋」にて
朝食を終えると、郷士様は私に「遠眼鏡屋」のジョン・シルバー宛のメモを渡し、波止場に沿って歩き、大きな真鍮の望遠鏡を看板にした小さな酒場に注意していれば、すぐに見つかるだろうと言った。船や船乗りをもっと見られるこの機会に大喜びで、私は出発した。波止場は今が一番の賑わいで、大勢の人々や荷馬車、荷物の間を縫うようにして進み、やがて問題の酒場を見つけた。
それはなかなかに明るい小さな酒場だった。看板は塗り直されたばかりで、窓にはこざっぱりとした赤いカーテンがかかり、床には清潔な砂が撒かれていた。両側に通りがあり、どちらにも開いたドアがあったため、タバコの煙がもうもうと立ち込めているにもかかわらず、広くて天井の低い部屋の中はかなりよく見えた。
客はほとんどが船乗りで、彼らは大声で話していたので、私はドアのところでためらい、入るのをためらったほどだった。
私が待っていると、一人の男が脇の部屋から出てきた。一目で、彼がロング・ジョンに違いないと確信した。左足は付け根のすぐ下で切断されており、左肩の下には松葉杖を抱えていた。それを鳥のようにぴょんぴょんと跳ねながら、実に器用に操っていた。彼は非常に背が高く、がっしりしていて、ハムほども大きな顔をしていた。飾り気はなく青白いが、知的で笑みを浮かべていた。実際、彼は最高に陽気な気分のようで、口笛を吹きながらテーブルの間を動き回り、お気に入りの客には陽気な言葉をかけたり、肩を叩いたりしていた。
さて、実を言うと、トレローニー郷士の手紙で初めてロング・ジョンの名に触れた時から、私は彼が、私が古い「ベンボー亭」で長い間待ち構えていた、あの片足の船乗りではないかと心の中で恐れていた。しかし、目の前の男を一目見れば十分だった。私は船長や、黒犬や、盲目のピューを見てきた。だから海賊がどんなものか知っているつもりだった。私の考えでは、この清潔で気立ての良い主人とは全く違う生き物だ。
私はすぐに勇気を奮い起こし、敷居をまたぎ、松葉杖に寄りかかって客と話しているその男のところまでまっすぐ歩いていった。
「シルバーさんですか?」と私はメモを差し出しながら尋ねた。
「いかにも、坊主」と彼は言った。「それがわしの名前だ、確かに。して、お前さんは誰かね?」そして郷士様の手紙を見ると、彼はほとんど驚いたように見えた。
「おお!」と彼はかなり大きな声で言って、手を差し出した。「なるほど。お前さんがうちの新しい給仕係か。会えて嬉しいぜ。」
そして彼は、その大きくて力強い手で私の手を握った。
その時、奥の方にいた客の一人が突然立ち上がり、ドアに向かった。ドアは彼のすぐそばにあり、彼は一瞬で通りに出てしまった。しかし、その慌ただしい様子が私の注意を引き、一目で彼だとわかった。それは、最初に「ベンボー提督亭」にやって来た、指が二本ない、蝋のような顔の男だった。
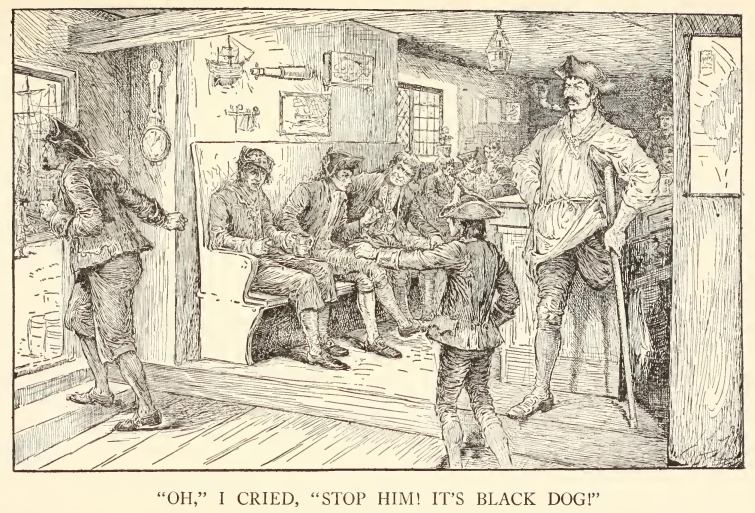
「ああ」と私は叫んだ。「捕まえて! 黒犬だ!」
「そいつが誰だろうと知ったこっちゃねえ」とシルバーは叫んだ。「だが、勘定を払ってねえぞ。ハリー、走って捕まえろ。」
ドアに一番近かった客の一人が飛び上がり、追跡を始めた。
「たとえホーク提督だろうと、勘定は払ってもらう」とシルバーは叫んだ。そして、私の手を放すと、「そいつを何て言った?」と彼は尋ねた。「黒い、何だって?」
「犬です、黒犬」と私は言った。「トレローニー郷士から海賊たちの話を聞いていませんか? 彼はその一人なんです。」
「ほう?」とシルバーは叫んだ。「このわしの店で! ベン、走ってハリーを手伝え。あのろくでなしの一人だったってのか? モーガン、そいつと飲んでたのはお前か? こっちへ来い。」
彼がモーガンと呼んだ男、白髪でマホガニー色の顔をした老船乗りが、噛みタバコを口の中で転がしながら、かなりバツが悪そうに前に出てきた。
「おい、モーガン」ロング・ジョンは厳しい声で言った。「お前さん、あの黒――黒犬ってやつに、今まで会ったことはねえんだろうな、え?」
「へえ、あっしは一度も」モーガンは敬礼して答えた。
「名前も知らなかったと?」
「へえ。」
「そりゃ結構なこった、トム・モーガン!」主人は声を張り上げた。「あんな輩とつるんでやがった日には、二度とこの店の敷居はまたがせねえ。覚えときな。で、やつは何を話してたんだ?」
「それが、よく分からねえんでさ」モーガンは答えた。
「てめえの肩に乗ってんのは頭か、それともただの木偶の坊か!」ロング・ジョンは怒鳴った。「よく分からねえだと! じゃあ、誰と話してたかも分からねえって言うのか、え? さあ言え、何をべちゃくちゃ喋ってたんだ――航海か? 船長か? 船の話か? 吐け! 何だったんだ?」
「竜骨くぐりの話をしてやした」モーガンは答えた。
「竜骨くぐりだと? そいつは結構、おあつらえ向きの話じゃねえか。覚えとけ。さっさと席に戻りやがれ、この間抜けが。」
そして、モーガンがよろよろと席に戻ると、シルバーは、僕にはお世辞に聞こえるようなひそひそ声で付け加えた。「トム・モーガンは正直な男でしてね。ただ、ちいと頭が足りねえんでさ。さて、と」今度は大声で続けた。「ええと――黒犬? いや、そんな名前は聞いたこともねえ。あっしは知らねえな。だが、どうも……そうだ、あのろくでなしには見覚えがある。昔、目の見えねえ乞食と一緒にここへ来てやがった。」
「その通りです、間違いありません」と僕は言った。「その目の見えない男も知っています。名前はピューでした。」
「そうだ!」シルバーはすっかり興奮して叫んだ。「ピュー! 確かにそいつの名前だ。ああ、いかにも悪党面だった! この黒犬って野郎を捕まえりゃ、トレローニー旦那へのいい土産話になるぞ! ベンは足が速い。あいつより速い船乗りはそうはいねえ。きっとすぐに追いつくはずだ、間違いねえ! 竜骨くぐりの話をしてたって? 俺がやつを竜骨くぐりにしてやる!」
これらの言葉を吐き出しながら、彼は松葉杖で酒場をドスンドスンと歩き回り、手でテーブルを叩き、その興奮ぶりはオールド・ベイリーの判事やボウ・ストリートの役人さえも信じ込ませるほどであった。「望遠鏡」亭で黒犬を見つけたことで、僕の疑念はすっかり再燃しており、この料理人を注意深く観察していた。しかし、彼はあまりに抜け目がなく、用意周到で、僕にはあまりに狡猾すぎた。やがて、追っていった二人の男が息を切らして戻り、人ごみの中で見失ったと白状して、まるで泥棒のように叱りつけられる頃には、僕ですらロング・ジョン・シルバーの無実を請け合っただろう。
「なあ、ホーキンズ君」と彼は言った。「あっしみてえな人間にとっちゃ、こいつはまったくひでえ話だと思わねえかい? トレローニー旦那はどう思うだろうか? この俺の店で、あの忌々しいオランダ野郎が、俺のラムを飲んで座ってたんだ! あんたが来てそれをはっきり教えてくれた。なのに、俺はまんまと目の前でやつを逃しちまった! さあ、ホーキンズ君、旦那にはあっしのことを取りなしてくだせえ。あんたはまだ若いが、利口な子だ。ここへ最初に入ってきた時から分かってたよ。つまりだ、この古い木偶の足で、俺に何ができたって言うんだ? 一等航海士だった頃なら、たちまちやつの横っ面にとりついて、あっという間にひねり上げてやったんだが、今じゃあ――」
そして、彼は突然ぴたりと止まり、何かを思い出したかのように顎が落ちた。
「勘定だ!」彼は突然叫んだ。「ラム三杯分! ちくしょうめ、勘定をすっかり忘れてやがった!」
そしてベンチに倒れ込むと、涙が頬を伝うまで笑い続けた。僕もつられて笑わずにはいられず、二人で腹を抱えて笑い転げ、その笑い声は酒場中に響き渡った。
「やれやれ、俺も年をとって耄碌したもんだ!」彼はようやくそう言うと、頬を拭った。「あんたと俺はきっとうまくやっていけるぜ、ホーキンズ君。誓ってもいい、俺なんざ給仕係に格下げされてもおかしくねえ。だが、さあ、そろそろ出かける準備だ。これじゃいけねえ。義務は義務だ、仲間たち。この古ぼけた鶏冠帽子をかぶって、あんたと一緒にトレローニー旦那のところへ行って、この一件を報告しなきゃならねえ。いいかい、こいつは重大なことなんだぜ、ホーキンズ君。あんたも俺も、お世辞にも面目が立ったとは言えねえ。あんただってそうだろ? 二人とも、間抜けだったってわけだ。だが、ちくしょうめ! 勘定の話は我ながら傑作だった。」
そして彼はまた笑い始め、あまりに心底から笑うので、僕には彼ほどその冗談が面白くはなかったものの、再び彼の陽気な笑いに加わらざるを得なかった。
埠頭を歩く短い間、彼は実に面白い道連れとなった。通り過ぎる様々な船について、その艤装やトン数、国籍を教え、今行われている作業――ある船は荷降ろしをし、ある船は積み荷をし、またある船は出航の準備をしている――を説明し、時折、船や船乗りに関するちょっとした逸話を語ったり、僕が完全に覚えるまで船乗りの言葉を繰り返したりした。僕は、彼が考えうる限り最高の船乗り仲間のひとりだと分かり始めていた。
宿屋に着くと、郷士とライブシー博士が席に着いており、スクーナー船の視察に出かける前に、トーストを浸したエールを1クォートほど飲み干しているところだった。
ロング・ジョンは、たいそう熱を込めて、しかも完璧な真実として、事の次第を始めから終わりまで語った。「そういうわけでしてな、ホーキンズ君、そうだろ?」と彼は時々言い、僕はいつでも全面的に彼の話を裏付けることができた。
二人の紳士は黒犬が逃げたことを残念がったが、どうしようもないということで全員の意見が一致し、褒め言葉をかけられた後、ロング・ジョンは松葉杖を取って立ち去った。
「今日の午後四時までに全員乗船だ」郷士は彼の背中に向かって叫んだ。
「アイ、アイ、サー」料理人は廊下から叫び返した。
「やれやれ、郷士」ライブシー博士は言った。「あなたの発見というやつは、だいたいいつもあまり信用していないのですが、これだけは言っておきましょう。ジョン・シルバーは私の気に入りました。」
「あの男は極上の切り札だ」と郷士は断言した。
「さて」と博士は付け加えた。「ジムも我々と一緒に乗船していいでしょうな?」
「もちろんだとも」と郷士は言った。「帽子を取れ、ホーキンズ。船を見に行くぞ。」
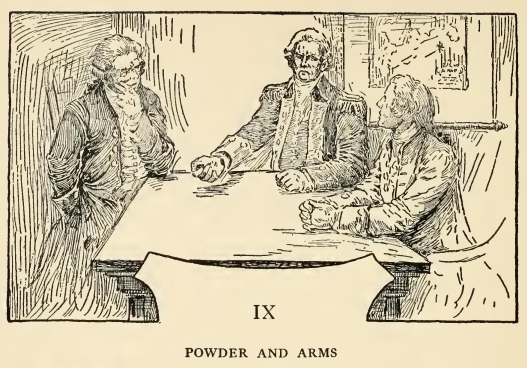
第九章 火薬と武器
ヒスパニオラ号は少し沖合に停泊しており、我々は他の多くの船の船首像の下をくぐり、船尾を回り込んだ。時には錨綱が我々のボートの竜骨の下で軋み、時には頭上を揺れ動いた。しかし、ようやく横付けすると、船に乗り込んだ我々を一等航海士のアロー氏が出迎えて敬礼した。彼は日焼けした年配の船乗りで、耳にイヤリングをつけ、斜視だった。彼と郷士は非常に親しく友好的だったが、トレローニー氏と船長の間では事情が違うことがすぐに見て取れた。
この船長は鋭い目つきの男で、船上のあらゆるものに腹を立てているように見えたが、その理由はすぐに分かることになった。我々が船室に降りるか降りないかのうちに、一人の水夫が後を追ってきたからである。
「スモレット船長が、だんなにお話があるそうで」と彼は言った。
「いつでも船長の命令に従う。こちらへお通ししろ」と郷士は言った。
船長は使いの者のすぐ後ろにおり、すぐさま入ってくると、背後でドアを閉めた。
「さて、スモレット船長、何か用かね? 万事順調だといいが。船の準備は万端、航海に支障はないかな?」
「さて、だんな」船長は言った。「お気に障るかもしれませんが、はっきり申し上げた方がよろしいでしょう。私はこの航海が気に入りません。船員たちが気に入りません。そして、私の一等航海士も気に入りません。以上、簡潔に申し上げました。」
「では、船もお気に召さないのかな?」郷士は尋ねた。僕にも分かるほど、ひどく腹を立てていた。
「それについては何とも申し上げられません、まだ試しておりませんので」と船長は言った。「良い船のようには見えますが、それ以上は。」
「おそらく、雇い主もお気に召さないのだろうな?」と郷士は言った。
しかし、ここでライブシー博士が割って入った。
「まあ、お待ちください」と彼は言った。「少しお待ちください。そのような質問は、ただ悪感情を生むだけです。船長は言い過ぎたか、あるいは言葉が足りなすぎたか。いずれにせよ、私はその言葉の説明を求めねばなりません。この航海が気に入らないと、あなたは言った。さて、それはなぜですかな?」
「私は、いわゆる封印命令という形で、この船をあの紳士が命じる場所へ航行させるために雇われました」と船長は言った。「そこまでは結構。しかし、今やマストより前にいる平水夫の一人一人が、私よりも多くのことを知っている始末です。これを公正と呼べるでしょうか?」
「いや」とライブシー博士は言った。「呼べませんな。」
「次に」船長は続けた。「我々が宝探しに行くということを、自分の部下から聞かされたのですぞ。さて、宝探しというのは厄介な仕事です。私はどんな理由があろうと宝探しの航海は好みません。とりわけ、それが秘密にされている場合、そして(失礼、トレローニーさん)その秘密がオウムにまで漏れているような場合は、なおさらです。」
「シルバーのオウムかね?」と郷士が尋ねた。
「言葉のあやです」と船長は言った。「つまり、秘密がだだ漏れだということです。私の考えでは、お二方とも、ご自分が何をしようとしているのか分かっておられない。しかし、私に言わせれば、これは生死をかけた、きわどい綱渡りです。」
「それは明白ですし、おそらく真実でしょう」とライブシー博士は答えた。「我々はそのリスクを承知の上です。しかし、あなたが思われるほど無知ではありません。次に、船員が気に入らないと言いましたな。彼らは腕の良い船乗りではないのですか?」
「気に入りませんな」とスモレット船長は答えた。「それに、言わせていただければ、船員は私自身が選ぶべきだったと考えております。」
「そうかもしれませんな」と博士は答えた。「友人は、あなたを連れて行くべきだったのかもしれない。しかし、もし失礼があったとしても、それは意図的なものではありません。そして、アロー氏が気に入らないと?」
「気に入りません。腕の良い船乗りだとは思いますが、士官として優れているには、船員たちと馴れ馴れしすぎる。一等航海士たるもの、一線を画すべきです――平水夫どもと酒を酌み交わすべきではない!」
「彼が酒を飲むというのか?」郷士は叫んだ。
「いいえ」と船長は答えた。「ただ、馴れ馴れしすぎるというだけです。」
「さて、それで、要するにどうしたいのです、船長?」博士は尋ねた。「あなたの要求を言ってください。」
「さて、皆さま、この航海を続けるおつもりですか?」
「鉄のように固い決意だ」と郷士は答えた。
「結構です」と船長は言った。「では、証明できないことばかりを申し上げる私の話を辛抱強く聞いてくださったのですから、もう少しだけお聞きください。彼らは火薬と武器を船首の船倉に積んでいます。さて、船室の下に良い場所がある。なぜそこへ移さないのですか? ――これが一点目。次に、あなたはご自分の部下を四人連れてきておられますが、聞くところによると、そのうち何人かは船首の方に寝床を割り当てられているとか。なぜ、ここ船室の隣の寝台を与えないのですか? ――これが二点目です。」
「まだあるかね?」とトレローニー氏が尋ねた。
「もう一つ」と船長は言った。「すでに喋りすぎです。」
「喋りすぎもいいところだ」と博士も同意した。
「私自身が耳にしたことをお話ししましょう」スモレット船長は続けた。「あなた方が島の地図を持っていること、その地図には宝の場所を示す十字の印がついていること、そしてその島は――」そして彼は、緯度と経度を正確に口にした。
「そんなことは誰にも言っていない!」郷士は叫んだ。
「船員たちは知っていますよ」と船長は答えた。
「ライブシー、お前かホーキンズに違いない」と郷士は叫んだ。
「誰が漏らしたかは大した問題ではありません」と博士は答えた。博士も船長も、トレローニー郷士の抗議をほとんど気にかけていないのが僕には分かった。もちろん僕も同じだった。彼はあれほど口の軽い男だったのだから。しかし、この件に関しては、彼が本当に正しく、誰もその島がどこにあるのかを話してはいなかったのだと僕は信じている。
「さて、皆さま」船長は続けた。「この地図をどなたがお持ちなのかは存じませんが、一つだけはっきりさせておきたい。地図は私とアロー氏にさえも秘密にされねばなりません。さもなくば、私は辞任させていただきたい。」
「なるほど」と博士は言った。「この件を秘密にし、船尾部分を要塞化して、友人の部下たちで固め、船内の武器と火薬をすべてそこに集めたい、と。言い換えれば、あなたは反乱を恐れているのですね。」
「だんな」スモレット船長は言った。「お気を悪くなさらないでいただきたいが、私の口に言葉を押し込む権利はあなたにはない。船長たるもの、そのようなことを口にするだけの根拠があれば、そもそも海に出ること自体が許されません。アロー氏については、私は彼が完全に正直な人間だと信じております。船員の中にもそういう者はいるし、私の知る限りでは全員がそうかもしれません。しかし、私にはこの船の安全と、乗組員一人一人の命に対する責任がある。私の見る限り、事態は少々よろしくない方向へ進んでいる。そこで、しかるべき予防措置を講じていただくか、さもなくば私を辞任させていただきたい。それだけです。」
「スモレット船長」博士は微笑みながら口を開いた。「山が鼠を産んだという寓話をご存じかな? 失礼ながら、あなたを見ているとその話を思い出します。ここへ入ってきた時、あなたはもっと多くのことを言うつもりだったはずだ。私のこのカツラを賭けてもいい。」
「博士」船長は言った。「あなたは賢いお方だ。ここへ来た時、私は解雇されるつもりでした。トレローニーさんが一言でも耳を貸してくださるとは思ってもいませんでした。」
「その通り、聞くつもりはなかった」郷士は叫んだ。「ライブシーがここにいなければ、とっとと追い返してやるところだった。だが、こうして話は聞いた。あなたの望み通りにしよう。しかし、あなたへの評価は下がったぞ。」
「それはご随意に、だんな」船長は言った。「私は自分の義務を果たすだけです。」
そう言って彼は立ち去った。
「トレローニー」博士は言った。「私の予想に反して、あなたは船に二人の正直者を乗せることに成功したようだ。あの男と、ジョン・シルバーだ。」
「シルバーはいいだろう」郷士は叫んだ。「だが、あの我慢ならん詐欺師めについては、断言するが、その態度は男らしくもなく、船乗りらしくもなく、まったくもって英国人らしくない。」
「まあ」と博士は言った。「いずれ分かるでしょう。」
我々が甲板に出ると、船員たちはすでに武器と火薬を運び出し始めており、「ヨーホー」と掛け声をかけながら作業していた。そのそばでは、船長とアロー氏が監督のために立っていた。
新しい配置は、僕の好みに実に合っていた。スクーナー船全体が改装されたのだ。主船倉の後部だった場所に、船尾側に六つの寝台が設けられた。この一続きの船室は、左舷側の通路で調理室と船首楼につながっているだけだった。もともとは船長、アロー氏、ハンター、ジョイス、博士、そして郷士がこの六つの寝台を占めるはずだった。今やレッドルースと僕がそのうちの二つを使い、アロー氏と船長は昇降口の甲板で寝ることになった。昇降口は両側に拡張され、ほとんど円形船室と呼べるほどになっていた。もちろん、天井はまだ非常に低かったが、ハンモックを二つ吊るすスペースはあり、一等航海士でさえその配置に満足しているように見えた。彼でさえ、おそらくは船員たちを疑っていたのだろう。しかし、それは推測に過ぎない。というのも、後で聞くことになるが、我々が彼の意見の恩恵にあずかる時間は長くはなかったからだ。
我々が皆、火薬や寝台の移動に懸命に取り組んでいると、最後の一人か二人の船員が、ロング・ジョンと共に、陸からのボートでやって来た。
料理人は猿のように身軽に舷側をよじ登ってくると、何が行われているかを見るやいなや、「よう、仲間たち!」と声をかけた。「こいつは何だい?」
「火薬を移してるんだよ、ジャック」と一人が答えた。
「なんだって!」ロング・ジョンは叫んだ。「そんなことをしてたら、朝の潮を逃しちまうぞ!」
「俺の命令だ!」船長は短く言った。「下へ行け。船員たちが夕食を欲しがるだろう。」
「アイ、アイ、サー」料理人は答えると、前髪に手を触れて敬礼し、すぐに調理室の方へ姿を消した。
「良い男ですな、船長」と博士は言った。
「おそらくは」とスモレット船長は答えた。「そいつは慎重にやれ、お前たち――慎重にだ」と、火薬を移している連中に声をかけ続けた。そして突然、僕が船の中央に備え付けられた旋回砲――真鍮製の長い九ポンド砲――を調べているのに気づくと、「おい、給仕係!」と叫んだ。「そこから離れろ! とっとと料理人のところへ行って仕事をもらえ。」
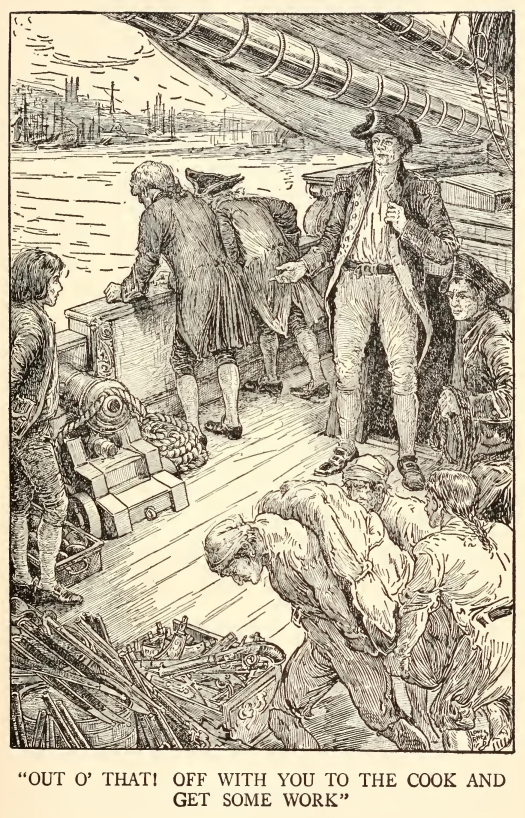
そして僕が急いで立ち去ろうとすると、彼がかなり大きな声で博士に言うのが聞こえた。「私の船では、えこひいきは許さん。」
請け合うが、僕はすっかり郷士と同じ考えになり、船長を心の底から憎んだ。
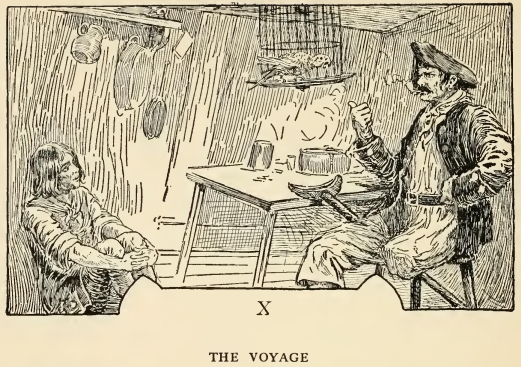
第十章 航海
その夜、我々は荷物を所定の場所にしまい込むのに大わらわで、郷士の友人であるブランディ氏などが次々とボートでやってきては、彼の航海の無事と安全な帰還を祈った。「ベンボー提督亭」の夜で、これほど働いたことは一度もなかった。夜が明ける少し前、掌帆長が号笛を鳴らし、船員たちがキャプスタンの巻き棒に取りかかった頃には、僕はくたくたに疲れ果てていた。だが、たとえその倍疲れていたとしても、甲板を離れようとは思わなかっただろう。短い号令、甲高い笛の音、船のランタンの揺らめく光の中で持ち場へと急ぐ船員たち――すべてが僕にとってあまりに新しく、興味深かったからだ。
「さあ、バーベキュー、一曲頼むぜ」と誰かが叫んだ。
「いつものやつを」と別の声がした。
「おうよ、仲間たち」と、松葉杖を脇に挟んでそばに立っていたロング・ジョンが言い、すぐさま僕がよく知っているあの節回しと歌詞で歌い出した。
「死人の箱に十五人――」
すると船員全員が合唱した。
「ヨーホーホー、ラム酒の瓶!」
そして三度目の「ホー!」で、彼らは力いっぱい巻き棒を押し回した。
その興奮のさなかにあっても、僕は一瞬にして懐かしい「ベンボー提督亭」に引き戻され、合唱の中にあの船長のだみ声が聞こえるような気がした。しかし、すぐに錨は巻き上げられ、やがて船首から滴を垂らしてぶら下がり、帆が風をはらみ始めると、陸地や船が両脇をかすめて過ぎ去っていった。そして、僕が横になって一時間の仮眠を取る間もなく、ヒスパニオラ号は宝島への航海を開始したのだった。
この航海を詳細に語るつもりはない。それはまずまず順調だった。船は良い船であることが証明され、船員は有能な船乗りであり、船長は自分の仕事を完全に理解していた。しかし、我々が宝島に到着するまでに、知っておくべき二、三の出来事が起こった。
まず、アロー氏は船長が恐れていた以上にひどい男だったことが判明した。彼は船員たちを統率できず、人々は彼を相手にしたい放題だった。だが、それは最悪の事態ではなかった。航海に出て一日か二日すると、彼はぼんやりした目、赤い頬、もつれる舌といった、酔っぱらいの兆候をみせて甲板に現れるようになったのだ。彼は何度も不名誉な形で船室へ戻るよう命じられた。時には転んで怪我をし、時には昇降口の脇にある小さな寝台で一日中横になっていた。また、一日か二日、ほとんどしらふで、少なくともまずまずの仕事ぶりを見せることもあった。
その間、我々はどうしても彼がどこで酒を手に入れているのか突き止めることができなかった。それが船の謎だった。いくら見張っていても、解決の手がかりはつかめなかった。本人に面と向かって尋ねても、酔っていれば笑うだけ、しらふの時には水以外は口にしたことがないと厳粛に否定するのだった。
彼は士官として役に立たないだけでなく、船員たちの間で悪影響を及ぼしていたが、このままでは遠からず自滅するのは明らかだったので、ある暗い夜、向かい波の中で、彼が完全に姿を消し、二度と見られなくなった時も、誰も大して驚かず、また、たいして悲しまなかった。
「海に落ちたか!」と船長は言った。「やれやれ、これで彼を鎖につなぐ手間が省けた。」
しかし、我々は一等航海士を失ってしまった。当然、船員の中から一人を昇格させる必要があった。掌帆長のジョブ・アンダーソンが船内で最も適任の男であり、彼は以前の肩書きのままだったが、事実上、一等航海士として務めた。トレローニー郷士は船乗り経験があり、その知識は非常に役立った。天候の良い日には、しばしば自ら当直を引き受けたからだ。そして、操舵長のイスラエル・ハンズは、慎重で抜け目のない、経験豊かな老練な船乗りで、いざという時にはほとんど何でも任せられる男だった。
彼はロング・ジョン・シルバーの腹心であり、彼の名前を挙げたことで、我々の船の料理人、船員たちが呼ぶところのバーベキューの話に移ることになる。
船上では、彼は両手をできるだけ自由に使えるように、松葉杖を首から下げた紐で吊るしていた。松葉杖の先を隔壁に押し当て、それに寄りかかりながら、船のあらゆる揺れに合わせて体を動かし、まるで陸にいるかのように料理をこなす様は、なかなかの見ものであった。さらに驚くべきは、大時化の海で甲板を横切る彼の姿だった。広い場所を渡るのを助けるために一本か二本の綱が張られており――それは「ロング・ジョンのイヤリング」と呼ばれていた――彼はそれを使って、ある場所から別の場所へと手繰り寄せるように移動した。ある時は松葉杖を使い、またある時はそれを紐で横に引きずりながら、他の男が歩くのと同じくらいの速さで動いた。それでも、以前彼と一緒に航海したことのある船員の中には、彼の落ちぶれた姿を見て同情の念を表す者もいた。
「バーベキューはただ者じゃねえ」操舵長は僕に言った。「若い頃にしっかり教育を受けてて、その気になりゃ本みてえな口のきき方ができる。それに勇敢さときたら――ライオンだってロング・ジョンの足元にも及ばねえ! やつが四人を相手に組みついて、素手でそいつらの頭をぶつけ合わせるのを見たことがあるぜ。」
船員は皆、彼を尊敬し、さらには服従さえしていた。彼には、一人一人に話しかけ、それぞれに特別な便宜を図る術があった。僕に対しては、飽くことなく親切で、いつも僕が調理室にいるのを喜んでくれた。調理室は彼が新品のピンのように清潔に保っており、皿は磨き上げられて吊るされ、隅には彼のオウムが鳥かごに入っていた。
「こっちへ来な、ホーキンズ」と彼はよく言ったものだ。「来てジョンと世間話でもしようぜ。お前さんほど歓迎される客はいねえよ、坊主。座ってニュースでも聞けや。こいつはフリント船長――有名な海賊にちなんで、俺のオウムをフリント船長って呼んでるんだ――フリント船長が、俺たちの航海の成功を予言してくれてる。そうだろ、船長?」
するとオウムは、息も切れないのが不思議なくらい、あるいはジョンが鳥かごにハンカチを投げるまで、ものすごい早口で「八レアル銀貨! 八レアル銀貨! 八レアル銀貨!」と叫び続けるのだった。
「さて、この鳥はな」と彼は言った。「たぶん二百歳くらいだろうぜ、ホーキンズ――こいつらはほとんど永遠に生きるからな。こいつより悪事を見てきたやつがいるとすれば、そいつは悪魔自身に違いねえ。偉大なるイングランド船長、あの海賊と一緒に航海したこともあるんだ。マダガスカルにも、マラバルにも、スリナムにも、プロビデンスにも、ポルトベロにも行ったことがある。難破した銀船の引き揚げにも立ち会った。そこで『八レアル銀貨』って言葉を覚えたんだ、無理もねえ、三十五万枚もあったんだからな、ホーキンズ! ゴアから出たインド副王の船の拿捕にもいたんだぜ。見かけは赤ん坊みてえだがな。だが、火薬の匂いは嗅いだことがあるんだろ、船長?」
「回頭用意」とオウムは叫んだ。
「ああ、こいつは上等な船だ」と料理人は言って、ポケットから砂糖を与えた。すると鳥は檻の格子をつつき、信じられないほど邪悪な罵り言葉を立て続けに吐き出した。「ほらな」とジョンは付け加えた。「朱に交われば赤くなるってことだ、坊主。この哀れで無垢な鳥が、こんなに口汚く罵るんだから、訳も分からずにな。覚えとけ。こいつは、言ってみりゃ、牧師の前でだって同じように罵るだろうよ」そしてジョンは、彼特有の厳かな仕草で前髪に触れた。その様子は、僕に彼が最高に善良な人間だと思わせるのだった。
その間も、郷士とスモレット船長は、互いにかなりよそよそしい関係のままだった。郷士はそのことを隠そうともせず、船長を軽蔑していた。一方、船長は話しかけられない限り口を開かず、話す時も鋭く、短く、無味乾燥で、一言の無駄もなかった。追い詰められると、船員たちについては自分が間違っていたようだということ、何人かは望み通りにきびきびと働き、全員がまずまずの態度だったことは認めた。船に関しては、すっかり気に入っていた。「あの船は、自分の妻に期待する以上に、風上へ一点近く切り上がってくれますよ。しかし」と彼は付け加えるのだった。「私が言いたいのは、まだ故郷へは戻っていないということ、そして私はこの航海が好きではないということです。」
これを聞くと、郷士はそっぽを向き、顎を突き出して甲板を行ったり来たりするのだった。
「あの男とこれ以上関わったら、私は爆発してしまうだろう」と彼は言った。
我々は何度か時化に見舞われたが、それはヒスパニオラ号の性能を証明するだけだった。船に乗っている者は皆、満足しているように見えた。もしそうでなかったとしたら、よほど気難しい連中に違いなかった。なぜなら、ノアが海に出て以来、これほど甘やかされた船乗り仲間はいなかったと僕は信じているからだ。ほんの些細な口実でグロッグ酒が倍になり、特別な日にはダフが出された。例えば、郷士が誰かの誕生日だと聞けば、いつでも船体中央部にはリンゴの樽が口を開けて置かれ、好きな者が自由に取って食べることができた。
「それで良い結果になった試しは一度もない」船長はライブシー博士に言った。「平水夫を甘やかせば、悪魔になる。それが私の信条です。」
しかし、そのリンゴの樽からは良い結果がもたらされた。これからお話しするように、もしそれがなかったら、我々は警告の兆候をつかむこともなく、裏切り者の手にかかって全員が命を落としていたかもしれないからだ。
事の起こりはこうだった。
我々は目指す島の風上に出るために貿易風帯を北上し、今や昼夜を問わず厳重な見張りのもと、その島へと南下していた。どう計算しても、往路の航海の最終日あたりだった。その夜か、遅くとも翌日の正午までには、宝島が視界に入るはずだった。我々は南南西に進路を取り、真横から安定した風を受け、海は穏やかだった。ヒスパニオラ号は着実に揺れ、時折、船首斜檣を波に突っ込んではしぶきを上げた。上下の帆はすべて風をはらみ、冒険の第一部が間もなく終わるというので、誰もが最高の気分だった。
さて、日没直後、僕の仕事がすべて終わり、寝床へ向かう途中、ふとリンゴが食べたくなった。僕は甲板へ駆け上がった。当直の者たちは皆、船首で島を探していた。舵をとる男は帆の風上側を見つめながら、静かに口笛を吹いていた。船首や船腹に当たる海のざわめき以外、音はそれだけだった。
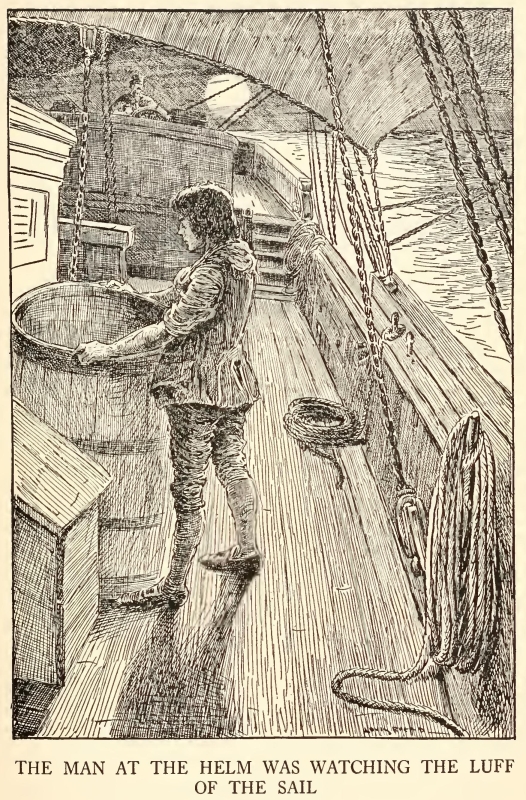
僕はリンゴの樽にすっぽりと体を滑り込ませたが、リンゴはほとんど残っていなかった。しかし、暗闇の中でそこに座っていると、水の音と船の揺れのために、眠りに落ちたか、あるいは落ちかけるかというところだった。その時、どしんという音を立てて、大柄な男がすぐそばに腰を下ろした。彼が肩を樽にもたせかけると、樽が揺れた。僕が飛び上がろうとしたまさにその時、男が話し始めた。それはシルバーの声だった。そして、十数語も聞かないうちに、僕はどんなことがあっても姿を現すまいと決心し、恐怖と好奇心の極みで震えながら、そこに横たわって耳を澄ませた。その十数語から、船に乗っている正直な者たちの命が、僕一人の肩にかかっていることを理解したからだ。
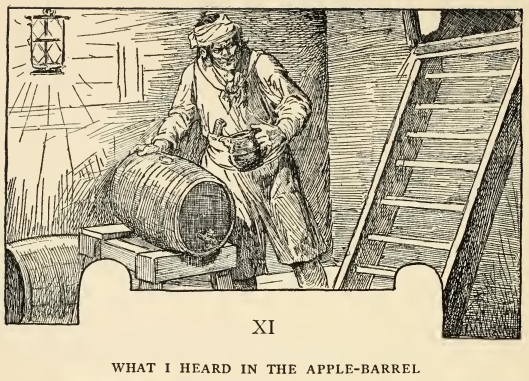
第十一章 リンゴ樽の中で聞いたこと
「いや、俺じゃねえ」とシルバーは言った。「フリントが船長だった。俺は操舵長だ、この木っ端の足のおかげでな。俺が足を失ったのと同じ砲撃で、年寄りのピューは目玉を失った。俺を手術した医者は名人だったぜ――大学出で、ラテン語なんかもすらすらでな。だが、そいつも他の連中と同じように、コルソ城で犬みたいに吊るされ、干物にされちまった。そいつらはロバーツの部下で、船の名前を『ロイヤル・フォーチュン』だの何だのに変えちまったせいだ。俺に言わせりゃ、一度名付けられた船は、そのままでいさせてやるべきだ。イングランド船長がインド副王の船を拿捕した後、俺たちみんなを無事にマラバルから連れ帰ってくれたカサンドラ号もそうだった。フリントの古い船、あのウォルラス号もそうだ。血の赤で染まり、金で沈みそうになるのを俺は見たもんだ。」
「ああ!」と別の声が、明らかに感嘆に満ちて叫んだ。船で一番若い水夫の声だった。「フリント船長は、まさに選りすぐりの男だったんですね!」
「デイヴィスも、聞くところによればたいした男だったらしい」とシルバーは言った。「俺はイングランド船長のところで九百ポンド、フリントのところで二千ポンドを貯め込んだ。平水夫にしちゃ悪くねえ稼ぎだ――全部銀行に安全に預けてある。今どきは稼ぐんじゃねえ、貯めるのが肝心なんだ。覚えとけ。イングランド船長の部下たちは今どこにいる? 知らねえ。フリントの部下は? そいつらのほとんどがこの船に乗って、ダフにありつけて喜んでる――その前は物乞いしてたやつもいるんだぜ。年寄りのピューは、目が見えなくなって、恥を知るべきだったろうに、国会議員の大様みてえに年に千二百ポンドも使いやがった。そいつは今どこにいる? まあ、今は死んで土の下だが、その前の二年間は、ちくしょうめ、飢え死にしそうだったんだ! 物乞いをし、盗みを働き、人の喉をかき切って、それでも飢えてたんだ、まったく!」
「結局、あまり意味がないんですね」と若い水夫は言った。
「馬鹿にとっちゃ意味がねえんだ、覚えとけ――金も、何もかもな」とシルバーは叫んだ。「だが、よく聞け。お前さんは若いが、利口なやつだ。一目見た時から分かってた。だから、一人の男として話をしてやる。」
この忌まわしい老悪党が、僕自身に使ったのと全く同じお世辞の言葉で、他の誰かに話しかけているのを聞いた時の僕の気持ちを想像してみてほしい。もしできたなら、樽越しに彼を殺してやりたいとさえ思った。その間も、彼は盗み聞きされているとは夢にも思わず、話を続けた。
「これが幸運を求める紳士たちの話だ。暮らしは荒っぽく、絞首刑の危険もあるが、闘鶏みてえに食い、飲む。そして航海が終われば、懐にはした金じゃなく、何百ポンドもの大金が入る。さて、そのほとんどはラム酒と派手な遊びに消え、またシャツ一枚で海に出る。だが、俺のやり方は違う。俺は全部貯め込むんだ、あちこちに少しずつな。疑われねえように、どこにも大金は置かねえ。いいか、俺はもう五十だ。この航海から戻ったら、本物の紳士になる。お前さんは、まだ時間があるって言うだろう。ああ、だが俺はその間も楽に暮らしてきた。欲しいものを我慢したことは一度もねえし、海にいる時以外は、柔らかい寝床で寝て、うまいものを食ってきた。で、俺はどうやって始めたか? お前さんと同じ、平水夫からだ!」
「でも」ともう一人が言った。「他の金はもう全部なくなっちまったんだろ? この一件の後じゃ、ブリストルに顔も出せないじゃないか。」
「ほう、どこにあると思ってたんだい?」シルバーは嘲るように尋ねた。
「ブリストルの、銀行とかに」と連れは答えた。
「そうだったさ」と料理人は言った。「俺たちが錨を上げた時はな。だが、今頃はうちの女房が全部持ってる。それに『望遠鏡』亭も売っちまった。借地権も、のれんも、内装もな。で、女房は俺に会いに来る手はずになってる。お前さんを信用してるからどこか教えてやってもいいが、仲間の間で嫉妬が起きるだろうからな。」
「女房を信用できるのかい?」ともう一人が尋ねた。
「幸運を求める紳士たちはな」料理人は答えた。「仲間内ではほとんど信用し合わねえ。それが正しいんだ、覚えとけ。だが俺には俺のやり方がある。仲間がしくじりをやらかしたら――俺を知ってるやつの話だが――そいつはもうこの世にはいねえ。ピューを恐れるやつもいたし、フリントを恐れるやつもいた。だが、フリント自身が俺を恐れていた。恐れちゃいたが、誇りにも思っていた。フントの部下は、海で一番荒っぽい連中だった。悪魔でさえ、やつらと海に出るのは怖がっただろう。さて、言っとくが、俺は自慢するような男じゃねえし、お前さんも俺がどれだけ気さくに付き合ってるか見てるだろう。だが、俺が操舵長だった頃、フリントの昔の海賊どもは子羊のようにおとなしかったもんさ。ああ、このジョン爺さんの船なら安心しな。」
「じゃあ、正直に言います」若者は答えた。「ジョン、あなたと話すまでは、この仕事がこれっぽっちも好きじゃなかった。でも、今、これで誓います。」
「お前さんは勇敢で、利口な若者だ」シルバーはそう答えると、樽全体が揺れるほど力強く握手をした。「幸運を求める紳士に、これほどふさわしい顔つきは見たことがねえ。」
この時までには、僕は彼らの言葉の意味を理解し始めていた。「幸運を求める紳士」とは、まぎれもなくただの海賊を意味していた。そして、僕が盗み聞きしたこの小さな場面は、正直な船員の一人――おそらく船に残された最後の一人――を堕落させる最終幕だったのだ。しかし、この点についてはすぐに安心することになった。シルバーが小さく口笛を吹くと、三人目の男がぶらりとやってきて、一行のそばに腰を下ろしたからだ。
「ディックは仲間だ」とシルバーは言った。
「ああ、ディックが仲間なのは分かってたさ」操舵長のイスラエル・ハンズの声が返ってきた。「ディックは馬鹿じゃねえからな」そう言って彼は噛みタバコを口の中で転がし、唾を吐いた。「だが、聞けよ」彼は続けた。「俺が知りたいのはこれだ、バーベキュー。いつまでこんな伝馬船みてえにうろうろしてなきゃならねえんだ? スモレット船長にはもううんざりだ。さんざんこき使いやがって、ちくしょうめ! あの船室に入りてえんだよ。やつらのピクルスやワインが欲しいんだ。」
「イスラエル」とシルバーは言った。「おめえの頭はたいして役に立たねえし、これまでもそうだった。だが、聞くことはできるだろう。少なくとも、耳だけはでかいからな。さて、俺が言うことを聞け。お前は船首で寝て、つらい暮らしをし、言葉は穏やかに、そして俺が合図をするまでしらふでいろ。覚えとけよ、坊主。」
「いや、文句は言わねえよ」操舵長はうなった。「俺が言いたいのは、いつなんだ? それが聞きたいんだ。」
「いつだと! ちくしょうめ!」シルバーは叫んだ。「まあいい、知りてえなら教えてやる。俺が引き延ばせる最後の瞬間、それがその時だ。ここには一流の船乗り、スモレット船長がいる。俺たちのためにこの船を操ってくれる。ここには郷士と医者がいて、地図だの何だのを持ってる――それがどこにあるか、俺は知らねえ。お前さんも知らねえだろ。だったら、この郷士と医者にブツを見つけさせて、船に運び込むのを手伝わせるんだ、いいな。それからだ。もしお前さんたち、このオランダ野郎どもを信用できるなら、スモレット船長に帰り道の半分まで船を操らせてから、事を起こしてやったっていいんだ。」
「だって、ここにいるのはみんな船乗りじゃないか」と若者のディックは言った。
「みんな平水夫だろ、お前さんが言いたいのは」シルバーは言い放った。「進路を保つことはできても、誰が進路を決めるんだ? お前さんら紳士方がいつもしくじるのはそこなんだ。俺の思い通りになるなら、スモレット船長に少なくとも貿易風帯まで戻らせる。そうすりゃ、計算違いもねえし、一日スプーン一杯の水で済むこともねえ。だが、お前さんらがどういう連中か、俺は知ってる。島で、ブツを船に乗せたらすぐに片を付けてやるさ。残念なこった。だが、お前さんらは酔っぱらうまで満足しねえ。胸が張り裂けそうだぜ、お前さんらみてえな連中と航海するのは!」
「まあまあ、ロング・ジョン」イスラエルは叫んだ。「誰がお前さんに逆らってるってんだ?」
「おい、今までどれだけのでかい船が拿捕されるのを見てきたと思う? どれだけの威勢のいい若者どもが処刑ドックで干物になるのを見てきたと思う?」シルバーは叫んだ。「みんな、このせっかち、せっかち、せっかちのせいだ。聞いてるか? 俺は海で一つや二つ、物事を見てきたんだ。お前さんらがただ進路を守り、風上へ一点向けていさえすりゃ、馬車にだって乗れるようになるんだ。だが、お前さんらはそうじゃねえ! 分かってるさ。明日にはラム酒をがぶ飲みして、首を吊られるのがおちだ。」
「ジョン、お前さんが牧師みてえなやつだってのはみんな知ってる。だが、お前さんと同じくらい船を操れるやつは他にもいた」とイスラエルは言った。「そいつらはちょっとしたお楽しみが好きだった。そんなに堅物じゃなく、陽気な仲間みてえに、好き勝手にやったもんさ。」
「そうかい?」とシルバーは言った。「で、そいつらは今どこにいる? ピューがその手合いだったが、乞食として死んだ。フリントもそうだったが、サバンナでラム酒がもとで死んだ。ああ、愉快な仲間たちだったとも! ただ、そいつらはどこにいるんだ?」
「でも」とディックは尋ねた。「やつらを始末する時、いったいどうするんだい?」
「それでこそ俺の仲間だ!」料理人は感心して叫んだ。「それこそが仕事ってもんだ。さて、どう思う? 置き去りにして島流しか? それはイングランド船長のやり方だろうな。それとも豚肉みてえに切り刻むか? そいつはフリントか、ビリー・ボーンズのやり方だ。」
「ビリーはそういう男だった」とイスラエルは言った。「『死人は噛みつかねえ』ってな。まあ、今じゃそいつ自身が死んじまった。今頃は事の顛末を知ってるだろうよ。港に来た荒くれ者の中じゃ、ビリーが一番だった。」
「その通り」とシルバーは言った。「荒っぽくて手早い。だが、よく聞け。俺は寛大な男だ――お前さんらが言うように、まったくの紳士だ。だが、今回は本気だ。義務は義務だ、仲間たち。俺は一票を投じる――死だ。俺が国会議員になって馬車に乗るようになった時、こんな船室のへ理屈屋どもが、祈りの最中の悪魔みてえに、不意に帰ってきてもらっちゃ困るんだ。待て、と俺は言う。だが、時が来たら、思いっきりやっちまえ!」
「ジョン」操舵長は叫んだ。「あんたは男だ!」
「見ればそう言うさ、イスラエル」とシルバーは言った。「一つだけ俺がもらう――トレローニーは俺がもらう。この手でやつの子牛みてえな頭を胴体からねじ切ってやる、ディック!」彼は言葉を切って付け加えた。「さあ、いい子だから、ちょっと立って、リンゴを一つ取ってきてくれ。喉を潤したいんでな。」
僕がどれほど恐ろしかったか、想像できるだろう! もし力があったなら、飛び出して逃げ出しただろう。しかし、手足も心臓も、僕を裏切った。ディックが立ち上がり始めるのが聞こえ、それから誰かが彼を止めたらしく、ハンズの声が叫んだ。「おい、よせやい! そんな船底の汚水みてえなもんをすするなよ、ジョン。ラム酒を一杯やろうぜ。」
「ディック」とシルバーは言った。「お前さんを信用する。樽には目盛りを付けてあるからな。これが鍵だ。平たいカップに一杯注いで、持ってこい。」
恐怖に震えながらも、僕は、アロー氏が身を滅ぼしたあの強い酒を手に入れたのは、こうだったに違いないと考えずにはいられなかった。
ディックは少しの間いなくなり、その間にイスラエルは料理人の耳元で立て続けに話した。僕が聞き取れたのは一言か二言だったが、それでも重要な情報をいくつか得た。同じような内容の切れ切れの言葉の他に、この一節全体が聞き取れたからだ。「これ以上、仲間になるやつはいねえ」つまり、まだ忠実な船員たちが船上にいるのだ。
ディックが戻ると、三人は次々と平たいカップを取って飲んだ――一人は「幸運に」、もう一人は「フリント爺さんに乾杯」、そしてシルバー自身は歌うように言った。「我々に乾杯、風上を向けろ、獲物は山ほど、ダフも山ほど。」
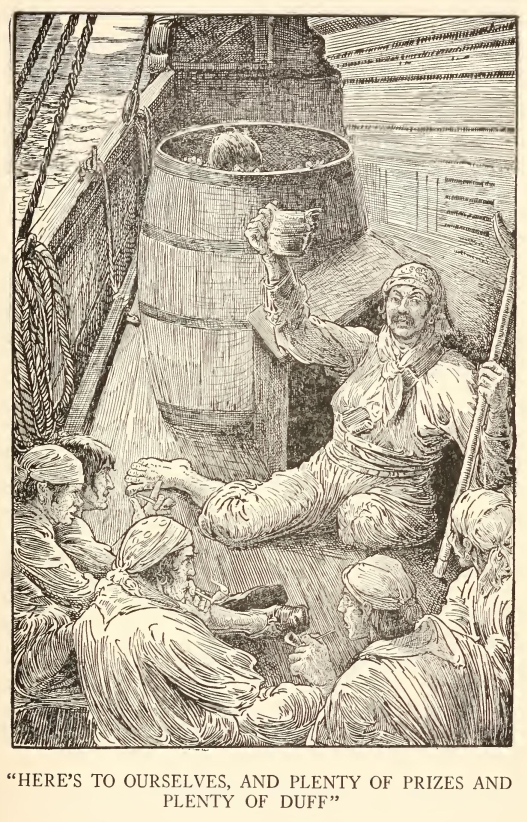
その時、樽の中にふっと光が差し込み、見上げると月が昇り、後マストのてっぺんを銀色に染め、前マストの帆の風上側を白く照らしていた。そして、ほとんど同時に、見張りの声が叫んだ。「陸地だ!」
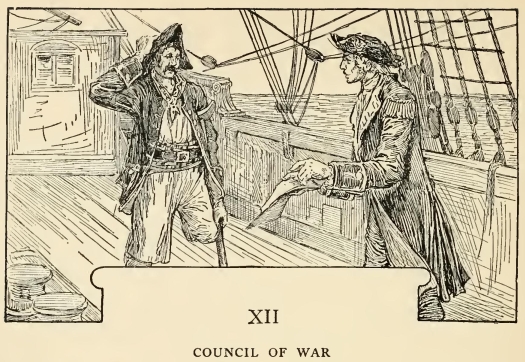
第十二章 軍議
甲板を横切る大きな足音がした。船室や船首楼から人々が転がり出てくるのが聞こえた。僕は一瞬のうちに樽の外へ滑り出し、前マストの帆の陰に飛び込み、船尾の方へ二重に進路を取り、ちょうどハンターとライブシー博士が風上の船首へ駆けつけるのに間に合うよう、開けた甲板に出た。
そこにはすでに全員が集まっていた。月の出現とほとんど同時に、帯状の霧が晴れた。我々の南西の方角に、二マイルほど離れて二つの低い丘が見え、その一方の後ろには三つ目のさらに高い丘がそびえていたが、その頂はまだ霧に覆われていた。三つとも鋭い円錐形に見えた。
それらを僕は、ほとんど夢見心地で見ていた。ほんの数分前の恐ろしい恐怖からまだ立ち直っていなかったからだ。そして、スモレット船長が命令を発する声が聞こえた。ヒスパニオラ号は風上へ二点ほど進路を寄せ、今や島の東側をちょうどかすめるコースを航行していた。
「さて、諸君」帆がすべて張られると船長は言った。「前方のあの陸地を、誰か見たことがある者はいるか?」
「はい、だんな」とシルバーは言った。「以前、料理人をしていた商船で、あそこで水を補給したことがあります。」
「停泊地は南側、小島の後ろにあるのだろう?」と船長は尋ねた。
「へえ、だんな。骸骨島と呼ばれてやす。昔は海賊の主な根城でして、船に乗ってた仲間が、やつらの呼び名を全部知ってやした。北の方にあるあの丘は前マストの丘、南へ向かって三つの丘が並んでやす――前マスト、主マスト、後マストでさ。ですが、主マスト――雲がかかってる一番でかいやつですが――そいつはたいていスパイグラスと呼ばれてやす。停泊地で船底掃除をしてる時に見張りを立ててたからで、あそこで船を掃除してたんでさ、失礼ながら。」
「ここに海図がある」スモレット船長は言った。「それがその場所かどうか、見てみろ。」
ロング・ジョンは海図を受け取ると、その目はらんらんと輝いた。しかし、紙の真新しさから、彼が失望する運命にあることが僕には分かった。これはビリー・ボーンズの櫃で見つけた地図ではなく、赤い十字の印と書き込みという唯一の例外を除いて、地名、高さ、水深など、あらゆる点で完璧な、正確な写しだったのだ。彼のいら立ちは相当なものだったに違いないが、シルバーはそれを隠すだけの精神力を持っていた。
「いかにも、旦那」と彼は言った。「間違いなく、ここがその場所です。実にきれいに描けている。一体誰が描いたんでしょうな? 海賊どもは無学すぎたでしょうからね。おお、ここに書いてある。『キッド船長の停泊地』――まさしく俺の船仲間が呼んでいた名前だ。南に沿って強い海流があって、それから西海岸を北上していく。旦那のおっしゃる通りでしたな」と彼は言う。「風上に舵を切って、島のかざかみに占位したのは正解でした。少なくとも、ここに入って船を傾けて修理するつもりなら、ですがね。この海域でこれ以上いい場所はありやせん。」
「ありがとう」とスモレット船長は言った。「後でまた力を貸してもらうことにしよう。下がっていいぞ。」
私は、ジョンがこれほど冷静にこの島についての知識を明かしたことに驚いた。そして正直に言うと、彼が私の方へ近づいてくるのを見たときには、半分恐怖を感じていた。もちろん彼は、私がリンゴ樽の中から彼の密談を盗み聞きしたことなど知る由もない。しかしこの時すでに、私は彼の残酷さ、裏表のある性格、そしてその力にひどい嫌悪感を抱いており、彼が私の腕に手を置いたときには、身震いを隠すのがやっとだった。
「ああ」と彼は言った。「こいつぁいい場所だ、この島は――ガキが上陸するにはもってこいの場所だぜ。水浴びもできるし、木登りもできる、ヤギ狩りだってできるだろうよ。お前さん自身、ヤギみてえにあの丘にひょいと登っちまうだろうな。いやはや、若返った気分だ。この木の脚のことなんざ、忘れちまいそうだった。若くて、足の指が十本あるってのはいいもんだ。そいつぁ請け合うぜ。ちょっと探検に行きたくなったら、このジョン爺に声をかけな。携帯食を用意してやるからよ。」
そして、実に親しげに私の肩をぽんと叩くと、彼はびっこを引きながら船首の方へ去り、船内へと降りていった。
スモレット船長、郷士、そしてライブシー博士は後甲板で話し込んでいた。私は自分の話を聞いてもらいたくてたまらなかったが、公然と彼らの邪魔をする勇気はなかった。何かうまい口実はないものかと思いを巡らせていると、ライブシー博士が私をそばに呼んだ。彼はパイプを船室に置き忘れてきたらしく、タバコの奴隷である博士は、私にそれを持ってこさせようとしたのだ。しかし、私が話せるくらい近く、それでいて他の者には聞こえない距離まで来ると、私はだしぬけに口を開いた。「先生、お話を。船長と郷士を船室へ連れて行ってください。それから、何か口実を作って私を呼んでください。大変な知らせがあるんです。」
博士は少し顔色を変えたが、次の瞬間にはもう平静を取り戻していた。
「ありがとう、ジム」と、彼はわざと大きな声で言った。「聞きたかったのはそれだけだ」まるで、彼が私に何か質問をしたかのようだった。
そう言うと、彼はきびすを返し、他の二人のもとへ戻っていった。彼らは少しの間話し合っていたが、誰も驚いた様子を見せず、声を荒らげることも、口笛を吹くことすらなかった。しかし、ライブシー博士が私の頼みを伝えたのは明らかだった。というのも、次に私が聞いたのは、船長がジョブ・アンダーソンに命令を下す声であり、総員が甲板に呼び出されたからだ。
「諸君」とスモレット船長は言った。「一言、言っておくことがある。我々が視認したこの土地こそ、我々が航海の目的地としてきた場所だ。トレローニー郷士は、皆も知っての通り、大変気前の良いお方でな、たった今、私に二言三言お尋ねになった。そして、私は船上の誰もが、甲板でもマストの上でも、これ以上望むべくもないほど見事に職務を果たしたと報告することができた。そこで、郷士と私、そして博士の三人で、船室に下りて君たちの健康と幸運を祝して杯を挙げることにした。君たちにはグロッグが振る舞われるだろうから、それで我々の健康と幸運を祝して乾杯してくれたまえ。これについて私がどう思うか、言おう。実に結構なことだと思う。もし君たちも私と同じように思うなら、この計らいをしてくださった紳士のために、威勢のいい海の歓声を上げてくれ。」
歓声が続いた――それは当然のことだった。しかし、それは実に力強く、心の底からの歓声だったので、告白するが、まさかこの男たちが我々の命を狙って陰謀を企てているとは、ほとんど信じられないほどだった。
「スモレット船長にもう一度!」最初の歓声が収まると、ロング・ジョンが叫んだ。
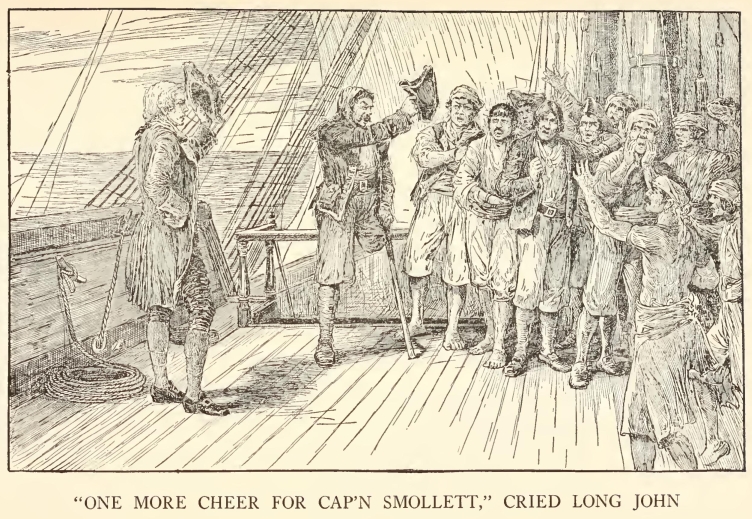
そしてこれもまた、心のこもった歓声だった。
それが終わると、三人の紳士は船室へと下りていった。そして間もなく、ジム・ホーキンズは船室へ来るように、との伝言が前方に伝えられた。
私が見ると、三人は皆テーブルを囲んで座っており、目の前にはスペイン産のワインのボトルと干しブドウがいくつか置かれていた。博士はパイプをふかしていたが、そのかつらは膝の上にあり、それは彼が動揺しているしるしだと私は知っていた。暖かい夜だったので船尾の窓は開け放たれ、月が船の航跡の向こうで輝いているのが見えた。
「さて、ホーキンズ君」と郷士が言った。「何か話があるそうだね。話したまえ。」
私は言われた通り、できるだけ手短に、シルバーの会話のすべてを詳細に語った。私が話し終えるまで誰も口を挟まず、三人のうち誰一人として身じろぎひとつしなかった。ただ、最初から最後まで、彼らの視線は私の顔に注がれていた。
「ジム」とライブシー博士が言った。「座りたまえ。」
そして彼らは私をテーブルのそばに座らせ、ワインをグラスに注ぎ、両手に干しブドウを山盛りにくれた。そして三人とも、一人ずつ、それぞれお辞儀をしながら、私の幸運と勇気を称え、私の健康のために、そして私への感謝を込めて乾杯してくれた。
「さて、船長」と郷士が言った。「あなたが正しく、私が間違っていた。私が馬鹿だったと認めます。ご命令をお待ちしています。」
「あなた以上に馬鹿だったのは私の方ですよ、郷士」と船長は返した。「反乱を企てる船員というのは、必ずその前に兆候を見せるものだと聞いていました。目さえあれば、誰にでもそのたくらみを見抜き、手を打つことができる、と。しかし、この船員たちは」と彼は付け加えた。「私の手に余ります。」
「船長」と博士が言った。「失礼ながら、それはシルバーの仕業です。実に注目すべき男ですよ。」
「帆桁の端から吊るされた姿は、さぞ見事なものでしょうな」と船長は応じた。「しかし、これはただのおしゃべり。何の解決にもなりません。私には三、四点、考えがあります。トレローニー郷士のお許しを得て、それらを申し上げたい。」
「あなたが船長です、 सर。話すべきはあなただ」とトレローニー郷士は尊大に言った。
「第一点」とスモレット氏は始めた。「我々は前進しなければなりません。引き返すことはできないからです。もし私が回頭を命じれば、連中は即座に蜂起するでしょう。第二点、我々には時間があります――少なくとも、この宝が見つかるまでは。第三点、我々には忠実な部下がいます。さて、郷士、遅かれ早かれ事を構えることになるのは必至です。そこで私が提案するのは、ことわざにもある通り、好機を逃さず、奴らが最も油断しているであろう晴れた日に一戦交える、ということです。トレローニー郷士、あなたがお屋敷から連れてきた召使いたちは、当てにできますな?」
「私自身と同じくらいに」と郷士は断言した。
「三人」と船長は数えた。「我々自身で七人、ここにいるホーキンズ君を入れれば。さて、信頼できる船員については?」
「おそらくトレローニー郷士ご自身の部下でしょう」と博士が言った。「シルバーに出会う前に、ご自身で選び抜いた者たちです。」
「いや」と郷士は答えた。「ハンズは私の部下の一人だった。」
「ハンズは信用できると思っていたのだが」と船長も付け加えた。
「しかも、奴らが皆イングランド人だとは!」と郷士は声を荒げた。「 सर、いっそ船ごと爆破してやりたい気分だ。」
「さて、皆さん」と船長は言った。「私に言える最善の策も、大したものではありません。よろしければ、停船し、厳重に見張りを続けましょう。人間にとって辛いことだとは分かっています。いっそ一戦交えた方が気は楽でしょう。しかし、味方が誰か分かるまでは、どうしようもありません。停船して、好機を待つ。それが私の見解です。」
「ここにいるジムが」と博士が言った。「誰よりも我々の助けになってくれるでしょう。男たちは彼には心を許しているし、ジムは観察眼のある子ですから。」
「ホーキンズ君、君には絶大な信頼を寄せている」と郷士が付け加えた。
これを聞いて、私はかなり絶望的な気分になってきた。自分はまったく無力だと感じたからだ。しかし、奇妙な偶然が重なり、安全がもたらされたのは、実に私を通してのことだった。その間、我々がいくら話し合っても、二十六人のうち信頼できると分かっているのはわずか七人。そしてその七人のうち一人は少年なので、我々の側の大人は六人、対する敵は十九人だった。
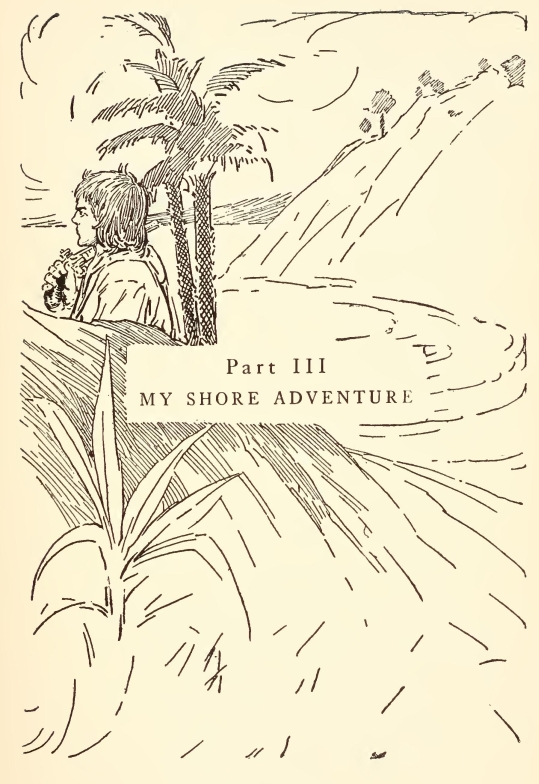
第三部 島での冒険
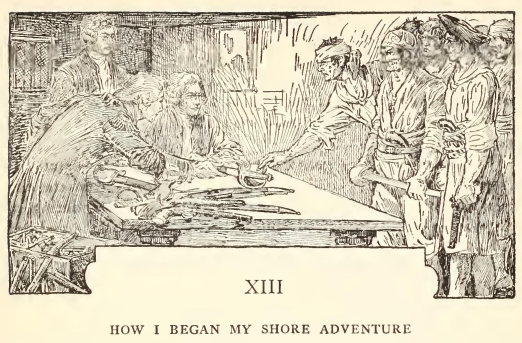
第十三章 冒険の始まり
翌朝、甲板に出たとき、島の様子はすっかり変わっていた。風は今や完全に止んでいたが、夜の間にかなり進んでおり、我々は今、島の低い東海岸から南東へ半マイルほどのところで無風状態に陥っていた。灰色の森が地表の大部分を覆っている。この単調な色合いは、低地の黄色い砂地の筋や、他の木々より高くそびえる松の仲間の多くの高木――あるものは一本で、あるものは群生して――によって確かに破られてはいたが、全体的な色調は均一で物悲しいものだった。丘々は植生の上にくっきりとそびえ立ち、剥き出しの岩の尖塔をなしていた。どれも奇妙な形をしており、島で最も高い、三、四百フィートはあろうかという望遠鏡山は、その形状もまた最も奇妙で、ほぼすべての側面から切り立つようにそびえ、その頂上は彫像を置く台座のように突然断ち切られていた。
ヒスパニオラ号は海のうねりの中で、排水口が水中に没するほど揺れていた。帆桁は滑車にぶつかって唸りを上げ、舵はあちこちに打ち付けられ、船全体がきしみ、うめき、工場のように揺れ動いていた。私は後方支索にしっかりとつかまらなければならず、目の前で世界がぐるぐると回った。というのも、船が進んでいるときはそれなりに船に強い私でも、このように停船して瓶のように揺さぶられるのは、吐き気を催さずに耐える術を学んだことがなかったからだ。とりわけ、空腹の朝はなおさらだった。
おそらくそのせいだったのだろう――あるいは、灰色の憂鬱な森と、荒々しい石の尖塔、そして険しい浜辺に打ち寄せて泡立ち、轟くのが見えも聞こえもする波のせいだったのかもしれない――少なくとも、太陽は明るく暑く輝き、岸辺の鳥たちは我々の周りで漁をしたり鳴いたりしていて、長い船旅の後なら誰でも陸に着くのを喜ぶだろうと思われたにもかかわらず、私の心は、いわゆる、鉛のように重くなった。そして、最初の一瞥以来、私は宝島という考えそのものが憎らしくなった。
我々の前には陰鬱な朝の仕事が待ち構えていた。風の気配はまったくなく、ボートを降ろして人を乗り込ませ、船を三、四マイルほど島の角を回って、骸骨島の背後にある避難港への狭い水路まで曳航しなければならなかったからだ。私はボートの一艘に志願したが、もちろん、そこに私の仕事はなかった。うだるような暑さで、男たちは仕事に不平を激しくぶつけていた。アンダーソンが私のボートの指揮を執っていたが、彼は乗組員をまとめるどころか、一番ひどい不平家と同じくらい大きな声で文句を言っていた。
「まあな」と彼は悪態をつきながら言った。「いつまでも続くわけじゃねえ。」
これは非常に悪い兆候だと私は思った。というのも、その日まで男たちはきびきびと、そして喜んで仕事に取り組んでいたからだ。しかし、この島を一目見ただけで、規律の綱は緩んでしまったのだ。
水路に入るまでずっと、ロング・ジョンは操舵手のそばに立ち、船を導いた。彼はその水路を手のひらを返すように知り尽くしており、測鉛索を持つ男が海図に記されているよりも深い水深をどこでも報告したにもかかわらず、ジョンは一度もためらわなかった。
「引き潮で強い洗掘があるんだ」と彼は言った。「ここの水路は、言ってみれば、鋤で掘り出されたようなもんだ。」
我々は海図の錨の印がある場所に停泊した。それぞれの岸から三分の一マイルほどの距離で、片側が本土、もう片方が骸骨島だった。海底はきれいな砂地だった。我々の錨が投じられると、鳥の群れが森の上を旋回しながら鳴き声を上げて舞い上がったが、一分も経たないうちに再び静まり返り、すべてが再び沈黙に包まれた。
その場所は完全に陸に囲まれ、森に埋もれており、木々は満潮線まで迫っていた。岸はほとんどが平らで、丘の頂は遠くに、あちこちと円形劇場のように立ち並んでいた。二つの小さな川、というよりは二つの沼が、この池とでも呼ぶべき場所に流れ込んでおり、その岸辺の葉は一種の毒々しい輝きを放っていた。船からは家や砦はまったく見えなかった。それらは完全に木々の中に埋もれていたからだ。もし船室への昇降口に海図がなければ、我々は島が海から現れて以来、初めてそこに停泊した者だったかもしれない。
そよ風一つ吹かず、聞こえるのは半マイル先の浜辺や外海の岩に打ち寄せる波の轟音だけだった。停泊地には奇妙なよどんだ匂いが漂っていた――湿った落ち葉や腐った木の幹の匂いだ。博士が、まるで腐った卵を味わう人のように、何度もくんくんと匂いを嗅いでいるのに気づいた。
「宝のことは知らんが」と彼は言った。「ここに熱病が蔓延していることに、このかつらを賭けてもいい。」
もしボートでの男たちの振る舞いが憂慮すべきものだったとすれば、船上に戻ってからのそれは、真に脅威的なものとなった。彼らは甲板にごろごろと横になり、ぶつぶつと話し合っていた。ほんの些細な命令も、険悪な顔で受け止められ、しぶしぶと、そしてぞんざいに実行された。誠実な船員たちでさえ、その雰囲気に感染したに違いない。船上には、他人をたしなめる者は一人もいなかったからだ。反乱、それは雷雲のように我々の頭上に垂れ込めていた。
そして、この危険に気づいていたのは、我々船室の仲間だけではなかった。ロング・ジョンは懸命に働き、グループからグループへと渡り歩き、善意のアドバイスに身を粉にしていた。そして模範という点では、これ以上を示す者はいないだろう。彼は普段にも増して、進んで愛想よく振る舞った。誰に対しても満面の笑みだった。命令が下されれば、ジョンは一瞬で松葉杖をついて立ち上がり、世界で一番陽気な「アイ、アイ、サー!」で応えた。そして他にすることがないと、他の者たちの不満を隠すかのように、次から次へと歌を歌い続けた。
あの陰鬱な午後のあらゆる陰鬱な出来事の中でも、このロング・ジョンの明らかな不安こそが、最悪のものに思えた。
我々は船室で評議を開いた。
「郷士」と船長は言った。「これ以上命令を下せば、船は一瞬にして奴らの手に落ちるでしょう。お分かりでしょう、郷士、こういうことです。私はぞんざいな返事をされる、そうではありませんか? さて、もし私が言い返せば、すぐにでも槍が飛び交うことになる。もし私が黙っていれば、シルバーはその下に何かあると見て取り、勝負は終わりです。今、我々が頼れる男は一人しかいません。」
「それは誰かね?」と郷士が尋ねた。
「シルバーです、郷士」と船長は答えた。「彼はあなたや私と同じくらい、事態を収拾したがっています。これはちょっとした揉め事です。彼に機会さえあれば、すぐにでも連中を説得するでしょう。そこで私が提案するのは、彼にその機会を与えることです。連中に午後の上陸を許可しましょう。もし全員が行くなら、我々は船で戦います。もし誰も行かないなら、まあ、我々は船室に立てこもり、神の正義に身を委ねます。もし何人かが行くなら、私の言葉を覚えておいてください、郷士、シルバーは子羊のようにおとなしく連中を船に連れ戻すでしょう。」
そう決まった。信頼できる者全員に装填済みのピストルが配られた。ハンター、ジョイス、レッドルースには我々の秘密が打ち明けられ、彼らは我々が予想していたよりも驚かず、むしろ良い気概でその知らせを受け取った。そして船長は甲板に上がり、乗組員に話しかけた。
「諸君」と彼は言った。「今日は暑い一日で、皆疲れて気分もすぐれないだろう。少し陸に上がっても誰も損はしない――ボートはまだ水上にある。ギグボートを使え。好きな者は午後いっぱい上陸してよい。日没の三十分前に号砲を撃つ。」
愚かな連中は、上陸すればすぐにでも宝につまずくことができるとでも思ったに違いない。彼らはたちまち不機嫌な顔つきは消え失せ、遠くの丘にこだまするほどの歓声を上げ、鳥たちを再び停泊地の周りに飛び立たせ、キーキーと鳴かせたからだ。
船長は賢明にも、その場に長居はしなかった。彼は一瞬で姿を消し、一行の編成をシルバーに任せた。そして、そうして正解だったと思う。もし彼が甲板に残っていたら、もはや状況を理解していないふりをすることさえできなかっただろう。それは火を見るより明らかだった。シルバーが船長であり、彼が率いるのは実に反抗的な乗組員だった。誠実な船員たち――そして、そのような者が船上にいることは、間もなく証明されることになるのだが――は、よほど愚かな連中だったに違いない。あるいは、真実はこうだったのだろう。すべての船員が首謀者たちの手本に影響されて不満を抱いていた――ただ、その程度に差があっただけだ。そして、根は善良な少数の者たちは、それ以上、唆されることも、強制されることもできなかったのだ。怠けて仕事をさぼることと、船を乗っ取って多くの罪のない人々を殺害することとは、まったく別の問題である。
しかし、ついに一行が編成された。六人の仲間が船に残り、シルバーを含む残りの十三人が乗り込み始めた。
その時だった。我々の命を救うことに大きく貢献した、最初の無茶な思いつきが頭に浮かんだのは。もしシルバーが六人の男を残していくのなら、我々の仲間が船を奪って戦うことはできないのは明らかだった。そして、六人しか残っていないのだから、船室の仲間が当面私の助けを必要としないことも、同じく明らかだった。私はすぐさま、陸へ行くことを思いついた。あっという間に私は船べりを滑り降り、一番近いボートの船首の席に丸くなって身を潜めた。そして、ほとんど同じ瞬間にボートは岸を離れた。
誰も私に気づかなかった。ただ、船首の漕ぎ手が「ジムか? 頭を下げてな」と言っただけだ。しかし、もう一艘のボートからシルバーが鋭くこちらを見て、そこにいるのが私かと尋ねてきた。その瞬間から、私は自分のしでかしたことを後悔し始めた。
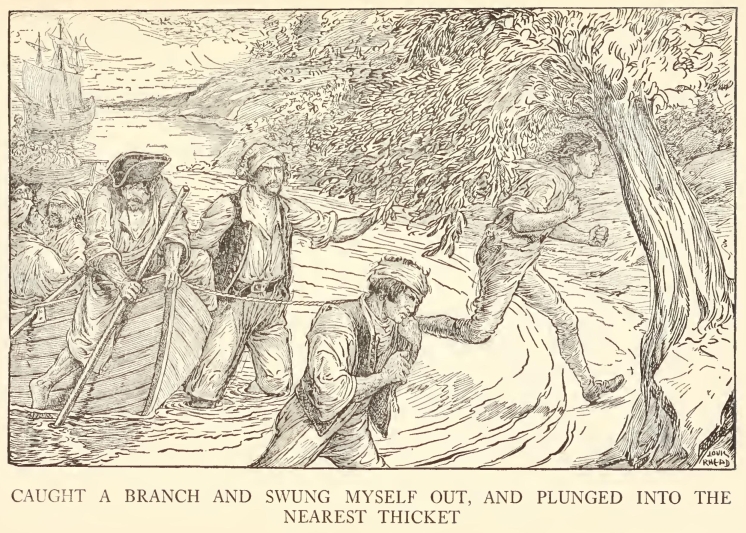
乗組員たちは浜辺を目指して競い合ったが、私の乗っていたボートは少し先に出ており、より軽く、漕ぎ手も優れていたため、連れのボートをはるか前方に引き離した。そして船首が岸辺の木々にぶつかり、私が枝をつかんで身を翻し、一番近い茂みに飛び込んだとき、シルバーたちはまだ百ヤードも後ろにいた。
「ジム、ジム!」と彼が叫ぶのが聞こえた。
しかし、私がそれに構わなかったのはご想像の通りだろう。跳び、身をかがめ、突き進み、もう走れなくなるまで、がむしゃらにまっすぐ走り続けた。

第十四章 最初の一撃
ロング・ジョンをまんまと出し抜いたことに私はとても喜び、自分がいる見知らぬ土地を興味深く見回し始めた。
私は柳やガマ、そして奇妙で異国風の沼沢樹が生い茂る湿地帯を横切った。そして今、起伏のある砂地の開けた土地の端に出てきた。広さは一マイルほどで、松の木が数本と、成長の仕方は樫に似ているが、葉の色は柳のように青白い、ねじくれた木々が多数点在していた。開けた土地の向こう側には丘の一つがそびえ、二つの風変わりでごつごつした頂が太陽の光を浴びて鮮やかに輝いていた。
私は今、初めて探検の喜びを感じた。島は無人だった。船仲間は後ろに置いてきた。そして目の前には、口のきけない獣や鳥しか生きていない。私は木々の間をあちこち歩き回った。ところどころに、私には見知らぬ花をつけた植物があった。ところどころで蛇を見かけ、そのうちの一匹は岩棚から頭をもたげ、独楽が回るような音を立てて、私にシューッと威嚇してきた。彼が deadly enemy[訳注:ガラガラヘビなどの毒蛇を指す] であり、その音が有名なガラガラという音だとは、夢にも思わなかった。
それから私は、この樫に似た木々――後に、常緑の樫と呼ぶべきだと聞いた――の長い茂みにやってきた。それらはイバラのように砂に沿って低く生え、枝は奇妙にねじくれ、葉は葺き屋根のように密集していた。その茂みは砂の小丘の一つから下に向かって広がり、進むにつれて背を高くしながら、広大な葦の湿地の縁にまで達していた。その湿地を通って、一番近い小川が停泊地へと流れ込んでいた。湿地は強い日差しの下で湯気を立てており、望遠鏡山の輪郭が陽炎の中に揺れていた。
突然、ガマの茂みの中で何やらざわめきが起こり始めた。野生のカモが一羽、グワッと鳴いて飛び立ち、もう一羽がそれに続いた。そしてすぐに、湿地の全面に鳥の大群が空中で叫び、旋回しながら舞い上がった。私はすぐに、船仲間の誰かが湿地の縁に沿って近づいているに違いないと判断した。そしてその判断は間違っていなかった。すぐに、非常に遠くから低い人間の声が聞こえ、耳を澄ましているうちに、その声は着実に大きく、そして近くなってきたからだ。
これにはひどく怯え、私は一番近い常緑の樫の陰に這い込み、ネズミのように息を殺して聞き耳を立てた。
別の声が応え、それから最初の声が――今ではそれがシルバーの声だと分かった――再び話を続け、長い間、立て板に水のごとくしゃべり続けた。時折、もう一方の声に遮られるだけだった。その響きからして、彼らは真剣に、ほとんど激しく話し合っているに違いなかった。しかし、はっきりとした言葉は私の耳には届かなかった。
ついに、話し手たちは立ち止まり、おそらくは腰を下ろしたようだった。彼らがそれ以上近づかなくなっただけでなく、鳥たち自身も静かになり始め、再び湿地のねぐらに戻り始めたからだ。
そして今、私は自分の務めを怠っていると感じ始めた。これほど無謀にもこのならず者たちと一緒に上陸したからには、せめて彼らの密談を盗み聞きするのが私のすべきことであり、身を隠すのに好都合な、低く茂る木々の下にできるだけ近づくのが、私の明白かつ当然の義務だと感じた。
話し手たちの方向は、彼らの声の響きだけでなく、侵入者たちの頭上でまだ警戒して舞っている数羽の鳥の振る舞いによって、かなり正確に分かった。
四つん這いになりながら、私は着実に、しかしゆっくりと彼らに向かって進んだ。そしてついに、葉の隙間から頭を上げると、湿地のそばにある、木々に囲まれた小さな緑の谷間がはっきりと見えた。そこでは、ロング・ジョン・シルバーともう一人の乗組員が、顔を突き合わせて会話をしていた。
太陽が彼らをさんさんと照りつけていた。シルバーは帽子を地面のそばに投げ出しており、その大きく、滑らかで、日に焼けた顔は、暑さでてらてらと輝き、どこか懇願するように相手の男に向けられていた。
「おい」と彼は言っていた。「お前さんを砂金みてえに思ってるからだ――砂金だ、そいつは請け合ってもいいぜ! もし俺がお前さんをタールみてえに気に入ってなけりゃ、ここにこうして警告しに来ると思うかい? もう万事休すだ――どうすることもできねえ。お前さんの首を救うために話してるんだ。もしあの荒くれ者の誰かがそれを知ったら、俺はどうなる、トム――なあ、教えてくれ、俺はどうなる?」
「シルバー」ともう一人の男が言った――私は彼が顔を赤らめているだけでなく、カラスのようにしゃがれた声で話し、その声が張り詰めたロープのように震えているのに気づいた――「シルバー」と彼は言う。「あんたは年寄りだし、正直者だ。少なくともそういう評判だ。それに、貧乏な船乗りが多くは持てねえ金も持ってる。それに、俺の見間違いでなけりゃ、あんたは勇敢だ。それで、あんたが、あんなクズどもの集まりに引きずり込まれるって言うのか? あんたに限ってそんなことはない! 神が見ている、この手を失った方がましだ。もし俺が自分の務めに背いたら――」
その時、突然、物音に彼の言葉は遮られた。私は誠実な船員の一人を見つけた――そして、まさにその同じ瞬間に、もう一人の知らせが届いたのだ。遠く離れた湿地の中から、突然、怒りの叫びのような音が上がり、それに続いてもう一つ。そして、身の毛もよだつ、長く尾を引く絶叫が一つ。望遠鏡山の岩々がそれを二十回もこだました。湿地の鳥の群れが再び舞い上がり、一斉の羽音とともに天を暗くした。そして、その死の叫びが私の脳裏でまだ鳴り響いているずっと後になって、静寂が再びその支配を取り戻し、ただ舞い降りる鳥たちのざわめきと、遠い波の轟音だけが、午後の気だるさをかき乱していた。
トムはその音に、拍車をかけられた馬のように跳び上がったが、シルバーは瞬き一つしなかった。彼はその場に立ち、松葉杖に軽くもたれかかり、飛びかかろうとする蛇のように仲間を見つめていた。
「ジョン!」と船乗りは叫び、手を差し伸べた。
「手を放せ!」とシルバーは叫び、私にはそう見えたが、熟練した体操選手のような速さと確実さで、一ヤード後ろへ跳びのいた。
「お望みなら手を放そう、ジョン・シルバー」ともう一人が言った。「俺を恐れさせるのは、あんたのやましい良心だ。だが、神に誓って教えてくれ、あれは何だったんだ?」
「あれか?」とシルバーは微笑みながら返したが、その警戒心はこれまで以上で、その目は大きな顔の中でただの点にすぎなかったが、ガラスの破片のようにきらめいていた。「あれか? ああ、ありゃアランだろうな。」
この言葉に、トムは英雄のように激昂した。
「アランだと!」彼は叫んだ。「ならば、真の船乗りとして、彼の魂に安らぎあれ! そしてあんた、ジョン・シルバー、長いこと俺の仲間だったが、もう仲間じゃねえ。犬死にしようとも、俺は自分の務めを果たして死ぬ。アランを殺したのか? できるなら俺も殺せ。だが、あんたには屈しない。」
そう言うと、この勇敢な男は料理人にまっすぐ背を向け、浜辺に向かって歩き出した。しかし、彼が遠くまで行く運命ではなかった。ジョンは叫び声を上げると木の枝をつかみ、脇の下から松葉杖をひったくり、その無骨な飛び道具をぶん、と唸りを立てて空に放った。それは哀れなトムの、背中の真ん中、両肩の間に、先端から、そして凄まじい勢いで突き刺さった。彼の両手は宙に舞い、はっと息をのむような声を上げ、そして倒れた。
彼がどれほどひどく傷ついたか、あるいはたいして傷ついていなかったのか、誰にも知る由はなかった。音から判断するに、おそらくその場で背骨が折れたのだろう。しかし、彼に回復する時間は与えられなかった。足も松葉杖もなくても猿のように身軽なシルバーは、次の瞬間には彼の上に乗り、その無防備な体に二度、柄までナイフを突き立てた。待ち伏せ場所から、彼が打撃を加えるたびに、荒い息遣いをするのが聞こえた。
気絶するのがどういうことか、私は正確には知らない。しかし、次のしばらくの間、目の前の世界が渦巻く霧の中に消えていくようだったことは知っている。シルバーと鳥たち、そして高い望遠鏡山の頂が、ぐるぐると、そして逆さまに私の目の前で回り、ありとあらゆる鐘の音が鳴り響き、遠くからの叫び声が私の耳の中でこだました。
我に返ったとき、その怪物は身なりを整え、松葉杖を脇に挟み、帽子を頭にかぶっていた。彼のすぐ前には、トムが芝生の上で動かずに横たわっていた。しかし、殺人者は彼のことなど微塵も気にかけておらず、その間、血に濡れたナイフを草の葉で拭っていた。他のすべては変わらず、太陽は湯気の立つ湿地と山の高い頂を容赦なく照らし続けていた。ほんの少し前に、私の目の前で実際に殺人が行われ、人の命が無慈悲に断ち切られたとは、ほとんど信じがたいことだった。

しかし今、ジョンはポケットに手を入れ、笛を取り出し、熱気を帯びた空気の中を遠くまで響き渡る、いくつかの変調をつけた音を吹いた。もちろん、私にはその合図の意味は分からなかったが、それは即座に私の恐怖を呼び覚ました。もっと多くの男たちがやってくるだろう。私は見つかってしまうかもしれない。彼らはすでに誠実な仲間を二人殺していた。トムとアランの後、次は私の番ではないだろうか?
私は即座に身を引き抜き、できる限りの速さと静かさで、森のより開けた場所へと這い戻り始めた。そうしている間にも、老いた海賊とその仲間たちの間で交わされる呼び声が聞こえ、この危険を告げる音は私に翼を授けた。茂みを抜けるとすぐに、私はこれまでにないほど走った。逃げる方向などほとんど気にせず、ただ殺人者たちから遠ざかることだけを考えた。そして走るにつれて、恐怖はどんどん膨れ上がり、ついには狂乱に近いものへと変わっていった。
実際、私以上に完全に途方に暮れている者がいるだろうか? 号砲が鳴ったとき、どうしてあのような、犯罪の煙がまだくすぶっている悪鬼どもの中に混じって、ボートへ下りていく勇気があるだろう? 私を見つけた最初の者が、シギの首をひねるように私の首をひねらないだろうか? 私がいないこと自体が、私の警戒心、ひいては私の致命的な知識の証拠にならないだろうか? もうすべて終わりだ、と私は思った。さようなら、ヒスパニオラ号。さようなら、郷士、博士、そして船長! 私に残された道は、餓死するか、反逆者たちの手にかかって死ぬか、そのどちらかしかなかった。
この間ずっと、言ったように、私は走り続けていた。そして、何も気づかずに、二つの頂を持つ小山の麓に近づき、常緑の樫がよりまばらに生え、その風格と大きさにおいて森の木々のように見える島の一角に入り込んでいた。これらに混じって、高さ五十フィート、あるいは七十フィートに近い松の木がいくつか散在していた。空気もまた、湿地のそばよりも新鮮な香りがした。
そしてここで、新たな恐怖が、私の心臓を激しく鼓動させ、足を止めさせた。
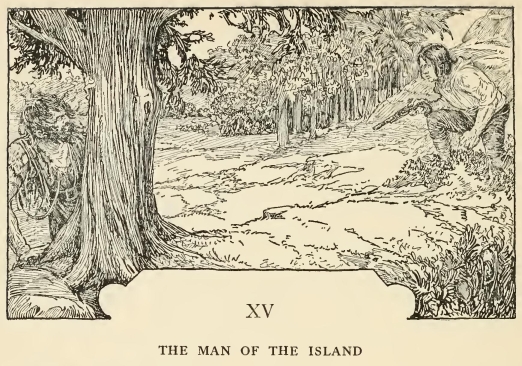
第十五章 島の男
丘の側面から――そのあたりは急で石が多かった――砂利が一筋崩れ落ち、ガラガラと音を立てて木々の間を跳ねながら落ちていった。私の目は無意識にその方向に向き、松の木の幹の背後に、ある人影が素早く飛び込むのを見た。それが何であったか、熊か、人か、それとも猿か、私には到底分からなかった。黒っぽく毛むくじゃらに見えた。それ以上は分からなかった。しかし、この新たな幻影の恐怖に、私は立ちすくんだ。
今や私は、どうやら両側から断ち切られたようだった。後ろには殺人者たち、前にはこの潜む正体不明の者。そしてすぐに私は、未知の危険よりも既知の危険の方を選ぶ気になった。森のこの生き物と比べれば、シルバー自身でさえそれほど恐ろしくは思えなかった。私はきびすを返し、肩越しに鋭く後ろを見ながら、ボートの方向へと歩みを戻し始めた。
即座にその人影が再び現れ、大きく迂回しながら、私の行く手を遮り始めた。私は疲れていたが、たとえ起きたばかりのように元気だったとしても、このような敵と速さを競うのは無駄だと分かった。その生き物は、鹿のように幹から幹へと軽やかに移動し、人間のように二本足で走っていたが、私がこれまで見たどんな人間とも異なり、走るときはほとんど体を二つ折りにするようにかがめていた。しかし、それが人間であることは、もはや疑う余地はなかった。
私は人食い人種について聞いたことを思い出し始めた。もう少しで助けを呼ぶところだった。しかし、どんなに野性的であれ、彼が人間であるという事実そのものが、私をいくらか安心させ、それに比例してシルバーへの恐怖が蘇り始めた。したがって、私は立ち止まり、何とか逃げ出す方法はないかと思いを巡らせた。そう考えているうちに、ピストルを持っていることを思い出した。自分が無防備ではないと気づくとすぐに、勇気が再び心に燃え上がり、私はこの島の男に断固として顔を向け、きびきびと彼に向かって歩き出した。
彼はこの時、別の木の幹の陰に隠れていた。しかし、彼は私を注意深く見ていたに違いない。私が彼の方向へ動き始めるとすぐに、彼は再び姿を現し、私に会おうと一歩踏み出したからだ。それから彼はためらい、後ずさりし、再び前に出て、そしてついに、私の驚きと混乱をよそに、ひざまずき、組んだ両手を懇願するように差し出した。
そこで私は再び立ち止まった。
「お前は誰だ?」と私は尋ねた。
「ベン・ガンだ」と彼は答えた。その声は錆びついた錠前のように、しゃがれてぎこちなかった。「哀れなベン・ガンだよ。この三年というもの、キリスト教徒と口をきいたことがねえ。」

今や、彼が私と同じ白人であり、その顔立ちはむしろ好ましいことさえ見て取れた。露出している肌はどこも太陽に焼かれ、唇さえも黒く、その浅黒い顔の中で明るい色の目がひどく際立って見えた。私が見たり想像したりしたどんな物乞いよりも、彼はみすぼらしさの極みにあった。彼は古い船の帆布や古い船乗り用の布のぼろ切れをまとっており、この異様なつぎはぎだらけの服は、真鍮のボタン、木の切れ端、タールを塗ったガスケットの輪など、実に様々でちぐはぐな留め具の集まりによって、かろうじて一つにまとめられていた。腰には古い真鍮のバックルがついた革ベルトを締めており、それが彼の装い全体の中で唯一しっかりしたものだった。
「三年!」と私は叫んだ。「難破したのか?」
「いや、違うぜ、相棒」と彼は言った。「置き去り刑だ。」
私はその言葉を聞いたことがあり、それが海賊たちの間ではよくある恐ろしい刑罰の一種で、罪人を少量の火薬と弾丸と共に上陸させ、どこか寂れた遠い島に置き去りにするものだと知っていた。
「三年前にな、置き去りにされたんだ」と彼は続けた。「それ以来、ヤギとベリーとカキで生きてきた。どこにいようと、人間は自分の力でやっていけるもんだ、と俺は思う。だがな、相棒、まともな人間の食い物が恋しくてたまらねえ。チーズのかけらなんざ、持ってねえだろうな? ないか? まあいいさ、何度も長い夜にチーズの夢を見たもんだ――大抵は焼いたやつだ――そしてまた目が覚めると、ここにいた。」
「もし船に戻れたら」と私は言った。「石のようにたくさんのチーズをやるよ。」
この間ずっと、彼は私のジャケットの生地を触ったり、私の手をなでたり、私のブーツを見たり、そして話の合間には、同胞の存在に子供のような喜びを示していた。しかし、私の最後の言葉に、彼ははっとしたような、ずる賢い表情になった。
「もし船に戻れたら、だと?」と彼は繰り返した。「どうしてだ、誰がお前さんを邪魔するってんだ?」
「お前じゃないことは分かっている」と私は答えた。
「その通りだ」と彼は叫んだ。「さて、お前さん――何て名前だ、相棒?」
「ジムだ」と私は彼に言った。
「ジム、ジム」と彼は、どうやらうれしそうに言った。「さてと、ジム、俺は聞いたらお前さんが恥ずかしくなるような、ひどい暮らしをしてきた。なあ、例えば、俺に敬虔な母親がいたなんて、思わねえだろう――俺を見て?」と彼は尋ねた。
「いや、特にそうは思わないな」と私は答えた。
「ああ、そうかい」と彼は言った。「だが、いたんだ――そりゃあもう、とびっきり敬虔な母親がな。それに俺は礼儀正しくて信心深い少年で、教理問答を早口でまくしたてることができたもんだ。一言一句聞き分けられねえくらいにな。そして、ジム、こうなっちまったんだ。始まりは、あのありがたい墓石の上での銭投げ遊びだった! それが始まりだったが、それだけじゃ済まなかった。それで、お袋が俺にそう言って、全部予言したんだ、あの敬虔な女は! だが、俺をここに置いたのは神の摂理だった。この寂しい島で、俺はすべてを考え抜いた。そして、信仰心を取り戻したんだ。もうラム酒はあまり口にしねえ。もちろん、運試しにちょっぴり一杯は、最初の機会にいただくがな。俺は善人になるって決めたし、その道も見えた。そして、ジム」――彼はあたりを見回し、声をひそめてささやいた――「俺は金持ちだ。」
今や私は、この哀れな男が孤独の中で気が狂ってしまったのだと確信した。そして、その気持ちが顔に出てしまったのだろう。彼は熱っぽくその言葉を繰り返した。「金持ちだ! 金持ちだって言ってるんだ。そして、いいか、俺はお前さんを一人前の男にしてやる、ジム。ああ、ジム、お前さんは星に感謝するだろうよ、きっと。俺を最初に見つけたのがお前さんでよかったってな!」
そしてこの時、突然彼の顔に影が差し、彼は私の手を握る力を強め、脅すように人差し指を私の目の前に突きつけた。
「さて、ジム、本当のことを言え。ありゃフリントの船じゃねえな?」と彼は尋ねた。
この言葉に、私は幸運なひらめきを得た。私は味方を見つけたと信じ始め、すぐに彼に答えた。
「フリントの船じゃないし、フリントは死んだ。だが、お前が聞くから本当のことを言うが――フリントの部下が何人か乗っている。俺たち残りの者にとっては、運の悪いことにな。」
「片――足の――男はいないか?」と彼は息を切らしながら言った。
「シルバーか?」と私は尋ねた。
「ああ、シルバー!」と彼は言った。「それが奴の名前だった。」
「彼は料理長で、首謀者でもある。」
彼はまだ私の手首をつかんでいたが、その言葉にぐいとそれをひねった。
「もしお前さんがロング・ジョンに送られてきたんなら」と彼は言った。「俺は豚みてえに始末されるだろうよ、そりゃ分かってる。だが、お前さんはどこにいたと思う?」
私は一瞬で心を決め、返事の代わりに、我々の航海の全容と、我々が置かれている窮状を彼に話した。彼は非常に熱心に私の話を聞き、私が話し終えると、私の頭を撫でた。
「お前さんはいい子だ、ジム」と彼は言った。「それに、お前さんたちはがんじがらめだな、そうだろ? まあ、このベン・ガンを信じな――ベン・ガンが何とかしてやる男だ。どうだい、お前さんの郷士は、助けてやった場合に、気前のいい人だと思うかい――お前さんが言うように、がんじがらめの状況でな?」
私は郷士がこの上なく気前のいい人だと彼に言った。
「ああ、だがな」とベン・ガンは返した。「門番の仕事とか、お仕着せの服とか、そういうことを言ってるんじゃねえ。それは俺の望みじゃねえんだ、ジム。俺が言いたいのは、もうほとんど自分のもの同然の金の中から、例えば千ポンドってな額を、気前よく出してくれるような人かってことだ?」
「きっとそうするだろう」と私は言った。「もともと、乗組員全員で分け合うことになっていたからな。」
「それに、故郷への船賃もか?」と彼は非常に抜け目のない表情で付け加えた。
「もちろんさ」と私は叫んだ。「郷士は紳士だ。それに、もし他の連中を追い払えたら、船を故郷まで動かすのに、お前の助けが必要になるだろう。」
「ああ」と彼は言った。「そうだろうな」そして彼は非常に安堵した様子だった。
「さて、いいか」と彼は続けた。「これだけは教えてやるが、それ以上は言わねえ。俺はフリントが宝を埋めたとき、フリントの船に乗っていた。船長と、屈強な船乗りが六人。連中は一週間近く陸にいて、俺たちは古い『ウォーラス号』で沖合を行ったり来たりしていた。ある晴れた日、信号が上がり、フリントが一人で小舟に乗ってやってきた。頭には青いスカーフを巻いていた。太陽が昇り始め、船首のあたりで見た船長は、死人のように真っ青だった。だが、そこにいたのは船長だけで、六人は皆死んでいた――死んで埋められたんだ。どうやってやったのか、船の誰も見当がつかなかった。少なくとも、戦いと殺人と突然の死だった――船長一人対六人だ。ビリー・ボーンズが航海士で、ロング・ジョンが操舵長だった。連中が船長に宝はどこだと尋ねた。『ああ』と船長は言った。『お前ら、好きなら陸へ行って、そこにいろ』と。『だが船はな、もっと稼ぎにいくぜ、ちくしょうめ!』そう言ったんだ。
「さて、俺は三年前、別の船に乗っていて、この島を視認した。『おい、みんな』と俺は言った。『ここにフリントの宝がある。上陸して見つけようぜ』。船長はそれに不満だったが、船仲間は皆同じ考えで上陸した。十二日間、連中はそれを探し、毎日俺への悪態はひどくなるばかりだった。そしてある晴れた朝、全員が船に戻った。『お前、ベンジャミン・ガン』と連中は言った。『ここにマスケット銃と』『シャベルと、つるはしだ。ここに残って、自分でフリントの金を見つけるんだな』と。
「さて、ジム、俺はここに三年いて、その日から今日まで、まともな人間の食い物を一口も食ってねえ。だが今、ここを見ろ。俺を見ろ。俺が平水夫みてえに見えるか? 見えねえ、とお前さんは言うだろう。俺もそうじゃなかった、と言うだろうよ。」
そう言うと、彼はウィンクして、私を強くつねった。
「お前さんの郷士に、その言葉を伝えてくれ、ジム」と彼は続けた。「『あの男も、昔のままじゃなかった』――それがその言葉だ。三年もの間、彼はこの島の男だった。昼も夜も、晴れの日も雨の日も。そして時々、祈りのことを考えたかもしれない(とお前さんは言うんだ)、そして時々、もし生きていれば、年老いた母親のことを考えたかもしれない(とお前さんは言うんだ)。だが、ガンの時間のほとんどは(こう言うんだ)――彼の時間のほとんどは、別の事柄に費やされていた、と。そして、俺がやるように、郷士を軽くつねるんだ。」
そして彼は、最も内密な様子で、再び私をつねった。
「それから」と彼は続けた。「それから、立ち上がって、こう言うんだ。ガンはいい男だ(とお前さんは言う)、そして彼は、生まれながらの紳士の方を、あの成り上がりの紳士どもよりも、はるかに信頼している――はるかにだ、それを忘れるな――自分もその一人だったからな、と。」
「うーん」と私は言った。「お前が言っていることが一言も分からない。だが、それはどうでもいいことだ。どうやって船に乗ればいいんだ?」
「ああ」と彼は言った。「それが問題だな、確かに。まあ、俺のボートがある。俺がこの両手で作ったやつだ。白い岩の下に隠してある。最悪の場合、暗くなってからそれを試すかもしれねえな。おい!」と彼は叫んだ。「あれは何だ?」
というのも、まさにその時、太陽が沈むまでまだ一、二時間はあるというのに、島中の木霊が目を覚まし、大砲の轟きに咆哮で応えたからだ。
「戦いが始まったんだ!」と私は叫んだ。「ついてこい。」
そして私は、恐怖もすべて忘れ、停泊地に向かって走り始めた。私のすぐそばでは、ヤギ皮をまとった置き去りの男が、軽々と楽に小走りでついてきた。
「左だ、左」と彼は言う。「左手に行け、相棒ジム! 木々の下だ! あそこが俺が初めてヤギを仕留めた場所だ。今じゃ奴らはここまで下りてこねえ。ベンジャミン・ガンを恐れて、みんなあの山のてっぺんにいる。ああ! そしてあそこが墓地だ」――彼はセメタリーと言いたかったのだろう。「あの塚が見えるか? 俺はここに来て、時々祈ったもんだ。日曜日がそろそろだろうと思った時にな。礼拝堂ってわけじゃなかったが、もっと厳かな感じがした。そしてな、こう言うんだ。ベン・ガンは人手が足りなかった――牧師もいなけりゃ、聖書も旗もなかった、と。」
そうやって彼は、私が走っている間、答えを期待もせず、受け取ることもなく、しゃべり続けた。
大砲の音の後、かなりの間隔を置いて、小火器の一斉射撃が続いた。
再び間が空き、そして、私の前から四分の一マイルも離れていない場所で、ユニオンジャックが森の上で空にはためいているのが見えた。
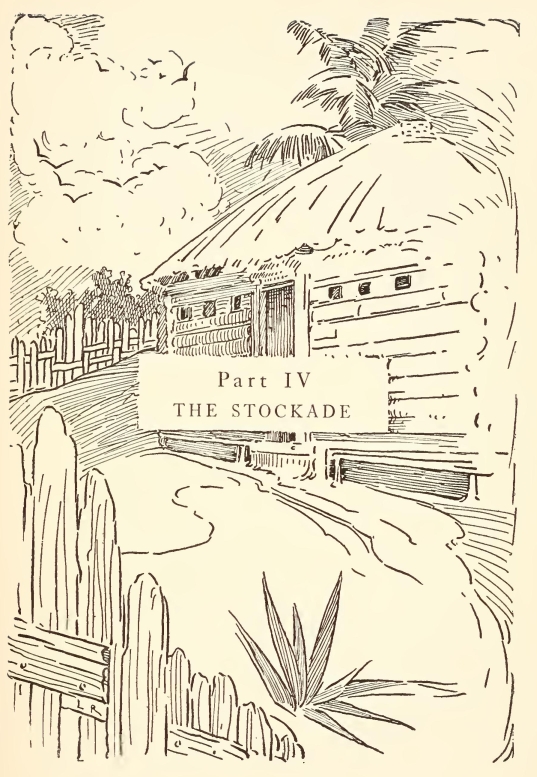
第四部 砦
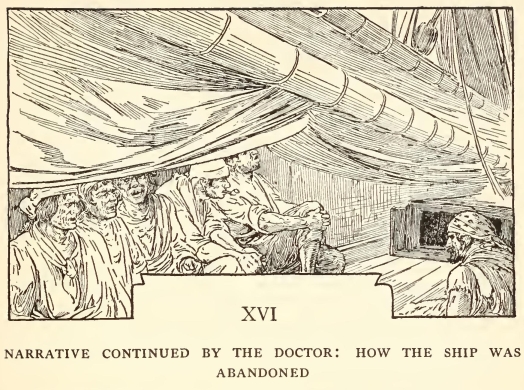
第十六章 語り手はふたたび博士へ――船を放棄するまで
ヒスパニオラ号から二艘のボートが上陸したのは、一時半――船乗りの言葉で言えば三点鐘の頃だった。船長、郷士、そして私は、船室で事態を協議していた。もしそよ風一つでも吹いていれば、我々は船に残された六人の反逆者に襲いかかり、錨綱を切り、海へと逃げ出していただろう。しかし、風はなかった。そして、我々の無力さに追い打ちをかけるように、ハンターが、ジム・ホーキンズがボートに忍び込み、他の者たちと共に上陸してしまったという知らせを持って降りてきた。
我々はジム・ホーキンズを疑うことなど思いもよらなかったが、彼の身の安全を案じた。男たちのあの気性では、あの少年と再び会えるかどうかは五分五分に思えた。我々は甲板に駆け上がった。継ぎ目ではピッチが煮え立ち、その場のいやな悪臭に吐き気を催した。もし熱病と赤痢の匂いを嗅いだ者がいるとすれば、それはこの忌まわしい停泊地でのことだった。六人の悪党は、船首楼の帆の下で不平を言いながら座っていた。陸では、ギグボートがしっかりと係留され、それぞれに一人の男が座っているのが見えた。川が流れ込むすぐそばだった。そのうちの一人が「リリバレロ」を口笛で吹いていた。
待ち時間は神経をすり減らすものだった。そこで、ハンターと私がジョリーボートで上陸し、情報を探ってくることになった。
ギグ船は右舷に傾いていたが、ハンターと私はまっすぐ、海図に記された砦の方向へと漕ぎ進んだ。ボートの見張りをしていた二人の男は、我々の出現に慌てふためいているようだった。「リリバレロ」の歌がぴたりと止み、二人がどうすべきか話し合っているのが見えた。もし彼らがシルバーに報告に行っていたら、事態は全く違った展開になっていただろう。だが、彼らは命令を受けていたのだろう、もとの場所に静かに座り込み、「リリバレロ」を再び口ずさむことに決めたようだ。
海岸線がわずかに湾曲していたので、私はその陰に隠れるように舵を取った。上陸する前にはもう、ギグ船の姿は見えなくなっていた。私はボートから飛び降りると、暑さしのぎに大きな絹のハンカチを帽子の下に敷き、安全のためにいつでも撃てるようにした二丁のピストルを手に、走らんばかりの速さで進んだ。
百ヤードも行かないうちに、私は砦にたどり着いた。
それはこういうものだった。小高い丘のほぼ頂上から、澄んだ水の泉が湧き出ている。その丘の上に、泉を囲むようにして、いざとなれば四十人は収容できそうな頑丈な丸太小屋が建てられており、両側にはマスケット銃を撃つための銃眼が設けられていた。その周囲は広く切り開かれており、さらに高さ六フィートの柵で囲まれている。柵には扉も出入り口もなく、時間と労力をかけなければ壊すのは難しく、それでいて攻め手を隠すにはあまりに隙間だらけだった。丸太小屋にいる者たちは、あらゆる点で有利だった。安全な場所に身を置き、ヤマウズラでも撃つように敵を狙い撃ちにできるのだ。必要なのは、十分な見張りと食料だけ。完全な奇襲でも受けない限り、連隊相手でも持ちこたえられそうだった。
私が特に心惹かれたのは、その泉だった。ヒスパニオラ号の船室も、武器弾薬、食料、極上のワインが豊富にあり、十分に良い拠点ではあったが、一つだけ見落としていたことがあった――水がないのだ。そんなことを考えていると、島中に響き渡る、男の断末魔の叫び声が聞こえた。私は凄惨な死に慣れていないわけではない――カンバーランド公爵殿下にお仕えし、フォントノワの戦いで手傷を負ったこともある――だが、自分の脈が跳ね上がったのは分かった。「ジム・ホーキンズがやられた」と、私はまずそう思った。
元兵士であったことは強みだが、医者であることはそれ以上の強みだ。我々の仕事に、ぐずぐずしている時間はない。私は即座に決断し、一刻の猶予もなく岸へと引き返し、ジョリーボートに飛び乗った。
幸運なことに、ハンターは腕のいい漕ぎ手だった。我々は水しぶきを上げてボートを飛ばし、あっという間にスクーナー船の横に着け、私は船に乗り移った。
船内は、案の定、誰もが動揺していた。郷士は、我々をこんな危険に巻き込んでしまったことを思い、真っ青になって座り込んでいた。何とも善良な御仁だ! そして前甲板の船員六人のうちの一人も、似たような有様だった。
「あそこにいる男は」とスモレット船長が彼を指して言った。「この手の仕事には不慣れでしてな。あの叫び声を聞いて、卒倒しかけたんですよ、先生。もう一押しあれば、我々の仲間入りでしょうな。」
私は船長に計画を話し、二人でその実行の段取りを決めた。
我々は老レッドルースを船室と船首楼の間の通路に配置し、装填済みのマスケット銃を三、四丁と、身を守るためのマットレスを渡した。ハンターはボートを船尾の窓の下に回し、ジョイスと私は火薬の缶、マスケット銃、乾パンの袋、豚肉の樽、コニャックの大樽、そしてかけがえのない私の薬箱を積み込み始めた。
その間、郷士と船長は甲板に残り、船長は乗組員の筆頭格である操舵手に声をかけた。
「ハンズ君」と彼は言った。「ここにいる我々二人は、それぞれ二丁のピストルを持っている。お前たち六人のうち誰か一人でも、何らかの合図を送るような真似をすれば、その男は死ぬことになるぞ。」
彼らは大いに虚を突かれたようだった。しばらく相談した後、全員が船首の昇降口からどやどやと降りていった。おそらく背後から我々を襲うつもりだったのだろう。だが、梁だらけの通路でレッドルースが待ち構えているのを見ると、すぐさま踵を返し、一人の頭が再び甲板にひょっこりと現れた。
「下がれ、犬め!」と船長が叫んだ。
するとその頭はまた引っ込み、それきり、この臆病な六人の船員たちの音沙汰はしばらくの間途絶えた。

この時までに、我々は手当たり次第に物を放り込み、ジョリーボートに積めるだけ積んでいた。ジョイスと私は船尾の窓から乗り出し、オールが許す限りの速さで再び岸を目指した。
この二度目の航海は、岸の見張りの連中をすっかり警戒させてしまった。「リリバレロ」はまたもや止み、小さな岬の陰に隠れて彼らの姿が見えなくなる直前、一人が岸に駆け上がって姿を消したのが見えた。私は計画を変更して彼らのボートを破壊してやろうかと一瞬考えたが、シルバーたちが近くにいるかもしれず、欲張りすぎたせいで全てを失う恐れがあった。
我々はすぐに前回と同じ場所に上陸し、砦に物資を運び込み始めた。最初の運搬は三人全員で、重い荷物を抱え、柵の上に放り込んだ。そしてジョイスに見張りを任せ――一人とはいえ、マスケット銃が六丁もある――ハンターと私はジョリーボートに戻り、再び荷を担いだ。こうして息つく暇もなく作業を続け、全ての積み荷を運び終えると、二人の従僕は砦で持ち場につき、私は全力でスカルを漕いでヒスパニオラ号へと戻った。
二度もボートで荷を運ぶという危険を冒したことは、実際以上に大胆に見えるかもしれない。もちろん、数の上では敵が有利だったが、武器の点では我々が勝っていた。岸にいる男たちは誰もマスケット銃を持っておらず、ピストルの射程内に入る前に、少なくとも六人は仕留められるだろうと我々は高をくくっていたのだ。
郷士は船尾の窓で私を待っていた。先ほどの青ざめた様子はすっかり消え失せている。彼はもやい綱を受け取ってしっかりと結び、我々は命がけでボートに荷を積み込み始めた。豚肉、火薬、乾パンが積み荷で、郷士と私、レッドルースと船長には、それぞれマスケット銃一丁とカトラス一本だけ。残りの武器と火薬は、水深二尋半の海に投げ捨てた。すると、澄んだ砂の海底で、太陽の光を浴びて輝く鋼がはるか下に見えた。
この頃には潮が引き始めており、船は錨を中心に向きを変えつつあった。二隻のギグ船の方向から、かすかに叫び声が聞こえてくる。東側にいるジョイスとハンターの無事を確認できて安心したものの、我々も出発すべき時が来たと警告するものでもあった。
レッドルースは通路の持ち場から下がり、ボートに飛び乗った。我々はボートを船尾の張り出し部分に回し、スモレット船長が乗りやすいようにした。
「さて、諸君」と彼は言った。「聞こえるか?」
船首楼からは返事がなかった。
「エイブラハム・グレイ、お前に言っているんだ。」
それでも返事はない。
「グレイ」スモレット氏は少し声を張り上げた。「私はこの船を去る。お前にも船長に従うよう命じる。お前が根は善人であることは知っているし、お前たちの誰一人として、彼らが言うほど悪い人間ではないだろう。私の手には時計がある。三十秒やる。その間にこちらへ来い。」
しばしの間があった。
「来い、若いの」船長は続けた。「そうぐずぐずするな。この立派な紳士方と私の命を、一秒一秒危険に晒しているのだぞ。」
突然、もみ合う音と殴打音が聞こえ、頬にナイフで切りつけられたエイブラハム・グレイが飛び出してきた。そして、笛の音に駆け寄る犬のように、船長のもとへ走ってきた。
「お供します、船長」と彼は言った。
次の瞬間、彼と船長は我々のボートに飛び乗り、我々は船を押し出して漕ぎ出した。
我々は船から離れたが、まだ砦にはたどり着いていない。

第十七章 再び博士の語り――ジョリーボート最後の航海
この五度目の航海は、それまでのどれとも全く違っていた。第一に、我々が乗っていた薬壺のように小さなボートは、ひどく荷を積みすぎていた。大人の男が五人、しかもそのうち三人――トレローニー、レッドルース、そして船長――は身長が六フィートを超える。これだけでも既に定員超過だ。それに加えて火薬、豚肉、乾パンの袋。船べりは船尾で水面すれすれになっていた。百ヤードも進まないうちに、我々は何度か水をかぶり、私のズボンと上着の裾はびしょ濡れになっていた。
船長は我々にボートの釣り合いを取らせ、少しは安定して進めるようになった。それでも、我々は息をすることも憚られた。
第二に、今や引き潮が始まっていた。強いさざ波を立てた潮流が、湾内を西に流れ、そして朝方我々が入ってきた海峡を通って南へ、外洋へと向かっている。さざ波でさえ、この過積載の小舟には危険だったが、最悪なのは、我々が本来の進路から押し流され、岬の陰にあるはずの上陸地点から遠ざけられてしまったことだ。流れに身を任せれば、ギグ船のそばに上陸することになり、そこにはいつ海賊が現れてもおかしくなかった。
「船首を砦に向けられません、船長」私は船長に言った。彼とレッドルースという元気な二人がオールを漕ぎ、私は舵を取っていた。「潮に流されてしまいます。もう少し強く漕げませんか?」
「ボートが沈みますよ」と彼は言った。「風上に舵を取ってください、先生――流れに打ち勝つまで、そのままの針路で。」
試してみると、船首を真東、つまり本来進むべき方向とほぼ直角に向けるまで、潮が我々を西へ西へと押し流し続けることが分かった。
「このままではとても上陸できません」と私は言った。
「それが唯一取れる針路なら、そうするしかありません」と船長は答えた。「上流に向かい続けなければ。お分かりですか、先生」彼は続けた。「一度でも上陸地点の風下に流されてしまえば、どこに上陸できるか分かったものではありませんし、ギグ船に乗り込まれる危険もあります。一方、このまま進めば、いずれ流れは緩むでしょう。そうなれば、岸に沿って引き返すことができます。」
「流れがもう弱まってきましたよ、旦那」と船首に座っていたグレイが言った。「少し針路を緩めても大丈夫です。」
「ありがとう」私は何事もなかったかのように言った。我々は皆、彼を仲間の一人として扱うことを、暗黙のうちに決めていたからだ。
突然、船長が再び口を開いた。その声は少し変わっているように思えた。
「大砲だ!」と彼は言った。
「それは考えていました」と私は言った。船長が砦への砲撃を懸念しているのだと確信していたからだ。「彼らが大砲を陸揚げすることなどできっこありませんし、もしできたとしても、森の中を引いてくることなど不可能です。」
「船尾を見てください、先生」と船長は答えた。
我々は長九ポンド砲のことをすっかり忘れていた。そして、恐ろしいことに、そこには五人の悪党どもが群がり、船を覆っていた頑丈な防水帆布――彼らが言うところの「上着」――を剥がしているではないか。それだけではない。その瞬間、大砲用の砲弾と火薬が船に残されたままであること、そして斧の一振りでそれが全て悪党どもの手に渡ってしまうことに思い至った。
「イスラエルはフリントの砲手でした」グレイがかすれた声で言った。
我々は危険を顧みず、ボートの船首をまっすぐ上陸地点に向けた。この時までに、我々は潮流の主流からかなり外れていたので、どうしてもゆっくりと漕がざるを得ない速度でも操船が可能で、船首を目標に固定することができた。だが最悪なことに、今取っているこの針路では、船尾ではなく船の側面をヒスパニオラ号に向けることになり、納屋の扉のような格好の的を晒すことになった。
あのブランデーで赤ら顔の悪党、イスラエル・ハンズが、甲板に砲弾をどすんと置くのが、音でも目でも分かった。
「一番の射撃の名手は誰かね?」と船長が尋ねた。
「トレローニー郷士です。ずば抜けています」と私は答えた。
「トレローニー郷士、あの男たちのうち一人を仕留めていただけませんか? できればハンズを」と船長は言った。
トレローニーは鋼のように冷静だった。彼は銃の火皿を確かめた。
「さあ」船長が叫んだ。「銃は慎重に、旦那。でないとボートが沈みますぞ。郷士が狙いを定める時は、全員で船のバランスを取るんだ。」
郷士が銃を構えると、漕ぐのをやめ、我々は反対側に身を乗り出してバランスを取った。全てが実に巧みに行われ、一滴の水もかぶらなかった。
その時までに、彼らは大砲を旋回台でぐるりと回しており、装填棒を持って砲口にいたハンズが、結果として最も無防備な位置にいた。しかし、我々に運はなかった。トレローニーが発砲したまさにその時、ハンズが身をかがめたため、弾は彼の頭上をかすめ、倒れたのは他の四人のうちの一人だった。
彼が上げた叫び声は、船上の仲間たちだけでなく、岸からの大勢の声にもこだまされた。そちらに目をやると、他の海賊たちが木々の間からぞろぞろと現れ、自分たちのボートに乗り込んでいるのが見えた。
「ギグ船が来ます、船長」と私は言った。
「ならば漕げ」船長が叫んだ。「今さら沈むのを気にしてはいられん。上陸できなければ、万事休すだ。」
「ギグ船の一隻だけに人が乗り込んでいます」私は付け加えた。「もう一隻の乗組員は、おそらく岸を回って我々の退路を断つつもりでしょう。」
「骨が折れるでしょうな」と船長は答えた。「陸に上がった船乗りというやつですよ。気になるのは彼らではなく、砲弾の方だ。カーペット・ボウルズ[訳注:室内で行うボウリングのようなゲーム]ですよ! 奥方の侍女でも外しようがない。郷士、火縄が見えたら教えてください。漕ぐのを止めますから。」
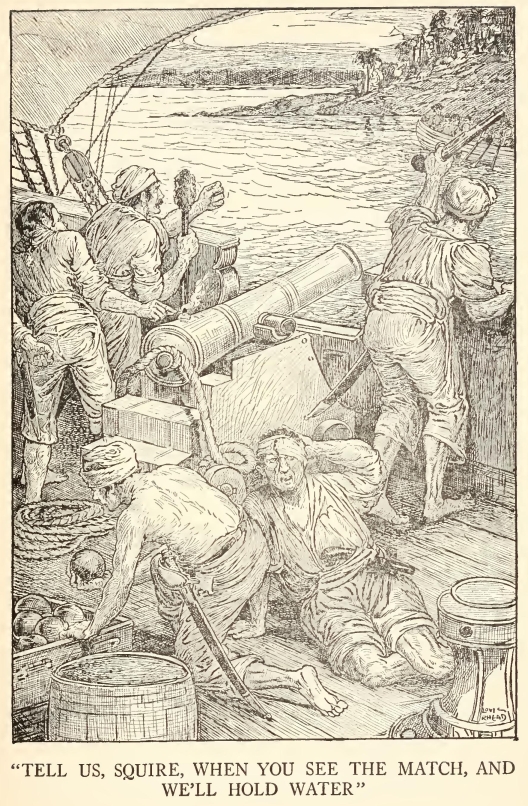
その間、我々は過積載のボートにしてはかなりの速さで進んでおり、その過程でかぶった水もわずかだった。今や岸は間近だ。三十か四十回も漕げば、浜に乗り上げられるだろう。引き潮で、木々の茂る下に狭い砂浜が現れていたからだ。ギグ船はもはや恐れるに足りない。小さな岬が既にその姿を我々の視界から隠していた。あれほど我々を苦しめた引き潮が、今度は味方となり、追っ手を遅らせていた。唯一の危険源は、大砲だった。
「できることなら」と船長は言った。「止まって、もう一人仕留めたいところだが。」
しかし、彼らが何ものにも邪魔されずに砲撃するつもりであることは明らかだった。倒れた仲間には目もくれていない。彼はまだ死んではおらず、這って逃げようとしているのが見えた。
「構え!」と郷士が叫んだ。
「待て!」と船長がこだまのように素早く叫んだ。
そして彼とレッドルースが力いっぱい逆さに漕ぐと、船尾がまるごと水中に沈んだ。発射音はまさにその瞬間に轟いた。これがジムが聞いた最初の音で、郷士の銃声は彼には届かなかったのだ。砲弾がどこを通過したのか、我々の誰も正確には分からなかったが、おそらく頭上をかすめ、その風圧が我々の災厄の一因となったのだろうと思う。
ともかく、ボートは船尾から、水深三フィートのところで実に静かに沈んでいき、船長と私を、互いに向き合ったまま、足で立たせた。他の三人は頭から完全に水に飛び込み、ずぶ濡れになって泡を吹きながら浮かんできた。
ここまでは大した損害はなかった。命を落とした者はおらず、安全に歩いて岸に上がることができた。しかし、物資は全て水底に沈み、さらに悪いことに、五丁の銃のうち、使える状態なのは二丁だけだった。私のは、とっさに膝からひったくり、一種の本能で頭上に掲げていた。船長はと言えば、弾帯で肩から提げ、賢明にも、撃鉄を上にして運んでいた。他の三丁はボートと共に沈んだのだ。
我々の不安をさらに募らせたのは、岸辺の森から既に人の声が近づいてくるのが聞こえたことだ。半ば不自由なこの状態で砦への道を断たれる危険だけでなく、もしハンターとジョイスが六人ほどの敵に襲われた場合、彼らに冷静に持ちこたえるだけの分別と行動力があるだろうかという懸念もあった。ハンターは頼りになると分かっていたが、ジョイスは未知数だった――従僕として、あるいは服の埃を払うには、陽気で礼儀正しい男だが、戦士には全く向いていなかった。
そんな思いを胸に、我々はできる限り速く、浅瀬を歩いて岸に上がった。哀れなジョリーボートと、火薬と食料の優に半分を後に残して。
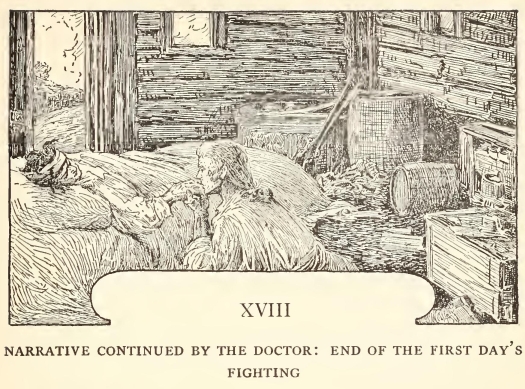
第十八章 再び博士の語り――初日の戦いの終わり
我々は砦との間を隔てる林を全速力で駆け抜けたが、一歩進むごとに海賊たちの声が近づいてくる。やがて、彼らが走る足音や、茂みを突っ切る際に枝が折れる音も聞こえてきた。
本格的な一戦になりそうだと悟り、私は銃の火皿を確かめた。
「船長」と私は言った。「トレローニーは射撃の名人です。あなたの銃を彼に。彼自身の銃は使い物になりません。」
二人は銃を交換した。トレローニーは、この騒動が始まってからずっとそうであったように、沈黙し冷静なまま、一瞬立ち止まって銃が使える状態か確かめた。同時に、グレイが丸腰であることに気づいた私は、自分のカトラスを彼に手渡した。彼が手に唾を吐き、眉をひそめ、刃を風切らせて唸らせるのを見て、我々全員の心は勇気づけられた。この新しい仲間が頼りになる男であることは、その全身から明らかだった。
さらに四十歩進むと、森の端に出て、目の前に砦が見えた。我々が柵の南側の中央あたりにたどり着いたのとほぼ同時に、七人の反逆者――甲板長のジョブ・アンダーソンを先頭に――が、鬨の声を上げながら南西の角に現れた。
彼らは虚を突かれたように立ち止まった。そして彼らが体勢を立て直す前に、郷士と私だけでなく、砦にいたハンターとジョイスも発砲する時間を得た。四発の銃声はやや散発的な一斉射撃となったが、それで十分だった。敵の一人が現に倒れ、残りはためらうことなく踵を返し、木々の間に飛び込んでいった。
再装填した後、我々は柵の外側を歩き、倒れた敵の様子を見に行った。彼は心臓を撃ち抜かれ、完全に絶命していた。
我々がこの幸運を喜び始めたまさにその時、茂みでピストルが炸裂し、弾が私の耳元をかすめ、哀れなトム・レッドルースがよろめいて地面に倒れ込んだ。郷士も私も応射したが、狙うべき的がなかったので、おそらく火薬を無駄にしただけだろう。それから再び装填し、哀れなトムに注意を向けた。
船長とグレイが既に彼を診ていたが、一目見ただけで、もう手遅れだと分かった。
我々の素早い応射が、反逆者たちを再び追い散らしたのだろう。それ以上の妨害を受けることなく、我々は哀れな老狩猟番を柵の上に引き上げ、うめき声を上げ、血を流しながら丸太小屋の中へ運び込むことができた。
この哀れな老人は、我々の苦難が始まってから今まで、驚きも、不平も、恐怖も、あるいは甘んじて受け入れる言葉さえも、一言も口にしなかった。今、丸太小屋に横たえられ、死を待つ身となっても。彼は通路でマットレスの陰に、トロイアの勇士のように横たわっていた。あらゆる命令に、黙って、粘り強く、そして忠実に従った。我々一行の中では二十歳も年長だった。そして今、無口で、年老いた、忠実なこの従僕が、死んでいくのだ。
郷士は彼のそばに膝まずき、その手に口づけをして、子供のように泣いた。
「おれは、死ぬんでやすか、先生?」と彼は尋ねた。
「トム」私は言った。「お前は家に帰るんだ。」
「その前に、あの連中に一発お見舞いしてやりたかったでやす」と彼は答えた。
「トム」と郷士は言った。「私を許してくれると言ってくれ、頼む。」
「おらが旦那様にそんなことを言うのは、無礼というものでは?」それが答えだった。「ですが、まあ、そういうことなら。アーメン!」
しばしの沈黙の後、誰か祈りの言葉を読んでくれないか、と彼は言った。「それが習わしでして」と彼は申し訳なさそうに付け加えた。そして間もなく、それ以上一言も発することなく、彼は息を引き取った。
その間、船長は――胸やポケットが不思議なほど膨らんでいるのに私は気づいていたが――実に様々な品々を取り出した。英国旗、聖書、丈夫なロープ一巻き、ペン、インク、航海日誌、そして数ポンドのタバコ。彼は敷地内に、伐採され枝を払われた長いモミの木が横たわっているのを見つけ、ハンターの助けを借りて、丸太小屋の角、材木が交差して隅になっている場所にそれを立てた。そして屋根に登ると、自らの手で旗を掲げたのだった。
これで彼は大いに安堵したようだった。丸太小屋に戻ると、まるで他のことは何も存在しないかのように、物資の数を数え始めた。しかし、それでもトムの臨終には気を配っており、全てが終わるとすぐに、別の旗を持ってきて、敬虔な手つきでその亡骸にかけた。
「気を落とさないでください、旦那」彼は郷士の手を握りながら言った。「彼は立派に逝きました。船長と船主への忠義のために撃たれた男に、案ずることは何もありません。神学的には正しくないかもしれませんが、事実です。」
それから彼は私を脇へ引いた。
「ライブシー先生」と彼は言った。「あなたと郷士殿は、救援の船が来るまで何週間かかるとお考えですかな?」
私は、それは週ではなく月の問題だと告げた。八月の終わりまでに我々が戻らなければ、ブランディ氏が捜索隊を送ることになっているが、それより早くも遅くもない、と。「ご自身で計算できますよ」私は言った。
「ええ、まあ」船長は頭を掻きながら答えた。「神の御恵みを大いに考慮に入れたとしても、先生、我々はかなり切り詰めた状況にありますな。」
「どういう意味です?」と私は尋ねた。
「残念なのは、二度目の積み荷を失ったことです、先生。そういう意味ですよ」と船長は答えた。「火薬と弾は、まあ何とかなるでしょう。しかし食料が少ない。非常に少ない――あまりに少なくて、ライブシー先生、余計な口が一つ減ったのは、むしろ好都合だったかもしれません。」
そして彼は、旗の下の亡骸を指さした。
まさにその時、轟音と風切り音とともに、砲弾が丸太小屋の屋根のはるか上を通過し、我々のずっと向こうの森にどすんと落ちた。
「おお!」と船長は言った。「撃ちまくれ! お前たちの火薬はもう残り少ないだろうに、諸君。」
二度目の試みでは、狙いはより正確になり、弾は柵の内側に落下し、砂煙を舞い上がらせたが、それ以上の被害はなかった。
「船長」と郷士が言った。「小屋は船からは全く見えないはずだ。彼らが狙っているのは旗に違いない。降ろした方が賢明ではないかね?」
「我が旗を降ろせだと!」船長は叫んだ。「いや、旦那、私はやらん」と彼が言った途端、我々全員が彼に同意したように思う。それは単に、屈強な船乗りらしい気概の表れというだけでなく、我々の敵に、彼らの砲撃など歯牙にもかけないということを示す、優れた戦術でもあったからだ。
夕暮れの間中、彼らは砲撃を続けた。弾は次々と頭上を越え、手前に落ち、あるいは柵の中の砂を蹴り上げたが、非常に高い角度で撃たなければならないため、弾は勢いを失って落下し、柔らかい砂の中に埋もれてしまった。跳弾を恐れる必要はなく、一発が丸太小屋の屋根を突き破り、床を抜けていったこともあったが、我々はすぐにその種の悪ふざけにも慣れ、クリケットの試合ほどにも気にしなくなった。
「この一件には一つ良いことがある」と船長は述べた。「我々の前の森は、おそらく敵がいないだろう。潮もかなり引いた。我々の物資も現れているはずだ。豚肉を取りに行く志願者はいないか。」
グレイとハンターが真っ先に名乗り出た。十分に武装して、彼らはこっそりと砦を出て行ったが、それは無駄な任務であることが判明した。反逆者たちは我々が想像する以上に大胆だったか、あるいはイスラエルの砲術を信頼しきっていたか。四、五人の男が我々の物資を運び出し、近くに停泊しているギグ船の一隻まで浅瀬を歩いて運んでいたのだ。そのギグ船は、流れに逆らって船体を安定させるために、オールを軽く漕いでいた。船尾にはシルバーが座って指揮を執っており、部下は全員、どこか秘密の武器庫から持ち出したマスケット銃で武装していた。
船長は航海日誌に向かい、次のように書き始めた。
アレクサンダー・スモレット、船長。デイヴィッド・ライブシー、船医。エイブラハム・グレイ、大工助手。ジョン・トレローニー、船主。ジョン・ハンターおよびリチャード・ジョイス、船主の従僕、陸の人間――以上、船の乗組員のうち忠誠を尽くした者の全て――は、切り詰めて十日分の食料と共に、本日上陸し、宝島にある丸太小屋に英国旗を掲げた。トーマス・レッドルース、船主の従僕、陸の人間は、反逆者に撃たれ死亡。ジェームズ・ホーキンズ、給仕――
そしてその時、私は哀れなジム・ホーキンズの運命を案じていた。
陸側から呼び声がした。
「誰かが我々を呼んでいます」見張りをしていたハンターが言った。
「博士! 郷士! 船長! おい、ハンター、お前か?」という叫び声が聞こえた。
そして私が戸口に駆けつけると、ちょうどジム・ホーキンズが、無事な姿で、柵を乗り越えてくるところだった。
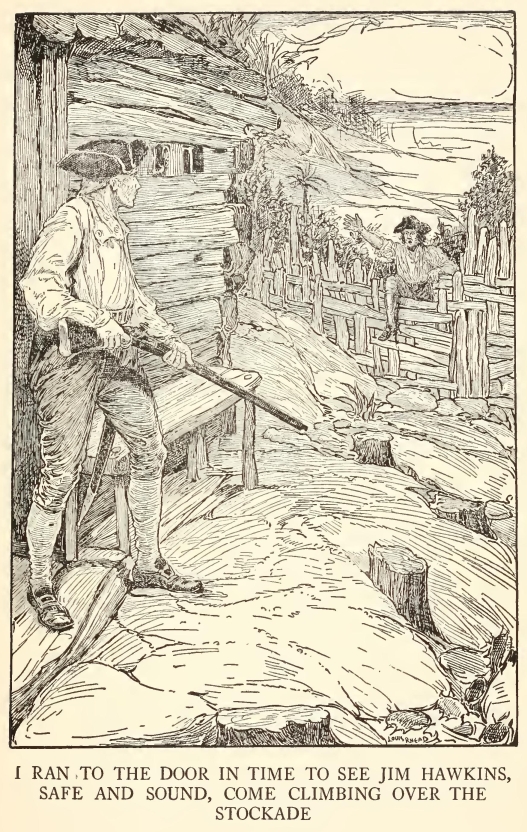
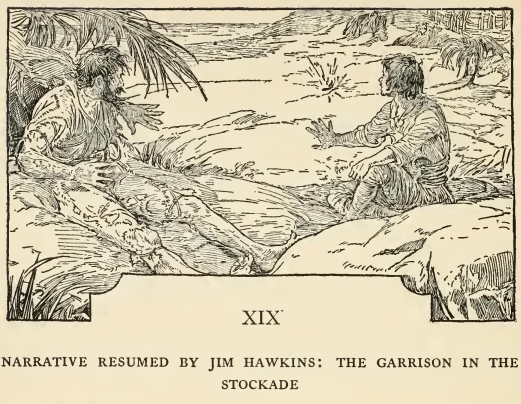
第十九章 再びジム・ホーキンズの語り――砦の守備隊
ベン・ガンは旗を見るやいなや立ち止まり、僕の腕をつかんで座り込んだ。
「ようし」と彼は言った。「ありゃあ、あんたの仲間だ。間違いねえ。」
「反逆者たちの可能性の方がずっと高いよ」と僕は答えた。
「まさか!」彼は叫んだ。「おい、こんな場所によ、運試しの紳士方[訳注:海賊のこと]以外に立ち寄る奴がいるもんかい。シルバーならドクロの旗を揚げるに決まってる。そいつは疑う余地もねえ。いや、ありゃあんたの仲間だ。いざこざもあったようだが、どうやらあんたの仲間が勝ったらしいな。で、フリントが何年も何年も前に建てた、あの古い砦に立てこもってるってわけだ。ああ、フリントはたいした頭の持ち主だった! ラム酒を除けば、あいつに敵う奴はいなかった。何も怖がらねえ男だった、あいつはな。ただシルバーだけは――シルバーは、そりゃあ紳士的だったがな。」
「うん」と僕は言った。「そうかもしれない。だとしたら、なおさら急いで仲間と合流しなくちゃ。」
「いや、相棒」とベンは返した。「あんたはだめだ。あんたは良い子だ、おれの目に狂いがなけりゃな。だが、しょせんは子供だ。さて、このベン・ガンは抜け目がない。ラム酒を飲んだって、あんたが行こうとしてる場所には行かねえ――ラム酒でもだめだ、あんたの生まれながらの紳士に会って、その名誉にかけて約束してもらうまではな。それから、おれの言葉を忘れちゃいけねえ。『とてつもなく(そう言うんだ)、とてつもなく信用できる』――そう言って、相手をつねるんだ。」
そして彼は、同じように利口ぶった様子で、三度目に僕をつねった。
「それで、ベン・ガンが必要になったら、どこに行けば会えるか分かるな、ジム。今日あんたがおれを見つけた、まさにあの場所だ。来る奴は、手に何か白いものを持って、一人で来なけりゃならねえ。ああ! それからこう言うんだ。『ベン・ガンには』ってな、『彼なりの理由がある』って。」
「うん」と僕は言った。「分かったと思う。君には何か提案があって、郷士か博士に会いたいんだね。それで、僕が君を見つけた場所に行けばいい。それで全部?」
「それで、いつかって? あんたはそう言うんだ」と彼は付け加えた。「そりゃあ、正午の観測から六点鐘[訳注:午後三時]くらいまでだな。」
「分かった」と僕は言った。「じゃあ、もう行ってもいい?」
「忘れねえだろうな?」彼は心配そうに尋ねた。「『とてつもなく』、それから『彼なりの理由がある』、そう言うんだ。『彼なりの理由がある』、それが肝心なところだ。男と男の約束としてな。よし、それじゃあ」――まだ僕を掴んだまま――「もう行っていいぞ、ジム。なあ、ジム、もしシルバーに会ったとしても、ベン・ガンのことを売ったりしねえよな? 無理やり聞き出そうとしても、口を割ったりしねえよな? しない、って言うんだ。それから、もしあの海賊どもが陸で野営したら、ジム、朝には未亡人ができるってこと以外に何がある?」
ここで彼の言葉は大きな発射音に遮られ、砲弾が木々をなぎ倒しながら飛んできて、僕たちが話していた場所から百ヤードと離れていない砂地に突き刺さった。次の瞬間、僕たちはそれぞれ別の方向へ一目散に逃げ出していた。
それから一時間ほど、頻繁な砲声が島を揺るがし、砲弾が森を破壊し続けた。僕は隠れ場所から隠れ場所へと移動したが、いつもこの恐ろしい飛来物に追われているように感じられた。しかし、砲撃が終わる頃には、砲弾が最も頻繁に落下する砦の方向へはまだ近づく気にはなれなかったものの、いくらか気力を取り戻し、東へ大きく迂回してから、岸辺の木々の間を這うように進んだ。
太陽は沈んだばかりで、海風が森をざわめかせ、停泊地の灰色の水面を波立たせていた。潮も遠くまで引いて、広大な砂地が姿を現している。日中の暑さの後で、その空気は上着を通して僕の体を冷やした。
ヒスパニオラ号は錨を下ろした場所にまだ停泊していたが、案の定、そのピーク[訳注:後部マストの帆桁の先端]からはドクロの旗――海賊の黒い旗――が翻っていた。僕が見ていると、また赤い閃光が走り、こだまを響かせる発射音が鳴り、もう一発の砲弾が空を切って飛んできた。それが砲撃の最後だった。
僕はしばらく横たわったまま、攻撃の後の慌ただしい様子を眺めていた。砦の近くの浜辺で、男たちが斧で何かを壊している――後で分かったことだが、それは哀れなジョリーボートだった。遠く、川の河口近くでは、木々の間に大きな焚き火が燃え盛っており、その地点と船との間を一隻のギグ船が行き来していた。あれほど陰鬱だった男たちが、子供のようにはしゃぎながらオールを漕いでいる。だが、その声にはラム酒の響きがあった。
やがて、砦の方へ戻ってもいいだろうと僕は思った。僕は停泊地を東に囲む、低く砂地の多い岬のかなり下の方にいた。この岬は、満潮時には骸骨島と陸続きになる。そして今、立ち上がると、岬のさらに下の方、低い茂みの中から突き出ている、孤立した岩が見えた。それはかなり高く、際立って白い色をしていた。これがベン・ガンが話していた白い岩かもしれず、いつかボートが必要になった時に、どこを探せばいいか分かっておこうと思った。
それから僕は森の中を迂回し、砦の裏手、つまり岸側に回り込み、すぐに忠実な仲間たちに温かく迎えられた。
僕はすぐに自分の話を終え、周りを見回し始めた。丸太小屋は、屋根も壁も床も、角材にしていない松の幹でできていた。床は所々、砂の表面から一フィートか一フィート半ほど高くなっている。戸口にはポーチがあり、その下から小さな泉が、少し変わった形の人造の泉水枡に湧き出ていた――それは他でもない、船で使う大きな鉄の釜で、底を打ち抜かれ、船長の言うところの「吃水線まで」砂に埋められていた。
小屋の骨組み以外にはほとんど何も残されていなかったが、一角には炉として石板が敷かれ、火を入れるための古びて錆びた鉄の籠が置かれていた。
小高い丘の斜面と砦の内側は、小屋を建てるために木が伐採されており、切り株を見れば、どれほど見事で背の高い木立が失われたかが分かった。木が取り除かれた後、土壌のほとんどは洗い流されるか、吹き寄せられた砂に埋もれてしまっていた。ただ、釜から流れ出る小川のそばだけは、厚い苔の層と、いくつかのシダや小さな這う茂みが、砂の中でまだ緑を保っていた。砦のすぐ周り――防御には近すぎると彼らは言った――には、まだ高く密集した森が茂っていた。陸側は全てモミの木だったが、海に向かう側には、多くのカシの木が混じっていた。
先ほど話した冷たい夕風が、この粗末な建物のあらゆる隙間からヒューヒューと吹き込み、床に絶え間なく細かい砂を降らせた。目には砂、歯には砂、夕食にも砂が入り、釜の底の泉では、まるで沸騰し始めた粥のように砂が踊っていた。煙突は屋根に開けられた四角い穴だったが、外に出ていく煙はごく一部で、残りは家の中に渦巻き、僕たちは咳き込み、涙を流し続けた。
それに加えて、新入りのグレイは、反逆者たちから離反する際に負った切り傷のために顔に包帯を巻いており、そして哀れな老トム・レッドルースは、まだ埋葬されずに、壁際に硬直して横たわり、ユニオンジャックに覆われていた。
もし何もしないで座っていることを許されていたら、僕たちは皆、憂鬱に沈んでいたことだろう。だが、スモレット船長は決してそのような男ではなかった。全員が彼の前に呼び出され、見張りの当番に分けられた。博士とグレイと僕が一方、郷士とハンターとジョイスがもう一方だ。皆疲れきっていたが、二人が薪集めに送り出され、さらに二人がレッドルースの墓を掘るように命じられた。博士は料理番に任命され、僕は戸口の歩哨に立ち、船長自身はあちこち動き回り、僕たちの士気を高め、必要なところではどこでも手を貸した。
時々、博士が戸口に来て、少し外の空気を吸い、煙でほとんど燻り出されそうになっていた目を休めた。そしてそのたびに、僕に一言声をかけた。
「あのスモレットという男は」と彼は一度言った。「私より優れた男だ。私がそう言うからには、大したことなのだよ、ジム。」
別の時には、やって来てしばらく黙っていた。それから首をかしげて、僕を見た。
「このベン・ガンというのは、人間かね?」と彼は尋ねた。
「分かりません、先生」と僕は言った。「正気かどうかも、あまり自信がありません。」
「その点に疑いがあるなら、彼は正気だよ」と博士は答えた。「無人島で三年間も爪を噛んで過ごしてきた男に、君や私と同じように正気に見えることを期待する方が無理だ、ジム。それは人間の本性に反する。彼が好物だと言っていたのは、チーズだったかね?」
「はい、先生、チーズです」と僕は答えた。
「さて、ジム」と彼は言った。「食べ物に凝ることの良いところを見るがいい。私の嗅ぎタバコ入れを見たことがあるだろう? そして私が嗅ぎタバコを吸うのを見たことはないはずだ。その理由は、この嗅ぎタバコ入れの中に、パルメザンチーズ――イタリアで作られる、非常に栄養価の高いチーズ――のかけらを入れているからだ。よし、これはベン・ガンのものだ!」
夕食の前に、僕たちは老トムを砂の中に埋葬し、しばらくの間、風の中で無帽のまま彼の周りに佇んだ。薪はかなり集まっていたが、船長の好みには足りなかったようで、彼はそれを見て首を振り、「明日はもっときびきびとやらねばならん」と言った。それから、豚肉を食べ、それぞれが濃いブランデー・グロッグを一杯飲むと、三人の指導者たちは隅に集まり、今後の見通しについて話し合った。
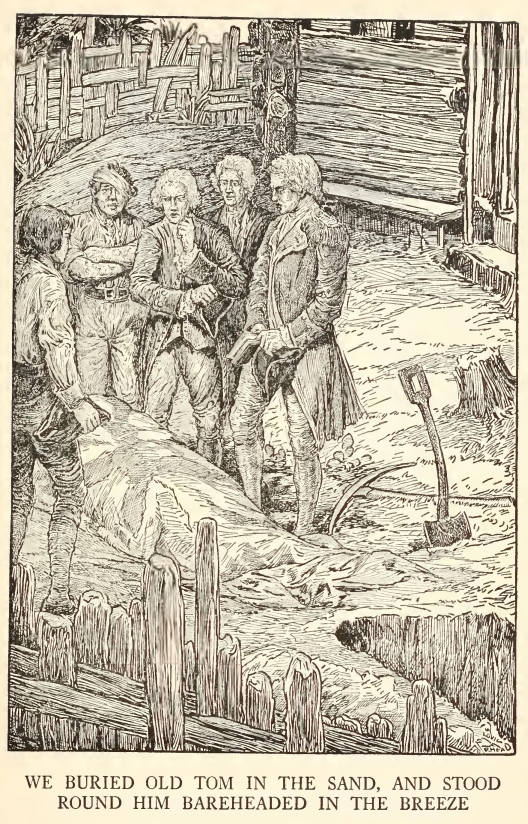
どうやら彼らは、どうすべきか途方に暮れているようだった。食料があまりに少なく、救援が来るずっと前に、飢えて降伏せざるを得なくなるだろうからだ。しかし、最善の望みは、海賊たちが旗を降ろすか、ヒスパニオラ号で逃げ出すまで、彼らを一人ずつ始末していくことだと決まった。十九人から既に十五人に減っており、他に二人が負傷し、少なくとも一人――大砲のそばで撃たれた男――は、死んでいなければ重傷だ。彼らを狙う機会があればいつでも、自分たちの命を最大限に注意して守りながら、実行する。それに加えて、我々には二つの強力な味方がいた――ラム酒と気候だ。
前者については、半マイルほど離れていたにもかかわらず、彼らが夜遅くまで大声で騒ぎ、歌っているのが聞こえた。そして後者については、博士が自分の鬘を賭けて、湿地で野営し、薬もない彼らの半分は、一週間も経たないうちに病床に就くだろうと断言した。
「だから」と彼は付け加えた。「もし我々が先に全員撃ち殺されなければ、彼らは喜んでスクーナー船に乗り込むだろう。いつでも船はあるのだから、また海賊稼業に戻れるだろうさ。」
「私が失った最初の船だ」とスモレット船長は言った。
ご想像の通り、僕は疲れ果てていた。そして、さんざん寝返りを打った末にようやく眠りにつくと、丸太のようにぐっすりと眠った。
僕が物音と話し声で目を覚ました時、他の者たちはとっくに起きて朝食を済ませ、薪の山をさらに半分ほども増やしていた。
「休戦旗だ!」と誰かが言うのが聞こえた。そしてその直後、驚きの叫び声とともに、「シルバー自身だ!」
それを聞いて、僕は飛び起き、目をこすりながら壁の銃眼へと駆け寄った。
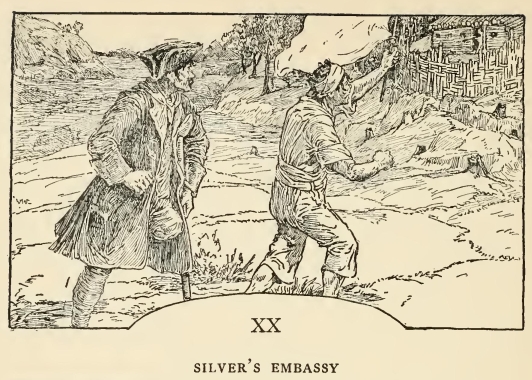
第二十章 シルバーの使節
案の定、砦のすぐ外に二人の男がいた。一人は白い布を振っており、もう一人は、他ならぬシルバー自身が、穏やかにそばに立っていた。
まだかなり早い時間で、僕がこれまでに屋外で経験した中で最も寒い朝だったと思う――骨の髄まで突き刺さるような冷気だった。空は明るく雲一つなく、木々の梢は太陽の光を浴びて薔薇色に輝いていた。しかし、シルバーが部下と立っている場所はまだ全て影の中にあり、彼らは夜の間に沼地から這い出してきた低い白い霧に膝まで浸かっていた。この冷気と霧は、この島の劣悪な環境を物語っていた。明らかに、湿気が多く、熱病が蔓延する、不健康な場所だった。
「室内にいろ、諸君」と船長は言った。「十中八九、これは罠だ。」
それから彼は海賊に呼びかけた。
「誰だ? 止まれ、さもないと撃つぞ。」
「休戦旗だ」とシルバーが叫んだ。
船長はポーチにいて、もしだまし討ちが意図されていた場合に備え、慎重に射線から身を避けていた。彼は振り返って僕たちに言った。「博士の当番は見張りを。ライブシー先生は北側を、頼む。ジムは東、グレイは西だ。非番の者は、全員マスケット銃を装填しろ。素早く、そして慎重にだ。」
そして彼は再び反逆者たちの方を向いた。「その休戦旗で何の用だ?」と彼は叫んだ。
今度はもう一人の男が返答した。
「シルバー船長が、乗り込んで交渉したいと、旦那」と彼は叫んだ。
「シルバー船長だと! 知らんな。誰だそいつは?」と船長は叫んだ。そして独り言のように付け加えるのが聞こえた。「船長、だと? なんたることだ、出世したもんだ!」
ロング・ジョンが自分で答えた。「おれですよ、旦那。この哀れな連中が、あんたが『脱走』した後に、おれを船長に選んだんでさ」――彼は「脱走」という言葉をことさら強調した。「もし条件が合えば、我々は降伏する用意があります。とやかく言うつもりはねえ。おれが頼むのはただ一つ、スモレット船長、あんたの言葉だ。この砦から無事に、五体満足で出させてくれ。それから、銃が撃たれる前に、射程外に出るまで一分間の猶予をくれ。」
「君」とスモレット船長は言った。「私は君と話したいとは微塵も思わん。もし私と話したいなら、来ればいい、それだけだ。もし裏切りがあるとすれば、それは君の側だろう。その時は神の御加護を祈るがいい。」
「それで十分だ、船長」ロング・ジョンは陽気に叫んだ。「あんたの一言で十分さ。おれは紳士ってもんを知ってる。そこんとこは請け合うぜ。」
休戦旗を持っていた男がシルバーを引き留めようとしているのが見えた。船長の返答がいかに横柄だったかを考えれば、それも不思議ではなかった。しかしシルバーは彼を大声で笑い飛ばし、まるで心配するなど馬鹿げているとでも言うように、その背中を叩いた。それから彼は砦に進み出て、松葉杖を投げ越し、片脚を上げ、見事な力強さと巧みさで柵を乗り越え、無事に反対側に着地した。
白状すると、僕は目の前で起こっていることに夢中になりすぎて、歩哨としては全く役に立たなかった。実際、僕はとっくに東側の銃眼を離れ、船長の後ろに忍び寄っていた。船長は今や戸口に腰を下ろし、膝に肘をつき、両手で頭を抱え、砂の中の古い鉄釜から湧き出る水を見つめていた。彼は「来たれ、乙女よ若者よ」を口笛で吹いていた。
シルバーは小高い丘を登るのにひどく苦労した。急な傾斜、密集した切り株、そして柔らかい砂のせいで、彼と彼の松葉杖は、風待ちの帆船のように無力だった。しかし、彼は黙って男らしくそれに耐え、ついに船長の前にたどり着くと、この上なく丁寧な敬礼をした。彼は一張羅で着飾っていた。真鍮のボタンがびっしりと付いた巨大な青いコートが膝まで垂れ下がり、上等なレース付きの帽子を後頭部に乗せていた。
「来たか」船長は頭を上げて言った。「座ったらどうだ。」
「中には入れてくれねえんですかい、船長?」とロング・ジョンは不平を言った。「外の砂の上に座るには、まったく、ひどく寒い朝でしてね。」
「おい、シルバー」と船長は言った。「もし君が正直者でいることを選んでいれば、自分の調理場に座っていられただろう。自業自得だ。君は私の船のコックか――その場合は丁重に扱われたはずだ――あるいはただの反逆者で海賊のシルバー船長か、そのどちらかだ。後者なら、首を吊るがいい!」
「まあ、まあ、船長」と海のコックは、言われた通り砂の上に座りながら答えた。「また立ち上がる時には、手を貸してもらわなきゃならねえな、それだけだ。ずいぶんと可愛らしい場所をお持ちで。おや、ジムじゃないか! おはようさん、ジム。先生、ご機嫌よう。いやはや、皆さんお揃いで、言ってみれば、幸せなご家族のようですな。」
「何か言うことがあるなら、さっさと言え」と船長は言った。
「ごもっともで、スモレット船長」とシルバーは答えた。「義務は義務、確かにその通りだ。さて、まあ聞いてくだせえ。昨夜のあんた方のやり口は見事だった。見事な手際だったと認めますぜ。あんた方の中には、てこ棒の扱いがうまい奴がいるようだ。それから、おれの仲間が何人か動揺したことも否定はしねえ――たぶん全員が動揺したかもしれねえ。おれ自身も動揺したかもしれねえ。たぶん、だからこそおれは交渉のためにここに来てる。だが、よく聞けよ、船長。二度目はそうはいかねえ、ちくしょうめ! 見張りを立てて、ラム酒も少し控えなきゃならねえな。あんた方は、おれたちがみんなべろんべろんに酔っぱらってたと思ってるかもしれねえ。だが言っておくが、おれはしらふだった。ただくたくたに疲れてただけだ。もしあと一秒早く目が覚めてりゃ、あんた方を現行犯で捕まえてやったところだ。おれがそいつのところに着いた時、そいつはまだ死んじゃいなかったぜ、本当だ。」
「それで?」スモレット船長はあくまで冷静に言った。
シルバーが言ったことは全て、彼にとっては謎だったが、その口調からはとてもそうとは察せなかっただろう。僕の方はと言えば、おぼろげながら見当がつき始めていた。ベン・ガンの最後の言葉が心によみがえったのだ。彼らが焚き火の周りで酔いつぶれて寝ている間に、ベン・ガンが彼らを訪ねたのだろうと僕は推測し、相手にする敵はあと十四人しかいないとほくそ笑んだ。
「さて、本題だ」とシルバーは言った。「おれたちはあの宝が欲しい。そして必ず手に入れる――それがおれたちの狙いだ! あんた方は、自分の命を助けたいと思ってる、そうだろう。それがそっちの狙いだ。あんた方は海図を持ってるな?」
「まあ、どうだろうな」と船長は答えた。
「へっ、そりゃあそうだ、わかってるさ」とロング・ジョンは応じた。「そんなガラガラ声で凄んだって無駄なこった。これっぽっちも役に立たねえ、そいつは請け合うぜ。俺が言いてえのは、あんたの海図が欲しいってことだ。俺自身は、あんたに危害を加えるつもりは毛頭なかったんだがな。」
「その手は私には通じんぞ」船長は遮った。「貴様らが何を企んでいたかは、すべてお見通しだ。だが、もはやどうでもいい。今となっては、もはや貴様らには何もできんのだからな。」
船長は平然とシルバーを見据え、パイプにタバコを詰め始めた。
「エイブ・グレイが……」シルバーは声を荒らげた。
「そこまでだ!」スモレット氏は叫んだ。「グレイは私に何も話しておらんし、私も何も尋ねてはおらん。それどころか、私は貴様も、グレイも、この島ごと地獄の業火で吹き飛ばしてやりたいくらいだ。それが、その件に関する私の考えだ、わかったか。」
この一瞬の激情が、かえってシルバーを冷静にさせたようだった。それまで苛立ちを募らせていた彼だったが、ここで気を取り直した。
「ごもっとも」と彼は言った。「紳士方が何を『筋が通っている』とお考えになるか、あるいはならないか、俺ごときがとやかく言う筋合いはねえ。それから船長、パイプを一服なさるようですんで、失礼して俺もご相伴にあずかりますぜ。」
彼はパイプにタバコを詰め、火をつけた。二人はしばらくの間、黙って煙草をふかしていた。時にお互いの顔を見つめ、時にタバコを揉み消し、時に身を乗り出して唾を吐く。その様子は、さながら芝居の一幕を見るかのようだった。
「さて」とシルバーは話を再開した。「提案がある。宝を手に入れるために、海図をこちらに渡すんだ。そして哀れな船乗りを撃ったり、寝込みを襲って頭をかち割ったりするのをやめる。そうすりゃ、こっちも選択肢をやろう。一つは、宝を船に積み込んだら、あんた方も一緒に乗り込む。そしたら俺の名誉にかけて、どこか安全な陸地に降ろしてやることを誓う。もしそれがお気に召さねえなら――俺の手下には手荒な連中もいて、あんた方にいじめられた恨みを持ってるやつもいるからな――あんた方はここに残ってもいい。食料は人数分、きっちり分けてやる。そしてさっきと同じく、最初に見つけた船に声をかけて、あんた方を拾いに来させることを誓う。どうだ、話のわかる男だろう。これ以上ない、またとない条件だぜ。それから」――彼は声を張り上げた――「この丸太小屋にいる全員、俺の言葉をよく聞いとけ。一人に言ったことは、全員に言ったことだからな。」
スモレット船長は席から立ち上がると、左の手のひらにパイプの灰を叩き落とした。
「それだけか?」と彼は尋ねた。
「ああ、一言一句違わねえ、ちくしょう!」とジョンは答えた。「これを断るってんなら、二度と俺の顔を見ることはねえ。マスケット銃の弾が代わりにご挨拶するだけだ。」
「結構」と船長は言った。「では、今度は私の話を聞くがいい。もし貴様らが一人ずつ、武器を捨ててここへ来るなら、全員に枷をはめ、本国へ連れ帰って正当な裁判を受けさせることを約束しよう。それが嫌だというなら、わが名はアレクサンダー・スモレット。国王陛下の旗を掲げたからには、貴様ら全員を海の藻屑にしてくれる。貴様らに宝は見つけられん。船も動かせん――貴様らの中にまともに船を操れる者など一人もおらん。私らと戦うこともできん――そこにいるグレイは、貴様ら五人から逃げ切ったのだぞ。船は身動きがとれん、シルバー君。貴様らは風下の海岸に追い詰められているのだ、いずれわかる。私はここに立って、そう断言する。そしてこれが、貴様らが私から聞く最後の親切な言葉だ。次に会った時は、神に誓って、貴様の背中に弾丸を撃ち込んでやる。さあ、行け。とっととここから出ていけ、手足を使って、大至急だ。」
シルバーの顔は、まさに絵に描いたようだった。怒りで目が飛び出さんばかりだ。彼はパイプから火種を振り落とした。
「手を貸せ!」と彼は叫んだ。
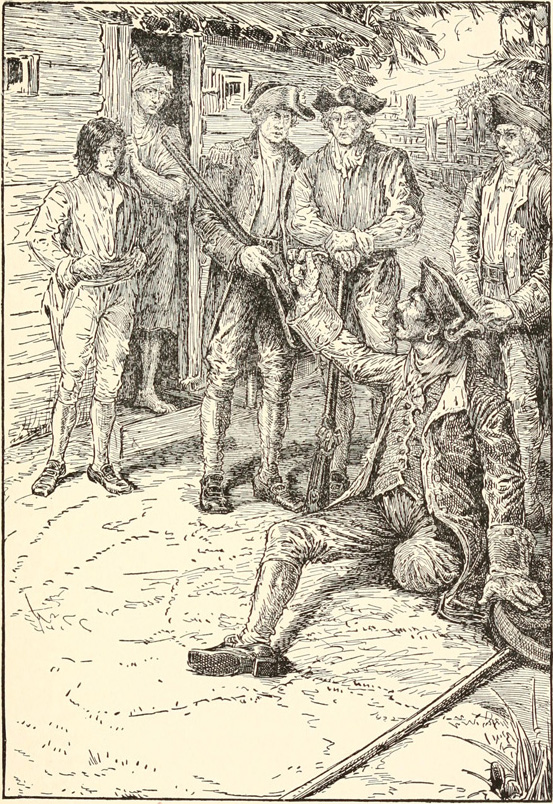
「手を貸せ!」と彼は叫んだ。「断る」と船長は応じた。
「断る」と船長は応じた。
「誰か手を貸してくれんか!」と彼は怒鳴った。
我々のうち、動く者は一人もいなかった。この世で最も汚い呪いの言葉を唸りながら、彼は砂の上を這っていき、ようやくポーチに掴まると、松葉杖で再び体を支えた。そして、泉に向かって唾を吐きかけた。
「これだ!」と彼は叫んだ。「お前らへの気持ちはな。一時間もしないうちに、お前らの古ぼけた丸太小屋なんざ、ラム酒の樽みてえにぶち壊してやる。笑え、ちくしょう、笑うがいい! 一時間もしないうちに、泣きっ面をかくことになるんだ。死んだやつが一番の幸運者になるだろうよ。」
そして恐ろしい罵りの言葉とともに、彼はよろめきながら去っていった。砂をかき分けるように進み、四、五度失敗した末に休戦の旗を持った男に助けられて柵を越え、次の瞬間には木々の間に姿を消した。
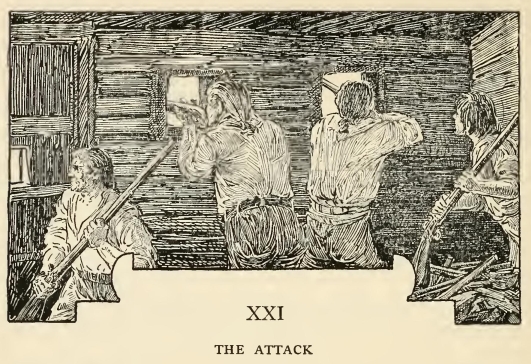
第二十一章 襲撃
シルバーが姿を消すとすぐ、その様子を注意深く見守っていた船長は、家の内部に振り返った。そして、持ち場についているのがグレイただ一人であることに気づいた。我々が船長の怒った顔を見たのは、それが初めてだった。
「配置につけ!」と彼は怒鳴った。そして、我々が皆すごすごと持ち場に戻ると、こう言った。「グレイ、君の名を航海日誌に記しておこう。船乗りとして、よく職務を果たした。トレローニーさん、あなたには驚きましたぞ。博士、あなたは国王陛下の軍服に袖を通した方ではなかったのか! もしフォントノワでもそのように戦っていたのでしたら、寝台にいた方がましだったでしょうな。」
博士の当番の者たちは皆、銃眼に戻り、残りの者たちは予備のマスケット銃に弾を込めるのに忙しかった。誰もが顔を真っ赤にし、諺に言う「耳に蚤」を入れられたのは、請け合いだ。
船長はしばらく黙ってその様子を見ていた。やがて口を開いた。
「諸君」と彼は言った。「私はシルバーに痛烈な一撃を食らわせてやった。わざと、燃え盛る鉄球のような言葉を投げつけてやったのだ。やつが言った通り、一時間もしないうちに奴らは乗り込んでくるだろう。数では我々が劣勢だ、言うまでもない。だが、我々には遮蔽物がある。そして、つい先ほどまでは、規律をもって戦えるとも言えたはずだ。諸君にその気があるなら、奴らを叩きのめせることに何の疑いもない。」
それから彼は見回りをして、彼の言う通り、万事準備が整っていることを確認した。
家の短い側面である東と西には銃眼が二つずつ。ポーチのある南側にも二つ。そして北側には五つあった。我々七人に対し、マスケット銃は二十丁ほどあった。薪は四つの山――テーブルと言ってもいいだろう――に積まれ、それぞれの壁の中央あたりに置かれていた。そのテーブルの上には、弾薬と装填済みのマスケット銃四丁が、守備の者がすぐに手に取れるように用意されていた。中央には、山刀がずらりと並べられていた。
「火を外へ出せ」と船長は言った。「寒さはもう過ぎた。煙で目をくらませるわけにはいかん。」
鉄の火籠はトレローニー郷士が丸ごと運び出し、燃えさしは砂の中に埋めて消された。
「ホーキンズが朝食をまだとっていない。ホーキンズ、自分で取って、持ち場に戻って食べろ」スモレット船長は続けた。「急げよ、小僧。戦いが終わる前に腹が減るぞ。ハンター、全員にブランデーを一杯ずつ配ってくれ。」
こうしたことが行われている間にも、船長の頭の中では防衛計画が完成しつつあった。
「博士、あなたは戸口を頼む」彼は再び指示を出した。「いいか、身をさらすな。中にとどまって、ポーチ越しに撃て。ハンター、そこの東側だ。ジョイス、君は西側だ。トレローニーさん、あなたは一番の射撃の名手だ――あなたとグレイで、この銃眼が五つある長い北側を受け持ってくれ。そこが一番危険だ。もし奴らがそこまでたどり着き、我々の銃眼から撃ち込んできたら、事態は厄介になる。ホーキンズ、君も私も射撃は大したことない。我々は装填と手伝いに回ろう。」
船長の言った通り、寒さは過ぎ去っていた。太陽が我々を取り囲む木々の帯の上に昇ると、その光は全力で空き地に降り注ぎ、立ち込めていた靄を一気に飲み干した。すぐに砂は焼け、丸太小屋の木材からは樹脂が溶け出した。上着は脱ぎ捨てられ、シャツは襟元を開け、袖は肩までまくり上げられた。我々は皆、それぞれの持ち場で、熱気と不安の熱に浮かされるようにして立っていた。
一時間が過ぎた。
「くそったれ!」と船長は言った。「無風帯のように退屈だ。グレイ、風を呼ぶ口笛でも吹いてくれ。」
まさにその時、攻撃の第一報がもたらされた。
「失礼します、船長」とジョイスが言った。「誰か見つけたら、撃ってもよろしいでしょうか?」
「そう言ったはずだ!」と船長は叫んだ。
「ありがとうございます」ジョイスは相変わらず静かで丁寧な口調で答えた。
しばらく何も起こらなかったが、その言葉で我々は皆、神経を研ぎ澄ませた。耳を澄まし、目を凝らす――射手たちはマスケット銃を手に構え、船長は丸太小屋の中央で口を固く結び、顔をしかめていた。
数秒が過ぎた。その時、突然ジョイスがマスケット銃をさっと構え、発砲した。その銃声が消えやらぬうちに、外から次々と銃声が繰り返された。それは散発的な一斉射撃で、雁の群れのように、柵の四方から続けざまに撃ち込まれた。数発の弾丸が丸太小屋に当たったが、一発も貫通しなかった。硝煙が晴れて消え去ると、柵と周りの森は以前と同じように静かで、人の気配はなかった。枝一本揺れず、マスケット銃の銃身のきらめき一つ、敵の存在をうかがわせるものはなかった。
「敵に当たったか?」と船長が尋ねた。
「いえ、船長」とジョイスは答えた。「当たらなかったと思います。」
「正直に言うのは良いことだ」スモレット船長は呟いた。「彼の銃に弾を込めろ、ホーキンズ。博士、そちら側は何人だった?」
「正確にわかります」とライブシー博士は言った。「こちら側では三発撃たれました。三つの閃光を見ました――二つはごく近くで、もう一つはもっと西の方です。」
「三発か!」船長は繰り返した。「トレローニーさん、あなたの方は?」
しかし、こちらはそう簡単には答えられなかった。北側からは多数の銃弾が飛んできた――郷士の計算では七発、グレイによれば八、九発。東と西からは一発ずつしか撃たれていない。したがって、攻撃の主力は北側からであり、他の三方は単なる陽動に過ぎないことは明らかだった。しかし、スモレット船長は配置を変えなかった。もし反乱者どもが柵を越えるのに成功すれば、守りのない銃眼を占拠し、我々を自分たちの砦の中で鼠のように撃ち殺すだろう、と彼は考えたのだ。
我々に残された考える時間も、そう多くはなかった。突然、大きな鬨の声をあげて、海賊の一団が北側の森から飛び出し、柵に向かって真っ直ぐに走ってきた。同時に、森の中から再び銃撃が始まり、ライフル弾が戸口を風切り音を立てて通り抜け、博士のマスケット銃を粉々に砕いた。
乗り込んできた連中は、猿のように柵を乗り越えてきた。郷士とグレイが立て続けに発砲し、三人が倒れた。一人は柵の内側に前のめりに、二人は外側に倒れた。しかし、そのうちの一人は明らかに怪我よりも恐怖が勝っていたようで、すぐに立ち上がると、あっという間に木々の間に姿を消した。
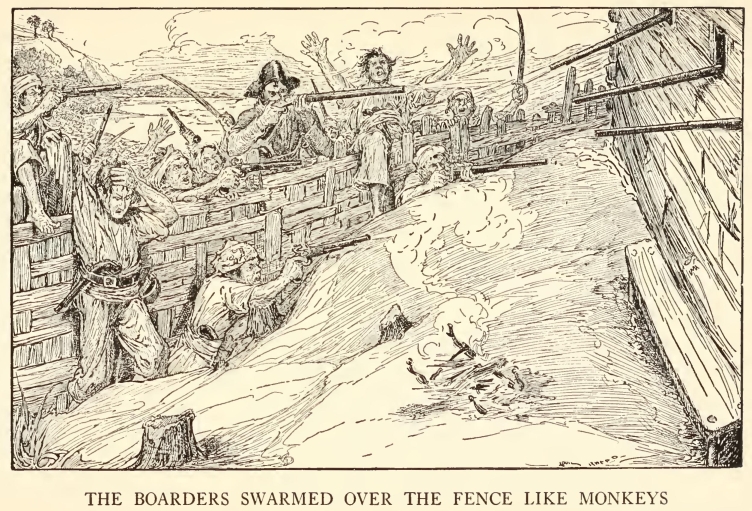
二人が倒れ、一人が逃げ、四人が我々の防御線の内側に足場を固めた。一方、森の陰からは七、八人の男たちが、それぞれ明らかに数丁のマスケット銃を手に、丸太小屋に向けて激しいが効果のない射撃を続けていた。
乗り込んできた四人は、叫び声を上げながら建物めがけて一直線に走ってきた。木々の間にいる男たちも、彼らを励ますように叫び返した。数発の銃弾が放たれたが、射手たちがひどく慌てていたため、一発も命中しなかったようだ。一瞬のうちに、四人の海賊は小高い土手を駆け上がり、我々に襲いかかってきた。
水夫長ジョブ・アンダーソンの頭が、中央の銃眼に現れた。
「やっちまえ、総員かかれ!」彼は雷のような声で怒鳴った。
その瞬間、別の海賊がハンターのマスケット銃の銃口を掴み、彼の手からひったくると、銃眼から引き抜き、強烈な一撃で哀れなハンターを床に打ちのめし、気絶させた。その間、三番目の海賊は無傷で家の周りを走り抜け、突然戸口に現れると、山刀を振りかざして博士に襲いかかった。
我々の立場は完全に逆転した。つい先ほどまで、我々は遮蔽物に隠れて無防備な敵を撃っていた。今や、無防備なのは我々の方で、一撃も返すことができない。
丸太小屋は煙に満ちており、それがかろうじて我々の安全を保っていた。叫び声と混乱、ピストルの閃光と銃声、そして一つの大きなうめき声が、私の耳に鳴り響いた。
「外だ、諸君、外へ出て、開けた場所で戦うんだ! 山刀を!」と船長が叫んだ。
私は山刀の山から一本をひったくった。同時に誰かが別の山刀を掴み、私の指の関節を切りつけたが、ほとんど痛みは感じなかった。私は戸口から、まばゆい太陽の光の中へ飛び出した。すぐ後ろに誰かがいたが、誰かはわからなかった。真正面では、博士が襲撃者を丘の下まで追いかけ、ちょうど私の目に留まったその時、相手の防御を打ち破り、顔面に深々と一太刀浴びせて仰向けにひっくり返させた。
「家の周りだ、諸君! 家の周りへ!」船長が叫んだ。大混乱の中だったが、彼の声に変化があったことに私は気づいた。
私は機械的に従い、東に向きを変え、山刀を振り上げたまま家の角を曲がった。次の瞬間、私はアンダーソンと鉢合わせになった。彼は大声で吠え、その短剣を頭上に振り上げ、太陽の光を浴びてきらめいた。恐怖を感じる暇もなく、その一撃が振り下ろされる寸前、私はとっさに横へ跳び、柔らかい砂に足を取られて、斜面を真っ逆さまに転がり落ちた。
私が最初に戸口から飛び出した時、他の反乱者たちは我々にとどめを刺そうと、すでに柵によじ登っていた。赤いナイトキャップをかぶった男は、山刀を口にくわえ、すでに柵のてっぺんに達して片足を乗り越えさせていた。さて、それからほんのわずかな時間しか経っていなかったため、私が再び立ち上がった時も、すべては同じ状況だった。赤いナイトキャップの男はまだ柵を半分越えたところで、別の男はまだ柵の上から頭をのぞかせているところだった。しかし、このほんのわずかな間に、戦いは終わり、我々の勝利となっていた。
私のすぐ後ろについてきていたグレイが、あの大きな水夫長が体勢を立て直す間もなく斬り倒していた。もう一人は、まさに家の中に撃ち込もうとしたところを銃眼から撃たれ、今は苦悶の中でもがいていた。手にはまだ煙を上げるピストルが握られていた。三人目は、私が目撃した通り、博士が一撃で仕留めていた。柵を乗り越えた四人のうち、行方が分からなかったのは一人だけで、その男は山刀を戦場に残し、今や死の恐怖に駆られて再び柵をよじ登って外へ出ようとしていた。
「撃て――家から撃て!」と博士が叫んだ。「そして君たち、遮蔽物の中へ戻れ。」
しかし、彼の言葉は聞き入れられず、一発の銃弾も放たれなかった。そして最後の侵入者はまんまと逃げおおせ、他の者たちと共に森の中へ消えていった。三秒後、攻撃隊の姿はどこにもなく、ただ倒れた五人――柵の内側に四人、外側に一人――が残るのみだった。
博士とグレイと私は、遮蔽物を目指して全力で走った。生き残った者たちはすぐにマスケット銃を置いてきた場所に戻り、いつ銃撃が再開されてもおかしくなかった。
この時までに、家の中の煙はいくらか晴れており、我々は勝利のために支払った代償を一目で悟った。ハンターは銃眼のそばで気を失って倒れており、ジョイスはその隣で、頭を撃ち抜かれて二度と動くことはなかった。そして中央では、郷士が船長を支えていた。二人とも同じように青ざめていた。
「船長が負傷した」とトレローニー氏が言った。
「奴らは逃げたか?」とスモレット氏が尋ねた。
「走れる者は皆、逃げましたよ。請け合います」と博士は答えた。「ですが、五人は二度と走ることはないでしょう。」
「五人か!」船長は叫んだ。「よし、上出来だ。五人対三人、これで我々が四人、奴らが九人だ。戦いが始まった時よりはマシな形勢だ。あの時は七人対十九人だった、あるいはそう思っていた。どちらにせよ耐えがたい状況だったからな」*
*反乱者たちの数はすぐに八人となった。スクーナー船上でトレローニー氏に撃たれた男が、その日の夕方、傷がもとで死んだからである。しかし、このことはもちろん、忠実な一行が知るのは後のことだった。
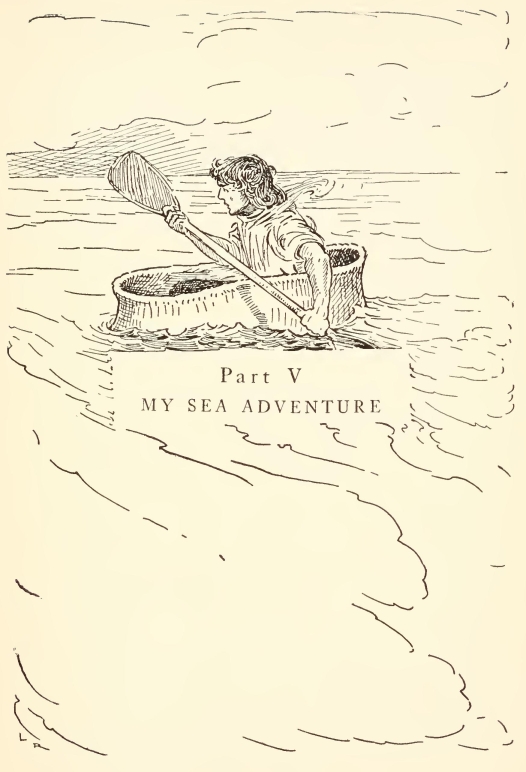
第五部 我が海の冒険
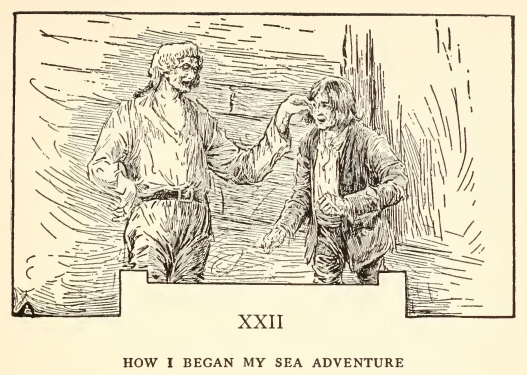
第二十二章 我が海の冒険の始まり
反乱者たちが戻ってくることはなかった――森からもう一発の銃声すら聞こえなかった。船長の言葉を借りれば、彼らは「その日の分の配給は受け取った」のだ。我々はその場所を独占し、負傷者の手当てをし、夕食の準備をする静かな時間を得た。郷士と私は危険を顧みず外で料理をしたが、外にいても、博士の患者たちから聞こえてくる大きいうめき声に慄然とし、自分たちが何をしているのかもわからなくなるほどだった。
戦闘で倒れた八人のうち、まだ息があったのは三人だけだった――銃眼で撃たれた海賊の一人、ハンター、そしてスモレット船長だ。そしてこのうち、最初の二人は死んだも同然だった。海賊は博士のメスの下で息絶え、ハンターは我々が手を尽くしたにもかかわらず、この世で意識を取り戻すことはなかった。彼は一日中、家の古い海賊が卒中の発作を起こした時のように、大きな息をしながら生き長らえたが、胸の骨は打撃で砕け、転倒した際に頭蓋骨を骨折していた。そして翌日の夜のいつだったか、何の兆候も音もなく、創造主のもとへと旅立った。
船長に関しては、彼の傷は確かに重かったが、命に別状はなかった。致命傷を負った臓器はなかった。アンダーソンの弾――最初に彼を撃ったのはジョブだった――は肩甲骨を砕き、肺にわずかに触れたが、ひどくはなかった。二発目はふくらはぎの筋肉をいくつか引き裂き、ずらしただけだった。博士によれば、彼は間違いなく回復するとのことだったが、それまでの間、そして今後数週間は、歩くことも腕を動かすことも、できる限り話すことさえも禁じられた。
私が偶然負った指の関節の切り傷など、蚤に刺されたようなものだった。ライブシー博士は絆創膏で手当てをし、おまけに私の耳を引っ張った。
夕食後、郷士と博士は船長の傍らに座ってしばらく相談していた。そして心ゆくまで話し終えると、時刻は正午を少し過ぎていたが、博士は帽子とピストルを取り、山刀を腰に差し、海図をポケットに入れ、マスケット銃を肩にかけると、北側の柵を越え、木々の間を足早に出かけていった。
グレイと私は、士官たちの相談が聞こえないように、丸太小屋の一番奥に一緒に座っていた。グレイは口からパイプを離すと、それを口に戻すのもすっかり忘れてしまうほど、この出来事に度肝を抜かれていた。
「おい、デイビー・ジョーンズの名にかけて」と彼は言った。「ライブシー先生は気でも狂ったのか?」
「まさか」と私は言った。「この船の乗組員の中で、先生が一番正気だと思うけど。」
「まあ、そうかもしれんがな、船乗り仲間よ」とグレイは言った。「先生が狂ってないとしても、もしそうだとしたら、覚えておけ、俺の方が狂ってる。」
「思うに」と私は答えた。「博士には考えがあるんだ。もし僕の考えが正しければ、今頃ベン・ガンに会いに行ってるんだよ。」
私の考えは正しかったことが、後に判明した。しかしその間、家の中は息が詰まるほど暑く、柵の内側の小さな砂地は真昼の太陽に照りつけられていた。私は別の考えを頭に浮かべ始めたが、それは決して正しいものとは言えなかった。私がし始めたこと、それは、鳥たちに囲まれ、心地よい松の香りが漂う涼しい木陰を歩く博士を羨むことだった。一方の私は、熱い樹脂で服が体に張り付くような暑さの中で焼かれ、周りにはおびただしい血と哀れな死体が転がっており、その場所に対して恐怖と同じくらい強い嫌悪感を抱くようになっていた。
丸太小屋を洗い流し、それから夕食の食器を洗っている間中、この嫌悪感と羨望はますます強くなっていった。そしてついに、パン袋の近くにいて、誰も私を見ていない時、私は脱走への第一歩を踏み出し、上着の両ポケットをビスケットで一杯にした。
馬鹿だと言われればその通りだ。確かに私は愚かで、無謀なことをしようとしていた。しかし、私はできる限りの用心をしてそれを実行する決心だった。このビスケットがあれば、もし何かあっても、少なくとも翌日の遅くまで飢えをしのぐことができるだろう。
次に手にしたのは二丁のピストルだった。すでに火薬入れと弾丸は持っていたので、武器は十分に揃ったと感じた。
頭の中にあった計画は、それ自体は悪いものではなかった。東の停泊地と外洋を隔てる砂の岬を下っていき、昨夜見つけた白い岩を探し、そこにベン・ガンのボートが隠されているかどうかを確かめるというものだ。それは今でも、やる価値のあることだったと信じている。しかし、柵の外に出ることは許されないと確信していたので、私の唯一の計画は、黙って抜け出し、誰も見ていない隙にこっそり出て行くことだった。そして、そのやり方があまりに悪かったため、計画そのものまで悪いことになってしまった。だが、私はまだ少年で、心は決まっていた。
さて、事態がようやく落ち着くと、私は絶好の機会を見つけた。郷士とグレイは船長の包帯の手伝いで忙しく、あたりに人影はなかった。私は柵を飛び越え、木々が最も密集している場所へと駆け込んだ。そして、私の不在が気づかれる前に、仲間たちの声が届かないところまで来ていた。
これは私の二度目の愚行であり、家に健康な男を二人しか残さなかった点で、一度目よりもはるかに悪かった。しかし、一度目と同様、それが我々全員を救う助けとなったのだ。
私は島の東海岸へとまっすぐ向かった。停泊地から見つかる可能性を避けるため、岬の海側を下っていくと決めていたからだ。すでに午後の遅い時間だったが、まだ暖かく日差しがあった。高い木々の間を縫って進んでいくと、はるか前方から、絶え間なく轟く波の音だけでなく、木の葉が揺れ、枝がきしむ音が聞こえてきた。それは、海風がいつもより強く吹き始めたことを示していた。やがて涼しい風が私のもとに届き始め、さらに数歩進むと、私は林の開けた縁に出て、水平線まで青く晴れ渡る海と、浜辺に沿って泡を立てて打ち寄せる波を見た。
宝島の周りで海が静かなのを、私は一度も見たことがない。太陽が頭上で燃え盛り、風がぴたりとやみ、海面が滑らかで青くても、それでもなお、この巨大なうねりは昼も夜も外側の海岸に沿って走り、轟音を立て続けていた。島の中で、その音の聞こえない場所は一箇所もないだろうとさえ思う。
私は大いに楽しみながら波打ち際を歩き、十分に南まで来たと考えると、茂みに身を隠し、用心深く岬の尾根まで這い上がった。
私の背後には海が、前方には停泊地があった。海風は、その異常な激しさゆえに早く吹き尽くしてしまったかのように、すでにおさまっていた。それに代わって、南と南東から、濃い霧の塊を運ぶ軽くて変わりやすい風が吹いていた。そして、骸骨島の風下に位置する停泊地は、我々が最初に入った時と同じように、静かで鉛色をしていた。その途切れることのない鏡のような水面に、ヒスパニオラ号は、マストのてっぺんから吃水線まで、そっくりそのまま映し出されていた。船尾の旗竿には、ジョリー・ロジャーが垂れ下がっていた。
船の横にはギグが一つ浮かんでおり、船尾にはシルバーが座っていた――彼はいつでも見分けがついた――。一方、二人の男が船尾のブルワークにもたれかかっていた。そのうちの一人は赤い帽子をかぶっていた――数時間前に柵にまたがっていた、まさにあのごろつきだ。彼らは話したり笑ったりしているようだったが、一マイル以上も離れていたので、もちろん話の内容は一言も聞こえなかった。突然、この世のものとは思えない、最も恐ろしい叫び声が始まり、最初はひどく驚いたが、すぐにフリント船長の声だと気づき、主人の手首にとまっているその鳥の鮮やかな羽毛まで見分けられるような気がした。
間もなく、ジョリー・ボートは岸に向かって漕ぎ出され、赤い帽子の男とその仲間は船室の昇降口から下へ降りていった。
ちょうどその頃、太陽は「遠見山」の向こうに沈み、霧が急速に立ち込めてきたため、本格的に暗くなり始めた。その晩のうちにボートを見つけるには、一刻の猶予もないと思った。
白い岩は、茂みの上から十分に見えたが、岬をさらに八分の一マイルほど下ったところにあった。そこまでたどり着くにはかなりの時間がかかり、しばしば四つん這いになって低木の間を這っていった。そのごつごつした側面に手を置いた時には、ほとんど夜になっていた。その真下には、非常に小さな緑の芝生の窪地があり、土手と、膝ほどの高さで密生する下草に隠されていた。そしてその谷間の中心には、案の定、ヤギの皮でできた小さなテントがあった。イングランドでジプシーが持ち歩いているようなものだ。
私は窪地に飛び降り、テントの側面を持ち上げた。そこにはベン・ガンのボートがあった――これほど手作りという言葉が似合うものもないだろう。丈夫な木でできた粗末で不格好な骨組みに、毛を内側にしてヤギの皮が張られていた。それは私にとっても非常に小さく、大人の男を乗せて浮くとは到底思えなかった。腰掛け板が一つ、できるだけ低く設置され、船首には足踏みのようなものがあり、推進用には両端に水かきがついたパドルがあった。
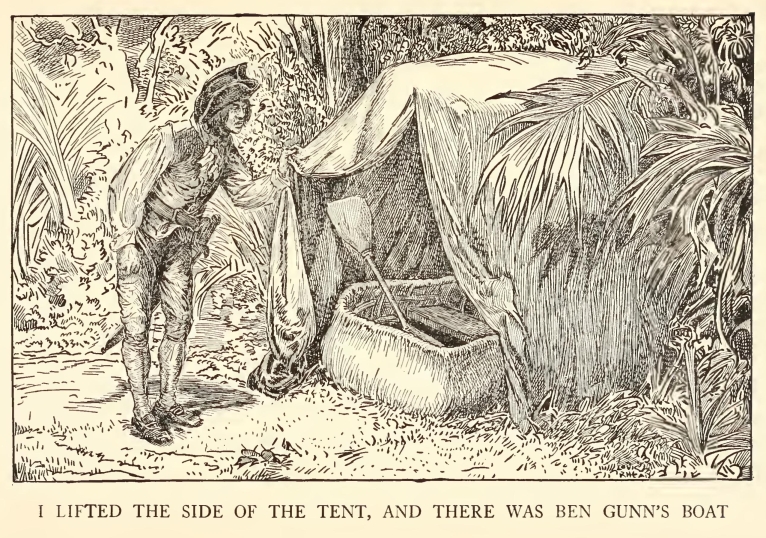
その頃、私は古代ブリトン人が作ったようなコラクルを見たことがなかったが、その後見たことがある。ベン・ガンのボートについて、これ以上的確な説明はないだろう。それは、人間が作った最初にして最悪のコラクルに似ていた。しかし、コラクルの大きな利点は確かに備えていた。非常に軽くて持ち運びが容易だったのだ。
さて、ボートを見つけたのだから、一度の無断外出としてはもう十分だと思われるだろう。しかしその間に、私は別の考えを思いつき、それに頑固なまでに執着するようになっていた。スモレット船長自身の反対を押し切ってでも、実行したに違いない。それは、夜陰に紛れて抜け出し、ヒスパニオラ号の錨綱を切り、好きなように座礁させるというものだった。朝の撃退の後、反乱者たちが何よりも望んでいるのは、錨を上げて海へ出ることだと、私は確信していた。それを阻止するのは素晴らしいことだと思ったし、見張りがボートもなしに放置されているのを見た今、ほとんど危険なく実行できると考えた。
私は暗くなるのを待って座り込み、ビスケットで腹ごしらえをした。私の目的のためには、万に一つのない夜だった。霧は今や天全体を覆い隠していた。最後の日の光が弱まり、消え去ると、完全な暗闇が宝島に下りた。そして、ついに私がコラクルを肩にかつぎ、夕食をとった窪地から手探りでよろめきながら這い出した時、停泊地全体で見えるのは二つの点だけだった。
一つは岸の大きな焚き火で、そのそばで敗北した海賊たちが沼地で酒盛りをしていた。もう一つは、闇の中のぼんやりとした光で、停泊している船の位置を示していた。船は引き潮で向きを変え、船首は今や私の方を向いていた。船上の明かりは船室にしかなく、私が見ていたのは、船尾の窓から漏れる強い光が霧に反射したものに過ぎなかった。
引き潮はすでにしばらく続いており、私はぬかるんだ砂地を長く歩かなければならなかった。そこで何度か足首の上まで沈みながら、ようやく引いていく水の縁にたどり着いた。そして少し水の中に入り、力と器用さをいくらか使って、コラクルを竜骨を下にして水面に浮かべた。

第二十三章 引き潮
コラクルは――この船との付き合いが終わるまでに、それを知る十分な理由があったのだが――私の身長と体重の者にとっては非常に安全なボートだった。浮力があり、波のある海でも巧みに動いた。しかし、操縦するには最も扱いにくく、不格好な乗り物だった。どう操ろうとしても、いつも横に流されるばかりで、くるくると回転するのが一番得意な動きだった。ベン・ガン自身でさえ、「癖を知るまでは、扱いにくい代物だ」と認めていた。
確かに、私にはその癖がわからなかった。コラクルは私が行きたい方向以外のあらゆる方向に向きを変えた。ほとんどの時間、我々は横向きになっており、もし潮の流れがなかったら、決して船にたどり着けなかっただろうと確信している。幸運なことに、私がどうパドルを漕ごうとも、潮は私を押し流し続けてくれた。そしてヒスパニオラ号は、見逃しようもないほど、ちょうど航路の真ん中にいた。
最初、船は闇よりもさらに黒い染みのように目の前に浮かび上がった。それから円材と船体が形を現し始め、次の瞬間には(というのも、進むにつれて引き潮の流れはますます速くなったからだ)、私は船の錨綱の横におり、それに掴まっていた。
錨綱は弓の弦のようにぴんと張っており、潮の流れが非常に強いため、船は錨を引っ張っていた。真っ暗な船体の周りでは、さざ波を立てる流れが、小さな山の小川のように泡立ち、せせらぎの音を立てていた。私の海ナイフで一切りすれば、ヒスパニオラ号はうなりを上げて潮に乗って流れていくだろう。
ここまでは順調だったが、次に、ぴんと張った錨綱を突然切断することは、蹴り上げる馬と同じくらい危険なことだと、ふと思い出した。もし私がヒスパニオラ号を錨から切り離すという無謀なことをすれば、十中八九、私とコラクルは水面からきれいにはじき飛ばされるだろう。
これで私は完全に足止めを食らった。もし再び幸運が特別に私に味方してくれなかったなら、計画を断念せざるを得なかっただろう。しかし、南東と南から吹き始めていたそよ風が、日没後に南西に変わっていた。私が思案しているちょうどその時、一陣の風が吹き、ヒスパニオラ号を捉えて潮の流れに乗せた。そして、大きな喜びとともに、私は握っていた錨綱が緩むのを感じ、それを掴んでいた手がほんの一瞬、水中に沈んだ。
それで私は決心し、ナイフを取り出し、歯で刃を開き、一本、また一本と綱を切断していき、ついに船は二本の綱だけで繋がれる状態になった。それから私は静かに横になり、再び風が吹いて綱の張りが緩むのを待って、最後の二本を切断しようとした。
この間ずっと、船室から大きな声が聞こえていたが、正直なところ、私の心は他の考えで完全に占められており、ほとんど耳を貸していなかった。しかし今、他にすることがなくなると、私はもっと注意を払うようになった。
一人は操舵手のイスラエル・ハンズの声だと分かった。彼は昔、フリントの砲手だった。もう一人は、もちろん、あの赤いナイトキャップの男だ。二人とも明らかに酔っ払っており、まだ飲み続けていた。私が聞いている間にも、一人が酔った叫び声とともに船尾の窓を開け、何かを投げ捨てた。空の瓶だと察した。しかし、彼らはただ酔っているだけではなかった。猛烈に怒っているのは明らかだった。罵りの言葉が雹のように飛び交い、時折、殴り合いで終わるに違いないと思われるような激しい口論が起こった。しかし、そのたびに喧嘩は収まり、しばらく声は低くなったが、また次の危機が訪れ、それもまた結果なく過ぎ去っていった。
岸辺では、大きな焚き火の明かりが、岸辺の木々を通して暖かく燃えているのが見えた。誰かが歌っていた。単調で古く、だらだらとした船乗りの歌で、各節の終わりには声が沈み、震えていた。そして、歌い手の忍耐力以外に終わりはないように思われた。私は航海の途中でそれを一度ならず聞いており、こんな歌詞を覚えていた。
「されど乗組員は一人だけ、七十五人で海に出たものを。」
そして私は、朝にあれほど残酷な損失を被った一団にとって、あまりにも悲しげで、ふさわしすぎる小唄だと思った。しかし、実際、私が見たところ、これら海賊たちは皆、彼らが航海する海と同じくらい無情だった。
ついにそよ風が吹いてきた。スクーナー船は横滑りするように、闇の中で近づいてきた。私は錨綱が再び緩むのを感じ、渾身の力を込めて、最後の繊維を断ち切った。
そよ風はコラクルにはほとんど影響を与えず、私はほとんど即座にヒスパニオラ号の船首に押し流された。同時に、スクーナー船は踵を返すように、潮の流れを横切って、船首と船尾を入れ替えながらゆっくりと回転し始めた。
私は鬼のように必死で動いた。いつ転覆させられるかと、一瞬たりとも気が抜けなかったからだ。コラクルを真横に押し出すことができないとわかったので、今度はまっすぐ船尾の方へ押した。ようやく危険な隣人から離れることができ、最後のひと押しをしたちょうどその時、私の手は船尾のブルワークを越えて船外に垂れていた軽い綱に触れた。私は即座にそれを掴んだ。
なぜそうしたのか、自分でもよくわからない。最初は単なる本能だったが、一度それを手にし、しっかりと結ばれていることがわかると、好奇心が優勢になり、船室の窓から一度覗いてみようと決心した。
私は綱をたぐり寄せ、十分に近づいたと判断すると、計り知れない危険を冒して背の半分ほどの高さまで立ち上がり、船室の天井と内部の一部を見渡せる位置についた。
この時までに、スクーナー船とその小さな伴侶は、かなり速く水面を滑っていた。実際、我々はすでに焚き火の高さまで来ていた。船は、船乗りが言うように、大きな音を立てていた。無数のさざ波を、絶え間なく水しぶきを上げて踏みつけていたのだ。そして、窓枠の上に目をやるまで、なぜ見張りが警戒しなかったのか理解できなかった。しかし、一瞥で十分だった。そして、その不安定な小舟から私が敢えてできたのは、ほんの一瞥だけだった。それは、ハンズとその仲間が、互いに相手の喉に手をかけ、死闘を繰り広げている姿だった。

私は再び腰掛け板に身を落としたが、遅すぎることはなかった。もう少しで船外に落ちるところだったからだ。その瞬間、私には、煙たいランプの下で揺れる、二つの激怒し、血に染まった顔以外、何も見えなかった。私は目を閉じ、再び暗闇に慣れさせようとした。
果てしなく続いたバラードもついに終わり、焚き火の周りの、人数が減った一団は、私が何度も聞いた合唱を歌い始めた。
「死人の箱に十五人――ヨーホーホー、ラム酒の瓶! 酒と悪魔が残りを片付けた――ヨーホーホー、ラム酒の瓶!」
まさにその瞬間、ヒスパニオラ号の船室で、酒と悪魔がどれほど忙しく働いていることかと考えていた時、コラクルが突然大きく傾き、私は驚いた。同時に、船は急に針路を逸れ、進路を変えたようだった。その間の速度は、奇妙なほどに増していた。
私はすぐに目を開けた。私の周りには小さなさざ波が立ち、鋭く逆立つような音を立て、わずかに燐光を発していた。ヒスパニオラ号自身も、その航跡に数ヤード遅れて私がまだ巻き込まれていたのだが、よろめいているように見え、その円材が夜の闇を背景に少し揺れるのが見えた。いや、さらに長く見ていると、彼女もまた南に向きを変えているのが確かになった。
肩越しに振り返ると、心臓が肋骨にぶつかるほど跳ね上がった。そこ、私の真後ろに、焚き火の明かりがあった。潮流は直角に曲がり、背の高いスクーナー船と踊るような小さなコラクルを一緒に巻き込んでいた。ますます速く、ますます高く泡立ち、ますます大きなうなり声を上げながら、それは渦を巻いて狭い海峡を抜け、外洋へと向かっていった。
突然、目の前のスクーナー船が激しく針路を逸れ、おそらく二十度ほど向きを変えた。そしてほとんど同時に、船上から次々と叫び声が上がった。昇降口のはしごを駆け下りる足音が聞こえ、私は二人の酔っぱらいが、ついに喧嘩を中断され、自分たちの災難に気づいたのだとわかった。
私はそのみすぼらしい小舟の底に平らに寝そべり、敬虔な気持ちで自分の魂を創造主に委ねた。海峡の終わりには、荒れ狂う砕け波の浅瀬に落ち込み、私の悩みはすべて速やかに終わるに違いないと確信していた。そして、死ぬことは耐えられるかもしれないが、近づいてくる運命を直視することは耐えられなかった。
そうして私は何時間も横たわっていたに違いない。絶えず大波に揺さぶられ、時折飛び散る水しぶきに濡れ、次の波で死ぬことを覚悟し続けていた。次第に疲労が私を襲い、恐怖の真っ只中にあっても、麻痺や時折の昏睡状態が私の心を襲った。そしてついに眠りが訪れ、海に揺られるコラクルの中で、私は家と古い「ベンボー提督亭」の夢を見た。
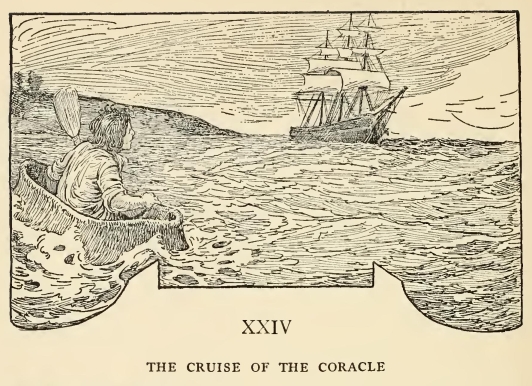
第二十四章 コラクルの航海
私が目を覚ますと、すっかり昼になっており、宝島の南西の端で揺られていることに気づいた。太陽は昇っていたが、巨大な「遠見山」の塊の向こうにまだ隠れていた。山のこちら側は、恐ろしい断崖となってほとんど海まで落ち込んでいた。
ホールボーライン岬とミズンマストの丘がすぐそばにあった。丘はむき出しで暗く、岬は高さ四十フィートか五十フィートの崖に囲まれ、巨大な落石の塊で縁取られていた。私は海に向かって四分の一マイルも離れておらず、最初の考えは漕いで上陸することだった。
その考えはすぐに諦めた。落石の間では、砕け波がしぶきを上げ、うなり声を上げていた。大きな反響音、飛び散っては落ちる重い水しぶきが、刻一刻と続いていた。もしこれ以上近づけば、ごつごつした岸に叩きつけられて死ぬか、そそり立つ岩壁を登ろうとして無駄に体力を消耗する自分の姿が見えた。
それだけではなかった。平らな岩の上を這い回り、あるいは大きな音を立てて海に飛び込む、巨大でぬるぬるした怪物を見たのだ――信じられないほど大きな、いわば柔らかいカタツムリのような生き物だ――四十から六十匹が一緒におり、その吠え声で岩に反響させていた。
その後、それらがアシカで、全く無害なものだと理解した。しかし、その見た目は、岸の困難さと波の高さと相まって、その上陸地点に嫌悪感を抱かせるには十分すぎた。私は、そのような危険に立ち向かうくらいなら、海で飢え死にする方がましだと感じた。
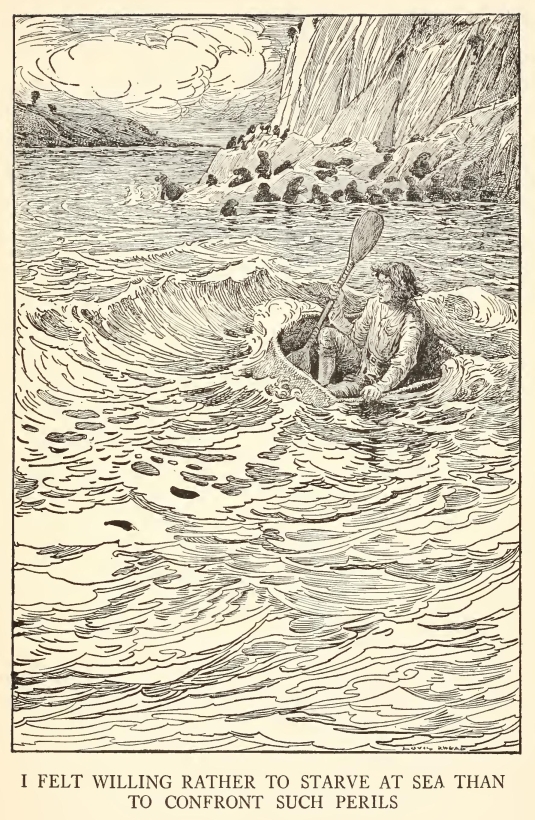
その間、私の前には、もっと良い機会があるように思われた。ホールボーライン岬の北では、陸地が長く続き、干潮時には長い黄色の砂浜が広がっていた。そのさらに北には、別の岬があった――海図に記されていた「森の岬」だ――背の高い緑の松に覆われ、その松林は海の縁まで続いていた。
私は、宝島の西海岸全体に沿って北へ向かう潮流についてシルバーが言っていたことを思い出した。そして、自分の位置からして、すでにその影響下にあることがわかったので、ホールボーライン岬を後にし、もっと穏やかに見える森の岬に上陸を試みるために体力を温存することにした。
海には、大きく滑らかなうねりがあった。風は南から安定して穏やかに吹いており、それと潮流との間に逆らいはなく、大波は砕けることなく上下していた。
もしそうでなかったら、私はとっくに死んでいただろう。しかし、実際には、私の小さくて軽いボートが、いかに簡単かつ安全に波に乗れるかは驚くべきことだった。しばしば、私はまだ底に横たわり、船べりから片目だけを出していると、すぐ上に大きな青い頂が盛り上がるのが見えた。それでもコラクルは、少し跳ね、ばねの上で踊るようにして、反対側の谷へと鳥のように軽やかに沈んでいった。
少しして、私は非常に大胆になり、座り上がってパドルを漕ぐ腕前を試してみた。しかし、コラクルは、ほんの少しの重心の変化でさえ、その挙動に激しい変化を生じさせる。そして、私が身動きするやいなや、ボートは優雅に踊るような動きをすっかりやめ、目もくらむような急な水の斜面をまっすぐに駆け下り、水しぶきを上げて、次の波の側面に船首を深く突き刺した。
私はずぶ濡れになり、恐怖にかられ、即座に元の姿勢に戻った。するとコラクルは再び調子を取り戻したかのように、以前と同じように穏やかに私を大波の間へと導いた。この船には手出し無用なのは明らかだった。そしてこの調子では、私がその進路に全く影響を与えられない以上、陸地にたどり着く望みは、一体どこに残されているというのか?
私はひどく怖くなり始めたが、それでも冷静さを保った。まず、細心の注意を払って動き、船乗り帽でコラクルの水を徐々にかき出した。それから、再び船べりから目を出し、この船がどうやってうねりの間をこれほど静かにすり抜けていくのかを研究し始めた。
私は、それぞれの波が、岸や船の甲板から見えるような、大きくて滑らかで光沢のある山ではなく、まさしく陸地のどんな山脈とも同じで、峰や平坦な場所や谷に満ちていることを見出した。コラクルは、放っておかれると、左右に向きを変えながら、いわば、これらの低い部分を縫って進み、急な斜面や、崩れ落ちそうな高い波の頂を避けていた。
「さて」と私は独りごちた。「今の場所に横たわって、バランスを崩さないようにしなければならないのは明らかだ。しかし、パドルを船べりから出して、時々、穏やかな場所で、陸に向かって一、二度押してやることができるのも明らかだ」思うが早いか、私は実行に移した。私は最もきつい姿勢で肘をついて横たわり、時折、弱いひと漕ぎかふた漕ぎをして、船首を岸に向けた。
それは非常に骨の折れる、遅々とした作業だったが、それでも私は目に見えて前進していた。森の岬に近づくにつれて、その地点は間違いなく通り過ぎてしまうとわかったが、それでも東へ数百ヤードは進んでいた。私は、実に、岸に近づいていた。涼しげな緑の木々の梢が風に一緒に揺れているのが見え、次の岬には必ずたどり着けると確信した。
ちょうど良い頃合いだった。というのも、私は今や喉の渇きに苦しみ始めていたからだ。上からの太陽の輝き、波からの幾千もの反射、私に降りかかっては乾き、唇を塩で固める海水が、相まって私の喉を焼き、頭を痛ませた。すぐ近くに見える木々の光景は、切望のあまり気分が悪くなるほどだったが、潮流はすぐに私をその岬から運び去り、次の海域が開けると、私は自分の考えの性質を変える光景を目にした。
私の真正面、半マイルも離れていないところに、帆を張ったヒスパニオラ号が見えた。もちろん、捕まるだろうと覚悟した。しかし、私は水の欠乏でひどく苦しんでいたので、その考えに喜ぶべきか悲しむべきか、ほとんどわからなかった。そして、結論を出すずっと前に、驚きが私の心を完全に占領し、私はただ見つめて驚くことしかできなかった。
ヒスパニオラ号は主帆と二枚の船首三角帆を張っており、その美しい白い帆布は太陽の光を浴びて雪か銀のように輝いていた。最初に彼女を見つけた時、帆はすべて風をはらんでいた。彼女は北西に進路をとっており、船上の男たちは停泊地に戻る途中で島の周りを回っているのだろうと推測した。やがて、彼女はますます西へと向かい始めたので、私を見つけて追跡のために向きを変えているのだと思った。しかし、ついに彼女は風の真正面に入り込み、帆が裏帆になって完全に停止し、帆を震わせながら、しばらく無力な状態でそこに立っていた。
「不器用な連中だ」と私は言った。「まだフクロウのように酔っぱらっているに違いない」そして、スモレット船長なら彼らをどう働かせるだろうかと考えた。
その間にもスクーナー船は徐々に風下に流され、再び帆に風をはらんで別の方角へ進み、一分ほど快走しては、またもや風に真正面から逆らってぴたりと動きを止めた。これが何度も何度も繰り返された。あちらへこちらへ、上へ下へ、北へ、南へ、東へ、西へと、ヒスパニオラ号はひらりひらりと舞うように進んでは、そのたびに帆をだらしなくはためかせ、最初の状態に戻ってしまうのだった。誰も舵を取っていないことは、私にも明らかになった。だとすれば、男たちはどこにいるのだ? 泥酔しているか、船を捨てたかのどちらかだろう、と私は考えた。もし乗り込むことができれば、船長の元へこの船を返すことができるかもしれない。
潮流は、コラクル舟とスクーナー船を同じ速さで南へと運んでいた。後者の航行はといえば、あまりに乱暴で断続的であり、そのつど帆が風をはらまずに長時間立ち往生するため、たとえ後退こそしていないにせよ、前進しているとは到底言えなかった。もし勇気を出して身を起こし、パドルを漕ぐことさえできれば、追いつけるのは確実だった。その計画には冒険の匂いがして私の心を掻き立て、フォア・コンパニオン[訳注:前部昇降口]のそばにある水樽のことが、膨れ上がる勇気を倍加させた。
私は立ち上がった。するとほとんど間髪を入れず、またもや水しぶきが雲のように降りかかってきたが、今度は決意を固く持ち、全力と細心の注意を払って、舵手のいないヒスパニオラ号の後を追ってパドルを漕ぎ始めた。一度、あまりに大きな波をかぶってしまい、心臓が鳥のようにばくばくと高鳴る中、舟を止めて水を掻き出さねばならなかった。しかし、次第に要領を得て、時折船首に波を受け、顔に泡を浴びる程度で、波間を縫ってコラクル舟を操れるようになった。
今や私はスクーナー船に急速に追いつきつつあった。舵柄の真鍮が、揺れ動くたびにきらりと光るのが見えたが、甲板には依然として人っ子一人現れない。船は見捨てられたのだと考えるしかなかった。もしそうでなければ、男たちは船倉で酔いつぶれているのだろう。それならば、彼らを閉じ込めて、この船を意のままにできるかもしれない。
しばらくの間、船は私にとって最悪の動きをしていた――つまり、ほとんど停滞していたのだ。もちろん常に左右に揺れながらも、ほぼ真南に船首を向けていた。風下に流されるたびに帆が部分的に風をはらみ、その力で一瞬にして再び風上へと船首を向けてしまう。これが私にとって最悪だと言ったのは、帆が砲声のように鳴り響き、滑車が甲板をごろごろと音を立てて転がるこの状況では、船が無力に見えるにもかかわらず、潮流の速さに加え、当然ながら大きい風圧差の分だけ、私から離れ続けていたからだ。
しかし、ついに好機が訪れた。風が数秒間、非常に弱まり、潮流が徐々に船体を回転させた。ヒスパニオラ号はその中心を軸にゆっくりと向きを変え、ついに私に船尾を見せた。船室の窓はぽっかりと開いたままで、テーブルの上のランプは、日中にもかかわらずまだ燃え続けている。メインセイル[訳注:主帆]は旗のように垂れ下がっていた。潮流の力を除けば、船は完全に静止していた。
ほんの少し前まで、私は距離を離されさえしていたが、今や努力を倍加し、再び追跡対象に追いつき始めた。
船まで百ヤードもない距離になったとき、風が再びぱっと吹いた。ヒスパニオラ号は左舷に風を受け、ツバメのように身を傾けて滑るように走り出した。
最初の衝動は絶望だったが、二番目の衝動は歓喜へと向かっていた。船は向きを変え、私に対して真横になった――さらに回り続け、我々を隔てていた距離の半分、そして三分の二、四分の三を埋めていった。船首の下で波が白く沸き立っているのが見えた。コラクル舟の低い位置から見上げると、船は途方もなく高くそびえていた。
そして、突然、私は状況を理解し始めた。考える暇も、行動して身を守る暇もほとんどなかった。私がうねりの頂点にいたとき、スクーナー船が次のうねりに向かって突っ込んできた。バウスプリット[訳注:船首斜檣]が頭上を覆った。私は跳び上がり、コラクル舟を水中に踏みつけながら跳躍した。片手でジブブーム[訳注:船首の突出帆の支柱]を掴み、足はステイとブレースの間に引っかかった。息を切らしてしがみついていると、鈍い衝撃が、スクーナー船がコラクル舟に突っ込み、粉砕したことを告げた。私はヒスパニオラ号の上に取り残され、退路を断たれたのだった。
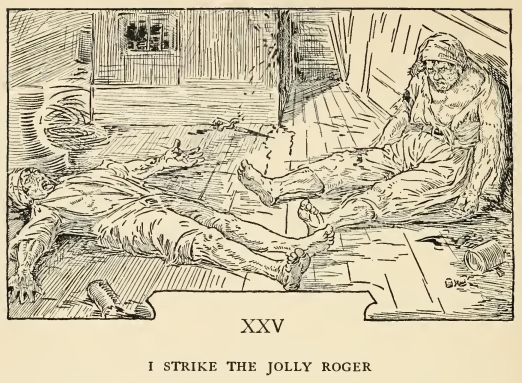
第二十五章 海賊旗を降ろす
私がバウスプリットにどうにか体勢を落ち着けた途端、フライングジブ[訳注:最前部の三角帆]がはためき、反対舷から風を受けて、銃声のような音を立てた。スクーナー船は竜骨まで揺さぶられたが、次の瞬間には、他の帆はまだ風を受けているものの、ジブは再びばさりと翻り、だらりと垂れ下がった。
この衝撃で、私はもう少しで海に放り出されるところだった。もはや一刻の猶予もない。私はバウスプリットを這い戻り、甲板に頭から転がり込んだ。
私は船首楼の風下側にいた。まだ風をはらんでいるメインセイルが、後部甲板の一部を私の視界から隠していた。人影は一つも見えない。反乱以来一度も拭かれていない厚板には、無数の足跡が残り、首の折れた空き瓶が、まるで生き物のように排水溝をごろごろと転がっていた。
突然、ヒスパニオラ号が真正面から風を受けた。私の背後でジブがけたたましい音を立て、舵がばたんと打ち付けられ、船全体がむかつくような揺れと震えに見舞われた。それと同時に、メインブームが船内側に大きく振れ、滑車の中でシート[訳注:帆を操作するロープ]が軋み、風下側の後部甲板が私の目に晒された。
そこには確かに二人の見張りがいた。赤い帽子の男は、てこ棒のように硬直して仰向けに倒れ、両腕は十字架のように広げられ、開いた唇からは歯がのぞいていた。イスラエル・ハンズはブルワーク[訳注:舷墻]にもたれかかり、顎を胸につけ、両手は甲板の上にだらりと投げ出され、日焼けした顔は獣脂の蝋燭のように真っ白だった。
しばらくの間、船は悪癖のある馬のように跳ねたり横っ飛びしたりを繰り返し、帆は右舷に風を受けたり左舷に受けたりし、ブームはマストが悲鳴を上げるほど左右に揺れ続けた。時折、軽い水しぶきの雲がブルワークを越えて降りかかり、船首がうねりに重々しく打ち付けられた。この巨大な帆船が起こす荒天は、今や海の底に消えた自家製の歪なコラクル舟とは比べものにならなかった。
スクーナー船が跳ねるたびに、赤い帽子の男はあちこちに滑ったが――見るも不気味なことに――その姿勢も、歯をむき出した不気味な笑顔も、この手荒い扱いで少しも乱れることはなかった。跳ねるたびに、ハンズはさらに身を沈め、甲板に崩れ落ちていくように見えた。足はますます外側へと滑り出し、体全体が船尾の方へ傾いていったため、彼の顔は次第に私から見えなくなり、しまいには彼の耳と、ほつれた巻き毛のもみあげしか見えなくなった。
同時に、私は二人の周囲の厚板に、黒ずんだ血しぶきが飛び散っていることに気づき、彼らが酔った怒りにまかせて殺し合ったのだと確信するようになった。
私がそうして眺め、思いを巡らせていると、船が静止した穏やかな一瞬に、イスラエル・ハンズが半分ほど向きを変え、低い呻き声をあげながら、私が最初に見た体勢へと身を捩った。痛みと致命的な衰弱を物語るその呻き声と、だらりと開いた顎の様子は、私の心を強く打った。しかし、リンゴ樽の中から聞き耳を立てた会話を思い出すと、哀れみの情はすべて消え去った。
私は船尾の方へ歩き、メインマストまでたどり着いた。
「乗船ご苦労、ハンズさん」と私は皮肉を込めて言った。
彼は重々しく目を動かしたが、驚きを表すにはあまりに衰弱しきっていた。彼にできたのは、ただ一言、「ブランデー」と呟くことだけだった。
ぐずぐずしている時間はないと悟った私は、再び甲板を横切って揺れるブームを避け、船尾に滑り込み、コンパニオンの階段を降りて船室へと入った。
そこは想像を絶するほどの混乱ぶりだった。錠のかかった場所は、海図を探すためにことごとくこじ開けられていた。床は泥で厚く汚れ、無法者どもが自分たちの野営地の周りの沼地を歩き回った後、腰を下ろして酒を飲んだり相談したりした跡だった。真っ白に塗られ、金箔の縁取りが施された隔壁には、汚れた手形が模様のように付いていた。隅には何十本もの空き瓶が、船の揺れに合わせてカチャンカチャンと音を立てていた。テーブルの上には、医者の医学書の一冊が開いたまま置かれ、葉の半分が引きちぎられていた。おそらくパイプの火種にでもしたのだろう。この混乱の真っ只中で、ランプは今なお煤けた光を放ち、アンバー[訳注:黄褐色絵具]のように薄暗く茶色がかっていた。
私は地下室へ入った。樽はすべてなくなり、瓶のほうも驚くほどの数が飲み干されて捨てられていた。反乱が始まって以来、彼らのうち誰一人として、しらふでいた者はいなかったに違いない。
あたりを探し回り、ハンズのためにブランデーが少し残った瓶を一つ見つけた。自分用には、ビスケットをいくつか、果物のピクルス、干しブドウの大房、そしてチーズをひとかけら探し出した。これらを持って甲板に上がり、自分の食料は舵頭の後ろ、操舵手の届かない場所に置き、水樽のところまで進んで冷たい水を腹一杯飲み、それから、ようやくハンズにブランデーを渡した。
彼は瓶を口から離すまでに、一ジル[訳注:約140ml]は飲んだに違いない。
「ああ」と彼は言った。「ちくしょうめ、こいつが欲しかったんだ!」
私はすでに自分の隅に腰を下ろし、食べ始めていた。
「ひどい怪我か?」と私は尋ねた。
彼は唸った。いや、吠えたと言った方がいいかもしれない。
「あの医者が船に乗ってりゃあな」と彼は言った。「二、三日もすりゃあ良くなるだろうが、俺には運ってもんがまるでないんでな、それが問題なんだ。そこのクズ野郎ときたら、とっくに死んじまってる」と、彼は赤い帽子の男を指して付け加えた。「どのみち船乗りじゃなかったがな。それで、お前さんはどこから来たんだ?」
「そうだな」と私は言った。「この船を手に入れるために乗り込んできた、ハンズさん。今後の通知があるまで、私をあんたの船長だと思ってもらおう。」
彼は不機嫌そうな顔で私を見つめたが、何も言わなかった。頬にはいくらか血の気が戻っていたが、まだひどく具合が悪そうで、船が揺れるたびにずるずると滑り落ち、甲板に崩れ落ちそうになるのは変わらなかった。
「ところで」と私は続けた。「この旗は気に入らないな、ハンズさん。失礼して、降ろさせてもらう。こんなものより、ない方がましだ。」
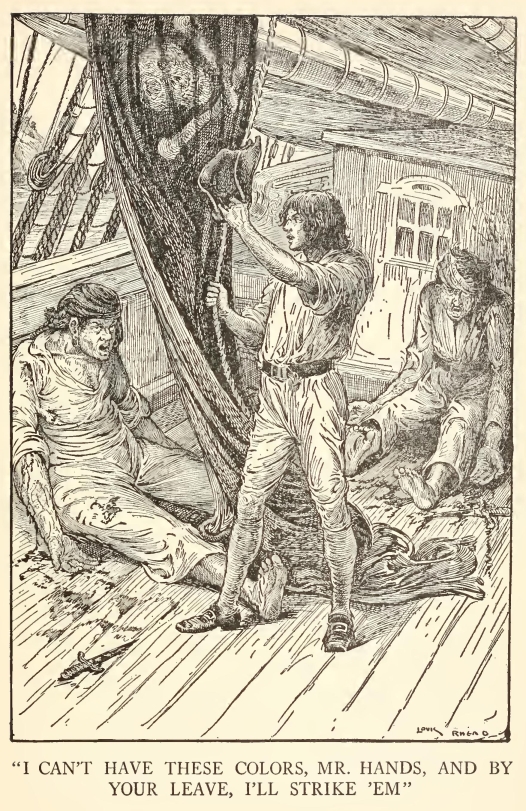
そして再びブームを避け、私は旗の掲揚索へと走り寄り、呪わしい黒旗を引きずり下ろし、海へと放り投げた。
「国王陛下万歳!」と私は帽子を振りながら言った。「これでシルバー船長もおしまいだ!」
彼は鋭く、そして狡猾な目で私を見ていた。その間もずっと、顎は胸についたままだった。
「思うに」と彼はついに口を開いた。「思うに、ホーキンズ船長、あんたはそろそろ陸に上がりたくなる頃だろう。ちと話をしようじゃないか。」
「ああ、もちろんだとも、ハンズさん。話してくれ」と私は答え、食欲も旺盛に食事に戻った。
「こいつは」と彼は死体を弱々しく指して話し始めた。「――オブライエンって名前でな、生粋のアイルランド野郎だった――こいつと俺で帆を張って、船を戻そうとしてたんだ。まあ、こいつはもう死んだがな、船底の汚水みたいにな。で、誰がこの船を動かすんだって話だが、俺には分からん。俺がヒントをやらなきゃ、あんたにゃ無理だ、俺が見る限りな。さあ、よく聞け。あんたが俺に食い物と飲み物をくれて、古傷を縛るスカーフかハンカチでもくれりゃあ、俺があんたに船の動かし方を教えてやる。これで五分五分ってとこだろ、どうだ。」
「一つ言っておく」と私は言った。「キッド船長の停泊地には戻らない。北の入江に入って、静かに座礁させるつもりだ。」
「そりゃあ、そうだろうとも!」と彼は叫んだ。「なんだ、俺もそれほど間抜けな陸lubber[訳注:船乗りが陸の人間を侮っていう言葉]じゃなかったわけだ。分かるさ、なあ? 一か八かやってみたが、負けた。あんたに風は吹いてる。北の入江? そりゃあ、俺に選択の余地はねえよ、まったくな! 処刑ドックまでだって、喜んで操船を手伝ってやるぜ、ちくしょうめ! ああ、やってやるとも。」
まあ、私には、彼の言うことにも一理あるように思えた。我々はその場で取引を決めた。三分もしないうちに、私はヒスパニオラ号を宝島の海岸に沿って順風に走らせていた。正午までには北の岬を回り、満潮になる前に北の入江まで南下できるという良い見込みがあった。そこでなら安全に座礁させ、潮が引いて上陸できるようになるまで待つことができるだろう。
それから私は舵柄を固定し、船室の自分の衣類箱のところへ降りていった。そこで母の柔らかい絹のハンカチを手に入れた。これを使って、私の助けを借りながら、ハンズは太ももに受けた深く血を流す刺し傷を縛った。少し食べ、ブランデーをもう一口二口飲むと、彼は目に見えて元気を取り戻し始め、背筋を伸ばして座り、より大きくはっきりとした声で話し、あらゆる面で別人のように見えた。
風は我々に申し分なく味方した。我々は鳥のように風に乗って滑り、島の海岸が次々と流れ去り、景色は刻々と変わっていった。やがて高地を過ぎ、背の低い松がまばらに生える低い砂地を疾走し、すぐにそこも通り過ぎて、島の北端をなす岩山の角を曲がった。
私は新たな指揮官という立場に大いに高揚し、明るい日差しと、様々に変化する海岸の景色に満足していた。水もおいしい食べ物も十分にあり、脱走のことで私を厳しく苛んでいた良心も、成し遂げた偉大な征服によって静まっていた。思うに、もし操舵手の目が甲板で嘲るように私を追い、その顔に絶えず浮かぶ奇妙な笑みがなければ、私に望むものは何も残っていなかっただろう。それは痛みと弱さの両方を含んだ笑み――やつれた老人の笑みだった。しかし、それだけでなく、彼が狡猾に私の仕事を見張り、見張り、見張り続けるその表情には、一抹の嘲りと、裏切りの影が宿っていた。
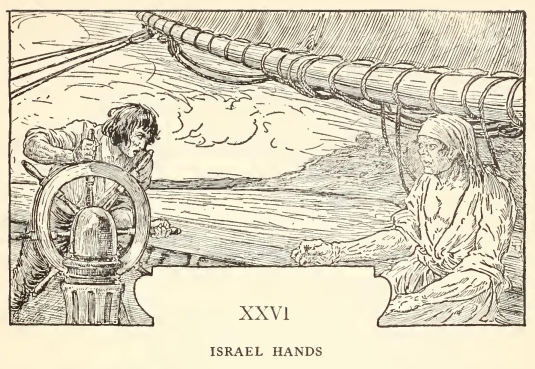
第二十六章 イスラエル・ハンズ
風は、我々の望み通りに、西へと向きを変えた。島の北東の角から北の入江の入り口まで、より容易に航行できるようになった。ただ、我々には錨を下ろす力がなく、潮がかなり満ちるまで座礁させる勇気もなかったので、時間を持て余すことになった。操舵手は私に船を風上に向けて停船させる方法を教えた。何度か試みた後、私は成功し、我々は二人とも黙って次の食事をとった。
「船長」と彼は、例の不快な笑みを浮かべながら、やがて口を開いた。「ここに俺の古い船仲間、オブライエンがいます。こいつを船外に放り投げちまっちゃどうです。俺は普段、細かいこたあ気にしねえし、こいつの始末をつけたことに何の咎めも感じちゃいねえが、今となっては飾っとくようなもんでもねえでしょう、そうだろ?」
「私にはそんな力はないし、そんな仕事はごめんだ。私としては、あいつはあそこに寝かせておく」と私は言った。
「このヒスパニオラ号は不運な船だ、ジム」と彼は瞬きしながら続けた。「このヒスパニオラ号では大勢の人間が殺された――あんたと俺がブリストルで乗船して以来、哀れな船乗りどもが山ほど死んでいった。こんなひどい不運は見たことがねえよ、俺はな。このオブライエンもそうだ――死んだろ? さて、俺は学者じゃねえし、あんたは読み書きも計算もできる坊やだ。単刀直入に聞くが、死んだ人間はそれで終わりだと思うか、それともまた生き返ると思うか?」
「肉体は殺せても、魂は殺せない、ハンズさん。それはあんただって知っているはずだ」と私は答えた。「そこにいるオブライエンは別の世界にいて、我々を見ているかもしれない。」
「ああ!」と彼は言った。「そいつは不運だな――どうやら人殺しは時間の無駄だったようだ。だがまあ、俺が見てきた限りじゃ、魂なんてものは大して当てにならねえ。魂相手に一か八かやってみるさ、ジム。さて、あんたが腹を割って話してくれたんだ、親切に頼むぜ、ちと下の船室に降りて、俺に――ええと、その――ちくしょうめ! 名前が出てこねえ。まあ、ワインを一本持ってきてくれ、ジム――このブランデーは頭にきつすぎる。」
さて、操舵手の口ごもり方は不自然に思えたし、ブランデーよりワインを好むという考えに至っては、私は全く信じなかった。話のすべてが口実だった。彼は私に甲板を離れてほしかった――それは明らかだったが、その目的が何なのかは皆目見当がつかなかった。彼の目は決して私と合わず、あちこち、上下へとさまよい、空を見上げたかと思えば、死んだオブライエンにちらりと視線を投げかけた。その間ずっと彼は笑みを浮かべ、罪悪感と決まり悪さからか、しきりに舌なめずりをしていたので、子供でも彼が何か企んでいると分かっただろう。しかし、私はすぐさま返事をした。自分の有利な点がどこにあるか、そしてこれほど鈍い相手なら、最後まで疑念を隠し通すのは容易だと分かっていたからだ。
「ワインだって?」と私は言った。「その方がずっといい。白がいいか、赤がいいか?」
「ああ、どっちでも大して変わりゃしねえよ、船仲間」と彼は答えた。「強くて、たっぷりありゃあ、何だっていいさ。」
「分かった」と私は答えた。「ポートワインを持ってこよう、ハンズさん。だが、探さなきゃならないな。」
そう言うと、私はできるだけ大きな音を立ててコンパニオンを駆け下り、靴を脱ぎ、梁の渡された通路を静かに走り、船首楼のはしごを登り、フォア・コンパニオンからひょいと頭を出した。彼がそこに私を見るとは思っていないだろうとは分かっていたが、私は可能な限りの警戒を怠らなかった。そして案の定、私の最悪の疑いはあまりにも真実であることが証明された。
彼は座った姿勢から四つん這いになっていた。動くたびに足がかなり鋭く痛むのは明らかだった――彼が呻き声を押し殺すのが聞こえたからだ――それでも、彼はかなりの速さで甲板を横切っていった。半分のうちに彼は左舷の排水溝にたどり着き、巻かれたロープの中から長いナイフ、というよりは短い短剣を拾い上げた。それは柄まで血で変色していた。彼は一瞬それを見つめ、下顎を突き出し、手のひらで切っ先を試し、そして急いで上着の胸に隠すと、再びブルワークにもたれた元の場所へと戻っていった。
私が知る必要があったのはこれだけだった。イスラエルは動き回ることができ、今や武装している。そして、私を追い払うためにこれほどの手間をかけたのであれば、私が犠牲者になる運命であることは明白だった。彼がその後どうするつもりなのか――北の入江から沼地の野営地まで島を這って横断しようとするのか、それともロング・トム[訳注:船に備え付けられた大砲]を撃ち、仲間が先に助けに来ることを期待するのか――それは、もちろん私には言いようもなかった。
しかし、一点だけは彼を信用できると確信していた。その点では我々の利害が一致していたからだ。それはスクーナー船の処置についてだった。我々は二人とも、船を安全な場所にしっかりと座礁させ、時が来ればできるだけ少ない労力と危険で再び離礁させられるようにしたいと望んでいた。そして、それが済むまでは、私の命は間違いなく助かるだろうと考えていた。
そうして心の中で事態をあれこれ考えている間も、私の体は怠けていたわけではなかった。私はこっそり船室に戻り、再び靴を履き、手当たり次第にワインの瓶を一つ手に取った。そして今、これを口実に、私は甲板に再び姿を現した。
ハンズは私が離れた時と同じように、ぐったりと体を丸め、まぶたを閉じていた。まるで光に耐えられないほど衰弱しているかのようだった。しかし、私がやって来ると彼は顔を上げ、手慣れた男のように瓶の首を叩き割り、お気に入りの乾杯の言葉「幸運を!」と共にぐいっと一口飲んだ。それから少し静かにしていたが、やがてタバコの棒を取り出し、一切れ噛みタバコを切ってくれと頼んだ。
「そいつをひとかじり切ってくれ」と彼は言った。「ナイフもねえし、あったとしても力がほとんどねえんだ。ああ、ジム、ジム、俺はもうおしまいだ! ひとかじり切ってくれ、これが最後になるだろうよ、坊や。俺は長い故郷[訳注:墓のこと]へ行くんだ、間違いなくな。」
「いいだろう」と私は言った。「タバコは切ってやる。だが、もし私が君で、自分のことをそれほど悪く思っているなら、キリスト教徒らしく祈りを捧げるだろうな。」
「なぜだ?」と彼は言った。「さあ、理由を言ってみろ。」
「なぜかって?」私は叫んだ。「あんたはさっき死人について尋ねていたじゃないか。あんたは信頼を裏切り、罪と嘘と血にまみれて生きてきた。あんたが殺した男が、今この瞬間、足元に横たわっている。それでなぜかと聞くのか! 神の慈悲のためだ、ハンズさん、それが理由だ。」
私は少し熱を込めて話した。彼が懐に隠し、邪悪な考えで私を始末しようと企んでいる血まみれの短剣のことを思っていたからだ。彼は彼で、ワインをぐいっと飲み干し、珍しく厳粛な口調で語った。
「三十年間」と彼は言った。「俺は海を渡り、良いことも悪いことも、もっと良いことももっと悪いことも、晴天も荒天も、食料が尽きるのも、ナイフが飛び交うのも、何でも見てきた。さて、今お前に言おう。俺は善行が良い結果を生んだのを一度も見たことがねえ。先に殴った奴が俺の好みだ。死人に口なし。それが俺の考えだ――アーメン、そうあれかし。さて、よく聞け」と彼は突然口調を変えて付け加えた。「この馬鹿げた話はもう十分だ。潮はもう十分に満ちた。俺の命令に従え、ホーキンズ船長。さっさと乗り入れて、終わらせちまおう。」
全部で、我々が走るべき距離は二マイルもなかった。しかし、航海は繊細なもので、この北の停泊地への入り口は狭くて浅いだけでなく、東西に横たわっていたため、スクーナー船を中に入れるには巧みに操船する必要があった。私は機敏で優秀な部下だったと思うし、ハンズが素晴らしい水先案内人であったことは間違いない。我々は何度も向きを変え、岸をかすめるようにして巧みに入っていった。その確実さと見事さは、見ていて楽しいほどだった。
岬を通過するやいなや、陸が我々の周りを囲んだ。北の入江の岸は、南の停泊地と同じくらい木々が密集していたが、空間はより長く、より狭く、実のところそうであるように、川の河口のようだった。我々の真正面、南の端には、最後の崩壊段階にある難破船が見えた。それは三本マストの大きな船だったが、あまりに長く風雨に晒されていたため、滴る海藻の大きな網に覆われ、甲板には岸の茂みが根付き、今では花々が咲き誇っていた。悲しい光景だったが、それは停泊地が穏やかであることを我々に示していた。
「さあ」とハンズが言った。「あそこを見ろ。船を座礁させるにはうってつけの場所だ。きれいで平らな砂浜、猫の足跡一つない[訳注:波一つない穏やかな水面の意]、周りは木々に囲まれ、あの古い船の上では庭のように花が咲いている。」
「一度座礁させたら」と私は尋ねた。「どうやってまた離礁させるんだ?」
「こうするんだ」と彼は答えた。「干潮の時に向こう岸にロープを一本持っていき、あの大きな松の木に一巻きする。それを持ち帰り、キャプスタン[訳注:巻き上げ機]に一巻きして、潮を待つ。満潮になったら、全員でロープを引けば、自然の摂理のようにすんなり離礁する。さあ、坊や、準備しろ。もうすぐだ、船の勢いがつきすぎてる。右舷へ少し――そうだ――そのまま――右舷――左舷へ少し――そのまま――そのまま!」
彼はそう命令を下し、私は息を殺してそれに従った。すると、突然、彼が叫んだ。「さあ、野郎ども、風上だ!」そして私が舵をいっぱいに回すと、ヒスパニオラ号は素早く旋回し、木々の茂る低い岸辺に船首から突っ込んでいった。
これらの最後の操船の興奮で、それまで操舵手に対して鋭く保っていた警戒がいくらかおろそかになっていた。その時でさえ、私は船が岸に触れるのを待つことに夢中で、頭上に迫る危険をすっかり忘れ、右舷のブルワークから身を乗り出して、船首の前に広がる波紋を見つめていた。もし突然の不安が私を襲い、頭を振り向かせなければ、私は命をかけて戦うこともなく倒れていたかもしれない。きしむ音を聞いたのかもしれないし、彼の影が視界の隅で動いたのを見たのかもしれない。あるいは猫のような本能だったのかもしれない。しかし、確かに、私が振り向くと、そこにはハンズが、すでに私の方へ半ばまで近づき、右手に短剣を握っていた。
我々の目が合った時、我々は二人とも大声で叫んだに違いない。だが、私のが恐怖の甲高い叫びだったのに対し、彼のは突進する暴れ牛のような怒りの雄叫びだった。その瞬間、彼は前方に身を投げ出し、私は船首の方へ横っ飛びに跳んだ。そうする際に、私は舵柄から手を離した。舵柄は風下側へ鋭く跳ね返り、これが私の命を救ったのだと思う。それはハンズの胸を打ち、一瞬、彼をぴたりと止めたからだ。
彼が体勢を立て直す前に、私は彼に追い詰められていた隅から安全な場所へ脱出し、甲板中を逃げ回ることができた。メインマストのすぐ前で私は立ち止まり、ポケットからピストルを抜き、冷静に狙いを定めた――彼はすでに振り向き、再びまっすぐ私を追ってきていたが――そして引き金を引いた。撃鉄は落ちたが、閃光も音も続かなかった。火薬は海水で湿っていたのだ。私は自分の怠慢を呪った。なぜもっと早く、唯一の武器に火薬を詰め直し、再装填しておかなかったのか? そうすれば、今のように、この屠殺人の前でただ逃げ惑う子羊になることはなかっただろう。
彼は負傷していたにもかかわらず、驚くほど速く動くことができた。白髪混じりの髪が顔にかかり、その顔自体は焦りと怒りで赤旗のように真っ赤だった。もう一丁のピストルを試す時間も、実のところその気もあまりなかった。どうせ役に立たないと確信していたからだ。一つだけはっきりと分かっていた。彼の前からただ後ずさりしていてはいけない。さもなければ、先ほど船尾で追い詰められそうになったように、すぐに船首に追い詰められてしまうだろう。一度捕まれば、血に染まった九インチか十インチの短剣が、この世での私の最後の経験となるだろう。私は手のひらを、かなりの太さがあるメインマストに当て、神経を張り詰めて待った。
私が身をかわすつもりだと見て、彼も立ち止まった。そして一、二分、彼の側からの見せかけの動きと、私の側のそれに応じた動きが続いた。それは、ブラック・ヒル・コーブの岩場でよく遊んだようなゲームだったが、これほど心臓を激しく打ち鳴らしながらプレイしたのは、もちろん初めてだった。それでも、言ったように、それは子供のゲームであり、太ももを負傷した年配の船乗り相手なら、対等に渡り合えると思った。実際、私の勇気は非常に高まり始め、この一件がどう終わるかについて、いくつかの考えを巡らせる余裕さえあった。そして、長く引き延ばすことはできると確信しながらも、最終的に逃げ切る望みはないと分かっていた。
さて、事態がそのように膠着していると、突然ヒスパニオラ号が衝撃を受け、よろめき、一瞬砂に乗り上げ、そして、打撃のように素早く、左舷側に傾いた。甲板は四十五度の角度になり、パンチョン樽一杯分ほどの水が排水口に流れ込み、甲板とブルワークの間に水たまりを作った。
我々は二人とも一瞬のうちに転倒し、ほとんど同時に排水溝に転がり込んだ。腕を広げたままの死んだ赤い帽子の男が、硬直したまま我々の後を追って転がってきた。我々は実に近く、私の頭が操舵手の足に当たって歯がガチガチと鳴るほどの音がした。打撃を受けたにもかかわらず、先に立ち上がったのは私だった。ハンズが死体と絡み合っていたからだ。船が急に傾いたことで、甲板は走る場所ではなくなっていた。私は何か新しい逃げ道を見つけなければならなかったし、それは即座にでなければならなかった。敵はほとんど私に触れんばかりだったからだ。考えるよりも速く、私はミズンマストのシュラウド[訳注:マストを支える横索]に飛びつき、手繰り寄せるように駆け上がり、クロストゥリー[訳注:マストの横木]に腰を下ろすまで息もつかなかった。
機敏だったおかげで私は救われた。私が上へ逃げる途中、短剣は私の半フィートも下を突いていた。そしてそこには、口を開け、顔を私に向けて見上げるイスラエル・ハンズが立っていた。驚きと失望の完璧な彫像のようだった。
一息つく時間を得た私は、すぐさまピストルの火薬を交換し、そして、一丁が使える状態になると、念には念を入れて、もう一丁の弾を抜き、最初から装填し直す作業に取り掛かった。
私の新たな作業はハンズを完全に打ちのめした。彼は形勢が自分に不利になっていることを悟り始め、明らかにためらった後、彼も重々しくシュラウドによじ登り、歯に短剣をくわえて、ゆっくりと苦痛に満ちて登り始めた。負傷した足を引きずるのに、彼は果てしない時間と呻き声を費やした。彼が三分の一ほど登る前に、私は静かに準備を終えていた。そして、両手にピストルを持ち、私は彼に話しかけた。
「もう一歩でも動いてみろ、ハンズさん」と私は言った。「あんたの脳みそを吹き飛ばしてやる! 死人に口なし、だろ?」と私はくすくす笑いながら付け加えた。
彼はぴたりと止まった。彼の顔の動きから、彼が考えようとしているのが分かった。その過程は非常に遅く骨の折れるものだったので、新たに得た安全の中で、私は声を出して笑った。やがて、一、二度唾を飲み込んでから、彼は話した。その顔にはまだ極度の困惑の表情が浮かんでいた。話すために彼は口から短剣を離さなければならなかったが、それ以外の点では身じろぎ一つしなかった。
「ジム」と彼は言った。「どうやら俺たち、にっちもさっちもいかなくなったようだ、契約を結ぶしかあるまい。あの揺れがなけりゃあ、お前を仕留めてたんだがな、俺には運がねえ、まったくな。降参するしかねえようだ。こいつはきついぜ、分かるだろ、熟練の船乗りがお前みたいな船の若造に降参するってのはな、ジム。」
私は彼の言葉をうっとりと聞き、壁の上の雄鶏のように得意げに微笑んでいた。その時、一息に、彼の右手が肩越しに後ろへ引かれた。何かが矢のように空を切って飛んできた。私は衝撃を感じ、次に鋭い痛みを感じた。そして私は、肩をマストに縫い付けられていた。その瞬間の恐ろしい痛みと驚きの中で――それが自分の意志によるものだったとはほとんど言えないし、意識的な狙いがあったわけではないと確信している――私の両手のピストルが火を噴き、両方とも手から滑り落ちた。落ちたのはピストルだけではなかった。詰まったような叫び声と共に、操舵手はシュラウドから手を離し、頭から水中に飛び込んだ。

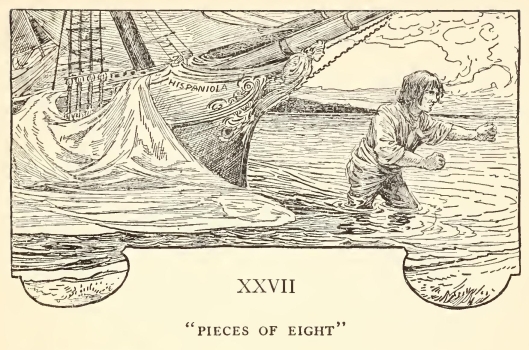
第二十七章 「八レアル銀貨。」
船が傾いているため、マストは水面の上に大きく突き出ており、クロストゥリーの私の止まり木の下には、湾の水面しかなかった。それほど高く登っていなかったハンズは、結果的に船に近く、私とブルワークの間に落ちた。彼は一度、泡と血の渦の中で水面に顔を出したが、再び沈み、二度と浮かび上がらなかった。水面が静まると、船の側面の影の中、きれいで明るい砂の上に、彼が体を丸めて横たわっているのが見えた。一、二匹の魚が彼の体のそばを素早く通り過ぎた。時折、水の揺らめきによって、彼はまるで起き上がろうとしているかのように、少し動いているように見えた。しかし、射殺され、溺死した彼は、どう見ても完全に死んでおり、まさに彼が私の殺害を企てたその場所で、魚の餌食となったのだった。
これを確信するやいなや、私は吐き気と目まいと恐怖を感じ始めた。熱い血が背中と胸を流れ落ちていた。肩をマストに縫い付けている短剣は、熱い鉄のように焼けるようだった。しかし、私を苦しめたのは、こうした現実の苦痛ではなかった。それらは、文句一つ言わずに耐えられるように思えたからだ。私を苦しめたのは、クロストゥリーからあの静かな緑色の水の中へ、操舵手の体のそばへと落ちてしまうのではないかという、心に巣食う恐怖だった。
爪が痛くなるまで両手でしがみつき、危険から目を背けるかのように目を閉じた。次第に正気を取り戻し、脈拍もより正常な速さに落ち着き、私は再び自分自身を取り戻した。
最初に考えたのは短剣を引き抜くことだったが、あまりに固く刺さっているのか、私の勇気がくじけたのか、激しい身震いと共に断念した。奇妙なことに、まさにその身震いが事を成した。実のところ、ナイフは私をかすめるところだったのだ。ほんのわずかな皮膚で私を留めていただけだったので、身震いがそれを引きちぎったのである。確かに血はより速く流れ出したが、私は再び自由の身となり、上着とシャツだけでマストに留められている状態になった。
これらを一気に引きちぎり、私は右舷のシュラウドを伝って甲板に戻った。これほど動揺している状態で、イスラエルが少し前に落ちた、水面の上に張り出した左舷のシュラウドを再び使う気には、何があってもなれなかった。
私は船室に降り、傷の手当てをできる限りした。傷はかなり痛み、まだかなり出血していたが、深くも危険でもなく、腕を使ってもひどく痛むことはなかった。それから私は周りを見回し、船が今や、ある意味で私自身のものになったので、最後の乗客――死んだ男、オブライエン――を片付けることを考え始めた。
彼は、私が言ったように、ブルワークに打ち付けられ、そこに横たわっていた。まるで何か恐ろしく、不格好な人形のようだった。等身大ではあったが、生命の色や美しさとはなんと異なっていることか! その体勢なら彼を簡単にどうにかできたし、悲劇的な冒険の習慣が死者に対する私の恐怖のほとんどをすり減らしていたので、私はまるで米ぬかの袋でも扱うように彼の腰をつかみ、一気に力を込めて船外に放り投げた。彼は大きな水音を立てて沈んでいった。赤い帽子が脱げ、水面に浮かんだままになった。水しぶきが収まるとすぐに、彼とイスラエルが並んで横たわり、二人とも水の揺らめきと共に揺れているのが見えた。オブライエンはまだかなり若い男だったが、ひどく禿げていた。彼は、自分を殺した男の膝にその禿げ頭を乗せ、素早い魚たちが二人の上を行き来していた。
今や私は船上で一人きりだった。潮はちょうど引き始めたところだった。太陽は日没まであと数度というところまで沈み、すでに西岸の松の木の影が停泊地を横切って伸び始め、甲板に模様を描いていた。夕風が吹き始め、東の二つの頂を持つ丘にうまく遮られてはいたが、索具がかすかに歌い始め、風をはらまない帆ががさがさと揺れ始めた。
私は船に危険が迫っていることに気づき始めた。ジブはすぐに降ろし、甲板にたたきつけたが、メインセイルはもっと厄介な問題だった。もちろん、スクーナー船が傾いたとき、ブームは船外に振り出され、その先端と帆の一、二フィートは水中にさえ浸かっていた。これがさらに危険を増していると思った。しかし、張りがあまりに強くて、手を出すのが半ば恐ろしかった。ついに私はナイフを取り出し、ハリヤード[訳注:帆を上げるロープ]を切った。ピーク[訳注:帆の上端]は即座に落ち、緩んだ帆布の大きな腹が水面に広く浮かんだ。そして、いくら引いてもダウンホール[訳注:帆を下げるロープ]がびくともしなかったので、私にできたのはそこまでだった。残りは、ヒスパニオラ号も私自身と同じく、運に任せるしかなかった。
この時までに、停泊地全体が影に覆われていた――最後の陽光が、森の空き地を通り抜け、難破船の花咲く外套の上に宝石のようにきらめいていたのを覚えている。肌寒くなり始め、潮は急速に海へと流れ去り、スクーナー船はますます舷側に傾いていった。
私は船首の方へ這っていき、下を覗き込んだ。十分に浅そうに見えたので、最後の安全策として切れたホーサー[訳注:係留用の大綱]を両手で持ち、そっと船外に身を躍らせた。水はかろうじて腰に届く程度だった。砂は固く、さざ波の跡で覆われていた。私は意気揚々と岸まで歩き、ヒスパニオラ号を、メインセイルを湾の水面に広く引きずったまま、横倒しにして残してきた。ほぼ同じ頃、太陽は完全に沈み、そよ風が夕闇の中、揺れる松の間を低く口笛のように鳴らしていた。
少なくとも、そしてついに、私は海を離れた。しかも手ぶらで戻ってきたわけではない。そこにはスクーナー船が横たわり、ついに海賊どもから解放され、我々の仲間が乗り込んで再び海に出る準備ができていた。私の心は、砦に帰り着き、自分の手柄を自慢すること以外には何もなかった。おそらく無断外出のことで少しは責められるかもしれないが、ヒスパニオラ号の奪還は決定的な答えであり、スモレット船長でさえ私が時間を無駄にしなかったと認めてくれるだろうと期待していた。
そう考えながら、意気揚々と、私は砦と仲間たちのいる家路へと顔を向け始めた。キッド船長の停泊地に流れ込む川のうち、最も東にある川が私の左手にある二つの頂を持つ丘から流れていることを思い出し、川がまだ細いうちに渡れるように、その方向へ進路を取った。森はかなり開けており、低い尾根に沿って進むと、すぐにその丘の角を曲がり、それからほどなくして、ふくらはぎの半ばまで水に浸かって川を渡った。
これで、私が島流しのベン・ガンに出会った場所の近くまで来たことになり、私はより慎重に、四方八方に目を配りながら歩いた。夕闇はほとんど完全に訪れ、二つの頂の間の裂け目に出ると、空に揺らめく光があるのに気づいた。私が判断するに、島の男が燃え盛る火の前で夕食を準備しているのだろう。しかし、彼がこれほど無頓着でいることに、私は心の中で不思議に思った。もし私がこの輝きを見ることができるなら、沼地の岸で野営しているシルバー自身の目にも届くのではないだろうか?
次第に夜はより黒くなり、目的地に向かって大まかにでも進むのがやっとだった。背後の二つの丘と右手の望遠鏡山はますますかすかになり、星はまばらで青白かった。私がさまよっていた低地では、茂みにつまずいたり、砂の穴に転がり込んだりし続けた。
突然、一種の明るさが私の周りに降り注いだ。見上げると、青白い月光が望遠鏡山の頂上に降り立ち、その後すぐに、何か広くて銀色のものが木々の後ろを低く動いているのが見え、月が昇ったことを知った。
これに助けられ、私は旅の残りを素早く進み、時には歩き、時には走りながら、焦る気持ちで砦に近づいていった。しかし、その前にある林を抜け始めると、私はペースを落とし、少し用心深く進むだけの分別は持ち合わせていた。味方に誤って撃ち殺されるなど、冒険の結末としてはあまりに情けないだろう。
月はますます高く昇り、その光は森のより開けた地区に、あちこち塊となって降り注ぎ始めた。そして私の真正面、木々の間に、異なる色の輝きが現れた。それは赤く熱を帯び、時折少し暗くなった――まるで、燃え尽きかけの焚き火の残り火のようだった。
それが何であるか、私にはどうしても思いつかなかった。
ついに私は空き地の境界までやって来た。西の端はすでに月光に浸っていた。残りの部分と、丸太小屋自体は、まだ長い銀色の光の筋でまだらになった黒い影の中にあった。家の反対側では、巨大な火が燃え尽きて真っ赤な残り火となり、月の柔らかな青白さと強く対照をなす、絶え間ない赤い反射光を放っていた。そよ風の音のほかには、動く人影も物音もなかった。
私は、心に大きな驚きと、おそらくは少しの恐怖も抱きながら、立ち止まった。大きな火を起こすのは我々のやり方ではなかった。実際、船長の命令で、我々は薪をいくらか節約していた。私は、自分が留守の間に何か悪いことが起こったのではないかと恐れ始めた。
私は東の端を回り、影にぴったりと身を潜め、暗闇が最も濃い手頃な場所で、柵を越えた。
念には念を入れ、私は四つん這いになり、音を立てずに家の角に向かって這っていった。近づくにつれて、私の心は突然、そして大いに軽くなった。それ自体は心地よい音ではなく、他の時にはしばしば不平を言ったものだが、その時ばかりは、友人たちが眠りの中で共にいびきをかいているのが、とても大きく平和で、音楽のように聞こえたのだ。見張りの美しい「異常なし」という海の叫び声も、これほど心強く私の耳に響いたことはなかった。
その一方で、一つだけ疑いのないことがあった。彼らはとんでもなくひどい見張りをしていた。もし今彼らに忍び寄っているのがシルバーとその部下たちだったら、誰一人として夜明けを見ることはなかっただろう。船長が負傷しているとはこういうことか、と私は思った。そして、これほど少ない警備の人数で彼らを危険な状態のままにしてきた自分自身を、再び厳しく責めた。
この時までに、私はドアにたどり着き、立ち上がっていた。中は真っ暗で、目で何も見分けることはできなかった。音に関しては、いびきをかく者たちの絶え間ない低い音と、時折聞こえる小さな音、何かをつついたりするような音があったが、その正体は全く分からなかった。
両腕を前に突き出し、私は着実に中へ歩き入った。自分の場所に横になろう(と私は心の中でくすりと笑いながら思った)、そして朝、彼らが私を見つけた時の顔を楽しもう、と。
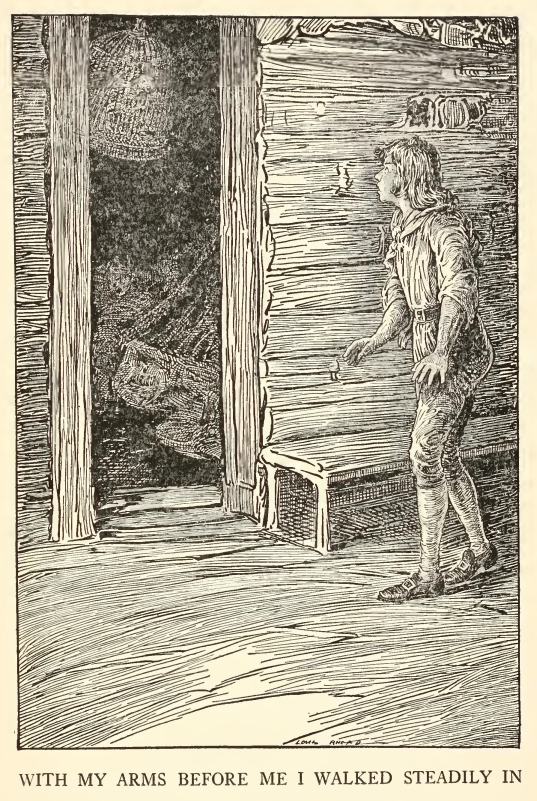
私の足が何か柔らかいものにぶつかった――それは眠っている者の足だった。彼は身じろぎしてうめいたが、目を覚ますことはなかった。
そして、その時、突然、甲高い声が闇の中から響き渡った。
「八レアル銀貨! 八レアル銀貨! 八レアル銀貨! 八レアル銀貨! 八レアル銀貨!」などと、休みなく、変わりなく、まるで小さな粉ひき車のきしむ音のように続いた。
シルバーの緑色のオウム、フリント船長! 私が木の皮をつついているのを聞いたのは彼女だったのだ。どの人間よりも優れた見張りをしていた彼女が、そのうんざりするような繰り返し言葉で、私の到着を告げたのだった。
私には立ち直る時間は残されていなかった。オウムの鋭く、途切れ途切れの声に、眠っていた者たちは目を覚まし、跳び起きた。そして、力強い罵り声とともに、シルバーの声が叫んだ。「誰だ!」
私は振り向いて逃げようとし、一人の人物に激しくぶつかり、跳ね返り、二人目の腕の中にまっすぐ飛び込んだ。彼は私を捕らえ、固く抱きしめた。
「たいまつを持ってこい、ディック」と、私がこうして捕らえられたのを見届けてから、シルバーは言った。
そして男たちの一人が丸太小屋を出て、やがて火のついた松明を持って戻ってきた。

第六部 シルバー船長
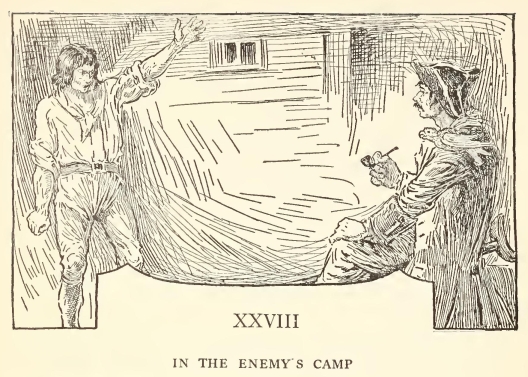
第二十八章 敵の陣営にて
たいまつの赤い炎が丸太小屋の内部を照らし出し、私の最悪の懸念が現実となったことを示した。海賊たちは家と食料を我が物としていた。コニャックの樽があり、以前と同じように豚肉とパンがあった。そして、私の恐怖を十倍にも増したのは、捕虜の姿は影も形もないことだった。全員が死んだとしか考えられず、彼らと共に死ぬために、なぜ自分はここにいなかったのかと、心が張り裂ける思いだった。
海賊は全部で六人いた。生き残っていたのはそれだけだった。そのうち五人は、酔いの浅い眠りから叩き起こされ、顔を真っ赤に腫れ上がらせて立っていた。六人目は肘をついてやっと身を起こしたばかりだった。その顔は死人のように青ざめ、頭に巻かれた血染めの包帯が、彼が最近負傷し、ごく最近手当てを受けたことを物語っていた。僕は、あの大きな襲撃の際に撃たれて森の中へ逃げ帰った男のことを思い出し、きっとこいつに違いないと思った。
オウムはロング・ジョンの肩にとまり、羽繕いをしていた。彼自身は、僕が見慣れた姿よりいくぶん顔色が悪く、険しい表情に見えた。使命を果たした時に着ていた上等なブロードクロスのスーツをまだ身につけていたが、それはひどく着古され、泥にまみれ、森の鋭い茨で引き裂かれていた。
「ほう」と彼は言った。「ジム・ホーキンズじゃねえか、おったまげたぜ! ふらっと立ち寄ったってわけかい? まあいい、歓迎するぜ。」
そう言うと、彼はブランデー樽に腰を下ろし、パイプに火をつけ始めた。
「ディック、火種を貸してくれ」と彼は言った。そして、うまく火がつくと、「それでいい、小僧」と付け加えた。「松明は薪の山にでも突っ込んどけ。それから、旦那方、気を楽にしな。ホーキンズ旦那のために突っ立ってる必要はねえ。旦那も許してくださるさ、そいつは請け合うぜ。それでな、ジム」――彼はタバコを吸うのをやめて言った――「おめえがここに現れるとはな、まったくこの年寄りのジョンには嬉しい驚きだ。初めて会った時から利口な奴だとは思っていたが、こいつばかりは俺の想像をはるかに超えてる、まったくだ。」
これらすべての言葉に、ご想像の通り、僕は何も答えなかった。彼らは僕を壁に背を向けさせて立たせていた。僕はそこに立ち、シルバーの顔をまっすぐに見つめていた。外見上は、願わくば、十分に気丈に見えただろうが、心の中は真っ暗な絶望に満ちていた。
シルバーは実に落ち着き払った様子でパイプを一口、二口吸うと、また立て続けに話し始めた。
「さて、いいか、ジム。おめえがここにいるからには」と彼は言った。「俺の考えを聞かせてやろう。俺はずっとおめえが気に入ってた。気骨のある若者で、俺が若くていい男だった頃の生き写しみてえだからな。いつだっておめえに仲間になって、分け前を取り、紳士として死んでほしかった。そして今、若いの、そうするしかなくなったんだ。スモレット船長は立派な船乗りだ、そいつはいつでも認める。だが規律にうるせえ。『義務は義務だ』とな。まったくその通りだ。船長には近づかねえことだ。博士自身、おめえにすっかり愛想を尽くしてる――『恩知らずの悪党』とまで言ってたぜ。要するに、話はこうだ。おめえはもう自分の仲間のもとへは戻れねえ。あいつらはおめえを受け入れねえだろう。それに、おめえ一人で第三の船団でも立ち上げない限りはな。そいつは寂しいだろうぜ。だから、シルバー船長と組むしかねえってわけだ。」
ここまでは上々だった。つまり、僕の仲間たちはまだ生きているのだ。シルバーの言葉――丸太小屋の一行が僕の脱走に腹を立てているという話――は半分本当だろうと思ったが、それを聞いても僕は苦悩するより安堵した。
「俺たちの手の中にあるおめえの身の上について、とやかく言うつもりはねえ」とシルバーは続けた。「まあ、現にそうなっちまってるんだがな、そいつは確かだ。俺はあくまで話し合いが好きでな。脅しでいいことになった試しがねえ。この仕事が気に入ったなら、よし、仲間になれ。もし気に入らねえなら、ジム、なぜ断るのに遠慮がいる? ――断ってくれて結構、大歓迎だぜ、船乗り仲間。これ以上公平な話が船乗りの口から出るもんなら、俺の脇腹も震えらあ!」
「では、答えてもいいのですか?」僕はひどく震える声で尋ねた。この嘲るような話しぶりのすべてに、僕は頭上に垂れ込める死の脅威を感じ、頬は燃えるように熱くなり、心臓は胸の中で痛いほど高鳴っていた。
「小僧」とシルバーは言った。「誰も急かしちゃいねえ。まあ落ち着け。誰も急がせたりしねえよ、相棒。おめえさんといると時間が経つのも楽しいからな、わかるだろ。」
「では」と僕は少し大胆になって言った。「もし僕に選ぶ権利があるというなら、一体何がどうなっているのか、なぜあなたたちがここにいて、僕の仲間はどこにいるのか、知る権利があるはずです。」
「何がどうなってるだと?」海賊の一人が低い唸り声で繰り返した。「ああ、それを知ってる奴がいたら、そいつは運のいい奴だぜ!」
「話しかけられるまでハッチを閉めとけ、つまり黙ってろってこった、友よ」シルバーはこの発言者に向かって獰猛に叫んだ。そして、最初の優雅な口調に戻ると、僕に答えた。「昨日の朝、ホーキンズ旦那」と彼は言った。「ドッグウォッチ[訳注:午後4時から8時までの当直時間]に、ライブシー博士が休戦の旗を持ってやって来た。博士は言った、『シルバー船長、一杯食わされたな。船が消えたぞ』と。まあ、俺たちは一杯やって、景気づけに歌でも歌っていたかもしれん。否定はしねえ。少なくとも、誰も外を見ていなかった。外を見ると、なんてこった、あの古船が消えちまってた! あんなに間の抜けた顔をした馬鹿どもは見たことがねえ。そいつは請け合うぜ、俺が見た中でも一番間抜けな顔だった。博士は言った、『さて、取引としよう』。俺たちは取引した、博士と俺がな。そして今、俺たちはここにいる。食料、ブランデー、丸太小屋、あんたが親切にも切り出してくれた薪、そして言わば、上はクロスツリーから下はキールソンまで、このありがたい砦の隅から隅まで全部だ。あいつらときたら、とっととどこかへ行っちまった。どこにいるかは知らねえ。」
彼は再び静かにパイプを吸った。
「それから、あんたのその頭で考え違いをしねえように言っておくが」と彼は続けた。「あんたがその協定に含まれていたと思うなら大間違いだ。最後に交わされた言葉はこうだ。『残るのは何人だ』と俺が聞くと、『四人だ』と博士は言った。『四人、うち一人は負傷している。あの少年については、どこにいるか知らん、あのいまいましい奴め』とな。『大して気にもならん。あいつにはほとほと愛想が尽きた』。これが博士の言葉だ。」
「それだけですか?」と僕は尋ねた。
「ああ、おめえが聞かされるのはそれだけだ、坊主」とシルバーは答えた。
「そして今、僕は選べと?」
「そして今、おめえは選ぶんだ。そいつは確かだぜ」とシルバーは言った。
「わかりました」と僕は言った。「僕も、これから何が待ち受けているかくらいわかるほどの馬鹿ではありません。最悪の事態になったところで、僕にはどうでもいいことだ。あんたたちと関わってから、あまりにも多くの人が死ぬのを見てきました。でも、二つ三つ、言っておかなければならないことがあります」この時までに、僕はすっかり興奮していた。「まず一つ目。あんたたちは今、ひどい状況にある。船を失い、宝を失い、仲間を失い、あんたたちの計画は何もかもおじゃんだ。誰がそうしたか知りたいなら――やったのは僕だ! 陸が見えた夜、僕はリンゴの樽の中にいて、あんたたちの話を聞いていた。ジョン、あんたも、ディック・ジョンソンも、今頃は海の底にいるハンズもだ。そして、あんたたちが話したことを一言残らず、一時間もしないうちに仲間たちに伝えた。スクーナー船については、錨綱を切ったのは僕だ。あんたたちが船に乗せていた連中を殺したのも僕だ。そして、あんたたちが二度と見つけられない場所に船を持って行ったのも僕だ。笑うのは僕の方さ。最初からこの一件、僕が主導権を握ってきたんだ。あんたたちなんて、蠅ほども怖くない。どうぞ、殺すなり、助けるなり、好きにすればいい。でも、一つだけ言っておく。もし僕を助けるなら、過ぎたことは水に流す。そして、あんたたちが海賊行為で裁判にかけられた時、僕はできる限りあんたたちを救ってやる。選ぶのはあんたたちだ。もう一人殺して何の得にもならないことをするか、それとも僕を生かしておいて、絞首台から救ってくれる証人を手元に置くかだ。」
僕は言葉を止めた。正直に言うと、息が切れていたのだ。そして驚いたことに、彼らのうち誰一人身じろぎもせず、皆まるで羊の群れのように僕をじっと見つめているだけだった。彼らがまだ呆然と見つめている間に、僕は再び口を開いた。「さて、シルバーさん」僕は言った。「あんたがここで一番の人だと思います。もし最悪の事態になったら、僕がどんな風に覚悟を決めたか、博士に伝えてくれたらありがたいです。」
「心に留めておこう」とシルバーは、あまりに奇妙な口調で言ったので、僕にはどうしても、彼が僕の頼みを笑っているのか、それとも僕の勇気に感心したのか、判断がつかなかった。
「それに一つ付け加えさせてもらうぜ」と、マホガニー色の顔をした老船乗り――モーガンという名で、ブリストルの波止場にあったロング・ジョンの酒場で見たことのある男だ――が叫んだ。「黒犬の正体を見抜いたのはこいつだ。」
「ああ、そうだ、それからな」と海のコックは付け加えた。「誓って言うが、もう一つ付け加えさせてもらう! ビリー・ボーンズから地図をせしめたのもこの小僧だ。最初から最後まで、俺たちはジム・ホーキンズにしてやられてるんだ!」
「それなら、こうしてくれる!」とモーガンは罵り言葉とともに言った。
そして彼は、まるで二十歳の若者のように飛び上がり、ナイフを抜いた。
「待て!」とシルバーが叫んだ。「何様のつもりだ、トム・モーガン? 自分がここの船長だとでも思ったか? とんでもねえ、俺が教えてやる! 俺に逆らえば、お前より先に逝った大勢の立派な男たちのところへ行くことになる。この三十年間、最初から最後まで、帆桁に吊るされた奴も、船外に放り出された奴も、みんな魚の餌になりにな。俺の目をまともに見て、その後いい一日を送れた奴は一人もいねえんだ、トム・モーガン、そいつは請け合うぜ。」
モーガンは立ち止まったが、他の者たちからはしゃがれた不満の声が上がった。
「トムは正しい」と一人が言った。
「一人の奴にこき使われるのはもうたくさんだ」と別の一人が付け加えた。「てめえにまでこき使われるなんてごめんだ、ジョン・シルバー。」
「旦那方の中に、この俺とやり合いてえ奴がいるのか?」シルバーは樽の上の席から身を乗り出し、右手にはまだパイプが赤々と燃えており、そう怒鳴った。「何がしてえのか、はっきり言ってみろ。口が利けねえわけじゃあるめえ。望む奴には望み通りのものをくれてやる。この俺が長年生き抜いてきて、最後の最後にラム樽から生まれたような若造に喧嘩を売られるとはな。やり方は知ってるだろう。お前らは自称、幸運の紳士様たちだ。いいだろう、俺はいつでも相手になる。度胸のある奴はカトラスを取れ。このパイプが空になる前に、松葉杖ごとそいつの内臓の色を拝ませてやるぜ。」
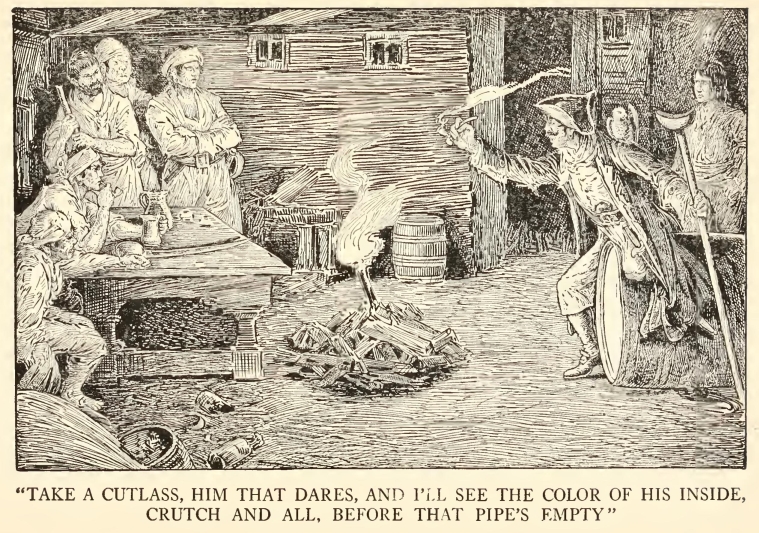
誰一人身じろぎもせず、誰一人答えなかった。
「それがお前らのやり方か?」彼はパイプを口に戻しながら付け加えた。「まあ、見てる分には陽気な連中だ。喧嘩する価値もねえがな。キング・ジョージの英語なら理解できるかもしれねえな。俺は選挙でここの船長になったんだ。俺がここの船長なのは、俺が断トツで一番の男だからだ。幸運の紳士様らしく戦おうとしねえなら、誓って言うが、服従しろ。そいつは確かだ! 俺は今、この小僧が気に入ってる。こいつより出来た小僧は見たことがねえ。この小屋にいるどぶ鼠みてえなお前ら二人分よりも、よっぽど男らしい。俺が言いてえのはこうだ。こいつに手を出そうって奴がいたら、顔を見せてもらおうじゃねえか――俺が言いてえのはそれだ、そいつは請け合うぜ。」
この後、長い沈黙が続いた。僕は壁際にまっすぐに立っていた。心臓はまだ大槌のように鳴り響いていたが、胸には一筋の希望の光が差し始めていた。シルバーは壁にもたれかかり、腕を組み、口の端にパイプをくわえ、まるで教会にでもいるかのように落ち着き払っていた。しかし、その目は油断なくあたりをさまよい、視線の端で、手に負えない手下たちを常に捉えていた。一方、彼らは徐々に丸太小屋の奥の方へ集まり、彼らのひそひそ話す低い声が、小川のせせらぎのように絶えず僕の耳に聞こえてきた。一人、また一人と顔を上げると、松明の赤い光が彼らの神経質な顔を束の間照らし出す。だが、彼らが視線を向けていたのは僕の方ではなく、シルバーの方だった。
「随分と言いたいことがあるようだな」シルバーはそう言って、空中にぺっと唾を吐いた。「大声で言ってみろ、聞かせてもらおうじゃねえか。さもなきゃ黙ってろ。」
「失礼します、旦那」男の一人が答えた。「あんたはいくつかの規則にはかなり自由なようだが、残りの規則にもう少し目を光らせていただきたいもんだ。この船員たちは不満だ。この船員たちは、脅しでどうにかなるような甘ちゃんじゃねえ。この船員たちには、他の船員たちと同じ権利がある。そう言わせてもらうぜ。そして、あんた自身の規則によれば、俺たちは話し合うことができるはずだ。失礼します、旦那。現時点であんたを船長と認めた上でのことだが、俺は自分の権利を主張し、会議のために外へ出させてもらう。」
そして、大仰な船乗りの敬礼をすると、この男――三十五歳ほどの、背が高く、人相が悪く、黄色い目をした男――は、冷静にドアの方へ歩み寄り、小屋の外へ姿を消した。一人、また一人と、残りの者たちも彼に続いた。それぞれが通り過ぎる際に敬礼をし、何かしらの口実を付け加えた。「規則に従って」と一人が言った。「フォクスル会議[訳注:船首楼で行われる船員たちの集会]だ」とモーガンが言った。そうして、あれこれと言いながら、全員が外へ出て行き、シルバーと僕だけが松明とともに残された。
海のコックはすぐにパイプを口から外した。
「さて、よく聞け、ジム・ホーキンズ」彼はかろうじて聞こえるほどの、しかし落ち着いた囁き声で言った。「おめえは死まで板半分の距離にいる。もっと悪いことに、拷問も待ってるぞ。あいつらは俺を船長から引きずり下ろす気だ。だが、よく覚えておけ。俺は何があってもおめえの味方をする。そうするつもりはなかった。いや、おめえが口を開くまではな。あれだけの金を失う上に、おまけに絞首刑なんて、ほとんど絶望的だった。だが、おめえが筋の通った奴だとわかった。俺は自分に言い聞かせた。ホーキンズの味方をしろ、ジョン、そうすればホーキンズもお前の味方になる、と。おめえはあいつの最後の切り札で、そして誓って言うが、ジョン、あいつもおめえの最後の切り札だ! 背中合わせで戦うんだ、と俺は言った。おめえは自分の証人を救い、あいつはおめえの首を救う!」
僕はぼんやりと理解し始めた。
「すべて失われたということですか?」と僕は尋ねた。
「ああ、まったくその通りだ!」と彼は答えた。「船は消え、首は消える――そういうこった。あの湾を覗き込んで、スクーナー船が見えなかった時――まあ、俺もタフだが、さすがに参ったよ。あいつらとその会議についてはな、よく聞け、あいつらはまったくの馬鹿で臆病者だ。俺がおめえの命を救ってやる――できることならな――あいつらから。だが、いいか、ジム――ギブアンドテイクだ。おめえはロング・ジョンを絞首台から救え。」
僕は当惑した。彼が求めていることは、あまりにも絶望的に思えた――彼、あの老獪な海賊、すべての首謀者である彼が。
「僕にできることなら、やります」と僕は言った。
「取引成立だ!」とロング・ジョンは叫んだ。「おめえが気丈に話してくれりゃ、誓って言うが、俺にもまだ勝ち目はある!」
彼は薪の間に立てかけられた松明までよろよろと歩いて行き、パイプに新しく火をつけた。
「いいか、ジム」彼は戻って来て言った。「俺の肩には頭が乗ってるんだ、ちゃんと考えてる。俺はもう郷士の側についた。おめえがあの船をどこか安全な場所に隠したことはわかってる。どうやったかは知らねえが、安全なのは確かだ。ハンズとオブライエンは甘かったんだろう。どっちも大して信用してなかったからな。さて、よく聞け。俺は何も質問しねえし、他の奴らにもさせねえ。俺は勝負がついた時がわかる男だ。そして、筋を通す若者だってこともわかる。ああ、おめえみてえな若いのと一緒なら――おめえと俺なら、大したことができたかもしれねえな!」
彼は樽からブリキの小ジョッキにコニャックを注いだ。
「一杯どうだ、相棒?」彼はそう尋ね、僕が断ると言った。「じゃあ、俺が一杯やるよ、ジム。一杯やらねえとやってられねえ。面倒が起きそうだ。面倒と言えば、なぜあの博士は俺に地図を渡したんだ、ジム?」
僕の顔にはあまりにもあからさまな驚きが浮かんでいたので、彼はそれ以上質問する必要がないと悟ったようだった。
「ああ、まあ、とにかく渡したんだ」と彼は言った。「そして、その下には何かがあるに違いねえ――何か、きっと何かがあるんだ、ジム――良いことか、悪いことか。」
そして彼はブランデーをもう一口飲み、最悪の事態を覚悟している男のように、その大きな金髪の頭を振った。
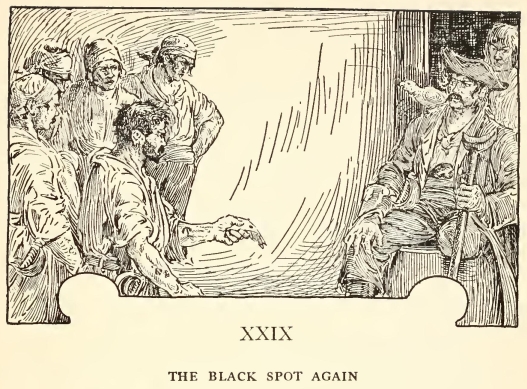
第二十九章 再びの黒丸
海賊たちの会議はしばらく続いていたが、やがてそのうちの一人が小屋に再び入ってきて、僕の目には皮肉な響きを帯びて見えた同じ敬礼を繰り返し、松明を少し貸してほしいと頼んだ。シルバーは簡潔に同意し、この使者は再び退き、僕たちは暗闇の中に残された。
「風向きが変わりそうだぜ、ジム」とシルバーは言った。この時までに、彼はすっかり親しげで打ち解けた口調になっていた。
僕は一番近くの銃眼に寄り、外を見た。大きな焚き火の燃えさしはほとんど燃え尽き、今では薄暗く弱々しく光るばかりで、あの陰謀者たちがなぜ松明を欲しがったのか理解できた。柵へと続く斜面の中ほどで、彼らは一団となって集まっていた。一人が明かりを持ち、もう一人がその真ん中で膝をついており、開いたナイフの刃が、月光と松明の光を浴びて、様々に色を変えながら彼の手の中で輝いているのが見えた。残りの者たちは皆、この最後の男の動きを見守るかのように、いくらか身をかがめていた。彼がナイフだけでなく本も手にしているのがかろうじて見て取れ、どうしてそんな場違いなものが彼らの手に入ったのかとまだ不思議に思っていると、膝をついていた男が再び立ち上がり、一行は皆一緒に小屋の方へ動き始めた。

「来ます」と僕は言った。そして、元の場所に戻った。彼らを覗き見しているところを見つけられるのは、僕の尊厳に関わるように思えたからだ。
「ああ、来させろ、小僧――来させろ」シルバーは陽気に言った。「俺の弾薬箱にはまだ弾が一発残ってる。」
ドアが開き、五人の男たちが中に固まって立っており、その中の一人を前に押し出した。他の状況であれば、彼が片足ずつためらいながらゆっくりと進み、閉じた右手を前に突き出している姿は滑稽に見えただろう。
「前に出ろ、小僧」とシルバーは叫んだ。「食って取ったりしねえよ。そいつを渡せ、のろまめ。規則は知ってる、使者を傷つけたりはしねえ。」
こうして勇気づけられ、海賊はよりきびきびと前に進み、何かをシルバーに手渡すと、さらに素早く仲間たちの元へ戻っていった。
海のコックは渡されたものを見た。
「黒丸か! 思った通りだ」と彼は言った。「その紙はどこで手に入れたんだ? おや、おっと! 見ろ、こいつは縁起が悪い! てめえら、聖書から切り取りやがったな。どんな馬鹿が聖書を切り刻んだんだ?」
「ああ、そうだ!」とモーガンが言った。「そうだとも! 俺が何て言った? そんなことをしちゃ、ろくなことにならねえって言っただろう。」
「まあ、てめえらで決着をつけちまったようなもんだな」とシルバーは続けた。「お前ら、これで全員絞首台行きだ、俺はそう思うぜ。聖書を持っていた頭の弱い間抜けは誰だ?」
「ディックだ」と一人が言った。
「ディックか? ならディックは祈りでも始めるこったな」とシルバーは言った。「ディックの幸運もこれまでだ、そいつは請け合うぜ。」
しかし、ここで黄色い目をした背の高い男が口を挟んだ。
「その話はやめろ、ジョン・シルバー」と彼は言った。「この船員一同は、正式な会議において、義務に従いあんたに黒丸を渡したんだ。義務に従って、そいつを裏返して、そこに何が書かれているか見るんだな。話はそれからだ。」
「ありがとよ、ジョージ」と海のコックは答えた。「おめえはいつも仕事が早くて、規則も暗記してる。感心するぜ、ジョージ。で、何て書いてあるんだ? ああ! 『解任』――そうか、そういうことか。実にきれいな字だ、本当にな。まるで印刷みてえだ、誓ってもいい。おめえの字か、ジョージ? おめえもこの船員たちの中でずいぶん指導的な立場になったもんだな。次は船長になるかもしれねえ、驚かねえぜ。もう一度その松明を貸してくれねえか? このパイプ、どうも吸い口が悪い。」
「おい、よせよ」とジョージは言った。「もうこの船員たちを騙すことはできねえぞ。あんたは自分の言うことには面白い男だが、もう終わりだ。その樽から降りて、投票を手伝ってもらおうか。」
「規則を知っていると言ったのはお前だと思ったがな」シルバーは軽蔑的に言い返した。「少なくとも、お前が知らなくても俺は知っている。俺はここで待つ――そして、忘れるな、俺はまだお前らの船長だ――お前らが不満をぶちまけ、俺がそれに答えるまでな。それまでの間、お前らの黒丸なんざ、ビスケット一枚の価値もねえ。その後で、どうなるか見てやろう。」
「ああ」とジョージは答えた。「心配する必要はねえ。こっちは正々堂々とやる。第一に、あんたはこの航海を台無しにした――それにノーと言えるなら、大した度胸だ。第二に、あんたは敵をこの罠からみすみす逃がした。なぜあいつらが外に出たがったのか? 知らねえが、出たがっていたのは明らかだ。第三に、あんたはあいつらが移動しているところを俺たちに襲わせなかった。ああ、お見通しだぜ、ジョン・シルバー。あんたは裏切るつもりだ、それが問題なんだ。そして、第四に、この小僧だ。」
「それだけか?」シルバーは静かに尋ねた。
「十分すぎる」とジョージは言い返した。「あんたのへまのせいで、俺たちはみんな絞首刑になって天日干しだ。」
「さて、いいか、この四つの点に答えてやろう。一つずつな。俺がこの航海を台無しにした、だと? さて、お前ら全員、俺が何を望んでいたか知っているはずだ。もしそれが実行されていたら、今夜、俺たちは全員生きて、元気で、『ヒスパニオラ号』に乗っていたはずだ。腹にはうまいプラム・ダフを詰め込み、船倉には宝を積んでな、誓ってもいい! さて、俺に逆らったのは誰だ? 正当な船長だったこの俺の手に無理強いしたのは誰だ? 上陸したその日に俺に黒丸を突きつけて、この踊りを始めたのは誰だ? ああ、結構な踊りだ――そこは同感だ――まるでロンドンの処刑ドックで、縄の端で踊るホーンパイプみたいに見えるぜ、まったくだ。だが、誰がやった? アンダーソンと、ハンズと、お前だ、ジョージ・メリー! そして、お前が、あの余計なことをした連中の最後の生き残りだ。そのお前が、海の藻屑になるべきてめえが、この俺を差し置いて船長になろうってんだから、その厚かましさには恐れ入る! とんでもねえ! これじゃあどんな法螺話も真っ青だ。」
シルバーは言葉を止め、ジョージとその仲間たちの顔から、これらの言葉が無駄ではなかったことが見て取れた。
「これが一つ目に対する答えだ」と被告は叫び、額の汗を拭った。彼は家を揺るがすほどの激しさで話していたのだ。「まったく、お前らに話すのもうんざりだ。お前らには分別も記憶力もねえ。お前らを海に行かせた母親たちがどこにいたのか、想像に任せるぜ。海だと! 幸運の紳士様だと! お前らの本職は仕立屋だろうよ。」
「続けろ、ジョン」とモーガンが言った。「他の点についても話してくれ。」
「ああ、他の点か!」とジョンは言い返した。「結構な連中じゃねえか。この航海は台無しになったと言う。ああ! まったく、どれほどひどく台無しになったかお前らに理解できたら、わかるだろうよ! 俺たちは絞首台に手が届くほど近くて、そのことを考えるだけで首がこわばる。お前らも見たことがあるだろう、鎖に吊るされた死体を。鳥が群がり、船乗りたちが潮に乗って下っていく時に指さす。『あれは誰だ?』と一人が言う。『あれか! あれはジョン・シルバーだ。よく知ってる男だ』と別のが言う。そして、別のブイに向かう時に鎖ががちゃがちゃ鳴るのが聞こえる。今、俺たちはまさにそんな状況なんだ、こいつと、ハンズと、アンダーソンと、その他のお前ら破滅を招く馬鹿どものおかげでな。そして、四つ目の点、この小僧について知りてえなら、なんてこった、こいつは人質じゃねえか? 人質を無駄にするつもりか? いや、俺たちはしねえ。こいつが俺たちの最後のチャンスになるかもしれねえ、驚くことじゃねえ。この小僧を殺すだと? 俺はやらねえぞ、仲間たち! そして三つ目か? ああ、三つ目については言うことがたくさんある。毎日、本物の大学出の医者に診てもらうことが、お前らにとってはたいしたことじゃねえのかもしれねえな――頭を割られたお前、ジョン――あるいは、六時間前まで悪寒で震えていて、今この瞬間も目の色がレモンの皮みてえな色をしているお前、ジョージ・メリー。そして、多分、援軍が来ることも知らなかったんだろう? だが、来るんだ、それももうすぐだ。その時になって人質がいてよかったと思うのが誰か、見てみようじゃねえか。そして二つ目の点、なぜ俺が取引をしたか――まあ、お前らは膝をついて這いつくばって、俺に取引を頼みに来たじゃねえか――膝をついてな、それほど意気消沈していたんだ――そして俺がいなけりゃ飢え死にしてたはずだ――だが、そんなことは些細なことだ! そこを見ろ――これが理由だ!」
そして彼は床に一枚の紙を投げつけた。僕はすぐにそれが何か分かった――船長の櫃の底の油布の中から見つけた、三つの赤い十字が記された黄色い紙の地図に他ならなかった。なぜ博士がそれを彼に渡したのか、僕には想像もつかなかった。
しかし、僕にとって不可解であったとしても、地図の出現は生き残った反逆者たちにとって信じられないことだった。彼らはネズミに飛びかかる猫のようにそれに飛びついた。それは手から手へと渡り、一人が別の一人からひったくった。そして、それを調べる際に伴う罵り言葉や叫び声、子供じみた笑い声からすれば、彼らはまるで本物の金塊に触れているだけでなく、それを積んで安全に海上にいるかのように思えただろう。
「そうだ」と一人が言った。「こいつはフリントの地図に違いねえ。J.F.、その下に傷、それに巻き結びだ。奴はいつもこうしてた。」
「実に結構だ」とジョージは言った。「だが、どうやってこいつを持って逃げるんだ、船もねえのに。」
シルバーは突然飛び上がり、壁に手をついて体を支えた。「今、警告しておくぞ、ジョージ」と彼は叫んだ。「もう一言でも生意気な口をきいてみろ、引きずり下ろして決闘だ。どうやって、だと? なぜ、どうして俺が知ってる? お前が俺に教えるべきだろう――お前と、お前らの干渉で俺のスクーナー船を失わせた残りの連中がな、くそったれ! だが、お前にはできねえ。ゴキブリほどの知恵もねえくせに。だが、丁寧な口はきけるはずだ、そしてきいてもらうぞ、ジョージ・メリー、そいつは請け合うぜ。」
「そいつは公平だ」と老人のモーガンが言った。
「公平! そうだろうよ」と海のコックは言った。「お前らは船を失い、俺は宝を見つけた。どっちが優れた男だ? そして今、俺は辞任する、誓ってな! 好きな奴を船長に選べ。俺はもうごめんだ。」
「シルバー!」彼らは叫んだ。「バーベキュー万歳! 船長はバーベキューだ!」
「そういう曲か、そうかい?」とコックは叫んだ。「ジョージ、お前の出番はもう一回待つことになりそうだな、友よ。俺が復讐心の強い男じゃなくて幸運だったな。だが、それは俺のやり方じゃねえ。さて、船乗り仲間たち、この黒丸は? もう大して役に立たねえな? ディックが自分の運を台無しにして聖書を汚した、ただそれだけのことだ。」
「それでも本に誓いのキスはできるだろう?」とディックは唸った。彼は明らかに、自分が招いた呪いに不安を感じていた。
「一部が切り取られた聖書だと!」シルバーは嘲るように言い返した。「とんでもねえ。バラッド集ほども効力はねえよ。」
「そうなのか?」ディックは一種の喜びを込めて叫んだ。「まあ、それも価値があることだな。」
「ほら、ジム――おめえに珍しいものを見せてやる」とシルバーは言い、僕にその紙を投げた。
それはクラウン銀貨ほどの大きさだった。片面は最後のページだったので白紙で、もう片面にはヨハネの黙示録の一節か二節が書かれていた――その中に、僕の心に鋭く突き刺さった言葉があった。「外には、犬どもや、人殺しどもがいる」。印刷された面は木の灰で黒く塗られており、それはすでにはがれ始めて僕の指を汚した。白紙の面には同じ材料で「カイニン」という一言が書かれていた。僕は今もその珍しいものを手元に持っているが、今では男が親指の爪でつけたような一本の引っかき傷以外、文字の痕跡は何も残っていない。
それがその夜の出来事の終わりだった。まもなく、全員で一杯飲んだ後、僕たちは眠りについた。シルバーの復讐は、ジョージ・メリーを見張りに立て、もし忠実でなければ死をもって脅すという、ささやかなものに留まった。
僕が目を閉じることができるまでには長い時間がかかった。その日の午後に僕が殺した男のこと、僕自身の極めて危険な立場、そして何よりも、シルバーが今繰り広げている驚くべき駆け引き――片手で反逆者たちをまとめ上げ、もう一方の手で、和解し、己の哀れな命を救うために、ありとあらゆる、可能な、そして不可能な手段にさえも手を伸ばしていた――について、考えるべきことは山ほどあった。彼自身は安らかに眠り、大きないびきをかいていたが、彼がどれほど邪悪であっても、彼を取り巻く暗い危険と、彼を待ち受ける不名誉な絞首台を思うと、僕の心は痛んだ。
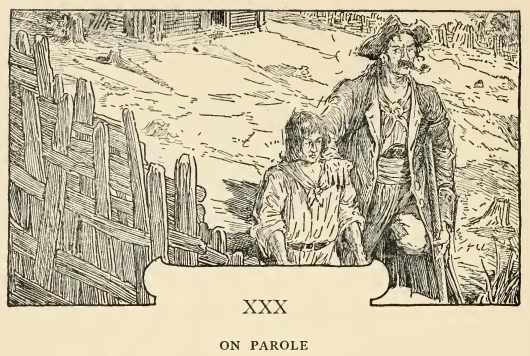
第三十章 仮釈放
僕は起こされた――いや、僕たち全員が起こされたのだ。ドアの柱にもたれて倒れていた見張りでさえ身を起こすのが見えた――森の端から僕たちを呼ぶ、はっきりとした元気な声によって。
「丸太小屋、おーい!」その声は叫んだ。「博士だ。」
そして、それは博士だった。その声を聞いて嬉しかったが、僕の喜びには混じり物があった。僕は自分の不服従で隠密な行動を混乱とともに思い出し、それが僕をどこへ――どんな仲間の中に、どんな危険に囲まれた場所へ――連れてきたかを見ると、彼の顔を見るのが恥ずかしくなった。
彼は暗いうちに起きたに違いなかった。まだ夜が明けきっていなかったからだ。僕が銃眼に駆け寄って外を見ると、かつてのシルバーのように、這うような霧の中に膝まで浸かって立っているのが見えた。
「博士殿! おはようございます、先生!」とシルバーは叫んだ。すっかり目を覚まし、一瞬にして上機嫌に満ちた顔になった。「実に早起きでございますな。ことわざにもあります通り、早起きは配給の得でございます。ジョージ、しっかりしろ、息子よ。ライブシー博士が船べりを越えるのを手伝ってやれ。患者たちは皆、元気にしておりました――皆元気で陽気でございます。」
彼はそう早口でまくし立てた。丘の頂上に立ち、松葉杖を脇に挟み、片手を丸太小屋の壁につき――声も、態度も、表情も、まったくいつものジョンだった。
「先生には驚きのプレゼントもございますよ」と彼は続けた。「ここにちょっとしたお客人がおりましてな――へっへっ! 新しい下宿人でございます、先生。バイオリンのようにぴんとして元気にしておりますよ。積荷監督官のように眠っておりました、ジョンのすぐ隣でな――頭と頭をくっつけて、一晩中でした。」
ライブシー博士はこの時までに柵を越え、コックのすぐ近くまで来ていた。そして、彼の声の調子が変わるのが聞こえた。「ジムではないだろうな?」
「いつものあのジムでございます」とシルバーは言った。
博士はぴたりと立ち止まった。口は開かなかったが、数秒間、動き出すことができないように見えた。
「まあ、いい」と彼はついに言った。「義務が先で、楽しみは後だ。君自身が言ったかもしれないな、シルバー。君の患者たちを診察させてもらおう。」
一瞬後、彼は丸太小屋に入り、僕に厳しい頷きを一つすると、病人の間で仕事に取りかかった。彼は何の不安も感じていないようだった。この裏切り者の悪魔たちの間で、自分の命が髪の毛一本でかかっていることを知っていたはずなのに。そして、彼はまるで静かなイギリスの家庭に普通の往診に来たかのように、患者たちに陽気に話しかけた。彼の態度が男たちに影響したのだろう。彼らは何事もなかったかのように彼に接した。まるで彼がまだ船医で、自分たちがまだ忠実なマスト前の船員であるかのように。
「順調だね、友よ」彼は頭に包帯を巻いた男に言った。「これほどの九死に一生を得た者はそうはいない。君の頭は鉄のように硬いに違いない。さて、ジョージ、調子はどうだ? ずいぶんときれいな色をしているな。おい、君の肝臓はひっくり返っているぞ。あの薬は飲んだかね? 彼はあの薬を飲んだか、諸君?」
「へい、へい、先生、確かに飲みやした」とモーガンは答えた。
「なぜなら、わかるかね、私は反逆者たちの医者として、あるいは監獄医とでも呼んだ方がいいかな」とライブシー博士は最も愉快な口調で言った。「私はジョージ国王陛下(神の祝福あれ!)と絞首台のために一人も患者を失わないことを名誉にかけているのだ。」
悪党どもは顔を見合わせたが、この痛烈な一撃を黙って飲み込んだ。
「ディックの具合が悪いようです、先生」と一人が言った。
「そうかね?」と博士は答えた。「では、こちらへ来なさい、ディック。舌を見せてみろ。いや、具合が悪くなかったら驚くよ! この男の舌はフランス人も裸足で逃げ出すほどだ。また熱病だな。」
「ああ、そうだ」とモーガンが言った。「そいつは聖書を汚した罰だ。」
「それは――君たちがどう呼ぼうと勝手だが――救いようのない馬鹿で、きれいな空気と毒の区別も、乾いた土地と不潔で疫病の蔓延る沼地の区別もつかないほどの分別しかないからだ」と博士は言い返した。「最もあり得ることだと思うが――もちろん、ただの意見にすぎないが――君たち全員、そのマラリアを体から追い出す前に、ひどい目に遭うことになるだろう。沼地に野営するとはね。シルバー、君には驚いたよ。君は全体的に見れば多くの者よりは馬鹿ではないが、健康の規則に関する初歩的な考えすら持ち合わせていないように見える。」
「さて」と彼は、彼らに一通り薬を与え、彼らが本当に笑えるほど謙虚に、血に飢えた反逆者や海賊というよりは、むしろ慈善学校の生徒のように処方箋を受け取った後で付け加えた。「さて、今日の仕事は終わりだ。そして今、あの少年と話をしたいのだが、よろしいかな?」
そして彼は無造作に僕の方へ頭を向けた。
ジョージ・メリーはドアのところにいて、まずい味の薬をぺっぺっと吐き出していた。しかし、博士の提案の最初の言葉を聞くと、顔を真っ赤にして振り向き、「だめだ!」と叫び、悪態をついた。
シルバーは開いた手で樽を叩いた。
「静かにしろ!」彼は吠え、その様はまさに獅子のようだった。「博士殿」と彼はいつもの口調に戻って続けた。「先生がこの小僧を気に入っておられると知っておりましたので、そのことを考えておりました。我々は皆、先生のご親切に心から感謝しております。ご覧の通り、先生を信頼し、まるでグロッグのように薬を飲み干しております。そして、皆が納得する方法を見つけたと存じます。ホーキンズ、君は若い紳士として――貧しい生まれではあるが、君は若い紳士だ――錨綱を解いて逃げ出したりしないと、名誉にかけて誓ってくれるかね?」
僕はすぐに求められた誓いを立てた。
「では、博士殿」とシルバーは言った。「柵の外へお出でください。先生がそこにおられれば、私が内側から小僧を連れて参ります。柵の丸太越しに話ができるでしょう。ごきげんよう、先生。郷士殿とスモレット船長によろしくお伝えください。」
シルバーの険しい表情だけが抑えていた不満の爆発は、博士が小屋を出るとすぐに起こった。シルバーは二枚舌を使っている、自分だけ別に和解しようとしている、共犯者や犠牲者の利益を犠牲にしている、一言で言えば、彼がまさに行っているそのものズバリのことで、手ひどく非難された。僕には、この場合、それがあまりにも明白に思えたので、彼がどうやって彼らの怒りをそらすのか想像もつかなかった。しかし、彼は他の者たちよりも二枚も三枚も上手であり、昨夜の勝利は彼らの心に絶大な優位性を与えていた。彼は彼らを想像できる限りの馬鹿や間抜けと呼び、僕が博士と話す必要があると言い、彼らの顔の前で地図をひらひらさせ、宝探しに出かけるまさにその日に協定を破る余裕があるのかと彼らに尋ねた。
「とんでもねえ!」と彼は叫んだ。「協定を破るのは、時が来た時に俺たちの方だ。それまでは、ブランデーで博士のブーツを磨いてでも、あの医者をたらしこんでやる。」
そして彼は彼らに火をおこすように命じ、僕の肩に手を置き、松葉杖をついて堂々と外へ出た。彼らを混乱の中に残し、説得されたというよりは、彼の能弁さに沈黙させられたのだった。
「ゆっくりだ、小僧、ゆっくり」と彼は言った。「急いでいるところを見られたら、連中は瞬く間に俺たちに襲いかかってくるかもしれねえ。」
そこで僕たちは、非常にゆっくりと砂地を横切り、柵の向こう側で博士が待っている場所へと進んだ。そして、話が楽にできる距離になるとすぐに、シルバーは立ち止まった。
「これも書き留めておいてくだせえ、博士殿」と彼は言った。「この小僧が、俺がどうやって彼の命を救い、そのために船長の座を追われたかを話すでしょう。そいつは請け合いますぜ。博士殿、俺みてえに風上にぎりぎりで舵を取っている男が――まるで、自分の最後の息を賭けて銭投げ遊びでもしているようなもんで――何か一言、良い言葉をかけてやっても、あんまりだとは思わんでしょう? どうか心に留めておいてくだせえ。今や俺の命だけじゃねえ――この小僧の命もかかってるんです。どうか俺に公平に話してくだせえ、博士殿。そして、慈悲の心で、 आगेに進むための希望を少しばかり与えてくだせえ。」
シルバーは外に出て、仲間たちと丸太小屋に背を向けると、まるで別人のようだった。頬はこけて見え、声は震えていた。これほど真剣な魂はなかった。
「どうした、ジョン、怖いのか?」とライブシー博士は尋ねた。
「博士殿、俺は臆病者じゃねえ。いや、そうじゃねえ――それほどはな!」と彼は指を鳴らした。「もしそうなら、口には出さねえ。だが、正直に白状するが、絞首台を思うと震えが来るんだ。あんたは善良で誠実な人だ。あんたより良い人を見たことがねえ! そして、俺がした良いことを忘れねえだろう、悪いことを忘れねえのと同じくらいにな、俺は知ってる。そして、俺は席を外す――ほら、こうして――あんたとジムを二人きりにする。これも俺のために書き留めておいてくだせえ。大したことですからな、これは!」
そう言うと、彼は少し後ろへ下がり、声が聞こえない距離になると、木の切り株に腰を下ろして口笛を吹き始めた。時々、座ったままくるりと向きを変え、僕と博士の方を見たり、あるいは、彼らが焚き火――彼らは忙しく火を熾し直していた――と、豚肉とパンを朝食のために運び出している小屋との間の砂地を行き来する、手に負えないならず者たちの方を見たりした。
「さて、ジム」と博士は悲しげに言った。「君はここにいる。自分の蒔いた種は自分で刈り取らねばならん、ジム。神のみぞ知るが、君を責める気にはなれない。だが、これだけは言っておこう。親切であろうとなかろうとだ。スモレット船長が元気だった時、君はあんな風に出て行ったりはしなかっただろう。そして、彼が病気でどうしようもなかった時に、ジョージの名にかけて言うが、それはまったくもって卑劣な行いだ!」
ここで僕は泣き始めたことを白状しよう。「博士」僕は言った。「どうか勘弁してください。僕はもう十分に自分を責めました。どうせ僕の命は失われたも同然で、シルバーが僕をかばってくれなければ、今頃は死んでいたはずです。そして博士、信じてください、僕は死ぬ覚悟はできています――そして、当然の報いだと思います――でも、僕が恐れているのは拷問です。もし彼らが僕を拷問にかけたら――」
「ジム」と博士は遮り、その声はすっかり変わっていた。「ジム、そんなことはさせられない。飛び越えてこい、そして一緒に逃げるんだ。」
「博士」と僕は言った。「僕は約束しました。」
「わかっている、わかっている」と彼は叫んだ。「だが、もう仕方ないんだ、ジム。私がすべて引き受けよう、非難も不名誉も、何もかもだ、ジム。だが、ここにいることは許せない。跳べ! 一跳びすれば外だ、そしてカモシカのように逃げるんだ。」

「いいえ」と僕は答えた。「あなた自身、そんなことはしないとよくご存知でしょう――あなたも、郷士様も、船長も。そして、僕もしません。シルバーは僕を信じてくれた。僕は約束した。だから、戻ります。でも、博士、まだ話が終わっていません。もし彼らが僕を拷問にかけたら、僕は船がどこにあるか口を滑らせてしまうかもしれません。僕は運と危険を冒したおかげで船を手に入れました。船は北の入り江、南の浜辺にあり、満潮線より少し下です。干潮時には、すっかり陸に上がっているはずです。」
「船だと!」と博士は叫んだ。
僕は手早く自分の冒険を説明し、彼は黙って最後まで聞いてくれた。
「これには何か運命めいたものを感じる」と僕が話し終えると彼は言った。「一歩一歩、君が我々の命を救っている。そして、我々が君の命を失わせると思うかね? それでは恩を仇で返すようなものだ、ジム。君は陰謀を暴き、ベン・ガンを見つけた――君がこれまでにした、そしてこれからするであろう、たとえ九十まで生きようとも、最善の行いだ。おお、ジュピターの名にかけて、ベン・ガンの話だが! なぜ、これが問題そのものだ。シルバー!」彼は叫んだ。「シルバー! 一つ忠告をしてやろう」コックが再び近づいてくると彼は続けた。「あの宝を追うのに、あまり急がないことだ。」
「なぜです、先生、私はできる限りのことをしておりますが、それはできません」とシルバーは言った。「失礼ながら、私はあの宝を探すことによってしか、自分の命とこの小僧の命を救うことはできんのです。そいつは請け合いますぜ。」
「では、シルバー」と博士は答えた。「もしそうなら、もう一歩踏み込んで言おう。それを見つけた時には、嵐に気をつけろ。」
「先生」とシルバーは言った。「男と男の間で、それはあまりにも言い過ぎであり、あまりにも言葉足らずだ。あんたが何を狙っているのか、なぜ丸太小屋を出たのか、なぜ俺にあの地図を渡したのか、俺にはわからねえ、そうでしょう? それでも俺は目を閉じて、希望の一言もなくあんたの命令に従った! だが、いや、これはあんまりだ。もしあんたが何を言いたいのかはっきり言わねえなら、そう言ってくれ。俺は舵を離す。」
「いや」と博士は考え込むように言った。「私にはそれ以上言う権利がない。それは私の秘密ではないのだよ、シルバー。さもなければ、誓って言うが、君に話しただろう。だが、君と一緒に行けるところまで行こう、そして一歩先まで。さもなければ、きっと船長に私のカツラを直される羽目になるだろう! そしてまず、君に少し希望を与えよう。シルバー、もし我々二人がこの狼の罠から生きて出られたら、私は偽証にならない限り、君を救うために最善を尽くそう。」
シルバーの顔は輝いた。「それ以上は言えませんでしょう、先生、たとえあんたが俺の母親だったとしても」と彼は叫んだ。
「さて、それが私の最初の譲歩だ」と博士は付け加えた。「二つ目は忠告だ。少年をそばに置いておきなさい。そして、助けが必要な時は、大声で叫ぶんだ。私は君のためにそれを探しに行く。それだけでも、私がでたらめを言っているわけではないことがわかるだろう。さようなら、ジム。」
そしてライブシー博士は柵越しに僕と握手をし、シルバーに頷くと、早足で森の中へ去って行った。
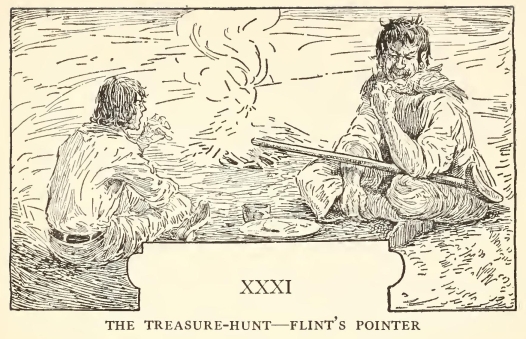
第三十一章 宝探し――フリントの指針
「ジム」と、二人きりになるとシルバーは言った。「俺がおめえの命を救ったなら、おめえは俺の命を救った。その恩は忘れねえ。博士がおめえに逃げろと手招きしてるのを、この目で見た。そしておめえが断るのも、はっきりと聞こえるようだったぜ。ジム、こいつはおめえに一本取られたな。襲撃が失敗してから初めて見えた一筋の希望だ。これもみんなおめえのおかげだ。そして今、ジム、俺たちはこれから宝探しに出かけるわけだが、封印命令付きと来たもんだ。こいつは気に入らねえ。おめえと俺は、背中合わせでぴったりくっついてなきゃならねえ。そして、運命や幸運なんかに逆らってでも、俺たちの首を守り抜くんだ。」
ちょうどその時、焚き火のそばから男の一人が朝食の準備ができたと声をかけてきた。俺たちはすぐに砂浜のあちこちに腰を下ろし、乾パンと揚げた塩漬け肉にありついた。連中は牛の丸焼きでもできそうなほどの火をおこしており、その熱気たるや、風上からでさえ用心しなければ近づけないほどだった。その同じ浪費癖から、おそらく俺たちが食べきれる量の三倍は調理したのだろう。そして一人が空ろな笑いを浮かべ、残飯を火の中に放り込むと、珍妙な燃料を得た炎は再びごうごうと燃え盛った。これほど明日のことを考えない連中を、俺は生まれてこのかた見たことがない。「その日暮らし」という言葉こそ、彼らの生き様を言い表す唯一の表現だろう。食料を無駄にし、見張りを寝かせ、いざこざが起きてもさっさと片付けてしまう度胸はあっても、長期にわたる作戦行動にはまったく不向きな連中であることが、俺には見て取れた。
肩にフリント船長を乗せ、がつがつと食事をしながらも、シルバーでさえ連中の無謀さを一言も咎めなかった。俺はますます驚いた。これほどまでに彼が狡猾さを見せたことは、今までなかったように思えたからだ。
「おう、おめえら」と彼は言った。「この料理番様が、この頭で考えてやってるんだから、運がいいと思え。俺は欲しいものを手に入れたぜ、まったく。奴らが船を持ってるのは確かだ。どこにあるかはまだ分からねえが、宝を見つけさえすりゃ、あとは駆けずり回って探し出しゃいい。そしたらよう、おめえら、ボートを持ってる俺たちの勝ちってもんだ。」
熱いベーコンで口をいっぱいにしながら、彼はそうまくしたてた。こうして仲間たちの希望と自信を取り戻させ、それと同時に、自分自身のそれをも立て直していたのではないかと、俺は強く思った。
「人質についてだが」と彼は続けた。「あいつが、あんなに大事に思ってる連中と話すのも、あれが最後だろうよ。俺は聞きたいことを聞けた。その点は感謝してやる。だが、もうおしまいだ。宝探しに行くときは、こいつを縄につないで連れていく。万一の事故に備えて、金塊同然に大事に扱ってやるからな、覚えとけ。船と宝の両方を手に入れて、陽気な仲間たちと海に出たら、その時はホーキンズの旦那と話し合ってやろうじゃねえか。もちろん、あいつの親切に報いるためにも、分け前はきっちりくれてやるさ。」
男たちが上機嫌になるのも無理はなかった。一方の俺は、ひどく打ちのめされていた。もし今シルバーが描いてみせた計画が実行可能となれば、すでに二重の裏切り者である彼は、ためらうことなくその手を取るだろう。彼はまだ両陣営に片足を突っ込んでおり、こちら側についたところでせいぜい絞首刑を免れるのが関の山なのだから、海賊たちと共に富と自由を選ぶに決まっている。
いや、たとえ事の成り行きで彼がライブシー博士との約束を守らざるを得なくなったとしても、その先にどれほどの危険が待ち受けていることか! 部下たちの疑念が確信に変わったその瞬間、俺たちは命がけで戦わねばならなくなるのだ――片足の男と、まだほんの子供の俺とで、屈強で元気な五人の船乗りを相手に!
この二重の不安に加えて、仲間たちの行動にまつわる謎が、なおも俺の心に重くのしかかっていた。理由の分からぬ砦の放棄、不可解な地図の譲渡、そしてさらに理解しがたいのは、博士がシルバーに残した最後の警告――「それを見つけた時はスコールに気をつけろ」という言葉だ。これだけのことがあれば、俺が朝食をどれほど味気なく感じ、いかに不安な心持ちで、俺を捕らえた者たちの後について宝探しの旅に出たか、容易に想像がつくことだろう。
もし誰かが見ていたとしたら、俺たちはさぞかし奇妙な一行に見えたことだろう。全員が薄汚れた船乗りの服をまとい、俺を除いては皆、頭のてっぺんからつま先まで武装していた。シルバーは二丁の銃を体にたすき掛けにし――一丁は前に、もう一丁は後ろに――腰には大きな斬り込み刀を差し、角尾の上着の両ポケットにはピストルを忍ばせていた。その異様な姿をさらに引き立てるように、肩にはフリント船長がとまり、意味のない船乗りの言葉をわけのわからぬ調子でしゃべり散らしている。俺は腰に縄を巻かれ、海のコックの後をおとなしくついていった。彼は縄の端を、ある時は空いている方の手で、またある時はその強靭な歯でくわえていた。どこからどう見ても、俺はまるで芸を仕込まれた熊のように引かれていた。
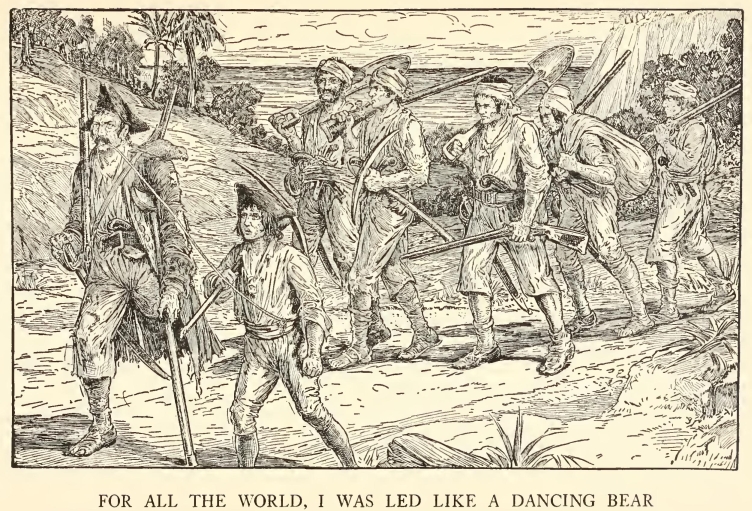
他の男たちも様々に荷を背負っていた。ある者はつるはしとシャベルを――それはヒスパニオラ号から真っ先に陸揚げした必需品だった――、またある者は昼食用の豚肉やパン、ブランデーを運んでいた。俺は、食料がすべて俺たちの備蓄から出ていることに気づき、昨夜のシルバーの言葉が正しかったことを理解した。もし彼が博士と取引をしていなければ、船に見捨てられた彼と反乱者たちは、真水と狩りの獲物だけで食いつなぐ羽目になっていただろう。水だけでは彼らの口には合わなかっただろうし、船乗りはたいてい射撃が下手だ。その上、これほど食料が不足している状況では、火薬が潤沢にあるとは到底思えなかった。
さて、かくして装備を整えた俺たちは全員で出発した。頭を割られた男――本来なら日陰で休んでいるべき男――まで加わり、ぞろぞろと一人また一人と浜辺へ向かうと、そこには二艘のギグボートが待っていた。このボートでさえ、海賊たちの酔った上での愚行の跡をとどめていた。一艘は腰掛け板が壊れ、両方とも泥だらけで淦も汲み出されていない有様だった。安全のため二艘とも持っていくことになり、俺たちはそれぞれに分乗して、停泊地の水面へと漕ぎ出した。
漕ぎ進む間、地図についての議論が交わされた。赤い十字は、言うまでもなく、目印としてはあまりに大きすぎた。そして、これから聞いてもらうことになるが、裏書の文言には曖昧な点があった。読者も覚えているだろうが、それはこうだ。
高い木、望遠鏡山の肩、北北東よりやや北へ。
骸骨島、東南東よりやや東へ。
十フィート。
かくして、「高い木」が主要な目印となった。さて、俺たちの真正面には、高さ二百から三百フィートの高原が停泊地を縁取っていた。その高原は、北側では望遠鏡山のなだらかな南の肩に接し、南側ではミズンマスト山と呼ばれるごつごつした断崖の丘へと再び盛り上がっている。高原の上には、高さもまちまちな松の木がびっしりと点在していた。あちこちで、一本だけ種類の違う木が、周りの木々より四十ないし五十フィートも抜きんでて聳え立っており、これらのうちどれがフリント船長の言う「高い木」なのかは、現地でコンパスの示す方位を頼りに判断するしかなかった。
だが、そういうわけであるにもかかわらず、ボートに乗った男たちは、まだ半ばも進まないうちから、めいめい自分のお気に入りの木を見つけていた。ロング・ジョンだけが肩をすくめ、現地に着くまで待てと彼らを諭していた。
俺たちはシルバーの指示に従い、むやみに体力を消耗しないよう、ゆっくりと漕いだ。かなり長い時間をかけて、二番目の川――望遠鏡山の木深い裂け目を下る川――の河口に上陸した。そこから左に折れ、高原に向かって斜面を登り始めた。
最初のうちは、重くぬかるんだ地面と、密生した湿地の植物に行く手を阻まれ、なかなか進むことができなかった。しかし、少しずつ丘の傾斜は急になり、足元は石ころだらけになって、森の様相も変わり、木々の間隔も開けてきた。実のところ、俺たちが今近づきつつあるのは、この島で最も心地よい場所の一つだった。香りの強いエニシダや、花の咲く多くの低木が、ほとんど草に取って代わっていた。緑のニクズクの木の茂みが、松の赤い幹とその広大な影であちこちに彩られ、ニクズクのスパイスのような香りが松の芳香と混じり合っていた。加えて、空気は爽やかで心を浮き立たせ、降り注ぐ陽光の下、それは俺たちの五感にとって素晴らしい清涼剤となった。
一行は扇状に広がり、叫び声を上げたり、あちこち飛び跳ねたりしながら進んだ。その中央あたり、他の連中からかなり遅れて、シルバーと俺が続いた。俺は縄でつながれ、彼は深い息をつきながら、滑りやすい砂利の中を、まるで地面を耕すように進んでいった。実際、時折俺が手を貸さなければ、彼は足を踏み外して坂を転げ落ちてしまっただろう。
そうして半マイルほど進み、高原の縁にさしかかった時、一番左端にいた男が、まるで恐怖に襲われたかのように大声を張り上げた。叫び声は立て続けに起こり、他の者たちはその方角へ走り始めた。 「宝を見つけたはずはねえ」と、老いたモーガンが右の方から俺たちのそばを急ぎながら言った。「宝はてっぺんにあるはずだからな。」
実際、俺たちもその場所にたどり着いてみると、それはまったく違うものだった。かなり大きな松の木の根元に、緑の蔦に絡まれて、人間の骸骨が横たわっていた。蔦は小さな骨のいくつかを部分的に持ち上げてさえいた。地面には、ぼろぼろになった衣服の切れ端がわずかに残っている。一瞬、その場にいた全員の心に冷たいものが走ったと俺は思う。 「船乗りだ」とジョージ・メリーが言った。彼は他の者より大胆で、すぐそばまで寄って衣服の切れ端を調べていた。「少なくとも、こいつは上等な船乗り用の生地だ。」 「ああ、ああ」とシルバーが言った。「そのようだな。こんな所で司教様を見つけるとは思えねえからな。だが、なんだってこんな格好で骨が横たわってるんだ? 自然じゃねえ。」
確かに、改めて見ると、その死体が自然な体勢でいるとは到底思えなかった。多少の乱れ(おそらく、彼を食らった鳥の仕業か、あるいは徐々にその遺骸を覆っていった蔦のせいだろう)はあったものの、男は完璧にまっすぐ横たわっていた。足はある一方を指し、両手はダイバーのように頭上に上げられ、まったく正反対の方向を指し示していた。
「このおれの石頭にもピンと来たぜ」とシルバーが言った。「ここにコンパスがある。向こうには骸骨島のてっぺんが、歯みたいに突き出してる。そいつを、この骨の線に沿って方位を測ってみてくれ。」 言われた通りにすると、死体はまっすぐ島の方向を指し示しており、コンパスは「東南東よりやや東へ」と正しく読み取れた。
「思った通りだ」と料理番は叫んだ。「こいつは道しるべだ。このまっすぐ先が、俺たちの北極星、そしてお楽しみの金貨のありかだ。だが、ちくしょうめ! フリントのことを考えると、背筋が寒くなるぜ。こいつは奴の冗談の一つだ、間違いねえ。奴と、あの六人はここで二人きりだった。奴は一人残らず殺したんだ。そしてこいつをここまで引きずってきて、コンパスで方角を合わせて寝かせやがった。なんてこった! 骨は長いし、髪は黄色だった。ああ、こいつはアラダイスだろう。アラダイスを覚えてるか、トム・モーガン?」 「ああ、ああ」とモーガンは答えた。「覚えてるさ。あいつは俺に借金があったし、俺のナイフを陸に持っていきやがった。」
「ナイフと言えば」と別の男が言った。「なんで奴のナイフがこの辺に落ちてねえんだ? フリントは船乗りの懐をまさぐるような男じゃなかった。鳥だって、ナイフなんざ放っておくだろう。」 「ちくしょう、その通りだ!」とシルバーが叫んだ。 「ここには何も残っちゃいねえ」とメリーが、まだ骨の周りを手探りしながら言った。「銅貨一枚も、タバコ入れもだ。どうも自然じゃねえ。」 「ああ、まったく、そうだな」とシルバーも同意した。「自然じゃねえし、気味も悪ぃ。とんでもねえ! なあ、おめえら、もしフリントが生きてたら、ここは俺たちにとって、とんだやばい場所になってたぜ。奴らは六人だった。俺たちも六人だ。そして奴らは今、骨になってる。」
「奴が死んだのは、この目でしかと見た」とモーガンが言った。「ビリーに連れられてな。そこに横たわって、目にはペニー硬貨が乗せられてた。」 「死んだ――ああ、確かに奴は死んで地獄へ行ったさ」と包帯の男が言った。「だが、もし亡霊ってやつが歩き回るなら、そいつはフリントに違いねえ。ああ、まったく、ひでえ死に方だったぜ、フリントは!」 「ああ、まったくだ」と別の男が言った。「ある時は怒り狂い、ある時はラムをよこせとわめき、またある時は歌いだす。『十五人』が奴の十八番だった。正直言って、あれ以来、あの歌を聞くのがどうも好きになれねえ。ひどく暑くて、窓が開け放してあってな、あの古い歌がはっきりと聞こえてくるんだ――もう死に神がそいつの首に縄をかけてるってのによ。」
「よせよせ」とシルバーが言った。「そんな話はしまえ。奴は死んだ。歩き回ったりしねえよ、俺が知る限りはな。少なくとも、昼間は歩き回らねえ。そいつは請け合うぜ。心配は身の毒だ。さあ、ダブロン金貨を目指して進め。」 俺たちは確かに出発した。しかし、照りつける太陽と白昼の光にもかかわらず、海賊たちはもはや森の中をばらばらに走り回ったり叫んだりすることはなく、肩を寄せ合い、息を殺して話すだけだった。死せる海賊への恐怖が、彼らの魂に重くのしかかっていたのだ。

第三十二章 宝探し――木々の中の声
この恐ろしい出来事で意気消沈したことと、シルバーや病人を休ませるためとが相まって、一行は坂を登りきるとすぐに腰を下ろした。
高原はやや西に傾斜していたため、俺たちが足を止めたこの場所からは、左右どちらにも広大な眺望が開けていた。前方には、木々の梢の向こうに、白波に縁取られた森の岬が見えた。後方には、停泊地と骸骨島を見下ろすだけでなく、砂嘴と東の低地をはるかに越えて、東側に広がる大海原を望むことができた。俺たちの真上には望遠鏡山がそびえ立ち、所々には松の木が点在し、また所々では断崖絶壁が黒々と口を開けている。聞こえる音は、四方から響いてくる遠くの砕け波の音と、茂みで鳴く無数の虫の声だけだった。海には人影一つ、帆影一つない。その眺めの広大さこそが、孤独感をいや増していた。
シルバーは座ったまま、コンパスでいくつかの方位を測った。 「『高い木』が三本あるな」と彼は言った。「骸骨島からほぼ一直線上だ。『望遠鏡山の肩』ってのは、あそこの低い方の場所のことだろう。こうなりゃ、お宝を見つけるなんざ赤子の手をひねるようなもんだ。先に飯にするか、そんな気もしてきたぜ。」 「どうも気分がすぐれねえ」とモーガンがうなった。「フリントのことを考えちまったせいだ――たぶんな。」 「ああ、まあ、息子よ、奴が死んでて運が良かったと星に感謝するんだな」とシルバーは言った。
「醜い悪魔だった」と三人目の海賊が身震いしながら叫んだ。「顔も真っ青だったしな!」 「ラムのせいでああなったんだ」とメリーが付け加えた。「青い! ああ、確かに青かった。本当の話だぜ。」 骸骨を見つけてからこの手の話になって以来、彼らの声はどんどん小さくなり、今やほとんどささやき声になっていた。そのため、彼らの話し声が森の静寂を破ることはほとんどなかった。その時、突然、俺たちの前方の木々の真ん中から、細く、高く、震えるような声が、あの聞き覚えのあるメロディーと歌詞を歌い始めた。 「死人の箱にゃ十五人――ヨーホーホー、ラム酒の瓶もな!」
俺は、この時の海賊たちほどひどく狼狽した人間を見たことがない。六人の顔から、まるで魔法にでもかかったようにさっと血の気が引いた。ある者は飛び上がり、ある者は他の者にしがみついた。モーガンは地面にひれ伏した。 「フリントだ、ちくしょうめ!」とメリーが叫んだ。
歌は始まった時と同じくらい突然止んだ。まるで誰かが歌い手の口を手で塞いだかのように、音の途中でぷつりと途切れたと言っていいだろう。澄み切った陽光の中、緑の梢を抜けてくるその声は、俺には軽やかで心地よくさえ聞こえた。だからこそ、仲間たちの受けた衝撃は、なおさら奇妙に思えた。
「おい」とシルバーが、灰色の唇を震わせながらやっとのことで言葉を絞り出した。「これじゃいかん。向きを変えるぞ。こいつは奇妙な始まりだが、声の主は分からん。だが、誰かがふざけてるだけだ――生身の人間だ、そいつは請け合うぜ。」 話しているうちに彼の勇気は戻り、顔にもいくらか血の気が差してきた。他の者たちもすでにこの励ましの言葉に耳を貸し始め、少し我に返りかけていた。その時、同じ声が再び響き渡った。今度は歌ではなく、遠くからの微かな呼び声で、望遠鏡山の裂け目にこだまして、さらに微かに聞こえた。 「ダービー・マグロー」と、その声は嘆いた――この音を表すのに、これほどふさわしい言葉はないだろう――「ダービー・マグロー! ダービー・マグロー!」と、何度も何度も。そして少し調子を上げ、俺が省くことにする罵りの言葉と共に、こう続けた。「ラムを船尾に持ってこい、ダービー!」

海賊たちは、まるで地面に根が生えたかのように立ち尽くし、目は頭から飛び出さんばかりだった。声が消え去ってからもしばらくの間、彼らは恐ろしげに、黙って前方を凝視していた。 「これで決まりだ!」と一人が喘いだ。「ずらかろう。」 「あれが奴の最後の言葉だった」とモーガンがうめいた。「奴が甲板で言った、最後の言葉だ。」 ディックは聖書を取り出し、しきりに祈りを唱えていた。船乗りになって悪党仲間と付き合う前は、ディックは良い育ち方をしたのだ。 それでもシルバーは屈しなかった。彼の頭の中で歯がガチガチと鳴るのが聞こえたが、彼はまだ降参してはいなかった。 「この島でダービーの名を聞いたことがある奴なんざいやしねえ」と彼はつぶやいた。「ここにいる俺たち以外にはな」。そして、一大決心をして叫んだ。「仲間たちよ、俺はあのお宝を手に入れるためにここに来たんだ。人間だろうが悪魔だろうが、負けるもんか。生きてるフリントを恐れたことなんざ一度もねえ。ちくしょう、死んだ奴なんぞ相手にしてやる。ここから四分の一マイルも行かねえ所に、七十万ポンドが眠ってるんだぞ。青い顔した酔いどれの老いぼれ船乗り――しかも死んでる奴――のために、これほどの金貨に背を向ける冒険紳士が、いったいどこにいるってんだ?」
しかし、彼の部下たちに勇気が蘇る気配はなく、むしろ、彼の不敬な言葉に恐怖を増したようだった。 「やめろ、ジョン!」とメリーが言った。「亡霊に逆らうんじゃねえ。」 他の者たちは恐ろしさのあまり返事もできなかった。勇気さえあれば、めいめい逃げ出していただろう。だが、恐怖が彼らを一つにまとめ、ジョンのそばに引き留めていた。まるで彼の勇気が助けになるかのように。彼自身は、自分の弱さをほとんど克服していた。 「亡霊だと? まあ、そうかもしれん」と彼は言った。「だが、一つ腑に落ちねえことがある。こだまがあった。さて、影のある亡霊なんぞ見たことがある奴は一人もいねえ。だったら、なんで亡霊にこだまがあるってんだ? そいつは自然じゃねえだろう、なあ?」 この議論は俺にはずいぶん弱々しく思えた。しかし、迷信深い人間に何が効くかは決して分からないもので、驚いたことに、ジョージ・メリーはひどく安堵した。 「ああ、そいつはそうだ」と彼は言った。「あんたの肩にはまともな頭が乗ってるぜ、ジョン、間違いねえ。向きを変えろ、おめえら! この船は進路を間違えてるぜ、俺はそう思う。それに考えてみりゃ、フリントの声に似てはいたが、結局のところ、それほどはっきりしたもんでもなかった。今じゃ誰か別の奴の声に似てる気がする――もっと似てるのは――」 「ちくしょう、ベン・ガンだ!」とシルバーが吼えた。 「そうだ、その通りだ!」とモーガンが膝から飛び上がって叫んだ。「ベン・ガンだったんだ!」 「大して変わりはねえんじゃねえか?」とディックが尋ねた。「ベン・ガンだって、フリントと同じで、肉体はここにはねえだろ。」 しかし、古参の船乗りたちはこの発言を嘲笑で迎えた。 「なんだって、ベン・ガンなんぞ誰も気にしねえよ」とメリーが叫んだ。「生きてようが死んでようが、あんな奴、誰も気にかけやしねえ。」
彼らの気力が戻り、顔に自然な血色が蘇ったのは、驚くべきことだった。すぐに彼らは、時折耳を澄ませながら、またおしゃべりを始めた。そして間もなく、それ以上物音がしないのを確認すると、道具を肩にかついで再び出発した。メリーが先頭に立ち、シルバーのコンパスを手に、骸骨島との正しい直線上を進んでいく。彼の言ったことは真実だった。生きていようが死んでいようが、誰もベン・ガンを気にしなかった。 ディックだけはまだ聖書を握りしめ、恐ろしげな視線で周りを見回しながら歩いていた。しかし、同情してくれる者はなく、シルバーは彼の用心深さをからかいさえした。 「言っただろう」と彼は言った。「言ったはずだ、おめえは聖書を台無しにしちまったってな。誓いの言葉にすら使えねえもんを、亡霊がありがたがると思うか? こんなもんもくれやしねえよ!」と、彼は松葉杖で一瞬立ち止まり、太い指をぱちんと鳴らした。 しかし、ディックの気は休まらなかった。実際、この若者が病気になりかけていることは、すぐに俺にも分かった。暑さと疲労、そして恐怖による衝撃が引き金となり、ライブシー博士が予言した熱病が、明らかに急速に悪化しつつあった。
ここ、頂上は歩きやすい開けた場所だった。前に述べたように、高原は西に傾斜していたため、俺たちの道はわずかに下り坂になっていた。大小の松の木がまばらに生え、ニクズクやツツジの茂みの間にも、熱い太陽に焼かれた広い空間が広がっていた。俺たちは島をほぼ北西に横切るように進み、一方では望遠鏡山の肩の下にますます近づき、もう一方では、かつて俺がコラクル舟で揺られ震えていたあの西の湾を、より広く見渡すようになった。 最初の一本目の高い木にたどり着いたが、方位を測ると違うことが分かった。二本目も同様だった。三本目は、下草の茂みの中から、二百フィート近くも空にそびえ立っていた。それはまさに植物の巨人で、小屋ほどもある赤い幹を持ち、その周りには一中隊が展開できるほどの広大な影を落としていた。東からも西からも、遠くの海上から目立ち、航海図に航行目標として記載されていてもおかしくないほどだった。
しかし、今や仲間たちの心を捉えたのはその大きさではなかった。七十万ポンドもの金貨が、その広がる影の下のどこかに埋められているという事実だった。近づくにつれて、金のことが頭を占め、それまでの恐怖をすっかり飲み込んでしまった。彼らの目は頭の中で燃え盛り、足取りは速く、軽やかになった。彼らの魂はすべて、その財宝に、彼ら一人一人を待ち受けている、生涯にわたる贅沢と快楽に縛り付けられていた。 シルバーは松葉杖をつき、うなり声を上げながらびっこを引いて進んだ。彼の鼻の穴は広がり、ひくついていた。熱くテカテカ光る顔に蝿がとまると、狂人のように悪態をついた。俺を繋いでいる縄を猛烈に引き、時折、殺意に満ちた目で俺に視線を向けた。彼は自分の考えを隠そうともせず、俺もまた、その考えを印刷された文字のように読み取ることができた。金を目前にして、他のすべては忘れ去られていた。彼の約束も、博士の警告も、ともに過去のものとなっていた。彼が宝を奪い、夜陰に紛れてヒスパニオラ号を見つけ出して乗り込み、この島にいる善良な者たちの喉をことごとく掻き切り、そして当初の計画通り、罪と富を積んで船出することを望んでいるのは、疑いようもなかった。
こうした恐怖に震える俺にとって、宝探しに夢中な連中の速いペースについていくのは困難だった。時折つまずくと、そのたびにシルバーは荒々しく縄を引き、殺意のこもった視線を俺に投げつけた。俺たちの後ろに遅れ、今や最後尾についてくるディックは、熱が上がるにつれて、祈りの言葉と呪いの言葉をぶつぶつと口走っていた。このことも俺の惨めさを増し、とどめを刺すように、かつてこの高原で演じられた悲劇のことが頭から離れなかった。あの不信心な、青い顔の海賊――サバンナで酒を求め、歌い叫びながら死んだ男――が、この場所で、自らの手で六人の共犯者を切り捨てたのだ。今ではかくも平和なこの木立も、当時は叫び声で満ちていたに違いないと俺は思った。そして、そう思っただけで、今もその叫び声が響いているようにさえ思えた。
俺たちは今や、茂みの縁に立っていた。 「万歳、おめえら、みんな一緒に!」とメリーが叫び、先頭の者たちが駆け出した。 そして突然、十ヤードも行かないうちに、彼らが立ち止まるのが見えた。低い叫び声が上がった。シルバーはペースを倍にし、取り憑かれたように松葉杖の先で地面を突きながら進んだ。そして次の瞬間、彼と俺もまた、ぴたりと足を止めた。 俺たちの前には、大きな穴が掘られていた。さほど新しいものではなく、側面は崩れ落ち、底には草が生えていた。その中には、真っ二つに折れたつるはしの柄と、いくつかの梱包用の木箱の板が散らばっていた。その板の一枚に、熱した鉄で焼印された「ワルラス号」――フリントの船の名――を俺は見た。 すべては明白だった。隠し場所は発見され、荒らされていた。七十万ポンドは、消え去っていたのだ!
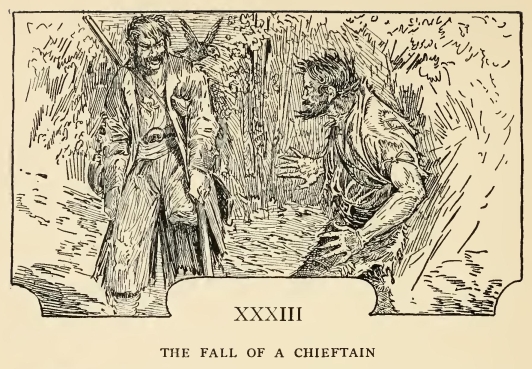
第三十三章 首領の失墜
これほどのどんでん返しは、この世にまたとあるまい。六人の男はそれぞれ、まるで殴られたかのように立ち尽くした。しかしシルバーの場合、その衝撃はほとんど一瞬で過ぎ去った。彼の魂のすべての思いは、まるで競走馬のように、その金に向かって全力で突き進んでいた。それが、一瞬にして、ぴたりと止められたのだ。それでも彼は冷静さを保ち、気性を取り戻し、他の者たちが失望を悟る間もなく、計画を変更した。
「ジム」と彼はささやいた。「こいつを持て。面倒なことになるぞ。」 そう言って、彼は俺に二連式のピストルを手渡した。 同時に、彼は静かに北へ移動し始め、数歩で俺たち二人と他の五人との間に、あの窪地を挟む形にした。それから俺を見てうなずいた。それはまるで「窮地に陥ったな」と言っているかのようであり、実際、俺もそう思った。彼の表情は決して友好的とは言えず、俺はこの度重なる変節にうんざりして、思わずこうささやかずにはいられなかった。「また寝返ったのか。」
彼が答える時間は残されていなかった。海賊たちは、罵りの言葉と叫び声を上げながら、次々と穴に飛び込み、板を脇に放り投げながら、指で地面を掘り始めた。モーガンが金貨を一枚見つけた。彼はそれを、罵詈雑言の嵐と共に掲げた。それは二ギニー金貨で、十五秒ほどの間、彼らの手から手へと渡された。 「二ギニーだと!」メリーはそれをシルバーに向かって振りながら吼えた。「これがてめえの七十万ポンドか? おめえは取引上手だな、ええ? 何一つしくじったことのねえ男様だよ、この木偶の坊が!」
「掘れよ、おめえら」とシルバーは、この上なく冷淡な不遜さで言った。「豚の餌でも見つかるかもしれねえな。」 「豚の餌だと!」メリーは金切り声で繰り返した。「仲間たち、聞いたか? 今に教えてやるが、あそこにいる男は最初から全部知ってたんだ。奴の顔を見ろ、そう書いてあるぜ。」 「ああ、メリー」とシルバーが言った。「また船長気取りか? おめえは確かに、でしゃばりな若造だ。」
しかし、今度は誰もが完全にメリーの味方だった。彼らは穴から這い出し始め、背後に猛烈な視線を投げかけた。俺は、俺たちにとって好都合なことに気づいた。彼らは全員、シルバーとは反対側に這い上がったのだ。 さて、俺たちはそこに立っていた。片側に二人、もう一方に五人、間には穴があり、誰も先制攻撃を仕掛けるほどの気概は持ち合わせていなかった。シルバーは微動だにしなかった。彼は松葉杖に寄りかかってまっすぐに立ち、俺がこれまで見た中で最も冷静な様子で、彼らを見つめていた。彼は勇敢だった、それは間違いない。
ついにメリーは、演説が事態を打開するかもしれないと考えたようだった。 「仲間たち」と彼は言う。「向こうには二人きりだ。一人は、俺たち全員をここまで連れてきて、こんな無様な目に遭わせた老いぼれの片輪。もう一人は、俺が心臓をえぐり出してやろうと思ってる、あの小僧だ。さあ、仲間たち――」 彼は腕と声を振り上げ、明らかに突撃を率いるつもりだった。しかし、まさにその時――パン! パン! パン! ――三発のマスケット銃の銃声が茂みから閃いた。メリーは頭から穴の中に転落した。包帯の男は独楽のようにくるりと回り、横ざまにばったりと倒れた。彼は死んでいたが、体はまだ痙攣していた。そして、残りの三人は向きを変え、死に物狂いで逃げ出した。

瞬きする間もなく、ロング・ジョンはもがいているメリーにピストルの二つの銃身から弾を撃ち込んでいた。男が断末魔の苦しみの中で彼を見上げた時、「ジョージ」と彼は言った。「これで決着だな。」 その瞬間、博士とグレイ、そしてベン・ガンが、まだ煙を吹くマスケット銃を手に、ニクズクの木々の間から俺たちに合流した。
「前へ!」と博士が叫んだ。「駆け足だ、諸君。奴らがボートに着く前に回り込まねば。」 そして俺たちは猛烈な速さで駆け出した。時には胸の高さまである茂みをかき分けながら。 言っておくが、シルバーは必死で俺たちについてこようとしていた。あの男がやってのけた仕事は、胸の筋肉がはち切れんばかりに松葉杖で跳び続けるという、どんな健常者にも真似のできない離れ業だった。博士もそう考えている。それでも、俺たちが坂の頂に着いた時には、彼はすでに三十ヤードも遅れ、窒息寸前だった。 「先生」と彼は呼びかけた。「あれを見ろ! 急ぐことはねえ!」
確かに、急ぐ必要はなかった。高原のより開けた場所で、生き残った三人が、最初に走り出したのと同じ方向、ミズンマスト山に向かってまだ走っているのが見えた。俺たちはすでに彼らとボートの間に回り込んでいた。そこで俺たち四人は腰を下ろして息を整え、ロング・ジョンは顔の汗を拭いながら、ゆっくりと追いついてきた。 「ありがてえ、先生」と彼は言う。「俺とホーキンズにとっちゃ、まさに間一髪ってところでしたな。それで、おめえがベン・ガンか!」と彼は付け加えた。「へえ、とんだお人だ。」 「俺はベン・ガンだ、そうだとも」と、置き去りにされた男は、当惑してうなぎのように身をよじりながら答えた。「それで」と長い沈黙の後で付け加えた。「ご機嫌いかがです、シルバーさん? おかげさまで、元気です、とあんたは言う。」 「ベン、ベン」とシルバーはつぶやいた。「おめえに一杯食わされるとはな!」
博士はグレイを、反乱者たちが逃げる際に置き去りにしたつるはしの一つを取りに戻らせた。そして、ボートが置いてある場所へとゆっくり丘を下りながら、事の顛末をかいつまんで話してくれた。それはシルバーを大いに引きつける話だった。そして、半ば白痴の置き去りにされた男、ベン・ガンが、始めから終わりまでの英雄だった。 ベンは、島での長く孤独な放浪の間に、あの骸骨を見つけ――その所持品を漁ったのは彼だった――、宝を見つけ、掘り出した(穴の中に折れて落ちていたのは、彼のつるはしの柄だった)。そして、何度も骨の折れる旅を重ねて、その宝を背負って高い松の木の根元から、島の北東の角にある二つの尖った丘の洞窟まで運び、ヒスパニオラ号が到着する二ヶ月も前から、そこに安全に保管していたのだ。
博士が攻撃のあった日の午後に、彼からこの秘密を聞き出し、翌朝、停泊地がもぬけの殻になっているのを見た時、彼はシルバーの元へ行ったのだ。もはや無用となった地図を渡し――ベン・ガンの洞窟には彼が塩漬けにしたヤギの肉が豊富にあったので――食料を渡し、砦から二つの尖った丘へ安全に移動する機会を得るためなら、何でもかんでも与えた。マラリアから逃れ、金を監視するためだった。 「ジム、お前のことだが」と彼は言った。「心苦しくはあったが、私は自分の義務を果たした者たちのために最善と思うことをしたのだ。もしお前がその一人でなかったとしたら、それは誰のせいかね?」
その朝、私が反乱者たちのために用意された恐ろしい失望に巻き込まれることを知ると、彼は洞窟まで走り、郷士に船長の護衛を任せ、グレイと置き去りの男を連れて出発し、松の木のそばで待ち受けるべく島を斜めに横切ってきたのだ。しかし、すぐに我々のパーティーの方が先に出発したことに気づき、足の速いベン・ガンを先に送り出し、一人でできるだけのことをやらせた。その時、ベン・ガンはかつての船仲間たちの迷信深さを利用することを思いついた。そして、それは大いに成功し、グレイと博士が追いついて、宝探しの連中が到着する前にすでに待ち伏せを完了することができたというわけだ。
「ああ」とシルバーが言った。「俺にとっちゃ、ここにホーキンズがいたのが幸いでしたな。先生、あんたなら、この老いぼれジョンが八つ裂きにされても、気にも留めなかったでしょうよ。」 「微塵もな」とライブシー博士は陽気に答えた。
この時までに、俺たちはギグボートにたどり着いていた。博士はつるはしでそのうちの一艘を破壊し、それから俺たちは全員でもう一艘に乗り込み、海路で北の入り江を目指して出発した。 八、九マイルの道のりだった。シルバーは、すでに疲労で死にそうだったが、俺たちと同じようにオールを漕がされ、俺たちはすぐに穏やかな海上を滑るように進んだ。まもなく俺たちは海峡を抜け、島の南東の角を回った。四日前、俺たちがヒスパニオラ号を曳航した場所だ。
二つの尖った丘を通り過ぎる時、ベン・ガンの洞窟の黒い入り口と、そのそばに立ち、マスケット銃に寄りかかっている人影が見えた。郷士だった。俺たちはハンカチを振り、彼に万歳三唱を送った。その声には、シルバーの声も誰にも劣らず心から加わっていた。
さらに三マイル進んだ、北の入り江の入り口のすぐ内側で、何と、独りでに漂っているヒスパニオラ号に出くわしたではないか。最後の満ち潮で船体が浮き上がったのだ。もし南の停泊地のように風が強かったり、潮の流れが速かったりしたら、二度と見つけることはできなかったか、あるいは助けようもないほど座礁しているのを見つけることになっただろう。実際のところ、主帆が破れている以外は、ほとんど損傷はなかった。もう一つの錨が用意され、一尋半の水深に下ろされた。俺たちは全員で再び漕いでラム入り江――ベン・ガンの宝の家に最も近い場所――へ向かった。そしてグレイが、一人でギグボートをヒスパニオラ号へ戻し、そこで夜の見張りをすることになった。
浜辺から洞窟の入り口まで、なだらかな斜面が続いていた。その頂上で、郷士が俺たちを迎えた。俺に対しては、心から親切で、俺の無軌道な行動を咎めるでもなく、褒めるでもなく、何も言わなかった。シルバーの丁寧な敬礼には、いくらか顔を紅潮させた。 「ジョン・シルバー」と彼は言った。「お前はとんでもない悪党で詐欺師だ――途方もない詐欺師だよ、君。私はお前を訴追しないようにと言われている。よろしい、ならばそうしよう。だが、死んだ者たちが、君、石臼のように君の首にぶら下がっているぞ。」 「ご親切にどうも、旦那様」とロング・ジョンは答え、再び敬礼した。 「礼など言うな!」と郷士は叫んだ。「これは私の甚だしい職務怠慢だ。下がれ。」
そうして俺たちは全員、洞窟の中に入った。そこは広々として風通しの良い場所で、小さな泉と澄んだ水の池があり、シダが覆いかぶさっていた。床は砂だった。大きな焚き火の前にはスモレット船長が横たわっていた。そして遠い隅の方に、炎に薄暗く照らされて、金貨の大きな山と、金の延べ棒で築かれた四角い塊を俺は目にした。それこそが、俺たちがはるばる探しに来て、すでにヒスパニオラ号から十七人の命を奪った、フリントの宝だった。それを蓄えるためにどれほどの犠牲が払われたか、どれほどの血と悲しみ、海の底に沈められた立派な船、目隠しをされて板を歩かされた勇敢な男たち、放たれた大砲の弾、恥辱と嘘と残酷さがあったか、おそらく生きている人間には誰にも語ることはできまい。しかし、この島にはまだ三人の男――シルバー、老いたモーガン、そしてベン・ガン――がいた。彼らはそれぞれ、報いを分かち合うことを空しく望んだように、これらの犯罪に一枚噛んでいたのだ。
「入れ、ジム」と船長が言った。「お前はお前のやり方で良い子だよ、ジム。だが、お前と私がまた一緒に航海に出ることはないだろうな。お前は私にとって、生まれついての幸運児すぎる。そこにいるのはジョン・シルバーか? 何をしに来たんだ、お前は?」 「義務に戻りました、船長」とシルバーは答えた。 「ほう!」と船長は言った。彼が言ったのはそれだけだった。 その夜、友人たちに囲まれて食べた夕食は、何と素晴らしいものだったことか。ベン・ガンの塩漬けヤギ肉に、ヒスパニオラ号から持ってきたご馳走と年代物のワインの瓶。これほど陽気で幸せな人々は、きっといなかっただろう。そしてそこにはシルバーがいた。火の光がほとんど届かない後ろの方に座っていたが、心から食事を楽しみ、何か必要があればさっと前に出てきて、俺たちの笑い声にさえ静かに加わっていた。往路の航海の時と寸分違わぬ、あの物腰の柔らかい、礼儀正しく、へつらうような船乗りだった。
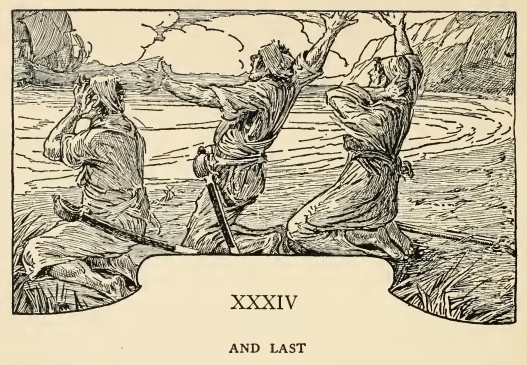
第三十十四章 そして、最後
翌朝、俺たちは早くから仕事に取りかかった。この大量の金を、陸路で一マイル近く浜辺まで運び、そこからボートで三マイル先のヒスパニオラ号まで運ぶのは、これだけ少ない人数の働き手にとっては、かなりの重労働だったからだ。島にまだ残っている三人の男たちのことは、さほど気にならなかった。丘の肩に一人見張りを立てておけば、突然の襲撃に備えるには十分だったし、それに、彼らはもう戦いにはうんざりしているだろうと俺たちは考えていた。
かくして、作業はてきぱきと進められた。グレイとベン・ガンがボートで往復し、その間、残りの者たちは宝を浜辺に積み上げた。金の延べ棒二本を縄の端で吊るすと、大人の男一人分の良い荷物になった。ゆっくりと歩くのが嬉しくなるほどの重さだ。俺はと言えば、運搬にはあまり役に立たなかったので、一日中洞窟で鋳造貨幣を乾パン袋に詰める作業に追われた。
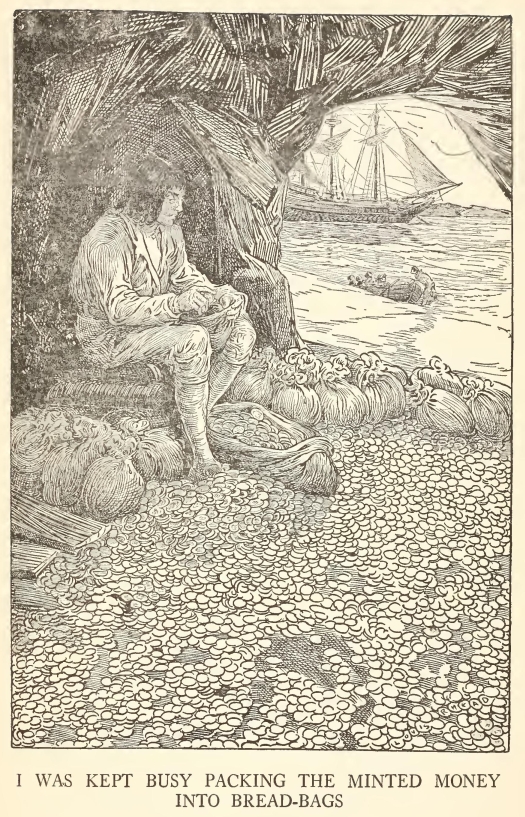
それは奇妙なコレクションだった。貨幣の多様さという点ではビリー・ボーンズの蓄えに似ていたが、規模も種類もはるかに大きく、俺はそれを仕分けること以上に楽しいことはなかったと思う。イギリス、フランス、スペイン、ポルトガル、ジョージ金貨にルイ金貨、ダブロン金貨に二重ギニー金貨、モイドール金貨にセキン金貨、過去百年間のヨーロッパのあらゆる王の肖像、まるで糸くずか蜘蛛の巣の切れ端のようなものが刻印された奇妙な東洋の貨幣、丸いもの、四角いもの、首にかけるためか真ん中に穴が開けられたもの――世界中のほとんどすべての種類の貨幣が、そのコレクションの中にあったに違いない。そしてその数たるや、まるで秋の木の葉のようで、俺はかがみすぎて背中が痛み、仕分け作業で指が痛くなったほどだ。
来る日も来る日もこの作業は続いた。毎晩、一財産が船に積み込まれたが、翌日にはまた別の財産が待っていた。そしてこの間ずっと、生き残った三人の反乱者たちの消息は何も聞こえてこなかった。 ついに――三日目の夜だったと思う――博士と私が、島の低地を見下ろす丘の肩を散歩していると、下の深い闇の中から、風が、悲鳴と歌声の入り混じったような音を運んできた。俺たちの耳に届いたのはほんの一節で、その後は元の静寂に戻った。 「神よ、彼らを許したまえ」と博士は言った。「反乱者たちだ!」 「みんな酔っ払ってるんですよ、旦那」と、俺たちの後ろからシルバーの声が割り込んだ。
言っておくべきだが、シルバーは完全な自由を許されており、毎日冷たくあしらわれているにもかかわらず、再び自分を特権的で親しい部下と見なしているようだった。実際、彼がこれらの軽蔑によく耐え、飽くことなき礼儀正しさで皆に取り入ろうとし続けたのは、注目に値した。しかし、彼を犬よりましに扱った者は、いまだに昔の操舵手をひどく恐れているベン・ガンか、あるいは彼に感謝すべきことがあった俺自身を除いては、一人もいなかったと思う。もっともその点では、俺は誰よりも彼を悪く思う理由があったはずだ。高原で彼が新たな裏切りをたくらんでいるのを、この目で見ていたのだから。したがって、博士が彼に答えたのは、かなりぶっきらぼうな口調だった。 「酔っているか、うわごとを言っているかだ」と彼は言った。
「その通りでございます、旦那」とシルバーは答えた。「あんたや俺にとっちゃ、どっちだって大差ありませんがね。」 「私にお前を人道的な人間と呼べとは、まさか言うまいな」と博士は冷笑を浮かべて返した。「だから私の気持ちは、お前を驚かせるかもしれんぞ、シルバー君。だが、もし彼らがうわごとを言っていると確信できれば――少なくとも一人は熱病に倒れていると、私は道義的に確信しているが――私はこの野営地を離れ、我が身にどんな危険が及ぼうとも、私の医術で彼らを助けに行くだろう。」 「失礼ながら、旦那、それは大きな間違いでさあ」とシルバーは言った。「あんたは貴重な命を失うことになる。そいつは請け合いますぜ。俺は今や、あんたの味方、一心同体です。あんたにどれほどの借りがあるか分かっている以上、あんた自身は言うに及ばず、この一行が弱体化するのは見たくねえ。ですが、下にいるあの連中は、約束を守れねえ――いや、たとえ守りたかったとしても、できやしねえ。その上、あんたの善意を信じることもできねえでしょうよ。」 「そうだろうな」と博士は言った。「お前こそ約束を守る男だ、我々はそれを知っている。」
さて、それが三人の海賊について我々が聞いた、ほぼ最後の知らせだった。ただ一度だけ、遠くで銃声が聞こえ、彼らが狩りをしているのだろうと推測した。会議が開かれ、彼らを島に置き去りにすることが決定された――言っておくが、ベン・ガンはこれ以上ないほど喜び、グレイも強くそれに賛成した。我々は、十分な量の火薬と弾丸、塩漬けヤギ肉の大部分、いくつかの薬品、そしてその他の必需品、道具、衣類、予備の帆、一尋か二尋のロープ、そして博士の特別な希望により、かなりの量のタバコを残していった。
それが、島での我々のほぼ最後の行動だった。その前に、我々は宝を積み込み、万一の事態に備えて十分な水と残りのヤギ肉を船に乗せていた。そしてついに、ある晴れた朝、我々は錨を上げた。それが我々にできる精一杯のことだった。そして、船長が砦で掲げ、その下で戦ったのと同じ旗をはためかせながら、北の入り江から外洋へと乗り出した。 あの三人は、我々が思っていたよりもずっと近くで我々を見ていたに違いない。それはすぐに証明された。狭い海峡を抜ける際、我々は南の岬にかなり接近しなければならなかった。そしてそこで、三人が砂嘴の上に一緒にひざまずき、懇願するように腕を上げているのを我々は見た。彼らをあのような惨めな状態で見捨てるのは、我々全員の心を痛めたと思う。しかし、再び反乱を起こされる危険を冒すわけにはいかなかった。そして、絞首台にかけるために本国へ連れ帰るのは、残酷な種類の親切だっただろう。博士は彼らに呼びかけ、我々が残した物資のことと、それを見つける場所を伝えた。しかし、彼らは我々の名を呼び続け、神に免じて慈悲をかけ、こんな場所で死なせないでくれと訴え続けた。
ついに、船が針路を変えず、今や急速に声の届かない距離まで遠ざかっていくのを見て、彼らのうちの一人――誰だったかは分からない――が、しわがれた叫び声と共に飛び上がり、マスケット銃を肩に構え、シルバーの頭上をかすめて主帆を貫く一発を放った。 その後、我々は船べりの陰に隠れ、次に私が外を見た時には、彼らは砂嘴から姿を消しており、砂嘴そのものも、広がる距離の中にほとんど溶け込むように見えなくなっていた。少なくとも、それで一件落着だった。そして正午前には、私の言いようのない喜びに、宝島の最も高い岩が、青く丸い海の中へと沈んでいった。
我々はひどい人手不足で、船に乗っている者は皆、手を貸さなければならなかった。ただ船長だけは、船尾のマットレスに横たわって命令を下していた。彼はかなり回復していたが、まだ安静が必要だったのだ。新たな船員なしで本国への航海を危険にさらすことはできなかったので、我々は船首をスペイン領アメリカの最寄りの港に向けた。そして実際のところ、逆風や二度の強風に見舞われ、そこに到着する前に我々は皆、疲れ果ててしまった。 ちょうど日没時に、我々は陸に囲まれたこの上なく美しい湾に錨を下ろした。するとすぐに、黒人やメキシコのインディアン、そして混血の人々でいっぱいの陸からのボートに囲まれ、彼らは果物や野菜を売り、小銭のために海に潜ってみせると申し出た。かくも多くの陽気な顔(特に黒人たちの)、熱帯の果物の味、そして何よりも町に灯り始めた光景は、島での我々の暗く血なまぐさい滞在と、実に魅力的な対照をなしていた。そして博士と郷士は、私を連れて、夜の早い時間を過ごすために上陸した。ここで彼らはイギリスの軍艦の艦長に出会い、彼と語り合い、彼の船に乗り込み、要するに、非常に楽しい時を過ごしたので、我々がヒスパニオラ号の舷側に戻ってきた時には、夜が明け始めていた。
甲板にはベン・ガンが一人でいた。我々が乗り込むやいなや、彼は奇妙な身振りを交えながら告白を始めた。シルバーがいなくなった、と。数時間前、あの島流れの男が、シルバーが陸舟で逃げるのを黙認したというのだ。そして今、彼は我々にこう請け合った。あれは我々の命を守るためだった、もし「あの片足の男が船に残っていたら」、我々の命は間違いなくなかっただろう、と。だが、話はそれだけではなかった。あの海のコックは、手ぶらで去ったわけではなかったのである。彼は誰にも気づかれずに隔壁を切り裂き、金貨の袋を一つ持ち出していた。おそらく三、四百ギニーの価値はあろうその金貨を、これからの放浪の足しにするためだった。
彼とこれほど安く手を切れたことを、我々は皆、喜んでいたと思う。
さて、かいつまんで話せば、我々は船員を数人雇い入れ、順風満帆の航海を経て、ヒスパニオラ号はブリストルへと帰り着いた。ちょうどブランディ氏が僚船の準備を考え始めていた頃であった。出航した者たちのうち、生きて戻ったのはわずか五人だった。「残りの連中は、酒と悪魔にすっかりやられてしまった」のだ。もっとも、あの歌に出てくる船ほどひどい有様ではなかったが。
七十五人で船出し、生き残りはただ一人。
我々は皆、十分な分け前の宝を受け取り、それぞれの性分に従って、賢く使ったり、愚かにも浪費したりした。スモレット船長は今では船乗りを引退している。グレイは金を貯めただけでなく、にわかに出世欲に目覚め、己の職務を熱心に学んだ。今では立派な全装帆船の航海士兼共同船主となり、妻をめとり、一家の主となっている。ベン・ガンに至っては、千ポンドを手に入れたが、それを三週間で使い果たすか失くしてしまった。もっと正確に言えば十九日間で、というのも二十日目には物乞いに逆戻りしていたからだ。その後、彼は島で恐れていた通り、門番小屋を与えられた。そして今も生きている。田舎の少年たちの人気者であり、少々からかいの的でもあり、日曜日や祝祭日には教会で評判の歌い手となっている。
シルバーについては、その後何の音沙汰もない。あの恐るべき片足の船乗りは、ついに私の人生から完全に姿を消したのだ。だが、おそらく彼は黒人の女房と再会し、今ものうのうと、彼女とフリント船長と一緒に暮らしているに違いない。そう願うべきだろう。なにしろ、彼が来世で安楽を得る見込みは、ほとんどないのだから。
銀の延べ棒と武器は、私の知る限り、今もフリントが埋めた場所に眠っている。そして私に関する限り、間違いなくこれからもそこに眠り続けるだろう。たとえ牛と荷車の綱で引っぱられようとも、あの呪われた島へ私が再び戻ることなど断じてない。私が今でも見る最悪の悪夢は、島の岸辺に轟く波の音を聞くとき、あるいは、フリント船長の甲高い声がまだ耳の奥で鳴り響き、ベッドから飛び起きるときなのだ。「八レアル銀貨! 八レアル銀貨!」と。
完

