グレート・エクスペクテーションズ(大いなる遺産)

[1867年版]
チャールズ・ディケンズ 著

第一章
父の姓はピリップ、洗礼名はフィリップだったが、幼い私はその両方を「ピップ」としか発音できなかった。だから、自分をピップと呼び、みんなにもそう呼ばれるようになった。
父の姓ピリップについては、父の墓石と姉――鍛冶屋のジョー・ガージェリーの妻であるジョー夫人の証言に基づく。私は父も母も見たことがなく、また写真の時代よりずっと前だったため、二人の肖像を見たこともなかった。だから、二人がどんな人だったかについての最初の空想は、まったく根拠のないものだったが、もっぱらその墓石から想像したのだった。父の墓石に刻まれた文字の形が妙に四角くて、私は父を四角い体格でがっしりした、黒髪で縮れた髪を持つ色黒の男だと思い込んだ。「上記の妻ジョージアナ」と記された碑文の文字遣いと流れから、子どもらしく母はそばかす顔で病弱だったのだろうと決めつけた。両親の墓の脇にきちんと並べられていた、長さ約1フィート半ほどの五つの小さな石板――早々にこの世の生存競争を諦めた五人の幼い兄弟のために捧げられたもの――のおかげで、私は彼らが皆、ズボンのポケットに手を入れたまま仰向けに生まれ、この世では一度も手を出さなかったと、まことしやかに信じていた。
我が家の周辺は川沿いの湿地帯だった。川の曲がりくねる道筋をたどれば、海まで二十マイルほどの距離である。私が物事の輪郭や正体を最も鮮烈かつ広く認識したのは、ある忘れがたい寒々とした夕方だったと覚えている。そんな時刻、私は確かに知った――このイラクサに覆われた荒れ地が墓地であり、フィリップ・ピリップとその妻ジョージアナが、この教区で亡くなり埋葬されていること。アレクサンダー、バルトロメウ、アブラハム、トビアス、ロジャー――先述の二人の幼な子たちもまた、死に埋葬されていること。教会の外の暗く平らな荒野には、溝や土手、門が走り、そこにぱらぱらと牛が草を食んでいて、それが湿地帯であること。さらにその先の低く鉛色の線が川、その向こうの遠い荒々しい巣窟から風が吹きつけてくるのが海。そして、すべてが怖くなって涙ぐむ小さな震える固まり、それがピップだった。
「騒ぐな!」恐ろしい声が教会の玄関脇の墓の間から立ち上がる男の口から発せられた。「じっとしろ、小悪党め。さもないと喉をかっ切るぞ!」
男はみすぼらしい灰色の服をまとい、片足には大きな鉄の鎖をつけていた。帽子はなく、履き古した靴、頭にはぼろ布を巻いている。水浸しで泥まみれ、石で足をひどくし、火打石で切り傷を負い、イラクサで刺され、茨で体中が裂けていた。足を引きずり、震え、鋭い目つきでにらみ、唸り声をあげ、私の顎をつかむと歯をガチガチ鳴らしていた。
「ああ! どうか喉を切らないでください、旦那さま」と私は恐怖で懇願した。「どうかお願いです、旦那さま」
「名前を言え!」男は言った。「早く!」
「ピップです、旦那さま」
「もう一遍だ」男は私をじっと見つめて言った。「はっきり言え!」
「ピップです。ピップ、旦那さま」
「どこに住んでるか教えろ。指させ!」
私は、村がハンノキと丸坊主の木立の中、教会から一マイル以上離れた平地にある方角を指差した。
男はしばし私を見つめた後、私を逆さまに持ち上げてポケットの中身をあさった。中にはパンのかけらしか入っていなかった。男の力があまりに突然で強かったので、教会がぐるりとひっくり返り、尖塔が足元に見えるような気分になったのだ。教会が元に戻ったとき、私は高い墓石の上に座らされ、男が貪るようにパンを食べるのを震えながら見ていた。

「おい小僧、なんて頬がふっくらしてるんだ」男は舌で唇を舐めながら言った。
確かに私はその年齢にしては小柄で弱かったが、頬だけはふっくらしていたと思う。
「俺が食えないもんか」と男は脅すように頭を振って言った。「本気で食ってやろうかと思ってるぞ!」
私はどうかやめてくださいと必死に願い、男に乗せられた墓石から落ちまいと必死にしがみついた。泣かないためでもあった。
「いいか、よく聞け!」男は言った。「母親はどこだ?」
「そこです、旦那さま!」
男はびくりと身を震わせ、数歩走って立ち止まり、肩越しに振り返った。
「そこです、旦那さま。あとジョージアナ、つまり母です」と私はおずおずと説明した。
「おう!」と男は戻ってきた。「じゃあ、その隣の男が父親か?」
「はい、旦那さま。彼もです。この教区の故人です」
「ふん!」と男はうなり、考え込んだ。「お前、誰と暮らしてる? ――もし生かしてやるとしての話だが、まだ決めてないがな」
「姉です、旦那さま――ジョー夫人です。ジョー・ガージェリー、鍛冶屋の妻です、旦那さま」
「鍛冶屋か」と男は言い、足元の鉄鎖に目をやった。
男は何度か不穏な目つきで足と私を見比べた後、私の両腕をつかみ、できる限り後ろに反らせた。彼の目が私の目を強く見下ろし、私は無力に見上げるしかなかった。
「さて」と男は言った。「生かすかどうかはさておき、やるべきことがある。やすりってわかるか?」
「はい、旦那さま」
「“ウィトルズ”はわかるか?」[訳注: “wittles”は食料の意味。]
「はい、旦那さま」
男は一つ質問のたびに、私をさらに反らせて恐怖心を煽った。
「俺にやすりを持ってこい」また傾けた。「食い物もだ」さらに傾けた。「両方持ってこい」さらに傾けた。「さもないと心臓も肝臓もえぐり出してやる」さらに傾けた。
私は死ぬほど怖くなり、目が回るほどだったので両手で男にしがみつき、「どうかまっすぐ立たせてくだされば、気分も悪くならず、もっとちゃんとお話を聞けます」と言った。
男は私を思い切りぐるりと回転させ、教会が風見鶏ごと跳ね上がるような気分になった。再び墓石の上に私を立たせ、こう続けた――
「明日の朝早く、やすりと食い物を持ってこい。あそこの古い砲台まで持ってくるんだ。それをやれば命は助けてやる。だが、誰かに俺のことを話したり、何か合図をしたりしたら――どんなに些細なことでも――心臓も肝臓もえぐり出して焼いて食う。俺は一人じゃないと思うなよ。俺の連れの若い男がここに隠れてる。その男に比べりゃ俺なんか天使だ。その男は俺の言葉を全部聞いてるし、独特のやり方で子どもの心臓や肝臓に忍び寄る方法を持ってる。部屋に鍵をかけて布団をかぶっても、そいつは忍び寄ってきてお前を裂く。今、俺はその男を必死で抑えて、お前に危害を加えさせていないんだ。さて、どうする?」
私はやすりも食べ物も必ず持って行くと答え、砲台へ朝早く行くと約束した。
「できなきゃ天罰が下ると誓え!」男は言った。
私はそう誓い、男は私を降ろした。
「さて」と男は続けた。「約束を守れよ、あの若い男のことも忘れるな。さっさと帰れ!」
「お、おやすみなさい、旦那さま」と私はやっと声を絞り出した。
「ああ、もう!」男は冷たい湿地を見渡しながら言った。「カエルかウナギにでもなりたいもんだ!」
そう言って、男は震える体を両腕で抱きしめ、体をまとめるようにしながら低い教会の壁へよろよろと向かった。彼が墓の間をすり抜けていく様子は、私の幼い目には、死者たちが墓から手を伸ばして彼の足首を引きずり込もうとするのを、必死でかわしているように見えた。
男は壁を乗り越えると、足が痺れているのか、ぎこちなく振り返った。男がこちらを振り返るのを見て、私はすぐに家へ向かい、できるだけ早く走った。それでも途中でふと振り返ると、男は再び川の方へ、痛む足を引きずりながら、湿地に点在する大きな石をたどっていた。あれは増水時や雨の時の足場なのだ。
湿地はただの長い黒い水平線で、川もそれより細くて浅い水平線にしか見えなかった。空はただ怒ったような赤と黒の帯が交じり合って並んでいるだけ。川岸には、視界の中で唯一直立している黒いものが二つ見えた。一つは水夫たちが目印にする、たるを棒の上に載せたような醜いビーコン、もう一つはギロチン台で、かつて海賊が吊るされた鎖がぶら下がっている。男はそのギロチン台の方へ足を引きずっていた。まるで自分が蘇った海賊で、またギロチン台に戻って自分自身を吊るしに行くかのように見えた。その想像にぞっとし、牛たちが首を上げて男を見送っているのを見て、牛たちもそう思ったのかとふと思った。恐ろしい若い男を探してあたりを見回したが、何の痕跡もなかった。だが私はまたしても怖くなり、全速力で家に駆け戻った。
第二章
私の姉ジョー夫人は、私より二十歳以上年上で、自分自身や近所の人々の間で「手塩にかけて」私を育てたという評判を確立していた。当時私はその意味を知らず、姉の手は硬くて重たく、私にも夫のジョーにもよく振り下ろされていたので、ジョーと私は二人とも「手塩にかけて」育てられたのだと思っていた。
姉ジョー夫人は、容姿が良いとは言えなかった。私は彼女がジョー・ガージェリーを力ずくで結婚させたのだろうと、漠然と思っていた。ジョーは色白で、なめらかな顔の両脇に亜麻色の巻き毛があり、目の青さは自分の白目と混ざり合ったような、決断力のない色をしていた。彼は穏やかで善良、優しくてのんびりした、お人好しで愛すべき男だった――力も弱さもヘラクレスのようなものだ。
姉ジョー夫人は黒い髪と目を持ち、頬の赤みがあまりにも際立っていたので、私は彼女が石鹸の代わりにナツメグおろしで体を洗っているのではないかと、時々疑ったものだった。彼女は背が高く骨ばっていて、いつも粗末なエプロンを身に着けていた。そのエプロンは背中で二重の輪で留められ、前面の四角い胸当てには針やピンがびっしり刺さっていた。彼女はこれを着けていることを自慢とし、ジョーが着けていないことを責め立てた。もっとも私は、彼女がなぜそんなにエプロンを着ける必要があったのか、そしてつけるなら毎日外せばいいのにと思った。
ジョーの鍛冶場は我が家に隣接していて、家も他の多くの家と同じく木造だった――当時はほとんどそうだった。私が墓地から家に駆け戻ったとき、鍛冶場は閉まっていて、ジョーは台所で一人座っていた。私たちは同じ苦しみを味わう者同士として、密かな仲間意識があったので、私が戸の掛け金を上げてジョーの正面からそっと覗き込むと、彼はすぐに打ち明け話をしてくれた。
「ジョー夫人、ピップ、お前を探しにもう十二回は外に出てるぞ。今も出てるから、十三回目だな」
「そうなの?」
「ああ、ピップ」ジョーは言った。「しかも悪いことに、ティックラー(お仕置き用の鞭)を持ってる」
この不吉な知らせに私はチョッキの唯一のボタンをいじり、気落ちして火をじっと見つめた。ティックラーとは、私の体に何度も当たってすり減った蝋の先を持つ竹の鞭である。
「座って、立ち上がって、ティックラーをひっつかんで、荒々しく出て行った。それが彼女さ」ジョーは火かき棒で炉の火をかき混ぜながら、ゆっくりと言った。「荒々しく出て行ったな、ピップ」
「長く行ってるの、ジョー?」私はジョーを大きな子ども扱いして、対等以上には思わなかった。
「そうだな」ジョーはオランダ時計を見上げながら言った。「この最後の外出は五分くらいだよ、ピップ。もうすぐ戻るぞ。ドアの後ろに隠れて、ふきんを盾にしろ」
私はその忠告に従った。姉ジョー夫人はドアを勢いよく開け、後ろに何か障害物があるのを見てすぐに原因を見抜き、ティックラーで捜査を続行した。最後には私を――私はよく夫婦喧嘩の弾として使われた――ジョーに投げつけた。ジョーは私をとにかく受け止め、暖炉の脇に私を誘導し、自分の大きな足で囲ってしまった。
「どこ行ってたの、この猿っ子め!」ジョー夫人は足を踏み鳴らした。「すぐに言いなさい、私をどれだけ心配と苛立ちで擦り切れさせる気なのか。もし五十人のピップがいて、五百人のガージェリーがいたって、そこから引きずり出してやるから!」
「ただ墓地に行っただけです」と私はスツールの上から泣きながら、体を擦りながら答えた。
「墓地!」姉は繰り返した。「私がいなけりゃとっくに墓地行きで、そのまま埋まってたわよ。誰が手塩にかけて育てたの?」
「あなたです」と私は言った。
「なぜ私がそんなことしたのか、知りたいくらいだわ!」姉は声を上げた。
「わかりません」と私はすすり泣いた。
「私だってわからないわよ! もう二度とやらないわ。あなたが生まれてからこのエプロンを外したことがないのよ。鍛冶屋の妻(しかもガージェリーの)で、母親までやらされるなんてたまったもんじゃない」
私は火をうなだれて見つめながら、頭の中は湿地で出会った鉄鎖の男、謎の若い男、やすり、食べ物、そして家で盗みをはたらくという恐ろしい誓いでいっぱいだった。
「ふん!」ジョー夫人はティックラーを元の場所に戻しながら言った。「墓地だって? よく言ったもんだ、あんたたち二人が」ちなみにそのうち一人は何も言っていない。「そのうち私を二人で墓地送りにするんだから、私がいなきゃ何もできやしない!」
ジョーは足越しに私を覗き込み、もし姉がいなくなった場合、私とジョーの二人がどんな組み合わせになるのか、頭の中で計算しているようだった。その後、右側の亜麻色の巻き毛とヒゲをいじりながら、険悪な空気の時はいつものように、青い目で姉の後を追っていた。
姉にはパンとバターの切り方に独特の威力があった。まず左手でパンをエプロンの胸当てにしっかりと押し付け――ときにはピンや針がパンに刺さり、私たちの口にも入った――、バターを(けして多くはない量で)医者の膏薬のごとくナイフに取り、パンに両面で素早く塗り、ふちを器用に整えてから、ナイフを膏薬の縁で拭い、最後に分厚く切り取ったひと塊を、パンから離す前にさらに二つに割り、ジョーと私に一つずつ分け与えた。
この時ばかりは空腹だったが、自分の分は食べられなかった。恐ろしい知り合いと、そのさらに恐ろしい相棒のために、何か残しておかなければならないと思ったのだ。姉の倹約ぶりを私はよく知っていたし、台所の貯蔵庫にはろくなものがないと予想した。だから自分のパンとバターをズボンの足の中に隠すことにした。
これを決行するには、決死の覚悟が必要だった。高い家の屋根から飛び降りるか、深い水に飛び込むくらいの決意だった。そのうえ、無邪気なジョーの存在がさらに難しくさせた。同じ苦しみ仲間としての暗黙の連帯感から、私たちはときどきそれぞれのパンのかじり方を見せ合って競い合うのが習慣だった。今晩もジョーは何度も自分のパンが減っていく様子を私に見せ、対抗を促したが、私はそのたび、黄色いマグカップを膝に、パンとバターはもう片方の膝に載せたまま動かなかった。ついに腹を決めて、最も自然なタイミングを見計らい、ジョーがこちらを見たその隙に、パンとバターをズボンの足に滑り込ませた。
ジョーは、私が食欲を失ったと思い、不安そうにパンをかじったが、美味しそうに見えなかった。口の中でいつもより長く転がし、しばらく考え込んでから、薬でも飲むように一気に飲み込んだ。二口目にと首を傾けていたとき、私のパンとバターが消えているのに気づいた。
ジョーが食べかけで固まって私を見つめる様子は、姉の目にも明らかだった。
「今度は何なの?」姉はカップを置きながら鋭く言った。
「なあ、わかるだろう!」ジョーは私に真剣に訴えるように頭を振って言った。「ピップ、無茶するなよ。どこかに詰まるぞ。ちゃんと噛まずに丸呑みしただろう、ピップ」
「今度は何なの?」姉はさらにきつい口調で繰り返した。
「もし吐き出せそうなら、吐き出せ、ピップ」とジョーは狼狽して言った。「礼儀も大事だが、健康第一だ」
姉はついに堪忍袋の緒が切れ、ジョーの二つのヒゲをつかんでしばらく壁に頭を打ちつけた。私は隅で罪の意識にさいなまれながら見ていた。
「さあ、わかったら理由を言いなさいよ!」姉は息を切らしながら言った。「この呆け豚!」
ジョーは無力な目で姉を見てから、またパンをかじり、私を見た。
「わかるかい、ピップ」ジョーは最後のひとかじりを頬張り、まるで二人きりのように小声で言った。「お前と俺はずっと仲間だ。俺からお前のことを密告することは絶対ない。でもだな――」ジョーは椅子をずらし、床を見回し、また私を見て――「そんな、めったにない丸呑みは初めてだ!」
「丸呑みしたのか!」姉が叫んだ。
「なあ、ピップ」ジョーは姉を見ずに、まだ頬にパンを入れながら私を見て言った。「俺も昔は丸呑みしたもんだ。しょっちゅうさ。ボルター仲間もたくさんいた。でもお前ほどの丸呑みは見たことがない。死ななかったのが奇跡だ」
姉は無言で私の髪をつかみ、引きずり出して「薬を飲ませるよ!」とだけ言った。
当時、どこかの医者がタール水を良い薬だと復活させていて、ジョー夫人はその効能をまずさと同じくらい信じていた。普段でも私にはこの液体を相当量飲ませ、私はいつも新しい柵のような匂いをさせて歩く羽目になった。この晩ばかりは事が重大だったので、姉は私の頭を脇にかかえ、まるで長靴を抜くようにして、1パイントものタール水を私の喉に流し込んだ。ジョーも半パイント飲まされたが、「急に具合が悪くなったから」と無理やり飲まされ、その後しばらくむしゃむしゃ思い悩みながらも、確かに具合が悪くなっていた。
良心の呵責は恐ろしいものだが、それが少年で、しかももう一つの秘密の負担――ズボンの足に隠したパンとバター――と重なると、それはひどい罰になる。姉を盗むつもりであること――私は家財をジョーのものと考えないので、ジョーを盗むとは思わなかった――と、座っている間も用事を命じられて台所を歩く間も、片手は常にパンとバターに気を配らねばならず、気が変になりそうだった。湿地の風で火が燃え上がるたび、外から鉄鎖の男の声が聞こえてきて、「明日まで待てない、今すぐ食わせろ」と脅してくるように思えた。若い男が辛抱しきれず今夜私の心臓と肝臓を奪いにくるかもしれない、と想像し、私の髪は本当に逆立っていたと思う。しかし、誰かの髪が本当に逆立つことがあるだろうか?
クリスマス・イブだったので、翌日のプディングを銅べらで七時から八時までかき混ぜねばならなかった。その間も足にパンとバターを隠したまま(男の鉄鎖を思い出してしまう)、運動でそれが出てしまいそうになり、なんとも厄介だった。幸い、抜け出して自分の屋根裏部屋にそれをしまい、良心の一部を預けることができた。
「聞いてよ!」かき混ぜ終えて暖炉脇で温まっていた私は言った。「大砲の音じゃない、ジョー?」
「ああ」ジョーは言った。「また囚人が逃げ出したぞ」
「それ、どういう意味?」私は尋ねた。
ジョー夫人はいつも解説役で、冷たく「逃亡。逃亡」と言い捨てた。まるでタール水のように定義を押しつける。
ジョー夫人が針仕事に俯く間、私は口の形でジョーに「囚人って何?」と尋ねた。ジョーも大げさに口を動かしたが、「ピップ」しか読み取れなかった。
「昨夜も一人、日没の合図の大砲の後で逃げて、警告の大砲を撃ったんだ。今度はまたもう一人だ」ジョーは声に出して言った。
「誰が撃ってるの?」私が尋ねた。
「ほんと、うるさい子だよ!」姉は針と糸で私を指し、「質問したら嘘も教えられるわよ」と眉をひそめた。
姉が自分でも嘘をつくと認めているようで、不躾だなと思ったが、彼女は人前以外は礼儀正しくなかった。
ここでジョーはさらに私の好奇心をあおるため、口を大きく開けて「サルクス」の形を作った(ように私には見えた)。そこで私は姉を指して「彼女?」と口を動かしたが、ジョーは首を振り、再び強調するように口を開けたが、私には分からなかった。
「ジョー夫人」私は最後の手段で言った。「できれば、大砲の音がどこから聞こえるのか知りたいんですが」
「おやまあ!」姉はわざとらしく叫んだ。「監獄船(ハルク)からさ!」
「おお!」私はジョーを見た。「ハルク!」
ジョーは「ほら、言っただろう」とでも言いたげに咳払いした。
「ねえ、ハルクって何?」私は言った。
「この子はほんとに!」姉は針と糸で私を指しながら言った。「一つ答えたら十も聞いてくる。ハルクは監獄船だよ。湿地の向こうだ」我々の地方では、湿地を「メッシュ」と呼んでいた。
「誰が監獄船に入れられるのかな、なんで入れられるのかな?」私は一般論として、やけくそで言った。
それに姉は耐えられず、すぐに立ち上がった。「言っとくけどね」彼女は言った。「私は人の人生を質問攻めでつぶすために手塩にかけたんじゃない。監獄船に入れられるのは、殺人や盗み、偽造、悪事をはたらくからよ。最初はみんな質問から始まるんだから。さっさと寝なさい!」
私は寝るときに蝋燭を持たせてもらえず、暗闇を上がるときには、姉の指貫がタンバリンがわりに頭に響いていた。ハルクが近くにあるのは私にとって便利だ、と冷や汗をかいて思った。質問から始め、今まさにジョー夫人を盗もうとしているのだから。
今となっては遠い昔のことだが、後から思うと、恐怖下の子どもがどれだけ秘密を守るか、大人は知らないものだと思う。どんなに非合理的な恐怖でも、恐怖でありさえすれば絶対なのだ。私は心臓と肝臓をねらう若い男が怖かった。鉄鎖の男が怖かった。自分自身――恐ろしい約束をさせられた自分――が怖かった。全能の姉にも頼れず、もし誰かに何か要求されたなら、恐怖の秘密のうちに何でもやったかもしれないと思うと今でもぞっとする。
その晩、もし眠っていたとしたら、川を強い潮に流されて監獄船に向かい、ギロチン台で幽霊海賊がメガホンで「ここに上がって今すぐ絞首刑になれ、後回しにするな」と叫ぶ夢を見ていただろう。私は眠るのが怖かった。夜中に盗みに入るわけにはいかない。火打石と鋼で火を起こすしかなく、その音はまさに海賊が鎖を鳴らすのと同じくらい大きく響くだろうから。
小窓の外の黒い天鵞絨のカーテンが灰色に染まり始めるやいなや、私は起きて階下に下りた。床板も隙間もすべてが「泥棒だ!」「ジョー夫人を起こせ!」と叫んでいる気がした。季節柄、台所の貯蔵庫はいつもより潤沢で、吊るされたウサギと目が合ってウィンクしたような気さえしてひどく怯えた。確かめる暇も、選ぶ暇もなかった。パン、チーズの皮、ミンチパイの残り半分(昨晩のパンと一緒にハンカチに包んだ)、石瓶のブランデー(自室でスペイン甘草水を作るためのガラス瓶に移し替えた。石瓶は台所の水差しで薄めてごまかした)、肉の骨(ほとんど肉はついてなかった)そして美しい丸ごとのポークパイを盗んだ。パイは最初持って行くのを迷ったが、棚に登ってみると、土鍋に大事そうに隠してあり、しばらくは見つからないだろうと判断して持ち出した。
台所から鍛冶場につながる扉があり、それを開けてジョーの道具箱からやすりを一本取り出した。元通りに戸締りをして、昨夜帰ってきた時の扉から外に出て、霧の湿地へと駆け出した。
第三章
その朝は霧が深く、ひどく湿っていた。夜のあいだ、何かの妖精が窓で泣き続け、ハンカチ代わりに使ったかのように、窓の外に湿り気が張り付いていた。今、私はその水気が生垣やまばらな草の上に、蜘蛛の巣よりも粗い糸のように垂れ下がっているのを見た。柵も門もびしょ濡れで、湿地の霧はあまりにも濃く、村への道を示す木製の指示板――誰も信じず、決して来ない方向――も、すぐ近くまで行かないと見えなかった。私はそれを見上げながら、圧し掛かる良心の呵責に「ハルクへ行け」と呪われているような気がした。
霧は一層濃くなり、私が何かに突進するのではなく、すべてが私に向かって突進してくるようだった。罪を抱えた心にはなんとも不愉快な感覚だった。門も溝も土手も、霧のなかから飛び出してきて、「他人のポークパイを持った少年だ! 捕まえろ!」と叫んでいるようだった。牛たちも同じ勢いで現れては、目を大きく見開き、鼻息を立てて、「おい、小泥棒!」と言わんばかりに見てきた。黒い牛一頭は白い襟巻きをしていて――目覚めた良心には牧師のような気品すら感じられ――、私をじっと見つめ、私が動けばその鈍い頭を私に合わせて動かしたので、私は思わず「仕方なかったんです、旦那さま! 自分のためじゃないんです!」と泣き出してしまった。牛は頭を下げ、鼻から煙を吐き出し、後ろ足で蹴って尻尾を振ると、すっと消えてしまった。
私は川を目指していたが、どれだけ急いでも足は暖まらなかった。冷たく湿った空気が、鉄鎖が男の足に食い込んでいるのと同じように、私の足にまとわりついていた。砲台への道はよく知っていた。日曜日にジョーと来たことがあって、ジョーは古い大砲の上に座り、「お前が本式に弟子入りしたら、ここで楽しくやろうな!」と言っていた。しかし霧に惑わされ、私は少し右に行き過ぎてしまい、川沿いの泥と杭の上の石の土手を引き返さねばならなかった。急いで溝を越え、土手を這い上がると、男が背中を向けて腕組みし、前かがみになって眠っていた。
私は、持ってきた朝食で驚かせた方が喜ぶだろうと、そっと近づいて肩を叩いた。男は即座に飛び上がった――だがそれは昨夜の男ではなく、まったく別の男だった!
しかもこの男もみすぼらしい灰色の服を着て、足には大きな鉄鎖、足を引きずり、声もかすれ、寒さに震え、先ほどの男とほとんど同じだった。ただ顔が違い、広くて平たい縁の帽子をかぶっていた。そのすべてを一瞬で見てとった。なぜなら、男は私に罵声を浴びせ、殴りかかってきたからだ。だがパンチは弱く空振りし、男自身がよろけて転びそうになり、霧の中へ駆け込んでいった。途中で二度つまずき、姿を見失った。
「若い男だ!」私は心臓を射抜かれるような思いで思った。肝臓の位置を知っていたら、そちらも痛んだことだろう。
その後すぐ、砲台にたどり着くと、先の男――体を抱え、足を引きずりながら、まるで一晩中そのままだったかのように――が待っていた。男は凍えきっていたに違いない。私は目の前で倒れて凍死するのではと半ば思った。男の目つきはあまりにも飢えていて、やすりを渡したとき、彼は草の上にそれを置いたが、私の包みがなければそれを食べようとしたのではないかと思ったほどだ。今度は私を逆さまにして中身を探すことはせず、まっすぐ立ったまま包みとポケットの中身を差し出させた。
「その瓶には何が入ってる?」男は言った。
「ブランデーです」と私は答えた。
彼はすでにミンスミートを喉に押し込んでいたが、その様子は「食べている」というよりも、「何かを大急ぎでどこかにしまい込もうとしている」男のようだった。それでも酒を取るために一旦手を止めた。彼は終始ひどく震えていて、歯で瓶の首を噛み切らずに済むのがやっとというほどだった。
「マラリアにやられてるんじゃないか」と俺は言った。
「お前の意見に賛成だよ、坊や」と彼は答えた。
「このあたりは悪いんだ」と俺は言った。「沼地で寝てたんだろう、あそこはひどくマラリアになりやすいからね。リウマチにもなるし。」
「死ぬ前に朝飯は食ってやる」と彼は言った。「たとえあそこの絞首台にすぐ吊るされることになっても、俺は食ってやるさ。震えには勝ってやる、賭けてもいい。」
彼はミンスミート、肉の骨、パン、チーズ、ポークパイを一気にほおばりながら、時折あたりに立ちこめる霧を疑わしげに見回し、しばしば食べるのも止めて耳を澄ませた。川で何かが鳴ったような音や、沼地で獣が息をするような音が実際に、または想像で彼を驚かせ、そのたびに突然こう言った。
「お前、嘘つきの小悪党じゃないだろうな? 誰か連れてきたんじゃないだろうな?」
「いえ、絶対に! いいえ!」
「誰にも後をつけさせてないか?」
「いいえ!」
「よし」と彼は言った。「信じるぞ。お前が今の年で、こんな哀れな追われ者を、死にかけたこの俺みたいなやつを狩る手伝いができるような奴だったら、本当にずる賢い犬だ!」
彼の喉で何かがカチリと鳴った。まるで体の中に時計の仕掛けでもあって今にも打ちそうな音だった。そして、彼は粗末な袖で目をぬぐった。
その孤独を哀れに思い、彼がだんだんパイに落ち着いていくのを見ながら、俺は思い切ってこう言った。「気に入ってくれて嬉しいよ」
「なんだって?」
「美味しそうに食べてくれて嬉しいって言ったんだ」
「ありがとな、坊や。うまいよ。」
俺はよく家の大型犬が餌を食べるのを観察していたが、今この男の食べ方と犬の食べ方との間に、はっきりとした類似点を見出した。男は犬みたいに、力強く鋭く、突然ガブリと噛みつく。ひと口ごとに、かみ砕く間もなく呑みこみ、食べながら常に横目で警戒していた。まるで四方八方から誰かがパイを奪いに来ると思っているかのようだった。そんなふうに落ち着かず、味わう余裕もないし、誰かと食卓を囲むどころではなかった。もし誰かが同席しても、きっとその人にも噛みついただろう。あらゆる点で、彼は犬そっくりだった。
「その人の分、残しておかなくて大丈夫?」と俺はおそるおそる言った。しばらくの沈黙の後、礼儀として言うべきか迷っていたのだ。「あれの追加はもうないからさ。」その確信が、俺をそう言わせた。
「残す? 誰の?」と彼はパイの皮を噛み砕くのを止めて言った。
「ほら、あの若い人さ。あなたと一緒に隠れてたって言ってた」
「ああ、あいつか!」と彼はややガラガラ声で笑った。「あいつ? あいつは食い物なんかいらないよ」
「でも、必要そうに見えたけど」と俺は言った。
男は食べるのを止め、鋭く驚いた目つきで俺を見つめた。
「見えた? いつだ?」
「さっきだよ」
「どこで?」
「あそこ」俺は指差して言った。「あそこで居眠りしてるのを見つけて、あなたかと思ったんだ」
彼は俺の襟をつかみ、じっと見つめたので、彼の最初の「喉を切る」という考えが復活したのかと思った。
「あなたと同じ格好で、でも帽子をかぶっていて――」俺は気を遣って言葉を選びながら続けた。「それと、やっぱりヤスリを借りたい理由も同じで……。昨夜、大砲が鳴ったの聞かなかった?」
「じゃあ、本当に撃ってたんだな!」と彼は独りごとのようにつぶやいた。
「それは驚きだよ」と俺は返した。「家でも聞こえたし、こっちより遠いのに、それに閉め切ってたのに」
「そりゃあな!」と彼は言った。「こんな沼地に一人きりで、頭も腹も空っぽで、寒さと飢えで死にかけてると、一晩中、大砲の音や人の声しか聞こえないもんさ。見るんだ、兵士どもが、たいまつで顔を照らしながら赤い制服で取り囲んでくるのを。自分の番号を呼ばれ、問い詰められ、銃の音、号令、――『用意! 狙え! しっかり狙え、男ども!』って声が聞こえて、捕まる。でも、実際は何もないんだ! 昨夜、追っ手の一隊が来るのを一度見たんなら――あいつらがドンドン行進しながら――百回だって見た気がするさ。砲撃なんて、朝になっても霧が大砲で揺れるのが見えたくらいだ。でも、あの男は――」それまで俺の存在を忘れたように話していたが、「何か気付いたか?」
「ひどく顔が腫れてた」と俺は、ほとんど無意識のまま思い出して言った。
「ここか?」と男は左の頬を平手で乱暴に叩いた。
「そう、そこだよ!」
「どこにいる?」彼は残りの食べ物を灰色の上着の胸元に押し込んだ。「どっちへ行ったか教えろ。血に飢えた猟犬みたいに引きずり下ろしてやる。この鉄のせいで足が痛ぇ! ヤスリを貸せ、坊や。」
俺はもう一人の男が霧の中に消えた方向を指し示し、彼はそれをちらりと見上げた。しかし、すぐに濡れた草の上に倒れこむようにして、狂ったように鉄の足かせをヤスリで削り始め、自分の足がすでに擦りむけて血がにじんでいても、まるで感覚がないかのように乱暴に扱った。彼がこんなに興奮しているのを見ると再び恐ろしくなり、家からこれ以上離れているのも怖くなった。帰らなきゃ、と告げたが彼は無視したので、こっそり逃げ出すのが一番だと判断した。最後に見た彼は、膝の上に頭を下げ、必死に足かせを削りながら、自分の足と鉄に向かって苛立ち混じりの呪い言をつぶやいていた。最後に聞いたのは、霧の中で足を止めて耳を澄ませた時、まだヤスリの音がしていた。
第四章
台所に警官が待ち構えていて、俺を捕まえるのを待っているだろうと覚悟していた。だが、そこに警官はおらず、盗難の発覚もまだだった。ジョー夫人は今日の祝宴の準備で大忙しで、ジョーは台所の戸口に追いやられていた――どうしても彼の運命は、姉が家中を熱心に掃除している時には、いずれはちりとりの中に導かれるものだった。
「一体全体、どこへ行ってたのさ?」これがクリスマスの挨拶としてのジョー夫人の第一声だった。
俺はキャロルを聞きに行っていた、と言った。「ああ、まあね」とジョー夫人。「もっと悪いこともできたかもしれないしね」間違いなくその通りだ、と俺は思った。
「私が鍛冶屋の女房でなきゃ、つまり、エプロンを外したことのない奴隷でなきゃ、キャロルを聞きに行ったっていいんだけどね」とジョー夫人は言った。「キャロルは好きなんだけど、それが一番の理由で一度も聞いたことがないのよ」
ジョーは俺の後について台所にこっそり戻ってきたが、ちりとりが俺たちの前から引っ込んだのを見計らってのことだった。ジョー夫人が彼を鋭く睨むと、ジョーは和解を示すように手の甲で鼻をこすり、視線を外すと、こっそりと二本の人差し指を交差させて俺に見せた。これは、ジョー夫人が機嫌が悪い時の俺たちの合図だった。これは彼女の通常運転と言っていいほどで、ジョーと俺はしょっちゅう、手の指だけ見れば十字軍の騎士像みたいに交差していた。
祝いのディナーは、塩漬け豚の脚と青菜、それに中身を詰めたローストチキン二羽。昨日の朝、立派なミンスパイも作ってあり(ミンスミートがなくなっても気づかれなかったのはそのためだ)、プディングもすでに茹でていた。これほどの準備のため、朝食は容赦なく簡略化された。「だって私は」とジョー夫人は言った――「今からあれもこれも控えてるのに、ここで正式な朝飯だ掃除だなんて、絶対にごめんだよ!」
だから俺たちは、まるで強行軍中の軍隊みたいに、切り分けられた朝食を受け取って、申し訳なさそうな顔でミルク入りの水をジャグから飲んだ。その間、ジョー夫人は新しい白いカーテンをつけ、広い暖炉には新しい花柄のフリルを張り替え、廊下向こうの小さな応接間も開けた。そこは年に一度この時だけで、あとは一年中銀紙の霞の中に閉じ込められており、マントルピースの上の四匹の白い陶器のプードル犬も、黒い鼻に花かごをくわえ、全員そっくり同じ格好で並んでいた。ジョー夫人は非常にきれい好きな主婦だったが、その清潔さは時に汚れそのものより不快だった。清潔は敬虔さに近いが、信仰でも同じことをやる人もいる。
姉はやることが多すぎて、教会には代理で行くことになった。つまりジョーと俺が行くわけだ。作業着姿のジョーは逞しく特徴的な鍛冶屋だったが、晴れ着になると「生活の良い案山子」にしか見えなかった。着ているものは何一つ体に合わず、どれも彼のものではないように見えたし、とにかく着るたびに擦れて痛そうだった。今日みたいな祝日には、教会の鐘が鳴る中、ジョーは「日曜の反省服」をフル装備で現れ、まるで苦行者のようだった。俺に関しては、姉には「助産婦警官」が俺を誕生日に捕まえて送り届けた「若き犯罪者」というイメージがあったのだろう。理性、信仰、道徳、友人たちの忠告に逆らって生まれてきた罪人のような扱いだった。新しい服を作ってもらいに行く時でさえ、仕立屋には「少年院風」に作るよう命じられ、手足を自由に使わせてくれたことはなかった。
だからジョーと俺が教会に行く姿は、同情心のある人には涙を誘う光景だったはずだ。しかし俺の外見上の苦しみなど、内面で味わった苦しみにくらべれば何でもなかった。ジョー夫人が食品庫や他の部屋に行くたびに感じた恐怖は、俺の手がやってしまったことを思い出して後悔する気持ちと同じくらいだった。重い罪を抱えて、教会がこの恐ろしい若者の報復から俺を守ってくれるかどうか、真剣に考えていた。婚礼の告示が読み上げられる時、「ここで申し立てる者はいるか!」というタイミングで、俺が立ち上がって聖具室で特別面談を申し出るべきではないか、とすら考えた。これがクリスマスでなく日曜だったら、実際にそうして小さな会衆を驚かせていたかもしれない。
教会の書記であるウォプスル氏が、今日の食卓の客だった。車輪職人のハブル氏とハブル夫人、そしてパンブルチュークおじさん(ジョーの叔父だが、ジョー夫人が自分のものにしていた)も来た。彼は近くの町の裕福な穀物商で、自分の馬車を運転していた。食事は一時半。ジョーと俺が帰宅した時、テーブルはすでに整えられ、ジョー夫人も着替え、料理も整い、玄関も(普段は絶対に開けないのに)客のために開けられていて、すべてが華やかだった。それでも、盗難については誰も一言も言わなかった。
時が来ても俺の気持ちは晴れず、客がやってきた。ウォプスル氏はローマ人のような鼻と大きな禿頭を持ち、低く響く声に誇りを持っていた。知人の間でも、彼に好き勝手にしゃべらせてやれば、牧師を気絶させるほど朗読できると理解されていたし、「もし教会が『開放』されたら、必ずや自分の名を残せる」と本人も言っていた。実際は開放されていないので、今は教会の書記だった。だが「アーメン」の一言にさえ猛烈な迫力を込めて言い、詩編を唱える時には、必ず全節を堂々と読み上げ、会衆全員を見回して「さあ私のやり方、どう思う?」と言わんばかりだった。
俺は客を迎えるためにドアを開けた――普段からそうしているかのようなふりをして――最初にウォプスル氏、次にハブル夫妻、最後にパンブルチュークおじさんに開けた。※俺は、厳しい罰則付きで「おじさん」と呼ぶことは許されていなかった。
「ジョー夫人」とパンブルチュークおじさんは言った。彼は大きく息切れした中年ののろまな男で、魚のような口とぼんやりとした目、逆立った砂色の髪をしており、まるでさっきまで首を絞められていて、今やっと意識を取り戻したばかりのようだった。「季節のご挨拶として――持ってきたんですよ、奥さん、シェリー酒を一本――それからポートワインを一本、奥さん」
毎年クリスマスに、彼はまるで新しい発明品でも持ってきたかのように、全く同じ言葉で二本のボトルをダンベルのように持って現れた。毎年、ジョー夫人は「まあ、パンブルチュークおじさん! なんてご親切!」と必ずこう返した。そして毎年彼は「奥さんの功績には及びません」と答え、そして「皆さん、お元気ですか? 六ペンス分の半ペニーは?」と、俺のことを指して尋ねた。
こうした時は台所で食事をし、ナッツやオレンジやリンゴのために応接間へ移動した。それは、ジョーが作業着から日曜服に着替えるのと同じくらい大きな変化だった。ジョー夫人はこの日、上機嫌で、特にハブル夫人の前ではいつもより愛想が良かった。ハブル夫人は空色の服を着た、小柄で鋭い感じの女性で、若い時に年上のハブル氏と結婚したため、通例として若々しい立場を保っていた。ハブル氏は、がっしりした肩と前かがみの高齢男性で、おがくずのような香りがし、足を広げて歩いていたので、俺の目には彼の両足の間に果てしない草原が広がっているように見えた。
この素晴らしい面々に囲まれれば、パンを盗んでいなくても気詰まりだっただろう。それは、テーブルクロスの鋭角のすき間に押し込まれ、テーブルが胸に食い込み、パンブルチュークおじさんのひじが目の前に飛び出していたからでもなければ、会話を許されなかった(話したくもなかった)のでもなく、鶏のドラムスティックの先っぽや、豚の一番食べ応えのない部位ばかり出されたからでもなかった。もし放っておいてくれさえしたら、そんなことは気にしなかった。でも、誰も俺を放っておかなかった。彼らは、時おり話題を俺に向けては、その矛先を俺に突き刺すことが、機会を逃すまいとばかりに大切だと考えているようだった。まるでスペインの闘牛場でいじめられる小さな牛のように、道徳の槍で突かれまくった。
それは食卓についた瞬間から始まった。ウォプスル氏は舞台俳優のような口調で祈祷を唱え――今思えば、ハムレットの亡霊とリチャード三世が宗教的に融合したようなものだった――「感謝の気持ちを忘れませんように」と結んだ。それに応じて姉は俺を睨みつけ、低い責める声で「聞いたでしょ? 感謝しなさい」と言った。
「とりわけ」とパンブルチュークおじさんが言った。「手塩にかけて育ててくれた人に感謝しなさい、坊や」
ハブル夫人は首を振り、俺を「将来ろくなことにならない」という沈痛な予感で見つめて「なぜ若者は感謝しないのかしら?」と尋ねた。この道徳的な謎はみんなには難しすぎたが、ハブル氏が「生まれつき悪いからだ」と簡潔に解決した。全員が「その通り!」とうなずき、特に不快な個人的な目つきで俺を見た。
ジョーの立場と影響力は、客がいる時は(いない時以上に)弱体化していた。でも彼はいつも、何かしら自分なりのやり方で俺を助けてくれた。そして食事時には、グレービーソースがあれば俺の皿にたっぷりかけてくれた。今日はたっぷりあったので、この時点で半パイントほど盛ってくれた。
食事が進むと、ウォプスル氏はその日の説教を厳しく批評し、例の「教会が開放されたら」自分ならどんな説教をするか語った。そして今日の説教の題材は選び方が悪いと指摘し、「世の中には題材がたくさんあるのに」と付け加えた。
「その通りだ」とパンブルチュークおじさん。「うまく仕上げるには塩が肝心だ。塩箱を持っていれば題材探しに苦労はいらない。豚肉だけを見たって、立派な題材だ!」
「まったくですね。若者向けの道徳もいくらでも汲み取れる」とウォプスル氏――俺が話題にされるのは予想済みだった――「そこをよく聞いておきなさい」と姉が俺に厳しく言った。
ジョーは俺にさらにグレービーをかけてくれた。
「豚は」とウォプスル氏は最も重々しい声で、俺の赤面にフォークを向けて言った――「浪費息子の仲間だった。豚の貪欲さは、若者への戒めだ」(豚肉が脂が乗って美味しいと褒めちぎっていた当人が言うのは皮肉だと思った)「豚で忌むべきことは、少年ではもっと忌むべきだ」
「少女もね」とハブル氏が口を挟んだ。
「もちろん、少女も、ハブル氏」とウォプスル氏はやや苛立って同意した。「でも今日は少女はいない」
「それに」とパンブルチュークおじさんが俺に鋭く言った。「感謝すべきことを考えなさい。お前が鳴き声をあげる子豚として生まれていたら――」
「まさにそうだったのよ、あの子は」と姉が強調した。
ジョーは俺にさらにグレービーをくれた。
「いや、四つ足の子豚のことだ」とパンブルチュークおじさん。「もしそう生まれていれば、今ここにはいなかったろう。いや――」
「せいぜい料理された形で」とウォプスル氏が皿を指した。
「でも私はその意味で言ってるんじゃない」とパンブルチュークおじさんは遮られたことを嫌って返した。「つまり、年長者と一緒に楽しみ、会話を聞いて賢くなり、贅沢の中で暮らすことができたか? できなかったろう。じゃあ、どうなった? その辺の肉屋にいくらで売られて、わらの上で寝てるところを左腕で抱え上げられ、右手で上着のポケットから小刀を出されて首を切られていたさ。手塩にかけて育ててもらうどころじゃない!」
ジョーは俺にさらにグレービーを差し出したが、さすがにもう取る勇気はなかった。
「お姉さまは本当にご苦労だったでしょうね」とハブル夫人が同情した。
「苦労? 苦労?」と姉は繰り返し、俺のこれまでの病気、夜泣き、高いところから落ちた件、低いところに落ちた件、自分を傷つけた件、どれほど俺の墓を願ったか、そのたびに俺が従わずに生きていたことなど、ありったけの罪状を語り始めた。
ローマ人はきっと鼻で互いを苛立たせたのだろう。おそらくあの落ち着きのなさの原因だ。とにかく、ウォプスル氏のローマ人の鼻は俺を苛立たせ、彼の前で自分の悪事を晒される間、思わず引っ張ってやりたくなった。だが、これまでの苦しみなど、姉の語りが終わった後に皆が(俺には痛いほど分かるほどに)憤りと嫌悪の目で俺を見ている沈黙が破られた時に感じた恐怖に比べれば、何でもなかった。
「さて」とパンブルチュークおじさんが話を豚肉に戻しながら言った。「茹でた豚肉もなかなか濃厚でうまいよな?」
「ブランデーでもどうぞ、おじさん」と姉が言った。
ああ、ついにその時が来てしまった! 薄いと文句を言われ、俺は終わりだ! テーブルの脚を布の下でしっかり両手で握り、運命に備えた。
姉は石のボトルを取りに行き、戻ってきてパンブルチュークおじさんのグラスにブランデーをついだ。他の誰も飲まなかった。パンブルチュークおじさんはグラスで遊び、持ち上げては光にかざし、また置き、俺の苦しみを長引かせた。その間に、ジョー夫人とジョーはパイとプディングのためにテーブルを片付けていた。
俺は彼から目を離せなかった。手と足でテーブルの脚をしっかり握りしめながら、彼がグラスを指先で回し、持ち上げ、微笑み、頭をのけぞらせて一気に飲み干すのを見た。直後、彼は飛び上がり、数度ぐるぐる回り、恐ろしい咳き込みダンスでドアから飛び出して行った。窓越しに、彼が激しく吐いたり、顔をしかめて狂ったようにしているのが見えた。
ジョー夫人とジョーが彼の元へ走る間、俺はしがみついたままだった。どうやってやったか分からないが、俺は彼を殺したと確信していた。絶望の中、彼が戻り、皆を見回しながら椅子に座り込み、「タールだ!」と一言うめいたのは、むしろ安堵だった。
俺はタール水の壺からボトルを満たしていた。これからもっとひどいことになるだろう。俺は今や霊媒のようにテーブルを動かしていた。
「タール!」と姉が驚いて叫んだ。「どうしてタールが入るのよ?」
だがパンブルチュークおじさんはその話題を一切認めず、手を振って消し去り、ホット・ジン・ウォーターを要求した。姉は動揺しつつもジン、お湯、砂糖、レモンの皮を用意して混ぜた。少なくとも当面、俺は救われた。テーブルの脚を今度は感謝の気持ちでしっかり握りしめた。
やがて落ち着き、手を放してプディングを食べることができた。パンブルチュークおじさんも、皆もプディングを食べた。食事が終わり、ジン・ウォーターの効果でパンブルチュークおじさんも上機嫌になった。俺は今日を乗り切れそうだと思い始めたが、姉がジョーに「きれいな皿を――冷たいの」と言った。
俺は再びテーブルの脚を抱え、まるで幼馴染で心の友のように胸に押し付けた。何が来るか分かっていて、今度こそ本当にダメだと感じた。
「皆さんにぜひ味わっていただきたいの――パンブルチュークおじさんからの素晴らしくおいしい贈り物!」と姉は最高の笑顔で言った。
ぜひとも味わわせるものか!
「皆さんご存知でしょうけど」と姉は立ち上がって言った。「パイですの、香ばしいポークパイ。」
皆は賛辞を述べ、パンブルチュークおじさんは得意げに「じゃあ、ジョー夫人、ぜひ切り分けてください!」と言った。
姉は取りに行った。俺は彼女が食品庫に向かう足音を聞き、パンブルチュークおじさんがナイフを構えるのを見、ウォプスル氏の鼻に食欲が戻るのを見、ハブル氏が「ポークパイはどんな料理の上にも乗せられる」と言うのを聞き、ジョーが「食べろよ、ピップ」と言うのを聞いた。自分が叫び声をあげたのか、心の中だけだったのか分からなかった。もう耐えられない、逃げなければ。俺はテーブルの脚を放し、命がけで走り出した。
だが玄関までしか走れなかった。そこで銃を持った兵士たちの一団に正面衝突したのだ。そのうちの一人が手錠を差し出し「ほら、急いで来い!」と言った。
第五章
兵士たちが銃床を家の玄関に打ち下ろして現れたことで、食卓の一同は混乱して席を立ち、手ぶらで台所に戻ったジョー夫人も「まあ、なんてことでしょう、パイが――!」と驚きの声をあげて立ち尽くした。
軍曹と俺は台所にいた。ジョー夫人が唖然と立ち尽くすその時、俺はやっと正気を取り戻し始めた。俺に声をかけていたのはその軍曹で、今は右手に手錠を持って皆を見回し、左手で俺の肩を押さえていた。
「失礼ですが、皆さん」と軍曹は言った。「先ほどこの利口な坊やに玄関でお伝えしました通り――」(実際は言っていなかった)「王の名の下に追跡中でして、鍛冶屋を探しています」
「それで、鍛冶屋に何の用なのさ?」と姉は素早く反論した。
「奥さん」と軍曹はにこやかに答えた。「自分としては、立派な奥さんと知り合えるのが光栄で嬉しいというところです。王の代理としては、ちょっとした仕事を頼みたいんです」
これがなかなか洒落ていたので、パンブルチュークおじさんは「またやった!」と声を上げた。
「鍛冶屋さん」と軍曹は今度はジョーを見つけて言った。「こいつらの一つが故障して、錠前の調子が悪いし、連結部もきっちり作動しない。今すぐ使わなきゃならんものだから、ちょっと見てくれませんか?」
ジョーは見て、「鍛冶場の火を起こして一時間かそこらかかる」と答えた。「そうか、それならすぐ始めてくれ」と軍曹。「王の任務だからな。うちの兵士たちも手伝わせるから、好きなように使ってくれ」そう言うと兵士たちを呼び、順番に台所に入って武器を隅に積み上げた。兵士たちは、両手を前で組んだり、膝や肩で体重を支えたり、ベルトやポーチを緩めたり、窓を開けて高い襟の上から厳かに外へ唾を吐いたりして過ごした。
これら一部始終を俺は無意識のうちに見ていた。恐怖で頭がいっぱいだったが、手錠が自分のものではないと気づき、兵士たちがパイのことをすっかり忘れていると分かると、少しだけ冷静さを取り戻した。
「時間、分かりますか?」と軍曹はパンブルチュークおじさんに訊いた。
「ちょうど二時半です」
「悪くない」と軍曹は言った。「二時間ほど足止めされても問題ない。ここから沼地まではどれくらい?」
「ちょうど一マイルです」とジョー夫人。
「よし、日暮れ前に包囲を始めるのが命令だ」
「囚人ですか、軍曹?」とウォプスル氏が当たり前のように聞いた。
「ああ、二人だ。まだ沼地にいるらしい。日暮れ前には逃げないはずだ。誰か見かけた人は?」
皆(俺以外)は自信たっぷりに「いいえ」と答えた。誰も俺を疑わなかった。
「まあ、きっと思ったより早く包囲されることになるだろう。さて鍛冶屋さん、準備ができたら王も準備万端だ」
ジョーは上着とベストとネクタイを脱ぎ、革のエプロンをつけて鍛冶場へ行った。一人が木の窓を開け、もう一人が火をつけ、さらにもう一人がふいごを踏み、残りは火のまわりに集まった。火はすぐに勢いよく燃え上がった。ジョーはハンマーでカンカンと打ち始め、皆がそれを眺めた。
追跡の興奮は皆の注意を引きつけ、姉もふだんより寛大になって兵士たちにビールをふるまい、軍曹にもブランデーを注いだ。しかしパンブルチュークおじさんは「ワインを」と強く言い、「それならタールは入ってない」と付け加えた。軍曹は「タール無しが好みなので、もし良ければワインを」と言い、満足げに王の健康と季節の挨拶に一口で飲み干した。
「うまい酒だろ、軍曹?」とパンブルチュークおじさん。
「ひとつ言わせてもらうと、その酒はあんたの用意だろ?」
パンブルチュークおじさんは太い笑い声で「そうかい、なぜだい?」
「なぜって、あんたは分かっている男だからな」と軍曹は肩を叩いた。
「そう思うかい?」とパンブルチュークおじさんは再び笑い、「もう一杯どうだ!」
「よろしい、乾杯だ」と軍曹。「こっちが上、そっちが下――その逆も――グラスで一番の音色で乾杯だ! あんたの健康を千年、今の見識をずっと保ってくれ!」
軍曹はまた一気に飲み干し、さらにもう一杯でもいい様子だった。パンブルチュークおじさんは、ワインを贈り物にしたことをすっかり忘れてしまい、自分が皆に振る舞う役割で大いに得意げだった。俺にも注いでくれた。さらにはもう一本のボトルも持ち出して同じように振る舞った。
彼らが鍛冶場のまわりに集まって楽しむ様子を見ながら、俺は、沼地の逃亡者がいかに食事を盛り上げる最高の「スパイス」になっているかと思った。逃亡者の話題がなければ、彼らは四分の一も楽しめなかったはずだ。今や皆が「二人の悪党」が捕まることを心待ちにし、ふいごは追跡者のために鳴り、火は彼らのために燃え、煙はその後を追い、ジョーのハンマーも彼らのために打たれ、壁の影も彼らを脅すように揺れ、外の薄暗い午後も、若い俺の哀れみの心には、彼らのために蒼ざめているように見えた。
ついにジョーの作業が終わり、音と炎が静まった。ジョーは上着を着て、皆で兵士について行って追跡の行方を見ようと提案した。パンブルチュークおじさんとハブル氏はタバコと婦人たちとのおしゃべりを理由に断ったが、ウォプスル氏はジョーが行くなら行くと答えた。ジョーは賛成し、「ピップも連れていく」と姉に許可を求めた。姉の好奇心がなければ絶対に許可は下りなかっただろうが、今回は「もしあの子が銃で頭を吹っ飛ばされても私を頼らないこと」とだけ条件をつけた。
軍曹は婦人たちに丁寧に別れを告げ、パンブルチュークおじさんとは戦友のように別れたが、湿度のない時にはそこまで彼の功績を認めていたかどうかは疑問だ。兵士たちは銃を持ち直して整列した。俺たち三人は、沼地に着いたら一切口をきかないよう厳命された。外の冷たい空気の中、進みながら、俺はこっそりジョーに「見つからなきゃいいね」とささやいた。ジョーも「逃げててくれればシリング払うよ、ピップ」と答えた。
村からの道連れは誰一人加わらなかった。というのも、天気は寒く今にも雪が降りそうで、道中は陰鬱で足元も悪く、暗くなり始めており、人々は屋内で暖かい火を囲みながら祝日を過ごしていたからである。数人が明るく輝く窓辺に駆け寄り、我々の後ろ姿を見送ったが、外に出てくる者はいなかった。案内標識を通り過ぎ、まっすぐ教会墓地へ向かった。そこで我々は軍曹の手の合図でしばらく立ち止まり、彼の部下が二、三人、墓石の間に散って調べ、玄関も点検した。何も見つからず戻ってきたので、今度は教会墓地の脇にある門を抜け、荒れ果てた湿地へと出た。東風に乗って鋭いみぞれが吹き付けてきたので、ジョーは僕を背負った。
その時、僕が八時間ほど前にあの場所にいて、二人の男が隠れているのを実際に見ていたことなど誰も思いもよらなかっただろう、あの陰鬱な荒野に出た時、僕はようやく初めて恐ろしい不安に襲われた――もし彼らに出くわした場合、僕のあの脱獄囚は、兵士たちをここに連れてきたのが僕だと疑わないだろうか? 彼は僕に「嘘つき小僧か」と問い、もし自分を追う側についたなら「獰猛な若犬だ」と言っていた。彼は、僕が本気で裏切り者になって彼を密告したと信じてしまうのではないか?
しかし、今さら自問しても仕方なかった。僕はジョーの背中に乗り、ジョーは僕を下に抱え、猟犬のように溝を乗り越えて進み、ウォプスル氏には転ばぬよう注意しながら励ましていた。兵士たちは我々の前方に広がって歩き、互いの間隔を開けてかなりの幅で進んでいた。僕たちは、最初に僕が歩き始めて、霧の中で外れたまさにその道をたどっていた。霧はまだ出ていないのか、あるいは風が追い払ったのかもしれない。低い赤い夕焼けの光の下、狼煙台や絞首台、防御砲台の塚、川の向こう岸までが、水っぽい鉛色ながらはっきりと見えた。
ジョーの広い肩越しに心臓が鍛冶屋の槌のように打ち鳴るなか、僕はあたりを見回して脱獄囚たちの痕跡を探した。しかし、何も見えず、何も聞こえなかった。ウォプスル氏は何度も激しく息を吹いたり呼吸を荒げたりして僕を驚かせたが、その音にはもう慣れていたので、追い求める相手と混同せずに済んだ。鉄ヤスリの音が聞こえた気がして恐怖で身体が震えたが、それはただのヒツジの鈴だった。ヒツジたちは食事をやめて怯えたようにこちらを見つめ、牛たちは風とみぞれに背を向けて怒ったような目でにらみつけた――まるでその両方の不快の責任が我々にあるかのようだった――けれど、そうしたものや、夕暮れの寒さが草の一本一本に震えている以外、荒れ果てた湿地の静けさは破られなかった。
兵士たちは古い防御砲台の方角へ進み、僕たちはその少し後ろを行っていた。その時、突然、全員が足を止めた。風と雨に乗って、遠くから長く響く叫び声が聞こえたのだ。それは繰り返された。東の方角から遠くで、しかし長く大きな声だった。いや、音の混乱から判断するに、二人以上の声が同時に叫んでいるようでもあった。
軍曹と近くの兵士たちが小声でそのことを話しているところへ、ジョーと僕が追いついた。さらに耳を澄ませていると、ジョー(判断が的確な男だった)も同意し、ウォプスル氏(判断が鈍いことで有名だった)も同意した。決断力のある軍曹は、その声に応答せず、進路を変えて「駆け足で」その方向へ向かうよう命じた。そこで我々は右(東の方向)へ斜めに進んだ。ジョーはすさまじい勢いで駆けてくれたので、僕はしがみついていなければ落ちそうだった。
今や完全な疾走となり、ジョーがこの時だけ口にした「嵐の走り」という言葉通りだった。土手を下り、土手を上り、門を飛び越え、溝に飛び込み、荒い葦をかき分けて突き進む。誰も行く先など気にしていなかった。叫び声が近づくにつれて、それが複数の声であることはますます明らかになった。時折、声が完全に止み、兵士たちも立ち止まる。再び叫び声が上がると、兵士たちはさらに速くその方向に向かい、僕たちもそれに続いた。やがて、叫び声に迫ると、一方が「殺人だ!」と叫び、もう一方が「脱獄囚だ! 逃亡者だ! こっちだ、逃亡囚は!」と声を上げた。すると両方の声がもみ合うように消え、再び叫びが上がる。その段階になると、兵士たちは鹿のように駆け、ジョーもそれに負けじと走った。
ついに叫び声の発生源を突き止め、軍曹がいち早く溝の底に飛び込み、彼に続いて二人の兵士が続いた。彼らは銃を構えたまま全員が飛び込んだ。
「両方ともここにいるぞ!」と軍曹が息を切らしながら叫んだ。「降伏しろ、この野獣どもめ! 離れろ!」
水しぶきが上がり、泥が飛び、罵声が飛び交い、殴り合いにまでなった。さらに数人の兵士が加勢に溝へ降りて、ついに二人の脱獄囚をそれぞれ引き離して引きずり出した。二人とも血まみれで息を切らし、罵倒しながらもがいていたが、僕はすぐに彼らが誰かを見分けることができた。
「いいか、覚えとけよ!」と僕の脱獄囚が、血まみれの顔をぼろ布の袖で拭い、指に絡んだ髪の毛を振りほどきながら言った。「俺がこいつを捕まえて、俺がお前たちに引き渡すんだ! 忘れるな!」
「だからって、どうしたってんだ」と軍曹は言った。「お前も同じ身の上だ。手錠だ!」
「見返りが欲しいわけじゃねえ。今、この瞬間以上の得なんて望んじゃいねえ」と僕の脱獄囚は貪るような笑い声をあげた。「俺がこいつを捕まえたんだ。こいつもわかってる。それで満足だ」
もう一人の脱獄囚は顔色が土気色で、以前からの左頬のあざに加えて体中が打撲と裂傷だらけだった。息も絶え絶えで、二人が別々に手錠をかけられるまで声も出せず、兵士に寄りかかって立っていた。
「聞いてくれ、衛兵……奴は俺を殺そうとしたんだ」それが彼の最初の言葉だった。
「殺そうとした?」と僕の脱獄囚は軽蔑のこもった口調で言った。「殺そうとして、やらなかったと? 俺はこいつを捕まえてここに引き渡したんだ。こいつが湿地から逃げられないようにしただけでなく、ここまで引きずってきたんだぞ。こいつはな、紳士様なんだ、この悪党が。ほら、刑務所船はまたしても紳士様を手に入れたぞ、俺のおかげで。殺すだと? 俺にはもっとひどいことができた。引きずって連れ戻したほうがよっぽどだ!」
もう一人の男はまだ「奴は……奴は……殺そうとした……証人になってくれ……」と呟いていた。
「聞いてくれ!」と僕の脱獄囚が軍曹に言った。「俺一人で刑務所船を脱出したんだ。命がけで突っ走った。ここの死ぬほど冷たい湿地も同じように逃げきれたはずだ――俺の足を見ろ、もう鉄はほとんど残ってねえ――もし、俺が奴がここにいるのを見つけなかったら。奴を自由にさせるか? 俺が見つけたやり方で奴が得するか? また俺を利用してやり直すか? 二度とごめんだ。もしあそこで死んでいたとしても」そう言って手錠のまま力強く溝を示した「俺は奴をがっちり掴んで離さなかっただろう。そうすれば、お前たちが来たとき、奴も一緒に俺に捕まっていたはずだ」
明らかにもう一人の男は仲間を心底恐れているようで、またも「奴は俺を殺そうとした。もう少しで殺されるところだったんだ、君たちが来なかったら」と繰り返した。
「嘘だ!」と僕の脱獄囚は激情を込めて叫んだ。「生まれついての嘘つきだ。死ぬときも嘘つくだろう。顔を見てみろ、そこに書いてあるだろう? その目で俺を見てみろ。できるもんなら、やってみろ」
もう一人は、神経質に口元をひくつかせて、顔に何とか軽蔑的な笑みを浮かべようとしたが、結局兵士や湿地や空を見回すだけで話者の方は見ようとしなかった。
「見ただろう?」と僕の脱獄囚は続けた。「いかにこいつが悪党か見えるだろう? うろうろと卑屈に目を泳がせてる。俺たちが一緒に裁かれたときも、こいつは決して俺を見なかった」
もう一人の男は、乾いた唇を動かし続け、遠く近く周囲を絶えず見回していたが、ついに一瞬だけ話者に視線を向け、「見る価値もないな」と言い、手錠をかけられた手に半ば嘲るような視線を送った。その瞬間、僕の脱獄囚は激しく逆上し、兵士たちが止めなければ飛びかかっただろう。「ほら見ろ、俺を殺そうとするって言っただろ!」とその男が叫び、その恐怖で震えている様子は誰の目にも明らかで、唇には白い粉雪のようなものが浮かんでいた。
「もうよい、話し合いは終わりだ」と軍曹が言った。「たいまつを灯せ」
銃の代わりに籠を持った兵士がひざまずき、それを開けている間に、僕の脱獄囚は初めて辺りを見回し、僕を見つけた。僕はジョーの背から降り、溝の縁に立ったまま動かなかった。彼がこちらを見た時、僕は必死に手を動かし、首を振った。僕が無実だと伝えたかったのだ。それが伝わったかどうかは全くわからなかった。彼はわからない表情で一瞥しただけで、すべては一瞬の出来事だった。しかし、もし彼が一時間、いや一日見つめていたとしても、それ以上に強いまなざしとして僕の記憶に残ることはなかったと思う。
籠を持った兵士がすぐに火を起こし、三、四本のたいまつに点火して配った。それまでほとんど暗かったのが完全に闇となり、じきに漆黒の夜となった。その場を離れる前、兵士が四人、輪になって二発空に向けて銃を撃った。やがて、後方の遠くでもたいまつの火がともり、川の向こう岸の湿地にも明かりが見えた。「よし、行進だ」と軍曹が言った。
しばらく進むと、前方で三門の大砲が轟き、耳の奥で何かが炸裂したような感覚が走った。「お前は船に戻るのを待たれているぞ」と軍曹が僕の脱獄囚に言った。「お前が来るのは知られている。道を外れるなよ、ここに寄れ」
二人は引き離され、それぞれ別の衛兵に囲まれて歩いた。今度は僕がジョーの手を握り、ジョーはたいまつを一本持っていた。ウォプスル氏はここで帰りたがったが、ジョーは最後まで見届けるつもりだったので、僕たちも隊に加わった。今度は川沿いの比較的良い道で、途中に小さな風車や泥の水門のある溝が現れると、道が少し分かれる程度だった。振り返ると、後から他の明かりがついてくるのが見えた。たいまつの火は地面に大きな火の染みを落とし、それが煙を上げて燃えているのも見えた。それ以外は、真っ暗闇しか見えなかった。たいまつの松脂の炎が周囲の空気を暖め、二人の囚人もそのぬくもりの中、足を引きずりながら少しは心地よさそうにしていた。彼らが足を痛めていたため速くは進めず、疲れ果てて何度か休憩を挟まなければならなかった。
一時間ほど歩いて、粗末な木造の小屋と船着き場に着いた。小屋には詰所があり、衛兵が我々を呼び止め、軍曹が応対した。それから小屋に入り、そこにはタバコと石灰の匂い、明るい火とランプ、銃架と太鼓、そして巨大な洗濯機のような造りの低いベッドがあった。三、四人の兵士がコートを着たままその上に寝ていて、僕たちに興味を示すことなく、ちらりと頭を上げてまた眠りに戻った。軍曹は何か報告し、帳簿に記入した。それから、僕が「もう一人の脱獄囚」と呼ぶ彼は衛兵に引かれて先に船へ向かった。
僕の脱獄囚は、あの一度きりしか僕を見なかった。小屋にいる間、彼は火の前に立ち、もの思いにふけるように火を見つめ、時折順番に足を焚き火の上に上げては、その足をしみじみと見つめて、最近の冒険を哀れんでいるようだった。突然、彼は軍曹に向かって言った。
「この脱走について言っておきたいことがある。そうすれば、俺のせいで疑いをかけられる奴が出なくて済むだろう」
「好きなだけ言え」と軍曹は腕を組んだまま落ち着き払って見下ろし、「だがここで言う必要はない。どうせこれからたっぷり話す機会も、聞かされる機会もあるさ」
「いや、これは別件だ。人間は飢え死にできねぇ、少なくとも俺はな。あっちの村で、教会がほとんど湿地に突き出してるあの村で食い物をくすねたんだ」
「盗んだ、ってことだな」と軍曹。
「どこから盗んだか教えてやる。鍛冶屋からだ」
「おやおや」と軍曹がジョーを見て言った。
「おや、ピップ」とジョーが僕を見て言った。
「壊れた食い物――そういうやつと、ちょっとした酒と、パイだった」
「鍛冶屋さん、パイがなくなったなんてことはないかね?」と軍曹が親しげに尋ねる。
「うちの女房がなくなったと騒いでた、ちょうどあんたが来たときにな。なあ、ピップ?」
「そうか」と僕の脱獄囚はジョーを陰気に見つめ、僕には一瞥もくれずに言った。「あんたが鍛冶屋か。なら悪いが、あんたのパイを食っちまった」
「かまいませんよ、神様がご存じの通り――少なくとも私のものだった分は」とジョーは、ジョー夫人のことを思い出しつつ言った。「何をしたかは知らないが、死ぬほど飢えたままにしておくわけにはいかん、可哀そうな人間だもの――なあ、ピップ?」
僕が前に気づいたあの音がまた彼の喉で鳴り、彼は背を向けた。船が戻り、衛兵が準備できたので、僕たちは彼のあとについて杭と石で組まれた船着き場へ行き、彼が自分と同じ囚人たちの漕ぐボートに乗せられるのを見送った。誰も驚きもせず、関心も示さず、喜ぶ者も悲しむ者もなく、誰一人声もかけなかった。ただ船の中の誰かが犬に怒鳴るように「漕げ!」と唸り、それが櫂の動きの合図だった。たいまつの光の中、泥浜から少し沖に浮かぶ黒い刑務所船が、不吉なノアの箱舟のように見えた。鉄格子と分厚い錆びた鎖で繋がれたその船は、僕の幼い目には囚人と同じく鉄で縛られているように映った。我々はボートが船に横付けされ、彼が艫を上がって消えていくのを見届けた。それからたいまつの先端は水に投げ込まれてジューッと音を立てて消え、まるで彼の人生も終わったかのようだった。
第六章
僕が思いがけず免責された盗みについての心の持ちようは、率直な告白へと僕を駆り立てはしなかったが、わずかばかりの良心は残っていたと思う。
ジョー夫人に関しては、秘密がばれる恐れが消えたとき、特に罪悪感は覚えなかった。ただ、僕はジョーのことが好きだった――当時の僕には、たぶんジョーが好きでいさせてくれた、というくらいの理由しかなかった――だから、ジョーに対しては心の中がなかなか落ち着かなかった。とくにジョーが鉄ヤスリを探しているのを見たときは、すべてを正直に打ち明けるべきだと思い悩んだ。でも実際には言わなかった。なぜなら、そうしたらジョーは僕を実際以上に悪い子だと思うかもしれないと疑ったからだった。ジョーの信頼を失い、夜ごと暖炉の隅で、もう二度と帰らぬ友である彼を寂しく見つめる羽目になるのが怖かったのだ。もしジョーが知っていたら、もう二度と彼が気まぐれに肉やプディングを見たとしても「あれは昨日の残りだな」と思うたび、僕は自分が食料庫を漁ったのではないかと疑われている気がしてしまうだろう。もしジョーが知っていて、その後一度でもビールが薄いとか濁っているとか言われれば、「きっと僕が樽にタールを入れたと思っている」と顔が赤くなってしまうだろう。要するに、僕は間違いだと分かっていながら勇気がなくて正しいことができず、間違いだと分かっていたことを避ける勇気もなかったのだ。当時の僕は世間知らずで、こういう行動を誰かの真似でやったわけでもなかった。ただ自分自身で、その時の行動を思いついたのだ。
刑務所船から遠く離れる前に眠くなったので、ジョーはまた僕を背負って家に連れて帰ってくれた。ジョーは大変だったに違いない。ウォプスル氏は疲れ果てて機嫌が悪く、もし教会が開いていたら、遠征隊全員を破門するところだっただろう。俗人の立場では、馬鹿げたほど何度も湿った地面に座り込んだので、コートを脱がせて台所の火で乾かしたとき、ズボンの証拠だけで死刑にされかねないほどだった。
その頃の僕は、眠ったまま床に降ろされたおかげで千鳥足になり、酔っ払いのように台所の床をふらふら歩き、灯りや人声の騒がしさで目覚めた。自分を取り戻すと(肩をどんと叩かれ、ジョー夫人から「全く、こんな子がいるもんだ!」と怒られて)、ジョーが囚人の自白を皆に話しているのを聞いた。皆は、どうやって食料庫に入り込んだのか思い思いに推理を披露していた。パンブルチューク氏は敷地を細かく調べた末、鍛冶屋の屋根から家の屋根へ登り、寝具を裂いて作ったロープで台所の煙突を降りたのだ、と断言した。彼は自分の二輪馬車で威張っていたので、皆もそれを認めざるを得なかった。ウォプスル氏だけは、疲労困憊の意地で「違う!」と叫んだが、理論がなくコートも着ていなかったので、全員から無視された。しかも彼は台所の火の前で激しく煙草を吸っていて、それが信頼を損なったことは言うまでもない。
その夜に僕が聞いたのはそれだけだった。姉は僕を、眠そうな姿が皆の目障りだとでもいうように強引に寝室へ連れていき、その手の力強さにまるで自分の足に五十足の長靴を履かされ、それらをすべて階段の縁にぶつけながら引きずられていくような気分だった。僕の心の状態は、朝起きる前から始まり、その話題が完全に消え去り、例外的な時にしかもう語られなくなっても、ずっと続いていた。
第七章
僕が教会の墓地で家族の墓石の文字を読んでいたとき、僕にはどうにかそれを綴るだけの学力があった。だが、その素朴な意味さえ正しくは解釈できていなかった。たとえば「the Aboveの妻」と書かれているのを、僕の父が高い世界に昇ったことへの賛辞だと思い込んでいたし、もし「Below」などと書かれていたなら、その親族は最悪だと信じて疑わなかっただろう。カテキズム(教義問答)で自分が「生涯同じ道を歩む」と宣言している意味も正確には理解できていなかった。「生涯同じ道を歩む」とは、家から村のある一方向にしか歩いてはいけない、車大工の店の方へ曲がったり、製粉所の方に登ったりしてはいけない、という義務が課せられていると本気で思い込んでいたのである。
僕が大きくなったら、ジョーに弟子入りする予定だった。そして、その名誉ある地位に就くまでは、ジョー夫人の言う「ポンペイ扱い」――僕流に言えば「甘やかし」は禁じられていた。だから、僕は鍛冶屋で小間使いをするだけでなく、近所の誰かが鳥を追い払ったり、石を拾ったり、他の雑用が必要になれば、必ず僕が雇われることになっていた。ただし、我が家の「高い身分」が損なわれぬよう、稼ぎはすべて台所の暖炉棚の貯金箱に入れられ、皆にそのことが公然と知らされていた。最終的にはこれが国債返済に充てられるのだろうと漠然と思っていたが、自分に何か得があるなどとは期待していなかった。
ウォプスル氏の大叔母が村で夜学を開いていた。要するに、限られた資産で無限の持病を抱えるおかしな年寄りで、毎晩六時から七時まで若者たちと一緒に眠り込む。その「教育の機会」に週二ペンス払う生徒たちの前で、彼女は寝てばかりいた。小さなコテージを借り、ウォプスル氏は二階の部屋を使っていて、我々生徒は彼が威厳たっぷりに朗読したり、時折天井をドンと叩く声を聞いたものだった。「試験」があるということになっていたが、実際は袖をまくり、髪を逆立てて、シーザーの亡骸の前でアントニーの演説を披露するだけだった。いつも必ず続いて「コリンズの『激情への頌歌』」が唱えられ、僕は特にウォプスル氏が「復讐」となって血塗られた剣を雷のごとく投げ下ろし、「戦争」を糾弾するラッパをにらみつける場面に陶酔した。後年、激情たちと実生活で出会ったとき、コリンズとウォプスルの印象はずいぶん損なわれてしまったが、当時は違った。
ウォプスル氏の大叔母はこの「教育機関」だけでなく、同じ部屋で小さな雑貨屋も営んでいた。何がいくらあるかも分からず、値段も覚えていなかったが、引き出しには油染みのメモ帳があり、これが「商品目録」としてバディが店の売買をすべて仕切っていた。バディはウォプスル氏の大叔母の孫娘だった。彼女がウォプスル氏とどういう親戚なのか、僕にもさっぱり分からなかった。彼女も僕と同じ孤児で、やはり「手で育てられた」身の上だった。彼女で特に印象深かったのは、手足である。髪はいつもぼさぼさ、手はいつも洗い損ね、靴はいつも壊れていて踵が擦り切れていた。この説明は平日のみに限る。日曜には、教会へ行くためにきちんと着飾っていた。
アルファベットを一人で、いやむしろバディの助けで、ウォプスル氏の大叔母よりはるかに多く助けられて、僕は茨の藪をかき分けるように苦労して覚えた。文字一つ覚えるごとに大いに悩まされ、傷ついた。そのあとは、あの盗人たる数字の九つに苦しめられ、毎晩のように正体を偽られ、見分けがつかなくなった。だが、ついに手探りで、読んだり書いたり計算したり、ごく初歩的なことはできるようになった。
ある晩、僕は囲炉裏の隅に座り、スレートでジョーへの手紙を書くために奮闘していた。湿地での追跡劇から一年ほど経った頃で、冬の厳しい寒波だった。参考用のアルファベットが足元にあり、僕は一、二時間かけて以下のような手紙を書き、滲ませた――
OPE i SHAL
SHORL B
LARX AN
「MI DEER JO i OPE U R KRWITE WELL i SON B HABELL 4 2 TEEDGE U JO AN THEN WE SO GLODD AN WEN i M PRENGTD 2 U JO WOT BLEVE ME INF XN PIP.」
ジョーは僕の隣に座っていて、しかも僕たちは二人きりだったので、手紙で伝える必要は全くなかった。でも、僕はこの文(スレートごと)を自分の手で渡し、ジョーはその知識の奇跡に感嘆した。
「やあ、ピップ、坊や!」とジョーは青い目を見開いて叫んだ。「なんて学者だ! なあ?」
「なりたいな」と僕はスレートを見ながら言ったが、自分の字がデコボコだと不安だった。
「ほら、Jがある」とジョー。「Oも見事だ! JとO、ピップ、J-O、ジョーだ」
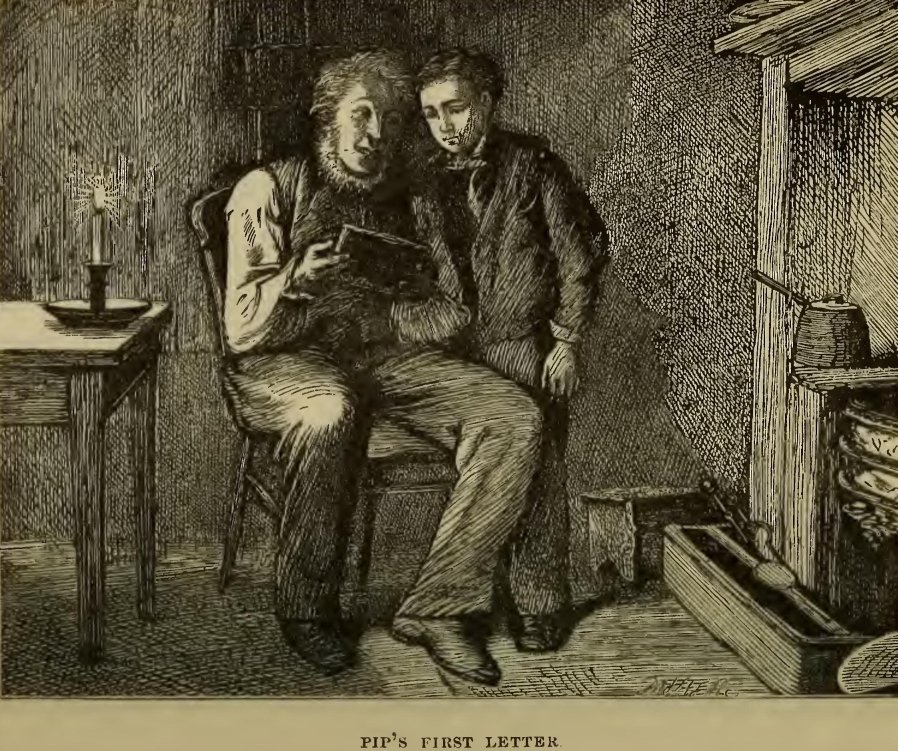
ジョーが声に出して読むのはこの一音節が最高記録で、先日の教会でも僕が祈祷書を逆さに持ったら、正しい向きと同じくらい便利そうにしていた。この機会に、ジョーを教えるときは最初からやらなければいけないのか確かめたくて言った。「でも、他のところも読んでよ、ジョー」
「他のところ、か、ピップ?」とジョーは、ゆっくりとくまなく目を走らせながら言った。「一つ、二つ、三つ。ほら、Jが三つとOが三つ、J-O、ジョーが三つあるぞ、ピップ!」
僕はジョーに身を寄せ、指で一緒に全文を読み上げてやった。
「すごい!」とジョーは読み終えると感嘆した。「本当に学者だな」
「ガージェリーってどう綴るの、ジョー?」と僕は控えめな恩着せがましさで尋ねた。
「綴らないよ」とジョー。
「でも、もし綴るとしたら?」
「仮定はできないさ」とジョー。「俺は本が大好きなんだけどな」
「本当に?」と僕。
「大好きだ。いい本か、いい新聞があれば、暖炉の前に座っていられれば、それ以上は望まない。最高だよ!」と、膝をこすりながら続けた。「でも、JとOに来て、やっと『J-O、ジョーだ』と言えた時、読書って本当に面白いなあ!」
この会話で、僕はジョーの教育が蒸気機関のようにまだ幼児期だと悟った。さらに尋ねた――
「ジョーも子どものころ、学校に行かなかったの?」
「いいや、ピップ」
「どうして行かなかったの?」
「そうだな、ピップ」とジョーは火掻き棒を手に、思案する時のいつもの癖でゆっくり火をいじりながら言った。「話すよ。俺の父親は酒飲みでな、酔うと母さんに容赦なく暴力をふるった。俺にもそうだった。父親が一番力を入れて叩いたのは、母さんと俺だったな、鍛冶屋の金床を叩くより熱心だった――聞いてくれてるか、ピップ?」
「うん、ジョー」
「だから、母さんと俺は何度も父さんから逃げ出した。母さんは働きに出て、『ジョー、今度こそ学校に行かせてあげるよ』と言ってくれたんだ。でもな、父さんは心が優しい男で、俺たちがいないと我慢できなかったんだ。だから大勢を連れて騒ぎを起こし、泊めてくれた家も手を焼いて俺たちを追い出した。そして家に連れ戻され、また殴られた。これが俺の勉強の妨げだったんだよ、ピップ」と言いながら、火をいじる手を止めて僕を見た。
「本当に、かわいそうなジョー!」
「でもな、ピップ」と、火掻き棒で火の上をコツコツ叩きながら続けた。「正義を重んじて言うが、父さんは心が優しい男だったんだよ」
僕は納得できなかったが、口には出さなかった。
「な、誰かが鍋の火を絶やさなきゃ、鍋は煮えないだろ?」
それは分かると僕は答えた。
「だから、父さんは俺が働くのには文句を言わなかった。俺は今の仕事、鍛冶屋に就いた。父さんもやればよかったんだけどな。ほんとによく働いたよ、ピップ。やがて稼ぎで父さんを養えるようになり、父さんが癲癇の発作で亡くなるまで面倒を見た。墓石には『どんな欠点があっても、心は優しい男だったと読者よ思い出してくれ』って刻みたかったんだ」
ジョーはこの二行を誇らしげに、丁寧に朗読したので、僕は「自分で作ったの?」と尋ねた。
「そう、自分だ」とジョー。「一瞬でできた。馬蹄を一撃で打ち出したみたいだった。自分でも信じられなかったよ。でも詩を刻むのは金がかかるんだ、どんなに短くても。母さんの方も貧乏で体も悪く、父さんのためにお金は使えなかった。母さんもすぐに亡くなって、やっと安らぎに辿り着いたんだ」
ジョーの青い目が少し潤み、火掻き棒の丸い頭で目をこすった。
「それからは独りで淋しくてね」とジョー。「そこで君の姉さんと知り合ったんだ。なあ、ピップ」――ジョーは僕が賛成しないのを分かっているといった表情で――「君の姉さんは立派な体格の女性だ」
僕は思わず火を見つめ、疑問の色を隠せなかった。
「家族や世間の評判がどうであれ、ピップ、君の姉さんは――」ジョーは言葉ごとに火掻き棒で火を叩きながら――「立・派・な・体・格・の・女・性・だ!」
僕はせいぜい「そう思ってくれてよかったよ、ジョー」と言うしかなかった。
「俺もそう思えてよかったよ、ピップ。ちょっと赤かったり骨っぽかったりしても、俺にとっちゃどうでもいいことさ」
「なら、どうでもいいよね」と僕は気の利いたことを言ってみた。
「まったくその通りさ! 君の姉さんと知り合った時、君を手で育ててるって評判だった。みんな親切な人だって言ってたし、俺もそう思ったよ。で、君に関して言えば――」ジョーはすごく嫌なものを見るような顔をした――「君がどんなに小さくて、ふにゃふにゃで、みすぼらしかったか知ってたら、自分を最低だとしか思えなかっただろうな!」
気分が悪くなったので「僕のことは気にしないで」と言った。
「でも気にしたんだよ、ピップ」とジョーは純真に言った。「君の姉さんと付き合い始めて、教会で式を挙げる時に言ったんだ――『あのかわいそうな子も連れておいで。神様、あの子に祝福を。鍛冶屋には彼の居場所があるからね!』」
僕は泣きながら謝り、ジョーの首にしがみついた。ジョーは火掻き棒を落として僕を抱きかかえ、「いつまでも親友だろ、ピップ? 泣くなよ、坊や!」と言ってくれた。
ひとしきり泣いた後、ジョーは話を続けた――
「さて、ピップ、ここまできた。これが現実さ、今の状況だ! さて、俺の学びに手を貸してくれる時――前もって言っとくが俺はひどく物覚えが悪いぞ、恐ろしくな――ジョー夫人にはあまり知られてはいけない。こっそりやらなきゃならない。なぜかって? 理由を言うよ、ピップ」
ジョーは再び火掻き棒を手にした。これなしには話が進められなかっただろう。
「君の姉さんは『支配』が好きなんだ」
「支配?」と僕は驚いた。なんとなく、ジョーが姉さんを政府に譲り渡したのかと、いやむしろそうであってほしいと思っていた。
「支配さ」とジョー。「つまり、君と俺を支配したがる」
「ああ!」
「それに、学者が家にいるのを好まない。特に俺が学者になるのは嫌がる。俺が反逆者みたいになるのを恐れてるんだ」
「どうして――」と聞きかけると、ジョーが止めた。
「待てよ。何を言いたいか分かってる、ピップ。君の姉さんが時々俺たちに対して『モーグル』になるのも否定しないよ。『バックドロップ』もあるし、重くのしかかることもある。姉さんが『ランペイジ』になるときはな、ピップ」ジョーは声をひそめてドアをちらりと見やった「正直に言って、彼女は『バスター』だ」
ジョーはこの単語を最低でも十二個の大文字Bで発音した。
「なぜ俺が成り上がらないか、と君は聞きかけたな?」
「うん、ジョー」
「それはな」とジョーは火掻き棒を左手に持ち替え、髭を撫で始めた。その仕草になると、もう希望はなかった。「君の姉さんは『大物』なのさ。大物だ」
「大物って何?」と僕は、彼を困らせようと期待して尋ねた。でもジョーは予想以上にすばやく、「それが彼女さ」と断言したので、僕は完全に打ち負かされてしまった。
「それに、俺は頭の切れる人間じゃないんだ」と、ジョーは視線を外し、再びひげに手を戻しながら話を続けた。「それから最後にな、ピップ――これだけは本当にお前に真剣に言っておきたいんだ、相棒――俺の母親は、本当に気の毒なほど女手一つで働きづめで、こき使われて、誠実な心も砕けてしまって、生きている間に安らぎなんて一度もなかった。だからこそ、俺は女に対して正しいことをしないで済ませてしまうことが、何よりも怖いんだ。むしろ逆に、俺自身が少しばかり損をする方がよほどいいと思う。ピップ、できることなら、俺だけが損したいと思うよ。お前に“ティックラー”[訳注: ピリップがジョー夫人から打たれるときに使われる鞭]なんて必要なければよかった。全部俺が引き受けられたらよかったのに。でも、これがありのままの俺なんだ、ピップ。多少の至らなさは、大目に見てくれよ。」
私はまだ幼かったが、その夜を境にジョーへの新たな敬愛の念が芽生えたのだと思う。その後も以前と同じく、お互い対等であったが、静かな時にジョーを眺めて考えごとをしていると、心の奥で彼を尊敬している自分に気づくようになった。
「さて」と、ジョーは立ち上がり、暖炉に薪をくべながら言った。「オランダ時計が、もうすぐ八時を打つぞって頑張ってるのに、まだ帰ってきてないじゃないか! パンブルチューク伯父さんの馬が、氷に足を取られて転んでなきゃいいが。」
ジョー夫人は、市場の日になるとパンブルチューク伯父さんと連れ立って出かけ、女性の目利きが必要な家財や日用品の買い物を手伝っていた。パンブルチューク伯父さんは独身で、家のことは召使いに任せていなかったからだ。今日は市場の日で、ジョー夫人もその買い物に出ていた。
ジョーが火をくべて炉端を掃除した後、私たちは戸口に出て、馬車の音を聞こうと耳を澄ませた。乾いた冷たい夜で、風は鋭く吹き、霜は真っ白で地面は固かった。今夜、湿地に寝転がっていたら人は死んでしまうだろう、と思った。そして星を見上げながら、もし凍え死にしながらあの星々を仰ぎ、あの煌めく群れのどこにも助けや憐れみを見出せないとしたら、どれほど恐ろしいことかと考えた。
「馬がきたぞ」とジョーが言った。「馬蹄の音が鐘みたいに響いてる!」
固い道を鉄のひづめが打つ音は、いつもより速い駆け足で、ちょっとした音楽のようだった。私たちはジョー夫人が降りるために椅子を用意し、窓が明るく見えるように火をかき立て、台所の様子が乱れていないか最終チェックをした。準備が整うと、彼らが到着し、目元までぐるぐると包まれていた。ジョー夫人はすぐに降り、パンブルチューク伯父さんも馬に毛布をかけてから台所に入り、私たち全員で冷たい空気を運び込んだため、火の熱気がすっかり追い出されてしまった。
「さあ」とジョー夫人は興奮と急ぎで自分をほどき、帽子を紐で肩にぶら下げたまま投げやりに言った。「今夜この子が感謝しないなら、一生しないわね!」
私は、なぜ感謝の表情をしなければならないのか全く知らぬまま、少年にできる限り感謝の顔をした。
「ポンペイド[訳注: だまされる、だの意]されなければいいんだけど」と姉は言った。「でも、私は心配してるのよ。」
「そんな子じゃありませんよ、奥さん」とパンブルチューク伯父さんが言った。「彼女はちゃんと分かってます。」
彼女? 私はジョーに向かって、口と眉で「彼女?」と問いかけた。ジョーも私に同じように「彼女?」と動かしてみせた。ジョー夫人がそれを見咎めると、ジョーはいつものように和を保とうと手の甲で鼻をぬぐい、彼女を見た。
「何よ?」と姉が苛立たしげに言った。「何をジロジロ見てるの? 家が火事なの?」
「――ある方がですね」と、ジョーは丁寧にほのめかした。「“彼女”って言ってましたが。」
「で、彼女は彼女でしょ?」と姉は言った。「いくらあんたでも、ミス・ハヴィシャムを“彼”とは呼ばないでしょうよ。」
「町のミス・ハヴィシャムかい?」とジョーが言った。
「他に下町にミス・ハヴィシャムがいるの?」と姉が返す。
「あの方が、この子を呼んで遊ばせたいって言ってるのよ。もちろん行くの。そして、そこでちゃんと遊んできなさい」と姉は私に首を振って見せ、元気にふるまうよう励ますのだった。「でなきゃ、こっぴどく働かせるからね。」
私は町のミス・ハヴィシャムのことを聞いたことがあった――何マイルも離れた人々まで、あの町のミス・ハヴィシャムのことを知っていた――が、彼女は莫大な財産を持ち、強情な老婦人で、大きく陰鬱な屋敷に強盗対策で立てこもり、人里離れて暮らしていると噂されていた。
「いやはや!」と、ジョーは驚いて言った。「どうやってピップのことを知ったんだろう?」
「愚か者!」と姉が叫ぶ。「誰が“知ってる”なんて言った?」
「――ある方がですね」と、ジョーはまた丁寧に続けた。「“この子を遊ばせたい”って言ってましたが。」
「パンブルチューク伯父さんに“誰か遊ばせる子を知らないか”って聞いたっていいじゃない。もしかしたら伯父さんは彼女の借家人かもしれないし、家賃を支払いに――四半期ごとや半年ごとなんて、あなたには無理でしょうけど――たまに行くかもしれないでしょ? で、その時、伯父さんが“立派な少年がいますよ”と紹介する。私がどれだけこの子のために奴隷のように働いてきたことか――あなたには分からないでしょうけどね、ジョセフ」と、まるで彼が無情な甥だと言わんばかりの非難の口調で言った。「その時に、この子を紹介したんじゃないの?」
「お見事!」とパンブルチューク伯父さんが叫ぶ。「素晴らしいご説明! 見事な論理だ! 本当に素晴らしい! さて、ジョセフ、これで事情が分かったでしょ。」
「いいえ、ジョセフ」と姉はまだ非難しながら言い、ジョーはまた手の甲で何度も鼻をぬぐった。「あなたはまだ――自分では分かってるつもりかもしれないけど――事情を分かってないのよ。パンブルチューク伯父さんは、もしかしたらこの子がミス・ハヴィシャムのところへ行くことで運命が開けるかもしれないと考えて、今夜自分の馬車で町へ連れて行き、泊めて、明朝自分の手でミス・ハヴィシャムの元へ連れて行ってくれるって言ってくださってるのよ。ああ、なんてこった!」と姉は、絶望的に帽子を投げ捨てながら叫んだ。「私はこんな愚か者たちに話してる間に、伯父さんを待たせ、馬は戸口で風邪をひきかけて、子どもは頭から足の先まで真っ黒じゃないの!」
そう言うなり、彼女はまるで鷲が子羊に飛びかかるように私に襲いかかり、私の顔は桶に押しつけられ、頭は水桶の蛇口の下に突っ込まれ、石鹸でごしごし洗われ、もみ洗いされ、タオルで拭かれ、どつかれ、こすられ、引っかかれ、私はもう自分が何なのか分からなくなるほどだった。(ここで一言言っておくと、結婚指輪が同情なく人の顔を通過したときの“跡”に関しては、私はどんな権威者よりも詳しい自信がある。)
洗浄が終わると、私は新品の、しかも非常に固い下着を着せられ、まるで若い懺悔者が荒布をまとうように、最もきつくて恐ろしく窮屈な正装に身を包まれた。それから私はパンブルチューク伯父さんに引き渡され、伯父さんはまるで保安官のように厳かに私を受け取り、ずっと言いたかったあの決まり文句を放った。「少年よ、常にすべての恩人に感謝しなさい、特に手ずからお前を育ててくれた人々には!」
「さようなら、ジョー!」
「神のご加護を、ピップ、相棒!」
私はこれまで一度もジョーと別れたことがなかった。感情と石鹸の泡とで、馬車から星を見ることも最初はできなかった。しかし星はひとつずつ輝き始め――どうして自分がミス・ハヴィシャムのところへ“遊びに”行くのか、何を“遊ぶ”よう求められているのか、その答えを何一つ照らしてはくれなかった。
第八章
パンブルチューク伯父さんの店は市場町の大通りにあり、穀物商と種屋らしく、こしょうっぽく粉っぽい雰囲気だった。あんなにたくさん小さな引き出しを持てるのは、さぞ幸せな人に違いないと思い、下段の一つ二つを覗き込み、中にくくられた茶色の紙包みを見ては、花の種や球根たちは晴れた日にあの監獄から抜け出して咲きたいと思ったりしないのだろうかと考えた。
こうしたことを考えたのは、到着した翌朝のことだった。前夜、私は屋根裏部屋に直行させられた。傾いた屋根で、ベッドのある隅は天井が低く、瓦が眉の高さからわずか30センチほどに思えた。その同じ朝、私は種とコーデュロイの間に奇妙な親近感を発見した。パンブルチューク伯父さんも店員もコーデュロイを履いていて、なぜかコーデュロイには種らしさがあり、種にはコーデュロイらしさが漂っていて、どちらがどちらだか分からなくなりそうだった。また、パンブルチューク伯父さんは向かいの鞍屋を監視しながら商売をしているようで、鞍屋は馬車屋を見張り、馬車屋は手をポケットに突っ込んでパン屋を眺め、パン屋は腕を組んで食料雑貨屋をじろじろ見て、食料雑貨屋は戸口であくびしながら薬局を見ている――そんな連鎖を観察できた。時計屋だけは、小さな机を虫眼鏡で覗き込み、外からはスモック姿の男たちがガラス越しに彼を観察していて、唯一自分の仕事に集中しているようだった。
私とパンブルチューク伯父さんは、店の裏の居間で八時に朝食をとった。店員は前室のエンドウ豆の袋の上で、紅茶とパンをかじっていた。パンブルチューク伯父さんは、まことに退屈な相手だった。姉の持論どおり、私の食事には戒めと懲罰の色が求められたらしく、パンの中身はできる限り多く、バターはできるだけ少なく、ミルクにはお湯を大量に混ぜ、正直に言えば最初からミルクがなかった方がまだ潔かった。しかも会話はひたすら算数で、私が「おはようございます」と丁寧に挨拶すると、威厳たっぷりに「七かける九は、少年?」と来る。見知らぬ場所で、空腹のまま、そんな風に急に問われて即答できる少年がいるだろうか! 私は空腹だったが、パンの一口も飲み込まないうちに、伯父さんは「七は?」「四は?」「八は?」「六は?」「二は?」「十は?」と、ひっきりなしに足し算を始めた。そのたびに必死で一口食べるのがやっとで、伯父さんは優雅に何も考えず、ベーコンや焼きたてパンを(敢えて言えば)むさぼるように食べていた。
そんなわけで、十時になってミス・ハヴィシャムの家に出発するときは本当にほっとしたものの、その婦人の家で自分がどう振る舞えばよいかはまるで見当がつかなかった。15分もしないうちにミス・ハヴィシャムの家に着いた。古いレンガ造りで陰鬱な家で、たくさん鉄格子がはめてあった。いくつかの窓は壁で塞がれ、残った窓も下の方はすべて錆びた鉄格子がかかっていた。前には中庭があり、そこも鉄格子で囲まれていたので、呼び鈴を鳴らして誰かが開けに来るまで待たねばならなかった。待っている間、私は中を覗き込んだ(その時ですらパンブルチューク伯父さんは「十四は?」と言ったが、私は知らぬふりをした)。家の脇に大きな醸造所があり、もう何年も使われていないようだった。
窓が開き、澄んだ声が「お名前は?」と尋ねた。案内役の伯父さんは「パンブルチューク」と答えた。声は「それでよろしい」と返し、窓が閉まって、若い女性が鍵束を手に中庭を横切ってきた。
「この子がピップです」とパンブルチューク伯父さんが言った。
「これがピップなのね?」と若い女性――とても美しく、誇らしげな様子だった――が返した。「入りなさい、ピップ。」
パンブルチューク伯父さんも入ろうとすると、彼女は門でそれを制した。
「あら」と彼女は言った。「ミス・ハヴィシャムに会いたいの?」
「もしミス・ハヴィシャムがお会いになりたいなら」と伯父さんは少し気まずそうに答えた。
「あら、でもね、彼女はそうじゃないのよ。」
あまりにも断定的で議論の余地もない言い方だったので、伯父さんは気分を害しながらも抗議できなかった。しかし、まるで私が何か悪いことをしたかのように厳しい目で私をにらみ、非難がましく「少年よ! ここでの振る舞いが、お前を手ずから育ててくれた人々の名誉となるようにしなさい!」と言い残して去った。私は彼が門越しに「十六は?」とまた問題を出すのではと心配したが、さすがにそうはしなかった。
若い案内人は門に鍵をかけ、私たちは中庭を横切った。敷石できれいに掃除されていたが、割れ目には草が生えていた。醸造所の建物から中庭へ通じる小道があり、その木の門は開いていて、奥の醸造所も高い外壁に向かってずっと開け放たれ、すべてが空虚で使われていなかった。外よりも風は冷たく、吹き抜ける風が船の索具に吹きつけるような甲高い音を立てていた。
私が見ているのに気づいた彼女は、「今ならあそこに醸された強いビールを全部飲んでも大丈夫よ、坊や」と言った。
「きっと飲めると思います、嬢さん」と私は恥ずかしそうに答えた。
「今さらビールを醸しても腐るだけよ、坊や。そう思わない?」
「そんな気がします、嬢さん。」
「誰もそんなことしないけどね」と彼女は続けた。「もう終わったの。あの場所も、このまま放っておかれて崩れるまで誰も何もしない。強いビールなら、地下室にまだたっぷりあって、屋敷を水没させるくらいよ。」
「この家、名前があるんですか、嬢さん?」
「一つはそうよ、坊や。」
「じゃあ、他にもあるんですか?」
「もう一つ。“サティス”っていうの。ギリシャ語かラテン語かヘブライ語か――全部同じようなものだけど――“十分”って意味。」
「十分の家、ですか。変わった名前ですね。」
「そう。でも、その言葉以上の意味だったの。誰でもこの家を持てば、他に何もいらないって。昔の人は満足するのが簡単だったのね。でも、坊や、ぼーっとしないで。」
彼女はしきりに「坊や」と呼び、軽んじている感じがあったが、私と同年代くらいに見えた。もちろん女の子で、美しく、自信に満ちていたので、私にはずっと年上の女王のように思えた。
私たちは横のドアから家に入った。正面玄関は外側に二重の鎖がかけられていた。まず気がついたのは、廊下がすべて暗く、そこに彼女がロウソクを灯して置いてあったことだ。彼女はロウソクを手に取り、私たちは廊下や階段を進むが、どこも闇で、ロウソクの明かりだけが頼りだった。
ついにある部屋の前に着き、彼女が「入りなさい」と言った。
私は、恥ずかしさが先に立って「お先にどうぞ、嬢さん」と答えた。
彼女は「ばかね、坊や。私は入らないわ」と言い、軽蔑した様子で去っていき、しかもロウソクまで持っていってしまった。
私はとても心細く、半分恐ろしかった。しかし他に方法もなく、戸をノックすると、中から入るように言われた。そこで入ると、かなり広い部屋で、ロウソクがたくさん灯されていた。外の光は全く入ってこない。家具からして化粧部屋だろうと推測したが、そのほとんどは私には初めて見る形や用途のものばかりだった。ひときわ目を引いたのは、布で覆われたテーブルと金色の鏡で、それは明らかに上等な婦人の化粧台だった。
もしその化粧台に上等な婦人が座っていなかったら、すぐにそれと分かったかどうか分からない。しかし、肘をテーブルにつき、頭を手に預けて座っているのは、私がこれまで、そしてこれからも二度と見ることのない、奇妙な女性だった。
彼女は、白いサテンやレース、シルクなどの豪華な衣装を身にまとい、靴も白、長い白いヴェールを髪から垂らし、髪にはブライダルフラワーを挿していたが、その髪は白かった。首や手には宝石が輝き、他の宝石もテーブルに散らばっていた。彼女が今着ている服ほど豪華ではないが、まだ仕舞いきれていないドレスや半分詰められたトランクも散乱していた。着替えはまだ終わっていなかった。片方にしか靴を履いておらず、もう一つは手元のテーブルの上、ヴェールもまだ整っていない、時計や鎖はまだ身につけておらず、胸元に飾るレースやハンカチ、手袋、花、祈祷書などが鏡台の前にごちゃ混ぜに置かれていた。
最初の数分でこれらすべてに気づいたわけではないが、思いのほか多くを一目で見ていた。しかし、私の視界に入るものはすべて、かつて白かったはずなのに今は色褪せ黄ばんでいた。そして、花嫁衣裳をまとったその人も、衣装や花と同じくしおれ、輝きを失い、沈んだ目だけが光を放っていた。そのドレスは本来若い女性の丸みのある体に合わせたものだが、今それをまとった体は痩せ衰え、皮と骨ばかりだった。かつて見せ物小屋の不気味な蝋人形を見に連れて行かれたことがあるし、古い教会で棺から掘り出された、豪華な衣服の灰の中の骸骨も見たことがあった。今や蝋人形と骸骨が、暗い目を動かして私を見ているかのようだった。叫び出したいほどだった。
「誰?」とその婦人がテーブルの向こうから言った。
「ピップです、奥さま。」
「ピップ?」
「パンブルチュークさんの子どもです。……遊びに来ました。」
「こちらにいらっしゃい。顔を見せて。近くに。」
私は彼女の目を避けて立ち、細部を観察することができた。その時、彼女の時計は八時四十分で止まり、部屋の時計も同じく八時四十分で止まっていることに気づいた。
「私を見なさい」とミス・ハヴィシャムが言った。「お前が生まれてから一度も太陽を見ていない女を、怖いと思う?」
私は「いいえ」と、嘘だと分かっていながら答えてしまった。
「私がここに触れているのが分かる?」と、彼女は両手を左胸に重ねて言った。
「はい、奥さま。」(その時、あの若者を思い出した。)
「何に触れている?」
「心臓です。」
「壊れているのよ!」
彼女はその言葉を熱心に、力強く、どこか誇らしげな奇妙な笑みを浮かべながら発した。しばらくその手を置いたまま、ゆっくりと重そうに手を離した。
「私は疲れた」とミス・ハヴィシャムは言った。「気晴らしがしたい。男も女も、もうたくさん。さあ、遊びなさい。」
どんなに議論好きな読者でも、こんな状況で不運な少年に“遊べ”と命じることほど難しい注文はないと認めてくれるだろう。
「私は時々病的な気まぐれを起こすの」と彼女は続けた。「今は“遊び”が見たいという気まぐれなのよ。さあ!」と右手の指をイラついたように動かしながら、「遊びなさい、遊びなさい、遊びなさい!」
しばらく私は、姉にこっぴどく“働かされる”恐怖から、パンブルチューク伯父さんの馬車の真似でもして部屋中を駆け回ろうかと思ったが、到底そんな芸当はできそうにないので諦め、ミス・ハヴィシャムを見つめ続けるしかなかった。彼女は私を不機嫌で頑固だと見なしたらしく、長い時間見つめ合った後で、
「ふてくされてるの? 頑固なの?」と尋ねてきた。
「いいえ、奥さま。あなたが気の毒で、今はどうしても遊べなくて申し訳ないんです。もし私のせいで不快になれば、姉に叱られるので、できるならやりますが、ここはあまりに新しいし、奇妙で、立派で……悲しくて……」と言いかけ、言いすぎたかと黙り、再び見つめ合った。
彼女は視線を私から外し、着ているドレスや化粧台、そして鏡の中の自分を見つめた。
「彼には全てが新しい、私には全てが古い。彼には奇妙、私にはなじみ深い。二人とも悲しいことだけは同じ……エステラを呼んで」
彼女はまだ鏡の中の自分を見ていたので、私は独り言だろうと黙っていた。
「エステラを呼んで」と彼女は私に鋭い目を向けて繰り返した。「それはできるでしょう? エステラを呼びなさい。ドアの所で。」
見知らぬ家の暗い廊下で、顔も見えず返事もないエステラの名を大声で呼ぶのは、まるで命令された“遊び”と同じくらい気まずいことだった。しかし、やがて彼女は答え、灯りを星のように持ってやって来た。
ミス・ハヴィシャムは彼女を招き寄せ、テーブルから宝石を取り上げ、その美しい胸元や茶色の髪に当ててみた。「いつかはあなたのものよ、エステラ。上手に使うのよ。さあ、この子とトランプをしてごらん。」
「この子と? なんてみすぼらしい労働者の子なの!」
私は、ミス・ハヴィシャムが「ええ? だからこそ、心を壊せるじゃないの」と答えるのを聞いた気がした――ただ、あまりに意外なので、空耳だったのかもしれない。
「坊や、何のゲームができるの?」とエステラは最大限の軽蔑を込めて尋ねてきた。
「“隣人を乞食に”しかできません、嬢さん。」
「乞食にしてやりなさい」とミス・ハヴィシャムがエステラに言った。こうして私たちはトランプを始めた。
その時、私は部屋の中のあらゆるものが、時計や懐中時計と同じく、ずっと前から止まってしまっていることに気づき始めた。ミス・ハヴィシャムは宝石を元の位置に正確に戻し、エステラがトランプを配る間に私はもう一度化粧台をちらりと見ると、片方だけで今は黄ばんだまま一度も履かれていない靴があり、足元を見ると、靴のない方のストッキングもかつて白かったが今は黄ばんで擦り切れている。この時間停止がなければ、しおれた花嫁衣裳も、痩せた体にかかればまるで死装束に見え、長いヴェールもまるで白布のように思えただろう。
彼女は死者のように座り、私たちはトランプをした。花嫁衣裳の装飾や縁取りは、まるで土気色の紙のように見えた。私は当時、古代の遺体が発掘されて陽の光の下で一瞬にして粉になるという話は知らなかったが、今思えば、あの部屋に自然光が一筋でも差し込めば、彼女は粉々になってしまったのではないかと思う。
「この子、トランプの“ナイト”を“ジャック”って呼ぶのよ!」とエステラは軽蔑たっぷりに言い、ゲームの途中で「なんて粗末な手だこと! なんて分厚いブーツ!」
私は自分の手を恥ずかしいと思ったことがなかったが、この時から自信をなくした。彼女の私への軽蔑はあまりに強く、伝染して私自身も自分を軽蔑し始めた。
エステラが勝ち、私が配る番になったが、まごついてミスディールした。彼女はすぐに私を「愚かで不器用な労働者の子」と侮った。
「君は彼女のことを何も言わないのね」と、ミス・ハヴィシャムは私に言った。「彼女は君にひどいことばかり言うけれど、君は何も言い返さない。彼女のことをどう思う?」
「言いにくいです」と私は口ごもった。
「耳元で言いなさい」とミス・ハヴィシャムが身をかがめて言った。
「とても誇り高いと思います」と私はささやいた。
「他には?」
「とてもきれいだと思います。」
「他には?」
「とても侮辱的です。」(その時、彼女は私を極度の嫌悪を込めて見ていた。)
「他には?」
「家に帰りたいです。」
「でも、あんなにきれいなのに二度と会わなくてもいいの?」
「また会いたいかどうか分かりません。でも今は帰りたいです。」
「もうすぐ帰れるわ」とミス・ハヴィシャムは大声で言った。「ゲームを最後までやりなさい。」
最初の奇妙な微笑を除けば、ミス・ハヴィシャムの顔が笑うことなどないと確信してしまいそうだった。今や顔は沈鬱で警戒した表情に凝り固まっており――たぶん周囲のすべてが止まった時からそうなったのだろう――もう二度と緩むことはなさそうだった。背中も丸まり、声も低く沈んでしまい、全身全霊が押し潰された重みで落ち込んでいるようだった。
私はエステラとゲームを終え、彼女に乞食にされてしまった。エステラはカードを私から勝ち取ると、カードそのものまで私から勝ち取られたことを軽蔑するようにテーブルに投げ捨てた。
「次はいつ君を呼ぼうか。……」とミス・ハヴィシャムが言った。「ちょっと考えるわ。」
今日が水曜だと言いかけた時、彼女は右手の指でまた苛立たしげな動きをして私を制した。
「もういいわ、曜日なんて知らないし、年の週なんて知らない。六日後に来なさい。分かった?」
「はい、奥さま。」
「エステラ、彼を下に連れて行きなさい。何か食べさせて、食べながら見て回らせてあげなさい。行きなさい、ピップ。」
私は行きと同じようにロウソクについていき、エステラは最初にそれを置いていた場所に立てた。横の出入口を開けてくれるまで、私は何となく、ずっと夜のままだと思い込んでいた。昼の光がどっと押し寄せると、長い間あの奇妙な部屋でロウソクの明かりを浴びていたような気分になった。
「ここで待ってなさい、坊や」とエステラは言って、姿を消し、扉を閉めた。
私は一人になった機会に中庭で自分の粗末な手と分厚いブーツを眺めた。それまで気にしたこともなかったが、今やみすぼらしい付属物にしか思えなかった。ジョーに、なぜトランプの“ナイト”を“ジャック”と教えたのか問いただそうと思った。ジョーがもう少し上品な育ちだったら、私もそうなれたのに――と考えてしまった。
彼女はパンと肉と小さなビールのマグを持って戻ってきた。マグは中庭の石の上に置き、私には目もくれず、まるで罪を犯した犬のようにパンと肉を渡した。私は屈辱と痛み、軽蔑され、侮辱され、怒り、哀しみ――なんと呼べばいいのか分からない感情で涙があふれそうになった。その瞬間、エステラは私を泣かせたことに素早い喜びを見せた。これで私は涙を堪えて彼女を見返す力を得た。すると彼女は、私が傷つきすぎたと感じたのか、どこか後悔のような気配を漂わせつつも、軽蔑の仕草で去っていった。
彼女が去ると、私は顔を隠せる場所を探し、醸造所への路地の門の陰に行き、袖で壁に顔を押し付けて泣いた。泣きながら壁を蹴り、髪を強く引っぱった。あまりにも苦しく、名前もつけられない痛みに、何か抵抗せずにはいられなかった。
姉のしつけは私を敏感にしていた。子どもがいる小さな世界では、育てる者が誰であれ、不公平ほど敏感に感じ取るものはない。子どもに受ける不正は些細なものでも、子ども自身が小さく、世界も小さいからこそ敏感なのだ。私は幼い時から姉の気まぐれで乱暴な仕打ちにずっと不当さを感じていたし、“手ずから育てる”ことは“乱暴に育てる”権利ではないと強く信じていた。その信念を、罰や恥、断食や徹夜やその他の懲罰のさなかにも心の奥で育て続けた。そのため、私は内向的で臆病になったのかもしれない。
私は、醸造所の壁を蹴り、髪を引っ張ることで一時的に傷心を処理し、袖で顔を拭い、門から出てきた。パンと肉はありがたく、ビールは体を温め、すぐに気分も回復した。
確かに、そこは鳩小屋に至るまで寂れ切った場所だった。鳩小屋は強い風にあおられて傾いていたので、もし鳩がいたら、まるで海の上にいる気分になっただろう。でも鳩も馬も豚もおらず、貯蔵庫にもモルトはなく、釜や桶からは麦やビールの匂いも感じられなかった。醸造所の機能や香りは最後の煙とともに消えてしまったようだった。裏の敷地には空樽が山積みされており、かつての栄光の名残のようなすっぱい匂いが残っていたが、もうサンプルにはならないほどすっぱかった――この点では、世の隠者たちも同じようなものだと思った。
醸造所の一番奥には古い壁に囲まれた荒れた庭があった。私は苦労してよじ登り、しばらく眺めると、その荒れた庭が屋敷のもので、雑草に覆われているが、緑と黄の小道に誰かが時おり歩く跡があり、エステラがちょうど私から離れて歩いていた。しかし彼女はどこにでも現れるような気がした。樽の上を歩いてみたくなって端まで行くと、彼女が背を向けて同じように樽の上を歩き、髪を両手に広げて一度も振り返らず、すぐに姿を消した。そう、醸造所の中でも――つまりビールを造っていた広い舗装の場所、醸造用具も残っていた場所――私は最初そこへ入り、暗さに圧倒されてドアの近くで立ちすくんでいた時、彼女が消えた火の間を通り、軽やかな鉄階段を上って高いギャラリーから空へ消えていくのを見た。
ちょうどその時、奇妙な幻覚が私を襲った。それは当時も奇妙だと思い、後年になってもなお不思議に思う体験だった。私は、霜の光で少しかすんだ視線を、右手の低い隅にある大きな木の梁に向けた。すると、首を吊った人影が見えた。全身黄ばんだ白で、片足だけ靴を履き、ドレスの擦れた縁は土色の紙のようで、その顔はミス・ハヴィシャムで、顔全体が何か呼びかけているように動いていた。その姿が、それまでなかったはずなのに突然現れた恐怖で、私は一度逃げ、次に駆け寄った。しかし、そこには誰もいなかったのだ。
冷たい光や通りすがりの人々、残りのパンや肉やビールの力がなければ、私は我に返れなかっただろう。だが、エステラが鍵を持って近づいてくるのが見えたから、早くしっかりしなければと気を取り直した。彼女に怖がっている姿を見られたら、ますます見下される理由を与えることになると思った。
彼女は私があまりに粗末な手と分厚いブーツであることを喜ぶかのように勝ち誇った目で私を見て、門を開けて立っていた。私は彼女を見ずに通り過ぎようとしたが、彼女は私に挑発的に触れた。
「どうして泣かないの?」
「泣きたくないからだよ。」
「泣いてるくせに」と彼女は言った。「目が半分見えないくらい泣いて、今にもまた泣きそうじゃない。」
彼女は嘲るように笑い、私を押し出して門に鍵をかけた。私はパンブルチューク伯父さんの家に直行し、彼が留守であることを大いに喜んだ。店員に次にミス・ハヴィシャムの所へ呼ばれる日を伝言し、四マイルの道を鍛冶屋の家に向かって歩き出した。道すがら見たことを反芻しながら、自分が単なる労働者の子で、手は粗末で、ブーツは分厚く、“ナイト”を“ジャック”と呼ぶ悪習があり、昨夜思っていたよりもはるかに無知で、卑しい境遇にいると深く思い悩みながら。
第九章
家に帰り着くと、ジョー夫人はミス・ハヴィシャムの家について何もかも知りたがり、次々と質問を浴びせてきた。そして私は、十分に長く答えなかったために、すぐさま首筋や背中をどしんどしんと叩かれ、恥ずかしげに顔を台所の壁に押し付けられる羽目になった。
もし他の若者たちの心にも、かつての自分と同じくらい「理解されないことへの恐れ」が隠れているのだとしたら――そして、私は自分だけが特別な化け物だったとは思っていないので、おそらくそうだろう――それは多くの言葉足らずの根本的な理由なのだろう。もし私が自分の目で見たミス・ハヴィシャムの屋敷のありさまをそのまま語ったところで、きっと理解されないだろうと確信していた。それだけでなく、ミス・ハヴィシャムその人もきっと理解されないとも思った。そして彼女は私にとってもまったく不可解な存在だったが、彼女の本当の姿(ましてやエステラのことなど)をジョー夫人の目の前に引きずり出すのは、何か下品で裏切りめいたことのように感じられた。だから、できるだけ少ししか話さず、またしても壁に顔を押し付けられたのだった。
最悪だったのは、あのいじめっ子のパンブルチュークおじさんが、知りたいという食い入るような好奇心に駆られて、わざわざティータイムに馬車でやってきて、詳細を聞き出そうとしたことだ。そのうえ、彼の魚のような目を見開き、口をぽかんと開け、砂色の髪を逆立て、胴回りを算数で膨らませながら苦しげに身を乗り出す姿を見るだけで、私はますます頑固な口ごもりになった。
「さて、坊や」とパンブルチュークおじさんは、暖炉のそばの名誉ある椅子に座るなり切り出した。「都会ではどうだったね?」
私は「まあまあでした」とだけ答え、ジョー夫人は私に拳を突き上げた。
「まあまあだと?」パンブルチューク氏が繰り返す。「まあまあとは何だね。まあまあとはどういう意味なんだ、坊や?」
白壁のしっくいは脳みそを頑固にするのかもしれない。とにかく、壁のしっくいが額についた状態で、私の頑固さは筋金入りだった。しばらく考えたふりをして、「まあまあ、という意味です」と新しい考えを思いついたかのように答えた。
姉は苛立ちのあまり飛びかかろうとした――私はまったく言い逃れできなかった、なぜならジョーは鍛冶場で忙しかったからだ――が、パンブルチューク氏が口を挟んだ。「いや! 怒ることはない、奥さん。この子は私に任せてください、奥さん。この子は私に任せて。」
パンブルチューク氏は私の方に体を向け、まるでこれから髪を切るかのように言った。
「まずは(頭を整理するためにだが)、四十三ペンスは?」
「四百ポンド」と答えたらどうなるか計算してみて、不利だとわかり、できるだけ近い答えをした――だいたい八ペンスずれていた。パンブルチューク氏はそれから私に「十二ペンスで一シリング」から「四十ペンスで三シリング四ペンス」までのペンステーブルをやらせたあと、まるで私を完全にやりこめたかのように勝ち誇って、「さて! 四十三ペンスは?」と問い詰めた。私は長い沈黙の末に答えた。「わかりません。」あまりにも苛立っていたせいで、本当に知らなかったかどうかも怪しいくらいだった。
パンブルチューク氏は頭をねじ込むようにして私からそれを引き出そうとし、「たとえば四十三ペンスは七シリング六ペンス三ファージングか?」と言った。
「はい!」と私は答えた。すると姉はすぐに私の耳をはたいたが、私はその答えでパンブルチューク氏の冗談が台無しになり、一瞬黙り込んだのを見て妙に満足した。
「さて、坊や! ミス・ハヴィシャムはどんな人だった?」パンブルチューク氏が気を取り直してまた始め、両腕を胸の前でぎゅっと組み、じっと見つめてきた。
「とても背が高くて、色黒でした」と私は言った。
「そうなの、叔父さん?」姉が尋ねる。
パンブルチューク氏はウィンクしてうなずいた。私はすぐに、この人はミス・ハヴィシャムに会ったことがないのだと察した。実際はまるで違うからだ。
「素晴らしい!」とパンブルチューク氏は得意げに言った。(「こうしてやればいいんだ! そろそろ我々も主導権を握ったぞ、奥さん?」)
「まったく、叔父さん、あなたがいつもこの子を見ていてくれればいいのに。扱い方をよくご存じだわ」とジョー夫人は言った。
「さて、坊や! 今日行ったとき、彼女は何をしていたね?」とパンブルチューク氏が続けた。
「黒いビロードの馬車に座っていました」と私は答えた。
パンブルチューク氏とジョー夫人は顔を見合わせ、「黒いビロードの馬車に?」と二人して繰り返した。
「はい」と私は言った。「それでエステラ――たぶん姪だと思いますが――がその馬車の窓から金のお皿でケーキとワインを差し入れていました。それでみんな金のお皿でケーキとワインを食べたんです。私は、自分の分を馬車の後ろで食べるように言われました。」
「他に誰かいたのか?」パンブルチューク氏が尋ねた。
「犬が四匹いました」と私は言った。
「大きい犬か小さい犬か?」
「巨大でした」と私は言った。「その犬たちが銀のかごから仔牛肉のカツレツを取り合っていました。」
パンブルチューク氏とジョー夫人はまたしても顔を見合わせ、完全に呆気にとられていた。私はもう半ば錯乱状態――拷問下で証言する無鉄砲な証人――で、何でも話してしまう勢いだった。
「その馬車はどこにあったの? いったい何なの?」とジョー夫人が尋ねた。
「ミス・ハヴィシャムの部屋です。」二人はまた見つめあった。「でも、馬はついていませんでした。」私は、四頭の豪華な馬を馬車につなごうと一瞬思ったが、思いとどまり、その一言を付け加えた。
「本当かしら、叔父さん? この子はいったい何を言ってるの?」
「私が思うに、奥さん」とパンブルチューク氏。「それはセダンチェアだ。彼女は気まぐれな人だからね――すごく気まぐれで、一日中セダンチェアに座って過ごすくらいだ。」
「叔父さん、実際に彼女が乗ってるのを見たことあるの?」とジョー夫人。
「どうして見られるものか」と彼はやっと認めて言った。「私は彼女に会ったことがないんだから! 一度も見たことがない!」
「まあ、叔父さん! それなのに話したことが?」
「それがね」とパンブルチューク氏はいらだたしげに言った。「私が行ったときは、彼女の部屋の外まで案内されて、ドアが少し開いていて、彼女はその向こうから私に話しかけてきただけだよ。そのくらい知らないなんて言うなよ、奥さん。ともかく、坊やはあそこで遊ぶために行ったんだろ。何をして遊んだんだ、坊や?」
「旗で遊びました」と私は言った。(このとき自分がどれほど嘘をついたか、今思い出しても驚かずにはいられない。)
「旗?」と姉が繰り返す。
「はい」と私は言った。「エステラが青い旗を振って、私は赤い旗を振って、ミス・ハヴィシャムが金色の星がちりばめられた旗を馬車の窓から振りました。それからみんなで剣を振り回して、万歳と叫びました。」
「剣だって?」と姉が言う。「剣なんてどこから?」
「戸棚の中からです」と私は言った。「ピストルも見ました――ジャムも――錠剤も。部屋には日差しはありませんでしたが、ろうそくの光で明るかったです。」
「それは本当だ、奥さん」とパンブルチューク氏は厳かにうなずいた。「それは私も見たことがある。」それから二人は私をじっと見つめ、私はわざとらしくあどけない顔をして二人を見返し、右手でズボンの右足を三つ編みにしていた。
もしもっと質問されていたら、私はきっと自分の正体を明かしていただろう。なにしろ、今にも裏庭に気球があったと言いかけるところだったし、さらにビール醸造所に熊がいたことにするかどうかで頭がいっぱいだったのだから。しかし二人は、私がすでに語った数々の奇談をめぐって議論に夢中だったので、私はそのまま逃れた。その話題のまま、ジョーが仕事からお茶を飲みに帰ってきた。姉は、その話が自分の気を晴らすために、ジョーに私の作り話を語って聞かせた。
さて、ジョーが青い目を見開き、厨房中を呆然と見回したとき、私は良心の呵責に襲われた。ただし、それはジョーに対してだけで、他の二人にはまったく感じなかった。ジョーに対してのみ、私は自分をひどい悪童だと思った。一方で二人は、ミス・ハヴィシャムとの付き合いや厚意から、いずれ私にどんな恩恵がもたらされるかを議論していた。ミス・ハヴィシャムが「何かしてくれる」のは疑いなかったが、その「何か」の内容については色々と意見があった。姉は「財産」を主張し、パンブルチューク氏は、私を立派な商売(例えば穀物や種子の商い)に弟子入りさせるための立派な見習い金を推した。ジョーは、仔牛肉のカツレツを争った犬のうちの一匹をもらえるだけだ、という妙案を出して、二人から大いに呆れられた。「馬鹿な頭でそれしか思いつかないなら、仕事でもしてなさい」と姉は言い、ジョーはその場を去った。
パンブルチューク氏が帰ったあと、姉が皿洗いをしている隙に、私は鍛冶場に忍び込んでジョーのそばにいた。夜の仕事が終わると、私は言った。「火が消える前に、ジョー、話したいことがあるんだ。」
「そうかい、ピップ?」とジョーは蹄鉄のベンチを炉のそばに引き寄せた。「じゃあ話してごらん。何だい、ピップ?」
「ジョー」と私は彼のまくり上げたシャツの袖口をつまみながら言った。「あの、ミス・ハヴィシャムの話、全部覚えてる?」
「覚えてるとも、すごい話だ!」とジョーは言った。
「あれはひどいんだ、ジョー。本当じゃないんだ。」
「何だって、ピップ?」とジョーは驚いてのけぞった。「まさか――」
「そうだよ、嘘だったんだ、ジョー。」
「でも全部じゃないだろ? まさかピップ、黒いビロードの馬車がなかったなんて――」私は首を振った。「でも犬はいたんだろ? ピップ、仔牛肉のカツレツはなくても、犬はいたんだろ?」
「いないよ、ジョー。」
「犬も?」とジョーは言う。「子犬も? なあ?」
「いないよ、ジョー、そんなもの何もなかったんだ。」
私は絶望的な面持ちでジョーを見つめ、ジョーは困り果てて私を見た。「ピップ、だめだぞ! どうするつもりなんだ?」
「ひどいよね、ジョー、そうだよね?」
「ひどいとも!」とジョーは叫んだ。「いったい何が君をそうさせたんだ?」
「わからないんだ、ジョー」と私はシャツの袖を放し、彼の足元の灰に座り込んでうなだれた。「でも、トランプでナップをジャックって教えてくれなきゃよかったし、靴がこんなに分厚くなければよかったし、手がこんなに荒れてなければよかった。」
それから私はジョーに、自分がどんなに惨めで、ジョー夫人やパンブルチューク氏には説明もできず、ミス・ハヴィシャムのところには美しい若い女性がいて、とても高慢で、私を「下品」と言い、それが本当にそのとおりだと感じて、下品でない自分になりたかったこと、そのせいで思わず嘘をついてしまったこと――ただしどうしてそうなったかは自分でもよくわからないこと――を話した。
これは形而上学的な問題で、ジョーにとっても私にとっても難しい事柄だった。だがジョーは、形而上学の領域から完全に問題を引き離して、見事に解決してしまった。
「一つだけ確かなことがある、ピップ」とジョーはしばらく考えた後で言った。「嘘は嘘だ。どんなふうに出てきても、本来出てきてはいけないものだし、嘘の親玉からやってきて、結局は同じところに行き着く。もう嘘はやめるんだ、ピップ。それが下品じゃなくなるための道じゃないぞ。それに、“下品”ってのがどういうことか、俺にはよくわからない。お前は何かにつけて“特別”だ。ものすごく小さいし、学問だって“特別”だ。」
「いや、僕は無知で遅れてるだけだよ、ジョー。」
「だってお前、昨夜あんな立派な手紙を書いただろ? しかも印刷体で! 俺は手紙を見たことがある――ああ、しかも上等な人からだって――だが、あんなにきれいな印刷体じゃなかったぞ」とジョーは言った。
「僕はほとんど何も学んでないんだよ、ジョー。ジョーが僕を買いかぶりすぎてるだけだ。」
「まあ、ピップ」とジョーは言った。「そうであろうがなかろうが、特別な学者になるにはまず“普通の”学者にならなきゃだめだ。王様だって、王冠かぶって玉座に座ってても、もともと王子のうちにアルファベットから始めなきゃ、議会の法令を印刷体で書いたりできないさ――ああ!」とジョーは意味ありげに首を振って加えた。「しかも“A”から始めて、ちゃんと“Z”までやらなきゃな。俺だってそれがどんなものかわかるけど、まあ、ちゃんとやったとは言えないけどな。」
この言葉には少なからず希望があり、私はちょっと元気づけられた。
「仕事とか稼ぎの上で“普通の”やつらは、“普通の”者どうし一緒にいた方がいいのかもしれない、特別なやつらと遊びにいくよりは――(ああ、そういえば旗があったのかと聞こうと思ってたんだった)」とジョーは考え込みながら続けた。
「なかったよ、ジョー」
「(そっか、旗がなかったのは残念だな、ピップ)」ジョーは言う。「まあ、それはさておき、今ここでそのことを考えると姉さんが騒ぎ出すから、それは避けた方がいい。さて、ピップ、本当の友達として言いたいのは、正しい道から“特別”になれないなら、邪道からなれることは絶対にないってことだ。だからもう嘘はつくな、ピップ。ちゃんとした人生を送り、幸せに死ぬんだ。」
「ジョー、怒ってない?」
「怒っちゃいないよ、坊や。ただ、あの嘘は――仔牛肉カツレツとか犬の喧嘩に関係したあの突拍子もないやつは――寝る前によく反省した方がいい。以上だ、ピップ、二度とやるなよ。」
自分の小さな部屋で祈りを捧げたとき、私はジョーの忠告を忘れなかった。けれども、私の心は乱れ、感謝の念もなく、床についてからも長い間、エステラがジョーを「いかにも下品な鍛冶屋」と思うだろうこと、彼の靴の厚さや手の粗さについて思い巡らせていた。ジョーと姉が今まさに台所で座っていること、自分が台所から寝室へ上がってきたこと、ミス・ハヴィシャムやエステラは決して台所なんてところには座らず、そんな下賤な日常とは無縁な世界にいること――そんなことばかり考えた。ミス・ハヴィシャムの屋敷で「昔していたこと」を思い返しながら眠りに落ちたが、それはまるで何週間も何ヶ月も前の思い出のようで、実際にはその日初めて起こったばかりのことだった。
あの日は私にとって忘れがたい日となった。なぜなら、その日が私を大きく変えたからだ。しかし、それはどんな人生にも言えることだ。もし人生から特定のある一日が消えたとしたら、その後の歩みはまったく違ったものになっていただろう。これを読んでいるあなたも、ちょっと立ち止まって、自分にとっての「鉄の鎖」や「黄金の鎖」、「いばら」や「花」の長い連なりが、あのある日の最初の一つから始まったのだと考えてみてほしい。
第十章
しばらくして朝、目覚めたとき、「自分が特別になるための一番いい方法は、ビディから知っていることを全部引き出すことだ」という名案がひらめいた。この輝かしい思いつきに従って、その晩ウォプスル氏の大おばさんのところへ行った際、私はビディに、人生を切り開きたい切実な理由があること、だから彼女が知っていることを全部教えてくれたらとても感謝する、と伝えた。ビディはとても親切な少女だったので、すぐに「いいわよ」と答え、実際、五分も経たないうちに約束を実行し始めてくれた。
ウォプスル氏の大おばさんによる教育法、つまり「課程」は、次のように要約できる。生徒たちはリンゴをかじり合い、藁を互いの背中に差し込んでふざけている。すると大おばさんが力を振り絞って、無差別に皆に向かってムチをふりかざす。その攻撃もどこ吹く風と、生徒たちは一列になってボロボロの本を回し読みする。その本にはアルファベットや数字、綴りが少し載っていた――少なくともかつては載っていた。やがてその本が回り始めると、大おばさんは眠りかリウマチの発作による昏睡状態に入る。生徒たちはそのすきに「誰が一番強く他人の足を踏めるか」を競う「ブーツ試験」に熱中する。その頭脳戦が続くうちビディが突進してきて、三冊のボロボロの聖書(何かの端材のような不格好な形)を配る。印刷もほとんど判読不能で、鉄錆の染みや、つぶれた虫の標本があちこちに挟まっている。ここでビディと手に負えない生徒たちのあいだで小競り合いが起きる。やがてビディがページ番号を言い、皆で(読めても読めなくても)大声で唱和する。ビディは高くて甲高い、一本調子の声でリードし、誰も内容など気にせず、敬意も払わず、ただ叫ぶだけ。この騒ぎがしばらく続くと、大おばさんが機械的に目覚め、適当に男の子を選んで耳を引っ張る。それでその日の授業は終わりとされ、私たちは知的勝利の叫びをあげて外へ飛び出していく。なお、スレートやインク(運が良ければ)で個人学習するのも自由だが、冬はクラスが開かれる雑貨屋兼大おばさんの居間兼寝室が、たった一本のしょんぼりした蝋燭しかないので、勉強しにくいのは仕方なかった。
この状況では、特別な人間になるには時間がかかりそうだと私は思った。それでも試してみると決意し、その夜さっそくビディは、値段表の「湿った砂糖」の欄から知識を分け与え、家で写すために、新聞の見出しから模写した大きな古い英字の「D」を貸してくれた。私はそれが何だかわからず、バックルのデザインだと思っていたが、ビディに教えてもらって初めて文字だと知った。
もちろん村にはパブがあり、ジョーはときどきそこでパイプをくゆらせるのが好きだった。私は姉から「今夜は学校帰りにスリー・ジョリー・バージメンに寄って、必ずジョーを連れて帰ること」と厳命されていた。そこで私はスリー・ジョリー・バージメンへ向かった。
バージメンにはカウンターがあり、脇の壁には恐ろしく長いチョークの貸し勘定が書き込まれていた。私はあれが一度も消されたことがない気がしていた。それは私が記憶する限りずっとあり、私の成長以上に伸びていた。けれどもこの辺りはチョークが豊富なので、皆これを有効活用しているのだろう。
土曜の夜だったので、主人はその記録を渋い顔で見ていた。だが私の用事はジョーにあり、主人ではなかったので、挨拶だけして奥の共用室に入った。そこには大きなキッチンの暖炉が輝き、ジョーはウォプスル氏と見知らぬ男と一緒にパイプをふかしていた。ジョーはいつものように「やあ、ピップ!」と声をかけてくれたが、その途端、見知らぬ男が私に目を向けた。
その男は、これまで見たことのない、いかにもひそやかな風情の人物だった。首をかしげ、片目を半分閉じて、まるで見えない銃で何かを狙っているようだった。口にはパイプをくわえ、じっと私を見ながらゆっくり煙を吐いてからうなずいた。私も頷き返すと、彼はさらに頷き、隣の席に座るよう席を空けてくれた。
しかし私は、いつもジョーの隣に座っていたので「いえ、結構です」と言い、ジョーが空けてくれた反対側の席に座った。見知らぬ男はジョーが別のことに気を取られているのを確かめると、再び私にうなずき、奇妙な仕草で自分の脚をなでた。
「さっき言ってたが」と見知らぬ男がジョーに向き直った。「あんたは鍛冶屋なんだな?」
「ええ。そう言いましたよ」とジョー。
「何を飲む? ――そういえば名前を聞いてなかったね。」
ジョーが名乗ると、男はその名を呼んだ。「何を飲む、ガージェリーさん? 私のおごりで、どうだい?」
「正直言って、他人の金で飲むことはあまりないんですよ」とジョー。
「習慣じゃないだろうが、たまにはいいじゃないか。しかも土曜の夜だ。さあ、注文してくれ、ガージェリーさん。」
「堅苦しいのは嫌だからね」とジョー。「ラムで。」
「ラム!」見知らぬ男は繰り返す。「もう一人の紳士はどうする?」
「ラム」とウォプスル氏。
「ラム三つ!」男は主人に叫ぶ。「みんなにグラスを!」
「この紳士は」とジョーはウォプスル氏を紹介し、「彼の話は面白いですよ。教会の書記です。」
「ほう!」と男は素早く私に目を向けて言った。「あの湿地の真ん中にぽつんと建ってる教会だね!」
「そうです」とジョー。
男は満足げにパイプをくわえながら、自分だけの席に足を投げ出した。つば広の旅帽をかぶり、下にはハンカチを帽子のように結んで髪を隠していた。火を見つめながら、その顔にずる賢い表情と半分の笑みが浮かぶのを私は見た。
「この辺りは知らないが、川の方は寂しい土地のようだね。」
「ほとんど湿地ですから」とジョー。
「なるほど、なるほど。ジプシーとか流れ者、浮浪者なんているのかい?」
「いませんね」とジョー。「たまに脱獄囚が出るくらいです。でもそいつらも簡単には捕まりませんよね、ウォプスル氏?」
ウォプスル氏は、昔の失敗を思い出すような威厳をもってうなずいたが、あまり乗り気ではなかった。
「捜索に加わったことが?」と男が尋ねる。
「一度だけね」とジョー。「捕まえようとしたわけじゃなくて、見物人として行ったんです。私とウォプスル氏とピップで。そうだろう、ピップ?」
「うん、ジョー。」
男は再び私を見た――なおも片目で私を狙うように――「骨組みのしっかりしたいい子だ。名前は?」
「ピップです」とジョーが答えた。
「洗礼名がピップか?」
「いいえ、そうじゃありません」
「姓はピップか?」
「いえ、家族でそう呼ぶようになっただけです。」
「息子さん?」
「ええと」とジョーは考えるふり――この店では何事も深刻そうに考えるのが流儀だった――「まあ……違いますね。」
「甥っ子か?」と男。
「うーん」とジョーはまた深く考え込むふり。「違いますね、正直に言って、甥っ子じゃないです。」
「じゃあ、一体全体何なんだ?」と男が聞いた。その強さに私は驚いた。
ウォプスル氏が口を挟んだ。職業柄、結婚できない親族関係を心得ている彼は、私とジョーとの関係を詳細に説明した。勢いで『リチャード三世』の凄まじい一節までやってのけ、「詩人もそう言っている」と付け加えれば説明は十分だと思ったのだろう。
ついでながら、ウォプスル氏が私を紹介するたび、必ず私の髪をくしゃくしゃにして目に押し込むのが恒例だった。なぜ、我が家を訪れるあの年代の大人は、みんな同じことをするのか不思議でならない。しかし幼い頃の私が家族の会話の話題になると、必ず誰かが大きな手で目を刺激するような仕打ちをしてきたものだった。
その間じゅう、見知らぬ男は私以外には目もくれず、いつか私を狙い撃つぞとばかりに見つめていた。しかし「何なんだ」という問いを投げかけたあとは何も言わず、ラム酒が運ばれてくるまで沈黙した。そしてついに、彼は奇妙な行動で狙撃を放った。
それは言葉ではなく、無言の身振りだった。しかも私だけに向けられたものだった。彼はラム酒を混ぜるとき、私をじっと見つめ、飲むときもまた私を見つめた。そして、混ぜて飲んだのは、スプーンではなくやすりだった。
彼はそれを、他の誰にも見えないように私だけに見せ、終わるとやすりを拭いて胸のポケットにしまった。それはジョーのやすりだと私はすぐにわかったし、彼が私の脱獄囚を知っているとも悟った。私は呆然と彼を見つめていた。だが彼はもはや私に注意を払わず、主にカブの話ばかりしていた。
土曜の夜の村には、大掃除をし、生活を一新するような静かな区切りの雰囲気が漂っていた。そのせいでジョーはいつもより三十分ほど長居をした。ラム酒も時間も尽きると、ジョーは立ち上がり、私の手を取って帰ろうとした。
「ちょっと待ってください、ガージェリーさん」と見知らぬ男が言った。「たしかポケットに新しいシリング貨があったはずだ。それがあれば、坊やにやろう。」
男は小銭の山からシリング貨を見つけ、くしゃくしゃの紙に包んで私に渡した。「君のものだ! いいね、自分のものだからな。」
私はマナーを忘れるほどじっと彼を見つめたまま、ジョーの手をぎゅっと握って礼を言った。彼はジョーにもウォプスル氏にも「おやすみ」と言い、私には、片目で狙いを定めるような視線――いや、もはや視線ではなく、片目を閉じるだけだったが、それでも瞳には何かを隠す力があるのだった――を残した。
帰り道、もし私が口を利く気分だったなら、一方的なおしゃべりになっただろう。なぜならウォプスル氏はパブの前で別れ、ジョーはラム酒を口から飛ばすかのように大口を開けて空気を吸い込みながら帰ったからだ。だが私は、昔の過ちと旧知が突然現れたことに呆然として、他のことは何も考えられなかった。
台所に戻ったとき、姉は比較的機嫌がよかった。そのおかげでジョーは、男からもらった新しいシリング貨の話を姉にした。「きっと偽物よ」とジョー夫人は勝ち誇って言った。「さもなきゃ子どもにやるはずないわ! 見せてごらん。」
私は紙から取り出して見せたが、本物だった。「でもこれは何?」とジョー夫人はシリングを投げ出し、紙切れをつかみ上げた。「一ポンド札が二枚?」
それはもう、脂ぎって膨れ上がり、町の家畜市を巡り歩いてきたような一ポンド札が二枚だった。ジョーは帽子を被り直し、バージメンまで持ち主に返しに走った。ジョーがいない間、私はいつものスツールに座り、男がもういないだろうと確信してぼんやり姉を見ていた。
やがてジョーが戻り、男はすでにいなかったが、一応バージメンに伝言を残してきた、と言った。それから姉は紙に包んでその札を、装飾用のティーポットにバラのドライフラワーと一緒に入れ、応接間の棚の上にしまい込んだ。その札は、その後も長い間、昼も夜も私の悪夢となった。
その夜は、見知らぬ男が見えない銃で私を狙っていることや、脱獄囚と内密に共謀していたという、忌まわしく粗野な過去――それまでうっかり忘れていたこと――を思い出して、眠れぬ夜となった。あの「やすり」もまた私を苦しめた。いつどこでまたあのやすりが現れるかと思うと恐ろしくて仕方がなかった。私は来週水曜のミス・ハヴィシャム訪問のことを思い浮かべて、やっとのことで眠りについた――そして夢の中で、誰が持ち主かわからないやすりが飛び出し、私は叫び声をあげて目を覚ました。
第十一章
約束の日、私はミス・ハヴィシャム邸に再び向かった。おそるおそる門のベルを鳴らすと、エステラが現れた。彼女は前回同様に私を中へ招き入れてから門をロックし、再び暗い廊下へ私を先導した。彼女はロウソクを取るまで私に目もくれなかったが、それを手に持ったとき、肩越しに私を見て、軽蔑したように「今日はこっちよ」と言い、全く違う場所へ連れて行った。
その廊下は長く、屋敷の地下一帯を囲むように伸びていた。私たちはそのうち一辺だけを進み、その突き当たりでエステラはロウソクを置き、ドアを開けた。そこには再び自然光が差し込み、私は小さな石畳の中庭に出た。向かい側には離れ家があり、かつて醸造所の管理人か番頭の持ち家だった名残があった。家の外壁には時計が掛かっていたが、それもミス・ハヴィシャムの部屋の時計や腕時計と同じく、八時四十分で止まっていた。
私たちはその家へ入った。ドアは開け放たれ、裏手の一階には天井の低い薄暗い部屋があった。その部屋には何人かが集まっており、エステラは私に「そこに立っていなさい、呼ばれるまで」と言った。「そこ」とは窓辺のことで、私はそこに行き、落ち着かない気分のまま外を眺めた。
窓は地面に面して開き、荒れ果てた庭の片隅が見えた。キャベツの茎の枯れ残りや、ずっと昔に丸く刈り込まれたが今では上部にだけ色も形も違う新芽が伸びているツゲが一本――まるでプディングの上部だけ焦げたようだ――があるのだった。私はそのツゲを見て、ぼんやりとそんな家庭的なことを考えていた。前夜、少しだけ雪が降ったが、私の知る限り他には残っておらず、この庭の冷たい影だけにわずかに解けずにあり、小さな渦を巻いて時折窓にぶつかり、まるで「なぜ来た」と私を責めるようだった。
私が入ったことで、部屋の会話が止み、他の人々が私を見ていると感じた。私は窓ガラスに映る暖炉の火しか見えなかったが、全身が固まるほど注視されているのを意識した。
部屋には三人の女性と一人の紳士がいた。窓辺に立って五分も経たぬうちに、彼ら全員が「ご機嫌取り」と「偽善者」なのに、互いにそれを知らぬふりをしているのが、なぜか伝わってきた。もし知っていると認めれば、自分もご機嫌取りで偽善者だと認めることになってしまうからだ。
皆、誰かの顔色を伺って待つような、気だるく陰鬱な雰囲気だった。最もおしゃべりな婦人は、あくびをこらえて話すほどだった。この婦人――カミラ――は、どこか姉に似ていたが、年上で顔立ちはもっとごつかった。実際、もっと親しくなってからは、これでも顔立ちがあるだけマシだと思うほど、真っ平らで高い「塀」のような顔だった。
「かわいそうに!」とカミラは唐突に、姉そっくりのきつい口調で言った。「自分の敵は自分だけ!」
「他人の敵である方がずっと立派さ」と紳士が言った。「その方がよほど自然だ。」
「レイモンド従兄弟」と別の女性が言った。「私たちは隣人を愛するべきよ。」
「サラ・ポケット」とレイモンド従兄弟は返した。「人が自分自身の隣人でなかったら、誰がそうなんだ?」
ミス・ポケットが笑い、カミラも笑って(あくびを押し殺しながら)「その発想!」と言ったが、むしろ二人とも、それは良い考えだと思っているようだった。もう一人、まだ口を開いていなかった婦人は、厳かに「まったくその通りね」と重々しく述べた。
「かわいそうな人!」とカミラはまた言い出した(その間、皆が私を見ていたのはわかっていた)。「とても変わってるのよ! トムの奥さんが亡くなったとき、子供たちに一番深い喪服の縁取りを付けることの重要性を、どうしても理解させられなかったのよ。『ああ、カミラ、子供たちが黒を着ていれば、それで十分じゃないか』ですって。まったくマシューそっくり! 考えられる?」
「良いところもある、良いところもある」とレイモンド従兄弟。「私だって良いところを否定はしないさ。でも彼は昔から品位というものを全然わかっちゃいないし、これからもわかることはないだろう。」
「私はどうしてもそうしなければならなかったのよ」とカミラが言った。「家の名誉のためにも、私はどうしても強く出なければならなかったわ。私は言ったの、『家族の面目にかけて、それはダメだ』って。飾りが深くなければ、家族の恥だとも言ったわ。朝食から夕食まで泣き通しで、消化を悪くしたのよ。とうとう彼はあの激しい調子で外に飛び出し、こう言ったのよ、あのDの言葉付きでね――『じゃあ好きにすればいい』ですって。ありがたいことに、私がすぐさまどしゃ降りの雨の中を出ていって、その品物を買いに行ったことは、ずっと慰めになるでしょうね。」
「彼が支払ったんでしょう?」とエステラが尋ねた。
「誰が払ったかは問題じゃないの、愛しい子」とカミラは返した。「私が買ったのよ。そのことは、夜中に目が覚めたときも、きっと安らかな気持ちで思い出すでしょうね。」
遠くの鐘の音が響き、私が通ってきた廊下からの叫び声か呼び声が反響して、話は中断された。エステラが私に「さあ、坊や!」と言った。私が振り返ると、彼女たちはみな極めて軽蔑した目で私を見た。私が部屋を出ていくとき、サラ・ポケットが「あらまあ! 次は何かしら!」と言い、カミラが憤慨して「こんな思いつきがあるかしら! そのアイ・ディー・ア!」と付け加えるのが聞こえた。
私たちが暗い廊下をロウソクを持って進んでいると、エステラが突然立ち止まり、振り向いて、からかうような態度で、顔を私のすぐ近くに寄せて言った。
「どう?」
「どう、ミス?」と私は、危うく彼女につまずきそうになりながら答えた。
彼女は私を見つめ、当然のように私は彼女を見つめ返した。
「私はきれい?」
「はい、とてもきれいだと思います。」
「私は失礼だと思う?」
「前ほどじゃないです」と私は答えた。
「前ほどじゃない?」
「はい。」
彼女は最後の質問をしたときに怒りを込め、私が答えるや否や、持てる力で私の顔を平手で打った。
「今はどう?」と彼女が言った。「この粗野な小怪物、今の私はどう思うの?」
「言いません。」
「どうせ上で話すつもりなんでしょ。そういうこと?」
「違います」と私は言った。「それじゃない。」
「じゃあ、なぜまた泣かないの、この小さな悪党?」
「もう二度とあなたのために泣かないから」と私は言った。もっとも、それは今までで一番嘘くさい宣言だったと思う。というのも、そのとき私は心の中で彼女のことで泣いていたし、後になってどれほど苦しめられたか、私はよく知っている。
この出来事のあと、私たちは二階へと進んだ。階段を上がっていると、降りてくる途中の紳士と出くわした。
「ここに誰がいるんだね?」とその紳士は立ち止まり、私を見て尋ねた。
「坊やです」とエステラが答えた。
彼は非常に大柄で、非常に色黒な男だった。頭が異様に大きく、その分大きな手をしていた。彼はその大きな手で私のあごをつかみ、顔をロウソクの光に向けて覗き込んだ。頭頂部は早くも禿げており、黒くてごわごわした眉毛が寝ずに逆立っていた。目は頭の奥深くにあり、不快なほど鋭く疑い深かった。大きな時計の鎖を下げており、あごひげやもみあげのあったであろう場所には濃い黒い点があった。彼は私とは何の関わりもない人物で、将来何かあるなどとは思いもよらなかったが、このとき彼をじっくり観察する機会を得たのだった。
「この近所の子か?」と彼が言った。
「はい、サー」と私は答えた。
「お前はどうやってここへ来た?」
「ミス・ハヴィシャムがお呼びになったんです、サー」と説明した。
「そうか! お行儀よくしろよ。私は坊主たちにずいぶん経験があるが、お前たちは悪い連中だ。気をつけろよ!」と言いながら、彼は人差し指の脇を噛み、私を睨みつけた。「いいか、行儀よくしろ!」
そう言って彼は私を放してくれた――ありがたかった、彼の手は香り付き石鹸の匂いがしたからだ――そして階段を降りていった。私は彼が医者なのではないかと考えたが、いや、あんな落ち着きのない説得力のない態度なら、医者ではないだろうと思った。このことを考えている暇もなく、すぐにミス・ハヴィシャムの部屋に着いた。そこは何もかも、私が前に見たままだった。エステラが私をドアのそばに立たせ、私はそこに立ったまま、ミス・ハヴィシャムがドレッサーから私を見やるまで動かなかった。
「そう!」と彼女は驚きもせずに言った。「月日は過ぎたのね?」
「はい、マーム。今日は――」
「よしよし、もういいわ!」と彼女は指をせかせかと動かしながら言った。「知りたくない。遊ぶ用意はできているの?」
私は少し混乱しながら、「たぶん、できていません」と答えざるを得なかった。
「またトランプじゃないの?」と彼女は鋭い目つきで尋ねた。
「はい、マーム。もしご要望なら、それはできます。」
「この家が古くて重苦しいと感じるのね、坊や」とミス・ハヴィシャムはいらだたしげに言った。「そして遊びたくないのね。じゃあ、働く気はあるの?」
この問いには、先ほどのよりも気持ちよく答えることができ、「はい、働く気はあります」と言った。
「では、あちらの部屋に行きなさい」と彼女は枯れた手で私の後ろのドアを指さした。「私が行くまで、そこで待ってなさい。」
私は階段の踊り場を横切り、彼女が指した部屋に入った。その部屋にも、まったく日が差し込まず、空気がこもっていて息苦しかった。古めかしく湿った暖炉には最近火が入れられたが、燃え上がるより消えそうで、部屋にたちこめる煙は澄んだ空気よりも冷たく感じられ、まるで自分たちの湿地の霧のようだった。高いマントルピースの上には冬枯れのキャンドルの枝がかすかに部屋を照らしていた――むしろ闇をかき乱していると言ったほうが正確だった。広々としていて、かつては見事だったのだろうが、見えるものすべてが埃とカビに覆われ、崩れかけていた。もっとも目立つのは長いテーブルで、テーブルクロスがかけられ、まるでごちそうの用意がなされていたときに家も時計もすべて時を止めてしまったかのようだった。その中央には何かの台座(エパーン)があったが、蜘蛛の巣に覆われて形も分からず、私はその黄ばんだ広がりを見つめるうち、それが黒いキノコのように生えているように思われた。まだら模様の足をもった蜘蛛たちがそこに帰ってきたり、またそこから出ていったりして、まるで蜘蛛の社会にとって何か重大な出来事があったかのようだった。
ネズミたちも壁板の裏でガタガタと音を立てていて、その出来事が自分たちにも大事なのだとでも言いたげだった。だが黒いゴキブリたちは騒ぎには無関心で、暖炉のまわりをどっしりとした老人のように、目も耳も悪く、お互いに会話もないまま、のそのそと動き回っていた。
私はこれらの這いまわるものに心を奪われ、遠目にじっと見ていた。するとミス・ハヴィシャムが私の肩に手を置いた。もう一方の手には杖を持ち、それに寄りかかっていて、この屋敷の魔女のように見えた。
「これよ」と彼女は杖で長いテーブルを指しながら言った。「私が死んだらここに横たわるの。みんながここに来て、私を見るのよ。」
彼女が今すぐそこに上がって死んでしまうのではないかという漠然とした不安、まるで見世物小屋の蝋人形そのものの実現で、私は彼女の手に触れられてすくみ上がった。
「あれが何だと思う?」と彼女はまた杖で蜘蛛の巣のある場所を指しながら聞いた。
「何だか分かりません、マーム。」
「あれは大きなケーキよ。花嫁ケーキ。私の!」
彼女は部屋中をぎょろりと見回し、それから私の肩に手を乗せ、手を小刻みに動かしながら「さあ、歩いて、歩いて!」と言った。
そこから私は、ミス・ハヴィシャムを部屋の中ぐるぐると歩かせるのが自分の仕事なのだと悟った。そこでさっそく歩き出すと、彼女は私の肩に寄りかかり、私たちはまるでパンブルチュークの馬車を真似ているかのような速さで進んだ。
彼女は体力がなく、しばらくすると「もっとゆっくり!」と言った。それでもせっかちで不規則な速度で歩き続け、歩くたびに彼女は私の肩に置いた手を引きつらせ、口をもぐもぐ動かし、考えが速く巡るから足も速くなるのだと私に思わせた。やがて「エステラを呼びなさい!」と言うので、私は踊り場に出て前回同様大声で名前を呼んだ。彼女の明かりが見えると部屋に戻り、また部屋をぐるぐる歩き始めた。
もしエステラが私たちの様子を見るだけで来ていたなら、私は十分に不満だったろう。だが彼女は下で見た三人の女性と紳士を連れてきたので、私はどうしていいかわからなかった。礼儀として止まろうとしたが、ミス・ハヴィシャムが肩を引きつらせるのでそのまま進んだ――彼らはこれがすべて私のせいだと思うのだろうと、私は恥ずかしい気持ちになった。
「親愛なるミス・ハヴィシャム」とサラ・ポケットが言った。「お元気そうですわ!」
「そうじゃないわ」とミス・ハヴィシャムは返した。「私は黄色い皮と骨よ。」
サラの言葉にカミラは明るくなり、哀れみ深くミス・ハヴィシャムを見つめながらつぶやいた。「かわいそうな方! ご気分が良いはずがないわ、かわいそうに。まったく!」
「あなたはどう?」とミス・ハヴィシャムはカミラに尋ねた。私たちはちょうどカミラのそばだったが、当然止まるべきところでミス・ハヴィシャムは止まらず、私たちは通り過ぎた。私はカミラに非常に疎まれているのを感じた。
「ありがとう、ミス・ハヴィシャム。おかげさまで、まあまあです。」
「何か問題でもあるの?」とミス・ハヴィシャムは非常に鋭く聞いた。
「特に申し上げることはありません」とカミラは答えた。「気持ちを表に出したくはありませんが、私は夜な夜なあなた様のことを思いすぎて、自分でも耐えきれません。」
「それなら考えなければいいじゃない」とミス・ハヴィシャムは返した。
「そう簡単に言われても!」とカミラはすすり泣きを抑えつつ、上唇をひきつらせ、涙をこぼした。「レイモンドが証人だけど、私は夜中に生姜やサル・ヴォラティルを飲まざるを得ないのよ。レイモンドが証人だけど、夜は脚が神経的に痙攣するし。でも愛する人を思って不安になると、窒息や痙攣は珍しいことじゃないの。もう少し愛情が薄くて鈍感だったら、もっと丈夫な胃袋と鉄のような神経が持てるのに。そうだったらいいのに。でも夜にあなたのことを思わずにいられるなんて――考えられないわ!」ここでまた涙が溢れる。
レイモンドとはその場にいた紳士――カミラの夫だと私は理解した。彼がここで助け船を出し、慰めと称賛を込めて「カミラ、きみの家族への思いが、だんだんきみの身体を蝕んで、脚の長さまで違ってきていることは誰でも知ってるよ」と言った。
「私は思うことがその人への大きな要求になるとは思いません」と、一度だけ声を聞いたことのある厳格そうな女性が言った。
サラ・ポケットは、今見ると小さく干からびた、クルミの殻でできていそうな顔に、猫のヒゲのない大きな口を持つ老婆だったが、これに同意して「そうね、ほんとよ」と言った。
「考えるのなんて簡単なものだわ」と厳格な女性が言った。
「何が簡単って、その通りね」とサラ・ポケット。
「そうよ、そうよ!」とカミラは足から胸へと感情が湧き上がるように叫んだ。「本当のことだわ! 愛情深いのは弱さだけど、仕方ないの。もし違ったら、きっと健康ももっと良かったでしょうけど、でもこの性格は変えられないわ。苦しみの元だけど、夜中に目覚めたとき、自分にそれがあることが慰めになるのよ。」ここでまた感情が爆発した。
ミス・ハヴィシャムと私は一度も止まらず、部屋の中をぐるぐる回り続けた。ときには訪問客のスカートに触れ、ときには部屋の端から端まで歩いた。
「マシューのことよ!」とカミラが言った。「自然なつながりを持とうとせず、ミス・ハヴィシャムの様子を見に来ることもない! 私はコルセットを解いてソファに倒れ、何時間も頭を垂れて髪は乱れ、足がどこにあるかも分からなくなって――」
(「君の頭よりずっと高いところさ、愛しい人」とカミラ氏が言った。)
「マシューの奇妙で説明のつかない行動のせいで、私は何時間もこんな状態になったけれど、誰も私に感謝しないわ。」
「正直言って、そりゃ感謝されないでしょう!」と厳格な女性が口を挟んだ。
「分かるでしょ、愛しい人」とサラ・ポケットが(底意地の悪い人物である)付け加えた。「自分に問いかけてみなさい、誰に感謝されると思っていたの?」
「感謝やそんなものは期待していません」とカミラは続けた。「私はずっとそのままでいましたし、レイモンドがどれだけ私が息が詰まったかの証人ですし、生姜がまったく効かなかったことも証人です。それに隣のピアノ調律師にも聞こえていたらしく、あの可哀そうな子どもたちは遠くで鳩が鳴いているのだと勘違いしたくらいなのに――それなのに今になって――」ここでカミラは喉に手を当て、化学反応でも起こすかのように新たな情緒の波を見せた。
このマシューの名が出ると、ミス・ハヴィシャムは私とともに立ち止まり、話し手をじっと見つめた。この変化がカミラの情動を一気に静めた。
「マシューは最後には私に会いに来るでしょう」とミス・ハヴィシャムは厳しく言った。「私があのテーブルに横たわったら、それが彼の場所――そこよ!」と杖でテーブルを指しながら。「あなたはそこ! あなたのご主人はそこ! サラ・ポケットはそこ! ジョージアナはそこ! これでみんな、自分が私を食い物にするときの立ち位置が分かったでしょう。さあ、出て行きなさい!」
名前を口にするたび、彼女は杖でテーブルの別の場所を叩いた。今、「歩いて、歩いて!」と言い、私たちは再び歩き始めた。
「どうしようもないわね」とカミラは叫んだ。「従って去るしかないわ。愛と義務の対象をたとえ短い時間でも見られたこと、それだけは悲しい満足として夜中に思い出すことにしましょう。マシューもその慰めを得られればいいのに、彼はそれを嘲るばかり。私は気持ちを表に出さないと決めているけど、親族を食い物にすると言われて追い出されるなんて――まるで怪物みたいに――そんなのひどいわ。考えただけで!」
カミラ氏がカミラ夫人の激しい胸に手を置きつつ割り込むと、夫人は見え透いた強さを装い、それは私には見えなくなったところで倒れて窒息するつもりなのだろうと思われたが、ミス・ハヴィシャムにキスの手振りをして出て行った。サラ・ポケットとジョージアナは誰が最後まで残るかで争ったが、サラがしたたかでジョージアナを出し抜いた。サラ・ポケットは「お元気で、ミス・ハヴィシャム!」と別れの効果を出し、クルミの殻のような顔で他の弱さを許す微笑みを浮かべて去った。
エステラが彼女たちを送り出している間、ミス・ハヴィシャムは私の肩に手を置いたまま、だんだんとゆっくり歩いた。ついに彼女は暖炉の前で立ち止まり、しばらくつぶやきながら火を見つめていたが、
「今日は私の誕生日よ、ピリップ」と言った。
私は「おめでとうございます」と言おうとしたが、彼女は杖を持ち上げた。
「誕生日の話は許さないの。今いた人たちにも、誰にも言わせない。みんなこの日に来るけど、話題にすることは許さない。」
もちろん、私はそれ以上口を出さなかった。
「お前が生まれるずっと前、この朽ち果てた山――」と彼女は杖の先でテーブルの蜘蛛の巣の山を突き刺しそうになりながら、しかし触れずに言った。「――これがここに運び込まれた。私とこれとは一緒に朽ち果ててきた。ネズミがかじったし、ネズミの歯より鋭いものが私をかじったわ。」
彼女は杖の頭を胸に当て、テーブルを見つめて立っていた。かつて白かったドレスも今は黄色く枯れ、テーブルクロスもすべて黄ばみ、あたり一面、触れれば崩れそうな有様だった。
「破滅が完成したとき――」と彼女は青ざめた顔で言った。「そして私が花嫁衣装のまま、花嫁のテーブルの上に横たえられたとき――必ずそうするわ、それがあいつへの最後の呪いになる――できれば今日がその日であればなお良い!」
彼女は自分自身がそのテーブルに横たわっているかのように、その場を見つめ続けた。私は黙っていた。エステラが戻り、彼女も黙っていた。私たちはしばらくそのまま時が止まったようだった。部屋の重苦しい空気と、遠くの闇に沈む暗さの中で、私はエステラも私もやがて朽ち果てるのではないかという不安にさえ襲われた。
やがて、段階を踏んで正気に戻るのではなく、突然ミス・ハヴィシャムが「二人でカードをしているところを見せて。なぜ始めていないの?」と言った。それで私たちは彼女の部屋に戻り、以前と同じように座った。私は前と同じく負け続け、ミス・ハヴィシャムはやはり私たちをずっと見つめ、エステラの美しさに私の注意を向けさせ、エステラの胸や髪に宝石を試しながらその美しさを一層強調した。
エステラもまた、前と同じように私に接した。ただ、話しかけることはなかった。私たちが何度かゲームをしているうちに、次に来る日が決まり、私は再び犬のような扱いで中庭に連れて行かれ、そこでまた好きに歩き回ることを許された。
今回、前回よじ登って覗き込んだ庭の壁の門が、そのとき開いていたか閉まっていたかは重要ではない。ただ、前回は門が見えず、今回は見えたということだ。門が開いており、エステラが客たちを送り出して鍵を持って戻ってきたことを知っていたので、私は庭へ入り、隅々まで歩き回った。そこはすっかり荒れ果て、古いメロン棚やキュウリ棚があり、それらはまるで帽子や靴の残骸、時には雑草のような鍋のかけらを生み出しているようだった。
庭と、何もない温室――そこには倒れかけたブドウの木と瓶しかなかった――を歩き尽くした私は、前に窓から見下ろした陰鬱な隅にたどりついた。家がもう空だと疑うこともせず、別の窓から中を覗き込むと、顔色の悪い赤いまぶたと明るい髪の若い紳士と、思いがけず目が合った。
その顔色の悪い若紳士はすぐに消え、私のそばに現れた。彼は本を読んでいたらしく、今見ると手がインクだらけだった。
「やあ!」と彼は言った。
「やあ!」と私は、たいてい「やあ」には「やあ」で返すのが良いと心得ていたので、丁寧に「坊や」を省略して答えた。
「誰が君を中に入れた?」
「ミス・エステラです。」
「誰が君にうろつく許可を出した?」
「ミス・エステラです。」
「さあ、やろう」と顔色の悪い若紳士が言った。
どうすることもできず、私は彼についていった。今でも何度も自問したが、他にどうしようもなかった。彼の態度はあまりに断定的で、私は呪文にかかったように従った。
「待って、理由もいるだろう」と彼は何歩か進んだところで振り向いた。「これが理由だ!」彼は苛立たせるような仕草で両手を叩き、片足を後ろに軽く振り上げ、私の髪を引っ張り、また手を叩き、頭を下げて私の腹に突っ込んできた。
最後の牛のような動きは、間違いなく無礼であるだけでなく、食後すぐにはとりわけ不愉快だった。それで私は彼に拳を振るい、もう一発を出そうとしたとき、彼は「おや、やる気か?」と言い、前後に踊り始めた。その身のこなしは私の経験ではまったく類がなかった。
「ルールだ!」と彼は言った。ここで左足から右足へ跳び移る。「正式なルール!」今度は右足から左足へ。「リングに出て、手順を踏もう!」ここで彼は前後にひらひら動き、私は成す術もなく見ていた。
彼の身のこなしに私は内心怯えたが、しかし私の腹にあの明るい髪の頭が突っ込んでくる理由は全くないと、道義的にも肉体的にも確信していた。だから何も言わずに、彼についていき、庭の隅に設けられた、二つの壁が交わり廃材で目隠しされた場所に向かった。彼は「ここでいいか?」と聞き、私が「はい」と答えると、「じゃあ少し外す」と言ってすぐに水の入った瓶と酢で湿らせたスポンジを持ち帰ってきた。「どちらにも使えるから」とそれらを壁際に置き、そして上着とベストだけでなくシャツまで脱ぎ始め、陽気かつ血に飢えたビジネスライクな態度を見せた。
彼は顔に吹き出物があり、口元にも湿疹があって健康そうではなかったが、この恐ろしい準備に私はすっかり気圧された。年齢は私と同じくらいだろうが、ずっと背が高く、全身の中で肘、膝、手首、かかとが特に発達していた。
いざ彼が完璧な機械的フォームで私に構え、私の体をじろじろ見て部位を吟味している様子を見ると、私はすっかり気後れした。だが思い切って最初の一発を繰り出すと、彼は背中から倒れ、血のにじむ鼻で私を見上げているのを見て、私は人生でこれほど驚いたことはなかった。
だが彼はすぐに立ち上がり、器用に自分自身をスポンジでぬぐいながら再び構えた。人生で二番目に驚いたのは、二度目の一撃で彼がまた倒れ、今度は黒い目で私を見上げていたことだ。
彼の根性には大いに敬意を抱いた。彼にはたいした力はなく、一度も私を強く打つことがなかったし、いつも倒されたが、それでもすぐに立ち上がり、自分自身をスポンジでぬぐい、水を飲み、「これぞ正統派!」という満足気な顔でまた向かってきた。私は申し訳ないが、彼を打つごとにだんだん強く打ってしまい、彼はぼこぼこにされたが、それでも何度でも立ち上がった。ついに後頭部を壁にぶつけてひどく倒れた。しかしそのあとも彼は立ち上がり、何度かぐるぐる回って私の居場所が分からなくなったが、ついには膝をついてスポンジを投げ上げ、「これは君の勝ちだ」という意味だとゼイゼイ言いながら宣言した。
彼はとても勇敢で無邪気に思えたので、私がこの勝負を仕掛けたわけではないにもかかわらず、勝利しても陰鬱な満足しか感じなかった。むしろ、着替えながら自分を野生の狼か何かのように思って恥じたくらいだ。ともあれ私は顔の血を拭い、彼に「手伝おうか?」と言い、彼は「ありがとう、いらない」と言い、私は「さようなら」と言い、彼も「どうも」と返した。
中庭に出ると、エステラが鍵を持って待っていた。だが彼女は私がどこに行っていたかも、なぜ待たせたかも聞かず、何か嬉しいことがあったように頬を赤らめていた。しかもまっすぐ門へ向かわず、通路に戻って私を手招きした。
「こっちへいらっしゃい。よかったらキスしてもいいわよ。」
彼女が頬を向けたので、私はそこにキスした。私は彼女の頬にキスするためなら多くのことを耐えただろう。だがそのキスは、「粗野で下品な少年」に投げ与えられる小銭のようなもので、何の価値もないと感じた。
誕生日の客、カード、そして喧嘩のせいで、私の滞在はとても長くなり、家に近づいたときには、湿地の先端の砂州に明かりが黒い夜空に輝き、ジョーの炉からは道を横切るように火の道が伸びていた。
第十二章
あの顔色の悪い若紳士のことが、私の心にどんどん重くのしかかってきた。喧嘩のことを考え、顔色の悪い若紳士が何度も背中を地面につけ、腫れあがり赤く染まった顔を思い返すたびに、必ず何か報いがあるに違いないと思えた。私は、彼の血が自分の手にかかったような気がして、法が必ずそれを裁くだろうと感じた。自分がどんな刑罰に問われるのか具体的には分からなかったが、田舎の子どもが貴族の家を徘徊し、勉学に励む英国の若者を叩きのめして回っても、厳罰を免れないのは明らかだった。何日間か、私は家にこもり、用事で出かける前には台所の戸口から極度に用心深く外をうかがい、郡刑務所の役人たちが飛びかかってくるのではないかと怯えていた。若紳士の鼻血がズボンを汚していたので、真夜中にその証拠を洗い落とそうとした。自分の指の皮も若紳士の歯で切れていたので、いざ裁判官の前に連れて行かれたとき、どうやってこの決定的証拠を説明しようかと、あり得ないほど入り組んだ言い訳を何度も考えた。
再びあの暴力の現場に戻る日が巡ってくると、私の恐怖は頂点に達した。とくにロンドンから特別に送り込まれた法の従者たちが門の陰で待ち構えているのではないか、あるいはミス・ハヴィシャム自身が、あの死装束のまま立ち上がってピストルで私を撃ち殺すのではないか、雇われた少年たち――雇われの大軍団――が醸造所で私を待ち伏せ、これでもかと殴りつけてくるのではないか、そんな妄想が頭をよぎった。だが、顔色の悪い若紳士だけは、こうした報復に加担するとは思えず、これらの仕返しはあくまで彼の親族たちが、彼のひどい顔を見て怒り心頭になった末の行為だとばかり考えていた。
とにかく、ミス・ハヴィシャムのところに行かなければならず、私は行った。すると驚いたことに、あの喧嘩のことは何も起こらなかった。それについて誰も一言も触れず、若紳士の姿もどこにも見当たらなかった。前回と同じく門は開いていたので庭を歩き、離れ家の窓も覗いた。しかし今度は内側からシャッターが閉められていて何も見えず、すべては静まり返っていた。唯一、あの隅だけが彼の存在を示していた。そこには彼の血の跡が残っていて、私はそれを土で隠した。
ミス・ハヴィシャムの自室と例の長いテーブルのある部屋の間にある踊り場には、庭用の椅子――背後から押す車輪付きの軽い椅子――が置かれていた。前回はなかったもので、この日から私はミス・ハヴィシャムをこの椅子に乗せ、(歩かせるのに飽きたら)部屋の中や踊り場、もう一つの部屋をぐるぐる押して回るという定期的な業務に就いた。私たちは何度もこの道をたどったし、時には三時間も続くこともあった。すっかり習慣となったので、私はこの巡回を「たくさんあった」とまとめて言うのだが、それはこの仕事のため昼に隔日で通うことになり、これから八ヶ月から十ヶ月ほどの期間を一気に総括しようとしているからだ。
お互い慣れてくると、ミス・ハヴィシャムは私に話しかけることが増え、「何を学んだのか」「これからどうなるのか」といった質問もした。私はジョーのもとで徒弟になるつもりだと話し、何も知らないから何でも知りたいのだと言って、何か援助してもらえないかと期待した。しかし彼女は私の無知の方を好むようだった。金銭や物をもらったことは一度もなかったし、働き賃をもらう約束すらなかった。
エステラはいつもそこにいて、私の出入りを管理したが、もうキスしていいとは二度と口にしなかった。時に冷たく許容し、時に恩着せがましく、時に親しげに、時には激しく憎んでいると言い放った。ミス・ハヴィシャムはよく、ささやき声や二人きりのときに「エステラはどんどんきれいになっていくかい?」と尋ね、私が「はい」と答えると(実際そうだった)、貪るように喜んだ。また、カードをするときも、エステラの気まぐれな態度をケチ臭く観察し、どんな態度でも満足げに見守った。時に彼女の気分があまりに多様かつ矛盾していて、私はどうしてよいか困ったが、ミス・ハヴィシャムはエステラを抱きしめて、「私の誇りと希望よ、彼らの心を打ち砕いて、容赦は無用」と耳元で囁くのだった。
ジョーは鍛冶場で「オールド・クレム」という歌の断片をよく口ずさんでいた。これは鍛冶屋の守護聖人に捧げるにしては不作法だったが、おそらくオールド・クレムはそういう存在なのだろう。鉄を打つリズムを真似た歌で、ただ名前を繰り返すための歌だった。たとえば、少年たちよ、叩け――オールド・クレム! ゴンと響け――オールド・クレム! たたけ、たたけ――オールド・クレム! カンと音を鳴らせ――オールド・クレム! 火を吹くぞ、火を吹くぞ――オールド・クレム! うなりながら高く――オールド・クレム! ある日、椅子が現れて間もなく、ミス・ハヴィシャムがせかせかと指を動かしながら「さあ、歌って!」と言ったので、私は驚いてこの歌を口ずさんだ。それが彼女の気に入り、彼女も低い声で夢うつつのように歌いはじめた。それから私たちは動きながらこの歌を歌うのが習慣になり、エステラもよく加わった。三人でさえ、その歌声は古びた家の中で風のささやきほどの静かさだった。
私はこの環境でどう育つというのか。私の性格がどれほど影響を受けたのか、不思議に思う人はいないだろう。黄ばんだもやの部屋から外の自然光に出るたび、精神も目もくらんで当然だった。
あの若紳士のことは、もし以前あれほど大げさな作り話をしていなければ、ジョーに話せたかもしれない。しかし、そうした事情から、ジョーは彼を黒いビロードの霊柩馬車の適任乗客とみなすに違いないと思い、私は何も言わなかった。それに、ミス・ハヴィシャムやエステラのことを家で話題にされたくない気持ちは時を追うごとに強まった。私はビディにだけは何でも話した。なぜ自然とそうなったのか、なぜビディが私の話すこと全てに深い関心を寄せてくれたのか、そのときは分からなかったが、今は分かる気がする。
一方、家の台所では私の苛立った心にとって耐えがたいほどの「相談」が続いていた。あのパンブルチュークの馬鹿は、夜になるとよくやってきて、私の将来について姉と議論したものだ。今でも(反省が足りないが)もし手が届いたら彼の馬車の車軸でも抜いてやっただろうと思う。あの哀れな男は、脳みそがあまりに小さく、私の将来について私なしで論じることができず、いざ目の前に私を呼び出して(たいていは首根っこをつかんで)、暖炉の前に立たせて「ああ、奥さん! ここにこの子がいます! あなたが手塩にかけて育てた子です。顔を上げて、感謝しなさいよ、ほら! さて、奥さん、この子のことですが!」と言い、私の髪をわざと逆立てた――私は幼いころから誰にもそんな権利はないと感じていた――そして私を袖で引っ張って前に立たせ、まるで自分の愚かさを映す見世物のように扱うのだった。
それから彼と姉は、ミス・ハヴィシャムについて、彼女が私に何をしてくれるか、どんな利益があるか、ばかげた憶測を繰り広げた。そのたびに私は悔し涙をこらえ、パンブルチュークに飛びかかって叩きのめしたい気分になった。姉は私に話しかけるとき、まるで道徳的に私の歯を一本一本抜いているような口ぶりだったし、パンブルチュークは自称後見人として私を値踏みしながら、まるで損な仕事に従事している不満げな建築士のように監督していた。
これらの話し合いの中で、ジョーはまったく口を挟まなかった。しかし、私が鍛冶屋から引き離されることにジョーが好意的ではないとジョー夫人が気づいていたため、進行中に何かとジョーに向けて話がなされた。私は今やジョーの弟子になるには十分な年齢だったし、ジョーが思案げに膝の上に火かき棒を置いて下段の灰をかき出しているだけでも、姉はその無邪気な仕草を反対の意思表示だと決めつけて、彼に飛びかかり、火かき棒を取り上げてジョーを揺さぶり、それを片付けてしまうほどだった。これら一連の議論の結末は、いつも極めて苛立たしいものだった。何の前触れもなく、突然姉があくびを止め、まるで偶然私に気づいたかのように私に襲いかかり、「さあ! もうお前は十分だよ! さっさと寝な! 今夜はもう十分迷惑をかけたんだろうね!」と言うのだった。まるで私が、自分の人生を煩わせることを彼らに懇願したかのような口ぶりで。
このような毎日が長く続き、このままいつまでも続くのだろうと思われていた。だが、ある日、ミス・ハヴィシャムが私と一緒に歩いていて、私の肩に寄りかかっていたとき、急に立ち止まり、不機嫌そうに言った――
「ピップ、大きくなってきたね!」
私は、どうしようもない事情であることを、物思いに沈んだ表情を通してそれとなく示すのが最善だと思った。
彼女はそのときそれ以上何も言わなかったが、やがてまた立ち止まって私を見つめ、さらにもう一度、そしてその後は眉をひそめ不機嫌な表情を続けた。次に私が伺った日、いつもの運動が終わり、彼女を化粧台に案内したとき、彼女はせっかちな指の動きで私を引き止めた――
「その鍛冶屋の名前をもう一度言いなさい。」
「ジョー・ガージェリーです、奥様。」
「つまり、あなたが弟子入りする予定の主人のこと?」
「はい、ミス・ハヴィシャム。」
「すぐにでも弟子入りした方がいいわね。ガージェリーは、あなたと一緒にここに来て、誓約書を持ってこられるかしら?」
私は、招かれることを光栄に思うだろうと、全く疑いなく伝えた。
「じゃあ、彼に来させなさい。」
「特に決まった時間はありますか、ミス・ハヴィシャム?」
「そんなこと知らないわ。とにかく、すぐ来させて、あなたと一緒に連れてきなさい。」
その夜家に帰り、ジョーにこの伝言を伝えると、姉はこれまで以上に恐ろしい「逆上」状態に突入した。姉は私とジョーに、まるで自分が敷き物のように足蹴にされたと思っているのか、どうして自分がこんな扱いを受けなければならないのか、どんな仲間にふさわしいと思っているのかと、矢継ぎ早に問い詰めた。質問の嵐がやっと収まると、姉はジョーに燭台を投げつけ、大声で泣き叫び、ちり取りを持ち出した――これはとても悪い兆候だった――粗末なエプロンを着けて、恐ろしい勢いで掃除を始めた。乾拭きだけでは満足せず、バケツとたわしを持ち出し、家中を徹底的に掃除してしまったので、私たちは裏庭で震えながら立ち尽くした。夜の十時になってやっとこっそり家に入ると、姉はジョーに「いっそのこと黒人奴隷の女とでも結婚すればよかったんじゃないの?」と言った。ジョーは何も答えず、ただ自分のひげを撫でてしょんぼりと私を見つめ、たしかにその方が良かったのかもしれないと思っているようだった。
第十三章
翌々日、ジョーが私と一緒にミス・ハヴィシャムのところへ行くために日曜用の上着を着て身支度をしているのを見るのは、私にとって苦痛だった。しかし、彼自身がこの機会に礼服が必要だと思い込んでいる以上、私が作業着のほうがよほど似合うと伝える気にはなれなかった。むしろ、彼がひどく不快な思いをしてまで、すべて私のためにシャツの襟を後ろでぐいと引き上げ、そのせいで頭頂の髪が羽毛の房のように逆立っているのを知っていたからだ。
朝食のとき、姉は私たちと一緒に街へ行き、パンブルチュークおじさんの家で降ろしてほしい、そして「お上品なご婦人方相手の用が済んだら迎えに来てよ」と宣言した。ジョーは、この言い方から最悪の事態を予感したようだった。その日、鍛冶場は休みとなり、ジョーは(仕事を休むごく稀な日には必ずそうするのだが)ドアにHOUTという一語をチョークで書き、彼が向かった方向を示す矢印の絵も添えた。
私たちは歩いて街へ向かった。姉は大きなビーバー帽をかぶり、編み藁のイングランド大印章のようなバスケットを抱え、木靴、替えのショール、晴れた日なのに傘も持っていた。これらの持ち物が懲罰的なのか誇示的なのかはっきりしなかったが、どちらかといえば財産を見せびらかすためのものだったのだろう――まるでクレオパトラや「逆上」した女王がパレードで富を誇示するように。
パンブルチュークの家に着くと、姉は勢いよく中に入り、私たちを置いていった。昼近くだったので、ジョーと私はまっすぐミス・ハヴィシャムの家へ向かった。エステラがいつものように門を開けると、ジョーはすぐさま帽子を脱ぎ、両手でつばの部分を細かく重さを量るように持った。まるで、ほんのわずかな重さの違いにまで気を配る切実な理由があるかのようだった。
エステラは私たちに構わず、よく知っている道へ案内した。私は彼女のすぐ後ろを歩き、ジョーが最後尾についてきた。長い廊下で振り返ると、ジョーはまだ帽子を丹念に量りながら、つま先立ちで大股に私たちの後を追ってきていた。
エステラは私たち二人とも部屋に入るよう言ったので、私はジョーの上着の袖を引き、ミス・ハヴィシャムの前へ連れていった。彼女は化粧台に座っていて、すぐにこちらを振り向いた。
「あら!」と彼女はジョーに言った。「あなたはこの子の姉の夫なの?」
私は、愛すべきジョーがあれほど自分らしくなく、また妙な鳥に見えるとは思いもしなかった。彼はまるで羽毛を逆立て、口を開けてミミズを欲しがる鳥のように、言葉も出ずに立ち尽くしていた。
「あなたはこの子の姉の夫なの?」とミス・ハヴィシャムが繰り返した。
苛立たしかったが、面会中ずっとジョーはミス・ハヴィシャムではなく私に話しかけることに頑なだった。
「つまりだね、ピップ」とジョーは、強い論理性と厳粛な信頼、そして大いなる礼儀正しさを同時に込めて言った。「お前の姉と結婚して、当時はまあ、いわば独り身だったわけさ。」
「それで!」とミス・ハヴィシャムは言った。「あなたはこの子を育てて、自分の弟子にするつもりだったのね、ガージェリーさん?」
「ピップ、お前も知ってる通り、俺たちはずっと仲良しで、それが俺たちの楽しみになると思ってたんだ。まあ、ピップ、お前がもしこの仕事に不満があったなら――汚れるからとか、すすだらけになるからとか――そういうのがあれば、ちゃんと考慮してたよ、わかるかい?」
「この子は」とミス・ハヴィシャムが言った。「何か不満を言ったことは? この仕事が好きなの?」
「それは、ピップ、お前自身もよく知ってる通り、俺の心からの願いだったんだ。」(私は、ジョーがその場の雰囲気に合わせて自分の決まり文句を変えようとするのが分かった)「お前に不満はなかったし、それはお前の心からの大きな願いだった!」
私は、ジョーがミス・ハヴィシャムに直接話すべきことを分からせようと、あれこれ顔や身振りで合図しても無駄だった。私がすればするほど、ますます私に対して親身で丁寧な態度になった。
「誓約書は持ってきたのか?」とミス・ハヴィシャムが聞いた。
「ピップ、知ってるだろう」とジョーは、ちょっと無理な注文だと言わんばかりに答えた。「お前も俺が帽子に入れるの見てただろう、だからここにあるさ。」そう言って、誓約書を取り出し、ミス・ハヴィシャムではなく私に手渡した。私は、エステラがミス・ハヴィシャムの椅子の後ろで意地悪く笑っているのを見て、親愛なる善良なジョーを恥ずかしく思った――いや、間違いなく恥ずかしかった。私は彼の手から誓約書を受け取り、ミス・ハヴィシャムに渡した。
「あなたはこの子に何の謝礼金も期待していなかったのね?」とミス・ハヴィシャムは、誓約書を読みながら言った。
「ジョー!」と私はたしなめたが、彼は全く答えなかった。「どうして答えないの――」
「ピップ」とジョーは、傷ついたように話を遮って言った。「それはお前と俺の間で答えるべきじゃない質問だし、お前も答えがノーだってよく知ってる。ノーだって知ってるんだよ、ピップ、だからどうして俺が言わなきゃならない?」
ミス・ハヴィシャムは、ジョーの本質を私が想像していた以上に理解したような目つきで彼を一瞥し、机の上の小さな袋を手に取った。
「ピップはここで謝礼金を稼いだわ。それがこれよ。この袋には25ギニー入っているわ。あなたの主人に渡しなさい、ピップ。」
ジョーは、彼女の奇妙な姿と奇妙な部屋にすっかり圧倒されてしまい、今この場になってもなお私に話しかけた。
「これはとても寛大だ、ピップ」とジョーは言った。「そしてありがたく受け取るよ、だけど、期待もしてなかった、近からず遠からず、どこでも。さあ、相棒」とジョーは私に火照りと凍え、両方の感覚を与えるような口調で(まるでその親しげな呼び方がミス・ハヴィシャムに向けられているかのようで)、こう続けた。「さあ、俺たちは義務を果たそう! お互いのため、そして君の寛大な贈り物で――伝わった――心の満足のために――彼らに――」ここでジョーは、自分がひどい窮地に陥ったことに気づいたが、最後は「そして俺自身からも、遠ざけてくれ!」という言葉で勝利を収めた。この言葉はジョーにとってあまりにも説得力に満ちていたので、彼は2回繰り返した。
「さようなら、ピップ」とミス・ハヴィシャムは言った。「エステラ、彼らを外に出して。」
「また来てよいのですか、ミス・ハヴィシャム?」と私は尋ねた。
「いいえ。これからはガージェリーがあなたの主人よ。ガージェリー! ちょっと!」
私がドアを出るとき、彼女がジョーに向かってはっきりと力強い声で、「この子はここで良い子だった。それが報酬よ。もちろん、正直な男なら、それ以上もこれ以外も期待しないでしょう」と言うのが聞こえた。
ジョーがどうやって部屋を出たのかは未だに分からないが、気がつくと彼は階下に降りる代わりにしっかりと階段を上っており、私が追いかけてつかまえるまで、どんな呼びかけにも耳を貸さなかった。やがて私たちは門の外に出て、門は施錠され、エステラもいなくなった。私たちが再び二人きりで日差しの下に立つと、ジョーは壁に背中をもたせかけ、「驚いたな!」と呟いた。そして、しばらくの間「驚いた」と何度も間をあけて口にし続けるので、私は彼の正気が戻らないのではと思い始めた。やがて彼は「ピップ、保証するよ、これはほんとに――驚きだ!」と語句を伸ばし始め、少しずつ会話ができるようになり、歩き出すことができた。
私は、ジョーの知恵がこの一件で冴えわたったのだろうと思う。その証拠は、パンブルチュークの居間で起こった出来事にある。私たちが顔を見せると、姉はあの忌まわしい種屋と話し込んでいた。
「で?」と姉は私たち二人に同時に言った。「何があったの? こんなみすぼらしい仲間のところにわざわざ帰ってきて、感心よね!」
「ミス・ハヴィシャムがね」とジョーは私をしっかりと見つめ、記憶をたどるようにして言った。「きちんと伝えてほしいって――あれはご挨拶だったか、尊敬の意だったか、ピップ?」
「ご挨拶です」と私は言った。
「それが俺の考えだった」とジョー。「ジョー夫人によろしく、と――」
「だから何よ!」と姉は言ったが、どこか満足げでもあった。
「それから」とジョーは、さらに私を見つめ記憶をたぐるようにして続けた。「ミス・ハヴィシャムの健康状態が――もしも――ピップ?」
「ご婦人方のお相手をする余裕があれば、と僕が補足した。」
「ご婦人の同席があれば、と」ジョーは深いため息をついた。
「まあ!」と姉はパンブルチュークをややご機嫌そうに眺めた。「最初からその言葉を届けてくれればよかったのに。でも遅くても悪くないわ。それで、若造には何をくれたの?」
「彼女は何もくれなかった」とジョーが言った。
姉が怒りかけたが、ジョーは続けた。
「彼女がくれたのは、彼の友人たちにだった。『友人たち』というのは、つまりこのジョー夫人の手に、という説明だった。言葉通り、『ジョー夫人』だ。もしかしたら」とジョーは考え込むように付け加えた。「ジョーなのかジョルジュなのか、彼女は分かってなかったかもしれない。」
姉はパンブルチュークを見た。彼は木製の肘掛け椅子の肘を撫で、彼女と暖炉にうなずいて、まるですべてを最初から知っていたかのようなそぶりだった。
「それで、いくらもらったの?」と姉は笑いながら聞いた。本当に笑っていた!
「みんなが10ポンドだと言ったらどうだろう?」とジョーが尋ねた。
「まあまあね。多すぎもせず、悪くもないわ」と姉は言った。
「それより多いんだ」とジョーは言った。
あの恐ろしい詐欺師パンブルチュークはすぐにうなずき、「それより多いですよ、奥さん」と言いながら椅子の肘を撫でた。
「まさか――」と姉が言いかけた。
「本当ですよ、奥さん」とパンブルチューク。「でもまあ、ちょっと待ってください。さあジョセフ、続けて! いいぞ、続けて!」
「みんなが20ポンドだと言ったらどうだろう?」とジョーが続けた。
「立派って言うわね」と姉は答えた。
「じゃあ、それより多いんだ」とジョー。
この卑しい偽善者パンブルチュークはまたうなずき、恩着せがましく笑いながら「それより多いですよ、奥さん。いいぞ、もう一押しだ、ジョセフ!」と言った。
「じゃあ、もうはっきり言うけど」とジョーは嬉しそうに袋を姉に手渡しながら言った。「25ポンドだ。」
「25ポンドです、奥さん」とあの下劣なペテン師パンブルチュークも立ち上がって握手をし、「これもあなたのご立派なお手柄ですよ(私が聞かれたときもそう言いました)そしてこのお金でお幸せに!」と言った。
もしあの悪党がここでやめていたら、彼の罪も十分にひどいものだったろうが、それだけでなく、彼は私に保護者顔で態度を強め、これまでの悪事をはるかに超えて自分のものにした。
「さて、ジョセフさんご夫妻」とパンブルチュークは私の腕を肘の上からつかみながら言った。「私は始めたことは必ず最後までやり通す主義だ。この少年はすぐにでも誓約書にサインさせねばならん。それが私流だ。即刻だ。」
「本当に、パンブルチュークおじさん」と姉はお金を握りしめながら言った。「あなたにはとても感謝してます。」
「気にしないでください、奥さん」とあの悪魔の穀物商は言った。「楽しいことは世界中どこでも楽しいものです。でもこの子はね、早く誓約させなきゃいかん、と言っていたんですよ、実を言うと。」
裁判所はすぐ近くの町役場で開かれていたので、私たちはすぐに行って、私がジョーの弟子として正式に誓約されることになった。私たちが行ったと言っても、私はまるでその場でスリをしたか、藁小屋に放火したかのように、パンブルチュークに押されていった。実際、法廷内の大半の人々は私が現行犯で捕まったと思っていたようで、彼に押されて人混みを通ると、「何をやらかしたんだ?」とか「まだ若いのに悪そうな顔だな」などの声が聞こえた。温和で善良そうな一人は、男が鎖に繋がれたソーセージ屋のイラスト付きの小冊子を私にくれて、「私の独房で読むべし」と題されていた。
そのホールは奇妙な場所だった。教会よりも高い仕切りがあり、そこに人々が身を乗り出して見物している。偉そうな判事たち(かつらをかぶった者もいた)は、腕を組んで椅子にもたれたり、嗅ぎタバコをかいだり、居眠りしたり、何かを書いたり、新聞を読んだりしていた。壁には黒光りする肖像画がいくつも掛かっていたが、私の素人目には焼き菓子と膏薬の合成画にしか見えなかった。そこで、隅のほうで私の誓約書が正式に署名・証明され、私は「誓約済み」となった。そしてパンブルチュークは、まるでこれから絞首台にでも上がるかのように、私をしっかりと捕まえていた。
外に出てみると、見物目的で盛り上がっていた少年たちに付きまとわれたが、私の「友人たち」が単に寄り添っているだけだと分かり、がっかりして離れていった。私たちはまたパンブルチュークの家に戻った。そこで姉は25ギニーの大金にすっかり興奮し、その臨時収入で「ブルー・ボア」で食事をすることを主張し、パンブルチュークが馬車でハブル夫妻とウォプスル氏を迎えに行くことに決まった。
決行が決まり、私はこの上なく憂鬱な一日を過ごすことになった。なぜなら、どういうわけか全員の頭の中では、私がこの宴会の中で邪魔者扱いになっていることが自明の理のようだったからだ。さらに悪いことに、彼らは折に触れて――つまりほかにやることがなくなるたびに――なぜお前は楽しまないのかと聞いてきた。そしてそんなとき私は、楽しいと言うしかなかった――本当は楽しくなかったのに!
とはいえ、大人たちは自分たちのやりたいようにやり、存分に楽しんだ。あの詐欺師パンブルチュークは、場の主催者として上座に座り、私の誓約について皆に語り、カード遊びや強い酒、夜遊びや悪い仲間など、誓約書の条項にある「ほぼ不可避」とみなされる悪事を行えば投獄されると悪魔的に祝辞を述べ、私を椅子の上に立たせて説明の口実にした。
私のこの大宴会の他の記憶といえば、眠ろうとすると起こされて「楽しめ」と言われたこと、夜遅くになってウォプスル氏がコリンズの頌歌を朗読し、血塗られた剣を雷のごとく投げつけたので、下の階の商人が「ここはアクロバットの宿じゃない」と伝えに来たこと、帰り道は全員上機嫌で、「おお麗しきご婦人よ!」を歌い、ウォプスル氏がバスを担当し、例のしつこいいやらしいリーダーに「自分こそ白髪の巡礼者だ」と強い声で主張したことぐらいだ。
そして、やっと自分の小さな寝室に戻ると、私は本当に惨めだったし、自分がジョーの仕事を好きになることは二度とないだろう、という強い確信を抱いた。かつては好きだったが、「かつて」は今ではなかった。
第十四章
家を恥じる気持ちほど惨めなものはない。そこには大きな恩知らずさがあるかもしれないし、その罰が応報的で当然であっても、それが惨めなことだけは断言できる。
家は、姉の気性のせいで、もともと私にとって居心地のよい場所ではなかった。しかし、ジョーのおかげでそれは神聖な場所となり、私は信じていた。応接間はとても上品なサロンだと、玄関扉は国家の殿堂の神秘的な門で、その厳粛な開閉には焼き鳥の供犠が伴うと、台所は地味だが清らかな部屋だと、鍛冶場は男らしさと自立への燃える道だと――そう信じていた。それがたった一年で一変した。今ではすべてが粗末で平凡に思え、ミス・ハヴィシャムやエステラに見せたくないとさえ思うほどだった。
私の不遜な心のありさまが、どこまで自分の責任で、どこまでミス・ハヴィシャムや姉のせいかは、今となってはもはやどうでもいい。変わってしまったのだ、もう取り返しはつかない。よかろうが悪かろうが、理由があろうとなかろうと、それはもう済んだことだ。
かつては、やがて袖をまくり鍛冶場でジョーの弟子になる日が来たら、自分は特別で幸せな存在になると思っていた。だが今、現実が目の前にあると、私はただ石炭の煤でまみれ、日々の重荷が金床よりも重く感じられるだけだった。後年になって(多くの人生でそうであるように)人生すべての関心やロマンに重い幕が下り、何もかもただ鈍い忍耐だけになるような時期があったが、あの時ほど重く、何も見えない幕が下りたことはなかった。ジョーへの見習いとして新たな道を歩み始めたときほどには。
その後の「修業時代」、日曜の夕暮れ時によく教会の墓地に立ち、風の吹く湿地の景色と自分の将来を重ねていた。どちらも平坦で低く、どちらも未知への道と暗いもやの果てに海があるように思えた。見習い初日の朝も、その後の時期と同じぐらい気が滅入っていたが、少なくとも誓約期間中、私はジョーに愚痴をこぼしたことがなかった。それだけは自分でも誇れる唯一のことだ。
だが、それに続くすべての功績はジョーのものであり、私の忠実さではなくジョーの忠実さのおかげだったから、私は家出して兵隊や船乗りになることもなかった。勤勉の美徳を自覚していたからではなく、ジョーがそれを身をもって教えてくれたから、私は嫌々ながらもそこそこ熱心に働けたのだ。誠実で善良な人間の影響がどこまで広がるかは分からないが、自分がその影響を受けたことだけははっきり言える。私の見習い時代に混じったささやかな善意は、すべて満ち足りたジョーの影響であり、落ち着かない私自身の野心から生まれたものではなかった。
自分が何を望んでいたのか、誰に言えよう? 私自身にも分からなかった。一番怖かったのは、運悪く自分が一番みすぼらしく薄汚れているときに、ふと顔を上げるとエステラが鍛冶場の木枠の窓越しに覗き込んでいるのを発見することだった。いつか彼女に見つかり、顔も手も真っ黒なまま一番汚い仕事をしている自分を見て、彼女が私を嘲笑い、軽蔑するのではないかという恐れにとりつかれていた。暗くなってからジョーのためにふいごを踏み、「オールド・クレム」を歌っていると(かつてミス・ハヴィシャムの家でも歌っていたことを思い出し)、炎の中にエステラの顔が浮かび、風に髪をなびかせ私を軽蔑した目で見ているように思えてくる。そんなとき、壁の黒い夜となった窓の方を見やると、彼女がまさに顔を引っ込めるところを見た気がして、ついに来たのだと信じてしまうのだった。
そのあと食事に行くと、家も食卓もこれまで以上にみすぼらしく見え、私は自分の家を心の中でますます恥じるのだった。
第十五章
ウォプスル氏の大おばの部屋が手狭になってきたので、あの奇妙な女性の下での教育は終わりを迎えた。ただし、ビディが自分の知っていること――価格表の一部から、かつて半ペニーで買ったコミックソングまで――を私にすべて教えてくれるまで、教育は続いた。その歌のまともに理解できる部分といえば、
When I went to Lunnon town sirs,
Too rul loo rul
Too rul loo rul
Wasn’t I done very brown sirs?
Too rul loo rul
Too rul loo rul
――という冒頭ぐらいだったが、賢くなりたい一心で私はこの歌を極めて真面目に暗記した。この詩について疑問に思ったのは、今でも思うが「Too rul」が詩の分量に比していささか多いということだけだった。
知識に飢えていた私は、ウォプスル氏にも何か教えてほしいと頼んだ。彼は快く応じてくれたが、のちに分かったのは、彼が私を劇的な人形として使いたかっただけで、私は否定されたり、抱きしめられたり、泣き叫ばれたり、怒鳴られたり、掴まれたり、刺されたり、様々な方法で振り回されたりするだけだったので、その教育はすぐにお断りした。もっとも、ウォプスル氏が詩的な激情で私をひどく痛めつけるまで、そのことには気づかなかったが。
私が学んだことは、すべてジョーに教えようとした。この事実は響きが良すぎるので、良心に従って補足説明しなければならない。私は、ジョーがもっと無知でなく、洗練されていたら、私と一緒にいても恥ずかしくないし、エステラに侮られることもなくなるだろうと思っていたのだ。
私たちの勉強場所は、湿地の外れの古い砲台跡だった。使うのは割れた石板と短い石筆、そしてジョーは必ず煙草のパイプを持参した。ジョーが日曜日ごとに何かを覚えていることは一度もなかったし、私が教えた知識を何一つ身につけたこともなかった。それでも彼は砲台跡でパイプをくゆらせる時、どこよりも賢そうな、知的な表情を見せ、自分がものすごく進歩していると思い込んでいるようだった。親愛なるジョー、彼自身がそう感じてくれていたなら、私はうれしい。
そこは静かで心地よく、川を行き交う帆船が土手の向こうに見え、干潮時にはまるで沈んだ船が水底を進んでいるようだった。沖へ出ていく船の白帆を見るたびに、なぜかミス・ハヴィシャムやエステラのことを思い出し、遠くに斜めに射す光が雲や丘や水面を照らすときも同じだった――ミス・ハヴィシャムやエステラと、あの奇妙な家、奇妙な生活が、何もかも美しいものと関係しているように思えた。
ある日曜、ジョーが「今日はとびきり冴えない」と自慢げにパイプを楽しみ、私はあきらめて土手の上に横になり、顎に手をあてて風景のあちこちにミス・ハヴィシャムやエステラの面影を探していた。ついにその二人についてずっと考えていたことを口に出す決心をした。
「ジョー、ミス・ハヴィシャムを訪ねるべきだと思わない?」
「まあ、ピップ」とジョーはゆっくり考えて言った。「何のために?」
「何のためって、ジョー? 誰だって誰かを訪ねるだろう?」
「まあ、世の中には訪問の目的が永遠に謎のままのやつもいるがな、ピップ。ただミス・ハヴィシャムを訪ねるとなると、何かを望んでるとか、期待してるとか思われるかもしれない」
「そうじゃないって言えばいいんじゃないか、ジョー?」
「言えば、そう信じてくれるかもな、相棒。だが、そうは思わないかもしれない」
ジョーは私と同じく自分の主張が通ったと感じ、パイプを強く吸って繰り返さないようにしていた。
「いいか、ピップ」とジョーは続けた。「ミス・ハヴィシャムはお前に良くしてくれた。あの時、俺を部屋に呼び戻して、これで全部だ、と言ってくれたんだ」
「うん、ジョー。僕も聞いた」
「全部、だ」とジョーは強調した。
「うん、ジョー。ちゃんと聞いたよ」
「つまりな、ピップ、彼女の意味はこうだ――これで終わり! それっきり! 俺は北へ、お前は南へ! 別々の道を行こう! ってことかもしれない」
私もそう考えていたし、ジョーも同じことを考えていたのは慰めにならなかった。むしろ、その可能性が高いように思えてきた。
「でも、ジョー」
「なんだい、相棒」
「こうして修業も一年目に入ったのに、僕はミス・ハヴィシャムにお礼も言わず、挨拶もせず、覚えていることも示していない」
「それはそうだな、ピップ。とはいえ、お前が蹄鉄を作って贈ったとしても――まあ、そもそも蹄鉄がないのに贈っても仕方がないし――」
「そういう贈り物じゃなくて、ジョー。お礼の品とかじゃないんだ」
だがジョーは贈り物の発想に固執した。「それか、玄関用の鎖を作ってやるとか――あるいはサメ頭のネジを2グロスほど用意するとか、トースト用フォークや焼き網を贈るとか――」
「僕は贈り物をしたいんじゃないよ、ジョー!」
「まあ」とジョーはやはり贈り物にこだわり、「もし俺がお前なら、やめとくな。だって、玄関鎖なんて既にあるし、サメ頭ネジは誤解の元だし、焼き網じゃどんな名工でも大した違いは出せんぞ、ピップ。焼き網は焼き網だからな。どんなに腕を振るっても、焼き網は焼き網なんだ。自分の望みに反しても、また逆らっても、焼き網は焼き網で、それはどうしようもない――」
「ジョー、お願いだから、そんなふうに話さないで! 僕は贈り物なんて考えてなかったよ」
「いや、ピップ」ジョーは、まるで最初からそう主張してきたかのようにうなずいた。「お前が正しい、ピップ」
「うん、ジョー。でも言いたかったのはね、今は仕事も少し暇だし、明日半休をくれたら、街まで行ってミス・……エステ……ハヴィシャムを訪ねてみたいんだ」
「彼女の名前はエステヴィシャムじゃないぞ、ピップ、洗礼名が変わったわけでもなければ」
「分かってる、ジョー、言い間違えたんだ。どう思う?」
結局、私がそうしたいならジョーも賛成だった。ただし、もし歓迎されず、意味のない感謝の訪問だと認められなければ、もう二度と行かないという条件を厳守することになった。私はその条件を受け入れると約束した。
さて、ジョーのところには週給の職人がいて、名前をオーリックと言った。自分の洗礼名はドルジだと主張していた――明らかにあり得ない名だったが、彼は村の知性への侮辱として、わざとその名を押し付けていたのだと思う。彼はがっしりした体格で、いつもだるそうに動く、褐色肌の力自慢だった。いつもせかせかせず、鍛冶場にも「たまたま」入り込むような感じだった。そして、飲食のために「陽気な船乗り亭」に行くときも、夜に帰るときも、カインやさまよえるユダヤ人のように、どこへ行くのか分からず、二度と戻ってこないつもりのようにのそりのそりと歩いていた。彼は湿地の水門番の家に下宿していて、平日はそこからポケットに手を突っ込み、昼飯を包んだ布を首に巻いて背中でぶら下げ、のそりのそりとやってきた。日曜はほとんど一日中水門の上で寝転び、藁小屋や納屋の壁にもたれていた。常に下を向いて歩き、声をかけられたり何かしら目を上げるよう求められると、半ば不満げで半ば困惑したような顔で見上げ、ただ一つの考え――自分がいつも何も考えていないのは奇妙で不当だ――という考えしか持ち合わせていないかのようだった。
この気難しい職人は私を好まなかった。私がまだ幼く臆病だったころ、鍛冶場の片隅には悪魔が住んでいて、彼はその悪魔と懇意にしていると教えられた。また七年に一度、鍛冶場の火は生きた少年でくべなければならず、私も燃料にされるだろうとも。私がジョーの弟子になると、オーリックは自分が追い出されるのではとの疑念が確信に変わり、私をますます嫌うようになった。しかし、彼が公然と敵意を示したり、何か言ったりすることはなかった。ただ、火花を私の方に飛ばすし、私が「オールド・クレム」を歌えば必ず音を外して割り込んできた。
ドルジ・オーリックは翌日も鍛冶場で作業していた。私がジョーに半休を願い出ると、彼はその場では何も言わなかった。ちょうど熱い鉄を扱っている最中で、私はふいご係だったからだ。しかし、しばらくすると、彼はハンマーを手によりかかりながら言った。
「旦那! ピップ坊やだけひいきってことはないですよね。若いピップが半休なら、年寄りオーリックも同じく頼みますよ」彼は二十五歳くらいだったが、いつも自分を老人のように扱っていた。
「で、お前は半休で何をするつもりだ?」とジョーが言った。
「俺がどう使おうが、あいつがどう使おうが同じだろ」とオーリックは答えた。
「ピップについて言えば、奴は町に行くんだ」とジョーが言った。
「そりゃまあ、オールド・オーリックも町に行くぜ」とその男が言い返した。「二人だって町に行けるさ。町に行けるのは一人だけじゃねぇ。」
「怒るなよ」とジョーが言った。
「好きにしてやるさ」とオーリックはうなった。「あいつらときたら、町だ町だと! さあ、親方! こいよ。この作業場じゃひいきは無しだ。男になれよ!」
親方は、職人の機嫌が良くなるまでその話題に乗ることを拒んだので、オーリックは炉の前に飛び込み、真っ赤に焼けた鉄棒を引き抜き、それをまるで私の体を貫くかのようにこちらに向かって振り回し、私の頭の上でくるりと回し、金床の上に置いて叩き始めた――まるで私自身を打ちのめしているように思え、火花が私のほとばしる血のように見えた――そして、鉄が冷えて自分が熱くなり、再びハンマーに寄りかかったとき、ようやくこう言ったのだった。
「さあ、親方!」
「もういいのか?」とジョーが尋ねた。
「ああ、もう大丈夫だ」とごついオールド・オーリックが言った。
「じゃあ、普段から他の誰にも劣らず仕事に励んでいるから、今日はみんな半ドンにしよう」とジョーが言った。
私の姉さんは庭で黙って立っていて、すぐそばで聞いていた――彼女は非常にずる賢いスパイで盗み聞きの名人だった――そしてすぐに窓のひとつから顔をのぞかせた。
「お前みたいな馬鹿がいるもんだね!」と彼女はジョーに言った。「あんななまけ者の巨体に休日なんか与えてさ。あんたは本当に金持ちだね、そんなふうに賃金を無駄にして。私があいつの親方だったらいいのに!」
「お前、できるもんならみんなの親方になりたがるだろうよ」とオーリックが嫌な笑みを浮かべて言い返した。
(「放っとけよ」とジョーが言った。)
「私は馬鹿も悪党も相手にできるさ」と姉さんは言い、ますます怒りで体を震わせ始めた。「馬鹿を相手にできなきゃ、親方も相手にできないだろうし、親方ってやつは馬鹿の王様だからね。悪党を相手にできなきゃ、お前も相手にできないだろうし、お前ってやつはこの辺からフランスまでで一番性悪な悪党だからね。なにさ!」
「お前みたいな口うるさい女狐だよ、ガージェリーのかみさん」と職人がうなった。「それで悪党を見抜けるってんなら、お前は大したもんだ。」
(「ほら、放っとけってば」とジョーが言った。)
「なんだって?」と姉さんが叫び、今にも泣き叫びそうな顔になった。「なんて言ったの? オーリックのやつ、私に何て言ったの、ピップ? 私の夫がそばにいるってのに、私のことなんて呼んだの? ああ! ああ! ああ!」これらの叫びは一つ一つが絶叫だった;そして私の姉さんについては、これまで見てきたどんな激しい女性にも当てはまることだが、激情は彼女にとって免罪符にならず、むしろ本当に激情に陥る代わりに、意識的かつ意図的に自分を無理やりその状態に持っていき、段階的に盲目的な怒りに達していたのは否定できないことである。「あの下劣な男が私を守るって誓ったその前で、私にどんな名前をつけたの? ああ、誰か抑えて! ああ!」
「へっ」と職人は歯の間からうなった。「俺があんたの旦那だったらな。井戸の下に押さえ込んで、息の根止めてやるぜ。」
(「だから放っとけって言ってるだろ」とジョーが言った。)
「ああ、聞いたかい!」と姉さんが叫び、両手を叩きながらまた叫んだ――これが次の段階だ。「あんなやつにこんな呼ばわりされるなんて! オーリックのくせに! 私の家で、私が既婚の女で、夫がそばにいるのに! ああ! ああ!」ここで姉さんは、手を胸や膝に打ちつけ、帽子を投げ捨て、髪を引き下ろして、まさに狂乱の道の最終段階に突入した。こうして完全に激怒し、立派な「フューリー(復讐の女神)」と化した彼女は、私が鍵をかけていたドアに突進してきた。
今や、ジョーのたび重なる注意も無視され、哀れなジョーとしては、職人に向かい合い、なぜジョー夫人との間に口を挟むのか、そしてさらに、男なら受けて立つのかと問いただすしかなかった。オールド・オーリックもこの状況では受けて立つしかないと感じ、すぐさま構えた。焦げたエプロンを外す暇もなく、二人はまるで巨人同士のように取っ組み合いを始めた。しかし、この近所でジョーとまともにやりあえる男など、私は見たことがなかった。オーリックは、あの青白い若者と同じくらい簡単に、すぐに石炭の粉まみれになり、そこから出てくる気配はなかった。それからジョーはドアの鍵を開け、気を失って窓辺に倒れた姉さんを抱き起こした(だが、たぶん、その決闘はしっかり見ていたと思う)、彼女は家の中に運ばれ、横たえられ、気付けをすすめられても、ジョーの髪を握り締めてもがくだけだった。やがて、嵐の後の不思議な静けさと沈黙がやってきた。そして私は、いつもこの手の静寂には日曜日で誰かが死んだような感覚を覚えるのだが、そのまま着替えに二階へ上がった。

私がまた降りてくると、ジョーとオーリックはせっせと掃除をしていて、オーリックの鼻の穴の片方に切り傷ができている以外は、取り乱した様子もなかったし、それも別に印象的でも飾りにもならなかった。ジョリー・バージメンからビールの壺が運ばれてきて、二人はそれを交互に平和的に分け合っていた。この静けさはジョーを落ち着かせ、哲学的な気分にさせたらしく、私が家を出る際に、心に留めておくとよいとばかりにこう言った。「荒れてるときもあれば、そうじゃないときもある――それが人生ってもんだ、ピップ!」
どんなに馬鹿げた感情を抱きながら(なぜなら、大人の深刻な気持ちも子供だと滑稽に見えるものだ)、私はまたミス・ハヴィシャムの屋敷へと向かった。その道すがら、門の前で何度も行きつ戻りつし、チャイムを鳴らす決心がつかず、鳴らさぬまま帰ろうかとも迷い、もし自分の時間が自由なら間違いなく戻っただろう、などということはここでは大した問題ではない。
門にはサラ・ポケットが現れた。エステラの姿はない。
「なんだい? また来たのかい?」とミス・ポケットは言った。「何の用だ?」
私がただミス・ハヴィシャムの様子を見に来ただけだと伝えると、サラは私を追い返そうかしばし迷ったようだった。しかし、責任を負いたくなかったのか、中に入れてくれ、ほどなくして「上がっておいで」という鋭い伝言を持ってきた。
すべては変わらず、ミス・ハヴィシャムは一人だった。
「で?」と彼女は私をじっと見つめて言った。「何も欲しがってないだろうね? 何もやらないよ。」
「ええ、もちろんです、ミス・ハヴィシャム。私はただ、徒弟修業がうまくいっていることをお伝えしたくて、いつも感謝していると申し上げたかっただけです。」
「それでいい、それでいい!」と、いつものそわそわした指先で言った。「たまには来なさい、誕生日には来なさい――ああ!」と急に叫び、自分と椅子を私の方へ向けた。「エステラを探してるんだろう? え?」
私は確かに――エステラを――見回していたので、彼女が元気かどうか気になっていると口ごもった。
「外国にいる」とミス・ハヴィシャムは言った。「淑女になるための教育中だ。もう手が届かないほど遠くにいる。前よりも美しく、見た者はみな彼女を称賛する。彼女を失ったと感じているか?」
その最後の言葉には悪意ある愉しみがこもっていて、彼女は実に不愉快な笑い声を上げたので、私は何と返せばいいのかわからなかった。彼女は私を考える暇も与えず、すぐに追い出した。サラ・ポケット――胡桃の殻のような顔をした彼女――に門を閉められ、私はこれまで以上に自分の家や仕事やすべてが不満に思え、それが「その行動」で得た全てだった。
私はハイストリートをぶらぶらしながら、憂鬱そうにショーウィンドウを眺め、もし自分が紳士なら何を買うだろうかなどと考えていた。すると本屋から出てきたのはウォプスル氏だった。彼は「ジョージ・バーンウェル悲劇」を手にしており、つい今しがた六ペンスでそれを買ったばかりで、パンブルチュークの頭上にそのすべての言葉を投げつけるつもりでいた。その私を見るなり、彼はまるで神の思し召しで徒弟が自分の前に現れたかのように思ったらしく、私の腕をつかんでパンブルチューク家の客間に同行するよう強く求めた。家にいても憂鬱だし、夜道も暗く心細かったので、誰かと一緒のほうがましだと思い、特に抵抗しなかった。こうして、街や店に明かりが灯り始めるころ、私たちはパンブルチューク家に入った。
「ジョージ・バーンウェル」の他の上演を見たことがないので、通常どれほど時間がかかるものか知らないが、その晩は九時半まで続いたことはよく覚えている。ウォプスル氏がニューゲートに到達したときには、彼が絞首台に上る日は永遠に来ないのではないかと思うほど、それまでで一番遅かった。彼がついに散り急いだことに文句を言ったときには、最初から葉っぱが落ちるように徐々に枯れていっていたくせにと、私は少し呆れた。もっとも、これは長さと退屈さの問題にすぎない。私を刺したのは、この一連の出来事が何の罪もない私自身と結びつけられたことだ。バーンウェルが道を踏み外し始めると、パンブルチュークの憤慨した視線によって、私は本当に申し訳ない気分になった。ウォプスル氏も、私を最悪の形で演出しようと努めた。私は凶悪で情けなく、何の事情もなく叔父を殺し、ミルウッドには何を言ってもやり込められ、主人の娘が私に好意を持つのはほとんど狂気の沙汰とされ、運命の朝にぐずぐずと時間稼ぎをしていたのも、私の性格の弱さを象徴していた。絞首刑にされて物語が終わり、ウォプスル氏が本を閉じた後も、パンブルチュークは私をじっと見つめ、首を振り、「教訓にしろよ、少年、教訓にしろ!」と言い続けた。まるで、私が誰か近しい親類を――もしその人が私の恩人になってくれるほど弱ければ――殺すことを考えているのがよく知られている事実であるかのように。
すべてが終わり、ウォプスル氏と夜道を歩いて家に帰るときには、夜空は真っ暗だった。町を出ると濃い霧が出てきて、湿っぽく重く垂れ込めていた。料金所のランプはぼんやりとかすみ、光はまるで霧の中に固体のように見えた。これについて話しながら歩いていると、料金所のかげに体を寄せている男に出くわした。
「おや!」と私たちは立ち止まって声をかけた。「オーリックか?」
「ああ」と彼は姿を見せた。「誰かと一緒にならないかと、ちょっと立ってたのさ。」
「遅いな」と私は言った。
オーリックは当然のように「で? お前らも遅いじゃないか」と返した。
「我々はな」とウォプスル氏が、自分の熱演に酔った様子で言った。「我々はな、知的な夜を過ごしていたのだよ、オーリックさん。」
オールド・オーリックは、それについて何か言う気もなさそうにうなり、三人で道を進んだ。私はしばらくして、彼が半ドンを町でどう過ごしたのか尋ねた。
「ああ」と彼は答えた。「全部町で過ごした。お前のすぐ後ろを歩いてたんだ。お前には見えなかったが、たぶんかなり近くにいたはずだ。ところで、またあの大砲が鳴ってるぞ。」
「ハルク船か?」と私は言った。
「ああ。檻から鳥が何羽か抜け出したんだ。大砲は暗くなってからずっと鳴ってる。すぐまた聞こえるさ。」
実際、さらに数ヤードも歩かないうちに、あの聞き覚えのある重々しい音が霧にこもってこちらに届き、川沿いの低地を重くうねりながら遠ざかっていった。まるで逃亡者を追い、脅しているかのようだった。
「今夜は逃げるにはいい夜だな」とオーリック。「今夜は、逃げる囚人を撃ち落とすのは難しいだろうな。」
この話題は私にとって意味深く、しばらく黙って考えた。ウォプスル氏は、その晩の悲劇で報われなかった叔父として、カンバーウェルの庭で独り言を始めた。オーリックはポケットに手を突っ込み、どっしりと私の隣を歩いた。とても暗く、濡れて、泥だらけで、私たちは泥を跳ね上げながら進んだ。時おり、また信号砲の音が鳴り響き、川沿いをうらめしげに転がった。私は自分の世界にこもって考え込んだ。ウォプスル氏はカンバーウェルで穏やかに死に、ボズワース・フィールドでは勇敢に、グラストンベリーでは激しい苦しみで死んだ。オーリックは時折「打ちのめせ、打ちのめせ、オールド・クレム! ガッチリ打ちのめせ、オールド・クレム!」とうなり声を上げた。どうやら酒を飲んでいるようだったが、酔ってはいなかった。
こうして私たちは村に着いた。通りかかったジョリー・バージメンは夜の十一時だというのに珍しく騒がしく、ドアは開け放たれ、慌てて用意されたらしい明かりがいくつも灯っていた。ウォプスル氏は(囚人が捕まったのだろうと推測しつつ)何事かと中へ駆け込んだが、すぐに慌てて飛び出してきた。
「何かあったぞ」と彼は立ち止まらずに言った。「お前の家で何かまずいことが起きた、ピップ。急げ!」
「何があったんだ?」と私は並んで走りながら尋ねた。オーリックもついてきた。
「よくわからんが、ジョー・ガージェリーが留守の間に家に押し入りがあったらしい。囚人の仕業と思われてる。誰かが襲われて怪我をした。」
私たちは走りながらこれ以上話す余裕もなく、家の台所に飛び込んだ。そこは人でいっぱいだった;村中の人が家や庭に集まり、外科医がいて、ジョーがいて、そして女たちの輪が台所の真ん中にできていた。私が入ると傍観者たちが道を開け、そこで私は姉さんの姿に気付いた――感覚も動きもなく、床に倒れていた。誰かに背後から頭を激しく殴られたのだ、暖炉に顔を向けていたときだった――二度と荒れ狂うことはない運命にあった、ジョーの妻でいる限りは。
第十六章
頭の中が「ジョージ・バーンウェル」でいっぱいだった私は、最初は自分が姉さんへの襲撃に何らかの形で関わっているのではないか、あるいは少なくとも近親者として、彼女に恩義があることが広く知られている自分が、最も疑われて当然なのではないかと考えた。しかし翌朝、より明るい中で、周囲で語られる話を耳にするうち、もっと合理的な見方ができるようになった。
ジョーは八時十五分から九時四十五分まで、ジョリー・バージメンで煙草をふかしていた。その間、姉さんは台所のドアに立っているのを目撃されており、帰宅途中の農夫と「おやすみ」を交わしていた。その男は時間についてはっきり言えなかった(無理に思い出そうとすると話がぐちゃぐちゃになった)が、九時前だったはずだと言う。ジョーが家に帰ったのは九時五十五分、そこで姉さんが床に打ち倒されているのを発見し、すぐに助けを呼んだ。その時点で火は特別消えてもおらず、ろうそくの芯もまだ短かったが、ろうそくは吹き消されていた。
家のどこからも何も盗まれていなかった。ろうそくが消されていた以外(それはドアと姉さんの間のテーブルに置かれていて、姉さんが暖炉に向かって立っていた時は彼女の背後だった)、台所も姉さんが倒れて出血した以外には乱れていなかった。しかし、現場にはひとつ特筆すべき証拠があった。姉さんは何か鈍くて重いもので、頭と背骨を殴打されていた;打たれた後、何か重いものが顔を伏せたままの彼女に勢いよく投げつけられた。そして、ジョーが姉さんを抱き起こした時、彼女の傍には切断された囚人の足かせが落ちていた。
ジョーは鍛冶屋の目でこの足かせを調べ、かなり前に切断されたものだと判断した。騒ぎでハルクから人が来て調べたところ、ジョーの見立ては裏付けられた。いつ囚人船から離れたものかは断言できないが、昨夜逃げた二人の囚人のものではない、とはっきり分かっていると言っていた。うち一人はすでに再逮捕され、足かせも外していなかった。
私は自分なりの推理をここで立てた。私はこの足かせが「私の囚人」のものであり――以前、沼地で彼が切断しているのを見聞きしたものだと信じた――しかし、彼がこれを最新の用途に使ったとは思わなかった。これを手に入れ、この残酷な目的に使ったのは他の誰か――オーリックか、私にやすりを見せたあの奇妙な男――のどちらかだと考えた。
オーリックについて言えば、彼は私たちが料金所で拾った通りに町へ行き、夜は町で目撃され、公衆酒場などで複数の人と一緒にいたし、私とウォプスル氏と一緒に戻ってきている。彼に不利な点は、姉さんとの喧嘩だけだったが、姉さんは誰彼構わず一万回は喧嘩している。あの奇妙な男について言えば、もし彼が二枚の銀行券を取り戻しに来たのなら、姉さんは返す準備があったので争いにはならないはずだ。しかも、襲撃者は音もなく突然に現れ、姉さんが振り向く暇もなく倒されていた。
私がたとえ意図せずとも武器を提供してしまったことは恐ろしかったが、そう考えざるを得なかった。私はこの秘密をついにジョーに打ち明けるべきか、子供時代の呪縛を解くべきか、毎日悩み苦しんだ。だが何ヶ月も、毎回否定的な結論に落ち着き、翌朝にはまた悩み直した。結局はこういうことだった;この秘密は今や私の一部となり、もはや引き剥がせなくなっていたのだ。それに、これまでの災いのもとになっただけに、今さら話してもジョーを遠ざけるだけだろうという恐れもあったし、逆に信じてもらえず、例の作り話(犬や仔牛肉)のたぐいだと思われるのも嫌だった。結局私は自分をごまかし続けることにして――正しいことと間違ったことの狭間で揺れているとき、結局そのまま何もしないものだ――新たな手がかりが得られたときには真実を打ち明けようと自分に言い聞かせていた。
巡査やロンドンから来たボウ・ストリートの警官たち――これはあの絶滅した赤いベストの警官時代の出来事だが――が家に出入りし、ほかの事件で読んだり聞いたりした通りのことをしていた。明らかに無関係な人間を何人も連行し、的外れな考えに固執し、状況に考えを合わせるのではなく、考えに状況を合わせようとした。また、ジョリー・バージメンのドア前に立ち、意味ありげで控えめな顔をして近所中の賞賛を集め、飲み方にも謎めいた作法があり、それがほとんど犯人逮捕と同じくらい重要に見えた。しかし実際にはそうでもなく、犯人は捕まらなかった。
このような権力が消え去った後も、姉さんは長く病床にあった。視界は乱れ、物が何重にも見え、幻のティーカップやワイングラスをしきりに手探りし、聴力も記憶も大いに損なわれ、言葉も意味不明だった。やがて階下に下りられるようになっても、意思を伝えるにはいつも私の石板が必要だった。ただし、彼女は(字も汚いし)スペルが非常に苦手で、ジョーは読むのがまた不得手だったので、二人の間には珍妙な誤解が絶えず、私はそのたびに呼び出された。薬の代わりに羊肉を出したり、ジョーの代わりにお茶、ベーコンの代わりにパン屋を出すことなど、私の失敗の中ではまだ可愛い方だった。
それでも、彼女の気性は大いに穏やかになり、辛抱強くなった。手足のすべての動きに震えを伴う不安定さが常態化し、さらに二、三ヶ月ごとに頭を抱えて一週間ほど陰気な精神の混乱に陥ることもしばしばだった。付き添いをどうするか困っていたが、ちょうど都合よく事態が解決する出来事があった。ウォプスル氏の大おばさんが長年の「生きる癖」に打ち勝ち、ビディが我が家の一員となったのだ。
姉さんが再び台所に姿を現してから、たぶん一ヶ月ほど経った頃、ビディは小さな斑点模様の箱に身の回りの品を詰めてやってきて、家に幸運をもたらしてくれた。何よりも、ビディはジョーにとって救いだった。ジョーは、今や打ちひしがれた妻の姿を見続けるのが辛くてたまらず、彼女の世話をしていると時折私の方を見つめて、涙ぐんだ青い目で「昔は立派な体つきの女だったんだぞ、ピップ」と言っていたものだ。ビディはまるで幼い頃から姉さんを知っていたかのように見事に世話をし始め、ジョーも次第に静かな暮らしをありがたく感じられるようになり、時折ジョリー・バージメンで気晴らしする余裕もできた。警察の人たちが、誰もが少なからずジョーを疑っていたこと(当人は知らなかったが)、そして彼ら全員がジョーをかつて見た中で最も深謀深い男とみなしていたことも、いかにもそれらしい話だ。
ビディが新しい役目で最初に成し遂げたのは、私がどうしても解けなかった難題を解明することだった。私は何度も挑戦したが、まったくうまくいかなかった。その難題とは――
姉さんは何度も何度も石板に、奇妙なTのような字を書き、それをとても重要なものとして私たちの注意を引いた。私はTで始まるものをありったけ試してみた――タールもトーストもタブも。だがどうしても当たらない。やがて、その記号がハンマーのように見えることに気づき、「ハンマーだ!」と大きな声で姉さんの耳に呼びかけると、彼女はテーブルを叩き始め、やや同意した様子を見せた。そこで家中のハンマーを一つずつ持ってきたが、どれも違った。今度は形が似ているので松葉杖かと思い、村で借りてきて姉さんに見せたが、彼女は大きく首を振りすぎて、弱った体が首の骨を外しそうで私たちは怖くなった。
ビディが姉さんの意図をすぐに理解できるとわかってから、この謎の記号はまた石板に現れた。ビディはじっと記号を見つめ、私の説明を聞き、姉さんを見つめ、ジョーを見つめ(石板上ではいつも頭文字で示されていた)、それから鍛冶場へ駆け込んだ。私とジョーも後に続いた。
「ほら、やっぱり!」とビディは顔を輝かせて叫んだ。「わかるでしょ? あれは彼だよ!」
オーリックに間違いない! 姉さんは彼の名前を忘れ、ハンマーでしか示せなかったのだ。彼を台所へ呼びたい理由を伝えると、彼はゆっくりハンマーを置き、腕で額の汗を拭い、エプロンでもう一度拭い、膝を曲げてだらしなくスラリとした独特の歩き方でやってきた。
正直、私は姉さんが彼を非難するものとばかり思っていたので、まったく違う結果にがっかりした。彼女はオーリックと良い関係を持とうと必死で、彼が現れたことを非常に喜び、何か飲み物を与えるよう合図した。彼女は、オーリックが歓迎を受け入れているかどうかじっと表情を見つめ、あらゆる方法で機嫌を取ろうとし、まるで厳しい主人に媚びる子供のように、へりくだった態度だった。それ以来、姉さんはほぼ毎日石板にハンマーを描き、オーリックは何も分からないふりをして台所に現れ、姉さんの前に陰気に立つのが日課となった。
第十七章
私は今や、村と沼地の範囲を超えて何事も起きない、規則正しい徒弟生活に落ち着いた。唯一の例外は誕生日が来て、ミス・ハヴィシャムを再訪したことくらいだった。門番は相変わらずサラ・ポケット、ミス・ハヴィシャムも変わらず、エステラについても同じようなことを語った。面会は数分で終わり、帰りにギニー金貨を渡され、次の誕生日にも来るように言われた。これは年中行事となった。最初は辞退しようとしたが、かえって怒らせてしまい、「もっと欲しいのか?」と詰られたので、それ以降はありがたく受け取った。
あの古びた家、暗い部屋の黄色い灯り、鏡台の椅子に座る色あせた幽霊のような姿――何もかもが変わらず、まるで時計が止まったことでこの場所だけ時が止まってしまい、自分や外の世界だけが年を重ねているように感じられた。思い出の中でも実際にも、この家に昼の光が射し込むことはなかった。そのせいで私はずっと混乱し、その影響でますます自分の職業を嫌い、家を恥ずかしく思い続けた。
だが、いつの間にかビディに変化が表れていることに気づいた。靴はかかとがすり減らなくなり、髪は明るく整い、手はいつもきれいだった。彼女は美人ではなかった――ごくありふれた娘で、エステラのようにはなれなかった――でも、親しみやすく、清潔で、気立てもよかった。家に来てまだ一年も経たない頃(喪服を脱いだばかりの時期だったのを覚えている)、私はふと、彼女の目がとても思慮深く、注意深いことに気づいた。とてもきれいで、善良な瞳だった。
それは、私が何かに熱中して本から文章を書き写し、二重の意味で自分を向上させようと策を弄していたとき、自分の目を上げるとビディが私の様子を見ていたのがきっかけだった。私はペンを置き、ビディも針仕事の手を止めた。
「ビディ、どうやってるの? 僕がすごく馬鹿なのか、君がとても賢いのか、どっちかだよ」
「何をどうやってるの? わからないわ」とビディは微笑んで言った。
彼女は家の暮らしを見事に切り盛りしていたが、私が言いたかったのはそれではなかった。それがあるからこそ、なおさら不思議だった。
「どうして、ビディ、君は僕が学ぶことを全部学んで、いつも僕に追いついていられるんだろう?」私はだんだん自分の知識に自惚れ始めていて、誕生日のギニーや小遣いもほとんど学びに使っていたが、今思えば、その知識はとても高くついた割に取るに足らないものだった。
「あなたにも聞きたいわ、どうやってるの?」とビディ。
「いや、それは違うよ。だって僕が鍛冶場から帰ると誰でも僕が勉強してるのが見えるけど、君は勉強なんてしてないじゃないか、ビディ」
「きっと風邪みたいにうつったのよ」とビディは静かに言って、また針仕事を続けた。
私は木の椅子にもたれて彼女の横顔を眺めるうち、彼女は本当に不思議な娘だと思い始めた。そういえば、彼女は鍛冶仕事の用語も作業の種類も工具の名前も全部心得ている。要するに、僕の知っていることは全部ビディも知っている。理屈の上では、もう私より鍛冶屋として優秀かもしれなかった。
「君は、ビディ、どんな機会も最大限に生かすタイプだよ。ここに来る前は機会なんてなかったのに、今はこんなに成長してる!」
ビディは一瞬私を見て、また針仕事を続けた。「でも、私が最初の先生だったでしょ?」と縫いながら言った。
「ビディ!」と私は驚いて叫んだ。「なに、泣いてるのか?」
「ううん、泣いてないわ」とビディは顔を上げて笑った。「なんでそんなこと思ったの?」
そう思ったのは、彼女の手元に涙がひとしずく落ちるのを目にしたからだった。私は黙って、ビディがウォプスル氏の大おばさんという厄介者に束縛され、みじめな小さな店と騒がしい夜学に囲まれて暮らしていたこと、その中でも今の彼女が育ってきたことを思い出した。私が不満や落ち着かなさに悩んだとき、自然に彼女に助けを求めていたことも思い出した。ビディは静かに針仕事を続け、もう涙は流さなかった。私は彼女を見つめながら、自分はビディに十分感謝していただろうか、もう少し心を開いて接すればよかったのではないか(そういう言葉は当時の私の心にはなかったが)と考えた。
「そうだね、ビディ」と、考え終えてから私は言った。「君は僕の最初の先生だった。その時は、まさかこうして台所で一緒にいるなんて思いもよらなかったよね」
「そうね、かわいそうに」とビディ。彼女は自分のことはさておき、私の姉さんのことに話を移し、立ち上がって彼女の世話に取り掛かった。「本当にそうだわ」
「さて」と私は言った。「また今までみたいに、君といろいろ話そう。そして、また君に相談しよう。今度の日曜、沼地を静かに散歩して、ゆっくり話そうよ、ビディ」
今や姉さんは決して一人にはされなかった;だがジョーは日曜の午後、喜んで姉さんを引き受けてくれ、私はビディと一緒に外へ出た。夏の麗らかな日だった。村を抜け、教会と墓地を過ぎて沼地に出て、遠くに帆船が見え始めると、私はいつも通り、ミス・ハヴィシャムやエステラのことを風景に重ねて考え始めた。川辺まで来て、水のさざ波が足もとで静かに響くのを聞きながら並んで座り、今こそビディに心の内を打ち明ける好機だと決めた。
「ビディ」と私は言い、秘密厳守を約束させてから、「僕は紳士になりたいんだ」
「でも、やめた方がいいわよ」と彼女。「うまくいかないと思う」
「ビディ」と私はややきつく言った。「僕にはどうしても紳士になりたい理由があるんだ」
「ピップが一番よくわかってるでしょ。でも、今のままの方が幸せじゃない?」
「ビディ」と私は苛立って叫んだ。「今のままじゃ全然幸せじゃない。自分の仕事も人生も嫌でたまらない。徒弟になってから一度も好きだと思えたことがない。ふざけないでくれよ」
「私、ふざけてた?」とビディは眉を上げて静かに言った。「ごめんなさい、そんなつもりじゃなかったの。ただ、ピップには幸せになってほしいの」
「じゃあ、はっきり言うけど、今のままじゃ絶対に、どんなことがあっても、僕は幸せにも心地よくもなれないよ、ビディ! 今とは全く違う人生を送れない限りは」
「それは残念ね」とビディは悲しそうに首を振った。
私も今まで何度も残念に思ってきており、自分と心の中で喧嘩しているような奇妙な気持ちの中で、ビディが私の思いそのものを口にしたことに、悔しさと悲しさで涙が出そうになった。私は彼女が正しいと認め、本当に残念だけど仕方がないと言った。
「もし落ち着いていられたら」と私は草をむしりながら言った。――子供の頃に髪の毛をむしり取って、ブルワリーの壁に蹴りつけたことがあったように――「もし半分でも鍛冶屋の仕事が好きでいられたら、今ごろもっとよかったのに。君や僕やジョーは何も不自由しなかっただろうし、修業が終わったらジョーと一緒に鍛冶屋をやってたかもしれない。君と仲良くして、この同じ川辺に日曜に座って、まるで違う人間になってたかもしれない。そしたら僕も君にふさわしい男になれたよね、ビディ?」
ビディは船を見つめながらため息をつき、「ええ、私はそれほど気にしないもの」と答えた。あまりありがたい言い方ではなかったが、彼女の善意は分かっていた。
「でも、実際は」と私はさらに草を抜いて噛みながら続けた。「今の僕はこんなふうだ。不満で落ち着かなくて……誰にも『粗野で卑しい』なんて言われなかったら、そんなこと気にしなかったのに!」
ビディは突然私の顔を見つめ、さっきまで船を見ていたときよりもずっと真剣な眼差しを私に向けた。
「それは本当でもないし、礼儀正しい言葉でもないわ」と彼女はまた船に目を向けながら言った。「誰がそんなことを言ったの?」
私は、自分がどこへ話を持っていこうとしているのか自覚しないまま言葉がこぼれたことに動揺した。だが、今さらはぐらかすこともできず、「ミス・ハヴィシャムの家の美しい若い女性だよ。誰よりも美しくて、僕は彼女に夢中で、彼女のために紳士になりたいんだ」と答えた。こんな馬鹿げた告白をしてしまい、むしった草を川に投げ込み、自分も後を追おうかという気分になった。
「彼女に仕返しするために紳士になりたいの? それとも彼女の心をつかみたいの?」とビディは静かにたずねた。
「わからない」と私は沈んで答えた。
「もし仕返しのためなら――」とビディは続けた。「でも、ピップが一番よく分かってるだろうけど、何も気にしない方が、もっと独立してていいと思う。それにもし彼女を手に入れるためなら――私は思うけど、あなたがどう考えるかは別として――その人はそこまでして得る価値はないんじゃないかな」
まさしく自分でも何度も考えたことだった。その瞬間、私にはそれが完全に明白だった。しかし、どうして自分のような、混乱しきった村の若者が、賢い人たちでさえ毎日のように陥るあの素晴らしい矛盾を避けることができるだろうか。
「それが全部本当かもしれない」と私はビディに言った。「でも、僕は彼女に夢中なんだ。」
要するに、そのことを考えたとき、私はうつ伏せになり、頭の両側の髪をしっかりと掴んで、力いっぱい引っ張った。自分の心の愚かしさが非常に馬鹿げていて場違いだと分かっていたので、むしろ自分の顔を髪で持ち上げて、小石にぶつけてしまえばよかった、と本気で思った。それくらいの罰を受けて当然だった。
ビディは最も賢い少女で、もう私に理屈を言うのをやめた。彼女は、手仕事で少し荒れてはいたが、温もりのある手で、私の手を一つずつ髪からそっと外してくれた。それから静かになだめるように私の肩を優しく叩いた。私は袖に顔を埋めて少し泣いた――ちょうどあの醸造所の中庭で泣いた時と同じように――そして、誰か、あるいは皆にひどい扱いを受けている、という漠然とした思いにとらわれていた。自分でも誰にかは分からなかった。
「私が嬉しいのはね」とビディが言った。「あなたが私に心を打ち明けてくれたこと。それからもう一つ嬉しいのは、もちろんあなたが、私がその秘密を守るし、それにふさわしくあり続けると信じてくれること。もしあなたの最初の先生(まあ、いかにも出来の悪い先生で、自分自身が教わるべきだった人だけど)が今あなたの先生だったとしたら、何の課題を出すかは分かっているつもり。でも、それはきっと難しい課題で、あなたはもうその先生の手を離れてしまったから、今さら役には立たないの。」そう言って、ビディは静かに私のためにため息をつき、土手から立ち上がって、声に新しい明るさを加えて言った。「もう少し歩く? それとも帰ろうか?」
「ビディ!」私は立ち上がって彼女の首に腕を回し、キスをして叫んだ。「僕は何でも君に話すよ。」
「紳士になるまではね」とビディ。
「そんなはずないよ、僕は絶対なれっこない。それなら、ずっと話すってことだよ。そもそも話すことなんてほとんどないさ。君は僕の知っていることを全部知ってる――こないだ家でもそう言ったよね。」
「ふうん」とビディは、ほとんど囁くように言いながら、船の方を見つめた。そしてさっきのような明るい声で繰り返した。「もう少し歩く? それとも帰ろうか?」
私はもう少し歩こうとビディに言い、二人はそのまま歩いた。夏の午後はゆっくりと夏の夕べに移ろい、あたりはとても美しかった。私は、結局この状況の中にいる方が、止まった時計が並ぶ部屋でろうそくの灯りの下、隣人を妬みながらエステラに軽蔑されるより、ずっと自然で健全なのではないかと考え始めた。エステラやその他の思い出や空想を頭から追い出し、目の前の仕事に打ち込む決意を持てば、きっと自分にとって良いことだろうとも思った。もし今隣にいるのがビディでなくエステラだったら、果たして幸せだろうか、と自問すると、確実にそうでないと認めざるを得なかった。そして自分自身に「ピリップ、お前はなんて馬鹿なんだ」と言った。
私たちは歩きながら色々と話し、ビディの言うことはすべて正しいように思えた。ビディは決して人を侮辱したり、気まぐれに態度を変えたり、今日はビディで明日は誰か別人ということはなかった。彼女は私を傷つけることで喜びなど得ず、むしろ自分の胸を傷つける方を選ぶだろう。なのに、なぜ私は彼女の方をずっと好きになれないのだろうか。
「ビディ」と、家路を歩きながら私は言った。「君が僕を正しい方向に導いてくれたらいいのに。」
「私もそうできたらいいのに」とビディ。
「もし僕が君を好きになれたら――昔からの仲だけど、こんな率直な言い方しても気にしない?」
「まあ、全然気にしないわ!」とビディ。「気にしないで。」
「もし僕が自分をそう仕向けられたら、それが一番いいんだけど。」
「でも、きっと無理だと思うわ」とビディ。
その晩、数時間前だったら全くあり得なかったと思えたのに、今はそうでもないと思えてきた。だから私は、必ずしもそうとは限らないと答えた。だがビディは「絶対に無理よ」とはっきり言った。私は心の中で彼女の言う通りだと思いながらも、彼女がそこまで断言することに少し腹を立ててもいた。
墓地の近くまで来ると、堤防を越え、水門のそばの柵を越えなければならなかった。すると、門か草むらかぬかるみからか(彼にぴったりのよどんだ様子で)、オールド・オーリックがぬっと現れた。
「おい!」と彼はうなった。「お前ら二人、どこ行くんだ?」
「どこって、家に帰るに決まってるだろう?」
「じゃあな」と彼は言った。「お前らを家まで送ってやらなきゃ気がすまねぇ!」
この「気がすまねぇ」は彼のお気に入りの口癖だった。私の知る限りその言葉自体に特別な意味はなかったが、彼は自分の偽の洗礼名と同じように、人を侮辱し、何か野蛮で有害なものを連想させるために使っていた。もっと幼い頃、もし彼が本当に「気がすまねぇ」となったら、鋭くてねじれた釣り針で私を引っかけるのだろうと漠然と思っていた。
ビディは彼に一緒に来てほしくなくて、私に小声で「来させないで、好きじゃないの」と言った。私も彼が好きではなかったので、「ありがとう、でも送ってもらわなくていい」と言わせてもらった。彼はその言葉に大声で笑い、引き下がったが、少し離れてついてきた。
ビディが、私の姉が説明できなかったあの殺人未遂事件に彼が関わっていると疑っているのか知りたくて、なぜ彼が嫌いなのか尋ねた。
「あのね」とビディは肩越しに彼を見ながら答えた。「私――私、彼が私のこと好きみたいで怖いの。」
「彼がそんなこと言ったのか?」と私は憤慨して聞いた。
「いいえ」とビディはまた肩越しにちらりと見て答えた。「そんなこと言われたことはないけど、目が合うといつも私に踊って見せるの。」
こんな変わった愛情表現だったが、私はその解釈が正しいと疑わなかった。私はオールド・オーリックが彼女を好きだと知って、まるで自分への侮辱のように怒りを覚えた。
「でも、それがあなたに何か関係ある?」とビディは冷静に言った。
「ないよ、ビディ、関係ない。ただ、気に入らないだけだ。賛成できない。」
「私も賛成できない。でも、それもあなたに関係ないでしょ。」
「そうだね」と私は言った。「でも、もし君が自分からそんな目で見られるのを許したら、君に対する評価は変わるよ。」
その夜以来、私はオーリックに注意するようになり、彼がビディに「踊り」を見せそうなときには、間に立って妨害した。彼は私の姉が突然気に入ったことで、ジョーの仕事場に居着いていたが、そうでなければ私は彼を追い出そうとしただろう。彼も私の意図をよく理解し、後々私も彼がそれを認識していることを知ることになる。
だが、もともと混乱していた私の心は、これでさらに五万倍も複雑になった。なぜなら、ある時期や季節になると、ビディはエステラより遥かに優れているし、自分が生まれ育った素朴で正直な労働者としての人生には恥じるべきことなど何もなく、自己尊重と幸福を得るのに十分だ、と確信したからだ。そういうときには、親愛なるジョーや鍛冶場への反発は消え、自分はジョーと共に働き、ビディと人生を共にする道を歩み始めていると心から思うのだった――が、突然、ハヴィシャム時代の記憶が破壊的な飛び道具のように降りかかり、私の心はまた粉々にされてしまう。散らばった心はなかなか拾い集められず、やっとまとまったと思った矢先に、「もしかしたらミス・ハヴィシャムが僕の将来を作ってくれるかもしれない」といった思いが浮かんで、また四散してしまうのだった。
もし「その時」が来ても、私はきっと迷いの真っ只中にいたに違いない。しかしその時は決して来ず、不意に早く終わることになる――これからそれを語る。
第十八章
ジョーの下での徒弟生活も四年目、ある土曜の夜だった。スリー・ジョリー・バージメンの暖炉の周りに、人々が集まっていた。みなウォプスル氏が新聞を音読するのに耳を傾けており、私もその一人だった。
世間を騒がせる殺人事件があり、ウォプスル氏は眉まで血まみれのような熱演ぶりだった。彼は記述のすべての忌まわしい形容詞を舐めるように味わい、検死の証人たち一人一人になりきっていた。被害者役では「もうだめだ……」とうめき、殺人者役では「覚えていろ!」と野蛮に怒鳴った。地元のお医者さんを真似て医師証言をし、高齢の料金所番を演じては震え上がり、まるでその証人の精神状態に疑いを抱かせるほどだった。ウォプスル氏の手にかかれば、検死官は『アテネのティモン』、警吏は『コリオレイナス』となった。彼は存分に楽しみ、私たちもみな心地よいひとときを過ごし、「故意による殺人」の評決にたどり着いた。
そのとき、初めて気がついたのだが、変わった紳士が私の向かいのベンチの背もたれによりかかり、私たちを見ていた。彼の顔には軽蔑の色があり、人々の様子を見ながら太い人差し指の側面を噛んでいた。
「さて」とその紳士は朗読が終わるとウォプスル氏に言った。「すべてご満足の結果におさまったことだろう?」
みな驚いて顔を上げた。まるで殺人者その人かのように。紳士は冷たく皮肉そうに全員を見回した。
「有罪、当然だろう?」と彼。「さあ、言え。さあ!」
「失礼ですが」とウォプスル氏は答えた。「あなた様とは面識ございませんが、私は有罪だと思います。」これを受けて、私たち全員が勇気を出して賛同のざわめきをあげた。
「分かっている」と紳士。「そうなると思っていた。だが、質問をしよう。イギリスの法律では、すべての人は有罪と証明されるまでは無罪とされるということを、君は知っているか、知らないのか?」
「私は……イギリス人として……」とウォプスル氏は言いかけた。
「さあ!」と紳士は人差し指を噛みながら。「質問をはぐらかすな。知っているか、知らないか。どっちだ?」
彼は頭も体も横に傾けた強圧的な尋問口調で、ウォプスル氏に指を突き付け、また噛んだ。
「さあ、知っているのか、いないのか?」
「もちろん知っています」とウォプスル氏。
「もちろん知っている。なら、最初からそう言えばいい。次の質問だ。」――ウォプスル氏を自分のもののように扱いながら――「これらの証人は、まだ誰も反対尋問を受けていないということを、君は知っているか?」
ウォプスル氏が「それについては……」と言いかけると、紳士は遮った。
「何だ? イエスかノーかで答えられないのか? もう一度聞く。よく聞け。これらの証人が誰も反対尋問を受けていないということを知っているか? イエスかノーか、一言だけでいい。」
ウォプスル氏はためらい、私たちはみな彼への評価を下げ始めた。
「よし」と紳士は言った。「手助けしよう。それに値しないが、手助けしよう。君が持っているその紙を見てみろ。それは何だ?」
「何だと言われましても……」とウォプスル氏は困惑して紙を見た。
「それは」と紳士はさらに皮肉な調子で言った。「さっき君が読んでいた印刷物か?」
「間違いありません。」
「間違いない。では、その紙を見て、被告が弁護人から一切弁護を控えるよう指示されたとはっきり記されているかどうか、目で追って確かめてみろ。さあ、どうだ?」
ウォプスル氏は「今読んだところですが」と弁解した。
「さっき読んだことなどどうでもいい。私は何を読んだかは聞いていない。主の祈りを逆さに読んでもいいし、今日すでにやったかもしれない。紙を見ろ。いや、段落の頭じゃなくて、下の方だ。そうだ、その下だ。」(私たちはウォプスル氏にごまかしがあると思い始めた。)「どうだ? 見つかったか?」
「ここです」とウォプスル氏。
「目でその箇所を追ってみて、弁護人から一切弁護しないよう指示されたと、はっきり書いてあるかどうか、教えてくれ。さあ、どうだ?」
ウォプスル氏は「正確な言葉ではありません」と答えた。
「正確な言葉ではない!」と紳士は辛辣に繰り返した。「だが、要旨は合っているのか?」
「はい」とウォプスル氏。
「はい」と紳士は右手をウォプスル氏に向け、我々全員を見回した。「それで、目の前にその一文がありながら、他人を弁明も聞かずに有罪と断じる人間の良心を、君はどう思う?」
私たちは皆、ウォプスル氏は思ったほどの人物ではなく、化けの皮が剥がれてきたと疑い始めた。
「さらに覚えておけ」と紳士はウォプスル氏に重々しく指を突き付け続けた。「そのような人物が、実際にこの裁判の陪審員に選ばれる可能性がある。そしてそうやって深く偏見を持ったまま帰宅し、家族のもとで、証拠に基づいて正しい評決を下すと神に誓っておきながら平気で枕を高くして眠るかもしれないのだ!」
私たちは皆、気の毒なウォプスル氏が度を越したと強く感じ、もうやめた方がいいと思った。
その紳士は、否応なく従わせる威厳と、私たち一人一人の秘密を握っていて暴露すれば一巻の終わりだという態度で、ベンチの背もたれから離れ、暖炉前のスペースに出てきた。左手をポケットに入れ、右手の人差し指を噛みながら立った。
「私の得た情報によると」と彼は全員を見回しながら言った。「ここにジョセフ――もしくはジョー・ガージェリーという名の鍛冶屋がいるはずだ。どれか?」
「わしだ」とジョーが答えた。
紳士は彼を手招きし、ジョーが出てきた。
「君の弟子で、通称ピリップという若者がいるな? 彼はいるか?」
「ここにいます!」と私は叫んだ。
その紳士は私に気付かなかったが、私は彼をすぐに思い出した。ミス・ハヴィシャムの元へ二度目に訪れた際、階段で出会ったあの紳士だった。私がベンチ越しに彼を見た瞬間から分かっていたし、今彼が私の肩に手を置いて向き合ったときも、彼の大きな頭、浅黒い肌、落ちくぼんだ目、濃い黒い眉、太い時計の鎖、顎や頬のごつごつした黒いひげ、そして大きな手から漂う香料入り石けんの匂いまで、細部まで思い出した。
「君たち二人と個人的に話したい」と彼は言った。「少し時間がかかる。君たちの家で話そう。ここで内容を先に漏らすつもりはない。後で友人たちにどれだけ話すかは自由だが、私は関知しない。」
みなが驚きのまま、私たち三人は静かにスリー・ジョリー・バージメンを出て、静かに家に向かった。歩く途中、紳士はときおり私を見ては指を噛んだ。家が近づくと、ジョーは状況の厳粛さを無意識に感じてか、先に行って玄関の扉を開けた。応接間で会談は行われた。そこはかろうじて一本の蝋燭の光がともっていた。
会談は、紳士がテーブルに座り、蝋燭を手元に寄せて手帳の記載を見直すことから始まった。その後、手帳をしまい、蝋燭を少し脇に置き、暗がりの中の私とジョーを見分けるように顔を覗き込んだ。
「私の名はジャガーズと言い、ロンドンの弁護士だ。まあ、そこそこ名は知られている。特殊な用件で来た。私自身の発案ではない。私に意見を求められていたら、ここへは来なかっただろう。だが求められず、私はここにいる。私は依頼人の密命を受け、その任務だけを果たす。それ以上でも、それ以下でもない。」
彼はこちらを見やすくするため、椅子の背に片足をかけ、もう片方は床につけて肘をのせた。
「さて、ジョセフ・ガージェリー。私は君の弟子を引き取る申し出を伝える役だ。もし本人の希望と利益のためなら、君は彼との契約を解消しても異存はないか? そのことで何か欲しいものはあるか?」
「いや、ピリップの邪魔をしたくて何か求めるなんて、とんでもない」とジョーはきょとんとしながら言った。
「神への誓いは結構だが、本質からはずれている」とジャガーズ氏。「要は、君が何か欲しいかどうか、だ。」
「答えはノーだ」とジョーはきっぱり言った。
ジャガーズ氏は、ジョーの無欲さを愚かだと考えているかのように見えたが、私は好奇心と驚きで混乱しており、それを確信する余裕はなかった。
「よろしい」とジャガーズ氏。「今の発言を覚えておけ。後で翻すなよ。」
「誰が翻すもんか」とジョー。
「そう言うつもりはない。君は犬を飼っているか?」
「飼っている。」
「では覚えておけ。自慢は良い犬だ、だが頑固はもっと良い犬だ。それを覚えておくんだな」とジャガーズ氏は目を閉じ、うなずいた。「さて、次はこの若者について。伝えるべき内容は、彼が大いなる期待を持つ身となったということだ。」
ジョーも私も息を呑み、互いを見つめ合った。
「私は彼に伝えるよう指示されている」とジャガーズ氏は私を指差して言った。「彼は相当な財産を得ることになる。さらに、現在その財産を持つ人物の望みで、直ちに今の環境から離れ、紳士として育てられる――つまり、大いなる期待を持つ若者としてだ。」
私の夢が叶った。荒唐無稽な空想すら現実に及ばなかった。ミス・ハヴィシャムが私の運命を大きく切り開いてくれるのだ。
「さて、ピリップ君」と弁護士は続けた。「これから君に言うことは、まず第一に、指示を出している人の希望で、君は常にピリップという名を名乗ること。これは簡単な条件だが、もし異議があれば今言いたまえ。」
私は心臓が早鐘のように打ち、耳鳴りがして、かろうじて異議はないと口ごもった。
「そうだろう! 次に、君の寛大な後見人の名前は、本人が明かすまで絶対の秘密だ。本人は君自身に直接名乗るつもりだが、それがいつどこでかは分からない。何年も先かもしれない。いずれにせよ、この件について何の問い合わせも、遠回しな言及も、一切禁じられている。もし心当たりがあっても胸にしまっておくこと。この禁止の理由が何であれ、それを君が詮索することは許されない。これが条件だ。君がそれを受け入れ、厳守することが求められる。もし異議があれば、今言いたまえ。」
私は再び、なんとか異議はないと口ごもった。
「そうだろう! さて、条件の話は終わりだ。」彼は私を「ピリップ君」と呼び、表面上は親しげに振る舞い始めたが、依然として強圧的な疑いの雰囲気があり、時折目を閉じて私に指を突き付け、必要なら私の不利になることを何でも知っていると示唆するようだった。「さて、具体的な手配の話に移ろう。『期待』という語を何度か使ったが、単なる期待だけではない。すでに私の手元に、君の教育と生活に十分な資金が預けられている。私は君の後見人としてふるまう。ああ!」(私がお礼を言いかけると)「私は報酬をもらうからこの任務を引き受けるだけだ。君は立場にふさわしい教育を受ける必要があるとみなされている。すぐに始めるべきだ。」
私は、前からずっと望んでいたと答えた。
「それはどうでもいい、ピリップ君。今望んでいるならそれでいい。すぐに適任の教師に預けられてもよいな?」
私はどもりながら「はい」と答えた。
「よろしい。君の希望も考慮するが、それが賢明だとは思わないが、私の任務だ。誰か希望する教師はいるか?」
私はビディとウォプスル氏の大叔母しか知らなかったので、否定した。
「私が多少知っているある教師が目的に合うと思う」とジャガーズ氏。「推薦はしないが、名前を挙げておこう。その人物はマシュー・ポケット氏だ。」
ああ、その名をすぐに思い出した。ミス・ハヴィシャムの親戚。カミラとその夫が話していたマシュー。ミス・ハヴィシャムの葬儀の際、棺の傍らにいるべきマシュー。
「名前を知っているのか?」とジャガーズ氏は鋭い目つきで私を見て、答えを待つ間は目を閉じた。
私はその名を聞いたことがあると答えた。
「ふん。名前を聞いたことがある、と。でも問題は、どう思うかだ。」
私は、彼の推薦に感謝していると――
「いや、若いの!」と彼は大きな頭をゆっくり振って遮った。「よく考えろ。」
私は同じく感謝していると――
「違う、若いの」と彼は同時に眉をひそめ、微笑んで言った。「それはうまくできているが、ダメだ。私は推薦したわけじゃない。ほかの言い方を探せ。」
私は訂正して、マシュー・ポケット氏を挙げてくれたことに感謝していると答えた。
「それだ!」とジャガーズ氏。「その紳士にぜひ会ってみるがよい。」
「分かりました。その方の家でお試ししたいです。」私はそう答えた。
「よろしい。ロンドンにいるその息子にまず会うといい。準備しておく。ロンドンにはいつ来る気か?」
私は(固まったままのジョーに目をやりつつ)すぐにでも行けるはずだと答えた。
「まず、新しい服が必要だ。作業着は不可だ。一週間後にしよう。金もいるな。二十ギニー置いていこうか?」
彼は平然と長い財布を出し、テーブルに金貨を数えて私の前に押し出した。これが彼が初めて椅子から両足を下ろした瞬間だった。金を渡してからは椅子にまたがって座り、財布を振りながらジョーを見た。
「ジョセフ・ガージェリー、呆然としているな?」
「しているとも!」とジョーはきっぱり言った。
「君が何も欲しくないと約束したな?」
「した。今も同じだ。これからもそうだ。」
「だがもし私の指示で、贈り物をしろと言われていたとしたら?」
「何の補償だ?」とジョー。
「彼の労働力の損失に対してだ。」
ジョーは私の肩に、まるで女性のような優しいタッチで手を置いた。私は後に、彼の優しさと力強さを合わせ持つ様子を、蒸気ハンマーにたとえて思い出す。「ピリップは、名誉と幸運のためなら、自由にしてやることが何よりの喜びだ。言葉では言い尽くせん。でも、金で埋め合わせができると思うなら――あの子が鍛冶場に来てくれて、ずっと最高の友だったことに――」
ああ、愛すべきジョーよ。私はあんなに簡単に君を捨て、感謝もせずに去ろうとしていた。今も、力強い鍛冶屋の腕が君の顔を覆い、広い胸が大きく上下し、声がか細く消えていく姿を思い出す。誠実で、優しい、忠実なジョーよ。君の手の震える温もりを、この日も天使の羽音のように感じる。
しかし私はその時、ジョーを元気づけようとした。私は自分の未来に夢中で、これまで二人で歩いてきた道を振り返る余裕がなかった。私はジョーに慰めてくれと頼み、(彼が言ったように)ずっと親友であったし、(私が言ったように)これからもそうであると述べた。ジョーは涙を拭い、それ以上何も言わなかった。
ジャガーズ氏は、まるでジョーを村の間抜け、私をその後見人であるかのように見ていた。ひとしきり静かになった後、彼は財布を手にして言った。
「さて、ジョセフ・ガージェリー、これが最後の機会だ。私に中途半端は通用しない。贈り物を受ける気があるなら、はっきり言え。なければ――」ここで彼は驚いた。ジョーが突如、戦いを挑む構えで彼を取り巻いたからだ。
「もし俺の家でいちゃもんつけてくるなら、出てけ! 男ならかかってこい! 俺の言うことは言った通りだ!」
私はジョーを引き離すと、彼はすぐに穏やかになった。ただ私に、「自分の家でいじめられる気はない」と穏やかに念を押しただけだった。ジャガーズ氏はジョーの挑発に立ち上がり、ドアのそばまで引いた。もう中に戻るそぶりも見せず、そこで最後の言葉を述べた。
「さて、ピリップ君、君は紳士になるのだから、できるだけ早くここを出た方がいい。一週間後にしよう。その間に私の住所を送る。ロンドンの乗り合い馬車事務所から乗って直接私のもとへ来なさい。私はこの役目に意見を持たない。ただ報酬をもらって引き受けている。それだけだ。いいか、よく理解するように。」
彼は私たち二人に指を突き付け、ジョーが危険だと思ったのか、そのまま立ち去った。
私はふと思い立ち、彼が雇い馬車の残るバージメンの方へ行くのを追いかけた。
「すみません、ジャガーズさん。」
「おお、どうした?」
「先生の指示に従いたいので、確認をと思いまして。出発までに、知人に別れを告げてもよろしいでしょうか?」
「かまわん」と彼は、いまひとつ理解していない様子で答えた。
「村だけでなく、町の方にも?」
「かまわん。」
私は礼を言って家に戻った。するとジョーはすでに玄関を施錠し、応接間を空け、台所の暖炉の前で膝に手を置き、じっと燃える石炭を見つめていた。私も火の前に座り、しばらく何も言わず石炭を見つめていた。
姉はいつもの椅子に座り、ビディは暖炉の前で針仕事をしていた。ジョーはビディの隣、その隣に私は座り、姉の向かいの隅だった。火を見つめるほど、どうしてもジョーの顔を見られなくなり、沈黙が長引くほど何も言い出せなくなった。
やっとのことで、「ジョー、ビディに話した?」と聞いた。
「いや、ピリップ」とジョーはまだ火を見つめながら、膝をしっかり握りしめて答えた。「お前に任せたんだ、ピリップ。」
「ジョーが言ってくれればよかったのに。」
「ピリップはこれで幸運な紳士になった」とジョーは言った。「神のご加護を!」
ビディは手仕事を落とし、私を見た。ジョーも膝を握りしめて私を見た。私は二人を見返した。しばらくして、二人は心から私を祝福してくれたが、そこにはどこか寂しさが混じっていて、私は少し反発を覚えた。
私はビディ(そしてビディを通してジョーにも)に、「自分の運命を作ってくれた人については、何も知ろうとも口にもしない」という重大な義務を強調した。それはいつか明らかになるだろうが、それまでは「謎の後援者によって大いなる期待を得た」とだけ話してほしいと伝えた。ビディは火を見ながら深くうなずき、特に注意するという。ジョーも「うん、ピリップ、俺も特に気をつける」と答え、再度祝福し、私が紳士になることに驚き続けていたので、私はあまりいい気分ではなかった。
その後、ビディは姉に起きた出来事を何とか伝えようと大変な努力をしたが、私の見た限り、その努力は全く実らなかった。姉は何度も笑ってうなずき、「ピリップ」「財産」とビディの言葉を繰り返したが、選挙の掛け声程度の意味しか込められていなかったとしか思えず、これ以上彼女の精神状態を暗く描写する術はない。
自分が経験していなければ信じられなかっただろうが、ジョーとビディが元の明るさを取り戻すにつれ、私は反対にどんどん憂鬱になっていった。自分の運命に不満があるわけではないが、もしかしたら自覚せずに自分自身に不満だったのかもしれない。
いずれにせよ、私は肘を膝に、顔を手に埋めて火を見つめていた。二人は私の旅立ちや留守中どうしようかを語り、私がちらりと視線を感じて顔を上げると、(特にビディはよく私を見ていた)どんなに好意的な眼差しでも、それに傷ついた。まるで私を信じていないと言われているような気がしたのだ。もちろん、二人がそんなことを言葉や態度で示したことなど一度もなかったのに。
そんな時は、立ち上がって戸口から外を眺めた。台所の扉はすぐ外に通じ、夏の夕べには換気のため開け放しにしてあった。そのとき見上げた星々さえ、私が今まで暮らしてきた田舎の景色に輝くには、どこか貧しくささやかな輝きにしか見えなかった。
「土曜の夜だ」と私は、パンとチーズとビールの夕食を囲んで言った。「あと五日で、その前の日だ! すぐだね。」
「ああ、ピリップ」とジョーはビールのマグ越しにややこもった声で。「すぐだな。」
「すぐ、すぐだね」とビディ。
「ジョー、月曜に町へ行って新しい服を注文したら、その場で着替えるか、パンブルチュークの家に送ってもらおうと思う。ここの人たちにじろじろ見られるのは嫌だから。」
「ハブル夫妻も、お前の新しい紳士姿を見たいかもな、ピリップ」とジョーは手のひらでパンを切りながら、私の手つかずの夕食を見て、昔パンの厚さを比べ合ったことを思い出しているようだった。「ウォプスルもそうかも。バージメンの連中もきっと歓迎してくれるだろう。」
「それが嫌なんだよ、ジョー。みんな大騒ぎして、下品で俗っぽい騒ぎになる。自分が自分じゃなくなりそうだ。」
「それはその通りだ、ピリップ。自分を我慢できなくなるなら――」
ビディが、姉の皿を手に持ちながら私に尋ねた。「ガージェリーさんや、お姉さんや、私たちに、いつ顔を見せてくれるか、考えたことはある? 顔を見せてくれるでしょう?」
「ビディ、」私はやや腹立たしげに返した。「君は本当に頭の回転が早いから、ついていくのが難しいよ。」
(「昔から頭が回る子だったさ」とジョーが口を挟んだ。)
「もうちょっと待ってくれたら、ビディ、僕がこう言うところだったんだ。服を束にして、ある晩ここに持って来るつもりだって。たぶん、旅立つ前の晩になると思う。」
ビディはそれ以上何も言わなかった。私は素直に彼女を許し、ほどなくして彼女とジョーに愛情を込めておやすみを言い、自分の部屋へ上がった。小さな部屋に入り、しばらく腰を下ろして見つめた。やがて永遠に別れることになる、取るに足らない部屋だが、いま自分はそこから飛び立とうとしている。この部屋には新しい思い出も満ちていて、それなのに、ここからこれから行くもっと素晴らしい部屋への思いの間で、かつて鍛冶場とミス・ハヴィシャムの屋敷、ビディとエステラの間で揺れ動いたのと同じような、複雑な心の分裂に陥った。
その日の陽は一日中屋根裏部屋の屋根を明るく照らしており、部屋は暖かかった。窓を開けて外を見下ろすと、ジョーが暗い戸口からゆっくり出てきて、外の空気に当たりながら何度か往復しているのが見えた。続いてビディが現れ、パイプを持ってきて火をつけてやった。ジョーがこんな遅くに煙草を吸うことは普段なかったので、何か慰めが欲しいのだろうと察した。
やがて彼は私の真下の戸口に立ち、パイプをくゆらせていた。ビディもそばで静かに話しかけていた。二人が私の名前を何度も愛情をこめて口にしているのが聞こえたので、私のことを話しているのだとわかった。もっと聞こえていても、これ以上は耳を傾けなかっただろう。私は窓から離れ、ベッドの脇の一脚しかない椅子に座った。輝かしい未来の初めての夜が、これほど孤独であったことが、とても悲しく、奇妙だった。
開け放たれた窓を見やると、ジョーのパイプの煙が薄くたなびいていた。それはまるで、ジョーからの祝福のように感じられた。押しつけがましくも、見せびらかされるでもなく、ただ私たちが共に分かち合う空気にしみ渡っていくようだった。私は明かりを消してベッドにもぐりこんだが、その寝床はもう落ち着かず、二度とあの頃の熟睡を得ることはなかった。
第十九章
朝になると、人生の見通しが大きく変わり、すっかり明るくなったので、もはや同じものとも思えなかった。私の心に最も重くのしかかっていたのは、出発まで六日間も間が空いていることだった。なぜなら、その間にロンドンに何か起きてしまい、到着したときには、ひどく荒廃しているか、完全に消えてしまっているのではないかという不安がぬぐえなかったからだ。
ジョーもビディも、私たちの別れの話をすると、とても思いやり深く朗らかだったが、それは私が話し出したときだけだった。朝食のあと、ジョーが応接間の棚から私の徒弟契約書を持ち出し、私たちはそれを暖炉にくべた。これで私は自由の身となった。解放されたばかりの新鮮な気持ちのまま、ジョーと教会へ行き、もし牧師が私の事情を知っていたら「金持ちが天国に入るのは……」のくだりは読まなかったろうと思った。
昼食のあと、私はひとりでぶらぶらと出かけ、湿地帯ときっぱり縁を切ろうと決めた。教会の前を通ると、(朝の礼拝でも感じたことだが)これからも毎週日曜日ごとに、ここに通い、その生涯を終え、やがては低い緑の丘の下に静かに葬られることになるこの貧しい人々に、崇高な憐れみを感じた。いつか彼らのために何かしようと心に誓い、村の全員にローストビーフとプラムプディングのディナー、エール一品脱、そして優越感をたっぷり贈る計画をおぼろげに立てたりした。
かつてあの墓地で足を引きずる逃亡者と出会ったことを、これまで恥ずかしさ混じりに思い出すことがしばしばあったが、この日曜、その場所であのみすぼらしく震え、足枷と罪人の札をつけた男を思い起こした今は、いっそう複雑だった。だが、あれはもうずっと昔のこと、きっと遠くに流刑され、私にとってはすでに死んだも同然、いやきっと本当に死んでいるだろうと慰めた。
もう湿った低地とも、堤防とも、水門とも、草を食む牛たちともお別れだ――彼らも鈍いながらもどこか敬意を帯びた様子で、偉大な「大きな期待」を持つ者を、できるだけ長く見つめているようだった。幼い日の単調な友よ、さようなら、これからはロンドンと偉業のために進むのであって、鍛冶屋の仕事や君たちのためではない! 私は誇らしげに砲台跡へ向かい、ミス・ハヴィシャムが私をエステラのために育てているのかどうかを考えながら横になり、眠ってしまった。
目を覚ますと、ジョーが隣に座ってパイプをくゆらせていたので驚いた。私が目を開けると、ジョーはにこやかに言った。
「最後だからな、ピップ、ついてきたんだ。」
「ジョー、来てくれて本当にうれしいよ。」
「ありがとな、ピップ。」
「親愛なるジョー、」私たちが握手したあとで私は続けた。「君のことは決して忘れないよ。」
「いやいや、ピップ!」とジョーは安心した声で言った。「それは確かだよ。ああ、坊や、祝福を。人間の心にしっかり刻みこめば、疑う余地はない。だが、ここまで急に変わると、それをきちんと理解するまでに、少し時間がかかっただけだ。そうだろう?」
なぜか私は、ジョーがあまりにも自分に自信を持っていることに満足できなかった。もっと感情をあらわにしたり、「それは立派だぞ、ピップ」とか言ってくれた方がよかったのに。だから最初の話題には触れず、変化が突然だったことだけ認め、「前からずっと紳士になりたいと思っていて、もしそうなったらどうするか、よく考えていた」とだけ答えた。
「そうかい?」とジョー。「こりゃ驚いた!」
「今になって思えば、ジョー、あの頃ここで勉強して、もう少し頑張ればよかったって、ちょっと残念だよね?」
「いや、どうかな」とジョー。「俺は本当に物覚えが悪いからな。自分の仕事しかわからない。物覚えが悪かったのは、昔から変わらないし、今さら惜しいとも思わないよ。ちょうど一年前と同じさ、わかるだろ?」
私の本意は、いずれ財産を手にしたときにジョーに何かしてあげるとして、もしジョーがもっと教養や礼儀を身につけていれば、なおよかったのに、ということだった。だがジョーは私の気持ちをまったく察していないようだったので、代わりにビディに話してみることにした。
私たちは家まで歩き、お茶を飲んだあと、私はビディを小道沿いの小さな庭に誘い、彼女の気持ちを高めようと一般的な話を切り出したあと、頼みごとをした。
「それでね、ビディ」と私は言った。「ジョーを少しでも助けてやってほしいんだ。」
「どうやって助けるの?」とビディが静かな目で訊いた。
「いや、ジョーは本当にいい人だよ――いや、きっと世界一素晴らしい人だと思ってる――でも、いくつかの点ではちょっと遅れをとっている。たとえば、ビディ、勉強とかマナーの面でね。」
私はビディの顔を見ながら話していたし、彼女は大きく目を見開いたが、私を見返しはしなかった。
「まあ、マナーね! ジョーのマナーじゃ不十分なの?」とビディは黒スグリの葉を摘んだ。
「ビディ、ここでは十分さ――」
「ここでは十分なの?」とビディは手元の葉を見つめながら口を挟んだ。
「最後まで聞いてくれ――でも、もし僕が財産を手にして、ジョーをもっと高い身分に引き上げようとしたときには、今のままのマナーでは彼のためにならないと思うんだ。」
「でもジョーはそれをわかってるんじゃない?」とビディが言った。
それは非常に苛立たしい質問だった(私にはそんな発想はまったくなかった)ので、私は語気を荒げて言った。
「ビディ、どういう意味だい?」
ビディは葉を手で細かくもみほぐしていた――黒スグリの茂みの匂いは、あの小さな庭のその夜を私にいつも思い出させる――そしてこう言った。「彼は誇り高いのかもしれないって、考えたことは?」
「誇り高い?」私は軽蔑を込めて繰り返した。
「誇りにもいろいろあるのよ」とビディは真正面から私を見て、首を振った。「誇りは一つじゃない――」
「それで? なぜ黙るんだ?」と私は言った。
「一つじゃないの」とビディは続けた。「自分ができることを、自分でしっかり務めている場から、誰にも引き上げられたくない、そういう誇りもあるの。正直に言うと、私はジョーがそうなんじゃないかと思う。私がこんなこと言うのは生意気かもしれないけど、あなたの方がずっとジョーをよく知っているはずだもの。」
「ビディ、それは残念だな。君がそんなふうになっているとは思わなかった。僕は君に嫉妬心とやっかみを感じるよ。僕が出世するのが面白くないんだろう?」
「そう思うなら、そう言えばいいわ。何度でも言えばいいわよ」とビディは答えた。
「君がそうだっていうなら、同じだろう。僕を責めないでくれ。僕は本当に残念だし、それは人間の悪い面だよ。君には、僕がいなくなったあとも、ジョーの成長を助けてほしかったんだけど、もう何も頼まない。残念だ、本当に人間の悪い面だ」と私は繰り返した。
「あなたが私を叱ろうと、褒めようと、私はここでできる限りのことをするつもりよ。そしてあなたが私にどんな印象を持って行っても、あなたを思い出す気持ちは変わらないわ。でも、紳士なら不公平であってはいけないわ」とビディは顔を背けた。
私はまた熱心に「それは人間の悪い面だ」と繰り返した(実際、後になって私はその考え自体は間違いではなかったと認めるが)、そして小道を歩いてビディから離れ、ビディは家へ、私は庭の門から外へ出て、夕食まで気の抜けた散歩をした。またしても、輝かしい未来の二度目の夜が、最初の夜と同じように孤独で満たされないものになったのを悲しく、奇妙に感じた。
だが、朝がまたもや私の景色を明るくし、私はビディにも寛大になり、この話題は水に流された。私は持っている中で一番良い服を身に着け、できるだけ早く町に出て店が開くのを待ち、トラッブさんの仕立屋に出向いた。トラッブさんは店の奥の居間で朝食をとっており、わざわざ出てきもしなかったが、私を招き入れた。
「やあ!」トラッブ氏は馴れ馴れしい調子で言った。「元気かい、今日は何の御用だ?」
トラッブさんは焼きたてのロールパンを三つに割り、バターをはさんで布団のようにし、覆いをかけていた。彼は裕福な独身男で、開けた窓の向こうには豊かな庭と果樹園があり、暖炉の横には鉄製の金庫が壁に埋め込まれていた。そのなかに繁栄の証が袋で詰まっているのだろうと私は思った。
「トラッブさん、こういう話をするのは自慢みたいで嫌なんですが、実はかなりの財産を手に入れまして」と私は言った。
トラッブ氏の態度が変わった。彼はベッドのバターを忘れて立ち上がり、テーブルクロスで手を拭き、「なんとまあ!」と叫んだ。
「私はロンドンの後見人のところへ行くので」と私は何気なく懐から金貨を取り出してみせながら言った。「それに見合う流行の服を新調したい。代金は現金で支払いたいんです」――さもなければ、作るふりをされるだけかと思ったので、念を押した。
「どうぞご心配なく」とトラッブ氏は丁重に身をかがめ、両肘の外側に手を置いて言った。「おめでとうございます。どうぞ店のほうにお入りください。」
トラッブさんの店員の少年は、そのあたり一帯で最も生意気な子だった。私が入店した際、彼は店内を掃いており、掃除中に私の上も掃いていった。私がトラッブ氏と店内に戻ったときもまだ掃いており、あらゆる角や障害物にほうきをぶつけては、鍛冶屋に対等であることを示しているようだった。
「その騒ぎをやめろ!」とトラッブ氏は厳しく命じた。「さもないとぶっ飛ばすぞ! ――どうぞおかけください。さて、これは」と彼は布を取り出し、カウンターの上に流れるように広げて光沢を見せた。「とても上質な品ですよ。貴方にぴったりで、超高級でございます。でも他のも見せましょう。4番を持ってこい!」(少年に、恐ろしい形相で。)
トラッブ氏は少年が4番をカウンターに置き安全な距離に下がるまで、決して目を離さなかった。続いて5番、8番を命じ、「ここでイタズラしたらただじゃおかないぞ」と言った。
彼は4番の布を丁寧に勧め、夏用として貴族や紳士に人気で、地元の名士――もし私をそう呼ばせてもらえれば――が着てくれるなら名誉だ、と言った。「5番と8番を持ってきてるのか、このごろつき!」とトラッブ氏はまた少年に怒鳴った。
私はトラッブ氏の助言を受けて生地を選び、再び居間で寸法を測られた。既に私の寸法は把握していたはずだが、「今の状況下では使えません、全然」と言い訳しながら、まるで私が大規模な地所で彼が一流の測量師であるかのように、入念に計測してくれた。彼の労力に見合う服などこの世にあるのか、と思うほどだった。ようやく終わると、木曜の夕方にパンブルチューク氏宅に届ける段取りを決め、彼は居間の鍵に手をかけて言った。「ロンドン紳士が地元の品を贔屓にしないのは当然ですが、たまに町の者としてご贔屓くだされば光栄です。ありがとうございました――ドア!」
この「ドア!」は少年に向けたが、少年は意味が分からなかったようだった。だが私は、主人が私の埃を手で払い落とすのを見て、金銭の力が道徳的にトラッブ少年の背にのしかかったのを実感した。
この記念すべき出来事の後、私は帽子屋、靴屋、靴下屋を回り、まるでマザー・ハバードの犬のように、多くの店の世話になる羽目になった。さらに馬車の切符も取り、土曜の朝七時発の便に席を確保した。どこでも財産の話をする必要はなかったが、一言漏らせば、店主は窓の外の通行人から私だけに集中した。注文をすべて終え、パンブルチューク氏の店へ向かうと、彼は待ち構えていた。
彼は待ちきれない様子だった。朝早く馬車で出かけ、鍛冶場にも立ち寄って事情を聞いていた。バーンウェルの応接間で私のために食事を用意し、私が通るときは「通路からどけ」と店員にも命じた。
「親愛なる友よ!」とパンブルチューク氏は二人きりになって両手で私の手を握りしめた。「おめでとう、当然の幸運だ、当然だ!」
率直で、良い表現だと思った。
「思えばこの私が、この道へ導く謙虚な道具だったとは、誇りに思うよ」としばし私を見つめたあとで言う。
私は「二度と言及しないでほしい」と念を押した。
「親愛なる若い友よ」とパンブルチューク氏。「もし君がそう呼ばせてくれるなら――」
「もちろん」と私は返すと、彼は再び両手で私の手を握り、感極まったように胴着のあたりを動かした(だいぶ下の方だったが)。「親愛なる若い友よ、不在中は私の力の限り、ジョセフ――ジョセフ! ジョセフ!!」と哀れむように繰り返し、首を振っては彼の限界を示した。
「だが、親愛なる若い友よ、お腹が空いているだろう、疲れているだろう。どうぞ、お座りください。これは宿屋から取り寄せた鶏、これも舌肉、他にもいくつか取り寄せたものがあるが、どうか軽蔑なさらずに。だが私は――もしかして――」
この「もしかして」は握手してもいいかの意味だった。了承すると彼は熱心に手を握り、また座った。
「ワインもある」とパンブルチューク氏。「さあ、運命の女神に乾杯しよう! 彼女が常に同じように賢明に人を選びますように! だが、私は――やはり――」
また手を握り、グラスを空けて逆さまにした。私も同じようにした。もし飲む前に自分自身を逆さまにしていたら、これ以上まっすぐ頭に回ることもなかっただろう。
パンブルチューク氏は私に肝の部分と最高の舌をよそい(もうあんな豚肉の行き止まりじゃない)、自分の分はほとんど気にもとめなかった。「鶏さんよ、お前がひなだったとき、自分がここでこのような人のために食されるとは思いもしなかったろうに。弱さかもしれんが――もしかして――」
もう「どうぞ」と答える必要もなくなったので、彼はそのまま手を握った。何度もこうされて刃物で怪我をしないのが不思議なくらいだった。
「それとお姉さん、あなたを手塩にかけて育てた方だ! 今はもうその名誉を完全には理解できないのは悲しいが。さあ――」
私がまた手を握られそうになったので、制した。
「姉さんの健康を祝おう」と私は言った。
「そうですとも!」とパンブルチューク氏は椅子にもたれて感心しきった様子で叫んだ。「これが高貴な心の証、赦しと親しさ。もしごく普通の人なら、繰り返しに見えるかもしれませんが――もしかして――」
また手を握ってから姉に乾杯した。「彼女の気性の激しさには目をつぶりたいが、悪気はなかったはず」と言った。
この頃になると、彼の顔が赤くなってきているのがわかった。私自身は、顔じゅうがワインに浸され、ヒリヒリしていた。
私は新しい服を彼の家に送ってほしいと伝え、彼は大いに喜んだ。村で目立ちたくない理由を話すと、これも大いに称賛された。彼以外に信頼できる者はいない、と彼は仄めかし、そして――もう握手していいか聞くこともなくなった。少年時代の計算遊びや、私が弟子入りしたときのこと、自分こそ私の親友だったと懐かしんで語った。もし私が何十杯もワインを飲もうと、彼がそんな存在でなかったことは明白だったはずだが、なぜか私は彼が実は素晴らしい実務家で心優しい人だったのではと思い込んだ。
やがて彼は自分の事業について相談するほどの信頼を寄せ、「この店舗を拡張すればかつてない穀物と種子の大合併・独占が可能で、大きな財産が得られる。足りないのはただ二語、資本増強だ。もし無関係な出資者が入れば、年に二回利益(五割)を取りに来るだけでいい。財産と気概ある若者には素晴らしい機会だと思うが、君はどう思う?」と意見を求められた。私は「しばらく様子を見て」と答え、それがあまりに重大で明快だったせいか、今度は「もう握手せずにはいられない!」と言って手を握った。
ワインはすっかり空き、パンブルチューク氏は何度も「ジョセフをしっかり励ます」と約束し、私にも何らかの貢献と奉仕を誓った(何なのかは知らない)。また、私について「この子は並みの子ではない、運命もまた並みのものではない」と常に言ってきた秘密も初めて明かし、それが今や実現したのは奇妙なことだと涙ぐんで語った。私も同意した。結局、私は陽の光の様子が妙に見えるほどぼんやりしながら外に出て、村の料金所まで何も考えずに歩いていた。
そこでパンブルチューク氏の呼び声で我に返った。彼は通りの向こうから身振りで私を止め、「これだけは――親しみを示す機会を逃したくない――古くからの友人として、どうか」とまた手を握った。少なくとも百回は握手し、彼は通行人の若い車引きまでどかしてくれた。そして私を何度も祝福し、私が道の曲がり角を過ぎるまで手を振り、私は野原に入り、垣根の下で長い昼寝をしてから家路についた。
ロンドンへ持っていく荷物はわずかだった。新たな身分にふさわしいものなど、ほとんど持っていなかったからだ。それでも、午後には荷造りを始め、翌朝必要なものまで詰め込んで、少しも時間が惜しいかのように振る舞った。
こうして火曜日、水曜日、木曜日が過ぎ、金曜の朝、私はパンブルチューク氏宅で新しい服に着替え、ミス・ハヴィシャムを訪れることにした。パンブルチューク氏の部屋は私のためにあけられ、タオルも新しく用意された。新しい服はやはり少し期待外れだった。多分、服というものは期待通り完璧に着こなせることなど決してないものだろう。だが、着て半時間も経ち、パンブルチューク氏の小さな鏡で何度も足元まで見ようと無駄なポーズを取っているうちに、だんだん馴染んできた。近隣の町で市が開かれていたため、パンブルチューク氏は留守だった。私は出発の時間を伝えていなかったので、再び握手することもなく旅立つことになり、それでよかったと思った。私は新しい格好で遠回りに裏道を通ってミス・ハヴィシャム邸へ向かい、手袋の長い指で気まずくベルを鳴らした。サラ・ポケットが門に現れ、私の変わりぶりに仰天してよろめき、顔色まで青ざめた。
「あなた? あなたなの? いったい何の用事?」
「明日ロンドンに発つので、ミス・ハヴィシャムにご挨拶したいのです」と私は言った。
突然だったので、私は中庭に閉じ込められ、彼女は入っていいかどうか確かめに行った。すぐに戻ってきて、私をじろじろ見ながら邸内へ案内した。
ミス・ハヴィシャムは、長いテーブルのある部屋で杖をついて運動中だった。部屋は昔と同じように薄暗く、私たちが入ると彼女は動きを止め、私たちの方を向いた。彼女はちょうど腐ったウェディングケーキの横にいた。
「行かなくていいわよ、サラ。――それで、ピップ?」
「明日ロンドンに発ちます、ミス・ハヴィシャム」と私は慎重に言葉を選んだ。「ご挨拶に伺いました。」
「まあ、ずいぶん立派になったじゃない、ピップ」と彼女は杖を私の周りで回し、まるで私を変身させた妖精の教母が最後の贈り物を与えるかのようだった。
「前回お会いしてから、こんな幸運に恵まれまして……本当に感謝しています、ミス・ハヴィシャム!」
「そう、そう!」と彼女は快哉を上げ、サラの落胆と嫉妬を楽しんでいた。「ジャガーズ氏から全部聞いているわ、ピップ。で、明日発つのね?」
「はい、ミス・ハヴィシャム。」
「裕福な方に引き取られるの?」
「はい、ミス・ハヴィシャム。」
「名前は明かされていない?」
「はい、ミス・ハヴィシャム。」
「ジャガーズ氏が後見人?」
「はい、ミス・ハヴィシャム。」
彼女はこの問答を心底愉しみ、サラ・ポケットの嫉妬に大いに満足している様子だった。「いいこと――前途有望ね。しっかり努力して、ジャガーズ氏の指示に従いなさい」彼女は私とサラを見比べ、サラの顔にはねじれた笑みが浮かんだ。「さようなら、ピップ――あなたはずっと“ピップ”のままよ、いいわね。」
「はい、ミス・ハヴィシャム。」
「さようなら、ピップ!」
彼女は手を差し出し、私はひざまずいて手に口づけした。別れ方は考えていなかったが、自然とそうした。彼女はサラを勝ち誇ったような目で見つめ、私は妖精の教母を後にした。彼女は杖に両手を添え、薄暗い部屋で、蜘蛛の巣に覆われた腐ったウェディングケーキの横に立っていた。
サラ・ポケットは私をまるで幽霊でも見送るかのように玄関まで案内した。私の変貌ぶりに最後まで動揺を隠せなかった。「さようなら、ミス・ポケット」と言ったが、彼女はただ凝視するばかりで、私が話したことも理解できていないようだった。屋敷を出ると、できるだけ早くパンブルチューク宅に戻り、服を脱いで包みにし、古い服に着替えて家へ帰った。その方がずっと気楽だった。
こうして、ゆっくり過ぎるはずだった六日間があっという間に過ぎ去り、明日という日が私の正面に立ちはだかった。五日、四日、三日、二日と夕べが減るごとに、ジョーとビディへの親しみが増していった。最後の夜、私は新しい服を着て二人を喜ばせ、華やかな姿で夜まで過ごした。特別な温かい夕食で、定番のローストチキンとフリップ酒も用意された。みんな気持ちは沈み、無理に明るくふるまっても効果はなかった。
私は朝五時に村を発つことになっており、小さな鞄一つで歩いていきたいとジョーに伝えてあった。自分でも――本当に――この希望は、もしジョーと一緒に馬車まで行ったら、その差が際立つのが恥ずかしかったからだと認めざるを得なかった。そんなつもりはなかったと言い聞かせていたが、最後の夜、自分の部屋に上がってからは、その理由を認めざるを得なかった。ジョーに「やっぱり一緒に行ってほしい」と頼もうという衝動に駆られたが、結局そうしなかった。
夜通し、夢の中で馬車はロンドンとは違う方向へ進み、馬の代わりに犬や猫や豚や人間が曳いていた。奇妙な旅の失敗ばかり見せられ、夜明けとともに目覚めると、鳥が鳴いていた。私は起きて半分着替え、窓辺で最後の外の景色を眺めているうちに、また眠ってしまった。
ビディは朝早くから朝食の支度をしていたらしく、私は一時間も眠らぬうちに、もう午後かと勘違いして飛び起きた。だがしばらくしても、ティーカップの音がしても、なかなか下へ降りる気になれなかった。結局、鞄を何度も開けたり閉めたりしていたが、ビディに「遅い」と呼ばれてやっと下りた。
慌ただしい味気ない朝食だった。私は席を立つと、まるで今思い立ったかのように「そろそろ行かなくちゃ」と言い、椅子にふんぞり返る姉にキスし、ビディにもキスし、ジョーの首に抱きついた。それから小さな鞄を持って家を出た。振り返ると、ジョーが私の背中に古い靴を投げ、ビディももう一足投げていた。私は立ち止まり、帽子を振った。ジョーは右腕を大きく振って「ほうら、行け!」としゃがれ声で叫び、ビディはエプロンで顔を覆った。
私は足早に歩きながら、思ったより簡単に出てこられるものだと感じ、馬車に靴を投げられる姿をハイストリートの前で見られるわけにはいかなかったとも考えた。口笛を吹き、気にしていないふりをした。だが村はとても静かで、朝靄が荘厳に昇っていき、私がこの土地でいかに幼く無垢だったか、そしてこの先がいかに未知で大きな世界か思い知ると、不意に激しく胸が波打ち、嗚咽とともに涙がこぼれた。村外れの道しるべの前で、私はそれに手を置き、「さようなら、親愛なる友よ!」と告げた。
天が知っている――涙を恥じる必要など私たちには決してない。それは、私たちのかたくなな心の上に積もった、目を曇らせる塵を洗い流す雨なのだ。私は泣いたあと、前よりも心が洗われ、自分の恩知らずを思い知り、よりやさしくなった。もし先に泣いていたら、私はきっとジョーと一緒にいたことだろう。
涙に和らげられ、また道中でも何度も涙がこみ上げ、馬車が町を出たあとでさえ、次の馬を替えるときに降りて引き返し、もう一晩家で過ごしてきちんと別れ直そうかと本気で考えた。馬を替えても決心がつかず、もう一度替えるときにでも降りようと自分を慰めた。その間、道の向こうからジョーそっくりの男が歩いてくるような気がして、胸が高鳴った――まさか、いるはずもないのに。
私たちはまた変わり、さらにまた変わり、もはや引き返すには遅すぎ、遠すぎたので、私はそのまま進んだ。そして、いまや霧はすべて厳かに立ち上がり、世界が私の前に広がっていた。
これにてピリップの「大いなる期待」第一部は終わる。
第二十章
私たちの町から大都市までの道のりは、およそ五時間の旅であった。私が乗っていた四頭立ての駅馬車が、ロンドンのチェープサイド、ウッド・ストリートのクロス・キーズ付近で混み合った交通の中に入り込んだのは、昼を少し過ぎた頃だった。
当時の英国人たちは、我々が何事においても最高であり、最良であることを疑うのは反逆だと、殊更に決め込んでいた。でなければ、私はロンドンの巨大さに怖気づきつつも、うっすらと、ロンドンにはどこか醜さや歪み、狭さ、そして汚れがあるのではないかと、疑ったかもしれない。
ジャガーズ氏はきちんと住所を私に知らせていた。「リトル・ブリテン」とあり、名刺には「スミスフィールドのすぐ外、馬車事務所のすぐそば」と書き添えられていた。それにもかかわらず、ぼろぼろの油じみた外套に、年の数ほども肩掛けを重ねたような辻馬車の御者が、私を馬車に詰め込み、折りたたみ式のきしむステップで四方を囲んで、まるで五十マイルも連れて行くかのようだった。御者が自分の台座によじ登るのにやたら時間がかかったのを覚えている。台座には風雨にさらされてボロボロになった緑色の古い布がかかっていた。それは見事な馬車で、外側に六つも大きな冠章があり、後部には何人もの従者が掴まれるようなぼろ布がぶら下がり、その下には素人従者が誘惑に負けて飛び乗れぬよう耕作用の鉄具までついていた。
私はまだその馬車の奇妙さを楽しむ暇もなく、わら床のようでもあり、古着屋のようでもあると感じながら、なぜ馬の鼻袋が車内にあるのだろうと不思議に思っていた。すると御者が降り始めたので、まもなく停まるのかと察した。実際、私たちはほどなくして、陰気な通りのとある事務所前で停車した。開いた扉には「MR. JAGGERS」と書いてあった。
「いくらだ?」と私は御者に訊いた。
御者は「1シリング――もし多く払いたいなら別だが」と答えた。
私は当然、余計に払うつもりはないと告げた。
「なら1シリングだ」と御者。「厄介事は御免だ。あの人を知ってるからな!」と、ジャガーズ氏の名を示して片目を閉じ、首を振った。
御者がシリングを受け取り、やがて台座に戻って去っていくと(それが彼には安堵だったらしい)、私は小さなトランクを手にフロントの事務所へ入り、「ジャガーズ氏はご在宅ですか」と訊いた。
「不在です」と事務員。「ただ今は法廷に出ております。あなたはピリップさんですか?」
私は、その通りであると示した。
「ジャガーズ氏から伝言があります、彼の部屋でお待ちくださいとのこと。どれくらいかかるか分かりません、案件があるので。ただし、彼は時間を無駄にしない人ですから、必要以上は掛からないでしょう。」
そう言って事務員は扉を開け、私を奥の部屋へ案内した。するとそこには、ビロードのスーツに半ズボンを着た片目の紳士がおり、新聞を読んでいるところを袖で鼻を拭きながら中断された。
「外で待ってろ、マイク」と事務員が言った。
私は邪魔をしてしまったのでは、と言いかけたが、事務員はなんの遠慮もなくその紳士を部屋から押し出し、さらに毛皮の帽子も投げて、私を一人にした。
ジャガーズ氏の部屋は天窓だけで照らされた陰鬱な場所だった。天窓は壊れた頭のように不規則に傾き、隣家たちも捻じれて私を覗き込もうとしているかのようだった。書類は思ったほど多くなく、逆に予想外の物もあった――古びた錆びついたピストル、鞘入りの剣、奇妙な箱や包み、そして棚には、鼻のあたりがひどく腫れ、痙攣するような顔の恐ろしい石膏像が二つもあった。ジャガーズ氏自身の大きな椅子は、漆黒の馬毛で覆われ、棺のように真鍮の鋲が並んでいた。私は彼がその椅子に寄りかかり、依頼人に指を噛みながら睨みつける様子を想像した。部屋は狭く、依頼人たちは壁に背中を押し付ける習慣があるようで、特にジャガーズ氏の椅子の正面の壁は肩で脂ぎっていた。あの片目の紳士も、追い出されたとき壁に寄っていたことを思い出した。
私はジャガーズ氏の椅子の向かいにある依頼人用の椅子に腰掛け、この陰気な空間に魅了されてしまった。事務員にも、主人と同じように何か人の弱みを知っているような雰囲気があると思い出した。上階にも同じような事務員がいるのだろうか、皆が同じように他人を支配しているのだろうかと考えた。この部屋の雑多な品々にはどんな経緯があるのか、なぜここにあるのかと不思議に思った。二つの腫れた顔はジャガーズ氏の家族なのだろうか、もしそんな不運な親類がいたなら、なぜ家に飾らず埃とハエのたかるこの棚に置くのか。不慣れなロンドンの夏の一日で、熱気と埃と砂に気が滅入ったのかもしれない。でも私は、どうにもその石膏像が耐えきれなくなり、立ち上がって外へ出た。
待ちながら空気を吸いに出ると事務員に告げると、「角を曲がればスミスフィールドですよ」と教えられた。私はスミスフィールドに出たが、そこは汚物と脂と血と泡で塗れた恥ずべき場所で、全身にこびりつくように感じたので、急いで別の通りに入った。すると、灰色の石造りの重々しい建物の裏から、セント・ポール大聖堂の黒いドームが膨らんで見えた。その建物を通行人に尋ねるとニューゲート監獄だと言う。監獄の壁沿いに行くと、車の騒音を消すために道路には藁が敷かれ、辺りには酒とビールの臭いのする人々が大勢いたので、裁判が開かれているのだと推察した。
そこに立っていると、非常に汚れて半分酔ったような司法関係者が「裁判を見てみないか」と声をかけてきた。半クラウンで正面席が取れると誘い、さらに「大法官様のカツラとローブ姿が見られる」と蝋人形のような口調で言い、やがて十八ペンスに値下げした。私は用事があるからと断ると、今度は中庭に連れて行かれ、絞首台を見せられたり、鞭打ち刑の場所を案内されたりした。そのうえ「明後日朝八時にあそこで四人が並んで処刑される」と恐ろしい話までされた。この恐ろしい体験は、ロンドンに対して強い嫌悪感を抱かせた。しかも案内人は頭から足元、ハンカチまでカビだらけの服で、どうやら死刑執行人から安く買ったのではと私は勝手に想像した。この男と1シリングで別れたのは幸運だったと思う。
私は事務所に戻り、ジャガーズ氏が戻ったかを確かめたが、まだだったので再び外へ出た。今度はリトル・ブリテンを一巡してバートロメュー・クローズに入ると、他にもジャガーズ氏を待っている者たちがいた。秘密めいた様子の男が二人、舗道の割れ目に足をはめながら話していた。その一人は「もしやるならジャガーズがやる」と言っていた。角には男三人と女二人の一団がいて、一人の女は汚れたショールで泣き、もう一人は「ジャガーズがついてるんだから、もう十分じゃないの」と慰めていた。やがて赤い目の小柄なユダヤ人がもう一人の小柄なユダヤ人を連れて現れ、片方が使いに出されると、残った方はランプの下で「オー・ジャガーズ、ジャガーズ! 他はみんなカグ・マガーズ、ジャガーズだけが頼り!」と興奮して踊っていた。こうした人気ぶりに私は強い印象を受け、ますます彼に敬意と好奇心を抱いた。
やがてバートロメュー・クローズの鉄門からリトル・ブリテンを見ていると、ジャガーズ氏が道を渡ってこちらへやって来るのが見えた。他の待ち人も同時に彼を見つけ、彼のもとへ小さな人だかりができた。ジャガーズ氏は私の肩に手を置いて無言で歩かせながら、追従者たちに話しかけた。
まず、あの秘密めいた二人の男に向かって言った。
「さて、君たちには言うことはない。私は知るべきことだけ知っていればよい。結果は五分五分だと最初から言ったろう。ウェミックに金は払ったか?」
「今朝まとめてきました、先生」と男の一人が従順に答え、もう一人はジャガーズ氏の顔を窺っていた。
「いつ払ったか、どこで払ったか、払ったかどうかも聞かない。ウェミックが受け取ったか?」
「はい、先生」二人が声を揃えた。
「よろしい。では帰ってよい。もうこれ以上はご免だ! 一言でも口をきいたら依頼は下りるぞ」とジャガーズ氏は手を振り、後ろに下がらせた。
「でも私たち、ジャガーズ先生――」と男の一人が帽子を脱ぎかけると、
「それがするなと言ったことだ」とジャガーズ氏。「君たちが考える必要はない。私が考える。それで十分だ。必要ならこちらから呼ぶ、君たちに探し回ってほしくない。これ以上はご免、もう一言も聞かん。」
男たちは見合わせ、深々と頭を下げて後ろへ引き下がり、それ以上声は出さなかった。
「次は君たちだ!」とジャガーズ氏は急に振り返り、ショールの二人の女に向かった。三人の男たちはすでに離れていた。「おお、アメリアだったか?」
「はい、ジャガーズ先生」
「だが覚えているか?」とジャガーズ氏は返す。「私がいなければ君はここにいなかったし、来られなかったんだぞ?」
「ええ、先生! 神様のご加護を、よくわかってますとも!」
「なら、なぜここにくる?」
「ビルのことで……」と泣く女が訴える。
「よし、言っておくぞ!」とジャガーズ氏。「ビルがいい手にあると知らないなら私が知っている。もしビルのことでここに来て騒ぐなら、君とビル両方に見せしめをして、手を引くぞ。ウェミックには払ったか?」
「はい、先生! 一銭残らず。」
「よろしい。それなら君のやるべきことは終わった。もう一言でも言ったら、ウェミックに金を返させるぞ。」
この恐ろしい脅しに女たちはすぐさま身を引いた。残ったのは興奮したユダヤ人だけで、彼はすでに何度もジャガーズ氏の外套の裾を唇に当てていた。
「この男は知らん!」とジャガーズ氏は同じく冷酷な調子で言い放った。「こいつは何の用だ?」
「ジャガーズ先生、アブラハム・ラザラスの兄弟でございますが?」
「誰だ?」とジャガーズ氏。「私の外套を離せ。」
その男は再び裾にキスしてから答える。「アブラハム・ラザラス、食器泥棒の疑いで。」
「遅かったな」とジャガーズ氏。「私は向こう側だ。」
「お願いです、ジャガーズ先生! まさかアブラハム・ラザラスの敵なのですか!」
「その通りだ。以上だ。どけ。」
「ジャガーズ先生! 少しの間を! 従兄弟が今まさにウェミック氏にどんな条件でも申し出ているところです。もし他方から手を引いていただけるなら――いくらでも! お金は問題じゃありません! ジャガーズ先生、お願い――!」
ジャガーズ氏は粛々と哀願者を振り払い、彼をまるで焼け石の上で踊るような格好で舗道に残した。もう妨げられることなく私たちはフロントオフィスへ着き、そこには事務員とビロードの男がいた。
「こちらがマイクです」と事務員が椅子を下りて、ジャガーズ氏に耳打ちするように近づいた。
「ほう」とジャガーズ氏は男の額の髪を引っ張る仕草を見て言った。「例の男は午後来るのか。どうだ?」
「ええ、ジャガーズ先生、だいぶ苦労しましたが、何とか使えそうな者を見つけました。」
「何を誓う気か?」
「さあ、先生、だいたい、なんでも。」
ジャガーズ氏は突然激昂した。「ここでそんな口をきいたら見せしめにすると警告したろう。このろくでなしめ、よくもそんなことを私の前で言えたな!」
依頼人は怯え、何をしたのか分からず唖然としていた。
「まぬけ!」と事務員が小声で肘で突きつつ言う。「ばか! 直接言うな!」
「もう一度、最後に聞くぞ」と私の後見人は厳しい口調で言った。「そいつは何を誓うつもりだ?」
マイクはジャガーズ氏の顔をじっと見て、答えを探るようにして、ゆっくりと答えた。「その人の品行か、事件当夜一晩中一緒だったこと、どちらかを。」
「よく考えろ。そいつの身分は?」
マイクは帽子・床・天井・事務員・そして私まで順に見回し、緊張した様子で答え始めた。「そいつをコスプレさせて――」 その時またジャガーズ氏が叫んだ。
「何だと? 言うつもりか!」
(「ばか!」と事務員がまた小声で肘を突いた。)
マイクはしばし途方にくれた末、顔を明るくして言い直した。
「そいつはちゃんとしたパイ売りの格好をしてます。パン屋みたいなもんです。」
「ここにいるのか?」
「角の方の階段に座らせてあります。」
「その男を窓の前に連れてこい、見てみる。」
事務所の窓の前に三人で立つと、まるで偶然のように依頼人が、白いリネンの短い服と紙の帽子をかぶった異様に背の高い男を連れて通り過ぎた。その偽装の菓子職人は酔っているようで、目の下に緑色に腫れたあざを化粧で隠していた。
「今すぐその証人を連れて帰らせろ」とジャガーズ氏は事務員に極度の嫌悪を込めて言った。「どうしてあんな奴を連れてきたのか問いただせ。」
それから私を自室へ連れていき、立ったままサンドイッチとポケットフラスコのシェリーで昼食をとりながら(パンにも威圧的に噛みついているようだった)、私への手配について説明した。私は「バーナード・イン」のハーバート・ポケット青年の部屋に宿泊し、月曜まで彼と過ごすこと、月曜には彼と一緒に父親の家へ行って、住み心地を試すことになった。また、私の小遣いの額(かなり寛大だった)も伝えられ、衣服や日用品を求めるための取引先のカードが引き出しから手渡された。「ピリップさん、あなたの信用は大丈夫だが、こうすれば私が請求書をチェックできるし、度が過ぎれば止められる。まあ、どこかで失敗するだろうが、それは私の責任じゃない。」
この励ましとも言える言葉をしばし考えた後、私は「馬車を呼べますか」と訊いたが、「近いから必要ない、もしよければウェミックが案内する」と言われた。
ウェミック氏が隣室の事務員であることが分かった。もう一人の事務員が上階から呼ばれ代理をし、私は後見人と握手を交わしてからウェミック氏と外へ出た。外にはまた新たな待ち人たちがたむろしていたが、ウェミック氏は「言っておくが無駄だ、一人も会ってもらえない」と冷静かつ断固とした口調で告げ、私たちはすぐに人混みを抜けて並んで歩いた。
第二十一章
街を歩きながら日中の光のもとでウェミック氏を観察すると、乾いた小柄な男で、角ばった木彫りの顔は不器用なノミで彫られたような表情をしていた。素材がもっと柔らかく道具が良ければえくぼになったかもしれない痕も、今はただの凹みだった。鼻のあたりにも三つ四つ彫りかけた痕があるが、仕上げもなく放置されている。シャツの擦り切れ具合から独身だと推測し、喪章の指輪を四つもはめ、さらにブローチには女性と墓標、壺と柳の図柄があった。懐中時計の鎖にも指輪や印章がいくつも下がっていて、まるで亡くなった友人たちの思い出に重く縛られているようだった。目は小さく鋭い黒色で、唇は薄く広くまだらだった。年の頃は四十から五十の間だろうと私は見た。
「ロンドンは初めてかね?」とウェミック氏が私に言った。
「はい」と私は答えた。
「私も昔は新顔だったよ」とウェミック氏。「今では妙な気分だ。」
「今は詳しいんですか?」
「まあね」とウェミック氏。「ここでの流儀は分かってる。」
「ロンドンってそんなに悪いところですか?」私は話の流れで訊いた。
「ロンドンでは騙されたり、盗まれたり、殺されたりもする。だが、そんなことはどこにでもやる人間はいるさ。」
「何か憎しみがある相手なら、でしょう?」と私は少し和らげて言った。
「さあ、悪血ってほどじゃない」とウェミック氏。「得になることがあればやるだけさ。」
「その方がたちが悪いですね」
「そう思うか?」とウェミック氏。「私からすればどちらも大差ないな。」
彼は帽子を後ろにかぶり、まっすぐ前だけを見て、道行くものには一切気を取られない自足した歩き方だった。口元はまるで郵便局のようで、機械的に笑っているようにさえ見えた。私たちがホルボーン・ヒルの坂を上りきるまで、それがただの作り笑いで、本当は全く笑っていないことに気づかなかった。
「マシュー・ポケット氏がどこに住んでるかご存じですか?」と私は尋ねた。
「知ってるよ」と彼は頷きつつ答えた。「ロンドン西のハマースミスだ。」
「遠いんですか?」
「そうだな、五マイルくらいか。」
「ご本人もご存じですか?」
「いや君は尋問好きだな!」とウェミック氏は感心したように私を見て言った。「知ってるとも。私はよく知ってる!」
その言い方にはどこか冷やかしや軽蔑の響きがあって、私は少し気分が沈んだ。そのまま横目で彼の木彫りの顔から励ましを探しているうちに、「ここがバーナード・インだ」と言われた。その発表は、私の気持ちを少しも和らげなかった。なぜなら私はこの施設を、町のブルー・ボア(青い猪亭)がただの居酒屋に過ぎないのに比べ、本格的なホテルだと思い込んでいたからだ。だが今やバーナードなる人物は幽霊か虚構にすぎず、彼のインは、トムキャットたちの溜まり場のような、みすぼらしい建物の集合体でしかなかった。
私たちは小さな扉からこの避難所に入り、薄暗い通路を抜けて、まるで平らな墓地のような寂しい小広場に出た。そこには私がこれまで見た中で最も陰気な木、最も陰気な雀、最も陰気な猫、最も陰気な家(せいぜい六軒ほど)が並んでいた。部屋の窓はどれも壊れかけのブラインドやカーテン、傾いた花瓶、ひび割れたガラス、埃だらけの荒廃や窮乏の証ばかりで、「貸室あり、貸室あり」の貼り紙が空部屋から睨むように掲げられていた。まるで新たな哀れな住人は決して現れず、バーナードの魂の恨みが、現住者のゆるやかな自殺と土埃の下の埋葬によって徐々に宥められているかのようだった。煤煙と埃の黒服をまとい、頭には灰をかぶり、ただの塵壺として贖罪と屈辱の日々を送っているのだった。ここまでは視覚の印象だが、さらに乾腐、湿腐、鼠や虫、隣接の馬車小屋などの黙した腐臭が微かに嗅覚にも訴え、「バーナードの混合物を試せ」とささやいてくる。
私の「大いなる期待」第一歩の現実があまりにもこれでは、私は呆然とウェミック氏を見た。「ああ、田舎を思い出す静けさだろう? 私もそうだ」と彼は勘違いして言った。
彼は私を隅に案内し、階段を上らせた。階段は今にもおが屑になって崩れそうで、そのうち上階の住人が戸を開けたとき、降りる手段がなくなってしまうのではと思った。最上階の部屋のドアには「MR. POCKET, JUN.」と書いてあり、郵便受けには「すぐ戻ります」とラベルがあった。
「こんなに早く来るとは思わなかったんだろう」とウェミック氏は説明した。「もう私の用はないかい?」
「ええ、けっこうです」と私は答えた。
「私は金庫番だから、これからもよく顔を合わせるだろう。では、失礼。」
「さようなら。」
私が手を差し出すと、ウェミック氏は最初それを見て、何か欲しがっているのかと思ったようだったが、すぐに自分を正して言った。
「そうか、握手の習慣があるんだな?」
私は少し戸惑い、ロンドンではそれが流行遅れなのかと思ったが、そうだと答えた。
「私はすっかりその習慣から遠ざかってしまって――最後だけだな。どうぞよろしく。さようなら!」
私たちは握手を交わし、彼が去ると、私は階段の窓を開けて首を挟みかけた。というのも、窓枠の糸が腐っており、ギロチンのように一気に落ちてきたからだ。幸い、頭を出す前だったので無事だった。この危機を脱した後は、窓の泥越しに曇ったインをぼんやり眺め、ロンドンはやはり過大評価だと自分に言い聞かせた。
ポケット青年の「すぐ戻ります」は私の感覚とは違い、私は窓越しに半時間も気を揉んで自分の名を何度もガラスの埃に指で書きつけてから、ようやく階段を上がる足音を聞いた。次第に帽子、頭、ネクタイ、ベスト、ズボン、靴と私と同じくらいの年ごろの青年が現れた。両脇に紙袋を抱え、一方の手には苺のバスケットを持ち、息を切らしていた。
「ピリップさん?」と彼が言った。
「ポケットさん?」と私は応じた。
「いやはや!」と彼。「申し訳ありません。あなたの土地からは昼の馬車があると聞いていたので、その便で来られると思っていました。実は、あなたのために市場へ――言い訳にはなりませんが――田舎から来られるなら食後に果物でもどうかと、コヴェント・ガーデン・マーケットへ買いに行ってきたのです。」
私は理由があって、目が飛び出しそうだった。彼の心遣いにうまく礼を言えず、これが夢のように思えた。
「いやはや!」とポケット青年。「このドアがまた固くて!」
紙袋を脇に抱えたままドアと格闘し、果物を潰しそうだったので、代わりに持ちましょうかと申し出た。彼は快く袋を渡し、ドアを猛獣と戦うように引っ張ると、いきなり開いて彼が私に倒れ込み、私は反対側のドアにもたれ、二人で笑った。それでも私は夢かと思うほど目が飛び出しそうだった。
「どうぞお入りください」とポケット青年。「ご案内します。だいぶ殺風景ですが、月曜までは何とかやっていけると思います。父が明日一日、私と一緒の方が楽しかろうと考え、ロンドン散歩でもどうかと。こちらのテーブルはコーヒーハウスから運ばれますし(これは正直に言っておきますが)、お代はあなた持ちです、ジャガーズ氏の指示でね。部屋も決して豪華ではありませんが、私は自分の食い扶持を稼いでいますし、父も何もくれるものはありませんし、あっても私は受け取りません。こちらが居間――家から持ってきた椅子やテーブルやカーペットです。テーブルクロスやスプーン、調味料はコーヒーハウスのものなので、私の功績ではありません。こちらが私の寝室、ちょっとカビ臭いですが、バーナードはどこもそうです。こちらがあなたの寝室、家具は今回のために借りたものですが、用は足りるでしょう。何か要るなら言ってください。部屋は静かで二人きりですが、喧嘩はしないと思います。でも、すみません、ずっと果物を持ったままでしたね。どうぞ袋を返してください、恐縮の至りです。」
私はポケット青年と向かい合い、1つ2つと袋を返しながら、彼の瞳にも自分と同じ驚きの色が浮かぶのを見た。そして彼は後ずさりしながら言った。
「なんとまあ、君はあのうろつき少年か!」
「そして君は」私は言った。「あの青白い若紳士だったんだ!」
第二十二章
青白い若紳士と私は、バーナード・インでしばし見つめ合い、ついに二人で笑い出した。「まさか君だったとは!」と彼。「まさか君だったとは!」と私。そしてもう一度見合って笑った。「まあ!」と青白い若紳士は陽気に手を差し出し、「これでもう済んだことだ。あんなに君を殴り飛ばしてしまったことを許してくれたら、君は寛大だと思うよ。」
この言葉から、ハーバート・ポケット(ハーバートが彼の名だった)は、今でも自分の意図と実際の結果を混同しているようだと分かった。だが私は控えめに返事をし、熱く握手した。
「その頃はまだ幸運を手にしてなかったんだね?」とハーバートが訊いた。
「うん」と私は応じた。
「そうだね、最近のことと聞いた。僕はあの時、幸運が舞い込むのを少し狙っていたんだ。」
「そうなんだ?」
「ああ。ミス・ハヴィシャムに呼ばれて、お気に召すかどうか試されたんだ。でもダメだった――少なくともダメだった。」
私は驚いたふりをするのが礼儀だと思い、その旨を述べた。
「悪い趣味だね」とハーバートは笑った。「でも事実さ。呼ばれて試しに滞在して、うまく行けば多分何か与えられただろうし、エステラの……何というか、許嫁とか。」
「それはどういうこと?」私は急に真面目になって訊いた。
彼は果物を皿に分けながら話していたので注意が散り、言葉が抜けてしまったのだ。「婚約者さ」と彼は説明しつつ果物の整理を続けた。「婚約、許嫁、まあそんな単語。」
「失望はどう受け止めたんだい?」
「ふん」と彼。「別に気にもならなかったよ。彼女は手強いからね。」
「ミス・ハヴィシャムが?」
「そうとも言えるが、僕はエステラのこと。あの子はとことん冷たくて高慢で気まぐれで、ミス・ハヴィシャムに仕込まれて、男全体に復讐するように育てられてる。」
「じゃあ彼女はミス・ハヴィシャムとどういう関係なんだ?」
「血縁じゃないよ」と彼。「ただの養女さ。」
「どうして男全体に復讐なんて? なぜ?」
「やれやれ、ピリップ君!」と彼。「知らないの?」
「知らない」と私は答えた。
「それは話せば長いから、夕食まで取っておこう。さて、今度は僕から質問していいかな。あの日どうやってあそこへ来たの?」
私はその経緯を話し、彼は最後まで真剣に聞き、それからまた笑い出して、痛くなかったかと尋ねてきた。私は彼が痛かったかどうかは訊かなかったが、その点は十分確信していた。
「君の後見人はジャガーズ氏なんだろう?」と彼が続けた。
「ああ。」
「彼はミス・ハヴィシャムの法務代理人で、誰よりも彼女の信頼を得ていることは知ってる?」
私はここが危ない話題だと感じ、隠し立てせずに、彼とはミス・ハヴィシャムの家で一度会っただけで、他では一度も見た記憶がないし、彼も私を覚えていないと思うと答えた。
「彼が君の家庭教師に父を薦め、父の所へ提案しにきたんだ。もちろんミス・ハヴィシャムとのつながりで父を知っていた。父はミス・ハヴィシャムの従兄ではあるが、だからといって親しくしているわけじゃない。父は御機嫌取りが下手でね、彼女に取り入ろうとしないから。」
ハーバート・ポケットは率直で気さくな人柄で、とても魅力的だった。私は当時も今も、彼ほど、秘密や卑劣なことに向かない青年を見たことがない。彼の雰囲気には不思議な希望が漂うが、同時に、あまり成功したり裕福になったりはしないだろうという囁きも感じる。なぜかは分からないが、夕食前のこの時点で私はそう思い込んでしまったのだ。
彼は今も青白い青年で、元気さと機敏さを見せつつも、どこか勝負に疲れたような弱さがあった。顔立ちは美男子ではないが、それ以上に愛嬌があり、明るく快活だった。体つきは私の拳骨が馴染みだったあの頃のように少し不格好だが、いつまでも軽やかで若々しく見えた。私の新調の服より、彼の古びた服の方がずっとよく似合っていたのは確かだ。
彼がこれほど打ち解けているので、私も警戒するのは年齢に合わぬ応対だと判断し、私の身の上話を語った。恩人が誰かは問うなと厳命されていることも強調した。また、私は田舎育ちの鍛冶屋で礼儀作法をほとんど知らないから、もし失敗や間違いをしたら教えてくれると大変ありがたいと申し出た。
「喜んで」と彼。「でも予言するけど、君はほとんど助言はいらないと思うよ。これからしょっちゅう一緒にいるだろうし、無用な遠慮はなくしたい。僕の名前はハーバートだから、下の名で呼んでくれる?」
私は感謝して応じ、自分の下の名はフィリップだと伝えた。
「フィリップという名前は好きじゃないんだ」と彼は笑いながら言った。「なぜかというと、フィリップって、つづりの教科書に載ってる道徳的な少年みたいに聞こえるからさ。あまりにも怠け者で池に落ちちゃったとか、太りすぎて目が見えなくなったとか、欲張りすぎてケーキを食べずに取っておいたらネズミに食べられちゃったとか、鳥の巣を探しに行くのに夢中で、その辺に住んでいたクマに食べられちゃったとか、そういう感じだ。君に一つ提案したいことがある。僕たちはとても気が合うし、君は鍛冶屋だったし――どうかな?」
「君が提案することなら、なんでも構わないよ」と僕は答えた。「でも、どういう意味かわからない。」
「親しみを込めて、ハンデルって呼ぶのはどうかな? ハンデルには“ハーモニアス・ブラックスミス(調和のとれた鍛冶屋)”っていう素敵な曲があるんだ。」
「とても気に入るよ。」
「じゃあ、親愛なるハンデル」と彼はドアが開くのを振り返りながら言った。「夕食が来たよ。君が用意してくれた食事だから、テーブルの上座に座ってくれ。」
僕はそんなこと遠慮したので、彼が上座に座り、僕はその正面に座った。素敵な小さなディナーで――当時の僕にはまるで市長の祝宴のように思えた――しかも大人の干渉なしで、ロンドンの真ん中で、独立した状況のもとで食べる食事は一層美味しく感じた。さらに、どこかジプシーめいた雰囲気もあって、宴をより引き立てていた。テーブルはパンブルチュークなら「贅沢の極み」と呼びそうなほど、すべてコーヒーハウスから取り寄せたもので揃えられていたが、周囲の居間はというと、牧草も乏しく定まらない雰囲気で、ウェイターは料理の蓋を床(そこでつまずいた)、溶かしバターを安楽椅子、パンを本棚、チーズを石炭箱、茹で鶏を隣の部屋の僕のベッドに置く始末――その夜寝るとき、パセリとバターの多くが凍ったままそこにあった。すべてが楽しい宴だったし、ウェイターがいなければ、僕の楽しみは何の妨げもなかった。
食事が進むうちに、僕はハーバートにミス・ハヴィシャムについて話してくれるという約束を思い出させた。
「そうだった」と彼は答えた。「すぐに話そう。じゃあ、ハンデル、まずは話の前にロンドンでのマナーを一つ。ナイフは事故防止のため口に入れないものなんだ。フォークはその用途に取っておくんだけど、必要以上に深く口に入れないのが普通。まあ、わざわざ言うほどのことでもないけど、みんながやってるようにするのがいいよ。あと、スプーンは普通、手の甲を上にして使わず、下にして使う。これには二つ利点があって、口に運びやすい(結局それが目的だし)、それに右ひじをカキの殻をこじ開けるみたいな体勢にしなくて済む。」
彼はこうした親切な助言をとても陽気にしてくれたので、僕たちは二人で笑い、僕もほとんど赤面しなかった。
「それじゃ、本題に入るよ、ミス・ハヴィシャムのことだ。彼女は、知っておくといいけど、甘やかされた子供だった。赤ん坊の時に母親を亡くし、父親は何でも彼女の望みを叶えてやった。父親は君の地元の方の田舎紳士で、ビール醸造業者だった。なぜビール醸造業がそんなに格が高いのかわからないけど、パン屋をやってたら上流になれないのに、ビールを作る人なら超一流になれる、ってのは否定できない事実だよ。毎日のように目にするだろ?」
「でも、紳士がパブ(酒場)を持つのはダメだよね?」と僕は言った。
「絶対にダメだ」とハーバート。「でもパブのほうが紳士を飼うのは問題ない。さて、ハヴィシャム氏は大金持ちで、とても誇り高かった。娘も同じだ。」
「ミス・ハヴィシャムは一人っ子だったの?」と僕は推測して聞いた。
「ちょっと待って、そこは今から話す。いや、一人っ子じゃない。異母兄弟がいた。父親は密かに再婚した――相手は彼の料理人だったと思う。」
「誇り高かったんじゃないの?」と僕。
「僕の親愛なるハンデル、その通りだよ。だからこそ、彼は秘密裏に再婚したんだ。そしてやがてその妻も亡くなった。妻が亡くなったあとで、初めて娘にすべてを打ち明けて、そして息子も家族の一員として、君が知っているあの家に住むことになった。息子は成長するにつれて、放蕩で浪費家で親不孝で――とにかくダメな奴になった。ついに父親は彼を勘当したけど、死ぬ間際には気が緩んで、そこそこ財産を遺した。ただしミス・ハヴィシャムほどではなかったけどね――さあ、ワインをもう一杯どうぞ。それと、話の途中で恐縮だけど、社交界ではグラスを飲み干した後、鼻の先にグラスの縁をつけて真っ逆さまにするほど律儀である必要はないんだ。」
僕は彼の話に夢中で、そんなことをしていたので、礼を言って謝った。彼は「全然構わないよ」と言って、話を続けた。
「こうしてミス・ハヴィシャムは莫大な財産を相続し、大変な玉の輿として注目された。異母兄もまた再び十分な財産を得たが、借金や新たな放蕩でまたしてもひどく浪費した。彼女と異母兄の間には、父親との間よりももっと根深い対立があったらしく、父親の怒りを煽ったのは彼女だと、異母兄は深い恨みを抱いていたと疑われている。さて、残酷な話の部分に入るよ――ハンデル、ちょっと話を止めるけど、ナプキンはタンブラーに入りきらないよ。」
なぜ僕がナプキンをタンブラーに押し込もうとしていたのか、まったく自分でもわからない。ただ、もっとましな目的なら使えるほどの粘り強さで、必死に押し込んでいたことだけは覚えている。また礼を言い、謝ったが、彼は明るく「本当に全然構わないよ!」と言って、また話を続けた。
「あるとき、例えば競馬場とか、舞踏会とか、どこかで、ある男が現れて、ミス・ハヴィシャムに言い寄った。その男を僕は見たことがない(これは25年前、僕たちが生まれる前の話だから)けど、父の話では、派手な男で、こういう目的のための男だったそうだ。ただ、礼儀正しい紳士に見えても、本当の紳士とは絶対に呼べないタイプだと父は強く断言していた。本当の紳士でない者は、どんなに取り繕っても表面だけで、木目のように本質が隠せない、と言うんだ。さて、その男はミス・ハヴィシャムに熱心に言い寄り、彼女もそれまであまり恋に落ちたことはなかったようだが、その時ばかりは全ての情熱を注いで彼を深く愛した。彼女は完全に彼を崇拝していたと言っていい。男は彼女の愛情につけこみ、巧みに大金を引き出し、しかも“結婚すればすべて自分が管理するから”という口実で、父親が兄に弱気で分け与えていたビール醸造所の権利まで法外な額で買い取るよう説得した。その頃、君の後見人(ジャガーズ氏)は、ミス・ハヴィシャムの相談役ではなかったし、彼女は気位が高く恋にも盲目で、誰の忠告にも耳を貸さなかった。親戚たちは貧しく打算的で、父だけは打算も嫉妬もなかったが貧乏だった。唯一独立心のある父は、彼女があまりにも男の思い通りにしているのを警告したが、彼女は怒って父を男の目の前で家から追い出し、それ以来彼は彼女に会っていない。」
僕は彼女が「マシューは、私があのテーブルの上に死んだとき、最後にはきっと会いにくる」と言っていたのを思い出し、ハーバートに、父親はそこまで彼女を憎んでいるのか尋ねた。
「そうじゃない」と彼。「でも彼女は、婚約者の前で父に“私に取り入って自分の出世を狙ったのに失望しただけだ”と非難して、もし今会いに行けば、たとえ父自身にも彼女自身にも、それを本当だと思われるだろう。さて、男の話に戻ろう。結婚の日取りも決まり、ドレスも買い、ハネムーンの計画も立て、招待客も呼んだ。その日がきたが、花婿は来なかった。男は手紙を書いて――」
「それを彼女は、結婚式の準備中、ドレスを着ているときに受け取ったんだよね? 8時40分に?」
「まさにその時刻だ」とハーバートはうなずいた。「その後、彼女がすべての時計を止めた時刻と同じだ。その手紙の内容が、結婚を無慈悲にも破棄するものだった以上のことは俺も知らない。彼女は重い病気を患い、回復したときには君が見たように家中を荒廃させ、それ以来一度も外の光を見ることはなくなった。」
「これで全部の話か?」と僕はしばらく考えてから聞いた。
「僕の知る限りはこれだけだ。それも自分でつぎはぎして推測しただけで、父は話題をいつも避けていたし、僕が招かれたときも絶対に必要なこと以外、何も教えてくれなかった。でも一つ言い忘れたことがある。その男は、彼女の異母兄と手を組んで、最初から仕組んでいたという説がある。つまり二人で共謀して、利益を分け合ったらしいってことだ。」
「だったらなぜ、その男は彼女と結婚して、全部の財産を手に入れなかったのかな?」と僕。
「既に結婚していたのかもしれないし、彼女をひどく傷つけることが異母兄の計画の一部だったのかもしれない」とハーバート。「いや、これは確証はないけどね。」
「その二人はどうなったんだ?」と僕はさらに考えて尋ねた。
「もっと深い恥と堕落、もしそれ以上があるなら――そして破滅に落ちていった。」
「今も生きているのか?」
「わからない。」
「さっき、エステラはミス・ハヴィシャムの血縁じゃなく、養子だと言っていたけど、いつ養子になったんだ?」
ハーバートは肩をすくめた。「僕がミス・ハヴィシャムのことを聞いて以来、いつもエステラはいた。詳しいことは知らない。そしてこれで、ハンデル」と言いながら、まるで話を手放すように、「僕の知っているすべてを君と分かち合った。」
「僕の知っていることも、全部君に話したよ」と僕は返した。
「本当にそう思う。だから、僕たちの間で競争や混乱が生じることは絶対にない。それに、君が人生の飛躍を得た条件、つまり誰に恩があるか詮索や議論を禁じられていることについても、僕や僕の関係者がそれを侵すことも、近づくことも絶対にないと保証するよ。」
実際、彼はこれをとても繊細に言ったので、今後何年も彼の父の家にいることになっても、この話題はもう終わったと感じた。けれど、彼は同時にとても含みを持たせていたので、僕への恩人がミス・ハヴィシャムだと彼が完全に理解していることも僕にはわかった。
彼がこの話題を持ち出したのは、互いの間から取り除くためだったということに、僕はそれまで気づかなかった。だが、このことについて話し合ったことで、僕たちはずっと気楽になり、今やっとそれが目的だったと理解した。僕たちはとても陽気で気さくに話し、僕は会話の途中で彼に「君の仕事は何?」と尋ねた。彼は「資本家――保険業者(船の保険)」と答えた。僕が部屋の中を見回し、船や資本の証しを探しているのに気づいたのか、彼は「シティ(ロンドンの金融街)でだよ」と付け加えた。
僕は、シティの保険業者がいかに裕福で重要な存在かという大きな幻想を抱き、そんな青年をノックアウトし、冒険的な目にあわせ、責任ある頭を割らせてしまった自分のことを恐れおののいた。しかしまたしても、なぜかホッとしたことに、ハーバート・ポケットは決して大成功も大金持ちにもなれそうにないという、妙な印象が僕に湧いてきた。
「僕は船の保険だけじゃ満足できない。生命保険の株も買って経営に関わりたいし、鉱山事業にも少しかじりたい。もちろん自分の責任で数千トンの船をチャーターすることも妨げにならないと思う。東インドに交易に行こうと思うんだ。絹やショール、香辛料、染料、薬品、貴重な木材なんかを扱うんだ。面白い商売だよ。」
「儲かるのかい?」と僕。
「とてつもなくね!」と彼。
またもや僕は圧倒され、ここには自分以上の大きな「期待」があるのでは、と思い始めた。

「西インド諸島にも取引に行こうと思ってる」と彼はチョッキのポケットに親指を入れて言った。「砂糖、タバコ、ラム酒もいいし、セイロンには特に象牙を仕入れに行きたい。」
「相当な数の船が要るね」と僕。
「まさに艦隊だよ」と彼。
こうした壮大な話にすっかり圧倒された僕は、彼がいま保険をかけている船は、どこへ主に航海しているのか尋ねた。
「まだ保険業は始めていないんだ」と彼は答えた。「今は様子を見てる段階さ。」
なぜか、その“様子を見ている”という仕事ぶりがバーナード・インに相応しい気がして、僕は納得したように「ああ」と言った。
「うん。会計事務所で働きながら、様子を見てる。」
「会計事務所って儲かるの?」と僕。
「それは――君は“そこにいる若者”って意味かな?」と彼は聞き返した。
「そう。君にとっては?」
「うーん、いや、僕には儲からない。」と、まるで計算して帳尻を出すような調子で言った。「直接的な利益はない。つまり、僕には何も支払われず、自分で自分を養っていかないといけない。」
確かにこれでは利益が出るようには見えず、僕はこんな収入では資本を積み上げるのは難しいだろうと首を振った。
「でも大事なのはさ」とハーバート・ポケットが言った。「“様子を見る”ってことなんだよ。それが一番大事。会計事務所で仕事しながら、様子を見る。」
どうやら、“会計事務所以外では様子を見れない”と言いたげだったが、僕は彼の経験に黙って従った。
「そしてそのうち、チャンスが見える。そしたら突撃して一気に資本を作って、あとはもう運用するだけさ。」
これは、あの庭での取っ組み合いのときの彼のやり方とよく似ていた。貧しさを受け止める態度も、あの時の敗北の受け止め方と全く同じだった。今も、彼の周りには生活必需品しかないことは明らかで、僕が目につけたものは全部、コーヒーハウスかどこかから僕のために届けられたものだった。
それでも、彼は心の中で一財産を築き上げていながら、全く偉ぶることもなく、僕は彼がうぬぼれていないことに感謝すら感じた。彼の本来の穏やかな性格に加えて、それがまた心地よかった。僕たちはすっかり打ち解けて仲良くなった。夕方には連れ立って街を散歩し、劇場に半額で入り、翌日はウェストミンスター寺院で礼拝をし、午後には公園を歩いた。そこで、あのたくさんいた馬の蹄鉄は誰が打ったのだろう、ジョーがやっていたらいいのに、と僕は思った。
冷静に考えても、あの日曜日からジョーやビディを離れてから何ヶ月も経っていた。その間隔はどんどん広がって、故郷の湿地はどこまでも遠く感じられた。ついこの前の日曜日まで、昔の教会に昔の服で通っていたなんて、地理的にも社会的にも、太陽系でも月面でもありえそうにない出来事に思えた。しかしロンドンの夕暮れ、群衆で賑わう通りや明るい灯りのなかで、僕があの貧しい古い家の台所をこんなに遠ざけてしまったことを責める声が聞こえてくるようだったし、夜更けにはバーナード・インで居眠りするポーターの足音が、偽者のように僕の胸に響いた。
月曜の朝、8時45分にハーバートは会計事務所へ出勤し、自分自身“様子を見る”のだろう、と思いながら僕も一緒に行った。彼は1、2時間で抜けて僕をハマースミスまで案内してくれることになっていたので、僕はそこで待つことにした。若き保険業者の卵はダチョウのように埃と熱の中で孵化するのだろうかと思うほど、月曜の朝にそうした見習いが集まる場所はどこもむんむんしていた。ハーバートが勤務する会計事務所も、観測所としては全然いい印象がなかった。中庭の奥の二階で、どこまでも薄汚れて、窓から見えるのは向かいの二階の裏側だけだった。
僕は正午まで待ち、“取引所”に行ってみると、船舶の掲示の下で煤けた男たちが座っていた。僕は彼らを大商人だと思ったが、なぜみんな元気がないのか不思議だった。ハーバートが戻ってきて、僕たちは有名なレストランで昼食を取った。僕はその店を敬意を持って見ていたが、今になって思うとヨーロッパ一の迷信だったと思う。なぜなら、あの日でさえ、テーブルクロスやナイフやウェイターの服のほうが、ステーキの上よりもずっとグレイビー(肉汁)が多かったからだ。この食事を良心的な値段で(脂肪分は請求されなかったが)済ませ、バーナード・インに戻って僕の小さなトランクを受け取り、馬車でハマースミスに向かった。到着したのは午後2時か3時頃で、ポケット氏の家まではほんの少し歩くだけだった。門のかんぬきを上げて、小さな庭に入ると、子どもたちが川辺で遊んでいた。僕の期待や先入観が影響していないと信じたいが、ポケット夫妻の子どもたちは「育てられている」よりむしろ「転がりながら育っている」ように見えた。
ジョー夫人は庭の椅子に足を乗せ、読書していた。乳母が二人、子どもたちが遊んでいる間、辺りを見回していた。「ママ、こちらが若いピップさんだよ」とハーバートが紹介すると、ジョー夫人は愛想よく品のある面持ちで僕を迎えてくれた。
「アリック坊やとジェーンちゃん」と乳母の一人が子ども達に叫んだ。「そんなに茂みにぶつかってたら、川に落ちて溺れちゃうわよ。お父さんになんて言われると思ってるの?」
同時にその乳母はジョー夫人のハンカチを拾い上げ、「まあ、これで今日は6回目ですわよ!」と言った。それにジョー夫人は笑い、「ありがとう、フロップソン」と言って椅子を一つに戻し、読書に戻った。その顔は新たに眉間にしわを寄せ、まるで一週間も読書しているかのように集中している様子だったが、数行も読まないうちに僕に目を向け、「あなたのお母様はお元気?」と尋ねてきた。あまりに思いがけない質問で僕は困惑し、「もし母がいたなら、きっと元気で、とても感謝し……」と訳のわからないことを言い始めたが、乳母が助け舟を出してくれた。
「まあ!」と乳母はハンカチを拾い上げながら叫んだ。「これで7回目ですよ! 今日はいったい何をしていらっしゃるんですか、奥様!」ジョー夫人はそのハンカチを、まるで初めて見る物のような驚きの表情で受け取り、すぐに思い出して笑い、「ありがとう、フロップソン」と言い、僕のことは忘れて読書を続けた。
僕が数えてみると、そこにいたポケット家の子供は全部で六人、さまざまな発育段階で転がりながら育っていた。人数を把握した矢先、空中で鳴くような赤ん坊の泣き声が聞こえた。
「ほら、赤ちゃんだわ!」とフロップソンが驚いて言った。「急いで上がって、ミラーズ。」
もう一人の乳母ミラーズが家に入り、やがて泣き声はだんだん静まり、赤ん坊の口に何か物が入っているかのように泣き止んだ。ジョー夫人はずっと本を読んでいたので、僕は何の本だろうと興味を持った。
僕たちはポケット氏を待っていたようで、とにかくそこで待つことになった。その間に、遊んでいる子どもたちがジョー夫人のそばに近づくたび、必ず自分でつまずいて夫人に倒れかかり、それに夫人が一瞬驚き、子どもはしばらく泣き続ける、という現象が繰り返されていた。なぜこんなことが起きるのか僕は理由がわからず、考え込んでいたが、やがてミラーズが赤ん坊を連れて降りてきた。赤ん坊はフロップソンに手渡され、フロップソンがジョー夫人に赤ん坊を手渡そうとした時、彼女も赤ん坊ごと見事にジョー夫人の上に頭から転がり込み、僕とハーバートが受け止めた。
「まあ、フロップソン!」とジョー夫人が本から目を上げて言った。「みんな転がり込んでくるのね!」
「まったくですよ、奥様!」とフロップソンは顔を真っ赤にして言う。「何をお持ちなんです?」
「私が持ってる?」とジョー夫人。
「まあ、足台じゃありませんか!」とフロップソンが叫んだ。「そんな風にスカートの下に隠していたら、みんな転ぶに決まってますよ。はい、赤ちゃんを持って、本を渡してください。」
ジョー夫人は指示に従い、不器用に赤ん坊を膝の上で踊らせながら、他の子どもたちがその周りで遊んだ。しかしそれもすぐに終わり、ジョー夫人は子どもたち全員を家に入れて昼寝させるよう命じた。こうして僕は、その家での育児法が「転がり育つ」と「横になって育つ」を交互に繰り返すことだと知った。
こうした状況のなか、フロップソンとミラーズが子どもたちを羊の群れのように家へ入れ、ポケット氏が僕に会いに出てきた時、彼の顔が困惑気味で、髪が乱れ、何かを整理しきれないような様子だったのも、驚くには値しなかった。
第二十三章
ポケット氏は、僕に会えて嬉しいと言い、僕も会って後悔していないことを願うと述べた。「というのも、私、本当に――」と息子と同じ笑顔を浮かべながら続けた。「恐ろしい人物ではありませんので。」彼は困惑して白髪も多かったが、若々しく、ごく自然体だった。自然体、というのは気取らないという意味である。どこか滑稽で、もし自分でもその滑稽さに気づいていなければ、ただの道化者になっていただろう。少し話した後、彼は眉を少しひそめてジョー夫人に「ベリンダ、ピップ君を歓迎してくれたかい?」と尋ねた。彼女は本から顔を上げて「ええ」と答え、心ここにあらずという感じで微笑み、「オレンジフラワーウォーターの味はお好き?」と聞いた。この質問は、その前も後も何の文脈もなく、単なる一般的な社交辞令として投げかけられたのだろう。
数時間後に僕は、ジョー夫人が、ある偶然の成り行きで亡くなった騎士の一人娘で、その父親は「もし誰か(誰だったかは忘れた――国王、首相、大法官、カンタベリー大主教、誰でもいい)が邪魔をしなければ、先祖が準男爵になっていたに違いない」と確信し、貴族に自らを連ねていたことを知った。彼は自分で英語文法をペン先で「強襲」したという理由で叙勲され、何かの礎石の式典で王族に鏝やモルタルを手渡したらしい。とにかく、娘には「将来は必ず爵位持ちと結婚すべきだ」と教え込み、庶民的な家事知識を一切身につけさせないよう育てたのだった。
この親の徹底した方針のおかげで、彼女は見目麗しく成長したが、家事などはまるでできない、全く実用性のない人間になった。そして彼女が若さの盛りにポケット氏と出会った。彼もまた若く、法律家か聖職者か迷っている時期だった。どちらに進むにせよ時間の問題だと考え、二人は親の知らぬ間に結婚した。親は祝福以外に与えるものもなく、結局祝福を与えて「娘は王子の宝だ」と告げた。ポケット氏はそれからずっとその「宝」を世間で運用してきたが、利息はあまり生み出さなかったようだ。それでも、ジョー夫人は「爵位と結婚できなかった」と同情され、ポケット氏は「爵位を得られなかった」と許されるふりで責められるという、妙な扱いを受けていた。
ポケット氏は僕を家に案内し、快適な個室を見せてくれた。それから、隣の部屋の二人の居住者にも紹介してくれた。ドラメルとスタートップだ。ドラメルは、妙に老けた重苦しい若者で、口笛を吹いていた。スタートップは年も見た目も若く、本を読みながら、まるで頭が知識で破裂しそうな様子だった。
ポケット夫妻は二人とも、誰か他人に家を管理されているような雰囲気があったので、僕は本当は誰が家の持ち主なのだろうと不思議に思ったが、やがてその「正体」が召使いたちであると気づいた。このやり方は、面倒を省くという意味では円滑だが、出費は大きく、召使いたちは食事や飲み物には贅沢をし、よく客を呼んでいた。夫妻にも十分な食事が提供されたが、僕には台所で下宿したほうがずっと良さそうに思えた――もちろん身を守る覚悟があればだが。というのも、一週間もしないうちに、近所の面識のない婦人から「ミラーズが赤ん坊をたたくのを見た」と手紙が届き、ジョー夫人は大泣きして「ご近所さんは自分のことだけ考えてればいいのに」と嘆いていたからだ。
やがて(主にハーバートから)僕は、ポケット氏がハロウ校とケンブリッジ大学で優秀な成績を収めたが、若くしてジョー夫人と結婚したため将来を棒に振り、「グラインダー(家庭教師)」になったと知った。多くの「鈍い刃」を研いできたが、そうした生徒の父親が有力者のときは「出世を世話する」と言いながら、肝心の生徒が去ると忘れてしまうのが常だった。そのうちその仕事にも嫌気が差し、ロンドンに出てきた。ここで希望を次第に絶たれつつも、機会を逃したり無駄にしたりした者の指導や、特定の目的のための指導・校正で生計を立てていた。そして、ごくわずかばかりの私財を加えて、今もこの家を維持していた。
夫妻にはおべっか好きの隣人がいた。未亡人で、誰にでも同意し、誰にでも祝福を与え、状況に応じて涙も微笑みも惜しまない、極めて共感的な性格の婦人、コイラー夫人である。僕がこの家に入った日に、彼女をエスコートして食事に向かった。階段で、「親愛なるジョー夫人にとって、ポケット氏が若い紳士を受け入れざるを得ないのは痛手です」と愛情あふれる口調で伝えられた。だが、僕のことは「もしみんなあなたのようなら別ですけど」と言い添えた。(当時、彼女と知り合って五分も経っていなかった。)
「でもね、親愛なるジョー夫人は」とコイラー夫人は続けた。「あんなに若くして不幸に遭ってしまって――もちろんポケット氏に非はありませんが――とても贅沢と優雅さを必要とされるのですよ。」
「はい、奥様」と僕は彼女が泣きだしそうなので遮った。
「そして、とても貴族的な気質で――」
「はい、奥様」とまたも遮った。
「――だから」コイラー夫人は言った。「親愛なるジョー夫人から親愛なるポケット氏の時間と関心が奪われるのは辛いことなのです。」
僕は「もし肉屋の時間と関心が奪われたらもっと大変なのに」と思ったが、黙って礼儀作法に注意を向けた。
食事中、ジョー夫人とドラメルの会話から、彼の名前がベントレーであり、準男爵位の継承権第二位だということがわかった。また、ジョー夫人が庭で読んでいた本はすべて爵位に関するもので、彼女は祖父が爵位名鑑に載る予定だった正確な日付まで知っていることも分かった。ドラメルは多くを語らなかったが、選ばれし者らしい口ぶりでジョー夫人を「同士」と認めていた。この話題に興味を示したのは彼とジョー夫人、そしておべっか好きのコイラー夫人だけで、ハーバートには苦痛な様子が見て取れた。話題が長引きそうな頃、給仕の少年が家の不幸を告げに入ってきた。要するに、料理人が牛肉を見失ったというのだ。僕が驚愕したのは、ここで初めてポケット氏が実に奇妙な行動に出たことだった。彼は肉を切っていた手を止め、両手を乱れた髪に差し入れ、まるで自分を髪の毛で引き上げようとするかのような大げさな仕草をしたのだ。しかし、全く持ち上がらないまま、また何事もなかったように切り分けを続けた。
それからコイラー夫人は話題を変えて僕を褒め始めた。最初は心地よかったが、あまりにも大げさだったので、すぐに興ざめしてしまった。彼女は、地元や古い友人について尋ねてくるとき、蛇のごとく僕に近寄り、時折スタートップやドラメルに話を振るときは、彼らがテーブルの反対側にいることを羨ましく思ったほどだった。
食事後、子どもたちが紹介され、コイラー夫人はその目や鼻や脚を褒めていた――これが子どもの知性を伸ばす賢い方法だそうだ。四人の女の子と二人の男の子、それに赤ん坊と、その次の赤ん坊候補がいた。フロップソンとミラーズが、まるでどこかで子どもをスカウトしてきたかのように連れてきた。ジョー夫人は、検分はしたが何をどうしたらいいかわからない様子だった。
「はい、フォークを渡して、赤ちゃんを持ってください、奥様」とフロップソンが言う。「その持ち方じゃ、頭がテーブルの下になってしまいますよ。」
ジョー夫人は逆の持ち方をして、今度は頭をテーブルの上にぶつけた。それは大きな音で全員に知らされた。
「まあまあ! もう一度私に返してください、奥様」とフロップソン。「ジェーンちゃん、赤ちゃんのために踊ってあげて!」
一番小さな女の子が立ち上がり、赤ちゃんの前で踊ると、赤ちゃんは泣き止んで笑った。それにつられてみんな笑い、ポケット氏も(その間に二度ほど髪を引っ張り上げようとしていた)笑い、僕たちも皆笑った。
フロップソンは、赤ちゃんを関節で折り曲げてジョー夫人の膝に収め、ナッツ割り器をおもちゃに渡した。同時に「この道具の取っ手が赤ちゃんの目に合わないように注意してください」と言い、ジェーンにもしっかり見ているように命じた。そして乳母たちは部屋を出て、給仕の少年と階段で小競り合いを始めた。少年はディナーの間に明らかにボタンの半分を賭博で失った様子だった。
ジョー夫人がオレンジを砂糖とワインに漬けて食べながら、ドラメルと二つの準男爵位について語り始めたとき、僕は大いに不安になった。その間、膝の上の赤ちゃんはナッツ割り器で実に恐ろしいことをしていた。ついにジェーンが危険を察し、そっと近寄って器用にそれを取り上げた。ジョー夫人はオレンジを食べ終えたころ、それに気づいて「いけない子ね、なんてことをするの? すぐに席に戻りなさい!」と叱った。
「ママ、赤ちゃんがお目々を突いちゃうところだったの」と小さなジェーンが舌足らずに言った。
「そんなことを私に言うなんて許せません!」とジョー夫人。「今すぐ席に戻りなさい!」
その威厳ある態度に、僕はまるで自分が彼女の怒りを買ったかのように恐縮してしまった。
「ベリンダ」とポケット氏がテーブルの端からたしなめる。「どうしてそんな理不尽なことを言うんだい? ジェーンは赤ちゃんを守るためにやったんだよ。」
「誰にも口出しはさせません」とジョー夫人は無垢なジェーンを睨みながら言った。「私は祖父の地位を心得ているつもりです。ジェーンなんかに!」
ポケット氏は再び両手を髪にやり、今度は実際に何インチか椅子から身体を持ち上げてしまった。「聞いてくれ!」彼はどうすることもできず天に向かって叫んだ。「赤ん坊は、人々の可哀想な祖父の地位のために、クルミ割りで殺されるべきなのか!」そしてまた椅子に沈み込み、沈黙した。
私たちは皆、気まずそうにテーブルクロスを見つめていた。ひとしきり沈黙が続いたが、その間にも、正直で抑えきれない赤ん坊は、小さなジェーンに向かって何度も跳びはねては、歓声を上げていた。どうやら家族の中で(使用人を除けば)、赤ん坊が明確な親しみを持っているのは、小さなジェーンだけのように私には思えた。
「ドラムルさん」とポケット夫人が言った。「フロップソンを呼んでくださらない? ジェーン、この親不孝者、さあ横になりなさい。さあ、かわいい赤ちゃん、ママと一緒にいらっしゃい!」
赤ん坊は誠実そのもので、全力で抗議した。ポケット夫人の腕の上で変な方向に身体を曲げ、柔らかい顔の代わりに編み上げの靴とえくぼのある足首を皆に披露し、大反抗のまま運び出されていった。だが結局は赤ん坊の勝ちだった。私は窓越しに、ほんの数分後、小さなジェーンにあやされている赤ん坊の姿を見たのだ。
そのとき、他の五人の子どもたちは食卓に残されたままだった。というのも、フロップソンには私的な用事があり、他にその子たちの世話をする人もいなかったからだ。こうして、私は彼らとポケット氏の間の関係を知ることになった。ポケット氏は、いつもの困惑した表情にさらに髪をぐしゃぐしゃにしながら、しばらく彼らをじっと見つめていた。まるで、なぜ彼らがこの家に住み着いているのか、なぜ自然の摂理で他の家に割り当てられなかったのか、理解できないという顔つきで。やがて、遠くから布教するかのような態度で、何問か質問をした――たとえば、ジョー坊やの襟ぐりに穴があいているのはなぜか尋ねると、「パパ、フロップソンが時間ができたら直すって」と答え、ファニー坊やの指にできた腫れ物について尋ねると、「パパ、ミラーズが忘れなければ湿布してくれるって」と返してきた。その後、父性愛にほだされ、子どもたち全員に1シリングずつ与え、「外で遊んでおいで」と言った。そして彼らが出ていくとき、髪を引っ張って自分を奮い立たせようと大きく努力しながら、どうしようもない問題を手放したのだった。
その晩、川ではボート漕ぎがあった。ドラムルとスタートップがそれぞれ自分の船を持っていたので、私も自分の船を調達し、二人に負けまいと決めた。田舎育ちの少年たちが得意とする多くの運動は私もかなりできたが、テムズ川――ほかの水域でもそうだが――にふさわしい優雅な漕ぎ方が足りないと自覚していたので、すぐさま、階段下で営業している賞金付きの小舟の優勝者に弟子入りすることにした。新しい仲間たちが紹介してくれたこの実践派の権威は、私に「君は鍛冶屋の腕をしている」と言って非常に困惑させた。その言葉がどれほど弟子を失いかけたか知っていたら、きっとそんな褒め方はしなかっただろう。
夜、家に戻ると、夜食用の盆が出た。皆心から楽しんで過ごせたはずだが、一つ厄介な家内の事件があった。ポケット氏は上機嫌だったが、女中がやって来て、「失礼ですが、旦那様にお話ししたいことがございます」と言った。
「ご主人に話すですって?」とポケット夫人は再び尊厳を取り戻して言った。「どうしてそんなことができると思うの? フロップソンに言いなさい。それか、他のときに私に言いなさい。」
「失礼ですが、奥様」と女中は返した。「ただちにご主人様にお話ししたいのです。」
そこでポケット氏は部屋を出ていき、私たちは彼が戻るまでなんとか自分たちを保った。
「なんてことだ、ベリンダ!」とポケット氏は、悲しみと絶望を表す顔で戻ってきて言った。「台所の床で料理人がべろべろに酔って気絶していて、新鮮なバターの大きな包みが戸棚に隠されて、ラードとして売る準備がしてある!」
ポケット夫人はすぐに親切そうな感情を見せ、「これはあの憎たらしいソフィアの仕業よ!」と言った。
「どういう意味だ、ベリンダ?」とポケット氏が詰問した。
「ソフィアがあなたに言いつけたのよ」とポケット夫人。「私は自分の目で見て、自分の耳で聞いたわ。つい今しがた部屋に入ってきて、あなたに話しかけたいと言ったでしょう?」
「でもベリンダ、彼女は僕を階下に連れて行って、あの女と包みも見せてくれたじゃないか」とポケット氏は返した。
「それであなたは、マシュー、騒ぎを起こしたことをかばうの?」とポケット夫人は言う。
ポケット氏は情けないうめき声を漏らした。
「私は、おじいさまの孫娘なのに、この家で何の権威もないの?」とポケット夫人。「それに、料理人はいつもとても感じの良い尊敬深い人だったわ。就職の面接に来たとき、まるで自然に“私は公爵夫人になるために生まれた方だと感じました”と言ったのよ。」
ポケット氏が立っていたところにはソファがあり、彼は瀕死の剣闘士のような姿勢でそこに倒れ込んだ。そのままの姿勢で虚ろな声で「おやすみなさい、ピップさん」と言ったので、私は寝ることにし、彼を残して部屋を後にした。
第二十四章
二、三日して、私は自分の部屋に落ち着き、何度かロンドンと行き来し、店から必要なものをすべて注文した頃、ポケット氏と私はじっくり話し合った。彼は私の進路について私自身よりよく知っていた。というのも、ジャガーズ氏から、私が特定の職業に就く予定はなく、裕福な若者たちと肩を並べられる程度に教育を受ければ将来困らないだろうと聞かされていたからだ。私は異論もなかったので当然同意した。
彼は私に、ロンドンのいくつかの場所に通って基礎的な知識を得ることと、すべての学習において彼を解説者・指導者として仰ぐことを勧めた。知的な助力があれば落胆することは少なく、やがて彼の助け以外は要らなくなるだろうと望んでいた。彼のこうした物言い、そして同様の多くの話から、彼は私と理想的な信頼関係を築いたと言える。そして、私も最初から言っておくが、彼はこの約束を果たすことに常に熱心で誠実だったので、私も自らの責任を果たすよう努力した。もし彼が教師として無関心だったなら、私も生徒として同じ対応をしていただろうが、その隙は与えられなかった。私たちは互いに正当な評価をし合っていた。そして私は彼の指導に、滑稽な点や不真面目な点、誠実さや善良さ以外のものを感じたことは一度もなかった。
こうして方向性が決まり、本格的に勉強を始めた私は、もしバーナード・インの自室を残しておけば、生活に良い変化が生まれるし、ハーバートと過ごすことで礼儀作法も良くなると考えた。この案にポケット氏は反対しなかったが、何よりもまず後見人の承認が必要だと主張した。それは、この計画がハーバートの出費を減らすことになる点を考慮しての配慮だと私は感じた。そこで私はリトル・ブリテンへ行き、ジャガーズ氏にその旨を伝えた。
「もし今、借りている家具やちょっとした物を買い取れれば、すっかり快適に暮らせるんですが」と私は言った。
「やってみな!」とジャガーズ氏は短く笑って言った。「お前はうまくやるって言ったろ。さて、いくら欲しいんだ?」
私はいくらか分からないと言った。
「さあ!」とジャガーズ氏。「いくらだ? 五十ポンドか?」
「いえ、そんなには……」
「五ポンドか?」とジャガーズ氏。
あまりの落差に、私はとまどいながら「いえ、それよりは多いです」と答えた。
「それより多いのか!」とジャガーズ氏は私を見据え、手をポケットに入れ、首をかしげて後ろの壁を見つめながら「どれくらい多い?」と言った。
「金額を決めるのは難しいです」と私はためらった。
「さあ!」とジャガーズ氏。「計算しよう。五の二倍でいいか? 三倍でいいか? 四倍でいいか?」
私は「四倍で十分だと思います」と答えた。
「四倍で十分か?」とジャガーズ氏は眉をひそめた。「さて、四の五倍は何になる?」
「何になるか、ですか?」
「ああ!」とジャガーズ氏。「いくらだ?」
「おそらく二十ポンドです」と私は笑いながら言った。
「私がいくらと考えるかはどうでもいい」とジャガーズ氏は知ったかぶりに頭を振って言った。「君がいくらと考えるか知りたいんだ。」
「もちろん二十ポンドです。」
「ウェミック!」とジャガーズ氏は事務所の扉を開けた。「ピップ君の書面による注文を受け取り、二十ポンド支払ってくれ。」
この強引な商売のやり方は私に強烈な印象を残したが、それは決して愉快な印象ではなかった。ジャガーズ氏は決して笑わない。しかし彼は大きくてピカピカの軋むブーツを履いており、答えを待つ間、大きな頭を垂れて眉を寄せながら、そのブーツを軋ませて、まるでブーツ自体が乾いた怪しげな笑いをするかのようだった。たまたま彼が出ていき、ウェミック氏が機嫌よく話好きだったので、私はジャガーズ氏の態度がどうにも掴めないとウェミック氏に話した。
「そう言ってやれば、彼はそれを褒め言葉と受け取るだろう」とウェミック氏は答えた。「彼は君がどう捉えるかなんて気にしていない――あれは個人的じゃなくて職業的なものだよ。」
ウェミック氏は机でビスケットをバリバリやりながら昼食をとっていた。そのビスケットの破片を、時折、口の切れ目にポストするように投げ入れていた。
「いつも思うんだ」とウェミック氏は言った。「まるで人間罠を仕掛けて、それを見張っているようだ。突然――パチン! 君は捕まる!」
人間罠が生活の潤いとは言えないと指摘せず、私は「彼はとても腕が立つんですね?」と尋ねた。
「深いよ」とウェミック氏。「オーストラリア並みにね。」ペンで床を指し、オーストラリアが地球の真裏にあることを示した。「もしそれより深いものがあれば、彼がそれだよ。」
それから私は「商売は繁盛しているのですか?」と聞くと、ウェミック氏は「絶好調!」と答えた。さらに「事務員は多いのか?」と尋ねると、こう返った――
「うちは事務員をあまり雇わない。なぜならジャガーズは一人しかいないし、誰も彼の二番煎じなんて望まないからだ。全部で四人しかいない。見てみたいか? 君も“仲間”みたいなものだし。」
私は申し出を受けた。ウェミック氏がビスケットを全部ポストし、背中のどこかに隠していた金庫の鍵を首元から鉄の辮髪のように取り出して、現金箱から私に金を払ったあと、私たちは二階に上がった。家は薄暗くてみすぼらしく、ジャガーズ氏の部屋にべっとりついた脂ぎった肩跡は、何年もの間この階段を上り下りした痕のようだった。前方の一階には、酒場の主人とネズミ捕りの中間のような、顔色の悪い膨れ上がった大男の事務員が、みすぼらしい身なりの三、四人を相手にぞんざいに応対していた。「ベイリー裁判所の証拠集めさ」とウェミック氏が出ながら言った。その上の部屋には、弱い目をした男と応対している、垂れた髪の小柄で締まりのないテリア犬のような事務員がおり(子犬時代にカットを忘れられたような様子)、ウェミック氏によればその男は「溶鉱屋」で、何でも溶かしてやると言い、汗びっしょりでまるで自分を溶かしかけたようだった。奥の部屋には、顔を汚いフランネルで包んだ高い肩の男が、ワックス加工されたような古びた黒服で、他の二人のメモを清書してジャガーズ氏用にまとめていた。
これが全員だった。再び一階に下りると、ウェミック氏は私を後見人の部屋に導いて「ここはもう見たよね」と言った。
「ところで」と私は、またもや目にしたあの二つの忌まわしいデスマスクに気づいて尋ねた。「あれは誰の顔なんです?」
「これかい?」とウェミック氏は椅子に上がり、ほこりを吹き飛ばしてからその凄まじい顔を手に取った。「これは有名人だよ。うちの名クライアントで、世間の評判も得た。この男(おいおい、お前は夜中にインク壺を覗き込んで眉毛に染みをつけたんだろ、この悪党め!)は主人を殺し――証拠固めは不得意だったが、計画自体は悪くなかった。」
「本人に似てるの?」と私は、その姿に身を引きつつ尋ねた。
「似てるかって? 本人そのものさ。ニューゲート監獄で、絞首の直後に取った型だよ。君、私に特に気があったんだろ、アートフル老人?」ウェミック氏はそう言いながら、自分のブローチ――女性と墓、壺を配した柳の意匠――を指し、「特注で作らせたんだ」と説明した。
「その女性は誰です?」と私は尋ねた。
「いや、ただの“遊び”さ。(遊び好きだっただろ?)いやいや、女性が絡んだのは一人だけ――でもこんな華奢な婦人じゃなかったし、この壺を覗き込むなんてことは酒でも入っていなきゃしなかったろうさ。」ブローチに目を向けながら、ウェミック氏はそのキャストを置き、ハンカチでブローチを磨いた。
「もう一方の奴も同じ最後だったの?」と私は尋ねた。「顔つきが似てる。」
「その通り」とウェミック氏は言った。「本物の顔つきだよ。馬の尾毛と小さな釣り針で鼻の穴を吊り上げられたみたいだろ。こいつも同じ最期だ。ここじゃ、それが自然の成り行きさ。遺言状の偽造犯だ、たぶん“遺言者”も眠らせてやったろう。お前は紳士ぶった奴だったな」(ウェミック氏は再びキャストに語りかける)「ギリシャ語まで書けると言ったくせに。ああ、大法螺吹きだった! お前ほどの嘘つきは見たことがないよ!」もう一人の“友人”を棚に戻す前に、ウェミック氏は最大の喪章指輪に触れ、「これも前日に買いに行かせたんだ」と言った。
二つ目のキャストをしまい椅子から降りるとき、私は彼の装身具は全て同じような由来ではないかと思った。本人が恥じる様子もなかったので、思いきって尋ねてみた。
「ああ、そうだよ。全部そういう贈り物だ。次々に集まるんだ。みんな珍品だし、立派な財産だ。大した価値はなくても、やっぱり財産であり持ち運びできる。君は将来明るいから関係ないが、私の方針は“持ち運べる財産を確保せよ”だ。」
私はその信条に敬意を表した。すると、彼は親しげに続けた――
「もし暇な時があったら、ウォルワースに遊びに来てくれ。寝床も用意できるし、光栄だ。見せる物は少ないが、いくつか珍品もあるし、庭や東屋も自慢なんだ。」
私は喜んでお招きにあずかりたいと言った。
「ありがとう。じゃあ、都合のいい時にぜひ。ジャガーズ氏とはもう食事したかい?」
「まだです。」
「彼はワインを出す、しかも上等だ。私はパンチを出す、悪くはないぞ。それから一つ忠告がある。ジャガーズ氏と食事するときは、家政婦に注目してみな。」
「何か特別なものが見られるのか?」
「“猛獣が手なずけられている”光景だ。珍しい話じゃないと思うかもしれないが、元々の猛獣ぶりと手なずけ具合による。ジャガーズ氏の力を見直すことになるだろう。目を離すな。」
私はその忠告で好奇心がかき立てられ、興味津々で従うと伝えた。帰り際、彼は「ジャガーズ氏の“仕事ぶり”を五分だけ見ていかないか?」と聞いた。
いろいろな理由、なかでも“仕事ぶり”が何を指すか分からなかったので、私は承諾した。私たちはシティに入り、人で混み合う警察裁判所にたどり着いた。そこでは、被害者の血縁者(凶悪な意味での)が、妙なブローチをつけて法廷に立ち、私の後見人は女を尋問――もしくは反対尋問――していた。彼は法廷の誰もに畏怖を与えていた。誰であろうと彼の気に入らない言葉を発すれば、即座に「記録しろ!」と命じ、認めない者には「白状させてやる!」、認めた者には「ほら、捕まえたぞ!」。判事たちは彼の指一本に震え上がり、泥棒も警官も彼の言葉に聞き惚れ、彼の眉一つ動くだけで身をすくめた。彼がどちら側か私には分からなかった――彼は裁判所全体を石臼ですり潰しているように見えた。私が抜き足差し足で退席したとき、彼は裁判官席の味方ではなく、イギリス法と正義の代表であるはずの老紳士の足を、机下で激しく震わせていた。今日はその椅子に座る資格を断罪していたのである。
第二十五章
ベントレー・ドラムルは、まるで本の作者に恨みがあるかのように本を手に取るほど、不機嫌な男だったが、出会う人にも同じ態度だった。見た目も動きも理解力も重たく、顔色は鈍く、舌は大きくて口の中でだらりとし、本人も部屋でだらりとしていた。怠惰で傲慢、吝嗇、口数少なく疑い深い。彼はサマセットシャーの裕福な家系で、家族がこの性格を大事に育てた結果、立派な年齢に達した時点で、ただの大馬鹿者だと気付いたのだった。こうして、ベントレー・ドラムルはポケット氏の元にやってきたが、その時には氏より頭一つ高く、ほとんどの紳士より六つも七つも頭が分厚かった。
スタートップは弱い母親に甘やかされ、学校に行くべき時期も家に置かれていたが、母親を熱烈に愛し、限りなく敬愛していた。彼は女のような繊細な顔立ちをしており、「見たことがなくても分かるだろう」とハーバートは私に言った――「母親そっくりなんだ」。当然、私は彼にはドラムルよりずっと親しみを感じたし、ボートを漕ぐ夜も、二人で並んで会話しながら帰ることが多かった。ドラムルは一人で岸辺の下や葦の間を漕いで追いついてきた。潮が速く流れるときでさえ、彼は不器用な両生類のように岸沿いを這って進んでいた。だから今でも、私の心には、彼はいつも薄暗がりや淀みに遅れてやってくる印象しか残っていない。私たち二人のボートが夕日や月明かりの中で川を割って進むときも、ドラムルは後ろから影のようについてきていた。
ハーバートは私の親友であり、私は彼に自分のボートの持ち分の半分を譲った。それで彼はしばしばハマースミスに来ることになり、私も彼の部屋の持ち分があることでロンドンへよく行った。二人でその間の道をよく歩いた。私はあの道が今でも好きだ(今は当時ほど素敵な道ではないが)、未熟ながらも希望に満ちた若い心で親しみを覚えた道である。
ポケット家に住んで一、二か月すると、カミラ夫人と彼女の夫が現れた。カミラはポケット氏の姉である。私がミス・ハヴィシャム邸で見かけたジョージアナも現れた。彼女は従姉妹で――消化の悪い独身女性で、禁欲を信仰心、肝臓の不調を愛情と呼んでいた。この人たちは、強欲と失望の憎しみで私を嫌っていた。当然、彼女たちは私の成功に卑劣に媚びへつらった。ポケット氏に対しては、自分の利益を知らない大人の赤ん坊として、例の寛容な態度を見せていた。ポケット夫人は軽蔑の的だったが、人生で大きな失望を味わった可哀想な人として扱い、それによって自分たちの価値も少しだけ高まるように見せていた。
こうした環境の中で私は落ち着き、勉学に励んだ。私はすぐに贅沢な習慣が身についてしまい、数か月前なら信じられないほどの金を使い始めたが、良きにつけ悪しきにつけ勉強は続けた。これは私に才覚があったというより、自分の欠点を自覚していたからにすぎない。ポケット氏とハーバートのおかげで私は急速に成長した。二人のどちらかが常に助けてくれ、障害を取り除いてくれたので、私がドラムル並の愚か者でなければ、これより劣る結果になるはずがなかった。
しばらくウェミック氏に会っていなかったが、ある夕方に自宅まで同行したいと手紙を送った。彼はぜひともと言ってくれて、六時に事務所で待つと言った。私は約束通り行き、彼が金庫の鍵を背中にしまうところに出くわした。
「ウォルワースまで歩いていくつもりかい?」と彼が言う。
「もちろん、そのおつもりなら」と私は答えた。
「大歓迎だ」とウェミック氏。「一日中机の下で足を丸めていたから、伸ばしたい。さて、晩飯は何を用意してると思う? 自家製のシチューと、惣菜屋の冷たいロースト鶏さ。柔らかいはずだ。なぜなら店主がうちの裁判の陪審員をやったばかりで、こっちは恩を売ってるからね。鶏を選ぶときに“いいの選んでくれよ、もし君をもう一日か二日箱に入れておくつもりならできたけど、こっちは手加減したんだから”と言ったら、“店で一番の鶏を進呈しましょう”と言われた。もちろんもらったよ。持ち運びできる財産だからね。ところで、“年老いた親”がいるけど大丈夫だよね?」
私はまだ鶏の話かと思ったが、「ご両親がいらっしゃるんですね」と礼儀上答えた。
「で、ジャガーズ氏とは食事した?」彼は歩きながら続けた。
「まだです。」
「今日の午後、君が来ると聞いて彼がそう言ってた。たぶん明日にでも招待されるよ。君の仲間も呼ぶつもりだ。三人いたろ?」
私はドラムルを親友とは思っていなかったが、「はい」と答えた。
「じゃあ全員呼ぶんだな――“仲間”って言い方は嬉しくなかったけど――何を出されても上等だ。種類は期待するな、質は保証する。もう一つ家の中で変わったことがある」とウェミック氏は一瞬間を置き、家政婦の話から続けるように言った。「彼は夜、ドアも窓も絶対閉めない。」
「泥棒に入られないんですか?」
「それなんだよ!」とウェミック氏。「彼は公言してる。“俺を盗む奴が見てみたい”ってね。前にも何百回と、うちの事務所でプロの泥棒相手に“私の家は知ってるだろう。どの窓も錠もないんだ。なぜ仕事をしにこない? どうだ、誘惑されないか? ”と言ってる。だが誰一人として試そうとはしない。」
「そこまで恐れられてるんですね?」
「そう、恐れているんだ。ただ、彼はそれでも抜け目ない。彼の家のスプーンは全部ブリタニア合金、銀器はない。」
「じゃあ、たとえ入っても大した物は……」
「だが、彼が得る物は大きい」とウェミック氏はさえぎる。「泥棒の命だ。何十人分も。彼は手に入るものは全部手に入れる人だ。彼がその気になれば何が手に入らないか分からない。」
私は後見人の偉大さに思いを巡らせていると、ウェミック氏がこう言った――
「銀器がないのは、あの人の“深さ”の表れさ。川が深いように、彼も深い。時計の鎖を見てみろ。本物だ。」
「とても重厚ですね。」
「重厚だとも。時計は金のリピーターで、百ポンドの価値がある。ロンドンにはこの時計のことを知ってる泥棒が七百人くらいいる。誰一人として、その鎖の一番小さい輪を触るよう仕向けられたら、火傷したように手を引くだろう。」
最初はこんな話、次いで一般的な話をしながら、ウォルワースの地区に到着した。
そこは裏道や溝、小さな庭が集まった場所で、少し寂しい隠れ家の趣だった。ウェミック氏の家は小さな木造コテージで、屋根の上部は砲台のように切り取られ、砲が描かれていた。
「自作だ。いいだろ?」
私は大いに褒めた。今まで見た中で最も小さい家で、奇妙なゴシック風の窓(ほとんどが偽物)、ゴシック風のドアは入るのもやっとの大きさだった。
「あれが本物の旗竿さ。日曜には本物の旗も掲げる。橋を渡ったら――こうやって――連絡を絶つんだ。」
橋は板一枚で、幅約四フィート・深さ二フィートの溝を渡していた。だが彼が誇らしげにそれを引き上げ、固定する様子は実に楽しそうだった。
「毎晩九時、グリニッジ標準時に銃が鳴る。あれだ。鳴ったらびっくりするだろう。」
その砲は格子細工のミニ要塞に据えられていた。天候から守るため、傘のような工夫をしてあった。
「裏には、見えないように豚や鶏、ウサギがいる。自分で小屋を組み立ててキュウリも育ててる。サラダの出来は夕食で判断してくれ。だから、もしこの家が包囲されても、食料の点ではかなり持ちこたえられる。」
そして十数ヤード離れた東屋に案内してくれたが、道が工夫されていて辿り着くのに時間がかかった。東屋にはグラスが用意され、パンチは飾り池で冷やされていた。池は円形で島があり、そこが今夜のサラダかもしれない。噴水も自作で、小さな水車を回してコルク栓を抜くと、かなりの勢いで水が吹き出て手の甲まで濡れた。
「大工も配管も庭仕事も全部自分でやる。いろんな仕事で気分転換になるし、年老いた親も喜ぶ。今すぐ紹介してもいいかな?」
私は喜んで承諾し、家の中へ入った。そこには、火のそばに座った年老いた男性がいた。フランネルの上着で清潔で元気そうで、よく世話されていたが、とても耳が遠かった。
「やあ、おやじどの!」とウェミック氏は陽気に握手した。「ごきげんいかが?」
「元気だ、ジョン、元気だ!」と老人。
「こちらはピップさんだよ、おやじどの。名前が聞こえたらいいのにね。ピップさん、思い切りうなずいてあげて。とにかくうなずけば喜ぶから!」
「これは息子の素晴らしい家ですな」と老人は私がせっせとうなずくのを見て言った。「この場所と美しい設備は、息子の後も国が管理して人々の憩いの場にすべきですよ。」
「うれしいだろ、パンチみたいに誇らしいな?」とウェミック氏は、顔を和らげて老人を眺め、「はい、もう一回うなずき。もう一回――もっと大きく。気に入ったろ? 疲れてなければもう一回どうぞ。どれほど喜ぶか分からないよ。」
私は何度もうなずき、老人は大喜びだった。彼は鶏に餌をやろうと立ち上がり、私たちは東屋でパンチを楽しんだ。パイプをくゆらせながら、彼はこの家を今の完成度まで持ってくるのに何年もかかったと教えてくれた。
「これはあなたの持ち家なんですか?」
「そう、少しずつ手に入れた。完全な所有権さ。」
「ジャガーズ氏は感心してますか?」
「見たことも聞いたこともない。父もね。事務所は事務所、プライベートはプライベート。事務所に入れば城は忘れるし、家に戻れば仕事は忘れる。だから君にも職業的な話はしないでほしい。」
私はその要望を守ると心に決めた。パンチが美味しかったので、九時近くまで飲み語り合った。「もうすぐ大砲だ」と、ウェミック氏はパイプを置いた。「おやじどのの楽しみだから。」
家に戻ると、老人は火かき棒を熱して式典の準備をしていた。ウェミック氏は時計を見ながら、時が来ると火かき棒を持って砲台へ向かった。やがて「スティンガー」は轟音とともに発射され、家が揺れ、グラスやカップが鳴った。老人は椅子の肘掛けにつかまらなければ吹き飛ばされそうになりながら、「鳴ったぞ! 聞こえたぞ!」と叫び、私はうなずき続けて本当に彼が見えなくなるほどだった。
その後、ウェミック氏は珍品コレクションを見せてくれた。ほとんどが犯罪に関するもので、有名な偽造事件で使われたペンや剃刀、髪の毛や死刑囚の自筆告白書――「全部嘘っぱちさ」が自慢――などがあった。その他には小さな陶器やガラス細工、彼自身が作った小物、老人が彫ったパイプ栓もあった。それらは、最初に案内された部屋(居間兼台所)の一角に展示されていた。暖炉の上には焼き串用の真鍮の装飾もあった。
昼間は老人の世話をするきちんとした小さな女の子がいて、食卓を整えると橋を下ろして帰っていった。夕食は素晴らしかった。家はやや老朽化していたが、豚がもう少し遠くにいればなお良かった。だが私はこのもてなしに心から満足した。寝室は小塔で、天井が非常に薄く、寝転がるとまるで旗竿が額にのしかかるような気がした以外は、欠点もなかった。
ウェミックは朝早くから起きていて、私は彼が私のブーツを磨いている音を聞いたように思う。その後、彼は庭仕事に取りかかり、私はゴシック窓から、エイジド老人に仕事をさせているふりをし、彼にとても献身的にうなずいているのを見た。朝食も昨晩の夕食と同じくらい素晴らしく、8時半きっかりに私たちはリトル・ブリテンへ向けて出発した。道すがら、ウェミックは次第に乾いた感じになり、無口になり、口元はまたしても郵便局のように堅くなった。ついに職場に着き、上着の襟から鍵を取り出した時には、まるでウォルワースの家財一切――お城も、跳ね橋も、あずまやも、池も、噴水も、エイジド老人も――が、最後のスタンガー砲でまとめて吹き飛ばされてしまったかのように、何の感慨も見せなかった。
第二十六章
ウェミックが言っていた通り、私は早い機会に、後見人の邸宅とその会計兼書記の邸宅とを比較することができた。私がウォルワースから事務所に入った時、後見人は自分の部屋で香り高い石鹸を使って手を洗っていた。彼は私を呼び寄せ、ウェミックが事前に話していた通り、私と友人たちを招待する旨を伝えてくれた。「堅苦しいことは抜きで、正装も不要で、明日来なさい」と念を押された。私はどこに行けばいいのか(彼の住まいを全く知らなかったので)尋ねると、彼は何事もはっきり認めるのを嫌う性分であるがゆえに、「ここへ来なさい、そして私が家へ連れて行く」と答えたのだと思う。この機会に一言述べておくが、彼はまるで外科医か歯科医のように、依頼人を洗い流していた。部屋の中にはそのためのクローゼットが備え付けてあり、香りの石鹸の匂いが香水店のように漂っていた。ドアの内側には異様に大きなロール式タオルが掛かっていて、裁判所から戻った時や依頼人を送り出した後は、必ずこのタオルで手を隅々まで拭いていた。
翌日午後六時に私たちが彼のもとへ赴いたところ、いつもより色の濃い案件を扱っていたようで、彼は頭をクローゼットに突っ込み、手を洗うだけでなく顔を洗い、喉をうがいしていた。そしてそれが終わって、ロールタオルを一周使い切った後も、ペンナイフを取り出して、爪の間の「案件」をこそげ取ってから上着を着ていた。
彼と一緒に通りに出ると、例によって何人かがうろうろしていて、彼に話しかけたそうにしていたが、彼の周囲に漂う香り高い石鹸のオーラがあまりにも決定的で、その日はみな諦めていた。私たちが西へ歩く間も、群衆の中から時折彼を認識する顔があったが、そういう時は彼は私に向かってより大きな声で話すだけで、決して誰かに応じたり、認識されたことに気づいた様子を見せたりしなかった。
彼は私たちをソーホーのジェラード・ストリート南側の一軒の家へ案内した。それなりに立派な家ではあったが、塗装が痛み、窓は汚れていた。彼は鍵を取り出して扉を開け、私たちは皆石造りのホールに入った。そこは殺風景で薄暗く、ほとんど使われていない様子だった。それから茶色い暗い階段を上って、同じく茶色い三つ続きの部屋へと進んだ。パネル張りの壁には花綱の彫刻があり、彼がその中に立って迎えてくれた時、私はそれらがどんな輪に見えるか、心の中で思っていた。
食事はこれらの部屋の中で一番良い部屋で供され、二つ目は彼の更衣室、三つ目は寝室だった。家全体を借りているが、実際ほとんどこの部分しか使っていないのだと告げられた。テーブルの上は快適に整えられていた――もちろん銀器はなかったが――彼の椅子の脇には大型のダムウェイターがあり、そこにはデキャンタや瓶が並び、デザート用の果物も四皿あった。彼はすべてを自分の手元に置き、何でも自分で配った。
部屋には本棚があり、背表紙から、証拠や刑法、犯罪伝記、裁判、議会法などの本とわかるものが並んでいた。家具はすべて頑丈で質がよく、彼の時計の鎖のようだった。ただし、事務的な雰囲気があり、装飾的なものはまったくなかった。隅には書類の小机とシェード付きランプがあり、夜になるとそのまま事務所を家に持ち帰るような様子だった。
彼は今まで私の三人の仲間の顔をほとんど見ていなかったので――これまでは私と二人で歩いていたので――ベルを鳴らした後、暖炉の前に立って彼らをじっと見定めた。驚いたことに、彼はほとんどドラムルだけに興味を示しているようだった。
「ピップ」と彼は私の肩に大きな手を置き、窓際へと移動しながら言った。「誰が誰だか分からん。『蜘蛛』はどれだ?」
「蜘蛛?」私は聞き返した。
「ぶつぶつしていて、だらしなく、ムッツリした奴だ。」
「あれがベントレー・ドラムルです」と私は答えた。「顔立ちが繊細なのがスタートップです。」
「繊細な顔立ちの方」にはまったく関心を示さず、「ベントレー・ドラムルというのか。あいつの面構えは気に入った」と彼は言った。
彼はすぐにドラムルに話しかけ始めた。ドラムルがぶっきらぼうに答えても全く気にせず、むしろその反応に引き込まれるかのように話を引き出そうとした。私は二人を眺めていたが、その間に家政婦が最初の料理を持って現れ、二人と私の間をさえぎった。
彼女は四十歳ほどかと思ったが、私は実際より若く見ていたかもしれない。やや背が高く、しなやかで素早い動き、極端に色白で、大きく色あせた目と豊かな流れる髪があった。心臓の疾患か何かで、絶えず息を切らしているように唇が開き、顔に驚きと動揺の奇妙な表情を浮かべていたのかもしれないが、私は数日前に劇場で『マクベス』を観ており、その顔は魔女の大鍋から立ち上る顔のように、燃え立つ空気にかき乱された印象だった。
彼女は料理をテーブルに置き、静かに私の後見人の腕を指で触れて食事の準備ができたことを知らせると、すぐに姿を消した。私たちは円卓につき、後見人はドラムルを片側に、スタートップをもう片側に座らせた。家政婦が運んだのは見事な魚料理で、その後には同じく上質な羊肉、さらに同じく選りすぐりの鳥料理が出た。ソースもワインも、欲しいものはすべて主がダムウェイターから出して供してくれ、テーブルをひと回りしたら必ず元の場所に戻した。同様に、各料理ごとに清潔な皿やナイフ・フォークも彼が配り、使い終えたものは椅子のそばの二つのバスケットに片づけていた。家政婦以外の給仕は現れず、彼女がすべての料理を出した。私はいつも、彼女の顔に、大鍋から現れる顔を見ていた。何年も後になって、私は暗い部屋で燃える酒を入れたボウルの後ろを、流れる髪の顔が通り過ぎるという、あの女性の不気味な似顔絵を描いてしまった。
家政婦に特別な注意を向けていたのは、彼女自身の強烈な外見とウェミックの話の両方によるものだが、彼女が部屋にいる時はいつも、後見人から目を離さず、彼の前に料理を出すときもおずおずと手を離し、呼び戻されるのを恐れ、何か言いたいことがあるなら近くにいる間に言ってほしい、と願っているようだった。私は、後見人にもそれを意識している様子と、常に彼女を緊張状態に置こうという意図を感じ取った。
食事は陽気に進み、後見人は話題を主導するというより、他人の話を受けていたが、私たちの性質の一番弱いところをうまく引き出していた。私は気づかぬうちに、浪費癖やハーバートを後援していること、自分の将来の大きな見通しについて自慢げに話していた。それは私たち全員に言えることだったが、中でもドラムルは顕著で、他人に対する不平や猜疑心をむき出しにする傾向が、魚が下げられる前にすっかり引き出されていた。
そして話題がボート漕ぎの腕前に移り、ドラムルが夜遅くまでのろのろと後方からついてくることをからかわれた。ドラムルはこれに対し、私たちの部屋のほうが我々自身よりもずっと好ましいと言い放ち、腕前では我々の上を行き、力では我々を藁のように散らすことができると豪語した。後見人は何ら見えない手腕で、ほんの些細なことで彼の気分を激昂寸前まで煽り、ドラムルは自分の腕をまくって筋肉を見せつけ、私たちもみな滑稽なほどに腕を見せ合った。
その時、家政婦がテーブルを片付けていた。後見人は彼女に気を留める様子もなく、顔を彼女とは逆側に向けて、指を噛みながらドラムルに興味津々な様子を見せていた。その時、不意に彼は家政婦の手を罠のようにパシッと押さえた。あまりにも素早く鋭い動作だったので、私たちはみなバカらしい争いをやめてしまった。
「力の話なら」とジャガーズ氏は言った。「私が手首を見せてやる。モリー、手首を見せてやれ」
捕らえられた彼女の手はテーブルの上にあったが、もう片方の手は腰の後ろに回していた。「旦那様」と彼女は小さな声で、じっと彼を見つめ、懇願するように言った。「お願いです」
「私が見せると言っている」とジャガーズ氏は動じずに繰り返した。「モリー、両方の手首を見せなさい。さあ、出しなさい」
彼は彼女の手を離し、その手首をテーブルの上に裏返して置いた。彼女はもう一方の手を背後から出し、二つの手首を並べて差し出した。片方の手首は深い傷痕が何本もついていて、ひどく損なわれていた。彼女が手を差し出している間、彼女はジャガーズ氏から目を離し、順に私たち全員を見渡した。
「ここには力がある」とジャガーズ氏は、指で筋をなぞりながら冷静に言った。「この女性の手首ほど力強いものは、男女問わず滅多にない。握力だけなら、これほど強い手は見たことがない」
彼が悠然と批評している間、彼女は私たち一人ひとりを順に見続けていた。彼の言葉が終わるや否や、また彼を見つめ直した。「もういい、モリー」とジャガーズ氏は軽くうなずいて言った。「賞賛されたぞ、もう下がっていい」彼女は手を引っ込めて部屋を出て行き、ジャガーズ氏はダムウェイターからデキャンタを取り出してグラスにワインを注ぎ、回した。
「九時半にはお開きだ、諸君」と彼は言った。「どうぞ時間を有意義に使いたまえ。皆に会えてうれしいよ。ドラムル君、君に乾杯」
もし彼がドラムルを目立たせるのが目的だったとすれば、見事に成功した。ドラムルは不機嫌そうな勝ち誇った様子で、私たちをどんどん見下す態度を露骨に強め、ついには我慢ならぬほどになった。その全ての段階を、ジャガーズ氏は奇妙な興味を持って見守っていた。まるでドラムルの存在が彼のワインにスパイスを加えているかのようだった。
私たちは若気の至りで酒を飲みすぎ、話しすぎた。ドラムルが「お前たちは金遣いが荒すぎる」と田舎者らしい嫌味を言った時、私は少々熱くなって、しかも不注意にも、スタートップがほんの一週間ほど前に彼に金を貸したことを持ち出した。
「まあ、彼は返すさ」とドラムルは応じた。
「返さないとは言っていない」と私は言った。「だが、それなら我々の金のことをあれこれ言うのはやめたらどうだ」
「お前が言うな!」とドラムル。「やれやれ!」
「どうせ君は、誰かにお金を貸そうなんて思わないんだろう?」
「その通りだ」とドラムル。「お前らの誰にも一銭も貸す気はない。誰にも貸さないさ」
「それでいて借りるのは、少し卑しいんじゃないか」
「お前が言うな。やれやれ!」
あまりに腹立たしい返しで、しかも私は彼の鈍重な無愛想さに全く太刀打ちできず、ハーバートの制止も無視して言い返した。
「ではドラムルさん、せっかくだから、君がこの金を借りたとき、ここにいるハーバートと私でどんな話をしたか教えようか」
「そんな話聞きたくもない」とドラムルはうなった。たぶん小声で「二人とも地獄に落ちてしまえ」とも付け加えた。
「でも、君が知りたくなくても話すよ。君はその金を受け取って、得意げにポケットに入れていたが、ハーバートがそんなに簡単に貸すのをすごく面白がっているようだったと、私たちは話したんだ」
ドラムルは大声で笑い、私たちの顔を見て高笑いした。その態度は、まさに図星であり、私たちをまるごと馬鹿にしていると明示していた。
するとスタートップが、私よりもずっと穏やかに彼をたしなめ、もう少し感じよく振る舞うよう諭した。明るく快活なスタートップと、正反対のドラムルは、常に互いを個人的侮辱のように受け止めている。今もドラムルはぶっきらぼうに応酬し、スタートップはちょっとした冗談で話題をそらそうとし、皆で笑った。その小さな成功がよほど癪に障ったのか、ドラムルは突然、何の警告もなくポケットから手を出し、肩を落として大ぶりのグラスをつかみ、スタートップの頭めがけて投げつけようとしたが、主催者が絶妙なタイミングでそれを押さえた。
「諸君」とジャガーズ氏はグラスを置き、重々しい鎖を引いて金時計を取り出し、「遺憾ながら九時半になった」と告げた。
それで皆立ち上がって帰り支度をした。通りまで出る前に、スタートップは「おい、ドラムル」と陽気に声をかけ、何事もなかったかのようだったが、ドラムルは全く応じず、同じ道の反対側を歩き、スタートップが前を歩き、ドラムルは家々の影に隠れてついていく、まるでボートで後ろからついてくる時のようだった。
玄関のドアがまだ閉まっていなかったので、私はハーバートをその場に残し、もう一度後見人に挨拶するため階上へ駆け戻った。彼は更衣室でブーツのコレクションに囲まれ、すでに手を洗っていた。
私は何か不愉快なことがあったことを詫びたくて来たのだと告げ、自分の責任が大きくないことを願うと言った。
「ふん」と彼は顔をすすぎながら水しぶき越しに言った。「大したことじゃない、ピップ。だが私はあの蜘蛛は好きだよ」
今は私の方を向いて頭を振り、息を吐き、タオルで体を拭いている。
「あなたが気に入っているのは嬉しいです」と私。「でも私は好きじゃありません」
「いやいや」と後見人は同意した。「彼とはあまり関わるな。できるだけ距離を置け。でも私は彼を気に入っている。ピップ、あの男は本物の部類だ。もし私が占い師なら――」
タオルから顔を出して、私の目を見た。
「でも私は占い師じゃない」と彼は頭をタオルに埋め、両耳を拭きながら言った。「私が何者かは分かっているだろう。おやすみ、ピップ」
「おやすみなさい、先生」
それから約一ヶ月後、「蜘蛛」のポケット家での滞在期間がついに終わり、家中(ミセス・ポケットを除いて)大いに安堵して、彼は実家の「巣穴」へ帰っていった。
第二十七章
「親愛なるピップ様
『本状はガージェリー氏のご依頼により差し上げます。同氏はウォプスル氏と共にロンドンへ参りますので、もしご都合よろしければお目にかかりたく、火曜日午前九時にバーナード・ホテルに伺いたいとのことです。ご都合悪い場合はご一報ください。ご姉様はご出発の折と変わりありません。私たちは毎晩台所であなたのことを話し、いま何を話して何をしているのか不思議に思っております。もしこのお知らせが出過ぎたこととお感じでしたら、昔を思い、ご容赦ください。以上をもちまして、愛情こめて、
あなたの感謝すべき忠実なる下僕
ビディ
追伸:彼は特に「ワット・ラークス」と書くよう強く望んでおります。あなたなら意味がお分かりになると申しております。ご紳士になられた今でも、彼に会うのはきっと嬉しいことでしょうし、そう信じて疑いません。彼にはこの文をすべて読み聞かせましたが、最後の一文だけは除き、再度「ワット・ラークス」と書くよう強く望んでおられます。』
この手紙は月曜の朝に郵便で届いたので、約束は翌日ということになる。率直に言えば、私はジョーが来ることをどんな気持ちで待っていたか。
喜びではなかった。これほど多くの絆で結ばれているにもかかわらず、むしろ大いに心が波立ち、やや屈辱を覚え、強い違和感に苛まれていた。もし金で来訪を止められるなら、私はきっと金を払っただろう。最大の安心材料は、ジョーがハマースミスではなくバーナード・インに来ること、つまりベントレー・ドラムルと顔を合わせることがないということだった。ハーバートやその父上なら、私も尊敬しているので見られても構わなかったが、私が軽蔑しているドラムルに見られることだけは我慢ならなかった。人生を通して、我々が最も蔑んでいる人間のためにこそ、一番卑劣な行動をとってしまうものだ。
私は部屋を常に何かしら不要かつ場違いな装飾で飾り立てることに熱を入れており、バーナードとのあのやりとりは結局かなりの出費となっていた。この時点で部屋の様子はすっかり変わり、近くの家具屋の帳簿に私の名前が何ページも目立つようになっていた。最近の私はすっかり進歩し、ついにはボーイを雇うほどになった――長靴のボーイだ――その少年に使われているようなもので、私は日々を過ごしていた。洗濯女の家族の中から「怪物」を作りだし、青い上着、カナリア色のベスト、白いネクタイ、クリーム色のズボン、そして既述の長靴を着せると、やらせる仕事は少ししかなく、食べさせる量は多大で、その両方の要求に私は日々悩まされていた。
この「復讐の亡霊」には火曜朝八時に玄関で待機するよう命じてあり(玄関ホールは床材代がかかるほど二平方フィートしかなかった)、ハーバートはジョーが好みそうな朝食の品を勧めてくれた。私はその配慮に本当に感謝したが、もしジョーが彼を訪ねて来るのなら、ここまで熱心に準備しただろうか、とふと疑念が湧いた。
ともあれ私は月曜の夜に町へ戻り、ジョーに備えて早起きし、居間と朝食テーブルをこれ以上ないほど豪華に整えた。だが残念ながらその朝はしとしと雨が降り、バーナードの建物は、すすだらけの涙を窓の外に流す弱々しい大男の煙突掃除屋のようで、どんな天使でもこの事実を隠せなかった。
時間が近づくと逃げ出したい気分になったが、命じておいたアヴェンジャー(復讐者)が玄関で待機しており、やがてジョーが階段を上がってくる音が聞こえた。ジョーだとすぐに分かったのは、彼がいつも大きすぎる長靴のせいで階段をぎこちなく上がり、各階の名前を読むのに時間がかかるからだった。ついに私たちの部屋の前で立ち止まり、私の名前のペイントした文字を指でなぞる音が聞こえ、その後はっきりと鍵穴に息を吹きかける音も聞こえた。最後に、かすかな一度だけのノックがあり、ペッパー――これが妥協の末につけられた復讐者の名前だった――が「ガージェリーさんです!」と告げた。彼が足元を拭き終えるのを待ちきれず、マットから持ち上げなければならないかと思ったが、ようやく部屋に入ってきた。
「ジョー、元気だったかい?」
「ピップ、元気にしてたか、ピップ?」
ジョーは誠実な顔を輝かせ、帽子を床に置き、両手で私の手を握って上下に振った。まるで私が最新式のポンプであるかのように。
「会えてうれしいよ、ジョー。帽子を預かるよ」
だがジョーは、両手で帽子をまるで卵の入った鳥の巣のように大切に持ち、絶対に手放そうとせず、帽子を持ったまま妙に落ち着かない様子で立ち話を続けた。
「お前さんは大きくなったなあ」とジョーは言った。「膨らんで、すっかりお上品になって」――「お上品」という言葉を思いつくのに少し考えた――「まさに国王と国の誉れだ」
「君もとても元気そうだ」
「ありがたいことに、まあ何とかやってるさ。それにお前さんの姉貴も悪くなっとらん。ビディも何もかも、変わらずしっかりしてる。仲間も後退はしてない、いや前進もしてないがな。ウォプスルだけはちょっと飲みすぎたかな」
ジョーは両手で鳥の巣を守りつつ、部屋の中や私のガウンの花模様をぐるぐると見回していた。
「飲みすぎたのか、ジョー?」
「うん、そうだな」とジョーは声を低くした。「彼は教会をやめて芝居に転向した。それで芝居のためにロンドンに来てるんだ。一つ頼まれたことがあってな」ジョーは鳥の巣を左脇に抱え、右手で卵を探るようにごそごそした。「もし気を悪くしなければ、これを渡してくれと言われたんだ」
ジョーの差し出したものは、ある小さなロンドンの劇場のくしゃくしゃの芝居ビラだった。それには「地方で名高いロスキアン流アマチュア俳優、最高の悲劇的演技で最近地元劇界を震撼させた唯一無二のスター、今週初登場!」と書かれていた。
「彼の芝居を観たのかい、ジョー?」
「観たとも」とジョーは力強く、厳かに答えた。
「すごい反響だったのか?」
「おう、確かに橙の皮の山だったぞ。特に幽霊が出てきた時はな。だが考えてみてくれ、観客が“アーメン”と言いながら何度も幽霊と俳優の間に割り込んできて、まともに芝居が続けられると思うか? 人には不運があって教会を辞めることもあるが、だからといって大事な時に邪魔していい理由にはならん。父親の幽霊が出ているというのに、注意を向けられないとは何ごとだ? しかも喪帽子が小さすぎて、黒い羽飾りの重みでどうしても落ちてしまうんだからな」
ジョー自身の顔も幽霊を見たようになり、その時ハーバートが部屋に入ってきたのが分かった。私はジョーをハーバートに紹介したが、ジョーは握手を避け、鳥の巣帽子をしっかり持っていた。
「ご挨拶します、旦那様」とジョー。「ピップさんとお二人が――」ここでアヴェンジャー(復讐者)がトーストを出しているのに目を留め、まるでこの若者も家族の一員にするつもりのようなので、私はしかめ面をしてそれを遮った。「いやつまり、お二方が――この狭いところでも体調がよろしいことを。今はロンドン的には良い宿かもしれませんし、評判もあるようですが、私なら豚もここには飼いませんね――おいしく太らせたいなら、ですけど」
こうして住まいの美点を称えつつ、私を「旦那様」と呼ぶ傾向も見せつつ、ジョーは席につくよう促されると、帽子を置くのにふさわしい場所を部屋中探し、結局暖炉の端っこに置いたが、その後何度も落ちることになった。
「ガージェリーさん、お茶ですか、コーヒーですか?」と、いつも朝の席を仕切るハーバートが尋ねた。
「どうも、旦那様」とジョーは体を硬直させて言った。「旦那様が一番お好みのもので結構です」
「コーヒーはいかがです?」
「どうも」とジョーは明らかに気落ちして答えた。「旦那様がご親切にコーヒーをお選び下さったのなら、逆らうつもりはありません。だが、コーヒーってちょっと胸焼けしませんか?」
「ではお茶にしましょう」とハーバートは注いだ。
その時ジョーの帽子がまた暖炉から落ち、慌てて席を立ち、同じ場所にきっちり戻した。まるですぐにまた落とさなくてはならない作法でもあるように。
「ガージェリーさん、いつ町にいらしたんですか?」
「昨日の午後だったかな?」ジョーは手で咳払いしながら言った。「いや違う。いややっぱりそうだ。うん、昨日の午後だ」(知恵と安堵と公平さを織り交ぜた様子で)
「ロンドン見物は何か?」
「ええ、旦那様」ジョーは言った。「私とウォプスルはまっすぐ靴墨倉庫を見に行きました。でも店先の赤いビラとはちょっと違ってましてね。あれは――」ここで「アーキテクチュラルーラル」と言いかけ、それを延々と歌にしそうだったが、幸い帽子がまた落ちそうになり、注意がそちらに移った。実際、彼の帽子には絶えず目と手を配る必要があり、まるでクリケットのウィケットキーパーのようだった。今にも落ちそうな帽子を素早くキャッチしたり、途中で止めて壁紙の柄までも利用してうまく操ったり、最後には洗面器にドボンと落ち、それを取り上げるのが私の役目だった。
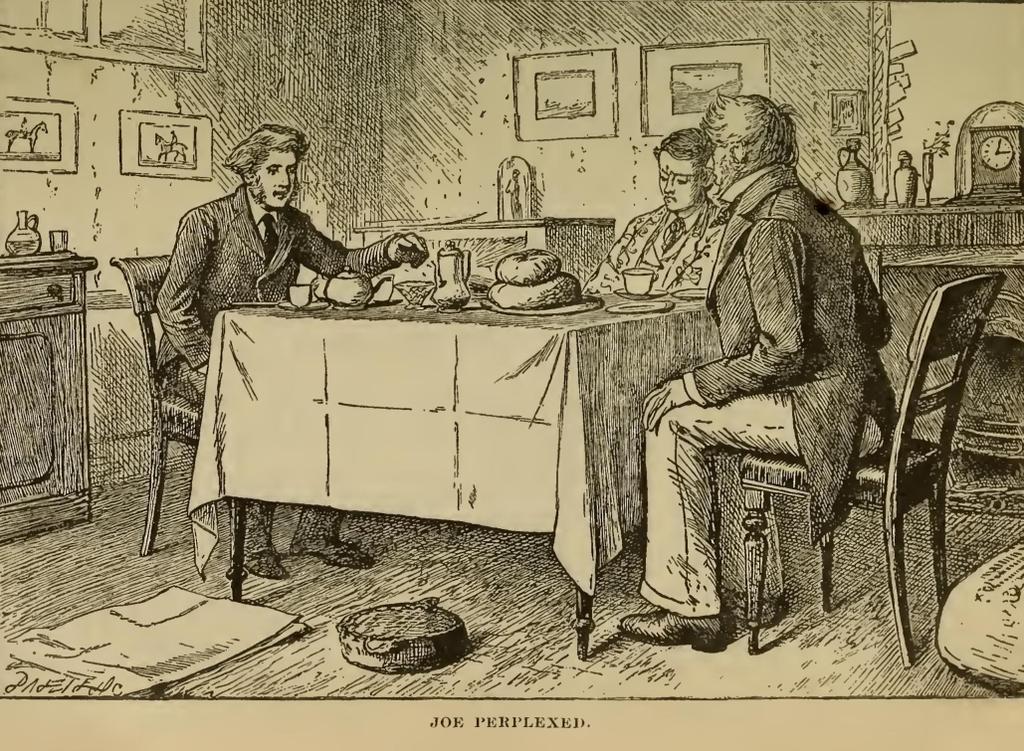
シャツの襟と上着の襟についても、考えれば考えるほど不可解で、なぜそこまで自分をこすり上げて身だしなみを整えたがるのか、なぜ晴れ着で苦しんでまで清めなければならないと思うのか理解できなかった。さらに、彼はフォークを口と皿の間で止めては不可解な沈思にふけり、妙な方向に目をやり、不思議な咳をし、テーブルから離れて座ったり、食べるより落とす方が多かったり、落としたのを見て見ぬふりをしたりしたので、私はハーバートがシティへ出かけてくれて本当にホッとした。
私は、自分がもっと気楽に接していればジョーももっと楽だっただろうに、そのことに思い至る感受性も理性も持ち合わせていなかった。私は彼に苛立ち、機嫌も悪くなっていたが、そんな私に彼は逆に思いがけない優しさを与えてくれた。
「今は二人きり、旦那様」とジョーは切り出した。
「ジョー、どうして私を“旦那様”と呼ぶんだい?」と私は苛立って口を挟んだ。
ジョーは一瞬、かすかな非難の色を浮かべて私を見た。滑稽なネクタイや襟であっても、その目には一種の品位が感じられた。
「今は二人きりになったので」とジョーは続けた。「長居するつもりも能力もないので、ここに来た理由を簡単に――いや、まず話し始めようと思う。なぜなら」とジョーは昔のように分かりやすく説明した。「お前に何か役立ちたいだけで、こうして立派な紳士さんの家で食事をご一緒させてもらっているんだ」
私はあの目を再び見たくなかったので、もうやめてくれとも口にしなかった。
「さて、旦那様」とジョーは続けた。「こういうわけだ。バーグマンでこの前な、ピップ――」ジョーは親しみがこもると“ピップ”、改まると“旦那様”と呼んだ――「そこへパンブルチュークが馬車でやってきた。あいつは昔から、お前の幼なじみだったと町中で言いふらして、私の気分を時々逆なでにするんだ」
「馬鹿な。君が本当の友達だったじゃないか」
「私もそう思うよ、ピップ」とジョーは軽く頭を振った。「でも今となっては大したことじゃない。で、ピップ。この同じパンブルチュークがバーグマンで(ここは働く者にとって一服とビールが何よりのごちそうなんだが、決して飲み過ぎじゃない)、こう言ったんだ。『ジョセフ、ミス・ハヴィシャムが君に会いたいと言ってるよ』と」
「ミス・ハヴィシャムが?」
「『会いたい』と、パンブルチュークは言った」ジョーは天井を見上げて目を転がした。
「それで? 続けてくれ、ジョー」
「次の日、旦那様」ジョーは、私が遠くにいるかのように語った。「身なりを整えて、ミスAに会いに行ったんだ」
「ミスA、ジョー? ミス・ハヴィシャム?」
「そうだよ、旦那様」とジョーは、まるで遺言を書いているかのような法律家調で言った。「ミスA、またはハヴィシャム嬢と言ってもよい。彼女はこう言った。『ガージェリーさん、あなたはピップと文通しているのか?』私はお前から手紙をもらっていたので『しています』と答えられた。(お前の姉貴と結婚したときは“します”と言ったが、ピップの友人に返事した時は“しています”だ)。『それでは、エステラが戻ってきて会いたがっていると伝えてくれ』と」
私は顔が熱くなるのを感じた。彼の使いの理由を知っていれば、もっと温かく迎えられたのにと、どこかで思っていたのだろう。
「家に帰って、ビディにこの伝言を書いてもらおうとしたんだが、ちょっと渋った。ビディは『本人は口頭の方が嬉しいでしょうし、今は休暇中なんだから、あなたが会いに行きなさい』と言ってくれた。これで私の話はおしまいだよ、旦那様」ジョーは席を立った。「ピップ、君のますますの幸福と繁栄を祈っている」
「もう帰るの、ジョー?」
「ああ、帰るよ」
「じゃあ昼食は?」
「いや、帰らない」
目が合い、その男気から“旦那様”がすっかり消えた。
「ピップ、古い友よ、人生は離別が連なってできているようなものだ。ある者は鍛冶屋、ある者は白金細工師、金細工師、銅細工師。それぞれの間には分かれ道ができ、それは避けられないし、受け入れなければならない。もし今日のことで少しでも悪いことがあったなら、それは私のせいだ。お前と私はロンドンでは一緒にいるべき二人じゃないし、それ以外でも、内輪で分かり合っている場所以外では無理なんだ。誇り高ぶっているわけじゃなく、正しくありたいだけで、もう二度とこの服でお前には会わない。私はこの服じゃ間違ってる。鍛冶場か台所か、沼地の外じゃ間違っているんだ。私の鍛冶屋の格好、手にハンマーかパイプの私なら、それほど嫌じゃなく思えるだろ。もしまた会いたくなったら、鍛冶場の窓から顔を覗かせて、古いエプロン姿で仕事に打ち込む鍛冶屋ジョーを見てくれ。それが一番自然なんだ。私は鈍いが、ようやく言いたいことが伝わったかな。じゃあ、神のご加護を、親愛なるピップ、古き友よ、神のご加護を!」
私は彼の素朴な品位を見誤っていなかった。彼がこれらの言葉を語った時、その服装がいかに滑稽であろうと、天国でも問題にならないような、気高いものだった。彼は私の額にそっと手を当てて出て行った。私は気を取り直して慌てて後を追い、近くの通りを探したが、彼の姿はもうなかった。
第二十八章
翌日には町へ戻らなければならないのは明らかだったし、悔恨の念が湧き上がる中で、ジョーの家に泊まるべきだということも、同じくらい明白だった。しかし、翌日の馬車の席を確保し、ポケット氏の家に行って戻ったあとで、その最後の点についてはまったく確信が持てなくなり、「ブルー・ボア」に宿泊するための理由や言い訳を作り始めた。ジョーの家では迷惑になるだろうし、突然行っても誰も予期していないから寝床の用意もないだろう。ミス・ハヴィシャムの家からは遠すぎるし、彼女は気難しいから気に入らないかもしれない。世の中のあらゆる詐欺師など、自己欺瞞にはかなわない。こうしたもっともらしい言い訳で、自分自身をだましていた。不思議なものだ。他人の偽造した半クラウン銀貨をうっかり受け取ってしまうのは、まあ仕方のないことだろう。だが、自分の作った偽コインを自分で本物だと思い込むとは! 親切そうな見知らぬ人が「安全のために」と銀行券をきれいに畳むふりをして、こっそり中身を抜き取ってクルミの殻とすり替える――だが、そんな手品よりも、私が自分で自分のクルミの殻を畳んで、それを本物の紙幣だと自分に渡しているほうが、よほどたちが悪い。
ブルー・ボアに泊まることを決めた後で、今度はアヴェンジャーを連れて行くべきかどうかで心が大いに揺れた。あの高価な召使いがブルー・ボアの馬車宿の入り口で堂々とブーツを見せびらかすのは、なかなか愉快な光景だと想像できたし、仕立屋の店でふいに彼を披露して、トラッブの小僧の無礼な度肝を抜くのも、ほとんど厳粛な場面のように思えた。しかし一方で、トラッブの小僧が彼の懐に入り込んで何かを吹き込むかもしれないし、あのどうしようもない小僧のことだ、ハイ・ストリートでからかわれるかもしれない。私の後援者がその話を耳にして、気に入らないと思う可能性もある。総合的に考えて、アヴェンジャーは置いていくことに決めた。
私が席を取ったのは午後発の馬車で、すでに冬だったため、目的地に着くのは暗くなってから2、3時間後になるはずだった。クロス・キーズからの出発時刻は2時。私は十五分前に現地に着いたが、アヴェンジャーが一緒だった――もし「一緒だった」という表現が、できるだけ私から逃げようとする彼にも当てはまるなら、だが。
当時は、罪人を船渠(ドックヤード)に護送するのに乗合馬車を使うのが通例だった。彼らが屋根の上に座る客として運ばれているという話は何度も聞いていたし、実際に鉄の足かせをぶら下げて馬車の屋根から足をだらりとさせている姿も何度か見たことがあったから、ハーバートが馬車宿で私に「今日は二人の罪人が一緒に乗るよ」と伝えてきても、驚く理由はなかった。しかし「罪人」という言葉を耳にするたび、私は本能的にたじろぐ古い理由があった。
「気にしないだろうな、ハンデル?」とハーバートが言った。
「いや、大丈夫!」
「でも、嫌そうに見えたぞ?」
「好きだとは言えないし、君だって特別好きなわけじゃないだろう。でも、気にはならないよ。」
「ほら、あそこにいるよ」とハーバートが言った。「タップから出てきた。いやしい、みじめな光景だな!」
彼らは看守に連れられてきていて、みな口を手でぬぐいながら出てきたので、きっと看守に一杯おごっていたのだろう。二人の罪人は手錠で繋がれ、足にもよく知っている型の鉄枷をはめられていた。見覚えのある囚人服も着ていた。看守はピストル二挺を持ち、分厚い警棒を脇に抱えていたが、罪人たちと仲良さげに談笑しながら馬をつなぐ様子を眺めていた。その様子は、まるで罪人たちが今はまだ公開されていない展覧会の展示物で、自分はその管理人であるかのようだった。一人は他方より背が高く体格もよかったが、なぜか世の中の不思議のままに、小さい方の服を割り当てられているようで、腕も脚も大きな針山のようで、服が滑稽なまでに彼を隠していた。しかし、その半分閉じた目を一目で見て私は気づいた――三人の陽気な船乗り亭でベンチに座っていた、あの見えない銃で私を脅した男が、そこにいたのだ!
彼が今の私をまったく気づいていないことは簡単に分かった。彼は私の方をちらりと見て、私の時計の鎖を値踏みし、それからつばを吐いてもう一人の罪人に何か言って笑い、二人で手錠を鳴らしながら体をねじって他のものを見ていた。背中に大きな番号が書かれ、まるで街の家のドアのよう。粗末でみすぼらしい外見は下等な動物のよう。足枷にはハンカチが申し訳程度に結ばれていて、周囲の誰もが彼らを遠巻きに見て近づかない。その様子は、ハーバートの言う通り、なんとも不快でみじめな光景だった。
しかし、それだけでは済まなかった。馬車の後部座席はロンドンから引っ越してきた家族が丸ごと取っており、二人の罪人には御者のすぐ後ろの前の席しか空きがなかった。このとき、四人目の席を取っていた短気な紳士が烈火のごとく怒り、そんな悪党と一緒にされるのは契約違反で有害悪質不名誉きわまりない――などと罵倒し始めた。馬車はすでに出発準備が整い、御者は苛立っており、私たちは皆、席に着こうとしていた。罪人たちは看守と共にやってきて、あの独特の、パン粥やフェルトや縄のクズや炉石の匂いをまとっていた。
「まあまあ、そんなに気にしないでくださいよ」と看守は怒る乗客に懇願した。「私があなたの隣に座ります。罪人たちは一番外側にしますし、あなたの邪魔はしません。彼らがいることすら気づかずに済みますよ。」
「俺のせいじゃないぜ」と、私が見覚えのある罪人がうなった。「俺は乗りたくて乗るんじゃない。俺の席は誰でも好きな奴が座ってくれたっていいんだ。」
「俺もだ」ともう一人も短く言った。「俺だって自分の意志なら、誰の邪魔にもなりゃしなかった。」二人はそう言って笑いながらクルミを割り、殻をあちこちに吐き出していた――私ももし彼らの立場なら、同じことをしたかもしれないと思う。
結局、怒りの紳士には他に選択肢がなく、このまま乗るか置いていかれるかだということになった。彼はぶつぶつ文句を言いながら席につき、看守が隣に、罪人二人ができるだけ身を引き上げて座り、私が知っている罪人は私のすぐ後ろ、私の頭に息がかかる位置に座った。
「じゃあな、ハンデル!」とハーバートが馬車が発車する時に叫んだ。彼が「ピップ」以外の名で私を呼んでくれることが、何と幸せなことかと思った。
罪人の呼吸が、頭の後ろだけでなく背骨に沿って鋭く感じられるあの感覚は、言い表しようがなかった。まるで骨の髄まで刺激的な酸で触れられたようで、歯が浮くほどだった。彼は他の誰よりも呼吸の仕事が多いようで、それをするたびに音も大きかった。私は彼を避けようと身を縮めて、片側の肩がどんどん上がっていくのを自覚した。
おまけに天気はひどく寒くて、二人の罪人は寒さを呪っていた。しばらく進むと皆が無気力になり、途中の宿を過ぎたあたりからは、うつらうつらしながら黙って震えていた。私もいつしか居眠りしながら、「この男に二ポンドを返すべきなのか、どうやればいいのか」と考えていた。馬にでも飛び込むように前に体を倒しかけて、はっと目を覚まし、その問題をまた考え始めた。
だが思ったより長く眠っていたようで、目が覚めた時には、暗闇とランプの不規則な明かりや影のなか、冷たく湿った風が吹きつける沼地の匂いを感じていた。暖を取るため、風除けになるよう罪人たちは私にもっと近づいていた。私が意識を取り戻した最初の瞬間に彼らが交わした言葉は、まさに私が考えていた「一ポンド札が二枚」という言葉だった。
「どうやって手に入れたんだ?」と、私が見たことのない罪人が言った。
「どうやって知るもんか」ともう一人が答えた。「どこかに隠してたんだろう。友達にもらったのかもな。」
「俺もな」と、もう一人が寒さへの呪いをこめて言った。「今ここにあればな。」
「一ポンド札二枚、それとも友達が?」
「一ポンド札二枚さ。友達なんざ全部一枚と交換しても惜しくねぇし、それでいい取引だって思うね。で、どうしたって?」
「で、だ」と私が知っている罪人が続けた。「全部で半分もかからなかったさ。ドックヤードの材木の山の裏で、『お前、出所するんだろう?』ああ、そうだ。で、あの少年を見つけて、食い物をやった礼に一ポンド札二枚を渡してくれって? ああ、わかった、そうしたさ。」
「バカだな」ともう一人がうなった。「俺なら男に使っちまうよ、飯と酒に。あいつは世間知らずだな。お前と何も関わりなかったのか?」
「まるでなかった。違う班、違う船だった。あいつは脱獄でまた裁かれて、終身刑になった。」
「で、そいつが――名誉にかけて聞くが――この辺りで出たのはそれっきりか?」
「それっきりさ。」
「お前はこの場所をどう思った?」
「最低だったな。泥、霧、沼地、仕事、仕事、沼地、霧、泥――それだけだ。」
二人はその場所を口汚く罵り、だんだん不機嫌に黙り込んだ。
この会話を聞いたあと、もし自分の素性がばれるかもという不安がなければ、私はきっと途中で降りて一人闇夜の街道に取り残されたことだろう。しかし、彼が私の正体に気づいていないのは確実だった。私はすっかり人が変わり、服装も境遇も違っていたから、偶然でもない限り気づかれることはまずなかった。それでも、同じ馬車に乗り合わせたという偶然が、いつ何時、彼の耳に私の名前が届いてしまう別の偶然を呼ばないとも限らず、恐ろしかった。そのため、町に着いたらすぐ降りて、彼の耳に入らない場所に行こうと決めた。そしてそれはうまくいった。小さなトランクは足元の荷台にあり、ちょっと留め金を外せばすぐ手にできた。私はそれを前に放り出し、自分もすぐに降りて、町の石畳の最初のランプの下に立った。罪人たちは馬車でそのまま川の方に運ばれていくのを私は知っていた。想像の中で、私は降ろし場のぬかるんだ階段に罪人たちを待つ囚人船の姿を見た――「やれ、漕げ!」と犬に命じるような声がまた聞こえ、黒い水に浮かぶ邪悪なノアの方舟のような船影が目に浮かんだ。
自分が何を恐れていたのか、はっきりとは言えない。ただ漠然とした大きな恐怖が私を支配していた。ホテルに向かって歩きながら、単なる顔見知りに正体を暴かれる不安を超えた、子供時代の恐怖が数分間よみがえった感覚に、心底震えた。
ブルー・ボアのコーヒールームは誰もいなかった。私は食事を頼んで席についても、ボーイは私に気づかなかった。ボーイがようやく私を思い出して詫びたあと、「パンブルチューク氏に呼び出しをかけましょうか?」と訊いてきた。
「いや、絶対にその必要はない」と私は答えた。
ボーイ――かつて私が徒弟になる約束の日、商人たちの抗議を届けてきたあのボーイ――は驚いた様子で、すぐにローカル新聞の汚れた古い一部を、まるで私が読むのを待つかのように目の前に置いた。私はその中に、こんな記事を読んだ――
「当地の読者諸氏には、近年当地出身の若き鉄工職人が劇的に財運を得た件について(ちなみに、当欄の詩人であるトゥービー氏の魔法の筆には格好の題材であろう)、同青年の最初の後援者であり、友人でもあったのが、当地の穀物・種子業に関わり、極めて便利で広々とした店舗をハイ・ストリートから百マイル以内に有する、かの高名な紳士であることを注記する。私情も交えて記すが、当地出身の先達が青年の成功の礎であったことを知るのは誇らしい。地元の賢人や美人諸氏は、誰の成功かと問うだろうが、アントワープのクイントン・マシスも鍛冶屋だった。VERB. SAP. [訳注: 「VERB. SAP.」はラテン語“Verbum sapienti sat est”(賢者には一言で十分)を略したもの]」
私はこう確信している――もし私が栄華の絶頂期に北極点に行っても、そこでもエスキモーや文明人が「パンブルチュークこそがあなたの最初の後援者であり成功の礎だった」と言ったに違いない。
第二十九章
朝早くから私は起きて外に出た。まだミス・ハヴィシャムの家に行くには早すぎたので、彼女の家側の田舎道をぶらぶらした――そこはジョーの側ではない。ジョーには明日会いに行けばいい――私は後援者のことを考えながら、彼女の私への計画を美しく想像していた。
彼女はエステラを引き取り、私のこともほぼ引き取ったも同然であり、私たちを結びつけようとしているのは間違いないだろう。打ち捨てられた家を私が蘇らせ、暗い部屋に陽を入れ、止まった時計を動かし、冷たい暖炉に火をともす――蜘蛛の巣を払い、害虫を滅ぼし、つまり、若き騎士が物語で成す輝かしい偉業の数々を果たし、姫と結婚する。それが私の役割なのだと、家の前に立ち止まり、その赤く焼けたレンガ壁、ふさがれた窓、緑の蔦がまるで筋張った老人の腕のように煙突にまで絡まる様子を眺めた。エステラこそが、その物語の霊感であり、中心だった。しかし、彼女にここまで心を奪われ、私の空想も希望もすべて彼女に向かっていたにもかかわらず、彼女の欠点や冷たさを美化して見ることはなかった。これは意図的にここで記しておく。なぜなら、これが今後の私の迷宮の鍵になるからだ。私の経験から言えば、世間一般の「恋する男」のイメージは必ずしも当たっていない。率直に言えば、私は理屈や約束にも、平安にも、希望にも、幸福にも、あらゆる逆境にも逆らってエステラを愛していた。そして、それを知っていてもなお愛さずにはいられなかったし、もし彼女が人間的な完全さを備えていると本気で信じていたとしても、その情熱は変わらなかっただろう。
私は家の門に、昔と同じ時間に着くよう歩いていった。震える手で鐘を鳴らし、呼吸を整え心臓の鼓動を抑えようと、門に背を向けた。脇の戸が開き、中庭を歩いてくる足音がしたが、私はそれを聞かないふりをした。たとえ門がきしむ音がしても。
ついに肩をたたかれ、私はびくっとして振り向いた。そこで、地味な灰色の服を着た男に出くわした。ミス・ハヴィシャムの家の門番として、まったく予想もしていなかった男だ。
「オーリック!」
「よぉ、坊ちゃん、あんた以外にも変わった奴はいるもんだ。さあ入んな、入んな。門を開けっ放しにしちゃいけねぇんだ。」
私は中に入り、彼は門を閉め、鍵をかけて鍵を抜いた。「ああ!」と彼は、私の数歩前を足取り重く進みながら振り返り、「俺だよ!」
「どうしてここに?」
「歩いてきたさ」とオーリックは言い返した。「荷物も手押し車で運ばせた。」
「ここに腰を据えるつもりか?」
「悪さしに来たわけじゃねぇだろ、坊ちゃん?」
私は内心、そうとも言い切れないと思った。彼はゆっくりと地面から私の脚、腕、顔へと重たい目線を動かし、その間に私は反論を胸の中で考える余裕があった。
「じゃあ鍛冶場はやめたんだな?」と私は言った。
「ここが鍛冶場に見えるか?」とオーリックは、周囲を恨めしそうに見回して言った。「どうだ、見えるか?」
私は彼に、いつ鍛冶場を辞めたのか訊いた。
「日々が全部同じでな、数えなきゃ分からねぇ。でも、あんたが出ていった後、しばらくしてからだ。」
「それは知ってたよ、オーリック。」
「へっ!」と彼は皮肉に言った。「学があるからな。」
やがて家に着くと、彼の部屋は脇の戸を入ったすぐのところにあり、小さな窓から中庭が見えた。狭いその部屋は、パリの門番室に似ていた。壁にはいくつかの鍵がかかっており、彼はそこに門の鍵を追加した。パッチワークの布団をかけたベッドは小さな仕切りの奥にあった。全体的にだらしなく、窮屈で眠そうな雰囲気があり、まるで人間のヤマネのための檻のようだった。彼自身もその一隅で影のように重く暗く座っており、まさに人間のヤマネそのものだった。
「この部屋、初めて見るな」と私は言った。「前は門番なんていなかった。」
「そうさ」と彼は答えた。「何も防備がねぇって噂になってな、罪人や野良犬みたいなのが出入りして危ないってことで、俺が推薦されたのさ。やり返せる奴だってな。それでここに来た。ふいごや金槌より楽だ――それ、弾が入ってるぜ。」
私の視線が暖炉の上の真鍮飾りの銃に引かれ、それを彼も追った。
「さて」と私は、これ以上話したくなくなって言った。「ミス・ハヴィシャムに会いに行っていいか?」
「さぁな」と彼は伸びをし、体を揺すって言った。「俺の役目はここまでだ。この鈴をこのハンマーで叩けば、あとは廊下を進んで誰かに出くわすだろう。」
「私は待たれているはずだよね?」
「二度も三度も言うが、俺には分からねぇな。」
そうして私は、かつて分厚いブーツで踏みしめた長い廊下を進み始めた。オーリックが鈴を鳴らす中、廊下の端でサラ・ポケットに出くわした。彼女は今や、私のせいで生まれつき青ざめて黄色くなったような顔つきだった。
「まあ!」と彼女が言った。「あなたですの、ピップさん?」
「そうです、ポケット嬢。ご家族の皆さんはお元気ですよ。」
「もっと賢くなった?」とサラは頭を悲しげに振った。「元気より賢い方がいいわよ。ああ、マシュー、マシュー! それで、道はご存知ね?」
私は暗闇でも何度も階段を上がったことがあったので、かなり知っていた。昔よりも軽いブーツで階段を上り、ミス・ハヴィシャムの部屋の扉をいつもの調子でノックした。「ピップのノックだ」と彼女がすぐに言い、「入って、ピップ」と続けた。
彼女はいつもの椅子で、古いドレスを着て、両手を杖に重ね、顎を乗せて炎を見つめていた。その横には、片方の手に履かれぬままの白い靴を持ち、下を向いている気品ある婦人――見たことのない女性が座っていた。
「入っておいで、ピップ」とミス・ハヴィシャムは顔も上げずにつぶやいた。「どうした、ピップ。女王様みたいに私の手にキスをするのね――さて?」
彼女は突然、目だけを動かして私を見上げ、皮肉めいた口調で繰り返した。
「さて?」
「ミス・ハヴィシャム」と私は戸惑いながら言った。「お招きいただいたと聞き、すぐに参りました。」
「さて?」
見知らぬ婦人が目を上げ、いたずらっぽく私を見た。そこでエステラの目だと気づいた。だが彼女はあまりにも変わり、美しく、女性らしさを増し、すべてが魅力的で、私はまるで自分が何も成長していないかのように感じた。彼女を見ているうちに、自分がまた粗野で取るに足らぬ少年に戻ってしまうようだった。ああ、彼女との距離と隔たり、その手の届かなさ!
彼女は手を差し出した。私は再会の喜びや、長い間この日を待ち望んできたことなど、しどろもどろに口にした。
「エステラ、ずいぶん変わったと思う?」とミス・ハヴィシャムが欲深そうな目で尋ね、椅子を杖で叩いてその席に座るよう促した。
「最初に入ったときは、エステラの面影が顔にも姿にもまるで見えなかったのですが、今は不思議と……」
「何? また“昔のエステラ”と言うつもり?」とミス・ハヴィシャムがさえぎった。「あの子は高慢で意地悪だった。あなたは逃げたがっていたでしょ? 覚えてないの?」
私はあれは昔のことだ、当時は何も知らなかったのだ、と混乱しながら答えた。エステラは平然と微笑み、「きっと私がひどかったのでしょう」と言った。
「彼は変わった?」とミス・ハヴィシャムが彼女に尋ねた。
「とても」とエステラは私を見ながら答えた。
「粗野で下品じゃなくなった?」とミス・ハヴィシャムがエステラの髪を弄びながら言った。
エステラは笑い、手に持った靴を見てまた笑い、私を見て靴を置いた。彼女は今も私を少年扱いしていたが、巧みに心を引きつけていた。
私たちはあの夢のような部屋で、昔私に強い影響を与えた雰囲気の中に座った。彼女はフランスから戻ったばかりで、これからロンドンへ行くのだという。誇り高く気が強い性格は相変わらずだったが、美しさに従わせており、それが彼女の魅力と切り離せないものになっていた。彼女の存在を、かつて私の少年時代を悩ませた金と上流階級への憧れ、家やジョーへの恥ずかしさ、炎や金床、夜の闇の中で彼女の顔を幻視した記憶――すべてから切り離すことはできなかった。つまり、過去も現在も、彼女は私の人生の奥底と結びついていた。
その日は一日ここで過ごし、夜にホテルへ、明日ロンドンへ戻るよう決まった。しばらく会話したのち、ミス・ハヴィシャムは私たち二人を荒れ果てた庭へ散歩に送り出した。帰ったら、昔のように彼女を車椅子で押してほしいと言った。
こうしてエステラと私は、かつて青白い少年紳士――今のハーバート――と出会った門を抜けて庭へ出た。私は心の中で震え、彼女の裾にすら畏敬の念をもった。彼女はまったく平然として、私の裾などに眼もくれない。出会いの場所に差しかかると、彼女は立ち止まって言った――
「あの日、あの喧嘩を隠れて見て楽しんだ私って、変わった子だったでしょうね。でも本当に楽しんだのよ。」
「君はぼくに素晴らしいご褒美をくれた」
「そうだったかしら」と彼女はそっけなく言った。「あの相手の子がここに連れてこられて私の相手をさせられるのが嫌で、彼のことが気に入らなかっただけよ」
「今では彼とは大の親友なんだ」
「そうなの? でも、たしかあなたは彼の父親から勉強を習っていたわね?」
「うん」
私はそれを言うのが気恥ずかしかった。いかにも子供っぽく思えたからだ。
「身分も運命も変わったんだから、付き合う人も変わったでしょう」とエステラが言った。
「当然だ」
「必然でもあるのよ」と彼女は高飛車に言った。「昔はふさわしかった仲間も、今ではまったくふさわしくないでしょ」
もしかしてジョーに会いに行こうという気持ちがまだ残っていたとしても、この一言で完全に消え去った。
「あの頃、自分の身に幸運が訪れるなんて、思いもしなかったでしょ?」とエステラは手を軽く振って言った。喧嘩の頃の話だ。
「まったく思わなかった」
彼女の完成された、優れた雰囲気と、私が隣を歩く少年らしさ、従順さ――その対比を私は痛烈に感じていた。だが、私は自分が彼女のために特別な存在だと思うことで、その痛みを自ら和らげていた。
庭は草が生い茂り、散歩には向かなかったので、二度三度回ってから再び醸造所の中庭に出た。私は、かつて彼女が樽の上を歩いていた場所を正確に示したが、彼女はそっけなく「あら、そうだったかしら」と言った。家から出てきて私に食べ物と飲み物をくれたことを思い出させても、「覚えていない」と言った。「私を泣かせたことまで覚えていないの?」と聞くと、「覚えていないわ」と首を振って辺りを見回した。彼女が何も覚えておらず、まったく気にもせずにいることが、私をまた(今度は内心で)泣かせた――それこそが一番つらい涙だった。
「知ってるでしょ」とエステラは、輝かしく美しい女性が子供に説くような態度で言った。「私には心なんてないのよ――もしそれが記憶力に関わるとしたらの話だけど」
私は「それは信じない」「そんな美しさに心がないはずがない」などとたわいないことを口走った。
「撃ち抜かれたり刺されたりする心臓はあるわよ、もちろん。それが止まったら私も死ぬでしょう。でもそういう意味じゃない。私には、やさしさも共感も――感情も――くだらないものも何もないのよ」
彼女が立ち止まり私をじっと見つめたとき、私は心の内に奇妙なものを感じた。ミス・ハヴィシャムに見た何かだろうか? いや違う。彼女のしぐさや表情の端々に、子供が一緒に過ごした大人から無意識に受け継ぐものが現れることはあるが、それにしても違うように思えた。私はもう一度見つめたが、彼女は相変わらず私を見ているのに、その印象は消えていた。
あれは、なんだったのだろう?
「本気よ」とエステラは、しかめ面ではなく顔全体の色が陰るようにして言った。「もしこれから一緒に過ごすことが多くなるなら、今のうちに信じておいたほうがいいわ。――だめ、そこで口を挟まないで。私はどこにも優しさなんて向けたことはない。そんなものは一度も持ったことがないの」
次の瞬間には、私たちは長く使われていなかった醸造所の中に入り、彼女はかつて私が見上げた高い回廊を指差し、あそこに登ってあなたが下でおびえているのを見たことを覚えていると言った。彼女の白い手を目で追ったとき、またしてもはっきりとつかみきれない同じ印象が私の中をよぎった。私は思わず身をすくめ、彼女が私の腕に手を載せた。その瞬間、幻はまた消えた。
あれは、なんだったのだろう?
「どうしたの?」とエステラが訊いた。「また怖がっているの?」
「君のさっきの言葉が本当なら、怖がったかもしれない」と私はごまかした。
「じゃあ信じてないのね? まあいいけど。でもミス・ハヴィシャムはもうすぐ、あなたにまた例の役をやらせるんじゃないかしら。けど、そんなものはもうやめてもいいと思うわ。さあ、もう一度だけ庭を回ってから戻りましょう。今日は私の残酷さであなたを泣かせたりしない。私の従者になって、肩を貸して」
彼女の美しいドレスは地面を引きずっていたが、今は片手で持ち上げ、もう一方の手で私の肩に軽く触れた。私たちはまた二、三度、荒れ果てた庭を歩いたが、それは私にとって花盛りのようだった。古い壁の隙間に生えた緑や黄の雑草がどんな名花よりも大切に思えた。
私たちの年齢差はほとんどなく、年齢の差が目立つとすれば彼女の方だった。しかし彼女の美しさと態度がもたらす近寄り難さは、私の喜びの中で常に苦しみの種だったし、「私たちは後援者に選ばれた相手なのだ」という確信が高まるほど、余計に私を悩ませた。なんて惨めな少年だろう!
やがて私たちは家に戻り、そこで私は驚いたことに、私の後見人がミス・ハヴィシャムに用事があって来ており、夕食にも残ると聞かされた。朽ちたテーブルのある部屋のシャンデリアには、私たちが外にいる間に、枝のような飾りに灯りがともされていた。ミス・ハヴィシャムは椅子に座り、私を待っていた。
私が彼女の椅子を押して、かつて祝宴用に飾られたテーブルの周りを回ると、それはまるで過去へと椅子を押し戻すような気持ちだった。しかし、その葬式のような部屋で、墓場の亡霊のようなミス・ハヴィシャムに見つめられながら、エステラはよりいっそう輝かしく美しく見え、私はいっそう強い魔法にかかってしまった。
時は知らぬ間に過ぎ、早めの食事の時刻が近づき、エステラは身支度のため部屋を出た。私たちは長いテーブルの中央近くで立ち止まり、ミス・ハヴィシャムは椅子から片腕を伸ばし、そのしわだらけの拳を黄色いクロスの上に乗せていた。エステラが扉を出る前に肩越しに振り向くと、ミス・ハヴィシャムは貪欲なほど執念深く、彼女に手の甲へとキスを投げた。
エステラがいなくなり、二人きりになると、彼女は私にささやいた――
「美しいかい? 優雅かい? 立派に成長したかい? 彼女を称賛しているかい?」
「誰だって彼女を見れば称賛するはずです、ミス・ハヴィシャム」
彼女は腕を私の首にまわし、座ったまま私の頭を自分の顔近くまで引き寄せた。「愛しなさい、愛しなさい、愛しなさい! 彼女はあなたをどう扱う?」
私は答えようとしたが(それが可能だったかも分からないが)、彼女は繰り返した。「愛しなさい、愛しなさい、愛しなさい! もし彼女があなたを好いてくれるなら、愛しなさい。もしあなたを傷つけるなら、愛しなさい。もし心を引き裂かれても――年を重ねるほどその傷は深くなるけれど――それでも愛しなさい、愛しなさい、愛しなさい!」
こんなにも激しい熱情を目にしたことはなかった。細い腕が私の首を締めつける筋肉の緊張が伝わってきた。
「聞きなさい、ピップ! 私は彼女を愛されるために引き取った。愛されるために育て、教育した。彼女が愛される存在になるように成長させた。愛しなさい!」
彼女が何度もその言葉を繰り返すので、確かにそう言いたいのだとは分かったが、その言葉が「愛しなさい」ではなく「憎みなさい」「絶望しなさい」「復讐しなさい」「死になさい」だったとしても、彼女の口から発せられたらこれほど呪いのように響くことはなかった。
「教えてあげる」と彼女は同じせっぱつまった熱情のささやきで言った。「本当の愛とは盲目的な献身、疑いなき自己卑下、完全な服従、自分や世界に逆らって信じ抜くこと、心も魂も打つ者に捧げ尽くすこと――私がそうしたように!」
彼女がそう言い、続けて叫び声をあげたとき、私は彼女の腰を抱いた。彼女は椅子の上で立ち上がり、死装束のようなドレスをまとって空をつかむように手を振り回し、壁にでもぶつかりそのまま死んでしまうのではと思わせた。
すべてはほんの数秒のことだった。私は彼女を席に引き戻しながら、なじみのある香りを感じ、振り向くと、私の後見人が部屋にいた。
彼はいつも(今まで言及しなかったが)立派なシルクの大きなハンカチを持ち歩いていた。それは彼の職業で実に役に立った。彼がこのハンカチを大げさに広げて、今にも鼻をかむかと思わせておいて、結局かまずに見せることで、依頼人や証人を恐れさせ、自白させたのを何度も見たことがある。今もそのハンカチを両手に持ち、私たちを見ていた。私と目が合うと、一瞬、静かに「なるほど? 奇妙だな」とでも言いたげな間を作ってから、見事な鼻かみの所作で本来の用途に使った。
ミス・ハヴィシャムも彼に気づいており(みな同様に彼を恐れていた)、必死に平静を装い、「相変わらず時間通りですね」と口ごもった。
「ええ、相変わらず」と彼も繰り返し、私たちに近づいた。「(元気かね、ピップ? ひと回り押してみようか、ミス・ハヴィシャム?)そうか、ここにいたのか、ピップ?」
私は何時に着いたか、ミス・ハヴィシャムの招きでエステラに会いに来たことを伝えた。彼は「ほう、立派な若い女性だ」と言い、片手でミス・ハヴィシャムの椅子を押し、もう片手をズボンのポケットに入れ、まるでそこに秘密が詰まっているかのような仕草をした。
「さて、ピップ! ミス・エステラには今まで何回会った?」と彼は止まって尋ねた。
「何回……?」
「ああ! 何度だ? 一万回くらいか?」
「おお! そんなに多くはありません。」
「二回か?」
「ジャガーズ」とミス・ハヴィシャムが口をはさんだ。私はほっとした。「私のピリップには構わず、あなたは彼と一緒に夕食に行きなさい。」
ジャガーズ氏は従い、私たちは暗い階段を手探りで一緒に降りた。まだ奥の石畳の中庭を抜けて、離れの部屋へ向かっている途中で、彼はミス・ハヴィシャムが食事をしたり飲んだりするのを何度見たかと訊ねてきた。しかも、いつもどおり「百回から一回の間で」自由に選べと言うのだ。
私は考えてから、「一度もありません」と答えた。
「そしてこれからもないだろう、ピリップ」と彼は眉をひそめて微笑みながら返した。「彼女は今のこの生活を始めてからは、決して人前で食べたり飲んだりする姿を見せていない。夜な夜な館をさまよい歩き、何か食事を摂るとしてもそのときにこっそり手に入れるのだ。」
「お願いです、先生」と私は言った。「質問してもよろしいでしょうか?」
「いいだろう」と彼。「ただし、私は答えないかもしれない。さあ、訊いてみなさい。」
「エステラの名前ですが。ハヴィシャム、なのでしょうか、それとも――?」私はそれ以上言葉が続かなかった。
「それとも何だ?」と彼。
「ハヴィシャム……でしょうか?」
「そうだ、ハヴィシャムだ。」
このやり取りののち、私たちは食卓に着いた。そこにはエステラとサラ・ポケットが待っていた。ジャガーズ氏が主宰し、エステラは彼の向かい、私は緑と黄色の友人(サラ・ポケット)の正面に座った。食事はとても美味しく、給仕は見覚えのない女中がしてくれたが、きっとこの謎めいた屋敷でずっと働いていたのだろう。夕食後、上質なポートワインのボトルが後見人の前に置かれ(彼は明らかにこのヴィンテージに精通していた)、二人の婦人は席を外した。
ジャガーズ氏のこの家での徹底した沈黙ぶりは、彼自身のなかでも際立っていた。彼は自分の表情さえも隠し、夕食中エステラの顔をほとんど見なかった。エステラが話しかければ、彼は耳を傾け、しかるべきときに返答したが、私には彼が彼女を見たようには思えなかった。一方、エステラは彼に何度も、興味と好奇心――あるいは不信感――をもって視線を送っていたが、その顔にはまったく意識の色が浮かばなかった。食事の間じゅう、彼は私との会話の中で私の「期待」についてしばしば話題に出し、サラ・ポケットをいっそう緑色と黄色に変えて楽しんでいるかのようだった。だが、その無自覚ぶりは徹底しており、あたかも私が自分から話題を持ち出したかのように――いや実際そうさせられているように――振る舞った。
そして、二人きりになると、彼は自分の持つ情報によって、すべてを控えているかのような雰囲気で座っていた。その態度が私には重すぎた。話すことがなければワインにまで尋問を始める始末であった。ワインをキャンドルの光にかざし、味見して口の中で転がし、飲み込み、グラスを見つめ、香りを嗅ぎ、再び試飲し飲み干し、またグラスに注ぎ、再びグラスを吟味する――まるでワインが私にとって不利な秘密を明かすのではないかと神経を尖らせてしまうほどだった。私は何度か会話を始めようとしたが、そのたびにジャガーズ氏はグラスを手に私を見つめ、ワインを転がしながら「どうせ答えられない」とでも言いたげな表情を見せた。
サラ・ポケットも、私を見かけることで怒りに駆られて発狂しそうになり、ひどく醜いモスリンのモップのような帽子を引きちぎって、地面に本来彼女の頭に生えていないであろう髪をばらまきかねない危険を感じていたのだろう。なので、私たちがその後ミス・ハヴィシャムの部屋へ戻ってウィストをしたとき、彼女は姿を見せなかった。その間に、ミス・ハヴィシャムは奇妙な趣向で、ドレッサーの上の最も美しい宝石をいくつかエステラの髪や胸元、腕に飾っていた。その美しさに、普段は表情を崩さぬ後見人でさえ、濃い眉の下から彼女を見上げ、わずかに眉を上げていた。

彼がどのように私たちの切り札を次々と手中に収め、手札の最後に安っぽいカードを出してキングやクイーンの威光を無残に打ち砕いたかについては、ここでは語らない。また、彼が私たち3人を、ずっと前から答えを知っているあまりに単純な謎のように見ていたのではないか、という私の感覚についても触れない。私が苦しんだのは、彼の冷たい存在感と自分のエステラへの思いが決定的に相容れないことだった。彼女について彼と話すのは耐えられない、彼が彼女に革靴を軋ませて歩くのを見るのも、手を引くように彼女を遠ざけるのも耐えられない――そんなことよりも、私の憧れがほんの数十センチの距離にあること、その思いが彼と同じ空間にあること、それこそが耐え難い苦痛だった。
私たちは九時までウィストをし、その後、エステラがロンドンに来るときは事前に知らせてもらい、駅馬車で迎えることが決まった。それから私は彼女に別れを告げ、触れ、そして去った。
後見人は「イノシシ亭」の私の隣の部屋に泊まった。夜遅くまで、ミス・ハヴィシャムの「愛せ、愛せ、愛せ!」という言葉が私の耳に響いていた。私はそれを自分用に言い換えて、枕に向かって何百回も「私は彼女を愛している、愛している、愛している!」と繰り返した。すると突然、かつて鍛冶屋の子だった自分のために、彼女が運命づけられているという感謝の念に包まれた。だが、もし彼女が、私が恐れているとおり、いまだにその運命に熱烈に感謝していないとしたら、いつになったら私に関心を持つようになるのだろう? いつになったら、彼女の中に今は眠っている心を呼び覚ますことができるのだろう?
ああ、私はそれが高尚で偉大な感情なのだと思っていた。しかし、エステラがジョーを見下すと知りながら、ジョーを遠ざけている自分の行動に、卑しさや小ささを感じたことはなかった。ほんの昨日のこと、ジョーは私の目に涙をもたらしてくれたのに、その涙はすぐに乾いてしまった――神よ、私をお許しください! ――すぐに乾いてしまったのだ。
第三十章
翌朝、ブルー・ボアで着替えながらよく考えた末、私は後見人に「オーリックはミス・ハヴィシャムの信頼を任せるにはふさわしくない男ではないか」と伝える決心をした。「もちろん、ピリップ、彼はその職にふさわしい男ではないさ」と後見人は、最初から一般論として満足げに言った。「信頼される職に就く人間が、その職にふさわしい人間だった試しはないからな。」この職が特別に間違った人間によって占められているわけではないと分かって、彼はむしろ上機嫌になったようだった。私がオーリックについて知っていることを話すと、満足そうに耳を傾けていた。「よし、ピリップ」と私の話が終わったとき、彼は言った。「すぐにでも行って、我らが友人に給料を払ってやろう。」この即断即決ぶりに私はやや怯み、少し待った方がと提案し、本人も手ごわいかもしれないとほのめかした。「いや、そんなことはない」と後見人は完璧な自信でハンカチの角をいじりながら言った。「私と言い合いをする姿をぜひ見てみたいものだ。」
その日、私たちは昼の駅馬車でロンドンへ戻る予定だったが、私はパンブルチュークの恐怖のもとで朝食を取ったため、カップを持つ手も震えるほどだった。これを口実に「少し歩いてきます」と伝え、ジャガーズ氏が用事を済ませている間にロンドン街道を先に歩き、馬車が追いついたら乗ると伝えた。こうして私は朝食後すぐにブルー・ボアを出ることができた。パンブルチュークの店の裏手に広がる田舎道を2マイルほど迂回してハイ・ストリートに戻ると、街の中心近くで危険を避けることができ、ほっとした。
久しぶりに静かな古い町にいるのは興味深く、時折知り合いに顔を見られたり、じっと見送られるのも悪くなかった。商店の何人かは店から飛び出し、わざと何か忘れ物でもしたかのように私の前を歩いて、道すがら顔を合わせて通り過ぎた。どちらがより芝居がかっていたか分からない――彼らの「そうしていない」ふりか、私の「気づかない」ふりか。それでも、私の立場は大いに注目されるもので、私はそれなりに満足していた――運命が私をあの「限度なきならず者」トラッブの小僧に出くわさせるまでは。
通りを見渡していると、トラッブの小僧が空の青い袋で自分を叩きながら近づいてくるのが見えた。彼を穏やかに無関心に眺めるのが一番だと考え、堂々とした表情で歩み寄った。自分でも上手くやったと思い始めたそのとき、トラッブの小僧は膝をガクガクと震わせ、髪を逆立て、帽子を落とし、全身を激しく震わせて道に飛び出し、「誰か助けてくれ! 怖いよ!」と大声で叫びながら、私の威厳に打ちのめされたかのような恐怖と悔悟を演じた。私が通り過ぎると、彼は歯をガチガチ鳴らし、極度の屈辱の印として地面に身を投げていた。
これは耐えがたいことだったが、まだ序の口だった。さらに二百ヤードも進まないうちに、またしても言葉にならない恐怖、驚き、憤りのうちに、再びトラッブの小僧が現れた。今度は狭い角を回ってきた。青い袋を肩にかけ、目には誠実そうな勤勉の光を宿し、トラッブの店に向かう決意を足取りに示していた。私を認めた途端、またしても大げさな狼狽ぶりを演じ始めるが、今回は回転しながら私の周りをぐるぐる回り、膝をがくがくさせ、手を挙げて許しを請う仕草まで見せた。その姿は見物人たちの大喜びを誘い、私は完全に呆然とした。
郵便局のある辺りまでさらに進むと、今度は裏道からトラッブの小僧が現れた。今度はまるで別人で、青い袋を私の外套のように肩からかけ、通りの反対側をやけに堂々と歩き、喜び勇んだ子供たちの一団を引き連れて、「知らないよ!」と手を振りながら時折叫んでいた。彼が私の横を通り過ぎるときの、シャツの襟を立て、髪をひねり、片腕を腰に当て、肘や体をくねらせながら「知らないよ、知らないよ、本当に知らないよ!」とわざとらしく言う態度の侮辱ぶりは、言葉では言い尽くせない。その直後、彼がニワトリのように鳴きながら橋を渡って私を追いかけ、かつて鍛冶屋だった頃の私を知っているかのような悲しげな鳴き真似をしたことで、私は町から追い出されるような形で恥を極め、田舎道へと出た。
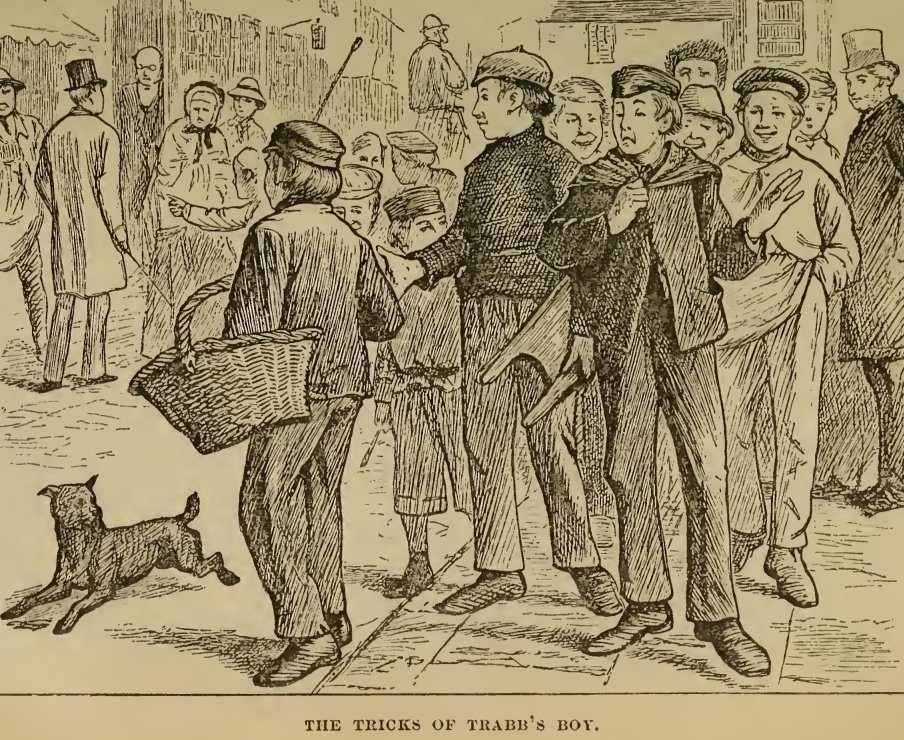
だがあの時、トラッブの小僧の命を奪うのでなければ、私に何ができたというのだろう。ただ耐えるしかなかった。通りで争ったり、彼の「心臓の血」以外のどんな償いも求めたりするのは、無駄で自分を貶めるだけだった。さらに彼は誰にも傷つけられない少年で、捕まえようとすればするりと逃げ回る、手に負えない蛇のような存在だった。それでも私は翌日、トラッブ氏に「ミスター・ピリップは、社会の利益を著しく損なう少年を雇用している者との取引を辞退する」と手紙を書き送った。
やがて駅馬車が時間どおりに到着し、私はまた屋根の席に座ってロンドンに着いた――無事に、だが心はすでにどこかへ行ってしまっていた。到着するとすぐジョーへの詫びとしてタラとかきの樽を送った(自分で行かなかった埋め合わせに)、それからバーナード・インへ向かった。
ハーバートは冷たい肉で夕食中で、私の帰宅を喜んで迎えてくれた。アヴェンジャーをコーヒーハウスに追加の料理を取りに行かせてから、私は今夜こそ友人に胸の内を打ち明けねばならないと感じた。アヴェンジャーが廊下にいる限り、信頼して話せるわけもなく、彼はせいぜい鍵穴の前室のようなものだったので、劇場に行かせた。あの仕事師への隷属ぶりの切実さは、彼に仕事を作ってやろうとする私の苦労が何よりの証だった。困り果てた末には、彼をハイドパーク・コーナーに「今何時か見てこい」と言ってやることさえあった。
食事を終え、暖炉の前で足を伸ばしていると、私はハーバートに言った。「ハーバート、君にとても大事なことを話したい。」
「ハンデル、君の信頼を光栄に思うよ。」
「これは僕自身と、もう一人の人に関することだ。」
ハーバートは足を組み、しばらく暖炉を斜めに見つめ、それが無駄だと気づくと私を見た。私が話を続けないからだ。
「ハーバート」と私は彼の膝に手を置いて言った。「僕は――エステラを愛している、いや、心から崇拝している。」
ハーバートは驚いた様子もなく、当然のように「そうだろう? それで?」と返した。
「それで、ハーバート? それだけなのか? それで?」
「その先は?」とハーバート。「もちろんそれくらい分かってるよ。」
「どうして分かったんだ?」と私は言った。
「どうしてって、ハンデル、それは君からさ。」
「僕は君に言ったことない。」
「言葉では言ってないさ。君が髪を切ったときも君は教えてくれないけど、僕は分かる。君がエステラを崇拝しているのは、君を知って以来ずっとだ。君はエステラへの崇拝とトランクをいっしょにこの部屋へ運んできたんだ。言葉にしなくても、君は一日中それを語っていた。自分の話をしてくれたときも、初めて彼女を見たときから心を奪われたと、はっきり語ったじゃないか。」
「なるほど」と私は新たな発見に不思議と嬉しくなりながら言った。「一度も彼女への思いが消えたことはない。そして彼女は、以前よりも美しく、気品に満ちて戻ってきた。昨日も会った。以前よりも倍も彼女を愛している。」
「それなら君は幸運だよ、ハンデル」とハーバート。「君は彼女のために選ばれ、運命づけられている。禁じられた話題に踏み込まずとも、君と僕の間ではそれは間違いない事実だ。エステラが自分を崇拝されることについてどう考えているか、分かったかい?」
私は陰鬱に首を振った。「ああ、彼女は僕には遥か遠い存在だ」と私は言った。
「忍耐だ、ハンデル、時間はたっぷりある。ところで、他にも言いたいことがあるのだろう?」
「恥ずかしいことだけれど、そして考えるだけなら言うのも同じだが、君は僕を幸運だと言ったね。たしかにそうだ。僕はほんの昨日まで鍛冶屋の子だった。今の僕は、何て言えばいいのかな……」
「“いい奴さ”と言えばいい」とハーバートは微笑みながら私の手を叩いた。「率直さとためらい、大胆さと臆病さ、行動力と夢想――それらが奇妙に入り混じった、いい奴だよ。」
私は自分にそんな混合があるか考えてみたが、どうも納得できず、まあ意義を唱えるほどでもないと思った。
「今日の自分を何と呼べばいいか、と考えるとき、僕の頭にあるのは、君がさっき言った“幸運”ということなんだ。自分で何も努力せず、ただ運命だけが僕をここまで押し上げてくれた。その点では、まさに幸運だ。でも、エステラのことを考えると――」
(「で、考えなかったことがあるのかい?」とハーバートが暖炉を見つめながら言い、それが親身な共感に感じられて嬉しかった。)
「――それで、ハーバート、僕はどれだけ自分が不安定で頼りなく、いくつもの偶然にさらされているか、言い表せない。さっき君が禁じた話題に触れずに言うなら、たった一人の人(誰とは言わないが)の誠実さ次第で、僕の“期待”はすべて決まる。そしてその“期待”が何なのかさえ、ぼんやりとしか分かっていない――実にあやふやで不満足なものだ。」こう言って、私は心の重荷が少し軽くなった。もっとも、それは昨日以来とくに重くなっていたのだが。
「ハンデル」とハーバートは明るく希望に満ちた調子で答えた。「恋の憂鬱に浸ると、人はせっかくの贈り物の馬の口の中を虫眼鏡でじっくり調べてしまうものさ。それにあまり集中しすぎて、動物のよい点を見逃している。君の後見人ジャガーズ氏は、君が“期待”を受けているだけじゃない、と最初に言わなかったかい? たとえ彼が言わなかったとしても(それは大きい“もし”だけど)、ロンドン中の誰よりも、彼がきちんと地盤を固めていない人とそんな関係を保つだろうか?」
私はそれは確かに強い論点だと――やや不承不承ながらも――認めた。
「強いどころじゃない」とハーバート。「これ以上強い理由は考えつかないよ。あとは、君は後見人の時を待つしかないし、後見人も依頼人の時を待つしかない。君はあっという間に二十一歳になる。そのころには何か新たな啓示があるかも。いずれにせよ、確実に近づいているんだから。」
「君は本当に楽天家だな」と私は心から感心した。
「楽天家でなきゃ困るよ。ほかに取り柄がないからね。ところでさっき言ったことは、僕自身の意見じゃなくて、父の意見なんだ。父が君の話について言った唯一のことは“もう決まったことだ。ジャガーズ氏が関わっている以上、未決ということはない”だった。それと……今から僕の父と僕自身について少し打ち明ける前に、君にちょっと嫌なことを言わなきゃならない。」
「無理だろう」と私は言った。
「いや、ちゃんと嫌なことを言うよ。いち、に、さん、さあ始めるぞ。ハンデル、君はさ――」と軽い口調ながら、彼は真剣だった。「僕はさっき考えてたんだが、エステラが君の相続の条件なら、後見人が一度も彼女について話題にしなかったのはおかしい。僕の理解が正しければ、後見人は一度も彼女について直接も間接にも触れなかったんだね? 君の後見人や君のパトロンが、最終的な君の結婚について何らかの意図を示唆したことすら?」
「一度もない。」
「ハンデル、僕は“酸っぱい葡萄”の気持ちなんてまったくない。彼女に縛られていないなら、君も彼女から離れられないか? ――嫌なことを言うと予告したろう。」
私は顔を背けた。なぜなら、かつて鍛冶屋を離れた朝、霧が荘厳に立ち上る中、村の道標に手を置いたときと同じ気持ちが、潮風のように胸に押し寄せてきたからだ。しばらく沈黙が続いた。
「でも、ハンデル」とハーバートは、まるで話が続いていたかのように続けた。「少年時代からそう強く根づいた思いは、とても深刻だ。彼女の育ちや、ミス・ハヴィシャムのことを考えてみろ。彼女自身がどんな人間か(ここで僕はますます嫌われる)。これは悲惨な結果を招くかもしれない。」
「分かっている、ハーバート」と私は顔を背けたまま言った。「でも、どうにもならない。」
「離れられないのか?」
「無理だ。絶対に。」
「努力もできない?」
「無理だ。絶対に。」
「そうか!」とハーバートはパッと立ち上がり、火をかき混ぜながら言った。「じゃあ、今度はもっと愉快な話をしよう!」
そう言って、部屋のカーテンを直し、椅子を元の位置に戻し、散らかった本などを片付け、廊下と郵便受けを覗き、ドアを閉めてからまた暖炉の前の椅子に戻り、左足を両腕で抱えて座った。
「父について、それと僕自身について、ちょっと言わせてくれ。父の家計がきらびやかでないのは、敢えて言うまでもないことだろう。」
「いつも十分にあるじゃないか」と私は場を和ませようとした。
「それは、塵芥屋も後ろのリサイクル屋も、強く同意してると思うよ。でも真面目な話だ、ハンデル、君もよく分かっているとおり、父が一度でも本気で家計を何とかしようとした時期があったのかわからないが、もしあったなら、今はもう昔の話だ。ところで、君の田舎でも、“あまり良いとはいえない結婚”の子どもほど、どういうわけか結婚に憧れるものだと気づいたことは?」
あまりに奇妙な質問なので、私は「本当にそうなのか?」と聞き返した。
「分からないさ」とハーバート。「それが知りたいんだ。というのも、うちの家族はまさにそうだから。可哀そうな妹のシャーロットは、十四歳になる前に亡くなったけど、その典型だった。妹のジェーンも同じだ。結婚したがる様子ときたら、短い人生を家庭の幸福だけを見つめて暮らしたみたいだ。フロックを着たアリックも、すでにキューで相応しい相手と結婚する手はずを整えているし、赤ん坊以外はみんな婚約していると思う。」
「じゃあ、君もか?」と私は言った。
「そうだよ」とハーバート。「でも秘密だ。」
私は秘密を守ると約束し、詳細を聞かせてくれと頼んだ。私の弱さにあれほど思いやりを見せてくれたハーバートの強さを知りたくなったのだ。
「名前は?」と私は尋ねた。
「クララ」とハーバートは言った。
「ロンドンに住んでいるのか?」
「うん、言っておくべきだったね」とハーバートは、なぜか急にしおらしくなって言った。「彼女は母の家系の馬鹿げた身分意識から見ると、少し下の階級なんだ。父親は客船の食料係だったらしい。多分、パーサー(事務長)の一種だと思う。」
「今は何をしている?」
「今は病人だ」とハーバートは答えた。
「暮らしは――?」
「一階に住んでいるよ」とハーバート。私の意図は経済状況を聞きたかったのだが、彼は階下に住んでいるという意味で答えたのだった。「顔を見たことはないよ。僕がクララを知ってからずっと上の部屋にこもっている。でも、いつも音は聞こえる。すごい騒ぎをするんだ、大声をあげたり、何か恐ろしい道具で床を叩いたり。」ハーバートは私を見て大笑いし、いつもの明るさを取り戻した。
「会うつもりは?」と私は尋ねた。
「もちろん、いつも会うつもりでいるよ。だって、あの騒ぎを聞くたび、天井を突き破って落ちてくるんじゃないかと心配になるから。でも、梁がいつまでもつか分からない。」
再び大笑いしたあと、ハーバートは再びしおらしくなって、「資本を手にしたらすぐに彼女と結婚するつもりだ」と真顔で言った。そして、「でも資本が手に入るまで結婚はできないんだよね」と、しみじみとした自明のこととして付け加えた。
私たちは火を見つめながら、この“資本”という幻がいかに実現困難なものか思いを巡らせた。私はポケットに手を入れ、何か紙が折りたたまれているのに気づいた。開いてみると、ジョーからもらった名優ウォプスル氏の芝居のビラだった。「あ、しまった」と私は思わず口にした。「今夜じゃないか!」
この一言で話題が変わり、私たちはあわてて芝居に行くことに決めた。私はハーバートの恋の成就を全力で応援すると約束し、ハーバートは婚約者が私の評判を知っていて、近いうちに紹介すると言い、私たちは固く握手を交わした。それからロウソクを消し、火を整え、ドアに鍵をかけ、ウォプスル氏と「デンマーク」を探しに出かけた。
第三十一章
デンマーク(劇場)に着くと、その国の王と王妃が台所のテーブルに据えられた二脚の肘掛け椅子に座し、宮廷を開いていた。デンマーク貴族の列席者は、巨大な先祖の皮ブーツを履いた貴族の少年、庶民出身と思われる顔の汚れた老貴族、そして櫛を挿し白絹の脚をした女性のような騎士で構成されていた。私の才能ある同郷ウォプスル氏は、腕を組み、陰うつな面持ちで立っていた。彼の巻き毛や額がもっと現実的だったら、と私は思った。
芝居が進行するにつれ、いくつか奇妙な出来事が起こった。この国の故王は、生前に咳に悩まされていただけでなく、墓場にも咳を持ち込み、幽霊となってもそれを引きずっていた。亡霊は杖に幽霊めいた原稿をくくりつけ、時おり不安げに目を通しては場所を見失いがちで、いかにも人間臭かった。だから、観客席から「ページをめくれ!」とアドバイスされ、幽霊は非常に不快そうだった。またその幽霊は、長い距離を歩いてきたような雰囲気なのに、実はすぐ隣の壁から出てくるのがバレバレで、そのせいで恐怖も嘲笑されていた。女王役はふくよかな婦人で、史実では鉄面皮だが、観客からは「真鍮が多すぎる」と評されていた。あごと王冠が幅広い真鍮バンドで繋がれ、胴や両腕も真鍮の輪で飾られて、「ケトルドラム」と呼ばれていた。
貴族の少年は一貫性がなく、あるときは水夫、あるときは旅役者、墓掘り人、牧師、果てはフェンシングの裁定者を演じていた。それが観客の不耐を招き、聖職者役で葬儀を拒否したときには、観客からナッツが投げられた。最後に、オフィーリアはあまりにゆっくりと音楽的に狂っていったので、スカーフを脱いで畳んで埋葬したとき、前列のいら立った男が「赤ん坊も寝かせたし、飯にしよう」と言ったが、あまりにも場違いだった。
これらの出来事はすべてウォプスル氏に降りかかり、観客は彼の疑問には大声で答え、議論が巻き起こった。例えば「耐えるのが貴いか」と言えば「そうだ」「違う」と両論が飛び交い、「コイントスで決めろ」と言う者まで現れた。「自分のような者は地上と天国の間を這ってどうすべきか」と問えば「そうだ、その通り!」と歓声が飛び、片足の靴下が乱れて舞台に出ると「その足の青白さは幽霊のせいか」などと談義が始まった。リコーダーを手にすれば「ルール・ブリタニアだ!」と合唱され、プレーヤーに「空気を切るな」と言えば「お前こそやめろ!」と突っ込まれてしまう。私の悲しいことには、毎度大爆笑が巻き起こった。
最大の試練は墓場の場面だった。それは原始林のようで、一方に小さな洗濯小屋、もう一方に料金所があった。ウォプスル氏が黒マントで入ってくると「葬儀屋さんが仕事の進捗を見に来たぞ!」と墓掘り人に声がかかった。頭蓋骨を持って感慨にふけったあとは、ナプキンで指を拭いたが、これすら「ウェイター!」と冷やかされた。空の黒い箱を棺に見立てて運んだときは会場が総立ちとなり、担ぎ手の中に特定できない男が混じっていたので一層盛り上がった。ウォプスル氏がオーケストラ席と墓の縁でラエルテスと格闘し、王を台所テーブルから突き落とし、足から少しずつ死んでいくまで、観客の笑いはやまなかった。
私たちは最初こそ拍手を試みたが、とても空しい努力で、すぐに諦めた。それで、私たちは同情しつつも、終始笑いをこらえきれなかった。どうしても滑稽で、でもウォプスル氏の朗読にはどこか立派なものを感じた――懐古的な思いではなく、あまりに遅く、単調で、登り下りが激しく、現実の誰もこんなふうに生や死について語らないだろうという点で、かえって印象的だった。芝居が終わり、彼が呼ばれたりブーイングされたりしたとき、私はハーバートに「早く帰ろう、彼に会うかもしれない」と言った。
私たちは階段を急いだが間に合わず、ドアの前には不自然なほど太い眉をしたユダヤ人の男が立っていた。彼は私に目を留めて言った――
「ピリップ様とご友人ですか?」
私とハーバートはその通りだと答えた。
「ウォルデンガーヴァー氏が、お目にかかりたがっております。」
「ウォルデンガーヴァー?」と私は繰り返したが、ハーバートが小声で「たぶんウォプスルだ」と囁いた。
「ああ、なるほど。ご案内いただけますか?」
「少しだけご同行を。」裏通りに入ると彼は振り向いて尋ねた。「どんなふうに見えました? ――私が衣装係です。」
彼がどんなふうだったかは分からないが、強いて言えば葬式みたいだった。巨大なデンマークの太陽か星の飾りが青いリボンで首から下がり、まるで特別な火災保険に入ったかのようだったが、「よくお似合いでした」と私は答えた。
「墓場の場面では、マントの見せ方が素晴らしかった。でも、女王の部屋で幽霊を見たときは、靴下でもっと工夫できたかもね。」
私は控えめに同意し、私たちは小さな汚れたスイングドアを通って、すぐ裏の熱い木箱のような部屋に入った。そこではウォプスル氏がデンマーク王の衣装を脱いでおり、私たちはドア(あるいは蓋)を開けて、互いに頭越しに彼を眺めることができた。
「諸君」とウォプスル氏は言った。「お目にかかれて光栄です。ピリップ様、招待状を送った無礼をどうかお許し下さい。かつての知り合いとして、演劇には常に富裕と高貴の誉れがふさわしいと、私は信じております。」
その間にも、ウォルデンガーヴァー氏は汗だくで衣装を脱ごうとしていた。
「ウォルデンガーヴァー氏のストッキングを破らないように脱がせてやれ」と衣装係が言った。「破いたら三十五シリングが消える。シェイクスピアもこれ以上の品は履いたことがないぞ。今は椅子で大人しくしていて、あとは俺に任せろ。」
そう言って彼は跪き、ウォプスル氏からストッキングを引っぺがし始めた。最初の片方が脱げたときには、もし転ぶ余地があれば確実に椅子ごとひっくり返っただろう。
私は芝居の話を切り出すのが怖かったが、やがてウォルデンガーヴァー氏が満足げに私たちを見上げて言った――
「諸君、舞台からどんなふうに見えたかね?」
ハーバートが後ろから(つつきながら)「見事でした」と言ったので、私も「見事でした」と答えた。
「私の役作りはどうだった?」ウォルデンガーヴァー氏は、ほとんど恩着せがましく質問した。
ハーバートが後ろからまたつつきながら「重厚で具体的でした」と言ったので、私もさも自分が考えたように「重厚で具体的でした」と強調した。
「ご賛同いただき光栄です」とウォルデンガーヴァー氏は、壁に押し付けられて椅子の座面を握ったまま、それでも威厳を保って答えた。
「でもね、ウォルデンガーヴァーさん」と衣装係が言った。「一つだけ、あなたの解釈は間違ってる。誰が何と言おうとそう思う。横向きになったときの脚の見せ方がダメだ。前に担当したハムレットもリハーサルで同じ間違いをしたから、スネに赤いシールを貼らせた。そのリハーサル(最後だったが)で私が舞台前に行き、横向きになるたび“シールが見えないぞ! ”と叫んだら、本番は見事な解釈になった。」
ウォルデンガーバー氏は私に微笑み、「忠実な従者だ――彼の愚かさは大目に見てやる」とでも言いたげな表情を見せ、そして声に出してこう言った。「私の観点はここにいる人たちには少し古典的で思慮深すぎるかもしれない。でも、彼らもきっと成長する、成長するさ。」
ハーバートと私は声をそろえて、「ええ、間違いなく成長するでしょう」と言った。
「ご覧になりましたかな、諸君」とウォルデンガーバー氏は言った。「ギャラリーに、演技――いや、上演ですね――を嘲笑おうとした男がいたのを。」
私たちは卑怯にも、そんな男を見かけたような気がすると答えた。私はさらに「きっと酔っていたんでしょう」と加えた。
「とんでもない、旦那」とウォプスル氏は言った。「酔ってなどいませんよ。雇い主が目を光らせていますからね。あの人の雇い主は、彼が酔うことなど絶対に許しません。」
「雇い主をご存じなのですか?」と私は尋ねた。
ウォプスル氏はゆっくりと目を閉じ、またゆっくりと開けた。「ご覧になったでしょう、諸君」と彼は言った。「無知で厚かましく、喉をしゃがれさせた、下卑た悪意のにじむ顔つきのロバが、――演じたとまでは言いませんが――もしフランス語で言わせてもらえれば、クラウディウス、デンマーク王の役をやっていたでしょう。あれが彼の雇い主です、諸君。これがこの業界なのですよ!」
私は、ウォプスル氏が絶望していたらもっと気の毒に思うべきだったのかどうかははっきりしなかったが、実際の彼の様子に十分すぎるほど同情を覚えた。だから、彼が振り向いてサスペンダーをつけてもらっている隙に(それがきっかけで私たちは出口に押し出されることになった)、ハーバートに彼を家に招いて夕食を共にしてはどうかと尋ねた。ハーバートは親切なことだと思うと言ったので、私はウォプスル氏を招き、彼も私たちと一緒にバーナーズへ行くことになった。彼は目までしっかりと包み込むように防寒していて、私たちは精一杯もてなした。彼は午前二時まで居座り、自身の成功を振り返ったり、今後の計画をあれこれ語ったりした。細かい内容は忘れてしまったが、概ね、最初は演劇界を復興し、最終的には自分が去った後に演劇が完全に壊滅状態となって希望も残らない、というような話だったと記憶している。
結局、私は惨めな気持ちで床につき、エステラのことを思いながらさらに惨めな気分になり、夢の中では、自分に課せられていた「期待」がすべて取り消され、ハーバートのクララと結婚の約束をさせられたり、二万もの観客の前で、台詞もろくに知らずにミス・ハヴィシャムの幽霊相手にハムレットを演じさせられる羽目になったりした。
第三十二章
ある日、私は本とマシュー・ポケット氏のもとで勉強に没頭していたが、郵便で一通の手紙を受け取った。表書きを見ただけで私は大いに動揺した――というのも、その筆跡は一度も見たことがなかったにもかかわらず、誰が書いたかすぐに察しがついたからだ。定型の冒頭――「親愛なるピップ様」や「親愛なるピップ」あるいは「親愛なる何某」など――はなく、こう綴られていた。
「私は明後日、昼の馬車でロンドンに行くことになっています。あなたが迎えに来る、ということになっているのでしょうか? いずれにせよ、ミス・ハヴィシャムはそう思っているようですし、私はそれに従って書いています。ミス・ハヴィシャムからよろしくとのことです。
敬具 エステラ」
もし時間があれば、この日のために何着も新調したいところだったが、そんな暇もないので、手持ちの服で我慢するしかなかった。たちまち食欲は消え失せ、当日が来るまで心の平穏も安らぎもなかった。しかし、到来したその日が安らぎをもたらすわけでもなかった。むしろ事態はますます悪化し、私は我が町のブルー・ボアを馬車が出る前から、ウッド・ストリートとチープサイドの馬車発着所をうろつく始末だった。そのタイミングを熟知していたにもかかわらず、発着所を五分以上目の届かないところにするのは危険だという非合理な気分に取り憑かれていた。こうして四、五時間にも及ぶ見張りのうち、最初の三十分をこなしたところで、ウェミック氏が私にぶつかった。
「やあ、ピップさん」と彼は言った。「どうしたんです? あなたの縄張りとは思えませんでしたよ。」
私は、誰かを馬車で迎えるために待っていることを説明し、「お城」と「年配氏」の様子を尋ねた。
「どちらも元気だよ、ありがとう。特に年配氏がね。絶好調だ。次の誕生日で八十二歳だよ。近所から文句が出なけりゃ八十二回祝砲を撃とうかと思ってるんだが、大砲が耐えてくれるかな。まあ、これはロンドン向きの話じゃないな。さて、僕がこれからどこに行くと思う?」
「オフィスですか?」と私は言った。彼がそちらの方向へ進んでいたからだ。
「まあ、ほとんどそうだね」とウェミック氏。「ニューゲートへ行くんだ。いま銀行家の小包事件を扱っていて、現場を視察してきたところで、これから依頼人と話をしなきゃならない。」
「依頼人がその強盗をやったのですか?」と私は尋ねた。
「とんでもない!」ウェミック氏はとても乾いた口調で答えた。「でも疑われているんだ。僕や君だって疑われるかもしれない。誰だってそうだよ。」
「でも、僕たちは疑われていません」と私は言った。
「やれやれ!」ウェミック氏は私の胸を指で突いて言った。「君は抜け目がないな、ピップさん! ニューゲートを見学したいかい? 時間はある?」
私はたっぷりと時間が余っていたので、この提案はむしろ気が紛れて歓迎だった。無意識に馬車発着所を見張り続けたいという気持ちと矛盾してはいたものの。私は「時間があるかどうか確認してきます」と独り言のように言いながら、オフィスに入り、店員に馬車の到着予定時刻を極めて正確に、しかも店員の気分を損ねるほどしつこく尋ねた――もちろん、実はすでに知っていたのだが。それからウェミック氏のもとに戻り、時計を見て驚いたふりをして、彼の申し出を受け入れた。
数分で私たちはニューゲートに着き、素っ気ない壁に鉄の足かせが吊るされている守衛室を抜けて、刑務所の内部に入った。当時の刑務所は大いに手入れが悪く、あらゆる公的な不正のあとの過剰反応――それが最大で最も長い罰となる――が到来するのはまだまだ先のことだった。だから、重罪人は兵士(ましてや救貧院の人々)より良い暮らしをしているわけではなく、スープの味を良くしたいがために刑務所に火を放つという発想もほとんどなかった。ウェミック氏が私を連れて入ったときは面会時間で、ビールを配る男が巡回し、囚人たちは中庭の鉄格子越しにビールを買い、友人と話していた。小汚く、醜く、乱雑で、陰鬱な光景だった。
ウェミック氏が囚人たちの間を歩く様子は、まるで庭師が自分の植物の間を歩いているようだった。夜のうちに新芽が出たのを見つけて「おや、キャプテン・トムか。いるのか? なるほど」と声をかけたり、「あれは貯水槽の後ろのブラック・ビルか? 二ヶ月も見ていなかったが、元気か?」と言ったりするのは、そう思わせるに十分だった。また、格子の前で一人ずつ不安そうに囁く囚人の話を聞いている時も、頑なな郵便局(彼の口)を動かさず、その発育状況を観察しているかのようだった。
彼は非常に人気があり、ジャガーズ氏の仕事の親しみやすい部分を担っているのだとわかった。一方で、ジャガーズ氏らしい威厳もにじませていて、一定以上の距離は決して近づかせないようだった。彼のクライアント一人一人への認知は、うなずき、帽子の位置を両手で少し整え、郵便局(口)をきつく締め、両手をポケットに入れる、という仕草で表現されていた。金額が足りない時には、「無理だよ、僕は下っ端だから。受け取れない。そんなこと下っ端に言わない方がいいよ。額が足りないなら、上司に相談しなきゃ。業界には上司がたくさんいるし、ある上司にとって割に合わなくても、別の上司には割に合うかもしれない――それが僕からのアドバイスさ。無駄なことはやめた方がいい。さて、次は誰だい?」と一歩下がって言った。
こうして私たちはウェミック氏の「温室」を歩き回った。すると彼が私に「これから握手する男に注目してくれ」と言った。彼がまだ誰とも握手していなかったので、その言葉がなくても気付いたと思う。
彼がそう言うやいなや、私には今でも目に浮かぶのだが、よれよれのオリーブ色のフロックコートを着た、がっしりした体つきの男が現れた。彼の顔色は赤みの上に特有の青白さが広がり、目は固定しようとするたび彷徨いがちだった。彼は鉄帽に手をやり、半分真面目で半分冗談めかした軍人風の敬礼をした。
「大佐、よう!」とウェミック氏。「元気かい、大佐?」
「ええ、元気です、ウェミックさん。」
「できるだけのことはしたけれど、証拠が強すぎたんだ、大佐。」
「ええ、強すぎましたね、でも――私は気にしません。」
「そうだな」とウェミック氏は平然と応じた。「君は気にしない。」そして私に向き直って、「この人は国王陛下に仕えた男だ。正規軍の兵士で、除隊金を払って軍を辞めたんだ。」
私は「そうなんですか」と言った。男の目が私を見、私の頭越しを見、私の周囲を見回した後、唇をなぞって笑った。
「私は月曜にはここを出られると思っています、ウェミックさん」と男は言った。
「かもしれないね」とウェミック氏。「でもどうなるか分からない。」
「あなたにお別れを言える機会をもらえて嬉しいです、ウェミックさん」と男は格子越しに手を差し出した。
「ありがとう」とウェミック氏は握手した。「君も元気でな。」
「逮捕された時に持っていたものが本物だったら、ウェミックさん」と男は握手をなかなか離さずに言った。「お世話になったお礼に、もう一つ指輪を贈らせていただいたのですが。」
「お気持ちだけ受け取っておくよ」とウェミック氏。「ところで、君は鳩好きだったよな。」男は空を見上げた。「君の知り合いに頼んで、タンブラー種の鳩を一対送ってもらえないだろうか。もう使い道がないのなら。」
「承知しました。」
「よし」とウェミック氏。「大事にするよ。では、大佐、さようなら!」再び握手し、私たちが歩き出すとウェミック氏は「造幣犯でね、腕の良い職人だったんだ。今日は判事の報告が出るから、月曜には確実に処刑される。それでも、鳩は持ち運びできる財産だからね。」そう言って、彼はその「枯れた植物」に目を戻し、次にどの鉢がこの場所に合うか考えるように周囲を見回した。
守衛室を通って刑務所を出ると、私の後見人の偉大さが看守たちにも囚人たちにも認められていることが分かった。「さて、ウェミックさん」と、鋲と釘が並ぶ門の間で私たちを監禁し、一方の扉をしっかり施錠してからもう一方を開ける看守が言った。「ジャガーズ氏は、あの水辺の殺人事件をどう扱うつもりですか? 過失致死にするんですか、それとも他の扱いに?」
「本人に聞いたらどうだい?」とウェミック氏。
「はは、無理だな」と看守。
「ほらね、ピップさん」とウェミック氏は私に向かって、自身の「郵便局」を伸ばしながら言った。「ここの連中は僕みたいな下っ端には何でも聞くけど、上司には絶対質問しないんだ。」
「この青年は君のオフィスの見習いか、実習生かい?」と看守はウェミック氏のユーモアに笑いながら尋ねた。
「まただよ、ほら!」とウェミック氏。「言っただろ? 下っ端に次々と質問するんだ。じゃあ、ピップさんがそうだとしたら?」
「そしたら」看守はまた笑って言った。「ジャガーズ氏がどんな人物か分かるってわけだ。」
「やれやれ!」とウェミック氏は、冗談めかして看守の肩を拳で叩きながら言った。「君は自分の鍵みたいに、うちの上司には何も聞けないくせにね。さあ、開けてくれよ、この狸じじい。でないと、うちの上司に訴訟でも起こしてもらうからな、不当監禁で!」
看守は笑いながら見送ってくれ、私たちが階段を降りて通りに出ると、門の上からまだ笑いながら見ていた。
「いいかい、ピップさん」とウェミック氏は真剣な声で私の耳元にささやき、より親しげに私の腕を取った。「ジャガーズ氏のように自分の地位を高く保ち続ける人はいない。常に高い位置を守る。それが彼の並外れた才能と一致している。さっきの大佐は彼に別れを言う勇気なんかないし、あの看守だって事件の意向を尋ねる勇気なんかない。その間に下っ端の僕が割って入る――分かるだろ? ――だから彼はみんなを意のままに操ることができるんだ、心も体もね。」
私は非常に感心したし、これが初めてではなかった。正直に言えば、私はもっと能力の低い後見人が欲しかったと、これもまた初めてではなく思った。
ウェミック氏とはリトル・ブリテンのオフィスで別れた。そこにはいつものようにジャガーズ氏の注意を求める人々がたむろしていた。私は再び馬車発着所の通りに戻り、残り三時間ほどの見張りを続けた。その間ずっと、なぜ自分がこんなにも牢獄と犯罪の影に取り囲まれているのか、不思議で仕方なかった。幼い頃、冬の夕暮れに荒涼とした湿地でそれに最初に遭遇し、その後も二度、薄れて消えたかに見えた染みが再び現れるように、人生の節目節目で再び現れたこと。今また、こんな形で自分の運命や出世に深く浸透していること。そんなことを考えながら私は、美しく誇り高いエステラが自分に向かってやってくる姿を思い浮かべ、牢獄と彼女との対比に心底嫌悪を感じた。ウェミック氏に出会わなければよかった、せめて彼の誘いに乗らずにいればよかった――そうすれば一年で最も大切なこの日に、ニューゲートの空気を纏い、服に埃をつけてエステラを迎えることもなかったのに。私は歩き回りながら足元の埃を払い、服の埃を払い、肺の空気を入れ替えた。彼女が来ることを思い出し、こんなにも自分が汚れた気分なのにうんざりした。そして、馬車がやってきて窓から彼女の顔と手が見えたとき、私はまだウェミック氏の「温室」の影が自分から離れていないような気がした。
あの瞬間、またもや過ぎ去った、名もなき影は何だったのか?
第三十三章
毛皮のついた旅行着のエステラは、これまで以上に繊細で美しかった。彼女の態度もこれまで私に向けてくれた以上に親しみやすくなっていて、その変化にはミス・ハヴィシャムの影響があるように思えた。
私たちは宿の中庭で、彼女の荷物を指示通りに集め終わったところで、私はふと、彼女がどこへ行くのか全く知らなかったことに気づいた――それまで、彼女以外のことは何も頭になかったのだ。
「私はリッチモンドに行くの」と彼女は教えてくれた。「覚えておくべきことは、リッチモンドは二つあること。サリー州とヨークシャー州。私が行くのはサリーのリッチモンドよ。距離は十マイル。馬車を手配して、あなたが私を送っていくの。これが私の財布――あなたがそこから私の経費を払うの。ええ、財布は受け取って! 私たち二人は指示に従うしかないの。自分の思い通りにできる立場じゃないのよ、私たちは。」
彼女が財布を渡しながら私を見た時、私はその言葉の中に何か内なる意味があるのではないかと期待した。彼女はそれを軽く言ったが、不機嫌ではなかった。
「馬車を呼ばなければなりません、エステラ。少し休みますか?」
「ええ、ここで少し休むことになってるわ。それから紅茶を飲んで、あなたがその間私の世話をするのよ。」
彼女は、そうしなければならないかのように私の腕に手を回した。私は、馬車を見つめていた給仕に、個室を案内するよう頼んだ。給仕はナプキンを取り出し、それがなければ階段の上の部屋に辿り着けないかのような様子で、私たちを真っ暗な狭い部屋へと案内した。その部屋には小さな鏡(この狭さには不要な贅沢品だ)、アンチョビソースの瓶、誰かのゲタが置いてあった。私はこの隠れ家を拒否したので、今度は三十人用の大きな食卓と、暖炉の中に燃え尽きたノートの葉と煤の山がある部屋に案内された。給仕はその燃え殻を見て首を振り、私が「レディに紅茶を」とだけ注文すると、がっかりした様子で部屋を出て行った。
私はこの部屋の空気――馬小屋と煮出しスープが入り混じったような匂い――から、馬車業が不調で、馬を煮て料理に使っているのかとさえ思った。しかし、エステラがいる限り、この部屋も私には全てだった。私は彼女と一緒にいられるなら、ここで一生過ごせると思った。(だが、実際その時は少しも幸せではなく、それを自覚していた。)
「リッチモンドではどこに滞在するの?」と私は尋ねた。
「かなりの費用をかけて、一人の婦人とその娘の家に住むの。その婦人には、私を連れ歩いたり、いろんな人に紹介したり、私を人々に見せたりする力がある――と、本人は言っているわ。」
「いろいろな人に会えて、注目されるのはうれしいでしょう?」
「ええ、たぶんそうね。」
彼女はあっけなく答えたので、私は「まるで他人事のように話すね」と言った。
「私がどう他人を語るか、どこで学んだの? さあさあ」とエステラは微笑して言った。「あなたに習う必要はないわ。私は自分のやり方で話すの。マシュー・ポケット氏との生活はどう?」
「とても快適に暮らしてるよ、少なくとも――」チャンスを逃しかけている気がした。
「少なくとも?」とエステラ。
「君がいない場所では、どこでもこれ以上快適にはなれないよ。」
「馬鹿ね」とエステラは平然とした口調で言った。「そんな馬鹿なこと言わないで。あなたの友達、マシュー氏は家族の中で一番優れてるんでしょ?」
「本当に優れてるよ。誰の敵でも――」
「“自分自身の敵”だなんて言わないで」とエステラ。「そういう男は嫌いなの。けれど、彼は本当に利害から離れ、小さな嫉妬や悪意にとらわれない人なのね?」
「間違いなく、そう言えるよ。」
「残りの家族についてはそう言えないでしょう」とエステラは私にうなずき、真剣でありながらもからかうような表情を見せた。「彼らはミス・ハヴィシャムに、あなたに不利な噂や含みを持たせるのよ。あなたを監視し、歪めて伝え、手紙を書き(時には匿名で)、あなたの存在が彼らの悩みの種であり生きがいなの。彼らがどれほどあなたを憎んでいるか、あなたには想像もできないでしょう。」
「僕に害はないだろう?」
エステラは答えずに、突然笑い出した。その笑いは本当に楽しそうで、私は困惑して彼女を見つめた。彼女が笑い終えた後(その笑いは本当に真に迫るものだった)、私は遠慮がちに言った。
「あなたが、彼らが僕に害を及ぼしても、面白がるとは思いたくない。」
「そんなことないわ、安心していいのよ」とエステラ。「私が笑うのは、彼らが失敗するからよ。ああ、ミス・ハヴィシャムの周りのあの人たちと、その苦しみったら!」彼女はまた笑った。理由を説明された後も、その笑いは私には不思議で、心からのものに違いないと確信しつつも、場に不釣り合いなほど強すぎると感じた。きっと、私の知らない何かがあるのだろうと思った。彼女は私の心中を見抜き、こう答えた。
「あなたでさえも、私がどれほど満足感を覚えるか分からないでしょう。あの人たちが邪魔され、滑稽な目に遭うのを見ると、私はとても愉快なのよ。だって、あなたは赤ん坊の頃からあの奇妙な家で育ったわけじゃないもの。私はそうなの。あなたは、同情や哀れみやら、優しいふりをした偽善の下で、彼らの陰謀に晒されながら、知恵を磨くことなんてなかったでしょう。私はそうしてきたの。あなたは、夜中に安らぎの蓄えを計算するようなあの偽善者の女の正体に、子供の丸い目をだんだん大きく見開いて気づいていく、なんて経験はなかった。でも私はあった。」
もはやエステラは笑いながら話していなかったし、その思い出は浅いところから引き出しているのではなかった。私は、彼女のあの表情の原因になるくらいなら、どんな「期待」も全部手放しても惜しくないと思った。
「二つ、あなたに言えることがある」とエステラ。「一つ目は、“滴り続ければ石も穿つ”ってことわざはあるけれど、あの人たちがどれだけ頑張っても、百年かけても、あなたのミス・ハヴィシャムの信頼を揺るがすことは絶対にないってこと。二つ目は、あなたがいるおかげであの人たちが空回りして卑劣なことをしているのであって、私はそのことをあなたに感謝している――だから、握手よ。」
彼女がふざけた調子で手を差し出したので――さっきの暗い気分は一瞬だけだった――私はその手を取って唇に当てた。「馬鹿ね」とエステラ。「いつになったら学ぶの? それとも前に私の頬にキスさせてあげたときと同じ気持ちで手にキスしたの?」
「どんな気持ちだったの?」
「ちょっと考えさせて。あれは、へつらう人や陰謀を企てる人たちに対する、軽蔑の気持ちだったわ。」
「もしそうなら、もう一度頬にキスしてもいい?」
「手を触る前に頼むべきだったわね。でも、いいわよ。」
私は身をかがめた。彼女の冷静な顔はまるで彫像のようだった。「さあ」とエステラは、私が頬に触れた瞬間すっと身をかわして言った。「次は私に紅茶を用意して、リッチモンドまで送りなさい。」
私たちの間柄が誰かに操られている人形のように、彼女が再びそうした態度に戻るのは辛かったが、結局どんなやりとりも私には痛みだった。彼女が私にどんな口調で接してきても、信じることも希望を持つこともできなかった。それでも私は、信じられないものを信じ、希望のないものに希望を懸け続けた。何度でも言うが、それがいつものことだった。
私はベルを鳴らし、給仕は再び「魔法の道しるべ」を持参して現れ、紅茶のための付属品を次々と運び込んだが、肝心の紅茶はなかなか現れなかった。お盆、カップ&ソーサー、皿、ナイフとフォーク(肉切り用含む)、スプーン各種、塩入れ、蓋付きの小さなマフィン、パセリで包まれたバター(まるで“葦の茂みの中のモーゼ”の再現)、粉のかかった薄いパン、台所の鉄格子の焼き目がついた三角形のパン、そして最終的には大きな家族用の湯沸かし器。給仕はこれを苦しみの表情で運び込んできた。長い間を置いて、とうとう貴重そうな小箱に入った小枝を持ってきた。私はそれをお湯に浸し、総動員した器具から、エステラのために一杯の何とも言えない飲み物を淹れた。
勘定を払い、給仕にも、馬丁にも、部屋係にも心づけを渡して――つまり家中を賄賂で敵に回し、エステラの財布はずいぶん軽くなり――私たちはポストコーチに乗り込んだ。チープサイドを抜け、ニューゲート・ストリートを駆け上がると、私はあれほど恥じていた壁の下にすぐに着いた。
「あれは何の建物?」とエステラが尋ねた。
私は最初知らないふりをしてから、正直に答えた。彼女はそれを見て頭を引っ込め、「哀れな人たち!」とつぶやいた。私は、どんなことがあっても自分がそこを見学してきたとは言えなかった。
「ジャガーズ氏は――」と私は話題を彼に押し付けるように言った。「あそこの秘密をロンドン一知っていると言われている。」
「彼はどこでもそうよ」とエステラは低い声で言った。
「あなたも彼にはよく会っているのでしょう?」
「定期的にというよりは、不定期にずっと見てきた。でも、子供の頃から彼を知っているつもりでも、全然分からないわ。あなたは?」
「疑い深い態度に慣れてしまえば、うまくやれているよ。」
「親しいの?」
「自宅で食事をしたこともある。」
「それはきっと変わった家なのでしょうね」とエステラは身を縮めた。
「変わった家だよ。」
私は彼女でさえ、後見人についてあまり多く語りたくはなかったが、ジェラード・ストリートでの夕食の話までしそうになった。だが、突然まばゆいガス灯の明かりに包まれ、その不思議な感覚がまたよみがえった。通り過ぎると、雷光に打たれたかのようにしばらく呆然とした。
私たちはそれから他愛もない話をしたが、そのほとんどは、道順やロンドンのどの辺りがどこなのかについてだった。彼女にとって大都会ロンドンはほとんど初めてで、ミス・ハヴィシャムの家から出たのもフランスへ行った時だけ、それもロンドンは通過しただけだったという。私は、彼女がロンドンにいる間、私の後見人が何か監督しているのか尋ねたが、彼女は「とんでもない」ときっぱり言った。
彼女が私に気を引こうとしているのは明らかだった。彼女は自分を魅力的に演出し、たとえ努力が必要だったとしても私を惹きつけるつもりでいた。しかし私は、それで幸せにはなれなかった。たとえ彼女が「お互いが他人によって処分される存在」といった調子を取らなかったとしても、彼女は自分の意志で私の心を握っているだけで、それを壊して投げ捨てることで彼女に少しでも優しさが芽生える訳ではないことが分かっていた。
ハマースミスを通るとき、私はマシュー・ポケット氏の家の場所を教え、「リッチモンドからそう遠くない、だから時々会えたらいい」と言った。
「ええ、会えるわ。都合の良い時に来ていいし、家族にも紹介されるわ。というより、もう紹介済みよ。」
彼女が行く家の家族は多いのか尋ねると、
「いいえ、母娘二人だけよ。母親は地位のある人だけど、収入を増やすのも嫌いじゃないみたい。」
「ミス・ハヴィシャムが、またあっさりあなたを手放すなんて意外だ。」
「それもミス・ハヴィシャムの計画の一部なの」とエステラは溜息交じりに言った。「私は彼女に定期的に手紙を書いて、会いに行き、経過を報告しなきゃならないの――私と宝石たちのことも――今ではほとんど全部私のものになったのよ。」
彼女が初めて私の名前を呼んだ瞬間だった。もちろん、彼女はわざとそうしたのだと分かっていたし、私はそれを大切に心に刻んだ。
リッチモンドにはあっという間に着いた。目的地は緑地のそばの家だった――格式高き家で、かつてはフープスカートにパウダー、つけぼくろ、刺繍入りの上着、巻き上げた靴下、フリルと剣が何度も集まった由緒ある場所だった。家の前の古木も、フープスカートやカツラ、硬いスカートと同じくらい不自然な形に刈り込まれていたが、やがて枯れ落ち、他の死者たちと同じ静けさの中へ消えていく運命だった。
古い声を響かせるベルが月明かりの中で鳴り響き――その昔は「緑のパニエが来たよ」「ダイヤモンド付の剣が来たよ」「赤い靴と青い装飾ひもの来客だよ」とたびたび告げたことだろう――チェリー色のメイド二人がひらひらと出てきてエステラを迎えた。荷物はすぐに玄関に吸い込まれ、エステラは私に手と微笑みで別れを告げ、そのまま家に吸い込まれていった。私はその家をじっと見つめ、彼女と一緒に住めたならどんなに幸せだろうと考えたが、実際には彼女と一緒にいる時ほど惨めなことはなかった。
私はハマースミス行きの馬車に乗り込んだ。重い心を抱えて乗り込み、降りる時はさらに重い心になっていた。自宅では、小さなジェーン・ポケットが小さな恋人に送られてパーティーから帰るところに出くわした。私は、その恋人がフロップソンの支配下にあるにもかかわらず、羨ましく思った。
マシュー・ポケット氏は出張講義で不在だった――家庭経済学の素晴らしい講師であり、子供や召使の管理については最高の教科書の著者として名を馳せていた。しかしジョー夫人は在宅で、赤ちゃんを静かにさせるために針箱を持たせていたことから、行方不明のミラーズ(フットガードの親戚と共に外出中)が戻るまでの間に針がいくつも紛失し、赤ん坊の体内・体外のどちらにも危険な状況になっていた。
マシュー・ポケット氏は、実践的な助言と明晰な洞察、賢明な判断力で有名だったので、私は胸の痛みを抱えながら彼に打ち明けようかと思った。しかし、ジョー夫人が「寝るのが一番」と言って赤ちゃんを寝かせ、自分は貴族の系譜書を読んでいるのを見て、――やっぱりやめておこうと思った。
第三十四章
「期待」に慣れてくると、自分自身や周囲の人々にそれがどんな影響を及ぼしているか、知らず知らずのうちに気づくようになっていた。自分自身の変化については、なるべく認めないようにしていたが、それが決して良いものばかりではないことは十分自覚していた。私はジョーに対する自分の態度について、常に後ろめたさを感じていた。ビディに対しても、決して気持ちの良い良心ではなかった。夜中に目覚めると――カミラのように――疲れきった心で、ミス・ハヴィシャムに会わなければもっと幸せで善良な人間になれたのに、ジョーと鍛冶屋を共同経営して大人になれたのにと、よく思ったものだった。夜、一人で暖炉を見つめていると、やはり我が家の鍛冶場や台所の火が一番だと思った。
それでも、エステラの存在は私の落ち着きのなさや心の不安と切り離せず、どこまでが自分の責任なのか混乱するほどだった。仮に「期待」がなかったとしても、エステラのことを思っていたら、果たして自分はもっと良い人間になれたのか、どうしても納得できなかった。他人への影響については、そんな迷いはなく、むしろ自分の立場が周囲に悪影響しか与えていないこと――とりわけハーバートにとって害でしかないことを、ぼんやりではあるが自覚していた。私の浪費癖は彼の柔軟な性格を浪費生活に引き込み、彼の質素な暮らしを乱し、不安や後悔で心を乱していた。他のポケット家の親族たちを卑しい手段に走らせたことについては、元からその素質があったからだと開き直っていたが、ハーバートの場合は全くの別問題だった。彼の簡素な部屋に似合わぬ家具を並べたり、カナリア色の従者アベンジャーを雇ったりして、かえって彼に悪いことをしたとしばしば胸が痛んだ。
そこで私は、気楽な生活を大いに取り戻すための「確実な方法」として、多額の借金を重ね始めた。私が借金を始めればハーバートもすぐに続き、「グローヴのフィンチ会」というクラブへの入会をスタートップの提案で決めた。その会の目的は――いまだに分からないのだが――隔週で高価なディナーを食べ、食後にできる限り喧嘩し、六人の給仕を酩酊させることらしかった。この愉快な社会目的は実に見事に達成されており、入会初日の乾杯の言葉で「紳士諸君、グローヴのフィンチ会においては、今後とも親睦と好意が最優先でありますように」と唱和された時、それ以外に意味があるとは誰も思わなかったほどだ。
フィンチ会の連中は馬鹿げた金の使い方をした。(会場はコヴェント・ガーデンのホテルだった。)私が初めて会員としてグローヴに行ったとき、最初に出会ったフィンチはベントレー・ドラムルだった。彼は当時、自分専用の馬車を乗り回しては街角の柱をなぎ倒していた。時に馬車から頭から転がり落ちることもあり、ある時はまるで石炭袋を荷下ろしするように、グローヴの玄関先に転がり込んだのを目撃したこともある。だが、これは少し先走った話で、私はまだフィンチ会員ではなく、会の規則上、成人になるまで正式会員にはなれなかった。
私は自分の財力を過信しており、ハーバートの出費を肩代わりしたい気持ちもあったが、彼は誇り高く、そんな提案はできなかった。だから彼もあちこちで困難に陥り、依然として道を模索し続けていた。私たちが夜遅くまで遊び歩くようになると、ハーバートが朝食時に絶望的な目で周囲を眺め、昼になるとやや希望を取り戻し、夕食時にはまた落ち込み、食後は遠くに資本(キャピタル)が見え始め、深夜には資本を手にしたような気分になり、午前二時ごろにはまたどん底に落ち込んで「ライフルを買ってアメリカへ行って、バッファロー狩りで一山当てようか」などと語り出すのが常だった。
私はたいてい週の半分ほどはハマースミスにいて、ハマースミスにいるときはリッチモンドをうろついていた。そのことについてはまた別に語ることにする。ハーバートも私がハマースミスにいると、よくやって来たし、その時期には彼の父親も彼が探している機会がまだ現れていないことを時折なんとなく感じ取っていたようだ。しかし、家族全体がごたごたしている中で、彼自身が人生のどこかに放り出されるのも、どうにかして片付くものとされていた。その間に、マシュー・ポケット氏はますます白髪が増え、問題を自分の髪の毛を引っ張ることで解決しようとすることも多くなった。一方、ポケット夫人は足台で家族をつまずかせたり、爵位の本を読んだり、ハンカチをなくしたり、祖父の話をしたり、「若き志」をベッドに押し込んで教育したりしていた。
私は今、自分の進む道をはっきりさせるために自分の人生のある時期をまとめているのだが、バーナード・インでの普段の生活ぶりを先に描写し終えてしまうのがいちばんよい方法だろう。
私たちはできる限り金を使い、その見返りは世間がくれる最小限のものしか得られなかった。常に多かれ少なかれ不幸せで、知り合いたちの多くも同じような有様だった。私たちの間には「常に楽しんでいる」という陽気な虚構があり、実際は決して楽しんでいないという骨ばった真実があった。私の知る限り、私たちの困窮ぶりは、ごくありふれたものだったと思う。
毎朝、ハーバートは常に新鮮な面持ちでシティへと出かけていった。私はよく彼のいる薄暗い裏部屋を訪ねたものだ。そこではハーバートはインク壺、帽子掛け、石炭箱、糸箱、暦、机とスツール、定規と一緒に過ごしていたが、彼がそれ以外のことをしていたのを見た覚えはない。もし私たち皆がハーバートほど誠実に、自分の引き受けたことをやっていたら、「美徳の共和国」に暮らせたかもしれない。彼には他にやることがなく、毎日の午後決まった時刻に「ロイズに行く」ことくらいだった――多分雇い主に顔を見せるという儀式だったのだろう。私の知る限り、彼がロイズと関わったのは、それ以外には行って帰ってくることだけだった。どうしても活路を見いださねばならぬと思い詰めたときは、混雑する時間に取引所(エクスチェンジ)に出向き、重々しい気分で中を行き来しては、集まった有力者たちの間を、まるで陰鬱な田舎踊りでもするかのように歩き回った。「なあハンデル」と、ある日そうした特別な日からの帰り道、ハーバートは言った。「分かったんだ、機会ってのは向こうからやってくるもんじゃなくて、こっちから出向いていくもんだって。だから僕は行ってきたんだよ」
もし私たちが互いにあまり好意を持っていなかったなら、朝ごとに決まって憎み合っていただろう。その時期の私は、部屋もアヴェンジャーの制服も見るのが我慢できなかった。朝食は借金が増すにつれて形式ばかりのものになり、ある朝食時に(宝石に関してと、地元紙なら書くであろう)法的措置を取るぞという手紙を受け取ったときは、思わずアヴェンジャーの青い襟をつかんで持ち上げ、靴を履いたキューピッドのように宙に浮かせてしまった――パンが欲しいと勝手に思い込んだ彼に腹を立てて。
時々――つまり我々の気分次第で不定期に――私はハーバートに、まるで大発見でもしたかのように言うのだった。
「ねえ、ハーバート、僕たち、うまくいってないね」
「ハンデル、実を言うと、まさにその言葉を僕も今しがた同じように思ってたよ、奇遇だね」とハーバート。
「それじゃ、ハーバート、僕たちの懐具合を調べてみよう」
私たちはこの目的で約束をするたび、深い満足を得た。これこそがビジネス、これこそが事態と対峙する方法、敵の喉元を締め上げるやり方だと私は思った。そしてハーバートも同じだったと思う。
私たちは夕食にちょっと特別なものと、普段よりちょっと上等なワインを頼み、気持ちを奮い立たせた。夕食が終わると、ペンの束、大量のインク、たっぷりの便箋と吸取紙を用意する。文具がたくさんあることには、不思議な安心感があった。
私は紙を一枚取り、きれいな字で「ピップの負債覚書」と見出しを書き、バーナード・インと日付も丁寧に書き加える。ハーバートも同じように「ハーバートの負債覚書」と書く。
そしてお互い、脇に積み上げた混乱した紙束――引き出しに放り込まれたり、ポケットの穴が空くほど持ち歩かれたり、ロウソクに火をつけるとき半分燃えたり、鏡に何週間も貼られていたり、様々な被害を受けた紙束――を参照する。ペンが走る音は私たちを非常に元気づけ、実際金を払っているのか、ただ帳簿をつけているのかわからなくなるほどだった。この立派な事務仕事と実際の支払いとが、価値としては同等に思えた。
少し書き進めると、私はハーバートに「進み具合は?」と訊く。ハーバートは、増え続ける数字を前に憂鬱そうに頭をかいていることだろう。
「どんどん増えていくよ、ハンデル。ほんと、どんどん膨らんでいく」
「しっかりしろ、ハーバート」と私は自分のペンをせっせと走らせる。「直視しろ、自分の懐を。正面から睨み返してやれ」
「そうしたいんだけど、ハンデル、向こうが僕を睨み返してくるんだ」
それでも私の決意の態度に感化されて、ハーバートはまた再開する。しばらくすると、今度は「コブズの請求書がない、ロブズのもない、ノブズのも」と言い訳をして、またあきらめようとする。
「なら、ハーバート、大まかに見積もって書き込めばいい」
「君は本当に機転が利くね!」とハーバートは感心して言う。「実に見事な商才だ」
私もそう思っていた。私はこの時ばかりは自分を一流のビジネスマンだとみなしていた。迅速、決断力、精力的、明快、冷静――そうした評判を自分で築き上げていた。すべての項目を書き上げたら、一つずつ請求書と照合し、チェックをつける。チェックをつけるたびに味わう自画自賛の気分は、まさに贅沢な感覚だった。すべての項目にチェックをし終えたら、請求書をきっちり畳み、裏にタイトルを書き、束ねて整理する。同じことを、(自分にはそんな管理の才能はないと謙遜しつつ)ハーバートの分にもしてやり、彼の帳簿も整理した気になった。
私のビジネス習慣にはもう一つ輝かしい特徴があった。それは「余裕を残す」ことだった。たとえば、ハーバートの借金が164ポンド4シリング2ペンスなら、「余裕を見て200ポンドにしておこう」。自分の分がその4倍なら、余裕を見て700ポンドにしておこう――という具合だ。この余裕枠(マージン)こそ賢明だと信じていたが、今思えば高くつく手だった。なぜなら、その分新たな借金をすぐ作ってしまい、余裕枠の分だけ借金が膨らみ、時にはさらにその先まで進んでしまうことすらあったからだ。
だがこうやって懐具合を調べ終えるときには、しばし安らぎと静けさ、徳のある沈黙があり、その間私は自分に絶大な自信を抱いた。努力と手際とハーバートの賛辞に癒やされつつ、左右にきちんと束ねた書類と文房具に囲まれ、まるで何かの銀行になったような気分だった。
こういう厳粛な時には、外のドアをきちんと閉め、邪魔が入らないようにした。ある晩、私が穏やかな気分に浸っていると、ドアの投函口から手紙が落ちてくる音がした。「ハンデル、君宛だ」とハーバートが取りに行き、戻ってきて手渡してくれた。「何事もなければいいが」と、封蝋と縁取りが重々しく黒いので言った。
その手紙はトラッブ商会の名で、「あなたは尊敬すべき方であり、ジョー・ガージェリー夫人が去る月曜午後6時20分にご逝去されましたので、来週月曜午後3時のご葬儀へのご参列をお願い申し上げます」という内容だった。
第三十五章
人生の道の上で墓穴が開かれたのはこれが初めてであり、その滑らかな大地にできた空白は驚くほど大きかった。キッチンの炉のそばに座る姉の姿が、昼も夜も私の頭から離れなかった。その場所が彼女抜きで存在しうるなんて、私の心にはどうしても理解できなかった。最近は彼女のことをほとんど、あるいはまったく思い出すことがなかったにもかかわらず、今は通りで彼女が近づいてくる気がしたり、すぐにドアをノックしそうな気がしたりした。彼女と何の関わりもなかった自分の部屋ですら、死の空白とともに、彼女の声や顔や姿が今も生きていて何度も来ていたかのような錯覚にとらわれた。
私の境遇がどうであれ、姉を優しい気持ちで思い出すことはほとんどできなかっただろう。しかし、優しさがなくとも後悔の衝撃というものはあり得るものだ。その影響下で(そして優しい感情の欠如を埋め合わせようとしてか)、私は姉を苦しめた犯人への激しい憤りに駆られた。十分な証拠があれば、オーリックや誰であっても容赦なく追い詰めていただろう。
私はジョーに手紙を書いて慰めの言葉を送り、葬儀には必ず行くと約束した。中間の日々は、前述のような奇妙な心持ちで過ごした。早朝に家を出て、「ブルー・ボア」で馬車を降り、鍛冶場への道を歩いた。
また素晴らしい夏空で、歩きながら、幼いころ姉に容赦なく当たられた日々が鮮やかに蘇った。しかし、今やそれらの記憶には優しい色合いがかかり、あの「ティックラー」ですらその鋭さが和らいでいた。そよぐ豆やクローバーの香りが、やがて私の思い出も、陽射しの中を歩く誰かの心を柔らかくする日が来ると、そっと囁いているかのようだった。
ついに家が見えてくると、トラッブ商会が葬儀屋として乗り込み、支配しているのがわかった。黒い包帯で目立つように飾られた松葉杖を持つ、陰気で滑稽な人物が二人、玄関に立っていた――その道具が誰に慰めをもたらすのか疑問だが――その一人は、ブルー・ボアの御者で、新婚夫婦を酔っ払って鋸挽き穴に落としたために解雇された男だった。村の子どもたちと多くの女たちが、この黒衣の門番や閉ざされた家と鍛冶場の窓を見物していた。近づくと、そのうちの一人(御者)がドアをノックした――まるで私が悲しみで疲れ果て、自分でノックできないかのような振る舞いだった。
もう一人の黒衣の門番(かつてガチョウを二羽賭けて食べたことのある大工)がドアを開け、私を応接間へ案内した。そこではトラッブ氏が一番良いテーブルを自分のものにし、板をすべて広げて黒いバザーのようなことをしていた。ちょうど私が着いたとき、誰かの帽子をアフリカの赤ん坊のように黒い布で包み終えたところで、私にも手を差し出した。私はその仕草に惑わされ、場の空気にも混乱し、思わず親愛の情をこめて握手してしまった。
親愛なるジョーは、大きな蝶結びの黒マントに包まれ、部屋の上座にぽつんと座っていた。主な喪主としてトラッブ氏に座らされたのだろう。私は身をかがめて「ジョー、元気だった?」と声をかけると、彼は「ピップ、昔は立派な体格だったもんな」と私の手を握り、それ以上は何も言わなかった。
ビディは、黒い服に身を包み、きちんとして控えめで、静かにあちらこちらでよく手伝っていた。私はビディにも話しかけたが、今は多く語るべき時ではないと考え、ジョーのそばに座り、「あれ――彼女――姉――は家のどこに?」と心の中で考え始めた。応接間の空気は甘い菓子の匂いでむっとしており、菓子のテーブルを探してみると、暗さに目が慣れるまでほとんど見えなかったが、カットされたプラムケーキやオレンジ、サンドイッチ、ビスケット、そして飾りとしてしか見たことのなかった二つのデカンタ(一本はポート、もう一本はシェリー)が置かれていた。このテーブルのそばにいると、従順なパンブルチュークが黒いマントと何ヤードもの帽子紐を身にまとい、しきりに何かを食べつつ私の気を引こうとしているのに気づいた。とうとう私の注意を引くと(シェリーとパンくずの息をしながら)「よろしいでしょうか、旦那様?」と控えめに言い、実際にやった。そのとき、ハブル夫妻も見かけた。奥方は隅で言葉も出ないほど感激していた。我々は「後を追う」ことになっており、トラッブ氏によってそれぞれ馬鹿げた束にされるところだった。
「ピップ」とジョーが私にささやく。「できることなら、おれは三、四人の仲間と一緒に、自分で彼女を教会まで運びたかったよ。けど、ご近所の手前、それじゃあ礼を欠くと言われてな」
「ハンカチを出して!」とこの時点で、トラッブ氏が気の抜けた業務口調で叫んだ。「ハンカチを! 準備はいいな!」
そこで私たちは皆、鼻血でも出したかのようにハンカチを顔に当て、二人ずつ列になって外に出た。ジョーと私、ビディとパンブルチューク、ハブル夫妻。姉の遺体はキッチンの裏から運ばれ、六人の担ぎ手が黒いビロードの覆いで息苦しく目隠しされるという葬儀屋の作法で、全体は十二本足の盲目の怪物のようだった。導き役は御者とその相棒だ。
村中はこの行列に大いに満足し、私たちは道中多くの視線を浴びた。若者たちは時折わざと道をふさぎ、要所で私たちを待ち伏せした。そうした場面では、角を曲がるたびに「来たぞ!」「あれだ!」と興奮して叫び、まるで声援されているようだった。また、私のすぐ背後で、卑屈なパンブルチュークが私の帽子紐を直したりマントを整えたりと、過剰な気遣いを続けたため、私はますます苛立った。ハブル夫妻は、この名誉ある行列の一員であることに非常に得意げで、見ていてさらに気が散った。
やがて湿地が広がり、川の帆船が見えてきた。私たちは教会の墓地へと入り、そこは私の見知らぬ両親――フィリップ・ピリップ、この教区の故人と、その妻ジョージアナ――の近くであった。そこで姉は静かに土に還り、ヒバリが高くさえずり、優しい風が雲や木々の美しい影を墓に落としていた。
この最中、パンブルチュークの俗物じみた振る舞いについては、全て私に向けられていたとだけ言っておく。たとえ、人は裸で生まれ裸で去る、人生は陰の如く束の間である――といった聖句が読まれている間ですら、彼はまるで急に莫大な財産を手にした若者の場合は別だ、とでも言わんばかりに咳払いをしていた。葬儀から戻ると、彼は私に「君のおかげで姉さんもこれだけの体面を保てた、彼女もそのためなら死も納得しただろう」と厚かましく言い、シェリーは残らず飲み干し、ハブル氏はポートを飲み、二人で(葬儀の場でよく見かけるが)亡き人とは別の人種で、不死身であるかのように話し始めた。最後に彼らはハブル夫妻と共に帰っていった――きっと「陽気な船乗り」で自分こそが私の後見人で最初の恩人だと吹聴するためだろう。
皆が去り、トラッブ氏とその手下たち(ただし少年は見かけなかった)が道具一式をまとめて帰ると、家の中は少し健康的な空気になった。その後まもなく、ビディとジョーと私で冷たい夕食を共にした。しかしそれは古いキッチンではなく応接間でとり、ジョーはナイフやフォーク、塩入れにまで神経質に気を遣っていたため、皆かなり気詰まりだった。だが、食後に彼にパイプを勧め、鍛冶場をぶらつき、外の大きな石に並んで腰かけると、ようやく打ち解けることができた。葬儀の後、ジョーは礼服と作業着の中間の服に着替えており、それが彼本来の自然な姿に見えて嬉しかった。
私が「自分の小さな部屋で寝てもいいか」と尋ねると、ジョーはとても喜んだ。私も嬉しかった。自分からそう頼むのは大きな進歩だと感じたからだ。夕暮れが迫るころ、ビディと二人きりで庭を歩く機会を得て、少し話をした。
「ビディ、こういう悲しいことがあったなら、君から手紙をくれてもよかったんじゃないかな」
「そう思われますか、ピップさん? そう考えていたら書いていました」
「冷たく言うつもりはないけれど、やはりそう考えるべきだったと思う」
「そうですか、ピップさん?」
彼女はとても静かで、きちんとして、良い子で、愛らしい様子だったので、また泣かせるのは嫌だった。下を向いたまま歩く彼女をしばらく見つめて、その点はもう追及しないことにした。
「ここにいるのは難しいだろうね、ビディ」
「ええ、もう無理です、ピップさん」と、ビディは後悔と確信の入り混じった口調で答えた。「ハブル夫人と話して、明日からは彼女のところに行きます。しばらくは一緒にガージェリーさんの世話をできればと思っています」
「どうやって暮らすつもり? お金が必要なら――」
「どうやって暮らすか、ですか?」とビディは頬を赤らめてさえぎった。「お話します、ピップさん。私はもうすぐここでできる新しい学校の女教師の職をもらえるよう努力します。ご近所の方からよく推薦もしていただけますし、勤勉で辛抱強く、自分も教えながら学んでいけると信じています。昔あなたからいろいろ学び、その後さらに成長できたのですから」と微笑んで私を見上げた。
「君はどんな環境でも、きっと成長し続けると思うよ」
「そうですね。だけど自分の悪い面を除けば」とビディは小さくつぶやいた。
それは私への非難というより、思わずもらした独り言のようだった。まあ、その点ももう追及しないことにした。私はもう少しビディと歩き、黙って彼女の伏し目を見ていた。
「姉さんの死のいきさつは聞いていないんだけど」
「とても簡単なことです。ここ最近はむしろ落ち着いていたのですが、発作が四日ほど続いたあと、夕方、お茶の時間に急に回復して、『ジョー』と普通に言ったんです。長く言葉を発したことがなかったので、私はすぐ鍛冶場からジョーさんを呼びに行きました。彼女はジョーさんのそばに座ってほしい、腕を首に回してほしいと合図をしたので、その通りにすると、彼女は満足そうにジョーさんの肩に頭を預けました。そして『ジョー』とまた言い、『許して』と一度、『ピップ』と一度言いました。もう二度と頭を上げることはなく、それから一時間後に、亡くなっているのに気づいてベッドに寝かせました」
ビディは泣きだし、薄暗くなっていく庭や小道、星も私の目にはぼんやり滲んで見えた。
「犯人は結局わからなかったの?」
「何も」
「オーリックは今どうしている?」
「服が汚れていたので、きっと石切場で働いているのでしょう」
「つまり、見かけたんだね? ――なぜ小道の暗い木を見ている?」
「姉さんが亡くなった夜、あそこに彼がいました」
「それが最後じゃないでしょう?」
「ええ、今夜みたいに歩いているときにも見かけました――でも無駄です」とビディは私が駆け出そうとしたのを制し、私の腕に手を置いた。「本当に一瞬で、もういません」
姉がいまだにこの男につきまとわれていると知ると、私は激しい憤りを新たにした。私はそのことを伝え、どんな金も労苦も惜しまず追い払うと約束した。やがてビディは私をなだめ、ジョーが私をどれほど愛しているか、何も文句を言わず、ただ静かに、力強く、優しい心で自分の務めを果たし続けていることを話してくれた。――彼についてどれほど褒めても足りない、と私も言った。
「本当に、彼のことは何を言っても言い過ぎにはならないよ。ビディ、これからはよくこういう話をしよう。僕もこれからはしょっちゅう帰ってくるつもりだから。ジョーを一人ぼっちにはしない」
ビディは何も言わなかった。
「ビディ、聞いている?」
「はい、ピップさん」
「それにしても、僕をピップ“さん”と呼ぶのは、どうも趣味が悪いと思うよ、ビディ。それはさておき、どういう意味なんだ?」
「どういう意味って?」とビディはおそるおそる訊いた。
「ビディ」と私は道徳的な自己主張の口調で言った。「君のその態度の意味を教えてもらいたい」
「この態度ですか?」
「繰り返さないでくれ。前はそんなことしなかったじゃないか」
「前は! ああ、ピップさん、前は!」
まあ、ここももう追及しないことにした。再び沈黙のまま庭を歩いたあと、私は核心に戻った。
「ビディ、僕はこれからちょくちょくジョーに会いに帰ると言ったけど、君は無言だった。その理由を教えてくれ」
「本当に、しょっちゅうお帰りになりますか?」とビディは足を止め、星明りのもとで澄んだ目で私を見上げて言った。
「なんてことだ!」と私は絶望的に言った。「本当に人間の悪い面を見た気分だ! もういい、ビディ。これ以上言わなくていいよ。本当にショックだ」
だから夕食の間、私はビディと距離を置き、自分の小さな部屋に上がるときにも、今日の教会と出来事にふさわしいと自分に言い聞かせつつ、できるだけ形式張った別れをした。夜、何度も目が覚めるたびに、ビディが私にした不親切、不義、不公正を反芻した。
翌朝、私は発つことになっていた。早くに家を出て、誰にも見られぬよう鍛冶場の木枠の窓から中を覗き込んだ。ジョーはすでに仕事にかかり、健康的な赤みを帯びた顔は、まるでこれからの人生に明るい陽が射しているかのようだった。
「さよなら、ジョー――いや、そのままで、神様、汚れた手を握らせてくれ! またすぐ、何度も帰ってくるよ」
「いくら早くても、いくらしょっちゅうでも大歓迎だよ、ピップ!」とジョー。
ビディはキッチンのドアで私を待っていて、新しいミルクとパンの皮を手渡してくれた。「ビディ」と別れ際に手を握り、「僕は怒ってない、でも傷ついている」と伝えた。
「お願いですから、傷つかないで」と彼女は哀れっぽく懇願した。「もし私が不親切だったなら、私だけが傷つけばいいんです」
また霧が立ち上る中を私は歩き去った。その霧が、「もう戻らないだろう、ビディは正しかった」と私に告げていたなら――それはおそらく、まったくその通りだったのだ。
第三十六章
ハーバートと私は相変わらず借金を増やし、帳簿を見直し、余裕枠を残すなど模範的な「取引」を重ねて悪化の一途をたどった。時は流れ続け、ついに私は成人した――ハーバートの予言通り、気づかぬうちにその日が来た。
ハーバート自身は私より八か月早く成人した。だが成年になった以外に特記すべきものがなかったので、バーナード・インでは特に盛り上がりもしなかった。しかし私の二十一歳の誕生日には、私たちは大きな期待と憶測を持っており、この日に後見人が何かはっきり言わざるを得ないだろうと考えていた。
リトル・ブリテンでは私の誕生日が周知されていた。その前日に、ウェミックから公式な通知が届いた。「おめでたい日に午後五時にジャガーズ氏が面会を希望」とあった。これで何か重大なことが起こると確信し、私はジャガーズ氏の事務所へと、時間ぴったりに向かった。
外の事務所でウェミックは私に祝辞を述べ、折りたたんだ薄紙で鼻の脇をこすって見せたが、それについては何も語らず、うなずいてジャガーズ氏の部屋へと案内した。十一月で、ジャガーズ氏は暖炉の前に立ち、両手をコートの後ろに入れていた。
「さてピップ、今日は君を“ミスター・ピップ”と呼ばなければならないな。おめでとう、ミスター・ピップ」
私たちは握手した――彼の握手はいつも驚くほど短いものだった――私は礼を述べた。
「おかけなさい、ミスター・ピップ」とジャガーズ氏。
私は着席し、彼はそのままの姿勢で靴先を見つめていた。私は墓石の上に立たされたあの昔を思い出し、劣勢な気分になった。棚の上のふたつの不気味な石膏像も彼の近くにあり、まるで会話に出ようとしているかのような表情だった。
「さて若い友よ」とジャガーズ氏は、まるで証人席の相手にするように切り出した。「少し話がある」
「お願いします、先生」
「君は、自分がいくらぐらいのペースで生活していると思う?」
「生活のペース、ですか?」
「そうだ」とジャガーズ氏は、なおも天井を見上げて。「どのくらいの――ペース――で?」そして部屋を見回し、ハンカチを鼻に半分寄せて手を止めた。
私は何度も帳簿をつけていたせいで、もはや自分の財政状況を少しも把握していなかった。私は答えられないと正直に認めた。この返事にジャガーズ氏は満足げに「そうだろうと思った!」と鼻をかんだ。
「さあ、今は私が君に質問したが、君の方から私に聞きたいことはあるか?」
「もちろん、いくつか伺えればありがたいのですが、以前お止めになったので」
「一つだけ聞け」とジャガーズ氏。
「今日、私の恩人が明かされるのでしょうか?」
「いや。ほかに」
「それは近いうちに明かされるでしょうか?」
「それは少し置いておけ」とジャガーズ氏。「別のことを」
私は他に逃げ道がなくなり、「何か、受け取るものがあるのでしょうか?」と尋ねた。ジャガーズ氏は得意げに「そう来ると思った!」と叫び、ウェミックに紙を持ってくるよう呼んだ。ウェミックが現れ、それを手渡すとまた消えた。
「さてピップ」とジャガーズ氏。「よく聞くんだ。君はここからかなり自由に金を引き出していた。ウェミックの帳簿に君の名が度々出てくる。だがもちろん借金があるな?」
「おそらく、その通りです」
「その通りと言わざるを得ないな?」とジャガーズ氏。
「はい」
「いくら借りているかは聞かない。どうせわからないし、知っていてもごまかすだろう。はいはい、君はごまかさないつもりでもそうなる。許してくれ、だが私の方がよく知っている。さて、その紙を持っているな。開封して何か見てみなさい」
「これは五百ポンドの銀行券です」と私は言った。
「それが五百ポンドの銀行券だ。なかなかの金額だと思うが、君もそう思うか?」
「そう思います!」
「では、はっきり答えなさい」とジャガーズ氏。
「もちろんです」
「もちろん、なかなかの金額だな。さて、ピップ。その大金は今日、君自身への贈り物だ。将来に向けての証として。そしてこの金額を年額とし、それ以上ではなく、その範囲で暮らすこと。つまり、これからは自分で金銭管理をし、四半期ごとにウェミックから125ポンドを受け取ること。君が“泉の本流”と直接やり取りするようになるまではだ。私が言った通り、私は単なる代理人だ。指示通りに動き、その分だけ報酬をもらう。指示が愚かでも、私が意見する立場にない」
私は、恩人の寛大さに感謝を述べようとしたが、ジャガーズ氏に遮られた。「ピップ、私は誰かに君の言葉を運ぶ役目はない」と彼は冷静に言い、コートの裾をまとめて話題も打ち切り、また靴先に眉をひそめて立ち尽くした。
しばらくして私はおずおずと、「さっき一度だけ保留にされた質問があります。もう一度伺ってもよろしいですか?」と切り出した。
「何だ?」と彼。
彼は絶対助けてはくれまいと知っていたが、やはり自分で新しく言い直すしかなく、私はためらいながら、「私の後見人――“泉の本流”とも呼ばれた方――は、間もなく」ここで言葉を切った。
「間もなく何だ?」とジャガーズ氏。「それでは質問にならないぞ」
「間もなくロンドンに来るとか、あるいは私をどこかに呼び出すとか、そういう可能性は――」と私は言葉を探して続けた。
「さて」とジャガーズ氏は、初めてその暗い目を私に向けて言った。「君の村で最初に会った晩の話に戻ろう。あのとき私が何と言ったか、覚えているか?」
「何年も先のことかもしれないとおっしゃいました」
「その通り。それが答えだ」
私たちは互いにじっと見つめ合い、私は何とか何か引き出そうと胸が高鳴ったが、彼がそれを見抜いていると感じるほど、ますます何も得られないと悟った。
「それもまだ何年も先だと思われますか?」
ジャガーズ氏は首を振った――否定の意味ではなく、何も答えるつもりがないという拒絶のしぐさで――そしてあの二つの恐ろしい石膏像は、私が見上げると今にもくしゃみをしそうなほど緊張した表情になっていた。
「よし」とジャガーズ氏は、手を温めていた脚の裏側をさらに温めながら言った。「ピップ、はっきり言おう。それは訊かれてはならない質問だ。それは私自身が困ることになる。もう少し踏み込もう」
彼は靴先を見下ろし、ふくらはぎをさすった。
「その人が明かされたとき」ジャガーズ氏は姿勢を正して言った。「君とその人で自分たちのことは自分たちで決める。その人が明かされたとき、私の役目は終わる。その人が明かされたとき、私が関知する必要は一切ない。――これが私の言えるすべてだ」
私たちはしばらく互いに見つめ合っていたが、やがて私は視線を外し、考え込むように床を見つめた。今の最後の言葉から、私はミス・ハヴィシャムが、何らかの理由で――あるいは無理由で――自分をエステラのために私を育てている計画について、ジャガーズ氏に打ち明けていないのだと感じ取った。そして彼はそれを不満に思い、嫉妬さえ感じているのか、あるいは本当にその計画に反対していて関わりたくないのかもしれないと思った。再び彼を見上げると、彼はずっと鋭く私を観察しており、今もそうしていた。
「もしそれがすべてのお話でしたら」と私は言った。「私から言うことはもうありません」
彼はうなずき、盗人も恐れる懐中時計を取り出して、どこで食事をするのかと尋ねた。私はハーバートと自分の部屋で食べると答えた。すると当然の流れで、私は彼にご一緒いただけませんかと尋ね、彼はすぐに招待を受け入れた。しかし、私が余分な準備をしないようにと、彼はどうしても私と一緒に歩いて帰ると言い張った。まずは手紙を二通ほど書く必要があり(もちろん)手を洗う必要もあった。そこで私は外の事務室でウェミック氏と話していると伝えた。
実際のところ、私の手元に五百ポンドが入ったとき、以前から何度も考えていたことがまた頭をよぎった。そしてウェミック氏は、そのことについて相談するのに適した人物だと思われた。
彼はすでに金庫を施錠し、帰宅の準備をしていた。机を離れ、脂ぎった事務用燭台を二つ取り出して消し器と並べ、扉のそばの台の上に置き、消す準備を整えていた。火は小さくし、帽子とオーバーコートも用意して、金庫の鍵で胸を叩いて運動がてら仕事を終えていた。
「ウェミック氏」と私は言った。「ご意見を伺いたい。私はある友人のために何かしたいんだ」
ウェミック氏は郵便局員のごとく身構え、そんな致命的な弱さには反対だというように首を振った。
「その友人は」と私は続けた。「商売で身を立てようとしているが、資金がなく、始めるのが困難で意気消沈している。どうにか彼のスタートを助けたいと思っている」
「現金でかい?」とウェミック氏は、おがくずよりも乾いた口調で言った。
「多少は現金で」と私は答えた。家にあるきれいにまとめられた書類の束を思い出して気まずくなった――「多少は現金で、そしてもしかすると私の遺産を見越して」
「ピップさん」とウェミック氏は言った。「それじゃ、ちょっと指を使って一緒にチェルシー・リーチまでのいろんな橋の名前を挙げてみよう。ロンドン橋、一つめ。サザーク、二つめ。ブラックフライアーズ、三つめ。ウォータールー、四つめ。ウェストミンスター、五つめ。ヴォクスホール、六つめ」彼は金庫の鍵の柄で掌を叩きながら、橋を数え上げていった。「つまり六つも選び放題なんだ」
「何のことかわからない」と私は答えた。
「橋を選びなよ、ピップさん」とウェミック氏。「橋の上を歩いて、橋の中央のアーチからテムズ川に金を放り込むんだ。結果はわかるだろう。友人のために使った場合も、結果はわかる――ただし、もっと不愉快で得るものもない終わり方さ」
彼はこう言い終えると、口を大きく開けて、まるで新聞を投函できそうなほどだった。
「これはかなり落胆させられる意見だ」と私は言った。
「そのつもりだ」とウェミック氏は言った。
「それでは、あなたの意見では――」と私は少し憤慨しながら尋ねた。「人は決して――」
「――持ち運びできる財産を友人に投資すべきでない?」とウェミック氏。「まったくその通り。もし友人と縁を切りたいなら別だが、その場合はどれだけ出せば縁を切れるかの問題になる」
「それが、あなたの熟慮した意見なのか、ウェミック氏?」
「ここではそれが私の熟慮した意見だ」と彼は返した。
「なるほど」と私は言い、彼が抜け道を用意しているのではと思い、さらに追及した。「でも、ウォルワースでは意見が違うのか?」
「ピップさん」と彼は真面目な顔で答えた。「ウォルワースは一つの場所で、この事務所は別の場所だ。エイジドが一人の人間で、ジャガーズ氏が別の人間なのと同じようなものさ。一緒にしてはいけない。ウォルワースでの私の気持ちはウォルワースでしか通用しない。ここでは公的な意見しか口にできない」
「わかった」と私は大いに安堵して言った。「じゃあ、必ずウォルワースを訪ねるよ」
「ピップさん」と彼は返した。「個人的な立場でなら、歓迎するよ」
私たちはこの会話を小声で交わした。なぜなら、私の後見人の耳は非常に鋭いと知っていたからだ。ちょうどそのとき、彼が手を拭きながら戸口に現れたので、ウェミック氏はオーバーコートを身につけ、燭台の火を消す準備をした。私たち三人は一緒に通りへ出て、玄関先でウェミック氏は自分の道へ、ジャガーズ氏と私は別方向へ歩き出した。
その晩、私は何度も、ジャガーズ氏にもジェラード・ストリートにエイジドやスティンガーや何か癒やしになる存在がいてくれれば――と願わずにはいられなかった。二十一歳の誕生日に、「成年になる」こと自体が、彼のような警戒と疑いに満ちた世界ではあまり意味がなさそうだと思い知らされたのは、なんともやるせないことだった。彼はウェミック氏よりはるかに博識で聡明だったが、それでも私は千倍もウェミック氏を夕食に招きたかった。そしてジャガーズ氏は私だけでなく、ひどく気分を沈ませる存在だった。というのも、彼が帰った後、ハーバートは暖炉の火を見つめながら、自分は何か重罪を犯してその詳細を忘れてしまったのではと思うほど、落ち込みと罪悪感に苛まれたと口にしたからだ。
第三十七章
ウェミック氏のウォルワースでの気持ちを伺うのは日曜日が最適だと考え、私は次の日曜日の午後をキャッスル訪問に充てた。城壁の前に着くと、ユニオンジャックがはためき、跳ね橋が上がっていた。しかしこの挑戦的な構えにもひるまず、私は門のベルを鳴らした。するとエイジドが、実に穏やかに私を迎え入れてくれた。
「息子がね」と老人は跳ね橋を下ろしながら言った。「お客が来るかもしれないと気にしてましてね、すぐ散歩から帰るだろうと伝言していきました。息子は散歩もきちんとしていて、本当に何でも規則正しいんですよ」
私はウェミック氏のようにうなずき、二人で暖炉のそばに座った。
「息子さんと知り合いになったのは」と老人が陽気に手を温めながら言った。「事務所でですかな?」私はうなずく。「ほぉ! 息子は仕事ができると聞いていますが?」私は力強くうなずく。「そうですとも。仕事は法律関係ですよね?」私はさらに強くうなずく。「だからこそ驚くんですよ」と老人は言った。「息子は法律で育ったのではなく、ワインの樽職人で育ったのですから」
私はジャガーズ氏の評判について老人がどう思っているのか気になり、その名を大声で叫んでみた。すると彼は大笑いし、快活に「そりゃそうだ、ごもっとも」と返したので私はひどく困惑した。今に至るまで、彼が何を意味し、どんな冗談だと思ったのか、まったく見当がつかない。
いつまでもうなずき続けているわけにもいかず、私は彼の職業が「ワインの樽職人」だったのかと大声で尋ねた。何度もその言葉を繰り返しながら老人の胸を軽く叩いて問いかけるうちに、ようやく意図が伝わった。
「いや」と老人は言った。「倉庫業さ、倉庫業。最初はあっちで――」彼は煙突の方を指したが、恐らくリバプールを指していたのだろう。「それからロンドン市内でだ。だが難聴という持病がありまして――」
私はパントマイムで大いに驚いてみせた。
「――そうなんですよ、耳が遠い。それで息子が法律の道へ入り、私の面倒も見てくれるようになって、少しずつこの素晴らしい家を作り上げたんです。でもね、さっきの話に戻ると」と老人はまた大笑いしながら続けた。「だからこそ、そりゃそうだ、ごもっとも、というわけさ」
私は、私の知恵を絞っても彼ほど楽しませられる冗談が言えただろうかと密かに思っていたが、突然、煙突の横の壁からカチッという音がして、小さな木製の扉が「JOHN」と書かれて開いたので驚いた。老人が私の視線を追って、誇らしげに「息子が帰ってきた!」と叫んだので、二人で跳ね橋へ出た。
堀を挟んでウェミック氏が私に敬礼を送る様子は、どんな金を払っても見たいほど愉快だった。エイジドは跳ね橋を動かすのが嬉しくてたまらない様子だったので、私は手伝いを申し出ず、静かに見守った。ウェミック氏が渡ってきて、私をミス・スキフィンズに紹介した。
ミス・スキフィンズは木彫りのような外見で、ウェミック氏と同じく郵便局関係の仕事だった。年齢はウェミック氏より二、三歳若いくらいで、「持ち運びできる財産」を持っているように思えた。ウエストから上の服の仕立てが、前も後ろも子供の凧のようで、ドレスの色がややあまりにもオレンジ、手袋もやけに鮮やかな緑だった。しかし彼女は気立ての良い人で、エイジドへの思いやりも深かった。すぐに私は、彼女がこのキャッスルをよく訪れていることに気付いた。中に入ってウェミック氏の工夫に感心した旨を伝えると、彼は暖炉の反対側も見てほしいと言い、自ら消えた。するとまたカチッという音がして、「Miss Skiffins」と書かれた扉が開き、次いでミス・スキフィンズの扉が閉まるとジョンの扉が開く、さらに二つが同時に開き、また同時に閉じた。ウェミック氏が戻ってくると、私はその機械仕掛けに心から感心していることを伝えた。彼は「これはエイジドにとって楽しくて便利なんだ。それにね、ここを訪れる人で、これらの秘密を知っているのはエイジドとミス・スキフィンズと僕だけなんだ」と言った。
「ウェミックさんが全部、自分の発想で自分の手で作ったんですよ」とミス・スキフィンズが付け加えた。
ミス・スキフィンズがボンネットを外す間(彼女は夜の間ずっと緑の手袋をはめて、来客がいることを示していた)、ウェミック氏は私を外に誘い、冬の島の様子を見て回った。私は、これがウォルワースでの意見を伺う良い機会だと考え、すぐに切り出した。
私は慎重に考えた末、まるで初めて相談するかのように話を始めた。私はハーバート・ポケットのために心を砕いていること、彼との出会いと決闘、彼の家庭や人柄、そして生活の糧が父親頼みで不安定なことを語った。自分が未熟で無知だった時、どれほど彼の助けになったか、私はそれに恩返しができていないどころか、彼は私や私の「遺産」などない方がよかったのではとも感じていること、ミス・ハヴィシャムのことは遠い背景にぼかしつつ、自分が彼の将来の競争相手だったかもしれないこと、しかし彼の気骨ある人柄を信じていることを伝えた。そして、彼が私の若き友として大切な存在なので、私自身の幸運の一部を彼にも分けてあげたい、何かしら収入――たとえば年百ポンドを――彼に与えて希望と勇気を持たせ、小さな共同経営の道を徐々に切り開いてやりたいと相談した。ハーバートに気付かれず、世界で相談できるのは他にいないこと、迷惑だろうが信頼せずにいられないのは、そもそも君が私をここに連れてきたせいだ、と最後に肩に手を置いて頼んだ。
ウェミック氏はしばらく黙っていたが、やがて少し驚いたようにこう言った。「ピップさん、これは実に素晴らしいことだよ」
「なら、どうか手助けしてほしい」と私は言った。
「むむ、僕の分野じゃないな」とウェミック氏は首を振った。
「ここは君の仕事場じゃない」と私。
「そうだ、まさにその通りだ」と彼は返す。「ピップさん、考え帽をかぶってみよう。君の望みは段階的に実現できると思う。スキフィンズ(彼女の兄)は会計士で代理人だ。彼に頼んで動いてみるよ」
「何万回でも感謝する」
「いや、こちらこそ」と彼は言った。「私たちはあくまでも私的な立場だけど、ニューゲートの蜘蛛の巣みたいなものがあって、それを払拭してくれる話だ」
その後も同じ趣旨の会話を交わしてキャッスルへ戻ると、ミス・スキフィンズがお茶の準備をしていた。トーストを焼く大役はエイジドに任された。彼はあまりに熱心で、目玉が溶けそうなほどだった。これは名ばかりの食事ではなく、実に盛大な現実の宴だった。エイジドが作ったバターたっぷりのトーストの山は山積みで、その向こうに彼の姿がかすむほどだった。ミス・スキフィンズはたっぷりのお茶を淹れ、裏庭の豚まで興奮して宴に加わりたがるほどだった。
旗はしかるべき時に降ろされ、礼砲も鳴り響き、私はウォルワースの外界から見事に隔絶されたような気分だった。静寂を破るのは時折開くジョンとミス・スキフィンズの小窓だけで、それも慣れるまでは妙に気になった。ミス・スキフィンズの手際の良さから、毎週日曜夜は彼女がここでお茶をいれているのだろうと推測した。彼女の胸元のブローチ――まっすぐな鼻と新月を持つ女性の横顔――もウェミック氏が贈った「持ち運びできる財産」だと思った。
私たちはトーストをすべて平らげ、相応のお茶を飲み、とても温かく脂ぎった顔になった。特にエイジドは、まるで油を塗った部族の老酋長のようだった。少し休んだ後、ミス・スキフィンズは、日曜午後は家族のもとへ帰るらしい小間使いに代わって、控えめで上品な手つきで食器を洗った。そしてまた手袋をはめ、皆で暖炉を囲むと、ウェミック氏が「さあ、エイジド、新聞を読んでくれ」と促した。
ウェミック氏が言うには、これは恒例であり、エイジドにとっては大きな楽しみだそうだ。「謝らないよ」とウェミック氏。「彼にはそんなに楽しみが多くないからね、そうだろ、エイジド?」
「そうだとも、ジョン」と話しかけられて満足そうな老人。
「彼が新聞から顔を上げたら、時々うなずいてやれば王様みたいに幸せさ。さあ、エイジド、全員が注目してるよ」
「わかったとも、ジョン!」と、嬉々とした老人。
エイジドの朗読は、ウォプスル氏の大叔母の教室を思い出させたが、その声がまるで鍵穴から聞こえてくるようなのが愉快だった。ろうそくは近くに寄せ、新聞や頭が火に入らないよう注意深い監視が必要だったが、ウェミック氏は根気強く優しく見守っていた。エイジドは助けられていることに気づかず読み続け、私たちは彼が顔を上げるたび大いに感心してうなずいた。
ウェミック氏とミス・スキフィンズが並んで座り、私は影の隅にいたが、やがてウェミック氏の口がじわじわと長くなり、徐々にミス・スキフィンズの腰に腕を回そうとしているのが見えた。やがて彼の手がミス・スキフィンズの反対側に現れたが、その瞬間、ミス・スキフィンズは緑の手袋で鮮やかにそれを止め、まるで服飾品を脱ぐように腕をほどき、きちんと前のテーブルに置いた。彼女の落ち着いた所作は見事で、もし心ここにあらずでなければ、機械的に行っているのではと思えるほどだった。
やがてまたウェミック氏の腕が消えていき、口も広がり始める。しばらくしてまた手がミス・スキフィンズの反対側に現れると、彼女は再び、今度はボクサーのように的確に、それをほどいてテーブルに戻した。テーブルが徳の道だとすれば、エイジドの朗読中、ウェミック氏の腕は徳の道から外れてはミス・スキフィンズによって引き戻されていた。
やがてエイジドは朗読しながら軽く居眠りした。ウェミック氏は小さなケトルとグラスの載った盆、赤ら顔の社交的な聖職者のような黒い瓶を取り出した。それで皆、温かい飲み物を楽しみ、エイジドもすぐ目を覚ました。ミス・スキフィンズが混ぜ、彼女とウェミック氏は同じグラスで飲んでいた。もちろん私はミス・スキフィンズを家まで送るほど無神経ではなく、むしろ先に辞去するのが礼儀と考え、エイジドに心から別れを告げて帰った。
一週間も経たぬうちに、ウォルワースからウェミック氏の手紙が届いた。「私的な件について多少進展したので、また話に来てほしい」とある。そこで私は再びウォルワースへ行き、また何度も市内で会い、Little Britain付近では決してこの話題を口にしなかった。結論として、我々は若くて有望な商人・海運仲買人を見つけた。彼は有能な協力者と資本を必要とし、将来的には共同経営者を求めることになる。彼と私は秘密の契約を交わし、私は五百ポンドの半額を手付けで支払い、その他の支払いも取り決めた――いくらかは収入から期日払いで、いくらかは財産の相続時に支払う予定だった。交渉はミス・スキフィンズの兄が担い、ウェミック氏は影で全てを指揮したが表に出ることはなかった。
全体が巧妙に運ばれたので、ハーバートは私が関与しているとは夢にも思わなかった。彼がある日、晴れやかな顔で帰宅し、若い商人クラリカーと知り合いになり、クラリカーが自分に好意的で、ついに道が開けたと大ニュースのように語った日のことは忘れられない。日々希望が大きくなり顔が輝くにつれ、彼は私をますます親愛な友だと思ったことだろう。私も彼が幸せそうな姿を見るたび、勝利の涙をこらえるのが大変だった。遂に話がまとまり、ハーバートはその日クラリカーの会社に入社し、何時間も幸福と成功を語り合った夜、私は寝床で本気の涙を流した――私の「遺産」が誰かの役に立ったのだと。
私の人生の大事件、転機がここに訪れようとしている。しかし、その話に入る前に、そしてその出来事がもたらす変化のすべてに進む前に、エステラについて一章だけ割きたい。私の心を長く満たしてきたテーマに、これだけしか与えられないのは少ないが。
第三十八章
もし私が死んだ後、リッチモンドのグリーン近くにあるあの古い家が幽霊に取り憑かれることがあれば、それはきっと私の幽霊に違いない。エステラがそこに住んでいた頃、私の内なる落ち着かない魂が、幾晩も幾昼夜もその家をさまよい続けていた。私の体がどこにあろうと、私の心は常にその家の周囲を彷徨っていた。
エステラが置かれていたのはブランドリー夫人という名の未亡人の家で、彼女にはエステラより数歳年上の娘がいた。母親は若々しく見え、娘は老けて見えた。母親は血色が良く、娘は黄色味がかっていた。母は享楽的、娘は信心深さを標榜していた。彼女たちはいわゆる良家で、交際範囲も広かったが、エステラとの間に心の通い合いはほとんどなかった。ただ、お互いに必要だという了解のもとで暮らしていた。ブランドリー夫人はミス・ハヴィシャムの隠遁前の友人だった。
ブランドリー夫人の家の中でも外でも、私はエステラに苦しめられ得るありとあらゆる拷問を味わった。彼女との関係は親しさを持ちながらも好意には至らず、私を混乱させた。彼女は私を、他の求婚者をからかう道具として利用し、私たちの親しさでさえも私の献身を蔑ろにする手段とした。もし私が彼女の秘書や家令、異母兄弟、貧しい親戚、あるいは彼女の許嫁の弟であっても、もっと絶望的にしか思えなかっただろう。エステラと名前を呼び合うことさえ、私の苦しみを増すばかりで、他の求婚者たちも同じように気が狂いそうだったに違いないが、私にはそれが確実だった。
彼女には尽きることのない求婚者がいた。私が嫉妬深くなりすぎて全員を求婚者だと思ってしまったにせよ、それを抜きにしても十分すぎるほど男たちがいた。
私はリッチモンドで彼女によく会い、都でも頻繁に噂を聞いた。しばしば彼女やブランドリー家をボートに乗せた。ピクニック、祝祭日、芝居、オペラ、音楽会、パーティー、ありとあらゆる楽しみがあり、私はそのすべてでエステラを追いかけた――だがどれも私には苦しみだった。私は彼女のそばにいた時間、ただの一時たりとも幸福を感じたことはなかった。それでも一日二十四時間、彼女と一緒にいられる幸福を夢見てばかりいた。
この時期――それは当時の私にはずいぶん長く感じられた――エステラは常に、私たちの関係が無理やりであることを示す調子に戻る癖があった。しかし時にはその調子や他の多くの調子もぴたりと止み、私を哀れむような素振りさえ見せた。
ある晩、リッチモンドの家の薄暗い窓辺で私たちが離れて座っていたとき、エステラはそんな調子をふと止めて言った。
「ピップ、ピップ、あなたは決して警告を受け入れないの?」
「何の警告を?」
「私からのよ」
「あなたに惹かれないように、という警告かい、エステラ?」
「そうよ、って聞くの? それが分からないなら、あなたは盲目だわ」
私は「恋は盲目」と言い返したかったが、いつも自制された。というのも、彼女がミス・ハヴィシャムの命令に逆らえないことを知っているのに、私が彼女に気持ちを押し付けるのは卑怯だと思ったからで、それも私の苦しみの一つだった。私は常に、彼女自身が自覚している私の不利を誇り高く受け止めているのでは、と恐れていた。
「とにかく」と私は言った。「今回は警告なんて受けていない。君が呼んでくれたんだから」
「そうね」とエステラは、いつものように冷ややかな微笑みで言った。
しばらく外の夕暮れを見つめた後、彼女は続けた。
「ミス・ハヴィシャムが、私を一日サティス・ハウスに呼び寄せたい時期がきたの。あなたが私を連れて行き、また迎えにきてくれる? 彼女は私に一人旅をさせたくないし、私の侍女を受け入れるのも嫌がるわ。そういう人たちに噂されるのが、たまらなく嫌なのよ。できるかしら?」
「できるか、って? エステラ!」
「じゃあ、明後日お願いね。すべての費用は私の財布から出してね。それが条件よ、いい?」
「従うしかない」と私は言った。
私がこの訪問や同様の訪問について受けた準備はこれだけだった。ミス・ハヴィシャムからは一度も手紙をもらったことがなく、筆跡すら目にしたことがない。私たちは二日後に出発し、私が初めて彼女に出会ったあの部屋で彼女を見つけたが、サティス・ハウスに変化はなかった。
彼女は以前にも増してエステラに執着していた。私はあえて「執着」と言うが、彼女の眼差しや抱擁には、何か本当に恐ろしいものが感じられた。彼女はエステラの美しさと言葉と所作に固執し、自身の震える指を噛みながらエステラを見つめていた。そのさまは、自分で育てた美しい生き物を食い尽くさんばかりだった。
エステラから彼女は私へと視線を移し、心の傷を抉るような鋭いまなざしで「彼女にどう扱われている、ピップ、どう扱われている?」と、エステラの前でも熱心に尋ねた。しかし夜、三人で揺れる火を囲んだときは、さらに異様だった。エステラの手を腕に絡めて握りしめ、彼女が定期的に送る手紙を引き合いに出しながら、エステラが魅了した男たちの名や身分を執拗に聞き出し、その名簿を読み上げるミス・ハヴィシャムの姿は、傷つき病んだ精神が凝縮されていた。彼女はもう一方の手を杖に置き、顎を乗せ、病的な輝きを放つ目で私を睨みつけた。その様はまるで亡霊のようだった。
私は、その光景に惨めさを感じ、従属の苦さや屈辱さえ覚えつつも、エステラがミス・ハヴィシャムの復讐のために男たちを苦しめる道具として育てられており、それが終わるまでは私のものにならないのだと悟った。送り出す際、彼女が他の求婚者の手の届かない存在であることを確信し、皆が賭けて負けるよう仕向けていることも見て取れた。私自身も、いつか受け取れるはずの賞品を目前にして拷問されているのだとわかった。だからこそ、私が長く待たされ、元後見人もこの計画に正式には関わりたがらなかったのだ。今まさにミス・ハヴィシャムを目の前に見て、また常に心に焼きついてきた彼女を思い浮かべ、彼女の人生が陽の当たらない暗く病んだ家の影として私の目に映った。
彼女の部屋を照らす燭台は壁掛けで高い位置にあり、滅多に換気されない部屋の空気の中で鈍く静かに燃えていた。私はそれらと、その薄暗い明かり、止まった時計、テーブルや床に散乱するウェディングドレスの残骸、そして火で大きく壁や天井に映し出された彼女の幽霊のような姿を見て、心の中で組み立てた全ての思考がそのまま現実となって目の前に返されているのを感じた。私はさらに、渡り廊下の向こうの大広間を思い描き、テーブルの中央から垂れ下がる蜘蛛の巣、クロスの上を這う蜘蛛、パネルの向こうへ走る鼠の足跡、床を徘徊する甲虫の動きに、まるでそれが書き記されているかのように感じた。
この訪問の際、初めてエステラとミス・ハヴィシャムの間で鋭い言い争いが起こった。
私たちは先ほどのように暖炉のそばに座っていた。ミス・ハヴィシャムがエステラの腕を絡めたまま、手を握っていたが、エステラは徐々に身を引き始めた。彼女は以前にも誇り高い苛立ちを見せ、強烈な愛情を耐えているだけで応じることはなかった。
「何だい!」とミス・ハヴィシャムは目を光らせて言った。「私に飽きたのかい?」
「自分自身に少し飽きただけよ」とエステラは腕を外し、大きな暖炉のマントルピースに寄りかかりながら火を見つめた。
「本当のことを言いなさい、この恩知らず!」ミス・ハヴィシャムは杖で床を打ち鳴らしながら叫んだ。「私に飽きたんだろう!」
エステラは何事もないように彼女を見つめ、再び火に目を落とした。その優雅な立ち姿と美しい顔には、もう一方の激情に対して冷淡な無関心が浮かび、むしろ残酷なほどだった。
「冷たい石みたいな子だ!」ミス・ハヴィシャムは叫んだ。「冷たい、冷たい心!」
「何ですって?」とエステラは、相変わらずの態度で体は動かさず、目だけを動かして答えた。「私が冷たいと責めるの? あなたが?」
「違うかい!」とミス・ハヴィシャムは激しく返した。
「あなたは知っているはずよ」とエステラは言った。「私はあなたが作ったものよ。賞賛でも非難でもすべて受け取って。成功も失敗も、つまりこの私も」
「ああ、見てごらん、見てごらん!」ミス・ハヴィシャムは苦々しく叫んだ。「育てたこの家の炉辺で、なんて冷たく、恩知らずな子なんだ! 傷だらけの胸に彼女を迎え、長年の愛情を注いできたのに!」

「せめて私はその契約に加わった覚えはないわ」とエステラは言った。「もし契約時に歩いたり話せたりしたなら精一杯だったはず。けれど何を望むの? あなたはとても良くしてくださったし、全てをあなたに負っています。何を望むの?」
「愛だ」とミス・ハヴィシャムは答えた。
「持っています」
「持っていない」とミス・ハヴィシャムは言った。
「養母さま」とエステラは、その優雅な態度を崩さず、声を荒げることもなく、怒りも優しさも見せずに返した。「私はあなたに全てを負っています。私が持つものはすべて自由にどうぞ。与えられたものは何でもまたお返しします。それ以上は何も持っていません。与えなかったものを求められても、感謝と義務では不可能です」
「愛を与えたことがないとでも!」ミス・ハヴィシャムは私の方を向いて狂おしく叫んだ。「燃え上がる愛を、常に嫉妬と痛みと共に与えてきたのに、彼女はこんな風に私に話す! 私を狂人と呼ばせて、狂人と呼ばせて!」
「どうして私があなたを狂人と呼ぶ必要があるでしょう」とエステラは返した。「私以上にあなたの意図を知る者がいますか。私以上にあなたの確かな記憶を知る者がいますか。私はずっとあの炉辺の小さな椅子に座って、あなたの顔を見上げて教えを受けてきました。あなたの顔が怖かった頃も!」
「すぐに忘れ去った!」ミス・ハヴィシャムは呻いた。
「いいえ、忘れていません」とエステラは返した。「覚えています。私があなたの教えに背いたことがありますか。あなたの教訓をおろそかにしたことがありますか。この胸に、あなたが排除したものを受け入れたことがありますか。私に公平でいてください」
「なんて誇り高い子だ!」ミス・ハヴィシャムは両手で白髪をかき上げた。
「誇りを教えたのは誰?」とエステラは返した。「私が学んだ時、誰が褒めてくれた?」
「なんて冷たい子だ!」ミス・ハヴィシャムはまたしてもその手振りで呻いた。
「冷たさを教えたのは誰?」とエステラ。「私が学んだ時、誰が褒めてくれた?」
「でも私にまで誇り高く冷たくするなんて!」ミス・ハヴィシャムはほとんど叫ぶように腕を広げた。「エステラ、エステラ、私にまで誇り高く冷たくするなんて!」
エステラは一瞬、穏やかな驚きの表情でミス・ハヴィシャムを見つめたが、それ以上は動揺せず、間が過ぎるとまた火に視線を戻した。
「なぜ、離れていた私が会いに来ているのに、そんなに理不尽になるのか、私には分かりません」エステラは沈黙の後、目を上げて言った。「私はあなたの苦しみやその原因を忘れたことはありません。あなたやあなたの教育に不実だったこともありません。自分で責めるような弱さを見せたこともありません」
「私の愛に応えるのが弱さになるとでも!」ミス・ハヴィシャムは叫ぶ。「でも、そうよ、彼女はそう言うだろう!」
「私は思い始めているわ」とエステラはしばらく静かに驚いたあと、物思いにふけるように言った。「どうしてこうなったのか、ほとんど理解できる気がする。もしあなたが、養女をずっとこの部屋の暗い閉ざされた中だけで育てて、彼女が一度もあなたの顔を見ることのない光、つまり昼間というものの存在すら教えずに育てたとしたら――もしそうしておいて、ある目的のために彼女に昼間を理解し、知ってもらいたいと思ったのなら、きっとがっかりして腹も立ったでしょう?」
ミス・ハヴィシャムは頭を手で抱えるようにして、椅子の上で身を揺すりながら低くうめいていたが、返事はしなかった。
「それとも」とエステラは続けた。「――こっちの方が近い例だけど――もしあなたが、彼女の知性が芽生えたその瞬間から、その全力を尽くして昼間というものが存在するのだと教え込んだけれど、それが彼女の敵であり、破滅をもたらすものだと教え、常にそれに背を向けなければならない、と。昼間はあなたを破滅させ、彼女もまたそうなるのだと。そして、もしそうやって育てたあとで、何かの目的で彼女に当たり前のように昼間を受け入れてもらいたいと望んだけど、彼女にはそれができなかったとしたら、そのときもやはりがっかりして腹が立ったでしょう?」
ミス・ハヴィシャムは(私には顔が見えなかったので、そう聞こえただけかもしれないが)じっと耳を傾けているようだったが、やはり返事はなかった。
「だから」とエステラは言った。「私は、作られたままの自分として受け入れてもらうしかない。成功は私のものではないし、失敗も私のものではない。でも、その両方が合わさって私ができているの。」
ミス・ハヴィシャムはいつの間にか、どうやってそうなったのか私にはよくわからないが、色あせた花嫁道具の遺品が散乱する床の上に身を落ち着けていた。私はその隙を見て――ずっとそういう機会をうかがっていた――手でエステラに彼女を見ているよう合図し、部屋を出た。私が去るとき、エステラは大きな暖炉のそばに立ったままで、ずっとそうしていた。ミス・ハヴィシャムの灰色の髪は他の花嫁の残骸とともに床に広がり、見るも無残な光景だった。
私は心が沈んだまま、星明かりの中を一時間以上も中庭や醸造所、廃れた庭のあたりを歩き回った。ようやく勇気を出して部屋に戻ると、エステラがミス・ハヴィシャムの膝元に座り、今にも崩れそうな古い衣服のほつれを繕っていた。その様子は、後に大聖堂で見かけた色あせた古い旗のぼろきれを見るたびに思い出す光景だった。そのあと、エステラと私は昔のようにカードをした――もっとも、今ではお互い腕前も上がり、フランス式のゲームを楽しんだ――そうして夜は過ぎ、私は寝室へと向かった。
私が寝たのは、中庭を挟んだ別棟だった。これはサティス・ハウスで初めて横になる夜だったが、眠りは私のもとを決して訪れなかった。無数のミス・ハヴィシャムが私を悩ませた。枕のこちら側にも、あちら側にも、ベッドの頭の方にも、足元にも、更衣室の半開きの扉の向こうにも、更衣室の中にも、上の部屋にも、下の部屋にも――いたるところに彼女がいた。夜がなかなか二時に近づかない頃、私はとうとう、ここで横になることはもう耐えられないと思い立ち、起き上がることにした。そこで服を着て中庭を横切り、長い石造りの廊下へ出て、外の中庭まで出て頭を冷やそうとした。だが廊下に入るや否や、ロウソクを消してしまった。というのも、ミス・ハヴィシャムが幽霊のようにすすり泣きながら歩いていくのが見えたからだ。私は少し離れて彼女のあとを追い、彼女が階段を上っていくのを見た。彼女は手に裸のロウソクを持っていて、それはきっと自分の部屋の燭台から取ってきたのだろうが、その光に照らし出された彼女はこの世のものとは思えない姿だった。私は階段の下に立って、祝宴の間のカビ臭い空気を感じたが、彼女が扉を開けるのは見えなかった。そして彼女がその部屋の中を歩き、自分の部屋へ、また元の部屋へと移動し、絶え間なくすすり泣き続けるのが聞こえた。しばらくして、私は暗闇の中で外に出ようとしたり戻ろうとしたが、どちらもできず、ようやく夜明けの光が差し込んで手探りで場所を確かめられるまで、身動きが取れなかった。その間ずっと、階段の下に行けば彼女の足音が聞こえ、上をロウソクの光が通り過ぎ、止まぬすすり泣きが響いていた。
翌日私たちが出発するまで、彼女とエステラの間のわだかまりが蒸し返されることはなかったし、その後も同じような機会にそれが再発することはなかった――私の記憶する限り、同じような機会は四度あった。しかし、ミス・ハヴィシャムのエステラに対する態度が変わることはなかったが、私はその中に以前にはなかった「恐れ」のようなものが混じり始めていると感じた。
この人生の一頁をめくるにあたって、ベントレー・ドラムルの名を書かずに進むことはできない。できるものなら、どれだけ喜んでそうしたことか。
あるとき、フィンチの仲間たちが勢ぞろいし、例によって誰もが誰とも意見を合わせずに「親睦」を深めていたが、議長役のフィンチが「本日はドラムル氏がまだ女性に対して献杯していない」として議事を進行した。これは会の厳粛な規則であり、その日は奴の番だった。デカンタが回されるなか、彼が私を憎々しげに睨んだような気がしたが、我々の間に友情などなかったのだから当然かもしれない。だが、彼が「エステラ!」と献杯を呼びかけたとき、私は憤慨して驚いた。
「エステラって誰だ?」と私は言った。
「お前の知ったことか」とドラムルが返した。
「どこのエステラだ? どこの者か言う義務があるはずだ」と私は言った。フィンチの規則ではそう決まっていた。
「リッチモンドのエステラだ、諸君。そして比類なき美人だ」とドラムルは私を無視して言った。
よりによって、あの取るに足らぬ馬鹿野郎が美を語るなど! 私はハーバートに小声で囁いた。
「僕はそのご婦人を知っているよ」とハーバートが乾杯が済んだ後、テーブル越しに言った。
「本当に?」とドラムル。
「僕も知っている」と私は顔を赤くして言い添えた。
「本当に? おお、神様よ!」とドラムル。
これが、あの鈍重な野郎が繰り出せる唯一の反撃――グラスや陶器を投げる以外には――だったが、私はそれが機知に富んだ皮肉であったかのように腹を立て、すぐに立ち上がって「知らない女性を持ち出して一席設けるとは、名誉あるフィンチの無礼も甚だしい」と抗議した。我々はいつも「グローヴに下る」と議会風に言っていたが、そのグローヴで、何も知らぬ女性を提案するなど無礼きわまりないと。するとドラムルは立ち上がり、「その意味は何だ?」と詰め寄ってきた。私は極端な返答で「僕がどこにいるかわかっているだろう」と返した。
このあとクリスチャンの国で果たして流血なしに済ませられるのかどうか、フィンチたちの意見は割れた。議論が白熱し、少なくとも六人が六人に「自分がどこにいるかわかっているだろう」と言い合う始末だった。しかし最終的に決まったのは(グローヴは名誉の法廷なのだから)、もしドラムル氏が女性から「知り合いである」との証明書を持参できれば、ピップ氏は「つい感情的になったこと」を紳士として、フィンチとして遺憾の意を表すること、とされた。翌日がその提出日となり(誇りが冷めぬうちに)、ドラムルはエステラの手による簡潔な証明――何度か彼女と踊ったことがある、という内容――を持参した。私としては「つい感情的になったこと」を遺憾とし、「どこにいるかわかる」などという主張は撤回せざるを得なかった。その後、ドラムルと私は一時間ほど鼻息を荒げあい、仲間たちは無差別な反論を繰り返し、最終的には親睦が著しく進んだ、ということになった。
私は軽く語っているが、私にとっては決して軽いことではなかった。というのも、卑劣で不器用で陰気な奴――人並みにも劣る奴にエステラが好意を見せていると考えるだけで、言いようもなく苦痛だったからだ。今でも、私のエステラへの想いは純粋で無私の情熱だったからこそ、彼女があんな奴に身を屈するのが耐えられなかったのだと思っている。無論、誰であれエステラが好意を示していれば私は苦しんだだろうが、より価値ある相手ならば、その苦しみもまた違ったものになったろう。
調べてみるのは簡単だったし、私はすぐに、ドラムルがエステラの後を追い始めたこと、そして彼女がそれを許していることを知った。ほどなくして、彼はいつも彼女を追いかけていたし、私と彼は毎日顔を合わせることになった。彼は鈍く粘り強く食らいつき、エステラは時に励まし、時に冷たくあしらい、時に持ち上げ、時にあからさまに見下し、親しげにしたかと思えば、彼が誰だったかも忘れたような態度を取った。
ジャガーズ氏が「蜘蛛」と呼んだあの男は、待ち伏せに慣れていたし、一族ゆえの忍耐強さも持っていた。そのうえ、彼には金と家系への愚鈍な自信があり、それが集中力や決意の代わりになることもあった。だからこそ、蜘蛛は粘り強くエステラを見張り、多くの輝く虫たちよりも粘り抜き、絶妙のタイミングで姿を現したものだった。
リッチモンドで開かれたあるアセンブリー・ボールで(当時はほとんどの場所でアセンブリー・ボールがあった)、エステラは他の美人たちを圧倒していたが、その夜ドラムルは彼女にまとわりつき、しかも彼女が容認しているかのようだったので、私は彼についてエステラに話そうと決意した。次の機会をうかがい、それはブランドリー夫人が彼女を迎えに来るのを待つ間、エステラが花に囲まれて座っていたときだった。私はいつものように、その場に付き添っていた。
「疲れた?」と私は尋ねた。
「少しね、ピップ」
「無理もないよ」
「むしろ、私は疲れている場合じゃないわ。寝る前にサティス・ハウス宛の手紙を書かないといけないもの」
「今夜の勝利を報告するの?」と私は言った。「でも、たいした勝利じゃないよ、エステラ」
「何のこと? そんなことがあったなんて知らなかったわ」
「エステラ、あそこにいる男を見てごらん、僕らを見ているよ」
「なぜ彼を見る必要があるの?」とエステラは私の方を見たまま返した。「あなたの言葉を借りれば、あそこにいるあの男に、私が注目すべき理由があるの?」
「まさにそれを君に問いたいんだ。だって、彼は今夜ずっと君の周りをうろついていた」
「蛾とか、醜い生き物はいろいろ、ロウソクの灯りにたかるものよ」とエステラは彼にちらりと視線をやった。「ロウソクはそれを防げるの?」
「いや」と私は返した。「でも、エステラはそれを防げるのでは?」
「そうね!」と彼女はしばらくして笑い、「たぶん、そう。あなたの好きなように」
「でも、エステラ、僕の話を聞いてくれ。ドラムルのように皆が軽蔑する男を君が励ますのは辛いんだ。君も彼が軽蔑されているのを知っているじゃないか」
「それで?」と彼女。
「彼は中身も外見も不格好だ。狭量で気難しく、陰気な馬鹿者だ」
「それで?」
「彼には金と馬鹿げた家系以外に取り柄はない。そうだろう?」
「それで?」とまた彼女は言い、そのたびに彼女の美しい目は大きく見開かれた。
その一語を超えるために、私は彼女の「それで?」をそのまま強調して繰り返し、「それで――それが僕を苦しめる理由なんだ」と言った。
もし彼女が私を苦しめるためにドラムルに好意を見せているのなら、まだ心の整理もついただろう。だが、彼女はいつものように、私を完全に蚊帳の外に置いてしまったので、とてもそうは思えなかった。
「ピップ」とエステラは部屋を見渡しながら言った。「あなたがどう感じるかなんて気にしないで。それが他の誰かにどう影響するか、あるいはそういう意図があるかもしれないけど、議論する価値なんてないわ」
「いや、あるよ。だって、君が“あんな下品な男に自分の魅力を無駄にしている”と言われるのが我慢できないんだ」
「私は我慢できるわ」とエステラ。
「そんなに誇り高く、頑なにならないでくれ、エステラ」
「この一息で私を誇り高くて頑なだと言い!」とエステラは手を広げた。「さっきは私が下品な男に身を落としていると責めたくせに!」
「君は間違いなくそうしてる」と私はやや早口で言った。「今夜だって、僕に見せたことのない表情や微笑みを彼に見せていたじゃないか」
「じゃあ、あなたは私にどうしてほしいの?」とエステラは突然、真剣で(少なくとも怒っているような)表情で向き直った。「あなたを欺いて罠にかけてほしいの?」
「じゃあ、君は彼を欺き、罠にかけているのかい?」
「ええ、そして他の多くの人も――あなた以外の全員を。ほら、ブランドリー夫人が来たわ。もう言わない」
こうして、私の心を満たし、繰り返し痛めつけてきたこの主題に一章を割き終えた今、私は妨げられることなく、さらに長い間私の上に迫っていた出来事――私がエステラの存在を知るより以前、彼女の幼い知性がミス・ハヴィシャムの衰えた手によって初めて歪められ始めた日々から準備されてきた出来事――へと進む。
東洋の物語では、征服の絶頂で玉座の上に落ちる予定の重い石板が、長い年月をかけて採石され、天井に据えられ、支える綱が岩の中を何里も貫いて通され、ついに夜中、王が起こされて斧を手渡され、それで綱を断ち、石板が落ちてくる。私の場合も同じだった。近くも遠くも、終わりに向けての全ての準備が整い、一瞬にして打撃が下され、私の拠り所の屋根が崩れ落ちたのだった。
第三十九章
私は二十三歳になっていた。自分の「期待」について新たな情報は何ひとつ得られず、誕生日も一週間過ぎていた。バーナード・インを離れて一年以上になり、今はテンプルに住んでいた。私たちの部屋はガーデン・コート、川沿いにあった。
ポケット氏と私は、元の関係とは少し違ってしまったものの、友情は変わらなかった。相変わらず何一つ定職につけずにいたが――それは今の中途半端な立場からくる落ち着かなさによるものと信じたい――読書には熱中し、毎日決まった時間を本に費やしていた。ハーバートの件は相変わらず進行中で、私の生活も、前章の終わりに記した通りだった。
ハーバートは商用でマルセイユに旅立っていた。私は独りで、孤独感に沈んでいた。不安と焦燥に苛まれ、明日か来週には道が開けると望みながら、ずっと裏切られ続けていた。陽気な友の顔と機知に富んだ応答が、ひどく恋しかった。
天気はひどいものだった。嵐と雨、嵐と雨、泥、泥、泥――どの通りも泥でいっぱいだった。日々、重く厚い雲が東からロンドンに押し寄せ、今なお押し寄せていた。まるで東の果てに永遠の雲と風があるかのように。あまりにも突風が強く、町中の高い建物の屋根の鉛が吹き飛ばされ、郊外では木々がなぎ倒され、風車の帆がもぎ取られ、海岸では難破と死の報せが届いていた。暴風雨が吹き荒れるなか、私が本を読み始めたその日が、いちばん酷い天気だった。
今ではテンプルもあの頃とは違い、孤独な雰囲気は薄れ、川にもあそこまで無防備ではない。私たちは最後の棟の最上階に住んでいて、川を遡る風が家をまるで大砲の一斉射撃か、海の大波のように揺らしていた。雨が窓に打ちつけると、私は本から顔を上げ、嵐にさらされた灯台の中にいるかのような気がした。ときおり、煙突から煙が逆流してきて、こんな夜外に出たくないと言わんばかりだった。戸口を開けて階段を見下ろすと、階段のランプは吹き消されていた。窓の黒いガラス越しに手で顔を覆いながら見ても(あんな風雨の中、窓を少しでも開けるなんてとても無理だった)、中庭のランプは消え、橋や岸辺の灯りも震え、川の船の石炭の火も、赤熱したしぶきのように雨の中を風にあおられて流されていった。
私は時計を机の上に置き、十一時になったら本を閉じるつもりで読書を続けていた。ちょうど本を閉じると、セントポールや市内の多くの教会の時計が鳴り出した――先導するもの、伴奏するもの、遅れて鳴るもの。だがその鐘の音は風にかき消され、不思議に歪んで聞こえた。私はその音に耳を傾け、風がそれをどう破っていくか考えていたとき、階段で誰かの足音が聞こえた。
どんな神経質な妄想が、私に死んだ姉の足音と結びつけさせたかはどうでもいい。すぐにその思いは過ぎ去り、私は再び耳を澄ませた。足音は途中でつまずくように聞こえた。階段の明かりが消えているのを思い出し、私は読書用ランプを手に階段の上に出た。下にいる誰かは、私の明かりを見て立ち止まったようで、静まり返っていた。
「誰か下にいるのか?」と私は呼びかけ、下を覗き込んだ。
「います」と闇の中から声がした。
「何階を探している?」
「最上階。ピップさん」
「それが私だ――なにかあったのか?」
「いいえ、なんでもありません」とその声は返し、男は上がってきた。
私はランプを手すりにかざして立ち、男はゆっくりその光の中に入った。そのランプは本用のもので、光の輪はごく狭かった。そのため彼はほんの一瞬だけ光に入って、すぐまた出ていった。その一瞬、私は見知らぬ顔が私を見上げ、何とも言えぬ感動と満足の表情を浮かべているのを見た。
男の動きに合わせてランプを向けると、彼はざっくりした海の旅人のような服装で、長い鉄灰色の髪をしていた。年は六十ほど。筋骨たくましく、天候に焼けて肌が荒れていた。最後の二、三段を上がってランプの光の中に二人が収まったとき、私は呆然とした驚きとともに、彼が両手を差し出しているのを見た。
「ご用件は?」と私は尋ねた。
「ご用件?」彼は繰り返し、立ち止まった。「ああ、そうだ。ご説明します、よろしければ」
「中に入りたいのですか?」
「ええ、入りたいんです、ご主人」
私は冷ややかな口調で問いかけてしまった。なぜなら彼の顔に浮かぶ明るい満足げな認識が、まるで私にもそれを返してほしいと期待しているようで、腹立たしく思えたからだ。それでも私は彼を部屋に案内し、ランプをテーブルに置いて、できるだけ丁寧に事情を説明するよう促した。
彼は部屋を見回し、まるで自分にも何か関わりがある物を眺めているような、不思議な喜びの表情を浮かべていた。そして粗末な外套と帽子を脱いだ。その頭は深く刻まれて禿げ上がり、鉄灰色の長い髪が両脇にだけ生えていた。だが、それでも私は彼が何者かは分からなかった。むしろ次の瞬間、またしても両手を差し出されて、ますます謎が深まった。
「何のつもりだ?」私は半ば彼が狂人ではないかと疑いながら言った。
彼は私を見るのをやめ、ゆっくり右手で頭を撫でた。「遠くからずっと楽しみにしてきたんだが、がっかりだ……でもお前は悪くない、誰のせいでもない。少しだけ、待ってくれ。半分だけでいい、頼む」
彼は暖炉前の椅子に腰かけ、両手で額を覆った。私は彼を注意深く見つめ、少し身を引いたが、それでも彼が誰かは思い出せなかった。
「近くに誰かいるかい?」と彼が肩越しに言った。
「なぜ、夜中に私の部屋に来た見知らぬ人間がそんなことを聞く?」と私は返した。
「お前は根性あるな」と彼は、全く理解できず、しかも苛立たしい愛情をこめて首を振った。「立派な青年になった! でも俺には触るな、あとで後悔するぞ」
私は彼の意図を察して思いとどまった――私は彼を知っていた! それでも一つの特徴も思い出せなかったが、私は彼を知っていた! もし風と雨が時を飛び越え、全てをなぎ払って、私たちが初めて墓地で対面したあの場所に私たちを戻したとしても、私はこれ以上にはっきり彼――あの囚人――を見分けることはなかっただろう。ポケットからヤスリを出して私に見せる必要も、首の手拭いを外して頭に巻く必要も、両腕で自分を抱きしめ、部屋を震えながら歩き回り、認識を求めて振り返る必要もなかった。今や私は彼を見分けていた。それなのに、少し前までは彼だと疑いさえしなかったのだ。
彼は私の元に戻り、また両手を差し出した。私は茫然自失してどうすべきか分からず、しぶしぶ彼に手を差し出した。彼は力強くそれを握り、唇に押し当て、まだ手を離さなかった。
「お前は立派だった、坊や。立派だった、ピップ! 俺は決して忘れなかった!」
彼の態度が、まるで私を抱きしめようとするかのように変わったとき、私は彼の胸に手を当てて押しやった。
「待て!」と私は言った。「近づくな! 俺が子供のころにしたことに感謝しているなら、その感謝は生き方を改めることで示してくれたと信じたい。もし感謝のためだけに来たのなら、それは必要なかった。だが、どんな気持ちでここまで来たかは分からないが、その善意には応えたい。しかし、君も分かるだろう――私は――」
彼のじっとした視線があまりにも異様で、言葉が途中で止まってしまった。
「さっき言いかけてたな」と彼は、しばらく沈黙したのちに言った。「きっと分かるだろう、って。何を分かるべきなんだ?」
「昔の偶然の関わり合いを、今この状況で再び持ちたいとは思わないということだ。君が悔い改め立ち直ったのなら嬉しいし、それを君にも伝えたい。私に感謝したいと考えて来てくれたことは嬉しいが、私たちはやはりまったく違う道を歩んでいる。君は濡れているし、疲れているようだ。何か飲むか?」
彼は首に手拭いをゆるく巻き直し、鋭い目つきで私を観察しながら、手拭いの端を噛んでいた。「そうだな」と彼はまだその端を口にくわえたまま、「飲みたい(ありがとう)、出発前に」
サイドテーブルにはすでに用意があった。それを暖炉そばのテーブルに運び、何がいいか尋ねた。彼はボトルの一つを無言で指さし、私はホットラムのお湯割りを作った。手を震わせまいとしたが、彼が椅子にもたれ、手拭いの端を口にぶら下げたまま私を見ている様子は、どうにも平静を保てなかった。ついにグラスを差し出すと、彼の目には涙が溢れていた。
私はその間ずっと立っていて、早く帰ってほしいという気持ちを隠そうとしなかった。だが、男の柔らかくなった表情に、私は少し心を打たれ、わずかな自責の念が湧いた。「さっきはきついことを言ったかもしれない」と私は慌ててグラスに何か注ぎ、自分も椅子を引いて座りながら言った。「悪気はなかったし、もしそう聞こえたなら申し訳ない。君の幸せを願っている!」
私がグラスを口に運ぶと、彼は驚いたように手拭いの端を落とし、手を差し出した。私はそれを握り、彼は飲み干してから、袖で目と額を拭った。
「どうやって暮らしてきたんだ?」と私は聞いた。
「羊飼いや家畜商、他にも何でもやった、あっちの新世界でな。ここから何千マイルも荒れた海の向こうで」
「うまくやれたのか?」
「実にうまくやった。俺と一緒に渡った奴らも悪くはないが、俺ほどの者はいない。俺は有名なんだ」
「それはよかった」
「そう言ってほしかったんだ、坊や」
その言葉や口調の意味を考える間もなく、私はふと別のことが頭に浮かび、質問した。
「昔、君が私に使いをよこしたことがあっただろう。あのときの使者に、その後会ったことがあるかい?」
「一度も顔は見ていない。会うはずもなかった」
「彼はちゃんと来て、二枚の一ポンド札を持ってきてくれた。あのとき私は貧しい少年だったから、それはちょっとした財産だった。でも君と同じで、その後はうまくやってきたから、返させてほしい。ほかの貧しい子のために使ってくれていい」私は財布を取り出した。
彼は私が財布を開け、二枚の新しい一ポンド札を取り分けるのを見ていた。それを重ねて長く折り、ねじって、ランプで火をつけ、灰皿に落とした。
「ちょっとお聞きしてもいいですかね」と、彼は微笑みともしかめ面ともつかぬ表情で、「あんたはどうやってうまくやったのかね、あの寒い湿地で会ったあと」
「どうやって?」
「ああ」
彼はグラスを空にし、立ち上がって暖炉のそばに立ち、分厚い茶色い手をマントルピースにかけた。片足を火格子に載せて靴を乾かし始めたが、彼は自分の靴も火も見ず、じっと私を見つめた。そのとき初めて私の体は震えだした。
私は唇を開け、声にはならなかったが、ようやく「ある財産を継ぐ者に選ばれたのだ」と答えた。
「単なる虫けらが質問してもいいですかね、なんの財産です?」
「分からない」と私はたじろぎながら言った。
「単なる虫けらがもう一つ質問してもいいですかね、誰の財産です?」
私は再びたじろぎ、「分からない」と答えた。
「推測してみていいかな」とその囚人は言った。「成人になってからの収入の頭の数字、当てられるかな。五?」
私は心臓が乱れ打ちするのを感じ、椅子から立ち上がってその背に手を置き、彼を茫然と見つめた。
「保護者のことだが」と彼は続けた。「未成年の間は何か保護者、弁護士でもいたはずだ。その弁護士の名前の頭文字、Jじゃないか?」
私の置かれた状況の真実が一気に襲いかかり、失望や危険、屈辱、あらゆる結果が洪水のように押し寄せ、私は呼吸するのもやっとだった。
「こう考えてみたらどうだ」と彼は続けた。「その弁護士を雇ったのが、海を越えてポーツマスに来て、君に会いたかった俺だったとする。『どうやって私を見つけたのか』と君はさっき言ったな? 俺はポーツマスからロンドンのある人物に君の住所を調べてもらう手紙を書いた。その人物の名は? ウェミックだ」
私は一言も発することができなかった。椅子の背と胸に手を当て、息が詰まりそうなまま、彼を茫然と見つめ、ついには椅子にしがみつき、部屋がぐるぐる回るような感覚に陥った。彼は私を抱えてソファに運び、クッションに寄りかからせ、今やはっきりと思い出し、ぞっとするほど近くにその顔を寄せた。
「ああ、ピップ坊や、俺がお前を紳士にしたんだ! 俺がやったんだよ! あの時、俺は誓った、稼いだギニーは全部お前のために使うと。その後も誓った、もうけたらお前も豊かにすると。俺は粗末な生活をして、お前が贅沢できるようにした。俺は必死で働き、お前が働かずに済むようにした。どうだ、坊や? 恩に着せるつもりか? そんなことはない。ただ知ってほしい。あの追われた汚い犬がお前に命を救われ、ついには紳士を作り上げた――その紳士が、お前なんだ!」
私はこの男に対する嫌悪、恐怖、そして身をすくませるほどの嫌悪感を、これ以上ないほど強く感じた。
「よく聞け、ピップ。俺はお前の第二の父だ。お前は俺の息子――どんな息子よりも大事な息子だ。お前が使うためだけに金をためてきた。孤独な小屋で雇われ羊飼いをしていた時、顔と言えば羊の顔しか見ず、人間の顔を忘れかけていたが、いつもお前の顔が浮かんだ。昼も夜も飯を食っているとき、何度もナイフを落として『またあの子が俺を見ている!』と思った。あの霧の湿地でお前を見たように、ありありと見えた。『神よ、俺を打て!』と毎回空の下で叫んだ。だがもし自由と金を手に入れたら、あの子を紳士にしてやると誓った。そして実行したんだぞ。見ろよ、坊や! この部屋だって貴族のようじゃないか? 貴族? いや、貴族と賭けをして金で勝てるようになるとも!」
彼は興奮と勝ち誇った様子で、私が気を失いかけていたことにもまったく気づかなかったのが、せめてもの救いだった。
「見てみろ!」そう言って、私の懐中時計を取り出し、指輪をこちらに向け(私は蛇に触られたように身を引いた)、「金の時計、見事だな? これぞ紳士の証! ダイヤとルビーの指輪、これも紳士の証だ! リネンも美しい、服もこれ以上はない! 本もたくさんだ、棚に百冊以上! しかも読んでるじゃないか、俺が来た時も読んでた。ははは! 俺にも読んでくれよ、坊や! もし外国語で分からなくても、俺はそれでも誇りに思うさ!」
またしても彼は私の両手をとって唇にあて、私は全身が氷のように冷たくなった。
「もう話さなくていい、ピップ」と彼はまた袖で目と額を拭い、喉の奥であの「カチッ」という音を立て(私はそれをよく覚えている)、その誠実さゆえかえって恐ろしかった。「黙っているのが一番だ。お前は俺ほどこれを待ち望んではいなかったし、心の準備もできていなかった。でも、俺だと思ったことはなかったのか?」
「いや、まったく、一度もない」と私は答えた。「決して、決して!」
「まあ、でも実際俺だった、しかも俺一人だ。誰も知らない、ジャガーズ氏だけ」
「他には誰もいなかったのか?」と私は問うた。
「いないよ」と彼は驚いたように返した。「他に誰がいる? それに、坊や、ずいぶんいい男になったな! どこかに“輝く瞳”があるんじゃないか? お前が思いを寄せている相手の」
ああ、エステラ、エステラ!
「金があれば、坊や、あの子も手に入るぞ。いや、君みたいな紳士なら自力で勝ち取れるさ。でも金で後押ししてやる! 続きを話すぞ、坊や。あの小屋と雇われ生活から、主人が死んで金を残してくれて、自由になって独り立ちした。何をするにも、お前のためだった。『神よ呪ってくれ、もしこれがあいつのためでなければ!』と。何もかもが驚くほど順調だった。さっきも言った通り、俺は有名なんだ。残された金と、最初の数年で得た儲けをジャガーズ氏に全部送った――お前のために――彼が最初にお前のところに来たときも、俺の手紙通りに」
ああ、彼が来なければよかったのに! 彼が私を鍛冶屋に残してくれていれば――決して満ち足りてはいなかったが、それでも比べれば幸福だったのに!
「それからな、坊や、こうして誰にも知られずに紳士を作り上げていると知ることが、俺には何よりの報いだったんだ。あの植民地の連中の血統馬どもが、俺の上に土ぼこりを跳ね上げて歩くかもしれねえ――だが俺はどう思ったと思う? 自分にこう言い聞かせたんだ。『俺はお前らよりも、もっと立派な紳士を作ってるんだぞ!』ってな。そして誰かが別の誰かに、『あいつは数年前は囚人で、今も運がいいだけの無学で粗野なやつさ』なんて言ったとき、俺はまた自分にこう言うんだ。『俺が紳士じゃなくたって、学なんかなくたって、俺の手には紳士がいる。お前らはみんな財産や土地は持ってるが、育て上げたロンドンの紳士を持ってるのは誰だ?』――こうして自分を奮い立たせてきたんだ。そしてこの思いでいつも決意を固めてきた――いつか必ず自分の坊やに会いに行き、彼の土地で自分の正体を明かすってな。」
彼は私の肩に手を置いた。私は、もしかしたらその手には血がついているかもしれないと思い、身震いした。
「ピップ、あの土地を離れるのは楽じゃなかったし、安全でもなかった。でも俺はやり遂げたくてな、それが難しいほど決意は強くなった。俺の心はしっかり決まってた。とうとうやったんだ。坊や、やり遂げたんだ!」
私は頭を整理しようとしたが、呆然としていた。話の間中、私は彼よりも風と雨の音の方にばかり気を取られていたように感じたし、今もなお、彼の声はそれらの音と切り離せなかった。それらがいくら大きくても、彼の声は沈黙のようだった。
「あんたは俺をどこに置く?」と彼はやがて尋ねた。「どこかに泊めてくれ、坊や。」
「寝るために?」と私は言った。
「ああ、ぐっすり長く寝たい」と彼は答えた。「何ヶ月も海に揺られて、海に洗われてきたんだ。」
「私の友人で仲間の者が今は留守だから、彼の部屋を使うといい」と私はソファから立ち上がって言った。
「明日戻らないよな?」
「いや」と私はほとんど反射的に答えた。どんなに努力しても、そう答えるしかなかった。「明日は戻らない。」
「それならいいんだ、坊や」と彼は声を落として言い、長い指で私の胸をぐっと押さえた。「用心が必要なんだ。」
「どういう意味だ? 用心とは?」
「神に誓って、死なんだ!」
「何が死だと言うんだ?」
「俺は終身刑だった。戻ってきたら死刑だ。近年は戻ってきたやつが多かったし、捕まったら確実に絞首刑さ。」
これ以上必要なものは何もなかった。みじめな私は、長年この男から金銀の鎖で縛られてきた挙げ句、彼が命を賭して私のもとに来てくれた――その命が今、私の手の中にあるのだ。もし彼を憎悪するのでなく愛していたら、もし彼に強い敬愛と親しみを感じていたら、今よりも悪くはならなかっただろう。むしろ、そのほうが自然に心を動かされ、彼の身を守ることにも優しさが加わっただろう。
私がまずしたのは、外から光が漏れぬように雨戸を閉め、扉もきっちりと施錠することだった。その間、彼はテーブルでラム酒を飲み、ビスケットを食べていた。その姿を見ていると、まるでまた沼地で食事をしていた囚人の彼そのものだった。今にもしゃがみ込んで足の枷を削り始めるのではと思われた。
私がハーバートの部屋に行き、そこ以外の階段への出入り口を塞いだあと、「寝ますか?」と尋ねた。彼は「うん」と答えたが、明朝着る「紳士のシャツ」を貸してくれと言った。私はそれを出して用意し、彼がまた両手で私の手を握りしめておやすみを言ったとき、血の気が引いた。
どうやって彼から離れたのか記憶もないまま、さっきまで一緒にいた部屋で暖炉をかき立て、火のそばに座ったが、怖くて寝る気になれなかった。一時間かそれ以上、呆然と座り続け、ようやく考える余裕が出てきたとき、私は初めて、自分がどれほど打ちのめされているか、乗っていた船が粉々に壊れてしまったことをはっきりと自覚した。
ミス・ハヴィシャムが私に向けていた意図など全て幻だった。エステラは私のために用意されていたのではなかった。私はサティス・ハウスでただ都合の良い存在、貪欲な親族たちに対する棘、あるいは他に練習台がいないときの機械じかけの心を持つ模型として苦しんでいただけだった。まず私が感じた痛みはそれだった。しかし、もっとも鋭く深い苦しみは――私がジョーを見捨ててしまったのは、何をしでかしたかもわからない罪人、今にもこの部屋から連れ出され、オールド・ベイリーの扉で絞首刑にされるかもしれない囚人のためだったということだった。
今の私には、たとえあらゆる代償を払ってでもジョーのもとへ、ビディのもとへ戻ることはできなかった。ただただ、自分が彼らに対してどれほど価値のないことをしたか、その意識が何よりも勝っていたからだ。この世のどんな知恵をもってしても、彼らの素朴さや誠実さから得られる安らぎ以上の慰めは得られなかっただろうが、私は決して、決して、自分のしたことを取り消すことはできないのだった。
突風に乗った風や激しい雨音の中に、私は追っ手の気配を感じていた。二度ほど、外の扉を誰かがノックし、ささやく声まで聞こえた気がした。この恐怖の中で、私はこの男が来ることへの不吉な予感を、今になって思い出したり、あるいは想像したりし始めた。ここ数週間、彼に似た顔を街で見かけた気がしていたし、その数が彼が海を渡って近づくにつれ増えてきたようにも思えた。彼の邪悪な魂が、何らかの使いを私のもとへ送り込んでいたのかもしれず、そして今夜、この嵐の夜に、彼は約束通り現れ、私のもとにいたのだった。
こうした思考とともに、私は彼を子供の頃に見たときから、絶望的に暴力的な男だと感じていたことも思い出した。もう一人の囚人が彼に殺されかけたと繰り返していたこと、自分自身が彼を溝の中で獣のように引き裂き戦う姿を見たこと――これらの記憶から、私は彼と真夜中の孤独な部屋に閉じ込められているのは安全ではないかもしれないという、半ば無意識の恐怖を火の明かりのもとに引きずり出した。その恐怖はやがて部屋いっぱいに膨れ上がり、私は蝋燭を手に取り、恐る恐る「重荷」を見に行かずにいられなかった。
彼は頭にハンカチを巻き、眠りながらも顔は険しく暗かった。しかし、ぐっすりと静かに眠っていた――枕元に拳銃を置いているにもかかわらず。私はそっと部屋の鍵を外側に移し、外から施錠してからまた火のそばに戻った。やがて椅子からずり落ちて床に横たわった。目覚めたときも惨めさの自覚は消えていなかった。東の教会の時計が五時を打ち、蝋燭は溶け尽くし、火は消え、風雨が漆黒の闇をさらに深めていた。
これでピップの「第二の期待」の段階は終わる。
第四十章
恐ろしい訪問者の安全を(できる限り)守るための対策を講じなければならなかったのは、私にとって幸いだった。というのも、目覚めたときにまずこのことが頭を占めていたおかげで、他の思考は混乱したまま遠くに追いやられていたからだ。
彼を部屋に隠し続けるのは絶対に無理だと一目で分かった。そんなことをすれば必ず疑いを招く。今や「アヴェンジャー」はいないが、私は炎のように口うるさい老女と、その姪と称する生きたボロ布のような娘に世話されていた。この二人から部屋を隠すのは好奇心と大げさな噂を呼ぶだけだ。二人とも目が悪いと自称しているが、それはいつも鍵穴から覗いているせいではないかと私は睨んでいたし、必要のない時に限っていつも近くにいる――これは盗み癖以外で唯一信用できる特徴だった。これらの人物に余計な謎を作らないため、朝になったら「田舎から叔父が突然来た」と発表することにした。
この方針は、まだ暗闇の中で灯りを探っている最中に決めた。結局火は見つからず、私は隣のロッジに行き、そこの夜警にランタンを持ってきてもらうしかなかった。黒い階段を手探りで降りる途中、私は何かにつまずいた。それは、隅にしゃがみ込んでいる男だった。
その男は私が「ここで何をしている?」と尋ねても何も言わず、私の手を避けて黙っていたので、私はロッジに走って夜警に急いでもらい、戻る途中でこの出来事を話した。風は相変わらず激しく、ランタンの灯を危険にさらしたくなかったので、階段の消えた明かりはつけず、下から上まで調べたが誰もいなかった。あるいは、その男は私の部屋に忍び込んだのかもしれないと思い、夜警のランタンで自分の部屋――恐ろしい客が眠る部屋も含めて――慎重に確かめた。どこも静かで、他に誰もいなかった。
この夜に限って階段にうろつく者がいたという事実は私を不安にさせた。私は夜警にブランデーを手渡しつつ、何か希望につながる説明でも聞き出せるかと思い、「今夜、酔って帰宅した紳士を門で見かけなかったか」と尋ねた。彼は「三人ほど、それぞれ違う時間に見かけた」と言った。一人はファウンテン・コートに住み、二人はレーンに住んでいて、全員の帰宅を見届けたとのことだった。また、私の部屋のある家のもう一人の住人は何週間も田舎に行っていて、昨夜は戻っていない――というのも、階段を上がるとき、その部屋の扉に封印があるのを見たからだ。
「今夜は天気がひどかったんでね、旦那」と夜警はグラスを返しつつ言った。「さっき言った三人以外、私の門を通ったのは十一時ごろ、あなたを訪ねてきた見知らぬ人だけだったと思いますよ。」
「叔父だ」と私はつぶやいた。「そうだな。」
「あなたはその方に会ったんですか?」
「ええ、もちろん。」
「一緒にいた方もですか?」
「一緒にいた?」と私は繰り返した。
「私にはご一緒のように見えましたよ」と夜警は言った。「その方が尋ねてきたときも、その人と一緒だったし、そのあとも同じ道を通って行きました。」
「どんな人だった?」
夜警は特に覚えていなかったが、労働者風で、ほこり色の服に暗い上着を着ていた気がすると言った。夜警はこの件を私より軽く受け止めていた――当然だ、私のような疑いと恐怖の理由がないのだから。
私はこれ以上説明を延ばさず夜警を帰し、二つの出来事を合わせて考えると強く不安を感じた。別々なら無害な偶然――たとえばどこかの酔客が私の階段まで迷い込み、そこでうっかり眠ってしまっただけかもしれないし、私の名もなき訪問者が道案内に誰かを連れてきただけかもしれない――だが、重なるとなると、疑い深く不安になっていた私は恐ろしく思えた。
私は火をつけ直し、その青白く生気のない炎の前でうとうとした。丸一晩眠ったように感じたところで六時の鐘が鳴った。まだ明け方まで一時間半はあったので、またうとうとした。時には意味のない長話が耳に残り、時には煙突の風音が雷のように聞こえ、ついには深い眠りに落ち、朝の光で飛び起きた。
その間、私は一度も自分自身の状況を考えられず、今でもそれができなかった。自分のことに注意を向ける力がなかった。私は非常に沈んで苦しんでいたが、それも何がどう苦しいのかは漠然としていた。将来の計画を立てるなど、とてもできる状態ではなかった。雨に濡れた鉛色の朝、雨戸を開けて外を見たときも、部屋から部屋へ歩き回ったときも、また火の前で震えながら洗濯婦の来るのを待っていたときも、自分がどんなに惨めかを思ったが、なぜそうなのか、どれくらいそうなのか、何曜日か、そもそも自分が何者なのかさえ定かではなかった。
やがて老女と姪が入ってきた――姪は埃まみれの箒と区別がつかないような頭で――そして私と火を見て驚いた様子だった。私は「叔父が夜中に来て今は寝ている」と伝え、朝食の準備もそれに合わせて変更するよう頼んだ。その間に私は身支度を整えたが、彼女たちは家具を叩き、埃を立てていた。私は夢うつつのような気分で再び火の前に座り、「彼」が朝食に現れるのを待つことになった。
しばらくして、彼の部屋の扉が開き、彼が出てきた。私は彼の姿を見るのがどうしても耐えられず、昼間に見る彼の方がいっそう不気味に思えた。
「どう呼べばいいのかさえ分からない」と私は低く言った。「私はあなたを叔父だと伝えた。」
「それがいい、坊や。叔父と呼びな。」
「船の上では、何か名前を使っていたんだろう?」
「ああ、坊や。『プロヴィス』という名前にした。」
「これからもその名前を使うつもり?」
「そうだな、坊や。他と変わらない名前だ――お前が別のを望むならともかく。」
「本当の名前は?」と私は小声で尋ねた。
「マグウィッチだ。同じく小声で、洗礼名はエイベル。」
「若い頃は何をしていた?」
「悪党さ、坊や。」
彼はごく真剣に答え、その言葉をまるで職業の一つのように使った。
「昨夜、寺院の中に入ったとき――」と私は口をつぐんだ。まるであれが本当に昨夜だったのか、ずっと昔のように思えた。
「ああ、坊や?」
「門から入って夜警に道を尋ねたとき、誰か一緒だった?」
「一緒に? いや、坊や。」
「でも誰かいたんじゃ?」
「よく覚えてない」と彼は迷いがちに言った。「この場所の勝手も知らなかったし。でも、確かに誰か一緒に入った気もするな。」
「ロンドンで顔を知られている?」
「知られてないといいがな!」彼は首に指を巻きつける仕草をし、それを見て私は熱くなり、吐き気がした。
「昔、ロンドンで知られていたことは?」
「そうでもない、坊や。だいたい地方にいた。」
「――ロンドンで裁かれたのか?」
「どの時だ?」と彼は鋭い目で言った。
「最後の時。」
彼はうなずいた。「その時にジャガーズ氏と初めて知り合った。ジャガーズが俺の弁護をしてくれた。」
私は彼が何の罪で裁かれたのか尋ねかけたが、彼はナイフを取り上げ、くるりと回して「俺のやったことは、もう償い済みだ!」と言って食事に取りかかった。
彼の食べ方はがつがつしていて非常に不愉快だったし、すべての動作が無作法で騒々しく、貪欲だった。歯も何本か失っており、食べ物を口の中で回し、頭を横にして強い歯で噛み砕く様子は、まるで飢えた老犬のようだった。もし私に食欲があったとしても、彼のせいで消えていただろう。私はただ彼からどうしようもなく強い嫌悪感を覚え、黙ってテーブルクロスを見つめていた。
「俺は大食らいなんだ、坊や」と、彼は食事が終わると一種の礼儀として言った。「昔からそうだった。もしもっと小食な性分だったら、もっと軽いトラブルで済んだかもな。同じく、俺には煙草が欠かせない。向こうで最初に羊飼いとして雇われたとき、もし煙草がなかったら俺自身が気のふれた羊になってただろうよ。」
そう言いながら、彼はテーブルから立ち上がり、着ていたピーコートの胸から短い黒いパイプと「ニグロヘッド」と呼ばれる粗悪な葉巻タバコを一握り取り出した。パイプに詰め、余りはまたポケットに引き出しのように戻した。それから、火ばさみで火のついた炭を取り、パイプに火をつけた。暖炉の前で背を向けて立ち、両手を私の方に差し出した。
「そしてこれさ」と言いながら、パイプをくゆらせ私の手を上下に振った。「これが俺の作った本物の紳士だ! 見てるだけでいい、坊や。俺の望みは、ただそばで見てることだけさ!」
私はすぐに手を引き、ようやく自分の状況を考え始められるようになった。何に縛られ、どれほど重い鎖なのか、彼のしゃがれ声を聞き、鉄灰色の髪を脇に残した皺だらけの頭を見上げながら、ようやく理解できるようになった。
「俺の紳士が街の泥を踏むなんていけない。彼の靴に泥がついてはいけない。俺の紳士には馬が必要だ、ピップ! 乗る馬、馬車を引く馬、召使いが乗る馬も要る。コロニストが馬を持ってて(しかも血統馬まで!)俺のロンドン紳士が持たないなんてありえない。違う靴を見せてやろうぜ、ピップ、な?」
彼は分厚い札入れをポケットから取り出し、テーブルに放り出した。
「この中には使い道のある金が入ってる、坊や。お前のものさ。俺の持ってるものは全部お前のもの。怖がるな、まだまだある。俺は自分の紳士が紳士らしく金を使うのを見に来たんだ。それが俺の喜びだ。俺の、俺だけの喜びさ。そして――」と、部屋を見渡しながら指を大きな音で鳴らして言った。「くたばれ! 判事もカツラも、ほこりを蹴り上げるコロニストも、全員まとめて俺の作った紳士の方が上だ!」
「やめてくれ!」と私は恐怖と嫌悪のあまり叫んだ。「話がしたい。どうすればいいのか、どうやってあなたを危険から守るのか、どれくらい滞在するつもりなのか、計画を知りたい。」
「聞きな、ピップ」と彼は突然態度を変え、しおらしく腕を私に置いた。「まずはな、さっきのは言い過ぎた。俺が言ったことは下品だった。許してくれ、ピップ。下品にはならん。」
「まずは」と私はうめくように続けた。「どうすれば身元がバレて捕まるのを防げる?」
「いや、それは後だ。下品だったことが先だ。俺は長年かけて紳士を作った。彼にふさわしい態度を知っている。さっきのは下品だった。許してくれ、坊や。」
私は滑稽さに思わず苦笑しながら、「もういい。だから頼むからその話はやめてくれ!」と言った。
「でもな、ピップ、俺は下品になるためにここに来たんじゃない。さあ、続けてくれ。」
「どうやって危険を避けるのか?」
「まあ、危険はそれほどでもない。タレコミでもない限り、たいしたことはない。ジャガーズ氏がいるし、ウェミック氏がいるし、お前がいる。他に誰がいる?」
「たまたま街で顔を見られて身元がバレるようなことは?」
「まあ、そんなにはいない。新聞に『A.M.、ボタニー湾より帰還』なんて載せる気もないし、何年も経ってる。誰が得をする? それでも、もし危険が五十倍あっても、俺は必ずお前に会いに来ただろう。」
「どれくらい滞在するつもりだ?」
「どれくらい? 帰る気はない。俺はここに骨をうずめるつもりだ。」
「どこに住む? どうやって身を守る? どこなら安全だ?」
「坊や、金さえあればカツラも買えるし、白粉もある、眼鏡も黒服も短パンもある。他の者がやれたなら俺にもできるさ。生活の場所や方法については、お前の意見を聞きたい。」
「今は穏やかだけど、昨夜は“死”だと誓ったじゃないか。」
「今もそうだ」と彼はパイプをくわえ直しながら言った。「それもロープで死ぬ、ここからそう遠くない場所でな。だからこそ深刻に受け止めろ。だが、どうせならここにいるさ。今さら帰っても同じこと――いや、もっと悪い。俺は昔から腹をくくってる。どんなワナでもくぐり抜けてきた。案山子の上だって怖くない。中に死が潜んでるなら出てこい、立ち向かうまでだ。それまでは信じない。そして、また俺の紳士を見せてくれ。」
またもや彼は両手で私の手を握り、誇らしげに所有者のように私を見つめながら、満足げにパイプをくゆらせた。
私は、ハーバートが戻ったらすぐにでも、彼に近所の静かな下宿を確保し、移ってもらった方がよいと判断した。そしてこの秘密をハーバートに打ち明けることが、私の安堵のためだけでなく、避けられない必要であることも明らかだった。しかしプロヴィス氏(私は彼をそう呼ぶことに決めた)はそれにすぐ同意せず、「まずハーバートの顔を見て、気に入ったら、誓いを立てさせてからだ」と言い張った。「そしてな、坊や」と言って、ぼろぼろの小さな黒い聖書をポケットから取り出した。「ちゃんと誓わせるぞ。」
この恐ろしい後見人がこの小さな黒い本を世界のどこへでも持ち歩くのは、緊急時に人々に誓いを立てさせるためだけだと断言することはできないが、他の用途で使っているのを私は見たことがない。この本自体、どこか裁判所から盗まれてきたような風情があり、その過去を知っていることと自身の経験からか、何らかの法的なおまじないとして強い信頼を寄せていた。この本を取り出した最初の場面で、私は彼が昔墓地で私に忠誠を誓わせたことや、昨夜独りで誓いを立てていたと語ったことを思い出した。
今の彼は船員の作業服姿で、まるでオウムや葉巻を売り歩く男のように見えたので、私は着替えについて相談した。彼は「短パン」に変装の効果を強く信じていて、司祭と歯医者を足して二で割ったような服装を構想していた。私はどうにか説得して、裕福な農夫風の服装をさせることにし、髪は短く切って白粉を少しつけることで落ち着いた。最後に、まだ洗濯婦や姪に見られていなかったので、着替えが済むまで彼には彼女たちの目に触れないようにさせた。
これらの対策を決めるのは簡単そうに見えるが、混乱しきっていた私には時間がかかり、外に出られたのは午後二時か三時になってからだった。彼には自室にこもるよう厳命し、決して扉を開けないように言い聞かせた。
テンプルの裏手、ほとんど窓越しに声が届くほど近いエセックス・ストリートに、評判の良い下宿屋があるのを知っていたので、まずそこへ行き、幸運にも二階を「叔父プロヴィス」用に借りることができた。それから必要な品々を店々で買い集めた。その後、私はリトル・ブリテンへ向かった。ジャガーズ氏は机にいたが、私の姿を見るとすぐに立ち上がり、暖炉の前に立った。
「さて、ピップ、慎重になりなさい」と彼は言った。
「はい、先生」と私は答えた。来る途中、言うべきことを十分考えてきたつもりだった。
「自分のことも他人のことも決して口外しないこと。分かるね――他人もだ。何も話さないでほしいし、私も何も知りたくないし、好奇心はない。」
彼がその男が来たことを知っているのは明らかだった。
「私が知りたいのは、私が聞かされたことが本当かどうか、それだけです。間違いだろうとは思いませんが、せめて確認したいのです」と私は言った。
ジャガーズ氏はうなずいた。「だが、君は『聞いた』と言ったか『知らされた』と言ったか?」と彼は首を傾げ、床を見ながら尋ねた。「『聞いた』なら直接話したことになる。ニューサウスウェールズの男と口頭で話せたはずがないだろう。」
「『知らされた』と言いましょう、ジャガーズ先生。」
「よろしい。」
「エイベル・マグウィッチという人物から、長年正体不明だった恩人は自分だと知らされました。」
「それがその男だ」とジャガーズ氏は言った。「ニューサウスウェールズの。」
「彼だけですか?」
「彼だけだ。」
「あなたのせいで私が勘違いや誤解をしたなどとは思いませんが、私はずっとミス・ハヴィシャムだと思い込んでいました。」
「その通り、ピップ」とジャガーズ氏は目を冷たく向け、指を噛みながら言った。「私には一切責任はない。」
「でも、どうしてもそう思える材料が揃っていたんです」と私は気落ちして訴えた。
「証拠がない、ピップ」とジャガーズ氏は首を振り、裾を整えた。「見かけで判断しないこと。証拠で判断すること。それが一番の規則だ。」
「もう言うことはありません」と私はため息をついて、しばらく黙って立ち尽くした。「情報の確認はできました。それで十分です。」
「そして、ニューサウスウェールズのマグウィッチがついに正体を明かしたわけだね」とジャガーズ氏は言った。「君はこれまで私が君と接する際、一切事実だけに徹してきたことを理解しているだろう。少しの逸脱もなかった。それはよく分かっているね?」
「はい、先生。」
「私はマグウィッチに――ニューサウスウェールズにいた彼に――最初に手紙をもらったとき、事実から逸脱することは決してしないと警告した。もう一つ注意も与えた。彼の手紙には、いつか君に会いたいというぼんやりした希望がほのめかされていたので、私はそれ以上その話を聞きたくない、恩赦を得られる見込みはほぼない、彼は一生流刑者であり、この国に現れたら重罪で即刻死刑になると警告した。私はその警告をマグウィッチに――ニューサウスウェールズに――書き送った。彼はきっと守っただろう。」
「きっと、そうでしょう。」
「ウェミックからも聞いているが」とジャガーズ氏はさらに私を見据えて続けた。「彼はポーツマスから“パーヴィス”または――」
「プロヴィスです」と私は言った。
「プロヴィス、ありがとう。たぶんプロヴィスだったな? 君はプロヴィスだと知っているのか?」
「はい。」
「やはりプロヴィスか。プロヴィス名義の植民地人から、マグウィッチのために君の住所を尋ねる手紙がポーツマスから来た。ウェミックはすぐ返事を出したそうだ。たぶんプロヴィス経由で君はマグウィッチの説明を受けたんだな?」
「プロヴィス経由で受け取りました。」
「よろしい。ピップ」とジャガーズ氏は手を差し出した。「会えてよかった。マグウィッチ――ニューサウスウェールズに――手紙を書くなら、長年の勘定書類と残高も併せて送る旨を伝えてほしい。まだ残高があるからね。では、ピップ!」
私たちは握手を交わし、彼はいつまでも私を凝視していた。私が扉で振り返ると、彼はまだじっと私を見つめていた。棚の上の醜い石膏像二つも、瞼をこじ開けてまで「なんて男だ!」と叫ぼうとしているかのようだった。
ウェミックは外出中で、机にいても私の役には立たなかっただろう。私はまっすぐテンプルに戻り、恐ろしいプロヴィスが安全にラム酒と水を飲み、ニグロヘッドを吸っているのを見つけた。
翌日、注文していた服がすべて届き、彼は着替えた。だが何を着ても(私には実に陰気なことに思えたが)前の格好より似合わなかった。どんなに着飾らせても、ますます沼地でうろつく逃亡囚にしか見えなかった。そう感じたのは、彼の風貌や態度が次第に私に馴染んできたせいもあるが、彼が片足を引きずるのはまだ鉄の重りをつけているようで、頭のてっぺんからつま先まで「囚人」の気配が染みついているせいでもあった。
孤独な小屋暮らしの影響も残っていて、どんな服も抑えきれない野性味を与えていた。加えてその後の烙印を押された人生、今また逃げ隠れしているという自覚――これらがすべて彼の動作や佇まい、食べ方、飲み方、背中を丸めてうろつく様子、巨大な角柄ナイフを脚で拭って食事を切り分ける様子、グラスやカップを重たい金属製の食器のように扱う様子、パンをくさび形に切り、皿のソースを最後まで拭い取り、それで指先を拭いてから飲み込む――そのすべて、名もなき無数の仕草のひとつひとつに「囚人」「重罪人」「奴隷」の色がはっきりにじみ出ていた。
彼が白粉をつけるよう提案したのは自分だったが、短パンをやめさせる代わりに私は白粉を認めた。しかし、それを施した彼の姿は、まるで死体に紅をさしたような不気味さだった。抑えたいものがすべて、その薄い仮面の下から噴き出し、頭頂から炎のように現れた。結局、白粉はすぐやめ、彼は短く刈った灰色の髪のまま過ごすことになった。
彼が私にとっていかに恐ろしい謎であるか、言葉では言い表せない。夜、彼が安楽椅子の肘掛けを拳で握りしめ、深い皺の頭を胸にうなだれて眠り込むと、私は彼を見つめ、彼が何をしでかしたのか想像し、あらゆる罪を彼に背負わせ、逃げ出したい衝動に駆られた。その嫌悪感は時とともに増し、ハーバートがもうすぐ帰ると知っていなければ、彼が私のためにしてくれたすべて、そして命を危険にさらしていることさえ無視して、実際に衝動に負けていたかもしれない。ある晩、私は本当にベッドから飛び起き、みすぼらしい服を着て、彼と全財産を残してインド軍の一兵卒になるつもりでいた。
幽霊の方がまだましだったろう。長い夜、風雨の唸りが絶えず続く中、あんな孤独な部屋で彼といるのは、幽霊以上の恐怖だった。幽霊なら、私のせいで捕らえられて絞首刑になることはない。その可能性と恐れが、私の苦しみにさらに拍車をかけていた。彼が眠っていない時や、ぼろぼろのトランプで奇妙な一人遊びをしていない時――(勝った分はナイフをテーブルに突き立てて記録するのだった)、あるいはどちらでもない時、彼は私に本の朗読を頼んだ――「外国語でな、坊や!」。私が応じると、彼は一言もわからないまま、暖炉の前で誇らしげに立ち、私が顔を手で覆いながら指の隙間から彼を見ると、私の腕前を部屋の家具に黙って見せびらかしているかのようだった。かつて自分の作り出した怪物に追われる想像上の学生よりも、私はずっと惨めだった。自分を作り出したこの怪物に愛されれば愛されるほど、私は強く彼を拒絶せずにいられなかった。
まるで何年も続いたように書いているが、実際には五日ほどのことだった。その間、私はずっとハーバートを待ち続け、帰ってくるまで昼間外出する勇気はなかった。夜暗くなってからプロヴィスを散歩に連れて出る以外、私は閉じこもっていた。やがてある夜、夕食後私は疲れ切ってうたた寝していた。夜も悪夢で眠れぬ日々が続いていたのだ。階段に聞き慣れた足音が響き、私は夢中で目を覚ました。プロヴィスも私の音で飛び起き、瞬時にジャックナイフを手にしていた。
「静かに! ハーバートだ!」と私は言った。するとハーバートが、六百マイルもフランスを走破した新鮮な空気をまとって、部屋に飛び込んできた。
「ハンデル、親愛なる友よ、元気か、また元気か、さらに元気か? まるで一年も離れていたような気がする! いや、実際そうだったに違いない、何しろ君はすっかりやせて青ざめてしまったじゃないか! ハンデル、ぼくの――おや! すまない。」
彼は走り寄って僕と握手しようとしたが、プロヴィスに気づいて止まった。プロヴィスはじっと彼を見つめながら、ゆっくりと折り畳みナイフをしまい、別のポケットを探って何かを取り出そうとしていた。
「ハーバート、親友よ」と僕は言った。ハーバートが呆然と立ち尽くしている間に、僕は二重扉を閉めた。「とても奇妙なことが起きた。彼は……僕の客なんだ。」
「大丈夫だ、坊や!」とプロヴィスが進み出て、黒い小さな本を両手で持ちながら、今度はハーバートに向き直って言った。「右手で受け取れ。もし少しでも口を滑らせたら、神様がその場でお前を撃ち殺すぞ! キスしろ!」
「彼の望み通りにしてくれ」と僕はハーバートに言った。ハーバートは少し不安そうに、それでも友好的なまなざしで僕を見てから従った。プロヴィスはすぐに彼と握手して、「これでお前は誓ったことになる。もしピップが君を紳士にしなかったら、ぼくの誓いも信じてくれるな!」と言った。
第四十一章
僕がプロヴィスとハーバートと三人で暖炉の前に座り、僕がすべての秘密を語った時のハーバートの驚きと不安は、とても言葉で言い表せるものではなかった。僕の感情がハーバートの表情に映っているのを見たが、何よりもまず僕の恩人であるこの男への嫌悪感があった。
もし他に何の隔たりがなくとも、彼と僕たちの間に決定的な溝を作ったものは、僕自身の物語に対する彼の誇りである。彼が帰ってきてからの唯一の「下品」な振る舞いについて――僕が秘密を明かし終えた途端、彼はハーバートに語り始めた――以外は、自分の善意に僕が文句を言う可能性など考えていなかった。僕を紳士に仕立て、潤沢な資金でその地位を支えるのを見に来たという彼の自慢は、彼自身のためであると同時に僕のためでもあった。これは僕たち双方にとって大いに誇るべきことであり、喜ばしいことだという結論が、彼の中ではすっかり出来上がっていた。
「だが、ピップの友よ」と彼はしばらく語った後、ハーバートに言った。「わかってるさ、帰ってきてから一度だけ、ほんの一瞬、俺は下品だった。ピップにもそう言った。でも、そのことで心配するな。俺はピップを紳士にしたし、これからピップが君を紳士にするが、君たちふたりに恥をかかせるような真似はしないよ。坊や、ピップの友よ、俺はずっと上品にしていると約束する。あの時の半分だけ下品になったあとは、今もずっと“口輪”をはめているし、これからもそうする。」
ハーバートは「もちろん」と答えたが、特に慰められた様子はなく、困惑したままだった。僕たちは、彼が宿に帰ってふたりきりになれる時間を待ち望んでいたが、彼は明らかに僕たちをふたりきりにしたくない様子で、いつまでも腰を上げなかった。真夜中になってやっと、僕は彼をエセックス・ストリートまで送り、暗い扉の中に無事に入るのを確認した。扉が閉まったとき、僕は彼が到着した夜以来初めて安堵の瞬間を味わった。
階段の男のことを完全に忘れることはできず、夜に客を外に連れ出すときも帰るときも、常に周囲を気にしていた。危険に気づいているとき、大都市で見張られているという疑念を完全に払拭するのは難しいが、僕の動向に気を配る者は誰もいないように思えた。通り過ぎる人々はそれぞれの道を行き、僕がテンプルに戻ったとき、通りには誰もいなかった。誰も僕たちと一緒に門を出ず、誰も僕と一緒に門に入らなかった。噴水のそばを通ると、彼の部屋の窓が明るく静かに輝いていた。建物の入口でしばし立ち止まり、階段を上がる前に見渡すと、ガーデン・コートは階段と同じくらい静まり返っていた。
ハーバートは両腕を広げて迎えてくれ、僕は初めて本当の友がいることのありがたさを心から感じた。彼にいくつかの慰めと励ましの言葉をもらい、僕たちは「どうすべきか」という問題を考えることにした。
プロヴィスが使っていた椅子はそのままになっていた――彼は、一定の場所に居座り、落ち着かない様子でパイプや黒たばこ、折り畳みナイフ、トランプなどを持ち回る“兵舎流”の癖があった。椅子がそのままだったので、ハーバートは無意識にそれに座ったが、次の瞬間飛び上がって椅子を遠ざけ、別の椅子に座り直した。それでもう、彼が僕の後援者に嫌悪感を抱いていることは言葉にせずとも伝わったし、僕も同じだった。僕たちは一言も交わさずにその思いを共有した。
「どうすればいいんだろう」と僕は、ハーバートが別の椅子に収まったのを確認して言った。
「かわいそうなハンデル」と彼は頭を抱えながら答えた。「あまりのことで頭が働かない。」
「僕もだよ、ハーバート。最初に打撃を受けたときは何も考えられなかった。でも、何かするしかない。彼は馬や馬車、贅沢な暮らしなど、あれこれ新しい出費に夢中だ。どうにかして止めなくては。」
「つまり君は……受け入れられないと?」とハーバートが言いかけた。
「どうして受けられる? 彼のことを考えてみてくれ、見てみてくれ!」
ふたりとも思わず身震いした。
「でも恐ろしいことに、ハーバート、彼は僕に強く執着しているんだ。こんな運命があるものか!」
「かわいそうなハンデル」とハーバートは繰り返した。
「それに」と僕は言った。「ここで打ち切るとしても、もう一銭も受け取らなくても、すでに彼から受けたものを思えば……それに、僕は重い借金がある――期待がなくなった今の自分にはとても――職もなく、何の役にも立たない。」
「まあまあ!」とハーバートはたしなめた。「何の役にも立たないなんて言うな。」
「僕は何の役に立つ? 僕が唯一できることは兵隊になることくらいだ。もし君の友情と愛情に相談するつもりがなかったら、僕はもう兵隊になっていたかもしれない。」
もちろん、そこまで言ったところで声が詰まった。そしてもちろん、ハーバートは僕の手を温かく握るだけで、それに気づかぬふりをしてくれた。
「いずれにしても、ハンデル」と彼はやがて言った。「兵隊になるのはだめだ。もし君がこの後援や好意すべてを断つなら、いつか返済できるかもしれないという希望がわずかにあるだろう。でも兵隊になったら望みはほとんどない。それに馬鹿げている。君はクラリカーの店の方がずっと良い。小さな店だけど、僕は今パートナーになろうと頑張ってるんだ。」
かわいそうに! 彼は、その資金の出所が誰なのか、まったく気づいていなかった。
「でも、もう一つ問題がある」とハーバートが言った。「この男は無学で頑固で、長い間一つの考えに取り憑かれてきた。さらに言えば、僕の思い違いかもしれないが、とても危険で荒々しい性格の持ち主に見える。」
「その通りだ」と僕は答えた。「証拠を話そう」と言って、僕はこれまで話していなかった、あのもう一人の脱獄囚との遭遇について語った。
「考えてみてくれ」とハーバートは言った。「彼は命懸けでここに来て、その一念を成就させた。その瞬間に、君が彼の足元を崩し、すべてを無にしたら、彼がどんな行動に出るか、考えたことは?」
「考えてきたよ、ハーバート。あの運命の日以来、彼が捕まる道を自ら選ぶのではないかと、ずっと夢にも見た。」
「それなら、君が彼を見捨てたら、彼が本当に自暴自棄になる危険が大きいということだ。イギリスにいる限り、それが君に対する彼の力であり、君が彼を見捨てた時の彼の向かう道だ。」
この考えにはじめて打ちのめされたのではなかったが、その帰結が僕を“ある種の殺人者”のように感じさせるので、椅子にじっとしていられず、うろうろと歩き回り始めた。その合間にも、仮にプロヴィスが発見されて捕まったとしても、その原因が自分だと思えば、どんなに無実でも苦しむだろうとハーバートに言った。彼がそばにいて自由でいることさえ苦痛なのに、僕はこの運命より鍛冶屋に一生いた方がましだった!
だが、どうすべきかという問題から逃れることはできなかった。
「まず、何よりも大事なのは」とハーバートが言った。「彼をイギリスから出すことだ。君も一緒に行く必要があるだろう。そうすれば彼も行く気になるかもしれない。」
「でも、どこへ連れて行っても、彼が戻ってくるのを止められるだろうか?」
「ハンデル、それは明らかだろう。ニュゲート刑務所がすぐ近くにあるこの地で、君が彼に真相を打ち明けて自暴自棄にさせるのは、他の場所よりずっと危険だ。もし他の脱獄囚のことや、彼の過去から口実を作れれば――」
「またそれだ!」と僕はハーバートの前で絶望を両手で示して言った。「僕は彼の人生を何も知らない。ただ彼が僕の運命に絡みついているのに、僕にとっては幼いころに僕を脅かした惨めな男以上の存在ではないんだ!」
ハーバートは立ち上がり、僕の腕を取って、ゆっくりと歩き始めた。
「ハンデル」とハーバートは立ち止まりながら言った。「君はこれ以上彼の恩恵を受けられないと確信しているのだろう?」
「確信している。君だって僕の立場ならそう思うだろう?」
「彼と決別するしかないと確信しているのか?」
「ハーバート、君がそれを聞くのか?」
「そして、君は彼が君のために命を賭けていることに対して、彼の命を無駄にさせまいとする思いがあるのだね? ならば、まず彼をイギリスから出さなければならない。それが済んだら、あとは何とかなる。ふたりで何とかしよう、親友よ。」
僕たちは互いに手を握り合い、それだけで少し気が楽になり、また歩き出した。
「さて、ハーバート」と僕は言った。「彼の過去を知る手立てについてだが、僕の知る限り一つしか方法がない。率直に本人に聞くことだ。」
「そうだ、聞くべきだ」とハーバートは言った。「明日の朝食のときに」 彼は、帰り際に明日の朝食を一緒にすると言っていた。
こうして計画が決まり、僕たちは床についた。僕は彼についての荒唐無稽な夢ばかり見て、まったく疲れが取れなかった。そして、夜の間に失っていた、彼が脱獄囚として見つかるのではないかという恐れが、目覚めとともに戻ってきた。その恐れは、目覚めている間は決して消えることがなかった。
約束の時間に彼はやってきて、折り畳みナイフを取り出し、食事を始めた。彼は「紳士の本格的な登場」に向けての計画で頭がいっぱいで、僕に預けてある財布を早く使い始めるよう促した。今の部屋も彼自身の下宿も仮住まいだと考えていて、すぐにハイド・パーク近くの「イカした棲み家」を探せとすすめた。食事が終わり、ナイフを腿で拭いている時、僕は前置きなしに言った――
「昨晩あなたが帰ったあと、僕は友人に話したんだ。兵士たちが湿地であなたと争っているところを僕たちが見つけたこと、覚えているだろう?」
「覚えてるとも!」と彼は言った。
「僕たちは、その男について、そしてあなた自身について知りたいと思っている。昨夜語った以上のことを、僕も彼も知らないのはおかしいだろう? 今、それを聞くのにちょうどいい時じゃないか?」
「よし」と彼は考え込んだ末に言った。「ピップの友よ、お前は誓ったな?」
「もちろんだ」とハーバートが答えた。
「俺の話すことは全部、あの誓いが適用されるんだぞ」
「承知している」
「でな、俺のやったことはすべて償い済みだ」と念を押した。
「それでいい」
彼は黒いパイプを取り出し、ネグロヘッドたばこを詰めようとしたが、そのもつれが話の筋を妨げると感じたのか、たばこをしまい、パイプを上着のボタン穴に挿し、両手を膝に置いた。しばらく怒ったような目で火を見つめ、やがて僕たちを見回して語り始めた。
第四十二章
「坊やとピップの友よ。俺は自分の人生を歌や物語みたいに語る気はない。でも手短に言えば、こうだ。牢屋に入り、牢屋を出て、牢屋に入り、牢屋を出て、牢屋に入り、牢屋を出て。これだ。それが俺の人生さ、ピップが俺の味方をしてくれるまでな。
俺はまあ、絞首刑以外はなんでも味わった。銀のティーポットみたいに何度も閉じ込められ、あちこち運ばれ、町を追い出され、さらし台に立たされ、鞭打たれ、追い回され、こき使われた。どこで生まれたかなんてお前らと同じくらい分からない。最初に自分を知覚したのはエセックスで、カブを盗んで生きていたころだ。誰か、鍛冶屋の男が俺から逃げていって、火も一緒に持っていかれて、俺は凍えるばかりだった。
自分の名前がマグウィッチだと知っていた。洗礼名はエイベル。なぜ知っていたか? 生垣の鳥がカワラヒワ、スズメ、ツグミって呼ばれてるのを知っていたのと同じくらいさ。全部ウソかもしれないと思ったが、鳥の名が本当だったから、自分の名もそうだと思った。
調べた限り、若いエイベル・マグウィッチを見て怖がらずに近づく奴はいなかった。みんな追い払うか、捕まえるかだった。俺は何度も捕まった。捕まって捕まって、ついには“捕まるのが当たり前”になった。
みすぼらしい小さなガキの時、鏡を見ることもなかった(家具付きの家なんて知らなかったからな)、でも「強情な奴」と呼ばれるようになった。『この子はひどく悪い子ですよ』と、刑務所の見学者たちは俺を指して言ったものだ。『この子は牢屋で暮らしてるみたいな子だ』と。それで俺をじっと見て、俺も見返して、頭の大きさを測られたり(腹の方がよかったのに)、読めない小冊子を渡されたり、理解できない説教を聞かされたりした。決まって悪魔について言われた。だが俺はどうしたらよかった? 腹に何か入れなきゃ死ぬだろ? ……まあ、もう“下品”な話はやめとく。坊やとピップの友よ、俺が卑しくなることは心配するな。
歩き回り、物乞いし、盗み、時々働き(お前らなら雇ったかどうか怪しいが)、密猟も少し、農作業も少し、荷馬車も少し、干し草作りも少し、行商も少し――ろくに稼げず、厄介ごとにしかならないことを少しずつやって大人になった。トラベラーズ・レストで隠れていた脱走兵に読み書きを教わり、サインを一回一ペニーで書く旅回りの巨人に字を習った。もう以前ほどしょっちゅう捕まらなくなったが、鍵金属はしっかり消費した。
エプソムの競馬で、二十年以上前の話だが、ある男と知り合った。この火かき棒でロブスターの爪みたいに頭蓋骨を割ってやりたいほどの奴だ。名前はコンピソン。――坊や、昨日君が語った通り、あの溝で俺が殴りつけていたのがその男だ。
コンピソンは紳士気取りで、寄宿学校に通い、教養もあった。話し上手で、上流の作法にも長けていた。見た目も良かった。大レースの前夜、俺は彼をヒースの屋台で見つけた。彼と他の連中がテーブルに座っていて、店主が俺を紹介した。
コンピソンは俺をじっと見て、俺も見返した。彼は時計、鎖、指輪、ブローチ、立派な服を身につけていた。
『見た感じ、運が悪そうだな』と彼は言った。
『はい、旦那、もともと運は良くありません』(その時キングストンの留置場から出たばかりで、罪は浮浪だった。もっと重い罪だったかもしれんが、そうじゃなかった)
『運は変わるもんだ』とコンピソンは言った。『君の運も変わるかも』
『そうならいいですね、余地はたくさんあります』
『何ができる?』と聞かれ、
『食って飲むことならできます、材料を用意してくれれば』
コンピソンは笑い、俺をまた見て、五シリング渡し、翌晩も同じ場所に来いと約束した。
翌晩同じ場所に行くと、彼は俺を雇い、“相棒”にした。で、コンピソンの仕事とは何だったか? 詐欺、筆跡偽造、盗難証書の流通、そういう類だ。自分の頭で罠を仕掛け、手は汚さず利益だけ得て、他人をはめるのが仕事。鉄のヤスリより心がなく、死体のように冷たく、悪魔の頭を持っていた。
コンピソンにはもう一人“アーサー”という男がいた。下の名前じゃなく姓だ。体が弱っていて影のようだった。数年前、彼とコンピソンは裕福な女性を巻き込んで大金を得たが、コンピソンは賭け事で浪費していた。アーサーは貧困の中で死にかけ、コンピソンの妻(彼女はよく蹴られていた)が時々彼を気遣っていたが、コンピソンは誰にも何にも同情しなかった。
俺はアーサーを見て警戒すべきだったかもしれんが、しなかった。その必要もない。だから俺はコンピソンと組み、彼の手のひらの上の道具に過ぎなかった。アーサーはコンピソンの家の屋根裏に住み(ブレントフォード近く)、コンピソンは食事代や部屋代をきっちり請求していたが、そのうちアーサーはあっけなく死んだ。二度か三度目に会った夜、彼は夜中にフランネルの寝間着姿で汗だくで降りてきて、コンピソンの妻に言った。『サリー、彼女が今ぼくの部屋にいる、追い払えない。全身白で、白い花を髪に挿して、正気じゃない。腕には死装束がかかっていて、朝五時にそれを着せると言ってる』
コンピソンは強がったが臆病者だった。『おい、そんな女は生きてるんだぞ。どうやって上がったんだ、ドアも窓も閉まってるのに?』
『どうやっているのか知らないけど、ベッドの足元の隅に立って怒ってる。あんたが心を壊したところ――あんたが壊した! ――そこから血が垂れてる』
コンピソンは強がるが、決して自分では近づかない。『このうつけた病人のところへ行け』と妻に言い、俺にも手伝えと言った。
コンピソンの妻と俺は彼をまたベッドに運び、彼はひどくうなされた。『ほら、見てみろ! あの死装束を振ってる! 見えないか? 目を見てみろ! 正気の沙汰じゃないだろ?』次に『あいつに着せられたらおしまいだ! 取り上げてくれ、取り上げて!』と叫び、俺たちにしがみついて、彼女と話し続けて、俺まで見えた気がした。
コンピソンの妻は慣れていたので酒を飲ませ、やがて落ち着いた。『ああ、消えた! あの世話人は来たのか?』『ああ、来たわ』『鍵をかけて閉じ込めてくれと伝えたか?』『ええ』『あの酷いものを取り上げてくれと?』『ええ、全部大丈夫』『君はいい人だ、絶対に僕を見捨てないで、ありがとう!』
しばらく静かだったが、五時前になると急に叫びだした。『来た! また死装束を持ってる。開いてる。隅から出てきた。ベッドに来る。ふたりとも押さえてくれ――どちらかが両側で――あれに触らせるな。ああ、今度は外した。肩にかけさせないで。起こして巻きつけさせないで。持ち上げられる。押さえてくれ!』それで彼は必死に体を起こし、そして死んだ。
コンピソンは、両方にとって良い厄介払いだと平然としていた。俺たちはすぐ商売に戻り、まず彼が俺に(いつもながら巧妙に)自分の本――この小さな黒い本だ、坊や、さっき君の友に誓わせた本――に誓いを立てさせた。
コンピソンが企て、俺がやったことは長くなるから省くが、要するに、あの男は俺を完全に意のままにし、常に借金漬け、常に支配され、危険にさらされていた。奴は俺より若かったが、頭が切れ、学もあり、五百倍も上手だった。俺の女房も苦労した――いや、まだあの人の話はしていなかったな――」
彼は記憶の本でページを見失ったような顔で辺りを見回し、暖炉に顔を向け、両手を膝に広げ、また手を上げては戻した。
「その話はいい。コンピソンとの時代は俺の人生で最悪の時期だった――そう言えば十分だ。俺が単独で軽犯罪の罪に問われて裁判にかけられたことを言ったか?」
僕は「いいえ」と答えた。
「そうなんだ。疑いで捕まったのは4~5年の間で2、3度あったが、証拠がなかった。最後に、コンピソンと俺は重罪で起訴された――盗難証書流通の件で、ほかにもいろいろあった。コンピソンは『弁護は別、連絡は取らない』と言ったきり。俺はあまりにも貧乏で、ジャガーズを雇う前に服を全部売ってしまった。着ているもの以外はな。
法廷で最初に気づいたのは、コンピソンがいかにも紳士で、巻き毛に黒い服に白いハンカチ、そして自分はみすぼらしい悪党だったこと。検察が証拠を端的に述べたとき、いかにそれが俺にばかり重く、奴には軽いか分かった。証人が証言するときも、常に前に出てきて現金を受け取っていたのは俺で、悪事に深く関わっているのも俺。だが弁護側になると、コンピソンの弁護士が言った。『皆さん、ここに二人の人物がいます。一人は若く、良い教育を受けた者、もう一人は年長で悪い環境に育った者。若い者はほとんど関わっていない。年長者は常に関わっている。もし一人が真犯人ならどちらか、二人ならどちらがより悪質か、疑いようがないでしょう』と。人柄の話になれば、コンピソンは学校に通い、同級生が証言し、何の非もなかった。俺は過去に裁判にかけられ、あちこちで知られていた。そして最後の弁論、コンピソンは時々白いハンカチで顔を押さえ、詩まで引用して話をしたが、俺は『この隣の男はとんでもない悪党です』としか言えなかった。判決は、コンピソンには善良な評判と悪い仲間のせいで情状酌量、俺には何もなく有罪。俺が『ここを出たらその面をぶっ壊してやる!』と言うと、コンピソンは判事に保護を頼んで二人の看守が間に立った。量刑では、コンピソンが7年、俺が14年。判事はコンピソンには惜しみがちで、俺は暴力的な累犯者として見なされた。」
彼は興奮で顔を赤らめたが、それを抑え、何度か深呼吸し、手を差し出して僕に安心させるように言った。「俺は卑しくならない、坊や!」
彼はすっかり汗をかいたので、ハンカチで顔や首、手を拭いてから続けた。
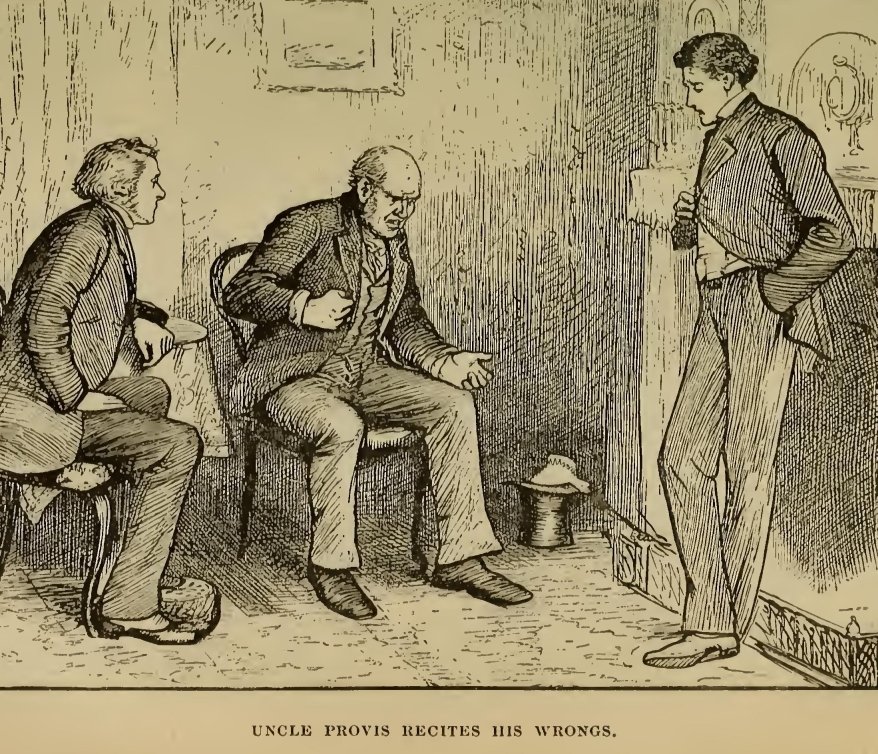
「俺はコンピソンに“その面をぶち壊してやる”と言い、絶対にやると誓った。俺たちは同じ監獄船に送られたが、長い間手が出せなかった。やっと背後から頬を打って、振り向かせて殴ろうとしたとき、見つかって捕まった。あの船の独房は、泳ぎと潜りの達人には大したことなかった。俺は岸に逃げ出し、墓地に隠れて、そこにいる死人をうらやみながら過ごしていた時、初めて“坊や”に会った!」
彼はまた僕に愛情の表情を向け、それがかえって僕には嫌悪感を抱かせた。
「坊やから、コンピソンもあの湿地にいると聞いた。あいつは俺が岸に上がったと知らずに、俺から逃げようと必死で逃げたんだと思う。俺は奴を捕まえ、顔をぶん殴り、『これが一番の仕返しだ、自分のことなどどうでもいい、貴様を引きずって戻してやる』とばかり、兵士が来なくても髪を引っ張って船に戻すつもりだった。
もちろん、向こうは最後まで有利だった――評判が良かったからな。俺が逆上して暴力を振るったせいで、奴は軽罪で済んだ。俺は鉄鎖につながれ、再び裁判にかけられ、終身刑になった。だがこうしてここにいる、坊やとピップの友よ。」
彼はまた汗を拭き、ゆっくりとタバコを取り出し、パイプを詰めて吸い始めた。
「彼は死んだのか?」と僕は沈黙のあとで尋ねた。
「誰がだ、坊や?」
「コンピソンだ」
「もし生きていれば、奴は俺が死んだと思いたいはずだ」と彼は鋭い目で言った。「それきり奴のことは何も聞いていない。」
ハーバートは鉛筆で本の表紙に何か書いて僕にそっと渡した。プロヴィスは火を見つめながら黙って煙をくゆらせている。そこにはこう記されていた――
「若いハヴィシャムの名はアーサー。コンピソンこそがミス・ハヴィシャムの恋人を名乗った男。」
僕は本を閉じ、ハーバートに軽くうなずいて本を脇に置いたが、僕たちは何も言わず、プロヴィスが暖炉の前で煙草を吸うのを見つめていた。
第四十三章
プロヴィスへの嫌悪感がどれほどエステラに由来するのか、今さら考えても仕方がない。馬車乗り場でエステラに会う前、刑務所の汚れを拭い落とそうとした自分と、今エステラの誇り高く美しい姿と、僕が匿う帰還した流刑囚との絶望的な隔たりを思う今の自分とを比べても仕方がない。道のりがなめらかになることも、結末が良くなることもないし、彼のためにも僕のためにもならない。
彼の話によって、あるいはむしろ元からあった不安が形と意味を持ったことで、僕の心に新たな恐怖が生まれた。もしコンピソンが生きていて、彼の帰還を知ったら、何が起こるかは明らかだった。コンピソンが彼を死ぬほど恐れていることは、二人の誰よりも僕がよく知っていた。そして、あのような男が、自分の身を守るために密告という安全な手段で敵を排除するのをためらうとは思えなかった。
僕は決してプロヴィスにエステラのことを口にすまいと決意した。しかし、ハーバートには、外国に行く前にエステラとミス・ハヴィシャムの両方に会わなければならない、と伝えた。これは、プロヴィスが自分の過去を語ってくれたその日の夜、僕たちだけになった時のことだった。翌日リッチモンドに向かう決心をし、実際に向かった。
ブランドリー夫人の家に行くと、エステラの侍女が呼ばれ、「エステラは田舎に行っています」と告げられた。「どこに?」と聞くと「いつものようにサティス・ハウスへ」と。「でも、いつもは僕も一緒なのに」と言うと、「いつ帰るのか」と尋ねても、侍女は「しばらくして戻るだけだと思う」と曖昧に答えるばかりだった。何も分からないまま、わざとそう言っているように感じられ、僕は完全に失意の帰途についた。
その晩も、プロヴィスを送ったあと(彼を送るときは必ず周囲に気をつけた)、ハーバートと相談した結果、僕がミス・ハヴィシャムのもとから戻るまで、外国行きについては何も言わないことに決めた。その間、ハーバートと僕はそれぞれ、どう言い出すのが最善か考えることにした。プロヴィスが疑われていると装うか、それとも僕が海外経験がないから旅行を提案するか。僕が提案さえすれば、彼は必ず同意するだろう。彼をこれ以上危険な状況に置いておけないのは、ふたりとも分かっていた。
翌日、僕はジョーのところに行く約束があると嘘をついて出発することにした。ジョーや彼の名前に関しては、僕はどんな卑劣な真似でもやってしまいそうだった。プロヴィスは僕がいない間、細心の注意を払うようにし、ハーバートが僕の代わりに彼の面倒をみることになった。僕の不在は一夜だけで、帰ったら彼が望む「より規模の大きい紳士としての出発」に向けて行動を始めるつもりだった。その時、彼を買い物やその他の口実でロンドンの川向こうに連れ出すのが、一番うまく国外に逃がす方法かもしれない、と僕もハーバートも思いついた。
こうしてミス・ハヴィシャムのもとへ行く道を整え、まだ夜も明けきらぬうちに早朝の乗合馬車で出発した。夜明けは雲に覆われ、霧の切れ端をまとった乞食のような一日だった。ブルー・ボアの宿に着くと、誰かが門の下から楊枝を手に馬車を見ていた――それはベントレー・ドラムルだった!
彼が僕に気づかぬふりをしたので、僕も同じようにした。どちらにも見え透いた芝居だったが、二人ともコーヒールームに入り、彼は朝食を終え、僕も注文した。彼がこの町に来た理由は分かっていたので、彼の姿を見るのは僕には毒でしかなかった。
読めなくなった古い新聞を、まるで真剣に読んでいるふりをしていた。だが、その地元記事よりも遥かにくっきりと読めるのは、全体に散りばめられたコーヒーやピクルス、魚のソース、グレイヴィ、溶かしバター、ワインなどの染みばかりで、まるで風疹にでもかかったかのような有様だった。私はそんな新聞を手に、テーブルに腰掛けていたが、彼――ドラムルは暖炉の前に立っていた。次第に、彼が暖炉の前を独り占めにしていることが、私には大いなる侮辱に思えてきた。自分も暖炉の恩恵にあずかるべきだと決意し、立ち上がった。薪をかき回そうと暖炉に近づき、彼の脚の後ろに手を伸ばして火かき棒を取ったが、それでもドラムルを知らぬふりで通した。
「これは無視か?」とドラムルが言った。
「おや!」と私は火かき棒を手にしたまま言った。「君だったのか? やあ、元気か? 誰が暖炉をふさいでるのかと思ってたところだ。」
そう言って思い切り火をかき回し、それが済むとドラムルの横に並んで、肩を張り、背中を暖炉に向けて立った。
「今、着いたのか?」とドラムルは肩で私を少し押しやった。
「ああ」と私は今度は自分の肩で彼を押し返しながら応じた。
「いやな場所だな」とドラムル。「君の田舎だろ?」
「そうだ」と私はうなずいた。「君のシュロップシャーに似てるって聞いたが。」
「全然似てないね」とドラムルは言った。
ここで、ドラムルは自分の靴を見つめ、私も自分の靴を見た。するとドラムルは私の靴を見、それから私はまた彼の靴を見た。
「ここには長くいるのか?」私は一歩も暖炉を譲る気はなく、尋ねた。
「もう飽きるほどにはね」とドラムルはあくびのふりをしながらも、同じく譲る気はなかった。
「長く滞在するのか?」
「わからん」とドラムル。「君は?」
「わからない」と私も言った。
このとき、私の血がひりひりして、もしドラムルの肩があと髪の毛一本でも場所を奪おうとしたら、私は彼を窓に投げ飛ばしただろうし、逆に私の肩が同じことをすれば、ドラムルが私を最寄りのボックス席に突き飛ばしたに違いない。彼は軽く口笛を吹いた。私も同じく口笛を吹いた。
「このあたり、広大な湿地があるんだろ?」とドラムル。
「そうだ。それがどうかしたか?」と私は答えた。
ドラムルは私を見てから、また私の靴を見つめ、「ふん」と笑った。
「何が可笑しいんだ、ドラムル?」
「いや、別に。今から馬で出かけて、その湿地を探検してこようと思ってさ。変わった村やら、面白いパブや鍛冶屋があるって聞いた。ウェイター!」
「はい、旦那様」
「俺の馬は準備できてるか?」
「玄関前に回してございます」
「なあ、聞け。あのご婦人は今日は乗らんぞ。天気が悪いからな」
「かしこまりました」
「それと、食事はいらん。これからご婦人の家で食事するからな」
「かしこまりました」
それからドラムルは、分厚い頬に侮蔑的な勝ち誇りを浮かべて私を見やった。その表情は、彼の鈍重さにもかかわらず、私の胸をえぐるようで、私は童話の強盗が老婆を抱えて暖炉に座らせたように、彼を自分の腕で持ち上げて火の中に放りたい衝動に駆られた。
ただ一つ、私たち二人にとって明白だったのは、救いが来るまで、どちらも暖炉から離れられないということだった。私たちは互いに肩を並べ、足と足をそろえて、手を背中に回したまま、一歩も動かなかった。外の霧雨の中、馬が玄関に見え、私の朝食がテーブルに運ばれ、ドラムルの皿は片付けられ、ウェイターは私に食事を勧めた。私はうなずいたが、二人ともその場を動かなかった。
「その後、グローヴには行ったのか?」とドラムルが言った。
「いや」と私は短く答えた。「最後にフィンチたちと会ったときで懲りたよ」
「あれは俺たちが口論したときか?」
「そうだ」と私はぶっきらぼうに返した。
「やれやれ! 君はずいぶん寛大に許してもらったもんさ」とドラムルは嘲るように言った。「怒りっぽいのがいかんよ」
「ドラムル君、その件で忠告できるほど君は適任じゃない。僕が怒りを失ったとしても(その時そうだったとは認めないが)、グラスを投げたりはしない」
「俺は投げるがね」とドラムル。
私はぐっと我慢しつつ、何度か彼を一瞥し、ついには言った。
「ドラムル君、僕はこの会話を望んだわけじゃないし、楽しいとも思わない」
「僕も全然そうは思わない」と彼は肩越しに尊大に言った。「何も感じてない」
「だから」と私は続けた。「今後は一切、どんな会話も交わさないことを提案する」
「まったく同感だ」とドラムル。「僕もそうしようと思ってたし、むしろ黙ってそうするつもりだった。だが怒りは抑えたまえ。もう十分失ってるんじゃないか?」
「どういう意味だ?」
「ウェイター!」とドラムルは私の質問への答えの代わりに呼んだ。
ウェイターが再び現れた。
「聞こえたか? あのご婦人は今日は乗らない、俺はご婦人の家で食事する、それでいいな?」
「かしこまりました!」
ウェイターが私の冷めかけたティーポットを手のひらで確かめ、私に哀願するような目を向けて去っていったあとも、ドラムルは私の肩に触れないように注意しながら、ポケットから葉巻を取り出し端を噛み切ったが、動くそぶりはなかった。私は憤りで喉が詰まり、煮えたぎる思いだったが、ここから一言でも話を続ければエステラの名が出ざるを得ず、それだけは耐えられなかった。だから私は誰もいないかのように壁をじっと見つめ、沈黙を保った。この不毛な膠着がどれほど続いたか分からないが、ウェイターの差し金と思われる三人の裕福そうな農夫がコーヒールームに入ってきて、コートのボタンを外しながら手を擦り合わせ、勢いよく暖炉へなだれ込んできたので、私たちはやむなく場所を譲った。
私は窓越しに、ドラムルが馬のたてがみをつかみ、不格好に乗り上がり、横へ下がったりしながら立ち去るのを見ていた。もう行ったかと思ったら、彼は戻ってきて、口にくわえた葉巻に火をつけるよう呼びかけた。埃色の服を着た男が現れて火を渡し、ドラムルは鞍の上から身をかがめて葉巻に火をつけ、コーヒールームの窓に顎をしゃくりながら笑った。その男のよれた肩とぼさぼさの髪は、背中しか見えなかったが、オーリックを思い出させた。
私はあまりにも気が動転していたので、それが本当に彼だったかどうか気にする余裕もなく、結局朝食にも手を付けなかった。顔と手を洗い、天気と道中の疲れを流してから、あの忘れ難い古い屋敷へ向かった。いっそ一度も足を踏み入れず、決して見なければよかったと、今にして思う場所だった。
第四十四章
化粧台のある部屋、壁の蝋燭が灯るその場所で、私はミス・ハヴィシャムとエステラに出会った。ミス・ハヴィシャムは暖炉のそばの長椅子に腰を下ろし、エステラはその足元のクッションに座っていた。エステラは編み物をしていて、ミス・ハヴィシャムはそれを見守っていた。私が入ると二人ともこちらに目を上げ、そして私に何か変化があったことを見抜いた。そのことは二人が視線を交わした様子から伝わってきた。
「どんな風の吹き回しで来たの、ピップ?」とミス・ハヴィシャムが言った。
彼女はじっと私を見つめたが、どこか動揺しているようだった。エステラは編み物の手を一瞬止めて私を見つめ、また編み続けた。その指の動きから、まるで黙字法で告げられたかのように、私は自分の本当の後援者を知ったことを彼女が察しているのだと感じた。
「ミス・ハヴィシャム、私は昨日リッチモンドへ行き、エステラに話をしようとしました。しかし、何かの風に押されて彼女がここに来たのを知り、私も後を追いました」
ミス・ハヴィシャムが三度か四度目で座るように促したので、私は化粧台のそばの椅子に腰を下ろした。そこはかつて彼女がよく座っていた場所で、今や私の足元にも周囲にも荒廃が広がっていたが、その日は不思議と自然な居場所だと思えた。
「エステラに言いたいことは、いずれあなたの前で言います。あなたを驚かせもしませんし、不快にもしません。私は、あなたが私に望み得る限り不幸です」
ミス・ハヴィシャムはじっと私を見つめ続けた。エステラの編む指は、私の言葉に集中していることを示していたが、彼女は目を上げなかった。
「私は自分の後援者が誰かを知りました。幸運な発見ではなく、名声や地位、財産、何一つ私を豊かにしてくれるものではありません。これ以上は申し上げられません。それは私の秘密ではなく、他人のものなのです」
私はしばらく黙ってエステラを見つめ、次にどう言うべきか考えていた。ミス・ハヴィシャムが「それはあなたの秘密ではなく、他人のもの。で?」と繰り返した。
「最初にここへ連れてこられたとき、ミス・ハヴィシャム、あちらの村に住んでいた頃――今では二度と離れなければよかったと思う――私は本当に、どこにでもいるような少年が偶然呼ばれるのと同じく、何かの欲求や気まぐれを満たすための小間使い、つまり報酬をもらうための存在としてここに来たのでしょうか?」
「そうだよ、ピップ」とミス・ハヴィシャムはしっかりとうなずいた。「その通りだ」
「それでジャガーズ氏が――」
「ジャガーズ氏は」とミス・ハヴィシャムはきっぱりと言った。「何も知らなかったし、関わってもいない。彼が私の弁護士で、君の後援者の弁護士でもあるのは偶然だ。彼は多くの人とそういう関係にあるし、自然にそうなることもある。たまたまそうなっただけで、誰が働きかけたわけでもない」
彼女のやつれた顔からは、少なくともここまで何も隠し立てやごまかしがないことが明らかだった。
「でも、私が長い間信じていた誤解に陥ったとき、少なくともあなたはそれを黙認し、私をそのまま導いたのでは?」
「そうだ」と彼女はまたしっかりとうなずいた。「私は君をそのままにしておいた」
「それは親切でしたか?」
「私は誰だというのだ!」とミス・ハヴィシャムは杖で床を叩き、突然激怒して叫んだので、エステラも驚いて顔を上げた。「私は一体、神の御前で誰だというのか、親切にする義務が私にあるものか!」
私が訴えたのは弱い不満に過ぎず、本来そんなつもりではなかった。そう伝えると、彼女はそのまま沈思し続けた。
「まあ、もういい。それで?」
「私はここでの勤めに対しては、弟子入りという形で十分に報われてきました。ただ自分のために訊いただけです。このあとお話しすることは、もっと無私の目的――そうであってほしい願いも込めて――です。私の誤解を黙認したことで、あなたはあなた自身の利己的な親族たちに罰を与え、あるいは実験したのでしょうか? もしよろしければ、その意図を表す言葉をご自身で補ってください、非難するつもりはありません」
「そうだよ。だって彼らがそう望んだのだから! 君もそうだったろう。私のこれまでの人生を考えてみなさい。彼らや君に、そうしてくれるなと頼み込む理由が私にあったかい? 君自身が自分の罠を仕掛けたのだ。私は一度たりともその罠を作ったことはない」
またしても彼女は激しく、しかし突発的にこう言ったので、私は彼女が落ち着くのを待ってから続けた。
「私はあなたの親族の中の一家と関わり、ロンドンに出てからは常に彼らの中にいました。彼らも私と同じく、正直に誤解していたことを知っています。ですから、あなたが望もうと望むまいと、また信じようと信じまいと、私がこれを伝えなければ裏切りであり卑劣になるでしょう。もしあなたがマシュー・ポケット氏と息子ハーバートを他の親族と同様に見ているなら、それは大きな誤りです。彼らは寛大で、正直で、率直で、何かを企むような人間ではありません」
「彼らはあなたの友人なんでしょう?」とミス・ハヴィシャム。
「彼らは、私が彼らの立場を奪ったと思っていたときでさえ、私を友人にしてくれました。サラ・ポケットやジョージアナ、カミラたちが私に冷たかったときにも、です」
この比較が彼女に良い印象をもたらしたらしく、私は嬉しく思った。ミス・ハヴィシャムはしばらく鋭い眼差しで私を見つめ、それから静かに言った。
「彼らのために何を望むの?」
「ただ」と私は答えた。「他の親族と一緒くたにしないでほしいのです。同じ血を引いていても、決して同じ性質ではありません」
ミス・ハヴィシャムは再びじっと私を見つめ、「彼らのために、何を望むの?」と繰り返した。
「あなたにはお見通しでしょうが」と私は少し顔を赤らめて答えた。「やはり私は何かを望んでいます。ハーバートに彼の一生のためになる援助を、彼に気付かれない形でしていただけたら、その方法をお示しできるのです」
「なぜ彼に知られずにやる必要があるの?」と彼女は棒を握り直して、より注意深く私を見つめながら尋ねた。
「なぜなら」と私は答えた。「私は二年以上前から彼に内緒でこの援助を始めており、裏切られたくないのです。なぜ最後までやり遂げられないかは説明できません。それは私の秘密ではなく、他人のものなのです」
彼女は徐々に私から視線を外し、火に目をやった。沈黙とろうそくの光の中で、長く思えるほど火を見つめていたが、赤い炭が崩れる音で我に返り、また私を見た――最初は虚ろに、やがて集中した注意で。エステラはずっと編み物を続けていた。ミス・ハヴィシャムが私に注意を定めると、まるで会話が途切れていなかったかのように言った。
「ほかには?」
「エステラ」と私は彼女の方に向き直り、震える声を抑えようと努めながら言った。「君が好きだ。長い間、心から君を愛してきたことを知っているだろう」
彼女は指を動かしながら私を見つめ、無表情のまま顔を上げた。ミス・ハヴィシャムも私と彼女を交互に見やった。
「もっと早く言うべきだった。しかし、ずっと誤解していたせいで、ミス・ハヴィシャムが私たちを結びつけようとしていると希望を抱いてしまった。君が自分の意志でどうにもならない立場だと思っていたから、言わずにいた。だが、今は言わなければならない」
エステラは微動だにせず、編み針を動かしながら首を横に振った。
「その仕草で分かっている」と私は応じた。「分かっている。君を自分のものと呼べる望みがないことも。私は自分が間もなくどうなるのか、どんなに貧しくなるのか、どこへ行くことになるのか、何も分からない。だが、君を愛している。初めてこの家で会ったときから、ずっと君を愛してきた」
彼女は依然として無表情で針仕事を続け、またもや首を横に振った。
「もしミス・ハヴィシャムが、貧しい少年の感受性をもてあそび、何年も空しい希望と無駄な追いかけで苦しめたのだとしたら、それは残酷を極めている。しかし、彼女も深くは考えなかったのだろう。自分自身の試練に耐えるあまり、私の苦しみを忘れていたのだと思う、エステラ」
私はミス・ハヴィシャムが胸に手を当てて、それをそのまま押さえながら、エステラと私を交互に見つめているのを見た。
「どうやら」とエステラはとても冷静に言った。「私には理解できない感情や幻想があるようね。あなたが私を愛していると言っても、それが言葉として何を意味するかは分かるけれど、それ以上のものじゃない。あなたの言葉は私の胸に何一つ響かないし、何も感じないの。私はあなたの言葉なんて全く気にしない。これまでにも警告しようとしたわ、違う?」
私は惨めに「そうだ」と答えた。
「そう。でもあなたは警告を受け入れなかった、私が本気だとは思わなかったからでしょ? 違う?」
「君が本気じゃないと思いたかった、そう願っていた。君のように若く、経験もなく、美しい人が――それは人間の本性に反すると思ったんだ」
「それが私の本性なのよ」と彼女は返した。そして言葉に力を込めて付け加えた。「私の中で形作られた本性よ。他の人たちとあなたを区別してこれだけ言えば、もう十分。これ以上はできない」
「本当なのか」と私は言った。「ベントレー・ドラムルがここに来て、君に言い寄っているのは?」
「本当よ」と彼女は、まったく軽蔑しきった無関心な態度で答えた。
「君は彼を励まし、一緒に乗馬し、今日まさに彼と食事を共にするのか?」
彼女は私がそれを知っていることに少し驚いたようだったが、再び「本当よ」と答えた。
「彼を愛していないはずだ、エステラ!」
そのとき初めて彼女の指が止まり、少し怒ったように「何度言えば分かるの? それでもまだ私が本気じゃないと思うの?」と返した。
「君は彼と結婚したりはしないだろう、エステラ?」
彼女はミス・ハヴィシャムの方を見て、少し考えてから手元の作業を止めた。そして、「なぜ本当のことを言ってはいけないの? 私は彼と結婚するつもりよ」と言った。
私は顔を手で覆い、彼女のその言葉にどれほど苦しめられたかにしては、自分でも意外なほど感情を抑えることができた。顔を上げると、ミス・ハヴィシャムの顔にはあまりにもおぞましい表情が浮かんでいて、私の激情と悲しみの中でも強烈な印象を残した。
「エステラ、お願いだ、ミス・ハヴィシャムの導きでこんな破滅的な決断をするのはやめてくれ。僕を永遠に拒んでもいい、もうそうしたのは分かっている。でも、ドラムルよりもふさわしい人に自分を委ねてほしい。ミス・ハヴィシャムが君を彼に与えるのは、君を本当に愛する少数の人間たちや、君を賞賛する多くの人間たちにとって、最大の侮辱であり傷なのだ。その少数の中には、僕ほど長くは愛していなくても、君を同じくらい深く愛する人がいるかもしれない。その人と一緒になってくれるなら、僕は君のためにもっと耐えられる!」
私の激情は、彼女の中にもし理解できれば同情に触れたかもしれないような不思議な驚きを引き起こした。
「私は」と彼女は再び穏やかな声で言った。「彼と結婚するつもりよ。結婚の準備は進んでいるし、もうすぐ結婚するわ。なぜ私の養母の名前を持ち出して傷つけるの? これは私自身の意志よ」
「自分の意志で、あんな男と結婚するのか、エステラ?」
「誰となら結婚したらいいの?」と彼女は微笑んで返した。「自分にとって何の意味もない相手が一番早くそのことを感じるでしょう? ――もし人がそんなことを感じるものなら。もう決まったの。大丈夫、私も夫もきっとうまくやれるわ。いわゆる『破滅的な決断』に導かれたというのは違う。むしろミス・ハヴィシャムは結婚をまだするなと言ったけれど、私は今の生活に飽きたの。もう魅力なんてほとんどないから変えてもいいと思うの。もう言わないで。私たちは決して分かり合えない」
「なんて卑劣で愚かな男なんだ!」と私は絶望的に訴えた。
「私が彼にとって祝福になるなんて心配しないで」とエステラ。「私はそんな存在にはならない。さあ、これでお別れよ、夢見る坊や――それとも大人?」
「エステラ!」と私は答えた。苦い涙が彼女の手にこぼれ落ち、どうしてもこらえきれなかった。「たとえイギリスに残り、みんなと同じように顔を上げていられるとしても、どうして君がドラムルの妻である姿を見られるだろう?」
「ばかね」と彼女は返した。「そんなのすぐに忘れるわよ」
「決して忘れられない、エステラ!」
「一週間もすれば、私のことなんて考えなくなるわ」
「君が消える? 君は僕の存在の一部で、僕の自分そのものだ。ここに初めて来たあの日、君に傷つけられた貧しい少年の心以来、僕が読んだ本のすべての行に、君はいた。川でも、船の帆でも、湿地でも、雲でも、明るさの中でも闇の中でも、風の中でも森でも、海でも、街でも――僕が見てきたあらゆる光景に、君の姿があった。僕の頭の中で生まれたどんな美しい幻想も、いつも君が体現していた。ロンドンの頑丈な建物を形作る石よりも、君の存在と影響は僕にとって現実で、決して動かしようがなかった。この先もそうだ。エステラ、僕の命の最後の瞬間まで、君は僕の人格の一部であり、僕にあるわずかな善の一部であり、悪の部分の一部でもある。でも、これからは君を善いものとだけ結びつけて思い出す。たとえ今、どんな苦しみを感じていても、君は僕に害よりずっと多くの善をもたらしてくれた、と僕は信じる。――神が君を祝福し、許してくれますように!」
どうやってこの断片だらけの言葉を自分の中から絞り出したのか分からない。内なる傷からほとばしる血のように、激情があふれ出た。私は彼女の手を唇に当ててしばし離さず、そして去った。しかしその後、すぐに、より強い理由で――エステラがただ信じられないという顔で私を見ていたが、ミス・ハヴィシャムの幽霊のような姿は、手で胸を押さえながら、哀れみと後悔の表情そのものに変わっていたことを、私は思い出すことになる。
すべて終わった、すべて去った! あまりにも多くのことが終わり、過ぎ去ったので、門を出たとき、外の光は入ったときよりも暗く感じられた。しばらくは路地や小道に身を潜め、その後ロンドンまで歩いて帰る決心をした。そのときには、宿に戻ってドラムルに会うことも、馬車に乗って人と話すことも、自分のためになるとすればただとことん歩き疲れることしかない、と思い至っていたのだ。
ロンドン・ブリッジを渡ったのは真夜中を過ぎていた。あの時代、川のミドルセックス岸寄りに西へ向かう狭い路地の入り組みを進み、私がテンプルに最も近道で入るには、ホワイトフライアーズの川沿いの門から入るのが常だった。明日まで自分は戻らないことになっていたが、鍵を持っていたし、ハーバートが寝ていても自分ひとりでベッドに入れるはずだった。
テンプルが閉じたあと、ホワイトフライアーズ門から戻ることは滅多になかったし、泥だらけで疲れ切っていたので、門番が私をじっと見て門を少しだけ開けてくれたときも、不快には思わなかった。名前を名乗って彼の記憶を助けた。
「はっきりしませんでしたが、たぶんそうかと思ってました。こちらに手紙が届いています。持ってきた使いが『ぜひ、ここで読んでくれ』と言ってました」

私は驚きつつその手紙を受け取った。宛名はフィリップ・ピリップ殿、その上に「ここでお読みください」と書かれていた。封を切ると、中にはウェミック氏の筆跡で――
「帰宅するな」
第四十五章
テンプルの門で警告を読んだ私は、すぐさまフリート街へ向かい、夜も遅くに馬車を拾ってコヴェント・ガーデンのハマムズへ向かった。あの時代、そこでは夜中でも必ず部屋が取れた。用意の良い管理人が私をすぐに中へ通し、棚に並ぶ蝋燭の次の一本に火を入れ、名簿の次の部屋に案内してくれた。それは建物の裏、一階の半地下のような部屋で、巨大な四本柱のベッドが部屋中を占拠し、傲慢にも一本の脚を暖炉に、もう一本を出入口に突っ込んで、かわいそうな洗面台を神聖不可侵のごとく押しつぶしていた。
私は夜間灯を頼んでおいたので、管理人はその善き時代の伝統的な蝋燭――まるで幽霊のような杖の形で、触れるとすぐに折れ、点火もできず、穴だらけの高いブリキの筒の底に孤独に収められたもの――を持ち込んでくれた。ベッドに入って、足も心も疲れ切ったまま横になったが、自分の目を閉じることは、この愚かなアルゴスの目(※ギリシャ神話の百目の巨人)を閉じるのと同じくらい無理だった。そして夜の闇と死の中で、私たちはじっと見つめ合った。
なんと陰鬱な夜だったことか! 不安で、憂鬱で、長い夜だった。部屋には冷たい煤と熱い埃が入り混じったもてなしのない臭いが漂い、ベッドの天蓋を見上げると、肉屋から来た青蠅や市場のゲジゲジ、田舎の幼虫たちが夏に備えて潜んでいるのだろうと思われた。そしてその中の何匹かが落ちてくるのではないかと想像し、顔に何か軽く落ちる感触を感じた気がして、さらに背中にもぞもぞと不快なものが這い上がってくるような考えに囚われた。しばらく眠れないでいると、静寂に満ちた部屋のあちこちから妙な音が聞こえてくるようになった。戸棚はささやき、暖炉はため息をつき、洗面台はカチカチと音を立て、引き出しの中ではギターの弦が時折鳴った。同時に、壁の円い穴の一つ一つが新たな表情を帯び、そのどれにも「帰宅するな」と書かれているように見えた。
夜の空想や物音がどれほど私を取り巻こうとも、「帰宅するな」という警告だけは消えなかった。それはどんな思考にも編み込まれ、まるで身体的な痛みのようになった。少し前、新聞で「夜中にハマムズに来て自殺した身元不明の紳士が朝、血の海で見つかった」と読んだばかりだった。彼がまさにこの部屋に泊まったのではと頭をよぎり、ベッドを出て血の跡がないか確かめ、廊下に出て、遠くに誰か(管理人)が眠っている明かりを見て心をなだめた。だがその間も、なぜ家に帰ってはいけないのか、家で何があったのか、いつ帰ればいいのか、プロヴィス(エイベル・マグウィッチ)は無事か――そんな疑問が頭から離れず、他の何も考えられなかった。エステラと今日永遠に別れたこと、その時の彼女の表情や口調、編み物の指の動きさえ思い返しても、思考の隅々で「帰宅するな」という警告がまとわりついていた。ついには心身ともに疲れ果ててまどろんだが、その時は「帰宅するな」が巨大な影のような動詞となり、命令法現在「君は帰宅するな、彼も帰宅するな、私たちも帰宅するな、君たちも帰宅するな、彼らも帰宅するな」を延々と変化させる羽目となった。続いて可能法でも「私は帰宅できない、帰宅すべきでない、帰宅してはならない」などと頭の中で繰り返し、ついには気が狂いそうになって枕を転がし、また壁の丸い目を見つめた。
私は朝七時に起こしてもらうよう頼んでいた。ウェミック氏に会うまでは誰にも会えないこと、そして彼のウォルワースの心情だけが頼りだと分かっていたからだ。あんな惨めな夜を過ごした部屋から出られるのは救いで、二度目のノックも聞かずにすぐ飛び起きた。
八時には「城の砦」(ウェミックの家)が見えてきた。ちょうど小間使いの少女が焼きたてのパンを二つ持って砦に入るところだったので、私は彼女について脇門を通り、跳ね橋を渡って、ウェミックが自分と高齢の父のためにお茶を淹れている場に黙って入った。開け放しの扉からベッドにいる高齢の父の姿が見えた。
「やあ、ピップさん!」とウェミック。「帰宅したんだね?」
「ああ」と私は答えた。「でも家には帰ってない」
「それでいいんだ」と彼は手を擦った。「テンプルの門ごとに手紙を残しておいたんだ。どの門から来た?」
私は答えた。
「昼のうちに他の門の手紙は処分しておくよ。証拠書類は極力残さないのが鉄則でね、いつ悪用されるか分からないから。ちょっと失礼するけど、Aged P.(お父上)のためにこのソーセージを焼いてくれないか?」
喜んで、と私は言った。
「じゃあ、メアリー・アン、お前は用事に戻っていいよ」とウェミックは少女に言い、彼女が消えると私にウィンクした。「これで二人きり、分かるだろ?」
私は彼の友情と注意深さに礼を述べ、Aged P.のソーセージを焼きながら、小声で話を続けた。ウェミックはパンにバターを塗っていた。
「さて、ピップさん」とウェミックは言った。「私と君は信頼関係にあるし、今日までにも秘密のやりとりをしてきた。公式な立場は別物だが、今は非公式な話だ」
私は同意した。あまりに緊張して、Aged P.のソーセージを火にかけすぎて炎上させ、あわてて吹き消さねばならなかった。
「昨日の朝、偶然なんだけど」とウェミックは話し始めた。「君を一度連れて行った場所――ここだけの話、なるべく名前は口にしない方がいい――で話を聞いたんだ」
「そのほうがいい。分かってる」と私は答えた。
「つまり、偶然耳にしたんだが」とウェミックは続けた。「とある人物がいて、それほど植民地的な生き方をしてるわけでもなく、携帯財産も持ち歩いていて――本当のところ誰だか分からないし、名前は出さない――」
「出す必要はない」と私は言った。
「――その人物がある場所で少し騒ぎを起こしたらしい。多くの人が行く場所で、みんな自分の意思で行くわけじゃないし、政府の費用で行くことも珍しくない――」
彼の顔を見ながら話を聞いていると、私はまたしてもAged P.のソーセージを炎上させそうになり、彼と自分の注意を大いに乱してしまったので、謝罪した。
「――その人物がその場所から姿を消し、それ以来消息不明になったというわけ。それで、君がテンプルのガーデン・コートの部屋にいるのが見張られていた、あるいはこれからも見張られるかもしれないという話も聞いた」
「誰に?」と私は尋ねた。
「そこは言えないな」とウェミックははぐらかした。「公式な責任に支障が出るかもしれないから。ただ、かつて他でも奇妙な話を聞いたことがあるように、たまたま聞いたってだけ。情報提供者として言うわけじゃない。ただ聞いただけ」
彼は私からソーセージを受け取り、Aged P.の朝食をきれいにトレイに載せた。届ける前に白いナプキンを持って部屋に入り、父親のあごの下に巻きつけ、枕を高くし、ナイトキャップを斜めにかぶせて粋な風貌に整えた。そして朝食を丁寧に前に置き、「元気かい、Aged P.?」と声をかけた。上機嫌な父親は「元気だよ、ジョン、ありがとう!」と答えた。Aged P.が見せられる状態ではないことは暗黙の了解らしく、私は知らぬふりを通した。
「私の部屋が見張られている(以前も疑ったことがある)が、それはあなたが示唆した人物と切り離せないのか?」と彼が戻ったとき尋ねた。
ウェミックは真剣な顔で言った。「自分の知識では断言できない。最初からそうだったかもしれないし、そうじゃなかったかもしれない。でも、今はそうだろうし、すぐにそうなるか、かなり危険な状況だ」
彼がリトル・ブリテンの誠実さゆえに言葉を控えていること、彼がここまで言ってくれることに感謝しながらも、私はそれ以上詮索しなかった。しかし、しばらく暖炉の前で考えた後、一つだけ質問したいと伝え、答えるか否かは彼の判断に任せると告げた。彼は朝食の手を止め、腕組みしてシャツの袖をつまみ、(室内では上着なしが彼の快適スタイルだった)うなずいて私の質問を待った。
「悪名高い男で、本当の名をコンピソンという者を聞いたことがあるか?」
彼はうなずいて答えた。
「生きているのか?」
もう一度うなずいた。
「ロンドンにいるのか?」
彼はまた一度うなずき、口をきつく結び、最後にもう一度うなずいて食事を続けた。
「さて」とウェミックは言った。「質問はここまで」――強調して繰り返したのは私への注意のためだった――「これからは私が昨日聞いたことにもとづいてしたことを話す。まず君をガーデン・コートで探した。いなかったので、クラリカー商会にハーバートを探しに行った」
「彼に会えたのか?」と私は大いなる不安を込めて尋ねた。
「会えたよ。名前も詳細も伏せたまま、もし誰か――トムでも、ジャックでも、リチャードでも――部屋やその近くにいるなら、君がいない間は外に出すよう伝えておいた」
「彼はどうしていいか困っただろうね?」
彼はどうすべきか迷っていた。特に、私が「今はトム、ジャック、リチャードをあまり遠くに移動させるのは危険だ」と意見を述べたことも、その迷いを深めたようだった。「ピリップさん、ひとつ申し上げます。今の状況下では、一度大都会に身を置いたなら、これほど心強い場所はありません。すぐに隠れ家から出てはいけません。じっと身を潜めて、事態が収まるまで待ち、たとえ外国へ出る場合でも、軽はずみに外へ出るものではありません」
私は彼の貴重な助言に礼を言い、ハーバートはどうしたのか尋ねた。
「ハーバートさんはね」とウェミック氏は言った。「しばらく頭が混乱していたが、やがて案を思いついた。実は内緒の話だが、彼は君もご存じの通り、寝たきりの父親を持つ若い女性に求愛している。その父親は、かつて会計係(パーサー)の仕事をしていて、川沿いの出窓のベッドで寝ては、船が川を上下するのを眺めている。君もその娘さんを知っているのでは?」
「直接は知りません」と私は答えた。
実のところ、彼女は「ハーバートのためにならず、お金のかかる友人」として私を歓迎しなかった。ハーバートが最初に私を彼女に紹介しようとしたときも、彼女の反応はあまり芳しくなく、ハーバートも事情を私に打ち明けて、しばらく時を置いてから紹介しようと考えていた。私が密かにハーバートの将来のため手助けを始めてからは、これもまた受け入れることができた。二人には当然、第三者を会わせる余裕もなかったので、私もクララ(クララ・バーリー)の評価が高まったと聞かされてはいたものの、実際には会ったことがなかった。ただし、こうした細かな事情はウェミック氏には話さなかった。
「その出窓の家だが」とウェミック氏は続けた。「川沿い、ライムハウスとグリニッジの間にあるプールの下流で、立派な未亡人が管理していて、家具付きの上階を貸している。ハーバートさんが私に『トム、ジャック、リチャードの仮の住まいにどうか』と相談してきた。私は三つ理由があってたいへん良いと思った。第一に、君たちの行動範囲から完全に外れていて、普段の雑多な通りからも離れている。第二に、君自身が近づかなくても、ハーバートさん経由でトム、ジャック、リチャードの安全は常に把握できる。第三に、時が来て外国船に乗せるときには、そこからすぐに移送できる。まさに願ってもない隠れ家だ」
この説明でだいぶ安心した私は、ウェミック氏に改めて礼を述べ、続けてもらった。
「さて、ハーバートさんは万全の覚悟でこの仕事に取り組み、昨夜九時までにはトム、ジャック、リチャード、どれでもいいが――君も私も詮索する必要はない――を無事に入居させた。元いた下宿では『ドーヴァーへ呼び出された』ということになっていて、実際にドーヴァー道を連れて行き、途中で引き離した。これの大きな利点は、君が関わらずに済んだことと、もし誰かが君の動向を探っていたとしても、君は遠く離れた場所で全く違う用事をしていたことになるので、疑いをそらせる。だから、昨夜帰ってきたとしても、家には戻らないよう勧めたのだ。混乱を増やすことで、より安全になる」
ウェミック氏は朝食を終えると、時計を見て上着に腕を通し始めた。
「さて、ピリップさん」と袖を通しながら言った。「私はできる限りのことをしたつもりだが、もし今後も――ウォルワース流で内々かつ個人的な立場で――何かできることがあれば喜んでやる。これが住所だ。今夜ここへ行って、自分の目でトム、ジャック、リチャードが無事か確認してから帰っても問題ない――昨夜帰宅しなかったもう一つの理由でもある。だが、家に戻った後はここへ戻らないこと。どうぞ遠慮なく、ピリップさん」すでに両手は袖から出ていて、私はその手を握った。「最後に一つ大切なことを強調しておきたい」彼は私の肩に手を置き、厳かな声で囁いた。「今晩のうちに、あの人の携行財産をしっかり確保しておくことだ。彼の身に何が起こるかわからない。携行できる財産だけは何があっても守るんだ」
この点をめぐってウェミック氏を納得させるのは無理だと悟り、私は何も言わなかった。
「もう時間だ」とウェミック氏。「そろそろ行かねば。もし、今日ここで暗くなるまで何も急ぎの用がないなら、ここで静かに一日を過ごすといい。君はだいぶ心労が重なっているようだから、エイジド(老父)と静かに過ごせばきっと体にいい。――すぐ起きてくるから――それと、あの豚を覚えているだろう?」
「もちろん」と私。
「じゃあ、少し食べていきなさい。君が焼いたあのソーセージは、あの豚の肉だ。何もかも一級品だった。懐かしさだけでも、ぜひ食べてみてくれ。じゃあな、エイジド・ペアレント!」と陽気に叫んだ。
「わかったよ、ジョン。わかった、坊や!」と中から老父の声。
私はほどなくウェミック氏の暖炉の前で眠りに落ち、エイジドと私は一日中、代わる代わる居眠りしながら静かな時間を楽しんだ。昼食にはローストポークと屋敷の畑で採れた青菜を食べ、眠気でうなずきそうになるたびに、良い意味でエイジドにうなずいて見せた。すっかり暗くなった頃、私はエイジドがトースト用の火を準備しているのを残し、部屋を出た。紅茶碗の数と、壁の小さな扉を見つめるエイジドの視線から、ミス・スキフィンズが今夜訪れるのだろうと推測した。
第四十六章
八時の鐘が鳴った頃、私は外に出た。空気は、ベンチの造船業者やマスト、オール、滑車の製造者たちの木片や削り屑で、悪くない香りがしていた。ブリッジより上と下のプール沿いの一帯は、私にはまったく未知の土地だった。川沿いに下ってみると、目的地は思っていた場所にはなく、しかも簡単には見つからなかった。その名はミル・ポンド・バンク、チンクスの入り江。チンクスの入り江への手がかりは「古い緑青色の銅製ロープ場」だけだった。
乾ドックで修理中の座礁船や、解体中の老朽船の船体、干潮のぬかるみやヘドロ、造船・解体の工場、何年も使われていないサビついた錨、山のように積まれた樽や木材、目的のロープ場ではない幾つものロープ場――そうした場所を行きつ戻りつしながら、私はついに曲がり角でミル・ポンド・バンクに出た。川風が自由に吹き抜けるこの場所には、木が二、三本生えており、壊れかけた風車の切り株と、月明かりに長く狭い視界が続く「古い緑青色の銅製ロープ場」があった。地面に設置された木枠の連なりは、年老いて歯の抜け落ちた干し草用熊手のようだった。
ミル・ポンド・バンクの奇妙な家々から、木造の正面に三階建ての出窓が並ぶ家を選び、表札を見ると「ウィンプル夫人」とあった。まさに求めていた名である。ノックすると、年配で愛想のよい、幸せそうな女性が現れたが、すぐにハーバートが現れて、何も言わずに私を応接間へ案内し、ドアを閉めた。見慣れた彼の顔がまったく馴染みのないこの部屋で当たり前のように座っているのは、不思議な感覚だった。私は、ガラスや陶器の入った隅の戸棚、暖炉の上の貝殻、壁にかかったキャプテン・クックの死、進水式、国王ジョージ三世がコーチマン風のカツラと皮ズボン、乗馬ブーツ姿でウィンザー城のテラスに立つ彩色版画などと同様に、彼を見つめた。
「すべて順調だよ、ハンデル」とハーバートは言い、「本人も満足している。君に会いたがっているけどね。僕の最愛の娘が父親と一緒にいるので、彼女が降りてきたら紹介するよ。その後で一緒に上の階へ行こう。あれが彼女の父親だ」
私は頭上の唸り声に気づき、顔にも出ていたのだろう。
「彼は困った爺さんなんだ」とハーバートは苦笑し、「でも、会ったことはない。ラム酒の臭いがしないかい? いつも飲んでいる」
「ラム酒を?」と私。
「ああ、そうさ。痛風には優しいだろうね。しかも、食料品は全部自分の部屋に置いて棚に並べてあって、自分で計量して配るんだ。部屋は雑貨屋みたいだよ」
そうこう話している間にも唸り声は次第に高まり、やがて大きな怒号に変わって消えた。
「どうなるかは当然だろう」とハーバートが説明し、「痛風で右手も全身も痛い男が、グロスター・チーズを切ろうとしたら自分を傷つけないはずがないさ」
爺さんは実際にひどく痛そうに、またしても大声で怒鳴った。
「プロヴィスを上階の下宿人に迎えられたのは、ウィンプル夫人にとっては幸運さ。あんな騒音、普通の人は我慢できないからね。いやはや、不思議な所だろう、ハンデル?」
実際、驚くほど清潔に管理された奇妙な家だった。
「ウィンプル夫人は最高の主婦だよ」と私がそう話すとハーバートは言った。「僕のクララは彼女の母のような存在がいなかったら、とてもやっていけなかっただろう。クララは母親も親戚もいないんだ、ハンデル。唯一の身寄りは、あのグラッフアンドグリムだけさ」
「まさか、それが本名じゃないだろう?」
「いやいや、それは僕のあだ名だ。本当はバーリー氏さ。家族に関して心配しなくて済む相手を愛するのは、僕の両親の息子にとって大きな幸運さ」
ハーバートは、以前からミス・クララ・バーリーとハマースミスの学校で知り合い、彼女が父親の看病のため家に戻ったとき、母親代わりのウィンプル夫人に二人の思いを打ち明け、それ以来、彼女の温かい配慮のもと幸福な関係を続けてきたことを改めて語った。バーリー氏本人は、痛風とラム酒と会計係時代の話以外の心理的な話題にはまったく無縁という事情だった。
私たちが小声で話していると、天井の梁を伝ってバーリー老人の唸り声が響く中、部屋のドアが開き、二十歳前後の華奢で黒い瞳をした、実に可愛らしい娘が籠を手に入ってきた。ハーバートは恥ずかしそうにその籠を受け取り、「クララ」と紹介した。まるで凶暴な鬼、バーリー老人に囚われた妖精のような魅力があった。
「見てごらん」とハーバートは籠の中身を見せながら、同情と愛情を込めて微笑んだ。「これが可哀そうなクララの毎晩の夕食割当さ。パンの配給、チーズの一切れ、ラム酒――これは僕が飲む。これはバーリー氏の明日の朝食。ラム肉のチョップ二枚、ジャガイモ三個、割った豆、少量の小麦粉、バター二オンス、塩ひとつまみ、黒胡椒いっぱい。全部煮込んで熱々にして出す。痛風には良さそうだろう!」
ハーバートが指差す一品一品を、クララが諦め顔で見つめる様子は実に自然で、ハーバートの腕に大人しく包まれる仕草には、信頼と愛情、そしてこのミル・ポンド・バンク――チンクスの入り江と古い緑青のロープ場――で守られるべき優しさがあった。私は、バーリー老人が梁で唸ろうとも、彼女とハーバートの婚約を決して壊したくないと思った。
私はクララを眺めて微笑ましく思っていたが、突然唸り声が激しくなり、頭上から恐ろしい衝撃音が響いた。まるで木製の義足を持った巨人が天井を突き破って降りてこようとするかのようだった。クララはハーバートに「パパが呼んでるわ、ダーリン!」と言い残して飛び出していった。
「とんでもないサメ(人食い爺)だろう!」とハーバート。「今度は何がご所望だと思う、ハンデル?」
「さあ、飲み物じゃないか?」
「その通り!」とハーバートは私の当てずっぽうに大喜びした。「彼は小さな桶に酒を混ぜてテーブルに置きっ放しさ。見ていればわかるよ、今からクララが爺さんの体を起こして飲ませるから。ほら、また怒号だ。……今飲んでる。……はい、また唸り声だから、今度はもう横になった!」
やがてクララが戻り、ハーバートが私を連れて二階へ上がった。バーリー氏の部屋の前を通ると、中で嗄れ声で唸る歌が聞こえた――内容は不吉なので好意的な言葉に置き換えておく。
「ああよ、目出度いぞ、ビル・バーリー爺さんだ。寝転ぶ古いビル・バーリーがここにいるぞ、目出度いぞ。ひっくり返ったカレイのように、ビル・バーリーはここに寝てるぞ、目出度いぞ。ああよ、ありがとう」
ハーバートによれば、見えないバーリー老人は日夜こんな調子で独り言を言い続けているのだという。昼間はベッドの望遠鏡で川を覗きながら、片目で港を監視するのが日課だそうだ。
家の最上階の二つの小部屋は清潔で風通しもよく、下階ほどバーリー氏の声も気にならず、そこでプロヴィスは快適に過ごしていた。彼は不安を見せることなく、むしろ何かしら柔らかくなったように感じられた――どう柔らかくなったのか、後から思い出そうとしてもうまく言葉にできなかったが、確かにそうだった。
その日の休息で私も考えをまとめ、コンピソンのことは彼に一切話すまいと決めていた。彼のあの男への憎悪が何か行動に走らせ、破滅を招くのを恐れたからだ。そこで、ハーバートと私が暖炉のそばに座ったとき、まずウェミック氏の意見や情報網について彼の信頼度を尋ねた。
「ああ、もちろん、ジャガーズ氏も知ってる」と彼はうなずいた。
「なら、ウェミック氏と話した内容、注意事項と助言を伝える」と私は言い、前述の通り、ニューゲート刑務所で(誰からかは不明だが)疑念の目がかかっていること、私の部屋が見張られていること、しばらくは身を潜め私も近づかないこと、国外逃亡の準備などを説明した。当然、時が来れば私も同行するか、ウェミック氏の判断で最も安全な形で従うことも伝えた。その先のことはあえて触れなかったし、プロヴィスの柔らかな様子を見ると、自分でも考えがまとまらず、不安だった。この状況で生活費を増やすなど、今の不安定な状況下では無意味どころか馬鹿げているのではないか、とも説明した。
彼もそれは否定せず、終始穏やかで理性的だった。この帰国自体が賭けだったのは承知しているし、無謀な真似はしない、良い支援がある限り安全だと自信を持っていた。
暖炉を見つめていたハーバートが「ウェミック氏の提案から着想したのだが、僕たちは水上の扱いに慣れているから、時が来たら自分たちで川を下って彼を連れて行ける。船や船頭を雇わなくて済み、疑いの目も減る。普段からテンプル桟橋に自分のボートを置いて、練習の名目で川を漕ぐ習慣をつけるのはどうだろう。そうすれば、二十回でも五十回でも目立たないし、回数を重ねれば何も怪しまれない」と提案した。
私はこの案を気に入り、プロヴィスも大変喜んだ。すぐにこれを実行に移し、プロヴィスもミル・ポンド・バンクの東側の窓のブラインドを下ろすことで、無事の合図とすることにした。
すべて決まり、私は帰ることにした。「一緒には帰らず、僕が少し先に出る方がいいね」とハーバートに言い、「ここに残していくのは気乗りしないが、君がここにいる方が僕の近くより安全だろう。さようなら!」
「親愛なる坊や」と彼は私の手を握りしめて言った。「いつまた会えるかわからない、さよならは嫌だ。おやすみと言ってくれ」
「おやすみ! ハーバートが定期的に行き来するし、時が来れば必ず僕も動く。おやすみ、おやすみ!」
プロヴィスは自室に残ることになり、私たちは階段の踊り場で彼の持つ灯りに見送られて下へ降りた。その姿を振り返ると、彼が最初に戻ってきた夜のことを思い出し、当時とは逆の立場ながら、今や彼と別れることがこれほど重く、不安になるとは想像もしなかった。
バーリー老人は私たちが通りかかっても、相変わらず唸り声と罵声を上げ続けていた。階段を下りきったところで、私はハーバートに「プロヴィスという名は使っていないだろうね」と確認し、「もちろん、ここではキャンベル氏になっている。ウィンプル夫人には、僕が彼を託されて世話をしている、隠遁生活が必要な人だとしか知らせていない」との説明だった。応接間でウィンプル夫人とクララが手仕事をしている前でも、私は自分の関心は明かさなかった。
黒い瞳の優しい娘と、真心を失わぬ母性的な女性に別れを告げると、「古い緑青の銅製ロープ場」の印象もすっかり変わった気がした。バーリー老人がどれほど年老いて、どれほど罵声を浴びせようと、このチンクスの入り江には若さと信頼と希望があふれている。私はエステラとの別れを思い出し、深い悲しみを抱えて帰路についた。
テンプルはこれまで以上に静かだった。最近までプロヴィスがいた部屋の窓は暗く、ガーデン・コートにも人影はなかった。私は噴水の周りを何度か歩き、階段を下りて自室へ向かったが、全くの独りきりだった。ハーバートも後から寝床に来て「全くの静けさだった」と報告してくれた。その後、窓を開けて月明かりを眺めながら「石畳は大聖堂の夜と同じくらい厳かに、誰もいない」と語った。
翌日、私はさっそく船の手配をした。すぐに済み、テンプル桟橋に船を置き、いつでも使えるようにした。それから訓練や練習の名目で、時には一人で、時にはハーバートと一緒に川を漕ぎだした。寒さも雨も雪も何度も経験したが、数回外出すると誰も気にも留めなくなった。最初はブラックフライアーズ橋より上流で訓練したが、潮の時間が変わるとロンドン橋方面へも行った。あの頃のロンドン橋は古く、潮の加減で水流が激しく、危険なことで知られていた。それでも私は見よう見まねで橋下を漕ぎ抜けることを覚え、プールの船の間やエリスまで下った。初めてミル・ポンド・バンクを通ったとき、ハーバートと二人でオールを漕いだが、往復どちらでも東側のブラインドが下ろされるのを見た。ハーバートは週に三度は必ず様子を見に行き、私に不安になるような知らせは一切なかった。それでも私は常に警戒心を拭えず、監視されているという思いに捉われ続けた。一度そう思い込むと、何人もの善意の人を疑ってしまうものだ。
要するに、私はいつも隠れているあの無鉄砲な男の身を案じてばかりいた。ハーバートは「潮が下る夜、窓から外を眺めていると、潮がクララのもとへ向かって流れていると思えて嬉しい」と言ったこともあったが、私は「潮はマグウィッチのもとに流れ、もし川面に黒い影があれば、それは彼を追う者かもしれない」と恐れた。
第四十七章
数週間が過ぎても変化はなかった。私たちはウェミック氏からの連絡を待ち続け、彼は一向に動きを見せなかった。もしリトル・ブリテン以外の彼を知らず、城での親しい付き合いもなければ、私は彼を疑ったかもしれないが、今の私は一瞬たりともそうは思わなかった。
私の財政事情は日に日に暗くなり、複数の債権者から催促されるようになった。ついに私自身も手元の現金不足に悩み、手放しても惜しくない装飾品を現金化することで何とかしのいだ。しかし、今の不安定な状況で後見人からこれ以上お金を受け取るのは、無慈悲な裏切り行為だと決意していた。そこで、ハーバートに頼み、開封せずにそのままポケットブックを返却して彼自身の手元に保管させた。彼が名乗りを上げてからは、その寛大さに甘えなかったことに、偽りか本物か自分でもわからぬ妙な満足感を覚えた。
時が経つにつれ、私の心にはエステラが結婚したという確信めいた不安が重くのしかかった。その現実を知るのが怖くて新聞も避け、最後の面会時の話を知るハーバートにも「二度と彼女の話はしないでくれ」と頼んだ。破れた希望の衣の切れ端をなぜしがみつくのか、自分でもよくわからない。読者であるあなたも、去年や先月、先週に似たような矛盾をやらかしたことがあるのではないか?
私の生活は不幸だった。その中でも最大の、山脈の上にそびえる山のような不安――それは消えることがなかった。それでも新たな恐れは生じなかった。どれほど恐怖に駆られて寝床から飛び起きても、ハーバートの帰宅が普段より速くて悪い知らせをもたらすのではと夜ごと耳を澄ませても、日々は過ぎていった。何もせず、苛立ちと不安に耐えながら、私はひたすらボートを漕ぎ、待ち、待ち、待ち続けるしかなかった。
潮の加減で川を下った帰りに、ロンドン橋の泡立つ流れを漕ぎ抜けられないこともあった。そんなときはカスタム・ハウス近くの波止場にボートを預け、後でテンプル桟橋まで運ばせた。これも水辺の人々に私とボートを見慣れさせる狙いがあった。この些細なことから、これから語る二つの出会いが生まれた。
ある二月下旬の夕暮れ、私は波止場に上がった。その日は潮に乗ってグリニッジまで漕ぎ下り、潮の変わり目で引き返した。晴天から霧が立ち込め始め、帰路は船の間を慎重に進んだ。往復とも窓の合図は「異常なし」だった。
寒さに震えていた私はすぐ夕食をとり、その後は寂しい夜をテンプルで過ごすより劇場へ行こうと思った。ウォプスル氏が名を馳せたあの劇場はこの水辺の近く(今はもうないが)にあったので、そこへ行くことにした。ウォプスル氏が演劇界を復活させるどころか、むしろ衰退の象徴のようになっていたのは知っていた。彼は芝居ちらしでは「忠実な黒人」として登場し、貴族の娘と猿と関わったり、ハーバートが見たのは「道化好きのタタール人」役で、顔は赤煉瓦色、帽子には鈴がいっぱいついていた。
私たちが「地理的なチョップハウス」と呼んでいた店で食事をした。テーブルクロスにはビールの泡で描かれた世界地図、ナイフにはグレイビーの地図。今でも市長管轄のチョップハウスは皆、地理的だ。パンくずをつまみながら居眠りし、ガス灯を見つめ、熱気に蒸されて時間を潰した。やがて意を決して劇場へ。
そこで私は、陛下の海軍の高潔なボースン(甲板長)に出会う。実に立派だが、ズボンの一部はきつ過ぎ、別の部分は緩すぎて気になった。彼は小男たちの帽子をひっくり返しつつ寛大で勇敢で、税金なんてとんでもないと憂国の士ぶりを見せる。彼のポケットには布で包んだプディングのような金塊があり、そのおかげで寝具姿の娘と盛大に結婚する。ポーツマスの全人口(前回国勢調査で九名)が浜辺に繰り出して祝歌を歌う。だが黒い顔のスワブ(悪党)が仲間二人を誘って人類を困難に陥れ、これが半夜かかってようやく解決する――小柄な食料雑貨屋が白帽子、黒ゲートル、赤鼻で時計に入り、グリドルを持って聞き耳を立て、後ろからグリドルで皆を叩き倒すことで。するとウォプスル氏(今まで出てこない)は勲章をつけて大使役で現れ、スワブたちは即座に投獄、ボースンにはユニオンジャックを贈る。感極まったボースンは旗で涙を拭き、ウォプスル氏に「お手を拝借」し、氏は堂々とそれに応じて隅に押し込まれ、皆がホーンパイプを踊る。その隅でふてくされた表情のウォプスル氏は、私に気付いた。
二幕目は新作のクリスマス・パントマイム。最初の場面で、私は赤毛糸の足と大きな蛍光顔、赤カーテンのような髪のウォプスル氏らしき人物が雷の製造をしているのを発見し、彼の巨体上司がディナーに帰宅して怯えているのを見てしまい、心が痛んだ。だが次第に正統な役で登場した。若い恋の精が、無知な農夫(父親)が娘の恋人をフロアサックに詰めて一階から落とすという暴挙のせいで助けを求め、厳格な魔法使いが南半球から暴風のように現れ、それがウォプスル氏だった。彼は高帽子に一巻の魔術書を抱え、主に話しかけられたり歌われたり踊られたりして時間を持て余していた。私の方をじっと驚いたように見つめ続けるのが目立って仕方なかった。
ウォプスル氏の視線はますます鋭さを増し、深く考え込み混乱している様子が不可解だった。彼が大きな時計のケースに消えた後も、その表情が頭から離れなかった。劇場を出て一時間後、入り口近くに彼が待っていた。
「こんばんは」私は握手しながら彼と並んで歩き出した。「君が僕に気付いたのはわかったよ」
「ええ、もちろん気付きました、ピリップさん。でも、他に誰がいたと思います?」
「他に?」
「実に奇妙なことですが――でも、私は確かにあの男を見たんです」
私は不安になり、彼に説明を求めた。
「最初に気付いたのが、あなたがいたからかどうか定かではありませんが、たぶん気付いたと思います」
私はつい周囲を見回した。こうした言葉には妙な寒気を覚えるものだ。
「ああ、今は見えませんよ」とウォプスル氏。「私が舞台から下りる前に彼は出ていきました。出ていくのを見ました」
私は疑い深くなっており、役者である彼にも罠があるのではと警戒し、黙って歩きつつ様子を探った。
「あなたと一緒かと一瞬思いましたが、あなたが全く気付かず、その人が背後で幽霊のように座っているとわかった時、そうでないと知りました」
私は再び寒気を覚えたが、彼がプロヴィスのことを探っているのではと警戒して、まだ何も話さなかった。プロヴィスがそこにいたはずがないのだから。
「私が馬鹿に思えるかもしれません、ピリップさん。ですが本当に不思議なのです! これから話すことは、もしあなたから聞かされても信じがたいでしょう」
「そうですか?」
「本当に。ピリップさん、昔々のクリスマスの日を覚えているでしょう。あなたがまだ子供の頃、私がガージェリー家で食事をし、兵士たちが手錠の修理に来たあの日です」
「よく覚えています」
「そして二人の脱獄囚の追跡に参加し、ガージェリーが君を背負って私が先導し、君も必死についてきた――」
「全部覚えていますよ」彼が思う以上に。
「そして、泥溝で二人を見つけ、二人が争い、一方が顔を酷く傷つけられていた」
「今もはっきり目に浮かびます」
「兵士が松明を灯し、両者を中央に囲み、私たちは最後まで見届けに行った。あたりは夜で、松明だけが顔を照らしていた――ここが大事です――闇の中に松明が二人の顔を照らし出していた」
「ええ、すべて覚えています」
「では、ピリップさん。今夜あなたの後ろに座っていたのは、その二人のうちの一人です。あなたの肩越しに私は彼を見ました」
「落ち着け!」と私は心で思い、尋ねた。「どちらだと思います?」
「傷つけられていた方です。間違いありません! 考えれば考えるほど確信が強まります」
「それは不思議ですね」私は努めて平静を装った。「本当に不思議だ」
この会話が私に与えた不安と、コンピソンが「幽霊のごとく」私の背後にいたという特別な恐怖は、誇張しようがない。隠れ家生活が始まって以来、数分でも彼のことを忘れた瞬間があっただろうか。だが、その一瞬にこそ、彼は私のすぐそばにいたのだ。百の扉を閉めて追い出したつもりが、すぐ脇にいた――そう考えると、自分の警戒心がもろくも崩れた気がした。そして、彼がそこにいたのは私がいたからに他ならない。どんなに危険がなさそうに見えても、危険は常に近くで活発に動いているのだ。
私はウォプスル氏に、「男はいつ店に入ってきたのか?」といった質問をした。しかし、彼はそれを答えられなかった。彼は私を見ており、私の肩越しにその男を見たのだった。男の姿をしばらく見てからようやく誰かを思い出したが、最初から漠然と私と結びつけており、昔村にいた頃の私の知り合いだと感じていたのだった。「どんな服装だった?」――裕福そうだったが、特に目立つものではなかった。黒い服だったと思うとのこと。「顔に傷などは?」――いや、そうは思わない、と言った。私もそうだと思った。ぼんやりとした気分で後ろの人々に特に注意を払ってはいなかったが、もし顔に目立つ傷があればきっと気づいただろうと思ったからだ。
ウォプスル氏が思い出せることをすべて伝えてくれ、私が今夜の疲れをねぎらって少しふさわしい飲み物をふるまったあと、私たちは別れた。テンプルに着いたのは十二時から一時の間で、門は閉まっていた。中に入って家に戻るとき、私のそばには誰もいなかった。
ハーバートはすでに帰宅しており、私たちは暖炉の前で非常にまじめな相談をした。しかし、今夜私が知ったことをウェミック氏に伝え、彼の示唆をひたすら待つしかなかった。カースル[ウェミックの家]に足繁く通いすぎては彼を困らせるかもしれないと思い、その伝達は手紙で行った。寝る前に書き、外に出てポストに投函したが、その時もまた近くに誰もいなかった。私とハーバートは、他に手立てはなく、ただ極めて用心深くしているしかないと合意した。そして私たちは実際、以前にも増して(それが可能ならば)慎重になり、私自身はチンクス・ベイスンには、舟を漕いで通るとき以外は決して近づかなかったし、その時もミル・ポンド・バンクを見るのは他のものを見るのと同じく、ただ目に入れるだけだった。
第四十八章
前章で言及した二度目の面会は、最初の面会から約一週間後に起こった。私は再び自分のボートをブリッジ下の船着き場に残し、時刻は前回より一時間ほど早い午後だった。どこで食事をするかも決めかねており、私はチープサイドをぶらぶら歩いていた。あの賑やかな人混みの中で、私ほど心が定まらない人間はいなかっただろう。その時、後ろから追いついてきた誰かが私の肩に大きな手を置いた。それはジャガーズ氏の手であり、彼は私の腕に自分の腕を通した。
「同じ方向へ行くなら、一緒に歩こう、ピップ。どこへ行くつもりだ?」
「テンプルへ行こうと思います」と私は言った。
「思う、だと?」とジャガーズ氏。
「ええ」と、珍しく尋問で彼を上回れた気分になった私は答えた。「実は分からないんです。まだ決めていませんから」
「食事に行くのだろう?」とジャガーズ氏。「それは認めてもいいだろう?」
「はい、認めてもいいです」
「そして、約束はないのか?」
「それも認めて差し支えありません」
「では」とジャガーズ氏は言った。「私と食事をしよう」
私は断ろうとしたが、彼が「ウェミックも来る」と付け加えたので、断る口実を受け入れる返事に変えた。すでに口にした数語は、どちらの返事にもなった。そして私たちはチープサイドを抜け、リトル・ブリテンへと斜めに進んだ。店の窓に灯りが次々と点り、通りのガス灯点灯人たちは午後の喧騒の中、梯子を立てる場所も見つけにくそうに、駆け上がったり降りたり、あちこちの霧のなかに赤い目を次々と開けていった。それは、ハマムズの私の燭台の白い目よりはるかに多く、霊のような壁に開いたものだった。
リトル・ブリテンの事務所では、いつものように手紙を書き、手を洗い、燭台の芯を切り、金庫に鍵をかけて、その日の業務を締めくくった。私はジャガーズ氏の暖炉のそばで手持ち無沙汰に立っていると、炎の上がり下がりによって、棚の上の二つの鋳型が悪魔的な「いないいないばあ」を私に仕掛けているように見えた。片隅で書類を書くジャガーズ氏をかすかに照らしている、太くて粗い事務用ロウソクは、まるで大勢の絞首刑にされた依頼人を偲ぶように、汚れた包帯で飾られていた。
私たちは三人で馬車に乗ってジェラード・ストリートへ向かった。着くとすぐに夕食が用意された。私はその場で、ウェミックのウォルワースでの感情に、たとえ視線すらも遠回しに示すことは思いもよらなかったが、彼と時折親しげに目を合わせることにはやぶさかではなかった。しかし、それは叶わなかった。彼はテーブルから目を上げるたびにジャガーズ氏の方を見て、私にはまるで別人のように、乾ききったよそよそしい態度だった。本当に双子のウェミックがいて、こちらは間違っている方なのだと思えるほどだった。
「ミス・ハヴィシャムの手紙をピップ氏に渡したかね、ウェミック?」とジャガーズ氏は、食事を始めて間もなく尋ねた。
「いえ、まだです」とウェミック。「郵便で出すところでしたが、ちょうどあなたがピップ氏を事務所にお連れになったので。これです」そう言って、彼は私ではなくジャガーズ氏に手紙を渡した。
「二行だけの手紙だ、ピップ」とジャガーズ氏はそれを私に手渡しながら言った。「ミス・ハヴィシャムが、君の住所を確信できなかったので私に預けてきた。彼女は、君が前に話したちょっとした用件で会いたいと言っている。行くつもりかね?」
「はい」と私は答えた。手紙もまさにそのとおりの内容だった。
「いつ行くつもりだ?」
「急な用事がありまして」と私は答えた。その時ウェミックは魚を「郵便局(口)」に入れていた。「だから、いつになるか分かりませんが、できるだけ早く行くつもりです」
「ピップ氏がすぐ行くつもりなら」とウェミックがジャガーズ氏に言った。「返事の必要はありませんね」
この言葉を、遅らせない方がいいという示唆と受け取り、私は明日行くことに決め、そう伝えた。ウェミックはワインを一杯飲み、満足そうな顔でジャガーズ氏を見たが、私には目を向けなかった。
「さて、ピップ! 我らが友人“スパイダー”は」ジャガーズ氏が言った。「うまく立ち回った。彼が賭けを制したな」
私はただ同意するだけで精一杯だった。
「ふむ、彼はそれなりに見どころがあるが、必ずしも思い通りにはいかんだろう。最後には強い方が勝つが、その強さが誰にあるかはまず見極めねばならん。もし彼が本気で、彼女を叩きのめすようなことになれば――」
「まさか!」私は顔を紅潮させ、胸も熱くなって口を挟んだ。「そんな悪党だとは本気で思っていないのでしょう、ジャガーズ氏?」
「そんなことは言っていない、ピップ。あくまで仮定の話だ。もし彼が本気で彼女を叩けば、彼の側に力がつくかもしれないが、知恵比べなら決して勝てない。こんな男がそうした状況でどうなるかなど、二つに一つで予想がつかないものだ」
「その二つとは?」
「我々の“スパイダー”のような男はな」とジャガーズ氏は答えた。「叩くか、へつらうか、だ。へつらってうなるか、へつらって黙るかだが、いずれにせよ叩くかへつらうかだ。ウェミックの意見を聞いてみな」
「叩くか、へつらうかだ」とウェミックは、私に向かってではなく答えた。
「それでは、ベントレー・ドラムル夫人に乾杯だ」とジャガーズ氏は言い、お気に入りのワインをデカンタから注いで三人に分けた。「主導権争いがご婦人の満足のいく形で収まることを祈ろう。ご婦人とご紳士の両方の満足など、けして得られんだろうが。さて、モリー、モリー、モリー、モリー、今日はやけに遅いぞ!」
その時、彼女は料理をテーブルに置きつつ、そばにいた。両手を引くと、数歩後ろに下がり、何か言い訳をつぶやいた。指先の動きが私の注意を引いた。
「どうした?」とジャガーズ氏。
「いえ。今話していた件が、少々つらくて」と私。
彼女の指先はまるで編み物をしているようだった。彼女は主人をじっと見つめ、自分が退室して良いのか、あるいは呼び戻されるのか、判断がつかずにいた。その眼差しは非常に真剣だった。――確かに、私はごく最近、まったく同じような目と手を、忘れがたい場面で見ていた!
ジャガーズ氏は彼女を退室させ、彼女は部屋を滑るように出ていった。しかし、彼女の姿はその場にいるかのように私の前に残った。私はその手と目、流れる髪を見て、私の知っている他の手、他の目、他の髪と比べた。荒れ果てた結婚生活と嵐のような人生を二十年経たあとの姿とも重ねた。私は再び家政婦のあの手と目を見て、かつて廃墟の庭と醸造所を――一人きりではなく――歩いたときに襲った説明しがたい感覚を思い出した。馬車で――一人ではなく――夜道を駆け抜けたとき、窓から私を見つめ、手を振る顔を見て再びよみがえった感覚も思い出した。劇場での識別に役立った連想の一つがあり、今や偶然エステラの名から、あの指先の動き、注意深い目へと一瞬で移ったことで、さらに確信をもたらした。私は、この女性がエステラの母親であることを、絶対的な確信をもって感じた。
ジャガーズ氏は私がエステラといるところを見ており、私が隠さなかった感情を見逃すはずがない。私が「つらい話だ」と言うと、彼はうなずき、背中を叩いてまたワインを回し、食事を続けた。
その後、家政婦が現れたのは二度だけで、どちらも滞在は短く、ジャガーズ氏は彼女に対して厳しかった。しかし、あの手はエステラの手、あの目はエステラの目であり、たとえ百回現れても、私の確信が揺らぐことはなかった。
その夜は沈鬱だった。ウェミックは、ワインが回ってきても、あたかも給料を受け取るかのように事務的にグラスを取り、上司からの尋問にいつでも答えられるようにしていた。ワインの量についても、彼の「郵便局(口)」はどんな手紙の数にも無頓着で対応しているようだった。私にとっては、彼は終始「間違った双子」であり、外見こそウォルワースのウェミックと同じだが中身は別人だった。
私たちは早めに席を立ち、三人で一緒に店を出た。ジェラード・ストリートの靴箱の中で帽子を探しながらも、私は正しい双子が戻りつつあるのを感じていた。ウォルワース方向へ六、七歩も進まぬうちに、私は正しいウェミックと腕を組んで歩いており、間違った双子は夜の空気の中に消え去っていた。
「いやあ、終わった、終わった!」とウェミックは言った。「彼は唯一無二の素晴らしい男だが、食事を共にするには気を引き締めねばならん。それがなければもっと楽に食べられるんだがな」
私はそれが実に的を射た表現だと感心して伝えた。
「君以外にはこんなことは言わないよ」と彼は言った。「君と私の間で話したことは、決して外には出ないと分かっているから」
私は彼に、ミス・ハヴィシャムの養女でベントレー・ドラムル夫人となった女性を見たことがあるかと尋ねた。彼はない、と答えた。唐突になりすぎないように、その後、エイジド(ウェミックの父)やミス・スキフィンズの話をした。ミス・スキフィンズの話題になると、彼は少し得意げな顔をして道の途中で立ち止まり、誇らしげに鼻をかんだ。
「ウェミック、」私は言った。「以前、初めてジャガーズ氏の家へ行く前に、あの家政婦に注目するよう言ってくれたのを覚えているか?」
「そんなこと言ったかな? ああ、そうだったろうな。まったく、今思い出しただけで、まだ気が引き締まりきらんよ」
「“野獣を飼いならしたもの”と、あなたは言っていた」
「で、君はどう呼ぶ?」
「同じ呼び方をするよ。ジャガーズ氏はどうやって彼女を飼いならしたんだい?」
「それは彼の秘密さ。彼女は長年彼のもとにいる」
「彼女の話を聞かせてくれ。特に関心があるんだよ。私たちだけの話だということは分かっているだろう?」
「よし!」ウェミックは答えた。「全ては知らない――いや、全ては知らないが、知っている範囲は話そう。もちろん今はプライベートな立場だ」
「もちろんだ」
「今から二十年ほど前、その女はオールド・ベイリーで殺人罪に問われ、無罪となった。とても美しい若い女性で、ジプシーの血が入っていたとも聞いた。ともかく事件は大騒ぎになったよ」
「でも、無罪になったんだね」
「ジャガーズ氏が弁護した」とウェミックは意味ありげに続けた。「当時は彼もまだ駆け出しでね。だが、人々が驚嘆するほど事件を切り抜け、彼の名を上げた。警察署で毎日陳述に奔走し、裁判でも自ら弁護こそできなかったが、代理弁護士の下で辣腕を振るったよ。被害者は年上で体格も大きく、嫉妬深い野性味あふれる女だった。二人とも放浪生活をしていて、このジェラード・ストリートの女は若くして箒の上をまたいで(いわゆる簡素な結婚式で)男と結婚した。被害者は、その男と年齢も体格も釣り合いが取れていた。事件はたぶん嫉妬が原因だった。被害者はホーンスロー・ヒース近くの納屋で死んでいた。激しいもみ合いの末、首を絞められていた。証拠はほとんどその女しか疑えないものだったが、ジャガーズ氏は“彼女にそれができたとは考えにくい”と主張した。君も知っているだろう」とウェミックは私の袖をつついた。「彼はその時、彼女の手の力なんて全く話題にしなかった。今は時々するが」
私は、以前ディナーの席で彼女の手首を見せられた話をウェミックに伝えていた。
「さて!」ウェミックは続けた。「この女は逮捕された時から非常に巧妙な服装で身を包み、本来よりずっと細く見せていた。特に袖が巧みに仕立てられていて、腕がとても華奢に見えた。怪我は多少あったが、放浪者にしては大したことはなかった。ただ手の甲に裂傷があった。それが爪痕かどうかが争点になった。ジャガーズ氏は“顔の高さまではないが、たくさんの茨をくぐり抜けたはずだ”と主張した。実際、彼女の皮膚から茨の破片が見つかり、証拠として提出されたし、茨そのものにも彼女の衣服の切れ端や血痕が残っていた。だが、彼の一番の主張はこれだ。相手側は、彼女が犯行時期に男の子供――三歳ほど――を激情のあまり殺した疑いがあると持ち出した。ジャガーズ氏はこう切り返した。“これらの傷は爪の痕ではなく茨の痕だ。君たちはこれを爪の痕だと言い、彼女が子供を殺したと仮説を立てる。その仮説を持ち出すなら、その結果も受け入れねばならない。もし子供を殺したなら、子供がしがみついて傷をつけた可能性もあるだろう。だが今問われているのはその殺人ではない。なぜその罪で裁かない? この事件で傷が問題なら、いくらでも説明できるのだ”とね。つまり、陪審員を圧倒して勝ち取ったんだ」
「彼女はそれ以来ずっと彼のもとに?」
「そうだが、それだけではない」ウェミックは言った。「無罪となった直後から、あの通り飼いならされた状態で仕えている。仕事の仕方は後から教わったが、最初から素直だった」
「子供の性別は覚えている?」
「女の子だったと言われている」
「今夜、私に話せることはもうない?」
「ない。君の手紙は受け取り、すぐに処分した。以上だ」
私たちは心から挨拶を交わし、私は新たな思いを胸に帰途についた。しかし、古い悩みから解放されることはなかった。
第四十九章
私はミス・ハヴィシャムの手紙を証明書代わりにポケットに入れた。奇妙な気まぐれで彼女が再会を不審がった場合、この手紙が役立つだろう。翌日、私は再び馬車で町へ向かった。ただし、途中の宿屋で下車し、そこで朝食をとり、残りの道のりは歩いた。なるべく人目を避けて町に入り、出て行くつもりだったからだ。
最良の陽光はすでに失われ、私は裏通りの静かな回廊を抜けた。かつて修道士が食堂や菜園を営んでいた廃墟の片隅は、今や物置や厩舎として使われ、墓の中の修道士と同じように静まり返っていた。大通り裏の鐘の音も、私にはいつにも増して陰鬱かつ遠く感じられ、急ぎ足で人目を避けるうち、それが葬送の調べのように耳に響いた。塔の周りをカラスが舞い、修道院の枯れ木に揺れるさまは、場所が変わってしまったこと、エステラは二度と戻らないことを告げているようだった。
裏庭をはさんだ別棟に住む召使いの一人だった年配の女性が門を開けてくれた。いつものように、暗い廊下には灯した蝋燭が置かれていて、私はそれを手に取って一人で階段を上がった。ミス・ハヴィシャムは自室ではなく、廊下向かいの大きな部屋にいた。ノックしても応答がなく、扉から覗くと、彼女はボロボロの椅子に座り、灰色の暖炉の火をじっと見つめていた。
私はいつものように中に入り、彼女の目線に入るよう暖炉の端に立った。彼女には完全な孤独の気配が漂い、もし私にこれ以上の害を与えていたとしても、同情せずにはいられなかった。私が彼女に哀れみを感じ、自分もこの荒廃した家の運命の一部となったのだと考えていると、彼女の目が私に向けられた。彼女はじっと見つめて、低い声で言った。「本物なの?」
「私です、ピップです。昨日ジャガーズ氏からあなたの手紙をもらい、すぐに来ました」
「ありがとう、ありがとう」
私はもう一つのボロ椅子を暖炉のそばに寄せて座った。その時、彼女の表情が変わり、まるで私を恐れているかのようだった。
「あなたが前回ここで触れた話題を続けて、私が石ばかりではないことを示したい。でも、今となっては、私の心に人間的なものがあるなんて、あなたが信じてくれることはないかしら?」
私が安心させる言葉をかけると、彼女は震える右手を伸ばしかけたが、私はその意図を理解する前に、彼女はすぐ引っ込めてしまった。
「あなたは友人のために、私に何か役立つこと、善いことを教えてくれると言いましたね。あなたがしてほしいこと、ですよね?」
「ぜひともしてほしいことです」
「それは何?」
私は彼女に、秘密裏の共同経営の経緯を説明し始めた。しかし、彼女の様子から、話をきちんと聞いているというより、私自身について考えているのだと感じた。実際そうだったらしく、私が話を止めてからしばらくして、ようやく自分が話を聞いていなかったことに気づいた様子だった。
「話をやめたのは」と、彼女はまた私を恐れているような態度で尋ねた。「私を憎みすぎて話すのも嫌だから?」
「違います、違います、そんなこと思わないでください、ミス・ハヴィシャム! あなたが話に集中していないのかと思って止めただけです」
「そうかもしれません」と彼女は頭を押さえた。「もう一度最初から話して。でも私は他のものを見ていないと……。いいわ、今なら聞ける」
彼女はいつもの決然とした仕草で杖に手をかけ、火を見つめて話に集中しようとした。私は説明を続け、自分の資金で取引を完了したかったが叶わなかったこと、そしてそれには他人の重大な秘密が関わっているため詳細を明かせないことを伝えた。
「そう」と彼女はうなずいたが、私の方は見なかった。「取引に必要な金額は?」
私は金額が大きくて伝えにくかった。「九百ポンドです」
「この目的のために私がその金を出したら、あなたは私の秘密を自分の秘密と同じくらい守ってくれる?」
「まったく同じくらい忠実に守ります」
「そうすれば、あなたは心安らかになる?」
「ずっと気が楽になります」
「今、とても不幸なの?」
彼女はまだ私を見ずに、今までにない同情的な口調で尋ねた。私はしばらく答えられなかった。声が出なかったからだ。彼女は左腕を杖の先に乗せ、そっと額をつけた。
「私は幸せとはほど遠いです、ミス・ハヴィシャム。でも、あなたのご存じない別の不安の種もあります。それが先ほどの秘密です」
しばらくして、彼女は顔を上げ、再び火を見つめた。
「他にも不幸の原因があると正直に言ってくれて、あなたは立派だわ。それは本当?」
「本当です」
「私はあなたの友人のためだけにしか役に立てないの? もしそれが済んだら、あなた自身のためにしてあげられることは何もないの?」
「何もありません。その問いかけに、そして何よりその口調に感謝します。でも、何もありません」
やがて彼女は席を立ち、書くものを探したが部屋にはなかったので、くすんだ金で縁取られた象牙のメモ帳をポケットから取り出し、同じくくすんだ金の鎖で首から下げた鉛筆で何かを書いた。
「ジャガーズ氏とは今も親しくしている?」
「ええ、昨日彼と食事をしました」
「これは、あなたが友人のために自由裁量で使うための金を、彼に払う権限です。私はここにお金を置いていませんが、もし彼に知られたくないなら、私から直接送ります」
「いえ、彼から受け取ることに何の異存もありません」
彼女は私に書いた内容を読み上げた。それは明確で簡潔で、私がその金を私的に使って利益を得ているのではないことを証明する文面だった。私はメモ帳を受け取ったが、彼女の手は再び震え、鉛筆の鎖を外して私に渡す時はさらに震えた。すべて、私の方は見ずに行われた。
「私の名前が最初のページに書いてあります。もし、いつかこの名前の下に“私は彼女を許す”と書ける日が来たら、私の壊れた心が塵となった後でも、どうか書いてください!」
「ミス・ハヴィシャム、今でも書けます。私にも多くの過ちがあり、感謝や導きを願うあまり、あなたを恨むどころではありません」
彼女は顔を私に向け、驚き、いや恐怖と言ってもよいほどの表情で、私の足元にひざまずいた。両手を組み、まるでかつて母親の隣で天に向かって祈ったであろう若き日の姿そのままに私に差し伸べていた。
白髪の彼女が、やつれた顔で私の足元にひざまずく姿は、全身に衝撃を与えた。私は彼女に立ち上がるよう懇願し、彼女を助け起こそうと腕を回したが、彼女は私の手を強く握り、その上に頭を垂れて泣いた。彼女が涙を流すのを見たのは初めてだった。私は、その涙が救いになることを願い、黙って彼女に身を寄せた。今や彼女はひざまずくのではなく、床に倒れ伏していた。
「ああ!」彼女は絶望的に叫んだ。「私はなんてことをしたの、なんてことを!」
「もしあなたが、私に害をなしたという意味なら、お答えします。大したことではありません。私はどんな状況でも彼女を愛していたでしょう。彼女は結婚したのですか?」
「ええ」
その質問は不要だった。家全体の新たな荒涼が、そう告げていたからだ。
「私はなんてことをしたの、なんてことを!」彼女は手をもみ、白髪をかきむしり、何度も何度もこの叫びに戻った。「私はなんてことを!」
私はどう答えてよいか、どう慰めてよいか分からなかった。感受性の強い子供を、自らの激しい恨みや傷ついた誇りの復讐心で、意のままに育て上げるという大きな過ちを犯したことは、私にもよく分かっていた。しかし、日の光を拒むことで、はるかに多くを自分から奪ったこと、隠遁生活で無数の自然な癒しの力からも遠ざかったこと、孤独な思考が病んでしまったこと――それが誰にでも起こる必然であるということも、私は同じくらい分かっていた。そんな彼女を、自己破壊の姿、世に適応できない存在、悲しみが狂気となった姿を見て、どうして同情せずにいられようか? 悔恨や自責や無価値感という、世界を呪う巨大な虚栄の病にとりつかれた哀れな人間を。
「あなたがこの前彼女に話しかけ、私自身がかつて感じた心をあなたの中に見て初めて、私は自分が何をしたか気づいたの。私はなんてことをしたの!」
「ミス・ハヴィシャム」と私は、彼女の嘆きが静まるのを待って言った。「私のことは心からも良心からもお忘れください。でもエステラは別です。彼女の本来持っていた善い部分を遠ざけてしまったことを、もし少しでも償えるなら、過去を百年嘆くよりもずっと良いはずです」
「分かっている、分かっている。でも、ピップ――あなた!」そこには新たな情愛を込めた真摯な女性の同情があった。「信じて。彼女が初めて来たとき、私は自分と同じ不幸から救おうとしただけだったのよ。初めはそれ以上何も考えていなかった」
「分かります。そう信じたい」
「でも、彼女が成長し、とても美しくなりそうだと分かると、私は次第に悪いことをしてしまった。賞賛と宝石と教え、そして私自身の姿を反面教師として彼女の前にいつも置き、彼女の心を奪い、氷に変えてしまったの」
「いっそ、自然な心のまま、傷ついたり壊れたりしていた方が良かったのに」と私は思わず言った。
その言葉にミス・ハヴィシャムはしばらく私を呆然と見つめ、またしても「私はなんてことを!」と叫んだ。
「私の全ての話を知っていれば、きっと私にもっと同情し、理解してくれるのに」
「ミス・ハヴィシャム」と私はできるだけそっと答えた。「私はあなたの話を知っていると思います。ここを離れて以来、ずっと知っています。そのことに深い同情を感じていますし、あなたとその影響を理解しているつもりです。これまでのやりとりが、エステラについて一つだけ問いかける口実を与えてくれるでしょうか? 今の彼女ではなく、ここに来たばかりの彼女についてです」
彼女は腕を椅子に乗せ、顔をうずめていたが、私をしっかりと見て「続けて」と答えた。
「エステラは誰の子ですか?」
彼女は首を振った。
「知らないのですか?」
再び首を振った。
「でもジャガーズ氏が彼女をここに連れてきた、あるいは送り届けたのですね?」
「連れてきたわ」
「どういう経緯だったか話していただけますか?」
彼女は低いささやき声で、慎重に言った。「私は長い間(どれくらいか分からない、ここの時計はおかしいですから)この部屋に閉じこもっていました。その時、彼に“女の子を育てて愛し、自分と同じ運命から救いたい”と頼みました。彼のことは、私と世間が絶縁する前に新聞で読んで知り、彼にこの家の荒廃を依頼した際に初めて会ったのです。彼は、そんな孤児を探してみようと言い、一晩、眠ったままの子をここに連れてきて、私はその子に『エステラ』と名付けました」
「その時、彼女は何歳くらいでした?」
「二つか三つ。彼女自身は何も知らず、自分は孤児で、私に引き取られたとだけ思っています」
私はあの女性がエステラの母親であると確信していたので、もはや証拠は必要なかった。だが、誰の目にも、このつながりは明白だった。
これ以上この面会を引き延ばして何が得られるだろう? 私はハーバートのために目的を果たし、ミス・ハヴィシャムはエステラについて知っていることをすべて話した。私は彼女の心を少しでも軽くしようとできる限りのことをした。これ以上どんな言葉であれ、私たちは別れた。
夕闇が迫る中、私は階下に戻り、外の自然な空気を吸った。入るとき門を開けてくれた女性に「すぐには出ません。敷地をひと回りしてから帰ります」と声をかけた。もう二度とここを訪れることはないだろうという予感があり、死にゆく光の中で最後の景色を見届けたいと思った。
かつて私が歩いた無数の酒樽の間――何年もの雨に朽ち、立てかけられたものには小さな沼や水たまりができている――を抜けて、私は荒れ果てた庭へと向かった。周囲をぐるりと巡り、ハーバートと私が争った隅も、エステラと歩いた小道も回った。どこも寒々しく、寂しく、荒涼としていた。
帰りがけに醸造所を通った。庭側の小さな扉の錆びた掛け金を上げて中に入り、反対側の扉から出ようとした。だがその扉は、湿気で木が膨らみ、蝶番も緩んで、敷居にはきのこが生えて、簡単には開かなかった。ふと私は後ろを振り返った。そのわずかな仕草で、幼い日の連想が鮮やかによみがえり、梁に吊られたミス・ハヴィシャムの幻を見た気がした。その幻覚の衝撃は強烈で、私は梁の下で身体中が震えるのを感じ、自分がただの想像だと気づくまで動けなかった――とはいえ、すぐ我に返ったのだが。
場所と時のもの悲しさ、そして一瞬の恐怖が、私に言葉にできぬ畏れを抱かせた。門を抜けて表の中庭に出ると、鍵のかかった正門を開けてもらうため女中を呼ぶか、あるいは二階に上がってミス・ハヴィシャムが無事か確かめるべきか、少し迷った。結局、後者を選び、二階へ戻った。
彼女を残した部屋を覗くと、彼女は暖炉のそばのボロ椅子に座り、火に背を向けていた。私は静かに立ち去ろうとした――その瞬間、凄まじい炎が立ち上るのを見た。同時に、火の渦に包まれ、頭上高くまで火柱を上げて叫びながら私に駆け寄る彼女の姿を見た。
私は二重のケープ付きの厚手コートを着ており、もう一枚の分厚いコートを腕にかけていた。それらを脱ぎ捨てて彼女に飛びつき、押し伏せ、覆いかぶせた。テーブルクロスも引きおろし、同じ目的で彼女にかけ、山のように積もった朽ち果てた物も一緒に引きずり落とした。その間も彼女は敵のように激しくもがき、覆えば覆うほど激しく叫び、逃れようともがいた――それがあったと分かるのは、あとで結果から記憶しているからであり、その最中、自分が何を感じ、考え、していたか自覚はなかった。私が気づいたのは、私たちが大テーブルのそばの床に倒れ、煙のなかに未だ燃える火の粉が舞い、それが数分前まで彼女の色あせた花嫁衣装だった、ということだった。
私は周囲を見回し、驚き、蜘蛛や甲虫が床を走り回って逃げていくのを見た。召使いたちが息せき切って駆け込んできた。私はまだ全力で彼女を押さえつけていた。誰なのか、なぜもがきあったのか、彼女が炎に包まれていたことも、火が消えたことも、私はほとんど理解していなかった。燃え残りが黒い雨のように落ちていくのを見て、ようやく理解できたのだった。
彼女は意識を失っていた。私は彼女を移動させるのも触れるのも怖かった。助けを呼んで、私は救助が来るまで彼女を離さず押さえ続けた。手を離せばまた火が燃え上がり彼女を焼き尽くすのではと、無意識に思ったのだ。医師が他の手当てを携えてやってきた時、私が立ち上がると、自分の両手が火傷しているのに驚いた――痛みも何も感じていなかったのに。
診察の結果、彼女は重傷を負ってはいるものの、それ自体が絶望的というわけではないと告げられた。主な危険は神経的ショックにあった。外科医の指示で、彼女の寝台はその部屋に運ばれ、大きなテーブルの上に置かれた。ちょうどその場所が、負傷の手当てには最適だったのである。1時間後に再び彼女を見たとき、彼女はまさに、私が彼女が杖を打ちつけるのを見て、「いつかここに横たわるだろう」と言っていた、その場所に横たわっていた。
彼女の衣服はすべて焼け落ちてしまったと聞かされたが、それでも彼女には、かつての不気味な花嫁姿の名残があった。というのも、彼女の体は首まで白い脱脂綿で覆われており、その上から白いシーツがゆるく掛けられていたために、「かつてあったものが、今は変わってしまった」という幻のような雰囲気がまだ漂っていたのだ。
使用人たちに尋ねてみると、エステラはパリにいるとのことで、私は外科医に、次の便で彼女に手紙を書いてくれるよう約束をもらった。ミス・ハヴィシャムの親族については私が引き受けることにし、マシュー・ポケット氏だけに連絡し、あとは彼の判断に任せて他の親族への報せをどうするか決めてもらうつもりだった。これは翌日、私が町に戻るとすぐに、ハーバートを通じて行った。
その晩、彼女はしばらくの間、出来事についてしっかりと話したが、そこにはどこか恐ろしいほどの生気があった。だが夜半近くになると、彼女の言葉は次第に乱れ始め、その後は、「私は何をしたのだろう!」と、無数に低く荘厳な声で繰り返し言うようになった。そして次に、「彼女が最初に来たとき、私は彼女を自分のような不幸から救おうと思った」と言い、さらに「鉛筆を取って、私の名前の下に『私は彼女を許す』と書いて」と続けた。彼女はこの三つの文の順序を決して変えなかったが、時折そのうちの一文の中の単語を抜かすことがあり、他の単語を加えることは決してなかった。ただ空白を作って次の単語へ進むだけだった。
私がそこにいても役に立つことはなく、家の近くには私を不安と恐怖で駆り立てる差し迫った理由があったので、夜の間に翌朝一番の馬車で戻る決心をした。町外れまで1マイルほど歩き、そこで馬車に拾ってもらうつもりだった。そこで朝6時ごろ、私は彼女に身をかがめてキスをした。ちょうどその時も、彼女は「鉛筆を取って、私の名前の下に『私は彼女を許す』と書いて」と、止まることなく言い続けていた。
第50章
夜のうちに私の手は2、3度手当てされ、朝にももう一度手当てされた。左腕はひじまでかなりひどく火傷しており、肩までの部分はそれほどでもなかったが、非常に痛んだ。しかし炎がその方向にだけ広がったので、それ以上ひどくならなかったことに感謝した。右手はそこまでひどくはなく、指を動かすことはできた。もちろん包帯はしていたが、左手と腕ほど不便ではなかった。左手と腕は吊り包帯で支えていたので、コートはマントのように肩にかけて首元だけ留めるしかなかった。髪は炎に巻き込まれたが、頭や顔は無事だった。
ハーバートがハマースミスに行って父親に会った後、部屋に戻ってきて、一日中私の世話をしてくれた。彼は最も優しい看護人であり、決まった時間ごとに包帯を外し、冷却液に浸してから、また丁寧に巻き直してくれた。その忍耐強い優しさには本当に感謝した。
最初のうちは、私はソファで静かに横たわっていても、炎のまばゆい光とその轟音、そして激しい焼けるにおいの印象が、非常に辛く、いや、ほとんど拭い去ることができなかった。うとうとと眠りかけても、ミス・ハヴィシャムの叫び声と、頭上に炎をまとって私に向かってくる彼女の姿で目が覚めた。こうした心の痛みは、どんな肉体の痛みよりもはるかに耐えがたかった。それを察したハーバートは、何とかして私の注意をそらそうと最大限努力してくれた。
私たちは舟の話は口にしなかったが、二人ともそのことを考えていた。それは、話題を避ける様子や、私が手を使えるようになるまで「何週間」ではなく「何時間」で回復させることを暗黙のうちに決めていたことからも明らかだった。
ハーバートと初めて会ったとき、私は当然のように「下流は大丈夫か」と尋ねた。彼は自信たっぷりに、明るく「大丈夫」と答えたので、それ以上は日が暮れるまで話題にはしなかった。しかし、ハーバートが包帯を取り替えていた時、今度は外の光よりも暖炉の明かりの方がよく見える中で、彼が自発的に話題を戻した。
「昨夜、プロヴィスと2時間ばかり一緒にいたよ、ハンデル」
「クララは?」
「可愛い子さ!」とハーバート。「グラッファンドグリムと一晩中上がったり下がったりしてたよ。クララが見えなくなると、彼はすぐに床を叩き始める。あれじゃ長くはもたないだろう、ラムと胡椒と――胡椒とラムと――そろそろ床を叩くのも終わりかな。」
「それで、君は結婚するんだね、ハーバート?」
「そうでなきゃ、どうやってあの子を守れる? ――腕をソファの背もたれに伸ばしてごらん、ハンデル、僕はここに座るから、包帯は気づかないうちにそっと外すよ。さて、プロヴィスの話だったね。ねえ、ハンデル、彼は人が変わったと思わない?」
「この前会ったとき、優しくなった気がすると言っただろう」
「その通りさ。昨夜はとても率直で、もっと彼の人生について話してくれた。覚えてるかい? 昔、ある女のことで大変苦労したと話しかけたけど、そこでやめてしまったこと――痛かった?」
私は驚いて体を動かしたが、それは彼の手のせいではなかった。彼の言葉に驚かされたのだ。
「忘れていたけど、言われてみれば思い出したよ、ハーバート」
「そう、その人生の部分に入っていったんだが、実に暗くて荒々しい話さ。話そうか? それとも今はやめた方がいい?」
「ぜひ聞かせてくれ。すべての言葉を。」
ハーバートは、私の答えがやや早口で熱心すぎたように思ったのか、身を乗り出して私の顔を確かめるように見た。「頭は冷静かい?」と言って、私の額に手を当てた。
「大丈夫だよ。続きを聞かせてくれ、ハーバート」
「どうやらね」とハーバートは言った。「――さあ包帯が一つ外れた、今度は冷たい方だ――最初はゾクッとするけど、すぐ楽になるよ――その女は若くて、嫉妬深くて、復讐心の強い女だったんだ、ハンデル、本当に――」
「どのぐらいまで?」
「殺人さ――そのあたり痛む?」
「感じないよ。どうやって殺した? 誰を殺した?」
「いや、その行為自体はそこまで恐ろしい呼び名に値しないかもしれない」とハーバートは言った。「でも、裁判にかけられ、ジャガーズ氏が弁護し、その弁護の評判でプロヴィスに名が知れたんだ。被害者は、別のもっと強い女で、納屋で争いがあった。誰が最初に仕掛けたのか、公正だったのか、不公正だったのかは曖昧だが、結末は明らかで、犠牲者は首を絞められていた。」
「女は有罪になったのか?」
「いや、無罪になった――おお、ハンデル、痛かったか!」
「これ以上優しくできないよ、ハーバート。で、その後は?」
「その無罪となった若い女とプロヴィスには小さな子どもがいた。プロヴィスはその子がとても可愛かったそうだ。その夜、嫉妬の対象となった女が絞殺されたまさにその晩、若い女が一瞬だけプロヴィスの前に現れて、子どもを(彼女が手元に置いていた)殺してやる、二度と会わせないと誓って、姿を消した――さあ、辛い方の腕はまた吊り包帯におさまった。次は右手だ、こっちはずっと楽だ。この明かりの方が包帯の水ぶくれがはっきり見えないから手元が安定してやりやすい――息苦しくないかい? 少し呼吸が速いようだけど」
「もしかしたら、そうかも。で、その女は誓いを守ったのか?」
「そこがプロヴィスの人生で最も暗い部分だ。彼女は誓いを守った。」
「つまり、プロヴィスはそう言っているんだね」
「そりゃそうだよ、僕には他に情報はないからね」とハーバートは驚いたように言い、再び身を乗り出して私の顔を見つめた。
「そうだろうね」
「さて」とハーバートは続けた。「彼がその子の母親にひどいことをしたのか、良くしてやったのか、プロヴィスは語らない。でも、彼女はあの悲惨な生活を4、5年は共にしたし、彼は彼女を憐れみ、寛容に接したようだ。だから、その子が死んだと証言を求められ、結局彼女を死に追いやることになるのを恐れて、プロヴィスは(子どもの死を悲しみながらも)身を隠し、裁判にも出ず、“エイベル”と呼ばれるある男としてぼんやり語られるだけだった。無罪になった後、彼女は姿を消し、こうして子どもも、母親もともに失った。」
「聞きたいことが――」
「ちょっと待って、話はもうすぐ終わる。あの悪魔コンピソン――多くの悪党の中でも最悪のやつ――は、プロヴィスがその時期に隠れていたことや理由を全部知っていて、その後ずっとそのことを盾にして、彼を貧乏なまま働かせ続けた。昨晩、それがプロヴィスのコンピソンへの敵意を一層激しくしているとはっきり分かったよ。」
「聞きたいのはね、特に、ハーバート、それがいつのことかプロヴィスは言ったのか?」
「特に? じゃあ思い出すよ。彼の表現だと、“今から二十年ばかり前で、コンピソンと組んだ直後だ”って。君は、あの小さな教会墓地で彼に出会った時、何歳だった?」
「たしか七歳くらいだったと思う。」
「ああ。じゃあ、事件があってから三、四年は経っていたと言っていたな。君は、彼にとってあの悲劇的に失われた小さな女の子を思い出させた。ちょうど君の年齢くらいだったはずだ。」
「ハーバート」と私は短い沈黙の後、急ぐように言った。「僕を窓の明かりで見たほうがいいか、暖炉の明かりで見たほうがいいか?」
「暖炉の明かりの方がよく見えるよ」とハーバートは再び近寄った。
「僕を見てくれ」
「見ているよ、ハンデル」
「触ってくれ」
「触っているよ、ハンデル」
「僕が高熱を出していたり、昨夜の事故で頭が混乱していると思わないか?」
「いや、ハンデル」とハーバートはしばらく考えてから言った。「ちょっと興奮しているけど、君は君自身だよ」
「確かに僕は正気だ。そして、僕たちが川下に匿っている男は、エステラの父親だ。」
第51章
なぜ私はあんなにもエステラの親の正体を突き止め、証明しようとしたのか、自分でも分からない。すぐに分かることだが、この問題は、もっと賢い人の手によって私の前に持ち出されるまでは、自分の中で明確な形を持ってはいなかった。
だがハーバートとあの重大な会話を済ませた後、私は熱にうかされたように、この問題を徹底的に追及すべきだという思いに取り憑かれた。もうこのまま放っておくべきではない、ジャガーズ氏に会って、真実そのものをつかむべきだと。私は本当に、それをエステラのためにしようとしていたのか、それとも、自分がこれほどまでに心を砕いてきた男に、これまで自分の周りを取り巻いていたロマンチックな関心の光を一部でも移そうとしていただけなのか、わからない。おそらく後者の方が真実に近いかもしれない。
とにかく、私はその夜、ジェラード街に出かけずにはいられなかった。だが、もし私が出かければ、私たちの逃亡者の安全が私一人にかかっている時に、私は倒れて役に立たなくなるかもしれないとハーバートが何度も説得してくれたので、ようやく落ち着いて怪我の手当てを受け、家にいることにした。そして、どんなことがあっても明日は必ずジャガーズ氏のもとへ行くという同意を何度も確認して、ようやく承知した。翌朝早く、私たちは一緒に外出し、ギルトスパー通りの角でハーバートと別れ、私はリトル・ブリテンへと向かった。
時折、ジャガーズ氏とウェミック氏が事務所の会計や書類を精査し、すべてを整える日があった。そのときは、ウェミック氏が帳簿や書類を持ってジャガーズ氏の執務室に入り、上階の事務員の一人が下の外側事務室にやってきた。この朝もその事務員がウェミック氏の席にいたので、帳簿の整理中だと分かったが、ちょうどウェミック氏も一緒にいるので、私が彼を巻き込んだと疑われないように事実を伝えられると安心した。
私の腕は包帯で覆われ、コートは肩に羽織るだけという姿も、目的に好都合だった。町に着いた時点ですぐに事故の簡単な報告は送っていたが、今はすべての詳細を説明する必要があった。そして、今回は特別な事情もあり、これまでのような乾いた堅苦しい会話ではなく、証言の規則に厳格に従うというより、ややくだけた口調で語ることになった。私が事故の経緯を説明している間、ジャガーズ氏はいつものように暖炉の前に立ち、ウェミック氏は椅子に寄りかかってズボンのポケットに手を突っ込み、ペンを水平に持ったまま私をじっと見ていた。あの二つの粗野な石膏像は、公式の手続きと結びつく私の頭の中で、今まさに火の匂いがしないかと思案しているようだった。
話が終わり、質問にも答え終えると、私はハーバートのための900ポンド受け取りの権限を示すミス・ハヴィシャムの証書を差し出した。ジャガーズ氏の目は、それを受け取った時に一瞬奥に沈んだが、すぐにウェミック氏に渡し、自分の署名用に小切手を書かせた。その間、私は小切手を書くウェミック氏を見ており、ジャガーズ氏はよく磨かれたブーツで体を揺らしながら、私を見つめていた。「パイプ、残念だが、君のためには何もできない」と、署名を終えて私が小切手をしまうと彼は言った。
「ミス・ハヴィシャムは、何かできないかと尋ねてくれましたが、私は何も要らないと答えました」
「各人、自分のことは自分で分かっているべきだ」とジャガーズ氏は言った。私はウェミック氏の口が「動産」とつぶやくのを見た。
「僕ならNoとは言わなかったな」とジャガーズ氏。「でも、自分のことは自分で分かっているはずだからな」
「誰にとっても、“動産”が大事だ」とウェミック氏はやや非難がましく私に言った。
いよいよ本題に入る時だと思い、私はジャガーズ氏に向かってこう言った――
「ただ、私はミス・ハヴィシャムに一つだけお願いしました。養女についての情報を求め、彼女は知る限りすべて話してくれました」
「そうか」とジャガーズ氏はブーツを見下ろしてから姿勢を正し、「自分なら話さなかったろうが、まあミス・ハヴィシャムの判断だ」
「私はミス・ハヴィシャム自身よりも、彼女の養女の過去を知っています。彼女の母親を知っているのです」
ジャガーズ氏は私を見つめ、「母親?」と繰り返した。
「この三日以内に、その母親に会いました」
「ほう」とジャガーズ氏。
「あなたも会っていますよ、しかももっと最近」
「そうか」とジャガーズ氏。
「私は、あなたさえご存じないエステラの過去を知っています。父親も知っている」
ジャガーズ氏はある瞬間、明らかに身構えたが、態度を変えないほど自己制御が効いていた。しかし、彼がエステラの父親を知らないと確信できたのは、この時だった。プロヴィスが「身を隠していた」と語っていたこと、そして彼がジャガーズ氏の依頼人となったのは4年後で、その時には自身の素性を主張する理由もなかったことを思い出して、私はその推測を確信したのだが、今まではそれを確信できなかった。
「パイプ、君はあの若い女性の父親を知っているのか?」とジャガーズ氏。
「はい」と私は答えた。「彼の名はプロヴィス――ニューサウスウェールズ出身です」
ジャガーズ氏でさえ、この言葉に驚いた。わずかな反応で、それを最大限抑え込んでいたが、確かに驚いたのだ。それをハンカチで鼻を拭く動作に紛らせていた。ウェミック氏がどう受け取ったかは分からない。私はちょうどその時、顔を見るのが怖かった。ジャガーズ氏に気づかれてしまうのを恐れたからだ。
「で、どんな証拠でプロヴィスはその主張をするんだ?」とジャガーズ氏は平然と、ハンカチを鼻に持っていきかけたまま尋ねた。
「彼はその主張をしていません。娘が生きているとも、存在しているとも知りません」
この時ばかりは、力強いハンカチさばきも止まった。私の返答があまりに予想外だったため、ジャガーズ氏はいつものように鼻を拭く動作をやめ、腕を組んで私を厳しい目で見つめた。
私は知る限りのことを、どうやって知ったかも含めて話した。ただし、実際にはウェミック氏から知ったことも、ミス・ハヴィシャムからだと匂わせた点だけは伏せておいた。その点は特に慎重にした。そして話し終わるまでウェミック氏の方は見なかった。十分に話し終えて、しばらく沈黙のうちにジャガーズ氏と対峙し、初めてウェミック氏に目を向けると、彼はペンを置いてテーブルにじっと集中していた。
「ふむ」とジャガーズ氏はようやく言い、テーブルの書類に向かった。「どの項目だったかな、ウェミック、パイプが来たときは?」
だが、私はこんな形で打ち切られるのに耐えられず、彼に対し、もっと率直で男らしくあってほしいと情熱的に、時に憤りを込めて訴えた。私が抱いてきた誤った希望、それがどれほど長く続いたか、そして自分がたった今明らかにした発見、さらに心の重荷のこともほのめかした。今しがた私が打ち明けた信頼の見返りとして、少しは信頼を与えてもらってもいいはずだ、と。私は彼を責める気はなく、疑ってもいないが、彼から真実の確証が欲しいのだと言った。そして、なぜそれを求めるのか、なぜそれを知る権利があると思うのか尋ねられたら、彼には取るに足らない夢かもしれないが、私はエステラを深く長く愛してきたこと、失った今も、彼女に関わることなら何より自分にとって大切なのだと告げた。ジャガーズ氏はこの訴えに対しても、まったく動じず沈黙し続けたので、私はウェミック氏に向かって「ウェミックさん、あなたが優しい心の持ち主だと知っている。あなたの楽しい家庭も、お父様も、仕事の合間に気持ちを和ませる明るい様子も見てきた。だから、どうかジャガーズ氏に一言、私のために口添えしてほしい。今の状況を考えれば、彼も私にもっと率直に接してくれるべきだと」と訴えた。
これほど奇妙に見つめ合う二人の男を私は見たことがない。最初は、ウェミック氏が即座に解雇されるのではと不安になったが、ジャガーズ氏がほほえみに近い表情を浮かべ、ウェミック氏がどんどん大胆になっていくのを見て、不安は消えた。
「これはどうしたことだ?」とジャガーズ氏。「君はお父さんがいて、君は楽しい家庭があると言うのか?」
「まあ、ここに持ち込まなければどうでもいいことだろう」とウェミック氏。
「パイプ」とジャガーズ氏は私の腕に手を置き、はっきり笑いながら言った。「この男はロンドン一の詐欺師に違いないな」
「とんでもない」とウェミック氏はさらに強気になった。「むしろあんたの方がそうかもね」
またしても、二人は先ほどと同じ奇妙な視線を交わした。それぞれ、相手に騙されていないか、疑っているようだった。
「君が楽しい家庭を?」とジャガーズ氏。
「仕事に差し障りがなきゃ、それでいいでしょう。今考えてみれば、あなたもそのうち家庭を持ちたくて、こうして色々画策してるかもしれないですね。仕事に疲れたら」
ジャガーズ氏は、しみじみと何度かうなずき、ため息さえついた。「パイプ、もう“くだらない夢”の話はよそう。君は僕よりも、そんなことについてずっと新鮮な経験がある。さて、本題だ。仮定の話をしよう。いいか、私は何も認めない」
彼は私が「何も認めない」と明言したことをきちんと伝えるのを待った。
「パイプ」とジャガーズ氏は言った。「こう考えてみろ。君の言ったような事情で、ある女が子どもを隠し持っていて、その事実を弁護士に伝えなければならなかった。弁護の幅を考えて事実確認が不可欠だと説かれて。ちょうどその時、彼は風変わりな金持ちの女性のために養子にする子どもを探す役割も持っていた」
「分かります」
「彼の周囲は邪悪な空気に包まれ、子どもとは将来破滅するために大量に生まれてくる存在としか見えなかった。子どもが刑事法廷で裁かれる姿も頻繁に目にしていた。子どもたちは投獄され、鞭打たれ、追放され、放置され、捨てられ、様々な形で死刑執行人の手に堕ちていく。彼の仕事で見る子どもは、みな“網にかかる魚の稚魚”みたいなもの――訴追され、弁護され、偽証し、孤児になり、どうかして滅びていくものばかりだった」
「よく分かります」
「ところが、そうした中で、救える可愛い子どもが一人いた。父親は死亡したと信じていて、何も騒げなかった。母親には法的立場からこういう力があった。“お前がしたこと、どうやったか、全部知っている。これこれの手順で疑いを逸らそうとしたのも知っている。全部たどった。必要なら子どもを出すが、そうでなければ子どもをよこせ。そうすればお前を全力で助けてやろう。お前が助かれば子どもも助ける。お前が駄目でも子どもは救う”――こうして、実際にその通りにして、女は無罪になった」
「よく分かりました」
「だが、私は何も認めない?」
「何も認めていません」ウェミック氏も「認めていません」と繰り返した。
「さらに、情熱と死の恐怖で女の精神は少しおかしくなっていて、釈放された後、世間を怖れて彼を頼った。彼は女を受け入れ、時にその荒々しい性質が見え隠れすると、以前と同じやり方で自分の力を示して抑え込んだ。この仮定の話が分かるか?」
「よく分かります」
「その子は成長し、金で結婚した。母親はまだ生きている。父親も生きている。母も父もお互いを知らず、数マイル、数ヤード――まあごく近くに住んでいる。その秘密は、君がかぎつけるまで守られていた。その場合を非常に慎重に考えてみろ」
「分かっています」
「ウェミック氏、君も自分にそう問いかけてみてくれ」
ウェミック氏も「分かりました」と言った。
「誰のためにその秘密を明かす? 父親のためか? 彼にとって母親は何の助けにもならないだろう。母親のためか? もしそんなことをした女なら、今のままの方が安全だろう。娘のためか? 二十年も逃れて今や安泰なのに、夫に親の正体を知らせて辱めに引き戻すことに、何の益がある? だが、君が彼女を愛していて、“くだらない夢”の主人公にしていたとしたら、よく考えてみれば――むしろ今すぐ包帯した左手を右手で斬り落とし、次にウェミック氏にも斬ってもらった方がましだ、と僕は言う」
私はウェミック氏を見た。彼の顔は非常に真剣だった。彼は真剣な面持ちで唇に人差し指を当てた。私も同じようにした。ジャガーズ氏も同じようにした。「さて、ウェミック」と彼は通常の態度に戻って言った。「パイプが来たとき、どの項目だったかな?」
しばらく彼らの仕事ぶりを見ていると、二人はさっきの奇妙な視線を何度も交わしていた。ただし今度は、互いに自分がプロらしくない弱さを見せたことに気づいているらしく、どこかぎこちない。そこで、今や両者とも頑として譲らず、ジャガーズ氏は命令口調、ウェミック氏は頑固に自分を正当化して、わずかなことでも譲らなかった。こんな悪い空気の二人を見るのは初めてだった。普段はとても仲がいいのに。
だが、ちょうどその時、都合よくマイク――毛皮の帽子をかぶり、袖で鼻をぬぐう癖のある、あの最初にここで出会った依頼人――がやってきて、二人は救われた。この男は、本人か家族の誰かがいつもトラブル(この場合ニューゲート監獄のこと)に巻き込まれているようだったが、今日は長女が万引きの疑いで捕まったと報告しに来た。ウェミック氏が対応し、ジャガーズ氏は暖炉の前で尊大に立って様子を見ていたが、マイクの目には涙が光った。
「何してる!」とウェミック氏は怒り心頭で言った。「泣きながらここへ来るのか!」
「そんなつもりじゃなかったんだ、ウェミックさん」
「嘘だ。どうしてそんなことを? ここでは涙を流さずに来られないなら、来る資格はないぞ!」
「気持ちを抑えられないんだよ、ウェミックさん」
「気持ち? もう一度言ってみろ!」
「よし」とジャガーズ氏は一歩前に出てドアを指さした。「この事務所から出ていけ。ここには“気持ち”などいらん。出ていけ」
「当然だ」とウェミック氏も。「出て行け」
かくして哀れなマイクは、非常に従順に退散し、ジャガーズ氏とウェミック氏の間には再び良好な関係が戻り、二人はちょうど昼食でもとったかのように、さっぱりした様子で仕事に戻った。
第52章
リトル・ブリテンから私は、小切手を懐にしてミス・スキフィンズの兄の会計士のもとへ向かい、彼はすぐにクラリカーを呼び出してくれたので、私は無事に話をまとめることができた。これは、私が“偉大な遺産”を知らされて以来、唯一成し遂げた善行であり、唯一完了した行いだった。
クラリカーは、その際、会社の経営が着実に伸びていること、東方に必要な小さな支店も作れるようになったこと、新たなパートナーになったハーバートがその責任者として赴任することを告げてくれた。私は、たとえ自分の身の振り方が決まっていたとしても、友人との別れに備えなくてはならないのだと悟った。今や、私の最後の錨が緩みかけ、まもなく風と波に流されるのだと感じた。
だが、ハーバートが夜ごとに帰宅しては、この変化を嬉々として語る姿には慰めを感じた。彼は私にとって新しい話ではないと知らずに、クララ・バーリーをアラビアンナイトの国へ連れて行く空想や、私もキャラバンで合流し、みんなでナイルを登って驚異を見る話など、夢を描いて語ってくれた。私自身の未来には大きな期待は抱けなかったが、ハーバートの道が順調に開けていること、老バーリー氏がラムと胡椒を続けてくれれば、娘は幸せになれるのだと感じていた。
時はもう3月に入っていた。左腕は経過も悪くなかったが、自然な回復には時間がかかり、まだコートを着ることはできなかった。右腕はかなり元通りで、不格好ではあるが十分使える状態だった。
ある月曜の朝、ハーバートと朝食を取っていると、ウェミック氏から次のような手紙が届いた。
「ウォルワースより。読んだら直ちに焼却を。週の初め、あるいは水曜あたり、やろうと思えば例の件をやってもよい。心が決まれば実行を。今すぐ焼却せよ。」
私はこれをハーバートに見せ、二人で暗記した後で火にくべた。それからどうするか相談した。もはや私の負傷を隠し通すことはできない。
「改めて考えたけど」とハーバートは言った。「テムズの水夫を雇うより、スタートップに頼む方がいい。いい奴だし、腕も確かで、僕たちに好意もあり、誠実だ」
私も何度か考えた案だった。
「でも、どこまで話す?」
「ごくわずかでいい。単なる思いつきの秘密の冒険ぐらいにしておいて、当日の朝になったら事情を明かせばいい。プロヴィスを乗せて出国する急ぎの理由があると」
「もちろん僕も同行する」
「行き先は?」
私は考えに考えた末、正直なところ、どの港でも構わない気がしていた――ハンブルク、ロッテルダム、アントワープ――とにかくイギリスを出られればよかった。途中で拾ってくれる外国船ならどこでもよかった。計画としては、川を十分に下ったところ――特にグレイブズエンドより下流に――ボートで進み、潮の引き際に乗じて先回りし、静かな場所で外国船を待ち、接近して乗り込む、というものだった。船の出航時刻を調べれば、どこで待てばいいかもほぼ見当がついた。
ハーバートも同意し、朝食後すぐに下調べを始めた。ハンブルク行きの蒸気船が都合が良さそうだと分かり、主にその船に目をつけた。他の外国船のダイヤも調べ、それぞれの外観や色も覚えた。しばらく別行動し、私は必要なパスポートの取得、ハーバートはスタートップへの連絡を担当した。どちらも問題なく済ませ、午後1時に再集合した時、私はパスポートを用意し、ハーバートはスタートップと合流の承諾を得た。
二人がオールを漕ぎ、私は舵を取り、プロヴィスは動かず静かに座ってもらう。急ぐ必要はないので、それで十分だった。ハーバートはその晩はミル・ポンド・バンクに夕食前に行き、翌火曜の晩は行かず、水曜日には家のそばの階段で合流する、その他の取り決めもその月曜のうちに完了し、それ以降はプロヴィスへの連絡を一切絶つことにした。
こうした手筈をしっかり確認して、私は帰宅した。
部屋の外扉を自分の鍵で開けると、私宛ての手紙が郵便箱に入っていた。とても汚れてはいたが、決して乱雑な筆跡ではなかった。手渡し(もちろん私が外出中に)で届いたもので、内容はこうだった――
「今夜か明日の夜九時に、古い湿地に来る勇気があるなら、石灰窯のそばの小さな水門小屋まで来た方がいい。お前の伯父プロヴィスに関する情報が欲しいなら、必ず来ること、誰にも知らせず、迷わず来ること。一人で来ること。この手紙を持参せよ。」
この奇妙な手紙を受け取る前から、私は十分に重いものを背負っていた。今どうすべきか、決めかねていた。最悪なのは、すぐに決断しないと今夜行きの馬車に間に合わなくなることだった。明日の夜は、脱出計画直前すぎて無理だ。それに、もしかしたらこの情報は脱出計画自体に大きく関わるかもしれない。
もし十分に考える時間があったとしても、私はやはり行っただろうと思う。だが、ほとんど考える間もなく――時計を見ると馬車の出発まであと30分しかない――私は行くことを決めた。間違いなく、あの「伯父プロヴィス」という言葉がなければ、行かなかっただろう。ウェミック氏からの手紙と、その日の慌ただしい準備が重なり、私は決断したのだった。
ほとんどどんな手紙であっても、激しく急いでいるときにはその内容をはっきり把握するのが非常に難しいものであり、この謎めいた手紙の指示――秘密を守れ、ということ――が機械的に頭に入るまで、私は二度も読み返さなければならなかった。その指示に同じように機械的に従って、私は鉛筆でハーバートに宛てたメモを残した。もうすぐ出発することになるが、どれほどの期間になるか分からない。だから自分自身でミス・ハヴィシャムの容態を確かめるため、急いで行って戻ってくることにした、と伝えた。その後、私はかろうじて外套を手に取り、部屋に鍵をかけ、裏道を通って馬車の発着所へ向かった。もし幌馬車を雇って表通りを行っていたら、間に合わなかっただろう。しかし私が進んだ道順で、ちょうど馬車が車庫を出てくるところに出くわし、乗り込むことができた。私はただ一人、車内の客として、膝まで藁に埋もれながら、我に返った。
というのも、手紙を受け取って以来、本当に自分を保てていなかった。あの朝のあわただしさに続いて、手紙が私をすっかり混乱させていたのだ。朝の慌ただしさと動揺は大きかった。ウェミックを長く、そして心配しながら待っていたというのに、結局彼の合図はやっとのことで不意にやってきた。そして今、私は自分がなぜ馬車に乗っているのか不思議に思い始め、本当にそこにいなければならない理由があったのか疑い始め、すぐにでも降りて引き返そうかと考え、匿名の手紙など無視すべきだったと自分を説得し、要するに、急いでいる人なら誰しも経験する矛盾と優柔不断の一連の過程をたどった。しかし、それでも「プロヴィス」の名が挙げられていたことで全てが決した。私はすでに知らぬ間に自分に言い聞かせていたのだ――もし私が行かなかったせいで彼に危害が及んだとしたら、自分を許すことなど決してできない、と。
馬車が停まったときには既に暗くなっていた。私にとって、その道中は車内からほとんど何も見えず、外に出ることもできない身体だったので、長く陰鬱に感じられた。「ブルー・ボア」は避け、街はずれの評判の低い宿に投宿し、夕食を注文した。食事の準備を待つ間に、私はサティス・ハウスを訪ねてミス・ハヴィシャムの様子を聞いた。彼女はまだ重病であったが、やや持ち直したと考えられていた。
私が泊まった宿は、かつて古い聖職者の館の一部だったらしく、小さな八角形の共有室で、まるで洗礼盤のような場所で食事をとった。自分で食事を切ることができなかったので、ツルツルした禿頭の年老いた宿の主人が代わりに切ってくれた。そのおかげで会話が始まり、彼は私の話を面白おかしく語ってくれた――もちろん世間で広まっている通り、パンブルチュークが私の最初の恩人であり、私の成功の礎であるという話である。
「その若い男を知っているのか?」と私が尋ねた。
「知ってるとも!」と宿の主人は繰り返す。「ほんの小さい頃からな。」
「彼はこの辺りに戻ってくることはあるのか?」
「あるさ」と宿の主人は言った。「今じゃ大事な友達の所に時々戻ってきて、恩人を冷たくあしらうんだ。」
「それは誰のことだ?」
「今言ってる人さ」と宿の主人は答えた。「パンブルチューク氏だよ。」
「他に誰にも恩知らずなんじゃないのか?」
「できるもんならそうするだろうが」と宿の主人は返した。「でもできないんだ。なぜかわかるかい? パンブルチュークが全てしてやったからさ。」
「パンブルチュークがそう言っているのか?」
「言うまでもないさ!」と宿の主人は答える。「言う必要もない。」
「でも本当にそう言っているのか?」
「そいつの話を聞いたら、血が白ワインビネガーに変わるくらいだよ、旦那」と宿の主人は言った。
私は心の中で「でも、ジョーよ、親愛なるジョー、お前はそんなこと一度も口にしなかった。ひたすら我慢強く、慈愛深いジョー、お前は決して不平を言わなかった。お前もだ、気立てのよいビディ!」と思った。
「事故のせいで食欲が落ちてるようだね」と宿の主人は、コートの下の包帯をちらりと見ながら言った。「もっと柔らかいところを食べたらどうだい?」
「いや、結構です」と私は答え、テーブルから身をそらして暖炉に思いを巡らせた。「もう食べられません。下げてください。」
ジョーに対する私の恩知らずな態度について、パンブルチュークの無恥な詐欺師ぶりほど鋭く突き刺さったことはなかった。彼が偽れば偽るほど、ジョーはひたすら真実であり、彼が卑しければ卑しいほど、ジョーは気高かった。
私は暖炉の前で1時間以上、深く、そして当然ながら心から謙虚になって考え込んでいた。時計の音で我に返ったが、落胆や悔恨から抜け出すことはできなかった。私はコートを首元まできちんと巻き、外へ出た。その前に、もう一度手紙を読み返そうとポケットを探したが見つからず、馬車の藁の中に落としたに違いないと思って不安になった。しかし、指定された場所が、かつて石灰窯のそばの小さな水門小屋であり、時刻が9時だとよく覚えていた。私は時間を惜しみ、すぐに沼地へ向かった。
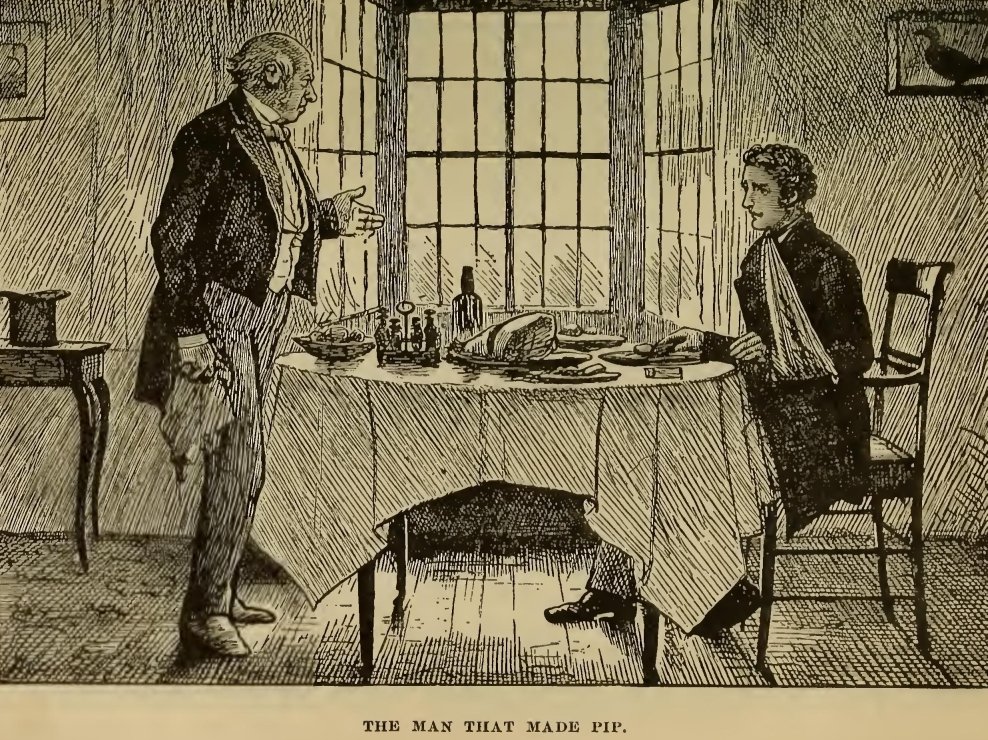
第五十三章
夜は暗かったが、囲われた土地を抜けて沼地へ出る頃には満月が昇り始めていた。その暗い線の向こうには、澄んだ空が細いリボンのように広がり、赤く大きな月がようやく収まるほどの幅しかなかった。数分もすると、月はその澄んだ空から立ち上り、積み重なる雲の山々の中へと昇っていった。
物悲しい風が吹き、沼地はひどく陰鬱だった。見知らぬ人なら耐えられなかっただろうし、私にとってさえも重苦しく、半ば引き返そうかと逡巡したほどだった。しかし、私はこの地をよく知っていたし、もっと暗い夜でも道が分かったはずであり、ここまで来てしまったからには引き返す理由がなかった。だから、気の進まぬまま来たからには、やはり気の進まぬまま進んだ。
私が進んでいたのは、かつての家のある方向でも、囚人たちを追った方向でもなかった。私は遠く離れた囚人船に背を向けて歩いており、砂洲の上に輝く古い灯りは肩越しに見ていた。石灰窯の場所も古い砲台と同じようによく知っていたが、両者は何マイルも離れていた。だから、もしその夜に両方に灯りがともっていたとしても、二つの明かりの間には長い空白の地平線が横たわっていただろう。
最初は幾つかの門を閉めて通り過ぎたり、道の堤に寝ていた家畜が起き上がって草や葦の間に去るのを待ったりしなければならなかった。しかし、しばらくすると沼地全体が自分だけのもののように思えた。
石灰窯に近づいたのは、さらに30分ほど経った頃だった。石灰は重く息苦しい臭いを放ちつつ燃えていたが、火はくべて放置され、作業員の姿はなかった。すぐ近くには小さな石切場があり、私の進路上にあった。その日は作業があったようで、道具や手押し車があちこちに置かれていた。
この掘り込みから再び沼地の高さまで登ると、古い水門小屋に明かりが見えた。私は歩を早め、手でドアをノックした。返事を待つ間、私は辺りを見渡し、水門が見捨てられ壊れていること、木造で瓦屋根の小屋が既に風雨に耐えられなくなりかけていること、泥やぬかるみが石灰で白く覆われていること、そして石灰窯のむせるような蒸気が幽霊のようにこちらへ漂ってくることに気付いた。それでも返事はなく、私はもう一度ノックした。やはり返事はなく、ドアの取っ手を試してみた。
取っ手は私の手で持ち上がり、ドアは開いた。中を覗くと、テーブルの上に灯ったロウソク、ベンチ、そして簡易ベッドの上のマットレスが見えた。二階もあるので、「誰かいるのか?」と呼びかけたが、応える声はなかった。時計を見ると9時を過ぎていたので、もう一度「誰かいるのか?」と呼びかけたが、やはり返事はなかった。私はどうしたものか迷いつつ、外に出た。
雨が激しく降り出していた。既に見たもの以外に何も見えなかったので再び小屋に戻り、ドアの内側で夜を見つめて立った。誰かが最近ここにいて、すぐに戻ってくるに違いない、さもなくばロウソクが灯っているはずがない、と考えていると、ふと芯が長いかどうか確かめる気になった。振り返ってロウソクを手に取った瞬間、激しい衝撃で明かりが消えた。次の瞬間、私は背後から頭にかけて投げられた強い引き絞りの縄に捕らえられたのだと理解した。
「これで――」抑えた声が罵りとともに言う。「捕まえたぞ!」
「何をするんだ!」私はもがきながら叫んだ。「誰だ、助けてくれ、助けて!」
両腕は体にぴったり縛られ、傷ついた腕を締め付けられて激痛が走った。時に力強い男の手、時に男の胸が私の口を押さえて叫び声を消し、熱い息が常にすぐそばにあった。私は暗闇の中、必死にもがきながら壁にしっかりと縛り付けられた。「そして――」またも抑えた声が罵りとともに言った。「もう一度叫んでみろ、すぐに片をつけてやる!」
傷ついた腕の痛みに気を失いそうになり、驚きで混乱しながらも、この脅しが容易に実行可能であることは分かっていたので、私は抵抗をやめ、せめて腕を少しでも楽にしようとした。しかし縄はあまりにきつく、それもできなかった。まるで火傷した腕が、今度は煮えたぎる鍋に入れられたようだった。
夜の光が急に消え、真っ暗闇に置き換わったことで、男が窓のシャッターを閉めたことが分かった。しばらく手探りした後、男は石打ち具と火打石を見つけ、火をつけ始めた。私は落ちる火花に、そして男がマッチを手に息を吹きかける唇と青白い炎に目を凝らしたが、はっきり見えたのはその唇とマッチだけで、それも断片的なものだった。火口は湿っていた――この場所なら当然だ――ので火花はことごとく消えていった。
男は焦る様子もなく、再び火打石を打ち付けた。火花が彼の周りに明るく飛び散ったとき、私は彼の手や顔の一部が見え、テーブルにうつむいて座っていることが分かった。それ以上は分からなかった。やがてまた青い唇が火口に息を吹きかけ、今度は明るい炎が立ち上り、照らし出されたのはオーリックだった。
誰の顔を見ることを期待していたのか分からない。だが彼ではなかった。彼を見て、私は本当に危険な状況にあることを悟り、彼から目を離さなかった。
彼は殺意を込めて慎重にマッチからロウソクに火を移し、マッチを落として踏み消した。それからロウソクをテーブルの向こうに置いて私がよく見えるようにし、両腕を組んでテーブルに伏せて私を見つめた。私は、太い縦のはしごに、壁から数インチ離れてしっかりと縛り付けられているのが分かった。それは固定されていて、上階への昇り口だった。
「これで――」しばらく互いに観察し合った後、彼は言った。「捕まえたぞ。」
「ほどいてくれ。解放してくれ!」
「ああ!」と彼は返した。「解放してやるとも。月まででも、星まででもな。時が来ればな。」
「なぜ私をここへ誘い込んだ?」
「分からないのか?」彼は殺気ある眼差しで言った。
「なぜ暗闇で襲ったんだ?」
「全部自分でやるつもりだからさ。二人より一人の方が秘密は守れる。ああ、お前は俺の敵、敵だ!」
彼がテーブルに両腕を組んで座り、頭を振りながら自分を抱きしめている、その姿には悪意がにじみ、私は震えた。黙って見つめていると、彼は脇に手を伸ばして、真鍮の装飾がついた銃を取り上げた。
「これを知ってるか?」と彼は私に銃口を向ける真似をしながら言った。「どこで見たか分かるか? 答えろ、狼め!」
「分かる」と私は答えた。
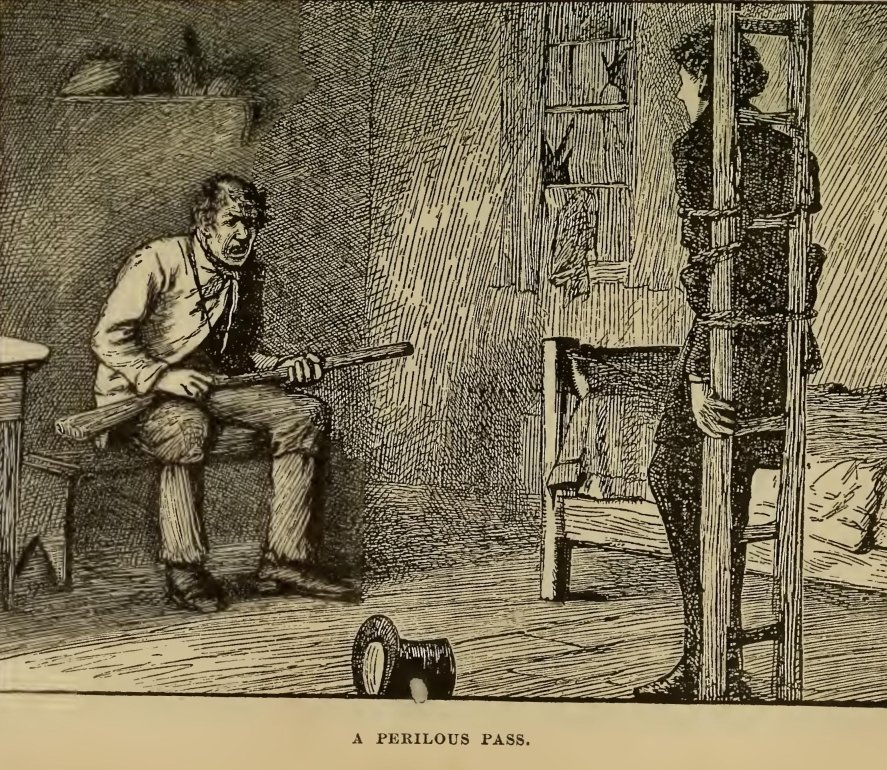
「お前のせいで、あの職を失った。お前のせいだ。答えろ!」
「他にどうしろと言うんだ?」
「それだけでも十分なのに、さらにお前はやったんだ。どうして俺と気に入った女の間に割り込めた?」
「いつ割り込んだ?」
「いつだってそうだった! お前がいつもオールド・オーリックの評判を彼女に悪く言ってたのさ。」
「自分で蒔いた種だ。自分でそうさせたんだ。お前が何もしなければ、私も何もできなかった。」
「嘘つきめ。お前はどんな苦労も金も惜しまず、俺をこの国から追い出そうとしたじゃないか?」と彼は、私がビディとの最後の会話で言った言葉をなぞるように言った。「今、教えてやるよ。今夜は、これまでになくお前の金を二十倍積んでも俺を追い出す価値があるってことだ。ああ! 最後の真鍮の一銭までな!」彼が重い手を振り上げ、口元を虎のようにゆがめて私を脅すと、私はそれが真実だと感じた。
「俺に何をするつもりだ?」
「俺はな――」と彼は重い拳でテーブルを叩き、その勢いで立ち上がった。「お前の命を奪うつもりだ!」
彼は身を乗り出して私をじっと見つめ、ゆっくりと手の拳をほどいて口元をぬぐい、よだれが出ているかのようにしながら再び腰を下ろした。
「お前は子供の頃からずっとオールド・オーリックの邪魔だった。今夜、お前は彼の前から消える。もう二度と現れやしない。お前は死ぬんだ。」
私は自分が墓穴の淵に立たされていることを悟った。一瞬、罠の中を見渡して逃げ道を探したが、望みはなかった。
「それだけじゃない」と彼は再び両腕をテーブルに組み、「お前の服も骨も、この世に一片たりとも残さない。お前の死体は石灰窯に放り込んでやる――二人分だって運べるぞ、俺は――誰が何を想像しようと、お前について何も分かりゃしないさ。」
私の心は、信じがたい速さでその死のもたらす全ての結果を追いかけた。エステラの父は私が彼を見捨てたと思い、捕まり、私を非難して死ぬだろう。ハーバートでさえ、私が彼のために残した手紙と、ミス・ハヴィシャムの門を一瞬だけ訪ねた事実を照らし合わせて、私を疑うかもしれない。ジョーもビディも、今夜の私の悔いがどれほど深かったかを決して知ることはないし、私がどれほど苦しみ、誠実であろうとしたか、どんな苦悩を味わったかも、誰も知ることはない。迫る死は恐ろしかったが、死よりもはるかに恐ろしかったのは、死後の誤解を恐れる気持ちだった。思考はあまりに速く、オーリックの言葉がまだ口元にあるうちに、私は将来生まれるエステラの子、そのまた子にまで蔑まれる自分を見ていた。
「さて、狼め」彼は言った。「お前を他の獣同様殺す前に――それが目的で、お前を縛り上げたのさ――たっぷり見てから、たっぷり苦しめてやる。ああ、敵だ!」
助けを呼ぶべきかという考えが頭をよぎったが、私ほどこの場所がいかに孤立しているか、その絶望的な状況を知る者も少ない。だが彼が私を眺めてほくそ笑んでいるうち、私は彼への軽蔑と嫌悪に支えられ、口を閉ざした。何があっても哀願はせず、最後までわずかな抵抗を示して死のうと決めた。極限の状況にありながら、他のすべての人には思いがやわらぎ、天に赦しを心から請い、親しい人々に別れを告げることができず、真意を伝えられず、この悲惨な過ちへの憐れみを求めることもできないと胸が締めつけられたが――それでも、もし死の間際にやつを殺せるのなら、そうしただろう。
彼は酒を飲んでいたようで、目は赤く充血していた。首にはブリキの瓶がぶら下がり、かつて彼が食べ物や飲み物をぶら下げていたのをよく見たものだ。その瓶を口に運び、強い酒を一口あおると、その烈しいアルコールの匂いが私の顔に流れてきた。
「狼め!」と彼はまた両腕を組み、「オールド・オーリックが何か教えてやる。お前の悪賢い姉貴を痛い目に合わせたのはお前だ。」
またしても私の心は尋常ならぬ速さで、姉への襲撃、その後の病気、死、すべてを彼の呂律の回らぬ遅い言葉より早く考え抜いていた。
「お前だな、悪党」と私は言った。
「お前のせいだ、お前のせいでこうなった」と彼は言い返し、銃を振り上げて私との間の空気を殴った。「あいつにも背後から襲いかかった、今夜お前にしたようにな。俺がやったんだ! 死んだと思って放ってきたが、もしあいつの近くにも今お前のそばにあるような石灰窯があったなら、生き返りやしなかった。だがやったのはオールド・オーリックじゃない、お前だ。お前が可愛がられ、俺がいじめられ叩かれた。オールド・オーリックはいじめられ叩かれた、そうだろ? 今度はお前の番だ。お前がやったんだ、今度はお前が償う番だ。」
彼はまた酒をあおり、ますます凶暴になった。瓶を傾ける様子から、もうそれほど残っていないのが分かった。彼がこれで自分を鼓舞して私を殺そうとしているのは明らかだった。その中の一滴一滴が私の命だと分かった。すべてが終わった後、私はさっき警告のごとく忍び寄ってきた白い蒸気――自分自身の幽霊のような蒸気――の一部となり、彼は姉のときと同じく急いで町に戻り、酒場で飲んでいる姿を目撃されるのだろう。私の頭は彼の町での姿を描き、その町の明かりや暮らしを、孤独な沼地と、そこに漂う白い蒸気に溶けて消える自分と対比させた。
彼の言葉一つにつき何年分も思考が駆け巡っただけでなく、彼の話すことがすべて絵のように私に浮かんだ。頭が極度に昂ぶった私は、場所を考えればそれが目に映り、人を思えばその姿が見えた。その鮮烈さは言葉では言い尽くせないほどだった。それでも私は、目の前の虎のような男から一瞬たりとも目を離せなかった。
彼が二度目の酒を飲むと、ベンチから立ち上がり、テーブルを脇へどかした。それからロウソクを取り上げ、殺意に満ちた手で明かりを遮り、私に光を集めて見下ろし、ぞっとするほど見物を楽しんだ。
「狼、さらに教えてやろう。あの夜お前が階段で躓いたのはオールド・オーリックだった。」
私は消えたランプのある階段を見た。見張りの提灯が壁に投げる重い手すりの影を見た。もう二度と見ることのない部屋を見た――ある部屋は半開き、ある部屋は閉まっていた――あらゆる家具が目に浮かんだ。
「なぜオールド・オーリックがそこにいたか? さらに教えてやろう、狼。お前とあの女のおかげで、俺はこの国で楽に暮らす道をほとんど断たれてしまい、新しい仲間や新しい主人に仕えることにした。中には手紙を書いてくれる奴もいる――分かるか? ――手紙を書くんだ、狼! 五十通もの筆跡でな。お前みたいに一通きりの下手くそじゃない。俺は、お前の姉の葬式の時からずっと、お前の命を奪う決心をし、機会をうかがってきた。奴らの動向も調べてな。オールド・オーリックは思った、『どうにかしてあいつを捕まえてやる!』と。で、探していると、お前の叔父プロヴィスを見つけたんだな?」
ミル・ポンド・バンク、チンクス・ベイスン、古い緑銅のロープ工場――すべてが鮮明に思い浮かんだ! プロヴィスの部屋、合図が不要になった今、かわいらしいクララ、母のように優しい女性、寝たきりのバーリー老人、私の人生が急流のように海へ流れていく中、すべてが流れていった!
「お前にも叔父ができたな! 俺はガージェリー家でお前がいかに小さい狼だったか覚えてるぞ、この指と親指で首筋をつまんで殺してやろうと思ったことも何度かあるんだ――日曜に柳の木の下をうろついてるのを見たときさ。あの頃は叔父なんかいなかった。だがオールド・オーリックが、お前の叔父プロヴィスが昔この沼地で切断された足かせをつけていたと聞いて、その足かせを俺はずっと持っていた、姉を殴るのにも使った、今夜お前を殴るようにな――それを知ったとき、どう思う?」
彼は嘲笑とともにロウソクを私の顔の近くにかざしたので、私は火傷を避けようと顔をそむけた。
「はは!」彼はまた同じことをして笑い、「火傷した子は火を恐れるな! オールド・オーリックはお前が火傷したのを知っていたし、叔父プロヴィスを密かに逃がそうとしてるのも知っていた。オールド・オーリックはお前の一枚上手さ、だから今夜来るのも分かっていた! さらに教えてやろう、狼、これで終わりだ。お前の叔父プロヴィスにとってもオールド・オーリックにとってのお前のような奴がいるんだ。甥っ子がいなくなったとき、気を付けろ、プロヴィス。誰にもお前の服も骨も見つからないとき、気を付けろ。マグウィッチ――そう、名前は知ってる! ――と同じ国で生きていたくない奴がいて、やつはかつて別の国でマグウィッチについて確かな情報を得ていた。だから絶対に密かに出国させはしないし、危険にさらすこともしない。五十通も筆跡の違う手紙を書く奴らだ、お前みたいな下手くそとは違う。気を付けろ、コンピソン、マグウィッチ、そして絞首台だ!」
彼は再びロウソクを私に近づけ、煙で顔や髪をあぶり、一瞬視界を奪われた。彼が再び明かりをテーブルに戻し、背中を向けたとき、私は祈りを思い浮かべ、ジョーとビディ、ハーバートのもとに心を飛ばしていた。
テーブルと反対側の壁との間には数フィートの空間があった。その中を彼は今、体をゆすりながら前後に歩き回った。彼の巨体は以前よりも一層力強く見え、手はだらりと重く脇に下がり、私をにらみつけていた。もはや一縷の望みもなかった。心の中は焦燥で荒れ狂い、次々と鮮烈な映像が思考の代わりに押し寄せてきたが、彼が私を完全に抹殺する決意がなければ、あそこまで話すはずがないということは冷静に理解できた。
突然、彼は瓶の栓を抜き、軽いはずの栓が錘のように落ちる音がした。彼は瓶をゆっくり少しずつ傾けて飲み、もう私を見ようともしなかった。最後の数滴を手のひらに注いでなめとった。すると、突然激しい勢いで瓶を投げ捨て、恐ろしい罵声とともに身をかがめ、長く重い柄の石槌を手に持つのが見えた。
決して彼には哀願しないと決めた覚悟は揺らがなかった。私は全力で叫び、全力であがいた。動かせるのは頭と脚だけだったが、その範囲で経験したことのないほどの力を振り絞ってもがいた。同時に、外から応じる叫び声が聞こえ、人影と明かりがドアからなだれ込むのが見え、声と騒ぎが響き、オーリックが男たちの渦から抜け出して、水の中を転がるようにテーブルを跳び越え、夜の闇へ逃げ去るのが見えた。
一瞬の空白の後、私は同じ場所で、縛めを解かれて床に横たわり、誰かの膝の上に頭を載せていることに気がついた。意識が戻ったときには、目は壁のはしごに向いていた――意識より先に目がそれを捉えていた――だから自分が失神した場所と同じ所にいると分かった。
最初は誰に支えられているのか気にもならず、ただはしごを見ていた。すると、その間に顔が現れた。トラブの少年の顔だった!
「大丈夫そうだな」とトラブの少年は真面目な声で言った。「でもすげぇ青い顔してるぜ!」
その言葉で私を支えていた者の顔が私をのぞき込み、私は支え主が誰かを知った。
「ハーバート! なんてことだ!」
「静かに」とハーバートが言った。「落ち着け、ハンデル。慌てるな。」
「そしてスタートップ、懐かしい仲間!」と私も叫んだ。彼も私をのぞき込んだ。
「彼がこれから何を手伝うか思い出して、落ち着いてくれ」とハーバートは言った。
その言葉で私は跳ね起きたが、腕の痛みに倒れ込んだ。「時間はまだあるのか、ハーバート? 今夜は何曜日だ? どれくらいここにいた?」私は、ここに長く――一日と一夜、いやそれ以上――倒れていたような強い不安に襲われていた。
「まだ間に合う。今夜はまだ月曜日だ。」
「神に感謝だ!」
「明日火曜日は休めるぞ」とハーバートは言った。「でも痛みにうめかずにはいられないな、ハンデル。どこをやられた? 立てるか?」
「ああ、大丈夫だ。歩ける。痛いのはこの脈打つ腕だけだ。」
彼らは私の腕を露出させ、できる限りの手当てをした。腕はひどく腫れ上がり熱を持ち、触れるだけでも耐えがたかった。しかし彼らはハンカチを裂いて新たな包帯を作り、吊るし直してくれた。町に戻って冷却剤を手に入れるまでの応急処置だった。やがて我々は小屋の扉を閉じ、暗い石切場を抜けて引き返した。トラブの少年――今や大きく成長した青年――が先導してランタンを持って歩き、その明かりこそ私がドア越しに見た光だった。だが月は前に見たときより二時間は高く昇り、夜は雨交じりながらだいぶ明るくなっていた。石灰窯の白い蒸気も我々から遠ざかっていき、さっき祈りを捧げた私は今、感謝の祈りを捧げた。
私はハーバートにどうやって救いに来たのか尋ねた――最初、彼は頑なに話したがらず、私に安静を強いた――が、やがて分かったのは、私はあわてて手紙を部屋に落としてきており、彼はたまたまスタートップを道で見かけて一緒に帰宅した際、その手紙をすぐに発見したということだった。その文面に不安を覚え、しかも自分に残された私の手紙との食い違いがますます不安を募らせた。不安が増すばかりだったため、彼はスタートップの進んでの同行を受けて、馬車発着所へ行き、次の便を調べた。午後の便がもう出てしまっていたことと、障害があるほど不安が高まり、ついに追い馬車で追いかける決心をした。こうして二人はブルー・ボアに到着し、私や消息を探したが得られず、ミス・ハヴィシャムの所に回ったが見つからなかった。その後、(ちょうど私が自分の話の地元バージョンを聞いていた頃だろう)ホテルに戻り、食事をとり、案内人を探そうとした。運よくアーチ下にはトラブの少年――昔からどこにでも現れる癖のまま――がいて、彼は私がミス・ハヴィシャムの家から食事場所の方へ行くのを見ていた。こうしてトラブの少年が案内役となり、町から沼地へ続く道で小屋まで向かった。途中ハーバートは、私が本当にプロヴィスの安全のために重要な用事でここに来たのかもしれないと考え、もしそうなら邪魔はまずいと判断し、自分だけ案内人とスタートップを石切場の端に残して小屋を回り込み、中の様子を何度も窺った。だが中からは粗野な声しか聞こえず、私がそこにいるのか半信半疑になりかけたとき、突然私が大声で叫び、彼らは応じて突入したのだった。
小屋で起きたことを私が話すと、ハーバートはすぐにでも町の治安判事のもとに行って逮捕状を取るべきだと主張した。しかし私もすでに考えていたが、そうすれば我々は足止めされるか戻る義務を負い、プロヴィスにとって致命的になる危険があった。この難点には誰も異論を挟めず、その夜オーリックを追うことは諦めた。今は状況から見て、トラブの少年には事件を軽く伝える方が賢明と判断した。彼はもし自分の介入で私が石灰窯行きを免れたと知れば、がっかりしてひどく落ち込んだだろう。トラブの少年が悪意の人間ではなく、ただ余りある活力と、誰の迷惑であろうと刺激と変化を求める性分なのは間違いない。別れるとき私は彼に二ギニーを与え(これは彼の希望に合致したようだ)、今まで悪く思っていたことを謝ったが、全く堪えてはくれなかった。
水曜日がすぐそこに迫っていたので、その夜のうちにロンドンへ戻ることにした。三人で追い馬車に乗った。事件が噂になる前に遠ざかっておくべきだったからだ。ハーバートは私の腕のために大量の薬品を手に入れ、夜通しそれをかけてもらいながら旅を耐えた。寺院(テンプル)へ着いたのは明け方で、私はすぐに床につき、一日中横になっていた。
横になりながら、病気になって明日の計画に支障が出るのではないかという恐怖が私を苦しめた。それ自体が私を倒してしまうのではないかと思うほどだった。幾度もの精神的消耗とあいまって、もし「明日」への異常な緊張がなければ、確実に倒れていただろう。「明日」はあまりに重い意味を持ち、直前なのに結果はまったく見えなかった。
その日プロヴィスと一切連絡を取らないという最も明白な用心さえも、逆に私の不安を募らせた。私は物音や足音のたびに驚き、彼が発見され逮捕され、その知らせが届くのではと疑い続けた。私は、彼が逮捕されたことを知っている、ただの不安や予感ではなく、事実が起き、それを神秘的に知ってしまったとまで自分を納得させようとした。日が過ぎても何も起こらないと分かっても、夜が更けていくうちに、明朝までに病に倒れることへの恐怖が私を完全に支配した。熱を持つ腕と頭はうずき、すでにうわごとを始めている気がした。自分を確かめるために高い数字を数えたり、知っている散文や詩の一節を繰り返したりした。疲労で一瞬眠ったり意識を飛ばしたりするたび、「今だ、ついにうわ言を始めた!」と飛び起きた。
その日一日は静かに過ごさせられ、腕は絶えず包帯を替えてもらい、冷たい飲み物を与えられた。眠るたびに、小屋で感じた「長い時が経ち、機会は失われた」という感覚で目覚めた。真夜中ごろ、私は起き上がり、ハーバートの所へ行き、二十四時間も眠って水曜日が過ぎたと確信していた。それが私の神経過敏の最後の発作だったが、以降はぐっすり眠ることができた。
水曜の朝、私は窓の外を見た。橋の明かりはすでに薄れ、昇る太陽が地平線にまるで火の沼のように広がっていた。川はまだ暗く神秘的で、橋の上では冷たい灰色が広がり、所々で空の輝きが暖かく映えていた。密集する屋根の上に教会の塔や尖塔が突き上がり、異様なほど澄んだ空気に包まれて、太陽が昇り、川からもやが一気に消え、無数の光が水面にきらめいた。私自身からもベールが消えたようで、私は心身ともに強く健康になったのを感じた。
ハーバートはベッドで眠り、古い友人の学生仲間はソファで眠っていた。私は一人で着替えできなかったが、まだ燃えている暖炉の火をくべ、コーヒーを用意した。やがて彼らも元気に目を覚まし、窓を開けて鋭い朝の空気を入れ、まだ上げ潮の川を眺めた。
「九時に潮が引き始めるときが合図だ」とハーバートは明るく言った。「ミル・ポンド・バンクのそっちで、ちゃんと準備して待っててくれよ!」
第五十四章
それは三月の、太陽は暑いが風は冷たい日だった。光の下では夏で、日陰では冬だった。我々はピーコートを着込み、私はバッグを持った。世間の持ち物のうち、バッグに入る必需品しか持たなかった。どこへ行くのか、何をするのか、いつ帰るのかさえも全くわからなかったが、そんなことに煩う暇もなかった。心はただプロヴィスの安全だけに集中していた。私は、ドアの前で立ち止まり、次にこの部屋を見るときにはどんな変化があるのか――もし再び見ることがあれば――と一瞬だけ考えた。
我々はテンプルの階段までゆっくり歩き、そこでしばらく立ち止まって、まるでまだ水に出るかどうか迷っているかのように振る舞った。もちろん、私はあらかじめボートの用意も万全にしておいた。誰が見ているわけでもなく、河岸の住人が二、三人いるだけだったので、ちょっとした迷いを装ってから、乗り込んで出発した。ハーバートがバウ(船首)、私が舵を取った。そのとき、ちょうど満潮、八時半ごろだった。
私たちの計画はこうだった。潮が九時に下げ始め、三時まで味方してくれるので、潮が返してからも静かに進み、暗くなるまで逆流に漕いで進むつもりだった。そうすれば、グレーヴセンドの下手、ケントとエセックスの間にある長い川筋に十分入ることができ、川は広く寂しく、水辺の住人もほとんどおらず、ぽつぽつと孤立した酒場が点在しているので、その中の一つを休息所として選ぶことができる。そこで一晩中じっとしているつもりだった。ハンブルク行きとロッテルダム行きの汽船は、木曜の朝九時ごろロンドンから出発する。どこにいるかによって、何時ごろそれらが来るか分かるので、最初の船を合図して呼び止めれば、もし万が一乗り損ねてももう一度チャンスがある。それぞれの船の見分け方も知っていた。
いよいよ計画の実行に移ることができた安堵感は、私には非常に大きく、数時間前まで自分がどんな状態だったか現実感が持てないほどだった。澄んだ空気、日差し、川の動き、そしてその流れそのもの――道が私たちと共に走り、私たちに共感し、元気づけ、励ましてくれているかのようで、私は新たな希望に心を洗われた。舟の中でほとんど役に立たない自分が情けなかったが、二人の友人ほどの漕ぎ手は滅多にいないし、彼らは一日中持続するしっかりとしたストロークで漕いでいた。
当時、テムズ川の蒸気船の交通量は今よりずっと少なく、水上のボートマンたちははるかに多かった。はしけや帆船の炭運搬船、沿岸商船の数は今とそんなに変わらなかったかもしれないが、大小の汽船に関しては、その十分の一や二十分の一もなかっただろう。朝早くから、オールを使ったボートがあちこちへと行き交い、潮に乗って下っていくはしけもたくさんいた。当時、橋と橋の間をオープンボートで航行するのは、今よりもずっと簡単で一般的なことだった。そして私たちは、数多くのスキッフやホエリーの間を軽快に進んだ。
まもなく旧ロンドン橋を通り過ぎ、牡蠣船やオランダ人たちが集まる旧ビリングズゲート市場も通り過ぎ、ホワイト・タワーやトレイターズ・ゲートも越えて、船団の列の中へと入っていった。そこにはリース、アバディーン、グラスゴー行きの汽船が、荷の積み下ろしをしていて、私たちが横を通ると水面よりずっと高くそびえ立って見えた。石炭船が何十隻も繋がれており、甲板上の作業台から石炭運びたちが体を投げ出しては、吊り上げられた石炭の計量分に対するカウンターウェイトとなり、それをバーゲにガラガラと流し込んでいた。ロッテルダム行きの明日の汽船も係留されており、私たちはそれをよく見ておいた。また、ハンブルク行きの明日の船も、私たちはそのバウスプリットの下を横切った。そして私は、船尾に座りながら、鼓動の速まる胸で、ミル・ポンド・バンクとミル・ポンドの階段が見えるのを確認した。
「あいつはいるか?」とハーバートが言った。
「まだだ。」
「よし! 俺たちを見てから降りてくることになってたよな。合図が見えるか?」
「ここからはよく見えないけど……あっ、見えた。――今見えた! 二人とも漕いで。ゆっくり、ハーバート。オール!」
私たちは階段にそっと一瞬だけ舟を寄せ、彼は乗り込むとすぐに出発した。彼はボートクロークと黒いキャンバス地の鞄持参で、心から願っていた通り、まるで川の水先案内人のような風貌だった。
「おお、坊や!」と彼は席に着きつつ私の肩に手を置いて言った。「忠実な坊や、よくやった、ありがとう、ありがとう!」
再び船団の間を、錆びた鎖や擦り切れた麻の係船用ロープ、揺れるブイ、沈みかけた壊れた籠、木片や削り屑、石炭の浮きかすをかき分けて進み、ジョン・オブ・サンダーランド号の船首像の下をくぐり(多くのジョンのごとく風に向かって演説中)、ベッツィ・オブ・ヤーマス号のふくらみと、飛び出た目の下を通り抜けた。造船所ではハンマーが鳴り、丸太を引く鋸の音、何やら分からぬ機械の騒音、浸水船のポンプの音、キャプスタンの音、出航する船の音、バルワーク越しにライトマンたちに叫ぶ海の男たちの罵声――そうしたものの間をくぐり抜け、ついに川幅が広がる清らかな流れへ、舟のフェンダーもいらない水域まで進んだ。
彼を乗せた階段でも、その後も、私は警戒して我々が疑われている兆しがないか目を配っていたが、何も見当たらなかった。確実に、あの時も今も、私たちを追う舟はなかった。もし他の舟が追うようなら、私は岸に寄せてその目的をはっきりさせるつもりだったが、何事もなく自分たちのペースで進んだ。
彼はボートクロークをまとい、先ほど言った通り、この場面の自然な一部のように見えた。特筆すべきは(おそらく過酷な人生経験ゆえだろうが)、私たちのうちで彼がもっとも不安そうでなかったことだ。無関心というわけではなかった。本人は、異国の紳士として私を見届けたいと話してくれたし、ただ受け身でも諦めきっているわけでもなかった。ただ、危険に対して、事前に思い悩むことは一切なかった。危険が来れば立ち向かうが、来るまでは気にしないのである。
「坊やがここに、俺のそばで煙草を吸いながらすわってるありがたさが分かるかい、坊や。毎日四つの壁に閉じ込められてたんだ。坊や、お前は俺がどれだけうらやましがられる境遇か分からないだろう。」
「自由の喜びは分かるつもりだよ」と私は答えた。
「いや」と彼は重く首を振った。「だがお前は俺ほど分からん。坊や、俺ほど分かるには鍵付きで閉じ込められてみなきゃな――でも、落ち込んでるつもりはない。」
どんなに大きな思いがあったとしても、彼が自由や命を危険にさらしたことは矛盾しているように思えた。しかし私は、危険のない自由など、彼の人生の習慣とはかけ離れすぎていて、彼にとっては他の人ほど魅力的でなかったのだろう、と考えた。私は間違っていなかった。彼は少し煙草を吸ってからこう言った――
「坊や、あっちの世界にいた時は、ずっとこっちを見てたんだ。金持ちになっても、そこにいるのが空虚でさ。誰もがマグウィッチを知ってて、来ようが去ろうが誰も気にしやしない。だが、ここじゃそうはいかない、坊や――少なくとも、ここに俺がいるって知られたらな。」
「すべてうまくいけば、もう数時間で君は完全に自由で安全になれるよ」と私は言った。
「ああ、そうだといいな」と彼は深呼吸をして答えた。
「そう思うかい?」
彼は舷側に手を浸し、あの柔らかな表情で微笑みながら言った――
「たしかにそう思ってるんだ、坊や。これ以上静かで楽な状況も無いだろうさ。だが……この水の中を舟が静かに心地よく流れていくからかもしれないが、さっき煙をくゆらせながら考えてたことと言えば、俺たちはこの川の底が見えないように、次の数時間の底も見通せやしないし、川の流れをつかまえておけないのと同じで、時間の流れも止められない。見てみろ、指の間をすり抜けて消えちまう!」と言い、濡れた手を掲げた。
「顔を見なければ、少し落胆しているのかと思ったよ」と私は言った。
「全然そんなことないぞ、坊や! 静かに流れていくのと、舟首でさざ波が日曜の賛美歌みたいな音を立ててるからだろう。たぶん、俺もちょっと年を取ってきたのさ。」
彼は表情を崩さず、パイプを口に戻し、まるで既にイングランドを離れたかのように落ち着き払っていた。それでも、忠告には素直に従った。私たちがビールの瓶を買い足そうと岸に寄せたとき、彼が下りようとしたので、私は「ここにいた方が安全だと思う」とそっと言うと、「そうかい、坊や」と言って静かに腰を下ろした。
川の空気は冷たかったが、明るい日差しがとても心強かった。潮の流れは強く、それを無駄にしないよう気をつけ、私たちの安定したストロークで順調に進んだ。潮が下がるにつれて、私たちは徐々に岸の森や丘から遠ざかり、泥の岸辺の間をどんどん下っていったが、まだグレーヴセンドを通過しても潮は味方していた。護送する彼はクロークにくるまれていたので、私はわざとフローティング・カスタムハウス(税関)に一、二隻分だけ接近して通過し、二隻の移民船の横や、前甲板に兵士が大勢見下ろしている大型輸送船の船首下をくぐり抜けて流れをキャッチした。やがて潮が緩み、錨泊していた船は向きを変え、上げ潮を利用してプール(ロンドンの船溜まり)へ向かう船が私たちを群れをなして追い越し始めた。私たちは流れの勢いを避けるため、できるだけ岸寄りに進み、浅瀬や泥洲に注意しながら進んだ。
時々潮に流されるままにして休息を取ったおかげで漕ぎ手たちは十分元気を保っており、十五分ほどの休憩で事足りた。岸に上がると、滑りやすい石に気をつけながら持参した食べ物を食べ、周囲を見渡した。そこは自分の沼地の田舎とよく似て、平坦で単調、かすんだ地平線が広がっていた。蛇行する川は何度も曲がり、浮標もぐるぐる回って、あらゆるものが取り残されて静止しているように見えた。最後の船団もついに見えなくなり、最後の緑色のバーゲ(藁を積み、茶色い帆を張っている)も続き、粗雑な子供の作ったような形のバラスト運搬舟が泥の中に沈み、杭の上の小さな灯台が泥の中でヨロヨロと立ち、ぬるぬるした杭や石、赤い標識や潮の跡、古い上陸用ステージや屋根のない建物までもが泥の中に沈みかけていた。周囲は一面の停滞と泥ばかりだった。
ふたたび舟を押し出して進み始めた。今度はずっと大変な作業だったが、ハーバートとスタートップは根気強く漕ぎ続け、日が沈むまで黙々と力を尽くした。そのころには、川が少し持ち上げてくれたので、岸の上まで見通せるようになっていた。赤い夕陽が低い地平線上、紫の霞の中に沈み、やがてそれが黒に変わろうとしていた。そこにはただ一面の平らな沼地があり、遠くには丘が見え、その間にはどこにも生命の気配がなく、手前で時折、もの悲しげなカモメが見られるだけだった。
夜の帳が一気に降りてきて、月も満月を過ぎて早くは昇らないので、私たちは短い相談をした。明らかに最初に見つけた孤立した酒場に寄るのが最善だった。二人は再びオールを握り、私は家らしきものを探して見張った。こうして私たちはほとんど言葉少なに、四、五マイルの退屈な道のりを進んだ。とても寒く、横を通った炭運搬船が、ガレーの火で煙を上げているのがまるで温かそうな家のように見えた。この頃にはすでに夜は朝まで続く暗さに変わっており、わずかな光は空よりもむしろ川の水面から反射して届いていた。オールで水を打つたびに、きらきらと映る星をかすめていた。
この陰鬱な時間、私たちは皆、誰かに尾行されているのではないかという思いに取り憑かれていた。潮の動きで不規則に岸に波がぶつかるたび、誰かしらが必ずその方向を警戒した。流れで岸がえぐれてできた小さな入江もいちいち疑わしく、みな神経質に目を向けた。「今の波紋は何だ?」とか「向こうに舟が見えるか?」などと密かにささやき、その後また沈黙に戻った。私はオールがスロットでこすれる音がいつもよりずっと大きく感じて、じりじりとした気持ちで座っていた。
やがて光と屋根が見え、やがて小さな石積みの突堤のそばに舟を着けた。仲間を舟に残して私は岸に上がり、光が酒場の窓に灯っているのを確かめた。そこはかなり汚い場所で、密輸業者には馴染み深いのだろうと思われたが、台所の暖炉は燃え、ベーコンと卵があり、各種の酒もあった。寝室も二部屋(「お粗末なものだが」と主人は言った)があり、宿の住人は主人とその妻、それに「突堤のジャック」と呼ばれる、まるで干潮線で育ったかのようなぬるぬるした年配の男だけだった。
この手伝いを連れて舟に戻り、全員で上陸し、オールや舵棒、ボートフックなどを引き揚げて舟を岸に上げた。台所の暖炉でしっかり食事を取ると、寝室を分け合うことにした。ハーバートとスタートップが一部屋、私と保護者がもう一部屋である。どちらの部屋も外気がまるで毒であるかのように遮断され、家族が持っているとは思えぬほどの汚れた衣類や箱がベッドの下に詰め込まれていたが、このうえない孤独な場所なので私たちは十分満足だった。
食事後、暖炉の前でくつろいでいると、ジャックが片隅に座り、ベーコンと卵を食べている間に見せてくれた、数日前に打ち上げられた溺死者から取ったという膨れた靴を履いていた。そのジャックが、「潮に乗って上がっていった四人漕ぎのガレーを見なかったか?」と私に尋ねた。見ていないと答えると、彼は「あいつらはじゃあ下ったんだな、しかし去るときは『上り』でもあった」と言った。
「何かしらの理由で気が変わって下ったんだろうよ」とジャックは言った。「四人漕ぎのガレーだったのか?」と私は尋ねた。
「そうよ、オール四本に二人座りだった。」
「ここに寄ったのか?」
「ああ、二ガロンの石壺でビールを買いに寄ったぜ。俺ならビールに毒でも入れてやりたかったさ」とジャック。「それかガラガラ音のする薬でもな。」
「なぜ?」
「理由は俺が知ってるさ」とジャックは、泥が喉に詰まったような声で言った。
「こいつは、思い違いをしてるんだ」と、主人が弱々しく冴えない目でジャックに頼るように言った。「こいつはそういう連中だったと思ってる。」
「俺が思うならそれだ」とジャック。
「カスタムハウス(税関)だと思うのか、ジャック?」と主人。
「そうだ」とジャック。
「じゃあ違うぞ、ジャック。」
「本当かよ!」
ジャックは、その返事に無限の意味と底知れぬ自信を込めて、靴を片方脱ぎ、中を覗いて石をいくつかキッチンの床に落とし、また靴を履いた。その仕草は、絶対に自分が正しいから何をしても気にしないというジャックの自信そのものだった。
「じゃあ、その連中がボタンをどうしたか説明できるのかよ、ジャック?」と主人は頼りなく問い返した。
「ボタンだと? 放り投げたに決まってる。飲み込んだんだ。畑に蒔いてカイワレにしたかもな。ボタンなんか!」
「調子に乗るなよ、ジャック」と主人は悲しげにたしなめた。
「税関吏はボタンをどうするか知ってるさ」とジャックは、侮蔑を込めてその忌々しい単語を繰り返した。「自分の勘に逆らうときにはな。四人漕ぎの二人座りがあっちの潮、こっちの潮と上ったり下ったり、理由がなきゃそんなことしやしねぇ。税関がいるに決まってる。」そう言い放ち、ジャックは軽蔑を込めて出ていった。主人は反論すべき相手がいなくなると、それ以上話を続けることができなかった。
このやりとりは私たち全員、そして私には特に不安をもたらした。外では陰鬱な風が唸り、潮は岸に打ち寄せ、私は自分たちが閉じ込められ脅かされているような気がした。不審な動きを見せていた四人漕ぎのガレーの存在は、どうしても気になって仕方がなかった。プロヴィスを寝かせたあと、私はスタートップ(彼もすでに事情を知っていた)とハーバートを誘い、外で再び相談した。汽船の時間(午後一時頃)までこの家に留まるべきか、それとも朝早く出発するべきか議論し、結局、汽船の出発一時間ほど前までここにいればよいだろう、そして潮に乗り汽船の航路に出ればよい、と決した。決意して家に戻り、床についた。
私はほとんど服を着たまま横になり、数時間はよく眠れた。目覚めると風が強まり、家の看板(ザ・シップ)がきしみ、バタンバタンと大きな音を立てていて私は驚いた。そっと起き出し、保護者がぐっすり眠っているのを確かめて窓から外を見た。窓からは舟を引き上げておいた突堤が見え、曇った月明かりに目が慣れると、二人の男が舟を覗き込んでいるのが見えた。彼らは窓の下を通り過ぎて舟着き場には行かず、沼地をノア岬の方へ横切っていった。
私はすぐにハーバートを起こしてこの様子を見せようと思ったが、彼らの方が疲れているし、いったん思いとどまった。再び窓に戻ってみると、二人の男は沼の上を進んでいたが、やがて見失った。とても寒かったのでまた横になり、この件について考えているうちにまた眠ってしまった。
私たちは早起きした。朝食前、四人で外を歩きながら、私は見たことを語るべきだと考え、打ち明けた。だが、護送対象の彼はやはり一番心配していなかった。たぶんその男たちは税関の者だろうし、私たちなんて眼中にないだろう、と静かに言った。私もそうかもしれないと自分に言い聞かせたが、不安は残った。私は彼と二人で遠く見える地点まで歩き、舟にはそこで拾ってもらうか、できるだけ近くで乗せてほしいと提案した。これは良い用心策だと判断し、朝食後すぐ、宿には何も言わず出発した。
彼は道中パイプをふかし、ときおり私の肩をたたいた。まるで危険にさらされているのが私で、彼が私を安心させているようだった。私たちはほとんど会話を交わさなかった。例の地点が近づいたとき、私は彼に隠れた場所で待つよう頼んで、偵察に進んだ――というのも、夜中に男たちはそちらへ向かったからだ。彼は素直に従い、私は一人で進んだ。岬の沖にはボートもなく、引き上げられた形跡もなかったし、人影もなかった。ただし、潮が高いので水面下に足跡があることもあったかもしれない。
遠くの隠れ場所から彼が顔を出し、私が帽子を振って呼ぶと、彼は再び合流し、私たちはそこで待った。ときにはコートにくるまって岸に横たわり、ときには体を温めるために歩き回りながら、舟が回り込んでくるのをじっと待った。無事に乗り込み、汽船の進路へと漕ぎ出したときには、すでに一時まであと十分ほどになっていたので、私たちは汽船の煙を探し始めた。
だが、煙が見えたのは一時半で、その後ろにもう一隻の汽船の煙も見えた。両方とも全速力でこちらに来ていたので、私たちは二つの鞄を用意し、ハーバートとスタートップに別れを告げることにした。私たちはみな固く握手を交わし、ハーバートも私も涙ぐんでいた。そのとき、川岸のすぐ前方から四人漕ぎのガレーが姿を現し、同じ進路へと漕ぎ出してきた。
川の曲がりと風向きのせいで、これまで私たちと汽船の煙の間には岸があったが、今や船が真正面から接近しているのが見えた。私はハーバートとスタートップに、潮の上流側に位置して汽船から見えるようにしてくれと叫び、プロヴィスにはクロークにくるまってじっとしているよう懇願した。彼は陽気に「任せてくれ、坊や」と言い、像のように動かなかった。一方、ガレーは巧みに操られ、私たちを横切り、並走してきた。オールの間隔だけ空けて、私たちと並び、私たちが流されれば流され、漕げば一、二回漕いで速度を合わせた。二人の座り手の一人は舵を取り、じっと私たちを見つめていた――漕ぎ手たちも同様だった。もう一人の座り手はプロヴィス同様、クロークにくるまって小さくなり、舵取りに何か指示をささやいていた。どちらの舟も一言も発しなかった。
しばらくしてスタートップが、どちらの汽船が先か見分け、「ハンブルク」と小声で伝えてくれた。汽船は急速に近づき、パドルの音が大きくなった。まるでその影が私たちを飲み込もうとしているかのように感じたそのとき、ガレーから声がかかった。私は応じた。
「そちらに帰還移送囚がいるな」と舵手の男が言った。「そのクロークにくるまってる男だ。本名はエイベル・マグウィッチ、別名プロヴィス。私はその男を逮捕する。協力を頼む。」
同時に、彼は乗組員に明確な指示を与えることもなく、ガレーを私たちの舟の側面に接舷させた。ガレーは突然ストロークを一つ前に漕ぎ、オールを上げてこちらに横付けし、私たちの舷にしがみつくまで、何が起こっているのか分からなかった。これで汽船上にも混乱が生じ、私たちに呼びかける声やパドル停止の命令が聞こえたが、汽船はなおも勢いよく迫っていた。同時に私は、ガレーの舵手が囚人の肩に手を置くのを見て、両舟が潮に押されて回転し始め、汽船の全員が狂ったように前方に駆け寄るのを見た。そしてまた同時に、囚人が立ち上がり、相手の上に身を乗り出して、ガレーの小さくなっている座り手の首からクロークを剥ぎ取るのを見た。その顔は、かつてのもう一人の囚人、あの男だった。その顔が恐怖で白くのけぞり、汽船で大きな叫び声が上がり、激しい水音がし、私の乗った舟が崩れ沈むのを感じた――すべてが一瞬の出来事だった。
私は、無数の水車と閃光の中でもがくような瞬間を過ごし、それが過ぎるとガレーに引き上げられていた。ハーバートもスタートップもいたが、私たちの舟はなく、二人の囚人も消えていた。
汽船に響く叫び声、蒸気の激しい噴出音、船の推進、それに加えて私たちも流されていたので、最初は空と水、岸と岸の区別もできなかった。しかしガレーの乗組員は素早く舟を立て直し、力強いストロークで前進してからオールを止め、全員が無言で、しかし熱心に舟の後ろの水面を見守った。やがて暗い物体が潮に乗って私たちの方へ近づいてきた。誰も声を出さず、舵手が手を上げると、全員そっとバックオールし、舟の進路をまっすぐ保った。近づいてきたのは、自由に泳げてはいないものの、マグウィッチであることが分かった。彼は引き上げられ、すぐに手錠と足枷を嵌められた。
ガレーはそのまま安定し、水面の熱心な監視が再開された。だが、ロッテルダム行きの汽船が接近してきて、何が起きたのか分からないらしくそのまま進んできた。呼び止めて停止させたころには、両汽船とも私たちの前から遠ざかり、私たちは荒れた航跡の中で揺れた。静けさが戻り、両汽船が見えなくなった後も、捜索は続けられたが、もはや万事休すと誰もが分かっていた。
ついに諦め、私たちは先ほどまでいた酒場へ向かって岸に漕ぎ寄せた。そこでは大きな驚きで迎えられた。私はマグウィッチ――もはやプロヴィスではない――のためにいくらかの薬などを手に入れることができた。彼は胸に重傷を負い、頭に深い切り傷を負っていた。
彼は自分が汽船のキールの下に入ってしまい、浮上したとき頭を打ったのだろうと言った。胸の怪我(呼吸困難を伴う)はガレーの舷側にぶつかったのだろうと考えていた。彼は、コンピソンに何をしたかは分からないが、クロークを剥いで身元を明らかにした時、あの悪党はよろめいて後ずさりし、二人とも一緒に水中に落ちた。マグウィッチが私たちの舟から引き離され、護送人が彼を引き留めようとしたことで舟が転覆したのだ、とささやいた。彼らは水中で激しく組み合い、やがてマグウィッチは自力で抜け出し泳ぎ去ったという。
私は彼の話がすべて真実だと疑う理由は一度もなかった。ガレーを操っていた監督役も二人が落水した経緯を同様に語った。
私はこの監督役に、宿で手に入る予備の衣類で囚人の濡れた服を着替えさせてよいか尋ねると、快く許可してくれた。ただし、囚人の持ち物はすべて預かると言い、かつて私の手にあった財布も彼の管理下に移った。また、私は囚人と一緒にロンドンへ同行する許可も得たが、友人二人までは許されなかった。
宿のジャックは、溺死者が沈んだ場所を指示され、遺体が岸に上がりそうな場所を捜索することを引き受けた。死体がストッキングを履いていたと聞くと彼の関心はさらに高まったようだ。おそらく一揃いの服を得るには十人以上の溺死者が要るのだろう。そのため彼の服装は部分ごとに傷み方が違っていた。
私たちは潮が変わるまで宿に滞在し、マグウィッチは担がれてガレーに運ばれた。ハーバートとスタートップはできるだけ早く陸路でロンドンへ戻ることになった。別れは痛ましく、私はマグウィッチの隣に座ったとき、これからは彼が生きている限り、私の居場所はここだと感じた。
もはや私は彼への嫌悪感を完全に忘れていた。追われ、傷つき、鎖に繋がれた彼が私の手を握る姿には、私の恩人たらんとし、何年にもわたって変わらず私に愛情と感謝と寛大さを抱き続けた男の姿しか見えなかった。ただただ、彼は私がジョーにしたよりも、はるかに立派なことを私にしてくれた人物だとしか思えなかった。
夜が更けるにつれ、彼の呼吸はますます苦しそうになり、しばしばうめき声をこらえきれなくなった。私は使える方の腕で少しでも楽な体勢にしようとしたが、彼が重傷を負ったことを心から悲しめなかったのは、自分でも恐ろしい気持ちだった。彼を指認できる者がまだ十分に生きているのは明らかだったし、情状酌量の余地も望めなかった。彼の裁判では最悪の評判が与えられ、その後脱獄し再度裁かれ、終身流刑の身で帰国し、今回の逮捕の原因となった男の死にも関わってしまったのだから。
昨日、私たちが後にした夕陽へと再び帰路につき、希望の流れが逆流していくかのように感じながら、私は彼に、彼が私のためだけに帰国したことを悔やんでいると伝えた。
「坊や」と彼は答えた。「俺は自分の運命を受け入れて満足だ。坊やに会えたし、俺がいなくても坊やは立派な紳士になれる。」
いや、私は彼と並んで過ごした間に、そのことについても考えたのだ。いや、ウェミック氏の示唆が今やっと分かった。彼が有罪となれば、財産は王室に没収されるのだ。
「坊や」と彼は言った。「もう今となっては、紳士は俺と関係があると知られない方がいい。ウェミックと一緒にたまたま会いにきたようにしてくれ。俺が最後に証言台に立つとき、見えるところに座ってくれればいい。それだけで十分だ。」
「君のそばにいられる限り、決して君のもとを離れない。神様が許してくれるなら、君が僕にしてくれたように、僕も君に誠実であり続けるよ!」
彼の手が私の手を握るとき震えているのを感じ、舟の底に横たわりながら顔を背けた。そしてあの昔の喉の音――今やすべての彼と同じく柔らかくなったそれ――が聞こえた。彼がこの話題に触れてくれて良かった、さもなければ、彼が私を富ませようとした夢が潰えたことを彼に教えずに済まなかったかもしれない。
第五十五章
翌日、彼は警察裁判所へ連行され、すぐに公判に付されるはずだったが、かつて彼が脱走したプリズンシップ(囚人船)の古い監視人を呼んで本人確認の証言をさせる必要があった。誰も疑っていなかったが、身元を証明するはずだったコンピソンは、すでに潮に流されて死んでおり、当時ロンドンには適任の看守がいなかった。私はその夜すぐにジャガーズ氏の私邸に直行し、弁護を依頼したが、ジャガーズ氏は一切認めようとしなかった。証人が来れば審理は五分で終わり、どんな力を使っても勝ち目がないと彼は言った。
私は、彼に財産の運命を知らせずにおくつもりだとジャガーズ氏に話した。ジャガーズ氏は「指の間からこぼれ落ちさせた」と憤慨し、いずれ嘆願して何とか一部でも取り戻そうと言った。しかしこの件では没収が免除される事情は何もなく、私に有利な要素は何一つないと隠さなかった。私はそれをよく理解した。私は彼の親族でもなく、認められた関係もなく、逮捕前に私のために何らかの書類や遺言を残したわけでもない。今やっても無意味だった。私は何の権利も持たず、以後も決して望みのない訴えに心を病ませないと固く決意した。
溺死した密告者が没収財産の報酬を狙い、マグウィッチの資産についてかなり詳細な情報を得ていたらしい形跡もあった。死体は現場からかなり離れた場所で発見され、ひどく損傷していたが、ポケットの中身で本人と判明した。中には、ニューサウスウェールズの銀行名と、かなりの価値の土地に関する記載があった。これらは、マグウィッチが獄中からジャガーズ氏に、自分が私に残すつもりでいた財産リストとして渡していた情報に一致していた。彼は最後まで自分の遺産がジャガーズ氏の力で無事に私に渡ると信じて疑わなかった。
三日後、囚人船の監督がついに来て、あっさり身元確認が成立した。彼は次回のセッション(開廷)で裁判を受けることとなり、それは一か月後だった。
この人生で最も暗い時期、ある晩ハーバートが沈んだ面持ちで帰宅し、言った――
「親愛なるハンデル、僕は近いうちに君のもとを離れなければならなくなりそうだ。」
彼の共同経営者からその話はすでに聞いていたので、私は彼が思うほど驚かなかった。
「カイロ行きを先延ばしにすれば、せっかくの好機を逃してしまう。残念だが、ハンデル、君が一番僕を必要とするときに、行かねばならないかもしれない。」
「ハーバート、僕はいつだって君を必要としている――君を愛しているからね。でも今が特段必要な時というわけじゃない。」
「君はとても孤独になるだろう。」
「そんなこと考える余裕もないよ。知っているだろう、僕は与えられた時間いっぱい彼と一緒にいて、できるなら一日中でもいたい。そして彼のそばを離れるときも、心は常に彼と共にある。」
彼が置かれた悲惨な状況は、私たち二人にとってあまりにも恐ろしすぎて、あからさまに言葉にすることはできなかった。
「親友よ」とハーバートは言った。「もうすぐ別れが迫っている――本当に間近だ。そのことが、君の将来について君に口を出す正当化になると思ってくれ。自分の今後について考えたことは?」
「いや、将来を考えるのが怖かったんだ。」
「だが、君自身のことは放置できない。親愛なるハンデル、君自身のことは放置してはいけない。せめて僕といくつか言葉を交わすだけでも、今すぐそのスタートを切ってほしい。」
「分かった、やってみるよ。」
「うちの支店で、ハンデル、どうしても――」
彼は適切な言葉を避けようとしたので、私は「事務員だろう」と言った。
「事務員だ。だが、そのうち(君の知っている事務員がそうなったように)共同経営者に育つ可能性も十分ある。さて、ハンデル――つまり、親愛なる友よ、僕と一緒にやらないか?」
彼は「さて、ハンデル」と、重大な話の導入のように言い出した後、一転して学生のような明るさで手を差し出してきた。その誠実な仕草に、私はとても心を動かされた。
「クララと僕とは何度もこのことを話し合ったんだ」とハーバートは続けた。「そして今夜も、あの可愛い子が涙を浮かべて、君にこう伝えてほしいと頼んできた。もし僕たちが一緒に暮らすことになったとき、君が僕たちと一緒に住んでくれるなら、彼女は君を幸せにするために最善を尽くすし、夫の友人が自分の友人でもあると信じてもらえるよう努力すると。僕たちはきっとうまくやっていけると思う、ハンデル!」
僕は心からクララに、そしてハーバートにもお礼を言ったが、彼が親切にも申し出てくれたことに今すぐ応じられるかはまだわからない、と伝えた。第一に、僕の心は他のことでいっぱいで、その話をはっきりと考える余裕がなかった。第二に――そう、第二には、ぼんやりとした何かが僕の心に残っていて、それはこのささやかな物語の終わり近くで明らかになるだろう。
「でも、もし君が――ハーバート、君の仕事に差し支えない範囲で――しばらくその話を保留にしておいてくれるなら……」
「いくらでもいいよ!」とハーバートは叫んだ。「半年でも、一年でも!」
「そんなに長くは必要ない」と僕は言った。「せいぜい二、三ヶ月だ。」
僕たちがこの話で握手を交わすと、ハーバートはとても喜び、その場で思い切って僕に告げてきた――どうやら週末には出発しなければならないだろうと。
「クララは?」と僕が尋ねた。
「可愛いあの子はね」とハーバートは答えた。「お父さんのもとで最後まで尽くしてるけど、もう長くはないよ。ウィンプル夫人の話では、もう確実にお別れが近いそうだ。」
「無感情なことを言うつもりはないが」と僕は続けた。「それが彼にとっても一番いいことかもしれない。」
「そう認めるしかなさそうだ」とハーバートは言った。「そしたら僕はまたあの可愛い子のもとに戻って、一緒に近くの教会へ静かに歩いていくんだ。覚えておいてくれ! あの愛しい子は家柄もなく、赤い本を見たこともなく、おじいさんについても何も知らない。僕の母の息子にとってはなんて幸運なんだろう!」
その週の土曜日、僕は希望に満ちつつも、僕を置いていくことを悲しみながら、港町行きの郵便馬車に座るハーバートに別れを告げた。僕はコーヒーハウスに入り、クララ宛てに短い手紙を書き、彼が旅立ったことを伝え、何度も彼の愛を彼女に送ってから、ひとりの家路についた――もしそれが「家」と呼べるならだが。今やそこは僕にとって家ではなく、どこにも僕の居場所はなかった。
階段でウェミック氏と出くわした。彼は僕のドアをノックしてみたが不発に終わり、今下りてくるところだった。逃亡未遂の悲惨な結果以来、彼とふたりきりで会うのは初めてだった。今回は個人的な立場で、その失敗について説明したいと言ってきたのだった。
「故コンピソンはね」とウェミック氏は言った。「じわじわと、今や取り扱われている商売の半分の内幕を探り当てていたんだ。それで、彼の仲間の何人かがトラブルに巻き込まれて話しているのを聞いて(彼の仲間はいつも何かしら問題を起こしていた)、僕はそれとなく耳を澄ませていた。彼が不在だとわかったとき、今こそが動く好機だと思ったんだ。今思えば、彼は自分の手下たちを日頃から欺いていたのだろう。君は僕を責めないよね、ピップさん? 僕は心から君のために尽くそうとしたんだ。」
「それは僕が一番よくわかってる、ウェミック氏。本当に感謝している。」
「ありがとう、ありがとう、本当に。ひどい結果だったよ」とウェミック氏は頭をかきながら言った。「こんなに落ち込んだのは久しぶりだ。僕が気になるのは、あんなにたくさんの動産を犠牲にしたことだよ。まったく!」
「僕が思うのは、その財産の持ち主のことだよ。」
「確かに、その通りだ」とウェミック氏。「君が彼のことを気の毒に思うのは全然構わないし、僕だって彼を助けられるなら5ポンド紙幣を出すよ。でも僕が考えるのはこうだ。コンピソンが彼の帰還をいち早く知り、絶対に彼を追い詰めようと決意していたんだから、救うことはできなかったと思う。でも動産は救えたはずなんだ。持ち主と財産の違いってやつさ、わかるだろ?」
僕はウェミック氏を上に誘い、ウォルワースまで歩く前に一杯飲んでいこうと勧めた。彼は快く応じた。彼が控えめに酒を飲んでいるとき、何の前触れもなく、少し落ち着かない様子を見せた後でこう言った――
「月曜に休暇を取ろうと思うんだが、どう思う、ピップさん?」
「この1年、そんなことしてないだろう。」
「いや、12年くらいしてないかもね」とウェミック氏。「そう、休暇を取るつもりだ。それだけじゃない、散歩に行くんだ。それだけでもない、君も一緒に来てくれないかと頼みたい。」
僕はその時あまり良い相手になれないと断ろうとしたが、彼が先回りした。
「君の都合はわかってるし、気分が優れないことも知ってるよ。でももし付き合ってくれるなら、とてもありがたい。遠出じゃないし、朝早いだけだ。朝8時から12時まで(朝食も含めて)くらいで済む。無理してでも来られないかな?」
彼にはこれまで何度も助けてもらったから、今回くらいは当然だと思い、行くよ、と返事した。彼はすごく喜び、僕もその様子に嬉しくなった。彼の特別な頼みで、月曜の朝8時半にキャッスルに迎えに行く約束をして、その場は別れた。
月曜の朝、時間どおりにキャッスルの門のベルを鳴らすと、ウェミック氏自らが迎えてくれた。いつもより身なりがきちっとしていて、帽子もつやつやして見えた。中にはラム酒とミルクが2杯、ビスケット2枚が用意されていた。エイジドも早起きしていたらしく、寝室を覗くとベッドは空だった。
ラム酒とミルク、ビスケットで気を引き締めて出かけようとしたら、ウェミック氏が釣り竿を肩に担ぐのを見て、僕はとても驚いた。「釣りには行かないだろう?」と言うと、「いや、散歩の相棒に好きなんだ」と返事があった。
変だとは思ったが、何も言わずに出発した。カンバーウェル・グリーンの方へ歩き、そこまで来ると突然ウェミック氏が言った――
「おや、教会があるじゃないか!」
特に驚くほどのことではなかったが、またしても、「中に入ろう!」と彼がひらめいたように言い出して、僕は少し驚いた。
僕たちは中に入り、ウェミック氏は釣り竿をポーチに置いて、周りを見渡した。その間に、ウェミック氏はコートのポケットから何かを紙に包んで取り出していた。
「おや!」と言った。「これ、白い手袋が2組ある! はめよう!」
白いキッドの手袋だったし、郵便局([訳注:ポケットの意味])も目一杯広がっていたので、僕はさすがに強い疑念を抱き始めた。その確信は、エイジドが横の扉から現れて、ある女性をエスコートしてきたときに確信に変わった。
「おや!」とウェミック氏。「ミス・スキフィンズだ! さあ、結婚式を挙げよう。」
あの慎み深いご婦人はいつも通りの装いだったが、今は緑のキッド手袋の代わりに白いものを手にはめていた。エイジドもまた、祭壇に捧げるべく同じことの準備をしていた。しかし、老紳士は手袋をはめるのに非常に苦労し、ウェミック氏は彼を柱に背を向けさせ、自分も柱の後ろに回って力いっぱい引っ張り、僕は老紳士の腰を抱えて支えるという工夫で、見事に手袋をはめることができた。
書記と牧師が現れ、僕たちはあの運命の柵の前に整列した。事前準備なしにすべてやるという彼の流儀どおり、ウェミック氏は式が始まる前にベストのポケットから何かを取り出して、「おや! 指輪だ!」と独りごちていた。
僕は新郎の付添人として行動し、ベビー帽のような柔らかいボンネットをかぶった小柄な小旗開けがミス・スキフィンズの友人役をしていた。花嫁の引き渡し役はエイジドに任されたが、そのせいで牧師が思わず驚く場面に遭遇した。牧師が「この女性をこの男性に嫁がせる者は誰か?」と尋ねたとき、老紳士は今どの箇所かまったくわからず、十戒をにこやかに見つめていた。再度「この女性をこの男性に嫁がせる者は誰か?」と尋ねると、まだ無意識のままなので、新郎がいつもの調子で「ねえエイジドP、わかってるだろ、誰が嫁がせるんだ?」と叫び、エイジドは元気よく「わかったよ、ジョン、わかった、坊や!」と答えてからようやく自分が渡すと言い、牧師はひどく暗い沈黙の後、何とか式が進行した。
とはいえ滞りなく式は終わり、教会を出るとき、ウェミック氏は洗礼盤の蓋を開けて白い手袋を中へ入れ、また蓋を閉めた。ウェミック夫人は将来への配慮から手袋をポケットにしまい、緑のものに付け替えた。「さて、ピップさん」とウェミック氏は釣り竿を肩に得意げに言った。「誰がこれを結婚式の一行だと思うだろうか!」
朝食はグリーンの先の高台にある小さな居心地のいい酒場に予約されていた。部屋にはバガテル台もあり、式の後に気分転換したい場合にも備えられていた。ウェミック夫人は、もうウェミック氏の腕を離すことなく、壁際の背の高い椅子にまるでチェロのようにもたれて座り、抱かれることをチェロのように素直に受け入れていたのが印象的だった。
素晴らしい朝食を楽しみ、誰かが何かを辞退すると、ウェミック氏は「契約で用意したものだから、遠慮なくどうぞ!」と言っていた。僕は新婚夫婦に、エイジドに、キャッスルに乾杯し、別れ際には花嫁に挨拶し、できる限り和やかに振る舞った。
ウェミック氏は僕を玄関まで送り、もう一度握手して祝福を伝えた。
「ありがとう!」とウェミック氏は手をこすりながら言った。「彼女は鶏の管理がうまいんだ、想像もつかないくらいさ。卵をあげるから、自分で確かめてごらん。ねえピップさん!」と僕を呼び戻し、小声で続けた。「これはウォルワース限定の話なんでね。」
「わかってるよ。リトル・ブリテンでは口外しない」と僕は答えた。
ウェミック氏はうなずいた。「先日君がうっかり話したことを考えると、ジャガーズ氏には知らせない方がいい。脳がやわらかくなったと思われるだろうからね。」
第五十六章
彼は裁判にかけられるまでの間、ずっと刑務所の病室で重い病状に苦しんでいた。肋骨を二本折り、肺に傷を負い、呼吸は日に日に苦しくなった。そのため声もほとんど聞こえないほど弱々しく、ほとんど話さなかったが、僕の話や朗読には常に耳を傾けてくれた。それが僕の最優先の務めとなった。
あまりに病状が悪いため、最初の一日か二日を過ぎてからは一般の牢ではなく、医務室に移された。おかげで僕は彼と過ごす機会を得られた。もし病気でなければ、彼は脱獄常習者として手錠をかけられていただろう。
毎日面会できたが、わずかな時間しか許されておらず、その間に彼の容態が少しでも変化すればその痕跡は顔に現れた。良くなったことは一度もなく、日に日にやつれ、弱っていった。
彼の示す諦観は、疲れ果てた男のそれだった。時に彼の態度や、つい漏れ出す囁きから、「もしもっと違う境遇だったら善人になれたのでは」と考えているように感じられたが、決して自分を弁解するようなことは口にせず、過去が変わるかのような希望も抱かなかった。
何度か、彼の悪名が看守や付き添いの者に話題にされたが、そのたびに彼は微笑み、僕に信頼の眼差しを向けた。まるで、幼いころから僕が彼の中に何か救いの光を見ていたと信じているかのようだった。それ以外は謙虚で悔い改めており、決して不満を口にしなかった。
セッション(裁判期日)が巡ってくると、ジャガーズ氏は審理の延期を申請させた。明らかに、彼がそれまで生きられないだろうという見通しからだったが、却下された。裁判はすぐに開かれ、彼は椅子に座ったまま被告席に出された。僕がそばに寄って彼が差し伸べた手を握ることには異議はなかった。
裁判はごく短く、明快だった。彼が勤勉に働き、法を守って立派に暮らしてきたことなど、言える限りのことは述べられたが、「戻ってきた」という事実を覆すことはできなかった。彼を裁く以上、有罪にするしかなかった。
当時(僕がその恐ろしい経験から学んだのだが)、判決の日を最後に設けて死刑宣告で締めくくるのが慣例だった。今でも記憶に焼き付いている光景がなければ、僕は三十二人もの男女が一斉に死刑判決を受けたことを信じられないだろう。その中で彼は最前に座り、息をつなぐだけでも大変だった。
今でもその場面は鮮やかによみがえる。四月の雨粒が法廷の窓に光り、四月の太陽が差し込んでいた。被告席には三十二人の男女が詰め込まれ、僕はその隅で彼の手を握って立っていた。中には居直る者、怯える者、泣き叫ぶ者、顔を覆う者、むっつりした顔であたりを見回す者もいた。女性囚からは悲鳴が上がり、やがて静まり返った。保安官たちは大きな鎖に花束をつけ、市民の飾りや役人、法廷係、満員のギャラリーはまるで劇場の観客のようだった。その中で三十二人と裁判官が厳かに対峙した。裁判官は悲惨な被告たちの中から、とりわけ幼いころから罪を重ね、何度も服役し、ついには流刑となり、激しい脱獄騒ぎの末に終身流刑となった一人を名指しした。その男は、しばらく改心して善良に暮らしていたが、運命の瞬間、かつての衝動と情熱に負け、安息と悔悟の地を後にし、追放された国に戻った。ここで告発され、逃亡を続けたが、ついに取り押さえられ、逃走時に告発者を死なせてしまった(それが故意かどうかは彼自身が知るのみ)。流刑地帰還の罪には死刑が定められており、彼の場合は加重事案として、死を覚悟せねばならない。
太陽が雨粒越しの法廷の大窓から差し込み、三十二人と裁判官の間に太い光の帯が生まれ、両者が大いなる裁きの前では等しく歩みを進めていることを思い出させるかのようだった。一瞬、その光の中に浮かび上がる顔となって、彼は立ち上がり、「閣下、私は神から死刑を宣告されましたが、あなたのご判断にも従います」と言い、また座った。しばらく静まり返り、裁判官は残りの者たちに言葉を続けた。そして全員に正式な判決が下り、支えられて退場する者、憔悴しながらも勇ましいふりで出ていく者、ギャラリーにうなずく者、ハーブのかけらを噛みしめる者など、さまざまだった。彼は最後に、椅子から助けられて、ゆっくりと退場した。他の者たちが運ばれていく間も、観客が立ち上がり(まるで教会の後のように衣服を整え)、あちこちの囚人や特に僕たち二人を指さしていた間も、ずっと僕の手を握っていた。
彼が上訴の報告(レコーダーズ・レポート)が出る前に死んでくれるよう、僕は心から願った。しかし、もしも長く生き延びたらと恐れて、その夜から内務大臣への嘆願書を書き始めた。彼のために戻ってきた経緯をできる限り熱意と哀切を込めて綴った。書き上げて提出した後も、慈悲深いと望みを託せる当局者らへの嘆願書を次々としたため、王室にまで届け出た。判決後数日、僕は眠るのも椅子でうたた寝するだけで、ほとんどこの嘆願に没頭していた。そして提出した後も、願いが叶うように願って、その場所の近くを歩き回った。今なお思い出すたび、冷たく埃っぽい春の夜のロンドン西部の通り並み、閉ざされた邸宅群、長く続く街灯が、僕にはこの記憶とともに悲しみを帯びている。
彼を見舞える時間はますます短くなり、監視も厳しくなった。僕が毒を持ち込むのではと疑われているように感じたので、看守の前で調べてくれと申し出てから枕元に座った。僕にも彼にも、誰も冷たくはなかった。必要な義務は果たされたが、決して苛酷ではなかった。看守は必ず彼の具合が悪くなっていると教えてくれ、病室の他の囚人や看病役の囚人たち(罪人とはいえ親切心を持つ者もいる、神に感謝!)も同じ報告をしてくれた。
日が経つにつれ、彼はたいてい天井を見つめて静かに横たわるようになり、僕が何か言葉をかけたときだけ一瞬だけ顔が明るくなった。時にはほとんど話す力もなく、手をそっと握ってくれるだけだったが、僕はその意味をよく理解できるようになった。
十日目、これまでになく彼の容態が変わったと感じた。彼の目は扉の方を向き、僕が入ると輝いた。
「坊や」と彼は僕がベッド脇に座るとつぶやいた。「遅いかと思った。けど、そんなはずないとわかってた。」
「ちょうど時間だよ」と僕。「門のところで待ってた。」
「いつも門で待ってるんだろ、坊や?」
「ああ。少しでも長く一緒にいたいから。」
「ありがとうよ、坊や、ありがとう。神のご加護を! 君は一度も僕を見捨てなかった。」
僕は無言で彼の手を握った。かつて彼を見捨てようとした自分を忘れられなかったからだ。
「それに何より嬉しいのはさ」と彼。「日陰にいたこの期間の方が、日が差していたときより、君は僕のそばで心地良さそうだった。これが一番だ。」
彼は仰向けになり、苦しそうに呼吸していた。どんなに愛してくれても、安らかな顔に時折翳りが戻った。
「今日、痛むかい?」
「何も文句はない、坊や。」
「君は一度も不平を言わなかったね。」
彼が最後の言葉を発したあと、微笑み、僕の手を胸に乗せてほしいと合図した。そうしてあげると、再び微笑み、両手で僕の手を包んだ。
時間が経ち、ふと見回すと、刑務所長が近くに立っていて、「もう少しいていいですよ」と囁いた。僕は感謝して、「話しかけてもいいでしょうか」と尋ねた。
所長はそっと看守を下げさせた。その静かな変化に、彼の顔から翳りが消え、愛情深く僕を見つめた。
「親愛なるマグウィッチ、今こそ伝えなければならない。僕の言うことがわかるか?」
手をやさしく握り返す。
「君にはかつて大切にし、失った子供がいた。」
強い握り返し。
「その子は生きていて、強い味方を得た。今も生きている。彼女はレディで、とても美しい。そして僕は彼女を愛している!」
最後の力を振り絞るように、彼は僕の手を唇に運ぼうとした。僕が手伝うと、静かに胸の上に手を戻し、自分の両手で重ねた。天井を見つめる安らかな表情が戻り、やがて消え、彼の頭はそっと胸に垂れた。
僕は、かつて二人で読んだあの聖書の話、「神よ、罪人なる彼に憐れみを」と祈ること以上にふさわしい言葉はないと、その枕元で心に思った。
第五十七章
完全にひとりきりになった僕は、テンプルの部屋を法的に退去できる最短で明け渡す旨を通知し、しばらくは間貸しに出すことにした。すぐに窓に張り紙を出した。なぜなら僕は借金があり、ほとんどお金もなく、状況に深刻な不安を感じ始めていたからだ。正確には、もし十分な気力と集中力があれば、もっと鮮明に自分の困窮を危惧しただろうが、当面の現実以外はほとんど理解できず、体調の悪化にも無頓着だった。
一、二日、僕はソファや床に、どこでもその場で倒れるまま横になり、重い頭と痛む手足、やる気も力もない状態で過ごした。そして、ある長い一夜が訪れ、不安と恐怖で満ちていた。朝になり、ベッドで起き上がろうとしたができなかった。
夜中にガーデン・コートまで降りてボートを探していたのか、何度か階段で我に返って怯えたのか、ベッドを抜け出した理由もわからず、ランプに火をつけ、彼(エイベル・マグウィッチ)が階段を上がってきて明かりが消えたと妄想したのか、誰かの狂おしい話し声や笑い声、うめき声に苦しめられ、それが自分自身のものではないかと半ば疑ったのか、部屋の隅に鉄製のかまどがあり、その中でミス・ハヴィシャムが焼かれていると叫ぶ声が聞こえたのか――これらを朝ベッドで整理しようとした。しかし石灰窯の煙のようなぼやけた幻覚がすべてを混乱させ、結局その靄越しに二人の男が僕を見ているのが見えた。
「何の用だ?」と僕は驚きながら尋ねた。「君たちを知らない。」
「まあ、すぐに話はつくと思いますが、お客さん、逮捕です」と一人が身をかがめて僕の肩に触れながら言った。
「何の借金だ?」
「百二十三ポンド十五シリング六ペンス。宝石商の勘定です。」
「どうしたらいい?」
「うちに来た方がいいですよ」と男は言った。「うちはとてもきれいな宿です。」
僕はなんとか起きて着替えようとした。次に意識が戻ったときには、彼らはベッドから少し離れて僕を見ていたが、僕はまだ横になっていた。
「この有様を見てくれ」と僕は言った。「行けるなら行くが、本当に無理だ。ここから連れて行かれたら道中で死ぬかもしれない。」
おそらく彼らは返事をしたか、論じたり、僕が思うほど悪くないと励ましたのだろうが、記憶にはこのやりとりしかなく、彼らが僕を連れ出すのを控えたことだけは覚えている。
高熱で人に避けられ、ひどい苦しみに悩まされ、しばしば正気を失い、時の感覚もなくなった。自分が家の壁の煉瓦の一つで、職人に解放してくれと懇願したり、自分が巨大な機関の鋼梁で渦巻く深淵の上で激しく動く一部品で、その役目から解放してくれと願ったり――そんな病の過程を、自分の記憶で確かに知っている。時に現実の人々と格闘し、それが殺人者だと信じ込み、だが突然、彼らが善意で僕を助けていると悟って力尽き、彼らの腕に横たえられることもあった。だが何よりも、すべての人が(重病の僕には顔も体も奇妙に変わって見えたが)最終的にはみなジョーに似ていくことが不思議だった。
病状の峠を越えてからも、この「誰もがジョーになる」現象だけは変わらなかった。夜に目を開ければ、ベッド脇の大きな椅子に座るのはジョー。昼に開ければ、窓辺でパイプをふかすのもジョー。冷たい飲み物を頼めば、それを差し出す優しい手もジョー。枕に身を沈めれば、希望と優しさにあふれる顔もジョーだった。
ついにある日、勇気を出して言った。「ジョーなのか?」
すると懐かしい故郷の声が「そうだよ、坊や」と答えた。
「ジョー、胸が張り裂けそうだ! 僕を叱ってくれ、殴ってくれ、恩知らずだと罵ってくれ。そんなに優しくしないでくれ!」
ジョーは本当に、歓喜のあまり頭を僕の枕に伏せて、首に腕を回していた。
「親愛なるピップ坊や、僕たちは昔から友達だろ。お前が元気になったら馬車で出かけよう――楽しみだな!」
その後ジョーは窓辺に移り、背を向けて目をぬぐっていた。僕はあまりにも弱って起き上がれず、「神様、どうかこの優しく信仰深い人を祝福してください」と心で繰り返し祈った。
次に目を覚ましたときもジョーは目を赤くして僕の手を握っていたが、僕たちは幸せな気持ちだった。
「どれくらい、ジョー?」
「つまり、ピップ、どれくらい病気が続いたかってことか?」
「ああ、ジョー。」
「今は五月の終わりだよ。明日は六月一日。」
「その間ずっと、ここにいてくれたのかい?」
「ほとんどずっとだよ。だって、ピップが病気だという知らせが手紙できてね。もともと独り者だった郵便配達人も今は結婚してるけど、たくさん歩いて靴底も減ってるのに、金じゃなくて結婚が彼の願いだったんだ――」
「ジョー、君の話を聞くのは本当にうれしいよ! でもビディに何と言ったか、途中で止まっちゃったよ。」
「そうだった」とジョー。「お前が見知らぬ人たちの中にいるかもしれないし、昔からの友達として行けば歓迎されるかもしれないって、ビディにはそう言ったんだ。するとビディは『すぐ行け』と言った。それがビディの言葉だった。『すぐ行け』って。要するに、あの娘は『一分も待たずに行け』って言ったようなもんだ。」
ここでジョーは話を切り上げ、僕はあまり話しすぎないように、また食事を定期的に少しずつ摂ること、彼の指示に従うことを命じられた。だから僕は彼の手にキスし、おとなしく横になったまま、彼がビディに僕の愛をこめて手紙を書くのを見ていた。
ビディがジョーに書き方を教えたのは明らかだった。弱った身で彼が誇らしげに手紙を書き始める様子を見ると、僕はまた嬉し涙がこぼれた。カーテンを外された僕のベッドは、空気がよくて広い居間に運ばれ、カーペットもなく、昼夜問わず清潔で新鮮な空気が保たれていた。ジョーは僕の机に座り、ペントレイから大工道具でも選ぶようにペンを選び、袖をまくってまるでバールか大槌を使うかのような身構えで書き始めた。左肘で机にしっかり体重をかけ、右足を後ろに伸ばして、やっと書き始める。下に書く線はとてもゆっくりで、上に戻すたびペンが大きく音を立てる。インク壺がない側にあると思い込み、空中にペンを浸して満足したり、つづりでつまずくこともあったが、全体的にはうまくやっていた。署名を終えると、指先で仕上げのインクの染みを頭に移し、あらゆる角度から出来栄えを眺めて満足そうだった。
ジョーを心配させないよう、また体力の都合もあって、ミス・ハヴィシャムのことを聞くのは翌日にした。回復したか尋ねると、ジョーは首を振った。
「亡くなったのかい、ジョー?」
「いや、そこまで断言できないよ、それは重い言葉だから。でも……」
「生きてはいないんだね?」
「それがいちばん近い表現だな。生きてはいない。」
「長く苦しんだの?」
「お前が倒れてから、おおよそ一週間くらいだったな。」
「ジョー、彼女の財産はどうなったか知ってる?」
「ほとんどはエステラ嬢に相続させたらしいよ。それとは別に、事故の2、3日前に自筆でマシュー・ポケット氏にきっかり四千ポンド遺すと書いていた。なんでそんな大金を彼に遺したかわかるかい? 『ピップの話を聞いたから』だって。ビディの話では、あれが正式な文言なんだ、『ピップの話を聞いたから、かのマシューに』って。冷たい四千ポンドだ、ピップ!」
ジョーが「冷たい」四千ポンドと言う根拠は不明だったが、彼にはその方が額が大きく響くらしく、その表現を誇らしげに繰り返していた。
この話を聞いて、僕は唯一の善行が完結したことに大きな喜びを覚えた。他の親戚に遺産があるか聞くと、
「ミス・サラには年25ポンド、胃が弱いから薬を買うため。ミス・ジョージアナは一括で20ポンド。ええと――あのコブがある野獣の名前は何だったっけ?」
「ラクダ?」と僕は何でそんなことを聞くのか思いながら答えた。
ジョーはうなずいた。「ラクダ夫人、つまりカミラ夫人だな、あの人には五ポンド、夜中に目が覚めたとき元気が出るように蝋燭(ラッシュライト)を買うためさ。」
これらの話の正確さは、私には十分明らかであり、ジョーの話に大いに信頼を持つことができた。「さてな」とジョーは言った。「おまえ、まだそんなに強くはなっていないんだからな、今日のところは追加で一杯のシャベル分以上は無理だ。オーリックのやつ、民家をぶち壊してやがった。」
「誰の家だ?」と私は尋ねた。
「いやまあ、あいつの素行が荒っぽいのは認めるよ」とジョーは申し訳なさそうに言った。「それでもな、イギリス人の家は城だって言うだろうし、戦時中以外に城をぶっ壊しちゃいけないんだ。どんなに欠点があったにせよ、あいつは心根では穀物と種の商人だったんだ。」
「じゃあ、パンブルチュークの家がやられたのか?」
「そうだ、ピップ」とジョーは言った。「レジの金箱を奪って、現金箱も取って、ワインも飲んで、食べ物も食って、顔を引っぱたいて、鼻をつまんで、ベッドの柱に縛りつけて、十二発やって、泣き叫ばないように口いっぱいに花の種を押し込んだんだ。だけど、あいつはオーリックだとわかってて、今は県の刑務所にいる。」
こうして私たちは、遠慮のない会話に移っていった。私は回復が遅かったが、それでもゆっくりと着実に弱さが和らいでいき、ジョーはずっとそばにいてくれた。そして私は自分がまた幼いピップに戻ったかのような気がした。
というのも、ジョーの優しさは私の必要にぴたりと合っていて、私はまるで彼の手の中の子供のようだった。彼は昔のような信頼と、昔のような素朴さ、昔のような控えめで守ってくれる話し方で私に語りかけてくれたので、私は、古い台所の時代以降の人生は、すべて消え去った熱病の心の迷いだったように思えてきた。彼は家事以外は何でもしてくれた。家事のためには、ジョーが到着した時に洗濯婦への支払いを済ませたあと、きちんとした女性を雇っていた。「本当にな、ピップ」と彼はよくその配慮の説明として言った。「あの女を見つけたとき、予備のベッドをビール樽みたいに叩いて、中の羽毛をバケツで売るために抜き出してたんだ。次にはお前のベッドも叩いて、お前がその上で寝ているのに抜き取るだろうし、スープの大皿や野菜皿で少しずつ石炭を運び出して、ワインや酒はウェリントンブーツに詰めて持ち出してたんだ。」
かつて私の徒弟入りの日を楽しみに待っていたように、今度は私が外出して馬車で出かける日を心待ちにした。そしてその日が来て、馬車がレーンに用意されると、ジョーは私をくるみ、腕に抱きかかえて運び、まるで今でも小さくて無力なあの子供であるかのように、馬車に乗せてくれた。
ジョーも馬車に乗り込み、私たちは一緒に田舎へとドライブした。木々や草地はもう夏の豊かな緑に包まれていて、夏の甘い香りがあたりに満ちていた。その日は日曜日で、美しい景色を見渡しながら、どれだけ自然が成長し、変化したかを考えた。小さな野草が芽吹き、鳥の声が昼も夜も、太陽や星のもとで力を増していたのに、貧しい私はベッドの上でうなされもがいていた……その記憶だけで、せっかくの安らぎが少し損なわれた。しかし、日曜の鐘の音を聞き、さらに広がる美しさを見つめるうち、私は自分が十分に感謝できていないことを感じた――いや、まだ感謝できるほどの力さえなかった――それで私は、かつてジョーに市場やどこかへ連れて行かれた時のように、ジョーの肩に頭を預けた。若い心には、それだけで胸が一杯だった。
しばらくして落ち着きを取り戻すと、昔のように、古い砲台の草地で寝転がっていた時のように、私たちは語り合った。ジョーはまったく変わっていなかった。昔の私の目に映ったままのジョーが、今も私の目にある。ただひたすら誠実で、ただひたすら正しい。
帰宅して、彼が私を抱えて運び、なんと軽々と! ――中庭を越え、階段を上ると、私はあの運命的なクリスマスの日、彼が湿地を越えて私を運んでくれたことを思い出した。私たちはまだ私の境遇の変化に触れていなかったし、彼が私の過去の事情をどこまで知っているのかもわからなかった。今の私は自分に自信がなく、彼を信じていたので、彼が切り出さない限り、自分から語るべきかどうか決めかねていた。
「ジョー、君は――」その晩、さらに考えて、彼が窓辺でパイプをくゆらせている時に尋ねた。「僕の後援者が誰だったか、知っているか?」
「聞いたぞ」とジョーは答えた。「ミス・ハヴィシャムじゃなかったってな、ピップ。」
「誰だったか聞いたのかい、ジョー?」
「そうだな! あのな、酒場でお前に銀行券を渡した人をよこした人物だって聞いたぞ、ピップ。」
「その通りだ。」
「驚いたなあ!」とジョーは、極めて穏やかに言った。
「その人が死んだって聞いたかい、ジョー?」私はだんだん自信がなくなってきて尋ねた。
「誰だ? 銀行券を送ったあの人か、ピップ?」
「ああ。」
「たしかにな」とジョーは長く考え込み、窓際をそっと見ながら言った。「そういう方向で何かあったと聞いた気がする。」
「その人の境遇については、何か聞いたかい、ジョー?」
「特には、ピップ。」
「もし、聞きたければ――」と言いかけた時、ジョーは立ち上がって私の寝椅子の傍に来た。
「いいかい、ピップ」とジョーは私に身をかがめて言った。「俺たちは、いつだって最高の友達だろう?」
私は答えるのが恥ずかしかった。
「よしよし」とジョーは、私が答えたかのように言った。「それでいい、それで決まりだ。だったらな、ピップ、二人の間で永遠に必要のないことについて、なぜ話さなきゃいけない? 二人の間で話すべきことは、必要なものだけで十分だ。ああ、お前のかわいそうな姉さんとあの大暴れぶりを思い出すな! それにティックラーのことも覚えてるだろ?」
「もちろん、覚えてるよ、ジョー。」
「いいかい、ピップ」とジョーは言った。「お前とティックラーを引き離そうと俺はできるだけやったが、俺の力はいつも思いにかなうほど強くはなかったんだ。だって、お前の姉さんがその気になると、反抗すれば俺にも降りかかってきたけど、反抗しなければお前にもっと強く当たる。それはよくわかった。男がヒゲをつかまれたり、揺すぶられたりするくらい、お前の姉さんが好きなだけやっても、子供を罰から救い出すのをやめさせることじゃない。でも、子供がそのせいで余計きつく当たられるなら、その男は自然とこう思う。『自分がやってることにどんな意味がある? 害はわかるが、良いことが見えない。だから良いことを指摘してくれ』と。」
「男が言うのか?」と私は、ジョーの言葉を促して言った。
「そうだ」とジョーは同意した。「それで、その男は正しいのか?」
「ジョー、彼はいつだって正しいよ。」
「じゃあ、ピップ」とジョーは言った。「おまえもその言葉に従え。もしその男がいつも正しいなら(たいていは間違ってるが)、今この時も正しいんだ。子供だったお前が何かを心に秘めたことがあるなら、それはジョー・ガージェリーの力がティックラーからお前を引き離すほど強くないと知ってたからだ。だから、もう二人の間でそのことは考えなくていいし、必要のない話題はやめよう。ビディは出発前にずいぶん俺の世話を焼いてくれた(ほんとに俺はとんでもなく鈍いからな)、こういうふうに考えるべきだ、ってな。そして、こう考えたらこう言うべきだと。それも両方やったから、今はこれをおまえに真の友人として言うぞ。つまり――無理はするな、でも夕食とワインと水はちゃんと飲んで、布団に入れよ。」
ジョーがこの話題をやんわりと終わらせた手際と、女性の勘で私の心を見抜いてジョーに心構えをさせておいてくれたビディの優しい配慮が、私は深く心に残った。だが、ジョーが私の貧しさや、私の「大いなる期待」がすべて陽が昇る前の湿地の霧のように消え去ったことを知っていたのかどうかはわからなかった。
ジョーについてもう一つ、最初は理解できなかったが、やがて悲しいほどによくわかったことがあった。それは、私が回復して元気になるにつれ、ジョーが私に対して少しずつぎこちなくなっていったことだ。私が弱く、完全に彼に頼っていた時には、ジョーは昔の口調に戻り、「ピップ、親友」と呼んでくれて、それが今や音楽のように心地よかった。私もまた、喜びと感謝に満ちて、昔のやり方に戻っていった。だが私がその状態にしがみついても、気づかぬうちにジョーの方はだんだんその手を緩めていった。そして私はその理由が自分にあり、その責任も自分にあると気づくようになった。
ああ! 私はジョーに、自分の誠実さを疑わせてしまったのだろうか。私が成功すれば彼に冷たくなり、縁を切るかもしれないと思わせてしまったのだろうか。私が強くなるにつれ、彼が無意識に「もうそろそろ手を離した方がいい」と感じ、私が自分から離れていく前に自ら距離を取ろうと思わせてしまったのだろうか。
ジョーの腕を頼りにテンプル・ガーデンを散歩した三度目か四度目のこと、私はその変化をはっきりと目にした。温かい陽の光の下、川を眺めて座っていたのだが、立ち上がる時、私はこう言った――
「見て、ジョー! 僕はもうしっかり歩けるよ。今度は一人で戻るところを見せるよ。」
「無理しすぎるなよ、ピップ」とジョーは言った。「でも、お前ができるようになったのを見るのは嬉しいぞ。」
その最後の「ぞ(sir)」という言い方が私には刺さったが、どうして抗議できよう! 私は庭の門までしか歩かず、本当はもっと歩けたのに、弱いふりをしてジョーの腕をまた借りた。ジョーは差し出してくれたが、どこか考え込んでいた。
私も同じく考え込んでいた。ジョーの変化にどう対処すればいいのか、良心の呵責の中で大きな悩みだった。自分の現状や落ちぶれたことを正直に伝えるのが恥ずかしくて、なかなか言い出せなかったが、そのためにジョーを巻き込みたくなかった。彼なら自分のわずかな貯金をはたいてでも助けようとするだろうし、それを受け入れるわけにはいかなかった。
その晩はお互いに物思いにふけっていた。だが、寝る前に私は決心した。明日――明日は日曜日――それが終わったら新しい一週間とともに新しい道を歩もう。月曜の朝になったら、ジョーにすべて話そう、この最後の秘密を捨てよう、自分の気持ち(まだうまく言葉になっていなかった「第二のこと」も)を伝えよう、なぜハーバートのところに行く決心をつけかねていたのかも話そう。そうすれば、きっと変化は乗り越えられるはずだ。私が心を晴らせば、ジョーもまた晴れるだろうと、心が通じ合った気がした。
日曜日は静かに過ごし、二人で田舎に出かけ、野原を歩いた。
「ジョー、僕は病気になってよかったと思うよ」と私は言った。
「おお、ピップ、親友よ、もうすっかり元気だな。」
「本当に僕にとっては忘れられない時だった。」
「俺にとっても同じさ」とジョーは言った。
「僕たちは一緒に過ごした時間を、絶対に忘れない。昔は、しばらくの間忘れてしまった時期もあったけれど、今度のことは決して忘れない。」
「ピップ」とジョーは、少し慌てたように、困った様子で言った。「いろんなことがあったな。そして……おお、親友よ、俺たちの間にあったことはもう、あったことさ。」
夜、私が寝床に入ると、回復中いつもそうしてくれたように、ジョーが部屋に入ってきた。朝と同じくらい元気か念を押した。
「ええ、ジョー、本当に。」
「そしてどんどん元気になっているんだな?」
「ええ、ジョー、着実に。」
ジョーは大きな手で私の肩の布団をぽんと叩き、少しかすれた声で「おやすみ」と言ったように思った。
私は翌朝、さらに元気になって目覚め、すぐにジョーにすべてを打ち明けようと決意した。朝食前に伝えよう。すぐに着替えて彼の部屋に行って驚かせてやろう。なぜなら、早起きしたのはこの日が初めてだったからだ。だが、彼の部屋に行くと誰もいなかった。しかも彼の荷物箱もなかった。
あわてて朝食のテーブルに行くと、封筒があった。中身はこうだった――
「邪魔したくなくて出発しました。もう元気になったから、ピップ、君はきっとこの先もっとやれる
ジョー
追伸 いつまでも最高の友達」
手紙には、私が逮捕された時の借金と費用の領収書が同封されていた。私はそれまで、債権者が訴訟の手続きを私の回復まで取り下げてくれたのだと思い込んでいた。まさかジョーが金を払っていたとは夢にも思わなかったが、ジョーが支払ってくれており、領収書は彼の名前になっていた。
今となっては、あの懺悔と告白、そして心の奥にあった「第二のこと」を、あの懐かしい鍛冶屋でジョーに打ち明ける以外に道はなかった。
私の決意はこうだった。私はビディの元に行き、どれほど謙虚に悔い改めて戻ってきたかを見せ、かつて抱いていた希望をすべて失ったことを伝え、昔の不幸な時代に築いた信頼を思い出してもらう。そしてこう言うのだ。「ビディ、君はかつて僕をとても好いてくれたと思う。僕の気まぐれな心が君から離れていたときでさえ、君のそばにいるときの方が心が穏やかでよかったんだ。もしもう一度、半分でも僕を好いてくれるなら、僕のすべての欠点と失望を背負ったままでも受け入れてくれるなら、許された子供のように迎えてくれるなら(本当に今の僕は、あやす声と優しい手がどれほど必要かわかってる)、以前より少しは君にふさわしくなったと思う――ほんの少しだけど。ビディ、君が決めてほしい。僕がジョーと一緒に鍛冶屋で働くか、この土地で別の仕事を探すか、それとも遠くの土地に行くか――そこには君の返事を聞くまで保留にしていた機会が待っている。さあ、ビディ、もし一緒に生きてくれると言ってくれるなら、きっと世界は僕にとっても君にとってももっと良い場所になるし、僕ももっと良い人間になれるよう努力するから。」
こうして私は三日間さらに回復し、あの懐かしい場所へ赴いた。そこで何があったか、今から語る。
第五十八章
私の「大いなる期待」が崩れ去ったという噂は、私が戻る前に故郷とその近辺にまで伝わっていた。宿屋「ブルー・ボア」でもそのことは広く知れ渡っており、宿屋の態度もガラリと変わっていた。かつて財産を手に入れようとしている時は熱心に私のご機嫌をとっていたボアも、今や財産を失った私にはまるで冷淡だった。
私が着いたのは夕方で、かつては軽やかにこなしていた旅路も、今ではすっかり疲れ果てていた。ボアは私のいつもの部屋を用意できなかった(たぶん「期待」に満ちた誰かが使っているのだろう)ので、鳩や馬車がいる場所の奥にある、かなり粗末な部屋しかあてがってくれなかった。それでも私は、その部屋でどんな高級な部屋よりもよく眠れ、夢の質も変わらなかった。
朝早く、朝食の準備ができるまで、私はサティス・ハウスの周りを散歩した。門や窓から垂れ下がっているカーペットには、来週の家財道具の競売の公告が貼られていた。屋敷そのものも古材として売りに出され、取り壊される予定だった。LOT 1は醸造所に白ペンキで書かれ、LOT 2は長い間閉ざされていた主建物の一部に記されていた。他の部分にもそれぞれ区画が割り当てられ、蔦はその表示のために引き剥がされ、地を這ってすでにしおれていた。ちょっと門から中を覗くと、オークション会社の事務員が樽の上を歩き、目録係に説明していた。昔、私が「オールド・クレム」のリズムで押していたあの車椅子が、即席の机になっていた。
ボアのコーヒールームで朝食に戻ると、パンブルチューク氏が宿の主人と話していた。パンブルチューク氏は、あの夜の事件後でも見た目は全然よくなっておらず、私を待ち構えていて、こう言った――
「お若いの、落ちぶれた姿を見るのは残念だが、他にどうなろうというのだ! 他にどうなろうというのだ!」
彼は偉そうに許しを与えるかのように手を差し出し、病み上がりで争う気力もなかった私は、その手を取った。
「ウィリアム」とパンブルチューク氏は給仕に言った。「マフィンを出しておけ。ついにこうなったか! ついにこうなったか!」
私は眉をひそめて朝食をとった。パンブルチューク氏は私のそばに立ち、まだ私がポットに触れる前に恩着せがましく紅茶を注いだ。
「ウィリアム、塩も出しておけ。昔は」と私に向き直って「君は砂糖を入れていたかな? ミルクは? そうだ、砂糖とミルクだ。ウィリアム、クレソンを持ってきてくれ。」
「ありがとう」と私はそっけなく言った。「でも、クレソンは食べない。」
「食べないのか」とパンブルチューク氏は大きくため息をつき、何度もうなずいた。まるでクレソンを食べないこと自体、私の没落にふさわしいかのように。「そうか。大地の素朴な恵み……いや、もう持ってこなくていいぞ、ウィリアム。」
私は朝食を続け、パンブルチューク氏は、相変わらず魚のような目でじっと見下ろし、うるさく呼吸していた。
「骨と皮ばかりじゃないか!」とパンブルチューク氏は声に出してつぶやいた。「だがここを出て行った時は(私の祝福を受けて)、私は自分のささやかな財産を彼のために広げてやったものだ。まるでミツバチが蜜を集めるように、あの時は桃のようにふっくらしていた!」
この言葉で、かつて私が新しい人生を得た時、彼が「握手してもよろしいか?」と卑屈な態度で手を差し出したことと、今のように、見せかけの寛大さで同じ手を差し出す態度のあまりの違いが思い出された。
「はあ」と彼はパンとバターを差し出しながら続けた。「さて、ジョーのところに行くのか?」
「頼むから」と私は思わず噴き出す。「君に僕の行き先が何の関係がある? そのポットから手を離せ。」
これは最悪の対応だった。パンブルチュークに絶好の言い訳を与えてしまったからだ。
「そうだよ、お若いの」と彼は問題のポットから手を離し、テーブルから一、二歩退いて、宿の主人と給仕にも聞こえるように言った。「そのポットから手を離すとも。君の言うとおりだよ、たまには君も正しい。私は君の衰えた体を、祖先の健全な食物で元気づけてほしいと思って、朝食に関心を持ちすぎたようだが、反省している。だが」――パンブルチュークは宿の主人と給仕に向き直り、私を指し示した――「この子がかつて私が育てたあの幸福な幼少時代のピップなのだ! まさかと思うだろうが、私は断言する、これがそうなのだ!」
二人は小さい声でうなずいた。給仕は特に感じ入った様子だった。
「これが私の馬車に乗せた子だ。これが手で育てられた子だ。これが、私が結婚によって姉に当たるジョージアナ・マリアの甥に当たる、その姉の息子だ。否定できるものなら否定してごらん!」
給仕は、私には否定できないし、それがますます厄介だと納得したようだった。
「お若いの」とパンブルチューク氏は、昔の調子で私を睨みつけて言った。「君はジョーのところに行くのだ。私に何の関係があるかと君は言う。私はこう言う、『君はジョーのところに行く』と。」
給仕は咳払いし、それを乗り越えてみろとでも言いたげだった。
「さて」とパンブルチューク氏は、まるで善徳のためにと言いたげに、実に苛立たしい口調で続けた。「ジョーに何と言うか、教えてやろう。ここにはボアの主人がいて、この町で知られているし、ウィリアムもいる。彼の父親はポトキンスだったと思うが、違ったかな?」
「違いません、先生」とウィリアム。
「この人たちの前で、私は君にジョーに言うべきことを教える。こう言うんだ――『ジョー、私は今日、私の最初の恩人であり、私の運命の創始者である人を見た。名前は出さないが、町の人はそう呼んでいる。その人を見たのだ』と。」
「ここにはいないけど」と私は言った。
「それも言えばいい」とパンブルチューク氏。「そう言えば、ジョーも驚くだろう。」
「いや、君は彼を誤解している」と私は言った。「僕はよく知っている。」
「こう言うんだ」とパンブルチューク氏は続けた。「『ジョー、あの人は君に恨みはないし、私にも恨みはない。その人は君の頑固さや無知もよく知っているし、私の性格や恩知らずも知っている。そう、ジョー』――ここでパンブルチューク氏は私に頭と手を振って――『彼は私が人間としての感謝の心をまったく持っていないことを知っている。彼だけが知っているんだ。君は知る必要がないが、彼は知っている』と。」
あんなに厚かましいことを、よくも私の前で言ったものだと、呆れ果てた。
「こう言うんだ。『ジョー、彼は私にちょっとした伝言を残した。それは、私がこうして落ちぶれたことに、天意のしるしを見たということだ。彼はそのしるしをジョーを見たときに知ったし、はっきり見えた。それはこの文章を指している、ジョー。「最初の恩人への恩知らずの報い、そして運命の創始者への恩知らずの報い」。だがあの人は、自分がやったことを後悔していない。正しいことだったし、親切で慈善的で、また同じことをするだろう』と。」
「残念だね」と私は皮肉を込めて言い、途中だった朝食を終えながら。「その人が何をして、それをまたするつもりなのかは言わなかったのか。」
「ボアの主人!」とパンブルチューク氏は主人に呼びかけた。「ウィリアム! 私がそれをするのは正しく、親切で、慈善的で、また同じことをするつもりだと、町中で話してくれてかまわない。」
その言葉を残し、このペテン師は二人と握手し、得意げに宿を出て行った。私はこの曖昧な「それ」の美徳に感心するより呆れるばかりだった。その後すぐ私も宿を後にし、大通りを歩くと、彼が店先で見物人相手に同じような演説をしているのが見えた。彼の一団は、私に非常に好意的でない視線を向けた。
だが、だからこそ、ジョーとビディの偉大な寛容さが、より一層輝いて見えた。私は二人の元へゆっくり向かった。足取りは弱々しかったが、近づくにつれて心の荷が軽くなり、傲慢さや虚偽をどんどん遠ざけている気がした。
六月の天気はとても心地よかった。空は青く、ヒバリが緑の麦の上を高く舞い上がり、これまでになく田園の美しさと平和を感じた。そこに住み、傍らに信じる人がいる人生の素晴らしい情景や自分自身の変化を思い描き、心が柔らかくなった。私は、長い旅を経て裸足で家に帰る人のような気持ちだった。
ビディが校長をしている学校は見たことがなかったが、静かさを求めて村へ入る回り道を通ったとき、校舎の前を通りかかった。残念ながらその日は休校日で、子どもたちもいなければビディの家も閉まっていた。彼女が日々の仕事に励む姿を、彼女より先にこっそり見られるかもしれないと期待していたが、かなわなかった。
だが鍛冶屋はすぐ近くで、私は甘い菩提樹の下、ジョーのハンマーの音を聞こうと耳を澄ませながら向かった。聞こえるはずなのに、ずっと静かなままだった。菩提樹も白いサンザシも栗の木もあり、葉が心地よくそよいでいたが、真夏の風の中にジョーの打つ音はなかった。
なぜか理由もなく不安になりながら鍛冶屋が見える場所まで行くと、そこは閉まっていた。炎も火花も送風機の音もない、すべてが静まり返っていた。
だが家には人の気配があり、居間には白いレースカーテンが揺れ、窓辺には花が飾られていた。私はそっと窓辺に近づき、花越しに覗こうとしたとき、ジョーとビディが腕を組んで立っていた。
最初、ビディは私を幽霊だと思ったかのように声をあげたが、すぐに私の腕の中に飛び込んできた。私は彼女に会えて涙し、彼女も私を見て涙した。私は彼女がとても生き生きとして見えたから、彼女は私がやつれて白い顔をしていたから。
「でも、ビディ、なんてきれいなんだ!」
「ええ、ピップ。」
「ジョーも、なんて立派なんだ!」
「ああ、ピップ、親友よ。」
私は二人を見比べ――そして、
「今日は私の結婚式なの!」とビディは嬉しさにあふれて叫んだ。「それでジョーと結婚したの!」
私たちは台所に入り、私は古いテーブルの上に頭を伏せた。ビディは私の手を唇に当て、ジョーは肩に手を置いてくれた。「驚かすほど強くはなかったんだよ、ピップ」とジョーは言った。そしてビディは「私がもっと気をつければよかったけど、幸せすぎて」と言った。二人とも私に会えて嬉しさと誇りと感激で一杯で、偶然私が来てくれたことで、彼らの記念日が完璧になったことに大喜びだった。
私がまず心から感謝したのは、この最後の淡い希望をジョーに告げることがなかったことだった。彼が私の看病でそばにいてくれた間、何度この思いが口をつきそうになったことか! 彼がもう一時間でも残っていれば、この思いを知ってしまっていただろう。
「ビディ、君は世界一の夫を手に入れたよ。もしベッドのそばでの彼を見ていたら――でもいや、これ以上彼を愛することなんてできないだろうね。」
「ええ、本当にできないわ、ピップ。」
「ジョー、君も世界一の妻を手に入れたよ。きっと君にふさわしいくらい、君を幸せにしてくれるはずだ、愛すべき正直で立派なジョー!」
ジョーは唇を震わせ、袖で顔を覆った。
「ジョーとビディ、二人とも、今日教会に行って、人々を愛し許す心で帰ってきたのだから、僕がこれまでしてもらったこと、ろくにお返しできていないこと、すべてに心から感謝するよ! 一時間以内に――すぐに外国に行く予定だけど――僕を牢屋から救ってくれたお金を、働いてかならず返す。だけど、二人とも、たとえ千倍返しても、この借りは一銭たりとも消せないし、消せるとしても消したりなどしないよ!」
二人は涙ぐみ、もう何も言わないでくれと頼んだ。
「でも、もう一つだけ。ジョー、君には愛すべき子どもが生まれて、冬の夜にここでその子が火のそばに座ることを願ってる。その子が、かつてここから出ていったピップを思い出させるような子であっても、ジョー、君はその子に、僕が恩知らずだったなんて言わないでくれ。ビディ、君も僕が冷たく不公平だったなんて言わないでくれ。二人がどれほど素晴らしかったか、僕は二人をどれほど敬愛していたか、そしてその子が僕の子であるように、きっともっと立派な人間になるようにとだけ伝えてくれ。」
「そんなことは言わないよ」とジョーは袖越しに言った。「ビディも言わない。誰だって言わない。」
「そして、もう二人が自分の優しい心でしてくれたのはわかっているけど、どうか許してくれると言ってくれないか! その言葉を聞いて、僕はこれから先も信じて頑張れるから!」
「おお、ピップ、親友よ」とジョー。「神様がご存じだ、もし許すことがあるなら、私は許すよ!」
「アーメン! 神様も私が許すってご存じです!」とビディも続けた。
「じゃあ、昔の部屋を見て、しばらく一人で休ませてほしい。そして、二人と食事をしてから、どうか分かれ道まで見送ってくれ、ジョー、ビディ!」
私は持ち物をすべて売り、債権者には分割払いのための支払いをし――彼らは十分な猶予をくれた――ハーバートのもとへ向かった。ひと月もしないうちにイギリスを離れ、二ヶ月後にはクラリカー商会の事務員となり、四ヶ月で最初の独立責任を担うことになった。なぜなら、バーリー氏のうなり声でミル・ポンド・バンクの天井梁は揺れることもなくなり、ハーバートはクララと結婚するため旅立ち、私は東支店の責任者として一人残されたからだ。
何年も経ってから私は商会の共同経営者になったが、ハーバートとその妻と共に質素に、だが幸せに暮らし、借金を返し、ビディやジョーと絶えず文通を続けた。私が三番目の共同経営者になった時、クラリカー氏がようやくハーバートに、私が彼の共同経営者にした秘密を打ち明けた。ハーバートは驚きと感動でいっぱいだったが、それで私たちの友情が損なわれることはなかった。私たちが大きな商会になったとか、大金持ちになったと思われては困る。商売は派手ではなかったが、評判は良く、堅実にやって十分にやっていけた。ハーバートの明るい勤勉さと機転に私たちがどれほど救われたか、私はかつて彼に適性がないと思い込んでいたことを不思議に思い、やがてその適性のなさは自分の方にあったのだと気づいた。
第五十九章
十一年間、私はジョーともビディとも実際には会わなかった――東洋で何度も心には浮かんでいたが――そんなある十二月の夕暮れ、暗くなってから一、二時間、私はそっと古い台所のドアの取っ手に手を触れた。音を立てないほど静かに触れ、誰にも気づかれずに中を覗いた。
そこには、昔のままの場所でパイプをくゆらせ、少し白髪は混じったものの元気そうなジョーがいた。そして、ジョーの脚で囲い込まれ、かつて私が座ったあの小さなスツールにちょこんと腰かけ、暖炉を見つめていたのは――もう一人の私だった!
「お前にちなんでピップと名付けたんだよ、ピップ、親友」とジョーは嬉しそうに言った。私はもう一つスツールを持ってきて子どもの隣に座った(でもその髪はくしゃくしゃにしなかった)。「お前みたいに育ってくれたらいいなって、そう願ってるんだ。」
私もそう思った。翌朝、その子を連れ出してたっぷり話をした。私たちはすっかり意気投合した。そして私は彼を墓地に連れて行き、ある墓石に腰かけさせると、彼は高い位置から私にその石がフィリップ・ピリップとその妻ジョージアナのものだと教えてくれた。
「ビディ」と私は、夕食後、彼女の膝で娘が眠っているときに話しかけた。「いつかこのピップを僕にくれないか、貸してくれるだけでもいいんだけど。」
「だめよ」とビディはやさしく言った。「あなたも結婚しなくちゃ。」
「ハーバートもクララもそう言うけど、たぶん僕は結婚しないよ、ビディ。もうすっかり二人の家庭に落ち着いてしまったし、きっとずっと独身でいるだろうね。」
ビディは子どもの手を唇に当て、それからその手で私の手を軽く握った。その仕草と、ビディの結婚指輪のやわらかな感触には、とても優雅な意味が込められていた。
「ピップ、」とビディが言った。「本当に彼女のことで悩んでいないの?」
「いや、悩んでいないと思うよ、ビディ。」
「昔からの古い友達として教えて。彼女のことはすっかり忘れたの?」
「親愛なるビディ、僕はこれまでの人生で、心の中で最も大きな場所を占めた記憶をひとつも忘れたことはないし、どんな小さな場所を占めた記憶でさえ、ほとんど忘れたことはない。でも、かつて“あの哀れな夢”と呼んだものは、すべて過ぎ去ったよ、ビディ――すべて過ぎ去ったんだ!」
とはいえ、そう口にしながらも、僕はその晩、ひとりでかつての屋敷跡を訪ねるつもりでいることを密かに自覚していた。そう、まさにその通りだった。エステラのために。
彼女が非常に不幸な生活を送り、夫からひどい仕打ちを受けて別居していること、そして、その夫が傲慢さ、貪欲さ、残酷さ、卑劣さの塊として名を馳せていることを耳にしていた。そしてまた、夫が馬の虐待がもとで事故死したことも聞いていた。その解放が彼女にもたらされたのは、今からおよそ二年前のことだった。僕の知る限りでは、彼女は再婚しているのかもしれなかった。
ジョーの家の早い夕食時刻のおかげで、ビディとの会話を急ぐことなく、暗くなる前に旧跡まで歩いていくには十分な時間があった。しかし、道すがら懐かしい物や昔のことに思いを馳せて立ち止まっているうちに、現地に着いた時にはすっかり日が傾いていた。
今や家もなく、醸造所もなく、何ひとつ建物は残っておらず、ただ古い庭の壁だけが残されていた。更地は粗末な柵で囲われていて、その上から覗くと、かつての蔦の一部が再び根を下ろし、静かな低い瓦礫の丘の上に緑を生い茂らせているのが見えた。柵の扉が半開きになっていたので、それを押して中に入った。
冷たい銀色の霧が午後を覆い、月はまだ昇っていなかったが、星々は霧の向こうに輝き、やがて月も昇ろうとしており、夜は暗くなかった。僕は、かつて家のどの部分があったか、醸造所がどこだったか、門や樽がどこにあったか、すべて思い描くことができた。そうしているうちに、荒れ果てた庭の小道の先に、ひとつの人影を見つけた。
その人影は、僕が近づくにつれて僕の存在に気付いたようだった。もともと僕の方へ歩いてきていたが、立ち止まった。さらに近寄ると、それが女性の姿だとわかった。もう少し近づくと、彼女は去ろうとしたが、そこで立ち止まり、僕が追いつくのを許した。そして、驚いたように声を震わせて僕の名前を呼び、僕も叫んだ――
「エステラ!」
「私はずいぶん変わったわ。それでも私だとわかったのね。」
彼女の美しさの瑞々しさは確かに失われていたが、その言葉にできない威厳も、言葉にできない魅力も、変わらず残っていた。それらの魅力は、以前にも見たことがあった。しかし、かつて誇り高かったその瞳に漂う、もの悲しくも優しい光は、今まで一度も見たことがなかった。また、かつて冷たかったその手の、友好的なぬくもりを感じたのも初めてだった。
近くのベンチに並んで座り、僕は言った。「こんなにも長い年月を経て、こうしてまたここで会うなんて、不思議なものだね、エステラ。君はよくここに戻ってくるのかい?」
「ここに来たのは、今日が初めてよ。」
「僕もだ。」
月が昇り始め、僕はかつて白い天井を静かに見つめていたその人の表情を思い出した。月が昇り始め、僕は、この場所で彼がこの世で最後に聞いた言葉を僕が口にしたときの、手のぬくもりを思い起こした。
沈黙が流れ、次に口を開いたのはエステラだった。
「何度もここに戻ろうと願い、そうしようと思ったけれど、いろんな事情でそれが叶わなかったわ。かわいそうな、この古い場所も……」
銀色の霧が月光の最初の光を浴び、その光は彼女の頬を伝う涙にも注がれた。僕がそれを見ているとは知らず、涙をこらえながら、彼女は静かに言った――
「歩きながら、どうしてこんな姿になったのか、不思議に思っていたの?」
「そうだよ、エステラ。」
「この土地は、私のものなの。私が手放さなかった唯一の財産よ。他のものは少しずつすべて失ってしまったけれど、これだけは手元に残したの。みじめな年月の中で、私が唯一、心から抗ったものがこれだったの。」
「ここは建て直されるのかい?」
「ついに、そうなの。だから、変わる前にお別れをしに来たのよ。そしてあなたは――」と、放浪者に語りかけるような優しい声で言った。「まだ外国で暮らしているの?」
「うん、そうだ。」
「そしてきっと、うまくやっているのでしょう?」
「十分に暮らせるだけ、かなり一生懸命働いているから――そうだね、うまくやっているよ。」
「あなたのことは、よく思い出していたわ。」とエステラが言った。
「本当かい?」
「最近は特によく。でも、長い間、私は、自分がどんな大切なものを投げ捨てたのか全く知らずにいたから、その記憶を遠ざけていたの。でも、義務とその記憶を受け入れることが両立できるようになってからは、心の中にそれを置くようになったの。」
「君はいつだって、僕の心の中に居続けていたよ。」と僕は答えた。
そしてまた、僕たちは沈黙した。やがてエステラが話し始めた。
「まさか、あなたとこの場所でお別れすることになるなんて思わなかったわ。――でも、私はとても嬉しい。」
「また別れるのが嬉しいのかい、エステラ? 僕にとって別れはつらいことだ。僕は、最後の別れの思い出をずっと悲しいものとして胸に抱えてきた。」
「だけどあなたは、あのとき私に言ってくれたわ――『神の祝福を、神のご加護を』って。あのときにそれを言えたなら、今もきっとためらわずに言えるはずよ。今の私は、どんな教えよりも強い苦しみを受けて、あなたの心がかつてどうだったか理解できるようになったの。私は砕かれて、壊れて――でも、きっと前より良い形になったと信じたい。どうか、あのときのように思いやりを持って、友達でいましょうと言って。」
「僕たちは友達だよ。」と僕は立ち上がり、ベンチから立ち上がった彼女に身をかがめて言った。
「そして、離れていても友達のままでいましょう。」とエステラが言った。
僕は彼女の手を取り、ふたりで廃墟を後にした。かつて僕が鍛冶場を離れたあの朝、霧が立ち上るのを見たが、今また、穏やかな光の中に、夕べの霧が立ち上っていた。その広々とした静かな光の中に、僕にはもう、彼女と再び別れる影はひとつも見えなかった。
終

