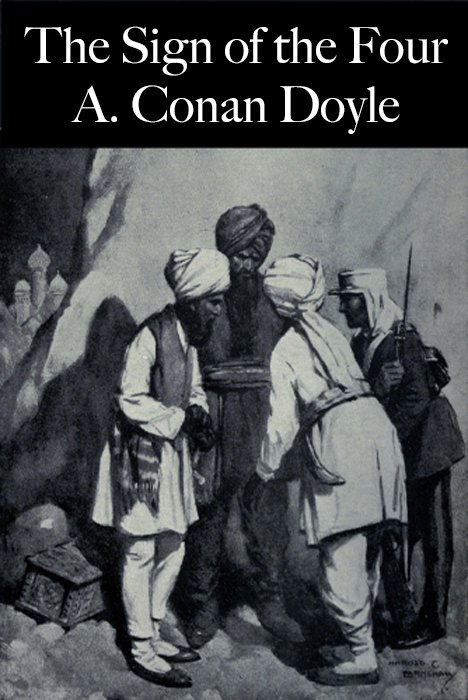
四つの署名
アーサー・コナン・ドイル著
第一章 推理の科学
シャーロック・ホームズは、マントルピースの隅から瓶を取り出し、きちんとしたモロッコ革のケースから皮下注射器を取り出した。彼は長く白く神経質な指で繊細な針を調整し、左腕のシャツの袖口をまくり上げる。しばらくの間、彼の目は無数の穿刺痕が点在する筋ばった前腕と手首に思慮深く注がれていた。やがて、鋭い針先をぐっと突き刺し、小さなピストンを押し下げると、満足げに長いため息をつきつつ、ビロード張りの肘掛け椅子に身を沈めた。
ここ数か月、私はこの光景を一日三回目にしてきたが、慣れがそれに対する私の心を和らげることはなかった。むしろ日増しに見るたびに私は苛立ちを覚え、抗議する勇気のなかった自分を思うたび、毎夜良心が痛んだ。何度も私は、この件について自分の魂を解放しようと誓ったものだが、私の同居人には、温度もなく平然とした空気が漂っていて、人に少しでも馴れ馴れしいことをする気を起こさせない何かがあった。彼の大きな能力や見事な態度、そして私が彼の非凡な資質を実際に経験したことが、私に躊躇と遠慮をもたらしていた。
だがその日の午後、昼食時に飲んだボーヌワインのせいだったのか、あるいは彼のあくまで悠然とした態度に余計苛立ったせいか、私はもはや我慢できないと感じた。
「今日はどちらだ?」私は訊ねた。「モルヒネか、それともコカインか?」
彼は開いていた古い黒字の本からけだるげに目を上げた。「コカインだ」と彼は言った。「七パーセント溶液だ。試してみるかい?」
「いや、断る」と私はぶっきらぼうに答えた。「アフガン戦役で体を壊してから、まだ完全には回復していない。これ以上余計な負担はかけられない。」
私の勢いに、彼は微笑した。「恐らく君の言う通りだろう、ワトソン」と彼は言った。「おそらく肉体的には害なのだろうな。だが、それでも私は、頭脳にかくも超越的な刺激と明晰さを与えてくれるこの影響を重んじている。その二次的作用など些細なことだ。」
「だが、よく考えてみてくれ!」私は熱心に言った。「その代償を数えてみろ! 君の頭脳はたしかに君の言う通り覚醒し興奮するかもしれないが、それは病的な過程であり、組織の代謝変化が増大し、ついには回復不能な弱さが残るかもしれない。それに、君自身も知っているだろう。後には必ず暗い反動が襲ってくる。割に合わないことだ。つかの間の快楽のために、君が天賦の才を失うかもしれない危険を冒す必要がどこにある? 私は同じ仲間としてだけでなく、医者として、少なからず君の健康に責任を持つ者として話しているのだ。」
彼は気分を害した様子はなかった。むしろ彼は指先を合わせ、肘掛にひじを乗せ、談話を楽しむ者のような態度をとった。
「私の精神は、停滞というものに反発するのだ」と彼は言った。「問題をくれ、仕事をくれ、最も難解な暗号や極めて複雑な分析をくれれば、私は自分らしい空気の中にいられる。そうなれば人工的な刺激など必要ない。しかし私は、単調な日々の生活が大嫌いなのだ。私は精神的な高揚を切望する。だからこそ今の職業を選んだ――いや、正確に言えば創り出したのだ。世界に私一人しかいないのだから。」
「唯一の非公式の探偵というわけだな?」私は眉を上げて言った。
「唯一の非公式のコンサルティング探偵だ」と彼は答えた。「私は探偵学における最終かつ最高の控訴裁判所だ。グレグソンやレストレード、アセルニー・ジョーンズが行き詰まった――これはいわば常態だが――とき、案件は私のもとに持ち込まれる。私は専門家としてデータを精査し、専門的な意見を述べる。そうした場合、私は何らの名誉を主張しない。新聞にも名前は載らない。私にとって最大の報酬は、そもそもこの特異な能力を発揮できる場が存在すること自体だ。だが、君もジェファーソン・ホープ事件で私の仕事に立ち会った経験があるだろう。」
「確かに」と私は和やかに言った。「人生であれほど衝撃を受けたことはなかった。私はそのことを、小冊子にまとめて『緋色の研究』というやや風変わりな題名を付けて公表したほどだ。」
彼は悲しそうに首を振った。「ざっと目を通したよ」と彼は言った。「正直に言って、あまり誉められたものではない。探偵というのは本来、冷静で感情に左右されぬ精密科学のはずだ。君はそこにロマンティシズムを持ち込もうとしたが、それは、例えばユークリッドの第五公準に恋物語や駆け落ち話をねじ込むようなもので、根本的に趣旨を外れている。」
「けれども現実にロマンスが存在したのだ」と私は反論した。「私は事実を曲げることなどできなかった。」
「一部の事実は伏せるべきだったか、あるいは少なくとも扱い方に十分な分別を持つべきだった。あの事件で本当に言及すべきは、私が原因を効果から逆算するという、分析的推理の妙を用いて事件を解明した点だけだった。」
私は、彼を喜ばせようと特に工夫した自作を批判されたことに腹を立てたし、彼がまるでパンフレットの隅々まで自分の活躍を描くべきとでも言いたげな自尊心にも疎ましさを感じた。ベイカー街で共に暮らした年月の間に、しばしば、彼の静かな教訓調の言動の底に、ささやかな虚栄心が潜んでいることに私は気付いていた。しかし私は何も言わず、痛む足をさすっていた。私はかつてジャジール銃の銃弾を受けて以来、歩行こそできるが、天候の変わり目ごとに鈍い痛みに悩まされていた。
「最近は、大陸にまで仕事の幅が広がってきている」とホームズがしばらくしてから言い、古びたブライヤーパイプに葉を詰めた。「先週はフランソワ・ル・ヴィラールから依頼があった。彼はご存じかもしれないが、近頃フランス警察で頭角を現している。彼は、ケルト系らしい鋭い直感力を持っているが、その分、上の段階の探偵術に不可欠な広範な正確な知識が欠けている。事件は遺言にまつわるもので、なかなか興味深い点があった。私は彼に、リガで1857年に起きた事件と、セントルイスで1871年にあった類似事件を紹介し、それが解決のヒントになったようだ。今朝、私宛に感謝の手紙が届いている。」そう言うと、彼はくしゃくしゃになった異国の便箋を投げてよこした。私はざっと目を通し、「マニフィーク!」「クー・ドゥ・メートル!」「ツール・ド・フォース!」など賛辞の言葉が並んでいるのを見て、フランス人の熱烈な賞賛ぶりを知った。
「弟子が師匠に向けた手紙のようだな」と私は言った。
「いや、彼は私の援助を買いかぶりすぎている」とホームズは軽く言った。「彼自身、なかなかの才がある。理想の探偵に必要な三つの条件のうち二つを彼は持っている。観察力と推論力だ。彼に足りないのは知識だけ――それはやがて身に付くだろう。今は私の小著をフランス語に訳しているところだ。」
「君の著作を?」
「え、知らなかったのか?」と彼は笑いながら言った。「ああ、私はいくつか小著を書いているよ。すべて技術的な主題ばかりだ。たとえばこれ――『各種タバコ灰の区別について』というものがある。そこでは百四十種類の葉巻、シガレット、パイプタバコを挙げ、それぞれの灰の違いをカラー図版で示している。これは刑事裁判でしばしば役立つ知識で、時に決定的な手がかりになる。犯人がインド産ルンカを吸いながら殺人を犯したとはっきり言えるなら、捜索範囲は大幅に絞られるからね。訓練された目には、トリチノポリーの黒い灰とバードズアイの白い塊との差は、キャベツとジャガイモの違いほど歴然としている。」
「君の細部への天賦の才には驚かされるばかりだ」と私は言った。
「私は細部の重要性をよく理解している。ここに足跡の追跡についての私の論文もある。石膏を使って足跡を保存する技法についての注釈も付けている。それから、職業が手の形に及ぼす影響についての面白い小論もある。屋根板職人、水夫、コルク切り、植字工、織工、ダイヤモンド研磨工などの手のリトタイプ付きだ。これは、特に身元不明の遺体や犯罪者の前歴調査で、科学的な探偵には大変実用的な知見となる。だが、私の趣味に付き合せて退屈させてしまったな。」
「全然そのようなことはない」と私は熱心に応じた。「君の理論が実地で応用される様子を傍で見られるだけに、一層興味深く思える。ところでさっき君は観察と推理について話していたね。普通は前者があれば後者も伴うんじゃないのか?」
「いや、そうとも限らないよ」と彼は贅沢そうに肘掛け椅子に凭れつつ、パイプから濃い青い煙をくゆらせながら言った。「たとえば、観察によって私は君が今朝ウィグモア通り郵便局へ行ったことを知り、推理によってそこで電報を打ったことを知った。」
「まったく正しい!」私は叫んだ。「どちらもぴたりだ! だが、どうやって導き出したのかわからない。自分でもふと思い立っただけで、誰にも話していないのだ。」
「これほど単純なことはないよ」と彼は私の驚きに可笑しそうに笑って言った。「馬鹿らしいほど易しく、説明する必要もないほどだが、観察と推理の区別を示すには良い例かもしれない。観察により、君の土踏まずに赤みがかった細かい土が付着しているのがわかる。ウィグモア通りの郵便局の正面では、舗道をはがして土を掘り返してあるので、避けて歩くのが難しい。その赤茶色の土は、この近隣で私が知る限り他には見当たらない。これが観察。その先は推理だ。」
「それで、どうして電報を出したと?」
「君が手紙を書いたのではないことは、朝から私が向かいにいたからわかる。さらに、あそこにある君の机が開いていて、中には切手のシートとハガキの厚い束があることも見ている。そうなると、郵便局にわざわざ行く用事は電報しか考えられない。他の可能性を消していけば、残る一つが真実というわけだ。」
「今回は確かにその通りだ」と私はしばし考えたのちに答えた。「だが、君の言うようにごく単純なことだな。君の理論をもっと厳しく試してみても失礼にはならないだろうか?」
「むしろ歓迎するよ」と彼は答えた。「それならコカインをもう一度やるのも防げる。君がどんな問題を持ち込もうと、喜んで取り組ませてもらおう。」
「君はかつて、《人は日常使っている物に無意識のうちにその個性の痕跡を残すものであり、訓練を積んだ観察者ならそれを読み取れる》と話していたね。私の手元に、最近手に入れた懐中時計がある。もしよければ、前の持ち主の性格や生活習慣について意見を聞かせてくれないか?」
私は試しに懐中時計を手渡し、心の中で少しおかしさを感じていた。というのも、これは不可能なテストと思っていて、彼のやや独断的な態度への戒めとしたい意図があったからだ。彼は時計を手の上で転がし、文字盤をじっと見つめた。裏蓋を開け、まず肉眼で、次に強力な凸レンズで中の機構を観察した。やがてがっかりした様子でパチンと蓋を閉じて時計を返した――私は思わず笑いをこらえそうになった。
「ほとんど手がかりがない」と彼は言った。「時計は最近掃除されたばかりで、有力な手がかりをすべて奪われている。」
「その通りだ」と私は答えた。「私に送られる前に、掃除に出してあった。」心の中で、私は彼が失敗を隠すためにとってつけた弁明をしているように思っていた。掃除前の時計からどんな手がかりが得られるというのか。
「とはいえ、満足のいく調査ではなかったが、まったく無駄だったわけでもない」と彼は天井を見上げ、夢見るような虚ろな目でつぶやいた。「君の訂正を受けつつ述べると、この時計は君の年上の兄のもので、兄が父親から相続した物と推察する。」
「背面のH.W.のイニシャルからかい?」
「まさに。Wは君自身の名前を示している。時計の製造年代はほぼ五十年前で、イニシャルも同じくらい古い。つまり先代のための時計ということだ。宝飾品は普通、長男が引き継ぎ、たいてい父親と同じ名前だ。君の父は、たしかかなり前に亡くなっていたはず。ゆえに長男の手に渡っていた。」
「今のところ正解だが、他には?」
「彼はだらしない性格――きわめて無頓着で、いい加減な人だった。将来も期待されていたのに、その機会をみすみす捨ててしまい、しばらくは貧窮生活を送り、時折一時的に運に恵まれることもあったが、結局酒に溺れて死んだ。それ以上は読み取れない。」
私は椅子から飛び上がり、苛立ちを覚えて部屋をせかせか歩き回った。
「これでは君の名折れではないか、ホームズ」と私は言った。「まさか君がここまで堕落するとは思わなかったよ。君は私の不幸な兄の過去を調べて、今、それをもっともらしい推理で語るフリをしているのだろう? まさかそんなものでこれだけのことを読み取れるなんて、信じられるものか。率直に言えば、これは奇術師めいた所業だ。」
「親愛なる先生」と彼は優しく言った。「どうか謝罪を受けてほしい。抽象的な推理問題として見ていたので、君の個人的で痛ましい思いにつながるとは忘れていた。だが、実のところ、君に兄がいたことすら、君が時計を渡すまで私は知らなかったのだ。」
「ならば、いったいどうしてこれらすべての事実を?」私は叫んだ。「どれもまったく正確だ。」
「ああ、それは単なる幸運だった。私には、もっとも可能性が高いことを述べるしかできなかった。ここまで正確に当たるとは思いもしなかった。」
「だが、単なる憶測ではなかろう?」
「いやいや、私は決して当てずっぽうはしない。そんなことは、論理的思考を破壊する悪習だ。君が不思議に思うのは、君が私の思考の流れについてこれず、また大きな推論の根拠となる小さな事実に気づいていないからにすぎない。たとえば、私はまず兄が不注意な人だと言った。その時計の下部をよく見ると、二か所へこみがあるだけでなく、小傷や擦り傷が無数についている――これは、硬貨や鍵など他の硬い物といつも一緒にポケットに入れていたからだろう。五十ギニーもする時計をぞんざいに扱う者が、几帳面な人間であるはずがない。高価な品を相続する人は、他にも相応の財産がある場合が多い、という推論も極端ではないだろう。」
私は彼の論理についていけている意思表示としてうなずいた。
「イギリスの質屋では、時計を預かると、通常、券の番号をピン先で内側に傷つけて記す。ラベルよりも安全で、紛失や番号違いの心配がないからだ。君の時計の内側には、レンズで確認できるものだけで四つの番号がある。すなわち、兄君は何度も質入れしていた、という推論。次に、時折は質草を出していた――つまり運が良い時もあった、という推論。そして、キーホールのある内板を見てみたまえ。周囲には何千本もの擦り傷――鍵が滑った跡がある。下戸の人間が、こんな傷をつけるものか? だが、酒飲みの時計には必ず見られる。夜酒に酔ってねじを巻き、このような跡が残るのだ。これがどこに謎がある?」
「まさに明白だ」と私は答えた。「君を疑ったのは申し訳なかった。君の素晴らしい才能をもっと信じるべきだった。現在、何か専門の仕事は抱えているのか?」
「ない。だからコカインだ。私は頭脳を使う仕事なしには生きていけない。他に何を生きる価値にできる? ほら、窓際に来てごらん。これほど陰鬱で憂鬱で無益な世界があるだろうか? 黄色い霧が通りを渦巻き、鈍色の家並みに漂っている。この上なく現実的で、味気なく、物質的な光景だ。医者よ、この世で凡庸な資質以外に役立つものがあるか? せっかくの能力も、それを生かす場がなければ意味がない。」
私はその独白に答えようと口を開きかけたとき、きびきびしたノックとともに、家主のハドソン夫人が真鍮の盆にカードを載せて入ってきた。
「お客様でございます、ご主人様」と彼女はホームズに言った。
「ミス・メアリー・モースタン……」彼は読んだ。「ふむ、その名に覚えはない。ハドソン夫人、お嬢さんをお通ししてくださるか。それからワトソン、君は帰らなくていい。いてくれた方がありがたい。」
第二章 依頼者の陳述
ミス・モースタンは毅然とした足取りで、外見上は落ち着いた様子で部屋へ入ってきた。彼女はブロンドの若い女性で、小柄で気品があり、手袋を完璧に付け、服装も実に洗練されていた。しかし、その服装には質素で飾り気のない雰囲気があり、節度ある生活ぶりを窺わせた。暗い灰色がかったベージュの地味なドレスは、装飾もなく編み上げもなく、同じくくすんだ色味の小さなターバン帽に、ほんの少しだけ白い羽根が覗いているだけだった。顔立ちには整った美しさや色白さなどはなかったが、表情は優しく愛くるしく、大きな青い瞳は不思議なまでに精神的で同情心に満ちていた。多くの国、多くの大陸を経験してきた私が今まで見た中で、これほど洗練され繊細な本性を確約してくれる表情はなかったと思う。ホームズが椅子を勧めると、彼女の唇がわずかに震え、手が小刻みに揺れ、内心どれほど強い動揺を抱えているかを隠しきれていなかった。
「ホームズさんにお越ししたのは」と彼女は言った。「以前、私の雇い主であるセシル・フォレスター夫人の家庭内の困りごとを解決してくださったことがあるからです。夫人はあなたの親切とご力量に大変感銘を受けていました。」
「セシル・フォレスター夫人」と彼は思いにふけるように繰り返した。「ええ、確かにお役に立った覚えがある。しかし、あの件はごく単純なものだったはずです。」
「でも夫人はそうは思っていませんでした――とはいえ、私の抱えている件は決して単純ではありません。これほど奇妙で、途方もなく不可解な状況も想像できないほどです。」
ホームズは手をこすり合わせ、目を輝かせた。鷹のような精悍な顔付きに、異様な集中の色が浮かび、身を乗り出してきっぱりとしたビジネスライクな口調で言った。「詳しくご説明ください。」
私は自分の立場が少々きまりの悪いものに感じられた。「ご容赦いただきたい」と私は席を立とうとした。
だが驚いたことに、若い彼女は手袋のまま片手を挙げて、私を引き留めた。「もし、あなたのご友人がここにいてくだされば、どれほど私に力となっていただけるかわかりませんわ。」
私は再び椅子に戻った。
「簡単に申し上げますと、こういう事情なのです。父はインド駐屯の陸軍将校で、私が幼い頃、私をイギリスに戻しました。母はすでに亡くなっていて、イギリスには親類もおりませんでしたが、愛情ある寄宿生活を送り、十七歳までエジンバラの養育所で育ちました。1878年、父は連隊の先任大尉として一年の休暇を取得し、帰国しました。父はロンドンから私に無事到着の電報を送り、すぐ来るようにと連絡してくれました。宿泊先はラングハム・ホテルでした。父の電報は愛情に満ちていました。私がロンドンに到着し、そのホテルへ向かうと、父モースタン大尉は確かに宿泊中だが、前夜外出して以来戻っていないと言われました。私は丸一日待ちましたが何の音沙汰もなく、ホテル支配人の助言で警察に通報し、翌朝すべての新聞に広告も出しました。しかし何の手掛かりも得られず、その日以来、父の消息はつかめていません。希望を胸に帰国し、安らぎや慰めを求めていた父が、まさか――」彼女は喉元に手を当て、嗚咽で言葉を詰まらせた。
「日時は?」とホームズは手帳を開きながら尋ねた。
「失踪は1878年12月3日です。もう十年近く前になります。」
「荷物は?」
「ホテルに残されたままでした。衣服、書籍、アンダマン諸島の珍しい品々がありましたが、手がかりになりそうなものは何もありません。父は現地で囚人護衛の責任者の一人でした。」
「ロンドンに友人は?」
「一人だけ知っています。連隊時代の同期、ショールト少佐という方で、ボンベイ歩兵第三十四連隊です。少佐は少し前に退役し、アッパー・ノーウッドにお住まいでした。もちろん連絡はしましたが、少佐も父がイギリスにいることすらご存じありませんでした。」
「奇妙な事件ですね」とホームズ。
「まだ一番不思議なことを話していません。約六年前、正確には1882年5月4日、タイムズ紙に、”メアリー・モースタン嬢の住所を求む、有利なことあり”という趣旨の広告が載りました。差出人の名前も住所もなし。当時私はセシル・フォレスター夫人家の家庭教師になったばかりで、夫人の助言に従い、同じ紙面に私の住所を掲載しました。その日、私あてに小さな段ボール箱が郵便で届き、中には大ぶりで光沢のある真珠が一つ入っていました。手紙も添えられていませんでした。その後毎年、同じ日に同じような箱が届き、毎回同じような真珠が贈られてきます。鑑定では極めて珍しい種類で相当な価値があると判明しました。ご覧になれば、美しいのが分かるでしょう。」そう言って、彼女は平たい箱を開き、私に見せてくれた。中には、今まで見た中で最も見事な真珠が六粒収められていた。
「実に興味深い話だ」とホームズ。「他に何か変わったことは?」
「ええ、つい今日のことです。それでお伺いしたのです。今朝、この手紙が届きましたので、お読みいただけますか。」
「ありがとうございます。封筒も拝見できますか。消印はロンドンS.W.、日付は7月7日。ふむ! 角に男の親指の跡――たぶん郵便配達人。最上質の用紙、封筒一束六ペンス。文房具選びにこだわりのある人だね。差出人なし。『今夜七時、ライシアム劇場外側左から三本目の柱の所に来たれ。信用されぬ場合は友二人同伴されたい。あなたは被害者である、必ず正義がなされる。警察を連れてきたならすべて水泡と帰す。あなたの無名の友より』……うーん、なかなか見事な謎だ。どうされるおつもりですか?」
「それを伺いたくてまいりました。」
「それなら我々で行きましょう。あなたと私――それから、ええ、ワトソン君こそ最適です。相手は”友二人”と言っている。彼とは以前にも協同した仲です。」
「でも、彼も来てくださるでしょうか?」彼女は、どこか哀願めいた声音で言った。
「お役に立てるのなら、誇りに思い、また幸いです」と私は真摯に答えた。
「本当にお優しいですね。」彼女は静かに頭を下げた。「私は世間と交わらずに過ごしてきましたので、ご相談できる友人もいませんでした。六時に参上すればよろしいでしょうか。」
「遅れないように」とホームズ。「もうひとつ確認したい。箱の住所書きと今の手紙の筆跡は同じかい?」
「こちらに持って来ました。」と彼女は紙を数枚取り出した。
「実に理想的な依頼人だな。正しい直感を持っている。さて……」彼は紙を並べ、素早い視線を何度も走らせた。「すべて変装した筆跡だが、手紙だけは違う。だが筆者は間違いなく同一人物だ。ほら、どうしても隠しきれないギリシャ文字の”e”の形、それから”s”の終筆のひねり。同一人物以外に考えられない。僭越ながらお尋ねしたいが、この筆跡にあなたのお父上と似た特徴は?」
「まったく似ておりません。」
「やはり。では六時にお待ちしています。資料は私が預からせていただきます。そちらで何か分かるかもしれません。現在、まだ三時半です。オルヴォワール。」
「オルヴォワール」と訪問者は答え、私たち二人に柔らかなほほえみを向けてから真珠の箱を胸元に戻し、足早に立ち去った。私は窓辺に立ち、道行く彼女を見送った。灰色のターバンと白い羽根も、人混みのなかに小さな点となって消えていった。
「なんと魅力的な女性だろう!」私は思わず口にした。
ホームズは再びパイプに火をつけ、まぶたを下げて椅子にもたれていた。「そうかね?」彼は淡々と言った。「すまないが、私は気づかなかったよ。」
「本当に君は機械そのもの、計算機みたいじゃないか!」私は叫んだ。「君には時として人間離れしたところさえある。」
彼は穏やかに微笑した。「客観的な判断力を私情で曇らせては、最も大切なことを見誤る。依頼人は私にとっては単なる単位、問題の要素に過ぎない。感情的要素は明晰な思考の妨げとなる。私の知人で最も魅力的だった女性は三人の幼児の保険金目的殺人で絞首刑になったし、最も人相の悪かった男は、ロンドンの貧民救済に二十五万ポンド近く使った慈善家だったのだから。」
「だが、さっきの女性は――」
「私は例外を認めない。例外は規則を否定する。筆跡から人物判定を研究した経験は? この人物の筆跡をどう見る?」
「読みやすく整然としている。事務的で、性格に芯がある人物と見た。」
「いや、違う」ホームズは首を振った。「この長い文字を見てくれ。ほとんど他の文字と変わらない。”d”は“a”とほとんど同じ、”l”も“e”かと見間違うほどだ。個性のある人は、どんなに悪筆でも長い文字に特徴が現れる。だがこの人物の“k”には優柔不断、頭文字には自尊心が表れている。それらの微妙な特徴で分かる。」彼は立ち上がった。「これから数件調べ物に出かける。ぜひこれを読むといい――実に傑作だ。ウィンウッド・リード著『人類の殉教』だ。1時間もあれば戻る。」
私は本を手に窓辺に座ったが、思いは遠く訪問者へと向かっていた。彼女の微笑み、その声の深く豊かな響き、人生を覆う不思議な謎……。もし父親の失踪時に17歳だったなら、彼女は今27歳だ――それは自意識を脱し、人生経験でやや落ち着きを得た甘美な年齢だ。私は物思いに沈み、危険な妄想が浮かぶたび、慌てて机に戻って最新の病理学書に没頭した。軍医で足も芳しくなく、金融事情も心もとない私が、それを思う資格などあるものか……。彼女は単なる問題の一要素、それだけだ。もし私の未来が暗いものであれば、男らしくそれを受け入れるほうが、蜃気楼でごまかすよりもずっと良い。
第三章 解決を求めて
ホームズが戻ったのは五時半を過ぎていた。彼は快活で、機敏で、上機嫌だった――これは、彼の場合、最も陰鬱な落ち込みと表裏一体で交互に現れる。
「これには大した謎はないな」と、彼は私が用意した紅茶を一口飲みながら言った。「事実は一つの解釈しか許さないように思える。」
「もう解決したのか?」
「いや、そこまでいかない。示唆に富む事実をひとつ見つけただけだ。ただし非常に重要な示唆だ。細部はこれからだ。さっきタイムズのバックナンバーを調べたところ、アッパー・ノーウッド在住、元ボンベイ歩兵第三十四連隊のショールト少佐が、1882年4月28日に亡くなっていることがわかった。」
「すまないが、これが何を意味するのかわからない。」
「そうか? ではこう考えてみよう。モースタン大尉が失踪する。ロンドンで会える人物はショールト少佐一人。その少佐は、大尉がロンドンにいることすら知らぬと答える。四年後、ショールトが死ぬ。――彼の死の直後に、モースタン大尉の娘に高価な贈り物が届き、その後も毎年繰り返される。やがて”あなたは失われた権利がある”とする手紙が届いた。その”失われた権利”とは、大尉の喪失以外に考えられない。そしてなぜ贈り物がショールトの死後に始まるのか――それは、ショールトの後継者がその謎を知っており、償いを試みていると考えれば腑に落ちる。これ以上の理論が君にはあるか?」
「だが、なんと奇妙な償いだ。それに、なぜ今になって手紙なのか? なぜ六年前ではなく今なのか? まして、”正義を与える”とあるが、どんな正義なのか? 父上が生きているとも思えないし、他には理不尽な仕打ちも思い当たらない。」
「難問はいくらでもある。確かにある」とホームズは思案深く言った。「だが今夜の探索がすべて解決してくれるさ。あ、四輪馬車が来た。ミス・モースタンが乗っている。準備はいいか? 約束の時刻だ。」
私は帽子と一番重いステッキを取り上げたが、ホームズは引き出しからリヴォルヴァーをそっと取り出し、ポケットに忍ばせるのを目撃した。今宵の任務が危ういものと見ているのだろう。
ミス・モースタンは暗い外套に身を包み、顔は落ち着いているが青ざめていた。これほど奇異な冒険に何の不安も覚えない女性など、もはや女ではないかもしれない。しかし彼女の自制心は見事で、ホームズの追加質問にも澄み切った声で全て答えた。
「ショールト少佐は父の大切なご友人でした」と彼女は言った。「父の手紙には、少佐への言及がたくさん出てきました。父と少佐はアンダマン諸島の守備隊を共に指揮していたので、とても親密でした。ところで、父の机から、誰にも解読できない奇妙な紙が見つかったのです。重要とは思えませんが、念のためお見せしようと持参しました。」
ホームズは紙を丁寧に広げ、膝の上で慎重に検分した。
「インド製の紙ですね。かつて板に貼られていた跡もある。記号は大きな建物の一部の見取り図のようだ。幾つものホール、廊下、通路が描かれている。ある地点に赤インクで小さな十字があり、その上に鉛筆で『左から3.37』と薄く書かれている。左隅には四つの十字が一直線に並び、腕が触れ合っている奇妙な印。傍らに大きく粗い字でこう書かれている――『四つの署名――ジョナサン・スモール、マホメット・シン、アブダラ・カーン、ドースト・アクバル』。……うむ、これが本件にどう関与するのか今は見当がつかない。しかし大事に保管されてきた書類だけに重要性は疑えない。手帳に入れてあったようだ、両面とも綺麗に保存されている。」
「父の手帳に入っていたものでした。」
「では、大切にご保管ください。後ほど役立つかもしれません。どうやら最初の思っていたよりも、これは深遠かつ微妙な事件になりそうです。考え直さねば……」彼は馬車に身を沈め、難しい顔でうつろな目付きになった。ミス・モースタンと私は小声で今夜の冒険とその行く末を語り合ったが、ホームズは彼方に意識を飛ばし、沈黙を崩さなかった。
九月の夜。まだ七時前だったが、どんよりした一日で、濃い霧雨がロンドンを厚く覆っていた。土色の雲はじめじめとした街並みの上に垂れ込め、ストランドを走るガス灯はぼんやりとぼやけた光の円を滑(ぬめ)るような歩道に落としていた。店先の黄色い光が湿っぽい空気に流れ出し、人影は移ろう光の中、怪しげに浮かんで消えた。私はこうした印象に左右される方ではないが、今宵の重苦しい天候とこの不思議な探索が重なって、どこか不安で陰うつな気分に包まれていた。ミス・モースタンも同じであるらしく、物憂げな表情だ。ただ一人ホームズだけはこうしたささいな情景に動じず、膝に開いた手帳に、ポケットランタンの明りの下、時折数字や覚書を書きつけていた。
ライセウム劇場では、すでに脇道の入場口に人だかりができていた。正面玄関にはハンサム・キャブや四輪馬車が絶え間なく到着し、正装した紳士やショールをまといダイヤで飾った婦人たちを次々と降ろしている。三本目の柱――我々の待ち合わせ場所――に着いたばかりのとき、小柄で浅黒く、きびきびした御者風の男が我々に声をかけてきた。
「モースタン嬢とご一緒の方々で?」と彼は尋ねた。
「わたしがモースタンです。このお二人は友人です」と彼女が答えた。
男は非常に鋭く探るような目つきで我々をじっと見つめた。「失礼ですが、お嬢さん」と、どこか頑なな口調で、「あなたのご同伴の方がお二人とも警官でないとお約束していただきたいのです」
「お約束します」と彼女は答えた。
男は鋭い口笛を吹くと、街の少年が四輪馬車を連れてきてドアを開けた。さきほどの男は御者台に乗り、我々は車内へと入った。腰を下ろすやいなや、御者は馬に鞭を入れ、我々の馬車は霧に包まれた街路を猛スピードで駆け抜けた。
状況は奇妙だった。我々は行き先も目的もわからぬまま車を走らせている。それでも、今回の招待が悪質な悪戯だということは――到底あり得ぬ仮説で――考え難く、むしろこの旅が重要な意味を持つものだと思わずにはいられなかった。モースタン嬢はいつものように毅然として落ち着いていた。私はアフガニスタンでの冒険談で彼女を元気づけようとしたが、正直なところ、自分もこの事態に興奮し、行き先が気になって話の筋が少しばかりもつれた。今も彼女は言うのだ――夜中に火縄銃がテントを覗きこみ、私はそれに向かって二連発の虎の子を撃った、と感動的な話を聞かせたと。最初は進む方角に心当たりがあったが、やがて車の速さや霧、私自身のロンドン土地勘のなさもあり、まるで方角が分からなくなってしまった。ただひたすら長い距離を走っていることだけしか分からなかった。だが、ホームズだけは決して見失わなかった。彼は馬車が広場や曲がりくねった裏通りを抜けるたびに地名を口にしていた。
「ロチェスター・ロウだ。今はヴィンセント・スクエア。ヴォクスホール・ブリッジ・ロードに出たな。どうやらサリー側に向かっているらしい。やはりそうだ。ほら、今橋の上だ。川がちらりと見える」
確かにテムズ川の一部がちらりと見え、街灯が広く静かな水面に映えていた。しかし馬車は構わず突き進み、やがて川向こうの迷路のような街並みに紛れた。
「ワーズワース・ロード。プライオリー・ロード。ラーク・ホール・レーン。ストックウェル・プレイス。ロバート・ストリート。コールド・ハーバー・レーン。なんとも華やかとは言えぬ土地への道行きだな」
実際、我々は物騒で陰鬱な界隈に入っていた。長々と続く安っぽい煉瓦家が、時おり街角の安酒場のけばけばしい明かりにだけ照らされる。そして小さな庭付き二階建て家屋が並び、さらに新築の真新しい煉瓦家屋が延々と続いていた――大都市の怪物のような触手が郊外に伸びているのだった。ついに馬車は新しくできたテラスの三軒目で停まった。他の家にはどこにも人気がなく、停まった家も暗闇に包まれていたが、ただ台所の窓だけがかすかに明るくなっていた。ノックするとすぐに、黄色いターバンと白いゆったりした衣、黄色い帯を締めたインド人の召使いがドアを開けた。三流の郊外住宅の平凡な玄関先に、東洋的な人物が立ち現れたのはどこか奇妙に場違いだった。
「サーヒブがお待ちです」と彼は言った。すると奥の部屋から甲高い声が響いた。「客を通しなさい、キトマガル。まっすぐ私のところへ」
第四章 禿頭の男の話
我々はインド人に導かれ、みすぼらしく薄暗く家具も粗末な廊下を進んだ。やがて彼は右手のドアを開け放った。まばゆい黄色い光が我々を包み、その中心には、頭頂部が異様に高く、周囲を赤毛がぶしゅっと取り囲み、禿げた光る頭がまるでモミの木の間から突き出した山頂のように際立った小男がいた。彼は立ったまま手をもじもじさせ、表情も笑ったりしかめったりと絶えず動き続け、決して一瞬たりとも静止していなかった。生来だらりと垂れた唇と、不揃いで目立つ黄色い歯並びを持ち、下顔をしきりに手で覆って隠そうとしていた。並外れた禿頭にもかかわらず、青年らしい印象を与えた。実のところ、つい先日三十歳になったばかりだった。
「モースタン嬢、お役に立てます、モースタン嬢」と彼は高く細い声で繰り返し、「紳士方もどうぞ。ささ、私の小さな聖域へお入りください。狭い部屋ですが、自分好みにしつらえてあります。サウス・ロンドンの荒野に咲いた美のオアシスです」
彼に通された部屋の様子には皆驚かされた。その貧相な家の中では、まるで真鍮の台座に飾られた最高級のダイヤのように場違いだった。最上級のカーテンやタペストリーが壁を彩り、ところどころ房でまとめられて豪華な額縁入りの絵画や東洋陶磁を露出させていた。琥珀色と黒のカーペットはふかふかで柔らかく、足が心地よく沈み込むほどだった。大きな虎皮が投げられ、東洋風の贅沢さをさらに高めていたし、隅には巨大なフーカー(水タバコ)が置いてあった。銀の鳩形ランプがほとんど見えない金線から吊るされていた。灯りがともると、空気はかすかに芳しく異国的な香りで満たされた。
「サディアス・ショールト」と男は相変わらずぎくしゃくと笑いながら言った。「それが私の名です。あなたがモースタン嬢ですね。そしてこちらの紳士方は――」
「こちらはシャーロック・ホームズ氏。こちらはワトソン博士です」
「お医者さまですか!」彼は興奮気味に叫んだ。「聴診器はお持ちですか? お願いしてもよろしいですか、どうぞ……僧帽弁[心臓弁の一つ]が非常に気になってまして。大動脈弁は大丈夫だと思うのですが、僧帽弁についてご意見を伺えれば」
私は頼まれるままに彼の心音を聞いたが、異常は特になかった。ただし、恐怖で全身を震わせていたのは間違いなかった。「正常のようです。不安になる必要はありません」と私は言った。
「ご心配をおかけしました、モースタン嬢」と彼は軽やかに言った。「私は持病持ちで、昔からあの弁が気になっていたのです。杞憂と聞き、安心しました。お父上も、余計な心臓の負担さえなければ、今もご存命だったかも知れません」
あまりにも無神経でそっけない言い草に、私は思わず張り倒してやりたくなるほど憤慨した。モースタン嬢は席につき、顔は唇まで真っ白になった。「心のどこかでは亡くなったと悟っておりました」と彼女は言った。
「ご希望の限り、すべてお話ししますし、正当なこともします。バソロミュー兄が何と言おうと、私はやりますよ。ご友人方にご同行いただけて嬉しい、護衛だけでなく、これから話すこと行うことに立ち会っていただけますから。三人いれば、バソロミュー兄にも怯まずに済む。しかし部外者はなし――警察も役人もごめんだ。我々だけですべて円満に片づけられる。何よりバソロミュー兄が世間に知られるのを嫌がりますから」彼は低いソファに座り、水っぽい青い目で我々を探るように見つめた。
「我々としても、仰ることを他言するつもりはありません」とホームズが言った。
私も同意の意を表した。
「それは結構、けっこう!」彼は言った。「モースタン嬢、キアンティかトカイ・ワインは? 他の酒は置きませんが。栓を開けましょうか? 結構ですか。では、煙草の匂いはご容赦願えませんか。私は神経質でして、フーカーの煙はなによりの鎮静剤なのです」彼は大きなボウルに火をつけ、煙はローズウォーターの中で心地よく泡立った。我々三人は半円に並び、顎に手を当てて身を乗り出し、中央で奇矯な小男が落ち着きなく煙草を吹かしていた。
「最初にこの話をしようと決めたときは、住所を差し上げようかとも考えました。ですが、あるいはお願いを軽く無視され、好ましからぬ人々を連れて来られることを恐れました。ですから失礼を承知で、まず私の従者ウィリアムズにお目通り願えるよう注意深く手筈をつけました。彼の判断には信頼を置いています。不満ならそこで何もせぬよう命じてありました。ご理解いただけると幸いです。私は隠遁気質で、洗練された趣味の人間なので、警官ほど非美的なものはありません。粗野な現実主義というものが大の苦手で、庶民ともほとんど接触しません。このように、小なりとはいえ優美な空気に身をおいて暮らしております。芸術の後援者とでも申しましょうか。これが私の弱点です。その風景画は本物のコローであり、サルヴァトール・ローザについては通人なら疑いもあるでしょうが、ブグローだけは間違いありません。私は近代フランス画壇が好みです」
「失礼ですが、ショールトさん。私はあなたに頼まれて参ったもので、何かお話しがあるはずです。もう遅いので、できるだけ簡単に済ませたいのです」とモースタン嬢が言った。
「どうしても少し時間をいただきます」と彼は答えた。「というのもノーウッドまで行き、バソロミュー兄に会わねばなりません。我々三人で彼を説得せねば。兄は私の取った方針に激怒しています。昨夜も激しい口論になりました。怒ると本当に恐ろしい男です」
「ノーウッドへ参るなら、すぐ出発したほうがよいのでは?」と私は口を挟んだ。
彼は耳まで赤くして笑った。「そんなことしたら大変です。兄上に何と言われるか分かりません。いきなりあなた方を連れて行くわけにはいきません。まず今の我々の立場を説明申し上げなければ。第一に、この話は私にも分からぬ点がいくつかあります。知る限りの事実を申し上げます。
私の父はご推察の通り、かつてインド陸軍にいたジョン・ショールト少佐です。11年前に退職し、アッパー・ノーウッドのポンディチェリー荘で暮らし始めました。インド滞在中に大いに成功し、多額の財産や貴重な骨董品の数々、そして現地人の使用人を連れ帰りました。その蓄えで屋敷を買い、贅沢な生活を送っていました。私と双子の兄バソロミューが唯一の子供でした。
モースタン大尉失踪の騒ぎは今も鮮烈に覚えております。我々は新聞記事を読み、父の友人だったと知っていたので、父の前でも事件について自由に話し合いました。父も話題に加わって推理を楽しんでいました。まさか父自身が事件の全てを胸に秘めていたとは、しかもモースタンの運命を唯一知る人物だとは、夢にも思いませんでした。
ただ一つ分かっていたのは、父の周囲には謎――実際危険――がつきまとっていたことです。父は一人で外出するのを極端に恐れ、常に二人の元賞金ボクサーを門番として雇っていました。今夜あなた方を車で送ったウィリアムズもその一人――かつてイングランドのライト級王者でした。父が何を恐れているのか、決して教えてはくれませんでしたが、木製の義足の男だけは異常に警戒していました。一度は本当に義足男に発砲したこともあります。その男は気の毒な品売りで、弁償にかなりのお金を払いました。最初のころ我々はただの気まぐれかと思っていましたが、後の出来事で考えを改めさせられました。
1882年初頭、父はインドからの手紙を受け取り、大変な衝撃を受けました。朝食の席で封を切ると、その場で気絶しかけ、その日以降急激に悪化して病の床につきました。手紙の内容はついに分からずじまいですが、短く乱れた字で書かれていたのを覚えています。父は何年も脾臓肥大を患っていましたが、以後さらに悪化し、4月末にはもう見込みがなく、最期の申し渡しがあると告げられました。
そのとき我々が部屋に入ると、父は枕を重ねて上体を起こし、苦しげな息づかいでした。ドアを鍵かけ両脇で手を取るよう懇願した後、感情と痛みのため途切れ途切れの声で、驚くべきことを告白しました。できる限り父の言葉通りに再現します。
『ただ一つ、この最期の時に心に重くのしかかるものがある。それは哀れなモースタンの孤児の扱いだ。生涯私の悪癖だった呪われた強欲のせいで、本来その半分は彼女のものである財宝を、ずっと与えずにきた。しかも私自身が自分のために使ったこともない――強欲な心とはなんと盲目的で愚かなことか。所有感のみがかえがたく、誰かと分かち合うことすら許せなかった。キニーネ壜の隣にある真珠をちりばめた首飾りを見なさい。それですら彼女に送るつもりで取り出したのに、手放せなかった。おまえたち息子が、アグラの財宝の公正な分け前を彼女に与えるのだ。だが私が生きているうちは何も送るな――首飾りすら。結局、人はこの程度で回復した例もあるからだ。
『モースタンの死について話しておく。彼は長年心臓が弱かったが、誰にもそれを隠していた。私だけが知っていた。インド時代のある出来事がもとで、二人でかなりの財宝を手に入れた。私はそれをイギリスへ運び、モースタンが到着した晩に彼は分け前を求めてやってきた。駅から歩いてきて、忠実なラル・チャウダー[人名]の手で迎えられた。二人は分配方法を巡り言い争いとなった。彼は怒りでイスから跳ね上がり、急に手を脇に当てて顔がどす黒くなり、そのまま後ろに倒れた。宝箱の角で頭を切った。私は慌ててのぞき込んだが、彼はもう死んでいた。
『しばらく途方に暮れて座り込んだ。第一の衝動は当然助けを求めようとしたことだが、しかし私が殺したとされる可能性があると気付いた。喧嘩中の突然死と頭の裂傷は疑いを招く。しかも正式な調査となれば、財宝の存在が明るみに出てしまい、それだけは何としても避けたい。彼はどこへ行くか地上の誰にも知らせていないと語っていた。ならば、そのまま誰にも知られる必要はないとも思った。
『悩み続けていると、ふと見るとラル・チャウダーが戸口にいた。彼は忍び入り、戸を閂で締めた。 “恐れなさるな、サーヒブ。誰にもバレませんよ。うまく隠しましょう” と。 “私は殺していない” と私は言ったが、彼は首を振って微笑んだ。“全部聞きましたよ。ケンカの声も一撃の音も。でも私の口は固い。今、家中みな眠っています。さあ二人で隠してしまいましょう” それが決定打となった。自分の召使ですら無実を信じぬなら、12人の偏見だらけの陪審に釈明できるわけもない。ラル・チャウダーと共にその夜遺体を始末し、やがてロンドンの新聞はモースタン大尉神隠しの話で持ちきりとなった。私の言う通り、非難される筋合いは少ないはず。ただ死体と財宝を隠し通したのが過ちであり、しかも自分の取り分だけでなくモースタンの分まで独占してしまった。償いをして欲しい。耳を……近づけなさい。宝の在り処は――』
『その瞬間、父は顔色を一変させ、目を見開き、顎を垂れ、生涯忘れ得ぬ叫び声をあげた。「入れるな、頼むから入れるな!」 我々は思わず背後の窓を振り返った。父の視線に釘付けだった。暗闇の中から顔がこちらを覗き込んでいた。鼻先がガラスに張り付いて白く浮かんでいるのが見えた。髭面で毛深い顔、野獣のような狂気の目、憎悪の極致といった表情。我々兄弟が窓に駆け寄った時にはその男は消えていた。戻った時には父の首は垂れ、脈も途絶えていた。
『その晩、庭を探したが、侵入者の痕跡は窓の下の花壇に唯一残された片足の足跡だけ。でなければ幻でも見ていたかと思っただろう。しかしまもなく、我々の周囲に不可解な隠れた力が渦巻いていることを示すさらなる証拠を得た。翌朝には父の部屋の窓が開かれ、戸棚や箱は荒らされ、胸には「四人の署名」と走り書きされた破れた紙切れが貼りつけられていた。この文句の意味や、その正体は結局分からずじまいだった。父の財産は一応盗まれた形跡はなく、ただ乱雑にされただけ。我々兄弟はこの特異な出来事を、生前父を悩ませていた恐怖と結びつけざるを得なかったが、今なお謎のままだ』
小男はフーカーに火をつけ直し、しばし考え込むように煙を吹きかけた。我々はその異様な話に引き込まれ、一言も発せず没頭していた。父の死に関する短い説明の間、モースタン嬢は真っ青になり、気絶するのではと心配したが、私は卓上のヴェネツィア製カラフェから水を注いで彼女にそっと手渡し、彼女はほどなく立ち直った。ホームズは椅子にもたれ、目を細くしてひときわ鋭いまなざしで宙を見ていた。その横顔を見て、彼が今朝、いかに凡庸な日常を嘆いていたかを思い出さずにはいられなかった。ここにはまさしく彼の知力を最大限に試す難題がある。サディアス・ショールトも、自らの話が及ぼした反応にあからさまな誇らしさを滲ませ、もごもご煙草を口にしながら話を続けた。
「父が語った財宝については、兄と私は言うまでもなく大いに興奮しました。何カ月も裏庭じゅうを掘り返し続けましたが、ついぞ発見できぬままでした。父の最期の言葉が、あともう少しで口にされるところだったと思うと悔しくてなりません。失われた財の豪華さは、唯一残された首飾りからも推し量れます。この首飾りをめぐり、兄バソロミューと私は少し意見が対立しました。真珠が非常に高価だと考え、彼は手放すことを嫌がっていました。率直に言えば、兄も父同様ほんの少し強欲なところがあります。もし首飾りを差し上げれば、噂を呼び、やがて面倒に巻き込まれるのではと心配したのです。せめて僅かでもモースタン嬢に届けようと、私は彼女の住所を調べ、一定間隔で一粒ずつ真珠を送っていたのです」
「ご親切にありがとうございました」とモースタン嬢は心から礼を言った。
小男は恐縮したように手を振った。「我々には信託者の責務がありました。それが私の考えでしたが、兄にはあまり通じなかった。我々自身十分裕福でしたし、私はこれ以上望みませんでした。それに、年頃のご婦人をあまり冷たく扱えば悪趣味ですから。『悪趣味は犯罪に通ず』――フランス人はこうした表現が得意です。この件で兄と意見が分かれ、私は家を出て独り暮らしを始めることにしたのです。古いキトマガルとウィリアムズも連れて。ですが昨日、重要な出来事を知りました。財宝の在り処が判明したのです。すぐにモースタン嬢に連絡し、これからノーウッドに出向いて分け前を請求するだけとなりました。昨夜、兄バソロミューには自分の考えを話してありますから、一応は予期された――歓迎されてはいないでしょうが――訪問者です」
サディアス・ショールトは話を終え、豪華なソファで身を震わせて座った。我々一同、事件が新たな局面を迎えたことに頭を巡らせて黙し込んだ。最初に立ち上がったのはホームズだった。
「あなたは最初から最後まで立派に対処なさった」と彼は言った。「我々も何らかの形で、あなたの分からぬ部分に光を当てられるかもしれません。だが今モースタン嬢がおっしゃった通り、すでに遅い時刻です。速やかに事を進めましょう」
新しい知己は、手際よくフーカーの管を巻き、カーテンの後ろから極めて丈の長いアストラカンの襟と袖付きのフロッグコートを取り出した。暑苦しい夜にもかかわらず、きっちりボタンを留め、耳当て付きの兎皮帽をかぶったので、動きのある細顔以外は何も見えなかった。「私は身体が弱いので」と言いながら廊下を先導した。「健康には極度に注意するしかありません」
外ではすでに馬車が待っており、計画どおりに発車した。ショールトは車内でひっきりなしに話し続け、車輪の音をかき消す勢いだった。
「バソロミューは頭の切れる男です。どうやって隠し場所を突き止めたと思います? 財宝は屋内のどこかだと見当をつけ、家の容積をすべて計測し、どこにも空間の取りこぼしがないか調べたのです。結果、建物の高さが74フィートなのに、全室の高さを合算しても70フィートしかなく、4フィートの空白が残る。そこが屋根裏部屋とにらんで、最上階のラチと漆喰の天井に穴を開けると、やはり誰にも知られていなかった小さな屋根裏が現れた。その中央に宝箱が梁の上に載っていた。そこから穴を通して降ろし、今もそのままです。宝石の価値はざっと50万ポンド以上と彼は見積もっています」
その莫大な金額と聞いて我々は目を見張った。もしモースタン嬢が正当に取り戻せれば、貧しい家庭教師からイングランド随一の大金持ちの令嬢に変貌することになる。友人として素直に喜ぶべきなのだろうが、正直自分の心は自己中心的な思いに支配され、胸が鉛のように重くなった。私は何とかおざなりのお祝いの言葉をしぼり出したが、そのまま俯いて黙り込み、ショールトの話もほとんど上の空だった。彼は病的な心気症患者そのもので、私はただぼんやりと、声の限り自覚症状を並べ立て、鞄からいくつも奇妙な薬の調合を取り出して効能を尋ねてくるのを意識するのみだった。願わくば、私が答えた内容の大半を覚えていないことを祈る。ホームズ曰く、私はヒマシ油は2滴以上飲んではいけないと釘を刺し、ストリキニーネ[注:毒物だが当時は強壮薬ともされた]を大量に鎮静剤として勧めていたそうだ。いずれにしても、ようやく馬車が急停車し、御者がドアを開けた時は心底ほっとした。
「こちらがポンディチェリー荘です、モースタン嬢」とサディアス・ショールトが彼女をエスコートしながら言った。
第五章 ポンディチェリー荘の悲劇
我々がこの夜の旅路の最終目的地に到着したのは、ほぼ十一時だった。ロンドンの湿った霧もいつしか後方に遠ざかり、夜はまずまずの天候だった。西からは暖かい風が吹き、厚い雲がゆっくりと空を横切り、ところどころに月が顔を覗かせた。遠くまで見通すには十分明るかったが、ショールトは馬車の側灯を外して、足元を照らしやすくした。
ポンディチェリー荘は独立した敷地にあり、非常に高い石塀が周囲を囲み、その上には割れガラスが埋め込まれていた。小さな鉄製の補強扉が唯一の出入口だった。案内役が特有の郵便配達めいたノックを叩いた。
「どなたです?」中から厳つい声が響いた。
「マクマードだよ。俺のノックももう覚えただろう?」
ガチャガチャと鍵の鳴る音と呻り声がし、扉が重たく開いた。中には、ランタンの黄色い灯りに照らされた首の突き出た、がっしりした小男が立っていた。
「サディアスさんかい? 他に誰が? 旦那からは誰か連れてくるなんて聞いちゃいないよ」
「何だって? 兄にちゃんと昨夜伝えておいたのに、マクマード、それは驚いたな。友人を連れてくるとな」
「今日は旦那さん部屋から出てきてませんぜ、サディアスさん。俺は命令は受けてません。規則厳守ですから、中に入れられるのはあんた一人。友達は外でお待ち願うしかない」
予想外の障害だった。ショールトは困った様子で辺りを見回した。「そんなこと言わんでくれ、マクマード」と彼は訴えた。「私が保証する。それだけじゃ足りぬか? お嬢さんを公道で待たせてなどおけんぞ」
「申し訳ないですが……旦那の友達かもしれませんけど、旦那の旦那さんの友達かどうかまでは分かりませんよ。私は言われた通りにするまでです」
「おいおい、マクマード、私のことを忘れるとは思えないがな」とホームズが朗らかに言った。「あなたは四年前アリソンの部屋でのベネフィット興行の夜、三ラウンドやり合ったあのアマチュアを覚えていないのか?」
「まさか、シャーロック・ホームズさんじゃないだろうな!」と賞金ボクサーが怒鳴った。「ありゃ本当に! あんたが黙って突っ立ってないで、俺にあのクロスヒット食らわしてくれてたらすぐ分かったのに。ああ、あんたは天賦の才を無駄にしたよ! もう少しでプロに行けた口だ!」
「見たか、ワトソン、もしほかがダメでも僕にはまだ科学的職業の素地がある」とホームズは笑った。「これでもう寒空に立たされることもなかろう」
「どうぞどうぞ、お入りなさい」とマクマード。「本当に申し訳ありませんが、規則が厳しくて。ご友人のことだけは確かめさせてもらいました」
中に進むと、砂利道が荒れ果てた庭を抜けて、巨大で角ばった家屋へと続いていた。暗闇に包まれ、月光だけが屋根裏窓をかすかに照らしているばかり。建物の大きさ、陰鬱さ、死のような静寂に胸が冷えた。ショールトも不安げで、ランタンを持つ手が震えていた。
「どうも理解できない。何か手違いがあるはずだ。兄バソロミューには確かに知らせてある。なのに部屋に明かりもない。一体どうなっているのか」
「いつもこんな厳重な警備を?」とホームズが尋ねた。
「ええ、父の習慣に倣ってます。兄は父のひいきで、もっと多くを教えてもらっていたかもしれません。あの明るい角の部屋がバソロミューの部屋です。月明かりで分かりますが、中からは灯りがこぼれていません」
「見えないな」とホームズ。「ただ、玄関脇の小窓にちらっと明かりが」
「そこは家政婦の部屋。バーンストン夫人がいるはずです。全部訊けば分かるでしょう。でもみんなで一度に押しかけては驚かせてしまうかも。少し待っていてもらえますか……おや、何だ?」
彼はランタンを掲げ、手が震えたせいで円い光が揺れ動いた。モースタン嬢が私の手首をつかみ、一同胸が高鳴るのを覚え、耳を澄ました。黒い館からは、夜の静けさにかき消されそうな、女のすすり泣きが聞こえてきた。
「バーンストン夫人だ。あの家にいる女はあの人だけです。ここで待っていてください」彼は急ぎドアノックし、老女が現れて喜びのあまり身を揺らすのが見えた。
「ああサディアス様、おいでくださって本当によかった! 本当によかった!」 扉が閉まるまで彼女の歓声が続き、それからはこもった声になった。
案内役はランタンを置いていった。ホームズはそれをゆっくり回し、館や荒れ地のゴミの山をくまなく観察した。モースタン嬢と私は並んで立ち、彼女の手は私の手の中にあった。愛とはなんと不思議なものか。出会ったばかりの者同士、言葉どころか視線一つ交わしたわけでもないのに、困難な時には本能的に互いにすがっていた。今思えば不思議だが、その時はあまりにも自然に、私がそっと彼女のそばに出ていったのだ。彼女自身も私に安心と保護を求める本能があったのだと言う。そうして私たちは、子供のように手をつなぎ合い、闇に包まれていながら心には安寧を得ていた。
「何とも不思議な場所ね」と彼女が見回して言った。
「まるでイングランド中のモグラが放たれたみたいだ。バララットの丘で砂金堀り跡を見たが、あれに似ている」
「理由も同じさ」とホームズ。「これは財宝を探して六年掘り返した痕跡だ。敷地が採石場のようになるのも無理はない」
その時、玄関がばたりと開き、ショールトが両手を前に突き出し、恐怖で顔をひきつらせて飛び出してきた。
「バソロミューが……何か変だ! 怖い、神経がもう耐えられない」彼はほとんど泣きそうで、分厚いアストラカンの襟から見える顔は怯えきった子供そのものだった。
「家に入りましょう」とホームズがきっぱりと言った。
「ええ、ぜひ」ショールトは懇願した。「私はもう何をどう指示すればいいのか……」
我々は全員、廊下左手の家政婦の部屋に入った。老女は怯えた顔でそわそわと手をいじり、うろうろしていたが、モースタン嬢を見てやや落ち着いた。
「まあ、なんて穏やかなお顔なんでしょう!」とヒステリックにすすり泣きながら叫んだ。「お会いできて本当によかった。この日ばかりはなんともつらくて……」
モースタン嬢は、働きすぎですり切れたその手をそっと撫で、優しく思いやりのこもった言葉をかけた。それが魔法のように、夫人の頬に血の気を戻すのだった。
「ご主人は部屋にこもってしまい、私が呼んでも全く応じないのです」と彼女は説明した。「一日中、何か言付けがないかと待っていたんですが、というのもご主人はよく一人になりたがる方なので……。でも一時間ほど前、何か異常があるのではと心配になって、階上へ上がり、鍵穴からそっと覗いてみたんです。サディアス様、ご自身で見てきてください。バソロミュー様が、喜びにもうちひしがれているときにも、十年お仕えしてそんな顔は一度も見たことがありませんでした。」
シャーロック・ホームズがランプを手に道を先導した。サディアス・ショールトは歯の根も合わぬほど震えていたので、私は階段を上る間、彼の腕を支えてやらなければならなかった。彼の膝はがくがくと震えていた。私たちが昇る途中、ホームズは二度、ポケットからレンズを取り出し、階段に敷かれたココナッツマットの上にある、私にはただの埃の汚れにしか見えない跡を丹念に調べていた。ランプを持ちながら、一段一段をゆっくりと進み、鋭い目つきで左右を見回していた。ミス・モースタンはおびえた家政婦とともに下に残った。
三階へと続く階段は、やや長い直線の廊下に続き、右手にはインド製の大きなタペストリーの絵、左側には三つの扉があった。ホームズは相変わらずゆっくりと几帳面に進み、私たちはそのすぐ後ろについていった。私たちの長い黒い影が廊下の奥に伸びていった。三つ目の扉が、私たちの求める部屋だった。ホームズがノックしたが応答はなく、それからノブを回して押し開けようとした。しかし、中から鍵がかけられ、分厚い頑丈な閂も見えた。ランプを当ててみると、鍵穴は完全にはふさがれていなかった。シャーロック・ホームズは身をかがめて鍵穴を覗き、すぐに鋭い息を吸って立ち上がった。
「これは悪魔的なものだ、ワトソン」と彼はこれまで見たことのないほど動揺した様子で言った。「君はどう思う?」
私は穴を覗き、恐怖のあまり飛び退いた。月明かりが部屋に差し込み、淡く不気味な輝きに満ちていた。私を真っ直ぐ見つめる顔が宙に浮かんでいた――下は影になっているため、本当に空中にぶら下がっているかのようだった。その顔はまさしく、同行しているサディアスのもの。その高く光る頭、赤毛の丸い生え際、血の気のない顔もそっくりだった。しかし、その表情だけが恐ろしく歪んでおり、不自然な引きつった笑みを浮かべていた。あの静寂と月明かりの中、それはしかめっ面や苦悶の表情よりも神経に障るものだった。あまりに似ていたため、私は再度サディアス本人がそばにいることを確かめてしまうほどだった。そこで、彼が以前「兄弟は双子だ」と言っていたのを思い出した。
「これはひどい!」私はホームズに言った。「どうすべきだ?」
「扉を破るしかない」と彼は答え、錠前めがけて全体重をかけて体当たりした。金具がきしみ声をあげたが、扉は開かなかった。私たちはもう一度二人で体当たりすると、今度はバキッと音を立てて扉が開き、バソロミュー・ショールトの部屋に踏み込んだ。
その部屋はまるで化学実験室のように調えられていた。扉の向かいの壁には二列に並んだ栓付きガラス瓶、テーブルの上にはバーナーや試験管、レトルトが散乱していた。隅には籐かごに入った酸のカーボイが置かれ、そのひとつからは濃色の液体が漏れ出して床に広がっていた。部屋の空気は独特の刺激臭で満たされていた。部屋の一角には使い古しの脚立が、木片や石膏片の中に倒れていた。その真上には男一人が通れるほどの天井の開口部があった。脚立の下には、長いロープが無造作に絡まっていた。
テーブルのそばの肘掛け椅子には、この家の主人がぐったりと座り、頭が左肩に崩れ落ち、あの恐ろしい、意味の読めぬ微笑が顔に浮かんでいた。彼はすでに硬直し冷たくなっており、明らかに何時間も前に死亡していた。私には顔の表情だけでなく、手足すべてが不気味にねじくれているように思えた。彼の手元には奇妙な道具――褐色で目の細かい木の棒、石の頭がハンマー状にくくりつけられ、粗い紐で縛られていた。そばには破れた便箋があり、何か言葉が乱雑に書きなぐられていた。ホームズはそれを見て、すぐ私に手渡した。
「ご覧の通りだ」とホームズは意味ありげに眉を上げて言った。
ランプの明かりで読んだその文面には、戦慄が走った――「四人の符号」。
「いったい、これはどういうことだ?」私は問うた。
「つまり殺人だ」と彼は遺体に身をかがめて言った。「ああ、やはりそうだった。ここを見てくれ!」彼は耳の上の皮膚に突き刺さる、細長い黒い物体を指差した。
「棘のようだな」と私は言った。
「その通り、棘だ。だが気をつけて抜くんだ。毒が塗ってある。」
私は指先でつまんで抜いた。それは非常に容易く皮膚から離れ、ほとんど跡も残らなかった。ごく小さな血痕が一点、刺し跡を示していた。
「まったく解けない謎ばかりだ」と私は言った。「ますます混迷するばかりだ。」
「いや、逆だ」と彼は言った。「一刻ごとに鮮明になってきている。あと数個の欠けた鎖を手に入れれば、事件の全体像が明らかになるはずだ。」
部屋に入ってからというもの、私たちはすっかり同行者の存在を忘れていた。彼はなおも戸口に立ち尽くし、恐怖そのものを表した震えながら手をもみ、呻き声をあげていた。だが突然、甲高く苛立った叫び声を上げた。
「宝は消えた! 誰かが奴から宝を奪ったんだ! 宝を下ろした穴がそこにある。私も運ぶのを手伝った。私が最後に彼を見た。昨夜、ここに彼を残し、階段を下りる時に彼が鍵をかける音を聞いた。」
「それは何時だった?」
「十時です。そして今や彼は死んだ……警察が呼ばれ、私は共犯として疑われてしまうんだ。ああ、絶対そうだ。でも、皆さんはそんなこと思ってないですよね? 私が犯人なら、こんな場所に案内するでしょうか? ああ、もう、私は気が狂いそうだ!」彼は腕を振り回し、足を踏み鳴らして、半ば錯乱したようだった。
「心配なさることはない、ショールトさん」とホームズはやさしく肩に手を置いた。「私の助言ですが、この件を警察に届けに駅まで行くといい。できるかぎり協力する旨を伝えるのです。私たちはここであなたの帰りを待つ。」
小男は半ば呆然と従い、闇の中を階段をよろめきながら降りていった。
第六章 シャーロック・ホームズの実演
「さてワトソン」とホームズは手をこすりながら言った。「三十分ほど我々だけの時間がある。その間を有効に使おう。君に話した通り、事件の全容はほとんど見えかけているが、過信は禁物だ。今は単純に見えても、もっと深い何かが隠されているかもしれない。」
「単純だって!」と私は思わず叫んだ。
「もちろんだ」と彼は臨床教授が講義するかのような口調で言った。「隅の椅子に座って、足跡の混入を避けてもらいたい。さあ、調査開始だ。まず、犯人たちはどこから来て、どうやって去ったのか? この扉は昨夜から開かれていない。窓はどうか?」彼はランプを持って窓際へ進み、独りごとのように観察を声に出していた。「内側から掛け金が降りている。枠もしっかりしている。側面に蝶番はなし。では開けてみよう。水道管は近くにない。屋根も届かぬほど高い。しかし誰かがこの窓から出入りしている。昨夜は小雨だった。窓台に泥の足跡。円形の泥の痕もある。床、テーブル付近にも同じ痕。見てみろ、ワトソン。なかなか見事な証拠だ。」
私は輪郭のはっきりした円い泥痕を見つめた。「これ、足跡じゃないようだ」と私は言った。
「いや、それ以上に価値があるものだ。これは木製義足の跡だ。窓台には靴の跡――幅広の金属ヒール、隣に木製のつま先の痕がある。」
「木足の男だな。」
「その通り。だが、もう一人いた――非常に有能な共犯者が。君、あの壁をよじ登れるか?」
私は窓の外を見やった。月光は家のその一角を明るく照らしていた。地上から優に十八メートルはあった。どこにも手がかりや割れ目もなかった。
「絶対に不可能だ」と私は答えた。
「自力ではな。しかし、もしここにロープを通して上から降ろしてくれる仲間がいれば、この壁のフックにロープの一端を固定し、身軽な男なら木足でも登れるはずだ。当然、降りるときも同様だし、共犯者はロープを引き上げ、フックを外し、窓を閉めて内側から掛け金を降ろし、最初に来た道で立ち去ればよい。ひとつ小さな補足として――」と彼はロープの先を指でなぞりながら続けた――「木足氏は器用だが水夫ではない。彼の手はごつごつしていなかった。私のレンズは、特にロープの端付近に複数の血痕を見つけた。それで分かるだろう、彼は高速で滑り降りて手の皮膚をすりむいたのだ。」
「なるほど、とてもよく分かった。だが謎はむしろ深まる一方だよ。この不可解な共犯者とやらはどうやってここへ入り込んだんだ?」
「共犯者だな!」とホームズは思案げにくり返した。「この共犯者には興味深い点が多い。彼の存在が、事件をありふれたものから一気に特異なものに引き上げている。どうやらこの共犯者は、イギリス犯罪史の中でも新たな領域を切り拓いたらしい――ただし、インドやセネガンビアには類似例がある気がするが。」
「で、彼はどこから入ったと思う?」私は重ねて問うた。「扉は閉められていたし、窓も手が届かない。まさか煙突からか?」
「いや、暖炉の口は狭すぎる。その可能性はすでに除外した。」
「じゃあ、いったいどうやって?」
「君は私のやり方を実践しないな」と彼は首を振った。「私は何度言ったろう、不可能なものをすべて消去していけば、残るのはいかにありえなくとも真実なのだと。扉からも窓からも暖炉からも来なかった。部屋に隠れることも不可能だ。ならば、彼はどこから来た?」
「……屋根の穴を通ってきたんだ!」私は叫んだ。
「その通りだ。必ずそうに違いない。ランプを持ってくれ。上の部屋――宝が見つかった秘密の部屋を調べてみよう。」
彼は脚立を登り、梁に両手をかけて屋根裏に身を引き上げた。それからうつぶせに寝そべってランプを掴み、私も後に続いた。
その部屋は一辺が三メートル、他方が二メートルほどで、床は梁の間に薄い板と石膏がはめられており、歩く際は梁を選んで進まなければならなかった。屋根は尖った頂上へ向かって傾斜し、これは明らかに建物本体の内側の殻だった。家具は一切なく、何年分もの埃が厚く積もっていた。
「ここだ、見なさい」シャーロック・ホームズは傾斜壁を押しながら言った。「これは屋根に出るための天窓だ。押し上げれば、ほら、すぐ外が屋根。これが“ナンバー・ワン”の侵入口だ。彼の個性を示す痕跡がないか探そう。」
彼がランプをかざすと、その顔にまたもや驚きの色がよぎった。私もその目線を追い、服の下で肌がぞっと冷たくなるのを感じた。床には裸足の足跡が何重にもはっきりと重なっていた――それは極めて明瞭で完全な形だったが、普通の大人の半分ほどの大きさしかなかった。
「ホームズ、これは……子どもの仕業じゃないか」と私は声をひそめて言った。
彼はすぐさま冷静さを取り戻した。「たしかに不意を突かれたが、自然なことだ。記憶がよみがえれば、先に予想できた。この部屋でもう学べることはない。下りよう。」
「じゃあ、あの足跡についての君の見解は?」下の部屋に戻ると、私は熱心に尋ねた。
「ワトソン君、少し自分で分析してごらん」と彼はいささか苛立って答えた。「私の手法は知っているだろう。応用してみるといい。仮説の比較は有益だ。」
「どんな仮説でも、この事実を説明するのは思いもつかない」と私は言った。
「いずれ君にも分かるようになるだろう」と彼はそっけなく言い、「ここで他に重要なことはもうないと思うが、一応見ておこう」と言ってレンズと巻尺を取り出し、膝をついたままで部屋中を測ったり調べたりした。長い鷲鼻が床ぎりぎりに近づき、小鳥のような鋭い目がギラリと輝いていた。まるで訓練された猟犬さながらの素早く、静かで、慎重な動きだった。私は思わず、もし彼がその精力と明晰さを法の擁護でなく、犯罪に向けていたら、どれほど恐ろしい犯罪者になっていただろうと思ってしまった。彼は独りごとを呟きながら部屋中を探し、やがて歓喜の叫び声を上げた。
「これは幸運だぞ」と彼は言った。「これで難航することはないだろう。“ナンバー・ワン”は運悪くクレオソートを踏んだ。この臭気の溜まりの脇に小さな足跡の縁が見えるだろう。カーボイが割れてこの液体が漏れ出したのだ。」
「それで?」私はたずねた。
「つまり、決まりだ」と彼は得意げに言った。「この臭いを追って世界の果てまで行ける犬を私は知っている。猟犬がニシンの匂いを郡を越えて追えるなら、この強烈な匂いならどこまでもいけるはずだ。三段論法の算術みたいなものだ。答えは――だが……おっと、法律の番人ご一行の登場だ。」
階下から重い足音と大きな声が聞こえ、玄関がバタンと閉まる音がした。
「彼らが来る前に」とホームズ、「この遺体の腕と脚に触れてみてくれ。何を感じる?」
「筋肉は板のように硬くなっている」と私は答えた。
「その通り。極端な強直状態にある。顔の歪み、このヒポクラテス的な微笑、つまり『リサス・サルドニクス』――古い医学者がそう呼んだ状態――これらを合わせると、君は何を思う?」
「強力な植物性アルカロイドによる死だ。ストリキニーネ様[訳注:猛毒の神経毒]の毒物で痙攣を引き起こすんだ。」
「まさに私も同じ考えだ。遺体の筋肉を見た瞬間、それがよぎった。この部屋に来てすぐ、毒の侵入経路を探した。ご覧の通り、棘が頭皮に刺さっていた。この部位は、もし男が椅子に座って真っ直ぐなら、ちょうど天井の穴に向く部分だ。棘をよく調べてみてくれ。」
私は慎重につまみ上げ、ランタンの光にかざした。それは長く鋭く黒く、先端近くは樹脂のような物質が乾いて輝いていた。鈍端はナイフできれいに丸く削ってあった。
「これはイギリス産の棘か?」と彼はたずねた。
「いや、違う。」
「これだけの情報で、なにがしかの推測ができるはずだ。だが、公式の御到着だ。我々の出番はここまでだ。」
話しているうちに、近付いてきた足音が廊下に響いた。ずんぐりと肥えた中年の男が灰色のスーツ姿で重々しく部屋に入ってきた。顔は赤くふくらみ、二つの小さな目が腫れぼったいまぶたの間から鋭くのぞいていた。すぐあとには制服の警部補、それにまだ怯えの残るサディアス・ショールトが続いた。
「こりゃ一大事だ!」と男はしわがれた声で言った。「なんという騒ぎだ! だが、ここに集まっているのは誰だ? ウサギ小屋みたいに人だらけじゃないか!」
「ご記憶でしょう、アセルニー・ジョーンズさん」とホームズは落ち着いた声で言った。
「ああ、もちろんだ!」と男は息を切らせて答えた。「シャーロック・ホームズ氏、理論家だな。忘れるものか、ビショップスゲートの宝石事件で、理屈や推論やらを散々聞かせてくれたことを。結局、あれだって幸運が導いたって思うだろ? 導きじゃなくて運だったと認めてくれよ。」
「いや、単なる推論の積み重ねですよ。」
「まあまあ、強がるなって。で、これはどういう事件だ? 悪いね、ややこしいぞ。ここは事実がすべて、理屈は不要だ。ちょうどノーウッドの別件で外出中、通報を受けて駆けつけた。さて、死因は?」
「私が論じるまでもないことでしょう」とホームズはそっけなく言った。
「まあ、たまには君も的中させるから否定はできないが……扉は内側から施錠だな。宝石は大金分が消失。窓はどうだった?」
「はめ殺し、でも窓台には泥の跡が残っていた。」
「ふむ、固定されていれば窓台の跡は無関係だ。てんかん発作の死だとしたら、宝石の消失はどう説明する? 私は理論を思いついたぞ。こういう“閃き”がたまに来る――そこの巡査とショールト氏は外へ。一人だけ残して……さて、ホームズ君、どう思う? ショールトは昨夜、自分で兄と会っていた。兄は発作で死亡し、ショールトが宝を持ち出した。どうだ?」
「その死体自らが親切にも、内側から鍵をかけたというわけですね。」
「ふむ、そこが問題だ。常識に従えばいい。このサディアス・ショールトは兄と会っていた、口論があった、それだけは確か。兄は死に、宝は消え、最後に兄を見たのはサディアス。ベッドは使われた形跡なし。とりわけサディアスは動揺し、見るからに不審な風体だ。私の網は彼を縛り始めている。」
「あなたはまだ事実のすべてを把握していませんよ」とホームズが言った。「この木片[訳注:毒棘]は毒物の疑いが濃厚で、死体の頭皮に刺さっていました。テーブルにはこう記されたカード、それに奇妙な石頭の凶器も残っていました。あなたの仮説とどう整合しますか?」
「全てを裏付ける」と太って尊大な巡査部長は言った。「部屋中インドの骨董品だらけ。サディアスがこの木片を持ち込んだなら、彼が凶器に使った可能性は十分ある。カードも煙幕――目くらましだ。ひとつ疑問は、彼がどうやって去ったかだ。ああ、なるほど、ここに屋根への穴があるじゃないか。」彼は巨体に似合わず素早く脚立を登り、天井をくぐり抜け、すぐさま天窓を発見したと勝ち誇った声が聞こえてきた。
「何かは見つけられるようだ」とホームズは肩をすくめた。「彼にも時おり、理性のひらめきがある。Il n’y a pas des sots si incommodes que ceux qui ont de l’esprit![訳注:愚者の中で一番やっかいなのは時おり才気の働く者である。]」
「見たろう!」アセルニー・ジョーンズは意気揚々と脚立を下りてきて言った。「事実こそ理論より上だ。私の見立ては正しい。天井に屋根への通路があり、しかも開いている。」
「それは私が開けたのです。」
「なるほど! じゃあ気づいていたのか?」発見が自分の手柄でないことにいくぶんがっかりした様子。「まあ、いずれにしろ、そこから犯人が逃げたわけだ。警部!」
「はい、部長」廊下から声が返る。
「ショールト氏をこちらへ……ショールト氏、これから話すことは、すべて証拠として使われることがあります。女王陛下の名において、あなたをお兄さんの死に関与した容疑で逮捕します。」
「ほら、やっぱり! 言った通りになったじゃありませんか!」と哀れな小男は両手を広げ、私たち皆を交互に見回した。
「ご心配なく、ショールトさん」とホームズ。「必ず嫌疑を晴らしてみせます。」
「理論家さん、あまり強気な約束は禁物だよ!」と探偵は鋭く言い放った。「君の思うほど簡単じゃない。」
「サディアス氏の嫌疑を晴らすだけでなく、昨夜この部屋にいた二人組のうち一人の名と特徴を進呈しましょう。私の推察では、名はジョナサン・スモール。学は浅く、小柄で身軽、右足は義足で、義足の内側がすり減っている。左足の靴底は四角く太く、かかとに鉄帯がある。中年で日焼けが濃く、元受刑者。さらに、手のひらの皮膚がかなり剥けている。これは捜査に大いに役立つはずだ。もう一方は――」
「もう一人は?」とアセルニー・ジョーンズは皮肉げな口調ながら、ホームズの精確さに明らかに感心している様子で訊いた。
「かなり妙な人物だ」とシャーロック・ホームズは踵を返して言った。「いずれ近いうちに二人組をご紹介できるだろう。――少し話がある、ワトソン。」
彼は私を階段の吹き抜けで呼び止めた。「今回の予想外の展開で、本来の目的を見失いかけていた。」
「全く僕もそう思っていた」と私は答えた。「ミス・モースタンをこの不吉な館に残すのは気がとがめる。」
「いや、君が彼女を送り届けるべきだ。彼女はセシル・フォレスター夫人とロウワー・カンバーウェルに住んでいる。遠くはない。私はここで待っていよう。あるいは疲れただろうか?」
「決して。むしろこの異様な出来事の全貌を見ないと落ち着かない。これほど奇妙な驚きが連続して胸がすっかり乱された。でも、ここまで来た以上、君と最後まで見届けたい。」
「君がいてくれると大いに助かる」と彼は言った。「我々は独自に事件を追い、ジョーンズには勝手に無駄な巣作りをやらせておこう。ミス・モースタンを送り届けたら、ラムベスの川べりにあるピンチン・レーン三番地に寄ってほしい。右手の三軒目が“鳥剥製屋”で、名はシャーマン。窓にイタチが兎をくわえている剥製がある。シャーマン老人を起こし、ホームズからの使いで“トビー”を今すぐ借りたいと伝えてくれ。犬を連れ帰るんだ。」
「犬かい?」
「ああ、変わった雑種だが、驚くべき嗅覚を持っている。ロンドン警察全部よりもトビー一匹のほうが役に立つ。」
「分かった、必ず連れてくる。今は一時だ。馬を替えれば三時までには戻る。」
「私はその間にバーンストン夫人と、寝室の隣にいるというインド人召使から情報を得てみる。そして、ジョーンズ流の物言いや皮肉もたっぷり拝聴しておこう。『Wir sind gewohnt das die Menschen verhöhnen was sie nicht verstehen.[訳注:人は理解できないものを嘲笑うことに慣れている。]――ゲーテはどこまでも含蓄深いな。』」
第七章 樽の一件
警察が呼んだ馬車に、私はミス・モースタンを送り届けた。女性らしい天使のような気丈さで、弱き者を支えている間は平静を保っていた彼女も、怯えた家政婦の傍らにいる時は明るく穏やかだった。だが馬車の中で初めてふらっとなり、その後は号泣にくれた――今夜の出来事はそれほど彼女の心身を痛めつけていた。その後彼女から、あの帰り道の私は冷たくよそよそしかったと聞いた。だが、彼女には知る由もなかった。私の胸の葛藤と、どれほど自制していたのかを。あの庭で手を差し伸べた時と同じく、私の思いは彼女に向いていた。だが、愛の言葉を口にするのを押しとどめた理由がふたつあった。彼女は弱り切り、動揺していた。そんな不利な時に愛を口にするのは卑怯だ。もっと悪いのは、彼女が資産家になるかもしれないことだ。ホームズの探索が成功すれば、彼女は相続人となる。定職もない身分の医師が、偶然の親密さに乗じて想いを告げるのは公正だろうか、卑しい下心と見なされはしないだろうか。彼女の心に一瞬でもそんな疑惑がよぎるのはどうしても堪え難かった。このアグラの宝が、私たちの間に越え難い壁となった。
セシル・フォレスター夫人宅に着いたのは、すでに二時近くだった。召使たちは何時間も前に休んでいたが、フォレスター夫人はミス・モースタン宛ての奇妙な手紙に興味を持ち、ずっと起きて彼女を待っていた。自らドアを開けた夫人は中年で優雅な女性だった。彼女の腕がミス・モースタンの腰にやさしく回され、母のような声で迎える様子に私は安堵した。有償の同居人などではなく、敬意をもたれた友人なのだと分かる。私は紹介され、事件の経過を語ってほしいと懇願されたが、任務の重要性を伝え、進展があれば必ず報告すると約束した。後ろ髪を引かれる思いで馬車を出すと、家の階段に映るその親密な二人の姿が今も瞼に浮かぶ。半開きのドアからホールのランプがステンドグラス越しに漏れ、バロメーターや光る階段の棒が見えた。この血なまぐさい闇の只中に、ほんの一瞬でも落ち着いた英国の家庭の情景を垣間見られて、心が和んだ。
しかし一連の出来事を思い返すほどに、事件は混迷を深めた。道すがら、これまでの経緯を頭の中でざっと追い直してみたが、最初の問題自体は今やかなり明確になった。すなわち、モースタン大尉の死、真珠の送付、広告、手紙――それらの謎はほぼ解けていた。しかしそこから導かれた先には、より暗く悲劇的な謎が口を開けていた。インドの財宝、モースタンの荷物から見つかった奇怪な地図、ショールト少佐急死の夜の不思議な出来事、宝の再発見と同時に発生した事件、足跡や凶器の異常、カードの文言、それがまたモースタン大尉の地図にも対応する――これは、凡庸な者なら絶望せずにはいられない迷宮である。
ピンチン・レーンは、ラムベスの下町に並ぶくすんだ二階建てのレンガ家だった。三番地をかなり長く叩かねば返事がなかった。ようやくカーテン越しに蝋燭の明かりが見え、上階の窓から顔が覗いた。
「酔いどれ野郎、どっか行け!」と顔が怒鳴った。「これ以上騒いだら、四十三匹の犬を放しちまうぞ!」
「一匹だけ放してくれ、それが目的だ」と私は応じた。
「引き下がれ! 勘弁してくれ。毒蛇を袋に入れてるから、騒ぎ続けると頭にぶつけるぞ!」
「いや、本当に犬を借りたいんです!」
「議論はご免だ!」とシャーマン氏は叫び、「三つ数えたら本当に投げるぞ!」
「シャーロック・ホームズさんの使いで――」と言いかけた途端、魔法のような効果を発した。窓は即座に閉じられ、間もなくドアの閂が外され開いた。シャーマン氏は痩せて猫背の老人で、首が細く、青い色眼鏡をかけていた。
「シャーロック氏の友人なら大歓迎だ」と彼は言った。「どうぞお入りを。アナグマに気をつけなさい、噛みつくからな。ああ、こら、こら、お客さんに噛みついちゃいけません!」――これはケージから赤い目を光らせているイタチへの言葉だった。「あれは気にせんでいい、ただのスローワームだ。毒牙もないし、僕は虫取りの役に自由にさせてるだけだ。初めに無愛想で悪かったな、子供どもにからかわれることが多く、こんな路地にはいたずらで起こされる人間が多いんだ。さて、ホームズ氏のお望みは?」
「あなたの犬を借りたいそうです。」
「ああ、トビーのことか。」
「その名だった。」
「トビーは左手に見える七番地だ。」彼は蝋燭を手に、奇怪な動物たちの間をゆっくり進んだ。薄暗い中、至る所からいくつもの目玉がこちらを見ていた。天井の梁にもじっとした鳥が連なっていた。
トビーはぶさいくで長毛、耳の垂れた犬で、スパニエルとランチャーの雑種、茶白の毛並みで鈍重な歩き方をしていた。最初は警戒したが、老人にもらった角砂糖を差し出すと受け取り、それで仲良くなったため、馬車にも素直についてきた。ちょうど三時を告げる宮殿の鐘が聞こえた時、私は再びポンディシェリー・ロッジに戻った。元ボクサーの門番マクマードも逮捕され、ショールト氏と共に留置場へ送られていた。門番の刑事にホームズの名を告げて犬連れで無事通してもらえた。
ホームズは玄関先で両手をポケットに突っ込んでパイプをふかしていた。
「ああ、連れてきてくれたな。よしよし、いい子だ!」アセルニー・ジョーンズは帰ったあとだった。「君が出てから、えらいエネルギーを見せてね。ショールト氏、門番、家政婦、インド人召使まで一網打尽に逮捕してしまった。今は上階に巡査が一人いるだけ、屋敷は我々だけだ。犬はここに繋いで、上に来てくれ。」
トビーを玄関のテーブルに繋ぎ、二人でまた階上へ向かった。部屋は前と変わらず、中央の死体だけが白布に覆われていた。片隅にくたびれきった巡査が座っていた。
「ボウズアイランプを貸してくれ」とホームズが言い、「このカードを首にかけてくれ。靴下と靴も脱がねば。これはワトソン、下まで持っててくれ。ちょっとばかり登る実演をする。手ぬぐいもクレオソートに浸して……よし、では屋根裏に来てくれ。」
私たちは再び屋根裏に上った。ホームズは明かりを足跡のほこりにあてた。
「この足跡をよく見てくれ」と言った。「何か気付くか?」
「子供か小柄な女性に見える。」
「大きさ以外は? 他には?」
「他の足跡と変わらないように思う。」
「いや、全然違う。見てくれ。これが右足の痕。そして私の素足で並べてつけてみる。決定的な違いは何か?」
「つま先が全部一緒に押しつぶされている。もう一つの足跡は、それぞれのつま先がはっきり分かれている。」
「まさにその通りだ。それが重要なんだ。その点を覚えておいてくれ。さて、あそこのフラップ窓まで行って、木枠の縁の匂いを嗅いでくれないか? 私はここにいるよ、このハンカチを持っているから。」
私はホームズの指示どおりに動いた。すると、たちまち強いタールのような匂いに気付いた。
「あそこがやつが脱出する時に足をかけた場所だ。君にこれだけ分かったなら、トビーなら迷いなく嗅ぎ分けられるはずだ。さあ、下に降りて犬を解き放ち、『ブロンディン』を見張っててくれ。」
私が外に出る頃には、シャーロック・ホームズはすでに屋根の上にいて、巨大なホタルのように屋根の稜線をのろのろと進む姿が見えた。煙突の山の陰で一度見失ったが、また現れ、それから向こう側に再び姿を消した。私がそこへ回っていくと、彼は角の屋根端に座っていた。
「ワトソンか?」と彼が叫んだ。
「ああ、僕だ。」
「ここだ。この下にある黒いものは何だ?」
「水桶だ。」
「蓋はしてあるか?」
「してある。」
「ハシゴの痕跡は?」
「ない。」
「ちくしょう、なんて危険な所だ。やつが上がれたなら、僕も降りられるはずだ。水道管はかなりしっかりしているようだ。とにかくやってみよう。」
足音がして、ランタンが壁沿いにどんどん降りてきた。それから軽く飛び降りると、水桶の上に降り立ち、そこから地面に下りた。
「追跡は簡単だった」とホームズは言い、靴下と靴を履き直しながら続けた。「ずっと瓦が緩んでいて、急いだせいでこんなものまで落としていった。これで私の診断が裏付けられたよ、君たち医者がよく言うように。」
彼が私に見せたのは、色とりどりの草で編まれ、安っぽいビーズがいくつか付いた小さな袋だった。その形と大きさは、タバコケースにどこか似ていた。中には黒い木でできた細い棘が六本ほど入っていて、片方は尖り、もう片方は丸くなっている。それはバソロミュー・ショールトを貫いたものと同じだった。
「えげつない代物だ」とホームズは言った。「刺さないように注意しろ。手に入ってうれしいよ、きっとやつが持っているのはこれだけだろう。だから、君や僕がうっかり体内に刺してしまう心配も減った。マルティーニ銃弾を浴びる方がまだましだ。ワトソン、六マイルほど歩く覚悟は?」
「もちろんだ」と私は答えた。
「君の足は大丈夫か?」
「ああ、大丈夫だ。」
「おいで、トビー! いい子だ、トビー! 匂いを嗅ぐんだ、トビー、嗅いでみろ!」彼はクレオソートが染みたハンカチを犬の鼻先に押しつけた。トビーは前足を広げ、頭を傾げてまるで有名なワインの香りを嗅ぐ通のような仕草をした。ホームズはそのハンカチを遠くに放り、太い紐を雑種犬の首輪に結び、水桶の足元まで引いていった。犬はすぐに甲高く震えるような鳴き声を立てながら、鼻を地面につけ、尻尾を上げて足早に進み、リードを強く引っ張ったので、私たちも全力でついていった。
東の空が次第に白んできて、寒々しい灰色の光の中でもかなり遠くまで見通せるようになった。四角く頑丈な家は黒々とした空の窓と、高くむき出しの壁が私たちの背後で悲しげに聳え立ち、荒れ果てていた。道は敷地内を横切り、無数の溝や穴の間を縫うように続いている。あたりには散らばった土山や貧弱に育った低木が点在し、全体的に不吉で呪われた雰囲気で、家にかかる黒い悲劇にふさわしい様相だった。
境界の壁にたどり着くと、トビーは壁沿いに鼻を鳴らせて進み、若いブナに隠れた角で止まった。二つの壁が合流するところは、いくつかレンガが緩くなっており、隙間は下部がすり減って丸みを帯びていた。まるでハシゴ代わりに何度も使われたかのようだった。ホームズは壁によじ登り、私から犬を受け取ると、向こう側へ下ろした。
「これが義足の男の手形だ」と、私が隣に上がるとホームズが言った。「白い漆喰に少し血がにじんでいるのがわかるだろう。昨日以来、まとまった雨がなかったのは本当に幸運だった。やつらに二十八時間も先行されていても、匂いはしっかり残っている。」
この間にロンドン街道をいろいろな人馬が行き交ったことを思うと、私は内心では懐疑的だった。だが、まもなく懸念は消えた。トビーは一度もためらうことなく、特有の揺れ歩きで進んでいった。クレオソートの強烈なにおいが、他のどんな匂いにも勝っているのは明らかだった。
「誤解しないで欲しい」とホームズは言った。「今回の事件が、ただ一人、化学品を踏んだせいで解決の見込みになったとは思わないでくれ。今や私は、多様な方法で奴らの足取りを追えるだけの知識を持っている。だがこの方法が一番手っ取り早く、しかも運よく与えられた手がかりを無視するのはかえって愚かだ。ただ、このせいで事件はかつて期待した知的な謎解きから外れてしまった。もっと名声を得られるかもしれなかったが、これではあまりに分かりやすすぎる。」
「いや、十分以上の名声だよ」と私。「正直言って、君がこの事件で出している成果には、ジェファーソン・ホープ殺人事件のとき以上に驚かされている。この事件はより深く不可解なものに思える。たとえば、どうやってそんなに自信をもって義足の男を描写できたんだ?」
「なんのことはない、簡単なことだよ。演技じみたことはしたくないが、すべては明らかで公然たるものだ。二人の看守の将校が囚人護送の任にあり、埋蔵財宝に関する重要な秘密を知る。イギリス人、ジョナサン・スモールという男が二人のために地図を作る。君も覚えているだろう、モースタン大尉のチャートにその名前があった。彼は自分と仲間を代表して署名し、『四人の署名』というわけだ。地図を手に入れた将校たちは、財宝を入手しイギリスへ持ってくる。だが、何か取り決めを守らずに済ませたのだろう。さて、なぜジョナサン・スモール自身が財宝を得なかったのか? 答えは明白だ。地図の日付は、モースタンが囚人と密接な関わりを持っていた時期だ。スモールとその仲間たちは囚人自身であり、逃げることができなかったのだ。」
「それは仮説じゃないか」と私が言った。
「それ以上だ。この事実をすべて説明できる唯一の仮説だ。続きを見てみよう。ショールト少佐は数年間、平穏に財宝を所有している。だがある日、インドから手紙を受け取り、ひどく怯える。それはなぜか?」
「彼が裏切った男たちが釈放されたとの手紙だった。」
「あるいは脱獄したのだろう。その方がありそうだ。刑期を知っていたはずだから、驚きはないはずだ。彼はどうする? 義足の男――白人だ、よく聞くがいい――に警戒する。実際、白人の商人を彼と取り違えて発砲している。白人はチャートの中で一人だけ、他はヒンドゥー教徒かムスリムだ。他に白人はいない。だから義足の男はジョナサン・スモールと断定できる。不合理に思えるか?」
「いいや。明快で論理的だ。」
「では、ジョナサン・スモールの立場になってみよう。彼は財宝を取り戻し、かつ自分を裏切った男への復讐を果たすためにイギリスに来た。ショールトの居所を突き止め、おそらく屋敷内の誰かと接触した。ラル・ラオという執事がいるが、我々はまだ会っていない。バーンストン夫人もあまり評判は良くないと言っている。しかし財宝の隠し場所だけは、少佐と亡くなった忠実な召使いしか知らなかった。スモールは財宝のありかを掴めなかった。だが突然、少佐が臨終だと知る。彼は財宝が秘密のまま消えることを恐れて警備をかいくぐり、死にかけの男の窓までたどり着く。しかし二人の息子がいるせいで中に入れなかった。だが夜中、憎しみに駆られて部屋に侵入し、個人の書類を探って何か財宝に関する覚書を探したが空振りに終わる。そして名刺に短い言葉を記し、訪問の痕跡を残して去る。もし少佐を殺していたら、殺害の証としてまさに同じような記録を遺体に残すつもりだっただろう。これは‘四人の仲間’にとって単なる殺人ではなく、あくまで義による行為だと示そうとしたわけだ。この種の奇矯な犯罪行為は過去にもよく見られ、犯人の手がかりになることが多い。ここまでわかったか?」
「とてもよく理解した。」
「ではスモールにできることは何か? 財宝捜索の進捗を密かに監視し続けるしかない。おそらくイギリスを離れ、時折帰ってきて様子をうかがう。屋根裏部屋発見の知らせが入ると、仲間が屋敷内にいる痕跡がまた現れる。ジョナサン・スモールは義足で、バソロミュー・ショールトの高い部屋には自力でたどり着けない。しかし不思議な仲間を連れており、そいつがその困難を乗り越える。その際、裸足でクレオソートを踏み、そこからトビーが現れ、アキレス腱を傷めた半給休職の軍人が六マイルも引きずる羽目になる。」
「だが実際に犯行を犯したのはその仲間の方だったのだろう?」
「その通り。そしてジョナサンにとっては不満だったろう。やつが部屋に入った時、怒って足で踏み鳴らしていたことからもわかる。バソロミュー・ショールトに個人的な恨みはなく、本心では縛り上げて口を塞ぐだけで済ませたかったはずだ。自分が首をくくるリスクを冒すのは望んでいなかった。ただ、獰猛な仲間が本性をむき出しにし、毒矢が役目を果たしてしまった。だからスモールは例の記録を残し、宝箱を地上に降ろして自分も追って出てきた。これが私が推理した事件の流れだ。外見に関しては、年齢は中年、アンダマン諸島のような地獄で長期間過ごして日焼けし、歩幅の長さから身長も割り出せる。やつは顎ひげがある。窓でサディアス・ショールトの印象に強く残ったのは、まさに毛深さだった。他には特にない。」
「その仲間とは?」
「ああ、それには特に謎はない。でもすぐに分かるさ。朝の空気はなんて清々しいんだ! あの小さな雲が、巨大なフラミンゴの羽根のようにピンク色に浮かんでいる。太陽の紅い縁がロンドンの雲海を押し上げてくる。いろんな人たちの上に光が差すが、君と僕ほど奇妙な目的のためにいる者はまずいまい。自然界の大いなる原理を前にすれば、自分たちのささやかな願いや努力がどんなに小さいかを思い知らされる。ジャン・パウルには詳しいか?」
「まあまあだ。カーライル経由で読んだ。」
「それは、小川から源泉へさかのぼるようなものだ。彼が言った妙で深い言葉がある。人間の偉大さの証明は、自分の小ささを認識する力にある、と。つまり、それは比較と認識の力がある証であり、それ自体が高貴さの証明だということだ。リヒターには多くの思考の糧がある。君は拳銃を持っていないだろう?」
「ステッキはある。」
「やつらのアジトにたどり着いた場合、必要になるかもしれない。ジョナサンは君に任せるが、もう一人が凶暴化すれば私は撃ち殺すつもりだ。」 そう言いながら、ホームズはリボルバーを取り出し、二つの薬室に弾を込めて、ジャケットの右ポケットにしまった。
この間ずっと、私たちはトビーの導きで、都市部へ通じる半ば田園風景の住宅道路を進んでいた。しかし今や連続する通りに出始め、労働者や港湾労働者がすでに動き始め、だらしない格好の女たちが雨戸を取り外したり玄関を掃いたりしていた。角の角ばったパブでは、ようやく客が現れ、むさ苦しい男たちが朝の一杯の後で袖で口髭を拭いて出てきた。不思議そうな犬たちがこちらを見つめたが、比類なきトビーは一切気を取られず、鼻を地面につけてさっさと進み、時折高く鋭い鳴き声で気配を示した。
私たちはストレサム、ブリクストン、カンバーウェルを通り、ケニントン・レーンの手前にたどり着いた。オーヴァルの東を横切る路地裏を通ってきたのだ。追っている男たちは不規則にジグザグの道を選び、見つかるのを避けていたようだ。メインの道を避けて、並行した裏通りを使っていた。ケニントン・レーンの終わりでは、ボンド・ストリート、マイルズ・ストリート経由で左へ進んでいた。マイルズ・ストリートがナイツ・プレイスと交差するあたりで、トビーは進行をやめ、耳を片方立て、片方垂らして右往左往し、犬の優柔不断そのものの様子を見せた。そしてぐるぐる回りはじめ、時々こちらを見上げて困惑した面持ちで訴えるようだった。
「犬に何があったんだ?」とホームズが低く言った。「まさか、タクシーに乗ったり、気球にでも乗ったわけじゃあるまい。」
「しばらくここにたたずんだのかも」と私は言った。
「ああ、大丈夫だ。もう動き出したよ」とホームズが安堵した調子で言った。
果たしてその通りで、再び匂いを嗅ぎ回ったあと、突然決意したかのようにものすごい勢いで突進した。今度は今までになく熱心で、もう鼻を地面につける必要さえなく、リードを引きちぎりそうな勢いだった。ホームズの目が輝いているのを見て、目的地が近いと感じ取っているのが分かった。
道はナイン・エルムズを下り、ホワイト・イーグル酒場を過ぎたところのブロデリック&ネルソンの大きな材木置き場に出た。ここで犬は、興奮した様子で脇の門から敷地に入った。中では大工たちがすでに作業を始めていた。トビーはおがくずと木屑の中を疾走し、小道を抜け、通路を曲がり、二つの材木の山の間を走り抜け、ついに台車に乗せられたままの大きな樽の上に、勝ち誇ったような鳴き声を上げて飛び乗った。舌を出し目をしばたきながら、トビーは樽の上で私たちから称賛を求めるように振る舞っていた。樽の側板や台車の車輪には黒い液がべっとり擦り付けられ、あたり一体にクレオソートの匂いが立ちこめている。
シャーロック・ホームズと私は顔を見合わせ、次の瞬間、二人同時にこらえきれず爆笑していた。
第八章 ベイカー街遊撃隊
「さて、これからどうする?」と私は尋ねた。「これでトビーの名声も地に落ちた。」
「犬はあくまで自分の判断で動いたまでだ」ホームズはトビーを樽から降ろして材木置き場の外へ連れて歩きながら言った。「ロンドンでどれほどのクレオソートが日々運ばれているか考えれば、匂いの道筋が交錯しても不思議はない。最近は特に木材の乾燥によく使うからね。可哀想だが、トビーは悪くない。」
「また元の匂いを探し直さないといけないな。」
「そうだ。幸い、それほど離れていない。ナイツ・プレイスの角でトビーが困惑した理由は、道筋が二つに分かれていたからだ。私たちが外れの方を選んだに過ぎない。もう一つをたどればいい。」
これには難なく対処できた。トビーを失敗した場所に連れていくと、広い範囲を嗅ぎ回ってから、新たな方向に駆け出した。
「今度は樽の積み先に誘導される危険は?」と私は言った。
「そこは心配していた。でも注意して見ると、犬は歩道沿いを進むが、樽は車道だった。今は間違いなく正しいほうを追っている。」
匂いは川沿いへと向かい、ベルモント・プレイスやプリンスズ・ストリートを抜けた。ブロード・ストリートの端で、そのまま川べりの木製の小さな桟橋に出た。トビーはそのまま端まで進み、暗い流れを見つめながら鼻を鳴らした。
「運が悪いな」とホームズ。「ここでやつらは舟に乗ったようだ。」川には小舟やボートが何隻か浮かび、また桟橋にも繋がれていた。一隻ずつトビーに嗅がせてみたが、どれも反応しなかった。
簡素な船着き場の隣に、小さなレンガ造りの家があり、二階の窓から木製の看板がぶら下がっている。「モルデカイ・スミス」と大書され、その下に「ボート貸し出します、一時間または一日単位」と記されている。扉の上には「蒸気船も所有」とあり、桟橋に積まれたコークス[石炭より高温で燃える燃料]の山がそれを裏付けていた。シャーロック・ホームズはぐるりと見回し、険しい顔つきになった。
「これは厄介だ」と彼は言った。「連中は思ったより手強い。ここまで細心に証拠隠滅されている。事前の画策があったようだ。」
ちょうど彼が家の扉に近づこうとした時、中から六歳ほどの髪のくるくるした坊やが飛び出してきて、続いて大柄で真っ赤な顔の女が大きなスポンジを手に追いかけてきた。
「戻ってきて、ジャック、洗わせなさいよ!」と女が叫ぶ。「戻りなさい、生意気坊主。お父ちゃんが帰ってきてそんなんだったら、えらいことになるよ。」
「可愛い子だなあ」とホームズが策略めいた調子で言う。「ほっぺたの赤いガキンチョじゃないか。なあ、ジャック、何か欲しいものは?」
坊やは少し考えて、「シリングが欲しい」と答えた。
「もっと欲しいものは?」
「二シリングあればもっといい」坊やはさらに考えた末に言った。
「じゃあ、これをやろう! 受け取れ! ――いい子だね、スミス夫人!」
「本当にもう、先生、とにかく元気で困るんですよ。うちの人が何日も家を空けてる時は特にね。」
「ご主人はいないのですか?」とホームズは落胆した調子で尋ねた。「それは残念だ、ちょうどお話ししたかったのに。」
「昨日の朝から出っ放しなんですよ。正直なところ、心配になってきました。でもボートのことなら、先生、私でも用は足りますよ。」
「蒸気船を借りたかったんです。」
「先生、実はうちの者も蒸気船で出て行ったんです。それが不思議で。コークスはせいぜいウーリッジ往復分しか積んでなかったはず。はしけで出たならグレーヴセンドだろうけど、蒸気船で何の用か……。コークスも足りません。」
「河下で買い足したのかも。」
「かもしれませんけど、あの人はそんなことしません。値段にいつも文句言ってますし。しかもあの義足の男、顔も言葉も変なやつ、あいつがいつもつきまとって……嫌な感じで。」
「義足の男?」ホームズが無邪気そうに尋ねた。
「はい、先生、褐色でサルみたいな顔したやつ、何度も夫を呼びに来て。昨夜もそいつが目を覚まさせて、しかも夫は彼が来るのを知ってて、蒸気船に火を入れてました。正直、先生、私は気がかりで。」
「でも、スミス夫人、そんなに怖がることはないよ。どうしてその夜に来たのが義足の男だと言い切れる?」
「声です、先生。変に太く濁った声で、窓を叩いて――たぶん三時ころ――『起きろよ、相棒、交代の時間だ』って。夫は長男のジムを起こして、そのまま二人とも何も言わず出ていったんです。義足が石畳を鳴らす音がはっきり聞こえました。」
「その義足の男は一人だった?」
「それは分かりません、先生。他には何も聞きませんでした。」
「残念ですね、スミス夫人、蒸気船が必要で、評判もよく聞いていたのですが――名前を何と言いましたか?」
「オーロラ号です、先生。」
「ああ! それは緑色で黄色い線の、幅広のやつじゃない?」
「違います。川一番の綺麗な船ですよ。塗り直して、黒地に赤い2本線です。」
「ありがとう、ご主人から連絡があったらいいですね。私たちは川を下るので、オーロラ号を見たらご主人にあなたが心配していると伝えましょう。煙突は黒ですか?」
「いえ、黒地に白い帯です。」
「おっと、脇が黒だったんですね。では、失礼しますスミス夫人。――ワトソン、ここに小舟の船頭がいる。川を渡ろう。」
「そういう人たちにはね」ホームズは小舟のシートで言った。「こっちの興味を悟られないようにするのが肝心だ。重要そうなことを聞けばすぐに口を閉ざしてしまう。嫌そうなふりで聞けば、案外色々なことを教えてくれるものさ。」
「進むべき道筋ははっきりしたと思う」と私。
「どうするつもりだ?」
「蒸気船を雇ってオーロラ号の後を追う。」
「それでは無謀すぎる。グリニッジまでの両岸のすべての桟橋に立ち寄ったかもしれない。下流は何マイルも着岸所だらけだ。一人では何日もかかるよ。」
「警察に頼もう。」
「いや、最後の段階でアセルニー・ジョーンズを呼ぶだろう。彼は悪い奴じゃないし、変に恨みを買いたくない。だが、ここまできた以上は自分の手で解きたい。」
「なら広告か何かで情報を求めては?」
「それは逆効果だ。奴らは追跡が迫っていると気付き、国外へ逃げかねない。現状でも逃げる可能性はあるが、安全と思っていれば急ぐ気はないはずだ。ジョーンズのエネルギーは役立つ。彼なら事件を新聞に流すだろうし、犯人はみな違う手がかりを追っていると考えるだろう。」
「じゃあ、どうしたらいい?」私が尋ねた。
「この二人馬車に乗ろう、帰って朝食をとって一時間仮眠だ。今晩また出動という可能性大だ。電報局に寄ってくれ! トビーは手元に置こう、まだ役に立つかもしれない。」
グレート・ピーター・ストリートの郵便局で、ホームズは電報を送った。「誰宛だと思う?」馬車に戻ると彼は問うた。
「わからない。」
「ジェファーソン・ホープ事件で使ったベイカー街の私設警察部隊を覚えてるか?」
「もちろん」私は笑った。
「今回はまさに彼らが役立つ場面だ。失敗すれば他にも手はあるが、まずは頼ってみる。今の電報は部下のウィギンズ宛だ。朝食中には連絡があるだろう。」
今は八時から九時の間で、夜通しの興奮で私はすっかり消耗していた。体も心もぐったり重く、専門職的なやる気に突き動かされるホームズとは違い、ただ一つの知的問題として事件を見る余裕もなかった。バソロミュー・ショールトの死そのものについては元々好感もなく、犯人たちに強い憎しみは抱けなかった。だが宝物は違う。それは一部なりとも間違いなくミス・モースタンのものだ。取り戻せる可能性があるなら、そのために命を捧げる覚悟さえあった。とはいえ、見つけたら彼女は私の手の届かない存在になるだろう。だがそんな理由で気持ちが揺らぐなら愛とは言えまい。ホームズが犯人探しに邁進できるなら、私は宝を求めるのに十倍も強い動機がある。
ベイカー街の湯と着替えですっかりさっぱりして下の部屋に降りると、朝食の支度ができていてホームズがコーヒーを注いでいた。
「ほらこれだ」彼は笑いながら新聞を指した。「元気なジョーンズと抜け目ない記者が共同でまとめたんだ。でもまずはハムエッグから食べなよ。」
私は紙面を手にとって見出しを読んだ――「アッパーノーウッドの怪事」。
「今日午前零時ごろ」とスタンダード紙は書く。「アッパーノーウッド、ポンディシェリー・ロッジのバソロミュー・ショールト氏が、何者かの手で命を奪われた状態で発見された。目立った暴力の痕跡はなかったが、同氏が父から相続したインド産の財宝が消え失せている。第一発見者はシャーロック・ホームズ氏とワトソン博士であり、彼らは故人の弟サディアス・ショールト氏とともに現場を訪れていた。ちょうど運良く、著名な捜査官アセルニー・ジョーンズ氏がノーウッド警察署にいたため、最初の通報から30分以内に現場に到着。豊富な経験と直観で犯人の手がかりを即座にキャッチし、すでに弟サディアス・ショールト氏、家政婦バーンストン夫人、インド人執事ラル・ラオ、門衛マクマードの4名を逮捕している。犯人は家の構造及び状況に精通していたと考えられる。ジョーンズ氏の技術的知識と観察力により、犯行は偶然の窃盗ではなく、屋根→屋根裏のトラップドア→遺体があった部屋と続く経路をたどったと判明。その明快さはこの事件の計画性を物語っている。警察の迅速かつ果断な対応は、現場に熟練かつ断固たる指導力ある捜査官がいることの重要性を雄弁に物語り、警察組織を分権化し個々の事件と密接に連携させるべきだと主張する論拠にもなろう。」
「見事だろう!」ホームズはにやにやしながら言った。「どうだ?」
「下手をすれば僕らも逮捕されていたかもしれないな。」
「僕もそう思う。今だって、やつにもう一度やる気が出たら危ないよ。」
その瞬間ベルがけたたましく鳴り、ハドソン夫人の抗議と困惑の声が聞こえてきた。
「まずい、ホームズ、本当に捕まりにきたのかも」と、私は半ば腰を上げて言った。
「いや、そこまで悪くはない。来たのは私設遊撃隊、ベイカー街遊撃隊だ。」
そう言うと、裸足の足音が大急ぎで階段を駆け上がり、甲高い声が入り乱れ、十数人のぼろをまとった悪ガキの群れが部屋になだれ込んできた。だが無秩序な突入とは裏腹に、すぐに一列に整列し、期待に満ちた表情でこちらを見上げる。ひときわ大きく年長の子供が、一団を代表するように前に出た。
「お言葉どおり、来ましたぜ旦那。三シリングとタナー[※訳注:1シリング6ペンス]でチケット代です。」
「これだ、ウィギンズ」ホームズは銀貨を渡した。「これからは報告はまず君がまとめてから私に。家中に入られるのは困るからな。だが今は全員に指示を出す。探してほしいのはオーロラ号という蒸気船。持ち主はモルデカイ・スミス。黒に赤い二本線、煙突は黒地に白帯。どこか川下にいるはずだ。一人はミルバンク向かいの船着き場に待機し、戻ったら即座に知らせる。両岸とも漏れなく手分けして見張れ。何か分かったらすぐ連絡しろ。いいな!」
「はい、旦那!」とウィギンズ。
「従来の報酬、発見者にはギニー銀貨。今日は前金だ、各自一シリング。さあ出発!」小銭を渡すと、子供たちは飛び出ていった。私はすぐに彼らが隊となって通りを駆けていくのを見た。
「水上にいる限り、あいつらが見つけてくれる」ホームズはパイプに火をつけながら言った。「どこでも行けて、誰の話も聞ける。今晩までには手がかりが来るだろう。それまで私たちは何もできない。オーロラ号かモルデカイ・スミスを見つけるまで、追跡の糸は拾えない。」
「トビー、残り物をやるか。ホームズ、君は寝るのか?」
「いや、私は疲れない不思議な体質でね。仕事なら疲れないが、遊ぶとくたくたになる。今は煙草を吸いながら、美しい依頼人に引き込まれたこの奇妙な事件を考えるのみだ。こんなに簡単な事件はないはずさ。義足の男は珍しいが、もう一人はきっと唯一無二だろう。」
「またそのもう一人か!」
「別に君に謎をかけているわけじゃないよ。だが、君なりに考えてみるといい。小柄な足跡、靴に締め付けられたことのないつま先、裸足、石頭の棍棒、素早い動き、小さな毒矢。どう思う?」
「野蛮人だ!」私は叫んだ。「ジョナサン・スモールの仲間のインド人の一人じゃないか?」
「いや違う。最初は珍しい武器を見てそう考えたが、足跡の特徴で考え直した。インド系の人々は小柄もいるが、あんな足跡は残せない。ヒンドゥー教徒は足が長く細いし、サンダルを履くムスリムなら親指が他の指から離れている。こうした小さな矢も吹き矢でしか使えない。さて、ではその野蛮人はどこから来たのか。」
「南米系だろう」私は推測した。
彼は手を伸ばし、棚から分厚い巻物を一冊取り出した。 「これは、いま出版されつつある地名辞典の第一巻だ。最新の権威と言っていいだろう。さて、どれどれ? 『アンダマン諸島――スマトラ島の北340マイル、ベンガル湾に位置する』。ふむふむ。何だこれは? 湿潤な気候、珊瑚礁、サメ、ポートブレア、流刑囚房舎、ラトランド島、綿の木……ああ、ここだ。『アンダマン諸島の先住民族は、おそらく地球上でもっとも小柄な人種であると主張できるだろうが、アフリカのブッシュマン、アメリカのディガー・インディアン、フエゴ島の先住民を支持する人類学者もいる。彼らの平均身長はおおよそ四フィート以下であり、成長した大人でもこれよりずっと低い者が多い。気性は荒々しく、陰鬱で、馴致しがたいが、ひとたび信頼を得ると、非常に献身的な友情を結ぶことができる』。ワトソン、それを覚えておけ。次に、これを聞いてみろ。『彼らは生来、醜悪であり、大きくいびつな頭、小さく凶暴な目、歪んだ顔立ちを持つ。しかし手足は驚くほど小さい。彼らはきわめて頑強で猛々しく、イギリス当局者のどんな努力も、少しも彼らを懐柔することはできなかった。彼らは、難破した船員たちにとって常に恐怖の対象であり、生き残りを石頭の杖で殴り殺したり、毒矢で射抜いたりする。この虐殺は必ず食人宴で締めくくられる』。たいそう愉快で愛想の良い連中だな、ワトソン! もしこの男が独力で行動していたら、事態はもっと恐ろしいものになっていたかもしれない。今の状況ですら、ジョナサン・スモールは、雇ったことを激しく後悔しているだろうと私は思う」
「だが、どうして彼はそんな奇妙な相棒を得たのだろう?」
「さあ、それは私にも分からない。ただ、スモールがアンダマン諸島から来たことは既に判明しているのだから、その島民が同行していても何ら不思議はない。いずれ私たちにも経緯が明らかになるはずだ。さて、ワトソン、君はすっかり疲れているようだ。そこに横になってみろ。私が君を眠らせてやろう」
彼は隅にあったバイオリンを手に取り、私が身を伸ばすと、低く夢のような調べを奏ではじめた――おそらく即興であろう、彼は即興演奏の才を持っていた。私は彼の痩せた手足、真剣な顔つき、そして弓の上下するさまをぼんやりと覚えている。やがて私は、やわらかな音の海に包まれて安らかに漂い、夢の世界でメアリー・モースタンの美しい顔が私を見下ろすのを感じた。
第九章 連鎖の断絶
目が覚めたのは夕方遅くで、すっかり体力も回復していた。シャーロック・ホームズは依然として、私が寝る前とまったく同じ姿勢で座っていたが、バイオリンを脇に置き、本に夢中になっていた。私が身じろぎすると彼は顔を上げ、それが暗く沈んでいることに気づいた。
「よく眠ったな」と彼は言った。「私たちの話で起こしてしまうかと心配だった」
「まったく何も聞こえなかったよ」と私は答えた。「何か新しい知らせでも?」
「残念ながら、ない。私は驚きと失望を隠せない。そろそろ確かな情報があると思っていたのだ。たった今ウィギンズが報告に来たが、舟の足取りはまったく掴めていないとのことだ。まったく厄介な躓きだよ、時間のすべてが大切なのだからな」
「何か僕にできることはないかな? いまはすっかり元気だし、また夜の張り込みでも構わない」
「いや、何もできることはない。ひたすら待つしかないのだ。私たち自身が出かけてしまえば、その間に連絡が入って機会を逃すかもしれない。君は好きにしていいが、私は警戒の持ち場に残る」
「じゃあ、カンバーウェルに寄ってセシル・フォレスター夫人を訪ねてくるよ。昨日頼まれていたんだ」
「セシル・フォレスター夫人に?」とホームズは目を輝かせて言った。
「もちろんモースタン嬢にも、だよ。二人とも事件の進展を知りたがっていたからね」
「だが、あまり多くは語らない方がいい」とホームズは言った。「女というものは、決して完全には信用できないものだ――どんなに立派な女性でもね」
私はこのひどい意見に反論することもせず、「一、二時間で戻るよ」と言った。
「分かった。幸運を祈る。ただ、もし川を渡るなら、トビーを返してきてくれ。もう彼を使う展開もなさそうだからな」
私は雑種犬のトビーを連れて、ピンチン通りの老博物学者の元へ、犬とともに半ソブリンを預けた。カンバーウェルではモースタン嬢が昨夜の冒険でやや疲れていたが、事件の進展に強い関心を示していた。フォレスター夫人もまた好奇心に満ちていた。私は事件の顛末を話したが、もっとも悲惨な部分は省略した。たとえばショールト氏の死については述べたが、その正確な状況や方法には触れなかった。それでも十分驚かせるには足りていた。
「まるで小説みたいだわ!」とフォレスター夫人が叫んだ。「傷ついた乙女、半ミリオンの財宝、黒人食人族、そして一本足の悪党。昔ながらのドラゴンや悪い伯爵の代わりに、これよ」
「救助に駆けつける二人の遍歴の騎士もいるし」とモースタン嬢が、私に明るい視線を送って言い添えた。
「メアリー、あなたの運命はこの捜索の結末に懸かっているのよ。あまり興奮していないみたいだけれど。本当に大金持ちになって、世界を手に入れたようなものじゃない?」
だが、彼女はそうした展望に浮かれる様子など微塵も見せなかった。むしろ誇らしげに頭を振り、関心など無いと言わんばかりであった。そのことが私の心に密かな喜びをもたらした。
「私が気がかりなのはサディアス・ショールトさんのことだけです」と彼女は言った。「ほかのことは大した問題じゃありません。彼はこの事件を通してとても親切で誠実にふるまってくれました。私たちの使命は、あのひどく根拠のない疑いを晴らし、彼の汚名をそそぐことです」
カンバーウェルを出たのはすでに夜で、自宅に着いたころにはすっかり暗くなっていた。友人の椅子のそばには本とパイプが置かれていたが、彼の姿はなかった。メモでも残っていないかと探してみたが、何もなかった。
「シャーロック・ホームズ氏は外出されたのでしょうか」とブラインドを下げにやって来たハドソン夫人に尋ねると、
「いえ、先生、お部屋にこもっておいでですよ。それがですねえ……」と声をひそめて「どうもご健康が心配なんです」
「なぜですか、ハドソン夫人?」
「それが、なんというか、ちょっと異様なんですよ。先生が出てからずっと、階上を行ったり来たり、行ったり来たり、もう足音を聞いているのも疲れるくらいで。それから独り言をぶつぶつ言ったり、鐘が鳴るたびに階段のところに出てきて『何だね、ハドソン夫人?』って。それで今はバタンと自室にこもりましたけど、やっぱり歩き回っている音が聞こえます。病気にでもならなきゃいいんですけど。ちょっと涼薬でも、と申し上げたら恐ろしい形相になさって、私はどうやって部屋を出たものか……」
「ご心配には及びませんよ、ハドソン夫人」と私は答えた。「そういう状態の彼を何度か見ています。なにかちょっとした問題が頭の片隅に引っかかっていて、落ち着かないのでしょう」私は女主人に気を楽にしてもらおうと明るく言ったが、それでも夜通し彼の足音がときおり聞こえ、その鋭利な精神がこの不本意な膠着状態に苛立っているのを思うと、私自身も多少の不安を感じずにはいられなかった。
朝になって彼はやつれた顔色であらわれ、両頬には微かに熱っぽい赤みが差していた。
「無理をしすぎているぞ、ホームズ」と私が言う。「昨夜ずっと歩き回っていたろう」
「寝付けなかった」と彼は答えた。「この忌々しい難題が頭から離れない。他のすべてを乗り越えてきて、こんな些細な障碍で妨げられるとは。人物も舟もすべて把握しているのに、連絡は全く来ない。あらゆるコネを使って調査させているし、利用可能な手段は尽くした。川の両岸もくまなく捜索したが手掛かりはないし、スミス夫人も夫の行方を知らない。やがて奴らが舟を沈めて逃げたと結論付けざるを得なくなりそうだが、それにもいくつか矛盾がある」
「あるいは、スミス夫人に偽の情報を掴まされたのかも」
「いや、それは考えにくい。調べさせたが、確かにああいった特徴の舟が存在する」
「川を遡った可能性は?」
「その可能性も考えて、リッチモンドまで捜索隊を派遣してある。今日中に何も得られなければ、今度は舟ではなく人間の方を直接探すつもりだが、でも何かしら進展があると信じたい」
しかし、その日中にウィギンズからも、その他の情報提供者からも一切知らせはなかった。ノーウッドの惨劇についてはほとんどすべての新聞に記事が載ったが、その論調はサディアス・ショールトにやや冷淡であった。新情報はどこにも見当たらず、ただ翌日に検視が行われるというだけだった。私は夕方カンバーウェルまで歩いて、成功しなかった報告を女性陣に済ませ、帰宅するとホームズは沈み込んだ様子で、ほとんど不機嫌だった。質問にもほとんど応えず、晩は高度な化学分析に没頭していた――それには多くの加熱や蒸留が伴い、ついには私が部屋から逃げ出したくなるほどの悪臭を発した。夜も遅くまで試験管をカチカチ鳴らす音が聞こえ、彼がまだ悪臭まみれの実験に熱中しているのが分かった。
夜明け近く、私ははっとして目覚めた。ベッドのそばに立っている彼がいた。粗末な船乗りの服にピーコート、首には赤いスカーフを巻いていた。
「川へ下るぞ、ワトソン」と彼は言った。「よく考えてみたら、手立ては一つしかないようだ。とにかく試してみる価値はある」
「なら僕も一緒に……」と私が言いかけると、
「いや、君はここにいてくれた方がずっと役に立つ。今日中に何か動きがあった場合に備えてな。あの晩ウィギンズが弱気なことを言っていたが、可能性はゼロじゃない。メモや電報が来たら開封して、君の判断で対処してくれればいい。信頼してもいいか?」
「もちろんだ」
「君がこちらから電報を送るのは難しいかもしれない、私がどこにいるかまだ分からないから。だがうまく行けば、あまり長くはかからないだろう。何らかの知らせは持って帰れるはずだ」
朝食時になっても彼から音沙汰はなかったが、『スタンダード』紙を開くと、事件に関する新しい言及を見つけた。「ノーウッドの殺人事件について――」とあり、「事態は当初考えられていたよりも、いっそう複雑かつ怪奇な様相を呈しつつある。新証拠によれば、サディアス・ショールト氏が関与していた可能性はまったくない。彼と家政婦のバーンストン夫人は昨晩に釈放されている。ただし警察は真犯人への手掛かりを握っており、スコットランドヤードのアセルニー・ジョーンズ氏が例の辣腕で捜査中。近日中にさらなる逮捕者も期待されるだろう」
「これはとりあえず安心だな。ショールト氏はこれで安全だ。だが警察がいう新たな手掛かりとは何だろう、といっても大抵は失敗を煙に巻くときの決まり文句だ」
私は新聞をテーブルに投げたが、そのとき苦情欄の広告に目が留まった。そこにはこうあった。
「紛失――火曜日未明三時ごろ、舟人モルデカイ・スミスとその息子ジムはスミスの波止場より黒地に赤い二本線を引いた蒸気ランチ《オーロラ号》で出発したまま戻らず。オーロラ号およびスミス親子の所在に関する情報を届け出た方には、スミス夫人(スミス波止場またはベイカー街221b)より五ポンド贈呈」
これは明らかにホームズの仕掛けだ。ベイカー街の住所が何よりの証拠であった。独創的なやり口だと思った。これなら逃亡者たちが読んでも、単に行方不明の夫を案じる妻の広告にしか見えないだろう。
長い一日だった。玄関のノックや通り過ぎる足音があるたび、それがホームズの帰還か広告への返答かとそわそわした。本を読もうとしても、心はすぐ奇妙な追跡劇と、私たちが追う異様な悪党コンビへ彷徨う。もしかして、友の推理には致命的な欠陥があるのでは? 自分で空論に酔ってはいないのか? ホームズの明敏な頭脳ですら、こういう時に往々にして奇をてらいすぎた説明――平凡なものを否定して突飛な理屈へ飛ぶ癖が、誤りを生むのではと思わざるを得ない。しかし反対に、私が実際に証拠を見、推論の過程も聞き及んでいる以上、もし仮にホームズの説が間違いでも、真相もまた同様に突飛なものであるに違いないと思わずにはいられなかった。
午後三時、大きな玄関のベル、廊下の威厳ある声――そして、やってきたのはアセルニー・ジョーンズ氏本人だった。だが、その様子はかつてノーウッドで事件を自信たっぷりに仕切ったあの押しの強い現実派の姿とはまったく違っていた。浮かぬ顔で、腰が低く、どこか申し訳なさそうであった。
「やあ、どうも、どうも」と彼は言った。「シャーロック・ホームズ氏は外出中だそうで」
「ええ、何時戻るか分かりませんが、お待ちになってもいいですよ。そこの椅子に座って、葉巻を一本どうですか」
「ありがとうございます、では遠慮なく」と赤いバンダナで顔を拭いながら彼は言った。
「ウイスキー・ソーダはいかがです?」
「では半分だけ。ここのところ随分悩まされましてね。このノーウッド事件で私の持論は覚えておいでですかな?」
「確か、意見を述べられていましたね」
「ええ、でも完全に見直さざるを得なくなりました。ショールト氏をついに網にかけたと思ったら、するりと抜けられた。彼は不動のアリバイを証明できたのです。兄の部屋を出てから誰かしらの目が離れたことがなく、屋根をよじ登ったり天窓を抜けたりは絶対できなかった。非常に難しい事件で、私の職業的名誉もかかっています。助力して下さるなら大変ありがたい」
「誰しも、助けを借りるときはあるものですね」と私は言った。
「あなたのご友人、シャーロック・ホームズ氏は驚嘆すべき人物ですな」と彼はしわがれた声で囁くように続けた。「あれほど捜査に強い男を他に知りません。手法は型破りで、推理に飛翔しがちではありますが、警官になっても相当優秀なオフィサーになったはずです。今朝もちょうど、彼から電報を貰いました。ショールト事件について何か手掛かりを掴んだようです。これです」
彼は電報を取り出して私に手渡した。時刻は正午、ポプラー発。「至急ベーカー街へ。私が戻らなければ待機されたし。ショールト一味の足取り間近。今宵、終幕を共にしたければ参加可」
「素晴らしい。どうやら再び手掛かりを得たようですね」と私が言うと、
「なあんだ、彼も外れたことがあるのですね」とジョーンズが露骨に満足そうに言った。「誰しも時には手を外しますよ。もしかしたらぬか喜びかもしれませんが、警察官としてどんなチャンスも逃してはなりません。――おっと、来客のようですね。さて……」
階段を登る重い足音と、喘息のようなひどい呼吸音。途中で何度か足を止め、苦しげに息を整えていたが、ついに我々の部屋の扉の前にたどり着き、中へ入ってきた。音から想像したとおり、年老いた、船乗り風情の男、くたびれたピーコートに身を包んでいた。背中は曲がり、膝は震え、呼吸は苦しそう。分厚いオークの杖によりかかり、肩を波打たせて空気を吸い込んでいる。顎に色柄のスカーフを巻き、顔はほとんど見えなかったが、濃い眉に覆われた鋭い黒い眼と長い灰色のもみあげが覗いた。その全体の印象は、年老い落ちぶれたが依然として上品な船長といった風情だった。
「どうしましたか?」と私は尋ねた。
男は老齢らしいゆっくりした仕草で周囲を見回した。
「シャーロック・ホームズ氏はここかね?」
「いえ、でも代理として話を伺いますよ。何か伝言ですか?」
「氏本人に直接伝えろと頼まれていてな」
「ですが私は代理です――モルデカイ・スミスの舟の件でしょう?」
「ああ、どこにあるかも、追ってる男たちがどこにいるかも、宝物がどこかも、全部知ってる」
「では話してください、私から彼に伝えます」
「いやいや、当人に言わねばならんのじゃ」と頑固に繰り返す。
「それならお待ちいただくしかありませんね」
「待っとらん、1日も無駄にせん。ホームズ氏がいないなら勝手に調べるがいい。あんたらの顔も気に入らんし、何も言わんぞ」
そう言ってドアの方へよろめいていったが、アセルニー・ジョーンズが前に立ち塞がった。
「待ておじいさん。大事な情報だ、好き勝手に帰しはしない。ホームズが戻るまでここで待ってもらうよ」
老人はドアへ駆け出しそうになったが、ジョーンズの広い背中に阻まれて、抗う無意味さを悟った。
「なんだこの仕打ちは!」と杖で床を叩いた。「紳士に用があって来たのに、見ず知らずの二人に拘束されるとは!」
「ご心配には及びません」と私は言った。「お手待ちいただいた分は、きちんとお支払します。ソファでおかけになってお待ちください。そう長くはなりますまい」
むっつりした様子でソファへ腰を下ろした彼を横目に、ジョーンズと私は葉巻とおしゃべりを再開した。すると突然、ホームズの声が割り込んだ。
「私にも葉巻を一本くれてもいいのでは?」
私たちは同時に飛び上がった。すぐそばの椅子にホームズが、静かな愉快さをたたえて座っていたのだ。
「ホームズ! 君なのか! だが、あの老人は……?」
「これが老人さ」と彼は白髪のかつらを差し出した。「ほら、かつらに髭、眉毛、何もかも。なかなかうまく変装できていたと思うけど、君たちのテストには耐えきれなかったか」
「まったく、ずるい奴だ!」とジョーンズは大笑いし、「役者でもやれば稀に見る名優だよ。みごとな貧民院咳、弱々しい足腰で週10ポンドは請け合いだ。だが目の光は見覚えがあったな。そう簡単に逃げられると思うなよ!」
「一日中その扮装で動いていた」とホームズ。「犯罪者にも顔を覚えられてきてね――この友人が私の事件を発表するようになってから特にさ。だから、人目につかない平凡な変装は重宝なのさ。電報は行ったか?」
「はい、それでここに来ました」
「君の捜査は?」
「成果無し。二人釈放、残りも証拠不足」
「構わん、代わりに二人とらえてやる。ただし、私の指示に従って動いてくれ。公式な功績は譲るが、やり方は私に委ねてくれればいいな」
「喜んで。もし男どもを捕まえられるなら」
「まず高速警察艇――蒸気ランチを19時にウェストミンスター桟橋で手配してほしい」
「簡単だ。いつも一隻はいるはず、念のため電話を入れるが」
「抵抗に備えて屈強な人員二名」
「ボートに2、3人いる。他には?」
「男たちさえ確保すれば、宝も手に入るはずだ。友人ワトソン、財宝箱はまず正当な持ち主のミス・モースタンに届けて開封させてやりたい」
「それは大変嬉しいことだ」
「やや勝手な手続きですが……まあ全体が規格外、見逃しましょう。宝は後日、当局へ」
「もちろんだ。あと一点、ジョナサン・スモール本人の証言を少し聞きたい。事件の詳細の詰めをしたいので、警戒付きでこの部屋でも他所でも構わないが」
「君が首尾よく捕えられれば拒む理由は無い」
「約束だな?」
「いいとも。他には?」
「君が夕食に付き合ってくれることぐらいかな。あと30分で用意できる。牡蠣とツグミ、それに選りすぐりの白ワインもある――ワトソン、家事の腕は分かってないだろう?」
第十章 島民の終焉
夕食は賑やかだった。ホームズがその気になれば、これほどよくしゃべる男もいない。その夜はとくに饒舌で、生気に満ちていた。奇跡劇、中世陶器、ストラディヴァリウスのバイオリン、セイロン島の仏教、未来の軍艦に至るまで話題が目まぐるしく変わったが、いずれも専門家顔負けの論であった。陰鬱だった数日前と打って変わり、冴え渡る機知で私たちを楽しませた。アセルニー・ジョーンズも打ち解けて宴を楽しみ、まさしく「ボン・ヴィヴァン」そのもの。私もまた、事件の終幕が近い喜びに浮き立ち、ホームズの明るさにつられた。夕食中、互いに事件の話題には一切触れなかった。
デザートを下げると、ホームズは時計を見てポートワインを三人分注いだ。「まあ一杯、われわれの小冒険の成功を祈って乾杯だ。さて、そろそろ出発の時間だ。ピストルはあるな、ワトソン?」
「古い軍用拳銃が机にある」
「持参したほうが良い。備えあれば憂いなし。タクシーは六時半に頼んでおいた」
桟橋に着いたのは少し過ぎて七時で、蒸気ランチが我々を待っていた。ホームズはそれを厳しく吟味した。
「警察艇だと分かる印は?」
「ええ、舷側の緑ランプです」
「それを外しなさい」
そうして細工を済ませ、われわれは乗り込み、綱が解かれた。ジョーンズ、ホームズ、私は船尾席に座った。舵の男、機関士、そして前方には屈強な警部二名。
「行き先は?」とジョーンズ。
「タワーへ。ジェイコブソン造船所の向かいで止めてくれ」
この艇はかなりの高速艇らしく、積荷のはしけがまるで止まっているかのように次々と追い抜いていった。ホームズも満足げに、蒸気船を追い越すたびにうなずいていた。
「川の上ではまず負けはしないな」と彼。
「いや、まあ、上には上がいるが《オーロラ号》に勝てる艇はそう多くない」
「我々が捕まえるべきはオーロラ号だ。あれは快速ランチとして有名なんだ。ワトソン、状況を説明しよう。私が細事ひとつで苛立っていたのを思い出すだろう?」
「ああ」
「あれから気分転換に化学実験に没頭した。偉大な政治家が言う通り、仕事の転換が最高の休息だ。水素炭化物の溶解に成功して再びショールト事件について考察した。小僧たちに川上・川下へ派遣したが、該当ランチはどこにも現れない。だが沈めて隠すのも非常手段、それがまったく不可能とも限らないが低学歴のスモールにその手練は無理だろう。ロンドンにしばらく滞在し、ポンディシェリーロッジを常時監視していた証拠もある、なら拠点をすぐ放棄して一気に逃げるよりも、最終逃走ルートを用意しつつ出航まで日数を置くはず、それが賢明な判断だと私は考えた」
「だが出発前に計画したとも考えられるのでは?」
「いや、それでは拠点が危機のとき使えなくなる。第二に注目すべきは、相棒のあまりに異様な風貌だ。多少着飾っても目立つのは確実、事件と関連付けられるリスクも高い。だから夜明け前に出発し、明るくなる前に基地へ戻る必要があった。スミス夫人の話では、出航は三時過ぎ、1時間もすれば十分明るくなり始める頃だ。遠くまで行くのは不自然だ。だからランチは最終脱出用にスミスへ多額報酬を払って預け、宝箱は宿へ急いで持ち帰った。報道の反応や警察の動きを2晩ほど見極めながら、夜陰に乗じてグレーヴズエンドかダウンズ停泊中の船に乗り込む、それが既定路線だろう」
「だがランチは? 宿に持ち帰れるものではない」
「その通り。だがランチを桟橋か波止場に放置すれば、追跡されたとき足が着いてしまう。ではどうするか。私が小悪党なら船大工や修理屋に、舵の改造など取り付けて預ける。それで物理的にも隠せるうえ、出したいときは数時間で出せるだろう」
「たしかに合理的だ」
「こうした素朴な策ほど盲点になりやすい。私は即行動した。船乗り扮装で片っ端から工場を周った。15軒は無駄足、16件目のジェイコブソンで、《オーロラ号》が2日前に一本足の男に預けられたと知った。理由は舵の微修理、だが『舵に異常はない、あそこに赤いラインの船がある』と工場長。――そのとき、モルデカイ・スミスが泥酔して現れた。名乗る声で本人と分かった。『今夜8時に使うぞ、今夜8時ぴったりだ、上客だから遅刻は許されない』どうやら相当大枚を握らされている。私は尾行したが酒場に沈没したので、少年を1人張り番に残した。出航時には岸辺にハンカチを振るように指示してある。私たちは本流から見張り、必ずや犯人も財宝も一網打尽にできるはず」
「たとえ違っていても見事な段取りだ」とジョーンズ。「だが私ならジェイコブソンの造船所で待ち伏せ逮捕するかな」
「それでは永遠に出航しません。スモールは用心深い、先遣隊を出して疑わしければ隠れ続けるだけでしょう」
「だがスミスに張り付けば宿の隠れ家を突き止められるのでは?」と私。
「その場合、まる一日無駄になる。スミス自身は住所も知らされていない可能性が高い。報酬と酒さえあれば余計な詮索もしないだろう。全手法の中でこれが最善と判断したのさ」
こう語り合いながらも、我々の舟は次々にテムズ川の橋をくぐり抜けていった。シティにさしかかるころ、セントポール大聖堂の尖塔が夕陽に金色に輝いているのが見えた。タワーに着いたころには宵の口に近かった。
「あれがジェイコブソンの造船所だ」とホームズがサリー岸の林立するマストを指差した。「この明かり船団の陰で上下しながら近づこう」彼は双眼鏡を取り出し岸辺をしばらく眺めた。「見張りの少年は持ち場にいるが、ハンカチの合図はまだだ」
「少し下流に出て様子をうかがいながら待った方が」とジョーンズは提案した。今や警官も機関士も皆が高揚していた。
「憶測で動くべきではない」とホームズ。「奴らが下流へ逃げる可能性は高いが、確証はない。この位置なら造船所の出入り口も見えるし、向こうからはこちらが見えまい。今夜は快晴、十分な明かりもある。ここでじっと様子を見よう。あちらのガス灯の下には、仕事終わりの連中がどっと群れているぞ」
「造船所帰りの奴らさ。どれも薄汚い連中だが、誰にも不滅の魂が備わっているものだな。一見しただけでは分からんものだ」
「人は魂を隠した動物とも言われている」と私。
「ウィンウッド・リードがそのことを詳しく論じている」とホームズ。「個人としてみれば不可解な人間も、群衆になれば算術的確率に従う。各人がどうするかは分からぬが、1000人中どれだけ何をするかは正確に予測できる。個々は千差万別、しかし割合は一定。不思議な話だが、統計とはそういうものだ――あれ、白い布の動きが見えたぞ」
「ほんとだ、君の少年だ」と私。「あそこに!」
「そして《オーロラ号》が出る、しかも猛スピードだ! 全速前進! あの黄色い灯のランチを追え。ちくしょう、万一逃げられたら一生自分を許せん!」
彼女は誰にも見られずに中庭の入口をすり抜け、二つ三つの小さな船の後ろを通ったので、私たちが気づいたときにはすでにかなり速度を上げていた。今や彼女は岸近くを川下へと猛スピードで駆けていた。アセルニー・ジョーンズは真剣な面持ちで彼女を見やり、首を振った。
「すごい速さだ」と彼は言った。「追いつけるかどうか疑わしいな」
「どうしても追いつかなければならない!」と、ホームズは歯の間から絞り出すように叫んだ。「火夫たち、もっと石炭を! 出せるだけの力を全部使え! 船を焼き尽くしてもかまわん、必ず奴らを捕まえるぞ!」
私たちは全力で彼女を追っていた。炉はうなり、強力な機関が金属の心臓のようにビュンビュンと音を立てていた。その鋭く急な船首が川面を切り裂き、波を左右にわけて進む。エンジンの鼓動ごとに、私たちの船は生き物のように弾んで身を震わせた。船首に掲げた大きな黄色いランタンが前方に長く揺れる光の漏斗を投げかける。前方の水面に黒いかたまり――それがオーロラ号であり、その後ろに巻き上がる白い泡が、彼女の速度を物語っていた。荷船や蒸気船、商船の間を縫うように、時に後ろにつき、時に回り込んで追いすがる。暗闇から船乗りたちの声が飛んできてもオーロラ号は轟然と進み、私たちもその航跡を逃さず追い続けた。
「もっとだ、みんな、もっと石炭を!」ホームズが機関室を覗き込み叫ぶ。下から赤々とした光が彼の鋭い顔を照らしている。「蒸気を限界まで上げろ!」
「少しずつ差を詰めているようだな」とジョーンズがオーロラ号から目を離さずに言った。
「間違いなくそうだ」と私は応じた。「あと数分で追いつくぞ」
ところが、運命の悪戯か、ちょうどその時、三隻の荷船を曳いたタグボートが私たちとオーロラ号の間に割り込んできた。操舵を思いきり切ってようやく衝突を避けることができたが、回り込んで進路を戻した時にはオーロラ号はすでに200ヤード以上リードしていた。それでもまだ姿を見失うことはなく、もやに包まれた薄明かりもやがて、きらきらと星が輝く夜へと変わりつつあった。ボイラーは限界まで圧力を上げ、華奢な船体が激しい振動ときしみを立てながら、私たちは猛スピードで進んだ。プールを突っ切り、西インド・ドックを過ぎ、長いデプトフォード・リーチを下って犬の島を回り込んで再び追いすがる。ぼんやりとした黒い影が、はっきりと優美なオーロラ号へと姿を変える。ジョーンズが探照灯を向けると、甲板上の人影がはっきり見えた。船尾にはひとり男が座っており、太腿の間には黒いものを抱え、それに身をかがめている。その脇にはニューファンドランド犬のような黒い塊が横たわる。少年が舵を取り、煉瓦色の炉の光を背に、私は裸の上半身になった老スミスが必死で石炭をくべているのを見た。最初のうちは私たちが本当に追っているか疑われたかもしれないが、彼らのとる進路ごとにきちんと追随してくるので、もはや疑いようはなかった。グリニッジでは約300歩、ブラックウォールでは250歩ほど後ろにつけていた。私はこれまで幾多の国でいろいろな獲物を追いかけてきたが、このテムズ川を駆ける狂気の追跡ほど心を沸き立たせられたことはなかった。着実に、ヤードごとに差を縮めていく。夜の静寂の中、相手の機関の息遣いときしむ音さえ聞こえてくる。船尾の男はなおも甲板にかがみ、何やら作業をする手が時折止まっては、一瞥で私たちとの距離を測っていた。私たちはついにぐんと近づいた。ジョーンズが大声で停止を命じる。両船は激しい速度のまま、わずか四隻分ほどしか離れていなかった。川幅のある直線で、片側はバーキング湿地、もう片側は陰鬱なプラムステッド湿原である。私たちの呼びかけに、船尾の男が甲板から跳ね上がり、両拳を振り上げて罵声を浴びせてきた。甲高くかすれた声で怒鳴るその男は、がっしりした体格で、両脚を踏ん張って立つ姿を見れば、右腿から下は木の義足であることがはっきりわかった。その怒号に応じて、甲板の上の塊が動き、やがてそれは体を伸ばした。小柄な黒人――私が今まで目にした中で最も小さく、巨大に歪んだ頭と、もじゃもじゃに乱れた髪を持つ男だった。ホームズはすでにリボルバーを引き抜いており、私もその獰猛で異形の姿を見て素早く銃を抜いた。彼は暗いオルスターかブランケットのようなものに身を包み、顔だけを覗かせていたが、その顔だけで夜眠れなくなるほどだった。これほどまでに獰猛で残忍な相を刻まれた顔は見たことがない。ギラギラと燃える小さな目、厚い唇は剥き出し、牙のような歯で私たちに半ば獣のように吼えかかる。
「手を上げたら撃て」とホームズは静かに言った。もはや一隻分の距離しかなく、ほとんど獲物に手が届くところまで来ていた。暗いランタンの光の下、両脚を広げて叫ぶ白人と、忌まわしい顔つきで歯を剥き出し私たちを睨む呪われた小男の姿が今も目に浮かぶ。
これほどはっきり観察できたのは幸運だった。こちらが見ている間に、彼は覆いの下から学校の定規のような短い丸い木片を取り出し、口元に当てた。私たちのピストルが同時に響く。彼はぐるりと回転し、両腕を振り上げて、むせぶような咳をひとつ漏らして流れに横向きに倒れ込んだ。濁流の白い波の中に、その毒々しく威嚇する瞳が一瞬だけ見えた。同時に、義足の男が舵を目一杯切り、船は南岸に向かって突進、私たちは船尾すれすれをすり抜ける。すぐさま回頭するも、あちらはすでに岸近くまで迫っている。そこは月明かりに一面の湿原が広がり、よどんだ池と朽ちた植物の茂みが点在する荒れ果てた場所だった。オーロラ号は鈍い音ともに泥に乗り上げ、船首が空を向き、船尾が水面にぎりぎり付いていた。逃亡者は飛び降りたが、義足がたちまち泥にすっぽり埋まり、どうあがいても前にも後ろにも一歩も進めない。彼は無力な怒りで叫び、健康な足で必死に泥を蹴るが、苦闘するほど杭状の義足はより深く食い込んでいくだけだった。私たちが横付けした時にはあまりにしっかり固定されていたので、ロープを肩にかけてようやく引きずり上げ、巨大な悪魚でも釣り上げたかのように私たちの船に引き入れた。父子のスミスは不機嫌にオーロラ号にうずくまっていたが、命じれば素直に乗船した。オーロラ号も引き上げ、私たちの船尾につないだ。甲板にはインド製の分厚い鉄の箱が一つ置いてある。間違いなくショールト家の呪われた財宝が入っていた箱だ。鍵はなかったが、かなりの重さで、私たちは細心の注意を払って自分たちの船室へと運び込んだ。川をゆっくり上りながら周囲をサーチライトで探ったが、インド人の影はどこにも見当たらなかった。テムズ川の泥の底深く、あの異国の訪問者の遺骨が静かに沈むのみである。
「ほら」とホームズが木のハッチを指差した。「あと一歩、発砲が遅れていたら危なかった」確かに私たちが立っていたすぐ背後に、あの殺人ダーツが一本突き刺さっていた。私たちが撃った瞬間に、彼の吹き矢がすり抜けていたのだ。ホームズは肩をすくめて平然とそれを眺めていたが、私としては、あの夜、死の恐怖がすれすれをかすめていったことに、思わず身震いせずにはいられなかった。
第十一章 偉大なるアグラの財宝
捕えられた男は、彼が長年追い求め、あらゆることをなしてきたあの鉄箱の向かいに座っていた。彼は日焼けで色黒、目には無謀さが宿り、マホガニー色の老成した顔には厳しい野外生活の証がくっきりと刻まれていた。顎は特に突出しており、一度決めたことはそう簡単に曲げない男だとわかる。年齢は五十前後だろうか。黒く縮れた髪には灰色が目立ち始めている。寛いだ表情の時は決して不快な顔立ちではなかったが、重たい眉と強い顎が怒りに動かされると恐ろしい形相になることは、この数日の間に私もよく知っていた。今は手錠を膝に乗せ、頭を垂れたまま、鋭くきらめく目で己の悪事の元となった箱を見つめていた。私は彼の硬く抑えた表情に怒りよりもむしろ悲しみを感じた。ふと彼が私を見上げ、どこかユーモアを帯びたきらりとした光を瞳に宿す。
「さて、ジョナサン・スモール」ホームズが葉巻に火をつけながら言った。「こんな結果になってしまい残念だ」
「私もです、旦那」誠実な口調で彼は答える。「この仕事で絞首台送りにはなりたくないですね。誓って申し上げますが、ショールト氏には指一本触れていません。あいつに毒矢を放ったのは、あのちっぽけな悪魔トンガです。私は手を汚していませんよ、旦那。血縁者でもないのに、あれほど悔しいことはありません。私はロープの端であの悪党を打ちすえましたけど、もう済んだことはどうしようもなかった。」
「葉巻をどうぞ」とホームズ。「ずぶ濡れだから、私のフラスコもお使いなさい。あんな小柄で非力な黒人が、あなたがロープを登っている間、どうしてショールト氏を押さえつけていられると?」
「旦那はまるで現場にいたみたいに詳しいですね。本当は、部屋が空いていることを期待していました。家の習慣もだいたい把握していて、その時間はショールト氏がいつも夕食に下りる頃だったんですよ。隠し事はしません。一番の弁明は、ただ事実を語ることだけです。もし相手があの老少佐だったら、迷わずやっつけていたでしょうね。この葉巻を吸うような気持ちでナイフを突き立てても、何とも思わなかったでしょう。でも相手がこの若いショールト氏だったのは、まったく運が悪すぎました。彼にはまったく恨みがなかったのに、こんな目に遭うなんて。」
「君はスコットランドヤードのアセルニー・ジョーンズ警部の拘束下にある。彼の判断で君を私の部屋へ連れていき、そこで事件の真相を聞かせてもらう。すべてを正直に話し給え。そうしてくれれば、君のために力になれるかもしれない。毒の作用が極めて早くて、君が部屋に入った時点ですでに被害者は亡くなっていたことを立証できると思う。」
「まさにそうでした、旦那。窓から入ったとき、奴が首を傾げたままニヤリと笑っていたのを見た時は、背筋が凍りましたよ。トンガが逃げ出さなければ、半分殺していたかもしれません。あいつはその時棍棒も矢も置き忘れていったんです。そいつがあなた方が私たちを追跡するきっかけになったんでしょうが、どうやって突き止めたのか……私には皆目見当がつきません。でも私はあなたを恨みませんよ。だが不思議なもんですね」と彼は苦笑しながら付け加えた。「五十万にもなる金を手にする権利があった私が、人生の半分をアンダマンで防波堤作りに費やし、残り半分はダートムーア山中で溝掘りをする羽目になるとは。あの商人アフメットの顔を初めて見た日、そしてアグラの財宝に関わったあの日は、私の運命にとって最悪の日だった。アグラ財宝を持った者に、幸せが訪れたことは一度もありません。あいつには死、ショールト少佐には恐怖と罪悪感、私には一生の奴隷労働をもたらしただけです。」
その時、アセルニー・ジョーンズ警部がごつい顔と大きな体を小さな船室に押し込んできた。「まったく、家族会議ってところだな」彼が言う。「フラスコを一杯もらおう、ホームズ。いや、皆、互いに祝杯を上げてもよさそうだ。あちらを生きたまま捕まえられなかったのが残念だが、選択の余地はなかった。ホームズ、君も今回ばかりはギリギリだったと認めるだろう。追いつくのがやっとだったな」
「終わりよければすべてよしだ」とホームズ。「だが正直、オーロラ号があれほど速いとは思わなかった」
「スミスいわく、川で一、二を争う高速ランチらしい。もう一人機関士がついていたら、絶対追いつけなかったとまで言っている。ノーウッドの件は本当に何も知らなかったと誓っていたよ」
「確かに何も知らんかったですよ」と囚人が叫ぶ。「私はただ、速いと聞いたそのランチを選んだんだ。何も話さず、報酬はたっぷり払う、無事にグレイブズエンド沖のエスメラルダ号まで運んでくれたら、さらに大金だと言っていただけです」
「何も悪くないなら、こちらも何の害も及ぼさない。犯人逮捕は素早いが、裁きはそう性急ではないからな」捕縛の成果で自信満々になったジョーンズが、いかにも偉そうな口ぶりになってきているのが、ホームズの微かな笑いからもうかがえた。
「まもなくヴォクソール橋に着く。そこでワトソン博士と宝箱を降ろそうと思う。これは本来なら大きな責任を負うやり方で、少々違法ではあるが、約束は約束だから仕方ない。ただし、貴重品なので必ず警部補を同行させる。馬車で運ぶのだな?」
「ああ、そうするよ」
「まず中身を確かめられぬのが残念だ。鍵がないので、こじ開けるしかないな。鍵はどこだ?」
「川底です」とスモールは短く答えた。
「ふむ! 余計な手間をかけてくれる。すでに十分厄介な思いをさせられたがな。ともあれ博士、くれぐれも注意してくれたまえ。中身とともにベイカー街の部屋へ戻ってくれ。我々はそこで駅へ向かうところで待っている」
こうして私は重い鉄箱と陽気そうな警部補をお供にヴォクソールで下船した。馬車で十五分ほど乗り、セシル・フォレスター夫人宅に到着。遅い時間なので使用人は驚いた様子だった。夫人は外出中で、夜遅くまで帰らぬとのこと。ただ、モースタン嬢は居間にいるというので、重い箱を持って居間に入った。警部補は親切にも馬車で私を待ってくれた。
彼女は開いた窓際に座り、薄い白い衣をまとい、首と腰にわずかに朱色の飾りがあった。籐椅子にもたれて深い悲しみを湛えた美しく落ち着いた顔に、ランプの柔らかな光が降りそそぎ、その豊かな髪に鈍い金属的な輝きを与えていた。ひとつ白い腕が無造作に椅子から垂れている。その姿はすべて、没入した憂いを物語っていた。私が足音を立てると、彼女はすっと立ち上がり、驚きと喜びの紅潮が頬を染めた。
「馬車の音が聞こえたわ」と彼女。「きっとフォレスター夫人が早くお帰りになったのだと思っていたけど、あなたが来るなんて夢にも思いませんでした。何か知らせが?」
「知らせ以上のものを持ってきました」と私は箱をテーブルに置き、明るく大げさに振舞った――もちろん心の中は重かったのだが。「世界中のどんなニュースよりも価値あるものを持ってきたんです。あなたに財産を持ってきたのですよ」
彼女は鉄の箱を見やった。「では、それが宝なのですね?」と冷静に訊いた。
「そう、これがアグラの財宝です。半分はあなたのもの、半分はサディアス・ショールトのもの。二人で分ければ、それぞれ二十万ポンド。考えてごらんなさい! 一万ポンドの年金。イギリスでも屈指の富裕な若い女性になりますよ。素晴らしいでしょう?」
私は少し演技が過ぎたらしく、彼女にはその言葉にどこかうわついた響きが感じられたようで、眉をわずかに上げ、不思議そうにこちらを見た。
「もしそれを手に入れることができたなら、あなたの御恩よ」と彼女。
「いや、私じゃない。これはすべて私の友人、シャーロック・ホームズのおかげです。私にはあれほどの分析力もないし、どんなに頑張っても手がかりをたどれなかったでしょう。事実、最後の瞬間まで失いかけたのです」
「どうか、座って詳しいお話を聞かせて」と彼女は言った。
私は、前回彼女と会ってから今日までに起こったことを簡潔に語った。ホームズの新しい追跡方法、オーロラ号の発見、アセルニー・ジョーンズの登場、夕べの遠征とテムズ川を下る激しい追走劇。彼女は夢中で身を乗り出し、きらきらと目を輝かせて聞き入った。あやうく私たちを貫きかけた吹き矢の場面にさしかかったとき、顔色が青ざめ、私は慌てて水を注いだ。
「大丈夫です」と彼女は言い、「もう平気。私が友人を比類なき危険に巻き込んでしまったのだと聞いて、思わずショックを受けてしまいました」
「もう全て終わったことです」と私は答えた。「もう怖いことはありません。これ以上陰惨な話はやめて、明るい話にしましょう。宝がここにあります。これほど明るい話はないでしょう。あなたに最初に見てもらおうと、私に運搬の許可が下りたのです」
「もっとも私にとって興味深いわ」と彼女。しかし声には熱意はなかった。これほど苦労と犠牲を重ねて手に入れた宝に興味を持たないのは無作法に思われる……たぶんそんな考えが脳裏をよぎったのだろう。
「なんてきれいな箱でしょう」と彼女は身をかがめて言った。「これはインドの工芸品?」
「はい、ベナレスの金工細工です」
「とても重いわ!」彼女は持ち上げようとして言った。「箱だけでもかなり価値がありそう。――鍵は?」
「スモールがテムズ川に投げ捨てました」と私は答えた。「フォレスター夫人のお宅から火かき棒をお借りします」正面には座った仏像を象った太くて幅広い金具がついていた。その下に火かき棒の先を差し込み、てこの原理で力を込める。はぜる音と共に錠前が飛びはねた。指を震わせながら蓋を開ける。私たちは驚きに立ち尽くした。箱の中は、空っぽだった!
これでは重いはずだ。鉄の厚みは周囲で二分の一インチ近くある。重厚で精巧、いかにも高価なものを運ぶための箱。だが、中に金銀や宝石のかけらすら残っていない。完全に、徹底的に空だった。
「財宝は失われたのね」とモースタン嬢は穏やかに言った。
私はその言葉の本当の意味をかみしめながら、心に大きな影がさっと払い去られていくのを感じた。アグラの財宝の重みがこれほどまでに私を圧していたとは、失われて初めて気がついた。自分が利己的で、不忠実で、間違っているとは思いながらも、それでも感じられるのは黄金の壁が二人の間から消えたことだけだった。「感謝します、神よ!」私は心の底からそう口にした。
彼女は突然、探るような笑みを浮かべ私を見つめた。「どうしてそんなことを?」
「君がまた、私の手の届くところにいるからだ」と私は彼女の手を取った。彼女はその手を引っ込めなかった。「私が君を愛しているからだ、メアリー。男が女を愛したこと以上に深く。あの宝、富があったことで、私はこの想いを口にすることができなかった。でも、今やそれは消え去った。だから言うのだ、――『ありがとう、神よ』」
「では私も、『ありがとう、神よ』と」と彼女はささやいた。私は彼女をそっと引き寄せた。誰かは財宝を失ったかもしれないが、私は今夜、かけがえない宝を得ることができたのだ。
第十二章 ジョナサン・スモールの奇妙な物語
あの警部補はまことに忍耐強い男で、私が再び馬車に戻った時にはかなり時間が経っていた。しかし、空っぽの箱を見せると、彼の表情は曇った。
「これで報奨金もパーだ!」と彼はぼんやりつぶやいた。「金にならなければ、報酬も下りん。今夜の働きは、もし中身があったら私もサム・ブラウンも十ポンドずつはもらえただろうに」
「ショールトさんは裕福な人です。財宝の有無にかかわらず、きっと報いたくれるでしょう」
それでも警部補は首を振り、「こりゃ厄介なことになった」と嘆いた。「アセルニー・ジョーンズ警部も同じ気持ちでしょうよ」
その予感は的中し、私がベイカー街に着いて空箱を見せると、探偵はまったく面白くなさそうな顔で迎えた。彼らホームズと囚人とともに、途中の警察署に立ち寄ったそうで、ちょうど到着したところだった。ホームズはいつもの気だるい様子で肘掛け椅子によりかかり、スモールは義足を健脚の上に組み、無表情に座っていた。私が空箱を示すと、彼は椅子にもたれ、声を上げて笑い出した。
「小癪な真似を!」とアセルニー・ジョーンズ警部は激怒した。
「ええ、誰にも触れさせやしませんよ」と彼は誇らしげに叫ぶ。「あれは俺たち四人の宝だ。もし俺に手に入れられないなら、誰にも渡さないさ。この宝に正当な権利を持つのは、アンダマンの監獄バラックにいる三人の仲間と自分だけだ、今それがよく分かった。他の誰にも使わせる気はなかったし、自分ももう使えない。最初から、俺は自分だけじゃなく仲間たちのためにも動いてきた。『四人のサイン』は俺たちの絆なんだ。奴らが今ここにいたら、きっと俺がやったこと――つまり、箱ごとよりも宝だけ川へ捨ててショールト家やモースタン家の誰にも渡さなかったこと――それで良かったんだと言うだろう。あれは彼らを裕福にするためじゃない、アフメットを殺したのは金のためじゃなかった。宝は鍵と並び、トンガも一緒に、どこか川底さ。追いつかれると悟った時、全部確実な場所に捨ててきた。ルピーは一枚だって手に入らないよ」
「ごまかすな、スモール」とジョーンズ警部。「その気なら、箱ごと川に投げ捨てた方が簡単だったろう」
「俺は簡単だったさ、でもあんたらには回収も容易だったろ。俺を追い詰めたくらい賢い奴らなら、鉄箱を川底から拾うくらい朝飯前さ。でも宝石が五マイル四方にばらばらになってしまえば、ちょっと骨が折れるだろう。俺だってつらかったよ、あの時は半ば狂っていたから。しかしもう終わったことだ。人生には浮き沈みがある。こぼれたミルクを嘆いても始まらん」
「これは重大な妨害行為だぞ、スモール」と警部は言う。「素直に法に協力していたなら、裁判でもずっと有利だったはずだ」
「法! どんな法だ!」と元囚人は叫んだ。「この金が誰の物だというんだ? 俺たちのじゃなかったら誰のだ? 俺がどんな思いでこの宝を得ようとしたか分かってるのか! 二十年もの間、熱病の沼地で働き詰め、夜は汚い監獄小屋で鎖につながれ、蚊に刺されて悪寒に苦しみ、黒い面の警官どもにいじめ抜かれる。これがアグラの財宝を得るために支払った代償だ。それなのにその報いを他人が享受するのを黙って見ていろだと? むしろ二十回首を吊る方がましだし、トンガの矢に打たれた方がましだ。自分は牢の中で朽ちていくのに、他の誰かがその金で宮殿でのうのうと暮らすなんて耐えられない!」スモールは感情を爆発させ、目は燃え、手錠は激情の手振りに応じてぶつかり合った。その激しい怒りと哀しみを見て、ショールト少佐があれほど恐怖にとらわれていたのも無理はないと私は実感した。
「だが我々はそんな経緯は何も知らない」とホームズは静かに言った。「君の話を聞かなければ、正義といってもどちらに味方すべきか分からないのだ」
「旦那、あなたはすごく公正な方だ。手錠をかけられたのはあなたのせいだが、何の恨みもない。正直に話せと言われれば、すべて包み隠さず語ろう。これから話すことは神に誓って真実さ。――ありがとう、そのグラスをそばに置いてくれ、渇いたら自分で飲むから。
俺はウスターシャー生まれ、パーショアの近くだ。今でもスモールという名の親類ならたくさんいるはずだ。あそこの田舎にちょっと帰ってみようかと思うこともあるが、俺は家の名誉にならなかった口だし、歓迎されるとも思えない。家族はみな堅実な、小作農で評判もよかったが、俺だけはいつも放浪癖が抜けなかった。だが十八の頃に女のことでしくじって、面倒から逃れるためにクイーンの志願兵になり、第3バフ連隊に入隊してすぐにインド行きとなった。
兵士稼業は長く続かなかった。銃の操作を覚えて間もなく、愚かにもガンジス川で泳いだのが運の尽き。たまたま連隊のホルダー軍曹も一緒の水浴びで、奴は軍隊一の泳ぎ手だった。俺が川の半ばにさしかかったところで、ワニにやられたのさ。右脚を膝上でバッサリ食いちぎられて、外科医が切断したのと同じくらい見事なもんさ。ショックと出血で気を失い、危うく溺れ死ぬところを、ホルダー軍曹が引き上げて岸へ運んでくれた。入院五か月、やっと義足つけて歩けるまでになったが、そのまま兵役免除、まともな仕事に就くこともできなくなってしまった。
言うまでもなく、当時の俺はどん底だった。使い物にならない身体で、まだ二十にならないうちにこのざまだ。でも、その不幸が災い転じて福となった。エイベル・ホワイトという男が、インディゴ(藍)農場の監督を探していた。うちの大佐の知り合いで、事故以来俺に目をかけてくれていた。それで、大佐が大いに推薦してくれ、仕事の大部分が馬で回ることなので、膝さえあれば鞍を把えて馬に乗るのは問題なく引き受けられた。日々監督として農場を回り、働きぶりに目を光らせ、さぼり者を報告する――それが仕事だった。給料も悪くなく、住居も快適で、インディゴ監督として余生を送ってもいいとまで思っていた。ホワイト氏も親切な男で、よく俺の小屋に来ては一服していった。白人同士は、この国よりも向こうの方が互いに親しみ合うもんだ。
だが、運は長く続かない。まったく何の前触れもなく、大反乱が勃発した。一か月前までスリーやケントのように平和だったインドが、一夜で二十万もの黒い悪魔に占拠されて、地獄そのものになった。大体のことは百もご承知だろうが、俺はただ目にしたことしか分からん。俺のいた農場はムトラという町、北西州との国境に近い。夜な夜な空は真っ赤に燃えあがる。避難する欧州人たちが、女ども子供ども連れてアグラの駐屯地まで通っていった。ホワイト氏は頑固な人物で、騒ぎは大したことはない、すぐ終わるとタカをくくっていた。ベランダでウィスキー・ペグや葉巻をふかしながら、国中が炎上するのを眺めていたんだ。もちろん俺もダウソン夫妻も、共に彼を支えるしかなかった。だが或る夕方、俺は遠くの農場から帰る途中で、道の谷底に何かがうずくまっているのを見つけた。様子を見に馬を下りると、そこにはダウソン夫人がズタズタにされ、半分はジャッカルや野犬に食い荒らされていた。もう少し先にはダウソン本人が顔を下に絶命し、使い果たしたリボルバーと、撃ち倒したセポイ兵が四人重なり合って倒れていた。狼狽して進退を迷ったが、その時、ホワイト氏のバンガローから煙が上がり、炎が屋根を突き抜けているのが見えた。もう助けは無理と判断し、ただ自分の命を守るしかなかった。茅を越え、夜遅くアグラの城にたどり着いた。
だがアグラも大して安全じゃなかった。国中が蜂の巣を突いたような大騒動。どこもかしこも、数百対何百万の戦いだった。しかも敵は我々が教育し、鍛えてきた自軍兵だ。アグラには第3ベンガル歩兵、シク兵、騎兵二隊、砲兵隊、事務員や商人の義勇軍――俺も義足ながら加わった。七月はじめ、シャグンジで反乱軍と戦い、最初は耐えたが、弾薬切れで市中へ退却。
地図で見れば分かるが、この地はまさに最前線。ラックナウは東へ百マイル強、カーンプルは南へ同じくらい。四方八方、蹂躙と虐殺と暴虐ばかり。
アグラの城はとにかく巨大で、近代部分には我々と家族、備蓄すべてが入ってまだ余る。しかし広大な旧市街は誰も近づかず、サソリやムカデの棲み処。巨大な空き広間、曲がりくねった廊下が迷路のように続き、滅多に誰も踏み込まなかったが、時折探検しに行く一団もあったほどだ。
「川は古い砦の正面を流れており、これが砦を守っている。しかし側面や背後にはたくさんの出入り口があって、当然ながら、駐在部隊が実際に占拠している区域と同じく、古い区域でも見張りをつけねばならなかった。我々は人数が足りず、砦の各隅を守り、大砲を扱うのが精一杯だった。したがって、数多くある出入口のすべてに強い守りを配置するのは到底不可能だった。そこで中央に衛兵詰所を設け、各門には白人一人と現地人二、三人を割り当てて、その警護に当たらせた。俺は、建物の南西側にある小さく孤立した扉の夜間警備を受け持つよう任じられた。配下にはシク教徒の騎兵二人――名前はマホメット・シンとアブダラ・カーン。もし何かあれば、マスケット銃を撃って合図するようにとの指示を受けていた。そうすれば、中央詰所からすぐ援軍が駆けつけてくれるというわけだ。だが、詰所はここから二百歩も離れており、その間には通路や廊下が迷路のように入り組んでいたので、実際に襲撃があった場合、間に合うのかどうか大いに疑問だった。
さて、生まれたての新兵として、しかも足に不自由がある身でこの小隊長を任されたことは、正直ちょっと誇らしかった。二晩、パンジャーブ兵と共に見張りを続けた。彼らは背が高く、いかにも獰猛そうな連中で、かつてチリアンワラで我々と戦った老練な兵士だった。英語もそこそこ話せるが、あまり多くを語ってはくれなかった。二人は夜通し、自分たちの奇妙なシク語でひたすらしゃべり合っていた。俺は門の外に立ち、広い曲がりくねった川や、大都市のきらめく灯りを眺めて過ごした。ドラムの太鼓、トムトムの音、反乱軍の阿鼻叫喚――彼らはアヘンやバングで酔いしれており、夜通し対岸の連中がいかに危険な存在か、ひしひしと感じさせられた。二時間おきに夜間勤務の将校が各詰所を巡回して、無事を確かめて回った。
三日目の夜は、闇が深く、汚れたような霧雨が降っていた。こんな天気の中、門に立ち続けるのは憂鬱な仕事で、俺は何度もシク兵に話しかけようとしたが、あまり成果はなかった。午前二時、巡回が通り過ぎたときだけが、一瞬夜の単調な緊張がほぐれるひとときだった。仲間が話に乗ってこないとわかると、俺はパイプを取り出し、マスケット銃を脇に置いてマッチで火をつけようとした。その瞬間、二人のシク兵が俺に飛びかかった。片方は俺の銃を奪い、頭に狙いをつけ、もう一人は太いナイフを喉元に押し当て、動いたらすぐにでも刺すと脅した。
最初は、こいつらが反乱軍と裏で通じていて、いよいよ襲撃が始まるのかと思った。もしこの門がセポイの手に落ちれば、砦は陥落し、女や子供はカーンプールのように虐殺されるに違いなかった。皆さんは俺が自分の身の弁明ばかりしていると思うかもしれないが、俺はそのとき本当に死を覚悟した。ナイフの切っ先を感じつつも、命がけでも喉から叫び声を上げ、中央詰所に警告しようと思った。だが、押さえつけていた男はこちらの考えを読んだらしく、身構えた俺にそっとささやいた。「騒ぐな、サーヒブ。砦は安全だ。この川のこちら側に反乱軍の犬どもはいない」その言葉には真実味があったので、もし大声でも出そうものなら、その場で殺されると男の黒い目を見て悟った。だから黙って、この連中が何を望んでいるのか見極めることにした。
「聞け、サーヒブ」と、より大柄で荒々しいほう、アブダラ・カーンが言った。「今ここで俺たちに協力するか、永遠に黙らされるかだ。これはためらうには重大すぎる話だ。キリスト教徒の十字架にかけて誓うなら心の底から俺たちの仲間だ。さもなくば今夜お前の死体を溝に放り込んで、俺たちは反乱軍の仲間に加わるまでだ。中間はない。死か生か、三分やるから決めろ。もうすぐ巡回が来る、それまでに片付けねばならん」
「どうして決断できる? 何を望むのかさえ聞いていない。ただ、砦を危険に晒すことなら絶対に加担はしない。ナイフを突き立てるなり好きにしろ」
「砦には何も関係ない」と彼は言った。「お前の同胞たちがこの地に来る理由、それと同じことをしてほしいだけだ。金持ちになれと言っている。今夜仲間に入るなら、裸のナイフにかけて、シク三重の誓いにかけて、戦利品の四分の一を平等に分けると誓う。これ以上公平な条件はない」
「だが、その財宝とは何だ?」と俺は尋ねた。「金持ちになれる話なら俺も悪い気はしない。どうすればいい?」
「では誓え」と彼は言った。「父の骨に、母の名誉に、お前の信仰の十字架にかけて、今この場でも後になっても俺たちを裏切らないと」
「砦を危険に晒さない限り、誓う」
「よし。では俺たちも四人で戦利品の四分の一ずつ分け合うと誓おう」
「三人しかいないはずだが」
「いや、ドースト・アクバルにも分け前がある。少しの間に経緯を話そう。マホメット・シン、お前は門で見張り、奴らが来たら知らせろ。こういうことだサーヒブ、誓いの重みを知る異国人なら俺たちも信じられる。もしお前がヒンドゥーだったら、いくら偽の神に誓っても、血祭りにあげて川に流していただろう。しかしシクはイギリス人を知っているし、イギリス人もシクを知っている。よく聞け。
「北方地方に小国ながら財産家のラジャーがいる。代々受け継いだ財産に加え、自身もかなりの量を貯め込んでいる。気の小さい男で、金を使うより溜め込む性分だ。不穏が起こると、虎と獅子、すなわちセポイとイギリス両方に媚びようとした。だが白人の時代だと察し、念には念を入れて財宝の半分は何があっても自分の手許に残るよう策を講じた。金銀は宮殿の地下に隠したが、最も貴重な宝石や真珠は鉄箱に入れ、信頼する家臣アフメットに商人に身をやつさせてアグラの砦まで運ばせ、和平まで預けさせた。どちらが勝とうと財宝自体は安全だ。こうして財宝を振り分けると、勢力の強い反乱軍に肩入れした。だが、こうすることで、その財宝の権利は忠実な兵のものになった。
「アフメットと名乗るこの偽商人はいまアグラの町にいて、砦に入ろうとしている。連れには養兄弟のドースト・アクバルがついていて、全てを知っている。ドースト・アクバルは今夜、アフメットを砦の側門に案内する予定で、この門を選んだ。ほどなくここにやって来て俺たちが待っているだろう。ここは人気がなく、誰にも知られない。アフメットの名はこの世から消え、ラジャーの財宝は俺たち四人で分配だ。どうする、サーヒブ?」
イングランドのウスターシャーなら人の命は神聖なものに思える。だが、死の危険と血の気配に慣れてしまうと、アフメットが生きようが死のうが大して意味はなくなる。しかし、財宝の話を聞くにつれ心が奪われ、イングランドに帰って家族や昔馴染みが金の詰まった自分の鞄を見て驚くだろうな、などと考えてしまった。実際、俺の心はもう決まっていた。だがアブダラ・カーンは俺がまだ迷っていると思ったのか、さらに強く言い寄ってきた。
「考えろ、サーヒブ。もしあの男が司令官に捕まれば処刑され、財宝は政府に没収されるだけで、誰の利益にもならない。それなら俺たちでやったほうがいい。全員大金持ちになれる。誰にも知られぬこの孤立した砦が最適の舞台だ。もう一度言うぞ、仲間になるか敵になるか」
「心の底からお前たちの味方だ」と俺は言った。
「それでいい」と言って、彼は火縄銃を俺に返した。「お前を信じる。俺たちの約束は破らぬ」
「お前の兄弟はこれを知っているのか?」と俺は聞いた。
「計画を立てたのはあいつだ。さあ、門のところでマホメット・シンと見張ろう」
雨はまだしとしと降り続けていた。大きな茶色い雲が空を流れ、石を投げれば届くくらいしか見通しが効かなかった。門の前には深い堀があるが、水はほとんど干上がっており、簡単に渡れる。荒々しいパンジャーブ兵たちと並び、これから死に行く男を迎えるのは奇妙な気分だった。
急に、堀の向こうに覆いをしたランタンの灯りがきらめくのが目に入った。灯りは土塁の間を消えたり出たりしながら、こちらにゆっくり近づいてきた。
「あいつらだ!」と俺は叫んだ。
「いつものように声をかけろ、サーヒブ」とアブダラがささやいた。「油断させてくれ。俺たちと一緒に中へ入れるように言い、あとは俺たちに任せろ。ランタンの覆いを外して本当に本人か確認するんだ」
灯はしばらく進んだり止まったりを繰り返し、ついに堀の向こうに二つの影が現れた。彼らが斜面をおり、泥を踏みしめ、門の半ばまで登ってきたところで、俺は声をかけた。
「そこにいるのは誰だ?」と小声で聞いた。
「味方だ」と返事があった。俺はランタンの覆いを外し、光を浴びせた。ひとりは黒い顎髭をカマー・バンドの辺りまで伸ばした巨漢のシク兵、見世物小屋でもめったに見ない大男。もうひとりは黄色いターバンを巻いた太っちょの丸い男で、手にはショールに包まれた包みを持っていた。恐怖に震え、痙攣でも起こしているかのように手を震わせ、小動物のように絶えず左右をきょろきょろと見回していた。そのまま見逃すわけにはいかなかったが、宝のことを思い出し、心を鬼にした。彼は俺の白い顔を見るや、小さく声を上げ、駆け寄ってきた。
「ご加護を、サーヒブ」と彼は息を切らしながら言った。「悲運の商人アフメットにご加護を。ラージプターナを越えてアグラの砦を目指したが、途中で略奪され、殴られ、侮辱された。今こうして無事に辿り着けたのは奇跡だ――私と私のささやかな持ち物が」
「その包みの中は何だ?」と聞くと、
「鉄の箱です。他人には無価値だけれど、私には失いたくない家宝が入っています。身の上はみすぼらしくありませんから、若きサーヒブやその上官にも、匿っていただければ必ずお礼をします」
これ以上話すと心が揺らぐので、さっさと済ませるのが一番だと思った。
「主衛所まで案内しろ」と俺は言った。シク兵二人が両脇を固め、巨漢がうしろに回り、男を闇の門の中へと進ませた。死がこれほど間近に迫っている男も珍しい。俺はランタンを手に門番のまま残った。
三人の足音が孤独な廊下に響く。突然足音が止まり、声や揉み合い、殴打音が聞こえた。恐怖に駆られて、やがて荒々しい足音がこちらへ駆けてくる。俺はランタンを長い廊下に向けて照らすと、太った男が顔に血を滲ませて、ものすごい速さで駆けてきた。そのすぐ後ろを虎のごとく大きな黒髭のシク兵がナイフを振りかざして追いかけている。あんなに速く走るやつは見たことがない。男はどんどん逃げ切りそうになり、もし俺の通過を許せば命拾いするだろうと感じた。哀れな気持ちになったが、財宝の誘惑がそれを打ち消した。俺は銃をその男の足元に投げ込んだ。男はウサギのように転げ、すぐに巨漢のシク兵が追いついて、ナイフを二度突き立てた。男はうめきもせず、その場に崩れて動かなくなった。おそらく転倒の衝撃で首の骨が折れたのだろう。ご覧のとおり、俺は約束通り、ことの次第を良いことも悪いこともそのまま話している。
彼は語り終えると、手錠のかかった両手を差し出し、ホームズが作っていたウイスキー水を受け取った。俺自身は、この冷酷な仕業だけでなく、その顛末を軽薄かつ無造作に語る態度にも最大限の嫌悪を覚えた。どんな罰が下されようと、同情の余地はないと感じた。シャーロック・ホームズもアセルニー・ジョーンズも、膝の上に手を置き、話に引き込まれてはいたが、顔には同じような嫌悪感が浮かんでいた。スモール自身もそれに気づいたのか、次に話すとき声や態度にやや挑戦的な色が混じった。
「確かに、悪いことだったのは間違いない」と彼は言った。「だが、俺の立場なら誰がこの財宝の山を断れただろう? 下手をすれば首を切られて命を落とすんだ。それに、いったんあの男が砦に入った時点で、先に手を下すか自分の命を諦めるかの二択だった。もし奴が逃げおおせば、全て露見して俺は軍法会議、下手すりゃ即刻銃殺だったろう。ああいう時代には情けも寛大さも無い」
「話を続けてくれ」とホームズが短く言った。
「さて、俺たちは遺体を担いで運んだ。重い男だったな、見かけは小柄でも。マホメット・シンだけ門番に残し、他の三人でシク兵たちがあらかじめ用意していた離れの場所へ連れて行った。そこは曲がりくねった通路の奥にある大きな空きホールだった。煉瓦壁はほとんど崩れていて、床の一部が沈んで天然の墓のようになっていた。アフメット商人の遺体をそこに横たえ、上に緩い煉瓦を載せてから、財宝の方へ戻った。
箱は最初に襲った場所に落ちていた。いま君たちの卓上に開いている箱と同じだ。細工された取っ手に絹紐で鍵が結びつけてあり、それを開けるとランタンの明かりが宝石の山に反射した。幼いころパーショアで夢見たような光景で、目が眩むほどだった。一つ一つ取り出してリストを作ると、第一級のダイヤモンドが百四十三個、その一つは『グレート・モガル』と呼ばれる世界第二位の大粒だった。ほかに立派なエメラルドが九十七個、ルビーが百七十個(うち小粒もある)、カーネリアン四十個、サファイア二百十個、メノウ六十一個。そのほかベリル、オニキス、キャッツアイ、ターコイズ、名前さえ知らない石も大量にあった。真珠も三百個近くあり、十二粒は金の王冠に嵌め込まれていた。ちなみに、それは箱から取り出され、俺が発見したときは入っていなかった。
宝を数えたあと箱に戻し、マホメット・シンに見せるため再び門まで運んだ。それから四人で改めて互いに忠誠を誓い、秘密を守る約束をした。戦乱が収まるまで、戦利品は安全な場所に隠しておき、いずれ平等に分け合うことにした。その場で分けると、高価な宝石を持ち歩けば疑われ、秘密にできる場所もない。そこで箱ごと遺体と同じホールの最も保存状態の良い壁の下に煉瓦を外して穴を作り、そこへ埋めた。位置を正確に記録し、翌日皆のために四通りの地図を描いて四人の印をつけた。我々は必ず共に行動することを誓った。この誓いだけは決して破っていないと胸を張って誓える。
さて、インドの反乱がどうなったか今更言うまでもない。ウィルソンがデリーを、サー・コリンがラクナウを奪回し、反乱の背骨は折れた。新兵が続々補充され、ナーナー・サーヒブは国境越えで消息を絶った。グレイティッド大佐指揮の機動部隊がアグラに入ってパンディー一味を一掃し、ようやく平穏が訪れかけた。俺たち四人はついに財宝を持ち出す時だと期待し始めたが、その矢先、俺たちはアフメット殺害容疑で逮捕された。
こういう事情だ。ラジャーはアフメットに財宝を託す際、本当に信用していたが、東洋の連中は猜疑心が強い。そこで更に信頼のおける別の家臣を、最初の男の監視につけた。その二人目は片時もアフメットから目を離さず、影のようにつきまとった。あの夜も彼の後をつけ、扉を入っていくのを見ていた。当然だが彼はアフメットが砦に逃げ込んだと思い、翌日自分も入城許可を申請したが、アフメットの足取りがどうしても掴めなかった。不審に思った彼は案内兵の軍曹に相談し、それが司令官の耳に入った。徹底的な捜索の末、遺体が発見された。こうして安全だと思っていたそのとき、あっけなく俺たち四人は殺人罪で裁判にかけられた――三人は当夜の番兵、もう一人は被害者の同行者であったためだ。宝については一言も問題とならず、ラジャーはインドから追放され無一文となっていたので、誰も興味を持たなかった。しかし殺人罪は明白で、全員が関与したのは明らかだった。シク三人は終身刑、俺は死刑判決を受けたが、後に彼らと同じく無期刑に減刑された。
このとき俺たち四人は不思議な運命になった。片足を繋がれて生涯牢獄暮らしがほぼ確定しながら、膨大な秘密を抱えていた。誰もが少しでも宝に手を伸ばせば宮殿暮らしだ。だが現実は看守に蹴られ殴られ、飯は米と水だけ。目の前にありながら財宝を手にできない。発狂しそうになったが、俺は昔から我慢強い性分だ。じっと耐えて時を待った。
ついに転機が訪れた。俺はアグラからマドラス、さらにアンダマン諸島ブレア島へ移送された。そこは白人の囚人はほとんどおらず、最初から模範囚だった俺は優遇され、ハリエット山麓の小さなホープ・タウンに小屋を与えられ、比較的自由にしていた。だがあたり一面マラリアの瘴気が漂い、開墾地の外は野蛮で人食いの現地人で溢れていた。暇なく掘削や芋栽培――とにかく日中は忙しかったが、夜には僅かな自由時間があった。その間、医者の薬剤調合を学び、多少医学も身につけた。逃亡の機会を窺っていたが、この地は大陸から何百マイルも離れ、風もほとんどなく、脱出は困難至極だった。
医者のソマートン博士は陽気で賭け事好きで、他の若い将校たちはよく彼の部屋で晩にカードに興じていた。俺の調剤室は隣にあって、小窓越しによく皆の様子を覗いたものだ。カードが趣味なので、見ているだけでも楽しかった。そこにはショールト少佐、モースタン大尉、ブロンリー・ブラウン中尉など現地軍の将校、医者自身、そして頭の切れる典獄役人たちが居て、抜け目なく巧みに遊んでいた。とても和気あいあいの集まりだった。
そのうち、俺が気づいたのは、兵士たちは必ず負け、典獄や監獄役人は必ず勝つことだった。不正があったとは言わないが、事実そうだった。監獄勤めで彼らはカードに熟達していたし、軍人は単なる暇つぶしでカードを投げる程度だった。夜になるたびに兵士たちはどんどん金がなくなり、そのせいでかえって熱くなった。とりわけショールト少佐の負けは酷く、最初は現金、その後は借用証、とうとう大金の借用書まで差し出す破目になった。僅かに勝つこともあったが、結局はズルズルと負け続け、昼間は陰鬱な顔をして酒に溺れるようになった。
ある晩、いつにも増して大負けした少佐が、モースタン大尉と一緒に俺の小屋の前を通った。二人は大の親友で、常に一緒にいた。少佐はわめいていた。
「もうダメだ、モースタン。俺は辞職せねばならん。もう破産だ」
「ばか言え、友よ」とモースタン大尉は肩を叩きながら言った。「俺も嫌な一撃を食らったが――」そこまでしか聞こえなかったが、その一言が俺には衝撃だった。
数日後、ショールト少佐が浜辺を歩いているのを見て、声をかけた。
「ご相談があるのですが、少佐」
「何だスモール」と彼は葉巻を咥えたまま尋ねた。
「隠し財宝は誰に届けるべきか、伺いたい。俺はその在りかを知っているが、自分で取り出せぬから、当局に差し出せば刑期を短縮してもらえるのではと思いまして」
「五十万だって、スモール?」と彼は俺の真剣さを確かめるように見つめた。
「その通りです、宝石と真珠で。手付かずのままそこにあります。しかも本来の所有者は追放されているから、来た者勝ちさ」
「政府のものだよ、スモール」と彼は口ごもったが、内心俺の罠にはまったと確信した。
「それなら副総督閣下に情報を出すべきだと思われますか?」と俺は静かに言った。
「いや、いや、軽率なことはすべきじゃない。詳しい話を聞かせてくれ」
俺は場所を特定されない程度に話を脚色しつつ、全てを語った。少佐は考え込んで動かなくなり、唇の痙攣から内心の葛藤が読み取れた。
「これは重要な話だ、スモール。今は誰にも口外するな。そのうちまた会おう」
二晩後、彼はモースタン大尉と共に、夜中にランタンを持って俺の小屋に来た。
「その話をモースタン大尉にも直接聞かせてほしい」
俺は先ほど通りに語った。
「確かめる価値がある、本当の話だな?」と少佐は言った。
モースタン大尉はうなずいた。
「いいか、スモール」と少佐は言った。「俺たちも話し合ったが、この秘密は政府案件ではなく私的な問題として、お前が好きに処分できるという結論に至った。そこでだが、いくらなら売る気がある? うまく話がまとまるなら俺たちも調査だけはしてみようと思う」彼は冷静を装ったが、目は欲望で輝いていた。
「では、こうしましょう」と俺も努めて冷静に答えたが、内心は同じく興奮していた。「俺たちの自由を手助けしてくれること、そして三人の仲間も救うこと。その代わり、あなた方も加えて五分の一の分け前を二人で分けてほしい」
「ふん、五分の一か。あまり魅力的じゃないな」
「一人五万です」
「だが、どうやって自由を助ける? 不可能だろう」
「そんなことはない。全て細かく考えている。唯一の問題は航海できる船と十分な食料が手に入らないこと。カルカッタやマドラスには適当な小型ヨットやヨールがあるはずだ。船を一隻用意してくれ。夜間俺たちが乗り込む。インドのどこにでも降ろせばそれで約束は果たしたことになる」
「一人だけなら?」
「全員か誰もか、だ。俺たちは誓っている」
「スモールは約束を守る男だな」と少佐は言った。「仲間想いで信頼できるだろう」
「だが汚い話だ」と大尉が言った。「だが、この金があれば我々の職も救われる」
「いいだろう、スモール。とりあえず話に乗ろう。まず君の話が本当か確かめなくてはならない。宝箱の場所を教えてくれ。俺は休暇をとって月例の船でインドに行き、確かめてこよう」
「そうはいかない」と俺は彼の熱に冷や水を浴びせた。「三人の仲間の同意が必要だ。四人一心同体なんだ」
「ふざけるな! 黒んぼ三人に権利があるものか」
「黒だろうが青だろうが、俺の仲間だ」
結局、二度目の会合を開き、マホメット・シン、アブダラ・カーン、ドースト・アクバルも出席した。話し合いの末、二人の士官にアグラ砦の地図を渡し、宝の隠し場所を記させることで合意した。ショールト少佐がまずインドへ行き、真偽を調べ、箱はそのままにしておき、小型ヨットを用意してラトランド島沖で待たせる。俺たちが船に乗り込めば彼は元の任務に戻る。次にモースタン大尉が休暇を取ってアグラに向かい、双方の取り分を現地で分配する。全ては厳粛な誓いのもとに交わされた。俺は徹夜で地図二通を書き、四人の印を記した。
さて、これ以上長話するとジョーンズ氏にも迷惑だろうし、できるだけ短く話そう。悪党ショールトはインドに発ったが、ついに戻らなかった。間もなくモースタン大尉が郵船の乗客名簿から少佐の名を見つけた。少佐の伯父が死んで大財産を相続し、軍も退役した。でも彼は俺たちを裏切りやがった。モースタン大尉もアグラに渡ったものの、財宝は跡形もなかった。悪党に全て奪われたのだ。その日から、俺は復讐だけを生き甲斐とした。朝も晩も、ショールト殺しだけが我が生の目的となった。アグラの財宝ですら、その欲求に比べたら小さなものになった。
俺が一度決意したことは必ず成し遂げてきたが、機が熟するまでには長い年月がかかった。医術の心得を得ていたが、ある日ソマートン医師が高熱で倒れていたとき、森の中でアンダマン島民の少年が囚人隊に拾われてきた。死にかけていて、人里離れた場所で息絶えようとしていた。その少年をなんとか回復させると、彼は蛇のように凶暴だったものの、次第に俺に懐き、小屋から離れなくなった。言葉も少し覚え、ますます俺に忠実になった。
トンガ――それが彼の名だが――は腕の良い舟乗りで、自前の大きなカヌーも持っていた。俺に恩義を感じ、何でもしてくれるので、ついに脱出を決意し、計画を打ち明けた。ある夜、見張りがいない古い桟橋に舟を回してもらい、水ガメや芋、ココナツやサツマイモを用意させた。
「トンガは忠実で本当に頼りになるやつだった。あんな忠誠心の強い仲間は他にいない。約束の夜、奴は波止場でちゃんと舟を待機させていた。だが運悪く、そこに囚人監視員がいてな――あの卑しいパターンで、これまで隙あらば俺を侮辱し、害を及ぼしてきた。俺は前々から必ず復讐してやると誓っていたし、この機会を逃す手はなかった。まるで運命が、出発する前に俺が貸しを返せるように、そいつを俺の目の前に送り込んだかのようだった。やつは背中を俺に向けて川岸に立ち、カービン銃[訳注:短銃身のライフル]を肩にかけていた。あたりを見回して頭をぶち割る石がないか探したが、見つからなかった。だが、ふと妙な考えが思い浮かび、武器になるものに思い至った。闇の中に座り込み、木製の義足を外した。長い跳躍三歩で奴に近づいた。あわてて奴はカービン銃を構えたが、俺は力一杯打ちつけて、頭蓋の前部を粉砕してやった。今でもその時の衝撃で木の義足にできたヒビを見ることができる。俺もバランスを崩して一緒に倒れたが、立ち上がると奴はもう静かに横たわったままだった。急いで舟へ向かい、一時間もすると、俺たちは海の真っただ中へと漕ぎ出していた。トンガはありったけの荷物――武器や神像まで――持ち込んでいた。中には長い竹槍もあり、アンダマンのココヤシで編んだむしろもあったので、それで即席の帆を作った。十日間、運を天に任せて漂い続け、十一日目に、シンガポールからジッダへ向かう途中の商船に拾われた。乗っていたのはマレー人巡礼団で、なかなか風変わりな連中だったが、トンガと俺はすぐに馴染むことができた。連中の良いところは、こちらのことに干渉せず質問もしてこないことだった。
さて、もし俺とこの小さな相棒がどんな冒険をしてきたか全部話そうとすれば、とても夜が明けるまでに終わりはしない。世界のあちこちを流れ歩き、どうしてもロンドンに辿り着けない何かが常に起きた。それでも俺は決して目的を見失わなかった。夜はしばしばショールトの夢を見た。寝ている間に何度ショールトを殺したかわからん。そしてついに、今から三、四年前、俺たちはイングランドにたどり着いた。ショールトの居場所を突き止めるのは難しくなかった。彼が財宝を手にしたままか売り払ったかを探るために動き始めた。協力してくれる人物と親しくなった――名前は明かさない、迷惑をかけたくないからな――そのおかげですぐに奴がまだ宝石を持っていると分かった。それから色々手を尽くして接近を試みたが、奴は用心深くて、息子だけでなくキットマットガー[訳注:インドの使用人]や二人のボクサーまで護衛につけていた。
そんなある日、奴が死にかけているという連絡が入った。逃げられる前にと思い、すぐさま庭に駆けつけ、窓から覗くと両脇に息子たちに見守られてベッドに横たわっていた。三人が相手でも突入してみせたところだが、眺める間にも口がだらりと開いて、死んだと分かった。その夜じゅうに奴の部屋へ忍び込み、隠し場所の記録がないか書類を調べたが、何一つ手がかりはなかった。舌打ちしながら部屋を出たが、せめてシーク仲間たちにとっても仇討ちの証を残してやろうと考えた。そこで、地図にあった通り「四人組の記号」を紙に落書きし、奴の胸元にピンで留めてきた。そのまま何の印もなく墓に入らせてたまるか、という思いがあった。
この頃、俺たちは見せ物小屋や縁日で「黒人食人族」としてトンガを見世物にして稼いでいた。生肉を食わせ、戦いの踊りを踊らせる。仕事が終わると帽子が小銭でいっぱいになるくらいには稼げた。ポンディシェリ・ロッジの話も耳に入ってきたが、何年ものあいだ変わったことは何もなかった。ただ宝を探し続けているという噂だけだ。だが遂に待ちわびた出来事――宝の発見――が起きた。屋敷の最上階、バソロミュー・ショールトの化学実験室だと分かった。すぐその場を下見に行ったが、この義足では屋根裏までどうにも近づけなかった。だが屋根の隠し戸とショールトの夕食時刻を知ることができた。これならトンガを使えばなんとかなると踏んだ。トンガの腰に長いロープを巻きつけて現場へ連れて行った。奴は猫のように自在に登るので、すぐに屋根裏に入った。だが不運にもバソロミュー・ショールトがそこにいて殺されてしまった。トンガは己の手柄を自慢げにしていた。俺がロープで上がると、まるで孔雀のように誇らしげに歩き回っていたので、すぐさまロープの先端でぶん殴り、「血に飢えた小鬼め!」と罵った。宝の箱を受け取り、ロープで下ろし、自分も滑り降りてから、机の上に「四人組の記号」を残してきた。これは宝が、正当な持ち主の手に戻った証だ。トンガはロープを引き上げ、窓を閉じて、来た道を再び脱出した。
もう特に話すことはない。船頭の一人からスミスの持つランチ、〈オーロラ号〉の速力の話を聞いていたので、逃走にはうってつけだと思った。スミス老人を雇い、無事に船まで送り届けてくれたら大金をやると約束した。奴は何かきな臭い事情があるのには気づいていたかもしれないが、俺たちの秘密には関与しなかった。これが真実のすべてだ。そしてこれをここで話すのは、別にお前さんたちを楽しませるためじゃない――今までお前さんたちは親切どころか厄介をかけてくれたものだ――だが、一切包み隠さず世間に語り、ショールト少佐にどれほど酷い目に遭わされたか、そして息子の死に関しては俺が潔白だと知ってもらうのが一番の防御だと思うからだ。」
「実に興味深い話だ」とシャーロック・ホームズが言った。「誠に面白い事件の結末に相応しい。君の話の後半で私に新しかったのは、自分でロープを用意していたことだけだ。そこまでは知らなかった。ところで、私はトンガが吹き矢を全部失っていると思っていたが、あいつは船の上で我々に矢を放ったな。」
「全部なくしましたよ、旦那。ただしその時吹き矢の中に入っていた一本だけは別です。」
「なるほど、当然そうなるな」とホームズ。「それは考え及ばなかった。」
「他にお尋ねになりたいことはありますかな?」と囚人が愛想良く尋ねた。
「いや、特にない、ありがとう」とホームズが答えた。
「さてホームズ君」とアセルニー・ジョーンズが言った。「君の道楽には付き合う主義だし、犯罪の目利きだってことも皆よく知っているが、公務は公務だ。君と君の友人の言う通り、だいぶ融通してやった。だがこれで語り手も無事に牢に入れたとなれば私も気が楽になる。馬車はまだ待っているし、下には二人の警部が控えている。今回の協力には感謝する。もちろん、君らも裁判で証言を求められるだろう。ごきげんよう。」
「ごきげんよう、両先生」とジョナサン・スモールが言った。
「まず君からだ、スモール」と用心深いジョーンズは席を立ちながら言った。「アンダマン諸島のあの監守にしたみたいに、私の頭をその義足でぶん殴られちゃたまらんからな。」
「これで我々の小さな劇も幕引きだな」と、しばらく静かに煙草をくゆらせた後、私は言った。「君のやり方を学ぶ機会は、これが最後になるかもしれない。ミス・モースタンが私の求婚を受け入れてくれたのだ。」
ホームズはひどく沈み込んだ声で呻いた。「やはりそうだったか。実に残念だ。」
私は傷ついた。「私の選択に何か不満があるのか?」
「いや、まったくない。あの娘は今まで会ったなかでも屈指の素晴らしいお嬢さんだ。第一、君と私が今までやってきた仕事にも十二分に役立つ才がある。父親の書類の中でアグラの地図を絶妙の形で守り抜いた手腕を見ればわかる。しかし、恋とは感情の産物だ。そして、いかなる感情も私が何より重視する冷静な理性と対立する。私は決して結婚しない。判断を曇らされたくないからだ。」
「私の判断力がその試練を乗り越えられることを祈ろう」と私は笑いながら言った。「だが、君は疲れて見えるな。」
「ああ、既に反動が来ている。これから一週間はぬけがらみたいにぐったりして過ごすことになりそうだ。」
「不思議なものだな」と私は言った。「君の中には、他の誰なら怠け者と言いそうなくらい無気力な時期と、比類なき精力的な時期が交互に現れる。」
「そうだ」とホームズは答えた。「私は立派な怠け者にも、それなりに活動的な男にもなりうる材料を持ち合わせている。ふとゲーテの一節を思い出す――
Schade dass die Natur nur einen Mensch aus Dir schuf,
Denn zum würdigen Mann war und zum Schelmen der Stoff.
(自然が君から一人の人間しか創らなかったのは残念だ、
立派な男にも、悪党にもなれる素材だったのに。)
ちなみに、このノーウッド事件に関してだが、やはり私の推測通り、屋敷内部に協力者がいた。それは他ならぬラル・ラオ、執事だった。結局ジョーンズは、今回の大漁でたった一匹だけ自力で釣り上げる栄誉を手にしたわけだ。」
「分配がずいぶん不公平だな」と私は言った。「君がすべての仕事をして、私は妻を得て、ジョーンズが手柄を独り占め、では君には何が残る?」
「私には」とシャーロック・ホームズは答えた。「コカインの瓶が残されている。」そう言って、彼は長く白い手を伸ばした。

