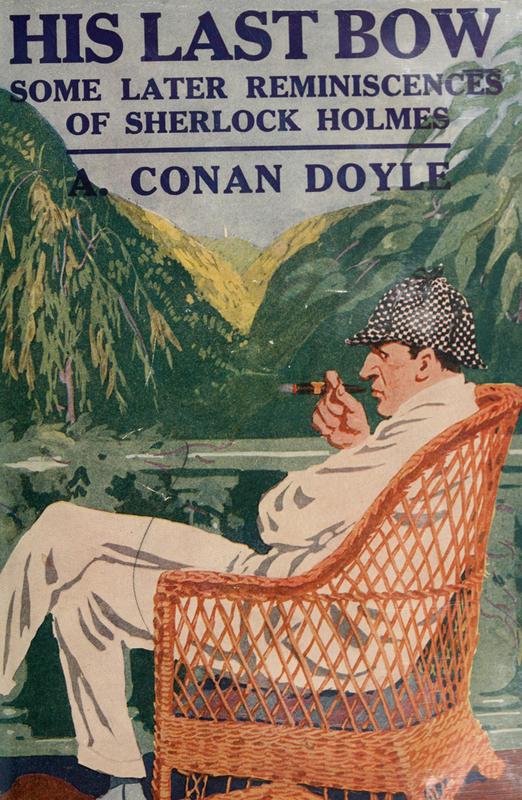
アーサー・コナン・ドイル著
序文
シャーロック・ホームズ氏の友人諸君には、彼が今も健在で、多少リウマチに悩まされてはいるものの、元気に暮らしていることをお伝えできるのは喜ばしいことだろう。ここ数年、彼はイーストボーンから五マイルほど離れたダウンズの小さな農場で、哲学と農業のあいだに心を分け合いながら静かな日々を送っている。この静養期間中、彼はさまざまな事件の解決を依頼されても、それがどんなに高額な報酬であっても一切応じなかった。彼は引退を永遠のものと決めていたのである。しかし、ドイツとの戦争が近づくと、彼はその卓越した知力と実行力を政府のために捧げ、歴史的な結果を残した。その顛末が本書『シャーロック・ホームズ最後の挨拶』に記されている。また、長らく私の手許に温めてきた過去のいくつかの事件も本書に加え、全体をまとめることとした。
ジョン・H・ワトソン医師
ウィステリア荘の事件
1.ジョン・スコット・エクルズ氏の奇妙な体験
私の手帳には、1892年3月末のある寒く風の強い日のできごとが記されている。昼食中にホームズは電報を受け取り、さっと返事を書きつけた。彼は何も口にしなかったが、その件がずっと気にかかっている様子で、食後は暖炉の前で煙草をくゆらせながら、時おりその電報に目をやり考え込んでいた。突然、彼は目にいたずらっぽい光を浮かべて私の方へ向き直った。
「さてワトソン、君のことを“文筆家”と見なしてもよいだろう。ところで、“グロテスク”という言葉をどう定義する?」
「奇妙――異様な、といったところかな」と私は答えた。
彼は私の定義に首を振った。
「きっとそれ以上のものがあるはずだ」と彼は言った。「どこかに悲劇的で恐ろしいものを暗示している。君が長年、耐え忍ぶ読者に向けて書いてきたあの数々の物語を思い返してごらん。どれほど多くの場合、グロテスクなものが犯罪へと転じてきたことか。赤毛組合の事件を思い出してみてほしい。あれも最初は十分にグロテスクだったが、結局は大胆な強盗未遂へと発展した。また、あの五つのオレンジの種の件も、極めてグロテスクな始まりから、殺人陰謀に直結した。“グロテスク”という言葉を聞くと、私は警戒せずにはいられない。」
「その件かい?」と私は尋ねた。
彼は電報を声に出して読んだ。
「今しがた、まったく信じられないほどグロテスクな体験をした。相談に乗っていただきたい。
スコット・エクルズ チャリング・クロス郵便局」
「男性かな、それとも女性かな?」と私は尋ねた。
「もちろん男性さ。女性が返信用切手付き電報を送ることはないよ。直接会いに来るだろう。」
「会うつもりかい?」
「ワトソン君、カラス大佐[訳注:異本ではカラス大佐。原文はCarruthers]を逮捕して以来、どれだけ退屈してきたかわかっているだろう。私の頭脳は、役割を与えられず空回りしているエンジンのようなものだ。人生は平凡で、新聞も不毛、犯罪の世界からはもはや大胆さもロマンスも消えてしまった。そんな状況で新しい問題が舞い込んできて、しかもそれがどんな些細なものであっても、断る理由があると思うかい? だが、私の勘が正しければ、依頼人が来たようだ。」
階段を上がる規則正しい足音が聞こえ、間もなく、がっしりとした背の高い、白髭の、どこから見ても立派で実直そうな人物が部屋へ案内されてきた。彼の重々しい顔立ちと尊大な態度には人生の歴史が刻み込まれている。足元のスパッツから金縁の眼鏡まで、保守的で敬虔な教会人、善良な市民、規範的で典型的なイギリス紳士そのものだ。しかし、何か驚くべき体験が彼の生まれつきの沈着さを乱し、髪は逆立ち、頬は紅潮し、怒りと混乱がその立ち居振る舞いに見て取れた。彼は即座に話し始めた。
「ホームズさん、私には非常に奇妙で不愉快な体験がありました。生まれてこの方、こんな境遇に置かれたことはありません。まったく不当で――言語道断です。何らかの説明をぜひともお願いしたい。」彼は怒りに満ちて膨れ上がった。
「どうぞおかけください、スコット・エクルズさん」とホームズはなだめるように言った。「まず第一に、なぜ私のもとに来られたのでしょうか?」
「実は、警察の案件とは思えませんでしたし、ですが、これからお話しする事実をお聞きになれば、このまま放置できるものではないと納得されるはずです。私立探偵という職業にはまったく共感できませんが、それでもあなたの評判を伺って――」
「なるほど。では、なぜすぐに来なかったのですか?」
ホームズは時計を見た。
「今は二時十五分です。あなたの電報は一時ごろに出されています。しかし、あなたの身だしなみを見る限り、寝起きの時点からすでに動揺されていたのがわかります。」
依頼人はぼさぼさの髪をなでつけ、ひげのそったばかりの顎に手をやった。
「おっしゃる通りです、ホームズさん。身だしなみのことなど一切考えませんでした。とにかくあの家から逃げ出せてほっとしただけです。ただ、ここに来る前に駆けずり回って調査していました。不動産屋に行きましたが、ガルシア氏の家賃はすべて支払われており、ウィステリア荘には何の問題もなかったとのことでした。」
「それはそれは」とホームズは笑いながら言った。「君は私の友人ワトソンと同じで、話を逆から始める悪い癖があるね。考えを整理して、どんな出来事が君を無精ひげのまま、ネクタイも曲がったまま助けを求めてきたのか、順を追って教えていただきたい。」
依頼人は自分の乱れた格好を見て、困ったような顔をした。
「まったく見苦しいものですね、ホームズさん。こんなことは生まれて初めてです。それでも、すべてお話しすれば、きっとお許しいただけるだけの事情があったとご納得いただけるはずです。」
だが彼の話は、始まるや否や中断された。外で騒めきがあり、ハドソン夫人が二人の屈強な、いかにも公務員然とした男を案内してきた。ひとりはよく知るスコットランド・ヤードのグレグソン警部、もうひとりはサリー州警察のベインズ警部だと紹介された。
「ホームズさん、今回は共同捜査です。そちらの方向に足取りがあったので」とグレグソンが言い、ブルドッグのような眼で依頼人を見つめた。「あなたがリーのポッパム・ハウスのジョン・スコット・エクルズ氏ですね?」
「私です。」
「我々は今日の午前中、あなたの後を追っていました。」
「電報から足跡を追われたのでしょう」とホームズ。
「まさにその通りです。チャリング・クロス郵便局で手がかりをつかみ、ここまで来ました。」
「だが、なぜ私を追うのですか? 何のご用でしょう?」
「昨夜、ウィステリア荘のアロイシウス・ガルシア氏が亡くなった件について、事情を伺いたいのです。」
依頼人は目を見開き、顔から血の気が引いた。
「亡くなった? 死んだと?」
「はい、亡くなっています。」
「どうして? 事故ですか?」
「地上のどんな事件よりも、明らかな殺人です。」
「なんてことだ! まさか――まさか私が疑われているのですか?」
「あなたの手紙が被害者のポケットから見つかりまして、その中で昨夜は彼の家に泊まる約束をしていたことが分かっています。」
「確かにそうです。」
「ほう、そうですか。」
警察の手帳が取り出された。
「待ってくれ、グレグソン」とシャーロック・ホームズが言った。「君が求めているのは事実関係の陳述だけだろう?」
「そして、スコット・エクルズ氏には、その供述が不利な証拠となる可能性があることを警告するのが義務です。」
「エクルズ氏はちょうど話そうとしていたところだった。ワトソン、少しブランデーとソーダを出してあげてくれ。では、ご来客が増えたことは気にせずに、どうか最初から順に、途中で中断されたのと同じようにお話しください。」
依頼人はブランデーを一口で飲み干し、顔色も戻ってきた。警部の手帳を気にしつつも、すぐに尋常ではない話を始めた。
「私は独身者でして、社交的な性分ゆえ多くの知人がおります。その中にメルヴィルという元ビール醸造業者の一家がいて、ケンジントンのアバマール・マンションに住んでいます。そこで数週間前、ガルシアという若者と知り合いました。彼はスペイン系で、何らかの形で大使館に関わりがあると聞きました。英語は完璧で、礼儀正しく、人生で見た中でも屈指の好青年でした。
彼とは妙に気が合い、出会ってから二日後には、リーの私の家までわざわざ訪ねてきました。そんなこんなで、彼の家――エッシャーとオクショットの間にあるウィステリア荘に数日遊びに来ないかと誘われたのです。そして昨日の夕方、その約束を果たすためエッシャーに向かいました。
行く前に彼から家の様子を聞いていました。彼は同郷の忠実な使用人と二人暮らしで、その男が身の回りの世話をすべてしてくれるそうです。英語も話せ、家事一切もこなす。さらに素晴らしい料理人――彼の旅先で拾ったという混血の男がいて、絶品のディナーを作るとか。サリーの奥地にしては変わった家庭だね、とお互いに笑ったものですが、想像以上に奇妙な体験をすることになりました。
現地へはエッシャーの南側約二マイルの道のりを馬車で向かいました。家はかなり大きく、道路から離れて立ち、曲がった私道は高い常緑樹の垣根に囲まれていました。古びて荒れ果てた建物で、入口の斑点だらけの古いドアの前の草の生えた通路に馬車が止まったとき、私は少し安易に誘いに乗ったのではと疑問に感じました。しかし、ガルシア氏自らが出迎えてくれて、大いに歓待されました。使用人――陰気で浅黒い男――が私の鞄を持って寝室まで案内してくれました。全体的に陰鬱な雰囲気でした。夕食はふたりきりで、主人はもてなそうと努力していましたが、どうも心ここにあらずで、話も要領を得ず、何を言っているのかよく分かりませんでした。テーブルを指で叩いたり、爪をかじったり、明らかな苛立ちや神経質な様子でした。料理もサービスも良くなく、無口な使用人の存在がさらに場を重苦しくしていました。何度も口実を作ってリーに帰りたいと思ったものです。
ひとつ、あなた方が調査されている事件と関係あるかもしれないことを思い出しました。夕食の終わり近く、使用人が手紙を持ってきました。主人がその手紙を読んでから、ますます落ち着きなくなり、会話を一切やめて煙草ばかり吸い、沈思黙考にふけっていましたが、中身については何も言いませんでした。十一時ごろ、やっと寝室へ。しばらくしてガルシア氏がドアをノックしてきました――その時、部屋は暗かったのですが――私がベルを鳴らしたかと尋ねたので、鳴らしていないと答えました。遅くにお騒がせしました、もうすぐ一時ですと言って、すぐに去りました。その後はすぐ眠りにつき、朝までぐっすり眠りました。
ここからが驚くべき話です。目覚めた時にはすでに明るく、時計を見たら九時近かった。八時に起こしてくれと頼んでいたので、忘れていたことに驚きました。跳ね起きてベルを鳴らしましたが反応なし。何度鳴らしても同じ。ベルが壊れているのかと思い、服を大急ぎで着て怒り心頭で階下に降り、熱い湯を頼もうとしました。ところが、誰もいない。廊下で叫んでも返事なし。家中の部屋という部屋を走り回りましたが、どこもがらんどう。主人の寝室も前夜教えられていたのでドアをノックしましたが無反応。ドアを開けると誰もおらず、ベッドも使われた形跡がない。主人も、使用人も、料理人も――みんな夜のうちに消え失せていた! これが私のウィステリア荘訪問の全顛末です。」
シャーロック・ホームズは手をすり合わせ、珍しい事件が増えたことを嬉しそうにしていた。
「あなたの体験は、私の知るかぎり、まったく前例のないものですね。さて、その後どうされましたか?」
「私はカンカンに怒りました。くだらない悪ふざけの被害者だと思いました。荷物をまとめて大きな音を立てて玄関を出て、手に鞄を持ったままエッシャーに向かいました。村の不動産屋アラン兄弟商会に行き、そこから家を借りたことを知りました。全てが単なる悪ふざけとは思えず、目的は家賃の踏み倒しだろうと考えました。三月末で四半期の払い日も近い。しかし、これは違いました。家賃は前納済みだと分かりました。次にロンドンのスペイン大使館に行きましたが、こんな男は知らないとのこと。ガルシアと最初に出会ったメルヴィル氏にも会いに行きましたが、私より彼のことを知らない様子でした。最後に、あなたから電報の返事をもらい、困難な案件の相談役として評判のあなたのもとに来たのです。ですが、警部殿、先ほどの話からすると、あなたは事件の続きをご存じのようですね。私が今お話ししたことはすべて真実であり、それ以外には、ガルシア氏の身の上については何も知りません。唯一の願いは、法のためにできるだけ協力することだけです。」
「確かにその通りでしょう、スコット・エクルズさん」とグレグソン警部も穏やかな口調で言った。「あなたの話は、我々が把握している事実と極めてよく一致しています。たとえば、夕食中に届いたという手紙。中身やその後どうなったか覚えていませんか?」
「ええ、覚えています。ガルシア氏は手紙を丸めて暖炉に投げ捨てました。」
「どう思う、ベインズ警部?」
田舎の警部は、太って赤い顔をし、頬や額のしわに隠れるほど小さいが、異様に輝く目を持っていた。ゆっくりと笑みを浮かべながら、ポケットから折りたたまれた変色した紙片を取り出した。
「暖炉が格子状だったので、奥の方に投げ入れたのですが、焼け残りを拾い上げました。」
ホームズは感心して微笑んだ。
「家の隅々まで綿密に調べた証ですね。」
「ええ、ホームズさん。私のやり方です。グレグソン警部、読んでも?」
ロンドンの警部がうなずいた。
「普通のクリーム色の紙で透かしなし、四分の一サイズ。刃の短いはさみで二回切り離され、三つ折りにして紫の蝋で慌てて封をし、平たい楕円形のもので押し付けてあります。宛名は『ガルシア氏 ウィステリア荘』。本文は――
『我らの色は緑と白。緑は開、白は閉。大階段、第一廊下、右七番目、緑のフェルト。幸運を祈る。D』
女性の筆跡で、細いペンで書かれていますが、宛名は明らかに違うペンか別人の手で、太く力強い字です。」
「非常に興味深い手紙ですね」とホームズは目を通しながら言った。「細部に目を配った調査、お見事です。いくつか小さな点を付け加えれば、楕円形の印は袖口リンクスに違いありません。他にあんな形のものはない。はさみは先が曲がった爪切り用で、二つの切れ端のカーブが一致しています。」
田舎の警部は満足げに笑った。
「全部調べ尽くしたつもりでしたが、まだ少し残っていたようです。私はこの手紙からは、何かが進行中で、そして例によって女が絡んでいる――それくらいしか読み取れません。」
エクルズ氏はそわそわと椅子の上で身動きしていた。
「その手紙が見つかってよかったです。私の話の裏付けになりますから。しかし、まだガルシア氏に何が起きたのか、家の者たちがどうなったのか聞いていません。」
「ガルシアについては簡単です」とグレグソンが言った。「今朝、ウィステリア荘から一マイル近く離れたオクショット・コモンで死体が見つかりました。頭部は砂袋か何かで打ち砕かれ、傷というより粉々に潰されていました。人気のない場所で、近くに家もありません。背後から襲われたようですが、犯人は死後も執拗に殴り続けた。極めて激しい暴行です。足跡も犯人の手がかりも一切ありません。」
「強盗目的ですか?」
「いいえ、強盗の形跡はありません。」
「これは非常につらい、実に恐ろしいことです」とエクルズ氏は不満げに言った。「私は昨夜、主人が夜中にどこかへ出かけて不幸な目に遭ったこととは一切関係ありません。それなのに、なぜ私が巻き込まれるのです?」
「単純な話です」とベインズ警部が答えた。「被害者のポケットに唯一残っていた文書が、あなたからの宿泊を知らせる手紙でした。その封筒から亡くなった男性の氏名と住所を特定したのです。今朝九時過ぎに家を訪ねたところ、あなたも含め誰一人おらず、そこで私はグレグソン警部にロンドンであなたを探すよう電報を送り、自分はウィステリア荘の現場調査をしました。その後ロンドンへ向かい、グレグソン警部と合流し、こうしてここにいるわけです。」
「では」とグレグソンが立ち上がりながら言った、「正式な手続きを取りましょう。スコット・エクルズさん、署までご同行いただき、書面で供述していただきます。」
「もちろんすぐ行きます。ただし、ホームズさん、あなたには引き続き調査を依頼します。費用も労力も惜しみませんので、真実を突き止めてください。」
ホームズは田舎の警部に向き直った。
「協力しても構いませんか、ベインズ警部?」
「光栄の至りです。」
「これまで極めて迅速かつ的確な捜査をされています。被害者の死亡時間について何か手がかりは?」
「一時ごろ現場にいたようです。その時間帯に雨が降り始めており、死は雨より前のことでしょう。」
「ですが、それは完全にありえません」と依頼人が叫んだ。「声は間違いありません。あの時間、部屋で私に声をかけたのは紛れもなく彼でした。」
「驚くべきことですが、不可能とは言えません」とホームズは微笑んだ。
「なにか手がかりでも?」とグレグソン。
「一見してさほど複雑な事件とは思いませんが、斬新で興味深い点も多い。最終的な意見は事実がもっと明らかになってからでなければ出せません。ところで、ベインズ警部、現場調査でこの手紙以外になにか特筆すべきものは見つかりましたか?」
警部は奇妙な表情でホームズを見た。
「ええ、非常に興味深いものがいくつかありました。署での手続きが終わったら現場を一緒に見ていただけませんか。」
「喜んで」とホームズは呼び鈴を鳴らした。「この方々をお見送りください、ハドソン夫人。それと、この電報を少年に届けさせてください――返信料五シリングを払ってもらうように。」
来客が去った後、しばらく沈黙が続いた。ホームズは眉間にしわを寄せ、身を乗り出す独特の姿勢でパイプをくゆらせていた。
「さてワトソン、君はどう思う?」
「スコット・エクルズの困惑は全く理解できない。」
「では、犯罪については?」
「家の仲間たちが姿を消したことと併せて考えると、彼らが何らかの形で殺人に関与し、法の裁きを恐れて逃げ去ったのでは?」
「確かに可能性はある。だが、よく考えてもみたまえ。なぜ使用人二人が一晩だけ客人のいるときに主人を殺そうとする? 他の晩はいつでも無防備だったのに。」
「それなら、なぜ逃げた?」
「そう、その逃亡自体が大きな事実だ。そしてもう一つの事実、スコット・エクルズの奇妙な体験。この二つを同時に説明できる仮説はないだろうか? あの不可解な手紙の文言まで説明できれば、暫定的な仮説として受け入れる価値がある。今後得られる新事実がその枠組みに収まるならば、仮説はやがて解決へと変わるだろう。」
「では、その仮説とは?」
ホームズは椅子に深くもたれ、目を細めた。
「まず、悪ふざけ説は成り立たない。重大な事件が進行中であり、スコット・エクルズをウィステリア荘へ呼び寄せたことにも関係がある。」
「どんな関係が?」
「順を追って考えよう。まず不自然なほど急速に親しくなった若いスペイン人とスコット・エクルズ。彼が自らリーまで訪れてまで接触し続け、ついにはエッシャーへ誘う。彼がエクルズに求めていたものは? エクルズに何を期待した? 私はエクルズに特別な魅力を感じない。頭もあまり切れない――ラテン系の才気ある男が共感しそうな人物ではない。ではなぜ、あまたの知人の中から彼を選んだのか? それは“典型的なイギリス的良識の体現者”、証人として英国人に強い印象を与える人物だからだろう。実際、両警部も彼の証言を疑わなかった。」
「何の証人に?」
「結果的には何も証言しなかったが、別の展開なら全てを証言していたはず。つまり“アリバイ”の証人だ。」
「なるほど、つまり彼はアリバイの証明者になり得たわけだ。」
「そう、彼が家にいる間に何かを済ませて戻れば、いざ告発されても“このイギリス紳士が夜通し家にいたと証言してくれる”――これが保険だった。」
「それは納得できる。だが他の者たちの失踪は?」
「まだすべての事実は揃っていないが、超えられない難点とは思えない。ただ、データに先立って仮説を組み立てるのは危険だ。理屈に都合よく事実をねじ曲げることになる。」
「それに、あの手紙は?」
「文面を思い出してみよう。“我らの色は緑と白”。競馬用語のようだ。“緑は開、白は閉”。明らかに合図だ。“大階段、第一廊下、右七番目、緑のフェルト”。これは密会の示し合わせだ。嫉妬深い夫が絡んでいるのかもしれない。危険な任務だったことは“幸運を祈る”という言葉からも明らかだ。“D”――これが手がかりだろう。」
「被害者はスペイン人。“D”はスペインでよくある女性名、“ドロレス”の頭文字では?」
「ワトソン、なかなかいい線だが、却下だ。スペイン人がスペイン人に手紙を書くならスペイン語のはず。この手紙は明らかに英語だ。さて、あとは優秀な警部が戻るまで辛抱強く待つしかない。しばし退屈から解放してくれた幸運に感謝しよう。」
サリー警部が戻る前に、ホームズの電報の返事が届いた。ホームズはそれを手帳にしまおうとしたが、私の期待に満ちた視線に気づき、笑いながら投げてよこした。
「我々は高名な人々の中で動いているようだな。」
電報には次のような氏名と住所が並んでいた。
ハリングビー卿(ディングル)、ジョージ・フォリオット卿(オクショット・タワーズ)、ハインズ・ハインズ判事(パードリー・プレイス)、ジェームズ・ベイカー・ウィリアムズ氏(フォートン・オールド・ホール)、ヘンダーソン氏(ハイ・ゲーブル)、ジョシュア・ストーン牧師(ネザー・ウォルスリング)
「これで捜査範囲がぐっと絞られたわけだ」とホームズ。「ベインズ警部もきっと似たようなリストを作っているだろう。」
「どういうことだい?」
「ワトソン君、すでに我々はガルシア宛ての手紙が密会の誘い、もしくは約束と見ている。文面通り読むなら、相手は大きな屋敷に住んでいる。しかも現場から一、二マイル以内――アリバイを成立させるために一時までにはウィステリア荘へ戻る必要があった。オクショット周辺の大邸宅は限られている。そこで、不動産屋からリストを入手したわけだ。もう一方の糸口はこの中のどこかにある。」
午後六時近くになって、我々はサリーの美しい村エッシャーに到着した。ベインズ警部も同行である。
ホームズと私は宿泊の用意をし、居心地の良い「ブル」[訳注:宿屋の名前]に落ち着いた。いよいよ警部とともにウィステリア荘を訪れることになった。三月の冷たい夜、鋭い風と細雨が顔を打ちつける――荒れ野のような道を通り、悲劇の現場へと向かった。
2.サン・ペドロの虎
寒さと憂鬱の中、二マイルほど歩いて高い木製の門に着いた。中は栗の木が並ぶ陰鬱な並木道。曲がりくねった並木道を進むと、低くて暗い家が現れ、スレート色の空に真っ黒な影を落としていた。入り口の左手の窓から、かすかな明かりが漏れている。
「中に警官がいる」とベインズ。「窓をノックしてみよう。」彼は芝生を横切り窓を軽く叩いた。曇りガラス越しに、暖炉横の椅子から飛び上がる男の姿と、室内からの鋭い叫び声が聞こえた。直後、顔面蒼白で息を切らす警官が、震える手にろうそくを持ってドアを開けた。
「どうした、ウォルターズ?」とベインズが鋭く尋ねた。
男はハンカチで額をぬぐい、ほっと大きなため息をついた。
「警部、来てくださって助かりました。長い夜でしたし、自分の神経も昔ほど強くないようです。」
「神経だと? 君の神経がそんなに弱いとは思わなかったが。」
「いえ、警部。ですが、この寂しい家と台所の奇妙なもの、それにさっきの窓の件で……お恥ずかしながら、窓をたたく音でまた来たかと思ったのです。」
「また来たとは、何がだ?」
「悪魔ですよ、もしかしたら。窓に現れたんです。」
「いつ、何が窓に?」
「ちょうど二時間ほど前です。日が暮れかかっていた頃。椅子で本を読んでいて、ふと見上げると、下のガラス越しに顔が覗いていたんです。いや、あんな顔は初めて見ました――夢に出そうです。」
「おいおい、ウォルターズ、警官らしからぬ話だな。」
「承知しています、警部。でも、あれは本当に震えました。色も黒でも白でもなく、土に牛乳をかけたような奇妙な色でした。サイズも普通の倍はありました。それにあの目――ぎょろりとした大きな目と、獰猛な動物のような白い歯。体が動かず息もできず、やっと消えたので外に追いかけましたが、茂みには誰もいませんでした。」
「君が優秀な警官でなければ、黒星をつけたところだ。悪魔だろうが、警官は職務中に取り逃がして神に感謝などしてはいかん。幻覚や神経の問題では?」
「それなら簡単に確かめられます」とホームズが懐中ランタンを灯した。「はい――やはり靴跡があります。サイズは十二番。顔の大きさからしても、まさに巨人ですね。」
「そいつはどうした?」
「茂みを突っ切って道路へ逃げたようです。」
「ふむ」と警部は真剣な顔で言った。「何者で、何をしに来たかはともかく、今は去った。さしあたって他に優先すべき事柄があります。さてホームズさん、家の中をご案内しましょう。」
寝室や居間を念入りに捜索しても、何も手がかりはなかった。住人たちはほとんど何も持ってこなかったようで、家具から細々した物まで家に備え付けられていた。マルクス商会(ハイ・ホルボーン)の刻印がある衣類も多く残っていた。すでに電報で問い合わせたところ、マルクス商会は支払いの良い客であったこと以外は何も知らなかった。パイプや小説――うち二冊はスペイン語――、古いピンファイア式拳銃、ギターなどが私物として残されていた。
「これらには何の意味もない」とベインズはろうそくを手に部屋から部屋へ移動しながら言った。「さてホームズさん、台所をご覧いただきたい。」
家の裏手にある、天井の高い陰気な部屋だった。隅には藁が敷かれており、料理人の寝床らしい。テーブルには食べかけの皿や料理の残骸が山積みだ。
「これを見てください。どう思います?」
彼は戸棚の奥にある奇妙な物体にろうそくを掲げた。それはしわくちゃで縮み切り、黒くて皮のように乾燥して、もはや何だったのか判別しがたい。小さな人間の形にも見えるが、最初はミイラ化した黒人の赤ん坊かと思い、次には曲がった古い猿かとも思えた。しかし結局、人間か動物か判然としなかった。胴には白い貝の二重の首飾りが巻かれていた。
「実に興味深い――これは面白い!」とホームズは不気味な遺物を覗き込みながら言った。「他に何か?」
ベインズは黙って流し台へ案内し、さらにろうそくを掲げた。そこには大きな白い鳥――羽のまま無残に引き裂かれた鳥の胴体と手足が散乱していた。ホームズはちぎれた頭部の肉垂(ワットル)を指差した。
「白い雄鶏ですね。実に興味深い。これは実に変わった事件ですよ。」
だがベインズ警部は、さらに恐ろしい証拠を最後に残していた。流しの下から亜鉛のバケツを取り出すと、中には大量の血液が入っていた。さらにテーブルの上からは、炭化した骨片を山ほど載せた皿を持ってきた。
「何かが殺され、焼かれている。これらは暖炉からかき出したものです。今朝、医者にも見せましたが、人骨ではないとのことです。」
ホームズは微笑み、満足そうに手をこすった。
「ベインズ警部、この独特で示唆に富む事件を見事に扱っておられます。僭越ながら、あなたの能力は今の環境を超えておられるようですね。」
ベインズ警部の小さな目が満足げに輝いた。
「おっしゃる通りです、ホームズさん。地方では退屈ばかりですから、こういう事件は腕の見せどころです。これらの骨、どう思われますか?」
「子羊か、あるいは子山羊だろうな。」
「そして白い雄鶏は?」
「実に興味深いですな、ベインズさん、非常に興味深い。ほとんど類を見ない例だと思います。」
「ええ、先生、この家には本当に奇妙な連中が、奇妙な習慣とともに住んでいたに違いありません。そのうちの一人は死にました。仲間が後を追って、彼を殺したのでしょうか? もしそうなら、すべての港が監視されているので、彼らを捕まえられるはずです。しかし、私はそうは思いません。ええ、先生、私はまったく違う見方をしています。」
「では、理論があるのですね?」
「ええ、そしてそれは自分自身で解明するつもりです、ホームズさん。それが私の名誉のためにも必要なのです。あなたはすでに世に名を知られていますが、私はまだこれから築かねばなりません。今回、あなたの助けを借りずに解決できたと言えるようになりたいのです。」
ホームズは快活に笑った。
「まあ、まあ、警部、あなたはあなたの道を、私は私の道を行きましょう。私の調査結果はいつでも差し上げますから、必要なら遠慮なくどうぞ。私はこの家で見たいものはすべて見ましたし、これからは他の場所で時間を使ったほうが有益でしょう。では、オ・ルヴォワール、幸運を!」
ホームズが熱心に事件の臭いを嗅ぎつけているのは、私だけが気付くさまざまな微細なサインから明らかだった。普段通り、表面上は無表情を装っているものの、目は輝き、動作も機敏になり、静かな興奮と緊張がにじみ出ていた。彼は何も言わず、私もいつものように質問はしなかった。ただ一緒に狩りを楽しみ、余計な邪魔をせずにその精緻な頭脳にささやかな支援をするだけで十分だった。すべてはやがて私にも明かされることだろう。
だから、私はただ待っていた――だが、失望は深まるばかりだった。日が過ぎても、友人は一歩も前進しない。ある朝、彼は町へ出かけ、何気ない会話から大英博物館を訪れたことを知った。この一度きりの外出を除けば、彼はほとんどを長い散歩や、村で知り合った噂好きな人々とのおしゃべりに費やしていた。
「ワトソン、田舎での一週間は君にとって本当に有益だよ」と彼は言った。「生け垣に新芽が芽吹き、ハシバミに花穂が見えるのはとても気持ちがいい。スコップとブリキ箱、初歩的な植物学の本があれば、有意義な日々を過ごせるさ。」実際、彼自身もその装備でうろついていたが、夕方に持ち帰る植物標本は貧相なものだった。
時おり散歩中にベインズ警部と出くわした。彼の丸く赤い顔は満面の笑みを浮かべ、小さな目を輝かせてホームズに挨拶した。事件についてはほとんど語らなかったが、そのわずかな言葉からも彼も現状に満足しているらしいと感じられた。しかし、事件から五日ほど経ったある朝、新聞を開くと大見出しが目に飛び込んできて、私はひどく驚いた。
オクショットの謎
解決
容疑者逮捕
私がその見出しを読み上げると、ホームズはまるで針で刺されたかのように椅子から飛び上がった。
「なんと!」彼は叫んだ。「ベインズが奴を捕まえたっていうのか?」
「どうやら、そのようだ」と私は記事を読み始めた。
「昨夜遅く、オクショット殺人事件に関して逮捕が行われたという知らせがエシャーと周辺地域に大きな興奮をもたらした。ご存知のとおり、ウィステリア・ロッジのガルシア氏はオクショット・コモンで遺体となって発見され、その身体には激しい暴力の痕があった。同じ夜、彼の従者と料理人が逃亡したことで、彼らが事件に関与しているのではないかと疑われた。被害者が家に貴重品を所持していた可能性が示唆されたが、それが動機かどうかは証明されていなかった。事件を担当したベインズ警部は、逃亡者の隠れ家を突き止めるためあらゆる手段を尽くし、彼らが遠くへは行かず、あらかじめ用意された避難先に潜んでいると考えていた。しかし、警察は当初からいずれは発見できると確信していた。なぜなら、料理人の外見が非常に特徴的で、黄色がかった顕著な黒人型の顔立ちをした大柄で醜いムラートであったからだ。事件後も、この男は目撃されている。同じ夜、彼は大胆にもウィステリア・ロッジを再訪し、ウォルターズ巡査に発見され追跡された。ベインズ警部は、この訪問には何らかの目的があり、再び現れると予想して、家を放棄したうえで植え込みに待ち伏せを設けていた。昨夜、男はその罠にかかり、抵抗の末、ダウニング巡査が激しく噛みつかれたが、ついに捕らえられた。被疑者は裁判所に連行される際、警察は勾留を申請し、今後大きな展開が期待されているという。」
「これはすぐにベインズに会わねば」とホームズは帽子を手に叫んだ。「出発する前にきっと捕まえられるはずだ。」私たちは村の通りを急ぎ、予想通り警部がちょうど宿を出るところを見つけた。
「新聞を見ましたか、ホームズさん?」と彼は新聞を差し出してきた。
「ええ、ベインズ、見ましたよ。お節介に思わないでいただきたいのですが、ひとつ友人として警告を申し上げたい。」
「警告ですか、ホームズさん?」
「私は慎重にこの事件を調べましたが、あなたが正しい線に乗っているとは確信できません。確信がなければ、あまり深入りしないほうがいいですよ。」
「ご親切にありがとうございます、ホームズさん。」
「あなたのためを思って言っているのです。」
ベインズの小さな目が一瞬、ウインクしたように私には見えた。
「お互い自分のやり方でやると約束しましたからね、ホームズさん。私は自分の道を行きます。」
「それは結構」とホームズ。「私を責めないでくださいよ。」
「ええ、先生、あなたが悪意で言っていないのは分かっています。でも、それぞれ自分のやり方がありますよ、ホームズさん。あなたにはあなたの、私には私の。」
「もうこの話はやめましょう。」
「情報はいつでもどうぞ。この男はまるで野蛮人で、馬車馬のような怪力で、悪魔のごとく凶暴です。ダウニングの親指を噛みちぎりそうになったほどです。英語はほとんど話さず、うめき声しか出しません。」
「あなたは彼が主君を殺した証拠を掴んだと?」
「私はそうは言っていませんよ、ホームズさん。そうは言っていません。それぞれ自分のやり方があります。あなたはあなたの、私は私の。それが約束です。」
ホームズは肩をすくめて私と歩き出した。「この男はよく分からない。どうやら墓穴を掘っているようにも見える。まあ、彼の言う通り、お互い自分のやり方でやってみて、どうなるか見てみよう。だが、ベインズ警部には何か腑に落ちないところがある。」
「ワトソン、あの椅子に座ってくれ」とホームズはバルの宿に戻ると私に言った。「状況を整理しておきたい。今夜君の助けが必要になるかもしれないからね。これまでの事件の経過を説明しよう。表面的には単純な事件だったが、逮捕に至るまでには驚くほどの困難があった。まだその点で埋めるべき隙間がある。
「まず、ガルシアが死んだ夜に受け取った手紙に戻ろう。ベインズ警部はガルシアの召使いたちが関与したと考えているが、それは違う。なぜなら、ガルシア自身がスコット・エクルズの滞在を手配していた――つまりアリバイ工作が目的だったからだ。ガルシアはその夜、何らかの計画を進めており、それは明らかに犯罪的なものだった。犯罪を計画する者だけがアリバイを用意するからだ。では、彼の命を奪ったのは誰か? それは当然、その犯罪計画の標的となった人物だろう。この点までは論理的に間違いない。
「ここでガルシアの家族の失踪理由が見えてくる。彼らも皆、謎の計画の共犯者だったのだ。計画が成功してガルシアが戻れば、イギリス人(スコット・エクルズ)の証言で疑いを逃れることができる。だが、もしガルシアが定められた時間までに帰らなければ、自分の命が犠牲にされたと判断し、二人の部下はあらかじめ決められた場所に逃げ込み、再度計画を立て直す――そう合意していた。その説明で事実はすべて整合するだろう?」
絡み合った謎が一気に解きほぐされた気がした。なぜこんな単純なことに今まで気づかなかったのかと、いつものように私は不思議に思った。
「でも、なぜ一人の召使いが戻ったのです?」
「逃走の混乱の中で、どうしても捨てられない何か大切な物を忘れてきたと考えれば説明がつく。だから何度も戻ろうとしたのだろう?」
「では、次の手は?」
「次は、ガルシアが夕食時に受け取った手紙だ。これは、もう一方の共犯者がいることを示している。では、それはどこだ? それが大きな屋敷でなければならないことは、すでに説明した通りだ。私は村に来てから、植物採集の合間を縫って大きな屋敷をすべて見て回り、住人の経歴も調べた。一軒だけ、心を捉える屋敷があった。オクショットの向こう側にある歴史あるジャコビアン様式のグランジ、ハイ・ゲーブルだ。現場からわずか半マイルほどしか離れていない。他の屋敷は、平凡で堅実な人々が住んでいて、ロマンとは無縁だ。しかしハイ・ゲーブルのヘンダーソン氏は、どうやら一風変わった人物で、奇妙な事件が起こる可能性が高い。私は彼とその家族に注意を集中した。
「個性的な連中だ、ワトソン――中でも本人が最も異彩を放つ。私は口実を設けて彼に会ったが、彼の深く暗い目を見て、私の真意を見抜いていると感じた。五十歳くらいで、体格はがっしりし、活発、鉄灰色の髪、黒々とした眉が盛り上がり、鹿のような足取りと皇帝の風格――激しく支配的な男だ。外国人か、長年熱帯地方に住んでいたのだろう。肌は黄色く、精気がないが、ムチのようにしなやかだ。友人で秘書のルーカス氏も明らかに外国人で、チョコレート色の肌、狡猾で猫のような動き、毒を含んだ優しい口調だ。こうしてウィステリア・ロッジとハイ・ゲーブル、二つの外国人グループが浮上してきた。謎が次第に繋がり始めている。
「この二人が家の中心で親密な関係だが、我々にとってもっと重要な人物がいる。ヘンダーソンには十一歳と十三歳の娘がいて、家庭教師のミス・バーネットは四十歳前後のイギリス人女性だ。忠実な従者も一人いる。この小さなグループこそが実質的な家族で、皆で各地を旅し回っている。ヘンダーソンは大変な旅行好きで、最近やっと一年ぶりにハイ・ゲーブルへ戻ってきた。巨万の富を持ち、どんな気まぐれも満たせる男だ。他には執事や下男、女中など、大邸宅によくいる、働きもせず食べ過ぎの使用人が大勢いる。
「この辺りの情報は村の噂と自分の観察で手に入れた。恨みを持つ解雇された使用人ほどいい情報源はない。たまたま、ヘンダーソンの癇癪で解雇された元庭師、ジョン・ワーナーを見つける幸運に恵まれた。ただし、こういう幸運は、私が日頃から狙っていたからこそ舞い込んだものだ。ベインズの言う通り、みな自分の方法がある。私のやり方が、ハイ・ゲーブルの秘密を解く鍵となった。ワーナーには屋敷内にも仲のいい使用人仲間がいて、皆が主人を恐れ嫌っていた。
「不思議な連中だ、ワトソン! まだ全貌は分からないが、とにかく奇妙な人々だ。家は二つの棟に分かれていて、使用人は片側、家族は反対側に住んでいる。両者を繋ぐのはヘンダーソンの従者が家族の食事を運ぶための一つの扉だけ。家庭教師と子供たちはほとんど外出せず、庭に出る程度。ヘンダーソンは決して一人で歩き回らず、暗い秘書が必ず付き従っている。使用人の間では、主人が何かをひどく恐れているという噂が絶えない。『悪魔に魂を売り、その借金取りが現れるのを怖れている』とワーナーは言う。彼らがどこから来たのか、誰なのか、誰も知らない。主人はとても暴力的で、二度も犬鞭で人を打ち、長い財布と高額の示談金で訴訟沙汰を免れてきた。
「さて、ワトソン、この新情報で状況を判断しよう。手紙はこの奇妙な家族から出され、あらかじめ計画された何かをガルシアに実行させる誘いだった。手紙を書いたのは誰か? 館の内部の誰かで、しかも女性だ。ならばミス・バーネットしか考えられない。すべての論理がそこへ収束している。とりあえず仮説として、どんな帰結をもたらすか見てみよう。ミス・バーネットの年齢と性格から、恋愛要素はあり得ないことも加えておく。
「もし彼女が手紙を書いたなら、彼女はガルシアの友人で共犯者だったはずだ。では、彼の死を知ってどうするだろう? もし彼が犯罪行為中に死んだなら、彼女は口を閉ざすかもしれない。しかし心の中では、彼を殺した者への憎悪があり、可能ならば復讐に協力するだろう。では、彼女に会い、協力を求めるべきか? それが最初に考えたことだ。だが、ここで陰惨な事実に突き当たる。ミス・バーネットは殺人の夜以来、誰の目にも触れていない。その晩を境に、完全に姿を消したのだ。彼女は生きているのか? ガルシアと同じ晩に命を落としたのか? それとも囚われの身なのか? ここがまだ解決していない点だ。
「ワトソン、この状況の困難さを分かってくれるだろうか。令状を請求できる根拠が何もない。我々の推理を裁判官に持ち込んでも、荒唐無稽に見えるだろう。女性の失踪も、この異常な家庭では一週間誰も姿を見せなくても何の不思議もない。だが、今この瞬間にも彼女の命が危ういかもしれない。できることは家を見張り、門でワーナーに警戒させることだけだ。このまま放置はできない。法律が動けないなら、我々が危険を冒すしかない。」
「どうするつもりだ?」
「彼女の部屋の場所は分かっている。屋外の建物の屋根から入れる。今夜、君と二人で、事件の核心に迫れるかどうか確かめに行こうと思う。」
告白しておくが、これはあまり気乗りのする冒険ではなかった。殺人の陰をひきずる古い屋敷、奇妙で手強い住人たち、近づく際の未知の危険、そして法的に不利な立場に自らを置くこと――これらすべてが私の熱意を冷ました。しかし、ホームズの氷のように冷静な理詰めに、どんな冒険も躊躇できなくなる力があった。唯一の解決策がこれしかない――私は黙って彼の手を握り、覚悟を決めた。
だが、私たちの調査がそこまで波乱に満ちた結末を迎える運命ではなかった。午後五時ごろ、三月の夕べの陰りが部屋に迫ってきた時、興奮した田舎者が飛び込んできた。
「行きましたよ、ホームズさん。最後の列車で出ていきました。あの女性は逃げ出して、私は下の馬車に乗せてきました。」
「見事だ、ワーナー!」とホームズは跳ね上がって叫んだ。「ワトソン、謎が急速に解けていくぞ。」
馬車の中には神経衰弱で半ば気を失った女性がいた。鷲鼻でやせ細った顔には、悲劇的な出来事の痕跡が刻まれている。彼女は首をうなだれていたが、やがて顔を上げ、虚ろな目を私たちに向けた。瞳孔は濃い点となり、灰色の虹彩の中心に沈んでいる。アヘンで朦朧としていたのだ。
「門で見張りをしていましたよ、言われた通りにね、ホームズさん」と、元庭師のワーナーは語った。「馬車が出てくるのを見て、駅まで追いました。女性は夢遊病者のようでしたが、列車に乗せようとした時だけ正気に戻って暴れました。車両に押し込まれそうになったのを、私が助けて馬車に乗せてきたんです。彼の顔――黒い目で睨みつける、あの黄色い悪魔――あれを見たら、私の命なんてすぐ終わりでしょうね。」
私たちは彼女を二階に運び、ソファに寝かせ、濃いコーヒーを二杯飲ませると、すぐに薬の霞が晴れていった。ホームズがベインズ警部を呼び寄せ、状況を手短に説明した。
「いやあ、先生、まさに私の欲しかった証拠を持ってきてくれましたよ」と警部は熱心にホームズの手を握った。「私も最初から同じ線で考えていました。」
「なに、君もヘンダーソンを追っていたのか?」
「ええ、ホームズさん、あなたがハイ・ゲーブルの植え込みで這い回っていたとき、私はその上の林の木の上にいました。どちらが先に証拠を掴むかの勝負だったんですよ。」
「それならなぜムラートを逮捕したんだ?」
ベインズはくすりと笑った。
「ヘンダーソン――彼の呼び名です――が自分が疑われていると感じていたのは確かです。そして、危険だと感じている限りは身を潜めて動かないだろうと思った。だからわざと間違った男を逮捕して、警戒を解かせたんです。そうすれば逃げ出すだろうし、ミス・バーネットに接触する機会ができると睨んだ。」
ホームズは警部の肩に手を置いた。
「君は出世するよ。直感と勘がある」と称賛した。
ベインズは嬉しそうに顔を赤らめた。
「駅には一週間ずっと私服警官を張り込ませていました。ハイ・ゲーブルの連中がどこへ行こうが、彼が見張っていました。でもミス・バーネットが脱出した時はさすがに手こずったでしょうが、あなたの男が拾ってくれて、すべてうまくいきました。彼女の証言なしには逮捕できませんから、早く供述を取るべきですね。」
「どんどん元気になってきている」とホームズは家庭教師を見て言った。「ところでベインズ、このヘンダーソンという男は何者なんだ?」
「ヘンダーソンの正体はドン・ムリーリョ――かつてサン・ペドロの虎と呼ばれた男です。」
サン・ペドロの虎! その男の全歴史が瞬時に私の脳裏に蘇った。かつて文明国を僭称する国を治めた中でも最も好色で血に飢えた暴君として名を馳せた男。強く、恐れ知らずで精力的、わずかばかりの美徳があったがゆえに、卑劣な悪徳を十年、十二年もの間、民を屈服させて押し付けることができた。その名は中米全域に恐怖をもたらした。やがて全国的な反乱が起きたが、彼は残忍さと同じだけ狡猾でもあり、危機を察知すると忠実な部下たちの操る船で財宝を密かに運び出していた。翌日叛徒たちが襲ったのは、もぬけの空の宮殿だった。独裁者と二人の子供、秘書、財宝はすべて消えていた。その瞬間から彼は世界から姿を消し、その正体は欧州メディアでたびたび話題になった。
「ええ、先生、ドン・ムリーリョ、サン・ペドロの虎です。調べれば分かりますが、サン・ペドロの旗の色は緑と白――あの手紙と同じです。ヘンダーソンと名乗っていましたが、私はパリ、ローマ、マドリードからバルセロナまで追跡しました。船が入港したのが86年。ずっと復讐の手が彼を狙っていましたが、ようやく居場所が知れたのです。」
「彼の所在が一年ほど前に判明したのです」とミス・バーネットが座り直し、緊張した面持ちで口を開いた。「すでに一度、命を狙われたことがありますが、何か邪悪な運命が彼を守りました。今回も、高貴で騎士的なガルシアが犠牲になり、怪物だけが無事だったのです。でも、また別の者が現れ、さらにまた次が現れ、いつか必ず正義が下るでしょう。それは明日の太陽が昇るのと同じくらい確かなことです。」彼女の細い手は固く握られ、やつれた顔は憎悪の激情で青ざめていた。
「だが、あなたはなぜこの事件に関わったのです?」とホームズが尋ねた。「イギリス人女性がどうしてこんな殺伐とした計画に?」
「他に正義を得る道が世界のどこにもないからです。イギリスの法律が、何年も前にサン・ペドロで流された膨大な血や、この男が略奪した財宝にどれほど関心を持つでしょう? あなたにとっては、まるで他の惑星で起きた犯罪のようなものでしょう。でも私たちは違います。悲しみと苦しみの中で真実を知ったのです。私たちにとって、地獄の悪鬼フアン・ムリーリョほど恐ろしいものはなく、犠牲者たちがいまだに復讐を叫ぶ限り、安らぎはありません。」
「確かに、あなたの言う通りだろう。彼が残虐だったことは聞いている。でも、あなた個人にはどんな関係が?」
「すべてお話しします。この悪魔は、将来有力なライバルになりそうだと思った男を、何かと理由をつけて殺害するという方針でした。私の夫――はい、私の本名はシニョーラ・ヴィクトル・デュランド――はロンドンのサン・ペドロ公使でした。彼と出会い、結婚しました。あれほど高潔な人は地上にいませんでした。不幸にも、ムリーリョは夫の評判を聞きつけ、不当な理由で本国に召還し、即座に銃殺したのです。夫は最期を予感し、私を連れて行きませんでした。彼の財産は没収され、私はわずかな蓄えと打ちひしがれた心だけでロンドンに残されました。
「それから、暴君が失脚しました。逃亡したのは今お話しされた通りです。しかし、彼の手で人生を破壊され、最愛の人を拷問や死に追いやられた者たちは、このままでは済ませませんでした。彼らは決して解散しない復讐の同盟を結んだのです。変装したヘンダーソンの正体が明らかになった後、私の役目は彼の家族に入り込み、仲間たちに動向を知らせることでした。そのため、家庭教師の職を獲得できたのです。彼は、毎日向き合って食事をしていた女が、自分の手で夫を永遠に葬り去った女とは夢にも思いませんでした。私は彼に微笑み、子供たちの世話をし、時を待ち続けました。パリでも暗殺未遂があり失敗。ヨーロッパ中を素早く転々とし、ついにイギリスに来てこの館を借りました。
「しかし、ここにも正義の使者は待ち構えていました。ガルシア――彼はサン・ペドロの元最高官の息子です――が忠実な二人の仲間とともに、復讐の念に燃えて待ち構えていました。昼間は何もできません。ムリーリョは用心深く、秘書ルーカス――全盛期にはロペスと呼ばれた男――としか外出しません。しかし夜は一人で寝るので、復讐者が狙えるのです。ある晩、私は最終指示を送りました。というのも、ムリーリョは常に警戒し、寝室をしょっちゅう替えていたからです。私は扉が開いているか確認し、車道に面した窓の緑もしくは白い光で、計画決行か延期かを伝えることになっていました。
「ですが、すべてが裏目に出ました。私の様子にロペスが不審を抱いたのです。彼は私の背後から忍び寄ってきて、手紙を書き終えたところで飛びかかりました。彼と主人は私を部屋に引きずり込み、裏切り者として裁判にかけました。その場で殺すことも考えたようですが、罪を逃れる手立てがなかったので踏み切れませんでした。長い議論の末、私の殺害は危険すぎると判断し、代わりにガルシアをこの世から永遠に排除することに決めました。私は口を塞がれ、ムリーリョに腕をねじられて住所を白状させられました。彼があと一歩で腕をもぎ取るほどの力でなければ、ガルシアの命がどうなるか気づいていたでしょう。ロペスが私の手紙の宛名を書き、袖口ボタンで封印し、従者ホセに持たせて送りました。彼らがガルシアをどう殺したのかは知りませんが、現場にいたのはムリーリョで、ロペスは私の監視役でした。恐らく、ガースの茂みで待ち伏せし、通りかかった瞬間に襲ったのでしょう。最初は家に侵入させ、泥棒として殺す案もあったようですが、もし捜査の渦中に巻き込まれれば正体が世間に知られ、さらなる復讐の口実を与えると考えたのです。ガルシアの死によって、後続の追手が怯んで断念することを期待していました。
「私が彼らの犯行を知っているという事実がなければ、すべてうまくいったでしょう。私の命も常に危険にさらされていたはずです。私は部屋に幽閉され、恐ろしい脅迫におびえ、精神を打ち砕くような虐待を受けました――この肩の刺し傷や腕中のあざをご覧ください。窓から助けを呼ぼうとした時には口を塞がれました。五日間、ほとんど食べ物もなく、生きるのがやっとの監禁生活が続きました。今日の午後になって、やっとまともな食事が出されましたが、口にした途端に薬が盛られていたと分かりました。夢うつつの中で、半ば引きずられるように馬車に乗せられ、同じくして列車へ運ばれました。列車が動き出す直前、やっと自力で脱出できることに気がつき、飛び降りました。再び引き戻されかけましたが、この親切な方の助けで馬車に乗せてもらい、無事逃げ延びました。今はもう、神に感謝します、二度とあの人たちの手にはかかりません。」
私たちは皆、この衝撃的な証言にじっと聞き入っていた。沈黙を破ったのはホームズだった。
「まだ困難は残っています」と彼は首を振った。「警察の仕事は終わりましたが、今度は法廷での仕事が始まります。」
「その通りです」と私は言った。「弁護士なら正当防衛だと主張するでしょう。背景に百もの罪があったとしても、裁けるのはこの一件だけです。」
「いやいや」とベインズは明るく言った。「法の力をもっと信じていますよ。正当防衛と、冷静な計画のもとで殺人を誘い出すのは別物です。どんな危険があろうと、冷血な殺意は許されません。いずれハイ・ゲーブルの住人たちがギルフォードの裁判所に立つのを見ることになるでしょう。」
だが、実際にはサン・ペドロの虎が報いを受けるまでにはまだ時間がかかった。狡猾で大胆な彼と従者は、エドモントン・ストリートの下宿屋を表から入り、裏口からカーズン・スクエアに抜けることで追跡の手を逃れた。その日以来、イギリスで彼の姿を見た者はいなかった。半年後、マドリッドのエスクリアル・ホテルでモンタルヴァ侯爵と秘書のルーリ氏が部屋で殺害された。犯行はニヒリズムによるものとされたが、犯人は捕まらなかった。後日、ベインズ警部が、秘書の暗い顔立ちと、主人の威厳ある特徴的な黒い目、盛り上がった眉についての人相書きを持ってベイカー街を訪ねてきた。私たちには、ついに遅ればせながら正義が下ったことに疑いの余地はなかった。
「混沌とした事件だったよ、ワトソン君」とホームズは晩のパイプをふかしながら言った。「君の好きな、あの簡潔な形にはまとめられないな。大陸二つにまたがり、二つの謎の集団の関与、しかもスコット・エクルズというごくまっとうな人物の存在――ガルシアには策士の才と強い自己保存本能があった証拠だ。注目すべきは、可能性の密林の中で我々が、協力者である警部とともに、本質を見失わず、曲がりくねった道を進み続けられたことだ。他に分からない点はあるか?」
「ムラート料理人が戻った理由は?」
「台所の妙な品が理由だろう。あの男はサン・ペドロ奥地の原始的な野蛮人で、あれが彼の呪物だった。逃亡後、仲間と事前に決めた隠れ家に潜んだ――そこにはすでに共犯者がいたのだろう――が、仲間にあんな目立つものは置いて行けと説得された。しかしムラートの心はそれに執着し、窓から偵察してウォルターズ巡査の姿を見つけて断念。三日間待った後も、信仰心か迷信に駆られて再度試みた。ベインズ警部は、私にはこの事件を軽く扱ってみせたが、実際には重要性を見抜いて罠を仕掛けていた。ほかに疑問は?」
「引き裂かれた鳥、血の入ったバケツ、焼け焦げた骨――あの異様な台所の謎は?」
ホームズは手帳をめくって微笑んだ。
「その件や他の点について、大英博物館で調べた。エッカーマンの『ヴードゥー教と黒人宗教』から引用しよう。
『本物のヴードゥー信者は、重要な行動の前には必ず犠牲を捧げる。それは穢れた神々の歓心を買うためである。極端な場合、人間を生贄にし、食人に及ぶことさえある。だが一般的には、生きたまま羽をむしる白い雄鶏か、喉を切って焼く黒い山羊が供えられる。』
――つまり、あの野蛮人は本格的な儀式に従っていたということさ。グロテスクだが、ワトソン、『グロテスク』と『恐ろしい』の間には紙一重の差しかないと、私はたびたび言ってきたね。」
ブルース=パーティントン設計書
1895年11月第3週、ロンドンは黄色く濃い霧に包まれていた。ベーカー街から向かいの家が見えることさえほとんどなく、月曜から木曜まで、一度も霧が晴れることはなかったと思う。初日はホームズが膨大な参考書カードの整理に明け暮れ、二日目と三日目は近ごろ趣味となった中世音楽の研究に忍耐強く時間を費やしていた。しかし、四日目の朝食後、椅子を引いてもなお重く粘つく褐色の渦が窓にまとわりつき、油じみた雫となってガラスに滴るのを見て、彼のせっかちな活動的気質も、これ以上冴えない日々に耐えられなくなった。彼は居間を落ち着きなく歩き回り、爪を噛み、家具を叩き、何もできないことにいら立っていた。
「新聞に何か面白いことはないか、ワトソン?」と彼は言った。
ホームズの言う「面白いこと」とは、つまり犯罪のことである。革命のニュース、戦争勃発の噂、政権交代の予兆などは載っていたが、彼の関心の範囲には入らない。私には、犯罪に関する記事といっても、ありふれて取るに足らないものばかりに見えた。ホームズはうめき声をあげ、再び部屋をそぞろ歩き始めた。
「ロンドンの犯罪者どもは全く退屈だな」と、獲物に恵まれなかった猟師のような不平気な声で言った。「この窓から外を見てごらん。人影がぼんやり浮かび上がり、うすら見えてはまた霧に消える。こんな日は、泥棒や殺人者は虎がジャングルをうろつくようにロンドンを歩き回れる。誰にも見つからず、現れるのは犠牲者の前だけだ。」
「ここのところ、小さな盗難事件は多発しているようですよ」と私は言った。
ホームズは鼻で笑った。
「こんな陰鬱な舞台が、そんな瑣末な事件のために用意されたとは思えない」と彼は言った。「もし私が犯罪者なら、この街は大混乱だろう。」
「全くその通りです!」と私は心から同意した。
「もし私がブルックスやウッドハウス、私の命を狙う五十人の誰かだったら、自分自身を追跡されたらどれだけ生き延びられるだろうか? 偽の呼び出し一つで終わりだ。ラテン国――暗殺の国――でこんな霧があったら大変なことだ。おや! やっとこの退屈な日々を破るものが来たぞ。」
メイドが電報を持ってきた。ホームズはそれを開くなり、どっと笑い出した。
「さて、さて! 今度は何が起きる?」と彼は言った。「マイクロフト兄さんがやって来る。」
「なぜ?」と私は尋ねた。
「なぜだと? 田舎道でトラムを見かけるようなものだ。マイクロフトは決まったレールを走る人間だ。パル・マルの宿、ディオゲネス・クラブ、ホワイトホール――それが彼の生活路線。かつて一度だけここに来たことがあるが、彼の路線を脱線させるものが何だというんだ?」
「説明はないのか?」
ホームズは兄の電報を私に手渡した。
| 「カドガン・ウェストの件で至急会いたい。今すぐ行く。」 |
| マイクロフト |
「カドガン・ウェスト? その名は聞いたことがある。」
「何も思い出せないね。でも、マイクロフトがこんな突飛な行動を取るなんて! まるで惑星が軌道を外れるようなものだ。ところで、マイクロフトがどんな人物か知っているか?」
私は「ギリシャ語通訳事件」のときに説明を受けたような朧げな記憶があった。
「君は政府の下で小さな役職を持っていると言っていたね。」
ホームズはくすりと笑った。
「当時の私は、君のことをそこまでよく理解していなかった。国家の重大事について語るときは慎重にならざるを得ない。彼が政府の下にいると考えるのは正しいよ。場合によっては、彼自身が“英国政府そのもの”と言っても過言ではない。」
「そんな馬鹿な、ホームズ!」
「驚かせようと思ったのさ。マイクロフトは年に四百五十ポンドの報酬を受け取り、ずっと下級職のままだ。野心もなければ、名誉や称号にも興味がない。ただし、国で最も必要不可欠な男であることは間違いない。」
「どうしてだい?」
「彼の地位は唯一無二だ。自分で築き上げたものさ。過去にも、これからも、似たような例は現れないだろう。彼はこの世で一番きちんとしていて、整理整頓された頭脳を持ち、情報を蓄積する能力にかけては誰にも引けを取らない。私が犯罪捜査に使っているのと同じ能力を、彼はこの特別な職務に使っている。すべての省庁の結論が彼の元に集まり、彼が中央取引所、つまり清算所となって調整をする。ほかの人間はみな専門家だが、彼の専門はあらゆる分野に通じていることだ。たとえば、ある大臣が、海軍、インド、カナダ、そして金銀複本位制の問題にまたがる情報を必要としたとしよう。各省庁から個別に報告を受けることはできても、すべてを総合し、それぞれがどう影響し合うかを即座に言えるのはマイクロフトだけだ。最初は彼のことを近道や便利屋として使っていたが、今や不可欠な存在になってしまった。彼の偉大な頭脳にはすべてが仕分けされ、瞬時に引き出せる。何度も彼の一言が国家の方針を決定したことがある。彼はそれが生きがいで、他のことは考えない。せいぜい私が訪ねて小さな問題について助言を求めるときだけ、頭をほぐす知的な遊戯として付き合ってくれるくらいだ。でも今日は木星が降りてくる。いったい何を意味するのか? カドガン・ウェストとは誰で、彼はマイクロフトとどう関係しているのか?」
「わかった!」と私は叫び、ソファの上の雑然とした書類の山に飛び込んだ。「あった、確かにここにある! カドガン・ウェストは、火曜日の朝、地下鉄で死体となって発見された若者だ。」
ホームズは身を乗り出し、パイプを唇に運ぶ途中で手を止めた。
「これは重大な事件に違いない、ワトソン。兄の習慣を変えさせた死とは尋常ではない。彼がどう関わっているのだろう? 私の記憶では、特に特徴のない事件だった。若者は電車から落ちて死んだらしい。財布も盗まれておらず、暴力の疑いもなかった。違うか?」
「検死審問があったよ」と私は言った。「新しい事実がいくつも明らかになった。よく調べてみると、実に奇妙な事件だと思う。」
「兄の反応からして、かなり異例の事件だろう。」彼は安楽椅子にすっぽりと体を沈めた。「さて、ワトソン、事実を聞かせてくれ。」
「男の名はアーサー・カドガン・ウェスト。二十七歳で独身。ウーリッジ兵器廠の事務員だった。」
「政府関係の職か。それで兄マイクロフトと繋がるわけだ。」
「月曜の夜、突然ウーリッジを出た。最後に目撃したのは婚約者のヴァイオレット・ウェストベリー嬢で、彼女を霧の中に置き去りにして午後七時半ごろ突然姿を消した。二人の間に喧嘩はなく、彼女にも理由は分からない。その後の消息は、ロンドンの地下鉄オルドゲイト駅付近で、軌道工のメイソンに死体を発見されるまで不明。」
「いつ発見された?」
「火曜の朝六時。線路の左側、駅に近いトンネルの出口付近で、頭部がひどく潰れていた――電車からの転落と考えれば納得がいく傷だった。遺体が運ばれたとすれば改札を通らなければならないが、必ず集札がいるので、それは不可能。つまり転落以外に考えにくい。」
「なるほど。事件の大筋は見えた。死体は生死を問わず、電車から転落した。ここまでは明確だ。続けてくれ。」
「現場付近を通る電車は、西から東へ向かうメトロポリタン線とウィルズデン方面の列車のみ。彼が死亡したのは深夜のことで、どこから乗車したかは不明。」
「乗車券があれば分かるだろう。」
「ポケットにはなかった。」
「乗車券がないとは! ワトソン、これは実に奇妙だ。私の経験上、メトロポリタン線のホームには乗車券を見せずに入れない。つまり持っていたはずだ。持ち去られたのは出発駅を隠すためか? それとも車内に落としたのか? どちらも考えられるが、興味深い点だ。強盗の形跡はなかったのだね?」
「なかったようだ。所持品のリストがここにある。財布には二ポンド十五シリング。キャピタル・アンド・カウンティーズ銀行ウーリッジ支店の小切手帳。これで身元が確認された。そのほか、当日のウーリッジ劇場のドレスサークル券が二枚、技術書類の小包がひとつ。」
ホームズが満足そうに声を上げた。
「これで繋がったぞ、ワトソン! 英国政府――ウーリッジ兵器廠――技術書類――兄マイクロフト。すべてが繋がった。しかし、もしや彼自身が今、説明にやって来るのでは?」
間もなく、背が高く立派な体格のマイクロフト・ホームズが部屋に案内されてきた。大柄で重厚な体つきは、どこか鈍重な印象を与えたが、その上に載った頭部は、額が広く、鋼のような灰色の目が鋭く光り、唇は引き締まり、表情は実に繊細で、第一印象の肉体的な大きさを忘れさせるほどの知的な迫力を放っていた。
その後ろには、我々の旧友であるスコットランド・ヤードのレストレードが、痩せて厳しい顔つきで続いていた。二人の険しい表情は、重大な任務を予感させた。刑事は無言で握手し、マイクロフト・ホームズは重たい外套を脱ぎ、安楽椅子にどっかりと座った。
「実に厄介なことだよ、シャーロック。」彼は言った。「習慣を変えるのは大嫌いだが、上からの命令とあれば仕方がない。今のシャムの情勢を思えば、オフィスを離れるのは非常に困る。しかし、これは本当に危機だ。これほど首相が動揺したのを見たことがない。海軍省も蜂の巣を突いたような騒ぎだ。事件の内容は読んだか?」
「今しがた確認した。技術書類とは何だったんだい?」
「そこが肝心だ! 幸い、まだ公にはなっていない。もし報道されたら大騒ぎになる。あの不幸な青年が所持していたのは、ブルース=パーティントン型潜水艦の設計図だった。」
マイクロフト・ホームズは、事態の重大さを噛みしめるように厳粛な口調で語った。兄弟と私は身を乗り出して耳を傾ける。
「聞いたことがあるだろう? 誰でも知っていると思ったが。」
「名前だけだ。」
「その重要性は、いくら強調してもしすぎることはない。これまで最も厳重に守られてきた国家機密だ。私の話を信じてほしいが、ブルース=パーティントン型が運用される範囲では、海戦は不可能になる。二年前、多額の予算が秘密裏に計上され、技術の独占権を手に入れた。機密保持にはあらゆる手段が講じられてきた。設計図は極めて複雑で、三十もの特許を含み、そのすべてが不可欠だ。設計図は兵器廠隣接の機密オフィスの厳重な金庫に保管され、扉も窓も防犯仕様だ。どんな場合も設計図を外部に持ち出してはならず、海軍の主任技術官ですら、閲覧したければウーリッジのオフィスまで足を運ばなければならなかった。なのに、今やロンドンの中心で、下級事務員の死体のポケットから見つかったのだ。公式見解としては、まったく恐ろしい事態だ。」
「でも、取り戻したんだろう?」
「いや、シャーロック、違うんだ! そこが問題だ。回収できていない。ウーリッジから持ち出されたのは十枚。カドガン・ウェストのポケットにあったのは七枚。最も重要な三枚が行方不明――盗まれて、消えた。すべてを投げ打ってでも取り組んでくれ、シャーロック。警察裁判所のいつもの些細な事件なんか忘れてくれ。これは国家的な危機だ。なぜカドガン・ウェストが設計図を持ち出したのか、失われた三枚はどこにあるのか、彼はどうして死んだのか、なぜあの場所で死体が見つかったのか、どうすれば災厄を食い止められるのか。これらすべてに答えを出してくれれば、国に大きな貢献をしたことになる。」
「なぜ自分で解決しないんだい、マイクロフト? 君の観察力も僕に劣らないだろう。」
「確かに、シャーロック。しかし、問題は詳細を集めることだ。細部を僕に渡してくれれば、椅子に座ったまま専門家として立派な意見を返せるが、現場を走り回ったり、駅員にクロスチェックしたり、虫眼鏡で地面を這ったりするのは僕の役目じゃない。君こそが唯一この事件を解明できる人間だ。もし今度の叙勲リストに自分の名前を見たいなら――」
友人は微笑して首を振った。
「僕は謎解き自体が目的だ。だが確かに興味深い点が多い。ぜひ調べてみよう。もっと詳細を。」
「要点をこの紙に書き留めておいた。役立ついくつかの住所もある。設計図の公式な管理者は有名な政府専門家ジェームズ・ウォルター卿で、肩書きと勲章は参考書の二行分にもなる。長年の功績があり、上流階級でも招待客として名を連ね、しかも愛国心は疑いようがない。金庫の鍵を持つのは彼ともう一人だけだ。設計図は月曜の勤務時間中、確かにオフィスにあった。ウォルター卿は三時ごろロンドンに向かい、鍵を持って出た。事件の起きた夜はずっとバークレー・スクエアのシンクレア提督宅にいた。」
「その事実は確認済みか?」
「ああ、兄のヴァレンタイン・ウォルター大佐が出発を、シンクレア提督が到着を証言している。だからウォルター卿はもはや直接の関係者ではない。」
「もう一人の鍵の持ち主は?」
「主任事務員で製図技師のシドニー・ジョンソン氏。四十歳、既婚で五児の父だ。無口で陰気な男だが、公務員としての記録は概ね優秀。同僚には不人気だが、仕事は熱心。本人と妻の証言によれば、月曜の定時以降は自宅におり、鍵もいつも時計鎖に下げていて離さなかった。」
「カドガン・ウェストについて教えてくれ。」
「十年勤務し、良い働きをしていた。短気で高慢な面もあるが、正直で真っ直ぐな男として知られている。何も問題はなかった。職場ではジョンソン氏の次席で、毎日設計図と接触する役割だった。他に扱う者はいない。」
「その夜、設計図をしまったのは誰だ?」
「シドニー・ジョンソン主任です。」
「となると、持ち出したのは明らかじゃないか。カドガン・ウェストの身に実際に見つかった。それで決まりだろう?」
「そう思うが、それでは説明がつかないことが多すぎる。まず、なぜ彼は設計図を持ち出したのか?」
「価値があったからでは?」
「数千ポンドは簡単に手に入っただろう。」
「売る以外に、ロンドンへ持ち出す動機は?」
「私には思いつかない。」
「ならば、売るために持ち出したと仮定しよう。偽の鍵が必要だ。」
「複数の偽鍵だ。建物と部屋、両方を開ける必要がある。」
「では彼はいくつも偽鍵を用意したことになる。設計図を売るためにロンドンへ出向き、翌朝には元通り金庫に戻すつもりだったのだろう。その任務のさなか、ロンドンで死んだ。」
「どうやって?」
「ウーリッジに戻る途中で殺され、車両から投げ出されたと仮定しよう。」
「死体が見つかったオルドゲイトは、ウーリッジへの経路であるロンドン・ブリッジ駅よりもかなり先だ。」
「ロンドン・ブリッジを通過する理由はいくらでも考えられる。たとえば、車内で誰かと重要な話し合いをしていたとか。それが激しい口論となり、命を落とした。逃げようとして転落し、相手がドアを閉めた、というような。濃霧で何も見えなかった。」
「現時点では、それ以上の説明はできない。しかし、シャーロック、まだ多くの疑問が残る。もし仮に、カドガン・ウェストが設計図をロンドンへ運ぶ決心をしたのだとしても、普通は外国のスパイと会う約束を立て、その夜は予定を空けるはずだ。それなのに劇場のチケットを二枚買い、婚約者を半分まで送り、それから突然姿を消した。」
「カムフラージュだろう。」と、会話を少し苛立たしげに聞いていたレストレードが口を挟んだ。
「だが奇妙なカムフラージュだ。それが第一の異論。第二に、ロンドンでスパイに会ったと仮定しても、設計図は翌朝までに戻さなければ紛失が発覚する。十枚持ち出したが、七枚しか所持していなかった。残り三枚はどうしたのか? 自分の意思で手放すはずがない。それに、売却の対価は? ポケットに大金が入っているはずだ。」
「私にはすべて明白だ。」とレストレードは言った。「彼は設計図を売るつもりだった。スパイと会い、値段が折り合わなかった。帰ろうとしたが、スパイがついてきた。電車内で殺され、重要な設計図だけ奪われ、死体は車外に投げ出された。すべて説明がつくのでは?」
「なぜ乗車券がなかった?」
「乗車券があれば、スパイの家の最寄り駅が分かる。だから犯人が取ったのさ。」
「素晴らしい、レストレード。理論的にはよくまとまっている。しかし、これが真実なら、事件はもう終わったも同然だ。一方では裏切り者は死に、他方では設計図はすでに大陸に渡っただろう。われわれにできることがあるのか?」
「行動あるのみだ、シャーロック!」とマイクロフトは立ち上がった。「私の本能がこの説明を否定している。君の力を尽くしてくれ! 犯行現場を調べろ! 関係者に会え! 手を尽くせ! これほど国家に貢献できる機会はなかったはずだ。」
「さて、さて。」とホームズは肩をすくめた。「ワトソン、行こう。レストレード、少し付き合ってもらえるかな? まずはオルドゲイト駅を調べよう。マイクロフト、ではまた。夕方までには報告するが、あまり期待しないでくれ。」
一時間後、ホームズ、レストレード、私は地下鉄沿線、ちょうどオルドゲイト駅手前のトンネル出口に立っていた。鉄道会社の高齢で愛想のよい紳士が案内役だった。
「ここが青年の遺体があった場所です。」と彼は線路から三フィートほど離れた地点を指した。「上から落ちるのは不可能です。ご覧の通り壁ですから。つまり電車から落ちるしかなく、月曜の深夜ごろ通った列車しか考えられません。」
「車両に暴力の痕は?」
「ありませんし、乗車券も見つかっていません。」
「ドアが開いていたという記録は?」
「ありません。」
「今朝、新しい証言が入った。」とレストレード。「月曜夜十一時四十分ごろ、普通のメトロポリタン列車でオルドゲイトを通過した乗客が、駅直前で重い物体が線路に落ちる鈍い音を聞いたそうです。ただし濃霧で何も見えなかった。特に届け出もしませんでした。――どうかしましたか、ホームズさん?」
友人は線路のカーブと分岐を食い入るように見つめ、唇を引き結び、鼻孔を震わせ、太い眉をぐっと寄せて、極度の集中の表情を浮かべていた。
「分岐だ……分岐。」
「それがどうした? どういう意味だ?」
「この路線に分岐は多くないのですね?」
「ええ、少ないです。」
「しかもカーブ。分岐とカーブ。――もしや……!」
「何ですか、ホームズさん? 手がかりですか?」
「着想です――まだ兆し程度。ただ、ますます面白くなってきた。唯一無二、まさに独特な事件だ。だが……線路上に血痕は?」
「ほとんどありませんでした。」
「だが頭部にはかなりの傷があったはず。」
「骨は砕けていましたが、外傷はそれほどでも。」
「それでも出血してよさそうなものだ。あの夜、線路に血痕がなかったということは、別の場所で出血した証拠では? ところで、あの“鈍い音”を聞いたという列車は調べられますか?」
「残念ながら、その列車はすでに解体され、車両も他に再配分されています。」
「大丈夫です、ホームズさん。」とレストレード。「私自身がすべての車両をくまなく調べました。」
ホームズはやや苛立ちを隠せない様子で言った。
「なるほど。だが、私が見たかったのは車両内部ではなかった。ワトソン、ここでできることは終わったな。もうこれ以上レストレードさんを煩わせる必要はない。次はウーリッジだ。」
ロンドン・ブリッジ駅で、ホームズは兄に電報を送り、私に見せた。
「闇の中に一条の光あり。ただしすぐ消えるかも。取り急ぎ、ベーカー街に届くよう、現在イギリスにいる外国スパイまたは国際エージェントの全リストと住所を使者に持たせてほしい。――シャーロック」
「これは役に立つぞ、ワトソン。」我々はウーリッジ行きの列車に乗り込んだ。「兄マイクロフトが本当に面白い事件を紹介してくれたお礼を言わねばな。」
友人の顔には、何か新しいヒントで思考が刺激されたとき特有の張りつめた活力がみなぎっていた。まるでだらけた猟犬が鋭い臭いに目を輝かせ、筋肉を躍動させるような変貌ぶりだった。
「ここには解くべき素材がある。」とホームズは言った。「自分の鈍さが悔やまれるよ。」
「今も私には見当もつかないよ。」
「私にも結末は見えない。ただ、ひとつの考えがある――それは、死は別の場所で起き、遺体は“車両の屋根”にあった、ということだ。」
「屋根の上に!」
「驚くだろう? だが、事実を考えてみてくれ。死体が発見されたのは、ちょうど列車がカーブし、分岐に差しかかる場所だ。屋根の上の物体が振り落とされるには格好の場所では? 分岐は車内の物には無関係だ。死体が屋根から落ちたか、さもなくばきわめて奇妙な偶然だ。そして血の問題。もし遺体が別の場所で出血していたなら、線路に血痕がないのも説明がつく。それぞれの事実は単独でも示唆的だが、重なると説得力が増す。」
「乗車券も!」と私は叫んだ。
「その通り。乗車券がなかった理由もこれで説明がつく。すべてが繋がる。」
「だが仮にそうだとしても、死の謎はさらに深まる。かえって不可解になる。」
「かもしれないな……。」ホームズはしばし沈思黙考し、やがてウーリッジ駅に着くまで黙り込んでいた。駅からタクシーに乗り、マイクロフトのメモを取り出した。
「これから午後の訪問をいくつかこなすぞ。まずはウォルター卿を訪ねよう。」
立派な庭のあるテムズ沿いの邸宅が、著名な官僚の家だった。到着した時、霧は晴れかけ、薄日が差していた。玄関の執事が応対した。
「卿は……今朝お亡くなりになりました。」
「なんと!」とホームズは驚愕の声を上げた。「死因は?」
「お入りいただき弟のヴァレンタイン大佐にお会いください。」
「そうしよう。」
薄暗い応接間で、五十代の背が高く美しい金髪の紳士――故人の弟が現れた。彼の目は血走り、頬はやつれ、髪も乱れており、家庭に突然の悲劇が訪れたことは明らかだった。話すことにさえ苦しそうだった。
「この忌まわしい醜聞のせいです。兄ジェームズ卿は名誉を何より重んじる人で、とても耐えられなかった。心が壊れたのです。彼は部の仕事を誇りにしており、今回の一件は打撃でした。」
「事件解明の手がかりを期待していたのですが。」
「警察に知っていることはすべて伝えたはずです。ウェストが犯人だと信じていましたが、他の事は全く信じがたい。」
「新しい情報はありませんか?」
「私自身は何も知りませんし、これ以上はご容赦ください。今はとても心を乱されておりますので、この面談も早めに終えていただきたい。」
屋敷を出て、ホームズはつぶやいた。
「予想外の展開だ。死因は自然か、それとも自殺か? もし後者なら、職務怠慢への自責の念だろうか? それは今後の課題として、次はウェスト家を訪れよう。」
町外れの小綺麗な家に、悲しみに沈む母親がいた。高齢の母は憔悴しており、話はできなかったが、側には蒼白の若い女性――ウェストの婚約者ヴァイオレット・ウェストベリー嬢がいた。彼女は最後に彼を見た人物だった。
「説明のしようがありません、ホームズさん。事件以来一睡もできず、何が本当なのか考え続けています。アーサーは世界で最も誠実で騎士道精神に富んだ愛国者です。国家機密を売るくらいなら自分の右手を切り落としたでしょう。彼を知る者なら、あり得ないと断言します。」
「しかし事実は?」
「ええ……認めます、説明できません。」
「金銭に困っていた?」
「いいえ、質素な生活で給料も十分。数百ポンドの貯金もあり、年明けに結婚する予定でした。」
「精神的に動揺していた様子は? 率直にお願いします。」
ホームズは彼女の様子の変化を見逃さなかった。彼女は顔を赤らめ、ためらった。
「はい。最近、何か気がかりなことがあったように思います。」
「いつから?」
「ここ一週間ほどです。思い詰めた様子で、心配事がありました。詰問したら、公式の仕事に関することで、“君にも話せないほど深刻だ”と言われました。それ以上は何も。」
ホームズは顔を曇らせた。
「続けてください。彼に不利でも、話していただきたい。」
「これ以上は……。ただ、何か言いかけてやめることが何度かありました。ある晩、機密の重要性について語り、外国のスパイなら高額で買うだろうとも言っていました。」
ホームズの表情はさらに硬くなった。
「他には?」
「こうも言っていました。“私たちはこの種のことに無頓着すぎる。裏切り者なら設計図を入手するのは簡単だ”と。」
「この発言は最近?」
「ええ、ごく最近です。」
「その最後の晩のことを。」
「劇場に行く予定でした。霧が濃くてタクシーは無理。歩いて向かい、途中でオフィスの近くを通りました。すると彼は突然、霧の中に駆け出しました。」
「何も言わずに?」
「叫び声を上げただけです。私はその場で待ちましたが、戻ってきませんでした。そのまま家に帰りました。翌朝、オフィスが開くと警察が来て、十二時ごろ悪い知らせを聞きました。ああ、ホームズさん、彼の名誉を救ってください。彼にとって何より大事なことでした。」
ホームズは悲しげに首を振った。
「ワトソン、次はオフィスを調べよう。」
タクシーで移動しながらホームズは言った。
「これではますますカドガン・ウェストに不利な状況だ。結婚を控え、金が必要だった。動機は十分。スパイに設計図の話までしている。危うく婚約者を共犯にするところだった。これはひどい。」
「でも、ホームズ、人物評価も大切じゃないか? それに、なぜ彼は彼女を道に残し、悪事に走ったのか?」
「まさにそこが疑問だ。ただし状況証拠は極めて不利だ。」
シドニー・ジョンソン主任事務員は、ホームズの名刺に敬意を払い、丁重に迎えてくれた。彼はやせ形で無愛想、眼鏡をかけた中年男性で、頬はやつれ、神経の高ぶりで手が震えていた。
「ひどいことです、ホームズさん。部長は亡くなり、ウェストも死に、設計図は盗まれた。月曜夜、私たちがドアを閉めた時点で、ここは政府内でも一番効率的なオフィスだったのに……まさかウェストがこんなことを!」
「彼の犯行と断定するのですか?」
「他の可能性が思いつきません。でも、私自身と同じくらい彼を信頼していました。」
「何時にオフィスは閉じました?」
「五時です。」
「閉めたのは?」
「いつも私が最後です。」
「設計図はどこに?」
「あの金庫です。私がしまいました。」
「警備員はいないのですか?」
「いますが他の部局も兼務です。元軍人で実に信頼できる男です。その晩は何も見ていません。もちろん霧は非常に濃かった。」
「もしウェストが就業後に侵入したいなら、三つの鍵が必要ですね?」
「その通りです。外扉、オフィス、金庫の三つ。」
「ウォルター卿とあなた以外に鍵の持ち主は?」
「私は金庫のみ。扉の鍵は持っていません。」
「ウォルター卿は整理整頓好き?」
「ええ、特にその三つの鍵は一つのリングにまとめていました。何度も見ています。」
「そのリングを持ってロンドンへ?」
「そう言っていました。」
「あなたの鍵は常に携帯?」
「ええ。」
「では、もしウェストが犯人なら、合鍵を作ったのだろう。しかし遺体からは合鍵が見つからなかった。もう一点、もしここで設計図を売るなら、コピーを作って原本はそのまま戻す方が安全では?」
「設計図を効果的にコピーするには相当な技術知識が要ります。」
「あなたかウォルター卿、もしくはウェストにはその知識が?」
「間違いありませんが、私を疑わないでください、ホームズさん。現物がウェストの身に見つかった以上、推測しても無意味です。」
「コピーで済むのに原本を持ち出したのは確かに奇妙だ。」
「奇妙ですが、事実です。」
「どの点を調べても不可解さが残る。失われた三枚は最重要なのですね?」
「その通りです。」
「三枚だけでブルース=パーティントン型の建造は可能?」
「海軍省にもそう報告したのですが、今日改めて図面を見直すと、返還された図面の一つに自動調節弁の図面が含まれていて、それがなければ建造は困難です。ただし、技術的には遅かれ早かれ突破されるでしょう。」
「それでも三枚は最重要なのですね?」
「間違いありません。」
「では敷地内を見学させてください。他に質問はありません。」
ホームズは金庫・部屋・鉄製のシャッターを調べた。そして外の芝生に出ると、ラウレルの木の枝が折れたり曲がったりしているのに気付いた。虫眼鏡で丹念に観察し、地面にかすかな痕跡も見つけた。最後に主任にシャッターを閉めてもらい、中央の合わせ目が完全に閉じきらず、外から室内の様子が見えることを示した。
「三日遅れで証拠は消えかけているが、何かの意味はあるかもしれない。さて、ワトソン、ウーリッジはこれ以上収穫がなさそうだ。ロンドンで更なる手がかりを探そう。」
だがウーリッジ駅に向かう途中、もう一つ収穫があった。窓口の駅員が、「月曜夜、カドガン・ウェストがロンドン行き八時十五分発ロンドン・ブリッジ行に乗るのを確かに見た」と証言した。彼は一人で三等の片道切符を買い、興奮と緊張で手が震え、お釣りも受け取りに苦労したという。時刻表から見ても、彼が七時半ごろ女性と別れた後、最初に乗れる列車だった。
「ワトソン、状況を再構成しよう。」ホームズはしばらくの沈黙の後に言った。「私たちが共に手がけた事件の中でも、これほど辿り着きにくい事件はなかった。新たな進展ごとに、次の難問が現れる。しかし、確実にいくつかの前進はあった。」
「ウーリッジでの我々の調査の結果は、全体として若いカドガン・ウェストにとって不利なものだった。しかし、窓辺の痕跡は、より好意的な仮説を支持するものだ。たとえば、彼が何らかの外国のエージェントに接触されたと仮定してみよう。極秘の誓約のもと、それについて誰にも話せなくなったとしても、婚約者に語った言葉からも分かるように、彼の思考には影響が及んでいたかもしれない。よろしい。では、彼がその晩、劇場に彼女と出かけていたとき、霧の中で偶然そのエージェントを見かけたとしよう。相手は事務所の方向へ向かっていた。彼は決断の早い、衝動的な男だった。義務が全てに優先した。彼は男を追跡し、窓に辿り着き、書類が盗まれるのを目撃し、犯人を追った。こうすれば、“原本でなくコピーを持ち出せばよいのに、わざわざ原本が盗まれるはずはない”という異論も解決できる。この外部の人物はどうしても原本を持ち出す必要があった。ここまでは筋が通っている。」
「次の段階は?」
「そこからが難しくなる。こんな状況なら、カドガン・ウェストが真っ先に犯人に飛びかかり、警報を鳴らすと考えるだろう。なぜ彼はそうしなかったのか? 書類を持ち出したのが、上司だった可能性は? それならウェストの行動も説明がつく。あるいは、上司が霧の中で彼をまいてしまい、ウェストは彼の部屋を知っているという前提で、先回りしてロンドンへ向かったのかもしれない。彼女を霧の中に立たせたまま連絡もせず出て行ったのだから、かなり切迫した事情だったのだろう。だが、ここで手がかりが途切れ、“どちらの仮説からも、ウェストの遺体が原本7点と共に地下鉄の屋根で発見される”までの間には大きな隔たりがある。今私の勘は逆方向から辿ることを促している。もしマイクロフトが住所リストをくれれば、容疑者を絞り、二つの線から追跡できるかもしれない。」
案の定、ベイカー街にはメモが届いていた。政府の使者が大急ぎで持ってきたものだ。ホームズはそれに目を通し、私に放り投げた。
末端の小物は多いが、これほど大がかりな件を扱う者は少ない。検討に値するのは、ウェストミンスター、グレート・ジョージ通り13番地のアドルフ・マイヤー、ノッティング・ヒル、カムデン・マンションズのルイ・ラ・ロティエール、ケンジントン、コールフィールド・ガーデンズ13番地のヒューゴー・オーバーシュタインのみ。最後の者は月曜日にロンドンにいたことが分かっており、すでに出発したらしい。何らかの手がかりをつかんだ由、安堵している。内閣は君の最終報告を極めて切迫して待っている。最高位からも厳しい要請が届いている。必要があれば国家権力を全て君の味方につける。――マイクロフト
「残念ながら」とホームズは微笑みながら言った。「女王陛下の騎馬隊も兵士も、この件には役立たないよ」彼は大きなロンドン地図を広げ、身を乗り出す。「さて、さて」とやがて満足げに叫んだ。「ようやく事態が我々の側に傾いてきた。ワトソン、これは本当にうまくいくかもしれないぞ」彼は突然愉快そうに私の肩を叩いた。「今から出かけてくる。ただの偵察だ。本格的な行動は信頼する相棒であり伝記作家である君が一緒でないとしない。ここで待っていてくれれば、1〜2時間で戻るだろう。暇なら、用紙とペンを用意して、“我々がいかにして国家を救ったか”の記録を書き始めてくれたまえ」
彼の高揚が私の心にも伝わった。彼がいつもの厳格な態度からここまで逸脱するのは、よほど喜ぶだけの理由があると分かっていたからだ。私は長い11月の夕べ、彼の帰りをいらだちながら待った。やがて9時を少し回ったころ、使いの者がメモを持ってきた。
ケンジントン、グロスター・ロードのゴルディーニ・レストランで食事中。すぐに来て合流してくれ。バール、暗いランタン、ノミ、リボルバーを持参のこと。――S.H.
薄暗く霧のたちこめる街を、紳士が持ち歩くには妙な装備だが、それらをそっと外套にしまい、指定の場所へ直行した。派手なイタリア料理店のドアそばの小さな丸テーブルに、友人は座っていた。
「何か食べたかね? ならコーヒーとキュラソーを一緒にどうだ。店主自慢の葉巻も吸ってみたまえ。思ったより毒性は弱い。道具は持ってきたか?」
「ここに、外套の中にある」
「よろしい。では、これまでの経過を簡単に説明し、今から何をするか話そう。ワトソン、君にも明らかなはずだが、この若者の死体は列車の屋根に“置かれた”ものだ。それは、彼が車内ではなく屋根から落ちたという事実を突き止めた瞬間から明らかだった」
「橋の上から落とされた可能性は?」
「それはありえない。屋根はわずかに丸みがあり、手すりもない。つまり、確実に“誰かが載せた”と断言できる」
「どうやって載せたんだ?」
「そこが最大の疑問だった。だが可能な方法は一つしかない。地下鉄はウエストエンドの一部区間で地上に出る。私は昔、乗車中に頭上すぐに窓が見えた記憶があった。もし、列車がそうした窓の下で停まれば、死体を屋根に載せるのは難しくない」
「まずありえない話に思えるが」
「すべての可能性が消えたとき、残るものがどんなにありえなくとも、それが真実であるという古い格言に頼るしかない。今回は他の全ての仮定が潰えた。ちょうどそのとき、ロンドンを発ったばかりの国際的エージェントが、地下鉄線路に面した家に住んでいると分かり、私が妙に陽気になった理由もそれだった」
「それが理由だったのか」
「そう。ヒューゴー・オーバーシュタイン、コールフィールド・ガーデンズ13番地が目標だ。最初にグロスター・ロード駅へ行き、親切な駅員に沿線を案内してもらった。コールフィールド・ガーデンズの裏階段の窓が線路に面しており、しかも大きな鉄道路線との交差のため、ちょうどその場所で地下鉄がしばしばしばらく停車することを確認した」
「素晴らしい、ホームズ! ついに掴んだな!」
「今のところは、だがな、ワトソン。進展はしているが、まだゴールは遠い。裏を見た後、正面も確認した。家はかなり大きく、上階は家具もほとんどない。オーバーシュタインは従者一人と暮らしていたが、彼も共犯者だろう。オーバーシュタインは戦利品をさばくため大陸へ行った。だが逃亡の意思ではない。逮捕状を恐れる理由はなかったし、素人の家宅捜索など思いもよらないだろう。だが、まさにそれを今からやる」
「令状を取って合法的に入れないのか?」
「証拠が足りない」
「何を期待している?」
「書簡や証拠が残っているかもしれない」
「気が進まないな、ホームズ」
「ワトソン君、君は外で見張りをしてくれ。犯罪行為は私がやる。こんなときに細事にこだわっている暇はない。マイクロフトの手紙、海軍省、内閣、そして報せを待つ高貴な方のことを考えてみたまえ。我々は行くしかない」
私は立ち上がって答えた。
「君の言う通りだ、ホームズ。我々は行かねばならない」
彼は跳ねるように立ち上がり、私と固く握手した。
「最後の最後で君が尻込みしないのは分かっていた」と彼は言い、その目には私がこれまで見たことのない、かすかな優しさが宿っていた。次の瞬間には、いつも通りの実務的な顔つきに戻った。
「ここから半マイルほどだが、急ぐことはない。歩いて行こう。道具は落とさぬように。君が不審者として逮捕されたら面倒だぞ」
コールフィールド・ガーデンズは、ヴィクトリア時代中期の典型的な、平坦なファサードに柱とポーチを備えた連棟住宅の一角だった。隣では子供のパーティーが開かれているようで、楽しげな声とピアノの音が夜に響いていた。霧はまだ漂い、我々を覆い隠してくれていた。ホームズはランタンを灯し、重厚な扉に光を当てた。
「これは厄介だ。しっかり閂と鍵がかかっている。地下の勝手口から入ろう。向こうに良いアーチがある。警官が来ても隠れられる。ワトソン、手を貸してくれ。私も君を引き上げよう」
1分後には、二人とも勝手口の陰に身を潜めていた。ほどなくして上の道路で警官の足音が霧の中に聞こえた。その音が遠ざかると、ホームズは下の扉に取り掛かった。彼が身をかがめて力を込めると、鋭い音と共に扉が開いた。我々は暗い通路に駆け込み、すぐに扉を閉じた。ホームズはカーブした、カーペットのない階段を先導した。小さな黄色い光が低い窓に当たった。
「ここだ、ワトソン。この窓に違いない」彼はそれを開けると同時に、低いうねりが轟音となり、列車が暗闇を突き抜けて走り去った。ホームズは窓枠を照らした。通過する機関車の煤で真っ黒だったが、所々擦れたり、曇っていた。
「ここに死体を休ませた跡がある。おや、ワトソン、これは? 間違いなく血痕だな」彼は窓枠の木部にかすかな変色を指差した。「階段の石にもある。これで証明は完了だ。列車が停まるまでここで待とう」
それほど待つ必要はなかった。次の列車は例によって轟音を立ててトンネルから出て、開けた場所で減速し、軋むブレーキ音と共に我々の真下で停車した。窓枠から車両屋根までは1.2メートルほどしかなかった。ホームズは静かに窓を閉めた。
「ここまでは証拠がそろった」と彼は言った。「どう思う、ワトソン?」
「見事だ。これ以上の推理はない」
「いや、そうは思わない。死体が屋根にあったという発想自体、そう難解でもない。それ以降の展開は、重大な国益が絡まなければ取るに足らないものだった。難題はこれからだ。だが、ここで何か手がかりが得られるかもしれない」
我々は台所階段を上り、一階の部屋に入った。一つは質素な食堂で、興味深いものはなかった。もう一つは寝室で、ここも空振りだった。残る部屋は書斎らしく、書類や本が散乱していた。ホームズは引き出しや戸棚を丹念に調べたが、表情に光は差さなかった。1時間探っても手がかりはなし。
「用心深い奴だ。証拠は何も残していない。危険な書簡は破棄か持ち去ったようだ。これが最後の望みだ」
机の上に小さなブリキの金庫があった。ホームズはノミでこじ開けた。中には数字や計算式が書かれた巻物がいくつもあり、用途は不明だった。「水圧」「平方インチあたりの圧力」などの語から潜水艦関連かと推測されたが、ホームズはそれらを投げ捨て、残るは新聞の切り抜きが入った封筒だけとなった。中身をテーブルに出すと、彼の顔に期待の色が浮かんだ。
「これは何だ、ワトソン? 新聞の広告欄の伝言記録だ。『デイリー・テレグラフ』の苦情欄だな。右上隅、日付はないが、内容は並び順で分かる。これが最初だ――
『もっと早く連絡が欲しかった。条件は合意済み。カードに記載の宛先に詳細を書いて送れ――ピエロ』
次は――
『説明不可能なほど複雑。詳細報告が必要。商品は納品時に受け渡す――ピエロ』
そして――
『事態は急ぐ。契約完了しなければ提案を撤回する。手紙で面談日時を決めてほしい。広告で確認する――ピエロ』
最後に――
『月曜夜九時以降。二度ノック。我々だけ。疑いすぎるな。現金払い、納品時――ピエロ』
なかなかの記録だ、ワトソン! もし相手側の人物を突き止められれば……」彼は指でテーブルを叩きつつ思案に沈み、やがて立ち上がった。
「いや、案外難しくないかもしれない。もうここですることはないな、ワトソン。『デイリー・テレグラフ』の事務所へ行って、今日の収穫を締めくくろう」
翌朝、朝食後にマイクロフトとレストレードが約束通りやってきた。ホームズは昨日の顛末を語った。レストレードは“我々警察にはこういうことはできませんよ、ホームズさん。あなたが我々に手が届かない結果を出せるのも当然だ。しかし、度が過ぎればあなたも友人も危険な目に遭うことになる”と頭を振った。
「イギリスのため、愛する家庭のため、美しきもののため、だよワトソン。祖国の祭壇の殉教者さ。でもマイクロフト、君はどう思う?」
「素晴らしい、シャーロック! 感心した。しかし、これをどう利用する?」
ホームズはテーブルの上の『デイリー・テレグラフ』を手に取った。
「今日のピエロの広告を見たか?」
「何? また出たのか?」
「ああ、これだ――
『今夜。同じ時刻、同じ場所。二度ノック。極めて重要。あなた自身の安全のため――ピエロ』
「おお!」とレストレード。「これに応じれば、奴は我々の手中だ!」
「私もそう思って掲載した。もし都合がつけば、今夜8時ごろコールフィールド・ガーデンズに一緒に来てくれれば、解決に近づくかもしれない」
シャーロック・ホームズの特筆すべき特性の一つは、“これ以上努力は無益だ”と確信した瞬間、頭脳を完全に切り替え、軽い事柄に没頭できる能力だった。私の方は全く逆で、その一日が果てしなく長く感じられた。国家的な重大事件であり、高位の人々が成り行きを見守り、実験は極めて直接的。神経をすり減らされた。やがて軽い夕食のあと、皆で出動することになり、ホッとした。レストレードとマイクロフトとはグロスター・ロード駅で落ち合った。オーバーシュタイン邸の勝手口は昨夜のまま開いており、鉄柵を乗り越えるのをマイクロフトが断固拒んだため、私が中から玄関を開けた。9時には全員、書斎で待機していた。
1時間、また1時間が過ぎた。11時の鐘が鳴り、希望が潰えそうだった。レストレードとマイクロフトはそわそわし、しきりに時計を見ていた。ホームズは半眼で静かに座っていたが、全神経を研ぎ澄ませていた。急に顔を上げた。
「来たぞ」
ドアの外にひそかな足音が通り過ぎ、戻ってきた。外でかすかな物音、そしてノッカーで二度ノック。ホームズが立ち上がり、我々に座ったままを合図した。廊下のガス灯はごく弱かった。ホームズが外扉を開くと黒い影が中に入り、直後に扉を閉めて施錠した。「こちらです!」という声が聞こえ、次の瞬間、男が我々の前に。ホームズが背後から襟首をつかみ、部屋に引き戻した。男はバランスを崩し、倒れた。その拍子に広いつばの帽子が飛び、ネクタイもほどけ、そこに現れたのは、ヴァレンタイン・ウォルター大佐の繊細な顔立ちと明るい長い顎鬚だった。
ホームズは驚いて口笛を吹いた。
「今回は私もお手上げだ、ワトソン。想定外の人物だったよ」
「誰なんだ?」とマイクロフト。
「かつて潜水艦部門を率いた故サー・ジェームズ・ウォルターの弟、ヴァレンタイン・ウォルター大佐だ。なるほど、全貌が見えてきた。彼はもうすぐ意識を戻す。尋問は私に任せたほうがいい」
我々は彼をソファに運んだ。やがて大佐は顔を上げ、己の目を疑うように呆然と周囲を見回し、額を押さえた。
「これは……? 私はオーバーシュタイン氏を訪ねに来たはずだ」
「すべて分かっていますよ、ウォルター大佐。英国紳士がなぜこのような行為に及んだのか理解できませんが、あなたとオーバーシュタイン氏の全ての書簡と関係、そしてカドガン・ウェスト青年の死の経緯も我々は把握しています。細部はあなたの口からしか聞けないので、悔い改めて告白することで、せめて名誉を取り戻すことをお勧めします」
男は呻いて顔を覆った。我々は待ったが、黙ったままだった。
「主要事項はすでに判明しています」とホームズ。「あなたが金策に追われ、兄上の持つ鍵の型を盗り、オーバーシュタインと『デイリー・テレグラフ』広告欄を通して連絡を取ったこと。月曜夜、霧の中で事務所へ行ったが、以前から疑念を抱いていたカドガン・ウェストに見咎められ、追跡された。彼はあなたの盗みを目撃したが、兄上の元へ書類を届ける可能性もあると考え、警報を出せなかった。自分の私事を捨てて、善き市民としてあなたの後をこの家まで追った。そこで事件が起き、ウォルター大佐、あなたは反逆に加え、さらに恐ろしい殺人という罪も犯したのです」
「違う、違う! 神に誓って私は殺していない!」
「では、カドガン・ウェストの最期について、屋根に遺体を置く前の経緯をお聞かせください」
「すべて話します。私は他は認めます。株の借金で金が必要だった。オーバーシュタインが五千ポンドを提示した。破滅を免れるにはそれしかなかった。でも殺人は無関係です」
「では何が?」
「彼は以前から疑っていたようで、まさに君の言う通り私の後をつけてきた。だが私は玄関先まで全く気づかなかった。濃霧で三メートル先も見えなかった。私は二度ノックし、オーバーシュタインが出てきた。そこへ青年が駆け寄り、書類をどうするつもりか問うた。オーバーシュタインは短い警棒をいつも持っていた。彼が家に押し入る勢いで追いかけてきた時、オーバーシュタインが彼の頭を殴った。それが致命傷となり、五分で息絶えた。廊下に倒れ、我々は途方に暮れた。そこでオーバーシュタインが“窓の下で列車が停まる”ことを思いついた。だがまず、私が持参した書類を調べた。三点は絶対必要で、手放せないと主張した。『全部返さねばウーリッジで大騒ぎになる』と私が言うと、『複雑すぎて複写が間に合わない、三点は必要だ』と。『なら、今夜全部まとめて戻さねば』と私は言った。しばらく考えて、彼は叫んだ。『三点は手元に、残りはこの青年のポケットに入れて列車屋根に遺体を乗せれば、全て彼の仕業とされるだろう』と。他の手はなかったので、その通りにした。窓から列車が停まるのを30分待ち、濃霧で見通しもなく、遺体を容易に屋根に降ろした。私の関与はここまでだ」
「兄上は?」
「何も言わなかったが、一度鍵の件で見咎められていたし、疑っていたと思う。その証が目に表れていた。ご存じのように、彼はそれ以降二度と元気を取り戻さなかった」
沈黙が落ちた。マイクロフトが口を開いた。
「償うことはできませんか? それで心の負担も罰も軽くなります」
「どう償えば?」
「オーバーシュタインは書類と共にどこに?」
「知らない」
「住所は聞かなかった?」
「パリのルーヴル・ホテル宛の手紙なら届く、と言っていた」
「それならまだ償いの余地がある」とシャーロック・ホームズ。
「できる限りのことはします。あの男に恩義はない。私の人生を滅ぼしたのは彼だ」
「ではペンと紙を。机で私の口述通りに書いてくれ。封筒は指定の住所で。よろしい。では――
『拝啓
取引について、すでにお気づきと思いますが、重要な詳細が一つ不足しています。全体を完成させるためのトレーシングを持っていますが、余分な手間がかかったので、さらに500ポンドの前金をお願いします。郵送や小切手は信用できず、現金か紙幣しか受け取りません。国外に伺うと目立つため、今は渡航できません。よって、土曜正午にチャリング・クロス・ホテルの喫煙室でお会いすることを希望します。必ずイギリス紙幣か金貨のみを』
これで十分だ。これで奴が釣れなければ驚きだ」
実際、これで釣れた! 歴史――少なくとも公には語られぬ、国の秘密の歴史――によれば、人生最大の大儲けを狙うオーバーシュタインはこの罠にかかり、英国の刑務所に15年間収監された。彼のトランクからは貴重なブルース=パーティントン設計図が発見された。それは欧州各地の海軍基地で売りさばこうとしていたものだった。
ウォルター大佐は刑期2年目の終わりに獄死した。ホームズはすっかり元気を取り戻し、ラッススのポリフォニック・モテットについての論文執筆に戻った。この論文は私家版として印刷され、専門家の間では決定版とされている。その数週間後、私は偶然、彼がウィンザーで一日過ごし、素晴らしいエメラルドのタイピンを持ち帰ったことを知った。購入したのかと聞くと、かつてちょっとした使命を果たして幸運にも感謝された高貴な婦人からの贈り物だと言う。それ以上は語らなかったが、私はそのご婦人が誰か察しがついた。エメラルドのタイピンを見るたびに、ホームズは“ブルース=パーティントン設計図事件”を思い出すことだろう。
悪魔の足
私は、シャーロック・ホームズ氏との長く親密な交友の中で得た奇妙な体験や興味深い回想のいくつかを随時記録してきたが、常に彼自身の公表嫌いが障害となってきた。彼の陰鬱で皮肉な性格は世間の喝采を何よりも嫌い、事件解決後には、あえて表舞台を正規の警官に譲り、的外れな称賛の嵐に冷笑を浮かべていたものだ。近年私が公表する記録が少ないのも、題材不足ではなく、彼のこの態度によるものである。私が彼の冒険に同行できたのは光栄であると同時に、慎重さと沈黙が求められる特権だった。
そんな彼から、先週の火曜日、突然電報が届いたのはかなり意外だった。彼は手紙を書くより電報を使う人間で、その文面はこうだった。「コーンウォールの怪事件、“私の扱った中で最も奇怪な事件”を公表してはどうだ」何の脈絡でこの事件を思い出したのか、なぜ私に書かせようとしたのか見当もつかないが、ひょっとして取り消し電報が来る前に、事件の詳細な記録を引っぱり出し、読者に物語を届けることにした。
それは1897年の春のことだった。ホームズの頑健な体も、絶え間なく続く過酷な仕事でついに限界の兆しを見せ、彼自身の時折の無茶も拍車をかけていた。その年の3月、ハーレー・ストリートのムーア・エイガー博士――その劇的な出会いはいつか書くつもりだ――が、「完全休養しなければ完全な破綻を来す」と厳しく命じた。本人は健康など全く無頓着だったが、仕事永久停止をちらつかされ、ついに環境の一新を受け入れた。こうして、その年の初春、我々はコーンウォール半島の突端、ポルデュー湾近くの小さなコテージで過ごすことになった。
そこは奇妙な土地で、ホームズの気難しい性質には格好の場所だった。白い漆喰の小さな家の窓からは、悪名高いマウント湾の全貌――無数の船乗りが命を落とした、黒い断崖と波頭のリーフが縁取る不吉な半円――を見下ろせた。北風なら凪いで安全だが、油断して入港すると、突然の南西の突風、錨が流され、風下の岸で難破という最悪の運命に晒される。慎重な船乗りは決して近寄らない。
陸側もまた陰気だった。どこまでも続く褐色の荒野に、時おり教会の塔が古い村の存在を示している。あちこちに消え去った民族の痕跡――石の遺構や焼けた遺骨を納めた塚、先史時代の争いを示す土塁。忘れ去られた民族の影と謎に満ちた土地は、友人の想像力を刺激し、彼はよく長時間荒野をさまよい、孤独に沈思していた。古代コーンウォール語にも惹かれ、カルデア語やフェニキア語との関連を論じるため、言語学の書籍を取り寄せたばかりだった。が、私の悲しみと彼の無邪気な喜びのうちに、ロンドンから逃れてきたはずの我々の元に、はるかに激烈で不可解な事件が舞い込んできたのである。我々の静かな日常は一瞬にして打ち砕かれ、コーンウォールだけでなくイングランド西部全域を騒がせる大事件の渦中へと投げ込まれた。当時「コーンウォールの怪事件」と呼ばれたこの件を、うろ覚えながら記憶している読者もいるだろう。ロンドンまで届いた報道は極めて不完全なものだったが、今ここに13年越しの真実を記したい。
先述の通り、この地方の村々は時おり塔を持つ教会でその存在を示していた。最寄りの村はトレダニック・ウォラスで、200人ほどの家が苔むした古い教会の周りに寄り集まっていた。この教区の牧師ラウンドヘイ氏は考古学にも明るく、ホームズとも知己を得ていた。中年で肥えた愛想の良い人物で、地元の話題も豊富だった。彼の招きで司祭館でお茶をご馳走になり、彼と暮らすモーティマー・トレゲニス氏とも知り合いになった。彼の住む家は広く、牧師は独身ゆえ間借り人を歓迎していたが、両者に共通点は少なかった。トレゲニス氏は痩せて色黒、眼鏡をかけ、実際の障害があるかのように前かがみだった。短い訪問の間、牧師はお喋りだったが、トレゲニス氏は陰気で内省的、自分のことを考え込んでいるようだった。
この二人が、3月16日火曜の朝食後、荒野への散歩支度をしていた我々の居間へ突然やってきた。
「ホームズさん、大変なことが……!」牧師は動揺した声で言った。「未曾有の惨事です。今あなたがここにいてくれるのも特別な天意でしょう。英国中で今必要なのはあなた一人です」
私は迷惑そうに牧師を睨んだが、ホームズはパイプを口から外し、猟犬のように背筋を伸ばした。手をソファに示し、二人を並んで座らせた。トレゲニス氏は牧師より冷静だったが、細い手の震え、鋭い眼差しが同じ感情を共有していると示していた。
「どちらが説明しますか?」
「あなたが発見者なのだから、牧師は伝聞でしょう。まずあなたから聞きましょう」とホームズ。
私は朝寝巻きの牧師と、きちんとした服装の下宿人を見比べ、ホームズの推理の的確さに彼らが驚く様子を楽しんだ。
「まず私から簡単に事情を話しましょう」牧師が言った。「それで詳細をトレゲニス氏から聞くか、現場へ急ぐかお決めください。昨夜、彼は自分の兄オーウェン、ジョージ、妹ブレンダの三人とトレダニック・ワーサの家でカードをして過ごし、10時過ぎに帰宅しました。その時は三人とも健康で元気でした。今朝、早起きの彼は朝食前にそちらへ散歩し、途中でリチャーズ医師の馬車に追い付かれました。医師はトレダニック・ワーサへの緊急呼び出しを受けたところでした。彼も同行して現地に着くと、驚くべき光景がありました。兄二人と妹は昨夜のまま食卓についており、カードも並んだまま、蝋燭は燃え尽きていました。妹は椅子にもたれて絶命、兄二人は両脇で笑い、叫び、歌い、正気を失っていました。三人とも、死者も狂人も、顔には凄絶な恐怖の痙攣が浮かび、目を覆いたくなる表情でした。家には老女中のポーター夫人以外誰もおらず、彼女は夜じゅう熟睡して何も聞いていません。何も盗まれず、乱れた気配もない――いったい何が女人を死に追いやり、健壮な男二人を狂わせたのか、全く説明がつきません。これが概要です、ホームズさん。解決していただければ、偉大なご功績となります」
なんとか友人を静養生活に引き戻したかった私の望みは、彼の険しい顔を一目見て無駄と分かった。しばらく沈黙のまま、彼は異様な事件に没入していた。
「調べてみましょう」と彼は言った。「外見からして、極めて特異な事件のようです。ラウンドヘイさん、ご自身で現場に?」
「いいえ。トレゲニスさんが帰宅後、私を呼びに来たのです」
「その家まではどれくらいの距離ですか?」
「内陸に1マイルほどです。」
「では一緒に歩いて行きましょう。しかし出発の前に、いくつか質問させていただきます、モーティマー・トレゲニスさん。」
これまでずっと沈黙していたトレゲニスだったが、私は彼の抑えの効いた興奮は、牧師のあからさまな感情よりもさらに激しいものだと気づいていた。彼は顔色が悪く、やつれきった表情でホームズをじっと見つめ、細い手を苦しげに握りしめていた。家族にふりかかった恐ろしい出来事について聞いているとき、その蒼白な唇は震え、暗い目には現場の恐怖が映し出されているようだった。
「お好きなだけ尋ねてください、ホームズさん」と、彼は熱心に言った。「こんなことを口にしたくはありませんが、正直にお答えします。」
「昨夜のことを教えてください。」
「ええ、ホームズさん、牧師がおっしゃった通り、私はそこで夕食をとり、食後に兄のジョージがウィストを提案しました。私たちは9時ごろテーブルにつきました。10時15分、私は席を立ちました。皆、テーブルを囲んで、実に楽しそうにしていました。」
「誰があなたを外に出したのですか?」
「ポーター夫人はもう寝ていたので、私は自分で出ました。玄関のドアを閉めて出ました。彼らがいた部屋の窓は閉まっていましたが、ブラインドは下ろされていませんでした。今朝もドアも窓も変わった様子はなく、見知らぬ者が家に来た形跡もありません。それなのに、彼らはみな、恐怖で完全に気が狂い、ブレンダは椅子の肘掛けに頭をもたせかけ、恐怖のあまり死んでいました。あの部屋の光景は、生涯忘れられません。」
「あなたの話す事実は、実に驚くべきものですね」とホームズ。「あなた自身、このことを何か説明できる理論をお持ちですか?」
「悪魔の仕業です、ホームズさん、悪魔の!」とモーティマー・トレゲニスは叫んだ。「人間の世界の話じゃありません。何かがあの部屋に現れて、彼らの理性の光を奪っていったのです。人間の手でこんなことができるでしょうか?」
「もし人間の手に余ることなら、私にもどうしようもありません」とホームズ。「ですが、そのような説明に頼る前に、まずはあらゆる自然な可能性を調べ尽くすべきです。さて、トレゲニスさん、ご家族は一緒に住んでおられ、あなたは別に部屋を借りておられたということは、何かご事情があったのですか?」
「その通りです、ホームズさん。でも、もう過ぎたことです。私たちはレドラスの錫鉱山の家族でしたが、事業を会社に売り、十分な資金で引退しました。お金の分け方で多少の確執があり、それがしばらくはわだかまりになっていましたが、今ではすっかり水に流し、仲良くやっていました。」
「一緒に過ごしたその晩を振り返って、事件の手がかりになりそうなことは何か思い当たりますか? 慎重に考えてみてください。」
「まったくありません。」
「皆、いつも通り元気でしたか?」
「今までで一番でした。」
「神経質な人たちでしたか? 何か不安を感じている様子は?」
「全然ありません。」
「他に助けになるようなことは何も?」
モーティマー・トレゲニスはしばし真剣に考え込んだ。
「一つだけ思い出しました」と、ついに言った。「テーブルでは私は窓に背を向けて座っていました。カードのパートナーだった兄ジョージが窓に向き合っていたのですが、一度、彼が私の肩越しにじっと何かを見ていたので、私も振り返りました。ブラインドは上がっていて窓は閉まっていましたが、芝生の茂みがぼんやり見えて、一瞬、何かが動いているように思いました。人か動物かも分かりませんが、何かがいた気がしたのです。兄に何を見ているのか尋ねると、同じような感じがしたと言いました。それだけです。」
「調べには行かなかったのですか?」
「はい、重要なことではないと思いました。」
「では、何の前兆もなく彼らを残してきたのですね?」
「まったくありません。」
「今朝、どうやって早く事件を知ったのか、よくわかりません。」
「私はいつも早起きで、朝食前に散歩をします。今朝も出かけたばかりのとき、医者の馬車が追いつき、ポーター夫人から急ぎの伝言を持った少年が来たと言われました。私はすぐに馬車に乗り込み、現場へ向かいました。あの恐ろしい部屋に入ったときには、ろうそくも暖炉の火もずっと前に消えていて、彼らは夜明けまで暗闇の中に座っていたのです。医者によれば、ブレンダは少なくとも六時間は前に亡くなっていたそうです。暴力の跡はなく、ただ椅子の肘掛けに寄りかかって、その顔にはあの表情が……。ジョージとオーウェンは歌の断片を口ずさみ、まるで二匹の大きな猿のようにわめいていました。見るも無残な光景でした。私は耐えきれず、医者も真っ青でした。実のところ、彼は椅子に崩れ落ちて意識を失いかけ、私たちは彼まで介抱するところでした。」
「実に驚くべきことです!」とホームズは立ち上がり帽子を取った。「すぐにトレダニック・ワーサに向かったほうが良さそうですね。最初からこれほど奇妙な問題を突きつける事件は、私も滅多に経験しません。」
その朝の調査は、ほとんど進展せずに終わった。ただし、冒頭から一つ、私に不吉な印象を残す出来事があった。悲劇の現場へ向かうには、狭く曲がりくねった田舎道を下っていく。私たちが進んでいると、馬車のガタガタという音が前方から聞こえ、道を譲るため脇に寄った。馬車が通り過ぎるとき、閉じた窓ごしに、ひどく歪み、笑みを浮かべた顔がこちらを睨みつけているのが一瞬見えた。その見開かれた目とむき出しの歯は、恐ろしい幻のように私たちの横を通り過ぎた。
「私の兄たちです!」とモーティマー・トレゲニスが唇まで真っ白になって叫んだ。「ヘルストンへ連れていかれるんだ。」
私たちは、黒い馬車がゴトゴトと進んでいくのを恐怖の中で見送った。それから、あの不吉な家――兄妹が奇怪な運命に見舞われたその場所へと向かった。
それは広くて明るい家で、コテージというよりはヴィラといった趣きだった。広い庭はすでにコーンウォールの空気の中で春の花で満ちていた。居間の窓はその庭に面しており、モーティマー・トレゲニスの話によれば、まさにその窓から邪悪な何かが侵入し、恐怖のあまり一瞬で彼らの心を打ち砕いたのだという。ホームズはゆっくりと、思案しながら花壇や小道を歩いた。私は彼があまりに考え込んでいたため、如雨露につまずいて中身をこぼし、二人の足と小道を水浸しにしたのを覚えている。家の中では、年配のコーンウォール出身の家政婦、ポーター夫人が、若い娘と共に家族の世話をしていた。彼女はホームズの質問に快く答えてくれた。夜中には何も聞こえなかったし、雇い主たちは最近とても機嫌が良く、これほど陽気で幸運だったことはないという。朝、あの忌まわしい部屋に入ったとき、彼女は怖さのあまり失神した。気を取り戻すと窓を開けて朝の空気を入れ、通りへと駆け下りて、農家の少年を医者のもとに走らせたという。ご婦人は二階のベッドに安置されているので、もしご覧になるならどうぞとのことだった。兄たちを施設の馬車に乗せるには、屈強な男が四人も必要だった。自分はもうこの家に一日もいたくないので、今日の午後にもセント・アイヴスの家族のもとに戻るつもりだという。
私たちは階段を上り、遺体を見た。ブレンダ・トレゲニス嬢は非常に美しい女性だったが、今や中年に差しかかっていた。暗くくっきりした顔立ちは死してなお端麗だったが、その顔には最後の人間らしい感情である恐怖の痙攣がなお残っていた。寝室から降りて、奇怪な悲劇の舞台となった居間へと向かった。暖炉には昨夜の火の燃え尽きた灰が残り、テーブルの上には蝋燭が四本、溶けて燃え尽き、カードが散乱していた。椅子は壁際に動かされていたが、それ以外は前夜のままだった。ホームズは軽やかに、素早く部屋を歩き回り、さまざまな椅子に座って位置を再現した。庭のどこまで見えるか試し、床や天井、暖炉も調べたが、彼の目が急に輝き、唇が引き締まる――すなわち何か突破口を見つけたという合図――を見ることは一度もなかった。
「なぜ火を?」と彼は一度だけ尋ねた。「春の宵に、この小さな部屋でいつも火を焚いていたのでしょうか?」
モーティマー・トレゲニスは、夜が寒く湿っていたので、自分が到着してから火をつけたのだと説明した。「これからどうなさるおつもりですか、ホームズさん?」
友人は微笑んで私の腕に手を置いた。「ワトソン、君がずっと非難してきたあのタバコによる自己中毒を、また始めるとしよう」と彼は言った。「ご許可いただければ、私たちはこれでコテージに戻ります。ここでこれ以上新しい事実が見つかるとは思えませんので。トレゲニスさん、頭の中で事実を整理し、何か思い当たることがあれば、必ずあなたと牧師にご連絡します。それでは、失礼します。」
私たちがポルデュー・コテージに戻ってから、ホームズは長い間、完全に沈黙し思索にふけっていた。彼は肘掛け椅子に体を丸め、青い煙に包まれて、やつれた禁欲的な顔はほとんど見えなかった。黒い眉は寄せられ、額には皺、目は虚ろで遠くを見ている。ついに彼はパイプを置き、勢いよく立ち上がった。
「だめだ、ワトソン!」と彼は笑いながら言った。「クリフ沿いを歩いて、石器時代の矢じりでも探そう。手がかりを探すよりも見つかる確率は高いだろう。材料が足りないのに頭を使えば、エンジンを空回しさせるようなものだ。自壊しかねん。海の空気、太陽、そして忍耐だワトソン――あとは自然とついてくる。」
「さて、落ち着いて我々の立ち位置を確認しよう」と、私たちが断崖を歩きながら彼は続けた。「我々が確かに知っているごくわずかな事実をしっかり把握しておけば、新たな事実が出たとき、それを正しく位置づけられる。まず第一に、お互い『悪魔の介入』などは認めないという点で一致しているな。それを頭から除外して考えよう。では残るのは、何らかの意図的または無意識の人間の働きによって、三人がひどい目にあったということだ。ここは確かな地盤だ。さて、それはいつ起きたか? トレゲニス氏の証言が正しければ、彼が部屋を出た直後だ。これは非常に重要な点だ。おそらく、彼が退出して数分以内だろう。カードはまだテーブルに置きっぱなしだったし、就寝時間は過ぎていたのに、誰も席を立っていない。だから、出来事は彼の退出直後、遅くとも昨夜11時前には起きたとみてよい。」
「次にすべきは、トレゲニス氏が部屋を出た後の行動をできる限り確認することだ。これには問題はないし、疑わしい点もなさそうだ。君は私のやり方を知っているから、如雨露を使って彼の足跡をはっきり残した手際に気づいただろう。濡れた砂地の小道は足跡がよく残る。昨夜も雨でぬかるんでいたし、サンプルを得てしまえば、その足跡を追って彼の動きをたどるのは難しくなかった。彼は手早く牧師館の方へ歩いたらしい。」
「もしトレゲニス氏が現場を離れた後、外部の誰かがカード仲間に作用したのだとすれば、その人物をどうやって再構成できるか? どうやってあれほどの恐怖を与えることができたのか? ポーター夫人は除外できる。明らかに無害だ。誰かが庭の窓まで忍び寄り、何らかの方法であれほどの衝撃を与えたのだろうか? この方向で唯一の示唆は、モーティマー・トレゲニス自身の証言、すなわち兄が庭で何か動くものを見たという話だ。だが夜は雨で暗く、誰かが恐怖を与えるためには、窓ガラスに顔をぴたりとつけるしかない。その窓の外には幅1メートルほどの花壇があるが、足跡は残っていない。とてもじゃないが、外部の人間がそこまで強い印象を残せたとは考えにくいし、動機も見当たらない。困難だろう?」
「実にその通りだ」と私はうなずいた。
「だが、もう少し材料がそろえば、案外越えられない壁ではないかもしれんよ、ワトソン。君の記録にも、これに匹敵するくらい難解な事件があったはずだ。今は、より正確なデータが得られるまでこの事件は脇に置き、あとは新石器人探しに専念しよう。」
私はホームズの精神的な切り替えの早さに驚いたことはあったが、この春のコーンウォールの朝ほど、それを強く感じたことはなかった。二時間もの間、彼は斧頭や矢じり、土器のかけらについて語り、まるで背後に恐ろしい謎が控えていることなど全く意に介さないようだった。午後になってコテージに戻ると、私たちを待っている来客がいた。その姿が私たちをすぐに現実に引き戻した。誰だか説明されるまでもなく分かった。巨体、岩のように刻まれた顔、獰猛な目と鷲鼻、天井に届きそうな灰色の髪、金と白が混じったひげ――そして絶えず咥えた葉巻によるニコチンの染み。これらはロンドンでもアフリカでも知らぬ者のない、偉大なライオン・ハンター兼探検家、レオン・スターンデール博士の特徴そのものだった。
この地方に滞在中と聞いてはいたし、何度か荒野で背の高い姿を見かけたこともある。しかし彼がこちらに近づくことはなく、私たちもまた、彼が隠遁を好み、たいていボーシャンプ・アリアンスの森深くにある小さなバンガローで過ごしていることを知っていたので、声をかけることなど思いもよらなかった。そこでは本や地図に囲まれ、独り静かに暮らし、隣人のことなどほとんど気にかけていないようだった。だから、彼が熱心な口調でホームズに「この謎めいた事件の解明に進展があったか」と尋ねてきたときは意外だった。「地元警察はまったくお手上げですが、あなたの幅広い経験から何か説明が思い浮かぶのではないかと。私がこの調査に加えてもらいたい唯一の理由は、長年この地で暮らしてきた間にトレゲニス家のことをよく知るようになったこと、実は母方をたどればいとこにあたることです。彼らの奇怪な運命は当然、私にも大きな衝撃でした。私もアフリカへの途上、プリマスまで行っていたのですが、今朝この知らせを受け、すぐに戻ってきたのです。」
ホームズは眉を上げた。
「そのせいで船に乗り損ねたのですか?」
「次の便にします。」
「それは友情の証ですね。」
「いとこなのです。」
「なるほど――母方のいとこ。荷物は船に乗せていましたか?」
「一部は乗せましたが、大半はホテルにあります。」
「そうですか。しかし、この出来事が今朝のプリマスの新聞に載るとは考えにくいですね。」
「いえ、電報をもらいました。」
「どなたから?」
探検家の精悍な顔に一瞬影が差した。
「あなたは実に詮索好きですね、ホームズさん。」
「それが私の仕事です。」
スターンデール博士は努力して動揺を抑えた。
「お話ししましょう。送り主はラウンドヘイ牧師です。」
「ありがとうございます」とホームズ。「さて、ご質問への回答ですが、この事件について私の頭はまだ完全には整理がついていません。しかし、結論に到達できる希望は十分にあります。今はそれ以上は申し上げられません。」
「ご自身の疑いがどこかに向いているか、ヒントでもいただけませんか?」
「いえ、お答えできかねます。」
「それなら、わざわざ来た甲斐がありませんので、おいとまします。」有名な博士はかなり不機嫌な様子でコテージを出ていった。ホームズも五分もしないうちに後を追った。その夜まで博士に会うことはなかったが、ホームズがゆっくりとした足取りで、やつれた顔で帰ってきたので、調査に大きな進展がなかったことはすぐに分かった。彼は待っていた電報に目を通し、それを暖炉に投げ入れた。
「プリマスのホテルからだ、ワトソン。牧師からホテル名を聞き、レオン・スターンデール博士の話が本当かどうか確認の電報を打った。実際、昨夜はそこに泊まり、荷物の一部はアフリカに送ってしまったが、事件に立ち会うため戻ってきたようだ。どう思う?」
「事件に深く関心があるのでしょう。」
「その通り――非常に深い関心だ。まだ我々がつかんでいなかった糸がある。それがこの迷路の先へ導いてくれるかもしれない。元気を出せ、ワトソン。我々の材料はまだすべて出揃っていない。揃えば、すぐにでもこの難題を乗り越えられるだろう。」
まさか、それがすぐに現実となり、しかも全く新しい調査の道が開かれるほど奇怪で不吉な出来事が起きるとは、私は想像だにしなかった。翌朝、私は窓のそばで髭を剃っていたとき、ひづめの音が聞こえ、見上げると馬車が猛スピードで道を下ってきた。家の前で止まり、友人の牧師が飛び降りて庭を駆け上がってきた。ホームズはすでに身支度を整えており、私たちは急いで出迎えた。
来訪者は興奮のあまり、しばらくうまく言葉も出なかったが、ついに途切れ途切れに悲惨な話を口にした。
「悪魔の所業です、ホームズさん! 私の哀れな教区は悪魔に取り憑かれました! サタンそのものが解き放たれたのです! 我々は彼の手中にあります!」彼は興奮のあまり踊り回り、顔は灰色、目は怯えたまま。ついに、恐るべき知らせを告げた。
「モーティマー・トレゲニスさんが、昨夜亡くなりました――家族と全く同じ症状で。」
ホームズは一瞬で立ち上がり、全身に活力がみなぎった。
「私たち二人とも馬車に乗れますか?」
「ええ、乗れます。」
「では、ワトソン、朝食は後回しだ。ラウンドヘイさん、私たちは全力で協力します。急ぎましょう、現場が乱される前に。」
下宿人であるトレゲニスは、牧師館の一角に二部屋を借りていた。下が広い居間、上が寝室で、どちらもクロッケー・ローンに面していた。私たちは医者や警察より早く到着したので、現場は何も手つかずだった。その霧のかかった三月の朝に、私が目にした現場を詳しく記録しておきたい。生涯消えることのない強烈な印象だった。
部屋の空気はひどく重苦しく、息が詰まるほどだった。最初に入った召使いが窓を開けていなければ、さらに耐えがたかっただろう。中央のテーブルにはランプが置かれ、煙を上げていた。その傍らに死者が座っていた。椅子にもたれかかり、細い顎髭が突き出し、眼鏡は額の上、やせた暗い顔は窓に向けてねじれ、亡き妹と同じ恐怖の歪みが現れていた。手足は痙攣し、指はねじれ、まさに恐怖の発作の中で息絶えた様子だった。服は着ていたが、急いで着替えた形跡があった。ベッドは使われており、悲劇は早朝に起きたことが分かった。
ホームズの無表情な外面の下に、どれほどの熱意が潜んでいたかは、あの部屋に入った瞬間の変貌ぶりを見れば分かった。たちまち全身が緊張し、目は輝き、顔は引き締まり、肢体は狩猟犬のように身震いした。彼はまず芝生、続いて窓から部屋、さらには寝室へと駆け回り、獲物を追う猟犬さながらだった。寝室では素早く一巡し、ついに窓を開けた。これが新たな興奮の源となったらしく、身を乗り出して歓声を上げた。すると階段を駆け下り、窓から芝生に身を投げ、また部屋に舞い戻る――まさに獲物の目前に迫った猟犬の勢いだった。ランプ(普通のスタンド式)を入念に調べ、火皿の寸法を測り、煙突の上部を覆う雲母のシールドを虫眼鏡で調べ、表面に付着した灰を削り取り、その一部を封筒に入れてポケットへしまった。ちょうど医者と警察が到着した頃、彼は牧師を手招きして、私たち三人は芝生へ出た。
「調査がまったく無駄でなかったのは幸いです」と彼は言った。「私は警察と議論する時間はありませんが、ラウンドヘイさん、警部によろしくお伝えになり、寝室の窓と居間のランプにご注目ください。どちらも示唆的ですが、合わせるとほぼ決定的です。警察がさらなる情報を求めるなら、コテージでお会いしましょう。さて、ワトソン、我々は他にすることがあります。」
おそらく警察は素人の介入を快く思わなかったのか、自分たちなりの有望な捜査線があると思い込んでいたのか、いずれにせよ二日間は何の連絡もなかった。その間、ホームズはコテージで煙をくゆらせ物思いにふけることもあったが、ほとんどの時間は一人で田舎道を歩き回り、長い時間を費やしてどこへ行ったとも語らなかった。彼の調査の方向性が分かったのは、ある実験のときだった。彼はトレゲニスの部屋にあったのと同じ型のランプを買い、牧師館で使われていたのと同じ油を入れて、燃え尽きるまでの時間を正確に計った。もう一つの実験は、もっと不快なもので、一生忘れられそうにない。
「ワトソン、覚えているだろう」と彼はある日の午後に言った。「これまで得た様々な情報に共通する点が一つある。それは、部屋の空気が最初に入った者に与えた影響だ。君は、モーティマー・トレゲニスが兄の家を訪れたとき、医者が部屋に入って椅子に崩れ落ちたと話したのを覚えているか? 忘れていたか? 私は確かにそうだったと請け合える。また、家政婦のポーター夫人は部屋に入った直後に気絶し、その後で窓を開けたとも語っていた。二つ目のケース、つまりモーティマー・トレゲニス自身の場合、私たちが到着したときのあのひどい空気は忘れようがない。しかも召使いは気分が悪くなり寝込んでいたという。これらは示唆に富んでいる。どちらのケースも部屋に有毒な空気があった。そしてどちらも、火あるいはランプが燃えていた。暖炉の火は必要だったが、ランプは昼の明るい時間まで灯されていた。なぜだ? 明らかに、燃焼、空気のこもり、そして人々の狂気や死――この三つの関連がある。分かるか?」
「そのように思えます。」
「少なくとも一つの仮説にはなる。どちらの場合も、何か燃やされたものが大気に奇妙な毒性をもたらしたと仮定してみよう。最初のケース、トレゲニス家では、その物質が暖炉に投じられた。窓は閉まっていたが、煙は多少煙突に抜けるだろう。よって毒の効果は二つ目のケースより弱いはずだ。事実、最初は女性だけが死亡し、他の者は一時的または永久的な狂気になった。二つ目のケースは完全な死だ。だから、毒が燃焼によって作用するという仮説を裏付けるように思える。」
「この論理をもとに、私はトレゲニスの部屋でその物質の痕跡を探した。最もありそうなのは、ランプの雲母製シールドだ。そこに、案の定、灰が付着し、周囲にはまだ焼け残った茶色の粉末の縁取りもあった。私はその半分を封筒に入れておいた。」
「なぜ半分だけ?」
「警察の邪魔をするつもりはない。発見した証拠は残しておく。警察が気づけば、雲母に毒が残っているはずだ。さてワトソン、ランプを灯そう。ただし窓を開けて、二人とも早死にしないように注意しよう。君は開いた窓のそばの肘掛け椅子に座ってくれ。いやな予感がするなら中止してもいいが、やり通すつもりだな? やはり私のワトソンだ。私の椅子は君と向かい合わせ、同じ距離を取ろう。ドアは少し開けておく。これで互いを観察し、危険な症状が出たら中止できる。いいな? では、封筒から粉末を取り出し、ランプの上に置く。さあ、ワトソン、どんな展開になるか待とう。」
それはすぐにやってきた。私は椅子に座った途端、濃厚でむせるようなムスク臭に気づいた。その一息目で、私の脳と想像力は制御不能となった。目の前に黒い雲が渦巻き、その中に、まだ姿は見えないが、私の感覚を打ち砕く何か言い知れぬ恐怖が潜んでいると確信した。闇の中であやふやな形がうごめき、それぞれが脅威と警告、言葉にできぬ境界の住人の到来を予感させた。その影だけで魂が焼き尽くされるようだった。氷のような恐怖が私を支配した。髪が逆立ち、目は飛び出し、口は開き、舌は革のように干からびた。脳内の混乱は限界に達し、何かが切れそうだった。叫ぼうとしたが、かすかに自分の声が遠くで響くのが聞こえた。同時に、逃れようとする意志で絶望の雲を突き抜け、ホームズの顔を一瞬垣間見た。蒼白で、硬直し、恐怖に歪んだ顔――死者たちの顔そのものだった。その幻が私に一瞬の正気と力を与えた。私は椅子から飛び上がり、ホームズを抱きかかえて、共にドアをよろめきながら抜け出し、次の瞬間、芝生に倒れ伏した。頭上には地獄のような恐怖から解放された輝かしい太陽だけがあった。やがて霧が晴れるように恐怖が消え去り、静けさと理性が戻った。私たちは芝生に腰を下ろし、汗ばんだ額を拭い合い、恐ろしい体験の名残を確かめ合った。
「本当にすまなかった、ワトソン!」とホームズはやっとのことで言った。「友人にまで無謀な実験をしてしまった。心から謝るよ。」
「いいえ」と私は込み上げる思いで答えた。「私にとって、あなたを助けることが一番の喜びであり、特権です。」
彼はすぐに、いつもの半分ユーモラスで半分皮肉な調子に戻った。「わざわざ気を狂わせる必要はないよ、ワトソン。正直、こんな実験を始める前からすでに十分狂っていた、と観察者なら言うだろう。まさかここまで即効性で、強烈だとは思っていなかった。」彼はコテージに駆け込み、ランプを腕いっぱいに伸ばして持ち出すと、茨の茂みに投げ捨てた。「部屋の空気が抜けるのを待とう。ワトソン、これで事件の仕組みには疑いの余地はないだろう?」
「全くありません。」
「だが、原因は依然として不明のままだ。あずまやに行って話そう。この忌まわしい臭気がまだ喉に残っている。すべての証拠は、最初の悲劇の犯人がモーティマー・トレゲニスであり、二つ目の犠牲者でもあったことを指し示している。まず思い出すべきは、家族の間に争いがあり、その後和解したという話だ。どれほど激しい争いだったか、和解がどれほど表面的だったかは分からない。私の印象では、ずる賢そうな顔に小さく鋭い目を光らせるトレゲニスは、とても寛大な性格とは思えない。次に、庭に人影があったという話で我々の注意をそらしたのは彼自身だった。彼には我々を混乱させる動機があった。最後に、彼が部屋を去る際にあの物質を火に投げ入れなかったとすれば、誰がやったのか? 事件は彼の退出直後に起きている。もし他の誰かが来たのなら、家族は必ず席を離れたはずだ。しかも平和なコーンウォールでは、夜十時過ぎに来客はありえない。よって、すべての証拠はモーティマー・トレゲニスを犯人と示している。」
「では、彼自身の死は自殺だと?」
「表面的にはありえなくもない。自分の家族にあんな運命をもたらした罪悪感で、自らも同じ手段を選ぶこともありうる。しかし、そう考えにくい理由もいくつかある。幸い、すべてを知っている人物がイングランドに一人いる。今午後、その人の口から事実を語ってもらう手筈だ。……おや、少し早く来られたようだ。どうぞこちらへ、レオン・スターンデール博士。我々が今しがた化学実験をしたばかりで、部屋の空気がまともでなく、こんな野外での応対となったことをお許しください。」
私は庭門の開閉音を聞いていたが、今や偉大なアフリカ探検家の威厳ある姿が小道に現れた。彼は驚いた様子で私たちのいるあずまやを見た。
「お手紙をいただいて一時間ほど前に参りましたが、なぜ呼ばれたのか分かりません」と言った。
「それは、これから明らかになるでしょう。ご協力に感謝します。今日の話題はあなたにも極めて個人的な関わりがあるので、盗み聞きの心配がない屋外でお話ししたいのです。」
探検家は葉巻を口から外し、厳しい目でホームズを見据えた。
「なぜ私が極めて個人的に関係あるのか、まったく分かりかねます。」
「モーティマー・トレゲニスの殺害についてです」とホームズ。
一瞬、私は武器を持っていればと思った。スターンデールの険しい顔は赤黒くなり、目は怒りに燃え、額の血管は浮き上がり、握りこぶしでホームズに詰め寄った。だが彼は踏みとどまり、激しい努力で冷静さを取り戻した。その冷ややかな態度は、先ほどの激情よりもむしろ危険を感じさせた。
「私は長く未開の地で、法も届かぬ場所に生きてきました」と彼は言った。「だから自分だけの法で行動する癖がついた。ホームズさん、私はあなたに危害を加えたくないが、そのことを忘れぬほうがいい。」
「スターンデール博士、あなたに危害を加えるつもりはありません。それを最もはっきりと示す証拠は、私が今知っていることを知りながら、警察ではなく、あなた自身を呼んだという事実でしょう。」
スターンデールは息を呑んで腰を下ろした。彼の冒険に満ちた人生で、恐らく初めて圧倒されたのだろう。ホームズの態度には、抗い難い落ち着いた力強さがあった。訪問者はしばし口ごもり、大きな両手を不安げに開いたり閉じたりした。
「どういう意味だ?」ついに彼は問うた。「もしこれがハッタリだというなら、ホームズさん、あなたは実験台として最悪の男を選んだと言っておく。もう回りくどい話はやめてくれ。どういう意味なのか、はっきり言ってくれ。」
「お話ししましょう」とホームズは言った。「私が打ち明ける理由は、率直さが率直さを生むと望むからです。今後どう動くかは、あなた自身の弁明次第です。」
「私の弁明?」
「ええ、そうです。」
「何に対する弁明だ?」
「モーティマー・トレゲニス殺害の嫌疑に対する弁明です。」
スターンデールはハンカチで額を押さえた。「まったく、あなたの進み方は見事だ」と言った。「あなたの成功はすべて、その驚異的なハッタリ能力にかかっているのか?」
「ハッタリを使っているのは、スターンデール博士、あなたの方です。そして私ではありません」とホームズは厳しく言った。「証拠として、私の結論の基礎となるいくつかの事実をお話ししましょう。プリマスからの帰還や、多くの荷物をアフリカへ送った件については、あなたがこのドラマを再構築する際に考慮すべき要素であると私に最初に知らせただけで、詳しくは触れません。」
「私は戻ってきた――」
「あなたの理由は聞きましたが、納得できませんし、十分とも思いません。その話はここまでにしましょう。あなたは私に、誰を疑っているかを尋ねに来た。私は答えを拒みました。その後、あなたは牧師館に行き、しばらく外で待ち、そして最終的に自分のコテージに戻りました。」
「どうしてそれを知っている?」
「あなたを追跡していました。」
「誰にも気付かなかったが。」
「私があなたを追う時には、普通そういうものです。あなたはその夜、自分のコテージで落ち着かずに過ごし、ある計画を立てました。そして早朝、その計画を実行に移した。夜明けとともにドアを出て、門のそばに積まれていた赤茶色の砂利をポケットに詰めました。」
スターンデールは激しく身を震わせ、驚愕の眼差しでホームズを見た。
「そして、教会から1マイルほどの距離を素早く歩いて行きました。その時、今履いている肋模様のテニスシューズを履いていました。牧師館では果樹園と脇の生け垣を通り抜け、トレゲニスの部屋の窓の下に出ました。その時はもう明るくなっていましたが、家の中はまだ誰も起きていませんでした。あなたはポケットから砂利を取り出し、それを上の窓に投げました。」
スターンデールは飛び上がった。
「あなたは悪魔そのものだ!」と叫んだ。
ホームズはその賛辞に微笑んだ。「2回、いや3回ほど砂利を投げてから、トレゲニスが窓に現れました。あなたは身振りで彼を呼び下ろした。彼は慌てて服を着て居間に降りてきた。あなたは窓から中へ入り、そこで短い面談をし、部屋を歩き回った。そして出て行って窓を閉め、外の芝生で葉巻をくゆらせながら中の様子を見守った。ついにはトレゲニスの死後、あなたは来た道を戻った。さて、スターンデール博士、あなたはその行為をどう正当化し、その動機は何ですか? ごまかしや戯れ言は通じません。この件は永久に私の手を離れることを約束します。」
訪問者の顔は、告発の言葉を聞きながら灰色に変わっていた。彼はしばらく顔を両手に沈めて考え込んだ。そして突然、衝動的に胸ポケットから写真を取り出し、私たちの前にある粗末なテーブルに投げ出した。
「これが私の理由だ」と彼は言った。
それは非常に美しい女性の胸像と顔を写した写真だった。ホームズはそれを覗き込む。
「ブレンダ・トレゲニスだ」とホームズが言った。
「そうだ、ブレンダ・トレゲニスだ」と訪問者が繰り返す。「私は長年、彼女を愛してきた。彼女もまた私を愛してくれていた。それが、人々が不思議がったコーンウォールでの隠遁生活の秘密だ。私は地上で唯一大切な存在のそばにいることができた。だが、私は彼女と結婚できなかった。何年も前に私を捨てた妻がいるが、イギリスの実に理不尽な法律のせいで離婚できなかった。ブレンダはずっと待ち続け、私も待ち続けてきた。そして、私たちが待ち続けた末がこれだ。」彼の大きな体が恐ろしい嗚咽で震え、まだら髭の下で喉元をつかんだ。だが、やがて気を取り直して続けた。
「牧師は知っていた。彼は私たちの信頼を受けていた。彼なら、彼女が地上の天使だったと証言するだろう。だからこそ彼は私に電報を打ち、私は戻った。荷物やアフリカがどうでもよくなったのは、愛する人にそんな運命が降りかかったと知ったからだ。これが、私の行動の原動力なのです、ホームズさん。」
「続けてください」と友人が促した。
スターンデール博士はポケットから紙包みを取り出し、テーブルの上に置いた。表には「Radix pedis diaboli」と赤い毒薬ラベルが付いていた。彼はそれを私の方へ差し出した。「あなたは医者だと聞きました。これをご存知ですか?」
「デビルズフットの根! いや、聞いたことがありません。」
「ご専門の知識に疎いのではありません」と彼は言った。「これ以外にヨーロッパでは、ブダペストの実験室に1つ標本があるだけだと思います。薬局方にも毒物学の文献にもまだ載っていません。根の形は人間と山羊が半分混ざったような足に似ているので、ある植物学の宣教師がこの奇抜な名前を付けました。西アフリカの一部地域では、呪術師たちが試練用の毒として使い、秘密にしています。この標本は、ウバンギ地方で非常に珍しい状況下で手に入れました。」彼は紙包みを開き、赤褐色の嗅ぎ煙草のような粉を見せた。
「さて?」とホームズが厳しく問いかける。
「これからすべてをお話しします、ホームズさん。すでに多くをご存知なので、すべて打ち明けるのが私のためでしょう。私とトレゲニス家との関係はすでに説明しました。妹のために、兄弟たちとも親しくしていました。金銭を巡る家族の争いで、このモーティマーとは疎遠になりましたが、和解したと思われ、その後も彼と他の兄弟たちと交際していました。彼はずる賢く、陰険で策謀好きな男で、いろいろと疑わしい点がありましたが、決定的な対立はありませんでした。
二週間ほど前、彼がコテージに来た時、私はアフリカの珍品を見せました。その中にこの粉もあり、奇妙な性質について説明しました。つまり、恐怖の感情を司る脳の中枢を刺激し、部族の司祭による試練を受けた不幸な現地人は、発狂か死が運命であると。ヨーロッパの科学では検出不能であるとも話しました。彼がどうやって手に入れたかは分かりません。私は部屋から出ていませんでしたが、キャビネットを開けたり箱を屈んで見たりしている間に、彼がこっそりこのデビルズフットを盗み取ったのは間違いありません。効果の量や時間について、しつこく質問されたのを覚えていますが、まさか私的な動機があるとは夢にも思いませんでした。
この件については、その後何も考えませんでした。ところが、牧師からプリマスに電報が届いたのです。この悪党は、私が船で出発した後で知らせが届くと思い、何年もアフリカで消息不明になるはずだと思ったのでしょう。でも私はすぐに戻りました。もちろん、話を聞くうちに自分の毒が使われたのだと確信せざるを得ませんでした。あなたに会いに来たのも、もしかしたら他に説明があるかもしれないと思ったからです。しかし、他に説明はありえませんでした。私は、モーティマー・トレゲニスが犯人だと確信しました。金のために、ひょっとすると他の家族が全員狂ってしまえば共同財産の唯一の管理人になれるという思惑で、悪魔の足の粉を使い、二人を発狂させ、私が生涯でただ一人愛し、愛された人――妹のブレンダを殺したのです。それが彼の罪――では、罰はどうあるべきか?
法に訴えるべきでしょうか? 証拠は? 事実であることは確実でも、こんな突飛な話を陪審に信じさせられるでしょうか? できるかもしれませんが、失敗は許されません。私の魂は復讐を叫びました。かつてもお話ししたように、私は人生の大半を法の外で過ごし、ついには自分自身が法となったのです。今回もそうでした。彼が他者に与えた運命を自らも受けるべきだと決めました。さもなければ自分の手で正義を下すつもりでした。今の私は、イングランド全土でも自分の命をこれほど軽んじる者はいないでしょう。
これですべてを話しました。後はあなたが補ってくれました。ご指摘の通り、私は不眠の夜を過ごした後、早朝に出発し、彼を起こすのが難しいと予想して砂利を集めて窓に投げました。彼は降りてきて、居間の窓から私を入れました。私は彼の罪を突きつけ、裁判官として、そして処刑人として来たと告げました。奴は椅子に沈み、私の拳銃を見て麻痺したようになりました。私はランプに火をつけ、粉をその上に置き、窓の外に立って、部屋を出ようとしたら撃つ覚悟で見張りました。5分で彼は死にました。神よ、あの死に様! だが、私の心は石で、愛しい人が味わった苦しみ以上のものは彼にもなかったのです。これが私の話です、ホームズさん。もしあなたが女性を愛したことがあれば、同じことをしたかもしれません。とにかく、私はあなたの手中にあります。お好きなようにしてください。すでに言った通り、いま私ほど死を恐れない者は生きていません。」
ホームズはしばらく沈黙していた。
「今後のご予定は?」ようやく尋ねた。
「アフリカ中央部で身を隠すつもりでした。私の仕事はまだ半分しか終わっていません。」
「残りの半分を終えてきてください」とホームズは言った。「少なくとも私は、あなたを止めるつもりはありません。」
スターンデール博士はその巨体を持ち上げ、厳かに一礼し、あずまやを出て行った。ホームズはパイプに火を点け、私にたばこ入れを差し出した。
「毒ではない煙はありがたいものだ」と彼は言った。「ワトスン、我々が介入すべき事件ではないな。我々の調査は独立していたし、今後もそうあるべきだ。君もあの男を告発したくはないだろう?」
「もちろんだ」と私は答えた。
「私は愛したことがないが、もしそうなら、もし愛する女性があんな最期を遂げたのなら、あの法を超えたライオン・ハンターと同じ行動をとったかもしれない……。さてワトスン、君の知性を侮辱してまで明白なことを説明するつもりはない。窓辺の砂利が、私の調査の出発点だったのは言うまでもない。牧師館の庭にはないものだった。スターンデール博士と彼のコテージに注目して初めて同じものを見つけた。昼間に灯っていたランプや、盾に残された粉末の痕跡も、明白な連鎖だった。そして今や、ワトスン、我々はこの件を心から離し、安らかな気持ちで、ケルト語のコーンウォール方言に見られるカルデア語の痕跡の研究に戻るとしよう。」
赤い輪の冒険
第一部
「――しかし、ウォーレン夫人、あなたが特に不安に感じる理由はないようですし、私の貴重な時間を割いて干渉する理由もないように思えます。本当に他にやるべきことがあるのです。」こう言って、シャーロック・ホームズは自分の大きなスクラップブックに向き直り、最近集めた資料の整理・分類を続けた。
だが、女家主は女性特有の粘り強さと、したたかさを兼ね備えていた。彼女は毅然として引き下がらなかった。
「去年、うちの下宿人の件を解決してくださったでしょう――フェアデール・ホッブズさんの。」
「ああ、そうだった――簡単な件でしたね。」
「でも彼は、あの親切や暗闇に光をもたらしてくれたことを、いつまでも話していました。私も迷ってつらい時、あの言葉を思い出したんです。先生なら、きっとできるはずだと。」
ホームズはお世辞や、そして公正に言えば、親切心には心を動かされる人だった。その二つの力が、彼をして諦めたようにガムブラシを置かせ、椅子を引かせた。
「さて、ウォーレン夫人、話を聞きましょう。煙草はお嫌いではないですね? ありがとう、ワトスン――マッチを。あなたは、新しい下宿人が部屋にこもりきりで姿を見せないことに不安なのですね。ウォーレン夫人、もし私があなたの下宿人だったら、何週間も顔を見せないこともありますよ。」
「確かにそうかもしれません、でも今回は違うんです。怖いんです、ホームズさん。怖くて眠れません。朝から晩まで、彼の速い足音があちこち動き回るのが聞こえるのに、一度も姿を見たことがない――私には耐えられません。主人も私と同じくらい神経をすり減らしていますが、主人は日中は仕事に出ています。私は一日中彼と同じ家にいるので、神経が持ちません。彼は何かを隠しているのでしょうか? 何をしたのでしょう? 女中以外は、私とその人だけ。気が気でないんです。」
ホームズは身を乗り出し、長く細い指を彼女の肩に置いた。ホームズがその気になれば、ほとんど催眠術のように人を落ち着かせる力があった。彼女の怯えた目は和らぎ、動揺した顔もいつもの平静さを取り戻した。彼女は示された椅子に腰かけた。
「引き受けるからには、すべての細部を理解しなければなりません」と彼は言った。「じっくり考えてください。最も小さな点が最重要かもしれません。男は十日前に来て、二週間分の部屋代と食費を払ったのですね?」
「はい、先生。いくらかと聞かれたので、一週間五十シリングだと言いました。家の一番上に、小さな居間と寝室があって、全部揃っています。」
「それで?」
「彼は『自分の条件で借りられるなら五ポンド払う』と言いました。私は貧しい女で、主人も稼ぎが少ないので、そのお金は大きかったです。彼は十ポンド紙幣を出して、その場で差し出しました。『この条件を守ってくれれば、ずっと同じだけ払う。守れなければ、その時点でやめる』と。」
「その条件とは?」
「家の鍵を持つことでした。それはよくあることです。下宿人はたいてい持ちます。それから、絶対に一人にして、どんな理由があっても決して邪魔しないこと。」
「それは特に驚くことでもありませんね?」
「普通ならそうです。でもこれは常軌を逸しています。十日間もいるのに、私も主人も女中も、一度も彼の姿を見ていません。あの素早い足音だけが、夜も朝も昼も聞こえてきますが、最初の夜以外は一度も外出しませんでした。」
「おや、最初の夜は外出したのですか?」
「はい、先生。すごく遅く――私たちがみんな寝てから帰ってきました。部屋を借りてからそうするつもりだと言い、ドアを閉めないでほしいと頼まれました。真夜中過ぎに階段を上がってくるのを聞きました。」
「食事は?」
「食事を運ぶ時は、彼が鳴らしたら、ドアの外の椅子に置いておくようにと、特に言われました。食べ終わるとまた鳴らしてくれて、同じ椅子から下げるんです。他に必要なものは、紙切れに書いて残します。」
「書くのですか?」
「ええ、先生。鉛筆で印刷文字みたいに。ただ単語だけです。これがその一つ――『石鹸』。これがもう一つ――『マッチ』。これが最初の朝に残したもの――『デイリー・ガゼット』。朝食と一緒にその新聞を置いています。」
「ワトスン、これは確かに少し風変わりだ」とホームズは興味深そうに、女主人が差し出した紙片を見ながら言った。「隠遁は理解できるが、なぜ印刷文字なのか。印刷は手間がかかる。なぜ筆記しない? どう思うワトスン?」
「筆跡を隠したいのでしょう。」
「なるほど。それにしても、なぜそんな簡潔な伝言ばかり?」
「想像もつきません。」
「これは想像力を刺激する分野だ。単語は一般的な太い芯の紫色鉛筆で書かれている。ご覧の通り、紙の端が印刷後にちぎられていて、『SOAP』の『S』が一部なくなっている。これも意味深ですね、ワトスン。」
「用心深さの表れ?」
「その通り。何か印、指紋か、身元を示しかねないものがあったのでしょう。さて、ウォーレン夫人、男は中背で、色黒で、髭を生やしていたと。年齢は?」
「若そうでした――三十を超えていません。」
「他に特徴は?」
「英語は上手でしたが、でも外国訛りだと感じました。」
「服装は?」
「とてもきちんとしていて、紳士然としていました。暗い色の服――特に変わった点はありません。」
「名前は?」
「ありません。」
「手紙や訪問客は?」
「ありません。」
「でも朝は部屋に入るのでは?」
「いいえ、先生。一切自分でやっています。」
「なるほど、実に奇妙ですね。荷物は?」
「大きな茶色のバッグが一つだけでした。」
「手がかりは少ないですね。部屋から何も出てきていないと?」
女主人はバッグから封筒を取り出し、中から二本の燃えカスのマッチと吸い殻をテーブルに出した。
「今朝、盆の上にありました。小さいものから大きなことが分かると聞いたので。」
ホームズは肩をすくめた。
「ここには何もありません。マッチはもちろん煙草を点けるのに使われたのでしょう。短さから明らかです。パイプや葉巻なら半分近く燃えます。しかし、これは確かに興味深い。男は髭と口髭があったというのですね?」
「はい、先生。」
「理解できません。これは無精ひげのない人間が吸ったとしか思えない。ワトスン、君の控えめな口髭さえ焼けるはずだ。」
「ホルダーでは?」
「いやいや、先端がもつれている。まさか部屋に二人いるのでは、ウォーレン夫人?」
「いいえ。食事もほとんど食べないので、一人でも生きているのが不思議なくらいです。」
「もう少し材料を待ちましょう。家賃も払ってくれるし、手がかからない下宿人です。本人が隠れて暮らすのは、あなたの知ったことではありません。理由もなくプライバシーを侵すわけにはいかない。私が引き受けたからには目を離しません。何か進展があれば報告してください。力が必要な時は必ず助けます。」
「この事件には確かにいくつか興味深い点があるな、ワトスン」と女主人が去ると、ホームズは言った。「単なる奇癖かもしれないし、もっと深い問題かもしれない。最初に疑うべきは、今部屋にいる人物が最初に部屋を取った人物とは別人である可能性だ。」
「なぜそう思う?」
「この吸い殻以外にも、部屋を取った後、唯一外出したのがその夜だけというのは不自然だ。戻ってきたのが本人とは限らず、また、英語は上手だったが、新しい住人は『MATCH』と複数形でない語を使っている。辞書から単語だけ抜き出したのかもしれない。簡潔な文も、英語力の不足を隠すためだろう。つまり、住人の交代があったとみてよい。」
「何のために?」
「そこが問題だ。調べるべき筋は一つある。」ホームズは、日々ロンドン各紙の身の上相談欄をスクラップした大きな本を取り出した。「何たる嘆きや叫び! 奇妙な出来事の宝庫だが、異常事例を研究する者にとってはきわめて貴重な狩場だ。手紙が使えない状況では、唯一の連絡方法は新聞広告だ。幸い、注目すべきはひとつの新聞だけ。これが『デイリー・ガゼット』の過去二週間分の記事だ。……これは関係ない。これはどうだ。『辛抱せよ。確実な通信手段を探す。しばらくはこの欄を。G』これは下宿人が来てから二日後だ。他にも手がかりは……あった。三日後、『うまく手配進行中。忍耐、慎重に。雲は晴れる。G』そして一週間後には、『道は開けつつある。もし合図があれば決めた暗号を思い出せ――Aは一回、Bは二回、以下同様。近日中に知らせる。G』これは昨日の新聞、今日の分には何もない。ウォーレン夫人の下宿人にぴったりだ。もう少し待てば、もっと明らかになるだろう。」
果たしてその通りになった。朝、私は暖炉の前に立つ友人を見つけた。満足そうな笑みを浮かべている。
「どうだ、ワトスン?」と彼はテーブルの新聞を持ち上げて言った。「『赤い高い家、白い石の外壁。三階、左から二番目の窓。日暮れ後。G』これで十分だな。朝食後、ウォーレン夫人宅の近所を下見しよう。おや、ウォーレン夫人、どうしました?」
依頼人は、何か大きな出来事があったと告げる勢いで部屋に飛び込んできた。
「警察沙汰です、ホームズ先生! もう我慢なりません! あの男には荷物ごと出ていってもらいます。すぐにでも本人に言いに行くところでしたが、まずは先生の意見を聞くのが筋だと。でももう限界です。主人が暴行を受けたのです――」
「ご主人が暴行を?」
「乱暴されたんです。」
「誰に?」
「それが分からないんです! 今朝のことです。主人はトッテナム・コート・ロードのモートン&ウェイライトのタイムキーパーで、朝7時前には家を出るんです。今朝も十歩ほど歩いたところで、後ろから二人の男が来て、主人の頭からコートを被せ、路肩の馬車に押し込んだんです。1時間ほど走って、道に放り出されました。主人は混乱していて、馬車がどうなったかも覚えていません。気がつくとハムステッド・ヒースにいて、バスで帰ってきました。今は家で横になっています。」
「興味深いですね。男たちの外見や会話に気付いたと?」
「いいえ、何も。まるで魔法のように持ち上げられ、また魔法のように落とされた感じだったと。少なくとも二人、多ければ三人。」
「その事件を下宿人と結びつけているのですね?」
「十五年も住んでいて、こんなことは初めてです。もうたくさんです。お金だけが全てではありません。今日中に出て行ってもらいます。」
「お待ちください、ウォーレン夫人。軽率なことはなさらないよう。これは思った以上に重要な事件かもしれません。今や下宿人に危険が迫っていることが明らかです。また、敵があなたの家の近くで待ち伏せし、朝の薄暗がりでご主人を本人と間違えた。間違いと分かって解放した。間違いでなければどうなったかは……推測するしかありません。」
「ではどうすればいいんです?」
「あなたの下宿人を一目見たいのです。」
「それにはドアを壊すしかありません。私はトレイを置いた後、必ず鍵をかける音を聞きます。」
「トレイを部屋に入れなければなりません。私たちが隠れていれば、それを見られるでしょう。」
女主人はしばし考えた。
「なら、向かいの物置部屋に……鏡を置いて、先生たちがドアの陰に隠れれば――」
「素晴らしい!」とホームズ。「昼食は?」
「一時頃です。」
「ではワトスン博士と私は時間通り伺います。ひとまず、お別れを。」
十二時半、私たちはウォーレン夫人宅の階段にいた。細長い黄色のレンガ造りの家、グレート・オーム・ストリートの一角だ。角の近くにあり、ハウ・ストリートの立派な家並みを見下ろせる。ホームズはその一つを指差して笑った。
「見てごらん、ワトスン。『赤い高い家、石の外壁』。あれが合図の拠点だ。場所も分かり、暗号も分かっている。これは簡単な仕事のはず。あの窓に『貸室』の札がある。空き家で仲間が出入りできるのだ。さて、ウォーレン夫人、準備は?」
「全部できています。靴を下で脱いで、そちらへご案内します。」
女主人の用意した隠れ場所は素晴らしかった。鏡の配置が巧みで、暗がりに座って向かいのドアをはっきり見ることができた。私たちが身をひそめ、女主人が去ったすぐ後に、遠くでベルの音が響いた。やがて女主人がトレイを持ち、閉ざされたドア脇の椅子に置き、重々しく去っていった。私たちはドアの隅に身を潜め、鏡の中に目を凝らした。女主人の足音が遠ざかると、鍵の回る音、取っ手の動き、そして二本の細い手が素早く現れて椅子からトレイを取り上げた。瞬間的に元に戻され、物置部屋の細い隙間から、暗く美しい恐怖に満ちた顔がこちらを睨みつけているのを私は見た。とたんにドアが閉まり、鍵がかけられ、再び静寂が訪れた。ホームズは私の袖を引き、二人でそっと階段を下りた。
「夕方また伺います」とホームズは待つ女主人に言った。「ワトスン、これなら我々の部屋で相談できる。」
「やはり予想通りだった、ワトスン。住人の交替があった。ただし女性だったのは予想外だった。」
「彼女は私たちに気づいた。」
「何かに怯えたのは確かだ。出来事の流れは明らかだろう? ある男女が、恐ろしい危険からロンドンに逃れてきた。その危険の大きさは用意周到さから見て取れる。男は何かやるべきことがあり、女を絶対安全な場所に残したい。それは難題だが、彼は巧みに解決し、女主人にさえ気づかせなかった。印刷文字の伝言は、筆跡で女性だと分かるのを防ぐためだった。男は女に近づけば、敵に手がかりを与えてしまう。直接連絡できないので、新聞の身の上相談欄を使った。ここまでは明白だ。」
「だが根本は何か?」
「まさに、ワトスン――君はいつも実務的だ。何が根本なのか? ウォーレン夫人の奇妙な問題は、進むにつれより不気味になってきた。これは単なる恋愛逃避などではない。危険の際のあの女性の顔、そして家主への襲撃。重大な秘密がある。しかも敵も女性が住人だと気づいていない。実に不可解で複雑だ。」
「なぜ君は深入りする? 得るものがあるのか?」
「何もない。だが芸術のための芸術さ、ワトスン。君も医者時代、報酬抜きで症例を調べたことがあるだろう?」
「修業のために。」
「修業は終わらないよ。最後こそ最大の学びだ。これは教訓的な事件だ。名誉も金もないが、誰しも解決したくなる。夕暮れになれば、一歩前進するだろう。」
夕刻、ロンドンの冬の闇は灰色のカーテンとなり、窓の黄色い四角やガス灯の淡い光だけが彩りを添えていた。下宿屋の暗い居間から外をうかがうと、薄暗がりの中、高い位置にかすかな灯りが見えた。
「あの部屋で誰かが動いている」とホームズがささやいた。「ほら、また現れた。手に蝋燭を持っている。向こうを伺っている。彼女が見ているか確認したいのだ。さあ、合図が始まった。君も記録してくれ、ワトスン。単発、これはAだな。で、いくつだった? 二十回。僕もだ。T。AT――意味ありげだ。もう一回T。二語目の始まりか。TENTA……ここで止まった? ATTENTAは意味をなさない。三語に分けても……また来た! ATTE――また同じ。三度繰り返すだと? ATTENTA三回! 何度繰り返す? ……今度は終わりのようだ。引っ込んだ。どう思う、ワトスン?」
「暗号だ、ホームズ。」
ホームズは急に笑った。「だが、さほど難しい暗号じゃない、ワトスン。これはイタリア語だよ! Aは女性宛。『注意せよ! 注意せよ! 注意せよ!』だ。」
「君の言う通りだ。」
「間違いない。緊急メッセージを三度繰り返して強調している。だが何に注意せよ? 待て、また窓に来た。」
またもや、うずくまった男の影と小さな炎が窓を横切って合図を送るのが見えた。今度はさらに速く、追うのがやっとだ。
「PERICOLO――ペリコロ、危険だな。ああ、また来た! PERI……なんだこれは――」
突然、明かりが消え、窓のかすかな四角も消えてしまい、三階部分は高い建物をぐるりと取り巻く暗い帯となり、その上や下の階の窓だけが輝いていた。あの最後の警告の叫びも、突然途絶えた。どうして、誰の手によって? 私たち二人の脳裏に、同じ考えが瞬時に浮かんだ。ホームズは、身をかがめて窓辺にいた体勢から跳ね起きた。
「これは一大事だ、ワトソン!」彼は叫んだ。「何か悪事が起きている! なぜ、あんなふうに伝言が途切れるんだ? スコットランド・ヤードに連絡すべき案件だ――だが、今は急を要していて、ここを離れるわけにもいかん。」
「警察を呼んできますか?」
「もう少し状況をはっきりさせてからだ。もっと無害な解釈もできるかもしれん。さあ、ワトソン、自分たちで向こうへ行ってみよう。」
第二部
私たちは急ぎ足でハウ通りを下りながら、今しがた出てきた建物を振り返った。最上階の窓にかすかに浮かび上がる女性の頭の影――その姿は固まったように夜の闇をじっと見つめ、息をひそめて中断された伝言の再開を待っているようだった。ハウ通りのフラットの出入り口には、マフラーと厚手の外套姿の男が手すりにもたれていた。玄関灯が私たちの顔を照らすと、その男ははっとした。
「ホームズ!」彼は叫んだ。
「おや、グレグソン!」とホームズはスコットランド・ヤードの刑事と握手しながら言った。「恋人たちの再会が旅の終わりとはね。何しにここへ?」
「多分、あなたと同じ理由でしょうな」とグレグソン。「どうやってこの事件に気づいたのか、見当もつきませんが。」
「別々の糸口だったが、結局同じもつれた糸玉に行き着いたというわけだ。私は信号を見ていた。」
「信号?」
「そう、あの窓からだ。途中で途切れたので理由を確かめに来た。だが、君がいるなら、私が続ける意味はないだろう。」
「ちょっと待ってください!」とグレグソンは熱心に叫んだ。「正直言って、ホームズさん、これまであなたが味方にいるとわかった事件で心強くなかったことは一度もありません。このフラットには出口が一つしかない、ですから奴は逃げられません。」
「奴とは誰です?」
「今回は我々が一歩リードですよ、ホームズさん。ここは譲っていただきましょう。」彼は杖で地面をコツンと鳴らすと、向こう側に止まっていた四輪馬車の御者が鞭を手にこちらへ歩み寄ってきた。「ホームズさん、ご紹介します。こちらはピンカートン探偵社所属のレバートン氏です。」
「ロングアイランドの洞窟事件の英雄ですな?」とホームズ。「お会いできて光栄です。」
アメリカ人は物静かで実務的な若者で、刃物のようにシャープな顔立ちには無精ひげもなかった。称賛の言葉に少し赤面した。「今まさに人生最大の獲物を追っています、ホームズさん。もしゴルジャーノを捕まえられたら――」
「なんですって! あの“赤い輪”のゴルジャーノを?」
「おや、ヨーロッパでも有名なんですね? アメリカでも奴のことは全部調べ上げています。五十件の殺人事件の黒幕とわかっているのに、決定的な証拠がない。ニューヨークからあとをつけ、ロンドンに来てからは一週間、何か口実ができるのを待っていた。グレグソン氏と私は、あの大きな集合住宅に追い詰めました。出入り口は一つだけ、逃げ道はありません。奴が入ってから三人が出てきましたが、絶対奴じゃありませんでした。」
「ホームズさんは信号の話をされていましたね」とグレグソン。「きっと、いつものように我々が知らないことをよくご存じなのでしょう。」
ホームズは、私たちに見えた状況を簡潔な言葉で説明した。アメリカ人は悔しそうに手を打った。
「奴に気づかれましたね!」
「なぜそう思うのです?」
「筋が通るでしょう? 奴は仲間に信号を送っていました――ロンドンには奴の手下が何人もいます。ところが、まさに危険を知らせている時に急に途切れた。つまり、窓から私たちを見つけたか、あるいは危険がすぐそばまで迫っていると感づいたに他ならない。何か提案は?」
「すぐに上がって直接見てみましょう。」
「でも逮捕状がありません。」
「不審な状況で空き部屋にいるんです」とグレグソン。「当座はそれで十分。捕まえてからニューヨークの協力も得られるでしょう。今ここで逮捕の責任は私が持ちます。」
我が国の刑事は、知恵では迂闊なこともあるが、勇気では決して間違えない。グレグソンは、スコットランド・ヤードの庁舎の階段を上る時と同じ、静かで実直な態度で、この絶望的な殺人犯の逮捕に向かった。ピンカートンの男は前に出ようとしたが、グレグソンはしっかり肘で制した。ロンドンの危険はロンドン警察の特権だった。
三階の左手の部屋のドアは半開きだった。グレグソンが押し開ける。中は絶対的な静寂と闇だった。私はマッチを擦って刑事のランタンに火を灯した。その炎が安定して灯ると同時に、皆が驚きの声を上げた。絨毯のない板張りの床に、新しい血痕の足跡が線を描いている。赤い跡は私たちの方に向かい、閉じたままの内側の部屋のドアへ続いていた。グレグソンがそのドアを開け、明かりを前方いっぱいに照らすと、私たちはみな肩越しに身を乗り出して覗き込んだ。
がらんとした部屋の真ん中に、巨漢の男がうずくまっていた。剃り上げた黒い顔は苦悶で異様に歪み、頭の周囲は恐ろしい血の朱の輪が広がっていた。膝は引き寄せられ、両手は苦しげに伸ばされ、太い褐色の喉の真ん中からは、柄の白いナイフが根元まで突き刺さっていた。この一撃で、あれほどの大男も屠殺された牛のように倒れたに違いない。右手のそばには恐ろしい角柄の両刃ナイフが落ち、近くには黒いキッドの手袋があった。
「なんてこった! 黒いゴルジャーノ本人だ!」とアメリカの刑事が叫んだ。「今回は誰かが俺たちより先手を打ったな。」
「これが窓辺のろうそくです、ホームズさん」とグレグソン。「それにしても、何をなさってるんです?」
ホームズは素早く窓辺へ行き、ろうそくに火を灯すと、窓ガラスの前でろうそくを前後に振った。それから闇を覗き、ろうそくを吹き消して床に投げ捨てた。
「これは役立つと思いますよ」と彼は言った。そして、二人の刑事が遺体を調べている間、深い思案に沈んで立っていた。やがて、「あなたは階下で待っていた間に三人がフラットから出てきたとおっしゃいましたが、よく観察しましたか?」と尋ねた。
「はい、しっかり見ました。」
「三十歳くらいで黒いあごひげ、中背で色の黒い男はいませんでしたか?」
「ええ、最後に通り過ぎました。」
「そいつが犯人でしょう。特徴をお教えできますし、足跡の型もはっきり取れている。それで十分でしょう。」
「ロンドンの何百万の中じゃ、大した手がかりじゃありませんよ、ホームズさん。」
「そうかもしれません。だから私はこの女性をあなた方の助けに呼ぶのが最善だと思ったのです。」
その言葉で私たちは皆振り返った。そこには、ドア枠にすっくと立つ、背の高い美しい女性――ブルームズベリーの謎の下宿人――がいた。彼女はゆっくりと進み、顔は恐怖で青ざめ、目は見開かれ、怯えた視線は床の黒い人影に釘付けだった。
「あなたが殺したのですね!」彼女はつぶやいた。「ああ、ディオ・ミオ、あなたが……!」 そして突然息を吸い込み、歓喜の叫びとともに跳び上がった。部屋中をぐるぐると踊りながら、手を叩き、暗い瞳は喜びに輝き、イタリア語の小さな感嘆詞が次々と口からこぼれた。その光景は恐ろしいほど異様だった。突然彼女は立ち止まり、私たち全員を見回した。
「でも、あなた方は警察でしょう? ジュゼッペ・ゴルジャーノを殺したんですね?」
「警察です、奥さん。」
彼女は部屋の影を見回した。
「で、ジェンナーロはどこ? 私の夫、ジェンナーロ・ルッカです。私はエミリア・ルッカ。私たちはニューヨークから来ました。ジェンナーロはどこ? さっきこの窓から私を呼んだのに、走ってきたんです。」
「呼んだのは私です」とホームズが言った。
「あなたが? どうやって呼べたのです?」
「あなたの暗号は難しくありませんでした。あなたの出席が望ましかったのです。ヴィエニと点滅させれば、きっといらっしゃると思いました。」
美しいイタリア女性は、畏敬の念をもってホームズを見つめた。
「どうやってそんなことがわかるのか、私には理解できません」と彼女。「ジュゼッペ・ゴルジャーノ……どうやって――」彼女は言いかけて、突然顔を誇りと喜びで輝かせた。「わかったわ! 私のジェンナーロ! 私の素晴らしい、立派なジェンナーロが、私を守るために、あの怪物を自らの手で殺したのですね! ああ、ジェンナーロ、なんて素晴らしい人! こんな男性にふさわしい女性なんて、どこにもいない!」
「さて、ルッカ夫人」と現実主義者のグレグソンが、ノッティング・ヒルの乱暴者を扱うかのように淡々と彼女の袖に手をかけて言った。「あなたが何者で、どんな関係かわかりませんが、今おっしゃったことで、ヤードにご同行願う理由は十分です。」
「ちょっと待ちたまえ、グレグソン」とホームズ。「このご婦人も我々と同じくらい情報提供に前向きかもしれません。奥さん、あなたのご主人はこの男を殺した罪で逮捕され、裁判にかけられることになります。あなたのお話は証拠として使われる可能性があります。ですが、ご主人が犯罪的動機でない理由でしたことであり、それを広く知ってほしいのであれば、全てをお話しいただくことが最善です。」
「ゴルジャーノが死んで、私たちはもう何も恐れません」と彼女は言った。「彼は悪魔で怪物でした。世界中のどんな裁判官も、夫を罰するはずがありません。」
「それなら」とホームズ。「この扉を施錠し、現場はそのままにして、このご婦人の部屋でお話を伺い、判断しましょう。」
三十分後、私たち四人はルッカ夫人の小さな居間に集まり、彼女から、私たちが偶然目撃した一連の陰惨な事件の経緯を聞いていた。彼女は流暢ながらも奇妙な英語で話したので、分かりやすく整えて記す。
「私はナポリ近郊ポジリッポの生まれで、父はアウグスト・バレッリ、地元の弁護士で一時は代議士でした。ジェンナーロは父のもとで働いていて、私は彼を愛するようになりました。彼には地位も財産もなく、美しさと力強さと情熱しかありませんでしたので、父は交際を禁じたのです。私たちは駆け落ちし、バーリで結婚し、私の宝石を売って渡米資金を作りました。四年前のことです。それ以来ニューヨーク暮らしでした。
最初は運に恵まれ、夫はイタリア人紳士に恩を売りました。バワリーで暴漢から救い、強い味方を得たのです。名前はティト・カスタロッテ。カスタロッテ&ザンバというニューヨーク最大の果物輸入会社の経営者です。ザンバ氏は病弱で、カスタロッテ氏が実質全権を持ち、従業員も三百人を超えます。彼は夫を部門長として雇い、あらゆる面で好意を示してくれました。独身で、我が子のように感じていたのでしょう。私たち夫婦も父親のように慕っていました。ブルックリンに小さな家を借りて将来も安泰だと思っていた時、あの黒雲が突然現れたのです。
ある晩、夫が同郷人を連れて帰りました。ゴルジャーノという名の巨漢です。皆さんが死体をご覧になった通りです。体だけでなく、全てが怪物じみていました。声は雷鳴、腕を振るえば家が揺れるほど。思考も感情も激情もすべて過剰で、しゃべる――いや怒鳴るようなその勢いは他を圧倒し、誰も黙って聞くしかありません。目は燃えるように人を捉え、まるで意のままに支配するかのよう。恐ろしくもあり、また不思議な人物でした。神よ、彼が死んでくれてありがとう!
彼は何度も訪ねてきましたが、私同様、夫も彼の存在を喜んでいなかったのは明らかでした。夫は青ざめて元気なく、彼の果てしない政治や社会問題の放言に黙って聞き入っていました。でも私は夫の顔に見たことのない感情を読み取りました。最初は反感かと思いましたが、次第にそれ以上だと分かってきました。それは恐怖――深い、隠された、身をすくめるような恐怖でした。その夜、私は夫に抱き付き、私への愛と大切なもの全てにかけて、何も隠さず話してほしいと懇願しました。
夫は語りました。その話を聞き、私の心まで氷のように冷えました。夫は若く熱い時代、不正に追い詰められて正気を失いかけていた頃、ナポリの“赤い輪”という秘密結社に加わったのです。カーボナリの流れを汲み、秘密と誓約はおぞましいものでしたが、一度入ったら脱退は不可能でした。アメリカに逃れた時、夫は全てを捨てたつもりでいました。ところが、ある晩ナポリで入会させられた張本人、殺人にまみれ“死神”と呼ばれた巨漢ゴルジャーノと街中で再会したのです。彼はイタリア警察から逃れニューヨークに来ており、すでにこの恐ろしい組織の支部を作っていました。夫はその日届いた招集状を見せてくれました。頭に“赤い輪”が描かれており、ある日集会が開かれ出席を命じられていました。
それだけでも十分恐ろしいのに、さらに悪いことが起きました。ゴルジャーノが夜ごと訪ねてくると、私との会話が増え、夫への言葉の時もあの恐ろしい野獣の目は私に向けられていました。ある夜、ついに秘密が明かされました。彼の中に“愛”――野獣のような粗暴な愛を呼び起こしてしまったのです。夫がまだ帰宅していない時、彼は強引に押し入り、私を熊のように抱きしめ、キスを浴びせ、一緒に逃げようと迫ったのです。私は必死で抵抗し叫びましたが、そこに夫が帰宅して襲いかかりました。ゴルジャーノは夫を殴り倒し、家を逃げ出しました。その夜、私たちは死敵を得たのです。
数日後、集会がありました。夫は何か恐ろしいことが起きた顔で帰宅しました。想像を絶する事件でした。組織は、資金調達のため裕福なイタリア人を脅迫していましたが、今回、親友のカスタロッテ氏が標的となりました。彼は脅しを拒み、警察に通報していたのです。見せしめとして家ごと爆破することが決まりました。誰が実行するかくじ引きになり、夫はゴルジャーノのにやけた顔を見ながら袋に手を入れました。仕組まれていたのでしょう、夫の手に“赤い輪”の円盤――殺人の命令書が握られていたのです。親友を殺すか、仲間に自分と私を復讐されるか。あの一味は、標的本人だけでなく愛する者まで巻き添えにする非道なやり方でした。それを知って以来、夫は恐怖に取り憑かれ、正気を失いかけていたのです。
その夜、私たちは抱き合い、互いに困難を乗り越える覚悟を固めました。翌晩が実行予定で、昼までに私たちはロンドンへ向かう途中でした。ただし、夫は親友に危険を十分警告し、また警察にも将来身を守れる情報を伝えてきました。
後は皆さんもご存じでしょう。私たちは常に敵が影のように付け狙うと確信していました。ゴルジャーノには私的な復讐理由もありましたが、いずれにせよあの執念深さと狡猾さ、無慈悲さは世界中に知られています。夫は、私に絶対安全な隠れ家を最初の数日で用意し、自身は自由な身としてアメリカ・イタリア両警察と連絡を取ろうとしました。彼がどこに住み、どんな生活だったのか私は知りません。知るのは新聞の小さな記事だけでした。でも、窓からイタリア人二人が家を監視しているのを見かけ、ゴルジャーノに居場所を突き止められたと察しました。やがて夫は新聞を通して、ある窓から信号を送ると伝えてきましたが、届いた信号は警告だけで、途中で突然途切れました。今思えば、ゴルジャーノが目前まで迫ったことを知り、そして幸いにも、夫は準備万端で立ち向かったのでしょう。これがすべてです。さて、紳士の皆さん、私たちが法に怯える理由があるでしょうか? 私のジェンナーロのしたことを咎める判事が世界にいるでしょうか?」
「さて、グレグソンさん」とアメリカ人が公式の刑事を見て言った。「イギリスの見解は分かりませんが、ニューヨークならこのご婦人の夫には感謝状が贈られますよ。」
「彼女にも署までご同行願いましょう」とグレグソン。「話が裏付けられれば、彼女もご主人も心配することはありません。ただ、ホームズさん、あなたがどうやってこの事件に関わったのか、さっぱり見当がつきません。」
「教育ですよ、グレグソン、教育。いまだに“古き大学”で知識探求中です。さて、ワトソン、君の珍事件コレクションにまた一品追加だな。ところで、まだ八時前、今日はコヴェント・ガーデンでワーグナーだ。急げば第二幕に間に合うかもしれん。」
レディ・フランシス・カーファックスの失踪
「なぜトルコ式なんだい?」シャーロック・ホームズが私のブーツをじっと見つめながら尋ねた。その時私は籐椅子に腰掛けていて、突き出した足が彼の興味を引いたらしい。
「イギリス製だよ」と私はやや驚いて答えた。「オックスフォード・ストリートのラティマーズで買った。」
ホームズは、疲れたような忍耐の微笑を浮かべた。
「風呂だよ!」と言う。「風呂! なぜ刺激的な自家製ではなく、緩めて高価なトルコ式を選んだ?」
「最近リウマチっぽくて年寄り気分でさ。トルコ風呂は医学的に“変調薬”と呼ぶ――心身のリセット、体の浄化ってやつさ。」
「ところでホームズ、君にとっては、僕のブーツとトルコ風呂の関係なんて論理的に自明なんだろうが、説明してくれないか。」
「推理の筋道はそんなに難解じゃないよ、ワトソン」とホームズは茶目っ気たっぷりに言った。「今朝君が馬車で乗り合わせた相手を当ててみせるような初歩的な推論と同じさ。」
「新しい例を出されても説明にならんよ」と私はむっとした。
「見事、ワトソン! 実に論理的な抗議だ。さて、どこまで話したっけ? 馬車の件から説明しよう。君の左袖と肩に泥はねがある。もし馬車の中央に座っていたなら、泥はねはないはずだし、あっても左右対称になっていたはず。つまり君は端に座っていて、横に誰かいたのは明らかだ。」
「確かに。」
「馬鹿みたいに単純だろう?」
「じゃあブーツと風呂は?」
「これも子供だましさ。君はいつも決まった結び方をするが、今日は珍しく複雑な二重結びになっている。つまり一度脱いだということ。誰が結んだ? 靴屋か風呂屋のボーイか。靴はほぼ新品だから靴屋ではない。となると風呂屋――単純だろう? でもトルコ風呂のおかげで役立った。」
「どう役立った?」
「気分転換したいから行ったと言ったな。僕からも転換を提案しよう。どうだ、ローザンヌへ旅行――一等車、費用はすべて王侯並みに支給――なんてのは?」
「素晴らしい! でもなぜ?」
ホームズは肘掛け椅子にもたれ、手帳を取り出した。
「世界で最も危険な人種の一つ――それは“流浪し友なき女性”だ。彼女たちは無害だし、時に非常に役立つが、他者に犯罪を引き起こさせるきっかけになりがちだ。無力で、渡り鳥のように国から国へ、ホテルからホテルへと移動する。しばしば安宿や下宿で身を隠し、そのまま失踪してもほとんど気づかれない。僕はどうもレディ・フランシス・カーファックスに災厄が降りかかった気がしてならない。」
一般論から個別の話題への突然の転換に、私は安心した。ホームズは手帳を繰った。
「レディ・フランシスは、故ルフトン伯爵家直系の唯一の生き残りだ。領地は男系に渡った。彼女には限られた資産しか残らなかったが、貴重な古いスペイン製の銀とダイヤモンドの宝飾品があり、それは彼女の大切な宝だった――あまりに大切にしすぎて、銀行に預けることもせず、いつも持ち歩いていた。なんとも哀れな人物さ、レディ・フランシス。まだ若々しく美しいが、奇妙な運命で、二十年前は立派だった家柄の最後の残照となってしまった。」
「それで、彼女に何が起きたんだ?」
「まさにそれが問題だ。生きているのか、死んでいるのか。彼女は几帳面な性格で、四年間、決まって二週間ごとに元家庭教師のドブニー嬢(今はカンバーウェル在住の隠居)に手紙を書いていた。ドブニー嬢が相談してきた。もう五週間も音信がない。最後の手紙はローザンヌのナショナル・ホテルから。そこを去り、住所も残さず。親族は心配しているし、資産も十分だから事件解決には費用を惜しまない。」
「情報源はドブニー嬢だけか? 他にも手紙くらい書く人がいたはず。」
「確実なのは銀行だ、ワトソン。独身女性の家計簿は日記みたいなもの。シルヴェスター銀行に口座がある。明細を見ると、前回はローザンヌの支払い、しかも高額だから現金も残っているはず。そのあと一件だけ引き出しがある。」
「誰宛、どこで?」
「マリー・ドヴァイン嬢宛だ。どこで書かれたかは不明だが、三週間足らず前にモンペリエのクレディ・リヨネで現金化された。金額は五十ポンド。」
「そのマリー・ドヴァイン嬢とは?」
「それも調べた。レディ・フランシス・カーファックスの侍女だ。なぜ彼女に小切手を渡したかは不明だが、君の調査ですぐ判明するだろう。」
「僕の調査?」
「それゆえ健康増進のローザンヌ行きだ。老アブラハムズが命の危険を訴えている限り、僕はロンドンを離れられないし、基本的にも国外に出ないほうがいい。スコットランド・ヤードも僕不在だと寂しがるし、犯罪界も不健康に騒ぐ。では行ってきてくれ、ワトソン。もし僕のささやかな助言が二ペンスの価値でもあるなら、大陸の電信越しに夜昼いつでも応じるよ。」
二日後、私はローザンヌのナショナル・ホテルに到着し、著名な支配人モーゼル氏から丁重な応接を受けた。レディ・フランシスは数週間滞在し、誰にも好かれていたという。年齢は四十前後、若い頃は絶世の美女だったに違いないという。宝飾品については何も知らないが、彼女の寝室の大きなトランクはいつも厳重に鍵がかかっていたと使用人が言っていた。侍女のマリー・ドヴァイン嬢も主人同様人気者で、ホテルの主任給仕と婚約しており、住所もすぐ分かった。モンペリエ、トラヤン通り11番地。私はこれらを記録し、ホームズ並みの手際だと満足した。
謎が残るのは一つだけ。突然の出発理由が分からないのだ。レディ・フランシスはここで幸せそうで、湖を見下ろす豪華な部屋でシーズンを過ごすつもりだったに違いない。それなのに一日限りの予告で出発し、無駄に一週間分の家賃まで支払っている。唯一意見を述べたのは侍女の恋人ジュール・ヴィバールだった。彼は、出発直前にホテルを訪ねてきた黒くて背の高い髭男を関連付けた。「サヴァージュ――本物の野蛮人だ! 」とヴィバールは叫んだ。男は町のどこかに部屋を持ち、湖畔を歩くレディ・フランシスと長く話し、やがて訪問したが、彼女は会うのを拒否した。その直後、彼女は去った。ヴィバールと婚約者も、来訪と出発の因果関係を疑っていた。ただ一つ、なぜマリーが主人を辞めたかは語りたがらなかった。それを知りたければモンペリエで本⼈に聞けという。
これが調査第一章の終わりである。第二章は、ローザンヌを去ったレディ・フランシスがどこへ向かったかの調査だ。ここには秘密主義が感じられ、何者かの追跡をかわそうとしたふしがある。でなければ荷物を堂々とバーデン行きにしなかったはずだ。彼女も荷物も回り道してライン川畔の温泉地に着いた。これは現地クック旅行社の支配人から得た情報だ。私はバーデンへ向かった。ホームズには経過を報告し、半分冗談のような称賛の電報が返ってきた。
バーデンでの足取りは簡単だった。レディ・フランシスはイングリッシャー・ホフに二週間滞在。そこで南米帰りの宣教師シュレシンガー博士夫妻と親しくなった。孤独なご婦人はたいてい宗教に慰めを求める。博士の人格と献身、伝道活動で病に倒れ快復中という事情もあり、彼女は大いに心を動かされた。レディ・フランシスは妻人と交代で看病し、博士は日がなベランダの椅子に横たわり、両脇に女性を侍らせて“ミディアン王国”中心の聖地地図を描いていた。やがて健康を取り戻し、夫妻はロンドンへ帰り、レディ・フランシスも同行した。ちょうど三週間前のこと。侍女のマリーは、数日前に涙ながらに辞め、二度と奉公しないと仲間に宣言していた。博士が全員分の勘定を支払って去った。
「ところで」と支配人が付け加えた。「レディ・フランシスの消息を探しているのは、あなただけじゃありません。1週間ほど前にも同じ目的の男が来ました。」
「名乗りましたか?」
「いえ。ただし明らかにイギリス人ですが、ちょっと変わった感じでした。」
「野蛮人?」私はホームズ流に事実をつなげて問うた。
「正にその通り! でかくて、髭ぼうぼう、日に焼けた男で、上流ホテルより農家の宿のほうが似合いそうでした。厳つくて気難しそう。怒らせたくないタイプですよ。」
ここに来て霧が晴れるように謎の輪郭が現れ始めた。敬虔な淑女が、不吉な人物に国から国へと執拗に追われている。彼女は怯えており、ローザンヌから逃げたのもその男のためだ。その後も追跡は続いた。いずれ追いつかれる。それはもう起きたのか? それが沈黙の理由か? よき同行者たちは、彼の暴力や脅迫から彼女を守れなかったのか? この長い追跡の背後にどんな恐るべき目的や計画があったのか? それが私の解くべき問題だった。
私はホームズに、着実に核心に迫っていると報告した。返ってきた電報は「シュレシンガー博士の左耳の特徴を送れ」というものだった。ホームズの冗談は時に風変わりで不愉快ですらあるので、無視して侍女マリーのいるモンペリエへ向かった。
元侍女の家を見つけ、話を聞くのは容易だった。彼女は献身的な女性で、主人が信頼できる人々と一緒にいると確信したのと、自身の結婚準備のために辞めたのだという。バーデン滞在中、主人はやや気難しくなり、一度は彼女の正直さすら疑ったことがあったが、それで別れはかえって楽だったという。主人は結婚祝に五十ポンドをくれた。マリーもまた、主人をローザンヌから追い出した男を強く警戒していた。自分自身、湖畔の公道で、その男が主人の手首を乱暴につかむのを目撃した。とても恐ろしい男だった。主人がシュレシンガー夫妻の同行を受け入れたのは彼への恐れゆえだと、彼女は信じて疑わなかった。主人からその話を直接聞いたことはないが、日々のしぐさの端々に常に神経質な不安が表れていたという。彼女が語り終わらぬうちに、突然椅子から飛び上がり、驚愕と恐怖で顔をゆがめた。「見て! あの悪党、まだ追ってきてる! 話したその男よ!」
開け放した窓の外、通りの真ん中を、黒々とした髭をたくわえた巨漢がゆっくりと歩き、家の番号を食い入るように見ていた。彼も私と同じく、侍女の行方を探しているのは明らかだった。私は衝動的に外へ飛び出し、彼に声をかけた。
「イギリス人ですね?」
「で、なんだ?」と彼は不機嫌な顔で答えた。
「お名前を伺っても?」
「だめだ。」と即答した。
気まずい状況だったが、時に直球が一番だ。
「レディ・フランシス・カーファックスはどこです?」
彼は呆然と私を見つめた。
「彼女に何をした? なぜ追いかける? 答えてもらいたい!」私は詰め寄った。
男は怒りにうなり声を上げ、虎のように私に飛びかかってきた。私はこれまでにも幾度となく争いに身を置いてきたが、彼の握力は鉄のように強く、その狂気じみた凶暴さはまるで悪魔のようだった。彼の手が私の喉元を締めあげ、私は意識が遠のきかけた。そのとき、向かいのキャバレーから髭面のフランス人労働者が青い作業着姿で棍棒を手に飛び出してきて、私を襲っていた男の前腕に鋭い一撃を加えたため、男は手を離した。男は一瞬、怒りに燃え、再び襲いかかるべきかどうか迷うように立ち尽くしたが、うなり声を上げて私の元を離れ、私が出てきたばかりのコテージへと入っていった。私は恩人に礼を言おうと、道端に立つ彼のそばへ向き直った。
「まったく、ワトソン君」と彼は言った。「見事に台無しにしてくれたね! どうやら夜行列車で一緒にロンドンへ帰ったほうがよさそうだ。」
一時間後、シャーロック・ホームズはいつもの身なりと態度で私のホテルの私室に腰を下ろしていた。突然現れた彼の行動の説明は、いたって単純だった。ロンドンを離れられる見通しがついたので、私の旅の次の明らかな目的地で先回りすることに決めたという。労働者に変装してキャバレーで私の到着を待っていたのだ。
「いやはや、ワトソン君、なんとも一貫性のある捜査だったね」と彼は言った。「君がやり残した失策は思い出せないくらいだ。君の行動は、あらゆる所に警戒心を呼び起こしただけで、結局、何も見つけられなかった。」
「君にだって、もっと良い結果が出せたとは限らないじゃないか」と私は苦々しく答えた。
「“限らない”ではないよ。私はもっと良い結果を出した。ほら、フィリップ・グリーン閣下だ。君と同じこのホテルに滞在している。彼を手掛かりに、もっと有望な調査ができるかもしれない。」
サルヴァー[訳注:盆]に載せられたカードが届けられ、それに続いて、通りで私を襲ったあの髭面の乱暴者が入ってきた。彼は私を見るなり驚いた様子だった。
「これはどういうことです、ホームズさん?」彼は言った。「あなたの手紙を受け取って来ましたが、この男は何の関係が?」
「こちらは私の旧友であり協力者のワトソン博士です。この件で私たちを手助けしてくれています。」
その男は巨大で日焼けした手を差し出し、簡単な謝罪の言葉を口にした。
「お怪我はありませんでしたか? あなたが私のことを彼女を傷つけたと非難したとき、自制心を失ってしまいました。最近は本当に自分でも制御が利きません。神経がむき出しの電線のようです。でも、正直言って私にはこの状況が手に余ります。ホームズさん、まず第一に知りたいのは、そもそもどうやって私の存在を知ったのかということです。」
「ミス・ドブニー、すなわちレディ・フランシスの家庭教師と連絡が取れたのです。」
「昔のスーザン・ドブニー、あの帽子のおばさんか! よく覚えていますよ。」
「彼女もあなたのことを覚えていますよ。あの頃は……あなたが南アフリカに行くほうがよいと判断される前でしたね。」
「なるほど、私の身の上をご存じなのですね。隠すことは何もありません。ホームズさん、誓って言いますが、この世にフランシスほど心から愛した女性はいませんでした。私は荒っぽい若者でしたが、同世代の誰より悪かったわけではありません。しかし、彼女の心は雪のように純粋でした。わずかでも粗野な影を許すことができなかった。だから彼女が私のしたことを知ったとき、それっきり私と口をきいてはくれませんでした。それでも彼女は私を愛してくれていた――それこそが驚きです! 私のためだけに、聖女のように独身を貫いたのです。年月が過ぎ、バーバートンで財を成し、もしかしたら彼女を探し出して心を通わせられるかもしれないと思いました。まだ未婚だと聞いていたので、ローザンヌで彼女を見つけ、できる限りのことはしました。彼女も気持ちが動いたと思いましたが、意志は強く、その次に訪ねたときには町を出ていました。バーデンまで追い、その後しばらくして侍女がここにいると聞きました。私は荒っぽい人間で、荒れた生活を送ってきた者ですから、ワトソン博士の言葉に一瞬自制心を失ってしまいました。ですが、どうか、レディ・フランシスがどうなったのか教えてください。」
「それは私たちがこれから見つけ出すことです」とホームズは非常に重々しく言った。「ロンドンでのご住所を伺ってもよろしいですか、グリーンさん?」
「ラングハム・ホテルに宿泊しています。」
「では、しばらくそちらに戻り、私からご連絡する場合に備えてお待ちいただけますか? 偽りの希望は持たせたくありませんが、レディ・フランシスの安全のためにできる限りのことは必ずいたします。今はそれしか申し上げられません。このカードを差し上げますので、私たちと連絡が取れるようにしてください。さて、ワトソン君、荷物をまとめたまえ。ハドソン夫人に電報を打って、明朝七時半に二人の空腹な旅人のために腕をふるってもらうように頼もう。」
ベイカー街の部屋に到着すると、私たちを待っていた電報があった。ホームズはそれを読み興味深げに声をあげて私に投げてよこした。「ギザギザ、あるいは裂けている」という文面、発信地はバーデンだった。
「これはどういう意味だ?」私は尋ねた。
「すべての鍵だ」とホームズは答えた。「この聖職者紳士の左耳について私が一見無関係な質問をしたのを覚えているね。君は答えなかった。」
「バーデンを離れていたから、調べることができなかった。」
「まさにそれが理由で、私はエングリッシャー・ホフの支配人にも同じ質問を送った。その回答がここにある。」
「それで分かったのか?」
「分かったとも、ワトソン君。私たちが相手にしているのは、非常に抜け目なく危険な人物だ。南米から来た宣教師シュレシンガー博士は、実はホーリー・ピーターズ――オーストラリアが生み出した最も悪辣な悪党の一人なんだ。しかもまだ新しい国なのに、見事な悪党を輩出している。彼の得意技は、孤独な女性の宗教心を巧みに利用してだますこと。そして彼の“妻”と称するフレーザーというイギリス人女性も、立派な共犯者だ。彼の手口の性質から、私はその正体に感づいた。そしてこの身体的特徴――1889年、アデレードの酒場で激しく噛まれた怪我――が私の疑念を確信に変えた。この哀れな女性は、どんな手段も選ばない非道な二人組の手にある。すでに殺されている可能性も高い。もし生きているとしても、何らかの形で監禁されて、ドブニー嬢や他の友人たちに手紙を書くこともできない状態になっているはずだ。ロンドンに到着していない、あるいは通過しただけという可能性もゼロではないが、前者は、登録制度の厳しい大陸警察をすり抜けるのは難しいので考えにくいし、後者も、ロンドンのように人を容易に監禁できる場所は他にないから、やはり考えにくい。私の直感では、彼女はロンドンにいる。しかし、現時点で居場所を知る手段はないので、今はやるべきことをやり、食事をとり、忍耐強く待つしかない。夜になったら、スコットランドヤードのレストレードに話をつけてくるよ。」
しかし、公式の警察もホームズの小規模ながら精鋭の組織も、この謎を解明することはできなかった。ロンドンの何百万という群衆の中で、我々が捜し求める三人は、まるでこの世に存在したことすらなかったかのように跡形もなく消えてしまっていた。広告も試みたが無駄だった。手掛かりをたどっても何も得られなかった。シュレシンガーが出入りしそうな犯罪者の巣窟はすべて調べ尽くしたが、何の成果も得られなかった。かつての仲間を見張ったが、彼らも彼を避けていた。だが、無力な焦燥の一週間の後、突然、光明が差した。ウェストミンスター・ロードのボヴィントンで、スペイン風の古いデザインの銀と宝石のペンダントが質入れされていたのだ。質入れしたのは大柄で、聖職者風の風貌の男。名も住所も明らかに偽名だった。耳については誰も注意しなかったが、その特徴はまさしくシュレシンガーのものだった。
ラングハムから来るあの髭面の友人は三度も様子を聞きに来た。三度目はこの新しい進展のほんの一時間後だった。彼の服はその大柄な体にぶかぶかになってきており、心労でやつれていくのが感じられた。「何かさせてくれさえすれば!」それが彼の口癖だった。ついにホームズは彼に役割を与えることができた。
「奴らが宝石を質に入れ始めた。これで捕まえられるだろう。」
「でも、それはレディ・フランシスになにか危害が加えられたということでは?」
ホームズは非常に重々しい顔で首を振った。
「もし今まで彼女を監禁していたなら、もう解放すれば自分たちに破滅が降りかかるのは明白だ。最悪の事態を覚悟しなければならない。」
「私は何をすれば?」
「彼らは、あなたの顔を見たことは?」
「ありません。」
「今後、別の質屋に行くことも考えられる。その場合、また一からやり直しだ。だが、今回は適正な値で、面倒もないまま済んだのだから、すぐに現金が必要ならまたボヴィントンに来る可能性が高い。紹介状を書いてあげるから、店で待たせてもらいなさい。奴が現れたら、あとをつけて行き先を突き止めてくれ。ただし、無用な行動は厳禁だ。何より暴力だけは絶対に避けてくれ。私の承知と同意なく何事も行わないと、約束してほしい。」
二日間、フィリップ・グリーン閣下(ちなみに彼はクリミア戦争でアゾフ海艦隊を指揮した有名な提督の息子である)は何の報告も持ってこなかった。三日目の夕方、彼は蒼白になり、興奮で全身震わせながら、私たちの部屋に飛び込んできた。
「やりました! やりましたぞ!」と叫んだ。
興奮のあまり要領を得なかったが、ホームズは彼をなだめ、肘掛け椅子に腰掛けさせた。
「さて、順を追って話してください」とホームズ。
「つい一時間ほど前に来たんです。今度は妻のほうで、持ってきたペンダントはもう一つと対になっていました。背が高く青白い顔で、イタチのような目つきの女です。」
「それで間違いない」とホームズ。
「彼女が店を出たので、そのあとをつけました。ケニントン・ロードを歩いていき、私はその後ろについて行きました。やがて彼女はある店に入りました。ホームズさん、それは葬儀屋だったのです。」
ホームズははっとした様子で「それから?」と、冷静な顔の奥に烈火のごとき魂をのぞかせる声で尋ねた。
「彼女はカウンターの女と話していました。私も入店し、“遅いですね”というようなことを言っているのが聞こえました。女は弁解していて、“普通と違ったので時間がかかりました”と答えていました。二人とも私に気づいて、私はいくつか質問してから店を出ました。」
「よくやってくれました。次は?」
「女は外へ出てきましたが、私は戸口に隠れていました。どうやら彼女の警戒心を刺激したようで、あたりを見回していました。やがてタクシーを呼んで乗り込み、私も都合よく別のタクシーを捕まえて追いかけました。最後に下車したのはブリクストンのポルトニー・スクエア36番地です。私は通り過ぎて角でタクシーを降り、家を見張りました。」
「誰か見かけましたか?」
「窓は一つを除いてすべて暗く、下の階のブラインドが下ろされていて中は見えませんでした。私はどうしたものかと考えていると、覆い付きの荷馬車が二人の男を乗せてやってきました。彼らは荷馬車から何かを取り出し、玄関に運び込みました。ホームズさん、それは棺でした。」
「ほう!」
「私は一瞬、飛び込もうかと思いました。ちょうど扉が開いて男たちと棺が運び込まれるところでした。扉を開けたのはあの女です。でも、私の姿に気づき、たぶん私だと認識したようでした。彼女が驚いた様子であわてて扉を閉めました。あなたへの約束を思い出して、ここへ戻ってきたというわけです。」
「素晴らしい働きだ」とホームズは半紙に何か書きつけながら言った。「法的には令状が必要だ。君はこの手紙を持って当局へ行き、令状を取ってきてくれ。多少の手間はかかるかもしれないが、宝石売却の件で足りるだろう。レストレードが手続きをしてくれる。」
「でも、その間に彼女が殺されるかもしれません。棺とは、いったいどういうことでしょう? 彼女のためでなければ、誰のためだというのです?」
「できる限りのことはやります、グリーンさん。一刻も無駄にしません。あとは私たちに任せてください。さあ、ワトソン君」と、依頼人が去るとホームズは続けた。「彼が警察の正規部隊を動かしてくれる。私たちは例によって“非正規兵”、独自のやり方だ。状況は極めて切迫している。非常手段もやむを得ない。一刻も猶予はない、急いでポルトニー・スクエアへ向かおう。」
「状況を再構成してみよう」と馬車の中でホームズは続けた。「この悪党どもは、哀れな女性をロンドンに誘い込み、忠実な侍女を遠ざけた。彼女が手紙を書いたなら、すべて途中で奪われているだろう。どこか協力者を通じて家具付きの家を借り、そこに入った途端、彼女を監禁した。そして最初から狙いだった高価な宝石類を手に入れた。その一部はすでに売り始めている――彼らの目からすれば何の危険もない。彼女を解放すれば、当然、彼らの罪を告発される。だから解放はできない。でもいつまでも監禁しておくこともできない。結局、殺すしかないということだ。」
「納得できる推理だ。」
「では、別の視点で考えてみよう。二つの異なる思考の道筋をたどれば、交差する点が見つかり、そこに真相があるはずだ。今度は棺から逆算しよう。これは、レディが死んだことを疑いの余地なく示している。さらに、正式な埋葬、医師の死亡証明書、当局の許可が伴う。もし明らかに殺害されていたなら、裏庭にでも埋めていただろう。だが、ここではすべてが公然かつ正規の手続きだ。これは何を意味するか? 医師を欺き、病死を装うような手段――毒殺かもしれない――で殺したということだろう。しかし、なぜ医師を呼び寄せたのか? 共犯でない限り、それは考えにくい。」
「医師の死亡証明は偽造したのでは?」
「危険すぎる、ワトソン。そこまで彼らがやるとは思えない。ちょっと止めてくれ、御者さん! ……ここが葬儀屋だ、質屋のすぐそばだ。ワトソン、君が中に入ってくれないか? 君なら信用される。ポルトニー・スクエアの葬儀が明朝何時に行われるか訊いてきてくれ。」
店の女性は、明朝八時だとためらいなく教えてくれた。「分かるかい、ワトソン、何の秘密もない。すべて合法だ。何かしら法的手続きは完了していて、彼らはほとんど恐れるものはないと思っている。正面突破あるのみだ。武器は?」
「ステッキだけだ。」
「まあ、それで十分だ。“正義ある者は三度武装す”――警察を待つ余裕も、法の枠内に収まる余裕も我々にはない。御者さん、発車してくれ。さあ、ワトソン、今回はいつものように運命を共にしよう。」
彼はポルトニー・スクエア中央の大きな暗い家のドアベルを激しく鳴らした。すぐに扉が開き、高身長の女のシルエットが薄暗いホールに浮かび上がった。
「何の御用?」女は鋭く問い、暗闇の中から私たちをうかがった。
「シュレシンガー博士に会いたい」とホームズ。
「そのような者はいません」と彼女は答え、ドアを閉めようとしたがホームズが足で押さえた。
「ならば、ここに住む男に会いたい。どんな名で呼ばれようと構わない」とホームズは動じずに言った。
女は迷い、やがてドアを大きく開けた。「じゃあ、入って」と言い、ドアを閉めてホール右側の居間に私たちを通し、出ていく際にガス灯を明るくした。「ピーターズはすぐ来ます」と言った。
本当にその通りで、部屋を見回す間もなく、ドアが開いて大柄で無精ひげのない禿頭の男が軽やかに入ってきた。大きな赤ら顔に垂れ下がった頬、表面上は善良そうだが口元が残忍かつ悪どい印象だった。
「どうも、何か間違いではありませんか?」と、彼は調子の良い甘えた声で言った。「おそらく道をお間違えでしょう。通りの先をあたってみては――」
「その必要はありません。時間が惜しいのです」とホームズ。「あなたはアデレード出身のヘンリー・ピーターズ、元バーデン及び南米のシュレシンガー博士、その人です。私は自分がシャーロック・ホームズだと確信しているのと同じくらい、そう確信しています。」
ピーターズ――今後こう呼ぼう――は仰天し、手ごわい敵をじっとにらみつけた。「ホームズさん、あなたの名が怖いとは思いませんよ」と彼は平然と答えた。「やましいことがなければ、動じません。用件は何です?」
「バーデンからあなたが連れてきたレディ・フランシス・カーファックスをどうしたのか知りたい。」
「むしろ私が教えてもらいたいくらいだ」とピーターズは平然と答えた。「私は彼女に百ポンド近く立て替えがあるのに、その代わりといえば、質屋もまともに値をつけてくれない安物のペンダントだけ。バーデンでは、妻と私に彼女が付きまとった――確かに私はそのとき別名を使っていたが――そしてロンドンまでついてきた。私は彼女の宿代と切符代を払った。ロンドンに着くと彼女は姿を消し、残ったのは時代遅れの宝石だけ。ホームズさん、探し出してくれたら、私がお礼しますよ。」
「私は必ず探し出します」とホームズ。「この家の中を、彼女が見つかるまで調べさせていただきます。」
「令状は?」
ホームズはポケットからリボルバーを半ば抜き出した。「これが、しばらくの間、令状代わりです。」
「まるで強盗だな。」
「そう思っていただいて構いません」とホームズは陽気に応じた。「こちらの連れも危険なチンピラです。二人でこの家を調べます。」
相手はドアを開けた。
「アニー、警官を呼んで!」と叫んだ。女のスカートの音が廊下を駆け抜け、玄関の開閉音がした。
「時間がないぞ、ワトソン」とホームズ。「止めるなら、怪我を覚悟したまえ。あの棺はどこだ?」
「棺とは何だ? 使用中だ。中に遺体がある。」
「その遺体を見せてもらう。」
「絶対に見せない。」
「では、無理にでも」ホームズは素早く男を押しのけ、廊下へ進んだ。半開きのドアが目の前にあった。入ると、それは食堂だった。半分明かりのついたシャンデリアの下、テーブルの上に棺が置かれていた。ホームズはガス灯を明るくし、棺の蓋を開けた。深い棺の底にはやつれきった遺体が横たわっていた。明かりの下にさらされた顔は、年老いてしぼんでいた。どんなに虐待や飢餓や病気を重ねても、これほどまでに衰えた遺体が、あの美しいレディ・フランシスであるはずがない。ホームズの顔には驚きと安堵が浮かんでいた。
「神に感謝を」と彼はつぶやいた。「別人だ。」
「ホームズさん、今回は盛大にやらかしましたね」と、ついてきたピーターズが言った。
「この死者は誰だ?」
「本当のことを言えば、うちの妻の昔の乳母ローズ・スペンダーです。ブリクストンの救貧院で見つかりました。ここへ連れてきて、ファーバンク・ヴィラ13番地のホーソム医師を呼び、大事に看護しました――住所を覚えておいてくださいよ、ホームズさん――三日目に亡くなりました。死亡証明書は“老衰”――でもあくまで医者の見立てですから、あなたならもっと分かるでしょう。葬儀はケニントン・ロードのスティムソン社に依頼し、明朝八時に埋葬されます。何か不備でも? ホームズさん、今回は完全な失敗ですな。棺の蓋を開けて、レディ・フランシスを見つけるつもりが、九十の婆さんだったと知ったときのあなたの顔、写真に撮っておきたかったですよ。」
ホームズは敵の嘲笑にも無表情を保っていたが、握りしめた拳が激しい悔しさを物語っていた。
「家の中を調べさせてもらう」とホームズ。
「させるものか!」ピーターズが怒鳴った。そのとき女の声と重い足音が廊下に響いた。「警察官が来たぞ。この連中は無理やり家に押し入ってきた。追い出してくれ!」
軍服姿の巡査部長と警官が立っていた。ホームズは名刺を差し出した。
「これが私の名と住所。こちらは友人のワトソン博士。」
「よく存じておりますよ」と巡査部長。「ですが令状なしでは滞在できません。」
「もちろんです。理解しています。」
「逮捕しろ!」とピーターズ。
「この紳士の居場所ならすぐ分かりますから」と巡査部長は威厳たっぷりに言い、「今はお引き取りください。」
「ワトソン君、行くしかない。」
数分後、私たちは再び通りにいた。ホームズはいつも通り冷静だったが、私は怒りと屈辱で熱くなっていた。巡査部長が後を追ってきた。
「申し訳ありませんが、法ですから。」
「当然です、巡査部長。」
「ご用事がおありだったのでしょう。私にできることがあれば――」
「行方不明の女性です。あの家にいる可能性が高い。令状が届くはずです。」
「では、あの連中を見張っておきましょう。何かあれば必ず知らせます。」
まだ九時だった。私たちは再び全力で調査に乗り出した。まずブリクストン救貧院へ向かい、数日前に善意の夫婦がやってきて、元召使いだという老女を引き取ったのが事実であることを確認した。老女がその後亡くなったと聞いても、誰も驚く様子はなかった。
次は医者の元へ行った。老女は老衰で死にかけていたが、実際に医師立ち会いのもとで亡くなり、証明書も正式に発行された。「まったく普通のケースで、事件性はありません」と医師。気になったのは、この階層の人間なのに召使いが一人もいなかったことだけだったという。
最後にスコットランドヤードへ行った。手続き上の問題で令状は翌朝まで時間がかかるとのこと。朝九時ごろ来ればレストレードと一緒に執行できると告げられ、その日は終わった。ただし、夜遅くなってから巡査部長が現れ、「あの大きな家で明かりがちらちらしていたが、誰も出入りしていない」と報告があった。私たちは忍耐強く明日を待つしかなかった。
ホームズはイライラして会話もできず、眠ることもできなかった。私は彼を置いて部屋を出ると、彼は煙草に火をつけ重苦しい眉間に皺を寄せ、長い神経質な指で椅子の肘掛けを叩きながら、あらゆる可能性を考え巡らせていた。夜中に何度も彼が家の中をうろつく音がした。ようやく朝、呼びに来られる直後、彼が私の部屋に飛び込んできた。寝間着姿で、青白い目のくぼんだ顔が、彼の夜が眠れなかったことを物語っていた。
「葬儀の時間は八時だったな? 今は七時二十分だ。なんてこった、ワトソン、私の頭脳はどこに行ったんだ? 急げ、急げ! 生死の問題だ――百に一つしか生きる望みはない。もし間に合わなければ、一生自分を許せない!」
五分も経たないうちに、私たちはベイカー街を馬車で飛び出した。しかし、ビッグベンを通過したときは七時三十五分、ブリクストン・ロードに着いたときは八時を打った。だが、遅れたのは私たちだけではなかった。十分遅れても霊柩車はまだ家の前にあり、ちょうど私たちの馬車が止まるや否や、三人の男が棺を玄関から運び出してきた。ホームズはすかさず飛び出し、彼らの前を塞いだ。
「戻せ!」彼は先頭に手をかざし叫んだ。「今すぐ棺を戻すんだ!」
「何を言うんだ! 令状はどこだ?」と怒り狂ったピーターズが棺の向こう側から顔を出してどなった。
「令状は今向かっている。棺はそれまで家に置いておく。」
ホームズの威厳ある声に運搬人たちは従った。ピーターズはどこかへ消え、棺は再びテーブルに戻された。「早く、ワトソン、早く! ドライバーだ!」ホームズは叫んだ。「君も、棺の蓋を外せたら金貨をやろう! 余計なことは考えるな、すぐやれ! よし、もうひとつ! 全員で引っ張れ! よし、外れた!」
全員の力で棺の蓋を剥がした瞬間、内部からは驚くほど強烈なクロロホルム[訳注:麻酔薬]の臭いが立ちこめた。棺の中には、頭部が脱脂綿に包まれ、麻酔薬がしみ込ませてある女性の遺体が横たわっていた。ホームズはそれを取り除き、気高く美しい中年女性の顔を露わにした。瞬時に彼は腕を回してその体を起こした。
「もうだめか、ワトソン? まだ望みはあるか? まさか間に合わなかったのでは!」
三十分もの間、窒息と毒性ガスの影響で、レディ・フランシスはもはや蘇生の見込みもないかと思われた。しかし、人工呼吸やエーテル注射、あらゆる医療手段を尽くした末、やがて生命の兆しが現れ、まぶたがわずかに動き、鏡に曇りが生じ、少しずつ生気が戻った。ちょうどそのときタクシーが到着し、ホームズはブラインド越しに外を見て言った。「レストレードが令状を持って来た。だが、奴らはもう逃げ出しているだろう。そして――」廊下を急ぐ重い足音を聞きつけると続けた。「我々よりも彼女を看病する資格のある人が来たようだ。おはよう、グリーンさん。できるだけ早くレディを移したほうがいい。葬儀は予定通り進めて、あの棺の中の年老いた女性だけを静かに眠らせてやろう。」
「この事件を記録に加えたいなら、ワトソン君」とその晩ホームズは言った。「それは、最も優れた頭脳であっても一時的に曇ることがある好例としてのみだ。こうした失敗は誰にもある。偉大なのは、それを認めて修正できる者だ。私も、その点だけは誇れるかもしれない。夜中ずっと、どこかに見落とした手がかり、妙な一言、不思議な観察があったのではと悩んでいた。夜明け近くに、突然、思い出した。グリーン氏の報告した葬儀屋の妻の台詞だ。“普通と違ったから時間がかかった”――それは棺のことだった。つまり特注サイズだったということ。なぜだ? そこで思い出した、深い棺と、その底に横たわった小さな遺体。なぜあんなに大きな棺が必要か? もう一人分のスペースを確保するためだ。二人を一つの死亡証明書で埋葬するつもりだった。すべて明白だったのに、私の目が曇っていた。もし八時に埋葬されていたら、レディ・フランシスも一緒に葬られていた。唯一の望みは棺の出発前に間に合うことだった。
奇跡的に彼女は生きていた――だが、望みは限りなく薄かった。連中はこれまで殺人を犯したことがなく、最後の最後で暴力をためらったのだろう。死因を隠して埋葬できれば、仮に発掘されてもどうとでも弁解できる。彼らにその程度の考慮が働くことに賭けた。君も現場を見たはずだ。あの上の階のひどい部屋に長期間監禁し、最後にクロロホルムで無力化して運び出し、棺の中にもたっぷり染み込ませて蓋を閉めた――なんとも巧妙な手口だ、ワトソン。犯罪史上でも私には新しい。もしこの元宣教師夫妻がレストレードの手から逃げ切るなら、またどこかで派手な事件を起こすことだろう。」
瀕死の探偵
ハドソン夫人――シャーロック・ホームズの家主――は、つくづく忍耐強い女性であった。彼女の一階の間は、昼夜を問わず、奇妙でしばしば好ましくない人物たちに占領されるばかりか、住人自身の生活ぶりも型破りで不規則きわまりなく、彼女の忍耐を何度も試すことになった。信じがたいほどの無精、突拍子もない時間に弾くバイオリン、室内での拳銃射撃、奇妙でときに悪臭を放つ科学実験、そして常に漂う暴力と危険の雰囲気――これほどロンドンで最悪の下宿人はいなかっただろう。一方で、彼の支払いは王侯のごとく豪勢だった。ホームズが私と共にいた年月、部屋代だけで家が一軒買えたのではないかと思うほどだった。
家主はホームズに対して最大級の畏敬の念を抱き、どんな横暴なふるまいにも決して口をはさむことはなかった。それどころか、彼女はホームズに好意さえ持っていた。ホームズは女性に対して特有の優しさと礼儀正しさを持ち合わせていたのだ。女性そのものには警戒心や不信感を抱いていたが、常に騎士道的な態度は崩さなかった。その誠実な思いを知っていた私は、結婚二年目のある日、彼女が私の部屋を訪れて、ホームズの深刻な病状を涙ながらに語ったとき、真剣に耳を傾けた。
「あの方はもう死にかけています、ワトソン先生。三日間、どんどん衰えて、今日一日も持たないかもしれません。お医者様を呼ぶのも許してくれませんでした。今朝、あのやせ細った顔に、ぎょろりと大きな目で見つめられたとき、もう限界だと思いました。『あなたの許しがあろうがなかろうが、ホームズさん、いますぐお医者様を呼んできます』って言ったんです。そしたら、『ワトソンを呼んでくれ』って。どうか、すぐに行ってください。そうでないと、生きているうちに会えなくなりますよ。」
私は愕然とした。それまで何も聞いていなかったからだ。コートと帽子をつかんで飛び出したのは言うまでもない。馬車の中で彼女に詳しい話を聞いた。
「詳しいことはあまり分かりません。ロザーハイスの川沿いの路地で事件を調べて、それで病気になったようです。水曜の午後から床に伏して、一度も起き上がっていません。この三日間、食事も水分も一切口にしていません。」
「なんてことだ! なぜ医者を呼ばなかったんです?」
「ご本人が絶対に嫌がったんです。あの方の強情さは先生もご存じでしょう? 私なんか、とても逆らえません。でも、今の姿をご覧になれば、長くはないとすぐ分かります。」
実際その姿は痛ましいものだった。霧の立ちこめる十一月の薄暗い日、病室は重苦しい空気に包まれていたが、それよりも、ベッドからじっとこちらをにらむやせ細った顔が、私の心に冷たいものを感じさせた。目は熱にうるみ、両頬は紅潮し、唇には黒ずんだかさぶたがこびりついていた。やせた手は絶えずカバーの上で痙攣し、声はかすれ、途切れがちだった。私が部屋に入ると、最初はぐったりしていたが、私の姿を見ると目にかすかな光が宿った。
「どうやら悪い時代になったようだ、ワトソン君」と、彼は弱々しい声で言ったが、どこか昔の無頓着な口調が残っていた。
「ホームズ君!」私はベッドに近づいた。
「下がれ! そこから一歩も近づくな!」彼は、今まで危機のときしか見せたことのない鋭い命令口調で言った。「ワトソン君、近づいたら家から追い出すぞ。」
「なぜだ?」
「私の望みだからだ。それで十分だろう?」
――確かに、ハドソン夫人の言う通り、彼はいつにも増して強情だった。しかし、その疲弊しきった様子は見るに忍びなかった。
「助けになりたいだけなんだ」と私は言った。
「そう、それなら私の言うことを守ってくれるのが一番の助けだ。」
「分かった、ホームズ。」
彼は態度を少し和らげた。
「怒っていないか?」と、息を切らせながら尋ねた。
この惨状を目にして、どうして怒ることなどできよう。
「君のためなんだ、ワトソン君」と、彼はかすれた声で言った。
「私のため?」
「私に何が起きているのか分かっている。これはスマトラで流行している苦力[クーリー:アジアの下級労働者]の病気だ――オランダ人のほうが我々よりよく知っているが、今のところ大した対策も取られていない。ただ一つ確かなのは、間違いなく致命的であること、そして恐ろしく伝染性が高いということだ。」
彼は今や熱に浮かされたような勢いでしゃべり、長い手を小刻みに動かして私を遠ざけようとした。
「接触による伝染だ、ワトソン――そうなんだ、接触だ。距離を取っていれば大丈夫だ。」
「なんてことだ、ホームズ! そんなことが私の心に一瞬でも重くのしかかると思うのか? 見知らぬ人が相手でも私は気にしない。長年の友人である君に対して、義務を果たさずにいられると思うのか?」
私は再び近づこうとしたが、彼は激しい怒りの眼差しで私を制した。
「そこに立っているなら話そう。そうでなければ部屋を出てくれ。」
私はホームズの非凡な資質に深い敬意を抱いていたため、彼の意向には、たとえ全く理解できぬ時であっても常に従ってきた。しかし今や私の医師としての本能が目覚めていた。彼が他の場所で私の主であっても、病室では少なくとも私が主導権を持つ。
「ホームズ、君は自分を見失っている。病人は子どもと同じだ、私はそう扱うつもりだ。君の意思に関わらず、症状を診て治療をする。」
彼は私を憎々しげな目で見た。
「無理に医者をつけるなら、せめて私が信頼できる人間にしてくれ。」
「つまり、私には信頼がないんだな?」
「友情はもちろん信じている。しかし事実は事実だ、ワトソン。君は結局、経験も資格も限られた開業医に過ぎない。こんなことは言いたくないが、仕方がない。」
私はひどく傷ついた。
「そんな言葉、君らしくないよホームズ。それだけで君自身の神経の状態がよく分かる。しかし君が私に信頼を寄せていないなら、無理に医者を務める気はない。サー・ジャスパー・ミークやペンローズ・フィッシャー、ロンドンで最良の医師を誰でも連れてこよう。ただし、誰かが必要ということは譲れない。私がここで君が死ぬのを何もしないで見ていると思うなら、それは大きな間違いだ。」
「君の善意は分かっている、ワトソン。」病人はすすり泣きとも呻きともつかぬ声で言った。「君自身の無知を証明してやろうか? タパヌリ熱について何を知っている? 黒いフォルモサの腐敗については?」
「どちらも聞いたことがない。」
「東洋には多くの病気の謎、奇妙な病理学的な可能性がある、ワトソン。」彼は一文ごとに力を振り絞るようにして話した。「最近の医学犯罪学的調査で私は多くを学んだ。その過程でこの病を得たのだ。君には何もできない。」
「たぶんそうだろう。しかし私は、熱帯病の最高権威であるエインストリー博士が今ロンドンにいるのを知っている。ホームズ、もう議論は無意味だ。今すぐ彼を連れてくる。」私は決意してドアへ向かった。
私はかつてない衝撃を受けた! 一瞬にして、瀕死の男が虎のように私の行く手をふさいだ。捻った鍵の鋭い音がした。次の瞬間、彼はベッドに倒れ込んだ。途方もない力を一度に爆発させて、息も絶え絶えだった。
「力づくで鍵を取ろうとしても無駄だ、ワトソン。君はここにいる、そして君が出ていいと言うまで出られない。でも君のために譲歩しよう。」(この間も彼は息も絶え絶えの短い言葉を発した)「君は私のことを思って行動してくれているのは分かっているよ。君の希望も叶えてやる、だが私に少し時間をくれ。今ではない、ワトソン、今はダメだ。今は四時だ。六時になったら出てもいい。」
「そんなの狂気だ、ホームズ。」
「あと二時間だけだ、ワトソン。六時には必ず出してやる。待てるか?」
「選択肢はなさそうだな。」
「全くない、ワトソン。ありがとう、服の整理は自分でできる。君は距離を取ってくれ。さて、もう一つ条件がある。誰に助けを求めるかは、君の希望ではなく、私の指定した相手にしてくれ。」
「もちろんだ。」
「ワトソン、君がこの部屋に入ってから初めてまともなことを言ったな。あそこに本がある。私はいささか疲れた――電池が不導体に電気を流す時どんな気持ちになるのだろうか? 六時になったらまた話をしよう。」
だが、その時刻を待たずに事態は急変した。それは、ホームズがドアに飛びかかった時に匹敵するほど私に衝撃を与える出来事であった。私はしばらくベッドの静かな人影を見つめていた。顔はほとんど布団で隠れ、眠っているようだった。読書に集中できず、私はゆっくりと部屋を歩き回り、有名な犯罪者の写真で埋め尽くされた壁を眺めた。最後に、私は何気なく暖炉棚へ近づいた。パイプ、タバコ入れ、注射器、ペンナイフ、リボルバーの弾、その他のガラクタが散らばっていた。その中に、白黒の小さな象牙の箱があった。滑らかな作りで、蓋が横にスライドする。私はそれを手に取って詳しく見ようとした――
その時、彼は恐ろしい悲鳴を上げた――通りでも聞こえそうな絶叫だった。私は全身の皮膚が冷たくなり、髪の毛が逆立つのを感じた。振り返ると、けいれんした顔と狂乱した目がちらりと見えた。私は小箱を手に持ったまま、動けなくなっていた。
「置け! 今すぐだ、ワトソン――今すぐだ、早く!」彼の頭は枕に沈み、私が箱を元に戻すと安堵の深い溜息をついた。「私は自分の物に触られるのが大嫌いなんだ、ワトソン。君も知っているだろうが、我慢の限界だ。君は医者だというのに、患者を発狂させるつもりか。座ってくれ、休ませてくれ!」
この出来事は私に極めて不快な印象を残した。理由もなく激しく興奮し、その直後に乱暴な言葉を吐く様は、彼の通常の穏やかさからは想像もできないもので、心の混乱がいかに深いかを示していた。高貴な精神が崩壊するほど悲しいものはない。私は約束の時刻まで沈鬱に座っていた。彼も私と同じく時計を見ていたらしく、六時になる前に、再び熱に浮かされたような調子で話し始めた。
「さて、ワトソン。君のポケットに小銭はあるか?」
「あるよ。」
「銀貨は?」
「けっこうある。」
「ハーフクラウンはいくつ?」
「五枚ある。」
「ああ、少なすぎる! 残念だ、ワトソン! まあ仕方ない、それを君の懐中時計のポケットに入れてくれ。他の金は左のズボンのポケットへ。ありがとう、そのほうがバランスがいい。」
これはまるで狂気沙汰だった。彼は身震いし、また咳ともすすり泣きともつかぬ声を出す。
「では、ワトソン、ガス灯をつけてくれ。ただし絶対に半分以上はつけないこと。頼むから慎重になってくれ、ワトソン。ありがとう、それでいい。ブラインドは下ろさなくていい。さて、手紙や書類をこのテーブルに手の届く範囲に置いてくれ。ありがとう。次に暖炉棚のガラクタもいくつか。素晴らしい、ワトソン! そこに砂糖トングがある。それであの小さな象牙の箱をつまんで、ここに書類の間に置いてくれ。よし! では、クルヴァートン・スミス氏を呼びに行ってくれ。住所はロウアー・バーク街13番だ。」
正直なところ、私は医者を呼びに行く気力が弱まっていた。ホームズは明らかに譫妄状態で、彼を一人にするのは危険に思えた。しかし今や彼は、さっきまで頑なに拒んでいた相手に会いたくてたまらない様子だった。
「その名前は聞いたことがないな。」
「それも無理はない、ワトソン。驚くかもしれないが、この病について世界で最も詳しいのは医者ではなく、プランターだ。クルヴァートン・スミス氏はスマトラの有名な居住者で、今ロンドンにいる。彼の農園でこの病が流行し、医療援助も遠かったため、自ら研究した。その結果、かなり深い知識を得た。彼は非常に几帳面な人物で、私は君が六時以前に出かけてしまわないようにしたかった。そうしなければ、書斎にはいなかっただろう。彼に来てもらって、この病について彼独自の見識を借りることができれば、きっと助けてもらえるはずだ。」
私はホームズの話を一続きにまとめて記したが、実際には彼は呼吸を切らし、痛みで手をもがく合間に語った。数時間の間に彼の容態はさらに悪化していた。頬の紅潮はより濃く、目は黒いくぼみからさらに輝きを増し、額には冷たい汗がにじんでいた。それでも、彼の言葉には相変わらず気丈さと軽妙さが残っていた。最後の瞬間まで、彼は常に主導権を握っていた。
「君がどうやって私を置いてきたか、正確に伝えてほしい」と彼は言った。「君自身が感じている印象――瀕死の男、死にかけて譫妄状態の男、ということだ。実のところ、なぜ海の底が一面カキで覆われていないのか不思議だ、あの生物は異様に繁殖力があるのに。ああ、また話が逸れた! 脳が脳を支配するのは不思議なものだ。何を言っていたっけ、ワトソン?」
「クルヴァートン・スミス氏への指示のことだ。」
「ああ、そうだ、思い出した。私の命がかかっている。彼に頼んでくれ。私たちの間には確執がある。彼の甥――ワトソン、私は不正を疑って彼にそれを気づかせてしまった。甥は悲惨な死を遂げた。彼は私に恨みを持っている。君が彼をなだめてくれ。頼む、どうしても彼をここへ。彼だけが私を救える!」
「もし担いででもタクシーに乗せて連れてくるよ。」
「そんなことは絶対にしないでくれ。説得して来させるんだ。そして彼より先に戻る。何か理由をつけて一緒に帰らないように。忘れるな、ワトソン。君は絶対に私を裏切らない。私たちには天敵がいて増殖を抑えているのかもしれない。ワトソン、君と私は役目を果たした。世界がカキだらけになるのを許すのか? いや、恐ろしい! 君の感じたままを伝えてくれ。」
私は部屋を出るとき、ホームズの壮大な知性が愚かな子どものようにうわごとを言っている姿が脳裏に焼きついていた。彼は鍵を手渡してくれたので、彼自身が閉じこもらないよう私も鍵を持っていった。ハドソン夫人は廊下で震えながら涙を流して待っていた。私はフラットを出るとき、ホームズの高く細い声でうわごとを唱えているのが聞こえた。下でタクシーを呼んでいると、霧の中から男が近づいてきた。
「ホームズさんの具合はいかがですか?」と彼は尋ねた。
見覚えのある人物、スコットランドヤードのモートン警部だった。普段着のツイードを着ていた。
「とても具合が悪い」と私は答えた。
彼は実に奇妙な目つきで私を見た。あまりにも残酷な想像だが、もしや彼の顔に勝ち誇った表情が浮かんでいたようにさえ思われた。
「噂には聞きました」と彼は言った。
タクシーが来たので、私はその場を離れた。
ロウアー・バーク街は、ノッティングヒルとケンジントンの境界近くにある立派な住宅が並ぶ通りだった。私の乗ったタクシーが止まった家は、古風な鉄柵、大きな折戸、輝く真鍮細工に包まれ、控えめで上品な雰囲気を漂わせていた。内側には薄紅色の電灯に照らされた厳めしい執事が立っていた。
「クルヴァートン・スミス様はご在宅です。ワトソン先生ですね。かしこまりました、お名刺をお持ちします。」
私の名はクルヴァートン・スミス氏には何の印象も与えなかったようだ。半開きのドアから、高く不平がちで鋭い声が聞こえてきた。
「誰だい? 何の用だ? やれやれ、ステイプルズ、私は何度も言っているだろう、勉強中は絶対に邪魔をするな、と。」
執事が静かに事情説明をする。
「私は会わんぞ、ステイプルズ。こんなことで仕事の邪魔はされたくない。私は留守だと伝えなさい。どうしても会いたいなら、明日の朝来いと。」
再び執事が低く説明する。
「まぁ伝えておけ。明日の朝来るか、来ないかは勝手だ。私は仕事の邪魔をされたくない。」
私は、病床で苦しむホームズが分単位で助けを待っているのを思い浮かべた。今は礼儀を尽くす余裕などなかった。彼の命は私の迅速さにかかっていた。謝る執事が伝言を伝える前に、私は彼を押しのけて部屋に入った。
甲高い怒りの叫びとともに、暖炉脇の肘掛け椅子から男が立ち上がった。私は黄色く脂ぎった大きな顔と、重たい二重顎、その下から睨みつける鈍い灰色の眼、もじゃもじゃの薄茶色の眉を見た。頭頂は大きく禿げ上がり、ピンク色の丸い頭に小さなビロードの喫煙帽がちょこんと傾いて乗っている。頭蓋骨は非常に大きかったが、全体の体つきは小柄で華奢で、肩と背中が曲がり、子供の頃にくる病を患ったようだった。
「これは何事だ!」彼は甲高い金切り声で叫んだ。「なぜこんな乱入を許す? 明日の朝会うと伝えさせただろう!」
「申し訳ないが、これは急用なのです。シャーロック・ホームズが――」
私の友人の名前を口にした瞬間、彼の態度は一変した。怒りの表情は一瞬で消え、顔が鋭く緊張した。
「ホームズから来たのか?」
「今しがた彼の元を離れたばかりです。」
「ホームズがどうした? 容体は?」
「非常に危険な状態です。それでお伺いしたのです。」
彼は椅子を勧め、自分も腰を下ろした。私は暖炉の上の鏡に映った彼の顔をちらりと見て、悪意と嫌悪の笑みが浮かんでいるのを見た気がした。だがそれは神経的な痙攣を私が勘違いしたのだと自分に言い聞かせた。彼は次の瞬間、真剣な表情で私に向き直った。
「それはお気の毒に。」と彼は言った。「私はホームズ氏とは仕事上でしか面識はありませんが、彼の能力と人格には敬意を持っています。彼は犯罪の愛好家、私は病気の愛好家といったところです。彼には悪党、私には微生物。あそこが私の収容所ですよ。」彼はサイドテーブルに並んだ瓶や壺を指差した。「あのゼラチン培地には世界最悪の犯罪者たちが収監されています。」
「あなたの東洋の病への特別な知識が、ホームズ氏があなたに会いたがった理由です。あなたをロンドンで唯一、彼が頼れる人物だと考えています。」
小男はびくりとし、喫煙帽が床に落ちた。
「なぜだ? なぜホームズ氏が私なら助けられると思う?」
「東洋の病気に詳しいからです。」
「だが、なぜ彼がその病気が東洋由来だと思うのか?」
「彼は仕事でイーストエンドの中国人船員と関わっていたからです。」
クルヴァートン・スミス氏はにっこりして喫煙帽を拾い上げた。
「なるほど、そういうことか。事態があなたの想像ほど深刻でないといいのですが。発病してどれくらいです?」
「三日ほどです。」
「譫妄は?」
「時々あります。」
「ふむ、これは深刻ですね。彼の呼びかけに応えないのは人非人でしょう。ワトソン先生、私は仕事の邪魔をされるのは非常に不満ですが、この件は例外です。すぐに伺いましょう。」
私はホームズの指示を思い出した。
「別の約束があります。」
「分かりました。私一人で伺います。ホームズ氏の住所は控えています。30分以内には必ず到着します。」
私は沈んだ気持ちでホームズの部屋に戻った。私の留守中に最悪の事態が起きていたかもしれない。だが安堵したことに、彼の様子はかなり良くなっていた。顔色は相変わらずだが、譫妄はすっかり消え、かすかな声ながら普段以上に明快に話した。
「会えたか、ワトソン?」
「はい、来てくれます。」
「素晴らしい、ワトソン! 君は最高の使者だ。」
「一緒に戻りたがったよ。」
「それはまずい、絶対にダメだ。何の病気か尋ねられたか?」
「イーストエンドの中国人の話をした。」
「よし! ワトソン、君は友人としてできる限りのことをした。もう退場していい。」
「彼の診断を聞くまで待つよ、ホームズ。」
「もちろんだが、彼が我々二人きりだと思ったほうが、より率直で貴重な意見を聞ける理由がある。ベッドの頭の後ろにちょうど隠れられるスペースがある。」
「ホームズ!」
「他に手はないんだ、ワトソン。この部屋は隠れるには不向きだが、それがかえって怪しまれない。ちょうどあそこだ、ワトソン。」突然、彼はやつれた顔でぴしりと座った。「車の音だ、ワトソン! 急げ、君が好きなら! 何があっても動くな――絶対に動くな、分かったな? 声も出すな! 耳を澄ませていろ。」その直後、彼の突如の力は消え、話しぶりも弱々しいうわごとに変わった。
私は押し込まれた隠れ場所で、階段を上がる音と寝室のドアの開閉を聞いた。しばらく、病人の荒い息遣いだけが続く沈黙。訪問者はベッド脇に立ち、ホームズを見下ろしているのだろう。やがてその静寂が破られた。
「ホームズ!」彼は執拗に呼び覚ますような調子で叫んだ。「聞こえないのか、ホームズ?」布団を激しく揺すったような音がした。
「スミスさんですか?」ホームズはささやいた。「まさか来てくれるとは思いませんでした。」
もう一人は笑った。
「そうだろうとも。でも、こうして来た。まるで恩返しだな、ホームズ、恩返しだ!」
「ご厚意を感謝します。あなたの特別な知識を――」
訪問者は嘲笑した。
「そうか。君だけが私の価値を分かっている男というわけだ。何の病気か分かるか?」
「同じものです。」
「ああ、症状が分かるのか?」
「よく分かっています。」
「それも無理はない、ホームズ。君の場合も同じだろうな。ヴィクターは四日目で死んだ、若くて頑健な男だった。確かに、君が言う通り、ロンドンの真ん中で滅多にない東洋の病にかかるなんて驚きだ。しかも私が特別に研究してきた病気。奇妙な偶然だな、ホームズ。君がそれに気づいたのは鋭いが、因果関係があると疑うのは失礼だ。」
「あなたがやったと分かっていた。」
「ああ、そうか。でも証拠はないだろ? それに、君は私の悪評を広めておいて、いざ自分が困ると助けを求めて這いつくばってくるとは、どういうつもりだ?」
私は病人の苦しそうな呼吸を聞いた。「水をくれ!」と彼は喘いだ。
「もうすぐだが、一言話しておきたいから水をやるだけだ。こぼすなよ。それでいい。私の言うことが分かるか?」
ホームズがうめいた。
「助けてくれ。水に流そう、頼む。君のことは忘れる、約束する。ただ治してくれ。」
「何を忘れる気だ?」
「ヴィクター・サヴェージの死のことさ。さっき君がほとんど認めた。私はそれを忘れる。」
「忘れるも覚えているも君の好きにしろ。私は君が証言台に立つとは思っていない。全く別の“箱”に入るんだ、ホームズ。君が私の甥の死因を知っていることなどどうでもいい。今話しているのは君のことだ。」
「そうだ、そうだ。」
「私を呼びにきた男――名前は忘れた――君はイーストエンドの船員から感染したと言っていたな。」
「他に説明がつかなかった。」
「君は自分の頭脳に自信があるようだが、今回はもっと賢いやつに出会った。思い出してみろ、ちょうど発症時期に何か変わったことはなかったか?」
「ない、何も。」
「よく考えろ。」
「考える力も残っていない。」
「では手助けしよう。郵便で何か届いたか?」
「郵便?」
「小箱か何か?」
「もう駄目だ……」
「聞け、ホームズ!」彼は瀕死の男を揺さぶったようで、私は隠れ場所でじっと耐えねばならなかった。「絶対に聞け。箱のことを覚えているか――象牙の箱だ。水曜日に届いた。開けたな、覚えているか?」
「そう、開けた。中に鋭いバネがあった。冗談かと――」
「冗談じゃない、その報いを受けることになる。君はそれを欲しがり、手に入れた。私の邪魔をしなければ傷つけなかったのに。」
「思い出した」ホームズは喘いだ。「バネだ! 血が出た。この箱……テーブルの上に」
「まさにそれだ、よし、証拠は私のポケットに。だが君は真実を知った――自分が殺されたと知って死ぬがいい。君はヴィクター・サヴェージの運命を知りすぎたので、同じように送ってやった。もうすぐ死ぬぞ、ホームズ。私はここで君の死を見届ける。」
ホームズの声はほとんど聞き取れないほど小さくなった。
「何だって?」スミスが言った。「ガスを明るくしろ? もう影が忍び寄っているというのか? よし、明るくしてやろう、よく見えるようにな。」彼は部屋を横切り、灯りが一気に明るくなった。「他に何かしてほしいことはあるか?」
「マッチと煙草を――」
私は喜びと驚きのあまり、叫びそうになった。彼はいつもの声で話していた。やや弱々しくはあったが、間違いなく私の知っている声だった。長い沈黙があり、クルヴァートン・スミスが黙って相手を見下ろしているのを感じた。
「これはどういうことだ?」やがて彼が乾いたしわがれ声で言った。
「役を演じきる一番の方法は、その役になることだ」ホームズが言った。「三日間、君が水をくれるまで、私は一切の飲食を絶った。本当に辛いのは、煙草を我慢することさ。ああ、煙草があるな」マッチを擦る音がした。「ずいぶん楽になった。おやおや、誰か来たようだな?」
外で足音がし、ドアが開いてモートン警部が現れた。
「すべて用意はできています。こいつが犯人です」とホームズが言った。
警部は通常の注意事項を述べた。
「ヴィクター・サヴェージ殺害の容疑で逮捕する」と締めくくった。
「それに、シャーロック・ホームズ殺害未遂も加えてくれ」と友人はくすくす笑いながら言った。「重病人の私に代わって、スミス氏はガスを明るくして合図してくれた。ところで、被疑者の上着右ポケットには小箱が入っているので、念のため取り上げてくれ。そっと扱うことだ。ここに置いてくれ。法廷で重要な役割を果たすかもしれない。」
突然の押し問答、金属音、悲鳴が起こった。
「ケガするだけだ、じっとしていなさい」と警部が言った。手錠をかける音がした。
「見事な罠だ!」甲高い声が叫んだ。「これで裁判台に立つのは君だぞ、ホームズ。私は彼を治しに来たのだ、同情して来てやった。君はどうせ、私が言ってもいないことをでっちあげて、君の妄想を裏付けるつもりだろう。君はいくらでも嘘をつける。私の証言は君と同等だ。」
「なんということだ!」とホームズ。「君のことを完全に忘れていた。ワトソン、千回も謝りたい。君を見落とすとは! クルヴァートン・スミス氏はすでに会ったのだったな? 下にタクシーはあるか? 私は着替えてから行こう、警察署で役に立てるかもしれない。」
「今ほどそれがありがたいことはないよ」ホームズは着替えの間、クラレットとビスケットで栄養補給しながら言った。「だがご存じの通り、私は不規則な生活だから、普通の人ほど苦ではない。ハドソン夫人に本気で信じさせることが欠かせなかった。彼女が君に伝え、君がスミスを呼ぶ。その点、君の才能には偽装の才がないのが幸いだった。もし君が秘密を知っていたら、スミスに切迫感を与えることはできなかった。彼の執念深い性格を考えれば、必ず自分の仕業を見届けに来ると確信していた。」
「でも、ホームズ、君の顔色は? あの気味の悪い顔は?」
「三日間の絶食は美貌を損なうものだ、ワトソン。他は、スポンジで拭けば元通り。額にワセリン、目にベラドンナ、頬に紅、唇の周りに蜜蝋のかす、立派な偽装ができる。仮病については論文を書こうと思ったこともある。時折ハーフクラウンやカキや他の関係ない話を混ぜると、譫妄らしい効果が出る。」
「でも本当に感染症でなかったなら、なぜ私を近づけなかった?」
「分かるだろう、ワトソン。君の医術を軽んじているわけではない。だが、どんなに弱っていても、脈も熱も上がっていない死にかけの男を君の鋭い診断が見逃すとは思えなかった。四ヤードも離れれば騙せる。失敗したらスミスをおびき寄せられなかった。あの箱には触らないでくれ。横から見ると、バネが毒蛇の牙のように出ているのがわかるだろう。おそらく、この怪物と財産分与をめぐって対立したサヴェージも、同じ仕掛けで殺されたのだろう。私の郵便は多岐にわたり、怪しい荷物には警戒している。しかし彼が計画を成し遂げたと信じ込ませれば、告白を引き出せると確信した。そのため私は徹底して演じた。ありがとう、ワトソン、上着を手伝ってくれ。警察署の後はシンプソンズで何か栄養のあるものでも食べよう。」
彼の最後の挨拶:シャーロック・ホームズの戦時奉仕
それは8月2日、夜の九時のことだった――人類史上最も恐ろしい八月の始まりだった。すでに神の呪いが堕落した世界に重くのしかかっているかのような、不気味な静けさと、蒸し暑く淀んだ空気に漠然とした不安が漂っていた。太陽はとっくに沈んだが、西の空低く、血のような赤い裂け目が傷口のように残っていた。頭上には星が輝き、下には港の灯火がちらちらと光っていた。二人の著名なドイツ人が、長く低い切妻屋根の館を背に、庭園の石欄干のそばに立ち、彼らが四年前に鷲のように飛来して巣を作った大きな白亜の崖の麓、広々とした海岸線を見下ろしていた。二人は頭を寄せ合い、低く親密な声で話していた。下から見れば、二本の葉巻の赤い火は、闇の中で睨みつける悪魔の目のように見えただろう。
フォン・ボルクは実に非凡な人物で、皇帝の忠実な諜報員の中でも並ぶ者がほとんどいない。その才能によって彼は英国内務という最重要任務を託され、そして着任以来、その才能は世界のほんの一握りの真相を知る者たちにますます認められるようになっていた。その一人が、今ここにいる同僚で、公使館の首席書記官バロン・フォン・ヘルリングだった。彼の100馬力の巨大なベンツが、主人をロンドンへ運ぶために田舎道をふさいでいた。
「私の見るところでは、君はたぶん一週間以内にベルリンへ帰ることになるだろう」と書記官は言った。「その時君がどんな歓迎を受けるか、驚くだろうな。君のこの国での働きは、最高レベルで高く評価されているという話を私は知っている。」この書記官は巨漢で、厚みと高さのある大柄な体格、遅く重々しい話し方が政界での武器だった。
フォン・ボルクは笑った。
「騙すのは難しくありませんよ。これほど従順で素朴な国民もほかにいません。」
「そうは思わないな」相手は考え込むように言った。「彼らには奇妙な限界があって、それを把握しなければならない。あの表面的な素朴さこそ、異邦人への罠となる。一見、全く柔らかいように見えるが、ある時突然、非常に硬い何かにぶつかり、そこが限界だと知ることになる。そしてその事実に適応せざるを得ない。例えば彼らには、どうしても守らなければならない独自の作法がある。」
「つまり“グッドフォーム”とか、そういうことですか?」フォン・ボルクは、苦労を思い出したようにため息をついた。
「つまり英国人特有の偏見だ。たとえば、私自身のひどい失敗を例に挙げよう。私の実績を君は知っているから、失敗談も話せるが――到着直後のことだ。ある閣僚のカントリーハウスに週末の招待を受けた。会話は驚くほど無防備だった。」
「分かるよ」とフォン・ボルクはドライにうなずいた。
「そうだ。その情報をまとめてベルリンに送った。ところが困ったことに、宰相があまりに直截で、その内容を知っていると示してしまった。これが一気に私に疑惑が集中する原因となった。そのせいでどれだけ苦労したか。あの時の英国人の対応は、ちっとも柔らかくなかったよ。名誉回復に二年もかかった。だが君の場合、スポーツ好きという仮面が役立っている。」
「いや、仮面じゃなく本物だ。私は生まれつきのスポーツマンなんだ。本当に楽しんでいる。」
「それならなお効果的だ。君はヨットも狩猟も競馬もポロも彼らと同じように楽しみ、オリンピアでは四頭立て馬車の賞まで取ったそうじゃないか。若い将校とボクシングをする話も聞いた。結果どうなる? 誰も君を深刻に受け取らない。“いいやつだ”“ドイツ人にしてはまともだ”“酒とナイトクラブと遊びと都会の放蕩者”。その裏では、この静かな屋敷が英国の陰謀の中心で、スポーツ好きの地主こそヨーロッパ随一のスパイ――天才だよ、フォン・ボルク、天才だ!」
「おだてすぎですよ、バロン。だが確かに、私の四年間の努力に無駄はなかった。私の“コレクション”を見せたことがなかったですね。ちょっと中へどうですか?」
書斎のドアはテラスに直結していた。フォン・ボルクはドアを押し開け、先導しながら電灯のスイッチをカチリと入れた。続いて後ろから入ってきた大柄な人物の後ろでドアを閉め、格子窓に掛けられた重いカーテンを念入りに整えた。こうした用心深い手順をすべて終え、問題がないことを確認してから、彼は日焼けした鷲鼻の顔を客人に向けた。
「いくつかの書類がなくなった」と彼は言った。「妻と家族が昨日フリッシングへ発った際に、重要でないものは持っていった。だが、残りの書類については当然、大使館の保護を求めるつもりだ」
「ご安心を。あなたの名前はすでに随員の一員として登録されています。あなたにも荷物にも問題は生じません。もちろん、我々が出発せずに済む可能性もわずかに残っています。イギリスがフランスを見捨てるかもしれません。我々の調べでは、両国間に拘束力のある条約は存在しません」
「ベルギーは?」
「ええ、ベルギーも同様です」
フォン・ボルクは首を振った。「それは考えにくい。あそこには明確な条約がある。そんな屈辱を味わえば、イギリスは立ち直れまい」
「少なくとも、とりあえずは平和が保たれます」
「だが、名誉はどうする?」
「ふん、旦那、今は功利主義の時代です。名誉なんて中世の概念ですよ。それにイギリスは準備ができていません。信じがたいことですが、我々が目的をタイムズの一面に広告したような特別戦争税五千万ポンドにもかかわらず、この国の人々はまだ目を覚ましていません。たまに疑問の声が上がれば、私の役目はその答えを用意すること。どこかで不満が生じれば、私の仕事はそれをなだめることです。ですが、肝心な準備――弾薬の備蓄、潜水艦攻撃への対応、高性能爆薬の手配――はいまだに手つかずです。どうしてイギリスが参戦できましょう。しかも、アイルランドの内戦や暴徒、その他諸々で国内を混乱させている最中に」
「彼らも将来は考えざるを得ないでしょう」
「それはまた別の問題です。将来に関してはイギリス向けに非常に明確な計画があり、あなたの情報は極めて重要になります。今がまさに勝負の時です。イギリスが今動けば我々の準備は万全、明日ならさらに準備は整います。味方と戦う方が賢明だと私は思いますが、それは彼ら次第。この一週間が運命の週です。さて、書類の話に戻りましょう」彼は肘掛け椅子に座り、頭上の光を受けながら落ち着いて葉巻をくゆらせた。
大きなオーク材のパネルと書棚に囲まれた部屋の隅にはカーテンが掛けられていた。それを引くと、大きな真鍮枠の金庫が現れる。フォン・ボルクは時計の鎖から小さな鍵を外し、しばらく錠前を操作した後、重いドアを開いた。
「ご覧ください」と彼は手を振って立ちどいた。
明かりが開かれた金庫の中を照らし、大使館の書記官は興味津々の面持ちで書類でぎっしり詰まった仕切り棚の列を見つめた。それぞれの棚にはラベルが付され、彼の目は「フォード」「港湾防衛」「飛行機」「アイルランド」「エジプト」「ポーツマス要塞」「ドーバー海峡」「ロジース」「他多数」といったタイトルを読み取った。どの仕切りも書類や設計図で埋め尽くされていた。
「壮観だ!」と書記官は言った。葉巻を置き、太い手を静かに打った。
「これが四年の成果ですよ、バロン。田舎地主にしては悪くないでしょう。しかし、コレクションの真珠はこれから届く予定で、すでにそのための場所も用意してあります」彼は「海軍信号」と書かれたスペースを指さした。
「もう十分な資料があるのでは?」
「古くて無価値です。海軍本部がどうやら警戒し、すべての暗号を変更しました。これは痛恨の一撃、私の作戦で最大の挫折でした。しかし、小切手帳とアルタモントのおかげで今夜にはすべて解決します」
バロンは時計を見て、不満げにうなった。
「もうこれ以上は待てません。今はカールトン・テラスで事態が動いているところでして、私たちも持ち場に戻らないと。あなたの大仕事の結果を持ち帰れるかと期待していたのですが。アルタモントからは到着時刻の知らせは?」
フォン・ボルクは電報を差し出した。
「今夜必ず行く。新しいスパークプラグを持参する。――アルタモント」
「スパークプラグ?」
「彼は自動車の専門家ということにしていて、私も車庫を完備しています。我々の暗号では、想定される品目はすべて自動車部品の名で呼びます。ラジエーターなら戦艦、オイルポンプなら巡洋艦という具合に。スパークプラグは海軍信号です」
「ポーツマスから正午発ですね」と書記官は宛名を見つめた。「ところで、彼には何を払うのです?」
「今回の仕事には五百ポンド。もちろん、別途給料もあります」
「強欲な奴め。裏切り者は使えるが報酬は惜しいものだ」
「私はアルタモントには惜しみません。並外れた働きです。高く払っても彼は必ず成果を出す――彼の言い回しを借りれば“商品を納品する”のです。それに彼は裏切り者ではありません。我々のドイツ至上主義者でさえ、イングランドへの敵意は本物のアイリッシュ・アメリカンには遠く及びませんよ」
「ほう、アイリッシュ・アメリカンか」
「話を聞けば疑う余地はありません。時には、彼の英語があまりに独特で理解できないほどです。英語にも英王にも戦争を仕掛けているようなものです。さて、本当にお帰りですか? 彼はもうすぐ来るかもしれませんよ」
「いや、もう時間を大幅に過ぎています。ご想像の通り、今は皆が持ち場につく時。明朝は早く参るように。我々の小さな扉からデューク・オブ・ヨークの階段を経て信号書を届けてくれれば、あなたの英国での記録に誇らしい“終”を打てますよ。おや、トカイワインじゃないですか!」彼は重く封がされた埃まみれのボトルと、二つのグラスが載った盆を示した。
「旅の前に一杯どうです?」
「結構です。お祭りのようですね」
「アルタモントはワインの趣味が良くてね。私のトカイを気に入りました。彼は気難しいところがあるので、小さなことでもご機嫌を取らないといけないのです」二人は再びテラスへ出て、その端まで歩いた。バロンの運転手が車に触れると、エンジンが唸りを上げた。「あれがハリッジの灯りでしょう」と書記官はダスターコートを着込みながら言った。「なんと静かで平和な夜だこと。この一週間で他の光景になるかもしれません。英仏海岸も安穏では済まないでしょう。空もまたツェッペリンの約束どおりなら安泰とはいかぬ。ところで、あれは誰です?」
後ろに明かりが灯る窓がひとつだけあり、その前にランプが置かれ、テーブルには赤ら顔の優しそうな老婦人がカントリーキャップをかぶって座っていた。編み物をしながら、時折横のスツールにいる大きな黒猫を撫でている。
「あれはマーサです。残った唯一の召使いですよ」
書記官はくすりと笑った。
「まるでブリタニアの化身のようですね」と彼は言った。「自己陶酔と、心地よいまどろみの雰囲気がそっくりです。では、またお会いしましょう、フォン・ボルク!」最後に手を振って車に飛び乗ると、ヘッドライトの二本の光柱が闇を貫いた。豪奢なリムジンのクッションに身を沈めた書記官は、迫りくる欧州の悲劇に思いを巡らせ、村の通りを曲がる際、向かいから来た小さなフォード車をかすめそうになったことにすらほとんど気づかなかった。
フォン・ボルクは、車の灯りが遠く消え去ったのを見届けてから、ゆっくりと書斎に戻った。通りすがりに、年老いた家政婦がランプを消して自室へ退いたことに気づいた。家族と使用人の多い生活だったので、自宅の静寂と暗さは彼にとって新鮮な体験だった。しかし、皆が無事であり、台所に残る老婦人を除けば家全体が自分の手中にあることに安堵した。書斎の片付けはなかなかの仕事であり、書類を焼く炎で彼の精悍な顔は赤らんだ。机の脇には革のカバンが置かれており、彼は金庫の貴重な中身を几帳面かつ手際よく詰め始めた。だが、作業を始めてまもなく、敏感な耳が遠くの車の音を捉えた。フォン・ボルクは満足げに声を上げ、カバンを留め、金庫を閉じ、鍵をかけ、急いでテラスに出た。ちょうど小さな車のライトが門で停まったのが見えた。乗客が素早く降りて彼のもとへ歩み寄り、運転手は大柄な年配の男で、灰色の口髭を蓄え、長い待機に備えるよう腰を据えた。
「どうだ?」フォン・ボルクは期待に満ちて駆け寄った。
男は小さな茶封筒を掲げて勝ち誇ったように叫んだ。
「今夜は握手してくれていいぜ、旦那。ついに“獲物”を持ち帰った」
「信号は?」
「電報どおりさ。全部そろってる。手旗、灯火、マルコーニ――全部の写しだ。本物はさすがに危険すぎたが、これは間違いなく本物だ。信じていい」彼はラフな親しみからドイツ人の肩を叩いたが、相手は嫌そうに身を引いた。
「さあ、中へ」彼は言った。「家には私しかいない。これを待っていたのだ。むしろ写しの方がいい。原本がなくなれば全暗号を変えられてしまう。写しは大丈夫だろうね?」
アイリッシュ・アメリカンは書斎に入り、長い手足を肘掛け椅子に伸ばした。六十歳ほどの背の高い痩せた男で、輪郭のはっきりした顔に小さなヤギ髭があり、アンクル・サムの風刺画に似ていた。半分吸った湿った葉巻が口元にぶら下がり、座るとマッチで再び火をつけた。「何か準備してるようだな」と部屋を見回しながら言った。「ところで、旦那」と金庫に目をやりながら付け加えた。「まさかそこに書類を入れてるのか?」
「そうだが?」
「おいおい、そんな無防備な代物に? 君が一流のスパイ扱いとはな。アメリカの泥棒なら缶切りで開けちまうぜ。俺の手紙がこんなところに放り込まれると知ってたら、書く価値もなかったさ」
「どんな泥棒でもこの金庫は手ごわいぞ」とフォン・ボルクは答えた。「どんな道具でも金属は切れまい」
「だが、鍵は?」
「いや、ダブルコンビネーションロックだ。意味がわかるか?」
「さっぱりだな」とアメリカ人。
「要するに、数字だけでなく単語も必要なんだ」彼は鍵穴の周りに二重のディスクを示した。「外が文字用、内が数字用だ」
「なるほど、そりゃすごい」
「だから、思うほど単純じゃない。これを作らせたのは四年前で、どんな単語と数字を選んだと思う?」
「見当もつかないな」
「単語は“August”、数字は“1914”。そして今がまさにその時なのだ」
アメリカ人の顔には驚きと称賛が浮かんだ。
「こりゃ見事だ! 先見の明があったな」
「ああ、当時の何人かは日付まで予見していた。とうとうその日が来て、明朝には出発さ」
「俺も一緒に頼むぜ。この忌々しい国に独りで残りたかない。一週間もすればジョン・ブルが暴れ出すだろう。遠くから眺めていたいもんだ」
「だが君はアメリカ市民だろう?」
「ああ、だがジャック・ジェームズだってアメリカ市民だったが、今はポートランドで服役中さ。イギリスの警官に市民権なんて通用しない。『ここは英法と秩序だ』ってな。ところで旦那、ジャック・ジェームズの話だが、あんたは部下の面倒をあまり見てないな」
「どういう意味だ?」とフォン・ボルクは鋭く聞いた。
「雇い主だろ? なら部下の安全も見てやるべきさ。だが、やられっぱなしじゃないか。たとえば、ジェームズ――」
「ジェームズの自業自得だ。知っているだろう。彼は独断専行すぎた」
「確かにジェームズは馬鹿だったが、ホリスはどうだ?」
「彼は正気を失っていた」
「まぁ、最後は少しおかしくなった。朝から晩まで芝居を続け、百人が逮捕の機会を狙っていれば気も狂うさ。今度はスタイナーだ――」
フォン・ボルクは激しく身震いし、赤ら顔が一段と青ざめた。
「スタイナーがどうした?」
「捕まったのさ。それだけだ。昨夜、彼の店が急襲され、今じゃ書類と一緒にポーツマスの牢屋だ。あんたは逃げるが、あの哀れな奴は刑務所送り、命が助かれば御の字だ。だから俺も一刻も早く海を渡りたいんだよ」
フォン・ボルクは強靭な男だったが、明らかに動揺は隠せなかった。
「なぜスタイナーに足がついた?」彼は呟いた。「これが今までで最悪の打撃だ」
「いや、もっと危なかったかもな。俺の居場所も割と近かったと思うぜ」
「まさか!」
「間違いない。フラットンの大家が誰かに探りを入れられてな。俺は早くずらかるべきだと悟った。だが、気になるのは警官がなぜこうも手際よく嗅ぎつけるかだ。君が俺を雇ってから五人目の逮捕だぞ、俺が動かなきゃ六人目になる。どう説明する? 部下がこうもやられて恥ずかしくないか?」
フォン・ボルクは顔を真っ赤にした。
「よくもそんな口がきけるな!」
「俺が度胸なきゃこんな仕事しないさ。だが正直に言おう。ドイツの政治家は、部下が任務を果たし終えたら消えても構わんというじゃないか――そう聞いたんだ」
フォン・ボルクは立ち上がった。
「私が部下を売ったとでも言うのか!」
「そこまで言う気はない。だがスパイか裏切り者がいる。君がそれを見つけるべきだ。いずれにせよ、俺はもうリスクは負わない。オランダに行くよ、できるだけ早くな」
フォン・ボルクは怒りを抑えた。
「今さら仲違いしても仕方あるまい。我々は長い間同志だった。君は素晴らしい働きと危険を冒してきた。それは忘れない。オランダに行くといい。ロッテルダムからニューヨーク行きの船に乗ればいい。来週には他の航路は危なくなるからな。その本は私が受け取り、残りと一緒に梱包しよう」
アメリカ人は小包を手にしたまま、差し出そうとはしなかった。
「報酬は?」
「何だって?」
「金さ、報酬だ。ガナーが最後にごねやがって、百ドル上乗せしないと俺も君も危ないところだった。『何もやらん!』と本気で言ったが、最後の百ドルで納得した。結局、最初から二百ポンドかかったんだ。ただで渡す気はない」
フォン・ボルクは苦々しく微笑んだ。「私の誠意を全く信用していないようだな。金を渡す前に本を受け取りたいわけか」
「まあ、ビジネスだよ旦那」
「いいだろう。君の言うとおりにしよう」彼はテーブルに座り、小切手を書いて破ったが、すぐには相手に渡さなかった。「結局こういう関係なら、アルタモント君、こちらも君を信用できないということだ。分かるか?」後ろを振り返ってアメリカ人を見つめた。「小切手はここに。私はその小包の中身を確かめる権利がある」
アメリカ人は黙って小包を差し出した。フォン・ボルクは紐を解き、紙を二重に剥がした。ひとしきり唖然として小さな青い本を見つめた。「実用養蜂ハンドブック」と金文字で表紙に印刷されている。一瞬、巨悪のスパイはこの奇妙に無関係な題名に目をみはった。次の瞬間、首筋から鉄のような力で捕まれ、顔の前にクロロホルムを染み込ませたスポンジが押し付けられた。
「もう一杯どうだね、ワトソン!」とシャーロック・ホームズがインペリアル・トカイのボトルを差し出した。
テーブルに座っていたがっしりした運転手が、進んでグラスを差し出した。
「これは良いワインだな、ホームズ」
「素晴らしいワインだよ、ワトソン。我々のソファの友人は、これはシェーンブルン宮殿のフランツ・ヨーゼフ専用セラーのものだと太鼓判を押してくれた。窓を開けてくれないか、クロロホルムの蒸気では美酒が台無しだ」
金庫は開いたままで、ホームズはその前に立ち、書類を次々と手早く調べてはフォン・ボルクのカバンに詰めていた。ドイツ人はソファで荒く寝息を立て、上腕と脚をベルトでしっかり縛られていた。
「急ぐことはないよ、ワトソン。邪魔は入らない。ベルを押してもらえるか。家には老マーサしかいないが、彼女は見事に役を演じてくれた。この話を始めた時、私が彼女をここに紹介したんだ。ああ、マーサ、ご安心を。すべて順調だ」
優しげな老婦人が戸口に現れた。ホームズににこやかに会釈しつつ、ソファの男を心配そうに見た。
「大丈夫ですよ、マーサ。彼は怪我をしていません」
「それは良かった、ホームズさん。彼なりに優しいご主人でしたよ。昨日、奥様とドイツへ一緒に行かないかと誘われましたが、そちらのご都合もおありでしょう?」
「もちろん、マーサ。あなたがここにいてくれさえすれば私は安心でした。今夜もあなたの合図を待っていました」
「書記官でしたね」
「分かっている。彼の車とすれ違った」
「なかなか帰らなくて。あなたの計画には、ここで会うのは不都合だろうと思いました」
「まったくその通り。ランプが消えて合図が出るまで三十分ほど待っただけです。明日はロンドン、クラリッジズ・ホテルで報告を頼みます」
「承知しました」
「出発のご用意は?」
「はい。今日、彼は七通の手紙を出しました。宛先もいつも通り控えてあります」
「ありがとう、マーサ。明日調べます。おやすみなさい」老婦人が姿を消すと、ホームズは続けた。「これらの書類自体はさほど重要ではありません。なぜなら、その内容は既にドイツ政府に送られています。これらは国外に持ち出すのが危険で残っていた原本です」
「では、無価値なのか」
「そうとも限らない、ワトソン。少なくとも、敵方が何を知っていて何を知らないかを示す参考にはなる。実のところ、これらの書類も多くが私を経由している。もちろん、内容は極めて信頼性が低い。敵が私の敷設図通りに機雷原を越えてソレントを航行してくれたら、老後の楽しみなんだが。さてワトソン」彼は作業を止め、親友の肩に手を置いた。「まだ明るいところで君をよく見ていなかったが、年月は君にやさしかったようだ。昔のままの快活な少年のようじゃないか」
「二十歳若返った気分だよ、ホームズ。君からハリッジで会おうとの電報をもらった時ほど嬉しかったことはない。でも君もほとんど変わらない。あの恐ろしいヤギ髭を除いては」
「国のためには犠牲も必要だよ、ワトソン」とホームズは髭を引っ張った。「明日にはこの悪夢も終わる。髪を切り、他にも身なりを整えれば、クラリッジズで元通りの私として現れるだろう。アメリカの“スタント”――いや、すまん、ワトソン。英語感覚がすっかり毒されてしまった――このアメリカの仕事の前の私に戻るとも」
「だが君は引退していたはずだ。南ダウンズの小さな農場で、蜂と本に囲まれ隠遁生活をしていると聞いたが」
「その通り、ワトソン。これが私の閑暇の結晶、晩年の大作だ!」彼はテーブルの本を掲げ、タイトルを読み上げた。「実用養蜂ハンドブック――女王蜂の分離観察録付き」。ひとりでやり遂げた。昔ロンドンの犯罪界を見張ったように、今度は小さな働き蜂の群れを夜な夜な観察した結晶さ」
「それでどうしてまた現役復帰を?」
「ああ、私も不思議に思う。外相一人なら断れたが、首相までが私のつましい家を訪ねてきた――。実は、ソファにいるこの男が我々の手に余る存在だった。何がうまくいかないのか誰にも分からず、行き詰まっていた。明らかに強力で秘密の中枢があった。暴く必要があった。私は強い要請を受けて調査を始めた。二年かかったが、退屈ではなかったよ。私がシカゴで巡礼を始め、バッファローのアイルランド秘密結社で“卒業”し、スキバリーンで警察に厄介をかけ、ついにはフォン・ボルクの下級エージェントの目に留まったと知れば、複雑さが分かるだろう。それ以来、彼の信頼を勝ち得てきたが、それが邪魔になったとも言えない。彼の計画の多くは密かに失敗し、五人の有能なエージェントが牢に入った。私はよく見張り、熟した時に摘み取った。さて、あなたは大丈夫ですね!」
この最後の言葉は、ホームズの説明を静かに聞いていたフォン・ボルクに向けられた。彼は今、激情に駆られドイツ語で罵倒を浴びせていた。ホームズは書類の精査を続けながら、囚人の毒舌を聞き流した。
「音楽性はないが、ドイツ語ほど表現力豊かな言語はない」と彼は相手が疲れ果てて黙った時に言った。「おやおや!」と図面の隅に目を凝らしてから箱に入れた。「これでもう一人捕まるだろう。会計士がこんな悪党だったとはな。以前から気にはしていたが。フォン・ボルクさん、あなたは多くの罪を犯しましたよ」
囚人はなんとか身を起こし、不思議と憎悪の入り混じった目で捕縛者を見つめた。
「必ずやり返してやるぞ、アルタモント」と彼はゆっくりと言った。「一生かかっても必ず!」
「よく聞くセリフだ」とホームズ。「昔、故教授モリアーティのお気に入りだった。セバスチャン・モラン大佐もよく歌っていた。そして私は今も南ダウンズで蜂を飼っている」
「呪われろ、二重スパイめ!」ドイツ人は縛られたまま身をよじり、殺意のこもった視線を送った。
「いえいえ、そこまで悪くはありません」とホームズは微笑んだ。「私の話し方で分かるように、シカゴのアルタモントなる人物は存在しません。私はその仮面を使い、今は消えました」
「では、あなたは誰なんだ?」
「誰であれ大差はありませんが、そこまでご興味がおありならお答えしましょう。フォン・ボルクさん、あなたのご家族とは以前から縁があります。ドイツでもいろいろ仕事をしてきましたので、名前くらいはご存知でしょう」
「教えてもらいたい」とプロイセン人は厳しく言った。
「アイリーン・アドラーと先代ボヘミア王の仲を裂いたのは私です。当時、あなたの従兄ハインリッヒは皇帝特命使節でした。また、ニヒリストのクロップマンによる暗殺からグラーフェンシュタイン伯、あなたの母上の兄を救ったのも私ですよ。それに――」
フォン・ボルクは驚いて身を乗り出した。
「その人物は一人だけだ!」
「その通りです」とホームズ。
フォン・ボルクは呻き、ソファに崩れ落ちた。「それじゃ、これらの情報はほとんどお前から……。何もかも水の泡だ。私は破滅だ!」
「確かに信頼性には欠けますね」とホームズ。「検証が必要ですが、今は検証する時間もありません。あなたの提督は新兵器が意外と大きかったり、巡洋艦が思いのほか速かったりして驚くことでしょう」
フォン・ボルクは絶望的に自らの喉をつかんだ。
「他にも細かい点は今後明らかになるでしょう。だが、あなたには珍しい美徳がある。スポーツマン精神です。多くの人間を出し抜いたあなたが、ついに自分も出し抜かれたと分かれば、私を恨むことはないでしょう。あなたは祖国のために最善を尽くした。私も自分の国のために最善を尽くした。自然なことではありませんか。それに――」ホームズはうつ伏せの男の肩に優しく手を置いた。「卑劣な敵に捕まるよりはまだましでしょう。書類の準備はできました、ワトソン。囚人の移動を手伝ってくれますか。すぐにロンドンに向かいましょう」
フォン・ボルクの移動は容易ではなかった。強靭で必死な男だったからだ。だが、二人が両腕を持って歩くうちに、かつて著名な外交官の祝福を受けて歩いた誇り高い庭道を、今はゆっくりと運ばれていった。最後に激しく抵抗したが、手足を縛られたまま小さな車の予備席に乗せられ、貴重なカバンも横に詰め込まれた。
「できるだけ快適にしているつもりです」とホームズが最終確認をしながら言った。「葉巻を一本くわえさせても失礼にはなりませんか?」
だが激怒したドイツ人に礼儀は無意味だった。
「お分かりだろう、シャーロック・ホームズ」と彼は言った。「あなたの政府がこの扱いを認めるなら、これは戦争行為です」
「そちらの政府とこの行為はどうなんです?」ホームズはカバンを叩きながら言った。
「あなたは私人だ。逮捕の権限などない。この一連の行為は明らかに違法で無法だ」
「まったくその通りです」とホームズ。
「ドイツ国民の拉致だ」
「しかも私的な書類の強奪ですね」
「自分の立場は理解しているだろう。もし村を抜けるときに助けを叫んだら――」
「旦那、そんな愚かなことをすれば、うちの村のパブの看板が『吊るされたプロイセン人亭』に変わるでしょう。イギリス人は我慢強いが、今は少々苛立っていますから、刺激しない方が賢明です。素直にスコットランド・ヤードまでご同行いただき、そこで友人のバロン・フォン・ヘルリングに連絡を取って、大使館の随員枠に加われるかお試しください。ワトソン、君もまた古巣に戻るのだろう? ならロンドンまで同行してもらおう。さあ、テラスで一緒にしばし語ろう。これが最後の静かな語らいになるかもしれないから」
二人は親密な会話を数分交わし、かつての日々を回想した。囚人は必死に縄をほどこうと身をよじっていた。車に向かうとき、ホームズは月明かりの海を指さし、思案深く首を振った。
「ワトソン、東風が吹いてくる」
「そうは思わないよ、ホームズ。今夜はとても暖かい」
「さすがワトソン! 時代が変わっても君は不動の点だ。だが、それでも東風は来る。これまで英国に吹いたことのない冷たく激しい風がね。多くの者がその嵐に耐えられないかもしれない。だが、それもまた神の風、嵐の後にはより清く、より強く、より良い国が太陽の下に現れるはずだ。さあ、始動してくれ、ワトソン。五百ポンドの小切手は早く現金化した方がいい。書いた本人が止めかねないからね」
〈終わり〉

