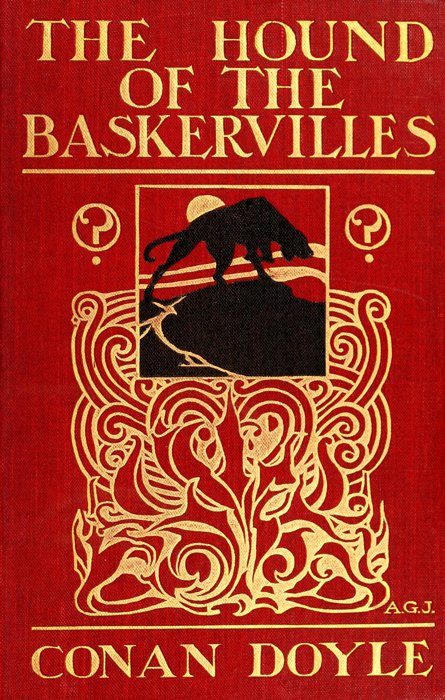
バスカヴィル家の犬
シャーロック・ホームズの新たなる冒険
A・コナン・ドイル著
親愛なるロビンソンへ
この物語の発端は、あなたが語ってくれた西部地方の伝説にあります。そのこと、そして細部の助力に心から感謝します。
敬具
A・コナン・ドイル
ヒンドヘッド、
ハズルミア
第1章 シャーロック・ホームズ氏
シャーロック・ホームズ氏は、たいてい朝はとても遅いのだが、夜通し起きていることも珍しくないこの男が、今朝は朝食のテーブルについていた。私は暖炉の前に立ち、昨夜の訪問者が置いていった杖を手に取った。それは立派で太く、先が丸く膨らんだ木の杖で、「ペナン・ロイヤー」と呼ばれる種類である。頭のすぐ下には、幅一インチ近い銀の太い帯が巻かれていた。「ジェームズ・モーティマー M.R.C.S.へ、C.C.H.の友人たちより」と刻まれており、日付は「1884年」だった。まさに昔ながらの開業医が持ち歩いたような杖で、品格と堅実さ、安心感が漂っていた。
「さて、ワトソン、君はどう思うかね?」
ホームズは私に背を向けて座っていた。私は何も彼に気づかせていなかった。
「どうして私が何をしているかわかったんだい? 君は後頭部にも目があるのだろう。」
「少なくとも、私の前にはよく磨かれた銀メッキのコーヒーポットがあるからね」と彼は言った。「だが、ワトソン、君はあの訪問者の杖をどう見る? 残念ながら彼とは行き違いになり、彼の用件もわからない以上、この偶然の置き土産は重要になる。君の推理を聞かせてくれ。」
「私はこう思う」と私はできる限り相棒の推理法に倣って考えた。「モーティマー博士は成功した高齢の医師で、周囲の人々から敬意をもたれている。だからこそ、こうした贈り物をもらったのだろう。」
「いいね!」とホームズ。「素晴らしい。」
「おそらく田舎の開業医で、徒歩による往診が多いのだと思う。」
「なぜそう思う?」
「この杖は、もとこそ見事な品だったが、かなり傷んでいる。都会の医師がこれを持ち歩くとは考えづらい。鉄のフェルール(石突き)がすり減っているから、相当歩き回ったのは明らかだ。」
「まったくその通りだ」とホームズは言った。
「そして『C.C.H.の友人たちより』だが、これはおそらく何とかハント、つまり地元の狩猟会で、そこに外科的な助力をしたお礼に贈られたのではないかと思う。」
「実に、ワトソン、君は冴えている」とホームズは椅子を引いてタバコに火をつけながら言った。「君が私のささやかな業績について執筆してくれてきた記録では、君自身の能力をいつも控えめに評価しているが、実際はそうではない。君自身が発光体でなくても、光を伝える導体だ。天才ではなくとも、天才を刺激する不思議な力を持つ人がいる。正直言って、私は君に多大な恩義を感じている。」
彼がここまで言ったことはかつてなく、私は正直言って大きな喜びを覚えた。なぜなら、いつも私の賞賛や、彼の手法を広めようとする努力に無頓着な彼に、少しばかり苛立ちも感じていたからだ。私は彼の手法をここまで習得し、認められる形で応用できたことを誇りに思った。ホームズは今度は私の手から杖を取って数分間肉眼で調べた。そして興味深げにタバコを置くと、杖を窓辺へ持ち出し、凸レンズでさらに検分した。
「興味深いが、初歩的だ」と彼は、愛用の長椅子の隅に戻りながら言った。「この杖にはいくつかの特徴がある。そこからいくつかの推理が成り立つ。」
「何か見落としがあったかな?」と私はやや自慢げに尋ねた。「何か重大なことを見逃してはいないだろうか?」
「残念ながら、ワトソン君、君の結論の多くは誤りだ。君が私を刺激する、と言ったのは、正直に言えば、君の誤謬を指摘する過程で、時に真実にたどり着くことができるからだ。しかし、今回は完全に間違っているわけではない。この人物が田舎の開業医で、かなり歩き回ることは確かだ。」
「では、私は当たっていたんだね。」
「その点については。」
「だがそれだけか。」
「いやいや、ワトソン君、それだけではない。たとえば、医師への記念品はハントよりも病院から贈られる方が自然だし、『C.C.』という頭文字を病院名の前につけるなら、『チャリング・クロス』が連想される。」
「君の言うとおりかもしれない。」
「確率的にはそちらに傾いている。これを仮説として出発点にすれば、この未知の訪問者像を新たに描きなおせる。」
「では、『C.C.H.』が『チャリング・クロス病院』を意味するとして、どんな推理ができる?」
「何か思いつかないか。君は私の手法を知っている。応用してみたまえ。」
「思いつくのは、町の病院で勤務した後、田舎に移ったということくらいだ。」
「もう少し踏み込めると思うよ。こう考えてみよう。医師にこうした贈り物がされるのはいつだろう? 友人たちが善意の証として記念品を贈るのは、当然、モーティマー博士が病院勤務を辞めて独立開業する時だ。記念品が贈られたことはわかっている。町の病院から田舎の開業医へ転身したとも見ている。ならば、その贈り物は転身の際のものと推理しても不自然ではないだろう?」
「確かにもっともらしい。」
「次に、彼が病院のスタッフだったとは考えられない。ロンドンで確立された医師でなければその地位にはなれないし、そういう人が田舎に流れることはない。では彼は何者か。病院勤務でありながらスタッフでなければ、ハウスサージャンやハウスフィジシャン、つまり実質的に最上級の学生だったと考えられる。そして彼が去ったのは5年前――杖にはその日付がある。だから、君の想像した重々しい中年医師像は消え失せ、そこに現れるのは三十歳未満の若く、愛想が良く、野心がなく、少々うっかり者で、愛犬家である男――おそらくテリアより大きく、マスティフより小さい犬を持っている人物だ。」
私は思わず苦笑した。ホームズは長椅子にもたれ、煙草の煙を天井へ輪のように吹き上げていた。
「後半部分については確かめようがない」と私は言った。「だが、年齢や経歴については調べるのは難しくない。」私は小さな医学書棚から『医師名簿』を取り出し、その名を調べた。モーティマーの名は何人かあったが、我々の訪問者は一人しか該当しなかった。私はその経歴を声に出して読んだ。
「モーティマー、ジェームズ、M.R.C.S.、1882年、グリムペン、ダートムーア、デヴォン。チャリング・クロス病院ハウスサージャン、1882年から1884年。比較病理学のジャクソン賞受賞論文『疾病は先祖返りか?』スウェーデン病理学会通信会員。著書『アタヴィズムの奇習』(ランセット1882年)、『我々は進歩するか?』(心理学雑誌1883年3月号)。グリムペン、ソーズリー、ハイ・バロウ小教区医務官。」
「地元のハントの記載はないな、ワトソン」とホームズは茶目っ気たっぷりに笑った。「だが、田舎医だという君の見立ては見事だ。私の推理も大筋で正当だったと言っていいだろう。形容詞については、確か愛想よく、野心がなく、うっかり者と言ったな。世の中で推薦状をもらうのは愛想のいい男、ロンドンでの出世を捨てて田舎を選ぶのは野心のない男、杖を忘れて名刺は忘れないのはうっかり者だけだ。」
「犬については?」
「主人の後をついて、この杖をくわえて歩き回る習慣がある。杖が重いので、犬は真ん中をしっかり噛む。その歯形がはっきり残っている。この間隔からして、テリアには顎幅が広すぎ、マスティフには狭すぎる。これは……そうだ、間違いなくカーリー・ヘア・スパニエルだな。」
彼は立ち上がり、部屋を歩きながらそう述べた。今、彼は窓辺のくぼみに立ち止まった。その声に確信がこもっていたので私は驚いて見上げた。
「どうしてそんなに確信できるんだ?」
「ごく単純な理由さ。まさにその犬が、今ドアの前に来ているし、飼い主の呼び鈴も聞こえた。動かないでくれ、ワトソン。彼は君と同業者だし、君の存在が役立つかもしれない。今こそ運命の劇的な瞬間だ、ワトソン。今、階段を上る足音が君の人生に入ってくるのだが、それが吉と出るか凶と出るかはわからない。科学者ジェームズ・モーティマー博士が、犯罪専門家シャーロック・ホームズに何を求めて来るのか? どうぞ、お入りください!」
訪問者の姿は私の想像とは違っていた。典型的な田舎医を想像していたが、実際は非常に背が高く痩せた男で、嘴のように突き出た長い鼻が、ふたつの鋭い灰色の目の間に見えた。その目はゴールドリムの眼鏡の奥で生き生きと輝いていた。服装は医者らしいがややだらしなく、フロックコートはくすみ、ズボンも擦り切れていた。若いのに背中はすでに丸まり、前屈み気味に歩き、全体にやさしげな好奇心が漂っていた。彼は入ってくるや否や、ホームズの手にある杖を見つけて、歓声を上げて駆け寄った。「本当によかった。どこに置いてきたかわからなくて、ここか、運送会社かと心配していたところです。この杖は何があっても失いたくありません。」
「贈り物ですね」とホームズ。
「はい、そうです。」
「チャリング・クロス病院から?」
「向こうの友人二、三人から、私の結婚を祝していただきました。」
「それは、まずいな」とホームズは首を振った。
モーティマー博士は眼鏡越しにおだやかに驚いて瞬きをした。「なぜまずいのです?」
「あなたが我々の小さな推理を台無しにしてしまったからです。ご結婚、でしたか?」
「はい。結婚して病院を辞め、コンサルタント医としての道を断念しました。自分の家庭を持つ必要があったのです。」
「なるほど、それなら大きく外れてはいない」とホームズ。「さて、ジェームズ・モーティマー博士――」
「ミスターです、先生。謙遜ながらM.R.C.S.です。」
「なるほど、几帳面な方ですね。」
「科学好きの道楽者です、ホームズさん。未知の大海の岸辺で貝殻を拾うようなものです。おそらく、今お話ししているのはシャーロック・ホームズ氏ご本人で――」
「いいえ、こちらは友人のワトソン博士です。」
「お会いできて光栄です。お名前はご友人との関係でよく伺っています。ホームズさん、あなたにはとても興味があります。これほど長頭型の頭蓋骨や、これほど明確な眼窩上隆起は想像していませんでした。頭頂裂のラインを指でなぞらせていただいても構いませんか? ご本人の頭蓋骨が手に入るまでは、型をとって博物館に飾りたいくらいです。お世辞ではありません、本当にあなたの頭蓋骨が欲しいのです。」
シャーロック・ホームズは奇妙な訪問者を椅子に促した。「あなたもご自身の分野では熱心な方のようだ、私と同じく」と彼は言った。「人差し指から察するに、あなたは自分でタバコを巻くのですね。遠慮なくお吸いください。」
男は紙と煙草を取り出し、驚くほど器用に巻き上げた。長く震える指は、まるで虫の触角のように素早く動いた。
ホームズは沈黙したが、素早い視線が、奇妙な人物への興味の深さを私に伝えていた。「さて」とついに口を開く。「私の頭蓋骨の観察だけが、昨夜そして今日またここへいらした目的ではありませんね?」
「いいえ、違います。ですが、その機会も得られて嬉しく思います。私は、ホームズさん、実務能力のない人間であり、突然非常に重大かつ異常な問題に直面したため、ご相談に伺ったのです。あなたがヨーロッパで二番目の専門家であると認めておりますので――」
「ほう、それなら一番は誰か、お聞きしても?」
「厳密に科学的な見地からは、ベルティヨン氏の業績に強く惹かれます。」
「それなら彼に相談したほうがよいのでは?」
「申し上げた通り、厳密な科学者にとっては。だが、実務家としてはあなたが群を抜いているのは周知の事実です。もし無礼がありましたら――」
「ほんの少しだけね」とホームズ。「では、モーティマー博士、手短にあなたが私に求めている問題の本質を、率直に話していただきたい。」
第2章 バスカヴィル家の呪い
「私のポケットには一通の手稿があります」とジェームズ・モーティマー博士が言った。
「お持ちになってるのは、入室したときから目にしていましたよ」とホームズ。
「これは古い手稿です。」
「18世紀初頭のものですね。偽物でなければ。」
「どうしてわかるのです?」
「あなたが話している間、紙の端を一、二インチほど見せてくれていた。書類の日付を十年単位で見分けられない専門家などいません。私の小論をお読みかもしれませんが――これは1730年ごろでしょう。」
「正確な日付は1742年です。」モーティマー博士はそれを胸ポケットから取り出した。「この家系の書類は、突然かつ悲劇的な死を遂げたサー・チャールズ・バスカヴィルから私に託されたものです。彼の死は三か月ほど前にデヴォンシャーで大きな騒ぎとなりました。私は彼の主治医であるとともに、個人的な友人でもありました。彼は強い意志を持ち、抜け目なく、私同様に想像力には乏しい実務家でした。しかし、この文書を非常に重く受け止めており、最期の運命にも十分心構えがありました。」
ホームズは手を伸ばして手稿を受け取り、膝の上で平らにした。「ワトソン、長いsと短いsが混在しているのに注目するといい。こうした点が年代特定の助けになる。」
私は彼の肩越しに、黄ばんだ紙と色あせた書体を覗き込んだ。冒頭には「バスカヴィル館」、その下に大きく乱雑な数字で「1742」とあった。
「何かの陳述書のようだ。」
「そう、バスカヴィル家に伝わるある伝説の記録だ。」
「だが、あなたが今回ご相談になりたいのは、もっと現代的かつ現実的な件なのですね?」
「まったくその通り。ごく差し迫った、極めて現実的な問題で、しかも24時間以内に決断せねばなりません。ただ、この手稿は短く、一件と密接に関係しています。ご許可いただければ、お読みします。」
ホームズは椅子にもたれ、指先を合わせて目を閉じ、覚悟を決めた様子を見せた。モーティマー博士は手稿を光にかざし、高くかすれた声で、奇妙な古風な物語を朗読し始めた。
――バスカヴィル家がこれほど苦しんできた災いが、再び解き放たれて我らを破滅に導かぬように。
――そして彼女の父の農場。
――ムーアに照る月明かり。
――彼女が自宅にたどり着くまでに。
――彼らに。
――残りの人生を。
――闇の力が頂点に達するあの暗い時に。
「バスカヴィル家の猟犬の起源については多くの言い伝えがあるが、私はヒューゴー・バスカヴィルの直系の子孫であり、この話を父から、またその父から伝え聞いたので、ここに記す通り、事実としてこれを信じている。そして息子たちよ、同じ正義が罪を罰すると同時に、最も慈悲深くそれを赦すこともあるのだということ、祈りと悔い改めによってどんな重い呪いも取り払うことができると信じてほしい。この物語から、過去の報いを恐れるのではなく、むしろ将来に慎重であることを学ぶがよい。我々の家系が
「さて、学識あるクラレンドン卿が記した『大反乱』の時代、このバスカヴィル荘園を治めていたのがヒューゴー・バスカヴィルであったことは動かしがたい事実である。そして彼は、極めて乱暴で不信心、神をも恐れぬ男であった。これについては、あの地方には聖人が育たなかったことから、近隣の者たちも目をつぶったかもしれないが、彼にはとりわけ放埒で残虐な性質があり、その悪名は西部中に知れ渡っていた。さて、このヒューゴーが、バスカヴィルの領地近くに土地を持つ百姓の娘に恋をした(もっとも、これほど暗い情熱を「恋」と呼べるものか疑わしいが)。だが、その若い娘は分別があり評判も良かったので、ヒューゴーの悪名を恐れて常に彼を避けていた。そうして迎えたあるミカエル祭の日、ヒューゴーは五、六人の放蕩で邪悪な仲間たちとともに農場に忍び込み、娘の父や兄たちが留守であることを見計らって、娘をさらい屋敷へと連れ去った。娘は屋敷の上階の一室に閉じ込められ、ヒューゴーとその仲間は、いつものように夜毎の長い酒宴を始めた。
さて、上階の可哀想な娘は、下から響いてくる歌声や叫び声、恐ろしい罵り言葉に気が狂いそうになっていた。ヒューゴー・バスカヴィルが酒を飲んだ時に使う言葉は、本人すら呪われかねないものだったという。ついに恐怖のあまり、彼女は最も勇敢な男でも尻込みするようなことをやってのけた。屋敷の南壁を蔦が覆っていた(今もそうである)のを利用し、軒下から這い降りて、三リーグ離れた家へ向かって荒野を走って帰ろうとしたのである。
しばらくして、ヒューゴーは客を残して、食べ物と酒――いや、もっと悪質なものかもしれない――を娘に運ぼうとしたが、部屋は空で、娘は逃げていた。すると彼はまるで悪魔に取り憑かれたかのようになり、階段を駆け下りて大広間の大テーブルに飛び乗り、酒瓶や皿を蹴散らして、仲間たちの前で「今夜中にあの娘を捕まえれば、自分の身も魂も悪魔に差し出す」と叫んだ。その剣幕に客たちが唖然とする中、他の誰よりも悪か、あるいは酒に酔った一人が「猟犬を使え」と叫んだ。ヒューゴーは家を飛び出し、馬丁たちに自分の牝馬に鞍を付けさせ、猟犬の檻を開けるよう命じ、娘のハンカチを渡して犬に嗅がせるやいなや、「全力で追え」と荒野に駆け出した。
しばしの間、客人たちは呆然と立ち尽くし、何が起きたのか理解できなかった。しかしほどなくして正気に戻り、このままでは荒野でとんでもないことが起きると気付いた。屋敷中が騒然となり、ピストルを持ち出す者、馬を用意する者、もう一瓶ワインを求める者と、てんでばらばらだったが、やがて十三人全員が馬に乗って追跡を始めた。頭上に月が輝き、彼らは横一列に並び、娘がたどったはずの道を急いだ。
一、二マイルほど進んだところで、夜の羊飼いとすれ違い、追跡の一行を見なかったかと叫んで尋ねた。羊飼いは恐怖のあまり声も出ない様子だったが、ついには「娘が猟犬に追われていくのを見た」と答えた。「だが、それだけではない」と彼は言い、「ヒューゴー・バスカヴィルが黒馬で私の前を駆け抜け、その後ろには神よ、二度とお目にかかりたくないほどの、地獄から来たような猟犬が音もなくついていった」と言った。酔っぱらいたちは羊飼いを罵倒し、さらに先へ進んだが、やがて恐怖で肌が粟立った。というのも、荒野の向こうから馬が駆けてきて、泡だらけで手綱を引きずり、鞍は空のまま通り過ぎたのだ。一行は身を寄せ合い、恐怖に駆られながらもなお荒野を進んだ。もしも一人きりだったなら、誰もが馬の頭を引き返したであろう。そうやってゆっくりと進んでいくと、ついに猟犬たちに遭遇した。勇猛さと血統で知られる犬たちは、荒野のくぼ地――我々の言葉で「ゴヤル」と呼ぶ――の縁に群がり、うち何匹かは逃げ腰になり、何匹かは毛を逆立て、目を見開いてくぼ地の先を凝視していた。
一行はそこで馬を止めた。出発時よりはるかにしらふだったことは想像に難くない。その場を進もうとする者はほとんどいなかったが、最も勇敢――あるいは最も酔っていた――三人がゴヤルを下っていった。くぼ地は広い空間へと開け、そこには古代の人々が建てた大きな石がふたつ、今も残っている。その広場の中央には、倒れた若い娘が横たわっており、恐怖と疲労で命を落としていた。しかし三人の無鉄砲な男たちの髪の毛を逆立てさせたのは、彼女の遺体でも、傍らに横たわるヒューゴー・バスカヴィルの死体でもなかった。ヒューゴーの死体の上に立ち、その喉元に食らいついていたのは、忌まわしい巨大な黒い獣――猟犬の姿をしているが、これほど大きな犬を人が見たことはないというほどのものだった。見ている間に、その獣はヒューゴー・バスカヴィルの喉を食い破り、燃えるような目と血に濡れたあごを三人に向けた。その瞬間、三人は恐怖に叫び声をあげ、命からがら馬を駆けて逃げ帰った。そのうちの一人は、その夜のうちに見たものの恐怖で命を落としたとされ、残る二人も長く正気を失ったという。
以上が、息子たちよ、この家系を苦しめてきたとされる猟犬の出現の物語である。私がこれを記したのは、明らかになった事実は、憶測や噂に比べて恐ろしくないからだ。また、我が家系の多くが不幸な死を遂げてきたことも否めない。死は突然で、血なまぐさく、不可解であった。しかし、聖書にあるように、神の摂理の無限の慈悲に身を委ねることができる。神は無実の者を永遠に罰することはしないと信じている。息子たちよ、私はここにお前たちを神の摂理に委ね、忠告として、夜に荒野を越えてはならぬと告げておく。
[これはヒューゴー・バスカヴィルが息子ロジャーとジョンに宛てたものであり、妹エリザベスには決して話さぬよう指示されている。]」
モーティマー博士がこの奇妙な記述を読み終えると、眼鏡を額に押し上げ、シャーロック・ホームズをじっと見つめた。ホームズはあくびをし、煙草の吸い殻を暖炉に投げ入れた。
「どうだね」と彼が言った。
「面白いとは思われませんか?」
「おとぎ話の収集家にはたまらない代物だな。」
モーティマー博士は折りたたんだ新聞をポケットから取り出した。
「では、ホームズさん、今度はもう少し最近の話をお聞かせしましょう。これは本年五月十四日付の『デヴォン・カウンティ・クロニクル』です。サー・チャールズ・バスカヴィルの死について、死の数日前までの事実が簡潔に記されています。」
私の友人は身を乗り出し、表情が真剣になった。来訪者は眼鏡をかけ直し、読み始めた。
「サー・チャールズ・バスカヴィルの突然の死は、次回選挙でミッド・デヴォンの有力な自由党候補と目されていたことで、郡に暗い影を落としている。サー・チャールズはバスカヴィル館に住み始めて日が浅いが、その人柄の温厚さと並外れた寛大さによって、交流したすべての人々の愛情と尊敬を勝ち得てきた。新興成金が幅を利かす今の時代に、没落した名家の末裔が自らの才覚で財を成し、それを持ち帰って家名を復興させる事例は新鮮である。よく知られているとおり、サー・チャールズは南アフリカの投機で莫大な利益を得た。運命の逆転を待つことなく利益を確定し帰国したのは、賢明だったと言えよう。バスカヴィル館に住み始めてわずか二年、彼が着手していた再建と改良の計画が、今回の死によって中断されたことは広く語られている。子のない彼は、生前からその幸運を近隣一帯が享受できるよう望んでおり、多くの人がその突然の死を嘆く理由を持っている。彼の地域および郡の慈善事業への多額の寄付は、しばしば報道されてきた。
「サー・チャールズの死に関する状況は、検視審問によって完全に解明されたとは言い難いが、少なくとも地元の迷信に由来する噂を払拭するには十分な事実が明らかとなった。事件に不正や犯罪性を疑う理由は一切なく、死因が自然なものであったことは疑いない。サー・チャールズは寡夫であり、ある意味で風変わりな性格の持ち主だった。莫大な財産を有しながらも質素を好み、館の屋内使用人はバリモア夫妻のみで、夫が執事、妻が家政婦を務めていた。彼らおよび複数の友人の証言から、サー・チャールズの健康は以前から損なわれており、特に心臓に疾患があったこと、顔色の変化や息切れ、神経性の発作がたびたびあったことが明らかになっている。主治医であり友人でもあったジェームズ・モーティマー博士の証言も、これを裏付けている。
「事件の経緯は単純である。サー・チャールズ・バスカヴィルは毎晩寝る前に、館の有名なイチイ並木道を散歩する習慣があった。バリモア夫妻の証言もこれを裏付ける。五月四日、サー・チャールズは翌日ロンドンに発つ意向を明かし、バリモアに荷造りを命じていた。その夜もいつものように夜の散歩に出かけ、道中は葉巻を吸っていたという。しかし彼は帰宅しなかった。十二時になっても玄関が開いたままであることに気付いたバリモアは、不安になりランタンを手に主人の捜索に出た。その日は雨で、イチイ並木道には足跡がはっきり残っていた。途中、並木の半ばに荒野へ抜ける門があり、ここでしばらく立ち止まった形跡がある。その後、サー・チャールズは並木道の端まで進み、そこで遺体が発見された。説明のつかない点は、サー・チャールズの足跡がその門を過ぎてから爪先立ちになったように見えたことである。また、ムルフィーというジプシーの馬商が近くの荒野にいたが、酒に酔っていたと自ら認めている。彼は誰かの叫び声を聞いたというが、どの方角からかは分からなかった。サー・チャールズの遺体には暴力の跡はなく、医師の証言によれば顔の歪みは常軌を逸するほどで、最初はモーティマー医師も友人である患者とは信じがたいほどだった。しかしこれは窒息や心臓衰弱による死では珍しくない症状であり、検死の結果も長期的な器質性疾患を示していたため、陪審は医学的証拠に基づき判決を下した。このような結論となったことは幸いである。なぜなら、サー・チャールズの後継者が館に住み続け、彼の事業を継ぐことは極めて重要だからだ。もし検死官のつまらぬ結論が、事件にまつわるロマンチックな噂を完全に打ち消していなければ、バスカヴィル館に住み手を見つけるのは難しかったかもしれない。次の相続人は、サー・チャールズの弟の息子であるヘンリー・バスカヴィル氏と理解されているが、彼がまだ生存していればの話である。最近の消息はアメリカにあり、現在、彼の幸運を知らせる手続きが進められている。」
モーティマー博士は新聞をたたみ、ポケットに戻した。「以上が、サー・チャールズ・バスカヴィルの死に関する公の事実です、ホームズさん。」
「ご教示に感謝する」とシャーロック・ホームズは言った。「確かに興味深い点を含む事件であるな。当時、新聞で多少は目にしたが、その頃はバチカンのカメオ事件にかかりきりで、ローマ教皇からの要請もあり、いくつか興味深い英国の事件に目が届かなかった。君の示した記事は公の事実がすべて載っているのか?」
「その通りです。」
「では、私的な事実を聞かせてもらおう。」ホームズは背もたれに寄りかかり、指先を合わせて、最も無表情で裁判官のような顔つきになった。
「こうして申し上げるのは……」とモーティマー博士は、強い感情の兆しを見せ始めながら言った。「これまで誰にも打ち明けていないことです。これを検死官に話さなかった理由は、科学者として大衆の迷信を支持するような立場に自分を置きたくなかったからです。もうひとつの理由は、バスカヴィル館が、新聞記事にもある通り、すでに不気味な評判を持っているため、これ以上それを悪化させたくなかったからです。実際的な利益がない以上、私の知っていることを少し控えめに伝えたのは正当だったと思っていますが、あなた方には包み隠す理由はありません。
「荒野は人口がまばらで、隣人同士の交流は密です。そのため、私はサー・チャールズ・バスカヴィルと親しくなりました。ラフター館のフランクランド氏と、博物学者のステープルトン氏を除けば、何マイルも離れた土地に教育ある男性はいませんでした。サー・チャールズは引っ込み思案な方でしたが、彼の病気が縁で親しくなり、科学への共通の興味から親交が深まりました。彼は南アフリカから多くの科学的知見を持ち帰り、よく夕べには、ブッシュマンやホッテントットの比較解剖について語り合ったものです。
「ここ数ヶ月の間に、サー・チャールズの神経が限界まで張り詰めているのが明らかになりました。彼は、先ほど私が読んだ伝説を非常に深刻に受け止めており、自分の領地内しか歩かず、夜に荒野へ出ることは決してありませんでした。信じ難いかもしれませんが、ホームズさん、彼は家系に恐ろしい運命がつきまとっていると本気で信じていました。実際、彼が語った先祖の記録も、気が滅入るものばかりでした。何かおぞましい存在が絶えず自分をつけ狙っているという思いに取り憑かれ、私が夜間の往診で奇妙な生き物を見たことはないか、猟犬の遠吠えを聞いたことはないかと何度も尋ねてきました。特に後者の質問は、興奮のこもった声で何度も聞かれました。
「よく覚えているのは、事件の三週間ほど前の夜、彼の屋敷に馬車で着いたときのことです。彼は玄関先にいました。私は馬車から降りたところで、彼が私の肩越しをじっと見つめ、恐怖に満ちた表情を浮かべているのに気付きました。私が振り返ると、屋敷の入口を大きな黒い子牛が通り過ぎるのを一瞬だけ見た気がしました。彼があまりに取り乱していたので、その場所に行って捜しましたが、何も残っていませんでした。しかしこの出来事は彼の心に強い影響を与えたようでした。その晩私はずっと彼のそばにおり、その際、彼が見せた動揺の理由として、最初に私に読ませたあの記録を託されたのです。この小さな出来事を語ったのは、後の悲劇を考えると重要性があるからですが、当時は全くの些事だとしか思いませんでした。
「ロンドン行きを勧めたのは私です。彼の心臓は確かに弱っており、実際には根拠のない不安であっても、絶え間ない緊張が健康に重大な悪影響を与えていました。都会の気晴らしに数ヶ月過ごせば、元気を取り戻すだろうと思ったのです。共通の友人で彼の健康を心配していたステープルトン氏も、同じ意見でした。だが、出発の直前にあの恐ろしい悲劇が起きたのです。
「サー・チャールズが亡くなった夜、発見者である執事のバリモアは、馬丁のパーキンズを馬で私のもとへ向かわせました。私は遅くまで起きていたので、出来事から1時間以内にバスカヴィル館に到着できました。私は検死審問で言及されたすべての事実を確認し、裏付けました。イチイ並木道を足跡に沿って下り、彼が待っていたと思われる荒野門の場所を見ました。その後、足跡の形が変わったことにも気付きました。柔らかい砂利の上にはバリモアの足跡以外にはなかったことも確認しました。そして最後に、私が到着するまで誰も触れていなかった遺体を慎重に調べました。サー・チャールズはうつ伏せになり、両腕を伸ばし、指は地面に食い込み、顔は激しい感情で歪んでいて、私は彼だと断言するのもためらうほどでした。身体的な損傷はまったくありませんでした。ただ一つ、バリモアが検死審問で虚偽の証言をしました。彼は遺体の周囲の地面に痕跡はなかったと言いましたが、彼は気づかなかっただけです。私は見ました――少し離れた場所でしたが、新しくてはっきりしたものでした。」
「足跡ですか?」
「足跡です。」
「男のものか、女のものか?」
モーティマー医師は一瞬奇妙な目つきをして、声をほとんど囁きに落として答えた。
「ホームズさん、それは巨大な猟犬の足跡でした!」
第三章 問題
この言葉を聞いた瞬間、私は身震いせずにいられなかった。医師の声には、彼自身が語っていることに深く動揺している様子が表れていた。ホームズは興奮して身を乗り出し、彼の目は鋭く乾いた光を放っていた――彼が強く興味を引かれた時に見せるあの光だ。
「あなたはそれを見たのか?」
「君を見ているのと同じくらい、はっきりと。」
「それで、何も言わなかったのか?」
「言う意味があっただろうか?」
「なぜ他の誰もそれを見なかったのだ?」
「その痕跡は遺体から二十ヤードほど離れていて、誰も気に留めなかったのだ。私だって、あの伝説を知らなければ注意を払わなかったかもしれない。」
「荒野には羊飼いの犬がたくさんいるのでは?」
「それは間違いないが、あれは羊飼いの犬ではなかった。」
「大きかったのか?」
「巨大だった。」
「だが、遺体には近づいていなかったのか?」
「ああ。」
「その夜はどんな様子だった?」
「湿っていて寒かった。」
「だが、実際に雨は降っていなかったのか?」
「降っていなかった。」
「並木道はどんな造りだ?」
「両側に十二フィートの高さの古いイチイの生け垣が二本あって、貫通できないほどだ。中央の歩道は幅が八フィートほどある。」
「生け垣と歩道の間には何かあるのか?」
「ああ、両側に六フィート幅の芝生がある。」
「イチイの生け垣の一か所に門があると理解しているが?」
「ああ、荒野に通じる小門(ウィケット・ゲート)がある。」
「他に開口部は?」
「ない。」
「つまり、イチイ並木に入るには、館から下ってくるか、荒野門から入るしかないわけだな?」
「反対側の端に夏の家(サマー・ハウス)からの出口がある。」
「サー・チャールズはそこまでたどり着いていたのか?」
「いや、そこから五十ヤードほど手前に倒れていた。」
「さて、モーティマー医師、これは重要な点だが、君が見た足跡は小道の上にあったのか、芝生の上ではなかったのか?」
「芝生には痕跡が残らない。」
「足跡は小道のどちら側だった? 荒野門と同じ側か?」
「ああ、門と同じ側の小道の縁にあった。」
「非常に興味深い。もう一つ。小門は閉まっていたか?」
「閉まっていて南京錠がかかっていた。」
「高さは?」
「四フィートほどだ。」
「なら、誰でも乗り越えられる?」
「そうだ。」
「小門のそばで他に何か痕跡は見たか?」
「特に何もなかった。」
「なんてことだ! 誰も調べなかったのか?」
「いや、私が自分で調べた。」
「何も見つけなかったのか?」
「すべてが混乱していた。サー・チャールズは明らかに五分か十分はそこに立ち止まっていた。」
「どうしてわかった?」
「葉巻の灰が二度落ちていたからだ。」
「素晴らしい! これは我々の同類だぞ、ワトソン。このあと足跡は?」
「彼自身の足跡がその小さな砂利の上に残っていて、他には見分けられなかった。」
シャーロック・ホームズは苛立たしげに膝を叩いた。
「私がそこにいたなら!」彼は叫んだ。「これは明らかに並外れて興味深い事件で、科学的専門家にとって途方もない好機を秘めていた。その砂利のページには、私なら多くを読み取れただろうが、今ごろは雨に濡らされ、好奇心旺盛な村人の靴で台無しにされてしまっただろう。ああ、モーティマー医師、なぜ私を呼ばなかったのだ! 君には大いに責任があるぞ。」
「ホームズさん、あなたを呼べば、この事実を世間に公表せざるを得ませんでしたし、私はすでにその理由を述べました。それに……それに――」
「なぜためらうのか?」
「どんなに鋭敏で経験豊富な探偵でも、手も足も出せない領域というものがあります。」
「つまり、それは超自然的なものだと言いたいのか?」
「はっきりそうとは言いません。」
「しかし、そう考えているのは明らかだ。」
「この悲劇以来、私はいくつかの出来事を耳にしました。それらは自然界の秩序では説明のつかないものです。」
「たとえば?」
「恐ろしい事件が起こる前に、何人かの人々がこのバスカヴィルの悪魔に似た生き物を荒野で目撃していますが、それは科学で知られるいかなる動物とも考えられません。彼らは皆、それが巨大で、光を放ち、不気味で幽霊のようだったと一致して語っています。私は彼らを個別に問いただしました。中には頑固な田舎者、馬鍛冶、荒野の農夫も含まれますが、皆この恐ろしい幻影について、伝説の地獄の猟犬とまったく同じ話をしました。今やこの地方には恐怖の支配があり、夜に荒野を渡るのは勇気ある者だけです。」
「君は科学者でありながら、それが超自然的なものだと信じるのか?」
「どう信じていいのか、私には分からない。」
ホームズは肩をすくめた。「私はこれまで、この世のことだけを調査対象にしてきた」と彼は言った。「ささやかながらも、悪と戦ってきたつもりだが、悪の元凶そのものと闘うのは、さすがに分不相応かもしれないな。だが君も、足跡が物質的であったのは認めるだろう。」
「もとの猟犬も、男の喉を引き裂くほど物質的だったが、同時に悪魔的でもあった。」
「君はすっかり超自然主義者の側に回ったようだな。しかしモーティマー医師、ひとつ聞かせてくれ。君がそう考えているなら、なぜ私に相談に来たのだ? 君は一方でサー・チャールズの死は調べても無駄だと言い、もう一方で私に調査を望んでいる。」
「私はあなたに調査を望むとは言っていません。」
「それでは、私に何をしてほしいのか?」
「ヘンリー・バスカヴィル卿について、どうすべきか助言してほしいのです。彼は――」モーティマー医師は時計を見た。「ちょうど一時間十五分後にウォータールー駅に到着します。」
「彼が相続人なのか?」
「そうです。サー・チャールズが亡くなったとき、我々はこの若者を探し、カナダで農業をしていることを突き止めました。寄せられた情報によれば、彼は非常に立派な人物です。今は医師としてではなく、サー・チャールズの遺言執行人および信託者として話しています。」
「他に相続権を主張する者はいないのだな?」
「いません。我々が突き止められた唯一の親族は、ロジャー・バスカヴィル、三人兄弟の末弟で、故サー・チャールズが長男です。二番目の兄弟は若くして亡くなり、彼がこのヘンリーの父でした。三番目のロジャーは家族の異端児で、古いバスカヴィル家の血を受け継ぎ、肖像画のヒューゴーそっくりだったそうです。イギリスから追われて中央アメリカに逃亡し、1876年に黄熱病で亡くなりました。ヘンリーがバスカヴィル家最後の一人です。今から一時間五分後にウォータールー駅で彼に会います。今朝サウサンプトンに到着したという電報がありました。さて、ホームズさん、あなたなら彼をどうすべきだと助言しますか?」
「なぜ彼が先祖の館に行ってはならないのか?」
「自然なことに思えますが、バスカヴィル家の者がそこに行くたびに不幸が起きています。もしサー・チャールズが生前に私と話せたなら、最後のこの家系の者、莫大な財産の継承者を、あの死の場所に連れていくなと警告したに違いありません。しかし、貧しく荒凉としたあの辺りの繁栄は、彼の存在にかかっているのも事実です。サー・チャールズが成し遂げた善行も、館に住む者がいなければ無に帰します。私自身の明白な利害に心が引かれていないか心配で、この問題をあなたに持ち込み、助言を仰ぐのです。」
ホームズはしばし考えた。
「要はこういうことだ」と彼は言った。「君の見解では、ダートムーアには悪魔的な力が働いており、バスカヴィル家の人間には危険な土地だ――そういう意見だな?」
「そこまで断言はしませんが、その可能性を示す証拠がある、とは言えます。」
「なるほど。しかし、もし君の超自然説が正しいなら、悪魔はロンドンでもデヴォンシャーでも同じように若者に災いをもたらせるはずだ。教区の理事会みたいに、地元だけでしか力を発揮できない悪魔なんて考えられないよ。」
「あなたは軽く扱い過ぎます、ホームズさん。ご自身がこうしたものと実際に直面すれば、そんな言い方はしないでしょう。つまり、あなたの助言は、若者はデヴォンシャーでもロンドンでも同じくらい安全だということですね。彼の到着まであと五十分です。どうなさいます?」
「助言はこうだ。タクシーを呼び、玄関でドアを引っかいているスパニエルを家に帰し、ウォータールー駅でヘンリー・バスカヴィル卿を迎えたまえ。」
「その後は?」
「その後は、私が結論を出すまでは、彼には何も言わないように。」
「どれくらいで結論が出るのです?」
「二十四時間だ。明日の十時に、モーティマー医師、ここに来てくれたまえ。できればヘンリー・バスカヴィル卿も一緒に連れてきてくれると、今後の計画に役立つ。」
「そうしましょう、ホームズさん。」彼は約束をシャツのカフスに書き留め、例の奇妙な、首を突き出した物忘れ気味の様子で急いで出ていった。ホームズは階段の上で呼び止めた。
「もう一つだけ質問がある、モーティマー医師。サー・チャールズ・バスカヴィルの死の前に、あの幻影を荒野で見たのは何人いた?」
「三人です。」
「死後に見た者は?」
「私の聞く限り、いません。」
「ありがとう。おはよう。」
ホームズは静かな満足感のある表情で席に戻った。これは彼にとって打ってつけの仕事が待っている時の顔だ。
「出かけるのか、ワトソン?」
「君の役に立てないなら、出ようと思う。」
「いや、親愛なる友よ、君の力を借りるのは行動の時だ。だがこれは素晴らしい、ある意味まったく類のない事件だ。ブラッドリーの店を通りがかったら、一番強いシャグタバコを1ポンド送るよう頼んでくれないか。ありがとう。君がもし夕方まで戻らずにいてくれるなら助かる。そうしてくれれば、この今朝われわれに持ち込まれた興味深い問題について、印象を照らし合わせられるだろう。」
私は、友が証拠の一つ一つを吟味し、いくつもの仮説を構築しては比較し、重要な点と瑣末な点を見極めて決断する、あの激しい思索の時間には、ひとり静かに籠ることが必要だとよく知っていた。それゆえ、私はその日をクラブで過ごし、夕方までベイカー街には戻らなかった。居間に戻ったのは、ほぼ九時だった。
ドアを開けた第一印象は、火事でも起きたのかと思ったほどで、部屋は煙でいっぱいになり、テーブルのランプの灯りもぼやけて見えた。しかし中に入ると、私の不安はすぐに解けた。喉を締めつけ咳き込ませる、強烈で粗野なタバコの辛い煙だった。煙の向こうに、寝間着姿のホームズが肘掛け椅子に丸くなり、黒い陶器のパイプをくわえているのがぼんやりと見えた。周囲には紙の巻物がいくつも転がっている。
「風邪を引いたのか、ワトソン?」彼が言った。
「いや、この毒々しい空気のせいだ。」
「言われてみれば、ずいぶん煙いな。」
「煙いどころじゃない、耐えられないよ。」
「なら窓を開けてくれ! 君は一日クラブにいたようだね。」
「ホームズ、君は――!」
「当たりだろう?」
「確かにそうだが、どうして?」
私の当惑した顔を見て、彼は楽しげに笑った。「君の純真さには、僕のわずかな推理力でも使う甲斐があるよ。紳士が、雨模様でぬかるみの日に出かけ、夕方には帽子も靴もきれいなままで帰ってきた。つまり、その間ずっとどこかに留まっていたわけだ。親しい友人もいない。なら、どこにいた? 自明じゃないか?」
「まあ、言われてみれば自明だな。」
「世の中は、誰も決して気づかない自明なことで満ちている。さて、僕がどこにいたと思う?」
「君もどこかに留まっていたのだろう。」
「いや、実はデヴォンシャーに行ってきた。」
「精神的に、か?」
「その通り。体はこの肘掛け椅子にずっといて、僕の不在中にコーヒーを二大杯も消費し、信じられない量のタバコを吸ってしまったよ。君が出かけた後で、スタンフォードに頼んでこの地方の陸地測量局の地図を取り寄せ、一日中その上で精神を飛ばしていた。自分でも道に迷うことはないと自負しているよ。」
「大きな縮尺の地図か?」
「ああ、とても大きい。」
彼は一枚の地図を広げて膝の上に乗せた。「これが我々の関係する地区だ。中央がバスカヴィル館だ。」
「森に囲まれているな?」
「その通り。イチイ並木道も、名称は記されていないが、この線に沿って延びているはずだ。右手が荒野だ。この小さな建物の塊がグリムペン村で、モーティマー医師の拠点がある。半径五マイル以内に、ぽつぽつと家があるばかりだ。ここが物語に出てきたラフター館。自然主義者のステープルトン氏の家と思しき建物もある。荒野の農場が二つ、ハイ・トーとファウルマイア。そして十四マイル離れたプリンスタウンの大監獄。その間と周囲には、不毛で生命の気配のない荒野が広がっている。ここが悲劇の舞台であり、我々が再び芝居を演じることになるかもしれない場所だ。」
「荒れた場所だろうな。」
「ああ、その舞台設定こそふさわしい。もし悪魔が人間の世界に介入するなら――」
「君自身、超自然解釈に傾きつつあるのか?」
「悪魔の手先も肉体を持つことはあるだろう。最初から二つの問題が我々を待っている。ひとつは犯罪がそもそも行われたのかどうか、もうひとつは、その犯罪の内容と手段だ。もちろん、モーティマー医師の推測通り、自然法則の外にある力が相手なら、調査は無意味だ。しかしそれ以前に、他のあらゆる仮説を尽くしてからにすべきだと思う。もし君が構わなければ、窓はまた閉めよう。濃い空気は思考の集中に役立つ。不思議なことに、箱に入って考えるわけではないが、論理的にはそこまでいくかもしれない。君は今日、一日この件を考えてみたか?」
「ああ、ずいぶん考えた。」
「どう思う?」
「非常に混乱している。」
「確かに独特な事件だ。特徴もはっきりしている。たとえば、足跡の変化――君はどう見る?」
「モーティマーは、あの部分ではつま先立ちで歩いたと言っていた。」
「それは誰かの受け売りだ。なぜ大人が並木道をつま先立ちで歩く?」
「では、どうなんだ?」
「走っていたのだ、ワトソン――必死に、命がけで、心臓が破れるまで走って――そして倒れて死んだのだ。」
「何から逃げて?」
「そこが我々の問題だ。男は走り始める前から、恐怖で正気を失っていた兆候がある。」
「どうしてそう言える?」
「彼が自分を脅かしたものは、荒野からやってきた――そう推定している。もしそうなら、そしてそれが最も蓋然性が高いなら、正気を失った者だけが、家に向かうのではなく、家から逃げて走るだろう。ジプシーの証言が正しいとすれば、助けの望みが最も薄い方向へ叫びながら走った。そのうえ、あの夜誰を待っていたのか、なぜ自分の家ではなくイチイ並木で待っていたのか?」
「誰かを待っていたと思うのか?」
「男は年老いて虚弱だ。夕方の散歩は理解できるが、地面は湿っていたし、夜は荒れていた。そんな中、五分も十分も立ち尽くすのは普通ではない。モーティマー医師は、葉巻の灰からそれを推理した――彼の実践的な観察力には感心だ。」
「だが、彼は毎晩外に出ていたんだ。」
「彼が毎晩ムーア・ゲートで待っていたとは考えにくい。むしろ証拠からすると、彼はムーアを避けていた。その夜だけはそこに待っていた。ロンドンへ発つ前夜のことだ。話が形になってきたぞ、ワトソン。筋が通ってきた。よし、バイオリンを取ってくれないか。そして、この件については、明朝モーティマー医師とヘンリー・バスカヴィル卿に会うまで、いったん思考を中断しよう。」
第四章 ヘンリー・バスカヴィル卿
私たちの朝食の席は早々に片付けられ、ホームズは約束された面会を待ちながらガウン姿でくつろいでいた。依頼人たちは時間通りに現れた。ちょうど十時の鐘が鳴ったとき、モーティマー医師が案内され、その後ろから若きバロネットが続いた。彼は小柄で機敏、黒い瞳をもつ三十歳ほどの男で、がっしりとした体格、太い黒眉に闘志を感じさせる精悍な顔立ちだった。赤みがかったツイードのスーツを着ており、屋外で多くの時を過ごしてきた者特有の風雨にさらされた風貌だ。にもかかわらず、その落ち着いた視線と自信に満ちた佇まいには紳士らしさが漂っていた。
「こちらがヘンリー・バスカヴィル卿です」とモーティマー医師が言った。
「ええ、そうです」と彼は言った。「不思議なことに、シャーロック・ホームズさん、もし今朝友人があなたのところに行こうと提案しなかったら、自分で訪ねてきたと思うんですよ。あなたがこうした謎解きを得意としていると聞いていますが、今朝の私は自分の手には負えない謎を抱えているんです。」
「どうぞ、おかけください、バスカヴィル卿。ロンドンに到着されてから何か特別な体験をされたとおっしゃいましたか?」
「大したことじゃありません、ホームズさん。ただの悪戯かもしれません。今朝届いたこの手紙――もし手紙と呼べるならですが――のことです。」
彼は封筒をテーブルの上に置き、私たちは身を乗り出してそれを覗き込んだ。封筒はごく普通の質で、灰色がかっていた。宛名「ヘンリー・バスカヴィル卿 ノーサンバーランド・ホテル」は粗い文字で書かれており、消印は「チャリング・クロス」、投函日は昨夜となっていた。
「ノーサンバーランド・ホテルに泊まることを知っていたのは誰です?」とホームズが鋭い目で訪問者を見つめながら尋ねた。
「誰も知るはずがありません。ドクター・モーティマーと出会った後で、そこに決めたんです。」
「でも、モーティマー医師はすでにそこに泊まっていたのでしょう?」
「いえ、私は友人の家に滞在していました」と医師が答えた。
「私たちがそのホテルに行くつもりだという手がかりはなかったわけですね。」
「ふむ。誰かがあなたの動向に非常に強い関心を持っているようですね。」ホームズは封筒から二つ折りにされた半分のフールスキャップ紙を取り出し、開いてテーブルに広げた。その中央には、印刷された単語を切り抜いて貼り付けるという手法で、ひとつの文章が作られていた。
あなたが命と理性を大切に思うなら、ムーアに近づくな。
「ムーア」という単語だけがインクで書かれていた。
「ところで、ホームズさん、これがどういう意味なのか、そして私のことにこれほど興味を持つのは誰なのか、お教え願えませんか?」
「どうお考えです、モーティマー医師? 少なくとも、ここには超自然的なものは見受けられませんね?」
「はい、ですが書いた者がこの事件を超自然的なものと信じている可能性はあります。」
「どの事件です?」とバスカヴィル卿が鋭く尋ねた。「どうも皆さんの方が私自身よりも遥かによく事情をご存じのようですね。」
「この部屋を出る前に、私たちの知っていることはすべてお話しします、バスカヴィル卿。それをお約束します。今はひとまず、この興味深い書簡について考えましょう。これは昨日の夕方に作られ、投函されたものに違いありません。ワトソン、昨日のタイムズはあるか?」
「この隅にあります。」
「すみませんが、その中面、主な記事のページをいただけますか?」ホームズは素早く紙面を流し読みした。「自由貿易についての良い記事ですね。少し抜粋してみましょう。
『あなた自身の特別な産業や貿易が保護関税によって恩恵を受けると騙されるかもしれないが、理の当然として、そうした立法は長い目で見ればこの国から富を遠ざけ、輸入品の価値を下げ、この島の生活水準全体を引き下げる結果になる。』
「どうだい、ワトソン?」ホームズは満面の笑みで手をこすりながら言った。「実に見事な主張だと思わないか?」
モーティマー医師は専門的な関心をもってホームズを見つめ、バスカヴィル卿は困惑した黒い目で私に視線を送った。
「関税のことはさっぱりですが、このメモと関係があるとは思えませんね」と彼は言った。
「いや、むしろ核心に近づいていると思いますよ、バスカヴィル卿。ワトソンは私の手法をよく知っていますが、それでもこの文章の意味を十分には理解していないようだ。」
「確かに、私には関連が分かりません。」
「だがね、ワトソン、実は非常に密接な関連がある。ひとつがもう一方から抜き取られたんだ。『あなた』『あなたの』『あなたの』『命』『理性』『大切に』『近づくな』『~から』。これらの単語がどこから取られたか、今なら分かるだろう?」
「確かにその通りだ! いや、これは見事だ!」とバスカヴィル卿が叫んだ。
「もし疑いが残るとすれば、『近づくな』と『~から』が一続きで切り抜かれている事実で解決される。」
「本当だ、そうなっている!」
「実に驚かされます、ホームズさん」とモーティマー医師が驚嘆しつつ言った。「言葉が新聞からのものだというのは予想できますが、どの新聞で、しかも社説からとまで特定されるとは思いもよりませんでした。どうやって分かったのですか?」
「医師、あなたは黒人の頭骨とエスキモーの頭骨を見分けられますね?」
「もちろんです。」
「なぜ分かるのです?」
「それが私の専門的な趣味です。眼窩上隆起、顔面角、上顎曲線など――」
「これが私の専門的な趣味ですし、差は同じくらい明白です。タイムズの記事の活字と、夕刊の安っぽい印刷の違いは、あなたの黒人とエスキモーの差と同じくらい私には明白です。活字の見分けは犯罪専門家の基礎知識の一つです。もっとも若い頃一度だけリーズ・マーキュリーとウェスタン・モーニング・ニュースを間違えたことはありますが、タイムズの社説は独特で、他からはあり得ません。昨日作られたものなので、昨日号から抜き出された可能性が高いわけです。」
「では、ホームズさん、誰かがこのメッセージをハサミで――」
「爪切りバサミです」とホームズ。「刃が短いため『近づくな』の部分は二度切られているのが分かります。」
「なるほど。つまり誰かが短いハサミで切り抜き、糊で――」
「ガムですね」とホームズ。
「ガムで貼り付けた。でも『ムーア』だけは手書きなんですか?」
「印刷された『ムーア』が見つからなかったのでしょう。他の単語はどれも簡単で、どの号にも載っていそうですが、『ムーア』は珍しい。」
「なるほど、それで説明がつきます。他に何か読み取れることはありますか?」
「いくつか示唆はあるが、手がかりを消すことに細心の注意が払われている。宛名も粗い文字だ。ただ、タイムズは高学歴者しか読まない新聞だ。つまり、手紙を書いたのは教養ある人間で、無教養を装いたかったということ。それに自分の筆跡を隠そうとしたのは、その字があなたの目に触れる、あるいは知られる可能性があるからだろう。さらに、単語がきちんと一列に並んでおらず、『命』などは明らかにずれている。これは不注意というより、作成者が動揺して急いでいた可能性を示唆する。これほど重要な内容で不注意は考えにくいから、急いでいたのだろう。なぜ急ぐ必要があったのか。早朝までに投函すれば卿の出発前に届くはずだ。妨害を恐れた――それは誰からだったのか?」
「徐々に推測の域に入ってきましたね」とモーティマー医師。
「むしろ、可能性を天秤にかけて最も有力な線を選ぶ段階だ。科学的想像力の応用だが、常に手がかりが出発点にある。これは推測だろうが、私はこの宛名がホテルで書かれたとほぼ確信している。」
「どうしてそんなことが分かるんです?」
「よく見ると、ペンとインクの両方で筆者は苦労している。ひとつの単語でペンが二度もはね、インク切れも三度ある。つまりインク壺はほとんど空だった。個人のペンやインク壺ならこんな状態は珍しいが、ホテルのペンやインク壺なら珍しくない。だから私は、チャリング・クロス周辺のホテルのごみ箱を調べてタイムズ社説の切れ端を見つければ、すぐにこの奇妙なメッセージの送り主を特定できると考えている。おや、これは?」
ホームズは言葉の切り抜きが貼られたフールスキャップ紙を、目のすぐ近くで慎重に調べていた。
「何か?」
「いや、何もない」と言って紙を投げ出した。「何の透かしもない半紙だ。この不可解な手紙からは、これ以上は引き出せまい。ところで、バスカヴィル卿、ロンドン到着以来、他に何か興味深いことは?」
「いや、ホームズさん、特にありません。」
「誰かにつけられたり、見張られたりした覚えは?」
「まるで一幕ものの冒険小説の登場人物みたいですね。なぜ私がそんな目に遭うのでしょう?」
「それについてはこれから話しましょう。ほかに何か報告すべきことは?」
「普通なら気にも留めないことでしょうけど。」
「日常の枠を外れることは何でも報告してほしい。」
バスカヴィル卿は微笑した。「まだイギリス生活はよく知らないんです。ほとんどをアメリカとカナダで過ごしてきましたから。でも、靴を一足なくすのがこちらの日常だとは思えませんね。」
「靴が一足なくなったのですか?」
「ミスレイ(置き忘れ)ただけですよ、卿」とモーティマー医師が叫んだ。「ホテルに戻れば見つかるでしょう。こんな些細なことでホームズさんを煩わせる必要はありません。」
「でも、日常の枠外の出来事を聞きたいと言われましたので。」
「その通り」とホームズ。「どんなに馬鹿げて見えても構いません。靴をなくした、と?」
「正確に言えば、置き忘れたかもしれません。昨夜ドアの外に両方出しておいたのに、朝には一足しかなかった。磨きの係にも聞きましたが要領を得ません。一番困るのは、昨日ストランドで買ったばかりで、一度も履いてない靴なんですよ。」
「一度も履いていないのに、なぜ出しておいたのですか?」
「タン(明るい茶色)の靴で、一度もワックスがかけてなかったので、磨いてもらおうと思って。」
「つまり、昨日ロンドン到着後すぐに靴を買ったのですね?」
「いろいろ買い物をしました。モーティマー医師も一緒でした。地元の領主になるならきちんとした格好をしないといけませんし、西部での暮らしではだいぶ無頓着になってましたから。ほかにも色々買いましたが、この茶色の靴は六ドルもして、一度も履かないうちに一足盗まれたわけです。」
「それにしても、妙な盗難ですね」とホームズ。「私もモーティマー医師と同意見で、すぐ見つかると思いますが。」
「さて、諸君」と卿はきっぱりと言った。「自分の知る限りはすべて話しました。今度は約束通り、何が起きているのか教えてください。」
「ご要望はもっともです」とホームズ。「モーティマー医師、昨日私たちに話した内容をそのままお話しください。」
こうして励まされた科学者はポケットから書類を取り出し、昨日朝と同じように一連の事件を説明した。バスカヴィル卿は熱心に聞き入り、時折驚きの声をあげていた。
「いやはや、すごい遺産を相続したものだ」と長い話が終わると彼は言った。「もちろん、あの魔犬の話は子供の頃から聞いていた。家の伝説ですから。でも、本気で取り合ったことはなかった。だが、叔父の死となると――まだ頭の中がごちゃごちゃで整理がつかない。警察を呼ぶべきか聖職者に頼むべきか、諸君もまだ迷っているようだ。」
「その通りだ。」
「それにホテルに届いたこの手紙の件も加わりますね。これは事件の一部なのでしょうか。」
「誰かが私たちよりもムーアで起きていることを知っているようです」とモーティマー医師。
「そして」とホームズが続けた。「あなたに善意を持つ者が警告しているともとれます。」
「あるいは、自分の都合で私を脅して追い払いたいのかもしれません。」
「それも確かに考えられます。とにかく、モーティマー医師には興味深い問題を紹介していただき感謝します。さて、現実的な決断を下さなければなりません、バスカヴィル卿。あなたがバスカヴィル・ホールへ行くのが賢明かどうか、です。」
「なぜ行ってはいけないのです?」
「危険があるようです。」
「それはこの家系の悪魔的存在からの危険ですか? それとも人間からの危険ですか?」
「それを見極めなければなりません。」
「どちらであれ、私の答えは決まっています。地獄にも悪魔はおらず、この地上にも私が自分の家に行くのを止められる者はいない。それが私の最終的な答えです。」卿の黒い眉が寄せられ、顔が暗赤色に染まった。バスカヴィル家の烈しい気性は、この最後の血筋にも健在であることが明らかだった。「ともかく」と彼は続けた。「まだ情報を消化する時間がありません。一度に理解し決断するには大きすぎる話です。一人静かに考える時間がほしい。さて、ホームズさん、今は十一時半です。私はすぐホテルに戻ります。二時にあなたとワトソン医師に昼食をご一緒していただけませんか。そのときには、私なりの考えをもっとはっきりお伝えできるでしょう。」
「ワトソン、都合は?」
「問題ありません。」
「なら、ぜひお越しください。馬車を呼びましょうか?」
「歩く方がいいです。この件で少し気が動転していますから。」
「私もご一緒に歩きましょう」とモーティマー医師。
「それでは二時にまた。では、さようなら!」
私たちは、二人の足音が階段を下り、玄関のドアがバタンと閉まるのを聞いた。その瞬間、ホームズは夢想的な姿から一転、行動の人へと変わった。
「ワトソン、帽子と靴を! 一刻の猶予もない!」 彼はガウン姿で自室に駆け込み、すぐにフロックコート姿で戻ってきた。私たちは一緒に階段を駆け下り、通りへ出た。モーティマー医師とバスカヴィル卿は二百ヤードほど先、オックスフォード・ストリートの方角にまだ見えていた。
「追いかけて止めましょうか?」
「いや、ワトソン、そんなことは絶対にしない。君と歩ければ私は十分満足だ。友人たちも賢明だ。今日は散歩に最適な素晴らしい朝だからね。」
ホームズは歩調を速めて、二人との距離を半分ほどに縮めた。それでも百ヤードの距離を保ちながら、私たちは彼らの後ろをオックスフォード・ストリートからリージェント・ストリートへと進んだ。一度、彼らは店のショーウィンドウを覗いて足を止めた。そのときホームズも同じように立ち止まった。するとすぐに彼は満足げに小さな声を上げ、彼の熱心な視線の先には、通りの向こう側に停まっていたハンサム・キャブの中の男が、ゆっくり動き出すのが見えた。
「ワトソン、あれが我々の男だ! 行こう! 少なくとも姿だけはしっかり見ておこう。」
その瞬間、私は、もじゃもじゃした黒いひげと鋭いまなざしが、馬車の側窓越しにこちらをじっと見ていることに気づいた。とたんに、馬車の天井の昇降口がぱっと開き、何事かが御者に怒鳴られ、馬車は狂ったようにリージェント・ストリートを駆けだした。ホームズはすぐさま周囲を見回して他の空車を探したが、一台も見当たらなかった。そこで彼は交通の流れの中を必死に追いかけたが、相手の出発が早すぎて、馬車はすでに視界の外に消えていた。
「これだ!」と、ホームズは歯ぎしりしながら、車の波をかき分けて息を切らし、真っ青な顔で戻ってきた。「こんな運の悪さ、しかもこんなまずい手際が今まであっただろうか? ワトソン、ワトソン、君が誠実な人間なら、これもきちんと記録して、私の成功の中に混ぜておいてくれ!」
「いったい、あの男は誰だったんだ?」
「見当もつかない。」
「スパイか?」
「まあ、これまでの話からも明らかなように、バスカヴィルはロンドンに来て以来、誰かにしっかり付けられていた。でなければ、彼がノーサンバランド・ホテルを選んだと、あんなに早く知れ渡るはずがない。最初の日に追われていたなら、二日目も追われていると考えた。君も気づいていたかもしれないが、私はモーティマー医師が伝説を読んでいる間に二度窓際に行った。」
「覚えているよ。」
「私は通りにたむろしている人間を探していたが、見当たらなかった。我々が相手にしているのは相当賢い男だ。この事件は非常に根が深い。善意か悪意か、どちらの力が我々に働きかけているのか、まだ判断がつかないが、力と計画性が常に感じられる。我々の友人たちが立ち去ったとき、私はすぐさま彼らの“見えざる随行者”を突き止めようと後を追った。しかし相手は用心深く、徒歩ではなく馬車を利用していた。これなら遅れて後ろからつけたり、逆に追い抜いたりして、気づかれずに済む。さらに、彼らが馬車を使った場合も追跡が容易だ。だが、ひとつ明白な不利がある。」
「御者の支配下に置かれるということか。」
「その通り。」
「番号を控えなかったのが悔やまれるな!」
「ワトソン君、私がどれだけ間抜けでも、まさか番号を控え損ねたと本気で思ってはいまい? 我々の男は2704号だ。しかし今のところ役には立たない。」
「これ以上どうすればよかったというんだ?」
「馬車を見たとき、すぐに踵を返して別方向に歩き、余裕を持ってもう一台馬車を雇い、距離を保って後をつけるべきだった。あるいは、ノーサンバランド・ホテルへ先回りし、そこで待ち受けてもよかった。そうすれば、その“見えざる随行者”がバスカヴィルを家まで追っていったとき、逆に彼の行動を追跡できたはずだ。だが、こちらの軽率な早合点を、相手は驚くべき迅速さと機転で逆手に取り、我々は自ら手の内を見せてしまい、相手を取り逃がした。」
この会話の間、私たちはゆっくりとリージェント・ストリートを歩いていたが、モーティマー医師とその連れは、もうとっくに前方に姿を消していた。
「もう追いかける意味はない」とホームズは言った。「影はすでに去り、戻ってこないだろう。今後は自分たちの持ち札をきちんと見極めて、有利に使うべきだ。馬車の中の男の顔を断言して証言できるか?」
「ひげだけなら証言できる。」
「私もだ――つまり、おそらくあれは偽ひげだったと思える。こんな繊細な任務に当たる賢い男にとって、ひげなど顔を隠す以外に用はない。さあ、ワトソン、ここに入ろう!」
彼は地区の伝令局のひとつに入り、支配人から温かく迎えられた。
「ああ、ウィルソンさん。以前、お手伝いした小さな事件をまだ覚えているのかい?」
「忘れるもんですか、先生。あなたには名誉ばかりか、命まで救ってもらいました。」
「いやいや、そこまで大げさじゃないよ。確か、ウィルソンさんの少年たちの中にカートライトという有望な子がいたね?」
「はい、今でもおります。」
「呼んでくれないか? ……ありがとう! それと、この五ポンド札を細かくしてもらえると助かる。」
十四歳の、きびきびとした利発そうな顔の少年が、支配人の呼び出しに応じてやってきた。今や彼は、有名な探偵を畏敬のまなざしで見つめている。
「ホテル名簿を見せてくれ」とホームズ。「ありがとう。さて、カートライト、ここにチャリング・クロス近辺のホテルが二十三軒載っているのがわかるか?」
「はい、先生。」
「これらすべてを順番に回るんだ。」
「はい、先生。」
「どのホテルでも、まず外のポーターにシリング銀貨を渡す。ここに二十三枚ある。」
「はい、先生。」
「それで“昨日の使用済み書類を見せてほしい”と言う。重要な電報が間違って届けられたので、それを探している、と説明するんだ。わかったか?」
「はい、先生。」
「だが、実際に探すのは、はさみで穴をあけた『タイムズ』紙の中面だ。これがその見本だ。これでわかるな?」
「はい、先生。」
「外のポーターは必ずホール・ポーターを呼ぶから、その人にもシリングを渡す。ここにも二十三枚ある。そして、おそらく二十三軒中二十軒では、“昨日の紙はすでに焼却済みか処分済み”と言われるだろう。残りの三軒では、書類の山を見せられるから、その中からこのページを探すんだ。見つかる確率は非常に低いけれどな。予備費として十シリング渡しておく。夕方までに、ベイカー街に電報で報告してほしい。さて、ワトソン、我々は今度は電報で、2704号の馬車の御者の身元を調べるとしよう。それまでの間、ボンド・ストリートの画廊でものぞこうじゃないか。」
第五章 三本の切れた糸
シャーロック・ホームズには、驚くほど自在に頭脳を切り替える力があった。この奇妙な事件に巻き込まれていることも、二時間のあいだは完全に忘れてしまったかのようで、彼は近代ベルギー派の絵画にすっかり没頭していた。画廊を出てホテルに着くまで、彼は芸術の話しかせず、その知識もごく初歩的なものにとどまっていた。
「ヘンリー・バスカヴィル卿が上でお待ちです」と受付係が言った。「お着きになったらすぐ、ご案内するよう頼まれております。」
「宿帳を拝見してもよろしいですか?」とホームズ。
「どうぞ、まったくご自由に。」
記帳簿には、バスカヴィルの名のあとに新たに二人分の名前があった。一人はニューカッスルのセオフィラス・ジョンソン一家、もう一人はアルトンのハイ・ロッジから来たオールドモア夫人とその女中である。
「確か、昔知っていたジョンソン氏じゃないか?」とホームズはポーターに尋ねた。「弁護士で、白髪で足を引きずって歩く人じゃ?」
「いえ、旦那様、このジョンソンさんは炭鉱王で、たいへん活動的な方です。先生と同じくらいのご年輩ですよ。」
「職業の記憶違いじゃないかな?」
「いえ、旦那様! 長年このホテルを利用されていて、よく知られています。」
「なるほど、納得した。オールドモア夫人も名前に覚えがあるんだが、失礼ながら、友人を訪ねて別の知人に出会うこともありますから。」
「ご病気のご婦人です、旦那様。ご主人はかつてグロスター市長を務められました。ご滞在の際はいつも当ホテルです。」
「ありがとう。残念ながら面識はなさそうだ。――ワトソン、今の質問で非常に重要な事実が明らかになった。我々が調べている人物たちは、当ホテルに腰を落ち着けていない。つまり、彼らはバスカヴィルを監視したいが、同時に絶対に姿を見られたくないということだ。これは非常に示唆的だ。」
「何を示唆しているんだ?」
「つまり――やあ、どうした、これは!」
階段の上を曲がったところで、私たちはヘンリー・バスカヴィル卿本人と出くわした。彼は顔を真っ赤にして怒っており、片手に古くて埃まみれの靴を握りしめていた。あまりの怒りに言葉もおぼつかず、やっと発した言葉も朝に聞いたものよりはるかに強い西部の訛りであった。
「このホテルの連中は、俺を馬鹿にしてるつもりらしいな」と彼は怒鳴った。「下手にちょっかい出すと痛い目見るってこと、思い知らせてやるぞ。もし俺の靴が見つからなかったら、ただじゃ済まさん。冗談なら受けて立つが、今回は度が過ぎてる。」
「まだ靴を探しているのか?」
「そうだ、絶対に見つけてやる。」
「でも、なくなったのは新しい茶色の靴だったはずだろ?」
「確かにそうだ。だが今度は古い黒の靴がなくなった。」
「えっ、まさか――?」
「その“まさか”さ。俺は三足しか持っていない――新しい茶色、古い黒、あとは今履いてるエナメル靴だけだ。昨夜は茶色の片方が消え、今日は黒の片方がこっそり盗まれた。で、見つかったのか? 黙って見ていないで、答えてくれ!」
そこへドイツ人の給仕が慌てて現れた。
「いえ、旦那様。館内すべて調べましたが、どこにも見当たりません。」
「じゃあ、日が暮れるまでに靴が戻らなかったら、支配人に直談判して、このホテルを出るからな。」
「必ず見つけ出します、旦那様。少しだけご辛抱願います。」
「頼むぞ。これ以上、俺の持ち物はこの泥棒の巣窟で失いたくない。――ともかく、ホームズさん、こんな些細なことでご迷惑をおかけして――」
「いや、とても重要なことだと思う。」
「そんなに深刻そうな顔をするとは。」
「どう説明する?」
「説明なんてできるもんか。こんな馬鹿げた、妙な事件は初めてだ。」
「妙、という点ではね……」とホームズは考え込む。
「君にはどう見える?」
「まだ完全には理解できていない。この事件は非常に複雑だ、バスカヴィル卿。叔父上の死と併せて考えると、私の扱った五百件の重大事件の中でも、これほど深刻なものは他にないかもしれない。ただ、手元には複数の糸口がある。間違った糸を追って時間を無駄にするかもしれないが、いずれ本筋にたどり着くだろう。」
昼食は和やかに進み、この事件についてはほとんど話題に上らなかった。食後、私たちは個室に移り、そこでホームズがバスカヴィル卿に今後の方針を尋ねた。
「バスカヴィル館へ行くつもりだ。」
「いつだ?」
「今週末に。」
「総合的に見て、その判断は賢明だと思う。ロンドンでは君が付け回されている証拠が十分にあるし、この大都市の人混みでは相手の正体や目的の解明は難しい。もし悪意があるなら、君に危害を加えられても、我々には防ぐ術がない。今朝、私の家を出てから、君たちが尾行されていたことを知っていたか?」
モーティマー医師は激しく驚いた。「尾行されていた? 誰に?」
「それは残念ながら、まだわからない。ダートムーアのご近所や知人に、黒くて立派なひげの男はいないか?」
「いや――ちょっと待て、そうだ。バリモア、サー・チャールズの執事が、立派な黒ひげの男だ。」
「ほう! バリモアは今どこに?」
「館の管理をしている。」
「本当にそうか、あるいはロンドンにいる可能性はないか、確かめた方がいい。」
「どうやって?」
「電報用紙をくれ。“ヘンリー卿の準備はできているか? ”でいい。宛先はバリモア宛、バスカヴィル館。最寄りの電報局は? ――グリムペンだな。では、グリムペン郵便局長にももう一通。“バリモア宛電報は必ず本人の手に渡すこと。不在ならノーサンバランド・ホテルのヘンリー卿へ返電を”と。これなら今晩までには、彼が館にいるかどうかわかる。」
「その通りだ」とバスカヴィル卿。「ところで、モーティマー医師、そもそもバリモアとは何者だ?」
「亡くなった前管理人の息子で、家系としては四代続いて館を守ってきた。彼と妻は、この地域でも最も立派な夫婦だと私は思っている。」
「だが」バスカヴィル卿は言う。「家族が誰もいない間は、あの夫婦が立派な邸宅を好きなだけ使い、仕事もないってことだよな。」
「それも確かだ。」
「バリモアはサー・チャールズの遺言で恩恵を受けたのか?」とホームズ。
「彼にも妻にもそれぞれ五百ポンドずつ残された。」
「ほう! そのことは前もって知っていたのか?」
「知っていた。サー・チャールズは自分の遺言の話をよくしていたから。」
「それは興味深い。」
「まさか、遺産をもらった人全員を疑う目で見るわけじゃないでしょうね、ホームズさん。私も千ポンドいただいたのです。」
「そうですか! 他には誰か?」
「小口の遺贈は多数あるし、多くの慈善団体にも。残りはすべてヘンリー卿へ。」
「残りはいくら?」
「七十四万ポンドです。」
ホームズは驚いて眉を上げた。「そこまで巨額とは思わなかった。」
「サー・チャールズは裕福と言われていたが、実際に証券を調べるまではこんなに資産があるとは思わなかった。全財産はほぼ百万円に迫っていた。」
「なるほど! そうなれば、命がけの危険を冒しても手に入れたい額だな。もう一点、モーティマー医師。もし、若いご友人に万一のことがあれば――不吉な仮定で申し訳ない――誰が相続する?」
「チャールズ卿の弟ロジャー・バスカヴィルは独身で亡くなりましたから、遠縁のデズモンド家に移ります。ジェームズ・デズモンドはウェストモーランドの高齢の牧師です。」
「ありがとう。その詳細も興味深い。ジェームズ・デズモンド氏には会ったことが?」
「一度、サー・チャールズを訪ねて来たことがあります。とても敬虔で立派な方で、遺産の分配を断固として受け取りませんでした。」
「この質素な男がサー・チャールズの莫大な遺産を継ぐのか。」
「館は相続人が決まっていますが、現オーナーが望めば資産の配分も変えられます。」
「ヘンリー卿、すでに遺言はお書きですか?」
「いや、まだだ。昨日になって初めて現状を知ったばかりだし。だが、金は爵位と館とともにあるべきだと考えている。それが叔父の考えでもあった。財産がなければ、バスカヴィル家の栄光は守れない。屋敷も土地も金も一体であるべきだ。」
「まったく同感だ。さて、ヘンリー卿、私は君が迷わずデヴォンシャーへ下るべきだと思う。ただし一点だけ条件がある。決して一人で行ってはいけない。」
「モーティマー医師も一緒に行く。」
「だが、モーティマー医師には診療があるし、家も君の邸からは遠い。どれほど親切でも、常時助けることは難しいだろう。いや、ヘンリー卿、信頼できる人物が常に君のそばにいる必要がある。」
「君自身が来ることはできないか、ホームズさん?」
「いざというときは私も必ず駆けつけるつもりだが、私自身の顧問業務や各地からの相談が絶えない現状では、無期限にロンドンを離れることは不可能だ。今も、イングランド随一の名家の名誉がゆすりで危機に瀕していて、それを止められるのは私だけだ。だから、ダートムーアに行くのはどうしても無理だ。」
「では、誰を推奨する?」
ホームズは私の腕に手を置いた。「もし私の友人が引き受けてくれるなら、困難なときにこれほど頼りになる人物はいない。私自身も自信を持って勧める。」
この提案はまったく予想外だったが、返事をする前にバスカヴィル卿が私の手を力強く握りしめた。
「いやあ、本当にありがたいよ、ワトソン先生。君なら状況も私と同じくらい把握しているし、ぜひバスカヴィル館まで来て力になってほしい。」
私は冒険の約束に強く心惹かれるたちであり、ホームズの言葉と、バスカヴィル卿が私を仲間として歓迎してくれたことに大きな喜びを感じた。
「喜んで行こう」と私は言った。「これ以上有意義な時間の使い方はないだろう。」
「そして逐一、私に詳細な報告をしてほしい」とホームズ。「いざというときには、私が指示を出す。土曜日までには全て整うだろう?」
「ワトソン先生、よろしいですか?」
「まったく問題ない。」
「では、もしも別の連絡がなければ、土曜日にパディントン発十時半の列車で会うことにしよう。」
我々は立ち上がって帰ろうとしたとき、バスカヴィルが歓声をあげ、部屋の片隅に飛び込むとキャビネットの下から茶色のブーツを取り出した。
「なくなったブーツだ!」と彼は叫んだ。
「すべての問題がこれほど容易に消えてくれるといいがな」とシャーロック・ホームズが言った。
「しかし、これは非常に奇妙なことです」とモーティマー医師が口を挟んだ。「昼食前にこの部屋は入念に調べましたよ。」
「僕も調べた。隅から隅までだ」とバスカヴィルも言った。
「あの時には確かにブーツなどなかったはずだ。」
「だとすれば、我々が昼食を取っている間にウェイターがここに置いたのだろう。」
ドイツ人の給仕が呼ばれたが、彼はその件について何も知らないと言い張り、どんな調査も解決には至らなかった。こうして、次から次へと現れる小さな謎――しかもそのどれもが一見無意味に思える――の連続に、また一つ新たな項目が加わったのである。サー・チャールズの死という陰惨な事件はひとまず脇に置いておくとしても、我々は二日という短い間に、印刷された手紙の受領、黒い顎髭のスパイの登場、茶色い新しいブーツの紛失、古い黒いブーツの紛失、そして今度は新しい茶色いブーツの返還と、不可解な出来事を次々と経験したのだった。ベイカー街への帰途、ホームズは黙してキャブに座り、私にもわかるほど思案げな表情を浮かべていた。私同様、彼もまた、これら不思議で一見無関係な出来事すべてがどう繋がるのか、懸命に考えていたのだ。午後から夜遅くまで、彼は煙草をくゆらせながら思索に没頭していた。
夕食直前になって、二通の電報が届けられた。最初のものはこうだった。
「バリモアが館にいることを今知った。バスカヴィル」
二通目はこうだ。
「指示通り二十三のホテルを回りましたが、タイムズ紙の切り抜きは見つかりません。カートライト」
「これで二つの糸口が切れたな、ワトソン。全てが不利に働く事件ほど刺激的なものはない。別の手がかりを追わねばなるまい。」
「まだスパイを乗せた御者が残っている。」
「その通りだ。私は公式登録簿から彼の名前と住所を取り寄せるよう電報を送った。これがその返事かもしれん。」
しかし、鳴らされたベルは、返事よりもさらに満足のいくものをもたらした。扉が開くと、いかにも荒っぽい風体の男が入ってきた。どうやらその人本人らしい。
「本部から、この住所の紳士が2704号について尋ねていると聞きました」と彼は言った。「私は七年このキャブをやっていますが、一度も苦情を受けたことはありません。直接ここへ来て、どんな文句があるのかお伺いしようと思いまして。」
「いや、何も君に文句などないのだ、いい人だ」とホームズが言った。「反対に、私の質問に明確に答えてくれれば、半ソブリンを進呈しよう。」
「今日は運がいいみたいですね」と御者はにっこりして言った。「どんなご用件ですか?」
「まず、君の名前と住所を聞いておこう。また必要になるかもしれないからな。」
「ジョン・クレイトン、バラのターピー街3番地です。私のキャブはウォータールー駅近くのシップリー・ヤードから出しています。」
シャーロック・ホームズはそれを書き留めた。
「さて、クレイトン。今朝十時にこの家を見張っていた客、その後リージェント街を二人の紳士とともに追った客について、すべて話してくれ。」
男は驚いたように、少しばつが悪そうにした。「まあ、私が何を話しても意味がないでしょう。だって、あんたはもう私と同じくらい知ってるみたいだ」と彼は言った。「実は、その紳士に“自分は探偵だから、誰にもこの件は話してはいけない”と言われました。」
「これは非常に深刻な問題なんだ、君。もし何か隠そうとすれば、君自身が困った立場に陥るかもしれないぞ。客は自分が探偵だと名乗ったのか?」
「ええ、そう言いました。」
「それはいつ?」
「私から降りるときです。」
「他に何か言ったか?」
「名前も名乗りました。」
ホームズは私に勝ち誇ったような素早い視線を投げた。「名前まで? それは軽率だ。何という名前だった?」
「その方の名前は、シャーロック・ホームズさん、だと。」
この返答ほど、私の友人が打ちのめされた様子を私は見たことがない。一瞬、彼は呆然として座っていたが、やがて大きく笑い出した。
「やられたな、ワトソン――完璧にやられた!」と彼は言った。「私と同じくらい素早く、しなやかな剣だ。今回は見事に一本取られた。シャーロック・ホームズと名乗ったのか?」
「ええ、そうです。それがその紳士の名前でした。」
「素晴らしい! どこでその人を拾ったのか、そしてその後の経緯を教えてくれ。」
「トラファルガー広場で九時半に呼び止められました。自分は探偵だから、今日一日私の言うことをすべて聞き、質問は一切するな、そうすれば二ギニー払うと言われまして、二つ返事で承知しました。まず、ノーサンバーランド・ホテルに行って、二人の紳士が出て来るまで待ちました。その二人がタクシーに乗ると、私たちもその後を追いました。」
「この家の前までだな」とホームズ。
「ええ、たぶんそうでしょう。ですが、私ははっきりとは分かりません。ただ、客のほうはよく分かっていたようです。道の半ばで止まり、一時間半ほど待ちました。その後、二人の紳士が歩いて通り過ぎたので、我々もベイカー街を下って――」
「分かっている」とホームズが言った。
「リージェント街の四分の三ほど行ったあたりで、私の客が屋根の窓を開けて“ウォータールー駅まで全速力で行け”と叫びました。私は馬を鞭打って、十分もかからずにつきました。二ギニーきちんと受け取って、彼は改札の中へ消えていきました。去り際に振り向いて、『君が今日一日運転したのはシャーロック・ホームズ氏だと知っておくと面白いかもしれない』と言いました。おかげで名前を覚えていた次第です。」
「なるほど。それで、その後は彼を見ていないわけだな?」
「ええ、駅に入ってからは。」
「そのシャーロック・ホームズ氏は、どんな男だった?」
御者は頭をかいた。「描写は難しいですが、年は四十くらい。背丈は中くらいで、あんたより二、三インチ低い。服装は立派で、顎髭は四角く整えられた黒で、顔色は青白かった。それ以上は思い出せません。」
「目の色は?」
「いや、それは覚えてません。」
「他に何か特徴は?」
「いえ、何も。」
「では、これが約束の半ソブリンだ。もし何か分かったら、もう一枚用意してある。おやすみ!」
「おやすみなさい、ありがとうございます!」
ジョン・クレイトンはニヤニヤしながら去り、ホームズは肩をすくめて苦笑いを浮かべ、私のほうを見た。
「これで三つ目の糸も切れて、振り出しに戻ったな」と彼は言った。「なんて抜け目ない奴だ! 我々の家の番号も、バスカヴィルが私を訪ねたことも、リージェント街で私が誰かも見抜き、私が御者の番号を控えたと推理し、ドライバーを探し出すと予想して、こんな大胆な伝言を寄越してきた。ワトソン、今回はまさに我々にふさわしい敵が現れたということだ。ロンドンでは私は完敗だ。君がデヴォンシャーでうまくいくことを祈るしかない。だが――心配なんだ。」
「何がです?」
「君を送り出すことだ。厄介な事件だよ、本当に危険な。調べれば調べるほど気が重くなる。冗談に聞こえるだろうが、誓って言うが、君が無事にベイカー街に戻ってきてくれる日が楽しみだ。」
第六章 バスカヴィル館
ヘンリー・バスカヴィル卿とモーティマー医師は、約束の日にきちんと支度を整え、予定通りデヴォンシャーへ向かうこととなった。シャーロック・ホームズも私とともに駅まで見送りに来て、最後の忠告と助言を与えてくれた。
「君の考えや疑いを暗示することは控えよう、ワトソン。事実をできる限り詳細に報告してくれればいい。推理は私に任せておいてくれ。」
「どんな事実を報告すればいい?」
「事件に何らかの関連があると思えば、それが遠回りに見えてもすべて――特に若いバスカヴィルとその隣人たちとの関係や、サー・チャールズの死に関する新しい情報が重要だ。ここ数日、私なりに調査したが、どうも成果は芳しくなかった。確かなことはひとつだけ、次の相続人であるジェームズ・デズモンド氏は温厚な老人で、彼がこの迫害の首謀者ではないということだ。彼は疑いから除外していいだろう。残るは、実際にバスカヴィル卿を取り巻く人々だ。」
「まずバリモア夫妻を追い払うべきでは?」
「とんでもない。それは大きな過ちだ。もし彼らが無実であれば、ひどい不正義となるし、有罪ならば証拠を掴む機会を失う。容疑者リストから外してはならない。それから館には馬丁もいたはずだ。荒野には農場主が二人。モーティマー医師は誠実な人物だと私は信じているが、彼の奥さんについては何も知らない。自然科学者のステープルトン氏と、評判では魅力的な妹もいる。ラフター館のフランクランド氏もまだ未知数だし、他にも一、二人の隣人がいる。これらの人々が君の特別な研究対象だ。」
「全力を尽くします。」
「武器は持っているだろうな?」
「ああ、念のために。」
「それがいい。リボルバーは昼夜問わず近くに置き、決して警戒を怠らないように。」
仲間たちはすでに一等車を確保し、プラットホームで我々を待っていた。
「いいえ、何の進展もありません」とモーティマー医師はホームズの質問に答えた。「一つだけ確かに誓えるのは、この二日間、誰にも尾行されていなかったということです。外出するたび、細心の注意を払っていましたから、誰かいたら絶対に見逃さなかったはずです。」
「常に一緒に行動していたのですか?」
「昨日の午後以外は。私は町に来たときは、一日は完全に遊びにあてることにしているので、博物館で過ごしました。」
「私は公園の人々を見に行った」とバスカヴィルが言った。
「でも、何も問題ありませんでした。」
「それでも、軽率でしたよ」とホームズは首を振り、険しい顔で言った。「バスカヴィル卿、どうか単独で出歩かないでください。もしそうすれば大きな不幸があなたを襲うでしょう。他のブーツは見つかりましたか?」
「いえ、もう永遠に失われたままです。」
「そうか、それは興味深い。では、さらばだ」と列車がホームを滑り出し始めるとホームズは続けた。「あの奇妙な伝説の一節を心に留めて、暗い時間帯には荒野に近づかないように。」
プラットホームが遠ざかる中、私はホームズの背の高い、厳格な姿が静かにこちらを見送っているのを振り返って見た。
旅程は快適であっという間に過ぎ、私は同行する二人とより親密になり、モーティマー医師のスパニエルと遊んだりして過ごした。数時間も経たぬうちに、茶色かった大地は赤みを帯び、レンガの建物は花崗岩に変わり、赤い牛が生い茂る草に囲まれた牧草地に草を食んでいた。豊かな、だが湿気の多い気候を物語る、青々とした草と繁茂する植生だった。若きバスカヴィル卿は窓から外を熱心に見つめ、懐かしいデヴォンの景色を認めては歓声をあげていた。
「私がこの土地を離れて以来、世界中を見てきましたが、これに比べられる場所はありません、ワトソン博士」と彼は言った。
「デヴォンシャーの男で、自分の郷土を誇らない者はいないようだね」と私は言った。
「それは土地よりも人間の資質に依るところが大きい」とモーティマー医師が言った。「この友人の丸みを帯びた頭を見れば、内にケルトの情熱と忠誠心を秘めているのが分かる。気の毒なサー・チャールズの頭は、珍しい型で、ゲールとアイヴァンの特徴が半々だった。ところで、バスカヴィル館に最後に行ったときは、君は若かったのでは?」
「父の死のときはまだ十代で、館を見たことはありません。父は南海岸の小さな家に住んでいましたから。その後すぐ友人を頼ってアメリカへ渡ったので、実を言うと、ワトソン博士と同じくらい私にも全てが新しいのです。荒野を見るのが本当に楽しみでなりません。」
「それならもうすぐ願いがかなうよ。あれが荒野の最初の眺めだ」とモーティマー医師が窓の外を指差した。
緑の田園と低い林の向こうに、遠く灰色の哀愁漂う丘が不思議なギザギザの頂をのぞかせ、夢の中の風景のように朧げに見えた。バスカヴィルは長い間、そこから目を離さぬまま座っており、その顔に、この奇妙な土地への思いの深さが表れていた。長きに渡り先祖が支配し、深い爪痕を残したその地を、ついに初めて目にしたのだ。ツイードの服にアメリカ訛り、無骨な鉄道車両の一隅にいても、彼の表情からは、気高く、激しく、誇り高い血筋の正統な継承者ぶりがありありと感じられた。その太い眉、敏感な鼻孔、大きなへーゼル色の瞳には、誇りと勇気、強さが宿っていた。もしあの荒涼たる荒野で困難で危険な探索が待ち受けていたとしても、彼はきっと共に危険を分かち合ってくれる頼もしい相棒となるだろう。
列車は小さな田舎の駅に止まり、我々は降り立った。低い白い柵の外には、二頭立ての四輪馬車が待っていた。我々の到着は大きな出来事のようで、駅長やポーターたちが手荷物運びに寄ってきた。素朴で美しい田舎の景色に心和まされたが、門の脇には軍服姿の屈強な男が二人、短銃を手に立ち、我々を鋭く観察しているのが目に留まった。御者はごつごつとした顔をした小柄な男で、ヘンリー・バスカヴィル卿に敬礼すると、すぐに馬車は白い広い道をすべるように走り出した。道の両脇に緩やかに広がる牧草地、古い切妻屋根の家々が濃い緑の葉陰から顔をのぞかせていた。しかし、平和で日の差し込む田園の背後には、夕暮れ空を背景に、長く暗い荒野の稜線が、ギザギザと不気味な丘を従えてそびえていた。
馬車は脇道に入り、何世紀も車輪に削られた深い小路を登っていく。両側の高い土手には、しっとりと濡れた苔や肉厚のチャセンシダが覆い、枯れ葉色のシダや斑入りの野イチゴが沈む夕日に輝いていた。道はなおも上り坂が続き、狭い花崗岩の橋を渡り、灰色の岩の間を泡立ちながら流れる賑やかな小川に沿って進んだ。道も川も、雑木やモミの生い茂った谷を曲がりくねりながら遡っていく。バスカヴィルは歓声をあげて周囲を見回し、次々と質問を投げかけていた。彼の目に映るもの全てが美しく思えたようだが、私には秋の訪れを感じさせる一抹の哀愁が漂っているように思えた。黄色い葉が小路を覆い、我々の通過とともに舞い落ちてくる。車輪の音は、腐りかけた草が積もる道に吸い込まれて消える。――まるで自然が、バスカヴィル家の後継者の帰還を哀しげに迎えているように思えた。
「おや!」とモーティマー医師が声を上げた。「これは何だ?」
荒野の一角、ヒースに覆われた急な丘が我々の前に現れた。その頂上には、台座の上の騎馬像のように、乗馬した兵士が銃を構えて険しい表情で立っていた。道を行く我々を監視しているのだ。
「これはどういうことだ、パーキンス?」とモーティマー医師が尋ねた。
御者は半身を返して言った。「プリンスタウンから脱獄囚が出てましてね。三日ほど前からで、監視員が道という道、駅という駅を見張ってますが、まだ見つかってません。農家の人たちは皆、不安がっていますよ、実際。」
「情報を提供すれば五ポンドもらえるんだろう?」
「ええ、でも五ポンドのために命の危険を冒すのもね。普通の囚人じゃないんで。奴はどんなことでもしでかす男です。」
「そいつは誰なんだ?」
「セルデン、ノッティング・ヒルの殺人鬼です。」
私はその事件をよく覚えている。なぜなら、ホームズがその犯罪の異様な残忍さと、犯人のすべての行動に見られた無意味な残虐性に興味を抱いたからだった。死刑が減刑されたのは、彼の完全な正気に疑問があったためであり、それほどまでに彼の振る舞いは凄惨だった。私たちのワゴネットは丘を登りきり、目の前には広大な荒野が広がっていた。ねじれた岩塚やごつごつした岩山が点在している。冷たい風がそこから吹き下ろし、私たちは身震いした。あの荒涼とした平原のどこかに、あの凶悪な男が野獣のように穴に潜み、彼を社会から追放した人々すべてに対する憎しみで心を満たしながら隠れているのだ。荒れ果てた荒野、身を切るような風、そして薄暗い空と、この恐ろしい雰囲気を完成させるのに、これ以上の要素は必要なかった。バスカヴィルさえも黙り込み、コートの襟をきつく引き寄せた。
私たちは肥沃な土地を後ろに、そして足元に置いてきた。今振り返ると、傾いた陽の光が小川を金色の糸に変え、耕されたばかりの赤土や広がる森の絡み合いに輝きを与えていた。これから進む道は、巨大なすす色やオリーブ色の斜面を抜けて、ますます荒々しくなり、巨石が点在していた。ときおり、石造りの壁と屋根でできた荒野のコテージが現れたが、蔦ひとつ絡まることもなく、その厳しい輪郭を和らげてはいなかった。突然、私たちは下方に杯のようなくぼ地を見下ろした。そこには、長年の嵐でねじれ曲がった低木のオークやモミがまばらに生えていた。木々の上に高く細い二つの塔がそびえていた。御者が鞭で示した。
「バスカヴィル館です」と彼は言った。
主人は立ち上がり、頬を紅潮させ、瞳を輝かせてじっと見つめていた。数分後、私たちはロッジの門に到着した。そこは、鍛鉄製の幻想的な透かし模様が迷路のように張り巡らされ、両脇の風雨にさらされた柱には地衣類が斑点のように付き、バスカヴィル家の猪の頭が頂に飾られていた。ロッジは黒い花崗岩の廃墟で、梁がむき出しになっていたが、その向かいには新しい建物が半分だけ建設されており、これはサー・チャールズが南アフリカで得た金の最初の成果であった。
門をくぐると並木道に入り、車輪の音は再び葉の上でかき消され、古い木々が枝を伸ばし、私たちの頭上に陰鬱なトンネルを作っていた。バスカヴィルは長く暗いドライブの先に、幽霊のように遠く霞む館を見上げて身震いした。
「ここでですか?」彼は低い声で尋ねた。
「いや、違う。イチイの並木道は反対側にある」
若き後継者は暗い顔であたりを見回した。
「こんな場所なら、伯父が不吉な予感に襲われたのも無理はない」と彼は言った。「誰だって怖くなるさ。半年もすればここに電灯をずらりと並べて、ホールのドアの前には一千カンデラのスワンとエジソンを灯して、まるで別世界のようにしてやるつもりだ」
並木道は広い芝生に開け、その向こうに館があった。薄暗くなり始めた光の中、中央部は重厚な建物で、その前にポーチが突き出しているのが見えた。正面はすべてツタで覆われ、窓や紋章に遮られて一部だけ刈り込まれていた。中央のブロックからは、古びた、胸壁付きで多数の銃眼が開けられた双塔がそびえていた。塔の両側には、より新しい黒い花崗岩の翼棟が続いている。重々しい格子窓から鈍い明かりが漏れ、高く急な屋根からは煙突が突き出し、その一つから黒い煙が一本立ち上っていた。
「ようこそ、サー・ヘンリー! バスカヴィル館へお帰りなさい!」
背の高い男がポーチの影から現れ、ワゴネットのドアを開けた。館内の黄色い光を背にした女性の姿も見える。彼女も出てきて、荷物を降ろすのを手伝った。
「まっすぐ家に帰ってもよろしいですか、サー・ヘンリー?」とモーティマー医師が言った。「妻が待っているもので」
「ぜひ夕食を共にしていかれては?」
「いえ、どうしても帰らねば。きっと何か仕事が待っているでしょう。館内を案内したいところですが、バリモアの方がよい案内役になります。何かあれば遠慮なく昼夜を問わずお呼びください。では失礼します」
車輪の音が並木道の奥へと消えていき、サー・ヘンリーと私は館に入り、重々しい音を立てて扉が閉まった。私たちがいたのは、広く高い天井で、年季の入った黒ずんだオーク材の太い梁が渡る、堂々とした部屋だった。大きな古風の暖炉には、背の高いアイアンドッグ(薪受け)の背後で薪がパチパチと燃えていた。長旅ですっかり体が冷え切っていた私とサー・ヘンリーは、手を暖炉にかざした。それから、古いステンドグラスの高い細長い窓や、オークの壁板、鹿の頭部、壁の紋章などを見回した。中央のランプのほの暗い光の中、すべてが薄暗く沈んで見えた。
「まさに想像していた通りの館だ」とサー・ヘンリーは言った。「まさしく古い名家の家そのものではないか。五百年もの間、先祖たちがここで暮らしてきたかと思うと、なんとも厳かな気持ちになるよ」
彼が館内を見回す顔には、少年のような熱意が浮かんでいた。彼の立つ場所には光が当たっていたが、壁には長い影が垂れ下がり、まるで黒い天蓋のように彼の頭上に覆いかぶさっていた。バリモアは荷物を部屋に運び終え、今は私たちの前に控えめな態度で立っていた。彼は背が高く、立派な容貌で、黒く四角いひげと蒼白な高貴な顔立ちが印象的だった。
「すぐにご夕食をお出ししましょうか?」
「もう用意できているのか?」
「あと数分でございます。お部屋にはお湯もご用意しております。私ども夫婦は、サー・ヘンリー様が新たなご手配をなさるまで喜んでお仕えいたしますが、新しい状況ではこの館には相応の使用人が必要だということをご理解いただければと存じます」
「新しい状況とは?」
「サー・チャールズ様は非常に隠遁的な日々を送っておられ、私ども二人で十分お世話ができました。しかし、サー・ヘンリー様はより賑やかなご生活を望まれるでしょうから、使用人の体制も変える必要がございます」
「つまり、ご夫婦で辞めたいと?」
「サー・ヘンリー様のご都合の良い時に、という意味でございます」
「しかし、あなた方のご家族は何世代にもわたりこの家に仕えてこられたのでは? この場所で新たな生活を始めるにあたって、古い家系の縁を絶つのは残念だ」
執事の蒼白な顔に、私は一瞬、感情の兆しを見た気がした。
「私も同じ気持ちですし、妻もそうでございます。しかし正直申し上げますと、私どもはサー・チャールズ様に深い愛着があり、彼の死は大きな衝撃となり、この館にいること自体が非常に辛くなってしまったのです。もう、このバスカヴィル館で心安らかに過ごせることはないと思います」
「では、今後はどうするつもりなのか?」
「きっと何か商売を始めることができるでしょう。サー・チャールズ様のご厚意で、そのための資金もいただいております。では、今お部屋にご案内いたします」
古いホールの上部には四角い手すり付きのギャラリーが巡らされ、両側の階段で上がることができた。その中央から二つの長い廊下が建物の端まで延びており、そこからすべての寝室が開いていた。私の部屋はバスカヴィルと同じ棟で、ほとんど隣り合わせだった。これらの部屋は館の中央部よりずっと新しい造りで、明るい壁紙とたくさんのろうそくが、到着時に感じた陰鬱さをいくらか和らげていた。
しかし、ホールに面した食堂は、まるで陰と暗さに包まれていた。長い部屋で、一段高くなった家族席と、その下の従者席とが分かれており、一方の端には楽士のためのギャラリーが見下ろしていた。黒い梁が頭上を横切り、その向こうには煙で黒ずんだ天井が広がっていた。列をなした松明が燃え、かつての宴の色彩と賑わいがあれば雰囲気も和らいだだろう。しかし今は、二人の黒服の紳士が、シェードのかかったランプの小さな輪の中に座っているだけで、声も低くなり、気分もしずんでしまった。エリザベス朝の騎士からリージェンシー時代の伊達男まで、あらゆる服装の先祖たちが壁に並び、無言で私たちを見下ろしている。その静かな同伴者たちに威圧され、私たちはほとんど口もきかず、食事が終わって新しいビリヤード室で煙草を吸えるのがありがたかった。
「いや、本当に陽気な場所じゃないな」とサー・ヘンリーは言った。「そのうち慣れるだろうが、今はまったく場違いな感じだよ。伯父が一人でこんな家にいたら、神経質になるのも無理はない。まあ、君がよければ今夜は早く寝て、明日はもう少し明るく感じるかもしれないな」
私は寝る前にカーテンを少し開け、窓から外を見た。窓は館の玄関前の芝生に面していた。その先では、木立が風に揺れ、うめくような音を立てていた。雲間を半月がすばやく横切り、その冷たい光の下、木々を越えて、岩の切れ端と、もの悲しく低く続く荒野の稜線が見えた。私はカーテンを閉じ、その印象が全体の雰囲気と実に調和していると感じた。
だが、それが本当の「最後の印象」ではなかった。私は疲れているのに眠れず、寝返りを打っては眠ろうとしたが、どうしても眠りが訪れなかった。遠くで時を告げる時計の音が響いていたが、それ以外は死のような静けさが館を包んでいた。そして、まさに夜半の静寂の中、私の耳に、はっきりと紛れもない音が聞こえてきた。それは、女性のすすり泣く声、どうにもならない悲しみに引き裂かれ、押し殺すような嗚咽だった。私はベッドに起き上がり、注意深く耳を澄ました。音は遠くからではなく、確かに館の中からだった。私は神経をはりつめて三十分ほど待ったが、再び聞こえてきたのは時計の音と、壁のツタが風に擦れる音だけだった。
第七章 メリピット館のステープルトン一家
翌朝の新鮮な美しさは、私たち二人の心に前夜バスカヴィル館で受けた陰鬱で灰色の印象をいくらか和らげてくれた。朝食の席につくと、日の光が高い格子窓から差し込み、窓を覆う紋章から水のような色彩の斑点を床に投げていた。暗かった壁のパネルも金色の光で青銅のように輝き、とても前夜あれほどまでに私たちの心を沈ませた部屋とは思えなかった。
「原因は館じゃなくて、僕たち自身だったんだな」バロネットは言った。「旅で疲れていて、馬車で冷え切っていたから、どうしても暗い気分になってしまったんだ。今は元気になったし、また明るく感じるよ」
「いや、単なる気分の問題だけではなかったと思う」と私は答えた。「たとえば、あなたは夜中に女性がすすり泣く声を聞きませんでしたか?」
「それは妙だな。半分眠っている時、確かにそんな声を聞いたような気がした。しばらく待ってみたが、それきりだったので夢かと思ったよ」
「私ははっきりと聞いたし、確かに女性のすすり泣きだったと思う」
「すぐにでもそのことを聞いてみよう」彼は呼び鈴を鳴らし、バリモアにその経験について尋ねた。執事の蒼白な顔が、問いを聞いた途端、さらに青ざめたように見えた。
「館にいる女性は二人だけです、サー・ヘンリー」彼は答えた。「ひとりは皿洗いの娘で、別棟で寝ています。もうひとりが私の妻ですが、彼女からそのような声が出たとは断言できます」
だがこれは嘘だった。なぜなら、朝食後、私は長い廊下でバリモア夫人とすれ違い、その顔全体に朝日が当たっているのを見たからだ。彼女は体格のよい無表情な女性で、口元には厳しい決意が刻まれていた。しかし、その目だけは腫れぼったく赤く、私を見つめた。夜、泣いていたのは彼女だった。そして、夫がそれを知らないはずがない。それなのに、ばれる危険を承知で否定したのはなぜか。そして、なぜ彼女はあれほどまでに深く泣いたのか。すでにこの蒼白で立派な黒ひげの男のまわりには、謎と陰の気配が漂い始めていた。サー・チャールズの遺体を最初に発見したのも彼だったし、老人の死の経緯も、彼の説明に頼るしかなかった。結局、リージェント街の馬車で私たちが見かけたのはやはりバリモアだったのだろうか。ひげの感じはよく似ている。御者はもっと背の低い男だったと言っていたが、その程度の印象違いは十分あり得る。いずれにしろ、まずはグリムペンの郵便局長に会い、「偽電報」が本当にバリモア本人の手に渡ったのか確かめるのが先決である。いかなる答えであろうと、少なくともシャーロック・ホームズに報告すべき材料は得られるだろう。
朝食後、サー・ヘンリーにはたくさんの書類があったので、今が出かける好機だった。荒野の端に沿って四マイル歩くと、小さな灰色の村に着いた。そこには二つほど大きな建物があり、それが宿屋とモーティマー医師の家だった。郵便局長はこの村の食料品店主でもあり、電報をはっきり覚えていた。
「確かに電報はバリモアさんに指示通りお届けしました」
「誰が届けたのですか?」
「うちの息子です。ジェームズ、おまえが先週、バスカヴィル館のバリモアさんに電報を届けたな?」
「はい、お父さん。届けました」
「本人に直接渡したのか?」
「いえ、そのときバリモアさんは屋根裏にいたので、直接ではなくバリモア夫人に渡して、すぐに届けると約束されました」
「バリモアさんを見かけたのか?」
「いいえ、屋根裏にいると聞きましたので」
「見ていないのに、なぜ屋根裏にいると分かった?」
「そりゃ、奥さんが言うんですから。電報が届かなかったならバリモアさんご本人が文句を言うでしょうよ」
これ以上追及しても無駄のようだった。しかし、ホームズの策略にもかかわらず、バリモアがロンドンにいなかったという証拠は何も得られなかった。もし仮に、サー・チャールズの最期に会ったのも新しい相続人をつけ回しているのも同じ男だったとしたら――それはどういう意味なのか? 他人の手先なのか、あるいは何か邪悪な目的を持っているのか? バスカヴィル家を苦しめることで彼にどんな得があるのか? 私は『タイムズ』紙の社説の切り抜きによる奇妙な警告を思い出した。それが彼の仕業なのか、あるいはその計画を阻止しようとする別の誰かのものなのか? 考え得る唯一の動機はサー・ヘンリーが示唆したように、もし一家を怖がらせて追い出せば、バリモア夫妻にとって安定した新しい住まいが得られるというものだった。しかし、その説明では、この若いバロネットを取り巻く、複雑で巧妙な陰謀の説明には到底足りないはずだ。ホームズ自身が、彼の数々の難事件の中でもこれほど入り組んだものはないと言っていた。私は、灰色で寂しい道を帰りながら、友人が一刻も早く手すきになり、この重荷を肩代わりしてくれることを祈った。
ふいに、私の思索は背後から駆け寄る足音と、自分の名を呼ぶ声に遮られた。私はモーティマー医師かと思って振り返ったが、驚いたことに見知らぬ男が追いかけてきていた。彼は小柄で、すらりとしていて、髭はなく、きちんとした顔立ち、亜麻色の髪に痩せた顎、年の頃は三十代から四十くらいで、灰色のスーツ、ストローハットをかぶっていた。肩には植物標本用のブリキ箱を下げ、緑色の蝶捕り網を片手に持っていた。
「突然お声掛けして失礼します、ワトソン先生」彼は息を切らせて近づいてきた。「この荒野では、私たちは打ち解けた者どうしですから、正式な紹介を待つことはありません。モーティマー先生から私の名を聞いたことがあるかもしれません。私はメリピット館のステープルトンです」
「その網と箱で察しはつきました」と私は言った。「ステープルトン氏が博物学者であると知っていましたので。しかし、私をどうやってご存知に?」
「モーティマー先生の診療所を訪ねていたとき、窓から通りかかるあなたを指さしてくださったのです。道が同じ方向でしたので、追いかけて自己紹介しようと思いました。サー・ヘンリー様のお加減はいかがですか?」
「とてもお元気ですよ」
「サー・チャールズの悲劇的な死後、新しいバロネットがこちらに住むのを拒まれるのではと皆心配していました。裕福な方がこんな場所に隠れて暮らすようなものですからね。ですが、こちらの田舎にとっては非常に大きな意味があります。サー・ヘンリー様はこの件について、迷信じみた恐れはお持ちではないでしょうか?」
「そのようなことはないと思います」
「もちろん、家系に付きまとう魔犬伝説はご存知でしょう?」
「ええ、聞いています」
「このあたりの農民がいかに信じやすいか、まったく驚くべきことだ! あの荒野でそんな怪物を見たと断言する者が、何人もいるんだよ。」
彼は微笑みながらそう言ったが、その目つきには、これをもっと真剣に受け止めている気配が読み取れた。
「この話はサー・チャールズの想像力を強くとらえ、私はそれが彼の悲劇的な最期につながったのだと疑っていない。」
「どうしてそんなことに?」
「彼はひどく神経が高ぶっていたから、どんな犬の姿でも、彼の病んだ心臓には致命的な影響を与えかねなかった。私は、あの最後の夜、イチイの並木道で、本当に何かその手のものを見たのだと思っている。私はあの老人が大好きだったので、何か災難が起こるのではないかと心配していたし、彼の心臓が弱いことも知っていた。」
「どうしてそれを知っていたんだ?」
「友人のモーティマーが教えてくれた。」
「つまり、あなたはサー・チャールズが犬に追いかけられ、その結果恐怖で死んだと考えているのか?」
「他にもっと納得できる説明があるかい?」
「私はまだ結論に達していない。」
「シャーロック・ホームズ氏はどうだ?」
その言葉に、一瞬息を呑んだが、同伴者の平静な顔と揺るぎない瞳を見て、驚かせる意図はないと察した。
「私たちがあなたのことを知らないふりをしても無駄だ、ワトソン博士」と彼は言った。「あなたの探偵の活躍はここにも伝わっているし、彼を有名にすれば自分も知られてしまうものだ。モーティマーがあなたの名前を教えてくれたとき、彼も否定できなかった。あなたがここにいるということは、シャーロック・ホームズ氏もこの件に興味を持っているはずで、彼がどのように考えているのか知りたくて仕方がないのだ。」
「申し訳ないが、その問いにはお答えできない。」
「彼自身が我々を訪ねてくださる予定はあるのだろうか?」
「今は街を離れられない。他にも手がけている事件がある。」
「それは残念だ! 彼なら我々にとって謎でしかないことに何らかの光を当ててくれるかもしれないのに。しかしあなた自身の調査について、私が少しでもお役に立てることがあれば、遠慮なくご指示いただきたい。もし、あなたの疑念の内容や事件の調査方法のごく一端でも示していただけるなら、今すぐにでも助言や手助けができるかもしれない。」
「私はただ友人のヘンリー卿を訪ねているだけで、特に助力は必要としていないとお約束する。」
「それは結構なことだ!」とステープルトン氏は言った。「用心深く慎重でいるのはまったく正しい。軽率な詮索をしてしまったこと、お詫びする。もうこの件には二度と触れないと約束しよう。」
私たちはちょうど、道から細い草道が分かれて荒野を横切る地点にたどり着いた。右手には急で岩がごろごろした丘があり、かつては花崗岩の採石場だった場所だ。その正面は暗い崖になっており、そこかしこにシダやイバラが生い茂っている。遠くの小高い丘の向こうからは、灰色の煙がふわりと上がっていた。
「この荒野道を適度に歩けば、メリピット館に着きます」と彼は言った。「もしよければ、妹を紹介させていただきたいので、少しお時間をいただけませんか。」
私はまず、ヘンリー卿のそばにいるべきではないかと思った。しかし、そのとき卿の書斎の机には書類や請求書の山が散乱していたのを思い出した。私がそれに役立つはずもないし、ホームズからも、近隣住民の観察を命じられていた。私はステープルトン氏の誘いを受け、二人でその道を歩き始めた。
「この荒野は本当に素晴らしい場所だ」と彼は、波打つ丘陵と、鋭い花崗岩の峰が奇妙な波頭のように現れる長い緑のうねりを見回しながら言った。「荒野には飽きることがない。どんな秘密が隠されているか想像もつかないほどだ。広大で、荒涼としていて、神秘的だ。」
「よく知っているのか?」
「ここに来てまだ二年だ。地元の住民から見れば新参者だろう。サー・チャールズが根を下ろしたすぐ後にやってきた。しかし、私の好奇心がこのあたりを隅々まで探検させたし、私より詳しい者はほとんどいないと思う。」
「習得は難しいのか?」
「とても難しい。たとえば、あの北の大平原を見てほしい。あちこちから奇妙な丘が突き出ている。何か気づくことはあるか?」
「全速力で駆けるには絶好の場所だ。」
「普通そう考えるだろうが、その考えで命を落とした者も何人もいる。あの明るい緑の点々が見えるか?」
「ああ、他より肥沃に見えるな。」
ステープルトン氏は笑った。「あれが大グリムペン湿地だ。一歩でも踏み誤れば、人でも獣でも死が待っている。昨日も湿地に迷い込んだポニーを見た。二度と出てこなかった。しばらくの間、泥穴から首をもたげていたが、ついには吸い込まれてしまった。乾季でも渡るのは危険だが、この秋の雨の後では恐ろしい場所だ。それでも私は、中心部まで入って生きて戻ってこられる。おや、またあの哀れなポニーが!」
茶色いものが緑のスゲの間で転げ回っていた。やがて長く苦しげにのたうつ首が伸び上がり、恐ろしい悲鳴が荒野に響き渡った。その声は私をぞっとさせたが、同行者は私よりずっと神経が強いようだった。
「もう終わりだ」と彼は言った。「湿地が飲み込んだ。これで二日連続だ。多分もっとたくさんいる。乾季にはあそこを通る癖がついていて、湿地がその獲物を捕らえるまで違いに気づかない。あれが大グリムペン湿地という悪所さ。」
「それでも君は中に入れるのか?」
「ああ、ごく活発な人間なら通れる道が一、二本ある。私はそれを見つけた。」
「なぜそんなおそろしい場所に入る必要がある?」
「向こうの丘が見えるだろう? あれはすべて、越えられない湿地によって四方を切り離された島みたいなものだ。年月をかけて湿地があの丘を取り囲んだ。その中に、珍しい植物や蝶がいる。たどり着ける知恵があれば、の話だ。」
「いつか運試しに行ってみたくなるな。」
彼は驚いた顔で私を見た。「頼むからそんな考えは捨ててくれ」と彼は言った。「もしあなたが死んだら、私の責任だ。生きて戻る望みなどまったくない。私は複雑な目印を覚えているからできるだけだ。」
「おや、あれは何だ?」と私は叫んだ。
長く低い、言葉では言い表せないほど哀しいうめき声が荒野を渡ってきた。空気全体がその音に満たされ、どこから来たのかはまったく見当がつかなかった。鈍くかすかなうねりが、やがて深い轟きになり、再び悲しげに脈打つざわめきへと戻った。ステープルトン氏は奇妙な表情で私を見た。
「変わった場所だろう、荒野は。」
「でも、あれは何だ?」
「農民たちは、バスカヴィル家の猟犬が獲物を呼んでいるのだと言っている。私も何度か聞いたことがあるが、今夜ほど大きな声は初めてだ。」
私は恐怖を覚えながら、緑の草むらが斑点のように広がる広大な平原を見回した。何も動くものはなかった。ただ、私たちの背後のトーからカラスが二羽、騒がしく鳴いていた。
「あなたは教養のある方だ。あんな馬鹿げたことを信じているわけではないだろう?」と私は言った。「あの奇妙な音の原因は何だと思う?」
「湿地は時々不思議な音を立てる。泥が落ち着いたり、水が湧いたり、いろいろだ。」
「いや、あれは生き物の声だった。」
「そうかもしれない。ヨシゴイの鳴き声を聞いたことがあるか?」
「いや、一度も。」
「イギリスでは今やほとんど絶滅した鳥だが、荒野では何でも起こりうる。あれが最後のヨシゴイの鳴き声だったとしても、私は驚かない。」
「今まで聞いた中で最も不気味で奇妙な音だった。」
「ああ、荒野自体が不気味な場所だ。あそこの丘の斜面を見て、ごらん。あれをどう思う?」
急な斜面全体に、灰色の円形の石の輪が幾つも――少なくとも二十はあった。
「あれは何だ? 羊の囲いか?」
「いや、あれは我々のご先祖の住まいだ。先史時代の人間が荒野に密集して住んでいた。その後、特に住んだ者もいないから、彼らの生活の痕跡がそのまま残っている。屋根のないウィグワム(テント小屋)さ。中に入れば炉や寝床の跡も見えるだろう。
「まるで町みたいだ。いつの時代のものなんだ?」
「新石器時代――正確には不明だ。」
「彼らは何をしていた?」
「この斜面で家畜を飼い、青銅の剣が石斧に取って代わろうとしたころ、錫鉱の採掘も覚えた。向かいの丘の大きな溝を見ろ。あれがその証拠だ。ええ、この荒野には非常に変わった点が多いのですよ、ワトソン博士。おっと、失礼、ちょっとお待ちください。あれはきっとキクロピデスだ。」
小さなハエか蛾が私たちの前を横切り、ステープルトン氏はいきなり驚異的な俊敏さでそれを追いかけ始めた。哀れなことに、虫はそのまま大湿地の方へ真っすぐ飛んでいき、氏も一瞬もためらうことなく、草の塊から塊へと跳ね渡りながら緑の網を振り回して追いかけていった。灰色の服と、ぎくしゃくと不規則にジグザグに進む姿は、まるで巨大な蛾のようだった。私はその驚異的な活発さに感心しつつも、あの裏切りやすい湿地で足を滑らせないかと不安を抱きながら見守っていた。すると背後で足音がし、振り返ると女性が道のそばに立っていた。彼女はメリピット館の方角――煙の立ちのぼる方向――から現れたが、荒野のくぼみがあったため、近づくまで姿は見えなかった。
この女性が、例のミス・ステープルトンに違いないと私は思った。なにしろ、この荒野に女性はほとんどいないし、彼女が美人だと誰かが言っていたのを思い出していた。実際、彼女はまさしく美しく、しかも極めて珍しいタイプだった。兄のステープルトン氏が明るい髪と灰色の瞳で中間色の容貌なのに対し、彼女はイングランドではまず見かけないほど色黒で、スリムで上品、そして長身だった。誇り高く整った顔立ちは、感情が表れていなければ無表情にすら見えただろうが、繊細な口元と美しい黒い瞳が熱い感情を示していた。完璧なプロポーションと上品な服装、孤独な荒野の小径に現れた彼女は、まるで幻のようだった。私が振り返ると、彼女は兄を見つめていたが、すぐに私の方へ速足で近づいてきた。私は帽子を上げ、何か説明をしようとしたが、彼女自身の言葉が私の考えをすっかり変えてしまった。
「戻りなさい!」と彼女は言った。「今すぐロンドンへ、すぐに。」
私はただ呆然と彼女を見つめるしかなかった。彼女の目は燃えるようで、いらだった足取りで地面を叩いていた。
「なぜ戻らねばならないのです?」
「説明はできません。」彼女は低く熱心な声で、少し舌足らずな話し方だった。「でも、お願いですから私の言うことを聞いてください。戻って、二度とこの荒野に足を踏み入れないで。」
「でも私は来たばかりなんです。」
「あなた、あなた!」と彼女は叫んだ。「忠告があなた自身のためだと分からないのですか? ロンドンへ戻って! 今夜にも! どんな手段を使ってでもここから去って! 静かに、兄が来ます! 今言ったことは口外しないで。あそこのトクサの間にあるランを摘んでくださいますか? この荒野にはランが豊富なのですが、残念ながら今はちょっと時期が遅いのです。」
ステープルトン氏は追跡をあきらめ、息を切らし顔を紅潮させて戻ってきた。
「やあ、ベリル」と彼は言ったが、その挨拶の調子はあまり親しげとはいえなかった。
「まあ、ジャック、とても暑そうね。」
「ああ、キクロピデスを追いかけていたんだ。珍しくて、秋も終わりになると滅多に見つからないんだ。逃してしまったのは残念だ!」彼は気にも留めていない様子だったが、小さな明るい瞳は頻繁に彼女と私の間を行き来していた。
「もう自己紹介は済んだようだね。」
「ええ。私はヘンリー卿に、この時期では荒野の本当の美しさを味わうには少し遅いと話していました。」
「ところで、君はこの方を誰だと思っている?」
「きっとヘンリー・バスカヴィル卿でしょう。」
「いいえ、違うのです」と私は言った。「ただの庶民ですが、彼の友人です。私の名はワトソン博士です。」
彼女の表情に、困惑の赤みがさっと走った。「話がかみ合っていなかったようですね」と彼女は言った。
「それほど長くは話していなかったろう」と兄が、相変わらず探るような目つきで言った。
「ワトソン博士が住人だと思い込んで話しました。しかし、彼にはランの見ごろかどうかはあまり関係ありませんね。でも、よろしければご一緒にメリピット館をご覧になりませんか?」
少し歩くと、目的の家へたどり着いた。荒野の真ん中に建つ寒々とした家で、かつては牧畜業者の農家だったものだが、改修され現代的な住宅になっていた。果樹園で囲まれていたが、荒野特有でどの木も矮小で弱々しく、全体として侘しさと寂しさが漂っていた。出迎えたのは奇妙にやせこけ、錆びた服を着た年老いた召使いで、家の雰囲気にぴったりだった。しかし中は広々とした部屋があり、そこには女性のセンスだと分かる上品な調度が並んでいた。窓から果てしなく広がる花崗岩混じりの荒野を眺めると、なぜこんな教養ある男と美しい女性がこんな場所で暮らしているのか、ただ驚くばかりだった。
「変わった場所を選んだだろう?」と彼は、私の考えを見透かしたように言った。「でも、私たちはそれなりに幸せにやっているよね、ベリル?」
「ええ、十分幸せです」と彼女は言ったが、その言葉には確信がなかった。
「私は学校をやっていたんだ」とステープルトン氏は言った。「北部の地方だった。私の性格には単調で面白みに欠けていたが、若者たちと共に過ごし、彼らの心を育て、自分の人格や理想を刻み込む機会はとても貴重だった。しかし運命は私たちに味方しなかった。学校で深刻な疫病が発生し、三人の少年が亡くなった。その打撃から立ち直れず、多くの資産も取り返しがつかなくなった。しかし、少年たちとの楽しい交流がなくなったこと以外は、むしろ不遇を喜べるくらいだ。私は植物学や動物学が大好きで、ここには無限の研究の場がある。妹も私と同じくらい自然を愛している。すべて、ワトソン博士、あなたが窓から荒野を眺めていた表情から、こんな話になったのです。」
「確かに、少し退屈なのではないかと思いました――あなたではなく、むしろ妹さんにとって。」
「いいえ、私は決して退屈しません」と彼女はすぐに言った。
「本もあり、研究もあり、魅力的な隣人もいます。モーティマー博士はその道では非常に博識ですし、亡きサー・チャールズも素晴らしい話し相手でした。彼とは親しくしていましたし、今でも寂しさは言葉にできません。今日の午後、ヘンリー卿にご挨拶に伺ってもご迷惑にはなりませんか?」
「きっと喜ばれるでしょう。」
「では、その旨お伝えいただけますか。卑しい身なりですが、新しい環境に慣れるまで、少しでもお役に立てることがあればと思っています。ワトソン博士、二階に私の蝶類コレクションをご覧になりませんか? 南西イングランドでは最も充実していると自負しています。それを見ていただいている間に昼食の用意もできるでしょう。」
だが私は、自分の役目に戻りたくて仕方がなかった。荒野の物悲しさ、不運なポニーの死、バスカヴィル家の伝説と結びついた奇怪な音、こうしたものが私の心を陰鬱に染めていたのだ。そのうえ、ミス・ステープルトンによる明確な警告が加わった。あれほど切実に忠告された以上、重大な理由があると考えざるを得なかった。私は昼食の誘いを丁重に断り、来たときの草道をとってすぐに引き返した。
しかし、地元の人には近道があるようだった。まだ道に出る前に、ミス・ステープルトンが小道脇の岩に腰かけているのを見て、私は驚いた。彼女は息を切らして頬を紅潮させ、脇腹を押さえていた。
「ワトソン博士、先回りしようと全力で走ってきました。帽子をかぶる暇さえなかった。長居はできません、兄に気づかれますから。さっきあなたをヘンリー卿と勘違いして、愚かなことを言ってしまい、本当に申し訳ありません。今言ったことはすべてお忘れください。あなたには全く関係のないことです。」
「でも、忘れることなどできませんよ、ミス・ステープルトン。私はヘンリー卿の友人で、彼の身を案じています。なぜあなたはあれほど熱心に、ヘンリー卿をロンドンへ戻したがったのですか?」
「女の気まぐれです、ワトソン博士。私をもっと知るようになれば、私が言ったりしたりすることに必ずしも理由を説明できないことがお分かりになるでしょう。」
「いや、違う。あなたの声に震えがあったのを覚えている。あなたの目の表情も覚えている。お願いだ、お願いだから、正直に話してくれ、ミス・ステープルトン。ここに来てからずっと、私は周囲に影が付きまとっているのを感じている。人生そのものが、あの広大なグリムペンの泥炭地のようになってしまった。どこにでも小さな緑の島があり、そのどれかに足を踏み入れれば沈み込んでしまうが、道を示してくれる案内人もいない。だから、あの時あなたが言おうとしたことを、どうか教えてほしい。必ずヘンリー卿にあなたの警告を伝えると約束する。」
一瞬、彼女の顔にためらいの色が浮かんだが、答える時には再びその眼差しは硬くなっていた。
「ワトソン先生、あなたはそれを大げさに考えすぎているわ」と彼女は言った。「兄も私も、サー・チャールズの死にはとてもショックを受けました。私たちは彼ととても親しくしていました。お気に入りの散歩道が、あの荒野を越えて私たちの家に通じていたのですから。彼は、家系に付きまとう呪いに深く心を悩ませていました。この痛ましい出来事が起きて、彼が口にしていた恐怖には、やはり根拠があるのだろうと自然に思ったのです。だから、家族の別の人がここに住みに来たと聞いて、とても心配になり、彼にも危険を警告すべきだと感じた、それだけのことだったのです。」
「でも、その危険というのは何なのです?」
「あなたは、あの猟犬の話をご存じでしょう?」
「私は、そんな馬鹿げた話は信じない。」
「でも私は信じています。もしあなたがヘンリー卿に影響力をお持ちなら、一族にとって常に命取りだったこの場所から連れ出してあげてください。世界は広いのです。なぜ、危険なこの地に住もうとするのです?」
「それが“危険な場所”だからだ。それがヘンリー卿の性分だ。これ以上はっきりした情報がなければ、彼を動かすことはできないだろう。」
「はっきりしたことは言えません。なぜなら、私自身も何も確かなことは知らないからです。」
「もう一つだけ伺います、ミス・ステープルトン。もしあなたが、初めて私に声をかけた時、それ以上の意味はなかったのなら、なぜ兄上にその話を聞かせたくなかったのですか? 兄上や他の誰にも異論のある話ではないでしょう。」
「兄は屋敷に人が住んでほしいと強く思っています。荒野に住む貧しい人たちのためにもそうするのが良いと考えているからです。だから、私がヘンリー卿をこの地から去らせるようなことを言ったと知ったら、兄はとても怒るでしょう。でも、私はもう自分の義務は果たしました。これ以上は何も言いません。そろそろ戻らないと、兄に気づかれて、あなたに会ったことを疑われてしまいます。さようなら!」
彼女は振り返ると、数分もしないうちに散在する岩の間へと姿を消した。私は漠然とした不安を胸に抱えたまま、バスカヴィル館へと道を急いだ。
第八章 ワトソン博士の最初の報告
ここからは、私がシャーロック・ホームズ宛に書き送った手紙をそのまま転記して、出来事の流れを追うことにする。机の上にその手紙が並んでいる。一枚だけ抜けているが、あとは当時書かれたままであり、私の記憶が鮮明であるとはいえ、この悲劇的な事件についての私の心情や疑念を、これほど正確に伝えられるものは他にない。
バスカヴィル館 十月十三日
親愛なるホームズ、
これまでの私の手紙や電報で、この世界の果てのような場所で起こったことはほぼ逐一お伝えしてきたつもりだ。ここに長くいるほど、この荒野の精神が心の奥にまで染み込んでくる。その広大さ、そしてどこか不気味な魅力だ。一度荒野に足を踏み入れると、現代イングランドの痕跡はすっかり消え失せるが、その一方で、先史時代の人々の住居や営みを至るところで感じずにはいられない。歩いていると、忘れ去られた人々の家々や墓、神殿の跡とされる巨大な一枚岩があちこちに目につく。傷だらけの丘陵の斜面に並ぶ灰色の石造りの小屋を眺めていると、自分の時代が遠ざかり、もし毛皮をまとった毛むくじゃらの男が低い入口から這い出てきて、燧石の矢じりを弓に番えても、その姿の方がこの地には自然に思えてしまう。どうして彼らが、これほど不毛な土地に密集して住んでいたのかは実に不思議だ。私は考古学者ではないが、彼らは戦もせず、迫害され、他の誰も住まない土地を受け入れるしかなかった民族だったのかもしれないと想像する。
しかし、こうした話は君が私に託した使命とは無関係で、君の極めて実際的な精神には興味のないことだろう。太陽が地球の周りを回るのか、地球が太陽を回るのかということに、君が全く無関心だったことを私はよく覚えている。なので、サー・ヘンリー・バスカヴィルについての事実に話を戻そう。
ここ数日間、報告がなかったのは、今日まで特筆すべき出来事がなかったためだ。だが今日、非常に驚くべき事件があり、これについては追って詳述する。まずはその他の状況について、君を最新の状態にしておきたい。
その一つは、これまであまり触れてこなかったが、荒野に逃亡中の囚人についてだ。今や、彼は完全に遠くへ逃げ去ったものと思われ、この地方の孤立した住民たちにはかなりの安堵となっている。彼が逃亡してから二週間が経ち、その間に彼を見た者も、何も聞いた者もいない。この荒野でこれほど長く生き延びるのは到底考えにくい。もちろん、隠れる場所には事欠かない。どの石小屋でも身を潜めることはできるだろう。ただし、食べ物がない。荒野の羊を捕まえて屠殺でもしない限りは無理だ。だから、彼はもう去ったと考えられ、周辺の農家も安眠できるようになった。
我々の屋敷には、健康な男が四人いるので身の安全は保てるはずだが、ステープルトン家のことを思うと不安な時もあった。彼らの家は助けを呼べる場所から何マイルも離れている。使用人の女性一人、年老いた下男、妹と兄、しかも兄はあまり丈夫ではない。あのノッティング・ヒルの犯罪者のような凶悪な男に進入されたら、ひとたまりもないだろう。ヘンリー卿も私も彼らの状況を気にかけ、馬丁のパーキンズを泊まり込みで送ったらどうかと提案もしたが、ステープルトン氏はそれを断固拒否した。
実は、我が友である男爵は、この麗しい隣人にかなり関心を持ち始めている。それも無理はない。この寂しい土地では、活動的な男にとっては時間を持て余すし、彼女はとても魅力的で美しい女性だ。彼女には、どこか南国的で異国的な雰囲気があり、冷静で感情を表に出さない兄とは際立った対照をなしている。だが兄にも、内に秘めた情熱のようなものが感じられる。兄は彼女に強い影響力を持っているようで、会話中も彼女がしきりに兄の顔色をうかがうのを何度も目にした。彼が彼女に優しくしていることを願う。彼の瞳には乾いたきらめきがあり、薄い唇はきつく結ばれていて、それが強情で、時に冷酷さも併せ持つ性格をうかがわせる。君ならきっと興味深い人物と感じるだろう。
彼は初日にバスカヴィル卿を訪ねてきた。翌朝には私たち二人を連れて、「邪悪なヒューゴー」の伝説が生まれたとされる場所を案内してくれた。荒野を何マイルも歩いた先の、いかにもいわくありげな陰気な場所だった。ごつごつした岩山に挟まれた短い谷間があり、そこから開けた草地に出た。白いワタスゲが点々と咲き、その中央には二つの大きな石が突き出ていた。上部はすり減り、鋭くなっていて、まるで怪物の腐食した巨大な牙のようだ。何もかも昔の悲劇の現場にぴったり当てはまる。ヘンリー卿もたいそう興味を持ち、ステープルトン氏に超自然的なものが人間社会に干渉する可能性を本当に信じているのか、何度も尋ねていた。口調は軽かったが、卿が本気であることは明らかだった。ステープルトン氏は慎重に答えていたが、言葉少なに留めているのが見て取れ、男爵の気持ちに配慮して真意を言葉にしていないのは明白だった。彼は、他にも家系が悪しき影響に悩まされた例をいくつか話してくれ、この件については世間一般の考え方を共有しているのだという印象を私達に残した。
帰り道、メリピット・ハウスで昼食をとり、そこでヘンリー卿は初めてミス・ステープルトンと知り合った。彼女を一目見た瞬間から、強く惹かれている様子だったし、私の見立てでは彼女も同じ思いだったと思う。帰り道でも彼女の話を何度も持ち出し、それ以来、兄妹とはほとんど毎日のように顔を合わせている。今夜は彼女たちがこちらで夕食をとるし、来週はこちらから伺うという話も出ている。普通なら、こうした結婚はステープルトン氏にとっても歓迎すべき縁談のはずだが、私は何度も、ヘンリー卿が妹に好意を示すたび、彼の顔に強い嫌悪の色が浮かぶのを見逃さなかった。妹への愛着が強いのは確かで、彼女がいなくなれば孤独になるだろうが、それでこの輝かしい結婚を妨げるようでは、あまりにも身勝手というものだ。それでも彼は二人の親密さが恋愛へと発展することを望んでいないのは確かで、私は何度も、彼が二人きりの時間を作らせまいと気を配っているのに気づいた。ちなみに、君の「ヘンリー卿を決して一人で外出させるな」という指示は、恋愛沙汰が加わればますます厄介になる。もし君の命令を一字一句守ったら、私の人気もたちまち地に落ちてしまうだろう。
先日――正確には木曜日だが――モーティマー博士が昼食に来た。彼はロング・ダウンで古墳を発掘していて、先史時代の頭蓋骨を手に入れ、非常に喜んでいる。あれほど一途な熱中家は他にいない。ステープルトン兄妹も後から加わり、博士の案内で、ヘンリー卿の希望で、あの夜に何が起きたのかを正確に説明してもらった。イチイ並木は両側に刈り込まれた高い生け垣が続く陰気な小道で、両端には狭い芝生がある。奥には古びて崩れかけの東屋がある。途中には、サー・チャールズが葉巻の灰を落としたという荒野への門があり、白い木製の扉に掛け金がついている。その先には広大な荒野が広がっている。君の推理を思い出し、あの夜の出来事を頭の中で再現してみた。老紳士があそこに立ち、荒野の向こうから何かがやってくるのを見て、恐怖のあまり正気を失い、やみくもに走り続け、ついには恐怖と疲労で命を落とした――そんな光景が目に浮かぶ。彼が逃げた長い暗いトンネルがそこにはあった。そして彼は何から逃げていたのだろう? 荒野の牧羊犬か? それとも黒く、声もなく、怪物のような幽霊の猟犬か? 何か人間の仕業なのか? 蒼ざめた顔で用心深いバリモアは、まだ何か隠しているのではないか? すべてがぼんやりとしているが、常にその背後には犯罪の暗い影がつきまとっている。
前回の手紙以来、もう一人の隣人にも会った。それが南へ四マイルほど離れたラフター館のフランクランド氏だ。年配で、顔は赤く、白髪、気が短い。彼の情熱はイギリス法にあり、訴訟で莫大な財産を使い果たした。議論そのものが好きで、どちらの立場にも同じ熱意で立つので、当然ながら高くつく趣味となっている。時には通行権を閉鎖し、村を挑発して開かせようとする。時には他人の門を自ら壊して、そこに昔から道があると言い張り、所有者に不法侵入で訴えるよう仕向ける。古い荘園や共同体の権利に詳しく、その知識を時にはファーンワージー村民の味方に、時には敵に使うので、村を練り歩いて称賛されることもあれば、人形を燃やされて非難されることもある。今は七件ほどの訴訟を抱えていると言われており、残りの財産もそれで消えてしまい、毒気も抜けて無害になるだろう。法の話を離れれば、気の良い親切な人物で、君が周囲の人々について詳しく報告するよう求めたので、ここに記す。今は天文の素人観測家として、立派な望遠鏡を持ち、自宅の屋上に寝そべって一日中荒野を眺め、逃亡犯の姿を探している。彼がそのエネルギーをこれにだけ注げば問題ないが、ロング・ダウンの古墳から新石器時代の頭蓋骨を掘り出したことについて、モーティマー博士を「遺族の同意なく墓を開いた」として訴えるつもりだという噂もある。彼のおかげで我々の生活は単調にならず、ちょっとした笑いを提供してくれる存在だ。
さて、これで逃亡犯、ステープルトン家、モーティマー博士、そしてラフター館のフランクランド氏についてお伝えした。最後に最も重要なバリモア夫妻、特に昨夜の驚くべき出来事について書こう。
まずロンドンから君が送ってきた試験電報についてだが、バリモアが本当にここにいたかどうか確かめるためのものだった。すでに説明した通り、郵便局長の証言からこのテストは無効であり、どちらとも証明できない。私がその旨をヘンリー卿に話すと、彼は率直な性格なので、すぐにバリモアを呼んで、自分で電報を受け取ったのか問いただした。バリモアは「はい」と答えた。
「少年が直接あなたの手に届けたのか?」とヘンリー卿。
バリモアは驚いたように少し考えてから、
「いいえ。その時私は物置部屋にいて、妻がそれを持って来てくれました。」
「返事は自分で書いたのか?」
「いいえ。何と答えるか妻に伝え、妻が下に降りて返事を書きました。」
夕方になって、彼は自分からこの件に話を戻した。
「今朝のご質問の意味がよく分からなかったのですが、ヘンリー卿。それは私が卿の信頼を失うようなことをしたという意味ではありませんよね?」
ヘンリー卿はそうでないことを保証し、ロンドンから届いた新しい衣服一式をかなり多く彼に与えて、彼を安心させた。
バリモア夫人は私にとって興味深い存在だ。彼女はがっしりとした体格で、視野が狭く、極めて堅物で、やや禁欲的な傾向がある。これほど感情を表に出さない女性は想像しにくい。しかし、初夜に彼女が激しく泣いているのを聞いたことは君に話した通りだし、その後も何度か、泣きはらした跡を顔に見たことがある。彼女の心にはいつも深い悲しみが巣くっている。時に、彼女が何か罪の記憶に悩まされているのではと考えたり、また時には、バリモア氏が家庭内で暴君なのではないかと疑ったりする。この男には以前からどこか奇妙で疑わしいところがあると感じていたが、昨夜の出来事ですべての疑念が決定的になった。
もっとも、その出来事自体はささいなことに思えるかもしれない。私はもともと眠りの浅い方だが、この家で警戒しているせいでさらに寝付きが悪くなっている。昨夜、二時ごろ、不意に誰かがこっそり私の部屋の前を通る足音で目が覚めた。私は起きてドアをそっと開け、廊下を覗いた。長い黒い影が廊下に落ちていた。蝋燭を手にした男が、足音を忍ばせながら廊下を進んでいる。シャツとズボン姿で、足には何も履いていない。輪郭しか分からなかったが、その背丈からバリモアだと判断できた。彼は極めてゆっくり、用心深く歩き、その様子全体が何とも言えず後ろ暗く、こそこそした雰囲気を漂わせていた。
前にも説明したが、廊下は広間を囲むバルコニーでいったん途切れ、向こう側からまた続いている。私は彼が見えなくなるまで待ち、後を追った。バルコニーを回ると、彼は奥の廊下の端まで行っており、開いたドアから漏れる光で、彼が部屋に入ったことが分かった。その部屋はすべて家具が入っておらず、誰も使っていないので、彼の行動はますます謎めいていた。光はじっと動かず灯っており、彼がその場に立ち尽くしているのだろうと推測できた。私はできる限り音を立てずに廊下を進み、ドアの角からそっと中を覗いた。
バリモアは窓辺にしゃがみ、蝋燭を窓ガラスに押し当てていた。横顔がこちらに半ば向いており、荒野の暗闇をじっと見つめて、期待と緊張に顔がこわばっているようだった。数分間、身じろぎもせず見つめ続けていた。やがて彼は深い溜め息をつき、苛立ったように身振りして蝋燭の火を消した。私はすぐに自分の部屋に戻り、間もなく再びこっそりと帰ってくる足音がした。その後しばらくして、私が浅い眠りに落ちていると、どこかで鍵の回る音が聞こえたが、どの部屋かまでは分からなかった。これが何を意味するのか、私にはまったく見当がつかない。しかし、この陰鬱な屋敷の中で、何らかの秘密の企みが進行しているのは間違いなく、いずれ必ずその正体を突き止めてみせるつもりだ。君には推測ではなく事実だけを書くように言われているので、私の考えはここでは述べない。今朝、ヘンリー卿と長く話し合い、昨夜の観察に基づいて行動計画を立てた。今はまだ詳しくは書かないが、次の報告はきっと興味深いものになるだろう。
第九章 荒野の光【ワトソン博士の第二報告】
バスカヴィル館 十月十五日
親愛なるホームズ、
もしも私が、任務の初期にほとんど便りを送れなかったことを気にされていたなら、今こそその埋め合わせをしていると認めてもらわなければならない。今や出来事は次々と私たちに押し寄せてきている。前回の報告では、バリモアが窓辺にいる場面で筆を置いたが、今回すでにかなりの情報を手にしており、もし私の見立てが間違っていなければ、君もきっと驚くだろう。事態は私が予想もしなかった方向へ進展した。この四十八時間で、いくつかの点では劇的に明らかになったが、同時に一層複雑にもなった。しかし、これからすべてを語るので、君自身で判断してほしい。
私の冒険の翌朝、朝食前に廊下を下り、前夜バリモアがいた部屋を調べてみた。彼が熱心に眺めていた西側の窓には、他のどの窓とも異なる特長があった――屋敷の中で最も間近にムーアを見渡せるのだ。二本の木の間に隙間があり、その場所からはムーアを真下に見晴らすことができるが、他の窓からだと遠くにしか見えない。つまり、バリモアがその窓を選んだのは、ムーア上の何か、もしくは誰かを見張るためだったということになる。夜はとても暗かったので、彼がどうやって誰かを見分けようとしたのか想像しがたい。私は当初、何らかの恋愛沙汰があるのではないかとも考えた。そうであれば、彼のこっそりした動きやバリモア夫人の不安の理由にもなるだろう。彼は目立つ風貌の男で、田舎娘の心を奪うのに十分な魅力があるので、この仮説にも一理あるように思えた。私が自室に戻った後に聞こえたドアの開く音も、密会のために外に出たことを意味していたのかもしれない。朝の時点で私の疑念はその方向だったので、たとえその後に結果が違ったとしても、ここで私の推理を伝えておく。
だが、バリモアの行動の真相が何であれ、それを自分だけで抱えて説明がつくまで黙っているのは耐えがたい責任だった。朝食後、私はバスカヴィル卿の書斎で彼と面会し、見たことをすべて話した。彼は私が予想したほど驚かなかった。
「バリモアが夜中に徘徊していることは知っていた。いずれ彼に話をしようと思っていた」と彼は言った。「君が言う時間帯に、二、三度廊下を行き来する足音を聞いたことがある」
「それなら、彼は毎晩あの窓に行っているのかもしれませんね」と私は言った。
「そうかもしれない。ならば、後をつけて彼が何をしているのか確かめてみよう。君の友人ホームズがここにいたらどうするだろうな」
「きっと今おっしゃった通りにすると思います」と私は答えた。「バリモアの後をついて、その行動を探るでしょう」
「それなら一緒にやろう」
「でも、きっと気づかれてしまうのでは」
「彼は少し耳が遠いし、とにかくやってみるしかない。今夜は私の部屋で待機しよう」バスカヴィル卿は楽しげに手をこすり合わせ、ムーアでのやや退屈な生活に冒険が加わることを心から歓迎しているのが明らかだった。
彼はサー・チャールズのために図面を描いた建築家やロンドンから来た請負業者と連絡を取り合っており、近々この屋敷で大きな変化が始まることが予想される。プリマスから装飾業者や家具職人も来ていて、友人が一族の威厳を取り戻すために労力も出費も惜しまないつもりであるのは明白だ。屋敷が改修され、新たに家具が入れば、あとは妻さえいれば完全だろう。内緒だが、もし相手の女性さえその気なら、それも不足することはなさそうだ。彼が隣人のミス・ステープルトンに夢中になっているのは、これまで見たことがないほどだからだ。とはいえ、恋の道は思ったほど順調ではない。たとえば今日、その表面に思いがけない波紋が生じ、友人はかなり困惑し苛立っていた。
先程のバリモアに関する会話のあと、バスカヴィル卿は帽子を手に取り、外出の準備を始めた。私も当然のように同行しようとした。
「何だ、ワトソン、君も来るのか?」と、彼は不思議そうに私を見た。
「ムーアに行かれるのなら」と私は答えた。
「ああ、そのつもりだ」
「ご存知の通り、私の指示があるのです。お邪魔して申し訳ありませんが、ホームズがどれほど熱心にあなたのそばを離れないよう言ったか、お聞きだったでしょう。特に、ムーアにお一人で行かれるのは控えてほしいと」
バスカヴィル卿はにこやかに私の肩に手を置いた。
「親愛なる友よ、ホームズは賢い男だが、私がムーアに来てから起きたことのいくつかは予見できなかった。分かってくれるだろう? 君は絶対に場を台無しにするような人間ではないと信じている。だから私は一人で出かけなければならない」
私は非常に困った立場に置かれ、何と言ったらよいのか、どうすべきか分からなかった。考えをまとめる間もなく、彼はステッキを手にして出て行ってしまった。
だが、後になってよく考えてみると、どんな理由があろうと彼を見失ったことに良心の呵責を強く覚えた。もし君に報告しなければならないとき、私の不注意が原因で災難が起きていたらどう思うだろう、と想像すると、顔が赤くなるほどだった。まだ追いつくのに遅くはないかもしれないと思い、私はすぐにメリピット・ハウスの方向へ歩き出した。
全速力で道を進んだが、バスカヴィル卿の姿は見えない。ムーアへの小道が分かれる地点で、もしかしたら方向を間違えたのではと不安になり、見晴らしの利く丘に登った――例の採石場が切り込まれているあの丘である。そこからすぐに彼の姿が見えた。ムーアの小道を四分の一マイルほど先に進んでおり、隣にはミス・ステープルトンとしか思えない女性がいた。二人はすでに気持ちが通じ合っていて、約束して会ったのだと分かった。ゆっくりと歩きながら深く会話を交わし、彼女は何かを真剣に語っているかのように手をせわしなく動かし、彼も熱心に耳を傾け、時折強く首を振って意見を否定していた。私は岩陰で二人を見守り、次にどうすべきか非常に迷った。会話の中に割って入るのは無礼だが、友人から一瞬たりとも目を離すべきではないというのが私の責務だ。友人を見張るなど忌まわしい行いだが、それでも他に方法が思いつかず、丘から見守りつつ、後で正直にそのことを伝えて良心の呵責を和らげるしかないと思った。本当のところ、もし突然彼に危険が迫ったら私には何もできない距離だったが、この立場の難しさは理解してもらえるだろうし、私にできる限りのことはやったはずだ。
バスカヴィル卿と女性は道の上で立ち止まり、会話に夢中になっていたが、私は自分以外にも彼らを見ている者がいることに気がついた。空中に浮かぶ緑色の細いものが目に入り、それが棒の先につけられていると分かった。動いているのはステープルトン氏で、蝶捕り網を持ち、私よりはるかに二人に近づいていた。ちょうどその時、バスカヴィル卿がミス・ステープルトンを傍らに引き寄せ、腕を回したが、彼女は顔をそむけて振り払おうとしているように見えた。彼が彼女に身を屈め、彼女が片手を挙げて抗議する仕草を見せた。その瞬間、二人は飛びのいて振り返った。ステープルトン氏が原因だった。彼は網をぶら下げて夢中で走り寄り、興奮のあまり身振り手振りで踊りそうな勢いだった。一体何が起こっているのか想像もつかなかったが、どうやらステープルトン氏はバスカヴィル卿に罵声を浴びせているようで、卿は説明をしようとするも、相手が受け入れず徐々に怒りが高まっていった。女性は高慢な沈黙を守っていた。やがてステープルトン氏はくるりと背を向け、妹に向かって命令口調で手招きした。彼女は一瞬バスカヴィル卿を見やったが、結局兄の側について歩き去った。自然学者の怒りのジェスチャーから、妹もその不興に含まれているのは明らかだった。バスカヴィル卿はしばらくその後ろ姿を見送った後、肩を落として来た道を戻ってきた。
この一件が何を意味するのか全く分からなかったが、私は友人の知らぬ間にこのような親密な場面を見てしまったことに、ひどく後ろめたさを覚えた。だから丘を駆け下りて、ふもとで彼と出会った。彼は怒りに頬を赤らめ、眉をひそめて、どうしたものか途方に暮れている様子だった。
「やあ、ワトソン! どこから湧いて出たんだ?」彼は言った。「それでも後をつけてきたのか?」
私はすべてを正直に説明した――どうしても後に残れず、後を追ってここまで来たこと、そしてすべてを見てしまったことを。彼の目が一瞬怒りに燃えたが、私の率直さに怒りも消え、最後には苦笑いすら浮かべた。
「この辺りの原っぱのど真ん中なら、男が人目を気にせず過ごせると思うだろうが、なんてことだ、プロポーズするのを村中に見られていたとは――しかもお粗末なプロポーズだ! 君はどこで観劇していた?」
「丘の上です」
「ずいぶん後ろの席だな。でも彼女の兄貴は最前列だった。あいつが現れたのは見たか?」
「見ました」
「彼が狂人だと感じたことはあるか?」
「いいえ、特にありません」
「そうか。俺も今日までは正気だと思っていたが、今日のあれでどちらかが拘束衣を着るべきじゃないかと思い始めた。俺の何が悪いっていうんだ? ワトソン、君はしばらく俺のそばにいたな。はっきり言ってくれ、この俺が、愛する女性にふさわしい夫になれない理由が何かあるのか?」
「全くないと思う」
「あの男が俺の身分に文句をつけるはずがない、となると、俺自身に何か気に入らない点があるのか。俺はこれまで誰にも危害を加えた覚えはないし――それなのに、指先に触れることさえ許さないとは」
「そんなことまで言ったのか?」
「ああ、それ以上のことも。ワトソン、彼女と知り合ってまだ数週間だが、初めて会った時から彼女こそが自分のために生まれてきた人だと感じたんだ。彼女も俺といるときは幸せそうだった――これは断言できる。女性の目の輝きは言葉以上に雄弁だ。だが、あの兄貴は決して二人きりにならせようとしなかった。今日初めて、ようやく少し話す機会ができた。彼女も会えて喜んでいたが、愛の話は一切できず、彼女もさせまいとした。彼女は繰り返しここは危険な場所だと言い、自分が去るまで安心できないと訴えた。俺は、君と出会ってからは急いで立ち去る気はなくなった、もし本当に出て行ってほしいなら、君自身も一緒に行くしかないだろうと伝えた。はっきりと結婚を申し込んだんだ。しかし彼女が答える前に、あの兄貴が狂ったような顔で走ってきて、怒りに顔を真っ白にし、あの鋭い目は燃えるようだった。俺が何をしていたのか、なぜ彼女の意に沿わない好意を押しつけるのか、男爵だからといって何でも許されると思っているのかと責め立てられた。もし彼が兄でなければもっとはっきり反論できたのだが、妹への気持ちはやましくないし、彼女に名誉を与えてほしいと願うと伝えた。だがそれで状況はむしろ悪化し、俺もつい頭にきて、彼女の前なのに激しく言い返してしまった。結局、あいつが彼女を連れて去っていったのは君も見た通りだ――俺はこの地方でも屈指の困惑男だ。ワトソン、これがどういうことか説明してくれたらきっと一生君には敵わなくなるだろうな」
私はいくつか説明を試みたが、正直なところ私自身まったく分からなかった。友人は称号も財産も年齢も人格も容姿も申し分なく、不利な点は家系に流れる不吉な運命くらいしか思い当たらない。それほどの好条件で、しかも本人の意思を無視して拒絶され、女性も抗議しないというのは、まったく不思議なことだった。しかし、午後になってステープルトン氏自身が訪れ、私たちの憶測は一掃された。彼は午前中の無礼を詫びるために来て、バスカヴィル卿と長い個人面談をした。その結果、両者は完全に和解し、金曜日には和解の印としてメリピット・ハウスで食事をすることになった。
「今も彼が狂人でないとは断言できない」とバスカヴィル卿は言った。「今朝のあの目つきを忘れることはできないが、彼ほど立派な謝罪をした男もいないだろう」
「彼は自分の行動について説明したのか?」
「妹が彼のすべてだと言った。それは自然なことだし、彼女の価値を理解しているのはむしろ喜ばしい。二人はずっと一緒で、彼は彼女以外友人もない孤独な男だったそうだ。だから彼女を失うことなど考えられなかった。だが、俺が彼女に惹かれていると気づかず、実際にそうだと目の当たりにして初めて、激しいショックを受けて我を失ったと。これまでのことは本当に申し訳なく、妹のような美しい女性を自分だけのものにしようとしたのは愚かで利己的だったと認めていた。もし彼女が去るなら、近所の俺のような男のもとであれば救いだとも言った。ただ、それでもしばらくは受け入れる余裕が必要なので、三か月間だけは求愛を控え、親しい友人として過ごしてほしいと約束を求められた。俺はそれを約束した、それで一件落着だ」
こうして小さな謎が一つ解明された。この沼地のような混沌の中で、どこかで底に手が届いたことは大きな収穫である。なぜステープルトン氏が、誰よりも適した求婚者であるバスカヴィル卿に難色を示したのか、今では分かった。さて、次は夜中のすすり泣き、涙に濡れたバリモア夫人の顔、西側の格子窓への執事の秘密の行動という、絡み合った糸玉から解きほぐしたもう一つの糸口について語ろう。親愛なるホームズ、私が君の期待を裏切っていないと、自分を使者に選んだことを後悔していないと、ぜひ祝福してほしい。これらすべての謎が一晩の働きで見事に解決したのだ。
「一晩の働きで」と書いたが、実際には二晩かかった。最初の夜はまったく成果がなかった。私はバスカヴィル卿と彼の部屋で夜中の三時近くまで起きていたが、階段の時計以外には何の物音も聞こえなかった。実に憂鬱な徹夜で、結局私たちは椅子の上で眠ってしまった。しかし幸運にも落胆せず、もう一度挑戦することにした。翌夜はランプを暗くし、タバコをくゆらせて一言も発しなかった。時間の進みが信じられないほど遅く、まるで獲物が罠にかかるのを待つ猟師のような忍耐強い興味に救われた。一時、二時と過ぎ、またもあきらめかけたそのとき、私たちは突然椅子の上で体を起こし、疲れ切った感覚が一気に研ぎ澄まされた。廊下をきしむ足音が聞こえたのだ。
私たちはその足音が遠ざかるまで慎重に聞き耳を立てていた。それから男爵が静かにドアを開け、後を追った。すでにバリモアはギャラリーを回って廊下は真っ暗だった。私たちはそっと忍び足で進み、もう一つの棟に近づいた。ちょうど背の高い黒髭の男が、背を丸めて廊下を歩いているのを目撃した。彼は前と同じドアを通り、ろうそくの灯りが暗闇の中、廊下に一本の黄色い光線を投げていた。私たちは慎重に足を進め、板の一枚一枚に体重をかける前に確かめながら近づいていった。念のため靴を脱いでいたが、それでも古い板は私たちの足元でみしみしと音を立てた。到底気づかれずに近づけるとは思えなかったが、幸い彼は耳が遠く、しかも自分のしていることに夢中であった。ついにドアにたどり着き、そっと覗くと、彼は窓際にかがみ、ろうそくを持ち、白く鋭い顔を窓ガラスに押し付けていた――ちょうど二日前に私が見た光景そのままだった。
我々は何の作戦も立てていなかったが、ヘンリー・バスカヴィル卿は、常に最も直接的な方法を自然に選ぶ男である。彼は部屋に入っていき、同時にバリモアが窓のそばから、鋭く息を吸い込みながら跳ね起き、蒼白になり、震えながら我々の前に立った。彼の青白い顔に浮かぶ暗い目は、恐怖と驚愕に満ち、サー・ヘンリーと私を交互に見つめていた。
「バリモア、ここで何をしている?」
「何もしておりません、旦那様。」彼は極度に動揺していて、ほとんど言葉にならなかった。ろうそくの震えで影が上下していた。「窓です、旦那様。夜は各窓がちゃんと締まっているか見て回るのです。」
「二階の窓までか?」
「はい、旦那様、すべての窓を。」
「いいか、バリモア」とサー・ヘンリーは厳しい口調で言った。「我々は真実を必ず聞き出すつもりだ。早く話してしまった方が身のためだぞ。さあ! 嘘はなしだ! その窓で何をしていた?」
バリモアはどうしていいかわからない様子で我々を見つめ、両手をぎゅっと握りしめて、絶望と苦悩に満ちていた。
「悪いことは何もしていません、旦那様。ただろうそくを窓にかざしていただけです。」
「なぜ、ろうそくを窓にかざしていた?」
「どうか、それは聞かないでください、サー・ヘンリー――本当にお願いです! これは私の秘密ではなく、私には話せません。もし私自身のことだけだったら、隠したりはしません。」
ふと考えが浮かび、私は震える執事の手からろうそくを取った。
「これは合図に使っていたのに違いない」と私は言った。「返事があるか見てみよう。」私は彼がした通りにろうそくをかざし、夜の闇を見つめた。木々の黒い塊と、雲の後ろにある月明かりで少し明るい原野がぼんやりと見えた。そして私は歓喜の声を上げた。暗闇の帳の中心に、小さな黄色い光点が突然現れ、窓枠に囲まれた黒い四角の真ん中にしっかりと輝いているのだ。
「ほら、見えるだろう!」私は叫んだ。
「いえ、旦那様、それは違います――違うんです!」とバリモアが遮る。「本当に、旦那様――」
「窓の前でろうそくを動かしてみろ、ワトソン!」と卿が叫ぶ。「見ろ、向こうの光も動く! さて、バリモア、これが合図でないと言い張れるか? さあ、答えろ! お前の共犯者は誰だ? どういう陰謀なんだ?」
バリモアの顔はあからさまに反抗的になった。「これは私のことです。旦那様には関係ありません。何も話しません。」
「それなら、今すぐ屋敷を出ていけ。」
「承知しました、旦那様。そうしなければならないなら、そうします。」
「そして不名誉のまま去ることになるぞ。まったく、お前も恥ずかしいだろう。お前の家族は百年以上も私の家と共にこの屋敷で暮らしてきたのに、今になって私に対する闇の陰謀の中にいるとは。」
「違います、旦那様、違う、あなたに対してでは――!」それは女の声で、バリモア夫人が夫よりもさらに蒼白で恐怖に満ちた顔で扉の前に立っていた。ショールとスカート姿の大柄な彼女は、その顔に浮かぶ強い感情がなければ滑稽に見えたかもしれない。
「行くしかないんだ、エリザ。これで終わりだ。荷物をまとめてくれ」とバリモアが言った。
「ジョン、ジョン、私があなたをこんな目にあわせたのね? すべて私のせいです、サー・ヘンリー――全部私のせいです。彼は私の頼みで、私のためだけにやったんです。」
「なら、はっきり話してくれ! どういうことだ?」
「不幸な弟が原野で飢え死にしかけているのです。目の前で死なせるわけにはいきません。あの光は、食べ物の準備ができたという合図で、向こうの光は食べ物を持っていく場所を示しているのです。」
「では君の弟は――」
「脱獄犯です、旦那様――セルデンという犯罪者です。」
「その通りです、旦那様」とバリモアが言った。「私の秘密ではないので話せませんでしたが、今はお聞きになった通りです。もし陰謀があったとしても、あなたに対してではありません。」
これが、夜ごとにこっそり外出していた理由と窓の明かりの正体だった。サー・ヘンリーと私は呆然としてバリモア夫人を見つめた。あの真面目な人物が、国中で悪名高い犯罪者と同じ血筋だとは信じられなかった。
「そうです、旦那様、私の旧姓はセルデンで、彼は私の弟なんです。子供のころ、私たちは彼を甘やかしすぎて、欲しいものは何でも与え、ついには世の中は自分のためにあると思い込むようになってしまいました。その後、悪い仲間と付き合うようになり、ついには悪魔に取り憑かれて母を悲しませ、家名を地に落としました。どんどん罪を重ねていき、とうとう絞首刑寸前まで堕ちましたが、神の慈悲で救われたのです。でも私にとっては、いつまでも乳母として世話をしたかわいい弟のままでした。それで彼は脱獄したのです。私がここにいることを知っていて、私たちが助けを断れないと分かっていました。ある晩、疲れ切って飢えた彼が監視の目をかいくぐって来たとき、私たちはどうすればよかったのでしょうか? 私たちは彼に食事を与え、世話をしました。あなたが戻ってきてからは、弟は騒ぎが収まるまで原野が一番安全だと思い、身を隠していました。でも私たちは毎晩、まだそこにいるかを確かめるため、窓に明かりをともしました。返事があれば、夫が食べ物を持っていったのです。毎日どこかへ行ってくれるのを願っていましたが、いる限り見捨てることはできませんでした。これがすべての真実です。私は正直なキリスト教徒です。このことで責められるべきは夫ではなく、すべて私のために行動した私自身です。」
バリモア夫人の話ぶりは誠実さに溢れ、誰もが信じるほかなかった。
「本当か、バリモア?」
「はい、サー・ヘンリー。一言一句その通りです。」
「なるほど、妻のために力を尽くしたことは責められないな。私が言ったことは忘れてくれ。二人とも部屋に戻りなさい。この件については明日改めて話そう。」
二人が去った後、我々は再び窓から外を見た。サー・ヘンリーは窓を開け放ち、冷たい夜風が顔に打ちつけた。遠く闇の中、まだ小さな黄色い光点が輝いていた。
「よくもまあ、あんなことを」とサー・ヘンリーがつぶやいた。
「ここからだけ見える場所にあるのかもしれない。」
「たぶんな。どれくらい離れていると思う?」
「クレフト・トーのあたりだと思う。」
「一、二マイルもないくらいか。」
「そこまで遠くないだろう。」
「バリモアが食べ物を運んでいるのなら、さほど遠くはないはずだ。あの悪党は、ろうそくのそばで待っているのだな。ワトソン、私はあの男を捕まえに行くぞ!」
私も同じことを考えていた。バリモア夫妻が自発的に打ち明けたわけではなく、秘密は強引に引き出した。あの男は社会の脅威で、容赦も情けも無用の悪党だ。今この機会に彼を元の場所に戻すのは我々の義務だった。あの粗暴で凶暴な性格を思えば、我々が手をこまねいていれば他の誰かが犠牲になる。例えば、ステープルトン夫妻が夜に襲われる可能性だってある。それを思うと、サー・ヘンリーが強く決意する気持ちも理解できた。
「私も行こう」と私は言った。
「じゃあ、拳銃を持って靴を履いてくれ。早いほうがいい。やつは明かりを消して逃げてしまうかもしれない。」
五分後、我々は玄関を出ていた。暗い木立を急ぎ抜け、秋風のうなりと落ち葉のざわめきの中を進んだ。夜の空気は湿り気と腐敗の匂いに満ちていた。ときおり月が雲間から顔を出したが、すぐにまた雲が空を覆い、我々が原野に出るころには細い雨が降り始めていた。前方にはまだ明かりが変わらず燈っていた。
「武装しているか?」私は聞いた。
「狩猟鞭がある。」
「やつは危険な男だ。素早く近づいて、不意を突いて捕まえよう。」
「なあワトソン」と卿が言った。「ホームズなら何と言うだろう? あの“悪の力が高まる闇の一時間”というやつは?」
彼の言葉に応えるように、広大な原野の闇の中から、以前グリムペン湿地帯の端で聞いたあの奇妙な叫び声が突然響いた。夜の静寂を突き破り、風に乗ってやってきたその声は、長く低い唸りから高まる遠吠えへ、そして消えていく悲しい呻きへと変化した。何度も何度も空気が震えるほど響き渡り、鋭く、荒々しく、脅威に満ちていた。卿は私の腕にしがみつき、その顔は闇の中で真っ白に輝いていた。
「神よ、ワトソン、あれは何だ?」
「分からない。原野にこういう音があるんだ。前にも一度聞いた。」
その声は消え、静寂が我々を包んだ。耳を澄ませても何も聞こえなかった。
「ワトソン」と卿が言った。「あれは猟犬の叫びだった。」
彼の声がかすれていたので、突然襲った恐怖を私は感じた。
「この音を何と呼んでいる?」と彼が聞いた。
「誰が?」
「この辺りの人たちが。」
「田舎の無学な人たちだよ。彼らの言うことなど気にしなくていい。」
「教えてくれ、ワトソン。何と言っている?」
私はためらったが、問いから逃げられなかった。
「“バスカヴィル家の猟犬”の叫びだと。」
彼はうめき声を漏らし、しばらく黙っていた。
「あれは確かに猟犬だった」とついに言った。「だが、何マイルも遠く、あちらの方から聞こえたように思う。」
「どこからともなく響いていた。」
「風に乗って高まり、消えていった。あれはグリムペン湿地帯の方角じゃないか?」
「ああ、そうだ。」
「じゃあ、あそこだ。ワトソン、お前もあれが猟犬の声だと思ったろう? 私は子供じゃない。正直に言っていい。」
「前に聞いたときはステープルトン氏が一緒だった。彼は珍しい鳥の鳴き声かもと言っていた。」
「いや、猟犬だ。神よ、あの伝説に真実があるのか? 私があんな闇の力に狙われているなんてことが? お前は信じていないだろう、ワトソン?」
「いや、信じていない。」
「だが、ロンドンで笑っていたのと、こうして原野の闇の中であんな声を聞くのとはまるで違う。叔父が――叔父のそばには猟犬の足跡があった。すべてがつながる。私は臆病者じゃないが、あの声を聞くと血が凍る。手を触ってみてくれ!」
彼の手は大理石のように冷たかった。
「明日になれば大丈夫だ。」
「だが、あの声が頭から離れそうにない。どうすればいいと思う?」
「引き返そうか?」
「いや、絶対にだめだ。我々は男を捕まえるために来たのだ。あの脱獄犯を追い、地獄の猟犬が我々を追うかもしれん。それでも行くぞ! 原野に悪魔が放たれていようとやり遂げる!」
我々は闇の中、岩山が黒く取り囲む中を、前方の黄色い光点を目指してゆっくり進んだ。夜闇では光の距離は非常に錯覚しやすく、時には遥か地平線の上に、時にはすぐ目の前にあるように見えた。だがついに光の発する場所が分かり、ようやく本当に近づいたのだと確信した。風よけのように両側を岩で囲まれた隙間に、ちらつくろうそくが立てられていた。そのおかげで風に消されず、またバスカヴィル・ホールからしか見えない位置だった。花崗岩の大きな岩が我々の接近を隠してくれたので、身をかがめて合図の明かりを観察した。原野の真ん中に、命の気配もなく、ただ一本のまっすぐな黄色い炎と両脇の岩の輝きがあるのは不思議な光景だった。
「どうする?」とサー・ヘンリーが小声で聞いた。
「ここで待とう。彼はきっと明かりの近くにいる。姿が見えないか見てみよう。」
そう言い終わらないうちに、我々は彼を見つけた。ろうそくの立つ岩の隙間から、邪悪な黄色い顔――あらゆる悪徳の刻まれた恐ろしい獣の顔――が覗いた。泥まみれで、剛毛のような髭と絡まった髪をたくわえ、まるで昔この地の穴に住んでいた原始人のようだった。炎が彼の小さなずる賢い目に映り、右から左へと鋭く見回すその様子は、狩人の足音に気づいた野生の獣そのものだった。
何かに疑いを抱いたのは明らかだった。バリモアにしか分からない合図を与えなかったか、あるいは他の理由で何か異変を感じたのかもしれないが、その邪悪な顔に恐れがはっきり読み取れた。いつ明かりを消して闇に消えるかわからない。私は飛び出し、サー・ヘンリーも同時に動いた。囚人は我々を見て悪態を叫び、岩を投げつけてきたが、その岩は我々を隠していた岩に砕けて当たった。彼のずんぐりとした体が跳ね起きて逃げるのが一瞬見えた。ちょうどその時、運良く月が雲間から現れた。私たちは丘の頂上を走り抜け、男が丘の向こう側を山羊のような身のこなしで岩を跳び越えながら逃げていくのを見た。拳銃でうまく撃てば足を止められたかもしれないが、自分の身を守るために持ってきただけで、丸腰の逃走者を撃つ気にはなれなかった。
我々も健脚なほうだが、到底追いつけないとすぐに悟った。男は月明かりの中、遠くの岩山をすばやく移動する小さな点となっていった。息が切れるまで走り続けたが、距離はどんどん離れていった。ついに我々は立ち止まり、それぞれ岩に座り込んで、遠ざかる男を見送った。
そしてそのとき、非常に奇妙で思いがけないことが起こった。我々は岩から立ち上がり、追跡を諦めて帰ろうとした。右手の低い月の上に、ギザギザの花崗岩の頂が黒々と浮かび上がっていた。その月を背景に、漆黒の彫像のように、トーの上に男の姿が見えた。ホームズ、これは幻覚ではない。私は生涯でこれほどはっきりと何かを見たことがない。その男は高く痩せた体格で、足を少し広げ、腕を組み、頭を垂れて、広大な泥炭と花崗岩の荒野を見下ろしているようだった。まるであの恐ろしい地の精霊のようだった。それは脱獄犯ではなかった。さっきの男が消えた場所からは遠く離れているし、体格もはるかに大きい。私は驚きの声を上げて卿に指さしたが、その一瞬で男の姿は消えていた。鋭く突き出た花崗岩の頂だけが月の縁を切り取っていたが、そこにはもはや無言で動かない人影はなかった。
私はその方向へ行き、あの岩山を探したいと思ったが、そこまではかなり距離があった。バスカヴィル卿は、あの叫び声で神経がまだ震えており、それは一族の暗い過去を思い出させるものだったので、とても新たな冒険に乗り出す気分ではなかった。彼はあの岩山にいた孤独な男を目撃しておらず、その異様な存在感と威圧的な態度が私に与えた衝撃を理解することもできなかった。「きっと監視員だろう」と彼は言った。「あの男が逃げて以来、湿原にはそういう連中がたくさんいるんだ」まあ、彼の説明が正しいのかもしれないが、私はそれを裏付ける証拠がもう少し欲しいと思っている。本日、我々はプリンストンの人々に、失踪した男がどこにいるか知らせるつもりだが、彼を自分たちの手で捕まえて連れ戻すという栄誉を実際に得られなかったのは残念でならない。これが昨夜の冒険のすべてであり、親愛なるホームズ、私が報告の任を十分に果たしたことを認めてもらいたい。私が君に伝えていることの多くは、確かに本筋から外れているかもしれないが、それでもやはり、すべての事実を君に伝え、どの情報が君の推理に最も役立つかを君自身に選ばせるのが最善だと感じている。我々は確かに進展してはいる。バリモア夫妻に関しては、彼らの行動の動機がわかり、状況は大いに明らかになった。しかし、湿原とその不可思議な住人たちは、依然として謎に包まれている。もしかしたら、次の報告ではこの点にも光を当てることができるかもしれない。何よりも、君がこちらへ来てくれるのが一番なのだが。いずれにせよ、数日中にはまた連絡するつもりだ。
第10章 ワトソン博士の日記抜粋
これまでは、私がこの最初の数日間にシャーロック・ホームズへ送った報告書から引用していた。しかし今、私は記述を進めるうちに、この方法を続けられなくなり、再び当時つけていた日記と自分自身の記憶に頼らざるを得なくなった。ここから先は、その日記からいくつか抜粋し、私の記憶に細部まで鮮明に刻まれている場面へと進みたいと思う。まずは、脱獄囚を追ったものの失敗に終わり、その他さまざまな奇妙な体験をした翌朝から始める。
10月16日――どんよりとした霧と細雨の一日だった。館は湧き上がる雲に包まれ、時折それが上がると、うら寂しい湿原の起伏が、山の斜面に細い銀色の筋となって現れ、遠くの巨石が濡れて輝くのが見えた。外も中ももの悲しい雰囲気だ。バスカヴィル卿は、夜の興奮の反動で沈み込んでいる。私自身も胸に重苦しさを感じ、言い知れぬ危険の予感――常に付きまとう危険であり、その恐ろしさは明確にできないからこそ増していた。
このように感じるのも無理はないだろう。これまでの出来事の一連を考えてみれば、すべてが何らかの邪悪な力の働きを指し示している。館の前の当主の死、それは一族の伝説の条件を見事に満たしていたし、農民たちからは何度も湿原に奇怪な生き物が現れたという報告があった。私は自分の耳で、遠くで吠える犬のような音を二度聞いている。それが本当に自然の法則から外れたものだなどとは、到底信じがたい。物質的な足跡を残し、空気をその咆哮で満たす幽霊犬など、考えるべきではない。ステープルトン氏やモーティマーなら、そうした迷信に取り込まれるかもしれないが、私がこの世にあって誇れるものが一つあるとすれば、それは常識だ。いかなることがあろうとも、そのような存在を信じることはない。それを信じるのは、口から炎を吐く悪魔の犬まで語りたがるこの土地の哀れな農民たちと同じレベルに堕ちることだ。ホームズならそんな空想には耳を貸さないし、私は彼の代理人なのだ。しかし、事実は事実であり、私は二度もこの湿原であの鳴き声を聞いた。仮に本当に巨大な猟犬が放たれていたとしたら、すべての説明がつく。しかし、そんな犬がどこに身を潜め、何を食べているのか、どこから現れたのか、なぜ昼間誰にも目撃されていないのか――自然的な説明もまた、多くの難点を含んでいる。そして、犬とは別に、ロンドンでの人為的な行動――馬車の男や、バスカヴィル卿に湿原に近づくなと警告する手紙――もある。これは確かに現実の出来事だが、それは敵であると同時に、守ろうとする友人の仕業であった可能性もある。その友人、あるいは敵は今どこにいるのか? ロンドンにとどまっているのか、それともこちらまでついてきたのか? あの岩山で見たあの見知らぬ男こそが、その人物なのだろうか?
一度しかその男を見ていないのは事実だが、それでも断言できることがいくつかある。彼はこの地で見かけた誰でもなく、私は近隣住民すべてに会っている。ステープルトン氏よりもはるかに背が高く、フランクランド氏よりもはるかに痩せていた。バリモアの可能性も考えたが、彼は私たちの後ろにおり、私たちを追ってくることはできなかったはずだ。つまり、ロンドンで私たちをつけてきた見知らぬ男と同じように、今もまた見知らぬ男が我々をつけているのだ。我々はまだ彼を振り切れていない。もしあの男を捕まえることができれば、ついにすべての難題が解決に向かうかもしれない。私はこの目的のために全力を尽くすつもりだ。
最初の衝動は、自分の計画をすべてバスカヴィル卿に話すことだった。しかし、次に思い直し、むしろ独自に行動し、誰にも極力口を閉ざしておくのが賢明だと結論した。彼は沈黙し、上の空である。あの湿原の音で彼の神経は著しく動揺している。私は、さらに彼の不安を煽るようなことは何も言わず、自分の目的のために独自に行動することにする。
今朝、朝食後にちょっとしたやりとりがあった。バリモアがバスカヴィル卿に話をしたいと願い出て、しばらく書斎に籠もっていた。私はビリヤード室で何度か声を荒げるのを聞き、その話題が何であるかほぼ察しがついていた。やがて卿がドアを開けて私を呼んだ。「バリモアは不満があるらしい」と彼は言った。「彼は、義弟のことを自分の意志で打ち明けたのに、我々がそれを利用して追い詰めたのは不公平だと考えている」
執事は青ざめてはいたが、落ち着いて立っていた。
「口調が過ぎたかもしれません、旦那様」と彼は言った。「もしそうなら心からお詫びします。ただ、今朝お二人が帰ってきて、セルデンを追いかけていたと知ってとても驚いたのです。あの男も十分苦しんでいるのに、私まで追い討ちをかけたくはありませんでした」
「自分からすべて話してくれていたなら、また別のことだった」とバスカヴィル卿。「だが君は――いや、正確に言えば君の奥さんは――追及されて仕方なく話したのだ」
「まさかそれを利用なさるとは思いませんでした、旦那様。本当にそうは思いませんでした」
「あの男は社会の危険だ。湿原には孤立した家が点在しており、奴の顔つきを見れば、何をしでかしてもおかしくないと分かる。例えばステープルトン氏の家など、彼しか守る者がいない。奴が逮捕されるまでは誰も安全ではいられない」
「絶対に家に押し入ったりしません。これだけは誓って申し上げます。ただし、もう二度とこの国で人に迷惑をかけることはありません。数日もすれば、必要な手はずが整い、南アメリカへ向かうことになります。どうか、旦那様、警察に彼がまだ湿原にいることは伝えないでください。警察も追跡を諦めましたし、船が用意できるまで静かに身を潜めていられるのです。あなたが警察に知らせれば、私も妻も巻き込まれてしまいます。どうか、警察には何も言わないでください」
「ワトソン、君はどう思う?」
私は肩をすくめた。「無事に国外へ出てくれれば、納税者の負担も減るだろう」
「だが、出発までの間に誰かを襲う可能性は?」
「そんな無茶なことはしません。必要なものはすべて渡しました。犯罪を犯せば、隠れ家がばれてしまいます」
「その通りだ」とバスカヴィル卿。「よし、バリモア――」
「神のご加護を、旦那様。本当にありがとうございます。もしまた捕まっていたら、妻はきっと耐えられなかったでしょう」
「我々は重罪の共犯者になったようだな、ワトソン? だが、今聞いた話を聞けば、もう彼を引き渡す気にはなれない。これでおしまいだ。いいか、バリモア、もう行っていい」
男は感謝の言葉をつぶやきながら部屋を出ようとしたが、ふいにためらい、戻ってきた。
「旦那様には大変よくしていただきましたから、何かお役に立てればと思います。実はひとつ知っていることがありまして、もっと早くお伝えすべきだったのかもしれませんが、調査のずっと後になって分かったことです。これまで誰にも話したことはありません。サー・チャールズの死についてです」
バスカヴィル卿と私は、思わず身を乗り出した。「死因が分かったというのか?」
「それは分かりません」
「では何が?」
「あの晩、彼がなぜ門のところにいたのか、その理由を知っています。女性に会うためでした」
「女性に会う? 彼が?」
「はい、旦那様」
「その女性の名前は?」
「名前は分かりませんが、イニシャルなら分かります。L. L. です」
「どうしてそれが分かったんだ、バリモア?」
「ええ、旦那様、叔父様はあの朝、手紙を受け取ったんです。彼は公の人物で、その親切な性格から、困っている人はみな助けを求めて手紙を送ってきました。だから普段なら何通も届くのですが、その朝はたまたま一通だけでした。それでよく覚えているのです。その手紙はクーム・トレーシーからで、女性の筆跡でした」
「それで?」
「そのまま何も気にせず終わるはずでしたが、つい先日、妻がサー・チャールズの書斎を掃除していた際――死後、一度も手をつけていなかったのですが――暖炉の奥に燃え残りの手紙の灰を見つけまして。その大半は炭化していましたが、ページの端の一部だけはつながっていて、黒い地に灰色の文字が読めました。それは手紙の追伸のようで、こう書かれていました。『どうか、どうか、紳士としてこの手紙を焼いてください。そして十時に門のところへ来てください』。その下に L. L. のイニシャルがありました」
「それは残っているのか?」
「いえ、旦那様。動かしたらバラバラになってしまいました」
「その筆跡の手紙を他にも受け取っていたことは?」
「いえ、特に気にして見ていませんでした。たまたま一通だけだったので覚えているのです」
「L. L. とは誰か、見当もつかないのか?」
「いいえ、旦那様。あなたがたと同じく分かりません。でも、その女性を突き止められれば、サー・チャールズの死についてもっと分かると思います」
「バリモア、なぜこれほど重要な情報を隠していたんだ?」
「それが分かった直後に、私たち自身の問題が起きまして。それに何より、私も妻もサー・チャールズには大変お世話になっていましたので、お亡くなりになったご主人のためにも、女性が絡んでいる以上、軽々しく掘り返すべきではないと思ったのです。誰しも――」
「ご主人の名誉を傷つけると思ったのか?」
「いえ、何の利益もないと思ったのです。でも今、あなたがたに親切にしていただいたので、知っていることはすべてお話ししておくのが誠実だと思いました」
「よろしい、バリモア。もう行っていい」執事が部屋を出ていくと、バスカヴィル卿は私に向き直った。「さて、ワトソン、この新事実をどう思う?」
「闇がますます深くなったように思えます」
「僕もそうだ。しかし、L. L. の正体さえ突き止められれば、すべてが解明するだろう。少なくとも、事実を知っている人物がいることが分かった。どうすべきだと思う?」
「すぐにホームズに知らせましょう。彼が探し求めていた手がかりになるはずです。もし彼を呼び寄せることにならなければ、私の勘違いです」
私はさっそく自室に戻り、この朝の会話を報告書にまとめてホームズ宛に送った。彼からのベーカー街の手紙は最近、短く簡潔なもので、私が提供した情報についてのコメントもほとんどなく、私の任務についてもほぼ言及がなかった。きっと恐喝事件に全力を注いでいるのだろう。しかし、この新たな要素にはきっと注意を引かれるはずだし、再び興味を持ってくれるだろう。今ここに彼がいればと思う。
10月17日――今日は一日中雨が降りしきり、ツタの上をざわめき、軒から滴り落ちていた。あの寒々しく、吹きさらしの湿原にいる脱獄囚のことを考えた。哀れな男だ。どんな罪を犯したにせよ、十分な苦しみを味わってきたはずだ。そして、もうひとりの男――馬車の中の顔、月に浮かぶ影――のことも思い浮かべた。彼もまた、豪雨の中で、あの見えざる監視者、闇の男として彷徨っているのだろうか。夜、私は防水外套をまとい、雨が顔に打ちつけ、風が耳元で唸る中、陰鬱な想像に満ちてぬかるんだ湿原を歩き回った。今や堅い高地さえ沼地と化し、こんな時に大湿原に足を踏み入れる者には神のご加護が必要だろう。私はあの孤独な監視者を見かけた黒い岩山を見つけ、そのごつごつした山頂から、私自身もまた寂しげな丘陵地帯を見渡した。赤茶けた大地に雨雲が流れ、重く鉛色の雲が低く垂れ、奇妙な丘の斜面に灰色の帯を引いていた。左手の霧に半ば隠れた谷間には、バスカヴィル館の二本の細い塔が木々の間から突き出ていた。それ以外に人間の営みを示すものは見当たらず、ただ丘の斜面に点在する先史時代の小屋跡だけがあった。二晩前に同じ場所で見たあの男の姿はどこにもなかった。
帰り道、フォウルマイアの奥地にある農家から続く荒れた湿原道を、モーティマー医師がドッグカートでやってきて、私を追い越した。彼はこれまで私たちによく気を配ってくれており、ほとんど毎日館に様子を見に来ている。彼は半ば強引に私をカートに乗せ、家まで送ってくれた。彼は自身の飼っていた小さなスパニエルが行方不明になったことを大いに気にしていた。その犬は湿原に迷い込んだまま戻ってこなかったのだ。私はできるかぎり慰めの言葉をかけたが、グリムペン湿地の小馬のことを思い出し、その犬が再び戻ることはないだろうと内心思った。
「ところで、モーティマー」と私は荒れた道を揺られながら話しかけた。「この辺りで君の知らない人はほとんどいないのだろう?」
「ほとんどいないと思うよ」
「では、イニシャルがL. L.の女性を知っているか?」
彼はしばらく考えていた。
「いや、農夫や地主の中にはいない。でもジプシーや労働者の中には分からない人もいる。――いや、待てよ」と彼は少し考えた後に付け加えた。「ローラ・ライアンズという女性がいる。イニシャルはL. L.だ。彼女はクーム・トレーシーに住んでいる」
「どんな人物なんだ?」
「フランクランド氏の娘だ」
「なんだって! あの偏屈なフランクランドの?」
「そう。画家のライアンズという男と結婚したが、あいつはろくでなしで、スケッチに来ては彼女を見捨てていったらしい。どうやら、悪いのは一方的ではなかったようだ。父親のフランクランド氏は、許可なく結婚した彼女に一切かかわろうとしなかったし、他にも理由があったようだ。そんなわけで、老人と若者、どちらも罪人で、この娘はひどい目にあっている」
「どうやって暮らしている?」
「フランクランド氏がわずかに仕送りしているらしいが、自分の財政も混乱しているから大した額ではなさそうだ。どんな理由があろうと、彼女を完全に破滅させるわけにはいかない。彼女の身の上話は広まり、何人かが彼女の自立を助けてやった。ステープルトン氏もそうだし、サー・チャールズもしかり。私も少しばかり出したよ。タイプライター事務を開設してやったんだ」
彼は私の問いの目的を知りたがったが、私はうまくはぐらかした。私たちの調査に誰も巻き込む必要はない。明朝にはクーム・トレーシーへ出向き、この曰くありげなローラ・ライアンズ夫人に会うことができれば、この謎の連鎖の一端は大きく明らかになるはずだ。私は確かにヘビのごとき知恵を身につけてきた。というのも、モーティマーが不都合なほど詮索を始めたとき、私はさりげなくフランクランド氏の頭蓋骨の型について尋ねてみせ、それから先はずっと骨相学の話に終始したからだ。私はシャーロック・ホームズと何年も暮らしてきた甲斐があった。
この荒れ狂うもの悲しい日の最後に、もうひとつ記しておくべき出来事がある。先ほどバリモアと交わした会話で、私はまたひとつ重要な切り札を得たのだ。
モーティマーは夕食まで残り、その後バロネットとエカルテをした。執事が図書室にコーヒーを持ってきてくれたので、私はその機会にいくつか質問をすることにした。
「さて」と私は言った。「君の大事な親類は出ていったのか、それともまだあそこに潜んでいるのか?」
「わかりません、旦那様。どうか出ていってくれていることを祈りますよ、ここには厄介ごとしかもたらしていませんから! 最後に食べ物を置いておいてからは何も聞いてません。それも三日前のことです。」
「その時は彼に会ったのか?」
「いいえ、旦那様。でも次に行った時には、もう食べ物がなくなっていました。」
「じゃあ、確かに彼がそこにいたんだな?」
「そう思われますよ、旦那様、もし他の男が持っていかなければ。」
私はコーヒーカップを口に運びかけたまま、バリモアをじっと見つめた。
「じゃあ君は、もう一人別の男がいると知っているのか?」
「はい、旦那様。あの荒野にはもう一人います。」
「その男を見たことがあるのか?」
「いいえ、旦那様。」
「じゃあ、どうやって知ったんだ?」
「セルデンが、旦那様、一週間ほど前に教えてくれました。あいつも隠れてますが、私の知る限り囚人じゃないようです。ワトソン先生、私はあまり気味が良くありません――はっきり申し上げますが、どうにも不安です。」彼は突然、真剣な情熱を込めて言った。
「よく聞きなさい、バリモア! 私はこの件について、君の主人以外に何の利害も持っていない。彼を助けるためだけにここに来ている。君が不安に思っていることを率直に教えてくれ。」
バリモアはしばらくためらった。自分の感情を言葉にするのが難しいか、先ほどの激情を後悔しているようだった。
「全部が気味悪いんです、旦那様」と彼はついに叫び、荒野に面した雨に打たれる窓の方へ手を振った。「どこかで悪事が企まれていて、何か大きな悪が進行していると誓ってもいい! ヘンリー卿がロンドンに戻るのを見るのが本当に嬉しいですよ!」
「だが、何がそんなに君を怯えさせているんだ?」
「サー・チャールズの死をご覧ください! 検視官が何と言おうと、あれだけでも十分に恐ろしいことでした。夜の荒野の物音もそうです。金を積まれても日が沈んだ後にあそこを横切る男はいませんよ。あそこに隠れて、じっと見張っているあの見知らぬ男もそうです! 彼は何を待っているんでしょう? 何を意味しているんでしょう? バスカヴィルの名を持つ者にとっては、ろくなことにはならない。私はヘンリー卿の新しい召使いが屋敷を引き継ぐ日には、これら全てから解放されて本当に嬉しいですよ。」
「その見知らぬ男についてだが」と私は言った。「何か知っていることはあるか? セルデンは何と言っていた? 奴の隠れ場所や、何をしていたのかは?」
「あいつは一、二度その男を見たが、なかなか用心深くて何も漏らさないそうです。最初は警察かと思ったが、すぐに自分の目的で動いていると分かったそうです。見たところ紳士風の男らしいですが、何をしているのかは全く分からなかったようです。」
「どこに住んでいると言っていた?」
「丘の斜面にある古い住居――昔の人が使っていた石の小屋の中です。」
「食べ物はどうしているんだ?」
「セルデンが調べたところ、あの男には手伝いの少年がいて、必要な物を運んできているそうです。おそらくクーム・トレーシーまで買い物に行っているのでしょう。」
「よろしい、バリモア。この件についてはまたいずれ話そう。」執事が去った後、私は黒い窓のそばへ歩き寄り、曇ったガラス越しに吹きすさぶ雲と風に揺れる木々の影を見つめた。屋内でさえこれほど荒れた夜、あの荒野の石の小屋ではどれほどだろうか。こんな場所、こんな時に潜み続けるほどの憎悪が、いったい人の心にどれほど強く燃えているのか。そして、これほどまでに自分を追い詰めてまで成し遂げようとする深い目的とは何なのか。あの荒野の小屋こそが、私をこれほど苦しめてきた謎の中心なのだろう。もう一日たりともこの核心に迫る努力を怠るまいと誓った。
第十一章 トーの男
私の日記の抜粋であった前章は、奇怪な出来事が恐ろしい結末へと急速に動き出す十月十八日までの物語を語った。続く数日間の出来事は今も鮮明に心に刻まれており、当時の記録を参照せずとも語ることができる。次の話は、私が二つの重要な事実――クーム・トレーシーのローラ・ライアンズ夫人がサー・チャールズ・バスカヴィルに手紙を書き、彼の死の現場と同じ場所・時刻に会う約束をしていたこと、そして荒野に潜む男が丘の石の小屋にいること――を突き止めた翌日から始まる。この二つの事実を得てなお暗闇を照らせなければ、私の知恵か勇気が欠けていることになるだろう。
前夜はモーティマー医師が夜遅くまでヘンリー卿とカードをしていたため、私がライアンズ夫人について知ったことを彼に話す機会はなかった。しかし朝食時にその発見を伝え、クーム・トレーシーまで同行したいか尋ねた。最初は彼も乗り気だったが、しばらくして二人で考えると、むしろ私一人で行った方が良い結果が得られるのではないかという結論になった。形式張った訪問ほど話を引き出しにくいからだ。私は少し後ろめたさを感じつつ、ヘンリー卿を残して新たな探索に出発した。
クーム・トレーシーに着くと、パーキンズに馬の世話を頼み、目的の婦人について尋ねて回った。彼女の部屋はすぐに見つかり、中心街にあり立派なものだった。メイドに案内されると、部屋の奥でレミントン式タイプライターの前に座っていた女性が、私を見るなりにこやかに立ち上がって迎えてくれた。しかし私が見知らぬ男だとわかると表情が曇り、再び椅子に腰かけて訪問の目的を問いかけてきた。
ライアンズ夫人の第一印象は、非常に美しいというものだった。目も髪も濃いヘーゼル色で、頬はかなりそばかすが目立つものの、褐色の肌にバラの中心にひそむような繊細なピンク色が浮かんでいた。感嘆――それが私の最初の印象だ。しかし次には批評の念が生まれた。どこかしら顔立ちに微妙な違和感があり、表情に粗さ、目に冷たさ、唇にゆるさのようなものが、その美しさを損なっていた。しかし、そうした印象は後から浮かぶものであり、その時私はただ美しい女性の前にいて、彼女が訪問の理由を尋ねていることを意識していた。私はこの任務がいかに繊細なものであるかを、その瞬間まで理解していなかったのだ。
「ご尊父を存じております」と私は口火を切った。
ぶしつけな切り出しであったが、婦人はそれをきっぱりと感じさせた。「父と私には何の共通点もありません」と彼女は言った。「私は父には何の恩も感じていませんし、彼の友人も私の友人ではありません。亡きサー・チャールズ・バスカヴィルや他の親切な方々がいなければ、父は私が飢え死にしても平気だったでしょう。」
「実は、そのサー・チャールズ・バスカヴィルのことでお話しに参りました。」
婦人の顔のそばかすが浮き立った。
「彼について私が何をお話しできるでしょうか?」と彼女は言い、指先でタイプライターのキーをいじりながら緊張を見せた。
「あなたは彼と知り合いだったのですね?」
「すでに申し上げた通り、彼の親切にはとても感謝しています。私が自立できているのは、主に彼が私の不幸な状況に関心を持ってくれたおかげです。」
「彼と文通していましたか?」
婦人は素早くヘーゼル色の目に怒りをきらめかせて私を見上げた。
「その質問の目的は何ですか?」と彼女は鋭く問い返した。
「目的は公のスキャンダルを避けることです。ここで私が尋ねる方が、事態が私たちの手の及ばぬところに行くより良いでしょう。」
彼女は沈黙し、顔はますます青ざめていた。やがて、どこかやけっぱちな挑戦的な様子で私を見上げた。
「いいでしょう、お答えします。ご質問は何ですか?」
「サー・チャールズと文通していましたか?」
「確かに、彼の思いやりと寛大さに感謝して、何度か手紙を書きました。」
「その手紙の日付は覚えていますか?」
「いいえ。」
「彼に会ったことは?」
「はい、クーム・トレーシーへ来られた時に一、二度。彼は非常に控えめな方で、善行も人目につかぬようにされる方でした。」
「それほどめったに会わず、また手紙もあまり書かないのに、どうして彼はあなたの事情をよく知り、助けることができたのでしょうか?」
彼女は即座に私の疑問に答えた。
「私の悲しい身の上を知る紳士が何人かいて、その方々が一致して私を助けてくれたのです。その一人がサー・チャールズのご近所で親友だったステープルトン氏です。彼は非常に親切で、サー・チャールズは彼を通じて私の事情を知りました。」
私はすでに、サー・チャールズが何度かステープルトン氏に施しを託していたことを知っていたので、婦人の話には真実味があった。
「サー・チャールズに会ってほしいと頼む手紙を書いたことは?」
ライアンズ夫人は再び怒りで顔を紅潮させた。「本当に、これは非常に妙なご質問です。」
「失礼ですが、もう一度伺います。」
「では、はっきり申し上げますが、絶対にありません。」
「サー・チャールズの死の日には?」
その瞬間、紅潮は消え、死人のような顔になった。彼女の乾いた唇は「いいえ」とも言えず、私はそれを聞くより先に見て取った。
「あなたの記憶違いでしょう」と私は言った。「手紙の一節を引用することもできます。――『どうか、どうか紳士としてこの手紙を焼いてください。そして十時に門へ来てください』と。」
彼女は気を失いかけたようだったが、必死の努力で持ち直した。
「紳士というものはいないのですか?」と彼女は苦しげに言った。
「あなたはサー・チャールズに不正をなさった。彼は確かに手紙を焼いた。しかし焼かれても判読できる場合もあります。今こそお認めになりますか、あなたが書かれたのですね?」
「はい、書きました!」と彼女は魂を吐き出すように叫んだ。「私は書きました。否定する必要なんてありません。助けてほしかったからです。お会いできれば力を貸していただけると思ったので、会ってほしいと頼んだのです。」
「なぜそんな時間に?」
「その時初めて、彼が翌日ロンドンへ行くと知り、数か月も戻らないかもしれないと思ったのです。早く行くのは無理な理由がありました。」
「なぜ屋敷への訪問ではなく、庭での待ち合わせだったのですか?」
「その時間に独身男性の家に女性が一人で行けると思われますか?」
「で、実際に行ったのですか?」
「行きませんでした。」
「ライアンズ夫人!」
「いえ、これは神に誓って本当です。何かが邪魔して行けなかったのです。」
「それは何です?」
「それは私的なことなのでお話しできません。」
「では、サー・チャールズとまさに彼の死の場所と時刻で会う約束はしたが、実際には行かなかったと認めるのですね?」
「それが真実です。」
私は繰り返し問い詰めたが、それ以上のことは引き出せなかった。
「ライアンズ夫人」と私は長く、実りの少なかった面談の最後に言った。「あなたは全てを率直にお話しにならないことで、大きな責任を負い、ご自身を非常に不利な立場に追い込んでいます。警察の助けを求めることになれば、どれほどご自身が危うくなるかお分かりでしょう。もし潔白なら、なぜ最初からその日のサー・チャールズへの手紙を否定したのですか?」
「それを理由に誤解されて、スキャンダルに巻き込まれるのが怖かったのです。」
「なぜサー・チャールズに手紙を焼くようにそれほど強く頼んだのですか?」
「もし手紙をご覧になったのなら、お分かりでしょう。」
「私は全ての内容を読んだとは言っていません。」
「でも一部を引用しました。」
「追伸だけです。手紙は焼かれていて、全部が読めたわけではありません。もう一度伺います。なぜ彼の死の日に受け取ったその手紙を、サー・チャールズが焼くよう何度も頼んだのですか?」
「それはとても個人的な理由です。」
「だからこそ、公の調査を避けるべきなのです。」
「わかりました。お話ししましょう。ご存じかもしれませんが、私は軽率な結婚をして大変後悔しています。」
「そのことは聞いています。」
「私は嫌悪する夫からの絶え間ない迫害に悩まされています。法律は夫の味方で、いつまた一緒に暮らすことを強いられるかわかりません。この手紙を書いた時、ある出費さえ賄えれば自由になれるかもしれない望みが出てきました。それは私にとって――心の平安、幸せ、自尊心――全てを意味しました。サー・チャールズの寛大さを知っていたので、直接事情を話せば助けてくださると思ったのです。」
「では、なぜ会いに行かなかったのですか?」
「その間に、別の方から援助を受けたのです。」
「それならサー・チャールズに説明の手紙を書けばよかったのでは?」
「そうするつもりでしたが、翌朝新聞で彼の死を知ったのです。」
彼女の話は筋が通っており、私の質問でもそれを崩すことはできなかった。私にできるのは、事件当時に本当に夫への離婚訴訟を起こしていたかどうかを調べることだけだった。
もし彼女が本当にバスカヴィル・ホールへ行っていたなら、それを否定するのは危険である。そこに連れて行くには罠が必要だし、朝までクーム・トレーシーへ戻れないだろう。そのような外出は隠し通せるものではない。したがって彼女の話はおそらく真実、あるいは少なくとも一部は真実だろう。私は困惑し、落胆して帰路についた。またしても、私の使命の目的地へ至る道のすべてを塞ぐ壁に突き当たったのだった。しかし、彼女の顔と態度を思い返すたびに、何かを隠しているとしか思えなかった。なぜあれほど青ざめるのか。なぜ強く否定し続けるのか。なぜ事件当時これほど口を閉ざしていたのか。その説明が、果たして彼女の言うような無邪気なものであるだろうか。しばらくはこれ以上進展できそうにないので、もう一つの手がかり――荒野の石の小屋――を探るしかなかった。
しかし、それは極めて曖昧な情報だった。帰路の馬車で、丘ごとに古代人の痕跡が残っていることに気づきながら、そのことを痛感した。バリモアの話は「見知らぬ男はこれらの廃屋の一つに住んでいる」というだけで、こうした小屋は荒野中に何百と点在している。しかし私には、自分自身の経験という道しるべがあった。実際にブラック・トーの頂でその男の姿を見ているからだ。ならばそこを中心に、荒野のすべての小屋を一つ一つ探せば、必ずや正しい小屋を突き止められるはずだ。もし中に男がいれば、いざとなれば拳銃を突きつけてでも、彼が誰なのか、なぜこれほど長く我々をつけ回しているのかを白状させてやる。リージェント・ストリートの人混みなら逃げられるかもしれないが、孤独な荒野で同じことはできまい。反対に、小屋を見つけても中にいなければ、何時間でも何日でも、彼が戻るまで見張り続けてやる。ロンドンでホームズが逃した相手だ――私がここで捕まえることができれば、大きな手柄となるだろう。
今回の調査では何度も運が味方しなかったが、ついに幸運が私の側にやって来た。その幸運の使者は、他ならぬフランクランド氏だった。彼は灰色の髭を生やし赤ら顔で、庭の門の外、高速道路に面した場所に立っていた。
「やあ、ワトソン先生」と彼は珍しく上機嫌で叫んだ。「馬に休ませてグラス一杯やりに入ってください。祝いの乾杯です!」
娘への態度を思えば彼への好感は持てなかったが、パーキンズと馬車を先に屋敷へ帰らせるには好都合だった。私は馬車を降り、ヘンリー卿には夕食に間に合うよう歩いて戻ると伝言を頼み、フランクランドの食堂に入った。
「今日は、私の人生で特別な日ですよ! ――記念すべき勝利の日だ!」と彼は何度も満足げに笑いながら言った。「二つの事件で勝利しました。この地方の連中に法律が法律であること、そして法を恐れぬ男がここにいることを教えてやるつもりです。ミドルトン翁の公園のど真ん中、玄関から百ヤードの所まで、私が通行権を勝ち取ったのですよ。どう思います? これであの権力者たちも庶民の権利を踏みにじれないと分かるでしょう、まったく! それからフェーンワーシーの連中がピクニックしていた森も閉鎖しましたよ。あの連中は土地の権利などないと思っているらしい、どこでも好き勝手に入り込んで、紙や瓶を散らかす。どちらの件も、ワトソン先生、私の勝利です。こんな嬉しい日は、サー・ジョン・モーランドが自分の猟場で猟をしたことで私が訴えた時以来ですよ。」
「どうやってそんなことを?」
「書籍で調べてみなさい、先生。面白いものですよ――『フランクランド対モーランド』、『クイーンズ・ベンチ裁判所』。200ポンドかかりましたが、判決は私のものです。」
「何か役に立ったのかね?」
「まったく、先生、まったく役に立ちませんでした。私がこの問題に興味を持っていないことを誇りに思っています。私は完全に公的義務感から行動しているのです。たとえば、フェンワージーの住民が今夜、私の人形を焼いて見世物にすることは間違いありません。前回も警察に、あんな恥ずべき催しはやめさせるべきだと言いましたが、郡警察の現状はスキャンダラスなものでして、私が当然受けるべき保護もしてくれません。フランクランド対レジーナ事件で、この問題は世間の注目を集めることでしょう。彼らには、私への扱いを悔いる時が来るだろうと言いましたが、もうすでに私の言葉は現実となっています。」
「どうしてです?」と私は尋ねた。
老人は得意げな表情を浮かべた。「というのも、私は彼らが知りたくてたまらないことを知っているからだ。しかし、どんなことがあっても、私はあの悪党どもに何の協力もしない。」
私は、この無駄話から逃げ出す口実を探していたのだが、今やもっと話を聞きたくなった。この老人のひねくれた性格は十分に見てきたので、強い関心を示すことが、彼の秘密を聞き出す上で最も確実な障害になると分かっていた。
「密猟か何かの話かな?」と私は無関心を装って言った。
「はは、坊や、そんなことよりずっと重要なことだよ! あの荒野の脱獄囚の件はどうだ?」
私は驚いて見つめた。「まさか、その居場所を知っているのか?」
「正確な場所までは知らないかもしれないが、警察に手を貸せば、確実に捕まえさせることができる。あの男を捕まえるには、まず食料の入手先を突き止めることだと気付いたことはないのかね?」
彼は確かに真実にかなり近づいているようだった。「確かに」と私は答えた。「だが、どうしてあの男がまだ荒野にいると分かる?」
「自分の目で、あの男に食料を運ぶ使者を見たからだよ。」
私はバリモアのことを思い、心が沈んだ。この意地の悪い噂好き老人の手にかかるのは重大なことだった。しかし、次の彼の言葉で、私はほっとした。
「君も驚くだろうが、食料を運んでいるのは子どもだよ。私は毎日、屋根の上の望遠鏡でその子を見ている。毎日同じ道を同じ時間に通る。あの子が向かう先は、脱獄囚以外に考えられないじゃないか。」
これは幸運だった。しかし私は興味を示すまいとした。子どもだ! バリモアは、正体不明の者の食料係は少年だと言っていた。フランクランドは脱獄囚ではなく、その少年を追っていたのだ。彼の知識が得られれば、私は長く苦しい捜索をしなくて済むかもしれない。だが、疑いと無関心こそが最良の手段だと悟った。
「むしろ、あれは荒野の羊飼いの息子が父親の昼食を運んでいるのでは?」
わずかな反論でさえ、老人独裁者の怒りに火をつけた。彼の目は私を憎々しげに見て、灰色の髭は怒った猫のように逆立った。
「本当にそう思うのかね!」と彼は、遠く広がる荒野を指さした。「あそこにあるブラック・トアが見えるか? その向こうにイバラの生えた低い丘があるだろう? あれは荒野の中でも一番岩だらけの場所だ。そんな所に羊飼いがいるものか。君の意見は実に馬鹿げている。」
私は素直に、「事情を知らずに申し上げました」と答えた。私の従順さが彼を満足させ、更なる秘密を引き出した。
「私が意見を持つ時には、必ず十分な根拠があるのだ。私はあの少年を何度も見ている。彼は毎日、時には一日に二度も、包みを持って……いや、待ちなさい、ワトソン博士。私の目が欺いているのか、それとも今まさにあの丘の斜面に何か動いているものがあるか?」
数マイル先だが、くすんだ緑と灰色の中に、小さな黒い点がはっきり見えた。
「さあ、先生、早く来てください!」フランクランドは叫び、階上へ駆け上がった。「あなた自身の目で確かめてください!」
三脚に据えられた立派な望遠鏡が、家の平らな屋根に置かれていた。フランクランドはそれを覗き、満足げな声を上げた。
「急いで、ワトソン博士、早く、丘を越えてしまう前に!」
確かに、そこにいた。小さな包みを肩にかついだ小柄な少年が、丘をゆっくりと登っていた。頂上に達したとき、私はそのぼろぼろで粗野な姿が、冷たい青空を背景に一瞬浮かび上がるのを見た。彼は周囲を用心深く、追跡を恐れる者のような様子で見回した。そして丘の向こうへ姿を消した。
「どうだ、間違いないだろう?」
「確かに、何か秘密の用事を持つ少年のようだ。」
「その用事が何かは、どんな田舎の警官でも見当がつくさ。しかし、私は絶対に一言も教えないし、ワトソン博士、あなたにも口止めしておく。絶対に一言もだ、分かったかね?」
「分かりました。」
「私はあの連中からひどい仕打ちを受けてきた――本当にひどいものだ。フランクランド対レジーナ事件で真実が明るみに出れば、国中が憤りで震えることだろう。私は警察には絶対に協力しない。あいつらにとっては、私の人形でなく私自身が火あぶりにされても平気だっただろう。まさかもう帰るのではないだろうな? この偉大な記念日に、私と一緒にデカンタを空けてくれ!」
だが、私は彼の誘いをすべて断り、彼が私と一緒に歩いて家まで送ろうという申し出も思いとどまらせることに成功した。彼の目が届く間は道路を歩き、やがて荒野へ入り、少年が消えた石だらけの丘を目指した。すべてが私に味方していた。私は、この千載一遇の機会を、努力や忍耐の不足で逃すことだけはないと心に誓った。
丘の頂上に着いた時、太陽はすでに沈みかけており、長い斜面は片側が金緑色に、反対側が灰色の影に覆われていた。遥かな地平にはもやがかかり、その中からベリヴァーとヴィクゼン・トアの奇妙な形が突き出ていた。広大な荒野には、音も動きもなかった。大きな灰色の鳥――カモメかチドリか――が青空高く舞い上がっていた。私とその鳥だけが、空の巨大なアーチと、その下の荒れ地との間に生きている者だと思えるほどだった。荒涼たる風景、孤独感、そして私の任務の謎めいた緊張感が、私の心に冷たいものをもたらした。少年の姿はどこにもなかった。しかし、下方の丘の裂け目には、古い石造りの小屋の輪があり、その中にだけ屋根の残るものが一つあった。私は心が踊った。ここが、見知らぬ者の巣なのだ。ついに私は彼の隠れ家の敷居に立った――彼の秘密は、もう手の届くところにある。
私は慎重に小屋へ近づきながら、ステープルトン氏が網を構えて蝶へ近づくように、ここが実際に住まわれてきた形跡があることを確かめた。岩の間には曖昧な小道があり、崩れかけた入口が扉代わりになっていた。中は静まりかえっていた。中に例の人物が潜んでいるのか、あるいは荒野を徘徊しているのかもしれない。私は冒険への高揚を感じた。煙草を投げ捨て、拳銃のグリップを手にし、素早く戸口まで行き、中を覗き込んだ。中は空だった。
だが、私が道を間違えていない証拠は十分にあった。ここが確かに男の住処なのだ。防水布に巻かれた毛布が、かつて新石器時代の人が眠った石板の上に横たわっていた。粗末な炉には火の灰が積もり、傍らには調理器具や半分水の入ったバケツがあった。空き缶が散乱し、長く滞在していたことを物語っている。目が薄暗さに慣れてくると、隅にはコップと半分ほど酒の入った瓶が見えた。中央には平らな石がテーブル代わりになり、その上には小さな布に包まれた包み――間違いなく少年の肩にかかっていたものだ――があった。中身はパン、缶詰のタン、桃の缶詰が二つ。私はそれを調べて、元に戻した時、下に何やら書き付けのある紙片があるのを見つけた。拾い上げると、鉛筆で乱雑にこう書かれていた――「ワトソン博士はクーム・トレーシーへ行った。」
私はその紙を手にしばし立ち尽くし、この簡潔な伝言の意味を考えた。つまり、追跡されていたのはサー・ヘンリーではなく、私自身なのだ。この謎の男は自分で私を尾行せず、少年――おそらくは――に後をつけさせ、この報告を受け取ったのだろう。私が荒野に来て以来、何もかも見張られ、報告されていたのかもしれない。常に何か見えない力、どこまでも巧妙で繊細な網に絡め取られている感覚があったが、それは決定的な瞬間にだけ、自分が本当に絡め取られていたと実感させられるのだ。
もし報告が一つあるなら、他にもあるかもしれないと、私は小屋の中を探した。しかし他には何もなく、この奇妙な住人の性格や目的を示すものは見当たらなかった。ただ、スパルタ的な生活をしており、快適さには無頓着な人物だということだけは分かった。激しい雨を思い出し、穴だらけの屋根を見上げると、彼をここに留まらせている意志の強さと不変さを理解した。彼は我々の敵なのか、それともひょっとして守護天使なのか? 私は、この小屋の正体を突き止めるまで絶対に離れないと誓った。
外では太陽が沈みかけ、西の空は真紅と金に燃えていた。その反射が、グリムペン湿地の中の遠い水たまりに赤く映っていた。バスカヴィル館の二つの塔が見え、グリムペン村を示す煙も遠くにぼんやり見えた。その二つの間、丘の向こうにはステープルトン家の屋敷がある。すべてが黄金色の夕暮れの中、甘く穏やかで平和だったが、私の心は自然の平和を分かち合えず、むしろ差し迫る面会の曖昧さと恐怖に震えた。神経を高ぶらせながらも、私は固い決意のまま、小屋の暗がりで住人の帰りを陰気にじっと待った。
ついに、彼の足音が聞こえた。遥か遠くから、靴が石を打つ鋭い音がした。もう一度、またもう一度、だんだん近づいてくる。私は小屋の奥の暗がりに身をひそめ、ポケットの中の拳銃を構えた。相手の姿が分かるまでは名乗り出ないつもりだった。しばしの静寂があり、足音が止まった。そして再び、足音が近づき、小屋の入口に影が差した。
「実に素晴らしい夕暮れだな、ワトソン君」と、聞き覚えのある声が言った。「どうやら外の方が快適そうだよ。」
第十二章 荒野の死
私はしばし息を呑み、耳を疑った。やがて感覚と声が戻り、魂を押しつぶしていた重圧が一瞬にして消えるのを感じた。あの冷たく、鋭く、皮肉な声は、世界にただ一人しかいない男のものだった。
「ホームズ!」私は叫んだ。「ホームズ!」
「出ておいで」と彼は言った。「銃には気をつけてくれ。」
私は粗末な鴨居をくぐり抜けて外に出た。すると、そこに彼が石の上に腰掛けていて、私の驚いた顔を見て灰色の目を楽しげに輝かせていた。やつれてはいたが、顔色は冴え、鋭敏で、日焼けし風に荒れた顔には活力があった。ツイードの服と布の帽子で、どこにでもいる観光客のような姿だったが、ホームズ特有の潔癖な身だしなみへの執着のおかげで、顎は滑らかに剃られ、シャツもベーカー街にいる時と同じく清潔だった。
「こんなに誰かに会えて嬉しいと思ったことはない」と私は彼の手を強く握った。
「あるいは、こんなに驚いたこともないだろう?」
「それは認めざるを得ない。」
「驚いたのは私も同じだよ。君が時々の隠れ家を見つけただけでなく、その中にいるとは、戸口から二十歩の所まで近づくまで思いもしなかった。」
「私の足跡で気づいたのか?」
「いや、ワトソン君。私は世界中の足跡の中から君のものを見分けるほど自信はないよ。本気で私を欺きたいのなら、タバコ屋を変えるべきだ。ブラッドリー、オックスフォード・ストリートの刻印がある煙草の吸い殻を見れば、友人ワトソンが近くにいると分かる。あそこ、道端に落ちているだろう? きっと空の小屋に突入したあの決定的瞬間に投げ捨てたのだろう?」
「まさにその通りだ。」
「やはりね――そして君の並外れた粘り強さを知っているから、中で武器を手の届く所に待ち伏せしていると確信していた。まさか私が犯罪者だと思っていたのか?」
「誰なのか知らなかったが、とにかく突き止めるつもりだった。」
「素晴らしいぞ、ワトソン君! どうやって私の居場所を突き止めた? もしかして、あの脱獄囚捜索の夜、月明かりの中で不用意に姿を見せてしまった時に私を見かけたのか?」
「確かにあの時見た。」
「それから、きっと小屋を一つ一つあたって、ついにここにたどり着いたのだね?」
「いや、君の少年が目撃されていて、それを手がかりに探した。」
「ああ、あの望遠鏡の老人か。最初にレンズが光るのを見た時は分からなかったよ。」彼は立ち上がり、小屋の中を覗いた。「なるほど、カートライトが物資を届けてくれたようだ。この紙切れは? 君はクーム・トレーシーへ行ってきたのか?」
「そうだ。」
「ローラ・ライアンズ夫人に会いに?」
「その通り。」
「よくやった! 我々の調査はどうやら並行して進んでいたようだ。結果を合わせれば、事件の全体像がかなり見えてくるだろう。」
「本当に君がここにいるのを心から嬉しく思う。責任も謎も、もう私の神経には重すぎていた。だが、一体どうやってここに来て、何をしていたんだ? てっきりベーカー街で恐喝事件の捜査をしていると思っていた。」
「それが君にそう思わせたかった理由だ。」
「つまり、私を利用しておいて、信頼はしていなかったということか!」私は少し憤慨して叫んだ。「私はもっと信頼に値すると思っていたぞ、ホームズ。」
「親愛なる友よ、君はこの事件でも他の多くの事件同様、私にとってかけがえのない存在だ。もし君を欺いたように見えたなら許してほしい。実のところ、それは君自身のためでもあったし、君が危険に巻き込まれることを見越して私自身で調査しようと考えたのだ。もし私がサー・ヘンリーや君と一緒にいれば、君たちと同じ視点になり、私の存在が強力な敵に警戒心を与えてしまうだろう。だが今のように、私はホールで生活していればできなかった行動が取れ、しかも事件の未知数として、決定的な時に全力を投じる用意ができていた。」
「でも、なぜ私に知らせなかったんだ?」
「君が知っていても役には立たず、むしろ私の居所がばれる恐れがあった。君はきっと私に何か教えたくなってしまうだろうし、親切心で何か快適なものを持ってきてくれたりして、余計なリスクが生じる。私はカートライトを連れてきた――覚えているだろう、例の郵便小僧――彼が私の簡単な用事を全部やってくれた。パンと清潔な襟。それ以上何がいる? 彼は俊足で頼れる目も持ち、両方とも大変役に立った。」
「では、私の報告書はすべて無駄だったのか!」――私は、その報告書を丹念に書き上げた労苦と誇りを思い、声を震わせた。
ホームズはポケットから書類の束を取り出した。
「これが君の報告書だよ。ずいぶん読み込んであるだろう? 私は送達の手配を万全にしていたから、たった一日遅れで届いていた。君の並外れた熱意と知性には、こういう困難な事件においても心から感謝している。」
私はまだ、騙されていたことが少し心に残っていたが、ホームズの温かい賛辞に、怒りは消え去った。また、彼の言う通り、私がホームズの存在を知らなかったことが目的のためには最良だったと心から思えた。
「それでよし」と彼は私の顔から陰りが消えるのを見て言った。「さあ、ローラ・ライアンズ夫人のところへ行った成果を聞かせてくれ。君がそこへ向かったのはすぐに分かった。あの町で我々に役立つ唯一の人物が彼女だと私も知っている。君が今日行かなければ、私が明日行っていただろうな。」
太陽は沈み、荒野にはたそがれが下りてきた。空気は冷え込み、私たちは暖を取るために小屋に入った。そこに並んで座り、私はホームズに夫人との会話を語った。彼は非常に興味を持ち、納得するまで何度も繰り返し話さなければならなかった。
「これは非常に重要だ」と、私が話し終えると彼は言った。「この極めて複雑な事件で、私が埋められなかった空白を埋めてくれる。君は、この夫人とステープルトン氏の間に親しい関係があるのを知っていたか?」
「親しい関係があるとは知らなかった。」
「この件については疑いの余地がない。彼らは会い、文通もし、完全な理解が成立している。これは我々の手に非常に強力な武器をもたらす。もしこれを使って彼の妻を引き離すことができれば――」
「彼の妻?」
「今、君に情報を与えよう。君が私にくれた全てに対する返礼だ。ここでミス・ステープルトンとして振る舞ってきた女性は、実は彼の妻なのだ。」
「なんてことだ、ホームズ! 君は本当にそれを確信しているのか? どうして彼はヘンリー卿が彼女に恋することを許したんだ?」
「ヘンリー卿が恋したところで、害が及ぶのはヘンリー卿自身だけだ。彼はヘンリー卿が彼女に愛を告白しないよう、特に注意していた。君自身も気づいた通りだ。繰り返すが、あの女性は彼の妻であって妹ではない。」
「だが、なぜこんな手の込んだ偽装を?」
「彼は、彼女が自由な女性として振る舞う方が、はるかに自分の役に立つと見越していたからだ。」
私の抑えきれぬ本能や漠然とした疑念が、唐突に形を成し、あの博物学者に集中した。麦わら帽子に蝶取り網を持つ無表情で色のない男の中に、私は何か恐ろしいもの――無限の忍耐と狡猾さを持ち、にこやかな顔の下に殺意を隠した怪物のような存在を見た。
「ならば、我々の敵は彼であり――ロンドンで我々を追っていたのも彼なのか?」
「そのように私は謎を解読した。」
「そして警告を送ったのは――やはり彼女か!」
「その通りだ。」
長らく私を取り巻いていた闇の中に、半ば見え、半ば推測される忌まわしい悪事の形がぼんやりと現れた。
「だが、本当に確かなのか、ホームズ? どうして彼女が彼の妻だとわかったんだ?」
「彼は初めて君に会ったとき、自分の経歴の一部をうっかり語ってしまったのだ。おそらくそのことを今でも何度も後悔しているだろう。彼はかつてイングランド北部で教員をしていた。教員ほど足取りをたどりやすい職業はない。教育関係の機関で、その職歴が簡単に分かる。少し調べただけで、ある学校が悲惨な状況で潰れ、その経営者――名前は違っていた――が妻と共に姿を消していることが分かった。容姿の特徴も一致した。さらに、その失踪した男が昆虫学に熱中していたと知り、完全に本人と特定できた。」
闇は薄れ始めていたが、まだ多くが影に隠されていた。
「もしその女性が本当に彼の妻だとすれば、ローラ・ライアンズ夫人の立場はどうなるんだ?」私は尋ねた。
「そこは君自身の調査が明るみをもたらした点の一つだ。君があの女性と面談したことで、状況は大きく整理された。私は彼女と夫との間で離婚が計画されていることを知らなかった。その場合、ステープルトン氏を独身者と見なして、当然自分が彼の妻になれると彼女は期待していたのだろう。」
「そして、もし彼女が真実を知ったら?」
「その時には、我々に協力してくれるかもしれない。まずは彼女に会うことが我々の第一の務めだ――二人揃って。ワトソン、君は持ち場を離れて長すぎると思わないか? 君の居場所はバスカヴィル館にあるはずだ。」
西の空に最後の赤い残光が消え、夜が湿地を覆っていた。かすかな星々が紫色の空に輝いていた。
「最後に一つだけ、ホームズ」私は立ち上がりながら言った。「君と僕の間に秘密はないはずだ。すべて、どういう意味なんだ? 彼の狙いは何なんだ?」
ホームズの声は沈んだ。
「それは殺人だ、ワトソン――洗練された、冷血で、計画的な殺人だ。詳しいことは聞かないでくれ。私の網は彼を締めつつある、彼の網がヘンリー卿を締めているのと同じようにな。そして君の助けにより、彼はほとんど私の手中にある。唯一の危険は、我々が準備できる前に彼が行動を起こすことだ。あと一日、二日もあれば事件は完全に片付く。だがそれまでは、病気の我が子を見守る母親のように、しっかりと君の任務を果たしてくれ。今日の君の行動は十分に正当化された。だが、それでも私は君が彼の側を離れなかったら良かったとも思う。静かに!」
恐ろしい悲鳴――絶望と苦悶の長い叫びが、湿地の静寂を破って響き渡った。そのおぞましい叫び声に、私の血は一瞬にして凍りついた。
「ああ、神よ!」私は息を呑んだ。「なんだ? どういうことだ?」
ホームズは跳ね起き、私は小屋の戸口に、肩を丸め前のめりになり、闇を見つめる彼の精悍な輪郭を見た。
「静かに!」彼はささやいた。「静かに!」
叫び声は強烈なために大きく響いたが、湿地の遠く離れたどこかから聞こえてきたのだった。今度はもっと近く、もっと大きく、より切迫した声で我々の耳に飛び込んできた。
「どこだ?」ホームズはささやいた。その声の震えから、鋼鉄の意志を持つ男が魂を揺さぶられているのが分かった。「どこだ、ワトソン?」
「あそこだと思う。」私は闇を指差した。
「いや、あっちだ!」
再び、苦悶の叫びが静かな夜をつんざき、今まで以上に大きく、近くから聞こえた。そしてそれに新たな音が混じった――重く低く唸るような音、音楽的でありながらも脅威的で、まるで海の絶え間ないざわめきのように高くなったり低くなったりする。
「猟犬だ!」ホームズが叫んだ。「行くぞ、ワトソン、急げ! 大変だ、間に合わなかったらどうする!」
彼は素早く湿地を駆け出し、私もその後を追った。しかし今や、我々の眼前の起伏の中から、最後の絶望的な叫び声と、鈍く重い衝撃音が響いた。我々は立ち止まり、耳を澄ませた。無風の夜の重苦しい静寂を破る音は、もう何もなかった。
私は、ホームズが取り乱したように額に手を当て、地面を踏みしめる姿を見た。
「奴に先を越された、ワトソン。遅かった。」
「いや、そんなはずはない!」
「私が迂闊だった。そして君も、ワトソン、見ろ、自分の役目を離れるとこうなる! だが、もし最悪の事態なら、必ず仇を討とう!」
我々は闇の中を盲目的に駆け、岩にぶつかりながら、灌木を押し分け、丘をよじ登り、坂を駆け下り、常にあの恐ろしい声がした方向を目指した。小高い場所に差しかかるたび、ホームズは周囲を熱心に見回したが、湿地は深い影に覆われ、何も動くものは見えなかった。
「何か見えるか?」
「何も。」
「だが、あれはなんだ?」
低い呻き声が耳に届いた。再び、それは我々の左手に響いた。その側には、岩の尾根が石ころだらけの斜面に切り立った崖をなしていた。そのごつごつした表面に、黒く不規則な物体が大の字に貼りついていた。我々が駆け寄ると、ぼんやりした輪郭がはっきりした形となった。それはうつ伏せに倒れた男の姿で、頭は恐ろしい角度に曲がり、肩は丸まり、体は宙返りでもしようとしたような格好に縮こまっていた。その異様な姿勢に、一瞬、私は呻き声が魂の抜ける音だったとは理解できなかった。今や、我々が身をかがめても、闇の中のその姿からは、ささやきも衣擦れも上がらなかった。ホームズは彼に手を置き、叫び声と共に手を引っ込めた。彼が擦ったマッチの光が、血で固まった指と、砕けた頭蓋骨からじわじわ広がるおぞましい血溜まりを照らした。そしてそれは、我々の心を凍らせ、吐き気を催させる別のものも照らし出した――ヘンリー・バスカヴィル卿の死体だった!
あの独特な赤みがかったツイードのスーツ――ベイカー街で彼に初めて会った朝、彼が着ていたあの服――を私たちは絶対に忘れないだろう。そのはっきりとした一瞬の印象を捉えた途端、マッチの火は消え、希望もまた我々の魂から消え失せた。ホームズは呻き、彼の顔は闇の中で青白く光っていた。
「この悪党め! 悪党め!」私は拳を握りしめて叫んだ。「ああホームズ、僕は彼を運命に任せてしまった自分を一生許せないだろう。」
「私の方が君よりも責任が重い。事件を確実に、完全に仕上げるために、私は依頼人の命を犠牲にしてしまった。これは私の経歴の中で最大の打撃だ。しかし、どうして彼が私の警告を無視し、たった一人で命を張って湿地に出るなどと想像できただろうか――どうして分かっただろう?」
「あの悲鳴を聞きながら――神よ、あの悲鳴を! ――救えなかったなんて! この悪党の猟犬は今どこにいるんだ? この岩陰にいるかもしれない。そしてステープルトン氏は? 必ずこの罪を償わせる。」
「必ずだ。私がやる。叔父も甥も殺された――一方は怪物を見て恐怖のあまり死に、もう一方は必死に逃げるうちに命を落とした。だが今や、あの男と獣との関係を証明しなければならない。聞いたこと以外、獣の存在さえ証明できない。ヘンリー卿は明らかに転落死だ。だが、天に誓って、どんなに狡猾でも、明日には奴を私の手中に収めてみせる!」
我々は、無惨な死体を挟んで並び立ち、この突然で取り返しのつかぬ惨事に打ちひしがれていた。長く苦しい努力が、あまりにも痛ましい結末を迎えたのだ。やがて月が昇り、我々は可哀想な友が落ちた崖の上まで登り、頂から半分は銀色、半分は闇に包まれた湿地を見渡した。遥か遠く、グリムペンの方角に、一つの黄色い灯りが静かに輝いていた。それがステープルトン家の孤独な住まいから発せられていることは明らかだった。私は苦々しく拳を振り上げながらそれを見つめた。
「すぐにでも奴を捕まえよう!」
「まだ事件は完成していない。奴は最後まで油断がなく抜け目がない。問題は我々が知っていることではなく、証明できることだ。軽率な行動をすれば、悪党は逃げおおせるかもしれない。」
「どうすればいい?」
「明日やるべきことはたくさんある。今夜は、可哀想な友に最後の務めを果たすしかない。」
我々は急な斜面を下り、月に照らされた石の上に黒々と浮かぶ遺体に近づいた。そのねじれた四肢の苦悶の様に、私は思わず胸が痛み、涙で目が霞んだ。
「助けを呼ばねば、ホームズ! 館まで彼を運ぶのは無理だ。なんてことだ、君は気が狂ったのか?」
彼は叫び声を上げ、死体にかがみ込んだ。次の瞬間、彼は踊り出し、笑い、私の手を強く握りしめた。これが、あの冷静沈着な友人なのか? まさに隠された炎だった!
「髭だ! 髭を生やしている!」
「髭?」
「男爵じゃない――なんと、あの隣人の脱獄囚だ!」
我々は焦るように死体を仰向けにし、その濡れた髭が冷たい月に向かって伸びているのを見た。おおいかぶさる額と、落ちくぼんだ獣のような目。間違いなく、あの岩陰からロウソクの明かりに照らされた顔――セルデン、あの犯罪者だった。
そして一瞬ですべてが分かった。卿が古い衣服をバリモアに譲ったと語ったのを思い出した。バリモアはセルデンの逃走を助けるため、それを渡したのだった。靴、シャツ、帽子――すべてヘンリー卿のものだ。事件は依然として痛ましいが、少なくともこの男は法によって死を免れぬ運命だった。私は事情をホームズに説明し、胸の中は感謝と喜びで溢れていた。
「ならば服がこの哀れな男の死因というわけだ」と彼は言った。「ヘンリー卿の何か――おそらくホテルで盗まれた靴――から猟犬が嗅ぎつけて、この男を追い詰めたのだろう。しかし、ひとつどうにも奇妙なことがある。なぜセルデンは、あの暗闇の中で猟犬に追われていると分かったのか?」
「聞こえたのだろう。」
「だが、湿地で猟犬の音を聞いたからといって、こんな堅気の男が捕まりかねない危険を冒してまで狂ったように助けを叫ぶなど、尋常ではない。あの叫びでも分かる通り、彼は獣が追ってきていると知ってから相当走り回った。なぜ分かったのか?」
「僕には、もし我々の推測が正しいとして――」
「推測はしない。」
「ならば、なぜ今夜猟犬が放たれたのか。いつも湿地に放し飼いではないはずだ。ステープルトン氏は、ヘンリー卿が今夜湿地にいると確信していたのだろう。」
「私の疑問の方がさらに難解だ。君の疑問は、そう遠くないうちに説明がつくだろうが、私の謎は永遠に解けぬかもしれない。今考えるべきは、この哀れな男の亡骸をどうするかだ。キツネやカラスの餌食にはできない。」
「警察に連絡するまで、どこかの小屋に置いておこう。」
「その通りだ。我々ならそこまで運べるだろう。おや、ワトソン、これは? 本人だ、なんと驚くべき大胆さだ――疑っている様子を一言でも見せるな。一言でも口にしたら、私の計画はすべて崩れる。」
人影が湿地を横切って近づいてきた。私は葉巻の赤い火を見た。月明かりに、その小柄で颯爽とした博物学者の姿が分かった。彼は我々を見ると立ち止まり、再び歩み寄った。
「なんと、ワトソン先生。こんな夜分にあなたに会うとは思いませんでした。しかし、これは……誰か怪我を? まさか、ヘンリー卿では……」彼は私を追い抜いて死体にかがみ込んだ。鋭い息を飲む音がし、葉巻が指から落ちた。
「こ、これは……?」彼はどもった。
「プリンストンから逃げ出したセルデンだ。」
ステープルトン氏は青ざめた顔で我々を見たが、驚きと落胆を何とか抑え込んでいた。彼は鋭くホームズから私へと視線を飛ばした。「これはなんともショッキングな出来事ですね! どうして彼は死んだのです?」
「この岩から落ちて首を折ったようです。私はワトソン先生と散歩していて、叫び声を聞いたのです。」
「私も叫び声を聞きました。それで出てきたのです。ヘンリー卿のことが心配で。」
「なぜ特にヘンリー卿を?」私は思わず尋ねた。
「彼にこちらに来るよう提案したのです。来なかったので驚き、叫び声を聞いてからは彼の安全が心配になったのです。ところで――」彼の目が再び私からホームズへと動いた。「叫び声以外に何か聞きましたか?」
「いいえ」とホームズ。「あなたは?」
「いいえ。」
「それはどういう意味です?」
「ほら、村人たちが言っている幽霊犬の話があるでしょう。夜になると湿地でその声が聞こえると。今夜、そういう音はなかったかと。」
「そんなものは聞こえなかった」と私は言った。
「この哀れな男の死について、どうお考えですか?」
「不安や過酷な環境で錯乱し、狂ったように走り回ってここから転落したのでしょう。」
「それが最も合理的な説ですね」とステープルトン氏は大きく息を吐いた。私にはそれが安堵のため息に思えた。「ホームズさんはどう思われます?」
ホームズは軽く頭を下げた。「さすがですね。」
「ワトソン先生が来て以来、あなたもいらっしゃるのだろうと思っていました。悲劇の現場に間に合われたわけですね。」
「ええ、確かに。私の友人の説明で十分でしょう。私は明日、ロンドンに嫌な思い出を持って帰ることになります。」
「ああ、明日お帰りに?」
「そのつもりです。」
「今回のご滞在で、私たちを悩ませていた事件に何か光は見いだせましたか?」
ホームズは肩をすくめた。
「常に望む成功が得られるとは限らない。調査には事実が必要で、伝説や噂では足りない。満足な事件とは言えなかった。」
友人は最も率直で、気取らない口調で話した。ステープルトン氏はじっと彼を見つめた後、私に向き直った。
「この哀れな男を私の家に運ぶことも考えましたが、妹が怖がるでしょうからできません。顔に何か覆いをしておけば、朝まで大丈夫でしょう。」
こうして決まった。ステープルトン氏の厚意は断り、ホームズと私はバスカヴィル館へ向かった。振り返ると、広い湿地をゆっくりと歩く人影と、その後ろに銀色の斜面に黒く滲む小さな染みが見えた。そこに、恐ろしい最期を遂げた男が横たわっているのだった。
「ついに奴と直接対峙する時が来たな」とホームズは言いながら湿地を歩いた。「恐るべき胆力だ。自分の計画の犠牲となるのが間違った男だと知った瞬間、あそこまで平静を保てるとは。ロンドンでも言ったが、ワトソン、これほど手強い敵はかつてなかった。」
「君の姿を見せてしまったのが残念だ。」
「私も最初はそう思った。だが、避けようもなかった。」
「彼が君の存在を知った今、計画にどんな影響があるだろう?」
「より慎重になるか、逆に一気に思い切った手段に出るかもしれない。多くの賢い犯罪者と同様、彼も自分の才覚に自信過剰で、完全に我々を欺いたと信じているかもしれない。」
「すぐにでも逮捕しないのはなぜだ?」
「ワトソン君、君は生まれついての行動派だ。何かしら精力的に動こうとする本能がある。しかし、仮に今夜、彼を逮捕したとして、一体それで何が良くなるというのだ? 我々には、彼に対して証明できるものが何もない。それが、奴の悪辣な狡猾さなのだ! もし奴が人間の手先を使っているのなら、証拠をつかむこともできるだろう。だが、あの巨大な犬を白日の下に引きずり出したところで、その飼い主の首に縄をかける助けにはならない。」
「しかし、状況証拠は揃っているはずだ。」
「影も形もない――ただの推測と憶測に過ぎない。こんな話と証拠で法廷に出れば、我々は笑いものにされて追い出されるだろう。」
「サー・チャールズの死がある。」
「外傷ひとつなく死体で発見された。君も私も、彼が恐怖のあまり死んだこと、そして何が彼を怯えさせたかを知っている。だが、十二人の頑固な陪審員にそれを分からせるにはどうしたらいい? 犬の痕跡はどこにある? その牙の跡は? もちろん、我々は犬が死体には噛みつかず、サー・チャールズはあの獣に追いつかれる前にすでに死んでいたと分かっている。だが、それを証明しなければならないし、今の我々にはその手立てがない。」
「では、今夜はどうする?」
「今夜になっても大して状況は変わらない。またもや犬と男の死の間には直接的な繋がりがない。我々は犬を実際に見ていない。声は聞いたが、その犬がこの男を追っていた証拠はない。動機もまるで見当たらない。いや、ワトソン君、現時点では我々には何の立証材料もなく、だからこそ、どんな危険を冒してでも証拠をつかむ価値があるのだと受け入れるしかない。」
「では、どうやってそれをつかむつもりだ?」
「ローラ・ライアンズ夫人が、状況をきちんと知れば我々に協力してくれるのではと大いに期待している。それに、私自身の策もある。明日の苦労は明日考えればよいが、日が暮れるまでには優位に立てることを願っている。」
彼からこれ以上情報を引き出すことはできなかった。彼は何か考え込んだまま、バスカヴィル館の門まで歩いていった。
「君も来るか?」
「ああ、もう隠れている理由もないだろう。しかし、最後にひとつだけ、ワトソン。ヘンリー卿には犬のことは一切言うな。セルデンの死は、ステープルトン氏の言う通りだと思わせておけ。明日、彼が君の報告通りなら、あの人々と食事をとる大事な場面を控えているから、その方が気を楽にできるはずだ。」
「僕も同席することになっている。」
「それなら、君は断って、彼ひとりで行かせるように。簡単に手配できるさ。さて、もし夕食に間に合わなければ、軽く夜食でも取ろう。」
第十三章 網を張る
ヘンリー卿は、シャーロック・ホームズの訪問を驚きというよりむしろ喜んで迎えた。ここ数日の出来事で、いずれロンドンからやってくるだろうと予期していたのだろう。ただ、ホームズが荷物もなく、その理由についても説明しないことには、さすがに眉をひそめた。だが我々で手分けして必要なものは揃え、遅い夕食をともにしながら、必要な範囲でこれまでの経験を彼に説明した。まず、バリモア夫妻にセルデンの件を伝えなければならない不愉快な役目が私に回ってきた。バリモアにとっては、むしろ大きな安堵だったかもしれないが、バリモア夫人はエプロンを顔に押し当てて激しく泣いた。世間から見れば、彼は暴力的で半ば獣、半ば悪魔と見なされていたが、彼女にとっては、少女時代から知る我が子も同然の、わがままな小さな少年、手を放さずついてきた子どもだったのだ。誰にも悼まれる女性が一人もいない男こそ、本当に悪しき存在である。
「ワトソンが朝出かけてから、今日は一日中、屋敷でふさぎ込んでいたよ」とヘンリー卿が言った。「でも、約束は守ったんだ。もし独りで歩き回らないと誓っていなければ、もっとにぎやかな夜になっただろう。ステープルトン氏から来てほしいという伝言があったからね。」
「確かに、もっとにぎやかな夜になっただろうな」とホームズがさも意味ありげに言った。「ところで、君は自分が首の骨を折って死んだと皆に思われていたことに気付いていないだろう?」
ヘンリー卿は目を見開いた。「どうして?」
「この哀れな男が君の服を着ていたんだ。服を渡した召使いは警察の厄介になるかもしれない。」
「そんなことはないだろう。どれも名前は入っていなかったはずだ。」
「それなら運がいい。実際、君たち全員にとって幸運だったよ。この件では全員が法のグレーゾーンにいるからな。私は良心的な探偵として、まずこの屋敷の全員を逮捕すべきかもしれない。ワトソンの報告書は実に罪深い証拠だ。」
「ところで、事件の方は?」とヘンリー卿が尋ねた。「この混乱から何か分かったのか? ワトソンと私は、ここに来てからたいして賢くなった気がしない。」
「もう少しで状況をはっきり説明できると思う。非常に困難で複雑な事件だった。まだ解明したい点はいくつもあるが、確実に光は見えてきている。」
「僕らも一つ体験したとワトソンが話したはずだ。あの荒野で犬の声を聞いた。あれが迷信の産物でないことは誓ってもいい。西部で犬には慣れているし、あれが犬の声だと分かる。もしあれに口輪をはめて鎖につなげたら、君こそ史上最高の探偵だと誓ってもいい。」
「君が協力してくれるなら、必ず口輪をはめて鎖につなげてみせる。」
「何でも言う通りにするよ。」
「よろしい。そして理由を問わず、盲目的に従ってもらいたい。」
「好きなようにしてくれ。」
「そうしてくれるなら、我々の小さな問題も間もなく解決できるだろう。私は――」
彼は急に言葉を切り、私の頭越しにじっと空中を見つめた。ランプの灯りが彼の顔を照らし、その表情はあまりに真剣かつ静かで、まるで警戒と期待を象徴する古典彫刻のようだった。
「どうしたんだ?」と私たちは同時に叫んだ。
彼は視線を落とすと、内にこみ上げる感情を抑えているのが分かった。顔立ちは平静だったが、その目は愉快そうな勝ち誇った輝きを帯びていた。
「鑑賞家の礼儀だから許してくれ」と彼は、反対側の壁を埋める肖像画の列を指し示した。「ワトソンは私が美術に詳しくないと言うが、それは単にこの件に限って見解が異なるからだ。これは本当に見事な肖像画のシリーズだよ。」
「それは嬉しいな」とヘンリー卿は驚いたように友人を見た。「私はこういうものには疎いし、馬や牛の方がよほど評価できると思っていた。君がこういうことにも興味があるとは知らなかったよ。」
「良いものは見れば分かる。そして今、私はそれを見ている。あそこにいる青いシルクの婦人はクネラーの作だし、カツラをかぶった太った紳士はレイノルズだろう。全部一族の肖像画だね?」
「その通り。」
「名前は分かるのか?」
「バリモアがいろいろ教えてくれて、だいたい覚えているよ。」
「望遠鏡を持っている紳士は?」
「あれはバスカヴィル提督で、ロドニー提督の下で西インド諸島に従軍した人だ。青い上着に巻物を持っているのはサー・ウィリアム・バスカヴィルで、ピットの時代に庶民院の委員長を務めていた。」
「そして私の正面にいるカヴァリエ――黒いビロードにレースの男は?」
「ああ、君にも知る権利がある。あれこそ全ての元凶、悪名高いヒューゴー、バスカヴィル家の犬の始まりとなった男さ。絶対に忘れられない存在だ。」
私は興味と少しの驚きとでその肖像を眺めた。
「なるほど!」とホームズ。「思ったより物静かでおとなしい人に見えるが、その目には潜む悪魔がいたのだろう。私はもっと逞しく粗暴な人物を想像していた。」
「真贋には問題ない。裏に名前と日付、一六四七年とある。」
ホームズはそれ以上多くを語らなかったが、あの古い放蕩者の肖像に妙に惹かれたらしく、夕食の間中、その絵に目を向け続けていた。ヘンリー卿が自室に引き上げてから、私はやっと彼の思考の先を追うことができた。彼は私を晩餐の間に連れて戻り、寝室用の燭台を手に、壁の年月を感じさせる肖像画にかざした。
「何か気付くことは?」
私は幅広い羽根帽子、巻き毛の髪、白いレースの襟、その間に切り取られた真っ直ぐで厳しい顔を眺めた。粗暴な顔ではないが、堅く冷酷な口元と、冷ややかで不寛容な目が印象的だった。
「誰かに似ていないか?」
「ヘンリー卿の顎にどこか似ている。」
「ほのかな面影があるかな。だが、ちょっと待て!」彼は椅子の上に立ち、左手で明かりを掲げ、右腕で幅広い帽子と長い巻き毛をすっぽり隠した。
「なんと!」私は驚いて叫んだ。
キャンバスからステープルトン氏の顔が浮かび上がったのだ。
「ほら、今なら分かるだろう。私は顔の装飾ではなく骨格を見る訓練をしている。犯罪の捜査者にとって最初に必要なのは、変装を見抜く目だ。」
「これは驚いた。まるで彼の肖像画みたいだ。」
「そう、これは身体的にも精神的にも先祖返りの好例だよ。家系の肖像を調べていると、生まれ変わりの思想にも納得したくなる。彼はバスカヴィル家の血筋、それは明白だ。」
「継承権を狙っているのか。」
「その通り。この偶然の発見で、最も明白な失われた繋がりが得られた。ワトソン君、これで奴を捕らえたも同然だ。明日の夜までには、きっと彼は自分の蝶のようにもがき、我々の網にかかっているはずだ。ピンとコルクとカードに乗せて、ベーカー街のコレクションに加えよう!」彼は絵から離れながら、珍しく高らかに笑い声を上げた。その笑いは、誰かにとっては不吉な兆しに違いなかった。
私は早くも朝起きていたが、ホームズはそれより早く、着替え中の私の窓の下を通って屋敷に戻ってきた。
「今日は忙しい一日になりそうだ」と彼は言い、行動する喜びに手をこすり合わせた。「網はすべて張られ、これから引き揚げにかかる。今日中にあの大きくて痩せた顎の主を捕まえるか、それとも網をすり抜けられるか分かるだろう。」
「もう荒野に行ってきたのか?」
「グリムペンからプリンスタウンにセルデンの死について報告した。もうこの件で誰も煩わされることはないと約束できる。それと、忠実なカートライトにも連絡した。もし私の無事を知らせてやらなければ、犬が主人の墓の前で衰弱するように、私の小屋の前で餓死してしまいかねなかったからな。」
「次はどうする?」
「ヘンリー卿に会う。あ、来たな。」
「おはよう、ホームズ」ヘンリー卿が言った。「参謀長と作戦会議の陣頭指揮官みたいだな。」
「まさにその状況だ。ワトソンが指示を仰いでいた。」
「私も同じくだ。」
「よろしい。今夜、ステープルトン夫妻と食事の約束をしていると聞いている。」
「ぜひ君も来てくれ。彼らはとても親切な人たちで、きっと喜ぶよ。」
「残念だが、ワトソンと私はロンドンへ行かなければならない。」
「ロンドンへ?」
「現状では、我々はそちらの方が有益だと判断した。」
ヘンリー卿の顔が明らかに曇った。
「君たちが最後まで助けてくれると思っていたのに。この館も荒野も、一人きりじゃ心細い。」
「君は私を完全に信じて、私の言う通りにしてほしい。君の友人たちには、ぜひ同席したかったが、緊急の用事でロンドンに呼ばれたのだと伝えてくれ。すぐにまたデヴォンシャーに戻ると。必ずその伝言を?」
「どうしてもそうしろと言うなら。」
「ほかに選択肢はないのだ。」
ヘンリー卿の陰鬱な表情から、これを見捨てられたと深く傷ついていることが分かった。
「いつ発ちたいのか?」と彼は冷たく尋ねた。
「朝食のあとすぐだ。クーム・トレーシーまで馬車で行くが、ワトソンは荷物を置いて君に戻る意志を示しておく。ワトソン、ステープルトン氏に行けないことを伝える手紙を出してくれ。」
「僕もロンドンに行きたくなってきたな。なぜ一人で残らなきゃならない?」
「それが君の持ち場だからだ。私に従うと約束しただろう。だから残れ。」
「分かった、残るよ。」
「もう一つ指示がある! メリピット館へ馬車で行き、帰りは馬車を返して歩いて帰ると伝えろ。」
「荒野を歩いて?」
「ああ。」
「でも、それは君がさんざん警告してきたことじゃないか。」
「今回は安全にやれる。君の度胸と勇気を信頼しているからこそ勧めるのだ。絶対に必要なことだ。」
「分かった、やってみる。」
「そして命が惜しければ、メリピット館からグリムペン街道へ通じる一直線の道以外、荒野を歩いてはならない。帰り道は必ずその道を通ること。」
「言われた通りにするよ。」
「よろしい。朝食後すぐ出発して、午後にはロンドンに到着したい。」
私はこの計画に大いに驚いたが、前夜ホームズがステープルトン氏に「明日で滞在を終える」と言っていたのを思い出した。しかし、まさか私まで同行するとは思っていなかったし、なぜこの決定的な時に二人とも現場を離れるのか理解できなかった。ただ、従うしかなかったので、憂鬱そうなヘンリー卿に別れを告げ、数時間後にはクーム・トレーシーの駅に着き、馬車を返した。ホームズの指示で、プラットフォームにはひとりの少年が待っていた。
「ご用はございますか?」
「この列車でロンドンへ行くんだ、カートライト。着いたらすぐ、バスカヴィル卿宛に、私の名で電報を打ってくれ。もし私が落とした財布を見つけたら、ベーカー街に書留で送るように、と。」
「承知しました。」
「あと、駅の窓口で私宛の伝言がないか聞いてきてくれ。」
少年が戻り、ホームズは私に電報を手渡した。そこにはこう書かれていた。
「電報受領。署名無し令状持参で出発。五時四十分到着。レストレード。」
「今朝私が送った電報への返事だ。彼はプロの中でも最良の一人だし、我々には彼の助けが要るかもしれない。さあワトソン、君の知り合いのローラ・ライアンズ夫人を訪ねよう。」
彼の作戦意図が見え始めてきた。バスカヴィル卿を利用して、ステープルトン夫妻に我々が本当に去ったと信じさせ、必要な瞬間に現場に戻るつもりなのだ。ロンドンからの電報をヘンリー卿がステープルトン氏に話せば、相手の疑念も完全に消えるはずだ。すでに、我々の網は痩せ顎の大魚を取り囲みつつあるように感じた。
ローラ・ライアンズ夫人は事務所にいた。シャーロック・ホームズは、率直かつ直接的な口調で面会を切り出し、彼女はかなり驚いた様子だった。
「私は、故サー・チャールズ・バスカヴィルの死に関する事情を調査している」と彼は言った。「ここにいる友人ワトソン博士から、あなたが話したこと、そして隠していることについても聞いている。」
「私が何を隠していると?」
「あなたはサー・チャールズに十時に門で会うよう頼んだと認めた。そこが彼の死の場所であり、時間でもある。しかし、これらの出来事の関連については一切語っていない。」
「何の関係もないわ。」
「それなら、これはまったく奇妙な偶然ということになる。しかし、結局はその関係を立証できると思う。私は率直に申し上げます、ライアンズ夫人。この事件は殺人だと考えており、その証拠はあなたの友人ステープルトン氏、さらにはその妻にも及ぶ可能性があります。」
婦人は椅子から飛び上がった。
「彼の妻ですって!」
「もはやこれは秘密ではありません。妹だとされてきた人物は、実は彼の妻なのです。」
ライアンズ夫人は席に戻った。椅子のひじ掛けを握る手が、爪先まで真っ白になるほど力が入っているのを私は見逃さなかった。
「彼の妻……? 彼の妻……? 彼は結婚していません。」
シャーロック・ホームズは肩をすくめた。
「私に証明してみせてください。もしそれができるなら――」
彼女の目の鋭い輝きが、言葉以上に多くを物語っていた。
「そのつもりで来た」とホームズは言い、ポケットから数枚の書類を取り出した。「これが、四年前にヨークで撮影された二人の写真だ。『ヴァンデレウル夫妻』という署名があるが、彼の顔はすぐに分かるだろうし、彼女の顔も見知っていれば分かるはずだ。これが、ヴァンデレウル夫妻について当時セント・オリヴァー私立学校を経営していた頃の、信頼できる証人三人による書面での証言だ。これを読んで、この人々の正体を疑えるか確かめてほしい」
彼女はそれらに目を通し、そして必死な女の固くこわばった表情で私たちを見上げた。
「ホームズさん、この男は、もし私が夫と離婚できたなら結婚すると言っていました。あの悪党は、あらゆる方法で私に嘘をついてきました。一言たりとも本当のことを言ったことはありません。なぜ――なぜなのか? 私はすべて自分のためだと思い込んでいました。でも今は、私は彼の手の中の道具でしかなかったのだと分かりました。なぜ、私に誠実でなかった男に対して、私が誠実であり続けなければならないのでしょう? なぜ、彼自身の悪事の結果から彼を守ってやる必要があるのでしょう? 何でも聞いてください、私は何ひとつ隠し立てしません。一つだけ誓いますが、あの手紙を書いたとき、親切にしてくれたあの紳士に害が及ぶなどとは夢にも思っていませんでした」
「あなたを全面的に信じる」とシャーロック・ホームズは言った。「これらの出来事を語るのはさぞ苦痛だろう。ひょっとすると、私が事の経緯を話し、何か重大な誤りがあれば指摘してもらう方が、あなたにとって楽かもしれない。この手紙を送るよう仕向けたのはステープルトン氏なのか?」
「彼が口述しました」
「理由としては、あなたが離婚にかかる法的費用をサー・チャールズから援助してもらえる、というものだったのだろう?」
「まさにその通りです」
「そして、手紙を送った後で、彼は面会をやめるよう説得した?」
「他の男にそんな目的のためのお金を出してもらうのは自尊心が傷つく、自分は貧しいが二人を隔てる障害を取り除くために最後の一銭まで使う覚悟だ、と言いました」
「なかなか一貫した性格のようだな。それから、あなたは新聞で死亡記事を読むまで何も知らなかったのか?」
「はい」
「そして彼は、サー・チャールズとの約束について口外しないと誓わせた?」
「誓わされました。死は非常に不可解なもので、事実が明るみに出れば、私は必ず疑われるだろうと言われました。彼に脅されて、沈黙を守りました」
「なるほど。しかし、あなたにも疑いはあったのだろう?」
彼女はためらい、俯いた。
「彼のことは分かっていました。でも、もし彼が誠実でいてくれたなら、私はずっと彼に誠実でいたと思います」
「総じて、あなたは幸運だったと言えるだろう」とシャーロック・ホームズは言った。「あなたは彼を自分の支配下に置くことができた、そして彼もそれを知っていた。それなのに、あなたは今も生きている。あなたはこの数か月、まさに断崖の縁を歩いてきたのだ。さて、ライアンズ夫人、ここでお別れしよう。恐らくまたすぐに連絡することになるだろう」
「我々の事件はだんだんと全体像が見え始め、困難も次々と薄れてゆく」とホームズは、私たちが町から到着する特急列車を待つ間に言った。「私は間もなく、近年でも特に異様で衝撃的な犯罪の一つを、一つの物語としてまとめて語れる立場になるだろう。犯罪学を学ぶ者なら、66年のリトル・ロシアのゴドノーの事件や、もちろんノースカロライナ州のアンダーソン殺人事件を思い出すだろうが、この事件には他にない独自の特徴がある。いまなお、この狡猾な男への決定的な証拠はつかめていない。だが、今夜床に就くまでには、すべてが明らかになっていなければ私は驚くだろうな」
ロンドン行きの特急が轟音とともに駅へ滑り込み、小柄で筋張ったブルドッグのような男が一等車から飛び降りた。三人で握手を交わしたが、レストレードが敬意を込めてホームズを見つめている様から、二人が初めて一緒に捜査した頃に比べて、彼が多くを学んだのだとすぐに分かった。当時、理論家の推理に実務家が嘲笑を浮かべていたのを、私はよく覚えている。
「何か手応えは?」と彼が尋ねた。
「ここ数年で最大級だ」とホームズ。「出発までまだ二時間ある。食事でもしながら待とう、そしてレストレード、ロンドンの霧をダートムアの澄んだ夜気で洗い流してやろう。行ったことは? ああ、ならば初めての訪問はきっと忘れられないものになるさ」
第十四章 バスカヴィル家の猟犬
シャーロック・ホームズの欠点の一つ――もしそれを欠点と呼ぶならだが――は、自分の計画を完全に他人に明かすことに、実に消極的だったということである。これは一部には、彼自身の支配欲の強い性格に由来し、周囲の人々を驚かせ、圧倒することを好んだからだろう。また、職業的な慎重さから、決して危険を冒さないという信条による部分も大きい。その結果、彼の代理人や助手として働く者にとっては、非常に苛立たしい思いをさせられることが多かった。私も何度もその憂き目に遭ったが、今夜のような長い暗闇の道中でほどその思いを強くしたことはなかった。大きな試練が目前に迫り、いよいよ最終的な行動に出ようという矢先になっても、ホームズは何も語らず、私は彼がどう動くのか推測するしかなかった。馬の一歩ごと、車輪のひと回りごとに、我々はこの冒険の頂点へと近づいていたので、期待で神経は高ぶる一方だった。
借りたワゴネットの御者が乗っていたため、会話は妨げられ、私たちは緊張と期待で張り詰めた心を持て余しながら、取るに足らない話題しか口にできなかった。その不自然な抑制から解放され、やがてフランクランド氏の家を通り過ぎ、ホールと現場が近いことを知ったときはほっとした。私たちは玄関まで馬車で乗りつけることなく、並木道の門近くで降りた。ワゴネットには支払いを済ませ、すぐにクーム・トレーシーへ帰るよう命じ、私たちは歩いてメリピット・ハウスを目指した。
「武装はしているか、レストレード?」
小柄な探偵は笑った。「ズボンさえあれば尻ポケットがあり、尻ポケットがあれば何かしら入っているさ」
「よし、私と友人も非常時に備えている」
「ずいぶん秘密主義ですね、ホームズさん。今度はどんな手です?」
「待ち伏せだ」
「まったく、気味の悪い場所ですね」と探偵は身震いしながら言い、陰鬱な丘の斜面とグリムペン湿地を覆う巨大な霧の海を見渡した。「前方に家の明かりが見えます」
「あれがメリピット・ハウスで、我々の目的地だ。これからはつま先歩きで、声もささやき以上にせぬようお願いする」
私たちは家を目指して慎重に道を進んだが、ホームズは家から二百ヤードほど手前で私たちを止めた。
「ここでいい。右手の岩がいい目隠しになる」
「ここで待つのか?」
「ああ、ここで小さな待ち伏せをする。レストレード、この窪みに入ってくれ。ワトソン、君は家の中に入ったことがあったな? 部屋の配置は分かるか? この端の格子窓は?」
「台所の窓だと思います」
「その隣でひときわ明るいのは?」
「間違いなく食堂です」
「ブラインドが上がっているな。君が土地勘が一番ある。そっと様子を見に行って、何をしているか見てきてくれ――だが、くれぐれも気づかれぬように!」
私は小道をつま先歩きし、低い塀の陰に身を屈めて、背の低い果樹園の影に沿って忍び寄った。カーテンのない窓から、中の様子がよく見えた。
部屋にいたのは二人だけ――ヘンリー・バスカヴィルとステープルトン氏だった。二人は丸テーブルを挟み、横顔がこちらに向いていた。二人とも葉巻をくゆらし、テーブルにはコーヒーとワインがあった。ステープルトン氏は饒舌に話していたが、バスカヴィル卿は顔色が悪く、どこか落ち着きがなかった。忌まわしい湿地を独りで歩くことへの不安が重くのしかかっているようだった。
私が見ていると、ステープルトン氏が立ち上がり、部屋を出た。バスカヴィル卿は再びグラスに酒を注ぎ、椅子にもたれて葉巻をくゆらせていた。ドアのきしむ音と、砂利を踏む靴音が聞こえた。その足音は私がうずくまる塀の向こう側の小道を通り、自然学者が果樹園の隅にある小屋の扉の前で立ち止まるのが見えた。鍵が回り、彼が中に入ったとき、何やら中から不審なガサガサという音が聞こえた。中にいたのはほんの一分ほどで、また鍵の回る音がして、彼は私の横を通り過ぎて家に戻った。再び客人と合流するのを見届けて、私は慎重に仲間のもとへ戻り、見たことを報告した。
「ワトソン、女性はいなかったのか?」ホームズが報告を聞き終えて尋ねた。
「いなかった」
「では、どこにいるのだ? 他の部屋も台所以外に明かりはなかったのだろう?」
「どこにいるのか、見当がつかない」
私は、グリムペン湿地の上には濃く白い霧が垂れ込めていたと述べておいた。その霧はゆっくりと私たちの方に流れてきており、低く厚い壁のように我々の側に押し寄せていた。月の光が霧に当たり、それは巨大な、煌めく氷原のように見え、遠くのトー(岩山)の頂がその上に岩のように浮かんでいた。ホームズはじっと霧の動きを見つめ、いら立たしげに呟いた。
「ワトソン、あれはこっちに来ているぞ」
「まずいことなのか?」
「非常に、いや、地上で唯一私の計画を狂わせるものだ。もう長くはかからないだろう。すでに十時だ。成功も、彼の命も、霧が小道を覆う前に彼が出てくるかにかかっている」
私たちの頭上は澄みきった夜空だった。星は冷たく輝き、半月が全体を淡い光で包んでいた。目の前には家の黒い塊があり、ギザギザの屋根と煙突が、銀の星空のもとにくっきりと浮かび上がっていた。下階の窓から漏れる黄金色の光が、果樹園と湿地を横切って伸びていた。その一つが突然消えた。召使たちが台所を離れたのだ。残る明かりは、殺意を秘めた主人と何も知らぬ客人が葉巻を手に談笑する食堂だけだった。
毎分ごとに、湿地の半分を覆った白い綿毛のような霧が、家にじりじりと近づいてきた。すでに最初の細いひと筋が、明かりの四角い窓を横切っている。果樹園の奥の塀はもう見えず、木々は白い霧の渦の中から浮かび上がっていた。見ているうちに、霧の帯が家の両隅を這い回り、やがて濃い一塊となって、上階や屋根がまるで幽霊船のように影の海に浮かぶさまになった。ホームズは目の前の岩を激しく叩き、じれったげに足を踏み鳴らした。
「あと十五分で出てこなければ小道は覆われる。三十分もすれば、手の先も見えなくなるぞ」
「もっと高い場所へ下がろうか?」
「そうだ、その方がいいだろう」
こうして霧の海が迫るにつれ、私たちは次第に後退し、家から半マイルほど離れた。それでも、月光を受けて銀色に輝く霧の岸は、なおもゆっくり、容赦なく迫っていた。
「行き過ぎだ」とホームズが言った。「彼が霧に追いつかれる危険を冒すわけにはいかない。どんなことがあっても、ここで持ちこたえるしかない」彼はひざまずき、地面に耳を当てた。「ありがたい、何か足音が聞こえるようだ」
モーアの静寂を破る、早足の足音がした。私たちは石影に身を屈め、目の前の銀の縁を持った霧をじっと見つめた。足音は大きくなり、霧のカーテンの向こうから、待ち受けていた人物が現れた。彼は星明かりの夜に出ると驚いた様子で周囲を見回し、すぐに小道を素早くこちらに進み、私たちのすぐ脇を通り過ぎて背後の長い坂を登り始めた。歩きながら、しきりに肩越しに後ろを振り返る――落ち着かない人間のしぐさだった。
「しっ!」とホームズが叫び、ピストルを構える鋭い音が聞こえた。「来るぞ、気を付けろ!」
這う霧の中から、薄く、鋭く、絶え間ない足音が響いた。霧の塊は私たちから五十ヤードほどの距離まで迫り、三人とも息をのんで凝視した。いかなる恐ろしいものがそこから現れるのか分からなかった。私はホームズのそばにおり、一瞬彼の顔を見ると、それは青白く、勝ち誇った表情で、月明かりに目が輝いていた。だが次の瞬間、彼の目が前方で凝固し、唇が驚愕で開かれた。その同時にレストレードが恐怖の叫び声を上げ、地面に身を投げた。私は跳ね起き、無意識にピストルを握りしめ、ただその姿の恐怖で思考が麻痺した。現れたのは猟犬――だが、人間の目で見たことのない、巨大な漆黒の犬だった。口からは炎が吹き出し、目は赤く燃え、鼻面やたてがみ、喉元が炎のようにちらついていた。どんな錯乱した夢の中でも、これほど凶暴で、恐ろしい、地獄の化身のような姿は思い描けないだろう。その黒い影と獰猛な顔が、霧の壁から私たちに襲いかかってきたのだ。
巨大な黒い怪物は、長い跳躍で小道を駆け下り、我々の友の足跡を追っていた。私たちはあまりの衝撃に動けず、犬が前を通り過ぎるまで正気を取り戻せなかった。そして、ホームズと私は同時に発砲した。怪物は恐ろしい悲鳴を上げ、少なくとも一発は命中したことが分かった。しかし奴は止まらず、さらに走り続けた。遥か前方で、ヘンリー卿が振り返り、月明かりに青ざめた顔で、両手を上げて、追いかける恐ろしい怪物を呆然と見つめていた。しかしあの犬の悲鳴が、私たちの恐怖を吹き飛ばした。傷つくならば、奴は生身のものだ。倒せるはずだ。今まで見た中で最も速くホームズが駆け出し、私は自分が足に自信があるにも関わらず、彼に置いていかれた。私がレストレードを引き離す以上に、ホームズは私を引き離した。走るうち、前方からヘンリー卿の悲鳴と、猟犬の唸り声が次々聞こえた。私は、野獣が獲物に飛びかかり、彼を地面に叩きつけ、喉元に噛みつく瞬間に追いついた。だが次の瞬間、ホームズがリボルバーの弾を五発、怪物の脇腹に撃ち込んだ。最後の断末魔の咆哮と、宙を切る歯の音を発して、犬は仰向けに転がり、四肢を狂ったように空中に振り回したかと思うと、やがてぐったりと横たわった。私は息を切らしながら、光る頭部にピストルを押し当てたが、すでに引き金を引く意味はなかった。巨大な猟犬は死んでいた。
ヘンリー卿は倒れたまま気絶していた。私たちは襟元を引きちぎり、傷がなく間一髪間に合ったことに、ホームズは感謝の祈りを口にした。すでに卿のまぶたは痙攣し、弱々しく動こうとしていた。レストレードがブランデーを彼の口に注ぐと、怯えた二つの目が私たちを見上げた。
「なんてことだ……」彼はささやいた。「あれは何だ? 一体、天にも地にも何だったんだ?」
「何にせよ、もう死んだ」とホームズ。「バスカヴィル家の幽霊は、これで永遠に葬られた」
大きさも力も、目の前に横たわるこの怪物は恐ろしいものだった。純粋なブラッドハウンドでも、純粋なマスティフでもなく、二種を掛け合わせたようだ――痩せて獰猛で、小型の雌ライオンほどもあった。死んでなお、その巨大な顎は青白い炎を滴らせているように見え、小さく深く落ちくぼんだ残酷な目は火に縁取られていた。私は輝く鼻面に手を当て、暗がりに掲げると自分の指が燻るように光っていた。
「リンだな」と私は言った。
「うまく調合したものだ」とホームズは死骸に鼻を近づけて言った。「臭いはなく、嗅覚を邪魔しなかった。ヘンリー卿、このような恐怖にさらしてしまい深くお詫びする。猟犬が現れるのは予想していたが、まさかこれほどのものだとは。しかも霧のせいで迎え撃つ時間もなかった」
「君は私の命を救ってくれた」
「まず危険にさらしてしまったがな。まだ立てるか?」
「もう一口ブランデーを。それで何でもできる気がする。……よし、手を貸してくれ。これからどうするつもりだ?」
「ここにいてもらう。今夜はこれ以上の冒険は無理だ。待っていれば、私か誰かがホールまで送り届けよう」
彼は立ち上がろうとしたが、まだ顔色はひどく青ざめ、全身が震えていた。私たちは岩に腰かけさせ、彼は顔を両手で覆って身を震わせていた。
「ここでお別れだ」とホームズ。「残る仕事がある。すべての瞬間が重要だ。我々の事件は解決した、あとは犯人を捕まえるだけだ」
「家で奴を見つける可能性は千に一つだ」とホームズは、私たちが小道をすばやく引き返しながら続けた。「銃声で奴も万事休すと悟ったはずだ」
「だいぶ距離があったし、この霧で音も消されたかもしれない」
「彼は猟犬を呼び戻すために追いかけたのだ――それだけは間違いない。いや、もう今ごろは逃げてしまっているはずだ! だが、念のため家中を捜索しよう。」
玄関の扉は開いており、私たちは飛び込むようにして中に入り、部屋から部屋へとあわただしく走り回った。廊下では、よぼよぼの老従者が驚きの表情で出迎えた。食堂以外には明かりはなかったが、ホームズはランプを手に取り、家中の隅々まで残らず調べていった。だが、私たちが追っていたその男の痕跡はどこにもなかった。だが、二階に上がると、一つだけ寝室の扉が鍵がかかっていた。
「中に誰かいるぞ」とレストレードが叫んだ。「物音がする。開けろ!」
中からはかすかなうめき声とガサガサとした音が聞こえた。ホームズは扉の錠前の上を足の裏で蹴りつけ、扉は勢いよく開いた。私たち三人はピストルを手に、部屋の中へと飛び込んだ。
そこに、私たちが予想していたあの絶望的で挑戦的な悪党の姿はなかった。その代わり、あまりに奇妙で予想外の光景が眼前に広がり、私たちはしばし呆然と立ちつくした。
その部屋は小さな博物館のようになっており、壁にはガラス蓋付きのケースがずらりと並び、この複雑で危険な男が趣味として集めていた蝶や蛾の標本が収められていた。部屋の中央には柱が一本立っており、屋根を支えるために昔設置されたと思われる、虫食いの太い梁がそれに渡されていた。その柱には一人の人物が縛り付けられており、シーツで何重にも巻かれていたので、しばし男か女かすら判別できなかった。一枚のタオルが喉に巻かれ、柱の後ろで結ばれていた。もう一枚のタオルが顔の下半分を覆い、その上から二つの暗い目――悲しみと恥辱、そして深い問いかけに満ちた目――が私たちを見返していた。私たちはすぐに猿轡を外し、縄を解き、バリモア夫人はその場に崩れるように倒れこんだ。美しい頭が胸の上にぐったりと垂れたとき、私は彼女の首に鮮やかな鞭痕が赤く浮かんでいるのを見た。
「なんて奴だ!」とホームズが叫んだ。「レストレード、君のブランデーを! 彼女を椅子に座らせてくれ! 虐待と疲労で気絶している。」
やがて彼女は再び目を開いた。
「彼は無事ですか?」と彼女は尋ねた。「逃げおおせましたか?」
「もう逃げ切れません、奥さん。」
「いえ、主人のことではありません。ヘンリー様は? ご無事なのですか?」
「ええ。」
「それに、あの猟犬は?」
「死にました。」
彼女は長いため息を吐いた。
「神様、ありがとうございます。ああ、この悪魔! 私がどんな仕打ちを受けたかご覧なさい!」彼女は袖から腕を突き出し、私たちはその腕があざだらけになっているのを見て恐怖に震えた。「でも、こんなものは――なんでもありません! 彼が私の心と魂をどれほど苦しめ、汚してきたか……。私は全て耐える覚悟でした。虐待も孤独も、偽りだらけの人生も、彼の愛さえ信じることができれば。それなのに、今や私がただの道具でしかなかったと知りました。」彼女は激情に駆られて泣き崩れた。
「あなたはご主人に善意を持っていないようですね」とホームズが言った。「ならば、彼がどこにいるのか教えてください。これまで彼に加担してきたことがあるなら、今ここで協力し、罪滅ぼしをするのです。」
「彼が逃げ込めるのは一か所だけです」と彼女は答えた。「湿地の中心にある島に古い錫鉱があります。彼はそこで猟犬を飼っており、いつでも身を隠せるよう準備もしていました。必ずそこへ向かったはずです。」
窓の向こうには、白い羊毛のような霧の壁が広がっていた。ホームズはランプを掲げた。
「見てください」と彼は言った。「今夜は誰一人としてグリムペン湿地に道を見つけることはできない。」
彼女は手を打ち、笑みを浮かべた。目も歯も、烈しい喜びに輝いていた。
「彼は中に入ることはできても、二度と戻ってこられません」と彼女は叫んだ。「今夜は道しるべの杖も見えやしません。あれは私と二人で植えたのです。湿地の中を安全に通るために。でも今日、もし私が全部引き抜いておけたら、きっと彼もあなた方の思いのままだったのに!」
その晩、霧が晴れるまで追跡は不可能だと私たちは悟った。ひとまずレストレードに家の見張りを任せ、ホームズと私はヘンリー卿とともにバスカヴィル館へ戻った。ステープルトン一家の真相はもはや隠しきれなくなっていたが、彼は愛していた女性の真実を知っても勇敢に受け止めた。しかし夜の出来事の衝撃で神経はすっかり参ってしまい、朝になる頃には高熱でうわごとを言い、モーティマー医師の介護を受けていた。二人はその後、世界一周の旅に出る運命となり、ヘンリー卿があの不吉な屋敷の主になる前の健やかな男に戻るまで、長い時間を共に過ごすこととなった。
そして、私はこの奇怪な物語の結末に急ぐことにする。私は読者にも、長きにわたり私たちの心を曇らせ、ついには悲劇へと導いたあの暗い恐れと漠然とした疑念を、共に感じていただきたいと願ってきたのだ。猟犬の死んだ翌朝、霧が晴れ、私たちはバリモア夫人に案内され、湿地の中の道筋を見つけた場所まで連れて行かれた。彼女が夫の足取りをたどることに歓喜と熱意を示すのを見て、私たちはこの女性の人生がいかに恐ろしいものであったかを実感した。私たちは、細長い半島状の湿った泥炭の土手の先端に彼女を残し、そこから点々と立てられた小さな杖が、草むらや泥沼の間を縫うように続く道を示していた。悪臭を放つアシやぬめった水生植物が腐敗の匂いと重い瘴気を顔に浴びせ、うっかり足を滑らせれば、何度も太腿まで沈み込む暗い、うねるような泥の中で足元が大きく揺れた。歩くたびに泥が足首をつかみ、まるで悪意の手が私たちをその不浄な深みに引きずり込もうとするかのようだった。危険な道を進む途中、一度だけ先に誰かが通った痕跡を見つけた。ワタスゲの塊の間から黒い何かが泥から突き出していた。ホームズは道を外れてそれを掴もうとし、腰まで泥に沈んだ。私たちが引き上げなければ、二度と固い地面に足をつけることはなかっただろう。彼は空中に古びた黒い靴を掲げた。「メイヤーズ、トロント」と革の内側に印字されていた。
「泥風呂に浸かった甲斐があったな」と彼は言った。「これはヘンリー卿が失くした靴だ。」
「ステープルトンが逃走中に捨てたのだろう。」
「まさにその通り。猟犬に匂いを覚えさせた後、手に持ったまま逃げていた。ここで捨てたんだ。少なくとも、彼はここまでは無事に来たと分かる。」
だが、それ以上のことは永遠に分からなかった。推測できることは多くあったが、泥の中では足跡を見つけるのは不可能だった。泥はすぐに浮き上がって足跡を覆い隠してしまうのだ。ようやく大湿地を抜けて固い地面にたどり着いたとき、私たちは必死にその痕跡を探したが、何一つ見つけることはできなかった。大地が真実を語るなら、ステープルトンはあの夜、霧の中をもがきながら目指した島の避難所には、ついにたどり着けなかったのだろう。グリムペン湿地の奥深く、汚泥に覆われた巨大な沼の底に、この冷酷で無慈悲な男は永遠に埋もれてしまったのだ。
彼が凶暴な相棒を隠していた、湿地に囲まれた島には多くの痕跡が残っていた。巨大な駆動輪と、ゴミが半分詰まったシャフトが、放棄された鉱山の位置を示していた。その傍らには、鉱夫たちが悪臭のために立ち去ったであろう、崩れかけた小屋の跡があった。その一つには釘と鎖、そして齧られた骨が散乱し、獣がつながれていたことが分かった。がれきの中には、絡まるような茶色い毛が付いた骸骨が横たわっていた。
「犬だ!」とホームズが言った。「おや、巻き毛のスパニエルだ。可哀そうに、モーティマーももう愛犬に会えないな。ここにはもう、我々が解き明かせなかった秘密は残っていないだろう。彼は猟犬を隠せても、鳴き声を抑えることはできなかった。昼間でも不気味と感じるほどの叫び声は、ここから聞こえていたのだ。緊急時にはメリピット館の外屋にも犬を隠せたが、それは常に危険で、決定的な日、つまり全ての計画の終わりと見なした時にしかできなかった。この缶の中のペーストは、きっとあの怪物に塗りつけた発光塗料に違いない。もちろん、家系の地獄犬伝説と、サー・チャールズを死に追いやるための恐怖心から思いついたのだ。あれほど哀れな脱獄囚が叫んで逃げたのも無理はない。我々の友人もそうだし、我々自身も、もしあんな怪物が暗闇を駆けて自分を追いかけてきたら、同じように叫んでいただろう。巧妙な企みだった。獲物を死に追いやるだけでなく、あんなものを見た農民が、誰一人として正体を確かめに近寄ろうとはしないだろう。ロンドンでも言ったが、今また言おう。我々が追い詰めた中で、彼ほど危険な男はいなかった」――ホームズは長い腕を広げ、緑と茶の斑点が広がる巨大な湿地が、やがて褐色の丘へと溶けていく先を示した。
第十五章 回顧
十一月の末、私とホームズはベイカー街の居間で、肌寒く霧深い夜に、燃えさかる暖炉を挟んで向かい合っていた。デヴォンシャー訪問の悲劇的な結末以来、彼は二つの重要な事件の捜査に取り組んできた。ひとつはノンパレル・クラブの有名なカード不正事件でのアップウッド大佐の非道を暴き、もうひとつは、継娘カレール嬢の死に関して殺人の嫌疑がかけられた不運なモンパンシエ夫人を弁護したことだった。ちなみにカレール嬢は、六か月後にニューヨークで無事に結婚して生きているのが発見されたのだった。友人は困難で重要な事件を次々と解決したことで上機嫌だったので、私はバスカヴィル家の謎について詳細を語ってもらうことができた。私はその機会をじっと待っていた。なぜなら彼は決して複数の事件を同時に考えず、今現在の仕事以外に思考を割くことはなかったからだ。だが、ヘンリー卿とモーティマー医師はロンドンに来ており、神経衰弱を癒すため勧められた長旅に出かける途上だった。その日の午後、彼らが私たちを訪ねてきたので、自然とその話題になった。
「すべての経緯は」とホームズは言った。「ステープルトンを名乗った男の立場から見れば、実に単純かつ明快だった。しかし、動機も分からず事実の一部しか知らなかった我々には、極めて複雑に思えたのだ。私はバリモア夫人と二度話すことができ、事件は完全に解明された。今や我々に知られざる秘密は何も残っていないと思う。私の事件簿の“B”の項目に、この件に関するメモが残っているはずだ。」
「できれば、記憶にある限りで一連の出来事の概略を聞かせてほしい。」
「もちろんだが、すべてを正確に覚えているとは保証できない。強い集中力は、過去のことを不思議なほど消し去ってしまうものだ。自分の事件を完璧に把握した弁護士も、数週間法廷に立てば前の事件の細部は頭から抜けてしまう。それと同じで、私の頭の中では新しい事件が前の事件を次々と押しのけていく。今はカレール嬢の件でバスカヴィル館の記憶も薄れている。明日にはまた新しい問題が持ち込まれ、今度はフランス嬢や悪名高いアップウッドの記憶も吹き飛ぶだろう。しかし猟犬事件については、できるだけ正確に経過を説明しよう。もし抜けている点があれば、君が補ってくれ。
私の調査で、家系の肖像画は嘘をついていなかったことが明らかになった。つまり、あの男は間違いなくバスカヴィル家の一員だったのだ。彼は、悪評のまま南米に逃げ、独身で死んだとされるロジャー・バスカヴィル(サー・チャールズの弟)の息子だった。実際には彼は結婚しており、子どもが一人いた。つまり、あの男の本名も父親と同じだ。彼はコスタリカの美女ベリル・ガルシアと結婚し、公金を横領した上でヴァンデレールと名を変え、イングランドに逃れてヨークシャー東部で学校を開いた。なぜこの事業を選んだかと言えば、帰国の船旅で結核の家庭教師と知り合いになり、その能力で学校を成功させたからだ。しかしフレイザー教師が死に、学校は評判を落として悪名高くなり、ヴァンデレール夫妻はステープルトンと名を変えた。彼は残りの財産と未来の計画、そして昆虫学への情熱を携え、イングランド南部へやって来た。大英博物館で聞いたところによれば、彼はその道の大家として認められており、ヴァンデレールの名はヨークシャー時代に初めて記載した蛾の名に永久に残っている。
ここからが、我々にとって実に興味深い時期となる。あの男は調査を重ね、二人の命しか自分と莫大な財産の間に立ちはだかっていないことを知った。デヴォンシャーに赴いたとき、計画はまだ曖昧だったと思われるが、最初から悪事を企んでいたことは、妻を妹として同行させたことからも明らかだ。妻を囮に使うという発想は最初からあったに違いないが、詳細までは決めかねていたのだろう。最終的にはあの財産を手に入れるつもりであり、そのためにはどんな道具も、どんな危険もいとわなかった。まずは先祖の屋敷の近くに住まいを定め、次にサー・チャールズや近隣住民と親交を結んだ。
バスカヴィル卿本人が家系の猟犬伝説を語り、それが自らの死の道を開いてしまった。ステープルトン(以後そう呼ぶ)は、卿が心臓が弱く、ショックで死ぬことをモーティマー医師から学んだ。そして、サー・チャールズが迷信深く、この恐ろしい伝説を本気で信じていたことも知った。彼の巧妙な頭脳は、バスカヴィル卿を殺す方法を即座に思いついたのだが、それでいて殺人の罪を自分に着せることはほぼ不可能だった。
この着想を得ると、彼は実に巧妙に実行に移した。普通の犯罪者なら、ただ凶暴な猟犬を使うだけで満足しただろう。しかし、動物を悪魔のように見せるために人工的な工夫をしたのは、彼の天才的ひらめきだった。犬はロンドンのフラム・ロードのロス&マングルズという業者から買い、最も大きく凶暴なものを手に入れた。それをノース・デヴォン線で運び、目立たぬよう広野を長距離歩かせて家まで導いた。彼は昆虫採集の際にすでにグリムペン湿地を調査し、猟犬の隠し場所も確保していた。そこに犬を収容し、好機を待ったのだ。
だが、その機会はなかなか訪れなかった。バスカヴィル卿は夜になっても屋敷の外へは出ようとしなかった。ステープルトンは何度も犬を連れて待ち伏せをしたが、無駄に終わった。その間、彼か、あるいは協力者が農民たちに目撃され、悪魔犬伝説に新たな裏付けが加わったのだ。妻を利用してバスカヴィル卿を罠にかけようともしたが、ここで予想外に妻が自立心を見せた。彼女は老紳士を色仕掛けで誘い込むことを拒否し、脅しても――残念ながら暴力すら――動じなかった。彼女は一切関わろうとせず、ステープルトンは行き詰まった。
だが、サー・チャールズが彼に信頼を寄せ、不幸なローラ・ライアンズ夫人への慈善を一手に任せたことで、事態は動き出した。独身と偽ることで彼女を完全に支配し、離婚が成立すれば結婚するとほのめかした。そんな中、サー・チャールズがモーティマー医師の助言で間もなく屋敷を離れると知り、彼は一気に計画を進めざるを得なくなった。逃げられては元も子もないからだ。彼はライアンズ夫人に手紙を書かせ、老紳士にロンドン出発前夜の面会を懇願させた。そして巧妙な理屈で彼女を現場に行かせず、自らが待ち続けていた機会を手にしたのだ。
「夕方、クーム・トレーシーから戻る途中で彼はちょうど間に合って猟犬を手元に呼び、例の忌まわしい塗料を施し、獲物となる老人が待っているであろう門まで犬を連れてきた。主人にあおられた犬は小門を飛び越え、不運なバスカヴィル卿を追いかけ、彼は絶叫しながらイチイの並木道を駆け下った。あの薄暗いトンネルのような場所で、炎のような顎と燃えるような目をした巨大な黒い生き物が標的目がけて跳ねる様子は、さぞおぞましい光景だったに違いない。卿は並木道の端で、心臓発作と恐怖から倒れて息絶えた。犬は草地の縁を走り、卿は小道を駆けていたので、男の足跡しか残らなかった。男が倒れたのを見て、犬はおそらく近づき匂いを嗅いだが、死んでいるとわかると立ち去った。その際に残された足跡をモーティマー博士が実際に発見したのである。犬は呼び戻され、急いでグリムペン湿原のねぐらへと戻された。こうして当局を困惑させ、村に恐れを撒き、ついには我々の関知するところとなる謎が生まれた。
「以上がサー・チャールズ・バスカヴィルの死の経緯だ。その悪魔的な狡猾さがおわかりだろう。実際、真犯人を告発することはほとんど不可能だった。唯一の共犯者は決して秘密を漏らさない者であり、この奇怪で想像もつかない手口は、かえって効果を増すこととなった。事件に関わった二人の女性――バリモア夫人とローラ・ライアンズ――はどちらもステープルトン氏に強い疑念を抱いた。バリモア夫人は彼が老人に対して何か企んでいることも、猟犬の存在も知っていた。ライアンズ夫人はどちらも知らなかったが、取り消されていない約束の時間に死が起きたことで印象づけられた。しかし、いずれも彼の支配下にあり、ステープルトン氏は彼女たちを恐れることはなかった。彼の計画の前半は成功したが、より困難な後半が残っていた。
「ステープルトン氏はカナダに相続人がいることを知らなかった可能性が高い。だが、いずれにせよ、親しい友人であるモーティマー博士からヘンリー・バスカヴィルの到着について詳しく知らされることとなった。ステープルトン氏の最初の考えは、このカナダから来た若い男を、デヴォンシャーに来させずロンドンで抹殺してしまうことだった。彼の妻は老人を罠にかける手助けを拒んで以来、信用できなくなり、自分の影響力を失うことを恐れて長く目を離すこともできなかった。だからこそ彼女をロンドンに連れていったのだ。二人はクレイヴン・ストリートのメックスボロー私設ホテルに宿泊し、そこは私の調査員も証拠を求めて訪れた場所の一つだった。彼は妻を部屋に閉じ込め、自身は髭をつけて変装し、モーティマー博士をベイカー街や駅、ノーサンバランド・ホテルまで尾行した。妻は彼の計画に薄々感づいていたが、夫への恐怖――それは暴力的な仕打ちに根ざしていた――から、危険にあるヘンリー卿に警告の手紙を書くことすらできなかった。その手紙がステープルトン氏の手に渡れば、自身の命が危うくなるからだ。結局、彼女は警告の言葉を切り抜いて貼り付け、筆跡を変えて宛名を書き、手紙を送るという手段に出た。その手紙はバスカヴィル卿に届き、彼に危険を知らせる最初の警告となった。
「ステープルトン氏にとって何よりも重要だったのは、必要とあれば猟犬を使う際、いつでもその跡を追わせられるよう、サー・ヘンリーの持ち物――衣類の何か――を入手しておくことだった。彼は特有の素早さと大胆さで早速これに取り掛かった。ホテルの靴磨きか女中が、計画に手を貸すよう十分な報酬を与えられたことは間違いない。ただし偶然にも、最初に手に入れられた靴は新品だったため、目的には使えなかった。そこで靴は返却され、別の靴――つまり古い靴――が入手された。この出来事は非常に示唆的で、私には本物の猟犬が使われていることを疑う余地なく証明した。古い靴を手に入れようとし、新品にこだわらない理由は他に考えられないからだ。事件が異様で滑稽であればあるほど、より綿密な検証に値する。複雑に見える要素こそ、正しく科学的に扱えば、事件の真相解明には最も有効な手がかりとなるのだ。
「その翌朝、我々を訪ねてきた友人たちの一行も、常に馬車の中からステープルトン氏に尾行されていた。彼の部屋や私の外見に関する知識、その他の振る舞いから見ても、ステープルトン氏が過去に犯した犯罪はバスカヴィル事件一件にとどまらないと私は考えている。過去三年間で西部地方には四件の大規模な強盗事件があり、いずれも犯人は逮捕されていない。中でも五月のフォークストン・コート事件では、仮面姿の単独犯が小姓に冷酷にも発砲していることが特筆される。ステープルトン氏が資金難をこうして補っていたのは疑いようがなく、長年にわたり絶望的で危険な男であり続けてきたのだ。
「その朝、彼が見事に我々を撒き、さらには私の名を御者に託して送り返してきた、その大胆さにも機知の冴えが見て取れた。その瞬間、彼はロンドンで私が事件を引き継いだことを理解し、自分にはもはや勝ち目がないと悟った。そしてダートムーアに戻り、卿の到着を待ったのだ。」
「ちょっと待ってくれ!」と私は口を挟んだ。「事件の流れは正確に説明されたと思うが、ひとつ明らかになっていない点がある。主人がロンドンにいた間、猟犬はどうしていたんだ?」
「その件には私も注意を払ってきたし、確かに重要な問題だ。ステープルトン氏には共犯者がいたことは間違いないが、すべての計画を打ち明けて自分が主導権を握られることはなかっただろう。メリピット館にはアンソニーという老使用人がいた。ステープルトン夫妻と長年の関わりがあり、教師時代にまで遡れることから、夫妻が本当は夫婦であることも知っていたはずだ。この男はすでに姿を消し、国外に逃亡している。アンソニーという名前がイギリスでは珍しいが、スペイン語圏や南米ではアントニオがごく一般的な名前であることは示唆的だ。この男もバリモア夫人同様、流暢な英語を話したが、奇妙な舌足らずな訛りがあった。私自身、この老使用人がステープルトン氏が印をつけた道筋をたどってグリムペン湿原を渡るのを見たことがある。したがって、主人不在の間は彼が猟犬の世話をしていた可能性が高い。ただし、猟犬が何のために使われていたかまでは知らなかっただろう。
「こうしてステープルトン夫妻はデヴォンシャーへ下り、まもなくヘンリー卿と君も後を追った。さて、その頃の私自身の立場だが、思い出してもらえるかもしれないが、私は切り抜きの文字が貼られた紙を調べた際、水印を確認しようと紙を目に近づけた。そのとき、かすかに“ホワイト・ジャスミン”と呼ばれる香水の匂いを感じた。犯罪専門家には、七十五種類の香りを識別する能力が不可欠であり、私自身の経験でも、香りの即座の認識が事件解決の鍵となったことは一度や二度ではない。この香りが女性の存在を示唆し、私の思考はすでにステープルトン夫妻へと向かっていた。こうして、我々が西部地方へ向かう以前に、私はすでに猟犬の存在と犯人をほぼ特定していたのだ。
「私の狙いはステープルトン氏の動向を見極めることだった。しかし、君と一緒にいては彼に警戒され、監視することはできない。だから私は、君さえも欺いてロンドンにいるように見せかけ、実は密かに現地入りしていた。とはいえ、君が思うほど過酷な状況でもなかった。小さな不便など事件の捜査には決して影響させてはならない。私は主にクーム・トレーシーに滞在し、必要なときだけ現場近くの小屋を利用していた。カートライトも一緒に来ており、田舎の少年に変装して私に大いに協力してくれた。食事や清潔な衣類の補給も彼頼みだった。私がステープルトン氏を監視している間は、カートライトが君を見張っていたので、全体の糸を手元で操ることができた。
「君への報告書がすぐにベイカー街からクーム・トレーシーに転送され、私の手元に届いたことはすでに話した通りだ。それらは私にとって非常に助けとなった。とりわけ、偶然にも事実が記されたステープルトン氏の経歴の一節は、私にとって決定的だった。私は男と女の正体を突き止め、やっと全体像を把握した。事件は脱獄犯とバリモア夫妻の関係によって一層複雑になっていたが、君がこれを見事に解明してくれた。ただ、私も自分の観察から同じ結論に達していた。
「君が私を湿原で発見したときには、事件の全容を完全に把握していたが、陪審にかけられるだけの証拠はまだなかった。ステープルトン氏がその夜ヘンリー卿を襲い、脱獄犯が犠牲になった事件でさえ、殺人の立証には大した助けにはならなかった。もはや現行犯で捕まえるしかなかったが、そのためにはヘンリー卿を孤立無援の餌として使うしかなかった。こうして我々の作戦は成功し、依頼人には大きな精神的衝撃を与えたものの、事件を完結させ、ステープルトン氏を破滅に追い込むことができた。ヘンリー卿を危険にさらしたことは、事件の采配として私自身にとって痛恨の極みだが、あの獣の恐るべき姿や、あんな短時間であたりを覆った霧までは予測できなかった。我々の目的は達成されたが、その代償も大きかった。ただし、専門医とモーティマー博士の見立てによれば、これは一時的なものにとどまるという。長旅で、彼は傷ついた神経と心を癒やすことができるだろう。彼が女性に寄せた愛情は深く誠実であり、今回の事件で最も悲しんでいるのは、彼女に騙されていたことだろう。
「残るは、彼女が果たしてきた役割について述べることだ。ステープルトン氏が彼女に対して、その影響力が愛情からなのか恐怖からなのか、あるいは両方かは定かではないが、いずれにしても彼女に絶対的な支配を及ぼしていたことは疑いない。彼の命令で、彼女は妹を装うことを受け入れたが、殺人の直接的な共犯にさせようとしたときに、その支配の限界が露呈した。彼女は夫を巻き込まずにできる範囲でヘンリー卿を警告しようとし、繰り返しその努力を重ねた。ステープルトン氏自身も嫉妬深い性格だったようで、ヘンリー卿が夫人に言い寄るのを目の当たりにすると、それが自分の計画の一部であっても、激しい激情を抑えきれず、普段巧妙に隠している熱い気性を露呈させた。親密な関係を推し進めることで、頻繁にヘンリー卿がメリピット館を訪れるようになり、いずれは待望の機会が訪れることを確実にした。しかし運命の日、妻は突然彼に反旗を翻した。彼女は脱獄犯の死について何かを知り、ヘンリー卿が夕食に来る夜に猟犬が納屋にいることを悟った。彼女は夫の犯意を問い詰め、激しい口論となり、そこで初めて夫に他の女性への愛人がいることを知った。彼女の忠誠心は一瞬で憎悪に変わり、夫は彼女が裏切ると悟った。そこで彼女を縛り上げ、ヘンリー卿への警告を封じた。夫は、村人全員が卿の死を家系の呪いと見なすであろうから、その既成事実を受け入れ、口を閉ざすだろうと期待していたのだろう。しかし、これは完全な誤算だったと私は思う。私たちがいなかったとしても、彼の運命は変わらなかったはずだ。スペインの血を引く女性はそのような侮辱を決して容易には許さない。――さて、ワトソン君、これ以上は私の手元の記録を見ずには詳しく話すことができない。だが、本件で本質的に未解決の点は残っていないはずだ。」
「ヘンリー卿を、叔父のように“恐れ死に”させることはできなかったんだな。」
「犬は獰猛で、半ば飢えていた。たとえその姿で恐怖死させることができなくとも、少なくとも抵抗する力を麻痺させることはできただろう。」
「疑いないね。ただ、最後の疑問がひとつ残る。もしステープルトン氏が相続人になったとして、どうやって自分が屋号を隠してすぐ近くで暮らしていたことを説明するつもりだったのか? この事実をどうやって疑惑や調査を招かずに主張できたんだろう?」
「それは大きな難題で、私にそれを解決せよというのは少々酷な注文だ。過去と現在は私の調査範囲だが、人の未来の行動までは予測しきれない。バリモア夫人の話では、ステープルトン氏もこの問題について何度か語っていたそうだ。三つの方法が考えられた。南米から財産を請求し、現地のイギリス当局に自分の身分を証明して、イギリスに来ることなく遺産を手に入れる方法。あるいはロンドンに短期間滞在する間だけ巧妙な変装を施す方法。さらにもう一つは、共犯者に証明書類を渡して相続人として立て、自分はその収入の一部に口を利く方法だ。彼の性格からして、いずれかの方法で難題を切り抜けていただろう。――さて、ワトソン君、我々は数週間にわたる厳しい仕事を終えたのだ。今宵一夜くらい、もっと愉しいことに心を向けてもいいだろう。ユグノー教徒(レ・ユグノー)の切符が手に入ったが、ド・レシュケ兄弟の歌を聴いたことは? それなら三十分後に出かける支度をしてくれないか。途中、マルチーニで軽く夕食を取ろう。」
終

