
シャーロック・ホームズの冒険
A. コナン・ドイル著
冒険第一話 ボヘミアの醜聞
I
シャーロック・ホームズにとって、彼女は常に「その女」だ。彼が彼女のことをほかの呼び名で語るのを、私はほとんど聞いたことがない。彼の目には、アイリーン・アドラーは、全女性の中でひときわ際立ち、他を圧倒していた。ホームズが彼女に恋愛感情を抱いていたわけではない。すべての感情、特に恋愛感情は、彼の冷静で正確、しかも見事に均衡の取れた精神には、ひどく不快なものだったのだ。彼は、おそらく人類史上最も完璧な推理と観察の機械だったと言えるだろう。しかし、恋人としての自分を想像すれば、それは偽りの姿となったに違いない。彼は、やさしい情熱については、皮肉や嘲笑の調子でしか語らなかった。それらは観察者にとっては称賛すべきものであり、人間の動機や行動のベールを剥がすのにとても役立った。しかし、訓練された理論家がそうした感情を自分の繊細で精密な気質に入り込ませれば、精神活動のすべてに疑念をもたらす厄介な要素となる。鋭敏な器具に砂粒が入ったり、彼自身の高倍率レンズにヒビが入ったりするのと同じくらい、強い感情は彼の性質を動揺させるのだ。それでも彼にとって唯一の女性がいた――それが、今は亡きアイリーン・アドラー、いささか評判の怪しい女性だった。
私は最近、ホームズとほとんど会っていなかった。私の結婚が、二人の距離を自然に遠ざけていた。自分自身の満ち足りた幸福と、初めて一家の主となった男の周囲に生まれる家庭中心の関心ごとで、私はほとんどの時間を割かれていた。一方、社会的なものを徹底的に嫌うホームズは、ベイカー街の下宿に留まり、古書の山に埋もれ、週ごとにコカインと野心、その眠気と自身の鋭い情熱との間を行き来していた。彼は相変わらず犯罪研究に強く惹かれ、卓越した洞察力と観察力で、警察が絶望して放棄した手がかりや謎の解明に没頭していた。時折、私は彼の消息をぼんやり耳にすることがあった。たとえば、トレポフ殺人事件でオデッサに呼ばれたこと、トリンコマリーでのアトキンソン兄弟の奇怪な悲劇を解決したこと、またオランダ王家のためにきわめて繊細かつ成功裏に任務を果たしたこと、などである。しかし、そうした活動のしるしも、大衆紙の読者として共有したにすぎず、かつての友人について私が知っていることはほとんどなかった。
ある夜――それは1888年3月20日のこと――私は往診の帰り(今は民間の診療に戻っていた)に、ベイカー街を通りかかった。あの懐かしい玄関が、求婚時代や『緋色の研究』の暗い事件と結びついて、いつまでも記憶に残るその扉を通り過ぎたとき、私は無性にホームズに会いたくなり、彼がその驚くべき才能をどのように使っているかを知りたくなった。彼の部屋は明るく照らされており、ふと見上げると、背の高いやせた彼の影が二度、カーテン越しに黒く映った。彼は頭を胸に落とし、両手を背中で組み、部屋を素早く、熱心に歩き回っていた。彼のあらゆる癖や気分を知り尽くしている私には、その姿と態度だけで状況がわかった。彼はまた仕事に没頭している。薬物で生み出された夢から覚め、新たな問題の匂いを追っているのだ。私はベルを鳴らし、かつて私自身の部屋でもあったあの部屋に通された。
彼の態度は熱烈なものではなかった。もともとそうだが、それでも私に会えて嬉しそうだった。ほとんど言葉は交わさず、しかし親しげなまなざしで、アームチェアに座るよう合図し、葉巻ケースを投げて寄越し、隅のスピリットケースとガス発生器を示した。それから暖炉の前に立ち、例の内省的なまなざしで私を見つめた。
「結婚して幸せそうだな」と彼は言った。「ワトソン、君はこの前会ったときより三キロ半は太ったな」
「三キロだよ」と私。
「いや、もう少しかと思った。ほんの少し増えた気がするね、ワトソン。それと、また開業したようだな。君が診療を再開するとは聞いていなかったが」
「どうしてわかったんだい?」
「見た、推理したのさ。君が最近ひどく濡れたことがあり、不器用でだらしない女中がいることも分かっている」
「おいおい、ホームズ、それはいくらなんでも度が過ぎてるよ。君はもし数世紀前に生まれていたら間違いなく火あぶりにされてたろう。確かに木曜に田舎道を歩いて、ひどい格好で帰ってきたが、着替えたあとでどうしてそれが分かるんだい。それにメアリー・ジェーンのことも、妻がすでに辞めさせることにしたけど、どうやって推理したんだ?」
彼はくすくすと笑い、長い神経質な指をこすり合わせた。
「至極簡単さ」と彼は言った。「左靴の内側、ちょうど暖炉の明かりが当たるあたりに、六本ほどのほぼ平行な傷がある。泥のこびりつきを取ろうと、誰かがいい加減に靴底の縁をひっかいた跡だ。だから、ひどい天気の中を歩き回り、ロンドンのあちこちにいる、特に悪質な靴を傷つける女中がいると推理したのさ。それから開業の件だが、ヨードホルムの匂いをさせて部屋に入ってきて、右手の人差し指に硝酸銀の黒い跡、シルクハットの側面が膨らんでいる――そこに聴診器をしまっている印だ――これだけ揃えば、医師として現役だと判断しない方がおかしいだろう」
私は彼の推理の鮮やかさに思わず笑ってしまった。「君が理由を説明してくれると、いつも驚くほど簡単に思えるんだ。自分にもできそうに思えるのに、君の推理が展開されるたびに、説明されるまでさっぱりわからない。でも私の目だって君と変わらないはずだ」
「まったくその通り」と彼は言い、タバコに火をつけてアームチェアに深くもたれた。「君は“見てはいる”が“観察していない”んだ。その違いは大きい。たとえば、君はこの部屋へ続く階段を何度も見ているだろう?」
「しょっちゅうだ」
「何回くらい?」
「そうだな、何百回にもなる」
「じゃあ段数は?」
「段数? 知らないな」
「そこだよ! 君は観察していないが、見てはいる。それが僕の言いたいことさ。僕は十七段だと知っている、なぜなら“見て”、しかも“観察している”からだ。さて、こういう小さな問題に興味があるなら、そして僕のささいな経験のいくつかを記録してくれているくらいだ、これにも興味があるかもしれない」彼はテーブルの上に開いていた厚手のピンク色の便箋を投げてよこした。「さっき最後の郵便で来たんだ。声に出して読んでみてくれ」
その手紙には日付も署名も住所もなかった。
「本日夜7時45分に、あなたを訪ねる紳士がございます。非常に重大な件についてご相談したいとのことです。あなたが近ごろ欧州王家の一つに尽くされたご活躍から、極めて重大な事柄を託すに十分信頼できる方と各方面から伺っております。どうかその時刻にお部屋においでください。なお、来訪者が仮面を着用していたとしても、気を悪くなさらぬようお願いいたします」
「これは謎だな」と私は言った。「どういう意味だと思う?」
「まだ情報が足りない。データなしに理屈をこねるのは最大の失敗だ。いつの間にか事実を理論に合わせてねじ曲げてしまう。理論を事実に合わせなければならないのに。さて、この手紙自体についてはどう推理する?」
私は注意深く筆跡と用紙を調べた。
「書いた人は裕福な人物だろう」と私はホームズのやり方を真似て言った。「この紙は一束でも半クラウン以下では売っていないはずだ。特に丈夫で厚い」
「特に――それがまさに肝心な点だ」とホームズ。「これはイギリスの紙じゃない。光にかざしてみてごらん」
私はその通りにした。すると、大きな“E”、小さな“g”、それに“P”、大きな“G”、小さな“t”が織り込まれていた。
「これをどう読む?」とホームズ。
「製紙会社の名前か、あるいはイニシャルだろう」
「いや、違う。“G”に小文字の“t”は“Gesellschaft”、つまりドイツ語で“会社”の意味。英語の“Co.”のような省略表記だ。“P”は当然“Papier”、つまり“紙”だ。さて、“Eg”は? 大陸地名録を見てみよう」彼は棚から重い茶色の本を取った。「エグロー、エグロニッツ――あった、エグリア。これはボヘミア、カルルスバードの近くだ。『ヴァレンシュタインの死の舞台、ガラス工場と製紙工場の多さで有名』――おい、どう思う?」彼は目を輝かせ、タバコから見事な青煙をくゆらせた。
「この紙はボヘミア製だね」
「その通り。そして書いた人物はドイツ人だ。“This account of you we have from all quarters received.”(このような評判を各方面から受けております)――この文章構造に注目。フランス人やロシア人には書けない。ドイツ人ならではの動詞の扱いだ。あとはこのボヘミアの紙に書き、仮面を好んで顔を隠すドイツ人が何を望んでいるかだ。――おっと、彼が来たようだ。これで謎がすべて明らかになるだろう」
ちょうどそのとき、馬のひづめと車輪のきしむ音に続いて、ベルが鋭く鳴った。ホームズは口笛を吹いた。
「音からして二頭立てだ」と彼。「ああ、そうだ」窓から外をうかがいながら続けた。「立派なブローアムと見事な馬二頭――一頭150ギニーはする。金の匂いがするな、ワトソン」
「これはおいとました方がいいかな、ホームズ」
「まさか、ドクター。ここにいてくれ。君抜きでは役に立たんよ。これは面白くなりそうだ。逃すのは惜しい」
「でも依頼人が――」
「心配無用。僕も君の助けが要るかもしれないし、彼もそうだ。ほら、来るぞ。ドクター、あのアームチェアに座って、よく見ていてくれ」
重々しくゆっくりした足音が階段と廊下に響き、やがてドアの前で止まった。次いで、威厳ある大きなノックが響く。
「どうぞ!」とホームズ。

入ってきた男は、少なくとも身長が2メートル近くあり、胸も手足もヘラクレスのようにたくましかった。着ているものは英国でなら悪趣味と見なされかねないほど豪奢だった。アストラカンの太い帯がダブルのコートの袖と前身頃に飾られ、肩に羽織った深い青のマントは炎のような絹で裏打ちされ、首元には真紅のベリル一個をあしらったブローチがとまっていた。ふくらはぎまであるブーツは高級な茶色の毛皮縁で、彼の姿全体から野性的な豪奢さが漂っていた。手にはつばの広い帽子、顔の上半分には頬骨まで覆う黒い仮面――今まさにつけたばかりらしく、まだ手がその位置にあった。顔の下半分から察するに、性格は強烈で、厚い垂れた唇と、頑固な決意を感じさせる長く真っ直ぐな顎が印象的だった。
「手紙、受け取りましたね?」彼は低く荒々しい声で、強いドイツ語訛りを交えて言った。「今夜伺うと申し上げたはずです」彼は私たち二人を見比べ、誰に話すべきか迷っているようだった。
「どうぞおかけください」とホームズ。「こちらは友人であり同僚のワトソン博士。時おり私の事件を手伝ってくれている方です。さて、どちら様とお呼びすれば?」
「フォン・クラーム伯爵、ボヘミア貴族とお呼びください。この紳士――ご友人は、極めて重要な件でも信頼できる名誉と分別の人と伺っています。そうでなければ、私はあなたと二人きりで話したい」
私は立ち上がろうとしたが、ホームズは私の手首を取り、椅子に押し戻した。「二人ともダメなら、どちらもダメです。この紳士に話せることは、私にも話して構いません」
伯爵は広い肩をすくめた。「ではまず、二年間の絶対的な機密保持を誓っていただかねばなりません。その頃にはもう重要性も失われていますが、現時点では欧州の歴史に影響を与えかねない重大事なのです」
「誓いましょう」とホームズ。
「私も」
「この仮面はご容赦を」と奇妙な来訪者は話を続けた。「私を雇う高貴なお方の命令で、身元を明かすわけにはいかないのです。また、先ほど名乗った肩書きも正確なものではありません」
「それは承知していましたよ」とホームズは乾いた口調で言った。
「きわめて繊細な事情であり、巨大なスキャンダルが生じ欧州の王家の一つが深刻な危機に陥るのを防ぐため、万全の注意が求められます。率直に申しますと、問題は、ボヘミアの世襲王家であるオルムシュタイン家に関係しています」
「それも承知しています」とホームズはアームチェアに深く身を沈め、目を閉じてつぶやいた。
来訪者は、ヨーロッパ一の鋭い推理家、精力的な実行者と聞いていた人物が、気だるげに横たわっているのを見て、意外そうな表情を浮かべた。ホームズはゆっくりと目を開き、いら立たしげに巨大な依頼人を見た。
「陛下がご自身の件をお話しくだされば」と彼は言った。「より的確な助言ができるでしょう」
その男は立ち上がり、激しい動揺のあまり部屋を行き来した。そして絶望したような仕草で仮面を引きはがし、床に投げ捨てた。「君の言う通りだ、私は王だ。なぜ隠す必要があろう!」
「まったくその通りです」ホームズはつぶやいた。「陛下がウィルヘルム・ゴットライヒ・ジギスモンド・フォン・オルムシュタイン、カッセル=フェルシュタイン大公にしてボヘミア国王であることは、すぐに分かりました」
「だが分かるだろう、」来訪者はもう一度椅子に座り、高い白い額に手をやりながら言った。「私はこうした用件を自分で処理する習慣がない。しかし、あまりに繊細な話なので代理人には任せられなかった。私はプラハから匿名で、君に相談しに来たのだ」
「ではご相談を」とホームズは再び目を閉じて言った。
「経緯は簡単です。五年前、私は長期のワルシャワ滞在中に、よく知られた女冒険家アイリーン・アドラーと知り合いました。ご存じの名前かと」
「博士、索引を見てくれ」とホームズは目を閉じたままつぶやいた。彼は長年にわたり、人物や事件についての記事を切り抜き整理しており、どんな話題でもすぐに情報を引き出せる仕組みにしていた。今回も、ユダヤ教のラビと深海魚についての論文を書いた海軍士官の項の間に彼女の伝記を見つけた。
「さて」ホームズ。「ふむ! 1858年ニュージャージー生まれ。コントラルト――ふむ! スカラ座、ふむ! ワルシャワ帝国歌劇場のプリマドンナ――なるほど! すでに舞台は引退――はは! 現在ロンドン在住――そうか! 陛下はこの女性と関係を持ち、いくつかのやっかいな手紙を書き、いまそれを取り戻したいというわけですね」
「まさにその通りです。しかし――」
「秘密結婚だったのですか?」
「いや」
「公的な証書や書類は?」
「ない」
「では、話が見えません。この女性が手紙を持ち出して脅迫したりしても、その真実性をどう証明できます?」
「筆跡です」
「いや、偽造できる」
「私の私用便箋です」
「盗まれた可能性がある」
「私自身の封印です」
「模倣できる」
「私の写真です」
「買える」
「二人で写っている写真です」
「おや、それはまずい。ご無分別でした、陛下」
「私は愚かだった――狂気の沙汰だった」
「大いにご自身を危険にさらしましたね」
「当時はまだ皇太子でした。若かった。今、やっと三十歳です」
「写真は必ず取り戻さねばなりません」
「すでに手を尽くしましたが失敗しました」
「陛下は代価を支払うべきです。買い取るしかありません」
「彼女は売るつもりがありません」
「ならば盗むしかない」
「五度も試みました。二度は私の差し向けた賊が家を荒らしました。一度は旅の荷物をすり替えました。二度は道で襲撃もしました。だが何の成果もありません」
「何の手がかりも?」
「全くありません」
ホームズは笑った。「なかなか面白い問題ですね」
「私には深刻な問題ですが」と王は恨めしげに言った。
「まったくその通り。さて、彼女はその写真で何をしようとしているのですか?」
「私を破滅させるためです。」
「どうやって?」
「私は結婚することになっています。」
「それは聞いています。」
「クロティルデ・ロートマン・フォン・ザクセン=メニンゲン、スカンジナビア王の次女とです。ご存知かもしれませんが、彼女の家系は非常に厳格な主義を持っています。彼女自身もまた、繊細さの極みのような女性です。もし私の行いに少しでも疑念の影が差せば、この話はすべて水の泡となるでしょう。」
「それで、アイリーン・アドラーは?」
「写真を彼らに送ると脅しています。しかも、必ず実行するでしょう。私は彼女をよく知っています。あなたはご存じないでしょうが、彼女は鋼の魂を持った女性です。女性としてはこの世で最も美しい顔立ちであり、しかも最も意志の強い男の頭脳を持っています。私が他の女性と結婚しようものなら、彼女はどんな手段にも訴えるでしょう――どこまでも、です。」
「彼女がまだ写真を送っていないという確信は?」
「あります。」
「なぜです?」
「婚約が公に発表された日に送ると言っているからです。それは来週の月曜日です。」
「おや、それならまだ三日猶予がありますね」とホームズはあくびをしながら言った。「それは幸いです。ちょうど今、いくつか大事な案件があるもので。陛下はもちろん当分ロンドンに滞在されるのでしょう?」
「もちろんです。ラングハム・ホテルに、フォン・クラム伯爵の名で滞在しています。」
「では、進展があればお手紙を差し上げます。」
「ぜひそうしてください。私は気が気でなりません。」
「それから、報酬については?」
「お好きなだけどうぞ。」
「本当に?」
「写真が手に入るなら、私の領土の一州を差し出しても惜しくありません。」
「では、当面の費用は?」
王はクロークの下から重そうなシャモア革の袋を取り出し、テーブルの上に置いた。
「ここに金貨で三百ポンド、紙幣で七百ポンド入っています。」
ホームズは手帳の一枚に領収書を書き、王に手渡した。
「それから、マドモワゼルの住所は?」と彼は尋ねた。
「セント・ジョンズ・ウッド、サーペンタイン・アベニュー、ブライオニー・ロッジです。」
ホームズはそれを書き留めた。「もう一つだけお伺いします。写真はキャビネサイズでしたか?」
「そうです。」
「では、これで失礼いたします、陛下。すぐに良い報告ができることを願っております。それではワトソン、また明日」と、王の馬車の車輪の音が通り過ぎるのを聞きながら付け加えた。「もしよろしければ、明日の午後三時にお越しください。この件について相談したいのです。」
II
午後三時きっかりに私はベイカー街に着いたが、ホームズはまだ戻っていなかった。家主の話では、彼は朝八時過ぎに家を出たという。私はストーブのそばに腰を下ろし、どれだけ時間がかかっても彼を待つつもりでいた。この依頼にはすでに大いに興味をそそられていた。というのも、すでに記録した二つの事件にあったような陰惨さや奇妙さには欠けているものの、その内容の特殊さや、依頼人の地位の高さが、この事件に独自の色合いを与えていたからだ。実際、調査自体の性質はさておき、友人であるホームズが状況を鮮やかに把握し、鋭く的確な推理を展開していくのを観察できるのは、私にとって何より楽しいことだった。そして彼が、どんなに複雑な謎でも素早く巧みに解きほぐしていく様子を追いかけることは大きな喜びだった。彼が必ず成功することに慣れすぎてしまい、失敗の可能性など考えたことすらなかった。
四時近くになってようやくドアが開き、酔っぱらいのような厩務員が、だらしない身なりで、赤ら顔に伸びたもみあげのまま部屋に入ってきた。ホームズの変装術には慣れていた私ですら、三度見直してやっと彼だと確信できたほどだった。彼は軽くうなずくと寝室に消え、五分後には古くからのツイードのスーツ姿で、きちんとした身なりに戻って現れた。ポケットに手を突っ込み、暖炉の前で足を伸ばして、しばらくの間、心から愉快そうに笑い続けた。
「いやはや、これは――!」と彼は叫び、それからむせて、またもや大笑いし、しまいには椅子にぐったりともたれてしまった。
「どうしたんです?」
「本当に可笑しくてね。僕が今朝どう過ごして、何をしたか、君には絶対に当てられないよ。」
「想像もつきません。アイリーン・アドラー嬢の家や生活を観察していたのでしょう?」
「その通りだが、結末がちょっと普通じゃなかった。まあ、話そう。今朝、八時過ぎに家を出た時、私は職探し中の厩務員になりきっていた。馬好きの連中には独特の連帯感があって、仲間入りすれば何でも教えてくれる。ブライオニー・ロッジはすぐに見つかった。後ろに庭があり、前面は道路に面して建てられた小ぢんまりしたヴィラだ。ドアにはチャブ錠。右手に広い居間があり、家具は立派で、床すれすれまである大きな窓がある。しかも、あの馬鹿げたイギリス式の窓止めで、子どもでも開けられるやつだ。裏側は特に変わった所はなかったが、廊下の窓は馬車小屋の屋根から手が届きそうだった。家の周りをぐるりと歩き回って、あらゆる角度から観察したが、他には特に面白い発見はなかった。
それから通りをぶらついていると、思った通り、庭の塀沿いの小道に厩舎があった。そこで馬丁たちと一緒に馬を磨いてやり、その代わりに、二ペンスと、ハーフ&ハーフのグラス一杯、シャグタバコ二服、それにアイリーン・アドラー嬢について知りたいだけの情報を手に入れた。おまけに、全く興味のない近所の他の連中の身の上話まで、半ば強制的に聞かされたけどね。」
「それで、アイリーン・アドラーについては?」と私は尋ねた。
「おや、あの辺の男たちの心をすっかり奪ってしまっているらしい。サーペンタイン厩舎の連中は口を揃えて、地球上でいちばん上品な女性だと言っていたよ。彼女は静かに暮らし、コンサートで歌い、毎日五時には外出して、七時きっかりに帰宅して夕食。普段はほとんど外出しないが、歌う時だけは例外だ。男の来客は一人だけだが、頻繁に訪ねてくる。黒髪でハンサム、颯爽とした男で、最低でも一日一回来て、しばしば二度来る。彼はインナー・テンプル所属のゴドフリー・ノートン氏だ。御者たちを相手にする利点がよく分かるだろう。彼を少なくとも十数回、サーペンタイン厩舎から家まで送っていて、彼について何でも知っているのさ。ひととおり話を聞き終えた後、私はまたブライオニー・ロッジの近くを歩きながら、作戦を練りはじめた。
このゴドフリー・ノートンは、どうやら重要な人物らしい。弁護士というのも気になる。二人の関係は何なのか、彼が頻繁に訪れる目的は? もし彼女が依頼人なら、写真は彼に預けられているかもしれない。だが、そうでなければその可能性は低い。この問題の行方次第で、私がブライオニー・ロッジで調査を続けるべきか、それともテンプルの氏の事務所に目を向けるべきか決まる。微妙な問題だが、調査の幅が広がる。細かい話で君を退屈させるかもしれないが、状況を理解してもらうには僕の小さな苦労も知ってもらわないとね。」
「しっかり聞いているよ」と私は答えた。
「まだ思案していると、ブライオニー・ロッジにハンサム・キャブが到着し、中から男が飛び降りてきた。非常にハンサムで、黒髪、鷲鼻、口ひげ――明らかに例の男だ。大いに急いでいる様子で、御者に待つよう叫び、メイドを押しのけて家に駆け込んだ。まるで自分の家のようだった。
彼は家の中に三十分ほどいて、その間、居間の窓越しに彼が興奮して歩き回り、腕を振りながら話している様子が見えた。彼女の姿は見えなかった。やがて、前よりもさらに慌ただしい様子で彼が現れ、ハンサム・キャブに飛び乗ると、懐中時計を取り出して真剣に見つめ、『グロース&ハンキーのリージェント・ストリート店、続いてエッジウェア・ロードのセント・モニカ教会まで。二十分で着いたら半ギニー出すぞ!』と叫んだ。
二人は走り去り、私は追いかけるべきかと迷っていると、路地から小さなランドー馬車がやって来た。御者はボタンを半分しか留めておらず、ネクタイは耳の下、馬具の革ひもも全部外れていた。馬車が止まるか止まらないかのうちに、彼女が玄関から飛び出して乗り込んだ。ちらりとしか見えなかったが、命を賭けても惜しくないほど美しい女性だった。
『セント・モニカ教会へ、ジョン! 二十分で着いたら半ソブリンよ!』
これは見逃せない、ワトソン。走って追いかけるか、馬車の後ろに飛び乗るか迷っていると、ちょうどタクシーが通りかかった。運転手は私のボロ姿を見て二度見したが、反応する前に私は飛び乗り『セント・モニカ教会まで。二十分で着いたら半ソブリンだ!』と言った。十一時三十五分過ぎで、事の成り行きは察しがついた。
私の御者も飛ばしてくれたが、他の二台は先についていた。教会の前には馬の汗が湯気を立てているタクシーとランドーが止まっていた。私は運転手に支払い、中に駆け込むと、教会には追ってきた二人と、式服姿の聖職者しかいなかった。三人は祭壇の前で固まって何やら話し込んでいる。私は教会にふらりと入った物好きのように脇廊下から近づいた。すると突然、祭壇の三人がこちらを振り向き、ゴドフリー・ノートンが全速力で私の方へ駆けてきた。」
「助かった!」と彼は叫んだ。「君でいい、来てくれ!」
「それから?」
「来てくれ、早く、あと三分しかない。そうしないと式が無効になってしまう!」
「私は半ば引きずられるように祭壇まで連れて行かれ、何が何だかわからないまま、耳元でささやかれる言葉にうなずき、全く知らない事柄について保証し、結果的にアイリーン・アドラー独身女性とゴドフリー・ノートン独身男性の結婚をしっかりお膳立てしてしまった。あっという間に式は終わり、両側から新郎新婦にお礼を言われ、神父が目を細めて私を見ていた。人生でこれほど馬鹿げた立場に陥ったのは初めてだよ。さっき笑いが止まらなかったのもそのせいだ。どうやら二人の結婚許可証に不備があったようで、神父は目撃者なしでは絶対に式を挙げないと言い張ったらしい。そこへ私が現れて、花婿は通りに出て証人を探す手間が省けたというわけだ。花嫁は私に一ソブリンくれたので、これは記念に時計鎖につけておくつもりだ。」
「これはまったく予想外の展開だ」と私。「それで、その後は?」
「私の計画は大いに狂わされた。二人がすぐに出発する恐れがあり、私も迅速かつ果断に動かなければならなくなった。だが教会のドアで彼らは別れ、彼はテンプルへ、彼女は自宅へ戻った。『いつも通り五時には公園をドライブするわ』と彼女が言うのが聞こえた。それ以外は何も聞き取れなかった。二人はそれぞれ別方向へ去り、私は私自身の手配に取りかかった。」
「それは?」
「冷たいローストビーフとビール一杯さ」と彼はベルを鳴らしながら答えた。「食事を考える暇もなかったし、今夜はもっと忙しくなりそうだ。ところで、博士、君の協力が必要だ。」
「喜んで。」
「法を犯しても構わないかい?」
「少しも。」
「捕まる危険もあるけど?」
「正当な理由があれば。」
「理由は申し分ない!」
「それなら僕に任せてくれ。」
「君なら頼りになると思っていた。」
「それで、何をすればいい?」
「ミセス・ターナーが食事を運んできたら説明しよう。さて」と、彼は女主人が用意してくれた簡素な食事に空腹そうに向き合いながら、「食事中に話すが、時間がない。もうすぐ五時だ。二時間後には現場にいないといけない。アイリーン嬢――いや、今やマダムだ――は七時にドライブから戻る。それに合わせてブライオニー・ロッジで待ち伏せる。」
「それで、どうするんだい?」
「それは僕に任せてくれ。すでに手はずは整えてある。ただ一点だけ、絶対に守ってもらいたいことがある。何が起きても、絶対に手出ししないこと。わかったかい?」
「中立を保てばいい?」
「一切何もしないこと。恐らくちょっとした騒動が起きるが、絶対に加わらないでくれ。やがて僕が屋内に運ばれることになる。四、五分後には居間の窓が開くだろう。その開いた窓のすぐ傍に構えていてくれ。」
「はい。」
「僕の姿が見えるはずだ。」
「はい。」
「そして僕がこう――手を挙げたら、その時に渡すものを部屋に投げ入れ、同時に『火事だ!』と叫んでくれ。理解できたかい?」
「完全に。」
「それほど危険なものじゃない」と彼はポケットから葉巻型の長い筒を取り出して言った。「ごく普通の配管工用の発煙ロケットで、両端に着火キャップがついていて自動点火できる。君の役目はそれだけだ。君が『火事だ!』と叫べば、周囲の人間も一斉に声を上げる。それが済んだら通りの端まで歩いてくれ。十分後に合流する。これで説明は十分だろう?」
「僕は中立で、窓のそばに行き、合図があったらこれを投げ入れて『火事だ!』と叫び、通りの角で君を待つ――ということだね。」
「その通り。」
「それなら君を信じて任せてくれ。」
「素晴らしい。そろそろ新しい役柄に着替える時間だ。」
彼は寝室に消え、数分後、気のよさそうで単純そうなプロテスタントの聖職者に変身して戻ってきた。幅広の黒帽子、だぶだぶのズボン、白いネクタイ、同情的な微笑み、そして好奇心と善意に満ちた表情――これはまさにジョン・ヘア氏[訳注: 当時の有名俳優]くらいしか真似できないだろう。ホームズは単に服装を替えるだけではなかった。表情、態度、まるで魂そのものまで、役によって変化するのだった。彼が犯罪専門家にならなければ、舞台は名優を、科学界は名探偵を失っていただろう。
私たちがベイカー街を出たのは六時十五分で、サーペンタイン・アベニューに着いた時には、あと十分ほどで約束の時刻だった。すでに薄暗く、街灯がちょうど灯り始めたところで、私たちはブライオニー・ロッジの前を行きつ戻りつ、その主の帰宅を待った。家はホームズの簡潔な描写から想像していた通りだったが、思ったよりも人通りが多く、静かな住宅街のわりに賑やかだった。みすぼらしい男たちが一角でタバコを吸いながら笑い、砥石屋が仕事をし、衛兵の二人が乳母とじゃれ合い、何人もの洒落た若者が葉巻をくわえてぶらぶらしていた。
「見てごらん」と家の前を歩きながらホームズが言った。「この結婚は事態をむしろ単純にしてくれた。写真は今や両刃の剣だ。彼女もまたゴドフリー・ノートン氏に写真を見られるのは、我々の依頼人が王女に見られるのを嫌がるのと同じくらい避けたいはずだ。さて、問題は写真がどこにあるかだ。」
「どこだろう?」
「彼女が持ち歩いているとは考えにくい。キャビネサイズで、女性の服に隠すには大きすぎる。王が襲って捜索する可能性があることも、彼女は知っているはずだ。実際、そのような試みがすでに二度あった。となれば、彼女は写真を持ち歩いていないと見て差し支えない。」
「では、どこに?」
「銀行か、弁護士。両方の可能性があるが、私はどちらも違うと思う。女性は本来秘密好きで、自分で隠したがるものだ。他人に預ける理由がない。自分で守るなら信頼できても、ビジネスマンにはどんな間接的な圧力がかかるか分からない。しかも、数日中に写真を使うと決めているのだから、すぐ手の届く場所――自宅にあるはずだ。」
「だが、二度も泥棒に入られている。」
「ふん、奴らは探し方を知らなかっただけさ。」
「君はどうやって探す?」
「探さない。」
「どういう意味だい?」
「彼女自身に見せさせる。」
「だが、彼女は拒むだろう。」
「拒めないようにする。――おや、車輪の音がする。彼女の馬車だ。さあ、僕の指示を一言一句違えずに実行してくれ。」
彼がそう言ったちょうどその時、馬車の側灯の光が並木道の曲がり角から現れた。小ぎれいなランドー馬車が、ガタガタとブライオニー・ロッジの玄関前まで駆けつけてきた。馬車が止まると、角でぶらぶらしていた男の一人が小銭をもらおうと扉を開けに飛び出したが、同じ考えの別の男に肘で押しのけられた。激しい口論が始まり、それに衛兵二人が一方の男の肩を持って加わり、さらにハサミ研ぎ屋ももう一方に加勢したことで、喧嘩は一層激しくなった。殴り合いとなり、瞬く間に馬車から降りたばかりの女性が、顔を紅潮させた男たちの小さな輪の中心に巻き込まれてしまった。男たちは拳や杖で激しく殴り合っていた。ホームズは女性を守るため群衆の中に飛び込んだが、彼女にたどり着いたその時、叫び声を上げて地面に倒れ、顔から血が勢いよく流れ出した。ホームズが倒れると、衛兵たちは一方向に、他の男たちは逆方向に逃げ去った。周囲で騒動を見物していた、身なりの良い人々が慌てて駆け寄り、女性を助けホームズの手当てをしようとした。私は、彼女のことをやはりアイリーン・アドラーと呼ぶが、彼女は急いで階段を上がったものの、玄関ホールの明かりを背に美しいシルエットとなり、通りの方を振り返って立ち止まっていた。
「その方はひどく怪我をなさったの?」と彼女は尋ねた。
「もう死んでるよ!」と何人かが叫ぶ。
「いやいや、まだ息がある!」と別の声が叫んだ。「でも、病院に運ぶ前に死んじまうだろう。」
「勇敢な人だよ」と女性の一人が言った。「あの人がいなかったら、奥様の財布も時計も盗られていたわよ。あの連中は仲間で、相当荒っぽい連中さ。あら、今息をしてる。」
「道端に寝かせておくわけにはいかないわ。中に運びましょうか、奥様?」
「もちろんよ。居間に運んでちょうだい。ソファがあるから。こちらへどうぞ!」
ホームズはゆっくりと、厳かにブライオニー・ロッジの主室へと運び込まれ、ソファに寝かされた。私は窓辺の持ち場からその様子を見守っていた。部屋のランプはついていたが、ブラインドは下ろされていなかったので、私はソファに横たわるホームズの姿がよく見えた。その時、彼が自分の役割に後ろめたさを感じたのかどうかは分からないが、少なくとも私は、この美しい女性に対して共謀している自分を人生でこれほど恥じたことはなかった。彼女が負傷者を心優しく世話するその姿を見て、なおさらだった。それでも今さら降りることは、ホームズに対する最大の裏切りになる。私は心を鬼にして、オーバーの下から煙幕ロケットを取り出した。結局、私たちは彼女を傷つけているわけではない。ただ、誰かが傷つけられるのを防いでいるだけなのだ、と自分に言い聞かせた。
ホームズがソファの上で身を起こし、息苦しそうに窓の方を指さす仕草をした。メイドが駆け寄って窓を大きく開け放った。その瞬間、ホームズが合図のように手を挙げたのが見えた。私はその合図で「火事だ!」と叫びながら、ロケットを部屋の中へ投げ込んだ。私の声が響くや否や、紳士も馬丁もメイドも、身なりの良い者も悪い者も、部屋中が「火事だ!」と大騒ぎになった。濃い煙が部屋中に渦を巻き、開いた窓から外へと流れ出した。私は人々が慌てて動き回るのを一瞬見て、すぐ後に中からホームズの声が「誤報だ」と皆を安心させるのが聞こえた。私は騒然とした人込みを抜けて通りの角へ向かった。10分ほどして、友人の腕が私の腕に絡んできたときには、現場から離れられたことに心底安堵した。ホームズはしばらく黙ったまま速足で歩き続け、エッジウェア・ロードへと抜ける静かな路地に入ったところで口を開いた。
「見事な手際だったよ、ワトソン君。申し分ない。すべてうまくいった。」
「写真は手に入ったのか?」
「どこにあるか分かった。」
「どうやって分かった?」
「彼女が見せてくれた――君にもそう言っただろう。」
「まだ事情が飲み込めない。」
「いや、別に謎めかすつもりはない」と彼は笑った。「全く単純な話さ。君も気づいただろうが、通りにいた連中は全員が雇われた共犯だ。今夜のために揃えられていたんだ。」
「それは察しがついた。」
「それで騒ぎが起きた時、私は掌に少し湿った赤い塗料を仕込んでいた。前へ飛び出し、倒れ、顔に手を当てて哀れな負傷者を演じた。古い手だよ。」
「それも推測できた。」
「それから運び込まれた。彼女は私を中に入れざるを得ない。どうしようもないからね。そして居間に通された。そこが私が睨んでいた部屋さ。寝室と並んでいて、どちらかだと睨んでいた。ソファに寝かされ、私は空気を所望する動作をした。窓を開けざるを得なくなり、君に出番が巡ってきた。」
「それがどう役立ったんだ?」
「決定的だったよ。女性は家が火事だと思うと、本能的に一番大切なものを真っ先に守ろうとする。これは抗い難い衝動で、私は何度もこの習性を利用したことがある。ダーリントンの身代わり事件でも役立ったし、アーンスワース城の件でもだ。既婚女性なら赤ん坊を、未婚なら宝石箱を真っ先に抱える。今日の彼女には、我々が探しているもの以外に何も家に大切なものはないはずだ。彼女は必ずそれを確保しに行く。火事騒ぎは完璧だった。煙と叫び声で、どんな剛胆な人間も動揺する。彼女も素早く反応した。写真は、右手のベルの引き紐のすぐ上、引き戸になった隠し棚の中だ。彼女は一瞬でそこに駆け寄り、半分引き出したところを私は見逃さなかった。私が誤報だと叫ぶと、彼女は写真を戻し、ロケットにちらりと目をやって部屋から飛び出し、それきり彼女の姿は見ていない。私は立ち上がり、丁重に詫びて屋敷を後にした。すぐに写真を奪おうか迷ったが、御者が中に入ってきて私をじっと見ていたので、安全のため待つことにした。少しでも早まれば、すべてが台無しになる。」
「これからどうする?」
「ほぼ終わったも同然だ。明日、国王を連れて取りに行く。君も一緒に来るかい? 居間に通されて彼女を待つことになるが、たぶん彼女が現れた時には我々も写真も消えているだろう。写真を自分で取り戻すのは、陛下にとっても満足だろう。」
「明日は何時に?」
「朝の八時だ。彼女はまだ起きていないだろうから、邪魔も入らない。それに、急ぐ必要がある。結婚すれば彼女の生活も習慣も一変するだろうからね。すぐに国王に電報を打たねば。」
我々はベーカー街へ戻り、玄関で立ち止まった。ホームズが鍵を探していると、通り過ぎざまに誰かが言った。
「おやすみなさい、シャーロック・ホームズさん。」
その場には何人か人がいたが、その声はオーバーを着た細身の若者が足早に通り過ぎるのと同時に聞こえた。
「あの声、どこかで聞いたことがある」とホームズは街の薄暗い通りを見つめながら言った。「一体、誰だったんだろう?」
III
その晩はベーカー街に泊まり、翌朝トーストとコーヒーをとっていると、ボヘミア国王が部屋に駆け込んできた。
「写真を手に入れたのだな!」と彼はホームズの両肩をつかみ、顔を食い入るように見つめた。
「まだです。」
「でも、望みは?」
「あります。」
「では急ごう。私はいても立ってもいられない。」
「馬車が必要だ。」
「いや、私のブロムが待っています。」
「それは好都合ですね。」我々は階下へ降り、再びブライオニー・ロッジへ向かった。
「アイリーン・アドラーは結婚した」とホームズが言った。
「結婚? いつ?」
「昨日だ。」
「相手は誰だ?」
「ノートンというイギリス人の弁護士だ。」
「だが、彼女は彼を愛していないだろう?」
「私は、彼女が彼を愛していることを願っている。」
「なぜ願う?」
「それなら陛下は今後何も心配する必要がないからです。彼女が夫を愛していれば、陛下を愛していない。陛下を愛していなければ、陛下の計画を妨げる理由もない。」
「なるほど。しかし……ああ、彼女がもし私と同じ身分だったなら! どれほど立派な王妃になったことか!」彼は沈んだ様子で黙り込んだ。その沈黙は、我々がサーペンタイン・アヴェニューに到着するまで破られなかった。
ブライオニー・ロッジの扉は開いており、年配の女性が玄関に立っていた。我々が馬車を降りると、彼女は皮肉な目つきでじっと見ていた。
「シャーロック・ホームズさんでいらっしゃいますね?」
「私がホームズですが」と、ホームズは驚きと問いかけの入り混じった視線を向けて答えた。
「そうですか。奥様から、あなたが見えるかもしれないと聞いておりました。奥様は今朝、ご主人と一緒にチャリング・クロス発五時十五分の大陸行き列車でお発ちになりました。」
「何ですって!」ホームズは愕然と後ずさった。「つまり、イギリスを発ったと?」
「二度と戻らないと。」
「書類は?」と国王がしわがれた声で尋ねた。「すべて失ったのか。」
「さて、どうでしょう。」ホームズは女中を押しのけて居間へ駆け込んだ。国王と私も続いた。部屋の家具はあちこちに散乱し、棚や引き出しは開け放たれ、彼女が出発前に急いで物色したことがうかがえた。ホームズはベルの引き紐へまっしぐらに向かい、小さな引き戸を開けて手を差し入れ、写真と手紙を取り出した。写真はイブニングドレス姿のアイリーン・アドラー本人で、手紙には「シャーロック・ホームズ様 ご来訪まで預かり置き」と宛名があった。ホームズは手紙を開封し、三人で読んだ。日付は前夜の深夜だった。内容はこうだった――
「親愛なるシャーロック・ホームズ様
見事でした。私は完全に騙されました。火事騒ぎが 起こるまで、全く疑っていませんでした。しかし、 自分がどうやって秘密を明かしたかに気付き、考え ました。数ヶ月前からあなたに警戒するよう忠告 されていました。もし国王が代理人を雇うなら、 きっとあなたに頼むだろうと。そしてあなたの住所 までも教えられていました。でも、そのすべてが あっても、私はあなたに見抜かれてしまいました。 疑い始めてからも、あんなに親切な年配の牧師様 に悪意を抱くのは難しかったのです。でも御存じの 通り、私も女優として訓練を積んでおります。 男装は私にとって珍しいことではありません。 よくその自由さを活用しています。ジョン―― 御者――にあなたを見張らせ、自分は階上へ駆け 上がり、いわゆる外出着に着替えて、あなたが 立ち去るのと同時に下りてきました。
その後、あなたを追ってご自宅のドアまで ついて行き、私が本当にシャーロック・ホームズ 氏に注目されていることを確かめました。 それから、つい不用意にもおやすみなさいと 声をかけ、テンプルの夫のもとへ向かいました。
あの手強い相手に追われては、最善は逃亡だと 夫婦で判断しましたので、明日お越しになっても 住処はもぬけの殻でしょう。写真については、 ご依頼人も安堵してよいでしょう。私は今、 彼よりも優れた人を愛し、また愛されています。 国王は、これ以上困らされることなく、自由に 行動なさることができます。私は、彼に不当に 扱われたため、自己防衛と今後何らかの行動が 取られた場合の切り札として、写真だけは手元に 置いておきます。彼が所望するであろう写真を 一枚残しておきますので、お持ちになってください。 それでは、ホームズ様、ごきげんよう。
アイリーン・ノートン(旧姓アドラー)」
「なんて女性だ――なんて素晴らしい女性だ!」国王は手紙を読み終えると叫んだ。「彼女がいかに機敏で決断力があるか、言った通りだろう? あの人が私と同じ身分だったら、どれほど立派な王妃になったことか!」
「私が見た限り、陛下とはまったく“別の次元”にいらっしゃるようですが」とホームズは冷ややかに言った。「陛下のご依頼をより満足のいく形で果たせなかったのは残念です。」
「いや、逆だ、親愛なるホームズ氏!」と国王は叫んだ。「これほどうまくいったことはない! 彼女の言葉は決して破られない。写真は火の中にあるのと同じくらい安全だ。」
「そう仰っていただき、うれしい限りです。」
「私はあなたに大きな恩義を感じています。ぜひお礼をさせてください。この指輪を――」彼はエメラルドのヘビの指輪を外し、手のひらに載せて差し出した。
「陛下が私よりもずっと高く評価するであろうものを、私は頂きたいのです」とホームズ。
「ご希望のものをおっしゃってください。」
「この写真を。」
国王は驚いてホームズを見つめた。
「アイリーンの写真を? もちろん、もし望むなら。」
「感謝します。それでは、この件についてはこれ以上申し上げることはありません。おはようございます。」ホームズは一礼し、国王が差し出した手には気づかぬふりで私とともに部屋を後にした。
こうして、大スキャンダルがボヘミア王国を直撃しそうになり、シャーロック・ホームズの名案も一人の女性の知恵に敗れ去ったのである。ホームズはかつて女性の機知を冗談の種にしたものだが、最近ではそんな話を聞かなくなった。そしてアイリーン・アドラーや彼女の写真について語る時、必ず「かの女」と敬意を込めて呼ぶのである。
第二の冒険 赤毛連盟
私は昨年の秋、友人シャーロック・ホームズ氏を訪ねたことがあった。彼はそのとき、非常に太っていて、赤ら顔で、燃えるような赤毛をした年配の紳士と深刻な話をしていた。私はお邪魔かと思って引き返そうとしたが、ホームズが私を無理やり部屋に引っ張り込み、ドアを閉めてしまった。
「これ以上いいタイミングはないよ、ワトソン君」と、彼は親しげに言った。
「ご迷惑かと思っていました。」
「いや、ちょうどいい。大いに助かる。」
「なら、隣の部屋で待ちます。」
「そんな必要はない。このジェベズ・ウィルスンさんは、私の多くの成功した事件でパートナー兼協力者となってくれた人で、今回の件でもきっと大いに役立ってくれるだろう。」
太った紳士は椅子から半分立ち上がり、小さな丸々とした目で素早く好奇心に満ちた一瞥をして、頭を下げて挨拶した。
「ソファにどうぞ」とホームズは言い、裁判官のような気分の時によくするように、指先を合わせて肘掛け椅子にもたれかかった。「ワトソン君、君が日常の常識や単調な生活からかけ離れた奇妙な出来事を愛していることはよく知っている。君がこれまで私のちょっとした冒険を熱心に記録し、時に美化さえしてくれたことが、それを証明しているよ。」
「確かに、あなたの事件にはいつも大いに興味を持っています」と私は言った。
「先日も言っただろう、ミス・メアリー・サザーランドの簡単な事件の前に、奇妙な出来事や異常な組み合わせは、想像力の産物よりも、現実の人生の方がずっと大胆に現れるものだ、と。」
「私はその意見には少し疑問を挟みました。」
「君はそうだったね、ワトソン君。でも、私は絶えず事実を積み上げていくから、君の理性もいつか音を上げて、私が正しいと認めるだろう。さて、ジェベズ・ウィルスンさんが今朝わざわざ訪ねてくれて、非常に風変わりな話を始めてくれた。私が長い間聞いた中でも、最も奇妙なものの一つになりそうだ。ワトソン君が話の冒頭を聞いていないこともあるし、また内容の特殊さから私自身ウィルスンさん本人からすべての細部を聞きたいので、最初からやり直していただいてもいいですか。普段なら、少し話を聞いただけで過去の膨大な事例から指針を得られるのだが、今回は私の知る限り、きわめて独特な事例だと認めざるを得ません。」
ずんぐりした依頼人は、いくらか誇らしげに胸をそらし、よれよれで汚れた新聞を外套の内ポケットから取り出した。首を前に突き出し、膝の上で広げた新聞の広告欄を見つめる彼を、私はホームズの真似をして、その服装や容貌から何か読み取れないかと観察してみた。
私の観察眼をもってしても、この男から読み取れる情報は驚くほど少なかった。我々の前に腰を下ろした訪問者は、どこからどう見ても、ありふれた英国の商人といった風体だ。肥満気味の身体、尊大さを隠さない態度、そして何をするにも緩慢な動作。彼が身に着けているのは、だぶついた灰色のシェパードチェックのズボン。清潔とは言い難い黒のフロックコートは、その前を開け放している。くすんだ色合いのベストからは重厚な真鍮のアルバートチェーンがのぞき、四角い穴のあいた金属片が、奇妙な装飾として揺れていた。古びてよれたシルクハットと、襟が皺になった茶色のベルベットのオーバーコートが、傍らの椅子に無造作に置かれている。全体を見渡し、注意深く観察の目を凝らしても、その男から特筆すべき個性は見出せない。ただ一点、燃え盛る炎のような赤毛と、その下に刻まれた深い不満と失意の表情を別にすれば――。
私の当惑を、シャーロック・ホームズは見逃さなかった。その鋭い眼光がちらりと私を捉え、疑問符を浮かべた私の表情を読むと、彼はくすりと笑って首を横に振った。 「ワトソン君、見たままの事実以外、この紳士から読み取れることはほとんどない。かつて肉体労働に従事し、嗅ぎ煙草を嗜み、フリーメイソンの一員であり、中国に滞在した経験があり、そしてごく最近、大量の書き物をした――まあ、これっぽっちのことだがね」
ジャベズ・ウィルスン氏は、椅子から乗り出すようにして身を起こした。指先はテーブルの上の新聞を押さえたままだが、その目は驚愕に染まり、ホームズに釘付けになっている。 「い、一体どうしてそんなことまでお分かりになるんです、ホームズさん?」彼はかすれた声で尋ねた。「私が肉体労働をしていたなどと……。おっしゃる通りです。私は若い頃、船大工でした」
「そのお手を見れば一目瞭然ですよ、ウィルスンさん。あなたの右手は左手よりも一回り大きい。長年使い込んできたことで、筋肉がそうさせたのです」
「では、嗅ぎ煙草とフリーメイソンの件は?」
「それを説明するのは、あなたの明晰な頭脳を侮辱するようなものですよ。ご自身の組織の厳格な掟にもかかわらず、円弧とコンパスをかたどったブレストピンを付けていらっしゃるのですから」
「ああ、なるほど! それはうっかりしておりました。しかし、書き物は?」
「あなたの右の袖口は、五インチにわたって磨かれたように光っている。対して左袖の肘のあたりは、机に寄りかかって滑らかになっている。あなたがペンを走らせる姿が目に浮かぶようです」
「では、中国は?」
「右手首のすぐ上にある魚の刺青です。その彫り方は中国でしか見られません。刺青に関しては、私も少々ばかり研究を嗜んでおりましてね。専門誌に論文を寄稿したこともある。魚の鱗を淡い薔薇色に染め上げるその技法は、中国ならではのものなのです。おまけに、懐中時計のチェーンに古い中国の硬貨が下がっているのを見れば、答え合わせはより容易になる」
ジャベズ・ウィルスン氏は、腹の底から快活な笑い声を上げた。「いやはや、お見事! 最初は何か魔法でも使われたのかと思いましたが、種明かしをされれば、なるほど、そういうことでしたか」
「ワトソン君、どうやら私は説明をしすぎたようだ」ホームズは芝居がかった仕草で肩をすくめた。「『未知なるものは壮大に見える』というだろう? こうもあっさり手の内を明かしてしまっては、私のささやかな名声も地に落ちてしまう。ウィルスンさん、例の広告は見つかりましたかな?」
「はい、ここに」と彼は言い、太く赤い指で新聞の一角を指し示した。「すべてはこれが始まりでした。ホームズさん、どうぞご自身でお読みください」
私は彼から新聞を受け取り、奇妙な広告に目を通した。
赤毛連盟へ アメリカ合衆国ペンシルベニア州レバノン出身、故イゼキア・ホプキンスの遺贈により、連盟の会員を対象として、週給四ポンドの名目的な職務に新たな空席が生じました。 心身ともに健全で、満二十一歳以上の赤毛の男性が応募資格を有します。 応募者は、月曜日午前十一時、フリート街ポープズ・コート七番地、連盟事務所のダンカン・ロスまで、直接お越しください。
「これは一体、何を意味しているんだ?」私はその不可解な広告を二度読み返し、思わず呟いた。
ホームズは愉快そうにくすくす笑い、椅子の中で身体をくねらせた。彼が上機嫌な時の癖である。「これは少々、常軌を逸しているようだね」と彼は言った。「さて、ウィルスンさん、事の起こりからお話し願いましょう。ご自身の事、ご家族の事、そしてこの広告があなたの人生に何をもたらしたのかを。先生、新聞名と日付のメモを頼む」
「『モーニング・クロニクル』、一八九〇年四月二十七日。ちょうど二ヶ月前だ」
「よろしい。では、ウィルスンさん」
「はあ、今しがた申し上げた通りの身の上でしてね、ホームズさん」ジャベズ・ウィルスンは額の汗を拭った。「シティの近く、コバーグ・スクエアで小さな質屋を営んでおります。大きな店ではありませんし、ここ数年は糊口をしのぐのがやっとという有様で。以前は助手を二人置いていましたが、今では一人だけ。その一人にさえ、満足な給金を払うのが難しい始末でして。もっとも、彼は仕事が覚えたいからと、半額でいいと言ってくれているのですが」
「その殊勝な若者の名は?」とシャーロック・ホームズが尋ねた。
「ヴィンセント・スポールディングと申します。名前ばかりは若々しいですが、歳はいくつになるのか。あれほど気の利く助手はおりませんよ、ホームズさん。彼ほどの腕なら、もっと良い勤め先を見つけて、私の倍は稼げるはずです。しかし本人が満足している以上、私が彼の将来に口を出すのもおかしな話ですからな」
「なるほど。正規の賃金以下で働く従業員とは、今の御時世、雇い主にとっては望外の幸運ですな。あなたの助手も、その広告に負けず劣らず興味深い」
「まあ、彼にも欠点はありますよ」とウィルスン氏は言った。「写真が趣味でしてな。頭を使うべき時に、カメラをパチパチいじくり回しているかと思うと、現像すると言って地下の倉庫に籠ってしまう。それさえなければ、本当に良い働き手なのですが。他に悪い癖もありません」
「今も?」
「ええ。彼と、簡単な食事と掃除を任せている十四の娘、それだけです。私は妻に先立たれ、子供もおりません。三人で静かに暮らし、なんとか借金もなく屋根の下でやっております。
ことの起こりは、あの広告でした。ちょうど八週間前の今日、スポールディングがあの新聞を手に事務所に下りてきて、こう言ったのです。
『ああ、ウィルスンさん、私が赤毛だったらなあ!』
『どうしてそんなことを言うんだ?』
『ほら、また赤毛連盟に空きが出たんです。これにありつけたら、ちょっとした財産ですよ。会員よりも空席の方が多いらしくて、理事たちも資金の使い道に困っているとか。髪の色さえ変えられれば、私もすぐにでも応募するんですがねえ』
『一体、何の話だ?』私は尋ねました。私は根っからの出不精でして、商売も向こうからやって来るものですから、何週間も店の敷居を跨がないこともざらなのです。ですから世間の出来事には疎く、いつもニュースに飢えておりました。
『赤毛連盟をご存知ないんですか?』彼は目を丸くしました。
『聞いたこともない』
『あなた様こそ、その空席にうってつけだというのに、もったいない話です』
『それで、どれほどの稼ぎになるんだ?』
『年に二百ポンドにはなります。それでいて仕事は楽なもので、今の商売の邪魔にもなりません』
二百ポンド、という言葉に、私の耳はダンボになりました。ここ数年、商売も思わしくなかったので、その額はまさに天の助けです。
『詳しく話してくれ』
『これがその広告です。この住所へ行けば、すべて分かります。私の聞き及んだところでは、この連盟はアメリカの富豪、イゼキア・ホプキンスという男が設立したそうです。彼自身が赤毛で、同じ髪を持つ者たちに深い同情を寄せていた。亡くなる際に莫大な遺産を信託し、その利子で赤毛の男たちに楽な仕事を与えよ、と。給金は素晴らしいのに、仕事はあってないようなものだと』
『だが、そんな話なら、何百万人という赤毛の男が殺到するだろう』
『それが、そうでもないらしいのです。ロンドン在住の成人に限られていますから。このアメリカ人は若い頃ロンドンに住んでいたそうで、故郷への恩返しのようです。それに、淡い赤や暗い赤ではだめ。燃えるような、本物の真っ赤な髪でなければ』
『ウィルスンさん、あなたなら間違いなく選ばれます。ただまあ、数百ポンドのためにわざわざ骨を折るのもどうかとは思いますがね』
さて、ご覧の通り、私の髪は我ながら見事な赤でして、もし競争があったとしても、誰にも引けは取らないと自負しておりました。スポールディングがあまりに事情に詳しいので、彼を頼りに、その日の店は任せて、広告の住所へ向かうことにしました。彼も休日ができて嬉しそうでした。
ホームズさん、あんな光景は後にも先にも見たことがありません。北から、南から、東から、西から、赤みがかった髪の男という男がシティに集まり、フリート街は赤毛の川と化し、ポープズ・コートに至っては、まるでオレンジ商の荷車がひっくり返されたかのような有様でした。世の中にこれほど多くの赤毛がいるとは。麦わら色、レモン色、オレンジ、煉瓦色、アイリッシュ・セッターのような赤茶色、くすんだ土色。ありとあらゆる赤がありましたが、スポールディングの言う通り、本物の燃えるような赤毛はそう多くはありません。人の波を見て一度は諦めかけましたが、スポールディングが許しませんでした。どうやったのか分かりませんが、彼は人垣を押し分け、突き飛ばし、なんとか私を事務所へ続く階段の前まで導いたのです。階段は、希望に胸を膨らませて上る者と、失意に肩を落として下りてくる者で二筋の流れができていましたが、我々もその流れに乗り、やがて事務所の中にたどり着きました」
「実に愉快なご経験ですな」とホームズは、依頼人が記憶を呼び覚ますように鼻煙草を深く吸い込むのを見やりながら言った。「どうぞ、お続けください」
「事務所には、安物の木の椅子が二脚とテーブルが一つあるきり。その奥に、私よりもさらに赤い髪をした小柄な男が座っていました。彼は一人一人の候補者と短い言葉を交わしては、必ずどこかに欠点を見つけ出して追い返していました。空席があるとはいえ、そう簡単にはいかないものだと悟りました。しかし、我々の番が来ると、その小男は他の誰に対するよりも私に好意的で、私たちが部屋に入るなりドアを閉め、個人的に話ができるように計らってくれたのです。
『こちらがジャベズ・ウィルスンさん。連盟の空席に応募しに来ました』と私の助手が紹介しました。
『そして、これ以上ないほどの適任者だ』と相手は言いました。『すべての条件を満たしておられる。これほど見事な髪は、私も初めて見ました』彼は一歩下がり、首を傾げ、私の髪をじっと見つめました。私は気恥ずかしさで頬が熱くなるのを感じました。すると彼は突然、ずいと前に出て、私の両手を力強く握りしめ、採用を心から祝福してくれたのです。
『ためらう必要はなさそうだ。ですが、万が一ということもありますので、失礼』そう言うや、彼は両手で私の髪を鷲掴みにし、ありったけの力で引っ張ったのです。あまりの痛みに私は叫びました。『目に涙が浮かんでいますな。よろしい。実を言うと、我々は過去にカツラと染料で二度も騙された経験がありましてね。人間不信にもなるというものです』彼は窓辺へ行くと、外に向かって大声で叫びました。『空席は埋まった!』。下からは落胆のどよめきが聞こえ、群衆は蜘蛛の子を散らすように去って行き、やがてポープズ・コートには、私と管理人以外、一人として赤毛の男はいなくなりました。
『私の名はダンカン・ロスと申します。私もこの基金の恩恵を受けている一人です。ところで、ご結婚は? ご家族は?』
私は独り身だと答えました。すると彼の顔がさっと曇りました。
『それは由々しき問題だ。基金の目的は赤毛の繁栄にもある。独身とは、実に残念です』
これで不採用かと、今度は私の顔が曇りました。しかし彼はしばらく考え込んだ後、こう言ったのです。『まあ、あなたほどの髪をお持ちの方です。特例を認めましょう。いつから勤務できますか?』
『それが、店の方が少々……』
『ご心配なく、ウィルスンさん!』スポールディングが口を挟みました。『店は私が責任をもって見ておきますから』
『勤務時間は?』と私は尋ねました。
『午前十時から午後二時までです』
質屋の商売は、主に夕方、ことに給料日前の木曜と金曜の夜に立て込みます。午前中に小遣い稼ぎができるのは、実に好都合でした。助手も優秀ですから、まず問題はないでしょう。
『結構ですな。それで、報酬は?』
『週に四ポンドです』
『仕事の内容は?』
『実質的には、名目上のものです』
『名目上、とは?』
『その時間、あなたはずっとオフィスに、少なくともこの建物の中にいなければなりません。一歩でも外に出れば、その職は永久に失われます。遺言にそう明記されているのです。どんな理由があろうと、途中で抜けることは許されません』
『たかが四時間です。外に出る気など毛頭ありません』
『病気であろうと、商売の都合であろうと、一切まかりならん。とにかく、その間はここにいていただかねば』
『それで、何をすれば?』
『『ブリタニカ百科事典』を書き写していただきます。最初の巻はあの棚に。インク、ペン、吸い取り紙はご自分でご用意ください。机と椅子はこちらで。明日から始められますかな?』
『もちろんですとも』
『それではウィルスンさん、改めて、この栄えある職に就かれたことをお祝い申し上げます』 こうして私は、助手に付き添われて家路につきましたが、あまりの幸運に、どう喜んでいいものやら分からないほどでした。
その日は一日、そのことで頭がいっぱいでした。夕方になる頃には、これは手の込んだ悪戯か詐欺に違いないという疑念が頭をもたげ始めましたが、その目的が何なのか、皆目見当もつきません。ただ百科事典を書き写すだけで、これほどの大金が手に入るなどという話が、果たしてこの世にあるものか。スポールディングはしきりに私を元気づけてくれましたが、寝る頃にはすっかり馬鹿らしくなり、もう諦めようとさえ思いました。しかし翌朝、物は試しと、一ペニーのインク瓶と羽ペン、そしてフールスキャップ紙を七枚買って、ポープズ・コートへと向かったのです。
そして、我が目を疑いました。すべてが完璧に整えられていたのです。約束の机が置かれ、ダンカン・ロス氏が出迎えて、私が仕事に取り掛かれるよう手筈を整えてくれました。私は『ブリタニカ百科事典』の「A」の項目から書き写し始め、彼は時折、監督するように部屋を覗きに来ました。やがて二時の鐘が鳴ると、彼は「ご苦労様」と声をかけ、私の仕事ぶりをひとしきり褒め称えた後、事務所の扉にがちゃんと鍵をかけたのでした。
そんな日々が、淡々と過ぎていきました、ホームズさん。毎週土曜日になると支配人が顔を出し、一週間分の給金だと言って金のソブリン貨を四枚、ぽんとテーブルに置いていくのです。次の週も、そのまた次の週も、すべてがその繰り返しでした。私は毎朝十時に出勤し、午後二時には退勤する。そんな規則正しい生活が続きました。いつしかダンカン・ロス氏は朝に一度、顔を見せるだけになり、やがてぱったりと姿を見せなくなりました。それでも私は、一瞬たりともあの部屋を離れる勇気はありませんでした。いつ彼が戻ってくるか分かりませんでしたし、何より、これほど条件が良く、私にとってあつらえ向きの職を失う危険を冒すことなど、到底できなかったのです。
そうして八週間が瞬く間に過ぎ去りました。私は百科事典の『A』の項をひたすら書き写し、ついに『修道院(Abbots)』から『弓術(Archery)』、『武具(Armor)』、『建築(Architecture)』、そして『アッティカ(Attica)』にまでたどり着きました。この調子でいけば、そう遠くないうちに『B』の項目に入れるだろうと、そんなことばかり考えておりました。書き損じの紙も合わせれば、棚のひとつが私の原稿で埋め尽くされるほどでした。そして、突然、すべてが終わってしまったのです」
「終わり、ですか?」
「ええ、その通りです。それも、今朝のことでした。いつものように十時に出勤いたしますと、事務所のドアは固く閉ざされ、鍵がかかっている。そしてその真ん中には、画用紙ほどの厚いカードが、一本の鋲で無造作に留められていたのです。これが、その紙切れです。どうぞ、ご覧ください」
彼は手のひらほどの白い厚紙を差し出した。そこには、こう記されているだけだった。
赤毛連盟は 本日を以て解散す
一八九〇年十月九日
私とシャーロック・ホームズは、そのあまりに素っ気ない告知と、それを見せる依頼人の悲痛な横顔をしばし見比べていたが、やがてこの一件の途方もない滑稽さに耐えきれなくなり、二人して腹を抱えて笑い出してしまった。
「何がおかしいのですか!」依頼人は顔を真っ赤にして叫んだ。「もし私を笑いものになさるおつもりなら、よそをあたりますので!」
「いえいえ、とんでもない」ホームズは叫ぶように言うと、椅子から立ち上がりかけた彼を押し戻した。「これほど面白い事件は、そうそうお目にかかれるものではありません。ええ、実に、実に興味深い。ぜひとも調査させていただきたい。ただ、お気を悪くされないでいただきたいのですが、この状況にはどこか、抗いがたい滑稽さが漂っているのも事実なのです。それで、ドアにその札を見つけた時、あなたはどうなさいました?」
「もう、茫然自失とはこのことでした。どうしていいか分からず、隣近所の事務所を訪ねて回りましたが、誰も何も知らないと言うばかり。最後に、階下の大家である会計士をつかまえて、赤毛連盟の行方を尋ねてみたのです。すると彼は、そんな団体は聞いたこともない、と。ではダンカン・ロスという人物はご存じかと訊けば、その名も初耳だと言うではありませんか」

「『ああ、あの赤毛の紳士のことかね?』と彼は言いました。 『そうです』と私は答えました。 『ああ、あの方の名前はウィリアム・モリスだよ。弁護士でね。新しい事務所が見つかるまで、一時的に私の部屋を間借りしていただけさ。昨日、引っ越して行ったよ』 『どちらへ行けば、お会いできますか?』 『新しい事務所さ。住所も教えてくれたな。たしか、セント・ポール寺院の近く、キング・エドワード街十七番地だ』と」
「それで、ホームズさん、私はすぐさまその住所へ駆けつけました。ですが、そこは人工膝蓋骨の製造工場でして、ウィリアム・モリスにもダンカン・ロスにも、誰一人心当たりがないと言うのです」
「それから、どうなさいました?」とホームズは促した。
「サックス=コバーグ広場の自宅へ戻り、助手に事の次第を話しました。ですが、彼も首を傾げるばかり。郵便で何か知らせがあるかもしれないから、待った方がいい、としか言いません。しかし、私には到底納得できませんでした。こんな素晴らしい職を、みすみす手放すわけにはいかない。そこで、困っている人々に助言を与えてくださると評判のあなた様のもとへ、すぐに馳せ参じた次第です」
「実に賢明なご判断です」とホームズは言った。「これは稀に見る興味深い事件です。ぜひ、調査をお引き受けしましょう。お話の様子では、当初の奇妙な見かけの裏に、思いもよらぬ重大な問題が潜んでいる可能性が高い」
「重大な問題ですとも!」ジャベズ・ウィルソン氏は声を張り上げた。「週に四ポンドもの収入を失ったのですよ!」
「あなた個人に関する限り」ホームズは言った。「この奇妙な連盟に、さほど不満を抱く理由はないように思えますがね。むしろ、あなたは三十ポンドほどの純益を得て、おまけに『A』で始まるあらゆる事柄について深い知識を身につけられた。損は何もしていないはずです」
「ええ、しかし……。しかし、私は彼らの正体を知りたいのです。一体何のために、こんないたずらを――もしこれが本当にいたずらだったらの話ですが――仕掛けたのか。ずいぶんと高くついた冗談ですよ。なにしろ彼らは、三十二ポンドもの大金を投じたのですから」
「我々がその謎を解き明かしましょう。さて、いくつか質問よろしいですかな、ウィルソンさん。最初に広告を見つけてきた、あなたの助手ですが、彼を雇ってからどれくらいになりますか?」
「あの時で、ちょうど一月ほどでしたか」
「どういった経緯で?」
「広告を見て、応募してきました」
「応募者は彼一人だけでしたか?」
「いえ、十人以上はおりました」
「なぜ、彼を選んだのです?」
「手先が器用で、給金が安く済んだからです」
「つまり、半値で雇ったと」
「その通りです」
「ヴィンセント・スポールディングというその青年は、どんな人物ですかな?」
「小柄ですが、がっしりした体格で、動きが非常に機敏です。年は三十を過ぎているはずですが、髭がまったく生えておりません。額には、酸で焼かれたような白い染みがあります」
ホームズは興奮したように、椅子からぐっと身を乗り出した。「やはり! 思った通りだ。彼の耳に、ピアスを開けた跡があることにお気づきでしたか?」
「ええ、あります。若い頃にジプシーに開けてもらった、と申しておりました」
「ふむ」ホームズは深く考え込むように、再び椅子の背に体を沈めた。「彼は今もあなたのもとに?」
「ええ。つい先ほどまで、店におりました」
「あなたが留守の間も、商売に支障は?」
「何の不満もありません。朝はさほど忙しくありませんから」
「結構です、ウィルソンさん。二、三日のうちに、私の見解をお伝えできるでしょう。今日は土曜日ですから、月曜日までには何らかの結論を出せるかと」
「さて、ワトソン」依頼人が去った後、ホームズが口を開いた。「君はこの一件をどう見る?」
「さっぱり見当もつかない」私は正直に答えた。「実に不可解な事件だ」
「一般的に言ってね」とホームズは言った。「事件が奇抜であればあるほど、謎は少ないものなのさ。逆に、何の特徴もない、ありふれた顔の犯罪者こそが、本当に厄介な相手だ。人の顔とて、特徴がなければ見分けがつかないだろう。それにしても、今回は迅速に行動せねばなるまい」
「これからどうするんだ?」と私が尋ねる。
「煙草を吸う」と彼は答えた。「これはパイプ三服分の難問だ。五十分は話しかけないでくれたまえ」彼は猫のように椅子に体を丸めると、両膝を抱え込んだ。その膝頭は、彼の鷲鼻に触れんばかりだった。黒いクレイパイプをくちばしのように突き出し、深く煙を吸い込むと、そのまま目を閉じてしまった。私は彼が眠りに落ちたのだと思い、自分もうとうとし始めたが、やがて彼は唐突に椅子から跳ね起き、決然とした仕草でパイプをマントルピースに置いた。
「サラサーテが今日の午後、セント・ジェームズ・ホールで演奏会を開く」と彼は言った。「どうだね、ワトソン。君の患者たちは、数時間ほど君がいなくても大丈夫かね?」
「今日は何の予定もない。私の仕事は、それほど多忙というわけではないからな」
「ならば帽子を取ってくれたまえ。まず市中を少し回り、途中で昼食をとろう。プログラムを見るとドイツ音楽が多いようだ。イタリアやフランスのものより、ずっと私の好みに合う。内省的な音楽は、まさしく今の私の気分にぴったりだ。さあ、行こう!」
我々は地下鉄でオルダーズゲートへ向かい、そこから少し歩いて、今朝話に聞いたサックス=コバーグ広場に到着した。そこは、煤けた、うらぶれた一角だった。四列のくたびれた煉瓦造りの家々が、申し訳程度の芝生と、力なく葉を茂らせる月桂樹の植え込みを囲んでいる。煤煙に汚れた空気の下、雑草交じりの芝生と色あせた常緑樹が、懸命に生きながらえようとしているように見えた。角の家には、三つの金色の玉と「ジャベズ・ウィルソン」と白文字で書かれた茶色の看板が掲げられ、ここが赤毛の依頼人の営む質屋であることを示していた。シャーロック・ホームズは首を傾げ、目を細めながら、その家並みをじっくりと観察した。彼は通りをゆっくりと上り、また下り、再び質屋の前に戻ってくると、今度は手にしていたステッキで、舗道を二、三度、力強く打ち鳴らした。そして、おもむろにドアをノックした。すると間髪を入れず、きびきびとした物腰の、髭のない若者がドアを開け、彼を中へ招き入れようとした。
「ありがとう」とホームズは言った。「ただ、ここからストランドへはどう行けばよいか、お聞きしたかっただけだ」
「三つ目の角を右、四つ目を左です」助手は即座にそう答えると、ぱたんとドアを閉めた。
「なかなかの切れ者だ」ホームズは歩きながら言った。「思うに、彼はロンドンで四番目に賢い男だろう。そして、その大胆さにかけては、おそらく三番目だ。彼のことは、私も以前から知っている」
「どうやら」と私は言った。「ウィルソン氏の助手が、この赤毛連盟の謎に深く関わっていると見ているのだな。道順を尋ねたのも、彼を一目見るためだったのだろう?」
「彼の顔を見るためではない」
「では、何のために?」
「彼のズボンの膝を見るためだ」
「それで、何が見えたんだ?」
「私が予期していた通りのものをさ」
「では、舗道を叩いたのはなぜだ?」
「ワトソン君、今は観察の時であって、お喋りの時ではない。我々は敵地に潜入した斥候なのだ。サックス=コバーグ広場については、いくらか情報が得られた。今度は裏手を探ってみよう」
サックス=コバーグ広場の裏手にある通りは、まるで別世界だった。市中から北や西へと人や物を運ぶ大動脈であり、車道は絶え間ない商業の流れで埋め尽くされ、歩道もまた、行き交う人々の群れで黒ずんでいる。これほど壮麗な商店や事務所が、あの寂れた淀んだ広場の背後に建っているとは、にわかには信じがたい光景だった。
「さて」ホームズは角に立ち、家並みを一望しながら言った。「ここの建物の並びは、覚えておく必要がある。ロンドンの正確な地理を把握しておくのは、私の趣味でね。あれがモーティマーの煙草店、次が小さな新聞屋、コバーグ支店のシティ・アンド・サバーバン銀行、菜食主義者のレストラン、そしてマクファーレンの馬車製造所か。よし、向こうのブロックまで続いているな。さて、ワトソン君、これで下調べは終わりだ。あとは純粋な楽しみの時間としよう。サンドイッチとコーヒーで腹ごしらえをしたら、音楽の国へ旅立つのだ。そこには甘美と繊細と調和があり、赤毛の依頼人に悩まされることもない」
我が友は無類の音楽好きで、演奏家としてもかなりの腕を持つだけでなく、作曲の才能も並外れていた。その午後、彼は客席で恍惚とした表情で音楽に聴き入り、長い指をしなやかに動かしては拍子をとり、その微笑む横顔と夢見るような瞳には、あの怜悧で冷徹な探偵、シャーロック・ホームズの面影は微塵もなかった。彼の持つ二面性は、その不可思議な性格の中で交互に現れるのだった。極度の精密さと抜け目のなさは、時に詩的で瞑想的な気分への反動として現れるかのようだった。彼の気質は、気だるい無気力状態から、猛烈なエネルギーの発露へと大きく揺れ動いた。長椅子に身を沈めて書物に耽ったり、即興演奏に没頭したりした後にこそ、彼の推理力は直観の域にまで高まり、その思考の過程を知らぬ者には、彼がまるで超自然的な知識の持ち主であるかのように見えた。その午後、セント・ジェームズ・ホールで音楽に魂を奪われている彼の姿を見ながら、私は、彼がこれから狙いを定める獲物にとって、恐るべき時が迫っているのを感じずにはいられなかった。
「さて、君は家に戻るのだろう?」コンサートが終わると、彼が言った。
「ああ、その方がよさそうだ」
「私には、これから数時間を要する仕事が残っている。このコバーグ広場の一件は、由々しき事態だ」
「なぜ、そこまで重大だと?」
「かなり大掛かりな犯罪が計画されている。我々が間に合えば、阻止できる見込みはある。だが、今日は土曜日だということが、少々厄介でね。今夜、君の協力が必要になるかもしれん」
「何時に?」
「十時で十分だろう」
「では、十時にベーカー街へ行こう」
「それでいい。――それからワトソン君、一つ頼みがある。今夜は少々物騒なことになるやもしれん。念のため、君の軍用リボルバーを懐にしてきてくれたまえ」彼は手をひらりと振ると踵を返し、またたく間に雑踏の中へと消えていった。

自分をことさらに鈍感な人間だとは思いたくないが、シャーロック・ホームズと行動を共にしていると、いつも己の愚鈍さを痛感させられる羽目になる。彼と同じ話を聞き、同じものを見ているはずなのに、彼には出来事の全貌だけでなく、これから起きることまで見通せているかのようだ。一方の私には、すべてが支離滅裂で、奇怪な謎としか思えない。ケンジントンの自邸へ帰る道すがら、私はこの一日の出来事を反芻した。百科事典を書き写す赤毛の男の奇妙な物語から、サックス=コバーグ広場での調査、そしてホームズが残した謎めいた別れの言葉まで。今夜の探索とは一体何なのか。なぜ武装する必要があるのか。我々はどこへ向かい、何をしようというのか――。いくら考えを巡らせても、答えのかけらも見つからず、結局は夜を待つしかないと腹を括るしかなかった。
九時一五分に家を出て、公園を横切り、オックスフォード街を抜けてベーカー街へと向かった。ドアの前には二台のハンサム馬車が停まっており、建物の中からは複数の話し声が聞こえてくる。部屋へ入ると、ホームズが二人の男と熱心に言葉を交わしていた。一人は見覚えがあった。スコットランドヤードの制服に身を包んだ、ピーター・ジョーンズ警部だ。もう一人は長身痩躯で、陰気な顔つきをした男で、やけに艶のあるシルクハットと、見るからに格式ばったフロックコートが、その憂鬱さを一層引き立てていた。
「やあ、これで全員そろったな」ホームズはピーコートのボタンを留めながら、重そうな狩猟用の鞭を手にした。「ワトソン、スコットランドヤードのジョーンズ氏は知っているね? そしてこちらはメリーウェザー氏。今夜の我々の冒険に、同行していただくことになっている」
「また二人一組での猟ですな、先生」ジョーンズがしたり顔で言った。「こちらの友人は、獲物を追わせれば天下一品ですが、いざ追い詰めて仕留める段になると、やはり我々のような年季の入った猟犬が必要になるというわけですな」
「無駄足にならなければよいが」と、メリーウェザー氏は気乗りしない様子で呟いた。
「ホームズさんを信じて間違いありませんよ」警部は尊大に言った。「やり方が少々理論的で風変わりすぎるところはありますが、探偵に必要な資質は、誰よりもお持ちです。ショルトー事件やアグラの財宝の一件でも、公式の我々より正確な見立てをしたことが、一度ならずありましたからな」
「あなたがそうおっしゃるなら、結構ですがね」見知らぬ男は力なく応じた。「それにしても、今夜のカード遊びを諦めねばならんとは、残念でならん。二十七年間、土曜の夜のラバーを欠かしたことなど、一度もなかったというのに」
「今夜は、これまでになく高いレートの勝負ができますよ」シャーロック・ホームズは言った。「あなたにとっては三万ポンド、そしてジョーンズ警部、あなたにとっては追い続けてきた獲物そのものが賭け金となる」
「ジョン・クレイ、殺人、窃盗、偽造、詐欺の天才。まだ若輩ながら、この道では頂点に立つ男です。このロンドンで、奴の腕に手錠をかけることが私の年来の悲願でした。ジョン・クレイは傑物です。祖父は公爵家の出、本人もイートン校からオックスフォード大学へ進んだ。その頭脳も指先の技術も、まさに超一流。彼の犯行の痕跡は至る所に残されているというのに、決して本人の姿を捉えることができない。ある週はスコットランドで金庫を破り、次の週にはコーンウォールで孤児院の資金集めに奔走している。何年も奴を追ってきましたが、一度としてその姿を見たことがないのです」
「今夜、そのご紹介ができることを願っていますよ。私もジョン・クレイとは二、三度、知恵比べをしたことがあり、彼が裏社会の頂点に立つ男であることには、まったく同感です。さて、もう十時を過ぎました。そろそろ出発するとしましょう。お二人は最初のハンサムに。ワトソンと私は、後から参ります」
シャーロック・ホームズは長い道中、あまり口をきかず、午後に耳にした曲をハミングしながらキャブの座席に身を預けていた。私たちは果てしなく続くガス灯に照らされた迷路のような通りをガタガタ進み、やがてファリンドン・ストリートへと出た。
「もうすぐ着くよ」と、ホームズが言った。「このメリウェザーという男は銀行の重役で、個人的にもこの件に深い関心を持っている。ジョーンズも同行させたほうがいいと思ってな。あいつはまったくの間抜けだが、悪い奴じゃない。唯一の長所は、ブルドッグのように勇敢で、一度誰かに食らいついたらロブスターのようにしつこいところだ。さあ、到着した。彼らが待っているはずだ。」
私たちは、今朝見かけたのと同じ人通りの多い大通りに到着した。キャブを下車し、メリウェザー氏の案内で狭い路地を進み、彼が開けてくれた脇の扉から中へ入った。中には小さな廊下があり、その先には頑丈な鉄の扉があった。これも開けられ、螺旋状に曲がる石の階段を降りていくと、またしても重厚な扉が現れた。メリウェザー氏がランタンに火を灯し、今度は暗く、土の匂いがする通路を案内してくれた。三つ目の扉を開けると、巨大な地下室、あるいは貯蔵庫に出た。そこには周囲を取り囲むように木箱や大きな箱が積み上げられていた。
「上から襲われる心配はなさそうですね」と、ホームズはランタンを掲げて辺りを見回しながら言った。
「下からも大丈夫ですよ」と、メリウェザー氏は床に敷き詰められた石畳を杖で叩きながら答えた。「おや、これは驚いた。ずいぶん響く音がしますね」と、見上げて驚いた様子を見せた。
「もう少し静かにしていただけませんか」と、ホームズが厳しい口調で言った。「今ので今回の作戦が台無しになるところでした。どうか、そこの箱の上にでも腰掛けて、余計なことはなさらないでいただけますか?」
重々しい面持ちのメリウェザー氏は、すっかり気を悪くした顔で木箱の上に腰掛けた。一方ホームズは床に膝をつき、ランタンと拡大鏡を使って石の隙間を細かく調べ始めた。ほんの数秒で満足したらしく、すぐに立ち上がって拡大鏡をポケットにしまった。
「少なくともあと一時間は待たねばならない」と、ホームズが言った。「あいつらが動くのは、質屋さんが安心して床についた後だ。そのあとは一刻も無駄にしないだろう。仕事が早ければ逃走の時間が稼げるからな。さて、博士、あなたもお気づきだろうが、私たちは今、ロンドン有数の銀行のシティ支店の地下室にいる。メリウェザー氏は取締役会の会長であり、今この地下室にロンドンの凶悪犯が関心を寄せている理由を説明してくれるだろう。」
「フランスの金塊ですよ」と、メリウェザー氏がささやいた。「何度か、それを狙った犯行があるかもしれないとの警告を受けてきました。」
「フランスの金塊?」
「ええ。数ヶ月前、資金強化のためフランス銀行からナポレオン金貨を三万枚借り入れたのです。それがまだ一度も開封されず、地下室に保管されていることが知られてしまったんです。私が座っているこの箱には、鉛箔で包んだナポレオン金貨が二千枚入っています。今は通常の支店よりもるかに多くの金塊が備蓄されているため、我々取締役も不安を感じていました。」
「それはもっともですね」と、ホームズが言った。「それでは、そろそろ配置を決めましょう。恐らく一時間以内に事が動きます。その間、メリウェザーさん、ランタンに覆いをかけましょう。」
「暗闇の中で待つのですか?」
「申し訳ないが、そうなります。実はカードを持ってきて、四人いるし一勝負しようと思っていたのですが、状況が切迫していて灯りを点けておくわけにはいきません。まずは位置決めです。相手は大胆な連中。こちらが有利とはいえ、油断すれば危険です。私はこの箱の後ろに立つので、皆さんはその箱の陰に隠れてください。私が合図の光を出したら、一気に飛び出してください。万が一撃ってきたら、ワトソン、遠慮なく撃ち返してください。」
私はリボルバーをコックした状態で、隠れている木箱の上に置いた。ホームズはランタンの覆いを引き、私たちは完全な闇の中に置かれた。その闇は、私のこれまでの人生で経験したことのないほどの絶対的な暗闇だった。熱した金属の匂いだけが、ランタンがすぐにも点灯できる状態であることを示していた。待ち構える緊張で神経は高ぶり、急な暗闇と、地下室の冷たく湿った空気に気持ちが沈んだ。
「奴らの逃げ道は一つしかない」と、ホームズがささやいた。「それは家を通ってサックス=コバーグ・スクエアへ戻る道だ。ジョーンズ、君は例の件を済ませてくれたか?」
「正面玄関に警部と巡査二人を張り込ませてある。」
「これで抜かりはない。あとは黙って待つだけだ。」
なんと長く感じられたことか! 後から比べてみると実際はわずか一時間と四分の一だったのに、私には夜が明けるのではないかと思えるほど長く感じた。体は疲れ、こわばったが、少しでも動くのが怖くてじっとしていた。神経は極限まで張り詰め、同僚たちの穏やかな呼吸音だけでなく、ジョーンズの重く深い息づかいと銀行重役の細くため息交じりの呼吸まで聞き分けられるほどだった。身を潜めている箱の向こう、床の方を注視していると、突然、光のきらめきが目に入った。
最初は石の床に小さな不気味な火花のようなものが見えただけだった。それがやがて伸びて黄色い線となり、前触れも音もなく、石の間に隙間が開いたように思え、そこから手が現れた。白く、まるで女性のような手で、光の中心をまさぐっている。しばらくの間、その指をくねらせる手が床から突き出ていたが、突然消えて、また闇に包まれた。ただ一点、石の隙間だけがかすかに光っていた。
しかし、その消失は一瞬のことだった。バリッと裂けるような音とともに、広い白い石の一つが横倒しになり、四角い大きな穴が開き、そこからランタンの光が漏れてきた。穴の縁からは、きりりとした少年のような顔が様子をうかがい、両手を穴の端にかけて、肩まで、腰まで体を引き上げ、片膝を縁にのせた。次の瞬間には穴のそばに立ち、同じく小柄でしなやかなもう一人――顔色が悪く、非常に赤い髪の男――を引き上げていた。
「大丈夫だ。ノミと袋は持ったな? やばい、アーチー、飛び降りろ、俺が何とかする!」
シャーロック・ホームズが飛び出して侵入者の襟首をつかんだ。もう一人は穴へ逃げ込んだが、ジョーンズがスカートをつかんだらしく、布の裂ける音がした。光がリボルバーの銃口を照らしたが、ホームズの狩猟鞭が男の手首を叩き、ピストルは石の床にカチンと落ちた。
「無駄ですよ、ジョン・クレイ」と、ホームズが穏やかに言った。「もう逃げ場はありません。」
「ごもっとも」と、相手は驚くほど冷静に答えた。「仲間はうまく逃げたようだが、あなたが彼の上着の裾をつかんだのが見えましたよ。」
「扉のところには三人待機しています」と、ホームズ。
「なるほど。ずいぶん周到にやりましたね。敬意を表しますよ。」
「こちらこそ」と、ホームズが応じた。「赤毛連盟のアイデアは斬新で見事でした。」
「じきに仲間にも会えますよ」と、ジョーンズ。「あいつは僕より穴を降りるのが早い。ちょっと手錠を……」
「私に汚い手で触らないでいただきたい」と、捕らわれの男は、手錠をかけられながら言った。「私の家系には王族の血が流れています。私に話しかけるときは、必ず『サー』や『どうか』をお付けください。」
「わかりましたとも」と、ジョーンズが呆れたように鼻で笑いながら言う。「では、サー、どうか上へ上がってください。タクシーで殿下を警察署までお運びしますよ。」
「それは結構」と、ジョン・クレイは平然と答えた。私たち三人に大きく一礼すると、静かに刑事たちに連行されていった。
「本当にホームズさん」と、地下室から出る際、メリウェザー氏が言った。「銀行としては感謝の言葉もありません。これほど周到に、しかも見事に計画された銀行強盗未遂を防いでくださった方はかつてありません。」
「私もジョン・クレイ氏には私的にいくつか貸しがありましてね」と、ホームズ。「この件では多少の出費もありましたので、それは銀行に請求させていただきますが、それ以上に大いに満足です。何よりも、非常に特異な体験ができましたし、『赤毛連盟』の奇抜な顛末を聞くことができたのですから。」
「ワトソン、分かるだろう」と、ベイカー街の部屋で早朝、ウィスキー・ソーダのグラスを手にしながらホームズが説明した。「最初から明白だったろう。あの奇妙な『連盟』の広告や『百科事典』の写しの目的は、あのあまり聡明でない質屋を何時間も店から引き離すこと以外になかった。手の込んだ手段だが、むしろこれ以上の方法を思いつくのは難しい。赤毛という共犯者の特徴から、この方法を思いついたのだろう。週に4ポンドという餌で彼を釣り寄せたが、彼らにとっては数千ポンドがかかった計画だったのだから大した出費ではない。広告を出し、一人が臨時事務所を担当し、もう一人が応募を勧めて、毎朝確実に質屋を不在にさせた。助手が半給で働き始めたと聞いた時点で、何か強い動機があると確信したよ。」
「でも、その動機が何かはどうやって分かったんです?」
「もし家に女性がいたら、ただの下世話な色恋沙汰を疑っただろう。でも、それはあり得なかった。店は小規模で、家の中にこれほどの手間や出費に見合うものはない。なら、目当ては家の外だ。助手が写真好きで、よく地下室に消えることを思い出した。地下室――この絡まった糸の端はそこにあった。そこで助手について調べてみると、ロンドンでも最も冷静で大胆な犯罪者の一人だった。やつは地下で何かをしていた――数ヶ月も毎日何時間もかけて。目的は何か? 他の建物にトンネルを掘っている以外に考えられなかった。
そこまで推理した上で現場を訪れた。君を驚かせたが、舗道を杖で叩いたのは、地下室が前後どちらに伸びているか確かめたかったからだ。前方にはなかった。そこでベルを鳴らすと、案の定、助手が出てきた。これまで何度かやり合ったが、顔を直接見るのは初めてだった。顔はほとんど見ず、膝に注目した。君も気づいただろう、膝が擦り切れて、汚れて、しわくちゃだった。長時間の穴掘り作業の証拠だ。残る疑問は、何を掘っていたかだけだった。角を曲がると、シティ・アンド・サバーバン銀行が隣接しているのを見て、全ての謎が解けた。君が演奏会帰りに帰宅したあと、私はスコットランド・ヤードと銀行の取締役会長を訪ね、あとは君が見た通りだ。」
「今夜、彼らが実行することをどうして分かったのですか?」
「連盟事務所を閉じた時点で、もうジャベズ・ウィルスン氏の存在を気にする必要がなくなった――つまり、トンネルが完成した証しだ。でも、そのまま放置すれば発見されるかもしれないし、金塊が移される恐れもある。土曜日なら、逃走に二日間使えるから、彼らに最適の日だった。だから今夜だと思ったのさ。」
「見事な推理ですね」と私は心から感嘆した。「これだけ長い推理の鎖なのに、どの輪も確かにつながっている。」
「退屈しのぎになったよ」と、ホームズはあくびをしながら答えた。「まったく、また退屈が押し寄せてきた気がする。私の人生は、平凡という牢獄から抜け出そうとする長い努力の連続さ。こうした小さな難問が、それを助けてくれるんだ。」
「あなたは人類の恩人ですよ」と、私は言った。
ホームズは肩をすくめた。「まあ、少しは役に立っているのかもしれないね」と言った。「『人は無であり、作品こそが全てだ』と、ギュスターヴ・フローベールがジョルジュ・サンドに書き送ったように。」
第三の冒険 身元の謎
「ワトソン君」と、ベイカー街の下宿で火を挟んで座っているとき、シャーロック・ホームズが語りかけた。「人生というものは、人間の想像力が生み出すどんな物語よりも、はるかに奇妙で不可解なものだよ。現実に起こることを、物語として創作する勇気のある作家などまずいないだろう。もし窓から手を取り合って大空を舞い上がり、この大都会の屋根をそっと外して、中で繰り広げられている奇妙な出来事や偶然、策略、すれ違い、代々受け継がれる運命の鎖がどんな突飛な結果を生むのか覗き見たなら、型通りで先の見えるフィクションなど、たちまち色褪せてしまう。」
「それでも私は納得できません」と、私は答えた。「新聞に載る事件は、たいてい話が単純すぎて、下世話なものばかりです。警察の報告なんて、写実主義を極めているはずなのに、正直、魅力も芸術性も感じられません。」
「写実的な効果を出すには、ある程度の取捨選択と配慮が必要です」と、ホームズが言った。「警察の報告書にはそれがなく、判事の決まり文句ばかりに重点が置かれ、観察眼を持つ者にとって肝心な細部が軽視されている。世の中でいちばん不自然なものは、実は『ありふれたもの』なんだよ。」
私は微笑んで首を振った。「あなたの立場なら、そう思って当然でしょう。あなたは三大陸にまたがって、誰にも解決できない難事件の助言役ですから、普通では考えられない珍妙な事件にもよく出会う。でも――」私は床から朝刊を拾い上げた。「実際に確かめてみましょう。最初に目についた見出しは……『夫による妻への残虐行為』。半コラム分も記事がありますが、読まなくても筋書きは分かっています。どうせ他の女に酒、口論、暴力、あざ、同情的な妹か大家が出てくるのでしょう。一番下手な作家でもこれ以上単純には書けません。」
「君の例は、むしろ君の主張に不利だな」と、ホームズが新聞を手に取り、ざっと目を通して言う。「これはダンダス家の離婚事件だが、実は私もいくつか細かい点の調査を頼まれていた。夫は禁酒家で他の女性もなく、問題行動は『毎食後に入れ歯を外して妻に投げつけるようになった』ということだった。こんな行動、普通の作家の想像力にはまず浮かぶまい。ほら、スナッフをどうぞ、ワトソン君。今回の例は私の勝ちということで。」
ホームズは真ん中に大きなアメジストのはめ込まれた古風な金のスナッフボックスを差し出した。その豪華な品が、彼の日常の質素な暮らしぶりとあまりに対照的だったので、私は思わず口にした。
「ああ」と、ホームズ。「しばらく君に会っていなかったな。これはボヘミア国王からの贈り物だ。アイリーン・アドラーの件で力を貸したお礼さ。」
「その指輪は?」私はホームズの指に輝く見事な宝石に目をやった。
「オランダ王家からのものだ。だが、そちらの件はあまりに機微に富んでいて、君にも話せないんだ。君は私の小さな事件のいくつかを記録してくれたのに申し訳ないが。」
「今は何か事件を抱えているのですか?」私は興味津々で尋ねた。
「十件か十二件ほどあるが、どれも面白味に欠ける。重要ではあるが、興味深くはない。実際、観察や因果関係の鋭い分析が生きるのは、大事件よりも些細な出来事にこそ多い。大きな犯罪ほど、動機は単純で分かりやすいものだ。今抱えている中で唯一込み入っているのは、マルセイユから依頼されたものくらいだ。それ以外は特に目を引くものはない。だが、まもなくもっと面白い依頼が来るかもしれない。ちょうど今、私の依頼人が来るところだと見て間違いない。」
彼は椅子から立ち上がり、開け放たれたブラインドの間に立って、くすんだ中間色のロンドンの通りを見下ろしていた。私がその肩越しに覗くと、向かいの歩道に、大柄な女性が立っているのが見えた。首には重そうな毛皮のボアを巻き、広いつばの帽子には大きくカールした赤い羽根が、デヴォンシャー公爵夫人風に小粋に耳に傾けて飾られていた。その堂々たる装いの下から、彼女はおずおずと、ためらいがちに私たちの窓を見上げている。その身体は前後に揺れ、指先は落ち着きなく手袋のボタンをいじっていた。突然、水泳選手が岸を離れるときのように、彼女は思い切って道路を急ぎ足で渡り、私たちは玄関ベルの鋭い音を聞いた。
「私はあの症状を以前にも見たことがある」とホームズは煙草を暖炉に投げ入れながら言った。「歩道での逡巡は、いつも恋愛沙汰の証拠だ。相談したいのだが、あまりにも繊細な事柄かもしれないと迷っている。しかし、ここにもまた差異がある。女性が男性から本当にひどい仕打ちを受けた場合、もう逡巡はしないし、よくある症状はベルの針金が切れてしまうことだ。つまり今回の件は恋の悩みだが、怒りよりも困惑や悲しみが強いのだろう。だが本人が疑問を解消しにやって来るようだ。」
彼がそう語るや否や、ドアをノックする音がし、ボタン付き制服の少年が入ってきて「ミス・メアリー・サザーランドです」と告げた。その後ろにご本人が、小さな黒い制服姿の少年の背後で、まるで帆を一杯に張った商船の後ろに小さな水先案内船がいるかのごとく、どっしりとした姿で現れた。シャーロック・ホームズは、彼の持ち前の自然な礼儀正しさで彼女を迎え、ドアを閉めてから椅子に座るよう彼女を丁重に案内した。そして、彼特有の細部に目を光らせながらも、どこか上の空のような観察の仕方で彼女を見つめた。
「ご自身が近視でいらっしゃると、タイプライターの仕事は大変ではありませんか?」と彼は言った。
「最初はそうでした」と彼女は答えた。「でも今では、見なくてもキーがどこにあるかわかるんです。」すると突然、彼の言葉の意味に気づき、彼女は激しく身を震わせて顔を上げ、その大きな朗らかな顔に恐れと驚きの色が浮かんだ。「ホームズさん、私のことをご存知なんですね。でなければ、そんなことがわかるはずありません!」
「気にしないでください」とホームズは笑って言った。「それが私の商売ですから。もしかしたら、他の人が見落とすことを、見抜く訓練をしてきたのかもしれません。そうでなければ、なぜあなたは私に相談しに来たのです?」
「ホームズさん、私があなたのことを知ったのは、イセリッジ夫人からです。警察もみんなあきらめていた彼女のご主人を、あなたがすぐに見つけてくださったと。ああ、ホームズさん、私にもどうか同じことをしてください。私は裕福じゃありませんが、自分名義で年間百ポンドの収入があり、タイプライターの仕事で得る分も少しあります。そのすべてを差し上げても、ホズマー・エンジェル氏がどうなったか知りたいのです。」
「なぜそんなにも急いで私を訪ねて来たのですか?」とシャーロック・ホームズは、指先を合わせたまま、天井を見上げながら尋ねた。
再び、ミス・メアリー・サザーランドのやや茫然とした顔に驚きの色が浮かんだ。「ええ、私は勢いよく家を飛び出しました。だって、ウィンディバンクさん――つまり私の父が、あまりにも軽くこの件を受け流すのを見て腹が立ったんです。彼は警察にも行かず、あなたにも行こうとしませんでした。結局、何もしようとしないし、ずっと『何も問題はない』と言い張るので、私は腹が立って、服を着てすぐあなたのもとへ来たんです。」
「お父様――いや、違う名字ですから、義父ですね」とホームズ。
「ええ、義父です。私は父と呼びますけど、変ですよね。だって、彼は私より五歳と二か月しか年上じゃないんです。」
「お母様はご健在ですか?」
「ええ、元気です。父が亡くなってすぐにあんなに早く再婚したときは、私は不満でした。しかも、母より十五歳近くも若い男性と。父はトッテナム・コート・ロードで配管工をしていて、立派な商売を残して亡くなりました。その商売は母と工場長のハーディさんとで続けていたんですが、ウィンディバンクさんが来てからは、彼がワインの行商で偉そうにしていたので、母に商売を売らせてしまいました。営業権と利権で4700ポンドを手に入れましたが、生きていた父ならもっと取れたはずです。」
私は、シャーロック・ホームズがこの取りとめのない話に苛立つのではと予想していたが、彼は逆に、極めて集中した注意で聞いていた。
「あなた自身の小さな収入は、その商売からですか?」
「いいえ、全く別です。オークランドの叔父のネッドが私に残してくれたものです。ニュージーランドの株で、年利4.5パーセントです。2500ポンドありましたが、利子しか手を付けられません。」
「非常に興味深いですね」とホームズ。「年百ポンドもの大金を手にされ、さらにご自身の稼ぎもあるわけですから、きっと旅行もされたり、色々ご自分の好きなことを楽しんでいらっしゃるでしょう。独身女性なら年に60ポンドもあれば十分暮らせると私は思います。」
「ホームズさん、私はそんなに要りません。でも、家にいる限りは家族の負担になりたくないので、私の収入は滞在中だけ彼らが使っています。もちろん、それは一時的なことです。ウィンディバンクさんが私の利子を毎四半期ごとに受け取って母に渡し、私はタイプライターの稼ぎで十分やっていけます。1枚2ペンスで、1日に15枚から20枚は打てます。」
「あなたのご事情はよくわかりました」とホームズ。「こちらは私の友人ワトソン博士です。私と同じように、何でもご自由にお話しください。さて、ホズマー・エンジェル氏とのご関係を詳しくお聞かせください。」
ミス・サザーランドの顔が赤らんで、緊張した様子で上着のフリンジをいじった。「最初に彼に会ったのは、ガス工組合の舞踏会でした。父が生きていたころは毎年チケットを送ってくれて、亡くなった後も母に送ってきてくれたんです。でもウィンディバンクさんは行きたがらなかったし、私たちがどこかに出かけるのがいつも嫌いでした。日曜学校の催しでさえ怒るくらいで。でも、その時はどうしても行きたくて、押し切ったんです。だって、父の友人たちばかり集まるのですから。服がないとも言われましたが、紫色のベルベットの服が箪笥にしまったままでした。それでも彼は仕事でフランスに行くことになり、結局、母と私、そして元工場長のハーディさんと一緒に行き、そこでホズマー・エンジェル氏に出会ったのです。」
「ウィンディバンクさんがフランスから戻った時、とても怒ったのでは?」とホームズ。
「いえ、とても寛大でした。覚えているのは、笑って肩をすくめて『女性には何を言っても無駄だ』と言ったことです。」
「なるほど。つまり、そのガス工組合の舞踏会で、ホズマー・エンジェル氏という紳士に出会ったのですね。」
「はい、その夜に出会い、翌日彼が無事帰宅したか確かめに訪れ、それから二度散歩に出かけました。でもその後、父が戻ってきて、ホズマー・エンジェル氏はもう家に来られなくなりました。」
「そうですか?」
「ええ、ご存知の通り父はそういうことを嫌っていました。客を招くのも嫌がり、女は家庭の中で幸せにすべきだと言っていたんです。でも私が母に言っていたのは、女には自分の輪が必要だということ。でも、私はまだ自分の輪がなかった。」
「ホズマー・エンジェル氏は、あなたに会いに来ようとしなかったんですか?」
「父が一週間後に再びフランスへ行く予定だったので、ホズマーはそれまで会うのは控えた方がいいと手紙で言ってきました。その間は毎日手紙をくれました。朝、私が手紙を受け取るので父に気づかれませんでした。」
「その時点で婚約されていたのですか?」
「はい、ホームズさん。最初の散歩の後で婚約しました。ホズマー――エンジェル氏はレドンホール・ストリートにある会社の出納係でした――」
「どんな会社ですか?」
「それが一番困るところで、わかりません。」
「では、どこに住んでいたのですか?」
「会社の建物内で寝泊まりしていました。」
「住所はご存知ありませんか?」
「レドンホール・ストリートしか分かりません。」
「手紙の宛先はどうしていました?」
「レドンホール・ストリートの郵便局留めにしていました。もし会社に送ると、他の事務員に女性から手紙が来たとからかわれる、と言うので、私もタイプライターで書いて送りましょうかと申し出ましたが、彼はそれを嫌がりました。『自筆でないと、まるで機械が二人の間に入るみたいで嫌だ』と。それだけ私を大切に思ってくれていたんです、ホームズさん。些細なことまで気を配ってくれました。」
「非常に示唆的ですね」とホームズ。「私も常々小さなことが最も重要だと思っています。他にも何か些細な特徴を思い出せますか?」
「ホズマー・エンジェル氏はとても内気な方でした。昼間よりも夕方に歩く方を好み、目立つのが嫌いだと言っていました。控えめで紳士的で、声も優しかったです。若い頃に扁桃腺炎とリンパ腺が腫れたことがあり、それで喉が弱く、小声でためらいがちに話す癖が残ったそうです。服装もいつもきちんとしていて、地味でしたが、目が私と同じように弱いので、眩しさを避けるため色付きの眼鏡をかけていました。」
「それで、あなたの義父ウィンディバンクさんが再びフランスへ行った時、何が起きましたか?」
「ホズマー・エンジェル氏が再び家に来て、父が戻る前に結婚しようと提案しました。とても真剣で、何があっても彼に誠実でいると聖書に手を置いて誓わせました。母もそれは当然だと言い、彼をとても気に入っていて、私以上に好意的でした。すぐに結婚する話になった時、私は父のことが気になり始めましたが、二人とも『父のことは気にしなくていい、後で説明する』と言い、母も『自分がうまく取りなすから』と言いました。私はそれが少しおかしいと思いました。義父とはいえ、数歳しか違わない人に許可を求めるのも変でしたが、こそこそするのは嫌だったので、会社のフランス支店があるボルドーの父に手紙を出しました。ところが、その手紙は結婚式当日の朝、差出人不明で戻ってきてしまいました。」
「つまり、届かなかったのですね?」
「はい、父はその直前にイギリスに発っていました。」
「それは残念でした。結婚式は金曜日に予定されていたのですね。教会で?」
「はい、ホームズさん。とても静かに、セント・セイヴィア教会で、その後はセント・パンクラス・ホテルで朝食の予定でした。ホズマーが馬車で迎えに来てくれたのですが、私たち二人だったので私と母を馬車に乗せて、自分はもう一台の四輪馬車に乗りました。それが通りの唯一の他の馬車でした。私たちは先に教会に着き、四輪馬車が到着するのを待っていましたが、ホズマーは降りてこなかったんです。御者が降りて確認したのですが、誰もいなかった! 御者も自分の目で彼が確かに乗ったのを見ていたので、何が起きたのが見当がつかないと言っていました。あれが先週の金曜日です、ホームズさん。その後、彼がどうなったのか、何の手がかりも得られていません。」
「あなたは非常にひどい扱いを受けたようですね」とホームズ。
「そんなことありません! 彼はそんなことをするほど悪い人じゃありません。朝からずっと、何があっても誠実に、と言い続けていましたし、万一何か予想外のことが起きて私たちが離れることになっても、私は約束を守り続けるようにと。それが結婚式の朝としては奇妙な話でしたが、今となっては意味があると思います。」
「確かにそうです。あなたは、予想もしなかった災難が彼に起きたと考えているのですね?」
「はい、ホームズさん。彼は何か危険を予期していたのだと思います。でなければ、あんな話をするはずありません。」
「ですが、何が起きたのか、見当もつきませんか?」
「全くありません。」
「もう一つ質問です。お母様はこの件をどう受け止められましたか?」
「怒って『この話は二度としないで』と言われました。」
「お父様には? お話ししましたか?」
「はい。父も私と同じで、何か事件が起きたのだろう、またホズマーから連絡があると思っていました。父が言うには『誰がわざわざあなたを教会まで連れてきて、そこで放り出すものか』と。もし、私からお金を借りていたり、結婚して財産を手に入れていたなら話は別ですが、ホズマーはお金に関してとても独立していて、私のお金には一切触れませんでした。それなのに何が起きたのか、なぜ手紙も書けないのか、考えると頭がおかしくなりそうで、一睡もできません。」彼女はマフから小さなハンカチを取り出し、激しく泣き始めた。
「お引き受けしましょう」とホームズは立ち上がって言った。「きっと何かしらの結論にたどり着けるでしょう。この重荷は私に任せ、どうかこれ以上ご心配なさらないように。何より、ホズマー・エンジェル氏のことは、彼があなたの人生から消えたように、記憶からも消すようお努めください。」
「もう会えないとお思いですか?」
「残念ながら、そう思います。」
「では、彼に何があったのでしょう?」
「その点は私にお任せください。彼の正確な特徴と、もし差し支えなければ彼からの手紙をお借りしたいのです。」
「先週のクロニクル紙に彼の広告を出しました。これがその切り抜きと、彼からの手紙が四通あります。」
「ありがとうございます。ご住所は?」
「カンバーウェル、ライオン・プレイス31番地です。」
「ホズマー氏の住所は知らない、と。お父様の勤務先は?」
「フェンチャーチ・ストリートの大手クラレット(赤ワイン)輸入業者、ウエストハウス&マーバンクに勤務しています。」
「ありがとう。よく事情が分かりました。書類はこちらでお預かりします。私の助言を思い出し、この件はもう忘れるようにしてください。」
「ご親切にありがとうございます、ホームズさん。でも私はホズマーに誠実でありたいのです。彼が戻ってきた時、私はずっと待っています。」
馬鹿げたほど派手な帽子とぼんやりした顔立ちにもかかわらず、この訪問者の素朴な信念には、私たちも思わず敬意を抱かずにいられなかった。彼女は小さな書類の束をテーブルに置き、呼び出しがあればまた来ると約束して帰っていった。
シャーロック・ホームズは数分間、指先を合わせたまま、足を前に投げ出し、天井を見上げて黙っていた。そして、ラックから年季の入ったオイル染みのクレイパイプを取り出し、火をつけて椅子にもたれ、濃い青い煙を渦巻かせながら、無限の倦怠の表情を浮かべた。
「あの娘は実に興味深い研究対象だった」と彼は言った。「彼女自身が問題よりもずっと興味深かったよ。ちなみに、彼女の悩み自体はありふれたものだ。私の索引を調べれば、アンドーヴァーの77年、それに昨年ハーグで似たような事件がある。しかし、この古い型の話にも、私にとって新しい点が二、三あった。しかし、当の彼女自身が何より示唆に富んでいた。」
「あなたは、私にはまったく分からなかった多くのことを彼女から読み取ったようですね」と私は言った。
「見えなかったのではなく、気づかなかっただけだよ、ワトソン。どこを見るべきか知らないと、本当に重要なことを見逃すものだ。私はどうしても君に、袖の重要性や、親指の爪の意味、靴紐一本で人生が変わることを理解させられない。さて、君はあの女性の外見から何を読み取った? 説明してみてくれ。」
「ええと、灰色がかった広いつばのストローハットに、レンガ色の羽根。上着は黒で、黒いビーズが縫い込まれ、黒いジェットの小さな飾りのフリンジがありました。ドレスはコーヒー色よりも少し濃い茶色で、首元と袖に紫色のベルベットがあしらわれていました。手袋は灰色がかった色で、右人差し指が擦り切れていました。靴は見ませんでした。小さな丸い金のイヤリングを垂らしていて、いかにも庶民的で気楽な、でもそこそこ暮らし向きは良さそうな印象でした。」
シャーロック・ホームズは静かに手を打ち、くすくすと笑った。
「本当に、ワトソン、君は驚くほど進歩しているよ。実に見事だった。確かに、肝心なことはすべて見落としているが、手法には辿り着いたし、色彩を見る目も鋭い。だが、決して全体的な印象に頼ってはいけない。細部に集中するんだ。私はまず最初に、女性の場合は袖を見る。男性の場合はズボンの膝を見るのが良い。さて、君も見た通り、この女性の袖にはビロードが使われていたが、これは痕跡を残しやすい非常に便利な素材だ。手首の少し上、タイプライターが机に押し付けられる所に二重の線がはっきりと残っていた。手動式のミシンでも似た跡が残るが、それは左腕の親指から遠い側、つまり幅の広い部分を横断するのではなく、特定の部分だけに出る。だが今回は違う。それから顔に目をやると、鼻の両脇にピンネズの跡があったので、近視とタイプライターについて言及したら、ずいぶん驚いた様子だったね。」
「僕も驚いたよ。」
「しかし、これはごく当たり前のことだ。さらに靴に目をやると、見かけは似ているが実は違う靴を履いていた。一方には飾りのついたトウキャップ、もう一方は無地。そして片方は五つあるボタンのうち下の二つだけ留めてあり、もう一方は一番上・三番目・五番目のボタンが留まっている。きちんとした身なりの若い女性が、家を出る際にこんなふうに違う靴を半分しか留めずに出てきたということは、急いで家を出たという推論は難しくない。」
「他には?」私は興味津々で尋ねた。友人の鋭い推理にはいつも心を奪われるのだ。
「それと、彼女は家を出る前、完全に身支度を整えた後で手紙を書いたことに気づいた。君は右手の手袋の人差し指が破れていたのは見たが、手袋と指の両方がスミレ色のインクで染まっていたのは見落としたようだ。急いで書こうとしてペンを深く浸けすぎたのだろう。今朝のことに違いない、でなければ指にこんなにはっきり跡は残らない。まあ、どれも初歩的な観察だが、さて仕事に戻ろう、ワトソン。ホズマー・エンジェル氏の広告記事を読んでくれないか?」
私は小さな印刷物を明かりにかざした。「行方不明 14日朝、ホズマー・エンジェル氏。身長約5フィート7インチ、がっしりした体格、黄味がかった顔色、黒髪、中央が少し禿げ、黒くてふさふさしたもみあげと口髭、色付き眼鏡、やや舌足らずな話し方。最後に目撃された際の服装は、シルクの縁取りの黒いフロックコート、黒いベスト、金のアルバートチェーン、グレイのハリスツイードのズボン、ゴムサイドのブーツに茶色のゲートル。リーデンホール・ストリートの事務所に勤務していたことが知られている。情報を……」などなど。
「それで十分だ」とホームズは言い、手紙に目を通しながら続けた。「手紙の内容はごくありふれたものだ。ホズマー・エンジェル氏について分かる手掛かりは、バルザックの引用が一度あることくらい。ただし、君も気づくだろう、非常に注目すべき点が一つある。」
「全部タイプで打たれているね」と私は言った。
「それだけじゃない。署名までタイプだ。下のきちんとした『ホズマー・エンジェル』を見てごらん。日付はあるが、宛名はリーデンホール・ストリートだけで曖昧だ。署名がタイプというのは非常に示唆的だ――いや、決定的と言ってもいい。」
「どうして?」
「君には分からないかね? これが事件にどう関わるか。」
「さっぱりだ、もしその理由が、後で婚約不履行で訴えられた時に署名を否認できるように、ということくらいしか思いつかない。」
「いや、それがポイントじゃない。しかし、この件は二通の手紙を出せば決着がつく。一通はシティのある会社宛て、もう一通は例の若い女性の義父、ジェームズ・ウィンディバンク氏宛てで、明日夕方六時にここに来てもらえるか尋ねる内容だ。身内の男性と話すのが一番だからね。さて、ワトソン、返事が来るまでは何もできない。しばらくこの謎は棚上げにしておこう。」
私はこれまでにも友人の鋭い推理力と驚異的な行動力を幾度となく実感してきたので、彼がこの奇妙な事件に余裕を見せているのも、きっと確信を持つだけの根拠があるに違いないと感じていた。唯一、彼が失敗したのはボヘミア王とアイリーン・アドラーの写真事件だけだった。しかし『四つの署名』の怪事件や『緋色の研究』の異様な事件を思い返せば、彼が解けない謎はまずあり得ないだろうと思った。
そのとき私は彼のもとを離れた。ホームズは黒いクレイパイプをくゆらせながら、次に会うときには必ずミス・メアリー・サザーランドの行方不明の花婿の正体に繋がる全ての手掛かりを握っているだろうと、私は確信していた。
当時、私自身も非常に重大な職務上の案件を抱えており、その翌日は一日中、患者の枕元にかかりきりだった。ようやく六時近くに手が空き、急いでハンサムキャブに飛び乗り、ベーカー街へ向かった。謎の幕切れに間に合うかどうか、半ば不安だった。だが、シャーロック・ホームズは一人きりで、長身の痩せた身体を椅子の奥に丸め、うたた寝していた。薬品の瓶と試験管がずらりと並び、塩酸のツンとした匂いが漂っていたので、彼が一日中、大好きな化学実験に没頭していたのがわかった。
「で、解決したのかい?」と私は部屋に入って尋ねた。
「ああ。バリウムの亜硫酸塩だった。」
「いやいや、謎の方だ!」私が叫ぶと、
「ああ、そっちか。てっきり今調べていた塩の話かと。だが、昨日も言った通り、実のところ事件に謎などなかった。ただし細部にはいくつか興味深い点がある。唯一の難点は、あのろくでなしに適用できる法律がなさそうなことだ。」
「で、結局誰で、何のためにミス・サザーランドを捨てたんだ?」
私がそう尋ねた途端、ホームズが口を開くより早く、廊下で重い足音とドアを叩く音が聞こえた。
「ミスの義父、ジェームズ・ウィンディバンク氏だ」とホームズ。「彼から六時に来ると手紙があった。どうぞ!」
入ってきた男は、がっしりした中肉の三十歳ほど、髭はなく、黄味がかった肌、愛想の良い調子で、驚くほど鋭い灰色の目をしていた。私たち一人一人に探るような視線を投げ、光沢のあるシルクハットを脇台に置き、軽く会釈して椅子に腰を下ろした。
「こんばんは、ジェームズ・ウィンディバンクさん」とホームズ。「このタイプ打ちの手紙はあなたですね、六時に約束をされた。」
「はい、少し遅れてしまいましたが、何分自分の都合で動ける身ではありませんので。ミス・サザーランドがこのようなことでお手を煩わせて申し訳ない。家の恥を他人に晒すのは本意ではありませんでしたが、あの子はご覧の通り非常に興奮しやすく衝動的で、一度決めたことはなかなか諦めません。警察と関係ない方ならまだ良いのですが、家の不幸が世間に広まるのは気持ちの良いことではありません。それに、こんなことに費用をかけるのは無駄ですし、ホズマー・エンジェル氏を見つけることなんてできるわけがありませんでしょう?」
「いえ、むしろ私は必ずホズマー・エンジェル氏を見つけ出せると確信しています」とホームズは静かに言った。
ウィンディバンク氏は激しく体を震わせ、手袋を落とした。「それは嬉しいお話ですね。」
「興味深いことですが」とホームズは続けた。「タイプライターにも人の筆跡同様、それぞれ独自の個性があります。新品でない限り、同じ書きぶりのものは一つとしてありません。一部の文字は他より早く摩耗し、片側だけ削れるものもある。ウィンディバンクさん、あなたのこの手紙では、どの文字にも『e』に少し滲みが出ており、『r』のしっぽが欠けています。これ以外にも十四の特徴があるのですが、とりあえず目立つのはその二つです。」
「会社ではすべてその機械でやり取りしていますから、摩耗しているのは確かです」と訪問者は、鋭い目つきでホームズを見つめながら答えた。
「では、実に興味深い実験をお見せしましょう、ウィンディバンクさん」とホームズは続けた。「私はそのうち、タイプライターと犯罪の関係について小論を書いてみようと思っています。四通、行方不明の男から来たという手紙がありますが、すべてタイプ打ちです。どれも『e』は滲み、『r』はしっぽがない。そして、もしこの拡大レンズでご覧になれば、他の十四の特徴も同じであることが分かります。」
ウィンディバンク氏は椅子から跳ね上がり、帽子を取った。「こんな馬鹿げた話に付き合っている暇はありませんよ、ホームズさん。もし犯人が捕まったら教えてください。」
「もちろんです」とホームズは言い、さっと歩み寄ってドアに鍵をかけた。「では今、捕まえたことをお知らせしましょう!」
「な、何だって! どこで?」ウィンディバンク氏は唇まで真っ白になり、罠にかかった鼠のように周囲を見回した。
「そんなことは許されませんよ、本当に」とホームズは穏やかに言った。「逃げ道はありません、ウィンディバンクさん。あまりにも見え透いた筋書きですし、こんな簡単な問題を私が解けるはずがないと言ったあなたのお世辞は、まったくいただけません。さあ、お掛けになって、ゆっくり話しましょう。」
訪問者は椅子に崩れ落ち、顔面蒼白、額に汗を浮かべていた。「法に触れることじゃない……」彼はうわずった声で言った。
「私もそれが残念だ。しかしウィンディバンクさん、あなただけの話としても、これは私の前に現れた中でも最も卑劣で冷酷な仕打ちだった。では、一連の経緯をざっと説明しますから、間違いがあれば訂正してください。」
男はうなだれて椅子にうずくまり、すっかり打ちのめされた様子だった。ホームズは足を暖炉の縁に乗せ、ポケットに手を突っ込んだまま、半ば独り言のように語り始めた。
「この男は自分よりずっと年上の女性と金目当てで結婚した。そして、その娘が同居している間は娘の金も自由に使っていた。二人の暮らしぶりにしてはかなりの額で、これを失えば大きな違いになる。だから失うまいと努力した。娘は性格も容姿も良く、ちょっとした収入もあり、いずれ結婚するだろうと思われた。彼女が結婚すれば年百ポンドの収入がなくなる。そこで義父はどうしたか? 彼女を家に引き留めて、同年代の人との付き合いを禁じた。しかしそれも長くはもたず、娘は権利を主張し、ついにある舞踏会へ行くと宣言した。そこで義父は頭は切れるが心は冷たい策を思いついた。妻と共謀し、色付き眼鏡でもみあげと口髭で顔を隠し、声も変え、近眼の娘の目をごまかし、ホズマー・エンジェル氏になりすまして自ら求婚を始めたのだ。」

「最初はただの冗談のつもりだったんです……」と訪問者はうめいた。「まさかあそこまで夢中になるとは。」
「そうでしょう。しかし娘はすっかり夢中になり、自分の義父がフランスへ行ったと思い込んでいたので、裏切りを疑う気配もなかった。相手の熱烈な態度に心を奪われ、母親も盛んに褒めそやしたので効果は増した。そしてホズマー・エンジェル氏は度々訪ねてくるようになり、一層本気らしくふるまった。こうして会合と婚約が成立し、他の男性へ心が向かうのを防いだ。だが、いつまでもごまかし続けることはできない。フランス行きという嘘も面倒だ。いっそ劇的な形で終わらせ、娘の心に永遠に刻み込み、長く他の求婚者が現れないようにするしかない。だからあの聖書にかけた忠誠の誓い、そして式当日の朝何かが起こるかもしれないという示唆があったのだ。ジェームズ・ウィンディバンクは、ミス・サザーランドをホズマー・エンジェルに縛り付け、その運命を不明にすることで、少なくとも十年は彼女が他の男性と結婚しないでいることを狙った。教会の扉まで彼女を連れて行き、そこで古典的な手口――四輪馬車の一方のドアから乗って他方から消える――で跡形もなく姿を消した。これが事件の全容でしょう、ウィンディバンクさん!」
ホームズの話の間に、訪問者は次第に自信を取り戻し、今や氷のような冷笑を浮かべて立ち上がった。
「そうかもしれませんし、そうでないかもしれませんね、ホームズさん。でもあなたほど鋭いなら、今この状況こそ法を犯しているのはあなたで、私ではないと気付くべきです。私は最初から何も違法なことはしていませんが、あなたがドアに鍵をかけ続ける限りは、あなた自身が暴行・監禁で訴えられますよ。」
「おっしゃる通り、法には触れません」とホームズは言いながらドアを解錠して開け放った。「しかし、これほど罰を受けるべき男はいない。娘さんに兄弟や友人がいたら、鞭であなたの背を打つべきだ。いや……」と、男の冷笑を見て顔を赤くし、「本来なら依頼人のためにやることではないが、ここに乗馬鞭があるし、自分へのご褒美に――」ホームズが素早く鞭へ歩み寄ろうとしたその時、階段を駆け下りる騒音、玄関のドアが激しく閉まる音が響き、窓からジェームズ・ウィンディバンク氏が全速力で通りを走り去っていくのが見えた。
「あれほど冷血な悪党も珍しい!」とホームズは笑いながら椅子に身を沈めた。「あの男は、今後どんどん罪を重ね、最後には絞首台行きだろう。まあ、この事件もいくつか興味深い点があった。」
「推理の過程がまだ全部分かりません」と私は言った。
「まず最初から、ホズマー・エンジェル氏が奇妙な行動を取るのには、何か強い動機があると明らかだった。そして事件で唯一利益を得たのは義父だけだった。二人の男が一緒に現れることはなく、一方がいない時にもう一方が現れるのも示唆的だった。色付き眼鏡と変な声、ふさふさした髭も、すべて変装を示していた。署名までタイプしたのは、彼の筆跡が娘にとってあまりにも馴染み深いもので、少しでも見せれば気付かれてしまうからだ。これら一つ一つの事実と、その他の細かい点が全て同じ方向を指していた。」
「それをどう裏付けたのですか?」
「相手を特定すれば、確証を得るのは簡単さ。男の勤務先は分かっていた。広告記事の特徴から、変装によるもの――髭・眼鏡・声――を排除し、会社に照会した。予想通り、特徴が一致する社員はジェームズ・ウィンディバンクだけだった。タイプライターの癖も既に見抜いていたから、会社の住所に手紙を出し、ここに来てくれと依頼した。返事もやはりタイプ打ちで、同じ特徴があった。さらにフェンチャーチ・ストリートのウェストハウス&マーバンク社からも、特徴がウィンディバンクに一致するという返事が届いた。ヴォワラ・トゥ!」
「では、ミス・サザーランドには?」
「話しても信じないだろうね。ペルシャの古い言葉を思い出すよ――『虎の子を奪う者にも危険あり、女の迷妄を奪う者にも危険あり』。ハーフィズもホラティウスに劣らぬ人生観を持っている。」
第四話 ボスコム谷の謎
私たち夫婦はある朝、朝食をとっていた。そこへメイドが電報を持ってきた。それはシャーロック・ホームズからで、こう書かれていた。
「二日ほど都合がつきますか? ボスコム渓谷の惨劇に関して西イングランドから至急電報が入りました。一緒に来てくだされば幸いです。空気も景色も申し分なし。11時15分発パディントン駅を出発。」
「どう思う?」と妻が私に問いかけた。「行くの?」
「正直、何と言っていいか……今けっこう予定が詰まっているんだ。」
「アンスラスターならあなたの仕事を代わってくれるわ。最近ちょっと顔色も良くないし、気分転換にもなると思う。それに、あなたはいつもホームズ氏の事件に興味津々でしょう?」
「確かに、彼の事件のおかげで得たものを思えば、興味を持たない方が恩知らずだろうね。」私は答えた。「でも、行くならすぐに荷造りしないと、あと30分しかない。」
アフガニスタンでの野営生活の経験が、少なくとも私を素早く準備のできる旅行者にしてくれた。荷物も少なく簡素なもので済む。言われた時間より早く、私は鞄を持ってタクシーに乗り込み、パディントン駅へと向かった。プラットフォームには、長身でやせぎすなホームズが、灰色の長い旅行用マントとぴったりした布製の帽子でさらにその体格を強調しながら、行き来しているのが見えた。
「本当に来てくれてありがたいよ、ワトソン。」と彼は言った。「信頼できる誰かが一緒にいるというのは、私には大きな違いがある。地元の助けというのは、たいていまるで役に立たないか、偏っているものだからね。君が二つの隅の席を確保してくれれば、私が切符を取ってくる。」
客車は私たちだけだったが、ホームズが持ち込んだ大量の書類が散乱していた。その山を彼は漁ったり読んだり、時にメモを取り、考え込んだりしながら、レディングを過ぎるまで過ごした。やがて彼はそれらを一つにまとめて巨大な紙の塊を作り、網棚に放り上げた。
「事件のことは何か聞いているかい?」と彼が尋ねた。
「いや、何も。ここ数日新聞も見ていない。」
「ロンドンの新聞でも詳しくは出ていない。私は最近の新聞を全部見て、概要を把握したのだが、どうやらこれは、ひどく難しい単純な事件の一つのようだ。」
「それは逆説的だね。」
「だが、これはまさに真実だ。奇抜さは常に手がかりになる。事件が無個性でありふれているほど、真相を突き止めるのは難しい。この事件では、しかし殺された男の息子に対してかなり重大な容疑がかかっている。」
「つまり殺人事件なんだね?」
「推測の域を出ないが、そうみなされている。私は直接見てみるまでは何も決めつけたくない。今わかる範囲で状況を簡単に説明しよう。
ボスコム渓谷は、ヘリフォードシャーのロスから遠くない田園地帯だ。その土地で最大の地主はジョン・ターナー氏で、オーストラリアで財を成し、数年前に帰国した人物だ。彼が持つ農場の一つ、ヘザリー農場はチャールズ・マッカーシー氏に貸していた。彼もまた元オーストラリア在住者だった。二人は植民地時代からの知り合いで、帰国後はできるだけ近くに住むのも自然な成り行きだったらしい。ターナー氏の方が裕福だったので、マッカーシー氏はその借家人となったが、関係は対等で、しばしば一緒にいたそうだ。マッカーシーには18歳の息子が一人、ターナーには同い年の娘が一人いるが、どちらも妻は亡くなっている。二家族とも周囲のイギリス人家庭との交流を避け、隠遁生活をしていたが、マッカーシー親子はスポーツ好きで、近所の競馬にもよく顔を出していた。マッカーシー家には召使いが男一人、女一人。ターナー家には少なくとも六人はいたらしい。家族構成はこんなところだ。さて、事実関係に移ろう。
6月3日、つまり月曜のこと、マッカーシー氏は午後3時ごろヘザリー農場を出て、ボスコム池へ向かった。そこは渓谷を流れる小川が広がってできた小さな湖だ。彼は午前中、召使いの男とロスへ出かけており、男には「3時に重要な約束がある」と急ぐよう伝えていた。その約束から彼は二度と生きて戻らなかった。
ヘザリー農場からボスコム池までは四分の一マイルで、途中、二人の人物が彼を見ている。一人は名も知られていない老女、もう一人はターナー家の猟場番ウィリアム・クラウダーだ。両名とも、マッカーシー氏は一人で歩いていたと証言している。猟場番によれば、マッカーシー氏が通り過ぎて数分後、息子のジェームズ・マッカーシーが銃を持って同じ方向へ行くのを見たそうだ。父親はまだ視界にあり、息子はその後を追っているように見えたという。猟場番はそのことを気に留めなかったが、その夜事件が起きたと知って初めて思い出した。
その後、猟場番ウィリアム・クラウダーが二人を見失った後にも、マッカーシー親子の姿を見た者がいた。ボスコム池の周囲は木が茂り、縁には草とアシが生えている。ボスコム渓谷の屋敷の門番の娘、14歳のペイシェンス・モランが森で花を摘んでいた。彼女は林の端、湖のそばでマッカーシー親子が激しい口論をしているのを見たと証言している。父親が非常にきつい言葉で息子を叱咤し、息子は父を殴ろうと手を振り上げたのを目撃した。暴力的な雰囲気に怖くなって逃げ出し、家に帰ると母に「二人が池のそばでけんかしていた。きっと殴り合いになるわ」と告げた。言い終わらぬうちに、若いマッカーシー氏が息を切らして門番の家に駆け込んできた。「父が森で死んでいるのを見つけた、助けてくれ」と頼んだのだ。彼はひどく動転しており、銃も帽子も持っていなかった。右手と袖には新しい血の跡が見えた。皆で現場に向かうと、池のそばの草で父親の遺体が横たわっていた。頭部は何度も重く鈍いもので殴られ、ひどく損傷していた。その傷は、付近に落ちていた息子の銃の台尻でつけられた可能性が高い。こうした状況から、若いマッカーシー氏は即座に逮捕され、火曜日の検死審問では「故意による殺人」と評決され、水曜日にはロスの治安判事に引き渡され、次回の大陪審にかけられることとなった。これが検死審問と警察裁判で明らかになった主な事実だ。」
「これ以上有罪を示す証拠は想像できないな」と私は言った。「状況証拠が犯人を指し示すなら、今度こそまさにそうだ。」
「状況証拠というのは、非常にやっかいなものだよ」とホームズは考え込むように言った。「一見、明確に一つの方向を指しているようでいて、見方を少し変えると、まったく違うものを同じようにはっきり指し示すかもしれない。ただ、今回の事件が被疑者にとって非常に不利なのは事実だし、実際に彼が犯人である可能性もある。ただ、この近隣には数人、特に地主の娘であるミス・ターナーなど、彼の無実を信じてレストレード警部――『緋色の研究』でおなじみだろう――を雇い、弁護のために奔走させている。レストレードも困惑して私に相談してきたので、こうして中年男二人が家で朝食をのんびり消化する代わりに、時速50マイルで西へ向かっているというわけだ。」
「事件の事実があまりにも明白だから、君が名声を得る余地は少なそうだ」と私は言った。
「明白な事実ほど欺くものはないよ」と彼は笑って答えた。「それに、レストレード警部には見落とされた明白な事実が他にもあるかもしれない。君も知っているだろうが、私は自慢でなく、彼には使えず想像もつかない手段で彼の理論を証明するか、覆すつもりだ。たとえば君の寝室の窓が右側にあるとすぐに分かったが、レストレード警部にはそれすら気づかないだろう。」
「どうして――」
「君のことはよく知っているからさ。君の軍人らしい几帳面さもね。君は毎朝髭を剃るが、この季節は日差しの中で剃る。だが、左側の奥にいくにつれて剃り残しが増え、顎の角のあたりではかなりぞんざいになっている。つまり、その側は右側より明るくないわけだ。君ほどの几帳面な人が、左右同じ明るさで鏡を見て、そんな結果で満足するとは思えない。これは観察と推論のささやかな例に過ぎないが、私の本分はそこにある。これが今回の捜査にも役立つかもしれない。さて、検死審問で出た細かい点が一つ二つある。」

「それは?」
「逮捕はすぐではなく、農場へ戻った後だった。警察の警部が彼に『君は逮捕された』と告げると、彼は『驚きません、それも当然です』と述べた。この発言が評議員の疑念を完全に払拭する効果をもたらした。」
「それは自白じゃないか」と私は叫んだ。
「いや、その後すぐに無実を主張している。」
「これほど有罪を示す出来事の後では、きわめて怪しい発言だ。」
「むしろ、今のところ、それがこの事件の中で私が見出せる唯一の希望の光だ。どんなに無実でも、自分に不利な状況を理解できない愚か者ではないはずだ。もし自分の逮捕に驚いたふりや憤慨してみせたら、私はむしろ高度な計算に基づいた芝居と疑ったろう。率直に状況を認めたのは、彼が無実であるか、あるいは相当な自制心と胆力の持ち主のどちらかだろう。『当然の報い』という発言も、父の死体のそばに立ち、その日に親不孝をして口論(少女の証言では手を挙げたらしい)したと自責の念に駆られていたなら、決して不自然ではない。むしろ罪の意識より健全な心の表れのように私には思える。」
私は首を振った。「これよりずっと軽い証拠で絞首刑になった人も多いよ。」
「その通り。そして多くの無実の人もまた絞首刑になった。」
「その青年の説明は?」
「彼に味方する者には心強いものではないが、いくつか興味深い点もある。ここにあるから自分で読んでみてくれ。」
彼は書類の山から地元ヘリフォードシャーの新聞を取り出し、該当箇所を指し示してくれた。私は客車の隅で落ち着いて、注意深く読み始めた。こう記されていた――
「故人の一人息子ジェームズ・マッカーシー氏は、次のように証言した――『私は三日間ブリストルに出かけていて、月曜の朝やっと帰宅しました。父はその時家におらず、メイドから父はジョン・コブ(馬丁)とロスへ馬車で出かけたと聞きました。まもなく馬車の音が庭に聞こえ、窓から外を見ると父が降りて、急ぎ足でどこかへ立ち去るのが見えました(どちらへ向かったかは分かりません)。私は銃を手にとり、ウサギの巣を見にボスコム池方面へぶらぶら出かけました。途中で猟場番ウィリアム・クラウダーに会いましたが、彼の証言とは違い、私は父を追っていたわけではありません。父が前にいるなど知らなかったのです。池から100ヤードほどのところで、“クーイー! ”という叫びを聞きました。これは私たちの間の合図でした。それで急いで池に行くと、父が立っていました。父は私を見てひどく驚き、荒々しく『何をしているんだ』と尋ねました。そこから口論になり、ほとんど手が出そうになりました。父は非常に激しい気性の人間でしたので、私は危険を感じてその場を去り、農場の方へ戻ることにしました。しかし150ヤードほどしか進まないうちに、背後から恐ろしい叫び声が聞こえ、また急いで引き返しました。父は地面に倒れ、頭にひどい傷を負って瀕死でした。私は銃を落として父を抱き起こしましたが、ほとんどすぐに息絶えました。しばらく父のそばにひざまずき、それから一番近いターナー氏の門番の家へ助けを求めに行きました。戻った時、父のそばには誰もおらず、どうしてこうなったかまったく分かりません。父は無口で近寄りがたい性格でしたが、積極的な敵も知らず、これ以上は何も知りません。』
「検死官:父上は亡くなる前に何か言葉を残しましたか?
証人:何かつぶやきましたが、“rat”という言葉だけ聞き取れました。
検死官:それはどういう意味だと思いますか?
証人:分かりません。うわ言だと思いました。
検死官:最後の口論の原因は?
証人:お答えしたくありません。
検死官:それは困ります。
証人:本当に申し上げられません。ただ、悲劇とは無関係です。
検死官:その判断は法廷がします。答えないのは今後の裁判で不利になりますよ。
証人:それでもお答えできません。
検死官:“クーイー”はお二人の合図だったそうですね?
証人:はい。
検死官:では、なぜ父上はあなたに気づく前、ブリストルから帰宅したと知らぬうちにその合図を発したのですか?
証人(かなり動揺して):分かりません。
陪審員:現場に戻って父上の重傷を見たとき、何か不審なものは?
証人:はっきりしたものはありません。
検死官:どういう意味ですか?
証人:私は動転して父のことしか考えられませんでしたが、走り寄るとき、左手の地面に何かがあったような気がします。灰色の何か、上着か、あるいはプラッドだったかもしれません。父のそばから立ち上がって探しましたが、もうなくなっていました。
『助けを呼びに行く前に消えていたのですか?』
『はい、なくなっていました。』
『それが何かは分かりませんか?』
『分かりません。ただ何かあった気がします。』
『遺体からどれくらい離れていました?』
『12ヤードほど。』
『林の端からは?』
『同じくそれくらい。』
『すると、それが移動されたとしたら、あなたが12ヤード以内にいた時ですね?』
『はい、でも私は背を向けていました。』
――これで証言は終わりです。」
「ほう」と私は欄を見下ろしながら言った。「検死官は結論で若いマッカーシー氏にずいぶん厳しい口調だったようだね。父親が息子に合図した時間の矛盾、口論の内容を拒む理由、父の最期の言葉の説明の不可解さ、どれも息子にとって不利な点ばかりだ。」
ホームズは小さく笑い、自分をクッションのきいた座席に伸ばした。「あなたも検視官も、かなり苦労して、この若者に有利な点を挙げておられる」と彼は言った。「だが君たちは、彼に想像力がありすぎるとも足りなすぎるとも、交互に評価していることに気づかないのか。もし陪審員の同情を引くような喧嘩の理由すら思いつけなければ想像力が足りないことになるし、一方、死に際に“ネズミ”を口にしたり、消えた布切れのような突飛な話を自分で思いついたのなら、今度は想像力がありすぎるということになる。いや、私はこの若者の言うことが事実だという前提で事件に臨むつもりだ。そしてその仮説がどこへ導くのか見てみよう。さて、ここにポケット版のペトラルカがある。この事件については、現場に着くまで一言も話さないことにしよう。スウィンドンで昼食を取るが、あと二十分で着くようだ。」
美しいストラウド渓谷を抜け、広々と光るセヴァーン川を渡って、ついに私たちがロスの可愛らしい田舎町に到着したのは、ほぼ午後四時のことだった。ホームズと私を待っていたのは、痩せてイタチのような、どこか人目を避けるような、ずる賢そうな男だった。彼の田舎の雰囲気にあわせた明るい茶色のダストコートと革製レギンスにも関わらず、私はすぐにスコットランド・ヤードのレストレード警部だとわかった。彼と共にヘレフォード・アームズに向かい、そこには既に部屋が予約されていた。
「馬車を手配しておきましたよ」とレストレードは、私たちが紅茶を飲みながら言った。「あなたの行動力を知っていますから、現場を見ずには落ち着かないだろうと思いましてね。」
「それはご親切に、また光栄なことです」とホームズ。「ただ、全ては気圧の問題です。」
レストレードは驚いた顔をした。「どういう意味です?」
「気圧計は? 29だな。無風で雲一つない。ここに煙草がたくさんあって、ソファも田舎のホテルにしては上出来だ。今夜は馬車は使わないだろう。」
レストレードは寛大に笑った。「すでに新聞で結論を出されたのでしょう。事件は明白で、調べれば調べるほど明らかになります。それでも、婦人の頼みですから断るわけにいきません。しかも非常に強いご要望でして。あなたの噂を聞いてどうしても意見が聞きたいと。私が何度も、私のやったこと以上のことはできないと説明したにも関わらず。――おや、ちょうど彼女の馬車が来たようです。」
その言葉が終わらぬうちに、この世で見た中でもっとも美しい若い女性の一人が、部屋に勢いよく飛び込んできた。紫色の瞳が輝き、唇はわずかに開き、頬はピンク色に染まり、普段の慎み深さも圧倒的な興奮と心配の前では消え失せていた。
「ああ、シャーロック・ホームズさん!」彼女は私たち一人ひとりを見比べ、最後には女性の直感でホームズに視線を定めた。「来てくださって本当にうれしいんです、それを伝えたくて来ました。私はジェームズがやっていないと信じています。本当にそうなんです。だから、ぜひそれを信じた上で調査に取り組んでください。その点だけは絶対に疑わないでください。私たちは幼いころからの知り合いで、彼の欠点も誰よりも知っています。でも彼は虫一匹殺せないほど心優しいんです。本当に知っている人なら、こんな罪を着せられるのは馬鹿げていると分かるはずです。」
「彼の無実を証明できるよう努力しましょう、ミス・ターナー。」とホームズ。「私にできることはすべてやります。」
「証拠を読んで、何らかの結論は出されたのですか? 抜け道や矛盾点は見つかりませんか? あなた自身、彼が無実だと思いませんか?」
「私は、その可能性が高いと考えています。」
「ほら、ご覧なさい!」と彼女は頭を反らせ、レストレードを挑むように見て言った。「希望が持てます。」
レストレードは肩をすくめた。「同僚は少々早急な結論を出しがちです。」
「でも、彼が正しいんです。ジェームズがやるはずがありません。そして父親との喧嘩のことですが、彼が検視官に理由を話さなかったのは、私が関わっているからだと確信しています。」
「どう関わっているのですか?」とホームズ。
「隠し事はできません。ジェームズとその父親は私のことで何度も揉めていました。マッカーシーさんは、私たちを結婚させたがっていました。私とジェームズは兄妹のように育ちましたが、彼はまだ若く、世間を知らず、当然そんなことはまだしたくなかったのです。それで度々喧嘩になり、おそらく今回もその一つだったのでしょう。」
「お父上は?」とホームズ。「その結婚に賛成でしたか?」
「いえ、父も反対でした。賛成していたのはマッカーシーさんだけです。」ホームズが鋭い視線を送ると、彼女の若い顔にさっと赤みが差した。
「貴重な情報をありがとうございます。明日お父様にお会いできますか?」
「医者が許さないと思います。」
「お医者さん?」
「ええ、ご存じないのですか? 父は何年も前から弱っていましたが、今回の件で完全に倒れてしまいました。今は寝込んでおり、ウィローズ先生が“身体も神経もぼろぼろだ”と言っています。マッカーシーさんは、昔ビクトリア州時代から父を知っていた唯一の友人でした。」
「ほう、ビクトリアで! それは重要です。」
「ええ、鉱山で。」
「なるほど、金鉱で財を成したと聞いています。」
「その通りです。」
「ありがとうございます、ミス・ターナー。大変参考になりました。」
「明日、何か分かったら私にも教えてくださいね。きっと刑務所へジェームズに会いに行くのでしょう? もしそうなら、彼が無実だと私が知っていることを、どうか伝えてあげてください。」
「もちろん、ミス・ターナー。」
「もう帰らないと。父がとても具合が悪くて、私がいないと寂しがりますから。さようなら、ご成功をお祈りします。」彼女は入ってきたときと同じ勢いで部屋を去り、馬車の車輪の音が通りを遠ざかっていくのが聞こえた。
「ホームズ、君には呆れたよ」と、しばらくの沈黙のあと、レストレードは威厳を込めて言った。「期待させておいて、落胆させるだけではないか。私は特別に心が優しいわけではないが、これは残酷だ。」
「私はジェームズ・マッカーシーの無実を証明できる見通しが立ったと思っている」とホームズ。「彼に面会する許可証は?」
「あるが、君と私だけだ。」
「それでは、外出しないという決心は取りやめよう。今からヘレフォード行きの列車に乗って、今夜中に彼に会いに行けるだろうか?」
「十分間に合う。」
「では行こう。ワトソン、退屈かもしれないが二時間もかからない。」
私は二人と駅まで歩き、その後、町の通りをぶらぶら歩いてからホテルに戻り、ソファに横になって黄表紙の小説を手にした。しかし、その物語の薄っぺらな筋立ては、我々が今まさに手探りしているこの深い謎の前ではあまりにも貧弱で、私はたびたび現実の事件のほうへ意識を引き戻され、ついには本を部屋の向こうへ投げ捨て、今日一日の出来事について思いを巡らせた。この不幸な若者の話がもし完全に事実だとしたら、父と別れ、叫び声に引き返して林間の空き地に駆け戻るまでの間に、どんな地獄のような、まったく予想もつかぬ大惨事が起こり得たのか。何か恐ろしい、致死的な出来事だ。一体何だったのだろう? 負傷の様子から医学的な直感で何かわからないか。私はベルを鳴らし、検視の逐語記録が載っている地方新聞の週刊紙を取り寄せた。外科医の証言には、左頭頂骨後方三分の一と左後頭骨半分が鈍器の一撃により破壊されていた、とあった。私は自分の頭でその場所を確認した。明らかに、後ろからの一撃であるはずだ。これは被告にとって有利な点となる。なぜなら、喧嘩していたときには父子は向かい合っていたからだ。しかし、父親が打撃の直前に背を向けた可能性もあるので、決定的ではない。それでもホームズに伝えておく価値はあるかもしれない。次に、死に際の奇妙な「ネズミ」発言。あれは何を意味するのか。譫妄ではありえない。突発的な一撃で死ぬ者が普通譫妄状態になることはない。むしろ、自分の最期の状況を説明しようとしたのだろう。しかし、何を伝えたかったのか。頭をひねって考えた。それから、若マッカーシーが目撃した灰色の布の一件。もし事実なら、犯人は逃走時に自分の衣類、たぶんオーバーコートの一部を落とし、それを取り戻すために、息子が背を向けて十歩ほど離れた場所でひざまずいている隙に、再び現場に戻って持ち去ったことになる。全体として、なんと謎と不自然さに満ちた事件だろう。レストレードの意見も無理はないと思う一方、シャーロック・ホームズの洞察力への信頼が揺らぐことはなかった。どんな新事実も、若マッカーシーの無実を確信させる方向へ進んでいる気がしたからだ。
ホームズが戻ったのは遅い時間だった。彼は一人で帰ってきた。レストレードは町の宿に泊まっているのだった。
「気圧計はまだ高いままだ」と彼は座りながら言った。「地面を調べる前に雨が降らないことが重要だ。その一方で、こういう精密な仕事をするには、やはり体調万全で臨むべきだから、長旅で疲れているときは避けたかった。若マッカーシーに会ってきた。」
「何か分かったのか?」
「いや、何も。」
「何も手がかりは?」
「一つもなかった。一時は、彼が犯人を知っていてかばっているのかとも思ったが、今は彼も皆と同じく途方に暮れているのだと確信した。頭の回転が速い青年ではないが、見た目は良く、根は誠実そうだ。」
「だが、あんな魅力的なミス・ターナーとの結婚に乗り気でなかったというのは感心できないな」と私は言った。
「いや、それには痛ましい事情があってね。この青年は、彼女に夢中で狂おしいほど愛している。しかし二年前、まだ十代の頃、彼女が五年間寄宿学校に行っていて本格的に知り合う前、なんと愚かなことにブリストルのバーメイドに引っかかって、役所で結婚してしまった。誰もそのことを知らないが、今あの青年が、どれだけ悔しい思いをしているか想像できるだろう。彼は心から結婚したいのに、絶対に不可能だと知っているから責められている。それが父親に結婚を迫られたとき、絶望的になって両手を振り上げた理由だ。一方、彼には生活手段もなく、父親は非常に厳格な人物で、真実を知れば絶縁されただろう。この三日間はブリストルでそのバーメイドの妻と過ごしていたが、父親はその所在を知らなかった。ここは重要な点だ。だが、悪いことにも良いことがあって、バーメイドは新聞で彼が大変な窮地に陥ったのを知ると完全に見捨て、実はすでにバミューダ・ドックヤードに夫がいると書き送ってきた。つまり今や二人の間には何の絆もない。その知らせで、若マッカーシーも随分気が楽になったようだ。」
「だが、もし彼が無実なら、犯人は誰なのか?」
「うむ、それが問題だ。特に注目すべき点が二つある。第一に、被害者は池で誰かと会う約束をしており、その相手は息子ではあり得ない。なぜなら息子は出かけていて、いつ戻るか父親も知らなかったからだ。第二に、被害者は息子が戻ったと知らぬうちに『クーイー!』と叫んだ。事件の核心はこの二点にある。――さて、今夜はジョージ・メレディスの話でもしよう。細かいことは明日まで取っておこう。」
ホームズの予想通り雨は降らず、朝は明るく雲ひとつない晴天となった。九時にレストレードが馬車で迎えに来て、私たちはヘザリー農場とボスコム池へ向かった。
「今朝は深刻な知らせがある」とレストレード。「館のターナー氏が重篤で、命も危ないそうです。」
「高齢の方ですか?」とホームズ。
「六十歳くらいだが、海外生活で体を壊し、ここ数年は健康が衰えていた。今回の件でとどめを刺されたようなものだ。マッカーシーとは古い友人で、しかも多大な恩人だ。ヘザリー農場も無償で貸していたと聞いている。」
「ほう、それは興味深い。」
「ええ、他にも色々と援助していたようだ。ここいらでは皆、ターナー氏の親切を語るよ。」
「なるほど。しかし、マッカーシー氏は自分の財産が乏しくターナー氏に大きく頼っていたにもかかわらず、まるで当然のようにターナー氏の娘と息子の結婚を進めようとしていた。しかも、ターナー氏自身は反対だったと娘さんが言っていた。そのことから何か推測できませんか?」
「推測や仮説なんてごめんだね」とレストレードは私にウィンクして言った。「私は事実だけで手一杯さ。」
「おっしゃる通りです」とホームズはしおらしく応じた。「事実を扱うのがお好きなんですね。」
「少なくとも、君が苦労している一つの事実はつかんだよ」とレストレードは少し熱を帯びて返した。
「それは――」
「マッカーシー老人を殺したのは、息子マッカーシーだってことさ。他の説は全て絵空事だ。」
「絵空事でも、霧よりは明るいよ」とホームズは笑った。「だが、あれが左手のヘザリー農場じゃないか?」
「そうだ。」二階建てでスレート屋根、灰色の壁には黄色い地衣類が点々と広がる、広々としつつも居心地良さそうな建物だった。しかしカーテンが引かれ、煙の上がらぬ煙突が、この家にまだ事件の重苦しさが残っていることを物語っていた。玄関で、ホームズの頼みにより家政婦は当時主人が履いていた靴と、息子の靴(ただし事件時のものではない)を見せてくれた。ホームズはそれらを七、八ヶ所から慎重に計測し、次いで中庭へ案内を求め、私たち一同は曲がりくねった小道を辿ってボスコム池へ向かった。

現場の手掛かりを追うホームズは、まるで別人のようだった。ベイカー街での静かな思索家や論理家しか知らぬ者なら、彼を見間違えたことだろう。顔は紅潮し、眉は黒い二筋となって寄り、目は鋼のような輝きを放っていた。顔を下に向け、肩を丸め、唇を固く引き結び、長くしなやかな首には鞭のような血管が浮かんでいる。鼻孔は獣が獲物を追うときのように広がり、心はただ一点、目の前の調査だけに集中していた。話しかけても耳に入らず、せいぜい短く苛立った返事が返るだけだった。彼は素早く、無言で小道を進み、ときに立ち止まり、ときに急ぎ足になり、ときには小さく牧草地に迂回までするほどだった。レストレードと私はその後をついて歩いた。レストレードは興味なさげに、私は友人の一挙手一投足が何か明確な目的に向かっていることを確信しながら、熱心に見守っていた。
ボスコム湖は、周囲を葦に囲まれた、幅およそ50ヤードほどの小さな池で、ヘザリー農場と裕福なジョン・ターナー氏の私有公園との境界に位置している。対岸の林の上には、裕福な地主の邸宅を示す赤い突き出した尖塔が見えた。ヘザリー側の湖畔は森が非常に深く、木々の端から湖畔の葦までの間に、幅二十歩ほどのぬかるんだ芝生の帯があった。レストレード警部は遺体が発見された正確な場所を示してくれたが、実際、その地面はとても湿っていたので、倒れた男が残した痕跡もはっきりと見て取れた。ホームズにとっては――その熱心な表情と鋭いまなざしから分かったが――踏み荒らされた草の上には、さらに多くのことが読み取れたようだった。彼はまるで匂いをたどる犬のように周囲を回り、それから私たちの方へ向き直った。
「どうして池に入ったんです?」と彼は尋ねた。
「熊手であたりを探しました。何か凶器や痕跡が残っているかと思ってね。でも一体どうやって――」
「おやおや、そんな暇はない! あなたの左足の内向きの癖があちこちに残っている。もぐらでも辿れるくらいだ。そして、その足跡は葦の中で途切れている。ああ、もし私が、彼らが水牛の群れのように来て辺り一帯を踏み荒らす前にここにいたら、どんなに簡単だったことか。ほら、ロッジ管理人と一緒に来た人たちの足跡がここだ。遺体の周り六、七フィートほどはすべて踏みつけられてしまっている。しかし、こっちには同じ足跡が三種類、別々に残っている。」そう言いながら、ホームズはルーペを取り出し、防水コートの上に腹這いになって、私たちというよりむしろ独り言のように話し続けた。「これはジェームズ・マッカーシーの足跡だ。二度は歩いていて、一度は素早く走っているので、足裏の跡が深く、かかとはほとんど見えない。これは彼の証言と合致する。父親が地面に倒れているのを見て走ったのだ。それから、こちらが父親の足跡――行ったり来たりしている。これは何だ? 銃の床尾だ、息子が立って話を聞いていた時のものだ。そしてこれは? ははっ! なんだこれは? つま先立ち、つま先立ち! しかも四角い、非常に珍しい靴だ! 来て、去り、また戻ってきて――もちろん、これはマントを取りに戻ったのだろう。さて、どこから来たのか?」ホームズは行ったり来たりして、時に足跡を見失い、また見つけながら、私たちは森の端まで進み、その地域最大のブナの大木の陰に入った。ホームズはその反対側まで足跡を辿り、満足げな小さな声を漏らしながら再びうつ伏せになった。彼は長い間そこに留まり、落ち葉や枯れ枝をひっくり返し、何やら埃のようなものを封筒に集め、ルーペで地面だけでなく、手の届く限り木の樹皮まで念入りに調べていた。苔むした中にギザギザの石が一つ落ちていて、それも注意深く調べて持ち帰った。それから彼は森を抜ける小道をたどり、幹線道路に出たところで、すべての痕跡は消えていた。
「これはなかなか面白い事件だったな」と、ホームズはいつもの口調に戻って言った。「右手のあの灰色の家がロッジだろう。ちょっとモランに会って、もしかしたら手紙も書くつもりだ。それが済んだら、馬車で昼食に戻ろう。君たちは先に馬車へ行っていてくれ、すぐに追いつく。」
私たちが再び馬車に戻り、ロスの町へと引き返したのは、それからおよそ十分後だった。ホームズはまだ森で拾った石を持っていた。
「レストレード、君も興味があるだろう」と言い、ホームズはその石を差し出した。「殺人はこれで行われたのさ。」
「傷跡は見えませんが。」
「跡は残っていない。」
「では、なぜそれだと分かるのです?」
「その下に草が生えていた。ここ数日しかそこに置かれていなかった。持ち去られた痕跡もない。傷とも一致する。他に武器の痕跡もない。」
「では、犯人は?」
「背が高く、左利きで、右足を引きずり、厚底の狩猟靴を履き、灰色のマントをまとい、インド産の葉巻を吸い、葉巻ホルダーを使い、鈍い小刀をポケットに持っている男だ。他にもいくつか特徴があるが、これだけでも捜索には十分だろう。」
レストレードは笑った。「私はまだ懐疑的ですよ。理論は結構ですが、私たちが向き合うのは現実主義の英国陪審員なのです。」
「ヌ・ヴェロン」とホームズは穏やかに答えた。「君は君のやり方で、私は私のやり方で進める。私は午後忙しいので、夜の列車でロンドンに戻る予定だ。」
「この事件を未解決のままですか?」
「いや、解決した。」
「だが、謎は?」
「すでに解けている。」
「では、犯人は誰ですか?」
「今説明した紳士だ。」
「でもそれは誰なんです?」
「調べるのは難しくないはずだ。このあたりは人口も多くない。」
レストレードは肩をすくめた。「私は実務家ですからね、左利きで足を引きずる紳士を探して歩き回るわけにはいきませんよ。そんなことをしたらスコットランド・ヤードの笑い者です。」
「分かった」ホームズは静かに言った。「君にはチャンスを与えた。ほら、君の部屋だ。さようなら。出発前に手紙を入れるよ。」
レストレードを宿に送り届けた後、私たちはホテルへ向かい、テーブルには昼食が用意されていた。ホームズは沈黙し、難しい顔で思索にふけっていた。まるで困難な状況に追い込まれているようだった。
「ちょっとワトソン、こっちに座ってくれ。少し君に説教させてくれないか。どうしたものか迷っていて、君の助言が欲しい。葉巻でも吸って、私の持論を聞いてくれ。」
「どうぞ、話してください。」
「さて、この事件について考えると、若いマッカーシーの話には二つ気になる点があったね。君もすぐ気づいたろうが、私には彼に有利に、君には不利に働いた。一つは、彼の証言によれば父親が最初に『クーイー!』と叫んだこと。もう一つは、死に際して奇妙に『ラット』という言葉を口走ったことだ。彼はいくつか呟いたが、息子が聞き取れたのはそれだけだった。この二点から調査を始めるが、彼の証言が完全に正しいと仮定してみよう。」
「では、その『クーイー!』は?」
「明らかに息子に向けたものじゃない。息子は、父親の知る限りブリストルにいた。たまたま近くにいたから聞こえただけだ。『クーイー!』は、父親が誰か、約束した相手を呼んだのだ。しかし『クーイー』はオーストラリア特有の呼び声で、オーストラリア人同士が使う。つまり、マッカーシーがボスコム湖で会うつもりだったのは、オーストラリアにいたことがある人物だと強く推測できる。」
「では『ラット』は?」
シャーロック・ホームズはポケットから折りたたんだ紙を取り出し、テーブルに広げた。「これはビクトリア植民地の地図だ。昨夜、ブリストルに電報で取り寄せた。」彼は地図の一部に手をかぶせて言った。「何と読める?」
「ARAT」と私は答えた。
「では今は?」彼は手をどけた。
「BALLARAT。」
「その通り。被害者が言おうとしたのはこの言葉で、息子が聞き取れたのは最後の二音だけだった。犯人の名前を言おうとしていたのだ。バララットの誰それ、と。」
「驚くべきことだ!」私は叫んだ。
「いや、これは明白なことさ。そして、これで捜査範囲はかなり絞り込まれた。灰色の衣服の所持も、息子の証言が正しいなら第三の確定事項になる。こうして曖昧だったものが、『バララット出身の灰色のマントを持つオーストラリア人』という明確な像になった。」
「確かに。」
「しかも、この土地に明るいやつだ。池には農場側か屋敷側からしか近づけず、見知らぬ者がうろつける場所ではない。」
「まったくその通り。」
「そして今日の現場調査だ。地面の観察で、さっきあの愚かなレストレードに話した犯人像の細かい特徴が得られた。」
「どうやって分かったんです?」
「私の方法は細部の観察に基づいているのを知っているだろう。」
「身長は歩幅から、大体見積もれるでしょう。靴跡から靴の特徴も。」
「ああ、あれは特異な靴だった。」
「でも、足を引きずることは?」
「右足の跡が左ほど鮮明でなかった。体重のかけ方が違う。なぜか? 足を引きずっていたからさ。」
「左利きは?」
「検視で医師が記録した傷の様子に、君も気づいたはずだ。背後からの一撃だが、左側に傷がある。左手でなければ不自然だ。あの木の後ろに立ち、父子のやりとりを見ていた。そこで煙草も吸っていた。私は葉巻の灰を見つけ、それがインド産の葉巻だとすぐ分かった。私は煙草の灰について少し研究し、140種類のパイプ、葉巻、紙巻き煙草の灰について小論文を書いたこともある。灰を見て、苔の中に投げ捨てられた吸い殻も発見した。インド産で、ロッテルダムで巻かれた葉巻だった。」
「葉巻ホルダーは?」
「吸い口が口に入った形ではなかった。つまりホルダーを使っていた。端が噛み切られておらず、切り口は雑だった。鈍い小刀で切ったのだと推理した。」
「ホームズ、君はこの男に逃げ場のない網をかけて、まさに絞首台の縄を切るようにして無実の命を救ったんだな。すべてが示す先は――」
「ジョン・ターナー氏です」そう叫びながら、ホテルの給仕が私たちの部屋のドアを開き、訪問者を案内してきた。
現れた男は、異様で圧倒的な風貌だった。ゆっくりと足を引きずり、肩を丸めて歩く様は病み衰えた老人のそれだが、ごつごつとした深い皺のある顔立ちと、並外れて頑強な体躯は、強い肉体と性格の持ち主であることを示していた。もつれた髭と白髪、突き出した垂れ眉が威厳と貫禄を醸し出していたが、顔色は灰白色で、唇や鼻の脇には青みすら帯びていた。一目見て、彼が重篤で慢性的な病に苦しむ身であることは明らかだった。
「どうぞソファにおかけください」とホームズは優しく言った。「私の手紙は受け取りましたか?」
「ええ、ロッジ管理人が持ってきました。あなたがここで会いたいと書かれていたのは、騒ぎになるのを避けるためですね。」
「屋敷へ伺えば噂になると思ったのです。」
「では、なぜ私に会いたいのですか?」彼は絶望のまなざしでホームズを見つめ、質問の答えは既に分かっているという様子だった。
「その通りです」ホームズは、言葉ではなくその視線に答えるように言った。「私はマッカーシー事件のすべてを知っています。」
老人は顔を両手で覆い、「神よお救いください!」と叫んだ。「ですが、あの若者が害されることだけは絶対にさせませんでした。もし公判で不利になりそうなら、私は必ず真実を話すつもりでした。」
「そう言っていただき安心しました」とホームズは厳かに言った。
「今だって話す覚悟はありました。だが、愛しい娘のために――彼女には耐えられません。逮捕されたと聞くだけで心が壊れてしまう。」
「そうなるとは限りません」とホームズは言った。
「なんですって?」
「私は公的な捜査官ではありません。あなたの娘さんの要請でここに来ているのですし、私は彼女のために動いています。ただし、若いマッカーシーの嫌疑は晴らさねばなりません。」
「私は余命いくばくもない身です。糖尿病を長年患っています。医者も一月もつかどうかと言っています。それでも、獄中死するよりは自宅で死にたい。」
ホームズは立ち上がり、テーブルに向かい、ペンと紙束を手にした。「真実をお話しください。それを書き留めます。あなたが署名し、ワトソンが証人となる。必要最終手段として、若いマッカーシー救済の切り札にします。絶対に必要なとき以外は使いませんと約束します。」
「その方が良いでしょう。アサイズまで生きていられるかも分かりませんし、私にはもうどうでもいい。ただ、アリスにはショックを与えたくない。では、すべてを明かしましょう。この件は長い時間をかけて進んできましたが、話すのにはそれほどかかりません。
「あなたは亡きマッカーシーという男を知らなかったでしょうが、あいつは悪魔そのものでした。本当に、ああいう男の餌食になるのはご勘弁願いたい。奴の呪縛は二十年も私に続き、私の人生を台無しにしました。なぜ奴の支配下に置かれたか、まずそこから話しましょう。
「六十年代初頭、採鉱地でのことです。私はまだ若く、血気盛んで無鉄砲、何でもやる覚悟でした。悪い仲間と付き合い、酒に溺れ、鉱山では運もなく、ついには山賊まがいとなり、いわゆる追いはぎになったのです。六人組で、時に駅馬車を襲い、時に採鉱地に向かう荷馬車を襲いました。『バララットのブラック・ジャック』と名乗っていましたし、今でも現地ではバララット団として記憶されているはずです。
「ある日、バララットからメルボルンへ金輸送隊が出て、我々は待ち伏せて襲撃しました。護衛の騎馬警官六人と、我々六人、まさに接戦でしたが、第一射で四人を倒しました。しかし、こちらも三人がやられ、ようやく金を奪って逃げました。私は馬車の御者、つまり例のマッカーシーにピストルを突きつけました。あのとき撃ち殺しておけばよかった、と今でも思いますが、そのときは見逃しました。ただ、あの男が私の顔を忘れまいとする目で見つめたのをはっきり覚えています。結局、金を手にして裕福となり、疑われることもなくイングランドへ移住しました。そこで仲間と別れ、静かで立派な生活を送ろうと決意しました。ちょうど売りに出ていたこの土地を買い、罪滅ぼしのつもりで善行に励み、結婚もしましたが、妻は若くして亡くなり、私には愛しいアリスだけが残されました。まだ赤ちゃんの手が私を正しい道へと導いてくれたのです。私は心を入れ替え、過去を償おうと努力しました。すべてがうまくいっていたのに、マッカーシーが私を再び支配し始めたのです。
「投資のためロンドンへ出た際、リージェントストリートでマッカーシーに会いました。彼は着る物も靴もろくにない有様で――
『やあジャック』と奴が腕を叩いて言うのです。『俺たちはもう家族同然だ。俺と息子と二人、君の世話になるよ。断ればどうなるか分かるな? イギリスは法治国家だから、警官がいつでも呼べるぜ。』
「こうして奴らは西部へやってきて、どうしても追い払えず、以来ずっと私の一番良い土地に、家賃も払わず住み着いていました。安らぎも平穏も忘却もなく、どこへ行っても奴のずる賢い顔がそばにちらつく。アリスが成長するにつれ、事態はさらに悪化しました。私は警察よりも娘に過去を知られることを恐れていると、奴はすぐに気づいたのです。奴が望むものは何でも手に入れ、土地でも金でも家でも、要求されるままに与えました。ついに、私が絶対に渡せないもの――アリスを求めてきたのです。
「奴の息子が成長し、私の娘も成長し、私が弱っていることも知っていましたから、もし自分の息子が全財産を相続できれば大成功だと考えたのでしょう。しかし、私はそこだけは断固として譲らなかった。呪われた血が私の家系に混ざるのは耐えられなかったのです。少年に対して個人的な悪意はなかったが、それでも血がすべてでした。私は屈しなかった。マッカーシーは脅し、私は彼を受けて立った。私たちは話し合うために、家と家の中間にある池で会うことになりました。
「私がそこへ下りていったとき、彼は息子と話しているところでした。そこで私は葉巻をくゆらせながら、彼が一人になるのを木の陰で待っていました。しかし彼らの会話に耳を傾けているうち、私の中にある黒く苦々しい感情が一気に表にあふれ出してきたのです。彼は、まるで娘が道端の女ででもあるかのように、彼女自身の気持ちも顧みず、息子に私の娘と結婚するよう強く勧めていました。その男の力のもとで、私や私の最も大切に思うものすべてが左右されていると考えると、気が狂いそうでした。このしがらみを断ち切ることはできないのか? 私はすでに死を覚悟した絶望の淵にいたのです。頭は冴え、体もまだ充分に動きましたが、自分の運命はもはや決まったものと思っていました。しかし、私の記憶と、私の娘だけは――もしもあの穢らわしい舌を黙らせることができたなら――救うことができたのです。私はやりました、ホームズさん。もう一度同じことをするでしょう。重い罪を背負いましたが、それを償うために私は殉教者のごとき人生を歩んできました。しかし、私の娘までもが私を縛った同じ罠にかかるのは、到底耐えられなかった。私は、あの男が毒蛇か何かであったかのように、一切の良心の呵責もなく彼を打ち倒しました。その叫び声で息子が戻ってきましたが、私は森に身を隠すことができました。ただ、逃走中に落とした外套を取りに戻らねばなりませんでした。これが、紳士方、すべての真実です。」
「私はあなたを裁く立場にはありません。」老人が作成された供述書に署名すると、ホームズはそう言った。「どうか、私たちが決してこのような誘惑にさらされませんように。」
「私もそう願います、先生。それで、あなたはこれからどうなさるおつもりですか?」
「あなたの健康状態を鑑みて、私は何もしません。あなた自身もご存じの通り、間もなくより高次の法廷でこの行いの責任を問われることになるでしょう。私はあなたの告白を預かります。万が一マッカーシーが有罪となれば、それを使わざるを得ません。しかし、そうでなければ、この告白が人の目に触れることは永久にありません。あなたが生きていても死んでいても、その秘密は私たちの間で守られます。」
「では、さようなら。」と老人は厳かに言った。「あなた方ご自身が死の床に伏すとき、私に与えてくださった安らぎを思い出し、きっと心穏やかでいられることでしょう。」その堂々たる体を震わせながら、彼はよろよろと部屋を後にした。
「神よ、我らを救いたまえ!」長い沈黙の後、ホームズが言った。「なぜ運命は、こんなにも無力な人間たちに、こんな悪戯を仕掛けるのだろう? 私はこのような事件を耳にするたび、バクスターの言葉を思い出し、『神の恵みによって、そこにシャーロック・ホームズがいなかっただけのことだ』とつぶやくのだ。」
ジェームズ・マッカーシーはホームズがまとめ、弁護人に提出した数々の異議申し立てに基づき、アサイズ裁判で無罪となった。ジョン・ターナー老人は私たちの面会から七か月後に亡くなったが、今では息子と娘が、過去に横たわる暗い雲を知ることなく、幸せに暮らせる見込みが十分にある。
第五話 五つのオレンジの種
1882年から1890年にかけてのシャーロック・ホームズ事件の記録やメモをざっと見返してみると、奇妙で興味深い特徴を持ったものがあまりに多く、どれを選び、どれを省くか悩ましい限りである。中にはすでに新聞で世に知られたものもあれば、私の友人が持っていた特異な資質を十全に発揮する場を与えなかったものもある。また、彼の分析力をもってしても解明できず、物語としては結末のない始まりにすぎない事件もあれば、部分的にしか解決できず、その説明も推測や憶測に基づくばかりで、彼が何よりも重んじた絶対的な論理的証明には至らなかったものもある。とはいえ、こうした最後の類の中にも、あまりにも際立った詳細と驚くべき結末を持つ事件があり、いまだに、そしておそらくこれからも完全に解明されることのない点があるにもかかわらず、これについて記してみたいという誘惑に駆られる。
1887年は、私が記録を残している限りで、興味深い事件が数多く続いた一年だった。その年の記録には、「パラドルの間の冒険」や、家具倉庫の地下室に贅沢なクラブを構えていた「アマチュア乞食協会」のこと、英国の帆船ソフィー・アンダーソン号の失踪事件、ウッファ島でのグライス・パターソン一家の奇妙な冒険、そして最後にカンバーウェル毒殺事件などが並んでいる。ちなみにこの最後の事件では、シャーロック・ホームズが死者の時計を巻き直すことで、死亡者が二時間以内に寝床についたことを証明し、それが事件解決の極めて重要な決め手となった。これらの事件については、またいずれ別の機会に詳しく紹介しようと思うが、今ここで筆を執るに至った奇妙な巡り合わせほど、特異な特徴を示すものはない。
それは九月も終わりに近いある日で、秋分の嵐が例年にも増して激しく吹き荒れていた。一日じゅう風はうなり、雨は窓を叩きつけ、ここ、手作りの大都市ロンドンの真ん中にいてさえ、人は日々の暮らしの惰性から一瞬心を引き離され、文明という檻の隙間から人間に吠えかかる、荒ぶる自然の力の存在を認めざるを得なかった。夕方になるにつれ嵐はいっそう激しくなり、風は煙突で子どもが泣くように叫び、すすり泣いた。シャーロック・ホームズは暖炉の片側で気だるげに犯罪記録のクロスインデックス作りに没頭し、私は反対側でクラーク・ラッセルの優れた海洋小説を読んでいた。外の突風のうなりが物語の文章と溶け合い、雨音がまるで長い波のうねりのように聞こえるほどだった。妻は実家に帰省中で、私は数日間だけ、再びベイカー街の懐かしい部屋に住むことになっていた。
「おや」と私は相棒に目をやって言った。「今のはベルじゃないか? こんな夜に誰が来るんだろう。君の友人かな?」
「君以外には誰もいないよ」と彼は答えた。「私は訪問客を歓迎しないからね。」
「じゃあ依頼人か?」
「もしそうなら、よっぽど深刻な事件だ。こんな日、こんな時間に出かけてくる理由があるとしたら、それしかない。だが、どちらかといえば、大家さんの知り合いの誰かの方がありそうだ。」
しかしシャーロック・ホームズの推測は外れた。廊下に足音が近づき、ドアを叩く音がした。彼は長い腕を伸ばして自分の方からランプをそらし、新しい来客が座るであろう空っぽの椅子の上へと向けた。「どうぞ!」と彼が声をかける。
入ってきたのは、せいぜい二十二歳ほどの若者で、身なりもよく清潔感があり、どこか繊細で上品な雰囲気を湛えていた。手に持った湯気を立てる傘と、長く光沢のあるレインコートは、彼がどれほど激しい風雨の中をやってきたかを物語っていた。ランプの明かりに照らされて彼は落ち着きなくあたりを見回し、その顔色は蒼く、目には重い憂いが宿っていた。大きな不安に押しつぶされている人間の目だった。
「お詫びを申し上げます。」と彼は金縁のピンネズを目にかけつつ言った。「ご迷惑をおかけしていなければ良いのですが。嵐や雨の痕跡を、あなたの快適なお部屋に持ち込んでしまったかもしれません。」
「コートと傘をどうぞ。」とホームズが言った。「ここに掛けておけば、すぐに乾くでしょう。南西から来られましたね。」
「はい、ホーシャムからです。」
「その靴のつま先についている粘土と白亜の混じった泥は、まさにあちら特有のものです。」
「相談に参りました。」
「それは簡単に受けられます。」
「助けもお願いしたいのです。」
「それは簡単とはいきません。」
「あなたのことは存じております、ホームズさん。タンクヴィル・クラブのスキャンダルで、プレンダガスト少佐を救われたと聞きました。」
「ああ、もちろん。彼はカードのいかさまの嫌疑をかけられた。」
「何でも解決できると仰っていました。」
「それは言いすぎです。」
「決して負けたことがないと。」
「負けたことは四度あります――三度は人間に、一度は女性に。」
「けれど、成功の数と比べれば微々たるものでしょう?」
「たしかに、たいていは成功しています。」
「ならば、私の件もお願いします。」
「どうぞ、椅子を暖炉のそばに寄せて、事件の詳細をお話しください。」
「単なる事件ではありません。」
「私のもとに持ち込まれるのは、どれもただの事件ではありません。私は最後の審判の場です。」
「ですが、あなたのご経験の中でも、これほど不可解で謎に満ちた出来事をお聞きになったことはないのではないかと思います。」
「興味をそそられます。」とホームズは言った。「最初から要点をお話しください。その後で私が重要と思われる点について質問させていただきます。」
青年は椅子を暖炉に引き寄せ、濡れた足を火にかざした。
「私の名はジョン・オープンショーと申しますが、自分自身のことは、この恐ろしい事件にほとんど関係ないように思えます。これは家系にまつわる出来事でして、話を理解していただくために最初から説明せねばなりません。
「祖父には二人の息子――私の叔父イライアスと、父ジョセフ――がいました。父はコヴェントリーで小さな工場を経営しており、自転車が発明された時期に事業を拡大しました。父は『オープンショーの壊れないタイヤ』の特許を持っており、商売は大いに繁盛して、やがて事業を売却し、十分な財を得て悠々自適の生活に入ったのです。
「叔父イライアスは若い頃アメリカへ渡り、フロリダでプランテーションを経営してかなり成功したと聞いています。戦争の時代にはジャクソン軍、さらにフッド大将の下で戦い、大佐にまで昇進しました。リー将軍が武器を置いた後、叔父は自分のプランテーションに戻り、三、四年そこで過ごしました。1869年か70年ごろ、ヨーロッパに戻り、ホーシャム近郊のサセックスに小さな地所を購入します。アメリカで相当な財産を築いていましたが、黒人に対する反感と、彼らへの参政権拡大を進める共和党政策への嫌悪から、アメリカを離れたのです。叔父は変わり者で激しく怒りっぽく、怒ると口汚く罵る性格でしたが、極端な隠遁志向でもありました。ホーシャムに住んでいた長い年月の間、町に足を踏み入れたことはおそらく一度もなかったでしょう。家の周りの庭や二、三の畑で運動はしていましたが、何週間も部屋から一歩も出ないことさえありました。大量のブランデーを飲み、煙草もヘビースモーカー、交際も一切せず、兄である父ですら近づけませんでした。
「私にはなぜか心を許してくれました。初めて会った時、私は十二歳くらいの子供でした。これは1878年のことで、叔父がイギリスに来て八、九年が経っていました。叔父は父に私を預かりたいと頼み、独特なやり方ですが実に親切にしてくれました。酒を飲んでいない時はバックギャモンやチェッカーでよく遊びましたし、使用人や商人への連絡役も私に任せてくれましたから、十六歳になる頃には家の主人同然でした。家中の鍵を預かり、好きな時に好きな場所へ出入りできました。ただし、彼の私室にだけは決して邪魔をしてはいけないという条件付きでした。ただ一つ例外がありました。屋根裏部屋にある納戸は、いつも鍵がかかっていて、私も誰も入ることを許されませんでした。子供心に好奇心から鍵穴を覗いたこともありましたが、古いトランクや包みが積み重なっているのがちらりと見える程度で、それ以上は分かりませんでした。
「ある日――それは1883年三月のこと――外国の切手が貼られた手紙が大佐の席の前のテーブルに置かれていました。彼が手紙を受け取るのは珍しいことで、請求書はすべて現金払い、友人もいませんでした。『インドからか!』と彼は手紙を取り上げ、『ポンディシェリーの消印だ! 何の用だ?』とつぶやきました。あわてて封を切ると、中から乾燥した五つのオレンジの種が飛び出し、皿の上にパラパラと落ちました。私は思わず笑ってしまいましたが、彼の顔を見てその笑いは凍りつきました。唇は垂れ下がり、目は飛び出さんばかり、肌の色はパテのように青白く、震える手に封筒を握りしめてにらみつけていました。『K.K.K.!』彼は叫び、『神よ、神よ、ついに罪が私を捕らえた!』
「『どうしたんです、叔父さん?』と私は叫びました。
「『死だ』と言い、席を立って部屋に引きこもってしまいました。私は恐怖に震えながらテーブルの封筒を手に取り、内蓋の糊付けのすぐ上に赤インクで大きくKの文字が三度書かれているのを見ました。他には乾燥した五つの種があるだけでした。なぜ叔父はこれほどまでに脅えたのか? 私は朝食の席を離れて階段を上がっていくと、叔父が古びた錆びた鍵(たぶん屋根裏部屋のもの)を片手に、もう片方には小さな真鍮の箱(現金箱のようなもの)を持って降りてくるところに出くわしました。
「『やつらの好きにはさせん、どうしても負けてたまるか』と彼は罵りながら言いました。『メアリーに今日は部屋に火を入れてくれるよう伝えろ。それからフォーダム――ホーシャムの弁護士を呼びにやれ。』
「私は言われた通りにし、弁護士が到着すると二階に呼ばれました。火は勢いよく燃えており、暖炉の中には焼け焦げた紙のふわふわした黒い灰が山のように積もり、そのそばに真鍮の箱が空のまま開いていました。箱の蓋には、今朝封筒で見た三つ並んだKの文字が印刷されているのに気づき、ドキリとしました。
「『ジョン、お前に遺言書の証人になってほしい』と叔父は言いました。『私の財産はすべて、その利点も不利も含めて、兄のお前の父に遺す。いずれお前にも渡ることだろう。もし平和に暮らせるならそれに越したことはない。もし駄目なら、この財産を一番の敵にでも渡してしまえ。こんな両刃の剣を遺すことを心苦しく思うが、どう転ぶかわからん。フォーダムさんが示した場所に署名してくれ。』
「私は指示通り署名し、弁護士はそれを持ち帰りました。この奇妙な出来事は、当然ながら私に強烈な印象を残し、何度も頭の中で思い返してはみましたが、まったく解けるものではありませんでした。しかし、漠然とした不安は拭えず、その感覚も時の経過とともにやや薄らいだものの、生活の平穏を破る事件が起こることもありませんでした。ただ、叔父の様子は明らかに変わりました。以前にも増して酒を飲み、ますます人付き合いを嫌うようになりました。大半の時間を部屋で過ごし、内側から鍵をかけて一人閉じこもっていましたが、時には酔いに任せた発作的な乱行に駆られ、家を飛び出しては、リボルバーを手に庭を駆け回り、『俺は誰も怖くない、人間にも悪魔にもおとなしく飼い慣らされてたまるか!』と叫ぶのです。その熱狂が収まると、今度はドアから飛び込むように戻り、鍵やかんぬきをかけて引きこもるのです。魂の奥底にある恐怖と、もう向き合い切れないかのように。そうした時、寒い日でさえ彼の顔が汗に濡れ、まるで洗面器から上がったばかりのように光っているのを見たこともあります。
「さて、ホームズさん、そろそろ本題に入りますが、あなたのご辛抱を無駄にしないよう結論だけ述べますと、ある晩、彼は再び酔った勢いで外へ飛び出し、そのまま戻ることはありませんでした。捜索に出た私たちは、庭の端の緑藻が浮かぶ浅い池に、彼がうつ伏せで沈んでいるのを見つけました。暴力の痕跡はなく、水深はせいぜい二フィート。奇行が知られていたことから、陪審は自殺と断定しました。しかし、死を極端に恐れていた叔父をよく知る私には、どうにも納得がいきませんでした。ともあれ事件は片づき、父が地所と銀行にある一万四千ポンドあまりの遺産を相続しました。」
「ちょっとお待ちください。」とホームズが口を挟んだ。「あなたの話は、私がこれまで耳にした中でも特に異常なものと予感します。叔父さんが手紙を受け取った日と、いわゆる自殺の日付を教えてください。」
「手紙が届いたのは1883年3月10日。死はその七週間後、5月2日の夜です。」
「ありがとう。では、続けてください。」
「父がホーシャムの屋敷を継いだのを機に、私は父に頼み、これまで固く閉ざされていた屋根裏部屋を念入りに調べてもらったのです。そこで私たちは、真鍮の箱を見つけました。しかし、中身はすでに焼き捨てられた後でした。蓋の内側には紙のラベルが貼られ、『K.K.K.』という三文字が繰り返し記されていました。その下には『手紙、覚書、領収書、記録簿』と。おそらく、これこそオープンショー大佐が焼き捨てた書類の中身だったのでしょう。他には特に見るべきものもなく、屋根裏部屋には叔父のアメリカでの生活を物語る書類や手帳が散乱していました。その一部は南北戦争時代のものから、叔父が軍務を立派に果たし、勇敢な兵士として名を馳せていたことが窺えました。また、南部諸州の再建期にあたる日付のものもあり、それらは主に政治に関する内容で、北部から送り込まれた『カーペットバッガー』と呼ばれる政治家たちに、叔父が強い反感を抱いていたことが見て取れました。
さて、父がホーシャムに居を構えたのは八十四年の初めで、八十五年の一月までは平穏無事な日々が続きました。ところが新年から四日目の朝、朝食の席で父が驚きの声を上げるのを私は耳にしたのです。父は、開封したばかりの封筒を片手に、もう一方の手には五つの乾いたオレンジの種を広げていました。これまで父は、大佐にまつわる話を私の馬鹿げた作り話だと笑い飛ばしていましたが、いざ同じことが我が身に降りかかると、ひどく怯え、うろたえている様子でした。
『ジョン、いったいこれはどういうことだ?』父の声はうわずっていました。
私の心臓は、鉛のようにずしりと重くなった。『K.K.K.です』と私は答えたのです。
父は封筒の中を覗き込みました。『本当だ、まさしくこの頭文字だ。しかし、この上に何と書いてある?』
『書類を日時計の上に置け』。私は父の肩越しに覗き込んで読みました。
『どの書類だ? どの日時計だ?』
『庭の日時計です。他にありません。ですが書類は、きっと焼き捨てられたものでしょう』
『馬鹿馬鹿しい!』父は虚勢を張りました。『ここは文明国だぞ。こんな悪ふざけが通用するはずがない。これはどこから来たんだ?』
『ダンディーからです』私は消印を見て答えました。
『くだらん悪戯だ。私が日時計や書類に何の関係がある? こんなものは無視するに限る』
『警察に相談したほうがいい』私はそう進言しました。
『笑いものになるだけだ。絶対にやらん』
『では、私に相談させてください』
『いや、断じてならん。こんなことで大騒ぎをするのはごめんだ』
父はひどく頑固な人でしたから、何を言っても無駄でした。しかし私の胸は、不吉な予感でいっぱいでした。
手紙が届いて三日後、父は友人のフリーボディ少佐を訪ねるため家を出ました。少佐はポーツダウン・ヒルの砦の一つで指揮官を務めています。私は、父が家を離れることでかえって危険から遠ざかれるような気がして、むしろ胸をなでおろしていたのです。しかし、それは甘い考えでした。父が家を出て二日目、少佐から至急来てほしいとの電報が届いたのです。父が、このあたりに多い深い白亜の穴に落ち、頭蓋骨を砕かれて意識不明で倒れている、と。私は急いで駆けつけましたが、父は意識を取り戻すことなく息を引き取りました。どうやらフェアハムから黄昏時に帰る途中だったようで、土地勘がなく、その白亜の穴には柵もなかったため、陪審は迷うことなく『事故死』の評決を下しました。父の死をめぐる事実をいかに注意深く調べても、殺人の痕跡はどこにも見当たりませんでした。暴行の跡も、誰かの足跡も、強盗の形跡も、見知らぬ者がその道を通ったという証言も、何一つなかったのです。それでも、私の心は少しも休まらず、何か恐ろしい陰謀が父を死に追いやったのだという確信にも似た思いが消えませんでした。
こうして私は、不吉な形で財産を相続することになりました。なぜそれを手放さなかったのかと、あなたもお思いでしょう。ですが、私には、我々の不幸が叔父の過去のある出来事に繋がっているという確信があったのです。だとすれば、どこへ逃げようと危険は変わらないと考えました。
父が亡くなったのは八十五年の一月。それから二年と八ヶ月が過ぎました。その間、私はホーシャムで平穏に暮らし、一族にかけられた呪いも、前の世代で終わったのかもしれないと希望を抱き始めていました。しかし、それはあまりに甘い期待でした。昨日の朝、あの災厄が、父の時とまったく同じ形で、再び私に降りかかってきたのです」
青年はチョッキのポケットからしわくちゃの封筒を取り出すと、テーブルの上に五つの小さな乾いたオレンジの種を振り落とした。
「これがその封筒です」と彼は続けた。「消印はロンドン東地区。中には、父が受け取ったものと同じ言葉が……『K.K.K.』、そして『書類を日時計の上に置け』と」
「それでどうしました?」とホームズが尋ねた。
「何もしていません」
「何も?」
「正直に申し上げますと……」彼は痩せた白い手で顔を覆った。「私は……どうしていいのかわからず、完全に途方に暮れています。まるで蛇に睨まれた兎のように、身動き一つとれないのです。どんな用心も通用しない、抗いようのない悪意に捕らえられている、そんな気がしてなりません」
「いかん!」ホームズは叫んだ。「すぐに行動しなければ命が危うい。救いは行動の中にしかない。絶望している場合ではありませんよ」
「警察には相談しました」
「ほう!」
「ですが、彼らは私の話を半ば笑いながら聞くだけでした。警部は、手紙はすべて悪質な悪戯で、親族の死も単なる事故であり、警告とは無関係だと考えているようです」
ホームズは拳を握りしめ、空中で振り上げた。「信じられん愚かさだ!」
「とはいえ、私の家に警官を一人常駐させてくれることにはなりました」
「その警官は今夜も一緒ですか?」
「いいえ。家で待つように言われています」
ホームズは再び、苛立ちを隠さずに空を打つような仕草をした。
「なぜ私のところへ? いや、なぜもっと早く来なかった?」
「あなたのことは存じませんでした。今日になってようやくプレンダーガスト少佐に相談したところ、あなたを訪ねるよう勧められたのです」
「つまり、手紙を受け取ってから丸二日が過ぎている。本来ならもっと早く手を打つべきだった。他に何か手がかりは?」
「一つだけ」ジョン・オープンショーはそう言うと、上着のポケットを探り、色褪せた青みがかった紙片を取り出してテーブルに広げた。「叔父が書類を燃やした日、灰の中に燃え残った紙切れが青かったのを覚えています。この一枚だけが、叔父の部屋の床に落ちていました。おそらく、他の書類の束から滑り落ち、焼却を免れたのでしょう。種についての記述以外、大した意味はないかもしれませんが、どうやら個人の日記の一ページのようです。筆跡は間違いなく叔父のものです」
ホームズがランプを寄せ、私たちは二人でその紙を覗き込んだ。端が不揃いに破れているところを見ると、帳面から引きちぎられたものらしい。表題には「一八六九年三月」とあり、その下には次のような不可解な記録が記されていた。
四日。ハドソン来る。綱領は従来通り。
七日。マコーリー、パラモア、およびセント・オーガスティンのジョン・スウェインに種を送る。
九日。マコーリー、済む。
十日。ジョン・スウェイン、済む。
十二日。パラモアを訪問。すべて順調。
「ありがとう」ホームズは紙を畳むと、依頼人に返した。「さて、一刻の猶予もない。議論している暇はない。すぐに家に戻って行動するのです」
「どうすれば?」
「やるべきことは一つ。そして、それを今すぐ実行してください。今見せてくれた日記の断片を、あの真鍮の箱に入れなさい。そして、叔父が他の書類はすべて焼き捨て、残っているのはこれだけだと説明する書き付けを添える。その上で、箱を指示通り日時計の上に置く。わかりますか?」
「はい、よくわかりました」
「復讐など今は考えてはいけない。いずれ法が然るべき裁きを下すが、今はまず危険を回避すること。謎を解き、犯人を罰するのは二の次です」
「ありがとうございます」青年は立ち上がり、オーバーコートを羽織った。「あなたのおかげで希望が湧いてきました。必ずご助言通りにします」
「一瞬たりとも油断してはいけない。何よりも身の安全を第一に考えてください。あなたに迫る危険は、極めて重大かつ差し迫っている。どうやって帰りますか?」
「ウォータールー駅から列車で」
「まだ九時前だ。通りは人通りも多いだろうから、無事に着くことを祈ろう。だが、くれぐれも油断は禁物です」
「武器は持っています」
「それはすばらしい。明日から事件に取り掛かります」
「では、ホーシャムでお会いできますね?」
「いや、秘密の根はロンドンにある。私はここで手がかりを探します」
「では、一日か二日のうちに、箱と書類の件をご報告に上がります。すべてご助言通りにいたします」彼は私たちと握手を交わし、去っていった。外では風が唸り、雨が窓ガラスを激しく叩きつけている。この奇怪で荒々しい物語は、嵐に吹き寄せられた海藻のように我々のもとへ舞い込み、そして再び嵐の中へと消えていった。
シャーロック・ホームズはしばらく黙って座り、頭を垂れて暖炉の赤い輝きを見つめていた。やがてパイプに火をつけると、椅子の背に深くもたれかかり、天井に向かって青白い煙の輪をいくつも吐き出した。
「ワトソン」と彼がついに口を開いた。「これまでの事件の中でも、これほど奇怪なものはなかったな」
「『四つの署名』の事件を除けば、な」
「まあ、そうだな。あれは別格か。だが、このジョン・オープンショー君の身に迫る危険は、ショルトー家のもの以上かもしれんぞ」
「しかし君は、その危険の正体について、はっきりした見当がついているのか?」
「その性質については、疑う余地もない」
「では、それは何なんだ? K.K.K.とは何者で、なぜこの不幸な一家をそこまで追い詰めるんだ?」
シャーロック・ホームズは目を閉じ、両肘を椅子の肘掛けに乗せると、指先を合わせた。「理想的な推理家たるもの、一つの事実を完璧に把握すれば、そこに至る一連の出来事も、そこから導かれる結果も、すべて推論できるはずだ。キュヴィエが一本の骨から動物の全体像を正確に描き出せたように、一連の出来事の環の一つを完全に理解した観察者は、その前後のすべてを正確に述べることができる。我々はまだ、理性のみで到達しうる境地を完全には理解していないのだ。多くの人々が五感をもってしても解けなかった問題が、書斎で解決されることもある。だが、その高みに達するには、推理家はあらゆる知識を自在に使いこなせねばならず、それには、見ての通り、あらゆる知識を所有していることが前提となる。現代の教育制度や百科事典をもってしても、それを完璧に成し遂げるのは難しいが、自分の仕事に役立つ知識だけを体系的に身につけるのは不可能ではない。私自身もその努力を続けている。そういえば君はかつて、私の知識の範囲をなかなか的確に分析してくれたことがあったな」
「ああ」私は笑って答えた。「あれは奇妙なリストだったな。哲学、天文学、政治学はゼロ。植物学は斑模様、地質学はロンドンから五十マイル以内の泥の染みには詳しいが、それ以外は素人。化学は風変わり、解剖学は非体系的、そして煽情的な小説と犯罪記録の知識は他に類を見ない。おまけにヴァイオリン奏者、ボクサー、剣士、そしてコカインとタバコによる緩やかな自殺志願者――たしか、そんな分析だった」
ホームズは最後の項目ににやりと笑った。「私の意見は今も当時と変わらんよ。小さな脳の屋根裏には、自分が使う道具だけを揃えておき、残りの雑多なものは図書室という名の物置に放り込んでおけば、必要な時に取り出せる。さて、今回のような事件では、持てる力のすべてを注がねばならん。そこの棚からアメリカ百科事典の『K』の巻を取ってくれないか。ありがとう。では、状況を整理し、推理を組み立てよう。第一に、オープンショー大佐がアメリカを離れたのには、よほど差し迫った理由があったに違いない。あの年齢の男が、長年の習慣をすべて捨て、快適なフロリダの気候を離れて、イギリスの田舎町で隠遁生活を送るなど、普通ではない。イギリスでの極端な引きこもりぶりから見て、彼は誰か、あるいは何かを恐れていたと考えられる。つまり、彼をアメリカから追い立てたのは恐怖心だったと仮定していい。では、その恐怖の対象が何かは、彼とその跡継ぎが受け取った、あの不気味な手紙から推測するしかない。消印に気づいたかね?」
「最初はポンディシェリ、次はダンディー、そして最後はロンドンだったな」
「東ロンドンだ。それで何がわかる?」
「どれも港町だ。差出人は船に乗っていたということか」
「見事だ、ワトソン。手がかりが一つ増えた。差出人は船乗りである可能性が高い。そしてもう一つ。ポンディシェリからの場合、警告から実行まで七週間かかったが、ダンディーでは三、四日だった。ここから何が推測できる?」
「距離が遠ければ、それだけ時間がかかるということか――」
「しかし、手紙も同じ距離を旅する」
「だとすると……いや、よくわからんな」
「一つの仮説として、犯人一味は帆船に乗っていた可能性が高い。任務に取り掛かる前に、例の警告と印を送りつけたのだろう。ダンディーからの時は、警告を送ってすぐに行動に移れた。もしポンディシェリから蒸気船で来ていれば、手紙とほぼ同時に到着したはずだ。だが実際には七週間の間があった。これは、郵便船で送られた手紙が先に着き、犯人たちは帆船でゆっくりと後を追ったからに他ならない」
「なるほど、ありそうなことだ」
「いや、それどころか、ほぼ確実だ。だからこそ、今回の事件の危険がいかに切迫しているかがわかる。今度の手紙はロンドンからだ。つまり、時間の猶予はほとんど期待できない」
「なんてことだ!」私は叫んだ。「この執拗な迫害は、いったい何を意味するんだ?」
「オープンショーが持っていた書類は、その船に乗る連中にとって極めて重要なものなのだろう。しかも、それは一人ではない。複数だ。一人で二人の男を殺し、検死官の陪審をごまかすことなどできん。彼らは複数で、しかも大胆不敵、手段を選ばない連中だ。どんな持ち主だろうと、必ず書類を回収する。とすれば、『K.K.K.』は個人の頭文字ではなく、ある結社の印と見るべきだ」
「だが、どんな結社なんだ?」
「ワトソン、君は――」シャーロック・ホームズは身を乗り出し、声を潜めて言った。「クー・クラックス・クランの名を聞いたことはないか?」
「ないな」
ホームズは膝の上の本のページをめくった。「ここだ」と彼は言い、しばらくしてから続けた。「『クー・クラックス・クラン。ライフルの引き金を引く音に似ていることから、こう名付けられた。この恐るべき秘密結社は、南北戦争後の南部諸州で元南軍兵士たちによって結成され、急速に各地に支部を広げた。特にテネシー州、ルイジアナ州、カロライナ州、ジョージア州、フロリダ州で著名である。その権力は主として政治的な目的、特に黒人有権者の威嚇や、彼らの見解に反対する者たちを殺害したり国外追放したりするために用いられた。彼らの暴挙の多くは、標的となった人物に対して、奇抜だが一般に認識されている形で警告を送ることから始まった――地域によっては樫の葉の枝だったり、他の地域ではメロンの種やオレンジの種だったりした。これを受け取った者は、公然と以前の生き方を捨てるか、国外に逃亡するかのいずれかを選ぶことができた。もしも事態に立ち向かえば、必ず死が訪れたが、それはたいてい奇妙で予想もしない方法だった。この結社の組織はあまりに完璧で、手法も体系化されていたため、記録に残る限り、誰一人として無事に立ち向かえた者も、その暴挙を犯人に結びつけられた事件もほとんどない。数年間、この組織はアメリカ政府や南部の良識ある市民の努力にも関わらず栄え続けた。しかし最終的には、1869年にこの運動は突然崩壊した。ただし、その後も同様の事件が散発的に発生している。』」
「ご覧のとおり」とホームズは本を閉じて言った。「この結社が突如として消滅したのは、オープンショーが彼らの書類とともにアメリカから姿を消した時期と一致している。これは因果関係があったのかもしれない。だからこそ、彼とその家族が今なお執拗な追跡を受けているのも無理はない。この記録や日記には、南部の有力者の名が含まれている恐れがあり、多くの者が、それが回収されるまで安心して眠れないことだろう。」
「では、我々が見たあのページは――」
「ああ、予想どおりの内容だ。確かこう書いてあったはずだ。『A、B、Cに種を送った』――つまり、結社の警告を送ったということだ。その後、AとBは出国、あるいは国外退去した旨の記録が続き、最後にCが訪問されたとある。残念だが、Cには悲惨な結末が待っていたのだろう。さて、ワトソン博士、この暗い事件に光を当てられるかもしれない。今のところ、若いオープンショーにとって唯一の希望は、私が指示したとおりにすることだ。今夜できること、言うべきことはもうない。だからバイオリンを取ってくれ。しばしの間、みじめな天気と人間のさらにみじめな性を忘れることにしよう。」
翌朝には空も晴れ、薄曇りの日差しが大都会を覆う霞のベール越しに静かに射し込んでいた。私が下りていくと、シャーロック・ホームズはすでに朝食をとっていた。
「待たずに始めてしまってすまない」と彼は言った。「今日はオープンショー青年の件で非常に忙しくなりそうだ。」
「どんな手を打つつもりだい?」と私は尋ねた。
「最初の調査の結果次第だな。結局ホーシャムまで行くことになるかもしれない。」
「最初からそこへは行かないのか?」
「いや、まずはロンドン市内で始める。ベルを鳴らしてくれれば、お手伝いがコーヒーを持ってきてくれるよ。」
私は待つ間、テーブルの上にあった新聞を取り上げ、ざっと目を走らせた。すると、ある見出しが目に留まり、私は心が凍る思いをした。
「ホームズ!」私は叫んだ。「遅かった!」
「そうか」と彼はカップを置きながら言った。「やはりそうだったか。どうやられた?」彼は落ち着いて話したが、動揺を隠せない様子が見て取れた。
「オープンショーの名と、『ワーテルロー橋近くの悲劇』という見出しが目に入った。記事を読むと、こうだ。『昨夜九時から十時の間、H管区所属のクック巡査がワーテルロー橋付近で勤務中、助けを呼ぶ声と水音を聞いた。しかし夜は非常に暗く、嵐が激しかったため、通行人の助けもむなしく救助は不可能だった。ただちに警報が発せられ、水上警察の協力で遺体はようやく引き上げられた。身元はポケットにあった封筒からジョン・オープンショーと判明し、ホーシャム近くに居住していたという。彼はワーテルロー駅から最終列車に乗ろうと急ぎ、暗さと慌てていたことで遊覧船用の小さな船着場の端を踏み外したものと推測される。遺体には暴力の跡はなく、不幸な事故であったことは間違いない。この事件を契機に、河川沿いの船着場の状態に当局の注意が集まることを願うものである。』」
しばし、私たちは無言で座っていた。ホームズは今まで見たこともないほど意気消沈し、打ちひしがれていた。
「これは私の誇りを傷つけるよ、ワトソン」と、しばらくして彼は言った。「ささいな感情だろうが、誇りが傷つく。今や、これは私個人の問題だ。神が私に健康を与えてくれるなら、この連中を必ず捕まえてみせる。助けを求めてきた男を、死地へ送り出すことになろうとは――!」彼は椅子から飛び上がり、やつれた頬に赤みを浮かべ、やせ細った長い指を神経質に握ったり開いたりしながら、部屋の中を興奮して歩き回った。
「奴らは狡猾な悪魔だ!」と、ついに彼は叫んだ。「どうやってあんな場所に彼を誘い込んだのか? エンバンクメントは駅への直線ルートじゃないはずだ。橋も、たとえあの夜でも人通りが多すぎて目的に適さなかったのだろう。まあ、ワトソン、最後に勝つのはどちらか、見ていこうじゃないか。私はこれから出かける!」

「警察へ?」
「いや、自分自身が警察だ。私が網を張った後で、やつらを捕らえるのは警察に任せるが、それまでは手は出させない。」
その日は一日中、私は本業に追われていた。ベーカー街に戻ったのは、もう夜遅くだった。だがシャーロック・ホームズはまだ帰っていなかった。彼が戻ってきたのは十時近く、蒼ざめ、やつれた顔で現れた。彼はサイドボードに駆け寄り、パンをちぎるや否や夢中でかじり、水を一気に飲み干した。
「お腹が空いているんだね」と私は言った。
「飢えていた。すっかり忘れていた。朝食以来、何も口にしていない。」
「何も?」
「一口も。考えている暇すらなかった。」
「成果は?」
「上々だ。」
「手がかりを?」
「手の中に収めている。オープンショー青年の仇はすぐに討たれるだろう。さあ、ワトソン、奴ら自身の悪魔的な商標を奴らに突き付けてやろう。これは名案だ!」
「どういうことだい?」
彼は戸棚からオレンジを取り出し、ばらばらに裂いて種を絞り出した。その中から五つを取り、封筒に入れた。封筒のふたの内側には「S. H. for J. O.」と記し、封をして宛名を書いた――「ジェームズ・カルフーン船長宛、バーク号ローン・スター号、サバンナ、ジョージア」。
「これで奴が港に入ったとき、手紙が待っていることになる」と彼はくすくす笑った。「今夜は眠れまい。オープンショーがそうだったように、これは運命の前兆になるだろう。」
「このカルフーン船長とは?」
「連中のリーダーだ。他の者も捕まえるが、まずはこいつからだ。」
「どうやって突き止めたんだ?」
彼はポケットから、日付と名前がびっしり書かれた大きな紙を取り出した。
「今日は一日中」彼は語り始めた。「ロイズ船籍簿や古い新聞を調べて、1883年1月と2月にポンディシェリーに寄港したすべての船の動向を追った。その期間に報告された総トン数の大きな船は三十六隻。その中で、ローン・スター号だけがすぐに目を引いた。出航地はロンドンとなっているが、その名は合衆国の州の一つを思わせる。」
「テキサスか。」
「私も確信はなかったが、アメリカ由来の船だと推測した。」
「それから?」
「ダンディーの記録を調べたところ、1885年1月にバーク号ローン・スター号がそこに寄港していたことがわかり、疑惑は確信に変わった。次に、現在ロンドンに停泊している船を調べた。」
「それで?」
「ローン・スター号は先週ここに到着していた。私はアルバート・ドックまで行ったが、今朝早く満潮に乗って川を下り、サバンナ行きの航海に出たところだった。グレーブゼントに電報を打ち、すでに船が通過したことを知った。風も東風だから、今ごろはグッドウィン沖を抜けてワイト島の近くまで来ているはずだ。」
「これからどうするつもりなんだ?」
「もう手は打ってある。船内で生粋のアメリカ人は、船長と二人の航海士だけ。他の乗組員はフィンランド人とドイツ人だ。しかも昨晩は三人とも外出していたことを、荷積みをしていた作業員から聞いた。船がサバンナに着くころには郵便船がこの手紙を届け、ケーブルでサバンナの警察にも三人が殺人容疑で指名手配されていることが知らされるだろう。」
だがどんなに綿密な人間の計画にも綻びはつきものだ。ジョン・オープンショーの殺人犯たちは、ついぞ自分たちの後を追う者がいることを示すオレンジの種を受け取ることはなかった。その年は分点の嵐がひどく長引いた。我々はサバンナのローン・スター号の消息を長く待ったが、ついぞ何の便りもなかった。やがて、大西洋のはるか沖合で、船の船尾の一部が波間に揺れているのが発見され、「L. S.」の文字が刻まれていた、との報せが届いた。それがローン・スター号の運命について我々が知りうるすべてである。
第六話 唇のねじれた男
アイザ・ホイットニー――故イライアス・ホイットニー博士(セント・ジョージ神学校校長)の弟――はひどい阿片中毒だった。大学時代に何か愚かな気の迷いからこの習慣が始まったと聞いている。デ・クインシーの夢や感覚の描写を読み、同じ体験をしようと煙草にローダナムを浸してみたのがきっかけだったらしい。結果、彼自身も多くの人間と同じく、阿片にはまるのはたやすいが、抜け出すのは難しいことを知った。それ以来、長年にわたり薬物の奴隷となり、友人や親族からは恐れと哀れみの混じったまなざしを向けられる存在となった。今も私の目には、黄色く土気色の顔、重く垂れたまぶた、針のように小さな瞳孔をした彼が椅子に丸くなって座っている、かつては気高かった男の成れの果ての姿が浮かんでくる。
ある夜――1889年6月のことだった――ちょうど人が最初のあくびをし、時計に目をやる頃合いに、玄関のベルが鳴った。私は椅子から身を起こし、妻は手元の刺繍を膝に置き、不満げな顔をした。
「患者さんね」と彼女。「あなた、また出かけなきゃならないわ。」
私はうめき声を上げた。ようやく疲れた一日から帰宅したばかりだったのだ。
ドアの開く音がしばし続き、数語のやり取り、そしてリノリウムの上を急ぐ足音。私たちの部屋のドアが勢いよく開き、黒いベールをかぶった地味な服装の女性が入ってきた。
「夜分に失礼します」と彼女は言いかけたが、突然自制心を失い、駆け寄って妻の首に腕を回し、肩に顔を埋めて泣きじゃくった。「ああ、困っているんです!」と彼女は叫んだ。「どうか助けてほしいんです。」
「まあ」と妻はベールを上げて言った。「ケイト・ホイットニーじゃないの。びっくりしたわ、ケイト! 最初は誰だかわからなかった。」
「どうしていいかわからなくて、まっすぐあなたのところに来たの。」彼女はいつもそうだった。困っている人々は、灯台の光に引き寄せられる鳥のように、妻のもとに集まってくるのだ。
「よく来てくれたわね。まずはワインとお水を飲んで、ここで落ち着いて全部話してちょうだい。ジェームズを寝かせた方がいいかしら?」
「いいえ、いいえ! お医者様の助言も欲しいの。アイザのことなの。もう二日も帰ってこなくて……とても不安で……」
彼女が夫の問題を私たちに相談するのは初めてではなかった。私には医師として、妻には旧友で学友として。私たちはできる限り優しい言葉で彼女をなだめ、慰めた。ご主人の居場所は知っているのか、連れ戻すことはできそうか、と尋ねた。
どうやら可能らしかった。最近、彼が発作を起こすと、町の東の果てにある阿片窟を利用しているという確かな情報があるらしい。これまでの乱行はたいてい一日ですみ、夕方には錯乱状態で帰宅していた。しかし今回は四十八時間も続き、きっと今ごろは港の掃き溜めの中で毒を吸い込むか、酔いから醒めて眠っているかだろう。「バー・オブ・ゴールド」という店、アッパー・スワンダム・レーンにいるはずだとのこと。ただ、どうすればいいのか、こんな場所に若い臆病な女性が入り、あの荒くれ者どもから夫を連れ出せるはずもない、と嘆いていた。
それが事の次第であり、解決策はひとつしかなかった。私が彼女を連れて行ってはどうか? いや、ふと思い直し、そもそも彼女が行く必要はない。私はアイザ・ホイットニーの主治医であり、彼に対して影響力もある。私一人ならうまく対処できるだろう。彼女には、もしその場所に本当にいるなら、二時間以内に馬車で帰宅させると約束した。こうして十分後には、私は温かい居間と肘掛け椅子を後にし、不思議な使命を帯びて東へ馬車を走らせていた。その時は奇妙だと思ったが、それがいかに奇妙な出来事になるかは、その後の成り行きのみが教えてくれた。
だが、冒険の第一段階は思ったほど困難ではなかった。アッパー・スワンダム・レーンは、ロンドン橋の東側、川沿いの高い倉庫街の裏にひっそりと潜む卑しい路地だ。古着屋とジン酒場の間に、洞窟のような真っ暗な入口へと続く急な階段があり、そこにお目当ての阿片窟があった。馬車に待つよう指示し、私は階段を降りた。中央がすり減った階段は酔っ払いの足に何度も踏みならされたものだ。ドアの上にはゆらゆら揺れるオイルランプ、その明かりで錠を見つけ、私は長く低い部屋に入った。そこは茶色い阿片の煙がこもり、移民船の船室のように木の寝台が段々に並んでいる。
薄暗がりの中、奇妙な姿勢で横たわる人々の身体がかすかに見えた。背を丸め、膝を折り、頭をのけぞって顎を上に突き出し、時折こちらをぼんやり見つめる濁った黒い目があった。闇の中に赤い小さな光の輪がちらちらと浮かんだり消えたりする。それは金属パイプの火皿で燃える毒の炎だった。多くは静かに横たわり、一部はぶつぶつ独り言を言い、またある者たちは奇妙に低い単調な声で話し合っていた。会話は断続的に続き、やがてそれぞれ自分の思いに沈んで黙り込み、隣人の言葉など気にも留めない様子だった。奥の方には小さな火鉢があり、そのそばの三本足の丸椅子に、あごを両手に載せて膝に肘をつき、じっと火を見つめる背の高いやせた老人が座っていた。
私が入ると、肌の黄色いマレー人の給仕が急いで近寄り、パイプと薬を勧めて空いた寝台に手招きした。
「ありがとう。用はすぐ済む」と私は言った。「ここに友人のアイザ・ホイットニー氏が来ているはずで、彼と話をしたい。」
右手から動きと呻き声が聞こえ、私は薄暗がりの中にホイットニーの姿を見つけた。彼は青ざめ、やつれ、身なりも乱れ、私をじっと見つめていた。
「なんてこった、ワトソンじゃないか」と彼は言った。ひどい禁断症状で、神経はすっかり参っていた。「なあワトソン、今何時だ?」
「十一時近い。」
「何曜日だ?」
「金曜日、六月十九日だ。」
「なんてことだ! 水曜日だと思っていた。……水曜日だよ。人を驚かせるなよ……」彼は腕に顔をうずめ、高い声で泣き始めた。
「本当に金曜日だ。君の奥さんは二日も君を待っている。恥ずかしくないのか!」
「ああ、その通りだ。でも君が混乱してるんだよ、ワトソン。僕は数時間しかここにいない、パイプ三本、いや四本、いくつだったか……。だがもう帰るよ。ケイトを――かわいそうなケイトを心配させたくない。手を貸してくれ。馬車はあるか?」
「ある。待たせている。」
「それなら帰る。でも勘定を払わないと。いくらか調べてくれ、ワトソン。僕はもう駄目だ、自分では何もできないんだ。」
私は、二列に並んだ寝台の間の狭い通路を歩いていた。薬物のひどい、頭をぼんやりさせる臭気を吸い込まぬよう息を止め、支配人の姿を探して辺りを見回していた。背の高い男が火鉢のそばに座っている横を通り過ぎたとき、不意にスカートを引っ張られる感触を覚え、低い声が囁いた。「そのまま私の前を通り過ぎて、後ろを振り返ってごらんなさい。」その言葉ははっきりと私の耳に届いた。私は足元を見下ろした。それはどう考えても、私の隣に座る老人から発せられたものだった。しかし、老人は今も変わらず、痩せこけ、深い皺が刻まれ、年老いて背を曲げ、アヘンパイプを膝の間にぶら下げて、まるで指から力なく落ちてしまったかのようにぐったりしていた。私は二歩進んでから振り返った。驚きの声を上げるのを必死にこらえた。彼は背を向けて、私以外の誰にも顔が見えないようにしていた。その姿はふっくらとし、皺も消え、うつろだった目には再び生気が宿っていた。そしてそこに暖炉の前で、私の驚きを見てにやりと笑っていたのは、他ならぬシャーロック・ホームズだった。彼は軽く手招きして私を呼び寄せ、そして再び顔を半分だけ他の客に向けると、たちまちまたよぼよぼとした唇のだらりとした老人に戻ってしまった。
「ホームズ!」私は小声で囁いた。「一体こんな所で何をしているんです?」
「声はできるだけ低く」と彼は答えた。「私は聴覚が優れているんだ。もし君が親切にもあの酔っ払いの友人を追い払ってくれるなら、ぜひ少し話をしたい。」
「外に馬車を呼んである。」
「それなら、その馬車で彼を家に帰してくれ。彼はもう何もできそうにないほどぐったりしているし、問題を起こす心配はない。馬車の御者に手紙を託して、君が当分私と行動を共にする旨を奥さんに伝えるといい。君が外で待っていてくれれば、五分で追いつく。」
ホームズの頼みを断るのは難しいものだ。彼の願いはいつも明確で、静かに、しかし圧倒的な自信をもって伝えられるからだ。ウィットニーさえ馬車に乗せてしまえば、私の目的はほとんど果たされたも同然だったし、あとは友である彼と再び奇妙な冒険に巻き込まれること以上に望むものはなかった。数分で私は手紙を書き、ウィットニーの支払いを済ませ、彼を馬車に乗せて闇の中へ送り出した。そして間もなく、よぼよぼとした姿がアヘン窟から現れ、私はシャーロック・ホームズと並んで通りを歩いていた。二つの通りを、彼は背を丸め、足取りもおぼつかない様子で歩いた。だが、辺りを素早く見回したあと、彼は背筋を伸ばし、急に陽気な笑い声を上げた。
「ワトソン君、」と彼は言った。「君はきっと、私が今度はアヘン吸引までコカイン注射やその他の“君が医学的見地から意見をくれた”悪癖リストに加えたと思っているだろう。」
「確かに、君があんな所にいるとは驚いたよ。」
「だが、私のほうこそ、君に会えて更に驚いた。」
「友人を探しに行ったんだ。」
「そして私は、敵を探しに。」
「敵を?」
「ああ。私の天敵……いや、むしろ獲物と言うべきか。要するに、ワトソン君、私は非常に奇妙な事件のただ中にいて、今夜もこれまで何度もそうしてきたように、この酩酊者どもの訳の分からないたわごとから手がかりを得ようと期待していたんだ。もしあの窟で私の正体がばれていたら、命は一時間とももたなかったろう。以前にもあそこを利用したことがあり、あの悪党のラスカー人は私に復讐を誓っているからね。あの建物の裏手、ポールズ・ワーフの角近くには、月夜のない晩に何が通ったか不思議な話が聞けそうな、隠し扉がある。」
「なんだって? まさか遺体でも流したって言うのか?」
「そうだよ、ワトソン。あの窟で殺された哀れな者一人につき千ポンドもらえたら、我々は大金持ちだ。あそこは川沿いで最悪の殺人の罠さ。ネヴィル・セント・クレアも二度と出てこられないかもしれない。しかし、我々の罠も今ここに来ているはずだ。」ホームズは両手の人差し指を歯の間に挟み、鋭い口笛を吹いた。その合図に応えるように遠くから同じく鋭い口笛が響き、その後すぐ車輪の響きと蹄の音が聞こえてきた。
「さあ、ワトソン。」ホームズはそう言って、背の高いドッグカートが闇を抜けて駆け寄ってくるのを見た。側面のランタンから金色の光の帯が道路を照らしている。「一緒に来てくれるね?」
「役に立つのなら。」
「信頼できる相棒はいつだって役に立つし、記録係はなおさらだ。『シーダーズ』の私の部屋は二人部屋だ。」
「『シーダーズ』?」
「ああ。あそこがセント・クレア氏の家だ。私は調査のためそこに滞在している。」
「どこにあるんだ?」
「ケント州リーの近くだ。これから七マイルの道のりだ。」
「だが、私は何も訳が分からないぞ。」
「もちろんだとも。そのうち全部分かる。さあ乗ってくれ。ジョン、君はもういいよ。これで半クラウンだ。明日十一時ごろ私を待っていてくれ。さあ、馬に任せて。じゃあまた!」
ホームズは馬に鞭を入れ、私たちは次々と続く薄暗く人気のない通りを突っ切って進んだ。やがて道幅が広がり、私たちは欄干付きの大きな橋を疾走し、その下には濁った川がゆっくりと流れていた。その向こうには、またもや煉瓦とモルタルの広大な無人の街並みが広がっている。静けさを破るのは警官の重く規則的な足音か、帰り遅れた酔客たちの歌や叫びだけだった。空には鈍色の雲が流れ、隙間からは星がちらほらと瞬いていた。ホームズは黙って運転し、頭を胸に垂れ、沈思黙考の面持ちで、私は隣に座りながら、この新たな探求が彼の力をどれほど酷使させているのかを思い、話しかけて彼の思索を妨げることを躊躇していた。数マイル走り、郊外の住宅地の端に差しかかったところで、彼は身震いし、肩をすくめ、満足げにパイプに火をつけた。
「君は素晴らしい沈黙の美徳を持っているね、ワトソン。」彼は言った。「だからこそ君は最高の相棒だ。本当に、誰かと話せるというのは私にとって貴重なことだよ。というのも、今はあまり良いことを考えていないからね。今晩、あの可愛い奥さんに玄関で何と言おうかと悩んでいたところだ。」
「私は何ひとつ知らされていないだろう。」
「ちょうどリーに着くまでに、事件の事実を話す時間がありそうだ。馬鹿みたいに単純な事件に見えるが、どうも手がかりらしいものが掴めない。糸はたくさんあるはずだが、その端を手にできないんだ。さあ、これから事件の概要をはっきり簡潔に話すから、ワトソン、君なら私には見えない火花が見えるかもしれない。」
「では聞こう。」
「数年前、正確に言うと1884年5月、リーという町にネヴィル・セント・クレアという紳士が引っ越してきた。彼は裕福な様子で、大きな別荘を借り、庭をきれいに整えて、全体として上等な暮らしぶりをしていた。徐々に近隣とも親しくなり、1887年には地元の醸造所の娘と結婚して、今では二人の子供がいる。職業はなく、いくつかの会社の株に興味を持つ程度、朝はたいていロンドン市内へ出かけ、毎晩キャノン・ストリート発5時14分の列車で帰宅していた。セント・クレア氏は現在三十七歳。節度ある性格で、良き夫、愛情深い父親であり、誰からも好かれる男だ。念のため付け加えると、今現在判明している全負債は88ポンド10シリング、資産はキャピタル&カウンティーズ銀行に220ポンドある。金銭の悩みがあったとは思えない。
「先週の月曜日、ネヴィル・セント・クレア氏はいつもより早く街に出かけた。その際、重要な用事が二つあり、息子には積み木のおもちゃを買って帰ると話していた。偶然にも、その日の午前中、夫人にアバディーン海運会社の事務所から電報が届いた。長らく待っていた小包が到着したという知らせだった。ロンドンに詳しければ分かるだろうが、その会社の事務所はフレズノ街、つまり君が私を見つけた今夜のアッパー・スワンダム・レーンの脇道にある。夫人は昼食後、街に出て買い物をすませ、会社の事務所で小包を受け取り、4時35分きっかりに駅へ向かう途中スワンダム・レーンを歩いていた。ここまでは分かるか?」
「とても分かりやすい。」
「思い出してほしいが、月曜日はひどく暑い日で、夫人はその界隈が嫌だったので、タクシーを探しながらゆっくり歩いていた。と、そのとき突然、叫び声のようなものが聞こえ、見上げると、夫が二階の窓から下を見て、自分に向かって手招きしているのが見えたという。窓は開いており、顔はひどく動揺していたと彼女は述べている。夫は両手を必死に振ったかと思うと、何か見えない力で後ろから引き戻されたように、突然窓から消えた。夫人の鋭い観察眼が気づいたのは、夫が出かける時に着ていた暗い色の上着は着ていたものの、襟もネクタイもしていなかった点だった。

「異常を確信した夫人は階段を駆け下りた。その建物こそが今夜私がいたアヘン窟だった。彼女は前室を抜けて階段を上ろうとしたが、例のラスカー人の悪党に阻まれ、さらに助手役のデーン人と共に路上へ押し出されてしまった。疑念と恐怖で取り乱しながら、夫人はスワンダム・レーンを駆け下り、幸運にもフレズノ街でちょうど巡回に出るところの警官と警部に出会った。警部と二名の警官が同行し、店主の抵抗を押し切って、セント・クレア氏が最後に目撃された部屋へと入った。だが、そこには彼の姿はなかった。その階全体にも、部屋に住み着いているらしい不気味な片足の者以外には誰もいなかった。彼もラスカーも、午後の間前室には自分以外入っていないと頑なに主張した。そのあまりの否定ぶりに警部も信じかけたが、その時夫人が机の上の小さな木箱に飛びつき、蓋を開けた。中から子供用の積み木があふれ出た。それは夫が買って帰ると約束していた玩具だった。
「この発見と、片足の男が見せた明らかな動揺により、警部は事態が重大だと認識した。部屋は入念に調べられ、結果はすべて恐ろしい犯罪を示唆していた。前室は簡素な応接間で、奥は裏の波止場に面した小さな寝室になっている。波止場と寝室の窓の間には狭いスリット状の土地があり、干潮時は乾いているが満潮時には1メートル半ほど水没する。寝室の窓は広く、下から開ける様式だ。調べると窓枠に血痕があり、床にもいくつか血の滴が落ちていた。前室のカーテンの陰には、セント・クレア氏の上着以外すべての衣服がまとめて押し込まれていた。靴、靴下、帽子、時計まで揃っていた。衣服には暴力の痕跡はなく、他に彼の痕跡もない。窓以外に出口は見当たらず、しかも窓枠の血痕は、彼が泳いで助かったとは到底思えない。事件当時は満潮で水位も高かったのだ。
「さて、この事件に直接関与していると思しき悪党について。ラスカーは極悪人として知られていたが、夫人の証言によれば、夫が窓から姿を見せた直後に階段下にいたので、せいぜい共犯者どまりだろう。彼は一貫して無実を主張し、下宿人のヒュー・ブーンの行動についても全く知らぬと言い張り、失踪した紳士の衣服の存在についても説明できなかった。
「ラスカー支配人についてはこれで説明した。次はアヘン窟の二階に住む不気味な片足の男で、セント・クレア氏を最後に目撃した人物だ。名はヒュー・ブーン。その醜い顔は、都心に通う誰もが一度は見たことがあるはずだ。彼は職業的な物乞いだが、警察の規制を避けるため、蝋マッチの小商いを装っている。スレッドニードル・ストリートの左側に、少し壁が角張った場所があるが、そこが彼の定位置だ。彼はそこで日々、胡坐をかき、膝にマッチ箱を載せて座っている。見るからに哀れな姿なので、そばの舗道に置いた脂ぎった皮の帽子には、通行人から小銭が絶え間なく落とされる。私はこの男の“職業ぶり”を以前から何度か観察していて、短時間でかなりの金を稼いでいるのに驚いたものだ。その姿は非常に独特で、橙色の髪、醜い傷でゆがんだ唇、いかつい顎、濃い色の鋭い目――どれも彼を物乞いの中で際立たせている。しかも彼は機転も利き、通行人からからかわれても必ず即座に切り返す。さて、この男こそがアヘン窟の下宿人であり、我々の探している紳士を最後に見た人物であると判明したのだ。」
「でも、片足の男が、一人で壮年の男に何ができたんだ?」
「足を引きずってはいるが、それ以外は頑健で力も強いようだ。君も医者として知っているだろうが、一つの肢体が不自由な分、他の部位がことさら発達することもある。」
「続きをどうぞ。」
「夫人は窓辺の血痕を見て気絶し、警官に付き添われて馬車で帰宅した。彼女の立ち会いは調査の役には立たなかったからだ。担当のバートン警部は、現場を入念に検証したが、手がかりになるものは何も見つからなかった。一つの失策は、ブーンを直ちに逮捕しなかったことだ。その数分間に彼はラスカー人と何か話したかもしれない。だがその後ほどなく身柄を拘束され、調べても犯行を示す証拠は出てこなかった。右袖に血痕があったが、彼は薬指の傷からだと主張し、窓にも直前に行ったと説明した。セント・クレア氏を見たことはない、部屋に衣類があった理由も分からないと否定した。夫人が窓で夫を見たと言うのも、気が狂ったか夢でも見たのだろう、と言い張った。彼は大声で抗議しながら警察署へ連行され、警部は引き続き現場に残り、潮が引いたら新たな手がかりが出るかもしれないと期待していた。
実際には、泥の中から現れたのは予想されたもの――つまり死体――ではなかった。だが、セント・クレア氏の上着が、潮の引いた川底から引き上げられたのだ。さて、ワトソン、そのポケットに何が入っていたと思うかね?」
「見当もつかないな」
「いや、君には到底思いつくまい。ポケットというポケットが、ペニーとハーフペニーでずっしりと重かったのだ。ペニーが四百二十一枚、ハーフペニーが二百七十枚。これでは潮に流されなかったのも無理はない。だが人間の身体は話が別だ。波止場と家の間には激しい渦があり、重い上着こそ残ったが、むきだしの身体は川に呑み込まれてしまったのだろう」
「だが、他の衣類は部屋で見つかったんだろう? 上着だけ羽織って川に飛び込むなんてことがあるものか?」
「いや、そうではない。だが、事実はもっともらしく説明できるんだよ。仮にだ、このブーンという男がネヴィル・セント・クレアを窓から突き落としたとしよう。誰の目にも、その瞬間は捉えられなかっただろう。ではその後、男はどうする? 当然、証拠となる衣服を処分せねばと考えるはずだ。彼は上着を掴み、投げ捨てようとして、はたと気づく。これでは水に浮いてしまう、と。彼に時間はない。階下では夫人が無理やり階段を上がろうとする音が聞こえ、ひょっとすると共犯のラスカーから、警官が通りを駆けてくると知らされていたやもしれん。一刻の猶予もない。彼は自らの隠し財産――乞食をして貯め込んだ金の隠し場所へ駆け寄り、手当たり次第に硬貨を掴んでは上着のポケットに詰め込み、重しにした。そうして窓から放り投げ、他の衣類も同じように始末しようとした。だが、まさにその時、階下の足音が間近に迫り、警官が踏み込んでくる寸前、かろうじて窓を閉めるのが精一杯だったというわけだ」
「なるほど、筋は通っているな」
「まあ、他にこれという仮説もない以上、当面はこの線で行くしかないだろう。先ほども言った通り、ブーンは逮捕され警察署へ連行されたが、今のところ彼に不利な証拠は何一つ見つかっていない。長年、職業的な乞食として知られてはいたが、その暮らしぶりはいたって静かで無害なものだったようだ。現状、事態はそこで行き詰まっている。そして解決すべき疑問――ネヴィル・セント・クレアは阿片窟で何をしていたのか、そこで彼の身に何が起きたのか、彼は今どこにいるのか、そしてヒュー・ブーンは彼の失踪にどう関わっているのか――は、依然として暗闇の中だ。これまでの私の経験でも、一見これほど単純でありながら、これほど解きがたい事件はちょっと思い当たらないな」
シャーロック・ホームズがこの奇妙な事件の顛末を語る間、私たちの馬車は大都会の喧騒を抜け、疾走していた。まばらな家並みもやがて後方へ消え去り、道の両側には田舎めいた生け垣が続くばかりとなった。彼が話を終えたのと時を同じくして、私たちは窓にまだ灯のともる二つの村を駆け抜けた。
「ここはリーのはずれだ」と、我が友は言った。「我々は短い間にイングランドの三つの州を越えてきたことになる。ミドルセックスを発ち、サリーの角をかすめ、今はケント州だ。あの木立の中の灯りが見えるかね? あれが“ザ・シーダーズ”だよ。そしてあのランプの傍らでは、間違いなく、我々の馬車の響きに耳を澄ませている人がいるはずだ」
「だが、どうしてベイカー街から指揮を執らないんだ?」と私は尋ねた。
「ここで調べねばならんことが山ほどあるからさ。セント・クレア夫人が親切にも二部屋用意してくれた。君も歓迎されるから心配はいらんよ、ワトソン。ご主人の消息も知れぬまま夫人にお会いするのは気が重いが……おっと、着いたようだ。止まれ、止まれ!」
私たちは広い庭園に囲まれた大きな屋敷の前で馬車を降りた。厩舎から少年が駆け寄って馬の手綱を取る。私はホームズの後に続き、砂利の敷かれた小道を進んだ。玄関に歩み寄ると、扉がさっと内側から開かれ、金色の髪をした小柄な女性が姿を現した。淡いモスリン・ド・ソワのドレスをまとい、首と手首にはふわりとしたピンクのシフォンを飾っている。彼女は光の中に浮かび上がるように、そこに佇んでいた。片手は扉に、もう一方の手は半ば宙に浮き、身を乗り出すようにして、その目は輝き、唇はわずかに開かれている。まさに、問いかけそのものといった風情だった。
「どうでした?」彼女は叫んだ。「どうなの?」そして私たちが二人いるのを見て希望に満ちた声をあげたが、ホームズが首を振って肩をすくめるのを見ると、その声はうめき声に変わった。
「良い知らせは?」
「ありません。」
「悪い知らせも?」
「ないです。」
「それは神様に感謝しなくては。でもどうぞ中へ。今日は一日中お疲れでしょう。」
「こちらは友人のワトソン博士です。これまで何度も大きな助けとなってくれました。幸運にも今回同行できまして、この調査に関わってもらっています。」
「お会いできて本当にうれしいです」と彼女は私の手を温かく握った。「急な出来事で行き届かないことも多いですが、どうかご容赦ください。」
「奥様、お気になさらずに。私は野戦経験もあり、たとえそうでなくとも何の謝罪もいりません。ご主人やホームズのために少しでも力になれるなら幸いです。」
「さて、シャーロック・ホームズさん」と夫人は明るい食堂に案内し、テーブルには冷たい夕食が用意されていた。「率直にお聞きしたいことが二つ三つあります。どうかはっきりお答えください。」
「もちろんです。」
「私の気持ちには配慮しないでください。私は取り乱したり倒れたりはしません。ただ、あなたの本当のご意見を伺いたいのです。」
「どんな点についてですか?」
「心の底ではネヴィルが生きていると思いますか?」
シャーロック・ホームズは困惑した様子だった。「正直に言って!」と彼女は繰り返し、暖炉前の絨毯に立ち、バスケットチェアにもたれるホームズを鋭く見下ろした。
「正直に申しますと、奥様――私はそうは思いません。」
「亡くなっていると?」
「はい。」
「殺されたのですか?」
「そこまでは断言できません。ですが、あるいは……」
「それなら、ホームズさん、私が今日ネヴィルから手紙を受け取ったのは、どう説明します?」
シャーロック・ホームズは電気が走ったように椅子から飛び上がった。
「なんですって!」彼は叫んだ。
「はい、今日です。」彼女は微笑みながら、小さな紙片を掲げた。
「見せていただけますか?」
「どうぞ。」
ホームズは興奮してそれを受け取り、テーブルに広げ、ランプを近くに引き寄せて食い入るように見つめた。私も椅子を離れてその肩越しに覗き込んだ。封筒は粗末なもので、グレイヴズエンドの消印とその日の――正確には前日の日付が押されていた。もう真夜中を過ぎていたからだ。
「雑な筆跡ですね」とホームズがつぶやいた。「奥様、これはご主人の筆跡ではありませんね。」
「ええ、でも中身は間違いありません。」
「宛名を書いた人は住所を確認しに行ったようですね。」
「どうしてわかるんですか?」
「名前の部分だけインクがしっかり黒く乾いていて、残りはグレーがかっています。これは吸い取り紙を使った証拠です。もし一気に書いて吸い取れば黒くなりません。つまり、名前を書いてから住所を書くまで間があった。すなわち、住所を知らずに調べた痕跡です。些細な点ですが、些細なことほど重要なのです。では手紙の中身を……やはり、何か同封されてましたね!」
「ええ、指輪が。この印章指輪です。」
「この筆跡がご主人のものと確信できますか?」
「急いで書いた時の彼の字です。」
「急いで書いた時の?」
「普段とは似ていませんが、よく知っているので間違いありません。」
「『最愛の君、どうか恐れないで。すべてうまくいく。大きな誤解があり、解決には少し時間がかかるだろう。辛抱強く待っていてくれ――ネヴィル』。本の見返しに鉛筆で書かれている。八折り判、水印なし。ふむ! 今日グレイヴズエンドで、指に汚れた男によって投函された。おや、封をしたのは、たぶんタバコを噛んでいた者だな。そして奥様、本当にご主人の筆跡に間違いありませんか?」
「間違いありません。ネヴィルが書いたものです。」
「そして今日、グレイヴズエンドで投函された。さて、セントクレア夫人、雲が少し晴れてきましたが、危険が去ったとは申し上げられません。」
「でも彼は生きているはずです、ホームズさん!」
「もしこれが私たちの目をくらます巧妙な偽造でなければ、ですが。指輪は証拠にはなりません。奪われたものかもしれない。」
「いいえ、違います。本当に彼の字です!」
「よろしい。しかし、月曜日に書かれたものが今日投函された可能性もあります。」
「それはあり得ます。」
「その間に多くのことが起きたかもしれません。」
「いや、そんな気落ちさせないでください、ホームズさん。彼が無事だと私はわかるのです。私たちには強い絆があり、もし彼に不幸があれば私にもわかります。最後に会った日、彼は寝室で指を切りましたが、私は食堂にいながら、何かあったと直感してすぐ駆け上がったのです。そんな小さなことで反応する私が、彼の死を感じ取れぬはずがありません。」
「私も、女性の直感が分析的推理より価値ある場合があると知っています。そしてこの手紙は、あなたの見方が正しいことを強く裏付けています。ただ、もしご主人が生きていて手紙を書けるのなら、なぜあなたのもとに戻らないのでしょう?」
「想像もできません。考えられません。」
「月曜に出かける前、何か言い残していませんか?」
「何も。」
「スワンダム・レーンでご主人を見かけた時は驚きましたか?」
「とても驚きました。」
「窓は開いていましたか?」
「はい。」
「ならば声をかけることもできた?」
「できたはずです。」
「でも、言葉にならない叫びをあげただけ?」
「ええ。」
「助けを求めていたと?」
「はい。手を振っていました。」
「ですが、驚きの叫びだった可能性もあります。予想外にあなたを見て、思わず手を挙げたのかも。」
「あり得ます。」
「誰かに引き戻されたように感じましたか?」
「突然消えましたから。」
「自分から引っ込んだとも考えられる。部屋の他の人は見ませんでしたか?」
「いいえ、でもあの恐ろしい男がいたと自白しましたし、ラスカーは階段の下にいました。」
「なるほど。あなたが見た限り、ご主人は普段の服装でしたか?」
「でも襟とネクタイはしていませんでした。首筋がはっきり見えました。」
「スワンダム・レーンについて何か話したことは?」
「一度も。」
「阿片を吸った様子は?」
「決してありません。」
「ありがとうございました、セントクレア夫人。私が絶対に確かめたかったのはこれらの点です。さて、少し食事をしてから休みましょう。明日はとても忙しくなるかもしれません。」
広く快適なツインベッドの部屋が用意されており、私は冒険の夜の疲れもあってすぐに床についた。しかしシャーロック・ホームズは、解けない問題が頭にあると、何日、時には一週間でも平気で眠らず、事実を並べ替え、あらゆる角度から考察し、真相に到達するか、証拠不十分と納得するまで執念深く考え続ける人だった。今夜も徹夜を覚悟しているのがすぐに分かった。彼は上着とベストを脱ぎ、青い大きなガウンを羽織り、ベッドやソファ、肘掛け椅子から枕やクッションを集めて東洋風の寝台を作り、その上にあぐらをかき、パイプ煙草とマッチ箱を手元に並べた。ランプの淡い光の中、私はホームズが古びたブライヤーパイプをくわえ、鋭い鷲鼻の顔を光に浮かべ、天井の隅をぼんやり見つめている姿を見た。そのまま私は眠りに落ち、ふいに彼の叫び声で目覚めると、もう夏の朝日が部屋に差し込んでいた。パイプはまだ口にあり、煙が立ち上り、部屋は煙草の煙でいっぱいだったが、昨夜見た煙草の山はすっかり消えていた。
「起きたかい、ワトソン?」
「ええ。」
「朝のドライブ、どうだ?」
「もちろん。」
「じゃあ、支度してくれ。まだ誰も起きていないが、厩舎の少年がどこで寝ているか知っているから、すぐに馬車を出せるよ。」そう言って彼はひとりごとのように笑い、目を輝かせ、昨夜の沈みがちな思索家とは別人のようだった。
私は服を着ながら時計を見た。誰も起きていないのも当然だ。まだ四時二十五分だった。ちょうど着替え終わる頃、ホームズが少年が馬をつないでいると伝えに戻ってきた。
「ちょっとした仮説を検証したいんだ」と彼はブーツを履きながら言った。「ワトソン、君は今、ヨーロッパで一番の間抜けを目の前にしていると思ってくれ。チャリングクロスまで蹴飛ばされて当然だ。でも、今やっとこの事件の鍵を手に入れたと思う。」
「どこにあるんだい?」私は笑って尋ねた。
「浴室に」と彼は答えた。「いや、本当だよ」私の疑いの目を見て付け加えた。「さっき行って取ってきた。今このグラッドストン・バッグに入ってる。さあ、行こう。鍵穴に合うかどうか見てみよう。」
私たちはできるだけ静かに階下へ降り、明るい朝日に出た。道には私たちの馬車があり、半分寝ぼけた厩舎の少年が立っていた。私たちは飛び乗り、ロンドン・ロードを疾走した。野菜を載せた荷馬車が数台、都に向かっていたが、両脇の別荘が並ぶ道は夢の中の町のように静まり返っていた。
「これはいくつかの点で奇妙な事件だった」とホームズは馬に鞭を入れながら言った。「私もモグラのように何も見えていなかったが、遅れて賢くなるのも、まったく分からぬよりはましだ。」
町に入ると、早起きの人々が窓から眠たそうに顔を出し始めていた。私たちはウォータールー・ブリッジ・ロードを下り、川を渡り、ウェリントン・ストリートを駆け上がって右折し、ボウ・ストリートに到着した。シャーロック・ホームズは警察内でよく知られており、入り口の二人の警官が敬礼した。一人が馬の頭を押さえ、もう一人が案内してくれた。
「当直は誰だね?」とホームズ。
「ブラッドストリート警部です。」
「ああ、ブラッドストリート。ご機嫌いかが?」大柄でがっしりした警官が、制帽と金ボタンの制服で石畳の廊下を歩いてきた。「ちょっと話があるんだ、ブラッドストリート。」
「どうぞ、ホームズさん。こちらへ。」
部屋は小さな事務室で、机には大きな台帳、壁からは電話が突き出ていた。警部は机に座った。
「ご用件は?」
「ブーンという物乞い――ネヴィル・セントクレア失踪事件で逮捕された男のことで来ました。」
「はい。身柄は拘束中です。」
「ここに?」
「留置場に。」
「おとなしいかね?」
「ええ、特に問題はありません。ただ、ひどく汚い奴です。」
「汚い?」
「ええ、手を洗わせるのも一苦労で、顔は鍛冶屋のように黒い。まあ、事件が片付けばきちんと刑務所風呂に入れてやりますが、あなたが見ても、きっとその必要性を感じるでしょう。」
「ぜひ会いたいですね。」
「そうですか。簡単ですよ。こちらへ。バッグは置いていっても――」
「いや、持っていきます。」
「では、どうぞ。」警部は私たちを廊下へ案内し、格子扉を開け、螺旋階段を下り、両側に扉が並ぶ白塗りの廊下に出た。
「右側三番目です」と警部。「これです!」彼はそっと上部の小窓を開けて中を覗いた。
「眠ってます。よく見えますよ。」
私たちも格子越しに覗いた。囚人はこちらに顔を向けて深い眠りについていた。中背で、みすぼらしい服、裂けたコートから色付きシャツがのぞいている。警部の言う通り、非常に汚れていたが、顔の汚れはその醜悪さを隠せなかった。古傷の太い痕が目から顎まで走り、片方の上唇を引き上げて三本の歯が常にむき出し、赤毛が額と目の上まで低く生えていた。
「見ものだろ?」と警部。
「確かに風呂が必要ですね」とホームズ。「そんな気がして、道具を持参したんです。」そう言ってホームズはグラッドストン・バッグから、私を驚かせるほど巨大なバス・スポンジを取り出した。
「はは! あんたも面白い人だ」と警部は笑った。
「ではご協力いただき、静かに扉を開けていただければ、もう少しまともな姿にしてみせますよ。」
「まあ、断る理由もないでしょう」と警部は言った。「ボウ・ストリートの留置場の面汚しには見えないな」彼はそっと鍵を錠前に差し込むと、私たちは皆、静かに独房に入った。眠っていた男は半身を動かしたが、すぐにまた深い眠りに落ちた。ホームズは水差しに身を屈め、スポンジを湿らせ、それを囚人の顔に勢いよく二度、上下にこすりつけた。
「ご紹介しましょう!」と彼は大声で言った。「ケント州リーのネヴィル・セント・クレア氏です!」
私は生まれてこの方、こんな光景は見たことがなかった。スポンジの下で男の顔の皮膚が、まるで木の皮のように剥がれていった。粗野な茶色の色合いは消え失せ、顔を横切っていたおぞましい傷跡も、ゆがんだ唇による嫌悪を誘うゆがみも、ことごとく消えていた。赤いもつれた髪も、ひと撫でするだけで取れてしまい、そこには、青白く悲しげで品のある顔立ちの、黒髪でなめらかな肌をした男が、ベッドに座り込み、目をこすりながら眠たげに周囲を見回していた。だが、状況を悟るや否や、突然叫び声をあげ、顔を枕にうずめて身を投げ出した。
「なんということだ!」と警部は叫んだ。「本当に、行方不明だった彼だ。写真で見覚えがある」
囚人は、運命を受け入れた男の投げやりな様子で振り返った。「そうだ」と彼は言った。「で、私はいったい何の罪で訴えられているんだ?」
「ネヴィル・セント――いや、そりゃ無理だ。自分を殺害したって訴えられるのは、自殺未遂くらいしかないな」と警部はニヤリと笑った。「まあ、私は警察に二十七年いるが、これはとびきりの珍事だ」
「もし私がネヴィル・セント・クレアなら、当然犯罪は何も起きていない。ゆえに私は不当に拘束されていることになる」
「犯罪ではないが、大きな誤りがあった」とホームズが言った。「奥さんを信じていれば、もっとよかったのに」
「妻のためじゃない、子供たちのためだったんだ……」囚人は呻いた。「神よ、子供たちに父親を恥じさせたくはなかった。なんて露見だ……どうすればいい?」
シャーロック・ホームズは彼の隣に腰を下ろし、やさしく肩を叩いた。
「法廷で真相を明らかにしようとすれば、当然公になるのは避けられない」と彼は言った。「だが逆に、警察当局に対して、あなたに全く嫌疑がないと納得させられれば、この件が新聞沙汰になる理由はないはずだ。ブラッドストリート警部なら、あなたが話すことを記録して上司に提出するだろう。その場合、この事件が法廷に持ち込まれることはないはずだ」
「神のご加護を!」囚人は激情をこめて叫んだ。「私は投獄されるのも、いや、死刑になるのさえも受け入れたろう――だが、家族にこの惨めな秘密が汚点として残るのだけは耐えられなかった。
「あなた方は、私の話を聞く最初の人間です。父はチェスターフィールドの教師で、私は良い教育を受けました。若い頃は各地を旅し、舞台にも立ち、やがてロンドンの夕刊紙で記者になりました。ある日、編集長が都市の物乞いについて記事を連載したいと言い、私は志願しました。そこから私の冒険は始まったのです。実際に物乞いを体験しなければ、記事の根拠となる事実は得られません。役者時代に、私は化粧術を身につけ、楽屋で名を馳せていました。その技術を活用したのです。顔を塗り、みじめさを増すために傷跡をつくり、肌色の絆創膏で片側の唇をねじりあげました。赤毛のかつらと、それらしい身なりをして、街で最も人通りの多い場所に立ち、表向きはマッチ売り、実態は物乞いとして仕事を始めました。七時間ほどそうして、夕方家に帰ると、驚くことに26シリング4ペンスもの収入があったのです。
「私は記事を書き、この件はそれきりと思っていましたが、しばらくして友人のために手形の保証人となり、25ポンドの支払い命令を受けました。金策に困り果てていたとき、ふと閃きました。債権者に二週間の猶予を願い出て、雇い主に休暇をもらい、その間、例の変装で街頭に立ちました。十日で必要な額を稼ぎ、借金を返済できました。
「さて、一週間2ポンドのきつい記者仕事に戻るのは、顔に少しペンキを塗って帽子を地面に置きじっとしているだけで同じ額を一日で稼げると知ってしまった後では、なかなかに酷なことです。誇りと金の葛藤は長く続きましたが、最後には金が勝ち、記者を辞めて、最初に陣取ったあの片隅で日々、みじめな顔で哀れみを誘い、小銭でポケットを膨らませるようになったのです。私の秘密を知っているのは一人だけ。スワンダム・レーンにあった安宿の管理人で、そこから毎朝みすぼらしい物乞いとして現れ、夕方には身なりの良い紳士に変身して帰ることができました。この男――ラスカー人ですが――には部屋代を十分に払っていたので、秘密は守られていました。
「やがてかなりの金が貯まりました。もちろんロンドンのどんな物乞いでも年700ポンド――私の平均収入より少ない――を稼げるわけではありません。化粧の腕と、経験で磨いた機転が、街でもちょっとした有名人にしてくれたのです。一日中、小銭と時折銀貨が途切れなく集まり、2ポンドに届かない日はまずありませんでした。
「裕福になるにつれ野心も膨らみ、郊外に家を買い、誰にも職業を疑われずに結婚もしました。妻は私が街に仕事に行くと思いこんでいましたが、その実態は知る由もありませんでした。
「先週の月曜、仕事を終えて例の阿片窟の上の部屋で着替えていると、窓の外に、なんと妻が立っていて、じっと私を見つめていたのです。私は驚きと恐怖で叫び声をあげ、両腕で顔を隠し、ラスカーの管理人に頼んで誰も部屋に来させないよう懇願しました。下で妻の声がしましたが、階段は登れません。私は急いで服を脱ぎ、物乞いの衣装と化粧を施しました。どんな妻の目でも、この変装は見破れません。だが、部屋を捜索されれば服が証拠になるかもしれないと思い至り、窓を開けて、朝寝室で自分につけた小さな傷を再び開きました。そして、収入を入れた革袋から小銭を移した重い上着をつかみ、窓からテムズ川へ放り投げました。他の服も投げるつもりでしたが、そのとき警官たちが階段を駆け上がり、数分後、私は認めますが、むしろほっとしたのですが、ネヴィル・セント・クレアとしてではなく、彼の殺人犯として逮捕されたのです。
「もう説明することはありません。私はできる限り変装を守り通そうと決めていました。だから顔を汚していたのです。妻がどれほど心配しているかは分かっていたので、警官の目の届かない隙に指輪を外し、ラスカー人に託し、急いで走り書きを添えて、心配する必要はないと伝えました」
「その手紙が届いたのは昨日でした」とホームズが言った。
「なんということだ! 妻はどんな一週間を過ごしたことか!」
「警察はそのラスカー人を見張っていた」とブラッドストリート警部。「まともに手紙を出すのは難しかっただろう。たぶん彼は、常連の船乗りに託し、それが何日か忘れられていたんだろうな」
「まさにその通りだ」とホームズはうなずき、「間違いないだろう。だが、今まで物乞いで訴追されたことは?」
「何度もありますが、私には罰金など痛くもかゆくもありませんでした」
「だが、これで終わりにしなければならない」とブラッドストリート。「警察がこれをもみ消すなら、ヒュー・ブーンの名はもう二度とあってはならん」
「最も厳粛な誓いを立てました」
「それなら、これ以上の措置は取られないだろう。ただし、また見つかったらすべて明るみに出る。ホームズさん、あなたには大いに感謝している。本当にどうやって結論に至るのか知りたいものです」
「今回の推理はね」と私の友人は言った。「クッション五つと刻み煙草一オンスのおかげさ。ワトスン、ベイカー街まで馬車を飛ばせば、ちょうど朝食に間に合うだろう」
第七話 青いガーネットの冒険
クリスマスの二日後、私は友人シャーロック・ホームズを訪ね、新年の挨拶をするつもりでいた。彼は紫色のガウン姿でソファに寝そべり、右手にはパイプラック、手近には明らかに読み込まれた、しわくちゃの朝刊が山積みされていた。ソファのそばには木製の椅子があり、その背もたれの角には、かなりくたびれてひび割れた、みすぼらしいソフト帽が掛けられていた。椅子の座面にはレンズとピンセットが置かれており、この帽子が調査のために掛けられていたことを示していた。
「お仕事中でしたか? ご迷惑だったかな」と私は言った。
「いや、全く。むしろ結果を語れる友がいて嬉しいよ。問題はごく些細なことだ」(彼は古帽子の方を親指で示した)「だが、無視できない興味深い点や教訓もある」
私は肘掛け椅子に腰掛け、パチパチ燃える暖炉の前で手を温めた。外は厳しい霜で窓には氷の結晶がびっしりだった。「どうせこの帽子も、見かけは地味でも、また何か恐ろしい事件のきっかけになるんだろう――謎の手掛かりで、犯罪の解決につながるとでも?」
「いや、いや。犯罪ではない」とシャーロック・ホームズは笑った。「単に、四百万人が数平方マイルにひしめき合えば、どんな奇妙な出来事も起こり得る――そんな人間交錯の中で、犯罪とは無縁だが印象的で奇抜な小事件が持ち込まれることも多い。すでに経験済みだろう?」
「まったくだ。直近六件のうち、三件は法律上の犯罪が全く絡んでいなかった」
「その通りだ。アイリーン・アドラーの書類の件、ミス・メアリー・サザーランドの奇妙な事件、そして先の“ゆがんだ唇の男”の冒険――これも同じく無害な部類だろう。ピーターソンを知っているな、あの案内係だ」
「ああ、知っている」
「この帽子は彼のものだ」
「彼の帽子なのか」
「いや、違う。彼が拾ったのだ。持ち主は不明。これはボロ帽子ではなく、知的な問題として見てほしい。まずどうやってここに来たか。クリスマスの朝、丸々と太ったガチョウと一緒に届いた。今ごろピーターソン宅の暖炉で焼かれていることだろう。事の次第はこうだ。クリスマスの朝四時ごろ、ピーターソンはささやかな宴の帰り道、トッテナム・コート・ロードを歩いていた。前方には、背の高い男性が、やや千鳥足で歩き、肩に白いガチョウを担いでいた。グッジ・ストリートの角で、この男と不良少年の小集団が揉め始めた。不良の一人が男の帽子をはたき落とし、男は防ごうと杖を振り上げ、背後の店の窓ガラスを割ってしまった。ピーターソンは男を助けようと駆け寄ったが、男は窓を割ったことに驚き、制服姿の役人が走ってくるのを見て、ガチョウを捨てて逃げ、小路の迷路に消えた。不良たちもピーターソンの登場で逃げ去り、彼は『戦利品』――このボロ帽子と申し分ないクリスマス用ガチョウ――を手に入れたというわけだ」
「当然、持ち主に返したんだろう?」
「それが問題なのだ。ガチョウの左足には『ヘンリー・ベイカー夫人宛』と書かれたカードが付いていたし、帽子の内側には『H.B.』のイニシャルもある。だが、この街にはベイカーが数千人、ヘンリー・ベイカーも何百人といる。誰に返せばよいか見当がつかない」
「それで、ピーターソンはどうした?」
「帽子とガチョウを私のもとに持ち込んだ。私ならどんな小さな問題でも興味を持つと知っていたからだ。ガチョウは今朝まで預かっていたが、霜にもかかわらず早く食べる方がよさそうだったので、ピーターソンが持ち帰った。私はこのボロ帽子――クリスマスディナーを失った紳士の持ち物――を預かっている」
「広告は出さなかったのか?」
「いや、出していない」
「それでは、持ち主の手掛かりは?」
「私たちが推理できる範囲だけだ」
「帽子から?」
「その通り」
「冗談だろう。こんなボロ帽子から何が分かるんだ?」
「私のレンズだ。やり方は知っているだろう。では君自身、持ち主の人物像をどう推理できるか?」
私はそのくたびれた帽子を手に取り、ややがっかりしながら眺めた。ごく普通の黒い丸型の帽子で、かなり傷んでいた。裏地は赤い絹だったが、かなり変色している。製造元の名はなかったが、「H.B.」のイニシャルが片側に走り書きされていた。帽子止め用の穴がつばに開いていたが、ゴムは失われていた。他はひび割れ、ひどく埃っぽく、数か所染みもあったが、インクを塗って汚れを隠そうとした形跡もあった。
「何もわからないよ」と私は帽子をホームズに返した。
「いや、ワトスン、それで十分だ。君は見ているのに、見たものから推理できていない。推論が慎重すぎるんだ」
「では、その帽子から何が読み取れるのか教えてくれ」
彼は帽子を手に取り、例の内省的な目つきで見つめた。「やや情報量は少ないが、はっきりした推論もあるし、かなり高い確度のものもある。持ち主が非常に知的だったことは明らかだし、三年前までかなり裕福だったが、今は落ちぶれている。先見の明もあったが、今はそれが鈍り、道徳的退廃が見られる。没落と合わせて考えると、たとえば飲酒など悪い習癖が働いているのかもしれない。さらに、明らかに妻にはもう愛されていない」
「ホームズ、それはさすがに……!」
「ただし、ある程度の自尊心は保たれている」と彼は私の抗議を無視して続けた。「座業的で、外出は少なく、すっかり体もなまっている。中年で、霜の混じった髪をここ数日以内に切っており、石灰クリームで髪を整えている。これらは帽子から導き出せる明白な事実だ。さらに言えば、家にはガスが通っていない可能性が高い」
「冗談だろう、ホームズ」
「まったく冗談ではない。今、これだけ伝えても、どうやってたどり着いたか分からないか?」
「正直、ついていけないよ。たとえば、知的だというのはどうやって?」
ホームズは帽子を自分の頭にかぶせてみせた。帽子は深く前にかぶさり、鼻梁まで届いた。「これは容積の問題なんだ。これだけ大きな脳みそには、何かが詰まっているはずさ」
「では、没落したという根拠は?」
「この帽子は三年前のものだ。こういう平らなつばの縁が巻いてあるのはその時期の流行品。そして最高級品だ。リブ絹の帯や立派な裏地を見れば分かる。この男が三年前にこれほど高価な帽子を買えたのに、その後一つも買い換えていないなら、確実に落ちぶれたのだ」
「それは納得できる。でも、先見の明や道徳的退廃というのは?」
シャーロック・ホームズはくつくつと笑った。「これこそ先見の明というやつさ」と言いながら、彼は帽子止めの小さな円盤と輪に指を置いた。「こういうものは帽子と一緒に売られているわけじゃない。持ち主がわざわざ注文して取り付けたのなら、風に飛ばされぬよう用心したということだ。ある程度の先見性があった証拠だよ。だが、ゴムが切れても取り替えずにいるところを見ると、以前より用心深さが薄れているのは明らかだ。これは精神的な衰えのしるしだろう。その一方で、フェルトの汚れをインクで隠そうとした形跡がある。つまり、自尊心を完全に失ったわけでもない」
「君の推理は、確かにもっともらしいな」
「さらにだ。持ち主が中年で、髪は白髪混じり、最近散髪したばかりで、ライムクリームを使っていることも、裏地をよく見ればわかる。ほら、拡大鏡でのぞいてごらん。床屋のハサミで切り揃えられたばかりの毛が何本も付着しているのが見えるだろう。どれも粘り気があって、ライムクリームの匂いがぷんぷんする。この埃は、街路のざらついた灰色の埃じゃない。室内特有の、けば立った茶色い埃だ。つまり、この帽子は大半を室内で壁に掛けて過ごしたということさ。おまけに、内側の湿り気の跡は、持ち主がひどい汗っかきで、健康状態があまり芳しくないことの動かぬ証拠だ」
「しかし奥さんのことはどうなんだ? ――君は、妻に愛想を尽かされたと言ったじゃないか」
「この帽子はもう何週間もブラシをかけられていない。いいかねワトソン、もし君が自分の帽子にこれだけの埃をためたまま外出しようとして、奥方が平気な顔で見送るようなら、私は君が奥方の愛情を失うという不幸に見舞われたのではないかと、本気で心配するだろうよ」
「だが、独り身かもしれないじゃないか」
「いや、違う。彼はあのガチョウを、妻への仲直りのしるしに持ち帰るところだったんだ。鳥の足についていたカードを思い出してみろ」
「君には本当にかなわないな。しかし、どうして彼の家にガスが通っていないとわかったんだ?」
「獣脂の染みが一つか二つなら偶然かもしれない。だが五つもあれば、持ち主が獣脂の蝋燭を日常的に使っているのは間違いない。おそらく、夜に帽子を片手に、もう一方の手に溶けかけた蝋燭を持って階段を上り下りするんだろう。いずれにせよ、ガス灯で獣脂の染みがつくはずがない。どうだ、これで合点がいったかね?」
「いやはや、実に巧妙だ」私は笑って言った。「だが、君自身が言ったように、犯罪があったわけでもなく、ただガチョウが一羽いなくなったというだけの、誰にも害のない話じゃないか。これだけの推理も、骨折り損のくたびれ儲けに思えるがね」
シャーロック・ホームズが何か言い返そうと口を開いた、まさにその時だった。ドアが勢いよく開き、使い走りのペーターソンが部屋に転がり込んできた。その顔は真っ赤に上気し、驚きで目を見開いている。
「ガチョウが、ホームズさん! あのガチョウがです、旦那!」彼は息を切らしながら叫んだ。
「なに? どうしたというんだ? 生き返って台所の窓からでも飛び出したのか?」ホームズはソファから身を起こし、興奮しきった男の顔を覗き込んだ。
「これをご覧ください、旦那! 妻が、ガチョウのそ嚢からこれを見つけたんです!」彼は手を差し出した。その手のひらの真ん中に、小さな豆粒ほどの青い石が、まばゆい光を放っている。その澄みきった輝きは、薄暗い手のくぼみの中で、まるで電光のようにきらめいていた。
シャーロック・ホームズは口笛をひとつ吹くと、さっと身を起こした。「ほう、ペーターソン! こいつはとんだ掘り出し物だ。君は自分が何を拾ったかわかっているのかね?」
「ダイヤモンドですかい? そりゃあ宝石でしょう。ガラスだって粘土みたいに傷つけられますから」
「ただの宝石じゃない。これは《あの》宝石だ」
「まさか、モーカー伯爵夫人の青いカーバンクルじゃないか?」私は思わず叫んだ。
「その通り。大きさも形も広告で見た通りだ。近頃毎日『タイムズ』紙に出ていたからな。これは正真正銘、唯一無二の代物だ。値段などつけようもないが、懸賞金の千ポンドでさえ、市場価格の二十分の一にも満たないだろう」
「せ、千ポンド! なんてこった!」ペーターソンはがくりと椅子に崩れ落ち、我々を代わる代わる見つめた。
「それが懸賞金だ。おまけに、伯爵夫人には個人的な思い入れがあってね。宝石が戻るなら財産の半分でも惜しまないだろうと、もっぱらの噂だ」
「確か、『コスモポリタン・ホテル』での盗難だったな?」と私は口を挟んだ。
「その通り。十二月二十二日、ちょうど五日前のことだ。配管工のジョン・ホーナーという男が、伯爵夫人の宝石箱からこれを盗んだとして告発された。証拠が極めて有力だったため、事件は大陪審に回付されている。ここだったかな、記事があるはずだ」彼はうずたかい新聞の山をかき分け、日付を確かめながら目当ての一枚を探し出すと、それを広げて読み上げ始めた。
「『コスモポリタン・ホテル宝石盗難事件。配管工ジョン・ホーナー(二十六歳)は、今月二十二日、モーカー伯爵夫人の宝石箱より“青いカーバンクル”として知られる至宝を窃取したる廉により、当法廷に召喚された。証人として出廷したホテルの上席アテンダント、ジェームズ・ライダーは、事件当日、ホーナーを伯爵夫人の化粧室に案内し、暖炉の火格子の修理をさせていたと証言。ライダーはしばらくその場にいたが、所用で数分間席を外し、戻ったところ、ホーナーは姿を消し、机はこじ開けられ、中身の抜かれた小さなモロッコ革の宝石箱がその上に放置されていたという。ライダーは直ちに警報を発し、同夜、ホーナーは逮捕されたが、宝石は本人の所持品からも、その部屋からも発見されなかった。伯爵夫人付きのメイド、キャサリン・キューザックは、ライダーの叫び声を聞いて部屋に駆けつけ、現場の状況を追認したと証言。B分署のブラッドストリート警部によれば、ホーナーは逮捕時に激しく抵抗し、自らの無実を強硬に主張したとのこと。被告には窃盗の前科があり、判事は略式裁判を認めず、事件を大陪審に送致することを決定した。ホーナーは審理中に激しい動揺を見せ、ついには気を失って法廷から運び出された』」
「ふむ、これが警察裁判所での顛末か」ホームズは考え込むように呟き、新聞を放り投げた。「さて、我々の課題は、宝石泥棒と、トッテナム・コート・ロードのガチョウのそ嚢とを結びつける、一本の鎖を見つけ出すことだ。わかるかねワトソン、我々のささやかな演繹ごっこが、にわかに重大かつ犯罪的な様相を呈してきた。ここに石がある。石はガチョウから出てきた。ガチョウは、あのくたびれた帽子の持ち主、ヘンリー・ベイカー氏のものだった。ならば、まずベイカー氏を探し出し、彼がこの謎においてどんな役割を演じているのかを突き止める必要がある。手始めに最も簡単な方法――夕刊各紙に広告を出す。それでだめなら、また別の手を考えよう」
「どんな文面にするんだ?」
「鉛筆と紙を。よし――『グッジ・ストリート角にて、ガチョウ一羽と黒のフェルト帽を拾得。心当たりのヘンリー・ベイカー氏は、本日午後六時半、ベイカー街二二一Bまでお越しください』――簡潔明瞭、これでいいだろう」
「ああ、実に結構だ。だが、彼はこれに気づくだろうか?」
「彼は間違いなく新聞に目を通すさ。貧しい者にとって、あの損失は痛手だからな。ガラスを割り、ペーターソンに追いかけられた時は、逃げるのに夢中だったろうが、後になって、みすみす鳥を手放したことを悔やんでいるに違いない。それに、名前を出しておけば、知り合いの誰かが気づいて知らせてくれるはずだ。さあペーターソン、急いで広告代理店へ走り、夕刊各紙にこれを載せてくれたまえ」
「どの新聞に?」
「そうだな……『グローブ』、『スター』、『ペル・メル』、『セント・ジェームズ』、『イブニング・ニュース』、『スタンダード』、『エコー』……その他、思いつく限りの新聞すべてだ」
「承知しました。それで、この石は……?」
「ああ、石は私が預かっておく。ありがとう。それからペーターソン、帰りにガチョウを一羽買ってきてくれ。君が食べてしまった分の代わりを、あの紳士にお渡ししなければならんからな」
ペーターソンが部屋を出ていくと、ホームズは石を指先でつまみ上げ、ランプの光にかざした。「実に美しい。見ろ、ワトソン、この輝きを。こういう代物は、いつだって犯罪の温床となる。すべての名高い宝石がそうだ。いわば悪魔の撒き餌だな。大きく古い宝石には、その一つ一つの面に血塗られた物語が刻まれている。この石はまだ二十年そこそこの若造だが――中国南部の、アモイ川のほとりで見つかったものだ。カーバンクルの特徴をすべて備えながら、色だけが青いという、いわくつきの石さ。だが、この若さにして、すでに不吉な歴史を背負っている。これまでに、二件の殺人と一件の硫酸沙汰、一件の自殺、そして数えきれないほどの強盗事件を引き起こしてきた。こんな可憐な玩具が、人を絞首台や独房へと送り込むとはな。さて、これを金庫にしまい、伯爵夫人に発見の報せをしたためるとしよう」
「ホーナーは無実だと思うか?」
「まだ何とも言えん」
「では、ヘンリー・ベイカー氏の方が、何か関わっていると思うかね?」
「いや、ヘンリー・ベイカー氏は完全に無実だろう。自分が担いでいた鳥が、黄金よりも価値のある代物だとは夢にも思っていまい。広告に返事があり次第、簡単なテストでそれはすぐに証明できる」
「それまでは、何もできないのか?」
「何もな」
「それなら、私は往診に行ってくる。だが、夕方には戻るつもりだ。こんな面白い事件の結末を見逃すわけにはいかないからな」
「ぜひ戻ってきてくれ。七時には夕食にする。ヤマシギがあったはずだ。……そういえば、今度のことを考えると、ハドスン夫人にあの鳥のそ嚢も調べてもらうべきかもしれんな」
私は往診に手間取り、ベイカー街に戻ったのは六時半を少し過ぎた頃だった。家の前には、スコッチ・ボネットをかぶり、顎までボタンをきっちり留めたコートを着た、背の高い男が立っている。玄関の明かりが作る半円の中で、彼は辛抱強く待っていた。私がポーチに足をかけたのと同時にドアが開き、私たちは一緒にホームズの部屋へ通された。
「ヘンリー・ベイカーさんですね」ホームズは立ち上がると、人懐こい笑顔で彼を迎えた。「どうぞ、暖炉のそばへ。ベイカーさん、今夜はひどく冷えますな。どうやらあなたの血行は夏向きのようだ。おやワトソン、ちょうどいいところへ来た。これはあなたの帽子ですね、ベイカーさん?」
「はい、間違いございません。私の帽子です」
男は背が高く、肩幅が広かったが、その肩は丸みを帯びていた。大きな頭に広い額、そして尖った顎髭へと続く顔つきは、知性を感じさせるものだった。しかし、鼻や頬は赤らみ、差し出された手はかすかに震えていて、私はホームズが立てた彼の習慣についての推理を思い出さずにはいられなかった。着古した黒のフロックコートは、ボタンを一番上までしっかりと留め、襟を立てている。袖口からはカフスもシャツも覗かず、むきだしの手首が突き出ていた。彼は言葉をひとつひとつ選ぶように、ゆっくりと、途切れがちに話した。その姿は、不運に見舞われた学者か文士といった風情だった。
「数日間お預かりしておりました。あなたから住所入りの広告でも出るかと思っておりましたが、なぜ出されなかったのか、いまだに腑に落ちないのですが」
ベイカー氏は気まずそうに笑みを漏らした。「近頃は、シリング銀貨一枚も、昔のようにはまいりませんでな。あの騒ぎで、帽子も鳥も、あのならず者どもに持ち去られたものとばかり思い込んでおりました。無駄金をはたいてまで取り戻そうという気にはなれませんでした」
「なるほど、ごもっともです。ところでガチョウですが、我々がやむなく食べてしまいました」
「た、食べてしまったと!」男は椅子から腰を浮かせ、声を上ずらせた。
「ええ。さもなくば、誰の役にも立たずに腐らせてしまうところでしたから。ですが、あちらのサイドボードの上に、代わりの鳥をご用意しました。重さも申し分なく、見たところ、あなたの鳥に劣らぬ上物かと存じますが」
「おお、もちろん、もちろん結構ですとも」ベイカー氏は安堵のため息をついた。
「元の鳥の羽や脚、そ嚢なども残してありますが、もしご入用でしたら――」
男は楽しげに声を立てて笑った。「はは、冒険の記念品にはなるかもしれませんが、我が旧友の〝バラバラ死体〟が、他に何の役に立つものやら。いえ、先生、もしお許しいただけるなら、あちらの立派な新しい鳥の方に、もっぱら関心を向けさせていただきます」
シャーロック・ホームズは私に鋭い視線を投げかけると、かすかに肩をすくめた。
「では、こちらがあなたの帽子と、ガチョウです。ところで、差し支えなければ、もう一羽の方のガチョウはどちらで手に入れられたか、教えていただけませんか? 私は鳥には少々うるさい方でして、あれほど見事に育った鳥は滅多にお目にかかれません」
「もちろんですとも」ベイカー氏は立ち上がり、新しいガチョウを腕に抱えた。「私のような境遇の者が数人おりまして、博物館の近くにある『アルファ・イン』という酒場によく集まるのです――まあ、昼間は博物館の中で過ごしているのですがね。今年、主人のウィンディゲートさんが『ガチョウ・クラブ』なるものを始めまして、毎週数ペンスずつ積み立てると、クリスマスにガチョウが一羽もらえるという仕組みです。私はきちんと支払いを済ませ、後は先生方ご存じの通りというわけです。いやはや、本当にありがとうございました。このスコッチ・ボネットでは、私の歳にも威厳にも、どうにも釣り合いが取れませんので」彼は芝居がかったほど大げさにお辞儀をすると、いそいそと帰っていった。
「さて、ヘンリー・ベイカー氏の件はこれで片付いたな」ホームズはドアが閉まるのを見届けてから言った。「彼がこの一件にまったくの無関係であることは疑いようがない。どうだワトソン、腹は減っているか?」
「いや、それほどでもない」
「ならば夕食は夜食に回すとしよう。さあ、手がかりを追うぞ」
「ぜひとも!」
外は凍てつくような寒さで、我々はオーバーコートを羽織り、マフラーを首に巻きつけた。空には雲ひとつなく、星々が鋭くきらめいている。道行く人々の吐く息は、まるでピストルから放たれた白煙のように宙に広がった。我々の靴音だけがくっきりと響き渡る中、医者の多いウィンポール街、ハーレイ街を抜け、ウィグモア街を経てオックスフォード街へと足を速めた。十五分ほどでブルームズベリーにたどり着き、ホルボーンへと下る角にある「アルファ・イン」という名の小さなパブの前に立った。ホームズはためらうことなく個室バーのドアを押し開けると、赤ら顔に白いエプロンをかけた主人にビールを二杯注文した。
「そちらのビールも、ガチョウと同じくらい上等だといいが」
「うちのガチョウ?」主人は驚いた顔をした。
「いかにも。先ほど、おたくのガチョウ・クラブの会員だというヘンリー・ベイカー氏と話していたところでね」
「ああ、なるほど。ですが旦那、あれはうちで育てたガチョウじゃありませんぜ」
「ほう、ではどこのだ?」
「コヴェント・ガーデンの問屋から、二ダースほど仕入れたんです」
「ほう。心当たりがあるかもしれん。名は?」
「ブレッキンリッジと申しますが」
「ああ、それは知らんな。では、ご主人、商売繁盛を祈るよ。おやすみ」
「さて、お次はブレッキンリッジ氏だ」ホームズは冷たい夜気の中でコートのボタンを留めながら言った。「いいかワトソン、たかが一羽のガチョウという、ありふれた家庭の品物の先に、無実を証明できねば七年の懲役を食らう男の運命がぶら下がっている。我々の調査が、かえって彼の有罪を証明してしまうかもしれん。だが、いずれにせよ、警察が見落とした糸口を、我々は偶然にも手にしたのだ。とことんまで追い詰めようじゃないか。南へ――前進!」
我々はホルボーンを横切り、エンデル・ストリートを下り、入り組んだスラム街を抜けてコヴェント・ガーデン市場へと向かった。ひときわ大きな屋台の一つに「ブレッキンリッジ」の名が掲げられている。競馬の騎手を思わせる、細面できれいに整えられたもみあげの男が、小僧に店のシャッターを下ろさせているところだった。
「こんばんは。ひどい冷え込みですな」とホームズは声をかけた。
問屋はうなずくと、こちらを値踏みするような目を向けた。
「どうやらガチョウは売り切れのようだ」ホームズは空になった大理石の陳列台を指さした。
「明日の朝なら五百羽はご用意できますがね」
「それじゃダメだ。」
「ガス灯の屋台にいくつかありますよ。」
「でも、あなたを勧められたんです。」
「誰に?」
「『アルファ』の店主に。」
「ああ、そうだった。彼には二ダースほど送ったよ。」
「あれは本当に立派な鳥でした。どこで仕入れたんです?」
私がこの質問をすると、売り手は驚くほど激しい怒りをあらわにした。
「ちょっと待てよ、旦那」と彼は頭を傾け、腕を腰に当てて言った。「何を企んでるんだ? はっきり言ってみろ。」
「いや、何も企んじゃいません。ただ、あなたが『アルファ』に卸したガチョウをどこから仕入れたのか知りたいだけです。」
「なら教えないよ。それだけだ!」
「まあ、大したことじゃありませんが、そんな些細なことでなぜそんなに熱くなるのか分かりませんね。」
「熱くなる? 俺がどれだけ面倒をかけられているか分かれば、あんたも熱くなるさ。金を払っていい品を仕入れたら、それで終わりのはずだろうに、『ガチョウはどこだ?』『誰に売った?』『いくらで売る?』と、まるで世界中にガチョウがそれしかいないみたいに騒がれるんだ。」
「私は他の誰とも関係ありませんよ」とホームズは気軽に言った。「もし教えてもらえないなら、賭けはなしというだけです。ただ、私は家禽に関しては自分の意見に自信があるので、私が食べた鳥は田舎育ちだと五ポンド賭けてもいい。」
「だったら、あんたは五ポンド損だよ。あの鳥は都会育ちだ」と売り手が言い放った。
「そんなはずはありません。」
「いや、そうなんだ。」
「信じられませんね。」
「俺ほど家禽を扱ってきた人間が他にいると思うか? 子供のころからずっとだ。『アルファ』に行った鳥は全部都会育ちだ。」
「どうしても信じられませんね。」
「じゃあ賭けるか?」
「正直、あなたのお金をもらうだけになりそうですが、あなたの頑固さに懲りてもらうために一ポンド賭けましょう。」
売り手は渋い笑みを浮かべて言った。「帳簿を持ってきてくれ、ビル。」
小さな少年が薄い冊子と分厚い油染みの帳簿を持ってきて、吊り下げられたランプの下に並べた。
「さて、先生」と売り手は言った。「もうガチョウは売り切れだと思ってたが、この勝負が終わる前に、うちの店にはまだ一羽残ってるってことを見せてやろう。この小さい本が見えるか?」
「ええ。」
「これは俺が仕入れている人たちのリストだ。分かるか? このページには田舎の仕入先が載っていて、名前の後の番号は大きな帳簿のどこに記帳されているかを示してる。さて、この赤インクのページを見ろ。これが町の仕入先のリストだ。三番目の名前を声に出して読んでくれ。」
「オークショット夫人、ブリクストン・ロード117番地――249」とホームズが読んだ。
「その通り。じゃあ帳簿でそのページを開いてみろ。」
ホームズは該当ページをめくった。「ここですね、『オークショット夫人、ブリクストン・ロード117番地、卵および家禽供給業者』。」
「さて、最後の記載は?」
「『12月22日 二十四羽 1羽7シリング6ペンス』。」
「そう、それだ。その下は?」
「『アルファのウィンディゲート氏に1羽12シリングで売却』。」
「これで何か言うことはあるか?」
シャーロック・ホームズはひどく落胆した表情を見せた。ポケットからソブリン金貨を一枚取り出し、カウンターに投げつけると、言葉もなく背を向けた。数歩離れたところで、彼は街灯の下で例の無声で朗らかな笑い声をあげた。
「ひげの形がああで、ポケットから『ピンク新聞』が覗いている男を見たら、賭け話で何でも聞き出せるよ」と彼は言った。「たぶん、もしあの男の前に100ポンドを積んでも、賭けの勝ち負けほど詳細な情報はもらえなかっただろう。さて、ワトソン、いよいよ我々の探索も終わりが近いようだ。残るは、今夜オークショット夫人のもとへ行くべきか、明日にすべきかという一点だけだ。あの無愛想な男の様子からして、我々以外にもこの件を気にしている者がいるのは確かだが、私としては――」
彼の言葉は、さっき立ち去った屋台から突然大きな喧騒が起こったことで遮られた。振り返ると、ネズミのような顔をした小男が、吊り下げランプの黄色い光の輪の中央に立っていた。その背後で、売り手のブレッキンリッジが屋台の戸口を枠にして、縮こまる男に向かって激しく拳を振り上げていた。
「お前とお前のガチョウにはもううんざりだ!」と彼は怒鳴った。「全員まとめて地獄へ行っちまえ! これ以上くだらない話で俺を煩わせたら、犬をけしかけるぞ。オークショット夫人をここに連れてくるなら答えてやるが、お前には関係ないだろう? 俺はお前からガチョウを買ったのか?」
「いや、でもその中の一羽は僕のだったんです」と小男が泣きそうな声を上げた。
「じゃあオークショット夫人に聞け!」
「彼女が君に聞けと言ったんだ。」
「知ったこっちゃない。プロイセン王にでも聞け! もうたくさんだ。消え失せろ!」彼は怒りに任せて前に詰め寄り、質問者は闇の中へと逃げていった。
「これは、ブリクストン・ロードまで行く手間が省けるかもしれない」とホームズがささやいた。「ついて来てくれ。あの男から何か引き出せるか見てみよう。」屋台の周りでたむろする人々の群れをすり抜けて、ホームズはすばやく小男に追いつき、肩にそっと手をかけた。小男は飛び上がり、ガス灯の下で顔から血の気が引いているのが見えた。
「あなたは誰ですか? 何のご用です?」彼は震える声で尋ねた。
「失礼ですが、先ほど売り手の方にされていたご質問を、つい聞き耳を立ててしまいました。お力になれるかもしれません。」
「あなたが? どうしてこの件について何かご存じなんです?」
「私の名はシャーロック・ホームズ。人の知らないことを知るのが私の商売です。」
「でも、これはあなたの知るはずのないことだ!」
「いえ、私はすべて承知しています。あなたはブリクストン・ロードのオークショット夫人が売ったガチョウを探している。そのガチョウはブレッキンリッジという売り手に渡り、さらにアルファのウィンディゲート氏へ、そして彼のクラブのヘンリー・ベーカー氏のもとへ行った。」
「おお、あなたこそ、ずっとお会いしたかった方です!」小男は両手を差し出し、指先を震わせながら叫んだ。「この件にどれだけ熱心なのか、うまく説明できません。」
シャーロック・ホームズは通りかかった四輪馬車を呼び止めた。「それなら、吹きさらしの市場よりも、暖かい部屋で話した方が良さそうですね。ところで、これ以上進む前に、あなたのお名前をうかがっても?」
男は一瞬ためらった。「私の名はジョン・ロビンソンです」と横目で見ながら答えた。
「いやいや、本当のお名前を」とホームズは優しく言った。「偽名ではやりにくいですからね。」
見知らぬ男の白い頬に赤みがさした。「では――」と彼は言った。「本名はジェームズ・ライダーです。」
「まさしく。『コスモポリタン・ホテル』の主任従業員ですね。どうぞ馬車へ。すぐにご希望のすべてをお話しできるでしょう。」
小男は、幸運の直前か破滅の瀬戸際か判然としないまま、半ば怯え、半ば期待に満ちた目で私たちを見比べ、それから馬車に乗り込んだ。三十分後、私たちはベーカー街の応接間に戻っていた。道中、誰も一言も発しなかったが、新たな同乗者の高く細い息遣いと、手を握ったり離したりする様子が、彼の緊張を物語っていた。
「さあ、着きました!」とホームズは明るく言い、部屋へと私たちを導いた。「この寒さには暖炉がうれしいですね。ライダーさん、寒そうだ。バスケットチェアにどうぞ。私はスリッパに履き替えてから、あなたの件を片付けましょう。さて! あのガチョウがどうなったか知りたいと?」
「はい、先生。」
「いや、正確にはあのガチョウではなく、あの一羽ですね。おそらく、あなたがご執心なのは――白くて尾に黒い筋のある鳥。」
ライダーは感情を抑えきれず震えた。「ああ、先生、その鳥がどこへ行ったかご存じなんですか?」
「ここに来ました。」
「ここに?」
「ええ、とても珍しい鳥でしたよ。あなたが興味を持つのも無理はありません。その鳥は死んだ後に卵を産んだんです――それはそれは美しい、小さな青い卵をね。私のコレクションにあります。」
来訪者はよろめいて立ち上がり、右手でマントルピースにしがみついた。ホームズは金庫を開け、青いカーバンクルを取り出した。それは星のように冷たく、輝く多面の光を放った。ライダーは引きつった顔でそれを凝視し、認めるべきか否か迷っているようだった。
「もう終わりだ、ライダー」とホームズは静かに言った。「しっかりしろ、火に倒れ込むぞ! 椅子に戻してやってくれ、ワトソン。彼は犯罪に手を染めるには血の気が足りなすぎる。ブランデーを少し。さあ、少し人間らしい顔つきになったな。なんと小心者だ!」
しばらく彼はよろめいて倒れかけたが、ブランデーで頬に赤みがさし、怯えた目で告発者を見つめて座った。
「私はほとんどすべての手がかりと、必要な証拠を握っている。だから、君が話すことはほとんど残っていない。ただし、残った小さな部分も聞いておこう。君もスッキリするだろう。ライダー、このブルーカーバンクルの噂は聞いていたな?」
「キャサリン・キューザックが教えてくれたんです」と、かすれ声で答えた。
「なるほど――令夫人付きの侍女だな。いやはや、簡単に手に入る巨額の富の誘惑には、君に限らず誰も抗えないものだが、君は手段を選ばなかった。私が見るに、君にはなかなか筋のいい悪党の素質がある。ホーナーという配管工が以前何かに関わったことを知っていて、疑いの目が彼に向けられると踏んだ。そこでどうした? 君と共犯のキューザックが令夫人の部屋でちょっとした作業を作り出し、彼が呼ばれるように仕組んだ。彼が去った後、宝石箱を漁り、騒ぎを起こし、哀れな男を逮捕させた。その後――」
ライダーは突然ラグの上に倒れ込み、相棒の膝にしがみついた。「お願いだ、勘弁してくれ!」と彼は叫んだ。「父や母のことを考えてくれ! 彼らの心が壊れてしまう! 僕は今まで悪事を働いたことはない! もう二度としない、誓うよ。聖書にでも誓う。どうか裁判にかけないでくれ! お願いだ、頼む!」
「椅子に戻れ!」とホームズは厳しく言った。「今は縮こまって必死にすがっているが、何も知らないホーナーが被告席で苦しんだ時、君はこれっぽっちも気にしなかっただろう。」
「逃げます、ホームズさん。国外へ出ます。そうすれば、彼への容疑は消えるでしょう。」
「ふむ、その件は後で話そう。では、次の行動の真相を聞かせてくれ。石はどうやってガチョウに入り、そして市場へ出たのか? 本当のことを話せ。それだけが君の助かる道だ。」
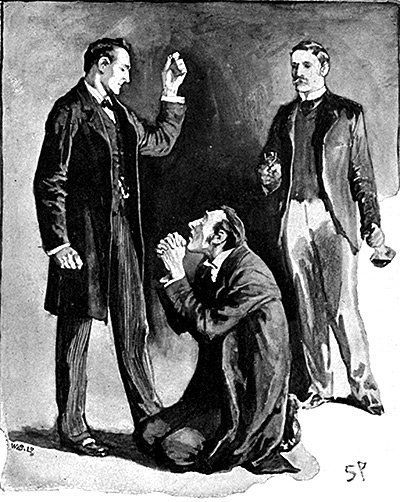
ライダーは乾いた唇を舐めた。「ありのままをお話しします」と彼は言った。「ホーナーが捕まった後、すぐにでも石を持って逃げるのが得策だと思いました。いつ警察が私や部屋を捜索するか分かりませんでしたから。ホテルの中には安全な隠し場所がありませんでした。私は用事があるふりをして外に出て、姉の家を目指しました。姉はオークショットという名前の男と結婚して、ブリクストン・ロードに住み、飼っている鳥を太らせて市場に出していました。道中、出会う人すべてが警官や探偵に見えて、寒い夜なのに汗が滝のように流れていました。姉に会うと、何があったのか、なぜそんなに顔色が悪いのかと聞かれましたが、ホテルで宝石泥棒があったので動揺しているとごまかしました。それから裏庭に出てパイプをふかし、どうすべきか考えました。
昔、モーズリーという悪党になり果てた友人がいまして、最近までペントンヴィル刑務所に入っていました。彼が出所して会った時、盗品のさばき方などを話してくれました。私も彼の弱みを握っていたので、彼に相談しても裏切られる心配はありません。彼の家のあるキルバーンまで石を持って行き、金に換える方法を教えてもらおうと決めました。ところが、ホテルから来るまでの苦しみを思い出し、途中で逮捕されて身体検査を受けでもしたら、チョッキのポケットに石があるのがバレてしまうと不安になりました。そのとき、私は壁にもたれかかり、足元を歩くガチョウたちを眺めていました。すると、史上最高の名探偵でも見抜けない妙案がひらめきました。
数週間前、姉がクリスマスに好きなガチョウを一羽やるよと言っており、姉は約束を守る人なので、私は今そのガチョウをもらい、その鳥の中に石を隠してキルバーンに持って行こうと思ったのです。裏庭の納屋の裏に大きくて白く尾に縞のある鳥を追い込み、首をつかんでくちばしを開け、指が届くところまで石を押し込みました。鳥はごくんと飲み込み、石が食道を通ってそのまま胃袋に入るのを感じました。ところが鳥が暴れ、姉が何事かと出てきました。
『何してるの、ジェム?』と姉が言いました。
『クリスマスにくれるって言ってたから、どれが一番太ってるか確かめてたんだよ』と私は答えました。
『あら、あなたの分は取り分けてあるわよ――"ジェムの鳥"って呼んでるの。あそこにいる大きな白いのよ。全部で26羽、あなたと私たち用に一羽ずつ、あとは二ダースが市場行き。』
『ありがとう、マギー。でも、できればさっき僕が触ってたやつがいいな。』
『もう一羽の方が1.5キロほど重いし、あなたのために特別に太らせたのよ。』
『いや、いいんだ。あのもう一羽、今もらっていくよ。』
『そんなに言うなら、いいわよ。どれがいいの?』
『群れの真ん中にいる、尾に縞のある白い鳥だよ。』
『分かったわ。殺して持っていきなさい。』
言われたとおりにして、その鳥をキルバーンまで運びました。相棒に事情を話すと、彼は大笑いしてナイフで鳥を開きました。私の心は凍り付きました――石の痕跡がなかったのです。とんでもない間違いに気づき、鳥を置いて姉の家へ駆け戻ると、裏庭にはもう鳥が一羽もいませんでした。
『鳥たちはどこだ、マギー?』と私は叫びました。
『業者に出したよ、ジェム。』
『どこの業者?』
『コヴェント・ガーデンのブレッキンリッジさんさ。』
『さっき選んだのと同じ、尾に縞のある鳥がもう一羽いた?』
『いたよ、ジェム。その二羽は見分けがつかなかったから。』
「それで、もちろんすべてが分かったので、私はできる限りの速さでブレキンリッジという男のところへ駆けつけました。しかし彼はその一団をすぐに売り払ってしまい、彼らがどこへ行ったのかについては一言も教えてくれませんでした。あなた方も今夜、彼の態度をお聞きになったでしょう。彼はいつもああやって私に対応するのです。姉は私が気が狂ったのだと思っています。時々、私自身もそうなんじゃないかと感じることがあります。そして今――今や私は、自分の評判と引き換えに富を手に入れようとして、結局一度たりともそれに触れることなく、盗人の烙印を押されたのです。神よ、どうか私をお救いください! どうかお救いください!」彼は両手に顔を埋め、激しくむせび泣いた。
長い沈黙が続き、ただ彼の荒い呼吸と、シャーロック・ホームズが机の端を指先で規則的に叩く音だけが響いていた。やがてホームズは立ち上がり、ドアを大きく開け放った。
「出て行きなさい!」と彼は言った。
「えっ、先生! ああ、神さまがあなたを祝福してくださいますように!」
「もう言葉は必要ない。出て行きなさい!」
それ以上の言葉は不要だった。その男は急ぎ足で階段を駆け下り、ドアをバタンと閉め、そして通りへ向かって足音が響いた。
「結局のところ、ワトソン」とホームズはクレイパイプを取ろうと手を伸ばしながら言った。「私は警察に雇われて彼らの失策を補う立場じゃない。もしホーナーが危険に晒されているのなら話は別だが、この男は証言台に立つことはないし、事件はおそらく立ち消えになるだろう。私は重罪の減刑をしているのかもしれないが、ひょっとすると一つの魂を救っているのかもしれない。この男はもう二度と過ちを犯さないだろう――あまりにもひどく恐怖を覚えたからだ。今投獄したら、人生ずっと牢獄の鳥になってしまう。それに、今は許しの季節だ。偶然、私たちの前に非常に珍妙で気まぐれな問題が現れ、その解決こそが報酬となった。ワトソン、ベルを鳴らしてくれないか。これからもう一つの調査に取りかかろう。今度もまた、鳥が主役になる事件だ。」
第八話 まだらの紐
私がこの八年間、友人シャーロック・ホームズの手法を研究した七十余りの事件の記録をざっと見返してみると、悲劇的なものあり、滑稽なものあり、ただ奇妙なだけのものも数多くあるが、どれ一つとして平凡なものはない。ホームズは金銭欲よりも探偵術への愛に突き動かされて行動していたから、平凡な事件には決して手を出さず、むしろ常識外れや奇想天外なものを好んだのである。そんな中でも、ストーク・モランのロイロット家という名高いサリーの一家にまつわる事件ほど、奇異な特徴を持つものは思い出せない。この事件が起きたのは、私がホームズと付き合い始めて間もない頃、私たちがベイカー街で独身者同士、部屋をシェアしていた時期のことである。この事件をこれまで記録に残すことを控えていたのは、当時、ある淑女と秘密を守る約束を交わしていたからだが、先月、その方が不慮の死を遂げられ、私の誓いはようやく解かれた。事実が今、世に明かされるのも悪くないだろう。というのも、グリムズビー・ロイロット博士の死については、真実よりも遥かに恐ろしい噂が世間に広まっていることを私は知っているからである。
それは1883年の四月初めのことだった。私は朝目覚めると、シャーロック・ホームズが完全に身支度を整え、私のベッドの脇に立っているのを見て驚いた。彼は普段は遅起きだし、暖炉の上の時計はまだ七時十五分を指していたので、私は驚き、やや迷惑そうに彼を見上げたものだ。私は規則正しい生活を送っていたからである。
「起こしてすまない、ワトソン」と彼は言った。「だが今朝は皆そうされている。ハドソン夫人もたたき起こされ、さらに私も起こされ、そして今、君を起こす番というわけだ。」
「何か火事でも?」
「いや、依頼人だ。どうやら若い女性がかなり興奮した様子で訪れ、どうしても私に会いたいと言っている。今、居間で待っているよ。朝のこんな時間に若い女性がロンドン中を歩き回り、眠っている人間を叩き起こすくらいなのだから、きっと非常に切迫した事情があるのだろう。もし面白い事件なら、君も最初から関わりたいはずだ。とにかく君にも機会を与えようと思って声をかけたのさ。」
「ホームズ、何よりも楽しみだよ。」
私は、ホームズの捜査に同行し、その直感のように素早い推理、しかも必ず論理的な根拠に裏付けられた問題解決を間近で見るのがこの上ない喜びだった。私は急いで服を身につけ、数分で支度を終えると、一緒に居間へ向かった。窓際に座っていた黒い服をまとい、厚いベールをかぶった女性が、私たちが入ると立ち上がった。
「おはようございます、奥さま」とホームズは快活に言った。「私の名はシャーロック・ホームズ、こちらは私の親友であり相棒のワトソン博士です。私と同じくご信頼いただいて結構です。おお、ハドソン夫人が火を入れてくれたようで嬉しいですね。どうぞ暖炉のそばへ。今、熱いコーヒーもご用意いたします。お寒いようですが。」
「寒いから震えているのではありません」と女性は低い声で言い、勧められるまま席を移した。
「では、なぜですか?」
「恐怖です、ホームズさん。私は……怖いのです。」彼女はそう言いながらベールを上げた。見ると本当に哀れなほど動揺しており、顔は引きつり青ざめ、落ち着きなく怯えた目はまるで追い詰められた動物のようだった。容貌や体つきは三十歳ほどの女性だが、髪には早くも白髪が混じり、表情は疲れ切っていた。シャーロック・ホームズは、素早く全体を見渡す独特の目つきで彼女を観察した。
「恐れることはありません」と彼は優しく言い、身を乗り出して彼女の前腕を軽く叩いた。「すぐに事態は収まります、疑いませんよ。今朝、列車でお越しになりましたね?」
「もうご存じなのですか?」
「いえ、ただ、左手の手袋のひらに帰りの切符の半券が見えましたので。早く家を出られたはずですが、駅に着く前に重たい道をドッグカートでかなり走ったようですね。」
女性は激しく身を震わせ、当惑した様子でホームズを見つめた。
「何も不思議なことではありませんよ、奥さま」と彼は微笑んだ。「ジャケットの左腕に泥はねが七か所もついています。しかもそれは新しい。こういう泥はねをするのはドッグカート以外になく、しかも御者の左側に座った場合だけです。」
「理由はどうあれ、まったく正しいです」と彼女は言った。「私は六時前に家を出て、二十分でレザーヘッドに着き、最初の列車でウォータールーに来ました。先生、この緊張にはもう耐えられません。このままでは私は気が狂ってしまいそうです。頼れる人は誰もいません――ただ一人だけ私を気にかけてくれる人がいますが、その人もほとんど力になりません。ホームズさん、私はあなたのことを、かつてあなたに大いに助けられたファリンショー夫人から聞きました。彼女からあなたの住所を教えてもらったのです。お願いです、私にもどうかお力をお貸しください。少しでもこの闇に光を当てていただけませんか。今はお礼をする余裕がありませんが、一ヶ月か六週間もすれば私は結婚して自分の収入を自由にできるようになります。そのときには必ずご恩返しをいたします。」
ホームズは机に向かい、鍵を開けて小さな記録帳を取り出し、調べた。
「ファリンショー……ああ、思い出しました。オパールのティアラの件ですね。ワトソン、君の時代より前の事件だ。奥さま、あなたのご友人の件と同様に、誠意を尽くして調査させていただきます。報酬については、私の職業自体が最大の報酬です。ただし、出費が生じた場合はご都合の良いときにご負担くだされば結構です。さあ、私どもが判断材料とできることを、何もかもありのままにお話しください。」
「悲しいかな!」と来訪者は答えた。「私の恐ろしい状況の本質は、恐れがあまりにも漠然としており、また疑いも他人には取るに足らない些細な点ばかりなので、一番頼りにしたいはずの人物でさえ、私の話をただ神経質な女の空想だと思ってしまうことなのです。彼はそう口にはしませんが、私にはその慰めるような口ぶりとそっぽを向く目で分かってしまいます。でもホームズさん、あなたが人の心の奥底に潜む悪まで見抜くと聞きました。私がどんな危険に囲まれているのか、どう歩むべきか、助言いただけるかもしれません。」
「全神経を傾けて伺います、奥さま。」
「私の名前はヘレン・ストーナー。私は義父と暮らしています。彼はイングランド最古のサクソン系の一族、ストーク・モランのロイロット家の生き残りなのです。」
ホームズはうなずいた。「その名はよく知っています」と彼は言った。
「この一族はかつてイングランドでも有数の富豪で、北はバークシャー、西はハンプシャーにまで領地が広がっていました。けれども先代の四人の相続人がいずれも放埒かつ浪費家で、最後はリージェンシーの時代の賭博者によって、家は完全に没落しました。今では数エーカーの土地と、築二百年の屋敷だけが残り、それすら重い抵当に押しつぶされています。前の当主はそこで貧乏貴族としてみじめに暮らしていましたが、一人息子である私の義父は現実に適応しようと親族に頼んで前借りし、医師の資格を得てカルカッタに渡りました。そこで医術と強い個性によって大きな評判を得ましたが、家で盗難事件が続いた際、激昂して現地の執事を撲殺し、死刑寸前までいきました。結局は長期服役となり、その後、陰気な失意の人となって帰国しました。
ロイロット博士がインドにいたとき、私の母、ストーナー夫人と結婚しました。彼女はベンガル砲兵隊のストーナー少将の若い未亡人でした。姉のジュリアと私は双子で、母の再婚時はまだ二歳でした。母はかなりの財産――年間千ポンド以上――を持っており、その全てを、私たちが一緒に住んでいる限りロイロット博士に遺していましたが、もし私たちが結婚した場合には、それぞれに年額の支給がなされる決まりでした。イギリスに戻って間もなく母は亡くなりました――八年前、クルー近くの鉄道事故で命を落としたのです。ロイロット博士はそれを機にロンドンでの開業を諦め、私たちをストーク・モランの古い屋敷に連れて行きました。母の遺産は暮らすには十分で、幸福を妨げるものは何もないように思われました。
けれども、そのころから義父の様子が恐ろしく変わり始めました。それまで近隣の人々も、ロイロット家の帰還を大いに喜び、交流を望んでくれたのですが、彼は家に閉じこもり、出てくることといえば誰かと激しい喧嘩をするためだけという有様でした。凶暴な気質は家系に代々伝わっていたのですが、義父の場合、それが熱帯地方での長い生活でさらに悪化したように思います。恥ずべき乱闘騒ぎが次々と起こり、そのうち二件は警察沙汰にさえなりました。やがて彼は村人たちの恐怖の的となり、彼の姿を見るとみな逃げ出す有様です。なにしろ並外れた怪力で、怒り出すと誰にも止められないのです。
先週も村の鍛冶屋を欄干ごしに小川へ投げ込むという騒ぎを起こし、私が集められるだけのお金を払って、ようやく公然たる問題になるのを防いだほどです。彼には友人が一人もおらず、流浪のジプシーたちだけが唯一の付き合いでした。彼は彼らに、いばらだらけの屋敷跡地で野営することを許し、時には彼らのテントに招かれて何週間も一緒に旅をすることもあります。また、インドの動物に目がなく、知人から送らせては、今もチーターやヒヒを放し飼いにしていて、村人たちは主人と同じくらいそれらを恐れています。
こんな生活では、姉のジュリアも私も、何の楽しみもありませんでした。召使いは誰も長続きせず、私たちが家事全てをこなしていました。姉が亡くなったときはまだ三十歳でしたが、すでに白髪が混じり始めていたのです。」
「では、お姉さまは亡くなられたのですね?」
「はい、二年前に亡くなりました。そして、まさにその死についてご相談したいのです。こんな生活ですから、同世代の人と知り合う機会も全くありませんでしたが、ただ一人、母の妹であるホノリア・ウェストフェイルおばがハローの近くに住んでおり、ときどき短い滞在を許されていました。二年前のクリスマス、ジュリアはおばの家で現役を退いた海兵隊少佐と出会い、婚約しました。義父はその婚約を知っても反対はしませんでしたが、結婚式の日取りが決まり、二週間も経たないうちに、あの恐ろしい事件が起きて、私は唯一の身内を失ったのです。」
シャーロック・ホームズは椅子にもたれて目を閉じ、頭をクッションに沈めていたが、半ばまぶたを開け、依頼人を見やった。
「ぜひ詳細にお話しください」と彼は言った。
「それは簡単です。あの恐ろしい時期の出来事はすべて、私の記憶に焼き付いています。屋敷はご説明した通り非常に古く、今は一つの棟しか使われていません。この棟の寝室はすべて一階にあり、居間は建物中央のブロックにあります。寝室は最初がロイロット博士、次に姉の部屋、そして私の部屋です。部屋同士はつながっていませんが、全て同じ廊下に面して開いています。お分かりいただけますか?」
「よく分かります。」
「三つの部屋の窓はすべて芝生に面しています。あの夜、ロイロット博士は早く自室に入りましたが、寝てはいなかったことは分かっていました。姉は博士が吸う強いインド産の葉巻の匂いに悩まされていたからです。姉は自分の部屋を出て、私の部屋でしばらく近づく結婚の話などをして過ごしました。十一時になって彼女は部屋を出ようとしましたが、ドアのところで立ち止まり、振り返りました。
『ねえヘレン、夜中に誰かが口笛を吹くのを聞いたことはある?』
『いいえ、一度もないわ。』
『まさか、寝ている間に口笛なんて吹けるわけじゃないでしょうね?』
『もちろんそんなことないわ。どうして?』
『というのも、ここ数日、必ず夜中の三時ごろ、低く澄んだ口笛の音が聞こえるの。私は眠りが浅いから、すぐに目が覚めてしまうんだけど、どこからか分からない――隣の部屋か、あるいは芝生からかもと思うの。ただ一応、あなたも何か聞いたことがあるのかなと思って。』
『私は聞いていないわ。きっとあの厄介なジプシーたちのせいじゃない?』
『たぶんね。でも、もし芝生からだったら、あなたも気付かないものかしら。』
『私はあなたよりも眠りが深いから。』
『まあいいけど、大したことじゃないわ。』姉は微笑んでドアを閉め、そのすぐ後、私は彼女が鍵でドアを閉める音を聞きました。」
「なるほど」とホームズは言った。「夜は必ず鍵をかけていたのですか?」
「はい、いつもです。」
「なぜですか?」
「先ほど申しましたように、博士はチーターやヒヒを飼っていましたから。鍵をかけないと安心して眠れませんでした。」
「なるほど、続きをどうぞ。」
承知いたしました。ワトソンの一人称を「私」とし、ホームズへの敬語をなくし、全体を小説らしい文体に修正します。
「あの夜は、どうしても眠ることができませんでした。えもいわれぬ不吉な予感に、心が苛まれていたのです。ご存じの通り、私と姉は双子でして、私たちの魂を結ぶ絆がどれほど繊細なものか、あなたならお分かりでしょう。夜は荒れ狂い、風が唸りをあげて屋敷を揺さぶり、窓という窓に雨が激しく叩きつけていました。その嵐の轟音を切り裂くように、突然、恐怖に引きつった女の絶叫が響き渡ったのです。それが姉の声だと、私にはすぐに分かりました。ベッドから飛び起き、ショールを肩に引っかけると、廊下へと駆け出しました。ドアを開けたその瞬間、以前、姉が話していたあの低い口笛のような音が、微かに聞こえた気がいたしました。そして間髪を入れず、重い金属塊が落ちるような、ガチャンという硬い響き。廊下を走ると、姉の部屋のドアが鍵のかかっていないまま、蝶番できしりながらゆっくりと開いていました。私は恐怖に凍りつき、その闇を見つめました。中から何が現れるのか、息もできずに。やがて、廊下のランプの光の中に、姉がその隙間から姿を現しました。顔は恐怖で蒼白になり、両手を虚空に彷徨わせ、まるで酔漢のように千鳥足でこちらへ……。私は駆け寄り、その体を腕で抱きとめましたが、次の瞬間、姉の膝が崩れ落ち、床にどうと倒れ込みました。姉は激しい苦痛にもだえ、手足は見るもおぞましい痙攣に襲われていました。一瞬、私のことすら分かっていないのかと思いましたが、私が身をかがめると、姉は突然、決して忘れ得ぬ声で叫んだのです――『ああ、神様! ヘレン! ……あれはバンドよ! ……斑点のあるバンドだったの!』。彼女はまだ何かを伝えようと、指で医者の部屋の方角を指し示しましたが、再び激しい痙攣が襲い、言葉を奪いました。私は叫びながら継父を呼びに走り、ちょうど部屋からガウン姿で飛び出してきた彼と廊下で出くわしました。私たちが姉のもとに戻ったときには、彼女はもう意識を失っていました。継父がブランデーを口に流し込み、村から医者を呼んでも、すべては手遅れでした。姉は二度と意識を取り戻すことなく、静かに息を引き取ったのです。これが、私の愛する姉の、あまりにも悲劇的な最期でした」
「お待ちください」とホームズが言った。「その口笛と金属音、本当に確かですか? 誓えますか?」
「それは検死官の尋問でも問われました。確かに聞いたという強い印象はあるのですが、嵐の轟音や古い家のきしみも混じっていましたし、あるいは私の気のせいだったのかもしれません」
「お姉さまは服を着ていましたか?」
「いいえ、寝間着のままでした。右手には焼け焦げたマッチの軸が、左手にはマッチ箱が握られていました」
「なるほど。つまり、何か異変を感じて明かりをつけ、周囲を見渡した、と。それは重要だ。それで、検死官の結論は?」
「調査は非常に丁寧に行われました。というのも、グリムズビー・ロイロット博士の素行は、郡内では以前から有名でしたから。しかし、死因として納得のいくものは何も見つからなかったのです。私の証言通り、ドアは内側から固く施錠され、窓も古い様式の鎧戸と頑丈な鉄格子で毎晩閉ざされていました。壁も念入りに調べられましたが、隙間一つない石造りで、床も同様でした。煙突は広いものの、四本の大きな留め金で塞がれています。ですから、姉があの時、完全に一人きりだったのは間違いないのです。その上、暴行の痕跡も一切ありませんでした」
「毒は?」
「医師たちが調べましたが、何も検出されませんでした」
「では、この気の毒な女性は何で亡くなったと?」
「私は、ただ恐怖と神経性のショックで亡くなったのだと信じています。ですが、一体何が彼女をそこまでおびえさせたのか、見当もつきません」
「当時、植林地にジプシーの一団がいましたか?」
「ええ、ほとんどいつも何人かいます」
「なるほど。それで、あの『バンド――斑点のあるバンド』という言葉については、どうお考えです?」
「時には、ただの譫妄だったのかと思いますし、あるいは何らかの徒党――たとえば、あの植林地のジプシーたちのことだったのかもしれません。彼らの多くが頭に巻いている斑点模様のハンカチが、あの奇妙な言葉を連想させたのではないかと」
ホームズは不満げに首を振った。
「実に厄介な難題だ」と彼は言った。「どうか、話を続けてください」
「あれから二年が経ち、私はこれまで以上に孤独な日々を送ってきました。ですが、ひと月ほど前、長年親しくしていた大切な方が、結婚を申し込んでくださったのです。パーシー・アーミテージという名で、レディング近くのクレイン・ウォーターにお住まいのアーミテージ氏の次男です。継父も特に反対はせず、私たちはこの春に結婚する予定でした。ところが二日前、西棟で修理工事が始まり、私の寝室の壁に穴があけられたため、やむなく姉が亡くなった部屋へ移り、彼女が使っていたベッドで寝ることになったのです。……想像してみてください。昨夜、そのベッドに横たわり、姉の悲劇を思い出していたとき、突然、あの夜と全く同じ低い口笛が、静寂の中に響いてきたのです。私は飛び起きてランプをつけましたが、部屋には何の異変もありませんでした。あまりの恐怖に再び眠りにつくことなどできず、服を着て夜明けを待ちました。夜が明けると同時にそっと家を抜け出し、向かいの『クラウン・イン』で馬車を借りてレザーヘッドまで……そして今朝、あなた方に助言を頂きたく、こうして参ったのです」
「賢明なご判断でした」と我が友は言った。「しかし、まだ話していないことはありませんか?」
「いいえ、すべてお話ししました」
「ミス・ロイロット、いや、違う。あなたは継父をかばっている」
「どういう意味でしょう?」
ホームズは答えず、訪問者の膝に置かれた手の、黒いレースの縁飾りをそっとめくった。白い手首には、四本の指と親指の跡が、五つの青あざとなってくっきりと残っていた。
「ひどい仕打ちを受けているのですね」とホームズが静かに言った。
女性は顔を赤らめ、傷ついた手首を慌てて隠した。「あの人は乱暴な人で……自分の力加減も、分かっていないのだと思います」
長い沈黙が流れた。ホームズは両手に顎を乗せ、パチパチと燃える暖炉の火をじっと見つめていた。
「これは極めて込み入った事件だ」と彼はようやく口を開いた。「結論を出す前に知るべきことが山ほどある。だが、時間は無駄にできない。もし今日、我々がストーク・モランへ伺ったとして、継父に知られずに部屋を見せていただくことは可能ですか?」
「好都合なことに、今朝、町へ大事な用事で出かけると申しておりました。ですから、夕方まで戻らないはずです。家には年老いて少し鈍い家政婦が一人おりますが、私がうまく外へ出すことができます」
「素晴らしい。ワトソン、君も同行に異存はないか?」
「もちろんだとも」
「では、二人で伺おう。あなたはこれからどうなさいます?」
「せっかく町へ来ましたので、いくつか用事を済ませるつもりです。でも正午の列車で戻りますので、お二人がいらっしゃる頃には必ず家におります」
「では、我々は昼過ぎには着くでしょう。私も少し片付けたい用事がある。朝食を召し上がっていかれては?」
「いえ、もう行かなければ。あなたに悩みを打ち明けて、少し胸のつかえがおりましたわ。午後、またお会いできるのを楽しみにしています」
そう言うと、彼女は黒い厚手のベールを顔に下ろし、静かに部屋を後にした。
「さて、ワトソン、君はどう思う?」シャーロック・ホームズが椅子にもたれかかりながら尋ねた。
「なんとも陰惨で、気味の悪い事件だと思う」
「ああ、暗く不吉な話だ」
「だが、もし彼女の言う通り床も壁も確かで、ドアも窓も煙突も完全に閉ざされていたのなら、姉君は間違いなく一人きりで、あの不可解な最期を迎えたことになる」
「では、夜中の口笛や、あの奇妙な最期の言葉はどうなる?」
「さっぱり見当がつかないな」
「夜の口笛、ジプシーの一団がこの老医師と親しいこと、医師が継娘の結婚を阻む強い動機を持つこと、死の間際の『バンド』への言及、それにヘレン・ストーナー嬢が聞いた金属音――あれは窓の鎧戸を固定する鉄棒が元に戻った音かもしれん――これらを総合すると、この線から謎が解けるやもしれん」
「だが、ジプシーたちが一体何をしたというんだ?」
「それは想像がつかない」
「その説にもいくつか難点がありそうだ」
「私も同感だ。だからこそ今日ストーク・モランへ行く。それらの難点が致命的かどうか、この目で確かめるのだ。だが、これは一体……!」
ホームズがそう叫んだのは、突然ドアが激しく開け放たれ、戸口を塞ぐようにひとりの巨漢がぬっと立っていたからだ。その服装は紳士と農夫を混ぜ合わせたような奇妙なもので、黒いシルクハットに長いフロックコート、膝までのゲートルを履き、手には狩猟用の鞭を握っている。背が高すぎて帽子が鴨居に当たりそうで、その肩幅は戸口いっぱいに広がっていた。太陽に焼かれた土色の顔には深いしわが刻まれ、あらゆる邪悪な情念の痕が染みついている。その奥深い、黄ばんだ目と高く痩せた鼻は、獰猛な猛禽類を思わせた。
「貴様がホームズか?」その男が言った。
「いかにも。だが、あなたを存じ上げる覚えはないが」とホームズは静かに応じた。
「私はストーク・モランのグリムズビー・ロイロット博士だ」
「これはどうも」とホームズは穏やかに言った。「どうぞお掛けください」
「その必要はない。俺の継娘がここへ来たな。跡をつけてきた。何を話した?」
「今日は少し冷えますな」とホームズ。
「何を話したと聞いている!」老人は怒りに震え、声を張り上げた。
「しかし、クロッカスの花つきは上々だと聞きましたよ」と我が友は平然と続けた。
「ほう、話をはぐらかす気か!」新たな来訪者は一歩踏み出し、鞭を振り上げた。「知っているぞ、この厄介者め! 噂は聞いている。貴様はホームズ、探偵ごっこにうつつを抜かす邪魔者だ!」
ホームズは微笑んだ。
「ホームズ、でしゃばり屋!」
笑みが深まった。
「ホームズ、スコットランド・ヤードの犬め!」
ホームズは愉快そうに声を立てて笑った。「実に面白いご意見だ」彼は言った。「お帰りの際はドアを閉めていただきたい。隙間風が入るものでね」
「言いたいことがあるから出ていくものか。俺のことに首を突っ込むな。ストーナー嬢がここに来たのは分かっている! 俺に逆らうとどうなるか、思い知らせてやる! 見ろ!」
そう言って、彼は素早く暖炉に歩み寄り、火かき棒を掴むと、その巨大な手でぐにゃりと曲げて見せた。
「俺に手出しをするな」と唸り、曲がった火かき棒を暖炉に投げ捨てると、嵐のように部屋を出て行った。
「なんとも愛想の良い紳士だな」とホームズは笑った。「私の腕はあれほど太くはないが、もし彼が残っていたら、私の握力も捨てたものではないと見せてやれたのに」
そう言って、ホームズは鉄の火かき棒を拾い上げると、一息で元通りまっすぐに伸ばしてみせた。
「警察の役人と間違われるとは面白い! だが、この一件で調査にも俄然張り合いが出てきた。あの小さな友人が、この乱暴者に我々の動きを気取られたせいで、害を被らねばよいがな。さて、ワトソン、朝食を済ませたら、私はドクターズ・コモンズまで歩いて資料を漁ってくるつもりだ」
シャーロック・ホームズが戻ったのは、一時近くだった。手には青い紙片があり、メモと計算が走り書きされていた。
「亡くなった奥さんの遺言書を見てきた」と彼は言った。「その正確な価値を把握するために、遺産となっている投資の現在価格を計算せねばならなかった。奥さんの死当時、総収入は千百ポンド弱だったが、農業価格の下落で今や七百五十ポンドにも満たない。娘たちがそれぞれ結婚すれば、年二百五十ポンドずつ受け取ることになる。つまり、もし二人とも結婚すれば、この男が自由にできる金はごくわずかになり、一人だけでも大きな打撃になるわけだ。彼が結婚を妨げようとする動機は、極めて強い。今朝の調査も無駄ではなかったな。さて、ワトソン、事態は深刻だ。特にあの老人が我々の介入を知った今、ぐずぐずしてはいられん。準備ができたらタクシーを呼んでウォータールーに向かうとしよう。君はリボルバーをポケットに入れていきたまえ。エリーのナンバー2は、火かき棒を曲げるようなお方に対しても充分な説得力がある。必要なのはそれと歯ブラシくらいのものだろう」
ウォータールー駅で運よくレザーヘッド行きの列車に飛び乗り、駅前の宿で馬車を借りると、私たちは四、五マイルほどサリーの美しい田園風景の中を走った。空は快晴で、羊雲が浮かび、木々や生垣には春の息吹が萌え、湿った大地の匂いが立ちこめていた。私には、この甘い春の約束に満ちた空気と、我々がこれから挑む陰惨な事件との間の、痛ましいほどの対比が感じられた。我が友は馬車の前部に座り、腕を組み、帽子を目深にかぶり、顎を胸に埋めて物思いに沈んでいたが、突然、私の肩を叩き、草地の向こうを指さした。
「あれを見てごらん」と彼が言った。
重々しい木立に囲まれた広大な公園が、なだらかな斜面を登っていた。その頂に近い樹々の間から、古い屋敷の灰色の切妻屋根と高い棟が突き出している。
「ストーク・モランだろうか?」と彼が問うた。
「へえ、あれがグリムズビー・ロイロット博士のお屋敷でございます」と御者が答えた。
「工事中のようだな。あそこで間違いない」
「あちらが村でございます」と御者は左手の家並みを指さした。「お屋敷へ行かれるんでしたら、この踏み段を越えて野道を行くほうが近道でさあ。ほら、あそこを歩いていらっしゃるご婦人が見えます」
「おそらくミス・ストーナーだ」とホームズが目を細めた。「そうさせてもらおう」
私たちは馬車を降りて料金を払い、馬車はレザーヘッドへと引き返していった。
「我々は建築家か何かの調査で来たと、そう思わせておく方がいいだろう」とホームズは言いながら踏み段を登った。「余計な噂は避けたいからな。こんにちは、ミス・ストーナー。ご覧の通り、約束通り参りました」
朝の依頼人は、安堵の表情を浮かべて私たちに駆け寄り、熱心に握手した。「本当にお待ちしておりました。すべて順調ですわ。ロイロット博士は町へ出かけており、夕方まで戻らないはずです」
「我々は先ほど、博士と面識を得たところです」とホームズは言い、これまでの経緯を簡潔に説明した。ミス・ストーナーは顔を蒼白にして聞き入った。
「まあ、やはり追ってきていたのですね」
「そのようです」
「あの人はとても狡猾で、いつどこで見張られているか分かったものではありません。お戻りになったら、何と言えば……」
「彼もまた警戒すべきだろう。自分より狡猾な誰かが後をつけていることに、やがて気付くかもしれない。今夜は絶対に、彼から身を守る手筈を整えてください。もし乱暴なことがあれば、すぐさまハロウにお住まいの伯母さまの家へ避難するのです。さて、時間を有効に使いたい。すぐに問題の部屋へ案内していただこう」
屋敷は灰色の苔むした石でできており、中央部分が高く、両側に曲線を描く二つの翼棟が――まるで蟹の鉗のように――突き出ていた。片方の翼棟は窓が壊れて木板で塞がれ、屋根も一部が崩れ落ち、荒廃の色を濃くしている。中央部分もさして手入れが行き届いているとは言えなかったが、右側の翼棟だけは比較的新しく、窓のブラインドや煙突から立ち上る青い煙が、家族の居住区であることを示していた。その端の壁には足場が組まれ、石壁が壊されていたが、作業員の姿はなかった。ホームズは手入れの悪い芝生をゆっくりと歩きながら、窓の外側を念入りに調べていた。
「こちらが以前あなたが寝ていた部屋、その隣が姉君の部屋、そしてこの本館に隣接するのがロイロット博士の部屋、ということで間違いないですね?」
「その通りです。そして今、私が寝ているのは真ん中の部屋、姉が使っていた部屋でございます」
はい、承知いたしました。ご指定の条件に基づき、原文を小説風の文体に修正します。
「では、改修が終わるまで、ということですね。ですが、あの端の壁には、特に修理が必要なようには見えませんでしたが」
「ええ、必要ありませんわ。あれは、私をあの部屋から追い出すための口実に過ぎないのだと思います」
「ほう。それは実に示唆に富んでいますな。さて、この狭い棟の反対側には、三つの部屋に繋がる廊下があると。そこには窓が?」
「はい。でも、とても小さな窓ですわ。人が通り抜けられるような大きさでは到底ありません」
「そしてお二人とも、夜は部屋のドアに鍵を掛けておられた。となれば、そちら側から侵入される心配はない。よろしい、では今一度お部屋へお戻りになり、雨戸にしっかりとかんぬきを掛けていただけますかな」
ミス・ストーナーがその通りにすると、ホームズは開け放たれた窓から身を乗り出し、念入りに調べ始めた。あらゆる手段で雨戸をこじ開けようと試みたが、びくともしない。ナイフを差し込み、かんぬきをこじ上げられるほどの隙間さえなかった。次に虫眼鏡を取り出し、蝶番を調べたが、それらは分厚い鉄製で、頑丈な石壁にがっしりと打ち込まれている。
「ふむ……」と、ホームズは困惑したように顎を撫でた。「私の推理には、いくつか欠陥があるらしい。このかんぬきが掛かっていれば、誰もここを通ることはできん。まあ、中から何か分かるかもしれん」
小さな脇戸から白塗りの廊下へ出ると、三つの寝室がそこから続いていた。ホームズは三番目の部屋の調査は不要だと言い、我々はすぐにミス・ストーナーが今使っている部屋――そして彼女の姉が命を落とした、あの部屋へと向かった。 そこは、古い田舎屋敷にありがちな、低い天井と大きな暖炉のある、陰鬱なこぢんまりとした部屋だった。隅には茶色のチェスト、もう一方の隅には白いカバーの掛かった細長いベッド、窓の左手には化粧台。他には小さな籐椅子が二つと、中央にウィルトン織のカーペットが一枚敷かれているだけだ。床板や壁の羽目板は、虫食いだらけの古いオーク材で、その色褪せた様子から、この館が建てられた当時のものかと思われた。 ホームズは椅子を一つ隅に寄せると静かに腰掛け、部屋の隅から隅まで、その鋭い視線を走らせ、微かな手がかりも見逃すまいと黙って観察を続けた。
「あのベルはどこに繋がっていますか?」やがてホームズが、ベッドの脇に垂れ下がる太いベル紐を指して尋ねた。その房飾りは、枕の上にまで届いている。
「家政婦の部屋に繋がっていますわ」
「他の調度に比べて、ずいぶん新しいように見えますが」
「はい。二年ほど前に取り付けられたものです」
「お姉さまが、お望みになったので?」
「いいえ。姉があれを使ったのを聞いたことがありません。私達は、用があれば自分で行っていましたから」
「なるほど。では、これほど立派なベル紐を取り付ける必要はなかったはずですな。……失礼、少し床を調べさせてください」 彼は虫眼鏡を手に床に這いつくばると、床板の隙間を丹念に調べ始めた。次に壁の羽目板も同じように調べ、最後にベッドのそばへ行くと、しばらくベッドそのものと壁を睨むように眺めていた。やがて、彼はベル紐を手に取り、ぐいと強く引いた。
「ふん。これは見せかけだ」と彼が言った。
「鳴らないのですか?」
「ええ、針金にすら繋がっていない。これは興味深い。ご覧の通り、これは換気口のすぐ上にあるフックに留められているだけです」
「まあ、なんておかしな! 今まで気が付きませんでしたわ」
「実に奇妙だ」ホームズはロープを弄びながら呟いた。「この部屋には、いくつか異様な点がある。例えば、一体どんな建築家が、部屋の外ではなく隣室に通じる換気口など作るというのでしょう」
「それも、ごく最近に作られたものですわ」とミス・ストーナーが言った。
「ベル紐と同じ時期に?」
「はい。その頃に、いくつか小さな改装がありましたので」
「それは随分と興味深い改装ですな。偽のベル紐に、換気しない換気口。……ミス・ストーナー、よろしければ、次は隣のお部屋を拝見したい」
グリムズビー・ロイロット博士の部屋は、彼の継娘の部屋よりは広かったが、殺風景なほどに家具は少なく、主の奇矯な性格を映しているかのようだった。キャンプ用のベッド、専門書で埋まった小さな本棚、肘掛け椅子、簡素な木椅子、丸テーブル、そして大きな鉄製の金庫が、主な調度品のすべてだった。ホームズは部屋をゆっくりと歩き回り、一つ一つを熱心に調べている。
「この中身は?」と、彼は金庫を叩いて尋ねた。
「義父の仕事の書類ですわ」
「なるほど。中をご覧になったことは?」
「一度だけ、何年も前に。書類がぎっしり詰まっていたのを覚えています」
「例えば、この中に猫が入っている、などということは?」
「いいえ! まさか、そんな馬鹿なことを!」
「では、これは何でしょうな?」そう言って、彼は金庫の上に置かれていたミルクの小皿を手に取った。
「猫はいません。でも、チーターとヒヒがおりますわ」
「ああ、そうでしたな。チーターは大きな猫科の動物ですが、このミルク皿一杯では足りないでしょう。さて、もう一つだけ、確かめておきたいことがある」 彼は木椅子の前に屈み込むと、その座面をじっくりと調べ始めた。
「ありがとう。もう結構です」彼は立ち上がると、虫眼鏡を懐にしまった。「おや、これは興味深い」
彼の目を引いたのは、ベッドの角に掛けてあった小さな犬用の鞭だった。だが、その鞭はそれ自体に巻き付けられ、紐で輪が作られていた。
「ワトソン、これをどう思う?」
「ごく普通の鞭さ。だが、なぜ輪に結んであるのかは見当もつかないな」
「普通ではないのだよ、ワトソン。ああ、世界とはなんと恐ろしい場所か。悪に走った知性ほど危険なものはない。さて、ミス・ストーナー、調査は十分です。よろしければ、お庭へ出ましょうか」
調査を終えて現場を後にした時ほど、友の顔が険しく、暗い影を落としているのを私は見たことがなかった。我々は何度か庭を行き来したが、ミス・ストーナーも私も、ホームズが物思いから我に返るまで、その思索を邪魔するのが憚られて、ただ黙って彼の後を歩いた。
「ミス・ストーナー、私の助言に、絶対に従っていただかねばなりません」やがて彼が口を開いた。
「必ず、従いますわ」
「この件は、一刻の猶予もありません。あなたの命が懸かっているのです」
「すべて、お任せいたします」
「まず、今夜、私とワトソン君があなたの部屋で夜を明かさねばなりません」
ミス・ストーナーも私も、あっけに取られてホームズを見つめた。
「そうする必要があります。ご説明しましょう。あれが村の宿屋ですな?」
「はい、クラウン・インですわ」
「よろしい。あなたの部屋の窓は、あそこから見えますね?」
「ええ、見えます」
「義父がお戻りになったら、頭痛を口実に、ご自分の部屋に閉じこもってください。そして彼が寝静まったのを確認したら、窓の雨戸を開け、かんぬきを外し、ランプを窓辺に置いて合図を送るのです。その後、必要なものだけを持って、そっと元の自分の部屋へお移りなさい。修理中とはいえ、一晩くらいなら問題なく過ごせるでしょう?」
「ええ、簡単ですわ」
「残りは、我々にお任せください」
「でも、あなた方は何をなさるおつもりで?」
「あなたの部屋で夜を明かし、あなたを悩ませてきたあの奇妙な物音の正体を突き止めます」
「ホームズさん」ミス・ストーナーが彼の袖に手を掛けた。「あなたにはもう、すべてお見通しなのではございませんか?」
「あるいは、そうかもしれん」
「でしたら、どうか、姉が何故死んだのか、教えてくださいまし」
「確証を得るまでは、口を閉ざしておきたいのです」
「せめて、私の考えが当たっているかどうかだけでも。姉は、何かにひどく驚いて……恐怖のあまり、亡くなったのでしょうか?」
「いいえ、私はそうは思いません。もっと、具体的な原因があったはずです。さて、ミス・ストーナー、我々はそろそろ失礼せねば。ロイロット博士が戻ってきて我々を見つければ、すべてが水泡に帰します。どうか、勇気をお出しなさい。私の言う通りにしていただければ、あなたを脅かす危険は、間もなく取り除かれるでしょう」
シャーロック・ホームズと私は、クラウン亭で寝室と居間を借りるのにさして苦労はなかった。部屋は上階にあり、窓からは並木道の門や、ストーク・モラン屋敷の居住棟が見渡せた。日が沈む頃、一台の馬車が現れ、グリムズビー・ロイロット博士の巨体が御者台に鎮座しているのが見えた。その隣の御者の少年の小さな姿が、奇妙な対比をなしている。少年が重い鉄の門を開けるのにもたついていたのだろう、博士の荒々しい怒声が風に乗って聞こえ、彼が握り拳を振り上げるのが見えた。馬車が敷地内へ進むと、やがて木々の間にぽつりと灯りがともった。
「ワトソン」暗がりの中でホームズが言った。「今夜、君を連れて行くのは少々気が引ける。危険が伴う」
「私に何かできることがあるのか?」
「君の存在が、おそらく極めて重要になる」
「ならば、喜んで行こう」
「感謝するよ」
「危険、と言うが、私には見えない何かを君は見たのだな?」
「いや。だが、私は君より少しだけ多く、そこから推理を組み立てた。君も私とまったく同じものを見たはずだ」
「あのベル紐以外は、特に何も。あれが何のためにあるのか、さっぱり見当がつかんが」
「換気口も見たはずだ」
「ああ。だが、隣室に通じるあんな小さな穴が、特に奇妙だとは思わなかった。鼠だって通り抜けられそうにない大きさだったからな」
「ストーク・モランへ来る前から、私は換気口の存在を確信していたよ」
「なんだって、ホームズ!」
「そうさ。彼女の話では、姉君はロイロット博士の吸う葉巻の匂いを感じたと言っていた。つまり、二つの部屋の間には、何らかの連絡通路があるはずだ。もしそれが大きければ、検死の際に指摘されている。だから私は、それが換気口だと推理したのだよ」
「しかし、それが何の害になるというんだ?」
「少なくとも、奇妙な一致がある。換気口が作られ、紐が垂らされ、そしてそのベッドで婦人が亡くなった。君はどう思う?」
「まだ繋がりが見えない」
「あのベッドに、何か変わった点があったことに気づかなかったか?」
「いや」
「床に固定されていた。あんなベッドを、君は見たことがあるか?」
「ないな」
「婦人はベッドを動かせない。つまり、常に換気口の真下にいなければならなかった。そして、紐は常に手の届くところにある。――あれは、ベルを鳴らすための紐ではなかったのだよ」
「ホームズ……君の言わんとすることが、ようやく見えてきた。我々は、何か巧妙で恐ろしい犯罪を、間一髪で食い止めようとしているのだな」
「その通り。巧妙で、そして恐ろしい。医者が道を踏み外せば、これ以上ない凶悪な犯罪者となる。優れた頭脳と神経を兼ね備えているからな。かのパーマーやプリチャードも、その名を馳せた犯罪医だった。だがこの男は、彼らをも凌ぐかもしれん。しかし、我々も負けはしない。痛烈な一撃をくれてやるさ。だが、今夜は油断ならん夜になる。せめてそれまでは、パイプでもふかして、この忌まわしい考えを振り払おうじゃないか」
九時頃、木立の向こうの明かりが消え、屋敷の方角は深い闇に包まれた。重苦しい二時間がゆっくりと過ぎ、やがて十一時きっかりに、まっすぐ前方の闇の中に、一つの明るい光がぽつりと灯った。
「合図だ」ホームズが立ち上がった。「真ん中の窓だな」
外へ出るとき、ホームズは宿の主人に、知人を訪ねるので戻りが遅くなるかもしれない、と一言告げた。すぐに我々は暗い道に出た。冷たい風が顔に吹きつけ、闇の中に揺れる一つの黄色い光だけを頼りに、我々はその陰鬱な使命へと向かった。
敷地へ忍び込むのは容易かった。古い石塀には、修理されずに放置された大きな穴が空いていたからだ。木立を抜け、芝生にたどり着き、いざ窓から中へ入ろうとした、その時だった。月桂樹の茂みから、歪んだ子供のような奇怪な生き物が飛び出し、地面に身を伏せると、手足をくねらせながら闇の中へと駆け去っていった。
「神よ!」私は囁いた。「今のが見えたか?」
ホームズも一瞬、私と同じように度肝を抜かれた様子で、私の手首を鉄の万力のように掴んだ。だが、すぐに彼は低く笑い、私の耳元に口を寄せた。
「なかなか賑やかな一家のようだ。あれはヒヒだよ」
私は博士の奇妙なペットたちのことをすっかり忘れていた。チーターもいるのだ。いつ何時、その獣が我々の肩に飛びかかってくるか分かったものではない。ホームズに倣って靴を脱ぎ、室内に忍び込むと、私はいくぶん安堵した。ホームズは静かに雨戸を閉め、ランプをテーブルの上に移し、部屋をぐるりと見回した。昼間と何も変わりない。彼は私のそばに忍び寄ると、手をメガホンのようにして耳元で囁いた。その声はあまりにかすかで、私は耳をそばだててようやく聞き取ることができた。
「物音一つ立てるな。我々の命に関わる」
私は頷いた。
「明かりは消しておく。換気口から見えてしまうからな」
私は再び頷いた。
「眠るなよ、ワトソン。命が惜しければな。拳銃を用意しておけ。私はベッドの端に、君はあの椅子に座る」
私はリボルバーを取り出すと、テーブルの隅に置いた。
ホームズは長くしなやかな籐の杖を持参しており、それをベッドの上に置いた。その隣には、マッチ箱と蝋燭の切れ端。それから彼はランプの火を吹き消し、部屋は完全な闇に包まれた。
あの恐ろしい夜警のことを、私は生涯忘れることはないだろう。呼吸の音すら憚られるほどの静寂の中、すぐ傍らにいるホームズが、私と同じように神経を極限まで張り詰めているのが肌で感じられた。雨戸は僅かな光さえも遮り、我々は絶対的な闇の中にいた。外からは時折、フクロウの悲しげな鳴き声が聞こえ、一度は窓のすぐそばで、猫のような長く低い唸り声がした。チーターが庭をうろついているのだと、それは告げていた。遠くの教会の時計が、四半時ごとに重々しく時を告げる。なんと長い時間だったことか。十二時、一時、二時、三時――我々はただひたすら、息を殺して事の成り行きを待ち続けた。
突然、換気口の方角に一瞬の光が走っては、すぐに消えた。だが、続いて強い油と、熱せられた金属の匂いが漂ってきた。隣室で誰かが、目隠しランタンに火を灯したのだ。かすかな物音がして、再び静寂が戻ったが、匂いは強くなる一方だった。私は耳を澄ませていた。やがて、別の音が聞こえてきた。それは、まるで細い蒸気の噴流が、湯気の立つやかんから漏れ出るような、ごく小さく、しゅうしゅうという音だった。 その瞬間、ホームズはベッドから躍り上がると、マッチを擦り、その灯りの中でベル紐に向かって猛烈に杖を振り下ろした。
「ワトソン、見えたか! あれだ!」彼が叫んだ。
だが、私には何も見えなかった。ホームズがマッチを擦った瞬間、私は低く澄んだ口笛のような音を聞いたが、突如として目に飛び込んできた眩しい光に目がくらみ、彼が何に向かってあれほど激しく杖を振るっているのか、判別できなかったのだ。ただ、彼の顔が死人のように青ざめ、凄まじい戦慄と憎悪に満ちているのが見えた。
彼は攻撃をやめ、じっと換気口を見上げていた。その時だった。およそ人の世のものとは思えぬ、凄まじい絶叫が夜の静寂を切り裂いた。その叫びは、苦痛と恐怖、そして怒りが一つになった、身の毛もよだつ金切り声となり、みるみるうちに大きくなっていった。村の遠くの家々にまで響き渡り、この屋敷の人々も寝床から飛び起きたに違いない。私たちの心まで凍らせるようなその声が、やがて静寂の中に吸い込まれて消えるまで、私はホームズを、ホームズは私を、ただじっと見つめ合っていた。
「どういうことだ?」私は息を呑んで尋ねた。
「これで、すべてが終わったんだ」ホームズは答えた。「そして、おそらくは、これでよかったのだろう。ピストルを持ってこい、ワトソン。ロイロット博士の部屋へ入るぞ」
厳しい面持ちでランプに火を灯すと、ホームズは廊下へと歩み出た。二度ドアを叩いても返事はなく、彼は取っ手を回して中へ入った。私はピストルを構え、その後に続いた。
私たちの目に飛び込んできたのは、まことに異様な光景だった。テーブルの上には暗灯が置かれ、シャッターが半分開いており、まばゆい光線が鉄製の金庫に注がれている。その金庫の扉は少し開いていた。そのテーブルのそば、木製の椅子にはグリムズビー・ロイロット博士が座っていた。長い灰色の寝間着をまとい、裸足の足首が覗き、赤いヒールのないトルコ風スリッパを履いていた。膝の上には、昼間目にした柄の短い長い鞭が横たわっている。顎は上に突き上げられ、目は天井の隅を恐ろしいほど硬直したまなざしで見つめていた。額には奇妙な黄色の帯が、茶色がかった斑点とともにきつく巻き付けられているように見えた。私たちが部屋に入ったとき、彼は一切の音も動きも見せなかった。
「帯だ! 斑点のある帯!」とホームズがささやいた。
私は一歩踏み出した。その瞬間、彼の奇妙な頭飾りが動き始め、髪の間から短くて菱形の頭部とふくらんだ首をもつ忌まわしい蛇がもたげてきた。
「沼地のアダーだ!」とホームズが叫んだ。「インドで最も恐ろしい毒蛇だ。噛まれてから十秒もせずに死に至る。暴虐に生きる者には暴力が跳ね返り、策士は自ら掘った落とし穴にはまるものだ。この生き物を巣に戻し、ストーナー嬢を安全な場所に移してから、郡警察に事の次第を知らせよう。」
そう言いながら、彼は素早く死体の膝から鞭を取り、輪を蛇の首にかけてそのおぞましい止まり木から引きずり下ろし、腕を伸ばしてそのまま鉄の金庫に放り込み、扉を閉じた。
これが、ストーク・モランのグリムズビー・ロイロット博士の死の真相である。すでに長くなり過ぎたこの物語を、悲報を怯える娘にどのように伝えたか、朝の汽車で彼女をハロウの善良なおばのもとへ送り届けたこと、公式の捜査がゆっくりと進んだ末に、「危険なペットと軽率に戯れていたことで博士が運命に見舞われた」と結論づけたこと等を、ここで細かく語る必要はない。この事件について私がまだ知らなかったことは、翌日戻る道すがらシャーロック・ホームズが語ってくれた。
「私はね」と彼は言った。「完全に誤った結論に達していたのだよ。これはつまり、ワトソン君、十分なデータがないまま推理するのがいかに危険かということを示している。ジプシーの存在、そして可哀想な娘が使った『帯』という言葉――彼女はマッチの明かりで一瞬しか目にできなかったものを説明しようとしたに違いないが――それらが、私を全く見当違いの方向に導いた。だが、部屋の住人を脅かす危険が窓や扉からは来ないことがはっきりした時、私はすぐに自分の立場を再考したのだ。それで、すぐにこの通風孔、そしてベッドに垂れ下がるベルの紐に注意を向けた。これが偽物であり、ベッドが床に固定されていたことを知った瞬間、紐は何かがこの穴を通ってベッドに渡るための橋なのではという疑念が浮かんだ。すぐに蛇という考えが頭をよぎり、博士がインドから動物を持ち込んでいるという事実と結びつけて、私は正しい線をたどっているのだろうと感じた。どんな化学検査でも発見できない毒を使うという発想は、東洋で訓練を積んだ狡猾で冷酷な人物ならではだ。その毒の即効性も、彼にとっては有利だったろう。毒牙が残す小さな暗い二つの痕を見抜ける検死官は、かなり鋭い人物に違いない。そこへ思い当たったのが口笛だ。もちろん、夜明けの光で被害者に蛇が見つかる前に、それを呼び戻さねばならなかったのだろう。あの牛乳を使って訓練し、呼べば戻ってくるようにしていたに違いない。しかるべき時刻に通風孔からそれを送り込めば、確実に紐を伝ってベッドに降りる。噛むかどうかは運次第で、もしかすると一週間毎晩無事なこともあるかもしれないが、遅かれ早かれ犠牲者は出る。
私は、博士の部屋に入る前からこうした結論に達していた。椅子を調べて、彼が通風孔に手が届くよう椅子の上に立っていたことも分かった。金庫、牛乳皿、そして鞭紐の輪を見て、残る疑念は完全に晴れた。ストーナー嬢が聞いた金属音は、継父がその恐ろしい住人を金庫に急いで戻す音に違いない。覚悟を決めた後の私の行動は、君も知っている通りだ。あの生き物のシューッという音を、君も聞いただろうし、私もすぐに明かりをつけて、それに攻撃をしかけた。」
「その結果、通風孔を通って逃げたと。」
「そして、もう一つの結果として、向こう側で主人に襲いかかった。私の杖の打撃が何度か当たり、それで蛇の怒りを刺激し、最初に目にした人物――つまり主人に飛びかかったわけだ。この意味で、私は間接的にグリムズビー・ロイロット博士の死に責任があるが、私の良心に重くのしかかることはなさそうだ。」
第九話 技師の親指
私が親友シャーロック・ホームズに紹介することになった案件のうち、私自身が関わることとなったのは二つだけである――ハザリー氏の親指事件と、ウォーバートン大佐の発狂事件だ。うち後者の方が、鋭い観察眼と独創性を持つ者にとってはより魅力的な題材だったかもしれないが、前者はその発端の奇妙さと細部の劇的さゆえに、たとえホームズが得意とする推理の余地が少なかったとしても、記録に値するのではないかと思う。この話は新聞にも何度か載ったのだが、どんな事件もそうであるように、こうした物語は、事実が徐々に展開し、発見が連鎖して真相に迫っていく過程を目の当たりにしたときの方が、単なる活字の半コラムでまとめられるよりも、はるかに印象的だ。私にとっても当時は大きな衝撃であり、二年の歳月を経た今も、その印象はほとんど薄れていない。
その出来事が起きたのは、私が結婚して間もない1889年の夏のことだった。私は民間医に戻り、ホームズのベイカー街の部屋からは離れて暮らしていたが、たびたび彼を訪ね、時には彼のボヘミアンな習慣を無理やり中断させて我が家に招くことさえあった。私の診療所は順調に発展し、パディントン駅にも近かったため、駅関係者の患者も何人かいた。その中の一人は、私が長患いの苦痛から救ったことで、私の評判を広め、知り合いの患者を次々と紹介しようと心を砕いてくれた。
ある朝、七時少し前、メイドがドアをノックして「パディントンから二人の男性が来ており、診察室でお待ちです」と告げた。私は急いで身支度をした。というのも、鉄道関係の急患は決して軽いものではないと経験上わかっていたからだ。階段を下りると、以前からの仲である車掌が部屋から出てきて、しっかりとドアを閉めた。
「ここに連れてきたぞ」と彼は肩越しに親指をしゃくって小声で言った。「大丈夫だ。」
「それは何だい?」と私は尋ねた。その口ぶりから、まるで珍しい生き物を私の部屋に閉じ込めたかのように感じた。
「新しい患者さんさ」と彼はささやいた。「自分で連れてきたんだ、逃げられる心配がないようにね。ほら、ちゃんと無事だよ。じゃあな、先生。俺にもやるべき仕事があるからね」そう言い残して、この頼りになる男は礼も言う暇も与えず立ち去った。
診察室に入ると、紳士が一人テーブルの傍らに座っていた。落ち着いたヘザー・ツイードのスーツに、柔らかい布の帽子を本の上に置いている。片手には血がまだらに染みついたハンカチを巻いていた。二十五歳にはとても見えないほど若く、精悍な顔立ちだったが、極度に青ざめており、何か強い動揺を必死で抑えている印象だった。
「先生、こんな朝早く起こしてしまい申し訳ありません」と彼は言った。「夜中にひどい事故に遭いまして、今朝の汽車でやってきました。パディントン駅で医者を探していると、親切な方がここまで案内してくれました。メイドさんにカードを渡したのですが、サイドテーブルに置いたままのようですね」
私はカードを手に取り見た。「ヴィクター・ハザリー氏 水力技師 ヴィクトリア通16A(3階)」――これが、この朝の訪問者の名刺である。「お待たせしてしまい申し訳ありません」と私は言い、図書室の椅子に座った。「夜行列車でいらしたとか。それだけでも退屈なものですよね」
「いや、私の夜は退屈なんてものじゃありませんでしたよ」と彼は言い、朗らかで高い声で笑い出した。勢いよく椅子にもたれ、体を震わせて笑い続ける。その笑いに、私の医師としての本能が警告を発した。
「やめなさい!」と私は叫んだ。「落ち着いて!」とカラフェから水を注いだ。
だが無駄だった。彼は大きな危機が去った後に強い人間を襲うヒステリー発作に陥っていたのである。しばらくして彼はようやく我に返り、ぐったりとしつつ顔を赤く染めていた。
「馬鹿なことをしてしまいました」と彼は息を切らせて言った。
「とんでもない。これを飲みなさい」私は水にブランデーを加えた。すると、血の気のなかった彼の頬に色が戻ってきた。
「これで大丈夫です。さて先生、親指……いや、正確にはかつて親指があった部分を診ていただけますか」
彼はハンカチをほどき、手を差し出した。私のような場慣れした医者でも身震いするほどの傷だった。四本の指が突き出し、親指があったはずの場所は赤く、スポンジ状の恐ろしい肉がむき出しになっている。根元からえぐり取られていた。
「なんてこった!」と思わず叫んだ。「これはひどい怪我だ。随分出血したでしょう」
「はい、かなり出ました。切断されたとき失神し、だいぶ長い間意識を失っていたと思います。気がつくとまだ血が流れていたので、ハンカチの端をきつく手首に巻き、枝で締め付けました」
「見事です。あなたは外科医になってもよかった」
「要は水力学なんです、自分の専門分野ですから」
「これは……」と私は傷口を調べながら言った。「非常に重く鋭利な道具でやられたのですね」
「まるで中華包丁のようなもので」
「事故ですか?」
「まったく違います」
「えっ、殺人的な襲撃ですか?」
「本当に殺意のあるものでした」
「なんてことだ……」
私は傷口を洗浄し、清潔にし、ガーゼと消毒包帯で覆った。彼は時折唇をかみしめながらも、眉ひとつ動かさず身を委ねていた。
「どうですか?」私は手当てを終えて尋ねた。
「完璧です! ブランデーと包帯ですっかり元気になりました。ずいぶん弱っていましたが、それだけのことがあったのです」
「できれば今は話さない方がいい。おそらく神経に障ることでしょう」
「いえ、もう大丈夫です。警察にも説明しなくてはなりませんし。ただ、この傷が証拠にならなければ、警察も私の話を信じてくれないかもしれません。それくらい非常に奇妙な体験で、しかも証拠が乏しい。たとえ信じてもらえても、私の出せる手がかりはあまりに曖昧で、正義が果たされるかどうかわかりません」
「なるほど!」と私は言った。「もしも何か解決してほしい問題であれば、公式の警察に行く前に、ぜひ私の友人シャーロック・ホームズに相談されることを強くお勧めします」
「その方のことは聞いたことがあります」と訪問者。「もし引き受けていただけるなら、ぜひお願いしたい。もっとも公式警察も使うつもりですが。彼に紹介してもらえますか?」
「もっといい方法があります。私が直接お連れします」
「本当に感謝します」
「すぐに馬車を呼びましょう。ちょうど朝食時に間に合いますよ。大丈夫ですか?」
「ええ、話すまでは落ち着かなくて」
「では、召使いに馬車を呼ばせます。すぐに支度をして参ります」私は急いで階上に駆け上がり、妻に手短に事情を説明し、五分後には新たな知り合いとともにベイカー街行きの馬車に乗っていた。
予想通り、シャーロック・ホームズは寝間着姿で居間をぶらぶらしながら、『タイムズ』紙の尋ね人欄を読み、昨日の吸い殻を集めて作った朝食前のパイプをふかしていた。彼は穏やかな愛想で私たちを迎え、ベーコンと卵を新たに注文し、朝食をともにした。食事が終わると、新しい患者をソファに寝かせ、枕をあてがい、手の届くところにブランデー入りの水を置いた。
「あなたが並みの経験をされたのでないことはよく分かります、ハザリーさん。どうぞ、そこに横になって、気楽にしてください。お話しいただける範囲で結構です。疲れたらいつでも休んで、元気を保つために少しずつ飲んでください」
「ありがとうございます。先生が包帯してくださってから、すっかり別人のようですし、お宅の朝食でもすっかり元気が出ました。できるだけお時間を取らせないよう、すぐに本題に入ります」
ホームズは大きな安楽椅子にゆったりと座り、表情はまぶたが重そうで疲れた様子だが、その奥には鋭い熱意が隠れている。私は彼の向かいに座り、私たちは患者の語る不思議な体験談に静かに耳を傾けた。
「ご存じの通り、私は孤児で独身、ロンドンの下宿で一人暮らしです。職業は水力技師で、グリニッジの名門ヴェナー&マセソン社で七年間修業した経験があります。二年前に修業を終え、父の死でそこそこの遺産も入り、独立してヴィクトリア通りに事務所を構えました。
独立開業の苦しさは誰もが味わうことですが、私の場合は格別でした。二年で相談が三件、小さな仕事が一つ、それだけが収入のすべてです。総収入は27ポンド10シリング。毎日朝九時から夕方四時まで、小さな事務所で待ち続け、ついには心が折れそうになり、もう仕事なんて来ないのではと思い込むようになりました。
ところが昨日、ちょうど帰ろうとしたとき、書記が来て、商用で会いたいという紳士がいると知らせてきました。カードには『ライサンダー・スターク大佐』の刻印。すぐ後ろに大佐本人が現れました。背は中背より少し高いくらい、だが非常にやせている。これほどやせた人は見たことがない。顔は鼻と顎に向かって尖り、頬の皮膚は骨にぴんと張りついている。それでもやせ方は病気ではなく、もともとの体質のようで、目は輝き、足取りはきびきびして自信に満ちていた。服装は質素ながら清潔で、年齢は三十代後半から四十に近いと見えました。
『ハザリーさんですね?』と彼はドイツ訛りで言いました。『あなたは、専門的な技量だけでなく、秘密を厳守できる人と推薦されています』
私は若者らしく嬉しく思い、会釈して尋ねました。『どなたがそんなに良くおっしゃってくださったのでしょうか?』
『それは今この時点ではお伝えしない方がいいでしょう。同じ情報源から、あなたが孤児で独身、ロンドンで一人暮らしとも聞いています』
『まったくその通りです。ただ、それが私の専門的資格にどう関係するのか、失礼ながら分かりません。ご用件は専門的なことと伺っておりましたが?』
『その通りです。しかし、私の話すことは全て本質に関係しています。あなたに仕事を依頼したいのですが、絶対的な秘密厳守が不可欠なのです――絶対ですよ、分かりますね。もちろん、これは家族と同居している者より、一人暮らしの人に期待できることです』
『私が秘密を守ると約束すれば、必ず守ります』
「私が話している間、彼はじっと私を見つめていました。これほど疑り深く、問いただすような目を、かつて見たことがあっただろうかと思ったほどです。
『それでは、約束してくださるのですね?』と、彼はついに言いました。
『はい、約束します。』
『絶対的かつ完全な沈黙を――事前も、作業中も、その後も。言葉でも書面でも一切、この件に触れないと?』
『すでにお約束したはずです。』
『よろしい。』彼は突然立ち上がると、稲妻のような素早さで部屋を横切り、ドアを勢いよく開け放ちました。外の廊下には誰もいません。
『問題ありません。』彼は戻りながら言いました。『時として、事務員が主人の用事に興味を持つこともあるからね。これで安心して話ができます。』彼は椅子を私のすぐそばに引き寄せ、再び先ほどと同じような疑念と考え込むような目つきで私をじっと見つめてきました。
この骨ばった男の奇妙な仕草に、嫌悪感とそれに近い恐怖が私の中に湧き上がってきました。顧客を失うことへの不安さえも、私の苛立ちを抑えきれませんでした。
『どうかご用件を早くお話しください。』と私は言いました。『私の時間も貴重なのです。』最後の一言は天に許しを乞うしかありませんが、思わず口をついて出てしまったのです。
『一晩の仕事で五十ギニーではどうでしょう?』と、彼が尋ねました。
『申し分ありません。』
『一晩と言いましたが、実際には一時間もかからないでしょう。ただ、故障した油圧プレス機について、あなたの意見を伺いたいだけなのです。問題点を教えてくだされば、あとは自分たちで直します。こういった依頼はいかがでしょうか?』
『仕事は軽そうですし、報酬も申し分ありません。』
『その通り。今晩、最終列車で来ていただきたいのです。』
『どちらへ?』
『バークシャー州のアイフォードです。オックスフォードシャーの境界に近い小さな村で、レディングから七マイルほどの場所です。パディントン駅から出る列車で、十一時十五分ごろに到着します。』
『わかりました。』
『私は馬車でお迎えに上がります。』
『では、そこから車で移動するのですね?』
『はい、私たちの家は田舎の外れにありまして、アイフォード駅から七マイルは離れています。』
『それなら、到着はほとんど真夜中になりそうですね。帰りの列車はもうないでしょうから、今夜は泊まるしかなさそうですね。』
『ええ、寝る場所はすぐご用意できます。』
『それは少し不便ですね。もっと都合の良い時間に伺うことはできませんか?』
『遅い時間に来ていただくのが最善だと考えました。不便をおかけする分、あなたのような若くて無名の方に、業界の第一人者に意見を求めるのと同等の報酬をお支払いするのです。ただし、もちろんご辞退いただく時間はまだ十分ありますが。』
私は五十ギニーのことを考えました。それがどれほど有用かも。『いえ、まったく問題ありません。ご都合に合わせるのは喜んで。ただ、もう少し詳しく、私に何をしてほしいのか理解したいのですが。』
『ごもっともです。秘密保持の誓約をお願いしたことで、あなたの好奇心を刺激したのも当然です。すべてを説明せずに深入りさせるつもりはありません。盗み聞きの危険はまったくありませんね?』
『まったくありません。』
『では、こういうことです。おそらくご存じでしょうが、フラーズアースは貴重な資源で、イングランドでも一、二か所にしか産出しません。』
『そう聞いたことがあります。』
『少し前に、私はレディングから十マイル以内のごく小さな土地を購入しました。幸運にも、その一画にフラーズアースの鉱脈があることを発見したのです。しかし調べてみると、その鉱脈は比較的小さく、しかも両側にもっと大きな鉱脈が接していることが分かりました――ただし、いずれも隣接する隣人の土地にありました。彼らは自分たちの土地が金鉱にも匹敵する価値を持っていることを全く知りませんでした。もちろん、私は彼らが本当の価値に気づく前に、その土地を買い取るのが自分の利益になります。しかし、残念ながらその資本がありませんでした。そこで何人かの友人に秘密を打ち明け、まずは自分たちの小さな鉱脈だけを密かに掘り、そこで得た資金で隣の土地を買い取ろう、と提案されたのです。私たちはこの計画をしばらく実行しており、そのために油圧プレスを設置しました。このプレスが先ほど申したように故障し、あなたの助言を仰ぎたいのです。ただし、私たちの秘密は非常に厳重に守っており、もしこの家に油圧技師が出入りしていることが知れたなら、すぐに疑いを招き、事実が明るみに出れば、これらの土地を取得し計画を遂行する機会は永遠に失われてしまいます。そのため、今夜アイフォードに向かうことを決して他言しないと約束していただいたのです。ご納得いただけましたか?』
『よく理解できました。ただ一つだけ、フラーズアースの採掘には油圧プレスがどのように役立つのか、私の理解では砂利のように穴から掘り出すものだと思っていたので、その点がよく分かりません。』
『ああ、それは我々独自の方法がありまして。採掘した土をレンガ状に圧縮し、正体を隠して運び出せるようにしているのです。まあ、それは些細なことです。ハザリーさん、私はあなたを全面的に信頼して、すべてをお話ししました。では、十一時十五分にアイフォードでお待ちしています。』
『必ず伺います。』
『誰にも一言たりとも口外しないでください。』彼は最後に長い間、疑うような目で私を見つめ、それから冷たく湿った手で私の手を握りしめ、急いで部屋を出ていきました。
さて、冷静になって考えてみると、この急な依頼には私自身も驚きを禁じ得ませんでした。一方では、報酬は自分で料金を決めた場合の十倍もの額ですし、これが今後の仕事に繋がる可能性もありますから、当然嬉しくもありました。しかし一方で、依頼主の顔つきや態度には不快な印象を拭えず、フラーズアースの話も、なぜ真夜中に来なければならないのか、なぜこれほどまでに秘密にしたがるのか、納得のいく説明とは思えませんでした。それでも、そんな不安は振り払い、しっかり夕食をとり、パディントンまで馬車で向かい、言われた通り口を閉ざして出発しました。
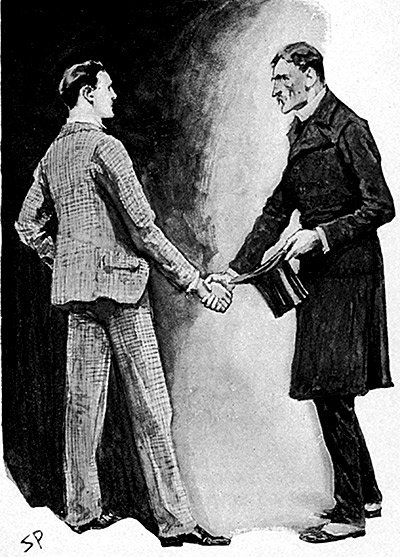
レディングでは、車両だけでなく、駅そのものも乗り換えなければなりませんでしたが、なんとかアイフォード行き最終列車に間に合いました。十一時を過ぎて、小さな薄暗い駅に到着し、下車したのは私一人だけでした。プラットホームには眠たそうなランタン持ちの駅員がひとりいるきりです。改札口を抜けると、朝の知り合いが影の中で待っていました。彼は無言のまま私の腕を取ると、開いていた馬車へと急がせました。両側の窓を引き上げ、木枠を叩き、馬車は馬が走れる限りの速さで走り出しました。」
「馬は一頭ですか?」とホームズが割り込んだ。
「はい、一頭だけでした。」
「毛色は分かりましたか?」
「ええ、乗り込むとき、側灯の明かりで見ました。栗毛でした。」
「疲れていましたか、それとも元気そうでしたか?」
「とても元気で艶やかでした。」
「ありがとうございます。失礼しました。どうぞ、続きを。」
「そうして私たちは出発し、少なくとも一時間は走りました。リサンダー・スターク大佐は七マイルだと言いましたが、走行ペースや所要時間からすると、実際は十二マイル近かったのではないかと思います。道中、大佐は黙ったまま私の隣に座り、時折こちらを鋭い視線で見つめているのに気が付きました。あの辺りの田舎道はあまり良くないらしく、馬車は激しく揺れました。窓の外を見ようとしましたが、ガラスはすりガラスで、たまに明かりがぼんやり通り過ぎるのが分かるだけでした。退屈を紛らわせようと何か話しかけても、大佐は短い返答ばかりで会話は続きません。やがて、道路のがたがたとした揺れが砂利道の滑らかな感触に変わり、馬車は止まりました。スターク大佐は素早く馬車を降り、私も続いて降りると、彼は私を目の前のポーチに急いで引き入れました。馬車から直接玄関ホールに入る形だったので、私は家の正面すら一瞬も見逃しました。敷居をまたいだ瞬間、背後でドアが重く閉まり、馬車が走り去る車輪の音がかすかに聞こえました。
屋内は真っ暗で、大佐はマッチを探しながら小声でつぶやいていました。すると突然、廊下の向こう側でドアが開き、長い金色の光の帯がこちらに差し込みました。その光が広がると、ランプを頭上に掲げた女性が現れ、顔をこちらに突き出してじっと見つめてきました。彼女は美しく、暗いドレスには高級な素材特有の光沢がありました。彼女は外国語で何か質問するような調子で話しかけ、相棒がぶっきらぼうな一言で答えると、彼女は驚いてランプを落としそうになりました。スターク大佐は近づいて彼女に何かを耳打ちし、彼女を来た部屋に押し戻すと、今度はランプを持って私のもとへ戻ってきました。
『少しの間、この部屋でお待ちいただけますか。』そう言って彼は別のドアを開けました。小さくて簡素な部屋で、中央の丸テーブルには何冊かのドイツ語の本が散らばっていました。スターク大佐はドア脇のハルモニウム(足踏み式オルガン)にランプを置き、『すぐに戻ります』と言い残して暗闇に消えました。
テーブルの本を見やると、ドイツ語は分からないながらも二冊は科学書、残りは詩集でした。窓から外の景色をうかがおうとしましたが、分厚いオーク材のシャッターが頑丈な横棒で施錠されていました。家の中は驚くほど静かで、どこかで古い時計が大きな音で時を刻んでいるほかは、すべてが死んだように静まり返っていました。何とも不安な気持ちがじわじわと募ってきました。これらのドイツ人は何者で、なぜこんな人里離れた場所に住んでいるのか? そしてここは一体どこなのか? アイフォードから十マイルほど離れていること以外、方角すら分かりません。レディングそのほかの大きな町も半径内にあるはずですが、とはいえこの静けさからして、確かに田舎にいることは間違いありません。私は気を紛らわせるため小声で鼻歌を歌いながら部屋を行き来し、五十ギニーの報酬に見合う働きをしているぞ、と自分に言い聞かせていました。
突然、何の前触れもなく、静寂の中でゆっくりとドアが開きました。そこには女性が立っていて、背後の廊下は闇、私のランプの黄色い光が彼女の切実で美しい顔を照らしていました。彼女は明らかに恐怖で青ざめており、その様子に私の胸も凍る思いがしました。彼女は震える指で私に静かにするよう合図し、恐れた馬のように後ろを気にしながら、たどたどしい英語でささやき始めました。
『お帰りになったほうがよいです。ここにいてはいけません。あなたにできることはありません。』
『しかし、奥さん、私はまだ目的の作業を果たしていません。機械を見るまでは帰れません。』
『待つ価値はありません。今ならドアから出られます、誰も止めません。』私が微笑んで首を振るのを見ると、彼女は急に抑えていた感情を解き放ち、手を強く握りしめて一歩踏み出しました。『お願いです、天にかけて、手遅れになる前にここを離れて!』
しかし私はもともと頑固な性分で、障害があるほど逆に挑みたくなるたちです。五十ギニーの報酬や、わざわざここまでやって来た労苦、不愉快な夜を思い、すべてが無駄になるのかと思うと納得できませんでした。せっかくの依頼を果たさず、報酬も受け取らずに逃げ帰るのは理不尽だと思いましたし、この女性が一種の妄想に囚われているだけかもしれません。内心は動揺していましたが、毅然とした態度を保ち、ここに留まるつもりだと伝えました。彼女はさらに訴えかけようとしたものの、上階でドアがバタンと閉まり、階段を数人が下りてくる足音が聞こえました。彼女は一瞬耳を澄ませ、絶望的な仕草で手をあげると、さっきのように音もなく姿を消しました。
新たに現れたのはリサンダー・スターク大佐と、分厚い二重あごからチンチラ髭が生えた、ずんぐりした男で、ファーガソン氏と紹介されました。
『彼は私の秘書兼支配人です。ところで、さっきこのドアは閉めておいたはずだが。すみません、隙間風を感じられたのでは?』
『いえ、私は部屋が少し息苦しかったので自分で開けたのです。』
彼はまた疑い深い目を向けました。『では、早速本題に入りましょう。ファーガソン氏と私が機械をご案内します。』
『帽子をかぶったほうがいいでしょうか?』
『いや、家の中ですから』
『えっ、この家の中でフラーズアースを掘っているのですか?』
『いいえ、圧縮するだけです。ともかく、あなたにしていただきたいのは機械の点検だけです。』
私たちは一緒に階段を上がりました。先頭はランプを持った大佐、続いて太った支配人、最後に私。古びた家はまるで迷路で、廊下や通路、狭くて曲がりくねった階段と、幾世代にもわたり踏みならされた低い扉の敷居が続きます。二階以上にはカーペットも家具もなく、壁の漆喰ははがれ、緑色のカビが不健康そうに広がっていました。私は平静を装いましたが、女性の警告を忘れず、二人の男から目を離しませんでした。ファーガソン氏は無口で陰気な男でしたが、少し話した限りでは少なくとも同郷のイギリス人だと分かりました。
スターク大佐はついに低い扉の前で立ち止まり、鍵を開けました。中は小さな四角い部屋で、三人がやっと入れるほど。ファーガソン氏は外に残り、大佐が私を中に案内しました。
『ここが油圧プレスの内部です。もし誰かがこの機械を起動したら、非常に厄介なことになるでしょう。この小部屋の天井は、実は下降するピストンの先端で、何トンという圧力でこの金属床に下りてくるのです。外側に小さな水圧柱があり、その力を伝達・増幅する仕組みはご存じでしょう。機械は一応動くのですが、どうも動きが重く、力が落ちたようです。どこを改善すればよいか、ご教示願えますか?」
私は彼からランプを受け取り、その機械を念入りに調べてみました。それは確かに巨大な装置で、想像を絶するほどの圧力を生み出すことができる代物でした。しかし、一度外に出て操作レバーを押し下げてみますと、「シュッ」という鋭い音ですぐに分かりました。わずかな水漏れがあり、そのせいで側面のシリンダーの一つから水が逆流していたのです。詳しく調べてみると、駆動棒の頭部を覆っていたインドゴム製のバンドが収縮してしまい、ソケットを完全に密閉できていませんでした。これが動力低下の明白な原因でしたので、私はそのことを彼らに指摘しました。彼らは私の説明に熱心に耳を傾け、修理方法について実用的な質問をいくつも浴びせてきました。私がすべてを明確に伝え終えると、再び機械のある主室へと戻り、純粋な好奇心から改めて装置をじっくりと観察したのです。
そして、ひと目見ただけで確信しました。あの「フラーズアース」の話は、まったくの作り話に違いない、と。これほど強力なエンジンが、それほど取るに足らない目的のために設計されるはずがありませんでした。壁は木製でしたが、床は大きな鉄製のトラフ(溝)になっており、その表面には一面に金属質の沈殿物がこびりついていました。私は腰をかがめ、それが何なのか確かめようと削り取っていた、まさにその時でした。ドイツ語のうめき声が聞こえ、顔を上げると、骸骨のように痩せこけた大佐が、冷たい目つきで私を見下ろしていたのです。
「何をしているのですかな?」と彼は言いました。
彼の語った手の込んだ作り話にまんまと乗せられた自分に、腹が立って仕方がありませんでした。
「いやはや、あなたがおっしゃるフラーズアースとやらに感心していたところです」と私は皮肉を込めて答えました。「もっとも、この機械が本当は何に使われるのか正確に分かれば、より的確な助言ができるのですがね」
その言葉を口にした瞬間、私は自らの無謀さを後悔しました。彼の顔は石のように硬直し、その灰色の瞳には邪悪な光が宿ったのです。
「よろしい」と彼は言いました。「ならばこの機械について、すべてをお教えしましょう」
そう言うが早いか、彼は一歩後ろへ下がると、小さなドアをバタンと閉め、ガチャリと鍵をかけてしまいました。私はすぐさまドアに飛びかかって取っ手を引きましたが、びくともしません。蹴りつけ、体当たりしても、分厚い扉は微動だにしなかったのです。
「おい!」と私は叫びました。「おい! 大佐! ここから出してください!」
そして静寂の中、突如として、私の心臓を凍りつかせるような音が響き渡りました。レバーが動くガチャガチャという金属音と、シリンダーから水が漏れる、あの「シュッ」という音でした。彼が、エンジンを始動させたのです。ランプは、先ほどトラフを調べていた時に床へ置いたままでした。その揺らめく灯りの中に、黒い鉄の天井が、ゆっくりと、しかし断続的に、私めがけて降りてくるのが見えました。この機械の恐るべき力を誰よりも知っている私には、それが間もなく自分を無惨な肉塊に変えてしまうことが分かっていたのです。私は悲鳴をあげてドアに体当たりし、爪が剥がれるのも構わず鍵穴を掻きむしりました。大佐に命乞いをしましたが、私の必死の叫びは、無情なレバーの音にかき消されるだけでした。天井はもう、頭上わずか一、二フィートのところまで迫り、手を伸ばせば、その冷たくざらついた表面に触れることができました。その時、ふと、自分の死の苦しみは、どのような姿勢で迎えるかに大きく左右されるだろう、という奇妙な考えが頭をよぎりました。うつ伏せになれば、凄まじい重みが背骨にのしかかるでしょう。骨が砕けるあの恐ろしい音を想像しただけで、全身に震えが走りました。仰向けの方がまだましかもしれませんが、死の黒い影が刻一刻と迫ってくるのを、果たして正視していられるだけの度胸が自分にあるだろうか。もはや立っていることさえできなくなった、その瞬間でした。私の目に、一条の希望の光が差し込んできたのです。
先ほど申し上げましたように、床と天井は鉄製でしたが、壁は木でできていました。最後に必死の思いで辺りを見回した時、二枚の板の間に細い黄色い光の筋が見えたのです。そしてその光は、小さなパネルが押し開かれるにつれてみるみる広がっていきました。一瞬、これが本当に死からの脱出口なのか信じられませんでした。次の瞬間には、私はそこに身を投げ出し、半ば意識を失いながらも、どうにか向こう側へと転がり込んでいました。パネルはすぐに私の背後で閉じられましたが、ランプが砕ける音、そして数秒後に鉄の天井と床が閉じる轟音が、私の脱出がいかに危機一髪であったかを物語っていました。
私は、手首を激しく掴まれてはっと我に返りました。見ると、石畳の廊下に横たわる私を、ろうそくを手にした女性が屈み込みながら引っ張り起こそうとしていました。私が愚かにも無視してしまった、あの警告を与えてくれた恩人でした。 「早く! 早く!」彼女は息を切らしながら叫びました。「すぐに奴らが来ますわ。あなたがいなくなったことに気づいてしまう。お願い、貴重な時間を無駄にしないで、早く!」
今度ばかりは、私も彼女の助言に逆らうことはありませんでした。よろめきながら立ち上がると、彼女に導かれるまま廊下を駆け抜け、螺旋階段を駆け下りました。階段は広い通路に続いており、そこへたどり着いた時、上の階と下の階から、二つの声が互いに呼びかけながら近づいてくる足音が響いてきたのです。案内役の彼女は絶望的な表情で周囲を見回しましたが、やがて寝室に通じる一つの扉を勢いよく開け放ちました。窓からは、月明かりが煌々と射し込んでいました。
「これしかありませんわ」と彼女は言いました。「高いけれど、あるいは飛び降りられるかもしれません」
その時、廊下の奥に灯りが見え、ランタンを片手に、もう一方の手に肉屋の鉈のような凶器を握ったリサンダー・スターク大佐の痩せこけた姿が、こちらへ走ってくるのが見えました。私は寝室を駆け抜けて窓を開け放ち、下を見下ろしました。月明かりに照らされた庭は静かで美しく、地面までは三十フィート(約九メートル)ほどしかありませんでした。私は窓枠によじ登りましたが、助けてくれた彼女とあの暴漢のやり取りを最後まで見届けるまでは、と飛び降りるのをためらいました。もし彼女が危害を加えられるようなら、どんな危険を冒してでも戻って助けるつもりでした。その考えが頭をよぎった瞬間、大佐はすでにドアのところまで来ており、彼女を押しのけて部屋へなだれ込もうとしていました。しかし彼女は必死に彼にしがみつき、引き留めようとしたのです。
「フリッツ! フリッツ!」彼女は英語で叫びました。「前の約束を思い出して。もう二度としないと誓ったでしょう。この方は黙っていますわ! ええ、絶対に黙っていますから!」
「馬鹿なことを言うな、エリーゼ!」彼は叫び、彼女を振りほどこうともがきました。「お前は我々を破滅させる気か。あいつは知りすぎたのだ。どけ!」
彼はついに彼女を突き飛ばすと、窓辺に駆け寄り、その重い武器で私に斬りかかってきました。私は窓枠に両手でぶら下がっていましたが、彼の一撃が私の手に命中しました。鈍い痛みとともに指先の力が抜け、私は庭へと真っ逆さまに落下していきました。
落下した衝撃で体は揺さぶられましたが、幸い怪我はなかったので、私はすぐに立ち上がり、一目散に茂みの中へと駆け込みました。危険が去ったわけではないと、本能が告げていたからです。しかし突然、猛烈なめまいと吐き気に襲われました。痛む手を見ると、そこで初めて、親指が切り落とされ、夥しい血が流れ出していることに気づいたのです。ハンカチを巻いて止血しようとしましたが、ひどい耳鳴りがしたかと思うと、次の瞬間にはバラの茂みの中で意識を失って倒れていました。
どれほどの時間、気を失っていたのか分かりません。かなり長い間だったに違いありませんでした。気がついた時には月は沈み、東の空が白み始めていました。衣服は夜露でぐっしょりと濡れ、コートの袖は、親指の傷から流れた血で赤黒く染まっていました。その疼くような痛みによって、一瞬にして昨夜のすべての出来事が蘇り、私は跳ね起きました。まだ追っ手から逃げ切れてはいないかもしれない、という恐怖に駆られたのです。
しかし驚いたことに、周囲を見回しても、あの家も庭も見当たりませんでした。私が倒れていたのは大通りに面した生け垣の隅で、少し下ったところには、昨夜私が降り立った駅舎が見えました。もしこの手の無惨な傷がなければ、あの恐ろしい一夜の出来事は、すべて悪夢だったのではないかと錯覚してしまったことでしょう。
私はぼんやりとした頭で駅に入り、朝の列車について尋ねました。一時間もしないうちにレディング行きの列車が出るとのことでした。昨夜と同じ駅員が当直していましたが、私がリサンダー・スターク大佐を知らないかと尋ねても、聞いたこともないという返事でした。昨夜、私のために馬車は待機していなかったかと聞いても、見ていないと言います。近くに警察署はあるかと尋ねると、三マイルほど先にあるとのことでした。
しかし、衰弱しきっていた私に、そこまで歩く力は残っていませんでした。ロンドンに戻ってから警察に届け出るしかないと決心したのです。ロンドンに着いたのは六時を少し過ぎた頃で、まずこの傷の手当てを受け、それから親切な医者殿にここまでお連れいただいた、という次第です。これが私の身に起こったことのすべてです。どうか、お力をお貸しください。あなた方のご助言どおりに行動いたします。
この異常な話を聞き終えたあと、私たちはしばらく沈黙していた。やがてシャーロック・ホームズは、彼が切り抜き記事を収めている重厚なスクラップブックのひとつを棚から引っ張り出した。
「あなたが興味を持ちそうな広告があります」と彼は言った。「約1年前、すべての新聞に掲載されたものです。読んでみましょう――『今月9日、油圧技師ジェレマイア・ヘイリング氏(26歳)行方不明。夜10時に宿を出て以後、消息不明。着衣は……』などなど。はは! これが大佐が前回機械の点検を必要とした最後のときだったのでしょうね」
「なんてことだ!」私の患者は叫んだ。「それであの女性の言葉の意味が分かりました」
「疑いようもありません。大佐は冷酷で大胆不敵な男で、目的のためには何も厭わない人物だったのです。まるで拿捕した船の生存者を一人も残さぬ海賊のように。さて、今は一刻も惜しい。もしご気分がよろしければ、すぐにスコットランド・ヤードに向かい、その後アイフォードへ出発しましょう」
三時間ほど後、私たちは全員、レディングから小さなバークシャーの村へ向かう列車に乗っていた。シャーロック・ホームズ、油圧技師、スコットランド・ヤードのブラッドストリート警部、私服刑事、そして私である。ブラッドストリート警部は県の地図を座席に広げ、コンパスでアイフォードを中心に半径10マイルの円を描いていた。
「はい、これです」と彼は言った。「この円が村から半径10マイルの範囲です。探している場所はその線のどこかにあるはず。たしか10マイルと言いましたよね?」
「1時間ほど馬車で走りました」
「気を失ってからも、その道のりを運ばれたとお考えですか?」
「そうならざるを得ません。私自身、どこかへ運ばれるぼんやりした記憶もあります」
「私には納得できないのは、あなたが庭で気絶しているのを発見したときに、なぜ命を助けたのかという点です。もしかすると、あの女性の訴えで悪党も心を動かされたのでしょうか」
「それはまずありえません。あんな容赦ない顔は見たことがありません」
「まあ、それももうすぐはっきりしますよ」とブラッドストリート警部は言った。「さて、円は描きましたが、問題はそのどこに奴らがいるかです」
「私には指し示せる場所がありますよ」とホームズが静かに言った。
「本当ですか!」警部が叫んだ。「あなたは意見がおありなのですね。では、みんなでどこが当たるか試してみましょう。私は南だと思います。あちらは人里離れていますから」
「私は東です」と患者が言った。
「私は西だ」と私服刑事が言った。「あちらには小さな静かな村がいくつもあります」
「私は北にします」と私は言った。「丘がなく、馬車が上り坂を走った記憶がないからです」
「面白いですね」と警部は笑って言った。「みごとに意見が分かれました。さて、誰の意見を採用しましょう?」
「みなさん間違っています」
「でも全員が、ということは……」
「いや、ありえるんです。私の推理ではここです」彼は円の中心を指した。「ここにいるはずです」
「でも、12マイルも馬車で走ったのに?」ハザリー([訳注:原文では患者の名が出ていませんが、物語上‘Hatherley’です])が驚いた。
「6マイル行って、6マイル戻っただけです。簡単なことですよ。あなた自身、乗ったとき馬が元気でつやつやしていたと言いましたよね。もし12マイルも悪路を走っていたら、そんなことはないはずです」
「なるほど、実に巧妙なごまかしですね」とブラッドストリート警部が考え込んだ。「この一味の正体はもう疑いようがありません」
「そうです」とホームズ。「彼らは大規模な偽造犯で、この機械を使い、銀の代用品となる合金を作っていたのです」
「以前から巧妙な一味が活動しているのは分かっていた」と警部は言った。「何千枚もの50セント銀貨を出回らせていた。レディングまでは追跡できたが、そこから先は足取りがつかめなかった。でもこの幸運で、今度こそ捕まえられるでしょう」
しかし警部の期待は外れた。あの犯罪者たちはついに法の裁きを受けることはなかった。私たちがアイフォード駅に到着したとき、近くの木立の向こうから巨大な黒煙が立ち上り、まるでダチョウの大きな羽のように空を覆っていた。
「火事か?」と警部は聞いた。
「はい」と駅長が答えた。「夜中に火の手が上がったと聞いていますが、今や全焼寸前です」
「誰の家だ?」
「ベチャー先生の家です」
「聞きますが」と技師が口を挟んだ。「ベチャー先生はドイツ人で、痩せていて、長く尖った鼻をしていませんか?」
駅長は大笑いした。「いいえ、先生はイギリス人ですし、地元でも立派な方です。ただし、外国人の患者さんが泊まっています。あの方は、もう少しバークシャー牛を召し上がるといいかもしれませんな」
駅長の話が終わらないうちに私たちは火事現場に向かっていた。道は低い丘を越え、前方には白く塗られた大きな建物が、隙間という隙間から火を噴き出しており、庭先では三台の消防車が懸命に放水していた。
「ここだ!」とハザリーは興奮して叫んだ。「あれが砂利道、あれが僕が倒れていたバラの茂み。二つ目の窓が僕が飛び出した窓だ」
「少なくとも、復讐は果たしましたね」とホームズが言った。「あなたの油ランプがプレス機で押し潰され、それが木の壁に火をつけたのでしょう。追跡に夢中だった彼らには気づく余裕もなかったはずです。さて、昨夜の仲間をこの群衆の中で探しましょう。もっとも、今ごろは百マイルは離れているでしょうが」
そして、ホームズの予感通り、その美しい女性、陰気なドイツ人、そして無口なイギリス人の消息は、以後全く途絶えた。その朝早く、農夫が数人と大きな箱を乗せた馬車がレディング方面へ急いでいたのを目撃していたが、足取りはそこで完全に消え、ホームズの知恵をもってしても、彼らの行方はついに分からなかった。
消防士たちは屋内の奇妙な構造に驚き、さらに二階の窓枠で新たに切断された人間の親指を発見して慄いた。しかし日没ごろには火はようやく鎮火したが、屋根は落ち、機械もねじれたシリンダーや鉄パイプ以外は何も残らないほどの廃墟となった。納屋には大量のニッケルとスズが保管されていたが、硬貨は一枚も見つからなかった。すでに述べた大きな箱と無関係ではあるまい。
あの油圧技師が、どうやって庭から意識を取り戻した場所まで運ばれたのかは、もし柔らかい土が証拠を残していなければ永遠の謎だっただろう。足跡から二人に運ばれたこと、それも一人は非常に小さな足、一人は異様に大きな足だったことが分かった。無口なイギリス人が、共犯者よりも臆病か、あるいは殺意が薄かったため、女性と協力して気絶した男を安全な場所に運び出した可能性が高いと考えられる。
「いやはや」と技師は苦々しそうに言った。「私にはひどい事件でしたよ。親指を失い、五十ギニーの報酬も失い、何が残ったというのか」
「経験です」とホームズが笑った。「間接的には役立つかもしれませんよ。その話を語れば、これからは最高の酒席の話題になりますから」
第十話 高名な独身男の冒険
セント・サイモン卿の結婚とその奇妙な結末は、もはや彼が身を置く上流社会において興味の対象ではなくなって久しい。新たなスキャンダルがそれを凌駕し、より刺激的な詳細が世間の噂話の的となり、この四年前の事件から人々の関心をそらしてしまった。しかし、私はこの件の真相が一般には明らかにされていないと確信しており、また私の友人シャーロック・ホームズがこの事案の解明に大きな役割を果たしたことから、彼の回想録をまとめるうえでこの特異な出来事を簡単にでも触れずにはおけないと感じている。
それは私自身の結婚を目前に控えた数週間前、まだベイカー街でホームズと部屋を共にしていた頃のことである。ある日、ホームズが午後の散歩から帰宅すると、一通の手紙がテーブルの上に置かれていた。私はというと、その日は一日中家にこもっていた。天気が急に崩れ、秋の強風とともに雨となり、アフガン遠征で土産に持ち帰った足の中のジャザイル銃の弾が鈍い痛みでうずいていたのだ。私は安楽椅子に体をあずけ、もう一つの椅子に足を投げ出し、周囲を新聞の山で取り囲んでいた。やがて時事ニュースを読み漁って飽き飽きし、新聞を放り出して無気力に天井を眺めつつ、テーブルの上の封筒に描かれた大きな紋章とモノグラムをぼんやりと眺めては、ホームズの高貴な差出人が誰なのかをぼんやりと考えていた。
「ずいぶん格式の高い手紙だね」と、ホームズが入ってきたときに私は言った。「確か今朝の手紙は、魚屋と港湾監視員からだったと思うけど。」
「そうだね、私の手紙は実にバラエティ豊かで面白いよ」と彼は微笑んだ。「ただ、だいたい地位の低い人のほうが、むしろ興味深いものだ。この手紙は、男を退屈させるか嘘をつかせるか、いずれにしても歓迎しがたい社交上の招待状の類だろう。」
彼は封を切り、中身にざっと目を通した。
「いや、これはどうやら面白いことになるかもしれない。」
「社交事ではないのかい?」
「いや、明らかに職業的な依頼だ。」
「しかも高貴な依頼人から?」
「英国でも有数の地位の持ち主だ。」
「それはおめでとう、ホームズ。」
「ワトソン、これは謙遜じゃなく言うが、依頼人の地位よりも事件自体の興味のほうが私には大切なんだ。もっとも、今回の調査ではいずれも欠けていないかもしれないがね。君は最近、新聞を丹念に読んでいたのではなかったか?」
「見てのとおりだよ」と私は苦笑いし、大きな新聞の束を指差した。「他にすることがなかったからね。」
「それは好都合だ。君が私に概要を教えてくれるかもしれない。私は犯罪記事と人生相談欄以外は読まないのでね。後者はいつも示唆に富んでいる。だが、最近の出来事をしっかり追っているなら、セント・サイモン卿の結婚についても知っているはずだ。」
「ああ、もちろん。非常に興味深く読んだよ。」
「それは良かった。今、私が持っているこの手紙はセント・サイモン卿からのものだ。君に読み上げよう。その代わり、君は関連する記事を新聞から探してくれ。内容はこうだ――
〈拝啓 シャーロック・ホームズ様―― バックウォーター卿から、あなたの判断力と慎重さには全幅の信頼を置けると聞きました。 そこで、非常に辛い出来事が私の結婚に関して起こりましたので、あなたに相談したく存じます。スコットランド・ヤードのレストレード警部が既に担当しておりますが、あなたの協力には何の異存もないと申しており、むしろ助けになるかもしれないとも言っております。午後四時に伺いますので、もし他のご予定があれば、どうか本件を最優先としていただきたく存じます。
敬具 セント・サイモン〉
「日付はグロヴナーマンション。羽根ペンで書かれていて、右手の小指の外側にインクの染みをつけてしまったようだ」と、ホームズは手紙を畳みながら述べた。
「四時に来るそうだ。今は三時だから、あと一時間だね。」
「それなら、君の助けを借りて、今のうちに事件の概要を整理できそうだ。その新聞記事をめくって、時系列で並べてくれ。私は依頼人について調べてみよう。」彼は暖炉脇の参考図書の列から赤い表紙の本を手に取った。「これだ」と言って膝の上で開く。「ロバート・ウォルシンガム・ド・ヴィア・セント・サイモン卿、バルモラル公の次男――ふむ。紋章:青地に上部に三つの間馬止め、中央に黒い帯。1846年生まれ。結婚には熟した四十一歳。前政権で植民地担当次官を務めた。父親はかつて外務大臣。父方でプランタジネット家の血筋を、母方でチューダー家の血筋を引く。ふむ、特に目新しいことはないな。ワトソン、君からもう少し実のある情報を頼む。」
「探すのは難しくないよ」と私は言った。「何しろ最近の出来事だし、私も注目していた。ただ、君が調査中だと知っていたので、邪魔をしたくなくて控えていたんだ。」
「ああ、グロヴナー・スクエアの家具運搬車の小事件か。あれはもう解決したよ――第一報から明らかだったがね。で、君の新聞情報を聞かせてくれ。」
「最初に見つけたのは『モーニング・ポスト』の個人欄で、数週間前だ。『ロバート・セント・サイモン卿、バルモラル公の次男と、サンフランシスコのアロイシャス・ドーラン氏の一人娘、ハッティ・ドーラン嬢との婚約が成立し、噂によれば近々結婚式が行われる予定』――これだけだ。」
「簡潔で要点を突いているね」ホームズは、長い細い脚を暖炉のほうに伸ばしながら言った。
「同じ週の社交欄にはもう少し詳しく書かれている。あった、これだ。『婚姻市場に保護が必要な時代が来るかもしれない。自由貿易主義のせいで、英国の名家の家計管理が次々と大西洋を越えてやってきた美しい従姉妹たちの手に渡っている。先週も、そうした魅力的な侵略者による戦利品リストに重要な一頁が加わった。二十年以上も恋の神の矢を寄せ付けなかったセント・サイモン卿が、カリフォルニアの大富豪の麗しき一人娘、ハッティ・ドーラン嬢との婚約を正式に発表したのだ。ドーラン嬢はウェストベリーハウスの祝賀会でその優美な姿と目立つ顔立ちで注目を集めた。彼女は一人娘で、その持参金は六桁を大きく上回ると言われ、将来的な期待もある。バルモラル公がここ数年で絵画を手放さざるを得なかったのは公然の秘密であり、セント・サイモン卿も自分の財産は小さなバーチムーアの地所だけ。よって、この結婚はカリフォルニアの令嬢だけが得をするものではなく、共和制のレディから英国貴婦人への容易でありふれた転身を可能にするものだ』。」
「他には?」とホームズがあくびをしながら聞いた。
「ああ、まだある。その後、『モーニング・ポスト』で、結婚式は非常に内輪で行われ、場所はハノーバースクエアのセントジョージ教会、招待客は親しい友人六人ほどだけで、式後はアロイシャス・ドーラン氏が借りたランカスター・ゲートの家に戻るとのことだ。その二日後――つまり先週の水曜日――には、結婚式が執り行われ、ハネムーンはピーターズフィールド近くのバックウォーター卿の邸宅で過ごすという簡単な発表があった。花嫁が消えるまでに出た記事はこれだけだ。」
「消えるまで?」とホームズが驚いて聞いた。
「花嫁が姿を消したんだ。」
「いつ消えたんだい?」
「結婚披露の朝食の最中に。」
「なるほど、それは当初思ったよりも興味深い。まさに劇的だ。」
「そう、普通ではないと思った。」
「式の前に消えることはあっても、ハネムーン中に消えることもたまにあるが、これほど早いのは記憶にないな。詳細を聞かせてくれ。」
「ただし、情報は非常に不完全だ。」
「だが、少しは補えるかもしれない。」
「今ある情報は、昨日の朝刊に載った一つの記事だけなので、読んでみるよ。見出しは『上流階級の結婚式における奇妙な出来事』だ。
『ロバート・セント・サイモン卿の一家は、彼の結婚に関連して起きた奇妙で痛ましい出来事のため、最大級の困惑に陥っている。式は昨日の新聞で簡潔に発表された通り、前日の朝に執り行われた。しかし、これまで根強く流れていた奇怪な噂が、ようやくここで確認された。関係者が事態の隠蔽に努めたものの、もはや世間の関心が強く、話題にしないのは意味がない。
式はハノーバースクエアのセント・ジョージ教会で簡素に行われ、花嫁の父アロイシャス・ドーラン氏、バルモラル公爵夫人、バックウォーター卿、ユースタス卿、クララ・セント・サイモン嬢(新郎の弟妹)、アリシア・ウィッティントン夫人のみが出席した。全員はその後、アロイシャス・ドーラン氏のランカスター・ゲートの家に移動し、朝食の席についた。だが、ある女性――名は判明していない――が、セント・サイモン卿に何らかの訴えがあるとして無理やり家に入ろうとし、トラブルが発生した。執拗で長引く騒動の末、執事と従僕によって追い出された。花嫁はこの不快な騒ぎの前に幸いにも家に入っており、他の出席者と共に朝食の席についたが、突然体調不良を訴えて自室に引き上げた。長時間戻らなかったため、父親が様子を見に行ったところ、女中から『花嫁はほんの一瞬自室に上がり、オルスターと帽子をつかむと、急いで階段を下りていった』と聞かされた。従僕の一人によると、その装いの女性が家を出るのを見たが、まさか主人だと思わず、来客の中にいると信じていたという。娘が失踪したと知るや、アロイシャス・ドーラン氏と新郎はすぐさま警察に連絡し、精力的な捜査を依頼した。事件の全容解明は間近と見られるが、昨夜遅くまで失踪した花嫁の行方は依然不明である。事件性を疑う噂もあり、最初の騒動を起こした女性が嫉妬や他の動機で失踪に関与したと見て、警察が彼女を逮捕したとの話もある。』」
「それで全部かい?」
「他の朝刊に小さな記事が一つあるが、意味深な内容だ。」
「それは?」
「騒ぎを起こしたフローラ・ミラー嬢が実際に逮捕されたということだ。彼女はかつて『アレグロ』のダンサーで、新郎とも数年来の知り合いらしい。これ以上の詳細はなく、世間に知れた内容はこれで全てだよ。」
「実に興味深い事件だ。これを逃す手はなかった。――だが、ちょうど客が来たようだ、ワトソン。時計を見ると四時を少し回っているから、きっと高貴な依頼人に違いない。君もぜひ同席してくれ。記憶の補助としても、証人がいる方が良い。」
「ロバート・セント・サイモン卿でございます」と、給仕の少年がドアを開けて告げた。入ってきた紳士は上品で教養のある顔立ち、高い鼻に青白い肌、口元にはやや気難しげな表情が浮かび、その瞳は人を指揮し、従わせてきた人の安定感を湛えていた。所作はきびきびしているが、歩き方にはわずかな前傾と膝の曲がりがあり、実際の年齢より老けて見せていた。帽子を脱ぐと、髪の縁は白く、頭頂部は薄かった。衣服は非常に念入りで、ほとんど洒落者といっていい。高い襟、黒いフロックコート、白いベスト、黄色い手袋、エナメル革の靴、明るい色のゲートル。ゆっくり室内に進みつつ、右手で金縁の眼鏡の紐をくるくると回していた。
「こんにちは、セント・サイモン卿」とホームズが立ち上がり、丁寧に会釈する。「どうぞバスケットチェアへ。こちらは友人兼共同研究者のワトソン博士です。暖炉のそばへどうぞ、事件についてお話ししましょう。」
「まったくもって苦しい出来事でして、お察しいただけるでしょう、ホームズさん。私は深く傷ついております。こういった繊細な案件を何度もお扱いになっていると聞いておりますが、同じような身分の方ばかりではないでしょう。」
「いえ、今や階層を下げております。」
「は、何とおっしゃいました?」
「この手の依頼の前回は、ある国王でした。」
「本当ですか! どちらの国王です?」
「北欧の王です。」
「えっ! 王妃を失われたと?」
「ご理解いただけると思いますが」とホームズは穏やかに言った。「他の依頼人のご事情も、今回同様に秘密を守ることをお約束しています。」
「もちろん、それが正しいご対応です。私自身の件については、ご質問には何でもお答えします。」
「ありがとうございます。新聞報道以上の情報は、まだ得ていません。たとえばこちらの記事、花嫁失踪については事実でよろしいですね。」
セント・サイモン卿は記事を一瞥した。「はい、この記事の範囲では事実です。」
「しかし、意見を述べるには補足が多く必要です。いくつか質問するのが一番早そうですね。」
「どうぞ。」
「ハッティ・ドーラン嬢に初めて会ったのはいつですか?」
「一年前、サンフランシスコで。」
「米国を旅行中だったのですか?」
「はい。」
「その時、婚約なさったのですか?」
「いいえ。」
「友好的な関係には?」
「彼女の社交的な様子に、私は楽しませてもらいましたし、それを彼女も感じていたでしょう。」
「お父上は大変な資産家とか?」
「太平洋岸で最も裕福だと言われています。」
「どのように財を築かれたのです?」
「鉱山です。数年前までは何もなかったのに、金鉱を掘り当てて投資し、一気に大金持ちになったのです。」
「さて、彼女――つまりあなたの奥様の性格についてはどのようにお考えですか?」
卿は眼鏡の紐をいっそう早く回しながら、暖炉を見つめて語った。「ご覧の通りです、ホームズさん。妻は二十歳になるまで父親が富豪になる前の自由な環境で育ち、鉱山キャンプで野山を歩き回っていました。ですから教育は教師より自然から受けたものです。イギリスで言うところのじゃじゃ馬娘で、強い意志と自由で伝統に縛られない性格。衝動的で――むしろ爆発的と言ってもいい。決断も早く、信念を貫く勇気があります。その一方で、もし彼女が高潔な女性でなければ、私が自分の名を与えることはありませんでした」――彼は咳払いした――「本質的には自己犠牲もいとわない、卑劣なことを極端に嫌う女性だと信じています。」
「写真はお持ちですか?」
「これを持ってきました。」卿はロケットを開き、私たちに美しい女性の肖像を見せた。それは写真ではなく、象牙のミニアチュールで、漆黒の髪、大きな黒い瞳、しなやかな口元が生き生きと描かれていた。ホームズはしばし見入り、やがてロケットを閉じて返した。
「それで、ロンドンに来て再会されたのですね?」
「はい。父がこのロンドン・シーズンのために連れてきまして、何度か会って婚約し、そして結婚しました。」
「かなりの持参金を持参されたとか?」
「適度な額です。うちの家系ではごく普通の額です。」
「結婚は成立しているので、持参金はあなたのもの、ということになりますね?」
「その点は、まだ特に確認していません。」
「当然ですね。結婚前日、ドーラン嬢には会いましたか?」
「はい。」
「機嫌は良かったですか?」
「これまでで一番明るかった。二人の将来について話し続けていました。」
「それは興味深い。では結婚式当日の朝は?」
「これまた実に快活でした――少なくとも式が終わるまでは。」
「式後に変化はありましたか?」
「実を言うと、その時初めて、多少気性が鋭いところを見た気がします。ただ、それは些細なことで、この事件とは無関係でしょう。」
「念のため、その話も聞かせてください。」
「ああ、まったく子供じみた話なんです。私たちが控え室へ向かう途中、彼女は花束を落としました。そのとき彼女は最前列の信者席の前を通っていて、花束は座席に転がり落ちました。少しの間だけ遅れましたが、その席にいた紳士がすぐに手渡してくれて、花束にも特に損傷はありませんでした。しかし、このことを彼女に話すと、彼女はそっけなく答えましたし、帰りの馬車の中では、この些細な出来事でひどく動揺しているように見えました。」
「なるほど! あなたは、その席に紳士がいたとおっしゃいましたね。つまり、一般の参列者もいたわけですね?」
「ええ、そうなんです。教会が開いているときに一般人を締め出すことは不可能ですから。」
「その紳士は奥様の知り合いではなかったのですか?」
「いいえ、決して。礼儀上、紳士と呼びましたが、見た目もごく普通の人でした。顔立ちなどはほとんど記憶にありません。ですが、本題からかなり逸れてしまっている気がします。」
「それでは、レディ・セント・サイモンは、結婚式から戻ったとき、出発時よりも沈んだ面持ちだったわけですね。ご自宅に戻ってから彼女はどうしていましたか?」
「彼女がメイドと話しているのを見ました。」
「そのメイドとは誰です?」
「アリスといいます。アメリカ人で、カリフォルニアから一緒にやってきました。」
「信頼のおける召使いですか?」
「むしろ、少し行き過ぎているように見受けられました。奥様はメイドに随分と自由を許しているようでした。もっとも、アメリカではそういったことの受け止め方も異なるようですが。」
「どのくらいの時間、アリスと話していました?」
「ほんの数分ほどです。私は別のことを考えていましたので。」
「ふたりの会話は聞いていないのですか?」
「レディ・セント・サイモンが『土地の権利をジャンプする』などと言っていました。ああいうスラングを使うのが癖なんです。意味は全く分かりませんが。」
「アメリカの俗語は時にとても表現豊かですからね。それで、そのメイドと話し終えた奥様は?」
「朝食室へ向かいました。」
「あなたの腕を取って?」
「いいえ、一人で。そういった細かいことではたいへん自立心のある人でした。それから、私たちが着席して十数分ほど経ったころ、彼女は急に立ち上がり、何か謝罪の言葉をつぶやいて部屋を出ていきました。そして二度と戻ってきませんでした。」
「しかし、このメイドのアリスは、自分の部屋に戻り、花嫁衣裳の上から長い外套を羽織り、ボンネットをかぶって出かけていったと証言していますね?」
「その通りです。そしてその後、彼女はフローラ・ミラーという女性と連れ立ってハイドパークへ向かうのを目撃されています。この女性は現在身柄を拘束されており、今朝すでにドラン氏の家で騒動を起こしていました。」
「なるほど、その若い女性とあなたのご関係について、もう少し詳しく教えていただけますか?」
セント・サイモン卿は肩を竦め、眉を上げた。「数年来、親しい間柄でした――いえ、とても親しいと言っていいでしょう。彼女は『アレグロ』にいました。私は彼女に不当な扱いはしていませんし、彼女が私に不満を持ついわれもありません。ですが、ご承知の通り、女性というのは、ホームズさん。フローラは可愛い人でしたが、とても気性が激しく、私に夢中でした。私が結婚することを知ったとき、彼女はひどい内容の手紙を何通もよこしてきました。実のところ、結婚式をこぢんまりと挙げたのも、教会でスキャンダルが起こるのを恐れてのことです。私たちが戻った直後、彼女はドラン氏の家の玄関に来て、中に押し入ろうとし、妻に暴言を浴びせ、さらには脅しまでしました。こういった事態を想定して、私は私服の警官を二人待機させていて、彼女はすぐに追い出されました。騒いでも意味がないと分かった途端、彼女は大人しくなりました。」
「奥様はこの場面をご存じでしたか?」
「いいえ、幸いなことに知らないままでした。」
「その奥様が、その後まさにこの女性と一緒に歩いているところを目撃されたのですね?」
「はい。そこがスコットランド・ヤードのレストレード警部も重大視している点です。フローラが妻を誘い出し、何か恐ろしい罠にはめたのではないか、というのです。」
「ふむ、それも一つの仮説ですね。」
「あなたもそう思われますか?」
「起こり得る、とは言いましたが、ありそうだとは言っていません。しかし、あなたご自身はその可能性をどう見ていますか?」
「フローラが虫一匹傷つけるとは思えません。」
「それでも嫉妬は、人の性格を一変させるものです。あなたご自身はこの出来事についてどんな見解をお持ちですか?」
「うーん、実のところ、私は見解を聞きに来たのであって、自分の説を述べるつもりはなかったのですが……。ですが、お尋ねですので申し上げますと、こうした出来事の興奮や、これほど大きな社会的飛躍を自覚したことで、妻が少し神経衰弱になった可能性も考えています。」
「つまり、突然精神に異常をきたした、と?」
「実際、私に背を向けた――いや、私だけではなく、多くの人が切望しても得られなかった立場に背を向けた、という事実を思うと、他に説明のしようがありません。」
「確かに、それも一つのあり得る仮説ですね」とホームズは微笑んで言った。「さて、セント・サイモン卿、私はほぼ必要な情報を得られたと思います。一つお尋ねしますが、朝食の席では窓の外が見える位置に座っていましたか?」
「通りの向こう側や公園が見えました。」
「なるほど。それでは、これ以上お引き止めすることはないでしょう。改めてご連絡いたします。」
「もしもこの問題を解決できれば」と、依頼人は立ち上がりながら言った。
「すでに解決しています。」
「え? 今なんと?」
「解決済みだと言いました。」
「では、妻はどこに?」
「それはすぐにお知らせします。」
セント・サイモン卿は首を振った。「私やあなたよりももっと賢い人物でなければ無理でしょうな」と言い、古風で威厳のあるお辞儀を残して去っていった。
「私の頭脳を自分と同等に扱ってくれるとは、セント・サイモン卿もなかなか粋ですね」とシャーロック・ホームズは笑いながら言った。「この尋問のあとで、ウイスキー・ソーダと葉巻でも楽しもうかな。依頼人が来る前にすでにこの事件の結論は出ていました。」
「なんと、ホームズ!」
「これまでに似たような事件の記録をいくつか持っています。とはいえ、これほど素早い経過のものはありませんでしたが。私の全ての尋問は、推論を確証へと変えるためのものでした。状況証拠は時に非常に説得力があります。ソローの例えで言えば、牛乳の中からマスを見つけるようなものです。」
「でも、私もあなたと同じ情報しか聞いていませんよ。」
「ただし、私はこうした先行例についての知識がある。それが大きな助けになるのです。数年前アバディーンで似た事件があり、その翌年にはフランス・プロイセン戦争後のミュンヘンでも同様のことがありました。本件もそうした一つです――おっと、レストレードが来ましたね。こんにちは、レストレード! サイドボードの上にもう一つグラスがありますし、葉巻も箱に入っていますよ。」
その公式の捜査官は、ピーコートにスカーフという、いかにも海軍風の格好で黒いキャンバスの鞄を手にしていた。軽い挨拶の後、彼は勧められた葉巻に火をつけて腰を下ろした。
「さて、どうしたんです?」とホームズは目を輝かせて尋ねた。「ご不満のようですね。」
「まったくその通りですよ。この忌々しいセント・サイモン結婚事件ときたら、さっぱり訳が分からん。手がかりは全部指の間からすり抜けていくし、一日中かかりきりでしたよ。」
「本当ですか! それは驚きました。」
「こんなにも混乱した事件がこれまであったでしょうか。手がかりは次から次へと消えてしまう。」
「それにしても、ずいぶん濡れているようですね」とホームズはピーコートの袖に手を置きながら言った。
「ええ、サーペンタイン池を引き揚げてましたから。」
「なんですって? 一体何のために?」
「レディ・セント・サイモンの遺体を捜していたんです。」
シャーロック・ホームズは椅子の背に身を預け、心から愉快そうに笑った。
「トラファルガー広場の噴水も捜索しましたか?」と尋ねた。
「なぜですか? どういう意味です?」
「どちらも同じくらい見つかる見込みしかありませんから。」
レストレードは怒りのこもった視線をホームズに投げた。「あなたは全部ご存じなんでしょうな?」と毒づいた。
「ちょうど今、その事実を聞いただけですが、私の考えはすでに決まっています。」
「ほう、ではサーペンタインは無関係だと思うのですか?」
「極めて可能性は低いと思います。」
「では、なぜ池の中からこれが見つかったのか説明してもらいましょうか?」そう言って彼は鞄を開き、水に濡れて変色した絹のウェディングドレス、白いサテンの靴一足、花嫁の冠とヴェールを床に広げた。「ほら、これです。」その上に新しい結婚指輪を置いてみせた。「どうです、ホームズさん。なかなか解きがいがあるでしょう。」
「ほう、なるほど!」と友人は青い煙輪をくゆらせながら言った。「それをサーペンタインから引き上げたのですか?」
「いえ、正確には池の岸辺付近で公園管理人が見つけたんです。これが彼女の持ち物で間違いないと確認されましたから、服があれば遺体も近くにあるはずだろう、と。」
「その論法なら、どんな男の遺体も洋服ダンスの近くにあることになりますね。それで何を証明しようと?」
「フローラ・ミラーが失踪に関与している証拠を探していたんです。」
「それは難しいのでは?」
「ほう、そう思うのですか?」とレストレードはやや憤慨気味に叫んだ。「ホームズさん、あなたの推理やら論法はどうも現実的じゃありませんね。このドレスがフローラ・ミラー嬢をしっかり証拠付けるのですよ。」
「どういうふうに?」
「このドレスにはポケットがあります。その中にカードケースが。そしてカードケースの中にメモがありました。これがそのメモです。」彼はそれをテーブルに叩きつけた。「お聞きなさい。『すべての準備ができたら私に会いに来て。すぐ来て。F.H.M.』 私はずっと、レディ・セント・サイモンはフローラ・ミラーに誘い出され、その共犯者たちと共に失踪した、と考えています。ほら、彼女のイニシャルで署名されたこのメモが、玄関先でそっと手渡され、誘き寄せられた証拠です。」
「見事ですね、レストレード」とホームズは笑いながら言った。「本当に素晴らしい。ちょっと見せてください。」彼は気のない様子で紙を手に取ったが、すぐに内容に釘付けになり、満足そうな小さな声を上げた。「これは確かに重要ですね。」
「ほう、そう思いますか?」
「非常に重要です。心からお祝い申し上げます。」
レストレードは勝ち誇って身を乗り出し、覗き込んだ。「なんだ、裏側を見てるじゃないか!」
「いや、これが正しい面です。」
「正しい面? 馬鹿な! こっちに鉛筆書きのメモがある。」
「そして、こっちにはホテルの請求書の断片のようなものがあって、私にはそれが非常に興味深い。」
「そんなもの何の意味もありませんよ。私も先に見ました。『10月4日、部屋代8シリング、朝食2シリング6ペンス、カクテル1シリング、昼食2シリング6ペンス、シェリーグラス8ペンス』――何のことやら。」
「あなたにはそうかもしれませんが、これもまた非常に重要なのです。それに、メモも重要です。少なくともイニシャルが、ね。改めてご祝辞を。」
「もう十分時間を無駄にしましたよ」とレストレードは立ち上がった。「私は地道な捜査が信条でしてね。暖炉の前で理屈をこねるのは性に合いません。では、ホームズさん、どちらが先に真相に辿り着くか見ものですね。」彼は衣服を鞄に押し込み、出口へ向かった。
「ひとつだけヒントをあげましょう、レストレード」とホームズは気だるげに呼び止めた。「この事件の本当の解決を教えます。レディ・セント・サイモンなる人物は――存在しないのですよ。そんな人間はこれまでも、これからもいません。」
レストレードは悲しそうにホームズを見て、私の方へ振り向くと、額を三度叩き、重々しく首を振り、足早に去っていった。
彼がドアを閉め終わらぬうちに、ホームズは立ち上がってオーバーコートを羽織った。「外での仕事も大事だ、という彼の意見にも一理あるな。ワトソン、しばらく君は書き物でもしていてくれ。」
ホームズが私のもとを離れたのは五時過ぎだったが、寂しく思う暇もなかった。というのも、まもなく菓子屋の男が大きな平たい箱を持って現れ、連れてきた若者の手を借りて包みを解き始めたのだ。やがて目を見張るような豪華な冷たい夕食が、私たちのささやかな下宿のマホガニーのテーブルの上に並べられていった。冷製のヤマシギ二羽、キジ一羽、フォアグラのパイ、それに古びた蜘蛛の巣だらけの瓶が数本。すべてのご馳走を広げ終えると、二人の配達人はまるでアラビアン・ナイトの魔法使いのように姿を消した。代金はすでに支払われ、この住所に届けるよう手配された、というだけの説明だった。
九時前になると、シャーロック・ホームズが軽快に部屋へ戻ってきた。顔立ちは厳粛だが、その目には自分の推理が外れていなかったことへの確信が宿っているようだった。
「夕食はちゃんと用意されているな」と、彼は手をこすりながら言った。
「お客さんを待っているみたいですね。五人分の用意があるし。」
「ああ、誰かが立ち寄るだろうと思ってね。それにしても、セント・サイモン卿がまだ来ていないとは意外だ。おや、今ちょうど階段を上がる足音が聞こえたようだ。」
それはまさしく朝の訪問者で、いつも以上にメガネを揺らし、貴族らしい顔立ちに動揺が色濃く現れていた。
「私の使いは無事届きましたか?」とホームズが尋ねた。
「ええ、その内容には仰天しましたよ。あなたのおっしゃることは確かな筋の情報なのですか?」
「これ以上ないほど確実です。」
セント・サイモン卿は椅子に沈み、額に手をやった。
「公爵がこの一件を知ったら――家門の者がこんな屈辱に晒されたとなれば……」
「まったくの偶然です。屈辱と呼ぶわけにはいきません。」
「あなたはずいぶん違った見方をなさる。」
「誰かを責めることはできません。むしろ、彼女がもう少し穏やかに事を運ばなかったのが残念ですが、母親もおらず、助言者もいない状況でしたから。」
「これは侮辱です、公然たる侮辱だ」とセント・サイモン卿はテーブルを指で叩いた。
「前例のない状況に置かれたこの少女の立場を考慮すべきでしょう。」
「考慮などしません。私はひどく憤慨していますし、恥ずべき扱いを受けました。」
「今、玄関のベルが鳴ったようですね」とホームズが言った。「ええ、廊下に足音がします。もし私の説得が不十分でしたら、この件についてより成功しそうな弁護人をお呼びしています。」彼はドアを開け、一組の男女を招き入れた。「セント・サイモン卿、ご紹介しましょう。フランシス・ヘイ・モールトンご夫妻です。奥様は、すでにご面識があるかと思います。」
この新たな来訪者の姿を認めるや、依頼人は椅子から跳ね起き、目を伏せ、フロックコートの胸に手を入れて、まさに気高き憤りの体現者のように立ち尽くした。女性はすばやく一歩踏み出し、手を差し出したが、彼は頑なに視線を上げようとしなかった。たぶん、その決意を守るには、それでよかったのかもしれない。彼女の訴えるような表情は、誰にも抗えないものだったから。
「ロバート、怒っているのね」と彼女が言った。「ええ、怒るのも無理ないわ。」
「わざわざ私に謝罪なさらなくて結構です」とセント・サイモン卿は苦々しく言った。
「ええ、本当にひどいことをしたのは分かってるわ。本当なら出ていく前にお話しすべきだったけど、私は取り乱してしまって、フランクと再会した瞬間から、自分が何をしているのか、何を言っているのか分からなくなってしまったの。ただ、祭壇の前で倒れて気絶しなかったのが不思議なくらい。」
「もしよければ、モールトン夫人、私と友人は席を外したほうがいいでしょうか?」
「ひとこと言わせていただければ」と、見知らぬ紳士が口を挟んだ。「この件では、もう十分すぎるほど秘密がありました。私としては、ヨーロッパ中もアメリカ中も、いっそこの事実を知ってくれたほうが気が楽です。」彼は小柄で引き締まった体格、日に焼けた肌、きれいに剃った顔立ちに鋭い眼差しと敏捷な身のこなしを備えていた。
「それでは、すぐにお話ししますわ」と、女性は言った。「フランクと私は1884年、ロッキー山脈近くのマクワイアのキャンプで出会ったの。父が鉱山の権利を持って働いていた場所よ。フランクと私は婚約していたけれど、ある日、父が豊かな鉱脈を掘り当てて大金持ちになったのに、かわいそうなフランクは持っていた権利が尽きてしまって、結局何も残らなかったの。父が裕福になればなるほど、フランクは貧しくなっていき、ついには父は私たちの婚約を認めなくなり、私をサンフランシスコへ連れて行ったの。でもフランクはあきらめなかったわ。彼は私を追ってサンフランシスコに来て、父に知られないように私と会ってくれたの。父に知られたら激怒するだけだったから、私たちは自分たちで将来を決めることにした。フランクは『自分も大金を稼いでくる、その時まで君を迎えに戻らない。でも必ず父と同じくらいの財産を手に入れて帰ってくるから』と言ったの。それで私は彼を待ち続けることを誓い、彼が生きている限り決して他の人とは結婚しないと約束したわ。『それならいっそ、すぐに結婚してしまおう』とフランクは言ったの。『そうすれば君が自分のものだと安心できるし、戻るまでは夫として名乗るつもりもない』と。私たちは話し合い、フランクが手配しておいた牧師さんもいて、すべて整っていたから、その場で結婚したの。そうしてフランクは自分の運を試しに旅立ち、私は父のもとへ戻ったの。
「その後、フランクがモンタナにいると聞き、アリゾナで新しい鉱山を探しているとも聞いたわ。さらにニューメキシコからの便りもあった。そのあと、新聞で鉱山労働者のキャンプがアパッチ族に襲撃され、死亡者の中にフランクの名前があるという長い記事を読んだの。そのとき私は気を失って倒れ、数か月も病床についたわ。父は私が衰弱していると思って、サンフランシスコ中の医者に診せてくれたの。一年以上もフランクの消息は途絶え、本当に死んでしまったのだと疑うこともなかった。その後、セント・サイモン卿がサンフランシスコにやって来て、私たちはロンドンへ渡り、婚約が整ったの。父はとても喜んでいたけれど、私はいつも、私の心の中でフランクの居場所を奪う人間はいないと感じていたの。
「それでも、もしセント・サイモン卿と結婚していたら、もちろん妻としての務めは果たしたつもりよ。愛は自分の意志ではどうにもできないけれど、行動は選べるもの。私は彼と祭壇に立ち、できる限り良い妻になるつもりでいたの。でも、ちょうど祭壇に差しかかったとき、後ろを振り返ると、一番前の席でフランクが私を見つめているのが見えたの。そのときは幽霊かと思ったわ。でももう一度見直すと、やっぱりそこにいて、私が彼を見てうれしいのか悲しいのかを尋ねるような目をしていた。あの時、私は倒れてしまわなかったのが不思議なくらい。あたりがぐるぐる回って、牧師さんの言葉が蜂の羽音のように聞こえてきた。どうしたらいいのかわからなくて……。式を止めて教会で騒動を起こすべきか迷っていると、フランクは私の気持ちに気づいたのか、唇に指をあてて静かにするよう合図してきた。彼は紙に何かを書いているのが見えたので、私に手紙を書いていると分かったわ。教会から出るとき、彼の席の前を通ったので、私は花束を彼に落としたの。その時、彼が花束を返すふりをして私の手に手紙を忍ばせてくれたの。手紙には、彼が合図したら自分のもとへ来てほしい、という一言だけが書かれていた。私はもう、最初の務めは彼にあると疑いなく思い、彼の指示に従うことに決めたの。
「家に戻ると、カリフォルニア時代からの彼の知り合いで、ずっと味方だったメイドに話したの。何も言わずに、いくつか荷物をまとめて、私のオーバーコートを用意するよう命じたわ。本当はセント・サイモン卿に話すべきだったけれど、彼のお母様やあの立派な方々の前で言うのはあまりにも辛かった。ただ逃げてしまってから説明しようと決心したの。食卓に着いてからまだ十分も経っていないうちに、窓の外の向かい側の道にフランクの姿を見つけたの。彼は私に合図して公園の方へ歩き出したから、私はそっと抜け出して、身支度を整えて、後を追ったの。そのとき、途中で誰か女性がセント・サイモン卿について何か話しかけてきたわ。聞き取れた範囲だと、結婚前に彼にも秘密があったように思えたけれど、私はうまくその人のもとを離れて、すぐにフランクに追いついたの。私たちは一緒に馬車に乗り、フランクがゴードン・スクエアに借りていた下宿へ向かったの。待ち続けたあの年月を経て、これが本当の結婚だったのよ。フランクはアパッチ族の捕虜になっていたけれど脱出し、サンフランシスコに戻ってきた時には、私が死亡したものと思ってイギリスへ渡ったことを知り、それを追いかけてきて、とうとうこの再婚の朝に私と再会したの」
「新聞で知ったんだ」とアメリカ人が説明した。「教会の名前と日時は出ていたが、花嫁の住まいまでは載っていなかった」
「それからどうするか話し合ったのだけれど、フランクはすべてを正直に話すべきだと言った一方、私はあまりに恥ずかしくて、みんなの前から消えてしまいたい気持ちだった。父に生きていることだけ手紙で知らせて、あとは姿を消してしまおうかと考えたくらい。あの朝食の席に貴族の方々が待っている中、自分が戻らないという状況を想像するのは本当に恐ろしかったの。だから、フランクが私の結婚衣装や持ち物をまとめて、誰にも見つからないようにどこかに捨ててくれたの。もしこのままだったら、私たちは明日にもパリに向かっていたと思うわ。でも、今晩この親切な方――ホームズさん――が訪ねてきて、どうやって私たちを見つけたのか本当に不思議なんだけれど、とても明快かつ親切に、私が間違っていてフランクが正しいのだと諭してくださったの。秘密にしておくことで自分たちが不利になると気づかせてくれた。その上で、セント・サイモン卿と二人で話す機会をくださると申し出てくださったので、すぐにこちらにまいりました。ロバート、これですべてお話ししたわ。もしあなたを傷つけてしまったのなら本当にごめんなさい。私のことを軽蔑なさらないでくださることを願っています」
セント・サイモン卿は、かたくなな態度を崩さぬまま、しかめ面で唇を固く結びながらこの長い話を聞いていた。
「失礼ですが、私はこのように公の場で最も個人的な話題を論じる習慣はありません」と彼は言った。
「それでは許してはいただけないのですか? せめてお別れの握手だけでも――」
「もちろん、あなたがそれでお喜びになるのであれば」彼は手を差し出し、冷たく彼女の差し出した手を握った。
「できれば、皆で仲良く夕食でも、とホームズさんが提案されたのですが」
「さすがにそれは少々行き過ぎでしょう」と卿は応じた。「最近起きたこの出来事を受け入れるしかないのは認めますが、それを祝って喜ぶ気にはとてもなれません。ご容赦いただきたい、これで皆さまにお別れを申し上げます」そう言って私たち全員に一礼し、堂々と部屋を出て行った。
「では、少なくともあなた方にはぜひご一緒いただきたい」とシャーロック・ホームズは言った。「私はアメリカ人に会うのがいつも嬉しいのです、モールトンさん。なぜなら、私のような者は、かつての王の愚行や大臣の失策が、やがて我々の子孫がユニオンジャックと星条旗の四分割された旗のもと、同じ世界国家の市民となる障害にはならないと信じているからですよ」
「この事件は実に興味深かった」と、訪問者たちが去ったあとホームズは語った。「なぜなら、一見不可解に思える出来事でも、説明は驚くほど単純である場合があることをはっきり示してくれるからだ。この女性の語った出来事の流れほど自然なものはないし、スコットランド・ヤードのレストレード警部のような人間から見れば、結果ほど不可思議なものもないだろう」

「では、あなた自身に落ち度はまったくなかったのですね?」
「最初から二つの事実が明らかだった。ひとつは、女性が進んで結婚式に臨んだこと、もうひとつは、帰宅してからほんの数分でその気持ちを翻したことだ。明らかにその朝、彼女の心を変えさせる何かがあったはずだ。それは何か? 外出中に誰かと話したわけではない。なぜなら、花婿と一緒だったからだ。では誰かに会ったのか? 会ったとすればアメリカからの知り合いだろう。なぜなら、彼女がこの国に来て間もないことから、わずかな滞在でこれほど深く心を動かす人物が現れるとは考えにくい。こうして、消去法によって、彼女がアメリカ人に会った可能性が浮かび上がる。それならば、そのアメリカ人とは誰なのか? なぜこれほどまでに彼女に影響を与えるのか? 恋人か、あるいは夫かもしれない。彼女の若き日々は荒々しい環境の中で過ごしていたと私は知っていた。その状況まで、セント・サイモン卿の話を聞く前に推測できた。彼が私たちに、教会の席にいた男、花嫁の態度の変化、花束を落として手紙を受け取るという分かりやすい仕草、腹心の侍女への相談、そして“クレイムジャンピング”という鉱山用語の暗示――他人の権利を奪うこと――を話してくれた時、全貌は完全に明らかになった。彼女は男と駆け落ちした。その男は恋人、もしくは以前の夫――おそらく後者だったということだ」
「でも、どうやって二人を見つけたのですか?」
「難しかったかもしれないが、レストレード君が持っていた情報は本人が思っている以上に価値があった。イニシャルももちろん重要だったが、それ以上に、彼がこの一週間以内にロンドンでも最高級のホテルのひとつで支払いを済ませたという事実が決め手だった」
「最高級とどうして分かったのです?」
「料金で分かった。寝台が8シリング、シェリーが1杯8ペンスなど、ロンドンでも屈指の高級ホテルしか取り得ない値段だ。そんなホテルは多くない。ノーサンバランド・アベニューの二軒目を訪ねてみると、フランシス・H・モールトンというアメリカ紳士が前日に退去したばかりだと分かった。帳簿で彼の名の項目を調べると、まさに見覚えのある請求明細が記されていた。彼の郵便物はゴードン・スクエア226番地に転送とあったので、そこへ行き、幸運にも二人が在宅中であったため、父親のような忠告をして、世間とセント・サイモン卿にも立場を明らかにした方がよいと指摘した。こちらで再会するよう彼らを招き、卿を呼び出したというわけだ」
「でも、結果はあまり良くなかったですね」と私は指摘した。「卿の態度は決して寛大とは言えませんでした」
「ワトソン」とホームズは微笑んで言った。「しかし、あれだけの努力をして求婚し結婚までこぎつけ、妻と財産を一瞬で失う身になったら、君もあんなに寛大ではいられないだろう。我々はセント・サイモン卿を寛大に見てやり、そして自分たちが同じ立場に立つことのない星に感謝すべきだ。さあ椅子を引き寄せて、私のヴァイオリンを取ってくれたまえ。あとは、物憂い秋の夜長をどう過ごすかという問題だけが残っている」
第十一冒険 ベリルの冠
「ホームズ」と私はある朝、窓辺に立って通りを眺めながら言った。「狂人がやってくるよ。家族がひとり歩きさせるのは気の毒じゃないか」
友人は椅子からゆったりと立ち上がり、ガウンのポケットに手を入れたまま私の肩越しに外を覗いた。明るく澄み渡った二月の朝で、昨夜降った雪がそのまま地面に深く積もり、冬の日差しの下で輝いていた。ベーカー街の中央は往来によって茶色く崩れた帯になっていたが、歩道の端や雪かきされた小山の上には、降ったままの白い雪が残っている。灰色の舗道も掃除されていたが、まだ滑りやすくて、通行人は普段より少なかった。実際、地下鉄の駅の方から来るのは、私の注意をひいた奇妙な男性一人だけだった。
彼は五十歳ほど、背が高く堂々とした体格で、がっしりとした特徴的な顔立ちに威厳のある雰囲気をまとっていた。黒のフロックコートに光沢のある帽子、きちんとした茶色のゲートル、仕立ての良いパールグレーのズボンという控えめながらも上品な服装だった。それなのに、彼の行動はその威厳とまったく正反対で、まるで運動に慣れていない男が無理に走るかのように、時折勢いよく跳ねたりしながら必死に走っていたのだ。走りながら手を上下に振り、頭を揺らし、顔をありえないほどゆがめていた。
「一体どうしたんだろう?」と私は尋ねた。「家の番号を見上げているよ」
「きっとここに来るんだよ」とホームズが手をこすりながら言った。
「ここに?」
「ああ、たぶん私に相談があって来るのだと思う。症状に見覚えがある。ほら、言った通りだろう?」ホームズがそう言う間にも、男は息を切らして玄関に駆け込み、ベルを鳴らし続け、家じゅうに響き渡った。
数分後、彼はまだ息を切らし、身振り手振りもそのままに私たちの部屋に現れたが、その目に浮かぶ悲しみと絶望のあまりの強さに、私たちの微笑みは一瞬で恐怖と同情に変わった。しばらくは言葉も出ず、体を揺らし、髪を引き抜くようにして、まさに理性の限界まで追い詰められた者のようだった。そして突然、彼は跳ね上がると壁に頭を打ち付け始めたので、私たちは慌てて駆け寄り、引き離して部屋の中央へ連れてきた。シャーロック・ホームズは彼を安楽椅子に押し込め、その隣に座ると、彼の手を優しく叩きながら、あの人を和ませる独特の穏やかな口調で話しかけた。
「ご自分のご事情をお話しにいらしたのですね?」とホームズ。「お急ぎでお疲れでしょう。どうぞ落ち着かれてから、どんなご相談でも詳しくお聞かせくだされば幸いです」
男はしばらく胸を上下させながら感情と戦っていたが、やがてハンカチで額を拭い、唇をきつく結び、こちらを向いた。
「私が狂人だと思われたでしょう?」と彼は言った。
「大変なご苦労をされたのだと察します」とホームズは答えた。
「神のみぞ知る、私は本当に――それほどまでに突然で恐ろしい出来事なのです。公の場での不名誉ならば、私はこれまで非の打ち所のない名声を保ってきた男ですから、受けて立つ覚悟もありました。私的な不幸も人生にはつきものです。しかし、その二つが同時に、しかもこのような恐ろしい形で訪れたからには、魂まで揺さぶられるのです。しかも、私だけではありません。もしこの恐ろしい事件の解決策が見つからなければ、この国の最も高貴な方々も苦しむことになるかもしれません」
「どうか落ち着いて、ご自身のこと、そして何が起きたのかを詳しくお聞かせください」とホームズは言った。
「私の名は、ご存知かもしれませんが、ホルダー&スティーブンソン銀行のアレクサンダー・ホルダーと申します。スレッドニードル街にあります」
その名は確かに、ロンドンで二番目に大きな私立銀行の代表として、私にもよく知られていた。そんな著名な市民をここまで追い詰めたのは一体何事か? 私たちは好奇心いっぱいで待ち構えていたが、彼は気力を振り絞って話し始めた。
「時間が貴重だと感じまして」と彼は言った。「だからこそ、警察の警部があなたの協力を得るよう勧めてくれた時、すぐに駆けつけたのです。ベーカー街まで地下鉄で来て、そこからは徒歩でした。雪で馬車が進まず息が切れましたが、私は普段運動をしない人間なので。今はだいぶ落ち着きましたので、簡潔かつ明瞭に事実をお話しします。
「ご存知の通り、銀行業においては、預金者を増やすだけでなく、資金を有利に運用することも大切です。そのなかでも、確実な担保があれば融資という形でお金を運用するのが最も利益率の高い方法のひとつです。近年、私たちはこの方法で多くの貴族に、絵画や書庫、銀器などを担保にして多額の貸付を行ってきました。
「昨日の朝、私は銀行のオフィスにいたところ、事務員がカードを持ってきました。その名前を見て私は思わず身を乗り出しました。何しろ、それは――いや、あなた方にさえ名前を明かすのは控えたほうがいいかもしれませんが、世界中の家庭に知れ渡るほど、イギリスでも屈指の高貴な人物の名前だったのです。その名誉に圧倒されつつも、彼が入室するや否や、すぐに本題に入る気配でした。
『ホルダーさん』と彼は言いました。『あなたのところは資金の貸付も行っていると聞きました』
『担保が確かであれば、当行では貸付も行っております』と私は答えました。
「『私にはどうしても今すぐ五万ポンドが必要なのです』と彼は言いました。『もちろん、こんな小額なら友人から十回でも借りられますが、私はむしろこれをビジネスとして扱い、自分で手続きを進めたいのです。私の立場をご理解いただければ、誰かに借りを作るのは賢明でないことがお分かりでしょう。』
『その金額を、どのくらいの期間ご入用なのですか?』と私は尋ねました。
『来週の月曜日には、私に多額の入金がある予定です。その際に必ず、お貸しいただいた金額と、あなたが妥当と思われる利子をお支払いします。しかし、どうしても今すぐにこのお金が必要なのです。』
『もし私の個人資産に余裕があれば、すぐにでもお貸ししたいのですが、そうすると少々無理をすることになるでしょう。ですが、会社としてお貸しするとなると、共同経営者の立場から申し上げて、たとえあなた様でも、きちんとしたビジネス上の手続きを踏まねばなりません。』
『その方がむしろありがたい』と彼は言い、椅子の脇に置いてあった四角い黒のモロッコ革のケースを持ち上げました。『ベリルの冠をご存知でしょう?』
『帝国の最も貴重な国有財産の一つですね』と私は答えました。
『まさにその通りです』。彼はケースを開きました。中には淡い肌色のビロードに包まれた、彼が名を挙げた見事な宝冠がありました。『巨大なベリルが三十九個も使われており、金細工の価値も計り知れません。この冠の最低評価でも、私がお願いした金額の倍になります。私はこれを担保として、あなたにお預けします。』
私はその貴重なケースを手に取り、困惑しながらそれとご依頼人を見比べました。
『価値に疑いをお持ちですか?』と彼は尋ねました。
『いえ、まったく。ただ……』
『私がこれを置いていくのが適切かどうか、ということでしょう。それについてはご心配なく。もし四日後に確実に取り戻せるという確信がなければ、こんなことは決してしません。これは形式的なものにすぎません。担保として十分でしょうか?』
『申し分ありません。』
『ホルダーさん、私はあなたに絶大な信頼を寄せている証として、これをお預けします。あなたの評判を伺ってのことです。どうかこの件を他言せず、何よりもこの冠を細心の注意をもってお守りください。もし何かあれば大きな社会的スキャンダルとなってしまいます。損傷ですら、紛失と同じくらい深刻です。このベリルは世界に他に存在せず、代替は不可能です。それでも私はあなたを信じて預けます。月曜の朝、自分で引き取りに伺います。』
ご依頼人が早く帰りたがっているのを見て、私はそれ以上何も言わず、会計係を呼び、五十枚の千ポンド紙幣を支払うよう命じました。しかし再び一人になり、貴重なケースが目の前のテーブルにあるのを見つめると、その責任の重さに不安を感じずにはいられませんでした。国有財産である以上、もし何かあれば恐ろしいスキャンダルになるのは間違いありません。すでに引き受けたことを後悔し始めました。しかし、今さら断るわけにもいかず、私はそれを自分の金庫にしまい、再び仕事に戻りました。
夜が来て、これほど貴重なものを事務所に置きっぱなしにするのは軽率だと感じました。銀行の金庫ですら破られた例があるのです、私の金庫が狙われない保証はありません。もしそうなれば、私はとんでもない立場に追い込まれてしまいます。そこで、数日間はこのケースを毎日持ち歩き、決して手元から離さないことに決めました。そのためにタクシーを呼び、宝冠を持ってストリサムの自宅へ向かいました。二階の寝室の書き物机にそれをしまい、やっと安心できました。
さて、ホームズさん、ここで私の家族についてお話ししておきたいのです。この状況をよくご理解いただくために。私の馬丁と下僕は屋敷の外で寝起きしており、除外して構いません。女中は三人、長年仕えており、信頼性は疑う余地がありません。もう一人、ルーシー・パーは、二人目の侍女で、数か月前から雇っていますが、前歴も良く、これまで問題はありませんでした。とても美しい娘で、しばしば若い男性が彼女を目当てに家の周りをうろつくことがありますが、それ以外には何の問題もありません。
これが使用人の状況です。家族と言っても少人数ですので、説明も簡単です。私は妻に先立たれ、一人息子アーサーがいます。彼には大変失望させられてきました、ホームズさん――本当に辛い思いをしました。私自身が悪いのでしょう。周囲からは甘やかしすぎだと言われます。確かにそうかもしれません。妻が亡くなったとき、彼だけが私の心の支えでした。彼の笑顔が曇るのを見るのが耐えられず、望むことは何でも叶えてきました。もっと厳しくしていれば良かったのかもしれませんが、私は精一杯のことをしてきたつもりです。
当然、彼が将来私の事業を継ぐことを望んでいましたが、彼は商才がありませんでした。奔放で気まぐれで、正直に言えば、大金を任せるのが不安でした。若い頃、上流階級のクラブに入り、魅力的な性格のせいで裕福な友人がすぐにできました。カードにのめり込み、競馬に大金をつぎ込んでは、繰り返し私のもとに来ては手当てを頼むようになったのです。危ない仲間から抜け出そうと努力したこともありましたが、サー・ジョージ・バーンウェルの影響で毎回元に戻ってしまいました。
実際、サー・ジョージ・バーンウェルほどの男が彼に影響力を持つのも無理はありません。彼はしばしばアーサーと一緒に我が家を訪れましたが、私でさえ彼の魅力には抗えないほどでした。アーサーより年上で、世の中を知り尽くし、話術も抜群、しかも極めてハンサムです。しかし冷静に考えると、その皮肉な物言いや時折見せる目つきから、決して信用してはいけない人物だと確信しています。私もそう思っていますし、女性特有の直感で人を見る娘のような存在、メアリーも同じ考えです。
そのメアリーについても触れておきます。彼女は私の姪ですが、五年前に弟が亡くなり天涯孤独になったので、私が引き取り、以来、実の娘のように接してきました。彼女は家の太陽のような存在――優しく、愛情深く、美しく、家事もやりくりも素晴らしいのに、控えめで穏やかで、とても女性らしい人です。彼女は私の右腕で、いなくてはならない存在です。彼女が私の意に背いたのはただ一度、アーサーが二度求婚しましたが、いずれも断りました。もし誰かがアーサーを更生させられるとしたら彼女だったでしょうし、結婚すれば息子の人生も変わったでしょう。でも今となっては、もう手遅れなのです――永久に。
これで、ホームズさん、私の家に住む者全員をお伝えできましたので、話を続けます。
その夜、夕食後に居間でコーヒーを飲みながら、アーサーとメアリーに例の出来事、そして我が家にある貴重なお宝のことを話しました。ただし依頼人の名前だけは伏せました。コーヒーを運んだルーシー・パーは、確かに部屋を出ていましたが、扉が閉まっていたかは断言できません。メアリーとアーサーは大いに興味を示し、有名な冠を見たがりましたが、私は動かさない方がいいと思いました。
『どこにしまったの?』とアーサーが聞きました。
『私の書き物机の中だよ』
『今夜泥棒が入らなきゃいいけど』と彼が言いました。
『ちゃんと鍵をかけてある』と私は答えました。
『そんな机、どんな古い鍵でも開くよ。俺は子供の頃、物置の鍵で開けたことがあるんだ』
彼は時々突拍子もないことを言うので、私は気にも留めませんでした。しかしその夜、彼は真剣な顔で私の部屋までついてきました。
『父さん……』とうつむいて、『二百ポンド貸してくれないか』
『いや、できない!』私はきっぱり言いました。『金銭面では今まで十分すぎるほど甘やかしてきた』
『本当に感謝しているよ。だけど、どうしてもこのお金がなきゃ、もうクラブに顔向けできないんだ』
『それはむしろ良いことだ!』と私は叫びました。
『でも、不名誉なまま辞めるのは耐えられない』と彼は言いました。『なんとかして金を工面しなければならない。貸してくれないなら、他の手を考えるしか……』
私は非常に腹が立ちました。今月に入って三度目の要求だったからです。『もう一銭もやらん!』と叫び、彼は黙って頭を下げ、部屋を出て行きました。
彼が去ったあと、私は書き物机を開け、冠が無事か確認し、また鍵をかけました。その後、家中がちゃんと施錠されているか見回りました――普段はメアリーに任せていますが、その夜は自分で確かめておこうと思ったのです。階段を下りると、メアリーが玄関脇の窓を閉めているのを見かけました。
『父さん……』と少し不安そうな顔で言いました。『ルーシーに今夜外出を許可した?』
『いや、していない』
『さっき裏口から帰ってきたの。きっと誰かに会いに横門まで出ていただけだと思うけど、あまりよくないし、やめさせた方がいいわ』
『明日の朝あなたから言ってあげなさい。あるいは私が言ってもいい。戸締まりは大丈夫か?』
『ええ、全部確かめたわ、父さん』
『なら、おやすみ』。私は彼女にキスをして、自分の寝室に戻り、すぐに眠りにつきました。
ホームズさん、私は事件に関係しそうなことは漏らさずお伝えしているつもりですが、説明が不十分な点があれば、どうぞご質問ください」
「いえ、非常に分かりやすいご説明です」
「ここからが特に丁寧にお話ししたい部分です。私はあまり眠りが深くないのですが、その夜は心配からいつも以上に眠りが浅かったのでしょう。午前二時ごろ、家の中で物音がして目が覚めました。目覚めたときには音は止んでいましたが、どこかで窓が静かに閉まったような印象が残っていました。耳を澄まし、じっと聞き入っていると、突然、隣の部屋で誰かがそっと歩くはっきりした足音がしたのです。私は胸が高鳴りながらベッドから抜け出し、ドレッシングルームの扉の陰から様子をうかがいました。
『アーサー!』私は叫びました。『なんてことを! 泥棒! よくもその冠に手を触れたな!』
ガス灯は半分つけたままでした。見るとシャツとズボン姿の息子が光のそばに立ち、冠を手にしています。彼はそれをこじ開けようとしているか、力一杯曲げているようでした。私の叫びに手を離し、死人のように青ざめました。私は冠を取り上げて調べると、金の角の一つ、三つのベリルがついていた部分がなくなっていました。
『この罰当たりめ!』私は逆上して叫びました。『壊してしまった! これで私は永久に名誉を失った! 盗んだ宝石はどこだ!』
『盗んだだって!?』彼は叫びました。
『そうだ、この泥棒め!』私は肩を掴んで怒鳴りました。
『盗まれたものなんてない、そんなはずがない』と彼。
『三つ無くなってるじゃないか。お前はそれを知っているはずだ。まだもう一つ外そうとしているのを見たぞ』
『もうたくさんだ』と彼は言いました。『これ以上侮辱されて黙ってはいない。この件についてはもう一言も言わない。明日、家を出て自分の道を歩く』
『警察に引き渡す!』私は悲しみと怒りに我を忘れて叫びました。『この件は徹底的に究明させる』
『私からは何も聞き出せませんよ』と彼は、普段からは考えられないほど激しい口調で言いました。『警察を呼ぶなら、警察が好きなだけ調べればいい』
この頃には騒ぎで家中が目を覚ましていました。最初にメアリーが駆け込んできて、冠とアーサーの顔を見てすべてを悟り、叫び声を上げてその場に倒れました。私は女中に警察を呼ばせ、そのまま事件を警察に委ねました。警部と巡査が家に入ると、アーサーは腕を組んで黙って立ち、私に「窃盗の罪で告発するつもりか」と尋ねました。私は「これはもはや私的な問題ではなく、国有財産を損なった以上、公の問題だ」と答えました。私は法の裁きを受けさせる決意でした。
『せめて、すぐに逮捕するのはやめてくれ。わずか五分間だけでも家を出させてくれれば、君にも私にも都合がいい』と彼は言いました。
『逃げるか、あるいは盗んだ物を隠すつもりだろう』と私は言いました。そして、自分が追い詰められていることを思い知ると、私は彼に、私の名誉だけでなく、私よりはるかに偉大な人の名誉も危険に晒されていると懇願しました。三つの石がどうなったかさえ話してくれれば、すべての騒ぎは避けられるのだと。
『腹をくくれ』と私は言いました。『現行犯で捕まったのだから、何を白状しても罪が重くなることはない。せめてできる限りの償いとして、ベリルのありかを教えてくれさえすれば、すべて水に流してやる』
『赦しがほしい奴に赦しをくれてやれ』と彼は私に背を向け、嘲るように言いました。もう私の言葉が彼に通じることはないと悟りました。もはや打つ手は一つしかありません。私は警部を呼び、彼を拘束させました。すぐに彼の身と部屋、家の隅々まで捜索が行われましたが、宝石の痕跡はまったく見つからず、どんなに説得しても彼は一言も口を開きませんでした。今朝、彼は留置場に移され、私は警察での手続きを終えた後、急いであなたのもとに駆けつけ、どうかこの事件を解明してほしいとお願いしている次第です。警察も現時点では全くお手上げ状態です。必要な出費は一切惜しみません。すでに千ポンドの懸賞金も出しました。ああ、どうすればいいのでしょう! 私は一夜にして名誉も宝石も息子も失ってしまいました。どうすればいいのでしょう……」
彼は両手で頭を抱え、言葉もなく泣きじゃくる子どものように前後に揺れ続けた。
シャーロック・ホームズはしばらく眉をひそめ、炎をじっと見据えたまま黙っていた。
「お客はよくいらっしゃいますか?」とホームズが尋ねた。
「私の共同経営者とその家族、それにアーサーの友人が時折。最近はサー・ジョージ・バーンウェルが何度か訪れました。他にはいません」
「社交の場にはよく出かけますか?」
「アーサーはよく出かけますが、私とメアリーは家にいます。どちらも社交が好きではありません」
「若い女性にしては珍しいですね」
「彼女はおとなしい性格でして。それに、もうそれほど若くもありません。二十四歳です」
「あなたの話からすると、今回の件は彼女にも大きな衝撃だったようですね」
「ひどいものです。私よりもショックを受けています」
「お二人とも、息子さんの有罪を疑っていないのですね?」
「どうして疑えるでしょう。私自身、彼が冠を手にしているところをこの目で見たのです」
「それだけでは決定的な証拠とは思いません。冠の他の部分に損傷は?」
「はい、曲がっていました」
「では、彼はそれを元に戻そうとしていた可能性もあるのでは?」
「神よ……あなたは私と彼のために最善を尽くしてくださっている。でも、それはあまりにも難しい課題です。なぜ彼はあの部屋にいたのでしょう? もし何のやましさもなかったなら、なぜ説明しなかったのでしょうか?」
「まさにその通りです。そして、もし彼が本当に犯人だったのなら、なぜ嘘をつかなかったのでしょう? 彼の沈黙は、私には両方の可能性を示しているように思えます。この事件には他にもいくつか奇妙な点があります。警察は、あなたの眠りを覚ましたあの物音についてどう考えているのですか?」
「警察は、それはアーサーが自分の寝室のドアを閉めた音かもしれない、と考えています。」
「ありそうな話ですね! まるで犯行を企てている男が、家中を起こすほどドアをバタンと閉めるとでも言うようなものです。それで、宝石が消えたことについては何と言っていましたか?」
「まだ床を叩いてみたり、家具を調べたりして、見つかるのを期待しています。」
「家の外を捜すことは考えましたか?」
「はい、驚くほど熱心に捜索しています。庭全体を念入りに調べ終えています。」
「さて、ホルダーさん」ホームズは言った。「これで、この事件があなたや警察が最初に思ったよりもずっと深刻なものだと、今は明白ではありませんか? あなたには単純な事件に思えたかもしれませんが、私には極めて複雑に見えます。あなたの仮説で考えると、どうなるでしょう。つまり、あなたの息子が寝室を出て、危険を冒してあなたの更衣室に行き、ビューローを開けて冠を取り出し、その一部を力ずくでちぎり取り、別の場所へ行き、三十九個のうち三つだけを誰にも見つからないよう巧妙に隠し、残り三十六個は最も発見されやすい部屋に持ち帰った――。こんな仮説が成り立つと思いますか?」
「でも、他にどんな説明があるのですか?」と銀行家は絶望的な身振りで叫んだ。「もし彼にやましい動機がなかったのなら、なぜ説明しないのでしょう?」
「それを見つけるのが我々の役目です」とホームズ。「ですからホルダーさん、これからご一緒にストリートハムへ向かい、この件をもっと詳しく調べてみましょう。」
ホームズは私も同行するよう強く勧めた。私はこの話に強く心を動かされ、興味と同情が高まっていたので、喜んで同行した。銀行家の息子の有罪は父親と同じくらい明白に思われたが、それでもホームズの判断力を信じていたので、彼が納得していない以上、まだ希望があるに違いないと感じていた。道中、ホームズはほとんど口を開かず、顎を胸にうずめ帽子を深くかぶって、沈思黙考していた。依頼人は、差し込んだ一筋の希望に少し元気を取り戻し、私と仕事の話などをしながら、雑談する余裕さえ見せた。短い鉄道の旅とさらに短い徒歩で、私たちは偉大な金融家の質素な邸宅フェアバンクに到着した。
フェアバンクは白い石造りのかなり大きな四角い家で、道路から少し奥まったところに建っていた。雪に覆われた芝生の前庭には馬車が通る円形の車寄せがあり、大きな鉄門が二つ、入り口を閉じていた。右手には小さな木立があり、そこから道に沿った二つの生け垣の間を通り抜けて台所の戸口へ至る狭い通路、つまり業者専用の入口があった。左手には厩舎へ続く小道が敷地外に伸びており、あまり使われない公道となっていた。ホームズは私たちを玄関で待たせ、家の周りをゆっくりと回り、正面、業者用の通路、裏庭から厩舎への小道へと歩いた。かなり長く家の外を調べていたので、ホルダーさんと私は暖炉の前でホームズの帰りを静かに待っていた。
私たちが座っていると、ドアが開き若い女性が入ってきた。彼女は中背よりやや高く、細身で、黒髪と黒い瞳が、肌の蒼白さをより一層際立たせていた。私が見た中で、これほど死にそうなほど青ざめた女性の顔は他に思い出せない。唇も血の気を失っていたが、目元には泣き腫らした跡があった。静かに部屋へ入ってきた彼女は、朝の銀行家よりもずっと深い悲しみを私に感じさせた。しかも彼女は明らかに強い意志を持ち、並外れた自制心の持ち主だった。私の存在を気にも留めず、まっすぐ叔父のもとへ行き、優しい女性らしい仕草で彼の頭を撫でた。
「お父さま、アーサーを釈放してくれるよう頼んだのでしょう?」
「いや、まだだよ。事の真相を徹底的に調べるまではできない。」
「でも、私は彼が無実だと確信しているの。女性の直感って、わかるでしょう? 彼は悪いことはしていないし、あなたが厳しくしたことを後悔することになるわ。」
「でも、もし無実ならなぜ沈黙を守る?」
「誰にも分かりません。きっと疑われたことが悔しくて、何も言わなかったのでしょう。」
「私がどうして疑わずにいられようか。実際に彼が冠を手にしているのを見たのだぞ。」
「でもそれは、ただ手に取って見ていただけよ。どうか、彼が無実だと私の言葉を信じて。もうこの話は終わりにして、何も言わないでください。可哀そうなアーサーが牢に入っているなんて、耐えられない!」
「宝石が見つかるまでは決して終わらせない――絶対にだ、メアリー! お前のアーサーへの愛情が、私への恐ろしい影響を見えなくしている。隠そうとするどころか、私はロンドンから紳士を呼んで、さらに徹底的に調べてもらっている。」
「この方?」と彼女は私を見て尋ねた。
「いや、彼の友人だ。彼は一人で調べたがっている。今は厩舎の裏手にいる。」
「厩舎の裏手ですって?」彼女は黒い眉を上げた。「いったいそこで何が見つかるというの? ――あっ、きっとこの方ね。どうか、私が確信している真実、すなわち従兄アーサーがこの罪に無関係であることを証明してくださいますように。」
「私もまったく同じ意見です。そしてあなたと共に、それが証明できることを願っています。」ホームズは靴の雪をマットで払いつつ答えた。「お目にかかります、ミス・メアリー・ホルダー。いくつかお尋ねしてもよろしいでしょうか?」
「どうぞ先生。この恐ろしい事件の解明に役立つのでしたら。」
「昨夜、ご自分では何も音を聞かなかったのですか?」
「ええ、叔父が大声を出すまでは何も。あの声を聞いて、私は降りてきました。」
「前夜、窓やドアを閉めたのはあなたですね。すべての窓を施錠しましたか?」
「はい。」
「今朝も全て閉まっていましたか?」
「はい。」
「あなたのメイドには恋人がいますね? 昨夜、叔父にそう話したと記憶していますが?」
「そうです。居間で給仕をしたのもその娘で、もしかすると叔父の冠についての話を聞いていたかもしれません。」
「なるほど。つまり彼女が恋人のもとへ出て行き、二人で盗みを企てた可能性がある、ということですね。」
「でも、そんなあやふやな仮説をいくら立てても仕方ないじゃありませんか!」と銀行家は苛立ちを見せた。「私はアーサーが冠を持っているのを見たんですよ?」
「少し待ってください、ホルダーさん。その話はいずれ戻るとして――この娘のことで、ミス・ホルダー。彼女が台所の扉から帰ってくるのを見ましたね?」
「はい。夜の戸締まりを確認しに行ったとき、彼女がこっそり入ってくるのに出くわしました。暗がりに男の人も見ました。」
「その男はご存じですか?」
「はい、あれは野菜を配達してくれる八百屋さんです。フランシス・プロスパーという人です。」
「彼は扉の左側、つまり必要以上に玄関から離れたところに立っていましたか?」
「ええ、そうでした。」
「その男は義足ですか?」
ミス・ホルダーの黒い瞳に、恐怖のようなものが浮かんだ。「まあ、まるで魔法使いみたいですね。どうしてわかったんですか?」と微笑みながらも、ホームズの鋭い顔に微笑みは返らなかった。
「では、今すぐ二階を拝見したいのですが」とホームズ。「その前に下の窓をもう一度見ておきたい。」
彼は家の窓をひとつひとつ素早く調べ、特に玄関ホールから厩舎の小道を見渡せる大きな窓だけは、じっくりと強力な虫眼鏡で窓枠を調べた。「では、二階へ行きましょう。」とついに言った。
銀行家の更衣室は、灰色のカーペットが敷かれた質素な小部屋で、大きなビューローと長い鏡があった。ホームズはまずビューローの錠前をじっと見つめた。
「どの鍵で開けたのですか?」
「息子自身が示した、納戸の戸棚の鍵です。」
「お手元に?」
「はい、化粧台の上にあります。」
シャーロック・ホームズは鍵を手に取り、ビューローを開けた。
「音のしない錠前ですね。これではあなたが気づかないのも無理はありません。これが冠の入っていたケースでしょうか。中を拝見します。」彼はケースを開けてダイアデムを取り出し、テーブルに置いた。それは見事な宝飾技術の一品で、三十六個の石はかつて見た中でも最高級だった。冠の一方の端はひび割れており、三つの宝石の付いた隅が引きちぎられていた。
「さて、ホルダーさん。こちらが失われた角に対応する部分です。ぜひ、これを折ってみていただけますか。」
銀行家は恐怖で後ずさりした。「とても試す気になれません。」
「では、私が。」ホームズは突然、指に力を込めたが、びくともしなかった。「少しはたわみますが、私の指でも今すぐ折るのは無理ですね。普通の人では到底できません。仮に私が折ったとすれば、ピストルの発射音ほどの大きな音がするでしょう。これがあなたの寝室のすぐ近くで起きたのに、あなたは何も聞かなかったのですか?」
「何が何だかわかりません。全てが謎です。」
「ですが、これから少しずつ明らかになるかもしれません。どう思いますか、ミス・ホルダー?」
「私も叔父と同じく困惑しています。」
「あなたが見たとき、息子さんの足には靴もスリッパもありませんでしたね?」
「はい。ズボンとシャツだけでした。」
「ありがとうございます。今回の捜査では運が非常に良かったので、この事件を解決できなければ、それは我々自身の落ち度ということになります。これから外をもう少し調べさせていただきます。」
ホームズは自分一人で外の調査に向かった。余計な足跡ができると作業が困難になるという説明だった。1時間以上も作業し、ついに雪まみれの靴といつもの無表情で戻ってきた。
「ホルダーさん、これで見るべきものは全て見ました。今後は自室に戻っての作業が最善です。」
「でも、ホームズさん、宝石はどこに……?」
「まだ分かりません。」
銀行家は両手を握りしめて叫んだ。「もう二度と見つからないでしょう! それに息子は? 希望はないのですか?」
「私の意見は変わりません。」
「それでは一体、昨夜私の家で起きたこの闇の出来事は何だったのですか?」
「明朝9時から10時の間にベイカー街の私の部屋に来ていただければ、できる限りお話ししましょう。私が捜査に全権を持ち、宝石さえ返還できれば報酬に上限は問わない、ということでよろしいですね?」
「財産を投げ打ってでも取り戻したい。」
「承知しました。それでは今日中に調査を進めます。さようなら。場合によっては今晩中に再度こちらへ来るかもしれません。」
ホームズが事件の全貌を心中で把握したことは、私には明らかだった。しかしその結論がどんなものかは、想像すら出来なかった。帰り道にも何度か話を振ったが、ホームズはいつもうまく話題をそらし、ついに私は諦めてしまった。まだ午後3時前に私たちは自宅に戻った。ホームズはすぐ自室に駆け上がり、数分後にはみすぼらしい浮浪者風の身なりで降りてきた。襟を立て、光沢のある安物のコート、赤いネクタイ、擦り切れた靴で、見事にその階層を体現していた。
「これで十分だろう」とホームズは暖炉上の鏡を覗き込んだ。「ワトソン、君にも同行してほしいが、今回は無理だろう。事件の本筋をつかんでいるかもしれないし、ただのぬか喜びかもしれない。すぐに分かるだろう。数時間で戻れればいいのだが。」彼は脇の肉をパン切れに挟み、簡単な食事をポケットに突っ込んで、現場へと向かった。
私はちょうど紅茶を飲み終えたところだったが、彼は上機嫌で、片方の手に古いゴム長靴を持って帰ってきた。靴を部屋の隅に放り投げると、自分で紅茶を淹れ始めた。
「ちょっと通りがかっただけだよ。まだこれから出かける。」
「どこへ?」
「ウエスト・エンドの向こう側さ。戻りは遅くなるかもしれないから、待っていなくていい。」
「進展は?」
「まあまあ、特に問題なし。さっきストリートハムには行ったが、家には立ち寄らなかった。これはなかなか面白い問題で、逃すのは惜しいくらいだ。とはいえ、これ以上油を売っている場合じゃない。この汚い服を脱いで、まともな自分に戻らないと。」
その態度から、言葉以上の自信を感じた。目は輝き、やつれた頬にも赤みがさしていた。彼は階段を駆け上がり、やがて玄関のドアがバタンと閉まる音がしたので、また事件現場へ出かけたのだとわかった。
私は夜中まで待ったが、帰宅の気配はなく、結局自分の部屋に引き上げた。彼が何日も徹夜で出かけることは珍しくなかったので、帰りが遅くとも驚かなかった。彼が何時に戻ったのかは分からないが、翌朝、私が朝食に降りると、彼はコーヒーを片手に新聞を読み、すっかり身なりも整えていた。
「ワトソン、先に始めて済まない。依頼人の今朝の約束は少し早いからね。」
「もう9時過ぎているよ。今、玄関のベルが鳴ったような……」
案の定、あの銀行家だった。昨朝よりさらにやつれ、広く厚みのあった顔はこけ、髪も心なしか白くなったように見えた。前日の激昂よりもさらに痛々しい、疲れ切った様子で、私は椅子を勧めると、重く腰を下ろした。
「私はなぜこれほど厳しく試練を与えられるのでしょう。二日前までは何の不安もない幸福な男でした。今や孤独と不名誉に満ちた老後が待っています。次々と不幸が襲いかかります。姪のメアリーまでが私を見捨てたのです。」
「見捨てた?」
「はい。今朝、彼女のベッドは手つかずで、部屋は空っぽ、玄関のテーブルに私宛ての手紙がありました。昨夜、私は悲しみのあまり『お前が息子と結婚してくれたら、きっと良かったのに』と言ってしまいました。軽率だったかもしれません。そのことに関して、彼女からこの手紙です――
『親愛なるおじさまへ――
私が違う行動をとっていれば、こんな不幸は起きなかったのではと思い、心が苦しいままではこの家に幸せに住むことはできません。これから先、私はおじさまの元を離れます。どうか私の未来についてご心配なく。すでに自分の道は決めています。それより何より、私を探さないでください。それは無駄な努力であり、私にとっても迷惑になります。生きていても死んでいても、私はずっとおじさまを愛しています。
メアリー』
「ホームズさん、これがどういう意味かわかりますか? 自殺の示唆でしょうか?」
「いいえ、決してそんなことはありません。むしろ最善の結果かもしれません。ホルダーさん、あなたの苦しみもそろそろ終わりに近づいていると思います。」
「本当ですか! 何かお聞きになったのですね? 宝石はどこに……?」
「1つ1000ポンドでも高すぎるとは思いませんね?」
「10倍出しても惜しくありません。」
「そこまでの必要はありません。3000ポンドで十分ですし、少しばかりのお礼も頂くことになるでしょう。小切手帳はお持ちですか? ここにペンがあります。4000ポンドで切ってください。」
銀行家は呆然としながらも、言われた小切手を書いた。ホームズは机へ行き、小さな三角形の金片と三つの宝石を取り出し、テーブルに置いた。
歓喜の叫びとともに、依頼人はそれをつかみ取った。
「これだ! 助かった、私は救われた!」
喜びの反動は悲しみと同じくらい激しく、彼は取り戻した宝石を胸に抱きしめた。
「ホルダーさん、あなたにはもう一つ、果たすべき義務があります」と、シャーロック・ホームズはやや厳しく言った。
「“借りがある! ”」彼はペンを手に取った。「言ってくれ、いくらでも払います。」
「いいえ、その借りは私に対するものではありません。あなたは、今回の件で立派に振る舞ったあの気高い青年、あなたの息子に心からの謝罪をしなければなりません。私に息子がいたなら、彼がしたように振る舞うのを誇りに思ったことでしょう。」
「では、アーサーが盗ったのではなかったのですね?」
「昨日も申し上げましたし、今日も繰り返しますが、そうではありません。」
「本当に確かなんですね! それなら、すぐに彼のもとへ行って、真実が明らかになったことを知らせてやりましょう。」
「彼はもう知っています。私がすべてを解決した後、彼と面会し、彼が話そうとしないのを見て、私の方から真相を伝えました。すると彼は私が正しいことを認め、私が完全には把握していなかったごくわずかな点を補足してくれました。しかし、今朝のあなたの知らせが、彼の口をさらに開かせるかもしれません。」
「お願いだ、どうかこの驚くべき謎の真相を教えてくれ!」
「承知しました。そして、私がどのようにして真実にたどり着いたかもお見せしましょう。まず、最も言いにくく、あなたにとっても聞きたくないことをお伝えしなければなりません。サー・ジョージ・バーンウェルとあなたの姪、メアリーとの間には通じ合うものがありました。二人はすでに一緒に逃亡しています。」
「私のメアリーが? そんなはずはない!」
「残念ながら、あり得るどころか、確かなことです。あなたもご子息も、この男の本当の素性をご家庭に迎え入れた際にはご存知ありませんでした。彼はイギリスでも最も危険な男の一人で、破産した賭博師にして、救いようのない悪党、心も良心も持ち合わせていません。あなたの姪は、そのような男のことを全く知りませんでした。彼が彼女に誓いの言葉を囁いたとき――それ以前に百人にもそうしてきたように――彼女は自分だけが彼の心を動かしたと思い込んでいました。悪魔だけが彼が何を言ったのか知っていますが、少なくとも彼女は彼の手先となり、ほぼ毎晩彼に会うようになっていたのです。」
「信じられない、絶対に信じない!」と、銀行家は顔を蒼白にして叫んだ。
「それでは、昨夜あなたの家で何が起こったのかをお話ししましょう。あなたが部屋に引き上げたと思い込んだ姪は、こっそり階下に降り、馬小屋通りに面した窓越しに恋人と話をしていました。彼は長い間そこに立っていたのか、足跡が雪を深く踏みしめていました。彼女は彼に王冠のことを話しました。その知らせに彼の金への卑しい欲望が燃え上がり、彼女を意のままに操りました。私は彼女があなたを愛していたことに疑いはありませんが、中には恋人への愛が他のすべての愛情を消し去ってしまう女性もおり、彼女もそうだったのでしょう。彼女が彼の指示を聞いていると、あなたが下りてくるのを見て、急いで窓を閉め、木足の恋人と使用人の逸話を話しましたが、それは事実だったのです。
「あなたの息子アーサーは、あなたとのやり取りの後、自室に戻って就寝しましたが、クラブの借金のことで気がかりでよく眠れませんでした。夜中に彼は自室の前を静かに通り過ぎる足音を聞き、起きて廊下を覗くと、従姉が忍び足で歩いているのを目撃しました。彼女はあなたのドレッシングルームに消えました。驚きのあまり、彼は服を軽く羽織り、暗闇の中でその成り行きを見守っていました。ほどなく彼女が再び部屋を出てくると、廊下の灯りの下で、彼女が貴重な王冠を手にしているのを見ました。彼女は階段を降り、アーサーは戦慄しながらも、あなたの部屋近くのカーテンの陰に素早く隠れ、下の広間で何が起きるかを見守りました。彼は、従姉がこっそり窓を開け、誰かに王冠を手渡し、再び窓を閉めて急いで部屋に戻るのを見届けました。その際、カーテンの陰に隠れた彼のすぐそばを通り過ぎたのです。
「彼女がその場にいる間は、愛する女性を公然と晒すことになるため、どうしても行動に移せませんでした。しかし、彼女が去るや否や、これがあなたにとってどれほどの災難であり、何としても正さねばならないことかに気づきました。彼は素足のまま急いで窓を開け、雪原に飛び出して通りを駆け抜け、月明かりの中に黒い人影を見つけました。サー・ジョージ・バーンウェルは逃げようとしましたが、アーサーは彼を捕まえ、二人は王冠をお互いに引っ張り合いながら格闘となりました。その中で、アーサーはサー・ジョージを殴り、彼の目の上を切りました。すると突然、何かがパキッと折れ、アーサーは自分の手に王冠があるのを見て、急いで家に戻り、窓を閉め、あなたの部屋に上がったのです。ちょうどその時、王冠が争いの中で曲がっているのに気付き、元に戻そうとしていたところ、あなたが現れたのです。」
「そんなことがあり得るのか?」と銀行家は息をのんだ。
「あなたは、その時、彼の気持ちも知らず罵倒しましたが、彼は本来ならあなたから最大級の感謝を受けるべきだったのです。本当のことを話すには、彼女を裏切ることになってしまうので説明できませんでした。しかし、彼はより騎士道的な立場をとり、彼女の秘密を守ったのです。」
「だから彼女は王冠を見て悲鳴を上げて気を失ったのですね!」とホルダー氏は叫んだ。「ああ、なんて私は愚かだったんだ! あの子が五分だけ外出させてくれと頼んだのも、きっと争いの現場に壊れたかけらが落ちていないか確かめたかったからだ。私はなんと残酷に彼を誤解していたのだろう!」
「私が屋敷に到着した時――」とホームズは話を続けた。「すぐに家の周囲を注意深く調べ、雪の中に手がかりがないか探しました。前夜以来雪は降っておらず、強い霜で足跡がよく残っていたのです。業者用の通路も見ましたが、踏み固められ判別できませんでした。しかしそのすぐ先、台所のドアの向こう側で、女性が立って男性と話していた跡があり、その男性の片足には丸い跡があって木製の義足と分かりました。さらに女性が急いでドアに戻った跡が深い爪先と軽いかかとで分かり、木足の男はしばらく待ってから立ち去ったのです。これは、あなたが話してくれた例の女中と恋人だろうと見当をつけ、調べたところ、その通りでした。庭を回っても、警察のものと見られる無作為な足跡しかありませんでしたが、馬小屋通りに入ると、そこには極めて長く複雑な物語が雪の上に描かれていました。
「長靴を履いた男の二重の足跡と、さらに裸足の男の二重の跡がありました。後者があなたの息子のものであることは、あなたの話から確信しました。前者は往復しており、後者は迅速に走っていました。裸足の跡が長靴の窪みの上を部分的に重ねていたので、裸足の男が後から通ったことも分かりました。私はその跡を追い、広間の窓に至ると、長靴の男が待ち続けて雪を踏みつけていたことが分かりました。さらに反対側、通りの百ヤード先まで歩くと、長靴の男が向きを変え、雪が乱れて争いの跡があり、ついには血のしずくが落ちているのを見つけ、私の推理が正しかったことが確認できました。長靴の男は通りを走り去り、さらに小さな血痕があり、彼が怪我をしたことが分かりました。大通りに来ると、舗道はきれいに掃かれていて、そこで手がかりは消えていました。
「しかし家に入ってからは、覚えているでしょうが、私は広間の窓の桟や枠をレンズで調べ、誰かがそこを通った形跡をすぐに見つけました。濡れた足で踏み込んだ際の足の甲の跡も確認できました。ここで私は、何が起きたのかある程度推測できるようになりました。窓の外で男が待ち、誰かが宝石を運んできた。息子さんがその現場を目撃し、泥棒を追いかけ争った。二人で王冠を引っ張り合い、二人がかりの力でなければ起きない損傷を与えました。息子さんは王冠を取り戻して戻ってきましたが、破片は相手の手に残してしまいました。ここまでは明らかです。問題は、その男が誰で、誰が王冠を運んだのか、ということです。
「私には古くからの格言があります。『不可能なものを除外したなら、どんなにあり得そうにないことでも、残ったものが真実である』と。あなたではないことは分かっていましたから、残るのは姪御さんと女中たちだけです。しかし仮に女中が犯人なら、なぜ息子さんが彼女たちの身代わりになる必要があるでしょう? その理由は全くありません。しかし、彼が従姉を愛していたのなら、彼女の秘密を守るためには十分な理由があったのです。しかも、その秘密は恥ずべきものでした。あなたが彼女を窓辺で見かけ、再び王冠を見て気絶したことを思い出したとき、私の推測は確信に変わりました。
「そして、彼女の共犯者は誰なのか? 明らかに恋人です。そうでなければ、彼女があなたへの愛や感謝を上回る気持ちを抱くはずがありません。あなたはほとんど外出せず、交友関係も限られています。しかしその中にサー・ジョージ・バーンウェルがいます。彼が女性の間で悪評高い男であることは、以前から聞いていました。彼こそが長靴を履いており、行方不明の宝石を持っていたのです。アーサーが彼を目撃したことを知っていても、青年が口を開けば自分の家族が危うくなるため、まだ安全だと高を括っていたのでしょう。
「その後、私が取った措置については、あなたのご判断にお任せします。私は浮浪者のふりをしてサー・ジョージの家へ向かい、うまく従者と知り合いになり、主人が前夜に頭を切ったことを聞き出し、最後は六シリング払って彼の古靴を買い取りました。それをストリサムに持って行き、足跡と完全に一致することを確かめたのです。」

「昨夜、通りでみすぼらしい浮浪者を見かけたよ」とホルダー氏が言った。
「まさに、それが私です。私が男を特定できたので、家に戻って着替えました。その後は微妙な立ち回りが必要でした。訴追すれば醜聞になるので、それを避けねばならず、あのような悪党なら我々の弱みも見抜いていると分かっていました。私は彼に会いに行きました。当然、最初は彼はすべてを否定しました。しかし、私が一つひとつ事実を挙げると、彼は虚勢を張り、壁から警棒をつかみました。ですが私は彼の性格を読んでおり、彼が振り上げる前にピストルを突きつけました。すると彼も少し冷静になりました。私は、彼が持っている宝石1個につき千ポンド支払うと伝えました。すると、彼が初めて悲しみを見せたのです。『なんてこった! 三つまとめて六百で手放しちまった!』 私はすぐにその宝石を買い取った受け取り人の住所を聞き出し、訴追しないことを約束しました。その足で彼のもとへ向かい、かなり値切られましたが宝石を千ポンドずつで取り戻しました。その後、息子さんを訪ねてすべて解決したと伝え、深夜二時ごろやっと床についたのです。実に骨の折れる一日だったと言えるでしょう。」
「イギリスを大きな公的醜聞から救った一日でした」と銀行家は立ち上がりながら言った。「感謝の言葉もありませんが、あなたのご尽力に対して私が恩知らずになることは決してありません。あなたの腕前は、私の聞き及んだどんな評判をも超えていました。今すぐ愛しい息子のもとへ飛んでいき、私が彼にした仕打ちを詫びなければなりません。可哀想なメアリーのことは、私の胸に深く突き刺さります。しかし、彼女が今どこにいるかは、さすがのあなたにも分からないでしょう。」
「おそらくこう言えるでしょう」とホームズは答えた。「彼女はサー・ジョージ・バーンウェルのいる所にいるはずです。そして、彼女の罪がどんなものであっても、近いうちに十分すぎるほどの報いを受けることになるでしょう。」
第十二話 銅櫟屋敷の冒険
「芸術そのものを愛する人間にとっては」シャーロック・ホームズは、『デイリー・テレグラフ』の広告欄を脇に放り投げながら言った。「最も取るに足らぬ、最も卑小な現れ方の中にこそ、最も鋭い喜びが得られるものなんだよ。ワトソン、君がこれまで我々の事件を記録する際に、この真理をよく理解してくれていたのは嬉しい限りだ。君は、私が関わった数々の大事件や世間を騒がせた裁判沙汰よりも、それ自体は些細でも、私が専門とする推理や論理的統合の力を存分に発揮できた出来事にこそ、重きを置いてくれているからな」
「それでも」私は微笑みながら応じた。「私の記録がセンセーショナリズムのそしりを免れないという批判は、全面的には否定できない気もするがね」
「君は、おそらく――」ホームズは火箸で赤々と燃える炭を一つ取り上げると、粘土パイプの代わりに、議論好きな時に好んで使うチェリーウッドの長いパイプに火をつけた。「おそらく、どの記録にも色と命を吹き込もうとしすぎて、道を逸れてしまったのさ。本来なら原因から結果への厳密な推論だけを記すべきだった。それこそが、この一連の出来事における唯一注目すべき点だったのだから」
「君の功績は十分に伝えてきたつもりだが」私はやや冷ややかに言った。友人のこの自負心――いや、時に自己中心的とさえ言える性格には、私も何度となく当惑させられてきたからだ。
「いや、自己中心でも思い上がりでもない」彼は、いつもの通り私の言葉ではなく思考に答えるように言った。「私が自分の芸術に正当な評価を求めるのは、それが私自身を超えた、非個人的なものだからだ。犯罪はありふれている。だが論理は稀少なのだよ。だから君は、犯罪よりも論理をこそ強調すべきだった。君は、本来なら講義となるべきものを、単なる物語の連作に貶めてしまった」
春先の寒い朝だった。私たちは朝食を終え、ベーカー街の古びた部屋で暖炉を挟んで座っていた。濃い霧がくすんだ家並みの間に垂れこめ、向かいの窓は重く黄色い霞の中で黒い影のようにぼやけている。部屋にはガス灯が灯され、まだ片付けられていない食卓の、テーブルクロスの白さや食器のきらめきに光を落としていた。ホームズは朝からずっと無言で新聞の広告欄ばかりを漁っていたが、どうやら探しものを諦めたらしく、不機嫌を隠しもせずに私の記録の欠点を講釈し始めたのだった。
「とはいえ」と彼は、しばらく長いパイプをくゆらせて炎を見つめた後、言葉を続けた。「君がセンセーショナリズムのそしりを受けることは、ほとんどないとも言える。というのも、君が興味を持ってくれたこれらの事件のうち、公的な意味での犯罪を扱っていないものもかなりあるからな。私がボヘミア王を助けた一件、ミス・メアリー・サザーランドの奇妙な体験、『唇のねじれた男』にまつわる問題、そして高貴な独身者に起きた出来事など、いずれも法の枠外にあった。だが、センセーショナルなものを避けるあまり、君は些末なものに寄りすぎたのかもしれない」
「結末はそうかもしれないが、その手法は斬新で興味深かったと自負しているよ」
「ふん、親愛なる友よ。大衆、あの偉大なる観察力に欠けた大衆が、織工なら歯で、植字工なら左手の親指で見分けがつくといったことすらほとんど出来ぬというのに、分析や推理の繊細な sắc合いなど気にかけるものか! だが、君が些末な方向へ流れたとしても、それを責める気にはなれない。なぜなら、大事件の時代は終わってしまったのだ。人間――少なくとも犯罪者は、冒険心も独創性も失ってしまった。私の仕事とて、今や失くした鉛筆の捜索や、寄宿学校の娘たちの悩み相談に成り下がってしまった。ついに私はどん底まで落ちたようだ。今朝届いたこの手紙こそ、私のゼロ地点を記すものだと思う。読んでみてくれ!」
彼はくしゃくしゃの手紙を私に放り投げた。
それは昨夜、モンタギュー・プレイスから投函されたもので、こうあった。
親愛なるホームズ様
私は、家庭教師としての就職をお受けすべきかどうか、大変悩んでおります。もしご迷惑でなければ、明日十時半にお伺いしてもよろしいでしょうか。
敬具 ヴァイオレット・ハンター
「その若い女性を知っているのか?」と私は尋ねた。
「いや、全く」
「今、ちょうど十時半だ」
「ああ、きっと彼女の呼び鈴だろう」
「君が思うより面白い話になるかもしれないぞ。青いガーネットの事件だって、最初はただの気まぐれに見えたが、後には大ごとになったじゃないか。今回もそうなるかもしれない」 「そうだといいが。だが疑問はすぐに解決されるだろう。もし私の勘が外れていなければ、今まさに本人がやってきたようだ。」
ホームズがそう言うと、ドアが開き、若い女性が部屋に入ってきた。彼女は質素ながらきちんとした身なりで、ウズラの卵のようにそばかすがちりばめられた快活な顔立ち、そして自立して生きてきた女性特有のきびきびとした所作をしていた。
「お邪魔して申し訳ありません」と彼女は言い、私の連れが立ち上がって迎えると続けた。「とても奇妙な経験をしまして、身寄りも親もなく、相談できる者もおりません。そこで、どうかご助言いただけないかと思い、ご足労をおかけした次第です。」
「どうぞおかけください、ミス・ヴァイオレット・ハンター。お力になれることがあれば、何でも喜んでいたします。」
ホームズが新しい依頼人の態度や話し方に好感を抱いたことは、私にもすぐに分かった。彼はいつもの鋭い眼差しで彼女を品定めし、それからまぶたを半ば閉じ、指先を合わせて、彼女の話に耳を傾ける体勢になった。
「私は五年間、スペンス・マンロー大佐のお宅で家庭教師をしていました」と彼女は話し始めた。「ですが、二か月前に大佐がノヴァ・スコシア州ハリファックスに任命を受けて、子供たちを連れてアメリカへ渡ってしまい、私は職を失いました。広告を出したり、募集に応募したりもしましたが、うまくいきませんでした。ついには貯金も底をつきはじめ、どうしてよいか分からず途方に暮れていたのです。
ウェスト・エンドに『ウェスタウェイ』という有名な家庭教師斡旋所がありまして、私は週に一度はそこに通い、自分に合いそうな職案がないかを確かめていました。ウェスタウェイというのは創業者の名前ですが、実際はミス・ストーパーが経営しています。彼女は自分の小さな事務所に座っていて、職を探している女性たちは控室で待ち、一人ずつ中に案内されて、彼女が帳簿を調べ、その人に合いそうな職があるかどうかを確認してくれるのです。
先週、いつものように事務所に通されたのですが、ミス・ストーパーは一人ではありませんでした。非常に太った、にこやかな顔をした男性が彼女のそばに座っていて、太い顎が幾重にも首の上に垂れ下がっていました。その男性は鼻に眼鏡をかけて、入ってくる女性たちを真剣な様子で見つめていました。私が入った途端、彼は椅子の上でびくっとし、すぐにミス・ストーパーの方を向いて、
『これでいい。これ以上の人はいない。素晴らしい! 素晴らしい!』と口にしました。彼はとても熱心な様子で手をこすり合わせ、とても親しみやすい雰囲気を漂わせていました。その様子を見るだけで、こちらも気持ちが和らぐほどでした。
『お仕事を探していらっしゃるのですね?』と彼は尋ねました。
『はい、そうです。』
『家庭教師として?』
『はい、そうです。』
『ご希望のお給料は?』
『前のスペンス・マンロー大佐のお宅では、月に4ポンドいただいておりました。』
『なんと、なんと! 搾取だ――まったくの搾取だ!』と彼は怒りを込めて、太い手を空中に投げ出しました。『それほど魅力や才能のあるご婦人に、こんなわずかな額を提示するなんて!』
『私の能力など、あなたが想像されているよりずっとささやかなものです』と私は答えました。『フランス語が少し、ドイツ語も少し、音楽と絵――』
『いやいや! そんなことは問題ではありません。重要なのは、あなたが淑女としての立ち居振る舞いを備えているかどうか、ただそれだけです。それがすべてです。もし備えていなければ、この国の歴史の中で重要な役割を果たすかもしれない子供の教育には不適格です。しかし、もし備えているなら、どうして三桁未満の給与で満足しろと言えるでしょう? 私のところでは、年給100ポンドから始まりますよ、奥様。』
ホームズさん、私のように困窮していた者にとって、そんな申し出は夢のように思えました。ですが、私の顔に疑いの色が浮かんだのを見てか、その紳士はポケットブックを取り出し、紙幣を一枚抜き出しました。
『私はいつもこうして、旅費や衣服などちょっとした出費に備えて、前もって給料の半分を若いご婦人方にお渡しすることにしているのです』と、彼は顔中にしわを寄せて目を細め、にこやかに微笑みながら言いました。
今までこんなに魅力的で思いやりのある男性に出会ったことはありません。私は既に店への支払いも滞っており、前渡しはとてもありがたかったのですが、それでも何かこの話全体に不自然なものを感じ、もう少し詳しく知りたいと思いました。
『ご住所を伺ってもよろしいでしょうか?』
『ハンプシャーです。田舎の素晴らしい場所で、ウィンチェスターから五マイルほど離れた「コッパー・ビーチ」という家です。本当に美しい田園地帯で、愛すべき古いカントリーハウスですよ。』
『それで、私の役目は? どんなことをすればよいのでしょう。』
『子供は一人――六歳のやんちゃ坊主が一人です。ああ、彼がスリッパでゴキブリを叩き潰すところをご覧になったら! パシッ、パシッ、パシッ! 瞬きする間に三匹片づけますよ!』彼は椅子にもたれて大笑いし、目が細くなりました。
子供の遊びの内容には少々驚きましたが、お父さんの笑い声に、きっと冗談だろうと思いました。
『つまり、私の唯一の役目は、その子供の世話なのですね?』
『いえいえ、それだけではありませんよ、お嬢さん』と彼は声をあげました。『ご婦人として当然のことながら、妻のちょっとした命令には従っていただきます。それがご婦人としてふさわしい内容であれば、特に問題はありません。お分かりですね?』
『はい、できる限りお役に立ちたいと思います。』
『その通り。例えば服装についてですが、我が家は少し変わった趣味を持っています――変わっていますが、心は優しいんですよ。もしこちらで用意した服を着るようお願いしても、ちょっとした気まぐれだと思って気にしないでいただけますね?』
『はい』と私は、かなり驚きながら答えました。
『ここに座ってほしい、あそこに座ってほしい――そんなお願いにも抵抗はありませんか?』
『いいえ、ありません。』
『では、私たちの家に来る前に、髪をすっかり短く切っていただくというのは?』
私は自分の耳を疑いました。ご覧の通り、ホームズさん、私の髪は豊かで栗色の少し珍しい色合いです。芸術的だと評されてきました。そんなにあっさり犠牲にするなんて、とても考えられません。
『それはどうしてもできません』と私は答えました。彼は小さな目でじっと私を見つめていましたが、私がそう言うと顔に影が差しました。
『それはどうしても必要なのです』と彼は言いました。『妻のちょっとした趣味でして、女性の趣味は尊重しなければなりません。どうしても髪を切ってくれないのですか?』
『本当に、それだけは無理です』と私はきっぱり答えました。
『ああ、それならもう仕方ありません。ほかはすべて申し分なかったのに、残念です。その場合は、ミス・ストーパー、もう少し他のご婦人方を見せていただきましょう。』
マネージャーのミス・ストーパーは、その間ずっと書類に目を通していましたが、私の方を一瞥し、明らかに不機嫌そうな顔をしました。私がこの申し出を断ったことで、かなりの手数料を逃したのだろうと察せられました。
『お名前を帳簿に残しておきますか?』
『お願いします、ミス・ストーパー。』
『まあ、こんな素晴らしいお話をこうも簡単に断っていては、あまり意味がないと思いますがね』と彼女はきつく言いました。『これでまた同じような職を見つけてさしあげるとは思わないでください。ごきげんよう、ミス・ハンター。』テーブルの上の鐘を鳴らし、私は案内係に導かれて外に出されました。
さて、ホームズさん、下宿に戻ると食料棚は空っぽで、テーブルの上には請求書が二、三枚。私は自分がとても愚かなことをしたのではないかと考えはじめました。考えてみれば、変わった趣味や命令に従うことを求められても、その分ちゃんと対価を払うというのです。家庭教師で年100ポンドももらえる人は、イギリスにもなかなかいません。それに、髪なんて私にとって何の役に立つのでしょう? 短い方が似合う人も多いし、私もそうなるかもしれません。翌日には、自分が間違ったのではないかと思うようになり、その次の日には確信に変わっていました。プライドも捨てて、また斡旋所へ行き、まだその職が空いているか尋ねようかと思っていたところ、この手紙があの紳士から届いたのです。今ここに持っていますので、読ませていただきます。
『コッパー・ビーチ、ウィンチェスター近郊
親愛なるハンター嬢へ――ミス・ストーパーがご親切にもあなたのご住所を教えてくださり、こちらからお便りいたします。あなたがご決断を再考されるお気持ちがないか、お伺いしたいのです。妻は私のあなたに関する話をたいそう気に入り、ぜひお越しいただきたいと強く願っております。私たちは、四半期ごとに30ポンド、つまり年120ポンドをお支払いし、私たちの気まぐれによってご迷惑をおかけするかもしれないことへの補償といたします。しかし、それほど大げさなことではありません。妻はある特定の電気的なブルーの色合いが好きで、午前中はそのようなドレスを着ていただきたいと思っておりますが、購入のご負担は不要です。フィラデルフィアにいる娘アリスのものがございますので、それがおそらくぴったり合うことでしょう。また、こちらやあちらに座ることや、指示された方法で過ごすことも、特にご不便ではないはずです。髪については、あなたの髪の美しさには感嘆せずにはいられませんでしたが、どうしてもこの点は譲れません。増額したお給料でご不便を埋め合わせできればと存じます。お子様に関するご負担はごく軽いものです。どうかぜひお越しください。ウィンチェスター駅まで馬車でお迎えにあがりますので、ご利用の列車をお知らせください。
敬具 ジェフロ・ルーカッスル』
「これがホームズさん、今しがた受け取った手紙です。私はもう受けることに決めました。ただ、最終決断の前に一度ご相談したいと思いまして。」
「そうお決めなら、それでよいでしょう」とホームズは微笑んだ。
「ですが、やはり断った方がよいとお思いですか?」
「正直に言えば、私の妹には決して勧めたくない職場です。」
「これは一体どういう意味なのでしょう、ホームズさん?」
「うーん、今のところは何とも言い難いですね。もしかして、あなた自身は何かご意見をお持ちでは?」
「私には一つだけ可能性があるように思えるのです。ルーカッスル氏はとても親切で温厚な方に見えました。もしかすると、奥様が精神を病んでいて、そのことが世間に知られぬように、彼はあらゆる面で奥様の気まぐれに従っているのではないでしょうか。」
「その可能性はあります。実際、現状では最もありうる仮説です。しかし、いずれにせよ若いご婦人が住むには、あまり快い家庭とは言えませんね。」
「でも、お給料が、ホームズさん、お給料が――!」
「ええ、もちろん給料は良い、良すぎるくらいです。それが私を不安にさせるのですよ。どうして彼らはあなたに120ポンドも払うのでしょう? 40ポンドでいくらでも人を選べるはずなのに。その裏には何か強い理由があるはずです。」
「私がこの事情を話せば、いざという時にご助力をお願いできると思いまして。ホームズさんが味方だと思えば、心強いです。」
「どうぞ、その気持ちのままでいらしてください。あなたのこの件は、ここ最近で最も興味深い問題になりそうです。いくつか、他にはない特徴があります。もし疑問や危険を感じたら――」
「危険ですって? どんな危険ですか?」
ホームズは深刻そうに首を振った。「もし危険がはっきり分かれば、それはもはや危険ではありません。ですが、昼夜を問わず電報一本で、私はいつでもあなたのもとへ駆けつけます。」
「それだけで十分です。」彼女は不安そうだった表情を一掃し、元気に椅子から立ち上がった。「これで気持ちがすっかり軽くなりました。今晩中にルーカッスル氏に手紙を書き、髪を切って、明日ウィンチェスターへ向かいます。」感謝の言葉を残し、私たち二人に別れを告げて、足早に帰っていった。
「少なくとも」と、彼女のしっかりとした足取りが階段を下りていくのを聞きながら私は言った。「あの方なら自分の身はしっかり守れそうですね。」
「そして、そうでなければ困ります」とホームズは厳かに言った。「近いうちに、彼女から何か知らせが来るのは間違いないでしょう。」
ホームズの予言が的中するまで、そう長くはかからなかった。二週間が過ぎ、その間私は何度も彼女のことを思い出し、この孤独な女性が人の世のどんな奇妙な横道に迷い込んだのかと考えていた。異常な高給、奇妙な条件、軽い仕事――何か普通ではないことが起きているのは明らかだったが、それが単なる趣味なのか、陰謀なのか、この男が慈善家なのか悪党なのか、私には見当もつかなかった。ホームズもまた、しばしば眉をひそめて思案にふけっていたが、この件について私が話を振ると、「データだ、データだ、データが必要だ!」と苛立たしげに手を振って答えた。「粘土なしでは煉瓦は作れない。」それでも最後には、「自分の妹なら絶対にあんな職には就けない」とつぶやくのだった。
そして、ついに私たちのもとに電報が届いたのは、ある夜遅く、私はそろそろ寝ようかと思っていた頃で、ホームズはいつものように夜通しの化学実験に取りかかろうとしていた。彼は黄色い封筒を開き、ぱっと目を通すと、それを私の方へ投げた。
「ブラッドショーで列車を調べてくれ」と言い、再び化学の勉強に戻った。
呼び出しは短く、切迫したものだった。
「明日正午までにウィンチェスターの『ブラック・スワン』ホテルに来てください。どうかお願いします。もうどうしてよいか分かりません。
ハンター」
「一緒に来てくれるかい?」とホームズが顔を上げて尋ねた。
「ぜひ行きたい。」
「それなら調べてくれ。」
「9時半の列車があります。ウィンチェスターには11時半着です。」
「ちょうどいい。では、明日に備えてアセトンの分析は延期した方がよさそうだな。」
翌朝十一時には、私たちはもうイギリスの古都へ向かう道中にあった。ホームズは車中ずっと新聞に目を通していたが、ハンプシャーの境を越えるあたりでそれを脇に置き、車窓の景色を眺めはじめた。それは理想的な春の日で、淡い青空にふわふわした白い雲が西から東へと流れていた。太陽は明るく輝き、空気には心地よい冷たさがあって、気分も弾む。遠くオルダショットの丘に向かって、農家の赤や灰色の小さな屋根が、新緑の間から顔を覗かせていた。
「なんて新鮮で美しいのでしょう!」と、私はベーカー街の霧の中から抜け出した男の感動そのままに叫んだ。
だがホームズは厳しい表情で首を振った。
「ワトソン、分かるかい? 私のような思考の癖を持つ者には、すべてを自分の専門分野に結びつけて見てしまうのが呪いみたいなものなんだ。君はこの点在する家々を見て、その美しさに心を打たれるだろう。だが私はそれらを見て、ただその孤立ぶりと、そこで犯罪がいかに気付かれずに行われる可能性があるか、そればかりを考えてしまうんだ。」
「なんてことだ! こんな可愛らしい田舎家と犯罪を結びつけるなんて!」
「私は常にある種の恐怖を感じる。私の経験から言えば、ロンドンの最も下劣で卑しい裏路地よりも、この微笑み美しい田園地帯のほうが、よりおぞましい罪の記録を持っているとすら思う。」
「恐ろしいことを言う!」
「だが理由は明白さ。世間の目というものは都市では法の及ばぬことも実現する。どんなに下劣な路地でも、子供の苦しむ叫びや酔っ払いの暴力の音は、近隣の同情や憤りを呼び、司法の仕組みもすぐ近くにあるから、ひとたび訴えればすぐに動き出す。犯罪から法廷まではほんの一歩だ。だが、これら離れた家々を見てごらん。自分の畑に囲まれ、ほとんどが法律のことなど知らない無学な人々で満ちている。年がら年中、悪行や極悪非道が行われていても誰も気付かないかもしれない。もしも今、私たちに助けを求めたあのご婦人がウィンチェスターの町に住むのであれば、私は何の心配も持たなかった。危険なのは、その5マイルの田園地帯だ。もっとも、彼女自身に直接危害が及ぶことはなさそうだ。」
「ええ。ウィンチェスターで私たちと会えるなら、逃げる自由はあるということです。」
「そのとおり。彼女には自由がある。」
「それじゃ一体何が問題なのです? 何か説明がつきませんか?」
「私は、いま分かっている事実に当てはまる説明を七つ考えてみた。しかし、どれが正しいかは、これから新たに得られる情報でしか判別できない。お、あれが大聖堂の塔だ。ミス・ハンターの話をすぐに聞けることだろう。」
「ブラック・スワン」は、ハイ・ストリートでも評判の宿屋で、駅からほど近い場所にあった。宿屋の一室で、我々を待つひとりの若い女性の姿があった。彼女が借り切った居間には、テーブルに昼食の用意が整えられていた。
「本当に、よくいらしてくださいました」彼女は真剣な面持ちで口を開いた。「お二人のご親切がなければ、どうしていいか、途方に暮れるところでした。あなた方のご助言が、どれほど私の支えになることか」
「さあ、何があったのか、お聞かせ願えますか」
「ええ、お話しします。ですが急がなければ。ルーカッスル氏には三時までに戻ると約束しておりますので。今朝、町へ出る許しは頂きましたが、まさかこのような目的だとは、あの人は夢にも思っていないでしょう」
「では、順を追ってすべてお話しいただこうか」ホームズは長く細い脚を暖炉の方へ投げ出し、聞く姿勢を整えた。
「まず申し上げておきますが、ルーカッスル夫妻から虐待のような仕打ちを受けたことは一度もございません。その点は、公平を期すためにお伝えしておきます。ただ、どうしてもあの人たちのことが理解できず、言いようのない不安がつきまとうのです」
「どんな点が理解できないのだね?」
「あの人たちの行動の、その理由がです。ですが、起こったことをありのままにお話しいたしましょう。私がこちらへ参りました時、ルーカッスル氏がこの宿で私を出迎え、ドッグカートでコッパー・ビーチの屋敷まで連れて行ってくれました。彼が言った通り、たしかに景色は素晴らしい場所でしたが、建物そのものはお世辞にも美しいとは言えませんでした。白壁の大きな四角い館ですが、あちこちに湿気や雨風でできた染みが浮かんでいます。屋敷は敷地に囲まれ、三方は森、もう一方はサウサンプトン街道へと下る野原になっています。その道は、玄関から百ヤードほどの所を曲がって通っていました。この前庭は屋敷の所有地ですが、周りの森はすべてサザートン卿の狩猟地だそうです。玄関の真ん前には銅色のブナの木々が生い茂っており、屋敷の名はそれに由来するとのことでした。

雇い主であるルーカッスル氏に車で送られ、その晩、彼の妻と子供に引き合わされました。ホームズ、あなたがベイカー街で推察なさったようなことは、まったくありませんでした。ルーカッスル夫人は、狂人などではありません。物静かで青白い顔をした、夫よりずっと若い女性で、おそらく三十にもなっていないでしょう。一方、旦那様は少なくとも四十五歳には見えます。二人の話から、結婚して七年ほどになること、彼が再婚で、先妻との間に娘がひとりいて、その娘はフィラデルフィアへ行ってしまったということがわかりました。ルーカッスル氏がこっそり教えてくれたのですが、娘が出て行ったのは、継母に対して理不尽な嫌悪感を抱いていたからだそうです。娘さんは二十歳を過ぎていたそうですから、若い継母との関係は、たしかに気詰まりなものだったのかもしれません。
ルーカッスル夫人は、その顔立ちだけでなく、心までも色のない人のように思えました。良くも悪くも、なんの印象も与えない。まるで存在感がないのです。ただ、夫と幼い息子にだけは、ひとかたならぬ愛情を注いでいるのがすぐに見てとれました。その淡い灰色の瞳は絶えず二人の間を往復し、どんな些細な望みも見逃すまいと、先回りして応えようとしていました。彼の方も、無骨ながらも陽気な態度で彼女に接しており、一見すると幸せな家庭そのものでした。それなのに、彼女には何か秘めた悲しみがあるようでした。ふと気づくと、深い物思いに沈み、痛ましいほど悲しげな表情を浮かべているのです。二度、三度、彼女が涙ぐんでいるのを偶然見てしまったこともあります。私は時々、あの子供の性根が、彼女の心痛の原因なのではないかと思いました。あれほど甘やかされ、意地の悪い子供には、生まれてこのかた会ったことがありません。年のわりに体が小さく、不釣り合いに頭が大きいのです。あの子の一生は、癇癪を爆発させるか、陰鬱にふさぎ込むかの、そのどちらかで成り立っているかのようでした。自分より弱い生き物を苦しめることだけが唯一の喜びらしく、鼠や小鳥、虫などを捕らえる手管には、気味が悪くなるほど長けていました。でも、あの子のことはこれ以上お話ししたくありませんし、ホームズ、実際のところ、私の物語の本筋とはほとんど関わりがないのです」
「どんな些細なことでも歓迎するよ」とホームズは言った。「君には関係ないと思えることでもね」
「大切なことは、漏らさずお話しするようにいたします。この屋敷に来てすぐに嫌な感じがしたのは、使用人たちのことでございます。二人しかおりません。男とその妻です。トラーという名の男は、がさつで無作法な、白髪まじりの髭面の男で、いつも酒の匂いをさせています。私が来てから二度もひどく酔っ払っていましたが、ルーカッスル氏はまるで意に介さない様子でした。妻の方は、非常に背が高く、屈強な女で、いつも顔をしかめています。ルーカッスル夫人以上に無口で、むしろ無愛想と言っていいでしょう。なんとも不愉快な夫婦ですが、幸い、私はほとんどの時間を保育室と自室、つまり建物の隅にある隣り合った二部屋で過ごしております。
コッパー・ビーチに着いてからの二日間は、何事もありませんでした。三日目の朝食後、ルーカッスル夫人が夫に何か囁きました。
『ああ、そうだ』彼は私に向き直ると言いました。『我々の気まぐれで髪を切ってくれて、本当に感謝している。おかげで君の魅力が損なわれるなんてことは、まったくないのがわかった。さて、今度はあの鮮やかなエレクトリック・ブルーのドレスが、君にどれほど似合うか見せていただこうじゃないか。部屋のベッドに用意してあるから、着てきてくれたまえ。我々二人とも、ぜひ見たいんだ』
用意されていたのは、独特な色合いの青いドレスでした。生地は上質なカシミアでしたが、誰かが袖を通したものであることは明らかでした。まるで私のために誂えたかのように、体にぴったりでした。ルーカッスル夫妻は、その姿を見て大げさなほど喜びました。二人は客間で私を待っていました。客間は屋敷の正面にあり、床まで届く三つの大きな窓が並んだ広い部屋です。中央の窓のすぐ前に椅子が置かれ、私は窓に背を向けて座るよう言われました。するとルーカッスル氏は、部屋の端から端まで歩き回りながら、これまでに聞いたこともないような滑稽な話を次から次へと聞かせてくれました。あまりに面白くて、私は笑い疲れてしまうほどでした。ところが、ルーカッスル夫人はユーモアのセンスがまるでないらしく、一度も微笑むことなく、膝に手を置いたまま、悲しげで不安そうな顔をしているのです。一時間ほど経つと、ルーカッスル氏は突然、今日の仕事の時間だと言い、私は着替えて保育室のエドワードのところへ行くように言いつけられました。
二日後、まったく同じことが繰り返されました。また着替えさせられ、窓際に座り、雇い主の面白い話に笑わされる。今度は、彼は黄色い表紙の小説を私に渡すと、椅子を少し横に向けさせ、私の影がページに落ちないようにしながら、声に出して読んでほしいと頼みました。私は章の途中から十分ほど読みましたが、突然、彼は話の途中でそれを止めさせ、着替えるようにと命じました。
ホームズ、こんな奇妙な茶番の意味が、どうしても気になって仕方がありませんでした。彼らがいつも、私が窓の方を向かないように細心の注意を払っていることに気づき、窓の外で何が起きているのか、無性に知りたくなったのです。最初は無理だと思いましたが、やがてある方法を思いつきました。手鏡は割れてしまっていましたが、幸い、その小さな欠片をハンカチに包んで持っていました。次に同じことがあった時、私は笑い声をあげるふりをしながら、そのハンカチを目元に当て、鏡の欠片越しに背後をうかがったのです。正直に申しますと、最初は何も見えませんでした。ですが、目を凝らすと、サウサンプトン街道の向こうに、灰色の服を着た、髭のある小柄な男が立って、こちらをじっと見上げているではありませんか。道は大通りで、人通りは絶えません。しかし、その男は牧場の柵に寄りかかり、ただひたすらこちらを見上げていたのです。ハンカチを下ろしてルーカッスル夫人を見ると、彼女が鋭い目で私をじっと見ていました。何も言いませんでしたが、彼女は私の手に鏡があること、そして私が背後を見たことを見抜いたのだと確信しました。彼女はすぐに立ち上がりました。
『ジェフロ』と彼女は言いました。『道に失礼な男がいて、ハンターさんをじっと見つめているわ』
『知り合いかね、ハンターさん』と彼が尋ねました。
『いいえ、この辺りに知り合いはおりません』
『ふん、無礼な奴だ! すまないが、振り向いて、手で追い払ってくれないか』
『放っておいた方がよろしいのでは?』
『いや、そうしないと、いつまでもあそこでうろつかれる。頼むから、向こうへ行けと手で合図してくれ』
言われた通りにいたしました。すると同時に、ルーカッスル夫人がさっとブラインドを下ろしました。それが一週間前のことで、それ以来、私が窓際に座らされることも、青いドレスを着ることも、そして道で男の姿を見ることもなくなりました」
「続けてくれたまえ」ホームズが言った。「君の話は、実に興味深くなってきた」
「話が前後して、出来事のつながりが見えにくいかもしれません。コッパー・ビーチに来た初日、ルーカッスル氏が、台所のそばにある小さな離れ家に私を連れて行きました。近づくと、鎖がじゃらじゃらと鳴る音と、何か大きな獣が身じろぎする気配がしました。
『ここから覗いてごらん』とルーカッスル氏は、板壁の隙間を指さしました。『大した番犬だろう?』
覗き込むと、ぼんやりとした薄闇の中に、爛々と光る二つの眼と、うずくまる獣の影が見えました。
『怖がることはないさ』私の驚きようを見て、雇い主は笑いました。『カルロという私のマスティフ犬だ。もっとも、こいつを扱えるのはトラーだけだがね。食事は一日に一度、それもほんのわずかしかやらんから、いつも腹を空かせた獣同然さ。トラーが毎晩、こいつを放す。もし誰かが噛みつかれでもしたら、神に祈るしかないな。どんなことがあっても、夜中に屋敷の敷居をまたぐんじゃないぞ。命の保証はできんからな』
その忠告は、決して大げさではありませんでした。二日後、真夜中の二時頃、ふと自室の窓から外を眺めました。美しい月夜で、芝生は銀色に輝き、まるで昼間のように明るかったのです。その静かな美しさに見とれていると、銅色のブナの木々の影で何かが動くのが見えました。やがて月明かりの下に姿を現したのは、子牛ほどもある巨大な犬で、黄褐色をして、顎の肉はたるみ、鼻面は黒く、ごつごつとした骨格が浮き出ていました。そいつはゆっくりと芝生を横切り、反対側の影の中へと消えていきました。あの物言わぬ恐ろしい番犬は、どんな泥棒よりも私を恐怖に陥れたのです。
そして今から、たいへん奇妙な体験をお話しします。ご存じの通り、私はロンドンで髪を切り、その大きな束をトランクの底にしまっておりました。ある晩、子供を寝かしつけた後、自室の家具を調べて持ち物を整理していました。部屋には古い箪笥があり、上の二段は空いていましたが、下の一段は鍵がかかっていました。上の引き出しにリネン類をしまっていたのですが、まだしまうものが残っていたので、三段目が使えないことに苛立ちを覚えていました。鍵のかけ忘れだろうと思い、自分の鍵束を試してみると、最初の鍵であっさりと開いたのです。引き出しの中には、たった一つのものしかありませんでした。――それは、私の髪の束だったのです。
手に取って確かめると、色合いも、太さも、間違いなく同じものでした。でも、そんなはずはありません。なぜ私の髪がこんな引き出しに? 私は震える手でトランクを開け、中身をすべてかき出し、底にしまっておいた自分の髪の束を取り出しました。二つを並べてみれば、寸分違わぬ同じものでした。これほど不可解なことがありましょうか。いくら考えても、わけがわかりませんでした。その髪は元通り引き出しに戻し、鍵を開けたことはルーカッスル夫妻には黙っていました。不用心に鍵をこじ開けたのは、私自身ですから。
私はもともと観察好きな性質でして、屋敷の間取りもだいぶ頭に入りました。ただ、一区画だけ、まったく使われていないように見える棟がありました。トラー夫妻の部屋に通じる扉の向かいにある扉がその棟につながっているのですが、いつも必ず鍵がかかっています。ある日、階段を上がっていると、ルーカッスル氏がその扉から出てくるところに鉢合わせました。手には鍵束があり、その顔には、いつもの陽気さとはかけ離れた、まるで別人のような険しい表情が浮かんでいました。頬は紅潮し、額には怒りの皺が刻まれ、こめかみの血管が青く浮き出ていました。彼は素早く扉に鍵をかけると、私に目もくれず、足早に通り過ぎていきました。
この出来事で、私の好奇心はますます掻き立てられました。子供と庭を散歩するふりをしながら、その棟の窓が見える側を何度も歩いてみました。窓は四つ並んでおり、三つはひどく汚れているだけ、もう一つは板で完全に塞がれています。どれも使われていないのは明らかでした。私がしばらくそのあたりをうろついていると、ルーカッスル氏が陽気な顔で出てきました。
『ああ、ハンターさん、先ほどは失礼。ちょっと仕事のことで頭がいっぱいでね』
気にしていないと答えました。『ところで、あちらには空き部屋がたくさんあるのですね。一つは板で塞がれてさえいましたわ』
彼は驚いた様子で、少しうろたえているように見えました。
『写真が趣味でね。あそこを暗室にしているんだ。いやはや、君は実によく気がつく。誰がそれほど目ざといと思っただろうか』彼は冗談めかして言いましたが、その目に笑いの色はなく、むしろ疑念と苛立ちが浮かんでいました。
ホームズ、その部屋に何か秘密があると知った瞬間から、私はどうしても中に入ってみたくなりました。それは単なる好奇心からではありません。何か、善いことにつながるに違いない、という義務感のようなものを感じたのです。いわゆる女の直感というものかもしれませんが、とにかく強くそう思い、機会をうかがっておりました。
そして昨日、とうとうその機会が訪れたのです。実は、ルーカッスル氏だけでなく、トラー夫妻も時々その部屋で何かしているらしく、一度、夫の方が大きな黒いリネンの袋を持って入っていくのを見かけたことがあります。このところ、彼は酒浸りで、昨日の夕方もひどく酔っていました。私が階段を上がった時、なんと、扉に鍵が差し込まれたままになっていたのです。間違いなく、彼の置き忘れでしょう。ルーカッスル夫妻は二人とも階下におり、子供も一緒でした。これ以上の好機はありません。私はそっと鍵を回して扉を開けると、息を殺して中へ滑り込んだのです。
私の前には、小さな通路があり、壁紙もカーペットもなく、奥で直角に折れ曲がっていました。その角を曲がると、三つの扉が一列に並んでおり、一番目と三番目の扉は開いていました。どちらも空っぽの部屋に通じており、埃っぽく寂しい雰囲気で、一方の部屋には二つ、もう一方には一つの窓がありましたが、いずれも汚れがひどく、夕暮れの光がかろうじてぼんやりと差し込んでいるだけでした。中央の扉は閉ざされており、その外側には鉄製ベッドの幅広い横棒が取り付けられ、一方の端は壁のリングに南京錠で固定され、もう一方は丈夫な紐で結ばれていました。扉自体も施錠されており、鍵は見当たりませんでした。この厳重に封鎖された扉は、外側の雨戸付きの窓と明らかに対応していましたが、扉の下から漏れるわずかな光により、その部屋が完全な暗闇でないことがわかりました。どうやら天窓があり、上から光を取り入れているようです。私は通路に立ち、不穏な扉を見つめながら、そこに隠された秘密は何なのかと思いを巡らせていました。すると突然、部屋の中から足音が聞こえ、その微かな明かりの隙間に影が往復するのを目にしました。その光景に私は理性を失った恐怖に襲われたのです、ホームズさん。張り詰めていた神経が一気に切れてしまい、振り返って走り出しました――まるで背後から恐ろしい手がドレスの裾をつかもうとしているかのように。通路を駆け抜け、扉を通り抜け、そのまま外で待っていたルーカッスル氏の腕の中に飛び込んでしまいました。
「そうか」と彼は微笑みながら言いました。「やはり君だったのか。扉が開いたのを見て、そうじゃないかと思っていたんだよ」
「とても怖かったんです!」私は息を切らしながら答えました。
「おやおや、お嬢さん! お嬢さん!」――その口調は驚くほど優しく、慰めるようでした――「で、一体何が怖かったのかな、お嬢さん?」
しかし、彼の声にはどこか過剰な感じがありました。やりすぎなのです。私は彼に対して強く警戒心を抱きました。
「愚かにも空き部屋のある棟に入ってしまったんです」と私は答えました。「でも、あの薄暗い光の中、あまりにも寂しくて不気味で、怖くなってすぐに走って出てきました。本当に、あそこは恐ろしいほど静かなんです!」
「それだけかね?」と、彼は鋭く私を見つめながら言いました。
「他に、何だと思ったんですか?」
「なぜ私があの扉に鍵をかけているか、わかるかね?」
「いいえ、全くわかりません」
「それは、関係のない者が入らないようにするためだよ。わかるかい?」彼は依然として非常に愛想よく微笑み続けていました。
「もし知っていたなら――」
「今は知っているね。もし君がもう一度、あの敷居をまたぐようなことをしたら――」ここで彼の笑みは一瞬にして怒りに歪み、悪魔のような顔で私を睨みつけました――「君を猟犬の餌にしてやるぞ」
あまりの恐怖に私はどうしたのか覚えていません。おそらく彼の脇をすり抜けて自分の部屋に駆け込んだのでしょう。気がつくと、私はベッドに横たわり、全身を震わせていました。そのとき、ホームズさん、あなたのことを思い出したのです。もう誰かの助言なしにはここにはいられない、そう思いました。家も、男も、女も、使用人も、あの子供さえも、皆が私には恐ろしかったのです。あなたさえ来てくだされば、きっとすべてうまくいく――そう思いました。もちろん、家から逃げ出すこともできたはずですが、恐怖と同じくらい好奇心も強く、結局、あなたに電報を打つ決意を固めました。帽子と外套を身につけ、家から半マイルほど離れた事務所まで歩いていき、そこで電報を送り、帰宅した時にはだいぶ気持ちが楽になっていました。玄関に近づいたとき、犬が放たれていないかという恐ろしい疑念が頭をよぎりましたが、トラーがその晩も酔いつぶれて意識を失っていたことを思い出しました。家の中であの凶暴な動物を御せるのは彼だけで、解き放つことができるのも彼しかいないのです。私は無事に家に入り、その夜はあなたに会えると思うと喜びで半分ほど眠れませんでした。今朝、ウィンチェスターに出る許可は難なく取れましたが、三時までには戻らなければなりません。というのも、ルーカッスル夫妻が出かけて夕方は家にいないので、その間、子供の世話をしなければならないのです。これで、私の冒険のすべてをお話ししました、ホームズさん。ぜひ、これがどういうことなのか、そして何より私がどうすべきなのか、教えていただけると嬉しく思います」
ホームズと私は、あまりに異様なその話に息を呑んで聞き入っていた。友人は椅子から立ち上がると、ポケットに両手を突っ込み、厳しい表情で部屋を行ったり来たりし始めた。
「トラーはまだ酔っているのですか?」と彼が尋ねた。
「はい。奥様がルーカッスル夫人に、どうにもならないと話しているのを聞きましたわ」
「それは好都合ですな。今夜、ルーカッスル夫妻は外出されますか?」
「はい」
「頑丈な鍵のかかる地下室は?」
「はい、ワインセラーがあります」
「あなたはこれまで、実に勇敢かつ賢明に行動されました、ハンターさん。もう一つだけ、お願いできないでしょうか。あなたを並々ならぬ女性だと思わなければ、こんなことは頼みませんよ」
「やってみます。何でしょう?」
「私と友人は、七時にコッパービーチ荘に到着します。その頃にはルーカッスル夫妻は出かけており、トラーも使い物にならなくなっているでしょう。残るはトラー夫人だけですが、彼女が騒ぎを起こすかもしれません。もしあなたが彼女に何か用事を言いつけて地下室へ行かせ、そのまま鍵をかけて閉じ込めてしまえば、事は非常にスムーズに進みます」
「やりますわ」
「素晴らしい! これで事件の核心に迫れる。もちろん、考えられる説明は一つしかありません。あなたは誰かの身代わりとして雇われ、その本人があの部屋に監禁されている。これは明らかです。その囚人が誰なのか、私には見当がついています。確かアリス・ルーカッスル嬢、アメリカへ渡ったと言われていましたね。あなたは彼女と背格好や髪の色が似ていたために選ばれた。彼女の髪はおそらく病気か何かで切り落とされ、それゆえあなたの髪も同じように切られたのです。そしてあなたは偶然にも、彼女の髪を見つけてしまった。道にいた男は、おそらく彼女の友人――あるいは婚約者でしょう。あなたが彼女の服を着て、あまりにも似ていたものですから、あなたが笑ったり身振りをしたりするのを見て、アリス嬢は幸福で、もはや自分を必要としていないのだと信じ込んでしまったのでしょう。犬が夜な夜な放たれるのは、彼が接触を試みるのを防ぐためです。ここまでは実に明白ですな。この事件で最も厄介なのは、あの子供の性格だ」
「それが一体何の関係があるんだ?」私は思わず叫んだ。
「ワトソン、君は医師として、両親を研究して子供の傾向を学ぶことが多いだろう。だが、その逆もまた真なり、だ。私はしばしば、子供の観察から親の性格の本質を掴む最初の手がかりを得てきた。この子供は異常なまでに残酷だが、それは純粋な残虐性からくる残酷さだ。その性質が、にこやかな父親に由来するのか、それとも母親からなのかはともかく、あの哀れな囚人にとっては悪い兆しでしかない」
「ホームズさん、おっしゃる通りですわ」依頼人は叫んだ。「今、千もの記憶が蘇ってまいりました。あなたの推理が核心を突いていると確信できます。ああ、一刻も早く、あの方を救い出してさしあげなくては!」
「慎重に行動しなければなりません。相手は実に狡猾です。七時までは何もできません。ですが、その時刻になれば我々がご一緒します。謎が解けるのも時間の問題でしょう」
我々は約束通りに行動し、ちょうど七時にコッパービーチ荘へ到着した。馬車は道中の宿屋に預けてきた。夕日を浴びて金属のように鈍く輝く黒い葉の木立は、たとえハンター嬢が玄関先で微笑んで我々を迎えていなかったとしても、一目でそれと分かる特徴的なものだった。
「うまくいきましたかな?」とホームズが尋ねた。
下の方から、ドンドンと大きな叩く音が聞こえてきた。「あれはトラー夫人が地下室にいる音ですわ」とハンター嬢が答えた。「ご主人は台所の敷物の上でいびきをかいています。これがご主人の鍵で、ルーカッスル氏の合鍵です」
「実によくやってくださいました!」ホームズは熱心に言った。「では、ご案内を。すぐにこの忌まわしい事件の幕を下ろしましょう」
我々は階段を上がり、扉の鍵を開け、通路を進んでハンター嬢が説明した通りのバリケードの前にたどり着いた。ホームズは紐を切り、横木を外すと、手持ちの鍵束を試したが、どれ一つとして合わない。中からは物音ひとつせず、その沈黙にホームズの顔が曇った。
「間に合わなかったか……」と彼が呟いた。「ハンターさん、ここから先は我々二人で行く方がいいでしょう。さあ、ワトソン、肩を貸してくれ。力ずくでこじ開けるぞ」
古びてがたついた扉は、我々の力であっけなく蝶番から外れた。二人で部屋に飛び込んだが、中はもぬけの殻だった。簡素な寝台と小さなテーブル、それに洗濯籠があるだけだ。天窓は開け放たれ、囚人の姿は見当たらない。
「これは悪辣な企みだ」とホームズが言った。「あの男はハンターさんの意図を察し、獲物を連れ去ったに違いない」
「どうやって?」と私が尋ねた。
「天窓からです。どうやったのかは、すぐに分かりますよ」彼は身軽に屋根へと飛び乗った。「ああ、ご覧なさい。軒に長くて軽い梯子が掛かっている。これを使ったのです」
「でも、そんなはずは」とハンター嬢が言った。「夫妻が出かけた時には、梯子などありませんでしたわ」
「彼が戻ってきてやったのです。あの男は狡猾で危険だ。今まさに、本人が階段を上がってくる足音が聞こえてきても驚かん。ワトソン、ピストルの用意をしておきたまえ」
その言葉が終わるか終わらないかのうちに、一人の男が部屋の戸口に姿を現した。ひどく太ってたくましい体格で、手には重そうな棍棒を握っている。ハンター嬢は彼を見て悲鳴を上げ、壁際に身をすくめたが、ホームズは素早く前に進み出て、男と対峙した。
「この悪党め!」ホームズが言った。「娘御はどこだ!」
男は部屋を見回し、開け放たれた天窓に視線を上げた。
「それはこっちの台詞だ!」彼は怒鳴った。「盗人どもめ! 間諜め! 捕まえてやったぞ! 貴様らはもう俺の手の中だ。思い知れ!」そう言い捨てると、男は階段を一目散に駆け下りていった。
「犬を放しに行く気ですわ!」ハンター嬢が叫んだ。
「私のリボルバーがある」と私は言った。
「玄関を閉めるんだ!」ホームズが叫び、我々は一斉に階段を駆け下りた。ホールにたどり着くや否や、戸外から猟犬の遠吠えが聞こえ、続いて甲高い悲鳴と、聞くもおぞましい唸り声が響き渡った。その時、赤ら顔で足元のおぼつかない初老の男が、横手の扉からふらふらと飛び出してきた。
「おお、神よ!」彼は叫んだ。「誰かが犬を放しちまった! 二日も餌をやってねえんだ。は、早く! 手遅れになる!」
ホームズと私は外へ飛び出し、トラーも後を追って家の角を曲がった。そこには、飢えた巨大な獣がいた。その黒い口吻はルーカッスルの喉元に深く食い込み、男は地面をのたうち回って絶叫している。私は駆け寄るなり犬の脳天を撃ち抜いた。白い牙がなおも喉に食い込んだまま、獣はぐったりと崩れ落ちた。我々は苦労して二人を引き離し、かろうじて息はあるものの、見るも無残な姿となったルーカッスルを屋敷の客間のソファに運び込んだ。そして、正気に戻ったトラーを妻のもとへ知らせにやり、私は医師としてできる限りの手当てを施した。
我々が皆でソファを囲んでいると、扉が開き、背の高い痩せた女が部屋に入ってきた。
「トラー夫人!」とハンター嬢が叫んだ。
「はい、お嬢様。ルーカッスル様が戻られた時、私を出してくださったんです。お嬢様のところへいらっしゃる前にね。ああ、もし私に計画を打ち明けてくださっていれば、無駄足だったとお伝えできたものを」
「ほう」ホームズは鋭い眼差しを彼女に向けた。「トラー夫人は、どうやらこの件について誰よりも多くをご存じのようですな」
「はい、その通りでございます。そして、知っていることはすべてお話しいたします」
「では、どうぞお掛けになって、お話しください。私にもまだ解けない点がいくつかありますので」
「すぐにご説明いたしますわ」と彼女は言った。「もし地下室から出られましたなら、もっと早くにお話しできたものを。万一、警察沙汰になりましたら、私があなた様方、そしてアリスお嬢様の味方であったことを、どうかお忘れなく。
アリスお嬢様は、継母様がいらしてからというもの、この家で幸せだったことは一日もございませんでした。何も口答えできず、ぞんざいに扱われておりましたが、事態が本格的に悪化したのは、ご友人の家でファウラー様とお会いになってからです。私の知る限り、アリスお嬢様には遺言によるご自身の権利がございましたが、あまりにお優しく我慢強いお方で、そのことをおくびにも出さず、すべてをルーカッスル様にお任せになっていたのです。彼はそれで安心しておりました。ですが、もしお嬢様がご結婚なさり、旦那様となる方が法的に権利を主張される立場となれば、そうはいきません。そこで、彼は彼女に書類へ署名させ、結婚しようとしまいと財産を使えるようにしたかったのです。しかし彼女が拒んだため、彼は執拗に彼女を責め続け、とうとうお嬢様は脳炎を患い、六週間も生死の境をさまよわれました。その後、やっと回復なさいましたが、すっかりおやつれになり、あの美しい髪も切り落とされてしまわれたのです。ですが、それでも彼女の恋人は変わることなく、誠実に支え続けておられました」
「ああ、あなたのお話で全体像がだいぶ明らかになりました。残りは推理で補えます」とホームズは言った。「つまり、ルーカッスル氏は監禁という手段に出られたのですね?」
「はい」
「そして、ハンターさんをロンドンから呼び寄せ、ファウラー氏の執拗な求愛を諦めさせるために、身代わりを立てられた、と?」
「その通りでございます」
「しかしファウラー氏は海の男らしく粘り強く、この屋敷を見張り続け、あなた様にお会いして、金銭か何かで協力を取りつけられた、と?」
「ファウラー様は、とてもご親切で気前の良いお方でした」とトラー夫人は静かに言った。
「そして、ご主人には十分な酒を与え、主人が外出した隙に梯子を用意された――と、こういうわけですな」
「まさに、その通りでございます」
「これは失礼いたしました、トラー夫人。我々を悩ませていた謎を、すべて解き明かしてくださいました。そして、ちょうど今、村の医者とルーカッスル夫人が到着したようだ。ワトソン、そろそろハンター嬢をウィンチェスターまで送ってやった方がよさそうだ。我々も、もはやこの家に留まる資格はないだろう」
こうして、玄関先に銅色のブナの木立がそびえる、あの不吉な屋敷の謎は解き明かされた。ルーカッスル氏は一命を取り留めたものの、心身ともに打ちのめされ、今では妻の献身的な看護によってかろうじて命をつないでいる。彼は昔からの使用人たちと共に今も暮らしているが、それはおそらく、彼らがルーカッスル氏の過去を知りすぎているため、手放すに手放せないのだろう。ファウラー氏とアリス嬢は、逃亡の翌日、サウサンプトンで特別許可を得て結婚し、彼は現在、モーリシャス島で政府の要職に就いている。ヴァイオレット・ハンター嬢については、私が密かに落胆したことだが、ホームズは彼女が事件の中心人物でなくなると、ほとんど関心を示さなくなってしまった。彼女は今、ウォルソールの女学校で校長となり、大いに成功を収めていると聞く。
終わり

