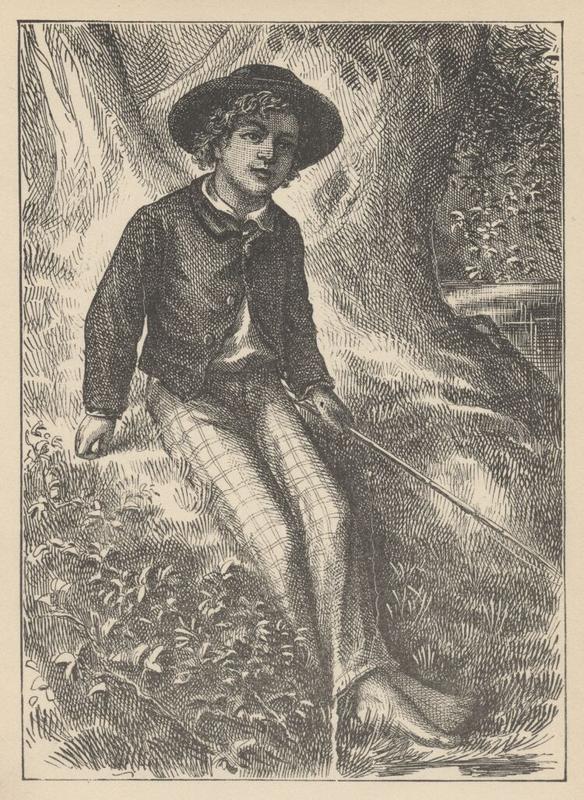
序文
この本に記された冒険のほとんどは、実際に起こった出来事である。一つか二つは私自身の経験であり、残りは私の学友であった少年たちの経験だ。ハック・フィンは実在の人物から着想を得ている。トム・ソーヤーも同様だが、特定の一個人をモデルにしたわけではない。彼は、私が知る三人の少年の特徴を組み合わせた存在であり、したがって建築でいうところの複合様式に属するものである。
作中で触れられている奇妙な迷信は、この物語の時代――すなわち、今から三十年ないし四十年前――において、西部の子どもたちや奴隷たちの間で広く信じられていたものばかりである。
本書は主として少年少女の娯楽のために書かれたものであるが、そのために大人の男女から敬遠されることのないよう願っている。というのも、大人たちにかつての自分自身の姿や、その頃どのように感じ、考え、語り、そして時にはいかに奇妙な企てに熱中したかを、楽しく思い出してもらうことも、私の計画の一部であったからだ。
著者
ハートフォードにて、一八七六年
第一章
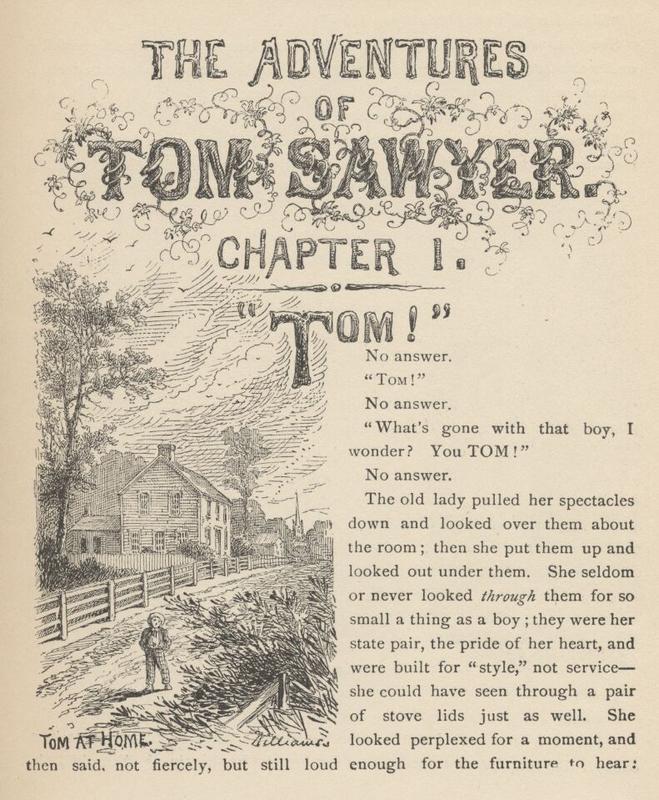
「トム!」
返事がない。
「トム!」
返事がない。
「あの子はいったいどこへ行ったんだか。トム、お前!」
返事がない。
老婆は眼鏡を鼻先までずらし、眼鏡越しに部屋の中を見回した。それから今度は眼鏡を額に押し上げ、その下から覗き込むようにあたりを見た。ほんの小さな男の子を探すのに、彼女が眼鏡を「通して」見ることは滅多になかった。それは彼女の晴れ着用の、いわば心の誇りともいうべき代物で、「粋」のために作られたものであり、実用のためのものではなかったのだ。それなら暖炉の蓋を二枚重ねて見たほうが、よっぽどましだったろう。彼女は一瞬途方に暮れた顔をしたが、やがて、厳しい口調ではなかったが、それでも家具に聞こえるくらい大きな声で言った。
「よし、今度捕まえたら、ただじゃおかないから――」
彼女は最後まで言い終えなかった。というのも、その時にはもう屈み込んで、箒でベッドの下を突っついていたからだ。その突きに合わせて息を弾ませる必要があったのである。彼女がそこから引っ張り出したのは、猫一匹だけだった。
「まったく、あの子には本当に敵わない!」
彼女は開け放たれた戸口へ行き、そこに立つと、庭を構成しているトマトの蔓やチョウセンアサガオの雑草の間を隈なく見渡した。トムはいない。そこで彼女は、遠くまで届くように計算した角度で声を張り上げ、叫んだ。
「おーまーえー、トーム!」
その時、背後でかすかな物音がした。彼女が振り返ると同時だった。小さな男の子の上着のたるんだ襟首をひっつかみ、その逃走を阻止したのである。
「いた! あの物置だと思ったよ。中で何をしてたんだい?」
「なんでもない。」
「なんでもないですって! その手を見なさい。それからその口も。いったい何だい、そのべたべたしたものは?」
「わかんないよ、おばさん。」
「いいや、あたしにはわかるさ。ジャムだ――そういうことさ。あのジャムに手を出すな、さもないとひっぱたくからねって、四十回は言ったはずだよ。その鞭をおくれ。」
鞭が宙を舞う――絶体絶命の危機――
「あっ! おばさん、後ろ!」
老婆はくるりと振り返り、スカートの裾を危ないところからさっと引き寄せた。少年はその隙に逃げ出し、高い板塀をよじ登り、その向こうへと姿を消した。

ポリーおばさんは一瞬あっけにとられて立っていたが、やがてくすくすと穏やかに笑い出した。
「しょうがない子だね。あたしはいつになったら物事を覚えるんだい? あの子には今までさんざん同じような悪戯を仕掛けられてきたんだから、今頃はもう警戒してなきゃいけないはずなのに。でも、年寄りの馬鹿が一番の馬鹿者ってことさ。老い犬に新しい芸は仕込めない、って言うからね。だけどまあ、あの子は二日続けて同じ手は使わないんだから、次は何が来るかなんて、どうしてわかりゃしないよ。あの子は、あたしがかんしゃくを起こす寸前まで、どれだけあたしをじらせるかちゃんとわかってるみたいだし、一分でもあたしの気をそらしたり、笑わせたりできれば、それで万事うまくいくってことも知ってるんだ。そうすりゃ、あたしはもうびた一文叩けなくなる。あたしはあの子にちゃんと務めを果たしちゃいない。それは神様に誓って本当だよ。まったくね。『鞭を惜しむと子どもはだめになる』とは、聖書にもある通りさ。あたしは自分たち二人のために罪と苦しみを積み上げているんだ、わかってるよ。あの子は悪魔[訳注:Old Scratchは悪魔の俗称]でいっぱいだけど、ああ、なんてこった! あの子は亡くなった妹の息子なんだ、かわいそうに。どうしたって、あの子を鞭打つ気にはなれないのさ。見逃してやるたびに、良心がひどく痛むし、叩くたびに、この年老いた心は張り裂けそうになる。まあいいさ、女から生まれたる者は、日短くして、悩みに満ちと聖書にもある通り、きっとそうなんだろう。今夜も学校をサボるだろうから、明日は罰として仕事をさせなきゃなるまい。他の子がみんな休みの土曜日にあの子を働かせるのは、そりゃあ大変なことだよ。でもあの子は、他の何よりも仕事が嫌いなんだから、あたしがあの子への務めをいくらか果たさなきゃ、あの子を破滅させてしまうことになる。」
トムは案の定、学校をサボり、大いに楽しんだ。彼が家に戻ったのは、小さな黒人の少年ジムが翌日分の薪をのこぎりで引き、夕食前に焚き付けを割るのを手伝うのに、かろうじて間に合う時間だった――少なくとも、ジムが仕事の四分の三をこなしている間、自分の冒険談をジムに語って聞かせるには十分間に合った。トムの弟(というよりは異父弟)のシッドは、自分の分担(木屑拾い)をすでに終えていた。彼は物静かな少年で、冒険好きで厄介な真似はしなかったからだ。
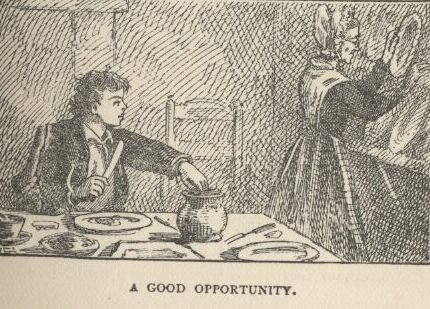
トムが夕食を食べ、隙を見ては砂糖を盗み食いしている間、ポリーおばさんは彼に狡猾さに満ちた、非常に深遠な質問を浴びせた――というのも、彼を罠にかけて、まずい事実を白状させようと目論んでいたからだ。他の多くの純朴な魂の持ち主と同様、自分には暗く謎めいた外交術の才能が備わっていると信じることが、彼女のささやかな虚栄心だった。そして彼女は、自分のもっとも透けて見えるような策略を、低劣な狡知の驚異として熟考するのが好きだった。彼女は言った。
「トム、学校はそこそこ暑かっただろう?」
「うん。」
「ものすごく暑かったんじゃないかい?」
「うん。」
「泳ぎに行きたくならなかったかい、トム?」
トムの胸を、一抹の恐怖がよぎった――居心地の悪い疑念の一片だ。彼はポリーおばさんの顔を窺ったが、何も読み取れなかった。そこで彼は言った。
「ううん――まあ、あんまり。」
老婆は手を伸ばしてトムのシャツに触り、言った。
「だけど、今はそんなに暑くないじゃないか」そして彼女は、誰にもその意図を悟られずにシャツが乾いていることを見抜いたのだと考えると、悦に入った。だが、彼女の思惑とは裏腹に、トムは今や風向きを察していた。そこで彼は、次の手を先回りした。
「何人かで頭にポンプの水をかけたんだ――僕のはまだ湿ってるよ。ほら?」
ポリーおばさんは、その状況証拠を見落とし、一杯食わされたことに腹を立てた。その時、彼女に新たな霊感がひらめいた。
「トム、頭に水をかけるのに、あたしが縫い付けたシャツの襟をほどく必要はなかっただろう? 上着のボタンを外しな!」
トムの顔から苦悩の色が消えた。彼は上着を開いた。シャツの襟はしっかりと縫い付けられていた。
「ちぇっ! まあ、行きなさい。てっきり学校をサボって泳ぎにでも行ったんだとばかり思ってたよ。でも許してやるよ、トム。お前はことわざにあるように、見かけによらない焼け焦げ猫みたいなもんだね――見た目よりはましだよ。今回はね。」
彼女は自分の洞察力が外れたことに半分残念に思い、トムが一度でも従順な行いに行き当たったことを半分喜んでいた。
しかし、シッドが言った。
「あれ、おばさんは襟を白い糸で縫ったと思ってたけど、黒い糸だよ。」
「おや、まあ、白い糸で縫ったはずだよ! トム!」
しかし、トムは残りの言葉を待たなかった。戸口から出ていくとき、彼は言った。
「シッド、今度のことでお前をぶっとばしてやるからな。」
安全な場所で、トムは上着の襟に突き刺してある二本の大針を調べた。糸が巻きつけてあり、一本には白い糸が、もう一本には黒い糸が通してあった。彼は言った。
「シッドがいなけりゃ、おばさんは気づきっこなかったんだ。ちくしょう! おばさんは白い糸で縫う時もあれば、黒い糸で縫う時もある。どっちか一つに決めてくれりゃいいのに――いちいち覚えてられるかよ。でも、今度のことでシッドをぶん殴ってやるのは確かだ。思い知らせてやる!」
彼は村の模範少年ではなかった。もっとも、その模範少年のことはよく知っていた――そして心から軽蔑していた。
二分も経たないうちに、彼は自分の悩み事をすっかり忘れてしまった。彼の悩みが、大人の男にとっての悩みと比べて、少しでも軽く、苦くないからではない。新たな、そして強力な関心事が、それらを圧倒し、一時的に彼の心から追い出してしまったからだ――ちょうど、大人の不幸が新しい事業の興奮の中で忘れ去られるのと同じように。この新しい関心事とは、彼が黒人から習ったばかりの、口笛の貴重な新技だった。彼はそれを邪魔されずに練習したくてたまらなかった。それは、音楽の合間に舌を口蓋に短い間隔で触れさせることによって生み出される、独特の鳥のような節回し、一種の流れるようなさえずりであった――読者がかつて少年であったなら、おそらくそのやり方を覚えているだろう。勤勉と集中によって、彼はすぐにそのコツを掴み、口いっぱいにハーモニーを、魂いっぱいに感謝を抱いて、通りを闊歩した。彼は、新しい惑星を発見した天文学者のような気分だった――疑いなく、強く、深く、混じりけのない喜びという点に関する限り、有利なのは天文学者ではなく、少年の方であった。
夏の夜は長かった。まだ暗くはなっていなかった。やがてトムは口笛を止めた。目の前に見知らぬ者がいた――自分より一回り大きな少年だ。この貧しくみすぼらしいセント・ピーターズバーグの村では、年齢や性別を問わず、新参者は人目を引く珍しい存在だった。この少年は身なりも良かった――平日にしては、あまりにも立派な身なりだった。これはまさに驚くべきことだった。彼の帽子はお洒落なもので、ぴったりとボタンを留めた青い布の上着は新しくて粋で、ズボンも同様だった。彼は靴を履いていた――しかも、まだ金曜日だというのに。おまけにネクタイまで締めていた。鮮やかなリボンの一片だ。彼には都会風の雰囲気が漂っており、それがトムの神経を逆なでした。トムがその見事な驚異を見つめれば見つめるほど、彼の鼻はますますその派手さを嘲り、自分自身の服装がますますみすぼらしく思えてくるのだった。どちらの少年も口を開かなかった。一方が動けば、もう一方も動く――ただし、円を描くように横に動くだけだ。彼らは常に顔と顔、目と目を合わせたままだった。ついにトムが言った。
「お前なんかに負けるか!」
「やれるもんならやってみな。」
「ああ、やってやるさ。」
「いや、できっこないね。」
「できるって言ってるだろ。」
「できっこない。」
「できる。」
「できない。」
「できる!」
「できない!」
気まずい沈黙。それからトムが言った。
「お前の名前は?」
「お前には関係ないことだろ。」
「そうかい、なら関係あることにしてやるさ。」
「じゃあ、なんでそうしないんだ?」
「ごちゃごちゃ言うなら、そうしてやる。」
「ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ。さあ、どうだ。」
「へえ、自分をすごく賢いとでも思ってるんだな? 片手を後ろで縛られてたって、お前くらいやっつけてやれるぜ、その気になればな。」
「じゃあ、なんでやらないんだ? やれるって言うじゃないか。」
「ああ、やってやるさ、もしお前がちょっかいを出すならな。」
「はいはい――そんな家族なら山ほど見てきたぜ。」
「利口ぶって! 自分が何様だと思ってるんだ? ああ、なんて帽子だ!」
「その帽子が気に入らないなら、叩き落としてみろよ。俺の挑戦を受けてみな――挑戦を受けるようなやつは、卵だって吸うんだぜ」[訳注:臆病者だという侮辱の言葉]
「嘘つき!」
「お前もな。」
「お前は喧嘩っ早い嘘つきで、受けて立つ勇気もないくせに。」
「あー、どっか行けよ!」
「おい――これ以上生意気な口をきくなら、石ころを拾ってお前の頭にぶつけてやるからな。」
「へえ、もちろんそうするんだろうね。」
「ああ、やってやるさ。」
「じゃあ、なんでやらないんだ? なんでやるって言い続けるんだ? なぜやらない? 怖いからだろ。」
「怖くなんかない。」
「怖いんだ。」
「怖くない。」
「怖いんだ。」

再び沈黙が流れ、互いに睨み合い、じりじりと横歩きで回り合った。やがて二人は肩と肩が触れ合う距離になった。トムが言った。
「ここから失せろ!」
「お前こそ失せろ!」
「嫌だ。」
「俺も嫌だ。」
こうして二人は、それぞれ片足を斜めに踏ん張って支えとし、全力で押し合い、憎しみを込めて互いを睨みつけたまま立っていた。しかし、どちらも優位に立つことはできなかった。二人とも熱くなって顔を紅潮させるまで揉み合った後、それぞれが用心深く力を緩めた。トムが言った。
「お前は臆病者の子犬だ。俺の兄ちゃんに言いつけてやる。兄ちゃんなら小指一本でお前をのしてやれるし、そうさせてやるからな。」
「お前の兄ちゃんなんか知るか。俺にはもっとでかい兄ちゃんがいるんだ――それに、そいつならお前の兄ちゃんをあの塀の向こうにだって放り投げられるぜ」[両者の兄は架空の存在であった]
「嘘だ。」
「お前がそう言ったって、そうなるわけじゃない。」
トムは親指の先で土の上に一本の線を引き、言った。
「この線を越えてみろ、そしたら立てなくなるまでぶん殴ってやる。挑戦を受けるようなやつは、羊泥棒だ。」
新しい少年はためらわずに線を越え、言った。
「さあ、やるって言ったな。今すぐやってみせろよ。」
「俺に近づくなよ。気をつけた方がいいぜ。」
「でも、お前がやるって言ったんだ――なんでやらないんだ?」
「ちくしょう! 二セントくれりゃ、やってやるぜ。」
新しい少年はポケットから二枚の大きな銅貨を取り出し、嘲るように差し出した。トムはそれを地面に叩きつけた。一瞬のうちに、二人の少年は猫のように掴み合いながら、泥の中で転げ回っていた。そして一分ほどの間に、互いの髪と服を引っ張り、引き裂き、互いの鼻を殴り、引っ掻き、埃と栄光にまみれた。やがて混乱は形をなし、戦いの霧の中からトムが現れた。彼は新しい少年にまたがり、拳で殴りつけていた。「まいったって言え!」と彼は言った。
少年はただ、逃れようともがくだけだった。彼は泣いていた――主に怒りから。
「まいったって言え!」――そして殴打は続いた。
ついに見知らぬ少年は、くぐもった声で「まいった!」と叫び、トムは彼を解放して言った。
「これで懲りただろ。次に誰にちょっかい出すか、気をつけた方がいいぜ。」
新しい少年は服の埃を払いながら去っていった。すすり泣き、鼻を鳴らし、時折振り返っては首を振り、次にトムを捕まえたらどうしてやるかと脅していた。それに対してトムは野次を飛ばし、意気揚々と歩き出した。そして彼が背を向けたとたん、新しい少年は石をひっつかみ、それを投げてトムの肩の間に命中させると、くるりと踵を返し、カモシカのように逃げ去った。トムはその裏切り者を家まで追いかけ、こうして彼がどこに住んでいるかを知った。それから彼はしばらく門のところで陣取り、敵に出てくるよう挑発したが、敵は窓から彼に顔をしかめるだけで、応じようとはしなかった。ついに敵の母親が現れ、トムを悪辣で、たちの悪い、下品な子供だと罵り、追い払うよう命じた。そこで彼は立ち去った。しかし、彼はその少年のために「待ち伏せ」して「お礼参り」をすると心に誓った。

その夜、彼はかなり遅くに家に帰り、用心深く窓から忍び込んだところ、叔母という名の伏兵に遭遇した。そして彼女が彼の服の状態を見るや、彼の土曜の休日を重労働の監禁に変えるという決意は、金剛石のごとき硬さになった。
第二章
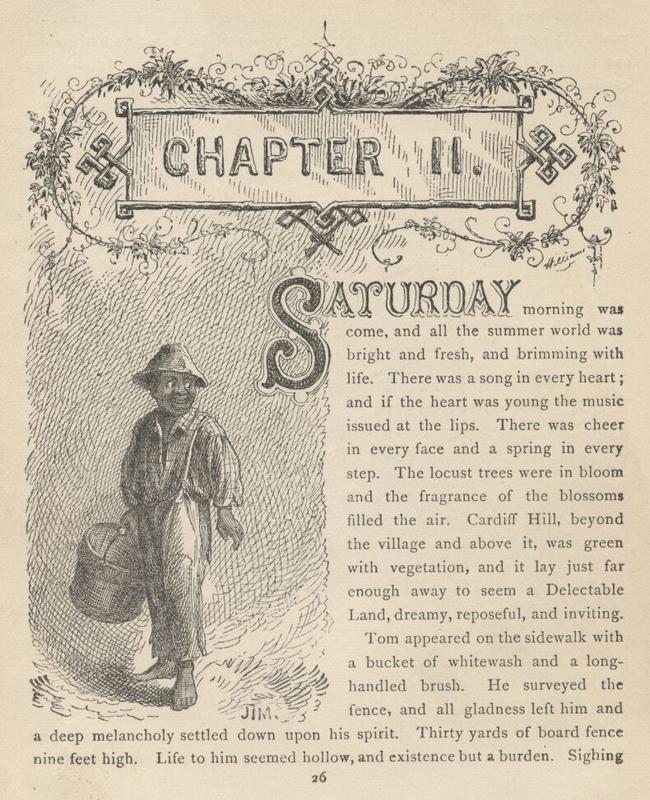
土曜の朝が来た。夏の世界はすべてが明るく新鮮で、生命力に満ち溢れていた。すべての心に歌があった。そして、もしその心が若ければ、音楽は唇からほとばしった。すべての顔に陽気さが満ち、すべての足取りに弾みがあった。ニセアカシアの木は花盛りで、その花の香りが空気を満たしていた。村の向こう、その上方にそびえるカーディフの丘は、草木で緑に覆われ、ちょうど良い距離にあるため、夢見るような、安らかで、魅力的な「喜びの国」のように見えた。
トムは漆喰のバケツと長い柄の刷毛を持って歩道に現れた。彼は塀を見渡し、すべての喜びが彼から去り、深い憂鬱が彼の心に沈み込んだ。高さ九フィート、長さ三十ヤードの板塀。彼にとって人生は空虚に思え、存在はただの重荷だった。ため息をつき、彼は刷毛を浸し、一番上の板に沿ってそれを滑らせた。その作業を繰り返し、もう一度やった。その取るに足らない白く塗られた筋を、まだ塗られていない広大な塀の大陸と比較し、落胆して植木箱に腰を下ろした。ジムがブリキの桶を手に、「バッファロー・ギャルズ」を歌いながら、門からスキップして出てきた。町のポンプから水を汲んでくることは、以前はトムの目にはいつも憎むべき仕事だったが、今はそうは思えなかった。彼はポンプのところには仲間がいることを思い出した。白人、混血、黒人の少年少女がいつもそこで順番を待ち、休み、おもちゃを交換し、口論し、喧嘩し、ふざけ合っていた。そして彼は、ポンプがわずか百五十ヤードしか離れていないにもかかわらず、ジムが水の入った桶を持って一時間以内に戻ってきたことはなく、それでもたいていは誰かが彼を迎えに行かなければならなかったことを思い出した。トムは言った。
「なあ、ジム、もし君が少しペンキを塗ってくれるなら、僕が水を汲んでくるよ。」
ジムは首を振って言った。
「だめだよ、トムの旦那。奥様がね、この水を汲みに行って、誰とも道草食っちゃいけないって言ったんだ。奥様は、トムの旦那が僕にペンキ塗りを頼むだろうって思ってたみたいで、だから自分の仕事をしに行けって言ったんだ――ペンキ塗りはご自分で面倒見るってさ。」
「ああ、おばさんが言ったことなんて気にしないでいいよ、ジム。いつもああ言うんだから。桶を貸してくれ――一分もかからないさ。おばさんには絶対わからないよ。」
「ああ、だめだよ、トムの旦那。奥様に頭をひっぱたかれちまう。ほんとだよ。」
「おばさんが! 誰かをひっぱたくことなんてないさ――指ぬきで頭をこつんとやるだけだろ――そんなの誰が気にするもんか。口ではひどいことを言うけど、口だけじゃ痛くもかゆくもない――少なくとも、泣きさえしなけりゃね。ジム、いいものをやるよ。白いビー玉をあげる!」
ジムは心が揺らぎ始めた。
「白いビー玉だよ、ジム! それに、こいつはとびっきりの一級品だぜ。」
「おやまあ! そりゃすごいビー玉だね! でもトムの旦那、奥様がすごく怖くって――」
「それに、もしやってくれるなら、僕の痛い足の指を見せてあげる。」
ジムも人の子――この魅力は彼にとってあまりにも大きすぎた。彼は桶を置き、白いビー玉を受け取り、包帯が解かれていく間、夢中になってその足の指に身を乗り出した。次の瞬間、彼は桶を手に、ひりひりする尻を抱えて通りを飛ぶように走り去り、トムは勢いよくペンキを塗り、ポリーおばさんはスリッパを手に、目に勝利の色を浮かべて戦場から引き上げていった。

しかし、トムの気力は長くは続かなかった。彼はこの日のために計画していた楽しみのことを考え始め、彼の悲しみは増していった。間もなく、自由な少年たちが、あらゆる種類の楽しい冒険に出かけるために、陽気に通り過ぎていくだろう。そして彼らは、仕事をしなければならない彼をさんざんからかうだろう――そのことを考えただけで、彼は火のように焼かれた。彼は自分の世俗的な財産を取り出して調べた――おもちゃの切れ端、ビー玉、がらくた。仕事の交換を買うには十分かもしれないが、純粋な自由を半時間買うには半分にも満たない。そこで彼は、その乏しい資財をポケットに戻し、少年たちを買収しようという考えを諦めた。この暗く絶望的な瞬間に、彼に霊感がひらめいた! 偉大で壮大な霊感に他ならなかった。
彼は刷毛を手に取り、静かに仕事に取りかかった。やがてベン・ロジャースが姿を現した――数ある少年たちの中で、まさに彼がその嘲笑を最も恐れていた少年だった。ベンの歩き方はホップ・ステップ・アンド・ジャンプ――彼の心が軽く、期待に胸を膨らませていることの十分な証拠だった。彼はリンゴを食べながら、時折、長くメロディアスな雄叫びを上げ、それに続いて重々しいディンドン・ドン、ディンドン・ドンという音を響かせていた。彼は蒸気船になりきっていたのだ。近づくにつれて、彼は速度を落とし、通りの真ん中を取り、右舷に大きく傾き、重々しく、そして骨の折れるような仰々しさで向きを変えた――彼はビッグ・ミズーリ号になりきっており、自分は九フィートの水を引いていると考えていたからだ。彼は船であり、船長であり、機関室のベルを兼ねていたので、彼は自分がハリケーン・デッキに立って命令を下し、それを実行していると想像しなければならなかった。
「停止だ、サー! チリン・チリン!」船足はほとんどなくなり、彼はゆっくりと歩道に近づいた。
「後進に切り替え! チリン・チリン!」彼の腕はまっすぐに伸び、体の脇で硬直した。
「右舷を後進! チリン・チリン! チョウ! チュチョウ・ワウ! チョウ!」その間、彼の右手は荘厳な円を描いていた――それは四十フィートの外輪を表していたからだ。
「左舷を後進! チリン・チリン! チョウ・チュチョウ・チョウ!」左手が円を描き始めた。
「右舷停止! チリン・チリン! 左舷停止! 右舷前進! 停止! 外側をゆっくり回せ! チリン・チリン! チョウ・オウ・オウ! 船首のもやい綱を出せ! 急げ! さあ――スプリングラインを出せ――そこで何をしてる! その切り株に二重に巻きつけろ! 渡し板のそばで待機――放せ! 機関停止、サー! チリン・チリン! シュッ! シュッ! シュッ!」(ゲージコックを試している)
トムはペンキ塗りを続けた――蒸気船には何の注意も払わなかった。ベンは一瞬呆然と見つめ、それから言った。「おいおい! お前、困ったことになったな!」
返事はない。トムは芸術家の目で最後のひと塗りを見渡し、それから刷毛をもう一度優しく滑らせ、先ほどと同じようにその出来栄えを吟味した。ベンは彼の隣に並んだ。トムはリンゴに涎が出そうになったが、仕事に固執した。ベンは言った。
「やあ、相棒、仕事かい?」
トムは突然振り返り、言った。
「なんだ、ベンじゃないか! 気づかなかったよ。」
「なあ――俺、泳ぎに行くんだ。お前も行けたらいいのにって思うだろ? でももちろん、お前は仕事の方がいいんだよな――そうじゃないか? もちろんそうだよな!」
トムは少年を少しの間じっと見つめ、言った。
「何を仕事って言うんだい?」
「なんだって、それが仕事じゃないか?」
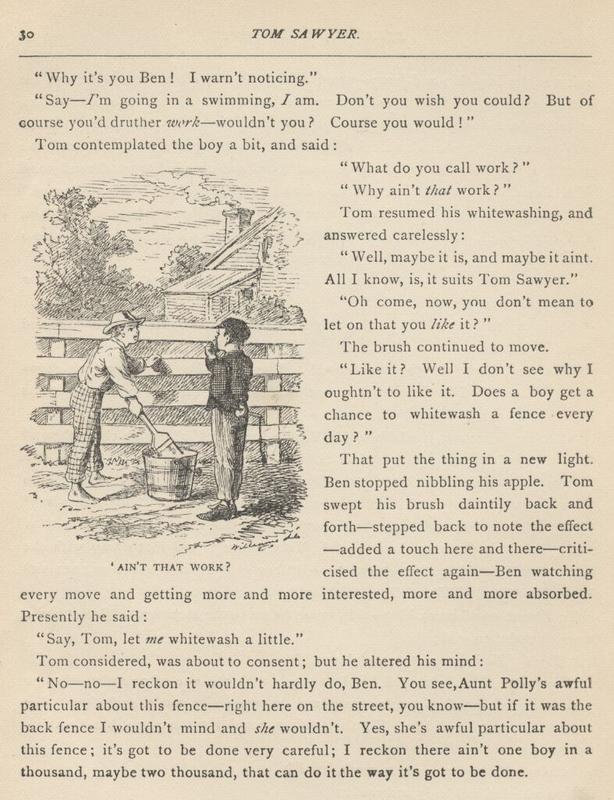
トムはペンキ塗りを再開し、無頓着に答えた。
「まあ、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。僕が知っているのは、これがトム・ソーヤーに合っているってことだけさ。」
「おいおい、まさかそれが好きだなんて言うつもりじゃないだろ?」
刷毛は動き続けた。
「好きかって? まあ、好きじゃいけない理由がわからないな。毎日塀のペンキ塗りができる少年なんて、いるもんかい?」
その一言で、事態は新たな様相を呈した。ベンはリンゴをかじるのをやめた。トムは刷毛を優雅に前後に動かし――一歩下がって効果を確かめ――あちこちにひと筆加え――再び効果を吟味した――ベンはその一挙手一投足を見つめ、ますます興味をそそられ、ますます夢中になっていった。やがて彼は言った。
「なあ、トム、僕にも少しペンキを塗らせてくれよ。」
トムは考え、同意しかけた。しかし、彼は考えを変えた。
「いや――いや――それはちょっと無理だろうな、ベン。ほら、ポリーおばさんはこの塀のことになると、ものすごくうるさいんだ――通りのすぐそばだからね――でも、裏の塀なら気にしないし、おばさんも気にしないだろうけど。そう、この塀にはものすごくこだわるんだ。とても丁寧にやらなきゃいけない。千人に一人、いや二千人に一人だって、やらなきゃいけないやり方でできる少年はいないと思うよ。」
「えっ――本当かい? おいおい、頼むよ――ちょっとだけ試させてくれ。ほんの少しだけ――もし君が僕だったら、僕は君にやらせてあげるよ、トム。」
「ベン、やらせてあげたいのはやまやまなんだ、本当だよ。でもポリーおばさんが――ほら、ジムがやりたがったけど、おばさんはやらせなかった。シッドがやりたがっても、シッドにもやらせなかった。これで僕がどんな立場かわかるだろ? もし君がこの塀に取りかかって、何かあったら――」
「ああ、ちぇっ、僕だって同じくらい丁寧にやるよ。さあ、やらせてくれ。なあ――僕のリンゴの芯をあげるよ。」
「うーん、じゃあ――いや、ベン、だめだ。怖いんだ――」
「全部あげるよ!」
トムは顔には渋々といった表情を浮かべながらも、心の中では大喜びで刷毛を手渡した。そして、かつての蒸気船ビッグ・ミズーリ号が太陽の下で汗水流して働く間、引退した芸術家は近くの日陰にある樽に腰掛け、足をぶらぶらさせ、リンゴをむしゃむしゃ食べながら、次なる罪なき者たちの虐殺を計画していた。材料に不足はなかった。少年たちがひっきりなしにやって来た。彼らはからかいに来たが、ペンキを塗るために残った。ベンがへとへとになる頃には、トムは次の権利をビリー・フィッシャーと、状態の良い凧と交換していた。そして彼が遊び終えると、ジョニー・ミラーが死んだネズミとそれを振り回すための紐で権利を買い取った――かくして、々、々、時間は過ぎていった。そして午後の中頃になる頃には、朝には貧しく一文無しの少年だったトムは、文字通り富に溺れていた。彼は前述の品々に加えて、ビー玉十二個、ジューズ・ハープ[訳注:口琴の一種]の一部、覗き込むための青い瓶ガラスの破片、糸巻きの大砲、何も開けられない鍵、チョークの欠片、デキャンタのガラス栓、ブリキの兵隊、おたまじゃくし二匹、爆竹六本、片目だけの子猫、真鍮のドアノブ、犬の首輪――ただし犬はなし――ナイフの柄、オレンジの皮四切れ、そしてぼろぼろの古い窓枠を手にしていた。
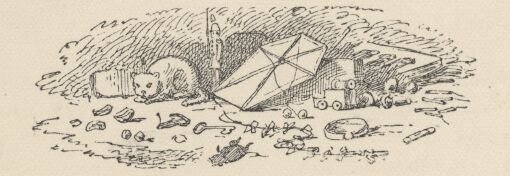
彼はその間ずっと、素晴らしく、快適で、怠惰な時間を過ごした――仲間も大勢いた――そして塀には三度も漆喰が塗られていた! もし漆喰が尽きなければ、彼は村の少年全員を破産させていただろう。
トムは、結局のところ、この世もそう捨てたものではない、と独りごちた。彼は知らず知らずのうちに、人間の行動に関する偉大な法則を発見していた――すなわち、人や少年に何かを渇望させるためには、それを手に入れるのが難しいものにすればよい、という法則だ。もし彼がこの本の著者ような、偉大で賢い哲学者であったなら、彼は今頃、「仕事」とは人が義務としてやらなければならないことであり、「遊び」とは人が義務としてやらなくてもよいことである、と理解していただろう。そしてこれは、なぜ造花を作ったり、踏み車で働いたりすることが仕事であり、一方、十柱戯をしたり、モンブランに登ったりすることがただの娯楽であるのかを理解する助けとなるだろう。イギリスには、夏になると毎日、二十マイルか三十マイルの路線を四頭立ての乗合馬車で走らせる裕福な紳士たちがいる。その特権に相当な金がかかるからだ。しかし、もしその奉仕に対して賃金が提示されれば、それは仕事に変わり、彼らは辞職するだろう。
少年は、自分の世俗的な境遇に起きた実質的な変化についてしばらく考えを巡らせ、それから報告のために本部へと向かった。

第三章
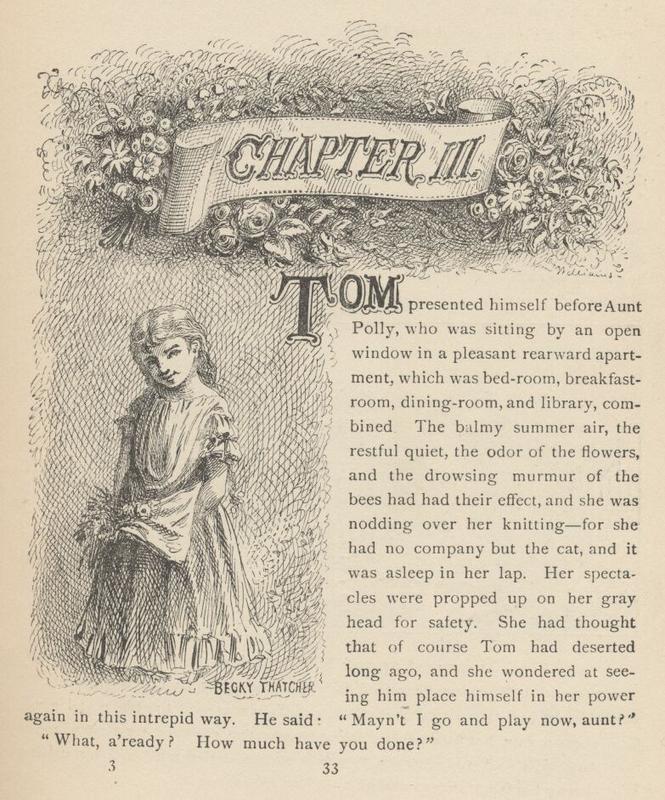
トムはポリーおばさんの前に姿を現した。彼女は、寝室、朝食室、食堂、そして書斎を兼ねた、心地よい奥の部屋の開いた窓辺に座っていた。うららかな夏の空気、安らかな静寂、花の香り、そして蜂の眠気を誘う羽音が功を奏し、彼女は編み物をしながらうたた寝をしていた――話し相手は猫しかおらず、その猫は彼女の膝の上で眠っていたからだ。彼女の眼鏡は安全のために、灰色の髪の上に押し上げられていた。彼女は当然トムはとっくに逃げ出したものと思っていたので、彼がこれほど大胆に再び彼女の支配下に身を置いたことに驚いた。彼は言った。「おばさん、もう遊びに行ってもいい?」
「なんだい、もうかい? どれだけやったんだい?」
「全部終わったよ、おばさん。」
「トム、嘘をつくんじゃないよ――我慢ならないからね。」
「ついてないよ、おばさん。本当に全部終わったんだ。」
ポリーおばさんは、そのような証言をほとんど信用しなかった。彼女は自分で確かめに出て行った。そして、トムの言葉の二割でも本当であれば満足だっただろう。塀全体が白く塗られ、それだけでなく、念入りに上塗り、再上塗りされ、地面にまで筋が一本加えられているのを見つけた時、彼女の驚きはほとんど言葉に尽くせなかった。彼女は言った。
「まあ、なんてこと! これには参ったね。お前はやる気になれば仕事ができるんだね、トム」そして彼女はこう付け加えて、その賛辞を薄めた。「でも、やる気になるのは、ものすごく珍しいけどね、言っておくけど。さあ、行って遊びなさい。でも、一週間以内には帰ってくるんだよ、さもないとひっぱたくからね。」
彼女は彼の偉業の素晴らしさにすっかり心を打たれ、彼を物置に連れて行き、とっておきのリンゴを選んで彼に手渡した。その際、ご褒美というものは、罪を犯さず、徳高い努力によって得られた時、その価値と風味がどれほど増すかという、ためになる説教も添えた。そして彼女が聖書の言葉で見事に締めくくっている間に、彼はドーナツを一つ「くすねた」。
それから彼は飛び出し、シッドが二階の奥の部屋に通じる外階段をちょうど上り始めるところを見た。土くれは手近にあり、瞬く間に空はそれで満たされた。それらは雹嵐のようにシッドの周りで荒れ狂った。そしてポリーおばさんが驚きから我に返り、救出に駆けつける前に、六つか七つの土くれが命中し、トムは塀を越えて姿を消していた。門はあったが、大抵の場合、彼は時間がなくてそれを使う暇がなかった。黒い糸のことを指摘して彼を厄介事に巻き込んだシッドに落とし前をつけた今、彼の魂は平穏であった。

トムは街区を迂回し、おばさんの牛小屋の裏手を通るぬかるんだ路地に入った。彼はやがて無事に捕獲と罰の及ばない範囲まで逃れ、村の広場へと急いだ。そこでは、事前の取り決めに従い、二つの少年「軍隊」が戦闘のために集まっていた。トムは一方の軍の将軍であり、ジョー・ハーパー(親友)がもう一方の将軍だった。この二人の偉大な指揮官は、自ら戦うようなことはしなかった――それはさらに小さな若輩者たちにふさわしいことだったからだ――而是、高台に並んで座り、副官を通じて下される命令によって野戦を指揮した。長く激しい戦いの末、トムの軍は偉大な勝利を収めた。それから死者が数えられ、捕虜が交換され、次の不和の条件が合意され、必要な戦闘の日が定められた。その後、軍隊は整列して行進し、トムは一人で家路についた。

彼がジェフ・サッチャーの家のそばを通りかかっていると、庭に新しい女の子がいるのを見つけた――愛らしい小さな青い目の生き物で、黄色い髪を二本の長いおさげに編み、白い夏のドレスと刺繍の入ったパンタレットを身につけていた。戴冠したばかりの英雄は、一発も撃たずに陥落した。エイミー・ローレンスという名の娘は彼の心から消え去り、その記憶さえも残さなかった。彼は彼女を狂おしいほど愛していると思っていた。彼の情熱を崇拝だと見なしていた。そして見よ、それはただの哀れで、はかない、ほんのわずかな好意に過ぎなかった。彼は彼女を射止めるのに何ヶ月も費やした。彼女が告白したのはほんの一週間前だった。彼はほんの七日間、世界で最も幸せで誇り高い少年だった。そして今、一瞬のうちに、彼女は訪問を終えた偶然の客のように、彼の心から去ってしまった。
彼はこの新しい天使を盗み見るように崇めていたが、彼女が彼に気づいたのを見ると、今度は彼女がそこにいることを知らないふりをして、彼女の賞賛を勝ち取るために、あらゆる種類の馬鹿げた少年らしいやり方で「見せびらかし」始めた。彼はこの奇妙な愚行をしばらく続けた。しかし、やがて、彼がいくつかの危険な体操の演技の真っ最中に、横を見ると、その小さな女の子が家の方へ向かって歩いているのが見えた。トムは塀に近づき、それに寄りかかり、悲しみながら、彼女がもう少し長く留まってくれることを願った。彼女は階段で一瞬立ち止まり、それからドアの方へ動いた。彼女が敷居に足をかけたとき、トムは大きなため息をついた。しかし、彼の顔はすぐに輝いた。彼女が姿を消す直前に、塀越しにパンジーを一つ投げたからだ。

少年は走り回り、花の二、三フィート手前で止まり、それから手で目を覆い、まるでその方向で何か面白いことが起こっているのを発見したかのように、通りの下の方を見始めた。やがて彼は藁を一本拾い、頭を大きく後ろに傾けて、それを鼻の上でバランスを取ろうとし始めた。そして、その努力の中で左右に動くにつれて、彼はパンジーにますます近づいていった。ついに彼の裸足がその上に乗り、しなやかな足指がそれを掴み、彼はその宝物を抱えてぴょんと跳ね、角を曲がって消えた。しかし、ほんの一瞬だけ――彼がその花を上着の内側、心臓の隣に――あるいは胃の隣かもしれないが、彼は解剖学にあまり詳しくなく、いずれにせよ、それほどやかましくもなかった――ボタンで留める間だけだった。
彼は今や戻ってきて、日暮れまで塀のあたりをうろつき、以前のように「見せびらかし」ていた。しかし、その女の子は二度と姿を現さなかった。もっとも、トムは、彼女がその間どこかの窓の近くにいて、彼の注意に気づいていたかもしれないという希望で、少し自分を慰めた。ついに彼は、哀れな頭を空想でいっぱいにしながら、しぶしぶと家路についた。
夕食の間中、彼の気分は非常に高揚していたので、おばさんは「この子に何が取り憑いたんだろう」と不思議に思った。彼はシッドに土くれを投げつけたことについて、きつく叱られたが、それを少しも気にしていないようだった。彼はおばさんの鼻先で砂糖を盗もうとし、そのために拳を叩かれた。彼は言った。
「おばさん、シッドが取るときは叩かないじゃないか。」
「まあ、シッドはお前みたいに人を困らせたりしないからね。あたしが見てなきゃ、お前はいつもその砂糖に手を出してるだろうよ。」
やがて彼女が台所に入ると、シッドは自分の無罪放免を喜び、砂糖壺に手を伸ばした――それはトムに対する一種の勝ち誇りであり、ほとんど耐え難いものだった。しかし、シッドの指が滑り、壺は落ちて割れた。トムは有頂天になった。あまりの有頂天さに、彼は舌を抑えて沈黙を守ったほどだ。彼は、おばさんが入ってきても一言も口を利かず、誰がこの悪さをしたのか尋ねるまで、じっと座っていようと心に決めた。そして、その時になったら告げ口をし、あのお気に入りの模範生が「お仕置き」されるのを見るほど、世の中に素晴らしいことはないだろう、と。彼は歓喜に満ち溢れ、老婆が戻ってきて、眼鏡越しに怒りの稲妻を放ちながら残骸の上に立っているとき、ほとんど自分を抑えきれなかった。彼は独りごちた。「さあ、来るぞ!」そして次の瞬間、彼は床にひっくり返っていた! 強力な平手が再び振り上げられたとき、トムは叫んだ。
「待ってよ、なんで僕をぶつのさ? ――割ったのはシッドだよ!」
ポリーおばさんは戸惑って立ち止まり、トムは癒しの同情を期待した。しかし、彼女が再び口を開いたとき、彼女はただこう言っただけだった。
「ふん! まあ、一発くらい余計に食らったって罰は当たらんだろうよ。あたしがいない間に、何か他の大胆ないたずらをしていたに違いないからね。」

それから彼女の良心が彼女を責め、何か親切で愛情のこもった言葉をかけたいと切に願った。しかし、それは自分が間違っていたと認めることになると判断し、しつけがそれを禁じた。そこで彼女は沈黙を守り、悩ましい心を抱えて自分の仕事に取りかかった。トムは隅でふてくされ、自分の悲惨さを誇張した。彼は、心の中ではおばさんが自分にひざまずいていることを知っており、その意識に陰鬱な満足感を覚えていた。彼は何の合図も出さないだろうし、何の合図にも気づかないふりをするだろう。時折、涙の膜を通して、切なげな視線が自分に注がれていることを知っていたが、彼はそれを認めようとはしなかった。彼は自分が死の病に伏し、おばさんが身をかがめて、ほんの一言の許しの言葉を懇願する姿を想像した。しかし、彼は壁に顔を向け、その言葉を言わずに死ぬだろう。ああ、その時、彼女はどんな気持ちになるだろうか? そして彼は、川から死体となって運ばれ、巻き毛はすべて濡れ、傷ついた心は安らかに眠っている自分を想像した。彼女はどんなに彼にすがりつき、彼女の涙は雨のように降り注ぎ、彼女の唇は神に息子を返してくださいと祈り、二度と、二度と彼を虐待しないと誓うだろう! しかし、彼はそこに冷たく白く横たわり、何の合図も送らないだろう――哀れな小さな受難者、その悲しみは終わりを告げたのだ。彼はこれらの夢の哀愁で自分の感情をかき立て、飲み込み続けなければならないほど、窒息しそうになった。そして彼の目は水のぼやけで泳ぎ、まばたきをすると溢れ出し、鼻の先から滴り落ちた。そして、この悲しみを愛でることが彼にとっては何という贅沢であったか、彼は世俗的な陽気さや耳障りな喜びがそれに割り込んでくるのを耐えられなかった。それはそのような接触にはあまりにも神聖すぎた。そして、やがて、いとこのメアリーが一週間という永遠に続くような田舎への訪問を終えて、再び家に帰れた喜びに満ちて踊るように入ってきたとき、彼は立ち上がり、彼女が歌と太陽を一方のドアから持ち込むと同時に、雲と闇に包まれてもう一方のドアから出て行った。

彼は少年たちがいつものように集まる場所から遠く離れてさまよい、自分の精神と調和する寂しい場所を探した。川に浮かぶいかだが彼を誘い、彼はその外縁に腰を下ろし、川の物寂しい広大さを熟考した。その間、自然が考案した不快な手順を経ることなく、ただ一度に、無意識のうちに溺れることができれば、と願っていた。それから彼は自分の花のことを思い出した。彼はそれを取り出した。しわくちゃでしおれており、それが彼の陰鬱な幸福感を大いに高めた。もし彼女が知ったら、彼を哀れんでくれるだろうか? 彼女は泣き、彼の首に腕を回して慰める権利があればいいのに、と願うだろうか? それとも、この空虚な世界すべてのように、冷たく背を向けるだろうか? この光景は、快い苦しみのあまりの苦痛をもたらしたので、彼はそれを心の中で何度も何度も練り直し、新しく様々な光を当てて、それがすり切れるまで繰り返した。ついに彼はため息をついて立ち上がり、闇の中へと去っていった。

九時半か十時頃、彼は人気のない通りを歩いて、崇拝する未知の人が住む場所へとやって来た。彼は一瞬立ち止まった。耳を澄ましても物音は聞こえなかった。二階の窓のカーテンに、ろうそくの鈍い光が投げかけられていた。その神聖な存在はそこにいるのだろうか? 彼は塀を登り、植物の間を忍び足で進み、ついにその窓の下に立った。彼は長く、感情を込めてそれを見上げた。それから彼はその下の地面に身を横たえ、仰向けになり、胸の上で手を組み、哀れなしおれた花を握りしめた。そしてこのようにして彼は死ぬのだろう――冷たい世界の中で、家なき頭の上に雨露をしのぐものもなく、額の死の汗を拭ってくれる友好的な手もなく、大いなる苦しみが来たときに、憐れみ深くかがみ込んでくれる愛する顔もないまま。そしてこのようにして、彼女は晴れやかな朝に外を見たときに彼を見るだろう。そして、おお! 彼女は彼の哀れな、生命のない体に一粒の小さな涙を落としてくれるだろうか、輝かしい若き命がかくも無残に枯れ、かくも時ならぬうちに絶たれたのを見て、一つの小さなため息をついてくれるだろうか?
窓が上がり、女中の不協和音な声が神聖な静寂を汚し、横たわる殉教者の亡骸に deluge の水が降り注いだ!

息の詰まった英雄は、安堵の鼻息とともに飛び上がった。空中で何かが飛ぶようなヒュッという音と、呪いの言葉のつぶやきが混じり合い、ガラスが砕けるような音が続き、小さな、ぼんやりとした姿が塀を越え、闇の中へと駆け去っていった。
それから間もなく、トムが寝間着に着替え、獣脂ろうそくの光でびしょ濡れの服を調べていると、シッドが目を覚ました。しかし、もし彼が何らかの「ほのめかし」をしようという漠然とした考えを持っていたとしても、彼はそれを思いとどまり、沈黙を守った。トムの目には危険が宿っていたからだ。
トムは祈りという追加の煩わしさもなく床につき、シッドはその省略を心に留めた。

第四章
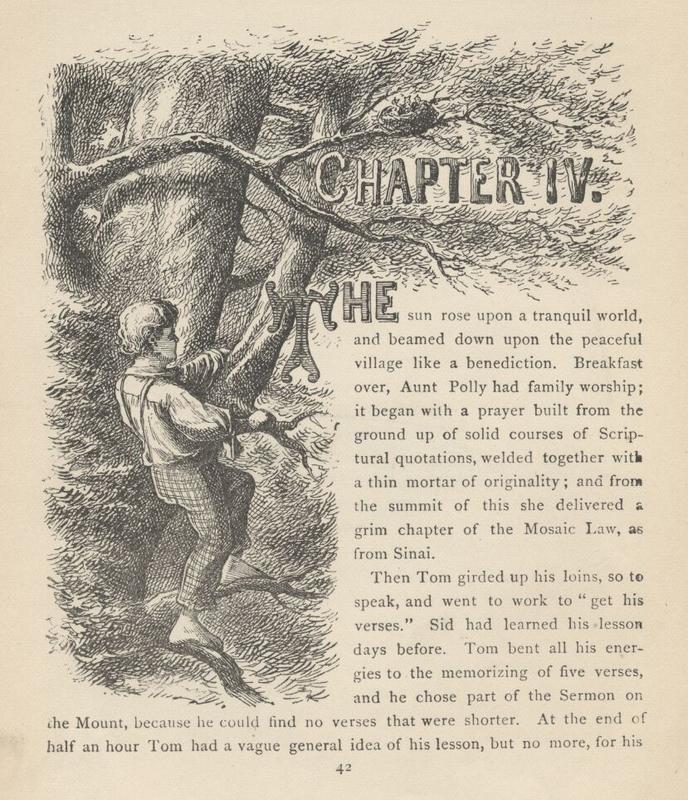
太陽は静かな世界の上に昇り、祝福のように平和な村を照らした。朝食が終わると、ポリーおばさんは家族礼拝を行った。それは、聖書の引用という堅固な層を、独創性という薄いモルタルでつなぎ合わせて築き上げられた祈りから始まった。そしてその頂上から、彼女はシナイ山から下されたかのように、モーセの律法の厳しい一章を読み上げた。
それからトムは、いわば、腰に帯を締め、彼の「聖句」を覚える作業に取りかかった。シッドは何日も前に自分の課題を覚えていた。トムは五つの聖句を暗記することに全力を注ぎ、彼は山上の垂訓の一部を選んだ。それより短い聖句を見つけることができなかったからだ。半時間後、トムは自分の課題について漠然とした全体像を掴んだが、それ以上ではなかった。彼の心は人間の思考の全領域を駆け巡り、彼の両手は気を散らす気晴らしで忙しかったからだ。メアリーが彼の本を持って暗唱を聞きに来たので、彼は霧の中を手探りで進もうとした。
「幸いなるかな、――あー、あー――」
「貧しき者」――
「そう――貧しき者。幸いなるかな、心の貧しき者――あー、あー――」
「霊において」――
「霊において。幸いなるかな、霊において心の貧しき者。その人たちは――その人たちは――」
「その人たちの」――
「その人たちのものだからである。幸いなるかな、霊において心の貧しき者。その人たちのものだからである、天の御国は。幸いなるかな、悲しむ人々。その人たちは――その人たちは――」
「さ」――
「その人たちは――あー――」
「さ、れ、る――」
「その人たちは、さ、れ――ああ、もうわからないよ!」
「される!」
「ああ、される! その人たちはされる――その人たちはされる――あー、あー――悲しむ者はされる――あー、あー――幸いなるかな、される人々――その人たちが――あー、その人たちが悲しむ者は、その人たちは――あー、何をされるんだい? なんで教えてくれないの、メアリー? ――なんでそんなに意地悪するんだい?」
「ああ、トム、なんて頭の固い子なの。からかってるんじゃないわ。そんなことしないわよ。もう一度行って覚えなきゃ。がっかりしないで、トム、あなたならできるわ――もしできたら、すごく素敵なものをあげるから。ほら、これでいい子ね。」
「わかった! 何だい、メアリー、何だか教えてよ。」
「気にしないで、トム。私が素敵だって言ったら、素敵なものなのよ。」
「そりゃそうだね、メアリー。わかった、もう一度やってみるよ。」
そして彼は「もう一度やってみた」――そして、好奇心と見込まれる利益という二重の圧力の下、彼は非常に熱心に取り組んだので、輝かしい成功を収めた。メアリーは彼に、十二セント半の価値がある、新品の「バーロウ」ナイフを贈った。そして、彼の全身を駆け巡った喜びの痙攣は、彼の根底を揺るがした。確かに、そのナイフは何も切れなかったが、それは「正真正銘の」バーロウであり、そこには想像を絶する壮大さがあった――もっとも、西部の少年たちが、そのような武器がその価値を損なうほどに偽造され得るという考えを、一体どこから得たのかは、壮大な謎であり、おそらく永遠にそうあり続けるだろう。トムはどうにかして食器棚をそれで傷つけ、整理箪笥に取りかかろうとしていたところ、日曜学校へ行くための着替えに呼び出された。

メアリーは彼にブリキの洗面器一杯の水と石鹸を一つ渡し、彼は戸口の外に出て、そこにある小さなベンチに洗面器を置いた。それから彼は石鹸を水に浸して置き、袖をまくり、水を静かに地面にこぼし、それから台所に入って、ドアの後ろのタオルで熱心に顔を拭き始めた。しかし、メアリーはタオルを取り上げて言った。
「まあ、恥ずかしくないの、トム。そんなに悪い子になっちゃだめよ。水はあなたを傷つけたりしないわ。」
トムは少々うろたえた。洗面器に再び水が満たされ、今度はその前にしばらく立ち尽くして覚悟を決めた。大きく息を吸い込むと、いざ取りかかった。やがて台所に入ってきたとき、彼は両目を固く閉じ、手探りでタオルを探していた。顔からは石鹸の泡と水が、輝かしい努力の証として滴り落ちていた。しかしタオルから顔を出すと、まだ満足のいく出来ではなかった。きれいな領域は顎と頬骨のあたりで、まるで仮面のようにぷっつりと途切れている。その線の向こう側には、潤いのない土壌のごとき黒々とした地帯が、首の前から後ろにかけて広がっていた。メアリーが彼を引き受け、仕上げにかかった。作業が終わると、トムは肌の色など関係なく、一人の人間、一人の同胞となっていた。びしょ濡れの髪はきれいにとかされ、短い巻き毛は優雅で均整のとれた髪型に整えられた。[彼はこっそりと、苦労してその巻き毛をまっすぐに伸ばし、髪を頭にぴったりとなでつけた。巻き毛は女々しいものだと考えており、自分の巻き毛が人生を苦々しいものにしていると思っていたからだ。]それからメアリーは、この二年というもの日曜日にしか使ったことのない服を一式取り出した――それは単に「よそ行きの服」と呼ばれていた――このことから、彼の衣装持ちがいかほどのものか窺い知れよう。トムが自分で服を着終えると、メアリーが「身なりを整えて」やった。こぎれいな少年用上着のボタンを顎まで留め、だぶだぶのシャツの襟を肩まで折り返し、服の埃を払い、斑点模様の麦わら帽子を頭に載せてやった。今の彼は、見違えるほど立派で、そして居心地が悪そうに見えた。実際、見た目どおりにひどく居心地が悪かった。一張羅ときれいな身なりというものには、彼を苛立たせる息苦しさがあったのだ。メアリーが靴のことを忘れてくれればと願ったが、その望みは打ち砕かれた。彼女は当時の習慣どおり、靴に獣脂をたっぷりと塗り込んで持って来たのだ。トムはかんしゃくを起こし、やりたくもないことばかりやらされる、と文句を言った。しかしメアリーはなだめるように言った。
「お願い、トム。いい子だから。」
そこで彼は、不満をぶつぶつ言いながら靴に足を入れた。メアリーもすぐに支度を終え、三人の子供たちは日曜学校へと出発した。そこはトムが心の底から嫌っている場所だったが、シッドとメアリーはお気に入りだった。
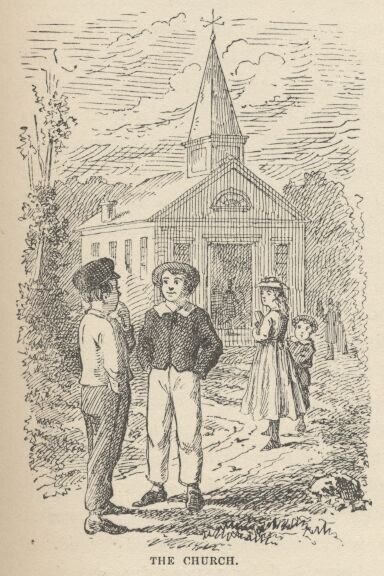
日曜学校の時間は九時から十時半までで、その後に教会の礼拝がある。子供たちのうち二人はいつも自発的に説教まで残ったが、もう一人もいつも残った――ただし、もっと強力な理由によってである。教会の、背もたれが高くクッションのない長椅子には三百人ほどが座れた。建物自体は小さく簡素なもので、尖塔の代わりにてっぺんに松板でできた植木箱のようなものが乗っているだけだった。戸口でトムは一歩下がり、日曜日のよそ行きを着た仲間に声をかけた。
「なあ、ビリー、黄色の券、持ってるか?」
「ああ。」
「何と交換してくれる?」
「お前は何をくれるんだ?」
「甘草のかけらと釣り針だ。」
「見せてみろ。」
トムが見せると、相手は満足し、品物は持ち主を変えた。それからトムは、白いビー玉二つを赤色の券三枚と、何か他のがらくたを青色の券二枚と交換した。やってくる他の少年たちを待ち伏せし、さらに十分か十五分、様々な色の券を買い続けた。そして、清潔で騒がしい少年少女の一団と共に教会に入り、自分の席に進むと、手近にいた最初の少年と喧嘩を始めた。教師である厳格な初老の男が仲裁に入った。その教師が少し背を向けた隙に、トムは隣の長椅子に座る少年の髪を引っ張り、その子が振り返ったときには本に没頭していた。やがて別の少年にピンを突き刺し、「痛い!」という声を聞こうとして、また教師から叱責された。トムのクラスは皆この調子だった――落ち着きがなく、騒がしく、厄介者ぞろいなのだ。聖句の暗唱になると、一人として完璧に覚えている者はおらず、終始助け舟を出してもらわねばならなかった。それでもなんとかやり遂げ、それぞれがご褒美をもらった。それは聖書の一節が書かれた小さな青い券で、二節暗唱するごとに一枚もらえた。青い券十枚で赤い券一枚と交換でき、赤い券十枚は黄色い券一枚に相当した。そして黄色い券を十枚集めると、校長からごく簡素な装丁の聖書(物価の安かった当時で四十セントの価値)が贈られた。ドレの挿絵入り聖書[訳注:19世紀フランスの画家ギュスターヴ・ドレによる豪華な挿絵入りの聖書]のためだとしても、二千もの聖句を暗記する勤勉さと熱心さを持ち合わせている読者がどれほどいるだろうか。しかしメアリーはこの方法で聖書を二冊手に入れていた――二年がかりの根気のいる仕事だった――し、ドイツ人の両親を持つ少年は四、五冊も獲得していた。その子はかつて三千もの聖句を一度も止まらずに暗唱したことがある。だが、その精神的な負担はあまりに大きく、その日以来、彼はほとんど白痴同然となってしまった。これは学校にとって痛ましい不運だった。というのも、来客のある重要な機会には、校長が(トムの言葉を借りれば)いつもこの少年を前に出して「見せびらかして」いたからだ。年長の生徒たちだけが、券を失くさずに辛気くさい勉強を続け、聖書を手に入れることができた。そのため、この賞品が授与されるのは稀で注目すべき出来事だった。受賞した生徒はその日一日、偉大で人目を引く存在となり、その場で生徒たちの心には新たな野心が燃え上がり、それは二週間ほど続くのが常だった。トムの知的な胃袋が、そうした賞品を本気で欲したことはおそらく一度もなかっただろう。だが、それに伴う栄光と喝采を、彼の全存在が長らく渇望していたことは疑いようもなかった。

やがて校長が説教壇の前に立ち、閉じた賛美歌集を手に、その頁の間に人差し指を挟み込み、静粛を求めた。日曜学校の校長がいつもの短いスピーチをするとき、手に賛美歌集を持つのは、コンサートで舞台に立ちソロを歌う歌手が必ず楽譜を手にするのと同じくらい必要なことだった――もっとも、なぜ必要なのかは謎である。というのも、当の本人は賛美歌集にも楽譜にも決して目をやることがないからだ。この校長は三十五歳の痩せた男で、砂色の山羊ひげを生やし、短い砂色の髪をしていた。彼は糊のきいた立ち襟のシャツを着ており、その上端は耳に届きそうなほどで、鋭い先端は口角のあたりで前方に曲がっていた――それは正面をまっすぐ見ることを強いる柵のようなもので、横を見るときは体ごと向きを変えなければならなかった。顎は、紙幣ほども幅と長さがあり、端に飾りの房がついた幅広のネクタイで支えられていた。ブーツの爪先は、そりの滑走部のように鋭く上を向いていたが、これは当時の流行で、若者たちが何時間も壁に爪先を押し付けて座り、根気よく苦労して作り出したものだった。ウォルターズ氏は真面目な顔つきで、心根は非常に誠実で正直だった。彼は神聖な物事や場所を深く敬い、世俗的な事柄とは完全に切り離していたため、自分でも気づかぬうちに、日曜学校での声には平日にまったく聞かれない独特の抑揚が備わっていた。彼はこんな風に話し始めた。
「さあ、子供たち、できるだけまっすぐ、きれいな姿勢で座って、一、二分ほど私に注目してください。そう――それでいい。良い子というのはそうするものです。窓の外を見ている女の子が一人いますね――私がどこか外にいると思っているのかもしれませんね――もしかしたら、木の上で小鳥たちに演説でもしていると思っているのかな。[拍手喝采のくすくす笑い]こうして、たくさんの輝くような、きれいな子供たちの顔が、正しいこと、善いことを学ぶためにこのような場所に集まっているのを見るのが、どれほど嬉しいことか、皆さんに伝えたいのです」云々。演説の残りを書き記す必要はないだろう。それは決まりきった型のもので、我々皆がよく知っているものだからだ。
スピーチの最後の三分の一は、一部の悪童たちの間で喧嘩やその他の遊びが再開されたこと、そして広範囲に広がったそわそわとした動きやひそひそ話によって台無しにされた。その波は、シッドやメアリーのような、孤立し、決して堕落しない岩の麓にまで打ち寄せていた。しかし、ウォルターズ氏の声が静まると同時に、あらゆる物音がぴたりと止み、スピーチの終わりは、声なき感謝の念の爆発をもって迎えられた。
ひそひそ話の大部分は、多かれ少なかれ珍しい出来事――来客の入場――によって引き起こされたものだった。サッチャー弁護士が、ひどく弱々しい老齢の男性を伴って入ってきた。そして、鉄灰色の髪をした恰幅の良い立派な中年の紳士と、おそらくその後妻であろう威厳のある婦人。その婦人は一人の子供の手を引いていた。トムはずっとそわそわし、いらだちと不満でいっぱいだった。良心の呵責にも苛まれていた――エイミー・ローレンスの目を見ることができず、彼女の愛情のこもった眼差しに耐えられなかったのだ。しかし、この小さな新参者を見た途端、彼の魂は一瞬にして至福の炎に包まれた。次の瞬間には、彼はありったけの力で「見せびらかし」を始めていた――少年たちを殴り、髪を引っ張り、変な顔をする――要するに、女の子を魅了し、喝采を勝ち取るために有効だと思われるあらゆる手管を弄していた。彼の有頂天な気分に一点の曇りがあるとすれば、それはこの天使の庭で味わった屈辱の記憶だった。しかし、その砂に書かれた記録も、今や押し寄せる幸福の波に洗われ、急速に消え去ろうとしていた。
来客たちは最上席に案内され、ウォルターズ氏のスピーチが終わるとすぐに、彼は来客たちを学校の皆に紹介した。中年の紳士はとんでもない大人物だった――何を隠そう、郡の判事その人である。子供たちがこれまで目にした中で、まったくもって最も威厳のある存在だった。彼らは判事がどんな物質でできているのだろうかと考え、彼が吠えるのを聞いてみたいと半分思い、また、本当に吠えるのではないかと半分恐れていた。彼は十二マイル離れたコンスタンティノープルから来たという――つまり、旅をし、世の中を見てきたのだ。この目で郡の裁判所――ブリキの屋根だと言われている――を見たのだ。こうした思いが呼び起こした畏敬の念は、印象的な静寂と、ずらりと並んだ凝視する目によって証明されていた。この人こそ、自分たちの町の弁護士の兄である、偉大なるサッチャー判事だった。ジェフ・サッチャーはすぐに前へ進み出て、この偉人と親しくなり、学校中の羨望の的になろうとした。こんなひそひそ話が聞こえてきたら、彼の魂にとっては音楽だったろう。
「見ろよ、ジム! あいつ、あそこに行くぞ。おい、見ろって! 握手するつもりだ――本当に握手してる! ちくしょう、お前もジェフになりたいだろ?」
ウォルターズ氏は「見せびらかし」にかかった。あらゆる種類の役人らしいそわそわとした動きや活動で、命令を下し、判断を下し、あちこち、標的を見つけられるところならどこででも指示を飛ばした。図書係は「見せびらかした」――両腕に本をいっぱい抱えてあちこち走り回り、取るに足らない権威者が好むような、やたらと大騒ぎをしてみせた。若い女の先生たちは「見せびらかした」――ついさっきまで殴られていた生徒たちの上に優しく身をかがめ、悪い子には可愛らしく警告の指を立て、良い子は愛情を込めて撫でてやった。若い男の先生たちは、ちょっとした叱責や、その他、権威と規律への細やかな注意を示す小さな見せびらかしで「見せびらかした」――そして、男女を問わずほとんどの教師が、説教壇のそばの図書室に用事を見つけた。それはしばしば二、三度やり直さねばならない用事だった(いかにも面倒くさそうに)。小さな女の子たちも様々な方法で「見せびらかし」、小さな男の子たちはあまりに熱心に「見せびらかした」ので、空気は紙つぶてと小競り合いのざわめきで満ちていた。そしてそのすべての上で、その偉人は座り、堂々たる判事らしい微笑みを会堂全体に投げかけ、自らの偉大さという太陽の光で身を暖めていた――彼もまた「見せびらかして」いたのだ。
ウォルターズ氏の恍惚を完璧なものにするために欠けているものが一つだけあった。それは、聖書という賞品を授与し、神童をお披露目する機会だった。何人かの生徒は黄色の券を数枚持っていたが、十分な数を持っている者はいなかった――彼は優等生たちの間を回って尋ねてみたのだ。今や、あのドイツ人の少年が正気で戻ってきてくれるなら、何でも差し出しただろう。
そして今、希望が絶たれたこの瞬間に、トム・ソーヤーが黄色い券九枚、赤い券九枚、青い券十枚を手に進み出て、聖書を要求したのである。これはまさに青天の霹靂だった。ウォルターズ氏は、この少年からの申し出など、今後十年は期待していなかった。しかし、どうしようもなかった――ここに保証付きの小切手があり、額面どおりの価値があるのだ。かくしてトムは、判事やその他の選ばれし者たちと同じ場所に引き上げられ、その大ニュースが本部から発表された。それはこの十年で最も驚くべきサプライズであり、その衝撃はあまりに大きく、新たな英雄を判事の高みまで引き上げ、学校は一人の代わりに二人の驚異の的を見つめることになった。少年たちは皆、嫉妬にさいなまれた――しかし、最も苦い痛みを味わったのは、自分たちがペンキ塗りの権利を売ってトムが蓄えた富と引き換えに券を取引したことで、この憎むべき栄光に貢献してしまったのだと、遅きに失して気づいた者たちだった。彼らは、狡猾な詐欺師、草むらに潜むずる賢い蛇の餌食になった自分自身を軽蔑した。
賞品は、校長がこの状況下で絞り出せる限りの熱意を込めてトムに手渡された。しかし、そこには真の感動がやや欠けていた。というのも、哀れな男の本能が、ここにはおそらく日の目を見るに耐えない謎があると教えていたからだ。この少年が二千もの聖書の知恵の束をその頭脳にしまい込んでいるなど、まったくもって馬鹿げた話だった――十二もあれば、彼の容量をいっぱいにすること間違いなしだった。
エイミー・ローレンスは誇らしく、喜んでいた。そしてその気持ちを顔に表してトムに見せようとしたが、彼は見ようとしなかった。彼女は不思議に思った。それからほんの少し不安になった。次に、ぼんやりとした疑念が浮かんで消え――また浮かんだ。彼女は見ていた。トムの盗み見るような一瞥が、彼女にすべてを物語った――そして彼女の心は張り裂け、嫉妬と怒りに燃え、涙がこみ上げ、誰もかもを憎んだ。とりわけトムを(彼女はそう思った)。
トムは判事に紹介された。しかし、舌はもつれ、息もろくにできず、心臓は震えていた――一つにはその男の恐るべき偉大さのためだったが、主には、彼が「彼女」の父親だったからである。もし暗闇の中であったなら、ひれ伏して彼を崇拝したかっただろう。判事はトムの頭に手を置き、立派な少年だと褒め、名前を尋ねた。少年はどもり、息をのみながら、やっとのことで答えた。
「トムです。」
「おや、トムじゃないだろう――それは――」
「トーマスです。」
「ああ、そうだ。もっと長い名前だと思ったよ。結構だ。だが、もう一つ名前があるだろう。教えてくれるかね?」
「トーマス、紳士にもう一つの名前を言いなさい」とウォルターズ氏が言った。「そして『サー』をつけなさい。礼儀を忘れてはいけませんよ。」
「トーマス・ソーヤー――です、サー。」

「そうだ! いい子だ。立派な子だ。立派で、男らしい少年だ。二千もの聖句とは大したものだ――実に、実に大したものだ。それを学ぶために費やした苦労を後悔することは決してないだろう。知識というものは、この世の何物にも代えがたい価値があるからな。偉大な人間、善良な人間を作るのは知識なのだ。トーマス、君もいつか偉大で善良な人間になり、そのとき振り返ってこう言うだろう。『すべては、少年時代の貴重な日曜学校のおかげだ――すべては、学ぶことを教えてくださった親愛なる先生方のおかげだ――すべては、私を励まし、見守り、美しい聖書――この素晴らしく、立派な聖書を、いつまでも私のものとして持てるように下さった、善良な校長先生のおかげだ――すべては、正しい躾のおかげなのだ!』とね。トーマス、君はそう言うだろう――そして、その二千の聖句をどんな大金とも交換しないだろう――ああ、決してしないだろう。さて、君が学んだことをいくつか、私とこのご婦人に話してはくれまいか――いや、嫌だとは言うまい。我々は学ぶ少年を誇りに思うのだからな。さて、十二人の弟子の名前は皆知っていることだろう。最初に任命された二人の名前を教えてくれないか?」
トムはボタン穴をいじりながら、きまり悪そうな顔をしていた。今や顔を赤らめ、目を伏せている。ウォルターズ氏の心臓は沈んだ。彼は心の中でつぶやいた。この少年が最も簡単な質問に答えられるはずがない――なぜ判事は彼に尋ねたのだ? それでも、声を張り上げて言わねばならないと感じた。
「紳士にお答えしなさい、トーマス――怖がることはない。」
トムはまだためらっていた。
「さあ、きっと教えてくれるわね」と婦人が言った。「最初の二人の弟子の名前は――」
「ダビデとゴリアテです!。」
この後の場面については、慈悲のカーテンを引くことにしよう。
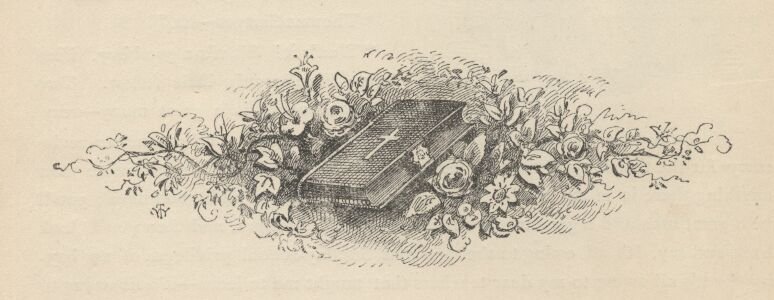
第五章
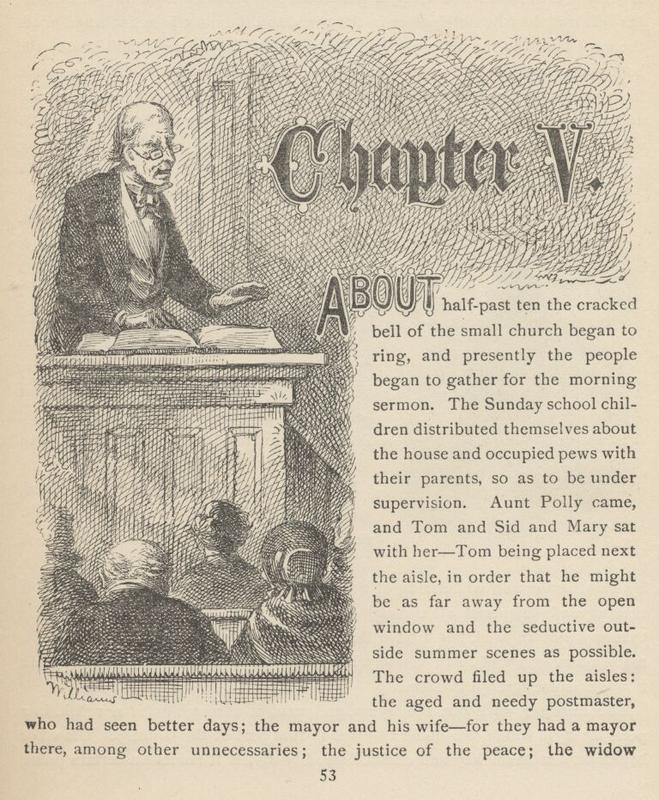
十時半ごろ、小さな教会のひびの入った鐘が鳴り始め、やがて人々が朝の説教のために集まりだした。日曜学校の子供たちは会堂のあちこちに散らばり、監督されるように親たちのいる長椅子に座った。ポリーおばさんもやって来て、トムとシッドとメアリーは彼女と一緒に座った――トムは、開いた窓や誘惑的な外の夏の景色からできるだけ遠ざけられるように、通路の隣に座らされた。群衆が通路を列をなして進んだ。昔はもっと良い暮らしをしていた、年老いて貧しい郵便局長。市長とその妻――というのも、この町には他の不要なものと共に市長もいたのだ。治安判事。ダグラス未亡人、色白で、賢く、四十歳、気前が良くて心優しく、裕福で、丘の上の邸宅は町で唯一の宮殿であり、セント・ピーターズバーグが誇る最ももてなしが良く、祝祭のこととなると最も気前が良い人物だった。腰の曲がった威厳のあるウォード少佐夫妻。遠方から来た新顔の名士、リバーソン弁護士。次に、村一番の美人、その後に続くのはローン地の服を着てリボンで飾った、若い男たちの心を打ち砕く娘たちの一団。それから町の若い事務員たちが一団となって――彼らは玄関ホールで、油をつけ、にやにや笑う崇拝者たちの壁となって、最後の娘がその間を通り抜けるまで、杖の頭をしゃぶりながら立っていたのだ。そして最後にやって来たのが、模範少年ウィリー・マファーソンで、母親がまるで切り子ガラスであるかのように、注意深く世話をしていた。彼はいつも母親を教会に連れてきており、すべての既婚婦人たちの誇りだった。少年たちは皆、彼を憎んでいた。あまりにも良い子だったからだ。それに、あまりにも頻繁に「引き合いに出され」ていた。彼の日曜日の常として、白いハンカチが後ろのポケットから――偶然に――はみ出していた。トムはハンカチを持っておらず、持っている少年を俗物だと見なしていた。

会衆がすっかり集まると、鐘がもう一度鳴り、遅れてくる者やぐずぐずしている者に警告を与えた。それから教会に厳かな静寂が訪れたが、それを破るのは二階席の聖歌隊のくすくす笑いとひそひそ話だけだった。聖歌隊は礼拝中ずっとくすくす笑い、ひそひそ話をしていた。かつて行儀の悪くない教会の聖歌隊があったが、今ではそれがどこだったか忘れてしまった。それはずっと昔のことで、ほとんど何も覚えていないが、どこか外国だったと思う。
牧師が賛美歌を告げ、それを味わうように、この地方で大いに賞賛されていた独特の様式で読み上げた。その声は中くらいの高さから始まり、着実に上がっていってある点に達すると、一番高いところの言葉に強いアクセントを置き、それから飛び込み台から飛び降りるかのように急降下した。
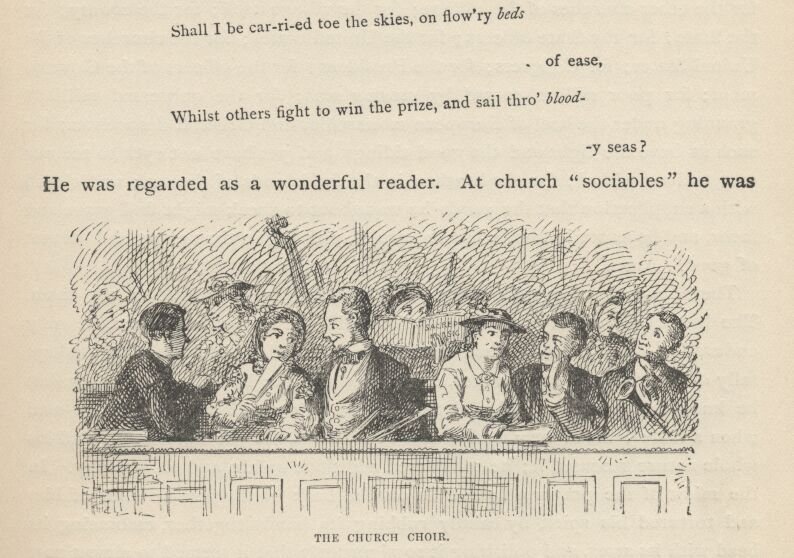
我は運ばるべきか、天なる国へ、安楽の花咲く寝台にて、
他者が賞を得んと戦い、血の海を渡る間に?
彼は素晴らしい朗読者と見なされていた。教会の「懇親会」ではいつも詩の朗読を頼まれ、彼が読み終えると、ご婦人方は両手を持ち上げては膝の上に力なく落とし、目を潤ませ、首を振り、あたかも「言葉では言い表せません。この死すべき地上にはあまりに美しすぎる、あまりに美しすぎるのです」と言わんばかりだった。
賛美歌が歌われた後、スプラーグ牧師は掲示板と化し、集会や団体の「お知らせ」などを読み上げた。そのリストは世の終わりまで続くのではないかと思われるほどだった――新聞が豊富にあるこの時代、ここアメリカでは、都市でさえもいまだに守られている奇妙な習慣である。伝統的な習慣というものは、それを正当化する理由が少なければ少ないほど、なくすのが難しくなるものだ。
そして今、牧師が祈った。それは善良で、心の広い祈りであり、細部にまで及んでいた。教会と、教会の小さな子供たちのために。村の他の教会のために。村そのもののために。郡のために。州のために。州の役人のために。合衆国のために。合衆国の教会のために。議会のために。大統領のために。政府の役人のために。荒れ狂う海に翻弄される哀れな船乗りたちのために。ヨーロッパの君主制や東洋の専制政治の圧政の下で呻く何百万もの被抑圧者のために。光と良き知らせを持ちながら、見る目も聞く耳も持たない者たちのために。海の彼方の島々に住む異教徒たちのために。そして最後に、これから語られる言葉が恵みと好意を得て、肥沃な土地に蒔かれた種のように、やがて善き実りの感謝すべき収穫をもたらしますように、という願いで締めくくられた。アーメン。
ドレスの擦れる音がして、立っていた会衆が腰を下ろした。この物語の主人公である少年は、祈りを楽しんではいなかった。ただ耐えていただけだ――いや、それすらしていたかどうか。彼は祈りの間中、そわそわしていた。無意識に祈りの細目を数えていた――聞いていたわけではないが、その内容は昔からよく知っており、牧師がたどるいつもの道筋もわかっていた――そして、ほんの些細な新しい事柄が差し挟まれると、彼の耳はそれを聞きつけ、彼の全性質がそれに反発した。追加は不公平で、卑劣なことだと考えたのだ。祈りの最中、一匹のハエが彼の前の長椅子の背に止まり、落ち着き払って両手をこすり合わせ、両腕で頭を抱え込み、体から離れてしまいそうなほど激しく磨き上げ、糸のように細い首をさらけ出し、後ろ足で羽をこすっては、まるで燕尾服の裾であるかのように体に撫でつけ、まるで自分が完全に安全だと知っているかのように、平然と身づくろいのすべてをこなして、彼の精神を苦しめた。実際、安全だった。トムの手はそれを掴みたくてうずうずしていたが、そんな勇気はなかった――祈りの最中にそんなことをすれば、自分の魂は即座に滅ぼされると信じていたのだ。しかし、最後の祈りの言葉と共に、彼の手は弧を描き、忍び寄り始めた。そして「アーメン」の声が発せられた瞬間、ハエは捕虜となった。おばさんがその行為を見つけ、彼にハエを放させた。
牧師は聖句を告げ、あまりに退屈な議論を単調に長々と続けたので、やがて多くの頭がこくりこくりと揺れ始めた――しかしそれは、無限の地獄の業火と硫黄を扱い、運命づけられた選民を、救う価値がほとんどないほど小さな集団にまで絞り込む議論だった。トムは説教のページ数を数えた。教会が終わると、彼はいつも何ページあったかを知っていたが、説教の内容についてはほとんど何も知らなかった。しかし、今回はしばらくの間、本当に興味を引かれた。牧師は、千年王国において、ライオンと子羊が共に伏し、小さな子供が彼らを導くという、世界の万軍が集う壮大で感動的な光景を描き出したのだ。しかし、その壮大な光景の哀感も、教訓も、道徳も、少年には届かなかった。彼が考えたのは、見守る国々の前での主役の目立ちようだけだった。その考えに顔を輝かせ、もしそれが手なずけられたライオンなら、自分もその子供になりたいものだ、と独りごちた。

さて、無味乾燥な議論が再開されると、彼は再び苦痛に陥った。やがて彼は持っていた宝物のことを思い出し、それを取り出した。それは恐ろしげな顎を持つ大きな黒い甲虫だった――彼はそれを「ピンチバグ」[訳注:挟み虫、クワガタムシの類]と呼んでいた。雷管を入れる箱に入っていた。甲虫が最初にやったのは、彼の指を挟むことだった。当然のように指ではじかれ、甲虫はもがきながら通路に飛び出し、仰向けに落ちた。そして、痛む指は少年の口の中へと運ばれた。甲虫はそこに横たわり、起き上がれずに無力な足をばたつかせていた。トムはそれを見つめ、欲しくてたまらなかったが、手の届かない安全な場所にいた。説教に興味のない他の人々も、この甲虫に気晴らしを見出し、同じようにそれを見つめていた。やがて、一匹の放浪プードルがぶらぶらとやって来た。心は悲しく、夏の気だるさと静けさで怠惰になり、束縛に疲れ、変化を求めてため息をついていた。彼は甲虫を見つけた。垂れていた尻尾が持ち上がり、振られた。彼は獲物を検分し、その周りを歩き、安全な距離から匂いを嗅ぎ、再び周りを歩き、大胆になって、もっと近くで匂いを嗅いだ。それから唇をめくり、用心深くそれに飛びかかったが、わずかに外れた。もう一度、さらにもう一度。この気晴らしを楽しみ始めた。甲虫を前足の間に挟んで腹ばいになり、実験を続けた。やがて飽きてしまい、無関心で上の空になった。彼の頭はこくりと揺れ、少しずつ顎が下がり、敵に触れた。敵はそれを捕らえた。鋭いキャンという鳴き声、プードルの頭が振られ、甲虫は二ヤードほど離れたところに落ち、再び仰向けになった。近くで見ていた者たちは、静かな内なる喜びで震え、いくつかの顔は扇やハンカチの後ろに隠れ、トムはすっかり幸せだった。犬は馬鹿げた顔つきで、おそらくそう感じていただろう。しかし、その心には憤りもあり、復讐への渇望もあった。そこで彼は甲虫のところへ行き、再び用心深い攻撃を始めた。円を描くようにあらゆる方向から飛びかかり、前足をその生き物の一インチ以内に着地させ、歯でさらに近くに飛びかかり、耳が再びばたつくまで頭を振った。しかし、しばらくすると再び飽きてしまった。ハエで気を紛らわそうとしたが、気晴らしにはならなかった。鼻を床にこすりつけるようにしてアリを追いかけたが、すぐに飽きてしまった。あくびをし、ため息をつき、甲虫のことなどすっかり忘れて、その上に座り込んだ。すると、苦痛に満ちた甲高い鳴き声が響き、プードルは通路を駆け上がっていった。鳴き声は続き、犬も走り続けた。彼は祭壇の前を横切り、もう一方の通路を駆け下り、ドアの前を横切り、最後の直線をわめきながら駆け上がった。進むにつれて苦悩は増し、やがて彼は光の輝きと速さで軌道を描く毛むくじゃらの彗星と化した。ついに、狂乱した受難者は進路を外れ、飼い主の膝に飛び込んだ。飼い主はそれを窓の外に放り投げ、苦しげな声は急速に細くなり、遠くで消えていった。
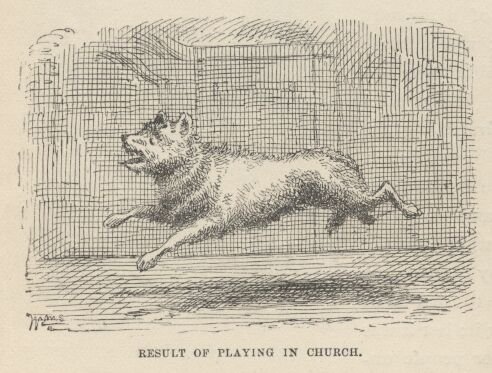
この頃には、教会全体がこらえきれない笑いで顔を真っ赤にし、息も詰まらんばかりで、説教は完全に中断していた。説教はやがて再開されたが、足を引きずるように、途切れ途切れに進んだ。感動を与える可能性はもはや皆無だった。というのも、最も厳粛な言葉でさえ、どこか遠くの長椅子の背に隠れて、まるで哀れな牧師が滅多にないほど面白いことを言ったかのように、抑えきれない不謹慎な笑いの爆発で絶えず受け止められていたからだ。試練が終わり、祝祷が告げられたとき、それは会衆全体にとって心からの安堵だった。
トム・ソーヤーはすっかり陽気になって家に帰った。神の礼拝も、少しばかり変化があれば満足できるものだと考えながら。ただ一つ、気分を害する考えがあった。犬が彼のピンチバグで遊ぶのは構わないが、それを持ち去るのは正しくないと思ったのだ。

第六章
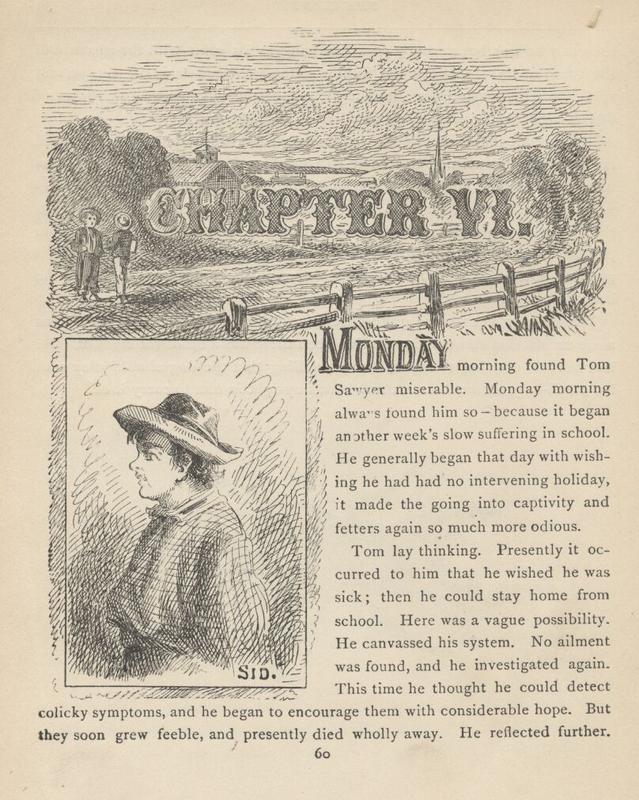
月曜の朝、トム・ソーヤーは惨めな気分だった。月曜の朝はいつもそうだった――学校での一週間の長々しい苦しみがまた始まるからだ。彼はたいていその日を、間に休みがなければよかったのに、と願うことから始めた。休みがあると、再び捕らわれの身となり、足かせをはめられるのが、いっそう忌まわしく感じられるのだ。
トムは横になって考えていた。やがて、病気になればいいのに、と思いついた。そうすれば学校を休んで家にいられる。これは漠然とした可能性だった。彼は自分の体をくまなく調べた。病気は見つからず、もう一度調査した。今度は疝痛の症状を感知できたように思い、かなりの希望を持ってそれを助長し始めた。しかし、症状はすぐに弱まり、やがて完全に消え去った。彼はさらに考えを巡らせた。突然、あるものを発見した。上の前歯が一本ぐらぐらしているのだ。これは幸運だった。彼は「手始めに」と呼んでいるうなり声を上げようとしたが、その時、もしその主張で法廷に臨めば、おばさんが歯を抜いてしまい、それは痛いだろう、という考えが浮かんだ。そこで、その歯は当面とっておき、さらに探すことにした。しばらく何も見つからなかったが、そのうち、医者が、患者を二、三週間寝込ませ、指を失う恐れさえあるという、ある病気について話していたのを思い出した。そこで少年は、痛む足の指をシーツの下から熱心に引き出し、点検のために持ち上げた。しかし、必要な症状が何なのかはわからなかった。それでも、試してみる価値は十分にあるように思われ、彼はかなり気合を入れてうなり始めた。
しかし、シッドは気づかずに眠り続けていた。
トムはさらに大きな声でうなり、足の指に痛みを感じ始めたような気がした。
シッドからの反応はない。
この頃には、トムは努力のせいで息を切らしていた。一休みしてから、体をいっぱいに膨らませ、見事なうなり声を連続して上げた。
シッドはいびきをかき続けていた。
トムは腹を立てた。「シッド、シッド!」と言って彼を揺さぶった。この方法はうまくいき、トムは再びうなり始めた。シッドはあくびをし、伸びをすると、鼻を鳴らして肘で体を起こし、トムをじっと見つめ始めた。トムはうなり続けた。シッドが言った。
「トム! おい、トム!」[返事なし]「おい、トム! トム! どうしたんだ、トム?」そして彼を揺さぶり、心配そうに顔を覗き込んだ。
トムはうめいた。
「ああ、やめろよ、シッド。揺するなよ。」
「どうしたんだ、トム? おばさんを呼ばなきゃ。」
「いや――いいんだ。そのうち治るさ、たぶん。誰も呼ばないでくれ。」
「でも、呼ばなきゃ! そんなにうなるなよ、トム、ひどいじゃないか。いつからそんななんだ?」
「何時間もだ。痛っ! ああ、そんなに動くなよ、シッド、死んじまう。」
「トム、どうしてもっと早く起こしてくれなかったんだ? ああ、トム、やめてくれ! お前の声を聞いてると鳥肌が立つよ。トム、どうしたんだ?」
「お前のことは全部許すよ、シッド。(うめき声)お前が俺にしたこと、全部だ。俺が死んだら――」
「ああ、トム、死ぬんじゃないだろうな? やめてくれ、トム――ああ、やめて。もしかして――」
「みんなを許すよ、シッド。(うめき声)みんなにそう伝えてくれ、シッド。それからシッド、俺の窓枠と片目の猫は、町に来た新しい女の子にあげてくれ、そして彼女に伝えて――」
しかし、シッドは服をひっつかんで行ってしまった。トムは今や、本当に苦しんでいた。彼の想像力があまりに見事に働いたので、うめき声にはすっかり本物らしい響きが加わっていたのだ。
シッドは階下へ飛んで行き、言った。
「ああ、ポリーおばさん、来て! トムが死にそうだよ!」
「死にそうだって!」
「はい。待たないで――早く来て!」
「馬鹿なこと! 信じないよ!」
しかし、彼女はそれでもシッドとメアリーを従えて階上へ駆け上がった。彼女の顔も青ざめ、唇は震えていた。ベッドの脇に着くと、彼女は息を切らしながら言った。
「トム! トム、お前、どうしたんだい?」
「ああ、おばさん、僕――」
「どうしたんだい――どうしたんだい、お前?」
「ああ、おばさん、痛い足の指が壊疽を起こしたんだ!」
老婦人は椅子に崩れ落ち、少し笑い、それから少し泣き、そして両方を同時にやった。これで落ち着きを取り戻し、彼女は言った。
「トム、なんて肝を冷やさせやがるんだ。さあ、そんな馬鹿なことはやめて、ベッドから出なさい。」
うめき声は止み、足の指の痛みは消えた。少年は少しばかばかしくなり、言った。
「ポリーおばさん、壊疽を起こしたみたいだったんだ。すごく痛くて、歯のことなんか全然気にならなかったよ。」
「歯だって! 歯がどうしたんだい?」
「一本ぐらぐらで、ものすごく痛むんだ。」
「はいはい、もうそのうめき声を始めるんじゃないよ。口を開けなさい。ふむ――歯は確かにぐらぐらしているね。でも、それで死ぬことはないよ。メアリー、絹糸と、台所から火のついた薪を持ってきておくれ。」
トムは言った。
「ああ、お願いだよ、おばさん、抜かないで。もう痛くないんだ。もし痛かったら、一歩も動かないって誓うよ。お願いだから、おばさん。学校を休みたくないんだ。」

「ああ、休みたくないのかい? じゃあ、この大騒ぎは全部、学校を休んで魚釣りに行けると思ったからなのかい? トム、トム、お前のことはとても愛しているのに、お前ときたら、あらゆる手を使って、そのとんでもない行いでこの老いた私の心を打ち砕こうとするようだね」この頃には、歯科用具の準備が整っていた。老婦人は絹糸の一端を輪にしてトムの歯に固く結びつけ、もう一端をベッドの柱に結んだ。それから火のついた薪を掴み、突然それを少年の顔のすぐそばに突き出した。今や、歯はベッドの柱からぶら下がっていた。
しかし、あらゆる試練には報いがあるものだ。朝食後、トムが学校に向かうと、出会う少年たちの羨望の的となった。上の歯並びにできた隙間のおかげで、新しく、見事なやり方で唾を吐けるようになったからだ。その見世物に興味を持った少年たちが、かなりの数、彼の後についてきた。そして、それまで指を切って魅力と尊敬の中心だった一人の少年は、今や突然、支持者を失い、栄光を剥ぎ取られていることに気づいた。彼の心は重く、トム・ソーヤーみたいに唾を吐くなんて大したことじゃない、と心にもない軽蔑を込めて言った。しかし、別の少年が「負け惜しみだ!」と言い、彼は栄光を失った英雄として去っていった。
まもなくトムは、村の少年たちののけ者、町の酔っぱらいの息子であるハックルベリー・フィンに出会った。ハックルベリーは町の母親たち全員から心底憎まれ、恐れられていた。彼が怠け者で、無法で、下品で、悪かったからだ――そして、母親たちの子供たちが皆、彼を大いに称賛し、禁じられた彼の交友を喜び、自分たちも彼みたいになれたらと願っていたからだ。トムも他のまともな少年たちと同じように、ハックルベリーの派手なのけ者ぶりに嫉妬し、彼と遊ぶことを固く禁じられていた。だから、機会があるたびに彼と遊んだ。ハックルベリーはいつも大人の男のお古を着ており、それは一年中ぼろぼろに咲き誇り、はためいていた。彼の帽子は広大な廃墟のようで、つばの広い三日月形の部分が切り取られていた。上着を着ているときは、かかとに届きそうなほど長く、後ろのボタンはずっと下の方についていた。ズボンは一本のサスペンダーで吊られていた。ズボンの尻はだぶだぶに垂れ下がり、中には何も入っておらず、裾のほつれた脚は、まくり上げていないときは地面の泥を引きずっていた。

ハックルベリーは自由気ままに行き来した。天気の良い日は戸口の階段で、雨の日は空の大樽で眠った。学校にも教会にも行く必要はなく、誰かを主人と呼んだり、誰かに従ったりする必要もなかった。好きな時に好きな場所で魚釣りや水泳ができ、好きなだけそこにいられた。喧嘩を禁じる者もいなかった。好きなだけ夜更かしできた。春に最初に裸足になるのも、秋に最後に革靴を履くのも、いつも彼だった。体を洗う必要も、きれいな服を着る必要もなかった。悪態のつき方も見事だった。一言で言えば、人生を貴重なものにするすべてのものを、その少年は持っていた。セント・ピーターズバーグの、悩まされ、束縛された、まともな少年は皆そう思っていた。
トムはロマンチックなのけ者に声をかけた。
「よう、ハックルベリー!」
「よう、トム。お前も元気かよ。」
「それ、何持ってるんだ?」
「死んだ猫さ。」
「見せてくれよ、ハック。おや、ずいぶん硬いな。どこで手に入れたんだ?」
「ある子から買ったんだ。」
「何をやったんだ?」
「青い券一枚と、屠殺場でもらった膀胱をやった。」
「青い券はどこで手に入れたんだ?」
「二週間前にベン・ロジャースから輪回しの棒と交換で買ったんだ。」
「なあ――死んだ猫って何にいいんだ、ハック?」
「何にいいかって? いぼを治すのさ。」
「まさか! 本当かい? もっといい方法を知ってるぜ。」
「知らないに決まってる。何だよ?」
「そりゃ、切り株の水さ。」
「切り株の水だと! そんなもん、びた一文の価値もねえよ。」
「価値がないって? 試したことあるのか?」
「いや、ねえよ。でもボブ・タナーがやった。」
「誰がそんなこと言ったんだ!」
「そりゃ、あいつがジェフ・サッチャーに言って、ジェフがジョニー・ベイカーに言って、ジョニーがジム・ホリスに言って、ジムがベン・ロジャースに言って、ベンが黒んぼに言って、その黒んぼが俺に言ったんだ。どうだ!」
「ふん、だから何だってんだ? みんな嘘つきだ。少なくとも黒んぼ以外はな。そいつは知らねえけど。でも嘘をつかねえ黒んぼなんて見たことねえよ。ちぇっ! さあ、ボブ・タナーがどうやったか教えてくれよ、ハック。」
「そりゃ、腐った切り株に雨水が溜まってるとこに手を入れたんだ。」
「昼間に?」
「もちろんさ。」
「切り株に顔を向けて?」
「ああ。少なくともそう思うぜ。」
「何か言ったか?」
「言わなかったと思う。知らねえよ。」
「ははあ! そんな馬鹿なやり方で切り株の水でいぼを治そうなんて話があるか! そんなんじゃ何の役にも立ちゃしない。一人きりで、切り株に水が溜まってる場所を知ってる森の真ん中に行って、真夜中きっかりに切り株に背を向けて手をつっこんで、こう言うんだ。『大麦、大麦、トウモロコシの粉、切り株の水、切り株の水、このいぼを飲み込め』って。それから目を閉じたまま、さっと十一歩歩いて、三回回って、誰とも口をきかずに家に帰るんだ。口をきいたら、おまじないが解けちまうからな。」
「ふうん、そりゃいいやり方みたいだな。でもボブ・タナーがやったのとは違う。」
「ああ、やってないに決まってるさ。だってあいつはこの町で一番いぼだらけの男の子だからな。もし切り株の水の効かせ方を知ってたら、いぼの一つもなかったはずだ。俺はその方法で手から何千ものいぼを取ったんだぜ、ハック。カエルと遊びすぎるから、いつもいぼがたくさんできるんだ。時々、豆で取ることもある。」
「ああ、豆はいいな。やったことあるぜ。」
「あるのか? お前はどうやるんだ?」
「豆を割って、いぼを切って血を少し出すんだ。それから豆の片方に血をつけて、穴を掘って、新月の真夜中ごろに十字路に埋めるんだ。で、残りの豆は燃やしちまう。ほら、血のついた豆の片割れが、もう片方を引き寄せようと、ずっと引っ張り続けるだろ。それで血がいぼを引っ張り出すのを助けて、すぐにぽろっと取れるんだ。」
「ああ、それだ、ハック――それだよ。でも埋めるときに『豆よ、下に。いぼよ、取れろ。もう俺を悩ますな!』って言うともっといいぜ。ジョー・ハーパーはそうやってるんだ。あいつはクーンビル近くまで行ったことあるし、ほとんどどこにでも行ってるからな。でもさ――死んだ猫ではどうやって治すんだ?」
「そりゃ、猫を持って、悪い奴が埋められた墓場に真夜中ごろに行くんだ。真夜中になると悪魔が一体、もしかしたら二、三体来る。でも見えねえんだ。風みたいな音がするか、話してるのが聞こえるかもしれねえ。で、奴らがそいつを連れ去るときに、猫を奴らの後から放り投げて言うんだ。『悪魔よ、死体に従え。猫よ、悪魔に従え。いぼよ、猫に従え。俺はお前らとはおさらばだ!』ってな。これならどんなイボでも取れる。」
「なるほどな。試したことあるのか、ハック?」
「いや、でもホプキンズのおばあさんが教えてくれたんだ。」
「ふうん、じゃあ本当なんだろうな。あの人は魔女だって言うからな。」
「おい! そりゃ、トム、俺は彼女が魔女だって知ってるぜ。父ちゃんに魔法をかけたんだ。父ちゃんが自分でそう言ってた。ある日、通りかかったら、彼女が自分に魔法をかけてるのが見えたんだって。だから石を拾って、もし彼女がよけなかったら、ぶつけてやったのに。で、まさしくその晩、父ちゃんは酔っぱらって寝てた小屋から転げ落ちて、腕を折ったんだ。」
「そりゃひどいな。どうして彼女が魔法をかけてるってわかったんだ?」
「なんだ、父ちゃんには簡単さ。父ちゃんが言うには、じっとこっちを見続けてるときは、魔法をかけてるんだって。特にぶつぶつ言ってたらな。ぶつぶつ言うときは、主の祈りを逆さまに唱えてるんだとさ。」

「なあ、ハッキー、いつ猫を試すんだ?」
「今夜さ。今夜、ホス・ウィリアムズのじいさんを迎えに来ると思う。」
「でも、土曜に埋葬されたじゃないか。土曜の夜に連れて行かなかったのか?」
「何を言うんだ! 真夜中まで呪文が効くわけないだろ? ――それに、そしたらもう日曜日だ。悪魔は日曜にはあまりうろつかないと思うぜ。」
「そんなこと考えもしなかった。そうだな。一緒に行ってもいいか?」
「もちろんさ――もし怖くないならな。」
「怖いだと! まさか。ニャーって鳴くか?」
「ああ――お前も機会があったらニャーって返せよ。この間は、お前のせいで俺がニャーニャー鳴き続けてたら、ヘイズのじいさんが石を投げてきて『あの忌々しい猫め!』って言うから、あいつの窓にレンガを投げ込んでやったんだ――でも、言うなよ。」
「言わないよ。あの晩はニャーって鳴けなかったんだ、おばさんが見張ってたから。でも今度は鳴くよ。なあ――それ、何だ?」
「ダニさ。」
「どこで捕まえたんだ?」
「森の中さ。」
「何と交換してくれる?」
「さあな。売りたくないんだ。」
「わかったよ。どのみち、すごく小さいダニだな。」
「ああ、自分のものでもないダニをけなすのは誰にでもできるさ。俺はこいつで満足してる。俺にはこれで十分いいダニだ。」
「ちぇっ、ダニならいくらでもいるさ。欲しけりゃ千匹だって手に入るぜ。」
「じゃあ、なんで手に入れないんだ? できっこないってよくわかってるからだろ。こいつはかなり早い時期のダニだと思うぜ。今年見た最初の一匹だ。」
「なあ、ハック――俺の歯と交換してやるよ。」
「見せてみろ。」
トムは紙切れを取り出し、注意深く広げた。ハックルベリーは物欲しそうにそれを見つめた。誘惑は非常に強かった。やがて彼は言った。
「本物か?」
トムは唇をめくり、歯の抜けた隙間を見せた。
「よし、わかった」とハックルベリーは言った。「取引成立だ。」
トムは、ついさっきまでピンチバグの牢獄だった雷管の箱にダニを閉じ込め、少年たちは別れた。それぞれが以前より金持ちになった気分だった。
トムが人里離れた小さな木造の校舎に着くと、彼は誠実な速さでやって来た者の態度で、さっそうと中に入った。帽子を釘にかけ、仕事に取りかかるような機敏さで自分の席に身を投げ出した。先生は、籐の底の大きな肘掛け椅子に王様のように鎮座し、勉強の気だるいざわめきにまどろんでいた。邪魔が入って目を覚ました。
「トーマス・ソーヤー!」
トムは、フルネームで呼ばれるときは面倒なことになると知っていた。
「はい!」
「ここへ来なさい。さて、君、なぜまたいつものように遅刻したのかね?」
トムは嘘に逃げ込もうとしたが、そのとき、恋の電撃的な共感によって見覚えのある背中から、二本の長い黄色いおさげ髪が垂れているのを見た。そしてその姿の隣は、校舎の女子席側で唯一の空席だった。彼は即座に言った。
「ハックルベリー・フィンと話をしていました!。」
先生の脈は止まり、彼はなすすべもなく見つめた。勉強のざわめきが止んだ。生徒たちは、この無鉄砲な少年は気が狂ったのではないかと思った。先生は言った。
「君は――君は何をしたと言ったかね?」
「ハックルベリー・フィンと話をしていました。」
その言葉に聞き間違いはなかった。
「トーマス・ソーヤー、これは私が今まで聞いた中で最も驚くべき告白だ。この罪には、単なる鞭では済まされない。上着を脱ぎなさい。」

先生の腕は疲れ果て、鞭の束が目に見えて減るまで働き続けた。それから命令が下った。
「さあ、君、行って女の子たちと座りなさい! そしてこれを警告としなさい。」
教室にさざ波のように広がったくすくす笑いは、少年をたじろがせたように見えた。だが実のところ、それはまだ見ぬ憧れの君への崇拝にも似た畏怖の念と、この上ない幸運に潜む恐ろしいほどの喜びが生んだ結果であった。トムが松材のベンチの端に腰を下ろすと、少女はつんと頭をそむけ、彼からすっと身を引いた。肘でつつき合ったり、目配せしたり、ひそひそ話したりする声が教室を行き交ったが、トムは目の前の長く低い机に腕を乗せ、じっと座ったまま、本を読んでいるふりをしていた。
やがて、彼への注目は途絶え、いつもの学校のざわめきが、よどんだ空気の中によみがえった。ほどなくして、少年は少女に盗み見を始めた。彼女はそれに気づくと、彼に向かって「あっかんべー」をし、一分ほどの間、後頭部を向けていた。彼女が用心深く再びこちらを向くと、目の前に桃が一つ置かれていた。彼女はそれを突き放した。トムはそっと元に戻した。彼女は再びそれを突き放したが、先ほどよりは敵意が薄れていた。トムは辛抱強く元の場所へ戻した。すると彼女は、そのままにしておいた。トムは石板にこう走り書きした。「どうぞ、もらってください。もっと持ってるから」。少女はその言葉に目をやったが、何の合図も送らなかった。今度は少年が、左手で隠しながら石板に何かを描き始めた。しばらくの間、少女は気づかないふりをしていたが、人間らしい好奇心が、やがてほとんど気づかれぬほどの兆候となって現れ始めた。少年はそれに気づかぬふりで、描き続けた。少女は、どちらともつかぬ態度で覗き込もうとしたが、少年はそれに気づいている素振りを見せなかった。とうとう彼女は根負けし、ためらいがちにささやいた。
「見せて。」
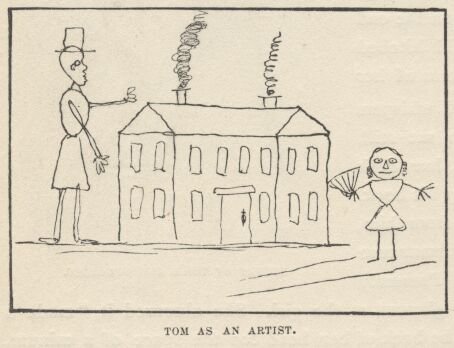
トムは、切妻屋根が二つあるみすぼらしい家の戯画を少しだけ見せた。煙突からは、コルク抜きのようにねじれた煙が立ち上っている。すると少女の興味はその絵に釘付けになり、他のことはすべて忘れてしまった。絵が完成すると、彼女はしばらくそれを眺め、そしてささやいた。
「素敵ね――男の人を描いて。」
絵描きは前庭に、デリック[訳注: 荷役用のクレーン]のような男を建てた。その男は家をまたげるほどの大きさだったが、少女はあら探しをするような子ではなかった。その怪物に満足し、ささやいた。
「きれいな男の人だわ――今度は私が通りかかるのを描いて。」
トムは、砂時計に満月の顔と藁の手足をつけ、広げた指には大げさな扇子を持たせた。少女は言った。
「すっごく素敵――私も絵が描けたらいいのに。」
「簡単だよ」トムはささやいた。「僕が教えてあげる。」
「まあ、ほんと? いつ?」
「お昼にさ。お昼ご飯は家に帰るの?」
「あなたがいるなら、ここに残るわ。」
「よし――決まりだ。君の名前は?」
「ベッキー・サッチャーよ。あなたの名前は? ああ、知ってるわ。トーマス・ソーヤーでしょ。」
「それは、お仕置きされるときの名前さ。いい子のときはトムだよ。トムって呼んでくれる?」
「ええ。」
さて、トムは石板に何かを走り書きし始め、少女からその言葉を隠した。しかし、今度の彼女は引っ込み思案ではなかった。見せてとせがんだ。トムは言った。
「ああ、何でもないよ。」
「ううん、何かあるわ。」
「何でもないって。君は見たくないよ。」
「見たいわ、ほんとに見たいの。お願い、見せて。」
「誰かに言うだろ。」
「言わないわ――絶対に、絶対に、ぜーったいに言わない。」
「誰にも言わない? 生きている限り、絶対に?」
「ええ、誰にも絶対に言わないわ。さあ、見せて。」
「ああ、君は見たくないって!」
「そんな意地悪するなら、絶対見てやるんだから」。そして彼女は小さな手を彼の手の上に置き、ちょっとしたもみ合いになった。トムは本気で抵抗するふりをしながらも、少しずつ手を滑らせ、ついにその言葉が現れた。「きみをあいしてる」。
「まあ、意地悪!」と、彼女は彼の手をぴしゃりと叩いたが、顔を赤らめ、それでも嬉しそうだった。
まさにその時、少年はゆっくりと、しかし運命的な力が自分の耳たぶを掴み、ぐいと引き上げるのを感じた。かくして彼は教室を横切って運ばれ、自分の席に座らされた。その間、学校中の生徒から浴びせられるようなクスクス笑いが降り注いだ。それから先生は、恐ろしい数分間、彼の上に仁王立ちになり、やがて一言も発さずに教壇へと戻っていった。しかし、トムの耳はジンジンと痛んだが、心は歓喜に満ちていた。

学校が静まり返ると、トムは真面目に勉強しようと努力したが、心の中の騒ぎはあまりに大きかった。順番が来て朗読のクラスに出たが、めちゃくちゃに読み間違えた。次に地理のクラスでは、湖を山にし、山を川にし、川を大陸に変えてしまい、再び混沌が支配するまで続いた。そして綴りのクラスでは、赤ん坊でも知っているような単語を立て続けに間違えて「落第」し、ついにクラスの最下位にまで落ち、何ヶ月もこれ見よがしにつけていたピューター製のメダルを明け渡す羽目になった。
第七章
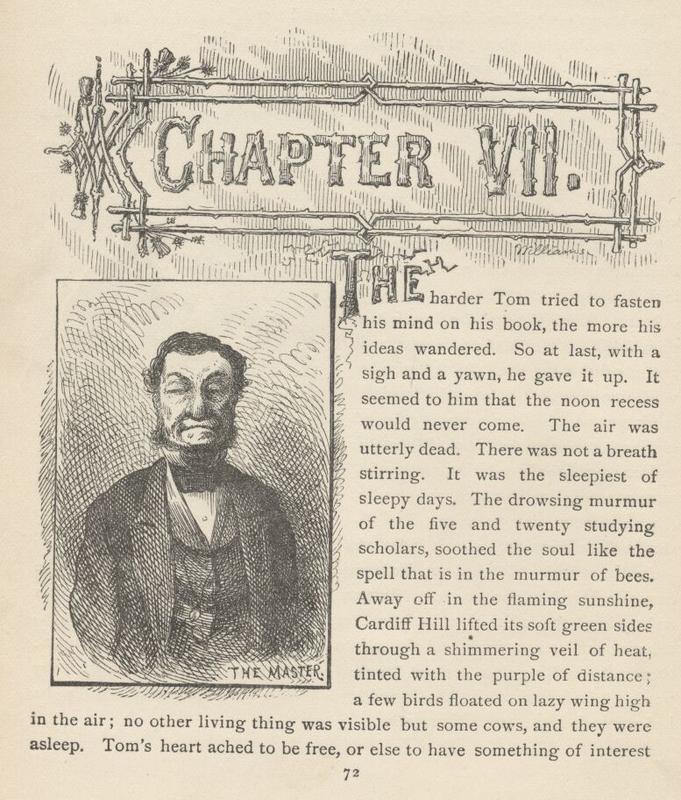
トムは本に集中しようとすればするほど、考えはあちこちにさまよった。ついに彼はため息とあくびとともに、それを諦めた。昼休みは永遠に来ないように思えた。空気は完全に死んでいた。そよ風一つ吹いていなかった。眠気を誘う日々の中でも、最も眠たい一日だった。二十五人の生徒たちが勉強する気だるいざわめきは、まるで蜂の羽音に潜む魔法のように魂をなだめた。燃えるような日差しの向こうでは、カーディフの丘が、陽炎のきらめくヴェールの向こうに柔らかな緑の斜面をのぞかせ、遠景の紫色に染まっていた。数羽の鳥が、だるそうに翼を広げ、空高く漂っていた。他に生き物の姿は見当たらず、いるのは数頭の牛だけで、それらも眠っていた。トムの心は、自由になりたい、さもなければこの退屈な時間をやり過ごす何か面白いことがしたいと、うずいていた。彼の手がポケットを探ると、その顔は祈りにも似た感謝の輝きで明るくなったが、本人はそれに気づいていなかった。そしてこっそりと、雷管の箱が出てきた。彼はダニを解き放ち、長く平らな机の上に置いた。この生き物もまた、この瞬間、祈りに等しい感謝の念に輝いていたに違いないが、それは早計だった。というのも、彼が感謝しつつ旅立とうとしたとき、トムがピンでその進路を逸らし、新たな方向へ向かわせたからである。
トムの親友は隣に座り、トムがそうであったように苦しんでいたが、今やこの娯楽に深く、そして感謝の念をもって夢中になった。この親友はジョー・ハーパーだった。二人の少年は、週の間はずっと固い友情で結ばれた友であり、土曜日には不倶戴天の敵となる。ジョーは襟からピンを抜き、囚人を訓練する手伝いを始めた。その遊びは刻一刻と面白さを増していった。やがてトムは、これではお互いの邪魔になり、どちらもダニから最大限の利益を得られないと言った。そこで彼はジョーの石板を机の上に置き、上から下まで真ん中に一本の線を引いた。
「いいかい」と彼は言った。「ダニが君の側にいる間は、君がかまってもいい。僕は放っておく。でも、もし君がそいつを逃して僕の側に来させたら、僕がそいつを向こう側に行かせない限り、君は手出ししちゃだめだ。」
「わかった、やれよ。さあ、始めろ。」
ダニはまもなくトムの手から逃れ、赤道を越えた。ジョーがしばらくそれをもてあそんでいると、ダニはまた逃げ出して、再び境界線を越えた。この陣地交代は頻繁に起こった。一人の少年が夢中になってダニをいじめている間、もう一人は同じくらい強い興味をもって見つめ、二つの頭は石板の上で寄り添い、二つの魂は他のすべてのものに対して死んでいた。ついに幸運はジョーに味方し、そこに留まるかのように見えた。ダニはあれこれと進路を試み、少年たち自身と同じくらい興奮し、やきもきしたが、あと一歩で勝利をその手に掴もうというところで、トムの指がうずき出すまさにその時、ジョーのピンが巧みにその進路を阻み、陣地を維持した。とうとうトムは我慢できなくなった。誘惑が強すぎたのだ。彼は手を伸ばし、自分のピンで加勢した。ジョーはたちまち怒った。彼は言った。
「トム、そいつに構うなよ。」
「ちょっとつつきたいだけだよ、ジョー。」
「だめだ、フェアじゃない。そいつには構うな。」
「ちぇっ、そんなにひどくはいじらないって。」
「構うなって言ってるだろ。」
「いやだね!」
「構うな! 俺の陣地にいるんだ。」
「おい、ジョー・ハーパー、そのダニは誰んだ?」
「誰のダニだろうと知ったこっちゃない――俺の陣地にいるんだから、お前は触るな。」
「ふん、俺は絶対触ってやるさ。俺のダニなんだから、好きにさせてもらう。死んでもな!」
トムの肩にすさまじい一撃が振り下ろされ、同じものがジョーの肩にも食らわされた。そして二分間、二人の上着から埃が舞い続け、学校中がそれを楽しんだ。少年たちは夢中になりすぎて、少し前に先生が抜き足差し足で教室を下りてきて、彼らの真上に立っていたことに気づかなかったのだ。先生は、その見世物の一部始終をじっくりと眺めてから、自らも変化に富んだ一幕を付け加えたのである。
昼休みになり学校が終わると、トムはベッキー・サッチャーのもとへ飛んでいき、耳元でささやいた。
「帽子をかぶって、家に帰るふりをするんだ。そして角まで来たら、他の子たちをまいて、路地を曲がって戻ってきて。僕は別の道を行って、同じようにあいつらをまくから。」
かくして、一人はある生徒のグループと、もう一人は別のグループと連れ立って去っていった。しばらくして二人は路地の突き当たりで落ち合い、学校に着いたときには、そこは二人だけのものだった。そして彼らは並んで座り、目の前に石板を置いて、トムはベッキーに鉛筆を渡し、彼女の手を自分の手で握って導き、そうしてもう一つ、驚くべき家を創造した。芸術への興味が薄れ始めると、二人はおしゃべりを始めた。トムは至福の境地に浸っていた。彼は言った。
「ネズミは好き?」
「いいえ! 大嫌いよ!」
「うん、僕もだよ――生きてるのはね。でも僕が言ってるのは死んだやつで、紐をつけて頭の周りでぶんぶん振り回すんだ。」
「いいえ、どっちにしろネズミはあまり好きじゃないわ。私が好きなのはチューインガムよ。」
「ああ、そりゃそうだ! 今持ってればなあ。」
「そうなの? 私、持ってるわよ。しばらく噛ませてあげるけど、返してくれなくちゃだめよ。」
それは結構なことだったので、二人は交代でガムを噛み、満足のあまりベンチに腰掛けて足をぶらぶらさせた。
「サーカスに行ったことある?」とトムは言った。
「ええ、それに、いい子にしてたら、お父さんがまたいつか連れて行ってくれるって。」
「僕はサーカスに三、四回は行ったよ――何回もね。教会なんてサーカスに比べたら屁でもない。サーカスじゃ、いつも何か面白いことが起きてるんだ。大きくなったらサーカスのピエロになるんだ。」
「まあ、そうなの! 素敵でしょうね。水玉模様で、とっても可愛いもの。」
「うん、そうだろ。それに、たんまり金がもらえるんだ――一日一ドル近くもね、ベン・ロジャースが言ってた。ねえ、ベッキー、婚約したことある?」
「それ、なあに?」
「え、結婚の約束だよ。」
「いいえ。」
「してみたい?」
「そうねえ。わからないわ。どんな感じなの?」
「どんな感じかって? 別にどうってことないよ。ただ男の子に、彼以外の人は絶対に好きにならない、ずーっと、ずーっと、ずーっとって言うだけさ。それからキスして、それでおしまい。誰にでもできるよ。」
「キス? どうしてキスするの?」
「えっと、それはね、その……まあ、みんなそうするものだからさ。」
「みんな?」
「うん、そうだよ、お互いに愛し合ってる人はみんなね。僕が石板に書いたこと、覚えてる?」
「え……ええ。」
「何て書いてあった?」
「あなたには教えないわ。」
「僕が君に教えようか?」
「え……ええ――でも、また今度ね。」
「だめだ、今。」
「だめよ、今じゃなくて――明日。」
「ああ、だめだ、今さ。お願い、ベッキー――ささやくから、すごく小さな声でささやくから。」
ベッキーがためらっていると、トムは沈黙を承諾とみなし、彼女の腰に腕を回し、口を耳に近づけて、とても優しくその物語をささやいた。そしてこう付け加えた。
「今度は君が僕にささやいて――全く同じように。」
彼女はしばらく抵抗したが、やがて言った。
「あなた、顔をそむけて。見えないように。そうしたら言うわ。でも、絶対に誰にも言っちゃだめよ――いい、トム? 言わないわよね、ねえ?」
「うん、絶対に、絶対に言わない。さあ、ベッキー。」
彼は顔をそむけた。彼女はおずおずと身をかがめ、その息が彼の巻き毛を揺らすほどに近づき、ささやいた。「わ――た――し――あ――な――た――を――あ――い――し――て――る!」
そして彼女は飛びのき、机とベンチの周りをぐるぐると走り回り、トムがそれを追いかけた。とうとう彼女は隅に逃げ込み、小さな白いエプロンで顔を覆った。トムは彼女の首に抱きつき、懇願した。
「さあ、ベッキー、もう全部終わったよ――あとはキスだけだ。怖がらないで――何でもないことだから。お願い、ベッキー」。そして彼は彼女のエプロンと手を引っ張った。
やがて彼女は諦め、手を下ろした。もみ合いで紅潮した顔が上がり、身を委ねた。トムは赤い唇にキスをし、言った。
「これで全部終わりだ、ベッキー。そしてこれからはずっと、いいね、僕以外の誰も愛しちゃだめだし、僕以外の誰とも結婚しちゃだめだ、絶対に、永遠に。いいかい?」
「ええ、あなた以外の誰も愛さないわ、トム。あなた以外の誰とも結婚しないわ――そしてあなたも、私以外の誰とも結婚しちゃだめよ。」
「もちろんさ。当たり前だ。それも約束の一部だからね。それに、学校に来るときも家に帰るときも、誰も見てないときは僕と一緒に歩くんだ――そしてパーティーでは君が僕を選び、僕が君を選ぶ。婚約してるっていうのは、そういうふうにするものなんだ。」
「とっても素敵ね。そんなこと、今まで聞いたことなかったわ。」
「ああ、すっごく楽しいんだ! ほら、僕とエイミー・ローレンスは――」
大きな瞳がトムの失言を物語り、彼は口をつぐんで狼狽した。
「ああ、トム! じゃあ、私があなたが初めて婚約した相手じゃないのね!」
子供は泣き始めた。トムは言った。
「ああ、泣かないで、ベッキー。僕はもう彼女のことなんてどうでもいいんだ。」
「ううん、そんなことないわ、トム――どうでもよくないくせに。」

トムは彼女の首に腕を回そうとしたが、彼女は彼を突き放し、壁に顔を向けて泣き続けた。トムはなだめる言葉を口にしながら再び試みたが、またしても拒絶された。すると彼のプライドが頭をもたげ、彼は大股で歩き去り、外へ出てしまった。彼はしばらく落ち着かずにうろうろし、時折ドアに目をやりながら、彼女が後悔して自分を探しに来ることを期待していた。しかし、彼女は来なかった。すると彼は気分が悪くなり始め、自分が間違っていたのではないかと恐ろしくなった。今さら新たに歩み寄るのは、彼にとって辛い葛藤だったが、意を決して中に入った。彼女はまだ隅に立ち、壁に顔を向け、すすり泣いていた。トムの心は痛んだ。彼は彼女のもとへ行き、一瞬立ち尽くした。どう切り出していいか、よくわからなかったのだ。そして、ためらいがちに言った。
「ベッキー、僕――僕、君以外はどうでもいいんだ。」
返事はない――ただ、すすり泣きが聞こえるだけ。
「ベッキー」――懇願するように。「ベッキー、何か言ってくれないかい?」
さらにすすり泣きが続く。
トムは一番の宝物、暖炉の自在鉤の先についていた真鍮のつまみを取り出し、彼女が見えるようにその周りで動かしながら言った。
「お願い、ベッキー、これ、受け取ってくれないかい?」
彼女はそれを床に叩きつけた。するとトムは家を飛び出し、丘を越え、はるか彼方へと去っていき、その日、二度と学校に戻ることはなかった。やがてベッキーは不審に思い始めた。彼女はドアへ駆け寄った。彼の姿は見えない。校庭へ飛んでいった。そこにもいなかった。そして彼女は叫んだ。
「トム! 戻ってきて、トム!」
彼女は耳を澄ましたが、返事はなかった。彼女の仲間は、静寂と孤独だけだった。そこで彼女は再び座り込んで泣き、自分を責めた。そうこうするうちに、生徒たちが再び集まり始め、彼女は悲しみを隠し、傷ついた心を鎮め、長く、陰鬱で、胸の痛む午後の十字架を背負わなければならなかった。周りの見知らぬ人々の中に、悲しみを分かち合える者は誰一人いなかった。
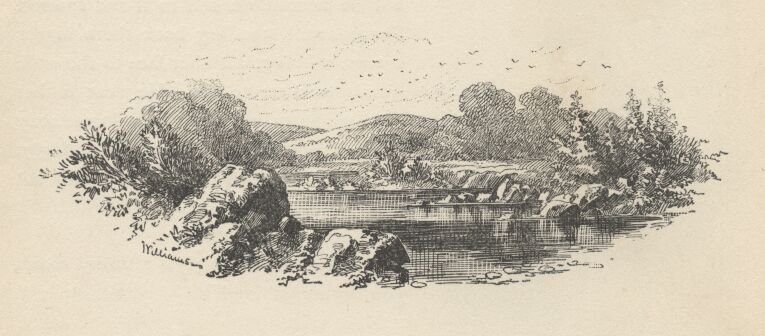
第八章
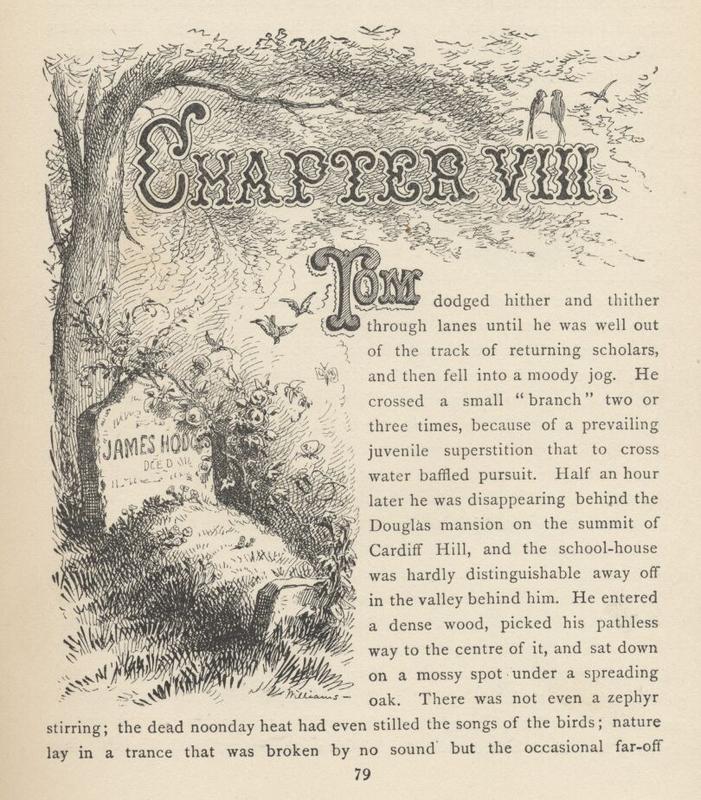
トムは、学校から帰ってくる生徒たちの通り道から十分に外れるまで、路地をあちこちと駆け抜け、やがて陰鬱な足取りでとぼとぼと歩き始めた。彼は小さな「小川」を二、三度渡った。水を渡ると追跡をかわすことができるという、子供たちの間で広まっている迷信のためである。三十分後、彼はカーディフの丘の頂上にあるダグラス邸の裏手へと姿を消し、背後の谷間には、校舎がかろうじて見分けられるほど遠くにあった。彼は鬱蒼とした森に入り、道なき道を進んでその中心部へとたどり着き、広がる樫の木の下の苔むした場所に腰を下ろした。そよ風一つ吹いていなかった。真昼の死んだような暑さは、鳥たちのさえずりさえも静まらせていた。自然は微動だにせず、時折遠くから聞こえるキツツキの木を叩く音だけがその静寂を破っていたが、それがいっそう、あたりに満ちる静けさと孤独感を深めているようだった。少年の魂は憂鬱に浸っていた。彼の感情は、周囲の環境と心地よく調和していた。彼は長い間、膝に肘をつき、両手で顎を支えながら物思いにふけっていた。人生とは、せいぜい厄介事の連続にすぎないように思えた。そして彼は、つい最近解放されたジミー・ホッジスを半分以上羨んでいた。風が木々の間をささやき、墓の上の草花を撫で、もう二度と悩んだり悲しんだりすることもなく、永遠に横たわり、眠り、夢を見続けるのは、さぞかし安らかなことだろう、と彼は思った。もし日曜学校の成績がきれいでありさえすれば、喜んで逝き、すべてを終わらせることができるのに。さて、あの娘のことだ。自分は一体何をしたというのだ? 何もしていない。世界で一番の善意で行動したのに、まるで犬のように――本当に犬のように扱われた。彼女はいつか後悔するだろう――もしかしたら、手遅れになってから。ああ、もし一時的に死ぬことができたら!
しかし、若者の弾力性に富んだ心は、長い間一つの窮屈な形に押し込められているわけにはいかない。トムはまもなく、知らず知らずのうちに再びこの世の関心事へと引き戻され始めた。もし今、背を向けて、謎めいた失踪を遂げたらどうだろう? もし遠くへ――海の向こうの見知らぬ国へ、はるか遠くへ行ってしまい、二度と戻ってこなかったら! そのとき彼女はどう感じるだろう! ピエロになるという考えが再び頭をよぎったが、今やそれは彼を嫌悪感で満たすだけだった。なぜなら、軽薄さや冗談、水玉模様のタイツは、ロマンチックという漠然として荘厳な領域にまで高められた精神に押し入ってくるとき、侮辱でしかなかったからだ。いや、兵士になろう。そして長い年月の後、戦いに疲れ果て、輝かしい名声を得て帰ってくるのだ。いや――もっといい、インディアンに加わり、バッファローを狩り、極西部の山脈や道なき大平原で戦いの道を行くのだ。そして遠い未来、羽飾りで身を固め、おぞましい化粧を施した偉大な酋長となって、ある気だるい夏の朝、日曜学校に勇ましく乗り込み、血も凍るような鬨の声をあげ、すべての仲間たちの目を、満たされぬ嫉妬で焼き尽くしてやるのだ。しかし、いや、これよりもっと華やかなものがある。海賊になるのだ! それだ! 今や彼の未来は目の前にくっきりと広がり、想像を絶する輝きで満ちていた。彼の名が世界に轟き、人々を震え上がらせる様を想像した! 長く、低く、黒い船体の快速船「嵐の精霊号」に乗り、恐ろしげな旗をマストに掲げ、踊るような海原を勇ましく突き進む様を! そして名声の絶頂で、故郷の村に突然現れ、教会に堂々と入っていくのだ。日に焼け、風雨にさらされた褐色の肌、黒いベルベットのダブレットと半ズボン、大きな長靴、深紅の飾り帯、馬用のピストルでいっぱいのベルト、罪で錆びついたカトラスを腰に差し、羽飾りの揺れるつば広の帽子をかぶり、ドクロと交差した骨の描かれた黒い旗を広げる。そして、恍惚に胸を膨らませながら、ささやき声を聞くのだ。「海賊トム・ソーヤーだ! ――スペイン領海の黒い復讐者だ!」

そうだ、決まった。彼の進むべき道は定まった。彼は家を飛び出し、その道に入るのだ。明日の朝、すぐに出発する。だから、今から準備を始めなければならない。彼は自分の財産を集めることにした。手近な腐った丸太のところへ行き、その一方の端の下をバーロウナイフで掘り始めた。すぐに、中が空洞のような音がする木に当たった。彼はそこに手を入れ、印象的にこの呪文を唱えた。
「ここに来てないもの、来たれ! ここにあるもの、とどまれ!」
それから彼は土をかき分け、松の屋根板を一枚露出させた。それを持ち上げると、底と側面が屋根板でできた、こぢんまりとした立派な宝物庫が現れた。中にはビー玉が一つ転がっていた。トムの驚きは限りなかった! 彼は困惑した様子で頭を掻き、言った。
「おい、こりゃ一体どうしたんだ!」
そして彼はビー玉をむしゃくしゃして投げ捨て、考え込んだ。実のところ、彼と仲間たちが皆、絶対だと信じていた迷信が、ここで失敗したのである。もし、ある必要な呪文と共にビー玉を埋め、二週間放っておき、そして先ほど使った呪文でその場所を開ければ、その間に失くしたすべてのビー玉が、どれほど広く離れていようとも、そこに集まってくるはずだった。しかし今、このことは現実に、そして疑いようもなく失敗した。トムの信仰の構造全体が、その根底から揺らいだ。彼はこれが成功したという話を何度も聞いたことがあったが、失敗したという話は一度もなかった。彼自身、以前に何度か試してみたが、その後隠し場所を見つけられなかったことは、彼の頭には浮かばなかった。彼はしばらくその問題について頭を悩ませ、最終的に、何者かの魔女が邪魔をして呪いを破ったのだと結論づけた。彼はその点を確かめたいと思った。そこで彼はあたりを探し回り、小さな漏斗状のくぼみのある砂地を見つけた。彼は腹ばいになり、そのくぼみに口を近づけて呼びかけた――
「アリジゴク、アリジゴク、俺が知りたいことを教えておくれ! アリジゴク、アリジゴク、俺が知りたいことを教えておくれ!」
砂が動き始め、やがて小さな黒い虫が一瞬現れ、そして怯えて再び下に潜り込んだ。
「教えようとしねえ! ってことは、やっぱり魔女の仕業だったんだ。わかってたさ。」
彼は魔女と争うことの無益さをよく知っていたので、落胆して諦めた。しかし、先ほど投げ捨てたビー玉を持っていた方がいいかもしれないと思い至り、そこで辛抱強くそれを探しに行った。だが、見つからなかった。今度は宝物庫に戻り、ビー玉を投げたときと全く同じ場所に注意深く立った。それからポケットから別のビー玉を取り出し、同じように投げながら言った。
「兄弟よ、お前の兄弟を探しに行け!」
彼はそれが止まった場所を見届け、そこへ行って探した。しかし、それは手前に落ちたか、遠くに行き過ぎたかのどちらかだったに違いない。そこで彼はさらに二度試した。最後の試みは成功した。二つのビー玉は、一フィートと離れていない場所に転がっていた。
ちょうどその時、おもちゃのブリキのラッパの音が、森の緑の回廊をかすかに下ってきた。トムは上着とズボンを脱ぎ捨て、サスペンダーをベルト代わりにし、腐った丸太の後ろの茂みをかき分けると、粗末な弓矢、木片の剣、ブリキのラッパが現れた。一瞬のうちに彼はそれらを掴み取り、シャツをはためかせながら、素足で飛び出していった。彼はまもなく大きなニレの木の下で立ち止まり、応えるようにラッパを吹き鳴らし、それからつま先立ちになって、あちらこちらを警戒するように見回し始めた。彼は慎重に言った――想像上の仲間たちに向かって。
「待て、我が陽気な仲間たちよ! 私が吹くまで隠れていろ。」
そこにジョー・ハーパーが現れた。トムと同じくらい軽装で、念入りに武装していた。トムは呼びかけた。
「待て! 我が許可なくシャーウッドの森に立ち入る者は何者か?」

「ギズボーンのガイは誰の許可もいらぬ。何者だ、お前は――その――」
「そのような口をきくとは」とトムは口添えした――彼らは本から記憶した「台本通りに」話していたからだ。
「そのような口をきくとは、お前は何者だ?」
「私か、いかにも! 私はロビン・フッドだ。その卑劣な骸がすぐに知ることになろう。」
「では、お前があの有名な無法者か? 喜んでこの陽気な森の隘路をかけて、お前と争おう。いざ尋常に勝負!」
彼らは木片の剣を手に取り、他の道具を地面にどさりと置き、足を合わせて剣を構え、厳粛で慎重な戦いを始めた。「二度打ち上げ、二度打ち下ろす」。やがてトムは言った。
「よし、コツを掴んだら、派手にやろうぜ!」
そこで彼らは「派手にやり」、その動きに息を切らし、汗を流した。やがてトムは叫んだ。
「倒れろ! 倒れろ! なぜ倒れないんだ?」
「倒れるもんか! お前こそ倒れろよ。分が悪いぞ。」
「なんだ、そんなことないさ。俺は倒れられない。本ではそうなってないんだ。本にはこう書いてある、『その時、背後からの一撃で、彼は哀れなギズボーンのガイを討ち取った』と。お前は振り返って、俺に背中を打たせなきゃならないんだ。」
権威には逆らえず、ジョーは振り返り、一撃を受けて倒れた。
「よし」とジョーは起き上がりながら言った。「今度はお前が俺に殺されなきゃだめだ。それがフェアだろ。」
「なんだよ、そんなことできないよ。本にはないんだから。」
「ちぇっ、そりゃずるいよ――それだけだ。」
「まあ、なあ、ジョー、お前がタック修道士か粉屋の息子マッチになって、六尺棒で俺を打ちのめすか、それとも俺がノッティンガムの代官になって、お前がしばらくロビン・フッドになって俺を殺すか、どっちかにしようぜ。」
これは満足のいく提案だったので、これらの冒険が実行された。それからトムは再びロビン・フッドになり、裏切り者の尼僧によって、手当を怠った傷口から血を流し、力を失っていくのを許された。そして最後に、泣きじゃくる無法者の一団を代表してジョーが、悲しげに彼を運び出し、彼の弱々しい手に弓を渡し、トムは言った。「この矢の落ちるところ、そこに哀れなロビン・フッドを緑の木の下に葬ってくれ」。そして彼は矢を放ち、後ろに倒れ、死ぬはずだったが、イラクサの上に落ちてしまい、死体にしては陽気に飛び上がってしまった。

少年たちは服を着て、武具を隠し、もはや無法者がいなくなったことを嘆きながら去っていった。そして、近代文明が、その代償として一体何を成し遂げたと主張できるだろうかと思いを巡らせた。彼らは、合衆国大統領に永遠になるよりも、シャーウッドの森で一年間無法者でいる方がましだと言い合った。
第九章
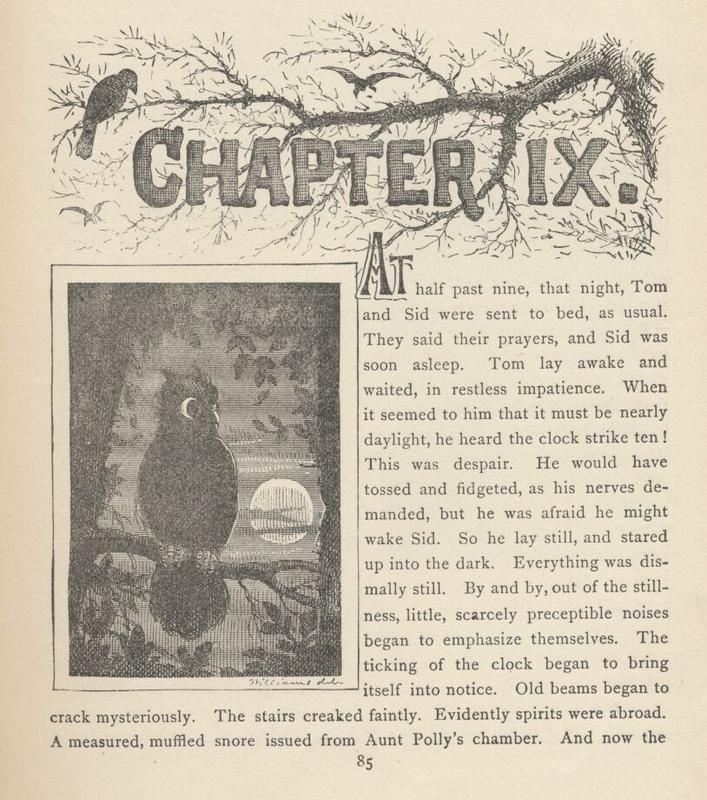
その夜、九時半になると、トムとシッドはいつものように寝かしつけられた。彼らはお祈りをし、シッドはすぐに眠りについた。トムは目を覚ましたまま、落ち着かずにじりじりと待っていた。もう夜明け近くに違いないと思えた頃、時計が十時を打つのが聞こえた! これは絶望的だった。神経が求めるままに寝返りを打ち、もぞもぞしたかったが、シッドを起こしてしまうのではないかと恐れた。そこで彼はじっと横たわり、暗闇を見つめていた。すべてが陰鬱なほど静かだった。やがて、その静寂の中から、ほとんど聞き取れないほどの小さな物音が、次第に際立ってきた。時計のチクタクという音が耳につくようになった。古い梁が不思議な音を立ててきしみ始めた。階段がかすかにきしんだ。明らかに幽霊が出没しているのだ。ポリーおばさんの部屋から、規則正しく、くぐもったいびきが聞こえてきた。そして今度は、人間のどんな知恵を絞っても場所を突き止められない、コオロギのうんざりするような鳴き声が始まった。次に、ベッドの頭の壁で死番虫が不気味に時を刻む音がして、トムは身震いした――それは誰かの命数が尽きたことを意味していた。それから、遠くの犬の遠吠えが夜の空気に響き渡り、さらに遠くから、よりかすかな遠吠えがそれに答えた。トムは苦悶していた。ついに彼は、時間が止まり、永遠が始まったのだと確信した。彼は我知らずうとうとし始めた。時計が十一時を告げたが、彼はそれを聞かなかった。そして、彼のまとまらない夢に混じって、この上なく物悲しい、けたたましい猫の鳴き声が聞こえてきた。近所の窓が開く音で、彼は目を覚まされた。「しっ! この悪魔め!」という叫び声と、おばさんの薪小屋の裏に空き瓶が叩きつけられる音で、彼は完全に目が覚めた。そして一分後には服を着て窓から外へ出て、L字型の棟の屋根を四つん這いで這っていた。彼は進みながら、用心深く一、二度「ニャー」と鳴いた。それから薪小屋の屋根に飛び降り、そこから地面に降り立った。そこにはハックルベリー・フィンが、死んだ猫を抱えていた。少年たちは動き出し、闇の中へと消えていった。半時間後、彼らは墓地の背の高い草をかき分けて進んでいた。

そこは、古風な西部式の墓地だった。村から一マイル半ほど離れた丘の上にあった。その周りには、狂ったように歪んだ板塀が巡らされており、ある場所では内側に傾き、他の場所では外側に傾き、どこにもまっすぐに立っているところはなかった。墓地全体に草や雑草が生い茂っていた。古い墓はすべて陥没しており、墓石は一つもなかった。てっぺんが丸く、虫に食われた墓標が、支えを求めても見つけられず、よろめくように墓の上に立っていた。かつては「誰それの思い出に捧ぐ」とペンキで書かれていたのだろうが、今では、たとえ明かりがあったとしても、そのほとんどはもう読めなかっただろう。
かすかな風が木々の間をうめき、トムはそれが、邪魔されたことに不平を言う死者たちの霊ではないかと恐れた。少年たちはほとんど口をきかず、話すときも息を殺していた。時間と場所、そしてあたりに満ちる厳粛さと静寂が、彼らの心を圧迫していたからだ。彼らは探していた、土が鋭く盛り上がった新しい墓を見つけ、その墓から数フィートのところに三本束になって生えている大きなニレの木の陰に身を隠した。
そして彼らは、長い時間のように思える間、沈黙して待った。遠くのフクロウの鳴き声だけが、死んだような静寂を乱す音だった。トムの考えは重苦しいものになっていった。彼は無理にでも何か話さなければならなかった。そこで彼はささやき声で言った。
「ハッキー、死んだ人たちは、俺たちがここにいるのが嬉しいと思うかい?」
ハックルベリーはささやいた。
「わかるといいんだけどな。ひどく厳かだな、なあ?」
「ほんとだよ。」
かなりの間があった。その間、少年たちはこの問題を心の中で吟味していた。それからトムはささやいた。
「なあ、ハッキー――ホス・ウィリアムズは俺たちが話してるのを聞いてると思うかい?」
「もちろんさ。少なくとも、その魂はな。」
トムは、一呼吸おいてから言った。
「ウィリアムズさんと呼べばよかった。でも、悪気はなかったんだ。みんな彼をホスって呼んでるから。」
「死んだ人のこと話すときは、言葉遣いに気をつけすぎるってことはないんだぜ、トム。」
これで座がしらけ、会話は再び途絶えた。
やがてトムは仲間の腕を掴んで言った。
「しーっ!」
「どうしたんだ、トム?」。そして二人は、高鳴る心臓を抱えて抱き合った。
「しーっ! まただ! 聞こえなかったのか?」
「俺は――」
「ほら! 今聞こえただろ。」
「ああ、トム、奴らが来る! 間違いなく来るぞ。どうしよう?」
「わかんない。俺たちが見えると思うか?」
「ああ、トム、奴らは猫みたいに暗闇でも見えるんだ。来なきゃよかった。」
「ああ、怖がるなよ。俺たちにちょっかい出すとは思えない。悪いことしてるわけじゃないんだから。じっとしてれば、気づかれないかもしれない。」
「そうしてみるよ、トム。でも、ああ、全身が震えてる。」
「聞け!」
少年たちは頭を寄せ合い、息もほとんどしていなかった。墓地の遠い端から、くぐもった声が聞こえてきた。
「見ろ! あそこだ!」とトムがささやいた。「なんだ?」
「鬼火だ。ああ、トム、こりゃひどい。」
ぼんやりとした人影が、闇の中を近づいてきた。古風なブリキのランタンを揺らしながら歩いており、その光が無数の小さなきらめきとなって地面に斑点を作っていた。やがてハックルベリーは身震いしながらささやいた。
「悪魔だ、間違いない。三匹も! ああ、トム、俺たちおしまいだ! お祈りできるか?」
「やってみるけど、怖がるなよ。俺たちを傷つけたりはしないさ。『今ぞ我、身を横たえ眠りにつかん、我――』。」

「しーっ!」
「どうしたんだ、ハック?」
「人間だ! 少なくとも一人はな。一人は、マフ・ポッターのじいさんの声だ。」
「まさか――本当かい?」
「絶対そうだ。動くんじゃないぞ。じっとしてろ。あのじいさんは、俺たちに気づくほど頭は回らない。いつものように酔っぱらってるんだろう――ろくでもない飲んだくれだ!」
「わかった、じっとしてる。今、奴らは立ち往生してる。見つけられないんだ。またこっちに来る。今、近いぞ。また遠ざかった。近い。すごく近い! 今度はまっすぐこっちに向かってる。なあ、ハック、もう一人の声も知ってるぞ。インジャン・ジョーだ。」
「本当だ――あの人殺しの混血野郎! それなら悪魔の方がよっぽどましだ。一体何を企んでるんだ?」
ささやき声は完全に消えた。三人の男が墓にたどり着き、少年たちの隠れ場所から数フィートのところに立っていたからだ。
「ここだ」と三番目の声が言った。その声の主はランタンを掲げ、若きロビンソン博士の顔を照らし出した。
ポッターとインジャン・ジョーは、ロープとシャベルを二本載せた手押し車を運んでいた。彼らは荷物を下ろし、墓を掘り始めた。博士はランタンを墓の頭に置き、ニレの木の一本に背中を預けて座った。彼はあまりに近く、少年たちが触れることができるほどだった。
「急げ、お前たち!」と彼は低い声で言った。「いつ月が出るかわからん。」
彼らはうなるように返事をし、掘り続けた。しばらくの間、シャベルが土や砂利を吐き出す、がりがりという音以外には何の音もなかった。それは非常に単調だった。ついにシャベルが鈍い木の音を立てて棺に当たり、それから一、二分もしないうちに、男たちはそれを地上に引き上げた。彼らはシャベルで蓋をこじ開け、遺体を取り出し、無造作に地面に放り出した。月が雲の陰から流れ出し、青白い顔を照らし出した。手押し車が用意され、死体がその上に置かれ、毛布で覆われ、ロープでその場所に縛り付けられた。ポッターは大きなバネナイフを取り出し、ぶら下がっているロープの端を切り落とし、そして言った。
「さあ、この厄介な代物が準備できたぜ、骨接ぎ屋。もう五ドル出すんだな。さもなきゃこいつはここに置いたままだ。」
「その通りだ!」とインジャン・ジョーが言った。
「おい、これはどういう意味だ?」と博士は言った。「お前たちは前金を要求し、私は払ったはずだ。」
「ああ、それ以上のこともしたな」とインジャン・ジョーは、今や立ち上がっている博士に近づきながら言った。「五年前に、お前は俺を親父さんの台所から追い出した。ある夜、食い物をくれって頼みに行ったときだ。お前は俺がろくな目的で来たんじゃないと言った。百年かかっても仕返ししてやると俺が誓ったとき、お前の親父は俺を浮浪者として牢屋に入れた。忘れたとでも思ったか? 俺にインディアンの血が流れてるのは伊達じゃねえ。そして今、お前を捕まえた。清算してもらわなきゃならねえんだ、わかるだろ!」
この時、彼は博士の顔に拳を突きつけ、脅していた。博士は突然殴りかかり、その悪党を地面に叩きつけた。ポッターはナイフを落とし、叫んだ。
「おい、相棒を殴るんじゃねえ!」そして次の瞬間、彼は博士と組み合い、二人は死に物狂いで格闘し、草を踏みつけ、かかとで地面をえぐった。インジャン・ジョーは、目に情熱の炎を燃やして飛び起き、ポッターのナイフをひったくり、猫のように身をかがめ、忍び寄りながら、機会をうかがって格闘する二人の周りをぐるぐると回った。突然、博士が身を振りほどき、ウィリアムズの墓の重い墓標を掴んでポッターを地面に打ち倒した――そしてまさにその瞬間、混血の男は好機と見て、若者の胸にナイフを柄まで突き刺した。彼はよろめき、ポッターの上に半ば倒れ込み、彼を血で染めた。そして同じ瞬間、雲がその恐ろしい光景を覆い隠し、怯えた二人の少年は闇の中を走り去っていった。
やがて月が再び現れると、インジャン・ジョーは二つの骸の上に立ち、それらを黙って見つめていた。博士は意味不明な言葉をつぶやき、長く息を一つ二つ吸い込み、そして動かなくなった。混血の男はつぶやいた。
「これで貸しは返したぜ――くそったれが。」
そして彼は死体から金品を奪った。その後、彼は致命的なナイフをポッターの開いた右手に握らせ、解体された棺の上に座った。三、四、五分が過ぎ、そしてポッターが身動きし、うめき始めた。彼の手はナイフを握りしめ、それを持ち上げ、一瞥し、そして身震いとともにそれを落とした。それから彼は起き上がり、体を押しやり、それを見つめ、そして混乱した様子で周りを見回した。彼の目はジョーの目と合った。
「おい、こりゃどういうことだ、ジョー?」と彼は言った。
「汚い仕事だ」とジョーは動かずに言った。
「なんでやったんだ?」
「俺が! 俺はやってない!」
「おい! そんな話は通じないぞ。」
ポッターは震え、青ざめた。
「酔いが覚めたと思ったんだがな。今夜は飲むんじゃなかった。だがまだ頭の中に残ってる――ここに来たときよりひどい。頭がごちゃごちゃで、ほとんど何も思い出せない。教えてくれ、ジョー――正直にな、なあ相棒――俺がやったのか? ジョー、そんなつもりはなかったんだ――魂と名誉にかけて、そんなつもりはなかったんだ、ジョー。どうだったのか教えてくれ、ジョー。ああ、ひどいことだ――あんなに若くて将来があったのに。」
「なあに、お前たち二人が取っ組み合ってて、あいつがお前を墓標で一発殴り、お前はばったり倒れた。それからお前は、ふらふらよろよろと立ち上がり、ナイフをひったくってあいつに突き刺したんだ。ちょうどあいつがお前に、もう一発ひどいのを食らわしたときにな。そしてお前は、今までくさびみたいに死んだようにここに横たわってたんだ。」

「ああ、俺は自分が何をしてるかわからなかった。もしわかってたなら、この場で死んでもいい。全部ウィスキーと興奮のせいだと思う。俺は今まで一度も武器を使ったことがないんだ、ジョー。喧嘩はしたが、武器は使ったことがない。みんなそう言うだろう。ジョー、言わないでくれ! 言わないって言ってくれ、ジョー――頼むよ、いい奴だろ。俺はいつもお前が好きだったし、お前の味方だったじゃないか。覚えてないか? 言わないよな、なあ、ジョー?」そして哀れな男は、冷酷な殺人者の前にひざまずき、懇願するように両手を組んだ。
「いや、お前はいつも俺に公平で正直だった、マフ・ポッター。お前を裏切ったりはしない。ほら、これで男として言えるだけのことは言った。」
「ああ、ジョー、お前は天使だ。このご恩は一生忘れない」。そしてポッターは泣き始めた。
「さあ、もうそのくらいにしろ。めそめそしてる場合じゃない。お前はあっちの道を行け、俺はこっちを行く。さあ、動け。足跡を残すなよ。」
ポッターは小走りで駆け出し、それはすぐに全力疾走に変わった。混血の男は彼の後姿を見送っていた。彼はつぶやいた。
「もしあいつが、見た目通り、殴られた衝撃と酒で頭が混乱してるなら、ナイフのことなんか、あんな場所に一人で取りに戻るのが怖くなるほど遠くまで行かないと思い出さないだろう――臆病者め!」
二、三分後、殺された男、毛布にくるまれた死体、蓋のない棺、そして開かれた墓は、月の監視下にあるだけだった。静寂もまた、完全に訪れていた。
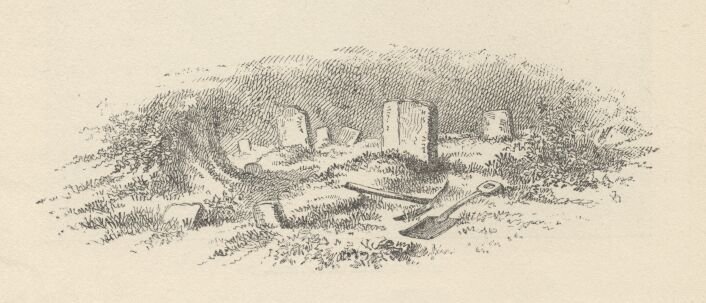
第十章
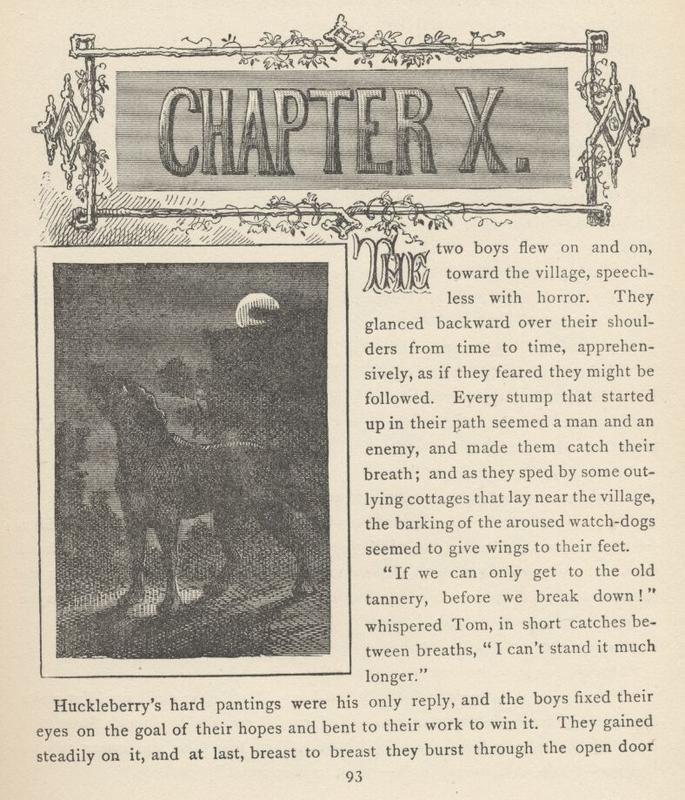
二人の少年は、恐怖に口もきけず、村に向かってひたすら走り続けた。彼らは時折、不安げに肩越しに後ろを振り返った。まるで追われているのではないかと恐れているかのようだった。行く手に現れる切り株はすべて人間であり、敵であるように見え、彼らは息をのんだ。そして村の近くに点在するいくつかの外れの小屋を駆け抜けるとき、目を覚ました番犬の吠え声が、彼らの足に翼を与えたかのようだった。
「壊れる前に、あの古いなめし革工場にたどり着きさえすれば!」トムは、途切れ途切れの息の合間にささやいた。「もうこれ以上は無理だ。」
ハックルベリーの荒い息遣いだけが彼の返事であり、少年たちは希望の目的地に目を据え、そこを勝ち取るために全力を尽くした。彼らは着実にそこへ近づき、そしてついに、胸を並べて開かれたドアを突き破り、その向こうの保護的な影の中に、感謝と疲労困憊で倒れ込んだ。やがて彼らの脈拍は落ち着き、トムはささやいた。
「ハックルベリー、この後どうなると思う?」
「もしロビンソン博士が死んだら、絞首刑になると思う。」
「ほんとかい?」
「なんだ、知ってるさ、トム。」
トムはしばらく考え、それから言った。
「誰が話す? 俺たちか?」
「何を言ってるんだ? もし何かあって、インジャン・ジョーが絞首刑にならなかったらどうする? そしたら、いつか俺たちを殺すだろうさ。俺たちがここに寝てるのと同じくらい、絶対確実にな。」
「ちょうど俺もそう考えてたんだ、ハック。」
「誰かが話すなら、マフ・ポッターにやらせればいい。あいつが馬鹿ならな。あいつはたいてい、十分に酔っぱらってる。」
トムは何も言わず、考え続けた。やがて彼はささやいた。
「ハック、マフ・ポッターは知らないんだ。どうして話せる?」
「なんで知らないってわかるんだ?」
「だって、インジャン・ジョーがやったとき、あいつはちょうどあの一撃を食らったばかりだったんだ。何か見えたと思うか? 何か知ってたと思うか?」
「ちくしょう、その通りだ、トム!」
「それに、ほら――もしかしたらあの一撃で、あいつ自身もやられちまったかもしれない!」
「いや、まさか、トム。あいつは酒を飲んでた。それは見えたし、それに、いつも飲んでる。まあ、親父が酔っぱらってるときは、教会で頭をぶん殴ってもびくともしない。親父自身がそう言ってる。だから、マフ・ポッターももちろん同じさ。でも、もし男がしらふだったら、もしかしたらあの一撃でやられるかもしれない。わかんないけどな。」
再び考え込んだ沈黙の後、トムは言った。
「ハッキー、絶対に口外しないって約束できるか?」
「トム、俺たちは口を閉ざしてなきゃならないんだ。わかってるだろ。もし俺たちがこのことをぺらぺらしゃべって、あいつらが絞首刑にならなかったら、あのインディアンの悪魔は、俺たちを二匹の猫みたいに溺れさせることなんて、何とも思わないだろう。なあ、トム、お互いに誓いを立てよう――そうしなきゃだめだ――口を閉ざすと誓うんだ。」
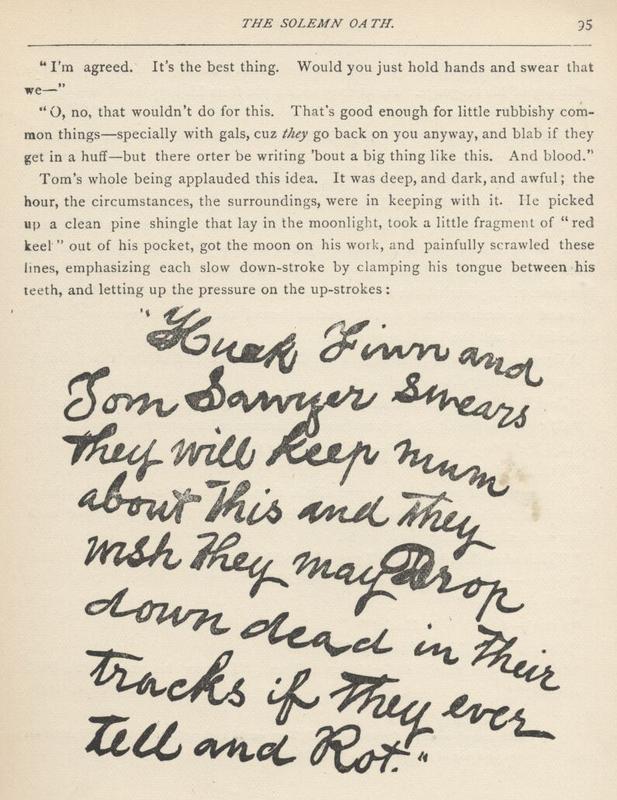
「賛成だ。それが一番いい。ただ手をつないで、俺たちは――って誓うのはどうだ。」
「ああ、だめだ、これにはそれではだめだ。それは、つまらない普通のことにしか通用しない――特に女相手にはな。だってあいつらはどうせ約束を破るし、腹を立てたらしゃべっちまう――でも、こんな大事なことには、書き物が必要だ。それと、血がな。」
トムの全身がこの考えを称賛した。それは深く、暗く、恐ろしいものだった。時間、状況、周囲の環境が、それと見事に調和していた。彼は月明かりの中に横たわっていたきれいな松の屋根板を拾い上げ、ポケットから「赤い石」の小さなかけらを取り出し、月に照らされながら作業に取りかかり、苦心してこれらの言葉を走り書きした。一画一画、ゆっくりと下ろすたびに舌を歯の間に挟んで力を込め、線を上げるときには力を抜いた。
「ハック・フィンとトム・ソーヤーは、この件について固く口を閉ざすことを誓う。もしもこのことを話したら、その場でばったり倒れて死んで、腐っちまっても構わないと願うものである。」
ハックルベリーは、トムの筆記の巧みさと、その言葉の崇高さに感嘆した。彼はすぐに襟からピンを抜き、自分の肉を刺そうとしたが、トムが言った。
「待てよ! やめとけ。ピンは真鍮製だ。緑青がついてるかもしれねえ。」
「緑青ってなんだ?」
「毒だよ。そういうもんだ。いっぺん飲み込んでみろよ――そしたらわかる。」
そこでトムは自分の針の一本から糸をほどき、少年たちはそれぞれ親指の腹を刺して、血を一滴絞り出した。やがて、何度も絞り出した末、トムは小指の腹をペンの代わりにして、どうにか自分のイニシャルの署名をすることができた。それからハックルベリーにHとFの書き方を教え、誓いは完了した。二人は何やら不気味な儀式と呪文を唱えながら、その羽目板を壁のすぐそばに埋めた。こうして、彼らの舌を縛る足枷は錠を下ろされ、その鍵は投げ捨てられたと見なされたのだった。
そのとき、廃墟のもう一方の端にある壁の崩れ目から、ある人影が忍び寄ってきていたが、二人はそれに気づかなかった。
「トム」とハックルベリーがささやいた。「これでもう、ぜったいに――いつまでも――話しちゃいけないってことか?」
「もちろんだよ。何が起ころうと関係ない。俺たちは黙ってなきゃいけないんだ。そうしなきゃ、ばったり死んじまう――知らねえのか?」
「ああ、たぶんそうなんだろうな。」
二人はしばらくささやき続けた。やがて一匹の犬が、すぐ外――ほんの十フィートも離れていない場所で、長く陰鬱な遠吠えを始めた。少年たちは恐怖のあまり、とっさに互いにしがみついた。
「どっちのことだろう?」とハックルベリーが息をのんだ。
「わからねえ――隙間からのぞいてみろ。早く!」
「いやだ、おまえがやれよ、トム!」
「できねえ――できっこないよ、ハック!」
「頼むよ、トム。まただ!」
「ああ、なんてこった、ありがてえ!」とトムがささやいた。「あの声は知ってる。ブル・ハービソンだ」*
[*もしハービソン氏がブルという名の奴隷を所有していたなら、トムは「ハービソンのブル」と言っただろう。しかし、息子や犬にその名がついていた場合は「ブル・ハービソン」となる。]
「ああ、よかった――なあ、トム、俺、死ぬかと思うほど怖かったぜ。てっきり野良犬だと思った。」
犬は再び遠吠えした。少年たちの心臓はまたしても凍りついた。
「なんてこった! ありゃブル・ハービソンじゃねえぞ!」ハックルベリーがささやいた。「頼む、トム!」
トムは恐怖に震えながらも折れて、目を隙間に当てた。彼が口にしたささやき声は、ほとんど聞き取れないほどだった。
「おい、ハック、野良犬だ!」
「早く、トム、早く! どっちのことなんだ?」
「ハック、俺たち両方にちげえねえ――すぐそばにいるんだから。」
「ああ、トム、俺たちもうおしまいだ。俺がどこへ行くことになるか、間違いねえだろうな。俺はひどい悪党だったから。」
「ちくしょう! これもみんな学校をサボったり、やっちゃいけねえって言われたことを何でもやったせいだ。俺だって、やろうと思えばシッドみたいにいい子になれたかもしれねえ――いや、もちろん、ならなかっただろうけど。でも、もし今度ばかりは助かったら、もう日曜学校に入り浸ってやる!」そう言うとトムは少し鼻をすすり始めた。
「おまえが悪いだと!」ハックルベリーも鼻をすすり始めた。「ちくしょう、トム・ソーヤー、おまえなんか俺に比べりゃただのパイみてえなもんだ。[訳注:ここでは「お人好し」くらいの意味]ああ、なんてこった、なんてこった、なんてこった、おまえのチャンスの半分でもありゃよかったのによ。」
トムはむせび泣きをこらえ、ささやいた。
「見ろ、ハッキー、見ろ! あいつ、こっちに背中を向けてるぜ!」
ハッキーは、心に喜びを抱いて見た。
「ほんとだ、ちくしょうめ! 前からそうだったか?」
「ああ、そうだ。でも、馬鹿な俺は気づかなかった。ああ、こりゃすげえや。それじゃあ、あいつは誰のことを言ってるんだ?」
遠吠えがやんだ。トムは耳をそばだてた。
「しーっ! なんだ、今の音は?」と彼はささやいた。
「……豚が鼻を鳴らすみてえな音だ。いや――誰かのいびきだ、トム。」
「それだ! どこだ、ハック?」
「あっちの端っこだと思う。とにかく、そう聞こえる。親父が時々、豚と一緒にあそこで寝てたけど、ありがたいことに、親父がいびきをかくときは、物が持ち上がるほどなんだ。それに、もう二度とこの町には戻ってこねえと思う。」
冒険心が少年たちの魂に再び燃え上がった。
「ハッキー、俺が先に行くから、ついてくる勇気はあるか?」
「あんまり気は進まねえな。トム、もしインジャン・ジョーだったらどうする!」

トムはひるんだ。しかし、すぐに誘惑が再び強くなり、少年たちは試してみることに同意した。ただし、いびきが止まったらすぐに逃げ出すという条件で。そして二人は、一人がもう一人の後ろについて、抜き足差し足で静かに進んでいった。いびきをかいている人物まであと五歩というところまで来たとき、トムが小枝を踏み、パキンと鋭い音を立てて折れた。男はうめき声を上げ、少し身をよじると、その顔が月明かりに照らされた。マフ・ポッターだった。男が動いたとき、少年たちの心臓は止まり、希望も消え失せたが、今や恐怖は過ぎ去った。彼らはつま先立ちで外へ出て、壊れた下見板を通り抜け、少し離れたところで立ち止まって別れの言葉を交わした。その長く陰鬱な遠吠えが、再び夜の空に響き渡った! 二人が振り返ると、見知らぬ犬がポッターの横たわる場所から数フィートのところに立ち、ポッターに顔を向け、鼻先を天に向けていた。
「うわあ、あいつだ!」と二人は同時に叫んだ。
「なあ、トム――二週間くらい前だったか、真夜中に野良犬がジョニー・ミラーの家の周りで吠えてたって話だぜ。それに、ちょうど同じ晩にヨタカが家に入ってきて、手すりにとまって鳴いたんだと。でも、まだ誰も死んでねえよ。」
「ああ、それは知ってる。だからどうしたってんだ。その次の土曜日に、グレイシー・ミラーが台所の暖炉に落ちて、ひどい火傷をしたじゃねえか。」
「そうだけど、死んじゃいねえ。それに、だんだん良くなってる。」
「わかったよ、まあ見てろ。あの子はおしまいさ、マフ・ポッターがおしまいなのと同じくらい確実にな。黒んぼたちがそう言ってる。あいつらはこういうことには何でも詳しいんだ、ハック。」
そして二人は、考え込みながら別れた。トムが寝室の窓から忍び込んだときには、夜はほとんど明けていた。彼は細心の注意を払って服を脱ぎ、自分の逃避行を誰も知らないと自らを祝いながら眠りに落ちた。彼は、穏やかにいびきをかいているシッドが目を覚ましていて、しかもそれが一時間も前からだったことには気づいていなかった。
トムが目を覚ますと、シッドはすでに服を着ていなくなっていた。陽の光には遅い時刻の気配が、空気には遅い時刻の感覚があった。彼はぎょっとした。なぜ起こされなかったのだろう――いつものように、起きるまでしつこく言われなかったのはなぜだろう? その考えが、彼の胸を不吉な予感で満たした。五分も経たないうちに彼は服を着て階下へ降りた。体は痛み、眠かった。家族はまだ食卓についていたが、朝食は終えていた。叱責の声はない。しかし、視線はそらされ、沈黙と厳粛な空気が漂い、罪人の心を冷たく突き刺した。彼は席に着き、陽気に振る舞おうとしたが、それは骨の折れる仕事だった。微笑みも、返事も引き出せず、彼は沈黙に陥り、心がどん底まで沈んでいくのをなすがままにしていた。
朝食の後、おばが彼を脇へ連れて行った。トムは鞭で打たれるのだという希望に、もう少しで顔を輝かせるところだったが、そうではなかった。おばは彼の上で泣き崩れ、どうしてこんなふうに年老いた自分の心を傷つけることができるのかと尋ねた。そしてとうとう、好きにするがいい、破滅して、この白髪頭を悲しみと共に墓場へ送るがいい、もう自分が何をしようと無駄なのだから、と言った。これは千回の鞭打ちよりもひどく、トムの心は今や体よりも痛んだ。彼は泣き、許しを請い、何度も何度も改心を約束し、そしてようやく解放された。しかし、得られたのは不完全な許しであり、築けたのはか弱い信頼に過ぎないと感じていた。

彼はあまりに惨めな気持ちでその場を去ったので、シッドに対して復讐心さえ感じることができなかった。したがって、後者が裏門から素早く退散したのは不必要だった。彼は陰鬱で悲しげに学校へとぼとぼと歩き、昨日学校をサボったことで、ジョー・ハーパーと共に鞭打ちを受けたが、その様子は、心がより重い悲しみに preoccupied され、些細なことには全く無関心な者のようであった。それから彼は自分の席に着き、肘を机に、顎を両手につけて、苦しみが限界に達し、もはやそれ以上進むことのできない者の石のような眼差しで壁を見つめた。彼の肘が何か硬いものに当たっていた。しばらくして、彼はゆっくりと悲しげに体勢を変え、ため息をつきながらその物体を手に取った。それは紙に包まれていた。彼はそれを広げた。長く、尾を引く、途方もないため息が続き、彼の心は砕け散った。それは、彼の真鍮製の五徳の飾り玉だった!
この最後の一本の羽が、ラクダの背を折ったのだった。
第十一章
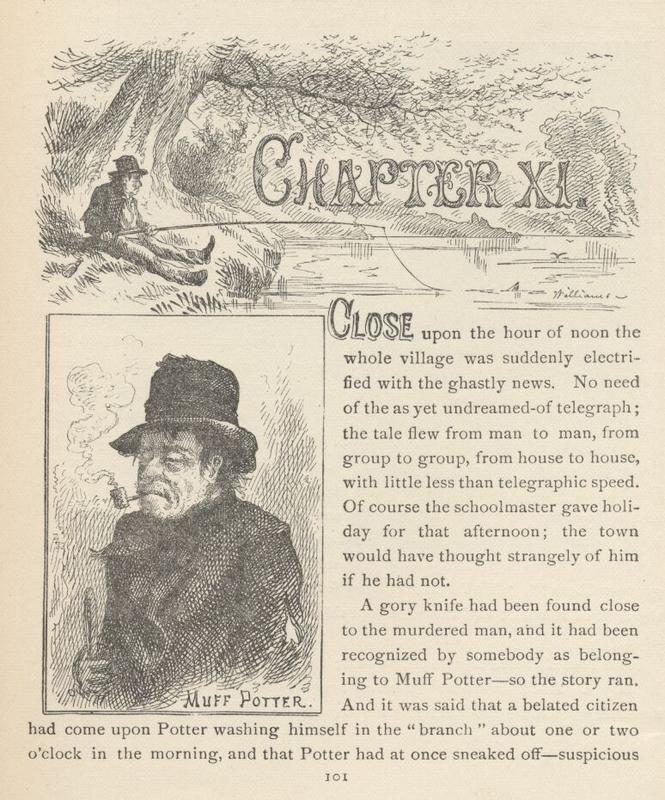
正午になろうかという頃、村中が突如としてその身の毛もよだつニュースに electrified された。まだ夢にも思われていない電信の必要などない。その話は人から人へ、集団から集団へ、家から家へと、電信に劣らぬ速さで駆け巡った。もちろん、学校の先生はその日の午後を休みにした。もしそうしなかったら、町の人々は彼を奇妙に思っただろう。

殺害された男のすぐそばで血まみれのナイフが発見され、誰かがそれをマフ・ポッターのものだと認めた――話はそう伝わった。そして、夜更かしをしていたある市民が、午前一、二時頃にポッターが「小川」で体を洗っているのを見かけ、ポッターはすぐにこそこそと立ち去ったと言われていた――疑わしい状況、特に体を洗うことはポッターの習慣ではなかった。また、この「殺人犯」を探して町中が捜索されたが(大衆は証拠を吟味し、評決に至ることに関しては遅くない)、見つからなかったとも言われていた。騎馬の者たちが四方八方のすべての道へと出発し、保安官は夜までに捕まえられると「確信していた」。
町中の人々が墓地へと向かっていた。トムの心の痛みは消え去り、彼はその行列に加わった。他のどこへでも行った方が千倍ましだったからではなく、恐ろしく、説明のつかない魅力が彼を引き寄せたからだ。その恐ろしい場所に到着すると、彼は自分の小さな体を人混みの中にもぐり込ませ、その陰惨な光景を見た。以前ここにいた時から、まるで一時代も経ったかのように感じられた。誰かが彼の腕をつねった。彼が振り向くと、ハックルベリーの目と合った。すると二人はすぐに視線をそらし、互いの視線に誰かが何か気づいたのではないかと訝しんだ。しかし、誰もが話し込み、目の前のぞっとするような光景に夢中だった。
「かわいそうに!」「気の毒な若者だ!」「墓荒らしどもへの教訓になるべきだ!」「マフ・ポッターは捕まったら絞首刑だな!」これが感想の大筋だった。そして牧師は言った。「これは天罰です。神の御手がここにあります。」
今やトムは頭のてっぺんから踵まで震え上がった。彼の目に、インジャン・ジョーの無表情な顔が飛び込んできたからだ。その瞬間、群衆が揺れ動き、もみ合い始め、声が叫んだ。「やつだ! やつだ! 本人が来たぞ!」
「誰だ? 誰が?」と二十もの声が上がった。
「マフ・ポッターだ!」
「おい、止まったぞ! ――見ろ、振り向いてる! 逃がすな!」
トムの頭上の木の枝にいた人々は、彼は逃げようとはしていない――ただ、疑わしげで当惑した表情をしているだけだと言った。
「ふてぶてしいやつめ!」と傍観者の一人が言った。「自分の仕事ぶりを静かに見に来たかったんだろう――まさか仲間がいるとは思わなかったんだろうな。」
群衆は今や二手に分かれ、保安官がポッターの腕をこれ見よがしに引いて通り抜けてきた。哀れな男の顔はやつれ、その目には恐怖が宿っていた。殺害された男の前に立ったとき、彼はまるで中風のように震え、両手で顔を覆って泣き崩れた。
「俺はやってねえ、みんな」と彼は嗚咽した。「誓って、名誉にかけて、俺はやってねえ。」

「誰がおまえを責めたってんだ?」と声が叫んだ。
この一撃は的を射たようだった。ポッターは顔を上げ、哀れな絶望を瞳に浮かべて周りを見渡した。彼はインジャン・ジョーを見て、叫んだ。
「ああ、インジャン・ジョー、おまえは約束したじゃないか、絶対に――」
「それはおまえのナイフか?」と、保安官によってそれが彼の前に突きつけられた。
ポッターは、もし彼らが支えて地面に楽に座らせてやらなければ、倒れていただろう。それから彼は言った。
「何かが俺に言ったんだ、もし戻ってきて、これを――」彼は身震いした。そして、力のない手を敗北の仕草で振り、言った。「話してくれ、ジョー、話してくれ――もう無駄だ。」
そしてハックルベリーとトムは、唖然として立ち尽くし、石の心を持つ嘘つきが平然と供述を紡ぎ出すのを聞いていた。二人は、晴れた空から神の稲妻が彼の頭上に落ちるのを今か今かと待ち望み、その一撃がいかに遅れているかを不思議に思っていた。そして彼が話し終えてもなお、生きて無傷で立っているのを見て、哀れな裏切られた囚人の命を救うために誓いを破ろうという揺れ動く衝動は薄れ、消え去った。明らかにこの悪党はサタンに魂を売っており、そのような力の所有物に手出しをすることは命取りになるだろうからだ。
「なぜ逃げなかった? 何しにここへ来たんだ?」と誰かが言った。
「どうしようもなかったんだ――どうしようもなかった」とポッターはうめいた。「逃げたかったんだが、ここ以外のどこへも行けないようだった」そして彼は再び泣き崩れた。
インジャン・ジョーは、数分後の検死審問で、宣誓のもと、全く同じように冷静に供述を繰り返した。そして少年たちは、稲妻が依然として控えられているのを見て、ジョーが悪魔に魂を売ったという信念を確かなものにした。彼は今や、彼らにとって、これまで見た中で最も不吉で興味深い対象となり、彼らは彼の顔から魅了された目を離すことができなかった。
彼らは、機会があれば夜に彼を見張り、その恐ろしい主人の姿を垣間見ようと心に誓った。
インジャン・ジョーは、殺害された男の遺体を持ち上げて運び出すための荷馬車に乗せるのを手伝った。そして、身震いする群衆の間で、傷口から少し血がにじんだとささやかれた! 少年たちは、この幸運な出来事が疑いを正しい方向に向けるだろうと思ったが、彼らは失望した。なぜなら、一人以上の村人がこう言ったからだ。
「それが起きたとき、マフ・ポッターから三フィート以内だったからな。」
トムの恐ろしい秘密と、うずく良心は、この後一週間ほど彼の眠りを妨げた。そしてある朝の朝食で、シッドが言った。
「トム、君は寝ている間にすごく転げ回ったり寝言を言ったりするから、僕、半分くらい起こされちゃうよ。」
トムは青ざめ、目を伏せた。
「それは悪い兆候だね」とポリーおばさんが真剣に言った。「何を気にしているんだい、トム?」
「何でもない。僕の知る限り、何でもないよ」しかし、少年の手は震え、コーヒーをこぼしてしまった。
「それに、君は変なことばかり言うんだ」とシッドが言った。「昨日の夜は、『血だ、血だ、そういうことなんだ!』って言ってたよ。それを何度も何度も。それに、『そんなに僕を苦しめないで――話しちゃうから!』って言った。何を話すんだい? 君が話すことって何?」
トムの目の前で、すべてがぐるぐると回っていた。今、何が起こっていたか知れたものではないが、幸いにもポリーおばさんの顔から心配の色が消え、彼女は知らず知らずのうちにトムを救うことになった。彼女は言った。
「あらまあ! あの恐ろしい殺人事件のせいだよ。私だって、ほとんど毎晩その夢を見るんだから。時には、私がやった夢を見ることもあるよ。」
メアリーも、自分も同じような影響を受けたと述べた。シッドは満足したようだった。トムは、もっともらしくできる限り早くその場を離れ、その後一週間、歯痛を訴え、毎晩顎に包帯を巻いた。彼は、シッドが夜ごと見張っていて、しばしば包帯をそっと外し、肘をついてしばらくの間耳を澄まし、その後再び包帯を元の場所に戻していることを知らなかった。トムの心の苦悩は次第に薄れ、歯痛は煩わしくなって捨てられた。もしシッドが本当にトムの支離滅裂なつぶやきから何かを理解したとしても、彼はそれを自分の胸にしまっておいた。
トムには、学校の仲間たちが死んだ猫の検死審問をいつまでもやめようとしないように思え、そのために彼の悩みは常に心の中にあった。シッドは、トムがこれまであらゆる新しい企ての先頭に立つのが常だったにもかかわらず、これらの審問で決して検死官を務めないことに気づいた。また、トムが証人として行動することも決してないことにも気づいた――そしてそれは奇妙だった。そしてシッドは、トムがこれらの審問に対して顕著な嫌悪感を示し、できる限り避けているという事実を見逃さなかった。シッドは不思議に思ったが、何も言わなかった。しかし、検死審問さえもついに流行らなくなり、トムの良心を苛むことはなくなった。
この悲しみの期間中、トムは一日か二日おきに機会をうかがい、小さな格子のはまった監獄の窓に行き、「殺人犯」に手に入る限りのささやかな慰め品をこっそり差し入れた。監獄は村のはずれの湿地に立つ、取るに足らない小さなレンガ造りの巣穴で、看守もいなかった。実際、そこが使われることはめったになかった。これらの差し入れは、トムの良心を大いに和らげるのに役立った。
村人たちは、インジャン・ジョーにタールを塗って羽をつけ、一本のレールに乗せて引き回したいと強く望んでいた。死体盗掘の罪で。しかし、彼の性格があまりに恐ろしいため、その件で先頭に立つことを厭わない者は見つからず、その話は立ち消えになった。彼は、二度の検死審問の供述を、どちらも喧嘩から始めるよう注意し、その前の墓荒らしを告白しなかった。そのため、現時点ではこの事件を法廷で審理しないのが最も賢明だと考えられた。

第十二章
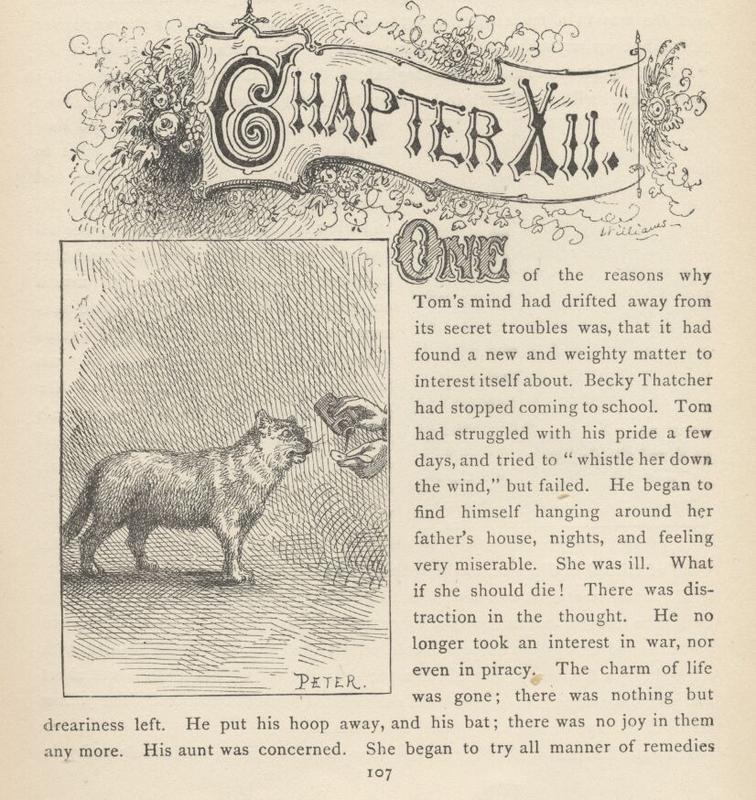
トムの心が秘密の悩みから離れていった理由の一つは、興味を引く新たな、そして重大な事柄を見つけたからだった。ベッキー・サッチャーが学校に来なくなったのだ。トムは数日間、自尊心と格闘し、彼女を「風に吹かれて忘れよう」と試みたが、失敗した。彼は夜になると彼女の父親の家の周りをうろつき、ひどく惨めな気持ちになっている自分に気づき始めた。彼女は病気だった。もし死んでしまったらどうしよう! その考えは彼を狂わせた。彼はもはや戦争にも、海賊ごっこにさえも興味を示さなかった。人生の魅力は消え去り、残されたのは退屈だけだった。彼は輪っかもバットも片付けた。もはやそれらに喜びはなかった。おばは心配した。彼女は彼にあらゆる種類の治療法を試し始めた。彼女は、特許薬や健康を生み出したり修復したりするためのあらゆる目新しい方法に夢中になる類の人々の一人だった。彼女はこれらのことにおいて根っからの実験家だった。この分野で何か新しいものが出ると、彼女はすぐにそれを試したくて熱に浮かされた。自分自身にではなく、彼女は決して病気になることがなかったので、手近な誰にでも試した。彼女はあらゆる「健康」雑誌や骨相学の詐欺的な出版物の購読者であり、それらが膨らませていた厳粛な無知は、彼女にとって鼻孔をくすぐる息吹だった。換気について、寝方について、起き方について、何を食べるべきか、何を飲むべきか、どれくらいの運動をすべきか、どのような心構えを保つべきか、どのような服装をすべきかについて、それらが含んでいたすべての「くだらないこと」は、彼女にとってすべて福音であり、当月号の健康雑誌が前月号で推奨したことすべてを慣習的に覆していることには決して気づかなかった。彼女は日がな一日単純で正直だったので、格好の餌食だった。彼女はインチキ雑誌とインチキ薬を集め、こうして死を武器に、比喩的に言えば、「地獄を従えて」青白い馬に乗って歩き回った。しかし、彼女は自分が癒しの天使であり、苦しむ隣人たちにとって偽装したギレアデの香油ではないなどとは、決して疑わなかった。
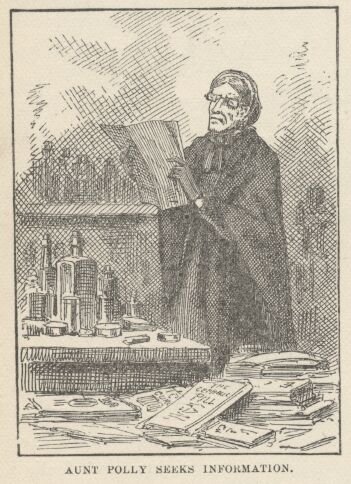
水治療が今、新しかった。そしてトムの意気消沈した状態は、彼女にとって棚ぼただった。彼女は毎朝夜明けに彼を外に出し、薪小屋に立たせて冷水の洪水で彼を溺れさせた。それからヤスリのようなタオルで彼をこすり下ろし、そうして彼を正気に戻した。次に、彼を濡れたシーツでくるみ、毛布の下にしまい、彼の魂が汗で清められ、「その黄色いシミが毛穴から出てくる」まで――トムが言うには――そうした。
しかし、これらすべてにもかかわらず、少年はますます憂鬱で青白く、意気消沈していった。彼女は温水浴、腰湯、シャワー、そして飛び込みを追加した。少年は葬儀屋のように陰鬱なままだった。彼女は水治療に、わずかなオートミール食と水ぶくれ膏薬を加え始めた。彼女は彼の容量を水差しのように計算し、毎日インチキ万能薬で彼を満たした。
この頃にはトムは迫害に無関心になっていた。この段階は老婦人の心を狼狽させた。この無関心は何としても打ち破らなければならない。今、彼女は初めてペイン・キラー(痛み止め)のことを耳にした。彼女はすぐに大量に注文した。彼女はそれを味わい、感謝の念で満たされた。それはまさに液体の形をした火だった。彼女は水治療もその他すべてをやめ、ペイン・キラーに信頼を寄せた。彼女はトムにティースプーン一杯を与え、深い不安とともに結果を見守った。彼女の悩みは即座に解消され、彼女の魂は再び平穏を取り戻した。なぜなら、「無関心」が打ち破られたからだ。もし彼女が彼の下で火を焚いていたとしても、少年はこれ以上荒々しく、心からの関心を示すことはできなかっただろう。
トムは、目を覚ます時が来たと感じた。この種の生活は、彼の打ちひしがれた状態ではロマンチックかもしれないが、感傷が少なくなりすぎ、気を散らす多様性が多すぎてきていた。そこで彼は救済のための様々な計画を考え、最終的にペイン・キラーが好きだと公言するという案に思い至った。彼はあまりに頻繁にそれを求めたので、厄介者になり、おばはとうとう、自分で勝手にして、もう私を煩わせないでくれと言って終わらせた。もしこれがシッドだったら、彼女は喜びを損なうような疑念を抱かなかっただろう。しかし、トムだったので、彼女は瓶をこっそり見張っていた。彼女は薬が本当に減っていることに気づいたが、少年がそれで居間の床のひび割れの健康を修復しているとは思いもよらなかった。
ある日、トムがひび割れに薬を投与している最中に、おばの黄色い猫がやってきて、喉を鳴らし、ティースプーンを欲深そうに見つめ、一口くれとねだった。トムは言った。
「欲しくないなら、ねだるなよ、ピーター。」
しかしピーターは、欲しいという意思表示をした。
「よく確かめた方がいいぜ。」
ピーターは確信していた。
「さて、おまえがねだったんだから、くれてやるよ。俺には意地悪なところはないからな。でも、もし気に入らないとわかっても、自分自身以外、誰も責めるんじゃないぞ。」
ピーターは同意した。そこでトムは彼の口をこじ開け、ペイン・キラーを注ぎ込んだ。ピーターは二ヤードほど空中に飛び上がり、それから雄叫びを上げて部屋中をぐるぐると駆け回り始め、家具にぶつかり、植木鉢をひっくり返し、大混乱を引き起こした。次に彼は後ろ足で立ち上がり、肩越しに頭を向け、抑えきれない幸福を声高に宣言しながら、狂乱の喜びの中で跳ね回った。それから彼は再び家中を駆け巡り、行く手にあるものすべてに混沌と破壊をまき散らした。ポリーおばさんが入ってきたのは、ちょうど彼が数回の宙返りを披露し、最後の力強い万歳を叫び、残りの植木鉢を道連れに開いた窓から飛び出していくのを見るタイミングだった。老婦人は驚きに石のように立ち尽くし、眼鏡越しに見つめていた。トムは床に転がって笑い死にしそうになっていた。
「トム、一体全体あの猫はどうしたんだい?」
「わからないよ、おばさん」と少年は息を切らしながら言った。
「まあ、あんなのは見たことがないよ。何であんなふうに行動したんだい?」
「ほんとに知らないよ、ポリーおばさん。猫は楽しいときはいつもあんなふうにするもんだよ。」

「そうなのかい、そうなの?」その口調には、トムを不安にさせる何かがあった。
「はい、おばさん。つまり、そうだと思うよ。」
「そう思うのかい?」
「はい、おばさん。」
老婦人は身をかがめていた。トムは、不安に強調された興味をもって見守っていた。遅すぎたが、彼は彼女の「意図」を察した。証拠のティースプーンの柄が、ベッドのひだ飾りの下から見えていた。ポリーおばさんはそれを手に取り、持ち上げた。トムはたじろぎ、目を伏せた。ポリーおばさんはいつもの取っ手――彼の耳――で彼を持ち上げ、指ぬきで彼の頭をぴしゃりと叩いた。
「さて、おまえさん、なぜあの哀れな口のきけない動物にあんなひどいことをしたんだい?」
「あいつを哀れに思ったからやったんだ――あいつにはおばさんがいなかったから。」
「おばさんがいなかった! ――このうすのろ。それが何の関係があるんだい?」
「大ありだよ。だってもしあいつにおばさんがいたら、自分で腹わたを焼いてたはずだ! まるで人間みたいに、何の感情もなく、はらわたを丸焼きにしてたにちげえねえ!」
ポリーおばさんは突然、自責の念に駆られた。これは物事を新しい観点から見ていた。猫にとって残酷なことは、少年にとっても残酷なことかもしれない。彼女は態度を和らげ始めた。彼女は気の毒に思った。彼女の目は少し潤み、彼女はトムの頭に手を置いて優しく言った。
「私は良かれと思ってやったんだよ、トム。それに、トム、あれは本当に君のためになったんだよ。」
トムは、真面目な表情の中にほんのかすかなきらめきをのぞかせながら、彼女の顔を見上げた。
「おばさんが良かれと思ってたのは知ってるよ。僕もピーターにそうだったんだ。あいつにもためになったんだよ。あんなに元気に走り回るの、見たことないよ、あれ以来――」
「ああ、もう行ってしまいなさい、トム、また私を怒らせる前に。そして、一度でいいから、いい子になれるようにやってみなさい。もう薬を飲まなくていいから。」
トムは時間より早く学校に着いた。この奇妙なことが最近毎日起こっていることに気づかれていた。そして今、最近の常として、彼は仲間と遊ぶ代わりに校庭の門のあたりをうろついていた。彼は病気だと言い、そしてそのように見えた。彼は、自分が本当は見ている方向――道の向こう――以外のあらゆる場所を見ているように見せかけようとした。やがてジェフ・サッチャーの姿が見え、トムの顔が輝いた。彼は一瞬見つめ、それから悲しげに顔をそむけた。ジェフが到着すると、トムは彼に話しかけ、ベッキーについての発言の機会へと慎重に「導いた」が、その軽薄な少年は決して餌に食いつかなかった。トムは、ひらひらするフロックが見えるたびに期待して見守り、それが目当ての人物でないとわかるとすぐにその持ち主を憎んだ。ついにフロックが現れなくなり、彼は絶望的に落ち込んだ。彼は空っぽの校舎に入り、苦しむために座った。するともう一つフロックが門を通り、トムの心臓は大きく跳ね上がった。次の瞬間、彼は外に出て、インディアンのように「暴れまわっていた」。叫び、笑い、少年たちを追いかけ、命がけで塀を飛び越え、側転をし、逆立ちをし――考えつく限りの英雄的なことをすべてやり、その間ずっと、ベッキー・サッチャーが気づいているかどうかを盗み見ていた。しかし、彼女はそれらすべてに気づいていないようだった。彼女は決して見なかった。彼がそこにいることに彼女が気づいていないなんてことがあり得るだろうか? 彼は自分の離れ業を彼女のすぐ近くまで持っていった。雄叫びを上げながら周りを走り回り、少年の帽子をひったくり、それを校舎の屋根に投げ上げ、少年たちのグループを突き破り、彼らを四方八方に転がし、自分自身もベッキーの鼻先で大の字に倒れ、彼女をほとんどひっくり返しそうになった――すると彼女は、鼻を高くして振り返り、彼には彼女がこう言うのが聞こえた。「ふん! 自分をすごく賢いと思ってる人もいるのね――いつも見せびらかしてばっかり!」
トムの頬は燃えるように熱くなった。彼は身を起こし、打ち砕かれ、しょんぼりしてこそこそと立ち去った。

第十三章
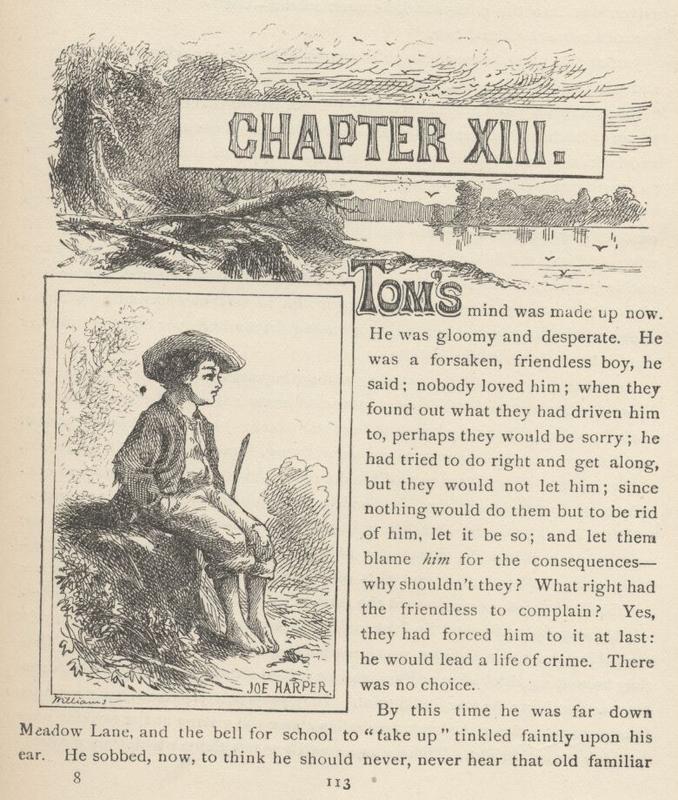
トムの決心は今や固まっていた。彼は陰鬱で絶望的だった。自分は見捨てられ、友人もいない少年だ、と彼は言った。誰も彼を愛していない。自分たちが彼を何に追い込んだかを知ったとき、おそらく彼らは後悔するだろう。彼は正しくあろうと、うまくやっていこうと努めたが、彼らはそれを許してくれなかった。彼らを満足させるのが自分を追い出すことしかないのなら、そうさせてやろう。そして、その結果を彼のせいにさせておけばいい――なぜいけない? 友人のいない者に文句を言う権利などあるものか? そうだ、彼らはとうとう彼をそこまで追い詰めたのだ。彼は犯罪の人生を送るだろう。選択の余地はなかった。
この時までに、彼はメドウ・レーンをずっと下っており、学校の「始まり」を告げる鐘が彼の耳にかすかに響いた。彼は今や、あの古く馴染んだ音を二度と、二度と聞くことはないだろうと思うと、すすり泣いた――それはとても辛いが、彼に強いられたことだった。冷たい世の中に追い出されたからには、従うしかない――しかし、彼は彼らを許した。すると、嗚咽が次から次へと込み上げてきた。
ちょうどその時、彼は魂の誓いを交わした同志、ジョー・ハーパーに出会った――目は険しく、心には明らかに重大で陰鬱な目的を秘めていた。明らかにここに「ただ一つの思いを持つ二つの魂」があった。トムは袖で目を拭いながら、家でのひどい扱いや同情の欠如から逃れるために、二度と戻らぬ覚悟で広大な世界を放浪するという決意について、むせび泣きながら語り始めた。そして、ジョーが自分を忘れないでくれることを願って話を終えた。
しかし、これはジョーがまさにトムに頼もうとしていたことであり、その目的で彼を探しに来たことが判明した。彼の母親は、彼が全く味わってもおらず、何も知らないクリームを飲んだとして彼を鞭で打った。彼女が彼にうんざりし、出て行ってほしいと願っているのは明らかだった。彼女がそう感じているのなら、彼にできることは屈することだけだった。彼は彼女が幸せになり、哀れな息子を非情な世の中に追い出して苦しみ死なせたことを決して後悔しないことを願った。
二人の少年は悲しみながら歩きながら、互いに支え合い、兄弟となり、死が彼らを悩みから解放するまで決して離れないという新たな盟約を結んだ。それから彼らは計画を練り始めた。ジョーは隠者になり、人里離れた洞窟でパンの耳を食べて暮らし、いつか寒さと欠乏と悲しみで死ぬことを望んだ。しかし、トムの話を聞いた後、彼は犯罪の人生にはいくつかの顕著な利点があることを認め、海賊になることに同意した。
セント・ピーターズバーグから三マイル下流、ミシシッピ川が幅一マイルをわずかに超える地点に、長く、狭く、木々に覆われた島があった。その上流側には浅い砂州があり、ここは集合場所として申し分なかった。そこは無人島で、対岸のはるか向こう、鬱蒼とした、ほとんど人の住まない森に面して横たわっていた。こうしてジャクソン島が選ばれた。彼らの海賊行為の対象が誰になるかという問題は、彼らの念頭にはなかった。それから彼らはハックルベリー・フィンを探し出し、彼はすぐに仲間になった。彼にとってはどんなキャリアも同じだったからだ。彼は無関心だった。彼らはまもなく別れ、村から二マイル上流の川岸にある人里離れた場所で、お気に入りの時刻――真夜中――に会うことにした。そこには小さな丸太のいかだがあり、それを捕獲するつもりだった。それぞれが釣り針と釣り糸、そして無法者らしく、最も暗く神秘的な方法で盗むことができる食料を持ってくることになった。そして午後が終わる前に、彼らは皆、「近いうちに町は『何かを聞く』ことになる」という事実を広めるという甘美な栄光を味わうことができた。この漠然としたヒントを得た者は皆、「黙って待つ」ようにと注意された。
真夜中ごろ、トムは茹でたハムといくつかの些細なものを持って到着し、待ち合わせ場所を見下ろす小さな崖の上の鬱蒼とした下草の中に立ち止まった。星が輝き、非常に静かだった。雄大な川は、休息する海のように横たわっていた。トムは一瞬耳を澄ましたが、静寂を乱す音はなかった。それから彼は低く、はっきりとした口笛を吹いた。それは崖の下から応えられた。トムはさらに二度口笛を吹いた。これらの合図は同じように応えられた。それから、用心深い声が言った。
「誰だ?」
「トム・ソーヤー、スペイン近海の黒い復讐者だ。名を名乗れ。」
「血まみれの手のハック・フィン、そして海の恐怖ジョー・ハーパー」トムは、お気に入りの文学作品からこれらの称号を用意していた。
「よろしい。合言葉を言え。」
二つのしゃがれたささやき声が、同時に同じ恐ろしい言葉を、物思いに沈む夜に告げた。
「血!」
それからトムはハムを崖から転がし落とし、自分もその後を追って降りた。その努力で皮膚も服もいくらか引き裂かれた。崖の下の岸辺に沿って、簡単で快適な道があったが、海賊にとって非常に価値のある困難さと危険さという利点が欠けていた。
海の恐怖はベーコンの半身を持ってきており、それをそこまで運ぶのにほとんど疲れ果てていた。血まみれの手のフィンは、フライパンと半乾きの葉タバコを大量に盗んできており、パイプを作るためのトウモロコシの穂軸もいくつか持ってきた。しかし、海賊の中で喫煙したり「噛みタバコ」をしたりするのは彼自身だけだった。スペイン近海の黒い復讐者は、火なしで出発するのは絶対にだめだと言った。それは賢明な考えだった。その時代、その地ではマッチはほとんど知られていなかった。彼らは百ヤードほど上流の大きないかだの上で火がくすぶっているのを見つけ、こっそりとそこへ行き、燃え木を一つ拝借した。彼らはそれを壮大な冒険に仕立て上げ、時々「しーっ!」と言ったり、突然指を唇に当てて立ち止まったりした。架空の短剣の柄に手をかけて動き、「もし『敵』が動いたら、柄まで突き刺してやれ」と陰鬱なささやき声で命令を下した。「死人に口なし」だからだ。彼らは、いかだ乗りたちが皆、村で物資を仕入れたり、どんちゃん騒ぎをしたりしていることをよく知っていたが、それでも、このことを非海賊的な方法で行う言い訳にはならなかった。
彼らはまもなく押し出した。トムが指揮を執り、ハックが船尾の、ジョーが船首のオールを漕いだ。トムは船の中央に立ち、眉をひそめ、腕を組み、低く、厳しいささやき声で命令を下した。
「風上へ、風を受けて進め!」
「アイアイ、サー!」
「そのまま、そのままー!」
「そのままです、サー!」
「少し風下へ!」
「了解、サー!」
少年たちがいかだを川の中央に向かって着々と単調に漕いでいく間、これらの命令が単なる「体裁」のためだけであり、特に何かを意味するものではないことは、間違いなく理解されていた。
「帆はどれを張っている?」
「コース、トップスル、そしてフライングジブ、サー。」
「ロイヤルを上げろ! マストの上へ、そこ、六人ほど――フォアトップマストスタンセールだ! 急げ!」
「アイアイ、サー!」
「メイントガンセールを広げろ! シートとブレースだ! さあ、諸君!」
「アイアイ、サー!」
「舵を風上へ――取舵一杯! 船が回頭するのに備えよ! 取舵、取舵! さあ、諸君! 気合を入れて! そのまー!」
「そのままです、サー!」

いかだは川の中央を過ぎ、少年たちは船首を正しい方向へ向け、そしてオールを漕ぐのをやめた。川は増水していなかったので、流れは二、三マイル程度だった。次の四十五分間、ほとんど言葉は交わされなかった。今、いかだは遠くの町の目の前を通り過ぎていた。二、三のきらめく光が、星を散りばめた水の漠然とした広大な広がりのはるか向こうで、平和に眠る町の場所を示していた。起こりつつある途方もない出来事に気づかずに。黒い復讐者は腕を組んだままじっと立ち、かつての喜びと後の苦しみの舞台に「最後の別れ」を告げ、そして「彼女」が今、荒々しい海に乗り出し、不敵な心で危険と死に立ち向かい、唇に厳しい笑みを浮かべて破滅へと向かう自分を見てくれたらと願っていた。彼の想像力にとって、ジャクソン島を村の視界から遠ざけるのはささいなことであり、彼は傷つき、そして満足した心で「最後の別れ」を告げた。他の海賊たちも最後の別れを告げていた。そして、彼らは皆あまりに長く見つめていたので、もう少しで潮流に流されて島の範囲外に出てしまうところだった。しかし、彼らは時間内に危険に気づき、それを回避するよう努めた。午前二時ごろ、いかだは島の上流二百ヤードの砂州に乗り上げ、彼らは荷物を陸揚げするまで行ったり来たりした。小さないかだの所持品の一部は古い帆で、これを茂みの一角に広げて食料を保護するためのテントにした。しかし、彼ら自身は天気の良い日には、無法者らしく野外で眠るつもりだった。
彼らは、森の陰鬱な深みから二十、三十歩入ったところにある大きな丸太の脇に火を起こし、それからフライパンでベーコンを焼いて夕食にし、持ってきたトウモロコシの「ポーン」のストックの半分を使い果たした。人里離れた未踏の無人島の原生林で、その野生的で自由な方法でごちそうを食べることは、輝かしい遊びのように思え、彼らは二度と文明社会には戻らないと言った。燃え盛る火が彼らの顔を照らし、その赤い輝きを、彼らの森の神殿の柱となった木の幹や、艶のある葉や花綱飾りのように垂れ下がる蔓の上に投げかけた。
最後のカリカリに焼かれたベーコンの一切れがなくなり、最後の割り当てのコーン・ポーンが食べ尽くされると、少年たちは満足感に満たされて草の上に寝転がった。もっと涼しい場所を見つけることもできたが、彼らは燃え盛るキャンプファイヤーというロマンチックな要素を自分たちから否定しようとはしなかった。

「最高じゃねえか?」とジョーが言った。
「たまんねえな!」とトムが言った。「もしあいつらが俺たちを見たら、何て言うだろうな?」
「何て言うかって? そりゃあ、ここに来たくて死にそうになるさ――なあ、ハッキー!」
「そう思うぜ」とハックルベリーは言った。「とにかく、俺は満足だ。これ以上いいもんはねえ。俺はいつも腹いっぱい食えねえし――それに、ここでは誰もやってきて、いちいちけちつけたり、いびったりしねえからな。」
「俺にぴったりの生活だ」とトムは言った。「朝起きる必要もねえし、学校に行く必要も、顔を洗う必要も、あんな馬鹿げたこと全部やる必要もねえ。わかるだろ、ジョー、海賊は陸にいるときは何もする必要がねえんだ。でも隠者は、かなり祈らなきゃならねえし、それに、どっちみち、あんなふうに一人ぼっちじゃ何の楽しみもねえんだ。」
「ああ、そうだね」とジョーは言った。「でも、そのことはあまり考えてなかったよ。やってみたら、海賊の方がずっといいな。」
「わかるだろ」とトムは言った。「近頃じゃ、昔みたいに隠者をありがたがる奴はいねえけど、海賊はいつも尊敬されるんだ。それに、隠者は見つけられる限り一番硬い場所で寝なきゃならねえし、頭に粗布と灰をかぶらなきゃならねえし、雨の中に立っていなきゃならねえし――」
「何で頭に粗布と灰をかぶるんだ?」とハックが尋ねた。
「知らねえ。でも、そうしなきゃいけねえんだ。隠者はいつもそうする。おまえが隠者だったら、そうしなきゃならねえ。」
「冗談じゃねえ、俺ならやらねえ」とハックは言った。
「じゃあ、どうするんだ?」
「知らねえ。でも、そんなことはやらねえ。」
「なんだよ、ハック、やらなきゃいけねえんだぞ。どうやってそれを避けるんだ?」
「そりゃあ、我慢しねえだけさ。逃げ出すよ。」
「逃げ出す! そりゃあ、おまえはとんだぐうたら隠者だな。恥さらしだぜ。」
血まみれの手は返事をせず、もっと良いことに精を出していた。彼は穂軸をくり抜き終え、今やそれに雑草の茎を取り付け、タバコを詰め、燃えさしを火種に押し当てて芳しい煙の雲を吹き出していた――彼は贅沢な満足感の真っ只中にいた。他の海賊たちはこの荘厳な悪習をうらやみ、近いうちにそれを習得しようと密かに決意した。やがてハックが言った。
「海賊は何をしなきゃならねえんだ?」
トムは言った。
「ああ、そりゃあ最高の時間を過ごすのさ――船を乗っ取って燃やし、金を手に入れて、幽霊とかがそれを見張ってるような島の恐ろしい場所に埋めるんだ。そして船の連中を皆殺しにする――板の上を歩かせるのさ。」
「それに、女たちを島に連れて行くんだ」とジョーが言った。「女たちは殺さない。」
「ああ」とトムは同意した。「女たちは殺さない――高潔すぎるからな。それに、女たちはいつも美しいんだ。」
「それに、最高の服を着てるんだぜ! いやいや! 金や銀やダイヤモンドだらけだ」とジョーは熱狂して言った。
「誰が?」とハックが言った。
「そりゃあ、海賊だよ。」
ハックは自分の服をしょんぼりと見下ろした。
「俺は海賊にふさわしい格好じゃねえみてえだな」と彼は、声に後悔の念を込めて言った。「でも、これしか持ってねえんだ。」
しかし、他の少年たちは、冒険を始めれば立派な服はすぐに手に入ると彼に言った。彼らは、裕福な海賊はきちんとした衣装で始めるのが慣例ではあるが、彼の貧しいぼろ服は手始めには十分だと理解させた。
次第に彼らの話は途切れ、小さな放浪者たちのまぶたに眠気が忍び寄り始めた。パイプが血まみれの手の指から落ち、彼は良心に呵責のない者、そして疲れた者の眠りについた。海の恐怖とスペイン近海の黒い復讐者は、眠りにつくのにもっと苦労した。彼らは心の中で祈りを唱えた。ひざまずいて声に出して唱えるよう強制する権威者が誰もいなかったので、横になったままだった。実のところ、彼らは全く祈らないことも考えたが、そこまで踏み込むのは恐ろしかった。天から突然、特別な雷が落ちてくるかもしれないと恐れたからだ。そしてすぐに彼らは眠りの間際に達し、そこに漂った――しかし今、侵入者が現れた。それは「退散」しようとしないものだった。良心だった。彼らは家出をしたことが悪いことだったのではないかという漠然とした恐怖を感じ始め、次に盗んだ肉のことを考え、そして本当の苦しみが始まった。彼らはお菓子やリンゴを何十回もくすねてきたことを良心に思い出させて、それを論破しようとした。しかし、良心はそのような薄っぺらなもっともらしさではなだめられなかった。結局、彼らには、お菓子を取るのは単なる「くすねる」ことであるのに対し、ベーコンやハムなどの貴重品を取るのは紛れもない「盗み」であり、聖書にはそれに対する戒めがあるという、動かしがたい事実を回避することはできないように思われた。そこで彼らは、この商売を続ける限り、二度と自分たちの海賊行為を盗みの罪で汚さないと心に誓った。すると良心は休戦を認め、これらの奇妙に矛盾した海賊たちは安らかに眠りに落ちた。
第十四章
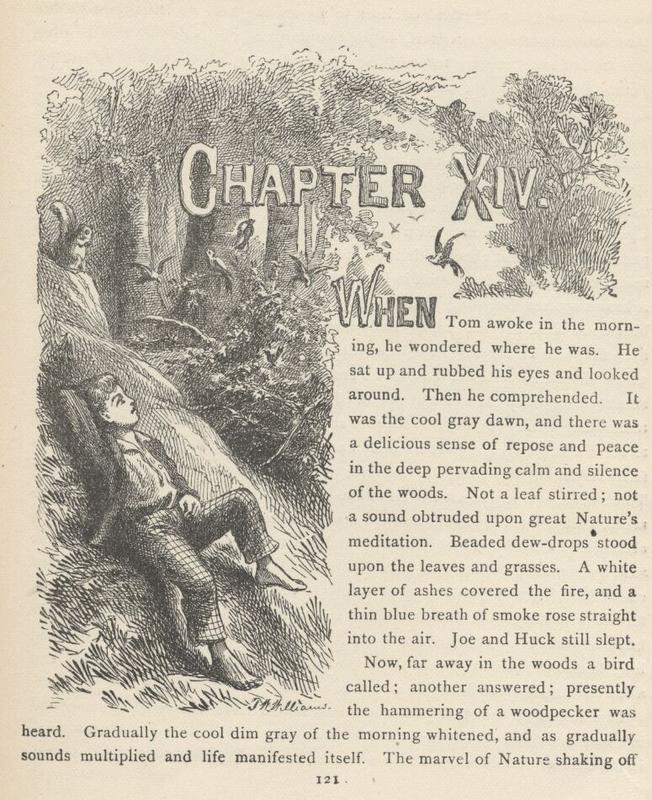
トムが朝目覚めたとき、彼は自分がどこにいるのか分からなかった。彼は起き上がって目をこすり、周りを見回した。そして理解した。それは涼しい灰色の夜明けで、深く広がる森の静寂と静けさの中に、心地よい休息と平和の感覚があった。一枚の葉も動かず、大自然の瞑想を邪魔する音は一つもなかった。露の玉が葉や草の上にきらめいていた。白い灰の層が火を覆い、細い青い煙の息吹がまっすぐに空へと昇っていた。ジョーとハックはまだ眠っていた。
やがて、遠くの森で一羽の鳥が鳴き、別の鳥がそれにこたえた。ほどなくして、キツツキが木を叩く音が聞こえてきた。ひんやりとした薄暗い朝の灰色が白んでいくにつれて、物音の数も次第に増え、生命の息吹が感じられるようになった。自然が眠りから覚めて活動を始めるという驚異が、物思いにふける少年の目の前で繰り広げられた。小さな青虫が、露に濡れた葉の上を這ってきた。時折、体の三分の二を空中に持ち上げてはあたりを「くんくん」と嗅ぎ、また進んでいく。トムに言わせれば、これは長さを測っているのだ。その虫が自らトムの方へ近づいてきたとき、彼は石のようにじっと動かなくなった。虫がこちらへ向かってくるか、あるいは別の場所へ行ってしまいそうになるたびに、彼の期待は高まったり沈んだりした。そしてとうとう、虫は苦悶するかのように体を弓なりにしてしばらく考え込んだ後、意を決したようにトムの脚の上に降り立ち、彼の体の上を旅し始めた。トムは心から嬉しくなった。なぜならそれは、新しい服が手に入るというしるしだったからだ――間違いなく、派手な海賊の制服が。今度は、どこからともなく蟻の行列が現れ、それぞれの仕事に取りかかった。一匹は、自分の五倍はあろうかという死んだ蜘蛛を腕に抱え、雄々しく奮闘しながら木の幹をまっすぐに登っていった。茶色い斑点のあるテントウムシが、目がくらむほど高い草の葉を登っていた。トムは身をかがめてそれに近づき、こう言った。「テントウムシ、テントウムシ、おうちへお帰り、おうちが火事だよ、子供たちがひとりぼっちだよ」。すると彼女は羽ばたいて、その様子を見に飛んでいった。少年は驚かなかった。この虫が火事の話を信じやすいことを昔から知っており、その純真さを利用したのは一度や二度ではなかったからだ。次にやってきたのはフンコロガシで、自分の球を力強く押していた。トムがその虫に触れると、脚を体にぴったりとくっつけて死んだふりをした。鳥たちは、この頃にはもう大騒ぎしていた。ネコマネドリ、すなわち北のモッキンバードが、トムの頭上の木に止まり、恍惚とした様子で近隣の鳥たちの鳴きまねをさえずった。それから、青い炎の閃光のように、けたたましい鳴き声のカケスが舞い降り、少年の手の届きそうな小枝に止まった。首をかしげ、飽くなき好奇心で見慣れぬ者たちをじっと見つめている。灰色のリスと、「キツネ」種の大きな仲間が走り寄り、時々立ち止まっては少年たちを観察し、けたたましく鳴いた。野生の生き物たちは、おそらく今まで人間を見たことがなく、怖がるべきかどうかさえ分からなかったのだろう。今や、すべての自然がすっかり目を覚まし、動き出していた。長い槍のような太陽の光が、遠近の鬱蒼とした木々の葉を突き抜けて降り注ぎ、数匹の蝶がひらひらと舞い込んできた。
トムは他の海賊たちを揺り起こした。彼らは皆、歓声を上げてがやがやと駆け出し、一、二分もすると服を脱ぎ捨て、白い砂州の浅く澄んだ水の中で、追いかけっこをしたり、折り重なって転げ回ったりしていた。雄大な水の広野の彼方で眠る小さな村への恋しさなど、彼らは微塵も感じていなかった。気まぐれな川の流れか、わずかな増水が彼らのいかだを運び去ってしまったが、そのことで彼らはむしろ満足した。いかだがなくなったことは、文明との間に架かる橋を焼き払うようなものだったからだ。

彼らはすっかり気分を爽快にし、心も晴れやかに、そして腹を空かせてキャンプに戻ってきた。そしてすぐにキャンプファイヤーを再び燃え上がらせた。ハックが近くに澄んだ冷たい水の湧き出る泉を見つけ、少年たちはオークやヒッコリーの広い葉でコップを作った。こんな森の魅力で甘みを増した水なら、コーヒーの代わりとして申し分ないと感じた。ジョーが朝食のためにベーコンをスライスしている間、トムとハックは少し待ってくれるように頼んだ。二人は川岸の有望そうなくぼみに行き、釣り糸を投げ入れた。すると、ほとんど間を置かずに釣果があった。ジョーがしびれを切らす間もなく、彼らは見事なバス数匹、サンパーチ二匹、そして小さなナマズ一匹を手に戻ってきた。大家族でも十分なほどの食料だ。彼らは魚をベーコンと一緒に炒めて、驚嘆した。これほど美味しい魚は今まで食べたことがなかったからだ。彼らは、淡水魚は釣ってから火にかけるのが早ければ早いほどうまいということを知らなかった。そして、野外での睡眠、野外での運動、水浴び、そしてたっぷりの空腹という調味料がどれほどの効果をもたらすかについても、ほとんど考えなかった。
朝食の後、彼らは木陰にごろごろと寝転がり、ハックが一服するのを待ってから、探検遠征のために森の中へ出かけていった。彼らは陽気に歩き回った。朽ちた丸太を乗り越え、絡み合った下草をかき分け、森の荘厳なる王たち、すなわち、その梢から地面までブドウの蔓という垂れ下がった王権の象徴をまとった巨木の間を通り抜けた。時折、草の絨毯が敷かれ、花々が宝石のようにちりばめられた心地よい片隅に行き当たった。

彼らは心を躍らせるものをたくさん見つけたが、驚くようなものは何もなかった。この島が長さ約三マイル、幅四分の一マイルであり、最も近い岸辺とは、幅わずか二百ヤードほどの狭い水路で隔てられているだけだということが分かった。彼らは一時間おきに泳いだので、キャンプに戻ったときには、もう昼下がりも半ばに差しかかっていた。あまりに空腹で、魚を釣るために立ち止まる気にもなれなかったが、冷たいハムで豪華な食事を済ませ、それから木陰に身を投げ出して語り合った。しかし、話はすぐに弾まなくなり、やがて途絶えた。森に漂う静寂と荘厳さ、そして孤独感が、少年たちの心に重くのしかかり始めた。彼らは物思いにふけり始めた。一種の漠然とした憧れのようなものが、彼らの心に忍び寄ってきた。それはやがて、ぼんやりとした形を取り始めた――芽生え始めたホームシックだった。「赤手」のフィンでさえ、我が家の戸口や空っぽの大きな樽のことを夢見ていた。しかし、彼らは皆、自分の弱さを恥じており、誰もその思いを口にする勇気はなかった。
しばらく前から、少年たちは遠くで奇妙な音がするのをぼんやりと意識していた。それは時々、時計の刻む音をはっきりとは認識しないまま聞いているような感覚に似ていた。しかし今、その神秘的な音はよりはっきりとし、認識せざるを得なくなった。少年たちははっとし、顔を見合わせ、それからそれぞれ聞き耳を立てる姿勢をとった。長く、深く、途切れることのない沈黙が続いた。そして、重く、くぐもった轟音が、遠くから漂ってきた。
「なんだろう!」とジョーが息を殺して叫んだ。
「さあな」とトムがささやいた。
「雷じゃねえぜ」とハックルベリーが畏敬の念のこもった声で言った。「だって、雷は――」
「静かに!」とトムが言った。「聞くんだ――しゃべるな。」
彼らは永遠とも思える時間を待った。そして再び、同じくぐもった轟音が、荘厳な静寂をかき乱した。
「見に行こうぜ。」
彼らは跳ね起き、町の方角の岸辺へと急いだ。岸辺の茂みをかき分け、水面を見渡した。小さな蒸気連絡船が、村から一マイルほど下流で、流れに任せて漂っていた。その広い甲板は、人でごった返しているように見えた。連絡船の周りには、たくさんの小舟が漕ぎ回ったり、流れに浮かんだりしていたが、少年たちには、その船に乗っている男たちが何をしているのか分からなかった。やがて、連絡船の側面から大きな白い煙の噴流がほとばしり、それが広がりながらゆっくりとした雲となって立ち上るにつれて、あの鈍い響きが再び聞き手のもとに届いた。
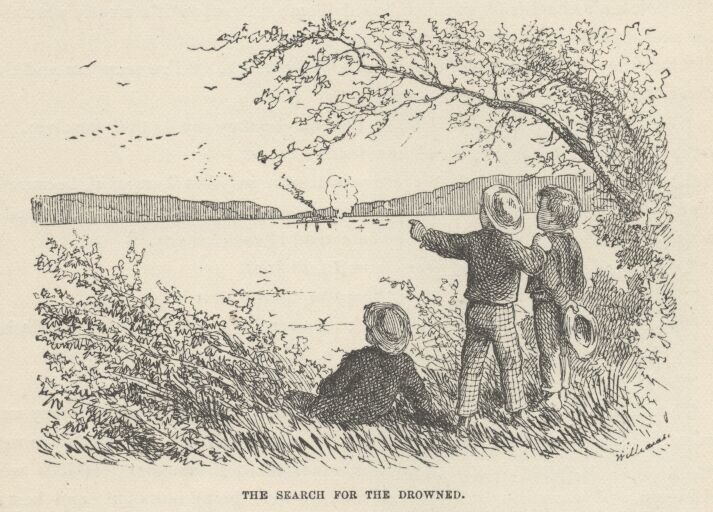
「今わかったぞ!」とトムが叫んだ。「誰か溺れたんだ!」
「それだ!」とハックが言った。「去年の夏、ビル・ターナーが溺れたときもそうだった。水面に向かって大砲を撃つと、そいつが水面に浮かび上がってくるんだ。そうそう、それからパンに水銀を入れて浮かべるんだ。そうすると、誰かが溺れている場所まで流れていって、そこで止まるんだ。」
「ああ、その話は聞いたことがある」とジョーが言った。「どうしてパンがそんなことをするんだろうな。」
「おお、パンがどうこうってわけじゃないんだ」とトムが言った。「たぶん、流す前にパンの上で唱える言葉が大事なんだと思うぜ。」
「でも、何も唱えちゃいねえぜ」とハックは言った。「おれは見たことあるけど、何もしてなかった。」
「うーん、そりゃおかしいな」とトムは言った。「でも、たぶん心の中で唱えてるんだよ。もちろんそうさ。誰だってわかることだ。」
他の少年たちも、トムの言うことには一理あると同意した。なぜなら、呪文による指示も受けていない無知なパンのかたまりに、かくも重大な任務を遂行する際に、非常に知的に行動することなど期待できるはずもなかったからだ。
「ちくしょう、今あそこにいられたらなあ」とジョーが言った。
「おれもだ」とハックが言った。「誰なのか知るためなら、何だってやるぜ。」
少年たちは、なおも耳を澄まし、見守っていた。やがて、ある啓示的な考えがトムの脳裏をよぎり、彼は叫んだ。
「なあ、みんな、誰が溺れたか分かったぞ――おれたちだ!」
彼らは一瞬にして英雄になった気分だった。これは華々しい勝利だ。彼らは行方不明になり、悼まれ、彼らのために心は張り裂けんばかりになり、涙が流されているのだ。この哀れな失われた少年たちへの不親切な仕打ちを責める記憶が呼び起こされ、甲斐なき後悔と悔恨に人々は身を任せている。そして何よりも素晴らしいのは、亡くなった者たちが町中の噂の的となり、このまばゆいばかりの名声に関する限り、すべての少年たちの羨望の的となっていることだ。これは素晴らしい。結局のところ、海賊になる価値はあったのだ。
黄昏が迫るにつれて、連絡船はいつもの業務に戻り、小舟は姿を消した。海賊たちはキャンプに戻った。彼らは、自分たちの新たな偉大さと、自分たちが引き起こしている輝かしい騒動に対する虚栄心で有頂天になっていた。彼らは魚を捕り、夕食を作って食べ、それから村が自分たちのことをどう考え、どう話しているかを推測し始めた。そして、自分たちのせいで人々が苦悩している様子を想像して描いた絵は、彼らの視点から見れば、実に満足のいくものだった。しかし、夜の影が彼らを包み込むと、彼らは次第に口数が少なくなり、明らかに心がどこか別の場所をさまよっている様子で、火を見つめて座っていた。興奮は今や去り、トムとジョーは、この素晴らしい気晴らしを自分たちほどには楽しんでいないであろう、家にいる特定の人々のことを考えずにはいられなかった。不安がよぎり、彼らは悩み、不幸な気分になった。知らず知らずのうちに、一つ二つため息が漏れた。やがてジョーは、他の者たちが文明への帰還をどう思うか――今すぐではないが――について、おずおずと遠回しな「探り」を入れ始めた。
トムは嘲笑で彼を一蹴した! ハックはまだ態度を決めていなかったので、トムに同調した。動揺したジョーは慌てて「弁解」し、臆病なホームシックの汚点が自分の衣服にできるだけつかないように、その場を切り抜けられたことに安堵した。反乱は、ひとまず効果的に鎮圧された。

夜が更けるにつれて、ハックはうなずき始め、やがていびきをかき始めた。次にジョーが続いた。トムはしばらくの間、肘をついて身じろぎもせず、二人を熱心に見つめていた。やがて彼は慎重に膝立ちになり、草むらとキャンプファイヤーが投げかける揺らめく反射光の中を探し回った。彼は、シカモアの薄い白い樹皮の大きな半円筒をいくつか拾い上げて調べ、最終的に自分に合いそうな二つを選んだ。それから彼は火のそばにひざまずき、「赤い竜骨石」[訳注:赤鉄鉱のこと。チョークのように使われた]で、それぞれの樹皮に苦労して何かを書きつけた。一つは丸めて上着のポケットに入れ、もう一つはジョーの帽子の中に入れ、持ち主から少し離れた場所に置いた。そして彼はまた、帽子の中に、ほとんど計り知れない価値を持つ、いくつかの学童の宝物を入れた――チョークのかけら、ゴムボール、釣り針三つ、そして「本物の水晶玉」として知られる種類のビー玉一つなどである。それから彼は、聞き耳を立てられない距離まで来たと感じると、木々の間を忍び足で進み、まっすぐに砂州の方向へ猛然と走り出した。
第十五章
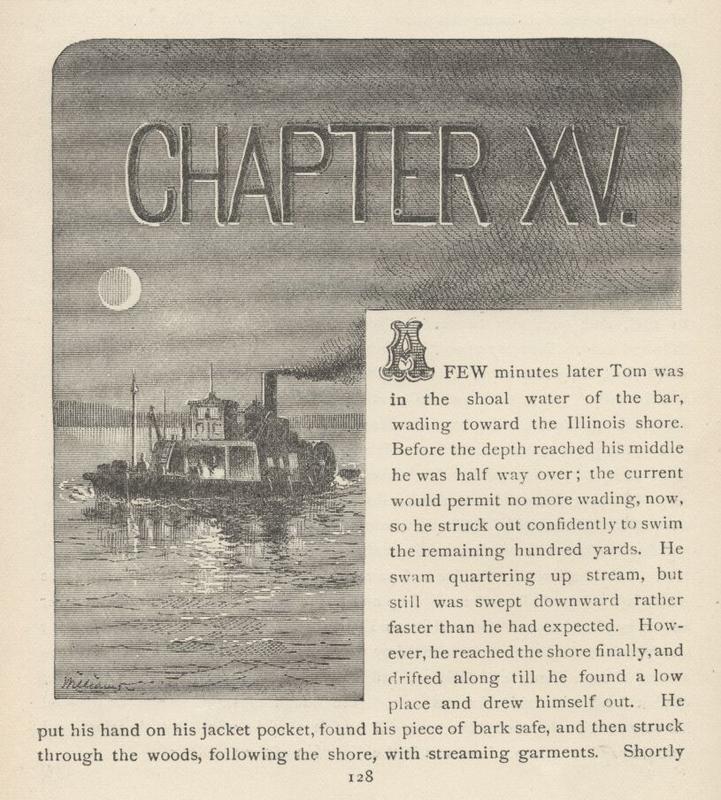
数分後、トムは砂州の浅瀬に入り、イリノイ州の岸に向かって歩いていた。水深が腰に達する前に、彼は半分ほど渡り終えていた。流れがこれ以上の歩行を許さなかったので、彼は自信を持って残りの百ヤードを泳ぎ始めた。彼は上流に向かって斜めに泳いだが、それでも予想以上に速く下流に流された。しかし、彼はついに岸にたどり着き、流れに沿って漂いながら低い場所を見つけて陸に上がった。彼は上着のポケットに手をやり、樹皮の切れ端が無事であることを確かめると、濡れた衣服のまま、岸に沿って森を突き進んだ。十時少し前、彼は村の向かい側の開けた場所に出て、木々と高い土手の影に連絡船が停泊しているのを見た。瞬く星々の下、すべてが静まり返っていた。彼は目を皿のようにして見張りながら土手を這い下り、水に滑り込み、三、四回水をかいて、船尾で「ヨール」[訳注:船に付属する小型ボート]の役目を果たしている小舟に乗り込んだ。彼は漕ぎ座の下に身を横たえ、息を切らしながら待った。
やがて、ひびの入った鐘が鳴り、声が「出航」を命じた。一、二分後、小舟の船首は連絡船の引き波に逆らって高く持ち上がり、航海が始まった。トムは成功を喜んだ。それがその夜の船の最終便であることを知っていたからだ。長い十二、三分後、外輪が止まり、トムは船外に滑り降りて薄闇の中を岸まで泳ぎ、万が一にも人に見つかる危険のないよう、五十ヤード下流に上陸した。
彼は人通りのない路地を飛ぶように走り、やがておばさんの家の裏の柵にたどり着いた。彼はそれを乗り越え、「エル」[訳注:母屋からL字型に突き出た増築部分]に近づき、居間の窓から中を覗いた。明かりが灯っていたからだ。そこにはポリーおばさん、シッド、メアリー、そしてジョー・ハーパーの母親が集まって話していた。彼らはベッドのそばにいて、ベッドは彼らとドアの間にあった。トムはドアに行き、そっと掛け金を上げ始めた。それから静かに押すと、ドアが少し開いた。彼はきしむたびに震えながらも慎重に押し続け、膝をついてなら通り抜けられると判断した。そこで彼は頭を突き入れ、用心深く中に入り始めた。
「どうしてロウソクがこんなに揺れるのかしら?」とポリーおばさんが言った。トムは急いだ。「あら、あのドアが開いているんだわ、きっと。ええ、もちろんよ。近頃は変なことばかり。行って閉めておいで、シッド。」
トムは間一髪でベッドの下に姿を消した。彼はしばらく横になって息を整え、それからおばさんの足にほとんど触れることができる場所まで這っていった。
「でも、私が言っていたように」とポリーおばさんは言った。「あの子は悪い子じゃなかったのよ、言ってみればね――ただ、いたずらっ子だっただけ。ただ陽気で、向こう見ずだっただけよ、わかるでしょう。子馬みたいに無責任なだけだったの。悪気は少しもなくて、あんなに心の優しい子は、今までいなかったわ」――そして彼女は泣き始めた。
「うちのジョーも全く同じでしたわ――いつも悪ふざけばかりで、ありとあらゆるいたずらをしましたが、あの子は本当に欲がなく、親切な子でした――ああ、なんてことでしょう、私がクリームを取ったからってあの子をひっぱたいたなんて。あれは酸っぱくなっていたから自分で捨てたのだと、一度も思い出さずに。そしてもうこの世であの子に二度と、二度と、二度と会えないなんて、かわいそうに虐げられた子!」そしてハーパー夫人は、心が張り裂けんばかりに泣きじゃくった。
「トムがあの世で幸せだといいけど」とシッドが言った。「でも、もし彼がいくつかの点で、もっと行儀が良かったら――」
「シッド!」トムは、見えなくてもおばさんの目の鋭い光を感じた。「トムがいなくなってしまった今、あの子の悪口は一言も許さないわ! 神様があの子の面倒を見てくださるから――あなたは心配しなくていいのよ! ああ、ハーパーさん、どうやってあの子を諦めたらいいのかわからない! どうやって諦めたらいいのか! あの子は、私の心をほとんど引き裂くほど苦しめたけれど、私にとって、あんなに慰めになる子はいなかったわ。」

「主は与え、主は奪いたもう――主の御名はほむべきかな! でも、とてもつらい――ああ、とてもつらい! ついこの前の土曜日に、うちのジョーが私の鼻先で爆竹を破裂させて、私はあの子を叩きのめしてしまいました。その時、こんなに早く別れが来るとは夢にも思いませんでした――ああ、もしやり直せるなら、あの子を抱きしめて、そのいたずらを祝福してあげたい。」
「ええ、ええ、ええ、あなたの気持ちはよくわかります、ハーパーさん、本当によくわかります。つい昨日の昼のこと、うちのトムが猫に痛み止め薬をたらふく飲ませて、私はあの生き物が家をめちゃくちゃにするかと思いました。そして神様、お許しください、私は指ぬきでトムの頭を叩いてしまいました、かわいそうな子、死んでしまったかわいそうな子。でも、あの子はもうすべての悩みから解放されたのです。そして、私が最後に聞いたあの子の言葉は、私を非難する言葉でした――」
しかし、この記憶は老婦人にはあまりにもつらく、彼女は完全に泣き崩れた。トムも今や鼻をすすっていた――そして、他の誰よりも自分自身を哀れんでいた。彼はメアリーが泣きながら、時々自分のために優しい言葉をかけてくれるのが聞こえた。彼はかつてないほど、自分自身に対して高貴な考えを抱き始めた。それでも、おばさんの悲しみに十分に心を動かされ、ベッドの下から飛び出して彼女を喜びで圧倒したいという強い衝動に駆られた――そして、その劇的な華々しさは彼の性分に強く訴えかけるものでもあったが、彼はそれをこらえ、じっと横たわっていた。
彼は聞き続け、断片的な情報から、最初は少年たちが泳いでいる間に溺れたのではないかと推測されていたこと、次に小さないかだがなくなっていることに気づいたこと、さらに、何人かの少年たちが、行方不明の少年たちが村に近いうちに「何か聞かせる」と約束していたと証言したこと、賢い大人たちが「あれこれをつなぎ合わせて」、少年たちがあのいかだで出かけ、やがて下流の次の町に現れるだろうと結論づけたことなどを理解した。しかし、昼近くになって、いかだが村から五、六マイル下流のミズーリ州の岸に打ち上げられているのが発見され――その時、希望は絶たれた。彼らは溺れたに違いない。そうでなければ、空腹に駆られて、もっと早くとは言わないまでも、日暮れまでには家に帰ってきたはずだ。遺体の捜索が実を結ばなかったのは、溺れたのが川の中央だったに違いないからだと信じられていた。なぜなら、少年たちは泳ぎが達者だったので、そうでなければ岸に逃げられたはずだからだ。この日は水曜の夜だった。もし日曜日まで遺体が見つからなければ、すべての希望は捨てられ、その朝に葬儀の説教が行われることになっていた。トムは身震いした。
ハーパー夫人は、すすり泣きながらおやすみなさいを言って、帰ろうとした。すると、二人の bereaved な女性は、互いの衝動に駆られて抱き合い、心ゆくまで慰めの涙を流し、そして別れた。ポリーおばさんは、シッドとメアリーにおやすみなさいを言うとき、いつになく優しかった。シッドは少し鼻をすすり、メアリーは心の底から泣きながら去っていった。
ポリーおばさんはひざまずき、トムのために祈った。その祈りはあまりにも感動的で、あまりにも心に訴えかけるものであり、その言葉と震える老いた声には計り知れない愛がこもっていたので、彼女が終わるずっと前から、トムは再び涙にくれていた。
彼女が寝床に入ってからも、トムは長い間じっとしていなければならなかった。彼女は時々、悲痛な叫び声を上げ、落ち着きなく身を投げ出し、寝返りを打っていたからだ。しかし、ついに彼女は静かになり、ただ眠りの中で少しうめくだけになった。今、少年はそっと抜け出し、ベッドのそばでゆっくりと立ち上がり、手でロウソクの光を覆い、彼女を見つめて立った。彼の心は彼女への哀れみでいっぱいだった。彼はシカモアの巻物を取り出し、ロウソクのそばに置いた。しかし、何かが心に浮かび、彼は考え込みながらためらった。彼の顔は、考えの幸福な解決策で輝いた。彼は急いで樹皮をポケットに入れた。それから彼は身をかがめて色あせた唇にキスをし、まっすぐに忍び足で去り、後ろ手にドアの掛け金をかけた。
彼は来た道を引き返し、渡し場に着いたが、そこには誰もいなかった。そして、大胆に船に乗り込んだ。船には見張りが一人いるだけで、その見張りはいつも寝床に入って石像のように眠っていることを知っていたからだ。彼は船尾の小舟を解き、それに滑り込み、すぐに慎重に上流へと漕ぎ出した。村から一マイルほど漕ぎ上ったところで、彼は斜めに横切り始め、力強く漕いだ。彼は向こう岸の上陸地点にうまく着いた。これは彼にとって慣れた作業だったからだ。彼は小舟を拿捕しようという気になった。それは船と見なされ、したがって海賊の正当な獲物であると主張できるからだ。しかし、徹底的な捜索が行われ、それが露見につながるかもしれないことを彼は知っていた。そこで彼は岸に上がり、森に入った。
彼は腰を下ろして長い休息を取り、その間、眠らないように自分を苦しめ、それから用心深く最後の道のりを下り始めた。夜はとっくに更けていた。彼が島の砂州の真横にたどり着いたときには、すっかり明るくなっていた。彼は太陽がすっかり昇り、その輝きで大河を金色に染めるまで再び休み、それから流れに飛び込んだ。少しして、彼はびしょ濡れでキャンプの入り口に立ち止まり、ジョーが言うのを聞いた。
「いや、トムは真の仲間だ、ハック。きっと戻ってくる。見捨てたりしないさ。そんなことをしたら海賊の恥になるってことを、あいつは知ってる。トムはそういうことをするほどプライドが低くない。何か企んでるんだ。いったい何だろうな?」
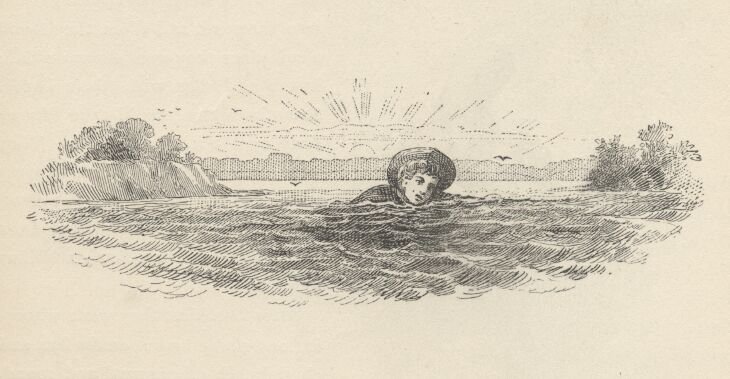
「まあ、どっちにしろ、この宝物は俺たちのものだよな?」
「ほとんどな、でもまだだ、ハック。この書き付けには、あいつが朝食までにここに戻ってこなかったら、おれたちのものだって書いてある。」
「その本人が、ただいま見参!」とトムは見事な劇的効果を狙って叫び、堂々とキャンプに足を踏み入れた。
ベーコンと魚の豪華な朝食がすぐに用意され、少年たちがそれにむしゃぶりついている間、トムは自分の冒険を(そして脚色を加えて)語り聞かせた。話が終わったとき、彼らは虚栄心と自慢に満ちた英雄の一団となっていた。それからトムは日陰の隅に隠れて正午まで眠り、他の海賊たちは魚釣りと探検の準備をした。
第十六章
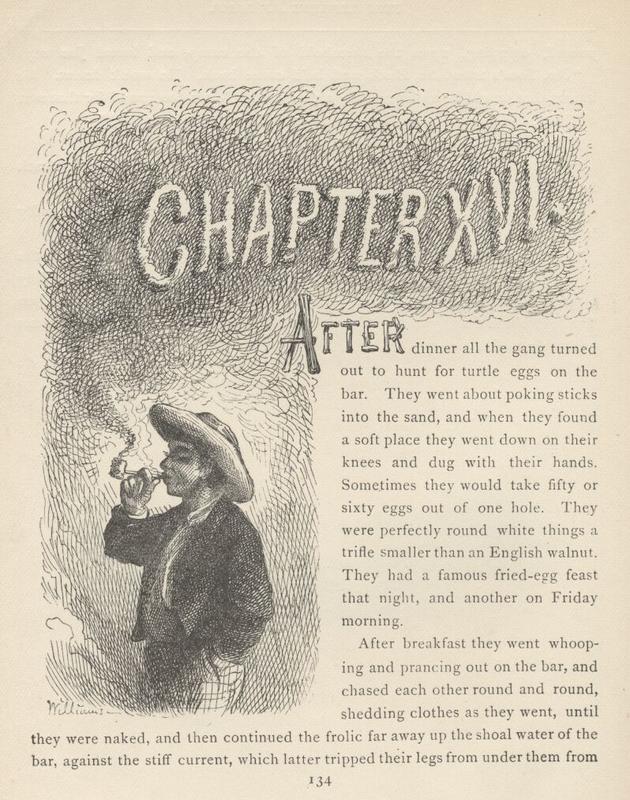
昼食後、一味は全員で砂州にカメの卵を探しに出かけた。彼らは砂に棒を突き刺して回り、柔らかい場所を見つけるとひざまずいて手で掘った。時には一つの穴から五十個か六十個の卵を取り出すこともあった。それは英国産のクルミより少し小さい、完全な球形の白いものだった。その夜、彼らは素晴らしい目玉焼きの饗宴を催し、金曜の朝にもう一度楽しんだ。

朝食後、彼らは奇声を上げながら砂州に飛び出し、服を脱ぎ捨てながら互いにぐるぐると追いかけっこをした。やがて裸になると、砂州の浅瀬をはるか遠くまでふざけ合いながら進んでいった。強い流れが時々彼らの足をすくい、それがまた一層の楽しみを増した。そして時々、彼らは一団となってかがみ込み、手のひらで互いの顔に水をかけ合った。息が詰まるような水しぶきを避けるために顔をそむけながら徐々に近づき、最後には掴み合ってもみ合い、一番強い者が相手を水中に沈めた。すると全員がもつれ合った白い手足となって水中に没し、息を吹き出し、水を吐き出し、笑い、息を切らしながら、一斉に水面に現れた。
すっかり疲れ果てると、彼らは走り出て、乾いた熱い砂の上に大の字になり、そこに横たわって砂をかぶり、やがてまた水に向かって駆け出し、最初の遊びをもう一度繰り返した。ついに、彼らの裸の肌が肌色の「タイツ」をかなりうまく表現していることに気づいた。そこで彼らは砂に輪を描き、サーカスを始めた――道化師は三人。誰もこの最も誇り高い役職を隣人に譲ろうとはしなかったからだ。
次に、彼らはビー玉を取り出し、「ナックルズ」や「リングトー」、「キープス」といった遊びを、その楽しみが飽き飽きするまで続けた。それからジョーとハックはもう一度泳いだが、トムは入ろうとしなかった。ズボンを蹴り飛ばしたときに、足首に巻いていたガラガラヘビのガラガラの紐を蹴り飛ばしてしまったことに気づいたからだ。彼は、この神秘的なお守りの加護なしに、どうしてこれほど長く足がつらなかったのか不思議に思った。彼はそれを見つけるまで二度と水に入らず、その頃には他の少年たちは疲れて休む準備ができていた。彼らは次第に離れ離れになり、「ふさぎ込み」、広い川の向こう、太陽の下でまどろむ村を恋しそうに眺め始めた。トムは、足の親指で砂に「ベッキー」と書いている自分に気づいた。彼はそれを掻き消し、自分の弱さに腹を立てた。しかし、それでも彼は再びそれを書いた。そうせずにはいられなかったのだ。彼はもう一度それを消し、それから他の少年たちをまとめ、彼らに加わることで誘惑から逃れた。
しかし、ジョーの元気はほとんど回復不能なほどに落ち込んでいた。彼はホームシックで、その惨めさに耐えがたいほどだった。涙はもう表面すれすれまで来ていた。ハックも憂鬱だった。トムも意気消沈していたが、それを見せまいと懸命に努力した。彼にはまだ話す準備のできていない秘密があったが、この反抗的な憂鬱がすぐに解消されなければ、それを持ち出さなければならないだろう。彼は、大いに陽気さを装って言った。
「なあ、この島には前にも海賊がいたに違いないぜ。もう一度探検しよう。どこかに宝を隠してるはずだ。金銀でいっぱいの腐った箱を見つけたら、どう思う――なあ?」
しかし、それはかすかな熱意を呼び起こしただけで、返事もなく消え去った。トムは他にも一つ二つ誘惑を試みたが、それらも失敗に終わった。気落ちする仕事だった。ジョーは棒で砂をつつきながら、非常に憂鬱な顔で座っていた。とうとう彼は言った。
「ああ、みんな、もうやめようぜ。家に帰りたい。すごく寂しいんだ。」
「おいおい、ジョー、そのうち気分も良くなるさ」とトムが言った。「ここにいる魚釣りのことを考えてみろよ。」
「魚釣りなんてどうでもいい。家に帰りたいんだ。」
「でも、ジョー、こんなにいい泳ぎ場はどこにもないぜ。」
「泳ぎなんて面白くない。入っちゃいけないって言う人がいないと、なんだかどうでもいいみたいだ。おれは家に帰るつもりだ。」
「ああ、ばかばかしい! 赤ん坊め! おふくろに会いたいんだろう、たぶん。」
「そうさ、おふくろに会いたいよ――おまえだっておふくろがいればそう思うさ。おれはおまえより赤ん坊じゃない」そしてジョーは少し鼻をすすった。
「じゃあ、泣き虫は母親のところに帰してやろうぜ、なあ、ハック? かわいそうに――お母さんに会いたいのかな? それならそうしてあげよう。おまえはここが好きなんだろう、ハック? おれたちは残ろうぜ、なあ?」
ハックは、「う、うん」と、気乗りしない様子で言った。
「一生おまえとは口をきかないからな」とジョーは立ち上がりながら言った。「もういい!」そして彼は不機嫌そうに立ち去り、服を着始めた。
「誰が気にするもんか!」とトムが言った。「誰も頼んでないさ。家に帰って笑われろ。ああ、おまえは立派な海賊だよ。ハックとおれは泣き虫じゃない。おれたちは残る、なあ、ハック? 行きたきゃ行かせろよ。たぶん、あいつがいなくてもやっていけるさ。」
しかし、トムはそれでも落ち着かず、ジョーがむっつりと服を着続けるのを見て不安になった。そして、ハックがジョーの準備をうらやましそうに見つめ、不吉な沈黙を守っているのを見るのも不快だった。やがて、別れの言葉もなく、ジョーはイリノイ州の岸に向かって歩き始めた。トムの心は沈み始めた。彼はハックに目をやった。ハックはその視線に耐えられず、目を伏せた。それから彼は言った。
「おれも行きたい、トム。どっちみち寂しくなってきたし、これからはもっとひどくなるだろう。おれたちも行こうぜ、トム。」
「いやだ! おまえたちが行きたいなら行けばいい。おれは残るつもりだ。」
「トム、おれは行った方がいい。」
「じゃあ行けよ――誰が止めてるんだ。」
ハックは散らばった服を拾い始めた。彼は言った。
「トム、おまえも来てくれたらなあ。よく考えてくれよ。岸に着いたら待ってるから。」
「ああ、とんでもなく長く待つことになるだろうな、それだけだ。」
ハックは悲しそうに立ち去り、トムは彼を見送りながら、プライドを捨てて一緒に行きたいという強い欲求が心を引っ張るのを感じていた。彼は少年たちが立ち止まることを願ったが、彼らはなおもゆっくりと歩みを進めていった。トムは、急にとても寂しく静かになったことに気づいた。彼はプライドと最後の闘いをし、それから仲間たちの後を追いかけ、叫んだ。
「待って! 待って! 話したいことがあるんだ!」
彼らはやがて立ち止まり、振り返った。彼らのいる場所に着くと、トムは秘密を明かし始め、彼らは不機嫌そうに聞いていたが、やがて彼が目指している「要点」が分かると、歓声の雄叫びを上げ、「素晴らしい!」と言い、最初に話してくれていたら、出発しなかったのにと言った。彼はもっともらしい言い訳をしたが、本当の理由は、その秘密でさえも彼らを長く引き留めておくことはできないだろうという恐れがあったため、最後の誘惑としてとっておくつもりだったのだ。
少年たちは陽気に引き返し、意欲的にスポーツに興じ、トムの途方もない計画について絶えずおしゃべりをし、その天才的な発想に感心した。卵と魚の美味しい夕食の後、トムは今度はタバコを習いたいと言った。ジョーはその考えに飛びつき、自分も試してみたいと言った。そこでハックはパイプを作り、タバコを詰めた。この初心者たちは、ブドウの蔓で作った葉巻以外は吸ったことがなく、それは舌を「刺す」し、いずれにせよ男らしいとは見なされていなかった。
さて、彼らは肘をついて寝そべり、おずおずと、そして自信なさげに煙をふかし始めた。煙は不快な味がし、彼らは少しむせたが、トムは言った。
「なんだ、こんなに簡単なのか! これが全部だと知っていたら、とっくに習ってたのに。」
「おれもだよ」とジョーが言った。「なんてことないな。」
「そうさ、何度も人がタバコを吸っているのを見て、ああ、おれもできたらなあ、なんて思ったけど、できるとは思わなかったよ」とトムは言った。
「おれも全く同じだ、なあ、ハック? おれがそんな風に話しているのを聞いたことがあるだろ――なあ、ハック? 聞いてないって言うならハックに任せるぜ。」
「ああ――何度もな」とハックは言った。
「まあ、おれもだよ」とトムは言った。「ああ、何百回も。一度、食肉処理場のそばで。覚えてるか、ハック? ボブ・タナーとジョニー・ミラー、それにジェフ・サッチャーがいたとき、おれがそう言ったんだ。覚えてるか、ハック、おれがそう言ったのを?」
「ああ、そうだな」とハックは言った。「あれは、おれが白いビー玉をなくした翌日だ。いや、その前の日だった。」
「ほら――言っただろ」とトムは言った。「ハックが覚えてる。」
「おれは一日中このパイプを吸っていられると思うぜ」とジョーは言った。「気分が悪くならない。」
「おれもだ」とトムは言った。「一日中吸っていられる。でも、ジェフ・サッチャーには無理だろうな。」
「ジェフ・サッチャー! なんだ、あいつは二服でひっくり返るぜ。一度やらせてみろよ。あいつならわかるさ!」
「きっとそうだろうな。それにジョニー・ミラー――ジョニー・ミラーが一度これに挑戦するところを見てみたいな。」
「ああ、本当にな!」とジョーは言った。「なんだ、ジョニー・ミラーがこれ以上できないなんて、ありえないぜ。ほんの一吸いであいつは参っちまう。」
「まったくだ、ジョー。なあ――みんなが今のおれたちを見られたらなあ。」
「おれもだよ。」
「なあ、みんな、このことは誰にも言うなよ。で、いつかあいつらがいるときに、おれがおまえのところに行って、『ジョー、パイプ持ってるか? 一服したいんだ』って言うんだ。そしたらおまえは、何でもないみたいに、さりげなく言うんだ、『ああ、いつものパイプともう一本あるけど、タバコがあんまり良くないんだ』って。そしたらおれが、『ああ、構わないさ、強けりゃいいんだ』って言う。それからおまえがパイプを出して、おれたちは平然と火をつける。そしたらあいつらの顔を見てみろよ!」
「ちくしょう、そりゃあ面白いぜ、トム! 今すぐやりたいくらいだ!」
「おれもだ! それで、海賊やってる間に覚えたんだって言ったら、あいつらも一緒に行けばよかったって思うだろうな?」
「ああ、思うもんか! 絶対に思うに決まってるさ!」
そうして話は続いた。しかし、やがて少し勢いがなくなり、途切れがちになった。沈黙の間隔が広がり、唾を吐く回数が驚くほど増えた。少年たちの頬の内側のあらゆる毛穴が噴水となり、舌の下の地下室から水を汲み出すのが間に合わず、浸水を防ぐのがやっとだった。あらゆる努力にもかかわらず、小さな氾濫が喉を下り、そのたびに突然の吐き気が続いた。二人とも今や顔色が悪く、惨めな様子だった。ジョーのパイプが力のない指から落ちた。トムのパイプも続いた。両方の噴水は猛烈に噴き出し、両方のポンプは力いっぱい水を汲み出していた。ジョーは弱々しく言った。
「ナイフをなくしちまった。探しに行った方がよさそうだ。」
トムは震える唇で、途切れ途切れに言った。
「手伝うよ。おまえはあっちの方へ行け、おれは泉の周りを探すから。いや、来なくていいよ、ハック――おれたちで見つけられるから。」

そこでハックは再び腰を下ろし、一時間待った。それから寂しくなり、仲間たちを探しに行った。彼らは森の中で遠く離れており、二人とも顔は真っ青で、ぐっすりと眠っていた。しかし、何かトラブルがあったとしても、それはもう解決したのだと、彼には分かった。
その夜の夕食では、彼らは口数が少なかった。謙虚な様子で、ハックが食後に自分のパイプを用意し、彼らの分も用意しようとすると、彼らはいいえと言い、あまり気分が良くない――昼食で食べた何かが体に合わなかったのだと言った。
真夜中頃、ジョーが目を覚まし、少年たちを呼んだ。空気には何かを予感させるような、重苦しい圧迫感があった。少年たちは身を寄せ合い、息苦しいほど蒸し暑い雰囲気にもかかわらず、火のそばの親密な交わりを求めた。彼らはじっと座り、緊張して待っていた。厳粛な静寂が続いた。火の光の向こうは、すべてが漆黒の闇に飲み込まれていた。やがて、震えるような光が差し込み、一瞬、木々の葉をぼんやりと照らし出しては消えた。しばらくして、もう少し強い光が来た。そしてまた一つ。それから、かすかなうめき声が森の枝をため息のようにつきぬけ、少年たちは頬に一瞬の息吹を感じ、夜の精霊が通り過ぎたのではないかという空想に身を震わせた。間があった。今、不気味な閃光が夜を昼に変え、彼らの足元に生えている小さな草の葉の一本一本を、はっきりと区別して見せた。そして、三つの青ざめ、驚いた顔も照らし出した。深い雷鳴が天を転がり落ち、遠くでくぐもった轟音となって消えていった。冷たい空気が一陣吹き抜け、すべての葉をざわめかせ、火の周りに灰の薄片を雪のようにまき散らした。もう一度、激しい閃光が森を照らし、その直後に、少年たちの頭上の梢を引き裂くかのような轟音が続いた。彼らはその後の深い闇の中で、恐怖に抱き合った。大粒の雨が数滴、葉の上にぱらぱらと落ちてきた。
「早く! みんな、テントへ行け!」とトムが叫んだ。

彼らは飛びのき、暗闇の中で木の根や蔓につまずきながら、それぞれ違う方向へ突進した。猛烈な突風が木々を吹き抜け、あらゆるものを歌わせながら進んでいった。目もくらむような閃光が次々と走り、耳をつんざくような雷鳴が轟いた。そして今や、どしゃぶりの雨が降り注ぎ、勢いを増す暴風がそれを地面に沿ってシートのように叩きつけた。少年たちは互いに叫び合ったが、うなる風と轟く雷鳴が彼らの声を完全にかき消した。しかし、一人、また一人と、ついに彼らはよろよろとテントの中にたどり着き、寒さと恐怖に震え、水浸しになりながら避難した。しかし、不幸の中に仲間がいることは、感謝すべきことのように思えた。他の騒音が許したとしても、古い帆が激しくばたついているため、彼らは話すことができなかった。嵐はますます激しくなり、やがて帆は留め具から引きちぎられ、突風に乗って飛び去った。少年たちは互いの手を取り合い、何度も転んだり打ったりしながら、川岸に立つ大きなオークの木の陰へと逃げ込んだ。今、戦いは最高潮に達していた。空に燃え盛る絶え間ない稲妻の炎の下で、地上のすべてが、影のない、くっきりとした輪郭で浮かび上がっていた。しなる木々、泡で白く波立つ川、飛び散る飛沫、流れる雲の切れ間と斜めに降る雨のベールを通して垣間見える、対岸の高い崖のぼんやりとした輪郭。時折、巨大な木が戦いに敗れ、若い木々をなぎ倒しながら轟音とともに倒れた。そして、絶え間ない雷鳴は今や、耳をつんざくような爆発的な音となって、鋭く、鋭く、言葉にできないほど恐ろしかった。嵐は、島を粉々に引き裂き、焼き尽くし、梢まで水浸しにし、吹き飛ばし、そこにいるすべての生き物の耳を聞こえなくさせるかのような、比類なき一撃で頂点に達した。家なき若い頭が外にいるには、荒れ狂う夜だった。
しかし、ついに戦いは終わり、軍勢はますます弱まる脅威とうなり声を残して退き、平和が再びその支配を取り戻した。少年たちは、かなり畏怖の念を抱きながらキャンプに戻った。しかし、そこにはまだ感謝すべきことがあると気づいた。なぜなら、彼らの寝床のシェルターであった大きなシカモアの木が、今や落雷で破壊されており、その惨事が起こったとき、彼らはその下にいなかったからだ。
キャンプのものはすべてびしょ濡れで、キャンプファイヤーも同様だった。彼らは、同世代の少年たちと同様に、不注意な若者であり、雨に対する備えを何もしていなかったからだ。これは落胆すべき事態だった。彼らはびしょ濡れで、冷え切っていたからだ。彼らは自分たちの苦境を雄弁に語った。しかし、やがて彼らは、火が、それが組まれていた大きな丸太の下(それが上向きに湾曲して地面から離れている場所)にかなり深く食い込んでいたため、手のひら幅ほどの部分が濡れずに済んだことを発見した。そこで彼らは、保護された丸太の下側から集めた細切れや樹皮を使って、辛抱強く働き、火を再び燃え上がらせることに成功した。それから彼らは大きな枯れ枝を山と積み、轟々と燃える炉を作り、再び心を躍らせた。彼らは茹でたハムを乾かしてごちそうを食べ、その後、眠るための乾いた場所がどこにもなかったので、朝まで火のそばに座り、真夜中の冒険を誇張し、美化した。
太陽が少年たちの上に忍び寄り始めると、眠気が彼らを襲い、彼らは砂州に出て横になって眠った。やがて彼らは日に焼かれて目を覚まし、うんざりしながら朝食の準備に取りかかった。食事の後、彼らは体がなまり、関節がこわばり、再び少しホームシックになった。トムはその兆候を見て、できる限り海賊たちを元気づけようとした。しかし、彼らはビー玉にも、サーカスにも、水泳にも、何にも興味を示さなかった。彼は彼らにあの重大な秘密を思い出させ、一筋の希望の光をもたらした。それが続く間に、彼は彼らを新しい工夫に興味を持たせた。それは、しばらく海賊をやめて、気分転換にインディアンになるというものだった。彼らはこの考えに惹かれた。そこで、彼らが裸になり、頭からかかとまで黒い泥で、まるでシマウマのように縞模様に塗られるのに、それほど時間はかからなかった――もちろん、全員が酋長だ――そして、彼らはイギリス人の入植地を攻撃するために森を駆け抜けた。
やがて彼らは三つの敵対的な部族に分かれ、恐ろしい雄叫びを上げて待ち伏せから互いに襲いかかり、何千人もの敵を殺し、頭の皮を剥いだ。それは血なまぐさい一日だった。その結果、それは非常に満足のいく一日となった。

彼らは夕食時に、空腹で幸せな気分でキャンプに集まった。しかし、ここで問題が生じた――敵対するインディアンは、まず和平を結ばなければ、もてなしのパンを共に分かち合うことはできない。そして、これは平和のパイプを吸わなければ、単純に不可能だった。彼らが聞いたことのある他の方法はなかった。二人の野蛮人は、海賊のままでいればよかったとほとんど思った。しかし、他に方法はなかった。そこで、彼らはできる限りの陽気さを見せてパイプを求め、それが回ってくると、正式な作法に従って一服した。
そして、見よ、彼らは野蛮人になってよかったと思った。何かを得たからだ。彼らは今や、なくしたナイフを探しに行かなくても、少しタバコを吸えることに気づいた。深刻に不快になるほど気分が悪くなることはなかった。彼らは、努力を怠ってこの大きな可能性を無駄にするようなことはしなかった。いや、彼らは夕食後、慎重に練習し、かなりの成功を収めた。そして、彼らは陽気な夜を過ごした。彼らは、六大部族の頭の皮を剥ぎ、皮を剥ぐよりも、この新しい習得を誇りに思い、幸せに感じていた。我々は、当面彼らに用はないので、彼らがタバコを吸い、おしゃべりをし、自慢するのに任せておくことにしよう。
第十七章
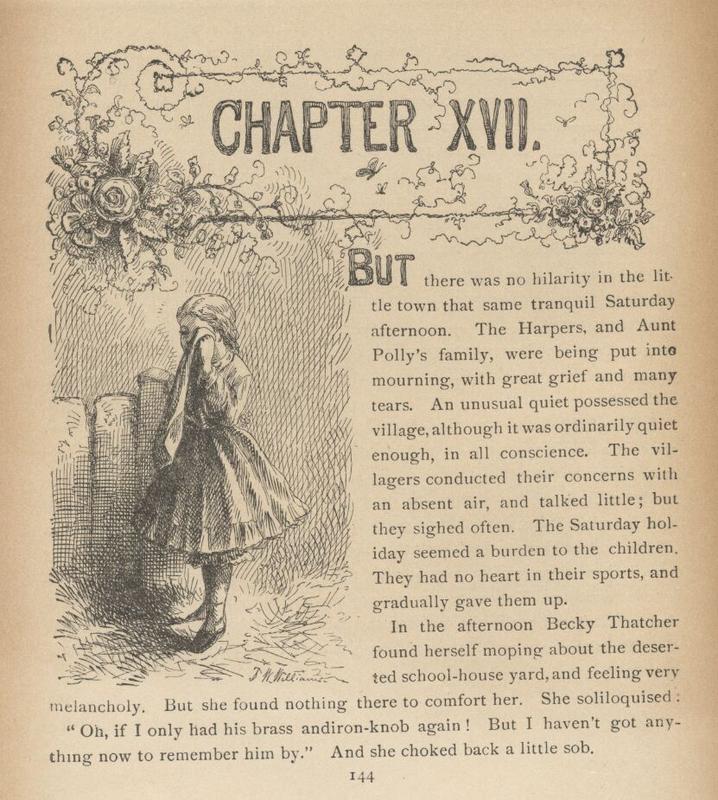
しかし、その同じ穏やかな土曜の午後、小さな町には陽気さはなかった。ハーパー家とポリーおばさんの家族は、深い悲しみと多くの涙とともに、喪に服していた。村には珍しい静けさが漂っていたが、良心に照らしてみれば、普段から十分に静かだった。村人たちは上の空で用事をこなし、口数も少なかったが、頻繁にため息をついた。土曜の休日は、子供たちにとって重荷のようだった。彼らは遊びに身が入らず、次第にそれをやめてしまった。
午後、ベッキー・サッチャーは、人気のない校庭をふらふらと歩き回り、非常に憂鬱な気分になっていた。しかし、彼女を慰めてくれるものはそこには何もなかった。彼女は独り言を言った。
「ああ、もしもう一度、真鍮の暖炉の飾り玉があったなら! でも、今は彼を思い出すものが何もないわ」そして彼女は小さなすすり泣きをこらえた。
やがて彼女は立ち止まり、独り言を言った。
「ちょうどここだったわ。ああ、もしやり直せるなら、あんなことは言わなかったのに――世界中の何をもらっても言わなかったわ。でも、彼はもう行ってしまった。もう二度と、二度と、二度と彼に会えないんだわ。」
この思いに彼女は打ちのめされ、涙を頬に伝わせながらさまよい去った。それから、トムとジョーの遊び仲間である少年少女のかなりの一団が通りかかり、柵越しに眺めながら、敬虔な口調で、最後に彼を見たときトムがどうしたこうした、ジョーがこれこれの些細なこと(今となっては容易にわかるように、恐ろしい予言をはらんでいた!)を言った、などと話していた。そして、各話し手は、亡くなった少年たちがその時立っていた正確な場所を指さし、それから次のようなことを付け加えた。「そして、僕はちょうどこんな風に立っていたんだ――今みたいに、君が彼だとして――こんなに近くにいたんだ――そして彼は、ちょうどこんな風に微笑んだんだ――そしたら、何かぞっとするようなものが全身を駆け巡ったんだ、わかるだろ――もちろん、それが何を意味するかなんて考えもしなかったけど、今ならわかるよ!」
それから、誰が生前の少年たちを最後に見たかについて論争が起こり、多くの者がその悲しい栄誉を主張し、証人によって多かれ少なかれ改ざんされた証拠を提示した。そして、最終的に誰が亡くなった者たちを最後に見たか、そして最後の言葉を交わしたかが決定されると、幸運な当事者たちはある種の神聖な重要性を帯び、他の全員から口をあんぐりと開けて見られ、羨望の的となった。他に誇るべきものを持たない哀れな一人の少年は、その記憶をかなり明白な誇りをもって言った。
「まあ、トム・ソーヤーには一度殴られたことがあるよ。」
しかし、その栄光への立候補は失敗に終わった。ほとんどの少年がそう言うことができたので、その栄誉はあまりにも安っぽくなってしまった。一団は、亡くなった英雄たちの思い出を畏敬の念のこもった声で語りながら、ぶらぶらと立ち去った。
翌朝、日曜学校の時間が終わると、鐘はいつものように鳴るのではなく、弔いの鐘を鳴らし始めた。それは非常に静かな安息日で、その悲しげな音は、自然に横たわる物思いにふける静けさと調和しているように思われた。村人たちが集まり始め、玄関でしばらく立ち止まっては、悲しい出来事についてささやき声で話し合った。しかし、家の中ではささやき声はなかった。女性たちが席に着くときの、葬儀のようなドレスの衣擦れの音だけが、そこの静寂を乱していた。小さな教会がこれほど満員になったのを、誰も思い出すことができなかった。やがて、待つ間があり、期待に満ちた沈黙が流れ、そしてポリーおばさんが、シッドとメアリーを連れて入り、彼らにハーパー家が続いた。全員が深い喪服に身を包んでおり、会衆全員、老牧師も同様に、敬虔に立ち上がり、喪主たちが最前列の席に着くまで立っていた。再び、時折くぐもったすすり泣きで破られる、心を通わせるような沈黙があり、それから牧師は両手を広げて祈った。感動的な賛美歌が歌われ、それに続いて聖句が読まれた。「わたしは、よみがえりであり、命である。」
儀式が進むにつれ、牧師は行方知れずとなった少年たちの美点や人好きのする振る舞い、そして類い稀なる将来性をありありと描き出してみせた。そこにいた誰もが、その言葉に思い当たる節があると感じ、これまで頑なにそうした美点から目を背け、哀れな少年たちの欠点や粗ばかりを執拗に見てきたことを思い出しては、胸に痛みを覚えた。牧師はまた、今は亡き少年たちの人生における感動的な出来事をいくつも語り、彼らの優しく、寛大な人柄を浮き彫りにした。人々は今や、それらの逸話がいかに気高く美しいものであったかを容易に理解し、そして、当時はそれが牛革の鞭で打たれて然るべき極悪非道ないたずらにしか見えなかったことを、悲しみと共に思い出すのであった。哀れを誘う話が進むにつれて会衆はますます心を動かされ、ついには全員がこらえきれずに泣き崩れ、悲嘆にくれる遺族と共に苦悶のすすり泣きの合唱に加わった。説教壇の牧師自身も感情に負け、涙を流していた。
その時、階上の観覧席でがさりと音がしたが、誰も気づかなかった。一瞬の後、教会の扉がきしんだ。牧師がハンカチの上から涙に濡れた目を上げると、そのまま釘付けになった。一人、また一人と牧師の視線を追い、やがてほとんど一斉に、会衆は立ち上がって呆然と見つめた。そこへ、死んだはずの三人の少年が通路を行進してくるではないか。トムを先頭に、ジョーが続き、そしてハックが、みすぼらしいぼろを垂らした姿で、気まずそうに最後尾からこそこそとついてくる。彼らは使われていない観覧席に隠れて、自分たちの葬式の説教を聞いていたのだ。
ポリーおばさん、メアリー、そしてハーパー夫妻は、生還した我が子たちに飛びつき、むさぼるようにキスをしては感謝の言葉を口にした。一方、哀れなハックは当惑し、居心地悪そうに立っていた。どうすればいいのか、この多くの歓迎せざる視線からどこへ隠れればいいのか、さっぱりわからなかった。彼はためらい、こっそり立ち去ろうとしたが、トムが彼を捕まえて言った。
「ポリーおばさん、そりゃないよ。誰かがハックに会えて嬉しいって言ってやんなきゃ。」
「そうともさ。あたしが会えて嬉しいよ、この母親のいない可哀想な子!」そしてポリーおばさんがハックに注いだ愛情のこもった気遣いは、彼を以前にも増して居心地悪くさせる唯一のものであった。
突然、牧師が声を張り上げて叫んだ。「すべての恵みの源なる神をたたえよ――歌え! ――そして心を込めるのだ!」
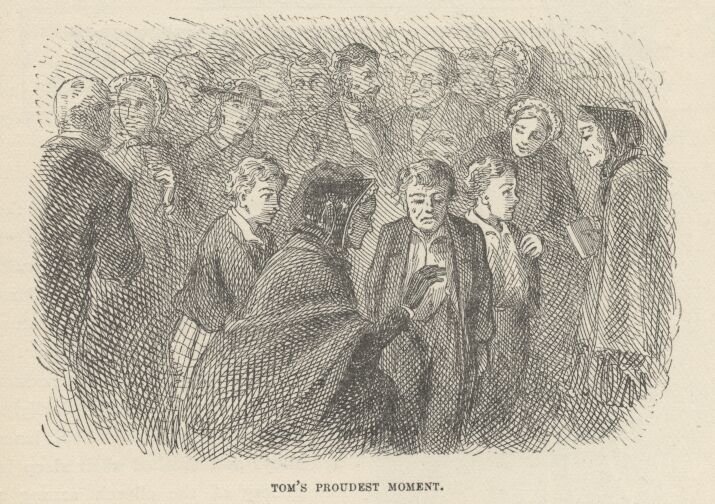
そして人々は歌った。讃美歌百番が勝利の鬨の声のように湧き起こり、その歌声が垂木を揺るがす中、海賊トム・ソーヤーは周りにいる羨望の眼差しを向ける少年たちを見回し、これこそが生涯で最も誇らしい瞬間だと心の中で認めたのであった。
一杯食わされた会衆がぞろぞろと外へ出ていく道々、彼らは口々に言った。もう一度あんな風に歌われる讃美歌百番が聞けるなら、また馬鹿にされても構わないくらいだと。
その日トムは、ポリーおばさんの気まぐれな気分に応じて、一年分にも相当するげんこつとキスを浴びた。そして、そのどちらが神への深い感謝と自分への愛情をより表しているのか、彼にはほとんどわからなかった。
第十八章

海賊仲間と共に帰還し、自分たちの葬式に出席する――それがトムの壮大な秘密の計画であった。彼らは土曜の夕暮れ時、丸太に乗ってミズーリ州側の岸に渡り、村から五、六マイル下流に上陸した。町の外れの森で夜明け近くまで眠り、それから裏道や路地をこっそり抜けて、教会の観覧席にある壊れた長椅子の混沌の中で眠りの続きをとったのである。
月曜の朝、朝食の席で、ポリーおばさんとメアリーはトムにとても優しく、彼の望むことには何でも気を配った。いつもより会話も多かった。その中でポリーおばさんが言った。
「まあね、あんたたちが楽しい時間を過ごすために、みんなを一週間近くも苦しませるなんて、大した冗談だったとは言わないよ、トム。でも、あたしがこんなに苦しむのを平気でいられるなんて、あんたがそんなに薄情だったとは悲しいことさ。葬式に出るために丸太で渡って来られたんなら、こっちへ渡ってきて、死んだんじゃなくて家出しただけだって、どうにかして知らせることもできたはずだよ。」
「そうよ、できたはずよ、トム」とメアリーが言った。「それに、もし思いついていたら、そうしたと私は思うわ。」
「そうかい、トム?」ポリーおばさんは顔を輝かせ、切なそうに言った。「ねえ、教えておくれ。もし思いついていたら、そうしてくれたかい?」
「ぼく――うーん、わかんないや。そしたら、何もかも台無しになっちゃうもの。」
「トム、あたしはあんたがそれくらいあたしを愛してくれていると期待していたんだがね」ポリーおばさんは少年を気まずくさせるような、悲しげな口調で言った。「たとえ実行しなかったとしても、それを考えるくらい気にかけてくれていたら、それだけでも意味があったんだよ。」
「まあ、おばさん、そんなに責めないで」メアリーがなだめた。「トムの軽はずみなやり方なのよ。いつも大急ぎで、何も考えないんだから。」
「だから余計にたちが悪いんだよ。シッドだったら考えたさ。それに、シッドだったら来て、実行もしただろうよ。トム、いつか手遅れになったとき、あんたは振り返って、ほんの少しのことで済んだのに、あたしのことをもう少し気にかけてやればよかったと後悔するだろうさ。」
「そんなことないよ、おばさん。ぼくがおばさんのこと、大事に思ってるって知ってるでしょ」とトムは言った。
「もっとそれらしい行動をしてくれたら、よくわかるんだがね。」
「今となっては、思いつけばよかったって思うよ」トムは悔悟の口調で言った。「でも、とにかくおばさんの夢は見たんだ。それだけでも、いいことじゃないか?」
「大したことじゃないね――猫だってそれくらいはするさ――でも、何もないよりはましだね。どんな夢を見たんだい?」
「ええと、水曜の夜の夢なんだけど、おばさんがそこのベッドのそばに座っていて、シッドが薪箱のそば、メアリーがその隣に座ってたんだ。」
「まあ、本当にそうしていたよ。いつもそうしてるからね。あんたの夢が、あたしたちのことでそれくらいの手間をかけてくれたのは嬉しいよ。」
「それから、ジョー・ハーパーのお母さんがここにいた夢も見た。」
「あら、本当にいたよ! ほかにも夢を見たのかい?」
「うん、いっぱい。でも、今はもうぼんやりしちゃって。」
「まあ、思い出してみてごらん――できないかい?」
「なんだか、風が――風が吹いて――その――」
「もっと頑張って、トム! 風が何かを吹いたんだよ。さあ!」
トムは額に指を押し当て、一分ほど考え込んだ後、言った。
「思い出した! 今、思い出したよ! ろうそくを吹き消しそうになったんだ!」
「なんてこと! 続けて、トム――続けておくれ!」

「それで、おばさんが言ったような気がするんだ、『あら、どうもあのドアが――』って。」
「続けて、トム!」
「ちょっと考えさせて――ほんの少しだけ。ああ、そうだ――おばさんは、ドアが開いてるみたいだって言ったんだ。」
「あたしがここに座っているのと同じくらい確かなことだよ! 本当にそう言ったよ! ねえ、メアリー! 続けて!」
「それで――それで――うーん、確かじゃないけど、おばさんがシッドに行かせて――それで――」
「それで? それで? あたしはシッドに何をさせたんだい、トム? 何をさせたんだい?」
「シッドに――シッドに――ああ、ドアを閉めさせたんだ。」
「まあ、なんてこと! こんなこと、生まれてこのかた聞いたことがないよ! 夢に意味がないなんて、二度と言わないでおくれ。一時間もしないうちに、セリニー・ハーパーにこのことを知らせてやらなきゃ。迷信だなんてくだらないことで、彼女がどう言い逃れるか見ものだよ。続けて、トム!」
「ああ、もう全部、昼間みたいにはっきりしてきたよ。次におばさんは、ぼくは悪い子なんかじゃなくて、ただいたずら好きで向こう見ずなだけで、責任感がないのは――ええと――子馬か何かみたいなもんだって言ったんだ。」
「その通りだよ! まあ、なんてこと! 続けて、トム!」
「それからおばさんは泣き始めた。」
「そうだよ。泣いたとも。一度だけじゃない。それで――」
「そしたらハーパーのおばさんも泣き始めて、ジョーも全く同じだって、自分が捨てたクリームを取ったからってあの子を鞭で打たなきゃよかったって言ったんだ――」
「トム! あんたには霊が乗り移っていたんだよ! 預言していたんだ――そういうことさ! なんてことだ、続けて、トム!」
「それからシッドが言ったんだ――あいつが言ったのは――」
「僕は何も言わなかったと思うけど」とシッドが言った。
「いいえ、あなたは言ったわ、シッド」とメアリーが言った。
「あんたたちは黙ってトムに続けさせな! あいつは何て言ったんだい、トム?」
「あいつは――確かこう言ったんだ。ぼくが行っちまった先で幸せになってればいいけど、時々もっといい子にしていればよかったのにって――」
「ほら、聞いたかい! あいつが言った、まさしくその言葉だよ!」
「するとおばさんが、ぴしゃりと黙らせた。」
「そうしたとも! そこに天使がいたに違いない。どこかに天使がいたんだよ!」
「それからハーパーのおばさんが、ジョーがかんしゃく玉で彼女を怖がらせた話をして、おばさんはピーターと鎮痛剤の話をした――」
「あたしが生きているのと同じくらい本当のことだよ!」
「それから、川をさらってぼくらを探す話や、日曜に葬式をする話で、いっぱい話したんだ。そしておばさんとハーパーのおばさんは抱き合って泣いて、彼女は帰って行った。」
「全くその通りに起こったよ! このあたしがここに座っているのと同じくらい確かに、その通りに起こったんだ。トム、あんたはまるで見てきたみたいに話すじゃないか! それで、それからどうしたんだい? 続けて、トム!」
「それから、おばさんがぼくのために祈ってくれていると思った――おばさんの姿が見えて、言う言葉が一つ残らず聞こえたんだ。そしておばさんはベッドに入った。ぼくはあまりに気の毒になって、スズカケノキの樹皮を一枚取って、『ぼくらは死んでない――ただ海賊になってるだけ』って書いて、ろうそくのそばのテーブルに置いたんだ。そうしたら、眠っているおばさんの顔があまりに優しそうに見えたから、ぼくは身をかがめて、唇にキスをしたんだと思う。」
「そうかい、トム、本当にかい! その一言で、あんたのしたこと全部許してあげるよ!」そして彼女は少年を、罪人の中の罪人のような気分にさせるほど、力いっぱい抱きしめた。
「とても親切なことだ、たとえそれがただの――夢だったとしてもね」シッドはかろうじて聞こえる声で独り言を言った。
「黙りな、シッド! 人間は夢の中でも、起きている時と同じことをするもんだよ。さあ、これは大きなマイラム種のりんごだよ、トム。あんたがもし見つかった時のために取っておいたんだ――さあ、学校へお行き。あたしたちすべての良き神にして父なるお方に感謝するよ。あんたが戻ってきてくれて。神は、神を信じ、その言葉を守る者たちに対しては、忍耐強く慈悲深いお方だ。もっとも、あたしにそんな資格がないのはよくわかっているけどね。でも、もし資格のある者だけが神の祝福を受け、困難な道を越えるためにその御手を差し伸べられるのなら、この世で微笑む者も、長い夜が来た時に神の安息に入る者も、ほとんどいなくなってしまうだろうからね。さあ、お行き、シッド、メアリー、トム――みんな行きなさい――もうずいぶん邪魔をされたからね。」
子供たちは学校へ向かい、老婦人はハーパー夫人を訪ね、トムの驚くべき夢物語で彼女の現実主義を打ち負かすために出かけていった。シッドは家を出る時、心に浮かんだ考えを口に出さないだけの分別は持ち合わせていた。その考えとはこうだ。「ずいぶん薄っぺらいな――あんなに長い夢で、間違いが一つもないなんて!」
今やトムは、なんと英雄になったことだろう! 彼はスキップしたり跳ね回ったりはせず、世間の目が自分に注がれていると感じる海賊にふさわしく、威厳のある堂々とした足取りで歩いた。そして実際、目は注がれていた。彼は通り過ぎる人々の視線や言葉に気づかないふりをしようとしたが、それらは彼にとって何よりの糧であった。自分より年下の少年たちが彼のかかとに群がり、まるで彼が行列の先頭の鼓手か、町にやってきた猛獣使いの象であるかのように、彼と一緒にいること、彼に認められることを誇りに思った。同い年の少年たちは、彼がどこかへ行っていたことなど知らないふりをしたが、それでも嫉妬に身を焦がしていた。彼らは、トムのあの浅黒い日焼けした肌と、輝かしい名声のためなら何でも差し出しただろう。そしてトムは、サーカスと引き換えにだって、そのどちらも手放さなかっただろう。

学校では、子供たちがトムとジョーを大いにもてはやし、その目から雄弁な賞賛の言葉を送ったため、二人の英雄が鼻持ちならない「天狗」になるのに、そう時間はかからなかった。彼らは渇望する聴衆に自分たちの冒険を語り始めた――だが、それは始まりに過ぎなかった。彼らのような想像力があれば、話の種が尽きることはまずない。そしてついに、二人がパイプを取り出して悠然と煙をふかし始めると、栄光はまさに頂点に達した。
トムは、もうベッキー・サッチャーがいなくても平気だと決心した。栄光だけで十分だ。栄光のために生きよう。今や自分は有名人なのだから、彼女も「仲直り」したいと思うかもしれない。まあ、させておけばいい――自分だって他の誰かさんのように、平然としていられることを見せてやろう。やがて彼女がやってきた。トムは彼女が見えないふりをした。彼はその場を離れ、少年少女のグループに加わって話し始めた。すぐに彼は、ベッキーが顔を紅潮させ、目を輝かせながら、陽気にいったりきたりしているのに気づいた。同級生を追いかけるのに夢中なふりをし、捕まえるたびに笑い声をあげていた。だがトムは、彼女がいつも自分の近くで捕まえ、そのたびに意識的な視線をこちらに向けているようにも見えたことに気づいていた。それは彼の内なる悪意に満ちた虚栄心をすべて満たした。そして、それが彼を勝ち取るどころか、かえって彼を「つけあがらせ」、彼女が近くにいることに気づいている素振りを見せまいと、ますます躍起にさせた。やがて彼女はふざけるのをやめ、ためらいがちに歩き回り、一度か二度ため息をついては、トムの方をこっそりと、そして物欲しげにちらりと見た。その時彼女は、今やトムが誰よりもエイミー・ローレンスと親しげに話していることに気づいた。彼女は鋭い痛みを感じ、たちまち落ち着かなくなり、不安になった。立ち去ろうとしたが、足は言うことを聞かず、かえってそのグループの方へ彼女を運んでしまった。彼女はトムのほとんど肘が触れるほどの場所にいた少女に、見せかけの快活さで言った。
「あら、メアリー・オースティン! 悪い子ね、どうして日曜学校に来なかったの?」
「来たわよ――見なかった?」
「え、うそ! 来たの? どこに座ってたの?」
「ピーターズ先生のクラスよ、いつもいるところ。あなたのことは見たわ。」
「そう? あら、おかしいわね、見なかったなんて。ピクニックのこと、話したかったのに。」
「まあ、素敵ね。誰が開いてくれるの?」
「ママがやらせてくれることになったの。」
「まあ、すごい! 私も行かせてもらえるといいな。」
「ええ、大丈夫よ。ピクニックは私のためのものだもの。私が来てほしい人は誰でも呼んでいいのよ。あなたにも来てほしいわ。」
「なんて素敵なの。いつやるの?」
「そのうちね。たぶん夏休みごろかしら。」
「まあ、なんて楽しいんでしょう! 女の子も男の子もみんな呼ぶの?」
「ええ、私と友達の人はみんな――あるいは友達になりたい人もね」。そして彼女はトムの方をこっそりとちらりと見たが、彼はエイミー・ローレンスと、島のひどい嵐の話や、いかに稲妻が「ぼくが三フィートも離れていないところに立っている間に」巨大なスズカケノキを「粉々に」引き裂いたかについて、話し続けていた。
「あら、私も行っていい?」とグレース・ミラーが言った。
「ええ。」
「私も?」とサリー・ロジャースが言った。
「ええ。」
「私もいい? ジョーも?」とスージー・ハーパーが言った。
「ええ。」
そして、トムとエイミー以外のグループ全員が招待を請うまで、喜びの手を叩きながら、そのやり取りは続いた。それからトムは、まだ話しながら、冷ややかに背を向け、エイミーを連れて行ってしまった。ベッキーの唇は震え、目に涙が浮かんだ。彼女は無理に陽気に振る舞ってこれらの兆候を隠し、おしゃべりを続けたが、もはやピクニックから、そして他のすべてから、生命は失われていた。彼女はできるだけ早くその場を離れて身を隠し、彼女のような性別の者が言うところの「思いっきり泣く」をした。それから彼女は傷つけられたプライドを抱え、不機嫌に座っていたが、やがて鐘が鳴った。彼女ははっと起き上がり、目に復讐の色を浮かべ、編んだお下げを一つ振ると、自分は何をすべきかわかっていると言った。

休み時間、トムは意気揚々と自己満足に浸りながら、エイミーとのいちゃつきを続けた。そして、ベッキーを見つけてはその様を見せつけ、彼女の心を切り裂こうと、あたりをうろつき続けた。ついに彼は彼女を見つけたが、彼の気分の水銀柱は急降下した。彼女は校舎の裏の小さなベンチに、アルフレッド・テンプルと仲良く座って絵本を見ていた――そして二人はあまりに夢中で、本の上で頭を寄せ合っていたため、世界の他の何ものにも気づいていないようだった。嫉妬がトムの血管を真っ赤に燃え上がらせた。彼は、ベッキーが和解のために差し伸べた機会を投げ捨てた自分を憎み始めた。彼は自分を馬鹿だと罵り、思いつく限りの罵詈雑言を並べ立てた。彼は悔しさで泣きたかった。エイミーは、心が歌っていたので、歩きながら楽しそうにおしゃべりを続けたが、トムの舌はその機能を失っていた。彼はエイミーが何を言っているのか聞こえず、彼女が期待して言葉を切るたびに、彼はぎこちない同意の言葉をどもることしかできず、それも的外れであることがしばしばだった。彼は何度も何度も校舎の裏手へとうろつき、そこにある憎むべき光景で自分の眼球を焼き付けた。そうせずにはいられなかった。そして、彼がそう思っただけかもしれないが、ベッキー・サッチャーが自分がこの世に存在していることすら一度も疑っていないように見えたことが、彼を狂わせた。しかし、彼女は見ていたのだ。そして、自分が戦いに勝っていることも知っており、自分が苦しんだように彼が苦しむのを見て喜んでいた。

エイミーの楽しげなおしゃべりは耐え難いものになった。トムは、やらなければならないことがある、時間が迫っている、とほのめかした。しかし無駄だった――少女はさえずり続けた。トムは思った。「ああ、こいつめ、いつになったらこいつから解放されるんだ?」ついに彼はそれらの用事を片付けなければならなくなった――すると彼女は無邪気に、学校が終わる頃には「その辺にいる」わと言った。そして彼は急いで立ち去り、そのことで彼女を憎んだ。

「他のどんな男の子でも!」トムは歯ぎしりしながら思った。「町中のどんな男の子でもいい、だが、あの自分がおしゃれで貴族だと思っているセントルイスの気取り屋だけはごめんだ! ああ、いいだろうさ、お前がこの町を初めて見た日に、俺はお前をぶちのめしてやったんだ、旦那。またぶちのめしてやる! 外で捕まえるまで待ってろよ! ただ捕まえて――」
そして彼は、架空の少年を打ちのめす身振りをした――空中にパンチを繰り出し、蹴り、えぐり出した。「おお、やるのか、そうか? もう十分だって叫ぶのか? さあ、これで懲りたか!」そして、架空の鞭打ち刑は、彼の満足のいく形で終了した。
トムは昼に家へ逃げ帰った。彼の良心は、エイミーの感謝に満ちた幸福にもう耐えられず、彼の嫉妬は、もう一方の苦痛にこれ以上耐えられなかった。ベッキーはアルフレッドとの絵本鑑賞を再開したが、時間が経ってもトムが苦しむために現れないので、彼女の勝利は曇り始め、興味を失った。真面目さと上の空が続き、そして憂鬱になった。二、三度、足音に耳をそばだてたが、それは偽りの希望だった。トムは来なかった。ついに彼女は完全に惨めになり、やりすぎなければよかったと願った。哀れなアルフレッドが、どうしてかわからずに彼女を失いつつあるのを見て、「おお、これは愉快だ! これを見て!」と叫び続けると、彼女はついに我慢の限界に達し、「ああ、うるさくしないで! そんなもの興味ないわ!」と言って泣き崩れ、立ち上がって歩き去った。
アルフレッドは彼女のそばに駆け寄り、慰めようとしたが、彼女は言った。
「あっちへ行って、一人にしてちょうだい、お願いだから! あなたなんて大嫌い!」
そこで少年は立ち止まり、自分がいったい何をしたのだろうかと考えた――彼女は昼休み中ずっと絵を見ると言っていたのだから――そして彼女は泣きながら歩き去った。それからアルフレッドは、物思いにふけりながら、誰もいない校舎に入っていった。彼は屈辱を感じ、怒っていた。彼は容易に真相を推測した――あの少女は、トム・ソーヤーへの腹いせに、単に自分を利用しただけなのだ。この考えが浮かんだ時、彼のトムへの憎しみは少しも減らなかった。彼は、自分にあまり危険が及ばない方法で、あの少年を面倒に巻き込む方法はないものかと思った。トムの綴り字の教科書が彼の目に入った。これこそが彼の機会だった。彼はありがたく午後の授業のページを開き、インクをこぼした。

その瞬間、彼の後ろの窓から中を覗き込んでいたベッキーはその行為を目撃し、正体を明かさずに立ち去った。彼女は今、トムを見つけてそのことを告げるつもりで、家路についた。トムは感謝し、二人の間の問題は解決するだろう。しかし、家まで半ばも行かないうちに、彼女は心変わりした。ピクニックの話をしていた時のトムの仕打ちが、灼けるように蘇り、彼女を羞恥で満たした。彼女は、傷つけられた綴り字の教科書の件で彼が鞭打たれるのを放置し、おまけに、彼を永遠に憎むことを決意した。
第十九章
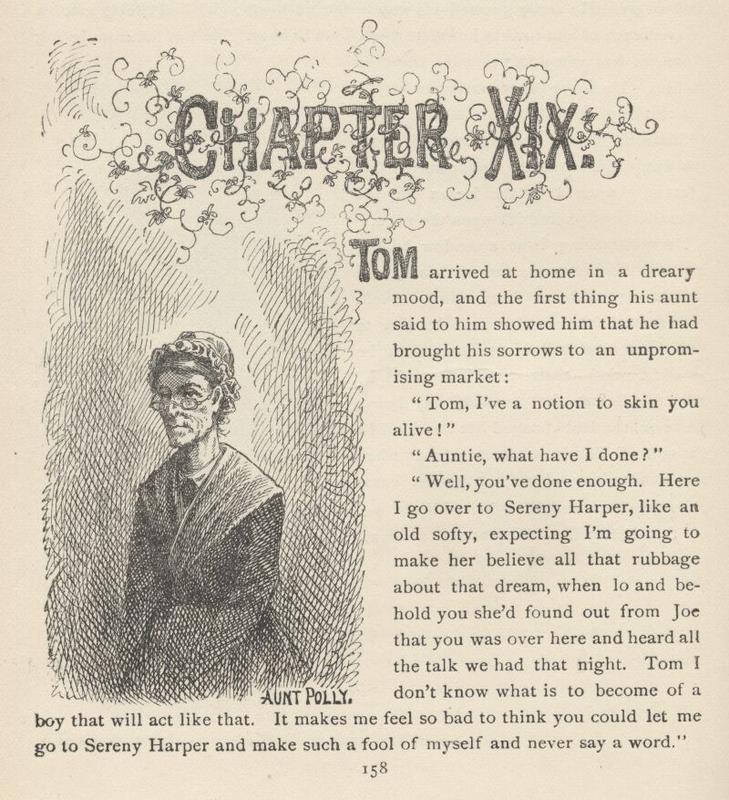
トムは憂鬱な気分で家に着いたが、おばさんが最初に彼に言った言葉で、自分の悩みを持ち込む先を間違えたことを悟った。
「トム、あんたの皮を生きながら剥いでやりたい気分だよ!」
「おばさん、ぼくが何をしたっていうの?」
「まあ、あんたは十分やったさ。あたしが、年寄りの甘ちゃんみたいにセリニー・ハーパーのところへ行って、あの夢についてのくだらない話を全部信じさせようと思っていたら、どうだい、彼女はジョーから、あんたがあの夜こっちに来て、あたしたちが話していたことを全部聞いていたってことを、とっくに聞き出していたんだよ。トム、そんなことをする子がどうなるのか、あたしにはわからない。あたしがセリニー・ハーパーのところへ行って、あんな馬鹿な真似をするのをあんたが黙って見ていたなんて思うと、本当に悲しくなるよ。」
これは物事の新たな側面だった。今朝の自分の抜け目のなさは、トムにとってはそれまで良い冗談で、非常に巧妙だと思われた。それが今では、ただ卑劣でみすぼらしく見えるだけだった。彼はうなだれ、一瞬何も言うことが思いつかなかった。それから彼は言った。
「おばさん、あんなことしなきゃよかったって思う――でも、考えが及ばなかったんだ。」
「ああ、坊や、あんたは決して考えない。自分のわがまま以外は何も考えないんだ。あたしたちの苦しみを笑うために、夜中にジャクソン島からわざわざここまで来ることは考えられるし、夢の嘘であたしを騙すことも考えられる。でも、あたしたちを気の毒に思って、悲しみから救ってやろうなんてことは、決して考えられないんだね。」
「おばさん、今となっては意地悪だったってわかるけど、意地悪するつもりはなかったんだ。本当だよ、正直に。それに、あの夜、おばさんたちを笑うためにここに来たんじゃないんだ。」
「じゃあ、何のために来たんだい?」
「ぼくらが溺れ死んでないから、心配しないでって言いに来たんだ。」
「トム、トム、あんたがそんな良い考えを一度でも持ったと信じられたら、あたしはこの世で一番感謝する人間になるだろうけど、あんたがそんなこと一度も考えなかったのは、あんた自身が知っている――そしてあたしも知っているよ、トム。」
「本当に、本当なんだ、おばさん――もしそうでなかったら、一歩も動けなくなってもいい。」
「ああ、トム、嘘をつかないでおくれ――やめておくれ。事態を百倍も悪くするだけだよ。」
「嘘じゃないよ、おばさん。本当のことなんだ。おばさんを悲しませたくなかった――ただそれだけのために来たんだ。」
「それを信じるためなら、全世界を差し出してもいい――そうすれば、たくさんの罪が覆い隠されるだろうからね、トム。あんたが家出して、あんなひどいことをしたことさえ、ほとんど嬉しく思うだろうよ。でも、筋が通らないじゃないか。だって、どうしてあたしに言わなかったんだい、坊や?」
「ええと、ほら、おばさんが葬式の話をし始めたら、ぼくらすっかり、教会に来て隠れるっていうアイデアで頭がいっぱいになっちゃって、どうしてもそれを台無しにする気になれなかったんだ。だから、樹皮をポケットに戻して、黙ってたんだ。」
「何の樹皮だい?」
「ぼくらが海賊になったって知らせるために書いた樹皮だよ。今となっては、ぼくがキスした時におばさんが目を覚ましてくれてたらなって思うよ――本当にそう思う。」
おばさんの顔の厳しい線が和らぎ、突然、その目に優しさが宿った。
「あたしにキスをしたのかい、トム?」
「うん、したよ。」
「本当にしたのかい、トム?」
「うん、したよ、おばさん――絶対に確かだよ。」
「どうしてあたしにキスしたんだい、トム?」
「だっておばさんのことが大好きだし、おばさんはそこでうめき声をあげていたし、ぼくはすごく気の毒だったから。」
その言葉は真実のように響いた。老婦人は声を震わせるのを隠せず、こう言った。
「もう一度キスしておくれ、トム! ――さあ、もう学校へお行き。これ以上あたしを煩わせないでおくれ。」
彼が去った瞬間、彼女は戸棚に駆け寄り、トムが海賊ごっこに着ていったジャケットの残骸を取り出した。そして、それを手に持ったまま立ち止まり、独り言を言った。
「いや、そんな勇気はない。かわいそうな子、きっと嘘をついたんだろう――でも、それはありがたい、ありがたい嘘だよ。そこからこんなにも慰めが得られたんだから。神様が――きっと神様はあの子を許してくださるだろう。だって、それを話すなんて、なんて心根の優しい子なんだろう。でも、それが嘘だと知りたくはない。見ないでおこう。」
彼女はジャケットをしまい、一分ほど物思いにふけって立っていた。二度、その服を再び取ろうと手を伸ばし、二度、思いとどまった。もう一度、彼女は思い切って、今度はこう考えて自分を奮い立たせた。「これは良い嘘だ――良い嘘だ――これで悲しんだりしないぞ」。そうして彼女はジャケットのポケットを探った。一瞬後、彼女は流れ落ちる涙を通してトムの樹皮の切れ端を読み、こう言っていた。「今ならあの子が百万の罪を犯したとしても、許してやれるよ!」

第二十章
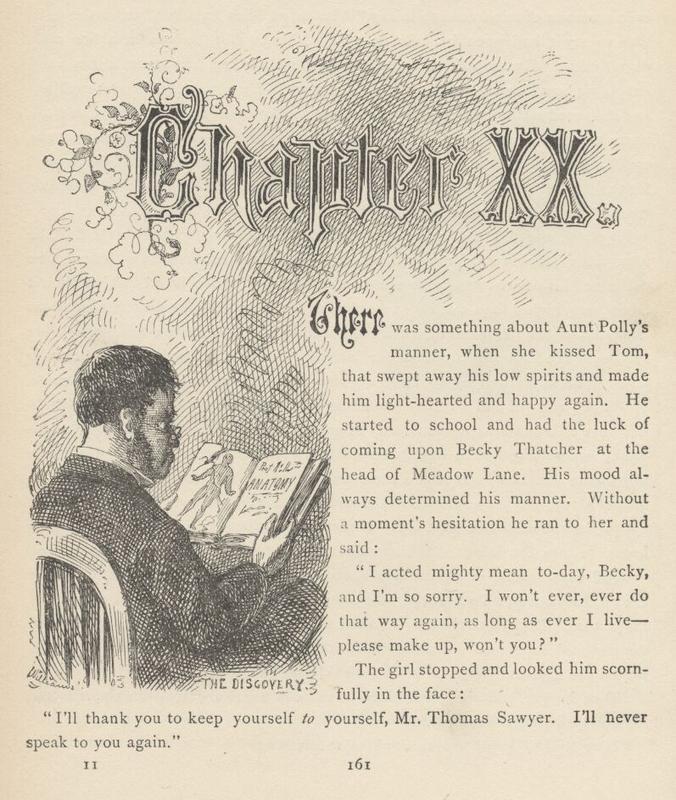
ポリーおばさんがトムにキスをした時の態度には、彼の沈んだ気分を一掃し、再び彼を陽気で幸福な気持ちにさせる何かがあった。彼は学校へ向かい、幸運にもメドー・レーンの入り口でベッキー・サッチャーに出くわした。彼の気分は常に彼の態度を決定した。一瞬のためらいもなく、彼は彼女に駆け寄り、言った。
「今日は本当にひどいことをしたよ、ベッキー。本当にごめん。もう二度と、生きている限り、あんなことはしないから――お願いだから仲直りしてくれないかい?」
少女は立ち止まり、軽蔑したように彼の顔を見つめた。
「ご自分のことだけになさったらどうですの、トーマス・ソーヤーさん。もう二度とあなたとは口をききませんわ。」
彼女はつんと頭をそらし、通り過ぎていった。トムはあまりに呆然として、「誰が気にするもんか、お利口さん」と言うべきタイミングを逃してしまった。だから彼は何も言わなかった。しかし、それでも彼は相当な怒りに燃えていた。彼は校庭をぶらぶらしながら、彼女が男の子だったらいいのに、そしてもし男の子だったらどんなに打ちのめしてやるかと想像した。やがて彼は彼女に出くわし、通り過ぎる際に辛辣な言葉を浴びせた。彼女も一つお返しをし、怒りの亀裂は完全なものとなった。ベッキーは、その燃えるような憤りの中で、傷つけられた綴り字の教科書の件でトムが鞭打たれるのを見るのが待ちきれず、学校が「始まる」のがもどかしいほどだった。もし彼女にアルフレッド・テンプルのことを暴露しようという未練が少しでも残っていたとしても、トムの侮辱的な一言がそれを完全に吹き飛ばしてしまっていた。
哀れな少女よ、彼女は自分がどれほど速く困難に近づいているかを知らなかった。校長のドビンズ先生は、満たされぬ野心を抱えたまま中年期に達していた。彼の切なる願いは医者になることであったが、貧困は彼が村の校長以上のものになることを許さなかった。毎日、彼は机から謎めいた本を取り出し、授業のない時間になるとそれに没頭した。彼はその本を鍵のかかる場所に保管していた。学校の悪ガキで、その本をちらりとでも見たいと渇望していない者はいなかったが、その機会は決して訪れなかった。少年少女は皆、その本の性質について持論を持っていたが、二つの説が一致することはなく、真相を突き止める術もなかった。さて、ベッキーがドアの近くに置かれた机のそばを通りかかった時、彼女は鍵が錠に刺さっていることに気づいた! それは貴重な瞬間だった。彼女は周りを見回し、自分が一人きりであることを見つけると、次の瞬間にはその本を手にしていた。表題――誰それ教授の解剖学――は彼女の心に何の情報ももたらさなかったので、彼女はページをめくり始めた。すぐに彼女は、見事に彫られ、彩色された口絵に行き当たった――全裸の人間の姿である。その瞬間、ページに影が落ち、トム・ソーヤーがドアから入ってきて、その絵をちらりと目にした。ベッキーは本を閉じようとひったくり、運悪くも絵のページを真ん中から半分引き裂いてしまった。彼女はその本を机に突き返し、鍵を回し、羞恥と悔しさでわっと泣き出した。
「トム・ソーヤー、あなたって本当に意地悪ね、こっそり人に近づいて、人が見ているものを見るなんて。」

「君が何か見てるなんて、どうしてわかるんだい?」
「恥を知るべきよ、トム・ソーヤー。どうせ私を言いつけるんでしょ。ああ、どうしよう、どうしよう! 鞭で打たれちゃうわ、学校で鞭で打たれたことなんてないのに。」
それから彼女は小さな足を踏み鳴らして言った。
「好きなだけ意地悪すればいいわ! 私、これから起こることがわかってるんだから。見てなさい、きっとわかるわ! 大嫌い、大嫌い、大嫌い!」――そして彼女は再びわっと泣き出し、家から飛び出していった。
トムは、この猛攻撃にやや狼狽して、じっと立っていた。やがて彼は独り言を言った。
「女の子ってのは、なんて奇妙な種類の馬鹿なんだろう! 学校で叩かれたことがないだと! ちぇっ! 叩かれるのがなんだってんだ! まったく女の子らしいや――あいつらはひ弱で臆病なんだ。まあ、もちろん、このちっぽけな馬鹿のことをドビンズのじじいに言いつけるつもりはないさ。だって、彼女に仕返しするには、そんな卑怯じゃない他の方法があるからな。でも、それがどうした? ドビンズのじじいは、誰が本を破ったか聞くだろう。誰も答えない。そしたら、いつものやり方をするんだ――まず一人に聞き、次に別の一人に聞く。そして、当の女の子のところに来れば、言わなくてもわかるんだ。女の子の顔はいつも白状するからな。あいつらには根性がないんだ。彼女は叩かれるだろう。まあ、ベッキー・サッチャーにとっては、ちょっとした窮地だな。だって、逃げ道はないんだから」トムはしばらくそのことを考え、そして付け加えた。「まあ、いいさ。彼女だって、ぼくが同じような窮地に陥るのを見たいだろうからな――せいぜい冷や汗をかくがいいさ!」
トムは外で騒いでいる生徒たちの群れに加わった。数分後、先生が到着し、学校が「始まった」。トムは自分の勉強に強い興味を感じなかった。女子生徒の側にこっそり目をやるたびに、ベッキーの顔が彼を悩ませた。あらゆることを考えると、彼は彼女を哀れみたくはなかったが、それでもそうせずにはいられなかった。本当に名に値するような高揚感は、どうしても湧いてこなかった。やがて、綴り字の教科書の発見があり、その後しばらくは、トムの心は完全に自分自身のことでいっぱいになった。ベッキーは苦悩の無気力から奮い立ち、その成り行きに大いに興味を示した。彼女は、トムが本にインクをこぼしたことを否定して、自分の窮地から抜け出せるとは思っていなかった。そして彼女は正しかった。否定は、トムにとって事態を悪化させるだけのように見えた。ベッキーは、それを喜ぶべきだと思い、喜んでいると信じようとしたが、確信が持てないことに気づいた。最悪の事態になった時、彼女は立ち上がってアルフレッド・テンプルのことを言いつけようという衝動に駆られたが、努力して自分を抑え、黙っていることにした――なぜなら、彼女は自分に言い聞かせたのだ、「彼はきっと私が絵を破ったことを話すわ。彼の命を救うためだって、一言も言わないわ!」と。
トムは鞭打ちを受け、席に戻ったが、全く意気消沈してはいなかった。というのも、彼は、何かのふざけ合いの中で、知らず知らずのうちに自分が綴り字の教科書にインクをこぼしたのかもしれないと思っていたからだ――彼は形式のために、そしてそれが慣習だったために否定し、主義からその否定を貫いたのだった。
丸一時間が過ぎ去り、先生は玉座でうなずき、空気は勉強のざわめきで眠気を誘った。やがて、ドビンズ先生は体をまっすぐにし、あくびをし、それから机の鍵を開け、本に手を伸ばしたが、それを取り出すか、そのままにしておくか決めかねているようだった。ほとんどの生徒は気だるそうに目を上げたが、その中には、彼の動きを熱心な目で見つめている二人がいた。ドビンズ先生はしばらくぼんやりと本を指でなぞっていたが、やがてそれを取り出し、椅子に腰を下ろして読み始めた! トムはベッキーに視線を送った。彼は、銃口を頭に向けられた、追いつめられ、なすすべもない兎が、彼女のような表情をするのを見たことがあった。即座に、彼は彼女との喧嘩を忘れた。早く――何かをしなければ! それも一瞬のうちに! しかし、まさにその緊急事態が彼の創意工夫を麻痺させた。そうだ! ――彼にひらめきがあった! 走って本をひったくり、ドアを飛び出して逃げるのだ。しかし、彼の決心はほんの一瞬揺らぎ、機会は失われた――先生が本を開いてしまったのだ。もしトムが、無駄にした機会をもう一度取り戻せたなら! 遅すぎた。もうベッキーを助ける術はない、と彼は言った。次の瞬間、先生は学校全体に向き直った。すべての目が彼の視線の下に沈んだ。その視線には、罪のない者でさえ恐怖に打ちのめす何かがあった。十を数える間、沈黙が続いた――先生は怒りを溜めていた。そして彼は言った。「この本を破ったのは誰だ?」
物音一つしなかった。ピンが落ちる音さえ聞こえただろう。静寂は続き、先生は罪のしるしを求めて、顔から顔へと探った。
「ベンジャミン・ロジャース、お前がこの本を破ったのか?」
否定。再び沈黙。
「ジョセフ・ハーパー、お前か?」
再び否定。このゆっくりとした拷問のような進行の下で、トムの不安はますます募っていった。先生は少年たちの列をじっと見つめ――しばらく考え、それから少女たちの方へ向き直った。
「エイミー・ローレンス?」
首を振る。
「グレイシー・ミラー?」
同じ仕草。
「スーザン・ハーパー、お前がやったのか?」
再び否定。次の少女はベッキー・サッチャーだった。トムは興奮と状況の絶望感で、頭のてっぺんから足の先まで震えていた。
「レベッカ・サッチャー」[トムは彼女の顔をちらりと見た――恐怖で真っ白だった]――「お前が破ったのか――いや、私の顔を見なさい」[彼女の手が懇願するように上がった]――「お前がこの本を破ったのか?」
稲妻のように一つの考えがトムの脳を駆け巡った。彼は跳ね起きて叫んだ――「僕がやりました!」

学校中が、この信じがたい愚行に当惑して見つめた。トムは一瞬立ち尽くし、バラバラになった思考力をかき集めた。そして罰を受けるために前に進み出た時、哀れなベッキーの瞳から彼に注がれた驚き、感謝、そして崇拝の輝きは、百回の鞭打ちにも値する報酬のように思えた。自分自身の行為の気高さに鼓舞され、彼はドビンズ先生がかつて下した中でも最も無慈悲な鞭打ちを、叫び声一つ上げずに受けた。そしてまた、学校が終わった後二時間残るようにという命令の、さらなる残酷さも平然と受け入れた――というのも、彼は、自分の監禁が終わるまで外で誰が待っていてくれるか、そしてその退屈な時間を損失とも思わないであろうことを、知っていたからだ。
その夜、トムはアルフレッド・テンプルへの復讐を計画しながら床についた。というのも、ベッキーが恥と悔恨の念に駆られて、自分自身の裏切りも忘れずに、すべてを彼に話したからだ。しかし、復讐への渇望でさえ、やがてはより楽しい物思いに道を譲らねばならず、彼はついに、ベッキーの最後の言葉が夢うつつに耳に残る中、眠りに落ちた――
「トム、どうしてそんなに気高いことができるの!」
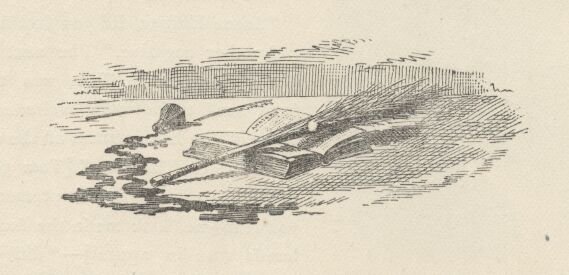
第二十一章
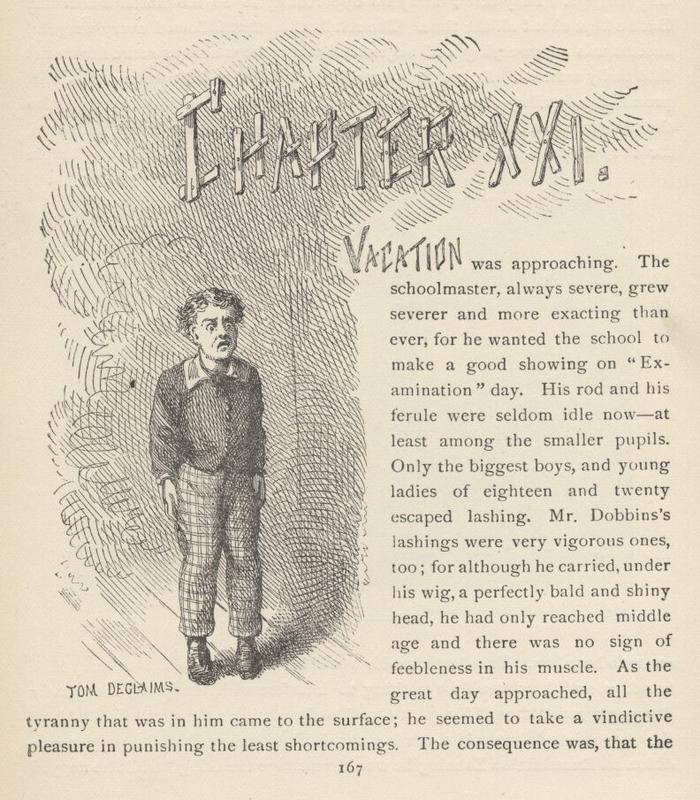
休暇が近づいていた。いつも厳しい校長は、これまで以上に厳しく、要求がましくなった。というのも、彼は「試験」の日に学校が良い成績を示すことを望んでいたからだ。彼の鞭と定規は、今やほとんど休む暇がなかった――少なくとも、年下の生徒たちの間では。鞭打ちを免れるのは、最年長の少年たちと、十八歳や二十歳の若いご婦人たちだけだった。ドビンズ先生の鞭打ちは、また非常に強烈なものであった。というのも、彼はかつらの下に、完全につるつるで光沢のある禿頭を隠していたが、まだ中年期に達したばかりで、その筋肉に衰えの兆候はなかったからだ。その偉大なる日が近づくにつれ、彼の内なるすべての暴虐性が表面に出てきた。彼は、ほんの些細な欠点をも罰することに、執念深い喜びを感じているようだった。その結果、年下の少年たちは恐怖と苦しみの中で日々を過ごし、夜は復讐を企てることに費やした。彼らは先生にいたずらをする機会を一つも見逃さなかった。しかし、先生は常に一歩先を行っていた。復讐が成功するたびに続く報復は、あまりに徹底的かつ壮大であったため、少年たちは常にひどく打ち負かされて戦場から退却した。ついに彼らは共謀し、輝かしい勝利を約束する計画を思いついた。彼らは看板屋の息子を仲間に引き入れ、計画を話し、助けを求めた。彼には喜んで協力するだけの理由があった。というのも、先生は彼の父親の家に下宿しており、その少年を憎むに足る十分な原因を与えていたからだ。先生の妻は数日後に田舎へ旅行に行く予定で、計画を妨げるものは何もなかった。先生はいつも、大事な行事の前にはかなり酔っぱらって準備をするのが常であり、看板屋の息子は、試験の夜に校長が適切な状態に達したら、彼が椅子で居眠りをしている間に「事を運ぶ」と言った。それから、適切な時間に彼を起こし、急いで学校へ向かわせるという手はずだった。
時満ちて、その興味深い行事がやってきた。夜八時、校舎は明るく照らされ、葉や花の輪飾りや花綱で飾られていた。先生は、後ろに黒板を背負い、一段高い壇上に置かれた大きな椅子に王のように座っていた。彼はかなり上機嫌に見えた。彼の両側に三列、正面に六列の長椅子が、町のお偉方と生徒たちの両親で占められていた。彼の左手、市民たちの列の後ろには、広々とした仮設の壇上があり、そこにはその夜の行事に参加する生徒たちが座っていた。不快極まりないほどに洗われ、着飾らされた小さな少年たちの列。不格好な大きな少年たちの列。ローンやモスリンの服をまとい、むき出しの腕、祖母の古めかしい装身具、ピンクや青のリボンの切れ端、そして髪に飾った花を見せびらかす少女たちや若いご婦人たちの雪の山。家の残りの部分はすべて、参加しない生徒たちで埋め尽くされていた。

行事が始まった。ごく小さな男の子が立ち上がり、はにかみながら暗誦した。「この年頃の者が、舞台で公に話すなど、とてもお望みではありますまい」云々――まるで機械が使うような、痛々しいほど正確で、痙攣的な身振りを伴いながら――ただし、その機械が少々故障していると仮定しての話だが。しかし、彼はひどく怯えながらも、無事にやり遂げ、作り物のようにお辞儀をして退場すると、盛大な拍手喝采を浴びた。
少し恥ずかしそうな小さな女の子が、舌足らずに「メリーさんのひつじ」云々を暗誦し、同情を誘うようなお辞儀をして、相応の拍手を受け、顔を赤らめて幸せそうに座った。
トム・ソーヤーはうぬぼれた自信を持って前に進み、消えることのない、不滅の「我に自由を与えよ、しからずんば死を」の演説を、見事な激しさと狂乱の身振りで高らかに語り始めたが、その途中でつまずいた。恐ろしい舞台恐怖症が彼を襲い、足はがくがくと震え、窒息しそうになった。確かに、彼は会場からの明白な同情を得ていたが、会場の沈黙もまた得ていた。それは同情よりもさらに悪いものだった。先生が眉をひそめ、これが惨事を決定的なものにした。トムはしばらくもがいた後、完全に打ち負かされて退場した。弱々しい拍手の試みがあったが、それはすぐに消え去った。
「少年は燃える甲板に立ちて」が続き、また「アッシリア人は下り来たりて」など、他の朗誦の名作も披露された。それから、読書練習と、綴り字の試合があった。数少ないラテン語のクラスは、名誉ある発表を行った。さて、その夜の主役が登場する番である――若いご婦人たちによる、オリジナルの「作文」だ。一人ずつ順番に壇上の端に進み出て、咳払いをし、(可憐なリボンで結ばれた)原稿を掲げ、「表現」と句読点に骨の折れる注意を払いながら、朗読を始めた。テーマは、彼女たちの母親たちが、そのまた母親たちが、そして疑いなく、十字軍の時代まで遡るすべての女系の先祖たちが、同様の機会に輝かせてきたものと同じであった。「友情」。「過ぎし日の思い出」。「歴史における宗教」。「夢の国」。「教養の利点」。「政治形態の比較対照」。「憂鬱」。「親孝行」。「心の渇望」などなど。

これらの作文に広く見られる特徴の一つは、大切に育てられ、甘やかされた憂鬱であった。もう一つは、浪費的で贅沢な「美辞麗句」のほとばしりであった。もう一つは、特に大切にされている言葉やフレーズを、完全に使い古されるまで無理やり持ち込む傾向であった。そして、それらを著しく特徴づけ、損なっていた特異性は、それぞれの作文の最後に、決まって不自由な尻尾を振るう、根深く、耐え難い説教であった。主題が何であれ、道徳的・宗教的な精神が啓発されながら熟考できるような何らかの側面に、それをねじ込むための、頭を悩ます努力がなされた。これらの説教の目に余る不誠実さは、学校からその慣習を追放するには十分ではなかったし、今日でも十分ではない。おそらく、世界が存在する限り、決して十分ではないだろう。私たちの国のすべての学校で、若いご婦人たちが作文を説教で締めくくる義務を感じない学校はない。そして、学校で最も軽薄で、最も宗教的でない少女の説教が、常に最も長く、最も容赦なく敬虔であることを見出すだろう。しかし、この話はもう十分だ。ありのままの真実は口に合わない。
「試験」に戻ろう。最初に読まれた作文は、「これぞ、人生か?」と題されたものであった。読者は、その抜粋に耐えられるかもしれない。
「人生のありふれた道のりにおいて、若き心は、来るべき祝祭の場面を、いかに楽しげな感情をもって心待ちにすることでしょう! 想像力は、薔薇色の喜びの絵を描くのに忙しいのです。空想の中で、流行の官能的な信奉者は、祝祭の群衆の中にいる自分を見ます。『すべての観察者の観察対象』として。雪のように白い衣に身を包んだその優雅な姿は、楽しい踊りの迷宮を舞い、その目は最も輝き、その足取りは陽気な集いの中で最も軽いのです。
「このような甘美な空想の中で、時は速やかに過ぎ去り、彼女がかくも輝かしい夢を見てきたエリュシオンの世界への入場を告げる、歓迎すべき時が訪れます。彼女の魅了された視界には、すべてがなんと妖精のように見えることでしょう! 新しい場面はそれぞれ、前のものより魅力的です。しかし、しばらくすると、彼女はこの立派な外見の下では、すべてが虚栄であり、かつて彼女の魂を魅了したお世辞も、今では耳に痛く響くことに気づきます。舞踏室はその魅力を失い、そして、損なわれた健康と苦い心を抱えて、彼女は、地上の快楽は魂の渇望を満たすことはできないという確信と共に、立ち去るのです!」
といった具合である。朗読の間、時折、「なんて素敵!」「なんて雄弁!」「なんて真実!」といった囁き声の感嘆を伴う、満足げなざわめきがあった。そして、それがことさらに痛ましい説教で締めくくられた後、拍手は熱狂的であった。
それから、痩せた、憂鬱な少女が立ち上がった。その顔は、錠剤と消化不良から来る「興味深い」青白さをしていた。そして「詩」を読んだ。二連もあれば十分だろう。
「ミズーリの乙女、アラバマに別れを告ぐ
アラバマよ、さようなら! 汝を深く愛す! されど、しばし汝を離れん、今! 悲しき、ああ、悲しき汝への思い、我が心に満ち、 燃ゆる思い出、我が額に群がる! 我は汝の花咲く森をさまよい、 タラプーサの川辺にて遊び、読み、 タラシーの戦う洪水に耳を傾け、 クーサの岸辺にてオーロラの光を求めしを。 されど、満ち溢るる心を抱くを恥じず、 涙ぐむ目の後ろを向くを赤面せず。 見知らぬ地より今、我は去るにあらず、 見知らぬ人々に残し、このため息を捧ぐるにあらず。 歓迎と家は、この州にて我がものなりき、 その谷を我は去り――その尖塔は速やかに我より消えゆく。 そして、冷たからん、我が目も、心も、tête も、 愛しきアラバマよ! 汝に冷たくなるときは!」
そこにいた者で、「tête」が何を意味するか知っている者はごくわずかだったが、それでもその詩は非常に満足のいくものであった。
次に現れたのは、色黒で、黒い瞳、黒い髪の若いご婦人で、印象的な一瞬の間を置き、悲劇的な表情を浮かべ、そして、落ち着いた、厳粛な口調で読み始めた。

幻視
夜は暗く、荒れ狂っていた。高き玉座の周りには、ただ一つの星もきらめいていなかった。しかし、重々しい雷鳴の深い響きは絶えず耳に振動し、一方、恐ろしい稲妻は、天の雲の部屋を怒りに満ちた様子で駆け巡り、かの高名なるフランクリンによってその恐怖に加えられた力を嘲笑っているかのようであった! 騒々しい風さえも、その神秘的な家から一斉に吹き出し、その助けによって場面の荒々しさを増すかのように、あたりを吹き荒れていた。
かくなる時、かくも暗く、かくも陰鬱なれば、我が魂は人の情けを乞い求めんとした。されど、その代わりに、
「我が最愛の友、我が助言者、我が慰め手、我が導き手―― 悲しみにありては我が喜び、喜びにありては我が第二の至福」なる者が、我が傍らに来たれり。
彼女の身のこなしは、若くロマンチストな者が空想のエデンの園、陽光差す散歩道に描く、あの輝ける存在のようであった。その超越した美しさのほかには何の飾りも纏わぬ、美の女王そのものであった。その足取りはあまりに柔らかく、物音ひとつ立てないほどであった。そして、その優しき触れ心地がもたらす魔法のようなときめきがなければ、他の控えめな美しきものたちと同様、気づかれることも、求められることもなく、滑るように去っていったことであろう。その顔には、あたかも十二月の衣に凍てつく涙が宿るがごとく、不可思議な悲しみが漂っていた。彼女は外で荒れ狂う風雨を指し示し、目の前に現れた二つの存在を熟視するよう私に促したのである。
この悪夢のような文章は原稿用紙十枚ほどにも及び、長老派教会以外の者にとってはあらゆる希望を打ち砕くほどの説教で締めくくられていたが、なんと最優秀賞を獲得したのである。この作文は、その夜の催しにおける最高傑作と見なされた。村長は、作者に賞を授与するにあたり、熱のこもった演説を行った。その中で彼は、この作文はこれまで聴いた中で群を抜いて「雄弁」であり、かのダニエル・ウェブスター[訳注:19世紀アメリカの政治家・演説家]でさえ誇りに思うだろうと述べた。
ついでに言えば、「麗しき」という言葉が過剰にもてはやされ、人生経験が「人生の頁」と表現される作文の数は、例年通りの水準に達していたことを付記しておく。
さて、先生はといえば、上機嫌と紙一重のほどに気分を良くし、椅子を脇にどけると、聴衆に背を向け、地理の授業の練習台として、黒板にアメリカの地図を描き始めた。しかし、その手元はおぼつかず、描かれた地図は見るも無残な出来栄えで、会場からはくすくすという忍び笑いがさざ波のように広がった。先生は何が起きているか察し、立て直そうとした。線を消し、描き直す。だが、かえって歪みはひどくなるばかりで、忍び笑いはますます大きくなった。今や先生は、この嘲笑に屈するものかと、全身全霊を地図作成に注いだ。すべての視線が自分に突き刺さっているのを感じていた。うまくいっているはずだ、と自分に言い聞かせたが、くすくす笑いは止まらない。それどころか、明らかに大きくなっている。それもそのはず。先生の頭上には屋根裏部屋があり、そこには昇降口が開いていた。その昇降口から、一本の猫が、紐で胴体を吊るされて下りてきたのである。猫は鳴き声を上げないよう、頭と顎にぼろ布を巻き付けられていた。ゆっくりと降下しながら、猫は体を反らせて紐に爪を立て、下に揺れては空を切った。くすくす笑いはどんどん高まる――猫は夢中になっている先生の頭まであと六インチ――下へ、下へ、もう少し、というところで、猫は必死の爪で先生のかつらをひっつかみ、それにしがみついたかと思うと、その戦利品を手にしたまま、一瞬のうちに屋根裏部屋へと引き上げられていった! そして、先生の禿げ上がった頭頂部から放たれた光の、なんとまばゆかったことか――看板屋の息子が、そこに金箔を塗っていたのだ!

これで会はお開きとなった。少年たちの復讐は果たされたのだ。そして、夏休みがやって来た。
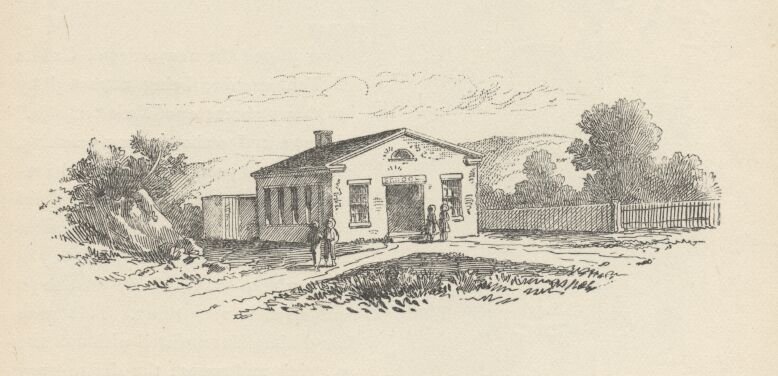
第二十二章
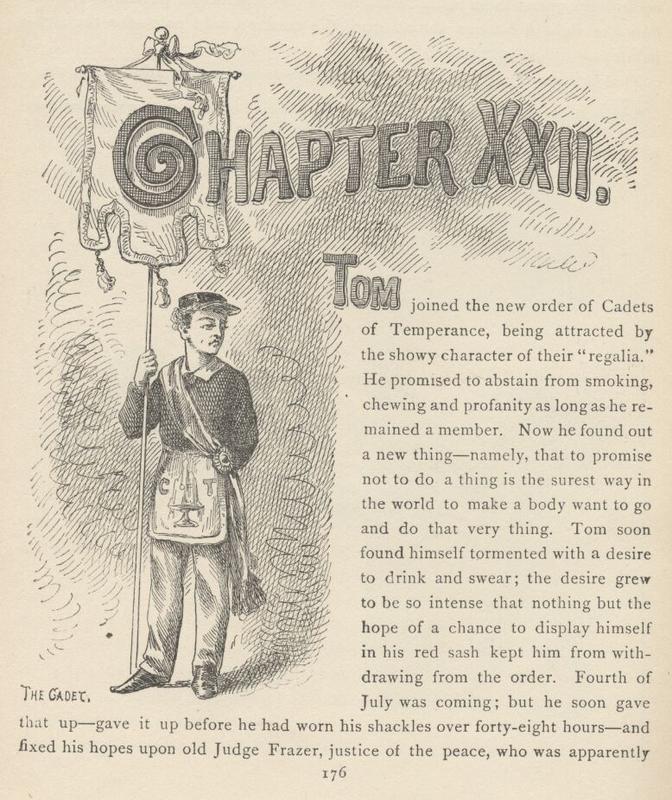
トムは、新設された「禁酒少年団」に加入した。そのきらびやかな「団服」に惹かれたからである。彼は、団員である限り、喫煙、噛みタバコ、そして不敬な言葉遣いを断つと誓った。そしてトムは、ある新たな発見をした――すなわち、何かをしないと約束することは、まさにそのことをしたくてたまらなくなる、この世で最も確実な方法であるということを。トムはすぐに、酒を飲み、悪態をつきたいという欲望に苦しめられるようになった。その欲望はあまりに強烈になり、赤い飾り帯を身につけて人前に出る機会があるという希望だけが、彼を退団から引き留めていた。七月四日の独立記念日が近づいていた。だが、トムはそれもすぐに諦めた――入団から四十八時間も経たないうちに諦めてしまったのだ――そして、次の希望を、明らかに死の床にあると思われた治安判事のフレイザー老判事に託した。高名な役人であるからには、盛大な公葬が執り行われるに違いない。三日間というもの、トムは判事の容態を深く気遣い、その知らせに飢えていた。時に彼の希望は高まり――高まりすぎて、団服を取り出して鏡の前で練習してみることさえあった。しかし、判事の病状は、実にもどかしいほど一進一退を繰り返した。ついに快方に向かっていると宣告され――そして回復期に入った。トムはうんざりし、さらには裏切られたような気分にさえなった。彼はすぐさま退団届を提出した――するとその夜、判事はぶり返して亡くなった。トムは、あのような男は二度と信用しないと心に決めた。
葬儀は立派なものだった。禁酒少年団は、故人が羨ましさで死んでしまうほど見事なスタイルでパレードを行った。しかし、トムは再び自由の身となっていた――それにはそれなりの価値があった。今や酒も飲めるし、悪態もつける――ところが、驚いたことに、そうしたいとは思わなかった。できるという単純な事実が、欲望とその魅力を奪い去ってしまったのである。
やがてトムは、あれほど待ち焦がれた夏休みが、少しばかり手持ち無沙汰になってきていることに気づき、不思議に思った。
彼は日記を試みた――だが、三日間何も起こらなかったので、やめてしまった。
町に初めて黒人ミンストレル・ショー[訳注:白人が顔を黒く塗って演じるショー]の一座がやってきて、一大センセーションを巻き起こした。トムとジョー・ハーパーは自分たちで一座を立ち上げ、二日間は幸せだった。

栄光の七月四日さえ、ある意味では失敗だった。激しい雨が降り、そのせいでパレードは中止。そして、世界で最も偉大な人物(とトムは思っていた)、現職のアメリカ合衆国上院議員であるベントン氏も、圧倒的な期待外れに終わった――身長が二十五フィート[訳注:約7.6メートル]もなかったし、その近辺ですらなかったからだ。
サーカスが来た。少年たちはその後三日間、ぼろの絨毯で作ったテントでサーカスごっこをして遊んだ――入場料は男の子がピン三本、女の子が二本――そしてサーカスごっこも飽きられた。
骨相学者と催眠術師がやって来た――そしてまた去っていき、村は以前にも増して退屈で陰鬱になった。
少年少女のパーティーもいくつかあったが、あまりに少なく、あまりに楽しかったので、パーティーとパーティーの間の虚しさを、より一層辛く感じさせるだけだった。
ベッキー・サッチャーは夏休みの間、両親と過ごすためにコンスタンティノープルの家へ帰ってしまっていた――だから、人生のどこにも明るい兆しはなかった。
殺人事件の恐ろしい秘密は、慢性的な苦痛だった。それは、永続性と痛みにおいて、まさに癌であった。
そして、はしかが流行した。

長い二週間、トムは囚人のように横たわり、世の中の出来事から完全に切り離されていた。彼はひどく病み、何事にも興味を示さなかった。ようやく起き上がって、弱々しい足取りで町へ下りてみると、すべてのもの、すべての生き物が、憂鬱な変化を遂げていた。「信仰復興運動」があり、誰もが「信仰に目覚め」ていた。大人だけでなく、少年少女までもが。トムは、罪深き顔をした祝福すべき誰かに会えるかと、万に一つの望みを抱いて歩き回ったが、どこへ行っても失望が彼を打ちのめした。ジョー・ハーパーは聖書を勉強しており、トムはその憂鬱な光景から悲しげに背を向けた。ベン・ロジャースを探し当てると、彼は貧しい人々を訪ね、宗教的な小冊子の入った籠を配っていた。ジム・ホリスを訪ねると、彼は最近かかったはしかを警告としての貴重な祝福だと説いた。出会う少年一人一人が、彼の憂鬱にさらなる重しを加えた。そして、絶望のあまり、ついにハックルベリー・フィンの懐に避難を求めたところ、聖書の一節で迎えられた時、彼の心は砕け散り、家へと這い戻り、ベッドにもぐりこんだ。町の人間の中で自分だけが、永遠に、永遠に救われないのだと悟ったのである。
そしてその夜、猛烈な嵐がやって来た。叩きつけるような雨、恐ろしい雷鳴、目を眩ませる稲妻の閃光。彼はベッドの掛け布団で頭を覆い、恐怖と不安の中で自らの破滅を待った。この大騒ぎが自分に向けられたものであることに、微塵の疑いもなかったからだ。天の神々の堪忍袋の緒を、ついに自分が切らしてしまい、これがその結果なのだと信じていた。虫けら一匹を殺すのに大砲の砲列を持ち出すのは、壮大さと弾薬の無駄遣いに思えるかもしれないが、自分のような虫けらを地面から吹き飛ばすために、これほど金のかかった雷雨を用意することには、何ら不自然さを感じなかった。
やがて嵐はその勢いを失い、目的を達成することなく消え去った。少年の最初の衝動は、感謝し、改心することだった。二番目の衝動は、待つことだった――もう嵐は来ないかもしれないからだ。
翌日、医者たちが再びやって来た。トムはぶり返したのだ。今回、彼が寝たきりで過ごした三週間は、まるで永遠のように感じられた。ようやく外出できるようになった時、彼は自分が助かったことにほとんど感謝しなかった。自分の境遇がいかに孤独で、仲間もなく、見捨てられているかを思い出したからだ。彼は物憂げに通りをぶらつき、ジム・ホリスが、被害者である鳥を前にして、猫を殺人罪で裁く少年裁判で裁判官役を務めているのを見つけた。路地裏では、ジョー・ハーパーとハック・フィンが盗んだメロンを食べていた。哀れな少年たち! 彼らも――トムと同じく――ぶり返してしまったのだ。

第二十三章
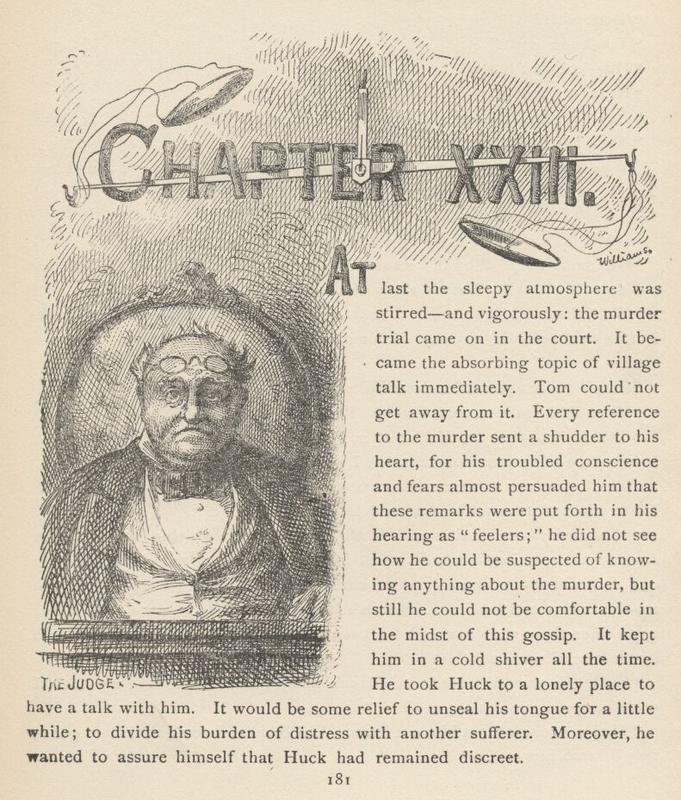
ついに、眠たげな町の空気はかき乱された――しかも激しく。殺人事件の裁判が法廷で始まったのだ。それはたちまち村の噂の中心となった。トムはそれから逃れることができなかった。殺人事件に言及されるたびに、彼の心臓は震えた。というのも、彼の悩める良心と恐怖は、そうした言葉が自分の耳元で「探り」として発せられているのだと、ほとんど彼に信じ込ませていたからだ。自分が事件について何か知っていると疑われるはずはないのだが、それでも、この噂の渦中にいては落ち着かなかった。彼は常に冷たい震えに襲われていた。彼はハックを人けのない場所に連れ出し、話をすることにした。ほんの少しでも口を開けば、いくらか気が晴れるだろう。苦しみの重荷を、もう一人の受難者と分かち合うのだ。さらに、ハックが口を堅く守っていることを確かめたかった。
「ハック、おまえ、あれのこと――誰かに話したか?」
「なんのことだ?」
「わかってるだろ。」
「ああ――もちろん、話してねえよ。」
「一言も?」
「ただの一言もだ、神に誓って。なんでそんなこと聞くんだ?」
「いや、怖くなって。」
「なんだよ、トム・ソーヤー。あんなことがバレたら、おれたち二日と生きてられねえぞ。おまえだってわかってるだろ。」
トムは少し安心した。しばらく間を置いてから言った。
「ハック、誰かに無理やり言わされたりしないよな?」
「おれに言わせるだと? そりゃ、あの混血の悪魔に溺れ死にさせられたいんなら、言わされるだろうな。それ以外に方法なんかねえよ。」
「ああ、それなら大丈夫だ。黙ってさえいれば、おれたちは安全だと思う。でも、念のため、もう一度誓おうぜ。その方が確実だ。」
「いいぜ。」
そこで二人は、恐ろしく厳粛な儀式をもって、再び誓いを立てた。
「町の噂はどうだ、ハック? 俺もずいぶん聞いたけど。」
「噂? そりゃもう、マフ・ポッター、マフ・ポッター、四六時中マフ・ポッターさ。おかげで冷や汗が止まらねえ。どこかに隠れたくなるぜ。」
「俺の周りでもまったく同じだ。あいつはもうおしまいだと思う。時々、あいつが可哀想に思わないか?」
「たいていな――たいていそうさ。ろくでなしだけど、誰かを傷つけるようなことは一度もしたことねえ。酔っぱらう金欲しさにちょっと釣りをするくらいで――あとはかなりぶらぶらしてるが、ちぇっ、そんなこたあ誰でもやってる――少なくともおれたちのほとんどはな、牧師さんとかそういう連中は別として。でも、あいつはいい奴なんだ――一度、二人分には足りねえのに、魚を半分くれたことがある。運がねえ時には、何度も助けてくれたしな。」
「ああ、俺の凧を直してくれたり、釣り糸に釣り針を結んでくれたりしたよ、ハック。あいつをあそこから出してやれたらなあ。」
「とんでもねえ! 出してやれるもんか、トム。それに、何の役にも立たねえよ。また捕まるだけだ。」
「そうだな――そうだろうな。でも、あいつが――あれをやってないのに、みんながひどい悪口を言うのを聞くのは嫌だ。」
「おれもだよ、トム。ちぇっ、あいつはこの国で一番血なまぐさい顔つきの悪党だとか、なんで今まで絞首刑にならなかったのか不思議だとか、そんなこと言ってるのを聞いたぜ。」
「ああ、いつもそんな調子だ。もしあいつが自由になったら、リンチにかけてやるって言うのも聞いた。」
「しかも、やりかねねえ。」
少年たちは長いこと話し込んだが、ほとんど慰めにはならなかった。黄昏が迫る頃、二人は人里離れた小さな監獄のあたりをうろついていた。自分たちの困難を晴らしてくれるような何かが起こりはしないかと、漠然とした希望を抱いていたのかもしれない。しかし、何も起こらなかった。この不運な囚人に関心を持つ天使や妖精はいないようだった。
少年たちは、これまでもよくしてきたように――監房の鉄格子へ行き、ポッターにタバコとマッチを渡した。彼は一階に収監されており、看守はいなかった。

彼らの贈り物に対するポッターの感謝の言葉は、いつも彼らの良心を打ちのめしてきたが――今回は、これまで以上に深く突き刺さった。二人はこの上なく卑劣で裏切り者のように感じた。ポッターがこう言った時だ。
「おめえさんたちは、わしに実によくしてくれた、坊主たち――この町の誰よりもな。その恩は忘れねえ、絶対に忘れねえぞ。わしはよく独り言を言うんだ。『わしは昔、坊主たちの凧やら何やらをみんな直してやったし、いい釣りの場所も教えてやった。できる限り力になってやった。なのに今じゃ、わしが困ってるってのに、みんな年寄りのマフのことなんか忘れちまった。だけどトムは忘れねえし、ハックも忘れねえ――あいつらはわしを忘れねえんだ』ってな、『だからわしもあいつらを忘れねえ』って。まあ、坊主たち、わしはひでえことをしちまった――酔っぱらって、頭がおかしくなってたんだ――そうとしか考えられねえ――だから、その償いに吊るされなきゃならねえ。それでいいんだ。それでいいし、それが一番なんだろうよ――そう願うぜ。まあ、その話はやめよう。おめえさんたちを悲しませたくねえ。おめえさんたちはわしの味方だったんだからな。でも、言いてえのは、おめえさんたちは絶対に酔っぱらうんじゃねえぞ――そうすりゃ、こんな所に来ることはねえ。もうちっと西に寄ってくれ――そう、そうだ。こんなひでえ苦境にいる時に、親しげな顔が見えるってのは、最高の慰めなんだ。ここに来てくれるのは、おめえさんたちの顔だけだ。いい、親しげな顔だ――いい、親しげな顔だよ。お互いの背中に乗って、わしに触らせてくれ。そうだ。握手だ――おめえさんたちの手は格子を通るが、わしのはでかすぎてな。小さくて、弱い手だ――だが、この手はマフ・ポッターをうんと助けてくれた。できることなら、もっと助けてくれただろうよ。」
トムは惨めな気持ちで家に帰り、その夜の夢は恐怖に満ちていた。翌日も、そのまた翌日も、彼は法廷の周りをうろついた。中に入りたいという、ほとんど抗いがたい衝動に駆られながらも、必死に外に留まっていた。ハックも同じ経験をしていた。二人は努めて互いを避けた。時折、それぞれがどこかへさまよい出たが、同じ陰鬱な魅力が、いつもすぐに二人を引き戻した。トムは、暇人たちが法廷からぶらぶらと出てくるたびに耳をそばだてたが、聞こえてくるのは決まって悲痛なニュースだった――哀れなポッターを取り巻く網は、ますます容赦なく狭まっている。二日目の終わりには、村の噂は、インジャン・ジョーの証言は揺るぎなく確固としており、陪審員の評決がどうなるかについては、もはや微塵の疑いもないというものだった。
その夜、トムは遅くまで外におり、窓からベッドに入った。彼はとてつもなく興奮していた。眠りにつくまで何時間もかかった。翌朝、村中の人々が裁判所へ押し寄せた。この日が、その重大な日となるからだ。詰めかけた聴衆は、男女ほぼ同数だった。長い待ち時間の後、陪審員団が入廷し、席に着いた。そのすぐ後、ポッターが、青ざめ、やつれ、おびえ、希望を失った姿で、鎖につながれて連れてこられ、好奇の視線がすべて注がれる席に座らされた。劣らず目立っていたのは、相変わらず無表情なインジャン・ジョーだった。再び間があり、やがて判事が到着し、保安官が開廷を宣言した。弁護士たちのいつものささやき声と、書類をまとめる動きが続いた。こうした細々とした手続きと、それに伴う遅延が、魅力的であると同時に印象的な、準備の雰囲気を醸し出していた。
さて、一人の証人が呼ばれた。彼は、殺人事件が発見された日の早朝、小川で体を洗っているマフ・ポッターを見つけ、ポッターはすぐにこそこそと立ち去ったと証言した。いくつかの追加質問の後、検察側の弁護士が言った。
「証人を引き取ります。」
被告人は一瞬目を上げたが、自身の弁護士がこう言うと、再び目を伏せた。
「彼に尋問することはありません。」
次の証人は、死体の近くでナイフが発見されたことを証明した。検察側の弁護士が言った。
「証人を引き取ります。」
「彼に尋問することはありません」とポッターの弁護士は答えた。
三番目の証人は、そのナイフをポッターが持っているのを何度も見たと誓った。
「証人を引き取ります。」
ポッターの弁護士は、彼への尋問を拒否した。聴衆の顔に、いらだちの色が浮かび始めた。この弁護士は、何の努力もせずに依頼人の命を見捨てるつもりなのか?
数人の証人が、殺人現場に連れてこられた際のポッターの罪悪感に満ちた振る舞いについて証言した。彼らもまた、反対尋問を受けることなく証言台を降りることを許された。
その場にいる誰もがよく覚えているあの朝、墓場で起きた不利な状況の細部に至るまでが、信頼できる証人たちによって明らかにされたが、ポッターの弁護士によって反対尋問された者はいなかった。法廷の困惑と不満は、ざわめきとなって表れ、裁判長からの叱責を招いた。ここで検察側の弁護士が言った。
「その一言が疑いの余地もない市民たちの宣誓により、我々は、この恐るべき犯罪を、いかなる疑問の可能性もなく、被告席の不幸な囚人の仕業として立証いたしました。我々の立証は以上です。」
哀れなポッターからうめき声が漏れ、彼は顔を両手で覆い、体を静かに前後に揺らした。法廷には痛ましい沈黙が支配した。多くの男たちが心を動かされ、多くの女たちの同情は涙となって表れた。弁護側の弁護士が立ち上がり、言った。
「裁判長。本裁判の冒頭陳述において、我々は、依頼人が酒によって引き起こされた盲目的で無責任な錯乱状態の影響下で、この恐るべき行為に及んだことを証明する意図を予告いたしました。我々は考えを変えました。その弁護は行いません。」[そして書記官に]「トーマス・ソーヤーを召喚してください!」
法廷中のすべての顔に、ポッターの顔さえ例外ではなく、困惑した驚きが浮かんだ。トムが立ち上がり、証言台へ向かうと、すべての目が、訝しむような興味をもって彼に注がれた。少年はひどく怯えており、取り乱した様子だった。宣誓が行われた。
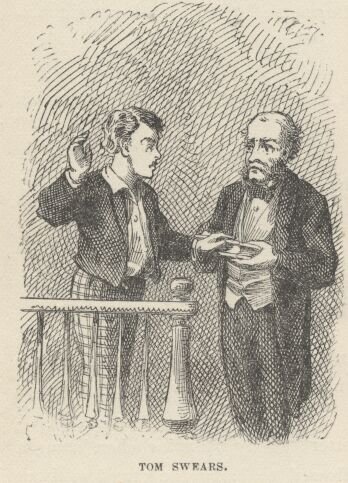
「トーマス・ソーヤー、六月十七日の真夜中頃、君はどこにいましたか?」
トムはインジャン・ジョーの鉄のような顔を一瞥し、言葉を失った。聴衆は息を殺して耳を傾けたが、言葉が出てこない。しかし、しばらくすると、少年は少し力を取り戻し、かろうじて声を絞り出し、法廷の一部に聞こえるように言った。
「墓場です!」
「もう少し大きな声でお願いします。怖がらなくていい。君は――」
「墓場にいました。」
インジャン・ジョーの顔に、軽蔑的な笑みがかすめた。
「ホス・ウィリアムズの墓の近くにいましたか?」
「はい。」
「はっきり――ほんの少し大きな声で。どれくらい近くにいましたか?」
「あなたと同じくらい近くです。」
「隠れていましたか、それとも?」
「隠れていました。」
「どこに?」
「墓の端にあるニレの木の陰です。」
インジャン・ジョーが、ほとんど気づかれないほどかすかに身を震わせた。
「誰か一緒にいましたか?」
「はい。僕と一緒に行ったのは――」
「待ちなさい――少し待ちなさい。連れの名前を言う必要はありません。然るべき時に、彼を召喚します。何か持って行きましたか。」
トムはためらい、混乱した様子だった。
「はっきり言いなさい、坊や――臆することはない。真実は常に尊いものだ。何を持って行ったのかね?」
「ただの――その――死んだ猫です。」
くすくすという笑いが起こったが、法廷がそれを制した。
「我々はその猫の骸骨を提出します。さて、坊や、起こったことすべてを話しなさい――君自身の言葉で――何も飛ばさずに、そして怖がらずに。」
トムは話し始めた――最初はためらいがちだったが、話に熱が入るにつれて、彼の言葉はますます滑らかに流れ出した。やがて、彼の声以外の物音は一切しなくなり、すべての目が彼に釘付けになった。聴衆は口を開け、息を殺して彼の言葉に聞き入り、時間を忘れ、その凄惨な物語の魅力に心を奪われていた。溜め込まれた感情の緊張が最高潮に達したのは、少年がこう言った時だった。
「――そして、博士が板を振り回して、マフ・ポッターが倒れた時、インジャン・ジョーがナイフを持って飛びかかって――」
ガシャン! 稲妻のごとき速さで、その混血の男は窓へ飛びつき、邪魔する者すべてを突き飛ばして、姿を消した!

第二十四章

トムは再び輝ける英雄となった――年寄りには可愛がられ、若者には羨望の的となった。彼の名前は、村の新聞に大きく取り上げられ、不滅の活字にさえなった。もし絞首刑を免れれば、いずれ大統領になるだろうと信じる者さえいた。
いつものように、気まぐれで理不尽な世間は、マフ・ポッターをその懐に抱き、以前に彼を罵ったのと同じくらい惜しみなく彼を可愛がった。しかし、そうした行いは世間の名誉となる。ゆえに、それに文句をつけるのは得策ではない。
トムの日々は、彼にとって栄光と歓喜の日々だったが、その夜は恐怖の季節だった。インジャン・ジョーが彼の夢のすべてに取り憑き、その目にはいつも破滅の色を宿していた。夜になってから外へ出ようとする少年を説得できる誘惑は、ほとんどなかった。哀れなハックも、同じ惨めさと恐怖の状態にあった。というのも、トムは裁判の重大な日の前夜、弁護士にすべての話を打ち明けており、ハックは、インジャン・ジョーの逃亡のおかげで法廷で証言する苦しみを免れたにもかかわらず、自分の関与がいつか漏れるのではないかとひどく恐れていたのだ。哀れな彼は、弁護士に秘密を守ると約束させたが、それが何になるというのか。トムの苛まれた良心が、夜中に彼を弁護士の家へと駆り立て、最も陰惨で恐ろしい誓いによって封じられていたはずの唇から、恐ろしい物語を絞り出させた以上、ハックの人間に対する信頼は、ほとんど消え去っていた。

昼間は、マフ・ポッターの感謝の言葉が、話してよかったとトムを喜ばせた。しかし夜になると、口を閉ざしたままでいればよかったと願った。
トムは、半分の時間はインジャン・ジョーが永遠に捕まらないのではないかと恐れ、残りの半分の時間は、捕まるのではないかと恐れた。彼は、あの男が死に、その死体をこの目で見るまでは、二度と安心して息をすることもできないだろうと感じていた。
懸賞金がかけられ、国中が捜索されたが、インジャン・ジョーは見つからなかった。全知全能で畏敬の念を抱かせる驚異の存在、探偵が一人、セントルイスからやって来て、嗅ぎ回り、首を振り、賢そうな顔をして、その職業の人間が通常成し遂げる類の、驚くべき成功を収めた。すなわち、彼は「手がかりを発見した」のである。しかし、殺人罪で「手がかり」を絞首刑に処すことはできない。だから、その探偵が仕事を終えて家に帰った後も、トムは以前と少しも変わらず不安を感じていた。
緩やかな日々が流れ去り、一日が過ぎるごとに、不安の重荷がわずかに軽くなっていった。
第二十五章
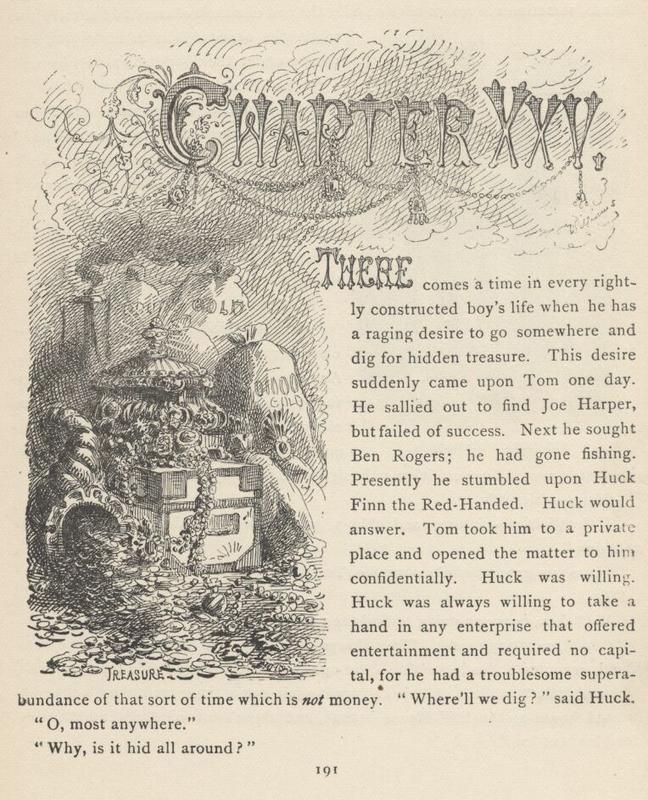
正しく作られた少年の一生には、どこかへ行って隠された宝物を掘り起こしたいという猛烈な欲望に駆られる時期がやって来る。この欲望が、ある日突然トムを襲った。彼はジョー・ハーパーを探しに勇んで出かけたが、見つけられなかった。次にベン・ロジャースを探したが、彼は釣りに行っていた。やがて彼は、「赤手」のハックルベリー・フィンにばったり出くわした。ハックならうってつけだ。トムは彼を人気のない場所に連れて行き、内密にその件を切り出した。ハックは乗り気だった。ハックは、面白そうで元手がいらない企てなら、いつでも喜んで一枚噛んだ。金にならない類の時間を、彼は厄介なほど有り余らせていたからだ。「どこを掘るんだ?」とハックが言った。
「ああ、だいたいどこでもさ。」
「なんだ、そこら中に隠してあるのか?」
「いや、とんでもない。すごく特別な場所に隠してあるんだ、ハック――時には島に、時には古い枯れ木の枝の先、ちょうど真夜中に影が落ちる場所の下にある腐った箱の中に。でも、たいていは幽霊屋敷の床下だな。」
「誰が隠すんだ?」
「そりゃ、強盗に決まってるだろ――他に誰がいるってんだ? 日曜学校の校長先生か?」
「知らねえよ。もしおれのだったら、隠したりしねえ。使っちまって、いい思いをするね。」
「俺もそうする。でも強盗はそんなことしないんだ。いつも隠して、そこに置きっぱなしにする。」

「もう取りに来ねえのか?」
「いや、来ようとは思うんだけど、たいてい目印を忘れちまうか、死んじまうんだ。とにかく、宝物は長いことそこに置かれて錆びちまう。そのうち誰かが、目印の見つけ方が書いてある古い黄ばんだ紙を見つけるんだ――ほとんどが記号とかヒエログリフだから、解読するのに一週間くらいかかる紙をな。」
「ヒエロ――なんだって?」
「ヒエログリフだよ――絵とかそういうので、何の意味もなさそうに見えるやつさ。」
「おまえ、その紙を持ってるのか、トム?」
「いや。」
「じゃあ、どうやって目印を見つけるんだ?」
「目印なんかいらない。やつらはいつも幽霊屋敷か島か、一本だけ枝が突き出てる枯れ木の下に埋めるんだ。まあ、ジャクソン島は少し試したし、またいつか試せる。それに、蒸留所[訳注:Still-House]の小川の上流には古い幽霊屋敷があるし、枯れ枝の木ならたくさんある――山ほどな。」
「その全部の下にあるのか?」
「なんてこと言うんだ! 違うよ!」
「じゃあ、どれに行けばいいか、どうやってわかるんだ?」
「全部行くんだよ!」
「なんだよ、トム、夏中かかっちまうぜ。」
「それがどうした? もし真鍮の壺に百ドル入ってるのを見つけたらどうする、全部錆びて灰色になってるやつだ。それか、ダイヤモンドでいっぱいの腐った箱とかな。どうだ?」
ハックの目が輝いた。
「そりゃすげえ。おれには十分すぎるほどすげえぜ。百ドルくれりゃ、ダイヤモンドなんかいらねえ。」
「わかった。でも俺はダイヤモンドを捨てるつもりはないね。中には一個二十ドルの価値があるのもあるんだぜ――六ビット[訳注:75セント]か一ドルくらいの価値がないやつなんて、ほとんどないんだ。」
「まさか! 本当か?」
「もちろんさ――誰に聞いてもそう言うぜ。見たことないのか、ハック?」
「覚えてる限りじゃ、ねえな。」
「ああ、王様は山ほど持ってるぜ。」
「まあ、おれは王様なんて知らねえよ、トム。」
「だろうな。でもヨーロッパに行ったら、うじゃうじゃ飛び跳ねてるのが見られるぜ。」
「飛び跳ねるのか?」
「飛び跳ねる? ――ばあさんでもあるめえし! 違うよ!」
「じゃあ、なんて言ったんだよ?」
「ちぇっ、ただ見られるって言っただけだよ――もちろん飛び跳ねてるわけじゃない――なんで飛び跳ねなきゃならないんだ? ――ただ見られるってことさ――そこら中にいるって感じだよ、わかるだろ、なんとなく。あのせむしのリチャードじいさんみたいにさ。」
「リチャード? 苗字はなんだ?」
「苗字なんかないよ。王様には名前しかないんだ。」
「まさか?」
「本当さ。」
「まあ、そいつらがそれでいいんなら、いいけどよ、トム。おれは王様になって、ニガーみたいに名前だけってのはごめんだね。ところで――最初はどこを掘るんだ?」

「そうだなあ。蒸留所の小川の向こう側の丘にある、あの古い枯れ枝の木に挑戦してみるか?」
「いいぜ。」
そこで二人は、壊れかけのつるはしとシャベルを手に入れ、三マイルの道のりを歩き始めた。暑さと息切れで到着し、近くのニレの木の陰に身を投げ出して休み、一服した。
「これ、いいな」とトムが言った。
「おれもだ。」
「なあ、ハック、もしここでお宝を見つけたら、おまえの分け前はどうするんだ?」
「そうだな、毎日パイとソーダ水を飲む。それから、来るサーカスには全部行く。きっと楽しい時を過ごせるぜ。」
「へえ、少しも貯金しないのか?」
「貯金? 何のために?」
「そりゃ、後で暮らしていくためだよ。」
「ああ、そんなの無駄だ。おやじがいつかこの町に戻ってきて、おれが急いで使わねえと、そいつに爪をかけやがる。言っとくが、あっという間に空っぽにしちまうぜ。おまえはどうするんだ、トム?」
「俺は新しい太鼓と、本物の剣と、赤いネクタイと、ブルドッグの子犬を買って、結婚するんだ。」
「結婚!」
「そうだ。」
「トム、おまえ――なんだよ、正気か?」
「まあ待てよ――そのうちわかる。」
「そりゃ、おまえができる一番馬鹿げたことだぜ。おやじとおふくろを見てみろよ。喧嘩だ! なんだ、あいつらいつも喧嘩してたぜ。よーく覚えてる。」
「そんなのどうってことない。俺が結婚する女の子は喧嘩なんてしない。」
「トム、思うに、みんな同じだぜ。みんな男をこき使う。なあ、しばらくこのこと考え直した方がいい。そうした方がいいって言ってるんだ。その女の名前はなんだ?」
「女なんかじゃない――女の子だ。」
「同じことだと思うぜ。女って言う奴もいりゃ、女の子って言う奴もいる――たぶん、どっちも正しいんだろ。とにかく、名前はなんだ、トム?」
「いつか教えるよ――今はだめだ。」
「わかった――それでいい。ただ、おまえが結婚したら、おれは今まで以上に寂しくなるぜ。」
「そんなことないさ。俺と一緒に住めばいい。さあ、ここから動いて、掘り始めようぜ。」
二人は半時間、汗を流して働いた。成果はなし。さらに半時間、骨を折った。やはり成果はなし。ハックが言った。
「いつもこんなに深く埋めるのか?」
「時々ね――いつもじゃない。普通は違う。たぶん、場所が違うんだ。」

そこで二人は新しい場所を選び、再び掘り始めた。作業は少しだるくなってきたが、それでも進展はあった。しばらく黙々と掘り進めた。ついにハックはシャベルに寄りかかり、袖で額の玉の汗を拭って言った。
「ここを掘り終わったら、次はどこを掘るんだ?」
「たぶん、未亡人の家の裏のカーディフの丘の向こうにある、あの古い木に挑戦すると思う。」
「そいつは良さそうだな。でも、未亡人がおれたちから取り上げちまうんじゃねえか、トム? 彼女の土地だぜ。」
「彼女が取り上げるだって! やれるもんならやってみろってんだ。こういう隠された宝物を見つけた奴が、その持ち主なんだ。誰の土地かなんて関係ない。」
それで納得した。作業は続いた。やがてハックが言った。
「ちくしょう、また場所が違うにちげえねえ。どう思う?」
「すごく不思議だな、ハック。わからない。時々、魔女が邪魔するんだ。たぶん、今がそうなんだと思う。」
「ばかな! 魔女は昼間は力がないぜ。」
「ああ、そうだな。そこまで考えてなかった。ああ、わかったぞ! 俺たち、なんて馬鹿なんだ! 真夜中に枝の影がどこに落ちるかを見つけなきゃいけないんだ。そこを掘るんだよ!」
「それじゃ、ちくしょう、この骨折りは全部無駄だったってことか。くそっ、夜中にまた来なきゃならねえのか。ひどく遠いぜ。おまえ、抜け出せるか?」
「絶対抜け出すさ。今夜やらなきゃだめだ。誰かがこの穴を見たら、ここに何があるかすぐにわかって、取りに来ちまうからな。」
「わかった、今夜おまえの所へ行って、猫の鳴き真似をするぜ。」
「わかった。道具は茂みに隠しておこう。」
その夜、少年たちは約束の時間頃にそこにいた。彼らは影に座って待っていた。そこは寂しい場所で、古い言い伝えによって厳粛な雰囲気に包まれた時間だった。ざわめく木の葉には精霊がささやき、薄暗い隅には幽霊が潜み、遠くからは猟犬の低い吠え声が聞こえ、フクロウが墓場のような声でそれに答えた。少年たちはこの厳粛さに気圧され、ほとんど口をきかなかった。やがて、十二時になったと判断し、影が落ちる場所に印をつけ、掘り始めた。彼らの希望は高まり始めた。興味はますます強くなり、それに伴って作業の熱意も増した。穴はどんどん深くなっていったが、つるはしが何かに当たる音に心臓が跳ね上がるたびに、新たな失望を味わうだけだった。それはただの石か塊だった。ついにトムが言った。
「もうだめだ、ハック。また間違ってる。」
「でも、間違ってるはずがねえ。影の場所はぴったりだったぜ。」
「わかってる。でも、もう一つあるんだ。」
「なんだ?」
「そりゃ、時間は推測しただけだからさ。たぶん、遅すぎたか、早すぎたんだ。」
ハックはシャベルを落とした。
「それだ」と彼は言った。「まさにそれが問題だ。ここは諦めなきゃならねえ。正しい時間なんてわかりっこねえし、それにこんな夜中に、魔女や幽霊がそこら中を飛び回ってて、こんなことは怖すぎる。ずっと何かが後ろにいるような気がするんだ。振り向くのも怖い。たぶん、前にも別のやつらが機会を狙って待ってるかもしれねえ。ここに来てからずっと、鳥肌が立ってるぜ。」
「ああ、俺もだいたいそんな感じだよ、ハック。やつらはたいてい、木の下に宝物を埋める時、見張りのために死体を一緒に入れるんだ。」
「なんてこった!」
「ああ、そうするんだ。いつもそう聞いてる。」
「トム、おれは死人がいる所であんまりうろつきたくねえ。きっと、そいつらと厄介ごとになるに決まってる。」
「俺だって、やつらを起こしたくはないさ。もしここのやつが、頭蓋骨を突き出して何か言ったらどうする!」
「やめろよ、トム! 恐ろしいぜ。」
「ああ、本当にそうだ。ハック、俺、ちっとも落ち着かない。」
「なあ、トム、この場所は諦めて、どこか別の所を試そうぜ。」
「わかった、その方がいいと思う。」
「どこにする?」
トムはしばらく考え、そして言った。
「幽霊屋敷だ。それにしよう!」
「ちくしょう、おれは幽霊屋敷は好きじゃねえよ、トム。なんだ、死人よりずっとひでえぜ。死人は話すかもしれねえが、幽霊みたいに、気づかないうちに経帷子を着て滑るように近寄ってきて、突然肩越しに覗き込んで歯ぎしりしたりはしねえ。そんなこと、おれは耐えられねえよ、トム――誰も耐えられねえ。」
「ああ、でも、ハック、幽霊は夜しか出歩かないんだ。昼間にそこで掘るのを邪魔したりはしないさ。」
「まあ、そりゃそうだな。でも、おまえもよく知ってるだろ、あの幽霊屋敷には昼も夜も誰も近づかねえってことを。」
「まあ、そりゃたいてい、人が殺された場所には行きたくないからだよ――でも、あの家の周りで何かが見られたのは夜だけだ――窓のそばを青い光が滑るように動くだけで、ちゃんとした幽霊じゃない。」
「まあ、青い光がちらついてるのを見たら、トム、その後ろに幽霊がぴったりくっついてると見て間違いないぜ。理屈に合ってる。だって、幽霊以外にそんなもん使うやつはいねえって、おまえも知ってるだろ。」
「ああ、そうだな。でも、とにかく昼間は出てこないんだから、俺たちが怖がる必要はないだろ?」
「まあ、わかった。おまえがそう言うなら、幽霊屋敷に挑戦しよう――でも、賭けだと思うぜ。」

この時までに、二人は丘を下り始めていた。眼下の月明かりに照らされた谷の真ん中に、その「幽霊」屋敷が、完全に孤立して立っていた。塀はとうの昔になくなり、生い茂る雑草が玄関の階段さえ覆い隠し、煙突は崩れ落ち、窓枠は空っぽで、屋根の角は陥没していた。少年たちはしばらく見つめ、窓を青い光がよぎるのではないかと半ば期待していた。そして、時間と状況にふさわしく、低い声で話しながら、幽霊屋敷を大きく迂回するために、はるか右へと進路を取り、カーディフの丘の裏側を飾る森を通って家路についた。
第二十六章
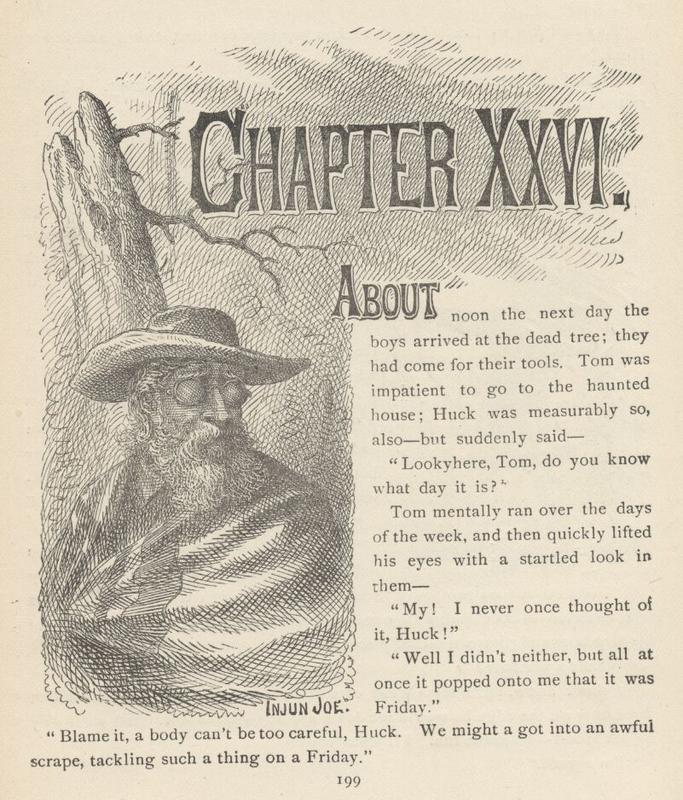
翌日の正午頃、少年たちは枯れ木の所に到着した。道具を取りに来たのだ。トムは幽霊屋敷へ行きたくてうずうずしていた。ハックもそれなりにそうだったが――突然言った。
「おい、トム、今日が何曜日か知ってるか?」
トムは心の中で曜日を数え、そしてはっとした表情で、さっと目を上げた――
「しまった! 全然考えてなかったよ、ハック!」
「まあ、おれもだ。でも、ふと金曜日だってことに気づいたんだ。」
「ちくしょう、いくら注意してもしすぎることはないな、ハック。金曜日にあんなことに手を出してたら、ひどい目に遭ってたかもしれない。」
「かもしれないだと! 遭ってたって言った方がいいぜ! 運のいい日もあるかもしれねえが、金曜日は違う。」
「そんなの馬鹿でも知ってる。おまえがそれを最初に発見したわけじゃないと思うぜ、ハック。」
「まあ、おれが最初だなんて言ってねえだろ? それに、金曜日だけじゃねえんだ。昨日の夜、ひでえ夢を見た――ネズミの夢だ。」
「まさか! 間違いなく厄介事の前触れだ。喧嘩してたか?」
「いや。」
「ああ、それはよかった、ハック。喧嘩してない時は、ただ周りに厄介事があるって印だからな。俺たちがしなきゃいけないのは、よく注意して、それに巻き込まれないようにすることだけだ。今日はこの話はやめて、遊ぼう。ロビン・フッドって知ってるか、ハック?」
「いや。誰だ、ロビン・フッドって?」
「そりゃ、イギリス史上、最も偉大な男の一人さ――そして最高にいい奴だ。強盗だったんだ。」

「ちくしょう、おれもなりてえな。誰から盗んだんだ?」
「保安官とか司教とか金持ちとか王様とか、そういう連中だけだ。でも貧しい人たちは絶対に困らせなかった。彼らを愛してたんだ。いつもきっちり公平に分け前を分け与えた。」
「へえ、そいつはいい奴だったにちげえねえな。」
「間違いなくそうさ、ハック。ああ、彼は史上最も高潔な男だった。今じゃそんな男はいないぜ、断言できる。片手を後ろに縛られても、イギリス中の誰にだって勝てた。それに、イチイの弓を使えば、一マイル半先から十セント硬貨を毎回射抜けたんだ。」
「イチイの弓ってなんだ?」
「知らない。もちろん、弓の一種さ。もしその硬貨の端っこにしか当たらなかったら、座り込んで泣いて――悪態をついたんだ。でも、ロビン・フッドごっこをしようぜ――すごく面白いんだ。教えてやるよ。」
「いいぜ。」
そこで二人は午後中ずっとロビン・フッドごっこをした。時折、幽霊屋敷の方へ憧れの眼差しを向け、明日の見通しや可能性について言葉を交わしながら。太陽が西に傾き始めると、二人は木々の長い影を横切って家路につき、やがてカーディフの丘の森の中に姿を消した。
土曜日の正午過ぎ、少年たちは再び枯れ木の所にいた。日陰で一服し、おしゃべりをした後、最後の穴を少し掘ってみた。大した希望があったわけではなく、ただトムが、宝物の六インチ手前まで掘って諦めた人が大勢いて、その後で別の誰かがやって来てシャベルの一突きで掘り当てた、という話がたくさんあると言ったからだ。しかし、今回はその手は通じず、少年たちは道具を肩にかけると、自分たちは運命を弄んだのではなく、宝探しの仕事に必要なすべての要件を果たしたのだと感じながら、その場を去った。
幽霊屋敷に着くと、焼けるような太陽の下でそこを支配する死のような静けさには、何か不気味でぞっとするものがあり、その場所の孤独と荒廃には、何か気が滅入るものがあったので、二人は一瞬、中に入るのをためらった。それから、ドアまで忍び寄り、震えながら中を覗き込んだ。そこには、雑草が生い茂り、床板がなく、漆喰の塗られていない部屋、古い暖炉、空っぽの窓、崩れかけた階段が見えた。そして、あちこちに、ぼろぼろになった見捨てられた蜘蛛の巣が垂れ下がっていた。やがて二人は、高鳴る鼓動を感じながら、そっと中に入った。ささやき声で話し、かすかな物音も聞き逃すまいと耳を澄ませ、いつでも逃げ出せるように筋肉を緊張させていた。
しばらくすると、見慣れたことで恐怖が和らぎ、二人はその場所を吟味するように興味深く調べ始めた。自分たちの度胸にむしろ感心し、また不思議にも思った。次に、二階を見てみたくなった。これは退路を断つようなものだったが、互いにけしかけ合ううちに、結果は一つしかなかった――道具を隅に放り投げ、階段を上った。上も同じように荒廃の兆候が見られた。一つの隅に、何か秘密を隠していそうな戸棚を見つけたが、その期待は裏切られた――中には何もなかった。今や彼らの勇気は高まり、しっかりと制御されていた。階下へ降りて作業を始めようとした、その時――
「しーっ!」とトムが言った。
「なんだ?」とハックが恐怖で青ざめながらささやいた。
「しーっ! ……ほら! ……聞こえるか?」
「うん! ……ああ、もう! 逃げよう!」
「静かに! 動くな! ドアの方にまっすぐ来る。」
少年たちは床に腹ばいになり、床板の節穴から目を覗かせ、恐怖にさいなまれながら待っていた。
「止まった……。いや――来る……。来たぞ。もう一言もささやくな、ハック。ああ、もう、ここから出られたらなあ!」
二人の男が入ってきた。少年たちはそれぞれ心の中で言った。「最近、町で一、二度見かけた、あの年寄りの、耳が聞こえず口もきけないスペイン人だ――もう一人の男は見たことがない。」
「もう一人」は、ぼろをまとい、むさくるしい風体で、その顔にはあまり好ましいものはなかった。スペイン人はセラペ[訳注:メキシコなどで用いられる肩掛け]に身を包んでいた。ふさふさした白い髭を生やし、ソンブレロ帽の下からは長い白髪が流れ、緑色のゴーグルをかけていた。二人が入ってきた時、「もう一人」は低い声で話していた。彼らは地面に座り、ドアの方を向き、壁に背をもたせると、話していた男は話を続けた。話が進むにつれて、彼の態度は警戒心が薄れ、言葉もはっきりしてきた。
「いやだ」と彼は言った。「全部考えたが、気に入らねえ。危険だ。」
「危険だと!」と、その「耳が聞こえず口もきけない」スペイン人がうなった――少年たちは心底驚いた。「弱虫め!」
その声に、少年たちは息をのみ、震え上がった。インジャン・ジョーの声だった! しばらく沈黙が続いた。そしてジョーが言った。
「向こうでの仕事より危険なことがあるか――だが、何も起こらなかった。」
「あれは別だ。川のずっと上流で、周りに家は一軒もなかった。成功しなかった以上、おれたちが試したことさえ、誰にも知られやしねえ。」
「じゃあ、昼間にここへ来ることより危険なことがあるか! ――見られたら誰だって怪しむだろう。」
「わかってる。だが、あの馬鹿げた仕事の後、ここほど都合のいい場所はなかったんだ。この小屋からは出たい。昨日も出たかったんだが、あの忌々しいガキどもが、丘の上で丸見えの所で遊んでやがるんじゃ、ここから動こうとしても無駄だった。」
「あの忌々しいガキども」は、この言葉に触発されて再び震え上がり、金曜日だということを思い出して一日待つことにしたのが、いかに幸運だったかを思った。心の中では、一年待てばよかったと願った。
二人の男は食べ物を取り出し、昼食にした。長く、考え込んだ沈黙の後、インジャン・ジョーが言った。
「おい、小僧――おまえは自分のいるべき川の上流へ帰れ。そこで俺からの連絡を待て。俺はもう一度だけ、様子見にこの町へ立ち寄る危険を冒す。少し探りを入れて、うまくいきそうだと思ったら、あの『危険な』仕事をやろう。そしたらテキサスだ! 一緒にずらかるぞ!」
これで話はまとまった。やがて二人ともあくびをし始め、インジャン・ジョーが言った。
「眠くて死にそうだ! おまえが見張りの番だ。」
彼は雑草の中に丸くなり、すぐにいびきをかき始めた。連れが一度か二度彼を揺すると、静かになった。やがて見張り役もこっくりし始め、頭はどんどん垂れ下がり、今や二人ともいびきをかき始めた。
少年たちは、感謝の長い息をついた。トムがささやいた。
「今がチャンスだ――来い!」
ハックが言った。
「無理だ。あいつらが目を覚ましたら、俺は死んじまう。」
トムはハックを促したが、ハックは尻込みした。とうとうトムは、ゆっくりと静かに立ち上がり、一人で歩き始めた。しかし、最初の一歩を踏み出した途端、いかれた床が耳障りな軋み音を立てたので、トムは恐怖のあまり死んだようにその場にしゃがみこんでしまった。二度目の挑戦はしなかった。少年たちはそこに横たわり、引き延ばされるような時間を数え続けた。やがて、時は尽き、永遠が白み始めるのではないかとさえ思われた。そしてついに陽が沈み始めたことに、二人は感謝の念を抱いた。
やがて、いびきの一つが止んだ。インジャン・ジョーが身を起こし、あたりを見回した。そして、膝に頭をうなだれている相棒に不気味な笑みを浮かべると、足で小突いて言った。
「おい! お前さん、見張り番じゃなかったのか! まあいい、何事もなかったみてえだしな。」
「おっと! 俺、寝てたか?」
「ああ、まあな。そろそろずらかる時間だ、相棒。残ったわずかな獲物はどうする?」
「さあな――いつも通り、ここに置いとくさ。南へ向かう時まで持ち出す必要はねえ。六百五十ドルの銀貨は、運ぶにはちと重い。」
「まあ――いいだろう。もう一度ここに来るのも手間じゃねえ。」
「ああ――だが、前みてえに夜に来るのがいいと思うぜ。その方がいい。」
「そうだな。だが、聞け。例の仕事にうってつけの機会が来るまでには、まだしばらくかかるかもしれん。何が起こるか分からねえし、ここはそんなにいい場所でもねえ。ちゃんと埋めちまおう――それも深く、な。」
「そりゃいい考えだ」と相棒は言い、部屋を横切ってひざまずくと、暖炉の奥の敷石を一枚持ち上げ、心地よい音を立てる袋を取り出した。彼はそこから自分用に二十ドルか三十ドル、インジャン・ジョーにも同額を抜き取り、残りを隅でひざまずいてボウイナイフで穴を掘っているインジャン・ジョーに渡した。
少年たちは一瞬にして、恐怖も惨めさもすべて忘れた。うっとりとした目で、二人の一挙手一投足を見守った。なんという幸運! その輝かしさは想像を絶していた! 六百ドルといえば、少年が六人いても金持ちになれる額だ! これぞ、この上ない幸運に恵まれた宝探し――どこを掘ればいいかなどと、面倒な不確かさに悩む必要もない。二人は絶えず互いを肘で突き合った。その雄弁な肘突きは、容易に理解できた。それはただ、「ああ、今ここにいて、ほんとによかったな!」という意味だったからだ。
ジョーのナイフが何かに当たった。
「ん?」と彼が言った。
「どうした?」と相棒が言った。
「半分腐った板だ――いや、箱みてえだな。おい、手を貸せ。何が入ってるか見てみよう。いや、待て、穴を開けちまった。」
彼は手を差し入れ、引き抜いた――
「おい、こいつは金だ!」
二人の男は、一握りの硬貨を調べた。金貨だった。階上の少年たちも、彼らと同じくらい興奮し、歓喜した。
ジョーの相棒が言った。
「こいつはさっさと片付けよう。暖炉の向こうの隅、雑草の中に古びた錆びたツルハシがあったぜ。さっき見たんだ。」
彼は走って行き、少年たちのツルハシとシャベルを持ってきた。インジャン・ジョーはツルハシを手に取り、吟味するように眺め、首を振り、何か独り言を呟くと、それを使って掘り始めた。箱はすぐに掘り出された。それほど大きくはなく、鉄の帯で補強されており、長い年月がそれを蝕むまでは、さぞ頑丈だったことだろう。男たちは至福の沈黙の中、しばらく宝物をうっとりと眺めていた。
「相棒、ここにゃ何千ドルもあるぜ」とインジャン・ジョーは言った。

「ムレルの手下が、ある夏、このあたりをうろついていたって話はよく聞くな」と、見知らぬ男が言った。
「知ってるさ」とインジャン・ジョーは言った。「どうやら、その通りだったようだな。」
「これでもう、あの仕事をする必要もなくなったな。」
混血の男は眉をひそめ、言った。
「お前は俺を知らねえ。少なくとも、あの件のすべてを知っちゃいねえ。ありゃ単なる強盗じゃねえ――復讐だ!」彼の目には邪悪な光が燃え上がった。「その仕事には、お前の助けがいる。それが終わったら――テキサスだ。お前のナンシーと子供らのとこへ帰って、俺からの連絡を待ってな。」
「まあ――お前がそう言うなら。こいつはどうする? また埋めるか?」
「ああ。[頭上では、狂喜乱舞] いや! 偉大なる酋長に誓って、だめだ! [頭上では、絶望の淵] 忘れかけてた。あのツルハシにゃ、新しい土がついてやがった! [少年たちは一瞬にして恐怖に打ちのめされた] なんでツルハシとシャベルがここにある? なんでそれに新しい土がついてるんだ? 誰がここに持ち込んだ――そして、そいつらはどこへ消えた? 誰か物音を聞いたか? ――誰か見たか? 何だと! また埋めて、奴らが戻ってきて地面が荒らされてるのを見させるってのか? とんでもねえ――とんでもねえ話だ。こいつは俺の隠れ家に運ぶ。」
「そりゃそうだ! もっと早く気づくべきだったな。一番のことか?」
「いや――二番だ――十字架の下のな。もう一つの場所はまずい。ありふれすぎてる。」
「分かった。そろそろ出発するのにちょうどいい暗さだ。」
インジャン・ジョーは立ち上がると、窓から窓へと移動し、用心深く外を覗いた。やがて彼は言った。
「誰がこの道具を持ってきたんだ? 二階にいると思うか?」
少年たちは息を呑んだ。インジャン・ジョーはナイフに手をかけ、一瞬ためらった後、階段の方を向いた。少年たちは戸棚のことを考えたが、もう力は残っていなかった。軋む足音が階段を上ってくる――この耐え難い状況が、打ちひしがれた少年たちの決意を呼び覚ました。彼らが戸棚へ飛び込もうとしたその時、腐った材木が砕ける音がして、インジャン・ジョーは崩れた階段の残骸とともに地面に落下した。彼は悪態をつきながら身を起こすと、相棒が言った。
「おい、そんなことして何になる? 誰かいようが、上にいるなら、放っておきゃいい――誰が気にするもんか。今飛び降りて、面倒に巻き込まれたいってんなら、誰が止める? あと十五分もすりゃ真っ暗だ。そしたら、ついてきたきゃ、ついてこさせりゃいい。俺は構わねえぜ。俺の考えじゃ、ここに道具を放り込んだ奴は、俺たちを見かけて、幽霊か悪魔か何かだと思ったのさ。今頃まだ逃げてるに違いねえ。」

ジョーはしばらく不平を言っていたが、やがて友の意見に同意した。残された日の光は、出発の準備を整えるために節約すべきだと。まもなく、二人は深まる夕闇の中、家を抜け出し、貴重な箱を抱えて川の方へと向かった。
トムとハックは、弱ってはいたが心底安堵して立ち上がり、家の丸太の隙間から彼らの後姿を見つめた。後を追うか? とんでもない。首の骨を折らずに再び地上に降り立ち、丘を越えて町へ戻る道を行けるだけで満足だった。二人はあまり口をきかなかった。自分自身を憎むことに、シャベルとツルハシをそこに持ってきてしまった不運を憎むことに夢中だったのだ。あれがなければ、インジャン・ジョーは決して疑うことはなかっただろう。彼は銀貨を金貨と一緒に隠し、彼の「復讐」が果たされるまでそこに置いておき、そして戻ってきた時に金が忽然と消えているという不運に見舞われたはずだったのだ。道具をあそこに持ってきてしまったとは、なんという、なんという不運だろう!
二人は、あのスペイン人が復讐の機会をうかがって町に現れたら見張りを続け、それがどこであろうと「二番」まで後をつけることを決意した。その時、トムにぞっとする考えが浮かんだ。
「復讐だって? なあハック、もしあいつが狙ってるのが俺たちだったらどうする!」
「よ、よせよ!」とハックは、卒倒しそうになって言った。
二人はそのことについてとことん話し合い、町に入る頃には、おそらく他の誰かのことだろうと信じることにした――少なくとも、証言したのはトムだけなのだから、トム以外の誰でもないだろう、と。
一人だけ危険に晒されるというのは、トムにとって、まことに、まことに些細な慰めでしかなかった! 仲間がいた方が、目に見えてましだと彼は思った。
第二十七章
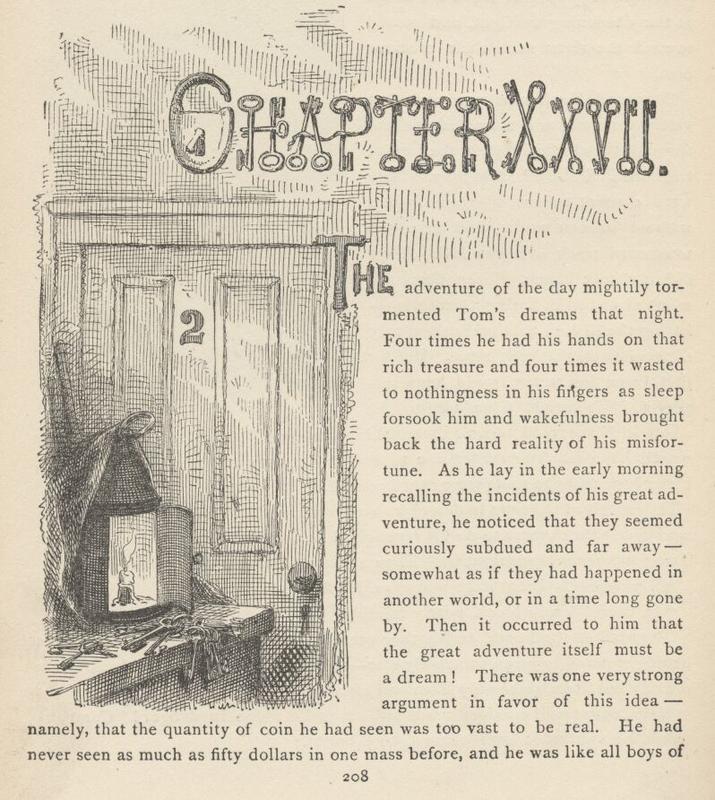
その日の冒険は、その夜のトムの夢をひどく苦しめた。四度も彼はその豊かな宝に手をかけたが、四度とも、眠りが彼を見放し、目覚めが彼の不運という厳しい現実を連れ戻すたびに、それは指の間から虚無へと消えていった。早朝、横になりながら大冒険の出来事を思い出していると、それらが奇妙に和らぎ、遠く感じられることに気づいた。まるで別の世界で、あるいは遠い昔に起こったことのようだった。その時、彼は、あの大冒険そのものが夢に違いないと思いついた! この考えを支持する非常に強力な論拠が一つあった。すなわち、彼が見た硬貨の量は、現実であるにはあまりにも莫大すぎたのだ。彼はこれまで五十ドルもの大金を一度に見たことがなく、同年代、同階層の少年たちと同様に、「何百」「何千」という言葉は単なる fanciful な言葉のあやで、そんな大金がこの世に実在するはずはないと思い込んでいた。百ドルもの大金が、実際に誰かの手元にあるなどとは、一瞬たりとも考えたことがなかった。彼の隠された宝物に対する観念を分析したとすれば、それは一握りの本物のダイム硬貨と、一ブッシェル分もの漠然として、素晴らしく、掴みどころのないドル紙幣で構成されていたことが分かっただろう。
しかし、冒険の出来事は、繰り返し考えるうちに、次第にはっきりと鮮明になってきた。そして彼は、やはりあれは夢ではなかったのかもしれない、という印象に傾いていった。この不確かさは払拭されねばならない。彼は急いで朝食をかきこみ、ハックを探しに行くことにした。ハックは平底船の舷に腰かけ、気だるそうに足を水にぶらつかせ、ひどく憂鬱な顔をしていた。トムは、ハックの方からその話題を切り出させることにした。もし彼がそうしなければ、あの冒険はただの夢だったと証明されることになる。
「よう、ハック!」
「よう、そっちこそ。」
一分ほどの沈黙。
「トム、もし俺たちがあのいまいましい道具を枯れ木に置いていきゃ、金は手に入ったのにな。ああ、なんてこった!」
「夢じゃないんだ、じゃあ、夢じゃないんだな! なんだか、いっそ夢だったらよかったのにって思うよ。ちくしょう、ほんとだぜ、ハック。」
「何が夢じゃないって?」
「ああ、昨日のことさ。半分夢だったんじゃないかと思ってたんだ。」

「夢だと! あの階段がぶっ壊れなきゃ、どれだけ夢だったか思い知らされてたぜ! 俺なんか一晩中、夢にうなされたんだ。あの片目に眼帯したスペインの悪魔が、ずっと追いかけてきやがって――くたばっちまえ!」
「いや、くたばらせるな。見つけるんだ! 金を追跡するんだ!」
「トム、あいつを見つけられるわけがねえよ。あんな大金を手に入れるチャンスなんて、一度っきりさ。そして、そいつはもう失われたんだ。どのみち、あいつに会ったら、俺はがたがた震えちまうだろうしな。」
「まあ、俺もそうだろうけど、それでも会いたいよ。そして追跡するんだ――あいつの『二番』までな。」
「『二番』――そう、それだ。俺も考えてたんだ。だけど、さっぱり分からねえ。お前は、あれが何だと思う?」
「分かんない。深すぎるよ。なあ、ハック――家の番号かもしれないぜ!」
「そりゃいい! ……いや、トム、違うな。もしそうだとしても、こんな場末の町じゃねえよ。ここには番号なんてないからな。」
「ああ、そうだな。ちょっと考えさせてくれ。そうだ――宿屋の部屋番号だ!」
「おお、それだ! 宿屋は二軒しかない。すぐに分かるぜ。」
「ここで待ってろ、ハック。すぐ戻るから。」
トムはすぐさま駆け出した。人目につく場所でハックと一緒にいるのは気が進まなかったのだ。彼は三十分ほどで戻ってきた。一番良い宿屋では、二号室は若い弁護士がずっと使っており、今もそうだった。もう一方の、それほど立派ではない宿屋では、二号室は謎に包まれていた。宿屋の主人の息子が言うには、いつも鍵がかかっていて、夜以外に誰かが入ったり出たりするのを見たことがないという。なぜそんな状態なのか、特別な理由は知らないらしい。少しは好奇心もあったが、それほど強くはなかった。その謎を最大限に利用して、あの部屋は「幽霊が出る」のだと考えて楽しんでいた。昨夜、そこに明かりがついていたのに気づいたという。
「これが分かったことだ、ハック。俺たちが探してるのは、まさにその二号室だと思う。」
「俺もそう思うぜ、トム。で、どうするんだ?」
「考えさせてくれ。」
トムは長い間考え込んだ。そして言った。
「いいか。その二号室の裏口は、宿屋とあの古ぼけたレンガ造りの店の間の、狭い路地裏に通じるドアだ。お前は見つけられるだけの鍵を全部手に入れろ。俺はおばさんの鍵を全部くすねる。そして、最初の暗い夜に、そこへ行って試してみるんだ。それから、インジャン・ジョーを見張っておけ。あいつは復讐の機会をうかがうために、もう一度町に立ち寄ると言ってたからな。もしあいつを見かけたら、後をつけろ。もしあいつがその二号室に行かなかったら、そこは違うってことだ。」
「おいおい、一人であいつを尾行するなんて嫌だぜ!」
「大丈夫、夜になるさ。あいつにお前が見えるわけないし、もし見えたとしても、何も思わないかもしれない。」
「うーん、もし真っ暗なら、尾行してみるか。分かんねえ――分かんねえけど、やってみるよ。」
「暗かったら、俺が尾行するに決まってるさ、ハック。だって、あいつは復讐ができないと分かって、まっすぐ金のところへ行くかもしれないだろ。」
「その通りだ、トム、その通りだ。俺が尾行するよ。ちくしょう、やってやる!」
「その意気だ! 弱気になるなよ、ハック。俺も弱気にならないからな。」
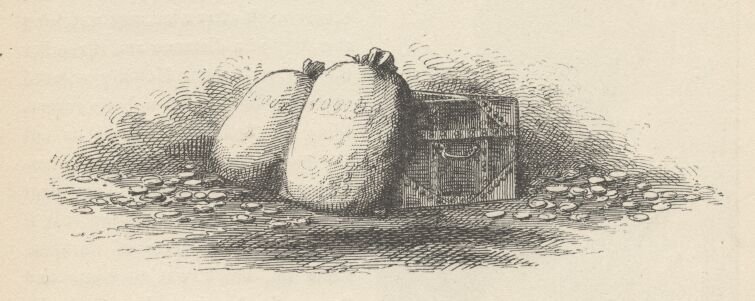
第二十八章
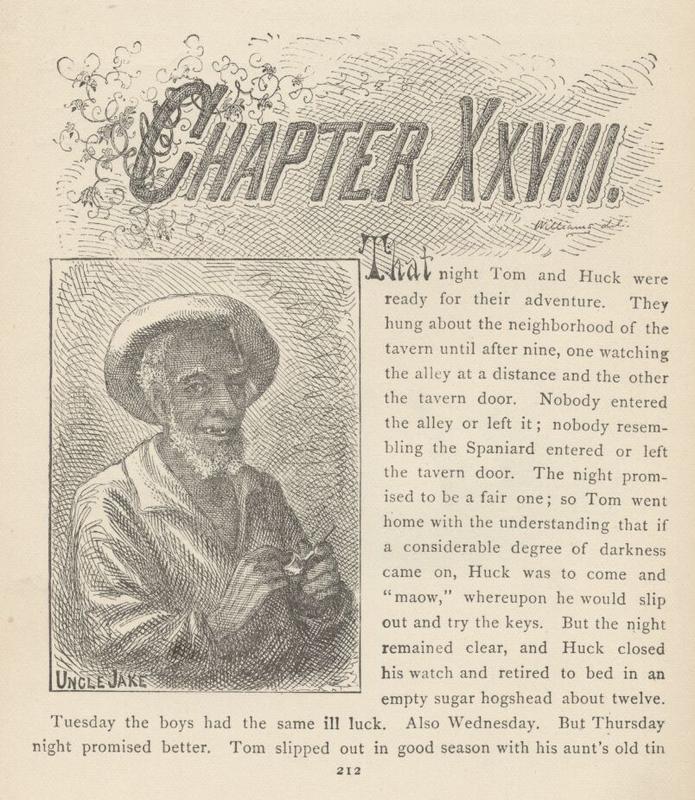
その夜、トムとハックは冒険の準備を整えていた。二人は九時過ぎまで宿屋の近辺をうろつき、一人は離れた場所から路地裏を、もう一人は宿屋の戸口を見張っていた。路地裏に出入りする者はおらず、スペイン人に似た男が宿屋の戸口に出入りすることもなかった。その夜は晴れそうだったので、トムは、もし十分に暗くなったらハックがやってきて「ニャーオ」と鳴き、そしたら自分が抜け出して鍵を試す、という約束で家に帰った。しかし夜は晴れたままで、ハックは十二時頃に見張りを終え、空の砂糖樽の中で寝床についた。

火曜日も少年たちは同じ不運に見舞われた。水曜日も同様だった。しかし木曜の夜は期待できそうだった。トムは頃合いを見計らって、おばさんの古いブリキのランタンと、それに目隠しをするための大きなタオルを持って家を抜け出した。彼はランタンをハックの砂糖樽に隠し、見張りを開始した。真夜中の一時間前、宿屋は閉まり、その明かり(あたりで唯一の明かりだった)も消された。スペイン人は見かけなかった。路地裏に出入りする者もいなかった。すべてが好都合だった。漆黒の闇が支配し、完全な静寂は、時折聞こえる遠雷のうなり声によってのみ破られた。
トムはランタンを取り、樽の中で火を灯し、タオルでしっかりと包むと、二人の冒険家は暗闇の中を宿屋へと忍び寄った。ハックが見張りに立ち、トムは手探りで路地裏へと入っていった。それから、ハックの心に山のようにのしかかる、不安な待ち時間が続いた。彼はランタンの光が見えればいいのに、と思い始めた。それは彼を怖がらせるだろうが、少なくともトムがまだ生きていることを教えてくれるだろう。トムが姿を消してから何時間も経ったように思えた。きっと気絶したに違いない。もしかしたら死んでしまったのかもしれない。恐怖と興奮で心臓が破裂したのかもしれない。不安に駆られたハックは、ありとあらゆる恐ろしいことを恐れ、息を呑むような大惨事が今にも起こるのではないかと身構えながら、気づけば路地裏にどんどん近づいていた。もっとも、呑むべき息はあまり残っていなかった。指ぬき一杯分ずつしか吸い込めないようで、心臓もあの打ち方ではすぐにすり減ってしまうだろう。突然、閃光が走り、トムが彼のそばを駆け抜けていった。「逃げろ!」と彼は言った。「命がけで逃げろ!」
繰り返す必要はなかった。一度で十分だった。ハックは、その言葉が繰り返される前に、時速三十マイルか四十マイルで走り出していた。少年たちは、村のはずれにある廃墟の屠殺場の小屋にたどり着くまで止まらなかった。ちょうどその物陰に入った途端、嵐が起こり、雨が降り注いだ。トムは息が整うとすぐに言った。
「ハック、ひどかったよ! 鍵を二つ、できるだけそっと試したんだ。でも、ものすごい音がする気がして、怖くて息もできなかった。鍵穴も回らなかったし。それで、何をやってるのかも分からずに、ドアノブを掴んだら、ドアが開いたんだ! 鍵がかかってなかったんだよ! 中に飛び込んで、タオルを外したら、シーザーの亡霊にかけて!」
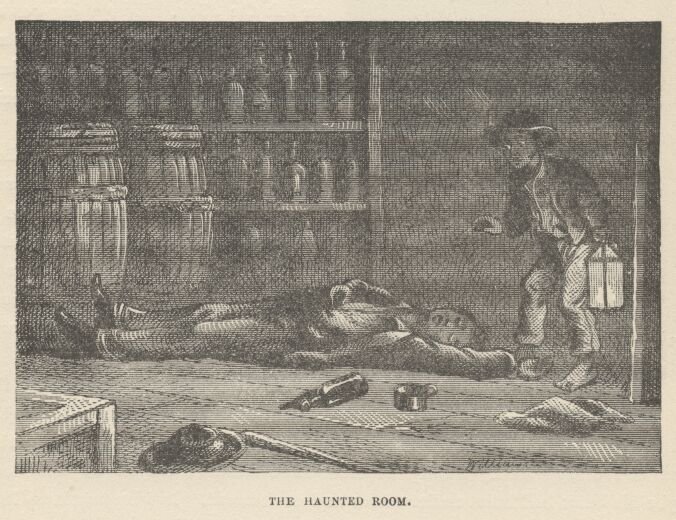
「何だ! ――何を見たんだ、トム?」
「ハック、もう少しでインジャン・ジョーの手に踏みつけるところだった!」
「まさか!」
「本当さ! あいつ、床の上でぐっすり眠ってたんだ。いつもの眼帯をして、両腕を広げてさ。」
「おいおい、どうしたんだ? あいつ、起きなかったのか?」
「いや、ぴくりともしなかった。酔っ払ってたんだと思う。俺はとにかくタオルを掴んで逃げ出したんだ!」
「俺だったら、タオルのことなんて思いつきもしなかっただろうな、きっと!」
「俺は思いつくさ。おばさんに失くしたなんて言ったら、ひどい目に遭わされるからな。」
「なあ、トム、あの箱は見たか?」
「ハック、あたりを見回す余裕なんてなかったよ。箱も見なかったし、十字架も見なかった。インジャン・ジョーのそばの床にあった瓶とブリキのカップ以外、何も見なかった。ああ、部屋には樽が二つと、もっとたくさんの瓶があったな。これで分かっただろ、あの『幽霊が出る部屋』の正体が。」
「どういうことだ?」
「そりゃ、ウィスキーの幽霊が出るのさ! もしかしたら、禁酒酒場にはみんな幽霊が出る部屋があるんじゃないか、なあ、ハック?」
「まあ、そうかもしれねえな。誰がそんなこと考えつくもんか。でもなあ、トム、インジャン・ジョーが酔っ払ってるんなら、今こそあの箱を手に入れる絶好の機会じゃないか。」
「そうだな! お前がやってみろよ!」
ハックは身震いした。
「いや、まあ――やめとくよ。」
「俺もやめとくさ、ハック。インジャン・ジョーのそばに瓶が一本だけじゃ足りない。三本あったら、あいつは十分酔っ払ってて、俺がやっただろうけどな。」
しばらく考え込む沈黙があり、それからトムが言った。
「いいか、ハック。インジャン・ジョーが中にいないって分かるまで、もうあのことはやめよう。怖すぎる。なあ、毎晩見張ってれば、いつかあいつが出て行くのを確実に見られる。そしたら、稲妻よりも速くあの箱をかっさらうんだ。」
「ああ、賛成だ。一晩中見張ってやる。毎晩だってやるぜ、お前がもう一方の役目をやるんならな。」
「分かった、やるよ。お前はフーパー通りを一周してニャーオと鳴けばいい。もし俺が寝てたら、窓に砂利を投げてくれ。そしたら起きるから。」
「了解、それで決まりだ!」
「さて、ハック、嵐は過ぎたし、俺は家に帰るよ。あと二時間もすれば夜が明ける。お前は戻って、ずっと見張っててくれるかい?」
「やると言ったろ、トム。やるよ。一年だって、あの宿屋に取り憑いてやる! 昼間は一日中寝て、夜は一晩中見張ってやるさ。」
「それでいい。じゃあ、お前はどこで寝るんだ?」
「ベン・ロジャースの干し草小屋さ。あいつが許してくれてるし、あいつの親父んとこの黒んぼのジェイクおじさんもな。ジェイクおじさんが水を運んでほしい時はいつでも運んでやるし、頼めばいつでも、もし余裕があれば何か食い物をくれるんだ。ありゃ、すごくいい黒んぼだぜ、トム。俺があの人を見下したりしないから、好かれてるんだ。時々、ちゃんと座って一緒に飯を食ったこともある。でも、このことは言うなよ。腹がぺこぺこの時は、普段ならやりたくないことでも、やらなきゃならねえことがあるんだ。」
「分かった。昼間にお前に用がなけりゃ、寝かせておくよ。邪魔しに行ったりしない。夜に何かあったら、すぐにこっちに来てニャーオと鳴いてくれ。」

第二十九章
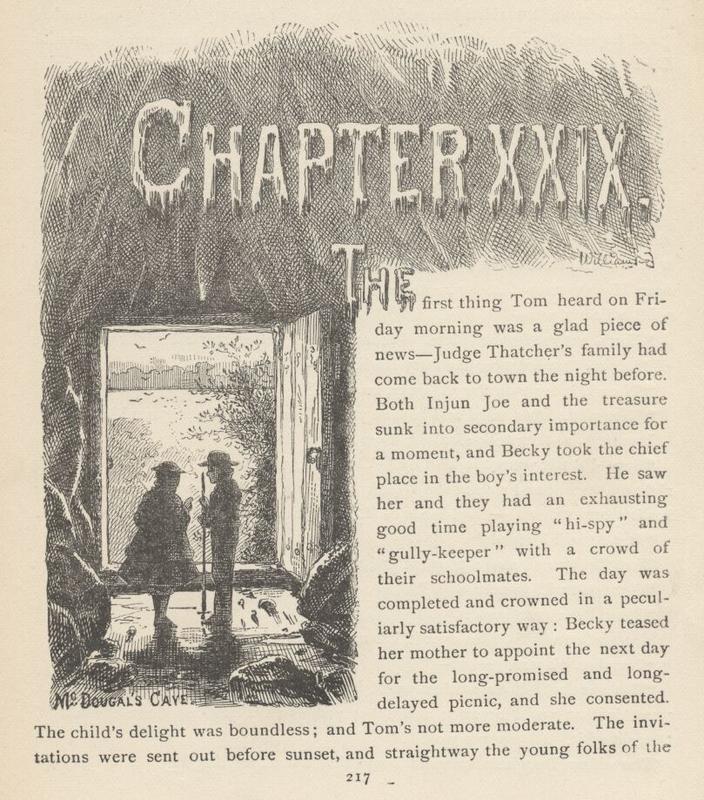
金曜の朝、トムが最初に聞いたのは嬉しい知らせだった。サッチャー判事一家が昨夜、町に戻ってきたのだ。インジャン・ジョーも宝物も、一瞬にして二の次となり、ベッキーが少年の関心の的となった。彼はベッキーに会い、大勢の学友たちと「ヒスピー」や「ガリーキーパー」をして、へとへとになるまで楽しい時間を過ごした。その日は、ことのほか満足のいく形で締めくくられた。ベッキーが母親に、かねてから約束され、延び延びになっていたピクニックを翌日に開くようねだったところ、母親が承諾したのだ。子供の喜びは果てしなく、トムの喜びもそれに劣らなかった。招待状は日没前に発送され、たちまち村の若者たちは準備と楽しい期待で熱に浮かされたようになった。トムは興奮のあまり、かなり遅い時間まで起きていられた。彼は、ハックの「ニャーオ」を聞き、翌日、宝物でベッキーやピクニックの仲間たちを驚かせることを大いに期待していた。しかし、彼はがっかりさせられた。その夜、合図は来なかった。
やがて朝が来て、十時か十一時になる頃には、陽気で浮かれた一行がサッチャー判事の家に集まり、出発の準備は万端だった。年配者がその存在でピクニックを台無しにするのは慣わしではなかった。子供たちは、十八歳の若い女性数名と、二十三歳そこそこの若い紳士数名の保護下にあれば十分に安全だと考えられていた。その日のために古い蒸気フェリーボートが貸し切られ、やがて、食料の籠を抱えた陽気な一団がメインストリートを行進した。シッドは病気で楽しみを逃さねばならず、メアリーは彼を楽しませるために家に残った。サッチャー夫人がベッキーに最後に言った言葉はこうだった。
「帰りは遅くなるでしょう。フェリー乗り場の近くに住んでいる女の子の誰かの家に、一晩泊めてもらった方がいいかもしれませんよ。」
「じゃあ、スージー・ハーパーの家に泊まるわ、ママ。」
「よろしい。いい子にして、迷惑をかけないようにね。」
やがて、二人が軽やかに歩いていると、トムがベッキーに言った。
「なあ、いいことを教えてやろう。ジョー・ハーパーの家に行く代わりに、丘をまっすぐ登ってダグラス未亡人の家に寄ろうよ。あそこにはアイスクリームがあるんだ! ほとんど毎日、山ほどあるんだぜ。それに、俺たちが来たら、すごく喜んでくれるよ。」
「まあ、楽しそう!」
それからベッキーは少し考えて言った。
「でも、ママが何て言うかしら?」
「どうして分かるもんか。」
少女はその考えを頭の中で巡らせ、しぶしぶ言った。
「いけないことだと思うわ――でも――」
「でも、なんてことないさ! 君のお母さんには分からないんだから、何の害がある? お母さんが望んでるのは君が無事だってことだけさ。もし思いついてたら、あそこへ行けって言ったに違いないよ。絶対そうだ!」
ダグラス未亡人の素晴らしいもてなしは、魅力的な餌だった。それとトムの説得が、やがて功を奏した。かくして、その夜の計画については誰にも何も言わないことに決まった。やがてトムは、もしかしたらハックがまさに今夜やってきて合図をするかもしれない、と思いついた。その考えは、彼の期待から多くの気力を奪い去った。それでも、ダグラス未亡人の家での楽しみを諦める気にはなれなかった。それに、なぜ諦めなければならないのか、と彼は考えた。昨夜は合図が来なかったのだから、今夜来る可能性がそれ以上にあるわけがない。その夜の確実な楽しみは、不確かな宝物に勝った。そして、少年らしく、彼はより強い衝動に身を任せ、その日はもう金の箱のことは考えないことに決めた。
町から三マイル下ったところで、フェリーボートは木々に覆われた谷間の入り口で停泊した。一行はどっと岸に上がり、まもなく森の奥や岩だらけの高みに、叫び声や笑い声が遠くまで響き渡った。暑くなり、疲れるためのありとあらゆる方法が試され、やがて放浪者たちは、頼もしい食欲を携えてキャンプによろよろと戻ってきて、ご馳走の破壊が始まった。饗宴の後、広がる樫の木の陰で、休息と談笑の爽やかな時間が流れた。やがて誰かが叫んだ。
「洞窟に行く準備ができたのは誰だ?」
全員だった。ろうそくの束が用意され、たちまち丘の上へと一斉に駆け出した。洞窟の入り口は丘の中腹にあった。Aの字の形をした開口部だ。その巨大な樫の扉は、かんぬきが外されていた。中は氷室のようにひんやりとした小部屋で、自然が作り出した固い石灰岩の壁は、冷たい汗で湿っていた。この深い闇の中に立ち、太陽に輝く緑の谷間を眺めるのは、ロマンチックで神秘的だった。しかし、その場の感動はすぐに薄れ、再びはしゃぎ始めた。ろうそくが一本灯されると、その持ち主に一斉に殺到した。もみ合いと勇敢な防戦が続いたが、ろうそくはすぐに叩き落とされるか吹き消され、そして陽気な笑い声と新たな追いかけっこが始まった。しかし、すべてのものには終わりがある。やがて行列は、本道の急な下り坂を列をなして下って行った。揺らめく光の列が、頭上六十フィートでほぼ接合する高い岩壁をぼんやりと照らし出していた。この本道は幅が八フィートか十フィートしかなかった。数歩ごとに、さらに高く、さらに狭い裂け目が両側から枝分かれしていた。マクドゥーガルの洞窟は、互いに入り組んではまた外れ、どこにも通じていない、曲がりくねった通路の広大な迷宮に過ぎなかったのだ。その複雑に絡み合った裂け目や割れ目を何日も何晩もさまよい続けても、決して洞窟の終わりを見つけることはできず、下へ、下へ、さらに下へと大地にもぐっていっても、ただ同じ――迷宮の下に迷宮があり、どれにも終わりはない、と言われていた。誰も洞窟を「知って」はいなかった。それは不可能なことだった。若者たちのほとんどはその一部を知っており、この知られた部分を大きく越えて冒険することは通例ではなかった。トム・ソーヤーは、誰にも劣らず洞窟のことを知っていた。

行列は本道を四分の三マイルほど進み、それからグループやカップルが脇道にそれ始め、薄暗い廊下を駆け抜け、廊下が再び合流する地点で互いを驚かせ合った。一行は、「知られた」場所を越えずに、三十分ほど互いをうまくかわすことができた。
やがて、次から次へとグループが洞窟の入り口によろよろと戻ってきた。息を切らし、陽気で、頭からつま先までロウの滴で汚れ、粘土でまみれ、その日の成功にすっかり満足していた。それから彼らは、時間を全く気にしていなかったこと、そして夜が間近に迫っていることに気づいて驚いた。鳴り響く鐘は、三十分も前から鳴り続けていた。しかし、この種の冒険の日の終わり方はロマンチックであり、したがって満足のいくものだった。その荒々しい積み荷を乗せたフェリーボートが流れに押し出された時、無駄になった時間を気にする者は、船の船長以外には六ペンス分もいなかった。

フェリーボートの明かりが波止場をきらめきながら通り過ぎた時、ハックはすでに見張りに就いていた。船上の物音は聞こえなかった。若者たちは、死ぬほど疲れている人々が普通そうであるように、静まり返っていたからだ。彼はあれが何の船で、なぜ波止場に止まらないのか不思議に思った。そして、そのことは頭から追い出し、自分の仕事に注意を向けた。夜は曇ってきて暗くなっていった。十時になり、乗り物の音は止み、まばらな明かりが消え始め、ぶらぶら歩く歩行者もいなくなり、村は眠りにつき、小さな見張り番は静寂と幽霊たちと共に一人取り残された。十一時になり、宿屋の明かりが消された。今や、どこもかしこも闇だった。ハックは、うんざりするほど長い時間に思えたが、何も起こらなかった。彼の信念は揺らぎ始めていた。意味があるのだろうか? 本当に意味があるのだろうか? 諦めて寝てしまってはどうか?
物音が彼の耳に届いた。彼は一瞬にして全神経を集中させた。路地裏のドアが静かに閉まった。彼はレンガ造りの店の角に飛びついた。次の瞬間、二人の男が彼のそばをかすめて通り過ぎ、一人は腕の下に何かを抱えているようだった。あの箱に違いない! つまり、彼らは宝物を運び出すつもりなのだ。今トムを呼んでどうなる? 馬鹿げている――男たちは箱を持って逃げ去り、二度と見つからないだろう。いや、彼らの後をぴったりとつけて、尾行するのだ。発見されないためには、闇を頼りにするしかない。そう自分に言い聞かせ、ハックは歩み出て、猫のように裸足で、男たちの後ろを滑るように進んだ。見失わない程度に、ちょうどよい距離を保ちながら。
彼らは川沿いの通りを三ブロック上り、それから左に折れて横道に入った。そして、カーディフの丘へ続く道に出るまでまっすぐ進み、その道に入った。丘の中腹にある古いウェールズ人の家のそばを、ためらうことなく通り過ぎ、さらに登り続けた。よし、とハックは思った。古い石切り場に埋めるつもりだな。しかし、彼らは石切り場では止まらなかった。通り過ぎて、山頂へと向かった。背の高いハゼノキの茂みの間の狭い道に分け入り、すぐに闇の中に隠れた。ハックは距離を詰め、短くした。もう彼らに見られることはないだろうからだ。彼はしばらく小走りで進み、それからペースを落とした。追いつきすぎるのを恐れたのだ。少し進み、それから完全に立ち止まった。耳を澄ませた。音はしない。自分の心臓の鼓動が聞こえるような気がする以外は、何も。フクロウの鳴き声が丘を越えてやってきた――不吉な音だ! しかし、足音はしない。なんてことだ、すべて見失ってしまったのか! 彼が翼の生えた足で飛び出そうとした時、四フィートと離れていない場所で男が咳払いをした! ハックの心臓は喉まで飛び出したが、彼はそれを再び飲み込んだ。そして、まるで十数もの悪寒に一度に取り憑かれたかのように震えながらそこに立ち尽くし、あまりの衰弱に、きっと地面に倒れてしまうだろうと思った。彼は自分がどこにいるか分かっていた。ダグラス未亡人の敷地へと続く踏み段から五歩以内にいることを知っていた。結構だ、と彼は思った。そこに埋めさせればいい。見つけるのは難しくないだろう。
その時、声がした――とても低い声――インジャン・ジョーの声だった。
「ちくしょう、あの女、客がいるのかもしれん――こんなに遅いのに、明かりがついてる。」
「俺には見えんが。」
これは、あの見知らぬ男の声だった――お化け屋敷の見知らぬ男だ。ハックの心臓に、死ぬような寒気が走った。これこそが、あの「復讐」の仕事だったのだ! 彼の考えは、逃げることだった。しかしその時、ダグラス未亡人が一度ならず自分に親切にしてくれたことを思い出した。もしかしたら、この男たちは彼女を殺すつもりなのかもしれない。彼は、思い切って彼女に警告できたら、と願った。しかし、自分にそんな勇気はないことを知っていた。彼らがやってきて、捕まってしまうかもしれない。見知らぬ男の言葉と、インジャン・ジョーの次の言葉――それは――の間に経過した一瞬のうちに、彼はこれらすべて、そしてそれ以上のことを考えた。
「茂みがお前の邪魔をしてるからだ。こっちだ――ほら、見えるだろ?」
「ああ。なるほど、客がいるようだな。諦めた方がいい。」
「諦めろだと、俺がこの国を永遠に去ろうとしてるってのによ! 諦めて、二度とチャンスがねえかもしれねえってのによ。前にも言ったが、もう一度言う。俺はあの女の獲物なんざどうでもいい――お前にやる。だが、あの女の亭主は俺に手荒だった――何度も手荒だった。何より、あいつは俺を浮浪者としてぶち込んだ治安判事だった。それだけじゃねえ。それの百万分の一にもなりゃしねえ! あいつは俺を鞭打ちにしやがった! ――牢屋の前で、黒んぼみてえによ! ――町中の奴らが見てる前でだ! 鞭打ちだ! ――分かるか? あいつは俺を利用して、死んでいきやがった。だが、俺はあの女で晴らしてやる。」
「おい、殺すな! それだけはよせ!」
「殺す? 誰が殺すなんて言った? あいつがここにいりゃ、殺してやっただろうがな。だが、女は違う。女に復讐したい時、殺したりはしねえ――馬鹿な! 容姿を狙うのさ。鼻を裂き――雌豚みてえに耳に切り込みを入れるんだ!」
「なんてこった、そいつは――」
「意見は自分の中にしまっとけ! それがお前にとっちゃ一番安全だ。俺はあの女をベッドに縛り付ける。もし出血多量で死んだとして、そいつは俺のせいか? 死んだって、俺は泣かねえよ。なあ相棒、この仕事を手伝ってもらうぜ。俺のためにな。だからお前はここにいるんだ。一人じゃ無理かもしれんからな。もしひるんだら、お前を殺す。分かったか? そして、もしお前を殺さなきゃならなくなったら、あの女も殺す。そしたら、誰がこの仕事をやったかなんて、誰も分かりゃしねえだろうよ。」
「まあ、やらなきゃならねえんなら、さっさとやろうぜ。早い方がいい――俺はもう震えが止まらねえ。」
「今やるだと? 客がいるってのにか? いいか、すぐにでもお前を疑うことになるぜ。いや――明かりが消えるまで待つ。急ぐことはねえ。」
ハックは、沈黙が訪れようとしているのを感じた。それは、どんな残忍な会話よりも恐ろしいものだった。そこで彼は息を止め、そろそろと後ずさりした。片足で不安定にバランスを取り、危うくあちらこちらに倒れそうになりながら、慎重に、そしてしっかりと足を踏み出した。同じように念入りに、同じ危険を冒して、もう一歩後ずさりした。そしてまた一歩、また一歩と――足元で小枝がぽきりと折れた! 彼の息は止まり、耳を澄ませた。音はしない――完全な静寂だった。彼の感謝は計り知れなかった。今や彼は、ハゼノキの茂みの壁の間で、来た道を引き返した。まるで船のように慎重に身を翻し、それから素早く、しかし用心深く歩き出した。石切り場に出た時、彼は安心し、軽快な踵を返して飛ぶように走った。下へ、下へと駆け下り、ウェールズ人の家にたどり着いた。彼はドアを叩き鳴らし、やがて老人の頭と、その二人のたくましい息子の頭が窓から突き出された。
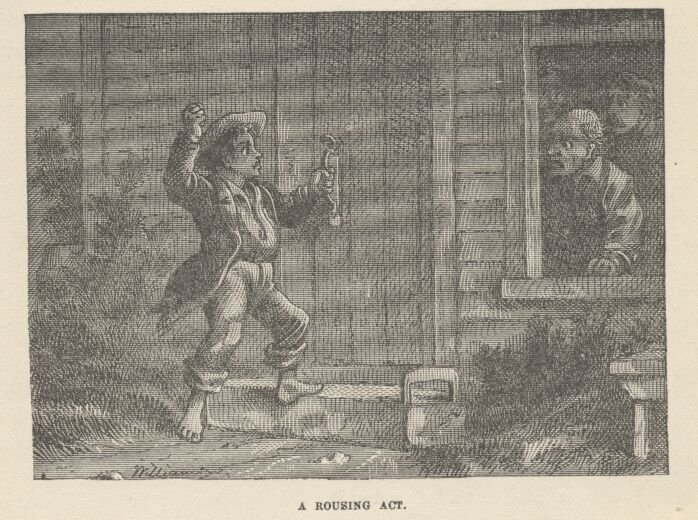
「何の騒ぎだ? 誰が叩いてる? 何の用だ?」
「入れてくれ――早く! 全部話すから。」
「なんだ、お前は誰だ?」
「ハックルベリー・フィンだ――早く、入れてくれ!」
「ハックルベリー・フィン、だと! 多くのドアを開けられる名前じゃなさそうだな! だが、入れてやれ、息子たち。何があったか見てみよう。」
「お願いだから、俺が言ったってことは絶対に言わないでくれ」それが、中に入ったハックの最初の言葉だった。「お願いだ――言ったら、きっと殺されちまう。でも、未亡人は時々俺に親切にしてくれたんだ。だから話したいんだ――話すよ、もしあんたたちが、俺だったとは絶対に言わないって約束してくれるならな。」
「なんてこった、こいつは何か話すことがあるに違いない。でなけりゃ、あんな風にはしないだろう!」と老人は叫んだ。「さあ、話してみろ。ここの誰も、絶対に口外しないからな、坊主。」
三分後、老人と息子たちは、十分に武装し、丘を上り、武器を手に、つま先立ちでハゼノキの小道に入っていった。ハックはそれ以上は同行しなかった。彼は大きな岩の後ろに隠れ、耳を澄ませた。重苦しく、不安な沈黙があり、そして突然、銃声の炸裂と叫び声が響いた。
ハックは詳細を待たなかった。彼は飛びのき、足の続く限り速く丘を駆け下りた。

第三十章
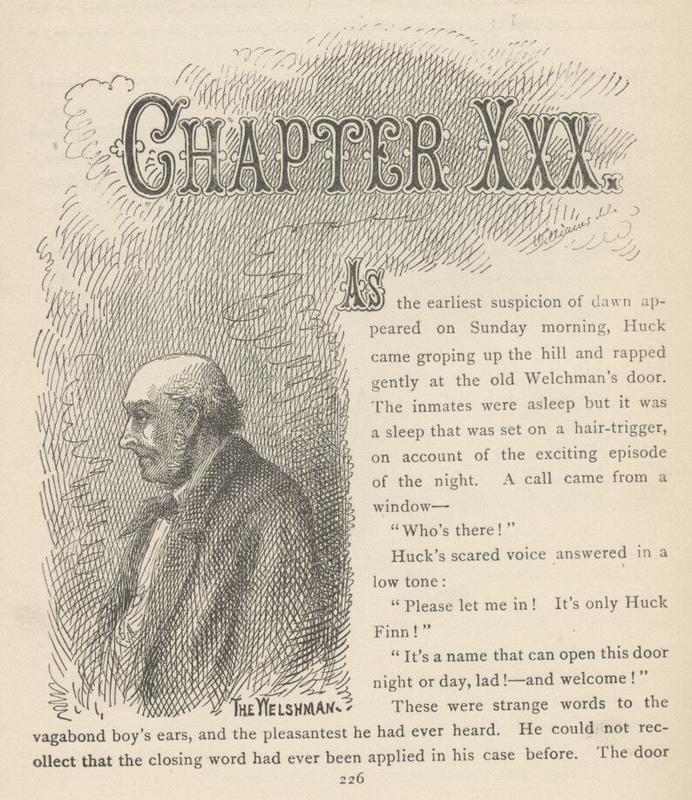
日曜の朝、夜明けの最初の気配が現れる頃、ハックは丘を這い上り、古いウェールズ人のドアをそっと叩いた。家の中の者たちは眠っていたが、それは昨夜の刺激的な出来事のせいで、髪の毛一本で張りつめたような眠りだった。窓から声がした。
「誰だ!」
ハックのおびえた声が低いトーンで答えた。
「お願いだ、入れてくれ! ハック・フィンだよ!」
「その名なら、このドアは昼も夜も開くとも、坊主! ――そして、ようこそ!」
これらは、放浪の少年の耳には奇妙な言葉であり、彼がこれまでに聞いた中で最も心地よい言葉だった。彼は、最後の言葉が自分の場合に適用されたことを、これまで一度も思い出すことができなかった。ドアはすぐに開けられ、彼は中に入った。ハックは椅子を与えられ、老人とその背の高い二人の息子は素早く身支度を整えた。
「さて、坊主、腹がぺこぺこだといいんだがな。というのも、日が昇るとすぐに朝食の準備ができるからな。それも、熱々のやつをな。心配するな! わしと息子たちは、お前が昨夜現れて、ここに泊まってくれることを望んでいたんだ。」
「すごく怖かったんだ」とハックは言った。「それで逃げた。ピストルが鳴った時、飛び出して、三マイルも止まらなかった。今来たのは、どうなったか知りたかったからさ。それに、夜が明ける前に来たのは、あの悪魔どもに出くわしたくなかったからだ。たとえ死んでたとしてもな。」
「まあ、かわいそうに、辛い一夜を過ごしたような顔をしてるな。だが、朝食を食べたら、ここにお前のためのベッドがある。いや、奴らは死んでないよ、坊主。それについては、わしらも残念でならん。お前の説明で、奴らがどこにいるか正確に分かったんだ。それで、つま先立ちで忍び寄って、奴らから十五フィートのところまで行った。あのハゼノキの小道は地下室みたいに真っ暗でな。ちょうどその時、わしはくしゃみが出そうになったんだ。最悪の運だった! 抑えようとしたんだが、だめだった。どうしても出てきてしまってな! わしが先頭でピストルを構えていたんだが、くしゃみであの悪党どもが小道から逃げ出そうとガサガサ音を立てたんで、『撃て、息子たち!』と叫んで、物音のした場所めがけてぶっ放した。息子たちもそうだ。だが、奴らはあっという間に逃げちまって、わしらは森の中を追いかけた。おそらく、一発も当たらなかっただろう。奴らは逃げ出す時に一発ずつ撃ってきたが、弾はヒュッと音を立ててそばを通り過ぎ、わしらに怪我はなかった。奴らの足音が聞こえなくなるとすぐに追跡をやめて、下りて行って保安官たちを叩き起こした。彼らは捜索隊を組織して、川岸を警備しに行った。夜が明け次第、保安官と一団が森をくまなく捜索する予定だ。わしの息子たちも、まもなく合流する。あの悪党どもの人相書きでもあれば、大いに助かるんだがな。だが、暗闇じゃ、どんな奴らか見えなかっただろう、坊主?」

「いや、見たよ。町で見て、後をつけたんだ。」
「素晴らしい! 説明してくれ――説明してくれ、坊主!」
「一人は、前に一度か二度このあたりをうろついてた、年寄りの耳と口のきけないスペイン人で、もう一人はみすぼらしい、きたねえ格好の――」
「それで十分だ、坊主、その男たちは知ってる! ある日、未亡人の家の裏の森で出くわしたら、こそこそと逃げていきやがった。行け、息子たち、保安官に伝えるんだ――朝食は明日の朝食べろ!」
ウェールズ人の息子たちはすぐに出発した。彼らが部屋を出て行こうとすると、ハックは飛び上がって叫んだ。
「ああ、お願いだから、俺が奴らのことをばらしたって、誰にも言わないでくれ! お願いだ!」
「お前がそう言うならいいだろう、ハック。だが、お前は自分のしたことの功績を認められるべきだ。」
「いやいや、だめだ! お願いだから言わないでくれ!」
若者たちがいなくなると、老ウェールズ人は言った。
「彼らは言わんよ――わしも言わん。だが、なぜ知られたくないんだ?」
ハックはそれ以上は説明しようとせず、ただ、あの男たちの一人についてすでに知りすぎており、その男に自分が何か不利なことを知っていると知られるくらいなら、全世界を差し出してもごめんだ、知っていることで確実に殺される、とだけ言った。
老人はもう一度秘密を守ると約束し、言った。
「どうしてあの連中を追うことになったんだ、坊主? 怪しそうに見えたのか?」
ハックは、慎重に考え抜いた返事を組み立てる間、黙っていた。そして言った。
「ええと、ほら、俺って、ろくでなしだろ――少なくとも、みんなそう言うし、俺もそうじゃないとは思わない。それで、時々、そのことを考えたり、何か新しいやり方を見つけようとしたりして、あまり眠れないことがあるんだ。昨夜もそうだった。眠れなくて、真夜中頃に通りをぶらぶら歩きながら、あれこれ考えてたんだ。それで、禁酒酒場のそばの、あの古くてがたがたのレンガ造りの店のところまで来て、壁にもたれてまた考え事をしようとした。そしたら、ちょうどその時、この二人が腕の下に何かを抱えて、俺のすぐそばをこそこそと通り過ぎていったんだ。盗んだものだろうと思った。一人が煙草を吸ってて、もう一人が火を欲しがった。それで、二人は俺の真ん前で立ち止まって、葉巻の火が顔を照らしたんで、でかい方が、白い髭と眼帯で、耳と口のきけないスペイン人だと分かった。もう一人は、みすぼらしい、きたねえ格好の悪魔みたいな奴だった。」
「葉巻の明かりで、ぼろ服まで見えたのか?」
この質問に、ハックは一瞬たじろいだ。そして言った。

「さあ、分かんない。でも、なんだか、見えたような気がするんだ。」
「それから、彼らは行ってしまい、お前は――」
「後をつけた――そう。そういうことだ。何が起こるか見てみたかったんだ。あんなにこそこそしてたからな。未亡人の家の踏み段まで後をつけて、暗闇に立って、きたねえ格好の奴が未亡人のために頼んでるのと、スペイン人が、あんたとあんたの息子さんたちに話した通り、あの女の容姿を台無しにしてやると誓うのを聞いたんだ。」
「何だと! あの耳と口のきけない男が、そんなことを全部言ったのか!」
ハックはまたしても、とんでもない間違いを犯してしまった! 彼は、老人にスペイン人が誰であるか、かすかなヒントさえ与えないように最善を尽くしていたのに、彼の舌は、彼がどんなに努力しても、彼を窮地に陥れようと決めているようだった。彼は何度かその窮地から抜け出そうと試みたが、老人の目は彼に注がれており、彼は失態に次ぐ失態を演じた。やがてウェールズ人は言った。
「坊主、わしを恐れることはない。全世界を貰っても、お前の髪の毛一本傷つけたりはせんよ。いや――わしがお前を守ってやる――守ってやる。このスペイン人は、耳と口が不自由ではないな。お前は意図せずそれを漏らしてしまった。もうそれを隠すことはできん。お前は、あのスペイン人について、秘密にしておきたい何かを知っている。さあ、わしを信じて――それが何か話してくれ。わしを信じろ――裏切ったりはせん。」
ハックは老人の正直な目を一瞬見つめ、それから身をかがめて彼の耳にささやいた。
「スペイン人じゃねえ――インジャン・ジョーだ!」
ウェールズ人は椅子から飛び上がらんばかりに驚いた。一瞬の後、彼は言った。
「これで、すべてはっきりした。お前が耳に切り込みを入れたり鼻を裂いたりする話をした時、わしは、それはお前自身の脚色だろうと思った。なぜなら、白人はそんな復讐はしないからな。だが、インディアン! それはまったく別の話だ。」
朝食の間も話は続き、その中で老人は、彼と息子たちが寝る前に最後にやったことは、ランタンを持って踏み段とその周辺に血痕がないか調べることだった、と言った。血痕は見つからなかったが、かさばる包みを一つ見つけたという――
「何の?」
もしその言葉が稲妻であったなら、ハックの青ざめた唇から、これほど衝撃的な突然さで飛び出すことはなかっただろう。彼の目は今や大きく見開かれ、息は止まっていた――答えを待って。ウェールズ人は驚き、見つめ返した――三秒――五秒――十秒――そして答えた。
「泥棒道具の包みだ。どうしたんだ、お前?」
ハックは、静かに、しかし深く、言葉にできないほど感謝しながら、ぐったりと背をもたせかけた。ウェールズ人は、真剣に、そして不思議そうに彼を見つめ、やがて言った。
「そうだ、泥棒道具だ。それでずいぶん安心したようだな。だが、何がそんなに驚かせたんだ? わしらが何を見つけたと思ったんだ?」
ハックは窮地に立たされていた。探るような目が彼に注がれていた。もっともらしい答えの材料のためなら何でも差し出しただろうが、何も思いつかなかった。探るような目は、ますます深く突き刺さってくる。意味不明な返事が浮かんだ。それを吟味する時間はなかった。そこで、彼は思い切って、弱々しくそれを口にした。
「日曜学校の本か何か、かな。」
哀れなハックは憔悴しきっていて、笑うことなどできなかった。だが、老人は高らかに、楽しげに笑った。頭のてっぺんからつま先まで、全身を揺すって笑い、しまいには、こんな笑いこそ懐に入る金みたいなもんだ、医者にかかる費用をごっそり減らしてくれるんだからな、と言った。そして、こう付け加えた。
「可哀想にな、お前さん。顔は真っ青で、疲れきっておる。ちっとも元気がないじゃないか。そりゃあ、少しばかり取り乱して、平静でいられんのも無理はない。だが、じきに良くなるさ。休んで寝りゃあ、きっと元気になる。わしはそう思うとるよ。」
ハックは、自分がなんて間抜けだったのか、あんなに怪しい興奮をあらわにしてしまったのかと思うと、腹立たしかった。というのも、未亡人の家の石段での会話を聞いてすぐに、酒場から持ち出されたあの包みが宝物だという考えは捨てていたからだ。とはいえ、それは宝物では ないだろう と思っただけで、そうではないと 知っていた わけではなかった。だから、包みが手に入ったとほのめかされただけで、冷静でいられなくなってしまったのだ。しかし、全体としてみれば、このちょっとした出来事が起こって良かったと感じていた。今や、あの包みが 例の 包みではないことが疑いようもなく分かり、心は落ち着き、この上なく安らかだった。実際、今やすべてが正しい方向へと流れているように思えた。宝物はまだ「2号室」にあるに違いない。あの男たちは今日中に捕まって牢屋に入れられるだろう。そうすれば、自分とトムは今夜、何の面倒もなく、誰にも邪魔される心配もなく、あの黄金を手に入れることができるのだ。
朝食がちょうど終わった頃、ドアをノックする音がした。ハックは隠れ場所へと飛び込んだ。このたびの事件に、たとえわずかでも関わりがあると思われたくなかったからだ。ウェールズ人は、何人かの紳士淑女を招き入れた。その中にはダグラス未亡人もいた。そして、市民の一団が丘を登ってくるのが見えた。石段を見物するためだ。つまり、噂は広まっていたのだ。ウェールズ人は、訪問客たちに昨夜の出来事を語って聞かせねばならなかった。命を救われたことに対する未亡人の感謝の言葉は、率直なものだった。
「いえいえ、奥様、何もおっしゃいますな。あなたには、私や息子たちよりも、もっと恩義を感じるべき方がもう一人おられます。ですが、その方は名前を明かすのを許してはくださらんのです。その方がいなければ、我々はあそこにはおりませんでした。」
当然ながら、この言葉は本題がかすんでしまうほどの巨大な好奇心をかき立てた。しかしウェールズ人は、その好奇心が訪問客たちの腹の底を食い破り、彼らを通じて町中に広まるのを黙って見ていた。彼は秘密を明かすことを頑なに拒んだのだ。他のことをすべて聞き終えた後、未亡人が言った。
「私はベッドで本を読みながら寝入ってしまって、あの騒ぎの間ずっと眠りこけていたのですわ。どうして起こしに来てくださらなかったのです?」
「起こすほどの価値もないと判断いたしました。あの連中がまた来ることはまずないでしょう。仕事に使う道具も残っておりませんでしたし、あなた様を叩き起こして死ぬほど怖がらせたところで、何になりましょう? 私のところの黒人の男たちが三人、夜が明けるまでずっとあなた様のお宅を見張っておりました。たった今、戻ってきたところです。」
さらに訪問客がやって来て、その話はさらに二時間ほど、何度も何度も語り直されねばならなかった。
昼間の学校が休みの間は、日曜学校もなかったが、誰もが早くから教会に集まっていた。あの胸を騒がせる事件がもっぱらの話題だった。二人の悪党の痕跡はまだ何一つ発見されていないという知らせが届いた。説教が終わり、サッチャー判事の妻が、人混みと一緒に通路を進むハーパー夫人の隣に並んで、こう言った。
「うちのベッキーは一日中寝ているのかしら? きっと疲れ果てているでしょうに。」
「あなたのベッキーですって?」
「ええ」と、彼女は驚いたような顔で言った。「昨夜はあなたのお宅に泊まったのではなくて?」

「いいえ、そんなことはありませんわ。」
サッチャー夫人は青ざめ、信者席に崩れ落ちた。ちょうどその時、ポリーおばさんが友人と快活に話しながら通りかかった。ポリーおばさんは言った。
「おはようございます、サッチャーさん。おはようございます、ハーパーさん。うちの子が見当たらなくてね。うちのトムは昨夜、どちらかのお宅に泊まったんでしょう? それで今頃、教会に来るのが怖いのね。あの子にはお説教しなくちゃ。」
サッチャー夫人は弱々しく首を振り、ますます顔色を失った。
「うちには泊まっていませんわ」と、ハーパー夫人は言い、不安げな表情を浮かべ始めた。ポリーおばさんの顔にも、はっきりとした不安がよぎった。
「ジョー・ハーパー、今朝、うちのトムを見なかったかい?」
「いいえ、おばさん。」
「最後に見たのはいつだい?」
ジョーは思い出そうとしたが、はっきりとは言えなかった。教会から出て行こうとしていた人々が足を止めた。ささやきが広がり、不吉な不安が皆の顔を覆った。子供たちや若い教師たちが心配そうに質問された。誰もが、帰りのフェリーボートにトムとベッキーが乗っていたかどうかは気づかなかったと答えた。暗かったし、誰かがいないかどうか確かめようなどとは誰も思わなかったのだ。ついに一人の若者が、二人はまだ洞窟の中にいるのではないか、という恐ろしい考えを口走った。サッチャー夫人は気を失って倒れた。ポリーおばさんは泣き崩れ、両手をもみしだいた。
警報は口から口へ、一団から一団へ、通りから通りへと駆け巡り、五分も経たないうちに教会の鐘がけたたましく鳴り響き、町中の人々が叩き起こされた。カーディフの丘の事件は瞬時にどうでもいいことになり、強盗たちのことなど忘れ去られた。馬には鞍が置かれ、小舟には人が乗り込み、フェリーボートには出航命令が下った。そして、この恐怖が始まってから三十分も経たないうちに、二百人もの男たちが、洞窟を目指して街道を、そして川を、駆け下っていった。
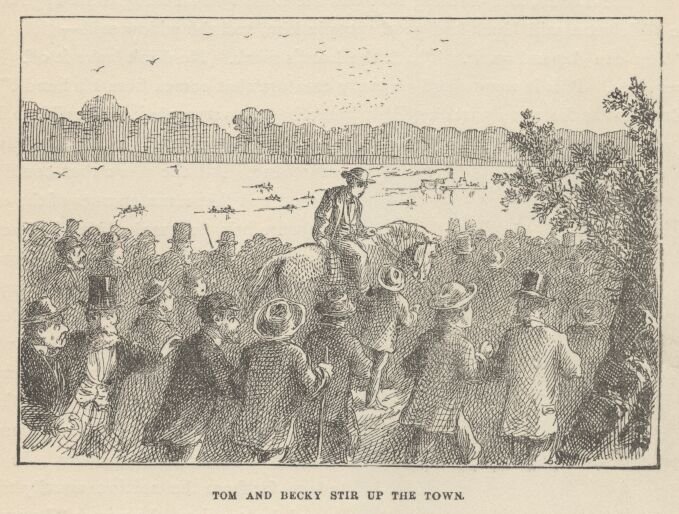
その長い午後、村は空っぽで、死んだように静まり返っていた。多くの女性たちがポリーおばさんとサッチャー夫人を訪ね、慰めようとした。彼女たちも一緒に泣いた。それはどんな言葉よりも慰めになった。退屈な夜が続く間、町は知らせを待ち続けた。しかし、ついに夜が明けた時、届いた知らせはただ、「もっとロウソクを、そして食料を送れ」というものだった。サッチャー夫人はほとんど狂乱状態だった。ポリーおばさんも同様だった。サッチャー判事は洞窟から希望と激励の伝言を送ったが、それは何の本当の慰めにもならなかった。
老いたウェールズ人は夜明け近くに家に戻ってきた。ロウソクの脂にはねられ、粘土にまみれ、ほとんど疲れ果てていた。彼が見たのは、用意されたベッドで、熱に浮かされてうわごとを言っているハックの姿だった。医者たちは皆、洞窟へ行ってしまっていたので、ダグラス未亡人がやって来て、患者の世話を引き受けた。彼女は、あの子のために最善を尽くすと言った。なぜなら、彼が善人であろうと、悪人であろうと、どうでもいい人間であろうと、彼は神様のものであり、神様のものである以上、おろそかにできるものなど何一つないからだ、と。ウェールズ人は、ハックにも良いところがあると述べ、未亡人はこう言った。
「間違いありませんわ。それは神様の印です。神様はそれをお付けにならずにはいらっしゃらない。決して。ご自分の手から生まれるすべての生き物のどこかに、必ずお付けになるのです。」
午前中の早い時間に、疲れ果てた男たちの集団が村へとぽつりぽつりと戻り始めたが、屈強な市民たちは捜索を続けていた。得られた知らせと言えば、洞窟のこれまで誰も足を踏み入れたことのない奥地までくまなく捜索されていること、隅から隅まで、裂け目という裂け目まで徹底的に調べられること、そして、迷路のような通路をさまよっていると、どこからともなく遠くで光がちらちらと動き回り、叫び声やピストルの発砲音が、陰鬱な回廊を通って耳に虚ろな反響を届けてくること、などだった。観光客が普段通る区域から遠く離れたある場所で、「ベッキー&トム」という名前が、ロウソクの煙で岩壁に描かれているのが見つかった。そしてそのすぐ近くには、脂で汚れたリボンの切れ端が落ちていた。サッチャー夫人はそのリボンに見覚えがあり、それを見て泣き崩れた。これが娘の最後の形見になるだろう、そして、これ以上に大切な思い出の品はありえない、なぜなら、あの恐ろしい死が訪れる前に、生身の体から最後に離れたのがこれなのだから、と彼女は言った。時折、洞窟の中で、遠くに光の点がきらめき、すると輝かしい歓声が沸き起こり、二十人ほどの男たちがこだまする通路を駆け下りていくことがあったという。しかし、その後に続くのはいつも、吐き気を催すような失望だった。子供たちはそこにいなかった。それはただの捜索者の光だったのだ。
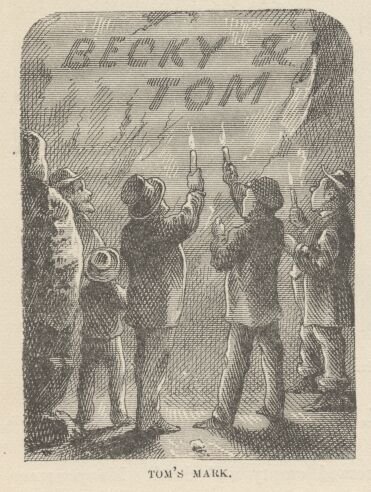
恐ろしい三日三晩が、その退屈な時間を引きずりながら過ぎていき、村は絶望的な無気力状態に陥った。誰も何をする気にもなれなかった。禁酒酒場の主人が店に酒を置いていたという、つい先ほどの偶然の発見も、それがどれほど衝撃的な事実であったにもかかわらず、人々の心をほとんど揺さぶることはなかった。意識がはっきりした合間に、ハックは弱々しく酒場の話題に話を向け、そしてついに、最悪の事態をぼんやりと恐れながら、自分が病気になってから禁酒酒場で何か発見されたかと尋ねた。
「ええ」と未亡人は言った。
ハックはベッドから跳ね起き、目を剥いた。
「何だい? 何があったんだい?」
「お酒よ! それで、店は閉鎖されたわ。横になって、坊や。なんてびっくりさせるの!」
「一つだけ教えてくれ、たった一つだけでいいんだ、お願いだ! それを見つけたのはトム・ソーヤーだったかい?」

未亡人はわっと泣き出した。「お黙り、お黙りなさい、坊や! 前に言ったでしょう、話しては いけない のよ。あなたはとても、とても重い病人なんだから!」
ということは、見つかったのは酒だけだったのだ。もし黄金だったら、大騒ぎになっていたはずだ。ということは、宝物は永遠に失われたのだ。永遠に! しかし、彼女は何を泣いているのだろう? 彼女が泣くなんて、奇妙なことだ。
そんな考えが、ハックの心の中をぼんやりと通り過ぎていき、その思考がもたらす疲労感の中で、彼は眠りに落ちた。未亡人は独り言を言った。
「あら、眠ってしまったわ、哀れな子。トム・ソーヤーが見つけるですって! 誰かトム・ソーヤーを見つけてくれさえすればいいのに! ああ、今となっては、捜索を続けるだけの希望も、体力も残っている者は、もうほとんどいないわ。」
第三十一章 洞窟の闇
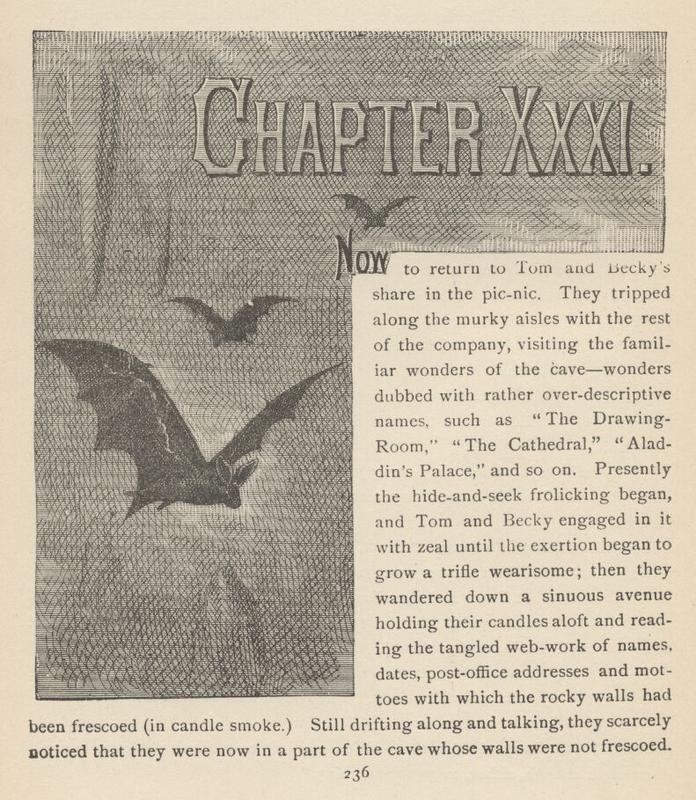
さて、話をトムとベッキーが参加したピクニックに戻そう。二人は一行の他の者たちと一緒に、薄暗い通路を軽やかに進み、洞窟の見慣れた名所を訪れていた。「客間」や「大聖堂」、「アラジンの宮殿」など、やや大げさすぎる名前が付けられた名所だ。やがてかくれんぼが始まり、トムとベッキーは夢中になってそれに興じていたが、さすがに少し疲れてきた。そこで二人は、曲がりくねった道へとさまよい込み、ロウソクを高く掲げながら、岩壁に(ロウソクの煙で)描かれた、もつれたクモの巣のような名前や日付、郵便局の住所、座右の銘などを読んでいた。話しながらぶらぶらと歩いているうちに、二人はいつの間にか、壁に落書きのない洞窟の区域に入っていることにほとんど気づかなかった。張り出した岩棚の下に自分たちの名前を煙で描き、さらに先へ進んだ。やがて、小さな水の流れが岩棚を滴り落ち、石灰の沈殿物を運びながら、気の遠くなるような年月をかけて、輝かしく朽ちることのない石でできた、レース飾りのような波立つナイアガラの滝を形成している場所に出た。トムは小さな体をその裏側にねじ込み、ベッキーを喜ばせるためにそれを照らし出した。彼は、それが狭い壁に挟まれた、急な自然の階段のようなものを覆い隠していることに気づいた。そしてたちまち、発見者になりたいという野心が彼を捉えた。
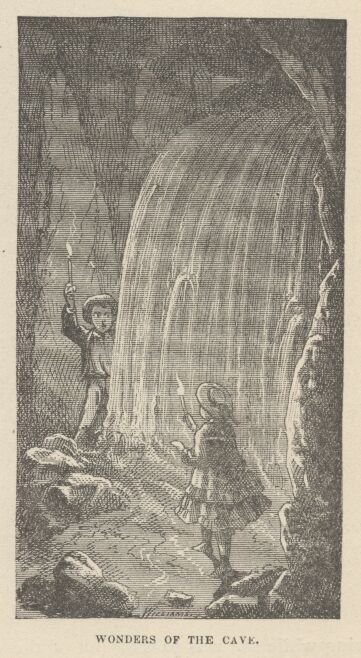
ベッキーは彼の呼びかけに応じ、二人は後で分かるように煙で目印をつけ、探検へと出発した。彼らはあちらこちらへと曲がりくねりながら、洞窟の秘密の奥深くへと下っていき、別の目印をつけ、地上の世界に話すための目新しいものを探して脇道へとそれた。ある場所で、広々とした洞窟を見つけた。その天井からは、人間の足ほどの長さと太さのある、きらめく鍾乳石が無数に垂れ下がっていた。二人はその周りを歩き回り、驚嘆し、感心し、やがてそこへと通じる数多くの通路の一つから洞窟を後にした。それは間もなく、魅惑的な泉へと二人を導いた。泉の水盤は、きらめく水晶の霜で覆われていた。そこは、巨大な鍾乳石と石筍が合体してできた、数多くの幻想的な柱に支えられた洞窟の真ん中だった。それは、何世紀にもわたる絶え間ない水の滴りが生み出した結果だった。天井の下には、巨大なコウモリの群れが、何千匹もがひと塊になってびっしりと集まっていた。光が生き物たちを刺激し、何百という数が鳴き声をあげながら、ロウソクめがけて猛然と襲いかかってきた。トムはコウモリの習性と、この種の行動の危険性を知っていた。彼はベッキーの手を掴むと、一番近くにあった通路へと彼女を急いで押し込んだ。それは間一髪だった。ベッキーが洞窟を出ようとしたまさにその時、一匹のコウモリがその翼で彼女のロウソクの火を打ち消したのだ。コウモリたちはかなりの距離を子供たちの後を追ってきた。しかし、逃げる二人は現れる新しい通路へと次々に飛び込み、ついにその危険な生き物たちを振り切った。トムはすぐに地底湖を見つけた。その薄暗い湖面は、その形が影の中に消えるまで遠くへと伸びていた。彼はその岸辺を探検したかったが、まずは腰を下ろしてしばらく休むのが最善だと結論づけた。この時初めて、その場所の深い静寂が、ねっとりとした冷たい手のように二人の心にのしかかってきた。ベッキーが言った。
「まあ、気づかなかったけど、他の人たちの声が聞こえなくなってから、すごく時間が経ったように思えるわ。」

「考えてみれば、ベッキー、僕たちはあの人たちよりずっと下にいるんだ。それに、北か南か東か、どっちの方角にどれだけ離れているかも分からない。ここじゃ聞こえるはずがないよ。」
ベッキーは不安になった。
「私たち、ここにどれくらいいるのかしら、トム? そろそろ戻った方がいいわ。」
「ああ、そうした方がいいと思う。たぶん、そうした方がいい。」
「道は分かるの、トム? 私には、ごちゃごちゃに曲がりくねっているようにしか見えないわ。」
「見つけられるとは思うけど、でも、あのコウモリがいる。もしあいつらにロウソクを消されたら、ひどいことになる。だから、あそこを通らないように、別の道を探してみよう。」
「分かったわ。でも、迷子にならなければいいけど。そうなったら、本当に恐ろしいわ!」少女は、その恐ろしい可能性を考えて身震いした。
二人はある通路を通り抜け、長い道のりを黙って進み、新しく現れる分かれ道ごとに、見覚えのある景色がないかちらりと見た。しかし、どれも見慣れないものばかりだった。トムが調べるたびに、ベッキーは励ましの印を探して彼の顔をうかがい、彼は陽気にこう言った。
「ああ、大丈夫だよ。これは違うけど、すぐに目的の道に出るさ!」
しかし、失敗を重ねるごとに彼の希望は薄れていき、やがて、目当ての道が見つかることを必死に願いながら、手当たり次第に分かれ道へと曲がり始めた。彼はまだ「大丈夫だ」と言い続けていたが、その心には鉛のような恐怖が重くのしかかり、その言葉はもはや響きを失い、まるで「万事休すだ!」と言っているかのように聞こえた。ベッキーは恐怖に苛まれながら彼のそばに寄り添い、涙を必死にこらえようとしたが、涙はあふれてきた。ついに彼女は言った。
「ああ、トム、コウモリなんて気にしないで、あの道で戻りましょう! どんどん悪い方へ行っているみたい。」
「静かに!」と彼は言った。
深い静寂。あまりにも深い静寂で、二人の呼吸さえもその静けさの中で際立っていた。トムは叫んだ。その呼び声は空っぽの通路をこだまし、遠くで嘲笑のさざ波に似たかすかな音となって消えていった。
「ああ、もうやめて、トム、恐ろしすぎるわ」とベッキーは言った。
「恐ろしいけど、やった方がいいんだ、ベッキー。聞こえるかもしれないだろ」そう言って、彼は再び叫んだ。
その「かもしれない」という言葉は、幽霊のような笑い声よりもさらに冷たい恐怖をもたらした。消えゆく希望をあまりにもはっきりと告白していたからだ。子供たちはじっと立ち尽くして耳を澄ましたが、何の返事もなかった。トムはすぐさま来た道を引き返し、歩みを速めた。しかし、間もなく彼の態度の迷いが、もう一つの恐ろしい事実をベッキーに明らかにした。彼は帰り道を見つけられないのだ!
「ああ、トム、目印をつけてなかったのね!」
「ベッキー、僕はなんて馬鹿だったんだ! なんて馬鹿なんだ! 戻りたくなるかもしれないなんて、考えもしなかった! だめだ、道が分からない。全部ごちゃごちゃだ。」
「トム、トム、私たち迷子よ! 迷子になっちゃった! この恐ろしい場所から二度と出られないわ! ああ、どうして他の人たちから離れてしまったのかしら!」

彼女は地面に崩れ落ち、あまりにも激しく泣きじゃくったので、トムは彼女が死んでしまうか、正気を失ってしまうのではないかと恐ろしくなった。彼は彼女のそばに座り、腕を回した。彼女は彼の胸に顔をうずめ、彼にしがみつき、恐怖と、どうにもならない後悔をぶちまけた。そして、遠くのこだまは、そのすべてをあざけるような笑い声に変えた。トムは彼女に希望を取り戻すよう懇願したが、彼女はできないと言った。彼は、彼女をこんな惨めな状況に陥れた自分を責め、罵り始めた。これには、より良い効果があった。彼女は、もう一度希望を持ってみる、立ち上がって、彼が導くところならどこへでもついていく、だからもうそんな風に言わないでほしい、と言った。彼だけが悪いのではなく、自分も悪いのだから、と。
こうして二人は再び動き出した。あてもなく、ただ手当たり次第に。彼らにできることは、動くこと、動き続けることだけだった。しばらくの間、希望がよみがえる兆しを見せた。それに何の根拠もなかったが、ただ、年齢や失敗への慣れによってその弾力性が失われていない限り、希望というものはよみがえる性質を持っているからだ。
やがてトムはベッキーのロウソクを受け取ると、それを吹き消した。この節約が意味するものはあまりにも大きかった! 言葉は必要なかった。ベッキーは理解し、彼女の希望は再び死んだ。彼女は、トムがポケットに丸一本のロウソクと、三、四本の切れ端を持っていることを知っていた。それでも彼は節約しなければならないのだ。
やがて、疲労がその権利を主張し始めた。子供たちは気を引き締めようとした。時間がこれほど貴重になった今、座り込むことを考えるのは恐ろしかったからだ。動くこと、どこかの方向へ、どんな方向へでも進むことは、少なくとも前進であり、実を結ぶかもしれない。しかし、座り込むことは死を招き、その追跡を早めることだった。
ついにベッキーのか弱い脚は、彼女をそれ以上運ぶことを拒んだ。彼女は座り込んだ。トムも彼女と一緒に休み、二人は家のこと、そこにいる友人たちのこと、快適なベッドのこと、そして何よりも、光のことを話した! ベッキーは泣き、トムは彼女を慰める方法を考えようとしたが、彼の励ましの言葉は使い古されて色あせ、皮肉のように聞こえた。疲労がベッキーに重くのしかかり、彼女はうとうとと眠りに落ちた。トムはありがたく思った。彼は彼女のやつれた顔を見つめ、心地よい夢の影響でその顔が滑らかで自然になっていくのを見た。やがて微笑みが浮かび、そこにとどまった。その安らかな顔は、いくらかの平穏と癒しを彼の心にも映し出し、彼の思考は過ぎ去った日々や夢のような思い出へとさまよっていった。彼が物思いに深く沈んでいると、ベッキーが軽やかな笑い声とともに目を覚ました。しかし、その笑い声は彼女の唇の上でかき消され、うめき声がそれに続いた。
「ああ、どうして眠ってしまったのかしら! 二度と、二度と目覚めなければよかったのに! いいえ! いいえ、そんなことないわ、トム! そんな顔しないで! もう二度と言わないから。」
「眠れてよかったよ、ベッキー。これで休めたはずだ。さあ、出口を見つけよう。」
「試してみましょう、トム。でも、夢の中でとても美しい国を見たの。私たちはきっとそこへ行くんだわ。」
「そうじゃないかもしれない、そうじゃないさ。元気を出して、ベッキー、探し続けよう。」
二人は立ち上がり、手を取り合って、希望もなくさまよい歩いた。洞窟にどれくらいいるのか見積もろうとしたが、分かったのは、何日も何週間も経ったように思えるということだけだった。しかし、ロウソクがまだなくならないことから、それはあり得ないことだと明らかだった。それから長い時間が経った後――どれくらい経ったかは分からなかった――トムは、静かに歩いて水の滴る音に耳を澄まさなければならない、泉を見つけなければ、と言った。二人はやがて一つ見つけ、トムはまた休む時間だと言った。二人ともひどく疲れていたが、ベッキーはもう少し歩けると思った。トムが反対するのを聞いて、彼女は驚いた。理解できなかった。二人は腰を下ろし、トムはロウソクを粘土で目の前の壁に固定した。すぐに考えが忙しくなり、しばらく何も言わなかった。それからベッキーが沈黙を破った。
「トム、お腹がすいたわ!」
トムはポケットから何かを取り出した。

「これ、覚えてる?」と彼は言った。
ベッキーはかすかに微笑んだ。
「私たちのウェディングケーキね、トム。」
「ああ、これが樽みたいに大きかったらなあ。これしか食べるものがないんだ。」
「ピクニックの時から、私たちのためにとっておいたのよ、トム。大人たちがウェディングケーキでそうするように、夢を見るためにね。でも、これが私たちの……」
彼女はそこで言葉を切った。トムがケーキを分けると、ベッキーは食欲旺盛に食べたが、トムは自分の分を少しずつかじった。ごちそうの締めくくりには、冷たい水がふんだんにあった。やがてベッキーが、また動き出そうと提案した。トムは一瞬黙っていた。そして言った。
「ベッキー、もし僕が何かを言ったら、耐えられるかい?」
ベッキーの顔は青ざめたが、耐えられると思った。
「それじゃあ、ベッキー、僕たちはここにいなきゃならない。飲む水があるからだ。あの小さなかけらが、僕たちの最後のロウソクなんだ!」
ベッキーは涙と嘆きに身を任せた。トムはできる限りのことをして彼女を慰めたが、ほとんど効果はなかった。やがてベッキーが言った。
「トム!」
「なんだい、ベッキー?」
「みんな、私たちがいなくなったのに気づいて、探しに来てくれるわ!」
「ああ、そうさ! きっと来てくれる!」
「たぶん、今頃探してくれているわ、トム。」
「そうだな、たぶんそうだと思う。そうだといいな。」
「いつ、私たちがいなくなったのに気づくかしら、トム?」
「ボートに戻った時だろうな。」
「トム、その時はもう暗いかもしれないわ。私たちが来ていないことに気づいてくれるかしら?」
「分からない。でも、どっちにしろ、君のお母さんは、家に着いたらすぐに君がいないことに気づくよ。」
ベッキーの顔に浮かんだ怯えた表情がトムを我に返らせ、彼は自分が失言をしたことに気づいた。ベッキーはその夜、家に帰る予定ではなかったのだ! 子供たちは黙り込み、考え込んだ。一瞬の後、ベッキーが新たに泣き崩れたことで、トムの心にあったことが彼女の心にも突き刺さったことが分かった。サッチャー夫人が、ベッキーがハーパー夫人の家にいないことに気づくのは、日曜の朝が半分過ぎてからかもしれないのだ。
子供たちは、自分たちのロウソクのかけらに目を釘付けにし、それがゆっくりと、無慈悲に溶けていくのを見つめていた。やがて半インチほどの芯だけが残るのを見た。か弱い炎が立ち上っては揺れ、細い煙の柱を登り、その頂点で一瞬ためらい、そして――完全な闇の恐怖が支配した!
それからどれほどの時が経って、ベッキーがトムの腕の中で泣いていることにゆっくりと気づいたのか、二人とも分からなかった。分かっていたのは、とてつもなく長い時間が過ぎたように思えた後、二人とも死んだような昏睡状態の眠りから覚め、再び苦しみに身を委ねたことだけだった。トムは、もう日曜日か、あるいは月曜日かもしれないと言った。彼はベッキーに話させようとしたが、彼女の悲しみはあまりにも重く、すべての希望は消え失せていた。トムは、自分たちはとっくにいなくなったことに気づかれているはずで、捜索は続いているに違いないと言った。叫べば、誰かが来てくれるかもしれない。彼は試してみた。しかし、暗闇の中では遠くのこだまがあまりにも恐ろしく響いたので、彼はもう試さなかった。
時間だけが過ぎ去り、空腹が再び囚人たちを苦しめ始めた。トムの分のケーキの半分が残っていた。二人はそれを分けて食べた。しかし、以前よりも空腹に感じられた。哀れな一口の食べ物は、欲望をかき立てただけだった。
やがてトムが言った。
「しーっ! 聞こえたかい?」
二人は息を殺して耳を澄ました。かすかな、遠くの叫び声のような音がした。トムは即座にそれに答え、ベッキーの手を引いて、その方向へと手探りで通路を下り始めた。やがて彼は再び耳を澄ました。再びその音が聞こえ、どうやら少し近くなったようだった。
「あの人たちだ!」とトムは言った。「来てくれる! 行こう、ベッキー、もう大丈夫だ!」
囚人たちの喜びは、ほとんど圧倒的だった。しかし、落とし穴がかなり多く、用心しなければならなかったため、彼らの速度は遅かった。間もなく二人は一つの落とし穴に行き当たり、立ち止まらなければならなかった。深さは三フィートかもしれないし、百フィートかもしれない。いずれにせよ、通り抜けることはできなかった。トムはうつ伏せになり、できる限り下まで手を伸ばした。底には届かなかった。彼らはそこで捜索隊が来るのを待つしかなかった。耳を澄ますと、遠くの叫び声は明らかに遠ざかっていった! 一、二分もすると、完全に聞こえなくなった。その心臓が沈むような絶望! トムは声が枯れるまで叫んだが、無駄だった。彼はベッキーに希望に満ちた言葉をかけた。しかし、不安な待ち時間が永遠のように過ぎても、何の音も聞こえてこなかった。
子供たちは手探りで泉へと戻った。疲れる時間がだらだらと続き、二人は再び眠り、飢えと悲しみに打ちひしがれて目覚めた。トムは、この時点でもう火曜日に違いないと思った。
その時、彼に一つの考えが浮かんだ。すぐ近くにいくつかの横道があった。何もしないで重苦しい時間の重みに耐えるよりは、これらのいくつかを探索する方がましだろう。彼はポケットから凧糸を取り出し、それを突起に結びつけ、トムを先頭に、手探りで進みながら糸を解き、ベッキーと一緒に歩き出した。二十歩ほど進んだところで、通路は「飛び降り場所」で行き止まりになった。トムは膝をついて下を探り、それから手の届く限り角の周りを探った。彼はもう少し右へ手を伸ばそうと努力した。その瞬間、二十ヤードも離れていない場所で、ロウソクを持った人間の手が、岩陰から現れた! トムは輝かしい歓声を上げた。すると即座に、その手の持ち主の体が現れた。インジャン・ジョーだった! トムは麻痺した。動けなかった。次の瞬間、その「スペイン人」が踵を返して姿を消したのを見て、彼は非常に安堵した。トムは、ジョーが自分の声に気づかず、法廷で証言したことの仕返しに殺しに来なかったことを不思議に思った。しかし、こだまが声を変えたに違いない。間違いなくそうだ、と彼は推論した。トムの恐怖は、体中のすべての筋肉を弱らせた。もし泉に戻るだけの力があれば、そこにとどまり、二度とインジャン・ジョーに会う危険を冒すようなことはすまい、と彼は自分に言い聞かせた。彼は、自分が見たものをベッキーに知られないように注意した。彼は、ただ「縁起担ぎに」叫んだだけだと彼女に告げた。

しかし、長い目で見れば、空腹とみじめさは恐怖に勝る。泉でのもう一つの退屈な待ち時間と、もう一つの長い眠りが変化をもたらした。子供たちは、猛烈な空腹に苛まれながら目覚めた。トムは、今頃は水曜日か木曜日、あるいは金曜日か土曜日でさえあり、捜索は打ち切られたに違いないと考えた。彼は別の通路を探検することを提案した。インジャン・ジョーやその他すべての恐怖を冒す気になっていた。しかし、ベッキーは非常に弱っていた。彼女は陰鬱な無気力状態に陥っており、奮い立たせることができなかった。彼女は、今いる場所で待ち、死ぬつもりだと言った。それも長くはないだろう、と。彼女はトムに、もし望むなら凧糸を持って探検に行くように言った。しかし、時々戻ってきて話しかけてくれるようにと懇願した。そして、あの恐ろしい時が来たら、そばにいて、すべてが終わるまで自分の手を握っていてくれるようにと、彼に約束させた。
トムは、喉に詰まるような感覚を覚えながら彼女にキスをし、捜索隊を見つけるか、洞窟から脱出できると自信ありげなふりをした。それから彼は凧糸を手に取り、空腹に苦しみ、来たるべき運命の予感に気分が悪くなりながら、ある通路を四つん這いになって手探りで下っていった。
第三十二章 生還
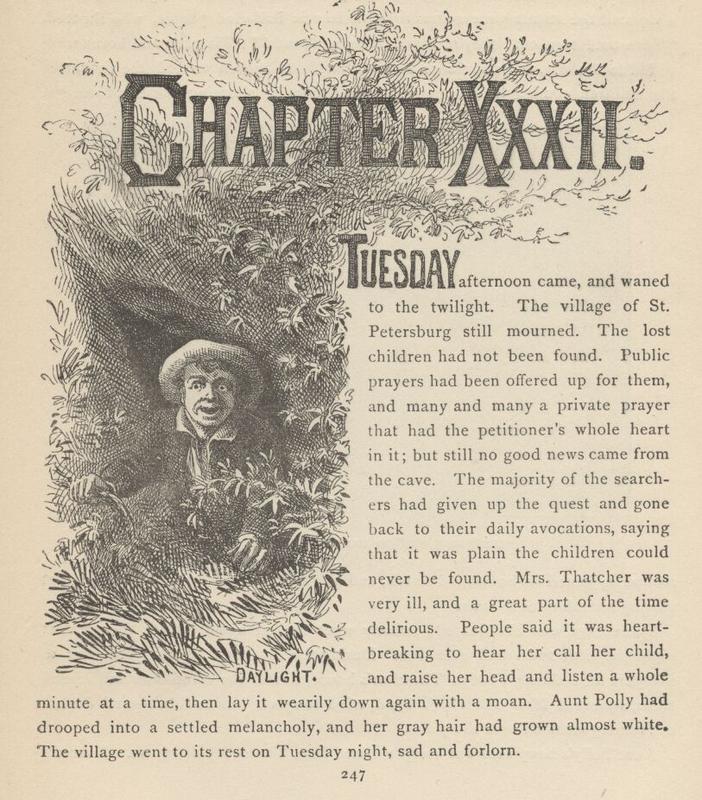
火曜日の午後が訪れ、そして夕暮れへと傾いていった。セント・ピーターズバーグの村は、まだ喪に服していた。行方不明の子供たちは見つかっていなかった。彼らのために公の祈りが捧げられ、祈願者の真心がこもった私的な祈りも数多く捧げられた。しかし、洞窟からの良い知らせは依然として届かなかった。捜索者の大半は探求をあきらめ、子供たちは決して見つからないのは明らかだと言って、日々の仕事に戻っていた。サッチャー夫人は重い病にかかり、ほとんどの時間を錯乱状態で過ごしていた。人々は、彼女が我が子の名を呼び、頭をもたげては一分間ずっと耳を澄まし、そして再びうめき声とともに力なく頭を横たえるのを聞くのは、胸が張り裂けるようだと語った。ポリーおばさんは、すっかり憂鬱に沈み込み、その白髪はほとんど真っ白になっていた。村は火曜の夜、悲しく、うちひしがれて眠りについた。
真夜中、村の鐘からけたたましい音が鳴り響き、一瞬のうちに通りは、半裸で狂乱した人々でごった返した。彼らは叫んだ。「出てこい! 出てこい! 見つかったぞ! 見つかったんだ!」ブリキの鍋や角笛がその喧騒に加わり、住民は一塊となって川の方へ向かい、叫ぶ市民たちに引かれた屋根なし馬車に乗ってやって来る子供たちと出会い、その周りに群がり、家路につく行進に加わり、万歳を叫びながら、見事なまでに大通りを練り歩いた!

村は照らし出され、誰も再び寝床にはつかなかった。それは、この小さな町がかつて見たことのない、最も偉大な夜だった。最初の三十分間、村人たちの行列がサッチャー判事の家を通り抜け、救出された二人を捕まえてはキスをし、サッチャー夫人の手を握りしめ、何か言おうとしては言葉にならず、涙をそこら中に降らせながら流れ出ていった。
ポリーおばさんの幸福は完全なものであり、サッチャー夫人の幸福もそれに近かった。しかし、その幸福が完全なものになるのは、洞窟にいる夫のもとへこの大ニュースを届けるために派遣された伝令が、その言葉を伝えた時だろう。トムはソファに横たわり、熱心な聴衆に囲まれながら、驚くべき冒険の物語を語った。話をおもしろくするために、多くの印象的な脚色を加えながら。そして、ベッキーを残して探検に出かけた様子を語って締めくくった。いかにして二つの道を凧糸が届く限りたどったか。いかにして三番目の道を凧糸が伸びきるまでたどり、引き返そうとした時に、遠くに昼の光のように見える点を見つけたか。糸を落とし、それに向かって手探りで進み、小さな穴から頭と肩を押し出すと、広大なミシシッピ川が目の前を流れているのを見たのだ!

そして、もしそれが夜であったなら、彼はその昼の光の点を見つけることはなく、その通路をそれ以上探検することもなかっただろう! 彼は、ベッキーのもとに戻って良い知らせを告げた時のことを語った。彼女は、そんなことで私を悩ませないで、疲れているし、もうすぐ死ぬと分かっているし、そうしたいのだから、と言ったという。彼は、いかに彼女を説得し、納得させたかを説明した。そして、彼女が手探りで進み、実際に青い昼の光の点を見た時、喜びのあまり死にそうになった様子を。いかにして彼が穴から抜け出し、それから彼女を助け出したかを。いかにして二人がそこに座り、喜びのあまり泣いたかを。いかにして小舟に乗った男たちが通りかかり、トムが彼らを呼び止め、自分たちの状況と飢えきった状態を告げたかを。いかにして男たちが、最初はその荒唐無稽な話を信じなかったかを。「なぜなら」と彼らは言った。「お前さんたちは、洞窟のある谷から川を五マイルも下ったところにいるんだぞ」と。それから二人を船に乗せ、ある家まで漕いで行き、夕食を与え、日没後二、三時間休ませてから、家まで連れて帰ってくれたのだ。
夜明け前、サッチャー判事と彼と共に行動していた一握りの捜索者たちは、自分たちが後ろに残してきた糸の手がかりをたどって洞窟内で発見され、この大ニュースを知らされた。
洞窟での三日三晩にわたる労苦と飢えは、すぐには振り払えるものではないことを、トムとベッキーはすぐに知った。二人は水曜日と木曜日はずっと寝たきりで、時間が経つにつれてますます疲れ、やつれていくように見えた。トムは木曜日には少し起き上がれるようになり、金曜日には町へ出かけ、土曜日にはほとんど元通りになった。しかしベッキーは日曜日まで部屋を出られず、その時の彼女は消耗性の病を患った後のように見えた。
トムはハックが病気だと知り、金曜日に見舞いに行ったが、寝室に入れてもらえなかった。土曜日も日曜日も同様だった。それ以降は毎日入れてもらえたが、自分の冒険については黙っているように、そして興奮させるような話題は持ち出さないようにと警告された。ダグラス未亡人がそばにいて、彼がその言いつけを守るか見張っていた。家でトムはカーディフの丘の事件を知った。また、「ぼろ服の男」の死体が、結局フェリー乗り場の近くの川で発見されたことも知った。おそらく、逃げようとして溺れたのだろう。
トムが洞窟から救出されてから約二週間後、彼はハックを訪ねに出かけた。ハックは今や、興奮する話を聞くのに十分なくらい元気になっていたし、トムは彼が興味を持つであろう話があると思っていた。サッチャー判事の家はトムの通り道にあり、彼はベッキーに会うために立ち寄った。判事と何人かの友人がトムに話をさせ、誰かが皮肉っぽく、また洞窟に行きたくはないかと尋ねた。トムは、別に構わないと思うと答えた。判事は言った。
「ふむ、君のような人間は他にもいるだろう、トム。私は少しも疑っていないよ。だが、その点は我々が手を打っておいた。もうあの洞窟で迷子になる者はいないだろう。」
「どうして?」
「なぜなら、二週間前にあの大きな扉をボイラーの鉄板で覆って、三重に鍵をかけたからだ。そして、鍵は私が持っている。」
トムはシーツのように真っ青になった。
「どうしたんだ、坊や! おい、誰か走って! 水を一杯持ってきてくれ!」
水が運ばれ、トムの顔にかけられた。
「ああ、もう大丈夫だ。どうしたんだい、トム?」
「ああ、判事、インジャン・ジョーが洞窟の中に!」
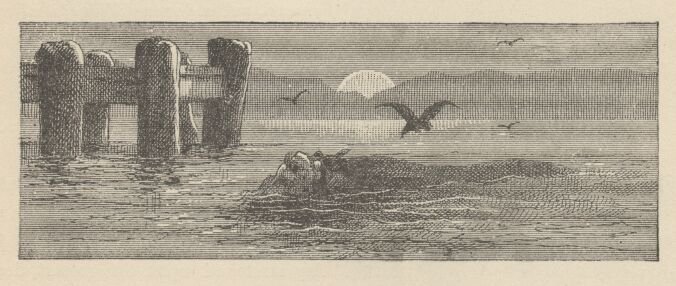
第三十三章 洞窟の財宝
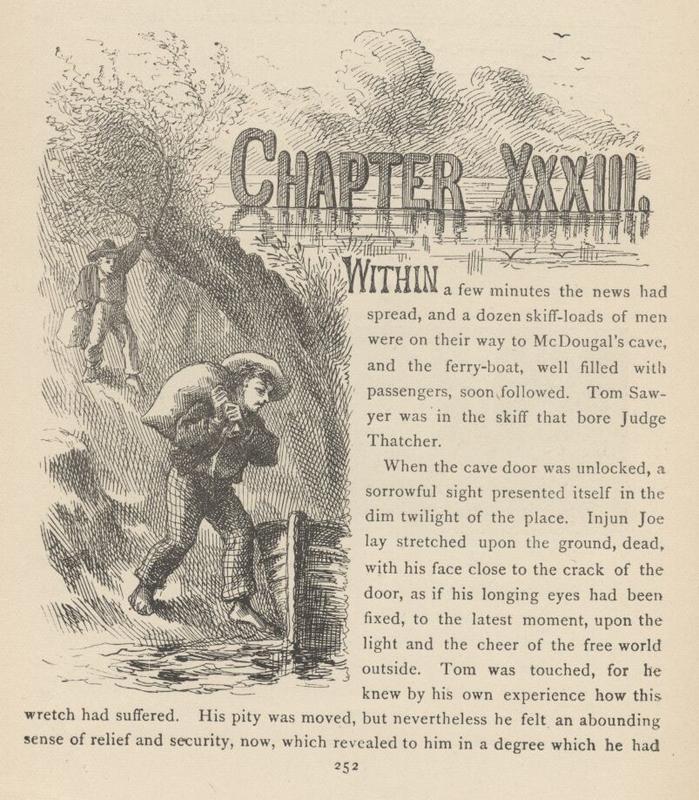
数分のうちにその知らせは広まり、十二艘の小舟に乗った男たちがマクドゥーガルの洞窟へと向かっていた。そして、乗客でいっぱいのフェリーボートもすぐにそれに続いた。トム・ソーヤーは、サッチャー判事を乗せた小舟に乗っていた。
洞窟の扉の鍵が開けられると、その場所の薄暗い光の中に、悲痛な光景が現れた。インジャン・ジョーが地面に伸びて死んでいた。顔を扉の隙間にぴったりと寄せ、まるでその渇望する目が、最後の瞬間まで外の自由な世界の光と賑わいを見つめていたかのようだった。トムは心を動かされた。この哀れな男がどれほど苦しんだか、自分自身の経験から知っていたからだ。彼の心には憐れみが湧いたが、それにもかかわらず、今や有り余るほどの安堵と安心を感じていた。そしてその感情は、この血に飢えた無法者に対して声を上げたあの日から、どれほど巨大な恐怖の重圧が自分にのしかかっていたかを、以前には十分に認識していなかったほどに、はっきりと彼に示した。
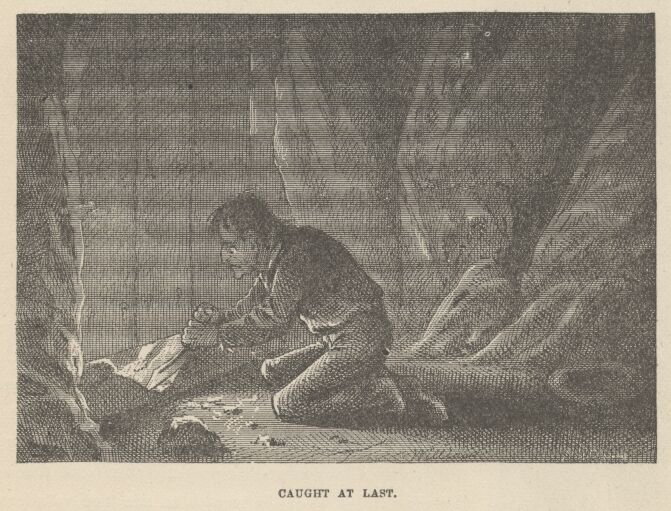
インジャン・ジョーのボウイナイフがすぐそばに落ちており、その刃は二つに折れていた。扉の大きな土台の梁は、気の遠くなるような労苦の末に、削られ、切り刻まれていた。しかし、それも無駄な労力だった。その外側には天然の岩が敷居を形成しており、その頑固な素材にはナイフは何の効果ももたらさなかったのだ。唯一の損害はナイフ自体に与えられたものだった。しかし、もし石の障害がなかったとしても、その労力はやはり無駄だっただろう。なぜなら、たとえ梁が完全に切り取られていたとしても、インジャン・ジョーは自分の体をドアの下にねじ込むことはできず、彼もそれを知っていたからだ。だから彼は、ただ何かをするために、退屈な時間を過ごすために、拷問されるような精神を働かせるために、その場所を切り刻んだに過ぎなかったのだ。普段なら、この玄関ホールには、観光客が残していったロウソクの切れ端が六つほど、岩の裂け目に差し込まれているのが見つかるはずだった。しかし、今は一つもなかった。囚人はそれらを探し出し、食べてしまったのだ。彼はまた、何匹かのコウモリをどうにかして捕まえ、それらもまた、爪だけを残して食べていた。哀れな不運な男は、餓死したのだ。すぐ近くのある場所には、頭上の鍾乳石から滴る水によって、何世紀にもわたって地面からゆっくりと石筍が成長していた。囚人はその石筍を折り、その切り株の上に石を置いた。その石には浅いくぼみを掘り、時計の針のように陰鬱な規則正しさで三秒に一滴ずつ落ちる貴重な雫を受け止めていた。それは二十四時間でデザートスプーン一杯分だった。その雫は、ピラミッドが新しかった頃も落ちていた。トロイが陥落した時も。ローマの礎が築かれた時も。キリストが磔にされた時も。征服王がイギリス帝国を築いた時も。コロンブスが航海した時も。レキシントンの虐殺が「ニュース」だった時も。

それは今も落ちている。そして、これらすべての出来事が歴史の午後へと沈み、伝説の黄昏へと沈み、忘却の深い夜に飲み込まれてしまった後も、なお落ち続けるだろう。すべての物事には目的と使命があるのだろうか? この雫は、このはかない人間の虫けらの必要に応えるために、五千年の間辛抱強く落ち続けてきたのだろうか? そして、一万年後に達成すべき別の重要な目的を持っているのだろうか? どうでもいいことだ。不運な混血の男が、その貴重な雫を受け止めるために石を掘ってから、幾年もの歳月が流れた。しかし今日に至るまで、観光客がマクドゥーガルの洞窟の驚異を見に来ると、最も長く見つめるのは、あの哀れな石と、ゆっくりと滴る水なのだ。インジャン・ジョーの杯は、この洞窟の驚異のリストの筆頭に立つ。あの「アラジンの宮殿」でさえ、それにはかなわない。
インジャン・ジョーは洞窟の入り口近くに埋葬された。そして、町々から、そして周囲七マイルのすべての農場や村から、人々がボートや馬車でそこに集まってきた。彼らは子供たちを連れ、あらゆる種類の食料を持参し、絞首刑と同じくらい満足のいく時間を葬式で過ごせたと告白した。

この葬式は、ある一つのことのさらなる進展を止めた。インジャン・ジョーの恩赦を求める知事への請願である。その請願書には多くの署名が集まっていた。涙ながらの雄弁な集会が何度も開かれ、感傷的な女たちの委員会が任命され、深い喪服に身を包んで知事の周りで泣きわめき、慈悲深い愚か者となって己の義務を踏みにじってくれるよう懇願することになっていた。インジャン・ジョーは村の市民を五人殺したと信じられていたが、それがどうしたというのだ? たとえ彼が悪魔そのものであったとしても、恩赦請願書に自分の名前を走り書きし、永久に損なわれた漏水装置から涙を一滴垂らす準備ができている弱虫たちは、いくらでもいただろう。
葬式の翌朝、トムはハックを人目につかない場所に連れて行き、重要な話をしようとした。ハックは、この時までにウェールズ人とダグラス未亡人からトムの冒険についてすべて聞いていたが、トムは、彼らが話していないことが一つあるだろうと言った。今話したいのはそのことだった。ハックの顔が曇った。彼は言った。
「それが何かは分かってる。お前は2号室に入って、ウイスキー以外何も見つけられなかったんだ。誰もそれがお前だとは言わなかったけど、あのウイスキーの騒ぎを聞いてすぐに、お前に違いないって分かったんだ。それに、お前が金を手に入れなかったことも分かってた。だって、もし手に入れてたら、他の誰にも黙ってても、どうにかして俺に教えに来たはずだからな。トム、なんだか俺たちにはあの盗品は手に入らねえって、ずっとそんな気がしてたんだ。」
「なんだよ、ハック、僕はあの酒場の主人のことなんか密告してないぞ。僕がピクニックに行った土曜日には、彼の酒場は何も問題なかったじゃないか。覚えてないのかい、あの夜、君が見張りをすることになってたのを?」
「ああ、そうだった! なんだかもう一年くらい前のことみたいだ。まさにあの夜、俺はインジャン・ジョーを未亡人の家まで尾行したんだ。」
「君が 尾行したのかい?」
「ああ、でも黙っててくれよ。インジャン・ジョーは仲間を残していったと思うんだ。そいつらに睨まれて、意地悪なことをされたくはない。俺がいなかったら、あいつは今頃テキサスでのうのうとしてたはずなんだ。」
それからハックは、自分の冒険のすべてをトムに内緒で語った。トムはそれまで、ウェールズ人が関わった部分しか聞いていなかったのだ。
「まあな」と、ハックはしばらくして本題に戻りながら言った。「2号室でウイスキーをくすねた奴が誰であれ、金もくすねたんだろうな。どっちにしろ、俺たちにとってはもうおしまいだ、トム。」
「ハック、あの金は2号室にはなかったんだ!」
「何だって!」ハックは仲間の顔を鋭く見つめた。「トム、お前、またあの金の足跡を掴んだのか?」
「ハック、それは洞窟の中にあるんだ!」
ハックの目が燃え上がった。
「もう一回言ってくれ、トム。」
「金は洞窟の中だ!」
「トム、本当のインディアンにかけて、今のは冗談か、それとも本気か?」
「本気だ、ハック。生まれてこの方、これほど本気だったことはない。僕と一緒にあそこに入って、取り出すのを手伝ってくれるかい?」
「もちろんさ! 道筋をつけて行けて、迷子にならない場所ならな。」
「ハック、世界で一番簡単なことさ、何の心配もいらない。」
「そいつは上等だ! どうして金が……」
「ハック、あそこに着くまで待ってくれよ。もし見つからなかったら、僕の太鼓も、持ってるもの全部も君にあげるよ。本当だ、ちくしょう。」
「分かった、そいつはすごい。いつ行くんだ?」
「今すぐだ、君がそう言うなら。もう体は大丈夫かい?」
「洞窟の奥深くかい? ここ三、四日、少しは歩けるようになったけど、一マイル以上は歩けないぜ、トム。少なくとも、そうは思えない。」
「僕以外の奴が行く道だと、あそこまで五マイルくらいあるんだ、ハック。でも、僕しか知らない、ものすごい近道があるんだ。ハック、小舟ですぐに連れて行ってやるよ。小舟をそこまで流して、僕一人でまた漕いで戻ってくる。君は指一本動かす必要はないよ。」
「すぐに出発しようぜ、トム。」
「分かった。パンと肉と、僕たちのパイプと、小さな袋を一つか二つと、凧糸を二、三本と、それから、ルシファーマッチとかいう、あの新しいやつがいくつか欲しいな。言っとくけど、前にあそこにいた時、あれがあったらなあって、何度も思ったんだ。」
昼を少し過ぎた頃、少年たちは留守にしている市民から小さな小舟を借り、すぐに出発した。「洞窟の谷」から数マイル下ったところで、トムが言った。
「さあ、見てくれ、ここの崖は洞窟の谷からずっと同じように見えるだろ。家もないし、材木置き場もない、茂みもみんな同じだ。でも、あそこに見える白い場所、地滑りがあったところが見えるかい? あれが僕の目印の一つだ。さあ、上陸しよう。」

二人は上陸した。
「さあ、ハック、僕たちが立っているこの場所から、僕が出てきたあの穴に釣り竿で触れることができるんだ。見つけられるか試してみてくれ。」
ハックはあたり一面を探したが、何も見つけられなかった。トムは得意げに、ウルシの茂みの密生した中へと行進し、言った。
「ここだよ! 見てくれ、ハック。この国で一番居心地のいい穴だ。このことは絶対に黙っててくれよ。ずっと強盗になりたいと思ってたんだけど、こういうものが必要だってことは分かってたんだ。でも、どこで見つけられるかが問題だった。今、手に入れたんだから、秘密にしておこう。ただ、ジョー・ハーパーとベン・ロジャースは入れてやる。だって、もちろんギャングがいなきゃ、格好がつかないからな。トム・ソーヤーのギャング団、響きが素晴らしいだろ、ハック?」
「ああ、本当にな、トム。それで、誰を襲うんだ?」
「ああ、だいたい誰でもさ。待ち伏せするんだ、それが主なやり方だ。」
「それで、殺すのかい?」
「いや、いつもじゃない。身代金[訳注:ランサム]を払うまで、洞窟に閉じ込めておくんだ。」
「身代金って何だい?」
「金だよ。友達からできるだけ金を集めさせるんだ。それで、一年経っても集まらなければ、殺す。それが一般的なやり方だ。ただ、女は殺さない。女は閉じ込めておくけど、殺さないんだ。彼女たちはいつも美しくて金持ちで、ものすごく怖がってる。時計とかは取るけど、いつも帽子を取って、丁寧に話すんだ。強盗ほど礼儀正しい奴はいないよ。どんな本を見てもそう書いてある。それで、女たちは君を好きになるんだ。洞窟に一週間か二週間もいると、泣くのをやめて、その後は追い出そうとしても出て行かなくなる。追い出しても、すぐにUターンして戻ってくるんだ。どの本にもそう書いてある。」
「へえ、そいつは本当にすごいな、トム。海賊よりいいと思うぜ。」
「ああ、いくつかの点ではいいよ。家にも近いし、サーカスとか、そういうのもあるからな。」
この時までにすべての準備が整い、少年たちはトムを先頭に穴に入った。彼らはトンネルの奥まで苦労して進み、それからつなぎ合わせた凧糸をしっかりと結び、先へ進んだ。数歩進むと泉に着き、トムは全身に震えが走るのを感じた。彼はハックに、壁際の粘土の塊の上にちょこんと乗ったロウソクの芯の燃えさしを見せ、自分とベッキーが、炎が最後の抵抗をして消えていくのを見つめていた様子を説明した。
少年たちは今や、ささやき声で話すようになっていた。その場所の静寂と暗闇が、彼らの心を圧迫していたからだ。彼らは進み続け、やがてトムのもう一つの通路に入ってそれをたどり、「飛び降り場所」に到着した。ロウソクの光が、それが実際には断崖絶壁ではなく、高さ二十フィートか三十フィートの急な粘土の丘に過ぎないという事実を明らかにした。トムはささやいた。
「さあ、すごいものを見せてやるよ、ハック。」
彼はロウソクを高く掲げて言った。
「角の向こうを、できるだけ遠くまで見てくれ。あれが見えるかい? あそこだ、向こうの大きな岩の上にあるやつ。ロウソクの煙で描かれているんだ。」
「トム、こいつは…… 十字架 だ!」
「さあ、お前の言う『二番』はどこだ? 『十字架の下』だっけな、おい? ちょうどあそこだ、ハック! インジャン・ジョーが蝋燭を突き出したのを見たのは!」
ハックはしばらくその神秘的な印を見つめていたが、やがて震える声で言った。
「トム、ここからずらかろうぜ!」
「なんだって! 宝物を置いていくのか?」
「ああ、置いてくんだ。インジャン・ジョーの幽霊が、きっとあの辺をうろついてる。」
「そんなことないさ、ハック。そんなことあるもんか。あいつが出るなら死んだ場所だろ。洞窟の入り口の、ここから五マイルも離れたとこだ。」
「いや、トム、違うんだ。金の周りをうろつくに決まってる。お化けってのはそういうもんだろ。お前だって知ってるはずだ。」
トムはハックの言うことが正しいのかもしれないと恐ろしくなってきた。不安が心に募る。しかし、やがてある考えが閃いた。
「おい見ろよ、ハック! 俺たち、なんて馬鹿なこと考えてたんだ! 十字架があるところに、インジャン・ジョーの幽霊が来るわけないじゃないか!」
まさに的を射た指摘だった。効果はてきめんだった。
「トム、そこまで考えてなかった。でも、その通りだ。あの十字架は俺たちにとって幸運の印だな。よし、下に降りてあの箱を探してみようぜ。」
トムが先に降り、粘土の丘に粗末な足場を刻みながら下っていった。ハックが後に続く。巨大な岩が立つ小さな洞窟からは、四つの通路が伸びていた。少年たちは三つの通路を調べたが、成果はなかった。岩の根元に最も近い通路に小さな窪みを見つけた。そこには毛布の寝床が敷かれ、古いズボン吊り、ベーコンの皮、そしてきれいにしゃぶられた鶏の骨が二、三本転がっていた。しかし、金の箱はなかった。二人はその場所を何度も何度も探したが、無駄だった。トムが言った。
「あいつは『十字架の下』って言った。まあ、ここが一番『十字架の下』に近い場所だよな。岩そのものの真下ってことはないはずだ。だって、地面にしっかりくっついてるんだから。」
二人はもう一度あたりを探し回り、それからがっかりして座り込んだ。ハックは何も思いつかなかった。やがてトムが口を開いた。
「おい見ろよ、ハック。この岩の片側の粘土の上には足跡と蝋燭の脂がついてるけど、他の側にはないぞ。これはいったいどういうことだ? きっと金は岩の下にあるんだ。この粘土を掘ってみるぞ。」
「そりゃあいい考えだ、トム!」ハックが生き生きと言った。
トムはすぐさま「本物のバーロウナイフ」を取り出し、四インチも掘らないうちに木にぶつかった。
「おい、ハック! 聞こえたか?」
ハックも掘り、掻き始めた。すぐに数枚の板が現れ、取り除かれた。その下には、岩の下へと続く自然の裂け目が隠されていた。トムはその中に入り、蝋燭を岩の下にできる限り差し出したが、裂け目の奥までは見えないと言った。探検しようと提案する。彼は身をかがめて下をくぐった。狭い道は緩やかに下っていく。右へ、左へと曲がりくねる道を進み、ハックがそのすぐ後を追った。やがてトムが短いカーブを曲がると、叫び声を上げた。
「なんてこった、ハック、これを見ろ!」
まさしく宝の箱だった。居心地のよさそうな小さな洞窟に、空の火薬樽、革ケースに入った二丁の銃、古びたモカシンが二、三足、革のベルト、そして水滴でびしょ濡れになったガラクタと一緒に置かれていた。
「ついに見つけたぞ!」ハックはそう言うと、黒ずんだ硬貨の山に手を突っ込んだ。「すげえ、俺たち大金持ちだぜ、トム!」

「ハック、いつか見つかるって信じてたぜ。信じられないくらいうまい話だけど、本当に見つけたんだ! なあ、ここでぐずぐずしてないで、さっさと運び出そう。俺がこの箱を持てるか試してみる。」
重さは五十ポンドほどあった。トムは不格好ながらも持ち上げることはできたが、楽に運ぶことはできなかった。
「やっぱりな」と彼は言った。「お化け屋敷でのあの日、あいつらが重そうに運んでたんだ。ちゃんと見てたからな。小さな袋を持ってこようと思ったのは正解だったな。」
金はすぐに袋に移され、少年たちはそれを十字架の岩まで運び上げた。
「さて、次は銃とかを持ってこようぜ」とハックが言った。
「いや、ハック、それはここに置いとけ。泥棒稼業を始めるときにぴったりの道具だ。ずっとここに置いといて、ここで俺たちの乱痴気騒ぎもやるんだ。乱痴気騒ぎにはもってこいの場所だぜ。」
「乱痴気騒ぎって何だ?」
「さあな。でも泥棒はいつも乱痴気騒ぎをやるもんだ。だから俺たちももちろんやらなくちゃ。さあ行こう、ハック、もうずいぶんここにいた。そろそろ遅くなる頃だ。腹も減ったしな。小舟に着いたら飯食って一服しようぜ。」
やがて二人はウルシの茂みから姿を現し、用心深くあたりを見回して安全を確かめると、すぐに小舟で昼食をとり、煙草をふかした。太陽が地平線に沈みかける頃、彼らは舟を押し出して漕ぎ出した。トムは長い黄昏の中、ハックと陽気にしゃべりながら岸辺を上っていき、日没後しばらくして上陸した。
「さあ、ハック」とトムが言った。「金は未亡人さんの家の薪小屋の屋根裏に隠そう。朝になったら俺が来て、勘定して山分けだ。そしたら森の中に安全な場所を見つけて隠すんだ。お前はここで静かに荷物の見張りをしててくれ。俺が走ってベニー・テイラーの小さな荷車をちょいと借りてくるから。一分もかからないさ。」
彼は姿を消し、すぐに荷車を引いて戻ってきた。二つの小さな袋を荷車に乗せ、その上に古いぼろ切れをいくつか投げかけると、荷物を後ろに引きずりながら出発した。ウェールズ人の家に着くと、二人は立ち止まって一休みした。まさに出発しようとしたその時、ウェールズ人が現れて言った。
「やあ、誰かね?」
「ハックとトム・ソーヤーです。」
「おお、よかった! 一緒に来なさい、君たち。みんなが待ちくたびれているよ。さあ、急いで、先に行きなさい。荷車は私が引いてあげよう。おや、思ったより軽くないな。レンガでも入っているのかね? それとも古鉄か?」
「古鉄です」とトムは答えた。
「そうだろうと思ったよ。この町の少年たちは、まともな仕事で倍の金を稼ぐよりも、鋳物工場に売るための六ビット[訳注: 75セント]ほどの古鉄を探すのに、よっぽど手間と時間をかけるからな。だが、それが人間というものだ。さあ、急いで、急いで!」
少年たちは何をそんなに急いでいるのか知りたかった。
「まあいいから。ダグラス未亡人の家に着けばわかるさ。」
ハックは、長いことあらぬ疑いをかけられるのに慣れていたので、いくらか不安げに言った。「ジョーンズさん、俺たち、何も悪いことはしてませんよ。」
ウェールズ人は笑った。「さあ、どうかな、ハック。それはわからんな。君と未亡人は仲が良いんだろう?」
「ええ。まあ、とにかくあの人は俺に良くしてくれます。」
「それならいいじゃないか。何を怖がる必要があるんだね?」
ハックののろい頭がその問いの答えを完全に見つけ出す前に、彼はトムと一緒にダグラス夫人の客間に押し込まれていた。ジョーンズ氏は荷車をドアのそばに置き、後から入ってきた。
部屋は煌々と照らされ、村の主だった人々が皆そこにいた。サッチャー家、ハーパー家、ロジャース家、ポリーおばさん、シッド、メアリー、牧師、新聞の編集者、その他大勢が、みな一張羅で着飾っている。未亡人は、これ以上ないほど心から少年たちを迎えたが、二人のその姿といったらなかった。粘土と蝋燭の脂で全身が汚れている。ポリーおばさんは屈辱で顔を真っ赤にし、眉をひそめてトムに向かって首を振った。しかし、二人の少年ほど辛い思いをした者はいなかった。ジョーンズ氏が言った。
「トムはまだ家にいなかったので、諦めかけたのですが、ちょうど私の家の戸口で彼とハックにばったり会ったものですから、急いで連れてきたのです。」
「まあ、それはよかった」と未亡人は言った。「こちらへいらっしゃい、二人とも。」
彼女は二人を寝室へ連れて行くと、こう言った。「さあ、顔を洗って着替えなさい。ここに新しい服が二着ありますよ。シャツも靴下も、全部揃っています。これはハックの分……いえいえ、お礼なんていいのよ、ハック。一着はジョーンズさんが、もう一着は私が買ったの。でも、二人ともぴったりのはずだから。さあ、着替えて。私たちは待っていますから、きれいになったら降りてきてちょうだい」そう言って彼女は部屋を出ていった。

第三十四章
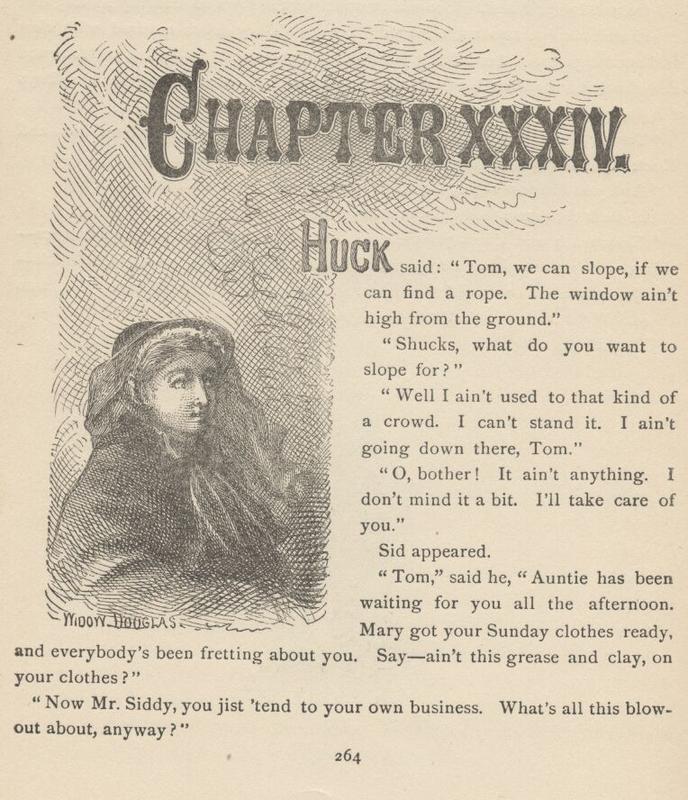
ハックが言った。「トム、ロープが見つかればずらかれるぜ。窓は地面からそう高くない。」
「ちぇっ! なんでずらかる必要があるんだ?」
「だって、ああいう人混みには慣れてねえんだ。我慢できねえ。俺は下には行かねえぞ、トム。」
「ああ、もう! どうってことないさ。俺は全然平気だ。お前のことは俺が見ててやるから。」
シッドが現れた。
「トム」と彼は言った。「おばさん、午後中ずっと君を待ってたんだよ。メアリーが日曜の服を用意して、みんな君のことでやきもきしてたんだ。ねえ、その服についてるの、脂と粘土じゃない?」
「おい、シディー坊や、お前は自分のことだけ心配してな。それにしても、この大騒ぎはいったい何なんだ?」
「未亡人さんがいつも開いてるパーティーの一つさ。今回はウェールズさんとその息子さんたちのためなんだって。この間の夜、大変なところを助けてもらったお礼にね。それからさ、聞きたいなら教えてあげてもいいけど。」
「なんだよ?」
「あのね、ジョーンズのじいさんが今夜、みんなを驚かせるようなことをしようとしてるんだ。でも僕、今日彼がおばさんにこっそり話してるのを聞いちゃったんだ。だから、もう大した秘密じゃないと思うけどね。みんな知ってるよ。未亡人さんだって、知らないふりしてるけど。ジョーンズさんは、ハックがどうしてもここにいなきゃだめだってさ。ハックがいなきゃ、その壮大な秘密とやらはうまくいかないんだってさ!」
「何の秘密だ、シッド?」
「ハックが泥棒たちを未亡人さんの家まで追跡したことさ。ジョーンズさんはそのサプライズで場を盛り上げようとしてたんだろうけど、きっと白けちゃうだろうね。」
シッドはとても満足げに、くすくすと笑った。
「シッド、お前がばらしたのか?」
「さあ、誰が言ったかなんてどうでもいいじゃないか。誰かさんが言ったんだ。それで十分さ。」
「シッド、この町でそんな意地の悪いことをするやつは一人しかいない。お前だ。もしお前がハックの立場だったら、こそこそ丘を駆け下りて、泥棒のことなんて誰にも言わなかっただろうな。お前には意地悪なことしかできないんだ。誰かが良いことをして褒められるのが我慢ならないんだろ。ほら、未亡人さんが言うみたいに『お礼は結構』だ」――トムはシッドの耳をひっぱたき、何度か蹴飛ばしてドアまで送り出した。「さあ、勇気があるならおばさんに言いつけに行けよ。そしたら明日はただじゃおかないからな!」
数分後、未亡人の客たちは夕食のテーブルにつき、一ダースほどの子供たちが、その地方とその時代の習慣に従って、同じ部屋の小さな脇テーブルに陣取っていた。頃合いを見計らって、ジョーンズ氏が短いスピーチを始めた。彼は、自分と息子たちに与えられた名誉について未亡人に感謝を述べたが、実はもう一人、その謙虚さゆえに……とかなんとか続けた。彼は、ハックがこの冒険で果たした役割という秘密を、得意の芝居がかったやり方で打ち明けた。しかし、それが引き起こした驚きはほとんど見せかけのもので、もっと幸運な状況下であれば得られたであろう、やかましく熱狂的な反応はなかった。とはいえ、未亡人は見事に驚いてみせ、ハックに山ほどの賛辞と感謝の言葉を浴びせたので、ハックは新しい服の耐え難いほどの不快感を、皆の視線と称賛の的になるという、まったくもって耐え難い不快感のせいで、ほとんど忘れてしまうほどだった。
未亡人は、ハックを自分の家に引き取って教育を受けさせ、金銭的な余裕ができたらささやかながら事業を始めさせてやりたい、と述べた。トムの出番が来た。彼は言った。「ハックにそんなものは必要ありません。ハックは金持ちなんです。」
この愉快な冗談に対して、当然起こるべき賛辞の笑いを抑えたのは、ひとえに列席者たちの行儀の良さのなせる業だった。しかし、その沈黙は少し気まずかった。トムがそれを破った。「ハックは金を持ってるんです。信じないかもしれないけど、大金持ちなんですよ。ああ、笑わなくてもいいです。見せてあげますから。ちょっと待っててください。」
トムは部屋を飛び出した。列席者たちは戸惑いと興味の入り混じった表情で顔を見合わせ、それから口をきけないでいるハックに問いかけるような視線を送った。
「シッド、トムはどうしたのかしら?」とポリーおばさんが言った。「あの子は……まったく、あの子の考えてることはさっぱりわからないわ。今まで一度も……」
トムが袋の重みに苦労しながら入ってきたので、ポリーおばさんは言葉を終えなかった。トムは黄色い硬貨の塊をテーブルの上にどっと注ぎ出し、言った。「ほら、言った通りでしょう? 半分はハックので、半分は俺のです!」

その光景に、誰もが息を呑んだ。皆が食い入るように見つめ、一瞬、誰も口をきかなかった。やがて、説明を求める声が一斉に上がった。トムは説明できると言い、そして実行した。話は長かったが、興味が尽きることはなかった。その魅惑的な語りの流れを遮る者は、ほとんど誰もいなかった。彼が話し終えると、ジョーンズ氏が言った。
「この場のために、ささやかなサプライズを用意したつもりだったのだが、もはや何ほどのこともないな。この一件の前では、私の出し物など実にちっぽけなものだ。それは認めよう。」
金が数えられた。総額は一万二千ドルを少し超えていた。その場にいた何人かは資産としてはそれ以上の価値を持っていたが、一度にこれほどの大金を目にした者は誰もいなかった。
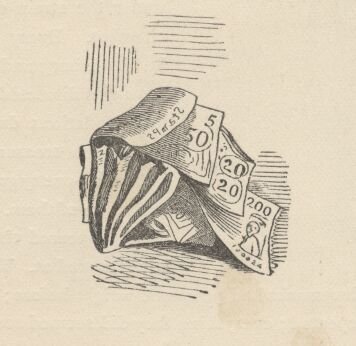
第三十五章
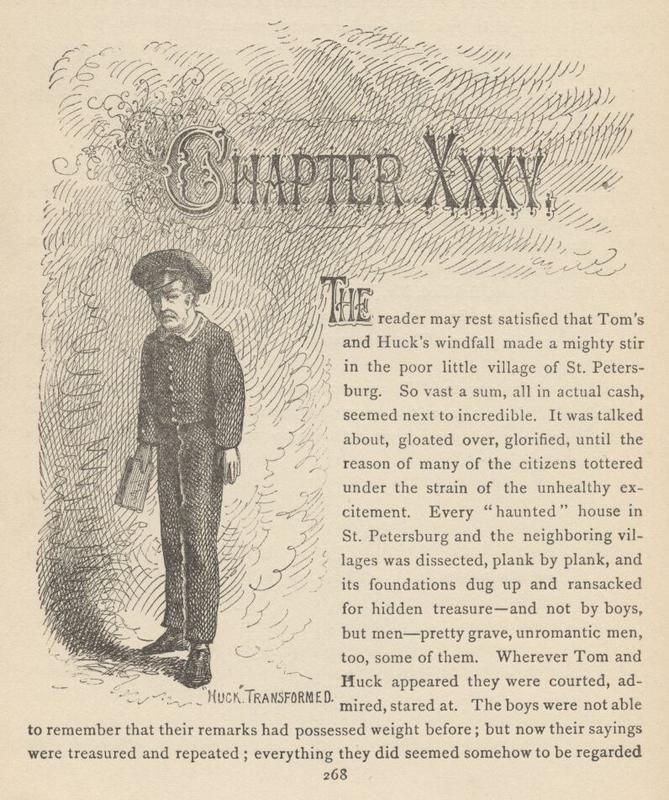
読者のご想像通り、トムとハックの棚ぼたは、貧しい小さな村セント・ピーターズバーグに大騒動を巻き起こした。それほどの巨額の金が、すべて現金であるという事実は、ほとんど信じがたいものだった。その話は語られ、うっとりと眺められ、美化され、ついには不健全な興奮のあまり、多くの住民の理性がぐらつき始めた。セント・ピーターズバーグとその近隣の村にある「お化け屋敷」はすべて、板一枚一枚に至るまで解体され、隠された宝を探して土台が掘り返され、荒らされた。それも少年たちによってではなく、大人たち――それも、かなり真面目で非ロマンティックな男たちによってである。トムとハックがどこに現れても、彼らはちやほやされ、賞賛され、じろじろと見られた。少年たちは、以前自分たちの発言に重みがあったとは覚えていなかったが、今や彼らの言葉は大切にされ、繰り返し語られた。彼らがすることは何もかもが、どういうわけか注目に値すると見なされるようになった。彼らは明らかに、ありふれたことをしたり言ったりする能力を失ってしまったのだ。さらに、彼らの過去の経歴が掘り起こされ、際立った独創性の印を帯びていることが発見された。村の新聞は、少年たちの伝記を掲載した。
ダグラス未亡人はハックの金を年六分の利で運用し、サッチャー判事もポリーおばさんの頼みでトムの金を同様にした。今や、どちらの少年にも、まさに驚異的としか言いようのない収入があった。平日は毎日一ドル、日曜日はその半分である。それはちょうど牧師の給料と同じだった――いや、約束された額と同じだった、というべきか。牧師はたいていそれを全額回収できなかったからだ。古き良き質素な時代には、週に一ドルと二十五セントもあれば、少年一人の食費、宿代、学費を賄え、ついでに言えば衣服と洗濯代にもなった。
サッチャー判事はトムを大いに見直していた。並の少年なら、自分の娘を洞窟から救い出すことなど決してできなかっただろう、と彼は言った。ベッキーが、トムが学校で彼女の身代わりに鞭打ちを受けたことを内緒で父親に話したとき、判事は目に見えて心を動かされた。そして彼女が、その鞭打ちを自分の肩からトムの肩に移すためにトムがついた大嘘を許してほしいと懇願すると、判事は見事な剣幕で、それは高潔で、寛大で、度量の大きい嘘だ――ジョージ・ワシントンの斧にまつわる賞賛された「真実」と肩を並べて、歴史の中を堂々と行進するに値する嘘だ! と叫んだ。ベッキーは、父親が床を歩き回り、足を踏み鳴らしてそう言ったときほど、大きく、そして立派に見えたことはないと思った。彼女はすぐにトムのところへ行き、そのことを話した。
サッチャー判事は、いつの日かトムが偉大な法律家か偉大な軍人になることを望んでいた。彼は、トムが国立陸軍士官学校に入学し、その後、国内最高の法科大学院で訓練を受けられるよう、自分が面倒を見るつもりだと語った。どちらの道に進むにしても、あるいは両方の道に進むにしても、準備が整うようにするためである。
ハックルベリー・フィンの富と、今や彼がダグラス未亡人の保護下にあるという事実は、彼を社会へと導いた――いや、引きずり込み、叩き込んだのだ。そして彼の苦しみは、ほとんど耐えがたいものだった。未亡人の使用人たちは彼を清潔に整え、髪をとかし、ブラシをかけ、毎晩、心に寄り添ってくれるようなシミ一つない、冷たいシーツのベッドに寝かせた。彼はナイフとフォークで食事をしなければならなかった。ナプキンとカップと皿を使わなければならなかった。本を学ばなければならず、教会に行かなければならなかった。あまりに上品に話さなければならなかったので、言葉は口の中で味気ないものになった。どこを向いても、文明の格子と足枷が彼を閉じ込め、手足を縛り付けた。
彼は三週間、その悲惨さに勇敢に耐えたが、ある日、行方をくらました。四十八時間、未亡人はひどく心を痛めながら彼を至る所で捜し回った。世間も深く憂慮し、人々は隅から隅まで捜索し、川をさらって彼の遺体を探した。三日目の早朝、トム・ソーヤーは賢明にも、廃墟となった屠殺場の裏手にある古くて空の樽をいくつか突っついて回り、その一つで逃亡者を発見した。ハックはそこで眠り、盗んできた食べ物の切れ端で朝食を済ませたばかりで、今はパイプをくわえて心地よさそうに寝転がっていた。髪はぼさぼさでとかされておらず、自由で幸せだった頃の彼を絵のように見せていたのと同じ、古ぼけたぼろ切れをまとっていた。トムは彼を叩き起こし、彼が引き起こした騒動を伝え、家に帰るよう促した。ハックの顔から穏やかな満足感が消え、憂鬱な影が差した。彼は言った。
「その話はよしてくれ、トム。やってみたけど、だめなんだ。だめなんだよ、トム。俺には向いてねえ。慣れてねえんだ。未亡人さんはいい人で、親切にしてくれる。でも、あのやり方には我慢できねえ。毎朝同じ時間に起こされるし、体を洗わされるし、髪はめちゃくちゃにとかされるし、薪小屋で寝ちゃいけないって言うし、あのいまいましい服を着なきゃならねえんだぜ、トム。息が詰まりそうだ。どういうわけか、空気が全然通らねえみてえだし、それに上品すぎて座ることも、横になることも、そこらで転げ回ることもできやしねえ。地下室の戸を滑り降りるのだって、もう何年もやってねえみてえな気分だ。教会に行って汗水たらして……あのつまらねえ説教は大嫌いだ! 中じゃハエも捕まえられねえし、噛みタバコもできねえ。日曜日は一日中靴を履いてなきゃならねえ。未亡人さんは鐘で飯を食い、鐘で寝て、鐘で起きる。何もかもがひどく規則正しくて、我慢できねえんだ。」

「まあ、みんなそうしてるんだぜ、ハック。」
「トム、そんなこた関係ねえ。俺はみんなじゃねえし、我慢できねえんだ。こんなに縛られるなんてひどいもんだ。それに、飯が簡単に手に入りすぎる。そんなんじゃ、食い物に興味がわかねえんだ。釣りに行くにもお伺いを立てなきゃならねえ。泳ぎに行くにもお伺いを立てなきゃならねえ。ちくしょう、何をするにもお伺いを立てなきゃならねえんだ。上品に話さなきゃならねえから、ちっとも気が休まらねえ。毎日屋根裏に上がってしばらく悪態をつかなきゃ、口の中に味がしなくなって死んじまうところだったぜ、トム。未亡人さんは煙草を吸わせてくれねえし、叫ばせてくれねえし、人の前であくびも伸びも体掻きもさせてくれねえんだ」[ここで、ひときわ苛立ちと傷心を込めて発作的に]「おまけに、ちくしょうめ、四六時中お祈りしてやがる! あんな女は見たことねえ! 俺は逃げ出すしかなかったんだ、トム。そうするしかなかったんだ。それに、もうすぐ学校が始まるだろ。そこにも行かなきゃならなかったんだ。そんなの、我慢できるもんか、トム。なあ、トム、金持ちになるってのは、言われてるほどいいもんじゃねえ。心配と苦労と汗の連続で、いっそ死んじまった方がましだって、いつも思うんだ。今の俺にはこの服が合ってるし、この樽が合ってる。もう二度と手放すもんか。トム、あの金がなけりゃ、こんな面倒なことにはならなかったんだ。だからよ、俺の分け前もお前が持ってってくれ。で、たまに十セントくれりゃいい。たくさんはよこすなよ、手に入れるのがそこそこ難しくなけりゃ、物なんてどうでもいいからな。それで、未亡人さんに俺のこと、うまく言ってくれよ。」
「ああ、ハック、そんなことできるわけないだろ。不公平じゃないか。それに、もう少しだけ我慢してみれば、きっと好きになるさ。」
「好きになるだと! ああ、そうだろうよ。熱いストーブの上にずっと座ってりゃ、好きになるみてえなもんだ。いやだ、トム、俺は金持ちになんかならねえし、あんな息の詰まるいまいましい家にも住まねえ。俺は森と川と樽が好きだ。これからもそいつらと一緒だ。ちくしょうめ! やっと銃と洞窟を手に入れて、泥棒稼業の準備が万端整ったってときに、こんな馬鹿げたことが起こって、何もかも台無しにしやがって!」
トムは好機と見た。
「おい聞けよ、ハック。金持ちになったからって、俺が泥棒になるのをやめるわけじゃないぜ。」
「本当か! そりゃすげえ。本気で言ってるのか、トム?」
「ここに座ってるのと同じくらい本気だ。でもな、ハック、お前がちゃんとしてなきゃ、仲間には入れてやれないぜ、わかるだろ。」
ハックの喜びはかき消された。「仲間に入れてくれないのか、トム? 海賊のときは仲間にしてくれたじゃないか。」
「ああ、でもあれとは違うんだ。泥棒は海賊よりも格が上なんだよ、一般的にはな。ほとんどの国じゃ、公爵とか、そういう貴族の中でもすごく地位が高いんだ。」

「なあ、トム、お前はいつも俺に優しくしてくれたじゃねえか。俺を締め出したりしないよな、トム? そんなことしないよな、なあ、そうだろ、トム?」
「ハック、俺だってしたくないし、したくなんかないさ。でも、世間の人はなんて言うと思う? きっとこう言うぜ。『ふん! トム・ソーヤー強盗団か! ずいぶん品のない連中が揃ってるな!』ってな。お前のことを言ってるんだぜ、ハック。お前も嫌だろ、俺も嫌だ。」
ハックはしばらく黙って、心の中で葛藤していた。やがて彼は言った。「わかった。一ヶ月だけ未亡人さんのところに戻って、やってみるよ。それで我慢できるようになるか試してみる。もし、お前が俺を仲間に入れてくれるならな、トム。」
「いいとも、ハック、話は決まりだ! さあ行こうぜ、相棒。未亡人さんには、お前に少し大目に見てくれるよう頼んでやるからさ、ハック。」
「本当か、トム。本当にそうしてくれるのか? そりゃいい。一番きついことをいくつか勘弁してくれりゃ、煙草も悪態もこっそりやって、なんとかやり通してみせるぜ。いつ強盗団を始めて泥棒になるんだ?」
「ああ、すぐにだ。仲間を集めて、今夜にでも入団式をやろうかな。」
「何をやるって?」
「入団式だよ。」
「そりゃ何だ?」
「お互いに助け合うこと、たとえズタズタに切り刻まれても絶対に団の秘密を漏らさないこと、そして仲間の一人を傷つけたやつは、そいつと家族全員を殺すことを誓うんだ。」
「そりゃ愉快だ。すごく愉快だぜ、トム!」
「ああ、そうだろうとも。その誓いは全部、真夜中に、見つけられる限り一番寂しくて、一番恐ろしい場所でやらなきゃならない。お化け屋敷が最高だけど、今はみんな壊されちまったからな。」
「まあ、真夜中ってだけでも十分いいぜ、トム。」
「ああ、そうだな。それから、棺桶の上で誓って、血で署名しなきゃならない。」
「そいつはいい! 海賊稼業より百万倍もいかしてるぜ。俺、腐っちまうまで未亡人さんのところにいるよ、トム。それで俺が評判のすご腕強盗になって、みんながその噂をするようになれば、きっと未亡人さんも、俺を拾ってやったことを誇りに思うだろうぜ。」

結び
かくしてこの年代記は終わる。これは厳密に一人の少年の物語であるからして、ここで筆を置かねばならない。これ以上物語を進めれば、それは一人の男の物語になってしまうからだ。大人の小説を書く場合、どこで終えるべきかははっきりしている――すなわち、結婚である。しかし、少年少女の物語を書く場合は、最も良いと思われるところで終えなければならない。
この本に登場する人物のほとんどは、今も健在で、豊かに、そして幸せに暮らしている。いつの日か、若者たちの物語を再び取り上げ、彼らがどのような大人になったのかを見てみる価値があると思われるかもしれない。ゆえに、現時点では彼らの人生のその部分については、一切明かさないのが賢明であろう。

