ハックルベリー・フィンの冒険
(トム・ソーヤーの相棒)
マーク・トウェイン著
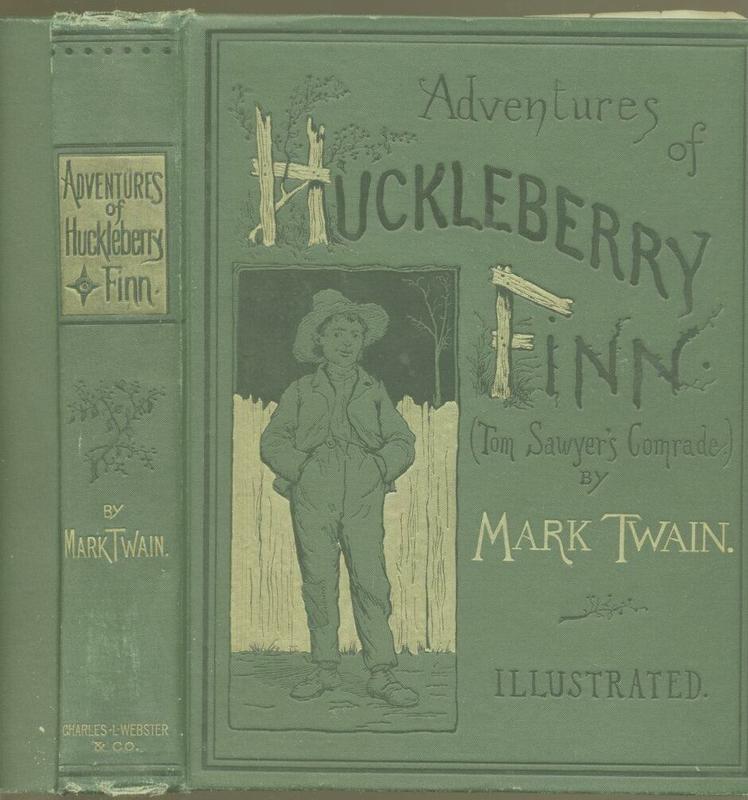

告
本物語に動機を見出さんとする者は、これを告訴す。本物語に教訓を見出さんとする者は、これを追放す。本物語に筋を見出さんとする者は、これを銃殺す。
著者ノ命ニ依リ 兵站部長 G・G
解題
本書においては、いくつかの種類の方言が用いられている。すなわち、ミズーリ州黒人方言、辺境南西部方言の極端な形、ありふれた「パイク郡」方言、そしてこの最後のものの変種が四種類である。これらの描き分けは、行き当たりばったりや当て推量で行われたものではない。骨を折り、これら幾つかの話し方に対する個人的な知見という信頼すべき導きと裏付けのもとに行われたものである。
この説明を記す理由は、さもなければ多くの読者が、登場人物たちは皆同じように話そうとしてうまくいっていないのだと考えるであろうからに他ならない。
著者
ハックルベリー・フィン
舞台:ミシシッピ川流域 時代:今から四、五〇年前
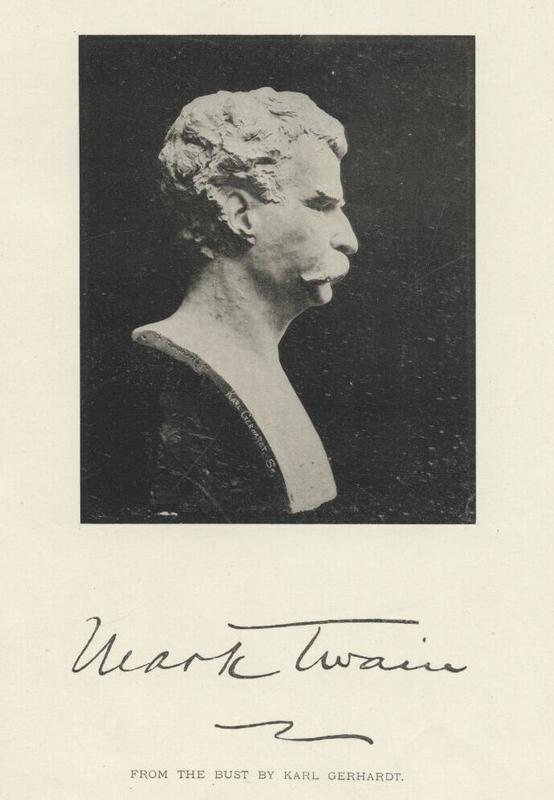
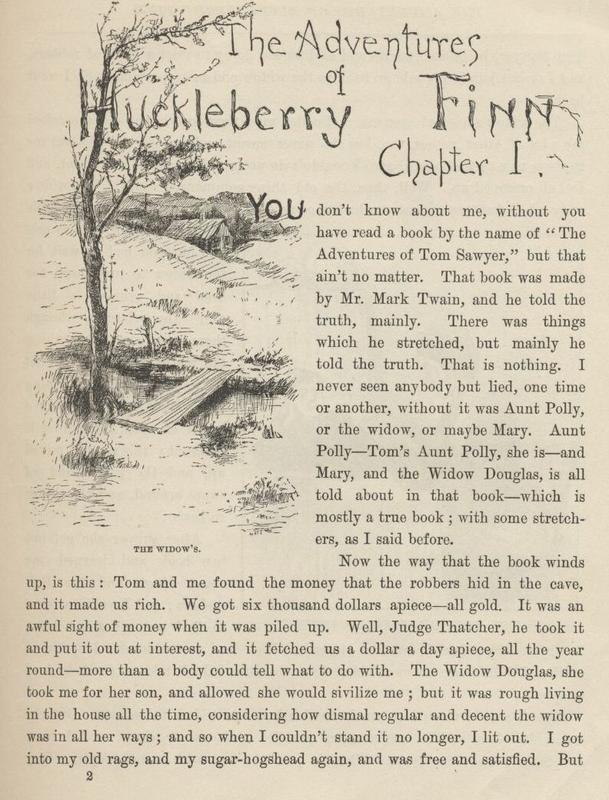
第一章
『トム・ソーヤーの冒険』って本を読んだことがなきゃ、あんたは俺のことは知らないだろう。でも、そんなこたどうでもいい。あの本はマーク・トウェインとかいう人がこしらえたもんで、だいたいは本当のことを話してる。ちょいと大げさに書いてるところもあるけど、だいたいは本当だ。別にたいしたことじゃない。嘘を一回もつかないやつなんて、ポリー叔母さんか未亡人さんか、あとはメアリーくらいで、俺は見たことがない。ポリー叔母さん――トムの叔母さんのことだ――とメアリー、それにダグラス未亡人さんのことは、みんなあの本に書いてある。さっきも言ったように、いくらか大げさなところはあるけど、ほとんどが本当の話だ。
さて、その本の結末はこうだ。トムと俺は、強盗どもが洞窟に隠した金を見つけて、それで金持ちになった。俺たちはそれぞれ六千ドルずつ手に入れた――全部金貨だ。積み上げると、そりゃあものすごい金の山だった。で、サッチャー判事がそれを預かってくれて、利子がつくようにしてくれた。おかげで一年中、毎日一人一ドルずつ入ってくることになった――どう使っていいかわからないくらいの大金だ。ダグラス未亡人さんは俺を息子として引き取って、俺を「お上品」にしてくれるって言った。だけど、四六時中家の中で暮らすのはきつかった。未亡人さんのやることは、何もかも陰気なくらいきちんとしてて、まともだったからだ。だから、もう我慢できなくなって、俺は逃げ出した。いつものボロ服を着て、砂糖樽に逆戻りして、自由で満ち足りた気分になった。ところがトム・ソーヤーが俺を探し出してきて、強盗団を始めるつもりだから、未亡人さんのところへ戻ってちゃんとした格好をするなら仲間に入れてやると言った。だから俺は戻った。
未亡人さんは俺を見て泣き出して、かわいそうな迷える子羊だのなんだの、いろんな呼び方をしたけど、別に悪気があって言ったわけじゃない。またあの新しい服を着せられて、俺は汗をだらだら流して、窮屈な思いをするしかできなかった。さて、それからまたいつものやつが始まった。未亡人さんが夕食の合図に鐘を鳴らすと、時間通りに行かなくちゃならない。テーブルについてもすぐには食べ始められなくて、未亡人さんが頭を垂れて、食べ物に向かって何やらぶつぶつ文句を言うのを待たなきゃならない。食べ物には別になんの問題もないんだが――つまり、ただ、全部別々に料理されてるってことだけで。がらくたの入った樽の中は違う。いろんなものがごちゃ混ぜになって、汁がそこらじゅうに染み渡って、食べ物がもっとうまくなる。
夕食の後、彼女は本を取り出して、モーゼと葦の舟の話を教えてくれた。俺はモーゼのことが知りたくてうずうずした。ところが、そのうち彼女が、モーゼはもうずいぶん昔に死んだってことをうっかり漏らしちまった。だから俺はもうモーゼのことなんかどうでもよくなった。死んだ人間なんて興味ないからだ。

すぐにタバコが吸いたくなって、未亡人さんに吸わせてくれって頼んだ。だけど、駄目だって言われた。みっともない習慣だし、不潔だから、もうやめるようにしなくちゃいけないって。一部の人間ってのはいつもこうだ。何も知らないくせに、人のやることにけちをつける。彼女ときたら、自分とは何の縁もゆかりもないし、死んじまったから誰の役にも立たないモーゼのことでやきもきしてるくせに、俺がちょっとはましなことをするのには、山ほど文句を見つけやがる。おまけに彼女は嗅ぎタバコをやるんだ。もちろん、それは別に構わない。自分がやってることだからな。
彼女の妹のミス・ワトソンが、一緒に住むためにちょうどやってきたところだった。ひょろっとした年増のばあさんで、でかい眼鏡をかけてる。そいつが今度は綴りの本を持って俺に食ってかかってきた。一時間くらいみっちりしごかれて、それから未亡人さんがやめさせてくれた。もうちょっとで我慢の限界だった。それから一時間は死ぬほど退屈で、俺はそわそわしていた。ミス・ワトソンはこう言う。「ハックルベリー、そこに足を乗せないで」「ハックルベリー、そんなに縮こまらないで、まっすぐ座りなさい」。そしてすぐにまたこう言う。「ハックルベリー、そんなにあくびして伸びをしないで。もう少しまともに振る舞えないの?」それから彼女は地獄のことをさんざん聞かせてくれたので、俺もそこへ行きたいもんだと言ってやった。すると彼女は怒り出したが、俺に悪気はなかった。ただどこかへ行きたかっただけだ。ただ変化が欲しかっただけで、場所にこだわりはなかった。俺が言ったことは悪いことだ、と彼女は言った。自分なら世界中をくれると言われてもそんなことは口にしない、天国へ行けるように生きるつもりなんだ、と。まあ、彼女が行くところへ行っても何の得もないと思ったから、俺はそこを目指すのはやめようと心に決めた。でも、そんなことは口にしなかった。面倒を起こすだけで、何の得にもならないからだ。

一度口火を切ると、彼女は天国のことを延々と話し続けた。天国では、一日中ハープを持って歩き回り、永遠に歌い続けるだけなんだそうだ。だから俺はたいしていいところだとは思わなかった。でも、口には出さなかった。トム・ソーヤーはそこへ行けると思うかと尋ねると、彼女はとんでもないと言った。それを聞いて俺は嬉しくなった。トムと俺は一緒にいたかったからだ。
ミス・ワトソンは俺にがみがみ言い続けて、うんざりするし、寂しくなってきた。やがて、黒人たちが連れてこられて祈りの時間になり、それからみんな寝床についた。俺はろうそくを一本持って自分の部屋へ上がり、テーブルの上に置いた。それから窓際の椅子に腰を下ろして、何か楽しいことを考えようとしたが、無駄だった。あまりに寂しくて、いっそ死んでしまいたいとさえ思った。星が輝き、森の木の葉がもの悲しくざわめいていた。遠くでフクロウが、死んだ誰かのことをホーホーと鳴いているのが聞こえた。ヨタカと犬が、これから死ぬ誰かのことを嘆いて鳴いていた。風が俺に何かをささやこうとしているようだったが、何を言っているのか聞き取れず、それでぞっと寒気がした。それから森の奥深くで、幽霊が出すような音が聞こえた。心に何か思うことがあって、それをうまく伝えられず、墓の中で安らかに眠れなくて、毎晩そうやって嘆きながらさまよっているときに出す、あの音だ。俺はすっかり落ち込んで怖くなって、誰かそばにいてくれたらと心から願った。ほどなくして、一匹のクモが俺の肩を這い上がってきたので、指ではじき飛ばすと、ろうそくの中に落ちた。俺が身動きする前に、クモはすっかり縮こまってしまった。それがひどく不吉な知らせで、俺に悪い運をもたらすだろうってことは、誰に言われなくてもわかった。だから俺は怖くなって、服がはだけるほど震えた。立ち上がってその場で三回くるりと回り、そのたびに胸で十字を切った。それから魔女除けに、髪を一房とって糸で結んだ。でも、これっぽっちも自信はなかった。そのおまじないは、見つけた蹄鉄をなくしたときにやるもので、戸口の上に釘で打ち付ける代わりにするんだ。クモを殺したときの不運を避ける方法になるなんて、誰からも聞いたことがなかった。
俺はまた腰を下ろし、全身をがたがた震わせながら、一服しようとパイプを取り出した。家の中は死んだように静まり返っていたから、未亡人さんには気づかれないだろう。やがて、ずいぶん経ってから、町の時計が遠くでゴーン、ゴーン、ゴーンと十二回鳴るのが聞こえた。そしてまた静寂が戻った――前よりもっと静かになった。すぐに、暗い木々の間で小枝がぽきりと折れる音がした――何かが動いている。俺はじっと座って耳を澄ました。やがて、向こうの方で「ミャーオ! ミャーオ!」という声がかすかに聞こえた。しめた! 俺はできるだけ小声で「ミャーオ! ミャーオ!」と答えると、明かりを消して窓から物置小屋の屋根に飛び降りた。それから地面に滑り降りて木々の間に這っていくと、案の定、トム・ソーヤーが待っていた。

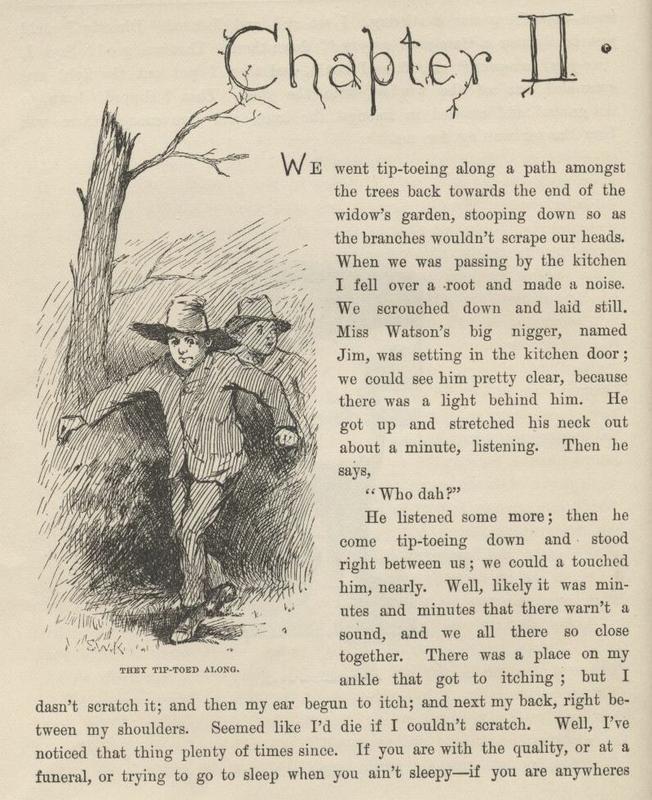
第二章
俺たちは未亡人さんの庭の端の方へ向かって、木々の間の小道を抜き足差し足で進んだ。枝が頭に当たらないように、身をかがめて。台所のそばを通りかかったとき、俺は木の根につまずいて音を立ててしまった。俺たちはさっと身をかがめて、じっと動かずにいた。ミス・ワトソンのところのでかい黒人、ジムという男が台所の戸口に座っていた。後ろに明かりがあったので、彼の姿はかなりはっきり見えた。彼は立ち上がって、一分ほど首を伸ばし、耳を澄ましていた。それからこう言った。
「誰や?」
彼はもうしばらく耳を澄ましていた。それから抜き足差し足で降りてきて、ちょうど俺たちの間に立った。もう少しで手が届きそうだった。きっと何分も何分も、物音一つせず、俺たちはみんなそんなに近くに固まっていた。足首がかゆくなってきたが、かくわけにはいかない。すると今度は耳がかゆくなり始めた。次は背中、ちょうど肩甲骨の間だ。かけなきゃ死んでしまいそうだった。まあ、このことには後で何度も気づかされた。偉い人と一緒にいるときとか、葬式のときとか、眠くもないのに寝ようとしているときとか――とにかく、かいちゃいけない場所にいるときに限って、全身千カ所以上もかゆくなるもんだ。やがてジムが言った。
「おい、誰や? どこにおるんや? ちくしょう、何か聞こえたはずやのに。よし、どうするか決めたで。ここに座って、もう一回聞こえるまで聞いとったるわ。」

そう言って、彼は俺とトムの間の地面に腰を下ろした。木に背中をもたせかけ、足を伸ばすと、片方の足が俺の足にほとんど触れそうになった。俺の鼻がかゆくなり始めた。涙が出るほどかゆかった。でも、かけない。すると今度は鼻の内側がかゆくなってきた。次は下の方までかゆくなってきた。どうやってじっとしていればいいのかわからなかった。この惨めな状態が六、七分も続いたが、それよりずっと長く感じられた。今では十一カ所もかゆかった。もう一分も我慢できないと思ったが、歯を食いしばって耐える準備をした。ちょうどそのとき、ジムが荒い息をし始めた。次にいびきをかき始めた――そして俺はすぐにまた楽になった。
トムが俺に合図をした――口で小さな音を立てるようなやつだ――そして俺たちは四つん這いになって、そろそろと離れていった。十フィートほど離れたところで、トムが俺にささやいて、面白半分にジムを木に縛りつけようと言った。でも俺は駄目だと言った。ジムが目を覚まして騒ぎを起こしたら、俺がいないことがばれてしまう。するとトムは、ろうそくが足りないから、台所に忍び込んで少しもらってくると言った。俺はやめてほしかった。ジムが目を覚ましてやってくるかもしれないと言った。でもトムはどうしてもやりたいと言う。だから俺たちはそこへ滑り込み、ろうそくを三本手に入れた。トムは代金としてテーブルに五セントを置いた。それから俺たちは外へ出て、早く逃げたくてたまらなかった。ところがトムはどうしても、ジムのところへ四つん這いで這っていって、何かいたずらをしないと気が済まないと言う。俺は待った。あたりはひどく静かで寂しく、ずいぶん長い時間に感じられた。
トムが戻るとすぐに、俺たちは小道を急ぎ、庭の塀を回り込み、やがて家の向こう側にある丘の急な頂上にたどり着いた。トムの話では、ジムの頭から帽子をそっと脱がせて、すぐ上の枝に引っ掛けてやったそうだ。ジムは少し身じろぎしたが、目を覚ましはしなかった。後になってジムは、魔女たちに魔法をかけられて、催眠状態にされ、州中を乗り回されたあげく、また木の下に座らされて、誰がやったかわかるように帽子を枝に掛けられたんだと言った。そして次にジムがその話をしたときには、ニューオーリンズまで乗り回されたと言っていた。それからというもの、話すたびにどんどん大げさになっていき、しまいには世界中を乗り回されて、死ぬほど疲れさせられ、背中は鞍ずれだらけになったと言った。ジムはそのことをとてつもなく自慢にしていて、他の黒人たちをほとんど相手にしなくなった。黒人たちは何マイルも離れたところからジムの話を聞きにやってきて、彼はこの地方のどの黒人よりも尊敬されるようになった。見知らぬ黒人たちは口をぽかんと開けて、まるで不思議なものでも見るかのように、彼の全身を眺めた。黒人たちはいつも、台所の暖炉のそばの暗がりで魔女の話をしている。だが、誰かが話していて、そういうことを何でも知っているようなそぶりを見せていると、ジムがひょっこり現れてこう言うんだ。「ふん! お前ら、魔女の何を知っとんねん?」するとその黒人は黙り込んで、引っ込んでいなければならなかった。ジムはいつもその五セント硬貨を紐で首からぶら下げていて、これは悪魔が自分の手でくれたお守りで、これに何かを唱えるだけで誰でも治せるし、いつでも好きなときに魔女を呼び出せると言っていた。でも、何を唱えるのかは決して言わなかった。黒人たちはあちこちからやってきて、その五セント硬貨を一目見るためだけに、持っているものを何でもジムに差し出した。でも、それに触ろうとはしなかった。悪魔がそれに触れたからだ。ジムは召使いとしてはほとんど使い物にならなくなった。悪魔に会って、魔女に乗り回されたことで、すっかり天狗になってしまったからだ。
さて、トムと俺が丘の頂上の端に着くと、俺たちは眼下の村を見下ろし、三つか四つの明かりが瞬いているのを見た。病人がいるのかもしれない。俺たちの頭上では星がとてもきれいにきらめいていた。そして村のそばには川があった。幅が一マイルもある、恐ろしく静かで壮大な川だった。俺たちは丘を下り、ジョー・ハーパーとベン・ロジャース、それに他の少年が二、三人、古い皮なめし工場に隠れているのを見つけた。そこで俺たちは小舟を解き、川を二マイル半ほど下って、丘の斜面の大きな傷跡のところまで行き、岸に上がった。
俺たちは茂みのかたまりのところへ行き、トムはみんなに秘密を守ると誓わせ、それから丘にある穴を見せた。茂みが一番深いところだ。それからろうそくに火をつけ、四つん這いになって中へ入っていった。二百ヤードほど進むと、洞窟が広がった。トムは通路をあちこち探り、やがて、穴があるとは気づかないような壁の下をくぐった。狭い場所を進んでいくと、じめじめして、汗ばんで、冷たい部屋のようなところに出て、そこで俺たちは立ち止まった。トムが言った。
「さあ、これからこの強盗団を始めて、トム・ソーヤー団と名付けよう。仲間になりたいやつは全員、誓いを立てて、血で名前を書かなきゃならない。」
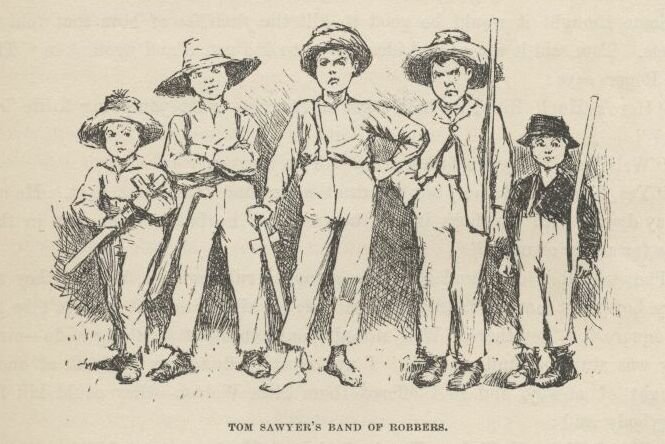
みんな乗り気だった。そこでトムは、誓いの言葉を書きつけた紙を一枚取り出して、読み上げた。それは、団に忠誠を誓い、決して秘密を漏らさないこと、もし誰かが団の仲間に何かをしたら、その人物とその家族を殺すよう命じられた仲間は必ずそれを実行し、殺して胸に十字の印を刻むまで、食うことも寝ることも許されないこと、それが団の印であること、などを誓うものだった。そして、団に属さない者はその印を使うことができず、もし使えば訴えられ、再び使えば殺されること。そして、団の仲間が秘密を漏らせば、喉をかき切られ、死体を焼かれて灰をまき散らされ、名前を血で名簿から消されて、団の仲間から二度と口にされることなく、呪いをかけられて永遠に忘れ去られること。
みんな、それは実に素晴らしい誓いだと言って、トムに自分で考えたのかと尋ねた。彼は、一部はそうだが、残りは海賊の本や強盗の本から取ったもので、格好いい団ならどこでもやっていることだと言った。
秘密を漏らした仲間の「家族」も殺すのがいいんじゃないかと言う者もいた。トムはそれはいい考えだと言って、鉛筆を取って書き加えた。するとベン・ロジャースが言った。
「ここにいるハック・フィンは、家族がいないぞ。あいつのことはどうするんだ?」
「なんだ、父親がいるじゃないか」とトム・ソーヤーが言った。
「ああ、父親はいるけど、近頃じゃどこにいるかさっぱりわからないんだ。前は皮なめし工場で豚と一緒に酔っぱらって寝てたけど、この一年以上、この辺りじゃ見かけないぜ。」
みんなでそのことを話し合ったが、俺を仲間外れにしようという雰囲気になった。どの少年にも家族か殺すべき誰かがいなければ、他の仲間に対して公平じゃないと言うのだ。さて、誰もどうすればいいか思いつかなかった――みんな行き詰まって、黙り込んでしまった。俺は泣き出しそうだった。だが、そのときふといい方法を思いついたので、ミス・ワトソンを差し出した――彼女を殺せばいい、と。みんなが言った。
「おお、それでいい。それで問題ない。ハックも仲間に入れるぞ。」
それからみんな、指にピンを刺して血を出し、署名した。俺は紙に自分の印をつけた。
「さて」とベン・ロジャースが言った。「この団の商売は何だ?」
「強盗と殺人に決まってるだろ」とトムは言った。
「でも、誰を襲うんだ? ――家か、牛か、それとも――」
「馬鹿言え! 牛なんかを盗むのは強盗じゃない。それは夜盗だ」とトム・ソーヤーは言った。「俺たちは夜盗じゃない。そんなのは格好悪い。俺たちはハイウェイマン[訳注:街道筋の追い剥ぎ]だ。道路で駅馬車や馬車を止めて、覆面をして、人々を殺して時計や金を奪うんだ。」
「いつも人を殺さなきゃいけないのか?」
「ああ、もちろんさ。それが一番いい。違う意見の権威もいるけど、たいていは殺すのが一番だと考えられてる――洞窟に連れてきて、身代金が払われるまで生かしておくやつらを除いてはな。」
「身代金? なんだそりゃ?」
「知らない。でも、そういうもんなんだ。本で見たんだから、もちろん俺たちもそうしなくちゃならない。」
「でも、それが何かわからなかったら、どうやってやるんだよ?」
「なんだってんだ、とにかくやらなきゃ駄目なんだ。本にそう書いてあるって言ってるだろ? 本に書いてあることと違うことをやって、全部めちゃくちゃにしたいのか?」
「おい、言うだけなら簡単だよ、トム・ソーヤー。でも、どうやってやるのか俺たちが知らないのに、どうやってそいつらから身代金を取るんだ? ――それが俺の知りたいことだ。なあ、お前はそれが何だと思うんだ?」
「うーん、わからない。でも、たぶん、身代金が払われるまで生かしておくってのは、死ぬまで生かしておくってことじゃないかな。」
「なるほど、それならわかる。それでいいじゃないか。どうして最初からそう言わなかったんだ? 死ぬまで身代金を取るために生かしておくんだな。そいつらも厄介なことになるぞ――何でも食い尽くして、いつも逃げようとするだろうからな。」
「何を言ってるんだ、ベン・ロジャース。見張りがいて、少しでも動いたら撃ち殺す準備ができてるのに、どうやって逃げられるんだ?」
「見張り! そりゃいいな。じゃあ誰かが一晩中起きてて、一睡もせずにそいつらを見張ってなきゃいけないってことか。馬鹿げてると思うぜ。ここに着いたらすぐ、棍棒で身代金を取っちまえばいいじゃないか?」
「本にそう書いてないからだ――それが理由だ。なあ、ベン・ロジャース、お前は物事をちゃんとしたやり方でやりたいのか、やりたくないのか? ――そこが問題だ。本を作った連中が、正しいやり方を知ってると思わないのか? お前がそいつらに何か教えてやれるとでも思うのか? とんでもない。だめだ、俺たちはちゃんとしたやり方で身代金を取るんだ。」
「わかったよ。構わないけど、とにかく馬鹿なやり方だと思うぜ。なあ、女も殺すのか?」
「おいおい、ベン・ロジャース、俺がお前みたいに無知だったら、そんなこと口に出さないぜ。女を殺す? いや、本の中でそんなことをするやつは見たことがない。女たちは洞窟に連れてきて、パイみたいに丁寧にもてなすんだ。そうすると、そのうちお前に惚れて、もう家に帰りたくないって言い出すんだよ。」
「まあ、そういうやり方なら賛成だけど、信用できないな。あっという間に洞窟は女と、身代金を待ってる男たちでごった返して、強盗の居場所がなくなっちまうぜ。でも、好きにしろよ、俺はもう何も言わない。」
リトル・トミー・バーンズはもう眠ってしまっていて、みんなが彼を起こすと、怖がって泣き出し、ママのところへ帰りたい、もう強盗なんかやりたくないと言った。
そこでみんなは彼をからかって、泣き虫と呼んだ。それで彼は腹を立てて、まっすぐ帰って秘密を全部ばらしてやると言った。だが、トムが黙っているようにと五セントを渡すと、今日はみんなで家に帰って、来週また会って、誰かを襲って何人か殺そうと言った。
ベン・ロジャースは、日曜日しかあまり出られないから、次の日曜日に始めたがった。だが、他の少年たちはみんな、日曜日にそんなことをするのは悪いことだと言い、それで話は決まった。彼らは集まってできるだけ早く日取りを決めることに同意し、それからトム・ソーヤーを団の第一隊長に、ジョー・ハーパーを第二隊長に選んで、家路についた。
俺は物置小屋をよじ登り、夜が明ける直前に窓から忍び込んだ。新しい服は油と泥でぐちゃぐちゃで、俺はくたくたに疲れていた。
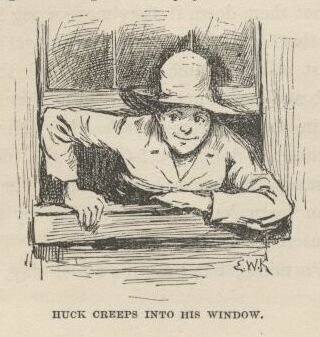
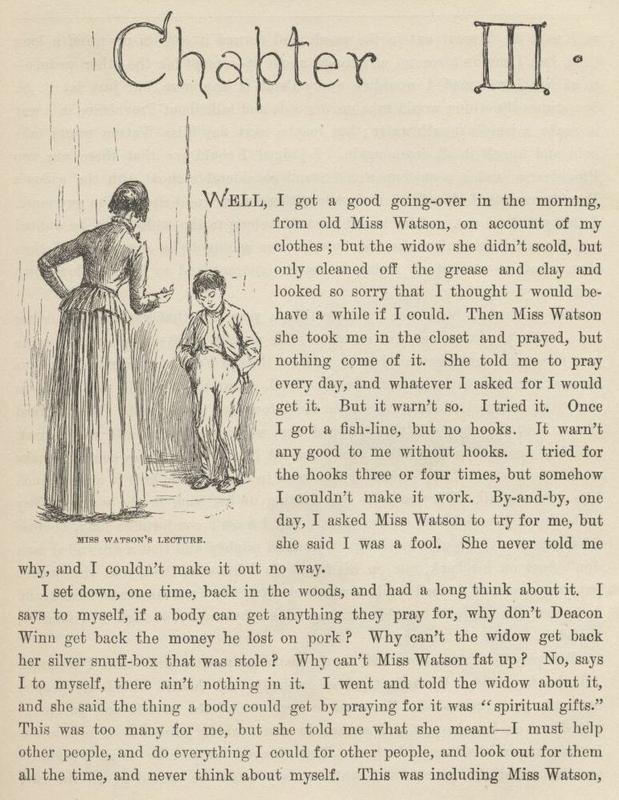
第三章
さて、朝になると、服のことで年寄りのミス・ワトソンにこっぴどく説教された。でも未亡人さんは叱らずに、ただ油と泥を落としてくれて、あまりに悲しそうな顔をするので、俺はできるならしばらくは行儀よくしようと思った。それからミス・ワトソンは俺を小部屋に連れて行って祈ってくれたが、何も起こらなかった。彼女は、毎日祈れば、何でも願ったものが手に入ると言った。だが、そうはならなかった。俺は試してみた。一度、釣り糸は手に入ったが、釣り針はなかった。釣り針がなきゃ何の役にも立たない。三、四回は釣り針を願ってみたが、どうしてもうまくいかなかった。そのうち、ある日、ミス・ワトソンに俺のために試してみてくれと頼んだが、彼女は俺を馬鹿だと言った。どうしてかは教えてくれず、俺にはさっぱりわけがわからなかった。
あるとき森の奥で腰を下ろして、そのことについてじっくり考えた。俺は独り言を言った。もし祈れば何でも手に入るなら、どうしてウィン執事は豚肉で損した金を取り戻せないんだ? どうして未亡人さんは盗まれた銀の嗅ぎタバコ入れを取り戻せないんだ? どうしてミス・ワトソンは太れないんだ? いや、と俺は自分に言い聞かせた。そんなうまい話があるもんか。俺は未亡人さんのところへ行ってそのことを話すと、彼女は、祈ることで手に入るのは「霊的な贈り物」だと言った。俺には難しすぎたが、彼女はその意味を教えてくれた――他の人を助け、他の人のためにできることは何でもし、いつも彼らのことを見守り、決して自分のことは考えないようにしなければならない、と。俺の解釈では、これにはミス・ワトソンも含まれていた。俺は森へ出て、長いことそのことを考え巡らせたが、何の得にもならないと思った――他の人たち以外には。だからとうとう、もうそのことについて悩むのはやめて、放っておくことにした。時々、未亡人さんは俺を脇へ連れて行って、よだれが出そうになるようなやり方で神様の話をしてくれることがあった。だが、たぶん次の日にはミス・ワトソンがしゃしゃり出てきて、それを全部ぶち壊しにする。俺には二種類の神様がいるのがわかるような気がした。哀れなやつでも、未亡人さんの神様と一緒ならかなりの見込みがあるだろうが、もしミス・ワトソンの神様につかまったら、もう助かる道はない。俺は考え抜いて、もし望んでくれるなら未亡人さんの神様につこうと決めた。もっとも、俺がそんなに無知で、どうしようもなく下品で意地悪なのに、神様が俺を得たところで、以前よりどう良くなるのかはさっぱりわからなかったが。
パップは一年以上も姿を見せていなかったし、俺にとっては好都合だった。もう二度と会いたくなかった。あいつはしらふで俺を捕まえられるときには、いつも俺をひどくぶった。もっとも、あいつが周りにいるときは、たいてい森へ逃げ込んでいたが。さて、この頃、町の十二マイルほど上流の川で、あいつが溺死体で見つかったと、人々は言っていた。とにかく、あれはあいつだと判断したそうだ。その溺死体はちょうどあいつと同じくらいの大きさで、ぼろをまとっていて、珍しいほど長い髪をしていた。それは全部パップそっくりだった。だが、顔からは何もわからなかった。あまりに長く水中にあったので、もはや顔のようではなかったからだ。死体は水面に仰向けに浮いていたそうだ。彼らはそれを引き上げて、土手に埋めた。だが、俺が安心していられたのは長くはなかった。あることを思いついてしまったからだ。溺死した男は仰向けではなく、うつ伏せに浮くものだと、俺はよく知っていた。だから、そのときわかったんだ。これはパップじゃない、男の服を着た女なんだと。だから俺はまた不安になった。いずれあの親父はまた現れるだろうと踏んでいた。現れてほしくはないと思っていたが。
俺たちは一ヶ月ほど、時々強盗ごっこをして遊んだが、それから俺は辞めた。少年たちはみんな辞めた。俺たちは誰も襲わなかったし、誰も殺さなかった。ただ真似事をしていただけだ。森から飛び出して、豚追いや、市場へ野菜を運ぶ荷馬車の女たちに突撃したりしたが、誰一人として捕まえられなかった。トム・ソーヤーは豚を「金塊」と呼び、カブや野菜を「宝石」と呼んだ。そして俺たちは洞窟へ行って、自分たちがやったことや、何人殺して印をつけたかについて、大騒ぎで話し合った。だが、俺には何の儲けにもならないように思えた。あるときトムは、燃える棒を持たせて少年を町中に走らせた。彼はそれをスローガン(団が集まる合図)と呼んだ。そして、スパイから極秘情報を得たと言った。翌日、スペインの商人と金持ちのアラブ人の大集団が、二百頭の象と六百頭のラクダ、そして千頭以上の「荷運び」ラバを引き連れて、洞窟谷で野営する予定だというのだ。ラバは全部ダイヤで荷を満載していて、護衛はたった四百人の兵士しかいない。だから俺たちは、彼が言うところの待ち伏せをして、全員を殺して獲物をかっさらうのだ、と。彼は、剣と銃をぴかぴかに磨いて、準備しなければならないと言った。彼はカブを積んだ荷車を追いかけるときでさえ、剣と銃を全部磨き上げなければ気が済まなかった。それがただの木ずりとほうきの柄で、腐るまで磨いたって、元の状態より灰一握り分の価値も上がりはしないというのに。俺は、そんな大勢のスペイン人やアラブ人に勝てるとは信じていなかったが、ラクダと象は見たかったので、翌日の土曜日、待ち伏せ場所にちゃんといた。そして合図が出ると、俺たちは森から飛び出して丘を駆け下りた。だが、そこにはスペイン人もアラブ人もいなかったし、ラクダも象もいなかった。あったのは日曜学校のピクニックだけで、それも一番下のクラスの子供たちだけだった。俺たちはそれをめちゃくちゃにして、子供たちを谷の上まで追いかけた。だが、手に入ったのはドーナツとジャムだけで、ベン・ロジャースはぼろの人形を、ジョー・ハーパーは賛美歌集と説教本を手に入れた。すると先生が突撃してきて、俺たちは全部放り出して逃げ出すはめになった。

俺にはダイヤなんて見えなかったから、トム・ソーヤーにそう言った。彼は、それでもそこには山ほどあったんだと言った。そして、アラブ人もいたし、象も何もかもいたと言った。じゃあ、どうして俺たちには見えなかったんだ、と俺は言った。彼は、俺がそんなに無知じゃなくて、『ドン・キホーテ』という本を読んでいれば、聞かなくてもわかったはずだと言った。それは全部魔法のせいだと言うのだ。そこには何百人もの兵士がいて、象や宝物もあったが、俺たちには魔術師と呼ばれる敵がいて、そいつらが腹いせに、全部を幼児の日曜学校に変えてしまったんだ、と。わかったよ、と俺は言った。じゃあ、俺たちがやるべきことは、その魔術師どもをやっつけることだ。トム・ソーヤーは俺を大馬鹿だと言った。
「なんだって」と彼は言った。「魔術師はジーニー[訳注:魔神]をたくさん呼び出せるんだぞ。そいつらにかかれば、お前なんか『あっ』と言う間にみじん切りにされちまう。あいつらは木みたいに背が高くて、教会みたいにでかいんだ。」
「ふーん」と俺は言った。「じゃあ、もし俺たちがジーニーを何人か味方につけたら――そしたら相手の連中に勝てるんじゃないか?」
「どうやって手に入れるんだ?」
「知らない。あいつらはどうやって手に入れるんだ?」
「そりゃ、古いブリキのランプか鉄の指輪をこするんだよ。そうするとジーニーが、雷と稲妻を轟かせ、煙をもうもうと巻き上げながら飛び出してきて、言われたことは何でもやってのける。あいつらにとっちゃ、弾丸製造塔を根こそぎ引き抜いて、それで日曜学校の校長の頭をぶん殴ることなんて、何でもないんだ――他の誰だって同じさ。」
「誰がそんなに暴れさせるんだ?」
「そりゃ、ランプか指輪をこすったやつさ。あいつらはランプか指輪をこすったやつのものになって、そのやつの言うことは何でも聞かなきゃならない。もし、ダイヤで四十マイルの長さの宮殿を建てて、それをチューインガムでいっぱいにしろとか、何でも好きなものを言いつけて、中国から皇帝の娘を嫁にもらうために連れてこいと言えば、あいつらはそれをやらなきゃならない――しかも、次の日の朝日が昇る前にやらなきゃならないんだ。それだけじゃない。その宮殿を、お前が望む国中のどこへでも、ワルツを踊らせながら運ばなきゃならないんだ、わかるか。」
「ふーん」と俺は言った。「そんなふうに宮殿を無駄にする代わりに、自分たちで持っておかないなんて、あいつらは相当な間抜けだと思うぜ。それに――もし俺がそいつらの一人だったら、古いブリキのランプをこすられたくらいで、自分の仕事を放り出してそいつのところへ行く前に、地獄の果てまで行ってやるね。」
「何を言ってるんだ、ハック・フィン。こすられたら、行きたくなくても行かなきゃならないんだ。」
「なんだって! 俺が木みたいに高くて、教会みたいにでかいのに? わかったよ、それなら行くさ。でも、俺ならそいつを国で一番高い木に登らせてやるぜ。」
「ちぇっ、お前と話しても無駄だ、ハック・フィン。お前はどうも何もわかってないらしい――まったくのどアホだ。」
俺はこのことを二、三日考え抜いて、それから、本当にそんなことがあるのか試してみることにした。古いブリキのランプと鉄の指輪を手に入れて、森へ出て、インディアンみたいに汗をかくまでこすりにこすった。宮殿を建てて売るつもりだった。だが、無駄だった。ジーニーは誰も来なかった。だから俺は、あの話は全部、ただのトム・ソーヤーの嘘っぱちだと判断した。あいつはアラブ人や象のことを信じていたんだろうが、俺に言わせれば違う。あれはどこからどう見ても日曜学校だった。

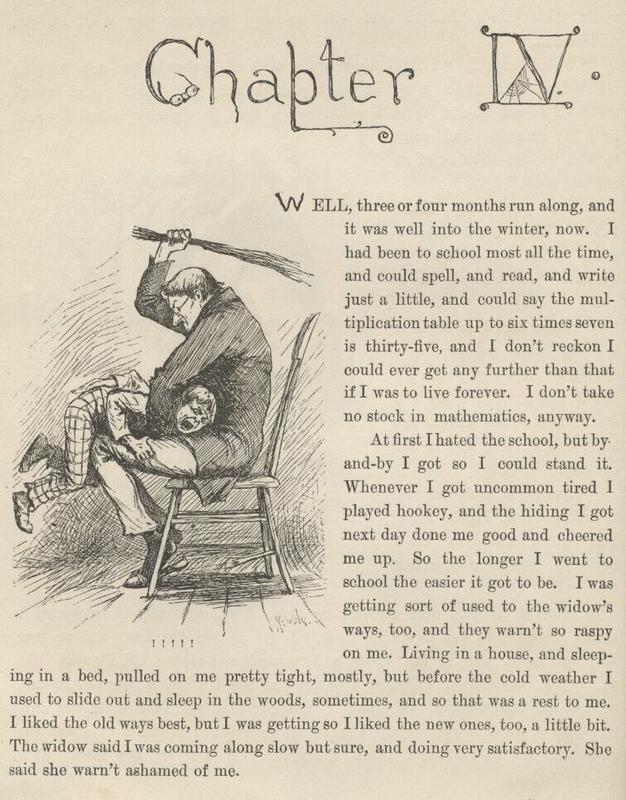
第四章
さて、三、四ヶ月が過ぎて、今ではすっかり冬になっていた。俺はほとんど毎日学校へ行っていて、綴りと読み書きがほんの少しできるようになった。掛け算も六七三十五までは言えたが、たとえ永遠に生きても、それ以上進めるとは思えなかった。どのみち、算数なんてものには興味がない。
最初は学校が嫌いだったが、そのうち我慢できるようになった。ひどく疲れたときは学校をさぼると、次の日にお仕置きを食らうのがかえって気持ちよくて、元気が出た。だから学校へ行けば行くほど、楽になっていった。未亡人さんのやり方にもいくらか慣れてきて、それほどいらいらしなくなった。家で暮らし、ベッドで寝るのはたいていかなり窮屈だったが、寒くなる前は、時々こっそり抜け出して森で寝たので、それが俺には休息になった。古いやり方が一番好きだったが、新しいやり方も少しは好きになってきていた。未亡人さんは、俺はゆっくりだが確実に成長していて、とても満足のいく出来だと言った。俺のことを恥ずかしくないと言ってくれた。
ある朝、朝食のときにうっかり塩壺をひっくり返してしまった。俺はできるだけ早く塩をつかんで左肩越しに投げ、不運を避けようとしたが、ミス・ワトソンの方が一足早く、俺を制した。彼女は言う。「ハックルベリー、手をどけなさい。いつも散らかしてばかり!」未亡人さんが俺をかばってくれたが、それで不運が避けられるわけではないことは、よくわかっていた。俺は朝食の後、心配で震えながら外へ出て、不運がどこに、どんな形で降りかかってくるのだろうかと考えた。いくつかの種類の不運を避ける方法はあるが、これはその類ではなかった。だから俺は何もせず、ただしょんぼりとうろつきながら、警戒していた。
俺は前の庭へ下りていき、高い板塀を越えるための踏み段を登った。地面には一インチほどの新雪が積もっていて、誰かの足跡が見えた。石切り場の方からやってきて、しばらく踏み段の周りに立ち、それから庭の塀に沿って進んでいったようだった。あれほど周りをうろついていたのに、中に入ってこなかったのは奇妙だった。俺には理解できなかった。どうにも不思議だった。後を追ってみようかと思ったが、まず身をかがめて足跡をよく見ることにした。最初は何も気づかなかったが、次に気づいた。左のブーツのかかとに、悪魔除けのために、大きな釘で十字が作られていた。
俺は一瞬で飛び起き、丘を駆け下りた。時々肩越しに振り返ったが、誰も見えなかった。俺はできるだけ早くサッチャー判事の家に着いた。彼は言った。
「おや、坊や、すっかり息が切れているじゃないか。利子を受け取りに来たのかね?」
「いいえ、旦那様」と俺は言った。「俺に何かあるんですか?」
「ああ、もちろんだとも。昨夜、半年分が入ったよ――百五十ドル以上だ。君にとっては大金だね。君の六千ドルと一緒に私が投資してあげた方がいい。君が持っていれば使ってしまうだろうからね。」
「いいえ、旦那様」と俺は言った。「使いたくありません。全然いらないんです――六千ドルも、何もかも。あなたに受け取ってほしいんです。あなたにあげたいんです――六千ドルも全部。」
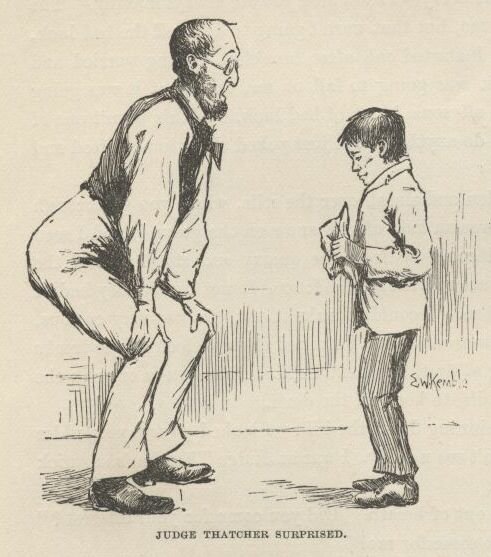
彼は驚いたようだった。どうにも理解できない様子だった。彼は言った。
「いったい、どういうことかね、坊や?」
俺は言った。「それについては何も質問しないでください、お願いします。受け取ってくれますよね?」
彼は言った。
「うーむ、困ったな。何かあったのかね?」
「どうか受け取ってください」と俺は言った。「そして何も聞かないでください――そうすれば嘘をつかずに済みますから。」
彼はしばらく考え込んで、それから言った。
「ほう! わかったぞ。君は全財産を私に『売りたい』んだな――あげるのではなく。それが正しい考え方だ。」
それから彼は紙に何かを書き、それを読み返して言った。
「ほら、ここには『対価として』と書いてある。つまり、私が君からそれを買い、代金を支払ったということだ。ここに君への一ドルがある。さあ、ここに署名しなさい。」
だから俺は署名して、そこを去った。
ミス・ワトソンのところの黒人、ジムは、拳ほどもある毛玉を持っていた。それは牛の第四胃から取り出されたもので、彼はそれを使って魔法をかけた。彼はその中に霊が宿っていて、何でも知っていると言った。だから俺はその夜、彼のところへ行って、パップがまた戻ってきたことを告げた。雪の中に彼の足跡を見つけたからだ。俺が知りたかったのは、あいつが何をするつもりなのか、そしてここに留まるつもりなのかということだった。ジムは毛玉を取り出して、その上で何かを唱え、それから持ち上げて床に落とした。それはどすんと落ちて、一インチほどしか転がらなかった。ジムはもう一度、さらにもう一度試したが、同じようにしかならなかった。ジムは膝をついて、それに耳を当てて聞いた。だが無駄だった。話してくれない、と彼は言った。金がないと話してくれないことがあるそうだ。俺は、真鍮が銀の間から少し見えていて、どうせ通用しない、つるつるの偽物の二十五セント硬貨を持っていると言った。真鍮が見えなくても、あまりにつるつるで脂っこい感じがするから、すぐにばれてしまうのだ。(判事からもらった一ドルのことは言わないでおこうと思った。)ひどい金だが、毛玉なら受け取ってくれるかもしれない、違いがわからないかもしれないから、と言った。ジムはそれを嗅ぎ、噛み、こすって、毛玉に本物だと思わせるようにすると言った。生のジャガイモを二つに割って、その間に二十五セント硬貨を挟んで一晩おけば、翌朝には真鍮は見えなくなり、脂っこい感じもしなくなるから、町中の誰でも一瞬で受け取るだろう、毛玉ならなおさらだ、と。まあ、ジャガイモがそんなことをするのは前から知っていたが、忘れていた。
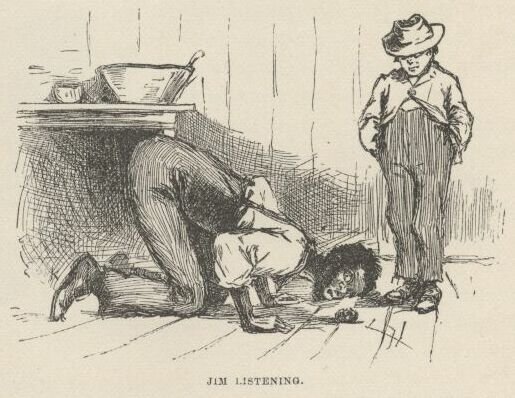
ジムは二十五セント硬貨を毛玉の下に置き、かがんで再び耳を澄ました。今度は毛玉は大丈夫だと言った。もし望むなら、俺の運勢を全部教えてくれるそうだ。俺は、続けてくれと言った。そこで毛玉はジムに話し、ジムはそれを俺に伝えた。彼は言う。
「あんたの親父さん、まだどうするか決めかねとるわ。どっかへ行こうかと思うときもあれば、またここにおろうかと思うときもある。一番ええのは、どっしり構えて、親父さんの好きにさしたることや。親父さんの周りには二人の天使が舞っとる。一人は白うてキラキラしとるし、もう一人は黒い。白い方が親父さんをしばらく正しい道に行かせようとすると、黒い方が割り込んできて、全部ぶち壊しにしてしまうんや。どっちが最後に親父さんを連れて行くか、まだ誰にもわからん。せやけど、あんたは大丈夫や。あんたの人生には、かなりの苦労と、かなりの喜びがあるやろう。ときには怪我をすることもあるし、ときには病気になることもある。せやけど、そのたびにまた元気になる。あんたの人生には二人の娘はんが飛んどる。一人は色が白うて、もう一人は色が黒い。一人は金持ちで、もう一人は貧乏や。あんたはまず貧乏な方と結婚して、そのうち金持ちの方と結婚するやろう。できるだけ水からは遠ざかって、危ない橋は渡らんことや。なんでかって、あんたは首を吊られる運命にあるって決まっとるからな。」
その夜、ろうそくに火をつけて自分の部屋へ上がると、そこにはパップ、あいつ自身が座っていた!
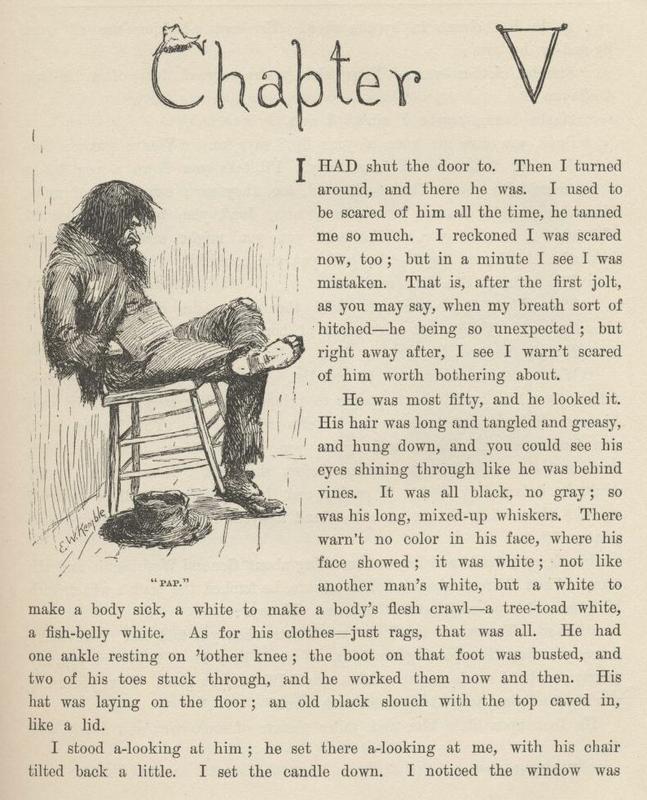
第五章
俺は戸を閉めていた。それから振り返ると、あいつがいた。いつもあいつが怖かった。あんまりひどくぶたれたからだ。今も怖いんだろうと思った。だが一分もすると、それが間違いだとわかった――つまり、最初の衝撃の後は、と言ってもいい。あまりに不意打ちで、息が詰まりそうになったが、その直後には、わざわざ気にするほどあいつを怖がってはいないとわかった。
あいつは五十近くで、見た目もそうだった。髪は長くて、もつれて、脂ぎっていて、垂れ下がっていた。その間から、まるで蔓の向こうにいるかのように、目が光っているのが見えた。髪は真っ黒で、白髪は一本もなかった。長くてごちゃごちゃした髭も同じだった。顔が見える部分には、色がなかった。真っ白だった。他の男の白さとは違う、気分が悪くなるような白さ、肌がぞわぞわするような白さ――ヒキガエルのような、魚の腹のような白さだった。服はと言えば――ただのぼろ切れ、それだけだった。片方の足首をもう片方の膝に乗せていた。その足のブーツは破れていて、二本の指が突き出ていて、それを時々動かしていた。帽子は床に置いてあった――蓋がへこんだような、古くて黒い、つば広の帽子だった。
俺は立ってあいつを見ていた。あいつは椅子を少し後ろに傾けて、そこに座って俺を見ていた。俺はろうそくを置いた。窓が開いているのに気づいた。物置小屋から登ってきたんだ。あいつは俺の全身をじろじろ見続けた。やがてこう言った。
「ぱりっとした服じゃねえか。ずいぶん偉くなったつもりなんだろう、ああ?」
「そうかもな、そうじゃないかもな」と俺は言った。
「口答えするんじゃねえ」とあいつは言った。「俺がいねえ間に、ずいぶんと飾り立てやがって。お前をひっぱたいて、その鼻っ柱をへし折ってやる。教育も受けたそうじゃねえか――読み書きができるってな。親父が読み書きできねえからって、自分が偉くなったとでも思ってんのか、ああ? その根性を叩き直してやる。誰がお前にそんな高尚な馬鹿げたことに手を出していいと言ったんだ、ええ? ――誰が許したんだ?」
「未亡人さんだ。彼女が言ったんだ。」
「未亡人さん、だと? ――で、誰がその未亡人さんに、自分に関係ねえことに口出ししていいと言ったんだ?」
「誰も言ってない。」
「よし、俺があいつにお節介の仕方を教えてやる。それからよく聞け――学校はやめろ、わかったか? 自分の親父を見下して、自分の方が偉いと見せびらかすような息子を育てる連中を、俺が懲らしめてやる。もう一度あの学校の周りをうろついてみろ、わかったな? お前の母親は死ぬ前に読めなかったし、書けもしなかった。家族の誰も、死ぬ前にできやしなかった。俺もできねえ。それなのに、てめえはこんなにふんぞり返りやがって。俺はそんな男じゃねえ――わかったか? おい、てめえの読むのを聞かせてみろ。」
俺は本を取り上げて、ワシントン将軍と戦争の話を読み始めた。半 分ほど読んだところで、あいつはその本を手でひっぱたき、家の向こう側へ叩き飛ばした。あいつは言った。
「本当だ。てめえはできるんだな。お前が言ったときは半信半疑だった。さあ、よく聞け。その気取った真似はやめろ。許さねえぞ。見ててやるからな、こ賢しいやつめ。もしあの学校のあたりでてめえを捕まえたら、ひどい目に遭わせてやる。そのうち宗教心まで持ちやがる。こんな息子は見たことがねえ。」
あいつは、何頭かの牛と少年の描かれた、青と黄色の小さな絵を取り上げて言った。
「これは何だ?」
「勉強をよくできたからって、もらったんだ。」
あいつはそれを引き裂いて言った。
「もっといいものをくれてやる――牛革の鞭をな。」
あいつはそこに座って一分ほどぶつぶつと唸り、それから言った。
「ずいぶんとまあ、いい匂いのする洒落者じゃねえか、ええ? ベッドに、寝具に、姿見に、床には絨毯まで敷いてやがる――だというのに、てめえの実の父親は皮なめし工場の豚と一緒に寝る羽目になってるってのによ。こんな息子は見たことがねえ。てめえのその気取った飾りっ気を、俺がひんむいてやるからな。まったく、お高くとまりやがって。金持ちになったそうじゃねえか。ええ? どういうこった?」
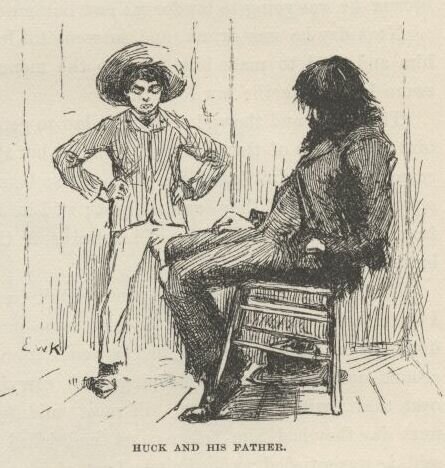
「嘘っぱちだよ――そういうことさ。」
「おい、こっちを見ろ――俺への口の利き方には気をつけな。もう我慢の限界なんだ――だから生意気な口を叩くんじゃねえぞ。町に来て二日になるが、てめえが金持ちになったって話しか耳にしねえ。川の下流でもその噂を聞いたんだ。だから来たのさ。明日、その金を俺によこせ――俺がもらう。」
「金なんて持ってないよ。」
「嘘つけ。サッチャー判事が持ってるはずだ。取り返してこい。俺が欲しいんだ。」
「金はないって言ってるだろ。サッチャー判事に聞いてみろよ。同じことを言うはずだ。」
「わかった。訊いてやる。それに、金を吐き出させてやるさ。でなきゃ、ただじゃおかねえ。おい、ポケットにはいくら入ってる? それをよこせ。」
「一ドルしかないよ。それに、これは――」
「何に使うかなんて関係ねえ――さっさと出しやがれ。」
パップは金を受け取ると、本物かどうか歯で噛んで確かめた。それから、町へウィスキーを買いに行くと言った。一日中、一滴も飲んでないと言うのだ。物置小屋から出ていったかと思うと、また頭を突っ込んできて、俺が気取った真似をして父親より偉そうな顔をしていると罵った。もう行っただろうと思った頃に、また戻ってきて頭を突っ込み、学校のことは忘れるなよ、もしやめなけりゃ待ち伏せしてぶん殴ってやると言い放った。
翌日、パップは酔っぱらってサッチャー判事のところへ行き、判事をどやしつけて金を渡させようとした。だが、うまくいかず、今度は法律の力で無理やり言うことを聞かせてやると息巻いた。
判事と未亡人は、俺をパップから引き離し、どちらかが後見人になれるよう、裁判所に訴え出た。しかし、担当になったのは赴任してきたばかりの新しい判事で、パップのことを知らなかった。だから、裁判所はできる限り家庭に干渉して家族を引き裂くべきではないと言った。父親から子供を取り上げるのは気が進まない、とも。そんなわけで、サッチャー判事と未亡人はこの件を諦めざるを得なかった。
これにはパップも上機嫌で、じっとしていられないほどだった。金を工面してこなければ、青黒い痣ができるまで牛革の鞭でぶってやると言った。俺はサッチャー判事から三ドル借りた。パップはその金を受け取ると、酔っぱらい、悪態をつき、わめき散らしながら町中を練り歩いた。ブリキの鍋を叩きながら真夜中近くまで騒ぎ続けたので、とうとう牢屋に入れられた。翌日、裁判にかけられ、さらに一週間、留置されることになった。だがパップは満足だと言った。息子の主人は自分であり、思い知らせてやると息巻いていた。
パップが釈放されると、新しい判事は彼をまともな人間に更生させると言った。そこでパップを自分の家に連れて行き、清潔で立派な服を着せ、家族と一緒に朝食、昼食、夕食を共にし、いわば、至れり尽くせりのもてなしをした。夕食後には、禁酒などについて語り聞かせた。するとパップは泣き出し、自分は馬鹿で、人生を無駄にしてきたと言った。しかし、これからは心を入れ替え、誰にも恥じない人間になるつもりで、判事には見下さずに助けてほしいと願った。判事はその言葉に抱きしめたいほど感動したと言った。それで判事は泣き、奥さんもまた泣いた。パップは、自分はこれまでずっと誤解されてきた人間なのだと言い、判事もそれを信じると言った。落ちぶれた人間に必要なのは同情だとパップは言い、判事もその通りだと言った。それで二人はまた泣いた。そして就寝の時間になると、パップは立ち上がって手を差し出し、こう言った。
「紳士淑女の皆さん、これを見てください。この手を取って、握ってください。これはかつて豚の手でありました。しかし、もはやそうではありませぬ。新しい人生を歩み始めた男の手であり、再び過去に戻るくらいなら死を選びます。この言葉を覚えておいてください――私が言ったことをお忘れなく。これは今や清らかな手なのです。さあ、握ってください――恐れなさるな。」
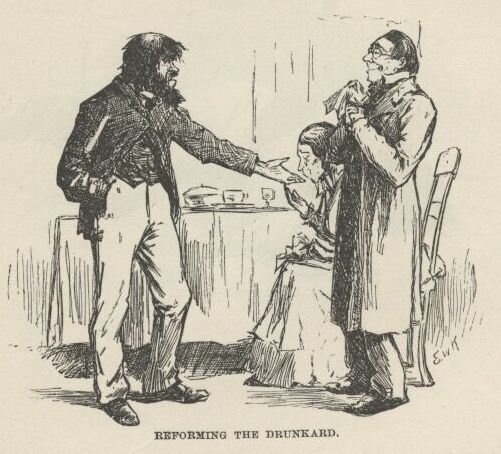
そこで皆、次から次へとその手を握り、涙を流した。判事の奥さんはその手にキスまでした。それからパップは誓約書に署名――つまり、自分の印をつけた。判事は、記録に残る限り最も神聖な瞬間だ、とか何とか言った。そして皆はパップを客間として使っている美しい部屋に案内し、寝かしつけた。ところが夜中、パップは猛烈な喉の渇きを覚え、ポーチの屋根によじ登ると、支柱を滑り降り、新しい上着を四十ロッド・ウィスキー[訳注:安物の強いウィスキー]一瓶と交換した。そして再びよじ登って部屋に戻り、愉快なひとときを過ごした。夜明け近く、彼は再び這い出し、へべれけに酔っぱらったままポーチから転げ落ちて左腕を二箇所骨折し、日の出後に誰かに発見された時には凍死寸前だった。人々がその客間を覗きに行った時には、中を航海するにはまず水深を測らねばならぬ有様だったという。
判事はすっかり意気消沈していた。彼は、ショットガンでも使えばパップを更生させられるかもしれんが、それ以外に方法は思いつかん、と言ったそうだ。
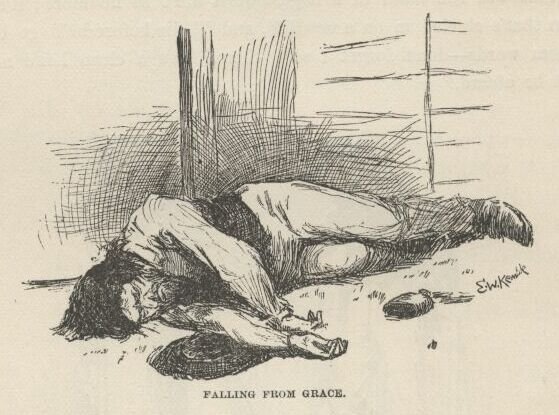
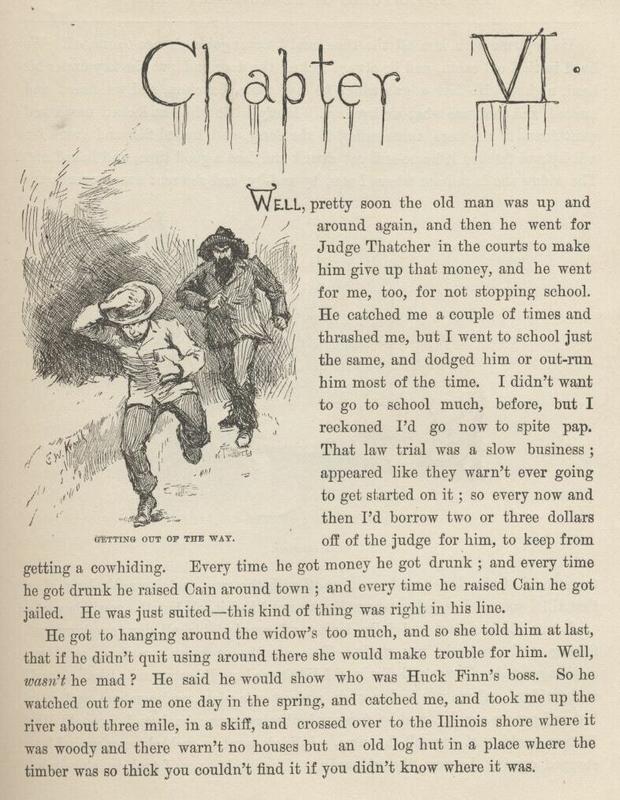
第六章
さて、ほどなくしてパップは元気を取り戻し、動き回るようになった。そして今度は、あの金を手に入れるためにサッチャー判事を法廷に訴え、さらには学校をやめない俺にもちょっかいを出し始めた。二、三度捕まってひどく殴られたが、俺はそれでも学校に通い続けた。たいていは、うまくパップをかわしたり、逃げ切ったりした。以前はそれほど学校に行きたくもなかったが、今はパップへの当てつけに行ってやろうと思った。裁判は遅々として進まなかった――まるで永遠に始まりそうもないように思えた。だから、牛革の鞭でぶたれるのを避けるため、俺は時々、判事から二、三ドル借りてパップに渡していた。パップは金を手に入れるたびに酔っぱらい、酔っぱらうたびに町で大騒ぎを起こし、大騒ぎを起こすたびに牢屋に入れられた。彼にはおあつらえ向きだった――こういう生き方が性に合っているのだ。
パップは未亡人の家にもあまりに頻繁にうろつくようになったので、とうとう彼女は、このあたりをうろつくのをやめないと面倒なことになるわよ、と告げた。さて、パップが怒らなかったと思うかい? 誰がハック・フィンの主人様か、思い知らせてやると言った。そしてある春の日、俺を待ち伏せして捕まえ、小舟で川を三マイルほど上り、イリノイ側の岸に渡った。そこは森が深く、家一軒なく、森が鬱蒼と茂っていて、場所を知らなければ見つけられないような場所に古い丸太小屋が一軒あるだけだった。
パップは俺を片時も離さず、逃げ出す機会はまったくなかった。俺たちはその古い小屋で暮らし、夜になるといつもパップはドアに鍵をかけ、鍵を自分の頭の下に置いて寝た。彼は盗んできたと思われる銃を持っていて、俺たちは魚を釣ったり狩りをしたりして食いつないでいた。時々、パップは俺を小屋に閉じ込め、三マイル離れた渡し場にある店まで行き、魚や獲物をウィスキーと交換して持ち帰った。そして酔っぱらっては上機嫌になり、俺をぶった。そのうち、未亡人は俺の居場所を突き止め、俺を取り戻そうと男を一人よこした。しかし、パップは銃でそいつを追い払った。それから間もなく、俺はそこでの暮らしに慣れ、気に入るようになっていた――牛革の鞭でぶたれるのを除けば。
一日中、のんびりと快適に過ごし、煙草を吸い、魚を釣り、本もなければ勉強もない。怠惰で陽気な暮らしだった。二ヶ月かそこら経つうちに、俺の服はぼろぼろの泥だらけになった。未亡人の家での暮らしがあれほど好きだったのが、どうしてなのか分からなくなった。あそこでは体を洗い、皿で食事をし、髪をとかし、決まった時間に寝起きし、四六時中本に悩まされ、いつもミス・ワトソンにガミガミ言われなければならなかった。もう二度と戻りたくなかった。未亡人が嫌うので悪態をつくのはやめていたが、パップは何も言わないので、また口にするようになった。森の中での暮らしは、総じてかなりいいものだった。

しかし、そのうちパップがヒッコリーの鞭をあまりに手軽に使うようになったので、俺は耐えられなくなった。体中がみみず腫れだらけになった。それに、パップは出かけては俺を閉じ込めることが多くなった。一度など、三日間も閉じ込められたままだった。ひどく心細かった。パップは溺れ死んで、俺はもう二度と外に出られないんだと思った。怖かった。何とかしてここから抜け出す方法を見つけようと決心した。これまで何度もこの小屋から出ようと試みたが、方法が見つからなかった。犬が通り抜けられるほど大きな窓すらないのだ。煙突を登ることもできなかった。狭すぎる。ドアは厚く、頑丈な樫の厚板でできていた。パップは出かける時、ナイフなどを小屋に残さないようにかなり気をつけていた。俺はその場所を百回くらいは探したと思う。まあ、ほとんどいつもそうしていた。それが唯一の時間の潰し方だったからだ。しかし、今回はとうとう何かを見つけた。取っ手のない、古びて錆びついた木挽き鋸だ。それは垂木と屋根の下見板の間に挟まっていた。俺はそれに油を塗り、作業に取りかかった。小屋の奥のテーブルの後ろには、隙間風が吹き込んで蝋燭の火を消さないように、古い馬用の毛布が丸太に釘で打ち付けられていた。俺はテーブルの下にもぐり込み、毛布をめくり上げ、一番下の太い丸太を、俺が通り抜けられるくらいに切り抜く作業を始めた。それはかなり時間のかかる仕事だったが、終わりが見えてきた頃、森の中でパップの銃声が聞こえた。俺は作業の痕跡を片付け、毛布を下ろし、鋸を隠した。ほどなくしてパップが入ってきた。
パップは機嫌が悪かった――つまり、いつもの彼らしかった。町へ行ってきたが、何もかもうまくいかないと言った。弁護士は、裁判が始まれば訴訟に勝って金を手に入れられるだろうと言ったそうだ。だが、裁判を長引かせる方法はいくらでもあり、サッチャー判事はそのやり方をよく知っている、とも。それに、人々は俺をパップから引き離して未亡人を後見人にするための別の裁判が開かれるだろうと噂しており、今度こそは未亡人側が勝つだろうと見ているそうだ。これにはかなり動揺した。もう未亡人の家に戻って、窮屈で、連中の言うところの「文明的」な暮らしをするのはごめんだったからだ。それからパップは悪態をつき始め、思いつく限りのありとあらゆる物や人々を罵り、そして誰一人罵り忘れていないことを確かめるかのように、もう一度全員を罵った。その後、仕上げとばかりに、一般的な悪態をあたり構わずまき散らした。その中には名前も知らない人々も大勢含まれており、彼らの番になると「どこの誰それ」と呼び、そのまま悪態をつき続けた。
パップは、未亡人が俺を手に入れるところを見てみたいものだと言った。見張っていて、もし連中がそんな真似をしようものなら、六、七マイル離れた場所に俺を隠してやると言った。そこなら、連中がくたばるまで探したって見つけられやしないだろう、と。それを聞いてまた不安になったが、ほんの一瞬だった。パップにそんな機会が訪れるまで、俺がここにいるはずがないと思ったからだ。
パップは俺に、小舟に行って買ってきたものを運ぶように言いつけた。五十ポンド入りのトウモロコシ粉の袋、ベーコンの塊、弾薬、四ガロン入りのウィスキーの瓶、そして詰め物用の古い本一冊と新聞二部、それに麻屑が少しあった。俺は荷物を一つ運び上げ、戻ってきて小舟の舳先に腰を下ろして休んだ。すべてを考え直し、逃げ出す時には銃と釣り糸をいくつか持って森に入ろうと思った。一箇所にとどまらず、主に夜間に国中を歩き回り、狩りや釣りをして生き延び、パップも未亡人も二度と俺を見つけられないほど遠くへ行こうと考えた。パップが十分に酔っぱらったら、今夜のうちに鋸で穴を開けて出て行こうと決めた。きっとそうなるだろう。その考えに夢中になって、どれくらいそこにいたか気づかなかった。パップが怒鳴りつけ、俺が眠っているのか溺れているのかと尋ねるまで。

俺はすべての荷物を小屋に運び終え、あたりは暗くなっていた。俺が夕食の準備をしている間、パップは一、二口ぐいっと飲み、いくらか気分がほぐれたのか、またいつもの調子でまくし立て始めた。彼は町で酔っぱらい、一晩中側溝で寝ていたので、その姿は見るも無残だった。まるでアダムかと思うほど、全身泥だらけだった。酒が回り始めると、彼はほとんどいつも政府の悪口を言い始める。今回もこう言った。
「これが政府様かよ! おい、見てみろ、どんなもんか。法律ってやつは、男が手間暇かけて、心配して、金かけて育て上げた息子を、その男自身から取り上げようと待ち構えてやがる。ああ、やっと息子が育って、働き始めて、親を楽させてやろうって時に、法律がしゃしゃり出てきてそいつを奪い去るんだ。それを政府様だとよ! それだけじゃねえ。法律はあのサッチャー判事の肩を持って、俺が自分の財産に手を出せねえようにしやがる。法律がやることはこうだ。六千ドル以上の財産を持つ男を、こんな古ぼけた罠みてえな小屋に押し込んで、豚にだって似合わねえような服を着てうろつかせやがる。それを政府様だとよ! こんな政府じゃ、男は自分の権利も主張できねえ。時々、もうきっぱりこの国を出てってやろうかって、本気で思うぜ。ああ、言ってやったとも。サッチャーの野郎に面と向かってな。大勢が聞いてたから、俺が何言ったか知ってるはずだ。言ってやったんだ、二束三文でこんな国とはおさらばして、二度と近づくもんか、ってな。一言一句この通りだ。俺は言った、俺の帽子を見ろ――これを帽子と呼べるならだが――てっぺんはめくれ上がり、残りは顎の下まで垂れ下がって、もはやまともな帽子じゃねえ、まるで俺の頭が煙突の継ぎ目に突っ込まれてるみてえだ、ってな。これを見ろ、って言ってやったんだ。俺がこんな帽子を被るなんて――権利さえ取り戻せりゃ、この町一番の金持ちだっていうのによ。」
「ああ、そうさ、こいつは素晴らしい政府様だ、素晴らしいね。おい、これを見ろ。オハイオから来た自由黒人がいやがった――ムラートで、ほとんど白人みてえに肌が白いんだ。見たこともねえような真っ白なシャツを着て、ピカピカの帽子を被ってやがった。この町の誰一人として、あいつみてえな上等な服は持ってねえ。それに金の懐中時計と鎖、銀の頭の杖まで持ってやがった――州一番の、いまいましい白髪頭の大金持ち気取りだ。それでどう思う? あいつは大学の教授で、あらゆる国の言葉を話せて、何でも知ってるって言うんだ。だが、最悪なのはそれじゃねえ。故郷じゃ選挙で投票できるって言うんだ。それで俺はぶち切れた。この国はどうなっちまうんだ、って思ったね。その日は選挙日で、酔っぱらいすぎてなけりゃ俺も投票に行くところだった。だが、この国にはあの黒んぼに投票させる州があるって聞かされて、やめたんだ。もう二度と投票なんかするか、って言ってやった。一言一句この通りだ。みんなが聞いてた。この国がどうなろうと知ったこっちゃねえ――俺は生きている限り、二度と投票なんかするか。それに、あの黒んぼのふてぶてしい態度ときたら――俺が突き飛ばして道からどかさなきゃ、道を譲ろうともしなかったんだぜ。俺は人々に言ってやったんだ、なんでこの黒んぼを競売にかけて売っぱらわねえんだ? ――それが知りたい、ってな。連中が何て言ったと思う? なんでも、州に六ヶ月滞在しなきゃ売れないんだとよ。あいつはまだそこまで長くはいなかった。どうだ、これが見本だ。自由黒人を、州に六ヶ月いるまで売ることもできねえような政府を、政府様と呼んでやがる。政府を名乗り、政府のふりをし、政府だと思い込んでいる政府が、うろつき回る、泥棒根性の、いまいましい、白いシャツを着た自由黒人を捕まえるのに、丸々六ヶ月もじっと待ってなきゃならねえんだ、そして――」
パップはまくし立て続けていたので、自分のふらつく足がどこへ向かっているのか気づいていなかった。そして、塩漬け豚肉の入った桶に頭からつんのめり、両方の脛をすりむいた。彼の演説の残りは、すべて最も過激な言葉遣いになった――主に黒んぼと政府に向けられたが、時々、桶にも悪態をついていた。彼は小屋の中を、片足で、次にもう片方の足で、かなりの間飛び跳ね回り、片方の脛を、次にもう片方の脛を押さえていた。そしてとうとう、突然左足を振り上げ、桶にけたたましい蹴りを食らわせた。しかし、それは賢明な判断ではなかった。そのブーツは、つま先の二本が先端から飛び出していたからだ。今度は、聞く者の髪が逆立つほどの叫び声を上げ、地面に倒れ込み、転げ回りながら足の指を押さえた。その時の悪態は、彼がこれまでにしたどんなものよりもひどかった。後で彼自身がそう言っていた。彼は全盛期のソーベリー・ヘイガンじいさんの悪態を聞いたことがあるが、それをも上回っていたと言った。だが、それは少し大げさに言っているだけかもしれない。
夕食後、パップはウィスキーの瓶を手に取り、これだけあれば二回酔っぱらって、一回は禁断症状[訳注:アルコール中毒による幻覚症状]が起こせるな、と言った。それが彼のいつもの口癖だった。一時間もすれば泥酔するだろうと俺は踏んだ。そうなったら鍵を盗むか、鋸で自分を切り出すか、どちらかだ。彼は飲み続け、やがて毛布の上に倒れ込んだ。しかし、運は俺に味方しなかった。彼はぐっすり眠り込まず、落ち着かない様子だった。長い間、うめき、もだえ、あちこちに体を打ちつけていた。とうとう俺は眠くて、どんなに頑張っても目を開けていられなくなり、気づかないうちにぐっすり眠ってしまった。蝋燭は燃えたままだった。

どれくらい眠っていたのか分からないが、突然、ものすごい悲鳴が聞こえて飛び起きた。そこには、血走った目をしたパップが、あちこち飛び跳ねながら蛇がいると叫んでいた。蛇が足に這い上がってくると言うのだ。そして飛び上がって悲鳴を上げ、一匹に頬を噛まれたと言った――だが、俺には蛇など一匹も見えなかった。彼は小屋の中をぐるぐると走り回り、「取っ払ってくれ! 取っ払ってくれ! 首を噛まれてるんだ!」と叫んでいた。あんなに狂気に満ちた目をした人間は見たことがない。やがて彼は疲れ果て、ぜいぜい言いながら倒れ込んだ。それから、ものすごい速さでごろごろと転げ回り、あたり構わず物を蹴飛ばし、空中に向かって手を伸ばして掴みかかり、悪魔に取り憑かれたと叫んでいた。そのうち力尽きて、しばらくじっと横たわり、うめいていた。それからさらに静かになり、物音ひとつ立てなくなった。森の奥からフクロウやオオカミの声が聞こえ、恐ろしいほど静かだった。彼は隅の方で横たわっていた。やがて、体を半分起こし、頭をかしげて耳を澄ませた。そして、とても低い声で言った。
「ザッ――ザッ――ザッ、死人だ。ザッ――ザッ――ザッ、俺を迎えに来やがった。だが俺は行かねえぞ。おお、ここにいやがる! 触るな――やめろ! 手を離せ――冷たいじゃねえか。放せ。ああ、哀れな悪魔を放っておいてくれ!」
それから彼は四つん這いになり、放っておいてくれと懇願しながら這い去り、毛布にくるまって古い松材のテーブルの下にもぐり込み、なおも懇願し続けた。そして泣き始めた。毛布越しに彼の声が聞こえた。
やがて彼は転がり出て、血走った目で飛び上がった。そして俺を見ると、襲いかかってきた。彼は飛び出しナイフを手に、「死の天使」と俺を呼び、殺してやると言いながら、小屋の中をぐるぐると追いかけ回した。そうすればもう俺は彼を迎えに来られない、と。俺は懇願し、自分はただのハックだと伝えた。しかし、彼は甲高い笑い声をあげ、怒鳴り、悪態をつき、俺を追いかけ続けた。一度、俺が急に方向転換して彼の下をくぐり抜けた時、彼は手を伸ばして俺の肩の間のジャケットを掴んだ。もうだめだと思った。しかし、稲妻のように素早くジャケットから抜け出し、命拾いした。やがて彼は疲れ果て、ドアに背中をもたれて倒れ込み、少し休んだら殺してやると言った。彼はナイフを体の下に置き、眠って力をつけ、そしたらどっちが上か思い知らせてやると言った。
そして彼はすぐにうとうとし始めた。俺は古い底の抜けた椅子を持ってきて、できるだけ音を立てないようにそっと登り、銃を下ろした。装填されているか確かめるために槊杖を滑り込ませ、それからカブの樽の上に銃を置き、パップの方に向けた。そしてその背後に座り、彼が動き出すのを待った。時間はなんとゆっくりと、静かに過ぎていったことか。
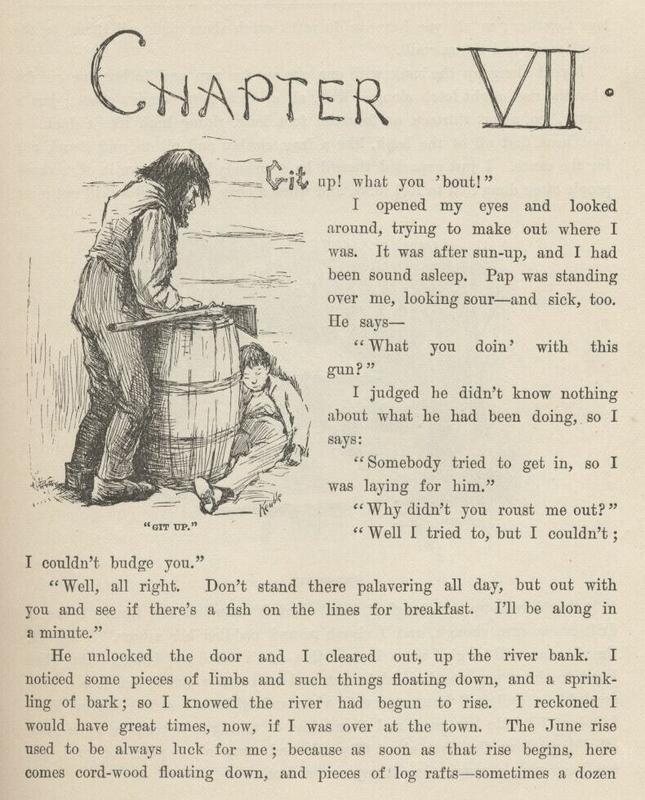
第七章
「起きろ! 何してるんだ?」
俺は目を開け、自分がどこにいるのか確かめようとあたりを見回した。日はすでに昇っており、俺はぐっすり眠っていた。パップが不機嫌で気分が悪そうな顔をして、俺を見下ろしていた。彼は言った。
「この銃で何をしてる?」
彼は自分が何をしていたか何も覚えていないようだったので、俺はこう言った。
「誰かが入ってこようとしたから、待ち伏せしてたんだ。」
「なぜ俺を起こさなかった?」
「いや、起こそうとしたんだけど、だめだったんだ。びくともしなかったよ。」
「まあ、いいだろう。一日中そこでぐずぐず喋ってないで、外に出て朝飯のために魚が仕掛けにかかってるか見てこい。俺もすぐに行く。」
彼がドアの鍵を開けたので、俺は川岸の方へ急いだ。木の枝切れなどがいくつか浮かんで下流に流れていくのが見え、木の皮もちらほらあったので、川が増水し始めたことが分かった。町にいれば、今頃は最高の時を過ごしているだろうと思った。六月の増水は、いつも俺にとって幸運だった。増水が始まるとすぐに、薪が流れてきたり、筏の切れ端が――時には十数本の丸太がまとまって――流れてきたりするからだ。それを捕まえて、薪屋や製材所に売ればいいだけなのだ。
俺は片目でパップを、もう片方の目で増水が何か運んでこないかを見ながら、岸辺を歩いて行った。すると、突然カヌーが流れてきた。アヒルのように軽やかに水面を滑る、十三、四フィートほどの、実に美しいカヌーだった。俺はカエルみたいに岸から頭から飛び込み、服を着たままカヌーに向かって泳ぎだした。きっと誰かが中に寝そべっているだろうと思った。人々はよくそうやって人をからかうからだ。小舟でほとんど近づいたところで、ひょっこり起き上がって笑うのだ。しかし、今回はそうではなかった。間違いなく流れてきたカヌーで、俺は乗り込んで岸まで漕いだ。これを見たら、親父も喜ぶだろう、十ドルはする代物だ、と思った。しかし、岸に着いてもまだパップの姿は見えなかった。蔓や柳で覆われた溝のような小さな入り江にカヌーを引き入れていると、別の考えが浮かんだ。これをうまく隠しておいて、逃げ出す時に森へ行く代わりに、川を五十マイルほど下ってどこかに腰を落ち着けよう。そうすれば、歩いて旅するような辛い思いをしなくてすむ。
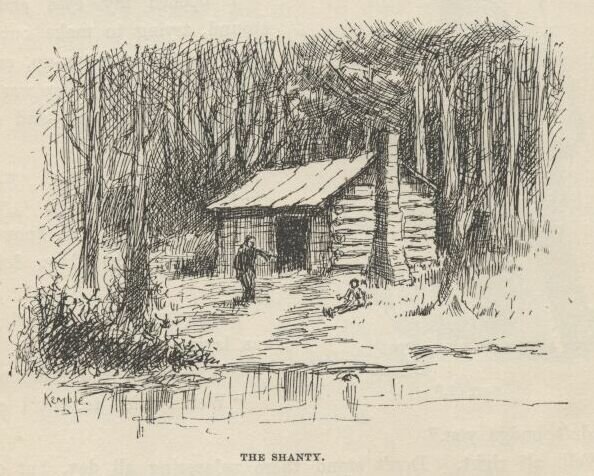
そこは小屋からかなり近かったので、いつでも親父が来るんじゃないかと思った。しかし、カヌーを隠し終え、柳の茂みから外を覗くと、親父は少し先の小道で、銃で鳥を狙っているところだった。だから、何も見ていなかった。
彼がやって来た時、俺は「延縄」を上げるのに懸命になっていた。彼は俺がのろまだと少し罵ったが、川に落ちたからこんなに時間がかかったんだと説明した。俺が濡れているのを見れば、あれこれ質問してくるだろうと分かっていたからだ。仕掛けからはナマズが五匹釣れ、俺たちは家に戻った。
二人とも疲れ果てていたので、朝食後に一眠りしている間、俺は考え始めた。もしパップと未亡人が俺を追跡するのを諦めさせる方法を見つけられれば、俺がいなくなったことに気づかれる前に十分に遠くへ逃げられるという運任せよりも確実だろう。何しろ、何が起こるか分からない。しばらくは良い方法が思いつかなかったが、やがてパップが水をもう一杯飲むために少し起き上がって、こう言った。
「今度、誰かがこのあたりをうろついていたら、俺を起こせ、いいか? あの男はろくな目的でここに来たんじゃねえ。俺なら撃ち殺してやっただろう。次からは俺を起こせ、いいな?」
それから彼はまた倒れて眠りについた。しかし、彼の言ったことが、俺がまさに求めていたアイデアを与えてくれた。俺は独り言を言った。これで、誰も俺を追おうとは思わないようにできるぞ。
十二時ごろ、俺たちは起きて岸辺を歩いた。川はかなり速く増水しており、たくさんの流木が流れていった。やがて、筏の一部が流れてきた――九本の丸太がしっかりと結びつけられている。俺たちは小舟で出て、それを岸まで引いてきた。それから昼食をとった。パップ以外の誰かなら、もっと獲物を捕まえるために一日中待っただろう。しかし、それはパップのやり方ではなかった。九本の丸太で一度には十分だった。彼はすぐに町へ行って売らなければならなかった。そこで彼は俺を閉じ込め、小舟に乗り、三時半ごろに筏を曳いて出発した。その夜は戻ってこないだろうと俺は踏んだ。彼が十分遠くまで行ったと思われるまで待ち、それから鋸を取り出し、再びあの丸太の作業に取りかかった。彼が川の向こう岸に着く前に、俺は穴から抜け出していた。彼と彼の筏は、はるか彼方の水面で、ただの点にしか見えなかった。
俺はトウモロコシ粉の袋を取り、カヌーを隠した場所まで運び、蔓や枝を押し分けて中に入れた。次にベーコンの塊も同じようにした。それからウィスキーの瓶も。そこにあったコーヒーと砂糖をすべて、弾薬もすべて持っていった。詰め物も、バケツとひょうたんも持っていった。ひしゃくとブリキのカップ、古い鋸と毛布二枚、フライパンとコーヒーポットも持っていった。釣り糸、マッチ、その他、一セントでも価値のあるものはすべて持っていった。その場所を空っぽにした。斧が欲しかったが、薪置き場にある一本しかなく、それを残しておく理由は分かっていた。銃を取り出し、これで準備は完了だ。
穴から這い出し、たくさんのものを引きずり出したので、地面はかなり踏み荒らされていた。そこで、外からできるだけうまくそれを直し、その場所に土をまいて、滑らかになった部分と鋸屑を覆い隠した。それから、丸太の切れ端を元の場所にはめ込み、その下に石を二つ、横に一つ置いて固定した。その場所は曲がっていたので、地面に完全には着いていなかったからだ。四、五フィート離れて立っていて、それが鋸で切られたものだと知らなければ、決して気づかないだろう。それに、ここは小屋の裏手で、誰かがうろつき回る可能性は低かった。
カヌーまではずっと草地だったので、足跡は残らなかった。確かめるためにあたりを歩いてみた。岸辺に立ち、川を見渡した。すべて安全だ。そこで銃を取り、森の中へ少し入って鳥を探していると、野生の豚を見つけた。このあたりの低地では、大草原の農場から逃げ出した豚はすぐに野生化するのだ。俺はこの一匹を撃ち、キャンプに持ち帰った。
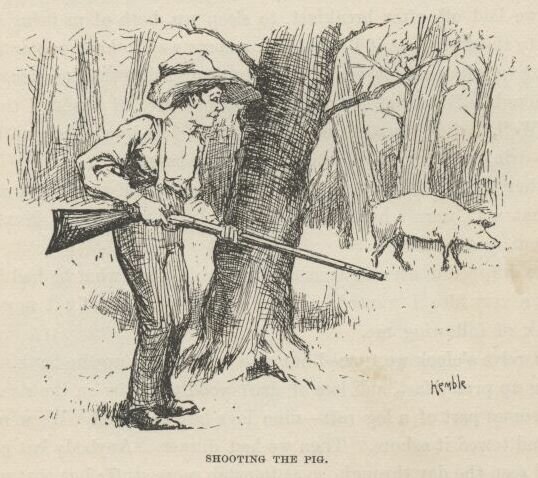
俺は斧を取り、ドアを打ち破った。かなり打ちつけ、切り刻んだ。豚を中に運び込み、テーブルの近くまで引きずっていき、斧で喉を切り裂き、血を流させるために地面に横たえた。地面と言ったのは、そこが本当に地面だったからだ――固く踏み固められ、板は敷かれていなかった。さて、次に古い袋を取り、引きずれるだけの大きな石をたくさん詰め込んだ。そして豚のいた場所から始め、ドアを通り、森を抜けて川まで引きずっていき、中に投げ込んだ。それは沈んで見えなくなった。地面には何かが引きずられた跡がはっきりと見て取れた。トム・ソーヤーがここにいたらなあ、と思った。彼ならこういう仕事に興味を持ち、凝った演出を加えてくれるだろう。トム・ソーヤーほど、こういうことで腕を振るえる奴はいない。
さて、最後に俺は自分の髪を少し抜き、斧に血をたっぷりとつけ、裏側に貼り付け、斧を隅に放り投げた。それから豚を抱え上げ、ジャケットで胸に抱きかかえ(血が滴らないように)、家からかなり下流まで行ってから川に投げ込んだ。ここで、もう一つ思いついた。そこで、カヌーからトウモロコシ粉の袋と古い鋸を取り出し、家まで運んだ。袋を元あった場所まで運び、鋸で底に穴を開けた。その場所にはナイフもフォークもなかったからだ――パップは料理に関して、すべて飛び出しナイフ一本で済ませていた。それから、袋を家の東側にある草地と柳の茂みを抜けて百ヤードほど運び、幅五マイルでイグサでいっぱいの浅い湖まで行った――季節によってはカモもたくさんいると言っていい。その湖の反対側からは、ぬかるみか小川が流れ出ており、何マイルも続いていた。どこへ行くのかは知らないが、川には通じていなかった。トウモロコシ粉がこぼれ落ち、湖まで細い跡を作った。偶然そうなったように見せるため、パップの砥石もそこに落としておいた。それから、もう漏れないように、トウモロコシ粉の袋の裂け目を紐で縛り、それと鋸を再びカヌーに運んだ。
あたりはもう暗くなっていた。そこで俺はカヌーを川岸に垂れ下がっている柳の下に流し、月が昇るのを待った。柳にカヌーをしっかりと結びつけ、それから一口食べ物を口にし、やがてカヌーに横になってパイプを吸いながら計画を練った。俺は独り言を言った。連中は石の詰まった袋の跡を追って岸まで来て、それから俺を探して川を浚うだろう。そして、トウモロコシ粉の跡を追って湖まで行き、俺を殺して物を盗んだ強盗を見つけるために、そこから流れ出る小川を下って探し回るだろう。川では俺の死体以外は何も探さないはずだ。それもすぐに飽きて、もう俺のことは気にしなくなるだろう。よし、これで好きな場所に泊まれる。ジャクソン島で十分だ。あの島はよく知っているし、誰も来やしない。それに、夜になれば町まで漕いで行って、こっそり忍び込んで欲しいものを手に入れられる。ジャクソン島こそがその場所だ。
俺はかなり疲れていて、気づいた時には眠っていた。目が覚めた時、一瞬どこにいるのか分からなかった。起き上がってあたりを見回すと、少し怖かった。それから思い出した。川は何マイルも向こうまで広がっているように見えた。月がとても明るかったので、岸から数百ヤード離れた場所を、黒く静かに滑っていく流木を数えることさえできそうだった。すべてが死んだように静かで、夜も更けているように見え、そして夜更けの匂いがした。俺が言いたいこと、分かるだろうか――それを表現する言葉を知らない。
俺は大きくあくびをして伸びをし、ちょうど綱を解いて出発しようとした時、水の向こうから音が聞こえた。耳を澄ました。やがて、それが何なのか分かった。静かな夜に、オールがオール受けでこすれる時に聞こえる、あの鈍い、規則的な音だった。柳の枝の間から覗くと、そこにあった――小舟が、はるか水の向こうに。何人乗っているかは分からなかった。それはどんどん近づいてきて、俺の真横に来た時、一人しか乗っていないのが見えた。パップかもしれない、と思ったが、彼が来るとは思っていなかった。彼は流れに乗って俺より下流へ行き、やがて流れの緩やかな場所で岸辺に近づいてきた。そして、俺が銃を伸ばせば触れるほど近くを通り過ぎていった。ああ、間違いなくパップだった――それに、オールの漕ぎ方からして、しらふだった。
俺は時間を無駄にしなかった。次の瞬間には、岸辺の影に隠れて、静かに、しかし素早く下流へと進んでいた。二マイル半ほど進み、それから川の中央に向かって四分の一マイルかそこら漕ぎ出した。もうすぐ渡し場を通り過ぎることになるので、人々に見つかって声をかけられるかもしれないからだ。流木の間に紛れ込み、カヌーの底に横になって、流れに任せた。

俺はそこに横たわり、ゆっくり休み、パイプで一服しながら、空を見上げていた。雲一つなかった。月明かりの下、仰向けに寝転がると、空がものすごく深く見えるもんだな。今まで知らなかった。それに、こんな夜は水の上だと、ずいぶん遠くの音まで聞こえるもんだ! 渡し場で人々が話しているのが聞こえた。彼らが何を言っているかも聞こえた――一言一句すべてだ。一人の男が、もうすぐ昼が長くて夜が短い季節になるな、と言っていた。もう一人の男は、今夜はその短い夜の一つじゃなさそうだ、と言って、それから二人は笑った。彼はもう一度同じことを言い、二人はまた笑った。それから彼らは別の仲間を起こしてその話をし、笑ったが、その男は笑わなかった。彼は何か威勢のいいことを吐き捨て、放っておいてくれと言った。最初の男は、これをうちの女房に話してやろう、きっと面白いと思うだろう、と言った。しかし、彼は、自分がこれまで言ってきたことの中には、これに比べれば何でもないこともある、と言った。一人の男が、もうすぐ三時だ、夜明けがあと一週間も待たせないでくれるといいが、と言うのが聞こえた。その後、話声はどんどん遠ざかっていき、もう言葉は聞き取れなくなった。しかし、ぶつぶつ言う声は聞こえ、時々笑い声も聞こえたが、それはずいぶん遠くから聞こえてくるようだった。
俺はもう渡し場のはるか下流にいた。起き上がると、そこにはジャクソン島があった。下流に二マイル半ほどのところに、木々が鬱蒼と茂り、川の中央にそびえ立っていた。灯りのない蒸気船のように、大きく、黒く、どっしりとしていた。島の先端にある砂州の気配はなかった――今はすべて水面下だった。
そこに着くのに時間はかからなかった。流れがとても速かったので、島の先端を猛スピードで通り過ぎ、それから流れの淀んだところに入り、イリノイ側の岸に上陸した。俺は知っていた岸の深い窪みにカヌーを乗り入れた。中に入るには柳の枝をかき分けなければならなかった。そしてしっかりと結びつけてしまえば、外からカヌーを見ることは誰にもできなかった。
俺は上がって、島の先端にある丸太に腰を下ろし、大きな川と黒い流木、そして三マイル離れた町を眺めた。そこには三つか四つの灯りが瞬いていた。巨大な材木筏が、一マイルほど上流を、真ん中にランタンを灯して下ってくるところだった。俺はそれがゆっくりと下ってくるのを見ていた。そして、俺が立っている場所のほとんど真横に来た時、「船尾のオール、そこだ! 船首を右舷に向けろ!」と男が言うのが聞こえた。その声は、まるで男が隣にいるかのように、はっきりと聞こえた。
空が少し白んできた。そこで俺は森の中に入り、朝食前に一眠りすることにした。
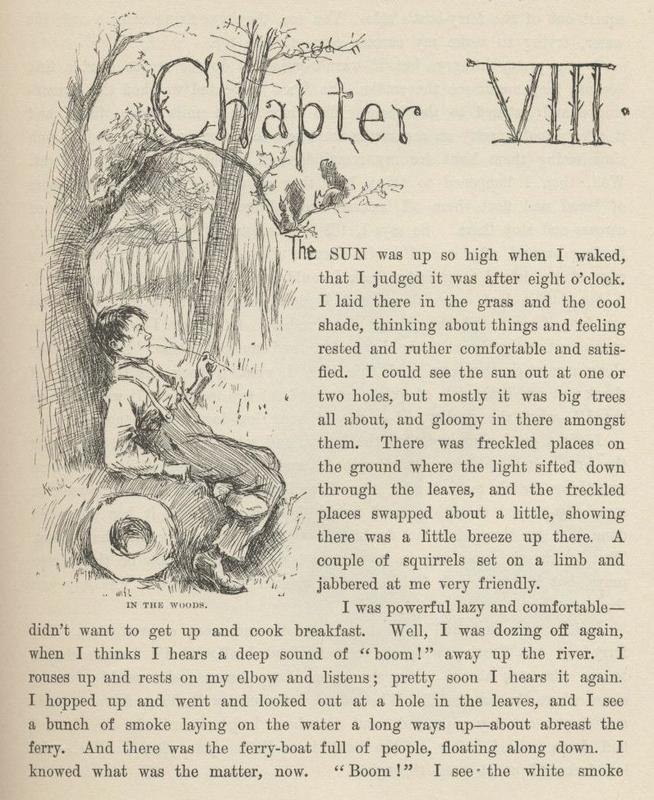
第八章
目が覚めた時には太陽がずいぶん高く昇っていたので、八時過ぎだろうと思った。俺は草むらの涼しい日陰に横たわり、物思いにふけりながら、すっかり休まり、むしろ快適で満足な気分だった。一、二箇所、穴から太陽が見えたが、ほとんどは大きな木々に囲まれ、その中は薄暗かった。地面には、葉っぱの間から光が差し込んでまだら模様ができており、そのまだら模様が少し揺れ動いていたので、上の方ではそよ風が吹いていることが分かった。二匹のリスが枝に座って、とても親しげに俺に話しかけてきた。
俺はひどく怠惰で快適な気分だった――起きて朝食を作る気にもならなかった。さて、またうとうとし始めた時、川の上流の方で「ドーン!」という深い音が聞こえたような気がした。俺は体を起こし、肘をついて耳を澄ました。やがて、またその音が聞こえた。俺は飛び起き、葉っぱの隙間から外を覗くと、はるか上流――渡し場の真横あたり――の水面に一団の煙が漂っているのが見えた。そして、人々でいっぱいの渡し船が流れに乗って下ってくるところだった。これで何が起こっているのか分かった。「ドーン!」渡し船の側面から白い煙が噴き出すのが見えた。連中は水面に向かって大砲をぶっ放していた。その衝撃で俺の死体を浮かび上がらせようってわけだ。
俺はかなり腹が減っていたが、火を起こすわけにはいかなかった。煙を見られるかもしれないからだ。そこで俺はそこに座って、大砲の煙を眺め、その音を聞いていた。そのあたりの川幅は一マイルあり、夏の朝はいつもきれいだ――だから、何か食うもんさえありゃ、連中が俺の亡骸を探してるのを眺めてるのも、なかなか悪くない気分だった。さて、その時、ふと思いついた。連中はいつもパンの塊に水銀を入れて流す。そうすると、必ず溺死体のもとへまっすぐ行って止まるからだ。だから、俺は言った。見張っていて、もし俺を追って流れてくるパンがあれば、相手になってやろう、と。運試しに、島のイリノイ側の岸辺に移ってみた。そしてがっかりはしなかった。大きな二つ繋がりのパンが流れてきて、長い棒でほとんど手に入れかけたが、足を滑らせて、パンはさらに遠くへ流れていってしまった。もちろん、俺は流れが一番岸に近づく場所にいた――それくらいは知っていた。しかし、やがてまた別のが流れてきて、今度はうまくいった。俺は栓を抜き、少量の水銀を振り出し、歯を立てた。それは「パン屋のパン」だった――上流階級の人々が食べるやつだ。安物のコーンブレッドなんかじゃない。
俺は葉っぱの間に良い場所を見つけ、丸太に座ってパンをむしゃむしゃ食べながら、渡し船を眺めていた。とても満足だった。その時、ふとある考えが浮かんだ。俺は言った。さて、未亡人か牧師か誰かが、このパンが俺を見つけてくれるようにと祈ったに違いない。そして、ほら、その通りになった。だから、あのことには何か意味があるのは間違いない――つまり、未亡人や牧師のような人が祈る時には何か意味があるんだ。でも、俺のためにはうまくいかないし、きっと正しい種類の人にしか効かないんだろう。

俺はパイプに火をつけ、ゆっくりと一服し、見張りを続けた。渡し船は流れに乗って漂っており、近づいてきたら誰が乗っているか見えるだろうと思った。パンが来たのと同じように、近くに寄ってくるはずだからだ。船がかなり俺の方へ下ってきた時、俺はパイプの火を消し、パンを釣り上げた場所へ行き、少し開けた場所の岸辺にある丸太の後ろに身を伏せた。丸太が二股に分かれているところから、覗き見ることができた。
やがて船がやって来て、板を渡せば岸に歩いて渡れるほど近くに寄ってきた。ほとんどみんなが船に乗っていた。パップ、サッチャー判事、ベッシー・サッチャー、ジョー・ハーパー、トム・ソーヤーと年老いたポリー叔母、シッドとメアリー、その他大勢だ。みんなが殺人事件について話していたが、船長が割って入って言った。
「よく見ろ、このあたりが一番流れが岸に寄る。もしかしたら岸に打ち上げられて、水際の茂みに絡まっているかもしれん。とにかく、そうだといいがな。」
俺はそうは思わなかった。みんなが押し寄せ、手すりから身を乗り出し、ほとんど俺の顔の目の前で、じっと、力の限り見張っていた。俺からは彼らがよく見えたが、彼らからは俺が見えなかった。それから船長が叫んだ。
「離れろ!」そして大砲が俺の目の前で轟音を立て、その音で耳が聞こえなくなり、煙でほとんど目が見えなくなった。もうだめだと思った。もし弾が入っていたら、連中が探していた死体を手に入れていただろう。まあ、ありがたいことに、俺は無傷だった。船は流れ去り、島の肩の向こうに見えなくなった。時々、ドーンという音が、だんだん遠くに聞こえ、やがて一時間後には、もう聞こえなくなった。島は三マイルの長さがあった。連中は島の端に着いて、諦めたのだろうと思った。しかし、まだしばらくはそうではなかった。彼らは島の端を回り、ミズーリ側の水路を蒸気で上り始め、時々ドーンと鳴らしながら進んでいった。俺はその側に渡って彼らを見ていた。島の先端の真横に来た時、彼らは撃つのをやめ、ミズーリ側の岸に寄り、町へ帰っていった。
俺はもう大丈夫だと分かった。他に誰も俺を探しに来る者はいないだろう。俺はカヌーから荷物を出し、深い森の中に素敵なキャンプを作った。毛布でテントのようなものを作り、その下に物を置いて雨に濡れないようにした。ナマズを一匹捕まえ、鋸で切り開いた。そして日没ごろ、キャンプファイヤーを熾して夕食をとった。それから、朝食用の魚を釣るために仕掛けをセットした。
暗くなると、俺はキャンプファイヤーのそばに座って煙草を吸い、かなり満足な気分だった。しかし、そのうち少し寂しくなってきたので、岸辺に行って座り、流れが打ち寄せる音を聞き、星や流れてくる流木や筏を数え、それから寝た。寂しい時には、これ以上良い時間の過ごし方はない。ずっと寂しいままでいることはできない、すぐに乗り越えられるものだ。
そして三日三晩が過ぎた。何も変わらない――ただ同じことの繰り返しだ。しかし、次の日、俺は島を下って探検に出かけた。俺はここの主人だ。いわば、すべてが俺のものなのだから、そのすべてを知りたかった。だが、主な目的は時間をつぶすことだった。熟して最高の状態のイチゴがたくさん見つかった。青い夏のブドウ、青いラズベリー、そして青いブラックベリーがちょうど実をつけ始めていた。そのうちどれも役に立つだろうと思った。
さて、俺は深い森の中をぶらぶらと歩き、島の端からそう遠くないだろうと思った。銃は持っていたが、何も撃たなかった。護身用だ。家の近くで何か獲物を殺そうと思っていた。その頃、俺はかなり大きな蛇をもう少しで踏みつけるところだった。それは草や花の中を滑るように去っていき、俺はそれを追いかけ、一発撃とうとした。俺は軽快に進み、突然、まだ煙を上げていたキャンプファイヤーの灰の上に飛び乗ってしまった。

心臓が喉まで飛び上がるかと思った。それ以上確かめるまでもなく、銃の撃鉄を戻すと、抜き足差し足、できる限りの速さで引き返した。時折、茂みの中で一瞬足を止めて耳を澄ましたが、自分の息遣いが荒すぎて、他の音は何も聞こえなかった。もう少し忍び足で進んでは、また耳を澄ます。その繰り返しだ。切り株を見れば人影かと思い、小枝を踏み折る音を立てれば、まるで誰かに息の根を半分、それも短いほうを断ち切られたような気分になった。
野営地に戻った頃には、すっかり意気消 trầmし、肝っ玉も縮み上がっていた。だが、ぐずぐずしている場合じゃない、と自分に言い聞かせた。そこで、持ち物を全部カヌーに積み込み、人目につかないようにした。火を消し、灰をあたりに撒き散らして、去年の古い野営地の跡みたいに見せかけてから、木に登った。
木の上には二時間もいただろうか。実際には何も見ず、何も聞かなかったが、気配だけはそれこそ千も万も感じた気がした。まあ、いつまでも木の上にいるわけにもいかない。とうとう下に降りたが、ずっと森の奥に身を潜め、警戒を怠らなかった。食べられたのは木の実と、朝食の残りだけだった。
夜になる頃には、腹がぺこぺこだった。そこで、あたりがすっかり暗くなったのを見計らい、月が昇る前に岸を離れ、イリノイ州側の岸へ向かってカヌーを漕いだ。四百メートルほどの距離だ。森の中に入って夕食を作り、このまま一晩ここで過ごそうと決心しかけた、その時だった。パカッ、パカッ、パカッ、パカッという音が聞こえた。馬だ、と俺は思った。次いで、人の話し声が聞こえてきた。俺はありったけのものを大急ぎでカヌーに放り込むと、様子を確かめようと森の中を這って進んだ。たいして進まないうちに、男の声が聞こえた。
「いい場所が見つかれば、ここで野営したほうがよさそうだな。馬がもうくたくただ。あたりを探してみよう。」
俺はそれを待たずに、そっとカヌーを押し出すと、静かに漕ぎ去った。いつもの場所につなぎ、今夜はカヌーの中で寝ることにした。
ろくに眠れなかった。考え事のせいで、どうしても眠れないのだ。それに、うとうとするたびに、誰かに首根っこを掴まれているような気がしてはっと目を覚ますのだった。だから、眠っても少しも疲れが取れなかった。やがて俺は独り言を言った。「こんな暮らしはもうごめんだ。この島にいるのが誰なのか、突き止めてやる。何が何でも、正体を暴いてやるんだ」。そう決めた途端、気分がずっと良くなった。
俺はパドルを手に取ると、岸からほんの少しだけカヌーを滑り出させ、あとは流れに任せて木陰の中を下っていった。月が輝き、影の外はほとんど昼間のように明るかった。一時間ほどもそうして進んだが、あたりは岩のように静まり返り、ぐっすりと寝静まっている。さて、この頃にはもう島の南端近くまで来ていた。さざ波を立てるような涼しい風が吹き始め、夜が明けそうだという合図のようだった。パドルでカヌーの向きを変え、船首を岸に向ける。それから銃を手に取り、そっとカヌーを降りて森の縁へ滑り込んだ。そこで丸太に腰を下ろし、葉の隙間から外を眺めた。月が役目を終え、闇が川を覆い始めるのが見えた。だが、しばらくすると木々の梢の上に青白い筋が見え、夜明けが近いことを知った。俺は銃を手に、あの焚き火を見つけた場所を目指してそっと歩き出した。一、二分ごとに立ち止まっては耳を澄ます。だがどういうわけか運がなく、その場所が見つからない。しかし、やがて、間違いなく、木々の向こうにちらちらと揺れる火の光を捉えた。俺は慎重に、ゆっくりとそこへ向かった。やがて様子をうかがえるくらい近くまで来ると、地面に男が一人横たわっていた。俺は危うく卒倒しそうになった。男は頭から毛布を被り、その頭が焚き火に突っこまれんばかりになっていた。俺は男から二メートルほど離れた茂みの後ろに座り込み、じっと目を凝らした。あたりはもう白み始めている。やがて男があくびをして伸びをすると、毛布をぱっと払いのけた。それはミス・ワトソンのところのジムだった! 思わず嬉しくなったね。俺は言った。
「よう、ジム!」そう言って、茂みから飛び出した。
ジムは飛び上がると、目を丸くして俺を凝視した。それから膝から崩れ落ち、両手を合わせて言った。
「ひぃっ、やめてくれ! わいは幽霊はんに悪いことしたこといっぺんもあらへん! 死んだ人らのことはいつかて大事にして、できることは何でもしてきたんや。あんたは川にお帰り、あんたがおるべき場所にな。わいに、いつかてあんたのダチやったこのジムじいに、何もしんといてくれ!」
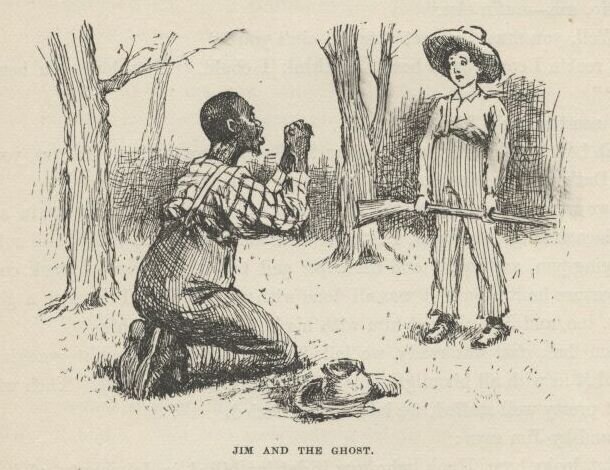
まあ、俺が死んでいないことをジムに理解させるのに、そう時間はかからなかった。ジムに会えて、俺は心から嬉しかった。もう寂しくはなかった。ジムが俺の居場所を誰かにしゃべるなんて心配は、これっぽっちもしていなかった。俺はぺらぺらと話し続けたが、ジムはただそこに座って俺を見つめるばかりで、何も言わなかった。そこで俺は言った。
「すっかり明るくなったな。朝飯にしようぜ。焚き火をちゃんとおこしてくれよ。」
「イチゴやらそんなもんを料理すんのに、焚き火起こしてどないすんねん。けど、あんた銃持っとるやろ? ほな、イチゴよりええもんが手に入るな。」
「イチゴやらそんなもん、だって?」と俺は言った。「そんなもの食って生きてたのか?」
「それしか手に入らんかったんや」とジムは言った。
「おい、ジム、この島にどのくらいいるんだ?」
「あんたが殺された次の晩に来たんや。」
「え、そんなにずっと?」
「ああ、ほんまや。」
「で、そんなゴミみたいなもんしか食ってないのか?」
「ああ、それ以外は何も。」
「そりゃあ、腹ぺこだろうな?」
「馬一頭でも食えそうや。ほんまに食えると思うで。あんたは、この島にいつからおるんや?」
「俺が殺された晩からだよ。」
「うそやろ! ほな、何食って生きてたんや? けど、あんたは銃持っとるんか。おお、そうや、銃持っとるんやな。そらええわ。はよ何か仕留めてきてくれ、わいが火をおこしとくから。」
そこで俺たちはカヌーのある場所へ行き、ジムが木々の間の草地で火をおこしている間に、俺はトウモロコシの粉とベーコン、コーヒー、コーヒーポットにフライパン、砂糖、ブリキのカップを持ってきた。ジムはすっかり度肝を抜かれていた。全部魔法の仕業だと思ったらしい。俺はでっかいナマズも一匹釣り上げた。ジムはそれをナイフでさばき、油で揚げてくれた。
朝食の準備ができると、俺たちは草の上に寝そべって、湯気の立つ熱々のそれを食べた。ジムは飢え死にしそうだったから、がむしゃらに詰め込んでいた。腹がはちきれそうになるまで食うと、俺たちはごろりと横になって怠けていた。やがてジムが言った。
「けど、ほらハック、あんたやなかったとしたら、あの小屋で殺されたんは一体誰やったんや?」
そこで俺は一部始終を話してやった。ジムは賢いやり方だと言った。トム・ソーヤーだって、これ以上うまい計画は立てられなかっただろう、と。それから俺は言った。
「ジム、おまえはどうしてここにいるんだ? どうやって来たんだ?」
ジムはひどく落ち着かない様子で、一分ほど何も言わなかった。それから言った。
「言わんほうがええかもしれん。」
「どうしてだ、ジム?」
「まあ、理由があるんや。けど、もしわいが話したとしても、あんたは誰にも言わんやろな、ハック?」
「言うもんか、ジム。」
「うん、あんたのこと信じるわ、ハック。わいは……わいは、逃げてきたんや。」
「ジム!」
「けどええか、言わんて言うたで。言わんて約束したやろ、ハック。」
「ああ、言ったよ。言わないって言ったし、その約束は守る。絶対にだ。みんなは俺のことを、ろくでもない奴隷解放論者だのなんだの言って、黙っていることを軽蔑するだろう。だが、そんなことはどうでもいい。俺は絶対にしゃべらないし、どのみちあそこへは戻らないんだから。さあ、全部話してくれよ。」
「まあな、ことの次第はこうや。奥様――ミス・ワトソンのことや――はな、いっつもわいをいびって、ひどい扱いをしとったけど、オーリンズにだけは売り飛ばさんて、いつも言うとったんや。けどな、近頃黒人商人がうろついとるのに気づいて、わいは不安になってきたんや。ほんで、ある晩、夜も更けてからこっそり戸口に近づいたら、戸が少し開いとってな、奥様が未亡人様に、わいをオーリンズに売り飛ばすつもりやて話しとるのが聞こえたんや。本当は売りたないけど、わいを売れば八百ドルにもなるし、そないな大金、我慢できんて。未亡人様は、そんなことせんように説得しようとしとったけど、わいは最後まで聞かずに逃げ出したんや。ほんま、一目散やったで。」
「わいは飛び出すと丘を駆け下りて、町の上のほうの岸で小舟を一艘盗もうと思っとったんやけど、まだ人がうろうろしとったんで、岸辺の古くて崩れかけた桶屋に隠れて、みんながいなくなるのを待ったんや。まあ、一晩中そこにおった。誰かがずっとうろついとったからな。朝の六時頃になると小舟が行き交い始めて、八時か九時頃には、通る舟はみんな、あんたの親父さんが町に来て、あんたが殺されたて言うとった話で持ちきりやった。後から来た舟には、現場を見に行こうっちゅうご婦人方や紳士方がぎょうさん乗っとった。時々岸に上がって、川を渡る前に一休みしとったから、その話で殺しのことは全部わかった。あんたが殺されたて聞いて、わいはほんまに気の毒に思っとったんやで、ハック。けど、もうそんなことないわ。」
「わいは一日中、削り屑の下に寝そべっとった。腹は減っとったけど、怖くはなかったで。奥様と未亡人様は、朝飯のすぐ後に野外礼拝に出かけて一日中留守にしとるのを知っとったし、わいが夜明け頃に牛と一緒にどっか行くのも知っとるから、屋敷の周りにおらんくてもおかしいとは思わんやろ。せやから、晩になって暗くなるまで、わいがおらんことに気づかんはずや。他の使用人たちも気づかんやろ。ご主人様たちがおらんようになったら、すぐに抜け出して休みを取るからな。」
「まあ、暗くなってから、わいは川沿いの道を上流に向かって歩き出して、家が一軒もないところまで三キロほど行った。これからどうするかは、もう心に決めとった。ええか、このまま歩いて逃げ続けたら、犬に追跡される。小舟を盗んで川を渡ったら、その小舟がなくなったことに気づかれて、わいが向こう岸のどのへんに上陸して、どこから足跡を追えばええか、わかってしまう。せやから、わいは言うたんや、いかだや、わいが狙うんは。いかだなら、足跡がつかへんからな。」
「そのうち岬の向こうから明かりが見えてきたんで、わいは水に入って、丸太を一本前に押し出しながら川の半分以上を泳いで、流木の中に紛れ込んだんや。頭を低うして、流れに逆らうように泳いで、いかだが来るのを待った。いかだが来ると、わいは船尾に泳ぎ寄ってしがみついた。しばらくの間、曇っててかなり暗かった。せやから、わいは這い上がって板の上に寝そべった。男たちはみんな、ランタンのある真ん中のほうにおった。川は増水しとって、流れも速かった。せやから、朝の四時までには四十キロは下流に行けるやろうし、そしたら夜明け前にこっそり水に飛び込んで岸まで泳いで、イリノイ側の森に逃げ込もうと思っとったんや。」
「けど、運がなかった。島の先端までもうすぐっちゅうところで、男が一人、ランタンを持って船尾のほうへ来始めたんや。こらもう待っとれんと思って、わいは船外に滑り落ちて、島に向かって泳ぎ出した。まあ、どこにでも上陸できると思っとったんやけど、できんかった。岸が険しすぎたんや。島の南端までもうすぐっちゅうところで、やっとええ場所を見つけた。森の中に入って、もういかだに手を出すのはやめとこうと決めた。あんなにランタンをうろうろさせとるうちはな。帽子の中にパイプと噛みタバコとマッチを入れとって、濡れとらんかったから、それで万事うまくいったんや。」
「じゃあ、その間ずっと肉もパンも食ってなかったのか? スッポンは捕まえなかったのか?」
「どないして捕まえるんや? こっそり近づいてひっつかむこともできんし、石を当てようにもどうすりゃええ? 夜中にそんなことできんやろ? それに、昼間に岸辺に姿を見せるつもりもなかったしな。」
「まあ、そりゃそうか。もちろん、ずっと森の中にいなきゃならなかったんだもんな。大砲を撃つ音は聞こえたか?」
「おお、聞こえたで。あんたを探しとるんやてわかった。連中がここを通り過ぎるのも見たわ。茂みの間からな。」
何羽かの若鳥が、一度に一、二メートルずつ飛んでは止まり、を繰り返しながらやってきた。ジムは、もうすぐ雨が降る印だと言った。ひよこがそんなふうに飛ぶときは雨の印で、だから若鳥がやっても同じことだろう、と言うのだ。俺が何羽か捕まえようとすると、ジムが止めに入った。死の前触れだ、と。昔、ジムの父親がひどい病気にかかった時、誰かが鳥を捕まえたら、ジムの婆さんが父親は死ぬだろうと言い、その通りになったそうだ。
ジムはまた、夕食に料理するものの数を数えてはいけない、と言った。不吉なことを招くからだそうだ。日没後にテーブルクロスを振るのも同じだという。それに、もし養蜂箱を持っている男が死んだら、次の朝、日が昇る前に蜂にそのことを伝えなければならない、さもないと蜂はみんな弱って働かなくなり、死んでしまうそうだ。ジムは、蜂は馬鹿を刺さない、とも言った。だが、俺はそれは信じなかった。だって、俺は何度も試したことがあるが、蜂は俺を刺さなかったからだ。
こういう話のいくつかは前に聞いたことがあったが、全部ではなかった。ジムはあらゆる種類の印を知っていた。ほとんど何でも知っている、と彼は言った。俺には、その印とやらは全部不吉なことばかりのように思えたので、縁起のいい印はないのかと尋ねてみた。彼は言った。
「ほとんどないな。それに、あっても何の役にも立たん。幸運がいつ来るか知ってどうするんや? 追い払いたいんか?」そしてこう続けた。「腕と胸に毛が生えとったら、そいつは金持ちになる印や。まあ、こないな印には少しは意味があるかもしれん。ずっと先のことやからな。ええか、多分、最初は長いこと貧乏せなあかんかもしれん。そしたら、がっかりして自殺してしまうかもしれんやろ、もし印で自分がいつか金持ちになるっちゅうことを知らんかったらな。」
「ジム、おまえは腕と胸に毛が生えてるのか?」
「何でそないなこと聞くんや? 見たらわかるやろ?」
「じゃあ、金持ちなのか?」
「いや、けど、いっぺん金持ちやったことがあるし、また金持ちになるつもりや。いっぺん十四ドル持っとったんやけど、投機に手を出して、すってんてんになったんや。」
「何に投機したんだ、ジム?」
「まあ、最初は株に手を出したんや。」
「どんな株だ?」
「そら、生きとる株や。家畜のことやで。牛に十ドルつぎ込んだんや。けど、もう二度と家畜に金を賭けるつもりはない。牛がわいの手元で死んでしもうたんや。」
「じゃあ、十ドル損したのか。」
「いや、全部損したわけやない。九ドルぐらい損しただけや。皮と脂肪を売って、一ドル十セントになった。」
「五ドル十セント残ったわけだな。また投機したのか?」
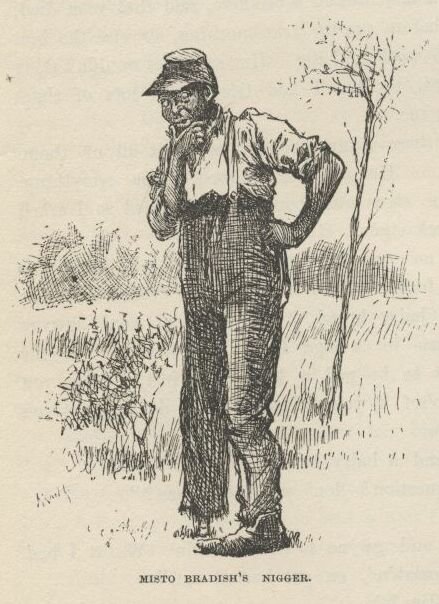
「ああ。ブラディッシュ旦那のとこの、あの片足の黒んぼ知っとるやろ? あいつが銀行を始めてな、一ドル預けたら、年の終わりには四ドル余分にもらえるて言うたんや。まあ、黒んぼはみんな預けたけど、たいして持っとらんかった。ぎょうさん持っとったんは、わいだけやった。せやから、わいは四ドル以上よこさんかい、て粘ってな、もらえんのやったったら、わいが自分で銀行を始めるて言うたんや。まあ、もちろん、あの黒んぼはわいを商売から締め出したかったんやろな。銀行が二つもあっても商売にならんて言うて、わいの五ドルを預けたら、年の終わりに三十五ドル払うて言うたんや。」
「せやから、そうしたんや。ほんで、その三十五ドルをすぐに投資して、金を回し続けようと考えたんや。ボブっちゅう名前の黒んぼが、材木運搬用の平底舟を一艘捕まえとってな、ご主人様はそれを知らんかった。わいはそいつから舟を買い取って、年の終わりに三十五ドル受け取れ、て言うといたんや。けど、その晩に誰かがその舟を盗んでしもうて、次の日になったら、あの片足の黒んぼが銀行は潰れたて言うたんや。せやから、わいらは誰一人、金をもらえんかった。」
「十セントはどうしたんだ、ジム?」
「まあ、使ってしまおうと思っとったんやけど、夢を見てな、その夢が、バラムっちゅう名前の黒んぼにやれ、て言うたんや。みんなはあいつを短く『バラムのロバ』て呼んどる。あいつは、まあ、間抜けの一人や。けど、運がええ、て言われとるし、わいは運がないのがわかっとった。夢は、バラムに十セントを投資させたら、わいのために一財産築いてくれる、て言うたんや。まあ、バラムは金を受け取って、教会におる時に、説教師が『貧しいもんに施すんは、神様に貸すようなもんや。百倍になって返ってくる』て言うのを聞いたんや。せやからバラムは、その十セントを貧しいもんにやってしもうて、どうなるか様子を見とったんや。」
「で、どうなったんだ、ジム?」
「何にもならんかった。どないしてもその金は回収できんかったし、バラムにもできんかった。もう担保を見んうちは、金は貸さんつもりや。百倍になって返ってくる、て説教師は言うとった! もしあの十セントが返ってきたら、それで帳消しにして、その機会に感謝するんやけどな。」
「まあ、どのみちいいじゃないか、ジム。いつかまた金持ちになるんだから。」
「そうや。それに、よう考えてみたら、わいは今でも金持ちや。わいは自分自身の持ち主やし、八百ドルの価値がある。その金が手元にあれば、もう何もいらんのやけどな。」
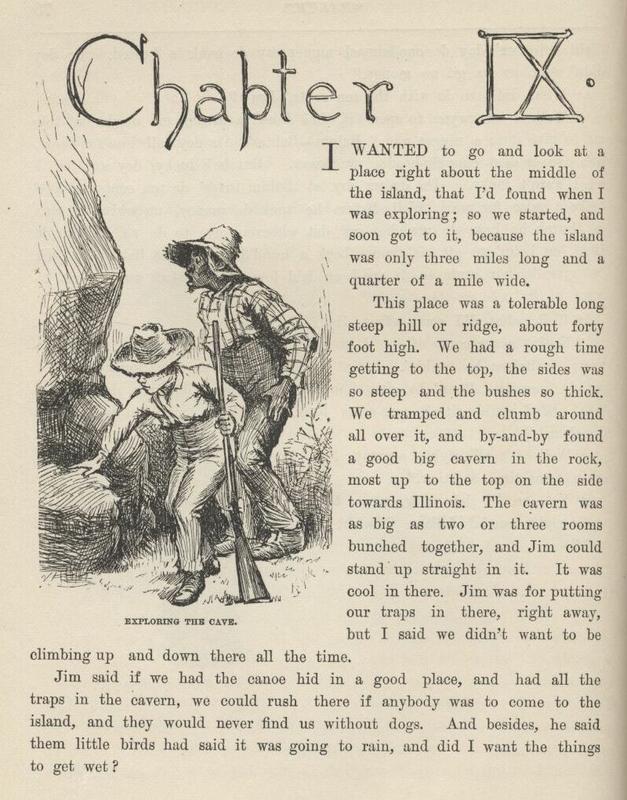
第九章
俺は島のちょうど真ん中あたりで、探検している時に見つけた場所へ行ってみたかった。そこで俺たちは出発し、すぐにそこへ着いた。島は長さ五キロ、幅四百メートルほどしかなかったからだ。
その場所は、高さ十二メートルほどの、かなり長くて険しい丘、というか尾根だった。側面は切り立っていて、藪も深かったので、頂上にたどり着くまで一苦労だった。俺たちはあたりを踏み分け、よじ登り、やがてイリノイ州側の斜面の頂上近くに、岩にできた大きな洞窟を見つけた。洞窟は部屋が二つか三つ合わさったくらいの大きさで、ジムがまっすぐに立てるほどの高さがあった。中は涼しかった。ジムはすぐに荷物を運び込もうと言ったが、俺はしょっちゅうあそこを上り下りしたくない、と言った。
ジムは、もしカヌーをいい場所に隠して、荷物を全部洞窟に入れておけば、誰かが島に来てもそこに駆け込めるし、犬でもいなければ絶対に見つからない、と言った。それに、あの小鳥たちが雨が降ると言っていたし、荷物を濡らしたいのか、とも言った。
そこで俺たちは戻ってカヌーを運び、洞窟の真下まで漕いでいくと、荷物を全部そこへ運び上げた。それから、近くの深い柳の茂みの中にカヌーを隠す場所を探した。俺たちは仕掛け糸から魚を何匹か外し、また仕掛けをセットして、昼食の準備を始めた。
洞窟の入り口は、大樽が転がして入れられるほど大きく、入り口の片側は床が少し突き出ていて平らだったので、火をおこすのにちょうどよかった。そこで俺たちは火をおこし、昼食を作った。
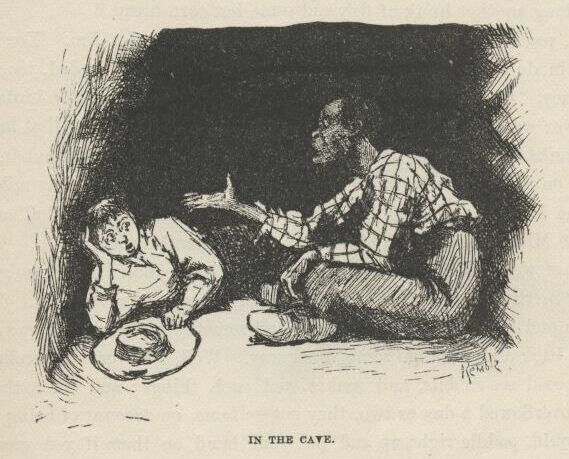
洞窟の中に毛布を敷いて絨毯代わりにし、そこで昼食を食べた。他の荷物は全部、洞窟の奥の使いやすい場所に置いた。やがてあたりが暗くなり、雷が鳴り、稲妻が光り始めた。鳥たちの言った通りだった。すぐに雨が降り出し、それも猛烈な勢いで、あんなに風が吹くのは見たことがなかった。典型的な夏の嵐だった。外は一面、藍色のような黒に見え、それがまた美しかった。雨はあまりに激しく降り注ぐので、少し離れた木々はぼんやりと蜘蛛の巣みたいに見えた。突風が吹くと木々がしなり、葉の青白い裏側がひるがえる。それに続いて、すべてを引き裂くような突風が吹き荒れ、枝という枝がまるで狂ったように腕を振り回す。そして、あたりが最も青黒くなった次の瞬間――ピカッ!――栄光のように輝き、嵐の中、何百メートルも先で、それまで見えなかった木々の梢が揺れ動くのがちらりと見える。一瞬でまた罪のように暗くなり、今度は雷がすさまじい轟音とともに炸裂し、それからゴロゴロ、ゴロゴロと、空の底のほうへ転がり落ちていくのが聞こえる。まるで空の樽を階段から転がし落とすみたいに――長い階段で、樽が何度も弾む、あの感じだ。
「ジム、こりゃあいいな」と俺は言った。「ここ以外のどこにもいたくないね。魚をもう一切れと、熱いコーンブレッドをくれよ。」
「まあ、ジムがおらんかったら、あんたはここにはおらんかったやろうな。夕飯もなしに、森の中でずぶ濡れになっとったはずや。ほんまやで、ぼうや。ニワトリはいつ雨が降るか知っとるし、鳥もそうや。」
川は十日か十二日間、増水し続け、とうとう岸を越えた。島の低い場所やイリノイ側の低地では、水深が一メートルから一メートル二十センチほどになった。イリノイ側では川幅が何キロにも広がったが、ミズーリ側は相変わらず八百メートルほどの距離だった。ミズーリ側の岸は、高い崖が壁のようにそそり立っていたからだ。
昼間、俺たちはカヌーで島中を漕ぎ回った。外は太陽が燃えるように照りつけていても、深い森の中はひんやりと涼しく、日陰になっていた。俺たちは木々の間を縫うように進み、時には蔓が密集しすぎて、引き返して別の道を探さなければならなかった。さて、古くて倒れた木の上にはどこでも、ウサギやヘビなんかがいた。島が水浸しになって一日か二日もすると、腹を空かせたせいですっかり人懐っこくなり、カヌーをすぐそばまで漕ぎ寄せれば、望むなら手で触れることもできた。ただし、ヘビとカメは別で、すぐに水の中に滑り込んでしまう。俺たちの洞窟がある尾根には、そういった生き物がたくさんいた。欲しければ、ペットには困らなかっただろう。
ある夜、俺たちは材木のいかだの切れ端を捕まえた。きれいな松の板だった。幅は三メートル六十センチ、長さは四メートル五十センチから四メートル八十センチほどで、上面は水面から十五センチか十八センチほど出ていて、頑丈で平らな床になっていた。昼間には丸太が流れていくのが見えることもあったが、俺たちは放っておいた。昼間は姿を見せないようにしていたからだ。
別の夜、俺たちが島の北端にいた時、夜明け直前に、木造の家が西側を流れてきた。二階建てで、かなり傾いている。俺たちはカヌーを漕ぎ出して乗り移り、二階の窓から中に入った。しかし、まだ暗くて何も見えなかったので、カヌーをしっかりつなぎ、その中で夜が明けるのを待った。
島の南端に着く前に、あたりが明るくなり始めた。俺たちは窓から中を覗き込んだ。ベッドとテーブル、古い椅子が二脚、床にはたくさんのものが散らばっているのが見え、壁には服が掛かっていた。一番奥の隅の床に、男のように見えるものが横たわっていた。そこでジムが言った。
「おーい、あんた!」
しかし、それはぴくりとも動かなかった。そこで俺がもう一度叫ぶと、ジムが言った。
「この男は眠っとるんやない――死んどるんや。じっとしとき。わいが見てくる。」
ジムは中に入り、身をかがめて覗き込むと、言った。
「死体や。ああ、ほんまや。裸やで。背中を撃たれとる。死んでから二、三日経っとるやろ。入ってきい、ハック。けど、顔は見たらあかんで――むごすぎるわ。」

俺は男の顔を一切見なかった。ジムが古いぼろ切れをいくつかその上にかけたが、その必要はなかった。俺は見たくなかったからだ。床には油で汚れた古いトランプのカードが山のように散らばり、古いウイスキーの瓶や、黒い布でできた仮面が二つあった。壁一面には、炭で描かれた、この上なく下品な言葉や絵があった。汚れた古い更紗のドレスが二着、日よけボンネット、女物の下着が壁に掛かっていて、男物の服もいくつかあった。俺たちはそれを全部カヌーに入れた――何かの役に立つかもしれない。床には男の子の古くて染みのついた麦わら帽子があったので、それも拾った。ミルクが入っていた瓶もあった。赤ちゃんが吸うためのぼろ切れの栓がしてあった。瓶も持っていきたかったが、割れていた。古びた古い箱と、蝶番が壊れた古い毛皮のトランクもあった。開けっ放しになっていたが、中には価値のあるものは何も残っていなかった。物が散乱している様子から、ここの住人は大急ぎで立ち去り、ほとんどの荷物を運び出す余裕もなかったのだろうと推測した。
俺たちは古いブリキのランタン、柄のない肉切り包丁、どこの店でも二十五セントはする真新しいバーロウナイフ、たくさんの獣脂ろうそく、ブリキの燭台、ひょうたん、ブリキのカップ、ベッドから剥がしたぼろぼろの古いベッドカバー、針とピン、蜜蝋、ボタン、糸といった裁縫道具一式が入った手提げ袋、手斧と釘数本、俺の小指ほどの太さの釣り糸に巨大な釣り針がいくつか付いたもの、鹿革の巻物、革の犬の首輪、蹄鉄、ラベルのない薬の小瓶をいくつか手に入れた。そして、まさに出発しようという時に、俺はまずまずの馬櫛を見つけ、ジムはぼろぼろの古いバイオリンの弓と、木製の義足を見つけた。革紐は切れていたが、それさえ除けば十分使える義足だった。もっとも、俺には長すぎ、ジムには短すぎたが。もう片方は、あたりを探し回ったが見つからなかった。
まあ、全体としてみれば、なかなかの獲物だった。俺たちがカヌーを押し出す準備ができた頃には、島から四百メートルほど下流におり、すっかり明るくなっていた。そこで俺はジムにカヌーの中に横にならせ、ベッドカバーで体を覆わせた。もし座っていたら、遠くからでも黒人だとわかってしまうからだ。俺はイリノイ州側の岸へ向かって漕ぎ、そうするうちに八百メートル近く流された。岸辺のよどんだ水の中をそろそろと進み、事故もなく、誰にも会わなかった。俺たちは無事にねぐらに帰り着いた。
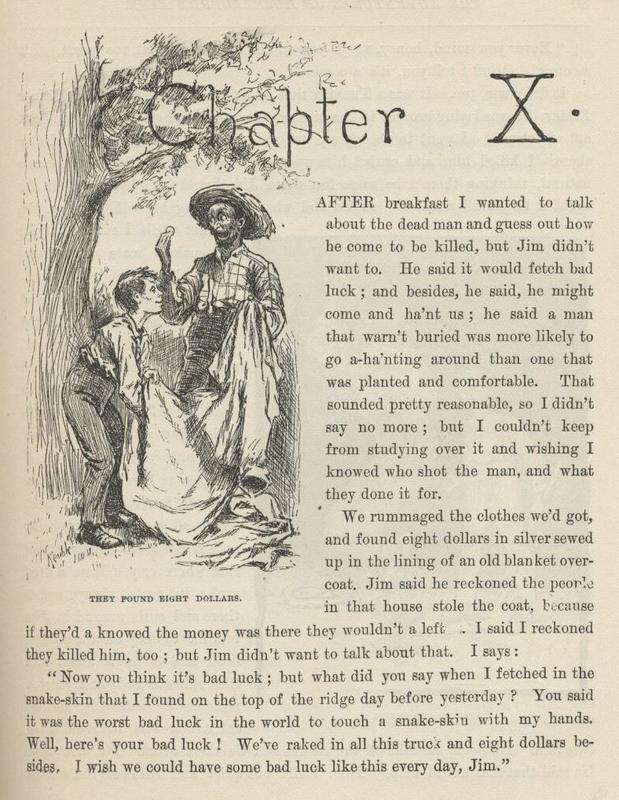
第十章
朝食の後、俺はあの死体のことについて話し、どうして殺されたのか推測してみたかったが、ジムは嫌がった。不吉なことを呼び込む、と言った。それに、化けて出るかもしれない、とも言った。埋葬されていない男は、ちゃんと埋葬されて安らかに眠っている男よりも、うろつき回って化けて出る可能性が高い、と言うのだ。それはもっともらしく聞こえたので、俺はそれ以上何も言わなかった。だが、そのことについて考えずにはいられず、誰があの男を撃ったのか、何のためにやったのか、知りたくてたまらなかった。
俺たちは手に入れた服をくまなく調べ、古い毛布のオーバーコートの裏地に縫い込まれていた八ドルの銀貨を見つけた。ジムは、あの家の連中はそのコートを盗んだのだろう、と言った。もし金が入っているのを知っていたら、置き去りにするはずがないからだ、と。俺は、連中が彼を殺したんだろう、とも言ったが、ジムはその話をしたくなかった。俺は言った。
「おまえはそれを不吉だと思ってる。だが、おととい俺が尾根のてっぺんで見つけた蛇の皮を持ってきた時、おまえは何て言った? 手で蛇の皮に触れるのは、この世で最悪の不運だ、って言ったよな。まあ、これがその不運とやらだ! 俺たちはこのがらくた全部と、おまけに八ドルも手に入れたんだぜ。こんな不運なら毎日でもあってほしいもんだ、ジム。」
「ええから、ええから。そないに調子に乗ったらあかんで。来るで。言うとくけど、ほんまに来るで。」
そして、それは本当にやって来た。その話をしたのは火曜日だった。さて、金曜日の昼食の後、俺たちは尾根の北端の草むらでごろごろしていたが、タバコが切れてしまった。俺は洞窟へ取りに行き、そこでガラガラヘビを見つけた。俺はそいつを殺し、ジムの毛布の足元に、いかにも自然な感じでとぐろを巻かせておいた。ジムがそれを見つけたら面白いだろう、と思ったのだ。さて、夜になる頃には、俺は蛇のことなどすっかり忘れていた。そして、俺が明かりを灯している間にジムが毛布の上に身を投げ出すと、そこには蛇の連れ合いがいて、ジムに噛みついた。
ジムは叫び声を上げて飛び上がった。明かりが最初に照らし出したのは、とぐろを巻いて再び飛びかかろうとしているそいつの姿だった。俺は棒で一撃のもとにそいつを仕留め、ジムはパップのウイスキー瓶を掴むと、がぶがぶと飲み始めた。

ジムは裸足で、蛇はかかとをまともに噛んでいた。死んだ蛇を放置しておくと、その連れ合いが必ずやって来てそばでとぐろを巻く、ということを俺が覚えていなかったばかりに、こんなことになったのだ。ジムは俺に、蛇の頭を切り落として捨て、それから皮を剥いで肉を一切れ焼くように言った。俺はその通りにし、ジムはそれを食べて、治癒の助けになるだろう、と言った。彼はまた、ガラガラを切り取って自分の手首に結びつけさせた。それも助けになる、と。それから俺は静かに抜け出し、蛇を茂みの中に遠くへ投げ捨てた。もし助けられるなら、これが全部俺のせいだとジムに知られるわけにはいかなかったからだ。
ジムは瓶を吸い続け、時々正気を失っては暴れたり叫んだりした。だが、我に返るたびに、また瓶を吸い始めた。足はかなり大きく腫れ上がり、脚も同様だった。しかし、やがて酔いが回ってきたので、もう大丈夫だろうと判断した。だが、パップのウイスキーを飲むくらいなら、蛇に噛まれたほうがましだった。
ジムは四日四晩寝込んだ。その後、腫れはすっかり引き、また動き回れるようになった。俺は、今回のことで懲りて、もう二度と蛇の皮を素手で掴むまいと心に決めた。ジムは、次は俺の言うことを信じるだろう、と言った。そして、蛇の皮を扱うのはとてつもなく不吉なことだから、まだこれで終わりではないかもしれない、とも言った。蛇の皮を手に取るくらいなら、新月を左肩越しに千回見るほうがましだ、と。まあ、俺もそんな気分になってきていた。もっとも、新月を左肩越しに見るなんてのは、人間がやりうる最も不注意で馬鹿げたことの一つだと、俺はいつも思っている。昔、ハンク・バンカーが一度それをやって、自慢していた。そして二年もしないうちに、彼は酔っぱらって弾丸製造塔から落ち、ぺちゃんこになって、いわば薄い層のようになってしまった。人々は彼を納屋の戸二枚の間に横向きに挟んで棺桶代わりにし、そうやって埋葬したそうだ。俺は見ていないが、パップがそう言っていた。だが、いずれにせよ、すべては馬鹿みたいにそんなふうに月を見たせいなのだ。

さて、月日は流れ、川の水位はまた両岸の間に収まった。俺たちがまずやったことの一つは、大きな釣り針に皮を剥いだウサギを餌として付け、それを仕掛けて、人間と同じくらいの大きさのナマズを釣ることだった。体長は一メートル八十八センチ、体重は九十キロを超えていた。もちろん、俺たちに扱える代物ではなかった。イリノイ州まで放り投げられていただろう。俺たちはただそこに座って、そいつが溺れるまで暴れ回るのを見ていた。腹の中からは真鍮のボタンと丸い玉、それにたくさんのゴミが出てきた。手斧で玉を割ると、中には糸巻きが入っていた。ジムは、長い間腹の中にあって、表面が覆われて玉のようになったのだろう、と言った。ミシシッピ川で釣れた魚としては、今までで一番大きかったと思う。ジムは、これより大きいのは見たことがない、と言った。村に持っていけば、かなりの値打ちがあっただろう。あそこの市場では、あんな魚は量り売りされ、誰もが少しは買うのだ。身は雪のように白く、フライにするとうまい。
翌朝、俺はだんだん退屈になってきたので、何か刺激が欲しい、と言った。川を渡って、町の様子を探ってこようと思う、と言った。ジムはその考えを気に入ったが、暗いうちに行き、用心深くしなければならない、と言った。それから彼は考え込み、あの古い服を着て、女の子みたいに変装できないか、と言った。それもいい考えだった。そこで俺たちは更紗のガウンの一つの丈を詰め、ズボンの裾を膝までまくり上げてそれを着た。ジムが後ろでホックを留めてくれると、まあまあ似合っていた。日よけボンネットをかぶり、顎の下で紐を結ぶと、誰かが俺の顔を覗き込むのは、まるで煙突の筒を覗き込んでいるみたいだった。ジムは、これなら昼間でも、まず誰にもわからないだろう、と言った。俺は一日中歩き回って、その格好に慣れる練習をした。やがてかなりうまくこなせるようになったが、ジムは、歩き方が女の子らしくない、と言った。それに、ズボンのポケットに手を入れるためにガウンをまくり上げるのはやめなければならない、とも言った。俺はそれに注意し、うまくできるようになった。

日が暮れてすぐ、俺はカヌーでイリノイ州側の岸を上流へと向かった。
渡し場の少し下流から町に向かって川を渡り始めると、流れに運ばれて町の南端に着いた。カヌーをつなぎ、岸辺を歩き始めた。長い間誰も住んでいなかった小さな小屋に明かりが灯っており、誰がそこに住み着いたのだろう、と不思議に思った。俺はそっと近づき、窓から中を覗いた。中には四十歳くらいの女がいて、松材のテーブルの上に置かれたろうそくの明かりで編み物をしていた。見覚えのない顔だった。見知らぬ女だ。あの町で俺が知らない顔なんて、まずありえないからだ。さて、これは幸運だった。俺は弱気になっていたからだ。ここに来たことを後悔し始めていた。声で俺だとばれてしまうかもしれない。しかし、この女がこんな小さな町に二日もいれば、俺が知りたいことは何でも教えてくれるだろう。そこで俺はドアをノックし、自分が女の子であることを忘れないようにしようと心に決めた。
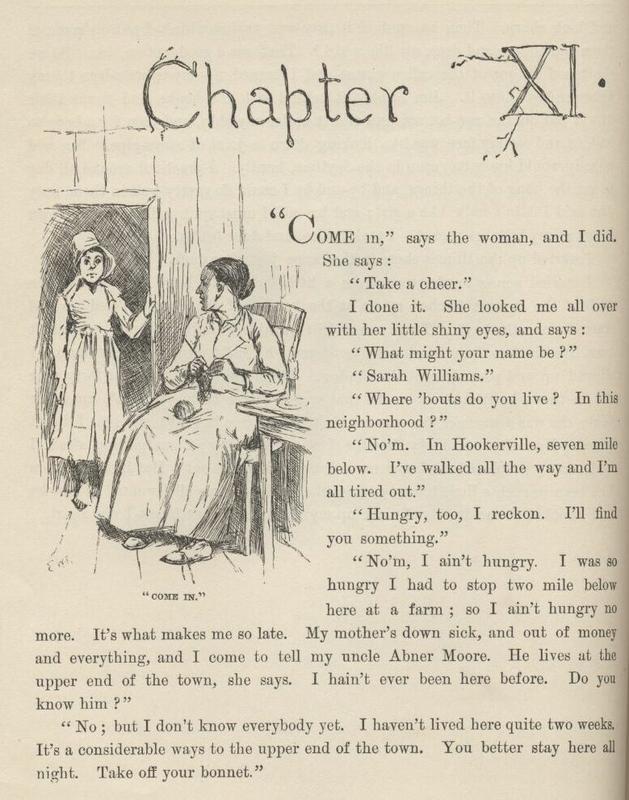
第十一章
「お入り」と女が言い、俺は中に入った。女は言った。「椅子におかけ。」
俺はそうした。女はキラキラ光る小さな目で俺を頭のてっぺんからつま先まで眺め回し、言った。
「お名前はなんていうのかしら?」
「サラ・ウィリアムズです。」
「どこに住んでるの? この近所?」
「いいえ。十一キロ下流のフッカーヴィルです。ずっと歩いてきたので、くたくたです。」
「お腹も空いてるでしょう。何か見つけてあげるわ。」
「いいえ、お腹は空いていません。あまりにお腹が空いたので、三キロほど手前の農家で休ませてもらったんです。だからもうお腹は空いていません。それでこんなに遅くなってしまいました。母が病気で倒れて、お金も何もかもなくて、アブナー・ムーア叔父さんに知らせに来たんです。叔父さんは町の北の端に住んでいる、と母は言っていました。私はここに来たのは初めてです。叔父さんをご存じですか?」
「いいえ。でも、まだみんなを知っているわけじゃないのよ。ここに住んでまだ二週間も経たないから。町の北の端まではかなり遠いわよ。今夜はここに泊まっていきなさい。ボンネットをお脱ぎなさい。」
「いいえ」と俺は言った。「少し休んだら、先へ行こうと思います。暗いのは怖くありませんから。」
女は、一人では行かせられない、と言ったが、夫がそのうち、多分一時間半もすれば帰ってくるから、一緒に行かせてあげる、と言った。それから女は夫のこと、川上にいる親戚のこと、川下にいる親戚のこと、昔はどれほど暮らし向きが良かったか、今のままにしておくべきだったのに、この町に来たのは間違いだったかもしれない、ということなどを延々と話し始めた。俺は、町の様子を探るためにこの女のところに来たのは間違いだったかと不安になった。しかし、やがて女はパップと殺人事件の話に移り、そうなると俺は喜んで彼女にぺらぺらとしゃべらせておいた。女は俺とトム・ソーヤーが六千ドル(彼女は一万ドルと言ったが)を見つけたこと、パップのこと、彼がどれほどひどい男だったか、俺がどれほどひどい奴だったか、そしてとうとう俺が殺された話になった。俺は言った。
「誰がやったんですか? フッカーヴィルでもその事件のことはかなり聞いていますけど、誰がハック・フィンを殺したのかは知らないんです。」
「まあ、ここの人たちだって、誰が彼を殺したのか知りたがっている人は大勢いるわよ。年寄りのフィンが自分でやったと思っている人もいるわ。」
「ええっ、本当ですか?」
「最初はほとんどみんながそう思ってたわ。もう少しでリンチに遭うところだったのよ。でも、夜になる前に考えが変わって、ジムっていう逃亡黒人がやったんだってことになったの。」
「なぜ彼が――」
俺は口をつぐんだ。黙っていたほうがいいと思ったのだ。女は俺が口を挟んだことにも気づかず、話を続けた。
「その黒人は、ハック・フィンが殺されたまさにその晩に逃げ出したのよ。だから、彼には懸賞金がかけられているわ。三百ドル。それに、年寄りのフィンにも懸賞金がかけられているのよ。二百ドル。ほら、彼は殺人の翌朝町にやってきて、事件のことを話し、渡し船での捜索にも加わっていたのに、その直後に姿を消したの。夜になる前にはみんな彼をリンチにかけたがっていたけど、いなくなってたのよ。まあ、次の日にはその黒人がいなくなったことがわかった。殺人があった夜の十時以降、誰も彼を見ていないことがわかったの。それで、みんな彼のせいだと思ったのよ。で、みんながその話で持ちきりの翌日、年寄りのフィンが戻ってきて、サッチャー判事のところへ泣きつきに行って、イリノイ州中でその黒人を探すための金をもらったの。判事はいくらか金を渡したわ。その晩、彼は酔っぱらって、ものすごく人相の悪い見知らぬ男二人と真夜中過ぎまでうろついて、それからそいつらと一緒に行ってしまったの。まあ、それ以来戻ってきていないし、この騒ぎが少し収まるまでは誰も彼が戻ってくるとは思っていないわ。今では、彼が自分の息子を殺して、強盗の仕業に見せかけたんだって、みんな思っているのよ。そうすれば、長い裁判で面倒な思いをせずにハックの金を手に入れられるからね。みんな、彼ならやりかねないって言ってるわ。ああ、彼はずる賢いと思うわよ。一年も戻ってこなければ、もう大丈夫でしょう。彼に不利な証拠は何もないし、その頃にはすべてが静まって、彼は何でもない顔でハックの金を手に入れるでしょうね。」
「ええ、そうでしょうね。それを邪魔するものは何もないように思います。みんな、もう黒人がやったとは思っていないんですか?」
「ああ、いいえ、みんなじゃないわ。彼がやったと思っている人も大勢いる。でも、もうすぐその黒人も捕まるだろうし、そしたら白状させられるかもしれないわ。」
「え、まだ彼を追っているんですか?」
「まあ、あなたってうぶなのね! 三百ドルが毎日そこらへんに転がっていて、誰でも拾えると思ってるの? その黒人はこの近くにいると思っている人もいるのよ。私もその一人だけど、周りには話していないわ。数日前、隣の丸太小屋に住んでいる老夫婦と話していたら、向こうのジャクソン島っていう島にはほとんど誰も行かないって、たまたま言ってたの。誰も住んでいないんですか、って私が聞いたら、ええ、誰も、って。私はそれ以上何も言わなかったけど、少し考えたの。その一、二日前に、島の北端のあたりで煙が上がっているのを、ほぼ間違いなく見ていたから、自分にこう言ったのよ。たぶん、あの黒人はあそこに隠れているに違いない。どのみち、あの場所を探してみる価値はあるわ、ってね。それ以来煙は見ていないから、もし彼だったとしても、もう行ってしまったのかもしれないけど。でも、夫が見に行くことになっているのよ。彼ともう一人の男とでね。夫は川上に行っていたけど、今日戻ってきて、二時間前にここに着いた途端に私が話したの。」

俺はもう不安でじっとしていられなくなった。何か手で作業をしなければならず、テーブルの上から針を一本取って、糸を通し始めた。手が震え、うまくいかなかった。女が話すのをやめた時、俺が顔を上げると、彼女はかなり興味深そうに俺を見つめ、少し微笑んでいた。俺は針と糸を置き、興味があるふりをした――実際、興味はあったのだが――そして言った。
「三百ドルって大金ですね。母が手に入れられたらいいのに。ご主人は今夜あそこへ行くんですか?」
「ええ、そうよ。さっき話した男と一緒に、ボートと、もう一丁銃を借りられないか見に、町のほうへ行ったわ。真夜中過ぎに行くでしょうね。」
「昼間まで待ったほうが見やすいんじゃないですか?」
「そうね。でも、黒人だって見やすいんじゃない? 真夜中過ぎなら、彼はたぶん眠っているだろうし、森の中をこっそり回って、彼の焚き火を探すには、暗いほうが好都合よ。もし焚き火があればの話だけど。」
「そこまでは考えていませんでした。」
女はかなり興味深そうに俺を見続けており、俺は少しも落ち着かなかった。やがて彼女は言った。
「お名前は何て言ったかしら、お嬢さん?」
「メ……メアリー・ウィリアムズです。」
どうも、前にメアリーと言った覚えがなかったので、俺は顔を上げなかった。サラと言ったような気がしたのだ。だから、なんだか追い詰められたような気分になり、それが顔にも出ているのではないかと不安になった。女がもっと何か言ってくれればいいのに、と思った。彼女が黙っている時間が長ければ長いほど、俺は不安になった。しかし、今、彼女は言った。
「ねえ、最初に来た時はサラって言わなかったかしら?」
「あ、はい、言いました。サラ・メアリー・ウィリアムズです。サラが下の名前で。サラって呼ぶ人もいれば、メアリーって呼ぶ人もいるんです。」
「あら、そういうことなの?」
「はい。」
それで少し気分は良くなったが、それでも早くここから出たかった。まだ顔を上げることができなかった。
さて、その女の人は、世の中がいかに不景気か、自分たちがどれほど貧しい暮らしを強いられているか、ネズミがまるでこの家の主でもあるかのように我が物顔でうろついているか、などといった話を延々と始めたので、俺はまたほっと胸をなでおろした。ネズミの話は本当だった。隅っこの穴から、ひっきりなしに一匹が鼻先を突き出すのが見える。女の人は、一人の時はネズミに何か投げつけるものを手元に置いておかないと、気が休まる暇もないと言った。そして、結び目のようにねじ曲げられた鉛の棒を見せて、普段ならこれで狙いは正確なのだが、一日二日前に腕をひねってしまい、今うまく投げられるかどうか分からない、と言った。それでもチャンスを窺い、いきなり一匹のネズミに投げつけたが、大外れで、「痛っ!」と叫んだ。腕にひどく響いたらしい。それから、次のやつはあんたがやってみな、と言われた。俺は親父が帰ってくる前にずらかりたかったが、もちろんそんなそぶりは見せなかった。鉛の塊を受け取り、最初に鼻を出したネズミに思い切り投げつけると、もしそいつがその場に留まっていたら、相当ひどい目に遭っていただろう。女の人は、お見事だと言い、次はきっと仕留められるだろうと請け合った。彼女は鉛の塊を拾って戻ってくると、手伝ってほしいと言って、一かせの毛糸を持ってきた。俺が両手を挙げると、彼女はその手にかせをかけ、自分と旦那の話を続けた。だが、ふと話を中断してこう言った。
「ネズミから目を離さないで。鉛は膝の上に置いて、すぐ使えるようにしときなさい。」
そう言って彼女が鉛の塊を俺の膝に落としたちょうどその瞬間、俺はそれを両脚でぴしゃりと挟み込んだ。彼女はまた話を続けた。だが、一分ほどだった。それから彼女はかせを外し、俺の顔をまっすぐ見て、とてもにこやかに言った。
「さあ、本当の名前は何て言うんだい?」
「な――なんですって、奥さん?」
「本当の名前は何だい? ビルかい、トムかい、それともボブかい? ――いったい何て名前なんだい?」
俺は木の葉のように震え、どうしていいかほとんど分からなかったと思う。だが、こう言った。
「お願いです、俺みたいな哀れな娘をからかわないでください、奥さん。もしここでお邪魔なら、俺は――」
「いいや、お邪魔じゃないよ。座って、そこにいなさい。あんたを傷つけたりしないし、誰かに言いふらしたりもしない。ただ、あんたの秘密を打ち明けて、私を信じておくれ。秘密は守るよ。それどころか、力になってあげる。うちの亭主だって、あんたが望むならそうするさ。分かってるよ、あんたは逃げてきた徒弟なんだろ、それだけのことさ。たいしたことじゃない。悪いことなんかじゃないんだ。ひどい扱いを受けて、逃げ出す決心をしたんだね。まあ、お前さん、私が言いふらすなんて思うもんじゃないよ。さあ、全部話してごらん、いい子だから。」
それで俺は、もうこれ以上ごまかし続けるのは無駄だと思い、約束を破らないでくれるなら、洗いざらいすべてを白状しようと言った。そして、父も母も死んでしまい、法律で川から三十マイルも奥地の、意地の悪い年寄りの農夫に年季奉公に出されたこと、その農夫の扱いがあまりにひどくて、もう我慢できなかったこと、彼が二、三日家を空けることになったので、その隙に娘の古い服を盗んで逃げ出してきたこと、そしてその三十マイルを三晩かけて歩いてきたことを話した。夜に旅をし、昼間は隠れて眠り、家から持ってきたパンと肉の袋で道中ずっとしのいできたし、食料は十分だった。アブナー・ムーア叔父さんなら面倒を見てくれると思うから、このゴーシェンの町を目指してきたんだ、と俺は言った。
「ゴーシェンだって、坊や? ここはゴーシェンじゃないよ。セント・ピーターズバーグさ。ゴーシェンは川をさらに十マイル上ったところだよ。誰がここをゴーシェンだって言ったんだい?」
「ええと、今朝夜が明ける頃、いつものように森に入って眠ろうとしていた時に会った男です。道が二股に分かれたら右へ行け、五マイル行けばゴーシェンに着く、と。」
「酔っ払ってたんだろうね。まったくのでたらめを教えられたんだよ。」
「ええ、酔ってるみたいでしたけど、もうどうでもいいです。先を急がないと。夜が明ける前にゴーシェンに着きます。」
「ちょっと待ちな。軽食を持たせてあげるよ。欲しくなるかもしれないからね。」

そう言って彼女は軽食を用意してくれ、こう言った。
「ねえ、牛が寝そべっている時、体のどっち側から先に起き上がる? さあ、ぱっと答えて――考え込んじゃだめだよ。どっちが先だい?」
「後ろ足です、奥さん。」
「じゃあ、馬は?」
「前足です、奥さん。」
「木のどっち側に苔が生える?」
「北側です。」
「丘の中腹で十五頭の牛が草を食んでるとしたら、そのうち何頭が同じ方向に頭を向けて食べてる?」
「十五頭全部です、奥さん。」
「ふむ、どうやらあんたは本当に田舎で暮らしてきたようだね。また私をだまそうとしてるのかと思ったよ。さて、本当の名前は何て言うんだい?」
「ジョージ・ピータースです、奥さん。」
「じゃあ、それを覚えておくんだよ、ジョージ。去り際にアレキサンダーだなんて言って、私が問い詰めたらジョージ・アレキサンダーだなんて言い逃れるんじゃないよ。それから、そんな古くさい更紗の服を着て女の人のところへ行くんじゃない。あんたの女装はかなり下手くそだけど、男ならだませるかもしれない。いいかい、坊や、針に糸を通そうとする時はね、糸をじっとさせて針をそれに近づけるんじゃない。針をじっとさせて糸を突っ込むんだ。女の人はたいていそうするけど、男はいつもその逆さ。それから、ネズミか何かに物を投げる時は、つま先立ちになって、できるだけぎこちなく手を頭の上まで振り上げて、ネズミから六、七フィートも外すんだ。女の子みたいに、肩を軸にして腕を棒みたいに振るのさ。男の子みたいに、手首と肘を使って腕を横に振るんじゃない。それから、よくお聞き、女の子が膝で何かを受け止めようとする時は、膝をぱっと開くんだ。あんたが鉛の塊を受け止めた時みたいに、ぴしゃりと閉じたりはしない。まったく、あんたが針に糸を通している時に男の子だって見抜いたよ。他のことは、確かめるためにやってみただけさ。さあ、叔父さんのところへお行き、サラ・メアリー・ウィリアムズ・ジョージ・アレキサンダー・ピータース。もし困ったことがあったら、ジュディス・ロフタス夫人、つまり私のところに知らせをお寄こし。できるだけのことはしてあげるから。ずっと川沿いの道を行くんだよ。次に旅をする時は、靴と靴下を持って行きな。川沿いの道は岩だらけだから、ゴーシェンに着く頃には、あんたの足はひどいことになってるだろうからね。」
俺は土手を五十ヤードほど上り、それから来た道を引き返して、家からかなり下流にあるカヌーの場所までこっそり戻った。カヌーに飛び乗ると、大急ぎで漕ぎ出した。島の先端まで行けるくらい上流へ進み、そこから川を横切り始めた。日よけ帽は脱いだ。もう目隠しはいらなかったからだ。川の真ん中あたりまで来た時、時計が鳴り始めるのが聞こえたので、漕ぐのをやめて耳を澄ませた。音は水面をかすかに、しかしはっきりと伝わってきた――十一時。島の先端に着いた時には息も絶え絶えだったが、一息つく間もなく、かつて俺のキャンプがあった森の中へまっすぐ突っ込み、高くて乾いた場所に焚き火を熾した。
それからカヌーに飛び乗り、一マイル半下流にある俺たちの場所へ、力の限り漕いで向かった。上陸し、森を抜け、尾根を登って洞窟の中へ入った。そこにはジムが地面でぐっすり眠っていた。俺はジムを揺り起こして言った。
「起きろ、さっさと動け、ジム! 一刻の猶予もない。追手が来るぞ!」

ジムは何も尋ねず、一言も口を開かなかった。だが、それから三十分の彼の働きぶりは、彼がいかに怯えているかを物語っていた。その頃には、俺たちがこの世で持っているものすべてがいかだの上にあり、隠してあった柳の入り江からいつでも押し出せる状態になっていた。俺たちはまず洞窟の焚き火を消し、それ以降は外で蝋燭の火ひとつ見せなかった。
俺はカヌーを岸から少し離れたところまで出し、あたりを見回した。だが、もしボートがいたとしても、星の光と影ではよく見えなかっただろう。それから俺たちはいかだを出し、物音ひとつ立てず――一言も交わさず――島の麓を過ぎ、影の中を静かに下っていった。
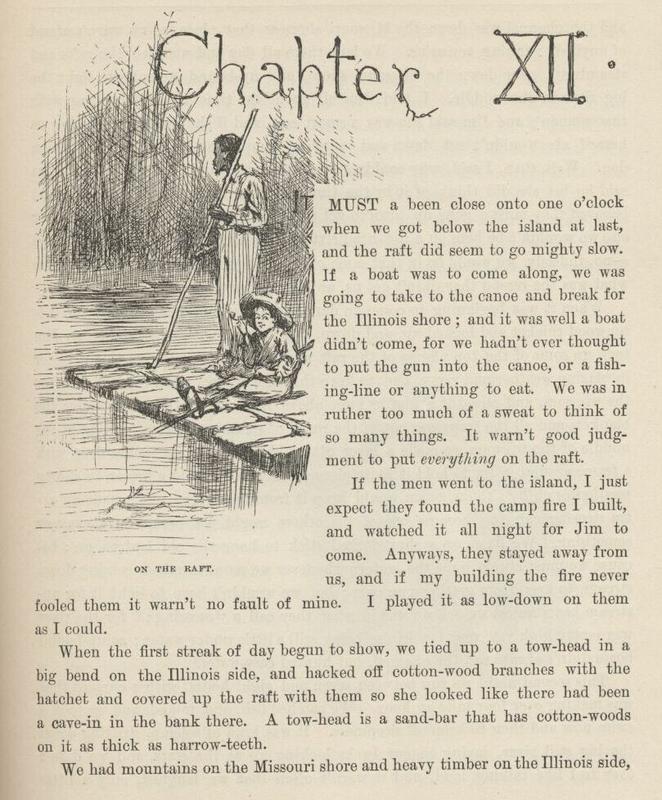
第十二章
ようやく島の麓を抜けたのは、一時近くになっていたに違いない。いかだの進みはひどくのろく感じられた。もしボートが来たら、俺たちはカヌーに乗り移ってイリノイ側の岸へ逃げるつもりだった。ボートが来なくて幸いだった。カヌーに銃や釣り糸、食料の類を何も積んでおくのを考えていなかったからだ。俺たちはあまりに慌てふためいていて、そこまで多くのことを考える余裕がなかった。何もかもいかだの上に置いておくのは、良い判断ではなかった。
もし連中が島へ行ったなら、俺が熾した焚き火を見つけ、ジムが戻ってくるのを一晩中見張っていたことだろう。いずれにせよ、彼らは俺たちに近づかなかったし、もし俺の焚き火が彼らを騙せなかったとしても、それは俺のせいじゃない。俺はできる限りの手を尽くしてやったのだ。
夜明けの最初の光が見え始めた頃、俺たちはイリノイ側の大きな川の湾曲部にある流木島にいかだを繋いだ。そして斧でハコヤナギの枝を切り落とし、いかだを覆い隠して、まるで岸が崩れたかのように見せかけた。流木島というのは、ハコヤナギが馬鍬の歯のように密集して生えている砂州のことだ。
ミズーリ側の岸には山々が連なり、イリノイ側には鬱蒼とした森が広がっていた。その場所では、航路はミズーリ側の岸に沿っていたので、誰かに見つかる心配はなかった。俺たちは一日中そこに横たわり、いかだや蒸気船がミズーリ側の岸を下っていくのを眺め、上流へ向かう蒸気船が川の中央で大河と格闘するのを見ていた。俺はあの女の人としゃべっていた時のことを洗いざらいジムに話した。ジムは、あの女の人は賢い人だ、もしあの人が自分で俺たちを追いかけてきたら、焚き火を見つけて座り込んで見張ったりはしないだろう――いや、絶対にしない、犬を連れてくるだろう、と言った。じゃあ、なんで旦那に犬を連れてくるように言えなかったんだろうな、と俺が言うと、ジムは、男たちが準備を整える頃にはきっとそのことを思いついただろう、だから町まで犬を調達しに行って、それで時間を無駄にしたに違いない、そうでなきゃ俺たちは村から十六、七マイルも下流のこの流木島にはいないはずだ――いや、まったくだ、俺たちはまたあの古びた町に逆戻りしていただろう、と言った。それで俺は、捕まらなかった限り、連中が俺たちを捕まえられなかった理由なんてどうでもいい、と言った。
あたりが暗くなり始めた頃、俺たちはハコヤナギの茂みから頭を出し、川の上流、下流、そして対岸を見渡した。何も見えない。そこでジムはいかだの甲板の板を何枚か持ち上げ、日差しが強い日や雨の日に潜り込むための、こぢんまりとした小屋を建て、持ち物を乾いた状態に保てるようにした。ジムは小屋に床を作り、いかだの水平面から一フィートかそこら高くしたので、毛布や道具類はすべて蒸気船の波が届かない場所になった。小屋の真ん中には、ずれないように枠で囲って、五、六インチの深さの土の層を作った。これは、じめじめした天気や肌寒い時に火を熾すためのもので、小屋があれば火が見られるのを防げる。俺たちは予備の操舵用の櫂も一本作った。他の櫂が流木か何かにぶつかって折れるかもしれないからだ。古いランタンを吊るすために、短い二股の枝も取り付けた。下流から蒸気船が来るのを見たら、轢かれないように必ずランタンを灯さなければならなかったからだ。だが、上流へ向かう船に対しては、いわゆる「横断水路」にいると分かった時以外は灯す必要はなかった。川はまだかなり増水していて、低い岸はまだ少し水面下にあったので、上流へ向かう船は必ずしも航路を通らず、流れの緩やかな場所を探して進んでいたからだ。
二日目の夜、俺たちは時速四マイル以上の流れに乗って、七時間から八時間ほど進んだ。魚を捕まえたり、話をしたり、眠気を覚ますために時々泳いだりした。静かな大河を漂っていくのは、どこか荘厳な気分だった。俺たちは仰向けに寝転んで星空を見上げ、大声で話したいとは決して思わなかったし、笑うこともめったになかった――ただ、くすくすと低い笑い声を立てるだけだった。天気はおおむね非常に良く、その夜も、次の夜も、そのまた次の夜も、俺たちには何も起こらなかった。
毎晩、俺たちは町を通り過ぎた。中には黒々とした丘の中腹のはるか上にある町もあり、きらめく光の塊が見えるだけで、家一軒見えなかった。五日目の夜、俺たちはセントルイスを通過したが、それはまるで全世界が照らし出されているかのようだった。セント・ピーターズバーグでは、セントルイスには二万か三万の人がいるとよく言われていたが、あの静かな夜中の二時に、あの見事な光の広がりを見るまで、俺はそれを信じたことがなかった。そこには物音一つなく、誰もが眠っていた。
今では毎晩、十時頃になるとどこかの小さな村でこっそり岸に上がり、十セントか十五セント分のトウモロコシ粉やベーコンなどの食料を買っていた。そして時には、居心地悪そうに止まり木に止まっている鶏を一羽拝借して、連れて行くこともあった。パップはいつも言っていた。「チャンスがあったら鶏を持っていけ。自分がいらなくても、欲しがるやつはすぐに見つかる。それに、良い行いは決して忘れられないもんだ」と。パップが自分で鶏を欲しがらなかったことなんて一度もなかったが、とにかくいつもそう言っていた。

朝、夜が明ける前に、俺はトウモロコシ畑に忍び込み、スイカやマスクメロン、カボチャ、あるいは採れたてのトウモロコシなどを拝借した。パップはいつも、いつか返すつもりなら物を借りるのは悪いことじゃない、と言っていた。だが、未亡人は、それは盗みの言い訳に過ぎず、まともな人間ならそんなことはしない、と言っていた。ジムは、未亡人も一部は正しく、パップも一部は正しいと思う、と言った。だから、一番良い方法は、リストの中から二つか三つを選んで、もうそれらは拝借しないことにする――そうすれば、残りを拝借しても悪いことにはならないだろう、と彼は考えた。そこで俺たちは、川を下りながら一晩中そのことについて話し合い、スイカをやめるか、カンタロープをやめるか、マスクメロンをやめるか、それとも何をやめるか、決めようと試みた。だが、夜が明ける頃には、すべてが満足のいく形で決着し、クラブアップルとカキをやめることにした。それまではどうも気分がすっきりしなかったが、今ではすっかり安心した。俺もその結果に満足だった。クラブアップルは決しておいしくないし、カキが熟すのはまだ二、三ヶ月先だったからだ。
時々、朝早く起きすぎたり、夜遅くまで寝なかったりする水鳥を撃ち落とした。総じて、俺たちはかなり贅沢な暮らしをしていた。
セントルイスから下って五日目の夜、真夜中過ぎに大嵐に見舞われ、ものすごい雷鳴と稲妻が轟き、雨は一枚のシートのように降り注いだ。俺たちは小屋の中に留まり、いかだは流れに任せた。稲妻が閃くと、前方にまっすぐな大河と、両岸にそびえる高い岩の崖が見えた。やがて俺は言った。「おい、ジム、あれを見ろ!」それは、岩に乗り上げて難破した蒸気船だった。俺たちはまっすぐそこに向かって漂っていた。稲妻がその姿をはっきりと照らし出した。船は傾き、上甲板の一部が水面上に出ていて、閃光が走るたびに、小さな煙突の支索一本一本がくっきりと見え、大きな鐘のそばには椅子があり、その背もたれには古びたつば広の帽子が掛かっていた。
さて、夜も更け、嵐の中、すべてが神秘的な雰囲気だったので、川の真ん中でそんなにも悲しげに、寂しげに横たわる難破船を見た時、俺は他のどんな少年も感じただろう気持ちになった。その船に乗り込んで、少しうろついてみて、そこに何があるのか確かめたくなった。そこで俺は言った。
「あれに上陸しようぜ、ジム。」
だが、ジムは最初、断固として反対した。彼は言った。
「わしは難破船なんかにかかわりとうない。わしら、ええ塩梅にやっとるんや。聖書にもあるように、ええ塩梅のままにしとくのが一番や。あんな難破船には見張りがおるに決まっとる。」
「見張りだなんて、ばあさんの話でもあるまいし」と俺は言った。「見張るものなんて、船室区画と操舵室くらいのもんだ。こんな夜に、いつ壊れて川下に流されるか分からないっていうのに、船室区画と操舵室のために命を懸けるやつがいると思うか?」ジムはそれに何も言い返せなかったので、言い返そうともしなかった。「それに」と俺は続けた。「船長の船室から、何か値打ちのあるものを拝借できるかもしれないぞ。葉巻だ、きっと――一本五セントもする、現金払いのやつだ。蒸気船の船長はいつも金持ちで、月に六十ドルも稼ぐんだ。欲しいものなら、それがいくらしようがびた一文気にしないんだぜ。ポケットに蝋燭を一本突っ込んでおけ。あそこをくまなく探すまで、俺は落ち着けないんだ、ジム。トム・ソーヤーがこんなものを見て素通りすると思うか? 絶対にしないさ。彼はこれを冒険と呼ぶだろう――そう呼ぶに違いない。そして、たとえそれが最後の行動になったとしても、あの難破船に上陸するだろう。それに、彼はそれをどれだけ格好良くやるだろうか? ――自分をひけらかしたり、何かしでかしたりしないだろうか? まるでクリストファー・コロンブスが天国を発見したかのように大騒ぎするだろう。トム・ソーヤーがここにいたらなあ。」
ジムは少しぶつぶつ言ったが、折れた。彼は、できるだけ話さないようにして、話す時もひどく低い声で話さなければならない、と言った。ちょうどその時、稲妻が再び難破船を照らし出し、俺たちは右舷のデリックにたどり着き、そこにいかだを繋いだ。
ここの甲板はかなり高かった。俺たちは左舷へ向かって、暗闇の中、甲板の傾斜をこっそりと下りていった。船室区画を目指し、足でゆっくりと道を探りながら、両手を広げて支索をよけた。あまりに暗くて、支索の気配すら見えなかったからだ。やがて俺たちは天窓の前端にぶつかり、その上に這い上がった。そして次の一歩で船長のドアの前に出たが、ドアは開いていた。そして驚いたことに、船室区画の廊下のずっと奥に、光が見えた! そしてまさにその同じ瞬間に、向こうから低い声が聞こえてくるようだった!
ジムは囁き声で、ひどく気分が悪いと言い、一緒に行こうと俺に言った。俺は分かったと言い、いかだへ向かおうとした。だが、ちょうどその時、ある声が泣き叫ぶように言うのが聞こえた。
「ああ、お願いだ、やめてくれ。絶対に言わないと誓うから!」
別の声が、かなり大きな声で言った。
「嘘つけ、ジム・ターナー。お前は前にもそんな態度をとった。いつも分け前より多くを欲しがり、いつもそれを手に入れてきた。手に入れなきゃ言いふらすと脅してきたからな。だが今回は、その脅し文句を一回多く言い過ぎたようだな。お前はこの国で一番卑劣で、裏切り者のクソ野郎だ。」
この時までに、ジムはいかだへ向かっていた。俺は好奇心で煮えくり返りそうだった。そして自分に言い聞かせた。「トム・ソーヤーなら今さら引き返さない。だから俺も引き返さない。ここで何が起こっているのか見てやるんだ」と。そこで俺は小さな通路で四つん這いになり、暗闇の中を船尾の方へ這っていき、俺と船室区画の横廊下との間に船室が一つだけになるまで進んだ。するとその中で、床に手足を縛られて伸びている男と、その上に立つ二人の男が見えた。一人は薄暗いランタンを手に持ち、もう一人はピストルを持っていた。ピストルを持った男は、床の男の頭にそれを向け続けながら言った。
「やってやりてえよ! そうすべきでもある――卑劣なスカンク野郎め!」

床の男は身を縮こまらせて言った。「ああ、お願いだ、ビル、やめてくれ。もう二度と言わないから。」
そして彼がそう言うたびに、ランタンを持った男が笑って言った。
「本当にそうだろうな! お前が言った中で、それ以上に真実なことはないぜ、賭けてもいい」そして一度、こう言った。「こいつの命乞いを聞け! それでも、もし俺たちがこいつを出し抜いて縛り上げていなかったら、俺たち二人とも殺されていただろう。いったい何のために? 何のためでもない。ただ俺たちが自分たちの権利を主張したからだ――それが理由だ。だが、お前はもう二度と誰も脅せなくなるだろうぜ、ジム・ターナー。そのピストルをしまえ、ビル。」
ビルは言った。
「嫌だね、ジェイク・パッカード。俺はこいつを殺すつもりだ――それに、こいつは昔のハットフィールドを同じように殺したじゃないか――殺されて当然だろ?」
「だが俺はこいつを殺したくない。それには理由があるんだ。」
「その言葉、ありがてえ、ジェイク・パッカード! 生きてる限り、あんたのことは忘れねえ!」と床の男は、むせび泣くように言った。
パッカードはそれに気づかないふりをして、ランタンを釘に引っ掛けると、暗闇の中にいる俺の方へ歩き始め、ビルに来るように合図した。俺はできるだけ速く二ヤードほど後ずさりしたが、船が傾いていたので、あまり速くは動けなかった。轢かれて捕まるのを避けるため、俺は上側の船室に這い込んだ。男は暗闇の中を手探りで進んできて、パッカードが俺の船室に着くと、言った。
「おい――ここに入れ。」
そして彼が入り、ビルが続いた。だが彼らが入る前に、俺は上段の寝台の隅に追い詰められ、来てしまったことを後悔していた。それから彼らはそこに立ち、寝台の縁に手を置いて話をした。彼らの姿は見えなかったが、飲んでいたウイスキーの匂いでどこにいるかは分かった。俺はウイスキーを飲まなくてよかったと思った。だが、どちらにしても大して変わりはなかっただろう。ほとんどの時間、俺は息をしていなかったので、彼らは俺を見つけられなかったはずだ。あまりに怖かったのだ。それに、あんな話を聞きながら息をすることなど、誰にもできなかっただろう。彼らは低く、真剣な声で話した。ビルはターナーを殺したがっていた。彼は言った。
「あいつは言いふらすと言った。そして、きっと言うだろう。今、俺たちの分け前を両方ともあいつにやったとしても、この騒ぎと俺たちの仕打ちの後では、何の違いもない。お前が生まれてきたのと同じくらい確かだ、あいつは州の証人になる。いいか、俺の言うことを聞け。俺はあいつを楽にしてやるつもりだ。」
「俺もだ」とパッカードは、とても静かに言った。
「ちくしょう、お前はそうじゃないのかと思い始めてたところだ。まあ、それならいい。行って、やっちまおう。」
「ちょっと待て。俺はまだ言い分を言っちゃいない。俺の話を聞け。撃つのはいいが、もしやらなきゃならないなら、もっと静かな方法がある。だが俺が言いたいのはこうだ。同じくらいうまくいって、同時に何の危険も伴わない方法で目的を達成できるなら、わざわざ絞首刑になるような真似をするのは賢明じゃない。そうじゃないか?」
「その通りだ。だが今回はどうするつもりだ?」
「まあ、俺の考えはこうだ。そこらをかき回して、船室で見落とした獲物を集め、岸へ向かってその荷を隠す。それから待つんだ。いいか、この難破船が壊れて川下に流されるまで、二時間もかからないだろう。分かったか? あいつは溺れ死ぬ。そして、誰も責める相手はいない、自分自身以外にはな。それは、あいつを殺すより、かなりましなやり方だと思う。俺は、避けられる限りは人殺しには反対なんだ。賢明じゃないし、道徳的にも良くない。俺は正しいだろ?」
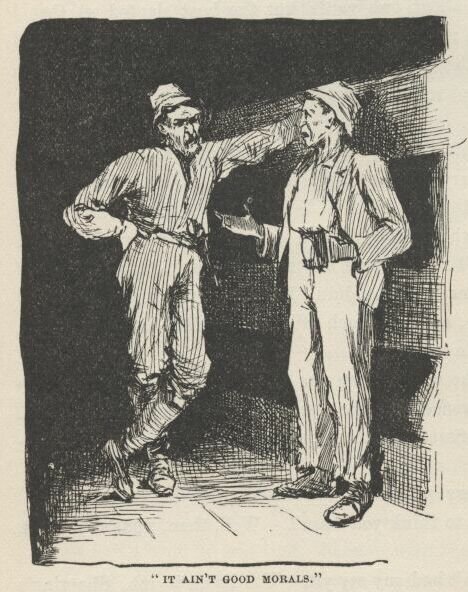
「ああ、そう思うぜ。だが、もし船が壊れて流されなかったらどうする?」
「まあ、とにかく二時間は待って様子を見ることができるだろ?」
「分かった。じゃあ、行こう。」
そうして彼らは出発し、俺は冷や汗をだらだら流しながら飛び出し、船首の方へ急いだ。そこは漆黒の闇だった。だが俺は、一種のしわがれた囁き声で、「ジム!」と呼びかけた。すると彼は、うめき声のような声で、すぐ肘のあたりで返事をした。俺は言った。
「急げ、ジム、ふざけたりうめいたりしてる場合じゃない。向こうに人殺しのギャングがいるんだ。もし俺たちが奴らのボートを探し出して、川下に流してやらなきゃ、奴らはこの難破船から逃げられない。そしたら、奴らのうちの一人がひどい目に遭うことになる。だが、奴らのボートを見つけられれば、奴ら全員をひどい目に遭わせることができる――保安官が捕まえてくれるからな。急げ――早く! 俺は左舷側を探す。お前は右舷側を探せ。いかだのところから始めて――」
「ああ、かなわん、かなわん! いかだ? いかだはもうありまへん! 綱が切れて流されてしもた! わしら、ここに置き去りや!」
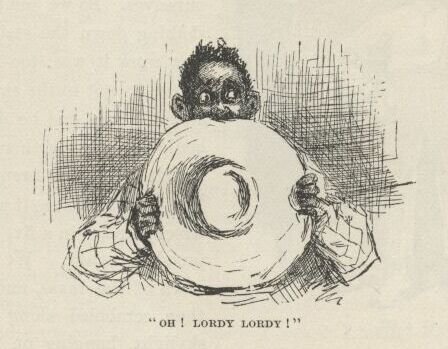
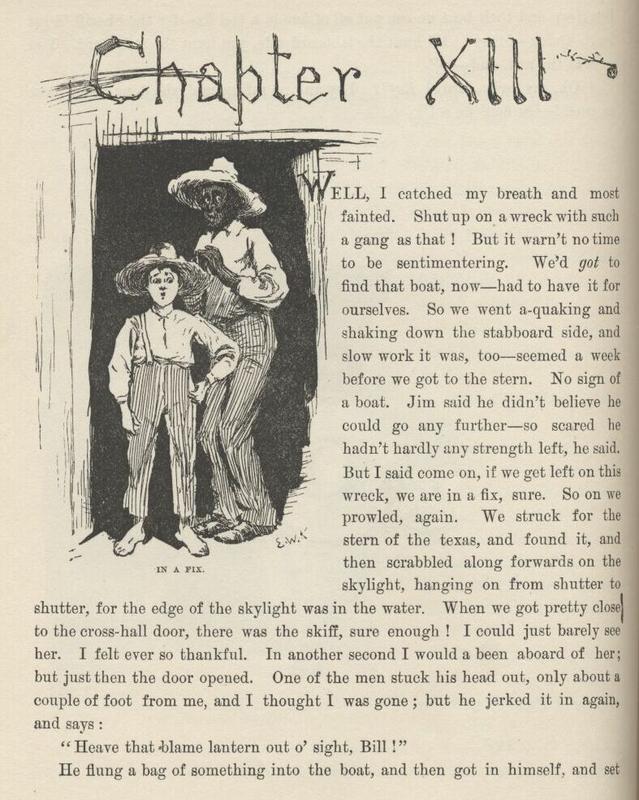
第十三章
さて、俺は息を呑み、ほとんど気を失いそうになった。あんな連中と一緒に難破船に閉じ込められるなんて! だが、感傷に浸っている場合ではなかった。今すぐあのボートを見つけなければならなかった――自分たちのために、それが必要だったのだ。そこで俺たちは、がたがた震えながら右舷側を下っていった。それは遅々とした作業で、船尾に着くまで一週間もかかったように思えた。ボートの気配はない。ジムは、もうこれ以上は進めないと思うと言った――あまりに怖くて、ほとんど力が残っていない、と。だが俺は、来い、もしこの難破船に取り残されたら、俺たちは間違いなく窮地に陥る、と言った。そこで俺たちは再びうろつき始めた。船室区画の船尾を目指し、それを見つけた。それから天窓の上を、鎧戸から鎧戸へとしがみつきながら前へ進んだ。天窓の縁は水に浸かっていたからだ。横廊下のドアにかなり近づいた時、確かに小舟があった! かろうじてそれが見えた。俺は心から感謝した。もう一秒後にはそれに乗り込んでいただろう。だが、ちょうどその時、ドアが開いた。男の一人が、俺から二フィートほどのところに頭を突き出した。俺はもうだめだと思った。だが彼はすぐに頭を引っ込め、言った。
「その忌々しいランタンを見えないところにやれ、ビル!」
彼は何か入った袋をボートに放り込み、それから自分も乗り込んで腰を下ろした。パッカードだった。それからビルも出てきて乗り込んだ。パッカードは低い声で言った。
「準備よし――押し出せ!」
俺はあまりに力が抜けて、鎧戸にほとんどしがみついていられなかった。だがビルは言った。
「待て――あいつの懐を探ったか?」
「いや。お前は?」
「いや。じゃあ、あいつはまだ金の分け前を持ってるな。」
「まあ、それなら来い。荷物だけ取って金を残しておく手はない。」
「おい、あいつ、俺たちが何を企んでるか怪しまないか?」
「多分な。だが、どっちにしろ手に入れなきゃならん。来い。」
そうして彼らは出て、中へ入っていった。
ドアは傾いている側にあったので、ばたんと閉まった。そして半秒後には、俺はボートの中にいた。ジムが俺の後に転がり込んできた。俺はナイフを抜き、ロープを切り、そして俺たちは出発した!
俺たちはオールには触れず、話さず、囁かず、ほとんど息さえしなかった。俺たちは、パドルボックスの先端を過ぎ、船尾を過ぎ、死んだように静かに、滑るように素早く進んだ。そして一、二秒後には、俺たちは難破船から百ヤード下流におり、闇がその最後の痕跡まで飲み込み、俺たちは安全で、それを知っていた。
三百か四百ヤード下流まで来た時、船室区画のドアのところでランタンが小さな火花のように一瞬光るのが見えた。それで俺たちは、あの悪党どもが自分たちのボートを見失い、今やジム・ターナーと同じくらい困った状況にあることを理解し始めたのだと分かった。
それからジムがオールを握り、俺たちはいかだを追いかけた。男たちのことを心配し始めたのは、この時が初めてだった――それまでは時間がなかったのだと思う。人殺しでさえ、あんな状況に陥るのはなんて恐ろしいことだろう、と考え始めた。俺は自分に言い聞かせた。「いつか俺自身が人殺しになるかもしれない。そしたら、俺はどう思うだろう?」と。そこで俺はジムに言った。
「最初に見える灯りの百ヤード下流か上流で、お前と小舟にとって良い隠れ場所になるところに上陸しよう。それから俺が行って、何かしらの作り話をして、誰かにあのギャングを助けに行ってもらって、彼らを窮地から救い出すんだ。そうすれば、時が来た時に絞首刑にできる。」
だが、その考えは失敗に終わった。すぐにまた嵐が始まり、今度は前よりもひどかったからだ。雨は降り注ぎ、灯りは一つも見えなかった。誰もが寝ていたのだろう。俺たちは川を轟音を立てて下り、灯りを探し、いかだを探した。長い時間が経って雨は小降りになったが、雲は残り、稲妻が弱々しく光り続けていた。やがて閃光が、前方に浮かぶ黒いものを照らし出し、俺たちはそれに向かった。
それはいかだだった。再びそれに乗り込めて、俺たちはひどく喜んだ。今度は、ずっと下流の右手の岸に灯りが見えた。そこで俺はそこへ行くと言った。小舟は、あのギャングが難破船で盗んだ戦利品で半分ほど埋まっていた。俺たちはそれをいかだの上に山積みにし、ジムにはそのまま下流へ流れ、二マイルほど進んだと思ったら灯りを見せ、俺が来るまでそれを燃やし続けるように言った。それから俺はオールを握り、灯りを目指して漕ぎ出した。それに近づくにつれて、三つか四つ、さらに灯りが現れた――丘の中腹に。それは村だった。俺は岸の灯りの上流に近づき、オールを休めて流れに身を任せた。通り過ぎる時、それが双胴の渡し船の旗竿に吊るされたランタンだと分かった。俺は、見張り番はどこで寝ているのだろうと思いながら、あたりをうろついた。やがて、船首のビットに、頭を両膝の間にうずめて止まり木に止まるように眠っている彼を見つけた。俺は彼の肩を二、三度軽く揺すり、泣き始めた。
彼は、驚いたように身じろぎした。だが、それが俺だけだと分かると、大きくあくびをして伸びをし、それから言った。
「やあ、どうした? 泣くな、坊主。何があったんだ?」

俺は言った。
「父さんと、母さんと、姉さんと、それから――」
そして俺は泣き崩れた。彼は言った。
「ああ、ちくしょう、そんなに嘆くな。誰にだって悩みはあるもんだ。これもきっとうまくいくさ。彼らに何があったんだ?」
「彼らは――彼らは――あなたはこの船の見張り番ですか?」
「ああ」と彼は、かなり満足げな様子で言った。「俺は船長で、船主で、航海士で、操舵手で、見張り番で、甲板長だ。時には貨物や乗客にもなる。俺は昔のジム・ホーバックほど金持ちじゃないし、彼のように誰彼構わず気前よく親切にはできないし、彼のように金をばらまいたりはできない。だが、俺は何度も彼に言ってきたんだ。俺はあんたと立場を交換したくはない、と。なぜなら、船乗りの人生こそ俺の人生だからだ、と俺は言うんだ。町から二マイルも離れた、何も起こらないような場所に住むなんて、彼の全財産とその倍の金を積まれてもごめんだね、と。俺は言うんだ――」
俺は割り込んで言った。
「彼らはひどい窮地に陥ってるんです、そして――」
「誰がだ?」
「父さんと、母さんと、姉さんと、フッカーさんです。もしあなたの渡し船であそこへ行ってくれたら――」
「どこへ? 彼らはどこにいるんだ?」
「難破船です。」
「どの難破船だ?」
「ええと、一つしかありません。」
「なんだって、ウォルター・スコット号のことじゃないだろうな?」
「はい。」
「なんてこった! いったいそこで何をしてるんだ、まったく?」
「ええと、わざわざそこへ行ったわけじゃないんです。」
「そうだろうとも! なんてこった、すぐにそこから離れなきゃ、助かる見込みはないぞ! いったいどうしてそんな目に遭ったんだ?」
「簡単なことです。フッカーさんが、あそこの町を訪ねていて――」
「ああ、ブースズ・ランディングだな――続けろ。」
「彼女はブースズ・ランディングを訪ねていて、ちょうど夕暮れ時、友人の――ええと名前は忘れました――家に一晩泊まるために、黒人の女中と一緒に馬渡し船で渡り始めたんです。ところが、操舵用の櫂を失くしてしまい、ぐるぐる回って、船尾から先に二マイルほど流され、難破船に馬乗りになってしまったんです。船頭と黒人の女中と馬はみんな助からなかったんですが、フッカーさんはなんとか難破船に掴まって乗り移ったんです。さて、暗くなってから一時間ほどして、俺たちが商売用の平底船で下ってきて、あまりに暗かったので、真上にくるまで難破船に気づかなかったんです。それで俺たちも馬乗りになってしまいました。でも、ビル・ウィップル以外はみんな助かりました――ああ、彼は本当にいいやつだった! ――いっそ俺だったらよかったのに、本当に。」
「なんてこった! こんなひどい話は聞いたことがない。それで、あんたたちはどうしたんだ?」
「ええと、俺たちは叫んだりわめいたりしたんですが、あそこは川幅が広すぎて、誰にも聞こえませんでした。それで父さんが、誰かが岸に上がってどうにか助けを呼ばなきゃならない、と言ったんです。泳げるのは俺だけだったので、俺が決死の覚悟で飛び込みました。フッカーさんは、もしもっと早く助けが見つからなかったら、ここへ来て彼女の叔父さんを探せ、彼が何とかしてくれるだろう、と言いました。俺は一マイルほど下流で陸に上がり、それからずっと、人々に何とかしてもらおうと駆けずり回っていたんですが、みんな、『なんだ、こんな夜に、こんな流れの中で? 正気の沙汰じゃない。蒸気渡し船に行け』と言うんです。今、もしあなたが行ってくれたら――」
「ジャクソンにかけて、行きたいもんだ。ちくしょう、行くべきかもしれねえ。だが、いったい誰がその金を払うんだ? あんたの親父さんが――」
「ああ、それは大丈夫です。フッカーさんが、特に、彼女の叔父さんのホーバックさんが――」
「なんてこった! 彼が彼女の叔父さんなのか? おい、あそこの向こうの灯りを目指して走れ。そこに着いたら西へ曲がって、四分の一マイルほど行くと酒場がある。ジム・ホーバックのところへ急いで連れて行ってもらえ、と伝えろ。彼が代金を払ってくれる。ぐずぐずするなよ、彼は知らせを聞きたがるだろうからな。彼が町に着く前に、姪御さんは無事に助けておくと伝えてくれ。さあ、急げ。俺はここの角を曲がって、機関士を起こしてくる。」
俺は灯りを目指して走り出したが、彼が角を曲がるやいなや、引き返して自分の小舟に戻り、水を汲み出し、それから流れの緩やかな場所で岸を六百ヤードほど上り、何艘かの木材運搬船の間に身を隠した。渡し船が出発するのを見るまで、落ち着けなかったからだ。だが、総じて、あのギャングのためにこれだけの面倒をかけたことで、俺はかなり心地よい気分だった。こんなことをする人間はそう多くはないだろう。未亡人がこのことを知ってくれたらいいのに、と思った。彼女なら、俺がこんないたずら者たちを助けたことを誇りに思ってくれるだろうと俺は判断した。いたずら者やろくでなしこそ、未亡人や善良な人々が最も関心を持つ類いの人間だからだ。
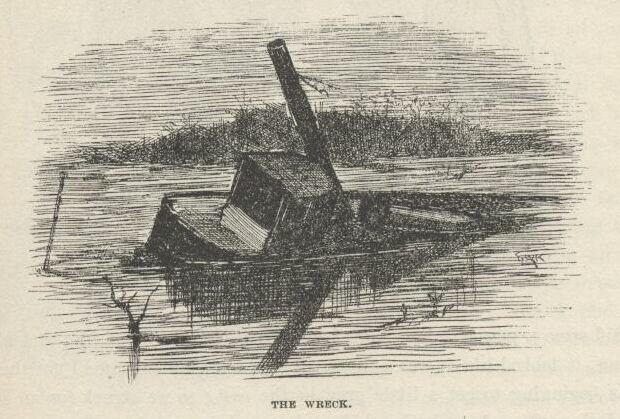
さて、間もなく、難破船が薄暗く、ぼんやりと、川を下って流れてきた! 俺の体を一種の冷たい震えが走り抜け、それから俺はそれに向かって漕ぎ出した。船はひどく沈んでいて、中にいる誰かが生きている見込みはほとんどないと、すぐに分かった。俺は船の周りをぐるりと回り、少し叫んでみたが、返事はなかった。すべてが死んだように静かだった。あのギャングのことを思うと、少し気が重くなったが、それほどでもなかった。彼らが耐えられるなら、俺も耐えられるだろう、と俺は考えたからだ。
そこへ渡し船がやって来た。そこで俺は、川の中央に向かって、下流へ長く斜めに漕ぎ出した。そして、視界から外れたと判断した時、オールを休め、振り返って、渡し船が難破船の周りを嗅ぎ回るのを見た。船長は、フッカーさんの叔父さんであるホーバック氏が彼女の遺体を欲しがるだろうことを知っていたからだ。それから間もなく、渡し船は諦めて岸へ向かい、俺は自分の仕事に取り掛かり、轟音を立てて川を下っていった。
ジムの灯りが現れるまで、ひどく長い時間がかかったように思えた。そして現れた時、それは千マイルも離れているように見えた。俺がそこに着く頃には、東の空が少し白み始めていた。そこで俺たちは島を目指し、いかだを隠し、小舟を沈め、死んだように眠りについた。
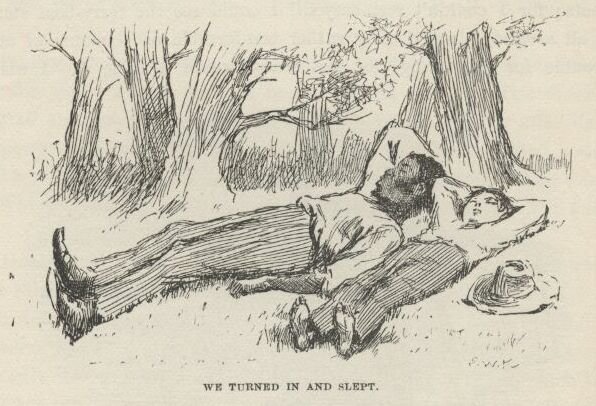
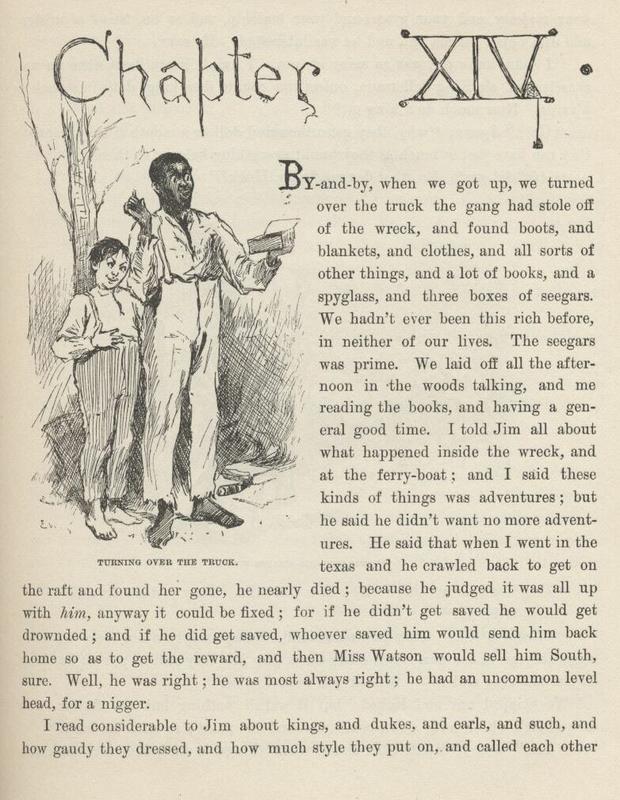
第十四章
やがて、俺たちが起きると、あのギャングが難破船から盗んだ荷物をひっくり返してみた。すると、ブーツや毛布、服、その他ありとあらゆるもの、そしてたくさんの本と望遠鏡、葉巻三箱が見つかった。俺たちは二人とも、生まれてこのかた、これほど金持ちになったことはなかった。葉巻は極上品だった。俺たちは午後中ずっと森の中で横になり、話をしたり、俺が本を読んだりして、総じて楽しい時間を過ごした。俺はジムに、難破船の中と渡し船で起こったことを洗いざらい話した。そして、こういうのが冒険なんだ、と言った。だが彼は、もう冒険はごめんだ、と言った。俺が船室区画に入っていき、彼がいかだに戻ろうと這い戻って、それがないと分かった時、彼はほとんど死にそうになった、と言った。どう転んでも、もう自分はおしまいだと思ったからだ。もし助からなければ溺れ死ぬだろうし、もし助かったとしても、助けてくれた人は誰であれ、褒美をもらうために彼を故郷に送り返すだろう。そうすれば、ミス・ワトソンはきっと彼を南部に売ってしまうだろう、と。まあ、彼は正しかった。彼はほとんどいつも正しかった。黒人にしては、彼は並外れて冷静な頭を持っていた。
俺はジムに、王様や公爵や伯爵などについて、彼らがどれほど派手な服を着て、どれほど気取っていて、「ミスター」の代わりに互いを「陛下」とか「閣下」とか「卿」とか呼び合うことについて、かなり読み聞かせた。ジムは目を丸くして、興味を示した。彼は言った。
「そんなにようさんおるとは知りまへんでした。わしが聞いたことあるんは、昔のソロモンはんくらいのもんで、トランプの札におる王様を数えへんかったらな。王様はどれくらいもらえるんや?」
「もらう?」と俺は言った。「なんだって、欲しけりゃ月に千ドルはもらえるさ。欲しいだけもらえるんだ。何もかもが彼らのものなんだから。」
「そらええなあ! ほんで、何せなあかんのや、ハック?」
「何もしないんだよ! なんだって、そんなこと言うんだ! ただ座ってるだけさ。」
「いや、ほんまかいな?」
「もちろんさ。ただ座ってるだけ――まあ、戦争がある時以外はな。そん時は戦争に行く。だが他の時は、ただぶらぶらしてるだけさ。それか鷹狩りに行く――ただ鷹狩りして、それから――しっ! ――何か物音が聞こえなかったか?」
俺たちは飛び出して見てみたが、それはずっと下流の方で、岬を回ってくる蒸気船の車輪の羽音に過ぎなかった。それで俺たちは戻ってきた。
「ああ」と俺は言った。「それから他の時、退屈な時は、議会とごちゃごちゃやるんだ。そして、もしみんなが言うことを聞かなきゃ、首をはねちまう。だが、たいていはハーレムでぶらぶらしてる。」
「どこでぶらぶら?」
「ハーレムだ。」
「ハーレムてなんや?」

「彼が奥さんたちを置いておく場所だよ。ハーレムを知らないのか? ソロモンは一つ持ってた。百万人の奥さんがいたんだ。」
「ああ、そうやったな。わし――わし、忘れてしもうとったわ。ハーレムいうんは、下宿屋みたいなもんやろな。たぶん、子供部屋では大騒ぎやろ。ほんで、奥さんたちもようけ喧嘩するやろし、そんで騒ぎが大きくなる。それでも、ソロモンはんは今まで生きた中で一番賢い人やて言われとる。わしはそんなもん信用しまへんわ。なんでかって? 賢い人が、そんなガンガンうるさい中でずっと暮らしたいと思うか? いや――思うわけないわ。賢い人やったら、ボイラー工場を建てるやろ。そしたら、休みたい時にボイラー工場を止められるからな。」
「でも、とにかく彼は一番賢い男だったんだ。未亡人がそう言ってたんだから、彼女自身の口から。」
「未亡人が何て言おうがかまへんわ。彼は賢い人なんかやなかった。わしが見た中で、一番どえらいやり方をする人やった。あの子を真っ二つに切り裂こうとした話を知っとるか?」
「ああ、未亡人が全部話してくれたよ。」
「ほな、ええか! それが世界一のとんでもない考えやなかったか? ちょっと考えてみい。そこに切り株がある――それが女の一人や。ここにあんたがおる――それがもう一人や。わしがソロモンはん。ほんで、この一ドル札が子供や。あんたら二人とも、これが自分のものやと主張する。わしはどうする? まともな知恵があるやつなら誰でもするように、近所を駆けずり回って、この札がどっちのもんか突き止めて、正しい方に無事に渡すか? いや、わしはこの札を真っ二つに切り裂いて、半分をあんたに、もう半分をもう一人の女にやるんや。それがソロモンはんが子供にしようとしたことや。さて、あんたに聞きたいんやが、半分の札に何の使い道がある? それじゃ何も買えへん。ほんで、半分の子供に何の使い道がある? わしやったら、百万あってもびた一文の値打ちもないわ。」
「でも、ちくしょう、ジム、お前は完全に要点を見逃してる――ちくしょう、千マイルも見当違いだ。」
「誰がや? わしか? あっち行け。わしにあんたの理屈を言うな。わしは、分別っちゅうもんは見りゃ分かる。あんなやり方に分別なんかないわ。争いは半分の子供についてやなかった、争いは丸一人の子供についてやったんや。ほんで、丸一人の子供についての争いを、半分の子供で解決できると思うようなやつは、雨宿りする知恵もないわ。わしにソロモンはんの話をするな、ハック。わしはあいつのことならよう知っとるわい。」

「でも、お前は要点を分かってないって言ってるんだ。」
「そんな論点なんか知るかいな! わいは自分の知っとることを知っとるんや。ええか、ほんまの論点はもっと下や、もっと深いとこにあるんやで。ソロモンはんの育てられ方に問題があるんや。子どもが一人か二人しかおらん男を考えてみい。そないな男が子どもを無駄遣いするやろか? いや、せえへん。でけへんのや。子どもらの価値っちゅうもんをよう分かっとる。せやけど、家に五百万人くらいの子どもが走り回っとる男やったらどうや。話は別や。猫を真っ二つにするみたいに、平気で子どもを真っ二つにしよるわ。なんぼでも代わりはおるんやからな。子どもが一人二人増えようが減ろうが、ソロモンはんにとっちゃ屁でもないこっちゃ。あのいまいましい奴め!」
こんな黒んぼは見たことがない。一度頭に思い込みができたら、もう絶対にてこでも動かないんだ。俺が今まで会ったどの黒んぼよりも、あいつはソロモンに手厳しかった。だから俺は別の王様の話をし始めて、ソロモンの話は流すことにした。ずっと昔にフランスで首をはねられたルイ十六世の話をした。それから、その息子の「ドルフィン」[訳注: 原文はDauphin(フランス王太子)だが、ハックはdolphin(イルカ)と聞き間違えている。]っていう王子様の話も。王様になるはずだったのに、捕まって牢屋に入れられて、そこで死んだって言う人もいる、ってな。
「かわいそうに、ちっこい坊やが。」
「でも、そこから抜け出して逃げて、アメリカに来たって言う人もいるんだ。」
「そらええな! けど、寂しい思いするやろなあ。ここには王様はおらんのやろ、ハック?」
「ああ。」
「ほな、仕事も見つからへんやんけ。どないするんやろ?」
「さあ、どうだか。警察官になるやつもいるし、人にフランス語の話し方を教えるやつもいるらしい。」
「なんでや、ハック。フランスの人間はわいらと同じように喋らんのか?」
「違うんだよ、ジム。あいつらの言うことなんて、一言も分かりゃしない。たったの一言もだ。」
「へえ、たまげたなあ! なんでそないなことになるんや?」
「俺が知るかよ。でも本当なんだ。本で読んだことがある。例えばさ、誰かがお前のところに来て『ポリ・ヴ・フランセ』って言ったら、どう思う?」
「何も考えへんわ。いきなり頭をぶん殴ったる。まあ、そいつが白人やなかったらの話やけどな。黒んぼにそんなこと言われたら黙ってへんで。」
「よせよ、別に悪口じゃないんだ。ただ、『フランス語を話せますか?』って言ってるだけなんだよ。」
「ほな、なんで普通にそう言わんのや?」
「いや、そう言ってるんだよ。それがフランス人流の言い方なんだ。」
「まったく、あほらしい言い方やな。もうその話は聞きたないわ。意味が分からん。」
「なあジム、猫は俺たちみたいに話すか?」
「いや、猫は喋らへん。」
「じゃあ、牛は?」
「いや、牛も喋らへん。」
「猫は牛みたいに話すか? 牛は猫みたいに話すか?」
「いや、どっちもそんなことせえへん。」
「あいつらが互いに違う話し方をするのは、自然で当たり前のことだよな?」
「そらそうや。」
「じゃあ、猫や牛が俺たちと違う話し方をするのも、自然で当たり前のことだよな?」
「ああ、そらもちろんや。」
「それなら、フランス人が俺たちと違う話し方をするのが、どうして自然で当たり前のことじゃないんだ? それに答えてみろよ。」
「ハック、猫は人間か?」
「いや。」
「ほな、猫が人間みたいに喋るんは筋が通らへん。牛は人間か? それとも牛は猫か?」
「いや、どっちでもない。」
「ほな、牛が人間や猫みたいに喋る義理はないわな。フランス人は人間か?」
「ああ。」
「ほな! ちくしょうめ、なんで人間みたいに喋らんのや? それに答えてみい!」
言葉を無駄にしても仕方がないと分かった。黒んぼに議論の仕方を教えるなんて無理な話だ。だから、俺は黙った。

第十五章
あと三晩も下れば、俺たちの目的地であるイリノイ州の南端、オハイオ川が合流するカイロに着くだろうと見当をつけていた。そこでいかだを売り払い、蒸気船に乗ってオハイオ川をずっと遡り、自由州のどこかへ行けば、もう面倒ごとはなくなるはずだった。
さて、二日目の夜、霧が出始めた。俺たちは砂州を見つけて、そこにいかだを繋ごうとした。霧の中を進むのは危険だからだ。俺がカヌーで先に進み、舫い綱を固定しようとしたが、繋げるようなものはか細い若木しかなかった。崩れやすい川岸の縁に生えていた一本に綱を巻きつけたが、流れが強く、いかだが猛烈な勢いで突っ込んできたせいで、若木は根こそぎ引き抜かれ、いかだはそのまま流されていってしまった。霧がどんどん濃くなっていくのが見え、俺は胸が悪くなるほど怖くなって、半ば一分ほども身動きができなかった。そうこうしているうちに、いかだはもう見えなくなっていた。二十ヤード先も見通せない。俺はカヌーに飛び乗り、いかだの舳先に戻ってパドルを掴み、一漕ぎしようとした。だが、カヌーは動かない。慌てていたせいで、繋いだ綱を解くのを忘れていたのだ。立ち上がって解こうとしたが、興奮のあまり手が震えて、何もまともにできなかった。
ようやく出発できると、俺はいかだを追って、砂州に沿って夢中で漕ぎ出した。そこまでは良かったが、砂州は六十ヤードほどの長さしかなく、その端を通り過ぎた途端、俺は真っ白な濃霧の中に飛び出してしまった。自分がどっちへ向かっているのか、死人同然、皆目見当もつかなかった。
パドルを漕ぐのはまずいな、と思った。下手に漕げば、川岸か砂州か何かに突っ込んでしまう。じっとして流れに任せるしかない。だが、こんな時に手をこまねいているのは、たまらなくじれったいものだ。俺は「おーい」と叫び、耳を澄ませた。ずっと川下のどこかで、小さな叫び声が聞こえた。途端に元気が出てきた。俺はその声を目指して猛然と漕ぎ出し、もう一度聞こえないかと神経を集中させた。次に声が聞こえた時、俺はそちらへ向かっているのではなく、右に逸れていることに気づいた。その次は左に逸れていた。しかも、声との距離はあまり縮まっていない。俺があちこちへふらふらと漕ぎ回っているのに、声の方は常にまっすぐ進んでいるからだ。
あいつが気を利かせて、ブリキの鍋でもずっと叩いてくれればいいのに、と思ったが、そんなことはしてくれない。叫び声と叫び声の間の静寂が、俺を苦しめた。俺は必死で漕ぎ続けたが、やがて叫び声が背後から聞こえてきた。もう完全に迷ってしまった。あれは誰か別のやつの声か、あるいは俺の向きが変わってしまったかのどちらかだ。
俺はパドルを放り出した。また叫び声が聞こえた。まだ背後からだが、場所が違う。声は鳴り続け、場所を変え続け、俺もそれに応え続けた。やがて声は再び俺の前方から聞こえるようになった。流れのせいでカヌーの向きが川下に戻ったのだと分かった。あれがジムの声で、他のいかだ乗りでなければ、もう大丈夫だ。霧の中では声の聞き分けなんてできやしない。霧の中では、何もかもが普段通りに見えたり聞こえたりしないものだからだ。
叫び声は続き、一分ほどすると、俺は崩れやすい川岸に猛スピードで近づいていた。岸には大きな木々が煙のような幽霊となってそびえ立っている。流れは俺を左へ押しやり、轟々と音を立てる流木の間をすり抜けていった。あまりの流れの速さに、流木が唸っているかのようだった。
一、二秒後には、あたりはまた真っ白な静寂に包まれた。俺は心臓の鼓動を聞きながら、身じろぎもせずにじっとしていた。百回も鼓動する間、息もしていなかったと思う。
もう諦めた。何が起こったのか分かった。あの川岸は島で、ジムは島の反対側を流れていってしまったのだ。十分もあれば通り過ぎられるような砂州じゃない。あれはちゃんとした島で、大きな木が生い茂っている。長さは五、六マイル、幅は半マイル以上あるかもしれない。
俺は耳を澄ませたまま、十五分ほどじっとしていたと思う。もちろん、一時間に四、五マイルの速さで流されてはいたが、そんなことは考えもしない。いや、まるで水の上で死んだように静止しているように感じるのだ。流木がちらりと横を通り過ぎても、自分がどれだけ速く進んでいるかなんて考えない。息を呑んで、「うわ、あの流木の速いこと!」と思うだけだ。夜中に一人で霧の中にいるのが、陰気で心細いなんて嘘だと思うなら、一度やってみるといい。すぐに分かるはずだ。
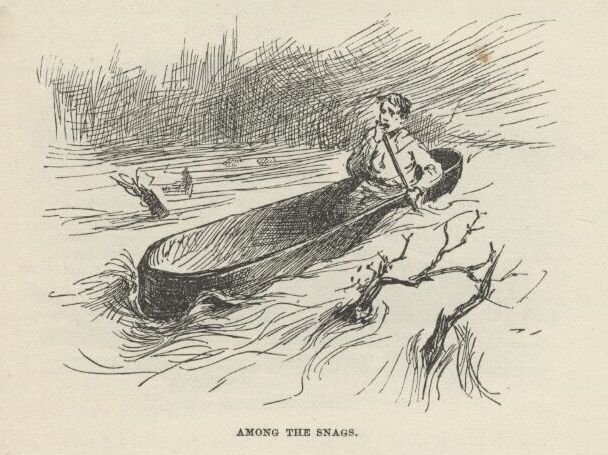
それから半時間ほど、俺は時々叫んでみた。とうとう遠くから返事があり、それを追おうとしたが、うまくいかない。やがて、砂州がいくつも集まった場所に入り込んでしまったようだと分かった。両側に砂州のかすかな影が見えるのだ。時にはその間に狭い水路があるだけで、見えない砂州も、川岸から垂れ下がった古い枯れ木やゴミに流れがぶつかる音で、そこにあることが分かった。砂州の間で叫び声を聞き分けるのはすぐに諦めた。どうせ少し追いかけてみただけだ。鬼火を追いかけるよりもひどい。音がこれほどあちこち動き回り、これほど素早く、これほど頻繁に場所を変えるなんて、見たこともなかった。
四、五回は、川から島を叩き落としてしまわないように、必死で岸から離れなければならなかった。だから、いかだも時々岸にぶつかっているに違いないと思った。そうでなければ、もっと先に進んで、声が聞こえなくなっているはずだ。いかだは俺より少し速く流れていたから。
やがて、俺は再び開けた川に出たようだったが、どこからも叫び声は聞こえなかった。ジムは流木に引っかかって、もうおしまいになったのかもしれない、と思った。俺はすっかり疲れ果てていたので、カヌーに横になり、もうくよくよするのはやめようと言い聞かせた。もちろん眠るつもりはなかったが、あまりに眠くてどうしようもなかった。だから、ほんの少しだけうたた寝しようと思った。
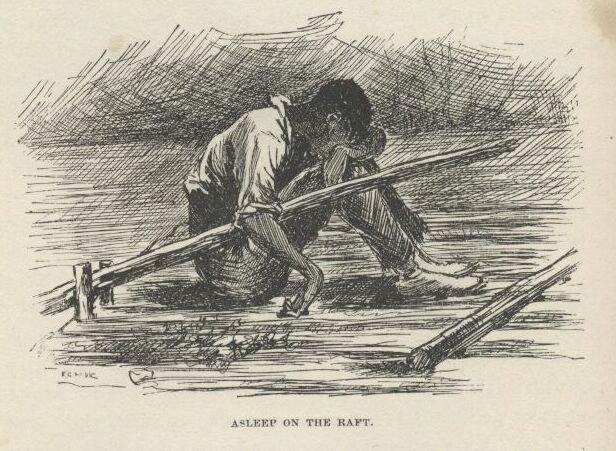
だが、それはうたた寝以上だったようだ。目を覚ますと、星が明るく輝き、霧はすっかり晴れていた。そして俺は、大きな川の湾曲部を、舳先を後ろにしてぐるぐると回りながら下っていた。最初は自分がどこにいるのか分からず、夢を見ているのだと思った。物事が思い出されてきても、まるで先週の出来事がぼんやりと蘇ってくるかのようだった。
ここはとてつもなく大きな川で、両岸にはこれまで見たこともないほど高く、鬱蒼とした木々が、星明かりで見る限り、まるで堅固な壁のようにそびえ立っていた。川下のはるか遠くに、水面に黒い点が見えた。俺はそれを追いかけたが、たどり着いてみると、それは二本の丸太を繋ぎ合わせたものに過ぎなかった。次にまた別の点を見つけて追いかけた。そしてまた別の点。今度こそ当たりだった。いかだだ。
いかだに着くと、ジムが膝の間に頭をうずめ、眠りこけて座っていた。右腕は舵取り用のオールにだらりと垂れ下がっている。もう一方のオールは折れていて、いかだの上は葉っぱや枝や泥で散らかっていた。ひどい目に遭ったようだ。
俺はいかだにカヌーを繋ぎ、ジムの鼻先で横になって、あくびをしたり、ジムの方へ拳を突き出して伸びをしたりして、言った。
「よう、ジム。俺、寝てたのか? なんで起こしてくれなかったんだよ。」
「ありがたや、ハックか? 死んでへんかったんか。溺れてへんかったんか。戻ってきたんか? ほんまやなんて、信じられへん。ほんまに信じられへんわ。顔を見せてみい、触らせてみい。おお、死んでへん! 戻ってきたんやな、生きてぴんぴんして、いつものハックや。いつものハックや、ありがたや、ありがたや!」
「どうしたんだよ、ジム? 酒でも飲んだのか?」
「酒? わいが酒を飲んだって? 酒を飲む機会なんぞあったかいな?」
「じゃあ、なんでそんなおかしなこと言うんだ?」
「わいがどんなおかしなこと言うとるんや?」
「どんなって、俺が戻ってきたとか何とか、まるで俺がどこかへ行ってたみたいなこと言ってるじゃないか。」
「ハック、ハック・フィン、わいの目を見い。ちゃんと目を見てみい。お前はどっかへ行っとらんかったんか?」
「どこかへ行ったって? 一体何言ってんだよ? 俺はどこへも行ってない。どこへ行くっていうんだ?」
「なあ、だんな、何かがおかしいで。わいはわいなんか、それとも誰なんか? わいはここにおるんか、どこにおるんや? それが知りたいんや。」
「そうだな、お前は間違いなくここにいると思うけど、頭がごちゃごちゃになったただの馬鹿だと思うぞ、ジム。」
「わいが馬鹿やて? ほな、これに答えてみい。お前、砂州に舫い綱を結ぶんや言うて、カヌーで出ていかんかったか?」
「いや、行ってない。何の砂州だ? 砂州なんて見てないぞ。」
「砂州を見てへんて? なあ、綱がほどけて、いかだが川をびゅーんと流されて、お前とカヌーは霧の中に置き去りにされたんやないか?」
「何の霧だ?」
「そら、あの霧や! 一晩中出とった霧や。ほんで、お前が叫んで、わいも叫んで、島の中でごっちゃになって、片方は迷子になって、もう片方も迷子になったも同然やったやろ。自分がどこにおるか分からんかったんやからな。ほんで、わいはたくさんの島にぶち当たって、えらい目に遭うて、もう少しで溺れ死ぬとこやったんやないか? なあ、そうやろ、だんな。そうやないか? それに答えてみい。」
「おいおい、もうたくさんだぜ、ジム。俺は霧も島も災難も、何も見てない。一晩中ここでお前と話してて、十分くらい前にお前が寝ちまったから、俺も同じように寝たんだと思う。そんな短い時間で酔っぱらえるわけないから、もちろん、お前は夢を見てたんだよ。」
「ちくしょうめ、どないして十分でそないな夢を全部見られるんや?」
「まあ、とにかく、お前は夢を見たんだよ。だって、そんなことは何も起こらなかったんだからな。」
「せやけど、ハック、わいにははっきり……」
「どんなにはっきりしてようが関係ない。全部でたらめだ。俺が知ってる。だって、俺はずっとここにいたんだから。」
ジムは五分ほど何も言わず、座って考え込んでいた。やがて、こう言った。
「ほな、わいは夢を見とったんやろな、ハック。けど、ちくしょう、今まで見た中で一番強烈な夢やで。それに、こないに疲れる夢は初めてや。」
「ああ、まあ、いいじゃないか。夢ってのは時々、ものすごく人を疲れさせるもんだからな。でも、そいつはすごい夢だったな。全部話してくれよ、ジム。」
そこでジムは、実際に起こった通りに、一部始終を話し始めた。もっとも、かなり話を盛ってはいたが。それから、これは警告として送られたものだから、「解釈」を始めなきゃならん、と言った。最初の砂州は、俺たちに良くしてくれようとする男を表していて、流れは、俺たちをその男から引き離してしまう別の男だと言う。叫び声は、時々やってくる警告で、それを理解しようと一生懸命にならなければ、災難から守ってくれるどころか、俺たちを不運に陥れるだけだ、と。たくさんの砂州は、喧嘩好きな連中や意地悪なあらゆる種類の人間とこれから遭遇する困難を表しているが、自分たちのことに集中して、言い返したり相手を怒らせたりしなければ、俺たちはそれを乗り越え、霧を抜けて、自由州である広くて澄んだ川に出ることができ、もう二度と面倒なことにはならないだろう、ということだった。
俺がいかだに乗った直後は、空はかなり暗く曇っていたが、今はまた晴れ始めていた。
「ああ、まあ、そこまではうまく解釈できたな、ジム」と俺は言った。「でも、これは何を表してるんだ?」
それは、いかだの上の木の葉やゴミ、そして折れたオールだった。今ではそれらがはっきりと見えた。
ジムはゴミを見て、それから俺を見て、またゴミに目を戻した。夢のことがあまりに強く頭にこびりついていたせいで、それを振り払って、すぐに事実を元に戻すことができないようだった。だが、ようやく事態を飲み込むと、彼はにやにやもせずにじっと俺を見つめて、こう言った。
「あれが何を表しとるかやて? 教えたるわ。わいが仕事と、お前を呼ぶ声でくたくたになって眠りについた時、わいの心は張り裂けそうやった。お前がおらんようになって、わいといかだがどうなろうと、もうどうでもええと思とったからや。ほんで、目が覚めて、お前が無事に戻ってきたのを見つけた時、涙が出てきた。あまりのありがたさに、ひざまずいてお前の足にキスしたいくらいやったんや。それやのに、お前が考えとったんは、どないして嘘ついてこのジム爺を馬鹿にしてやろうかっちゅうことだけやった。あそこにあるんはゴミや。ほんでな、友達の頭に泥を塗って、恥かかせるような奴のことをゴミっちゅうんや。」
それから彼はゆっくりと立ち上がり、小屋の方へ歩いていき、それだけを言うと中に入ってしまった。だが、それで十分だった。俺はあまりに自分が卑劣に思えて、取り消してもらうためにあいつの足にキスしたいくらいだった。
黒んぼのところへ行って頭を下げる決心がつくまで、十五分かかった。でも俺はそうしたし、その後、それを後悔したことは一度もなかった。俺は二度とあいつに意地悪をしなかったし、あいつがそんな風に感じるって知ってたら、あのいたずらだってしなかっただろう。

第十六章
俺たちはほとんど一日中眠り、夜になってから出発した。まるで長い行列のように、通り過ぎるのに時間がかかる巨大ないかだの少し後についていった。そのいかだは両端に四本ずつ長い大櫂を備えていたので、おそらく三十人もの男が乗っているのだろうと俺たちは判断した。船上には五つの大きな小屋が離れて建てられており、真ん中には焚き火があり、両端には高い旗竿が立っていた。たいそう立派なものだった。あんな船のいかだ乗りになるというのは、たいしたことだったに違いない。
俺たちは大きな湾曲部へと流れていった。夜は曇ってきて、蒸し暑くなった。川幅は非常に広く、両岸は鬱蒼とした木々で壁のように覆われていた。切れ目も灯りもほとんど見えない。俺たちはカイロの話をし、そこに着いた時に気づくだろうか、と案じた。たぶん無理だろう、と俺は言った。そこには十数軒の家しかないと聞いたことがあるし、もし灯りがついていなかったら、町を通り過ぎているとどうして分かるだろう? ジムは、二つの大きな川がそこで合流するなら、それが目印になるだろう、と言った。しかし俺は、島の端を通り過ぎて、また同じ川に戻ってきただけだと思うかもしれない、と言った。その言葉にジムは不安になった。俺もだ。そこで問題は、どうするか、ということだった。俺は、最初に灯りが見えたら岸へ漕ぎ着け、パップが交易用の平底船で後から来るんだけど、この商売は初めてで、カイロまであとどれくらいか知りたがってる、と話すことにしよう、と提案した。ジムもそれがいい考えだと思ったので、俺たちは一服しながら待つことにした。
あとは、町を鋭く見張り、見過ごさないようにするだけだった。ジムは、絶対に見つけると断言した。それを見つけた瞬間に自由の身になるからだ。もし見逃せば、また奴隷州に戻ってしまい、二度と自由のチャンスはなくなる。彼はしょっちゅう飛び上がって言った。
「あれか?」
だが、違った。鬼火か、蛍だった。それで彼はまた座り込み、前と同じように見張りを続けた。ジムは、自由がすぐそこまで来ていると思うと、体中が震えて熱っぽくなると言った。まあ、正直に言うと、俺も彼の言葉を聞いて、体中が震えて熱っぽくなった。なぜなら、彼がほとんど自由だということが、頭の中でだんだんはっきりしてきたからだ。そして、その責任は誰にある? そう、俺だ。どうしたって、そのことを良心から追い出すことはできなかった。それが俺を苦しめ始め、落ち着かなくなり、じっとしていられなくなった。自分がやっていることがどういうことなのか、これまで一度も身にしみて分かったことがなかった。でも、今は分かった。その思いが俺から離れず、どんどん俺の心を焦がしていった。俺は、ジムを正当な所有者から逃がしたわけじゃないんだから、自分に責任はないんだ、と自分に言い聞かせようとした。だが無駄だった。良心は立ち上がって、その度にこう言うのだ。「でも、お前はあいつが自由を求めて逃げていると知っていた。岸へ漕いで行って、誰かに告げることもできたはずだ」。その通りだった。どうやっても、それから逃れることはできなかった。そこが痛いところだった。良心は俺に言う。「哀れなミス・ワトソンがお前に何をしたというんだ。お前は彼女の黒んぼが目の前で逃げていくのを見ていながら、一言も言わなかったじゃないか。あの哀れな老婦人がお前に何をしたというんだ。お前は彼女にあんなひどい仕打ちができるのか? 彼女はお前に本を教えようとし、行儀を教えようとし、知る限りのあらゆる方法でお前に良くしてくれようとしたじゃないか。それが彼女のしたことだ」。
俺はあまりに卑劣で惨めな気分になり、いっそ死んでしまいたいとさえ思った。俺はいかだの上を行ったり来たりしながら、自分自身を罵った。ジムも俺の横を行ったり来たりしていた。二人ともじっとしていられなかった。彼が踊るようにして「カイロだ!」と言うたびに、弾丸が体を突き抜けるような衝撃が走り、もし本当にカイロだったら、俺は惨めさのあまり死んでしまうだろう、と思った。
俺が自分自身に話しかけている間、ジムはずっと大声で喋っていた。自由州に着いたらまずやることは、一セントも使わずに金を貯め始めることだ、と言っていた。そして十分な金が貯まったら、ミス・ワトソンの家の近くの農場で所有されている妻を買い取るのだ、と。それから二人で働いて二人の子供を買い取り、もし主人が売ってくれなければ、奴隷解放論者に頼んで盗み出してもらうのだ、と。
そんな話を聞いて、俺はほとんど凍りついた。彼はこれまでの人生で、そんなことを口にする勇気などなかったはずだ。自分がもうすぐ自由になると判断した途端、彼がどれほど変わったかを見ろ。古いことわざの通りだ、「黒んぼに一寸やれば一尺取る」。[訳注: 「一寸与えれば一尺を望む」ということわざ。ellは約114センチ。]これが、俺が考えなしだったことの結果だ、と俺は思った。俺が逃亡を手助したも同然のこの黒んぼが、臆面もなく、自分の子供たちを盗むと言い放っているのだ。子供たちは、俺が知りもしない男の所有物だ。俺に何の危害も加えたことのない男の。
ジムがそんなことを言うのを聞いて、俺は悲しかった。彼を見損なった。俺の良心はこれまで以上に激しく俺を責め立て、とうとう俺は良心に言った。「もうやめてくれ。まだ遅くはない。最初の灯りが見えたら岸へ漕いで行って、告げ口してやる」。すると途端に、俺は気が楽になり、幸せで、羽のように軽くなった。悩みはすべて消え去った。俺は灯りがないかと鋭く見張り始め、自分でも気づかないうちに鼻歌を歌っていた。やがて、一つ灯りが見えた。ジムが叫んだ。
「助かったで、ハック、助かった! 飛び上がってかかとを鳴らせ! あれこそ待ちに待ったカイロや、わいには分かるで!」
俺は言った。
「カヌーで行って見てくるよ、ジム。違うかもしれないからな。」
彼は飛び上がってカヌーの準備をし、俺が座れるようにと底に古い上着を敷き、パドルを渡してくれた。俺が岸を離れると、彼は言った。
「もうすぐわいは喜びで叫びだすやろな。そして言うんや、『これもみんなハックのおかげや。わいは自由の身や、ハックがおらんかったら自由になんかなれへんかった。ハックがやってくれたんや。ジムはお前のことを絶対忘れへん、ハック。お前はジムが持った中で一番の友達や。それに、今のジム爺にとっちゃ、お前がたった一人の友達なんや』ってな。」
俺は彼を密告しようと、汗だくで漕ぎ出していた。だが、彼がこう言った時、なんだか体の力が抜けてしまったようだった。俺はゆっくりと進み始め、自分が漕ぎ出したことを喜んでいるのかどうか、はっきりとは分からなかった。五十ヤードほど離れた時、ジムが言った。
「行くがええ、誠実なハック。ジム爺との約束を守ってくれた、たった一人の白人の紳士や。」
ああ、本当に気分が悪くなった。だが、俺は言った、やらなきゃいけない。これから逃げることはできないんだ、と。ちょうどその時、銃を持った二人の男が乗った小舟がやってきて、彼らが止まったので俺も止まった。一人が言った。
「向こうにあるのは何だ?」
「いかだの切れ端です」と俺は言った。
「お前はそれに乗ってるのか?」
「はい。」
「誰か他に男はいるか?」
「一人だけです。」
「ふむ、今夜、あの湾曲部の上の方で黒んぼが五人逃げ出したんだ。お前の連れは白人か、黒人か?」
俺はすぐには答えなかった。答えようとしたが、言葉が出てこなかった。一、二秒、気力を奮い立たせて口にしようとしたが、俺にはそんな勇気はなかった。ウサギほどの度胸もなかった。自分が弱気になっているのが分かった。だから、もう চেষ্টাするのはやめて、思い切って言った。
「白人です。」
「我々自身で確かめさせてもらうとしよう。」
「ぜひそうしてください」と俺は言った。「そこにいるのは親父なんです。灯りのあるところまでいかだを引くのを手伝ってくれると助かります。親父は病気なんです。お袋とメアリー・アンも。」
「ちくしょう! こっちは急いでるんだ、坊主。だが、仕方ないだろう。さあ、パドルをしっかり握れ。行こうぜ。」
俺はパドルを握り、彼らもオールを漕ぎ始めた。一、二回漕いだところで、俺は言った。
「親父はすごく感謝すると思いますよ、本当です。いかだを岸まで引くのを手伝ってほしいって言うと、みんな行ってしまうんです。一人じゃ無理なのに。」
「そりゃひでえ話だ。それに奇妙だ。なあ坊主、お前の親父さんはどうしたんだ?」
「親父は……その……ええと、大したことじゃないんです。」
彼らは漕ぐのをやめた。いかだまではもうほんのわずかな距離だった。一人が言った。
「坊主、そりゃ嘘だ。お前の親父さんはどうしたんだ? 正直に答えろ。その方がお前の身のためだ。」

「はい、正直に言います、本当です。でも、俺たちを見捨てないでください。親父は……その……皆さん、どうかこのまま漕いで、舫い綱を投げさせてくれさえすれば、いかだに近づかなくてもいいんです。お願いします。」
「後退しろ、ジョン、後退しろ!」と一人が言った。彼らは逆方向に漕ぎ始めた。「離れてろ、坊主。風下にいろ。ちくしょう、風でこっちに運ばれてきたに違いねえ。お前の親父は天然痘なんだな、分かってて黙ってたな。なんで正直にそう言わなかったんだ? 病気をそこら中に広めたいのか?」
「だって」と俺は泣きじゃくりながら言った。「これまでみんなにそう言ったんです。そしたら、みんな行ってしまって、俺たちを置き去りにしたんです。」
「かわいそうに、それも一理あるな。お前のことは本当に気の毒に思うが、我々は……まあ、ちくしょう、天然痘にはかかりたくないんだよ、分かるだろ。いいか、どうすればいいか教えてやる。一人で上陸しようとするな。何もかも粉々になっちまうぞ。このまま二十マイルほど流れていけ。そうすれば川の左手に町がある。その頃にはとっくに日が昇ってるだろうから、助けを求める時は、家族がみんな悪寒と熱で寝込んでいると言え。二度と馬鹿な真似をして、病気を当てさせるようなことはするな。我々は親切で言ってるんだ。だから、我々から二十マイル離れてくれ。いい子だからな。あの灯りのある場所で上陸しても無駄だ。あそこはただの薪置き場だ。なあ、お前の親父さんは貧しいんだろう。それに、かなり不運な目に遭っているようだな。ほら、この板の上に二十ドルの金貨を置いてやる。流れてきたら拾え。お前を置き去りにするのは気が引けるが、とんでもない! 天然痘を甘く見ちゃいけねえ、分かるだろ?」
「待てよ、パーカー」ともう一人の男が言った。「俺の分として二十ドルを板の上に置くぜ。さよなら、坊主。パーカー氏の言う通りにすれば、大丈夫だ。」
「その通りだ、坊主。さよなら、さよなら。もし逃亡した黒んぼを見かけたら、助けを呼んで捕まえろ。金になるぞ。」
「さようなら」と俺は言った。「もし見かけたら、逃亡した黒んぼは逃がしませんよ。」
彼らは去っていき、俺はいかだに戻った。気分は悪く、落ち込んでいた。自分が間違ったことをしたとよく分かっていたし、正しいことをしようと学んでも無駄だということも分かったからだ。小さい頃にちゃんと始められなかった人間には、もう見込みはない。いざという時、自分を支え、やり遂げさせてくれるものがないから、結局は負けてしまう。それから少し考えて、俺は自分に言った。「待てよ。もしお前が正しいことをしてジムを引き渡していたら、今より気分が良かったか?」。「いや」と俺は答えた。「気分は悪かっただろう。今と全く同じ気持ちだっただろう」。「それなら」と俺は言った。「正しいことをするのは面倒で、悪いことをするのは面倒じゃない、しかも報いはどっちも同じだっていうなら、正しいことを学んで何になるんだ?」。俺は行き詰まった。その問いには答えられなかった。だから、もうそのことについて悩むのはやめて、これからはその時々で一番やりやすい方を選ぶことにしよう、と決めた。
俺は小屋に入った。ジムはいなかった。あたりを見回したが、どこにもいない。俺は言った。
「ジム!」
「ここや、ハック。あいつらもう見えへんようになったか? 大きな声出すなや。」
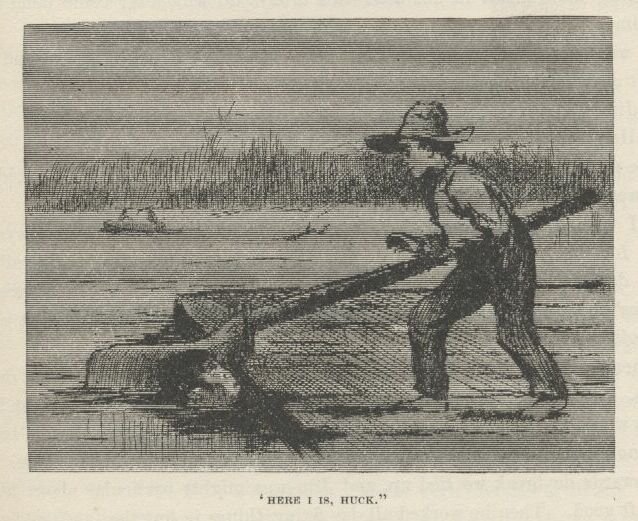
彼は川の中で、舵取り用のオールの下に、鼻だけを出していた。俺があいつらは見えなくなったと言うと、彼はいかだに上がってきた。そして言った。
「話は全部聞いとったで。あいつらがいかだに乗り込んできたら、すぐに川に飛び込んで岸へ向かうつもりやったんや。あいつらが行ってから、またいかだに泳いで戻るつもりやった。けど、いやあ、ようあいつらを騙したな、ハック! あれは最高に賢いやり方やったで! ほんまやで、坊主、あれでジム爺は助かったんや。ジム爺は、この恩は忘れへんで。」
それから俺たちは金の話をした。一人二十ドルはかなりの儲けだった。ジムは、これなら蒸気船の甲板席に乗れるし、自由州の行きたいところまで行くのに十分な金だ、と言った。あと二十マイルくらい、いかだで行くのは大したことないが、もう着いていればよかったのに、とも言った。
夜が明ける頃、俺たちはいかだを繋いだ。ジムはいかだをしっかり隠すことに、ものすごくこだわった。それから彼は一日中、荷物を束ねて、いかだを降りる準備をしていた。
その夜、十時頃、川の左手の湾曲部のずっと先に町の灯りが見えた。
俺は様子を見にカヌーで漕ぎ出した。すぐに、川で小舟に乗って延縄を仕掛けている男を見つけた。俺は近づいて言った。
「旦那、あの町はカイロですか?」
「カイロ? 違うね。とんだ間抜けだな、お前は。」
「何て町ですか、旦那?」
「知りたきゃ、行って確かめな。あと半ば一分も俺の周りでうろちょろしてたら、欲しくもないものを食らうことになるぞ。」
俺はいかだに戻った。ジムはひどくがっかりしていたが、俺は気にするな、次はカイロだろう、と言った。
夜が明ける前に、もう一つ町を通り過ぎた。また行こうかと思ったが、そこは高台だったのでやめておいた。カイロのあたりに高台はない、とジムが言っていた。俺は忘れていた。俺たちはその日、左岸にかなり近い砂州で休んだ。俺は何だか嫌な予感がし始めた。ジムも同じだった。俺は言った。
「もしかしたら、あの霧の夜にカイロを通り過ぎちまったのかもしれない。」
彼は言った。
「その話はやめとこ、ハック。哀れな黒んぼに運なんかないんや。あのガラガラヘビの皮が、まだ悪さしとるんやとずっと思とったんや。」
「あのヘビの皮なんて見なきゃよかった、ジム。本当に、目に入れなきゃよかった。」
「お前のせいやない、ハック。お前は知らんかったんや。自分を責めたらあかんで。」
夜が明けると、案の定、岸辺には澄んだオハイオ川の水が流れ、その外側にはいつもの濁ったミシシッピ川があった! つまり、カイロはもうおしまいだった。
俺たちはすべてを話し合った。岸に上がるわけにはいかない。もちろん、いかだを上流へ引っ張っていくこともできない。暗くなるのを待って、カヌーで引き返し、運に任せるしかなかった。だから俺たちは、仕事に備えて体力を温存するため、ハコヤナギの茂みの中で一日中眠った。そして暗くなってからいかだに戻ると、カヌーがなくなっていた!
俺たちはしばらくの間、一言も口をきかなかった。言うべきことなど何もなかった。これがまたガラガラヘビの皮の仕業だということは、二人ともよく分かっていた。だから、それについて話したところで何になる? まるで文句を言っているようにしか見えないし、そんなことをすれば、もっと不運が舞い込んでくるに決まっている。黙っておくのが賢明だと分かるまで、ずっと不運が舞い込み続けるだろう。
やがて俺たちは、どうするのが一番いいか話し合ったが、結局、いかだで下り続け、戻るためのカヌーを買う機会を待つしかない、という結論になった。パップがやるように、周りに誰もいないからといって借りていくつもりはなかった。そんなことをすれば、追っ手が差し向けられるかもしれないからだ。
だから俺たちは、暗くなってからいかだで漕ぎ出した。
あのヘビの皮が俺たちにもたらしたすべての出来事の後でも、ヘビの皮を扱うのが馬鹿げたことだとまだ信じない者がいるなら、この先を読んで、それが俺たちにさらに何をもたらしたかを見れば、今度こそ信じるだろう。
カヌーを買うなら、岸に係留されているいかだから買うのが一番だ。だが、係留されているいかだは見当たらなかった。だから俺たちは三時間以上も進み続けた。やがて夜は灰色になり、かなり濃くなってきた。これは霧の次に厄介なものだ。川の形が分からず、遠くも見えない。すっかり夜も更けて静かになった頃、蒸気船が川を上ってきた。俺たちはランタンに火を灯し、船が見てくれるだろうと思った。上りの船は、普通は俺たちにあまり近づいてこない。砂州に沿って外側を進み、岩礁の下の楽な水路を探すからだ。しかし、こんな夜は、川の流れに逆らって水路をまっすぐ突っ走ってくる。
船がどしんどしんと進んでくる音は聞こえたが、その姿がはっきり見えたのは、すぐ近くまで来た時だった。船はまっすぐ俺たちをめがけてきた。連中はよくそういうことをして、触れずにどれだけ近くを通れるか試すのだ。時々、外輪がいかだの大櫂を食いちぎることがあり、そんな時は水先案内人が窓から顔を出して笑い、自分はたいそう腕がいいと思っている。さて、その船がやってきて、俺たちは、かすめていくつもりだろう、と言った。だが、少しも進路を変える気配がない。大きな船で、しかもかなりの速さでやってくる。まるで周りに蛍の列をまとった黒い雲のようだ。だが、突然、船は大きく不気味に膨れ上がり、大きく開いた炉の扉がずらりと並んで真っ赤な歯のように輝き、その巨大な船首と防舷材が俺たちの真上に覆いかぶさってきた。俺たちに向かって怒鳴り声が上がり、エンジンを止める鐘がけたたましく鳴り響き、罵り声がわめき散らされ、蒸気がシューシューと音を立てた。そして、ジムが片方の側から、俺がもう片方の側から川に飛び込むのと同時に、船はいかだの真ん中を突き破って進んでいった。
俺は潜った。川底まで行こうと思った。三十フィートの外輪が俺の上を通過するのだから、十分な空間が必要だった。俺はいつも一分は水中にいられたが、この時は一分半はいたと思う。それから、もう破裂しそうだったので、急いで水面に向かって浮上した。脇の下まで水面に飛び出し、鼻から水を吹き出し、少し息を切らした。もちろん、流れは激しかった。そしてもちろん、あの船は止めてから十秒後にはまたエンジンをかけた。いかだ乗りのことなど大して気にもかけないからだ。だから、船はもう川を上ってごうごうと進んでいき、濃い霧の中に見えなくなっていたが、音は聞こえていた。
俺はジムを十数回呼んだが、返事はなかった。だから、俺が「立ち泳ぎ」をしている時に触れた板を掴み、それを前に押しながら岸を目指して泳ぎ出した。だが、流れは左岸に向かっていることに気づいた。つまり、俺は川の渡り場にいるということだ。だから進路を変え、そちらへ向かった。
そこは二マイルもある、長く傾斜した渡り場の一つだったので、渡りきるのにかなり時間がかかった。俺は無事に上陸し、土手をよじ登った。少し先しか見えなかったが、でこぼこの地面を四分の一マイルほど探りながら進むと、気づかないうちに、古風な大きな二階建ての丸太小屋に行き当たった。急いで通り過ぎて逃げようとしたが、たくさんの犬が飛び出してきて、俺に向かって吠えたり唸ったりし始めた。俺はこれ以上一歩も動かない方がいいと分かっていた。

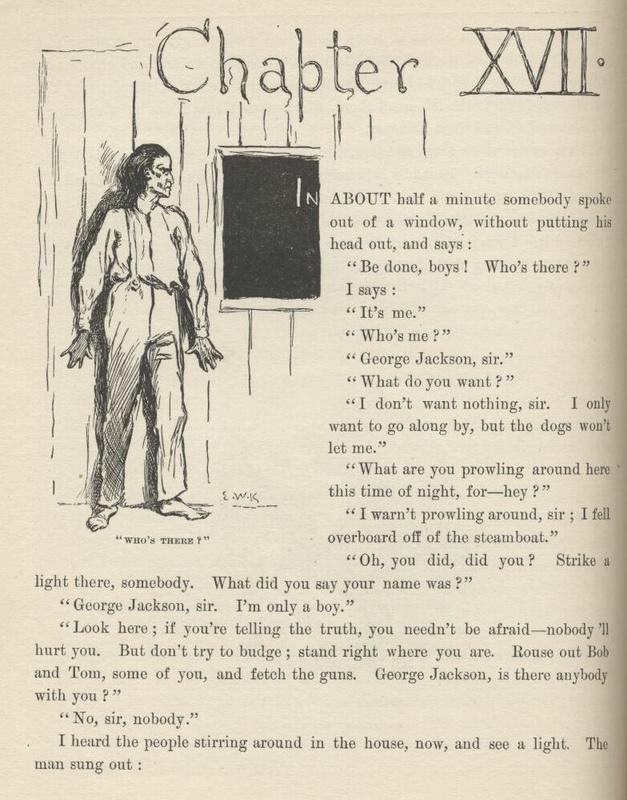
第十七章
一分ほどすると、誰かが窓から顔も出さずに言った。
「やめろ、お前たち! 誰だ?」
俺は言った。
「俺です。」
「俺とは誰だ?」
「ジョージ・ジャクソンです。」
「何の用だ?」
「何の用もありません。ただ通り過ぎたいだけなんですが、犬たちが通してくれないんです。」
「こんな夜更けに、ここで何をうろついているんだ、え?」
「うろついてなんかいません。蒸気船から川に落ちたんです。」
「ほう、そうか。誰か、明かりをつけろ。名前は何と言った?」
「ジョージ・ジャクソンです。ただの子供です。」
「いいか、もし本当のことを言っているなら、怖がる必要はない。誰もお前を傷つけたりはしない。だが、動くんじゃないぞ。そこにじっとしていろ。誰か、ボブとトムを起こして、銃を持ってこさせろ。ジョージ・ジャクソン、誰か一緒にいるのか?」
「いいえ、誰もいません。」
家の中で人々が動き回る音が聞こえ、明かりが見えた。男が叫んだ。
「その明かりをどけろ、ベッツィ、この馬鹿者が! 少しは考えろ。玄関のドアの後ろの床に置け。ボブ、お前とトムは準備ができたら、持ち場につけ。」
「準備万端だ。」
「さて、ジョージ・ジャクソン、シェパードソン家を知っているか?」
「いいえ、聞いたこともありません。」
「ふむ、そうかもしれんし、そうでないかもしれん。さて、全員準備はいいか。前に進め、ジョージ・ジャクソン。いいか、急ぐなよ。ゆっくり来い。もし誰か一緒にいるなら、下がらせろ。姿を見せたら撃つ。さあ、来い。ゆっくりだ。ドアは自分で押して開けろ。体をねじ込めるくらいでいい、分かったな?」
俺は急がなかった。急ぎたくても急げなかっただろう。一歩一歩ゆっくりと進むと、何の音もしなかったが、自分の心臓の音だけは聞こえるような気がした。犬たちは人間と同じように静かだったが、俺の少し後ろをついてきた。三段の丸太の階段に着くと、鍵を開け、かんぬきを外し、錠を外す音が聞こえた。俺はドアに手をかけ、少しずつ押していくと、誰かが言った。「よし、それでいい。頭を入れろ」。俺はそうしたが、首をはねられるんじゃないかと思った。
蝋燭は床に置かれていて、そこに全員がいた。四分の一分ほどの間、彼らは俺を、俺は彼らを見ていた。銃を俺に向けている三人の大男がいて、正直、俺はびくっとした。一番年上は白髪で六十歳くらい、他の二人は三十歳かそこら。三人とも立派でハンサムだった。そして、とても優しそうな白髪の老婦人と、その後ろに若い女性が二人いたが、よくは見えなかった。老紳士が言った。
「よし、大丈夫そうだ。入れ。」
俺が入るとすぐに、老紳士はドアに鍵をかけ、かんぬきをかけ、錠をかけた。そして若い男たちに銃を持って入るように言うと、全員で新しいラグカーペットが敷かれた大きな客間に入り、正面の窓の射程外になる隅に集まった。側面には窓はなかった。彼らは蝋燭をかざして俺をじっくりと見て、口々に言った。「なんだ、シェパードソン家の者じゃないな。いや、シェパードソン家の面影はまったくない」。それから老人が、武器を持っていないか調べさせてもらうが悪く思わないでほしい、と言った。危害を加えるつもりはなく、ただ確かめるだけだ、と。だから彼は俺のポケットの中を探るようなことはせず、ただ外側から手で触れて、大丈夫だと言った。彼は俺に、くつろいで自分の身の上を話すように言ったが、老婦人が言った。
「あら、ソウル、この子はびしょ濡れじゃないの。お腹も空いているんじゃないかしら?」
「本当だ、レイチェル。忘れていたよ。」
そこで老婦人が言った。
「ベッツィ」(これは黒人の女だった)、「急いでこの子に何か食べるものを用意しておやり。それから、娘たちの一人、バックを起こしてきておくれ……ああ、来たわね。バック、この小さな旅人を連れて行って、濡れた服を脱がせて、あなたの乾いた服を着せてあげなさい。」
バックは俺と同じくらいの年頃に見えた。十三か十四か、そのあたりだろう。俺より少し体は大きかったが。彼はシャツ一枚しか着ておらず、ひどく髪がぼさぼさだった。あくびをしながら片方の拳で目をこすり、もう片方の手で銃を引きずりながら入ってきた。彼は言った。
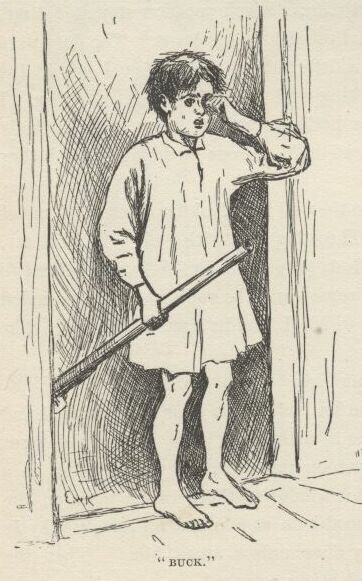
「シェパードソン家のやつらはいないのか?」
彼らは、いや、間違いだった、と答えた。
「ふん、もしいたら、一人くらいは仕留めてやったのにな」と彼は言った。
みんなが笑い、ボブが言った。
「おいおい、バック、お前が来るのが遅いから、俺たちみんな頭の皮を剥がれていたかもしれないぞ。」
「だって、誰も俺を呼びに来なかったんだ。いつも俺は後回しにされて、出番がないんだ。」
「気にするな、バック、坊主」と老人が言った。「そのうち十分に出番はあるさ、心配するな。さあ、行きなさい。お母さんの言った通りにするんだ。」
二階の彼の部屋に行くと、彼は自分のごわごわしたシャツと上着とズボンを貸してくれて、俺はそれを着た。着替えている間に、彼は俺に名前を尋ねたが、俺が答える前に、一昨日森で捕まえたカケスと子ウサギの話を始めた。そして、「ろうそくが消えた時、モーゼはどこにいたか」と尋ねてきた。俺は知らない、そんな話は聞いたこともない、と答えた。
「じゃあ、当ててみな」と彼は言った。
「どうやって当てるんだよ」と俺は言った。「聞いたこともないのに。」
「でも、わかるだろ? 簡単なことさ。」
「『どの』ロウソクだって?」と俺は言った。
「そりゃ、どのロウソクでもさ」とあいつは言う。
「あいつがどこにいたかなんて知るかよ。どこにいたんだ?」
「そりゃあ、『暗闇』の中にいたのさ! それが答えだ!」
「なんだ、どこにいたか知ってたんなら、なんで俺に聞いたんだよ?」
「ちくしょう、なぞなぞなんだよ、わかんねえのか? なあ、お前、ここにどのくらいいるんだ? ずっといなきゃだめだぜ。すげえ楽しいことができるぞ――今、学校は休みなんだ。犬は飼ってるか? 俺は飼ってるぜ――川に入って、お前が投げた木切れを拾ってくるんだ。日曜日に髪をとかして一張羅を着るとか、そういう馬鹿げたこと、好きか? 俺はごめんだね、でもお袋がやらせるんだ。この古ズボンめ、いまいましい! はいたほうがいいんだろうけど、はきたくねえな、暑くてかなわん。準備はいいか? よし。行こうぜ、相棒。」
冷めたコーン・ポーンに、冷たいコーンビーフ、バターとバターミルク――そいつが、あそこの連中が俺に出してくれたもんだ。今まで食ったどんなもんよりもうまかった。バックもお袋も、ほかの連中もみんな、トウモロコシの穂軸パイプを吸っていた。いなくなっちまった黒人の女と、若い娘二人を除いては。みんな煙草をふかして話し、俺は飯を食いながら話した。若い娘たちは体にキルトを巻きつけ、髪を背中に垂らしていた。みんなが俺に質問してくるので、俺は、パップと俺と家族みんながアーカンソーのどん詰まりにある小さな農場で暮らしていたこと、姉さんのメアリー・アンが駆け落ちして結婚して、それっきり音沙汰がなくなったこと、ビリーが二人を探しに行って、そいつも音沙汰がなくなったこと、トムとモートは死んじまったこと、それで俺とパップだけが残ったけど、パップは心労がたたってやせ細っちまったこと、だからパップが死んだとき、農場は俺たちのものじゃなかったから、残ったものを全部持って、甲板乗客として川を上り始めたら、船から落ちちまったこと、そんなわけでここに流れ着いたんだと話してやった。するとみんな、好きなだけここにいていいと言ってくれた。それからほとんど夜が明けてきたので、みんな寝床につき、俺はバックと一緒に寝た。そして朝、目が覚めたとき、ちくしょうめ、自分の名前を忘れちまったんだ。それで一時間ほど横になって思い出そうとしていたが、バックが目を覚ましたので、こう言った。
「なあバック、字は綴れるか?」
「ああ」とあいつは言う。
「俺の名前、お前には綴れないだろうな」と俺は言った。
「賭けてもいいぜ、できるさ」とあいつは言う。
「わかった」と俺は言った。「やってみな。」
「G・E・O・R・G・E、J・A・X・O・N――ほらな」とあいつは言った。
「へえ」と俺は言った。「たいしたもんだ。お前にはできないと思ってたぜ。練習もなしにすらすら綴るには、ちっとも簡単な名前じゃねえ。」
俺はこっそりその綴りを書き留めておいた。誰かが次に『俺に』綴らせたがるかもしれねえから、いつでもすらすら言えるようにしておきたかったんだ。まるで昔から使い慣れてるみたいに。
とんでもなくいい家族で、家もとんでもなく立派だった。田舎であんなに趣味が良くて、あれほど立派な家は見たことがなかった。玄関のドアには鉄の掛け金も、鹿皮の紐がついた木の掛け金もなく、町の家と同じように、回す真鍮の丸い取っ手が付いていた。客間にはベッドも、ベッドの気配すらなかった。もっとも、町の客間にはベッドが置いてあるところも多いが。大きな暖炉があって、底は煉瓦敷きだった。煉瓦は水をかけて別の煉瓦でこすって、いつもきれいに赤く保たれていた。ときどき、スパニッシュ・ブラウンと呼ばれる赤い水性塗料で上塗りすることもあった。町の連中がやるのと同じだ。そこには大きな真鍮の薪載せ台があって、丸太ん棒を支えることができた。マントルピースの真ん中には時計が置いてあり、ガラスの文字盤の下半分には町の絵が描かれていた。真ん中には太陽を表す丸い場所があって、その後ろで振り子が揺れているのが見えた。その時計が時を刻む音を聞くのは心地よかった。ときどき、行商人がやってきて時計を磨き上げ、調子を整えてやると、くたばっちまう前に百五十回も鐘を鳴らし始めるんだ。あそこの連中は、時計のためなら金は惜しまなかった。
さて、時計の両脇には、チョークみたいなもので作られ、けばけばしく彩色された、風変わりで大きなオウムが一体ずつ置かれていた。片方のオウムのそばには陶器の猫が、もう片方のそばには陶器の犬がいた。そいつらを押すとキューと鳴くんだが、口を開けたり、顔つきが変わったり、面白そうなそぶりを見せたりはしなかった。体の下から鳴き声が出るんだ。そいつらの後ろには、大きな野生の七面鳥の羽の扇が二つ、広げて立てかけてあった。部屋の真ん中のテーブルには、リンゴやオレンジ、桃やブドウが山盛りにされた、素敵な陶器の籠があった。本物よりもずっと赤くて黄色くてきれいだったが、本物じゃなかった。ところどころ欠けて、下の白いチョークか何かの地肌が見えていたからだ。
このテーブルには、赤と青で翼を広げた鷲が描かれ、周りにも模様が描かれた、美しい油布のテーブルクロスがかかっていた。フィラデルフィアからわざわざ取り寄せたものだそうだ。テーブルの四隅には、本も何冊か、きっちり正確に積み上げられていた。一冊は絵がたくさん入った大きな家庭用の聖書。もう一冊は『天路歴程』で、ある男が家族を捨てた話で、理由は書いてなかった。俺はときどき、これをかなり読み込んだ。書いてあることは面白かったが、難しかった。もう一冊は『友情の捧げもの』という本で、美しい話や詩でいっぱいだったが、詩は読まなかった。ほかには『ヘンリー・クレイ演説集』や、『ガン博士の家庭医学』という本もあった。これは、誰かが病気になったり死んだりしたときにどうすればいいかが全部書いてある本だった。賛美歌集や、ほかにもたくさんの本があった。それから、座面が割竹で編まれた素敵な椅子もあって、それも完璧にしっかりしていた――古い籠みたいに真ん中がへこんで壊れたりしていなかった。
壁には絵が掛かっていた――主にワシントンやラファイエット、それに戦闘の絵や、「ハイランドのメアリー」という絵、それから「独立宣言署名」という絵もあった。クレヨン画と呼ばれるものもいくつかあって、それは亡くなった娘の一人が、たった十五歳のときに自分で描いたものだった。今まで見たどんな絵とも違っていた――普通より、ほとんどが黒っぽいんだ。一枚は、ほっそりした黒いドレスを着た女の絵で、脇の下あたりで細くベルトを締め、袖の真ん中はキャベツみたいに膨らんでいて、黒いヴェールのついた大きな黒いシャベル型のボンネットをかぶっていた。白いほっそりした足首には黒いテープが交差して巻かれ、鑿みたいな、とても小さな黒いスリッパを履いていた。彼女はしだれ柳の下で、右肘を墓石について物憂げにもたれかかり、もう片方の手は横に垂らして白いハンカチと小さなハンドバッグを持っていた。絵の下には「ああ、汝に再び会うことはなきか」と書かれていた。もう一枚は、髪を全部まっすぐ頭のてっぺんまでとかし上げ、椅子の背もたれみたいな櫛の前で結んだ若いご婦人の絵だった。彼女はハンカチに顔をうずめて泣いていて、もう片方の手には死んだ鳥が仰向けになってかかとを上にしていた。絵の下には「ああ、汝の甘きさえずりを再び聞くことはなきか」と書かれていた。もう一枚は、若いご婦人が窓辺に立ち、月を見上げて、頬に涙を流している絵だった。片手には開いた手紙を持ち、その端には黒い封蝋が見えていた。彼女は鎖のついたロケットを口に押し当てていた。絵の下には「そして汝は去りしか、然り、汝は去りぬ、ああ」と書かれていた。これらはみんないい絵なんだろうが、どうにも好きにはなれなかった。少しでも気分が落ち込んでいるときに見ると、いつもぞっとして気が滅入っちまうからだ。みんな彼女が死んだのを残念がっていた。彼女はもっとたくさんの絵を描く計画を立てていて、今までの作品を見れば、彼女を失ったことがどれほどの損失だったかわかるからだ。だが俺に言わせれば、彼女の性分からして、墓場にいるほうが楽しい時間を過ごしているんだろうと思った。彼女は病気になる前、最高傑作だと言われる絵に取り組んでいた。そして来る日も来る日も、それを完成させるまで生かしてほしいと祈っていたが、その機会は訪れなかった。それは、長い白いガウンを着た若い女が、橋の欄干に立って、今にも飛び降りようとしている絵だった。髪は背中に垂れ、月を見上げ、顔には涙が流れていた。そして胸の前で二本の腕を組み、二本の腕を前に伸ばし、さらに二本の腕を月に向かって伸ばしていた――どの腕の組が一番良く見えるか確かめて、ほかの腕は全部消すつもりだったらしい。だが、さっきも言ったように、彼女は決心がつかないうちに死んでしまい、今ではその絵は彼女の部屋のベッドの頭上に飾られ、誕生日が来るたびに花が手向けられていた。それ以外のときは、小さなカーテンで隠されていた。絵の中の若い女は、どこか優しくて甘い顔立ちをしていたが、腕が多すぎて、なんだか蜘蛛みたいに見えちまった。

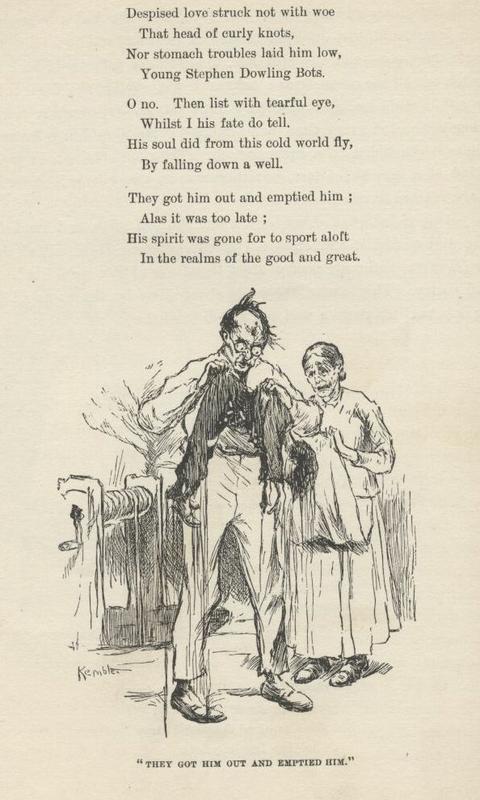
この若い娘は生きていた頃、スクラップブックを持っていて、『長老派評論』から死亡記事や事故、痛ましい苦難の事例を切り抜いて貼り付け、それをもとに自分の頭で詩を書いていた。それはとても良い詩だった。これは、スティーヴン・ダウリング・ボッツという名前の少年が井戸に落ちて溺れ死んだことについて彼女が書いたものだ。
故スティーヴン・ダウリング・ボッツ君に捧げる頌歌
若きスティーヴンは病み、 若きスティーヴンは死せしか? 悲しき心は沈み、 嘆く者らは泣きしか? 否、若きスティーヴン・ダウリング・ボッツの 運命はかくのごときにあらず。 悲しき心は彼を囲めど、 病の矢に射られしにあらず。 百日咳はその体を苦しめず、 斑点もて陰鬱なるはしかにもあらず。 これらは聖なる名を損なわず、 スティーヴン・ダウリング・ボッツの名を。 蔑まれし恋は苦悩もて打たず、 その巻き毛の頭を。 胃の不調も彼を倒さず、 若きスティーヴン・ダウリング・ボッツを。 おお、否。されば涙の目にて聞け、 我、彼の運命を語らん。 彼の魂はこの冷たき世より飛び去りぬ、 井戸に落ちて。 人々は彼を引き上げ、水を吐かせしが、 ああ、時すでに遅し。 彼の魂は天翔けり、 善き者、偉大なる者の国にて戯れんと。
エメライン・グレンジャーフォードが十四歳になる前にあんな詩が作れたんだから、その後どんなことを成し遂げたか、誰にもわかりゃしねえ。バックが言うには、彼女は詩をすらすらと、いとも簡単に書いたそうだ。考えるために立ち止まる必要もなかった。一行書きなぐって、もし韻を踏む言葉が見つからなければ、さっさとそれを消して別の行を書きなぐり、先へ進んだ。彼女はこだわりがなかった。悲しい話でありさえすれば、どんな題材を与えられても書くことができた。誰かが死ぬと、男だろうが女だろうが子供だろうが、その体が冷たくなる前には、必ず彼女が『追悼の辞』を携えて現れた。彼女はそれを追悼の辞と呼んでいた。近所の人たちの話では、まず医者が来て、次にエメライン、それから葬儀屋だった――葬儀屋がエメラインより先に来たのは一度きりで、そのときは彼女、死んだ人の名前、ウィスラーというんだが、そいつに合う韻が見つからなくて手間取っちまったんだ。それ以来、彼女はすっかり変わっちまった。文句は言わなかったが、なんだかふさぎ込んで、長くは生きなかった。かわいそうな娘だ。彼女の絵に腹が立って、少し嫌気がさしたときなんかは、何度も無理して彼女のかつての小部屋に行って、彼女の哀れな古いスクラップブックを取り出して読んだものだ。俺はこの家族が、死んだ連中もみんな好きだったから、俺たちの間に何もわだかまりが生まれないようにしたかった。哀れなエメラインは、生きていた頃、死んだ人たちの詩をみんな書いたのに、今、彼女が逝ってしまったというのに、彼女についての詩を作る者が誰もいないのは、なんだかおかしい気がした。だから俺も一、二編ひねり出そうと頑張ってみたが、どうにもうまくいかねえんだ。みんなエメラインの部屋をきちんと整え、彼女が生きていた頃に好きだったように、すべてのものを配置していた。そして、誰もその部屋で寝ることはなかった。黒人はたくさんいたが、奥方が自分で部屋の世話をし、そこでよく裁縫をしたり、聖書を読んだりしていた。
さて、客間の話に戻るが、窓には美しいカーテンがかかっていた。白い布地に、壁じゅうに蔦が這う城と、水を飲みに下りてくる牛の絵が描かれていた。小さな古いピアノもあって、中にはブリキの鍋でも入っているんだろう、若いご婦人たちが『最後の絆は断たれて』を歌い、『プラハの戦い』を弾くのを聞くほど素敵なことはなかった。すべての部屋の壁は漆喰で塗られ、ほとんどの部屋の床には絨毯が敷かれていた。そして家全体が外側は白く塗られていた。
それは二棟続きの家で、二つの建物の間の大きな開けた場所は屋根と床が張られていた。ときどき、昼間にはそこにテーブルが置かれ、涼しくて快適な場所だった。これ以上いい場所はない。料理だって、そりゃあうまくて、量も山ほどあった!

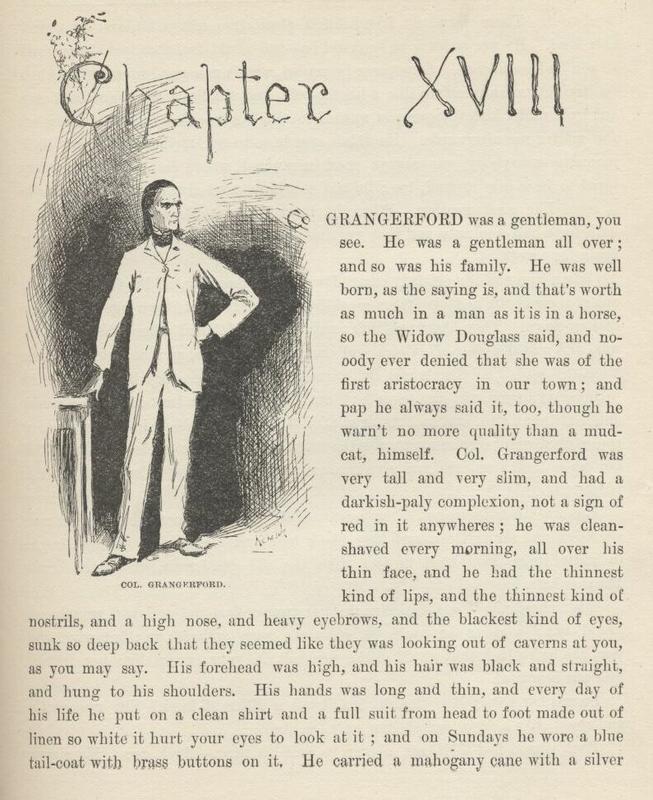
第十八章 グレンジャーフォード家
グレンジャーフォード大佐は、まあ、紳士だった。頭のてっぺんからつま先まで紳士で、それは家族も同じだった。いわゆる名家の生まれで、それは馬と同じで人間にとっても価値があることだとダグラス未亡人は言っていたし、彼女が俺たちの町で第一級の貴族であることに異を唱える者はいなかった。パップもいつもそう言っていた。もっとも、パップ自身は泥ナマズほどの身分もなかったが。グレンジャーフォード大佐は非常に背が高く、すらりとしていて、少し浅黒く青白い顔色で、赤みはどこにもなかった。薄い顔を毎朝きれいに剃り上げ、この上なく薄い唇と、この上なく薄い鼻孔、高い鼻、濃い眉、そして真っ黒な瞳を持っていた。その瞳は非常に奥まっていて、まるで洞窟の中からお前を見ているかのようだった。額は高く、髪は黒い直毛で肩まで垂れていた。手は長くて細く、毎日、目に痛いほど真っ白なリネンのシャツとスーツを頭からつま先まで着込んだ。日曜日には真鍮のボタンがついた青い燕尾服を着た。銀の頭のついたマホガニーの杖を持ち歩いていた。彼には軽薄なところが微塵もなく、大声を出すことも決してなかった。この上なく親切な男で――それはわかるだろう、だから信頼できた。ときどき微笑むことがあり、それを見るのは心地よかった。だが、自由の旗竿みたいにすっくと背筋を伸ばし、眉の下から稲妻がひらめき始めると、まずは木に登って、それから何が起きたのか確かめたくなるような男だった。彼は誰かに礼儀正しくしろと言う必要はなかった――彼がいる場所では、誰もが常に礼儀正しかった。みんな彼がそばにいるのを好んだ。彼はほとんどいつも太陽のようだった――つまり、彼がいると天気が良いように思えるんだ。彼が暗雲に変わると、半分の間、恐ろしく暗くなったが、それで十分だった。一週間は何も悪いことは起こらなかった。
朝、彼と奥方が階下に下りてくると、家族全員が椅子から立ち上がって挨拶をし、二人が腰を下ろすまで再び座ることはなかった。それからトムとボブがサイドボードのデキャンタのところへ行き、ビターズを一杯作って彼に手渡した。彼はそれを手に持ち、トムとボブの分ができるのを待った。そして二人がお辞儀をして「旦那様、奥様、ご機嫌よう」と言うと、彼らはほんの少しだけお辞儀をして「ありがとう」と答え、三人でそれを飲んだ。ボブとトムは、自分たちのタンブラーの底に残った砂糖とほんのわずかなウィスキーかアップルブランデーにスプーン一杯の水を注ぎ、それを俺とバックにくれた。俺たちも年長者たちに乾杯した。
ボブが長男で、トムが次男だった――背が高く、美しい男たちで、非常に広い肩幅と日に焼けた顔、長い黒髪と黒い瞳をしていた。彼らは父親と同じように、頭からつま先まで白いリネンをまとい、つばの広いパナマ帽をかぶっていた。
それからミス・シャーロットがいた。彼女は二十五歳で、背が高く、誇り高く、堂々としていたが、機嫌を損ねていないときはこの上なく良い人だった。だが、一度機嫌を損ねると、父親譲りの、その場でお前を萎縮させてしまうような眼差しをした。彼女は美しかった。
妹のミス・ソフィアも美しかったが、種類が違った。彼女は鳩のように優しく、おとなしくて、まだ二十歳だった。
一人一人に、世話をする黒人がついていた――バックにもだ。俺の黒人はとてつもなく楽な仕事だった。俺は誰かに何かをしてもらうのに慣れていなかったからだ。だが、バックの黒人はほとんどいつも走り回っていた。
今の家族はこれだけだったが、以前はもっといた――三人の息子がいたが、殺された。それから、死んだエメラインだ。
旦那様はたくさんの農場と百人以上の黒人を所有していた。ときどき、十マイルか十五マイル離れたところから大勢の人が馬に乗ってやってきて、五、六日滞在し、あちこちや川で宴会をしたり、昼間は森でダンスやピクニックをしたり、夜は家で舞踏会を開いたりした。こうした人々はほとんどが家族の親類だった。男たちは銃を持ってきた。言っておくが、立派な上流階級の集まりだった。
そのあたりにはもう一つ、貴族の一族がいた――五、六家族で、ほとんどがシェパードソンという名前だった。彼らもグレンジャーフォード家と同じくらい、気位が高く、家柄も良く、金持ちで、堂々としていた。シェパードソン家とグレンジャーフォード家は同じ蒸気船の船着き場を使っていて、それは俺たちの家から二マイルほど上流にあった。だからときどき、俺たちの家族大勢とそこへ行くと、立派な馬に乗ったシェパードソン家の連中を大勢見かけた。
ある日、バックと俺は森の奥深くまで狩りに出かけ、馬が近づいてくる音を聞いた。俺たちは道を横切っているところだった。バックが言った。
「早く! 森に飛び込め!」
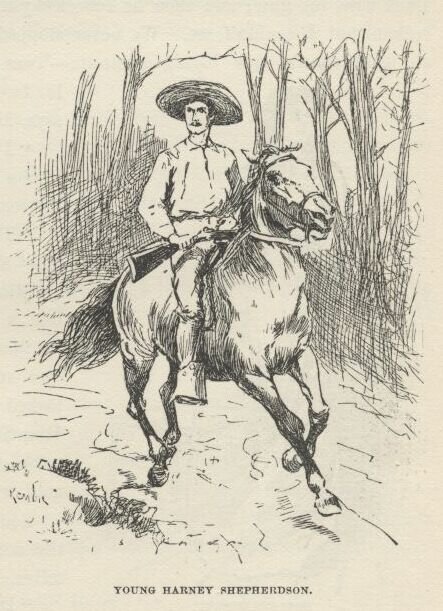
俺たちはそうして、森の葉陰から道を覗き見た。まもなく、素晴らしい若者が道を馬で駆け下りてきた。馬の乗りこなしは楽々としていて、兵士のようだった。鞍の前には銃を横たえていた。俺は前に彼を見たことがあった。若いハーニー・シェパードソンだった。俺の耳元でバックの銃が火を噴き、ハーニーの帽子が頭から転がり落ちた。彼は銃をつかみ、俺たちが隠れている場所へまっすぐ馬を走らせた。だが、俺たちは待ってはいなかった。森の中を走り出した。森はそれほど密ではなかったので、弾をよけるために肩越しに振り返ると、二度、ハーニーがバックに銃を向けるのが見えた。それから彼は来た道を戻っていった――帽子を取りに行ったんだろう、俺には見えなかったが。俺たちは家に着くまで走り続けた。旦那様の目は一瞬燃え上がった――主に喜びからだと俺は判断した――それから彼の顔つきはいくらか和らぎ、穏やかな口調で言った。
「茂みの後ろから撃つのは好かんな。なぜ道に出なかった、坊主。」
「シェパードソン家はそうはしません、父さん。彼らはいつも不意打ちをします。」
バックが話をしている間、ミス・シャーロットは女王のように頭を高く上げ、鼻の穴を広げ、目をきらりとさせた。二人の若い男たちは暗い表情をしていたが、何も言わなかった。ミス・ソフィアは青ざめたが、男が無事だとわかると顔色が戻った。

俺はできるだけ早くバックを、木々の下のトウモロコシ貯蔵庫のそばへ連れて行き、二人きりになると言った。
「あいつを殺したかったのか、バック?」
「ああ、もちろんさ。」
「あいつがお前に何をしたんだ?」
「あいつ? 俺に何もしてねえよ。」
「じゃあ、なんで殺したかったんだ?」
「なんでって――ただの確執のせいさ。」
「確執ってなんだ?」
「おい、お前どこで育ったんだ? 確執も知らねえのか?」
「聞いたこともねえよ――教えてくれ。」
「いいか」とバックは言った。「確執ってのはこうだ。一人の男が別の男と喧嘩して、そいつを殺す。すると、殺された男の兄弟が、今度はそいつを殺す。それから両方の家の兄弟たちが、お互いを狙い始める。そのうちにいとこ連中も加わって――しまいにはみんな殺しちまって、確執はなくなる。でも、そいつはけっこうのろくて、長い時間がかかるんだ。」
「こいつはもう長く続いてるのか、バック?」
「そりゃあ、もちろんさ! 三十年か、そのくらい前に始まった。何かでもめ事があって、それを解決するために裁判になった。その裁判で片方の男が負けて、それでそいつは訴訟に勝った男を撃ち殺したんだ――もちろん、当然のことさ。誰だってそうする。」
「何でもめたんだ、バック? ――土地か?」
「たぶんな――わかんねえ。」
「で、撃ったのは誰なんだ? グレンジャーフォードか、シェパードソンか?」
「ちくしょう、俺にわかるもんか。ずいぶん昔のことだ。」
「誰も知らねえのか?」
「ああ、いや、父さんは知ってると思うぜ、ほかの年寄りも何人かはな。でも、今じゃ最初のいさかいが何についてだったのかは知らねえんだ。」
「たくさん殺されたのか、バック?」
「ああ、かなりの数の葬式があった。でも、いつも殺すわけじゃねえ。父さんの体には散弾がいくつか入ってるけど、どうせたいして重くもねえから気にしてねえ。ボブはボウイナイフで少し切り刻まれたし、トムも一、二度怪我をした。」
「今年は誰か殺されたのか、バック?」
「ああ、こっちが一人、あっちが一人だ。三ヶ月くらい前、俺のいとこのバドが、十四歳だったんだが、川の向こう側の森を馬で走ってた。武器を持ってなかったんだが、そいつがとんでもない馬鹿だった。それで、寂しい場所で後ろから馬が来る音がして、見ると、バルディ・シェパードソンじいさんが銃を手に、白髪を風になびかせながら追いかけてくる。バドは馬から飛び降りて茂みに隠れる代わりに、逃げ切れると思ったんだ。それで、五マイル以上も、きわどい追跡劇になった。じいさんはどんどん追いついてくる。とうとうバドは無駄だと悟って、立ち止まって向き直った。弾痕が体の前にできるように、わかるだろ。そしたらじいさんが馬でやってきて、彼を撃ち殺した。でも、その幸運を長く楽しむ暇はなかった。一週間もしないうちに、俺たちの仲間があのじいさんを片付けたからな。」
「そのじいさんは臆病者だったんだろうな、バック。」
「臆病者なんかじゃなかったさ。とんでもない。シェパードソン家には臆病者なんて一人もいねえ――一人もな。グレンジャーフォード家にも臆病者はいない。なんだ、あのじいさんはある日、三人のグレンジャーフォードを相手に三十分も戦い抜いて、勝ったんだぜ。みんな馬に乗ってた。じいさんは馬から下りて、小さな薪の山のかげに隠れ、自分の馬を前に置いて弾除けにした。でもグレンジャーフォードの連中は馬に乗ったままで、じいさんの周りを跳ね回って、撃ちまくった。じいさんも撃ち返した。じいさんとその馬は、二人とも穴だらけでボロボロになって家に帰ったが、グレンジャーフォードの連中は家に『運んで』もらわなきゃならなかった――一人は死んでて、もう一人は次の日に死んだ。いや、もし誰かが臆病者を探してるんなら、シェパードソン家のあたりで時間を無駄にするべきじゃねえ。あそこではそんな『種類』は育たねえからな。」
次の日曜日、俺たちはみんなで三マイルほど離れた教会へ行った。全員馬に乗っていた。男たちは銃を持っていき、バックも同じで、膝の間に挟んだり、壁に立てかけたりした。シェパードソン家の連中も同じだった。説教はかなりひどいもんで――兄弟愛だの、そういう退屈な話ばっかりだった。でも、みんなは良い説教だったと言い、帰り道もその話で持ちきりだった。信仰とか善行とか、神の無償の恩恵とか予定説とか、俺にはなんだかよくわからねえことについて、ものすごい勢いでしゃべりまくっていた。俺にとっては、今までで一番荒々しい日曜日のように思えた。
昼食後一時間もすると、みんなあちこちでうたた寝を始めた。椅子に座ったままの者もいれば、部屋で寝ている者もいて、かなり退屈になった。バックと犬が一匹、日当たりのいい芝生の上で伸びて、ぐっすり眠っていた。俺は自分たちの部屋へ上がり、俺も一眠りしようと思った。すると、あの優しいミス・ソフィアが、俺たちの隣にある自分の部屋の戸口に立っていた。彼女は俺を自分の部屋に招き入れ、そっとドアを閉め、俺のことが好きかと尋ねた。俺は好きだと答えた。すると彼女は、誰にも言わずに何かをしてくれないかと頼み、俺はやると言った。それから彼女は、聖書を忘れて、教会の席の二冊の本の間に置いてきてしまったので、静かに抜け出してそこへ取りに行ってきてくれないか、誰にも何も言わずに、と頼んだ。俺はわかったと答えた。そこで俺はそっと抜け出し、道を急いだ。教会には誰もいなかった。せいぜい豚が一、二匹いるくらいで、ドアに鍵はかかっておらず、豚は夏になると涼しいから厚板の床を好むんだ。気づいただろうが、たいていの人間は、行かなきゃならないときしか教会に行かない。でも豚は違う。

俺は独り言を言った。何かがおかしい、娘が聖書ごときでこんなに焦るなんて不自然だ。そこで俺はそれを振ってみると、中から小さな紙切れが落ちてきた。鉛筆で「『二時半』」と書いてあった。俺はそれをくまなく探したが、ほかには何も見つからなかった。それだけでは何のことかわからなかったので、俺はその紙を本に戻し、家に帰って二階へ上がると、ミス・ソフィアが戸口で俺を待っていた。彼女は俺を中に引き入れてドアを閉めた。それから聖書の中を調べて紙を見つけると、それを読んだ途端、嬉しそうな顔をした。そして、考える間もなく俺をひっつかんで抱きしめ、お前は世界一いい子だ、誰にも言っちゃだめよ、と言った。彼女は一瞬、顔を真っ赤にし、目を輝かせた。そのせいで、彼女はものすごくきれいに見えた。俺はかなり驚いたが、息が整うと、その紙は何のことかと尋ねた。彼女は読んだかと尋ね、俺は読んでいないと答えた。彼女は字が読めるかと尋ね、俺は「いいや、下手な字だけだ」と答えた。すると彼女は、その紙はただのしおりで、場所を覚えておくためのものだと言い、もう遊びに行っていいわよ、と言った。
俺は川へ下りていき、このことを考え巡らしていた。まもなく、俺の黒人が後ろからついてきているのに気づいた。家が見えなくなると、彼は一瞬、後ろや周りを見回し、それから走ってきて言った。
「ジョージ旦那、沼地に来てくだされば、水蛇がうじゃうじゃいる場所をお見せしますぜ。」
俺は思った。こいつは妙だ。昨日も同じことを言っていた。俺が水蛇をわざわざ探し回るほど好きじゃないことくらい、知っているはずだ。いったい何を企んでいるんだ? そこで俺は言った。
「わかった。先に行け。」
俺は半マイルほどついていった。それから彼は沼地に入り、さらに半マイルほど足首まで水に浸かって進んだ。俺たちは、木や茂みや蔓がうっそうと茂った、乾いた小さな平地に着いた。彼は言った。
「旦那、そこへほんの数歩入ってくだせえ。そこにいやがります。あっしは前に見やした。もう見たくはねえんで。」
それから彼はじゃぶじゃぶと歩き去り、まもなく木々が彼の姿を隠した。俺はその場所へ少し入っていくと、寝室ほどの広さの、蔓に囲まれた小さな空き地に出た。そして、そこに男が一人、眠っているのを見つけた――そして、驚いたことに、それは昔なじみのジムじゃないか!
俺は彼を起こした。俺に再会すれば、さぞかし驚くだろうと思ったが、そうではなかった。彼は嬉しさのあまり泣きそうになったが、驚いてはいなかった。言うには、あの夜、俺の後ろを泳いできて、俺が叫ぶのを毎回聞いていたが、返事はできなかった。誰かに捕まって、また奴隷にされるのはごめんだったからだそうだ。彼は言った。
「わしはちいと怪我してな、速う泳げんかったんや。せやから、最後のほうはあんたからえらい離されとった。あんたが陸に上がったとき、陸の上なら叫ばんでも追いつけるやろうと思たんや。けど、あの家が見えたとき、わしはゆっくり行くことにしたんや。遠すぎて、連中があんたに何を言うとるかは聞こえんかった――犬が怖かったんや。けど、またあたりが静かになったとき、あんたが家の中におるんやとわかった。せやから、わしは森へ向こうて、夜が明けるのを待ったんや。朝早うに、黒人の何人かが畑へ行く途中、わしを見つけて、この場所へ連れてきてくれたんや。ここは水があるから犬も追ってこれん。毎晩、食いもんも持ってきてくれるし、あんたがどないしとるかも教えてくれるんや。」
「なんで俺のジャックに、もっと早く俺をここに連れてくるように言わなかったんだ、ジム?」
「まあ、何かでけるようになるまで、あんたの邪魔するんは意味ないやろ、ハック。けど、もう大丈夫や。わしは機会があるたびに鍋やらフライパンやら食料やらを買い集めとったし、夜にはいかだを直しとったんや。そんとき――」
「『どの』いかだだって、ジム?」
「わしらの古いいかだや。」
「まさか、俺たちの古いいかだが粉々になってなかったって言うのか?」
「いや、壊れとらん。そりゃまあ、えらいことになっとったけどな――片っぽの端はな。けど、大した被害はなかったんや。ただ、わしらの荷物がほとんど全部なくなっただけでな。もしわしらがもっと深う潜って、もっと遠くまで水中を泳いで、夜がもっと暗うのうて、あんたもわしもあないにびびって、世間で言うみたいに、あないなアホンダラやなかったら、いかだが見えとったはずや。けど、見えんくてよかったんかもしれん。今じゃほとんど新品同然に直し終わったし、なくなったもんの代わりに、新しい荷物も手に入ったんやからな。」
「どうやっていかだをまた手に入れたんだ、ジム――捕まえたのか?」
「わしが森におるのに、どないして捕まえられんねん? いや、黒人の何人かが、このへんの川の曲がり角で切り株に引っかかっとるのを見つけたんや。そんで、柳の茂みの中の入り江に隠したんや。そしたら、どっちが一番所有権があるかでもめとってな、わしはすぐにその話を聞きつけた。せやから、わしが割って入って、そのいかだは誰のもんでものうて、あんたとわしのもんやと教えてやって、騒ぎを収めたんや。わしはあいつらに言うたんや。『若い白人の旦那様の財産を横取りして、ひどい目に遭いたんか?』ってな。それから、一人十セントずつやったら、あいつらはえらい満足して、またいかだが流れてきて金持ちになれんかなあ、なんて言うとった。ここの黒人らは、わしにえらい親切やで、ハニー。わしが何ぞ頼んでも、二度頼む必要はないんや。あのジャックはええ黒人やし、かなり賢い。」
「ああ、そうだな。あいつは一度もお前がここにいるなんて言わなかった。来い、水蛇がたくさんいるところを見せてやるって言っただけだ。もし何か起きても、あいつは巻き込まれない。俺たちを一緒に見たことはないと言えるし、それは本当のことだ。」
次の日のことはあまり話したくない。かなり短く切り上げるつもりだ。俺は夜明け頃に目を覚まし、寝返りを打ってもう一度眠ろうとしたとき、あたりがどれほど静かだったかに気づいた――誰も動いている気配がなかった。それは普通ではなかった。次に、バックが起きていなくなっているのに気づいた。まあ、俺は不思議に思いながら起き上がり、階下へ下りていった――誰もいない。ネズミ一匹いないほど静かだった。外も同じだった。俺は思った。どういうことだ? 薪の山のそばで、俺のジャックに出くわし、言った。
「いったいどうしたんだ?」
彼は言った。
「ご存じねえんですかい、ジョージ旦那?」
「いや」と俺は言った。「知らねえ。」
「そりゃあ、ミス・ソフィアが駆け落ちしなすったんでさ! ほんとでさあ。夜中にいつの間にか――誰もいつだか知らねえんでさ。あの若いハーニー・シェパードソンと結婚するために駆け落ちしなすったんでさ。まあ、みんなそう思ってるんでさ。ご家族がそれに気づいたのは三十分ほど前――もう少し前かもしれねえ――そりゃあ、もう、一刻の猶予もなかったんでさ! あんなに大慌てで銃や馬を用意するなんざ、見たこともねえ! 女衆は親類に知らせに行きなすったし、ソウル旦那様と息子さんたちは銃を取って、川沿いの道を馬で駆け上がっていきなすった。あの若者がミス・ソフィアを連れて川を渡る前に捕まえて殺そうってんでさ。そりゃあ、ひどいことになりやすぜ。」
「バックは俺を起こさずに行ったのか。」
「そりゃあ、そうでさあ! 旦那様を巻き込むつもりはなかったんでさ。バック旦那様は銃に弾を込めると、シェパードソンを一人仕留めて帰ってくるか、さもなきゃ死ぬかって言いなすった。まあ、向こうには大勢いやがるでしょうから、チャンスがありゃあ、きっと一人仕留めてきやすぜ。」
俺は川沿いの道を、出せる限りの速さで駆け上がった。やがて、遠くで銃声が聞こえ始めた。蒸気船が着く丸太小屋と薪の山が見えてくると、俺は木々や茂みの下を伝って良い場所まで進み、それから手の届かないハコヤナギの木の枝分かれしたところに登って、様子をうかがった。木の少し手前に、高さ四フィートの薪の列があった。最初はその後ろに隠れようと思ったが、そうしなくて運が良かったのかもしれない。
丸太小屋の前の広場では、四、五人の男が馬に乗って暴れ回り、罵り、叫び、蒸気船の船着き場脇の薪の列の後ろにいる二人の若者を捕まえようとしていたが、うまくいかなかった。彼らの一人が薪の山の川側から姿を見せるたびに、撃たれた。二人の少年は山を背にしてしゃがみ、両方向を見張れるようにしていた。
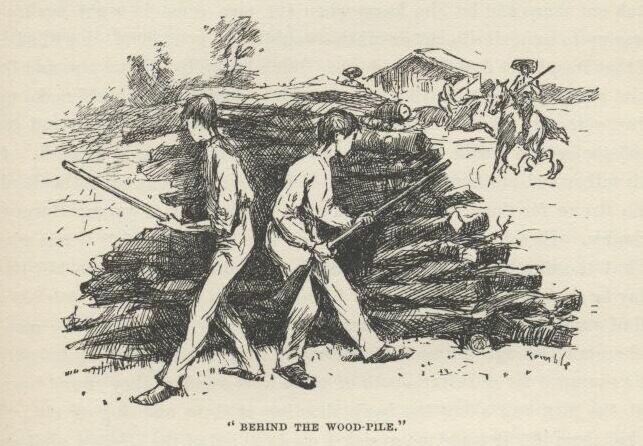
やがて、男たちは暴れ回ったり叫んだりするのをやめた。彼らは小屋に向かって馬を乗り始めた。すると少年の一人が立ち上がり、薪の列越しにじっと狙いを定め、男の一人を鞍から撃ち落とした。男たちは全員馬から飛び降り、怪我をした男を掴んで小屋へ運ぼうとし始めた。その瞬間、二人の少年が走り出した。男たちが気づく前に、彼らは俺がいる木の半分まで来ていた。そこで男たちは彼らに気づき、馬に飛び乗って後を追った。彼らは少年たちに追いついてきたが、無駄だった。少年たちの方が先に走り出していたからだ。彼らは俺の木の前の薪の山に着き、その後ろに滑り込んだ。こうして、彼らは再び男たちより有利になった。少年の一人はバックで、もう一人は十九歳くらいの、ほっそりした若者だった。
男たちはしばらく荒れ狂っていたが、やがて馬で去っていった。彼らの姿が見えなくなるとすぐに、俺はバックに大声で知らせた。彼は最初、木の中から聞こえてくる俺の声が何だかわからなかった。ひどく驚いていた。彼は俺に、よく見張っていて、男たちがまた見えたら知らせろと言った。あいつらは何か悪だくみをしているに違いない――長くはいなくなっていないだろう、と。俺はこの木から下りたかったが、怖くて下りられなかった。バックは泣き叫び始め、彼と彼のいとこのジョー(もう一人の若者だ)は、今日の借りはいつか必ず返すと誓った。彼の父親と二人の兄は殺され、敵も二、三人殺されたと言った。シェパードソン家が彼らを待ち伏せしたそうだ。バックは、父親と兄たちは親戚が来るのを待つべきだったと言った――シェパードソン家は彼らにとって強すぎたのだ。俺は若いハーニーとミス・ソフィアがどうなったか尋ねた。彼は、二人は川を渡り切って無事だと言った。俺はそれを聞いて嬉しかった。だが、バックが、あの日にハーニーを撃ったときに殺しそこねたことを悔しがる様子は――あんなのは聞いたことがなかった。
突然、バン! バン! バン! と三、四発の銃声が響いた――男たちが森を迂回して、馬なしで後ろからやってきたのだ! 少年たちは川へ飛び込んだ――二人とも怪我をしていた――そして彼らが流れに乗って泳ぎ下っていくと、男たちは岸辺を走りながら彼らを撃ち、「殺せ、殺せ!」と叫び続けた。俺は気分が悪くなって、木から落ちそうになった。何が起こったか『全部』は話すつもりはない――そんなことをしたら、また気分が悪くなるだろうから。あの夜、あんなものを見るために岸に上がらなければよかったと心から思った。俺は決してあれらの光景から逃れられないだろう――何度も夢に見るんだ。
俺は暗くなるまで木の上にいた。下りるのが怖かったからだ。ときどき、森の遠くで銃声が聞こえた。二度、小さな男たちの集団が銃を持って丸太小屋を馬で駆け抜けていくのを見た。だから、いさかいはまだ続いているんだと思った。俺はひどく落ち込んでいた。だから、もう二度とあの家に近づかないと決心した。どういうわけか、俺のせいだと思ったからだ。あの紙切れは、ミス・ソフィアが二時半にどこかでハーニーと会って駆け落ちするという意味だったんだと、俺は判断した。そして、あの紙のことや、彼女の奇妙な振る舞いを彼女の父親に話すべきだったんだと思った。そうすれば、たぶん彼は彼女を閉じ込め、このひどい騒ぎは決して起こらなかっただろう。
木から下りると、俺は川岸を少し下って這うように進み、水際に横たわる二つの遺体を見つけた。それを引きずって岸に上げ、それから彼らの顔を覆い、できるだけ早くその場を離れた。バックの顔を覆うとき、俺は少し泣いた。あいつは俺にすごく良くしてくれたからだ。
もうすっかり暗かった。俺は家に近づかず、森を突っ切り、沼地へ向かった。ジムは彼の島にはいなかったので、俺は急いで入り江へ向かい、柳の茂みをかき分けた。いかだに飛び乗って、あの恐ろしい土地から逃げ出したくてたまらなかった。いかだがなくなっていた! なんてこった、俺は恐怖に震えた! 一分近く息ができなかった。それから俺は叫び声を上げた。二十五フィートも離れていないところから声がした。
「おお! あんたか、ハニー? 騒ぐなや。」
ジムの声だった――あんなに心地よく響いた声は、後にも先にもなかった。俺は岸を少し走り、いかだに乗り込むと、ジムは俺を掴んで抱きしめた。俺に会えてとても嬉しかったのだ。彼は言った。
「ありがたや、坊主、わしはあんたがまた死んじまったと本気で思うとったで。ジャックがここに来てな、あんたが撃たれたんやろうて言うとったんや。いつまでたっても家に帰ってこんかったからな。せやから、わしはたった今、いかだを入り江の口のほうへ流し始めたとこやったんや。ジャックがまた来て、あんたが『ほんまに』死んだと教えてくれたら、すぐに出航できるように準備しとったんや。ああ、ほんまにあんたが戻ってきてくれて嬉しいで、ハニー。」
俺は言った。
「わかった――そりゃあいい。あいつらは俺を見つけられないし、俺は殺されて川を流されたと思うだろう――そう思わせるようなものが、あそこの上流にあるからな――だから時間を無駄にするな、ジム、できるだけ早く広い川へ漕ぎ出してくれ。」
いかだがそこから二マイル下り、ミシシッピ川の真ん中に出るまで、俺は安心できなかった。それから俺たちは合図のランタンを吊るし、再び自由で安全になったと思った。俺は昨日から何も口にしていなかったので、ジムがコーン・ドジャーとバターミルク、豚肉とキャベツと青菜を出してくれた――うまく料理すれば、これほどうまいものはない――そして俺は夕食を食べながら、俺たちは話し、楽しい時を過ごした。俺は確執から逃れられてものすごく嬉しかったし、ジムも沼地から逃れられて嬉しかった。結局のところ、いかだみたいな家はねえな、って俺たちは言い合った。ほかの場所はどこも息が詰まるほど窮屈に思えるが、いかだは違う。いかだの上だと、とてつもなく自由で、気楽で、心地いいんだ。
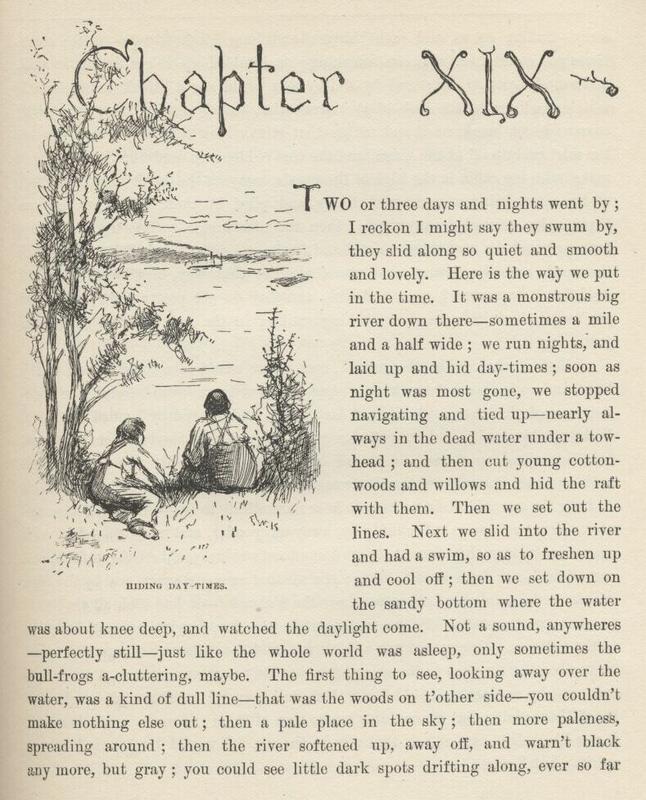
第十九章 いかだの上の暮らし
二、三日、昼も夜も過ぎていった。いや、泳いでいったと言ったほうがいいかもしれねえ。それくらい静かに、滑らかに、心地よく時が流れていったんだ。俺たちはこんなふうに時間を過ごした。このあたりの川はとてつもなく広く――ときには一マイル半もの幅があった。俺たちは夜に動き、昼間はどこかに停泊して隠れた。夜がほとんど明ける頃、俺たちは航行をやめていかだを繋いだ――たいていは、中州の下の淀んだ水域だった。それから若いハコヤナギや柳を切り倒し、それでいかだを隠した。次に釣り糸を垂らした。それから川に滑り込み、泳いで体をさっぱりさせ、涼んだ。それから、水深が膝くらいまでの砂底に腰を下ろし、夜が明けるのを眺めた。どこからも音はせず――完全に静まり返っていた――まるで世界中が眠っているかのようだった。ときどき、ウシガエルががたがた鳴くくらいだ。まず見えるのは、水のはるか向こうにある、ぼんやりとした一本の線――対岸の森だ。ほかには何も見分けがつかない。それから空に淡い場所が現れ、その淡い色が周りに広がっていく。それから、遠くの川面が和らぎ、もう黒くはなく、灰色になる。ずっと遠くに、小さな黒い点が流れていくのが見える――交易用の平底船か何かだ。そして長い黒い筋――いかだだ。ときどき、艪のきしむ音が聞こえたり、ごちゃごちゃした話し声が聞こえたりした。あまりに静かで、音が遠くまで届くからだ。やがて、水面に筋が見えてくる。その筋の様子から、流れの速い場所に切り株があって、水がそれにぶつかってあんなふうに見えるんだとわかる。水面から霧が立ち上り、東の空が赤くなり、川も赤くなる。川の向こう岸の、森の端に丸太小屋が見えてくる。たぶん薪置き場で、いかさま師どもが積み上げたもんだから、どこからでも犬を投げ通せるくらい隙間だらけだ。それから心地よいそよ風が吹いてきて、向こう岸からお前をあおぐ。森や花の匂いがするから、涼しくて、すがすがしくて、甘い香りがするんだ。だが、いつもそうとは限らねえ。ガーみてえな魚の死骸がそこらに置きっぱなしになってて、そいつがかなりひどい臭いを放つこともあるからな。そして次に、すっかり日が昇り、すべてのものが太陽の下で微笑み、さえずる鳥たちがただひたすらに歌い続ける!
今となっては多少の煙は目立たないだろうから、俺たちは釣り糸にかかった魚を何匹か外し、温かい朝飯の支度をする。それが済むと、川の寂寥とした景色を眺め、なんとなくのんびりと過ごし、やがては気怠さにまかせて眠りにつく。しばらくして目を覚まし、何があったのかと見渡すと、はるか向こう岸のほうを蒸気船が咳き込むように上っていくのが見えるかもしれない。あまりに遠くて、それが船尾外輪船か舷側外輪船かということ以外、何も分かりゃしない。それから一時間ばかりは、聞こえるものも見えるものもなく――ただただ骨の髄まで染みるような孤独が広がるだけだ。次に目に入るのは、向こうの方を滑っていくいかだだろう。たぶん、その上に乗った間抜けな男が薪を割っている。いかだの上ではたいてい誰かがそうしているものだから。斧がきらめいて振り下ろされるのが見える――音は何も聞こえない。斧が再び振り上げられ、男の頭上を越えたあたりで、ようやく『カコーン!』という音が聞こえるのだ。水の上を音が伝わってくるのに、それだけの時間がかかる。そんなふうにして、俺たちは一日をのんべんだらりと過ごし、静寂に耳を澄ますのだった。一度、深い霧が出たことがあり、通り過ぎるいかだやら何やらが、蒸気船に轢かれないようにブリキの鍋を叩いていた。平底船かいかだがすぐそばを通り過ぎた時には、連中の話し声や罵り声、笑い声が聞こえた――はっきりと聞こえたのだ。だが、その姿は影も形も見えない。なんだかぞっとするような気分だった。まるで亡霊が空中でそんなふうに騒いでいるみたいだった。ジムは、ありゃ亡霊にちげえねえと言ったが、俺はこう言ってやった。
「いいや、亡霊なら『クソ、このクソ霧が』なんて言わねえよ。」
夜のとばりが下りるとすぐ、俺たちはいかだを押し出した。川の中ほどまで来ると、あとは流れのままに任せる。それからパイプに火をつけ、水に足をぶらつかせながら、ありとあらゆることについて語り合った――蚊に食われない時なら、俺たちは昼も夜もいつも裸だった。バックの一家が作ってくれた新しい服は、着心地がいいというには上等すぎたし、それに俺はどのみち、服なんてものに大して興味はなかった。
時には、とてつもなく長い時間、この川全体が俺たちだけのものになることもあった。向こうには岸辺や島々が水を隔てて横たわっている。そして、ぽつんと光る火花――それは小屋の窓辺に灯る蝋燭の光だ。水面に一つか二つ、火花が見えることもある――いかだか平底船の上の、あれだ。そんな船から、バイオリンの音色や歌声が聞こえてくることもある。いかだの暮らしは最高だ。頭上には満天の星がちりばめられた空が広がり、俺たちはよく仰向けになってそれを眺め、星は作られたものなのか、それともただそこにあるだけなのか、議論したものだった。ジムは作られたもんだと言い張ったが、俺はただそこにあるだけだと思った。あんなにたくさん作るには、時間がかかりすぎると思ったからだ。ジムは、月があいつらを産んだのかもしれねえ、と言った。まあ、それはなんだか筋が通っているように思えたから、俺は何も反論しなかった。蛙が同じくらい沢山の卵を産むのを見たことがあるから、もちろん、そういうこともあり得るだろう。俺たちは流れ星もよく眺め、それが尾を引いて落ちていくのを見ていた。ジムは、ありゃ腐って巣から放り出されたもんだと言った。
一晩に一度か二度、蒸気船が闇の中を滑るように進んでいくのが見えた。時折、船は煙突から火の粉を世界中にぶちまけ、それが川面に雨のように降り注ぐ様は、恐ろしくも美しかった。やがて船は角を曲がり、その灯りが瞬いて消え、騒音も途絶え、川は再び静寂に包まれる。そして、船が去ってからずいぶん経って、その立てた波が俺たちのところに届き、いかだを少し揺らすのだ。その後は、どれほどの時間か分からないくらい、蛙か何かの鳴き声以外、何も聞こえなくなるのだった。
真夜中を過ぎると、岸の人々は寝床につき、二、三時間ほどは岸辺が真っ暗になる――小屋の窓に火花はもう見えない。この火花が俺たちの時計だった――再び最初の火花が見えれば、それは朝が近いという合図で、俺たちはすぐに隠れていかだを繋ぐ場所を探すのだった。
ある朝、夜が明けかける頃、俺はカヌーを見つけ、水路を渡って本土の岸へ向かった――ほんの二百ヤードほどの距離だった――そして、イトスギの森の中の小川を漕ぎ、ベリーが手に入らないかと一マイルほど上ってみた。ちょうど牛が通るような小道が小川を横切る場所を通りかかった時、二人の男が道を必死の形相で駆け上がってくるのが見えた。俺はもうおしまいだと思った。誰かが誰かを追いかけている時はいつでも、それは俺――あるいはジムのことだと相場が決まっていたからだ。急いでその場からずらかろうとしたが、連中はもうかなり近くまで来ていて、大声で叫び、命を助けてくれと懇願してきた――何も悪いことはしていないのに、追われているのだと言う――すぐそこまで男たちと犬が来ている、と。連中はすぐにでも飛び込もうとしたが、俺は言った。

「やめとけ。まだ犬や馬の音は聞こえねえ。藪をかき分けて小川を少し上る時間はまだある。そしたら水に入って、俺のところまで下ってきて乗り込め――そうすりゃ犬の鼻をくらませられる。」
連中は言われた通りにした。そして、乗り込むやいなや、俺は俺たちの砂州島へと急いだ。五分か十分もすると、遠くの方で犬と男たちの叫び声が聞こえた。連中が小川の方へ近づいてくる音は聞こえたが、姿は見えない。しばらく立ち止まってうろついているようだった。やがて、俺たちがどんどん遠ざかるにつれて、その声もほとんど聞こえなくなった。一マイルほどの森を後にし、川に出る頃には、あたりはすっかり静まり返っていた。俺たちは砂州島まで漕ぎ戻り、ワタの木立の中に隠れて、ようやく安全を確保した。
男の一人は七十歳かそれ以上で、頭は禿げ上がり、真っ白な髭を生やしていた。古くて型崩れしたソフト帽をかぶり、油で汚れた青いウールのシャツに、ぼろぼろの古いブルージーンズのズボンをブーツの先に突っ込んでいる。サスペンダーは自家製の毛糸編み――いや、片方しか着けていなかった。腕には、真鍮のボタンがてかてかになった古い燕尾型のブルージーンズの上着を引っ掛けていた。二人とも、大きくて分厚い、みすぼらしい絨毯生地の旅行鞄を持っていた。
もう一人の男は三十歳くらいで、同じくらいみすぼらしい格好をしていた。朝飯の後、俺たちはみんなで寝転がって話をした。そして最初に分かったのは、この二人はお互いを知らないということだった。
「あんた、何で面倒に巻き込まれたんだ?」と禿げ頭がもう一人に訊いた。
「ああ、歯の歯石を取る品物を売ってたんだ――実際、取れるんだがね、大抵はエナメル質も一緒にな――だが、一晩、長居しすぎちまってな。ちょうどずらかろうとしたところで、町のこっち側の小道であんたに出くわした。あんたが奴らが来ると教えてくれて、逃げるのを手伝ってくれと頼んできた。だから俺も面倒に巻き込まれそうなんだ、一緒に逃げようって言ったのさ。それが事の次第だ――あんたはどうなんだ?」
「わしか。わしはな、一週間ほど禁酒運動の集会を開いとったんじゃ。女どもには、老いも若きも大人気でな。なにせ、わしが酒飲みどもをさんざんにやり込めとったからな、本当じゃ。一晩に五、六ドルは稼いどった――一人十セント、子供と黒人は無料じゃ――商売はずっと上り調子じゃった。ところが、どういうわけか、昨日の夜、わしがこっそり私物の酒瓶で時間をつぶしとるという噂が広まってしまってな。今朝、黒人がわしを叩き起こして、連中が犬と馬を連れて静かに集まっとる、もうすぐやって来て、三十分ほど先に逃がしてやるが、その後は捕まえられるもんなら捕まえてみろと追ってくるだろう、と教えてくれたんじゃ。もし捕まったら、タールを塗って羽毛をつけられ、丸太に乗せられるのは確実じゃ。朝飯を待つ暇もなかった――腹も減っとらんかったしな。」
「おやじさん」と若い方が言った。「二人で組んでみるってのはどうだい? どう思う?」
「やぶさかではない。あんたの商売は――主に何だね?」
「本職は巡回印刷工さ。特効薬も少々。舞台役者――悲劇役者だ。機会があれば催眠術や骨相学もやる。気分転換に歌と地理を教える学校の先生もな。時には講演もする――ああ、いろんなことをやるよ――仕事でさえなけりゃ、手当たり次第何でもな。あんたの稼業は?」
「わしも若い頃は医者の真似事をずいぶんやった。手当て療法が一番の得意じゃ――癌や麻痺、そういった類の病気にな。それに、誰か事実を調べてくれる者が一緒なら、結構うまいこと占いをすることもできる。説教もわしの専門じゃ。野外伝道集会を回ったり、あちこちで伝道活動をしたりな。」
しばらく誰も何も言わなかった。やがて、若い男がため息をついて言った。
「ああ、悲しいかな!」
「何を悲しんでおるんじゃ?」と禿げ頭が言った。
「こんな人生を送る羽目になり、このような連中と成り下がってしまうとは、と嘆いているのだ」そう言って、彼はぼろ切れで目尻を拭い始めた。
「ふざけるな、この連中が気に食わねえってのか?」と禿げ頭が、かなりつっけんどんに、偉そうに言った。
「いえ、私には十分すぎる仲間です。私にふさわしい。かくも高貴であった私を、ここまで貶めたのは誰か? 私自身です。皆さんを責めているのではありません――とんでもない。誰のせいでもありません。すべては私が招いたこと。冷たい世が私に何をしようと構わない。一つだけ確かなことがある――私のための墓がどこかにある。世はこれまで通りに過ぎ去り、私からすべてを奪うだろう――愛する者、財産、すべてを。だが、それだけは奪えない。いつの日か、私はそこに横たわり、すべてを忘れ、私の哀れな傷ついた心は安らぎを得るだろう」彼は涙を拭き続けた。
「その哀れな傷ついた心とやらをどうにかしろ」と禿げ頭が言った。「なんでその哀れな傷ついた心をわしらに向けるんじゃ? わしらは何もしておらんぞ。」
「ええ、存じております。皆さんを責めてはおりません。私自身が身を落としたのです――そうです、私自身が。私が苦しむのは当然のこと――まったくもって当然――何の不平もありません。」
「どこから落ちてきたんじゃ? どこから落ちてきたというんじゃ?」
「ああ、信じてはくださらないでしょう。世は決して信じない――忘れましょう――どうでもよいことです。私の出生の秘密は――」
「出生の秘密だと! まさかあんたは――」
「紳士諸君」と若い男は、きわめて厳粛に言った。「皆さんに打ち明けましょう。皆さんなら信頼できると感じたからです。本来ならば、私は公爵なのです!」
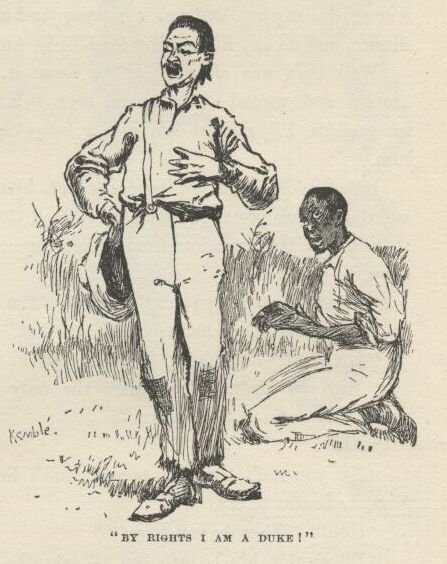
それを聞いたジムの目は飛び出さんばかりだった。俺の目もそうだったと思う。すると禿げ頭が言った。「まさか! 本気で言っとるのか?」
「ええ。私の曾祖父、ブリッジウォーター公爵の長男は、自由の清浄な空気を吸うため、前世紀の終わりにこの国へ逃れてきました。ここで結婚し、息子を残して亡くなりましたが、彼の父もほぼ同時期に亡くなりました。亡き公爵の次男が爵位と領地を奪い――赤子であった真の公爵は無視されたのです。私はその赤子の直系の子孫――私が正統なブリッジウォーター公爵なのです。そして今、私はここにいる。高貴な身分から引き裂かれ、人々に追われ、冷たい世に蔑まれ、ぼろをまとい、疲れ果て、心を砕かれ、いかだの上の罪人どもの仲間へと成り下がっているのです!」
ジムは彼を心から哀れんだ。俺もそうだ。俺たちは彼を慰めようとしたが、彼はあまり意味がない、大して慰めにはならないと言った。もし俺たちが彼を公爵と認めてくれるなら、それが他の何よりも力になると言う。だから俺たちは、どうすればいいか教えてくれるなら、そうすると言った。彼は、話しかける時はお辞儀をし、「殿下」とか「閣下」とか「猊下」と呼ぶべきだと言った――そして、単に「ブリッジウォーター」と呼んでも構わない、それはとにかく称号であって名前ではないから、と。そして、俺たちのうちの一人が食事の時に給仕をし、彼がしてほしいと思うどんな些細なことでもしてやるべきだ、と言った。
まあ、それはどれも簡単なことだったので、俺たちはそうした。食事の間中、ジムは彼の周りに立って給仕をし、「殿下、こちらはいかがでっしゃろか、それともあちらにしまっか?」などと言った。彼がそれに大いに満足しているのは、誰の目にも明らかだった。
しかし、年老いた男は次第に口数が少なくなっていった――あまり話さず、公爵の周りで繰り広げられているもてなしぶりに、あまり居心地が良さそうではなかった。何か思うところがあるようだった。そして、午後になって、彼はこう言った。
「おい、ビルジウォーター」と彼は言った。「あんたのことは心底気の毒に思うが、あんただけがそんな目に遭ったわけじゃないんじゃぞ。」
「なんですと?」
「そうじゃ。あんただけが高貴な身分から不当に引きずり下ろされたわけじゃない。」
「ああ、悲しいかな!」
「そうじゃ、あんただけが出生の秘密を抱えとるわけじゃないんじゃ」そして、驚いたことに、彼が泣き始めたのだ。
「待て! どういう意味だ?」
「ビルジウォーター、あんたを信じてもええか?」と老人は、まだ少しすすり泣きながら言った。
「死が二人を分かつまで!」彼は老人の手を取り、それを握りしめて言った。「あなたの存在の秘密、話してください!」
「ビルジウォーター、わしは、亡き王太子なんじゃ!」

請け合うが、今度こそジムと俺は目を丸くした。すると公爵が言った。
「あなたは何だと?」
「そうじゃ、友よ、紛れもない真実じゃ――あんたの目は今この瞬間、哀れな行方不明の王太子、ルイ十七世、ルイ十六世とマリー・アントワネットの息子を見ておるんじゃ。」
「あなたが! その年で! まさか! あなたが言っているのは、亡きシャルルマーニュ大帝のことでしょう。少なくとも六、七百歳にはなっているはずだ。」
「苦労がそうさせたんじゃ、ビルジウォーター、苦労がな。苦労がこの白髪と、この若禿げをもたらしたんじゃ。そうじゃ、紳士諸君、あんたたちの目の前にいるのは、ブルージーンズをまとい、悲嘆に暮れる、放浪し、追放され、踏みにじられ、苦しむ、フランスの正統な王なんじゃ。」
まあ、彼が泣いて嘆くものだから、俺とジムはどうしていいかほとんど分からなかった。とても気の毒だったし――そして、彼が仲間になってくれたことが嬉しくもあり、誇らしくもあった。だから俺たちは、公爵の時と同じように、彼を慰めようと努めた。しかし彼は、そんなことは無駄だ、死んで何もかも終わりにする以外に救われる道はないと言った。とはいえ、人々が彼の身分にふさわしい扱いをしてくれれば、しばらくは気分が楽になるとも言った。話しかける時は片膝をつき、常に「陛下」と呼び、食事の時は最初に給仕をし、彼が許すまでその前では座らないように、と。そこでジムと俺は、彼を「陛下」と呼び、あれやこれやと世話を焼き、彼が座っていいと言うまで立っていた。これが彼には大層効果があったようで、彼は陽気で心地よさそうになった。しかし、公爵は彼に少し不機嫌になり、物事の成り行きに少しも満足していない様子だった。それでも、王様は彼に対して実に友好的に振る舞い、公爵の曾祖父やビルジウォーターの他の公爵たちは皆、彼の父君に大いに重んじられ、宮殿への出入りもかなり許されていた、と言った。しかし、公爵はしばらくむっつりしていた。やがて王様がこう言った。
「どうやらわしらは、このいかだの上で、とんでもなく長い時間を一緒に過ごすことになりそうじゃな、ビルジウォーター。だから、むくれていて何になる? 物事が居心地悪くなるだけじゃ。わしが公爵に生まれなかったのはわしのせいじゃないし、あんたが王様に生まれなかったのもあんたのせいじゃない――だから、くよくよしてどうする? 目の前にあるもので最善を尽くす、わしはそうしとる――それがわしの信条じゃ。ここでわしらが出くわしたもんは、決して悪いもんじゃない――食い物はたっぷり、暮らしは楽ちんじゃ――さあ、手を貸しなされ、公爵、みんなで友達になろうじゃないか。」
公爵はそうした。ジムと俺はそれを見てとても嬉しかった。気まずい雰囲気はすっかりなくなり、俺たちは心からほっとした。いかだの上で不和があるなんて、惨めなことこの上ないからだ。いかだの上で何よりも望むのは、誰もが満足し、お互いに親切な気持ちでいられることなのだから。
こいつらが王様でも公爵でもなく、ただの下劣な詐欺師でペテン師だということに気づくのに、そう時間はかからなかった。だが俺は何も言わず、おくびにも出さなかった。自分の胸にしまっておいた。それが一番いいやり方だ。そうすれば喧嘩にもならないし、面倒に巻き込まれることもない。連中が俺たちに王様だの公爵だのと呼んでほしければ、家族の平和が保たれる限り、俺に異存はなかった。ジムに話したところでどうにもならないから、言わなかった。もし俺がパップから何も学ばなかったとしても、あいつみたいな連中とうまくやっていく最善の方法は、好きにさせておくことだ、ということだけは学んでいた。

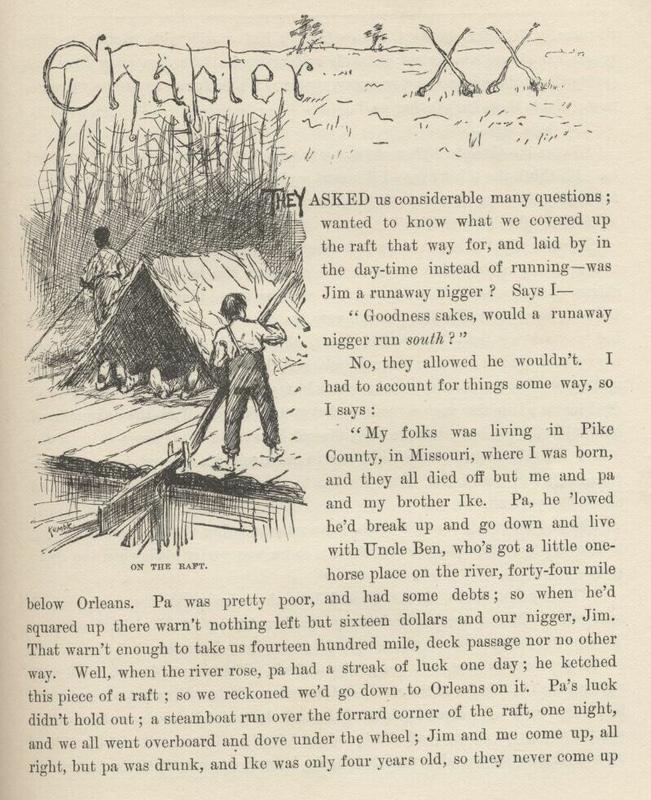
第二十章 いかだの上の王様たち
連中は俺たちにかなりの数の質問を浴びせてきた。なぜいかだをあんなふうに覆っているのか、昼間は航行せずに停泊しているのはなぜか、ジムは逃亡奴隷なのか、と知りたがった。俺は言った。
「とんでもない。逃亡奴隷が南へ逃げると思いますかい?」
いや、それはありえないだろう、と連中は認めた。俺は何とかして物事を説明しなければならなかったので、こう言った。
「俺の一家は、俺が生まれたミズーリ州のパイク郡に住んでたんですが、俺と親父と弟のアイクを残してみんな死んじまったんです。親父は、所帯をたたんで南へ下り、オルレアンから四十四マイル下流で小さな馬一頭の農場をやってるベン叔父さんのところで暮らすことにしたんです。親父はかなり貧乏で、借金もいくらかありました。だから借金を清算したら、手元には十六ドルと、うちの黒人のジムしか残らなかったんです。それだけじゃ、甲板船室だろうと他の方法だろうと、千四百マイルの旅はできませんでした。ところが、川が増水したある日、親父に幸運が舞い込んだんです。このいかだの切れ端を捕まえたんです。それで、こいつに乗ってオルレアンまで下ることにしたんです。でも、親父の幸運は続きませんでした。ある夜、蒸気船がいかだの前の角に乗り上げて、俺たちはみんな船外に投げ出され、外輪の下に潜り込みました。ジムと俺は無事だったんですが、親父は酔っ払っていたし、アイクはまだ四歳だったんで、二度と浮かんできませんでした。それで、その後の一、二日はかなり厄介なことになったんです。というのも、しょっちゅう人が小舟でやって来ては、ジムを俺から引き離そうとするんです。ジムが逃亡奴隷だと信じ込んでいるみたいで。だから、もう昼間は航行しないんです。夜なら、誰も邪魔してきませんから。」
公爵が言った。
「昼間でも航行できる方法を考え出すのは、私に任せたまえ。じっくり考えてみよう――それを解決する計画を考案してやる。今日はこのままにしておこう。もちろん、あそこの町を白昼堂々通り過ぎたくはないからな――健康的とは言えんだろう。」
夜に向かって空は暗くなり始め、雨が降りそうな気配だった。空の低いところで熱雷が走り、木の葉が震え始めていた――かなり荒れ模様になるだろうことは、容易に見て取れた。そこで公爵と王様は、俺たちの小屋を調べて、寝床がどんなものか確かめに行った。俺の寝床は藁のマットレスで、トウモロコシの皮のマットレスだったジムのよりは上等だった。皮のマットレスにはいつもトウモロコシの芯が混じっていて、それが体に突き刺さって痛いのだ。それに、寝返りを打つと乾いた皮が、枯れ葉の山の上で転がっているような音を立てる。そのガサガサという音で目が覚めてしまう。さて、公爵は俺の寝床を取ると言ったが、王様はそれを許さなかった。彼は言った。
「身分の違いを考えれば、トウモロコシの皮の寝床がわしにふさわしくないことは、おぬしにも示唆されたはずじゃがな。殿下、ご自身が皮の寝床をお使いなされ。」
ジムと俺はまた一瞬ひやひやした。また連中の間で揉め事が起こるんじゃないかと心配したからだ。だから、公爵がこう言った時は、かなりほっとした。
「圧政の鉄の踵の下で、常に泥に踏みにじられるのが私の運命だ。不運が、かつては高慢だった私の精神を打ち砕いた。私は屈し、服従する。それが私の運命なのだ。私はこの世で孤独だ――苦しませてくれ。私は耐えられる。」
すっかり暗くなるとすぐに、俺たちはいかだを出した。王様は、川の中央寄りを進み、町をずっと下るまで灯りを見せるなと俺たちに言った。やがて、小さな光の塊が見えてきた――あれが町だ――そして、半マイルほど離れて、無事に通り過ぎた。四分の三マイルほど下流まで来たところで、俺たちは合図のランタンを掲げた。そして十時頃、雨と風と雷と稲妻が、ありとあらゆるもののように襲ってきた。そこで王様は、天気が良くなるまで二人とも見張りを続けろと言い、それから彼と公爵は小屋に這い入って寝てしまった。俺は十二時まで下の見張りだったが、たとえ寝床があったとしても、どのみち寝るつもりはなかった。あんな嵐は、一週間のうち毎日見られるものじゃない、到底な。ああ、なんて風が唸りを上げるんだ! そして一、二秒ごとに閃光が走り、半マイル先の白波を照らし出し、雨の向こうに島々が埃っぽく見え、木々が風に打ち付けられて揺れ動く。それからドッシャーン!――ドン! ドン! ゴロゴロゴロ……ドン……ドン……ドン……ドン……と雷が轟き、唸り、やがて止む――すると、ピカッとまた閃光が走り、またとてつもない一撃が来る。波でいかだから洗い流されそうになることもあったが、俺は服を着ていなかったので、気にしなかった。流木で困ることはなかった。稲妻が絶えずきらめき、ちらついていたので、十分に早くそれらを見つけて、いかだの向きをあちらこちらに変えて避けることができた。
俺は真ん中の見張りだったが、その頃にはかなり眠かった。だからジムが、最初の半分は代わってやると言ってくれた。ジムはいつもそういうふうに、とても親切だった。俺は小屋に這い入ったが、王様と公爵が足をだらしなく広げていたので、俺の入る隙間はなかった。だから外で寝た――雨は気にならなかった。暖かかったし、波も今はそれほど高くなかったからだ。しかし二時頃、波は再び高くなり、ジムは俺を呼ぼうとした。だが、まだ害を及ぼすほど高くはないだろうと考えて、思い直した。しかし、その考えは間違っていた。というのも、間もなく突然、とてつもない大波がやって来て、俺を船外に洗い流したからだ。ジムは笑い死にしそうだった。どのみち、あいつはこれまでで一番笑い上戸な黒人だった。
俺は見張りを引き受け、ジムは横になっていびきをかき始めた。やがて嵐はすっかり収まった。そして最初の小屋の明かりが見えた時、俺はジムを叩き起こし、いかだをその日の隠れ場所に滑り込ませた。
朝食の後、王様は古くてぼろぼろのトランプを取り出し、公爵とセブンアップをしばらくやった。一ゲーム五セントだ。やがてそれに飽きると、「作戦を練る」と彼らが呼ぶことをやろうと言い出した。公爵は自分の旅行鞄に手を突っ込み、たくさんの小さな印刷されたビラを取り出して、大声で読み上げた。一枚のビラには、「パリの著名なアルマン・ド・モンタルバン博士」が、某月某日、某所で「骨相学の科学に関する講演」を行う、入場料十セント、「性格診断図を一枚二十五セントで提供」と書かれていた。公爵はそれが自分だと言った。別のビラでは、彼は「ロンドンのドルリー・レーン劇場出身、世界的に有名なシェイクスピア悲劇役者、ギャリック・ザ・ヤンガー」だった。他のビラでは、彼はたくさんの他の名前を持ち、「占い棒」で水や金を見つけたり、「魔女の呪いを解いたり」といった、他の素晴らしいことをやっていた。やがて彼は言った。
「しかし、演劇の女神こそが本命だ。舞台を踏んだことはあるかね、王族殿?」
「ない」と王様は言った。
「ならば、三日も経たぬうちに踏むことになるぞ、没落した偉大なるお方」と公爵は言った。「最初に着くまともな町で、ホールを借りて、『リチャード三世』の剣劇と『ロミオとジュリエット』のバルコニーの場面をやろう。どうだね?」
「儲かることなら何でも大歓迎じゃ、ビルジウォーター。しかし、見ての通り、わしは芝居のことなど何も知らんし、大して見たこともない。親父が宮殿でやっとった頃は、わしは小さすぎた。わしに教えられると思うか?」
「お安い御用だ!」
「よろしい。どのみち、何か新しいことに飢えとったところじゃ。早速始めよう。」
そこで公爵は、ロミオが誰でジュリエットが誰かを彼にすべて説明し、自分はロミオ役をやり慣れているから、王様がジュリエットになれると言った。
「しかし、ジュリエットがそんなに若い娘なら、公爵、わしの禿げ頭と白い髭は、彼女にはひどく奇妙に見えるかもしれんぞ。」
「いや、心配ご無用。この田舎者どもはそんなことには気づきもしない。それに、衣装を着けるのだから、それで世界はがらりと変わる。ジュリエットはバルコニーで、寝る前に月光を楽しんでいる。ナイトガウンを着て、ひだ飾りのついたナイトキャップを被っているのだ。ここにその役の衣装がある。」

彼はカーテン用の更紗でできたスーツを二、三着取り出した。それはリチャード三世ともう一人のための、中世の鎧だという。そして、長い白い綿のナイトシャツと、それに合わせたひだ飾りのナイトキャップも。王様は満足した。そこで公爵は本を取り出し、最も華麗な大見得を切るような調子で台詞を読んでみせた。その間、歩き回り、身振り手振りを交えて、どう演じるべきかを示した。それから彼は本を王様に渡し、自分の役を暗記するように言った。
川の湾曲部の三マイルほど下流に、馬一頭の小さな町があった。昼食の後、公爵は、ジムにとって危険なく昼間に航行する方法を考え出したと言った。そこで、町へ下ってその件を片付けることにすると言った。王様も、何か一儲けできないか見に行くと言って、一緒に行くことにした。コーヒーが切れていたので、ジムは俺もカヌーで彼らと一緒に行って、いくらか買ってくるといいと言った。
俺たちがそこに着いた時、人っ子一人動いていなかった。通りは空っぽで、日曜日のように完全に静まり返っていた。裏庭で日向ぼっこをしている病気の黒人を見つけ、彼に聞くと、若すぎたり病気だったり年寄りだったりしない者は皆、森の奥二マイルほどのところにある野外伝道集会に行っているとのことだった。王様は道順を聞き、その集会で稼げるだけ稼いでやろうと言い、俺も行っていいと言った。
公爵は、探しているのは印刷所だと言った。俺たちはそれを見つけた。大工の作業場の上にある、ちっぽけな仕事場だった――大工も印刷工も皆集会に行っていて、ドアには鍵がかかっていなかった。そこは汚くて散らかった場所で、壁中インクの染みだらけで、馬や逃亡奴隷の絵が描かれたビラが貼られていた。公爵は上着を脱ぎ、これで準備万端だと言った。そこで俺と王様は、野外伝道集会へと向かった。
半時間ほどでそこに着いた時には、すっかり汗びっしょりだった。ものすごく暑い日だったからだ。二十マイル四方から、千人もの人々が集まっていた。森は、あちこちに繋がれた馬車や荷馬車でいっぱいで、馬たちは荷馬車の飼い葉桶から餌を食べ、ハエを追い払うために足を踏み鳴らしていた。柱を立てて枝で屋根を葺いた小屋があり、そこではレモネードやジンジャーブレッドが売られ、スイカや青トウモロコシなどが山積みになっていた。
説教は同じような小屋の下で行われていたが、そちらはもっと大きく、大勢の人でごった返していた。ベンチは丸太の外側の板で作られており、丸い側に穴を開けて脚になる棒を打ち込んであった。背もたれはなかった。説教師たちは、小屋の一方の端に高い演壇を設けて立っていた。女たちは日よけ帽をかぶり、リンネルとウールの交織の服を着ている者もいれば、ギンガムチェックの服の者もいて、若い娘たちの中には更紗の服を着ている者も数人いた。若い男たちの中には裸足の者もおり、子供たちの中には麻布のシャツ一枚しか着ていない者もいた。年配の女たちの中には編み物をしている者もいれば、若い連中はこっそりいちゃついている者もいた。

俺たちが最初に来た小屋では、説教師が賛美歌を先導していた。彼が二行歌うと、皆がそれを歌う。大勢が実に力強く歌うので、聞いているとなかなか壮観だった。それから彼がまた二行歌い、皆が歌う――という具合だ。人々はますます目を覚まし、どんどん大きな声で歌った。そして終わり頃には、うめき始める者や、叫び始める者もいた。それから説教師が説教を始め、それも本気で始めた。演壇の一方の側からもう一方の側へと体を揺らし、それから演壇の前に身を乗り出し、腕と体を絶えず動かし、力の限り言葉を叫んだ。そして時々、聖書を掲げて広げ、あちこちに見せながら叫ぶのだ。「これぞ荒野の青銅の蛇なり! これを見て生きよ!」と。すると人々は「栄光あれ! ――アーア-メン!」と叫び返す。彼はそんなふうに続け、人々はうめき、泣き、アーメンと唱えた。
「おお、悔いる者の席へ来たれ! 罪に汚れた者よ、来たれ! (アーメン!)病める者、傷ついた者よ、来たれ! (アーメン!)足萎え、歩けぬ者、盲目の者よ、来たれ! (アーメン!)貧しき者、困窮せる者、恥に沈む者よ、来たれ! (アーア-メン!)疲れ、汚れ、苦しむすべての者よ、来たれ! ――砕かれた心で来たれ! 悔い改めた心で来たれ! ぼろと罪と汚れのまま来たれ! 清めの水は無料なり、天国の扉は開かれたり――おお、入りて安らぎを得よ!」(アーア-メン! 栄光あれ、栄光あれ、ハレルヤ!)
という調子だ。叫び声と泣き声のせいで、もう説教師が何を言っているのか聞き取れなかった。群衆のあちこちで人々が立ち上がり、涙を顔に流しながら、力ずくで悔いる者の席へと進んでいった。そして、悔いる者たちが皆、前のベンチに集まると、彼らは歌い、叫び、狂ったように、荒々しく藁の上に身を投げ出した。
さて、気づいた時には、王様が興に乗っていた。その声は誰よりも大きく聞こえた。次に彼は演壇へと突進していき、説教師が彼に人々へ話すよう懇願すると、彼はそれに応じた。彼は自分が海賊だと言った――三十年間、インド洋で海賊をしていた――そして、去年の春の戦いで乗組員がかなり減ったので、今は新しい船員を募るために故郷に戻ってきたのだ、と。そして、ありがたいことに、昨夜強盗に遭い、一文無しで蒸気船から岸に降ろされたが、それが嬉しいのだと言った。それは彼に起こった最も祝福された出来事だった。なぜなら、彼は今や生まれ変わった人間であり、人生で初めて幸せを感じているからだ、と。そして、貧しい身ではあるが、すぐにでもインド洋へ戻るための道を働きながら進み、残りの人生を海賊たちを真の道へと導くために捧げるつもりだ、と。その海のすべての海賊船員と知り合いである自分が、誰よりもそれができるのだ。金がなければそこに着くまでに長い時間がかかるだろうが、それでも必ず着く。そして、海賊を一人説得するたびに、こう言うだろう。「私に感謝するな、私に手柄を与えるな。それはすべて、ポークヴィルの野外伝道集会の愛すべき人々、人類の真の兄弟であり恩人である彼らと、あそこの愛すべき説教師、海賊が持った最も真実の友のおかげなのだ!」と。

そして彼はわっと泣き出し、皆も泣き出した。すると誰かが叫んだ。「彼のために寄付を集めよう、寄付を集めよう!」と。まあ、五、六人がそれをしようと飛び出したが、誰かが叫んだ。「彼に帽子を回させよう!」と。すると皆がそう言った。説教師もだ。
そこで王様は、帽子で涙を拭いながら群衆の中を練り歩き、人々を祝福し、賞賛し、はるか遠くの哀れな海賊たちにこんなにも親切にしてくれることに感謝した。そして、時折、頬に涙を伝わせた最高に可愛い娘たちが立ち上がって、思い出にキスをさせてくれないかと彼に頼んだ。彼はいつもそれに応じた。中には五、六回も抱きしめてキスをした娘もいた――そして彼は一週間滞在するように招待された。誰もが彼に自分の家に住んでほしいと言い、それは名誉なことだと言った。しかし彼は、これが野外伝道集会の最終日なので、何の役にも立てないだろうし、それに、すぐにでもインド洋に行って海賊たちのために働きたくてうずうずしているのだ、と言った。
俺たちがいかだに戻り、彼が集めた金を数えてみると、八十七ドル七十五セントになっていた。そして、森を通って帰り始める時に荷馬車の下で見つけた、三ガロン入りのウィスキーの瓶も持ってきていた。王様は、総じて言えば、これまで伝道活動で過ごしたどの日よりも上出来だったと言った。野外伝道集会で稼ぐには、異教徒なんて海賊に比べりゃ物の数じゃない、話にならない、と彼は言った。
公爵は、王様が現れるまでは、自分もかなりうまくやっていると思っていたが、その後はそれほどでもなくなった。彼はあの印刷所で、農民のために小さな仕事を二つ、活字を組んで印刷した――馬のビラだ――そして、四ドルの金を受け取った。そして、新聞のために十ドル分の広告を取ったが、前払いしてくれるなら四ドルで載せると言った――それで連中はそうした。新聞の値段は一年で二ドルだったが、彼は前払いしてくれるという条件で、一部半ドルで三件の購読を取った。連中はいつものように薪や玉ねぎで支払うつもりだったが、彼は自分がこの事業を買収したばかりで、これ以上ないほど値段を下げたので、現金で運営するつもりだと言った。彼は、自分で、自分の頭の中から作り出した短い詩を活字に組んだ――三連の――甘く悲しげな詩だった――題名は「然り、打ち砕け、冷たき世よ、この傷つく心を」――そして彼はそれを、新聞に印刷できる状態のまま置いてきて、料金は一切請求しなかった。まあ、彼は九ドル半を稼ぎ、それでまずまずの一日の仕事をしたと言った。
それから彼は、印刷したもう一つの小さな仕事を見せた。これは俺たちのためのものだったので、料金は請求していなかった。それには、肩に棒で担いだ包みを持った逃亡奴隷の絵があり、その下には「懸賞金200ドル」と書かれていた。文章はすべてジムに関するもので、彼を寸分違わず描写していた。それによると、彼は去年の冬、ニューオーリンズから四十マイル下流のサン・ジャック農園から逃亡し、おそらく北へ向かっただろう、そして彼を捕まえて送り返した者には懸賞金と経費が支払われる、とあった。

「さて」と公爵は言った。「今夜からは、望むなら昼間でも航行できる。誰かが来るのを見たら、ジムを手足ともロープで縛り、小屋に寝かせ、このビラを見せて、川上で捕まえたのだが、蒸気船で旅をするには貧しすぎるので、友人からこの小さないかだをツケで手に入れて、懸賞金をもらいに下っているのだ、と言えばいい。手錠や鎖の方がジムにはもっと似合うだろうが、我々がとても貧しいという話とはそぐわない。宝石のようだ。ロープが正しい小道具だ――舞台で言うところの、統一性を保たねばならん。」
俺たちは皆、公爵はなかなかの切れ者だと言い、昼間の航行について問題はないだろうと思った。その夜のうちに、公爵が印刷所でやった仕事があの小さな町で引き起こすであろう騒ぎの届かないところまで、十分な距離を稼げると判断した。そうすれば、望むならどんどん進める。
俺たちは身を潜めて静かにしており、十時近くになるまでいかだを出さなかった。それから、町からかなり離れたところを滑るように通り過ぎ、町の姿が完全に見えなくなるまでランタンを掲げなかった。
朝の四時にジムが見張りを交代しに俺を呼んだ時、彼は言った。
「ハック、わしら、この旅でこれ以上王様に会うことあると思うか?」
「いや」と俺は言った。「たぶんないと思う。」
「そうか」と彼は言った。「それならええわ。一人か二人の王様ならかまへんけど、それで十分や。こっちの王様はひどい酔っ払いだし、公爵も似たようなもんや。」
ジムが彼にフランス語を話させようとしていたことが分かった。どんなものか聞いてみたかったからだ。しかし王様は、この国に長くいすぎて、苦労も多かったので忘れてしまった、と言ったそうだ。
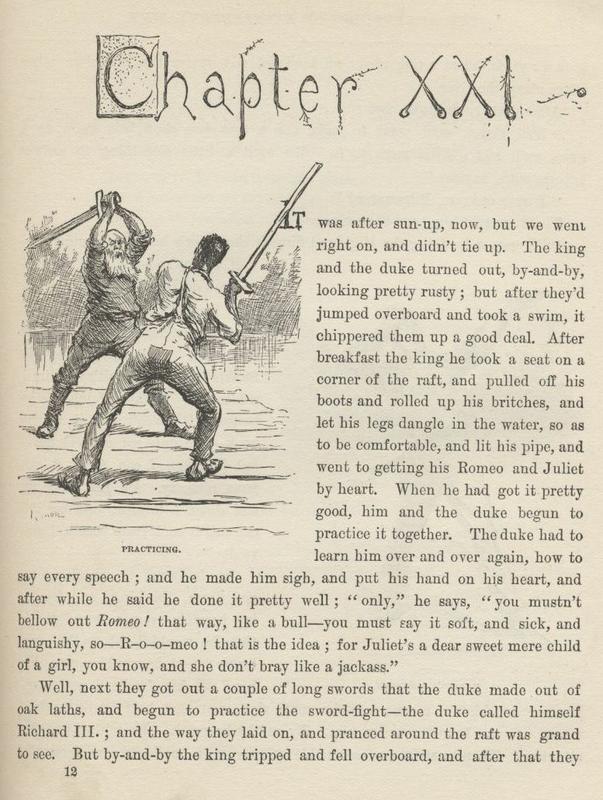
第二十一章 ハムレットの独白
もう日は昇っていたが、俺たちはそのまま進み、いかだを繋がなかった。やがて王様と公爵が、かなりみすぼらしい様子で出てきたが、川に飛び込んでひと泳ぎすると、ずいぶん元気になった。朝食の後、王様はいかだの隅に腰を下ろし、ブーツを脱ぎ、ズボンをまくり上げ、足を水にぶらつかせてくつろぎ、パイプに火をつけ、『ロミオとジュリエット』を暗記し始めた。かなり覚えたところで、彼と公爵は一緒に練習を始めた。公爵は、すべての台詞の言い方を彼に何度も何度も教えなければならなかった。彼にため息をつかせ、胸に手を当てさせ、しばらくすると、かなりうまくできるようになったと言った。「ただし」と彼は言った。「雄牛のようにロミオ!と怒鳴ってはいけない――柔らかく、病的に、物憂げに言わなければならん、こうだ――ロ-オ-オ-メオ! それがコツだ。ジュリエットは可愛らしくて甘い、まだほんの子供の娘だからな、ロバのようにがなり立てたりはしない。」
さて、次に彼らは、公爵が樫の木ずりで作った長い剣を二本取り出し、剣劇の練習を始めた――公爵は自分をリチャード三世と名乗った。二人がいかだの上で打ち合い、跳ね回る様は、見ていて壮観だった。しかし、やがて王様がつまずいて川に落ちてしまい、その後、彼らは休憩を取り、昔、川沿いで経験したいろいろな冒険について語り合った。
昼食の後、公爵が言った。
「さて、カペー[訳注:フランス王家の姓]よ、これを一流のショーにしたいのだから、もう少し何かを付け加えることにしよう。とにかく、アンコールに応えるための何かが必要だ。」
「オンコールとは何じゃ、ビルジウォーター?」
公爵はそれを説明し、そして言った。
「私はハイランド・フリングか船乗りのホーンパイプを踊って応えよう。そして、君は――そうだな、待てよ――ああ、思いついた――君はハムレットの独白ができる。」
「ハムレットの何じゃと?」
「ハムレットの独白だよ。シェイクスピアの中で最も有名なものだ。ああ、崇高だ、崇高だ! いつも観客を沸かせる。本には載っていない――一巻しか持っていないからな――だが、記憶からつなぎ合わせられると思う。ちょっとそこらを歩き回って、記憶の貯蔵庫から呼び戻せるか試してみよう。」

そこで彼は行ったり来たり歩き始め、考え込み、時々恐ろしく眉をひそめた。それから眉を吊り上げた。次に額に手を押し当ててよろめき、うめき声のようなものを漏らした。次にため息をつき、次に涙を落とすふりをした。その様は見ていて美しかった。やがて彼は思い出した。彼は俺たちに注目するように言った。それから、片足を前に突き出し、両腕を高く伸ばし、頭を後ろに傾けて空を見上げる、実に気高いポーズを取った。そして彼はわめき、吠え、歯ぎしりを始めた。その後、彼のスピーチの間中、彼は叫び、身振り手振りを交え、胸を張り、これまで俺が見たどんな演技よりも見事だった。これがそのスピーチだ――彼が王様に教えている間に、俺は簡単に覚えてしまった。
生きるべきか、死ぬべきか。それこそが剥き身の短剣、 かくも長き人生に災いをもたらすもの。 誰が重荷を負うだろうか、バーナムの森がダンシネインに来るまで、 されど死後の何物かへの恐怖が 罪なき眠りを殺し、 大いなる自然の第二の糧を、 そして我らをして、非道なる運命の矢を放たしむる、 知らぬ他者へと飛ぶよりも。 そこにこそ我らをためらわせる敬意がある。 そのノックでダンカンを起こせ! できるものならな。 誰が時の鞭と嘲りを耐え忍ぶだろうか、 圧政者の非道、傲慢なる者の侮辱を、 法の遅延、そしてその苦痛がもたらすであろう終焉を。 死せる荒野と真夜中、墓場があくびをする時、 厳粛なる黒の慣習的な装束にて、 されどその境より旅人の戻らぬ未発見の国が、 世に伝染病を吐き出し、 かくて決意の生来の色は、ことわざの哀れな猫のごとく、 心労に曇らされる。 そして我らが家々の屋根に垂れ込めたすべての雲は、 この配慮によりてその流れを逸らし、 行動の名を失う。 これぞ敬虔に望まれるべき結末なり。 しかし待て、美しきオフィーリアよ。 その重々しく大理石のごとき顎を開くな。 されど尼寺へ行け――行け!
まあ、年寄りはそのスピーチが気に入り、すぐにそれを覚えて、見事にこなせるようになった。まるでそのために生まれてきたかのようだった。そして、調子に乗って興奮すると、それを披露する時にわめき、叫び、後ろにのけぞる様は、まったくもって見事だった。
最初の機会に、公爵はいくつかのショーのビラを印刷させた。その後、二、三日、俺たちがいかだで流れ下る間、いかだは並外れて活気のある場所だった。なぜなら、剣劇とリハーサル――公爵がそう呼んでいた――以外、何も行われていなかったからだ。ある朝、俺たちがアーカンソー州をかなり下ったところで、大きな湾曲部にある馬一頭の小さな町が見えてきた。そこで俺たちは、その町の四分の三マイルほど上流、イトスギの木々にトンネルのように囲まれた小川の入り口にいかだを繋いだ。そしてジム以外の全員がカヌーに乗り、その町で俺たちのショーのチャンスがあるかどうか見に行った。
俺たちは実に運が良かった。その日の午後、そこでサーカスがある予定で、田舎の人々が、あらゆる種類の古くてがたがたの荷馬車や馬に乗って、すでに集まり始めていた。サーカスは夜になる前に去るので、俺たちのショーにはかなり良いチャンスがあるだろう。公爵は裁判所を借り、俺たちはビラを貼って回った。そこにはこう書かれていた。
シェイクスピア劇、堂々復活!!! 素晴らしき見世物! 一夜限り! 世界に名だたる悲劇役者、 ロンドン、ドルリー・レーン劇場より、デヴィッド・ギャリック(二世) および ロンドン、ホワイトチャペル、プディング・レーン、ピカデリー、ロイヤル・ヘイマーケット劇場 および ヨーロッパ大陸王室劇場より、エドマンド・キーン(一世) 両名による、崇高なる シェイクスピア・スペクタクル 題して 『ロミオとジュリエット』より バルコニーの場!!! ロミオ・・・・・・・・・・・・・・・・・ギャリック氏 ジュリエット・・・・・・・・・・・・・・・キーン氏 劇団員総出演! 新衣装、新舞台装置、新小道具! さらに: スリルと技巧、血も凍る ブロードソードの決闘 『リチャード三世』より!!! リチャード三世・・・・・・・・・・・・・・ギャリック氏 リッチモンド・・・・・・・・・・・・・・・キーン氏 さらに: (特別要望により) ハムレットの不滅の独白!! 名優キーン氏による! パリにて三百夜連続上演! 一夜限り、 ヨーロッパでの重要契約のため! 入場料二十五セント、子供と使用人は十セント。
それから俺たちは町をぶらついた。店も家も、ほとんどが古くてがたぴしで、塗装もされたことのない干からびた木造の建物だった。川が氾濫したときに水に浸からないよう、地面から三、四フィートの高さの杭の上に建てられている。家の周りには小さな庭があったが、そこで育っているのはチョウセンアサガオとヒマワリ、灰の山、古くて丸まったブーツや靴、瓶のかけら、ぼろ切れ、使い古しのブリキ製品くらいしか見当たらなかった。塀は様々な種類の板でできていて、ばらばらの時期に釘で打ち付けられたものらしかった。あちこちに傾いていて、門にはたいてい蝶番が一つしかなく、それも革製だった。塀の中にはいつだったか白く塗られたものもあったが、公爵に言わせれば、たぶんコロンブスの時代だろうとのことだった。庭にはたいてい豚がいて、人々がそれを追い出していた。
店はすべて一つの通りに並んでいた。店の前には白いキャラコの日除けが張られ、田舎から来た人々は日除けの柱に馬をつないでいた。日除けの下には空の反物箱が置かれ、ごろつきどもが一日中とまり木みたいに腰掛けては、バーロウナイフで木を削っていた。噛みタバコをくちゃくちゃやり、大あくびをしたり伸びをしたり――まったくどうしようもない連中だった。たいてい傘みたいにだだっ広い麦わら帽子を被っていたが、上着もチョッキも着ていない。互いをビルだの、バックだの、ハンクだの、ジョーだの、アンディだのと呼び合い、だらだらと間の抜けた話し方で、やたらと汚い言葉を使った。日除けの柱一本に一人くらいの割合でごろつきが寄りかかっていて、そいつはたいていズボンのポケットに両手を突っ込んでいた。手を出すのは、噛みタバコを貸すか、体を掻くときくらいのものだ。連中の間でいつも聞こえてくるのは、こんな会話だった。
「ハンク、噛みタバコを一口くんねえか。」
「だめだ。最後の一口しかねえ。ビルに頼んでみな。」

ビルは一口やるかもしれないし、嘘をついて持ってないと言うかもしれない。この手のごろつきの中には、一セントたりとも金を持たず、自分の噛みタバコさえ持っていない連中がいる。噛む分は全部借りて済ますのだ。誰かにこう言う。「ジャック、一口貸してくれねえか。たった今、ベン・トンプソンに最後の一口をやっちまったんだ」――これはほとんど毎回嘘で、よそ者しか騙されない。だがジャックはよそ者じゃないから、こう言い返す。
「お前があいつに一口やっただと? そりゃお前の姉さんの飼い猫の婆さんでも同じことを言うだろうよ。お前が俺から借りた分をまず返しやがれ、レイフ・バックナー。そうすりゃ一トンでも二トンでも貸してやる。延滞利息もつけねえでな。」
「まあ、いっぺん少しは返したじゃねえか。」
「ああ、返したな――六口ほどか。お前が借りたのは上等なタバコで、返してきたのは安物の黒んぼタバコ[訳注:ニガーヘッド。安価な黒いプラグタバコの一種]だったがな。」
上等なタバコというのは平たい黒い塊だが、ここの連中はたいてい天然の葉をねじったものを噛んでいる。一口借りるときは、普通ナイフで切り取ったりしない。歯の間に塊を挟むと、歯で食いちぎり、手でぐいと引っ張って二つにする。すると、タバコの持ち主は、返された塊を悲しそうに眺めて、皮肉たっぷりにこう言うことがある。
「ほらよ、一口は俺にくれ。お前は塊の方を持っていけ。」
通りも路地も、ただの泥だった。泥以外は何もない――タールのように真っ黒な泥で、場所によっては一フィート近く、どこでも二、三インチは深さがあった。豚があちこちでぶらつき、ブーブー鳴いていた。泥だらけの雌豚が子豚の一腹を引き連れて通りをのろのろとやって来て、人々がよけて通らなければならない道ばたにどさりと寝そべる。そして体を伸ばし、目を閉じ、耳をぱたぱたさせながら子豚に乳をやっている様は、まるで給料でももらっているかのように幸せそうだった。するとすぐに、ごろつきの誰かが「おい、そら! 行け、タイジ!」と叫ぶのが聞こえる。雌豚はすさまじい悲鳴を上げて逃げ出し、両耳には一、二匹の犬がぶら下がり、さらに三、四十匹が後から追いかけてくる。ごろつきどもは皆立ち上がって、その光景が見えなくなるまで見送り、面白がって笑い、騒ぎをありがたがっているようだった。それから、犬の喧嘩が始まるまで、また腰を下ろす。犬の喧嘩ほど、連中をすっかり目覚めさせ、心から楽しませるものはない――まあ、野良犬にテレビン油をぶっかけて火をつけたり、尻尾にブリキの鍋をくくりつけて死ぬまで走り回るのを見たりするのなら、話は別かもしれないが。
川岸では、いくつかの家が岸からはみ出すように建っていて、歪んで曲がって、今にも川に落ちそうだった。住人はもう引っ越していた。他のいくつかの家は、片隅の下の岸が崩れ落ちて、その角が宙ぶらりんになっていた。まだ人が住んでいたが、危険だった。時には家一軒分の幅の地面が一気に崩れ落ちることがあるからだ。時には四分の一マイルもの深さの土地が一夏のうちに、少しずつ崩れ、崩れ、崩れ続けて、とうとう全部川に落ちてしまうこともある。そんな町は、川が絶えず岸を食い荒らすので、いつも後へ、後へ、後へと下がらなければならない。
その日は正午に近づくにつれて、通りの荷馬車と馬がどんどん増え、さらに絶えずやって来た。田舎から来た家族は弁当を持参し、荷馬車の中で食べていた。かなりの量のウィスキーが飲まれていて、俺は三回喧嘩を見た。やがて誰かが叫んだ。
「ボッグスのじいさんが来たぞ! ――月一の酔っぱらいのために田舎からだ。来たぞ、おめえら!」
ごろつきどもは皆嬉しそうな顔をした。ボッグスをからかって楽しむのに慣れているのだろうと俺は思った。一人が言う。
「今度は誰を血祭りに上げるつもりかね。この二十年間、血祭りに上げるって言ってきた連中を全部血祭りに上げてりゃ、今頃はたいした評判になってたろうな。」
もう一人が言う。「ボッグスのじいさんが俺を脅してくれりゃいいんだがな。そしたら千年先まで死なねえってことがわかるからよ。」
ボッグスは馬に乗って突進してきて、インディアンみたいに叫んだりわめいたりしながら、大声でがなり立てた。
「道を開けろい。俺様はいくさの道を行くんだ。棺桶が値上がりするぜ。」

彼は酔っぱらって、鞍の上でふらふらしていた。五十歳は超えていて、顔は真っ赤だった。誰もが彼に野次を飛ばし、笑い、からかった。彼も言い返し、順番に片付けてやる、寝かしてやると言ったが、今は待てない、なぜなら町のシェルバーン大佐を殺しに来たからで、彼のモットーは「まずは肉料理、デザートは流動食」だとのことだった。
彼は俺を見ると、馬を寄せて言った。
「どっから来た、小僧? 死ぬ覚悟はできてるか?」
そして彼は馬を進めて行った。俺は怖かったが、一人の男が言った。
「本気じゃねえよ。酔っぱらうといつもあんな調子なんだ。アーカンソーじゃ一番人のいい大馬鹿さ――酔っててもしらふでも、誰も傷つけたりしねえ。」
ボッグスは町で一番大きな店の前まで馬で行くと、日除けの垂れ幕の下を覗き込めるように頭を下げて叫んだ。
「出てこい、シェルバーン! 出てきてお前がだました男に会え。俺が追ってるのはお前っていう犬畜生だ。必ず仕留めてやるからな!」
そうして彼は、口の限りシェルバーンを罵り続けた。通りは人でごった返し、皆が耳を傾け、笑い、はやし立てていた。やがて、年の頃五十五くらいの、見るからに誇り高そうな男――それに、町で一番身なりのいい男でもあった――が店から出てくると、群衆は彼が通れるように両側にさっと引いた。男はボッグスに、実に落ち着いてゆっくりと言った。
「もううんざりだが、一時までは我慢してやろう。一時までだ、いいな――それ以上は待たん。その時間を過ぎてから一度でも俺に口答えしてみろ、地の果てまで行こうと必ず見つけ出してやる。」
そして彼はくるりと向きを変え、店の中に入っていった。群衆はすっかり真面目な顔つきになり、誰も身動きせず、もう笑い声は聞こえなかった。ボッグスは馬を走らせ、通り中、叫べる限りの大声でシェルバーンを罵りながら走り去った。そしてすぐに戻ってきて、店の前で止まり、また罵り続けた。何人かの男たちが彼を取り囲み、黙らせようとしたが、彼は聞かなかった。あと十五分ほどで一時になるから、絶対に家に帰らなければならない、すぐに行くんだと彼らは言った。だが、効果はなかった。彼は力の限り罵り続け、帽子を泥の中に投げつけて馬で踏みつけ、やがてまた通りを怒り狂いながら駆け下りていった。白髪が風になびいていた。彼に近づける者は皆、どうにかして彼を馬から降ろし、どこかに閉じ込めて酔いを醒まさせようと必死だったが、無駄だった――彼はまた通りを駆け上り、シェルバーンをもう一度罵るのだった。やがて誰かが言った。
「娘さんを呼んでこい! ――早く、娘さんを! 娘さんの言うことなら聞くことがある。あいつを説得できる者がいるとすれば、娘さんだけだ。」
そこで誰かが走り出した。俺は通りを少し下って立ち止まった。五分か十分もすると、またボッグスがやって来たが、馬には乗っていなかった。彼は頭に何も被らず、両側から友人に腕を掴まれ、急かされながら、ふらふらと俺の方へ通りを横切ってきた。彼は静かで、不安そうな顔をしていた。後ろに引こうとはせず、むしろ自分から急いでいるようだった。誰かが叫んだ。
「ボッグス!」
誰が言ったのかとそちらを見ると、あのシェルバーン大佐だった。彼は通りの真ん中に微動だにせず立っており、右手にピストルを掲げていた――狙っているわけではなく、銃身を空に向けて持ち上げている。その同じ瞬間、若い娘が二人連れの男たちと走ってくるのが見えた。ボッグスと男たちは、誰が呼んだのかと振り返り、ピストルを見ると男たちは脇へ飛びのいた。ピストルの銃身がゆっくりと、着実に水平まで下りてきた――二つの撃鉄が起こされている。ボッグスは両手を上げて言った。「おお、神様、撃たないでくれ!」バーン! と一発目が火を噴き、彼はよろめきながら後ずさりし、空を掻きむしる――バーン! と二発目。彼は両腕を広げたまま、どすんと重々しく地面に仰向けに倒れた。若い娘は悲鳴を上げて駆け寄り、父親の上に身を投げ出して泣きながら言った。「ああ、殺された、父さんが殺されたわ!」群衆が彼らの周りに密集し、互いに肩をぶつけ合い、押し合いへし合いしながら、首を伸ばして覗き込もうとしている。内側にいる人々は彼らを押し戻そうとしながら、「下がれ、下がれ! 息をさせてやれ、息を!」と叫んでいた。

シェルバーン大佐はピストルを地面に放り投げると、踵を返して歩き去った。
人々はボッグスを小さな薬屋に運び込んだ。群衆は相変わらず周りに密集し、町中の人間がついてきた。俺は急いで窓際のいい場所を確保し、彼のすぐそばで中を見ることができた。彼らはボッグスを床に寝かせ、頭の下に大きな聖書を一冊置き、もう一冊を開いて彼の胸の上に広げた。だがその前にシャツを引き裂いたので、俺は弾丸が入った場所を見た。彼は十数回、長くあえいだ。息を吸うと胸が聖書を持ち上げ、吐き出すとまた下がる――その後、彼は動かなくなった。死んでいた。それから彼らは、叫び泣く娘を彼から引き離し、連れて行った。彼女は十六歳くらいで、とても可愛らしくて優しそうだったが、ひどく青ざめて怯えていた。
さて、やがて町中の人間がそこに集まり、もがき、押し合い、突き合い、窓際に寄って一目見ようとしていたが、場所を確保した人々は譲ろうとせず、後ろの連中は四六時中こう言っていた。「おい、お前ら、もう十分見たろ。お前らがずっとそこにいて、誰にもチャンスをやらないなんてのは、正しくも公平でもねえ。他の連中にもお前らと同じ権利があるんだ。」
かなりの口論が返ってきたので、俺はこっそり抜け出した。面倒なことになりそうだと思ったからだ。通りは人でいっぱいで、誰もが興奮していた。射殺を見た者は皆、それがどう起こったかを話しており、それぞれの男の周りには大勢の群衆が詰めかけ、首を伸ばして耳を傾けていた。長い髪で、頭の後ろに大きな白い毛皮のシルクハットを被り、柄の曲がった杖を持った、ひょろりと背の高い男が、ボッグスが立っていた場所とシェルバーンが立っていた場所を地面に印した。人々は彼についてあちこちと移動し、彼の一挙手一投足を見つめ、理解したことを示すように頷き、少し屈んで両手を腿に置きながら彼が杖で地面に印をつけるのを見ていた。それから彼は、シェルバーンが立っていた場所にまっすぐ硬直して立ち、眉をひそめ、帽子のつばを目深にかぶって、「ボッグス!」と叫び、そして杖をゆっくりと水平まで下ろし、「バーン!」と言った。後ろによろめき、もう一度「バーン!」と言って、仰向けにばったりと倒れた。その光景を見た人々は、彼が完璧にやったと言った。全くその通りに起こったのだと。それから十人以上の人々が瓶を取り出し、彼にご馳走した。
さて、やがて誰かがシェルバーンは吊るし首にすべきだと言った。一分もしないうちに誰もがそう言っていた。そして彼らは、怒り狂い、わめきながら、首吊りに使うために、目につく物干し綱を片っ端から引きちぎりながら走り去った。
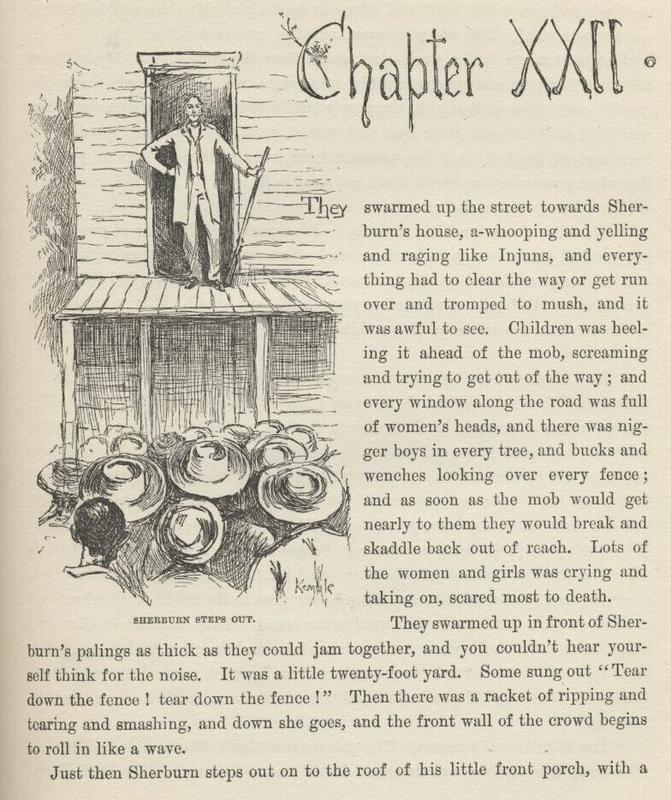
第二十二章
連中はインディアンみたいに雄叫びを上げ、荒れ狂いながら、シェルバーンの家へと群がっていった。行く手にあるものはすべて道を譲るか、さもなければ踏みつけられてぐちゃぐちゃにされるありさまで、ひどい光景だった。子供たちは暴徒の先頭を走り、悲鳴を上げながら逃げようとしていた。道沿いの窓という窓は女たちの頭でいっぱいで、木という木には黒人の少年たちが登り、塀という塀からは黒人の男や女が見下ろしていた。暴徒が彼らのすぐ近くまで来ると、皆蜘蛛の子を散らすように手の届かないところまで逃げ帰った。女や娘たちの多くは泣き叫び、死ぬほど怖がっていた。
連中はシェルバーンの家の柵の前に、ぎゅうぎゅう詰めになって群がった。その騒音で自分の考えも聞こえないほどだった。そこは二十フィート四方ほどの小さな庭だった。誰かが「柵を壊せ! 柵を壊せ!」と叫んだ。すると、引き裂き、破壊し、粉々にする音が響き渡り、柵は倒れ、群衆の最前列が波のように押し寄せ始めた。
その時、シェルバーンが家の小さな玄関ポーチの屋根の上に姿を現した。手には二連式の銃を持ち、完璧に落ち着き払い、悠然と、一言も発さずにそこに立った。騒ぎは止み、波は引き返した。
シェルバーンは一言も発さず――ただそこに立ち、見下ろしていた。その静けさはひどく不気味で居心地が悪かった。シェルバーンはゆっくりと群衆に視線を走らせた。その視線が当たると、人々は少しの間彼を睨み返そうとしたが、できなかった。彼らは目を伏せ、こそこそした様子になった。やがてシェルバーンは、ふっと笑った。楽しい種類の笑いではなく、砂の入ったパンを食べている時のような気分にさせる笑いだった。
それから彼は、ゆっくりと、軽蔑を込めて言った。
「お前たちが誰かを吊るし首にするだと! 笑わせる。人間を吊るし首にするだけの気概がお前たちにあると思っているとはな! ここにやって来た、哀れで友人もなく、見捨てられた女どもにタールを塗って羽をつける勇気があるからといって、人間に手を出すだけの根性があるとでも思ったのか? なぜだ、男一人いれば、お前たちのような連中が一万人いても安全だ――それが昼間で、お前たちが彼の背後にいない限りはな。
俺がお前たちを知っているかって? 腹の底まで見通している。俺は南部で生まれ育ち、北部でも暮らした。だから、そこら中の平均的な人間というものを知っている。平均的な人間なんぞ、臆病者だ。北部では、誰にでも踏みつけられるがままになり、家に帰るとそれを耐えるための謙虚な心を祈る。南部では、男がたった一人で、昼日中に男でいっぱいの駅馬車を止め、全員から強盗を働く。お前さんたちの新聞は、お前さんたちを勇敢な国民だと持ち上げるもんだから、自分たちがどこの国民よりも勇敢だと思い込んでいる。だが実際は、他と変わりなく勇敢なだけで、それ以上でもそれ以下でもない。なぜお前さんたちの陪審員は殺人犯を絞首刑にしない? 犯人の仲間が、暗闇の中で背後から自分たちを撃つのではないかと恐れているからだ――そして、連中はまさにそうするだろう。
だから、彼らはいつも無罪放免にする。そして、男が夜中に、百人の仮面をつけた臆病者を背後に引き連れて、その悪党を吊るし首にするのだ。お前さんたちの間違いは、男を一人も連れてこなかったことだ。それが一つ目の間違いで、もう一つは、暗闇の中で仮面をつけて来なかったことだ。お前さんたちが連れてきたのは、半人前の男――そこにいる、バック・ハークネスだ――そして、もし彼がお前たちを焚きつけなかったら、お前たちはほらを吹くだけで終わっていただろう。
お前たちは来たくなかった。平均的な人間は面倒と危険を好まない。お前たちも面倒と危険は好まない。だが、バック・ハークネスのような半人前の男が一人でも『吊るし首にしろ! 吊るし首にしろ!』と叫べば、お前たちは尻込みするのを恐れる――自分が何者であるか、つまり臆病者であることが見破られるのを恐れる――そして、お前たちは雄叫びを上げ、その半人前の男の上着の裾にぶら下がり、どんな大それたことをやってのけるかと誓いながら、ここに荒れ狂ってやって来る。この世で一番哀れな代物が、暴徒だ。軍隊とはそういうものだ――暴徒だ。彼らは生まれ持った勇気で戦うのではなく、集団から、そして将校から借りてきた勇気で戦う。だが、先頭に立つ男が一人もいない暴徒は、哀れを通り越している。さあ、お前さんたちがすべきことは、尻尾を巻いて家に帰り、穴にでも潜り込むことだ。もし本物の吊るし首が行われるとすれば、それは南部の流儀で、暗闇の中で行われるだろう。そして、彼らが来るときには仮面をつけ、男を一人連れてくるだろう。さあ、去れ――そして、お前さんたちの半人前の男も連れて行け」――そう言いながら、彼は銃を左腕にさっと乗せ、撃鉄を起こした。
群衆は突然さっと後ずさりし、それからばらばらになって、四方八方へと逃げ出した。バック・ハークネスも、かなりみじめな様子で彼らの後を追った。俺は望めばそこにいられただろうが、そうはしたくなかった。
俺はサーカスに行き、見張り番が通り過ぎるまで裏手でぶらぶらして、それからテントの下に潜り込んだ。俺は二十ドルの金貨といくらかの金を持っていたが、取っておいた方がいいと思った。家から離れて、見知らぬ人たちの中にいると、いつ金が必要になるかわからないからだ。用心しすぎるということはない。他に方法がないときにサーカスに金を使うことに反対はしないが、無駄遣いする必要はない。
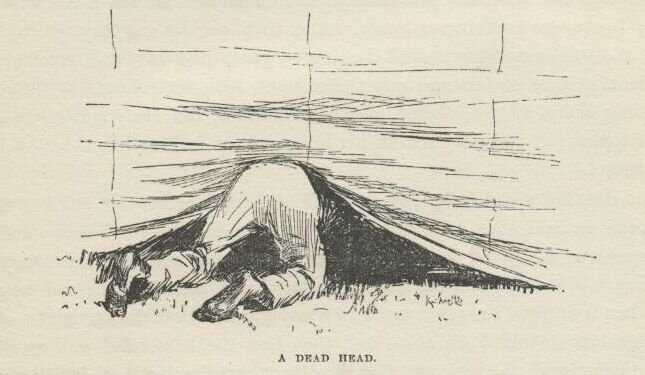
それはとびっきり上等なサーカスだった。男女が二人一組で、横に並んで乗り込んできたときは、これまで見た中で一番壮麗な光景だった。男たちはパンツと下着だけで、靴も履かず鐙もなく、両手を楽々と腿の上に置いていた――二十人くらいはいただろう――そして、どの女性も素晴らしい顔色で、完璧に美しく、まるで本物のお姫様の一団みたいで、何百万ドルもするような衣装を着て、ダイヤモンドでちりばめられていた。それはものすごく見事な光景で、あんなに美しいものは見たことがなかった。それから一人ずつ立ち上がり、リングを優雅に、波のように、しなやかに回り始めた。男たちはとても背が高く、軽やかで、まっすぐに見え、頭はテントの天井の下、はるか上で揺れたり滑ったりしていた。どの女性のバラの花びらのようなドレスも、腰の周りで柔らかく絹のようにひらひらと揺れ、彼女は最高に愛らしい日傘のようだった。
そして、どんどん速くなり、全員が踊り始めた。片足を空中に突き出し、次にもう片方の足を突き出す。馬はますます傾き、団長は中央の柱の周りをぐるぐる回りながら鞭を鳴らし、「ハイ! ――ハイ!」と叫び、ピエロがその後ろで冗談を飛ばしていた。やがて全員が手綱を放し、どの女性も腰に手を当て、どの男性も腕を組んだ。すると、馬たちはなんとまあ、身を傾けて体を躍らせたことか! そうして一人、また一人とリングに飛び降り、これまで見た中で一番可愛らしいお辞儀をしてから、駆け足で去っていった。観客は皆、手を叩き、ほとんど熱狂していた。
さて、サーカスの間中、彼らは最高に驚くべきことをやってのけた。そして、その間ずっと、あのピエロは人々をほとんど殺さんばかりにふざけ続けた。団長が彼に一言でも何か言おうものなら、瞬く間に、人が口にする中で一番面白い言葉で言い返してきた。どうしてあんなにたくさんのことを、あんなに素早く、あんなに的確に思いつくのか、俺には到底理解できなかった。なぜって、一年かかっても思いつきやしないだろう。やがて、酔っぱらいの男がリングに入ろうとした――乗りたい、誰よりも上手に乗れると言っていた。彼らは言い争い、彼を中に入れないようにしたが、彼は聞かず、ショーは完全に中断してしまった。すると人々は彼に野次を飛ばし、からかい始めたので、彼は腹を立て、暴れ出した。それで人々は騒ぎ出し、大勢の男たちがベンチから降りてきてリングに向かって群がり、「叩きのめせ! 叩き出せ!」と言い、一人か二人の女が悲鳴を上げ始めた。そこで、団長は短いスピーチをして、どうか騒ぎを起こさないでほしい、もし男がもう面倒を起こさないと約束するなら、馬に乗っていられると思うなら乗せてやると言った。それで皆が笑っていいよと言い、男は馬に乗った。彼が乗った途端、馬は暴れ出し、跳ね、駆け回り始めた。二人のサーカスの男が手綱にしがみついて押さえようとし、酔っぱらいの男は首にしがみつき、跳ねるたびに踵が宙を舞い、観客は総立ちで叫び、涙を流すまで笑っていた。そしてとうとう、サーカスの男たちがどんなに頑張っても、馬は振り切って、まるで飛ぶようにリングをぐるぐると駆け回り、あの酔っぱらいは馬の上に寝そべって首にしがみつき、片足が地面に届きそうなくらい片側に垂れ下がり、次にもう片方の足が反対側に垂れ下がり、人々はまさに熱狂していた。だが、俺には面白くなかった。彼の危険を見て、全身が震えていた。しかしすぐに、彼はもがいて馬にまたがり、手綱を掴んだ。あっちへよろよろ、こっちへよろよろ。そして次の瞬間、彼は飛び上がって手綱を放し、立ち上がった! 馬は火のついた家のように走っているというのに。彼はただそこに立ち、まるで生まれてこの方一度も酔っぱらったことがないかのように、楽々と優雅に回り続け――それから服を脱ぎ捨て始めた。彼はあまりにたくさんの服を脱いだので、空気が詰まるほどで、全部で十七着も脱ぎ捨てた。そして、そこには、すらりとしてハンサムで、これまで見た中で一番派手で美しい格好をした彼が立っていた。彼は鞭で馬を打ち、馬をぶんぶん走らせ――とうとう飛び降り、お辞儀をして、楽屋へと踊り去っていった。観客は皆、喜びと驚きでただただ吠えていた。

その時、団長は自分がどう騙されたかに気づき、俺が思うに、これまで見た中で一番意気消沈した団長だった。なぜって、あれは彼の部下の一人だったのだ! 彼はその冗談を全部自分の頭で考え出し、誰にも明かしていなかったのだ。さて、俺はまんまと騙された自分が情けなかったが、あの団長の立場になるのは千ドル積まれてもごめんだ。わからない。あれよりもっと上等なサーカスはあるかもしれないが、俺はまだ出会ったことがない。とにかく、俺には十分すぎるほど良かった。そして、どこかでまた出会ったら、毎回必ず俺の客になってやるつもりだ。
さて、その夜、俺たちのショーがあった。だが、客は十二人ほどしかいなかった――経費を払うのがやっとだ。そして彼らは終始笑っていたので、公爵は腹を立てた。それに、ショーが終わる前に、寝ていた一人の少年を除いて、皆帰ってしまった。それで公爵は、このアーカンソーのど田舎者どもはシェイクスピアにはついてこれない、連中が求めているのは低俗な喜劇だ――ことによると低俗な喜劇よりもっとひどいものかもしれない、と言った。彼らの好みがわかる、と彼は言った。そこで翌朝、彼は大きな包装紙を何枚か手に入れ、黒いペンキで手書きのビラを描き、村中に貼り付けた。ビラにはこう書かれていた。
裁判所にて! 三夜限り! 世界に名だたる悲劇役者 デヴィッド・ギャリック(二世)! および エドマンド・キーン(一世)! ロンドンおよびヨーロッパ大陸の 劇場より、 スリル満点の悲劇 王様のキリン または ロイヤル・ナンサッチ(天下の逸品)!!! 入場料五十セント。
そして一番下には、一番大きな文字でこう書かれていた。
婦女子禁制。
「どうだ」と彼は言った。「この一行で客が来なけりゃ、俺はアーカンソーを知らんということだ!」
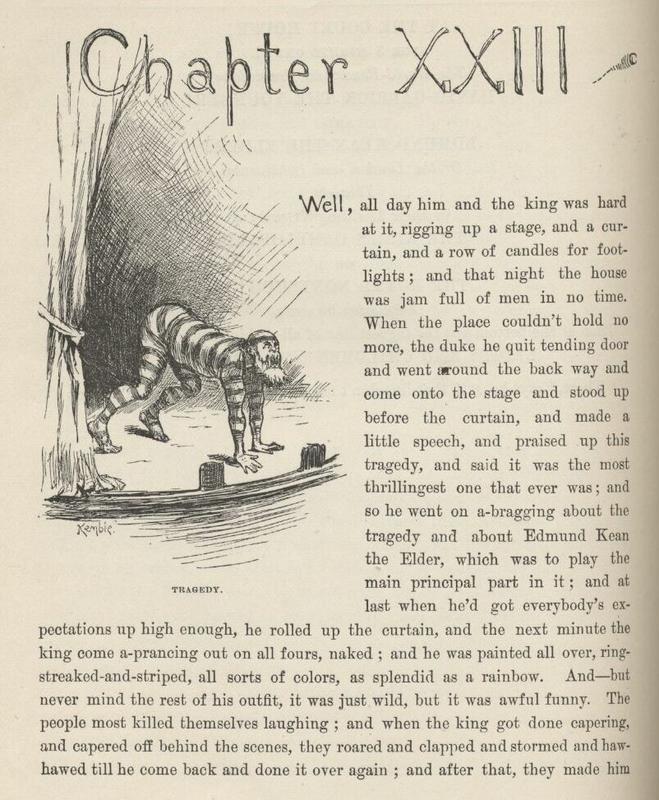
第二十三章
さて、一日中、公爵と王様は舞台とカーテン、それにフットライト代わりのろうそくの列を準備するのに大忙しだった。そしてその夜、小屋はあっという間に男たちでぎっしりになった。もうこれ以上入れなくなると、公爵は戸口の番をやめて裏口に回り、舞台に上がってカーテンの前に立ち、短いスピーチをした。この悲劇を褒め称え、これまでにないほどスリル満点のものだと言った。そうして彼は悲劇のことや、主役を演じるエドマンド・キーン(一世)のことを自慢し続けた。そしてとうとう、皆の期待を十分に高めたところで、彼はカーテンを巻き上げた。すると次の瞬間、王様が四つん這いになって、裸で、ぴょんぴょん跳ねながら出てきた。全身に、虹みたいに見事な、ありとあらゆる色の縞模様や輪っか模様が描かれていた。そして――まあ、その他の格好については言うまでもない。とにかく常軌を逸していたが、ひどく面白かった。人々は笑い死にしそうだった。王様が跳ね回り、舞台裏に跳ねていくと、観客は彼が戻ってきて再びそれをやるまで、わめき、手を叩き、足を踏み鳴らし、げらげら笑った。その後、彼らはもう一度やらせた。まあ、あの馬鹿じいさんがやったおどけを見れば、牛だって笑い出すだろう。
それから公爵はカーテンを下ろし、観客にお辞儀をして、この偉大な悲劇は、ロンドンのドルリー・レーン劇場での緊急の公演のため、あと二夜しか上演されないと告げた。ロンドンではすでに席は完売だという。そしてもう一度お辞儀をして、もし皆様にご満足いただき、ご教示することができたのなら、ご友人にこのことを伝え、見に来ていただくようお願いできれば、深く感謝いたします、と言った。
二十人ほどの人間が叫んだ。
「何だ、もう終わりか? これで全部か?」
公爵はそうだと言った。すると、大騒ぎになった。誰もが「騙された!」と叫び、怒って立ち上がり、舞台とあの悲劇役者たちに向かっていこうとした。だが、大柄で見た目のいい男がベンチの上に飛び乗り、叫んだ。
「待て! 一言だけ、諸君」彼らは耳を傾けるために立ち止まった。「我々は騙された――見事に一杯食わされたわけだ。だが、この町中の笑いものになって、生きている限りこのことを言われ続けるのはごめんだろう。違う。我々が望むのは、ここを静かに出て行き、このショーを褒めちぎり、町の残りの連中にも一杯食わせることだ! そうすれば、我々は皆同じ穴の狢だ。賢明じゃないか?」(「その通りだ! ――判事の言うことは正しい!」と誰もが叫んだ。)「よろしい、ならば――騙されたことについては一言も言うな。家に帰って、皆にこの悲劇を見に来るよう勧めるんだ。」
翌日、町中ではあのショーがいかに素晴らしかったかという話しか聞こえなかった。その夜も小屋は満員で、俺たちはこの群衆にも同じ手口で売りつけた。俺と王様と公爵がいかだの家に戻ると、皆で夕食を食べた。やがて、真夜中頃、彼らはジムと俺にいかだを後退させて川の真ん中を流し、町から二マイルほど下流に引き入れて隠させた。
三日目の夜、小屋は再び満員だった――そして今度は新しい客ではなく、前の二晩ショーに来た人々だった。俺は戸口で公爵のそばに立っていたが、入っていく男は皆、ポケットが膨らんでいるか、コートの下に何かを隠し持っているのが見えた――そして、それが香水でないことも、遠目にも明らかだった。樽一杯の腐った卵や、腐ったキャベツなんかの臭いがした。それに、もし俺が死んだ猫の気配がわかるなら――わかるに決まっているが――六十四匹は中に入っていった。俺は一分ほど中に押し入ってみたが、あまりに色々ありすぎて、耐えられなかった。さて、もうこれ以上人が入れなくなると、公爵は一人の男に二十五セントを渡して、少しの間戸口の番をしてくれと頼み、それから楽屋口に向かって歩き出した。俺も後を追った。だが、角を曲がって暗闇に入った途端、彼は言った。
「家々から離れるまで早足で歩け。それから、悪魔にでも追われたみたいにいかだまで走れ!」
俺はそうし、彼も同じようにした。俺たちは同時にいかだに着き、二秒も経たないうちに、暗く静かなまま、川の真ん中に向かって滑り降りていた。誰も一言も口をきかなかった。哀れな王様は観客と派手な時間を過ごすことになるだろうと思ったが、そんなことは全くなかった。やがて彼はウィグワムの下から這い出してきて言った。
「さて、今回は古い手はうまくいったかね、公爵?」
彼は全く町には行っていなかったのだ。
俺たちは村から十マイルほど下るまで、一切明かりをつけなかった。それから明かりをつけて夕食を食べ、王様と公爵は、あの人々をまんまと出し抜いたやり口に、腹の骨が緩むほど笑い転げた。公爵は言った。
「うぶな田舎者どもめ! 俺はわかっていたさ、最初の客は黙っていて、町の残りの連中を罠にはめるだろうと。そして、三日目の夜に俺たちを待ち伏せし、今度は自分たちの番だと考えることもな。まあ、確かに彼らの番だ。彼らがその機会にいくら払うか、何かと交換してでも知りたいもんだ。本当に知りたいよ、彼らがその機会をどう生かしているか。望むならピクニックにでも変えられるだろう――食料はたっぷり持ってきたんだからな。」
あの悪党どもは、その三晩で四百六十五ドルを稼いだ。あんなふうに荷馬車一台分もの金が運び込まれるのは、これまで見たことがなかった。やがて、彼らが眠っていびきをかいていると、ジムが言った。

「なあハック、あの王様たちのやり方にはたまげへんか?」
「いや」と俺は言った。「たまげない。」
「なんでたまげへんのや、ハック?」
「まあ、たまげないんだよ。そういう血筋だからな。たぶん、みんな同じようなもんだ。」
「せやけどハック、わしらのこの王様たちは、ほんまもんの悪党や。まさにそれや。ほんまもんの悪党やで。」
「ああ、それが俺の言ってることさ。俺がわかる限り、王様ってのはたいてい悪党なんだ。」
「ほんまかいな?」
「一度本で読んでみろよ――わかるから。ヘンリー八世を見てみろ。こいつなんて、あいつに比べりゃ日曜学校の校長先生みたいなもんだ。それに、チャールズ二世、ルイ十四世、ルイ十五世、ジェームズ二世、エドワード二世、リチャード三世、その他四十人以上。それに、昔大暴れして騒ぎを起こしたサクソン七王国連中も全部だ。おいおい、全盛期のヘンリー八世のじいさんを見せてやりたかったぜ。あいつは逸品だった。毎日新しい嫁を娶っては、翌朝にはその首をはねてた。卵を注文するのと同じくらい平気な顔でそれをやってのけたんだ。『ネル・グウィンを連れてこい』と彼が言う。人々は彼女を連れてくる。翌朝、『首をはねろ!』そして彼らは首をはねる。『ジェーン・ショアを連れてこい』と彼が言う。彼女がやって来る。翌朝、『首をはねろ』――そして彼らは首をはねる。『麗しのロザムンドを呼び出せ』麗しのロザムンドがベルに応える。翌朝、『首をはねろ』。そして、彼は毎晩、彼女たち一人一人に物語を語らせた。そうやって千と一つの物語を独り占めするまで続け、それから全部を一つの本にまとめて、『ドゥームズデイ・ブック』[訳注:史実ではウィリアム一世が作成した土地台帳]と名付けた――いい名前だし、的を射ていた。お前は王様を知らないだろ、ジム。でも俺は知ってる。そして、うちのこの古狸は、俺が歴史上で出会った中では一番まともな方だ。さて、ヘンリーは、この国と一悶着起こしたいと考えた。どうやって事を起こすか――予告するか? 国にチャンスを与えるか? いや。突然、ボストン港のお茶を全部海に投げ捨て、独立宣言を叩きつけ、かかってこいと挑発する。それが彼のやり方だった――誰にもチャンスを与えない。彼は父親のウェリントン公爵を疑っていた。さて、彼は何をしたか? 出頭を求めたか? いや――猫みたいに、マルムジー酒の大樽で溺死させた。人々が彼のいる場所に金を置きっぱなしにしていたとしよう――彼は何をしたか? 横領した。彼が何かをすると契約し、お前が金を払い、彼がそれをやるのを見届けなかったとしよう――彼は何をしたか? いつもその反対のことをした。彼が口を開いたとしよう――どうなる? すぐに口を閉じなければ、毎回嘘を一つ失うことになる。ヘンリーというのはそういう虫けらだった。もし俺たちがうちの王様たちの代わりに彼を連れていたら、うちの連中がやったよりもっとひどくあの町を騙していただろう。うちの連中が子羊だとは言わない。冷徹な事実に目を向ければ、そうじゃないからな。でも、あの古狸に比べれば何でもない。俺が言いたいのは、王様は王様なんだ、大目に見てやらなきゃいけないってことさ。総じて、連中はひどい代物だ。育てられ方がそうなんだ。」

「せやけど、この王様はほんまにひどい臭いがするで、ハック。」
「まあ、みんなそうさ、ジム。王様の臭いはどうしようもない。歴史書にもどうにもならないって書いてある。」
「さて、公爵の方は、いくつかの点ではまあまあまともな男やな。」
「ああ、公爵は違う。でも、大して違いはない。こいつは公爵にしてはかなりたちの悪いやつだ。酔っぱらうと、近眼の男でも王様と見分けがつかないだろう。」
「まあ、どっちにしろ、もうこれ以上はごめんやで、ハック。わしはこれで精一杯や。」
「俺も同じ気持ちだよ、ジム。でも、俺たちの手にあるんだから、彼らが何者かを覚えておいて、大目に見てやらなきゃ。時々、王様がいない国があるといいのにって思うよ。」
こいつらが本物の王様や公爵じゃないってことをジムに言って、何になる? 何の役にも立たないし、それに、俺が言った通りさ。本物と見分けがつかないんだから。
俺は眠りにつき、ジムは俺の番になっても起こさなかった。彼はよくそうした。夜が明ける直前に目を覚ますと、彼はそこに座って、両膝の間に頭をうずめ、独り言のようにうめき、嘆いていた。俺は気づかないふりをした。何のことかはわかっていた。彼ははるか向こうにいる妻と子供たちのことを考えていて、落ち込んでホームシックになっていたのだ。生まれてこの方、家から離れたことがなかったからだ。そして、彼は白人が自分の家族を思うのと同じくらい、自分の家族を大切に思っていると、俺は信じている。自然なことには思えないが、きっとそうなのだろう。彼はよく、俺が眠っていると思う夜に、そんなふうにうめき、嘆きながら、「哀れなリザベス! 哀れなジョニー! ほんまにつらいわ。もう二度とお前たちに会えへんのやろなあ、二度と!」と言っていた。ジムは、本当にいい黒人だった。
だがこの時、俺はなぜか彼の妻や子供たちのことを話し始めていた。やがて彼は言った。
「今回なんでこんなに気分が悪いか言うたら、さっき向こうの岸で、何かを叩くような、バタンと閉まるような音が聞こえて、わしがうちの小さなリザベスにひどい仕打ちをした時のことを思い出したからや。あの子はまだ四つくらいで、猩紅熱にかかって、ひどい目に遭ったんや。せやけど、良うなって、ある日、あの子が突っ立っとったんで、わしは言うたんや。
『戸ォ、閉めなはれ。』
あの子は閉めへんかった。ただそこに立って、わしの方を見上げてにこにこしとった。わしは腹が立って、もういっぺん、大声で言うたんや。
『聞こえへんのか! ――戸ォ閉めなはれ!』
あの子は同じように、にこにこしながら立っとった。わしは煮えくり返っとった! わしは言うた。
『わしが思い知らせたるわ!』
そう言うて、あの子の横っ面をひっぱたいたら、あの子は吹っ飛んでしもた。それからわしは別の部屋に行って、十分くらいおった。戻ってきたら、あの戸はまだ開いたままで、あの子はほとんど戸口に立って、下を向いて悲しそうにしとって、涙がぽろぽろ流れとった。ああ、わしはほんまに腹が立っとった! あの子の方に行こうとしたんやが、ちょうどその時――それは内側に開く戸やったんやが――ちょうどその時、風が吹いてきて、あの子の後ろで戸がバタンと閉まったんや、ばったーん!と――そしたら、ああ、あの子は微動だにせんかった! わしの息がほとんど止まりそうになって、わしはもう――もう――どんな気持ちやったかわからん。わしは全身震えながら、そっと這い出して、回り込んで、静かにゆっくり戸を開けて、あの子の後ろから頭を突き出して、そっと静かに、突然、ばあっ!と、叫べる限りの大声で言うたんや。あの子はびくともせんかった! ああ、ハック、わしは泣き出して、あの子を腕に抱きしめて、言うたんや。『ああ、かわいそうな子や! 全能の神様、どうか哀れなジムを許してくだせえ。わしは一生、自分を許すことなんてできまへんのや!』 ああ、あの子は完全に耳が聞こえず、口もきけへんかったんや、ハック、完全に耳が聞こえず、口もきけへんかった――それやのに、わしはあんなひどい仕打ちをしとったんや!」
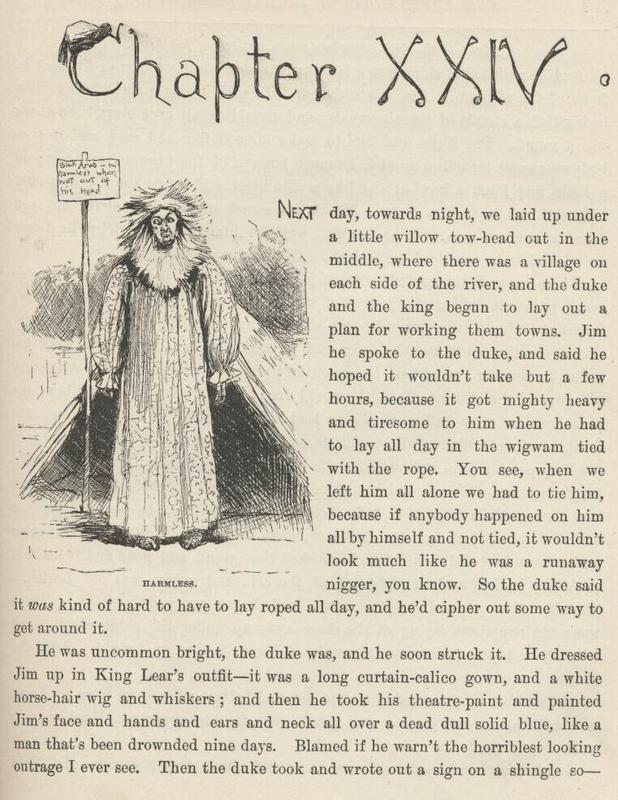
第二十四章
翌日の夜近く、俺たちは川の両岸に村がある真ん中の、小さな柳の砂州の下に停泊した。公爵と王様は、それらの町で一仕事するための計画を立て始めた。ジムが公爵に話しかけ、数時間で済むことを願うと言った。一日中ウィグワムの中でロープに縛られて横になっているのは、ひどく重荷でうんざりするからだ。わかるだろう、俺たちが彼を一人残していく時は、縛っておかなければならなかった。もし誰かが彼が一人でいて、しかも縛られていないのを見かけたら、逃亡中の黒人にはあまり見えないだろうからな。そこで公爵は、一日中縛られて横になっているのは確かに気の毒だと言い、それを回避する方法を考え出すと言った。
公爵は並外れて頭が切れる男で、すぐに名案を思いついた。彼はジムにリア王の衣装を着せた――それは長いカーテン用の更紗のガウンと、白い馬の毛のかつらとひげだった。それから、劇団用の絵の具を取り出し、ジムの顔と手と耳と首を、九日間も水に浸かっていた溺死体みたいに、生気のない、くすんだ真っ青な色に塗りたくった。誓ってもいいが、あんなに恐ろしい見た目の化け物は見たことがなかった。それから公爵は、一枚の屋根板にこんな風に看板を書いた。
病気のアラビア人――正気でいる限りは無害。
そして、その屋根板を細長い木に釘で打ち付け、その木をウィグワムの四、五フィート手前に立てた。ジムは満足だった。毎日何年も縛られて横になり、物音がするたびに全身を震わせているよりは、ずっとましだと言った。公爵は彼に、自由に気楽にしているように、もし誰かがちょっかいを出しに来たら、ウィグワムから飛び出して、少し暴れ、野獣のように二、三声吠えれば、連中は逃げ出して放っておくだろうと言った。それは全くもって的確な判断だった。だが、普通の人間なら、彼が吠えるのを待ちはしないだろう。なぜって、彼はただ死んでいるように見えるだけじゃない。それ以上だった。
あの悪党どもは、前の芝居『王の閨房の秘密』が大当たりだったもんだから、もう一度やりたがっていた。だが、さすがに噂が川下にまで伝わっているかもしれず、安全じゃないだろうと判断した。二人とも、これという計画がなかなか思いつかない。とうとう公爵が、一、二時間ほど頭をひねって、このアーカンソーの村で何か一儲けできる手はないか考えてみると言い出した。一方、王様の方は、何の計画もなしに、もう一つの村へふらりと立ち寄ってみることにしたらしい。あとは神の摂理が儲かる道へと導いてくれるのを信じるだけだ、なんて言っていた。まあ、俺に言わせりゃ、神様じゃなくて悪魔のことだろうが。
俺たちは前に立ち寄った町で、揃って既製服を買っていた。王様はそいつに着替え、俺にも着るように言った。もちろん、俺は言われた通りにした。王様の服は真っ黒で、いかにも偉そうで、糊のきいたみたいにしゃんとして見えた。服装一つで人間があんなに変わるとは、これまで知らなかった。だって、前は見るからにみすぼらしい、どうしようもない爺いだったのに、今じゃ新しい白いビーバーの帽子を脱いで、お辞儀をしてにっこり笑ったりすると、そりゃあもう立派で、善良で、信心深そうに見えるんだ。まるでノアの箱舟からまっすぐ出てきたみたいで、ひょっとしたら旧約聖書のレビその人じゃないかと思うくらいだった。ジムはカヌーを掃除し、俺はパドルを用意した。町から三マイルほど上流の、岬の陰になった岸辺に、でっかい蒸気船が一隻停泊していた。二時間ほど前からいて、貨物を積み込んでいるところだった。王様が言った。
「この身なりからすると、わしはセントルイスかシンシナティか、どこかその手の大きな町からやって来たことにした方がよさそうじゃな。ハックルベリー、あの蒸気船へ向かえ。あれに乗って村へ下ることにする。」
蒸気船に乗れると聞いて、二度も言われる必要はなかった。俺は村の半マイルほど上流の岸に着け、それから崖下の流れの緩やかなところをすいすいと漕いでいった。やがて、丸太に腰かけて汗を拭いている、人の良さそうなうぶな感じの田舎の若者が目に入った。ひどく暑い日だったからだ。若者の脇には、大きなカーペット地の旅行鞄が二つ置いてあった。
「岸に鼻先をつけろ」と王様が言う。俺はそうした。「若いの、どこへ行くのかね?」
「蒸気船です。オーリンズへ。」
「乗りなされ」と王様は言った。「少し待ちなさい、わしの召使いがその鞄を持つのを手伝うから。アドルファス、飛び降りてこの紳士を手伝ってやれ」――俺のことだと分かった。

俺は言われた通りにし、それから三人でまた出発した。若者はひどく感謝していて、こんな天気の中、荷物を運ぶのは骨が折れると言った。彼は王様にどこへ行くのかと尋ねた。王様は、川を下って今朝向こうの村に着き、これから数マイル上流の農場にいる旧友に会いに行くところだと答えた。若者が言う。
「最初にお見かけした時、こりゃウィルクスさんに違いない、ぎりぎり間に合ったんだな、と思ったんですよ。でも、すぐに考え直しました。『いや、違うだろう。もしそうなら、川を上ったりはしないはずだ』ってね。あなた、ウィルクスさんじゃないですよね?」
「いや、わしの名前はブロジェット――アレクサンダー・ブロジェット――牧師アレクサンダー・ブロジェットと申し上げるべきかな、主のはしたない僕の一人ですからな。しかし、もしウィルクスさんが何か見逃してしまったのなら、間に合わなかったことを気の毒に思う気持ちに変わりはない。何も見逃していなければよいのだが。」
「ええ、財産に関しては何も損はしませんよ。それは間違いなく手に入りますから。ただ、兄弟のピーターさんの死に目に会えなかった。まあ、それを気にするかどうかは誰にも分かりませんがね。でも、ピーターさんの方は、死ぬ前に彼に会うためなら、この世の何でも差し出したでしょう。この三週間、そのことばかり話していました。少年時代に一緒に過ごして以来、一度も会っていなかったそうですから。それに、もう一人の兄弟のウィリアムさんには一度も会ったことがなかった。耳が聞こえず口もきけない方です。ウィリアムさんは三十か三十五歳くらいでしょう。こっちに来たのはピーターさんとジョージさんだけでした。ジョージさんは結婚していた方で、彼と奥さんは二人とも去年亡くなりました。今残っているのはハーヴェイさんとウィリアムさんだけです。で、さっきも言ったように、二人は間に合わなかったんですよ。」
「誰か知らせを送ったんですか?」
「ええ、もちろん。一、二ヶ月前、ピーターさんが最初に倒れた時に。というのも、ピーターさんはその時、今度はもう良くならないような気がすると言っていたんです。ご存知の通り、かなり年をとっていましたし、ジョージさんの娘さんたちはまだ若すぎて、赤毛のメアリー・ジェーンを除けば、あまり話し相手にもならなかった。だから、ジョージさん夫婦が亡くなってからは、なんだか寂しそうで、あまり生きることに執着していないようでした。彼はハーヴェイさんに会いたがっていました――ついでに言えばウィリアムさんにもね。遺言状を書くのが嫌でたまらない、そういう種類の人だったんです。ハーヴェイさん宛てに手紙を残していて、その中に金の隠し場所と、残りの財産をどう分けてほしいかを書いておいたそうです。ジョージさんの娘たちが困らないようにってね。ジョージさんは何も残さなかったもんですから。彼にペンを執らせることができたのは、その手紙だけでした。」
「どうしてハーヴェイさんは来ないんでしょうね? どこに住んでるんです?」
「ああ、彼はイギリスに――シェフィールドに住んでいて、そこで説教をしているんです。この国には一度も来たことがありません。あまり時間がなかったんでしょうし、それに、手紙が届かなかった可能性だってありますからね。」
「それはお気の毒に。兄弟に会えずに亡くなるとは、哀れなことだ。あなたはオーリンズへ行くとおっしゃったかな?」
「ええ、でもそれは旅の一部にすぎません。来週の水曜日には、船でリオデジャネイロへ行くんです。叔父がそこに住んでいるんですよ。」
「それは長い旅ですな。しかし、素晴らしいことでしょう。わしも行ってみたいものだ。メアリー・ジェーンが一番上かな? 他の子たちはいくつだね?」
「メアリー・ジェーンが十九歳、スーザンが十五歳、ジョアンナが十四歳くらいです。ジョアンナは慈善活動に熱心な子で、みつくちなんです。」
「哀れな子たちだ! こんな冷たい世の中に、たった三人で残されるとは。」
「まあ、もっと悪い状況だってあり得ますよ。ピーターさんには友人がいましたから、彼らが娘さんたちに何の害も及ばないようにしてくれるでしょう。バプテスト教会の説教師ホブソンさん、ロット・ホーヴェイ執事、ベン・ラッカーさん、アブナー・シャックルフォードさん、弁護士のレヴィ・ベルさん、ロビンソン博士、それにその奥さんたち、バートリー未亡人、ええと、まあ、たくさんいますよ。でも、この人たちがピーターさんと一番親しくて、国へ手紙を書く時に時々名前を挙げていた人たちです。だからハーヴェイさんも、ここに着けば誰を頼ればいいか分かるでしょう。」

さて、爺さんは質問を続け、とうとう若者から根掘り葉掘り聞き出してしまった。あの忌々しい町にいる人間という人間、物という物、ウィルクス家のことなら何から何まで尋ねたんだ。ピーターの商売――皮なめし職人だったこと、ジョージの商売――大工だったこと、ハーヴェイの商売――非国教会の牧師だったこと、などなど、次から次へと。それからこう言った。
「どうしてわざわざ蒸気船まで歩いて行こうと思ったのかね?」
「あれは大きなオーリンズ行きの船なんで、あそこには停まらないんじゃないかと心配だったんです。船足が深いと、呼び止めても停まってくれませんから。シンシナティ行きの船なら停まるんですが、これはセントルイス発の船なんです。」
「ピーター・ウィルクスは裕福だったのかね?」
「ええ、かなり裕福でしたよ。家や土地を持っていましたし、現金で三、四千ドルをどこかに隠していたと噂されています。」
「いつ亡くなったと言ったかな?」
「言ってませんでしたが、昨夜です。」
「葬式は明日かな?」
「ええ、昼頃です。」
「うむ、何とも悲しいことだ。しかし、我々は皆、いつかは行かねばならん。だから、すべきことは備えておくことだ。そうすれば、万事うまくいく。」
「はい、それが一番です。母もいつもそう申しておりました。」
俺たちが蒸気船に着いた時、船は積み荷を終えるところだった。そしてまもなく出航してしまった。王様は船に乗るなんてひと言も言わなかったので、結局、俺の船旅はおじゃんになった。船が行ってしまうと、王様は俺にもう一マイル、人気のない場所までカヌーを漕がせ、そこで岸に上がってこう言った。
「さあ、急いで戻って、公爵と新しい旅行鞄をここまで連れてこい。もし公爵が対岸へ渡っていたら、そこまで行って連れてくるんだ。それから、なりふり構わずめかしこむように伝えろ。さあ、とっとと行け。」
爺さんが何を企んでいるか、俺には分かった。もちろん、何も言わなかったが。俺が公爵を連れて戻ると、カヌーを隠し、二人は丸太に腰を下ろした。王様は、若者が話したことをそっくりそのまま、一言一句違わずに公爵に聞かせた。その間ずっと、王様はイギリス人みたいに話そうと努めていた。ろくでなしのくせに、それがなかなかうまかった。俺には真似できないし、するつもりもないが、本当に大したもんだった。それから王様が言った。
「ビルジウォーター、耳が聞こえず口のきけない役はどうだ?」
公爵は、そんなものはお手のものだと言った。舞台で耳の不自由な役を演じたことがあると。そうして二人は蒸気船を待った。
昼下がり、小さなボートが二、三艘やって来たが、どれも川の上流から来たものではなかった。だが、ついに大きな船がやって来たので、二人は呼び止めた。船は短艇を寄越し、俺たちは乗り込んだ。その船はシンシナティから来たもので、俺たちが四、五マイルしか行かないと分かると、連中はかんかんに怒り、悪態をついて、岸には降ろさないと言い出した。だが、王様は落ち着いていた。こう言ったんだ。
「紳士方が一人一マイル一ドルを払って、短艇で送り迎えしてもらう余裕があるのなら、蒸気船だって彼らを運ぶ余裕くらいあるはずでしょう、違いますかな?」
それで連中も態度を和らげ、分かったと言った。村に着くと、短艇で俺たちを岸へ降ろしてくれた。短艇がやって来るのを見て、二十人ほどの男たちがわらわらと集まってきた。王様がこう尋ねると、
「どなたか、ピーター・ウィルクス氏のお宅がどこか教えていただけませんか?」
男たちは互いに顔を見合わせ、頷き合った。まるで「言った通りだろ?」とでも言うように。それから、一人が穏やかな、優しい口調で言った。
「お気の毒ですが、我々がお教えできるのは、彼が昨日の夕方までどこに住んでいたか、ということだけです。」
瞬きする間もなく、あのどうしようもない爺さんは崩れ落ちるように男にもたれかかり、その肩に顎を乗せ、背中に向かって泣き叫んだ。
「ああ、ああ、我らが哀れな兄弟よ――逝ってしまったとは、とうとう会えずじまいだったとは。おお、あまりに、あまりに酷い仕打ちだ!」

それから、わあわあ泣きながら振り返り、公爵に向かって手で訳の分からない合図をたくさん送った。すると、どうだ、公爵の方も旅行鞄を落とし、わっと泣き出したじゃないか。あれほど見事な詐欺師コンビには、生まれてこのかたお目にかかったことがない。
さて、男たちは二人の周りに集まって同情し、ありとあらゆる親切な言葉をかけ、彼らの旅行鞄を丘の上まで運んでやり、自分たちに寄りかかって泣かせてやり、王様に彼の兄弟の最期の様子をすべて話して聞かせた。王様はそのすべてを手で公爵に伝え、二人はまるで十二人の弟子を失ったかのように、亡くなった皮なめし職人のことで嘆き悲しんだ。いやはや、こんな光景に出くわしたことがあるなら、俺は黒人[訳注:原文は"nigger"。当時の人種差別的な言葉遣いをそのまま反映している]にでもなってやる。人類というものに愛想が尽きそうだった。
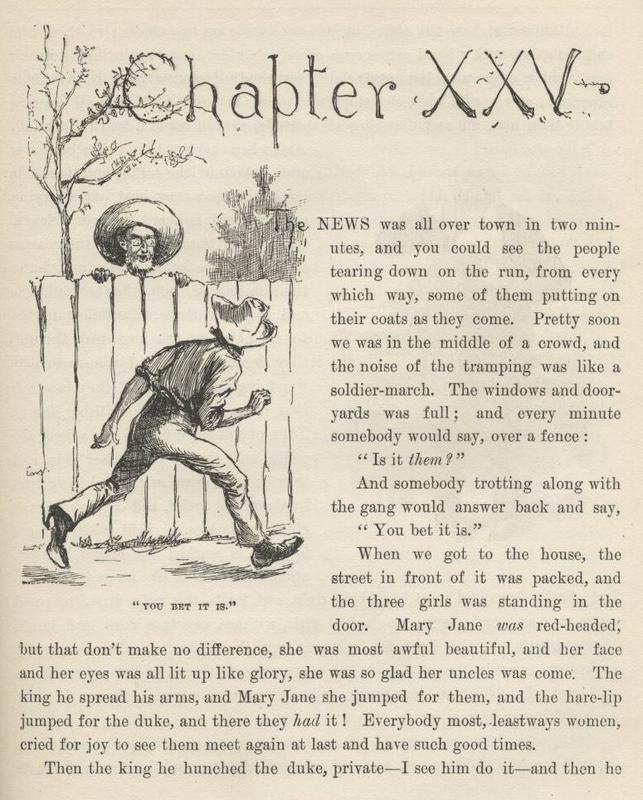
第二十五章
そのニュースは二分もたたないうちに町中に広まり、人々があちこちから駆けつけてくるのが見えた。中には走りながら上着を着ている者もいた。まもなく俺たちは群衆の真ん中にいて、足音はまるで軍隊の行進のようだった。窓も庭先も人でいっぱいだった。そして、ひっきりなしに誰かが塀の向こうから声をかける。
「あの人たちかい?」
すると、一団と一緒に小走りで来た誰かが振り返って答える。
「ああ、間違いない。」
屋敷に着くと、前の通りは人でごった返しており、三人の娘たちが戸口に立っていた。メアリー・ジェーンは確かに赤毛だったが、そんなことはどうでもよかった。彼女は恐ろしく美しく、その顔も瞳も、まるで後光が差しているかのように輝いていた。叔父たちが来てくれたのが、それほどうれしかったのだ。王様が両腕を広げると、メアリー・ジェーンがその胸に飛び込んだ。みつくちの娘は公爵に飛びつき、そこで二組はしっかりと抱き合った! ほとんど誰もが、少なくとも女たちは皆、ついに再会し、こんなに素晴らしい時を過ごしているのを見て、喜びの涙を流した。
それから王様は、こっそり公爵の脇腹をつついた――俺はそれを見た――そしてあたりを見回し、隅の二脚の椅子の上に置かれた棺を見つけた。すると、王様と公爵は互いの肩に手を回し、もう一方の手で目を覆いながら、ゆっくりと厳かにそちらへ歩いていった。誰もが道を開けるために下がり、話し声や騒ぎはぴたりと止み、人々は「シーッ!」と言い、男たちは皆帽子を脱いでうなだれた。ピンが落ちても聞こえるほどだった。二人はそこに着くと、身をかがめて棺の中を覗き込み、一目見て、それからオーリンズまで聞こえそうなほどの大声で泣き出した。そして互いの首に腕を回し、互いの肩に顎を乗せた。それから三分、いや四分だったか、あんな風に涙を流す男たちを俺は見たことがなかった。しかも、驚くなかれ、周りの誰もが同じように泣いていたのだ。あの場所は、見たこともないほど涙で湿っていた。やがて、一人が棺の片側に、もう一人が反対側に行き、ひざまずいて額を棺に乗せ、黙って祈りを捧げるふりをした。さて、こうなると、群衆は見たこともないほど心を動かされ、誰もが泣き崩れ、声を上げてすすり泣き始めた――哀れな娘たちもだ。そして、ほとんどすべての女たちが、娘たちのところへ行き、無言で、厳かにその額にキスをし、それから彼女たちの頭に手を置き、涙を流しながら空を見上げ、そしてわっと泣き出して、泣きながら、涙を拭いながら去っていき、次の女に場所を譲った。これほど胸が悪くなるような光景は見たことがなかった。
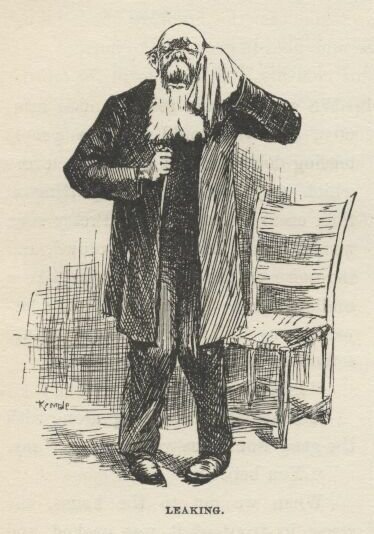
さて、やがて王様は立ち上がって少し前に進み、気分を盛り上げ、涙とくだらないおべっかだらけのスピーチをべちゃべちゃとまくしたてた。故人を失い、四千マイルもの長い旅の末に生きて会えなかったことは、自分と哀れな弟にとって辛い試練であるが、この温かい同情と聖なる涙によって、その試練は甘美なものとなり、清められた、と。だから、心から、そして弟の心からも感謝する、口では感謝を伝えられないからだ、言葉はあまりに弱く冷たいからだ、といった類のくだらない感傷的な言葉を、うんざりするほど並べ立てた。そして最後に、信心深そうな善人ぶったアーメンを泣きじゃくりながら口にすると、自分を解き放ち、張り裂けんばかりに泣き始めた。
その言葉が口から出るやいなや、群衆の中の誰かが賛美歌を歌い始め、誰もが力いっぱいそれに続いた。それは体を温め、教会が終わった時のような良い気分にさせてくれた。音楽というのは良いものだ。あの魂を溶かすような、豚に食わせるようなくだらない話の後では、これほど物事をすっきりさせ、正直で素晴らしい響きに聞こえたことはなかった。
それから王様はまた口を動かし始め、自分と姪たちは、一家の主な友人の何人かが今夜ここで一緒に夕食をとり、故人の遺灰と共に夜を明かす手伝いをしてくれるならうれしい、と言った。そして、あそこに横たわる哀れな弟が話せたら、誰の名前を挙げるか分かっている、なぜならその名はいずれも彼にとって非常に大切なもので、手紙にもよく書かれていたからだ、と。そこで、自分も同じ名前を挙げる、すなわち、以下の通りである、と……ホブソン牧師、ロット・ホーヴェイ執事、ベン・ラッカー氏、アブナー・シャックルフォード氏、レヴィ・ベル氏、ロビンソン博士、およびその夫人たち、そしてバートリー未亡人。
ホブソン牧師とロビンソン博士は、町の外れに一緒に狩りに出ていた――つまり、俺が言いたいのは、博士が病人をあの世へ送り出し、牧師がその正しい道を指し示していたということだ。弁護士のベルは、仕事でルイビルまで遠出していた。しかし、残りの人々はその場にいたので、皆やって来て王様と握手をし、感謝し、言葉を交わした。それから公爵と握手をしたが、何も言わず、ただにこにこして、まるで間抜けの集団みたいに頭をこくこくさせているだけだった。その間、公爵は手でいろいろな合図を送り、ずっと「ぐーぐー、ぐーぐーぐー」と、話せない赤ん坊のように言っていた。
そうして王様はべらべらとしゃべり続け、町のほとんどすべての人と犬について、名前を挙げて尋ね、町やジョージの家族やピーターに昔起こった、ありとあらゆる些細なことを話題にした。そしていつも、ピーターが手紙で教えてくれたことだというふりをした。だが、それは嘘だった。あの、俺たちが蒸気船までカヌーで乗せてやった、頭のからっぽな若者から、一つ残らず聞き出したことだった。
そのうち、メアリー・ジェーンが父親の遺した手紙を持ってきた。王様はそれを声に出して読み上げ、涙を流した。手紙には、住居と三千ドルの金を娘たちに、そして(繁盛していた)皮なめし工場と、他のいくつかの家と土地(約七千ドルの価値)、それに三千ドルの金をハーヴェイとウィリアムに与える、と書かれていた。そして、六千ドルの現金が地下室のどこに隠されているかも記されていた。そこで、この二人の詐欺師は、それを取りに行って、すべてを公明正大にしようと言い出し、俺にろうそくを持ってついてくるように言った。俺たちは地下室のドアを後ろで閉め、袋を見つけると、それを床にぶちまけた。すると、黄金色の硬貨が広がり、それは見事な光景だった。まあ、王様の目の輝きようといったら! 彼は公爵の肩を叩いて言った。
「おお、こいつは最高じゃないか! いやはや、まったくもって! どうだ、ビルジー、『王の閨房の秘密』より上だろう?」
公爵もそうだと言った。二人は黄金色の硬貨をいじくり回し、指の間からこぼれ落としては、床の上でじゃらじゃらと音を立てさせた。王様が言う。
「言うまでもないことだ。金持ちの死人の兄弟になり、取り残された外国の相続人の代理人を務める、これがわしとお前にとっての稼業だな、ビルジ。これも神の摂理を信じたおかげだ。長い目で見れば、これが一番いい方法だ。わしはあらゆる手を試したが、これより良い方法はない。」
ほとんどの人間なら、その山を見て満足し、信用してそのままにしただろう。だが、いや、彼らは数えなければ気が済まなかった。そこで数えてみると、四百十五ドル足りなかった。王様が言う。
「ちくしょうめ、あの四百十五ドルをどうしたんだろう?」
二人はしばらくそのことで悩み、あたりを探し回った。すると公爵が言った。
「まあ、彼はかなり重い病気だったんだ。おそらく勘違いしたんだろう――きっとそうだ。このままにして、黙っておくのが一番だ。それくらいは我慢できる。」
「おお、もちろんだとも、我慢できるさ。そんなことはどうでもいい――わしが考えているのは数のことだ。ここでは、とことん公明正大、公明正大でなければならん、分かるだろう。この金を上の階へ持って行って、皆の前で数えたいんだ――そうすれば、何も疑わしいことはない。だが、死人が六千ドルあると言っているのに、我々が――」
「待て」と公爵が言った。「不足分を補おう」。そしてポケットから黄金色の硬貨を取り出し始めた。
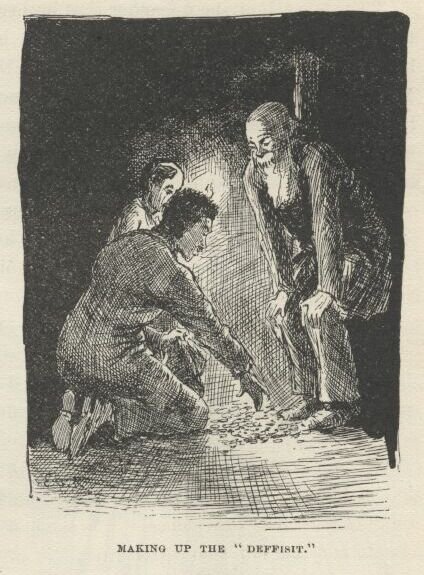
「それは実に素晴らしい考えだ、公爵――お前さんは本当に賢い頭を持っている」と王様は言った。「ありがたいことに、またしても『王の閨房の秘密』が助けてくれたな」。そして彼も黄色の金貨を取り出し、積み上げ始めた。
二人はほとんど無一文になったが、きっちり六千ドルを揃えた。
「なあ」と公爵が言った。「もう一つ考えがある。上の階へ行ってこの金を数え、それから娘たちに渡すというのはどうだ。」
「何てこった、公爵、抱きしめさせてくれ! これほど dazzling なアイデアは、生まれてこのかた聞いたことがない。お前さんは本当に驚くべき頭脳の持ち主だ。おお、これぞ最高の策略だ、間違いなし。疑いたければ疑うがいい――これで連中を黙らせてやる。」
俺たちが上の階に着くと、皆がテーブルの周りに集まった。王様は金を数え、三百ドルずつの山に積み上げた――見事な小さな山が二十個できた。誰もが腹を空かせたようにそれを見つめ、舌なめずりをした。それから彼らは金を再び袋にかき集め、王様がまたスピーチのために胸を膨らませ始めるのが見えた。彼が言う。
「友よ、あそこに横たわるわが哀れな弟は、この嘆きの谷に残された者たちに、寛大なる行いをしました。彼が愛し、庇護した、父も母も失ったこの哀れな子羊たちに、寛大なる行いをしました。ええ、そして彼を知る我々は知っています、もし彼が親愛なるウィリアムとわしを傷つけることを恐れなければ、もっと寛大にしたであろうことを。さて、そうではないでしょうか? わしの心に疑いはありません。では、そのような時に彼の邪魔をするような兄弟が、どんな兄弟でありましょうか? そして、彼がこれほど愛した、このような哀れで愛らしい子羊たちから奪う――ええ、奪う――ような叔父が、どんな叔父でありましょうか? もしわしがウィリアムを知っているならば――そしてわしは知っていると思うが――彼は――まあ、彼に直接聞いてみましょう」。彼は振り返り、手で公爵にたくさんの合図を送り始めた。公爵はしばらくの間、馬鹿げた、頭の鈍い顔で彼を見ていたが、突然意味を理解したらしく、王様に飛びつき、喜びのあまり力の限り「ぐーぐー」言いながら、彼を十五回ほど抱きしめてから離した。それから王様が言った。「分かっていましたとも。これで彼がどう感じているか、誰にでも納得がいくでしょう。さあ、メアリー・ジェーン、スーザン、ジョアンナ、この金をお取り――全部だ。あそこに横たわる、冷たいが喜びに満ちた彼からの贈り物だ。」

メアリー・ジェーンは王様のもとへ、スーザンとみつくちの娘は公爵のもとへ駆け寄った。それからというもの、あんなに抱き合ったりキスしたりする光景は見たことがなかった。そして誰もが目に涙を浮かべて押し寄せ、あの詐欺師たちの手がもげるほど握手をした。その間ずっと、こう言っていた。
「なんて優しい、良い方たちなんでしょう! ――なんて素敵なんでしょう! ――どうしてそんなことができるんです!」
さて、それからまもなく、皆がまた故人の話をし始めた。彼がいかに良い人で、いかに大きな損失だったか、などなど。やがて、顎の張った大男が外から入り込んできて、何も言わずに聞き耳を立て、あたりを見回していた。誰も彼に話しかけなかった。王様が話していて、皆がそれに聞き入っていたからだ。王様は、話し始めたことの途中で、こう言っていた――
「――彼らは故人の特別な友人でした。だからこそ、今夜ここに招待されたのです。しかし、明日は全員に来てほしい――誰も彼もです。なぜなら、彼はすべての人を尊敬し、すべての人を好んでいたからです。ですから、彼の葬送の儀が公に行われるのがふさわしいのです。」
そうして彼は、自分の話を聞くのが好きなようで、延々と月並みな話を続けた。そして、時々また「葬送の儀」という言葉を口にしたので、公爵はもう我慢できなくなった。そこで、小さな紙切れに「追悼式だ、この大馬鹿者」と書き、それを折りたたんで、「ぐーぐー」言いながら人々の頭越しに彼に渡した。王様はそれを読むとポケットに入れ、こう言った。
「哀れなウィリアム、不自由な身でありながら、彼の心は常に正しい。皆を葬儀に招待するように頼んできた――皆を歓迎してほしいと。しかし、彼が心配する必要はなかった――わしがちょうどそうしようとしていたところだ。」
それから彼は、まったく平然と話を続け、前と同じように、時々「葬送の儀」という言葉を口にした。そして三度目にそれを言った時、こう言った。
「わしが狂騒の儀と言うのは、それが一般的な言葉だからではない――追悼式が一般的な言葉だからだ――しかし、狂騒の儀こそが正しい言葉だからだ。追悼式はもうイギリスでは使われていない――廃れたのだ。我々は今イギリスでは狂騒の儀と言う。狂騒の儀の方が良い。なぜなら、それが目指すものをより正確に意味するからだ。それはギリシャ語のオルゴ、外、開かれた、公の、そしてヘブライ語のジーサム、植える、覆う、から作られた言葉だ。そこから埋葬となる。だから、ご覧の通り、葬送の狂騒の儀とは、公開の、つまり公の葬儀のことなのだ。」
あいつは俺がこれまで会った中で最悪の奴だった。さて、顎の張った男は、彼の顔を見て笑い出した。誰もがショックを受けた。誰もが「まあ、先生!」と言い、アブナー・シャックルフォードが言った。
「どうしたんだ、ロビンソン。ニュースを聞いていないのか? この方はハーヴェイ・ウィルクスさんだ。」
王様はにこやかに笑い、手を差し出して言った。
「わが哀れな弟の、親愛なる良き友にして主治医殿ではないか? わしは――」
「わしに手を触れるな!」と博士は言った。「あんた、イギリス人のように話すな、違うか? 今まで聞いた中で最悪の物真似だ。あんたがピーター・ウィルクスの弟だと! あんたは詐欺師だ、そういうことだ!」

まあ、皆の慌てようといったらなかった。彼らは博士の周りに群がり、彼をなだめようとし、説明しようとし、ハーヴェイが四十もの方法で自分がハーヴェイであることを示し、一人一人の名前も、犬の名前さえも知っていたことを話し、ハーヴェイの気持ちと哀れな娘たちの気持ちを傷つけないでくれと、何度も何度も懇願した。しかし、無駄だった。彼は怒鳴り続け、イギリス人のふりをして、あんな下手な言葉遣いしかできない男は、詐欺師であり嘘つきだと言った。哀れな娘たちは王様にしがみついて泣いていた。すると突然、博士は彼女たちの方を向いて言った。
「私は君たちのお父さんの友人であり、君たちの友人でもある。そして、友人として、君たちを守り、害やトラブルから遠ざけたいと願う正直な者として警告する。あの悪党に背を向け、彼とは一切関わるな。無知な放浪者だ、彼が言うところの、馬鹿げたギリシャ語やヘブライ語を操る。彼は最も見え透いた詐欺師だ――どこかで拾った、中身のない名前や事実を並べ立ててここにやって来た。そして君たちはそれを証拠だと信じ込み、もっと分別があってしかるべき、この愚かな友人たちに助けられて、自分自身を騙している。メアリー・ジェーン・ウィルクス、君は私が君の友人であり、しかも私心のない友人であることを知っているはずだ。さあ、私の言うことを聞きなさい。この哀れな悪党を追い出すんだ――頼むからそうしてくれ。いいかね?」
メアリー・ジェーンはすっと背筋を伸ばした。まあ、その美しいことといったら! 彼女は言った。
「これが私の答えです」。彼女は金の袋を持ち上げ、王様の手に置き、こう言った。「この六千ドルをお預かりください。そして、私と姉妹たちのために、お好きなように投資してください。領収書は結構です。」
それから彼女は片側から王様の腕に自分の腕を絡め、スーザンとみつくちの娘も反対側から同じようにした。誰もが手を叩き、床を踏み鳴らし、まるで嵐のようだった。その間、王様は頭を高く上げ、誇らしげに微笑んでいた。博士が言った。
「よろしい。私はこの件から手を引く。しかし、皆に警告しておく。いつか、この日のことを思い出すたびに、気分が悪くなる時が来るだろう」。そして彼は去って行った。
「結構ですよ、先生」と王様は、少し彼をからかうように言った。「連中に頼んで、あなたを呼んでもらうようにしますから」。それで皆が笑い、それは見事な一撃だと言った。
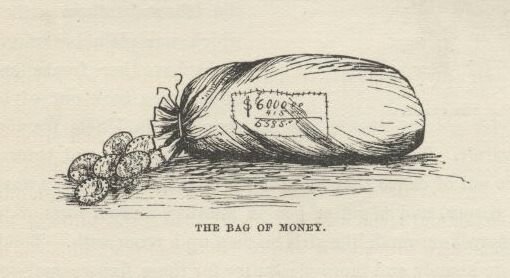
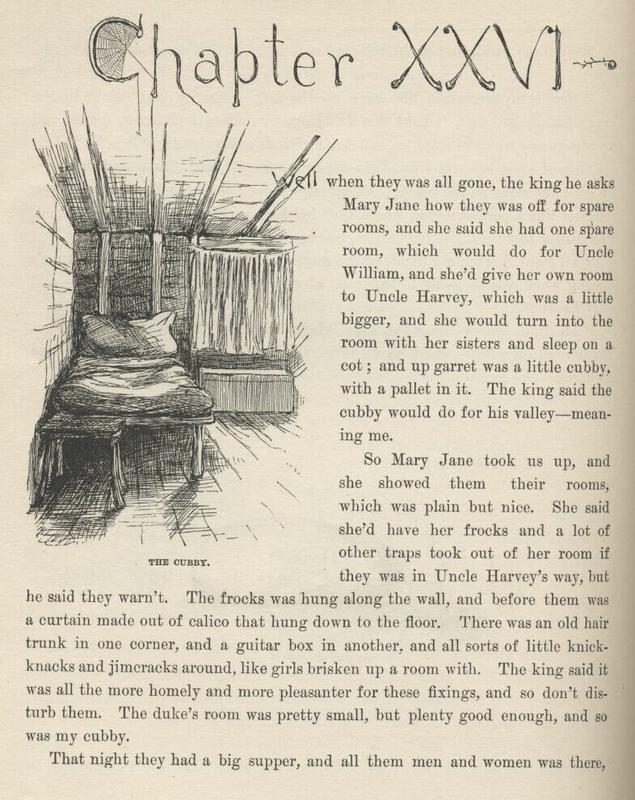
第二十六章
さて、皆が帰ってしまうと、王様はメアリー・ジェーンに空き部屋はあるかと尋ねた。彼女は、ウィリアム叔父様のために使える空き部屋が一つあり、自分の部屋は少し広いのでハーヴェイ叔父様に譲り、自分は姉妹たちの部屋に行って簡易ベッドで寝ると言った。屋根裏には、寝床のある小さな小部屋があるとのことだった。王様は、その小部屋は自分の従者――俺のことだ――にちょうどいいと言った。
そこでメアリー・ジェーンが俺たちを案内してくれた。彼女が二人に見せた部屋は、質素だが素敵だった。ハーヴェイ叔父様の邪魔になるなら、自分の部屋からドレスや他のたくさんのがらくたを運び出すと言ったが、彼は邪魔にはならないと言った。ドレスは壁に沿って掛けられ、その前には床まで垂れ下がる更紗のカーテンがあった。隅には古い革のトランクが一つ、もう一方の隅にはギターケースがあり、女の子が部屋をにぎやかにするために置くような、ありとあらゆる種類の小物やがらくたがそこらにあった。王様は、こうした飾り付けがある方が、よほど家庭的で快適だから、そのままにしておくようにと言った。公爵の部屋はかなり小さかったが、十分に立派だったし、俺の小部屋もそうだった。
その夜は盛大な夕食会が開かれ、あの男たちや女たちが皆来ていた。俺は王様と公爵の椅子の後ろに立ち、彼らの給仕をし、黒人たちが他の人たちの給仕をした。メアリー・ジェーンはテーブルの主賓席に座り、隣にはスーザンがいて、ビスケットがいかにまずいか、ジャムがいかにひどいか、フライドチキンがいかに不味くて固いか――といった、女たちが決まってお世辞を引き出すために言う、あの手のくだらないことを言っていた。そして人々は、すべてが最高級品だと知っていて、そう言った――「どうやったらビスケットがこんなにきれいに焼けるんですか?」とか、「一体全体、どこでこんなに素晴らしいピクルスを手に入れたんですか?」とか、あの手の馬鹿げたおしゃべりをしていた。夕食の席で人々がいつもやる、あれだ。

そして食事がすべて終わると、俺とみつくちの娘は台所で残り物を食べた。他の人たちは黒人たちが後片付けをするのを手伝っていた。みつくちの娘は、俺にイギリスのことを根掘り葉掘り聞き始めた。いやはや、時々、足元の氷がひどく薄くなっていくように感じた。彼女が言う。
「王様を見たことある?」
「誰だって? ウィリアム四世かい? ああ、見たことあるとも――俺たちの教会に来るんだ」。何年も前に死んだことは知っていたが、そんなそぶりは見せなかった。だから、俺が俺たちの教会に来ると言うと、彼女が言った。
「えっ――いつも?」
「ああ――いつもだ。王様の席は、俺たちの席の真ん前だよ――説教壇の向こう側だ。」
「ロンドンに住んでると思ってたけど?」
「ああ、住んでるよ。他にどこに住むって言うんだ?」
「でも、あなたはシェフィールドに住んでるんでしょ?」
俺は窮地に陥ったのが分かった。鶏の骨が喉に詰まったふりをして、どうやってこの場を切り抜けるか考える時間稼ぎをしなければならなかった。それから俺は言った。
「つまり、シェフィールドにいる時は、いつも俺たちの教会に来るってことさ。それは夏の間だけで、海水浴に来る時だけだ。」
「あら、変なこと言うのね――シェフィールドは海に面してないわ。」
「まあ、誰が面してるなんて言った?」
「だって、あなたが言ったじゃない。」
「言ってない。」
「言ったわ!」
「言ってない。」
「言ったわ。」
「そんなこと、ひと言も言ってない。」
「じゃあ、なんて言ったのよ?」
「海水浴に来るって言ったんだ――そう言ったんだ。」
「じゃあ、海に面してないのに、どうやって海水浴をするの?」
「おい、ちょっと聞けよ」と俺は言った。「コングレス・ウォーターって見たことあるか?」
「ええ。」
「じゃあ、それを手に入れるのにコングレスまで行く必要があったか?」
「いいえ。」
「まあ、ウィリアム四世だって、海水浴をするのに海まで行く必要はないんだ。」
「じゃあ、どうやってするの?」
「ここの人たちがコングレス・ウォーターを手に入れるのと同じ方法さ――樽で運ぶんだ。シェフィールドの宮殿には炉があって、王様はお湯を使いたがる。海からあんなに離れた場所で、あれだけの量のお湯を沸かすことはできない。そのための設備がないんだ。」
「ああ、なるほどね。最初からそう言ってくれれば、時間の節約になったのに。」
彼女がそう言った時、俺はまた窮地を脱したのが分かり、ほっとしてうれしくなった。次に彼女が言った。
「あなたも教会に行くの?」
「ああ――いつもだ。」
「どこに座るの?」
「もちろん、俺たちの席にさ。」
「誰の席?」
「だから、俺たちの――君のハーヴェイ叔父さんの席さ。」
「叔父さんの? 叔父さんがどうして席を必要とするの?」
「座るために必要だからさ。他に何に使うと思ったんだ?」
「だって、説教壇にいると思ってたわ。」
ちくしょう、あいつが牧師だってことを忘れてた。また窮地に陥ったのが分かったので、もう一度鶏の骨の芝居をして、考える時間を稼いだ。それから俺は言った。
「ったく、教会に牧師が一人しかいないとでも思ってるのか?」
「だって、どうしてそれ以上必要なの?」
「何だって! ――王様の前で説教するんだぞ? お前みたいな娘は見たことがない。十七人以上はいるんだ。」
「十七人! まあ! そんなにたくさんいたら、私なら最後まで座ってられないわ、たとえ天国に行けなくてもね。一週間はかかるでしょう。」
「馬鹿言え、全員が同じ日に説教するわけじゃない――一人だけだ。」
「じゃあ、残りの人たちは何をしてるの?」
「ああ、大したことはしてない。ぶらぶらしたり、献金皿を回したり――そんなところだ。でも、主に何もしていない。」
「じゃあ、何のためにいるのよ?」
「そりゃ、見栄のためさ。何も知らないのか?」
「まあ、そんな馬鹿げたことは知りたくもないわ。イギリスでは召使いはどんな風に扱われるの? 私たちが黒人を扱うより良く扱われる?」
「まさか! あそこじゃ召使いなんて、いてもいなくても同じだ。犬よりひどい扱いを受ける。」
「私たちみたいに、クリスマスや年末年始、独立記念日に休みをもらえないの?」
「おいおい、聞けよ! それだけで、お前がイギリスに行ったことがないって分かるぜ。だって、みつく――いや、ジョアンナ、あいつらは一年中、一日も休みがないんだ。サーカスにも、劇場にも、黒人ショーにも、どこにも行けない。」
「教会にも?」
「教会にもだ。」
「でも、あなたはいつも教会に行ってたんでしょ。」
さて、またやられた。俺が爺さんの召使いだってことを忘れていた。だが、次の瞬間、俺はとっさに言い訳をひねり出した。従者は普通の召使いとは違って、行きたくなくても教会に行かなければならず、家族と一緒に座るのが法律で決まっているんだ、と。しかし、あまりうまくいかず、話し終えた時、彼女が満足していないのが分かった。彼女が言う。
「正直に言って、今、私にたくさん嘘をついてない?」

「正直に言うよ」と俺は言った。
「一つも嘘はないの?」
「一つもない。嘘はひとかけらもないよ」と俺は言った。
「この本に手を置いて、そう言いなさい。」
見ると、それはただの辞書だったので、俺はそれに手を置いてそう言った。すると彼女は少し満足した様子で言った。
「じゃあ、少しは信じてあげる。でも、残りは絶対に信じないから。」
「何を信じないって言うの、ジョー?」と、スーザンを後ろに連れたメアリー・ジェーンが入ってきた。「彼にそんな風に話すのは、正しくないし、親切じゃないわ。彼は見知らぬ人で、故郷から遠く離れているのよ。自分がそんな風に扱われたらどう思う?」
「それがいつもあなたのやり方よ、メイム――いつも誰かが傷つく前に助けに入るんだから。私は彼に何もしてないわ。彼がいくつか大げさなことを言ったから、私は全部は信じないって言っただけ。私が言ったのは、それだけよ。彼だって、それくらいのことは我慢できるでしょ?」
「それが些細なことだろうと、大きなことだろうと、どうでもいいの。彼は私たちの家にいて、見知らぬ人なのよ。そんなことを言うのは良くなかったわ。もしあなたが彼の立場だったら、恥ずかしい気持ちになるでしょう。だから、他の人が恥ずかしい気持ちになるようなことを言うべきじゃないの。」
「だって、メイム、彼が言ったのよ――」
「彼が何を言ったかなんて関係ない――問題はそこじゃないの。問題は、あなたが彼に親切に接すること、そして彼に、ここは自分の国でも、自分の仲間の中いるわけでもないんだと思い出させるようなことを言わないことよ。」
俺は独り言を言った。「こいつは、俺があの老いぼれの毒蛇に金を奪われるのを黙って見ている娘だ!」
すると、今度はスーザンが割って入った。信じられないかもしれないが、彼女はみつくちの娘を墓場から呼び出したかのように、こっぴどく叱りつけた!
俺は独り言を言った。「そして、こいつも、俺が彼に金を奪われるのを黙って見ている娘だ!」
それからメアリー・ジェーンがもう一度口を挟み、いつものように、優しく愛らしく言った――それが彼女のやり方だった。しかし、彼女が話し終えた時、哀れなみつくちの娘はほとんど跡形もなくなっていた。それで彼女は叫んだ。
「分かったわ」と他の娘たちが言った。「じゃあ、彼に謝りなさい。」
彼女はそうした。そして、見事に謝った。あまりに見事だったので、聞いているのが心地よかった。そして、彼女がもう一度謝れるように、千の嘘をつけたらいいのに、と願った。
俺は独り言を言った。「こいつも、俺が彼に金を奪われるのを黙って見ている娘だ」。そして彼女が謝り終えると、三人は皆、俺がくつろいで、友達の中にいるんだと分かるように、精一杯もてなしてくれた。俺はあまりに卑劣で、落ち込んで、意地悪な気分になったので、独り言を言った。「決心がついた。あいつらのためにあの金を盗み出してやる、さもなきゃ破裂してやる。」
そこで俺は出て行った――寝ると言ったが、それはいつかという意味だった。一人になると、俺はそのことを考え始めた。独り言を言った。「あの医者のところへこっそり行って、あの詐欺師たちのことをばらそうか? いや――それはまずい。誰が教えたか言ってしまうかもしれない。そしたら、王様と公爵が俺にひどい目に遭わせるだろう。こっそり行って、メアリー・ジェーンに話そうか? いや――そんな勇気はない。彼女の顔が奴らにヒントを与えてしまうに違いない。奴らは金を持っていて、すぐにずらかって、持ち逃げするだろう。もし彼女が助けを呼んだら、事が終わる前に、俺も面倒に巻き込まれるだろう。いや、良い方法は一つしかない。どうにかしてあの金を盗まなければならない。そして、俺がやったと疑われないような方法で盗まなければならない。奴らはここでうまい汁を吸っていて、この家族とこの町から搾り取れるだけ搾り取るまで、ここを去るつもりはないだろうから、いずれチャンスは見つかるだろう。俺はそれを盗んで隠す。そして、ずっと川を下ったところで、手紙を書いて、メアリー・ジェーンに隠し場所を教えるんだ。しかし、今夜のうちに手に入れておいた方がいいかもしれない。あの医者は、見かけほど諦めていないかもしれないからだ。まだ奴らをここから追い出すかもしれない。」
そこで、俺は考えた。「あの部屋を探しに行こう」。二階の廊下は暗かったが、公爵の部屋を見つけ、手探りで探り始めた。しかし、王様が自分以外の誰かにあの金の管理を任せるはずがないと思い出した。そこで、彼の部屋へ行き、そこを探り始めた。だが、ろうそくがなければ何もできないことに気づいた。もちろん、火をつける勇気はない。だから、もう一つの手――待ち伏せして盗み聞きするしかないと判断した。その時、彼らの足音が聞こえてきたので、ベッドの下に飛び込もうとした。手を伸ばしたが、思った場所にベッドはなかった。しかし、メアリー・ジェーンのドレスを隠しているカーテンに触れたので、その中に飛び込み、ガウンの間に体をうずめ、じっと息を潜めて立っていた。
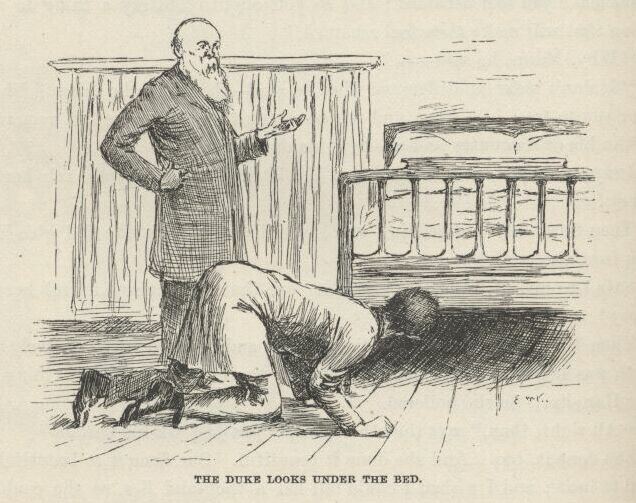
二人は入ってきてドアを閉めた。公爵がまずやったことは、かがんでベッドの下を覗き込むことだった。その時、俺はベッドが見つからなくてよかったと思った。それでも、何か内緒のことをしている時は、ベッドの下に隠れるのが自然なことなんだよな。それから二人は腰を下ろし、王様が言った。
「さて、何だ? 手短に頼むぞ。我々がここで奴らに噂される機会を与えるより、下の階で嘆き悲しむふりをしている方がましだからな。」
「まあ、こういうことだ、カペー。気が休まらない。落ち着かないんだ。あの医者のことが気にかかる。君の計画を知りたかった。私には考えがあるんだが、それは確かなものだと思う。」
「何だ、公爵?」
「午前三時前にここをずらかって、手に入れたものを持って川を下る方がいい、ということだ。特に、こんなに簡単に手に入ったんだからな――返してもらった、頭に投げつけられた、と言ってもいいくらいだ。もちろん、我々はそれを盗み返さなければならないと思っていたんだ。私は仕事を切り上げて、ずらかることに賛成だ。」
それを聞いて、俺はかなり落ち込んだ。一、二時間前なら少し違っただろうが、今はがっかりして落ち込んでいた。王様が怒鳴りつけた。
「何だと! 残りの財産を売らないでだと? 馬鹿の集団みたいに行進して、八、九千ドル相当の財産が、ただ手に入れられるのを待っているのを放っておくのか? ――しかも、全部良い、売り物になる品だぞ。」
公爵は不平を言った。金の袋だけで十分だ、これ以上深入りしたくない――大勢の孤児からすべてを奪いたくない、と。
「何を言うんだ!」と王様は言った。「我々は、この金以外は何も奪いやしない。財産を買う人々が損をするだけだ。なぜなら、我々が所有者でなかったことが分かるとすぐに――我々がずらかってから、そう長くはかからないだろう――売買は無効になり、すべては遺産に戻る。この孤児たちは家を取り戻す。それで奴らには十分だ。若くて元気だし、簡単に生計を立てられる。奴らは苦労しない。考えてもみろ――もっと恵まれていない人間が何千人も、何千人もいるんだ。ありがたいことだ、奴らには文句を言う筋合いはない。」
さて、王様は公爵を言いくるめた。それで、とうとう公爵は折れて、分かったと言った。しかし、ここに留まるのはひどく馬鹿げたことだと信じている、あの医者がうろついているんだから、と言った。だが、王様は言った。
「医者なんてくそくらえだ! あいつのことなど気にするものか? 町中の馬鹿は我々の味方じゃないか? そして、どんな町でも、それは十分な大多数じゃないか?」
そうして二人は下の階へ降りる準備をした。公爵が言った。
「あの金を良い場所に置いたとは思えないな。」
その言葉に、俺はほっとした。このままじゃ何のヒントも掴めずに終わっちまうかと思ってたところだったからだ。王様が言う。
「なぜだ?」
「メアリー・ジェーンはこれから喪に服すだろうからな。そしたらまず、部屋を片付ける黒んぼが、この服を箱に詰めてしまっちまえって言いつけられるだろうぜ。黒んぼが金を見つけて、ちょいと拝借しねえことがあると思うかい?」
「また冴えてるじゃねえか、公爵」と王様が言う。そして俺がいる場所から二、三フィートのところで、カーテンの下をごそごそ探り始めた。俺は壁にぴったり張り付いて、ぶるぶる震えながらも、息を殺していた。もし捕まったら、こいつらは俺に何て言うだろう。もし捕まったらどうするのが一番いいか、必死で考えようとした。だが、俺が半分も考えつかないうちに、王様は袋を見つけちまった。俺がそこにいるなんて、これっぽっちも疑っちゃいない。二人はその袋を、羽布団の下にある藁布団の破れ目から押し込み、藁の中に一、二フィートほど詰め込んで、これで大丈夫だと言った。黒んぼは羽布団を整えるだけで、藁布団をひっくり返すのは年に二回くらいのもんだから、もう盗まれる心配はない、というわけだ。
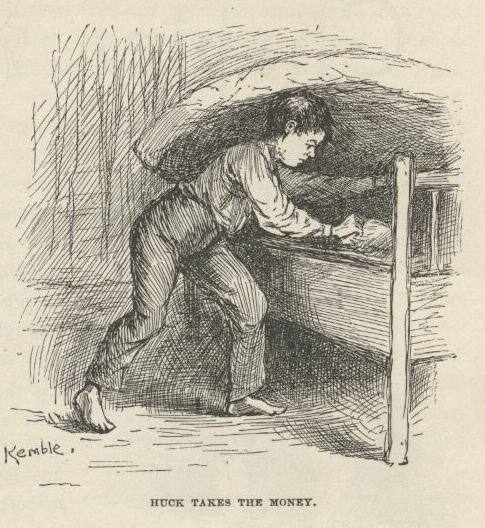
だが、そうは問屋が卸さねえ。あいつらが階段を半分も降りないうちに、俺はそいつを抜き取ってやった。手探りで屋根裏の俺のねぐらまで戻り、もっといい場所が見つかるまでそこに隠した。家の外のどこかに隠した方がいいだろうと俺は判断した。もし金がなくなったことに気づけば、家じゅうを引っ掻き回して探すに決まってる。そいつはよく分かってた。それから服を着たまま寝床に入った。だが、寝ようと思っても眠れるはずがなかった。この一件を片付けたくて、気が気じゃなかったんだ。やがて王様と公爵が上がってくる音がした。俺は寝床から転がり出て、梯子の一番上に顎を乗せて寝そべり、何かが起こるんじゃないかと待ち構えた。だが、何も起こらなかった。
俺はそのまま、夜更けの物音がすっかり止み、夜明け前の物音がまだ始まらない時間までじっとしていた。そして、梯子をそっと滑り降りた。
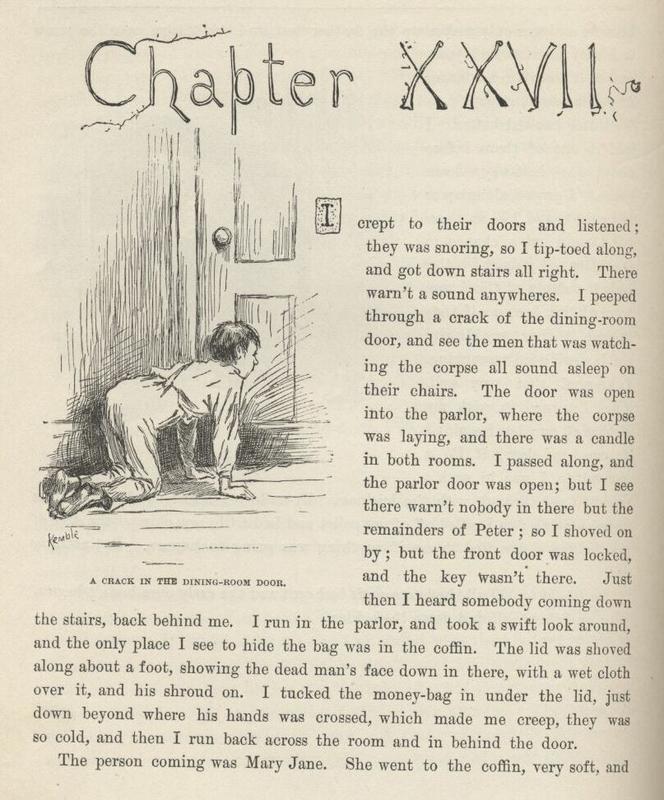
第二十七章
あいつらの部屋の戸口まで忍び寄って聞き耳を立てると、いびきが聞こえてきた。俺はつま先立ちで進み、どうにか階下まで降りた。どこもかしこも物音一つしない。食堂のドアの隙間から覗くと、遺体を見張っている男たちが、椅子に座ったままぐっすり眠りこけているのが見えた。ドアは遺体が安置されている客間へと通じていて、どちらの部屋にも蝋燭が灯っていた。俺は通り過ぎたが、客間のドアは開いていた。中にはピーターの亡骸以外、誰もいない。だからそのまま進んだが、玄関のドアには鍵がかかっていて、鍵もそこにはなかった。ちょうどその時、背後の階段を誰かが降りてくる音がした。俺は客間に駆け込み、さっとあたりを見回した。袋を隠せそうな場所は、棺の中しかなかった。蓋は一フィートほどずらしてあり、中には濡れた布を顔にかけられ、経帷子をまとった死人の顔が見えた。俺は金の袋を蓋の下、胸の上で組まれた手のすぐ向こう側に押し込んだ。その手がひどく冷たくて、ぞっとした。それから部屋を駆け抜け、ドアの陰に隠れた。
やって来たのはメアリー・ジェーンだった。彼女は静かに棺に近づき、ひざまずいて中を覗き込んだ。それからハンカチを取り出したので、泣き始めたのが分かった。声は聞こえなかったし、背中を向けていたが。俺はそっと抜け出し、食堂を通り過ぎるとき、見張りの連中に見られていないか確かめておこうと思った。隙間から覗くと、すべて問題なかった。連中は身じろぎ一つしていなかった。
俺は寝床に滑り込んだ。あれだけ苦労して危険を冒したのに、こんな結果になっちまって、ちょいと気が滅入っていた。「もし金がこのままあそこにあるなら、それでいいさ」と俺は独りごちた。「川を百マイルか二百マイル下ったらメアリー・ジェーンに手紙を書いて、あいつに遺体を掘り返させりゃ金は手に入る。だが、そうはならないだろう。蓋に釘を打つときに金が見つかるに決まってる」。そうなれば、王様がまた金を手に入れる。あいつからもう一度金をくすねるチャンスが来るまでには、ずいぶん時間がかかるだろう。もちろん、滑り降りて金を取り出したかった。だが、試す勇気はなかった。刻一刻と夜が明けていく。もうすぐ見張りの誰かが起き出すだろう。そしたら捕まっちまう――誰に頼まれたわけでもない六千ドルを手にしているところを。そんな面倒には巻き込まれたくない、と俺は自分に言い聞かせた。
朝、階下に降りると、客間は閉め切られ、見張りの姿はなかった。いるのは家族とバートリー未亡人、それに俺たちの仲間だけだった。何かあったんじゃないかとみんなの顔を窺ったが、何も読み取れなかった。
昼近くになって、葬儀屋が助手を連れてやってきた。二人は棺を部屋の真ん中に椅子を二脚並べてその上に置き、それから俺たちの椅子をずらりと並べた。近所からも椅子を借りてきて、ホールと客間と食堂はいっぱいになった。棺の蓋は前と同じようになっているのが見えたが、人が大勢いる中で、中を覗き込む勇気はなかった。
やがて人々が続々と集まり始め、詐欺師たちと娘たちは棺の頭側の最前列に座った。半時間ほど、人々はゆっくりと一列になって棺の周りを歩き、死人の顔をしばし見下ろし、中には涙を落とす者もいた。とても静かで厳粛な雰囲気で、娘たちと詐欺師たちがハンカチを目に当て、うなだれて少しすすり泣いているだけだった。他には、床をこする足音と鼻をかむ音しか聞こえない――葬式では教会以外のどんな場所よりも、人は鼻をかむものだから。
部屋が人でいっぱいになると、葬儀屋が黒い手袋をはめ、物腰柔らかに、なだめるように動き回り、最後の仕上げに取りかかった。人々や物をきちんと整え、居心地よくさせ、猫一匹立てるほどの音も立てない。彼は一言も話さなかった。人を動かし、遅れてきた者を押し込み、通路を開け、そのすべてを頷きと手振りだけでやってのけた。それから壁際に自分の場所を取った。あんなに物静かで、すべるように動き、忍びやかな男は見たことがない。それに、ハムみたいに愛想のない男だった。

どこからかメロディオンを借りてきた――調子の狂ったやつだ。準備がすべて整うと、若い女が座ってそれを弾き始めた。キーキーと赤ん坊の夜泣きみたいな音がして、みんながそれに合わせて歌い出した。俺に言わせりゃ、一番まともなのはピーターだけだった。それからホブソン牧師がおもむろに、厳かに口を開き、話し始めた。その途端、地下室から、聞いたこともないようなとんでもない騒ぎが勃発した。犬は一匹だけだったが、ものすごい騒ぎで、しかもそれがずっと続く。牧師は棺のそばに突っ立ったまま、待つしかなかった――自分の考えさえ聞こえないほどだ。まったく気まずい状況で、誰もどうしていいか分からないようだった。だがすぐに、あのひょろ長い葬儀屋が牧師に向かって、「ご心配なく――私にお任せを」とでも言うように合図するのが見えた。それから彼は身をかがめ、壁際をすべるように進み始めた。人々の頭越しに、肩だけが見えている。そうやって彼がすべるように進んでいく間も、わめき声と騒音はますますひどくなるばかり。そしてとうとう、部屋の二辺を回りきったところで、彼は地下室へと姿を消した。二秒もしないうちに、バシッという音が聞こえ、犬がものすごいうなり声を一、二度上げたかと思うと、あたりは死んだように静かになり、牧師は中断したところから厳かな話を再開した。一、二分すると、葬儀屋の背中と肩がまた壁際をすべるように現れた。そうして部屋の三辺をすべるように回り、立ち上がると、両手で口を覆い、人々の頭越しに牧師の方へ首を伸ばし、荒っぽいささやき声のような声で言った。「鼠を捕まえとったんでさ!」それから彼は身をかがめ、また壁際をすべるように自分の場所へ戻っていった。人々がたいそう満足しているのが見て取れた。当然、知りたかったのだろう。こんなささいなことは何の金にもならないが、人から尊敬され、好かれるのは、まさにこういうささいなことなのだ。あの町で、あの葬儀屋ほど人気のある男はいなかっただろう。
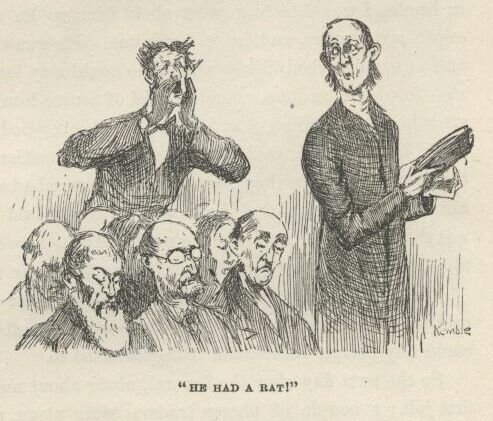
さて、葬式の説教はとても良かったが、うんざりするほど長くて退屈だった。それから王様が割り込んできて、いつものくだらないお説教を垂れ流し、ようやくそれが終わると、葬儀屋がねじ回しを手に棺に忍び寄り始めた。俺は汗びっしょりになり、鋭く彼を見つめた。だが、彼はまったく何もしなかった。ただ、粥のように静かに蓋を滑らせ、きつく、しっかりとねじで留めただけだった。これで万事休すだ! 金がまだ中にあるのかどうかも分からねえ。そこで俺は思った。「もし誰かがこっそりあの袋をくすねてたらどうだ? ――そうなったら、メアリー・ジェーンに手紙を書くべきかどうか、どうやって判断すりゃいいんだ? もし彼女が遺体を掘り返して何も見つけられなかったら、俺のことをどう思うだろう? ちくしょう」俺は言った。「俺は追われる身になって、牢屋に入れられるかもしれねえ。下手に動かず、おとなしくして、手紙なんか書かない方がいい。事態はひどくややこしくなっちまった。良くしようとして、百倍も悪くしちまった。まったく、最初から何もしなきゃよかったんだ、くそったれが!」
人々は彼を埋葬し、俺たちは家に戻った。俺はまた人々の顔を窺い始めた――そうせずにはいられなかったし、落ち着かなかった。だが、何も分からなかった。顔からは何も読み取れなかった。
王様は夕方、あちこち挨拶回りをして、みんなにいい顔をし、大層人懐っこく振る舞った。そして、イギリスの信者たちが自分のことを心配しているだろうから、急いで遺産を整理して故郷に発たなければならない、という考えを吹聴した。そんなに急がなければならないのは非常に残念だと彼は言い、みんなもそう言った。もっと長くいてほしかったが、そうもいかないのは分かると言った。そして彼はもちろん、自分とウィリアムが娘たちを故郷に連れて帰ると言った。するとみんなも喜んだ。そうすれば娘たちは安泰で、身内の元にいられるからだ。娘たちも喜んだ――あまりの嬉しさに、この世に悩みがあったことなどすっかり忘れてしまったほどで、好きな時にすぐ売っていい、準備はできている、と彼に言った。あの哀れな娘たちが大喜びしているのを見ると、こうも騙され、嘘をつかれているのが気の毒で胸が痛んだが、俺が割って入って全体の流れを変えられるような安全な方法は見当たらなかった。
さて、驚いたことに、王様は家と黒んぼたちと財産全部を、すぐさま競売にかけるという貼り紙を出した――売却は葬式の二日後。ただし、希望者は事前に個人売買も可能だという。
葬式の翌日、昼頃になって、娘たちの喜びに最初の衝撃が走った。黒人奴隷商人が二人やってきて、王様は奴隷たちを手頃な値段で売り払ったのだ。「三日後払いの手形」とかいうやつで。そして彼らは連れて行かれた。二人の息子は川上のメンフィスへ、母親は川下のオーリンズへ。哀れな娘たちと奴隷たちの心は、悲しみで張り裂けんばかりだと思った。彼らはお互いに泣きじゃくり、取り乱す様子は、見ているこっちが気分が悪くなるほどだった。娘たちは、家族が引き離されたり、町から売られたりすることになるなんて夢にも思わなかったと言った。あの哀れで惨めな娘たちと奴隷たちが、互いの首にすがりついて泣いていた光景は、決して忘れられない。もし、この売買がまやかしで、奴隷たちが一、二週間もすれば家に戻ってくると知らなかったら、俺はきっと耐えきれずに、俺たちの仲間を告発してしまっただろう。
この出来事は町でも大きな騒ぎになり、大勢の人が、あんなふうに母親と子供たちを引き離すなんてとんでもないことだと公然と言い放った。詐欺師たちの評判はいくらか傷ついた。だが、あの老いぼれの馬鹿は、公爵が何を言おうが何をしようが、頑として聞き入れなかった。言っておくが、公爵はひどくうろたえていた。
翌日は競売の日だった。朝も早い時間に、王様と公爵が屋根裏にやってきて俺を起こした。その様子から、何か面倒が起きたのだと分かった。王様が言う。
「一昨日の晩、わしの部屋におったか?」
「いいえ、陛下」――俺たちの仲間しかいないときは、いつもこう呼んでいた。
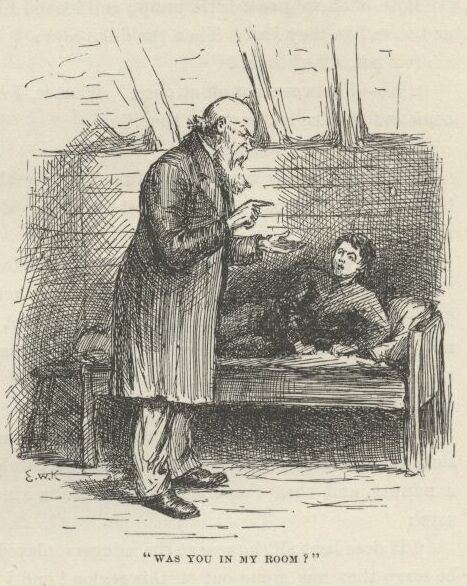
「昨日の晩か、その前の晩はどうだ?」
「いいえ、陛下。」
「正直に言うんだぞ――嘘はなしだ。」
「正直に申し上げます、陛下。本当のことを言っています。ミス・メアリー・ジェーンが陛下と公爵様をあの部屋にご案内して以来、一度も近づいておりません。」
公爵が言う。
「他に誰かが入っていくのを見たか?」
「いいえ、閣下。覚えている限りでは、いないと思います。」
「止まってよく考えろ。」
俺はしばらく考えて、好機を見出した。そして言った。
「そういえば、黒んぼたちが何度か入っていくのを見ました。」
二人は少し飛び上がり、まるで予想もしていなかったかのような、それでいて、やっぱりそうだったかのような顔をした。それから公爵が言う。
「何だと、全員か?」
「いえ――少なくとも、一度に全員ではありませんでした――つまり、一度に全員が出てくるのを見たのは、一回だけだったと思います。」
「ほう! それはいつだ?」
「葬式のあった日です。朝でした。寝過ごしたので、早くはありませんでした。ちょうど梯子を降りようとしたら、彼らが見えたんです。」
「それで、続けろ、続けろ! 何をしていた? どんな様子だった?」
「何もしていませんでした。それに、俺が見た限りでは、特に変わった様子もありませんでした。つま先立ちで離れていったので、陛下がもう起きていらっしゃると思って、部屋を片付けか何かをしにこっそり入ったんだろう、とすぐに分かりました。でも、まだお休みだと分かって、もし起こしていなければ、面倒を避けるために、起こさずにそっと出て行こうとしていたんだと思います。」
「こりゃたまげた、やられたぜ!」と王様が言う。二人ともかなり気分が悪そうで、相当間抜けな顔をしていた。彼らはしばらくそこに突っ立って考え込み、頭を掻いていたが、やがて公爵がかすれたような含み笑いを漏らして言った。
「黒んぼどもが、見事に一杯食わせやがったもんだ。この土地から出て行くのが悲しいふりをしやがって! 俺はあいつらが本当に悲しんでるんだと信じたし、あんたも、みんなもそうだ。黒んぼに役者根性がねえなんて、二度と言うんじゃねえぞ。まったく、あいつらのあの芝居ときたら、誰だって騙される。俺に言わせりゃ、あいつらは宝の山だ。もし俺に資本と劇場があったら、あれ以上の逸材は望まねえだろうな――なのに、俺たちはあいつらを二束三文で売っちまった。そうさ、しかもまだその歌も歌えねえ[訳注: 手形がまだ現金化できていないことの比喩]。なあ、その歌――手形はどこにある?」
「銀行で換金待ちだ。他にどこがある?」
「ああ、それなら結構だ、ありがたい。」
俺は、いくぶんおずおずと尋ねた。
「何かまずいことでも?」
王様が俺の方に振り向き、吐き捨てるように言った。
「てめえの知ったことか! 口を閉じて、自分のことにだけ構ってろ――もしあるならな。この町にいる間は、それを忘れんじゃねえぞ――分かったか?」それから公爵に言った。「こいつは飲み込んで、何も言わねえしかねえ。俺たちは黙ってることが一番だ。」
二人が梯子を降り始めると、公爵がまたくすくす笑って言った。
「薄利多売か! いい商売だな――ああ。」
v 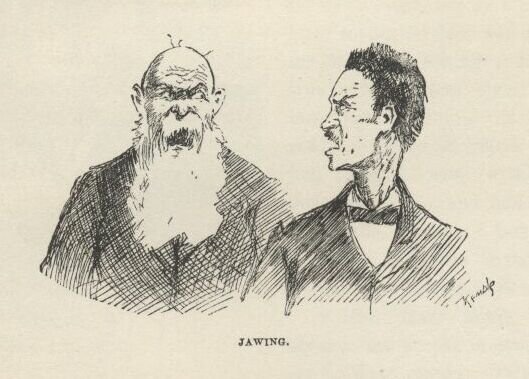
王様が彼に唸りかかって言った。
「わしは、あいつらを早く売り払うのが最善だと思ってやったんだ。利益がゼロになったどころか、かなりのマイナスで、持ち出しになったのが、てめえのせいと同じくらい、わしのせいだと言うのか?」
「ああ、もし俺の忠告を聞いてくれてりゃ、あいつらはまだこの家にいただろうし、俺たちはこんなことにはなってなかったさ。」
王様は安全な範囲で言い返し、それから矛先を変えてまた俺に食ってかかった。黒んぼたちがそんな様子で部屋から出てくるのを見たのに報告しなかったってんで、さんざんこき下ろしやがった――馬鹿でも何かがおかしいと気づいたはずだ、と。それから今度は自分自身をしばらく罵り、すべてはあの朝、遅くまで寝て自然な休息を取らなかったせいだ、二度とそんなことはするか、くそったれめ、と言った。そうして二人は言い争いながら去って行った。俺は、全部黒んぼたちのせいにできたうえに、あいつらに何の迷惑もかけずに済んだんで、心底ほっとした。

第二十八章
やがて起きる時間になった。俺は梯子を降りて階下に向かった。だが、娘たちの部屋の前まで来るとドアが開いていて、メアリー・ジェーンが古い革のトランクのそばに座っているのが見えた。トランクは開いていて、彼女は中に物を詰めていた――イギリスへ行く準備をしているのだ。しかし、今は畳んだガウンを膝の上に置いたまま、両手で顔を覆って泣いていた。それを見て、ひどく気の毒になった。誰だってそう思うだろう。俺は部屋に入って言った。
「メアリー・ジェーンさん、あんたは人が困っているのを見るのが耐えられない。俺もそうだ――たいていはね。話してくれないか。」
そこで彼女は話してくれた。やはり、奴隷たちのことだった――そうだろうと思っていた。彼女は言った。イギリスへの素晴らしい旅も、ほとんど台無しになってしまった。あの母親と子供たちが二度と会えないと知りながら、どうやったらあそこで幸せになれるのか分からない――そして、前にも増して激しく泣き崩れ、両手を振り上げて言った。
「ああ、なんてこと、あの方たちが二度と会えないなんて!」
「でも、会えますよ――二週間もしないうちに――そして俺はそれを知ってるんです!」と俺は言った。
しまった、考えるより先に口から出てしまった! そして俺が身動きする間もなく、彼女は俺の首に腕を回し、もう一度言って、もう一度、もう一度言って! とせがんだ。
俺は、あまりに突然、言い過ぎてしまったこと、そして窮地に立たされたことに気づいた。少し考えさせてくれと頼むと、彼女はそこに座っていた。とてもいらだち、興奮し、そして美しい。だが、歯を抜いてもらった人のように、どこか幸せで安堵したような表情をしていた。そこで俺は考えを巡らせ始めた。俺は独りごちた。「窮地に陥ったときに正直に本当のことを話すなんてのは、かなり危ない橋を渡ることになるんだろう。経験はないから確かなことは言えないが、とにかくそう思える。だけど、この場合に限っては、嘘より真実の方が良くて、実のところ安全なように思えてならねえ。これは心に留めておいて、いつかじっくり考えなきゃならねえな。何だか奇妙で、普通じゃねえ。こんなことは見たことがない」。さて、俺はついに自分に言い聞かせた。「一か八かやってみよう。今回は本当のことを話すんだ。火薬の樽の上にどっかり座って、どこまで吹っ飛ぶか試すみたいに火をつけるようなもんだけどな」。そして俺は言った。
「メアリー・ジェーンさん、町の外に少し離れたところで、三、四日滞在できる場所はありますか?」
「ええ、ロスロップさんのところなら。どうして?」
「理由はまだいいです。もし俺が、どうして奴隷たちが二週間もしないうちに――この家で――再会できると知っているのかを話して、その証拠も示したら――ロスロップさんのところに行って、四日間滞在してくれますか?」
「四日ですって!」と彼女は言った。「一年でも滞在しますわ!」
「分かりました」と俺は言った。「あんたから欲しいのは、ただその言葉だけです――他の男が聖書に誓うより、そっちの方が信用できる」。彼女は微笑み、とても愛らしく顔を赤らめた。俺は言った。「もしよろしければ、ドアを閉めて――かんぬきをかけます。」
それから戻って再び座り、こう言った。
「叫ばないでください。ただじっと座って、男らしく受け止めてください。本当のことを言わなければなりません。覚悟してください、メアリーさん。ひどい話で、受け入れるのは難しいでしょうが、仕方がないんです。あんたの叔父さんたちは、叔父さんなんかじゃありません。ただの詐欺師――札付きのならず者ですよ。さあ、これで最悪の部分は乗り越えました。残りはまあまあ楽に耐えられるでしょう。」
もちろん、彼女はひどく動揺した。だが、俺はもう浅瀬を越えた。だからそのまま続けた。彼女の目はどんどん燃え上がるように輝き出し、俺は洗いざらいすべてを話した。蒸気船に向かっていたあの若い馬鹿に最初に出会ったところから、彼女が玄関で王様の胸に身を投げ出し、彼が十六、七回もキスをしたところまで。すると彼女は、夕焼けのように顔を燃え上がらせて飛び上がり、言った。
「なんて人でなし! さあ、一分一秒も無駄にしないで――あの人たちにタールを塗って羽毛をくっつけて、川に放り込んでやりましょう!」

俺は言った。
「もちろんです。でも、それはロスロップさんのところへ行く前に、という意味ですか、それとも――」
「ああ」と彼女は言った。「私、何を考えているのかしら!」そう言って、すぐにまた座り直した。「今言ったことは気にしないで――お願いだから――しないでくれるわよね?」彼女は絹のような手を俺の手に置き、俺が先に死ぬと言ってしまうほど優しく言った。「考えもしなかったわ、あまりに動揺してしまって」と彼女は言う。「さあ、続けて。もうあんなことはしません。どうすればいいか教えて。あなたの言うことなら何でもします。」
「ええと」と俺は言った。「あの二人組は荒っぽい連中です。それに俺は、好むと好まざるとにかかわらず、もう少しの間あいつらと旅を続けなきゃならない事情があるんです――理由は言いたくありません。もしあんたがあいつらのことをばらしたら、この町の人たちが俺をあいつらの手から救い出してくれるでしょうし、俺はそれでいい。でも、あんたの知らない、別の誰かがひどい目に遭うことになる。その人を助けなきゃなりませんよね? もちろんです。だったら、あいつらのことはばらさないようにしましょう。」
そう言ったことで、いい考えが頭に浮かんだ。俺とジムがあの詐欺師たちから逃れる方法が、もしかしたらあるかもしれない。ここで奴らを牢屋に入れて、それから出発するんだ。だが、俺一人しか質問に答える人間がいない状態で、昼間に筏を動かしたくはなかった。だから、この計画は今夜かなり遅くなるまで実行したくなかった。俺は言った。
「メアリー・ジェーンさん、こうしましょう。そうすれば、ロスロップさんのところにそんなに長くいる必要もありません。どのくらい離れてるんですか?」
「四マイル弱よ――ここから裏手の田舎の方へ。」
「それなら大丈夫です。今すぐそこへ行って、今夜九時か九時半まで静かにしていてください。それから、何か思いついたと言って、また家まで送ってもらうんです。もし十一時より前に着いたら、この窓に蝋燭を置いてください。もし俺が現れなかったら、十一時まで待って、それでも現れなかったら、俺はもう行ってしまって、邪魔にならない安全な場所にいるということです。そしたら、外に出てこの話を広めて、あの詐欺師たちを牢屋に入れてもらってください。」
「分かったわ」と彼女は言った。「そうします。」
「そして、万が一俺が逃げられなくて、あいつらと一緒に捕まったら、あんたが、俺が事前にすべてを話したと言って、できる限り俺の味方になってくれなきゃなりません。」
「味方になるですって! もちろんなりますわ。あの人たちに、あなたの髪の毛一本触れさせません!」彼女がそう言うとき、鼻の穴が広がり、目がきらりと光るのが見えた。
「もし俺が逃げられたら、ここにはいません」と俺は言った。「あの悪党どもがあんたの叔父さんじゃないってことを証明するためにね。それに、もしここにいたとしても、俺には証明できません。あいつらが詐欺師でごろつきだってことは誓えますが、それだけです。まあ、それだけでも価値はありますが。でも、俺よりもっとうまくそれをやれる人たちがいます。俺みたいにすぐには疑われない人たちです。その人たちを見つける方法を教えましょう。鉛筆と紙をください。はい――『王の道化、ブリックスビル』。これをしまって、なくさないでください。裁判所があの二人について何か調べたくなったら、ブリックスビルに使いをやって、『王の道化』を演じた男たちがいると伝え、証人を何人か頼んでください――そうすれば、メアリーさん、瞬く間に町中の人がここにやってきますよ。それも湯気が立つほどの勢いでね。」
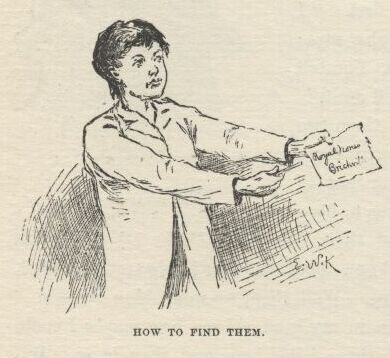
これでだいたいの段取りはついたと思った。そこで俺は言った。
「競売はそのまま続けさせて、心配しないでください。急な告知だったせいで、競売の一日後まで誰も代金を支払う必要はありませんし、あいつらはその金を手に入れるまでここを離れません。それに、俺たちが仕組んだやり方なら、売買は無効になって、あいつらは一銭も手に入れられないんです。奴隷たちの時と同じですよ――あれは売買じゃなかったし、奴隷たちはもうすぐ戻ってきます。ほら、あいつらはまだ奴隷たちの金さえ回収できてないんですから――ひどい窮地に陥ってるんですよ、メアリーさん。」
「分かったわ」と彼女は言った。「じゃあ、朝食に降りて、それからすぐにロスロップさんのところへ出発するわ。」
「いえ、それはだめです、メアリー・ジェーンさん」と俺は言った。「とんでもない。朝食前に行ってください。」
「どうして?」
「そもそも、どうして俺があんたに行ってほしかったと思いますか、メアリーさん?」
「そうね、考えもしなかったわ――それに、考えてみても、分からないわ。何だったの?」
「それは、あんたが鉄面皮な人じゃないからです。俺にとっちゃ、あんたの顔ほど分かりやすい本はありません。座って大きな活字を読むみたいに、すらすら読めちまう。あんたの叔父さんたちが朝の挨拶にキスしに来たとき、平気な顔でいられると思いますか、決して――」
「もう、やめて! ええ、朝食前に行きますわ――喜んで。姉さんたちはあの人たちと残していくの?」
「ええ、彼女たちのことは気にしないでください。もう少し我慢してもらわなきゃなりません。もしあんたたち全員が行ってしまったら、何か怪しまれるかもしれない。俺はあんたにあいつらにも、姉さんたちにも、この町の誰にも会ってほしくないんです。もし近所の人に、今朝の叔父さんたちの様子はどうかと尋ねられたら、あんたの顔が何かを物語ってしまうでしょう。いいえ、メアリー・ジェーンさん、すぐに行ってください。みんなには俺がうまく言っておきます。スーザンさんに、叔父さんたちによろしく伝えて、あんたは少し休んで気分転換するか、友人に会うために数時間出かけたって、今夜か明日の朝早くには戻るって言ってもらいますから。」
「友人に会いに行ったというのはいいけれど、あの人たちによろしくは伝えたくないわ。」
「分かりました。じゃあ、そうはしません」そう彼女に言うのは、別に悪いことじゃなかった。何の害もない。ほんのささいなことで、手間もかからない。そして、この世で人の道を最も平らにしてくれるのは、そういうささいなことなんだ。メアリー・ジェーンはそれで気持ちが楽になるだろうし、何の損にもならない。それから俺は言った。「もう一つ――あの金の袋のことです。」
「ああ、あれはあの人たちが持っているわ。それに、どうやって手に入れたかを思うと、自分がとても馬鹿みたいに感じるの。」
「いいえ、違います。あいつらは持っていません。」
「じゃあ、誰が持っているの?」
「俺も知りたいですが、分からないんです。俺が持っていました。あいつらから盗んだからです。あんたにあげるために盗んだんです。どこに隠したかも知っていますが、もうそこにはないかもしれません。本当に申し訳ない、メアリー・ジェーンさん。できる限り申し訳なく思っています。でも、俺は最善を尽くしました。誠実にやったんです。もう少しで捕まるところで、最初に目についた場所に押し込んで、逃げるしかなかったんです――そこはいい場所じゃありませんでした。」
「ああ、自分を責めるのはやめて――そんなこと、ひどいわ、許しません――仕方がなかったのよ。あなたのせいじゃないわ。どこに隠したの?」
彼女にまた悩みの種を思い出させたくはなかった。それに、あの金の袋を腹に乗せた死体が棺に横たわっている光景を彼女に思い描かせるような言葉を、どうしても口にすることができなかった。だから、しばらく何も言わなかった。それから言った。
「どこに置いたかは、できれば言いたくありません、メアリー・ジェーンさん。もし許してもらえるなら。でも、紙に書いておきますから、もしよければ、ロスロップさんへ行く道すがら読んでください。それでいいですか?」
「ええ、いいわ。」
そこで俺は書いた。「棺の中に入れました。あなたが夜中にあそこで泣いていた時、それはそこにありました。俺はドアの陰にいて、あなたのことをとても気の毒に思っていました、メアリー・ジェーンさん。」
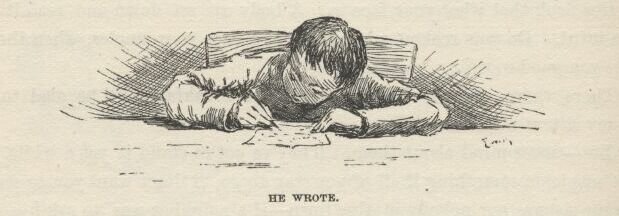
彼女が夜中にたった一人であそこで泣いていたこと、そしてあの悪党どもが彼女自身の屋根の下で寝そべり、彼女を辱め、強奪していたことを思い出すと、俺の目にも少し涙がにじんだ。それを折りたたんで彼女に渡すと、彼女の目にも涙が浮かぶのが見えた。彼女は俺の手を強く握りしめ、言った。
「さようなら。あなたの言った通り、すべてやります。もし二度と会えなくても、あなたのことは決して忘れません。何度も、何度も、あなたのことを思います。そして、あなたのことも祈ります!」――そして彼女は行ってしまった。
俺のために祈るだと! もし彼女が俺の正体を知っていたら、もっと身の丈に合った仕事を引き受けたことだろう。だが、それでも彼女はきっと祈ったに違いない――彼女はそういう人間なのだ。彼女は、その気になればユダのために祈るだけの気骨を持っていた――俺に言わせりゃ、彼女に尻込みなんてものはなかった。何と言われようと構わないが、俺の意見では、彼女は俺が今まで見たどんな娘よりも根性があった。まさに根性の塊だった。お世辞に聞こえるかもしれないが、お世辞じゃない。それに、美しさと――善良さにかけても――彼女は誰にも負けない。あの時、彼女がそのドアから出て行くのを見て以来、一度も彼女に会っていない。いや、一度も会っていないが、きっと何百万回も彼女のことを思い出しただろう。彼女が俺のために祈ると言ったことも。そして、もし俺が彼女のために祈ることが何か良いことになると考えたことがあったなら、俺はそれをやったか、さもなければ破裂していただろう。
さて、メアリー・ジェーンは裏口から出て行ったのだろう。誰も彼女が出て行くのを見なかったからだ。スーザンと兎唇のところへ行くと、俺は言った。
「あんたたちが時々会いに行く、川の向こう側に住んでる人たちの名前は何だっけ?」
二人は言った。
「何人かいるけど、主にはプロクター家よ。」
「その名前だ」と俺は言った。「すっかり忘れてた。ええと、メアリー・ジェーンさんが伝えてくれって。ひどく急いでそこへ行ったって――誰かが病気なんだそうだ。」
「誰が?」
「分からない。少なくとも、ちょっと忘れちまった。でも、確か――」
「まあ大変、ハンナじゃないでしょうね?」
「残念だけど」と俺は言った。「そのハンナだよ。」
「なんてこと、先週はあんなに元気だったのに! 重いの?」
「そんなもんじゃない。一晩中付き添ってたって、メアリー・ジェーンさんが言ってた。もう何時間も持たないだろうって。」
「まあ、なんてこと! 何の病気なの?」
とっさにまともな病名を思いつけなかったので、俺は言った。
「おたふく風邪だ。」
「おたふく風邪ですって、馬鹿言わないで! おたふく風邪の人に付き添ったりしないわよ。」
「しないって? いやいや、このおたふく風邪には付き添うさ。このおたふく風邪は違うんだ。新しい種類なんだって、メアリー・ジェーンさんが言ってた。」

「どう新しいの?」
「他の病気と混じってるんだ。」
「他の病気って何?」
「ええと、はしかと、百日咳と、丹毒と、肺病と、黄疸と、脳炎と、あと何だか分からねえけど色々だ。」
「まあ! それでおたふく風邪って言うの?」
「メアリー・ジェーンさんはそう言ってた。」
「じゃあ、一体全体、どうしてそれをおたふく風邪って言うのよ?」
「だって、おたふく風邪だからさ。それで始まるんだ。」
「でも、意味が分からないわ。誰かが足の指をぶつけて、毒を飲んで、井戸に落ちて、首を折って、脳みそをぶちまけて、誰かが通りかかって何で死んだのか尋ねたら、どこかの間抜けが『そりゃあ、足の指をぶつけたからさ』って答えるようなものよ。それに意味がある? ないわ。これにも意味なんてないわよ。うつるの?」
「うつるかって? なんだってそんな言い方するんだ。馬鍬はうつるかい――暗闇で? 一つの歯に引っかからなくても、別の歯に引っかかるに決まってるだろ? その歯だけ持って逃げるなんてできずに、馬鍬全体がついてくるだろ? まあ、この種のおたふく風邪は、いわば馬鍬みたいなもんでさ――しかも、一度しっかり引っかかったら、生半可な馬鍬じゃねえぞ。」
「まあ、ひどいわね」と兎唇が言った。「ハーヴェイ叔父さんのところに行って――」
「ああ、そうだな」と俺は言った。「俺ならそうする。もちろんそうする。一刻も無駄にしない。」
「じゃあ、どうしてそうしないの?」
「ちょっと考えてみな、そしたら分かるかもしれねえ。あんたたちの叔父さんたちは、できるだけ早くイギリスに帰らなきゃならねえんだろ? それで、あんたたちだけでそんな旅をさせるなんて、意地悪なことをすると思うかい? あんたたちを待っててくれるに決まってる。そこまではいいな。ハーヴェイ叔父さんは牧師だろ? よし、じゃあ、牧師が蒸気船の事務員を騙すかい? 船の事務員を騙すかい? ――メアリー・ジェーンさんを船に乗せるために? あんたも、そんなことはしないって分かってるだろ。じゃあ、どうする? こう言うだろうさ。『大変残念だが、私の教会の問題は、できる限りうまくやってもらうしかない。姪が恐ろしいプリュリブス・ウヌムおたふく風邪にさらされてしまったから、ここに腰を据えて、彼女に症状が出るかどうか、三ヶ月待つのが私の義務なのだ』と。でもまあ、ハーヴェイ叔父さんに話すのが一番だと思うなら――」
「馬鹿ね、メアリー・ジェーンにうつったかどうか分かるのを待ってる間に、みんなでイギリスで楽しい時間を過ごせるっていうのに、ここでぐずぐずしてるなんて。あんたって、ほんと間抜けなこと言うのね。」
「まあ、どっちにしろ、近所の人にでも話した方がいいかもしれねえな。」
「聞いてよ、もう。あんたって、生まれつきの馬鹿さ加減じゃ誰にも負けないわね。あの人たちが言いふらしに行くのが分からないの? 誰にも一切言わない以外に方法はないじゃない。」
「まあ、あんたが正しいかもな――ああ、俺もあんたが正しいと思う。」
「でも、ハーヴェイ叔父さんが心配しないように、彼女がしばらく出かけたことくらいは言っておくべきよね?」
「ああ、メアリー・ジェーンさんはそうしてほしがってた。彼女はこう言ってた。『ハーヴェイ叔父さんとウィリアム叔父さんに、私の愛とキスを伝えて、川の向こうのミスター――ミスター――ピーター叔父さんがとても大事に思ってた、あの金持ちの家の名前は何だっけ? ――ほら、あの――』。」
「あら、アプソープ家のことでしょう?」
「もちろんさ。ああいう名前は困るな、どうも半分も覚えられねえ。そう、彼女は言ったんだ。アプソープ家に、ぜひ競売に来てこの家を買ってくれるよう頼みに行ったって言ってくれって。ピーター叔父さんなら、他の誰よりもあの人たちに家を持ってほしいと思うだろうからって。そして、来てくれると言うまで、彼らに食い下がるつもりだって。それで、もし疲れすぎていなければ、家に帰ってくるし、もし疲れていたら、どっちにしろ明日の朝には帰ってくるって。プロクター家のことは何も言わずに、アプソープ家のことだけを話してくれって――それは完全に本当のことになる。彼女は家の購入について話すためにそこへ行くんだから。俺は知ってる、彼女自身がそう言ってたから。」
「分かったわ」と二人は言い、叔父さんたちを待ち伏せして、愛とキスを伝え、伝言を告げるために駆け出していった。
これで万事うまくいった。娘たちはイギリスに行きたいから何も言わないだろうし、王様と公爵は、メアリー・ジェーンがロビンソン博士の手の届くところにいるより、競売のために働いてくれている方が好都合だろう。俺はとてもいい気分だった。なかなかうまくやったもんだ、と我ながら思った。トム・ソーヤーだって、これ以上うまくはできなかっただろう。もちろん、トムならもっと凝ったやり方をしただろうが、俺はそういう育ちじゃないから、器用にはできない。
さて、競売は午後も終わりに近づいた頃、広場で開かれた。だらだらと続き、あのじいさんはそこにいて、いかにも腹黒そうな顔つきで、競売人の隣に立ち、時々聖書の一節を挟んだり、何か善人ぶったことを言ったりしていた。公爵は同情を引こうと、知る限りの媚を売って回り、とにかく自分を売り込んでいた。

だが、やがてその行事もだらだらと終わり、すべてが売れた――墓地にある、ちっぽけで取るに足らない区画以外はすべて。だから、そいつも売りさばかなければならない――王様がすべてを飲み込もうとする、あんな強欲なやつは見たことがない。さて、彼らがそれに躍起になっている間に蒸気船が着き、二分もしないうちに、群衆がわめき、叫び、笑い、騒ぎ立てながらやって来て、こう歌い出した。
「こっちが対抗馬だ! ピーター・ウィルクス翁の相続人が二組揃ったぜ――さあ、銭を払って好きな方を選びな!」
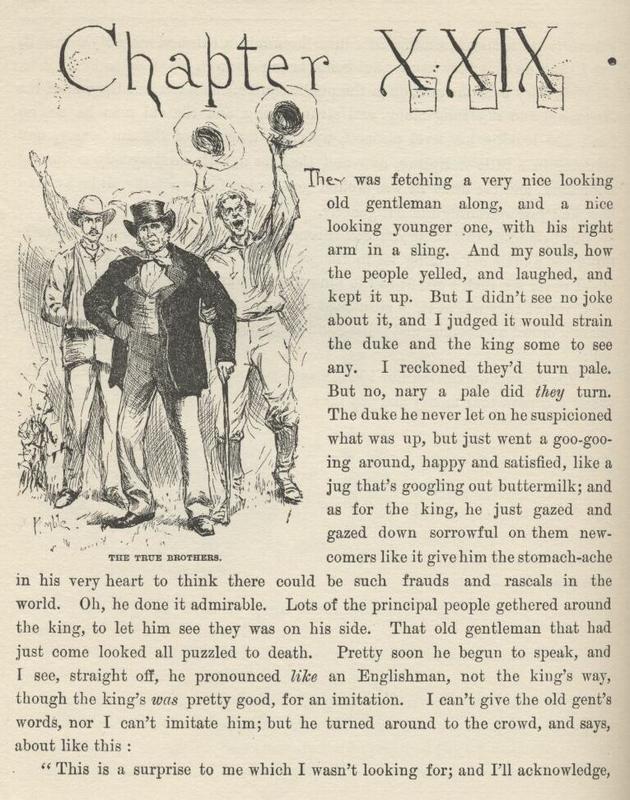
第二十九章
彼らが連れてきたのは、とても感じのいい老紳士と、感じのいい若者で、右腕を吊っていた。それにしても、まあ、人々はなんて叫び、笑い、それを続けたことか。だが、俺にはちっとも面白いとは思えなかったし、公爵と王様には、笑い事じゃ済まないだろうと思った。きっと青ざめるだろうと俺は踏んだ。だが、いや、青ざめるどころの騒ぎじゃない。公爵は、何が起こっているのか疑っている素振りも見せず、ただバターミルクがごぼごぼと注がれる水差しみたいに、幸せで満足げな顔をして媚を売って回っていた。王様に至っては、ただただ悲しげに新しい来訪者たちを見つめ、まるで世の中にこんな詐欺師や悪党がいるなんて、心の底から腹が痛むとでも言いたげな様子だった。おお、見事な演技だった。町の主だった人々の多くが王様の周りに集まり、自分たちは彼の味方だと示していた。たった今やってきた老紳士は、ひどく困惑しきっていた。やがて彼は話し始め、すぐに、彼がイギリス人みたいに発音するのが分かった――王様のとは違う。王様のも、真似としてはかなり上出来だったが。老紳士の言葉をそのまま再現することも、真似することもできないが、彼は群衆の方を向き、だいたいこんなふうに言った。
「これは私にとって予期せぬ驚きです。そして、率直に認めますが、これに対応し、答える準備が十分にはできておりません。というのも、私と弟は不幸に見舞われまして、彼は腕を骨折し、私たちの荷物が、昨夜、手違いでこの上流の町で降ろされてしまったのです。私はピーター・ウィルクスの弟ハーヴェイ、そしてこちらは彼の弟ウィリアムで、耳が聞こえず話すこともできません――今や片手しか使えないため、身振り手振りさえ十分にできません。私たちは、私たちが言う通りの者です。そして、一日か二日して荷物が届けば、それを証明できます。しかし、それまではこれ以上何も言わず、ホテルへ行って待つことにします。」
そうして彼と新しい口のきけない男は立ち去り始めた。すると王様が笑い、わめき立てた。
「腕を折っただと? ――いかにもありそうな話じゃねえか! ――それに、手話を習ってねえ詐欺師にとっちゃ、そいつは好都合だろうよ。荷物をなくしただと! そりゃあ結構なことだ! ――それに、この状況じゃ、実に巧妙なことだ!」
そうして彼はまた笑い、三、四人か、あるいは五、六人を除いて、他の誰もが笑った。その中の一人はあの医者だった。もう一人は、ルイビルへ行っていた弁護士のレヴィ・ベルで、古風な絨毯生地でできた旅行鞄を持った、鋭い目つきの紳士だった。彼は蒸気船から降りたばかりで、医者と低い声で話し、時々王様の方に目をやりながら頷いていた。もう一人は、大柄でがさつな、がっしりした男で、やってきて老紳士の言うことをすべて聞き、今度は王様の話を聞いていた。そして王様が話し終えると、このがっしりした男が進み出て言った。
「おい、ちょっと聞くが、あんたがハーヴェイ・ウィルクスなら、いつこの町に来たんだ?」
「葬式の前の日だ、友よ」と王様が言う。
「だが、何時頃だ?」
「夕方だ――日没の一、二時間ほど前だな。」
「どうやって来たんだ?」
「シンシナティからスーザン・パウエル号で下ってきた。」
「じゃあ、なんで朝っぱらから『岬』にいたんだ――カヌーに乗ってよ?」
「朝に『岬』にはおらんかったぞ。」
「嘘だ。」
何人かが彼に飛びかかり、老人で牧師である人にそんな口の利き方をするなと懇願した。
「牧師なんてくそくらえだ、こいつは詐欺師で嘘つきだ。あいつはあの朝、『岬』にいた。俺はあそこに住んでるんだ、違うか? まあ、俺はそこにいて、あいつもそこにいた。俺はあいつをそこで見たんだ。ティム・コリンズと少年と一緒に、カヌーで来た。」
医者が進み出て言った。
「ハインズ、もしその子を見たら、また分かるかね?」
「分かると思うが、どうかな。おや、あそこにいるじゃないか。簡単に見分けがつくさ。」
そいつが指さしたのは、俺だった。医者が言う。
「皆さん、新しい二人組が詐欺師かどうかは分かりません。しかし、もしこの二人が詐欺師でなければ、私は馬鹿だ、それだけです。この問題を調べるまで、彼らがここから逃げ出さないようにするのが、私たちの義務だと思います。さあ、ハインズ、来なさい。皆さんも来てください。こいつらを酒場に連れて行って、もう一組の連中と引き合わせよう。そうすれば、終わるまでには何か分かるでしょう。」
野次馬たちにはたまらない見世物だったが、王様の仲間にはそうでもなかったろう。ともかく、俺たちはみんなで出発した。日没ごろのことだった。医者は俺の手を引いて歩いた。すごく親切だったけど、俺の手をぜったいに離さなかった。

俺たちはホテルの大きな部屋に入り、蝋燭を何本か灯して、新しい二人組を連れてこさせた。まず、医者が口を開いた。
「この二人にあまり厳しく当たるつもりはないが、私は彼らを詐欺師だと思っている。それに、我々が何も知らない共犯者がいるやもしれん。もしいるとすれば、その共犯者どもはピーター・ウィルクスが遺した金の袋を持ち逃げするのではないかね? ありえない話ではない。もしこの男たちが詐欺師でないのなら、その金をこちらへ寄越し、身の潔白が証明されるまで我々が預かることに異存はあるまい――そうではないかね?」
誰もがそれに同意した。これで、あの二人組は出だしからかなり追い詰められたと俺は思った。だが、王様は悲しげな顔つきでこう言っただけだった。
「紳士諸君、金がそこにあればと願うばかりだ。この嘆かわしい一件を、公正に、公明正大に、徹底的に調査することに異を唱えるつもりは毛頭ない。だが、ああ、悲しいかな、金はそこにはないのだ。お望みなら、人をやって確かめてみるといい。」
「では、どこにあるのだ?」
「いやはや、姪御が私に預かってくれと渡してくれた時、私はそれをベッドの藁布団の中に隠したのだ。ここにいる数日のために銀行に預けるのもどうかと思い、ベッドなら安全だと考えたからでな。我々は黒人には不慣れで、イギリスの召使いのように正直なものと思い込んでいたのだ。私が階下へ降りた翌朝、黒人どもがそれを盗んでしまった。そして、奴らを売った時にはまだ金がなくなっていることに気づいていなかった。だから、奴らはまんまと金を持ち逃げしたというわけだ。ここにいる私の従者がそのことを証言できるだろう、紳士諸君。」
医者と数人が「くだらん!」と言った。誰も王様の言葉をまるっきり信じてはいないようだった。ある男が俺に、黒人たちが金を盗むのを見たかと尋ねた。俺はないと答えたが、奴らがこそこそと部屋から出て慌てて立ち去るのは見た、とは言った。その時は何も思わなかったが、たぶんご主人様を起こしてしまったとびくびくして、面倒ごとになる前に逃げ出そうとしていたんだろう、と。俺に聞かれたのはそれだけだった。すると、医者がくるりと俺の方を向いて言った。
「お前もイギリス人かね?」
俺がそうだと言うと、医者と他の何人かが笑って、「ばかな!」と言った。
さて、それから本格的な調査が始まり、俺たちはそこに釘付けになった。ああでもないこうでもないと、何時間も何時間もだ。誰も夕食のことなど口にせず、考えようともしないようだった――そして、調査は延々と続いた。これほどごちゃごちゃした話は見たことがない。連中は王様に作り話をさせ、本物の老紳士にも話をさせた。偏見に満ちた間抜けでなければ、老紳士が真実を語り、もう一方が嘘を並べていることくらい、一目でわかったはずだ。やがて、俺も知っていることを話すようにと引きずり出された。王様が横目でちらりと俺を見たので、俺はどちらの味方をすればいいか心得ていた。俺はシェフィールドの話を始めた。そこでどう暮らしていたか、イギリスのウィルクス家のことなど、あれこれと。だが、たいして話が進まないうちに医者が笑い出した。そして、弁護士のレヴィ・ベルが言った。
「座りなさい、坊や。私なら無理はしないね。君は嘘には慣れていないようだ。どうにも様になっておらん。練習が必要だな。ずいぶんぎこちないじゃないか。」
お世辞にも嬉しくなかったが、ともかく解放されてほっとした。
医者が何か言おうとして、向き直って言った。
「もし君が最初から町にいてくれたらな、レヴィ・ベル――」 王様が割って入り、手を差し伸べて言った。
「おや、この方が、亡き哀れな弟が手紙で何度も書き送ってきた旧友の方ですかな?」
弁護士と王様は握手を交わした。弁護士は微笑んで嬉しそうな顔をし、二人はしばらく話し込んだ後、隅の方へ寄って小声で話していた。やがて、弁護士が声を張り上げて言った。
「それで決まりだ。その注文書を受け取り、あなたのお兄さんのものと一緒に送りましょう。そうすれば、万事問題ないことがわかるはずです。」
そこで紙とペンが用意され、王様は座ると首をかしげ、舌を噛みながら、何かを走り書きした。それからペンが公爵に渡された――その時初めて、公爵は青ざめた顔をした。だが、彼はペンを取って字を書いた。すると弁護士は、新しい方の老紳士に向き直って言った。
「あなたと弟さん、どうか一行か二行書いて、署名をしてください。」

老紳士は字を書いたが、誰にも読めなかった。弁護士はひどく驚いた様子で言った。
「いやはや、これには参った」――そしてポケットからごそりと古い手紙の束を取り出し、それらを調べ、老人の書いた字を調べ、また手紙の束を調べた。そして言った。「これらの古い手紙はハーヴェイ・ウィルクスからのものです。そして、ここにこの二つの筆跡がある。誰が見ても、彼らが書いたものではないとわかる」(王様と公爵は、弁護士にしてやられたと気づき、一杯食わされたような、間抜けな顔をしていた)「そして、ここにこの老紳士の筆跡がある。誰が見ても、彼が書いたものではないと簡単にわかる――実のところ、彼が書いた引っ掻き傷は、そもそも文字ですらない。さて、ここにウィリアムからの手紙がいくつか――」
新しい方の老紳士が言った。
「恐れ入りますが、説明させてください。私の字は、そこにいる弟以外には誰も読めません――ですから、弟が私のために代筆するのです。そこにあるのは彼の筆跡で、私のではないのです。」
「なんと!」と弁護士は言った。「これはとんだことになった。ウィリアムの手紙もいくつか持っているのですがね。彼に一行かそこら書いてもらえれば、比べることが――」
「彼は左手では字が書けないのです」と老紳士は言った。「もし右手が使えれば、彼が自分の手紙も私の手紙も書いていたことがおわかりになるでしょう。両方ともご覧ください――同じ人間の筆跡です。」
弁護士はそれを実行し、言った。
「その通りだと信じましょう――そして、もしそうでなかったとしても、とにかく私が気づいていた以上に、はるかに強い類似点がある。いやはや、まったく! 解決の糸口が見つかったかと思ったが、一部は水の泡になってしまったようだ。しかし、とにかく一つだけ証明されたことがある――この二人は、どちらもウィルクス家の者ではない、ということですな」――そう言って、彼は王様と公爵の方へ顎をしゃくった。
どう思う? あの頑固者の大馬鹿野郎は、それでも降参しなかったんだ! 本当にしなかった。そんなのは公正なテストじゃないと言い張った。弟のウィリアムは世界一のたちの悪い冗談好きで、まじめに書こうともしなかった――ウィリアムがペンを紙に置いた瞬間、いつもの冗談をやるつもりなのがわかったんだ、と。そうして彼は熱弁をふるい、とうとうとまくし立て続けた。そのうち、本当に自分の言っていることを自分自身で信じ始めているようだった。だが、ほどなくして新しい方の紳士が割って入り、言った。
「一つ思いついたことがあります。ここに、私の兄――故ピーター・ウィルクスを埋葬のために死化粧した方はいらっしゃいますかな?」
「ああ」と誰かが言った。「俺とアブ・ターナーがやった。二人ともここにいる。」
すると老人は王様の方を向き、言った。
「おそらくこの紳士なら、彼の胸にどんな刺青があったか、お答えいただけるでしょうな?」
ちくしょう、王様はよっぽど素早く気を取り直さなきゃならなかった。さもなければ、川にえぐられた崖のように、がっくりと崩れ落ちるところだった。それほど不意を突かれたのだ。考えてもみろ、あんな不意打ちを食らったら、誰だってへこむに決まっている。だって、死んだ男の胸にどんな刺青があったかなんて、どうして彼にわかるっていうんだ? 王様は少し顔が青ざめた。それはどうしようもなかった。部屋は水を打ったように静まりかえり、誰もが少し身を乗り出して彼をじっと見つめていた。俺は心の中で思った。「今度こそ匙を投げるだろう――もう万策尽きた」。さて、どうだったか? 信じられないだろうが、彼は諦めなかった。連中が疲れ果てて人数が減るまで粘って、その隙に公爵と抜け出して逃げようと考えていたんだろう。とにかく、彼はそこに座っていた。そしてやがて、にやりと笑い始め、こう言った。
「ふん! こいつはなかなか難しい質問ですな! ええ、旦那、彼の胸にどんな刺青があったか、お教えしましょう。それはですな、小さくて、細い、青い矢ですよ――それです。そして、よおく見ないと見えません。さあ、どうですかな――え?」
いやはや、ここまであからさまな厚顔無恥の嫌な奴は見たことがなかった。
新しい方の老紳人は、さっとアブ・ターナーとその相棒の方を向き、今度こそ王様を追い詰めたと思ったのか、目を輝かせて言った。
「さあ――彼の言ったことを聞いただろう! ピーター・ウィルクスの胸に、そんな印はあったかね?」
二人はそろって口を開き、言った。
「そんな印は見ていない。」
「よろしい!」と老紳士は言った。「では、あなた方が彼の胸に見たのは、小さな、かすれたPとB(彼が若い頃に使わなくなったイニシャルだ)とWで、その間にダッシュが入っていた。つまり、P――B――Wだ」――そして彼は紙切れにそのように書き記した。「どうだ、あなた方が見たのはそれではないかね?」
二人は再びそろって口を開き、言った。
「いや、見ていない。我々は印などまったく見ていない。」
さて、これで誰もがかっとなり、口々に叫び始めた。
「こいつら全員まとめて詐欺師だ! 水にぶちこめ! 溺れさせろ! レールに乗せて町中引き回せ!」 誰もが一斉にわめき立て、あたりはがやがやと大騒ぎになった。だが、弁護士がテーブルの上に飛び乗って叫んだ。
「紳士諸君――紳士諸君! 一言だけ聞いてくれ――ほんの一言だけ――お願いだ! まだ一つ方法がある――死体を掘り起こして、確かめに行こうじゃないか。」

それで連中は納得した。
「うおおお!」と皆が叫び、すぐに出発しようとした。だが、弁護士と医者が大声で言った。
「待て、待て! この四人の男と少年を捕まえろ。そいつらも一緒に連れて行くんだ!」
「おう、やってやる!」と皆が叫んだ。「そして、もしその印が見つからなかったら、この悪党どもを全員リンチにしてやる!」
今度こそ怖かった。本当だ。だが、逃げ道はなかった。連中は俺たち全員を捕まえ、まっすぐ墓地へと行進させた。墓地は川下に一マイル半ほどのところにあり、町中の人間が俺たちの後についてきた。なにしろ、俺たちはものすごい騒ぎを立てていたし、まだ夜の九時だったからな。
俺たちの家のそばを通り過ぎる時、メアリー・ジェーンを町から出してしまわなければよかった、と思った。今なら、彼女に合図を送れば、さっと抜け出して俺を助け、あのろくでなしどものことを暴露してくれただろうに。
まあ、そんなわけで、俺たちは川沿いの道を、山猫みたいに騒ぎながらぞろぞろと進んでいった。さらに恐ろしいことに、空はどんどん暗くなり、稲妻がまたたき、ちらつき始め、風が木の葉の間を震わせ始めた。これは俺が経験した中で最もひどい災難で、最も危険な状況だった。俺はなんだか茫然としていた。何もかもが、俺の予想とは違う方向に進んでいた。本当なら、もし望めば自分のペースで事を進め、面白い見物を全部見て、いざという時にはメアリー・ジェーンに助け出してもらって自由になれる、そんな風に段取りをつけていたはずなのに。それが今や、俺と突然の死の間には、あの刺青の印以外、世界に何も隔てるものがない。もしそれが見つからなかったら――
そのことを考えるのは耐えられなかった。だが、どういうわけか、それ以外のことは何も考えられなかった。あたりはますます暗くなり、群衆からこっそり逃げ出すには絶好の機会だった。だが、ハインズという大柄でがっしりした男が俺の手首を掴んでいた――ゴリアテから逃げようとするようなものだ。彼は興奮のあまり俺をぐいぐい引きずり、俺は遅れないように走らなければならなかった。
墓地に着くと、連中はそこへなだれ込み、洪水のようにあたりを埋め尽くした。そして墓に着くと、シャベルは必要な数の百倍もあったが、ランタンを持ってくることを考えた者はいなかった。だが、連中は稲妻の明滅を頼りに、とにかく掘り始めた。そして、半マイルほど離れた一番近い家に、人をやってランタンを借りに行かせた。
こうして連中は夢中で掘り続けた。あたりはひどく暗くなり、雨が降り始め、風がびゅうびゅうと吹き荒れ、稲妻はますます激しくなり、雷がとどろいた。だが、連中はそんなことには少しも気づかなかった。この一件にすっかり夢中になっていたのだ。ある瞬間には、その大群衆の中のすべてと、一人一人の顔、そして墓から放り上げられる土が見えたかと思うと、次の瞬間には闇がすべてを拭い去り、何も見えなくなった。
ついに連中は棺桶を掘り出し、蓋のねじを外し始めた。すると、中を覗き込もうと、押し合いへし合い、肩をぶつけ合う、見たこともないような大混雑になった。あんな暗闇の中では、それは恐ろしい光景だった。ハインズは、あまりに強く引っ張ったりぐいぐい引いたりするので、俺の手首をひどく痛めつけた。彼は興奮して息を切らし、俺がこの世にいることさえすっかり忘れているようだった。
突然、稲妻が真っ白な光の洪水を放ち、誰かが叫んだ。
「なんてこった! 胸の上に金の袋があるぞ!」
ハインズは他の連中と同じように歓声を上げ、俺の手首を放すと、中へ割り込んで見ようと大きく身を乗り出した。あの暗闇の中、俺がどんなふうに飛び出して道を駆け抜けたか、誰にも説明できないだろう。
道には俺一人しかいなかった。俺はまさに飛ぶように走った――少なくとも、漆黒の闇と、時折の閃光と、ざあざあと降る雨音と、吹き荒れる風と、裂けるような雷鳴を除けば、道は俺だけのものだった。そして、間違いなく俺はかっ飛ばしていた!
町に着くと、嵐の中には誰も外に出ていないのがわかった。だから、裏通りを探したりせず、大通りをまっすぐ突っ切った。俺たちの家の方へ近づき始めた時、俺は目を凝らして家を見つめた。明かりはない。家は真っ暗だった――それがなぜか、俺を悲しく、がっかりさせた。だがついに、俺が通り過ぎようとしたちょうどその時、ぱっとメアリー・ジェーンの窓に明かりが灯った! 俺の心臓は突然、張り裂けんばかりに膨らんだ。そしてその同じ瞬間、家も何もかもが闇の中に俺の後ろとなり、この世で二度と俺の前に現れることはないのだった。彼女は俺が今まで会った中で最高の娘で、誰よりも根性があった。
町から十分に離れ、中州まで行けそうだとわかった瞬間、俺は借りられそうなボートを鋭く探し始めた。そして最初の稲妻が、鎖につながれていないボートを照らし出した時、俺はそれをひっつかんで押し出した。それはカヌーで、ロープ一本で結ばれているだけだった。中州は川の真ん中のはるか彼方、とてつもなく遠かったが、俺は時間を無駄にしなかった。そしてついにいかだにたどり着いた時、俺はあまりに疲れ果てていて、もし余裕があれば、そのまま横になって息を切らしていただろう。だが、そうはしなかった。いかだに飛び乗るなり、俺は叫んだ。
「出てこい、ジム、舫いを解け! ありがてえ、あいつらと縁が切れたぞ!」

ジムは飛び出してきて、あまりの喜びに両腕を広げて俺の方へやって来た。だが、稲妻の中で彼の姿をちらりと見た瞬間、俺の心臓は口から飛び出しそうになり、俺は後ろ向きに川へ落ちた。彼が年老いたリア王と溺れたアラビア人を一人で兼ねているのを忘れていたのだ。肝を潰すほど驚いた。だが、ジムが俺を釣り上げてくれ、抱きしめたり祝福したりしようとした。俺が戻ってきて、王様と公爵から逃れられたのが、それほど嬉しかったのだ。だが俺は言った。
「今はやめとけ、朝飯の時にしてくれ、朝飯の時に! 舫いを切れ、出発だ!」
こうして二秒後、俺たちは川を滑るように下り始めた。再び自由になり、広い川の上で二人きりになり、誰にも邪魔されないというのは、本当にいい気分だった。俺は少し飛び跳ねて、何度かジャンプしてかかとを鳴らさずにはいられなかった――どうしようもなかったのだ。だが、三度目のかかとを鳴らした時、よく知っている音が聞こえたのに気づき、息を殺して耳を澄まし、待った。そして案の定、次の稲妻が水面を照らし出した時、奴らが来た! ――ただひたすらオールを漕ぎ、小舟をぶんぶん言わせながら! 王様と公爵だった。
俺は板の上にへなへなと崩れ落ちて、万事休すと思った。そして、泣き出すのをこらえるのが精一杯だった。
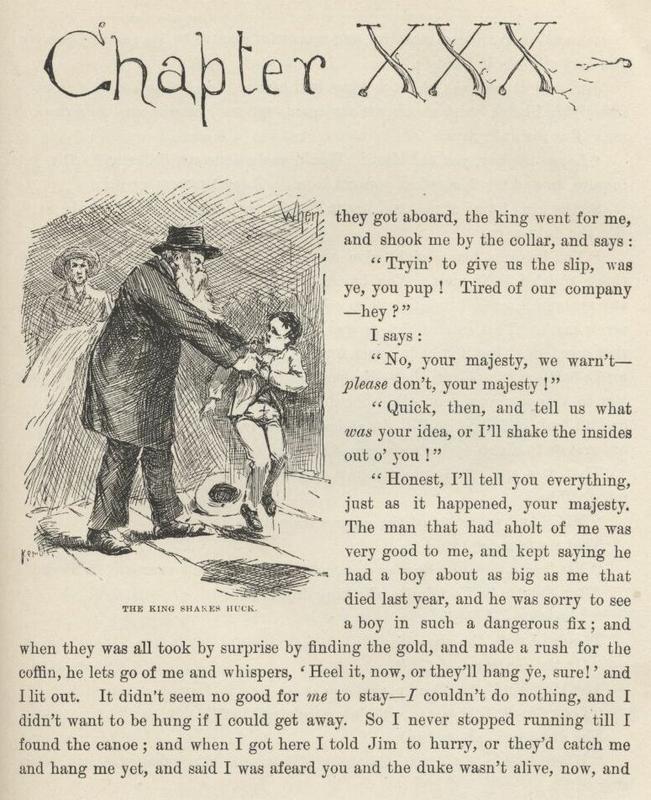
第三十章
二人がいかだに乗り込むと、王様が俺に詰め寄り、襟首を掴んで言った。
「俺たちを出し抜こうってのか、このガキめ! 俺たちの連れに飽き飽きしたってわけか、え?」
俺は言った。
「いいえ、陛下、そんなことは――やめてください、陛下!」
「さっさと言え、一体何を考えていたんだ、さもないと、はらわたを揺さぶり出してやるぞ!」
「本当です、陛下、起こったことをありのまま全部話します。俺を捕まえてた男がすごくいい人で、去年死んだ俺と同じくらいの息子がいるんだ、こんな危ない目に遭っている子供を見るのは気の毒だ、って何度も言ってたんです。それで、金が見つかって皆がびっくりして棺桶に殺到した時、その男は俺を放して、『さっさとずらかれ、さもないと間違いなく吊るされるぞ!』ってささやいてくれたんです。それで俺は逃げ出しました。俺が残っていても意味がないように思えました――俺には何もできないし、もし逃げられるなら吊るされたくなかったんです。だから、カヌーを見つけるまで止まらずに走りました。そして、ここに着いた時、ジムに急げ、さもないと捕まってまだ吊るされるぞ、と言いました。陛下と公爵はもう生きていないんじゃないかと心配で、すごく残念だったって。ジムもそうでした。だから、お二人が来るのが見えた時は、ものすごく嬉しかったんです。信じられないなら、ジムに聞いてみてください。」
ジムはほんまやで、と言った。王様はジムに黙れと言い、「ああ、そうかよ、そりゃたいそうありそうな話だ!」と言って、俺をもう一度揺さぶり、溺れさせてやると言った。だが、公爵が言った。
「その子を放せ、この大馬鹿野郎! お前なら違うことをしたとでも言うのか? 自由になった時、そいつのことを探しまわったか? 俺は覚えがねえぞ。」
そこで王様は俺を放し、あの町とそこにいる連中全員をののしり始めた。だが公爵は言った。
「てめえ自身をさんざんこき下ろした方がよっぽどいいぜ。一番そうされる資格があるのはてめえだからな。お前は最初から何一つまともなことをしちゃいねえ。ただ、あのでっちあげの青い矢の印を、あれだけ冷静に、厚かましく言い放ったのは別だがな。あれは見事だった――まったくもって最高だったぜ。そして、それが俺たちを救った。もしあれがなかったら、連中はあのイギリス人たちの荷物が着くまで俺たちを牢屋に入れていただろう――そして――刑務所行きだ、間違いなくな! だが、あの策略が連中を墓場へ連れて行き、金はそれ以上に俺たちに親切にしてくれた。あの興奮した馬鹿どもが、何もかも放り出して見物しようと殺到しなかったら、俺たちは今夜はネクタイして寝るところだったぜ――それも長持ち保証付きのな。俺たちが必要とするよりずうっと長いやつだ。」
二人は一分ほど黙り込んでいた――考えていたのだ。それから王様が、どこか上の空といった感じで言った。
「ふん! それで我々は、黒人どもが盗んだと思い込んでいたわけか!」
その言葉に俺は身を縮めた!
「ああ」と公爵は、どこかゆっくりと、もったいぶった、皮肉な口調で言った。「我々はな。」
半 分ほど経って、王様がのろのろと言った。
「少なくとも、私はそうだった。」
公爵は、同じ口調で言った。
「いやいや、私こそがそうだった。」
王様は少しむっとして言った。
「おい、ビルジウォーター、何の話をしている?」
公爵は、かなりきびきびと言った。
「そういうことなら、こっちから聞かせてもらおうか。あんたこそ何の話をしていたんだ?」
「ちぇっ!」と王様は、ひどく皮肉っぽく言った。「だが、俺にはわからんね――あんたは寝ていて、自分が何をしているか知らなかったのかもしれんがな。」
今度は公爵がむっとして言った。
「おい、そのくだらない戯言はやめろ。俺を馬鹿だと思ってるのか? あの棺桶に金を隠したのが誰か、俺が知らねえとでも思ってんのか?」
「いかにも! あんたが知っているのはわかっている。なぜなら、あんた自身がやったことだからな!」
「嘘だ!」――そして公爵は王様に掴みかかった。王様が叫んだ。
「手を放せ! ――喉から手をどけろ! ――全部撤回する!」
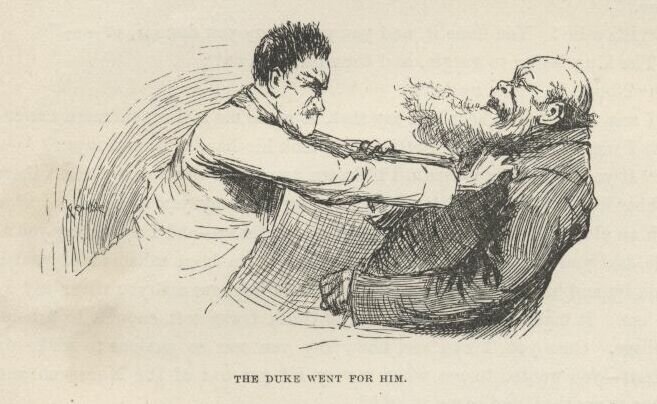
公爵は言った。
「よし、それならまず、あんたがその金をそこに隠したことを認めろ。いつか俺を出し抜いて、戻ってきて掘り出し、独り占めするつもりだったんだろう。」
「ちょっと待て、公爵――この一つの質問にだけ、正直に公平に答えてくれ。もしあんたがそこに金を置いていないのなら、そう言え。そうすれば信じるし、言ったことは全部撤回する。」
「この老いぼれ悪党め、俺じゃない、あんたも俺じゃないとわかっているはずだ。さあ、どうだ!」
「よし、それなら信じよう。だが、もう一つだけ答えてくれ――さあ、怒るなよ。金をくすねて隠そうという気はなかったか?」
公爵は少しの間何も言わなかった。それから言った。
「まあ、あったとしてもかまうもんか。とにかく、実行はしなかった。だが、あんたはそれを実行しようと考えただけでなく、実行したんだ。」
「もし俺がやったなら、この場で死んでもいい、公爵。これは本当だ。やろうとしていなかったとは言わん。なぜなら、やろうとしていたからだ。だが、あんた――つまり、誰かさんが――俺より先にやったんだ。」
「嘘だ! あんたがやったんだ。やったと言え。さもないと――」
王様は喉をごぼごぼ鳴らし始め、それから息も絶え絶えに言った。
「もういい! ――俺がやった!。」
彼がそう言うのを聞いて、俺はとても嬉しかった。それまでの気持ちよりずっと気が楽になった。そこで公爵は手を放して言った。
「もし二度と否定したら、溺れさせてやる。赤ん坊みたいにそこに座ってめそめそ泣いているのがお似合いだ――あんたのやったことを考えれば、当然の報いだ。何でもかんでも飲み込もうとする、あんな年寄りのダチョウは見たことがない――俺はあんたをずっと、実の父親のように信頼していたというのに。哀れな黒人たちに罪がなすりつけられるのをそばで聞いていて、一言も弁護しないなんて、恥を知るべきだった。あんなくだらない話を、俺がうぶにも信じたと思うと、自分が馬鹿らしくなる。ちくしょう、今ならわかるぜ、あんたがなぜあんなに不足分を埋めようと躍起になっていたか――『ロイヤル・ノンサッチ』やら何やらで俺が手に入れた金を巻き上げて、全部かっさらいたかったんだ!」
王様は、おどおどと、まだ鼻をすすりながら言った。
「いや、公爵、不足分を埋めろと言ったのはあんただ。俺じゃない。」
「黙れ! もうあんたの話は聞きたくもない!」と公爵は言った。「そして、今、その結果がどうなったかわかっただろう。連中は自分たちの金を全部取り戻し、それに加えて俺たちの金も、ほんのわずかな残りを除いて全部持っていっちまった。とっとと寝ろ。そして、お前が生きてる限り、二度と俺に不足分を埋めろなんて言うんじゃねえぞ!」
こうして王様はウィグワムにこそこそと入り込み、慰めに酒瓶に手を伸ばした。そして間もなく、公爵も自分の酒瓶に取り掛かった。そんなわけで、半時間もすると、二人はまた泥棒仲間みたいに意気投合していた。酔いが回るほど、仲睦まじくなり、互いの腕の中でいびきをかいて眠りこけてしまった。二人ともひどく上機嫌になったが、王様は、金の袋を隠したことを再び否定しないように覚えておくのを忘れるほどには、上機嫌にはならなかったことに俺は気づいた。それで俺は安心し、満足した。もちろん、二人がいびきをかき始めると、俺たちは長いことおしゃべりをし、俺はジムに何もかも話して聞かせた。
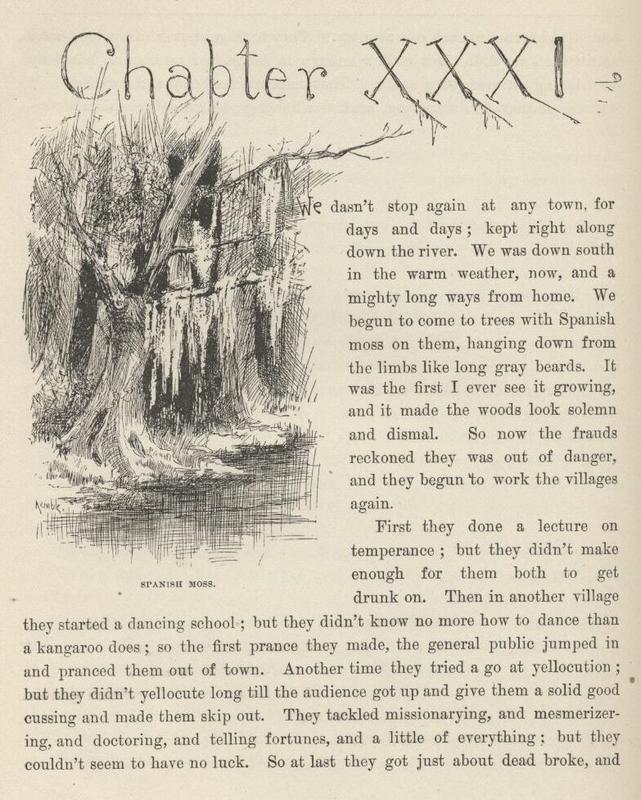
第三十一章
俺たちは何日も何日も、どの町にも立ち寄る勇気がなかった。ひたすら川を下り続けた。もう南部の暖かい地方まで来ていて、家からはとてつもなく遠かった。木の枝から長い灰色の髭のように垂れ下がった、スパニッシュ・モスが生えている木を見かけるようになった。それが生えているのを俺が見たのは初めてで、森が厳かで陰気に見えた。さて、詐欺師どもはもう危険はないと判断し、再び村々で悪事を働き始めた。
最初にやったのは禁酒の講演だったが、二人で酔っぱらうほどの金も稼げなかった。次に別の村でダンス教室を始めたが、カンガルーと同じくらいダンスの仕方を知らなかった。だから、最初のステップを踏んだ途端、一般大衆が飛び込んできて、二人を町から踊り出させた。またある時は、弁論術を試そうとしたが、長く弁論する間もなく、聴衆が立ち上がって、こっぴどく罵倒し、二人を追い出した。伝道活動、催眠術、医者、占い、その他あらゆることを手当たり次第に試したが、どうにも運がないようだった。とうとう二人はほとんど無一文になり、いかだが流れるままに寝そべって、一日中半分くらい、何も言わずに考え込み、ひどく落ち込んで絶望していた。
そしてついに、二人は心機一転、ウィグワムで頭を突き合わせ、二、三時間もひそひそと内緒話をするようになった。俺とジムは不安になった。その様子が気に入らなかった。二人はこれまで以上の悪巧みを考えているに違いないと思った。あれこれ考えた末、俺たちは、二人が誰かの家か店に押し入るか、偽札作りに手を出すか、何かそんなことをするつもりだと結論づけた。それで俺たちはすっかり怖くなり、そんな行為には世界中の何があっても関わらない、そして少しでも機会があれば、冷たくあしらって、ずらかって二人を置き去りにしよう、と約束した。さて、ある朝早く、俺たちはパイクスヴィルという名の、みすぼらしい小さな村から二マイルほど下流の、安全な場所にいかだを隠した。そして王様は上陸し、『ロイヤル・ノンサッチ』の噂がまだそこまで届いていないか、町へ行って様子を探ってくる間、皆隠れているようにと言った。(「家を物色しに、だろ」と俺は心の中で思った。「そして物色が済んだら、ここに戻ってきて、俺とジムといかだがどうなったか不思議に思うだろう――そして、不思議に思うだけで終わりさ」)そして、もし昼までに戻らなかったら、公爵と俺は万事うまくいっていると判断し、後から来るように、と言った。
そこで俺たちはその場にとどまった。公爵はいらいらして汗をかき、ひどく不機嫌だった。彼は俺たちを何から何までののしり、俺たちは何もまともにできないようだった。彼はどんな些細なことにもケチをつけた。何かが起こりかけているのは確かだった。昼になっても王様が戻らなかった時、俺は心から嬉しかった。とにかく、変化があるだろう――そして、その上にあの変化のチャンスがあるかもしれない。そこで俺と公爵は村へ行き、そこで王様を探し回った。やがて、小さな安酒場の裏部屋で彼を見つけた。ひどく酔っぱらっていて、大勢のならず者たちが面白半分に彼をいじめていた。彼は力の限り罵り、脅していたが、酔いすぎて歩けず、連中に何もできなかった。公爵は彼を大馬鹿野郎とののしり始め、王様も言い返し始めた。二人が本格的にやり合った瞬間、俺は飛び出して全速力で逃げ出し、鹿のように川沿いの道を駆け下りた。チャンスだと思ったからだ。そして、二人が俺とジムに再び会うまでには、長い時間がかかるだろうと心に決めた。俺は息を切らしながらも、喜びに満ちてそこへ着き、叫んだ。
「舫いを解け、ジム! もう大丈夫だ!」
だが、返事はなく、誰もウィグワムから出てこなかった。ジムがいなくなっていた! 俺は叫び声を上げた――そしてもう一度――そしてもう一度。そして、森の中をあちこち走り回り、わめき、叫んだ。だが、無駄だった――ジムはいなくなっていた。それから俺は座り込んで泣いた。どうしようもなかった。だが、じっと座ってはいられなかった。すぐに俺は道に出て、どうするのが一番いいか考えようとした。すると歩いている少年に出くわしたので、かくかくしかじかの格好をした見慣れない黒人を見なかったかと尋ねると、彼は言った。
「ああ。」
「どこで?」と俺は言った。
「ここから二マイル下の、サイラス・フェルプスさんの家だよ。逃亡黒人で、捕まったんだ。君、彼を探してたのか?」
「まさか! 一、二時間前に森で出くわしたんだ。そいつ、叫んだら肝臓をえぐり出してやるって言いやがって――それに、そこに寝てろって。だからそうしたんだ。それからずっとそこにいた。怖くて出てこられなかったんだ。」
「まあ」と彼は言った。「もう怖がらなくていいよ。だって、捕まったから。彼は南の方のどこかから逃げてきたんだ。」
「捕まってよかったよ。」
「ああ、そりゃあな! 彼には二百ドルの懸賞金がかかってるんだ。道端で金を拾うようなもんだよ。」
「ああ、そうだな――それに、俺がもっと大きかったら、その金を手に入れられたのに。俺が最初に見つけたんだ。誰が捕まえたんだ?」

「見知らぬ年寄りの男だよ――そして、その男は彼に関する自分の権利を四十ドルで売っちまったんだ。川を上らなきゃならなくて、待てないからだってさ。考えてもみろよ! 俺なら七年だって待つね。」
「俺もそうするよ、いつでもな」と俺は言った。「でも、そんなに安く売るってことは、彼の権利はそれ以上の価値がないのかもしれない。何か、まともじゃないことがあるのかもしれない。」
「でも、まともなんだよ――一点の曇りもなくね。俺自身、手配書を見たんだ。彼のことが隅から隅まで書いてある――写真みたいにそっくりで、ニューオリンズの下流にある、彼がいたプランテーションの名前も書いてある。いやはや、その儲け話に問題はないね、間違いない。なあ、噛みタバコをくれないか?」
俺は持っていなかったので、彼は去って行った。俺はいかだに戻り、ウィグワムに座って考えた。だが、何も思いつかなかった。頭が痛くなるまで考えたが、この窮地を脱する方法が見つからなかった。これだけ長い旅をして、あの悪党たちのためにあれだけ尽くしてきたのに、結局すべてが無駄になり、何もかもがめちゃくちゃに壊れてしまった。あいつらが、ジムにあんなひどい仕打ちをして、彼を一生奴隷に戻し、それも見知らぬ人々の間で、たった四十ドルの汚い金のために、そんなことができる心を持っていたからだ。
一度、俺は独り言を言った。どうせ奴隷でいなきゃならないなら、ジムにとっては家族のいる故郷で奴隷でいる方が千倍もましだろう、だからトム・ソーヤーに手紙を書いて、ミス・ワトソンにジムの居場所を伝えるように頼んだ方がいい、と。だが、すぐにその考えは二つの理由でやめた。一つは、彼女はジムが自分のもとを去ったという不義理と恩知らずな行いに腹を立て、うんざりして、またすぐに川下の奥地へ売り飛ばしちまうだろうということ。そして、もしそうしなくても、恩知らずな黒人を軽蔑するのは世の常で、誰もがジムにそれを常に感じさせるだろうから、ジムはみじめで恥ずかしい思いをするだろうということ。それに、俺のことを考えてみろ! ハック・フィンが黒人の自由を助けたという噂が広まるだろう。そして、もし俺が二度とあの町の人間に会うようなことがあれば、恥ずかしさのあまり、ひざまずいてそいつの靴でもなめるだろう。そういうものなんだ。人間は卑劣なことをしておきながら、その結果を引き受けたくない。隠しておける限り、不名誉ではないと考える。俺の状況はまさにそれだった。このことを考えれば考えるほど、良心が俺を責め立て、俺はますます邪悪で、卑劣で、みじめな気分になっていった。そしてついに、俺が哀れな老婆の、俺に何の害も与えたことのない黒人を盗んでいる間、俺の邪悪さが天の上からずっと見張られていたこと、そして神様は常に目を光らせていて、そんな惨めな行いが一定の線までしか許されないことを示しているのだと、神様の御手がまともに俺の顔をひっぱたいているのだと、突然気づいた時、俺はあまりの恐怖にその場に倒れそうになった。まあ、俺は邪悪に育てられたから、そんなに責められるべきじゃない、と言って自分を何とか慰めようとした。だが、俺の中の何かが言い続けた。「日曜学校があったじゃないか。そこへ行けたはずだ。もし行っていれば、あの黒人について俺がしてきたような行いをする人間は、永遠の業火に焼かれると教わったはずだ。」
俺は身震いした。そして、祈ってみよう、そして、今の自分のような少年でいるのをやめて、もっと良い人間になれるか試してみよう、とほぼ決心した。そこで俺はひざまずいた。だが、言葉が出てこなかった。なぜ出てこないんだ? 神様からそれを隠そうとしても無駄だった。俺自身からもだ。なぜ言葉が出てこないのか、俺はよくわかっていた。心が正しくなかったからだ。正直でなかったからだ。裏表があったからだ。俺は罪を諦めるふりをしていたが、心の奥底では、そのすべての中で最大の罪に固執していた。俺は口で、正しいこと、清いことをすると言わせようとしていた。あの黒人の持ち主に手紙を書いて、彼の居場所を伝えようと。だが、心の奥深くでは、それが嘘だとわかっていたし、神様もそれをわかっていた。嘘の祈りはできない――俺はそれを悟った。
だから俺は悩みでいっぱいだった。これ以上ないくらいに。そして、どうしていいかわからなかった。ついに、一つの考えが浮かんだ。俺は言った。「手紙を書きに行こう――そしてそれから、祈れるかどうか見てみよう」。いやはや、驚いたことに、俺はすぐに羽のように軽くなり、悩みはすべて消え去った。そこで俺は紙切れと鉛筆を取り、嬉しさと興奮に満ちて、座り込んで書いた。
ミス・ワトソン様、あなたの逃亡黒人ジムは、ここパイクスヴィルから二マイル下流におります。フェルプス氏が彼を捕まえており、もしあなたが送金なされば、懸賞金と引き換えに彼を引き渡すとのことです。
ハック・フィン

気分が良くなり、罪がすっかり洗い流されたように感じた。生まれて初めてそんな気分になった。そして、今なら祈れるとわかった。だが、すぐには祈らず、紙を置いてそこに座って考えていた――こんな風に事が運んでなんて良かったんだろう、そして俺はもう少しで道を踏み外し、地獄へ行くところだった、と考えながら。そして考え続けた。そして、川を下る旅のことを考え始めた。すると、昼も夜も、月夜の時も嵐の時も、ジムがいつも目の前に現れた。二人で漂いながら、話したり、歌ったり、笑ったりした。だがどういうわけか、彼に対して心を鬼にできるような場面は思いつかず、その逆の場面ばかりが浮かんだ。俺を起こさずに、自分の見張りの後も続けて俺の分の見張りをしてくれるジムの姿。霧の中から俺が戻ってきた時の、彼の嬉しそうな顔。あの血で血を洗う争いがあった沼地で、俺が再び彼に会った時のこと。そんな時々のこと。そして、いつも俺を「ハニー」と呼び、可愛がってくれ、俺のために思いつく限りのことをしてくれたこと、そして彼がいつもどれほど優しかったか。そしてついに、俺が船に天然痘の患者がいると男たちに嘘をついて彼を救った時のことを思い出した。彼はとても感謝して、俺はジムじいさんがこの世で持った最高の友達で、今ではたった一人の友達だ、と言ってくれた。そしてその時、ふと周りを見渡すと、あの紙が目に入った。
きわどい状況だった。俺はそれを手に取り、握りしめた。俺は震えていた。なぜなら、二つのことの間で、永遠に、決断しなければならないとわかっていたからだ。俺は一分ほど、息を殺すようにして考え、そして独り言を言った。
「よし、それなら、俺は地獄へ行く」――そして手紙をびりびりに破いた。
恐ろしい考えであり、恐ろしい言葉だったが、口に出してしまった。そして、俺はそれをそのままにしておいた。そして、二度と改心しようとは思わなかった。俺はそのことを頭からすっかり追い出し、もう一度、悪の道に戻ることにした。そっちの方が、そうやって育てられた俺には性に合っている。善人なんて柄じゃない。そして手始めに、ジムを再び奴隷制度から盗み出す仕事に取り掛かることにした。そして、もしもっと悪いことが思いつけば、それもやるつもりだった。なぜなら、一度足を踏み入れ、とことんやるからには、徹底的にやる方がましだからだ。
それから俺はどうやってそれを成し遂げるか考え始め、かなりの数の方法を頭の中で検討した。そしてついに、自分に合った計画を立てた。そこで、川下にある森の茂った島の位置を確認し、すっかり暗くなると、いかだをこっそり持ち出してそこへ行き、隠した。そして寝た。俺は一晩中眠り、明るくなる前に起きて、朝食をとり、よそ行きの服を着て、他の服やあれこれを包んで、カヌーに乗って岸へ向かった。フェルプスさんの家だろうと見当をつけた場所の下流に上陸し、包みを森の中に隠し、それからカヌーに水を満たし、石を積んで、岸辺にあった小さな蒸気製材所から四分の一マイルほど下流の、必要な時にまた見つけられる場所に沈めた。
それから俺は道を上り、製材所を通り過ぎる時に、「フェルプス製材所」という看板を見た。そして、二百ヤードか三百ヤード先にある農家に着いた時、俺は目を皿のようにして見回したが、もうすっかり明るくなっていたにもかかわらず、周りには誰もいなかった。だが、気にしなかった。まだ誰にも会いたくなかったからだ――ただ土地の様子を知りたかっただけだ。俺の計画によれば、俺は村から、下流からではなく、そこに現れることになっていた。だから、俺はただ一瞥して、まっすぐ町へ向かって歩き続けた。さて、町に着いて最初に見かけた男は、公爵だった。彼は『ロイヤル・ノンサッチ』のビラを貼っていた――三夜公演――あの時と同じように。奴らには厚かましさがあった、あの詐欺師どもには! 俺は避ける間もなく、彼のすぐそばまで来てしまった。彼は驚いた顔をして言った。
「やあ! お前、どこから来たんだ?」それから、どこか嬉しそうに、そして熱心に言った。「いかだはどこだ? ――いい場所に隠してあるか?」
俺は言った。
「いや、それこそ、閣下にお尋ねしようと思っていたことです。」
すると彼は、それほど嬉しそうな顔ではなくなり、言った。
「俺に尋ねるってのは、どういう考えだ?」と彼は言った。
「ええと」と俺は言った。「昨日、あの安酒場で王様を見た時、俺は独り言を言ったんです。酔いが覚めるまで、何時間も彼を家に連れて帰れないだろうって。だから、時間をつぶして待つために、町をぶらぶらしていました。ある男が、羊を一匹、小舟で川を渡って連れてくるのを手伝ってくれたら十セントやると言ってくれたので、一緒に行きました。でも、羊をボートまで引きずっている時、男が俺にロープを持たせて、後ろから羊を押そうとしたら、羊が強すぎて俺の手から逃げ出して、走っていっちまったんです。俺たちは追いかけました。犬もいなかったので、国中を追いかけ回して、疲れさせるしかありませんでした。暗くなるまで捕まえられませんでした。それから羊を連れてきて、俺はいかだに向かって下り始めました。そこに着いて、いかだがなくなっているのを見て、俺は独り言を言いました。『連中は面倒に巻き込まれて、去らなきゃならなかったんだ。そして、俺の黒人を連れて行っちまった。世界で俺が持ってるたった一人の黒人なのに。今、俺は見知らぬ土地にいて、もう財産も何もないし、生計を立てる方法もない』って。それで俺は座り込んで泣きました。一晩中森で寝ました。それで、いかだは一体どうなったんですか? ――それにジムは――かわいそうなジム!」
「ちくしょう、俺にはわからん――つまり、いかだがどうなったかはな。あの馬鹿じじいは取引をして四十ドル手に入れたんだが、俺たちが安酒場でそいつを見つけた時、ならず者たちがそいつと半ドル硬貨で賭けをして、ウィスキー代に使った分以外、一セント残らず巻き上げちまった。そして昨夜遅く、そいつを家に連れて帰って、いかだがなくなっているのに気づいた時、俺たちは言ったんだ。『あの小悪党が俺たちのいかだを盗んで、俺たちを振り切り、川を下って逃げやがった』ってな。」
「俺が自分の黒人を振り切ると思いますか? ――世界で俺が持ってるたった一人の黒人で、たった一つの財産なのに。」
「そのことは考えなかった。実のところ、俺たちはいつの間にか、彼を俺たちの黒人だと考えるようになっていたんだろう。ああ、そう考えていた――神様はご存知だ、俺たちは彼のために十分すぎるほど苦労したからな。だから、いかだがなくなって、俺たちがすっからかんになったのを見た時、『ロイヤル・ノンサッチ』をもう一度試す以外に方法はなかった。そしてそれ以来、俺はずっと歩き回っている、火薬入れみたいにからからだ。あの十セントはどこだ? こっちへよこせ。」

俺はかなり金を持っていたので、彼に十セント渡したが、何か食べ物を買うのに使って、俺にも少し分けてくれと頼んだ。それが俺の持っている金のすべてで、昨日から何も食べていなかったからだ。彼は何も言わなかった。次の瞬間、彼はくるりと俺の方を向いて言った。
「あの黒人が俺たちのことをばらすと思うか? もしそんなことをしたら、皮を剥いでやるぞ!」
「どうやってばらすんですか? 逃げたんじゃないんですか?」
「いや! あの馬鹿じじいが彼を売っちまったんだ。俺に分け前もよこさず、金ももうなくなっちまった。」
「売ったんですか?」と俺は言って、泣き始めた。「だって、彼は俺の黒人で、あれは俺の金だったのに。彼はどこにいるんですか? ――俺の黒人が欲しい。」
「まあ、お前の黒人は手に入らない。それだけだ――だから、めそめそ泣くのはやめろ。おい、聞け――お前、俺たちのことをばらす気じゃねえだろうな? ちくしょう、お前を信用できるとは思えん。もしお前が俺たちのことをばらしたら――」
彼は言葉を切ったが、公爵の目があんなに険悪なのを見たのは初めてだった。俺はしくしく泣き続けながら言った。
「誰もばらしたくありません。それに、ばらしている時間なんてありません。俺は出かけて、自分の黒人を見つけなきゃならないんです。」
彼は少し困ったような顔をして、ビラを腕にひらひらさせながら、額にしわを寄せて考え込んでいた。やがて彼は言った。
「一つ教えてやろう。俺たちはここに三日いなきゃならない。もしお前がばらさないと、そしてあの黒人にもばらさせないと約束するなら、どこで見つけられるか教えてやる。」
そこで俺が約束すると、彼は言った。
「サイラス・フ……」と言いかけて、男は口をつぐんだ。見るところ、本当のことを言いかけたんだろう。だが、そうやって口ごもり、また考え込み始めたのを見て、こいつは心変わりしたんだと俺は察した。そして、その通りだった。男は俺を信用する気はなく、三日間まるまる俺をどこかへ追いやれるように、念を入れようとしていたのだ。だから、すぐにこう言った。
「奴を買った男の名前はエイブラム・フォスター――エイブラム・G・フォスターだ。ここから田舎の方へ四十マイル、ラファイエットへ向かう街道沿いに住んでる。」
「わかった」と俺は言った。「三日もあれば歩ける。今日の午後にも出発するよ。」
「いや、駄目だ。今すぐ出発しろ。ぐずぐずするなよ。道中、余計なしゃべりもするんじゃない。口にチャックをして、まっすぐ進むんだ。そうすりゃ、俺たちと面倒を起こさずに済む。わかったか?」
それこそ俺が望んでいた命令であり、そのために芝居を打ったのだ。自分の計画を自由に実行するためには、放っておいてもらう必要があった。
「だからとっとと失せろ」と男は言った。「フォスター氏には好きに話すがいい。お前さんの話じゃ、ジムがお前さんのニガーだと信じ込ませられるかもしれん――書類なんぞいらねえ間抜けもいるからな。少なくとも、こっちの南部にはそういう奴らがいると聞いたことがある。それに、手配書も懸賞金もでっち上げだと説明すりゃ、なんでそんなもんを作ったのかって話も信じてくれるかもしれねえ。さあ、行け。何でも好きなように話すがいい。だが、ここからそこに着くまでの間は、決して口を開くんじゃないぞ。」

俺はそこを離れ、田舎道へと向かった。振り返りはしなかったが、なんとなく見られているような気がした。だが、そんなもの、すぐにまいてやれる自信はあった。一マイルほど田舎道をまっすぐ進んでから足を止め、森の中を突っ切ってフェルプス家の農場へと引き返した。ぐずぐずしないで、すぐに計画に取り掛かるべきだと思った。あの連中がどこかへ行ってしまうまで、ジムの口を封じておきたかったからだ。あんな連中とこれ以上関わり合いになるのはごめんだった。もう見たいものは全部見たし、きれいさっぱり縁を切りたかった。
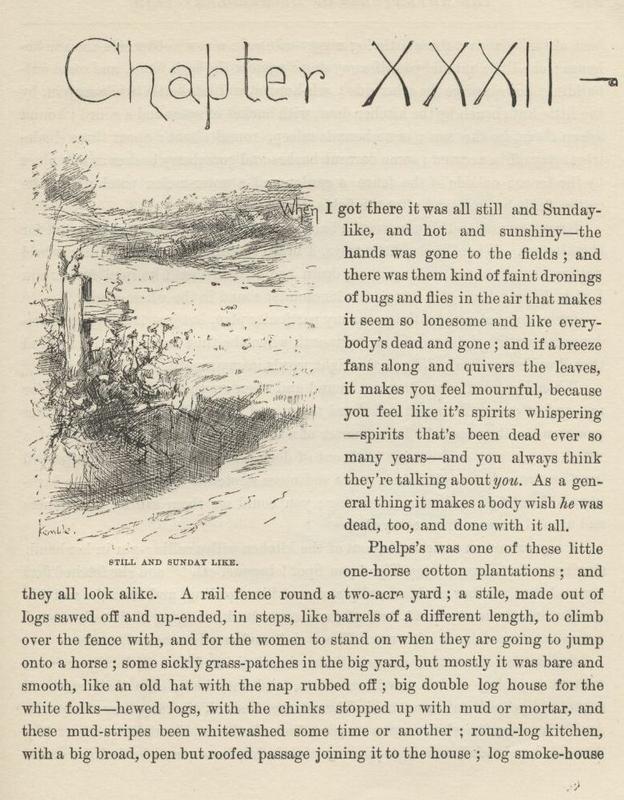
第三十二章
そこに着くと、あたりは静まり返り、まるで日曜日のようだった。じりじりと暑く、陽が照りつけている。働き手たちは畑へ出てしまっていた。空には虫やハエのかすかな羽音が響き、それがまたひどく寂寥感をかき立て、まるで誰もかもが死に絶えてしまったかのように感じさせる。そよ風が吹き抜け、木の葉を震わせると、なんとも物悲しい気分になる。それはまるで、何年も前に死んだ霊たちが囁いているように思えるからだ――しかも、そいつらはいつだって自分のことを話しているような気がするのだ。だいたいにおいて、こういう時は自分も死んで、何もかも終わりにしてしまいたいという気持ちにさせられるものだ。
フェルプス家の農場は、ちっぽけな綿花プランテーションの一つで、どこにでもあるような造りだった。二エーカーほどの庭が柵で囲まれている。柵を乗り越えるための踏み台は、丸太を切りそろえて階段状に立てたもので、長さの違う樽を並べたようにも見えた。女たちが馬に飛び乗るときにも使うのだろう。広い庭には病的な芝生がところどころに生えているが、ほとんどはむき出しの土で、毛羽立ちがすり減った古い帽子のように滑らかだった。白人たちが住むのは、大きな二階建ての丸太小屋――削った丸太を使い、隙間は泥やモルタルで埋められ、その泥の筋はいつだったかに白く塗られたようだ。丸太造りの台所は、屋根付きだが吹きさらしの広い通路で母屋とつながっている。台所の裏には丸太の燻製小屋。燻製小屋の向こう側には、小さな丸太のニガー小屋が三つ並んでいる。裏の柵際には、ぽつんと小さな小屋が一つあり、その向こうにはいくつか離れがあった。小さな小屋のそばには、灰汁取り桶と石鹸を煮るための大釜。台所の戸口のそばには長椅子があり、水の入った桶とひょうたんが置いてある。猟犬が一匹、日向で眠っていた。あたりには他にも猟犬が寝そべっている。隅の方に日陰を作る木が三本ほど。柵のそばの一角には、スグリやグーズベリーの茂み。柵の外には菜園とスイカ畑。その先には綿花畑が始まり、畑の向こうには森が広がっていた。
俺はぐるりと回り込み、灰汁取り桶のそばにある裏の踏み台を乗り越え、台所へと向かった。少し進むと、糸車のうなるようなかすかな音が、高く低く響いてくるのが聞こえた。その瞬間、俺は本気で死にたいと思った――あれこそ、この世で一番寂しい音だからだ。
俺はそのまま進んだ。これといった策を練るでもなく、ただ天の摂理を信じ、いざという時には正しい言葉を授けてくれるだろうと当てにしていた。というのも、天の摂理に任せておけば、いつも正しい言葉を授けてくれることに気づいていたからだ。
半分ほど進んだところで、まず一匹、次にもう一匹と猟犬が起き上がり、俺に向かってきた。もちろん俺は立ち止まり、犬たちと向き合ってじっとしていた。すると、まあ、なんと騒々しいことか。ほんの十五秒もすると、俺はまるで車輪の中心になったようだった――スポークは犬でできている。十五匹ほどの群れが俺の周りに密集し、首と鼻を俺の方へ突き出し、吠えたり唸ったりしている。しかも、まだ増えてくる。あちこちから、柵を飛び越え、角を曲がって駆けつけてくるのが見えた。
黒人の女が、麺棒を片手に台所から飛び出してきて、「あっちへ行け、タイジ! スポット! あっちへ行けってんだ!」と叫んだ。そして、まず一匹、次にもう一匹とひっぱたいて追い払い、残りの犬たちもそれに続いた。だが次の瞬間には、そのうちの半分が戻ってきて、俺の周りで尻尾を振り、懐いてきた。猟犬なんてものは、どうしたって人間に危害を加えることはないのだ。
女の後ろからは、小さな黒人の女の子と、リンネルのシャツ一枚しか着ていない男の子が二人出てきて、母親のガウンにしがみつき、その後ろから内気そうに俺を覗き見ている。いつもの彼らのやり方だ。すると今度は、白人の女が家から走ってきた。年は四十五か五十くらいで、髪をむき出しにし、手には糸紡ぎの棒を持っている。その後ろからは、小さな白人の子供たちが、黒人の子供たちと同じようにしてついてくる。女は満面の笑みを浮かべ、立っているのもやっとという様子で言った。
「あなたなのね、やっと! ――そうでしょ?」
俺は考えるより先に「はい、奥様」と口走っていた。

女は俺をひっつかむと、きつく抱きしめた。それから両手で俺の手を握り、何度も何度も揺さぶった。目には涙が浮かび、頬を伝って流れ落ちる。いくら抱きしめても、いくら揺さぶっても足りないといった様子で、こう言い続けた。「思ったほどお母さんには似てないわね。でも、そんなことどうでもいいわ、会えて本当に嬉しい! ああ、もう、食べてしまいたいくらいよ! 子供たち、いとこのトムよ! ――挨拶してちょうだい。」
だが、子供たちは頭をうなだれ、指を口にくわえ、母親の後ろに隠れてしまった。そこで女は続けた。
「ライザ、急いでこの子に温かい朝食を用意しておやり――それとも、船で朝食は済ませたの?」
俺は船で済ませたと答えた。すると女は、俺の手を引き、子供たちをぞろぞろと引き連れて、家へと向かい始めた。家に着くと、女は俺を割竹の椅子に座らせ、自分は俺の前に低い小さな腰掛けを下ろし、俺の両手を握りながら言った。
「これでやっと、あなたの顔がじっくり見られるわ。ああ、もう、この長い年月、どれだけこの日を待ち焦がれていたことか。やっと会えたのね! ここ二、三日、ずっと待っていたのよ。何があったの? ――船が座礁でもしたの?」
「はい、奥様――船が――」
「『はい、奥様』じゃないわ――『サリー叔母さん』って呼んで。どこで座礁したの?」
何を言っていいか、すぐにはわからなかった。船が川を上ってきたのか下ってきたのかも知らなかったからだ。だが、俺は勘を頼りにすることが多い。そして俺の勘は、船は川を上ってきた――つまり、オーリンズの方から来たのだと告げていた。とはいえ、大して助けにはならない。そのあたりの浅瀬の名前なんて知らないからだ。浅瀬の名前をでっち上げるか、座礁した場所の名前を忘れたことにするか――その時、いい考えがひらめき、それを口にした。
「座礁したんじゃありません――それで遅れたのはほんの少しです。シリンダーヘッドが破裂したんです。」
「まあ、大変! 誰か怪我はなかったの?」
「いいえ、奥様。ニガーが一人死んだだけです。」
「そう、それは幸いだったわ。だって、人が怪我をすることもあるんですもの。二年ほど前のクリスマスに、あなたのサイラス叔父さんが古いラリー・ルック号でニューオーリンズから上ってくるとき、シリンダーヘッドが破裂して、男の人が一人、足が不自由になったのよ。たしか、その人は後で亡くなったわ。バプテスト派の人だった。あなたのサイラス叔父さんは、バトンルージュにその人の親戚をよく知っている家族がいたの。そう、今思い出したわ、やっぱり亡くなったのよ。壊疽が始まって、切断しなくちゃならなかったんですって。でも助からなかった。そう、壊疽だったわ――それよ。全身真っ青になって、輝かしい復活を願いながら死んでいったんですって。それはそれは見るも無残な姿だったそうよ。あなたの叔父さんは、あなたを迎えに毎日町まで行っていたの。一時間ほど前に、また行ったところよ。もうすぐ帰ってくるわ。道で会ったでしょう? ――年配の男で、――」
「いいえ、誰にも会いませんでしたよ、サリー叔母さん。船は夜明けに着いたんです。それで、荷物は波止場に預けて、町や田舎の方を少しぶらぶらして時間を潰していたんです。あまり早く着きすぎないようにね。だから、裏道から来たんですよ。」
「荷物は誰に預けたの?」
「誰にも。」
「あら、まあ、盗まれちゃうわよ!」
「俺が隠した場所なら、大丈夫だと思います」と俺は言った。
「船でどうしてそんなに早く朝食が食べられたの?」
危うい綱渡りだったが、俺はこう言った。
「船長が俺がうろうろしているのを見て、陸に上がる前に何か食べておいた方がいいって言ってくれたんです。それで、テキサス・デッキ[訳注:蒸気船の上級船員用の船室区画]に連れて行ってくれて、士官用の昼食を好きなだけ食べさせてくれました。」
俺は不安で、ろくに話も聞いていられなかった。ずっと子供たちのことが気になっていたのだ。子供たちを脇へ連れ出して、少し探りを入れ、俺が一体誰なのか突き止めたかった。だが、その隙がまるでない。フェルプス夫人が立て続けにしゃべり続けるからだ。やがて、彼女の言葉に背筋が凍りついた。彼女がこう言ったからだ。
「でも、まあ、こんな話ばかりしていて、姉さんのことや、みんなのことを一言も聞いていなかったわ。さあ、私は少し黙るから、今度はあなたの番よ。何もかも話してちょうだい――みんなのことを、一人残らず全部。みんな元気にしてる? 何をしてるの? 私に何を伝えてくれって言われたの? 思いつく限りのことを、何もかも話してちょうだい。」
これはもう、完全に袋小路だ――それも、どうにもならないやつだ。天の摂理はここまでずっと俺の味方をしてくれたが、今や完全に座礁してしまった。これ以上進もうとしても無駄なことは明らかだった――もうお手上げだ。仕方ない、ここでもう一度、真実という危険な賭けに出るしかない、と俺は覚悟した。俺が口を開きかけたその時、彼女は俺をひっつかんでベッドの後ろに押しやり、こう言った。
「あの人が来たわ! もっと頭を下げて――そう、それでいいわ。もう見えないわね。ここにいるって気づかせちゃだめよ。あの人にいたずらを仕掛けるんだから。子供たち、一言もしゃべっちゃだめよ。」
俺は窮地に陥ったと悟った。だが、心配しても始まらない。ただじっとして、雷が落ちたときに身をかわす準備をしておくしかない。
老紳士が入ってくるとき、ほんの一瞬だけその姿が見えたが、すぐにベッドに隠れてしまった。フェルプス夫人は彼に飛びかかり、こう言った。
「あの子は来た?」
「いや」と夫は答えた。
「まあ、なんてこと!」と彼女は言った。「一体全体、どうしちゃったのかしら?」
「見当もつかんよ」と老紳士は言った。「正直に言うと、ひどく心配だ。」
「心配ですって!」と彼女は言った。「私は気が狂いそうだわ! きっと来たに違いないのよ。あなたが道で見逃したのよ。ええ、絶対にそうよ――そんな気がするの。」
「おい、サリー、道で見逃すなんてことがあるもんか――君も知っているだろう。」
「でも、ああ、もう、姉さんはなんて言うかしら! きっと来たのよ! あなたが見逃したに決まってるわ。あの子は――」
「ああ、もうこれ以上私を苦しめないでくれ。すでに十分苦しんでいるんだ。一体どうしたものか、さっぱりわからん。途方に暮れているし、正直に言って、かなり怖い。だが、あの子が来ている望みはないよ。来ていれば、私が見逃すはずがないんだから。サリー、これは大変なことだ――本当に大変だ――きっと船に何かあったに違いない!」
「あら、サイラス! あそこを見て! ――道の向こう! ――誰か来ない?」
彼がベッドの頭側にある窓に飛びついた。それがフェルプス夫人の狙っていた好機だった。彼女は素早くベッドの足元にかがみ込み、俺をぐいと引っ張り出した。彼が窓から振り返ると、そこには火事場の家のように輝く笑顔を浮かべた彼女と、その横におとなしく汗だくで立つ俺がいた。老紳士は目を丸くして言った。
「おや、それは誰だね?」
「誰だと思う?」

「見当もつかん。一体誰なんだね?」
「トム・ソーヤーよ!」
ちくしょう、俺は床にへたり込みそうになった。だが、そんな暇はなかった。老紳士は俺の手を掴んで握り、握り続けた。その間、女の人はどんなにはしゃいで踊り、笑い、泣いただろう。そして、二人してどんなにシッドやメアリーや、その他の親戚たちのことを質問攻めにしたことか。
だが、彼らが喜んでいたとしても、俺の喜びには到底及ばなかった。まるで生まれ変わったような気分だったのだ。自分が誰なのかわかって、本当に嬉しかった。さて、それから二時間、彼らは俺にべったりだった。とうとう顎が疲れてほとんど動かなくなった頃には、俺は自分の家族――つまり、ソーヤー家のことについて、ソーヤー家が六つあっても起こり得ないほどのことを語っていた。そして、ホワイト川の河口でシリンダーヘッドが破裂し、修理に三日かかったという話を詳しく説明した。これはすべてうまくいき、上々の首尾だった。なぜなら、彼らは修理に三日かかるものなのかどうか知らなかったからだ。ボルトの頭だと言ったとしても、同じようにうまくいっただろう。
さて、俺は体の片側はすっかり心地よくなっていたが、もう片側はすっかり居心地が悪くなっていた。トム・ソーヤーでいることは楽で快適だったし、しばらくはそのままでいられた。だが、やがて川下から蒸気船が咳き込むような音を立ててやってくるのが聞こえた。その時、俺は独り言を言った。もし、あの船にトム・ソーヤーが乗っていたらどうする? そして、もし彼が今にもここへ入ってきて、俺が静かにしろと合図する前に俺の名前を叫んだら? そう、そんなことには耐えられない。絶対に駄目だ。道を上って、彼を待ち伏せしなくてはならない。そこで俺は、町へ行って荷物を持ってくるとみんなに言った。老紳士が一緒に行こうとしてくれたが、俺は断った。馬は自分で御せると言い、わざわざ面倒をかけたくないと言ったのだ。
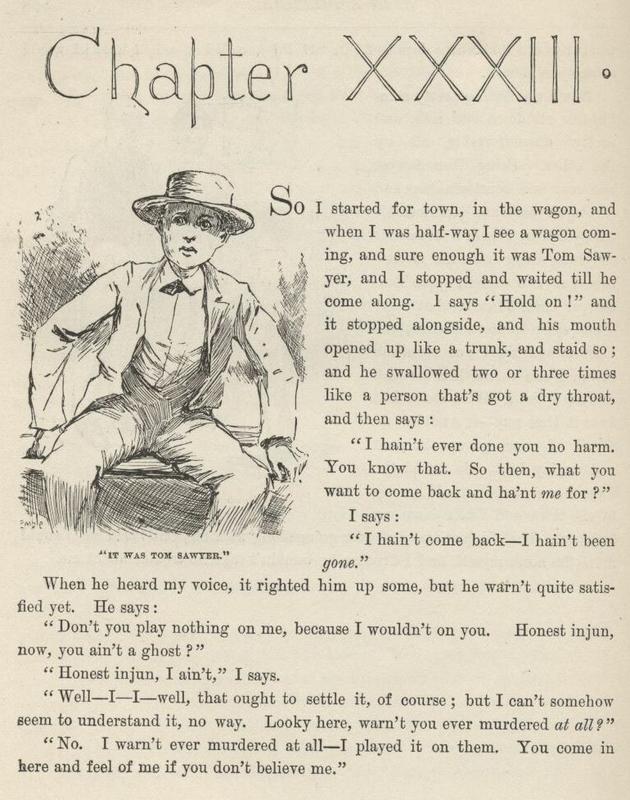
第三十三章
俺は荷馬車に乗って町へ向かった。半分ほど行ったところで、向こうから荷馬車がやってくるのが見えた。案の定、それはトム・ソーヤーだった。俺は馬車を止めて、彼が来るのを待った。「待った!」と俺が言うと、彼の馬車は隣に止まった。彼の口はトランクのようにあんぐりと開き、そのままになった。喉が渇いた人のように二、三度唾を飲み込むと、こう言った。
「俺はあんたに何の危害も加えてない。それはわかってるだろ。だったら、なんでまた戻ってきて俺を祟るんだ?」
俺は言った。
「戻ってきたんじゃない――どこへも行ってないんだ。」
俺の声を聞くと、彼は少し落ち着いたようだったが、まだ完全には納得していない。彼は言った。
「俺をからかうのはやめてくれ。俺はあんたにそんなことはしない。本当の本当だ、あんたは幽霊じゃないのか?」
「本当の本当だ、幽霊じゃない」と俺は言った。
「そうか――そ、そうか――まあ、それなら決まりなんだろうけど、どうにもこうにも、さっぱり理解できない。なあ、あんたは結局、殺されてなかったのか?」
「ああ。殺されてなんかないよ――奴らを騙したんだ。信じられないなら、こっちへ来て俺に触ってみろよ。」
そこで彼はそうした。そして納得した。俺にまた会えたのがよほどうれしかったらしく、どうしていいかわからないといった様子だった。そして、すぐに事の次第を全部知りたがった。壮大な冒険で、謎めいていて、彼の心を鷲掴みにしたからだ。だが俺は、それは後にしてくれと言い、彼の御者に待つように伝えた。俺たちは少し離れたところまで馬車を走らせ、俺がどんな窮地に陥っているのか、どうするのが一番いいと思うか、彼に話した。彼は、少し一人にして邪魔をしないでくれと言った。そして、考えに考え、やがてこう言った。
「よし、わかった。俺のトランクをあんたの馬車に乗せて、あんたのだってことにしてくれ。あんたは引き返して、ゆっくり時間を稼ぎながら、ちょうどいい頃に家に着くようにするんだ。俺は町の方へ少し行って、仕切り直してから、あんたより十五分か半時間遅れてそこに着く。最初は俺のことを知らないふりをしてくれよ。」
俺は言った。
「わかった。でも、ちょっと待ってくれ。もう一つあるんだ――誰も知らない、俺だけが知ってることだ。ここに、俺が奴隷の身分から盗み出そうとしているニガーがいるんだ。名前はジム――ミス・ワトソンのところのジムだよ。」
彼は言った。
「何だって! なんで、ジムが――」
彼は口をつぐみ、考え込んだ。俺は言った。
「お前が何を言うかはわかってる。『汚い、下劣なことだ』って言うんだろ。でも、そうだとして、それがどうした? 俺は下劣な人間なんだ。だから、ジムを盗み出す。お前には黙って、知らないふりをしていてほしいんだ。いいか?」
彼の目が輝き、こう言った。
「奴を盗み出すのを手伝うよ!」
その言葉に、俺はまるで撃たれたように、すべての力が抜けてしまった。今まで聞いた中で、最も驚くべき言葉だった――そして、正直に言って、トム・ソーヤーに対する俺の評価はかなり下がった。ただ、信じられなかった。トム・ソーヤーがニガー泥棒だなんて!
「おいおい!」と俺は言った。「冗談だろ。」
「冗談じゃないさ。」
「そうか、じゃあ」と俺は言った。「冗談だろうがなかろうが、もし逃亡ニガーの話を何か聞いたら、お前はそいつについて何も知らないし、俺もそいつについて何も知らないってことを、忘れずに覚えておけよ。」
それから俺たちはトランクを俺の荷馬車に移し、彼は彼の道へ、俺は俺の道へと馬車を走らせた。だがもちろん、嬉しくて考え事で頭がいっぱいだったから、ゆっくり走ることなんてすっかり忘れていた。だから、その距離にしてはずいぶん早く家に着いてしまった。老紳士が戸口に立っていて、こう言った。
「いや、これは驚いた! あの雌馬にこんなことができるとは、誰が思っただろうか。時間を計っておけばよかった。汗一滴かいていない――毛一本濡れていないぞ。素晴らしい。いやはや、今なら百ドルでもこの馬は売らんね――本当だとも。なのに、前は十五ドルで売ろうとしていて、それがせいぜいの価値だと思っていたんだからな。」
彼が言ったのはそれだけだった。俺が今まで会った中で、一番無邪気で、一番善良な老人だった。だが、驚くにはあたらない。彼はただの農夫というだけでなく、牧師でもあったからだ。プランテーションの裏手には、ちっぽけな丸太の教会があった。彼が自費で建てたもので、教会兼学校として使われており、説教で金を取ることは一度もなかった。そして、その説教は金を取らないだけの価値はあった。南部には、彼のような農夫兼牧師は他にもたくさんいて、同じようにやっていた。
半時間ほどして、トムの荷馬車が表の踏み台のところへやって来た。サリー叔母は窓からそれを見ていた。ほんの五十ヤードほどの距離だったからだ。そして言った。
「あら、誰か来たわ! 誰かしら? まあ、見知らぬ人みたいね。ジミー」(子供の一人だ)「走ってライザに、夕食のお皿をもう一枚出すように言ってきて。」
みんなが玄関に殺到した。もちろん、見知らぬ客なんて毎年来るわけではないから、いざ来ると、黄熱病よりも興味を引くのだ。トムは踏み台を乗り越え、家に向かって歩き始めた。荷馬車は村へ向かう道を走り去っていく。俺たちはみんな玄関に固まっていた。トムはよそ行きの服を着て、観客もいる――トム・ソーヤーにとっては、いつだって最高の舞台だ。こんな状況では、彼にとって、ふさわしいだけの気取りを付け加えることなど、何の造作もないことだった。彼は、羊のように庭をおずおずと歩いてくるような少年ではない。いや、彼は雄羊のように、落ち着き払い、堂々とやって来た。俺たちの前に来ると、彼は帽子を実に優雅に、そして繊細に持ち上げた。まるで、その中に眠っている蝶を起こさないように、箱の蓋を開けるかのように。そして言った。
「アーチボルド・ニコルズ様でいらっしゃいますか?」

「いや、坊や」と老紳士は言った。「残念ながら、御者に騙されたようだね。ニコルズさんの家は、ここから三マイルほど先だよ。まあ、入りなさい、入りなさい。」
トムは肩越しに振り返り、「遅かったか――もう見えなくなってしまった」と言った。
「ああ、行ってしまったよ、坊や。まあ、入って我々と一緒に夕食を食べなさい。その後で、馬をつないでニコルズさんのところまで送ってあげよう。」
「いえ、そんなご迷惑はおかけできません。とんでもない。歩きます――距離は気にしませんから。」
「だが、歩かせたりはしないよ――それでは南部の hospitality(もてなし)に反するからね。さあ、入りなさい。」
「ええ、どうぞ」とサリー叔母は言った。「私たちにとっては何の面倒でもありませんから、ちっとも。ぜひいてくださいな。三マイルは長くて埃っぽい道ですし、歩かせるわけにはいきません。それに、あなたがいらっしゃるのが見えた時に、もうお皿を一枚出すように言いつけてありますから、がっかりさせないでくださいな。さあ、入って、どうぞごゆっくり。」
そこでトムは、心から丁重に礼を述べ、説得されるままに家に入った。そして中に入ると、自分はオハイオ州のヒックスヴィルから来たよそ者で、名前はウィリアム・トンプソンだと名乗り――もう一度お辞儀をした。
さて、彼は延々と、延々としゃべり続けた。ヒックスヴィルやそこにいる人々について、思いつく限りのことをでっち上げて。俺は少し神経質になり、これがどうやって俺の窮地を救ってくれるのかと訝しんでいた。そしてとうとう、彼はしゃべりながら手を伸ばし、サリー叔母の口にいきなりキスをした。それから、何食わぬ顔で椅子に座り直し、話を続けようとした。だが、彼女は飛び上がって手の甲で口を拭い、こう言った。
「この厚かましい子犬め!」
彼は少し傷ついたような顔をして言った。
「驚きましたよ、奥様。」
「驚いたですって――まあ、私を何だと思ってるの? よっぽど――ねえ、私にキスするなんて、どういうつもりなの?」
彼はおとなしそうな顔をして言った。
「何の意味もありません、奥様。悪気はなかったんです。ただ――ただ――喜んでくれるかと思ったんです。」
「この生まれつきの馬鹿!」。彼女は糸紡ぎの棒を手に取った。それで彼をひっぱたくのを、かろうじてこらえているように見えた。「私が喜ぶなんて、どうして思ったの?」
「さあ、わかりません。ただ、みんなが――みんなが――そう言ったんです。」
「みんながそう言ったですって。そんなことを言った奴は、もう一人の気違いよ。聞いたこともないわ。みんなって誰よ?」
「ええ、みんなです。みんなそう言いました、奥様。」
彼女は必死でこらえていた。目はかっと見開かれ、指は彼をひっかきたいかのようにうずうずしていた。そして言った。
「『みんな』って誰よ? 名前を言いなさい。さもないと、馬鹿が一人減ることになるわよ。」
彼は立ち上がり、困惑した様子で帽子をもてあそびながら言った。
「すみません、こんなことになるとは思っていませんでした。みんなに言われたんです。みんながそうしろって。みんなが言ったんです、彼女にキスしろって。そしたら喜ぶって。みんなが言いました――一人残らずです。でも、すみません、奥様。もう二度としませんから――しません、本当です。」
「しないですって? まあ、そりゃあ当然しないでしょうね!」
「はい、奥様。本当です。もう二度といたしません――あなたがお願いするまでは。」
「私がお願いするまでですって! まあ、生まれてこのかた、こんなことは初めてだわ! あなたにお願いするくらいなら、私は天地創造以来のメトシェラ級の大馬鹿になるわよ――あなたみたいな人にお願いするくらいならね」[訳注:メトシェラは旧約聖書に登場する長寿の人物。]
「うーん」と彼は言った。「本当に驚きました。どうにも理解できません。みんなが喜ぶと言ったし、僕もそう思っていました。でも――」。彼は口ごもり、ゆっくりとあたりを見回した。どこかに味方になってくれる目はないかと探しているようだった。そして老紳士の目に留まると、こう言った。「奥様が僕にキスされて喜ぶと、あなたは思いませんでしたか、旦那様?」
「いや、わしは――わしは――うーん、いや、思わなかったと思うな。」
すると彼は、同じように俺の方を向いて言った。
「トム、君はサリー叔母さんが腕を広げて、『シッド・ソーヤー――』って言うと思わなかったかい?」
「あらまあ!」と彼女は叫び、彼に飛びかかりながら言った。「この生意気な悪がき、こんなに人をからかうなんて――」。そして彼を抱きしめようとしたが、彼はそれを押しとどめ、こう言った。
「だめだよ、まず叔母さんからお願いしてくれなきゃ。」
そこで彼女はためらうことなく、彼にお願いした。そして彼を抱きしめ、何度も何度もキスをし、それから老紳士に彼を預けた。老紳士は残りを引き受けた。少し落ち着いてから、彼女は言った。
「まあ、なんて驚いたことでしょう。あなたが来るなんて、全然思ってもいなかったわ。トムだけだと思っていたのに。姉さんからは、彼以外誰も来るとは手紙に書いてなかったもの。」
「それは、トム以外は誰も来る予定じゃなかったからだよ」と彼は言った。「でも、僕がお願いして、お願いして、最後の最後で僕も来させてくれたんだ。だから、川を下ってくる途中で、トムと僕で考えたんだ。まず彼が家に来て、僕が後からぶらっと立ち寄って、知らない人のふりをするっていう、とびっきりのサプライズにしようってね。でも、失敗だったよ、サリー叔母さん。ここはよそ者が来るには、あまり健康的な場所じゃないみたいだ。」
「ええ――生意気な子犬にとってはね、シッド。顎をぶん殴られてもおかしくなかったわよ。いつ以来かしら、こんなに腹が立ったのは。でも、もういいわ。そんなこと気にしない――あなたに会えるなら、千回でもこんな冗談に付き合うわ。まあ、あの芝居を考えつくなんて! 正直に言うと、あなたがあのキスをしたときは、驚きのあまり硬直してしまったわ。」

俺たちは、母屋と台所の間にある広い吹きさらしの通路で夕食をとった。食卓には七家族分はあろうかというほどの料理が並んでいた――しかも、全部温かい。じめじめした地下室の食器棚に一晩置かれて、朝になると古くて冷たい人食い人種の塊みたいな味がする、あのぐにゃぐにゃで硬い肉とはわけが違う。サイラス叔父さんは、かなり長い食前の祈りを捧げたが、それだけの価値はあった。それに、俺が何度も見てきたような邪魔とは違って、料理が少しも冷めなかった。午後は、かなりの時間おしゃべりが続いた。俺とトムはずっと聞き耳を立てていたが、無駄だった。二人は逃亡ニガーのことなど一言も口にしなかったし、俺たちも怖くてその話に持っていくことができなかった。だが、夜の夕食の時、小さな男の子の一人が言った。
「父さん、トムとシッドと僕で、見世物に行ってもいい?」
「だめだ」と老紳士は言った。「見世物はないと思うよ。それに、あったとしても行かせられない。あの逃亡ニガーが、バートンとわしに、あのけしからん見世物のことを全部話してくれたんだ。バートンがみんなに話すと言っていたから、今頃はもう、あの厚かましい怠け者どもは町から追い出されているだろう。」
そういうことだったのだ! ――だが、俺にはどうしようもなかった。トムと俺は同じ部屋の同じベッドで寝ることになっていた。だから、疲れていた俺たちは、夕食後すぐに「おやすみ」と言ってベッドへ行き、窓から這い出し、避雷針を伝って降り、町へと急いだ。王様と公爵に誰かが忠告してくれるとは思えなかったから、俺が急いで知らせに行かなければ、二人は間違いなく面倒なことになるだろうと思ったのだ。
道中、トムは、俺が殺されたと思われていたこと、その後すぐにパップが姿を消して二度と戻ってこなかったこと、ジムが逃げ出した時にどれだけ大騒ぎになったか、すべて話してくれた。俺はトムに、「ロイヤル・ノンサッチ」の悪党どものことや、いかだの旅について話せるだけのことを話した。俺たちが町に入り、中心部を抜ける頃――八時半をとうに回っていた――松明を持った群衆が、怒涛の勢いで押し寄せてきた。ものすごい雄叫びと怒号、ブリキの鍋を叩く音、角笛の音。俺たちは脇へ飛びのいて、彼らを行かせた。通り過ぎていく群衆の中に、王様と公爵が一本の丸太にまたがっているのが見えた――つまり、それが王様と公爵だとわかったのだ。全身タールと羽毛まみれで、とても人間の姿には見えなかったが――まるで、二つの巨大な兵士の羽飾りのようだった。ああ、それを見て気分が悪くなった。あの哀れで惨めな悪党どもが気の毒で、もう二度と彼らに対して憎しみを抱くことはできないように思えた。それは恐ろしい光景だった。人間というものは、互いに対して、とてつもなく残酷になれるものなのだ。
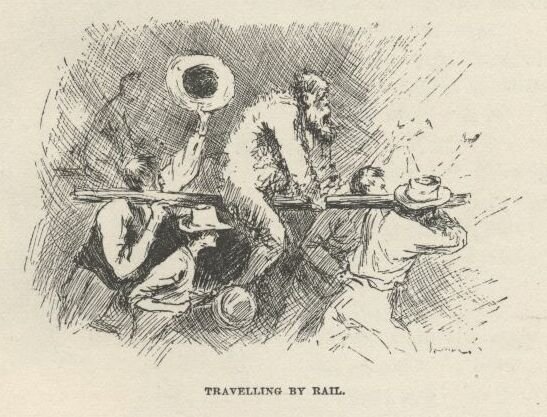
俺たちは手遅れだったと悟った――もうどうすることもできない。はぐれた連中に何人か話を聞くと、みんなごく無邪気な顔をして見世物に行き、哀れな老王が舞台で馬鹿げた踊りをしている最中まで、息を潜めていたそうだ。そして、誰かが合図をすると、観客は一斉に立ち上がり、彼らに襲いかかったという。
俺たちはとぼとぼと家へ引き返した。俺は来る前ほど威勢は良くなく、なんだか惨めで、卑屈で、罪悪感に苛まれていた――俺は何もしていないというのに。だが、いつもこうなのだ。正しいことをしようが、悪いことをしようが、関係ない。人間の良心なんてものは分別がなく、ただひたすらその人を責め立てるだけなのだ。もし俺が、人間の良心ほど物分かりの悪い黄色い犬を飼っていたら、毒殺してやるだろう。腹の中の他のどんなものよりも場所を取るくせに、何の役にも立たないのだから。トム・ソーヤーも同じことを言っていた。
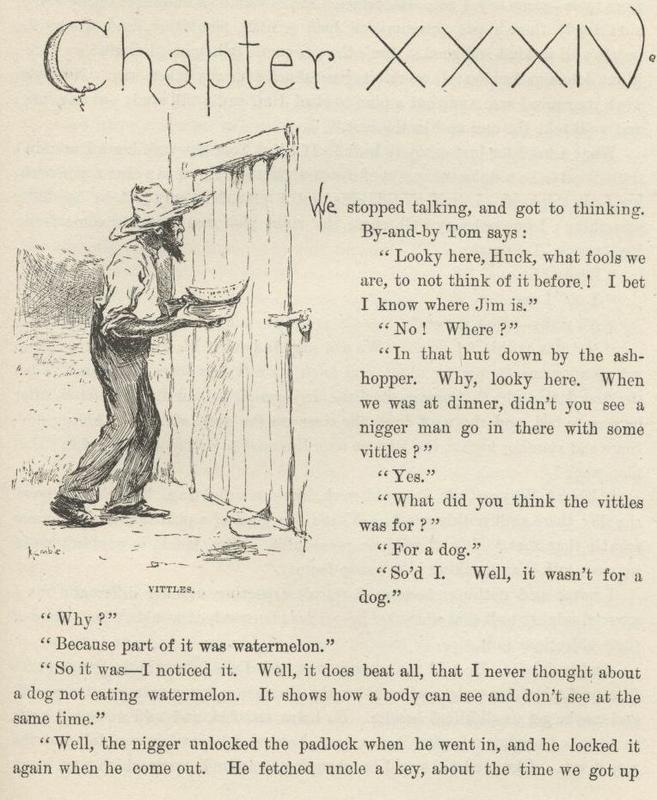
第三十四章
俺たちは話すのをやめ、考え込んだ。やがてトムが言った。
「なあ、ハック、俺たちってなんて馬鹿なんだろうな、もっと早く気づかなかったなんて! ジムがどこにいるか、当ててやろうか。」
「本当か! どこだ?」
「灰汁取り桶のそばにあるあの小屋さ。なあ、考えてみろよ。夕食の時、黒人の男が食べ物を持ってあそこに入っていくのを見なかったか?」
「見たよ。」
「あの食べ物は何のためだと思った?」
「犬のためだ。」
「俺もだ。でも、犬のためじゃなかったんだ。」
「どうして?」
「その一部がスイカだったからさ。」
「そうだった――俺も気づいた。ああ、犬がスイカを食べないなんて、考えもしなかったとは、本当に間抜けだ。人間ってのは、見ていても見ていないことがあるってことだな。」
「そう、あの黒人は入る時に南京錠の鍵を開けて、出る時にまた鍵をかけた。俺たちが食卓を立つ頃、叔父さんに鍵を持ってきてた――きっと同じ鍵だ。スイカは人間を示し、錠は囚人を示す。こんな小さなプランテーションで、しかもみんながこんなに親切で善良なところで、囚人が二人もいるとは考えにくい。囚人はジムだ。よし――探偵ごっこで突き止められてよかった。他の方法じゃ面白くも何ともないからな。さあ、お前は頭を働かせて、ジムを盗み出す計画を考えろ。俺も一つ考える。そして、気に入った方を選ぼう。」
ただの子供にしては、なんて頭脳だろう! もし俺にトム・ソーヤーの頭があったなら、公爵の地位とも、蒸気船の航海士とも、サーカスのピエロとも、思いつく限りのどんなものとも交換しないだろう。俺は計画を考え始めたが、それはただ何かをしていたいからに過ぎない。正しい計画がどこから来るかは、よくわかっていた。やがてトムが言った。
「準備はいいか?」
「ああ」と俺は言った。
「よし――言ってみろ。」
「俺の計画はこうだ」と俺は言った。「あそこにいるのがジムかどうかは、簡単に確かめられる。それから、明日の夜、俺のカヌーを持ってきて、島からいかだを運んでくる。そして、最初の暗い夜が来たら、おじさんが寝た後にズボンから鍵を盗み出し、ジムと一緒にいかだで川を下るんだ。昼間は隠れて、夜に移動する。昔、俺とジムがやっていたみたいにさ。この計画じゃだめか?」
「だめか? だめなわけないだろう。ネズミの喧嘩みたいにうまくいくさ。でも、あまりにも単純すぎる。何のひねりもないじゃないか。そんな簡単な計画に、何の面白みがある? ガチョウのミルクみたいに味気ない。おい、ハック、これじゃ石鹸工場に忍び込むより話題にもならないぞ。」
俺は何も言わなかった。違う答えを期待していたわけではなかったからだ。そして、彼が自分の計画を準備した暁には、そんな欠点など一つもないだろうと、よくわかっていた。
そして、その通りだった。彼は自分の計画を話してくれた。それを聞いて、俺は一瞬で、彼の計画は様式美において俺の計画の十五倍は価値があり、ジムを同じように自由の身にし、おまけに俺たち全員が殺される可能性もあると理解した。だから俺は満足し、その計画に乗ることにした。ここでその計画が何だったかを話す必要はないだろう。どうせその通りにはならないとわかっていたからだ。彼は計画を進めながら、あちこち手直しを加え、チャンスがあれば新しい見せ場をどんどん追加していくに決まっていると、俺は知っていた。そして、彼はその通りにした。
さて、一つだけ確かなことがあった。それは、トム・ソーヤーが本気で、あのニガーを奴隷の身分から盗み出す手助けをしようとしているということだった。それこそが、俺には理解しがたいことだった。ここにいるのは、立派で、ちゃんとしたしつけを受けた少年だ。失うべき評判もある。家には評判のある家族もいる。頭も切れて、馬鹿じゃない。物知りでもあり、無知でもない。意地悪でもなく、親切だ。それなのに、彼は今、何の誇りも、正義感も、感情もなく、こんなことに身を落とし、自分自身と家族を、世間の笑い者にしようとしているのだ。俺にはどうにも理解できなかった。とんでもないことだ。俺ははっきりと彼にそう告げるべきだとわかっていた。そうしてこそ真の友人であり、彼にこのことから手を引かせ、彼自身を救うことになるのだ。そして、俺は実際に彼に言おうとした。だが、彼は俺を黙らせて、こう言った。
「俺が自分のやっていることをわかっていると思わないのか? 俺はいつも、自分のやっていることをわかっているだろう?」
「ああ。」
「俺はあのニガーを盗み出すのを手伝うと言っただろう?」
「ああ。」
「だったら、それでいいじゃないか。」
彼が言ったのはそれだけで、俺が言ったのもそれだけだった。それ以上言っても無駄だった。彼がやると言ったことは、必ず実行するからだ。だが、俺には、どうして彼がこんなことに乗り気なのか、さっぱりわからなかった。だから、もうそのことは放っておいて、二度と気にしないことにした。彼がそうすると決めたのなら、俺にはどうしようもなかった。
俺たちが家に着くと、家は真っ暗で静まり返っていた。そこで俺たちは、灰汁取り桶のそばにある小屋を調べるために、そちらへ向かった。猟犬がどうするか見るために、庭を通り抜けていった。犬たちは俺たちのことを知っていて、夜中に何かが通り過ぎる時に田舎の犬がいつも立てる以上の物音は立てなかった。小屋に着くと、俺たちは正面と両側面を調べた。そして、俺が知らなかった側――つまり北側――に、かなり高い位置に四角い窓穴があるのを見つけた。そこには丈夫な板が一本、釘で打ち付けられているだけだった。俺は言った。
「これだ。この穴は、板をこじ開ければ、ジムが通り抜けられるくらい大きいぞ。」
トムは言った。
「三目並べみたいに単純で、学校をサボるのと同じくらい簡単だ。俺としては、それよりもう少し複雑な方法を見つけたいもんだね、ハック・フィン。」

「それじゃあ」と俺は言った。「前に俺が殺された時にやったみたいに、のこぎりで切り出すのはどうだ?」
「その方がそれらしいな」と彼は言った。「実にミステリアスで、面倒で、上出来だ。でも、きっと二倍は時間のかかる方法が見つかるさ。急ぐことはない。もう少し周りを探してみよう。」
小屋と柵の間、裏側には、小屋の軒に接して板で作られた差し掛け小屋があった。小屋と同じ長さだが、幅は狭く、六フィートほどしかなかった。戸口は南側にあり、南京錠がかかっていた。トムは石鹸釜のところへ行き、あたりを探し回り、蓋を持ち上げる鉄の道具を持ってきた。そして、それで留め金の一つをこじ開けた。鎖が落ち、俺たちは戸を開けて中に入り、戸を閉めてマッチを擦った。すると、その物置はただ小屋に寄りかかって建てられているだけで、つながってはおらず、床もなく、中には古びて錆びついた使い古しの鍬や鋤、つるはし、そして壊れた鋤があるだけだった。マッチの火が消え、俺たちも外へ出て、留め金を元に戻すと、戸は前と同じようにしっかりと閉まった。トムは上機嫌だった。彼は言った。
「これでよし。俺たちは彼を掘り出すんだ。一週間はかかるだろうな!」
それから俺たちは家に向かった。俺は裏口から入った――鹿皮の掛け金の紐を引くだけで、戸に鍵はかかっていない――だが、そんなのはトム・ソーヤーにとってはロマンチックではなかった。彼はどうしても避雷針を登らなければ気が済まなかった。だが、三度ほど半分まで登っては失敗して落ち、最後の時には頭を打ち付けそうになったので、諦めようかと思った。しかし、一休みした後、運試しにもう一度だけ挑戦すると言い、今度は成功した。
朝、俺たちは夜明けとともに起き、ニガー小屋の方へ下りて行った。犬を可愛がり、ジムに食事を運んでいる黒人と仲良くなるためだ――もし、食事を与えられているのがジムなら、の話だが。黒人たちはちょうど朝食を終え、畑へ向かうところだった。そして、ジム担当の黒人は、ブリキの皿にパンや肉などを山盛りにしていた。他の者たちが出発する頃、家から鍵が届いた。
この黒人は、人の良さそうな、少しとぼけた顔をしていて、縮れ毛は糸で小さな束にいくつも結わえられていた。魔女よけのためだという。彼は、近頃の夜は魔女にひどく悩まされていて、ありとあらゆる奇妙なものを見せられ、ありとあらゆる奇妙な言葉や物音を聞かされると言い、生まれてこのかた、こんなに長く魔法にかけられたことはないと信じていた。彼はすっかり興奮して、自分の悩みについてまくし立て始め、自分が何をしようとしていたかすっかり忘れてしまった。そこでトムが言った。
「その食べ物は何のためだい? 犬にやるのかい?」
黒人は、泥水にレンガを投げ込んだ時のように、顔中にゆっくりと笑みを広げ、こう言った。
「はい、シッドぼっちゃん、一匹の犬にでさあ。変わった犬ですよ。見に行きたいですかい?」
「うん。」
俺はトムをつつき、小声で言った。
「行くのか、こんな朝っぱらから? そんな計画じゃなかっただろ。」
「ああ、違った。でも、今はそれが計画なんだ。」
ちくしょう、俺たちはついて行ったが、あまり気は進まなかった。中に入ると、あまりに暗くてほとんど何も見えなかった。だが、ジムは確かにそこにいて、俺たちのことが見えた。そして、こう叫んだ。
「なんや、ハックやないか! ほんで、まあ! トムぼんまで!」
こうなるとわかっていた。予想通りだ。俺はどうしていいかわからなかったし、わかっていたとしても何もできなかっただろう。なぜなら、あの黒人が割って入ってきて、こう言ったからだ。
「おやまあ、なんてこった! こいつは旦那様方を知ってるんですかい?」
今や、あたりはかなりよく見えた。トムは黒人をじっと見つめ、不思議そうな顔をして言った。
「誰が俺たちを知ってるって?」
「へえ、この逃亡ニガーでさあ。」
「そんなはずはないと思うが、どうしてそんなことを考えたんだ?」
「どうしてですって? たった今、あんた方を知ってるみたいに叫んだじゃないですかい?」
トムは、困惑したような口調で言った。
「うーん、それは実に奇妙だな。誰が叫んだんだ? いつ叫んだ? 何を叫んだんだ?」。そして、完全に落ち着き払って俺の方を向き、言った。「君は誰かが叫ぶのを聞いたかい?」
もちろん、言うべきことは一つしかなかった。だから俺は言った。
「いや、俺は誰も何も言うのを聞いてないよ。」
それから彼はジムの方を向き、まるで初めて見るかのように彼をじろじろと眺め、言った。
「君は叫んだのか?」
「いいや、旦那様」とジムは言った。「わては何も言うてまへん、旦那様。」
「一言も?」
「へえ、旦那様。一言も言うてまへん。」
「俺たちに会ったことはあるか?」
「いいや、旦那様。わての知る限りではおまへん。」
そこでトムは、呆然として困惑した表情の黒人の方を向き、少し厳しい口調で言った。
「一体全体、君はどうかしちまったんじゃないのか? どうして誰かが叫んだなんて思ったんだ?」
「ああ、忌々しい魔女のせいでさあ、旦那様。わしゃ死にたいくらいですよ、本当に。いっつも悪さばっかりするんでさあ。わしを殺す気ですよ、あんまり怖がらせるもんで。どうか、このことは誰にも言わんでください、旦那様。さもないと、サイラスの旦那様に叱られてしまいますけん。旦那様は魔女なんていねえって言いますから。本当に、今ここに旦那様がいてくれたらよかったのに――そしたら何て言うでしょうな! 今回ばっかりは、旦那様も言い逃れできねえと、わしゃ思いますよ。でも、いっつもこうなんでさあ。頑固な人は、いつまでたっても頑固なまま。自分で調べて確かめようとはしねえ。こっちが調べて教えてやっても、信じようとしねえんでさあ。」

トムは彼に十セント銀貨をやり、誰にも言わないと約束した。そして、縮れ毛を結ぶための糸をもっと買うように言った。それからジムを見て、言った。
「サイラス叔父さんはこの黒んぼを絞首刑にするつもりなのかな。もし俺が、恩知らずにも逃げ出すような黒んぼを捕まえたら、引き渡したりなんかしないね。俺が吊るしてやる」黒んぼが戸口へ行って、その十セント硬貨を手に取って、本物かどうか噛んで確かめている間に、そいつはジムにこう囁いた。
「俺たちのことを知ってるなんて、絶対に口にするなよ。もし夜中に何か掘ってる音が聞こえたら、それは俺たちだ。おまえを自由にしてやるからな。」
ジムには、ただ俺たちの手を掴んで強く握り返すことしかできなかった。やがて、さっきの黒んぼが戻ってきたので、俺たちは、もしまた来てほしければいつでも来ると言ってやった。するとそいつは、特に暗くなってからがいいと言った。魔女はたいてい暗い時にやってくるから、そんな時には誰かそばにいてくれると心強いんだそうだ。
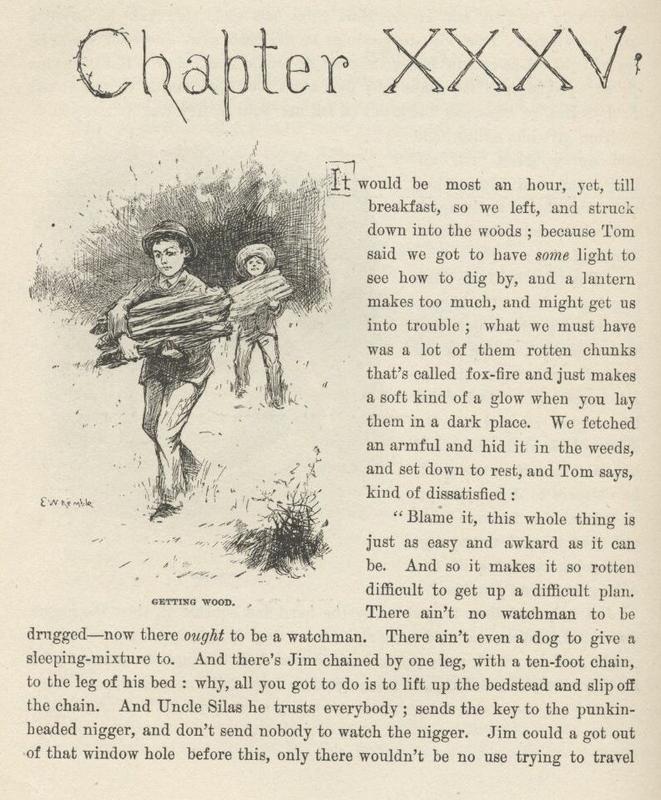
第三十五章
朝飯までまだ一時間近くあったので、俺たちは家を出て森の中へ入っていった。トムが言うには、穴を掘るのに何か明かりがいるけど、ランタンじゃ明るすぎて厄介なことになるかもしれない、必要なのは狐火と呼ばれる腐った木切れをたくさん集めることだ、と言うんだ。暗いところに置くと、ぼんやりとした光を放つやつだ。俺たちは両腕いっぱいの狐火を集めて雑草の中に隠し、腰を下ろして一休みした。するとトムが、なんだか不満そうな口調で言った。
「ちくしょう、何もかもが簡単すぎて、やりにくくてしょうがない。だから、難しい計画を立てるのが、とんでもなく難しくなっちまう。眠り薬を盛るべき見張りもいない――見張りはいるべきなのに。睡眠薬を飲ませる犬すらいないんだ。それにジムは、片足に十フィートの鎖をつけられて、ベッドの脚に繋がれてる。なんだ、ベッドの枠を持ち上げて鎖を外せば、それでおしまいじゃないか。それにサイラス叔父さんは誰でも信用する。カボチャ頭の黒んぼに鍵を渡しちまうし、その黒んぼを見張る人間も送り込まない。ジムだって、あの窓穴からとっくに逃げ出せてたはずだ。ただ、十フィートの鎖を足につけたままじゃ、旅なんてできっこないからやらなかっただけだ。まったく、なんてこった、ハック。こんな間抜けな状況は見たことがない。困難なことを全部こっちででっち上げなきゃならないんだ。まあ、仕方ない。手持ちの材料で最善を尽くすしかない。とにかく、一つだけいいことがある――本来なら困難や危険を用意すべき連中が何一つ用意してくれなくて、全部自分の頭でひねり出さなきゃならなかった方が、あいつを助け出した時の名誉は大きいってことだ。ほら、ランタンのこと一つ取ってもそうだ。冷静に考えれば、ランタンは危険だっていうことにしなくちゃならない。まったく、その気になれば、松明行列をしながらだって作業できると思うぜ、俺は。そうだ、今のうちに思いついたけど、最初の機会にノコギリを作る材料を探さなきゃな。」
「ノコギリなんて何に使うんだ?」
「何に使うかって? ジムのベッドの脚をのこぎりで切り落として、鎖を外すんだよ。」
「なんだ、さっきはベッドの枠を持ち上げれば鎖は外せるって言ったじゃないか。」
「やれやれ、これだからハック・フィンは。おまえはいつも、幼稚園児みたいなやり方しか思いつかない。まったく、本を読んだことがないのか? ――トレンク男爵も、カサノヴァも、ベンヴェヌート・チェッリーニも、アンリ四世も、そういう英雄たちの話をさ。そんなお上品なやり方で囚人を逃がすなんて、聞いたこともない。違うね、一流の権威たちがやる方法はこうだ。ベッドの脚を二つに切り、そのままにしておく。おがくずは見つからないように飲み込んじまう。切り口の周りには泥と油を塗っておけば、どんなに鋭い家令《セネスカル》だって、のこぎりの跡には気づかず、ベッドの脚は完全に元通りだと思う。そして、準備ができた夜、その脚を蹴飛ばせば、ガシャンと外れる。鎖を抜き取り、さあ、これで自由だ。あとは城壁に縄梯子を引っ掛けて、それを伝って降り、堀で足を折る――なにしろ縄梯子ってのは十九フィートも短いからな、知ってるだろ――そこには馬と忠実な家来たちが待っていて、おまえをひょいと抱え上げ、鞍に放り投げると、故郷のラングドックかナヴァールか、どこかへ向かって一目散だ。派手でいいだろ、ハック。この小屋にも堀があればなあ。もし逃亡の夜に時間があったら、一つ掘ってやろうぜ。」
俺は言った。 「小屋の下からあいつを引っ張り出すのに、堀なんて何に必要なんだ?」
だが、トムには聞こえていなかった。俺のことも、他の何もかも忘れていた。片手で顎を支えて、考え込んでいる。やがて溜め息をついて首を振り、また溜め息をついて、こう言った。
「だめだ、それは無理だ――それだけの必要性がない。」
「何がだよ?」と俺は言った。
「だから、ジムの足をのこぎりで切り落とすことさ」とトムは言った。
「なんてこった!」俺は言った。「そんな必要、あるわけないだろ。それに、一体何のためにあいつの足を切り落とすんだよ?」

「まあ、一流の権威の中にはやったやつがいるんだ。鎖が外せないもんだから、自分の手を切り落としてずらしちまったのさ。足ならもっといい。でも、それは諦めなきゃならない。この件にはそれだけの必要性がないし、それにジムは黒んぼだから、その理由も、それがヨーロッパの慣わしだってことも理解できないだろう。だから、やめておこう。でも一つだけ――縄梯子は持たせてやれる。俺たちのシーツを裂けば、簡単に縄梯子を作れるからな。それにパイに隠して届けてやれる。たいていその手でやるんだ。俺はもっとまずいパイを食ったことがあるぜ。」
「なんだって、トム・ソーヤー、変なこと言うなよ」と俺は言った。「ジムに縄梯子なんて必要ないだろ。」
「必要あるんだよ。おまえこそ変なこと言うな。何もわかってないくせに。あいつには縄梯子が必要なんだ。みんなそうするんだから。」
「一体全体、そんなもんで何をしろって言うんだ?」
「何をするかって? ベッドに隠しておけるだろ? みんなそうするんだ。だからあいつもそうしなくちゃならない。ハック、おまえは決まりきったことを何一つやりたがらないみたいだな。いつも何か新しいことを始めようとする。たとえそれで何もしなくたっていいじゃないか。あいつが逃げた後、それが手がかりとしてベッドに残るだろ? 連中だって手がかりが欲しいはずだ。もちろん欲しいさ。それなのに、おまえは何も残してやらないつもりか? そいつはひどい話じゃないか、そうだろ! そんなこと聞いたこともない。」
「まあいいさ」と俺は言った。「それが規則で、あいつに必要だっていうなら、わかった、持たせてやろう。規則に逆らうつもりはないからな。でも一つだけ言っておく、トム・ソーヤー――もし俺たちがシーツを裂いてジムの縄梯子なんか作ったら、サリー叔母さんともめることになるぜ、絶対にな。俺が思うに、ヒッコリーの木の皮で作った梯子なら金もかからないし、無駄もない。パイに詰めて藁布団の中に隠すにしても、ぼろ切れの梯子と変わらない。それにジムは経験がないんだから、どんな種類の梯子かなんて気にしやしないさ――」
「ああ、もう、ハック・フィン、俺がおまえみたいに無知だったら、黙ってるね――俺ならそうする。国の囚人がヒッコリーの皮の梯子で逃げたなんて、誰が聞いたことがある? まったく、馬鹿げてるにもほどがある。」
「わかったよ、トム。おまえの好きにしろ。でも、俺の忠告を聞く気があるなら、物干し綱からシーツを一枚拝借させてくれよ。」
トムはそれでいいと言った。そして、また別のアイデアを思いついたらしく、こう言った。
「シャツも一枚拝借しろ。」
「シャツなんて何に使うんだ、トム?」
「ジムが日記を書くのに使うんだ。」
「日記だなんて、冗談言えよ――ジムは字が書けないだろ。」
「字が書けないとしても――古い白鑞のスプーンか、古い鉄の樽の箍《たが》でペンを作ってやれば、シャツに印ぐらいはつけられるだろ?」
「なんだよ、トム。ガチョウの羽根を一本引き抜けば、もっといいペンが作れるぜ。その方が早いし。」
「囚人のいるドンジョンの天守閣の周りに、ペンを抜くためのガチョウがうろついてるわけないだろ、この間抜け。連中はいつも、手に入る中で一番硬くて、丈夫で、扱いにくい古い真鍮の燭台か何かでペンを作るんだ。それを壁にこすりつけて削り出すから、何週間も、何ヶ月もかかるんだぞ。ガチョウの羽根ペンなんて、たとえ持ってても使わない。それが決まりなんだ。」
「じゃあ、インクは何から作るんだ?」
「鉄錆と涙から作るやつも多い。でもそいつはありふれたやり方で、女子供のやることだ。一流の権威は自分の血を使う。ジムにもそれができる。それに、自分がどこに捕らえられているか世間に知らせるために、何かちょっとしたありふれた謎めいた伝言を送りたい時は、錫の皿の裏にフォークでそれを書いて、窓から放り投げればいい。『鉄仮面』はいつもそうしてた。あれは実にいい手だぜ。」
「ジムは錫の皿なんて持ってない。餌は鍋で食わされてるんだ。」
「そんなの関係ない。いくつか手に入れてやればいい。」
「誰もあいつの皿に書いたものなんて読めやしないさ。」
「そんなことは関係ないんだよ、ハック・フィン。あいつがやるべきことは、皿に書いて、それを放り投げることだけだ。読める必要なんてない。囚人が錫の皿とかに書いたものなんて、半分も読めやしないんだから。」
「じゃあ、皿を無駄にする意味はなんなんだ?」
「なんだってんだ、まったく。それは囚人の皿じゃない。」
「でも、誰かの皿だろ?」
「まあ、そうだな。でも、それがどうした? 囚人が誰の皿かなんて気にするか――」
トムはそこで言葉を切った。朝飯の角笛が鳴るのが聞こえたからだ。俺たちは急いで家に向かった。

その日の午前中、俺は物干し綱からシーツ一枚と白いシャツ一枚を拝借した。古い袋を見つけてそいつらを突っ込み、それから狐火を取りに行って、それも一緒に入れた。俺はこれを「拝借」と呼んだ。パップがいつもそう呼んでいたからだ。でもトムは、それは拝借じゃなくて、盗みだと言った。俺たちは囚人の代役なんだ、囚人は欲しいものを手に入れるためなら手段を選ばないし、誰もそのことで囚人を責めたりしない、とトムは言った。囚人が脱走に必要なものを盗むのは罪じゃない、それは囚人の権利なんだ、とトムは言った。だから、俺たちが囚人の代役を務めている限り、この場所にあるもので、牢獄から抜け出すために少しでも役立つものなら何でも盗む完全な権利があるんだ、と。もし俺たちが囚人じゃなかったら話はまったく別で、囚人でもないのに盗みをするのは、意地悪でどうしようもない奴だけだ、とトムは言った。だから俺たちは、手近にあるものは何でも盗むことに決めた。それなのに、トムは後日、俺が黒んぼたちの畑からスイカを一つ盗んで食った時、ものすごく大騒ぎした。そして俺に、理由を言わずに黒んぼたちに十セント硬貨を渡してこさせた。トムが言いたかったのは、俺たちが必要なものなら何でも盗んでいいということだったらしい。まあ、俺はスイカが必要だったんだが、と俺は言った。でもトムは、牢獄から出るのに必要だったわけじゃないだろ、そこが違うんだ、と言った。もし俺がナイフを隠して、家令《セネスカル》を殺すためにジムにこっそり渡すためにスイカが欲しかったのなら、それでよかったんだそうだ。俺はそれで話を終わりにしたが、スイカをくすねる機会を見つけるたびに、そんな金ぴかの屁理屈をいちいち考えなきゃならないなら、囚人の代役をやることに何の得があるのか、さっぱりわからなかった。
さて、さっきも言ったように、俺たちはその朝、みんなが仕事に取りかかって、庭のあたりに人影がなくなるまで待った。それからトムが袋を持って離れに入っていく間、俺は少し離れたところで見張りをしていた。やがてトムが出てきたので、俺たちは薪の山に腰を下ろして話をした。トムは言った。
「道具以外はすべて順調だ。道具もすぐになんとかなる。」
「道具?」と俺は言った。
「ああ。」
「何に使う道具だ?」
「決まってるだろ、掘るためだよ。まさか歯でかじってあいつを出すわけにはいかないだろ?」
「あそこにある古くて壊れたつるはしとかで、黒んぼ一人掘り出すには十分じゃないか?」と俺は言った。
トムは俺の方を振り向くと、こっちが泣きたくなるくらい哀れむような目つきでこう言った。
「ハック・フィン、おまえは囚人がつるはしやシャベル、その他あらゆる最新式の便利な道具を衣装棚に揃えて、自分で穴を掘って脱出したなんて話、聞いたことがあるか? さあ、聞きたいんだが――おまえに少しでも道理をわきまえる心があるなら――そんなやり方で、どうやって英雄になれるっていうんだ? そんなの、鍵を貸してやるのと同じじゃないか。つるはしにシャベルだって? そんなもの、王様にだって与えられやしないよ。」
「じゃあ」と俺は言った。「つるはしやシャベルがだめなら、何がいるんだ?」
「ケースナイフが二本。」
「あの小屋の土台の下を掘るのにか?」
「そうだ。」
「ちくしょう、馬鹿げてるぜ、トム。」
「どんなに馬鹿げていようと関係ない。それが正しいやり方なんだ――そして、それが決まりきったやり方なんだ。俺が聞いた限り、他に方法はない。俺はこういうことに関する情報が載ってる本は全部読んだんだ。連中はいつもケースナイフで掘り出すんだ――しかも土じゃないぞ、いいか。たいていは固い岩盤だ。そして、何週間も、何週間も、何週間も、永遠にやり続けるんだ。ほら、マルセイユ港にあるディフ城の地下牢にいた囚人の一人を見てみろ。あいつはそうやって掘り出したんだ。一体どれくらいかかったと思う?」
「さあな。」
「まあ、当ててみろよ。」
「わからん。一ヶ月半とか。」
「三十七年だ――そして、出てきたのは中国だった。そういうことだよ。この砦の底が固い岩盤だったらよかったのにな。」
「ジムは中国に知り合いなんていないぞ。」
「それが何の関係があるんだ? その男だってそうだった。おまえはいつも脇道に逸れる。どうして本筋から離れないでいられないんだ?」
「わかったよ――どこから出てこようと俺は構わない、とにかく出てくればいいんだ。ジムだってそうだろうさ。でも、一つだけ確かなことがある――ジムはケースナイフで掘り出すには歳をとりすぎてる。もたないよ。」
「いや、もつさ。土の土台を掘り抜くのに三十七年もかかるとでも思ってるのか?」
「どのくらいかかるんだ、トム?」
「まあ、本来かけるべき時間をかける危険は冒せない。サイラス叔父さんがニューオーリンズの方から便りを受け取るのに、そう長くはかからないかもしれないからな。ジムがそこから来たんじゃないってことがわかるだろう。そうなったら、叔父さんの次の手はジムの人相書きを出すか、何かそんなことだろう。だから、あいつを掘り出すのに、本来かけるべき時間をかける危険は冒せない。本当なら、二年くらいかけるべきだと思う。でも無理だ。状況がこんなに不確かなんだから、俺が勧めるのはこうだ。できるだけ早く、本気で掘り進める。その後で、三十七年かかったということにするんだ、俺たちだけでな。そうすれば、最初の警報が鳴った時に、あいつをさっと連れ出して、急いで逃がすことができる。うん、それが一番いい方法だと思う。」
「そいつは理にかなってるな」と俺は言った。「『~ということにする』だけなら金もかからないし、面倒もない。それでいいなら、百五十年かかったことにしたって構わないぜ。一度コツを掴めば、どうってことない。じゃあ、今からぶらっと行って、ケースナイフを二本くすねてくるよ。」

「三本くすねろ」とトムは言った。「一本はノコギリを作るのにいる。」
「トム、もし不規則で不信心な提案でなければだけど」と俺は言った。「燻製小屋の裏の、下見板の下に古くて錆びたノコギリの刃が突き刺さってるぜ。」
トムはなんだかうんざりしたような、がっかりしたような顔つきで言った。
「おまえに何を教えても無駄みたいだな、ハック。さっさと行ってナイフをくすねてこい――三本だ」そこで俺はそうした。
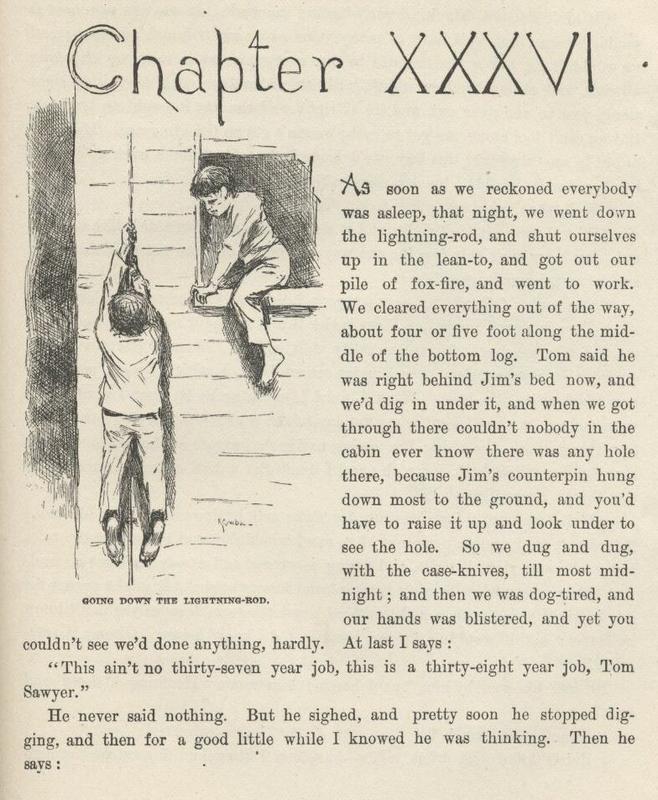
第三十六章
その夜、みんなが寝静まったと見計らって、俺たちは避雷針を伝って降り、離れに閉じこもると、集めておいた狐火を取り出して作業にかかった。丸太の一番下の、真ん中あたりに沿って四、五フィートほど、邪魔なものをすっかり片付けた。トムが言うには、そこはちょうどジムのベッドの真後ろで、その下を掘り進めば、たとえ穴が貫通しても、小屋の中の誰にも気づかれないだろうということだった。ジムのベッドカバーがほとんど地面まで垂れ下がっているから、それをめくり上げて下を覗き込まないと穴は見えないはずだった。俺たちはケースナイフで真夜中近くまで掘り続けた。しまいにはへとへとに疲れ果て、手のひらには水ぶくれができていたが、それでもほとんど何も進んでいないようにしか見えなかった。とうとう俺は言った。
「こいつは三十七年ものの仕事じゃない。三十八年ものの仕事だぜ、トム・ソーヤー。」
トムは何も言わなかった。だが、溜め息をつき、やがて掘るのをやめた。それからしばらくの間、トムが考え込んでいるのがわかった。そして、こう言った。
「無駄だ、ハック。これじゃうまくいかない。もし俺たちが囚人だったら、うまくいくんだ。そうすれば、欲しいだけ何年でも時間があるし、急ぐ必要もない。それに、見張りが交代する間、毎日数分しか掘れないから、手のひらに水ぶくれもできない。一年また一年とずっと続けられて、正しく、あるべきやり方でやれるんだ。でも俺たちはのんびりしてられない。急がなきゃならない。無駄にできる時間はないんだ。こんなやり方で、もう一晩もやったら、手が治るまで一週間は休まなきゃならなくなる――それまでケースナイフに触ることすらできないだろう。」
「じゃあ、どうするんだ、トム?」
「教えてやる。正しくもないし、道徳的でもない。それに、外に漏れたら困る。でも、方法は一つしかない。つるはしで掘り出して、ケースナイフで掘ったことにするんだ。」
「話がわかるじゃないか!」と俺は言った。「おまえの頭はどんどん冴えてくるな、トム・ソーヤー。つるはしだよ、道徳的だろうがなかろうが。俺に言わせりゃ、そんなものの道徳性なんてどうだっていい。黒んぼを盗むにしろ、スイカを盗むにしろ、日曜学校の本を盗むにしろ、一度やり始めたら、どうやってやるかなんてどうでもいいんだ、やり遂げられればな。俺が欲しいのは俺の黒んぼだ。あるいは、俺が欲しいのは俺のスイカだ。あるいは、俺が欲しいのは俺の日曜学校の本だ。もしつるはしが一番手っ取り早い道具なら、俺はその黒んぼなり、そのスイカなり、その日曜学校の本なりを、そいつで掘り出す。権威ある人たちがどう思おうと、死んだネズミほども気にしないね。」
「まあいいさ」とトムは言った。「こういう場合は、つるはしを使って『~ということにする』のにも言い訳が立つ。もしそうでなかったら、俺は賛成しないし、黙って規則が破られるのを見てたりはしない――だって、正しいことは正しいし、間違ったことは間違ってる。物事の道理を知っていて、無知じゃない人間が、間違ったことをする筋合いはないからな。おまえが、何も『~ということにする』ふりもせずに、つるはしでジムを掘り出すのは、まあ許されるかもしれない。おまえは道理を知らないからな。でも俺には許されない。俺は道理を知っているからだ。ケースナイフをくれ。」
トムは自分のナイフを持っていたが、俺は自分のを渡した。トムはそれを投げ捨てて言った。
「ケースナイフをくれって言ってるんだ。」
どうしていいかわからなかった――が、その時ひらめいた。俺は古い道具の中からつるはしを探し出してトムに渡した。トムはそれを受け取ると、一言も言わずに作業を始めた。
トムはいつも、そういうことにうるさかった。主義でいっぱいなんだ。
そこで俺はシャベルを持ち、二人で交代で掘ったりかき出したりして、土を飛ばしまくった。三十分ほどそれに没頭したが、それが俺たちの限界だった。それでも、かなりの大きさの穴ができていた。二階に上がって窓から外を見ると、トムが避雷針で必死に頑張っていたが、どうしても登れない。手がひどく痛むのだ。とうとうトムは言った。
「だめだ、無理だ。どうすりゃいいと思う? 何か方法はないか?」
「あるよ」と俺は言った。「でも、きっと決まり通りじゃないだろうな。階段で上がってきて、避雷針で登ったってことにしろよ。」
トムはその通りにした。

翌日、トムは家の中で白鑞のスプーンと真鍮の燭台を盗んだ。ジムのためにペンを作るためだ。それに獣脂のロウソクを六本。俺は黒んぼたちの小屋の周りをうろついて機会をうかがい、錫の皿を三枚盗んだ。トムはそれでは足りないと言ったが、ジムが投げ捨てた皿なんて誰も見つけやしないさ、と俺は言った。窓穴の下のドッグフェンネルやジムソンウィードの中に落ちるからだ――そうすれば俺たちがまた拾ってきて、あいつは繰り返し使える。それでトムは満足した。それからトムは言った。
「さて、考えなきゃならないのは、どうやってジムに品物を渡すかだ。」
「穴を通して入れればいい」と俺は言った。「穴ができたらな。」
トムはただ軽蔑したような顔つきで、そんな馬鹿げた考えは聞いたこともない、とかなんとか言って、また考え込み始めた。やがて、二、三の方法を考えついたが、まだどれにするか決める必要はないと言った。まずはジムに知らせておく必要がある、と言うんだ。
その夜、俺たちは十時過ぎに避雷針を伝って降り、ロウソクを一本持って、窓穴の下で聞き耳を立てた。するとジムのいびきが聞こえたので、ロウソクを投げ込んだが、ジムは起きなかった。それから俺たちはつるはしとシャベルで猛然と働き、二時間半ほどで仕事は終わった。俺たちはジムのベッドの下を這って小屋の中に入り、手探りでロウソクを見つけて火を灯し、しばらくジムのそばに立っていた。ジムは元気で健康そうに見えた。それから、俺たちは優しく、ゆっくりとジムを起こした。ジムは俺たちに会えて大喜びで、ほとんど泣き出しそうだった。俺たちを「ハニー」だの、思いつく限りの愛称で呼び、すぐにでも冷たいタガネを探してきて足の鎖を断ち切り、一刻も早く逃げ出そうと言い出した。しかしトムは、それがどれほど決まりに反しているかを説明し、腰を下ろして俺たちの計画をすべて話し、警報があったら一分で計画を変更できること、そして少しも怖がることはない、必ず逃がしてやるから、と請け負った。それでジムも納得し、俺たちはそこに座ってしばらく昔話をした。それからトムがたくさん質問をした。ジムが、サイラス叔父さんが一日か二日おきに一緒に祈りに来てくれること、サリー叔母さんが快適に過ごしているか、食べるものは十分か見に来てくれること、そして二人ともこの上なく親切なことを話すと、トムは言った。
「よし、どうすればいいかわかったぞ。あの二人を使って、おまえにいくつか品物を送ってやる。」
俺は言った。「そんなことするな。今まで聞いた中で一番の馬鹿げた考えだ」。しかしトムは俺にまったく注意を払わず、話を続けた。計画が決まると、いつもこうだった。
トムはジムに、縄梯子パイやその他の大きなものは、ジムに食事を運んでくる黒んぼのナットを使ってこっそり運び込むから、注意していて、驚かないように、そしてナットにパイを開けるところを見られないように、と言った。小さなものは叔父さんのコートのポケットに入れておくから、それを盗み出すように、と。機会があれば叔母さんのエプロンの紐に結びつけたり、エプロンのポケットに入れたりするとも言った。そして、それらが何で、何のためにあるのかも説明した。シャツに自分の血で日記をつける方法も、何もかも教えた。トムはジムにすべてを話した。ジムにはそのほとんどが意味不明だったが、俺たちが白人で、自分より物事をよく知っているのだろうと考えた。それで満足して、トムが言った通りにすべてやると言った。
ジムはトウモロコシの穂軸パイプとタバコをたくさん持っていたので、俺たちは実に楽しい社交の時間を過ごした。それから穴を通って這い出し、まるで噛み砕かれたような手で、家に戻ってベッドにもぐりこんだ。トムは上機嫌だった。人生で一番の楽しみで、最も知的な遊びだと言った。そして、もしうまい方法が見つかれば、残りの人生ずっとこれを続けて、ジムを子供たちに残して脱出させたい、と言った。ジムも慣れれば慣れるほど、もっと好きになるに違いないと信じているらしかった。その方法なら、八十年も引き延ばすことができ、記録に残る最高の時になるだろう、とトムは言った。そして、これに関わった俺たち全員が有名になるだろう、とも。
朝になると、俺たちは薪の山へ行って真鍮の燭台を手頃な大きさに切り刻み、トムはそれと白鑞のスプーンをポケットに入れた。それから黒んぼたちの小屋へ行き、俺がナットの気を引いている間に、トムはジムの鍋に入っていたトウモロコシのパンの真ん中に燭台のかけらを一つ押し込んだ。俺たちはナットと一緒に、それがどうなるか見に行ったが、見事にうまくいった。ジムがそれをかじった時、ほとんど歯が全部砕けそうになった。これほどうまくいくことはなかっただろう。トム自身もそう言った。ジムは、パンによく入っている石か何かだというふりをして、決してばらさなかった。でもその後は、フォークで三、四カ所突き刺してからでないと、何も口にしなくなった。
俺たちが薄暗い光の中に立っていると、ジムのベッドの下から猟犬が二、三匹、どやどやと入ってきた。そして次から次へと入ってきて、とうとう十一匹にもなり、息をする場所もないくらいになった。ちくしょう、離れの戸を閉め忘れてたんだ! 黒んぼのナットはただ一度「魔女だ!」と叫んだだけで、犬たちの間に床にひっくり返り、死にそうなうめき声を上げ始めた。トムはドアをぐいと開け、ジムの肉の塊を放り投げた。犬たちはそれに飛びつき、二秒後にはトム自身も外に出て、戻ってきてドアを閉めた。俺はトムがもう一方のドアも直したことを知っていた。それからトムは黒んぼに取りかかり、なだめたり、すかしたりして、また何か見たような気がしたのかと尋ねた。ナットは起き上がり、目をぱちぱちさせながら周りを見回し、言った。
「シッド旦那様、わてがアホやとおっしゃるでっしゃろけど、もし百万匹の犬か、悪魔か、なんかを見たと思わんかったら、この場で死んでもええですわ。ほんまに、見ましたんや。シッド旦那様、わては感じましたんや――感じましたんや、旦那様。体中にまとわりついて。ちくしょうめ、あの魔女の一匹でもええから、いっぺん、たったいっぺんでええから、この手で捕まえられたらなあ。それがわてのたった一つの願いですわ。でも、一番は、ほっといてほしいんです、ほんまに。」
トムは言った。 「よし、俺が思うことを教えてやる。どうしてあいつらは、ちょうどこの逃亡黒んぼの朝飯時にここへ来るんだ? それは腹が減ってるからだ、それが理由さ。おまえはあいつらのために魔女パイを作ってやれ。それがおまえのやるべきことだ。」

「でも、旦那様、どうやって魔女パイなんぞ作るんでっか? 作り方なんて知りまへん。そんなもん、聞いたこともおまへん。」
「それなら、俺が自分で作ってやるしかないな。」
「ほんまでっか、旦那様? ほんまに? わて、旦那様の足元の地面に感謝しますわ!」
「わかった、やってやるよ。おまえのためだ。おまえは俺たちに親切にしてくれたし、逃亡黒んぼのことも見せてくれたからな。でも、くれぐれも気をつけろよ。俺たちが来た時は、背中を向けてろ。それから、俺たちが鍋に何を入れても、それを見たと絶対に言うな。ジムが鍋の中身を取り出す時も見るな――何が起こるかわからないからな。そして何よりも、魔女の品物には触るなよ。」
「触るって、旦那様? 何をおっしゃってるんでっか? 指一本だって触れまへんわ。たとえ十億、百億ドル積まれたって、触りまへん。」
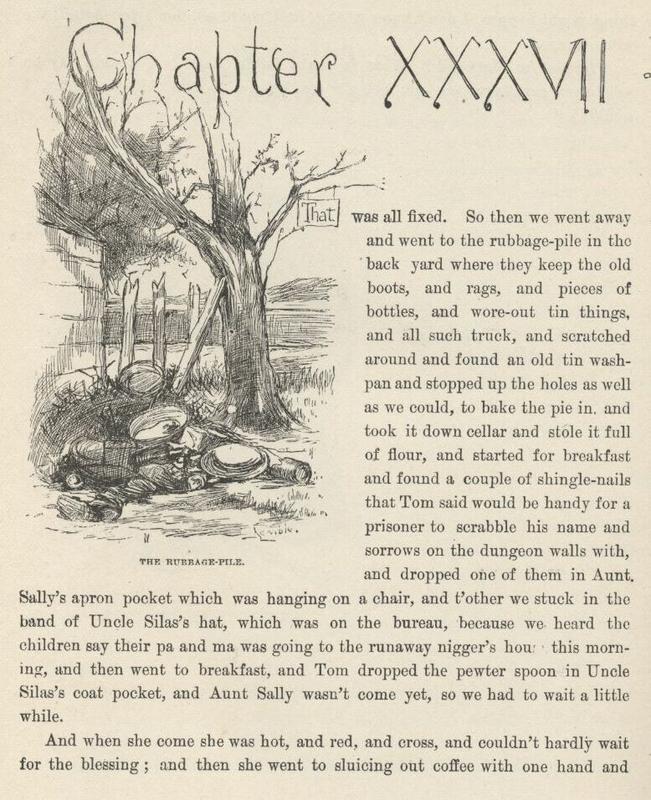
第三十七章
それで話はまとまった。俺たちはそこを離れ、裏庭のゴミ捨て場へ向かった。そこには古いブーツやぼろ切れ、瓶のかけら、使い古しのブリキ製品など、あらゆるガラクタが置いてある。あたりを引っ掻き回して古いブリキの盥《たらい》を見つけ、できるだけ穴を塞いでパイを焼くことにした。それを地下室に持っていって小麦粉をいっぱい盗み、朝食に向かった。途中で屋根板用の釘を二本見つけたが、トムが言うには、囚人がダンジョンの壁に自分の名前や悲しみを引っ掻き書くのに便利だろうとのことだった。一本は椅子にかかっていたサリー叔母さんのエプロンのポケットに落とし、もう一本は整理箪笥の上に置いてあったサイラス叔父さんの帽子のバンドに差し込んだ。子供たちが、父ちゃんも母ちゃんも今朝、逃亡黒んぼの小屋へ行くと言っていたのを聞いていたからだ。それから朝食に行くと、トムは白鑞のスプーンをサイラス叔父さんのコートのポケットに落とした。サリー叔母さんはまだ来ていなかったので、俺たちは少し待たなければならなかった。
サリー叔母さんがやって来た時、彼女は顔を真っ赤にしてかっかしていて、食前の祈りも待ちきれない様子だった。そして片手でコーヒーを注ぎながら、もう片方の手で一番近くにいた子供の頭を指ぬきでこづき、こう言った。
「家中くまなく探したけど、あんたのもう一枚のシャツがどこへ行ったのか、さっぱりわからないわ!」
俺の心臓は肺やら肝臓やらの間にずどんと落ち、硬いトウモロコシパンのかけらがそれを追って喉の奥へ滑り落ちたが、途中で咳にぶつかってテーブルの向こう側へ撃ち出され、子供の一人の目に当たった。その子は釣り針にかかったミミズみたいに体を丸め、鬨《とき》の声ほどもある叫び声を上げた。トムは鰓《えら》のあたりが青ざめ、十五秒かそこらの間、事態はかなり大変なことになった。もし買い手がいたら、半値で身売りしていただろう。だが、その後はまた元通りになった――あまりに突然のことで、すっかり肝を冷やしてしまったのだ。サイラス叔父さんが言った。
「実に奇妙なことだ、理解できん。確かに脱いだはずなんだが、なぜなら――」
「なぜなら、一枚しか着てないからでしょ。この人の言うことを聞いてちょうだい! あんたが脱いだのは知ってるわよ、あんたのぼんやりした記憶より、もっと確かな方法でね。だって、昨日、物干し綱にかかっていたもの――私自身がそこで見たんだから。でも、なくなったのよ、要するにね。だから、私が新しいのを作る時間ができるまで、赤いフランネルのに着替えてもらうしかないわ。これで二年で三枚目よ。あんたにシャツを着せ続けるだけで、こっちはてんてこ舞いなんだから。それに、あんたが一体どうやってシャツを全部なくしてしまうのか、私にはさっぱりわからないわ。あんたももういい年なんだから、少しは物を大事にすることを覚えてもいい頃だと思うけど。」
「わかっているよ、サリー。できる限り努力はしているんだ。だが、すべてが私のせいというわけでもないだろう。だって、ほら、着ている時以外はシャツを見たり触ったりすることはないんだから。それに、着ているシャツをなくしたことは一度もないと思うんだが。」
「まあ、なくさなかったとしても、それはあんたのせいじゃないわ、サイラス。できることなら、やったでしょうからね。それに、なくなったのはシャツだけじゃないのよ。スプーンも一本なくなったわ。それだけじゃない。十本あったのに、今は九本しかない。シャツは子牛が持っていったんでしょうけど、スプーンを子牛が持っていくわけがないわ、それは確かよ。」
「なんだって、他に何がなくなったんだい、サリー?」
「ロウソクが六本なくなったのよ――それがね。ロウソクはネズミが持っていったのかもしれないし、きっとそうでしょう。あんたがいつもネズミの穴を塞ぐって言ってやらないから、家ごと持っていかれないのが不思議なくらいだわ。それに、ネズミが馬鹿じゃなかったら、あんたの髪の毛の中で寝るでしょうね――あんたは絶対に見つけられないだろうから。でも、スプーンをネズミのせいにはできないわ、それはわかってる。」
「うむ、サリー、私のせいだ、認めるよ。私が怠っていた。だが、明日までには必ずあの穴を塞ぐよ。」
「あら、急がなくてもいいわ。来年で十分よ。マチルダ・アンジェリーナ・アラミンタ・フェルプス!。」
指ぬきがパチンと鳴り、子供はもたもたせずに砂糖壺から爪を引っ込めた。ちょうどその時、黒人の女が廊下に顔を出し、言った。
「奥様、シーツが一枚なくなってます。」

「シーツがなくなったですって! まあ、なんてこと!」
「今日中にあの穴を塞ぐよ」とサイラス叔父さんは悲しそうな顔で言った。
「ああ、もう黙ってちょうだい! ――ネズミがシーツを持っていったとでも言うの? どこへ行ったの、ライザ?」
「まったく見当もつきません、サリー奥様。昨日は物干し綱にありましたけど、なくなっちまいました。もうどこにもありゃしません。」
「きっと世も末ね。生まれてこの方、こんなこと見たことないわ。シャツに、シーツに、スプーンに、ロウソク六本――」
「奥様」と、若い肌の黄色い娘がやって来て言った。「真鍮の燭台がなくなってます。」
「ここから出てお行き、この小娘! さもないとフライパンでぶつわよ!」
まあ、彼女はまさに湯が沸くように怒っていた。俺は機会をうかがい始めた。嵐が静まるまで、こっそり抜け出して森へ行こうと思った。彼女は一人で反乱を起こし、怒り狂い続けていた。他の者は皆、とてもおとなしく静かにしていた。そしてとうとう、サイラス叔父さんが、なんだかばつの悪そうな顔で、ポケットからそのスプーンを探り出した。彼女は口を開け、両手を上げたまま、動きを止めた。俺ときたら、エルサレムかどこかにいられたら、と願った。だが、それも長くは続かなかった。なぜなら彼女がこう言ったからだ。
「やっぱり思った通りだわ。あんた、ずっとポケットに入れてたのね。きっと他のものもそこに入ってるんでしょう。どうしてそこに入ったの?」
「本当にわからないんだ、サリー」と彼は、なんだか謝るように言った。「わかっていたら、話すよ。朝食の前に『使徒行伝』の十七章の聖句を勉強していてね、たぶん、気づかずにそこへ入れてしまったんだろう。聖書を入れるつもりでね。そうに違いない、だって聖書が入っていないんだから。でも、行って見てくるよ。もし聖書が元の場所にあれば、私が入れたんじゃないことがわかる。そうなれば、私が聖書を置いてスプーンを手に取ったということになる、そして――」
「ああ、もう、いい加減にして! 少しは休ませてちょうだい! さあ、行って、あんたたちみんな! 私が落ち着きを取り戻すまで、二度とそばに寄らないで。」
たとえ独り言で言ったとしても、俺には聞こえただろう。ましてや声に出して言ったのだから。たとえ死んでいたとしても、起き上がって彼女に従っただろう。俺たちが居間を通り抜ける時、叔父さんは帽子を手に取った。すると屋根板用の釘が床に落ちた。叔父さんはそれをただ拾い上げて暖炉の棚の上に置き、何も言わずに外へ出た。トムは叔父さんがそうするのを見て、スプーンのことを思い出し、こう言った。
「まあ、もうあの人に物を託すのは無駄だな。当てにならない」それからこう続けた。「でも、叔父さんは知らず知らずのうちに、スプーンの件で俺たちにいいことをしてくれた。だから、俺たちも叔父さんの知らないうちに、いいことをしてやろう――ネズミの穴を塞いであげるんだ。」
地下室にはたくさんの穴があって、一時間もかかったが、俺たちは仕事をきっちり、しっかり、見事にやり遂げた。その時、階段を上る足音が聞こえ、俺たちは明かりを吹き消して隠れた。すると、片手にロウソク、もう片方の手に荷物を抱えた叔父さんが、一昨年みたいにぼんやりした顔でやって来た。叔父さんはうろうろと歩き回り、次から次へとネズミの穴を確かめ、全部見終わった。それから五分ほど立ち尽くし、ロウソクから垂れた蝋を指でいじりながら考え込んでいた。そしてゆっくりと、夢見るように階段の方へ向き直り、こう言った。
「ううむ、どう思い出そうとしても、いつやったのか思い出せん。これでネズミの件で私のせいじゃないと彼女に示せるんだがな。だが、まあいい――放っておこう。何の役にも立たないだろうし。」
そして叔父さんはぶつぶつ言いながら階段を上っていき、俺たちはそこを去った。叔父さんは本当にいい人だった。今もずっとそうだ。
トムはスプーンをどうするかでかなり悩んでいたが、どうしても必要だと言った。そこで考え込んだ。考えがまとまると、どうすればいいか俺に教えてくれた。それから俺たちはスプーン籠の周りで待ち伏せし、サリー叔母さんが来るのを見計らって、トムがスプーンを数え始め、脇に並べていった。俺はそのうちの一本を袖の中に滑り込ませた。トムが言った。
「あれ、サリー叔母さん、まだスプーンは九本しかないよ。」
彼女は言った。 「遊びに行っておいで、邪魔しないで。わかってるわよ、自分で数えたんだから。」
「でも、二回数えたんだよ、叔母さん。どうしても九本にしかならないんだ。」
彼女は我慢の限界といった顔をしたが、もちろん数えに来た――誰だってそうするだろう。
「まったく、本当に九本しかないわ!」と彼女は言った。「一体どうして――もう、いまいましい! もう一度数えるわ。」
そこで俺は持っていた一本をこっそり戻した。彼女が数え終わると、こう言った。
「なんて面倒なガラクタなの、今度は十本あるじゃない!」彼女は腹立たしげで、困惑もしていた。しかしトムは言った。
「でも、叔母さん、十本あるとは思えないな。」
「このうすのろ、私が数えるのを見なかったの?」
「わかってる、でも――」
「わかったわよ、もう一度数える!」

そこで俺は一本くすねた。すると、前と同じように九本になった。まあ、彼女はかんかんに怒っていた――あまりの怒りに全身が震えていた。彼女は何度も何度も数え、しまいには頭が混乱して、時々スプーン籠の中をスプーンだと思って数え始める始末だった。それで、三回は数が合い、三回は数が合わなかった。とうとう彼女は籠をひっつかむと、家の向こう側へ叩きつけ、猫をひっくり返した。そして、出て行って静かにさせてくれ、もし夕食までの間にまた邪魔しに来たら、皮を剥いでやると言った。こうして俺たちは余分なスプーンを手に入れ、彼女が出航命令を出している間に、彼女のエプロンのポケットに落とした。ジムは昼前に、屋根板用の釘と一緒にそれを手に入れた。俺たちはこの仕事に大満足で、トムはかかった手間の二倍の価値があったと言った。なぜなら、これで叔母さんはもう二度と、命がけでもスプーンを二度同じように数えることはできないだろうし、たとえ正しく数えられたとしても、それを信じないだろう、と言ったからだ。そして、次の三日間、頭がおかしくなるほど数え続けた後には、諦めて、もう二度と数えろと言う奴は誰でも殺してやると申し出るだろう、とトムは推測した。
その夜、俺たちはシーツを物干し綱に戻し、彼女の戸棚から一枚盗んだ。そして二、三日の間、それを戻したりまた盗んだりを繰り返した。とうとう彼女は自分が何枚シーツを持っているのかわからなくなり、もうどうでもよくなって、そのことでこれ以上気を揉むのはやめ、命がけでも二度と数えないことにした。そんなことするくらいなら死んだ方がましだ、と。
こうして、シャツとシーツとスプーンとロウソクについては、子牛とネズミとごちゃ混ぜの勘定のおかげで、すべてうまくいった。燭台については、大したことではなかった。そのうち忘れられるだろう。
しかし、あのパイは大変な仕事だった。あのパイには果てしなく苦労させられた。森の奥深くで準備し、そこで焼いた。そしてとうとう完成させた。それも非常に満足のいく出来栄えだった。だが、一日では終わらなかった。完成するまでに盥三杯分の小麦粉を使い果たし、あちこち火傷だらけになり、煙で目をやられた。というのも、俺たちが欲しかったのはパイ皮だけで、それをうまく支えることができず、いつも崩れてしまったからだ。しかしもちろん、俺たちはとうとう正しい方法を思いついた――それは、梯子もパイの中で一緒に焼くことだった。そこで二日目の夜、ジムと一緒にシーツを細い紐状にすべて引き裂き、それらを撚り合わせた。夜が明けるずっと前に、人を吊るせるほどの見事なロープが出来上がった。俺たちはそれを作るのに九ヶ月かかったということにした。
そして午前中にそれを森へ持っていったが、パイの中には入らなかった。シーツ一枚丸ごとで作ったので、もし欲しければパイ四十個分はあろうかというほどのロープができ、スープやソーセージや、その他好きなものに使える分がたっぷり余った。フルコースのディナーだってできたはずだ。

だが、その必要はなかった。パイ一個分あれば十分だったので、残りは捨ててしまった。洗い桶でパイを焼くのはやめておいた。はんだが溶けるのが怖かったからだ。しかし、サイラス叔父は立派な真鍮の湯たんぽを持っていた。先祖の一人がウィリアム征服王と一緒に『メイフラワー号』か何かの古い船でイギリスから持ってきたという代物で、長い木の柄がついており、叔父はそれをたいそう自慢に思っていた。屋根裏にしまわれていた、価値のある古い鍋やがらくたの山の中に隠されていたのだが、その価値というのは、役に立つからではなく――実際、何の役にも立たなかった――遺物だから、というわけだ。俺たちはそいつをこっそり持ち出して、小屋へ運んだ。最初のパイは失敗した。やり方が分からなかったからだ。だが、最後の一個は見事に焼き上がった。湯たんぽの内側に生地を敷き詰め、石炭の中に置き、中には布のロープを詰め込み、生地で蓋をし、さらに蓋を閉めて、その上に熱い燃えさしを乗せた。それから長い柄を持って、涼しく快適な五フィートの距離を保って待つこと十五分、見ているだけで満足できるパイが出来上がった。だが、そいつを食った人間は、爪楊枝を二樽ほど持ってきたくなるだろう。あの縄梯子で腹が下って七転八倒しないなんてことがあったら、俺の話は全くのでたらめということになる。次の機会まで続くほどの腹痛に見舞われるはずだ。
俺たちが魔女のパイをジムの皿に入れるとき、ナットは見なかった。そして、三枚のブリキ皿は食べ物の下の皿の底に置いた。こうしてジムはすべての品を無事に手に入れ、一人になるとすぐにパイを割り、縄梯子を藁のマットレスの中に隠した。そしてブリキ皿の一枚にいくつか印を刻んで、窓の穴から外へ放り投げた。

第三十八章
ペン作りはひどく骨の折れる仕事だったし、ノコギリも同様だった。ジムは、碑文が一番厄介な仕事になるだろうと言った。それは、囚人が壁に書き残さなければならないものだ。だが、それはどうしても必要だった。トムが言ったのだ、絶対にやらなきゃいけない、と。国事犯で、自分の碑文と紋章を残さずにいく者など一人もいない、と。
「レディ・ジェーン・グレイを見ろよ」とトムは言う。「ギルフォード・ダドリーを、それから老ノーサンバーランド公を! おい、ハック、そりゃあ面倒なことかもしれない。だが、どうするんだ? どうやって切り抜ける? ジムは碑文と紋章を作らなきゃいけないんだ。みんなそうしてる。」
ジムが言った。
「そやかてトムはん、わてには紋章なんておまへん。この古いシャツ一枚しか持ってへんし、これに日誌をつけなあかんことは、あんたも知ってはるやろ。」
「ああ、分かってないな、ジム。紋章ってのは全然違うものなんだ。」
「まあな」と俺は言った。「ジムが紋章を持ってないって言うのは、その通りだ。だって持ってないんだから。」
「そんなことは俺だって知ってるさ」とトムは言った。「だが、ここを出るまでには必ず一つ手に入れることになる。だって、ジムは正しいやり方で出ていくんだ。その経歴に一点の傷もつけさせやしない。」
そこで、俺とジムがそれぞれレンガのかけらでペンを研いでいる間――ジムは真鍮で、俺はスプーンで自分のを作っていた――トムは紋章を考え出す作業に取り掛かった。やがて、いいのがたくさん思いつきすぎて、どれにしたらいいかほとんど分からないが、一つに決めた、と言った。トムは言う。
「盾には、デキスター・ベース[訳注:盾の右下部分]にベンド・オー[訳注:黄金色の斜め帯]、フェス[訳注:盾の中央帯]にサルタイアー・マーレイ[訳注:桑の実色の十字]、コモン・チャージ[訳注:盾の意匠]として犬をクーシャント[訳注:伏せた姿]で描き、その足の下には奴隷制を表す鎖をエンバトルド[訳注:胸壁模様]で。チーフ・エングレイル[訳注:上部の波形模様]にはシェブロン・ヴェール[訳注:緑色の山形紋]、フィールド・アジュール[訳注:青色の地]には三本のインヴェクテッド・ライン[訳注:内向きの半円模様]、そしてノンブリル・ポイント[訳注:盾の中央下部]にダンセット・インデンテッド[訳注:ギザギザ模様]でランパント[訳注:立ち姿]。クレスト[訳注:兜飾り]は逃亡ニガー、セーブル[訳注:黒色]、肩に荷物を担ぎ、バー・シニスター[訳注:左上から右下への斜め帯]の上に。サポーター[訳注:盾を支える図]として二つのギュールズ[訳注:赤色]、これはお前と俺だ。モットーは『マッジョーレ・フレッタ、ミノーレ・アット』。本で調べたんだ。『急がば回れ』って意味さ。」
「たまげたな」と俺は言った。「だけど、その残りの部分はどういう意味なんだ?」
「そんなことに構ってる時間はない」とトムは言った。「死に物狂いでやらなきゃいけないんだ。」
「まあ、いいや」と俺は言った。「じゃあ、いくつかはなんだ? フェスってのは何だ?」
「フェス――フェスってのは――お前がフェスが何か知る必要はない。ジムがやるときになったら、作り方を教えてやる。」
「ちぇっ、トム」と俺は言った。「教えてくれたっていいじゃないか。バー・シニスターってのは何だ?」
「ああ、俺も知らない。だけど、それは必要なんだ。貴族はみんな持ってるからな。」
それがトムのやり方だった。説明するのが気に食わないと、絶対に説明しない。一週間問い詰めても、何一つ変わりはなかった。
トムは紋章のことをすべて片付けたので、今度はその仕事の残りの部分、つまり悲しげな碑文を考える作業に取り掛かった。ジムにはそれが必要だ、みんなそうしたんだから、と言った。トムはたくさんの碑文を考え出し、紙に書き出して、読み上げてくれた。
ここに、囚われし心、張り裂ける。
ここに、哀れな囚人、世と友に見捨てられ、その悲しき生涯を悩み終える。
ここに、孤独な心は砕け、疲れ果てた魂は、三十七年の孤独な監禁の末、安息の地へ旅立つ。
ここに、家なく友なく、三十七年の辛い監禁の末、ルイ十四世の庶子にして高貴なる異邦人、滅びる。
それらを読み上げるトムの声は震え、ほとんど泣き崩れそうだった。読み終えると、どれもこれも素晴らしい出来なので、どれをジムに壁へ刻ませるか、なかなか決められなかった。だが、ついに、全部刻ませることに決めた。ジムは、そんなにたくさんのものを釘で丸太に刻むには一年はかかるだろうし、それに文字の書き方も知らない、と言った。だがトムは、下書きをしてやるから、あとはその線をなぞるだけでいい、と言った。それからすぐに、こう言った。
「考えてみれば、丸太じゃだめだ。地下牢に丸太の壁なんてない。碑文は岩に刻まなきゃ。岩を持ってこよう。」
ジムは、岩は丸太よりひどいと言った。岩にそんなものを刻んでいたら、とんでもなく長い時間がかかって、絶対に出られない、と言った。だがトムは、俺にも手伝わせると言った。それから、俺とジムのペン作りがどれくらい進んでいるか見に来た。それはひどく面倒で骨の折れる仕事で、なかなか進まず、手の傷が治る暇もなかった。ほとんど進んでいないように見えたので、トムは言った。
「いい方法を思いついた。紋章と悲しげな碑文のためには岩が必要だ。その同じ岩で一石二鳥を狙える。製粉所にでかくて見事な砥石がある。そいつをくすねてきて、その上にいろいろ彫りつけて、ペンやノコギリもそれで研ごう。」

それはなかなかの名案だったし、その砥石もなかなかの代物だった。だが、俺たちはやってみることにした。まだ真夜中には少し早かったので、ジムに仕事を任せ、俺たちは製粉所へ向かった。砥石をくすね、家まで転がして帰ろうとしたが、これがとてつもない重労働だった。どうやっても、倒れるのを防げないことがあり、そのたびに俺たちはもう少しで押しつぶされるところだった。トムは、やり遂げる前に、どちらか一人は必ずやられるだろう、と言った。半分まで運んだところで、俺たちは完全にへばってしまい、汗で溺れそうだった。これではだめだ、ジムを呼びに行かなくては、と分かった。そこでジムはベッドを起こし、ベッドの脚から鎖を滑らせて外し、それを首にぐるぐる巻きつけ、俺たちの穴から這い出してそこへ向かった。ジムと俺がその砥石に取り掛かると、まるで何でもないかのように軽々と運べた。トムは監督をしていた。あいつほど監督の上手いガキは見たことがない。トムは何でもやり方を知っていた。
俺たちの穴はかなり大きかったが、砥石を通すには十分ではなかった。だがジムがツルハシを使うと、すぐに十分な大きさになった。それからトムが釘で砥石にいろいろと印をつけ、ジムに作業を始めさせた。釘をノミ代わりに、物置のがらくたの中から見つけた鉄のボルトをハンマー代わりにして。トムは、残りのロウソクが燃え尽きるまで作業して、それから寝ていい、砥石は藁のマットレスの下に隠してその上で眠れ、と言った。それから俺たちは、ジムが鎖をベッドの脚に戻すのを手伝い、自分たちも寝る準備ができた。だが、トムが何かを思いついて言った。
「ジム、ここにクモはいるか?」
「いえ、ありがたいことに、一匹もおりまへん、トムはん。」
「よし、じゃあ何匹か捕まえてきてやる。」
「そら勘弁してくだはい。わて、あれはいやや。怖いですんや。ガラガラヘビがおる方がまだマシでっせ。」
トムは一、二分考えてから言った。
「それはいい考えだ。きっと誰かがやったことがあるはずだ。やったに違いない。理にかなってる。ああ、最高のアイデアだ。どこで飼う?」
「何を飼うんでっか、トムはん?」
「決まってるだろ、ガラガラヘビさ。」
「ああ、なんてこった、トムはん! もしガラガラヘビがここに入ってきたら、わて、この丸太の壁を頭で突き破って、逃げ出しまっせ。」
「なんだよ、ジム、少しすれば怖くなくなるさ。手なずけられるんだ。」
「手なずける!」
「そうだ――簡単なことさ。どんな動物も親切にされて可愛がられれば感謝するし、可愛がってくれる人を傷つけようなんて思わないもんだ。どんな本にもそう書いてある。試してみろよ――頼むからさ。二、三日試してみるだけでいい。すぐに懐いて、お前を大好きになるさ。一緒に寝てくれるし、一分も離れようとしなくなる。首に巻きつけさせてくれるし、頭を口の中に入れさせてくれるようにもなる。」
「お願いです、トムはん――そんな話せんといて! 耐えられまへん! わての口に頭を入れさせてくれる――ご親切に、でっか? わてが頼むまで、えらい長いこと待つことになるでっしゃろな。それに、わてはヘビと一緒に寝たくありまへん。」
「ジム、馬鹿なこと言うなよ。囚人には何か口のきけないペットが必要なんだ。もしガラガラヘビを試したやつがいないなら、お前が最初に試すことで得られる栄光は、命を救うために考えつくどんな方法よりも大きいんだぞ。」
「そやかてトムはん、わてはそんな栄光はいりまへん。ヘビがわての顎に噛み付いたら、どこに栄光があるんでっか? いえ、わてはそんなことしたくありまへん。」
「ちくしょう、試してみることくらいできないのか? 俺はただ試してほしいだけなんだ――うまくいかなきゃ、続けなくていい。」
「そやかて、試してる間にヘビに噛まれたら、それでおしまいでっせ。トムはん、わては無茶なことでない限り、ほとんど何でもやります。でも、もしあんたとハックが、わてに手なずけさせるためにガラガラヘビをここに連れてきたら、わてはここを出ていきます。それは確かでっせ。」
「分かったよ、じゃあもういい、やめだ。お前がそんなに頑固ならな。ガーター蛇を何匹か捕まえてきて、尻尾にボタンを結びつけて、ガラガラヘビのふりをさせればいい。それで我慢するしかないだろうな。」

「それなら我慢できまっけど、おらん方がええに決まってますわ。ほんまに。囚人になるのが、こないに面倒で厄介なことやとは、今まで知りまへんでした。」
「まあ、正しくやればいつもそうなるもんだ。この辺にネズミはいるか?」
「いえ、一匹も見かけまへん。」
「よし、じゃあネズミを何匹か捕まえてきてやる。」
「なんでです、トムはん、わてはネズミなんていりまへん。あいつらは、人が寝ようとしてるときに、体をかき乱したり、ガサガサ動き回ったり、足に噛み付いたりする、とんでもない生き物でっせ。いえ、もし飼わなあかんのやったら、ガーター蛇にしといてくだはい。ネズミはいりまへん。何の役にも立ちまへんから。」
「だけど、ジム、ネズミは必要なんだ――みんな飼ってる。だから、もうごちゃごちゃ言うな。囚人がネズミを飼わないなんてことはない。そんな例は一つもないんだ。それに、ネズミを訓練して、可愛がって、芸を覚えさせると、ハエみたいに人懐っこくなる。だけど、音楽を聴かせなきゃいけない。何か音楽を演奏できるものは持ってるか?」
「粗末な櫛と紙切れ、それにジューズハープしかおまへん。でも、ジューズハープなんかじゃ、あいつらは興味示さんでっしゃろ。」
「いや、示すさ。あいつらはどんな音楽かなんて気にしない。ジューズハープでネズミには十分だ。どんな動物も音楽が好きだ――牢屋の中では、音楽に夢中になる。特に、悲しげな音楽がな。ジューズハープからは、それ以外の音楽は出てこない。いつもネズミの興味を引くんだ。お前に何があったのか見に出てくる。ああ、お前は大丈夫だ。準備は万端だ。夜寝る前と、朝早くにベッドに座って、ジューズハープを弾くんだ。『最後の絆は断たれて』を弾け――それが何よりも早くネズミを釣る曲だ。二分も弾けば、ネズミもヘビもクモも、みんなお前のことを心配し始めて、寄ってくるのが見えるだろう。そして、お前の周りにうじゃうじゃ群がって、最高の時間を過ごすのさ。」
「へえ、あいつらはそうでしょうな、トムはん。でも、ジムはどんな時間を過ごすんでっか? さっぱり分かりまへん。でも、やらなあかんのやったら、やります。動物たちを満足させて、家の中で面倒を起こさんようにしといた方がええんでっしゃろな。」
トムはしばらく考えて、他に何か忘れていることはないか確かめた。そしてすぐに言った。
「ああ、一つ忘れていた。ここで花を育てられると思うか?」
「分かりまへんけど、できるかもしれまへん、トムはん。でも、ここはかなり暗いし、わては花なんか要りまへんし、ものすごい手間がかかるでっしゃろ。」
「まあ、とにかく試してみろ。他の囚人たちもやったんだ。」
「あの大きなガマの穂みたいなビロードモウズイカの茎なら、ここで育つかもしれまへん、トムはん。でも、かかる手間の半分にも値せんでっしゃろ。」
「そんなことないさ。小さいのを一本持ってきてやるから、あっちの隅に植えて育てるんだ。そして、モウズイカなんて呼ぶなよ。ピッチオーラと呼べ――それが牢獄での正しい名前だ。そして、お前の涙で水をやるんだ。」
「なんでです、トムはん。わてには湧き水がたっぷりありまっせ。」
「湧き水じゃだめなんだ。涙で水をやらなきゃ。いつだってそうするもんだ。」
「そやかてトムはん、わてなら、他の男が涙で育て始めてる間に、湧き水でモウズイカの茎を二本は育てられまっせ。」

「そういうことじゃないんだ。涙でやらなきゃいけないんだ。」
「それじゃ枯れてしまいまっせ、トムはん。間違いなく。わて、めったに泣きまへんから。」
トムは困り果てた。だが、考え込んだ末、ジムはタマネギで何とかするしかないだろう、と言った。朝になったらニガーの小屋へ行って、ジムのコーヒーポットにこっそり一つ落としてやると約束した。ジムは「コーヒーにタバコを入れられる方がまだマシだ」と言い、モウズイカを育てる手間や面倒、ネズミにジューズハープを弾き、ヘビやクモやその他の生き物を可愛がったりおだてたりすること、それに加えてペンや碑文や日誌などの作業について、さんざん文句を言った。囚人になるのは、これまで引き受けたどんなことよりも面倒で心配で責任が重い、と。それでトムはほとんど堪忍袋の緒が切れそうになり、こう言った。囚人が自分の名を上げるために、これほど華々しいチャンスに恵まれたことは世の中に一度もないのに、ジムはその価値を理解するだけの分別がなく、ほとんど宝の持ち腐れだと。それを聞いてジムは申し訳なくなり、もう二度とあんな態度はとらないと言った。それから、俺とトムはベッドにもぐり込んだ。

第三十九章
朝になると、俺たちは村へ行って金網のネズミ捕りを買い、それを持ち帰った。一番良さそうなネズミの穴の蓋を開けておくと、一時間もしないうちに、極上のネズミが十五匹も捕まった。それから、その罠をサリー叔母のベッドの下の安全な場所に置いた。だが、俺たちがクモを探しに行っている間に、リトル・トーマス・フランクリン・ベンジャミン・ジェファーソン・エレクサンダー・フェルプスがそれを見つけ、ネズミが出てくるか見ようと扉を開けてしまった。そして、ネズミは出てきた。サリー叔母が部屋に入ってきて、俺たちが戻ったときには、彼女はベッドの上で大騒ぎしており、ネズミたちは彼女を退屈させまいと精一杯やっていた。そこで彼女は、俺たち二人をヒッコリーの鞭でぴしゃぴしゃと叩いた。あの余計なことをするガキのせいで、さらに十五、六匹捕まえるのに二時間もかかった。しかも、今度のやつらは一番上等というわけではなかった。最初の獲物が群れの中でも選りすぐりだったからだ。最初の獲物ほど見事なネズミの一団は見たことがない。
俺たちは、選りすぐりのクモや虫、カエル、毛虫などを立派に揃えた。スズメバチの巣も手に入れようとしたが、だめだった。一家が在宅だったのだ。俺たちはすぐには諦めず、できるだけ長く粘った。俺たちがやつらを疲れさせるか、やつらが俺たちを疲れさせるか、どっちかだと思ったからだ。そして、やつらが勝った。それから、俺たちはアライカンプ[訳注:elecampane、薬草の一種]を塗って、ほとんど元通りになったが、まともに座ることはできなかった。そして、ヘビを探しに行き、ガーター蛇と家ヘビを二十匹ほど捕まえて袋に入れ、それを俺たちの部屋に置いた。その頃には夕食の時間で、正直言って、実に素晴らしい一日の働きだった。腹が減っていたかって? ――いや、まさか! そして、俺たちが戻ったとき、そこには一匹のヘビもいなかった――袋の口をちゃんと結んでいなかったせいで、どうにかして抜け出して、いなくなってしまったのだ。だが、大した問題ではなかった。まだ屋敷のどこかにはいるはずだからだ。だから、また何匹か捕まえられるだろうと判断した。いや、しばらくの間、家の中にはヘビが不足するということは全くなかった。垂木やあちこちから、ぽたぽたと落ちてくるのがしょっちゅう見られた。そして、たいてい皿の中か、首筋の後ろに落ちてきた。ほとんどの場合、いてほしくない場所にだ。まあ、ヘビは綺麗で縞模様があり、百万匹いたところで害はなかった。だが、そんなことはサリー叔母には何の関係もなかった。彼女は、どんな種類であれ、ヘビを軽蔑しており、どんなことをしても我慢できなかった。そして、一匹が彼女の上にひらりと落ちてくるたびに、何をしている最中であろうと、その仕事を放り出して、飛び出していった。あんな女は見たことがない。そして、ジェリコまで届くような叫び声が聞こえた。火箸で一匹つかませようとしても、絶対に無理だった。そして、寝返りを打ってベッドに一匹いるのを見つけようものなら、這い出して、家が火事になったかと思うほどの雄叫びを上げた。彼女があまりに旦那を悩ませるので、旦那は、いっそヘビなんて創造されなければよかったのに、とほとんど願うほどだと言った。何しろ、最後のヘビが一匹残らず家からいなくなって一週間も経つのに、サリー叔母はまだ立ち直っていなかった。立ち直るどころではなかった。彼女が何か考え事をしているときに、羽で首筋を触ろうものなら、靴下から飛び出すほど驚いた。とても奇妙だった。だが、トムは、女はみんなそんなものだと言った。何かの理由で、そのように作られているのだと。
俺たちのヘビが一匹でも彼女の邪魔をするたびに、俺たちはひっぱたかれた。そして、彼女は、もし俺たちがまたこの場所にヘビを運び込んだら、今度のひっぱたきなど比べものにならないほどひどい目にあわせる、と言った。ひっぱたかれるのは気にしなかった。大したことではなかったからだ。だが、もう一度一揃い集めるのに苦労するのは気になった。しかし、俺たちはそれらを揃え、他のものもすべて揃えた。音楽が始まると、みんながジムのところに群がっていく様子は、ジムの小屋ほど陽気な小屋は見たことがないほどだった。ジムはクモが好きではなかったし、クモもジムが好きではなかった。だから、クモはジムを待ち伏せして、彼をひどい目にあわせた。そしてジムは、ネズミとヘビと砥石のせいで、ベッドにはほとんど自分の寝る場所がないと言った。そして、場所があっても、あまりに賑やかで眠れない、と。そして、いつも賑やかだった、と彼は言った。なぜなら、やつらは決して一度に全部眠ることはなく、交代で寝るからだ。だから、ヘビが眠っているときはネズミが甲板にいて、ネズミが寝床に入るとヘビが見張りに立つ。だから、いつも一つのギャングが自分の下で邪魔をし、もう一つのギャングが自分の上でサーカスを繰り広げている。そして、もし新しい場所を探しに起き上がると、横切るときにクモが襲いかかってくる、と彼は言った。もし今回ここから出られたら、給料をもらっても二度と囚人にはならない、と言った。
さて、三週間の終わりには、すべてがかなり良い形になっていた。シャツは早々にパイに入れて送られ、ジムはネズミに噛まれるたびに、インクが乾かないうちに起きて日誌に少し書き込んだ。ペンは作られ、碑文などはすべて砥石に刻まれた。ベッドの脚は二つに切り、おがくずは俺たちが食べたが、ものすごい腹痛を起こした。俺たちはみんな死ぬかと思ったが、死ななかった。今まで見た中で最も消化の悪いおがくずだった。トムも同じことを言った。

だが、言ったように、今やすべての作業がようやく終わった。そして、俺たちはみんなかなり疲れ果てていたが、特にジムがそうだった。旦那は、オーリンズの下流にあるプランテーションに、逃げたニガーを迎えに来るようにと二、三度手紙を書いたが、返事は来なかった。そんなプランテーションはなかったからだ。そこで、セントルイスとニューオーリンズの新聞にジムの広告を出すことに決めた。セントルイスの新聞に言及したとき、俺は寒気がして、ぐずぐずしている時間はないと悟った。そこでトムは、さあ、匿名の脅迫状だ、と言った。
「そりゃなんだ?」と俺は言った。
「何かが起きていると人々に警告するんだ。やり方は色々ある。だが、いつもどこかで見張っていて、城の総督に知らせる者がいるものさ。ルイ十六世がテュイルリー宮殿から逃げ出そうとしたときは、下女がやった。それはとても良い方法だし、匿名の脅迫状もそうだ。両方使おう。それに、囚人の母親が彼と服を交換して、彼女が残り、彼が彼女の服で抜け出すのが普通だ。それもやろう。」
「だけど、なあトム、なんでわざわざ誰かに何かが起きているって警告する必要があるんだ? 自分たちで見つけさせればいいじゃないか――そいつらの勝手だろ。」
「ああ、分かってる。だけど、やつらには頼れない。最初からずっとそうだった――すべて俺たちにやらせてきた。やつらは人を信じやすくて間抜けだから、何一つ気づかない。だから、もし俺たちが知らせてやらなければ、誰も、何も、俺たちの邪魔をしに来ない。そしたら、俺たちの苦労と努力の末のこの脱出劇は、まったく盛り上がらずに終わってしまう。何の意味もなくなる――何にもならないんだ。」
「まあ、俺としては、トム、その方がいいけどな。」
「ちぇっ!」とトムは言って、うんざりした顔をした。だから俺は言った。
「だけど、文句は言わないよ。お前のやり方が、俺のやり方だ。下女のことはどうするんだ?」
「お前がやるんだ。真夜中に忍び込んで、あの黄色い肌の娘のワンピースを盗むんだ。」
「おい、トム、それじゃ翌朝面倒なことになるぞ。だって、もちろん、彼女はたぶんその一枚しか持ってないだろうから。」
「分かってる。だけど、必要なのは十五分だけだ。匿名の脅迫状を運んで、玄関のドアの下に押し込むためにな。」
「分かった、じゃあやるよ。だけど、自分の服でも同じように運べるけどな。」
「それじゃ、下女には見えないだろ?」
「そうだけど、どのみち、俺がどんな格好してるかなんて、誰も見ないだろ。」
「そんなことは関係ない。俺たちがすべきことは、ただ俺たちの義務を果たすことだ。誰かが俺たちがやっているのを見るかどうかは心配しなくていい。お前には少しも主義ってものがないのか?」
「分かったよ、何も言わない。俺が下女だ。ジムの母親は誰がやるんだ?」
「俺が彼の母親だ。サリー叔母からガウンを一枚盗んでくる。」
「じゃあ、俺とジムが出るとき、お前は小屋に残らなきゃいけないな。」
「とんでもない。ジムの服に藁を詰めて、変装した母親の代わりに彼のベッドに寝かせておく。ジムは俺からニガーの女のガウンを脱がせてそれを着る。そして、みんなで一緒に回避するんだ。身分のある囚人が逃げるときは、それを回避と呼ぶ。王が逃げるときは、いつでもそう呼ばれるんだ、例えばな。王の息子でも同じだ。それが庶子だろうと、そうでなかろうと、関係ない。」
そこでトムは匿名の脅迫状を書き、俺はその夜、黄色い肌の娘のワンピースをくすねて、それを着て、トムに言われた通り、玄関のドアの下に押し込んだ。そこにはこう書かれていた。
用心せよ。厄介事が起きつつある。厳重に見張れ。 見知らぬ友より

次の夜、俺たちは、トムが血で描いたドクロと交差した骨の絵を玄関のドアに貼り付けた。そして、その次の夜には、棺桶の絵を裏口のドアに貼り付けた。あんなにびくびくしている家族は見たことがない。まるで、家のあちこちの物陰やベッドの下に幽霊が待ち構え、空中を震えながら漂っているかのように、これ以上ないほど怯えていた。ドアがバタンと閉まれば、サリー叔母は飛び上がって「きゃっ!」と言い、何かが落ちれば、飛び上がって「きゃっ!」と言った。彼女が気づいていないときに、うっかり触ろうものなら、同じことをした。彼女はどの方向を向いても安心できなかった。いつも背後に何かがいると思ったからだ――だから、いつも突然くるりと振り返って「きゃっ!」と言い、三分の二も回りきらないうちに、またくるりと振り返って、もう一度そう言った。そして、ベッドに行くのが怖かったが、起きていてもいられなかった。だから、計画は非常にうまくいっていた、とトムは言った。これほど満足のいく働きをするものは見たことがない、と言った。それは、正しく行われたことを示している、と。
そこでトムは言った、さあ、いよいよ大詰めだ! そこで、まさにその翌朝、夜明けとともに、俺たちは別の手紙を用意し、それをどうしたものかと思案していた。というのも、夕食のときに、彼らが両方のドアに一晩中ニガーを見張りに立たせると言っているのを聞いたからだ。トムは避雷針を伝って下りて、様子を探りに行った。裏口のニガーは眠っていたので、トムはその首筋に手紙を突き刺して戻ってきた。この手紙にはこう書かれていた。
私を裏切らないでください。私はあなたの友人になりたいのです。インディアン準州から来た凶悪な人殺しの一団が、今夜あなたの逃亡ニガーを盗みに来ます。彼らはあなた方を怖がらせて、家の中に閉じこもらせ、邪魔されないようにしようとしてきたのです。私はその一味の一人ですが、信仰に目覚め、悪事から足を洗い、再び正直な人生を送りたいと願っており、この地獄のような計画を裏切るつもりです。彼らは真夜中ちょうどに、北の方から、塀に沿って忍び寄り、偽の鍵を使って、彼を捕まえるためにニガーの小屋に入ります。私は少し離れた場所で見張り、もし危険があればブリキの角笛を吹くことになっています。しかし、その代わりに、彼らが中に入ったらすぐに羊のようにメーと鳴き、角笛は全く吹きません。そして、彼らが彼の鎖を解いている間に、あなたはそこへ忍び寄り、彼らを閉じ込めて、好きなように殺すことができます。私が言う通りにだけ行動してください。もしそうでなければ、彼らは何かを疑い、大騒ぎを起こすでしょう。私は報酬は望みません。ただ、正しいことをしたと知ることができればよいのです。
見知らぬ友より

第四十章
朝食の後、俺たちはかなり気分が良く、俺のカヌーに乗って川の向こうへ釣りに出かけた。昼飯を持って、楽しい時間を過ごし、いかだの様子を見に行くと、無事だったので、遅くに夕食に帰った。すると、家の人たちはひどく慌てふためいて、どっちがどっちだか分からないほどで、夕食が終わるとすぐに俺たちをベッドに行かせ、何が問題なのか教えてくれず、新しい手紙のことは一言も口にしなかった。だが、その必要はなかった。俺たちは誰よりもそのことをよく知っていたからだ。階段を半分ほど上り、彼女が背を向けたとたん、俺たちは地下室の食器棚に滑り込み、たっぷりの昼飯を詰め込んで部屋に持ち帰り、ベッドに入った。そして、十一時半ごろに起き、トムは盗んだサリー叔母のドレスを着て、昼飯を持って出かけようとしたが、こう言った。
「バターはどこだ?」
「ひとかたまり、トウモロコシパンの上に置いておいたよ」と俺は言った。
「そうか、置いてきたんだな――ここにはないぞ。」
「なくてもなんとかなるさ」と俺は言った。
「あってもなんとかなる」とトムは言った。「お前、地下室に滑り降りて取ってこい。それから、さっさと避雷針を下りてこっちに来い。俺はジムの服に藁を詰めて、変装した母親の代わりにして、お前が着いたらすぐに羊みたいにメーと鳴いて、出発する準備をしておく。」
そうしてトムは出て行き、俺は地下室へ下りた。人の拳ほどもあるバターの塊は、俺が置いた場所にあり、俺はそれを乗せたトウモロコシパンの厚切りを手に取り、明かりを吹き消し、非常にこっそりと階段を上り始めた。そして、一階までは無事にたどり着いたが、ここでサリー叔母がロウソクを持ってやって来た。俺はそれを帽子の中に押し込み、帽子を頭にかぶった。次の瞬間、彼女は俺を見つけた。そして言った。
「地下室に行ってたのかい?」
「はい、おばさん。」
「そこで何をしてたんだい?」
「何も。」
「何もだって!」
「はい。」
「じゃあ、なんでまた、こんな夜中にそこへ行こうなんて思ったんだい?」
「分かりません。」
「分からないだって? そんな風に答えるんじゃないよ。トム、あんたがそこで何をしてたのか知りたいんだ。」
「何もしてませんよ、サリー叔母さん。ほんとです、誓います。」
これで勘弁してくれるだろうと思ったし、普段ならそうだっただろう。だが、あまりに奇妙なことがたくさん起こっていたので、彼女は定規で測ったようにまっすぐでない些細なことにも、びくびくしていたのだろう。だから、彼女は非常にきっぱりと言った。
「あんたは、あの居間に入って、私が行くまでそこにいなさい。何かよからぬことをしていたに違いない。私が済む前に、それが何か突き止めてやるからね。」
そう言って彼女は立ち去り、俺はドアを開けて居間に入った。まあ、そこにはすごい人だかりができていた! 農夫が十五人、そして一人一人が銃を持っていた。俺はひどく気分が悪くなり、椅子にこそこそと近づき、腰を下ろした。彼らは座り込んで、何人かは小声で少し話していたが、全員がそわそわして落ち着かない様子だった。だが、そうではないように見せかけようとしていた。だが、俺には分かった。彼らはいつも帽子を取ったりかぶったり、頭を掻いたり、席を変えたり、ボタンをいじったりしていたからだ。俺自身も落ち着かなかったが、それでも帽子は脱がなかった。

サリー叔母が早く来て、俺の用事を済ませて、もし望むなら俺をひっぱたいて、そして俺を行かせて、トムに、俺たちがやりすぎたこと、そして、とんでもないスズメバチの巣に自分たちを突っ込んでしまったことを知らせたいと、心から願った。そうすれば、すぐに馬鹿な真似をやめて、この連中が我慢の限界に達して俺たちを襲ってくる前に、ジムと一緒に逃げ出せるのに。
ついに彼女がやって来て、俺に質問を始めたが、俺はまともに答えることができなかった。どっちが上だか下だか分からなかった。なぜなら、この男たちは今やひどくそわそわしていて、何人かは今すぐに出発して、あの無法者どもを待ち伏せしたいと言い、真夜中まであと数分しかないと言っていた。また他の者たちは、彼らを引き留めて、羊の合図を待つようにさせようとしていた。そして、ここに叔母が質問を浴びせかけてくる。俺は全身が震え、その場に崩れ落ちそうなくらい怖かった。そして、部屋はますます暑くなり、バターが溶け始めて、首筋や耳の後ろを流れ落ちてきた。やがて、彼らの一人が「俺は、今すぐ小屋に先に入って、やつらが来たときに捕まえるのがいいと思う」と言ったとき、俺はほとんど気を失いそうになった。そして、一筋のバターが額を伝って流れ落ち、サリー叔母がそれを見て、シーツのように真っ白になり、言った。
「なんてことなの、この子はどうしたっていうの? 生まれつきの脳膜炎よ、間違いなく。そして、それが滲み出てきてる!」
そして、みんなが見に駆け寄り、彼女は俺の帽子をひったくった。すると、パンとバターの残りが飛び出し、彼女は俺を掴んで抱きしめ、言った。
「ああ、なんてびっくりさせたの! そして、それ以上悪くなくて、どれほど嬉しくて感謝していることか。運が悪いときは、雨が降れば土砂降りになるもので、あの汁を見たとき、私たちはあなたを失ったと思ったわ。だって、色といい何といい、もしものことがあったら、あなたの脳みそはちょうどあんな風になるだろうって知っていたから――ああ、ねえ、なんであなたがそのために地下室に行っていたって言ってくれなかったの。私なら気にしなかったのに。さあ、ベッドに行きなさい。そして、朝まであなたの顔を見せないで!」
俺は一瞬で二階に上がり、もう一瞬で避雷針を下り、暗闇の中を物置小屋に向かって駆け抜けた。あまりに焦っていて、ほとんど言葉が出てこなかったが、できるだけ早くトムに、今すぐ飛び出さなければならない、一分も無駄にできない――向こうの家は銃を持った男たちでいっぱいだ! と伝えた。
彼の目は燃えるように輝き、言った。
「まさか! ――本当か? 最高じゃないか! おい、ハック、もしもう一度やり直せるなら、二百人は集められるぜ! もし延期できれば――」
「急げ! 急げ!」と俺は言った。「ジムはどこだ?」
「お前のすぐ肘のところだ。腕を伸ばせば触れる。服も着て、準備は万端だ。さあ、抜け出して羊の合図をしよう。」
だがそのとき、男たちがドアに近づいてくる足音が聞こえ、南京錠をガチャガチャいじり始めるのが聞こえ、一人の男がこう言うのが聞こえた。
「早すぎると言っただろう。まだ来てない――ドアは閉まってる。いいか、何人かお前たちを小屋に閉じ込めてやるから、暗闇で待ち伏せして、やつらが来たら殺せ。残りの者は少し散らばって、やつらが来るのが聞こえるか耳を澄ませていろ。」
そうして彼らは入ってきたが、暗闇で俺たちを見ることはできず、俺たちがベッドの下に急いで隠れる間に、もう少しで踏みつけられるところだった。だが、俺たちは無事に下に潜り込み、穴から素早く、しかし静かに抜け出した――ジムが最初、俺が次、トムが最後、それはトムの命令通りだった。今、俺たちは物置小屋にいて、すぐ外で足音が聞こえた。そこで、俺たちはドアに這って近づき、トムがそこで俺たちを止め、割れ目に目を当てたが、あまりに暗くて何も見えなかった。そして、ささやき声で、足音が遠ざかるのを待って、彼が俺たちをつついたら、ジムが最初に滑り出て、彼が最後に出ると言った。そこで、彼は割れ目に耳を当てて、聞き、聞き、聞き続けた。外ではずっと足音がガサガサしていた。そして、ついに彼が俺たちをつつき、俺たちは滑り出て、息を殺し、ほんの少しの音も立てずに身をかがめ、インディアンのように一列になって、こっそりと塀に向かって進んだ。そして、無事に塀に着き、俺とジムは乗り越えた。だが、トムのズボンが一番上の横木のささくれに引っかかってしまい、そのとき足音が近づいてくるのが聞こえたので、彼は引きちぎらなければならなかった。そのせいでささくれが折れて音が鳴った。そして、彼が俺たちの跡に飛び降りて走り出したとき、誰かが叫んだ。

「誰だ! 答えろ、さもないと撃つぞ!」
だが、俺たちは答えなかった。ただ、踵を返して、突っ走った。すると、突進してくる音と、バン、バン、バン!という銃声が響き、弾丸が俺たちの周りをぶんぶん飛び交った! 彼らが叫ぶのが聞こえた。
「いたぞ! 川へ向かって逃げた! 追え、お前たち、犬を放せ!」
そうして、彼らは全速力でやって来た。彼らがブーツを履いて叫んでいたので、俺たちには聞こえたが、俺たちはブーツを履いていなかったし、叫ばなかった。俺たちは製粉所への小道にいた。彼らがかなり近づいてきたとき、俺たちは茂みに身をかわして彼らをやり過ごし、それから彼らの後ろについた。彼らは、強盗を怖がらせないように、すべての犬を閉じ込めていた。だが、このときまでに誰かが犬を放してしまい、百万匹分の騒ぎ立てながら、こちらへやって来た。だが、それは俺たちの犬だった。だから、俺たちは追いつかれるまでその場に立ち止まった。そして、犬たちが俺たちしかいないこと、そして何の興奮も提供されないことを見ると、ただ挨拶だけして、叫び声とがやがやいう音のする方へまっすぐ突っ走って行った。それから、俺たちは再び蒸気を上げて、彼らの後を追いかけて、製粉所のほとんど近くまで行き、それから茂みを通って、俺のカヌーが結んである場所まで行き、飛び乗って、川の真ん中に向かって必死に漕いだが、必要以上の音は立てなかった。それから、俺のいかだがある島に向かって、楽に、快適に漕ぎ出した。そして、岸のあちこちで彼らが互いに怒鳴り合ったり、吠えたりするのが聞こえたが、やがて遠く離れると、その音はかすかになり、消えていった。そして、俺たちがいかだに足を踏み入れたとき、俺は言った。
「さあ、ジム、お前はまた自由の身だ。もう二度と奴隷にはならないと俺は賭けるぜ。」
「ほんまにええ仕事やったで、ハック。計画も素晴らしかったし、実行も素晴らしかった。あれほどごちゃごちゃしてて、見事な計画を立てられるやつは、誰一人おらんで。」
俺たちはみんな、これ以上ないほど喜んでいたが、トムが一番喜んでいた。ふくらはぎに弾丸を食らっていたからだ。
それを聞いたとき、俺とジムは、さっきまでほど威勢が良くはなかった。トムはかなり痛がり、血も出ていた。だから、俺たちは彼を小屋に寝かせ、公爵のシャツの一枚を破って包帯を巻いてやったが、彼は言った。
「布をよこせ。自分でできる。今は止まるな。ここでぐずぐずするな。回避作戦がこんなに見事に進んでいるんだから。スイープを握って、いかだを放せ! お前たち、見事にやったぞ! ――ほんとだ。俺たちがルイ十六世の件を扱っていたら、『聖ルイの子よ、天に昇れ!』なんて伝記に書かれなかっただろう。いや、とんでもない。俺たちなら、彼を国境の向こうへ追い出しただろう――それが俺たちが彼にしたことだ――そして、それもいとも簡単にやっただろう。スイープを握れ――スイープを握れ!」
だが、俺とジムは相談し――考えていた。そして、少し考えた後、俺は言った。
「言ってやれ、ジム。」
そこでジムは言った。
「ほな、わてにはこう見えまんねん、ハック。もしあの人が自由になるところで、わしらのうち誰かが撃たれたとしたら、あの人は『行け、わしを助けろ、こいつを助ける医者のことなんか気にするな』って言うやろか? それがトム・ソーヤーはんらしいことでっか? あの人がそんなこと言うやろか? 絶対に言わへん! ほな、ジムがそれを言うと思うか? いえ、わては医者なしでは、この場所から一歩も動きまへん。たとえ四十年かかろうとも!」

俺は、ジムが心根は白人だと知っていたし、彼が言ったことを言うだろうと分かっていた――だから、もう大丈夫だった。俺はトムに、医者を呼びに行くと言った。トムはかなり騒いだが、俺とジムはそれに固執し、一歩も引かなかった。そこでトムは、這い出して自分でいかだを放そうとしたが、俺たちはそうはさせなかった。それから、彼は俺たちに説教を垂れたが、何の役にも立たなかった。
そこで、俺がカヌーの準備をしているのを見ると、彼は言った。
「分かった、じゃあ、もしお前が行くというなら、村に着いたらどうすればいいか教えてやる。ドアを閉めて、医者をきつく、しっかりと目隠ししろ。そして、墓のように沈黙を守ると誓わせ、金貨でいっぱいの財布を手に握らせろ。それから、暗闇の中を裏路地やあちこち連れ回し、島々の間を回り道して、カヌーでここに連れてこい。そして、彼を調べてチョークを取り上げろ。村に戻るまで返してやるな。さもないと、彼はこのいかだに印をつけて、また見つけられるようにするだろう。それがみんなのやり方だ。」
だから俺はそうすると言って、出発した。ジムは、医者が来るのが見えたら、彼が再び去るまで森に隠れることになっていた。

第四十一章
医者は老人だった。俺が彼を起こしたとき、とても優しそうで、親切そうな老人だった。俺は、俺と弟が昨日の午後、スパニッシュ島で狩りをしていて、見つけたいかだの一部でキャンプしていたこと、そして真夜中ごろ、弟が夢の中で銃を蹴ってしまったに違いないこと、そのせいで銃が暴発して彼の足を撃ってしまったこと、そして、そこへ行って手当てをしてほしいこと、そしてそのことは誰にも言わないでほしいこと、誰にも知らせないでほしいことを話した。なぜなら、今晩家に帰って家族を驚かせたいからだ、と。
「ご家族は誰かね?」と彼は言った。
「あそこのフェルプス家です。」
「おお」と彼は言った。そして、一分ほどして、こう言った。
「彼はどうやって撃たれたと言ったかね?」
「夢を見ていたんです」と俺は言った。「そして、その夢が彼を撃ったんです。」
「奇妙な夢だ」と彼は言った。
そこで医者はランタンに火を灯し、鞍袋を手に取って、俺たちは出発した。だが、カヌーを見るとどうにも気に入らない様子だった。一人なら十分だが、二人では安全とは言えそうにないと言う。俺は言った。
「ああ、ご心配なく。俺たち三人でも楽々運んでくれましたから。」
「三人とは?」
「ええと、俺とシッド、それに……それに……それに銃です。そういう意味ですよ。」
「おお」と医者は言った。
しかし、医者は舷に足をかけてカヌーを揺すり、首を振ると、もっと大きなのを探してみると言った。だが、どれも鍵がかかって鎖でつながれていた。それで結局、俺のカヌーを使うことになり、戻ってくるまで待っているか、もっと探しまわるか、あるいは家に帰って皆を驚かせる準備でもしていたらどうかと言われた。俺は嫌だと言った。だから、いかだの見つけ方をきっちり教えてやると、医者は出発していった。
すぐにいい考えが浮かんだ。俺は独りごちた。「もし医者が、ことわざにあるみたいに羊の尻尾を三回振る間にあの足を治せないとしたら? もし三日か四日かかったとしたら? 俺たちはどうする? あいつが秘密をばらすまで、そこでぶらぶらしてるのか? とんでもない。俺ならどうするか、分かってる。待っていて、戻ってきた医者がまた行かなきゃならないなんて言ったら、泳いででも俺もそこへ行く。そいつを捕まえて縛り上げ、閉じ込めて、川を下るんだ。トムの用が済んだら、相応の礼をするか、あり金全部を渡して、岸に上がらせてやる。」
そうして俺は材木の山に忍び込んで一眠りすることにした。次に目を覚ましたときには、太陽はもう頭の真上にあった! 俺は飛び出して医者の家に向かったが、聞けば、夜中のうちに出かけたきり、まだ戻っていないという。なるほど、と俺は思った。こいつはトムにとって相当まずい状況だ。すぐに島へ向かわなきゃ。そうして俺は出発し、角を曲がったところで、サイラス叔父さんの腹に頭から突っ込みそうになった! 叔父さんは言った。
「おお、トムじゃないか! いったいどこに行ってたんだ、この悪ガキめ。」

「どこにも行ってませんよ」と俺は言った。「ただ逃げた黒んぼを探してただけです。俺とシッドとで。」
「一体どこまで行ったんだ?」と叔父さんは言う。「叔母さんがえらく心配していたぞ。」
「心配いりませんよ」と俺は言った。「俺たちは大丈夫でしたから。男たちと犬の後を追ったんですが、追いつけなくて見失っちまったんです。でも、水の上で声が聞こえた気がしたんで、カヌーを手に入れて後を追い、川を渡ったんですが、何も見つかりませんでした。それで岸沿いをぶらぶらしてたら、くたびれてヘトヘトになってしまって。カヌーをつないで眠りこんだら、一時間ほど前まで目が覚めなかったんです。それからここまで漕いできて様子を聞いて、シッドは郵便局で何か聞けることがないか見てます。俺は何か食い物を探しに行こうとしてたところで、それが済んだら家に帰るつもりです。」
そこで俺たちは「シッド」を迎えに郵便局へ向かった。だが、案の定、あいつはそこにいなかった。叔父さんは郵便局で手紙を一通受け取り、俺たちはもうしばらく待ったが、シッドは来なかった。それで叔父さんは、もう行こう、シッドは道草が終わったら歩いて帰るかカヌーで帰るかするだろう、俺たちは馬で帰るんだ、と言った。シッドを待っていたいと言っても聞き入れてもらえず、そんなことをしても無駄だから一緒においで、サリー叔母さんにお前たちが無事な顔を見せてやらなきゃ、と言われた。
家に着くと、サリー叔母さんは俺の顔を見て大喜びで、笑ったり泣いたりしながら俺を抱きしめ、いつものようにちっとも痛くないお仕置きをくれた。シッドが帰ってきたら同じ目にあわせてやるとも言っていた。
家の中は昼飯を食べに来た農夫とその女房たちでごった返していて、これほどやかましいおしゃべりは聞いたことがなかった。中でも最悪なのがホッチキス婆さんで、その舌は片時も休むことがなかった。婆さんは言った。
「いやはや、フェルプスさん、あたしゃあの小屋を隅から隅までひっくり返して見たけどね、あの黒んぼは気が狂ってたに違いないよ。あたしゃダムレルさんに言ったんだ。言ったよねえ、ダムレルさん? あの男は狂ってるってね。あたしゃそう言ったんだ。あんたたちも聞いたろ。あいつは狂ってるってね。何もかもがその証拠だよ。あの砥石を見てみなってんだ。まともな人間があんな気違いじみたことを砥石に書きなぐるもんかい? ここで誰やらさんが悲嘆にくれただの、ここで誰やらさんが三十七年も辛抱しただの、誰それさんの非嫡出子だの、くだらないことばっかりさ。まったくの狂人だよ。最初からそう言ってたし、途中でもそう言ったし、今だって、いつだってそう言うよ。あの黒んぼは狂ってる。ネブカドネザル王みたいにイカれてるんだってね」[訳注:ネブカドネザル二世。旧約聖書に登場するバビロニアの王。神の怒りに触れ、七年間狂気のうちに獣のように暮らしたとされる]

「それにあの布切れでできた梯子も見てよ、ホッチキスさん」とダムレル婆さんが言った。「一体全体、あんなものが何に必要だったのかしらねえ。」
「それこそ、あたしゃたった今、アターバックさんに言ってたことだよ。本人に聞いてみな。ねえ、あの布の梯子を見てみなってね。そうさ、見てみなってんだ。いったい何に使うつもりだったのかねえってね。ねえ、ホッチキスさん、ねえ。」
「それにしても、どうやってあの砥石を小屋の中に入れたんだい? それに、あの穴を掘ったのは誰なんだい? それから。」
「まったくその通りだよ、ペンロッドさん! あたしが言ってたのはね――そこの糖蜜の皿を回してくれないかね? ――あたしゃちょうど今、ダンラップさんに言ってたんだよ。どうやってあの砥石を中に入れたのかねえって。手助けなしでだよ、いいかい、手助けなしで! そこが問題なんだよ。とんでもない。手助けはあったんだ。それも大勢のね。あの黒んぼを手伝ったやつが十人はいるね。あたしに言わせりゃ、この屋敷の黒んぼを片っ端からひっぱたいてでも、誰がやったか吐かせるけどね。それにだね。」
「十人だって! 四十人いたって、あんなこと全部はできやしないよ。あのテーブルナイフのノコギリやらを見てみな、どれだけ手間がかかってるか。あれで切り落とされたベッドの脚を見てみな、六人がかりで一週間はかかる仕事だ。ベッドの上の藁でできた黒んぼの人形も見てみな。それから。」
「まったくおっしゃる通りですよ、ハイタワーさん! あたしがフェルプスさんご本人に言ってたこととそっくりだ。どう思います、ホッチキスさん、ってね。何のことです、フェルプスさん、ってあたしゃ言ったよ。あんなふうに切り落とされたベッドの脚のことですよ、ってね。どう思うかって? あたしに言わせりゃ、あれがひとりでに切れたわけがない。誰かが切ったんだ。それが、あたしの意見だよ。受け入れようが受け入れまいが、たいした意見じゃないかもしれんが、これがね、あたしの意見なんだ。もっといい意見があるなら、どうぞご自由にってんだ。あたしゃダンラップさんに言ったんだよ。」
「いやまったく、フェルプスさん、四週間も毎晩、家一軒分の黒んぼが入り込んでなきゃ、あんな仕事はできやしないよ。あのシャツを見てみな、隅から隅まで血で書かれたアフリカの秘密の文字でびっしりだ! きっと大勢でずっと書き続けてたに違いない。まったく、二ドル払ってでも誰かに読んでもらいたいもんだ。それを書いた黒んぼどもときたら、あたしなら引っ捕らえて鞭打ちにしてやるところだが。」
「手伝った人間ですって、マーブルズさん! まあ、少し前からこの家にいらっしゃったら、きっとそう思われるでしょうね。だって、連中は手の届くものは何でも盗んでいったんですよ。それも、あたしたちが四六時中見張っていたっていうのに。あのシャツだって、物干し綱からかっさらっていったんです! それに、布の梯子を作ったシーツなんて、一体何回盗まれなかったことか。それから小麦粉に、ろうそくに、燭台に、スプーンに、古い湯たんぽに、今じゃ思い出せないほどのものを千も。それに、あたしの新しい更紗のドレスまで。あたしとサイラスと、うちのシッドとトムが昼も夜もずっと見張ってたって言ってるでしょう。なのに、誰一人としてそいつらの姿も気配も音も、何一つ掴めなかったんです。そして最後の最後、ご覧なさいよ、まんまとあたしたちの鼻先をすり抜けて、あたしたちを出し抜いて、それだけじゃなくインディアン準州の強盗どもまで出し抜いて、あの黒んぼをまんまと連れて逃げおおせたんです。しかも、十六人の男と二十二匹の犬がすぐそこまで迫っていたっていうのに! 言っときますけど、こんな話、聞いたこともありませんよ。まったく、幽霊だってこれほどうまくはやるまいし、もっと賢くもできなかったでしょう。きっと幽霊だったに違いありませんよ。だって、うちの犬たちのことはご存じでしょう、あれ以上の犬はいませんからね。なのに、その犬たちが一度もやつの跡を追えなかったんですから! さあ、説明できるもんならしてみな! 誰か!」
「いや、こいつはたまげた。」
「まったく、信じられない。」
「神に誓って、わしなら。」
「家泥棒でもあるなんて。」
「なんてこった、そんな家に住むなんて怖くてできやしない。」
「住むのが怖い! まあ、リッジウェイさん、あたしなんて怖くて、ベッドに入るのも、起きるのも、横になるのも、座るのも、ろくにできなかったんですよ。だって、連中は――ああ、まったく、昨日の夜中、あたしがどんなに狼狽してたか、お察しがつくでしょう。あたし、家族の誰かが盗まれやしないかと本気で心配したんですから! もう、まともな判断力なんてなくなってたんです。昼間の今考えれば馬鹿みたいですけどね。でも、こう思ったんですよ。かわいそうな二人の息子が、二階のあの寂しい部屋で眠っている。神に誓って、あたしは心配で心配で、こっそり二階へ上がって、部屋に鍵をかけてしまったんです! 本当にそうしたんですよ。誰だってそうするでしょう。だって、ああいうふうに怖くなると、それがどんどん続いて、どんどんひどくなって、頭が混乱してきて、わけのわからないことをしでかすようになるでしょう。そうしているうちに、ふと考えるんですよ。もしあたしが男の子で、あんな二階の部屋にいて、ドアに鍵がかかってなくて、そしたら――」彼女は口をつぐみ、不思議そうな顔をした。そしてゆっくりと首を巡らせ、その目が俺を捉えた――俺は立ち上がって散歩に出かけた。
俺は独りごちた。今朝、俺たちがどうしてあの部屋にいなかったのか、外に出て少し頭を整理したほうがうまく説明できるだろう。俺はそうした。だが、遠くへは行けなかった。さもないと叔母さんが俺を呼び戻しに来るだろうから。やがて日が暮れる頃、人々は皆帰っていった。そこで俺は家に入り、叔母さんにこう話した。銃声と騒ぎで俺と「シッド」は目を覚ました、ドアには鍵がかかっていて、面白い見物ができると思ったから、避雷針を伝って降りたんだ、二人とも少し怪我をしたから、もう二度とあんなことはごめんだ、と。それから続けて、前にサイラス叔父さんに話したことを全部話した。すると叔母さんは、俺たちを許してくれると言った。たぶん、それでよかったんだろうし、男の子ならまあそんなもんだろう、叔母さんの知る限り、男の子なんてみんな向こう見ずな連中だから、と言った。だから、結局誰も怪我をしなかったんだし、過ぎ去ったことをくよくよするより、俺たちが生きて元気で、まだそばにいてくれることに感謝して過ごしたほうがいいんだろう、と判断したようだった。それから叔母さんは俺にキスをし、頭を撫でて、何やら物思いに沈んだ。そしてすぐに、はっと立ち上がって言った。
「あらまあ、もうすぐ夜だっていうのに、シッドがまだ帰ってこないじゃないの! あの子に一体何があったのかしら?」
俺は好機と見て、さっと立ち上がって言った。
「俺、すぐに町へ行って連れてきます。」
「だめよ」と叔母さんは言った。「あんたはここにいなさい。一度にいなくなるのは一人で十分。夕食までに戻らなかったら、叔父さんに行ってもらうから。」
結局、シッドは夕食の時間になっても戻ってこなかった。だから夕食のすぐ後、叔父さんが出かけていった。
叔父さんが戻ってきたのは十時頃で、少し不安そうな顔をしていた。トムの足取りはつかめなかったのだ。サリー叔母さんはかなり心配していたが、サイラス叔父さんは心配する必要はないと言った。男の子はそんなものだ、明日の朝にはきっと元気に戻ってくるさ、と。それで叔母さんも納得せざるを得なかった。それでも、しばらくは起きて待っている、あの子が見つけられるように明かりを灯しておく、と言った。

そして俺が寝に上がると、叔母さんもろうそくを持ってついてきて、俺を布団に寝かしつけ、あまりに優しく母親のように世話をしてくれるものだから、俺は自分が卑劣な人間に思えて、叔母さんの顔をまともに見られなかった。叔母さんはベッドに腰掛けて、長いこと俺と話をした。シッドがどれだけ素晴らしい子か、いつまでも話し足りないようだった。そして時々、あの子が道に迷ったり、怪我をしたり、もしかしたら溺れたりしていないか、今この瞬間もどこかで苦しんでいたり、死んでいたりして、助けてくれる人もそばにいないんじゃないかと、何度も俺に尋ねた。そうして涙が静かにこぼれ落ちるのだった。俺は、シッドは大丈夫、明日の朝には必ず帰ってくる、と叔母さんに言った。すると叔母さんは俺の手を握りしめたり、キスをしたりして、もう一度言って、何度も言って、とせがんだ。そうすると気が休まる、自分はとても辛いのだ、と。そして叔母さんが部屋を出ていくとき、俺の目をじっと優しく見つめて、こう言った。
「ドアに鍵はかけないよ、トム。窓も避雷針もある。でも、いい子にしてるだろう? 行ったりしないよね? あたしのために。」
神様はご存じだ。俺はトムのことが心配で、ひどく行きたかったし、行くつもりでいた。だが、あんなことを言われた後では、たとえ王国をもらうと言われても、行く気にはなれなかった。
だが、叔母さんのこともトムのことも気にかかり、俺はひどく寝苦しい夜を過ごした。夜中に二度、避雷針を伝って降り、家の正面に回ってみると、叔母さんが窓辺でろうそくのそばに座り、目に涙を浮かべて道をじっと見つめているのが見えた。何かしてやりたかったが、俺にできることは何もなかった。ただ、もう二度と叔母さんを悲しませるようなことはしないと誓うだけだった。そして三度目に夜明けに目を覚まし、下に滑り降りると、叔母さんはまだそこにいた。ろうそくは消えかかり、白髪頭を手に預け、眠り込んでいた。
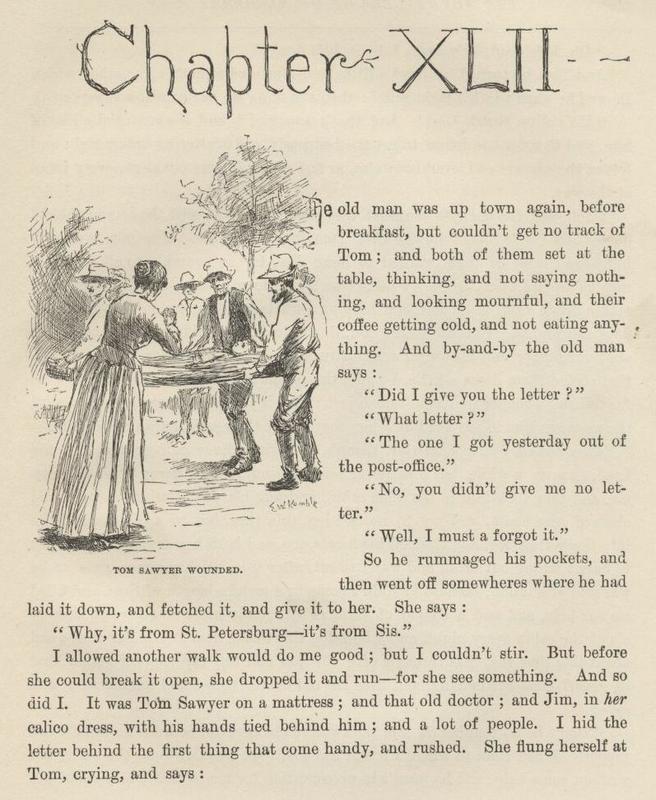
第四十二章
叔父さんは朝食前にまた町へ出かけたが、トムの足取りはつかめなかった。二人は食卓で押し黙って物思いにふけり、悲しげな顔で、コーヒーは冷め、何も口にしていなかった。やがて叔父さんが言った。
「手紙は渡したかな?」
「何の手紙?」
「昨日、郵便局で受け取ったやつだ。」
「いいえ、手紙なんて受け取ってないわ。」
「そうか、忘れていたようだ。」
叔父さんはポケットを探り、それからどこかへ置き忘れたらしく、取りに行って彼女に手渡した。彼女は言った。
「あら、セント・ピーターズバーグからだわ。お姉さんからよ。」
もう一度散歩に出たほうがよさそうだと俺は思ったが、身動き一つできなかった。だが、彼女が封を切る前に、手紙を落として走り出した。何かが見えたのだ。俺にも見えた。マットレスに乗せられたトム・ソーヤー、あの年寄りの医者、そして彼女の更紗のドレスを着て後ろ手に縛られたジム、それに大勢の人々だった。俺は手近なものの後ろに手紙を隠し、駆け出した。彼女は泣きながらトムに身を投げ出し、言った。
「ああ、死んでる、死んでるわ、きっと死んでるんだわ!」
するとトムが少し頭を動かし、何やらぶつぶつと呟いた。正気でないことがわかる。彼女は両手を上げて言った。
「生きてるわ、神様ありがとう! それで十分よ!」そして彼にさっとキスをすると、ベッドの用意をするために家へと飛んで帰り、道すがら黒んぼたちや他の皆に、舌の回る限り早口で、あれこれと指図を飛ばしていた。
俺は男たちの後について行き、ジムをどうするのか見届けることにした。年寄りの医者とサイラス叔父さんはトムの後を追って家に入った。男たちはひどく腹を立てており、中にはジムを吊し首にして、この辺りの他の黒んぼたちへの見せしめにすべきだと言う者もいた。ジムみたいに逃げようとしたり、大騒ぎを起こして一家を何日も夜も昼も死ぬほど怖がらせたりしないように、というわけだ。だが、他の者たちは、やめろ、そんなことをしても何にもならない、あいつは俺たちの黒んぼじゃない、持ち主が現れて弁償させられるのがオチだ、と言った。それで連中も少しは頭が冷えたようだった。というのも、何か悪さをした黒んぼを吊るせといつも一番騒ぎ立てる連中というのは、その黒んぼで鬱憤を晴らした後で、その代金を払うことには一番熱心でない連中だからだ。
それでも連中はジムをさんざん罵り、時々頭を二、三発殴りつけたが、ジムは何も言わず、俺のことも知らないふりをしていた。連中はジムを前と同じ小屋に連れて行き、自分の服を着せ、再び鎖につないだ。今度はベッドの脚ではなく、床の丸太に打ち込まれた大きな鎹にだ。両手も両足も鎖でつながれ、これからは持ち主が現れるか、一定期間内に現れなければ競売にかけられるまで、パンと水以外は何も与えられないことになった。連中は俺たちの掘った穴を埋め、毎晩銃を持った農夫が二人、小屋の周りを見張りに立ち、昼間はブルドッグを戸口につないでおくべきだと言った。この頃には仕事も終わり、別れの挨拶代わりに一通り悪態をついて引き上げようとしていた。そこへ年寄りの医者がやって来て、様子を見て言った。
「必要以上に手荒な真似はしないでやってくれ。悪い黒んぼじゃない。あの子を見つけた場所に着いたとき、助けなしでは弾丸を取り出せないとわかった。だが、助けを呼びに行くためにあの子を置いていけるような状態ではなかった。容体は少しずつ悪化していき、しばらくすると錯乱して、私をそばに寄せ付けようともしなくなった。私のいかだに印をつけたら殺すだの、そんな類のめちゃくちゃな馬鹿げたことを言うばかりで、どうにもならないとわかった。そこで私は言った、何とかして助けが必要だと。そう口にした途端、どこからかこの黒んぼが這い出してきて、手伝うと言った。そして、その通りにしてくれた。それも見事にだ。もちろん、逃亡中の黒んぼに違いないと見当はついたが、どうしようもなかった! 私はそこから一日中、そして一晩中、びた一文動けなかった。難儀なことだったよ、まったく! 悪寒に苦しむ患者が二人いて、もちろん町へ駆けつけて診てやりたかったが、できなかった。黒んぼが逃げでもしたら、私の責任になるからだ。だというのに、声をかけられるほど近くを通る小舟は一艘も来なかった。だから今朝の夜明けまで、そこに釘付けにされていなければならなかった。これほど優れた看護人、これほど忠実な黒んぼは見たことがない。それも、自分の自由を危険にさらしながらやってくれたんだ。すっかり疲れ切っていたし、近頃ひどくこき使われていたことも一目瞭然だった。私はその黒んぼが気に入った。諸君、あんな黒んぼなら千ドルの価値はある。それに、親切に扱ってやるべきだ。私には必要なものはすべて揃っていたし、あの子は家にいるのと同じくらい――いや、静かだったから、むしろそれ以上に――具合はよかった。だが、私はそこにいた。二人を抱えて、今朝の夜明けまでそこにいなければならなかった。その時、小舟に乗った男たちが通りかかり、幸運にも黒んぼは寝台のそばで膝に頭をもたせ、ぐっすり眠り込んでいた。だから私は静かに手招きし、男たちは忍び寄って彼を捕まえ、何が起きたかわからないうちに縛り上げてくれた。何の問題もなかった。あの子も夢うつつのような眠りの中にいたので、我々は櫂に布を巻き、いかだをつないで、とても静かにうまくこちらまで曳航してきた。黒んぼは最初から最後まで、少しも騒がず、一言も発しなかった。悪い黒んぼじゃないよ、諸君。それが私の考えだ。」

誰かが言った。
「なるほど、それは結構な話ですな、先生。そう言わざるを得ません。」
すると他の者たちも少し態度を和らげた。俺はジムのためにあんなに骨を折ってくれた年寄りの医者に心から感謝した。そして、俺の目に狂いはなかったことも嬉しかった。最初に会った時から、あの医者は善良な心を持ったいい人だと思っていたからだ。それから皆、ジムの行いは実に立派で、何らかの配慮と褒美を受けるに値するという意見で一致した。そこで彼らは一人残らず、心からきっぱりと、もうジムを罵らないと約束した。
それから彼らは出て行き、ジムを閉じ込めた。俺は、鎖を一つか二つ外してやるとか、パンと水に肉と野菜をつけてやるとか、誰かが言い出すのを期待したが、誰もそんなことは考えなかった。俺が口を出すのは得策ではないと思ったが、目の前に迫っている難局を乗り越えたら――つまり、逃げた黒んぼを探して俺とシッドがあの忌々しい夜を漕ぎ回った話をしたときに、シッドが撃たれたことを言い忘れたのはどうしてかという説明のことだが――何とかして医者の話をサリー叔母さんの耳に入れようと心に決めた。
だが、時間はたっぷりあった。サリー叔母さんは昼も夜も病室に付きっきりで、サイラス叔父さんがうろついているのを見かけるたびに、俺は彼を避けていた。
翌朝、トムの具合がずっと良くなったと聞いた。サリー叔母さんは仮眠を取りに行ったそうだ。そこで俺はこっそり病室へ向かった。もしトムが起きていたら、家族に聞かせても通用するような作り話をでっち上げられるだろうと思った。だが、彼は眠っていた。それも、とても安らかに。顔色も、来た時のような燃えるような赤みはなく、青白かった。俺は腰を下ろし、彼が目覚めるのを待った。三十分ほどすると、サリー叔母さんがすべるように入ってきた。俺はまたしても窮地に立たされた! 彼女は静かにするようにと身振りで示し、俺の隣に座って囁き始めた。もうみんなで喜べるわ、症状はすべて上々で、もうずっとあんなふうに眠っていて、見る見る顔色も良くなり、安らかになっている、十中八九、正気で目覚めるだろう、と。
俺たちはそこに座って見守っていた。やがてトムが少し身じろぎし、ごく自然に目を開け、あたりを見回して言った。
「やあ! なんだ、家にいるじゃないか! どうしてだ? いかだはどこ?」
「大丈夫だよ」と俺は言った。
「ジムは?」
「同じくだ」と俺は言ったが、あまり威勢よくは言えなかった。だが彼は気づかず、こう続けた。
「よし! 最高だ! これで俺たちは大丈夫、安全だ! 叔母さんには話したかい?」
俺は「うん」と言おうとしたが、彼女が割って入った。「何のこと、シッド?」
「何って、ことの成り行き全部さ。」
「何のこと全部?」
「何って、全部だよ。一つしかないじゃないか。俺たちがどうやってあの逃げた黒んぼを自由にしたか――俺とトムとで。」
「まあ! 逃げ―― この子はいったい何を言ってるんだい! ああ、また頭がおかしくなっちまった!」
「おかしくなんてなってないよ。自分が何を言ってるか、ちゃんとわかってる。俺たちが彼を自由にしたんだ――俺とトムとで。そう計画して、実行したんだ。それも見事にね」彼は口火を切った。叔母さんは彼を止めようともせず、ただ座ってじっと見つめ、彼がしゃべり続けるのを許していた。俺が口を挟んでも無駄だとわかった。「だってさ、叔母さん、ものすごい手間がかかったんだよ。何週間も――毎晩、何時間も、みんなが寝てる間にね。ろうそくも、シーツも、シャツも、あんたのドレスも、スプーンも、ブリキの皿も、テーブルナイフも、湯たんぽも、砥石も、小麦粉も、もう数えきれないくらいいろんなものを盗まなきゃならなかった。ノコギリやペンや碑文や、あれやこれやを作るのがどれだけ大変だったか、想像もつかないだろうな。それに、どれだけ楽しかったかなんて、半分も想像できないだろうよ。棺桶やら何やらの絵を描いたり、強盗からの匿名の脅迫状を作ったり、避雷針を上り下りしたり、小屋に穴を掘ったり、縄梯子を作ってパイに詰めて送ったり、スプーンなんかをあんたのエプロンのポケットに入れて送ったり――」
「なんてこと!」
「――それから、ジムの仲間として、小屋をネズミやヘビなんかでいっぱいにしたんだ。そしたらあんたがトムの帽子に入ったバターのせいで、あいつをここに長々と引き止めるもんだから、計画が台無しになるところだった。俺たちが小屋から出る前に男たちが来ちまったから、大急ぎで逃げなきゃならなかった。連中は物音を聞きつけて俺たちに発砲し、俺も一発もらった。俺たちは小道から外れて連中をやり過ごし、犬が来たときには俺たちには興味を示さず、一番騒がしい方へ向かっていった。俺たちはカヌーを手に入れ、いかだに向かって、それで万事うまくいった。ジムは自由の身になったんだ。全部俺たちだけでやったんだ。すごかっただろ、叔母さん!」
「まあ、生まれてこの方、こんな話は聞いたことがないよ! じゃあ、あんたたちだったんだね、この悪ガキどもが、この大騒動を引き起こして、みんなの頭をすっかり混乱させて、あたしたちを死ぬほど怖がらせたのは。今すぐにでも、あんたたちをこらしめてやりたいくらいだよ、本気でね。考えてもごらんよ、あたしが毎晩毎晩――とにかく、一度元気になってみな、この悪党め。きっと二人とも、ひどい目にあわせてやるからね!」
だがトムは、あまりに誇らしくて嬉しくて、もう我慢できなかった。彼の舌は回りっぱなしだった。叔母さんも口を挟み、ずっと火を噴くような勢いで、二人同時にまくしたてた。まるで猫の集会みたいだった。そして叔母さんは言った。
「いいかい、今のうちに存分に楽しんでおきな。言っとくけど、もしまたあいつにちょっかいを出してるのを見つけたら――」
「誰にちょっかいを?」トムは微笑みを消し、驚いた顔で言った。
「誰にって? 決まってるじゃないか、あの逃げた黒んぼにだよ。他に誰がいるっていうんだい?」
トムは真剣な顔で俺を見て、言った。
「トム、あいつは大丈夫だって言わなかったか? 逃げられなかったのか?」
「あいつが?」とサリー叔母さんは言った。「あの逃げた黒んぼのこと? まさか。無事に取り戻されて、またあの小屋にいるよ。パンと水だけで、鎖でがんじがらめにされてね。持ち主が現れるか、売られるかするまで!」

トムはベッドの上でむっくと起き上がった。目は熱を帯び、鼻の穴は魚のエラのように開いたり閉じたりしていた。そして俺に向かって叫んだ。
「あいつを閉じ込めておく権利なんてない! 行け! 一刻も無駄にするな。あいつを解放しろ! あいつは奴隷じゃない。この地上を歩くどんな生き物と同じくらい自由なんだ!」
「この子はいったい何を言ってるんだい?」
「言ったことは全部本気だよ、サリー叔母さん。誰か行かないなら、俺が行く。俺はずっとあいつを知ってるし、そこのトムだってそうだ。ミス・ワトソンは二ヶ月前に死んだ。彼女はあいつを南部に売ろうとしたことを恥じて、そう言ったんだ。そして、遺言であいつを自由にしたんだ。」
「それじゃあ一体全体、どうしてあんたはあいつを自由にしようとしたんだい? もうとっくに自由だったっていうのに。」
「そりゃあ、なんとも言えない質問だな。いかにも女らしい! なぜって、その冒険がしたかったんだ。そのためなら血の海を首まで浸かってでも――なんてこった、ポリー叔母さん!」
もし彼女がそこにいなかったなら、ちょうどドアの内側に、パイを半分食べた天使みたいに穏やかで満足げな顔で立っていなかったなら、俺はもうどうなってもいい!
サリー叔母さんは彼女に飛びつき、首がもげるほど抱きしめ、泣きじゃくった。俺はベッドの下にちょうどいい隠れ場所を見つけた。どうやら、俺たちにとってはかなりきまりの悪い状況になってきたからだ。俺がこっそり覗いていると、しばらくしてトムのポリー叔母さんは身を振りほどき、そこに立って眼鏡越しにトムを見下ろした。まるで彼を地にめり込ませるかのように。そして言った。
「そうさ、顔をそむけたほうがいい。あたしがあんたなら、そうするね、トム。」
「あらまあ!」とサリー叔母さんは言った。「そんなに変わってしまったかしら? でも、この子はトムじゃないわ、シッドよ。トムは――トムは――あら、トムはどこ? さっきまでここにいたのに。」
「ハック・フィンはどこかってことでしょう! 長年、うちのトムみたいな悪ガキを育ててきたんだもの、一目見ればわかるさ。そんなことにも気づかないなんて、とんだご挨拶だね。ベッドの下から出ておいで、ハック・フィン。」
俺はその通りにした。だが、少しも威勢はよくなかった。
サリー叔母さんは、俺が今まで見た中で一番混乱した顔をしていた。一人を除いては。それは、サイラス叔父さんが入ってきて、ことの次第を全部聞かされた時だった。叔父さんは言ってみれば酔っ払ったみたいになって、その日は一日中何もわからなくなり、その夜の祈祷会で説教をしたのだが、それがとてつもない評判を呼んだ。世界で一番の年寄りでも、その説教を理解できなかっただろうからだ。さて、トムのポリー叔母さんは、俺が誰で何者なのかを全部話した。そして俺も立ち上がって、いかに自分が窮地に陥っていたか、フェルプス夫人が俺をトム・ソーヤーだと勘違いした時――彼女が口を挟んで言った、「あら、気にしないでサリー叔母さんと呼んでちょうだい。もう慣れたし、今さら変える必要もないわ」――サリー叔母さんが俺をトム・ソーヤーだと思った時、俺はそれを受け入れるしかなかったこと、他に道はなかったこと、そしてトムなら気にしないだろうとわかっていたこと、なぜなら謎めいたことが大好きで、それを冒険に変えて大満足するに違いないから、ということを話さなければならなかった。そして、その通りになり、彼はシッドのふりをして、俺のために物事をできるだけ円滑に進めてくれたのだった。
そしてポリー叔母さんは、ミス・ワトソンが遺言でジムを自由にしたというトムの話は本当だと言った。だから、案の定、トム・ソーヤーは、とっくに自由の身になっていた黒んぼを自由にするために、あれだけの手間と面倒をかけたってわけだ! 俺は、その瞬間、その話を聞くまで、彼がどうしてああいう育ち方をしながら、黒んぼを自由にする手助けなんてできたのか、まったく理解できなかった。
さて、ポリー叔母さんの話では、サリー叔母さんからトムとシッドが無事に着いたという手紙が届いた時、彼女は独りごちたそうだ。
「これを見てごらんよ! 予想しておくべきだったわ。あの子を見張りもつけずにあんなふうに行かせてしまうなんて。だから今、あたしは川を千百マイルも延々と下って、あの生き物が今度は何をしでかしているのか突き止めに行かなくちゃならない。あんたからそれについて何の返事ももらえそうにないからね。」
「あら、あなたから何も聞いてないわよ」とサリー叔母さんは言った。
「まあ、不思議だこと! だって、シッドがここにいるなんてどういうことか尋ねる手紙を二度も書いたのよ。」
「あら、受け取ってないわよ、お姉さん。」
ポリー叔母さんはゆっくりと、厳しい顔で振り返り、言った。
「あんた、トム!」
「なんだよ?」と彼は、少し不機嫌そうに言った。
「『なんだよ』じゃないよ、この生意気な子! その手紙を出しなさい。」

「何の手紙?」
「例の手紙だよ。いいかい、もしあたしがあんたを捕まえなきゃならなくなったら――」
「トランクの中だよ。ほら、これでいいだろ。郵便局から取ってきた時のまんまだ。中も見てないし、触ってもいない。でも、面倒なことになるってわかってたから、もしあんたが急いでないなら、俺は――」
「まあ、あんたはお仕置きが必要だね、間違いなくね。それから、あたしが行くって知らせる手紙ももう一通書いたんだ。そして、思うに彼は――」
「いや、それは昨日届いたよ。まだ読んでないけど、大丈夫、それは持ってる。」
二ドル賭けてもいい、持ってないだろう、と言ってやりたかったが、たぶん言わない方が無難だろうと思った。だから俺は何も言わなかった。
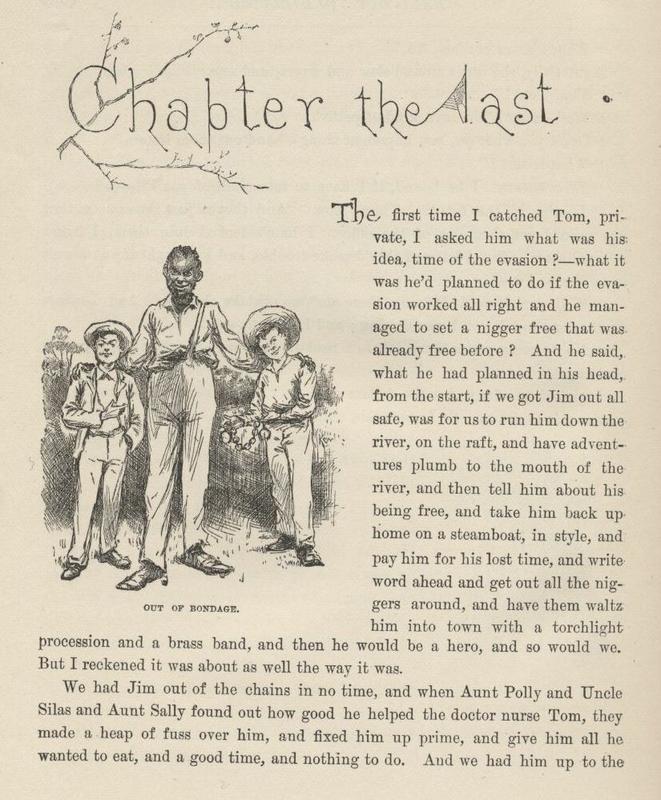
最終章
初めてトムと二人きりになった時、俺は彼に尋ねた。脱走の時の計画は何だったのか? もし脱走がうまくいって、とっくに自由だった黒んぼを自由にするのに成功したら、どうするつもりだったのか? と。すると彼は言った。最初から頭の中で計画していたのは、もしジムを無事に脱出させられたら、いかだで川を下り、河口までずっと冒険を続け、そこで彼に自由の身であることを告げ、蒸気船で堂々と家まで送り返し、失われた時間の埋め合わせに金を払い、先に手紙を書いて近所の黒んぼたちを総動員し、たいまつ行列とブラスバンドで彼を町に迎え入れさせることだった、と。そうすれば彼は英雄になり、俺たちも英雄になる、というわけだ。だが俺は、成り行きは今のままでよかったと思った。
俺たちはすぐにジムを鎖から解放した。ポリー叔母さんとサイラス叔父さん、それにサリー叔母さんは、ジムがどれほど献身的に医者を助けてトムを看護したかを知ると、彼を大いにもてなし、最高の待遇で世話をし、好きなだけ食べ物を与え、楽しい時間を過ごさせ、何もしなくていいようにした。俺たちはジムを病室に連れて行き、大いに語り合った。トムは、俺たちのために辛抱強く囚人でいてくれて、見事にやり遂げてくれた礼として、ジムに四十ドルを渡した。ジムは死ぬほど喜び、声を張り上げて言った。

「どや、ハック、わしが言うたとおりやろ? ジャクソン島で言うたやろ? わしは胸毛が生えとる、そのしるしが何かも言うた。それに、わしは一度金持ちになったことがあって、また金持ちになるんやとも言うた。それが本当になったんや。ほら、この通りや! どや! わしに文句は言わさんで。しるしはしるしなんや、よう覚えときや。わしは、今ここに立っとるのと同じくらいはっきりと、また金持ちになるってわかっとったんや!」
それからトムは延々としゃべり続け、こう言った。今度の夜にでも三人でここを抜け出して、旅支度を整え、一、二週間ほどインディアン準州へ行って、インディアンたちと胸のすくような冒険をしようじゃないか、と。俺は、いいぜ、それで結構だ、と言った。だが、旅支度を買う金がない。家からももらえそうにない。今頃パップが戻ってきて、サッチャー判事から金を全部せしめて、飲み尽くしてしまっただろうから。
「いや、そんなことはない」とトムは言った。「金はまだ全部そこにある。六千ドル以上もだ。それに、あんたのパップはあれ以来一度も戻ってきてない。少なくとも、俺がこっちに来た時にはいなかった。」
ジムが、どこか厳かに言った。
「あいつはもう戻ってこんで、ハック。」
俺は言った。
「どうしてだい、ジム?」
「理由はええんや、ハック。けど、あいつはもう戻ってこん。」
だが、俺がしつこく聞くと、ついに彼は言った。
「川を流れとった家を覚えとるか? 中に男が一人、布をかぶせられておったやろ。わしが入って行って布をめくって、お前を中に入れんかった。なあ、お前はもう金をもらえるで。あれがそうやったんや。」
トムはもうすっかり元気になり、首から時計代わりに弾丸を懐中時計の鎖でぶら下げて、しょっちゅう時間を確かめている。というわけで、もう書くことは何もない。俺はそれが心底嬉しい。本を一冊書くのがこれほど面倒なことだと知っていたら、手を出したりはしなかっただろうし、もう二度とやるつもりはない。だが俺は、他のやつらより先にインディアン準州へずらからなくちゃならない。サリー叔母さんが俺を養子にして「文明人」にしようとしてるからだ。そんなのはごめんだ。前にもう経験してる。
おわり。あんたらの友達、ハック・フィンより。


