シャーロック・ホームズは、ある朝、私たちが朝食の席についたとき、こう言った。「ワトソン、申し訳ないが、私は出かけなければならない。」
「出かける? どこへ?」
「ダートムーア、キングズ・パイランドへだ。」
私は驚かなかった。実のところ、彼がまだこの異常な事件に関わっていないことの方が不思議なくらいだった。この話題はイングランド中で話の種になっていたのだ。私の同伴者は一日中、うなだれて眉間にしわを寄せ、最もきつい黒タバコを詰めては吸い、私の問いかけや話しかけにもまったく耳を貸さなかった。新聞の号外が次々と届けられたが、ざっと目を通しただけで隅に放り投げてしまった。しかし、彼が黙っている間も、私は彼が何について考え込んでいるのか、よく分かっていた。世間を騒がせ、彼の分析力を駆り立てるに足る問題はただ一つ、ウェセックス・カップの本命馬が不可解に姿を消し、その調教師が悲劇的に殺された事件だった。だから彼が突然、事件現場へ行くと告げたとき、それは私が予想し、かつ望んでいたことに他ならなかった。
「もし邪魔でなければ、私も一緒に行きたいのだが」と私は言った。
「ワトソン、君が来てくれることは実にありがたい。君の時間も決して無駄にはならないと思う。この事件には、きわめて特異なものになりそうな要素がある。ちょうどパディントン発の列車に間に合いそうだし、道中でもう少し詳しく話そう。君のすばらしい双眼鏡も持ってきてくれるとありがたい。」
こうして、ひとしきり後、私はエクセター行きの一等車の隅に座っていた。シャーロック・ホームズは、耳当て付きの旅行帽から精悍な顔をのぞかせ、パディントン駅で手に入れた新聞の束に目を通している。私たちはすでにレディングを遠く後にし、彼は最後の新聞を座席の下に押し込み、私に葉巻入れを差し出した。
「順調だ」と彼は窓の外に目をやり、時計を見ながら言った。「今の時速は五十三マイル半だ。」
「四分の一マイルごとの標識は見ていなかった」と私は言った。
「私もだ。しかし、この路線の電信柱は六十ヤードごとに立っているから、計算は簡単だ。さて、君はジョン・ストレイカー殺害とシルヴァー・ブレイズ失踪の件について調べたか?」
「『テレグラフ』紙や『クロニクル』紙を読んだよ。」
「この事件は、新たな証拠を得るよりも、細部をふるい分けるために推理力を使うべき場合だ。あまりにも異例で、完全で、多くの人間にとって個人的な重要性があるため、推測と憶測と仮説の洪水に見舞われている。問題は、事実という枠組み――絶対的に否定できない事実――を、理論家や記者の装飾から切り離すことにある。そして、確かな基盤を得た上で、どんな推論ができるか、この謎の核心がどこにあるかを見極めるのが我々の務めだ。火曜の晩、馬主のロス大佐と、事件を担当しているグレゴリー警部の両名から、協力を求める電報を受け取った。」
「火曜の晩だって!」と私は叫んだ。「今日は木曜の朝じゃないか。なぜ昨日行かなかったんだ?」
「実は、ワトソン、私は判断を誤った――これは、君の記録を通して私を知る人が思う以上に、よくあることなのだ。イングランドで最も有名な馬が、ダートムーア北部のような人口の少ない場所で長く隠し通せるとは、どうにも信じがたかった。昨日は一日中、もう見つかったという知らせが来るのを待っていて、その誘拐犯こそがジョン・ストレイカー殺害の犯人だろうと思っていた。しかし、翌朝になっても、若いフィッツロイ・シンプソンの逮捕以外、何も進展がないと知り、私が動くべき時だと感じた。ただ、昨日は無駄になったわけではないとも思っている。」
「つまり、何か理論を立てたのか?」
「少なくとも、事件の本質的な事実はつかんだ。君にそれを列挙しよう。事件を他人に説明するほど、頭が整理されることはないし、君に協力してもらう以上、出発点を示すのは当然だ。」
私はクッションにもたれ、葉巻をくゆらせながら聞いた。ホームズは前のめりになり、左手のひらに長い細い人差し指で要点を数えながら、事件の概要を語り始めた。
「シルヴァー・ブレイズはアイソノミー系統の馬で、名高い先祖に劣らぬ輝かしい戦績を持っている。今五歳、ロス大佐のもとで次々と競馬の賞をもたらしてきた。事件の時点でウェセックス・カップの大本命、単勝オッズは三倍強だ。競馬ファンから常に絶大な支持を受け、これまで一度も期待を裏切っていないから、そのオッズでも巨額の賭け金が集まっていた。つまり、来週火曜のレースでシルヴァー・ブレイズが出場しないことを強く望む者が大勢いたわけだ。
「当然、キングズ・パイランドの大佐の厩舎では最大限の警備が敷かれた。調教師ジョン・ストレイカーは、かつてロス大佐の騎手で、体重が増えて引退後、五年間騎手、七年間調教師として仕え、誠実熱心な人物だ。その下には三人の若者がおり、厩舎には全四頭しかいない。毎晩一人が厩舎で当直、他は屋根裏で寝る。三人とも素行は申し分ない。ストレイカーは既婚で、厩舎から約二百ヤード離れた小さな住宅に住む。子どもはおらず、女中が一人、生活も安定している。周囲は寂しい田舎だが、北へ半マイルほど行くと、タヴィストックの業者が病人や空気の良いダートムーアを楽しみたい人向けに建てた小さな住宅群がある。タヴィストックの町は西へ二マイル、さらに荒野を越えて二マイル先には、サイラス・ブラウンが管理するメイプルトン卿の大規模な調教所がある。他の方向は一面の荒れ地で、時折ジプシーがさまようだけだ。これが事件前夜、月曜夜の状況だった。
「その晩、いつも通り馬は運動と給水を終え、九時に厩舎は施錠された。二人の若者は調教師の家に歩いて行き、台所で夕食を取り、もう一人のネッド・ハンターは厩舎の見張りを続けた。九時過ぎ、女中のイーディス・バクスターがハンターの夕食――カレー羊肉――を厩舎に運んだ。飲み物は持たず、厩舎には水道があり、当番は水以外飲んではならない決まりだった。道は荒野を横切るので真っ暗、彼女はランタンを携えていた。
「イーディス・バクスターが厩舎まで三十ヤードの所で、闇から男が現れ、立ち止まるよう呼びかけた。男がランタンの明かりに入ると、上品な身なり、グレイのツイードのスーツ、布の帽子、ゲートルを着け、先に丸い重い杖を持っていた。ただし、顔の異様な青白さと神経質な様子が強く印象に残ったという。年齢は三十をいくぶん超えているようだった。
『ここがどこかご存じですか?』と彼は尋ねた。『あやうく荒野で野宿するところでしたが、あなたのランタンの光が見えたので。』
『すぐそこのキングズ・パイランドの調教厩舎ですよ』と彼女は答えた。
『おお、それは運が良い!』と彼は叫んだ。『毎晩、厩舎には少年が一人で寝ていると聞きました。今あなたが持っているのは、その子の夕食でしょう。新しいドレスの代金を稼ぐ気はありませんか?』と言い、ベストのポケットから折りたたんだ白い紙片を取り出した。『今晩、この小包を少年に渡してくれたら、お金で買えるいちばん素敵なドレスをあげましょう。』
「彼女は男の切迫した様子に怯え、窓まで走って行き、いつものように料理を手渡した。すでに窓は開いており、中ではハンターが小さなテーブルに座っていた。彼女が出来事を話し始めると、男が再びやって来た。
『こんばんは』と彼は窓越しに言った。『ちょっとお話がしたかった。』彼女の証言によれば、そのとき彼の握った手から紙包みの端がはみ出ていたのに気づいた。
『何の用だ?』と少年が尋ねた。
『君の懐が潤うかもしれない話だよ。君のところはウェセックス・カップに二頭――シルヴァー・ブレイズとバイアードを出すね。正直な話をしてくれたら損はさせない。バイアードなら五ハロンで百ヤード差をつけられると聞いたが、本当に厩舎はそちらに賭けているのか?』
『くそっ、またあの手合いか!』と少年は怒鳴った。『キングズ・パイランド流のおもてなしをしてやる!』彼は立ち上がり、犬を解きに厩舎を駆け抜けた。女中は家へ逃げ帰ったが、ふり返ると男はまだ窓越しに身を乗り出していた。しかし、ハンターが猟犬を連れて外に出ると、男は消えており、建物の周囲を走り回っても手がかりはなかった。」
「ちょっと待ってくれ」と私は尋ねた。「犬を連れて少年が外に飛び出したとき、ドアは開け放しだったのか?」
「素晴らしい、ワトソン、その点は私も特に重要視して、昨日ダートムーアに特別な電報を送って確認した。少年は出る前に鍵をかけている。窓は、さらに言えば、大人が通れるほど大きくはなかった。
「ハンターは仲間の馬丁が戻るのを待って、調教師に出来事を伝えた。ストレイカーは話を聞いて興奮したが、本当の意味では事態の重大さを理解していなかったようだ。しかし漠然と不安が残り、夜中の一時、奥さんが目を覚ますと、彼は服を着ていた。問いただすと、馬のことで気がかりで眠れない、様子を見に厩舎へ行くという。奥さんは雨音が窓に当たるのを聞き、引き留めたが、彼は大きなマッキントッシュを着て家を出て行った。
「ストレイカー夫人は朝七時に目覚め、夫がまだ戻っていないことに気づいた。大急ぎで着替え、女中を呼び、厩舎へ向かった。ドアは開いており、中ではハンターが椅子にうずくまって、完全な昏睡状態だった。本命馬の馬房は空で、調教師もいなかった。
「屋根裏で寝ていた二人の若者もすぐに起こされたが、二人とも熟睡していて何も聞かなかった。ハンターは明らかに何らかの強い薬物の影響下にあり、話もできなかったので、休ませておき、残りの二人と女中らは失踪者の捜索に出た。調教師が運動のため早朝に馬を連れ出したのではという希望もあったが、家の近くの丘に登ると、荒野一帯を見渡しても馬の影はなく、かわりに惨劇の前兆を目にした。
「厩舎から四分の一マイルほどのところ、ジョン・ストレイカーのオーバーコートがハリエニシダの茂みに引っかかっていた。そのすぐ先のくぼ地の底で、不運な調教師の死体が発見された。頭は何か重い凶器で激しく砕かれ、腿には鋭利な刃物による長くきれいな切り傷があった。ただ、ストレイカーは必死に抵抗した形跡があり、右手には血まみれの小ナイフ、左手には赤と黒のシルクのネクタイを握っていた。これは前夜厩舎に現れた男が着けていたものだと女中が証言した。
「ハンターも昏睡から目を覚ますと、そのネクタイが例の男のものだと断言した。同時に、あの男が窓辺で自分のカレー羊肉に薬を混ぜ、見張りを無力化したのだと確信している。
「失踪馬については、事件現場のぬかるみの中に馬がいた証拠が明確に残っていた。しかしそれきり馬はいなくなり、懸賞金もかけられ、ダートムーア中のジプシーが目を光らせているが、いまだ手がかりはない。分析の結果、馬丁が残した夕食には目に見える量の粉末アヘンが混入していたが、家で同じ料理を食べた者には何の影響もなかった。
「以上が憶測を排した事件の主要事実だ。次に、警察の対応をまとめる。
「担当のグレゴリー警部は非常に有能な人物だ。もし想像力があれば警察界で大成しただろう。現地到着後、当然容疑がかかる人物を速やかに発見・逮捕した。その男――フィッツロイ・シンプソンといい、先の住宅群の住人だった。彼は名家の出身で、かつての財産を競馬で浪費し、現在はロンドンの紳士クラブでささやかなブックメーカー業で生計を立てている。彼の賭け帳を見ると、本命馬に対して五千ポンドもの大金を賭けていた。
「逮捕時、彼は素直にキングズ・パイランドの馬や、同じくメイプルトン厩舎のデズボロー(二番人気)について情報を得に来たと供述した。前夜の行動も否定せず、悪意はなく、あくまで情報収集が目的だと主張した。ネクタイを突きつけられると真っ青になり、それが殺された調教師の手にあった理由をまったく説明できなかった。ずぶ濡れの衣服は前夜の嵐の中を出歩いていた証拠であり、彼の持っていたペナン・ロイヤーの鉛入りステッキも、事件の傷害に使われた可能性が高い凶器だった。
「一方で、彼自身には傷がなく、ストレイカーのナイフの状態からして、襲撃者の一人は負傷しているはずだ。以上が事件の全体像だ、ワトソン。何か気づくことがあれば、ぜひ教えてほしい。」
私はホームズの明解な説明に、非常に興味を持って耳を傾けていた。ほとんどの事実は知っていたが、その重要性と相互関係を十分には理解していなかった。
「ストレイカーの切り傷は、脳への損傷で生じる痙攣の中で、自分のナイフでできたものかもしれないのでは?」と私は提案した。
「それは十分ありえる、むしろその可能性が高い」とホームズは言った。「その場合、被告に有利な主要な点が一つ消えることになる。」
「それでも、警察の立てている理論がどういうものなのか、いまひとつ分からない」と私は言った。
「どの理論にも重大な欠点があるのは否めない」とホームズは答えた。「警察の考えはこうだ。フィッツロイ・シンプソンは少年を薬で眠らせ、何らかの方法で合鍵を手に入れて厩舎のドアを開け、馬を連れ出し、どうやら誘拐しようとしたようだ。手綱もなくなっているから、シンプソンがこれを用いたのだろう。そしてドアを開けたまま、馬を荒野へ連れて行こうとしたが、そこへ調教師が出くわした。争いが起こり、シンプソンは重いステッキで調教師の頭を打ちぬき、ストレイカーの小ナイフで反撃されることもなかった。その後、馬は何らかの隠し場所へ連れ去られたか、あるいは争いの最中に逃げ出して荒野をさまよっているのかもしれない。これが警察の見解であり、確かに信じがたいが、他の説明はさらにあり得ない。しかし、現地に行けばすぐに検証できるだろうし、それまでの間にこれ以上進展することは難しそうだ。」
私たちが巨大なダートムーアの中心、まるで盾の中央の飾りのように位置する小さな町タヴィストックに到着したのは、夕方になってからだった。駅には二人の紳士が私たちを待っていた。一人は背が高く金髪で、獅子のような髪とあごひげ、そして奇妙に鋭い淡い青色の目を持っていた。もう一人は小柄で機敏な人物で、非常にきちんとした身なり、フロックコートとゲートルを着用し、整ったもみあげと片眼鏡をかけていた。後者が有名なスポーツマンであるロス大佐、前者がイギリス警察で急速に名声を高めているグレゴリー警部であった。
「来てくださって大変うれしい、ホームズさん」と大佐が言った。「警部殿はこちらで考えられる限りのことは全てやってくれましたが、ストレイカーの仇討ちと馬の捜索には一切の手を尽くしたいのです。」
「何か新しい進展はありましたか?」とホームズが尋ねた。
「申し訳ありませんが、ほとんど進展はありません」と警部が答えた。「外に屋根付き馬車を用意しています。明るいうちに現場をご覧になりたいでしょうから、車中でお話ししましょう。」
数分後、私たちは皆快適なランドー馬車に揺られ、風変わりなデヴォンの古都を走り抜けていた。グレゴリー警部は事件の話でいっぱいで話し続け、ホームズは時折質問や感嘆を挟み込んだ。ロス大佐は腕を組み、帽子を目深にかぶって背もたれにもたれながら沈黙していた。私は二人の探偵のやりとりを興味深く聞いていた。グレゴリー警部は、自身の仮説を述べ始めたが、その内容は列車の中でホームズが予想していたものとほとんど同じであった。
「フィッツロイ・シンプソンを取り巻く網はかなり狭まっています」と彼は言った。「私自身、彼が犯人だと思っています。ただし、証拠は状況証拠だけですし、何か新たな展開があればそれも覆るかもしれません。」
「ストレイカーのナイフについては?」
「彼は転倒した際に自分で負傷した、という結論に達しました。」
「道中、友人のワトソン医師も同じことを私に示唆してくれました。もしそうなら、このシンプソンという男には不利な証拠になりますね。」
「確かに、その通りです。彼はナイフも持っていませんし、傷の跡もありません。とはいえ、彼に不利な証拠は確かに強いものです。彼は本命馬の失踪に強い関心を持ち、馬丁に毒を盛った疑いもあります。嵐の夜に外にいたことは間違いなく、重いステッキを持っていましたし、死体の手には彼のネクタイが握られていました。陪審にかけるには十分でしょう。」
ホームズは首を振った。「腕利きの弁護士なら全部引き裂いてしまうさ。なぜ彼は馬を厩舎から連れ出す必要があった? 傷つける気ならその場でできただろう。合鍵は持っていたのか? 誰が彼に粉末アヘンを売った? 何より、この土地のよそ者である彼が、どうやってあの馬を隠せる? 使用人の少女に渡そうとした紙切れについて、彼自身はどう説明している?」
「それは10ポンド紙幣だったと本人は言っています。財布にも1枚ありました。しかし、それ以外の疑問点はそこまで深刻ではありません。彼はこの土地のよそ者ではないのです。夏に2度タヴィストックに宿泊していました。アヘンはおそらくロンドンから持ち込まれたものでしょう。合鍵は用済みになったら捨てたでしょう。馬は湿原の穴や廃坑にでも沈められているかもしれません。」
「ネクタイについては?」
「自分のものだと認めており、失くしたと主張しています。ただし、彼が馬を厩舎から連れ出した理由を説明できる新たな要素が出てきました。」
ホームズが耳をそばだてた。
「月曜の夜、事件現場から1マイルの場所にジプシーの一団が野営していた痕跡を発見しました。火曜にはもういなくなっていました。もしシンプソンと彼らの間に何らかのやり取りがあったとすれば、馬をジプシーに引き渡す途中で襲われ、今も彼らが馬を持っている可能性もあります。」
「確かに考えられるな。」
「ジプシーの捜索は続いています。タヴィストックの全ての厩舎や納屋も半径10マイル以内くまなく調べました。」
「近くにもう一つ調教場があるとか?」
「はい。それも見逃せない要素です。デズボロウ厩舎の馬が二番人気だったため、本命馬の失踪には利害関係があります。調教師のサイラス・ブラウンは大きな賭けをしていて、ストレイカーとは仲が悪かった。しかし、厩舎は調べましたが、何も関連は見つかりませんでした。」
「シンプソンとメープルトン厩舎の利害関係も?」
「全くありません。」
ホームズは馬車の座席にもたれ、会話は止んだ。数分後、御者が道路沿いのひなびた赤煉瓦の小さなヴィラの前で馬車を止めた。少し離れた牧草地の向こうには、灰色瓦の長い建物が見えた。その他の方向には、枯れゆくシダで銅色に彩られた湿原の低い起伏が水平線まで広がり、タヴィストックの尖塔と、メープルトン厩舎を示す西方の家並みだけが景色を遮っていた。私たちは皆、車を降りたが、ホームズだけは空を見つめたまま、思索に没頭して座席に残っていた。私が腕に触れると、ホームズは激しくハッとして我に返り、馬車を降りた。
「失礼しました」とホームズは、驚いたような顔のロス大佐に向かって言った。「ちょっと夢想していました。」 その目には鋭い光が宿り、抑えきれない興奮が感じられた。私は彼の様子に慣れていたが、何か手がかりを掴んだことを確信した。ただどこでそれを見つけたのかは想像もつかなかった。
「すぐに現場をご覧になりますか、ホームズさん?」とグレゴリー警部。
「いや、ここで少し詳細を確認したい。ストレイカーはこちらに運ばれたのですね?」
「はい。階上に安置されています。検死は明日です。」
「彼は長年あなたの部下だったのですか、ロス大佐?」
「とても優秀な使用人でした。」
「死亡時の所持品を調べましたか、警部?」
「持ち物なら応接室にあります。ご覧になりますか?」
「ぜひ見せていただきたい。」私たちは前室に入り、中央のテーブルを囲んで座った。警部が四角いブリキ箱の錠を開け、小さな持ち物の山を並べた。マッチ箱、2インチほどのロウソク、A.D.P.印のブライヤーパイプ、アザラシ革の煙草入れに細切りキャベンディッシュが半オンス、銀の懐中時計と金の鎖、金貨5枚、アルミの鉛筆、数枚の書類、そしてロンドンのワイス&カンパニー製で、非常に繊細で硬い刃を持つ象牙柄のナイフがあった。
「これは変わったナイフだ」とホームズは手に取り、隅々まで調べながら言った。「血痕があるので、これが死体の手に握られていたものだな。ワトソン、これは君の分野では?」
「白内障手術用のナイフです」と私は答えた。
「やはりそうか。とても繊細な作業用の刃で、こんな荒っぽい外出に持っていくのは奇妙だ。しかも折り畳めない。」
「先端にはコルクの円盤が付いていて、遺体のそばに落ちていました」と警部。「奥さんの話では、ナイフは寝室の化粧台に置いてあり、出かける時に夫が持ち出したそうです。武器としては頼りないですが、その場で手に取れるものとしては一番良かったのでしょう。」
「なるほど。書類の方は?」
「3枚は干し草商の領収書。1枚はロス大佐からの指示書。もう1枚はボンド街のマダム・ルシュリーエ作成の、ウィリアム・ダービシャー宛ての婦人服代37ポンド15シリングの請求書です。ストレイカー夫人によれば、ダービシャーは夫の友人で、時おり手紙をここに宛てていたそうです。」
「ダービシャー夫人はなかなか贅沢な趣味だったようだ」とホームズは請求書を見ながら言った。「ドレス一着で22ギニーとは高い。しかし、それ以上得られるものはなさそうだ。では現場に向かおう。」
応接室を出ると、廊下で待っていた痩せこけて苦悩の影が色濃く残る女性が、一歩踏み出して警部の袖に手を置いた。
「見つかったんですか? 見つけてくださったんですか?」と彼女は息を切らして言った。
「いいえ、ストレイカー夫人。ですが、こちらのホームズさんがロンドンから助力に来てくださり、我々も最善を尽くします。」
「以前、プリマスのガーデンパーティーでお会いしませんでしたか、ストレイカー夫人?」とホームズ。
「いいえ、違います。」
「おや、確かに見覚えが……鳩色の絹のドレスにダチョウの羽飾りをつけていませんでしたか?」
「そんな衣装は持っていません」と夫人。
「なるほど、それで確定ですね」とホームズは答え、謝罪して警部の後に続いた。少し湿原を歩くと、遺体が見つかった窪地に着いた。縁にはコートが掛けられていたハリエニシダの茂みがあった。
「あの夜は無風だったそうですね?」とホームズ。
「はい、ただし雨はひどかったです。」
「ならばコートは風で飛ばされたのではなく、意図的に置かれたわけだ。」
「その通りです。」
「地面はかなり踏み荒らされていますね。月曜の夜以来、たくさんの人が来たのでしょう。」
「ここにござが敷かれ、皆その上に立っています。」
「素晴らしい。」
「この袋にストレイカーの履いていた片方のブーツ、シンプソンの片方の靴、そしてシルヴァー・ブレイズの蹄鉄の型があります。」
「素晴らしい!」ホームズは袋を受け取り、窪地に降りるとゴザを中央に移動させ、うつ伏せになって泥地を綿密に観察した。「おや?」と彼は突然言った。「これは?」それは半分燃えたマッチで、泥にまみれて木片のようにしか見えなかった。
「なぜ見逃したのか……」と警部は悔しそうに言った。
「泥に埋まっていて見えなかった。私はそれを探していたから見つけた。」
「えっ、見つかることを予期していたのか?」
「不思議ではないと思った。」
ホームズは袋から靴を取り出し、泥の上の跡と比較した。その後、窪地の縁によじ登り、シダや茂みの間を這うように調べた。
「もうこれ以上の足跡はありません」と警部。「100ヤード四方、徹底的に見ました。」
「なるほど」ホームズは立ち上がった。「警部がおっしゃるなら、私がもう一度調べる無礼は避けます。しかし、明日現場の地形を把握しておきたいので、少し湿原を散歩したい。蹄鉄も幸運のお守りに持っていくとしよう。」
ロス大佐は、私の友人の静かで組織的なやり方に少し苛立ちを見せ、時計を見た。「警部、戻ってきてほしい。相談したいことがいくつかあるし、特に本命馬をカップの出場リストから外すべきかどうか、世間のためにも考えたい。」
「絶対にいけません」ホームズがきっぱりと言った。「名前はそのままにしておくべきだ。」
大佐はうなずいた。「ご意見を伺えてよかった。私たちはストレイカー邸で待っています。散歩が終わったら一緒にタヴィストックへ戻りましょう。」
大佐と警部は戻り、ホームズと私はゆっくり湿原を歩いた。メープルトン厩舎の向こうに日が沈み始め、前方の斜面は黄金色から夕陽を浴びて赤茶色に染まっていた。しかし、私の連れは風景に目もくれず、深い思索に沈んでいた。
「ワトソン、こう考えるんだ」とついに彼が口を開いた。「今はジョン・ストレイカー殺害犯のことはさておき、馬の行方だけを追ってみよう。事件の最中や直後に馬が逃げ出したとしたら、どこへ行くか? 馬は群れで動く生き物だ。一人ならキングズ・パイランドに戻るか、メープルトンに向かうだろう。湿原を野生でさまよう理由がない。もう誰かに見つかっているはずだ。ジプシーが連れ去る理由もない。彼らは警察を避けるため、厄介ごとはすぐに手を引く。しかも、あの馬を売る宛てもない。リスクは大きく、得るものがない。明らかだろう。」
「では、どこにいる?」
「既に言った通り、キングズ・パイランドかメープルトンしかあり得ない。キングズ・パイランドにはいない。つまりメープルトンだ。仮説としてそう仮定し、検証してみよう。この辺りの地面は警部の言う通り、乾いて固い。しかし、メープルトンの方角へ下るところに、あそこに窪地がある。月曜の夜は相当ぬかるんでいたはずだ。もし仮説が正しければ、馬はそこを通ったことになる。足跡を探すのはそこだ。」
私たちは会話しながらさっそうと歩き、数分で例の窪地に着いた。ホームズの指示で私は右岸を、彼は左岸を下り始めたが、50歩も進まないうちに彼が叫び、手を振っていた。柔らかな土の上に馬の蹄跡がはっきり残っており、ポケットから取り出した蹄鉄がぴったり合った。
「想像力の価値が分かるだろう」とホームズは言った。「グレゴリー警部に足りないのはこれだ。可能性を想像し、仮説に基づいて行動し、そして正しかった。では進もう。」
私たちは湿地を越え、四分の一マイルほど乾いた草地を進んだ。また斜面を下り、また足跡を見つけた。さらに半マイルほどで一度見失ったが、やがてメープルトン近くで再び見つけた。最初に気づいたのはホームズで、彼は勝ち誇った顔で指差していた。馬の足跡の隣には人の足跡があった。
「馬は単独だったのに」と私は叫んだ。
「その通り。さっきまで単独だった。おや、これは?」
足跡は急に向きを変え、キングズ・パイランド方向へ戻っていた。ホームズは口笛を吹き、私たちはそれを追った。彼は跡に目を凝らしていたが、私はふと脇に目をやり、同じ足跡が逆方向にも伸びているのを見て驚いた。
「やったな、ワトソン」とホームズは私が指摘すると言った。「長い遠回りをせずに済んだ。戻る跡を追おう。」
それほど遠くなかった。足跡はメープルトン厩舎の門へ続くアスファルト舗装で終わっていた。近づくと厩舎から下男が走り出てきた。
「ここで油を売られると困る」と彼は言った。
「ひとつだけ質問がある」とホームズは言い、ベストのポケットに指を入れた。「もし明日の朝5時にご主人のサイラス・ブラウンさんを訪ねたら、お目にかかれるだろうか?」
「間違いなく、朝一番で起きているのはご主人です。でも今ちょうど出てきましたよ。いや、私があなたからお金を受け取るところをご主人に見られたら、首が飛びます。後でなら。」
ホームズがポケットから取り出したハーフクラウンをしまい直すと、獰猛な表情の年配男がハンティングクロップを振りながら門から現れた。
「どうした、ドーソン! 余計な話はやめろ! 仕事に戻れ! それからお前――何の用だ?」
「10分だけお話を」とホームズは愛想良く言った。
「誰彼構わず相手にしている暇はない。見知らぬ奴はいらん。さっさと立ち去らないと犬をけしかけるぞ。」
ホームズは身を寄せ、調教師の耳元で何かをささやいた。彼は激しく身を震わせ、顔を真っ赤にした。
「嘘だ! でたらめだ!」
「それならここで論争するか、それとも部屋で静かに話すか?」
「……入れよ、好きにしろ。」
ホームズは微笑んだ。「数分で戻るよ、ワトソン。さて、ブラウンさん。お好きなように話をどうぞ。」
二十分ほど経ち、赤みがすっかり消えてあたりが灰色に染まったころ、ホームズと調教師が再び姿を現した。これほどの短時間で、サイラス・ブラウンほど劇的に変わった男を私は見たことがなかった。彼の顔は死人のように青ざめ、額には汗が光り、手は震えて狩猟鞭が風に揺れる枝のように左右に揺れていた。あの威圧的で横柄な態度もすっかり影を潜め、今や主人に従う犬のように、ホームズの隣をおどおどと歩いている。
「ご指示どおりにします。すべてやります」と彼は言った。
「一つたりとも間違いのないように」とホームズは彼を振り返って言った。サイラス・ブラウンはホームズの眼に込められた威圧を感じて身をすくめた。
「もちろん、間違いなんてありません。必ずそこにあります。先に戻しておくべきでしょうか、それとも――」
ホームズは少し考えてから急に笑い出した。「いや、そのままでいい。あとで君に手紙を書く。絶対にごまかしは無しだ、さもないと――」
「大丈夫です、お任せください!」
「うん、君なら大丈夫だろう。では、明日また連絡する」ホームズはきっぱりと背を向け、相手が差し出した震える手を無視して、私たちはキングズ・パイランドへと歩き出した。
「サイラス・ブラウンほど、いじめっ子と臆病者、卑怯者が見事に混じり合った男には、なかなかお目にかかれないな」とホームズは歩きながら感想を述べた。
「つまり、彼が馬を持っているということか?」
「最初はしらを切ろうとしたが、あの朝彼が取った行動をことごとく言い当ててやったので、私が見ていたと思い込み、観念したというわけだ。もちろん、君もあの特徴的に四角い足跡に気づいて、彼のブーツがぴったり一致しているのを見ただろう。それに、こんな大胆なことを部下が勝手にやるはずがない。私は、彼がいつものように一番に厩舎に降りていき、見慣れぬ馬が荒野をうろついているのを発見した場面を説明した。そして、その馬の額の白い斑点から、偶然にも自分が賭けている馬を凌ぐ唯一の馬が自分の手中に転がり込んだことに驚いた様子も。そのとき彼はとっさに馬をキングズ・パイランドへ戻そうとしたが、悪魔が囁いて、レースが終わるまで隠しておこうと考え、メイプルトンに持ち帰って匿った経緯まで詳細に語った。そこまで言われては、さすがに観念して自分の身の安全しか考えなくなったというわけだ」
「だが、彼の厩舎は捜索されたはずでは?」
「古狐のような連中には、いろんな手口があるものだ」
「だが、今も馬を彼に預けておいて危険では? 馬を傷つける動機が十分にあるだろう」
「心配ない。彼は自分の目の中のリンゴのごとく、その馬を守るさ。無事に馬を引き渡すことだけが助かる道だと、よくわかっている」
「ロス大佐は、どんな場合でも情けをかけるような人物には見えなかったが」
「事はロス大佐の一存では決まらない。私は私の方法で進め、話すことも話さないことも選べる。これが非公式の強みだ。ワトソン、君も気づいていただろうが、大佐の私に対する態度は少々横柄だった。少し彼にからかいを仕掛けたくなってきた。馬のことは何も言わないでくれ」
「もちろん、あなたの許可なくは言わない」
「だが、これはジョン・ストレイカー殺害の謎に比べれば取るに足らんことだ」
「その捜査に専念するつもりか?」
「いや、逆だ。今夜の夜行列車でロンドンに戻る」
私は友人の言葉に唖然とした。デヴォンシャーに来てまだ数時間、しかもあれほど鮮やかに始めた捜査を放棄するとは到底理解できなかった。これ以上何を聞き出そうとしても、彼は何も語らなかった。
私たちが調教師の家に戻ると、大佐と警部が居間で待っていた。
「私と友人は今夜の急行でロンドンへ戻ります」ホームズが言った。「あなた方の美しいダートムーアの空気を少々味わわせていただきました」
グレゴリー警部は驚いた様子で目を見開き、大佐は皮肉な笑みを浮かべた。
「ストレイカーの殺人犯逮捕を諦めたというわけですな」と大佐が言った。
ホームズは肩をすくめた。「確かに大きな障害がありますので」と答えた。「ですが、あなたの馬は火曜日に出走できると固く信じています。騎手のご準備もお願いします。それと、ジョン・ストレイカー氏の写真を頂けますか?」
警部は封筒から写真を取り出して渡した。
「さすがはグレゴリー警部ですね。私の望みをすべて予測してくださる。少しだけお待ちいただけますか? 召使いの娘に質問したいことがあります」
ホームズが部屋を出ると、大佐は遠慮なく言った。「ロンドンから呼んだ助言者には正直失望している。来た時と何も変わっていないように思える」
「少なくとも馬は出走できるという保証が得られました」と私は言った。
「保証ならあるさ」大佐は肩をすくめた。「だが、私は馬そのものが欲しい」
私は友人をかばおうと口を開きかけたが、ちょうどホームズが戻ってきた。
「さて諸君、タヴィストックへ向かう用意はできている」
私たちが馬車に乗り込むと、厩舎の少年がドアを開けてくれた。その時、ホームズは何か思いついたらしく、少年の袖に手を触れた。
「放牧場に羊が何頭かいるな。世話をしているのは誰だい?」
「僕です、旦那様」
「最近、何か異変はあったか?」
「さほどのことじゃありませんが、三頭ほど足を引きずるようになりました」
ホームズは大いに満足した様子で、くすくすと笑いながら手をこすり合わせた。
「大穴を狙ったぞ、ワトソン。まったくの大穴だ」彼は私の腕をつねりながら言った。「グレゴリー警部、この羊に現れた奇妙な流行病にご注意願いたい。さあ、御者、出発!」
ロス大佐は、いまだに友人の力量を疑う表情だったが、警部の顔には鋭い関心が浮かんでいるのが見て取れた。
「それはそんなに重要なのか?」と警部は尋ねた。
「きわめて重要だ」
「他に注目すべき点は?」
「夜中の犬の事件にだ」
「犬は夜中、何もしなかった」
「そこが奇妙なのだ」とシャーロック・ホームズが答えた。
四日後、ホームズと私は再び列車に乗り、ウィンチェスターへ向かっていた。ウェセックス杯のレースを見るためだ。ロス大佐が駅の外で待っており、私たちは彼の馬車で郊外のコースへ向かった。大佐の顔は険しく、態度も極めて冷たかった。
「馬は、まったく消息がつかめん」と彼は言った。
「見ればすぐ分かる自信はありますか?」ホームズが尋ねた。
大佐は怒気を込めて答えた。「二十年も競馬に関わってきたが、そんな質問を受けたのは初めてだ。子どもでもシルヴァー・ブレイズの額の白斑と斑点のある前脚を見れば分かる」
「賭けの状況は?」
「そこが妙でね。昨日なら十五倍で賭けられたが、今はどんどん倍率が下がって、三倍もつかない」
「ふむ。誰かが何かを知っているわけだな」
馬車がスタンド近くの囲いにつくと、私は出走表を確認した。
《ウェセックス杯。四・五歳馬対象。第二位三百ポンド、三位二百ポンド。新コース(一マイル五ハロン)》
- ヒース・ニュートン氏所有 ザ・ニグロ(赤帽、シナモン色ジャケット)
- ワードロー大佐所有 パグリスト(ピンク帽、青黒ジャケット)
- バックウォーター卿所有 デズバラ(黄帽、黄袖)
- ロス大佐所有 シルヴァー・ブレイズ(黒帽、赤ジャケット)
- バルモラル公所有 アイリス(黄黒縞)
- シングルフォード卿所有 ラスパー(紫帽、黒袖)
「もう一頭は除外して、君の言葉だけを頼りにしたのだが。――おい、これはどうした? シルヴァー・ブレイズが一番人気だぞ!」
「シルヴァー・ブレイズ、五対四!」場内の胴元が叫ぶ。「シルヴァー・ブレイズ、五対四! デズバラ、五対十五! 全体で五対四!」
「番号が出たぞ」私は叫んだ。「六頭全部、揃っている」
「六頭全部? じゃあ、私の馬も出ているってことじゃないか」大佐は動揺して叫んだ。「でも見えんぞ。私の色の馬はまだ通らなかった」
「まだ五頭しか通っていません。あれがそうでしょう」
ちょうどそのとき、力強い栗毛馬が計量所から駆け出し、黒と赤のジャケットをまとった騎手を乗せて私たちの前を通り過ぎた。
「違う、あれは私の馬じゃない! あの馬体には白い毛が一本もない。ホームズさん、これは一体どういうことだ?」
「まあ、様子を見よう」ホームズは泰然としたまま、私の双眼鏡を覗いた。「素晴らしい! 絶好のスタートだ!」彼は突然叫んだ。「来たぞ、カーブを回ってきた!」
馬車の上からは、直線コースを駆け上がる馬たちがよく見えた。六頭はじつに接戦で、絨毯でもかければ覆えそうなほどだったが、中盤でメイプルトン厩舎の黄色が先行。しかしゴール前でデズバラが力尽き、大佐の馬が猛烈な勢いで抜け、六馬身もの差をつけてゴール。バルモラル公のアイリスは大差の三着。
「とにかく、私の勝ちだ」大佐は目をこすりながら息をついた。「だがさっぱり訳が分からん。ホームズさん、いい加減に謎を明かしてくれないか?」
「もちろんです、すべてご説明しましょう。さあ、みなで馬を見に行きましょう。――ほら、ここにいます」ホームズは私たちを計量所へと案内した。「顔と脚をアルコールで洗ってご覧なさい。もとのシルヴァー・ブレイズですよ」
「信じられん!」
「私は馬を偽者の手から取り戻し、そのまま走らせることにしたのです」
「あなたは本当に素晴らしい! 馬は前よりも元気そうだ。あなたを疑ったことを心から詫びたい。馬を取り戻してくれたことに感謝する。ただ、ジョン・ストレイカー殺害犯を捕まえてくれれば、さらに恩に着る」
「それもすでに済ませている」ホームズは静かに言った。
私は大佐とともに呆然と彼を見つめた。「捕まえた? 犯人はどこだ?」
「ここにいる」
「ここ? どこだ?」
「今、私のそばにいる」
大佐は怒りで顔を赤らめた。「私はあなたに借りがあるのは認めるが、今の発言は悪質な冗談か侮辱だと受け取らざるを得ない」
シャーロック・ホームズは笑った。「あなたを犯罪に結び付けてなどいませんよ、大佐。本当の犯人は、すぐ後ろに立っています」そう言ってホームズはサラブレッドの艶やかな首筋に手を置いた。
「馬だ!」大佐と私は同時に叫んだ。
「そう、馬です。ただし、これは正当防衛だったと申し添えておきますし、ジョン・ストレイカーがあなたの信頼に値しない人物だったこともお伝えしておきます。――おっと、次のレースでちょっと稼げそうなので、長い説明はまた後ほど」
その夜、ロンドンへ戻る列車のプルマン車の片隅で私たちは寛いでいた。ロス大佐も私同様、ホームズの語るダートムーア厩舎での月曜夜の出来事と、彼が事件を解き明かすまでの経緯に聞き入って、あっという間に時間が過ぎた。
「正直に言うと」ホームズは語った。「新聞報道をもとに私が立てていた仮説は、すべて誤りだった。しかし、そこにはいくつも示唆があったのだが、それを覆い隠す細部が真の意味を読めなくしていた。私はデヴォンシャーへ向かう時点で、フィッツロイ・シンプソンこそが真犯人だと確信していた。ただ、証拠が決定的ではないことも分かっていた。だが厩舎に到着した馬車の中で、カレー料理の重大な意味に思い至った。私がぼんやり座り込んでいたのを覚えているだろう、ワトソン。あれほど明白な手がかりを見落とした自分に驚いていたのだ」
「今聞いても、その点がどう事件解明につながるのか分からない」と大佐が言った。
「あれが推理の最初の鎖だった。粉末アヘンは決して無味ではない。味は悪くないが、確かに分かる。普通の料理に混ぜれば、必ず違和感を感じて食べるのを止めてしまうだろう。しかしカレーほど、その味を隠してしまう料理はない。外部の者――つまりフィッツロイ・シンプソンには、その晩調教師の家でカレーを出させることなどできるはずもなく、彼がたまたまアヘン入りの料理と出くわしたなどというのは、あまりに不自然だ。だから、シンプソンは容疑から外れる。そうなると、あの晩カレーを夕食に選んだのはストレイカー夫妻のどちらかということになる。そして、その料理は少年用に分けられた後でアヘンが混ぜられた。他の者は同じ料理でも異常はなかったのだ。となると、使用人の目を盗んで料理に手を加えられる立場の者はどちらか、ということになる。
「この問題を考える前に、私は犬の沈黙の意味に気づいていた。ひとつの正しい推論は他の正しい推論を呼ぶものだ。シンプソンの件で厩舎には犬がいることは分かった。しかし、誰かが馬を連れ出したにもかかわらず、犬は吠えて二階の少年たちを起こすほどではなかった。つまり、犬がよく知っている人物だったのだ。
「私はすでにジョン・ストレイカーが深夜に厩舎へ降り、シルヴァー・ブレイズを連れ出したとほぼ確信していた。目的は? それが正当なものなら、少年を麻薬で眠らせる必要はない。過去にも、調教師が代理人を使って自分の馬に大金を賭け、八百長を仕組む例はあった。時に騎手を買収し、時にもっと巧妙な手段を使う。今回は何か。私は彼の所持品から糸口を探ろうと考えた。
「そしてそれは見つかった。君も覚えているだろう、死体の手に握られていた奇妙なナイフを。まともな人間が武器として選ぶようなものではなかった。ワトソン君も話していた通り、あれは外科手術でもっとも繊細な作業に使われる特殊なナイフだ。そしてそれは、その晩まさに繊細な仕事に使われようとしていた。大佐、あなたならご存じだろうが、馬の後肢の腱にごく浅い切り込みを入れれば、表面には跡が残らない。そうされた馬は、少しだけ跛行するようになり、訓練中の捻挫やリウマチのせいにされるが、不正行為とは疑われない」
「なんという悪党だ!」大佐が叫んだ。
「ここに、なぜストレイカーが馬を荒野へ連れ出したかの答えがある。あれほど気性のいい馬なら、ナイフのちくりに必ず暴れる。屋外でなければ絶対無理だった」
「そうか、それで蝋燭とマッチが必要だったのか!」
「その通り。彼の遺留品を調べて、犯行手段だけでなく動機まで分かった。大佐、世の中の男が他人の請求書を持ち歩くはずがない。自分の清算で手一杯だ。私はすぐに、ストレイカーが二重生活を送り、別宅を持っていたと断定した。請求書の内容から、女性、それも贅沢好きの相手がいたことが分かる。あなたがいくら太っ腹でも、使用人が二十ギニーの散歩用ドレスを買うとは思えない。私は、ミセス・ストレイカーにさりげなくそのドレスのことを確認し、彼女の元には届いていないと分かった。ミリナー(仕立屋)の住所を控え、ストレイカーの写真を持参すれば、ダービーシャーなる架空の人物の正体もすぐ割れると確信した。
「それからは全て明白だった。ストレイカーはランプの光が見えない窪地まで馬を連れ出した。シンプソンは逃走時にスカーフを落とし、ストレイカーがそれを拾った――おそらく馬の脚を縛るために使おうと考えたのだろう。窪地で馬の後ろに回り、マッチで火を点けたところ、馬は突然の閃光に驚き、直感的に危険を察して蹴り上げ、蹄鉄がストレイカーの額を直撃した。彼はすでに、雨にもかかわらず外套を脱いで作業の準備をしていたので、倒れた時ナイフで自分の腿を切ってしまった。これでお分かりだろうか?」
「素晴らしい! まるで現場にいたかのようだ!」大佐は叫んだ。
「最後の一手は、正直に言ってかなり賭けだった。だが、ストレイカーほど抜け目のない男が、この繊細な腱切りを、少しも練習せずにいきなり実行するとは思えなかった。では、いったい何で練習したのか? ふと羊たちに目がいき、私は質問をしてみた。驚いたことに、それで私の推測が正しかったと分かったのだ。
ロンドンに戻ってから、帽子屋を訪ねてみた。そこでストレイカーが『ダービーシャー』という名でよく来る客だと分かった。彼には非常に派手な奥さんがいて、高価なドレスに目がなかったという。この女性がストレイカーを借金まみれにし、そのせいで彼はこの惨めな陰謀に手を染めたのは間違いないと思う。」
「一つだけ、まだ説明されていないことがある!」とロス大佐が叫んだ。「馬はどこにあったのか?」
「それは逃げ出し、近所の方に保護されていた。その件はもう水に流すしかなさそうだ。ここはクラパム・ジャンクションだと思うが、あと10分もすればヴィクトリア駅に到着する。もしお時間があれば、部屋で葉巻でも吸いながら、他にも興味のある点があればお話ししよう。」
II. 段ボール箱の冒険
友人シャーロック・ホームズの卓越した知性を示す典型的な事件をいくつか選ぶにあたり、私はできるだけ扇情性の少ないもの、かつ彼の才覚が存分に発揮されたものを選ぶよう努めてきた。しかし残念ながら、センセーショナルな事件と犯罪を完全に切り離すことはできず、記録者たる私は、事件の本質を伝えるために不可欠な細部を省略して誤った印象を与えるか、あるいは偶然手元に集まった材料を使うしかないというジレンマに陥る。この短い序文をもって、私は奇妙かつ特に恐ろしい一連の出来事を記した手帳へと話を進めよう。
それは八月の焼けつくような暑い日だった。ベイカー街はまるでオーブンのようで、通り向かいの家の黄色いレンガ造りに照りつける光が目に痛いほどだった。冬の霧の中に陰鬱にそびえていたあの壁と同じものだとは、とても信じられなかった。ブラインドは半分下ろされ、ホームズはソファに体を丸め、朝の郵便で届いた手紙を何度も読み返していた。私自身はインドでの勤務経験があったおかげで、寒さよりも暑さに強く、気温が華氏90度でも苦にはならなかった。しかし、朝刊は面白みがなく、議会は休会中、市内はみな避暑に出て、私はニュー・フォレストの林やサウスシーの小石浜が恋しくてたまらなかった。残高の乏しさから休暇を先延ばしにしていたが、相棒にとっては田舎も海も少しも惹かれないようだった。彼は五百万人の中心に身を置き、張り巡らせた糸のように、未解決事件の噂や疑惑に敏感に反応しながら生きるのを好んでいた。自然への愛など、彼の数ある才能の中にはなかった。唯一の変化は、都会の悪人から田舎の犯罪者へと追跡対象を変えるときだった。
ホームズが会話に夢中になれないと察した私は、退屈な新聞を投げ出し、椅子に身を預けて物思いにふけっていた。すると突然、相棒の声が私の思考を破った。
「君の言う通りだ、ワトソン。たしかに、あんな馬鹿げた方法で争いを解決するなんてね。」
「全く馬鹿げている!」私は思わず叫び、ホームズが私の心の奥底の考えを繰り返したことに気づいて、驚いて身を乗り出して彼を見つめた。
「これはいったいどういうことだ、ホームズ? こんなこと、想像もできなかったぞ。」
私の困惑ぶりに、彼は愉快そうに笑った。
「覚えているだろう、少し前にポーの短編から、観察者が相手の心の中を読み取る場面を読んで聞かせたとき、君はそれを著者の技巧に過ぎないと考えた。私が普段から同じことをしていると言ったら、君は信じなかった。」
「いや、そんなことは――」
「少なくとも、言葉では否定したかもしれないが、眉はしっかり疑いを示していたよ。だから、君が新聞を放り出して考え込み始めたのを見て、これを読み取ってみせるいい機会だと思ったのさ。そして実際に君の考えに割って入って、私が君と心のつながりを持っている証拠を見せることができたわけだ。」
私はまだ納得できなかった。「君が読んでくれた例では、観察者が相手の動作から結論を導いていたはずだ。石につまずいたり、星を見上げたり、そんな場面だった。しかし私はずっと椅子に座っていただけで、どんな手がかりを与えたというんだ?」
「自分を過小評価してはいけない。人間の顔は感情を表現するためにあるのだし、君の顔はとても正直だ。」
「つまり、君は私の顔つきから考えを読み取ったと言うのか?」
「君の顔――特に目だよ。そもそも、どういうきっかけで君の考え事が始まったのか、自分でも覚えていないだろう?」
「いや、思い出せない。」
「では私が説明しよう。君が新聞を放り出した――その動作で私は君に注意を向けた。君はしばらく茫然とした表情で座っていて、それから新しく額装したゴードン将軍の絵に目を向けた。その時、君の顔の変化で何か考え始めたと分かった。しかしそれはあまり長く続かなかった。君の視線は、額装していないビーチャーの肖像――本の上に置いてあるやつ――に移った。それから壁を見上げて、もちろんその意味は明白だった。もしこの肖像を額装すれば、ちょうどあの空いた場所を埋めて、ゴードンの絵と対になる、と考えたのだ。」
「実に見事に私の思考を追っている!」
「ここまでは間違えようがない。だがそこから君の思考はビーチャーに戻り、じっと彼の顔を見つめていた。そして顔の皺が消えたが、思索は続き、君の顔は考え込む表情になった。君はビーチャーの生涯の出来事を思い出していた。私はよく知っているが、君が彼のことを考えるとき、必ず南北戦争の際に彼が北軍のために行動したあの使命――そして彼が我が国の粗暴な連中にどう扱われたかに対する、君の強い憤りを思い出すはずだ。君はその出来事に強い感情を持っていたので、ビーチャーのことを考えれば必ずそれも頭に浮かぶ。やがて君の視線が絵から外れたとき、私は今度は君の思考が南北戦争そのものに移ったと推測した。そして唇が引き締まり、目が輝き、手が握られたとき、君はあの絶望的な戦いで両軍が示した勇敢さを思い浮かべていたことを確信した。だがその後、君の顔はさらに沈み、首を振った。哀しみや恐怖、命の無駄な浪費について思いを巡らせていたのだ。君の手が自分の古傷に伸び、唇にかすかな笑みが浮かんだ――この国際問題の解決手段のばかばかしさが、思わず可笑しくなった証拠だ。この時点で私は君の考えが馬鹿げているという点に同意し、自分の推論がすべて正しかったことを喜んだ。」
「全くその通りだ!」私は言った。「でも説明を聞いても、やはり驚かされるよ。」
「表面的なことだよ、ワトソン。ただ、このあいだ君が疑ったから、敢えて君に示しただけさ。さて、ここにもう少し厄介な問題がある。君は今朝の新聞で、クロイドンのクロス通りに住むミス・カッシングに届いた小包の中身についての短い記事を見ただろう?」
「いや、何も見ていない。」
「それは見落としたようだ。新聞をこっちに投げてくれ。ほら、金融欄の下にある。朗読してくれないか。」
ホームズがこちらに投げ返した新聞を広げ、指示された記事を読んだ。見出しは「戦慄の小包」とあった。
「クロイドンのクロス通りに住むスーザン・カッシング嬢が、極めて悪趣味な悪戯の被害者となったと見られる事件が発生した。これに何らかの邪悪な意味があるのでなければ、そう評するほかない。昨日午後二時、郵便配達人によって小さな小包が届けられた。中には段ボール箱があり、粗塩で満たされていた。塩を捨てると、ミス・カッシングは驚くべきことに、人間の耳が二つ、しかも切り取られて間もないような状態で入っているのを発見した。この箱は前日の朝、ベルファストから小包郵便で送られたものである。送り主の手がかりはなく、ミス・カッシングは五十歳の独身女性で、非常に慎ましい生活をしており、知人や文通相手もほとんどいないため、郵便物を受け取ること自体が珍しいという。数年前、ペンジに住んでいた際、彼女は三人の若い医学生に部屋を貸したことがあったが、その騒々しく不規則な生活に耐えかねて、結局部屋を出てもらったという。警察は、この学生たちが彼女に恨みを抱き、解剖室の遺物を送りつけて脅そうとしたのではないかと考えている。三人のうち一人がアイルランド北部――たしかベルファスト出身だったという事実も、この説に一定の説得力を与えている。現在、この件はレストレード警部の指揮のもと、積極的に捜査が進められている。」
「これがデイリー・クロニクル紙の記事だ」とホームズは私が読み終えるといった。「では次にレストレードからの連絡だ。今朝、彼から手紙が届いた。こう書いてある――『この事件は、どうやらあなたの得意分野だと思います。我々も解決の見込みは十分にあると考えていますが、手がかりが少なくて難航しています。もちろん、ベルファストの郵便局には電報で問い合わせましたが、その日に出された小包の数が多く、該当のものを特定したり、発送主を覚えている者もいません。箱はハニーデュー・タバコの半ポンド箱で、これも手がかりになりません。医学生説が依然として最も有力と思われますが、もしお時間があれば、ぜひクロイドンまでお越しいただきたい。私は一日中、現場か警察署にいる予定です』――どうだいワトソン? 暑さに打ち勝って、私の記録に残せそうな事件を求めてクロイドンまで付き合ってくれないか?」
「何かすることがあればと思っていたところだ。」
「それなら決まりだ。呼び鈴を鳴らして靴磨きにタクシーを頼んでもらいたい。私はちょっと着替えて、シガーケースを満たしてくるよ。」
列車で移動中、雨が降り、クロイドンはロンドンよりも随分と涼しかった。ホームズはあらかじめ電報を打っておいたため、レストレード警部――相変わらず小柄で、きびきびして、フェレットのような鋭さを漂わせている――が駅で待っていた。五分も歩くと、クロス通りに着き、ミス・カッシングの家に到着した。
そこは二階建てのレンガ造りの家がずらりと並ぶ長い通りで、白く磨かれた石段と、エプロン姿の女性たちが家の前でおしゃべりする姿が印象的だった。通りの半ばでレストレードが足を止め、ドアをノックすると、小さな女中が出てきた。ミス・カッシングは応接間に座っており、我々はそこに通された。彼女は穏やかな顔立ちで、大きな優しげな瞳と、こめかみに沿ってカールした白髪が目立つ女性だった。膝には刺繍入りのアンティマカサーが載せられ、傍らのスツールには色とりどりの絹糸が入った籠が置かれていた。
「あのひどい物は、裏の物置にあります」と、レストレードが入るとミス・カッシングが言った。「どうか全部持っていってください。」
「もちろんです、ミス・カッシング。私も、ホームズさんにお見せするまでここに置いておいただけです。」
「なぜ私のいる前で見る必要があるのですか?」
「もしホームズさんが何か質問したいことがあるかもしれませんので。」
「私が何も知らないと言っているのに、質問されても意味がないではありませんか。」
「ごもっともです、ご婦人」とホームズは穏やかに応じた。「すでに十分ご迷惑をおかけしたことでしょう。」
「ええ、本当にそうです。私は静かに暮らしているのに、新聞に名前が出たり警察が家に来たりなんて初めてのことです。あんな物、ここには絶対に置いておきたくありません。ご覧になりたければ物置へどうぞ。」
裏庭に面した小さな物置だった。レストレードが中に入り、黄色い段ボール箱と、茶色い包み紙と紐を持ち出してきた。小道の端にベンチがあり、私たちはそこに腰掛け、ホームズがレストレードから受け取った品々を一つ一つ調べた。
「この紐は非常に興味深い」とホームズは言い、紐を光にかざして匂いをかいだ。「レストレード、これはどう思う?」
「タールが塗ってある。」
「その通り。これはタール処理した荒縄だ。それに、ミス・カッシングがハサミで切ったことも気が付いたはずだ。両端のほつれから分かる。これは重要だ。」
「重要だとは思えませんが」とレストレードが言った。
「重要なのは、結び目がそのまま残っていて、その結び方が独特な点だ。」
「とても丁寧に結ばれています。私もその点は既に記録しました」とレストレードは誇らしげに言った。
「では紐についてはここまで」とホームズは微笑み、「次は包み紙だ。茶色の紙で、はっきりとコーヒーの匂いがある。気付かなかったか? 疑いようがない。宛名はかなり頼りない字で印刷されている――『ミス・S・カッシング、クロス通り、クロイドン』。太いペン――たぶんJ――で、インクの質は良くない。『クロイドン』は元々『i』で綴られていて、後から『y』に直してある。つまり、これはクロイドンを知らない、学歴の低い男性が書いた宛名だ。さて、箱は黄色いハニーデュー・タバコの半ポンド箱で、特徴的なのは左下隅に二つの指紋があるだけ。中身は皮革などを保存するのに使う粗塩で、工業用のものだ。そして、その中にこれら奇妙な物が埋められている。」
ホームズはそう言いながら、二つの耳を取り出し、膝に板を渡して細かく調べた。私とレストレードは身を乗り出し、恐ろしい遺物と、思索にふけるホームズの顔とを交互に見つめた。やがてホームズは耳を箱に戻し、しばし沈思黙考した。
「当然気づいたと思うが」とついに口を開いた。「これは左右で対の耳ではない。」
「確かに気付いた。だが、もし解剖室の学生たちの悪ふざけなら、左右揃いでなくても簡単に送れるだろう。」
「その通り。だが、これは悪ふざけではない。」
「そう確信しているのか?」
「状況証拠は明らかにそうだ。解剖室の遺体は防腐液を注入されているが、この耳にはその痕跡がない。しかも新しい。鈍い刃物で切られているが、学生ならそんなことはしない。さらに、防腐剤として医者なら石炭酸か精製酒精を使うはずだが、粗塩など思いつかない。この事件は悪ふざけではなく、重大な犯罪だ。」
私は友人の言葉と、その顔に刻まれた厳しい表情を見て、得体の知れぬ恐怖が背筋を走った。このおぞましい出来事の背後には、奇妙で不可解な凶事が潜んでいるようだった。しかしレストレードは半信半疑といった様子で首を振った。
「悪戯説にも異論はあるが、他の仮説にはもっと大きな反論がある」と彼は言った。「この女性は過去二十年間、ペンジやこの地で静かに暮らしてきた。ほとんど家を空けたこともない。なのに、なぜ犯罪者が証拠を彼女に送りつける? 彼女が本当に何も知らないなら、なおさらだ。」
「まさにそれが解くべき問題だ」とホームズは応じた。「私は自分の推理が正しいと仮定して進める――つまり、二重殺人が起きたという前提だ。この耳の一つは女性のもの――小ぶりで形が良く、イヤリングの穴がある。もう一つは男性のもの――日焼けし、変色し、やはりイヤリングの穴がある。この二人は、もし生きていれば何かしら情報が入っているはず。今日は金曜日。小包は木曜の朝に出された。事件は水曜か火曜、あるいはそれ以前だ。もし二人が殺されたなら、犯人以外に誰が証拠をミス・カッシングに送るだろう? 小包の差出人が捜すべき犯人ということになる。だが、何のために? 事件が終わったと知らせるためか? あるいは彼女を苦しませるためかも知れない。しかしそれなら彼女は誰か分かっているはずだ。だが本当に知っているだろうか? 疑わしい。知っていれば警察を呼ばず、耳を埋めてしまえば誰にも分からなかったはずだ。犯人をかばいたいならそうしただろうし、かばいたくないなら犯人の名を明かすはず。ここには、解きほぐすべき絡まりがある。」
ホームズは高く速い声で話しながら、ぼんやりと庭の塀の向こうを見上げていたが、今や素早く身を起こし、家の方へ歩き出した。
「ミス・カッシングにいくつか質問したいことがある」とホームズが言った。
「それなら、私はここでお暇しよう」とレストレード警部。「他にも小さな用件があるのでね。ミス・カッシングからこれ以上得るものはないと思う。警察署にいるから、何かあればそこに来てくれ」
「我々も列車に乗る前に立ち寄ることにしよう」とホームズ。
しばらくして、私とホームズは再び表の部屋に戻った。無表情な女性は、まだ静かにアンティマカサーを手仕事していた。私たちが入ると、彼女はそれを膝の上に置き、澄んだ青い目でまっすぐに、そして洞察力をもってこちらを見つめた。
「私は確信しています、先生」と彼女は言った。「これは何かの間違いで、その小包はもともと私宛ではなかったのだと思います。スコットランド・ヤードの紳士にも何度も申しましたが、彼はただ笑うばかりです。私には、知る限り敵など一人もいませんし、どうして誰かがこんないたずらをするのでしょう?」
「私も、同じ意見に傾きつつあります、ミス・カッシング」とホームズは彼女の隣に腰を下ろしながら言った。「おそらく……」と言いかけて、言葉を切った。私は驚いて周囲を見回し、ホームズが女性の横顔を並々ならぬ注意で見つめているのに気づいた。驚きと満足が一瞬、その熱心な顔に表れたが、彼女が沈黙の理由を知ろうと視線を向けると、いつもの通り慎み深い表情に戻っていた。私も彼女の平らで白髪交じりの髪、きちんとしたキャップ、小さな金のイヤリング、穏やかな顔立ちをじっくり見つめたが、私の連れが興奮している理由はわからなかった。
「いくつかお聞きしたいことが――」
「もう質問はうんざりです!」とミス・カッシングはせっかちに叫んだ。
「妹さんが二人いらっしゃるそうですね」
「どうしてそれがわかるのですか?」
「部屋に入った瞬間、暖炉の上に三人の女性の肖像写真があるのを見ました。一人は間違いなくご自身で、他の二人もとてもよく似ていらっしゃるので、親子関係に疑いはありません」
「はい、その通りです。あれは私の妹たち、サラとメアリーです」
「そして、私の肘元には、リヴァプールで撮られた妹さんの写真がありますが、彼女は船員の制服を着た男性と一緒です。まだ独身のころのようですね」
「観察が早いのですね」
「それが私の商売です」
「おっしゃる通りです。でも、その後まもなくブラウナーさんと結婚しました。彼はあの時、南米航路の船に乗っていましたが、妹への思いが強すぎて長く離れていられず、リヴァプールとロンドン間の船に転職したのです」
「なるほど、コンカラー号ですか?」
「いいえ、最後に聞いたのはメイ・デイ号です。ジムは一度ここに会いに来たことがあります。それは彼が禁酒の誓いを破る前でしたが、その後は岸に上がるたびに酒を飲むようになり、ほんの一杯で正気を失うほどでした。ああ、また酒に手を出したあの日は本当に不幸な日でした。最初は私を遠ざけ、次にサラと喧嘩し、メアリーも今は手紙をくれなくなったので、二人の様子は分かりません」
ミス・カッシングが非常に心を動かされている話題に触れたことは明らかだった。孤独な生活を送る人によくあるように、最初は控えめだったが、やがてとても打ち解けて話すようになった。彼女は義弟である船員について多くの詳細を語り、話は元下宿人の医学生たちへと逸れ、彼らの不始末や病院名まで長々と話してくれた。ホームズは時折質問を挟みながら、全てを熱心に聞いていた。
「二番目のお姉さんサラについてですが」とホームズが言った。「お二人とも独身のご姉妹なのに、一緒に暮らさないのが不思議ですね」
「ああ、サラの気性をご存知ないからですよ。クロイドンに来た当初は試してみましたが、二ヶ月ほど前についに別れることになりました。姉妹の悪口は言いたくありませんが、サラは昔から干渉好きで気難しい人でした」
「リヴァプールの親戚とも喧嘩されたのですね」
「ええ、以前はとても仲が良かったんですよ。だからわざわざ向こうに住むようになったくらいで。でも今ではジム・ブラウナーの悪口ばかり言うんです。ここにいた最後の半年は、彼の酒癖や素行の話ばかりでした。彼女が何か首を突っ込み過ぎて、ジムにきつく言われたので、それが諍いの始まりだったと思います」
「ありがとうございます、ミス・カッシング」とホームズは立ち上がり、丁寧に一礼した。「サラさんはウォリントンのニュー・ストリートにお住まいでしたね? さようなら、そしてご自身には何の関わりもないことでご心労をおかけしたことをお詫びします」
外に出ると、ちょうど馬車が通りかかったので、ホームズが呼び止めた。
「ウォリントンまではどのくらいだ?」
「ほんの1マイルほどですよ、旦那」
「それは都合がいい。ワトスン、乗ろう。鉄は熱いうちに打て、だ。この事件は単純だが、実に教訓的な点がいくつかあった。途中で電報局に寄ってくれ、御者」
ホームズは短い電報を送り、その後は日差しを避けるため帽子を顔に傾けて馬車の中でくつろいでいた。やがて、さきほどの家とよく似た家の前で馬車が止まった。連れが御者に待つように命じ、ノッカーに手をかけたとき、黒い服にピカピカの帽子をかぶった若い真面目そうな男が戸口に現れた。
「ミス・カッシングはご在宅ですか?」とホームズ。
「サラ・カッシングさんは非常に重い病状です」と男は言った。「昨日から深刻な脳の症状が出ており、主治医の私としてはどなたにも面会させる責任は取れません。10日後にまたお越しください」
そう言って彼は手袋をはめ、ドアを閉めて街へと去っていった。
「仕方ないなら仕方ないさ」とホームズは明るく言った。
「そもそも彼女も多くは語ってくれなかったんじゃないか」
「私は何も話してもらうつもりはなかった。彼女を一目見たかっただけだ。まあ、もう十分手がかりは揃った。御者、どこかまともなホテルまで頼む。昼食を済ませたら、レストレードの所に寄ろう」
私たちは一緒に簡単な食事をとった。その間、ホームズが話題にしたのはバイオリンのことばかりで、自分のストラディヴァリウスをトッテナム・コート・ロードのユダヤ人質屋で55シリングで買ったが、実際は少なくとも500ギニーの価値があると誇らしげに語った。そこから話題はパガニーニに移り、ホームズはあの奇才の逸話を次々と語りながら、私たちはクラレットを一本空けて一時間も談笑した。午後もだいぶ遅くなり、日差しが柔らかに変わったころ、私たちは警察署に着いた。レストレードは入り口で待っていた。
「電報が届いてます、ホームズさん」と彼。
「ほう、返事が来たな!」
ホームズは封を破り、目を通した後、そのままポケットに丸めて入れた。「よし、これでいい」
「何か分かったのか?」
「すべて分かった!」
「なんだって!」とレストレードは驚いて見つめた。「冗談でしょ?」
「生涯でこれほど真剣だったことはない。忌まわしい犯罪が行われ、私は今やその全貌を明らかにしたと思う」
「そして犯人は?」
ホームズは名刺の裏に何か書き付け、それをレストレードに投げ渡した。
「その名だ。逮捕は早くても明日の夜までできない。できるなら、この事件に関して私の名は一切出さないでほしい。私は、解決が難しい事件にのみ関わることにしているからだ。行こう、ワトスン」
そう言って、私たちは駅へと歩き出し、レストレードはホームズの投げたカードを嬉しそうに見つめていた。
「この事件はね」とその夜、ベイカー街の部屋で葉巻をくゆらせながらホームズが言った。「君が『緋色の研究』や『四つの署名』で記録してくれた捜査と同じく、“結果から原因へ”と遡って推論を重ねるしかなかった。私はレストレードに、犯人を確保した後にしか判明しない詳細を知らせてほしい、と手紙を書いてあるよ。彼なら間違いなく任せて大丈夫だ。推理力は皆無でも、一度やるべきことが分かれば、ブルドッグのような粘り強さで必ずやり遂げる。それがスコットランド・ヤードで彼が出世した理由さ」
「じゃあ、君の事件はまだ完全ではないのか?」
「本質的にはほぼ完成だ。忌まわしい事件の首謀者は分かっているが、犠牲者の一人はまだ見つからない。君はどう考えている?」
「リヴァプール船のスチュワード、ジム・ブラウナーが容疑者なんだろう?」
「容疑以上の確信だ」
「でも、漠然とした手がかりしか見当たらないが……」
「いや、私の考えではこれほど明快な事件はない。主な手順を振り返ろう。まず、私たちは先入観なしでこの事件に臨んだ。理論も仮説もなかった。ただ観察し、そこから推論を引き出した。最初に見たのは、何の秘密もなさそうな穏やかな婦人と、彼女に若い妹が二人いることを示す写真だった。すぐに、箱はその妹たちのどちらか宛かもしれない、と閃いた。だがそれは後で確認できるから脇に置いた。それから庭に出て、黄色い箱の奇妙な中身を見た。
ひもは船の帆縫い職人が使う質のもので、現場から海の香りが感じられた。結び目も水夫に人気のある型、発送地は港町、男性の耳には船乗りによくあるピアスの穴。役者は全員、海の関係者だと確信した。
次に小包の宛名を見ると、“ミス S. カッシング”となっていた。もちろん長姉は“ミス・カッシング”だが、頭文字のSは他の姉妹にも当てはまる。となると、捜査の出発点を変える必要がある。だからこの点を明らかにしようと家に入った。ミス・カッシングに、これは宛先違いの可能性が高いと告げようとしたが、急に言葉を止めたのを覚えているだろう。見たばかりのことで非常に驚き、捜査範囲が一気に狭まったからだ。
医学者として知っているはずだが、耳ほど個体差の大きい部位はほかにない。ほとんど唯一無二で、他人と一致しない。去年の『人類学雑誌』に、私がその件で短論文を2本寄稿している。だから箱の耳を専門家の目で観察し、特徴を記憶していた。ところがミス・カッシングを見ると、女性の耳と完全に一致したのだ。偶然とは到底思えない。耳介の短さ、上部の広いカーブ、内側軟骨の形――すべてそっくりだった。
この発見がどれほど重大かわかった。犠牲者は極めて近い血縁者であろう、と。そこで家族の話を始め、彼女も有益な情報を与えてくれた。
まず、妹の名はサラで、つい最近まで同じ住所だった。だから宛先間違いが起きた理由も明白で、この小包は誰宛だったかも分かった。そして、三女の夫であるスチュワードの存在を知った。彼はかつてサラと非常に親しかったため、サラはリヴァプールまで引っ越してまで彼らの近くに住んだが、その後の喧嘩で絶縁。以降、数か月も連絡を断っていたので、もしブラウナーがサラに小包を送ろうとしたなら、旧住所宛になったはずだ。
これで事件は一気に整理がついた。気性激しく情熱的な――君も覚えているだろうが、地位の高い職を妻への思いで投げ捨てた――衝動的で時に酒癖の悪いスチュワードの存在。そして、妻が殺され、もうひとり――恐らく海の男――も同時に殺されたという推測。動機は明らかに嫉妬だ。なぜサラ宛に証拠品を送ったのか? おそらくリヴァプール在住時に、彼女が悲劇の発端となる何かに関与したからだろう。船はベルファスト、ダブリン、ウォーターフォードに寄港するので、ブラウナーが殺人を犯してすぐメイ・デイ号に乗ったと仮定すれば、最初に小包を投函できるのはベルファストだ。
この時点で、もうひとつの可能性も考慮した。実現性は低いが、恋敵がブラウナー夫妻を殺し、男の耳は夫のものだったという線だ。異論は多かったが、検証は必要だった。そこでリヴァプール警察の友人アルガーに電報を送り、“メアリー・ブラウナーが在宅か、そしてブラウナーがメイ・デイ号で出発したか”を確かめさせた。そして我々はウォリントンのサラを訪ねた。
まず、家系特有の耳がどこまで再現されているか見たかった。もちろん重要な情報が得られる可能性もあったが、それはあまり期待していなかった。事件は前日からクロイドン中の噂になっており、誰宛の小包か理解できたのは彼女だけだったはずだ。もし彼女が捜査協力の意思があれば既に警察に連絡しているはず。それでも形式上、訪問した。すると小包到着のニュース――彼女の病はその日から始まった――が彼女に脳障害を引き起こすほどの衝撃を与えていた。彼女がその意味を完全に理解し、しばらく協力は望めないことがますます明らかになった。
だが、我々は実際には彼女の助けを必要としていなかった。答えは警察署で待っていた。私はアルガーに返答を回すよう指示してあったからだ。内容は決定的だった。ブラウナー夫人の家は三日以上閉まっており、近隣住民は彼女が親戚を訪ねて南下したと思っていた。船会社の記録からもブラウナーはメイ・デイ号で出航したことが判明した。彼がテムズ川に戻るのは明晩のはずだ。着けば、鈍重だが粘り強いレストレードが待ち構えているだろうし、詳細もすべて明らかになるはずだ」
シャーロック・ホームズの予測は外れなかった。二日後、分厚い封筒が届いた。中には刑事からの短い手紙と、数ページにわたるタイプ原稿が同封されていた。
「レストレードはちゃんと逮捕したな」とホームズは私を見上げて言った。「内容を聞きたいかもしれないね。
『親愛なるホームズ様――
我々が立てた理論を検証するための計画に基づき――“我々”という言い回しはなかなか立派だろう、ワトスン――
私は昨日午後6時、アルバート・ドックに赴き、リヴァプール、ダブリン、ロンドン汽船会社所属のS.S.メイ・デイ号に乗船しました。調べたところ、ジェームズ・ブラウナーという名のスチュワードが乗っており、航海中にあまりにも異常な振る舞いをしたため、船長は彼を職務から外さざるを得ませんでした。彼の部屋に降りていくと、彼は両手に顔をうずめて胸の上で前後に揺れていました。彼は大柄で力強そうな男で、ひげを剃り、色黒で、かつて偽洗濯屋事件で協力してくれたオルドリッジにどこか似ていました。私の用件を聞くと立ち上がりましたが、私はすぐに警笛を口にくわえ、角を曲がったところにいるリバーポリスを呼ぼうとしました。しかし、彼には全く抵抗の気持ちがなく、静かに手錠を差し出しました。彼と一緒にその箱も持ち帰りましたが、船乗りがよく持つ大きな鋭いナイフ以外には何も incriminating な物はありませんでした。しかし証拠はもう十分です。署で取り調べを受けた際、供述を申し出たので、そのまま速記で記録し、三部タイプで写しを作りました。そのうちの一部を同封します。この事件は、私が思っていた通り、極めて単純なものでしたが、ご助力には感謝します。敬具――G.レストレード』
「ふむ! 本当に調べはごく単純なものだった」とホームズが言った。「だが、最初に我々が呼ばれたとき、彼はそうは思わなかっただろう。しかし、さて、ジム・ブラウナー自身の言い分を聞いてみよう。これは彼がシャドウェル警察署でモンゴメリー警部の前で述べた供述で、一言一句そのまま記録されているという利点がある。」
「言いたいことがあるかって? ああ、大いにあるさ。全部包み隠さず話さなきゃならん。俺を絞首台に送るもよし、見逃してもよし、どちらでも構わん。やったあの日から一睡もできちゃいないし、おそらくもう二度と眠れやしないと思ってる。時にはあいつの顔が、でも大抵はあの女の顔が目の前に浮かぶ。どちらかが、常に俺の前にいる。あいつは眉をひそめ、黒々とした顔をしているが、彼女は驚きの表情を浮かべていた。ああ、白い子羊のようなあの子が、今まで愛しか見せなかった顔に死の影を読んだ時、そりゃ驚くのも無理はない。
「だが、すべてはサラのせいだ。壊れた男の呪いがあの女を蝕み、その血を腐らせるように! 自分を正当化したいわけじゃない。自分がどんな獣だったかも、酒に戻ったことも分かってる。でも、もしあの女が我が家の戸をくぐることがなければ、メアリーは俺を許し、どんな困難でも離れなかったはずだ。サラ・カッシングは俺を愛していた――それが全ての根っこだ――俺が妻の泥についた足跡よりも、サラの体も魂も軽んじていると知ったとき、彼女の愛は毒のような憎しみに変わったのさ。
「三姉妹がいた。長姉は善良な人だったが、次女は悪魔、三女は天使だった。サラは三十三歳、メアリーは俺が結婚したとき二十九だった。俺たちは新居を構えたとき、日が暮れるまで幸せに満ちていたし、リバプール中でメアリーほどの女はいなかった。それから一週間サラを呼んだが、その一週間が一月になり、あれこれあって、彼女はすっかり我が家の一員になっていた。
「その頃俺は禁酒運動の青いリボンをつけていて、少しずつ貯金もして、何もかもが新しい銀貨のように輝いていた。まさかこんなことになるなんて、誰が想像しただろう? 一体誰が夢にも思っただろう?
「俺は週末ごとに家に帰ることが多く、時には船の積み荷の都合で一週間まるごと家にいられることもあった。そんなふうにして、義姉のサラと過ごす時間も増えた。彼女は背が高く、黒髪で素早くて気性が激しく、誇らしげに首を高く上げ、目には火花のような光があった。でも、小さなメアリーがいるとき、俺はサラに少しも気を引かれたことはなかった――神の御慈悲を願う者として誓う。
「時々、サラは俺と二人きりになりたがったり、散歩に誘い出そうとしたりしていた。でも、そのことは特に気にもとめていなかった。だが、ある晩、俺の目が開かれた。船から帰ると妻はいなくて、サラが家にいた。『メアリーはどこだ?』と聞くと、『ああ、勘定を払うために出かけた』と言う。俺は苛立って部屋の中を行ったり来たりした。すると彼女が言う、『メアリーがいなくても五分くらい幸せでいられないの、ジム? 私と一緒にいるだけじゃ満足できないなんて、私にとっては悪い冗談だわ』。『大丈夫だよ』と俺は優しく手を差し出したが、彼女は両手で俺の手をつかみ、それは熱病のように熱かった。俺はその目を見て、すべてを悟った。言葉なんていらなかった。俺は眉をひそめ、手を引っ込めた。彼女はしばらく黙って俺のそばに立っていたが、やがて肩を軽く叩き『しっかりしろよ、ジム』と嘲るように笑って部屋を出ていった。
「それ以来、サラは全身全霊で俺を憎むようになったし、彼女は本当に人を憎める女だった。そんな彼女を家に置いておいた俺は、まったくの馬鹿だ――酔っ払いの愚か者だ。でもメアリーには何も言えなかった。彼女を悲しませたくなかったからだ。表面上は以前と変わらぬ生活が続いていたが、しばらくしてメアリー自身にも変化が現れ始めた。彼女はいつもは信頼深く無邪気だったのに、今では妙に疑い深くなり、俺がどこに行ったか、何をしたか、誰から手紙が来たか、ポケットに何が入っているか、そんなことをしつこく聞くようになった。日ごとにおかしくなり、些細なことで喧嘩が絶えなかった。俺には全く訳が分からなかった。サラは俺を避けるようになったが、彼女とメアリーはいつも一緒だった。今になって思えば、サラが巧みに策略を巡らし、妻の心を俺に対して毒していたのだが、当時の俺はまるで盲目の甲虫で、何も分からなかった。それから俺は禁酒の誓いを破って再び酒に溺れたが、もしメアリーが変わらずいてくれたなら、飲み始めることはなかっただろう。今や彼女は俺に嫌悪感を抱く理由ができ、その溝はどんどん広がっていった。そして、そこへアレック・フェアバーンが現れ、事態は千倍も悪くなった。
「最初はサラに会いに家に来ていたが、すぐに俺たち夫婦にも会いに来るようになった。人懐っこく、どこへ行っても人を引きつける男だった。派手で威勢がよく、洒落者で、世界の半分を見てきたと豪語し、その話を面白おかしく語ることができた。船乗りのくせに礼儀作法も申し分なく、たぶん昔は甲板より船尾の方に馴染みがあったのかもしれない。一ヶ月の間、彼は家を出入りしていたが、俺は彼の軟派なやり方に何の疑いも持たなかった。しかしある日、ちょっとしたことがきっかけで疑念が生じ、それから俺の平和は永遠に失われた。
「ほんの些細なことだった。俺が不意に居間に入ると、妻の顔が誰かを待ちわびるように明るくなった。でも、俺だと分かった瞬間、その笑顔は消え、失望の色が浮かんだ。それですべてを悟った。アレック・フェアバーンの足音と俺の足音を間違えるはずはない。そのとき彼が目の前にいたら、俺はきっと殺していただろう。俺は癇癪を起こすと手がつけられないのだ。メアリーは俺の目に鬼火が宿るのを見て、慌てて俺の袖をつかんで『やめて、ジム、やめて!』と叫んだ。『サラはどこだ?』と俺が聞くと、『台所よ』と答えた。俺は台所に行き、『サラ、このフェアバーンって男は二度と俺の家の敷居をまたがせない』と言った。『なぜ?』とサラが尋ねる。『俺がそう命じるからだ』。『ああ、もし私の友達がこの家にふさわしくないなら、私もふさわしくないってことね』。『好きにしろ。ただし、フェアバーンがまたここに来たら、あいつの耳をお前に土産で送ってやる』。サラは俺の顔に怯え、何も言わず、その晩家を出ていった。
「さて、この女の所業がただの意地悪なのか、それとも妻の素行を悪くさせて俺を妻から遠ざけようとしたのか、今となっては分からない。とにかく、サラは近くの通りに家を借り、水夫たちに下宿を貸し始めた。フェアバーンはそこに出入りし、メアリーも姉と彼に会いにしばしば茶を飲みに行った。何度通ったかは知らないが、ある日俺が後をつけて、家に踏み込んだとき、フェアバーンは裏庭の塀を越えて逃げ出した――まったく臆病な野郎だ。俺は妻に、もう一度あいつと一緒にいたら殺すと誓い、泣きじゃくる妻を家へ連れ帰った。もう愛情のかけらもなかった。彼女は俺を憎み、恐れているのが分かったし、そのことが俺を酒に走らせ、今度は彼女も俺を軽蔑した。
「やがてサラはリバプールでは暮らしていけないと悟り、クロイドンの妹のもとに戻ったと聞いている。家の中は以前と変わりない日々が続いた。そして、あの最後の週がやってきて、全てが破滅した。
「こういう経緯だった。俺たちはメイ・デイ号で七日間の航海に出たが、樽が外れて船板を壊し、結局十二時間だけ港に戻ることになった。俺は船を降りて家に帰った。妻を驚かせてやろう、きっと喜んでくれるだろう――そんなことを考えながら自分の通りに入った。そこへ馬車が通り過ぎ、中を見ると妻がフェアバーンの隣に座っていた。二人は楽しげに話し、笑い、俺の存在など眼中にない様子だった。
「いいか、あの瞬間から俺は自分が自分じゃなくなった。その後のことはすべて夢のようにぼんやりしている。最近酒をひどく飲んでいたし、その二つが俺の頭を完全に狂わせた。今でも頭の中で何かがドンドン打ち鳴っているが、あの朝はナイアガラの滝が耳元で轟いているようだった。
「俺は馬車を追いかけて走った。手には重いオークの杖を握っていた。最初から頭に血が上っていたが、走るうちに冷静になって、気づかれずに二人を見張ろうと距離を置いた。二人はすぐに駅で降りた。切符売り場には人だかりができていたので、俺はかなり近くまで寄ることができた。二人はニュー・ブライトン行きの切符を買った。俺も同じ切符を買い、三両後ろの車両に乗った。着くと、二人は遊歩道を歩き、俺は常に百ヤード以内をつけていた。やがて二人はボートを借りて漕ぎ出した――とても暑い日だったので、水の上なら涼しいと思ったのだろう。
「あたかも二人が俺の手に落ちてくるようだった。少し霧が出ていて、数百ヤード先も見通せなかった。俺もボートを借りて漕ぎ出した。二人の舟影はぼんやり見えていたが、俺もかなり速く漕いだので、岸から一マイルは離れたあたりで追いついた。霧がまるでカーテンのように三人を包み込み、俺たちだけがその中にいた。俺の船が近づくと、二人の顔――あの顔は決して忘れられない。妻は叫び声を上げ、奴は狂ったように罵り、オールで俺を突こうとした。俺の目に死が映っていたのだろう。俺はそれをかいくぐり、杖で頭を叩き割った。妻のことは、あの時の激昂の中でも、もしかしたら許したかもしれない。しかし彼女は奴にしがみつき、『アレック!』と叫び、泣き叫んだ。俺はもう一度打ちつけ、彼女も奴の隣に倒れた。そこからは血を味わった獣のようだった。もしサラがいたら、きっとあの二人の隣に送り込んだだろう。俺はナイフを取り出し――もう、これ以上は言うまい。サラがこの結果を見て、自分の干渉がどれほどの事態を招いたか思い知る、そのことに獣じみた満足を覚えた。遺体をボートに縛り付け、船底の板を壊し、沈むのを見届けた。持ち主は霧で道を見失い、海に流されたと思うだろうと踏んでいた。身なりを整えて上陸し、誰にも怪しまれずに船に戻った。その夜、サラ・カッシング宛の小包を用意し、翌日ベルファストから投函した。
「これがすべての真実だ。俺を絞首台に送るも、好きにするがいい。だが、すでに俺は十分すぎるほど罰を受けている。目を閉じれば、あの二人の顔が俺を見つめている――俺の舟が霧を突き破ったときのように、じっと。俺は二人を一瞬で殺したが、あいつらは俺をじわじわと殺し続けている。この夜をもう一晩過ごせば、明日までに俺は狂うか死ぬかだろう。どうか、俺を独房に一人きりにしないでくれ、旦那。頼むから。それだけは――今あなたが俺を扱うように、あなたも苦しみの日には同じ扱いを受けますように。」
「これはどういう意味なのだ、ワトソン?」とホームズは厳かに言い、紙を机に置いた。「この連鎖する苦しみ、暴力、恐怖は、何のためにあるのか? 何かしらの目的に向かっているに違いない――でなければ我々の宇宙は偶然に支配されていることになるが、それは考えられない。しかし、何のために? これが人間の理性がいまだ解を見出せない、大いなる永遠の謎というものだ。」
III. 黄色い顔
この短編連作を発表するにあたり、私の同伴者が持つ特異な才能によって、我々が奇妙な事件の目撃者となり、ついには当事者となった数々の体験に基づいている以上、彼の成功談に偏って筆を進めるのは当然の成り行きである。そしてそれは、彼の名声のためばかりでなく――実のところ、彼が途方に暮れた時こそ、その精力と多才ぶりは最も称賛に値したのだが――失敗した事件では、他の誰も解決できず、物語が永遠に未完のまま終わることがあまりに多かったからでもある。ただ、時折、彼が誤った推理をした場合でも、真実が明らかになることもあった。私の記録にはそうした例が半ダースほどあり、「第二の血痕事件」と、今から語る事件は特に興味深い特徴を持っている。
シャーロック・ホームズは、ただ運動のためだけに身体を動かすことはほとんどなかった。並外れた体力を持ち、同じ体重の者の中では最高のボクサーだと私が見た中でも断言できるが、目的のない肉体労働はエネルギーの浪費と考えており、何か職業上の目的がある場合しか積極的に身体を動かすことはなかった。その時の彼はまさに不眠不休の働きぶりだった。そんな彼が体調を維持していたことは驚くべきことだが、食事は極めて質素で、生活習慣もほとんど禁欲的といえるほど簡素だった。時おりコカインを使うことを除いて、悪癖というものはなく、それも事件がなく、新聞も退屈な時、単調な日常への抗議としてだけ手を出していた。
ある年の早春、そんな彼が珍しく気を緩めて、私と一緒に公園を散歩したことがあった。楡の木には淡い新芽がほころび始め、トチノキのベタつく芽も五枚葉になろうとしていた。二時間ほど、親しい間柄らしくほとんど無言で連れ立って歩いた。ベイカー街の我が家に戻ったのは、ほぼ五時近くだった。
「失礼します、旦那」と、扉を開けたボーイが言った。「さっき、旦那を訪ねて来られた紳士がいました。」
ホームズは私を恨めしげに見た。「これが午後の散歩の成果か! その紳士はもう帰ったのか?」
「はい、旦那。」
「中にお通ししなかったのか?」
「いえ、旦那。中にお通ししました。」
「どれくらい待っていた?」
「三十分です、旦那。とても落ち着かないご様子で、ずっと部屋の中を歩き回っておられました。私は外の廊下にいたのですが、足音が聞こえてきました。ついには廊下に飛び出し、『あの男はいつまで来ないんだ?』と叫んだんです。確かにそうおっしゃいました。『もう少しだけお待ちください』と私が言うと、『それなら外の空気を吸って待つ、息が詰まりそうだ』とおっしゃって、『すぐ戻る』と言い残して外に出て行かれました。引き留めようとしましたが、無理でした。」
「まあ、よくやったよ」とホームズは言い、部屋へ入った。「それにしても残念だ、ワトソン。ちょうど事件が欲しいと思っていたのに、男性の様子からして、大事な用件らしい。おや? あのパイプは君のじゃないな。きっと置き忘れていったんだろう。なかなかいい古いブライヤーパイプで、茎は俗に琥珀と呼ばれるものだ。本物の琥珀マウスピースがロンドンにどれだけあるか……虫が入っているのが本物の証拠だと思い込んでいる人がいるが。ともかく、彼の心が乱れていたからこそ、大事にしているパイプを忘れていったのだろう。」
「どうして大事にしていたと分かるんだい?」と私は尋ねた。
「このパイプのもともとの値段は七シリング六ペンスくらいだろう。だが見てごらん、木の茎と琥珀の部分、両方一度ずつ銀のバンドで修理されている。この修理代は、パイプそのものより高かったはずだ。それでも新しいものを買わず、わざわざ直して使い続けるということは、このパイプをとても大切にしている証拠だ。」
「他に分かることは?」と私は聞いた。ホームズはパイプを手に取り、例の思索的な様子でじっと見つめていた。
彼はそれを持ち上げて、長く細い人差し指でトントンと叩き、まるで骨について講義する教授のようだった。
「パイプというのは、ときに非常に興味深いものだ」と彼は言った。「個性という点では、もしかすると時計や靴紐を除けば、これほどはっきりとしたものは他にない。もっとも、ここで見られる特徴は、さほど目立つものでも重要なものでもない。持ち主は明らかに筋骨たくましい左利きの男で、歯並びも見事、生活態度は大雑把で、倹約の必要も感じていないようだ。」
ホームズは何気なくこの情報を口にしたが、私の反応を見ようと、さりげなく私に目を向けた。
「七シリングもするパイプを吸うなら、裕福な男に違いないというわけか」と私は言った。
「これは“グロスヴェナー・ミクスチャー”で、1オンス八ペンスだ」とホームズは言い、手のひらに少し叩き出した。「半値でもいい煙草が手に入るのだから、倹約なんて考えていない証拠だ。」
「他の点は?」
「彼は普段、ランプやガス灯でパイプに火をつけている。片側が黒く焦げているのが見えるだろう。マッチではこんな風にはならない。なぜマッチをパイプの側面に当てる必要がある? だが、ランプで火をつけようとすれば、どうしてもボウルが焦げる。しかも焦げているのはパイプの右側だけだ。だから左利きの男だと推測できる。自分のパイプで試してみるといい。君は右利きだから、自然と左側を炎に近づけるはずだ。逆に持つことも一度はあるかもしれないが、いつもそうすることはない。このパイプは常に同じ持ち方をされていた。そして、彼はアンバー(琥珀)のマウスピースを噛み切っている。これは力強く、活動的で、歯並びの良い男でなければできないことだ。だが、どうやら階段を上がってくる音がする。パイプよりも面白いものが調べられそうだ。」
その瞬間、私たちの扉が開き、背の高い若い男が部屋に入ってきた。彼は暗いグレーのスーツをきちんと、だが控えめに着こなし、手には茶色のソフト帽を持っていた。私は彼を三十歳くらいだと見積もったが、実際はもう少し年上だった。
「失礼します」と彼はやや気まずそうに言った。「ノックすべきだったと思います。ええ、もちろんノックすべきでした。実は少し動揺していまして、すべてそれのせいにしてください。」彼は放心したように額に手をやり、それから、椅子に腰かけるというよりは崩れ落ちるように座った。
「ここ数日、眠れていないようですね」とホームズは気さくな口調で言った。「それは仕事よりも、楽しみよりも、神経をすり減らすものです。どうお手伝いできるか、お聞かせいただけますか?」
「ご助言を頂きたいのです。どうすればいいのか分からず、人生がすべてめちゃくちゃになった気がします。」
「私を顧問探偵として雇いたいということですか?」
「それだけじゃありません。分別ある人間――世間を知る人間として、あなたの意見を伺いたいのです。次にどうすればいいのか教えてもらいたい。どうか、神にかけて、教えてください。」
彼は途切れ途切れに短く鋭い息で話し、言葉を口にすること自体が大変な苦痛で、意志の力で何とか自分を抑えているようだった。
「とても繊細な問題なんです。自分の家庭のことを他人に話すなんて本当はしたくない。見ず知らずの二人に妻のことを話すなんてひどいことですが、もう限界なんです。どうしても助言が必要なんです。」
「グラント・マンロー氏――」とホームズが言いかけた。
来訪者は椅子から飛び上がった。「何ですって!」と叫んだ。「私の名前をご存じなんですか?」
「匿名を守りたいのであれば」とホームズは微笑みながら言った。「帽子の裏に名前を書かないか、あるいは相手に見せる側を反対に向けることをお勧めします。さて、私とこちらの友人は、この部屋で数々の奇妙な秘密に耳を傾けてきましたし、悩める方々に安らぎをもたらせたことも少なくありません。あなたにもきっとお力になれると信じています。時間が大切かもしれませんので、できるだけ早く事情をお聞かせ願えますか?」
来訪者は再び額に手をやり、話すことがいかに辛いかを示していた。所作や表情から、彼が誇り高く自制心の強い男で、傷をさらすより隠すタイプだと私には分かった。だが突然、固く握った拳を振り下ろすような仕草で、すべての自制をかなぐり捨て、語り始めた。
「こういうことです、ホームズさん」と彼は話し始めた。「私は結婚して三年になります。その間、妻と私は誰よりも深く愛し合い、幸せに暮らしてきました。意見の違いなど一度もなく、言葉にしろ行動にしろ、心にしろ、何ひとつ対立はありませんでした。それが、先週の月曜日から突然、私たちの間に壁ができてしまい、妻の心や人生の中に、通りすがりの見ず知らずの女性と同じくらい何も知らない部分があることに気づきました。私たちは疎遠になり、その理由を知りたいのです。
「先に、はっきり伝えておきたいことが一つあります、ホームズさん。エフィーは私を愛しています。その点は間違いありません。彼女は心から私を愛しており、今ほど強く愛していることはありません。私はそれを知っているし、感じています。この点だけは議論するつもりはありません。男なら女性が自分を愛しているかどうか、すぐに分かるものです。でも、私たちの間には今、秘密ができてしまい、それが解決しない限り、元通りにはなれません。」
「事実をお聞かせください、マンロー氏」とホームズがいくらか苛立たしげに言った。
「エフィーの過去について私が知っていることをお話しします。初めて出会ったとき、彼女は未亡人でしたが、とても若くて――まだ二十五歳でした。当時の名はヘブロン夫人。彼女は若いころアメリカのアトランタという町に渡り、そこでヘブロンという弁護士と結婚しました。夫は立派な弁護士で、ふたりの間には子どもも生まれましたが、ひどい黄熱病が流行し、夫も子どももそれで亡くなりました。私は彼の死亡証明書を見ました。そのことですっかりアメリカに嫌気がさし、エフィーはミドルセックス州ピナーの独身の叔母のもとへ戻りました。ちなみに、夫は彼女を経済的に不自由しないようにしてくれていて、約四千五百ポンドの資産があり、それは彼が上手に運用して、年利七パーセントの収入がありました。ピナーに来て半年で私は彼女と知り合い、恋に落ちて、数週間後には結婚しました。
「私はホップ(ビールの原料)の商人で、自分でも年に七百から八百ポンドの収入があり、二人でゆとりのある暮らしができました。ノーバリーに年八十ポンドの素敵なヴィラを借りました。私たちの住まいは町に近いわりにとても田舎らしい雰囲気で、近くには宿屋が一軒と家が二軒、それから私たちの家の前の畑の向こう側に小さなコテージが一軒あるだけで、そこから駅までの半分ほどは他に家はありませんでした。私の仕事は季節によって都心に出ることもありましたが、夏は手が空くので、田舎の家で妻と本当に幸せな時を過ごしました。この忌まわしい出来事が起きるまでは、私たちの間に影など一片たりともありませんでした。
「ここで、先に伝えておくべきことがあります。結婚の際、妻は自分の財産をすべて私に譲渡しました――正直、私はうまくいかなかったときのことを考えて気が進まなかったのですが、彼女がどうしてもそうしたいと言うので、結局そうしました。さて、六週間ほど前のことです。妻が私のもとにやってきました。
『ジャック』と妻は言いました。『あなた、私のお金を預かってくれるとき、“もし必要になったらいつでも言ってくれ”って言ってたでしょう?』
『もちろんだよ。全部君のものだ』
『それでね、百ポンドほしいの』
私は少し驚きました。ちょっとした新しいドレスでも欲しいのかと思っていたのです。
『いったい何のために?』
『あら』と妻は茶目っ気たっぷりに言いました。『あなたは私の銀行家だって言ったわよね。銀行家はお金を引き出す理由なんて聞かないものでしょう?』
『本当に欲しいなら、もちろんあげるよ』
『ええ、本当に必要なの』
『何に使うかは教えてくれないのかい?』
『いつか、きっと。でも今はダメなの、ジャック』
私はそれで納得するしかありませんでした。これが、私たちの間に初めてできた秘密でした。私は小切手を渡し、あとは全く気に留めませんでした。その後の出来事と関係があるのかどうか分かりませんが、念のためお伝えしておきます。
「さて、先ほど申した通り、私たちの家の近くにコテージが一軒あります。畑を挟んだだけの距離ですが、道をぐるっと回って小道を下らないと行き着けません。そのすぐ先にはスコッチ・ファーの小さな林があり、私はよくそこを散歩していました。木々というのは、なんとも親しみやすいものです。そのコテージは八か月も空き家で、可愛らしくて二階建てで、古風なポーチとスイカズラが絡んでいて、こんな家に住めたらいいのにと思ったことも何度もありました。
「さて、先週の月曜日の夕方、私はそのあたりを散歩していました。すると、空の運搬車が小道を上がってくるのと、ポーチの脇の芝生にカーペットなどが山積みになっているのが見えました。どうやらついにあのコテージに借り手がついたのです。私は通り過ぎながら、どんな人々が近くに越してきたのかと考えていました。そのときふと、二階の窓からじっと私を見ている顔に気づきました。
「その顔が何だったのか、ホームズさん、よく分かりませんが、背筋が凍るような気分になりました。少し離れていたので、はっきり特徴までは分かりませんでしたが、何か人間離れした、不自然なものを感じたのです。もっとよく見ようと近寄ろうとした途端、その顔は闇の中に引き込まれるように消えてしまいました。私は五分ほど立ち止まり、自分の印象を分析しようとしましたが、それが男なのか女なのかも分かりませんでした。ただ、その顔色が印象的で、死人のような白さ、不気味なほど固まった表情が、あまりにも異様でした。その時の動揺が大きかったので、私は新しい住人についてもっと知りたくなりました。コテージに近づいてノックすると、すぐに背が高く、痩せぎすで、厳しい感じの女性が現れました。
『何の用だい?』と彼女は北部なまりで聞きました。
『向こうの家の者です』と私は自分の家を示して言いました。『引っ越されたばかりのようなので、何かお手伝いできることがあれば――』
『用があればこっちから頼むわ』と彼女は言い、ドアを閉めてしまいました。無礼な対応に腹を立て、私は背を向けて家に戻りました。その夜は気を紛らわそうとしても、窓の顔やあの女の無礼さがどうしても頭から離れず、妻にはあの顔のことは黙っておくことにしました。妻は神経が細やかで、余計な不安を与えたくなかったのです。ただ、寝る前に一言、コテージに人が入ったことだけ告げましたが、妻は何の返事もしませんでした。
「私は普段、とても深い眠りをするタイプです。夜中に起きることなど家族の笑い話になるくらい珍しいのですが、その夜はなぜか――あの出来事のせいかどうか分かりませんが――異様に浅い眠りでした。うとうとしながらも、部屋で何かが起こっているのをぼんやり感じ、やがて妻が身支度を整え、マントと帽子をつけていることに気付きました。私は半分寝ぼけたまま、驚きや注意の言葉を口にしかけましたが、ろうそくの光に照らされた妻の顔を見た瞬間、言葉を失いました。そんな表情を見たこともなければ、彼女がそんな顔をするとは思いもしませんでした。死人のように青白く、息を荒げ、時折ベッドを気にするようにちらちらと見て、私が起きていないか確かめているのです。私がまだ眠っていると思ったのか、音もなく部屋を出ていき、続けて玄関のきしむ音が聞こえました。私はベッドで起き上がり、手すりを叩いて夢でないことを確かめ、枕の下から時計を取り出しました。午前三時でした。こんな夜中に、妻が田舎道に出ていくなんて、一体どういうことなのでしょう?
「二十分ほどベッドで考えていましたが、思えば思うほど不可解で、説明のしようがありませんでした。まだ悩んでいると、ドアがそっと閉まり、階段を上がる妻の足音がしました。
『どこに行ってたんだ、エフィー?』と私は言いました。
私が声をかけると、彼女は激しく驚き、息を呑んだ叫び声をあげました。その反応が、何よりも私を不安にさせました。まるで後ろめたさそのものが表れているようでした。妻はもともと率直で隠し事のない性格だったので、自分の部屋にこそこそと戻る様子や、夫の声に怯えるような姿を見るのは、私にとっては耐えがたいことでした。
『起きてたの、ジャック!』と彼女は神経質な笑い声を上げました。『あなたは絶対起きないと思っていたわ』
『どこへ行っていたんだ?』と私はさらに厳しく尋ねました。
『驚くのも無理ないわね』と彼女は言い、マントの留め具を外す手が震えているのが分かりました。『今までこんなことしたことないもの。実は、息が苦しくて、どうしても新鮮な空気が吸いたかったの。外に出なければきっと気を失っていたと思うわ。戸口に少し立っていただけ、今はもう大丈夫よ』
この間中、彼女は私の方を一度も見ず、声もいつもの調子とは違っていました。明らかに嘘をついているのが分かりました。私は何も言わず、壁に顔を向けて、心が千々に乱れ、疑念と不安でいっぱいでした。妻は何を隠しているのか? あの奇妙な外出でどこに行っていたのか? 真実を知るまで決して安らげないと思う一方、一度嘘をついた相手にもう一度聞くのは、どうしてもためらわれました。その夜は一晩中、あれこれ考えを巡らせ、どれもこれも現実味のない理屈ばかり思い浮かべていました。
「その日は本来なら仕事でロンドンに行く予定でしたが、動揺が大きく、とても仕事に集中できる気がしませんでした。妻も私と同じくらい動揺しているようで、私が明らかに嘘を信じていないと分かっているのか、しきりに私の様子をうかがう視線を感じました。朝食の間も、ほとんど言葉を交わさず、私は気分転換に散歩に出ました。
「クリスタル・パレスまで歩き、庭で一時間ほど過ごし、一時にはノーバリーに戻りました。その道すがらコテージの前を通りかかったので、窓をのぞき、昨日見たあの奇妙な顔をもう一度見られないかと思って立ち止まりました。すると、驚いたことに、突然ドアが開き、妻が出てきたのです。
私は言葉を失いましたが、私の驚きなど妻の顔に表れた驚愕には及びませんでした。彼女は一瞬、家の中に戻ろうとしたようですが、もう隠しきれないと分かったのか、唇に笑みを浮かべながらも、恐怖に満ちた真っ白な顔、怯えた眼差しで私の方へ出てきました。
『あら、ジャック』と妻は言いました。『新しいご近所さんにお手伝いできることがないか、ちょっと様子を見てきたのよ。どうしたの、そんな顔して? 怒ってるの?』
『なるほど』と私は言いました。『昨夜、君が出かけた先はここだったんだね』
『何のこと?』と彼女は言いました。
『君はここへ来た。間違いない。こんな夜中に、わざわざ訪ねる相手って、一体どんな人たちなんだ?』
『私はここには来ていません』
『知っていて嘘をつくのか? 話し方まで変わっているじゃないか。僕が君に秘密を持ったことがあったか? 僕はこのコテージに入って、真相を突き止める!』
『やめて、ジャック、お願い!』と彼女は激しい動揺の中で叫びました。そして私がドアに近づこうとすると、彼女は私の袖を強くつかんで引き戻しました。
『どうか、お願いだからやめて、ジャック』と彼女は必死にすがりつきました。『いつか必ず全部話すわ。でも今ここに入れば、不幸しか生まれない』と涙ながらに懇願し、私は振りほどこうとしましたが、彼女はなおも狂乱したようにしがみつきました。
「『私を信じて、ジャック!』と彼女は叫んだ。『たった一度だけ、私を信じて。決して後悔させたりしないわ。あなたのためでなければ、私があなたに隠し事なんてするはずないの。これは私たちの人生すべてがかかっているのよ。もし私と一緒に家に戻ってくれるなら、すべてうまくいくわ。けれど、このコテージに無理やり入るなら、私たちはもう終わりよ。』
彼女の態度にはあまりにも真剣で、絶望的なものがあったので、その言葉に私は動きを止め、戸口の前でためらい立ち尽くしてしまった。
『一つだけ条件がある。その条件が守られるなら、君を信じよう』と私はついに言った。『それは、これ以上この謎を続けないということだ。君は秘密を守っていてもいいが、これからは夜ごと家を抜け出したり、私に隠れて何かをしたりすることは約束してくれ。今までのことは忘れるつもりだが、今後同じようなことは二度とないと誓ってくれ。』
『きっとあなたは信じてくれると思っていたわ』と、彼女は安堵の大きなため息とともに叫んだ。『あなたの望みどおりにするわ。さあ、行きましょう……お願い、家に戻って。』
彼女はなおも私の袖を引きながら、私をコテージから家へと導いた。道すがら、私はふと振り返った。そのとき、上階の窓から、あの黄色く蒼ざめた顔がこちらをじっと見ていた。あの生き物と妻とに、どんなつながりがあるというのか。前日に見た、あの粗野で不作法な女と妻とに、どういう関係があるのだろう。これは奇妙な謎だ。しかし、私はこれを解き明かすまで心安らぐことがないだろうとも思った。
この後二日間は家に留まり、妻も約束を忠実に守っているように見えた。私の知る限り、彼女は一歩も家の外に出なかった。しかし三日目になって、彼女の厳粛な誓いが、その秘密の力の前には何の効力もないことが、はっきりとわかる出来事が起きた。
その日は私が街へ出かけたが、いつもの3時36分発ではなく、2時40分発の列車で帰宅した。家に入ると、メイドが驚いた顔で廊下を走ってきた。
『奥様はどこだ?』と私は尋ねた。
『お散歩に出られたと思います』とメイドは答えた。
途端に私は疑念に駆られた。妻が家にいないか確かめようと、私は駆け上がった。その途中、ふと上階の窓から外を見やると、今しがた話したばかりのメイドが、コテージの方へと野原を駆けていくのが見えた。その時、すべてが理解できた。妻はコテージへ行き、私が戻ったらメイドに呼ばせるよう頼んでいたのだ。怒りに体が震え、私は家を飛び出し、決着をつける覚悟で急いでコテージへ向かった。道ですれ違いざまに妻とメイドが急ぎ足で戻っていくのを見かけたが、声もかけずに通り過ぎた。私の人生に影を落とす秘密は、あのコテージにあるはずだ。何があっても、もう秘密のままにはさせまいと心に誓った。コテージに着くと、ノックもせずにドアノブを回し、廊下へと飛び込んだ。
家の中は静まり返っていた。台所ではやかんが火にかかり、黒猫が籠の中で丸くなっていた。だが、以前見かけたあの女の姿はない。別の部屋も見たが、同じく誰もいない。そして階段を駆け上がったが、上の二部屋も空っぽだった。家の中には人の気配がまったくなかった。家具や壁の絵はどれも安っぽくくだらないものばかりだったが、ただ一つ、あの奇妙な顔を見た窓の部屋だけは、快適で上品な調度で整えられていた。そして、そこで私は激しい憤りを覚えた。暖炉の上に、わずか三か月前、私の依頼で妻を撮った全身写真が飾られていたからだ。
家が無人なのに間違いないことを確認してから、私は重い気持ちでコテージを後にした。こんな思いを味わったのは生まれて初めてだった。家に戻ると、妻が廊下で私を迎えたが、私はあまりに傷つき、怒りが収まらず、彼女を押しのけて書斎へ入った。妻も私がドアを閉める前に追いかけてきた。
『約束を破ってしまって、ごめんなさい、ジャック』と彼女は言った。『でも、事情を全部知ったら、きっとあなたも許してくれるわ。』
『だったら、すべて話してくれ』と私は言った。
『無理よ、ジャック、どうしても話せないの』と彼女は叫んだ。
『あのコテージに住んでいるのは誰なのか、あの写真を誰に渡したのか、それを君が話さない限り、私たちの間に信頼なんて決して生まれない』と私は言い、彼女から離れて家を出た。それが昨日のことなのです、ホームズさん。それ以来、私は妻を見ていませんし、この不可解な出来事についてほかのことも何も分かりません。これは私たち夫婦の間に初めて生じた影であり、私はどうすればよいのか分からないほど動揺しています。今朝、ふと思い出したのです。あなたこそ助言を仰ぐべき相手だと。それで急いで参りました。どうか、何もかも包み隠さず、あなたにお任せします。もし私の説明で分かりにくい点があれば、何なりとご質問ください。でも、何よりも早く、この苦しみからどうすれば解放されるか教えていただきたいのです。これ以上は耐えられません。』
ホームズと私は、この異様な話に最大限の興味を持って耳を傾けていた。語り口は、極度の感情に支配された男らしく、途切れ途切れで、時にこと切れそうなほどだった。友人はしばらく黙ったまま、顎に手を当てて考え込んでいた。
「一つ聞きたい」とついに彼が言った。「窓で見たあの顔は、男の顔だと断言できるか?」
「その顔を見たときは、いつも少し離れた場所からだったので、断言はできません。」
「しかし、かなり不快な印象を受けているようだ。」
「不自然な色をしていて、顔立ちもどこかこわばっていました。私が近づくと、さっと消えました。」
「奥さんが百ポンドを求めたのはどれくらい前のことだ?」
「ほぼ二か月前です。」
「彼女の最初の夫の写真を見たことは?」
「いえ。彼が亡くなった直後、アトランタで大火事があり、書類はすべて焼失したんです。」
「それでも死亡証明書はあったと。あなたはそれを見たのですね?」
「はい。火事の後で再発行してもらったそうです。」
「アメリカで彼女を知っている人に会ったことは?」
「ありません。」
「彼女がアメリカを再訪したいと話したことは?」
「ありません。」
「手紙を受け取ったことは?」
「ありません。」
「分かりました。少し考えさせてください。もしそのコテージが今も完全に空き家なら、解明は難しいかもしれません。ですが、私の推測では、おそらくあなたが来たことを察知して、一時的に引き払っただけでしょう。今は戻っている可能性が高い。ですから、ノーバリーへお戻りいただき、もう一度コテージの窓を調べてみてください。人が住んでいると確信したなら、無理に入らず、私とワトソンに電報をください。受け取り次第、私たちは一時間以内にそちらへ行きます。すぐに真相を突き止められるはずです。」
「もし空き家のままだったら?」
「その場合は、明日私がそちらへ伺い、詳しく話し合いましょう。では、くれぐれも、不安になるのは本当にその理由が確認できてからにしてください。」
ホームズはグラント・マンロー氏を玄関まで見送り、戻ってくるとこう言った。「ワトソン、これは厄介な事件だと思うが、君はどう見る?」
「嫌な予感がする」と私は答えた。
「うむ。恐喝が絡んでいるか、私の見立てが間違いでなければ、だが。」
「犯人は誰だと思う?」
「コテージで唯一快適な部屋に住み、暖炉の上に彼女の写真を飾っているあの生き物に違いない。ワトソン、あの窓の蒼ざめた顔には妙な魅力がある。この事件を逃したら一生の損失だ。」
「君には理論があるのか?」
「ああ、仮説だが、まず間違いないと思う。この女性の最初の夫が、あのコテージにいる。」
「なぜそう思う?」
「彼女があれほど激しく第二の夫を近づけたがらない理由は、それ以外に考えられない。私の読みでは、こうだ――彼女はアメリカで結婚した。夫は忌まわしい性質を持つようになった。あるいは重い病気――例えばハンセン病や知的障害かもしれない。彼女は夫から逃げ、イギリスに帰国し、名前を変えて新しい人生を始めた。三年間再婚し、死亡証明書まで見せて夫を安心させていたが、あるとき、かつての夫か、あるいはその身辺に取り入った悪意のある女が彼女の居所を突き止める。脅迫状が届き、百ポンドで追い払おうとするが、相手はそれでもやって来る。夫に近所のコテージへ新しい住人が来たと聞かされ、妻はそれが追手だと悟る。夜、夫の眠りを見計らって説得に行くが失敗し、翌朝再び出向く。約束はするものの、どうしても追い払いたくて、写真を携えて三度目の訪問。そこへメイドが主人の帰宅を知らせ、妻はコテージの住人たちを裏口から逃がす。主人が着いたときには誰もいなかった。だが今夜、再び戻っていると私は見ている。どう思う?」
「全部推測だ。」
「だが、事実を一応説明できる。新たな事実が出てきて覆せば、そのとき見直せばよい。友人からノーバリーで連絡が来るまで、私たちにできることはない。」
だが、それを待たされる時間は長くはなかった。ちょうどお茶を飲み終えたころ、メッセージが届いた。「コテージにはまだ人がいる。窓にまたあの顔を見た。七時の列車で待つ。到着まで何もせず待機する。」
私たちがホームに降り立つと、彼はプラットホームで待っていた。駅灯の明かりの下、その顔はひどく青ざめ、興奮に震えていた。
「まだいます、ホームズさん」と彼はしっかりと友人の袖をつかんで言った。「コテージに灯が見えました。今夜こそ決着をつけます。」
「それで、どうするつもりです?」とホームズが闇の木立に囲まれた道を歩きながら訊いた。
「無理やり中に入り、自分の目で誰がいるか確かめたい。お二人にも証人としていていただきたい。」
「奥さんが『謎を解かない方がいい』と警告したにもかかわらず、決行するのですね?」
「ああ、決心は変わらない。」
「それが正しい考えだと思う。はっきりした真実の方が、曖昧な疑念よりはるかに良い。すぐ行こう。もちろん、法的には完全に違法だが、その価値はあるだろう。」
夜は非常に暗く、細い雨がぱらつき始めた。私たちは大通りからわだちだらけの狭い小道に折れた。マンロー氏は焦るように先を急ぎ、私たちも必死にそれについていった。
「あれがうちの灯です」と、彼は木立の合間に見える明かりを指してつぶやいた。「そして、これがこれから入るコテージだ。」
彼がそう言ったとき、私たちは小道の角を曲がり、建物が目の前に現れた。黒い前景に黄色い光が帯のように落ちていて、ドアが完全には閉まっていないことが分かった。上階の窓には鮮やかな灯りがともり、窓のシェード越しに黒い影が動いた。
「あの生き物だ!」とグラント・マンローが叫んだ。「自分で見て分かったでしょう。さあ、一緒に入って、すべてを明らかにしましょう。」
私たちは戸口へ近づいたが、突然、女性が影から現れ、ランプの光の帯に立ちはだかった。暗がりで顔は見えなかったが、両腕を差し出し、懇願する姿勢だった。
「お願い、やめてジャック!」と彼女は叫んだ。「今夜あなたが来る気がしていたの。考え直して、お願い! もう一度だけ信じてくれたら、絶対に後悔はさせない。」
「私は君を信じすぎた、エフィー!」と彼は厳しい声で叫んだ。「どいてくれ! 私は行かねばならない。友人たちと一緒に、この問題に決着をつける!」彼は彼女を押しのけ、私たちはすぐ後を追った。ドアを開け放つと年老いた女が飛び出し、行く手を遮ろうとしたが、彼は彼女を振り払った。瞬く間に私たちは全員で階段を駆け上がった。マンロー氏が明かりのある部屋へ突入し、私たちもそのあとに続いた。
そこは居心地のよい、立派な部屋で、テーブルにも暖炉にも二本ずつロウソクが灯っていた。隅の机にうつむいていたのは、小さな女の子のようだった。入った時、顔は見えなかったが、赤いドレスに長い白い手袋をしていた。振り返った瞬間、その顔を見て私は驚きと恐怖で叫び声を上げた。その顔は非常に不気味な青白さで、表情がまるでなかった。だが、その謎は一瞬で解けた。ホームズが笑いながら少女の耳の後ろに手をやると、仮面がぺろりと剥がれ、そこには燃えるように白い歯を見せて笑う黒人の小さな少女が現れた。私は思わず一緒に笑い出してしまったが、マンロー氏は喉を押さえたまま呆然と立ち尽くしていた。
「なんてことだ!」と彼は叫んだ。「これはどういうことなんだ?」
「私が説明します」と、夫人が毅然とした顔つきで部屋に入ってきた。「あなたは私の意志に反してすべてを知ることになった。もう最善を尽くすしかないわ。私の夫はアトランタで亡くなった。だが、私の子は生き残った。」
「君の子供?」
彼女は胸元から大きな銀のロケットを取り出した。「これは、あなたは開いたことがないわね。」
「開かないものだと思っていた。」
彼女がスプリングを押すと、表面がパタンと開いた。中には非常にハンサムで知的な顔立ちの男性の肖像があったが、その容貌は明らかにアフリカ系の特徴を備えていた。
「あれがアトランタのジョン・ヘブロンです」と夫人は言った。「これほど立派な人はいなかった。私は自分の人種を捨てて彼と結ばれたけれど、彼の生きている間、一瞬たりとも後悔したことはなかった。私たちの唯一の不運は、娘が私ではなく、彼の方の人種に似てしまったこと。それはよくあることだけど、ルーシーは父親よりもずっと黒い子になった。でも、肌の色がどうであれ、私はこの子を心から愛しているし、母親として何よりも大切な娘なのよ。」小さな少女はその言葉に反応して、夫人のドレスにしがみついた。「私があの子をアメリカに残したのは、体が弱かったからで、環境の変化が悪い影響を与えるかもしれなかったから。信頼できるスコットランド人の乳母に預けたの。娘を自分の子として否定しようなんて、思ったことは一度もない。けれど、あなたに出会い、あなたを愛するようになってからは、子供のことを打ち明ける勇気がなかった。神様お許しください、あなたを失うのが怖かったのです。弱さから、私は自分の子を選ばず、あなたを選んでしまった。この三年間、娘の存在を隠し続けてきたけれど、乳母からの便りで元気なことは知っていた。でも、ついに一度だけでも娘に会いたいという思いが抑えきれなくなった。危険だと分かっていながら、どうしても娘をイギリスに呼び寄せる決心をした。乳母に百ポンドを送り、このコテージについて指示し、私が関係していることが分からぬよう、隣人として住んでもらった。用心のあまり、昼間は絶対に外に出さず、窓から見られぬよう顔や手を隠すようにまで命じたの。そこまで慎重にならず、もっと賢明にふるまうべきだったけれど、あなたに知られたくないという恐怖で半狂乱だったのよ。
あなたが最初にコテージが使われていることを教えてくれたとき、私は本当は朝まで待つつもりだった。でも、興奮で眠れず、あなたが起きないのを知っていたから、こっそり抜け出したの。あなたに見つかってしまい、それが私の苦しみの始まりだった。その翌日には、あなたが私の秘密を知っていたのに、それを問いただそうとはせず、立派に振る舞ってくれた。でも三日後、あわやというところで、乳母と子供は裏口から逃げ出し、あなたは正面から入ってきた。そして今夜、ついにすべてを知ることになった。これから私と娘はどうなるのでしょう?」彼女は両手を胸の前で組み、答えを待った。
グラント・マンローが沈黙を破るまでの十分間は、とても長く感じられた。そして彼の返答は、思い返すたびに心が温かくなるようなものだった。彼は小さな子どもを抱き上げ、キスをし、さらにその子を抱いたまま、もう一方の手を妻に差し出してドアの方へ向かった。
「家に帰ってからのほうが、ゆっくり話ができるだろう」と彼は言った。「私はあまり出来た人間ではないが、君が思っているよりはずっとましな男だと思うよ、エフィー」
ホームズと私は彼らの後について小道を歩き、通りに出たところで友人が私の袖を引いた。
「私はね」と彼は言った。「ロンドンにいるほうがノーバリーにいるより、役に立てそうな気がする」
その事件について、彼が再び何かを口にしたのは、その晩遅く、寝室へ入ろうと灯したロウソクを手にして廊下を歩いているときだった。
「ワトソン」と彼は言った。「もし私が自分の能力に少しでも自信過剰になったり、事件に対して手抜きをしているように思ったら、そっと“ノーバリー”と耳打ちしてくれ。君には心から感謝するよ」
IV. 株式仲買人の事務員
私が結婚した直後、パディントン地区で患者の引き継ぎを購入した。前任者であるファーカー老人は、かつては素晴らしい一般診療を持っていたが、年齢と舞踏病[訳注:セント・ヴィタスダンス、チックや痙攣を伴う神経疾患]のために、その顧客数はかなり減っていた。世間は、「他人を癒す者は自らも健康であるべき」と考えるのが普通で、自分の体調すら薬で治せない人間の治療能力には疑いの目を向けるものだ。そうして前任者が弱るにつれて診療所は衰え、私が引き継いだ時には年収1200ポンドから300ポンド強にまで落ち込んでいた。それでも若さと活力に自信があり、数年もすれば以前のように繁盛するだろうと確信していた。
引き継いでからの三か月は多忙を極め、ベイカー街に足を運ぶ余裕もなく、ホームズとも顔を合わせることはほとんどなかった。彼もまた、仕事以外でどこかへ出かけることは稀だった。そんなある六月の朝、朝食後に『ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル』を読んでいると、玄関のベルが鳴り、続いて懐かしい友人の甲高い声が響いたので驚いた。
「やあ、ワトソン君!」と彼は部屋に入ってきながら言った。「会えて嬉しいよ! 『四つの署名』の冒険で巻き起こったあれやこれやの興奮から、奥さんはもうすっかり回復されただろうね」
「ありがとう。二人とも元気だよ」と私は熱く握手を交わした。
「それは良かった」と彼はロッキングチェアに腰を下ろしながら続けた。「だが、医者の仕事に忙殺されて、我々のあの推理の小事件に興味を失ってしまったわけではないだろう?」
「とんでもない」と私は返した。「昨晩も昔の記録を見返して、いくつかの事件を整理していたくらいだ」
「コレクションはもう打ち止めだとは思っていないだろう?」
「全然。できることなら、また新しい経験をしたいと思っている」
「たとえば、今日などはどうだろう?」
「今日でも、君が望むなら」
「それも、バーミンガムまで出かけるとしたら?」
「もちろん、君がそうしたいなら」
「診療所は?」
「隣の先生が出かける時は、私が代診することになっている。彼も私のためにそうしてくれる」
「それは申し分ない」とホームズは椅子に身を預け、半分閉じたまぶたの下から鋭く私を見つめた。「君は最近、体調を崩していたようだ。夏風邪はなかなか厄介だからな」
「先週、ひどい寒気で三日間家にこもったよ。でももうすっかり回復したと思っていたが」
「まったくその通り。とても健康そうに見える」
「それなら、どうして分かったんだ?」
「君は私のやり方を知っているだろう」
「推理したのか?」
「もちろんだ」
「何から推理したんだ?」
「君のスリッパさ」
私は新しいエナメルの靴を見下ろした。「どうして――」と口にしかけたが、ホームズはすぐに私の疑問に答えた。
「スリッパは新品だ。履き始めて数週間といったところだろう。今君がこちらに向けている靴底が、やや焦げている。最初は濡れて乾かす際に焦げたのかと思ったが、土踏まずのあたりに店員の書いた小さな紙片がまだついている。濡れていれば、それは剥がれているはずだ。つまり、君は足を火の前に投げ出して座っていたのだ。こんな湿った六月でさえ、健康ならそんなことはしないだろう」
ホームズの推理は、説明されてしまえば至極単純に思える。私が感心しているのを読み取ったのか、彼の微笑みにはわずかな苦味があった。
「説明するたびに自分の種を明かしてしまうのが、ちょっともどかしいよ」と彼は言った。「原因なき結果の方が、よほど印象的だからね。さて、バーミンガムに行く準備はできているか?」
「もちろんだ。どんな事件なんだ?」
「列車の中で全部話す。依頼人が外で四輪馬車に待っている。すぐに来られるか?」
「すぐに」と私は隣人にメモを書き、妻に事情を説明して階下に駆け戻り、ホームズと玄関先に立った。
「隣人も医者だね」と彼は表札を見て言った。
「ああ、私と同じように、診療所を買い取ったんだ」
「古くから続いているものか?」
「私のと同じで、どちらも家が建った時からだ」
「なるほど。では君の方が良い方を手に入れたな」
「そう思う。でも、どうして分かるんだ?」
「階段さ。君の家の方が三インチも深くすり減っているからね。さて、馬車にいる紳士が私の依頼人、ホール・パイクロフト氏だ。紹介しよう。御者さん、馬を急がせてくれ。列車に間に合うギリギリだ」
馬車で向かい合った男は、体格の良い、血色の良い若者で、率直で誠実そうな顔つきと、少し縮れた薄い金色の口髭をたくわえていた。光沢のあるシルクハットと、地味な黒の洒落たスーツで身を固めており、まさに「シティの若手紳士」という風情だった。その丸く赤らんだ顔は本来は快活そのものだが、口元はどこか困ったような、半ば滑稽な苦悩を漂わせていた。だが、彼がいかなる理由でシャーロック・ホームズを頼ったのかを知ることができたのは、私たち三人が一等車のコンパートメントに乗り込み、バーミンガムへ向けて列車が十分に走り出してからだった。
「ここからは七十分間はノンストップだ」とホームズは言った。「パイクロフト氏、君のとても興味深い体験を、できればもっと詳しく、私の友人にも話してほしい。何度も聞いて、時系列を正確に把握したい。ワトソン、これは何かがある事件かもしれないし、何もない事件かもしれない。ただ、少なくとも君も私も好む、普通とはかけ離れた奇妙な要素がある。パイクロフト氏、話の途中では口を挟まないから、どうぞ」
若き同伴者は、目を輝かせて私の方を見た。
「話の一番情けないところは、自分がまるっきりお人好しだったと白状せざるを得ないことです。もちろん、うまくいけば結果オーライですし、他にどうしようもなかったとも思っています。ただ、もし仕事を失って、何の見返りもなかったら、自分の間抜けさ加減を思い知ることになるでしょう。話すのはあまり得意ではありませんが、こういうことです。
私は以前、ドレーパーズ・ガーデンズのコクソン&ウッドハウスという会社に勤めていました。でも、ご存じの通り、ベネズエラ国債の件で春先に大損をしてしまい、ひどい目に遭いました。五年間勤めていたのですが、倒産の際にはコクソン老人が立派な推薦状を書いてくれました。ただし、事務員は全員、二十七人とも放り出されてしまったのです。あちこち就職を試みましたが、自分と同じような境遇の人間が大勢いるので、長い間まるで駄目でした。コクソンでは週三ポンドの給料で、七十ポンドほど貯金もありましたが、それもすぐに使い果たしてしまいました。ついには切手を買う金も、返信用封筒を用意する金も怪しくなりました。無駄に事務所の階段を上り下りして靴もすり減り、仕事にありつく望みは一向に近づきませんでした。
そんなある時、ロンドンのロンバード街にある大手証券会社、モーソン&ウィリアムズで欠員募集を見つけました。E.C.地区はご存じないかもしれませんが、ロンドンでも屈指の裕福な会社です。応募は書面のみ。ダメ元で推薦状と申込書を送りました。するとすぐに返事が来て、“次の月曜に出社してもらえれば、容姿に問題なければ即採用”とのことでした。こういうものは、どうやって決まるのか分かりません。マネージャーが書類の山から手当たり次第に一枚選ぶとも言います。とにかく、運が巡ってきたのです。これ以上嬉しいことはありませんでした。給料は一ポンド増、仕事内容もコクソンの時とほぼ同じです。
さて、ここからが奇妙な話になるのです。私はハムステッド寄りの17番、ポッターズ・テラスの下宿に住んでいました。その晩、就職が決まった嬉しさから、煙草をふかしていると、大家さんが『アーサー・ピナー 金融代理人』と印刷された名刺を持ってきました。その名前には聞き覚えはなく、何の用か見当もつきませんでしたが、ともかく部屋に通してもらいました。入ってきたのは、中背で黒髪・黒目、黒い顎髭の男で、鼻筋に独特のユダヤ系の雰囲気がありました。動作はきびきびしていて、時間の価値を知る人間らしく、言葉遣いも鋭かったです。
『ホール・パイクロフトさんですね?』
『はい』と私は椅子をすすめました。
『最近までコクソン&ウッドハウスにお勤めでしたね?』
『はい』
『今はモーソンに?』
『その通りです』
『実は、あなたの金融の腕前について、非常に驚くべき話を耳にしましてね。コクソンのマネージャーだったパーカーを覚えているでしょう? 彼はあなたのことをどんなに褒めても足りないといっていました』
そんなことを聞いて、嬉しくないはずがありません。私は職場ではそれなりに機転は利く方でしたが、まさかシティで話題になっているとは夢にも思いませんでした。
『記憶力はいい方ですか?』
『まぁ、人並みです』と私は控えめに答えました。
『失業中も市場の動向を追っていましたか?』
『ええ、毎朝、株式市況欄を読んでいました』
『それは熱心ですね! まさに成功の秘訣です。ちょっと試させてください。エアシャー鉄道は?』
『百六と四分の一から百五と七分の八です』
『ニュージーランド・コンソリデーテッドは?』
『百四です』
『ブリティッシュ・ブロークン・ヒルズは?』
『七から七シリング六ペンスです』
『驚いた!』と彼は両手を挙げて叫びました。『まさに聞いていた通りだ。君はモーソンの事務員にはもったいなさすぎる!』
この感激ぶりには正直面食らいました。「でも、他の人たちはそこまで私のことを評価していませんよ、ピナーさん。今の職も手に入れるのは苦労したくらいですし」
『いや、君はもっと大きく羽ばたくべきだ。君は本来いるべき場所にいない。さて、私のほうの話をしよう。私の提示できる条件は、君の能力からすれば物足りないが、モーソンと比べれば月とすっぽんだ。ところで、君はいつモーソンに出社する?』
『月曜からです』
『はは、私の賭けだが、君はモーソンには行かないと思うよ』
『モーソンに行かない?』
『そう、月曜には君はフランコ・ミッドランド金物会社の業務部長になるんだ。この会社はフランス各地の町や村に支店が百三十四、さらにブリュッセルとサンレモにもある』
あまりのことに言葉を失いました。「そんな会社、聞いたことがありません」
『当然だ。資本は全て非公開で集めたもので、あまりにうまい話だから公にしたくなかったのだ。兄のハリー・ピナーがこの会社を立ち上げ、株式発行後は取締役として経営に加わる。私はこのロンドンで人材を探してくれと頼まれた。若く、行動力があり、きびきびした男が必要だと。それでパーカーの推薦で君のところに今夜来たんだ。初任給はみすぼらしい五百ポンドしか出せないがね』
『年五百ポンドですって!』
『最初はそれだけ。ただし、代理店が扱うすべての取引額に1%の総括手当がつく。給料より多くなるのは請け合いだ』
『でも私は金物の知識がありません』
『気にするな。計算ができれば十分だ』
頭がくらくらして、椅子にじっとしていられないほどでした。けれども、急に疑念が頭をもたげてきました。
『正直に申し上げます。モーソンは年二百ポンドですが、安定しています。でも、そちらの会社については、ほとんど何も――』
『うん、さすがだ!』と彼は大喜びで叫びました。『君は説得されない男だ。その慎重さが素晴らしい。ほら、これは百ポンドの小切手だ。もし私たちと仕事をする気があるなら、給料の前渡しとしてポケットに入れてくれ』
『なんて太っ腹なんだ。新しい職務にはいつから?』
『明日一時にバーミンガムに来てくれ。ここに兄宛の手紙があるから、それを持っていくんだ。兄はコーポレーション・ストリート126Bの臨時事務所にいる。採用の最終確認は兄がするが、内々では決まっていると思っていい』
『本当に感謝の言葉もありません、ピナーさん』
『いやいや、当然のことだ。いくつか、ちょっとした形式だけ済ませておきたい。そこに紙があるね。“私は、年俸最低五百ポンドでフランコ・ミッドランド金物会社の業務部長として勤務することに何ら異存はありません”と書いてくれ』
私は言われた通りに書き、彼はそれを懐にしまった。
『もう一つ、細かいことだが。モーソンにはどう伝えるつもりか?』
私はあまりの喜びに、モーソンのことなどすっかり忘れていた。「辞表を書きます」
『それは困る。私は君の件でモーソンのマネージャーと揉めたんだ。君について尋ねに行ったら、あちらはとても失礼でね。“君がうちの社員を引き抜こうとしている”と非難されたんだ。ついかっとなって、“いい人材が欲しければ、もっと高い給料を出すべきだ”と言ってやったよ』
『向こうは、うちの安月給のほうがそちらの高給よりいいと言ってました』
『賭けてもいいが、私のオファーを伝えたら、向こうからは二度と連絡がないだろう』
『よし、受けてやる。うちは拾ってやったんだ、簡単には辞めないぞ、だそうです』
『なんてずうずうしい奴だ!』と私は言いました。「一度も顔を合わせたこともないのに、なぜ配慮しなきゃいけないんです? 書かないほうがいいなら、絶対に書きません」
『よろしい、それが約束だ』と彼は立ち上がった。「兄のために、こんな逸材が得られて嬉しい。これが百ポンドの前渡し、そしてこれが手紙だ。住所はコーポレーション・ストリート126B、明日一時が約束の時間だ。幸運を祈る!」
これが、私の覚えている限りでの会話のすべてです。ワトソン先生、こんな幸運が舞い込んで、どれほど嬉しかったか想像がつくでしょう。私は嬉しさのあまり夜中まで眠れず、翌日、約束に十分間に合う列車でバーミンガムへと向かいました。荷物をニュー・ストリートのホテルに預け、指定された住所へと向かいました。
約束の時間よりも四分の一時間早かったが、それは問題ないだろうと思った。126Bは、二つの大きな店の間にある通路で、その奥には石造りの曲がりくねった階段があり、そこから多くの部屋へと通じていた。それらの部屋は、会社や専門職の人々に事務所として貸し出されている。入居者の名前は壁の一番下に書かれていたが、「フランコ=ミッドランド金物会社有限責任会社」という名前は見当たらなかった。私はしばらくの間、がっかりした気持ちで立ちすくみ、すべてが手の込んだ悪ふざけではないかと疑っていた。すると、男がやってきて声をかけてきた。彼は昨夜見た男によく似ており、体格も声も同じだったが、髭は剃り落とされ、髪色も少し明るかった。
「あなたはホール・パイクロフトさんですか?」
「はい」と私は答えた。
「おお! あなたをお待ちしていましたが、少し早めにいらっしゃいましたね。今朝、兄からの手紙が届きまして、あなたのことを大変褒めていました。」
「ちょうど事務所を探していたところでした。」
「まだ社名を掲げていませんが、先週ようやくこの仮事務所を確保したばかりなのです。どうぞご一緒に上がってください、お話ししましょう。」
私は彼に従い、非常に高い階段を上った。すると、屋根裏のすぐ下に、埃っぽくて小さな、カーペットもカーテンもない部屋が二つあり、そこへ案内された。私は、これまで慣れ親しんできたような、光沢のある机や事務員が並ぶ大きなオフィスを想像していたので、椅子が二脚と小さな机一つ、帳簿とごみ箱があるだけの殺風景な部屋を見て、ついまじまじと見てしまったに違いない。
「気を落とさないでください、パイクロフトさん」と、新しい知人は私の顔を見て言った。「ローマも一日にして成らず、です。我々には潤沢な資金があるのですが、今はまだオフィスに見栄えがしません。どうぞお掛けになって、手紙を見せてください。」
私は手紙を渡すと、彼はとても注意深くそれを読んだ。
「兄のアーサーに相当いい印象を与えたようですね」と彼は言った。「彼は中々の目利きです。兄はロンドンを信奉していますが、私はバーミンガム派です。しかし今回は兄に従うつもりです。あなたは正式に採用されたと思ってください。」
「職務内容は?」と私は尋ねた。
「最終的には、パリの大規模な倉庫の管理を任せます。そこから百三十四の代理店にイギリスの陶器が供給される予定です。買収は一週間以内に完了しますが、それまでの間はバーミンガムにいて、役立ってもらいたい。」
「どんなことを?」
答えとして、彼は引き出しから大きな赤い本を取り出した。
「これはパリの名簿です」と彼は言った。「店名の後に業種が載っています。これを持ち帰って、金物屋をすべて住所つきでチェックしてほしいのです。私にはとても役立ちます。」
「業種ごとに分類されたリストがあるのでは?」と私は提案した。
「信頼できるものはありません。向こうの方法は我々と違うのです。根気よくやって、月曜の正午までにリストをください。では、パイクロフトさん、さようなら。熱意と知恵を示し続けてくれれば、きっとこの会社が気に入ることでしょう。」
私は大きな本を小脇に抱えてホテルへ戻ったが、心は複雑だった。一方では、正式に採用され、百ポンドの前払いも受け取った。だが、事務所の様子や社名が掲げられていないことなど、ビジネスマンなら気づく点がいくつもあり、雇用主の立場に疑念を抱かせた。しかし、どうなろうと金は手に入れているのだから、とにかく仕事に取り掛かることにした。日曜は一日中その作業に追われたが、月曜日までにようやくHまでしか進まなかった。雇い主の元へ行くと、またもや殺風景な部屋に彼はいて、水曜まで続けてまた来るように言われた。水曜になっても終わらなかったので、金曜――つまり昨日までやり続け、ようやくハリー・ピナー氏の元へリストを持参した。
「大変助かります」と彼は言い、「この仕事の難しさを見くびっていました。このリストは本当に役立つでしょう。」
「かなり時間がかかりました」と私は言った。
「さて、次は家具店のリストを作ってほしい。家具店はどこも陶器を扱っているからね。」
「わかりました。」
「明日の夕方七時に来て、進捗を知らせてください。無理はしないように。夜にデイズ・ミュージック・ホールで二時間くらい気晴らしするのもいいでしょう」彼は笑いながら言い、私は思わず身震いした。左側の二番目の歯が金でひどく詰められていたのだ。
シャーロック・ホームズは嬉しそうに手をこすり、私は依頼人を見て驚きを隠せなかった。
「驚くのも無理はありませんよ、ワトソン先生。しかし、こういうことです。ロンドンであの男と話したとき、私がモーソン社へ行かなかったことを嘲笑った時のことですが、彼の歯が全く同じように金で詰めてあるのに気付きました。両者とも金の輝きが目に入りました。声や体格も同じ、ただ髭と髪だけは変えられる物ですから違っていましたが、それ以外は同一人物と疑いようがありません。もちろん兄弟なら似ているでしょうが、全く同じ位置に同じように歯が詰めてあるなんてことはありえません。彼は私を部屋から送り出し、私は通りに出て、自分が頭で立っているのか、足で立っているのかわからないくらいでした。ホテルに戻り、冷水で頭を冷やし、考え込んでしまいました。なぜ彼は私をロンドンからバーミンガムへ送ったのか? なぜ先に到着できたのか? なぜ自分から自分に手紙を書いたのか? 私にはさっぱり分からず、どうにもならなかった。でも、私にとって暗闇の中のこの出来事も、シャーロック・ホームズなら明るみにできると思い至りました。夜行列車でロンドンへ行けば、今朝彼に会える、そしてあなた方お二人をバーミンガムに連れ帰れたというわけです。」
株式仲買店の事務員が驚くべき体験談を語り終えると、しばらく沈黙があった。それからホームズは目を細め、クッションにもたれて、まるで一口目に最高級ワインを味わった鑑定家のような満足げで批評的な表情をした。
「なかなかいい話だろう、ワトソン」と彼は言った。「これは面白い点がいくつもある。仮事務所でアーサー・ハリー・ピナー氏と面会するのは、我々にとって非常に興味深い経験になると思うが、君もそう思わないか。」
「でも、どうやって会う?」と私は尋ねた。
「それは簡単です」とホール・パイクロフトは明るく言った。「あなた方は仕事を探している私の友人ということにすればいい。私が二人を支配人に紹介するのは自然なことです。」
「まったくその通りだ」とホームズも言った。「その男に一目会い、彼の企みを見抜けるか確かめてみたい。ところで、君のどんな資質がそんなに価値があると思われているのだろう? あるいは……」彼は爪を噛み始め、窓の外をぼんやり見つめた。その後、ニュー・ストリートに着くまで彼からほとんど言葉はなかった。
その晩七時、私たち三人はコーポレーション・ストリートを歩き、会社の事務所へ向かった。
「早く着いても意味はありません」と依頼人が言った。「彼は私に会うためだけに来るようで、それまでは事務所は無人なんです。」
「それは意味深だな」とホームズが言った。
「ほら見ろ、言った通りだ!」と事務員が叫んだ。「あそこを歩いているのが彼です。」
彼は道の向こう側を忙しそうに歩く、小柄で色黒、身なりの良い男を指さした。私たちが見ていると、男は夕刊を売る少年に目をやり、馬車やバスの間を駆け抜けて新聞を買い、それを握って入口から姿を消した。
「行きましたよ!」とホール・パイクロフトが叫んだ。「あれが彼が入った会社の事務所です。私についてきてください、すぐに話をつけます。」
私たちは彼に続き、五階分の階段を上がり、半分開いたドアの前にたどり着いた。依頼人がノックすると、中から入るように声がした。中はパイクロフトの説明通り、素っ気ない、家具もほとんどない部屋だった。唯一の机の前に、さっき通りで見た男が座り、夕刊を広げていた。その顔を見上げた瞬間、私はこれほどまでに悲嘆や、それを超えた何か――人生でごく稀にしか目にしないような恐怖の色を帯びた顔を見たことがないと思った。額は汗で光り、頬は魚の腹のように青白く、目は狂気じみて見開かれていた。彼は事務員をまるで見知らぬ者のように見つめ、私たちの案内人もその様子に驚きを隠せなかった。
「具合が悪そうですね、ピナーさん!」と彼は叫んだ。
「ああ、あまり良くないんだ」と相手は、明らかに気を取り直そうとしながら、乾いた唇をなめて答えた。「ところで、君が連れてきたのは誰だ?」
「一人はバーモンジーのハリスさん、もう一人はこの町のプライスさんです」と事務員は流暢に言った。「どちらも私の友人で経験豊富ですが、しばらく職を探しておりまして、会社に空きがあればと望んでいるのですが。」
「なるほど! なるほど!」とピナー氏は青ざめた笑みを浮かべて叫んだ。「きっと何かできるでしょう。ハリスさん、あなたの専門は?」
「会計士です」とホームズ。
「ええ、そういう人材も必要です。そして、あなたは?」
「事務員です」と私。
「会社でお役に立てると思います。結論が出次第ご連絡しますので、今はどうかお帰りください。お願いですから、私を一人にしてください!」
この最後の言葉は、彼が必死に抑えていたものが突然弾け飛んだかのような調子だった。ホームズと私は互いに目を見交わし、パイクロフトは一歩前に出た。
「ご予定通り、私にはご指示をいただくはずですよ、ピナーさん」
「もちろんです、パイクロフトさん」と相手は冷静さを取り戻した口調で答えた。「ここで少々お待ちください。お友達もご一緒で構いません。三分ほどご辛抱いただければ、すぐにご対応いたします。」彼はとても丁寧に頭を下げ、奥のドアから部屋を出ていった。
「さて、どうする?」とホームズが小声で言った。「逃げたのか?」
「それはありえません」とパイクロフト。
「なぜ?」
「あのドアは内側の部屋につながっています。」
「出口は?」
「ありません。」
「部屋は家具付きか?」
「昨日は空でした。」
「なら一体何をしているんだ? どうも腑に落ちない。あれほど恐怖に取り憑かれた男は見たことがない。どうしてあんなに震えているのだ?」
「我々が探偵じゃないかと疑っているのでは」と私。
「きっとそうですよ!」とパイクロフト。
ホームズは首を振った。「入った瞬間から青ざめていた。何か別の理由だろう。」
その時、内側のドアから鋭いノック音がした。
「自分のドアを何で叩いてるんだ?」と事務員が叫ぶ。
再び、しかも今度はもっと激しくノックが響いた。私たちはドアを見つめた。ホームズの顔は固まり、身を乗り出して待ち構えていた。すると突然、低いうめき声と木を叩く音が響いた。ホームズは部屋を駆け抜け、ドアを押したが中から鍵がかかっていた。私たちも力いっぱいぶつかると、蝶番が一つ、また一つと外れ、ドアは音を立てて倒れた。中は空だった。
だが、それはほんの一瞬だった。手前の角にもう一つドアがあり、ホームズがそこを開けると、床には上着とベストが落ち、ドアの裏のフックにはピナー氏が自分のサスペンダーで首を吊っていた。膝は曲がり、首は恐ろしい角度で傾き、かかとがドアを叩く音が先ほどの騒音だった。私はすぐに彼の腰を支え、ホームズとパイクロフトがゴムバンドを解いた。彼を隣室に運ぶと、顔は土色で、紫色の唇が呼吸のたびにぴくぴく動いていた――五分前の彼からは想像もできない無残な姿だった。
「どうだ、ワトソン?」とホームズ。
私は彼を屈み込み調べた。脈は弱く不規則だったが、だんだん呼吸も深くなり、まぶたが小刻みに震えて白目がのぞいた。
「もう大丈夫だ、今や命に別状はない」と私は言った。「窓を開けて、水差しをください。」私は襟を緩め、冷水を顔にかけ、腕を上下させて呼吸を促した。やがて彼は大きく息をつき、本来の呼吸が戻った。「もう時間の問題だ」と私は言った。
ホームズは机の前で、ズボンのポケットに手を突っ込み、顎を胸に乗せて立っていた。
「そろそろ警察を呼ぶべきだろうな。しかし、できれば事件を完全に解明してから引き渡したいものだ。」
「全く謎ですよ」とパイクロフトは頭をかいた。「何で私をわざわざここまで連れてきて、しかも――」
「そんなのは明白だ」とホームズは苛立たしげに言った。「問題はこの最後の急な行動だ。」
「他はわかるのか?」
「だいたい明白だ。どう思う、ワトソン?」
私は肩をすくめた。「正直、全くお手上げだ。」
「いや、最初からの流れを考えれば、結論は一つしかない。」
「どういうことだ?」
「全体は二つの点にかかっている。まず、パイクロフトにあんな宣誓書を書かせて会社に入らせたことだ。これは大いに示唆的だと思わないか?」
「意味が分からない。」
「なぜわざわざ書かせたのか? 通常こんなものは口頭で十分だし、例外にする理由は何もない。つまり、彼らは君の筆跡の見本をどうしても手に入れたかった。他に方法がなかったからだ。」
「なぜ?」
「そこだ。なぜだ? それが分かれば問題もかなり進展する。理由は一つしかない。誰かが君の筆跡を真似したがっていた。まずはその見本が必要だったのだ。次に、もう一つの点がある。ピナーが君に職を辞めずにおくように強く勧めたことだ。しかも、その会社の責任者には、君を一度も見たことがないまま、月曜朝にホール・パイクロフトがやってくると信じ込ませていた。」
「なんてことだ!」と依頼人は叫んだ。「なんて間抜けだったんだ!」
「これで筆跡の意味も分かるだろう。もしも、全く違う筆跡で応募した者がやって来たら、その瞬間に計画はバレてしまう。しかし、その間に悪党は君の字を真似できるようになっていて、その地位は安泰だ。オフィスの誰も君を見たことがないのだから。」
「一人もいません」パイクロフトはうめいた。
「だから、君に疑念を持たせず、君がロンドンに行って真相を知るのを防ぐため、前払い金まで渡し、ミッドランド地方に引っ張り出し、大量の仕事を与えたのだ。すべて理にかなっている。」
「でも、なぜこの男が自分の兄と偽ったんだ?」
「それも明らかだ。共犯者は二人だけ。もう一人がオフィスで君のふりをしている。こっちは君の雇い主役だが、三人目を加えるのは避けたかった。だから、できる限り外見を変え、似ているのは兄弟だからだと思わせようとした。だが、金歯の偶然がなければ、君は決して疑わなかっただろう。」
ホール・パイクロフトは握りしめた拳を空中で振り回した。「なんてこった!」と彼は叫んだ。「俺がこんなふうに騙されている間に、もう一人のホール・パイクロフトはモーソン社で何をしていたんだ? どうすればいい、ホームズさん? どうしたらいいか教えてくれ。」
「モーソン社に電報を打たねばならない。」
「土曜は12時で閉まるんです。」
「それでもかまわん。守衛か係の者がいるかもしれん――」
「ああ、そうです、あそこは保有している証券の価値が高いので常駐の警備を置いているんでした。シティでその話を聞いた覚えがあります。」
「よろしい、彼に電報を打って、すべてが無事かどうか、そして君の名を持つ事務員が働いているか確かめよう。それははっきりしている。しかし、はっきりしないのは、我々の姿を見た途端、悪党の一人がすぐに部屋を出て首を吊った理由だ。」
「新聞だ!」と、背後で声がかすれた。男は座り上がっており、顔色は青ざめ、生気を失っていたが、瞳には正気が戻りつつあり、手はまだ首に残る太い赤帯を神経質にさすっていた。
「新聞か! そうだ!」とホームズは興奮の極みで叫んだ。「なんて間抜けだったんだ! 我々の訪問のことばかり気にして、新聞のことは全く頭に浮かばなかった。間違いない、秘密はそこにあるはずだ。」彼はそれをテーブルの上に広げ、勝ち誇ったように叫び声をあげた。「見てくれ、ワトソン。これはロンドンの新聞、イブニング・スタンダードの早版だ。ここに我々が求めていたものがある。見てくれ、見出しを――『シティの犯罪。モーソン&ウィリアムズで殺人。巨額強盗未遂。犯人逮捕』だ。さあワトソン、我々全員が知りたがっているのだから、声に出して読んでくれ。」
新聞の中でも、この記事が街で唯一の重大事件であったらしく、その内容はこうだ――
「本日午後、シティにて強盗未遂事件が発生し、一人が死亡、犯人が逮捕された。かねてより、著名な金融会社モーソン&ウィリアムズは、総額100万ポンドを優に超える証券を預かる立場にあった。責任の大きさを痛感した支配人は、最新式の金庫を導入し、昼夜を問わず武装した警備員を建物に常駐させていた。どうやら先週、新たにホール・パイクロフトという名の事務員が採用されたが、この人物こそ、有名な偽造犯で金庫破りのベディントンであり、兄弟と共に最近ようやく五年間の懲役を終え出所したばかりだったようだ。いかなる手段かはまだ不明だが、彼は偽名で事務所に職を得ることに成功し、その地位を利用して各種の錠前の型を取り、強固な金庫室および金庫の配置を詳細に把握していた。
モーソン社では、土曜は正午に事務員が退社するのが通例である。シティ警察のトゥーソン巡査部長は、午後1時20分にカーペットバッグを持った紳士が階段を降りてくるのを見て、少々驚いた。疑念を抱いた巡査部長はその男を尾行し、ポロック巡査の協力も得て、激しい抵抗の末に逮捕に成功した。すぐに大胆かつ巨額の強盗事件が発生したことが明らかとなった。バッグの中からは、ほぼ10万ポンド分のアメリカ鉄道債券と、その他鉱山会社等の証券が多数見つかった。現場を調べると、不運な警備員の遺体が金庫の中でも最も大きなものに押し込まれて発見された。もしもトゥーソン巡査部長の迅速な行動がなければ、月曜朝まで発見されなかっただろう。男の頭蓋骨は、背後から与えられた火かき棒の一撃で砕かれていた。ベディントンは、忘れ物をしたと装って侵入し、警備員を殺害した後、急いで大型金庫を荒らし、戦利品と共に逃走したものと思われる。彼と共に行動していたはずの兄弟については、今回の事件には関与していなかったようだが、警察は現在、行方を熱心に捜索中である。」
「さて、警察の手間を少し省けそうだな」とホームズは、窓際にうずくまるやつれた男の姿に目をやりながら言った。「人間というのは実に奇妙な生き物だ、ワトソン。悪党で殺人者であっても、兄弟の首が飛ぶと知っただけで自殺に走るほどの情を呼び起こすことがある。しかし、我々がなすべきことは決まっている。医者の私とで警備に残るので、パイクロフト君、君は警察を呼びに行ってくれ。」
V. 「グロリア・スコット号」
「ここにいくつか書類がある」と、冬の夜、暖炉を挟んで座るホームズが言った。「ワトソン、君にもぜひ目を通してもらいたいと思う。これは『グロリア・スコット号事件』の資料で、これが、その判事トレバー氏を読んだとたん恐怖のあまり死なせた伝言だ。」
彼は引き出しから少しくすんだ円筒を取り出し、紐をほどくと、ねずみ色の半紙に走り書きされた短いメモを手渡した。
「ロンドン向けのジビエ供給は順調に増加中、とのこと。ヘッドキーパーのハドソンが、今後フライペーパーと雌キジの保護の注文すべてを受けるよう、指示されたと聞いている。」
この不可解な伝言を読み上げて顔を上げると、ホームズは私の表情を見てくすくす笑っていた。
「いささか混乱しているようだね」と彼は言った。
「こんな伝言がどうして恐怖を呼ぶのか、さっぱり分からん。むしろ滑稽に思えるね。」
「もっともだ。だが事実、その読者である立派な老人は、まるでピストルの銃床で殴られたかのように、これであっさり倒れてしまったのさ。」
「ますます興味をそそられるよ」と私は言った。「だが、なぜ君はさっき、この事件を私に特に詳しく見てほしいと言ったんだ?」
「僕が生まれて初めて関わった事件だからだよ。」
私はしばしば、友人が犯罪研究の道に進むきっかけを探ろうとしたが、これまで彼が饒舌になるところをとらえたことはなかった。今、彼は肘掛け椅子の上で身を乗り出し、膝に書類を広げた。するとパイプに火をつけ、しばらく煙をくゆらせながら書類をめくっていた。
「ヴィクター・トレバーのことは聞いたことがないか?」と彼は尋ねた。「大学時代、僕が唯一親しくなった友人が彼だった。僕はあまり社交的ではなくてね、いつも部屋でひとり物思いにふけって、自分なりの思考法をあれこれ編み出していたから、同級生ともあまり付き合わなかった。フェンシングとボクシング以外は運動にも興味がなく、学問の専門も他の連中と全然違っていたので、接点がほとんどなかった。トレバーだけが唯一の知り合いで、それもある朝、彼のブルテリア犬が僕の足首にかみついたという偶然からだった。
「何とも味気ない友誼の始まりだが、効果的だったよ。僕は十日間も寝込む羽目になったが、トレバーは見舞いに来てくれた。最初はほんの短い会話だったが、やがて訪問は長くなり、学期が終わるころにはすっかり親友になっていた。彼は快活で血気盛ん、エネルギーに満ちあふれ、僕とは正反対の性格だったが、共通の話題もあり、しかも彼もまた孤独だったのが縁となった。結局、彼は長期休暇の間、ノーフォーク州ドニソープにある父親の家に招待してくれ、僕は一か月間その厚意に甘えることにした。
「トレバー氏はどうやらかなりの資産家で、治安判事でもあり地主だった。ドニソープは、ラングミアの北に位置する小さな村で、湿地が広がる地方だ。邸宅は古風で横に広く、オーク材の梁が巡らされた煉瓦造りで、石灰樹の並木道が玄関まで続いていた。沼地でのカモ猟は絶品で、釣りも実に素晴らしかった。蔵書は少ないが厳選されたもので、前の住人から引き継いだと聞いた。また料理人もまずまずで、ここで退屈する者がいるなら、よほど贅沢な男だろう。
「トレバー氏はすでに妻に先立たれており、友人のトレバーが一人息子だった。
「娘がいたが、バーミンガムを訪問中にジフテリアで亡くなったと聞いた。父親は私にとって非常に興味深い人物だった。学問はほとんどないが、ずば抜けた体力と精神力を兼ね備えていた。本はほとんど読まないが、旅を重ねて多くを見聞し、そのすべてを記憶していた。外見は、がっしりした体格に白髪交じりの髪、大地で焼けた褐色の顔、そして鋭くて時に恐ろしいほどの青い目を持っていた。しかし地方では慈悲深さで知られ、判事としても温情判決で有名だった。
「到着して間もないある晩、食後にポートワインを傾けながら、トレバー青年は、すでに僕が体系化しつつあった観察と推論の習慣について話し始めた。老人は、彼の息子が僕の些細な業績を大げさに話していると思ったようだった。
『さあ、ホームズさん』と彼は朗らかに笑いながら言った。『私を好きに観察なさって結構です。何か推理できますかな?』
『あまり多くはありませんが』と私は答えた。『過去一年の間、何か身の危険を警戒していたようですね。』
笑みが消え、彼は驚きのあまり私を凝視した。
『それは確かに本当だ』と彼は言った。『ヴィクター、覚えているだろう。密猟団を摘発したとき、連中は我々を刺すと誓い、サー・エドワード・ホリーなど実際に襲われた。あれ以来、警戒していたが、どうして分かったのか不思議だ。』
『立派なステッキをお持ちですね』と私は答えた。『刻印から見て、ここ一年以内に手に入れたものでしょう。ただ、わざわざ頭部に穴をあけて鉛を流し込み、武器として相当な威力にしています。何か恐れるものがなければ、そこまで用心しないはずです。』
『他には?』と彼は微笑んだ。
『若い頃、ボクシングをよくなさったでしょう。』
『また当たりだな。どうして分かった? 鼻がゆがんでいるからかね?』
『いいえ』と私は言った。『耳です。ボクサー特有のつぶれて厚くなった形をしています。』
『他には?』
『手のタコから、かなり土を掘ったご経験がある。』
『金鉱で稼いだのさ。』
『ニュージーランドにも行きましたね。』
『その通り。』
『日本にも滞在された。』
『全くそうだ。』
『そして何より、J・Aというイニシャルの人物と非常に親しい関係があり、後に完全に忘れようとした。』
トレバー氏はゆっくりと立ち上がり、大きな青い目で私を異様なまなざしで見つめ、そのまま机の殻に顔を突っ伏して、バタリと気を失った。
「ワトソン、君にも想像がつくだろうが、私も息子も驚きで言葉も出なかった。しかし発作は長くは続かず、襟を緩め、水差しの水を顔に振りかけると、彼は数回大きく息をつき、やがて座り直した。
『いや、君たちを驚かせてしまったな』と彼は無理に笑いながら言った。『見かけによらず心臓に弱いところがあってな、大したことでなくても倒れてしまう。君はどうやるのか分からないが、現実でも空想でも、探偵なんて君の前じゃ子ども同然だ。君にはその道が向いているよ、世界を見てきた男の言葉だ。』
そして、その大げさな前置きとともに発せられた推薦の言葉が、実のところ、ワトソン、私がそれまで一種の道楽でしかなかった探偵術で生計を立てられるかもしれないと初めて自覚したきっかけだった。しかしその時は、主人の突然の発作でそれどころではなかった。
『何か気に障ることを言ったのでは?』と私は言った。
『まあ、少し痛いところを突かれたな。どうして分かった? どこまで知っている?』彼は半分冗談めかして話したが、目の奥にはまだ恐怖がうかがえた。
『極めて単純です』と私は言った。『あの時、魚を引き込もうと腕をまくった際、肘の内側にJ・Aの刺青があるのを見ました。文字はまだ読み取れましたが、にじみとその周囲の皮膚の変色から、消そうとした形跡が明らかにありました。つまり、そのイニシャルはかつて貴方にとって非常に親しいものであり、後にどうしても忘れたいものだったのです。』
『なんて観察力だ!』と彼は安堵の溜息をついて叫んだ。『まったくその通りだよ。でももうこの話はやめよう。昔の恋人の亡霊ほど始末に負えないものはない。ビリヤード室で一服しよう。』
その日以来、表向きは変わらぬ親しみを見せつつも、トレバー氏の私に対する態度には常にわずかな警戒心が混じるようになった。息子でさえそれに気づいていた。「君は親父に相当な衝撃を与えたから、これからは君が何を知っているやら分からないと、ずっと思い込むさ」と彼は言った。彼自身はその気がなかっただろうが、あまりに頭から離れず、行動の端々に表れていた。ついには私も滞在が迷惑になると感じ、滞在を切り上げることにした。しかし、出発前日の出来事が、後に思わぬ重要性を持つことになった。
私たち三人は庭の椅子に腰かけ、ブロッズの風景を眺めながら日なたぼっこをしていた。その時、メイドがやってきて、「トレバー様にお会いしたいという方がいらしています」と伝えた。
『名前は?』と主人が尋ねた。
『名乗りませんでした。』
『用件は?』
『お知り合いだそうで、ほんの少しお話が……と。』
『ここへ通しなさい。』まもなく、背の低い、やせた男が、へりくだった態度と引きずるような歩き方で現れた。ジャケットは袖にタールのしみがあり、赤と黒のチェックシャツ、デニムのズボン、すり減った重いブーツを履いていた。顔は細く日焼けしてずる賢そうで、常にニヤけた笑いのせいで黄色い歯が見え、手は船乗り特有の半ば握られた形だった。芝生を横切ってくる彼を見て、トレバー氏が喉でしゃくり上げるような音を立てて飛び上がり、家の中へ走り込んだ。すぐに戻ってきたが、私のそばを通る時、強いブランデーの臭いがした。
『それで、何の用だね?』と主人が話しかけた。
水夫は目を細めて彼をじっと見つめ、相変わらずだらしなく笑っていた。
『俺が誰だか分からねえんですかい?』
『やや、まさかハドソンか?』とトレバー氏は驚いた様子で言った。
『おうとも、旦那』と水夫。『もう三十年以上になりますな、あんたに会うのは。あんたは立派な家に住まい、俺は今も樽の塩肉をつまむ日々でさあ。』
『いや、昔のことは忘れていないとも』とトレバー氏は叫び、彼に歩み寄って小声で何か告げた。「台所に行きなさい、食事も酒も出そう。仕事も何とか探してやろう。」
『ありがとうございます、旦那』と水夫は帽子に手をやった。『八ノットの貨物船で二年乗りっぱなしでしたが、人手も足りなくてくたくたですわ。ベドーズさんかあんたの所で、骨休めしようと思いましてな。』
『何? ベドーズの居場所を知っているのか?』
『ええ、旦那。昔の仲間の居所は全部承知してますよ』と男は不気味な笑みを浮かべ、メイドの後について台所へ引っ込んだ。トレバー氏は「金鉱からの帰りに船で一緒だっただけだ」と我々にぼそぼそ説明し、再び家の中へ消えた。一時間後、室内に入ると、彼は食堂のソファで泥酔して横たわっていた。この一件は私に非常に不快な印象を残し、翌日ドニソープを離れるのがむしろ嬉しかったほどだ。私の存在が友人にとって気まずさの種になっているのを感じたからだ。
すべて長期休暇の最初のひと月の出来事だった。私はロンドンの部屋に戻り、有機化学の実験に七週間没頭した。しかし秋も深まり、休暇が終わりかけたころ、友人から電報が届いた。「ぜひともドニソープに戻ってほしい、助言と助けが必要だ」と懇願する内容だった。もちろん私はすべてを投げうって、再び北へ向かった。
「駅には彼がドッグカートで迎えに来てくれたが、ひと目見て、この二ヶ月が彼にとっていかに辛い時期だったかがすぐに分かった。彼はやせ細り、やつれ果て、以前は印象的だったあの快活で朗らかな態度もすっかり影を潜めていた。
『親父が死にかけている』――それが彼の最初の言葉だった。
『まさか!』と私は叫んだ。『いったいどうしたんだ?』
『脳卒中さ。ひどい神経衝撃を受けて、一日中発作の瀬戸際だった。今、生きているかどうかも疑わしいくらいだ。』
ワトソン、君も想像がつくと思うが、この不意打ちの知らせに私はぞっとした。
『原因は何だ?』と私は問いただした。
『ああ、それが問題なんだ。乗ってくれれば、道中詳しく話すよ。君が帰る前の晩に来た、あの男のことを覚えているか?』
『もちろんだ。』
『あの日、家に入れたのが誰だったか分かるか?』
『見当もつかない。』
『あれは悪魔だったんだ、ホームズ。』
私は驚いて彼を見つめた。
『ああ、悪魔そのものだった。それ以来、私たちは一時も安らかな時間を持てなかった――一度もだ。親父はあの晩からずっと元気をなくし、今や完全に打ちのめされ、心を砕かれてしまった。すべてこの忌々しいハドソンのせいだ。』
『彼に一体どんな力があったんだ?』
『それがどうしても知りたいところだよ。あんなに情け深く、慈悲深く、善良だった親父が、どうしてあんな不良の手中に落ちてしまったのか! でも君が来てくれて本当にうれしいよ、ホームズ。私は君の判断と分別を心から信頼しているし、きっと最善の助言をしてくれると確信している。』
私たちは滑らかな白い田舎道を駆け抜けていった。前方には広々としたブロッズが、沈みゆく夕陽に赤く輝いていた。左手の茂みの向こうには、地主の邸宅を示す高い煙突と旗竿が見えてきた。
『親父はあいつを庭師にしたんだ』と私の連れは言った。『だがそれでは満足せず、執事に昇格させた。家はまるで彼の好き放題で、自由に出入りし、思うままに振る舞っていた。女中たちは、彼の酒癖とひどい言葉遣いに文句を言った。親父は皆の給料を上げて、迷惑料のつもりで慰謝した。あいつはよくボートや親父の上等な猟銃を持ち出して、勝手に狩猟に出かけた。そして、その間もあんなに人を小馬鹿にしたような、いやらしく横柄な態度をとるから、もし同じ年頃だったら二十回は殴り倒していただろう。ホームズ、本当にこの間、私は自分を必死で抑えてきたんだ。今はむしろ、もう少し自分を抑えずにいた方が、より賢かったのではないかと自問している。
『状況はどんどん悪化し、あの下劣なハドソンはますます図々しくなっていった。そしてついに、ある日親父に向かって私の目の前で無礼なことを言ったので、私は彼の肩をつかんで部屋から追い出した。あいつは顔を青ざめさせ、毒々しい目で何より強い脅しを残して、すごすごと退散した。その後、親父とあいつの間で何があったのかは分からないが、翌日親父が私のところへ来て、ハドソンに謝ってくれないかと言ってきた。当然だが私は断った。そして、どうしてそんなろくでなしに家でも自分自身にも好き勝手を許すのかと問いただした。
『“ああ、お前には分からないんだよ” と親父は言った。“だがいずれ分かる日が来る。どんなことがあっても、お前にはちゃんと分かってもらう。お前は自分の親父について悪いことなんて思わないだろう? ” 親父はとても動揺していて、一日中書斎にこもり、窓越しに見ると必死に何かを書いていた。
『その晩、私には大きな解放が訪れたように思えた。ハドソンが出て行くと言い出したのだ。夕食後、私たちが食堂にいると、彼は半分酔ったような口調でその意思を伝えてきた。
『“もうノーフォークにはうんざりだ”とやつは言った。“ハンプシャーのベドーズ氏のところへ行くさ。あっちもこっちと同じくらい歓迎してくれるだろうよ。”
『“ハドソン、意地悪な気持ちで出て行くんじゃないだろうな? ”と親父が言った。その弱々しい言い方に私は怒りがこみ上げた。
『“まだ謝罪されてない”とあいつは私の方を見ながら不機嫌そうに言った。
『“ヴィクター、お前はこの立派な男にだいぶきつく当たっただろう”と親父が私を向いた。
『“反対だ。私たちは両方とも、あいつに対して信じられないほど我慢強かったと思う”と私は答えた。
『“ほう、そうかい? ”と、やつは鼻で笑った。“いいだろう、友よ。いずれ分かるさ! ”そう言って部屋を出て行き、三十分後には屋敷を後にした。そのせいで、親父は哀れなほど神経質になった。夜ごと親父が自室をうろつく音が聞こえた。やっと自信を取り戻し始めた矢先に、ついに事件が起きたんだ。
『どうやって?』と私は身を乗り出した。
『とても奇妙な形でね。昨日の夕方、フォーディングブリッジの消印が押された手紙が親父に届いた。親父はそれを読むなり両手で頭を抱えて、まるで正気を失ったかのように部屋の中をぐるぐる回り始めた。何とかソファに座らせたが、口元とまぶたが片側だけ歪み、私はすぐに脳卒中だと分かった。フォーダム医師がすぐに駆けつけてくれた。親父をベッドに運んだが、麻痺は広がる一方で、意識は戻らず、恐らくもう助からないだろう。
『トレバー、なんてことだ!』と私は叫んだ。『一体その手紙の中に、どうしてそんな恐ろしい影響を与えるものがあったんだ?』
『何もだ。そこが不可解なところさ。内容は馬鹿げていて取るに足らないものだった。ああ、神よ、やはりそうだったのか!』
彼がそう言った時、私たちは屋敷の並木道のカーブを曲がり、薄暗がりの中で家中のブラインドがすべて下ろされているのが見えた。門前に駆けつけると、私の友人の顔は苦悩で歪み、黒服の紳士が家から出てきた。
『いつ亡くなったんですか、先生?』とトレバーは尋ねた。
『君が出てすぐだったよ。』
『意識は戻りましたか?』
『最期の瞬間に一度だけ。』
『私に伝言は?』
『“書類は日本のキャビネットの裏引き出しだ”とのことだった。』
友人は医師とともに亡骸のもとへ行き、私は書斎に残って、この一件について何度も考えを巡らせ、これまでにないほど沈んだ気持ちでいた。かつてボクサーであり、旅人であり、金鉱堀りでもあったこのトレバーという人物の過去は何だったのか。どうして彼はあの陰気な顔付きの水夫の手中に落ちてしまったのか。なぜ、腕の消えかけたイニシャルに触れられるだけで気絶し、フォーディングブリッジから手紙が来ただけで死ぬほど恐れたのか――私はふと思い出した。フォーディングブリッジはハンプシャーにあり、水夫が訪ねて恐喝しようとしたベドーズ氏もまたハンプシャーに住んでいると聞いていた。つまり、その手紙はハドソン(水夫)が罪をバラしたことを知らせるものか、あるいはベドーズが旧友に裏切りの危機が迫っていることを警告したものだった可能性が高い。ここまでは筋が通る。しかし息子の説明では、その手紙は取るに足らず、妙ちきりんな内容だったという。彼は読み違えているのではないか? だとすれば、それは一見無意味な言葉に見せかけて、別の意味を持たせた巧妙な暗号文に違いない。私はどうしてもこの手紙を見てみたかった。もし隠された意味があるなら、必ずや見抜いてみせる自信があった。私は一時間ほど薄暗い部屋で思案を巡らせていると、泣きはらした女中がランプを運んできた。その後ろから、顔は蒼白だが気丈に振る舞うトレバーが、膝に乗せたこの書類一式を持って入ってきた。彼は私の正面に座り、ランプをテーブルの端に引き寄せ、一枚の灰色の紙に殴り書きされた短い文を私に手渡した。「ロンドン向けの猟鳥の供給は順調に増加中。猟場主任ハドソンには、ハエ取り紙と雌キジの保護に関する注文をすべて受けるよう伝えたとのこと。」
私は、今君がそうだったように、きっと途方に暮れた顔をしたことだろう。それから何度も読み直した。やはり思った通り、奇妙な語句の中に何らかの秘密の意味が隠されているはずだ。あるいは「ハエ取り紙」や「雌キジ」にあらかじめ決められた意味があるのだろうか? だが、それは恣意的で解読できないはずだ。とはいえ、文中に「ハドソン」の名があることから、やはり内容は私の推測通りで、送り主は水夫ではなくベドーズだろう。逆から読んでみたり、交互の単語だけ拾ってみたり、いろいろ試したが、どれもうまくいかなかった。だが、ふとした瞬間に謎を解く鍵が手に入った。最初の単語から三語おきに拾っていくと、老トレバーを絶望の淵に突き落とすような警告文が現れたのだ。
それは短く簡潔な警告だった。私はそれを同行の彼に読み上げた。
「ゲームは終わった。ハドソンがすべてを話した。命がけで逃げろ。」
ヴィクター・トレバーは顔を両手で覆い、震えながら言った。「きっとこれに違いない。死よりつらい――それは破滅と恥を意味するからだ。でも“猟場主任”や“雌キジ”の意味は何なんだ?」
「本文自体には意味はないが、もし送り主を突き止める手段がなかった場合、我々には大きなヒントになるかもしれない。ほら、“The……game……is……”といった具合に、三語ごとに意味のある単語を置き、間はどんな語でも埋められる。思い付いた言葉を適当に入れたのだろうが、狩猟に関する単語が多いということは、送り主が猟や鳥の飼育に熱心な人物だと見てまず間違いない。君はベドーズについて何か知っているか?」
「そういえば」と彼は言った。「親父が毎年秋になると、ベドーズ氏の猟場に招かれていたのを思い出した。」
「なら、間違いなくこの手紙は彼からだ」と私は言った。「あとは、この水夫ハドソンが、なぜ二人の裕福で名望ある男たちにこんなに力を持っていたのか、その秘密を突き止めるだけだ。」
「ホームズ、これはきっと罪と恥の秘密なんだ!」と友人は叫んだ。「しかし君には何も隠し立てはしない。これが、親父がハドソンの脅威が切迫したと感じた時にまとめた書類だ。日本のキャビネットにあると医師に言っていたものを見つけた。読んでくれ、私にはとても読む勇気も力もない。」
これが、その時彼から手渡されたまさにその書類だ、ワトソン。私はその晩、あの古い書斎で彼に読み聞かせた通り、君にも読み上げようと思う。表紙にはこう書かれている――「バーク船グロリア・スコット号、1855年10月8日ファルマス出港から11月6日北緯15度20分西経25度14分での遭難に至る航海の若干の詳細」。手紙の形式で、こう始まっている――
『親愛なる息子よ―― 私の晩年が迫り、今や不名誉の影がその人生を覆おうとしているこの時、私は真実と誠実をもって、私の心を最も痛めるものは、法の恐怖でもなく、郡での地位の喪失でもなく、私を知るすべての人々の目に堕ちることでもないと書き記すことができる。ただ、お前が私のことで恥じ入ること、それだけが心をえぐるのだ――お前は私を愛してくれ、今まで私に失望させられたこともほとんどなかったはずだ。それでも、もしついにこの降りかかる運命が落ちてきたならば、この手紙を読んで、私自身の口からどこまで私が悪かったのか知ってほしい。逆に、もし何事もなく済み(神のご加護を!)、偶然この紙が焼かれずにお前の手に渡ったときは、どうかお前の大切なものすべてと、母の思い出と、私たちの間にあった愛にかけて、この手紙を火にくべ、二度と気にしないでほしい。
『それでもこの行を読んでいるなら、私はすでに世間に晒され、家から連れ去られているか、あるいは――多分こちらだろうが――心臓が弱いことを知っているだろう、お前の目の前で死んでもはや口を開くこともできなくなっているはずだ。いずれにせよ、もはや隠し立てする時ではない。私が記す一言一句は赤裸々な真実であり、これに救いを祈って誓う。
『私の本名はトレバーではない。若いころ私はジェームズ・アーミテッジであり、数週間前に君の友人が私にその秘密を見抜いたような言葉をかけたとき、いかに私が衝撃を受けたか君にも分かるだろう。アーミテッジとして私はロンドンの銀行に勤め、アーミテッジとして祖国の法を犯し有罪となり、流罪を宣告された。どうか私をあまり責めないでくれ、息子よ。いわゆる名誉のための借金を払うため、他人の金を使ってしまったのだ。すぐに返せると信じていたが、思いもよらぬ不運が重なり、あてにしていた金が届かず、帳簿の早期調査で私の不足が露呈した。当時の法律は今より遥かに厳しく、私の二十三歳の誕生日に、他の三十七人の囚人とともに囚人船グロリア・スコット号の船倉に鎖でつながれて、オーストラリア送りとなった。
『あれは五十五年のこと、クリミア戦争の真っ只中で、多くの囚人船が黒海の輸送に使われていた。政府はやむなく小さく不適当な船で囚人を送るしかなかった。グロリア・スコット号は中国の茶貿易で使われていたが、時代遅れで船首は丸く幅広。新型の快速帆船に遅れをとっていた。五百トン級の船で、囚人三十八名に加え、乗組員二十六名、兵士十八名、船長、三人の航海士、医師、牧師、看守四名がいた。総勢百人近くでファルマス港を出発した。
『囚人房の仕切りは、通常の厚いオーク材とは違い、ひどく薄く脆弱だった。私の後ろ側の隣人は、埠頭で引き立てられる時に特に目に留まった男だった。若く、つるりとした顔、長く細い鼻、ナッツクラッカーのような顎。頭を高く掲げ、威張った歩き方で、何よりもその異様な長身が際立っていた。私たちの誰一人として、彼の肩にも届かないほどで、六フィート半(約二メートル)あったはずだ。沈んだ顔ばかりの中、彼だけは精気と決意に満ちていて、吹雪の中の炎のように私には見えた。私は彼が隣人であることを嬉しく思い、深夜、耳元でささやき声が聞こえ、私たちを隔てる板に彼が穴を開けたことを知ったときには、なおさらだった。
『“やあ、友達! ”と彼は言った。“名前は何だ? 何をやった? ”
『私は答え、逆に君は誰だと尋ねた。
『“俺はジャック・プレンダーガストだ。神にかけて、俺の名をありがたく思うことになるぜ。”
『彼の事件は私も聞き覚えがあった。私が逮捕される以前、全国を震撼させた大事件だった。名家の出で才能もあったが、改心不能の悪癖の持ち主で、巧妙な詐欺の手法でロンドンの大商人から巨額の金をかすめ取っていた。
『“はは、俺の事件を覚えているな”と彼は誇らしげに言った。
『“もちろんだ。”
『“じゃあ、一つ妙な点を憶えているか? ”
『“何だそれは? ”
『“ほぼ25万ポンド手にしたんじゃなかったか? ”
『“そう言われていた。”
『“だが一銭も見つからなかっただろ? ”
『“ああ。”
『“じゃあ、その残りはどこにあると思う? ”と彼は訊いた。
『“見当もつかない”私は答えた。
「『ちょうどこの親指と人差し指の間に』と彼は叫んだ。『畜生め! 俺の名義の金はお前の頭の毛より多いぜ。もし金があって、それをどう使い、どうばらまくか知っていれば、何だってできるんだ! さて、そんな何だってできる男が、ネズミに食われて虫にたかられたカビ臭い古い棺桶みたいなチャイナ・コースターのくさい船倉で尻をすり減らして座ってるなんて、お前は思わないだろう。違うな、そんな男は自分の身も仲間の身もちゃんと守るもんさ。それは間違いない! そいつをつかまえておけ、そうすれば必ずお前を引き上げてくれると誓ってもいいさ』
『それが彼の話しぶりで、最初は何の意味もないと思っていた。だがしばらくして、彼が俺を試し、これ以上ないほど厳粛に誓わせたあとで、実際にこの船の支配権を奪おうという陰謀があるのだと理解させてくれた。囚人のうち十数名が乗船する前から計画を立てており、首謀者はプレンダーガストで、金が原動力だった。
『「俺には相棒がいる」と彼は言った。「抜け目のない奴で、樽の台木のように信頼できる男だ。今どこにいると思う? なんと、この船の牧師だよ――そう、牧師だ! 黒い上着を着て、きちんとした書類を持ち、船を丸ごと買えるほどの金を箱に入れて乗り込んできた。乗組員はみな彼のもの、身も心もな。大口割引でまとめ買いができるくらいだし、実際、彼らが雇われる前に全部買収してある。看守のうち二人と二等航海士のマーサーも仲間だ。船長だって、もし価値があると見れば味方に引き込んでいただろうよ」
『「それで、俺たちはどうするんだ?」と俺は訊いた。
『「どう思う?」と彼は言った。「今まで仕立屋がどんなに赤くしたって、俺たちがこいつら兵隊の制服をもっと赤く染めてやるさ」
『「だが、奴らは武装してるぞ」と俺は言った。
『「俺たちも武装するさ、坊や。俺たちみんなに二連発ピストルが一丁ずつある。乗組員が味方なら、この船を奪えなきゃ、女学校にでも送り込まれた方がマシってもんだ。今夜、お前の左隣の仲間に話して、信用できるかどうか見てみろ」
『そうしたら、もう一人の隣人は俺と同じような境遇の若者で、罪状は偽造だった。名前はエヴァンズ、だが後に俺と同じように改名し、今ではイングランド南部で裕福に暮らしている。自分を救う唯一の方法だとして、すぐに陰謀に加わることを承知した。ベイ(ビスケー湾)を越えるまでには、囚人のうち二人を除いて全員がこの計画の仲間になっていた。一人は精神に異常があり、信頼できなかったし、もう一人は黄疸にかかり使いものにならなかった。
『最初から、実際のところ俺たちが船を奪うのを妨げるものは何もなかった。乗組員はこのために選ばれた荒くれどもだった。偽の牧師は黒いカバンを手に俺たちの房に度々やってきたが、中身は伝道冊子ではなく、三日目には俺たち全員がベッドの足元にやすり、二連発ピストル一丁、火薬1ポンド、鉛弾20発を隠していた。看守のうち二人はプレンダーガストの手下で、二等航海士は右腕だった。俺たちに敵するのは船長、二人の航海士、看守二人、マーティン中尉、その部下18名、そして医者だけだ。それでも、油断はせず、夜の突然の襲撃を決行することにした。だが、それより早く事態が動いたのだ。
『出航して三週目ほどのある夕方、医者が病気の囚人の様子を見に来て、ベッドの底に手を伸ばしたとき、ピストルの形を感じ取った。もし彼が黙っていたら、すべて台無しになっていたかもしれないが、小柄で神経質な男だったので、驚いて叫び声を上げ、顔面蒼白になった。これで事態を即座に察知され、押さえつけられてしまった。警報を上げる前に猿轡をされ、ベッドに縛りつけられる。彼は甲板への扉の鍵を開けていたので、俺たちは一気にそこを突破した。哨兵二人が撃たれ、騒ぎを聞きつけて駆けつけた伍長も同様に撃たれた。次に士官室の扉前に兵士二人がいたが、銃に弾が入っていなかったのか発砲せず、銃剣を装着しようとしたところを撃たれた。さらに俺たちは船長室へ突入し、扉を開けた瞬間、中から爆発音が響き渡った。船長が大西洋の海図の上に脳漿を撒き散らして倒れており、牧師はその傍らで煙を上げるピストルを手にしていた。二人の航海士は乗組員に捕らえられ、すべてが決着したように思えた。
『士官室は船長室の隣で、俺たちは一斉にそこへなだれ込み、ソファにへたり込んで、みんな一斉に声を上げていた。自由になった興奮で気が狂いそうだった。そこにはロッカーが並んでおり、偽の牧師ウィルソンがその一つを壊して茶色いシェリー酒を12本取り出した。瓶の首を叩き割り、グラスに注ぎ、一息に飲み干そうとしたその瞬間、何の前触れもなく銃声が耳をつんざき、サロンは煙で視界ゼロに。煙が晴れると、そこはまるで屠殺場だった。ウィルソンと他八人が床の上でのたうち、テーブルの上の血とシェリー酒とが今でも思い出すだけで吐き気を催す。あまりの光景に呆然となり、もしプレンダーガストがいなかったら誰もが諦めていたと思う。彼は雄牛のように吠えて扉に突進し、生き残った者たちがその後に続いた。デッキに出ると、そこには中尉と兵士十人。サロンの上のスカイライトが少し開いていて、そこから銃撃されたのだった。こちらが駆けつける前に奴らは再装填できず、男らしく立ち向かったが、俺たちが優勢ですぐに決着がついた。畜生、あんな屠殺場みたいな船が他にあるか! プレンダーガストはまるで悪魔のごとく荒れ狂い、兵士たちを子供のように持ち上げては生死問わず海に投げ込んだ。ひどく傷ついた軍曹が驚くほど長く泳ぎ続けていたが、誰かが哀れんで頭を撃ち抜いた。戦いが終わると、敵方で生き残っていたのは看守、航海士、医者だけだった。
『その生き残りをどうするかで大きな争いが起きた。自由を手に入れたこと自体は嬉しかったが、皆が皆、冷血な殺人を望んでいたわけではない。武装した兵士を倒すのと、無抵抗な人間が殺されるのを黙って見ているのとは別の話だ。俺を含む囚人五人と水夫三人の八人は、そんなことは容認できないと言った。だがプレンダーガストとその仲間は聞く耳を持たなかった。完全に証拠を消さなければ安全はないと言い張り、生き証人など一人も残さぬと言い張った。俺たちも危うく囚人たちと同じ運命をたどるところだったが、結局、もし望むならボートで去ってもいいと言われた。俺たちは飛びついた。この血なまぐさい所業にはもううんざりだったし、これからもっとひどいことになると予感していた。水夫服一式ずつ、水一樽、塩漬け肉とビスケットの樽を一つずつ、コンパスを与えられ、プレンダーガストは海図を投げ渡し、「お前たちは北緯15度、西経25度で難破した船員だ」と言い残してロープを切り、俺たちを解放した。
『ここからが話の驚くべき部分だよ、息子よ。反乱の際、船員たちは前檣の帆を逆向きにしていたが、俺たちが離れると再び帆を正位置に戻し、北東からの微風にのってバーク船はゆっくり遠ざかっていった。俺たちのボートは長い緩やかなうねりの上に上下し、エヴァンズと俺は一番教養があったので、シートに座って位置を計算し、どの海岸を目指すか相談していた。ケープ・ヴェルデ諸島は北へ約五百マイル、アフリカの海岸は東へ約七百マイルだった。風が北に回ってきたので、結局シエラレオネを目指すことに決め、バークはすでに右舷後方に船体がほとんど見えないほど遠ざかっていた。そのとき突然、彼女の方から濃い黒煙がモクモクと空に立ちのぼるのが見え、まるで巨大な樹木のように水平線上に広がった。数秒後、雷のような轟音が耳に届き、煙が薄れていくとグロリア・スコット号の姿はどこにもなくなっていた。俺たちはすぐにボートの向きを変え、全力でその惨事の跡を示す水面の霞の方へ漕いだ。
『現場に着くまで一時間近くかかった。間に合わなかったかと最初は思った。壊れたボートや木箱、マストのかけらが波間に漂っていて、ここに船が沈んだことは分かったが、生存者は見当たらず、諦めて引き返そうとしたとき、助けを呼ぶ声が聞こえ、遠くに漂流物にしがみついている男を見つけた。ボートに引き上げてみると、火傷と疲労でぐったりした若い船員で、名前はハドソン。何が起きたかは翌朝まで語れなかった。
『話によると、俺たちが去ったあと、プレンダーガスト一味は残り五人の生き残りを処刑し始めた。看守二人は撃たれて海に放り込まれ、三等航海士も同様。プレンダーガスト自身が甲板下に降り、不運な軍医の喉を掻き切った。残るは一等航海士だけだったが、彼は勇敢で行動力のある男で、血まみれのナイフを持った囚人が近づくと、どうにか縄をほどき、デッキを駆け下りて船倉に飛び込んだ。
『拳銃を持った囚人たち十数名が後を追って降りていくと、彼はマッチ箱を手に火薬樽の一つ(百樽も積んでいた)横に座り、「手を出したら全員吹き飛ばすぞ」と叫んでいた。直後に爆発が起こったが、ハドソンによれば仲間の囚人の誤射によるものらしい。いずれにせよ、グロリア・スコット号とその悪党どもはこれで終わった。
『要点だけ語ったが、息子よ、これが俺が巻き込まれた恐ろしい事件の顛末だ。翌日、オーストラリア行きのブリッグ船ホットスパー号に救助され、船長も俺たちが難破船の生存者だとすぐに信じてくれた。輸送船グロリア・スコット号は海上で行方不明との記録しか残らず、その真相は一切漏れなかった。順調な航海の末、ホットスパー号からシドニーで上陸し、エヴァンズと俺は名前を変えて金鉱へと向かった。あらゆる国から集まった群衆の中で、身元を隠すのは簡単だった。
『それ以後のことは語る必要もないだろう。俺たちは成功を収め、各地を旅して、裕福な開拓民としてイギリスに戻り、田園の屋敷を買った。二十年以上、平穏で有益な人生を送り、過去は永遠に葬られたものと信じていた。にもかかわらず、あの船員が訪ねてきたとき、すぐにかつて難破船から救い上げた男だと分かった時の気持ちが分かるだろう。奴は何とかして俺たちの行方を突き止め、俺たちの恐怖を食い物にする覚悟で現れたのだ。俺が彼と穏便に済ませようとした理由、そして今や奴が他の犠牲者のもとへ脅迫とともに去ったことによって胸を満たす恐怖に、君も多少は同情してくれるだろう』
下には、ほとんど判読できないほど震えた文字でこう書き添えられていた。「ベドーズが暗号で書いてよこした。Hがすべてを話したと。主よ、我らの魂をお救いください!」
その夜、私はこの話を若いトレバーに読み聞かせた。ワトソン、状況を鑑みれば実に劇的な話だったと思う。彼は心底打ちのめされ、インドのテライ地方の茶園に赴任したと聞いているが、今はそこできっとうまくやっているはずだ。船員とベドーズについては、警告の手紙が書かれたあの日以来、二人とも消息を絶った。完全に、跡形もなく消えてしまった。警察にも訴えはなかったので、ベドーズは脅しを本当の事件と勘違いしたのだろう。ハドソンがうろついているのを目撃され、警察は彼がベドーズを殺して逃亡したと考えていたが、私は全く逆だと思う。追い詰められ、すでに裏切られたと信じたベドーズがハドソンに復讐し、可能な限りの金を持って国外逃亡したのだろう。これが事件の全貌だ、ワトソン博士。君の記録に役立つなら、喜んで提供しよう」
VI. マスグレーヴ家の儀式
私の友人シャーロック・ホームズの性格で、しばしば私が奇妙に思ったのは、考え方や推理の方法は誰にも劣らぬほど几帳面で論理的なのに、生活習慣となると、同居人を発狂させるほど無頓着な男であったことである。もっとも、私自身がこの点で特に堅苦しいわけではない。アフガニスタンでのごたごた続きの経験と、元々の自由な気性が重なって、医者としては少々だらしない部類かもしれない。しかし、私にも限度というものがある。葉巻を石炭入れにしまい、タバコをペルシャ製スリッパのつま先に押し込み、未返事の手紙をジャックナイフで暖炉の木枠に突き刺す、となれば、さすがの私も自分が規律正しい人間であるかのような気分になるというものだ。また、拳銃の練習は絶対に屋外ですべきだと常に考えてきたので、ホームズが突拍子もない気分の時に肘掛け椅子に座り、引き金の軽いリボルバーと百発のボクサー弾丸を持ち出して、向かいの壁に「V. R.」の文字(英国女王陛下の頭文字)を銃痕で刻むのを見ると、部屋の空気も見た目も台無しだと強く感じたものだ。
私たちの部屋には常に化学薬品や犯罪の遺留品がごちゃごちゃと置かれ、バター皿の中や、より不適切な場所からひょっこり現れることもあった。しかし、私の一番の悩みは彼の書類だった。ホームズは特に過去の事件に関わる書類を捨てるのを極度に嫌がったが、かといって年に一度か二度しか整理してくれない。私のこのまとまりのない回想録のどこかに書いたと思うが、彼が驚くべき偉業を成し遂げる情熱の爆発は、必ずその後に無気力な反動をもたらし、本やバイオリンとともにソファからテーブルへとほとんど動かずに過ごす時期がやってくるのだ。そんなわけで、書類は月ごとに山積みとなり、部屋の隅々まで赤いヒモでまとめた原稿の束が積まれ、絶対に燃やしてはいけないし、持ち主自身しか片付けられない。ある冬の夜、一緒に暖炉の前に座っていた私は、彼が切り抜きをスクラップ帳に貼り終えたところで、次の二時間を使って部屋を少しは片付けてはどうかと提案してみた。彼もさすがに正当な指摘を否定できず、やや不満げな顔で寝室へ引っ込み、やがて大きなブリキ箱を引きずって戻ってきた。それを部屋の真ん中に置き、腰掛けに座り込んで蓋を開けた。すでに三分の一は赤いヒモでまとめた書類の包みが詰まっているのが見て取れた。
「ここには事件が山ほど入っているぞ、ワトソン」と彼はいたずらっぽい目で私を見て言った。「もし君がこの箱の中身を全部知っていたら、新しいものを入れるより中から何か引っぱり出してくれと言うだろうね」
「これが君の初期の事件記録なのか?」と私はたずねた。「その頃の記録が手元にあればと何度思ったことか」
「ああ、そうだ。これらはみんな、君という伝記作家が俺を持ち上げてくれる前の話さ」彼はひとつひとつの包みを、いとおしそうに優しく扱いながら持ち上げた。「必ずしもすべて成功したわけじゃないが、中にはなかなか面白い小事件もある。これがタールトンの殺人記録、ぶどう酒商人ヴァンベリーの事件、老いたロシア婦人の冒険、アルミ杖の奇妙な話、足が不自由なリコレッティとその忌まわしい妻の記録もある。そして――おっと、これはなかなか珍品だぞ」
彼は腕を胸の底まで突っ込み、子供のおもちゃを入れるようなスライド式の蓋のついた小さな木箱を取り出した。その中から、彼はくしゃくしゃになった紙切れ、古風な真鍮の鍵、糸玉のついた木製の杭、そして錆びた金属製の円盤を三枚取り出した。
「さて、ワトソン。この品々をどう思う?」彼は私の表情を見て微笑みながら尋ねた。
「奇妙な品揃えだな」
「実に奇妙だ。そしてこれにまつわる話は、それ以上に奇妙だと感じるはずだ」
「これらの遺物にも歴史があるのか?」
「歴史があるどころか、これ自体が歴史そのものなんだ」
「それはどういう意味だ?」
シャーロック・ホームズはそれらを一つずつ手に取り、テーブルの端に並べていった。その後、椅子に腰を下ろし、満足げな光を目にたたえながら品々を見渡した。
「これらはな、私に“マスグレーヴ家の儀式”の冒険を思い出させてくれる、唯一残った品なんだ」
私は彼がその事件について何度か口にしているのを聞いたことがあったが、詳細を聞き出すことはできずにいた。
「ぜひ、その話を聞かせてほしい」
「この散らかったままにしておいていいのか?」と、彼はいたずらっぽく叫んだ。「君の几帳面さも、結局は大したことないな、ワトソン。しかし君の記録にこの事件を加えてもらえるなら私としてもうれしい。なぜならこの事件には、犯罪記録でも他のどの国の記録でも、おそらく類を見ない特徴があるからだ。私のささやかな功績を集めた記録も、これほど特異な事件を含まなければ不完全だろう。
「君も覚えているだろう、“グロリア・スコット号”の事件や、私がその運命を語った哀れな男との会話が、どれほど私を自分の天職へと導くきっかけになったかを。今の私は、名が広く知られ、世間からも警察当局からも疑わしい事件における最終の判断者と認められている。君が私と知り合った頃――『緋色の研究』に記された事件の頃――にも、私はすでにそれなりの、とはいえあまり実入りのよくない依頼を抱えていた。だからこそ、最初はどれほど困難だったか、成果を得るのにどれだけ時間を要したか、想像しにくいだろう。
「ロンドンへ出てきた当初、私は大英博物館のすぐ近く、モンタギュー通りの部屋を借りていた。そこで、余りある暇を、効率向上に役立ちそうなあらゆる分野の科学研究に費やしていた。たまに事件が舞い込むのは、主に昔の学友の紹介によるものだった。大学の最終学年の頃には、私や私の手法について噂が立っていたからだ。そうした中で三番目の事件が“マスグレーヴ家の儀式”だった。そして、この特異な事件の連鎖が呼び起こした関心や、大きな意味合いが明らかになったことこそ、私が今の地位への第一歩を踏み出したきっかけだと考えている。
「レジナルド・マスグレーヴは、私と同じカレッジにいた男で、私は彼と軽い知り合いだった。彼は学生たちの間で特に人気があるわけではなかったが、私にはその“プライドが高い”と評された態度も、実際は極度の内気さを隠そうとしたもののように思えた。見た目は典型的な貴族で、痩せ型、高い鼻、大きな目、物腰はだるげだが上品だった。彼は王国最古の家柄の一つの分家で、16世紀に北部マスグレーヴ家から分かれて西サセックスに根を張り、ハールストンのマナーハウスは今や県内最古の居住建造物かもしれない。その生まれ故郷の空気が彼にも染みついているようで、私は彼の青白い鋭い顔や、頭の構えを見るたびに、灰色のアーチや格子窓、そして封建時代の古びた館の残骸が思い浮かんだ。何度か言葉を交わしたが、彼は私の観察や推理の方法に強い関心を示していたのをよく覚えている。
「その後四年間、彼とはまったく会わなかったが、ある朝突然、彼がモンタギュー通りの私の部屋を訪ねてきた。彼はほとんど変わらず、流行の若者らしい服装で――元来しゃれ者だった――以前と同じ落ち着いた、洗練された態度を保っていた。
『調子はどうだ、マスグレーヴ?』と、固く握手を交わした後、私は尋ねた。
『父の死はご存じかと思う。二年ほど前に急に亡くなった。それ以来、ハールストンの領地管理を任されているし、地元の議員でもあるから、忙しい日々を過ごしている。しかしホームズ、君があの驚異的な能力を現実の仕事に役立てていると聞いたが?』
『ああ、今は知恵を武器に生きている』
『それはうれしい知らせだ。というのも、君の助言が今の私には非常に貴重だからだ。ハールストンではこのところ不可解な出来事が続いていて、警察にも手が出せないでいる。本当に前代未聞で、説明のつかない事態なんだ』
君も想像がつくだろう、ワトソン。長い無為の時間を焦がれて待っていた私にとって、まさに渇望していた機会が目の前に現れたのだ。心の奥底では、他の者が失敗したところで自分ならやれると信じていたし、ようやくその力を試すチャンスが訪れたのだ。
『ぜひ詳細を聞かせてほしい』私は叫んだ。
レジナルド・マスグレーヴは向かいの椅子に腰を下ろし、私が勧めたシガレットに火をつけた。
『ご存じの通り、私は独身だが、ハールストンでは多くの使用人を抱えている。広くて入り組んだ古い屋敷なので、管理に手がかかるんだ。それに私は領地を保有していて、キジ狩りの時期にはよく客を招くから、人数が足りないわけにもいかない。だから、女中が八人、料理人、執事、下男二人、そして小僧一人がいる。庭や厩舎にはまた別のスタッフがいる。
『その中でも最も長く仕えていたのが執事のブラントンだ。彼はもともと職を失った若い学校教師だったが、父が雇った後は持ち前の活力と人柄で家庭にはなくてはならない存在になった。容姿も立派で額も広く、二十年も仕えているが、今でも四十には達していないはずだ。その人柄や非凡な才能――数か国語を話し、ほぼあらゆる楽器を弾きこなす――からすれば、なぜ執事という地位に満足していたのか不思議なくらいだが、居心地がよかったのだろうし、変化を求める気力がなかったのかもしれない。ハールストンの執事は、訪れる人々の誰もが記憶に残す存在だ。
『だが、この非の打ち所のない男にも一つ弱点があった。少し女たらしなんだよ。静かな田舎では、彼のような男にはそうするのも易しかったのだろう。結婚していた時はよかったが、未亡人になってからは手を焼きっぱなしだった。数か月前、ようやく再婚する気かと期待した。というのも、家政婦の二番手であるレイチェル・ハウエルズと婚約したのだが、その後彼女を捨て、猟場管理人の娘ジャネット・トレゲリスと付き合いだした。レイチェルはとてもよい子だが、興奮しやすいウェールズ人気質で、激しい脳炎にかかり、昨日まで屋敷の中をまるで黒い瞳の影のようにふらふら歩き回っていた。これがハールストンでの最初の騒動だったが、次なる事件がそれを吹き飛ばすことになる。それは執事ブラントンの不名誉と解雇で幕を開けた。
『ことの起こりはこうだ。彼が聡明な男だとはすでに述べたが、その聡明さが彼を破滅に導いた。というのも、まったく自分に関係のないことにも抑えきれない好奇心を抱いてしまったからだ。その好奇心がどれほど彼を暴走させるか、私は偶然に気づかされるまで思い至らなかった。
『屋敷は広くて入り組んでいる、と言っただろう。先週のこと――正確には木曜の夜――私は夕食後に強いカフェノアール[訳注:ブラックコーヒー]を飲んでしまい、まったく眠れなくなった。二時まで粘ったが、もう諦めてろうそくに火をつけ、読んでいた小説を続けることにした。だが本はビリヤード室に置き忘れていたので、寝巻きにガウンを羽織り取りに行くことにした。
『ビリヤード室に行くには一階分階段を下り、図書室と銃器室に続く廊下の上を横切る必要がある。ところが廊下を覗き込むと、図書室のドアから明かりが漏れているのが見えた。私は寝る前にランプを消し、ドアも閉めていたはずだ。最初に思い浮かんだのは泥棒だった。ハールストンの廊下には古い武器のトロフィーがずらりと飾ってある。そこから一つバトルアックスを手に取り、ろうそくを置いて、忍び足で廊下の先へ進み、ドアの陰から中を覗いた。
『執事のブラントンが図書室にいた。彼は完全に服を着たまま安楽椅子に座り、膝に地図のような紙片を乗せて、額を手に当てて深く考え込んでいた。私は暗闇からただ呆然と見守っていた。テーブルの端に小さなろうそくがともされ、彼が着衣のままでいるのが分かった。すると突然、彼は椅子から立ち上がり、脇のビューローへ歩み寄ると鍵を開け、引き出しの一つを取り出した。そこから書類を取り出し、席に戻ると、それをろうそくの明かりの下で丁寧に広げ、じっくりと読み始めた。家の書類を平然と調べているこの様子に私は激しく憤り、つい一歩踏み出してしまった。するとブラントンが顔を上げ、私がドア口に立っているのに気づいた。彼は飛び上がり、恐怖で顔を青ざめさせ、もともと読んでいた地図のような紙を胸に押し込んだ。
「そうか」私は言った。「これが我々の信頼に対する報いというわけだな。明日限りで屋敷を去ってもらう」
『彼は打ちひしがれた表情で頭を下げ、無言ですごすごと私の前を通り過ぎた。テーブルにはまだろうそくが残っていたので、その明かりでブラントンがビューローから出した書類を見てみた。驚いたことに、それはまったく重要なものではなく、単に“マスグレーヴ家の儀式”と呼ばれる古風な慣習の質疑応答の写しだった。我が家独自の儀式で、代々成人したマスグレーヴ家の者が行うものだ。考古学者には興味があるかもしれないが、実用的な意味はない、家紋や紋章のような私的なものでしかないのだ』
「その紙については、また後で戻ろう」私は言った。
『本当に必要かな?』と彼はややためらいながら答えた。『ともかく話を続けよう。私はブラントンが残した鍵でビューローを施錠し、立ち去ろうとしたところ、彼が戻ってきて私の前に立っていた。
「マスグレーヴ様」と彼は感情に震えた声で叫んだ。「私は不名誉に耐えられません。身分以上に誇り高く生きてきましたが、不名誉は私を殺します。もし私を絶望に追い込むなら、私の血はあなたの手にかかることになります。どうしても私を置いておけないなら、せめて自分の意思で辞めることにして一か月後に去らせてください。それなら耐えられますが、顔なじみの者たちの前で追い出されるのだけは耐えられません」
「君のことを思いやる理由はほとんどない、ブラントン」私は答えた。「君の行動は実に恥ずべきものだ。しかし長く仕えてくれたこともあり、公然と不名誉を与える気はない。だが一か月は長すぎる。一週間で出て行くこと。理由は好きに言ってよい」
「たった一週間ですか」彼は絶望的な声で叫んだ。「せめて二週間……せめて二週間だけ!」
「一週間だ」私は繰り返した。「それでも十分大目に見ていると思え」
『彼はうなだれて立ち去り、私は明かりを消して自室へ戻った。
『この後二日間、ブラントンは今まで以上に熱心に職務をこなした。私は何も言わず、彼がどのようにこの不名誉を取り繕うのか興味深く見守っていた。だが三日目の朝、いつものように朝食後、私の指示を聞きに来ることはなかった。食堂を出たところで、レイチェル・ハウエルズに偶然会った。先にも話したが、彼女は最近まで病み上がりで、あまりに青白くやつれていたので「無理をせずベッドで休むように」と諭した。
「君はベッドにいるべきだ。元気になってから仕事に戻ればいい」
『彼女は実に奇妙な表情で私を見つめたので、私は彼女の精神状態を疑い始めた。
「私は十分元気です、マスグレーヴ様」
「医者に相談しよう。今は休むんだ。下に降りた時、執事に私が呼んでいると伝えてくれ」
「執事はもういません」
「いない? どこへ行った?」
「もういません。誰も見ていません。部屋にもいません。本当にいなくなってしまったんです!」彼女は壁にもたれかかり、何度も何度も甲高い笑い声をあげ、私はこの急なヒステリー発作に愕然としてベルを鳴らし人を呼んだ。彼女は泣き叫びながら部屋に運ばれ、私はブラントンの所在を調べ始めた。間違いなく彼は姿を消していた。ベッドには寝た形跡がなく、前夜部屋に入った後は誰にも見られていない。だが、朝には窓もドアも施錠されていたので、家を出た形跡もない。部屋には服も時計も金もそのままあったが、いつも着ている黒服だけが消えていた。スリッパもなかったが、ブーツは残されていた。となると、執事ブラントンは夜中にどこへ消えたのか? そして今どこにいるのか?
『もちろん家中を隅から隅まで探したが、何の手掛かりもなかった。特に使われていない旧館の棟などは迷路のようだが、部屋も地下室も徹底的に捜索した。それでも全財産を残したまま出ていくとは考え難いが、どこにもいない。地元警察を呼んだが成果はなし。前夜は雨だったので庭や小道も調べたが無駄だった。そうこうするうちに、元の謎を吹き飛ばすほどの新たな展開が起きた。
『レイチェル・ハウエルズはこの二日間、時にうわごとを言い、時にヒステリーを起こすほど体調が悪く、夜は看護婦が付き添うことになった。ブラントン失踪の三日目の夜、看護婦が彼女の寝息を確認しながらうたた寝していたところ、早朝に目が覚めるとベッドは空になり、窓は開き、彼女の姿はなかった。私はすぐに目を覚まし、下男二人と共に彼女を探しに出た。彼女の足跡は簡単に見つかり、部屋の窓の下から芝生を横切り、池の縁まで続いていた。足跡は砂利道のすぐそばで消えていた。その池は深さ八フィートある。足跡が池の縁で途絶えているのを見て、我々の気持ちは察してしかるべきだろう。
『もちろんすぐに池を引き揚げて遺体を探したが、何も発見できなかった。その代わり、思いもよらぬものを引き揚げた。古びて錆びた金属や色あせた小石やガラス片が詰まったリネンの袋だった。この奇妙な発見だけが池から得られたもので、昨日もくまなく捜索し、あらゆる手を尽くしたものの、レイチェル・ハウエルズもリチャード・ブラントンも消息は掴めなかった。郡警察もお手上げ状態で、私は最後の頼みの綱として君の元を訪ねたのだ』
君も想像できるだろう、ワトソン。この並外れた事件の連鎖に私はどれほど興奮し、それらをつなぐ糸口を懸命に探したかを。執事は姿を消した。女中も消えた。女中は執事を愛していたが、やがて憎む理由もできた。彼女はウェールズの血を引き、激しやすい性格だった。執事の失踪直後、彼女はひどく興奮していた。彼女は奇妙な中身の袋を池に投げ込んだ。これら全てが考慮すべき要素だが、どれも核心には届いていなかった。事件の連鎖の出発点はどこにあるのか――それこそが、このもつれた糸の端だった。
「『その書類を見せてくれ、マスグレーヴ』と私は言った。『君の執事が、職を失う危険を冒してまでわざわざ調べる価値があると思った書類だ。』
『これは我々の儀式の中でも、かなり馬鹿げたものなんだ』と彼は答えた。『ただ、古くから伝わるということで、そこだけは救いと言えるだろう。質問と答えの写しがここにあるから、よかったら目を通してみてくれ。』
彼は私に、ワトソン、この手元にあるまさにその書類を渡してくれた。そしてこれが、マスグレーヴ家の一族が成年に達したとき、皆が受けなければならなかった奇妙な問答だ。これから、その質問と答えをそのまま読んで聞かせよう。
『それは誰のものか?』
『去りし者のもの。』
『誰がそれを受け継ぐのか?』
『来たる者が受け継ぐ。』
『太陽はどこにあった?』
『樫の上に。』
『影はどこにあった?』
『楡の下に。』
『どのように歩を進める?』
『北へ十歩ずつ、東へ五歩ずつ、南へ二歩ずつ、西へ一歩ずつ、そしてその下へ。』
『それのために何を差し出す?』
『我々のすべてを。』
『なぜ差し出すのか?』
『信託のために。』
『原本には日付はないが、十七世紀半ばの綴りになっている』とマスグレーヴは言った。『だが、この謎の解明には、あまり役に立たないと思うのだが。』
『少なくとも』と私は言った、『もう一つの謎を与えてくれたことになるし、しかも最初のものよりもずっと興味深い。もしかすると、一方の謎の解決が、もう一方の謎の答えになるかもしれない。失礼だが、君の執事は非常に賢い男で、何世代にもわたる主人たちよりもはるかに鋭い洞察を持っていたように見えるよ。』
『君の言うことがよくわからない』とマスグレーヴは言った。『この書類は実用的な意味があるとは思えないが。』
『だが私には、きわめて実用的に思える。そしてブラントンも同じ考えだったに違いない。おそらく、君が彼を見つけたあの夜以前にも、彼は書類を見ていたのだろう。』
『十分ありうる。私たちはそれを隠そうともしなかったからな。』
『きっと彼は、最後にもう一度記憶を確かめたかったのだろう。彼は、何か地図や図面のようなものを持ち、それを原稿と照らし合わせていて、君が現れたときにそれをポケットにしまったのだと思う。』
『その通りだ。しかし、彼が我が家の古いしきたりとどんな関わりがあるのか、そしてこの意味不明な文句は何を指しているのか?』
『それを突き止めるのに、そう苦労はしないだろう』と私は言った。『もし許してくれるなら、サセックス行きの一番列車で現地に向かい、もう少し詳しく調べてみたい。』
その日の午後、私たちは二人してハールストンに着いた。有名な古い建物については、絵や解説をすでにご覧になったことがあるだろうから、ここでは簡単に説明するにとどめよう。建物はL字型をしており、長い方の翼が新しい部分、短い方が古い核となる部分で、そこから増築されてきた。古い部分の中央にある、低くて重厚な梁のある扉の上には「1607」と刻まれているが、専門家によれば梁や石組みは実際にはそれよりはるかに古い。厚い壁と小さな窓のため、この部分は前世紀に新しい翼が建てられる原因となり、今では物置や地下室としてしか使われていない。素晴らしい古木に囲まれた立派な公園が屋敷を取り囲み、依頼人が言及していた湖は、建物から二百ヤードほどの並木道のすぐそばにあった。
ワトソン、私はこの時すでに、ここに三つの謎があるのではなく、ただ一つの謎だけがあるのだと確信していた。そして、もしこのマスグレーヴ家の儀式を正しく読み解くことができれば、執事ブラントンとメイドのハウエルズに関する真実に至る手がかりが手に入るはずだと考えた。だからこそ、私はすべての精力をこれに注いだ。なぜこの使用人はこの古い定型文を必死に覚えようとしたのか。明らかに、歴代の地主たちが見逃してきた何かを彼が見いだし、そこから私利を得ようとしていたからだ。では、その「何か」とは何で、それが彼の運命にどう関わったのか?
儀式文を読むと、そこに記された歩測は、文中で言及されている何らかの場所を指しているに違いないことが私には明白だった。その場所を突き止めれば、マスグレーヴ家がなぜこれほど奇妙な形で秘密を守ってきたのか、その答えに近づけるはずだ。まず手がかりとなるのは「樫」と「楡」の木だ。樫については全く疑いがなかった。屋敷の正面、車道の左手に堂々とした樹齢を誇る樫が立っていた。私の見た中でも最も見事な木のひとつだった。
『この儀式が作られた当時から、あの木はあったのだろう』と馬車で通り過ぎながら私は言った。
『おそらくノルマン征服時代からあったのだろう』と彼は答えた。『周囲は二十三フィートある。』
『古い楡の木はないか?』と私は尋ねた。
『かつてはあそこに一本あったが、十年前に落雷で切り倒した。切り株は残っている。』
『どこにあったか分かるか?』
『もちろん。』
『他に古い楡は?』
『いや、古いものはないが、ブナの木ならたくさんある。』
『その楡が生えていた場所を見てみたい。』
私たちはドッグカートで到着したばかりだったが、依頼人は家に入ることもなく、私を芝生の楡の跡地へ案内してくれた。それは樫と屋敷のおよそ中間地点にあった。調査は順調に進んでいた。
『その楡の高さは分からないだろうか?』と私は尋ねた。
『すぐに分かる。六十四フィートだった。』
『どうしてそんなことが分かるのか?』と私は驚いて尋ねた。
『昔、家庭教師が三角法の練習で、敷地内の木や建物の高さを全部測らせたのだ。』
これは思いがけない幸運だった。これで必要なデータが思ったより早く揃ったのだ。
『ねえ、君の執事はそのことを尋ねたことがあるか?』
レジナルド・マスグレーヴは驚いた様子で私を見た。『そう言われてみれば、数か月前にブラントンが馬丁との口論のついでに、あの木の高さを聞いたことがある。』
これは実に良い知らせだった。調査の道筋が正しいことが分かったからだ。私は太陽を見上げた。低い位置にあり、あと一時間もしないうちに、古樫の一番高い枝の真上に来ると計算した。儀式に記された条件の一つがそのとき満たされるのだ。そして、楡の影は「幹」ではなく「影の先端」を意味するはずだ。そうでなければ幹そのものを目印にするだろうから。つまり、太陽が樫の上に来たとき、楡の影の先端がどこに落ちるかを突き止める必要がある。
『しかし、ホームズ、その楡はもう無いのだから、難しかっただろう?』
『いや、少なくともブラントンにできたのなら、私にもできるはずだ。それに実際、難しいことではない。私はマスグレーヴと書斎に行き、この杭を削り、長い糸を結び、一ヤードごとに結び目を作った。さらに、釣竿を二本繋ぎ、ちょうど六フィートの長さにした。それを持って楡の跡地へ戻った。ちょうど太陽が樫のてっぺんにかかっていた。私は竿を立てて影の向きを定め、長さを測った。九フィートだった。
さて、計算自体は簡単なものだ。六フィートの竿が九フィートの影を作るなら、六十四フィートの木は九十六フィートの影を作ることになるし、方向も一致する。私はその距離を測り、ちょうど家の壁際に来たところで、杭を地面に刺した。ワトソン、想像してみてほしい。その杭のほんの二インチ横に、円錐状のくぼみがあった。これはブラントンが測量したときにつけた跡であり、私は依然として彼の足跡を追っていることに確信を持った。
ここから私は、まず方位磁石で東西南北を定めてから歩測を開始した。片足ずつ十歩進むと、家の壁に沿って進むことになり、その場所にも杭を刺した。さらに東に五歩、南に二歩進めば、ちょうど古い扉の敷居に来た。そして西に二歩は、今度は石畳の廊下を二歩進むことを意味しており、つまりそこが儀式で示された場所だった。
ワトソン、これほどまでに冷たい失望を感じたことはなかった。一瞬、計算の根本が間違っていたのではないかと思った。夕陽が廊下の床を照らし、すり減った灰色の古い石がしっかりと固められて、長い間動かされた形跡がないのが一目でわかった。ブラントンがここで作業した様子はなかった。床を叩いても、どこも同じ音が返り、亀裂や隙間も見当たらなかった。だが幸いなことに、私の行動の意図を理解し始め、私と同じくらい興奮しだしたマスグレーヴが、計算を確認しようと原稿を取り出した。
『“そしてその下へ”だ! 君は“そしてその下へ”を抜かしている!』と彼が叫んだ。
私は掘ることだと思っていたが、すぐさま自分が間違っていたと気づいた。『となると、この下には地下室があるのか?』と叫んだ。
『ああ、屋敷と同じくらい古い地下室がある。こっちだ、この扉から行ける。』
私たちは石造りの螺旋階段を下り、彼がマッチで大きなランタンを灯した。すぐに、ここが本当に目的の場所であり、我々だけが最近訪れた者ではないことも明らかになった。
そこは以前は薪の保管に使われていたが、床に散らばっていたはずの薪の束が両側に寄せられ、中央が広く開けていた。その真ん中に、大きく重い石板があり、中央の錆びた鉄輪には分厚い羊飼い柄のマフラーが結び付けられていた。
『おお、これはブラントンのマフラーだ。彼がしていたのを見たことがあるし、間違いない! この悪党はここで何をしていたんだ?』と依頼人が叫んだ。
私の提案で、郡警察の警官を二人立ち会わせ、それから私はマフラーを引っ張って石を動かそうとした。少しだけ動いたが、結局は警官の助けを借りてようやく脇にずらすことができた。下には黒々とした穴が口を開け、皆で覗き込むと、マスグレーヴがランタンを持って膝をつき、穴の中に明かりを下ろした。
そこには、深さ約七フィート、幅四フィート四方ほどの小部屋があった。一方には、真鍮の縁取りのある木箱があり、上蓋は上に開き、古風な大きな鍵が錠前から突き出ていた。外側は厚い埃に覆われ、湿気と虫に食われて木が腐り、中には青白いカビが生えていた。底には私が今ここに持っているような古い金属の円盤、つまり古銭がいくつか散らばっていたが、それ以外には何も入っていなかった。
だが、その時私たちは古い箱どころではなかった。目を奪われたのは、その傍らにうずくまる人影だった。黒いスーツを着た男がしゃがみこみ、額を箱の縁にあずけ、両腕をのばして箱の両側に投げ出していた。その姿勢のせいで、顔中に血が集まり、誰にもその歪んだ赤黒い顔を見分けることはできなかったが、身長や服装、髪型だけで、遺体を引き上げたとき依頼人には間違いなく、行方不明だった執事だと分かった。死後すでに数日経っており、致命傷や打撲は見当たらなかった。遺体を地下室から運び出したとき、私たちは依然として、最初のものに劣らず難解な問題に直面していた。
ワトソン、正直に言えば、私はこの捜査にがっかりしていた。儀式で示された場所を見つければ謎は解けると踏んでいたのに、現場に辿り着いた今も、なぜこれほど入念に隠されたのか分からなかった。確かに、ブラントンの運命には光が当てられたが、彼がなぜそうなったのか、失踪した女性がどう関わったのかを突き止めなければならなかった。私は隅の樽に腰を下ろし、全体をじっくりと考え直した。
こういう場合、私のやり方はワトソン、君も知っている通りだ。私はまず相手の知性を推し量り、その上で自分だったら同じ状況でどうしたかを想像する。この場合、ブラントンはきわめて優秀だったので、個性による誤差を考慮する必要はなかった。彼は何か価値あるものが隠されていると知り、その場所を突き止めた。そして覆いの石が一人では動かせないと分かった。次にどうするか? 信頼できる人がいたとしても、外部の手を借りればドアの開閉や発覚の危険が伴う。それなら、できれば屋敷内の協力者がよかったはずだ。では誰に頼むか? この女は彼に惚れていた。男は、自分がどんなにひどい仕打ちをしても、女の愛を完全に失ったとはなかなか思えないものだ。だから、ちょっとした優しい言葉でハウエルズと和解し、共犯者に引き入れた。こうして二人で夜に地下室へ来て、二人がかりで石板を持ち上げた。ここまでは、まるで実際にその現場を見てきたかのように推理できた。
だが、男と女の二人がかりでも、あの石を動かすのはかなりの重労働だったはずだ。屈強なサセックスの警官と私でも苦労したのだから、どうやって補助したのか? おそらく、私ならこうするだろう。そこで私は、床に散乱している薪の束を調べた。すると案の定、三フィートほどの長さの木材の端が大きく凹み、いくつかは側面が重みで平らにつぶれていた。つまり、石板を少し持ち上げるたびに木片を隙間へ押し込み、やがて人が通れるだけの隙間ができたとき、石板の重みで押しつぶされた一束が支えとして使われたのだ。ここまでは確実な推論だ。
では、ここからどうやってこの夜中の悲劇を再現するか? 明らかに、穴に入れるのは一人だけで、それがブラントンだった。女は上で待っていた。ブラントンは箱の鍵を開け、(中身が消えていたことから)おそらく中身を上に渡した。そして――そして何が起きたのか?
この激しい気性のケルト女性の心に、復讐の炎が突如として燃え上がったのか。自分を裏切った男――我々が想像する以上に、彼女を傷つけた男――が自分の手中にあるのを見て、一瞬の衝動で木片を倒し、石板が元に戻って彼を生き埋めにしたのか。あるいは、単に木片が偶然外れてしまい、彼女は黙って成り行きを見守っただけなのか。いずれにせよ、私はその女が宝を手にしながら、螺旋階段を駆け上がり、背後から彼氏のくぐもった叫び声や石板を叩く狂乱の音を聞きながら、逃げ出す姿を想像した。
これこそが、翌朝の彼女の青ざめた顔、震える神経、ヒステリックな笑い声の秘密だった。しかし、箱の中身は何だったのか? 彼女はそれをどうしたのか? もちろん、依頼人が池から引き上げた金属片や石ころだったのだ。彼女は自分の犯罪の痕跡を消すため、最初の機会にそれを池に投げ捨てたのだろう。
私は二十分ほど動かずに、全体を考え抜いていた。マスグレーヴは青い顔のまま、ランタンを振りながら穴を覗き込んでいた。
『これはチャールズ一世時代のコインだ』と彼は箱に残っていた数枚を差し出して言った。『儀式の日付が正しかったことが裏付けられるね。』
『チャールズ一世の遺品が何か他にも見つかるかもしれない』と私は叫んだ。儀式の最初の二つの問いの意味が突然わかったからだ。『君が池から釣り上げた袋の中身を見せてくれ。』
私たちは書斎へ上がり、彼が中身を広げて見せた。その時は私も、彼がそれを取るに足りないものと考えた理由が分かった。金属はほとんど黒ずみ、石も光沢を失い鈍く曇っていたからだ。しかし私は一つを袖で磨いてみた。すると、それは暗い手のひらのくぼみの中で、火花のように美しく輝いた。金具は二重の輪になっていたが、元の形から曲がり、ねじれていた。
「『忘れてはならないのは』と私は言った、『王の死後もイギリスでは王党派が勢力を保っていたこと、そしてついに逃亡する際、彼らは最も貴重な財宝の数々を、平穏な時代が訪れた後に取り戻すつもりで地中に隠していった可能性が高いという点だ。』
『私の先祖、ラルフ・マスグレーヴ卿は、著名な王党派であり、放浪中のチャールズ二世の右腕だった』と友人は言った。
『なるほど、それは重要な手がかりになるな。本当におめでとうと言わねばなるまい、少々悲劇的な形ではあったが、君は非常に価値の高い遺品を手に入れた。それだけでなく、歴史的にも大変興味深い品だ。』
『それは一体何なんだ?』と彼は驚きのあまり息を呑んだ。
『それは、かつてイギリス王が戴いていた古代の王冠そのものだ。』
『王冠!』
『その通りだ。儀式文書を思い出してみたまえ。どう書かれていた? 「それは誰のものか?」――「去りし者のもの」。これはチャールズ一世の処刑後のことだ。次に「誰がそれを持つべきか?」――「来るべき者」。これは、すでに予期されていたチャールズ二世を指している。つまり、この傷だらけで形の崩れた王冠こそ、かつて王家のスチュアート家の額を飾ったものに違いないと私は思う。』
『じゃあ、それがどうして池の中に?』
『それはまた別の話で、説明には少し時間がかかる』。そう言って、私はこれまでに組み立ててきた推論と証拠の連鎖を、彼に詳しく説明した。語り終えるころには、夕闇が迫り、月が明るく空に輝いていた。
『それで、どうしてチャールズは帰国したときに王冠を手に入れなかったんだ?』とマスグレーヴが、遺品をリネンの袋へ押し戻しながら尋ねた。
『そこが唯一、我々には永遠に解明できないかもしれない点だ。おそらく、その秘密を知っていたマスグレーヴ家の人物が、その間に亡くなり、何らかの手違いで、意味を説明せずにこの手引きを子孫に残してしまったのだろう。それ以来、父から子へと引き継がれ、ついにその秘密を解き明かし、命を落とした者の手に渡ることとなったのだ。』
――というのが「マスグレーヴ家の儀式」の一件だ、ワトソン。王冠はいまハールストンに保管されている――もっとも、保有するまでに法的な面倒や相当な金銭が必要だったが。君が私の名前を出せば、きっと見せてくれるはずだ。あの女性については消息がまったく分からず、おそらくはイギリスを離れて、どこか遠い地で自らの罪の記憶と共に生きていったのだろう。」
VII. リージゲイトの地主たち
私の友人、シャーロック・ホームズの健康が、1887年春の激務による消耗から回復するまでには、しばらく時間を要した。ネーデルランド=スマトラ会社の全容や、バロン・モープルテュイの巨大な陰謀については、世間の記憶も新しく、政治や金融に深く関わるため、ここで詳述するにはふさわしくない。ただ、これらの事件が間接的に、私の友人に生涯の犯罪との戦いにおいて新たな武器の有効性を示すまたとない機会をもたらす、奇妙で複雑な難事件を呼び寄せることとなった。
私の記録を見返すと、4月14日にリヨンから電報が届き、ホームズがホテル・デュロンで病床にあると知らされた。その24時間後には、私は彼の病室に駆けつけ、症状が思ったほど重くないことに安堵した。それでも彼の鉄の体力さえも、二ヶ月以上に及ぶ捜査の重圧に屈していた。その間、ホームズは一日十五時間以上働き続け、時には五日間ぶっ通しで任務に没頭したと語っていた。かくも過酷な労苦の末に勝利を収めても、反動からは逃れられず、ヨーロッパ中にその名が轟き、部屋が祝電で足の踏み場もない有様にもかかわらず、私は彼が深い憂鬱に陥っているのを見出した。三カ国の警察が成し得なかった成功を収め、ヨーロッパ随一の詐欺師を完璧に出し抜いたという事実でさえ、彼を神経衰弱から救うことはできなかった。
三日後、私たちはベーカー街に戻ったが、気分転換が必要なのは明らかで、私も春の田舎で一週間過ごすのは大いに魅力的に思えた。私の旧友、ロス大佐はアフガニスタンで私の診療を受けて以来、サリー州リージゲイト近くに家を構えており、しばしば遊びに来るよう私に声をかけていた。最後に会った際には、「君のご友人が一緒でも歓迎する」と言ってくれた。多少の根回しは必要だったが、ホームズも独身者ばかりの家で自由に振る舞えると知ると、私の提案に快く応じ、リヨンから戻って一週間後には大佐の家に滞在することになった。ヘイター大佐は見識ある歴戦の軍人で、私の予想通り、ホームズとすぐに意気投合した。
到着した夜、私たちは夕食後、銃器室でくつろいでいた。ホームズはソファに寝そべり、大佐と私は彼の小さな銃のコレクションを眺めていた。
「そうだ」と大佐がふと思い出したように言った。「念のため、ピストルの一丁を寝室に持っていこうと思う。何かあったときのためにな」
「何かあるんですか?」と私は尋ねた。
「ああ、最近このあたりで不穏な事件があってね。地元の名士のアクトン老人の家が、先週月曜に荒らされたんだ。大した被害はなかったが、犯人はまだ捕まっていない。」
「手がかりは?」とホームズが大佐に鋭い視線を送った。
「今のところ全くないよ。だが、あれは大した事件じゃない、田舎の小さな犯罪さ。国際的な大事件のあとじゃ、ホームズさんには取るに足らないだろうね。」
ホームズは手を振って謙遜したが、微笑みからして内心は喜んでいるようだった。
「興味深い特徴はあったか?」
「まあ、ないと思う。泥棒は書斎を荒らしたが、ほとんど収穫なしだった。家中ひっくり返され、引き出しはこじ開けられ、戸棚も物色されたが、消えたのはポープの『ホメロス』の奇妙な一冊、銀メッキの燭台二つ、象牙のペーパーウェイト、小さなオーク材の気圧計、それと麻ひもの玉だけだ。」
「なんとも妙な取り合わせだな」と私は驚いた。
「要するに、手当たり次第に持ち去ったんだろう。」
ソファからホームズがうならされた。
「郡警察がその点から何か掴めるはずなんだが」とホームズは言った。「なぜなら、それは明らかに――」
だが、私は制止の合図をした。
「ここは休養のための場所だよ。神経がボロボロなんだから、新しい事件に取りかかるのはやめてくれ。」
ホームズは肩をすくめ、大佐におどけたような視線を送り、話題はより無難なものへと移った。
だが、私の医師としての配慮も空しく、翌朝、問題は私たちのもとに否応なく持ち込まれ、思いがけない方向へと展開していった。朝食中、慌てた様子の執事が飛び込んできた。
「ご存じですか、旦那様!」と息を切らせて言う。「カニンガム家で――!」
「泥棒か!」とコーヒーカップを宙に掲げたまま大佐が叫んだ。
「殺人です!」
大佐は口笛を吹いた。「なんてこった! 被害者は? 治安判事(J.P.)か、その息子か?」
「どちらでもありません、旦那様。殺されたのは御者のウィリアムです。心臓を撃たれ、即死でした。」
「誰が撃ったんだ?」
「泥棒です。撃った後、あっという間に逃げ去りました。ちょうど配膳室の窓から侵入したところを、ウィリアムが見つけ、主人の財産を守ろうとして命を落としました。」
「何時ごろだ?」
「昨晩、十二時前後かと。」
「よし、あとで様子を見に行こう」大佐は落ち着いて朝食に戻った。「厄介な事件だな」と執事が去った後で続けた。「カニンガム老人はこの辺りの有力者だし、立派な人物だよ。長年仕えてきた忠実な召使いを失って、相当堪えるだろう。どうやらアクトン家を襲ったのと同じ連中だろうな。」
「しかも、妙な品々を盗んだあの事件だな」とホームズが考え込むように言った。
「その通り。」
「ふむ。単純な事件かもしれないが、第一印象では少し奇妙だな。田舎の泥棒なら、同じ地域で続けて二件もやらないのが普通だ。昨夜、用心の話をした時も、この辺りは盗賊に狙われる最後の場所だと思ったくらいで、私もまだまだ修行が足りないようだ。」
「地元の仕業だと思うよ」と大佐。「そうなら、アクトン家もカニンガム家も、この辺りじゃ一番大きな屋敷だから格好の標的だ。」
「裕福なのか?」
「本来ならね。ただ、もう何年も訴訟続きで、両家とも財産を食い潰してる。アクトン老人はカニンガム家の土地の半分に権利があるらしく、弁護士が両家の財産を吸い上げている。」
「地元の犯人なら、捕まえるのも難しくないだろう」とホームズはあくびをした。「分かったよ、ワトソン、口出しはしない。」
「フォレスター警部がお見えです」と執事がドアを開けて言った。
公式な制服姿の、きびきびした若い警部が入ってきた。「おはようございます、大佐。お邪魔でしたらすみませんが、ベーカー街のホームズさんが滞在中と伺いまして。」
大佐はホームズを指差し、警部は会釈した。
「もしよろしければ、ホームズさんにも現場を見ていただければと。」
「運命には逆らえないな、ワトソン」とホームズは笑った。「ちょうどその話をしていたところだ、警部。詳細を聞かせてもらえるかな。」ホームズが椅子に深く腰掛ける様子を見て、私はもう止められないと悟った。
「アクトン家の件では手がかりがありませんでしたが、今回は多くの材料があります。両事件は同じ犯人によるものと思われます。目撃証言もあります。」
「ほう!」
「はい。ただ、撃たれたウィリアム・カーワンが倒れた直後、犯人は鹿のように素早く逃走しました。カニンガム氏は寝室の窓から、息子のアレック氏は裏口の廊下から犯人を目撃しました。警報が鳴ったのは十二時十五分前。カニンガム氏がちょうど床に就いたところで、アレック氏はガウン姿でパイプを吸っていました。ウィリアムが助けを呼ぶ声を両名が聞きつけ、アレック氏が駆けつけると玄関の階段下で二人がもみ合っていました。一発の銃声が響き、一人が倒れ、犯人は庭を横切って生け垣を越え、カニンガム氏は寝室の窓から道路に出る犯人を見ましたが、すぐに見失いました。アレック氏は瀕死のウィリアムの介抱に当たり、その隙に犯人は逃走しました。中背で暗色の服を着ていた以外、人物特定の手がかりはありませんが、地元民でなければいずれ判明するでしょう。」
「ウィリアムは何をしていたんだ? 死ぬ前に何か言ったか?」
「一言もありません。彼は母親と門番小屋で暮らしていました。とても忠実な男だったので、屋敷が無事か確かめに来たのでしょう。アクトン家の事件以来、皆が用心しています。犯人はちょうどドアをこじ開けたところで、ウィリアムが出くわしたのです。」
「出かける前に母親に何か言い残したか?」
「母親は高齢で耳も遠く、何も聞き出せません。今回のショックでさらに混乱し、元からあまり頭の回る人でもなかったようです。ですが、非常に重要な証拠が一つあります。これです!」
警部は手帳から小さな紙片を取り出し、膝の上に広げた。
「これは死者の指と親指の間に挟まっていた紙片で、どうやら大きな紙からちぎられたもののようです。ご覧の通り、そこに書かれている時刻は、ちょうどウィリアムが殺された時間と一致しています。犯人にちぎり取られたのか、あるいは犯人から引きちぎったのか分かりませんが、これはまるで約束のメモのようです。」
ホームズはその紙片を手に取った。その複写がここに示されている。
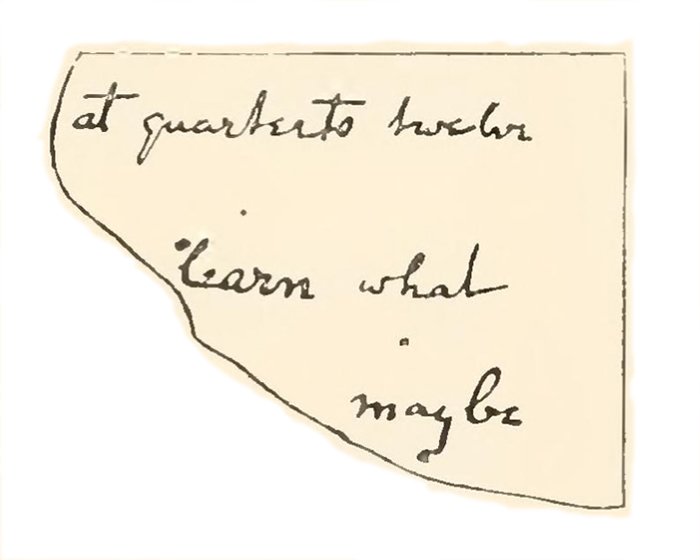
「もしこれが約束の文であれば」と警部は続けた。「ウィリアム・カーワンは誠実な男と評判でしたが、泥棒と通じていた可能性も考えられます。そこで出会い、侵入を手引きした後、何らかの揉めごとが起きたのかもしれません。」
「この筆跡は非常に興味深い」ホームズは紙片を熱心に調べながら言った。「これは想像以上に深い闇だな。」そう言って頭を両手に埋めると、警部は有名なロンドンの専門家が自分の事件にのめりこんだ様子に満足げな微笑みを浮かべた。
「今の仮説だが」やがてホームズが口を開いた。「召使いと泥棒が通じ合っていた可能性、そしてこれはその約束メモだという推測は巧妙で、まったく否定できない。だが、この筆跡はさらに――」再び頭を抱え、しばし深い沈思に沈んだ。やがて顔を上げると、病後とは思えぬ紅潮と生き生きとした目が戻っていた。彼はかつての精力を取り戻し、跳ねるように立ち上がった。
「よし」と彼は言った。「この事件の詳細を静かに観察してみたい。実に心惹かれる点がいくつもある。もしよろしければ、大佐、ワトソンを残して私だけ警部とご一緒して、いくつかの仮説を検証してみたい。三十分ほどで戻る。」
一時間半ほど経って、警部だけが戻ってきた。
「ホームズさんは外の野原を歩き回っています。私たち四人で屋敷まで来てほしいそうです。」
「カニンガム家に?」
「はい。」
「何のためです?」
警部は肩をすくめた。「よく分かりません。正直なところ、まだ本調子ではないのかもしれません。実に奇妙な様子で、ひどく興奮しています。」
「ご心配なく」と私は言った。「たいていの場合、彼の奇行にはちゃんとした理由があります。」
「人によっては、彼の方法の中に狂気があると言うかもしれませんがね」と警部はつぶやいた。「とにかく、彼が急かしているので、よろしければすぐに出発しましょう。」
外に出ると、ホームズは野原を行ったり来たり歩き、顎を胸に埋め、両手をズボンのポケットに突っ込んでいた。
「ますます面白くなってきたぞ」ホームズは言った。「ワトソン、君の田舎旅行は大成功だ。今朝は実に愉快だった。」
「現場まで行かれたようですね」と大佐が言った。
「ああ。警部と私はちょっとした偵察をした。」
「収穫は?」
「非常に興味深いものがいくつかあった。これから歩きながら説明しよう。まず、被害者の遺体を見た。確かに報告通り、リボルバーによる死だった。」
「疑っていたのか?」
「すべてを確かめておくに越したことはない。次にカニンガム氏父子から、犯人が生垣を破って逃げた正確な場所を教えてもらった。これは非常に重要だ。」
「確かに。」
「それから被害者の母親にも会ったが、彼女は高齢で衰弱しており、情報は得られなかった。」
「で、調査の成果は?」
「この事件は極めて特異なものだという確信だ。これからの訪問で、少しは謎が晴れるかもしれない。警部も同意見だと思うが、被害者の手に握られていた紙片――しかも、死の時刻が記されている点――は極めて重要だ。」
「手がかりになりそうですね、ホームズさん。」
「いや、まさに重要な手がかりだ。あのメモを書いた者こそ、ウィリアム・カーワンをあの時刻に呼び出した犯人だ。だが、その残りの紙片はどこに?」
「地面を丁寧に探しましたが、見つかりませんでした」と警部。
「死体の手から無理やりもぎ取った。そこまでして奪いたかったのは、自分に不利な証拠だったからだ。では、その後どうしたか? おそらく急いでポケットに突っ込んだのだろう。紙片の角が死体の握りに残っていたとは気付かずにな。あの残りの紙さえ見つかれば、事件解決に大きく近づくはずだ。」
「だが、犯人を捕まえる前に、どうやってポケットの中身を手に入れるんだ?」
「ふむ、ふむ、考えてみる価値はあったな。それからもう一つ明らかな点がある。このメモはウィリアムに宛てられていた。書いた本人がそれを持っていったはずはない。そうでなければ、自分の言葉で直接伝えればよかったはずだ。では、誰がこのメモを届けたのだ? それとも郵便で届いたのか?」
「調査しました」と警部が言った。「ウィリアムは昨日の午後の郵便で手紙を受け取っています。封筒は彼自身が破棄しました。」
「素晴らしい!」とホームズは警部の背中を軽く叩きながら叫んだ。「配達員にも会ったのですね。あなたと仕事をするのは実に愉快です。さて、ここがロッジです。よろしければ、ロス大佐、ご案内しましょう、犯行現場をお見せします。」
私たちは被害者が住んでいた美しいコテージの前を通り過ぎ、オーク並木の小道を歩いて、マルプラケの年号が玄関の鴨居に刻まれている立派なクイーン・アン様式の古い家へと向かった。ホームズと警部が先導し、家の脇門まで案内された。そこは道路沿いの生垣から庭を隔てた場所にあった。警官が台所の扉のところに立っていた。
「ドアを開けてくれ、警官」とホームズが言った。「さて、あの階段で、若いカニンガム氏が立って、ちょうど今我々がいるあたりで二人の男が揉み合っているのを見たんだ。老カニンガム氏はあの窓――左から二番目――にいて、犯人があの茂みの左側に逃げるのを目撃した。それからアレック氏が飛び出してきて、傷ついた男のそばに膝をついた。地面はとても硬いので、痕跡となるものは何も残っていない。」そう語りながら、二人の男が家の角を回って庭の小道を降りてきた。一人は年配で、深い皺と重たいまぶたを持つ逞しい顔立ち、もう一人は鮮やかに着飾った若者で、その明るく微笑む表情と派手な服装は、ここに集まった理由と奇妙な対照をなしていた。
「まだ続けているのかい?」と彼はホームズに言った。「ロンドンの連中は絶対に見落としがないと思っていたけど、どうもそんなに手際が良いわけでもなさそうだな。」
「まあ、少し時間をいただければいいでしょう」とホームズは機嫌よく答えた。
「そりゃ必要だろうな」と若いアレック・カニンガムが言った。「手がかりなんてひとつもないじゃないか。」
「一つだけはある」と警部が答えた。「それさえ見つければ――おや、どうしたんです、ホームズさん!」
私の友人の顔が突然、恐ろしい表情に変わった。目は上を向き、顔の筋肉が苦悶に歪み、抑えたうめき声とともにうつ伏せに倒れてしまった。その突然さと激しさに私たちは肝を冷やし、彼を台所へ運び込んだ。ホームズは大きな椅子にもたれかかり、しばらく重い息をしていた。やがて恥じ入ったように弱さを詫びて、再び立ち上がった。
「ワトソンなら、重い病気からようやく回復したばかりだと説明するだろう」と彼は言った。「私はこうした突然の神経発作を起こしやすいんだ。」
「馬車でご自宅まで送ろうか?」と老カニンガム氏が尋ねた。
「いや、せっかく来たので、ひとつ確かめたいことがある。それは簡単に検証できるだろう。」
「それは?」
「どうも、この不運なウィリアムが到着したのは、泥棒が家に侵入した『前』ではなく、『後』だった可能性がある気がしてならない。皆さんは、ドアがこじ開けられていたにもかかわらず、泥棒は家には入っていないと当たり前のように思っているようだ。」
「それは明らかだと思うが」とカニンガム氏が重々しく答えた。「ほら、私の息子アレックはまだ寝ていなかったし、誰か動き回れば必ず気づいたはずだ。」
「どこに座っていたのですか?」
「私はドレッシングルームで煙草を吸っていた。」
「それはどの窓です?」
「父の隣、左端の窓です。」
「二つともランプは点いていましたね?」
「もちろんだ。」
「これはなかなか奇妙な点がいくつかありますね」とホームズが微笑んだ。「前科のある泥棒が、家族の二人がまだ起きていると明らかな明かりのついている時間を狙って、わざわざ押し入るとは、普通は考えにくい。」
「度胸のある奴だったんだろうな。」
「確かに、普通でない事件だからこそ、私たちが説明を求めているのです」と若いアレック氏が言った。「でも、あなたの言うように、ウィリアムが犯人に立ち向かった時点でもう家の中のものを盗んでいたというのは、馬鹿げた考えだよ。家の中が荒らされて、物がなくなっていたはずじゃないか。」
「それは盗んだ物による」とホームズが言った。「今回は、非常に変わった手口の泥棒で、自分のやり方で行動する奴だということを忘れてはいけない。たとえば、アクトン邸から盗まれたものを見ても――ええと、なんだったかな? 糸玉、ペーパーウェイト、あと細々とした物ばかりだった。」
「まあ、あなたと警部が提案することなら何でも従いますよ」と老カニンガム氏が言った。
「まず第一に」とホームズが言った。「あなたご自身の名義で懸賞金を出してほしい。役所経由だと金額の協議で時間がかかることもあり、こういうことは素早くやるに越したことはないので。書式はここにメモしてきたので、署名をいただけますか。私は五十ポンドで十分だと思いましたが。」
「五百ポンドでも喜んで出しましょう」と治安判事は言い、ホームズの差し出した紙片と鉛筆を受け取った。「しかし、これは少し違うな」と内容を見て付け加えた。
「急いで書いたものです。」
「ほら、あなたは『火曜の午前一時十五分ごろ、何者かが侵入を試み』と書いているが、実際には十二時十五分だったんですよ。」
私はその間違いに心を痛めた。ホームズは事実の正確さに人一倍こだわっており、最近の病気が彼を弱らせているのは明らかだった。この小さな出来事だけでも、まだ本調子ではないと私に知らしめるに十分だった。彼は一瞬バツが悪そうにし、警部は眉をひそめ、アレック・カニンガムは思わず声をあげて笑った。しかし老紳士は訂正した上で、紙をホームズに返した。
「なるべく早く印刷に出してください。あなたの考えは素晴らしいと思います。」
ホームズはその紙片を慎重に手帳にしまった。
「さて」と彼は言った。「今度はこの奇妙な泥棒が、何も持ち出していないか、みんなで家中を調べてみるのがよさそうだ。」
家に入る前、ホームズはこじ開けられたドアを調べた。明らかにノミか鋭いナイフのようなもので鍵が壊されていた。木部にはその跡が残っていた。
「鉄格子は使ってないのですか?」
「必要だと思ったことがありません。」
「犬は飼っていますか?」
「はい、でも家の反対側につないであります。」
「召使いたちは何時に寝ますか?」
「十時ごろです。」
「ウィリアムもふだんはその時間には寝ていたのですね?」
「ええ。」
「それなのに、この夜だけは起きていたとは不思議ですね。では、カニンガムさん、家の中を案内していただけますか。」
石畳の廊下があり、その途中から台所が枝分かれし、木の階段で直接家の二階へと上るようになっていた。階段を上がると、踊り場があり、そこから正面ホールから上る装飾的な階段がさらに続いていた。この踊り場から、居間やいくつかの寝室――カニンガム氏と息子の部屋も含め――へ出られる。ホームズはゆっくり歩きながら、家の造りを注意深く観察していた。彼の表情から、何か手がかりを見つけたのだと分かったが、私にはその推理の行き先がまったく見当もつかなかった。
「おいおい」とカニンガム氏は少し苛立った様子で言った。「こんなことは無意味だろう。あそこの階段の突き当たりが私の部屋で、その向こうが息子の部屋だ。こんなところまで泥棒が忍び込めたとは、とても思えんが、どうだね?」
「そろそろ別の手がかりを探さないといけないみたいですね」と息子はやや意地悪く微笑んだ。
「それでも、もう少し付き合っていただきたい。例えば、寝室の窓から表がどれくらい見渡せるか知りたいのです。こちらが息子さんの部屋ですね」――彼はドアを開けた――「そして、こちらが警報があったときに煙草を吸っていたドレッシングルームでしょう。あの窓からはどちらが見えますか?」ホームズは寝室を横切って隣の部屋のドアを開け、中を見回した。
「もう満足かね?」とカニンガム氏は刺々しく言った。
「はい、見たかったものはすべて見られました。」
「それでは、どうしても必要なら私の部屋にもどうぞ。」
「ご面倒でなければ。」
治安判事は肩をすくめて、自分の部屋へ案内した。部屋は質素で、取り立てて特徴のないものだった。私たちが窓の方へ歩くと、ホームズは私と連れ立つ最後尾に下がった。ベッドの脇にはオレンジの盛られた皿と水差しが置いてあった。通り過ぎるとき、ホームズは驚くべきことに私の目の前でそれをわざと倒してしまった。ガラスの水差しは粉々に割れ、果物は部屋中に転がった。
「やっちまったな、ワトソン」と彼は平然と言った。「カーペットが台無しだ。」
私は困惑しつつ果物を拾い始めた。どうやらホームズは私に失敗の責任をかぶせたいようだった。他の者たちも同じように後片付けを手伝い、テーブルも立て直した。
「おや!」と警部が叫んだ。「ホームズはどこだ?」
ホームズの姿がなかった。
「少し待っていてください」と若いアレック・カニンガムが言った。「あの人、どうかしてると思うよ。父さん、一緒にどこへ行ったか見てこよう!」
彼らは部屋を飛び出していき、私たち――警部、大佐、私――はただ茫然と顔を見合わせていた。
「いやはや、アレック坊やの意見に同意したくなるな」と警部は言った。「病気の影響かもしれんが、どうも――」
その言葉を遮るように、「助けて! 助けて! 殺される!」という叫び声が響いた。私はその声が友人のものだと気づき、激しく部屋を飛び出して踊り場へ駆け上がった。叫び声はしだいにかすれ、うめき声のようなものに変わり、最初に見学した部屋から聞こえていた。私は駆け込んで、さらにドレッシングルームへ突進した。そこでは、カニンガム親子が倒れたシャーロック・ホームズの上に覆いかぶさっており、若い方は両手で彼の喉を締め、年配の方は彼の手首をねじっている様子だった。私たち三人はすぐに二人を引き離し、ホームズは青ざめ、明らかに衰弱した様子で立ち上がった。
「この二人を逮捕してください、警部!」ホームズは息を切らしながら言った。
「容疑は?」
「御者ウィリアム・カーワン殺害の容疑だ!」
警部は呆然と周囲を見回した。「おいおい、ホームズさん、まさか本気で――」
「見ろ、彼らの顔を!」とホームズは鋭く言った。
これほど明白な罪の自白を人間の顔に見たことはない。年配の方は呆然とし、険しく沈んだ表情を浮かべていた。一方、息子はあの気取った快活な態度をすっかり失い、獰猛な野獣のような目つきで顔つきも激しく歪んでいた。警部は無言でドアに歩み寄り、笛を吹いた。呼びつけられた二人の巡査が現れた。
「やむをえません、カニンガムさん」と警部が言った。「これが誤解で済めばよいのですが、見てのとおりで――おっと、やる気か!」彼は素早く手を伸ばし、若い男が引き金を引こうとしていたリボルバーが床に転がった。
「それは押収してください」とホームズは静かに足で押さえた。「裁判で役立つでしょう。だが、私たちが本当に求めていたのはこれだ。」彼は小さくしわくちゃになった紙片を掲げた。
「残りの紙片だ!」と警部が叫んだ。
「その通り。」
「どこにあったんです?」
「ここしかないと確信していた場所さ。すぐに全容を説明しよう。ロス大佐、ワトソン、いったん戻っていてくれ。一時間以内にはまた合流する。警部と私は容疑者から事情を聴かねばならないが、昼食時には必ず戻る。」
ホームズは宣言どおり、約一時に私たちと大佐の喫煙室で再会した。彼には小柄な老人――最初の泥棒騒ぎの現場のアクトン氏――が同行していた。
「この小さな件を説明するにあたって、アクトン氏にも立ち会ってもらいたかったのです。細部に強い関心をお持ちでしょうから。大佐、こんな波乱を呼ぶ私を招いたことを後悔なさっているのでは。」
「とんでもない」と大佐は熱意を込めて答えた。「あなたの捜査手法を見学できたのはこの上ない光栄です。期待を完全に上回るもので、いまだに手がかりの欠片すら見えていません。」
「私の説明で幻滅されるかもしれませんが、私は常に自分の方法は友人ワトソンにも、知的関心をもつ誰に対しても隠さない主義です。まず、ドレッシングルームで受けた乱暴のせいで少し体がこたえているので、ブランデーを一口いただきましょう。ここのところ、体力が落ちていて。」
「もう、あの神経発作は起きていないといいのですが。」
シャーロック・ホームズは愉快そうに笑った。「その話は後ほどにしましょう。今から事件の経緯を順序立てて説明します。疑問があれば、どうぞ途中で止めてください。
「探偵術において最も大切なのは、多くの事実の中から、どれが偶然でどれが本質的なのかを見極めることだ。でないと、注意も労力も分散してしまう。この事件では、最初から私は、すべての鍵は被害者の手に握られていた紙片に違いないと確信していた。
「その前に注目していただきたいのは、もしアレック・カニンガムの証言通り、襲撃者がウィリアム・カーワンを撃って即座に逃げたのなら、当然その者が死体から紙片を奪う暇などなかったはずだ。そうでなければ、それを奪ったのはアレック・カニンガム自身だったに違いない。なぜなら、老紳士が階下に降りたときには召使いたちも現場に集まっていたからだ。この単純な事実を警部は見落としていた。なぜなら、地元の名士たちは事件と無関係だという先入観があったからだ。私は常に先入観を持たず、事実が導くままに従うことにしている。だから調査の初期段階で、私はアレック・カニンガムの関与を疑い始めたのだ。
「さて次に、警部が見せてくれた紙片をじっくり調べた。すぐに、これは非常に特異な書類の一部だとはっきり分かった。これがその現物だ。何かひどく示唆的な点にお気づきだろうか?」
「ずいぶん不規則な字だな」と大佐が言った。
「そのとおりです」とホームズは言った。「これは間違いなく、二人の人物が交互に単語を書いたものに違いありません。例えば『at』や『to』の強いtの字と、『quarter』や『twelve』の弱いtを比べてみてください。すぐにわかります。ほんの少し観察すれば、『learn』や『maybe』が強い字で書かれており、『what』は弱い字で書かれているとはっきり断言できます。」
「なるほど、はっきりしてる!」と大佐は叫んだ。「どうして二人でこんなふうに書いたんだろう?」
「それは、この仕事がいかに危険なもので、二人のうち一人がもう一人を信用していなかったからに他ならない。なにをするにも互角に関わっている証拠を残そうとしたのだ。そして二人のうち、強い筆跡で『at』や『to』を書いた方が主導者だったのは明らかだ。」
「どうしてそれがわかるんです?」
「筆跡の特徴だけでも推測できるが、もっと確かな理由がある。この紙片をよく調べれば、強い字で書いた男がまず自分の単語だけを書き、空白を残してもう一人に埋めさせたことに気づくはずだ。その空白は十分でないこともあり、『quarter』は『at』と『to』の間に無理やり詰め込まれている。つまり、先に『at』と『to』が書かれていたという証拠だ。最初に自分の単語を全部書いた者が、この事件の首謀者だったことは動かない。」
「素晴らしい!」とアクトン氏が叫んだ。
「だが、非常に表面的なものだ」とホームズが言った。「しかし、ここからが重要な点だ。君はご存じないかもしれないが、筆跡から年齢を推定する技術は、専門家の手によってかなりの精度まで高められている。通常であれば、その人物が実際に属する年代を、まずまずの自信をもって特定することができる。もっとも、私は『通常』の場合と言っている。なぜなら、健康を害していたり体力が衰えている場合、たとえ若者であっても老人特有の筆跡が現れるからだ。この場合、一方は力強くしっかりとした筆運びであり、もう一方は少し弱々しい字で、tの横線が消えかけているものの、まだ判読可能であることから、一方は若い男性、もう一方は年老いてはいるが決して衰弱しきってはいない人物だと判断できる。」
「見事だ!」とアクトン氏がまた叫んだ。
「しかし、もうひとつ、より微妙で興味深い点がある。これら二つの筆跡には共通点がある。つまり、両者は血縁関係にある男性のものだ。君にはギリシャ文字のeの形で最も分かりやすいかもしれないが、私にはそれ以外にも多数の細かな特徴が見て取れる。家系特有の筆癖が、これら二つの筆跡から確実に読み取れると私は確信している。もちろん、今は私の調査の主要な結果のみを述べているが、他にも二十三の推論があった。それらは専門家にはより関心を引く内容だろうが、君にはそこまで必要ない。いずれも、カニンガム親子がこの手紙を書いたという私の印象をより強く裏付けるものだ。
「ここまで分かった以上、次に私が取るべき手順は当然、事件の詳細を調べ、それがどれほど手がかりになるかを検討することだった。私は警部とともに屋敷へ行き、見られるものはすべて見てきた。死体の傷は、私の見立てでは、リボルバーで4ヤード以上離れた距離から撃たれたものと断定できた。衣服に火薬の焦げ跡がなかったためだ。従って、アレック・カニンガムが『二人が格闘していた時に発砲された』と証言したのは明らかな嘘だと分かった。さらに、親子二人とも、男が道路に逃げた場所について一致した証言をしている。しかし、その地点には幅の広い溝があり、底は湿っていたのだが、そこには靴跡がまったくなかった。私は、このことからカニンガム親子が再び嘘をついているだけでなく、そもそも現場に見知らぬ男など存在していなかったことにも完全な確信を持った。
「そして今、この奇妙な犯罪の動機を考えなければならない。これを解明するため、まずアクトン氏宅での最初の窃盗の理由を探ろうとした。大佐の話から、アクトン氏とカニンガム家の間で訴訟が続いていることが分かった。もちろん、彼らが何らかの重要書類を手に入れる目的で書庫に侵入したのだと、すぐに思い至った。」
「まさにその通りだ」とアクトン氏が言った。「彼らの意図に疑う余地はない。私は現在の彼らの財産の半分に対して明快な権利を持っている。そして、もし一通の書類でも彼らが見つけていれば――幸いその書類は私の弁護士の金庫に保管されていたが――我々の訴訟は間違いなく不利になっていただろう。」
「ご明察だ」とホームズが微笑みながら言った。「これは危険で無謀な試みであり、その背後には若いアレックの影響があったと私は見ている。何も得るものがなかった彼らは、普通の盗難事件に見せかけて疑いを逸らそうとし、手当たり次第に持ち出せる物を持ち去った。ここまでは明白だが、まだ多くの謎が残っていた。私が何より欲しかったのは、あの手紙の失われた部分だ。アレックがそれを死者の手から引き剥がし、ほぼ間違いなく自分のバスローブのポケットに突っ込んだはずだと確信していた。他に隠せる場所があるだろうか? 問題はまだそこに残っているかどうかだけだった。調べる価値は十分にあったし、そのために私たちは皆で屋敷へ向かった。
「カニンガム親子は、君も覚えているだろうが、キッチンの裏口で我々と合流した。当然ながら、彼らにこの手紙の存在を思い出させてはならなかった。そうでなければ、即座に証拠を処分してしまっただろう。警部がその重要性を話し始めようとしたとき、私はまさに幸運に恵まれた――突然倒れて発作を起こしたふりをして話題をそらしたんだ。
「なんてことだ!」と大佐が笑いながら叫んだ。「じゃあ私たちが同情したのは全部無駄で、あんたの発作は芝居だったのか?」
「職業柄、見事な演技だった」と私は驚きつつ、この男が次から次へと繰り出す新たな才知に心底感服した。
「しばしば役立つ技術だよ」と彼は言った。「気を取り直すと、私はちょっとした工夫でカニンガム氏に『twelve(十二)』という語を書かせ、その筆跡を紙に書かれた『twelve』と見比べたのだ。」
「私はなんて馬鹿だったんだ!」と私は叫んだ。
「君が私の体調不良を気遣ってくれているのが分かったよ」とホームズが笑いながら言った。「君が感じた同情の痛みには申し訳なかった。さて、その後私たちは一緒に二階へ上がり、バスローブがドアの後ろに掛かっているのを見た。私は机をひっくり返して二人の注意を引き、その隙にポケットを調べた。予想通り、紙片はその一つに入っていたが、手にした瞬間、カニンガム親子が私に襲いかかり、そのままでは私は殺されていたかもしれない――君の迅速で親切な助けがなければね。今でもあの若者の喉への締めつけが残っているし、父親は紙を奪おうとして私の手首をひねり上げた。彼らは私がすべて知っていると悟ったのさ。絶対的な安全から一転して完全な絶望に陥ったことで、二人はまさに狂気に陥った。
「事件の動機について、その後カニンガム氏と少し話をした。彼は素直に白状したが、息子はまるで悪魔のようで、もしリボルバーに手が届いていたら、己でも他人でも撃ち殺していたに違いない。カニンガム氏は自分に不利な証拠が揃っていると知ると一気に意気消沈し、すべてを洗いざらい話した。どうやらウィリアムは、アクトン氏邸に押し入った夜、こっそり二人の主人を尾行し、その弱みを握ったうえで、暴露をちらつかせて脅迫しはじめたらしい。しかし、アレック氏はそうした駆け引きをするには危険すぎる男だった。彼にとってはちょうど、世間を騒がせていた泥棒騒ぎに乗じて、恐れる男をもっともらしく始末する絶好の機会だったのだ。ウィリアムはおびき出されて撃たれた。もし彼らが手紙の全文を手にし、細部まで注意を払っていたら、疑いの目が向けられることはなかったかもしれない。」
「その手紙は?」と私は尋ねた。
シャーロック・ホームズは次の紙片を私たちの前に差し出した。
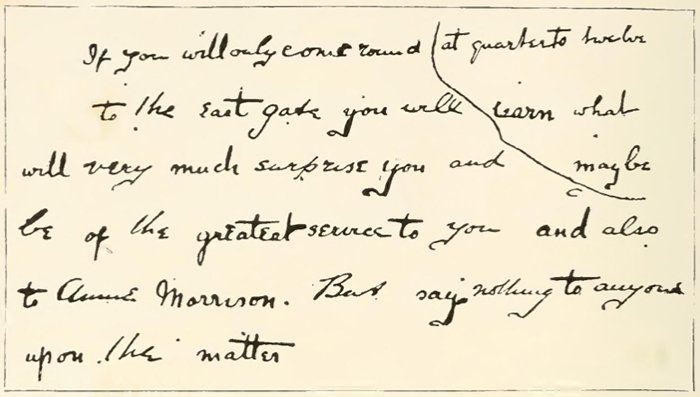
もし十二時十五分前に東門へ来てくれさえすれば
あなたを非常に驚かせること、あるいは
あなたにも、アニー・モリソンにも
大いに役立つことを知ることができます。
ただし誰にもこの件について話さないように
「まさに私が予想していた通りの文面だ」と彼は言った。「もちろん、アレック・カニンガム、ウィリアム・カーワン、アニー・モリソンの間にどういう関係があったかまでは分からない。しかし、罠が巧妙に仕掛けられていたことは間違いない。君も、このpの形やgの下の線に見られる遺伝の痕跡にはきっと感心しただろう。老人の筆跡ではiの点がないのも非常に特徴的だ。ワトソン、田舎での静かな休暇は大いに実りあるものだったようだ。明日には元気を取り戻してベーカー街に戻れるだろう。」
VIII. 曲がった男
私が結婚してから数か月後のある夏の夜のこと、私は自宅の暖炉の前で、最後の一服をくゆらせながら小説を読みつつ、うとうととしていた。その日は仕事が忙しく、心身ともに疲れ切っていたのだ。妻はすでに二階へ上がっており、しばらく前に玄関の鍵を閉める音がしたので、使用人たちも寝静まったと分かった。私は椅子から立ち上がり、パイプの灰を落とそうとしていた時、突然ベルのけたたましい音が鳴り響いた。
時計を見ると、十二時十五分前だった。こんな遅い時間に訪問者とは思えない。きっと患者で、もしかしたら夜通しの診察になるかもしれない。渋々ながらも私は廊下に出てドアを開けた。驚いたことに、そこに立っていたのはシャーロック・ホームズだった。
「やあ、ワトソン」と彼は言った。「まだ間に合うかと思って来たんだ。」
「おや、どうぞお入りください。」
「驚いた顔をしているな。無理もない! ほっとしているようにも見える。ふむ! 独身時代の『アルカディア・ミクスチャー』を今も吸っているんだな。その灰がコートについているからすぐ分かるよ。君が軍服を着ていた習慣は見てわかる。ハンカチを袖に入れている限り、純粋な市民としては通用しないぞ。今夜、泊めてもらえるだろうか?」
「もちろんだ。」
「君は独身時代用の部屋が一つあると言っていたし、今は客はいないな。帽子掛けがそれを物語っている。」
「ぜひ泊まってくれたまえ。」
「ありがとう。じゃあ空いているフックを使わせてもらうよ。イギリス人の職人が入った形跡があって残念だ。配管の修理じゃあるまいな?」
「いや、ガスだ。」
「なるほど。彼の靴でリノリウムに二つ痕が残っている。ちょうど光の当たる場所だ。いや、食事はいらないよ。ウォータールー駅で済ませてきたが、君と一服やろう。」
私はパイプタバコを差し出し、彼は向かいに座ってしばらく黙って煙をくゆらせていた。こんな時間に彼が訪ねてくるのは、よほど重要な用件に違いないと分かっていたので、私は彼が話し出すまで辛抱強く待った。
「君も最近はかなり忙しいようだね」と彼は鋭い眼差しを私に向けて言った。
「そう、今日は忙しかったよ」と私は答えた。「君にとっては馬鹿げて聞こえるかもしれないが、どうしてそれが分かったのか本当に不思議だ。」
ホームズは愉快そうにくすくす笑った。
「私は君の生活習慣を知っているからね、ワトソン。回診が短い日は歩き、長い日はハンサム(馬車)を使う。君の靴は使い込まれてはいるが、まったく汚れていない。つまり今、君はハンサムを使うほど忙しいということだ。」
「見事だ!」と私は叫んだ。
「初歩的なことさ」と彼は言った。「推理する者は、相手が見落としている一点だけを利用して、驚くべき効果を生み出せる。君の書く小話も同じで、問題のいくつかの要素を自分だけが握っていて読者に明かさない、という点で全く同じ効果を生んでいる。今の私は、まさにその読者と同じ立場だ。この手の中に、かつて誰の頭脳も悩ませたことのない奇妙な事件のいくつかの糸口を握ってはいながら、理論を完成させるのに必要なあと一つか二つが欠けている。でも必ず見つけ出してみせるよ、ワトソン、必ずな!」彼の目が輝き、やせた頬にうっすら朱が差したのはほんの一瞬で、次に見た時には、彼の顔はまたいつものインディアンのような無表情に戻っていた。そうした冷静さゆえに、多くの人々が彼を人間ではなく機械のようだと評したのだった。
「この事件は実に興味深い特徴を持っている」と彼は言った。「いや、極めて例外的な興味をかき立てられる特徴といってもよい。私はすでに調査を進めており、どうやら解決が見えてきた。もし君が最後の一歩を共に踏み出してくれるなら、非常に心強い助けになるだろう。」
「喜んで協力しよう。」
「明日、オールダショットまで行けるか?」
「ジャクソンが診療を代わってくれるだろう。」
「それはありがたい。ウォータールー駅11時10分発に乗りたい。」
「それなら間に合う。」
「では、もし君にまだ眠気がなければ、事件の概要と今後の課題を手短に話そう。」
「君が来るまでは眠かったが、今はすっかり目が覚めたよ。」
「事件にとって不可欠なことは省かず、できるだけ簡潔に話そう。もしかしたら君もすでに新聞記事を見たかもしれない。私が調べているのは、オールダショットのロイヤル・マローズ連隊、バークレー大佐の殺人事件とされているものだ。」
「まったく何も聞いていない。」
「今のところ世間ではほとんど注目されていない。事実が判明したのは、まだ二日前のことだ。要約するとこうなる。
「ロイヤル・マローズは、君も知っている通り、英国陸軍でも有数の名門アイルランド連隊だ。クリミア戦争でも大活躍し、インドの反乱時にも武勇を示し、それ以来あらゆる機会でその名を高めてきた。月曜の夜まで、この連隊を率いていたのはジェームズ・バークレー大佐で、かつては一兵卒だったが、反乱時の勇気で士官に昇進し、ついにはかつて自分が銃を担いだ連隊の指揮官にまでなった男だ。
「バークレー大佐は、軍曹時代に結婚しており、妻の旧姓はナンシー・デヴォイ。彼女の父親もその連隊の元カラ――サージェントだった。だから、二人が若くして新しい地位についたとき、当然ながら多少の社交上の摩擦はあった。しかし、順応も早かったようで、バークレー夫人も夫と同じく連隊の人々から人気があったという。加えて、彼女は非常に美しく、結婚して三十年以上経つ今なお、ひときわ際立った気品と美貌を保っている。
「バークレー大佐の家庭生活は、常に円満だったようだ。私が多くの事実を聞き出したマーフィー少佐によれば、二人の間に誤解があったという話は一度も聞いたことがないという。しかも、むしろバークレー大佐の妻への献身は、夫人の夫へのものより深かった。彼は一日でも妻と離れていると落ち着かないほどだった。一方、夫人は献身的で忠実ではあったが、そこまで露骨には愛情を示さなかった。ともあれ、連隊の中では模範的な中年夫婦と見なされていた。二人の関係に、これから起こる悲劇を予感させるものはまったくなかった。
「ただし、大佐自身にはいくつか奇妙な性格があった。普段は陽気で豪快な軍人だったが、時には激しい怒りや復讐心も見せたという。ただし、その矛先が妻に向いたことはない。また、マーフィー少佐や他の士官ら三人が共通して語ったのは、時折、説明のつかぬ沈鬱さが彼を襲うということだった。食堂での騒ぎや冗談の最中に、まるで見えない手で笑いを奪われたかのように、突然黙り込んでしまう。そうした気分になると、数日間も深い憂鬱に沈み込んでいた。また、少々迷信深いところ、特に夜一人きりになるのを極端に嫌うという、男らしい性格には不釣り合いな子供じみた一面もあったようだ。
「ロイヤル・マローズ第一大隊(旧第117連隊)は、数年前からオールダショットに駐屯している。既婚の士官たちは外の家で暮らしており、大佐もずっとラシーヌというヴィラを借りている。ラシーヌは敷地内に立ち、西側は幹線道路までわずか三十ヤードしかない。御者と女中二人が使用人で、子供も同居者もいなかった。
「では、月曜日の夜、九時から十時の間にラシーヌで起きた出来事を――
「バークレー夫人はカトリック教会の信徒で、ワット街の礼拝堂を拠点とするセント・ジョージ慈善ギルドの活動にも熱心だった。このギルドは貧しい人々に古着を提供する目的で設立されていた。その晩、八時から会合があり、夫人はそのために夕食を急いで済ませて出かけた。出がけには、ごくありふれた言葉で夫に『すぐ戻る』と言い残している。夫人は隣家のミス・モリソンを誘い、二人で出かけた。会合は四十分で終わり、九時十五分にはミス・モリソンを送り届けて帰宅した。
「ラシーヌには『朝の間』として使われている部屋があり、道路に面していて大きなガラスの引き戸で芝生に出られる。芝生は三十ヤードあり、低い塀と鉄柵一つで公道から隔てられている。夫人は帰宅後、この部屋に入り、自分でランプを灯し、ジャネット・スチュワートという女中にお茶を運ばせたが、これは普段の習慣とは違っていた。大佐はその時、食堂にいたが、妻が帰ったと聞くと朝の間へ入っていった。御者は彼が廊下を横切ってその部屋に入るのを見ている――大佐が生きている姿を見たのは、それが最後だった。
注文していた紅茶が運ばれてきたのは、それから十分ほど経った頃だった。しかし、メイドがドアに近づくと、主人と奥様が激しく口論している声が聞こえてきて驚いた。ノックしても返事はなく、ドアノブを回してみても中から鍵がかかっていて開かない。当然のことながら、彼女は急いで料理人のもとへ駆け下り、料理人と御者の三人で玄関ホールへ上がり、なおも続いている激しい口論に耳を澄ました。三人とも、聞こえる声はバークレー夫妻だけだと一致して証言している。バークレーの声は抑えられ、ぶっきらぼうで、三人には何を言っているのか聞き取れなかった。一方、奥様の声は非常に激しく、声を上げるとその言葉がはっきりと聞こえた。
「臆病者!」と彼女は何度も繰り返した。「今さらどうすればいいの? どうすればいいの? 私の人生を返して! 二度とあなたと同じ空気さえ吸いたくない! 臆病者! 臆病者!」
これが断片的に聞き取れた会話だったが、それが突然、男の恐ろしい叫び声と共に、何かが激しく壊れる音、そして女の鋭い悲鳴で終わった。何か重大な事件が起きたと確信した御者はドアに駆け寄って、力ずくでこじ開けようとしたが、中からは悲鳴が続けて聞こえてくるものの、どうしても入れなかった。しかも、メイドたちは恐怖で呆然として手助けもできなかった。
だが、ふとひらめいた御者は、玄関から外に出て、フランス窓が開いている芝生側へ回り込んだ。夏場はその窓が開いているのが普通だったようで、彼は難なく部屋に入ることができた。奥様はもはや叫ぶのをやめ、ソファで気を失って横たわっていた。椅子の側に足を投げ出し、暖炉の隅に頭をつけて倒れていたのは、哀れな軍人、血だまりの中で既に絶命していた。
当然、御者がまず考えたのは主人を助けることだったが、すぐに部屋のドアを開けなければと思い直した。しかし、ここで予想外の奇妙な難題にぶつかった。鍵がドアの内側にはなく、部屋のどこを探しても見つからないのだ。やむなく彼は再び窓から出て、警官と医者の助けを得て戻ってきた。強い疑いがかかっていた奥様は、依然として意識不明のまま自室に運ばれた。大佐の遺体はソファへ移され、現場の綿密な調査が始まった。
不運な退役軍人の負った傷は、後頭部に約二インチほどのギザギザの切り傷で、明らかに鈍器で激しく殴られたものだった。その凶器が何かを推測するのは難しくなかった。遺体のそばの床には、骨の柄がついた堅い彫刻木の珍妙な棍棒が落ちていた。大佐は戦地で集めた様々な武器のコレクションを持っており、この棍棒も警察の見立てではそのひとつらしい。使用人たちは見たことがないと言っているが、家には数多くの珍品があったため、見落とされていた可能性もある。警察が部屋でほかに重要な物を発見したわけではないが、ただひとつ不可解なのは、バークレー夫人にも被害者にも、そして部屋中どこを探しても、紛失した鍵が見つからなかったことだ。結局、オールダーショットから鍵屋を呼んでドアを開けるしかなかった。
「以上がそのときの状況だ、ワトソン。火曜日の朝、マーフィー少佐の依頼で私がオールダーショットに赴き、警察の捜査に加わった時点でこうだった。すでに興味深い難事件だったことは認めてくれるだろうが、私の観察によって、事態は一見した以上に遥かに奇妙なものであるとすぐに分かった。
「部屋の調査に先立って私は使用人たちを詳しく尋問したが、結果として得られたのは既に述べた事実ばかりだった。もうひとつ興味深い細部を、ハウスメイドのジェーン・スチュワートが思い出した。君も覚えているだろうが、彼女は口論の音を聞いて一度降り、他の使用人を連れて戻った。最初に一人でドアの前にいたとき、主人と奥様の声は非常に低く、ほとんど何も聞き取れなかったが、口調から喧嘩していると察したという。私が強く追及したところ、彼女は夫人が『デイヴィッド』という名を二度口にするのを聞いたことを思い出した。この点が、突然の口論の原因を探る上で極めて重要だ。君も覚えている通り、大佐の名はジェームズだ。
「この事件で、使用人も警察も最も強く印象に残ったのは、大佐の顔の歪みだった。それは、人間の顔が示しうる最も恐ろしい恐怖と戦慄の表情に凝り固まっていたという。あまりの凄まじさに、見るだけで気絶した者も複数いたほどだ。彼が自分の運命を予見し、それが極限の恐怖をもたらしたことは間違いない。もちろん、もし大佐が夫人による殺意の攻撃を目撃したとすれば、警察の見立てと辻褄が合う。傷が後頭部にあったことも、彼がとっさに振り向いた結果であれば、致命的な反証にはならない。夫人本人は、急性脳炎による一時的な精神錯乱で何も話せなかった。
「警察からは、君も覚えているミス・モリソン――その晩バークレー夫人と外出していた女性だが、彼女は帰宅時に夫人が不機嫌だった理由については何も知らないと否定していると聞いた。
「こうした事実を集めた上で、ワトソン、私はいくつものパイプをくゆらせ、決定的な要素と単なる偶然を切り分けようと努めた。明らかに、この事件で最も特徴的かつ示唆的だったのは、ドアの鍵の不可解な消失だった。どんなに細かく探しても部屋にはなかった。ということは、誰かが持ち去ったのだ。しかし、大佐にも夫人にもそれは不可能だ。ゆえに、第三者が部屋に入ったに違いない。そしてその第三者が入れたのは窓からだけだ。部屋と芝生を入念に調べれば、この謎の人物の痕跡が見つかるかもしれない。君も知っての通り、私はあらゆる手法を駆使したが、最終的に発見したのは、予想とまったく異なる痕跡だった。部屋には男が入り込んでおり、彼は道路から芝生を横切ってきていた。私は彼の足跡を五つ、はっきり確認した――ひとつは低い壁を乗り越えた道路上、ふたつは芝生、さらに二つのかすかな足跡が窓のそばの汚れた床板に残っていた。彼は芝生を駆け抜けてきたようで、つま先の跡がかかとより深く残っていた。しかし、私を驚かせたのはこの男ではなく、その連れだった。」
「連れだって?」
ホームズはポケットから大きな薄紙を取り出し、慎重に膝の上に広げた。
「これをどう思う?」と彼は尋ねた。
その紙には、小動物の足跡が写し取られていた。足のパッドが五つはっきり見え、爪も長め、全体の大きさはデザートスプーンほどもあった。
「犬だろう」と私は言った。
「カーテンを駆け上がる犬を聞いたことがあるか? この生き物がそれをやった明瞭な痕跡を見つけたんだ」
「じゃあ猿か?」
「だが猿の足跡ではない」
「では何だ?」
「犬でも猫でも猿でもない、我々が知るどんな動物でもない。私は寸法から復元を試みた。ここに、四つの足跡がじっと動かずに立っていた場所がある。前足から後足まで十五インチもある。首と頭の長さを加えれば、全長二フィート弱――尻尾があればもっと長いはずだ。だが、もうひとつ注目すべき寸法がある。動いているときの歩幅だが、どの場合も三インチほどしかない。つまり、胴体が長く脚が極端に短い動物だということだ。毛は残さなかったが、私が示したような形状で、カーテンを登れ、肉食性であることが分かる」
「どうして肉食性と分かる?」
「カーテンを登ったからだ。窓にはカナリアの鳥かごが吊るしてあり、この生き物は明らかにその鳥を狙っていた」
「すると、一体その動物は?」
「ああ、名が分かれば事件解決にも近付くだろう。おそらくイタチやオコジョの類いだろうが、私が見た中では最大級だ」
「それが事件と何の関係があるんだ?」
「そこもまだ不明だ。しかし多くを学んだろう。男は道路からバークレー夫妻の口論を眺めていた――ブラインドが上がり部屋は明るかった。彼は芝生を横切って部屋に入り、奇妙な動物を連れて、大佐を殴ったか、もしくは大佐がその姿に驚愕して転倒し、暖炉の隅で頭を打ったか、いずれかだ。最後に、侵入者が鍵を持ち去ったという奇妙な事実が残る」
「君の発見は、むしろ事態をますます混迷させていないか」と私は言った。
「その通りだ。しかし、少なくとも最初の推測よりずっと複雑な事件であることは明らかになった。私は考え直し、別の観点から事件に取り組むべきだと結論した。だが、ワトソン、本当にもう君を引っ張り回しすぎた。これ以上は明日のオールダーショット行きの途中で話してもいいだろう」
「いや、ここまで聞いた以上、やめられないよ」
「確実なのは、バークレー夫人が七時半に家を出たとき、夫とは良好な関係だったことだ。特別に愛情深いというほどではないが、御者が夫と楽しげに話すのを聞いていた。ところが帰宅直後には、夫の顔を見ないように最も離れた部屋に入り、動揺した様子でお茶を求め、夫が入ってくると激しく非難し始めた。つまり、七時半から九時の間に、夫への感情を一変させる何かが起きたのだ。だが、その間ずっとミス・モリソンが一緒にいた。彼女が否定しようと、何かを知っているのは確実だ。
「最初に思いついたのは、若い女性と年配の軍人の間に何かあって、それを夫人に打ち明けたのかもしれない、という推測だ。怒りながら戻った理由にもなるし、彼女が何もなかったと否定することとも矛盾しない。ただし、『デイヴィッド』への言及や、大佐の夫人への愛情、さらにはあの男の乱入――それらは従来の推測から外れる要素だ。要するに、私は大佐とミス・モリソンの間には何もなかったと判断し、むしろこの若い女性こそが、夫人の態度を一変させた原因の手掛かりを握っていると確信した。そこで当然ながら、ミス・モリソンのもとを訪ね、彼女が事実を知っていると告げ、夫人がこのままでは重大な罪で法廷に立つ危険があると説明した。
「ミス・モリソンは華奢で透き通るような小柄な女性、臆病な瞳に金髪だが、決して愚鈍でも感情的にもならず、理知的で分別があった。私が話した後、しばらく考えてから、決意を込めて素晴らしい証言をしてくれた。要点をまとめて伝えよう。
『私は友人に、何も話さないと約束しました。約束は大切です。でも、これほど重大な嫌疑がかかり、しかも彼女自身が病気で口を閉ざしているのなら、もう約束に縛られなくてもいいと思います。月曜の晩に何があったか、正直にすべてお話しします。
『私たちは九時少し前にワット街ミッションから戻ってくるところでした。途中、ハドソン通りという静かな通りを通らなければなりません。左側に一本だけ街灯があり、私たちがその灯りに近づいたとき、背中を丸め、肩に箱のようなものをぶら下げた男がこちらに歩いてきました。彼は背が曲がっていて、頭を低くし、膝を曲げて歩いていました。私たちの前を通り過ぎるとき、彼は頭を上げて灯りの下で私たちを見上げ、それと同時に恐ろしい声で叫びました。“神よ、ナンシーじゃないか! ” バークレー夫人は死人のように真っ青になり、彼が腕をつかまなかったら倒れていたでしょう。私は警察を呼ぼうとしましたが、夫人は意外にもその男に丁寧に話しかけました。
『“三十年前に死んだはずだと思っていたわ、ヘンリー”と、震える声で言いました。
『“そうだとも”と彼は言い、その声は耳を覆いたくなるほどでした。顔は黒ずみ、おぞましく、目がぎらぎらと光っていて、それが今も夢に出てきます。髪も頬ひげも白髪交じりで、顔はしわだらけ、干からびたリンゴのようでした。
『“少し先に行っててちょうだい”と夫人は私に言いました。“ちょっとだけこの人と話したいの。大丈夫、怖がることなんてないわ” 無理に強がるものの、真っ青なままで、唇の震えで言葉もなかなか出ませんでした。
『私は言われた通り少し先に進み、ふたりは数分間話していました。その後、夫人は目を怒らせてこちらに戻り、あの不具の男は街灯の下で両こぶしを振り上げ、まるで狂気のように怒り狂っていました。家の玄関まで、夫人は何も語らず、私の手を取ると、誰にも話さないでほしいと懇願しました。
『“昔の知り合いなの。今は落ちぶれてしまって……” 約束すると夫人は私にキスをして、それきり今日まで会っていません。これがすべての真実です。警察には隠していましたが、まさかこんな危険な状況になるとは思わなかったのです。すべて明らかになれば、夫人のためになるはずだと信じています』
「以上が彼女の証言で、ワトソン、私にとってはまさに闇夜の灯火だった。それまで断片的だったものが一挙に繋がり、私は事件の全貌をぼんやりと予感した。次にやるべきは、バークレー夫人に強烈な衝撃を与えたその男を探すことだ。まだオールダーショットにいればそう難しいことではない。不具の男なら必ず目立つ。私は一日中探し回り、今晩――まさに今晩、ワトソン――ついに彼を見つけた。男の名はヘンリー・ウッド。あの女性たちが出会った通り沿いの下宿に住んでいる。来てまだ五日ほどだ。私は選挙登録員を装い、大家と面白い雑談をした。男は奇術師で余興回りの芸人らしく、夜になると食堂を回って芸を披露している。あの箱には動物を入れており、大家はそれが何なのかおびえていた。芸で使うらしい。彼女が話せたのはそれくらいで、よくあんなに体が曲がっていて生きていられるものだとも言っていた。時々妙な言葉をしゃべり、この二晩は寝室でうめき泣いていたそうだ。金銭的には問題なかったが、預かり金に偽造コインのようなものを渡してきた。彼女が見せてくれたが、それはインドのルピーだった。
「これで、ワトソン、今我々がどんな立場にあるか、なぜ君に同行してほしいのかが分かるだろう。女性たちと別れた後、男は距離を保って後をつけ、夫婦の口論を窓越しに目撃し、部屋に駆け込み、連れていた動物が逃げ出した――そこまでは確かだ。だが、部屋で実際に何があったのかは、世界で唯一人、この男だけが知っている」
「そして、君は彼に尋ねるつもりなんだな?」
「もちろんだ――立会人の前で」
「その立会人が私か?」
「ぜひ頼む。彼が真相を話せばよし、拒否すれば逮捕状を申請するしかない」
「だが、戻ったときにまだ彼がいるとどうして分かる?」
「しっかり手を打ってある。ベーカー街の少年の一人を見張りにつけてあり、どこへ行こうと食らいついて離れない。明日、ワトソン、ハドソン通りで必ず彼を見つけられる。そして今夜、これ以上君を起こしていたら、私自身が犯罪者というものだ」
私たちが悲劇の現場に到着したのは正午頃だった。ホームズの案内で、私たちはすぐにハドソン通りへ向かった。彼は感情を押し隠す能力を持っていたが、それでも私はホームズが抑えきれない興奮状態にあることを容易に見て取ることができたし、私自身もまた、彼の調査に同行するたびに味わう、半分はスポーツ的、半分は知的な喜びに身震いしていた。
「ここがその通りだ」とホームズは言い、私たちは質素な二階建てのレンガ造りの家々が並ぶ短い通りに入った。「ああ、シンプソンが報告に来ているな。」
「ちゃんと中にいますよ、ホームズさん!」と、小さな浮浪児が駆け寄ってきて叫んだ。
「よくやった、シンプソン!」とホームズはその頭を撫でた。「行こう、ワトソン。これがその家だ。」
彼は重要な用件で来た旨を伝える名刺を中に送り、しばらくして私たちは会うべき男と対面した。暑い天気にもかかわらず、彼は暖炉の前にしゃがみ込んでおり、小さな部屋はまるでオーブンのようだった。男は椅子に体を歪めて縮こまって座っており、形容しがたいほどの不具を思わせたが、こちらに向けた顔は色黒でやつれてはいるものの、かつては相当な美男子だったに違いない。その男は黄ばんだ目で疑い深そうに私たちを見つめ、無言のまま椅子を二つ手で示した。
「インド帰りのヘンリー・ウッドさんですね」とホームズは親しげに言った。「バークレー大佐の死の件でまいりました。」
「そんなこと、俺が知るわけがないだろう。」
「それを確かめに来たのです。ご存知かもしれませんが、この件が解決しなければ、かつてのご友人であるバークレー夫人が殺人容疑で裁かれる可能性が高いのです。」
男は激しく身を震わせた。
「あなたが何者かも、なぜそんなことを知っているのかも知らないが、それが本当だと誓えるのか?」
「ええ、彼女が正気を取り戻し次第、逮捕するつもりで待っているだけです。」
「なんてことだ! あんたは警察の人間か?」
「いや、違います。」
「じゃあ、何の用なんだ?」
「正義が果たされるのは万人の務めだからだ。」
「彼女が無実だということは信じてくれていい。」
「ではあなたが犯人だ。」
「違う、俺じゃない。」
「それなら誰がジェームズ・バークレー大佐を殺したのだ?」
「それは神の正義が下ったのさ。でも覚えておいてほしい。もし俺が心の底で思った通り、奴の頭を叩き割っていたとしても、奴は俺の手によって当然の報いを受けていただけだろう。奴自身の良心の呵責で倒れなかったなら、俺がその血を背負っていたかもしれない。話を聞きたいんだろう? まあ、話しても恥じることはないから話そう。
こういうことだ。見ての通り、今では背中はラクダのように曲がり、肋骨も歪んでいるが、かつては陸軍第117歩兵連隊の伍長ヘンリー・ウッドといえば一番の伊達男だった。あの頃はインドの駐屯地、場所はバーティとでも呼ぼうか。先日死んだバークレーは同じ中隊の軍曹で、連隊一の美女、いや、おそらく息をして生まれた娘の中で一番の美人がナンシー・デヴォイ、軍旗軍曹の娘だった。彼女を愛した男は二人、そして彼女が愛したのは一人。今、暖炉の前で縮こまっている惨めな俺がそんなことを言っても笑うかもしれないが、俺の容姿を愛してくれていたのさ。
だが、俺の心を手にしてはいたが、彼女の父親はどうしてもバークレーと結婚させたがっていた。俺は向こう見ずで無鉄砲な若造だったし、バークレーには教育もあり、将来は士官候補だった。だが、ナンシーは俺一筋で、あと一歩で結ばれるところだった時に反乱[訳注: セポイの反乱]が勃発し、国中が地獄と化した。
俺たちはバーティに籠城していた。連隊、砲兵隊半中隊、シク教徒の中隊、民間人や婦女子がいた。周囲には一万人の反乱兵がいて、まるでネズミ籠を囲むテリア犬のような有様だった。二週目くらいで水が尽きてしまい、進軍しているニール将軍の部隊に連絡できるかどうかが生死の分かれ目だった。婦女子がいるから突破は絶望的で、唯一の望みだった。俺は志願してニール将軍に危機を知らせに行くことにした。申し出は受け入れられ、地理に詳しいとされていたバークレー軍曹と相談し、敵陣を突破できそうな道順を書いてもらった。その夜十時、俺は出発した。千人の命がかかっていたが、俺の心にはただ一人のことしかなかった。
俺は干上がった水路沿いに進み、敵の見張り兵の目を逃れられることを祈ったが、曲がり角を回ったところで、六人の敵兵が闇の中で待ち伏せていて、まっすぐ彼らの前に出てしまった。たちまち殴られて気絶し、手足を縛られた。だが本当の衝撃は頭ではなく心に来た。意識が戻り、断片的に彼らの会話を聞いているうちに、俺と一緒に道順を考えたあの仲間、つまりバークレーが、現地の召使いを使って俺を敵に売ったのだとわかった。
この部分はもう詳しく語るまい。バークレーがどんな奴かわかっただろう。翌日ニール将軍によりバーティは救出されたが、反乱兵は俺を連れて退却し、俺はそれから長い間、白人の顔を見ることもなかった。拷問され、脱走を試み、また捕まって拷問された。今の俺のありさまを見ればわかるだろう。反乱兵の一部がネパールに逃げ込む時、俺も連れて行かれた。その後、ダージリンのさらに奥地へと運ばれた。そこの山岳民が俺を連れていた反乱兵を殺し、俺はしばらく彼らの奴隷となり、やがて脱走した。だが南へは戻れず、北へ北へと行き、ついにはアフガン人の間に迷い込んだ。長いことさまよったが、やがてパンジャブに戻り、現地人の中で奇術や手品で生計を立てていた。こんな惨めな身体で英国に帰ったところで、古い仲間に名乗る気にもなれない。復讐心ですら、それをさせなかった。ナンシーや古い友人たちには、背筋を伸ばしたまま戦死したウッドとして思い出してほしかったのだ。みんな俺が死んだものと思い、それでいいと思っていた。バークレーがナンシーと結婚し、連隊で出世していると聞いても、何も言わなかった。
だが人は年を取ると故郷が恋しくなる。長年、英国の緑の野や生け垣の夢ばかり見ていた。とうとう死ぬ前に一目見ておこうと決意し、何とか旅費を貯めて戻ってきた。そして兵隊のいるこの街に来た。彼らの気質や楽しませ方はよく知っているから、手品で糊口をしのいでいた。」
「非常に興味深いお話だ」とシャーロック・ホームズが言った。「バークレー夫人との再会と、お互いの正体に気付いた経緯は既に伺っている。つまり、君は彼女の後をつけて帰宅し、窓越しに夫婦の口論を見た。その中で、彼女は君への仕打ちを彼に責め立てたのだろう。君自身の感情が抑えきれず、芝生を駆け抜けて部屋に乱入した。」
「その通りだ、旦那。俺の姿を見たバークレーは、今まで見たこともない顔をして、暖炉のへりに頭をぶつけて倒れた。でも、倒れる前からもう死んでいた。あいつの顔にはっきりと死を読み取ったよ。俺の姿を見たのが、そのまま罪の心臓に撃ち込まれた弾丸のようだった。」
「その後は?」
「ナンシーは気絶し、俺は彼女の手から部屋の鍵を取って開け、助けを呼ぼうとした。だが、その時、余計なことはせずに立ち去った方がいいと思い直した。このままじゃ疑いを招くし、捕まれば秘密もすべて露呈してしまう。慌てて鍵をポケットにねじ込み、棒はカーテンを登ったテディを追いかけている間に落としてしまった。テディを箱に戻してから、できるだけ早く逃げ出した。」
「テディとは?」とホームズが尋ねた。
男は身を乗り出し、隅の小屋の扉を持ち上げた。すると、痩せてしなやかな、足がイタチのようで、細長い鼻と真っ赤な目を持つ、美しい赤褐色の生き物が素早く飛び出した。
「マングースだ!」と私は叫んだ。
「まあ、そう呼ぶ人もいれば、イタチアナグマと呼ぶ人もいる」と男は言った。「俺は“蛇捕り”と呼んでる。テディはコブラ退治が得意だ。ここに牙を抜いたコブラがいて、テディは毎晩、食堂の連中のためにそいつを捕まえる芸を見せている。」
「他に何か?」
「バークレー夫人が本当に大変な事態になれば、またご連絡をお願いするかもしれません」
「その時は、もちろん出頭します」
「だが、そうでなければ、死者の不祥事を暴いても意味はない。彼の人生の三十年もの間、その良心がこの罪を責め続けていたことを思えば、少なくとも十分な報いだろう。あ、向こう側にマーフィー少佐がいる。じゃあな、ウッド。昨日から何か新しいことがないか聞いてみよう。」
私たちは角に到着する前に少佐に追いつくことができた。
「やあ、ホームズ。もうこの騒ぎが何もなかったことで済んだと聞いたろう?」
「どういうことだ?」
「検死審問が終わったばかりだ。医学的証拠から、死因は明らかに卒中だった。見ての通り、実に単純な事件だったのさ。」
「まったく表面的な話ですね」とホームズは微笑んだ。「さあワトソン、もうオールダーショットで用はなさそうだ。」
「ひとつ気になることがある」駅へ向かいながら私は言った。「夫の名がジェームズで、もう一人はヘンリーなのに、なぜ“デヴィッド”の話が出たんだ?」
「ワトソン、それこそが、もし私が君の理想とする論理家であれば、すべてを見抜けたはずのキーワードだ。あれは非難の言葉だったのだよ。」
「非難?」
「ああ。ダヴィデも時に道を外しただろう。しかも一度は、ジェームズ・バークレー軍曹と同じ方向に。ウリヤとバテシバの小さな一件を思い出さないか? 聖書知識が少々錆びついているが、サムエル記のどちらかに載っているはずだ。」
IX. 臨時患者
私はこれまで、親友シャーロック・ホームズ氏の精神的な特質をいくつか説明しようと、やや断片的な回想記を整理してきたが、その中で毎回、目的にかなう好例を選び抜く難しさを痛感してきた。ホームズが分析的推理の妙技を発揮し、その独自の調査法の価値を実証した事件では、むしろ事実そのものがあまりにも些細で平凡だったため、とても公表する気にはなれなかった。一方で、事実が極めて劇的かつ注目すべきものでありながら、原因解明におけるホームズ自身の寄与が、伝記作者としての私の望みには及ばなかった例も多い。「緋色の研究」や、のちの「グロリア・スコット号」事件などは、その両極端にある好例だろう。今から記すこの事件も、もしかするとホームズの活躍が十分に強調されていないかもしれない。だが、全体の経緯があまりにも特異であるため、このシリーズから外すことは私にはできなかった。
正確な日時は覚えていない――関係するメモのいくつかは紛失してしまったからだ――が、間違いなくホームズと私がベイカー街で同室生活を始めて最初の年の終わり頃だったと思う。天気は荒れ模様の十月で、私も健康がすぐれず秋風を恐れて終日家にこもり、ホームズもまた、一度没頭すれば夢中になるあの難解な化学実験に取り組んでいた。だが夕方近く、試験管を割ってしまったことで研究は思わぬ中断を余儀なくされ、彼は不機嫌そうな顔で椅子から跳ね起きた。
「今日一日の仕事が台無しだ、ワトソン」と言いながら窓辺に歩み寄った。「ほう、星が出て風も止んだ。ロンドンを一回りどうだ?」
私もさすがに狭い居間に飽きて同意した。私たちは三時間ばかり連れ立って町を歩き、フリート街やストランドを行き交う人生模様の万華鏡を眺めて過ごした。そのうちにホームズも不機嫌さがすっかり取れ、鋭い観察眼と巧みな推論を交えた彼独特の会話に私は魅了され続けた。ベイカー街に戻ったのは十時頃だった。玄関には馬車が一台止まっていた。
「ふむ、医者――開業医と見た」とホームズ。「開業歴は浅いが、何かと忙しいようだ。我々に相談に来たのだろう。帰ってきて正解だった!」
私はホームズの推理法に慣れていたので、馬車の中に吊るされた籐の籠に入っていた様々な医療器具の種類や状態から、彼が瞬時にそう結論した理由がわかった。私たちの部屋の窓に灯りがともっているのを見て、この遅い訪問が我々宛てであることが確認できた。こんな時間に同業者が訪ねてきた理由に興味を抱きつつ、私はホームズと一緒に居間へと向かった。
暖炉のそばの椅子から、色白で細面、淡い髭の男が立ち上がった。年の頃は三十四、五に見えたが、やつれた顔つきと青白い肌は、精気を吸い取られ若さを失った人生を物語っていた。物腰は神経質で内気、いかにも繊細な紳士といった印象で、立ち上がってマントルピースに置いた細く白い手も外科医というより芸術家のそれだった。服装は地味で黒のフロックコートに暗い色のズボン、ネクタイにわずかばかり色味を添えていた。
「こんばんは、先生」とホームズは朗らかに言った。「お待たせしたのはほんの数分ですね。」
「御者に声をかけられたのですか?」
「いえ、脇の卓上の蝋燭でわかりました。どうぞお掛けになって、ご用件をお聞かせください。」
「パーシー・トレヴェリアン医師と申します。ブルック街四〇三番地に住んでおります。」
「あなたは神経系の難病に関する論文の著者ではありませんか?」と私は尋ねた。
彼の青白い頬が、私がその業績を知っていると聞いて嬉しそうに赤らんだ。
「その本のことを耳にする機会がほとんどなく、もう忘れられたものとばかり思っていました」と彼は言った。「出版社からは売れ行きが芳しくないと聞かされていました。あなたも医者でいらっしゃいますね?」
「退役陸軍軍医だ。」
「私は昔から神経病が趣味でして、本当はその分野に専念したいのですが、最初は何でもやらないといけませんからね。とはいえ、これは本題から外れますね、ホームズさん。貴重なお時間を頂いて恐縮です。実は、最近私のブルック街の家で非常に奇妙な出来事が続き、今夜ついに我慢ならず、すぐにでもあなたの助言と助力を仰がねばならないと感じたのです。」
シャーロック・ホームズは椅子に腰掛け、パイプに火をつけた。「どちらも喜んでお力になろう」と言った。「詳しく事情をお話しください。」
「些細なことも多いので、お話しするのが恥ずかしいほどですが」とトレヴェリアン医師は言った。「ただ、あまりに不可解で、しかも最近になって事態が複雑化してきたので、すべてお話しして、ご判断を仰ぎます。
まずは私自身の経歴から申し上げねばなりません。私はロンドン大学出身でして、自慢するつもりはありませんが、当時の教授たちには将来を有望視されていました。卒業後も研究に励み、キングズ・カレッジ病院の下級医師を務め、カタレプシーの病理研究で注目され、神経系病変に関する単著でブルース・ピンカートン賞とメダルを受賞しました。今思えば、当時は誰もが私の前途に期待していたと言って差し支えないでしょう。
「しかし、最大の障害は資本不足だった。君にもわかるだろうが、野心的な専門医が開業するには、カヴェンディッシュ・スクエア界隈の十数本ある通りのどれかで始めなければならず、そこはいずれも家賃も内装費も莫大だ。それに加え、開業資金だけでなく、数年間は自分の生活費も用意しなければならないし、見栄えのする馬車と馬も雇わねばならない。これは到底、私の力の及ぶところではなかったので、節約に努めて十年かけてやっと表札を出せるくらいの貯金ができることを期待するしかなかった。だが、思いがけない出来事が突然、私の前に新たな展望を開いた。
それは、ブレッシントンという名の、まったく見知らぬ紳士が私を訪ねてきたことだった。ある朝、彼が私の部屋にやって来て、すぐさま本題に入ったのだ。
『君があのパーシー・トレヴェリアン博士で、最近、目覚ましい経歴を重ね、大きな賞を取った人か?』と彼は言った。
私はうなずいた。
『率直に答えてくれ』と彼は続けた。『そのほうが君のためになる。君には成功するだけの才知がある。だが、機転はどうだ?』
この唐突な質問には思わず笑みがこぼれた。
『自分なりの分は持っていると信じています』と私は答えた。
『悪い癖は? 酒に溺れたりしないか?』
『まったく、失礼な!』と私は叫んだ。
『それでいいんだ! 気を悪くしないでくれ。だが、念のために聞かねばならなかった。これだけの資質があれば、なぜ開業していないんだ?』
私は肩をすくめた。
『まあまあ、そういうことか』と、彼はせかせかとした調子で言った。『頭は切れるが、懐具合はさっぱりってわけだな? もし、私が君をブルック・ストリートで開業させてやると言ったら、どう思う?』
私はあっけにとられて彼を見つめた。
『いや、私のためにやるんだ、君のためじゃない』と彼は叫んだ。『率直に話そう。条件が合えば、私としても大満足だ。私は少しばかり金があって、どこかに投資しようと思っている。それを君に賭けてみようというわけだ』
『なぜです?』と私は息を呑んだ。
『まあ、他の投資と同じことだ。それに、たいていの投資よりも安全そうだ』
『私は何をすればいいのですか?』
『説明しよう。家は私が借りて、家具もそろえ、女中も雇い、運営も全部引き受ける。君は診察室で椅子をすり減らしていればいい。小遣いも渡すし、必要なものも何でも出す。その代わり、君の収入の四分の三を私に渡し、残りの四分の一を君が取る』
これが、ミスタ・ホームズ、ブレッシントンという男が私に持ちかけてきた奇妙な提案だった。細かい交渉の経緯は省くが、結局、私は次の聖母祭にその家へ移り、ほぼ彼の提案通りの条件で開業した。彼自身も同居することになったが、「居住患者」としてである。どうやら心臓が弱く、絶えず医師の監督が必要ということだった。彼は一階の最も良い二部屋を自分の居間と寝室に改装した。人付き合いを極端に避け、めったに外出せず、非常に変わった生活ぶりだった。ただ一つだけ規則正しいことがあった。毎晩決まった時間に診察室に来て帳簿を調べ、私の稼ぎ一ギニーごとに五シリング三ペンスを置き、残りは自分の部屋の金庫に持っていくのだ。
はっきり言えるが、彼は自分の投資を後悔したことは一度もなかった。開業当初から順調で、いくつかの好事例と病院時代の評判のおかげで、私はすぐに名声を得、この数年で彼を裕福な男にしてやった。
これが、ホームズさん、私の過去とブレッシントン氏との関係のすべてだ。あとは、私を今夜ここに来させた出来事についてお話すればよい。
数週間前、ブレッシントン氏はかなり動揺した様子で私のところに降りてきた。彼はウエスト・エンドで起きた強盗について話し、必要以上に興奮して、すぐにでも窓や扉に強力なボルトを付けるべきだと主張した。その後一週間ほど、彼はずっと落ち着かず、窓の外をしきりに覗いたり、普段夕食前にしていた散歩もやめてしまった。その様子から、彼は何か、あるいは誰かを死ぬほど恐れているように見えたが、そのことを尋ねるとひどく不機嫌になったので、話題にするのをやめざるを得なかった。時が経つにつれ、徐々に彼の恐怖心も薄れ、以前の習慣を取り戻したが、新たな出来事が彼をいまのような哀れな衰弱状態に突き落とした。
何が起きたのかと言えば、二日前に私がこんな手紙を受け取ったことだ。差出人も日付もない。
『現在英国に在住のロシアの貴族が、パーシー・トレヴェリアン博士の専門的援助を受けたいと希望している。数年来カタレプシー発作に悩まされており、同博士がこの分野の権威であることはよく知られている。もし博士がご在宅であれば、明日の夕方六時十五分ごろに伺いたい』
カタレプシーという病気は稀なため、研究には患者が少ないのが最大の難点だ。そのため、この手紙には大いに興味をそそられた。約束の時刻、私は診察室で待ち、案内係が患者を通した。
やって来たのは、年配でやせて、地味で目立たない、いかにもロシアの貴族という印象からは程遠い人物だった。私がより強い印象を受けたのは、付き添いの男のほうだった。背が高く驚くほどの美男子で、暗く精悍な顔つき、筋肉と胸板はヘラクレスのようだった。二人は腕を組んで現れ、若者は老人を椅子に優しく座らせたが、その外見からは意外なほどの気遣いだった。
『先生、突然のことをお許しください』とその若者は少し舌足らずな英語で言った。『この方は私の父で、父の健康は私にとって何よりも大切なのです』
この親思いの様子には胸を打たれた。『ご相談中もご一緒にいられますか?』と私は尋ねた。
『とんでもない!』と彼は身ぶりを交えて叫んだ。『父があの恐ろしい発作を起こすのを見るのは、私には耐えがたい苦痛です。もしそんな場面を目撃したら、私はきっと生きていられないでしょう。自分の神経もとても繊細なんです。先生がよろしければ、待合室でお待ちしていますので、父の診察をお願いします』
もちろん私は承知し、若者は部屋を出た。患者と私は病状について詳しく話し合い、私は詳細な記録を取った。患者は頭脳明晰とはいえず、返答も要領を得ないことが多かったが、それは言葉の問題だろうと考えた。だが突然、私が記録を取っていると、彼はまったく返事をしなくなった。ふと顔を上げると、彼は椅子に直立不動で座り、虚ろな、硬直した顔で私を凝視していた。またしても、あの謎めいた病に襲われたのだ。
第一に私が感じたのは、先ほども言ったように、哀れみと恐怖だった。だが、二番目の感情は医師としての満足だったと言わざるを得ない。私は脈拍や体温、筋肉の硬直や反射を調べ、いずれも特に異常はなかったが、これはこれまでの経験と一致する。私は亜硝酸アミルの吸入で良い結果を得ていたので、今回もその効果を試す絶好の機会だと思った。薬瓶は階下の実験室にあったので、患者を椅子に座らせたまま取りに行った。探すのに少し手間どったが、五分ほどで戻ってきた。ところが、驚いたことに、部屋は空っぽで患者の姿がなかった。
当然、私はすぐ待合室に駆け込んだ。息子もいなかった。玄関のドアは閉まっていたが、きちんと施錠はされていなかった。患者の案内係は新米の少年で、決して素早い方ではない。彼は階下で待機していて、私が診察室の呼び鈴を鳴らしたときだけ患者を送り出すのだが、何も聞かなかったという。こうして、事件は完全な謎として残った。間もなくブレッシントン氏が散歩から戻ってきたが、私はこの件について何も話さなかった。というのも、最近では彼と極力接触を避けていたからだ。
もう二度とあのロシア人親子に会うことはないだろうと思っていた。ところが、今晩まったく同じ時刻に、二人は再び現れたのだ。
『昨日は突然失礼しました、先生』と患者が言った。
『本当に驚きましたよ』と私は返した。
『実はですね』と彼は語った。『発作が収まると、それまでの記憶が完全に曖昧になるのです。見知らぬ部屋で目覚め、先生がいないので、ぼんやりしたまま外に出てしまいました』
『私も』と息子が言った。『父が待合室のドアを通り過ぎるのを見て、当然診察が終わったものと思いました。本当の事情に気づいたのは、家に戻ってからでした』
『まあ、何も問題はありません。私がひどく困惑しただけです』と私は笑いながら言った。『ですから、あなたも待合室でお待ちくだされば、診察の続きを喜んでいたします』
三十分ほどその老人と症状について話し合い、処方箋を書いて、彼が息子に連れられて帰るのを見届けた。
例のごとく、この時間帯はブレッシントン氏が運動に出る習慣だった。彼はほどなく帰宅し、階上へ上がった。直後、彼が階段を駆け下りてきて、まるで狂気じみた様子で私の診察室に飛び込んできた。
『誰か私の部屋に入ったな?』と彼は叫んだ。
『誰も入っていませんよ』と私は答えた。
『嘘だ!』と彼は怒鳴った。『上に来て見てみろ!』
彼は半狂乱で怒鳴っているようだったので、私はその乱暴な口ぶりには目をつむった。階上へ行くと、彼は明るい色のカーペットにいくつかの大きな足跡を指差した。
『これが私の足跡だと言うのか?』と彼は叫んだ。
それは明らかに彼の足跡よりもずっと大きく、しかも新しいものだった。ご存じのとおり、今日はひどい雨だったし、来客はこの患者たちだけだった。つまり、待合室にいた男が、私がもう一人を診ている間に、何らかの理由で居住患者の部屋に上がったのに違いない。何も盗まれていなかったが、足跡が侵入の事実を証明していた。
ブレッシントン氏は、この件に私が想像する以上に興奮していた。それも無理はないが、彼は実際、椅子に座って泣き出し、まともに話をすることもできなかった。彼の提案であなたを訪ねることになり、私もそれが適切だと思った。確かにこの事件は非常に奇妙だが、彼はその重要性を過大評価しているように思える。ぜひ私の馬車でご一緒いただければ、少なくとも彼を落ち着かせることはできるでしょう。もっとも、この不可解な出来事の説明までは期待していませんが」
シャーロック・ホームズは、この長い話を非常な集中力で聞いていた。その無表情な顔は相変わらずだったが、まぶたが深く垂れ、パイプの煙が話の奇妙な場面ごとに濃く立ち上るのが印象的だった。訪問者が話し終えると、ホームズは無言で立ち上がり、私に帽子を手渡し、自分の帽子も取ってトレヴェリアン医師の後について玄関へ向かった。十分ほどで、私たちはブルック・ストリートの医師宅に到着した。そこは、ウェスト・エンドの開業医にふさわしい、重厚で無表情な外観の館だった。案内の少年が私たちを通し、すぐに幅広の絨毯敷きの階段を上り始めた。
だが、思いがけない中断が私たちを足止めした。階段の上の明かりがふっと消え、暗闇から甲高く震える声が響いた。
「私はピストルを持っている。これ以上近づけば、本当に撃つぞ」
「いい加減にしてください、ブレッシントンさん!」とトレヴェリアン医師が叫んだ。
「ああ、先生か」その声は大きく安堵の息をついた。「だが、他の方々は本当に名乗った通りの人間か?」
暗闇の中からじっと見据えられるのを感じた。
「ええ、ええ、大丈夫です」やがて声が言った。「どうぞお上がりください。私の用心がご不快でしたら、申し訳ありません」
そう言いながら彼は階段のガス灯をつけ直した。私たちの前に現れたのは、異様な風貌の男だった。声も外見も、神経がすっかり参っていることを物語っていた。非常な肥満体だが、かつてはさらに太っていたらしく、頬にはブラッドハウンドのようにだぶついた皮が垂れていた。顔色は悪く、薄い黄土色の髪は緊張で逆立っているようだった。手にはピストルを持っていたが、私たちが近づくとポケットにしまった。
「こんばんは、ホームズさん」と彼は言った。「わざわざお越しいただき、まことにありがたい。私ほどあなたの助言を必要とする者はいませんよ。トレヴェリアン先生から、私の部屋に全く不当な侵入があった話はお聞きでしょう?」
「伺いました」とホームズ。「この二人の男は何者で、なぜあなたを悩ませるのですか?」
「そ、それはですね……」と居住患者は神経質に言った。「難しいことでして……お答えしかねます、ホームズさん」
「つまり、ご存じないのですか?」
「こちらへどうぞ。ぜひ中へ」
彼は私たちを広く快適な寝室に案内した。
「これです」と彼はベッドの端にある大きな黒い箱を指さした。「ホームズさん、私は決して裕福な男じゃありません。トレヴェリアン先生もご存じの通り、私が投資したのは一度だけ。それも、私は銀行というものを信用しません。絶対に銀行なんかに預けません、ホームズさん。この中に私の全財産が入っているのです。ですから、見知らぬ者が私の部屋に無理やり入り込むのは、一大事なのです」
ホームズは問い詰めるような目でブレッシントンを見つめ、首を横に振った。
「本当のことを言わなければ、助言のしようがありません」とホームズは言った。
「すべて話しましたよ」
ホームズは不快そうに踵を返した。「おやすみなさい、トレヴェリアン先生」
「私には何の助言もないのですか?」とブレッシントンは声を震わせて叫んだ。
「あなたに申し上げることは、ただ一つです。真実を語りなさい」
ほどなく私たちは通りに出て、家路を歩き始めた。オックスフォード・ストリートを渡り、ハーレー・ストリートの半ばまで来て、ようやくホームズが口を開いた。
「ワトソン、馬鹿げた用事に付き合わせてすまない。だが、根は実に興味深い事件だ」
「私には、さっぱり見当がつかない」と私は告白した。
「明らかなのは、理由はともかく、少なくとも二人の男がブレッシントンに接触しようと執念を燃やしているということだ。初回も二回目も、若いほうの男がブレッシントンの部屋に侵入し、共犯者が巧妙な手口で医師を引き離していたのは間違いない」
「カタレプシーは?」
「ワトソン、あれは見せかけだよ。専門家の前でそんなことは言えないが、あの症状は簡単に真似できる。私にもできるくらいだ」
「それで、その先は?」
「偶然にも、両日ともブレッシントンは外出していた。あえてこんな時間に診察を申し込んだのは、待合室に他の患者がいないことを確実にしたかったからだろう。ただ運悪く、この時間帯がブレッシントンの日課と重なっていた。つまり、彼の日常を完全には把握していなかったわけだ。もし強盗が目的なら、何かしら物色するはずだ。だが、私は人の目を見れば、その恐怖が財産ではなく自身の身に向けられているとわかる。この男がこれほど執念深い敵を二人も作って、その自覚がないなど考えられない。つまり、彼は二人の正体を知っていて、何らかの理由でそれを隠しているのだ。明日には、もう少し話してくれるかもしれない」
「もう一つ、まったく突飛な仮説だが、考えられなくもない。――あのロシア人親子の話自体がトレヴェリアン医師の作り話で、実は彼自身がブレッシントンの部屋に入っていた可能性は?」
ガス灯の下で、ホームズが私の奇抜な推理に愉快げな微笑みを浮かべているのが見えた。
「親愛なるワトソン君」と彼は言った。「それは最初に思いついた解決策の一つだったが、すぐに医師の話が裏付けられた。この若者は、階段のカーペットに足跡を残していたので、部屋の中の足跡をわざわざ見せてもらうまでもなかった。彼の靴はブレッシントンのような尖ったものではなく、つま先が四角く、医師のものよりも約1と1/3インチ長かったことを話せば、彼が別人であることは疑いようもないだろう。しかし、今夜はもう休もう。明日の朝、ブルック街からさらに何か知らせが入るだろうと予想しているからだ。」
シャーロック・ホームズの予言は、まもなく劇的な形で現実となった。翌朝七時半、夜明けのほのかな光の中、私は寝巻姿の彼がベッド脇に立っているのを見つけた。
「馬車が待っているぞ、ワトソン君」と彼は言った。
「何かあったのか?」
「ブルック街の件だ。」
「新しい知らせか?」
「悲劇的だが、はっきりしない」と彼はブラインドを上げつつ言った。「これを見てくれ――ノートの1枚で、『お願いだからすぐ来てくれ――P.T.』と鉛筆で殴り書きされている。我々の友人である医師は、これを書いたとき相当切羽詰まっていたのだ。さあ、急いで行こう、これは緊急の呼び出しだ。」
15分ほどで、我々は医師の家へ戻った。彼は恐怖に満ちた顔で駆け寄ってきた。
「なんということだ!」彼は両手でこめかみを押さえて叫んだ。
「何があった?」
「ブレッシントンが自殺したんだ!」
ホームズは口笛を吹いた。
「ああ、夜のうちに首を吊ったんだ。」
私たちは家の中へ入り、医師が先導して明らかに待合室らしきところに案内された。
「私は本当に、何をしているのか分からない」と彼は叫んだ。「警察はすでに二階にいる。私はひどく動揺している。」
「いつ気づいた?」
「毎朝早く、彼には紅茶が運ばれるんだ。女中が7時ごろ入った時、あの不幸な男は部屋の真ん中で吊られていた。彼は、以前重いランプがかかっていたフックに縄を結びつけ、昨日私たちに見せたあの箱の上から飛び降りたのさ。」
ホームズはしばし深く考え込んだ。
「もしよければ」と彼はついに言った。「二階へ上がって調べさせてもらいたい。」
私たちは医師に続いて階段を上がった。
寝室のドアを開けて入ると、目の前に恐ろしい光景が広がった。私はこの男ブレッシントンから受けた、だらしなさの印象について語ったことがあるが、今やフックにぶら下がった彼は、その印象がさらに誇張され、もはや人間とは思えない姿になっていた。首は丸裸にされた鶏のように引き延ばされ、そのために体全体がより肥満で不自然に見えた。彼は長い寝間着だけを身につけており、腫れた足首と不格好な足が無残にも突き出ている。彼のそばには、手帳にメモを取る精悍な警部が立っていた。
「ああ、ホームズさん」と彼は陽気に言った。「お会いできて嬉しいです。」
「おはよう、ラナー」ホームズは答えた。「私が邪魔だとは思わないでくれ。ここに至る経緯を聞いているか?」
「はい、少しは聞いています。」
「何か意見を持っているか?」
「私の見るところ、この男は恐怖で正気を失ったようだ。ベッドもよく寝ていた形跡がある。ご覧の通り、深く跡が残っている。自殺は朝五時ごろが最も多いとされている。それが彼の自殺した時刻だろう。非常に計画的なものだったようだ。」
「筋肉の硬直から判断すると、死後約三時間だと思う」と私は言った。
「部屋で何か変わったところは?」とホームズが尋ねた。
「洗面台の上にドライバーとネジがあった。夜中にかなり煙草を吸ったようだ。ここに暖炉から拾い出した葉巻の吸い殻が四本ある。」
「ふむ」とホームズは言った。「葉巻ホルダーは見つかったか?」
「いや、見ていない。」
「葉巻入れは?」
「はい、上着のポケットにあった。」
ホームズはそれを開き、中に一本だけ残っていた葉巻の匂いを嗅いだ。
「これはハバナだ。だが、他の吸い殻はオランダ人が東インドの植民地から輸入する特有の葉巻だ。藁で包まれていて、他のどんなブランドより細長いものだ。」彼は四本の吸い殻をポケットルーペで調べた。
「このうち二本はホルダーで、二本はそのまま吸われている。それに、二本はあまり切れ味のよくないナイフで切られ、二本は見事な歯で噛み切られている。これは自殺ではない、ラナー警部。極めて入念に計画され、かつ冷酷な殺人だ。」
「そんな馬鹿な!」と警部が叫んだ。
「なぜだ?」
「なぜ誰かが、こんな不器用な方法で人を殺す必要がある?」
「それをこれから解明するんだ。」
「どうやって中に入った?」
「玄関からだ。」
「朝にはしっかり施錠されていた。」
「ならば、出ていった後で施錠したのだろう。」
「どうして分かる?」
「彼らの痕跡があった。失礼、もう少し調べれば、さらに情報を提供できるかもしれない。」
彼はドアの方へ行き、錠を回して丹念に調べ、内側にあった鍵も取り出して調べた。ベッド、カーペット、椅子、暖炉棚、死体、そして縄――それぞれを順に調べ、やがて満足そうな様子を見せた。そして、私と警部の手を借りて、この哀れな遺体をシーツの下に静かに横たえた。
「この縄については?」
「これから切り取ったんです」とトレヴェリアン医師が、ベッドの下から大きな巻き縄を取り出した。「彼は異常に火事を怖がっていて、階段が燃えていた時に窓から逃げるため、いつもこれをそばに置いていたんです。」
「それなら犯人たちにとって好都合だったわけだ」とホームズは考え込んで言った。「うむ、状況は極めて明快だ。午後には、その理由も説明できるだろう。この暖炉棚のブレッシントンの写真を持ち帰る。調査の助けになるかもしれない。」
「でも、何も説明してくれていない!」と医師が叫んだ。
「ああ、事件の経緯はもう疑いない」とホームズは言った。「三人が関わっていた――若者と老人、そしてもう一人、身元不明の人物だ。最初の二人は、ロシアの伯爵とその息子に変装していたあの連中で、詳細な特徴が分かっている。彼らは屋内の共犯者によって入れられた。ひとつ助言するなら、警部、最近医師のところに雇われたという給仕少年を逮捕した方がいい。」
「そのいたずら小僧は行方不明です」とトレヴェリアン医師が言った。「女中と料理人が今、探しています。」
ホームズは肩をすくめた。
「この少年も、この劇のなかで決して小さくない役割を果たした」と彼は言った。「三人の男はつま先立ちで階段を上がった――まず老人、次に若者、そして最後に身元不明の男が続いた――」
「親愛なるホームズ!」と私は思わず叫んだ。
「ああ、足跡の重なり方に疑問はない。昨夜、どれがどれかを把握しておいたんだ。彼らはこうしてブレッシントンの部屋へと上がった。部屋のドアは施錠されていたが、針金を使って鍵を回した。その証拠に、この鍵の溝についた傷を見れば分かる。
「部屋に入った最初の行動は、ブレッシントンを猿轡で縛ることだったろう。彼は寝ていたか、恐怖で叫ぶこともできなかったかもしれない。壁は厚いから、叫んでも聞こえなかった可能性がある。
「彼を押さえつけた後、何らかの協議が行われた形跡がある。おそらく裁判めいたものだったに違いない。時間がかかったようで、その間に葉巻が吸われた。老人はあの籐椅子に座り、葉巻ホルダーを使った。若者は向こう側に座り、灰をタンスに落とした。三人目は部屋をうろうろ歩き回った。ブレッシントンはベッドの上で起き上がっていたと思うが、それは確証が持てない。
「やがて彼らはブレッシントンを吊るした。これは事前に計画されていて、持ち運び可能な滑車かブロックを用意していたのだろう。そのためにドライバーやネジがあった。だがフックを見つけ、手間が省けた。用が済むと彼らは去り、共犯者がドアを施錠したのだ。」
私たちは皆、ホームズが極めて微妙な証拠から推論した夜の出来事の概要を、息を呑んで聞き入った。警部は、すぐさま給仕少年についての調査に向かい、ホームズと私はベーカー街へ戻って朝食を取った。
「三時には戻るよ」と、食事が終わるとホームズは言った。「その時間に警部と医師がここに来る。恐らくその時までに、事件の残された謎もすべて解明できているはずだ。」
約束通り訪問者たちが現れたが、私の友人が姿を見せたのは四時十五分前だった。しかし、彼の表情から、すべてが順調だったことは明らかだった。
「何か進展は?」とホームズが尋ねた。
「少年を確保しました。」
「素晴らしい。私も犯人たちを突き止めた。」
「あなたが突き止めたのですか!」私たち三人は声を揃えて叫んだ。
「少なくとも身元は分かった。このいわゆるブレッシントンは、予想通り警察本部でもよく知られた人物で、襲撃者たちも同じくだ。彼らの名前はビドゥル、ヘイワード、モファット。」
「ワージングドン銀行団だ!」と警部が叫んだ。
「その通り」とホームズが答えた。
「するとブレッシントンはサットンだったのか。」
「まさに」とホームズ。
「それなら全てがはっきりした」と警部は言った。
だが、トレヴェリアン医師と私は呆然と顔を見合わせた。
「ワージングドン銀行事件をご存じだろう」とホームズは言った。「五人が関与していた――この四人と、カートライトというもう一人。管理人のトービンは殺され、犯人たちは七千ポンドを奪って逃げた。これは1875年の出来事だ。五人全員が逮捕されたが、証拠は決定的ではなかった。このブレッシントン、つまりサットンが一味の中で最も悪辣で、密告者に転じた。彼の証言でカートライトは絞首刑、他の三人はそれぞれ十五年の刑となった。彼らがこの間仮釈放となり、ご覧の通り裏切り者への復讐を果たそうとしたのだ。二度までは失敗し、三度目でついに成し遂げた。他に説明すべきことがあるかね、トレヴェリアン医師?」
「すべて極めて明快にご説明いただきました」と医師は言った。「間違いなく、彼が不安に駆られていた日は、新聞で彼らの釈放を読んだ日だったのでしょう。」
「その通りだ。強盗の話はただのごまかしだった。」
「それにしても、なぜあなたに真実を話せなかったのです?」
「それはね、先生、かつての仲間たちの復讐心をよく知っていたから、できるだけ自分の素性を隠そうとしていたのだ。彼の秘密は恥ずべきもので、口外することもできなかった。しかし、どんな悪党であっても、彼はなおイギリス法の庇護の下で生きていた。警部、たとえその庇護が守りきれずとも、正義の剣は必ず仇を討つということをお忘れなく。」
以上が、「寄宿患者」とブルック街の医師にまつわる奇妙な事件である。あの夜以降、三人の殺人者は警察の前から姿を消し、スコットランド・ヤードでは、不幸な運命をたどった蒸気船ノラ・クレイナ号――数年前、ポルトガル沖で全員が消息を絶った――の乗客の中に彼らがいたのではないかと推測されている。給仕少年に対する訴追は証拠不十分で頓挫し、「ブルック街の怪事件」と呼ばれたこの出来事が、これまで公に語られることはなかった。
X. ギリシャ語通訳
私がシャーロック・ホームズと長年親しく付き合っていながら、彼が家族について語るのを聞いたことはなく、自身の幼少期について触れることもほとんどなかった。こうした彼の無口さは、私にとって彼の非人間的な印象を一層強め、時には、彼をまるで孤立した現象、心なき頭脳――知性において卓越している分だけ人間的共感に欠ける存在――のように感じさせることもあった。女性嫌いと新しい友人を作ることへの消極的な性格もまた、彼の感情を抑制した性質を象徴していたが、それ以上に彼が家族への言及を徹底して避けていたことが印象的だった。私は彼に身寄りがない孤児だと信じ込んでいたが、ある日、非常に驚いたことに、彼が兄について語り始めたのである。
それは夏の夕方、紅茶の後のことだった。話題はゴルフクラブから黄道傾斜の変化の原因にまで飛び回り、やがて隔世遺伝や遺伝的素質についての議論に行き着いた。論点は、個人の特異な才能が、どこまで先祖に由来し、どこまで本人の訓練によるものか、というものだった。
「君の場合」と私は言った。「これまで聞かせてもらった話からすると、観察力や推理力は君自身の体系的訓練の賜物のように思えるが。」
「ある程度はそうだ」と彼は思慮深げに答えた。「うちの先祖は田舎の地主で、階級にふさわしい生活を送っていたらしい。だが、それでもこの傾向は血に流れているようで、祖母――フランスの画家ヴェルネの妹だった――の系統かもしれない。血に芸術が混じると、思いもよらぬ形をとるものだ。」
「だが、それが本当に遺伝だとどうして分かる?」
「兄のマイクロフトは、私以上にその資質を持っているからだ。」
これは本当に驚きだった。イギリスに彼ほどの能力を持つ人物がもう一人いるなら、警察や世間が知らないはずがない。私は、彼の謙遜から兄を自分の上と認めているのではと問いかけてみた。ホームズはその指摘に笑った。
「ワトソン君、私は謙遜を美徳に数える人々には同意できない。論理家には、物事をありのままに見るべきであり、自分を過小評価するのは、自己を誇張するのと同じく真実から逸れることになる。だから、マイクロフトの観察力が私より優れていると言うとき、それはまさに事実そのものなのだ。」
「君の弟かい?」
「いや、私より七歳年上だ。」
「どうして知られていないんだ?」
「いや、彼の世界ではよく知られている。」
「どこで?」
「例えばダイオゲネス・クラブだ。」
私はそのクラブを聞いたことがなく、顔に出ていたのだろう。シャーロック・ホームズは時計を取り出した。
「ダイオゲネス・クラブはロンドンでも最も風変わりなクラブで、マイクロフトも極めて変わり者だ。いつも四時四十五分から七時四十分まで必ずいる。今は六時だ。この素晴らしい夕べ、散歩がてら、二つの珍品を紹介しよう。」
五分後、私たちはリージェンツ・サーカスへ向かって歩いていた。
「君は不思議に思うだろう」と友は言った。「なぜマイクロフトがその能力を探偵に生かさないのか。だが彼には無理なんだ。」
「でも君は――」
「観察力と推理力では彼が上回ると言った。もし探偵術が安楽椅子での推理だけで済むなら、兄は史上最強の犯罪探知者だろう。だが、彼には野心も行動力もない。自分の推理を確かめるためなら、誤りを認めた方がまだましらしい。何度も問題を持ち込んだが、彼の説明が後に正しかったことが多い。それでも、事件を実際に裁判所へ持ち込むための実地調査は全くできなかった。」
「つまり職業じゃないのか?」
「まったく違う。私にとって生計手段でも、彼にとっては単なる道楽にすぎない。彼は数字に異常な才能があり、官庁の帳簿監査をしている。マイクロフトはパル・マルに住み、毎朝ワイトホールまで歩き、夕方戻る。それ以外の運動は全くせず、姿を見かけるのはその部屋とダイオゲネス・クラブだけだ。」
「その名は思い出せないな。」
「おそらく違うだろう。ロンドンにはな、内気な者もいれば人嫌いな者もいて、人付き合いを望まない男たちが多い。だが、そうした者であっても、座り心地のいい椅子や最新の雑誌には決して無関心じゃない。そういった連中のためにディオゲネス・クラブが設立されたのだ。今やそこには、この町で最も社交嫌いでクラブにふさわしくない男たちが揃っている。会員は誰一人、他の会員に少しでも関心を示すことを許されていない。よそ者用の談話室を除けば、どんな状況であれ会話は一切禁止だ。三度の違反が委員会に知られると、違反者は除名の対象になる。兄は創設者の一人で、私自身もここの雰囲気はたいへん心地よいと感じている。」
我々が話しながらパル・マルに到着し、セント・ジェームズ側から歩いていた。シャーロック・ホームズはカールトンから少し離れた扉の前で立ち止まり、私にしゃべらぬよう注意してから先導して中へ入った。ガラス張りのパネル越しに、広く豪華な部屋がちらりと見え、そこでは多くの男たちがそれぞれの隅で新聞を読んでいた。ホームズは私をパル・マル通りに面した小部屋に案内し、少しの間部屋を外した。戻ってきた彼の傍らには、彼の兄であることがすぐに分かる人物がいた。
マイクロフト・ホームズはシャーロックよりずっと大柄で、ずんぐりとした体格だった。体はまさしく肥満体だが、顔は大きいものの、あの兄弟特有の鋭い表情がどこかに残っていた。瞳は非常に明るく淡い灰色で、常に遠くを見つめるような内省的なまなざしを湛えており、それはシャーロックが全力を振るっているときにしか見せないものだった。
「お会いできて光栄です」彼はアザラシのひれのような大きく太い手を差し出して言った。「あなたが記録係になってから、シャーロックの噂はどこでも耳にしますよ。ところでシャーロック、先週はマンハウス事件のことで相談に来るかと思っていたのだがね。少々手に余るかと思っていた。」
「いや、解決したよ」と友人は微笑んで答えた。
「やはりアダムズだったのだろう?」
「そう、アダムズだった。」
「最初から確信していたよ。」二人はクラブの出窓に並んで腰かけた。「人間観察をしたいなら、ここが最高の場所だ」とマイクロフト。「ほら、立派な人種標本ばかりだろう。例えば、あそこに向かってくる二人を見てごらん。」
「ビリヤード係と、もう一人か?」
「正解だ。あのもう一人についてはどう思う?」
二人の男は窓の前で立ち止まった。一人はチョークの跡がベストのポケットにあるくらいで、ビリヤードに関係があると分かるのはそれだけだった。もう一人は小柄で浅黒く、帽子を後ろにずらし、いくつもの包みを脇に抱えていた。
「元軍人だな」とシャーロックが言った。
「しかもごく最近除隊したばかりだ」と兄が続けた。
「インド勤務だったな。」
「下士官だった。」
「王立砲兵隊だろう」とシャーロックが言った。
「やもめだ。」
「だが子どもがいる。」
「子どもたちだよ、ワトスン、子どもたちだ。」
「ちょっと、これはさすがにこじつけすぎじゃないか」と私は笑いながら口を挟んだ。
「いや」とホームズは答えた。「あの態度、威厳ある表情、日に焼けた肌を見れば、軍人でしかも兵卒以上、さらに最近インドから戻ったのは分かるだろう。」
「除隊後間もないのは、まだ“弾薬靴”と呼ばれる軍靴を履いていることからも明らかだ」とマイクロフト。
「騎兵独特の歩き方ではなかったが、帽子を片方にかぶっていた。額の片側だけ日焼けが薄いのがそれを示している。体格から工兵ではない。砲兵隊だ。」
「そして、全身喪服を着ていることから、最愛の人を亡くしたのだろう。自分で買い物しているということは妻を亡くしたのだ。しかも子ども用品を買っているのが分かる。ガラガラがあるから一人は幼児だ。おそらく妻は産褥で亡くなったのだろう。絵本も抱えているから、もう一人上の子もいる。」
この時初めて、友人が言った「自分より兄の方がさらに鋭い能力を持っている」という意味を私は理解し始めた。ホームズは私を見て微笑み、マイクロフトは鼈甲の嗅ぎ煙草入れからスナッフを一つまみし、大きな赤い絹のハンカチで上着についた粉を払った。
「ところでシャーロック」と彼は言った。「君の好みにぴったりの奇妙な事件が舞い込んできた。私は例によって本腰を入れて調査する気力がなかったので、ほんのさわり程度しか関われなかったが、なかなか興味深い推理材料にはなった。もし事実を聞きたいなら――」
「ぜひとも聞かせてほしいよ、マイクロフト。」
兄は手帳から一枚ちぎってメモを書き、ベルを鳴らしてウェイターに手渡した。
「ミスター・メラスに来てもらうよう頼んだ。彼は私の階上に下宿していて、多少の面識があるために困り事を打ち明けてくれたのだ。ミスター・メラスはギリシャ系で、非常に優れた語学者だ。主に法廷の通訳や、ノーサンバーランド・アベニューのホテルに滞在する東洋の富豪の案内役として生計を立てている。彼自身の言葉で、驚くべき体験を語ってもらうのがいいだろう。」
数分後、私たちのもとに背が低くずんぐりした男が現れた。オリーブ色の顔と漆黒の髪が南方系の出自を示していたが、話し方は教養あるイギリス人そのものだった。彼はシャーロック・ホームズと熱心に握手を交わし、名探偵が自分の話を聞きたがっていると知ると、暗い目が喜びで輝いた。
「警察は私の話を信じてくれません、本当に」と彼は泣きそうな声で言った。「前例がないというだけで、あり得ないと思っているのです。でも私は、顔に膏薬を貼ったあの可哀想な男の行方が分からない限り、決して心安らぐことはありません。」
「ぜひお話を伺いたい」とシャーロック・ホームズが促した。
「今日は水曜の夜ですね」とメラス氏は話し始めた。「つまり、これが起こったのは一昨日、月曜の夜のことです。私は通訳をしております――恐らく、そちらのご友人から聞かれているでしょう。あらゆる言語――いや、ほぼすべて――を通訳しますが、生まれも名前もギリシャなので、特にギリシャ語の通訳として知られています。長年にわたり、ロンドンでは筆頭のギリシャ語通訳であり、ホテルでは名前もよく知られています。
外国人が困ったときや、遅い時間に到着した旅行者から、奇妙な時間に呼び出されることは珍しいことではありません。だから月曜の夜、ラティマーという非常に洒落た若者が私の部屋に来て、玄関前で待っている馬車に同乗してくれと頼まれても驚きませんでした。彼は、ギリシャ人の友人が商談で訪ねてきたが母国語しか話せないので通訳が必要だ、と説明しました。彼の家はケンジントンに少し離れていると言い、急いでいる様子で、私が通りに出るとすぐに馬車へとせき立てました。
馬車と言いましたが、すぐに疑問を感じました。どうやら普通の四輪馬車より広く、内装は擦り切れていたものの高級な造りでした。ラティマー氏は私の正面に座り、チャリング・クロスとシャフツベリー・アベニューを通って走り出しました。オックスフォード・ストリートに出たとき、『ケンジントンへしては回り道ですね』と話しかけかけたところ、突然相手の異様な行動に言葉を失いました。
彼はまず、鉛を仕込んだ非常に恐ろしい棍棒をポケットから取り出し、何度も振って重さと強度を確かめるような仕草をしました。それから無言でそれを隣の座席に置き、さらに両側の窓を引き上げました。よく見ると、窓は紙で目隠しされており、外が一切見えません。
『景色を遮ってしまい申し訳ない、メラスさん』と彼は言いました。『実は、どこに向かっているのかを見せるつもりはないのです。万一、また来られては困りますからね。』
ご想像の通り、私はあまりのことに呆然としました。相手は頑強で肩幅の広い若者で、たとえ武器がなくても、力ずくで抵抗しても勝ち目はありませんでした。
『これは異常な行為ですよ、ラティマーさん』と私はどもりながら抗議しました。『今あなたがしていることは違法だと分かっているはずです。』
『確かに無茶かもしれませんが、きちんと埋め合わせはしますよ。ただし、今夜少しでも騒ぎを起こしたり、私の利益に反することをすれば、厳しい目に遭うと心得てください。誰もあなたがどこにいるか知らないのです。馬車の中でも家の中でも、あなたは私の手の中です。』
口調は静かでしたが、擦れた声の調子が非常に脅迫的でした。私は沈黙し、この異様な拉致の理由は何なのか考え続けました。いかなる理由にせよ、抵抗しても無駄で、成り行きを見守るしかないのは明らかでした。
ほぼ二時間、行き先の手がかりもないまま馬車は走り続けました。石畳の音がする時もあれば、滑らかで静かな舗装道路を走る感覚もありましたが、その音の違い以外、どこを走っているのか想像するすべさえありません。窓の紙は光も通さず、前方のガラス窓にも青いカーテンがかかっていました。パル・マルを出たのが七時十五分、時計を見ると到着は八時五十分でした。同行者が窓を下ろすと、ランプが灯る低いアーチ状の戸口が一瞬見えました。馬車から急かされて下りると、ぼんやりとした印象ながら、芝生や木立が両脇にあった気がします。そこが私有地か、純然たる田舎なのか、私には見当もつきませんでした。
中に入ると、色の付いたガス灯が弱く灯されており、ホールは広く絵が飾ってあるのがうっすら見えました。扉を開けたのは、背が低く、貧相で猫背の中年男でした。振り返ると、眼鏡をかけているのが明かりの中で分かりました。
『この人がメラスさんか、ハロルド?』と彼は言いました。
『そうです。』
『よく来てくれた、実に助かった! 恨みはないでしょうが、あなたなしでは進まなかった。正直に協力してくれれば損はさせませんが、何か悪巧みをしたら――神の御加護を祈ることです!』
彼は神経質にぶつ切りの口調で、時折クスクス笑いを挟みましたが、なぜか先ほどの男よりも強い恐怖を感じさせました。
『私に何の用があるのです?』
『ギリシャ人の紳士にいくつか質問して、その答えを伝えてもらうだけ。しかし言われた以上のことは言わないように――さもないと……』再び神経質な笑いが漏れた。『生まれてこなければよかったと思うことになりますよ。』
そう言いながら男は扉を開いて、贅沢な部屋に案内しましたが、またもや照明はランプ一つが半分消されているだけ。部屋は広く、足が絨毯に沈み込む感じからもその豪奢さが分かりました。ビロードの椅子、白い大理石の高いマントルピース、脇には日本の甲冑らしきものまで見えました。ランプの下に椅子があり、年配の男がそこに座るよう指示しました。若い男は一度いなくなりましたが、すぐ別の扉から戻り、ガウン姿の紳士を連れてきました。その人が薄暗い光の中に入ると、私はあまりの姿に戦慄しました。死人のように青白くやつれ果て、目だけが異様な輝きと突出ぶりで、明らかに気力はあっても体力は尽きているのが分かりました。だが何より衝撃的だったのは、顔中に膏薬が縦横に貼られ、口元には大きなパッドが固定されていたことです。
『石板はあるか、ハロルド?』老人が叫び、その奇妙な男が椅子に崩れ落ちるように座ると続けた。『手は自由か? さあ、鉛筆を渡せ。質問はメラスさんがするんだ。彼が答えを書く。まず、書類に署名するつもりがあるかどうか尋ねてくれ。』
男の目は怒りに燃えた。
『絶対にしない!』とギリシャ語で石板に書いた。
『いかなる条件でもか?』私は主人に促されて尋ねた。
『自分の知るギリシャ正教の神父がその場で彼女と結婚させてくれるならばのみ。』
老人は毒々しく笑った。
『それでどうなるか分かっているだろう?』
『自分のことなどどうでもいい。』
こうして、奇妙な半分口頭、半分筆談のやり取りが続いた。何度も書類に応じるか問わされ、何度も憤然とした否定を聞かされた。しかしやがて私は機転を利かせ、最初は無害な一文を質問に付け加え、相手が気付くか試し、無反応なのを見てもっと危険な仕掛けに出た。やり取りはこうだった。
『この頑なさで事態は好転しません。――あなたは誰です? 』
『関係ない。――私はロンドンのよそ者です。』
『自分の運命は自分のせいになりますよ。――ここに来てどのくらいですか? 』
『それで構わない。――三週間。』
『財産はあなたのものにはなりませんよ。――何か病気ですか? 』
『悪党どもには渡さない。――飢えさせられている。』
『署名すれば自由の身にします。――ここは何という家ですか? 』
『決して署名しない。――知らない。』
『彼女のためにもなりませんよ。――あなたの名前は? 』
『彼女の口から聞きたい。――クラティデス。』
『署名すれば彼女に会えますよ。――どこの出身ですか? 』
『それなら二度と会えない。――アテネ。』
あと五分もあれば、この連中の目の前で真相を引き出せたかもしれません。次の質問で決定的なことが聞き出せたかもしれなかったのです。だが、その瞬間ドアが開き、一人の女性が部屋へ入ってきました。はっきり見えませんでしたが、背が高く優雅な黒髪の女性で、白いガウンのようなものをまとっていました。
『ハロルド』と彼女は片言の英語で言いました。『もう我慢できなかった。あの――ああ、神様、ポール!』
最後の言葉はギリシャ語でした。同時に男は激しい力で口元の膏薬をはぎ取り、『ソフィー! ソフィー!』と叫びながら女性の腕に飛び込みました。だが抱擁は一瞬で、若い男が女性を引き離し、年配の男はやせ衰えた犠牲者をあっさり引きずって別のドアへ消えました。一時私は一人部屋に残され、何とかこの家の正体を探ろうと立ち上がりました。だが幸い一歩も動かぬうちに、年配の男が戸口に立ち、じっと私を見ていました。
『もう十分です、メラスさん』と彼は言いました。『あなたを極秘の事情に巻き込んだのです。我々も本当はご足労いただきたくなかったのですが、ギリシャ語で交渉していた友人が東方へ帰らざるを得なくなりました。あなたの評判を聞きつけ、代役をお願いしたという次第です。』
私は黙礼した。
『ここに五ポンド金貨があります』と歩み寄りながら男は言いました。『これで謝礼になればよいのですが。ただし――』そう言って胸を軽く叩き、ニヤリと笑って続けた。『この件について一言でも他人に話したら――たとえ一人でもですよ――そのときは、神があなたの魂に憐れみを与えてくださるように!』
この外見の取るに足りない男が私に与えた嫌悪と恐怖は言葉にできません。今やランプの光の下、彼の顔立ちは尖って黄ばんでおり、ひょろひょろとしたあご髭はみすぼらしかった。顔を突き出し、唇やまぶたは常にピクピクと痙攣し、舞踏病の患者のようでした。あの妙に引っかかるような小さな笑い声も、何か神経症の兆候ではないかと思わずにいられません。しかし彼の顔で最も恐ろしいのは目でした。鋼のような灰色が冷たく光り、奥底にはどうしようもなく冷酷な残虐さが潜んでいたのです。
「『この件について口外すればどうなるか、わかっているだろう』と彼は言った。『われわれには独自の情報網がある。さあ、馬車が待っている。私の友人が君を送り届けてくれるだろう。』
私は慌ただしくホールを通されて馬車に乗せられ、再び一瞬だけ木立と庭園を目にすることができた。ラティマー氏が私のすぐ後ろに続き、無言で私の正面に腰を下ろした。私たちは再び、果てしなく長い距離を無言のまま、窓を閉め切ったまま走った。やがて真夜中を少し過ぎたころ、ついに馬車は止まった。
『ここで降りてもらう、メラスさん』と同行者が言った。『ご自宅から遠くて申し訳ないが、他に手がない。馬車を追いかけようとすれば、君が危険な目に遭うだけだ。』
そう言いながらドアを開けたその瞬間、私が飛び降りるや否や、御者は馬に鞭を入れ、馬車はがらがらと走り去ってしまった。私は周囲を見回し、呆然とした。そこは、ところどころに暗いハリエニシダの茂みが点在する、荒れた原野のような場所だった。遠くには家々の並びがあり、上階の窓にぽつぽつと明かりがともっていた。反対側には鉄道の赤い信号灯が見えた。
私を運んできた馬車は、すでに姿を消していた。私は立ち尽くし、いったいここはどこなのだろうかと思案していると、暗がりの中から誰かがこちらへ近づいてくるのが見えた。近づいてきたのは鉄道のポーターだとわかった。
「ここは何という場所ですか?」と私は尋ねた。
「ワンズワース・コモンです」と彼は答えた。
「町へ出る列車に乗れますか?」
「マイルほど歩いてクラッパム・ジャンクションまで行けば、ちょうどヴィクトリア行きの最終列車に間に合いますよ」と彼は言った。
こうして、私の冒険は終わったのだ、ホームズさん。私はどこにいたのかも、誰と話したのかも、何一つわからない。ただ、今お話ししたこと以外は何も知らない。ただ確かなのは、ここで何らかの悪事が行われているということ、そしてあの哀れな男を助けたいという思いだけだ。翌朝、私はこの一部始終をマイクロフト・ホームズ氏に話し、その後で警察にも報告した。」
この異様な話を聞き終えた後、私たちはしばらく沈黙して座っていた。やがてシャーロックは兄の方を見て尋ねた。
「何か手は打ったか?」
マイクロフトはサイドテーブルに置かれていた『デイリー・ニュース』紙を手に取った。
「『アテネ出身のギリシャ人、ポール・クラティデス氏の行方について情報を提供してくれた方には謝礼を支払う。英語を話せない。ギリシャ人女性でファーストネームがソフィーの方の情報にも同様の謝礼を支払う。X2473』。これは全ての新聞に載せたが、返答はない。」
「ギリシャ公使館には?」
「問い合わせたが、何も知らないそうだ。」
「アテネ警察本部宛てに電報は?」
「シャーロックは家族の中でも一番精力的だな」とマイクロフトは私に向かって言った。「まあ、君がこの事件を引き受けてくれるなら、何か進展があれば教えてくれ。」
「もちろんだ」友人は椅子から立ち上がりながら答えた。「君にも、メラスさんにも知らせるよ。その間、メラスさん、私が君の立場なら、警戒しておくべきだろう。彼らはこの新聞広告で、君が裏切ったことを知っているはずだからね。」
帰り道、ホームズは電報局に立ち寄り、いくつか電報を打った。
「見ただろう、ワトソン。今夜は決して無駄ではなかった。私の興味深い事件の多くは、このようにマイクロフト経由でやって来る。今聞いた事件も、一つの説明しかありえないとはいえ、興味深い点がいくつもある。」
「解決の見込みはあるのか?」
「ここまで分かっていれば、残りを突き止められなければ不思議だ。君自身も、今聞いた事実を説明するための仮説を立てているはずだ。」
「漠然とだが、ある。」
「どんな仮説だ?」
「このギリシャ人の娘は、ハロルド・ラティマーという若いイギリス人に連れ去られたのだと思う。」
「どこから連れ去られた?」
「アテネ、かもしれない。」
シャーロック・ホームズは首を振った。「この若者はギリシャ語が全く話せない。だが、あの女性は英語をかなり話せた。つまり、彼女はある程度の期間イギリスにいたが、彼はギリシャに滞在したことがないということになる。」
「では、彼女がイギリスに遊びに来ていて、ハロルドが彼女を口説いて駆け落ちさせたのだろう。」
「それがもっともらしい。」
「それで兄――私はそういう関係だろうと思うが――がギリシャからやってきて口を挟もうとした。軽率にも、兄は若者とその仲間の力の及ぶところに自ら身を置いてしまい、彼らは兄を捕えて暴力をふるい、何か文書、もしかすると妹の財産を譲渡する書類に署名させようとした。兄はこれを拒否した。そこで彼らは通訳を雇う必要があり、以前別の通訳を使ってから、今度はメラス氏を選んだ。娘には兄の到着を隠していたが、偶然それが露見した。」
「すばらしい、ワトソン!」とホームズが叫んだ。「君は真相にかなり近いと思う。われわれはすべての切り札を持っている。あとは彼らの突然の暴挙だけが怖い。もし時間をくれれば、必ず捕まえられるはずだ。」
「だが、その家がどこにあるかは、どうやって見つける?」
「もし推測通り、あの娘の名がソフィー・クラティデス、あるいはその旧姓なら、彼女を追跡するのは容易だ。それが最大の望みだ。兄はまったくの異邦人だからな。ハロルドが彼女と関係を持ち始めてから、ある程度の時間が経っているはずだ。なぜなら、ギリシャにいる兄が事件を聞きつけてイギリスに来るまでに、少なくとも数週間はかかる。その間、彼らが同じ場所に住んでいたなら、マイクロフトの広告に何かしら返事があるだろう。」
話しながら私たちはベイカー街の自宅に着いた。ホームズが先に階段を上り、部屋のドアを開けると、驚いたように足を止めた。私も後ろから覗き込み、同じく驚いた。兄のマイクロフトが肘掛け椅子に腰かけ、煙草をふかしていたのだ。
「入れ、シャーロック! どうぞ、先生」彼はにこやかに、われわれの驚いた顔を眺めて言った。「私にこんなに行動力があるとは、思っていなかっただろう? だが、なぜかこの事件は私を惹きつけるのだ。」
「どうやってここに?」
「馬車で君たちを追い抜いた。」
「何か新展開が?」
「広告に返事が来た。」
「ほう!」
「君たちが出てすぐに届いたのだ。」
「その内容は?」
マイクロフト・ホームズは一枚の紙を取り出した。
「これだ」と彼は言った。「J字型のペンで、ロイヤルクリームの便箋を使い、体が弱そうな中年男性が書いている。『拝啓、本日付のご広告を拝見し、ご質問の若い女性をよく存じております。ご希望でしたら、彼女の悲しい過去についていくつかご説明できるかと存じます。現在、ベッケナムのザ・マートルズに住んでおります。敬具 J・ダヴェンポート』。
『ロウアー・ブリクストンから投函されている』とマイクロフト・ホームズが言う。「シャーロック、今から彼に会いに行って、詳しい話を聞いてみたらどうだ?」
「兄の命の方が、妹の過去よりも重要だ。まずスコットランド・ヤードでグレグスン警部を呼び、すぐにベッケナムへ向かうべきだ。男が殺されようとしている以上、一刻を争う。」
「途中でメラス氏も拾った方がいい」と私が提案した。「通訳が必要かもしれない。」
「素晴らしい」とシャーロック・ホームズは言った。「少年を呼んで四輪馬車を頼んでくれ。すぐに出発だ。」そう言ってテーブルの引き出しを開け、彼はさりげなくリボルバーをポケットに忍ばせた。「うん」と私の視線に応えて言った。「今聞いた話からすると、相当危険な連中を相手にしているようだ。」
パル・マルのメラス氏の部屋へ着いた時には、すでにほとんど暗くなっていた。ちょうど紳士が訪ねてきて、彼は出かけてしまった。
「どちらへ行ったか、ご存じですか?」とマイクロフト・ホームズが尋ねた。
「存じません、先生」とドアを開けた女性が答えた。「ただ、その紳士とご一緒に馬車で出て行かれました。」
「その紳士は名前を名乗りましたか?」
「いいえ、先生。」
「背が高く、ハンサムで髪の黒い若い男でしたか?」
「いえ、先生。小柄で眼鏡をかけて顔色の悪い紳士でしたが、とても愛想の良い方で、話している間ずっと笑っていらっしゃいました。」
「行こう!」とシャーロック・ホームズが突然叫んだ。「これは事態が深刻になってきた」と、スコットランド・ヤードへ向かう馬車の中で言った。「やつらはまたメラスを捕まえた。彼は、あの夜の経験からして、身体的な勇気に欠ける男だと十分に知っている。あのいかれた悪党は、目の前に現れた瞬間、彼を脅しつけることができた。おそらく今度も通訳として使うつもりだろうが、利用が済めば、裏切り者と見なして報復するかもしれない。」
われわれの望みは、電車を使うことで、馬車よりも早くベッケナムに着けるかもしれないということだった。しかしスコットランド・ヤードでは、グレグスン警部を呼び、家宅捜索のための法的手続きを済ませるのに一時間以上かかった。ロンドンブリッジ駅に着いたのは九時四十五分、そこからベッケナムのプラットフォームに降り立ったのは九時半過ぎだった。そこから半マイル馬車で走り、ザ・マートルズ――通りから引っ込んだ敷地内に建つ大きな暗い家――に到着した。ここで馬車を降ろし、みんなで屋敷の車道を歩いていった。
「窓は全部真っ暗だ」と警部が言った。「人気がないようだな。」
「鳥は飛び去って、巣は空っぽだ」とホームズが言った。
「なぜそう思う?」
「この一時間の間に、荷物を山ほど積んだ馬車が出て行った形跡がある。」
警部は笑った。「門灯の光で車輪の跡は見たが、荷物とは?」
「同じ車輪の跡が逆方向にもあったはずだ。ただ、出て行った時の方がずっと深い――つまり、馬車にかなりの重量の荷が積まれていたことは確かだ。」
「そこまで観察できないよ」警部は肩をすくめた。「ドアをこじ開けるのは簡単じゃないが、中に人がいれば気づくだろ。」
彼はドアノッカーを激しく叩き、ベルを引いたが、反応はなかった。ホームズはいつの間にか姿を消していたが、数分で戻ってきた。
「窓が開いている」と彼が言った。
「あなたが警察側でよかったですよ、ホームズさん」と警部は、巧妙に掛け金を外した様子を見て感心した。「これなら招待なしに入っても問題ないでしょう。」
私たちは一人ずつ、明らかにメラス氏がいたという広間に入った。警部がランタンを灯すと、二つのドア、カーテン、ランプ、日本の鎧が彼の描写通りにあった。テーブルにはグラスが二つ、空のブランデー瓶、食事の残りが置かれていた。
「待て、あれは何だ?」とホームズが突然言った。
私たちは全員、動きを止めて耳を澄ませた。どこか頭上から、低いうめき声が聞こえてきた。ホームズはドアに駆け寄り、廊下へ飛び出した。おぞましい音は二階からだ。彼は階段を駆け上り、私と警部がその後に続き、マイクロフトも巨体を揺らしながらできる限り速くついてきた。
二階には三つのドアがあり、その中央から不吉な音が漏れ出していた。時に鈍いうなりとなり、時に鋭い悲鳴へと変化する。そのドアは鍵がかかっていたが、鍵は外側に刺さっていた。ホームズはドアを開け放ち、駆け込んだが、すぐに喉を押さえて飛び出してきた。
「木炭の煙だ。少し待て、すぐに空気が入れ替わる。」
中を覗き込むと、部屋の唯一の明かりは、中央の真鍮製三脚の上で揺らめく鈍い青い炎だけだった。床に不気味な円を作り、奥の影には壁際にしゃがみ込んだ二つの人影がぼんやりと見えた。開いたドアからは、むせ返るほどの有毒なガスが漂い、私たちは咳き込みながら後ずさった。ホームズは新鮮な空気を吸い込むため階段の上に駆け上がり、すぐさま戻ってきて窓を開け、真鍮の三脚ごと庭へ投げ捨てた。
「あと一分で入れる」と彼は息を切らしながら言った。「ろうそくはどこだ? あの空気ではマッチは擦れまい。ドアのところで明かりを持て、マイクロフト、行くぞ!」
私たちは急いで毒ガスに倒れている男たちを引きずり出し、明るいホールに運んだ。二人とも唇は青く、意識はなく、顔は腫れて充血し、目は飛び出していた。その変わり果てた顔つきは、もしも黒いあごひげと太めの体つきがなければ、数時間前にダイオゲネス・クラブで別れたギリシャ人通訳だと分からなかっただろう。手足はしっかり縛られ、片方の目の上には強打の痕があった。もう一人は同様に縛られた、やせこけた長身の男で、顔にいくつもの絆創膏が奇妙な模様に貼られていた。彼はもううめき声をあげておらず、ひと目見て私には、彼にはすでに手遅れだと分かった。だがメラス氏はまだ生きており、私はアンモニアとブランデーで彼を蘇生させ、一時間もたたぬうちに、彼が目を開けた時、私の手が死の淵から彼を引き戻したのだと知ることができた。
彼の語った話は簡潔で、私たちの推理を裏づけるものだった。部屋に入ってきた訪問者は袖から警棒を抜き出し、今まさに殺されるという恐怖で彼を再び誘拐した。その男の笑い混じりの不気味な威圧は、ほとんど催眠術のようで、メラス氏は震える手と青ざめた頬で語ることしかできなかった。彼はベッケナムまで素早く連れていかれ、さらに劇的な第二回の尋問の場で通訳をさせられた。そこでは二人のイギリス人が、彼が要求を呑まなければ今すぐ殺すと脅した。だが、どんな脅しも通じないと知ると、彼らは彼を監禁室に投げ戻し、新聞広告で裏切りが発覚したとしてメラス氏を非難し、棒で殴って気を失わせた。彼はそれからの記憶がなく、気がついた時には私たちが見下ろしていたという。
かくして「ギリシャ語通訳事件」は終わったが、説明にはいまだ謎が残されている。広告に返事をくれた紳士の証言で分かったのは、不幸な若い女性は裕福なギリシャの家の出身で、イギリスの知人宅を訪れていたこと、その滞在中にハロルド・ラティマーという若者と知り合い、彼に支配されて駆け落ちに至ったことだった。友人たちはその出来事に衝撃を受け、彼女の兄にアテネで知らせたが、その後は手を引いたという。兄はイギリスに到着後、軽率にもラティマーとその共犯者ウィルソン・ケンプ――最悪の経歴を持つ男――の支配下に入り、言葉が通じぬために無力となり監禁された。彼らは拷問と飢えで彼に自分と妹の財産の権利放棄を強要した。兄は家に閉じ込められ、妹には存在を隠されていた。顔中の絆創膏は、もし彼女が偶然見かけても兄だと気づかせぬためだった。だが、女性特有の鋭さで、彼女は通訳が来た時に一目で兄だと見抜いた。とはいえ、彼女自身も監禁されており、家には御者とその妻しかおらず、どちらも共犯者の手先だった。秘密が漏れ、兄も屈しないと分かると、二人の悪党と彼女は、数時間で借り家を引き払って逃亡した。その前に、抵抗した男と裏切った男に復讐したつもりだったのだ。
数か月後、ブダペストから奇妙な新聞の切り抜きが届いた。それには、女を連れた二人のイギリス人が悲劇的な最期を遂げたこと、互いに刺し合って絶命したと現地警察が考えていることが書かれていた。しかしホームズは、今も異なる見解を持っており、もしギリシャ人女性の行方が分かれば、彼女と兄がどのようにして報復を成し遂げたかが分かるだろうと考えている。
XI. 海軍条約
私が結婚した直後の7月は、シャーロック・ホームズと共に関わり、その手法を観察する機会を得た興味深い三つの事件によって、記憶に残るものとなった。私はこれらの事件を「第二の汚点の冒険」「海軍協定の冒険」「疲れた船長の冒険」という見出しでノートに記録している。ただし、このうち最初の事件は、その重要性が極めて高く、王国の有力な家門を多数巻き込んでいるため、長年にわたり公表することはできないだろう。しかし、ホームズが関与したどの事件よりも、彼の分析的手法の価値をこれほど明確に示し、また関係者たちに深い印象を与えた例はなかった。私はいまだに、彼がパリ警察のデュビュク氏と、ダンツィヒの著名な専門家フリッツ・フォン・ヴァルトバウムに事件の真相を説明した際の面談記録を、ほぼ逐語的に手元に残している。両名は、後に枝葉に過ぎぬと判明した点に精力を費やしていたのだ。しかし、この物語が安全に語られるまでには、世紀が変わるのを待たねばならないだろう。それまでの間、私は二件目、つまり以前は国家的重要性を持つかもしれないと考えられ、いくつかの特異な出来事によって一風変わった性格を帯びた事件へと進むことにする。
学生時代、私はパーシー・フェルプスという名の少年と親しくしていた。彼は私とほぼ同じ年齢だが、二学年上だった。非常に秀才であり、学校の賞はすべて彼がさらい、ついには特待生としてケンブリッジへと進み、輝かしい経歴を続けていた。よく覚えているが、彼は家柄も申し分なく、私たちがまだ幼かった頃から、彼の母の兄が偉大な保守党政治家であるホールドハースト卿であることを知っていた。しかし、この派手な親類関係は、学校では彼にとってほとんど益にはならなかった。むしろ、私たちにとっては、彼を校庭で追い掛け回し、ゲートボールのスティックで脛を叩くのが面白いくらいだった。しかし、社会に出てからは様子が違った。私は彼がその能力と影響力によって外務省で良い地位を得たと漠然と聞いていたが、その後彼のことはすっかり頭から消えていた。そんな折、以下の手紙が彼の存在を思い出させてくれたのである。
ブライアーブレー、ウォッキング
突然、恐ろしい不幸が私の人生を打ち砕いた。
親愛なるワトソン、―― きっと君は「オタマジャクシ」フェルプスのことを覚えているだろう、君が三年生のとき、私が五年生だった。叔父の力添えもあって外務省で良い職を得たこと、信頼と名誉ある立場にいたことを、君も噂で耳にしていたかもしれない。その恐ろしい出来事の詳細については書いても無駄だろう。もし君がこの頼みを聞き入れてくれるなら、そのとき改めて事情を説明することになるかもしれない。私は九週間もの脳炎からようやく回復したばかりで、今もひどく弱っている。君の友人ホームズ氏を連れてきてくれないだろうか。事件について、彼の意見をぜひ聞きたい。関係当局はこれ以上できることはないと言っているが、君には何とかして連れてきてもらいたい。一刻も早く来てほしい。こんな恐ろしい不安の中では、一分一分が一時間のように感じる。もしこれまで助言を求めなかったとしたら、それは彼の才能を評価していなかったからではなく、あの衝撃以来、私は正気を失っていたからだと伝えてほしい。今は頭もはっきりしているが、再発を恐れて、あまり考えないようにしている。あまりにも弱っているので、見ての通り口述筆記で手紙を書いている。何とか連れてきてほしい。
君の古き学友
パーシー・フェルプス
私はこの手紙を読んでいるうちに、心を打たれるものを感じた。ホームズを連れてきてほしいという繰り返しの訴えには、哀れさすら漂っていた。もしどんなに難しいことであっても、私はきっと努力しただろうが、もちろんホームズがその芸術を愛することはよく知っていたので、彼は依頼人が望むのと同じくらい、喜んで力を貸してくれるだろうと確信していた。妻も一刻も早くホームズに話すべきだと賛成してくれたので、私は朝食後一時間も経たぬうちに、ベイカー街の古い部屋へと戻っていた。
ホームズはガウン姿でサイドテーブルに腰かけ、化学の実験に精を出していた。大きな曲がったレトルトが、バーナーの青い炎の上で激しく沸騰し、蒸留された液が二リットルの計量器にたまっていた。私が入室しても、友人はほとんど顔を上げなかった。私は彼の実験が重要なものであると見て取り、安楽椅子に座って静かに待つことにした。彼は瓶から瓶へと少量の液体をガラスピペットで吸い取り、最後にある試験管をテーブルに持ってきた。手にはリトマス紙がある。
「ちょうどいいところに来たな、ワトソン」と彼は言った。「この紙が青いままなら問題ない。赤く変われば――それは人の生死を意味する」彼はそれを試験管に浸し、紙はすぐに鈍く汚れた赤色に変わった。「ふむ、やはりな!」と声を上げる。「すぐ用意する、ワトソン。ペルシャ製のスリッパの中にタバコがある」彼は机に向き直り、数通の電報を書いて小使いに渡した。その後、私の向かいの椅子に深く腰を下ろし、長い細い膝を両手で抱え込むようにした。
「ごくありふれた殺人事件だ」と彼は言った。「君はもっと面白いものを持ってきたのだろう。君は犯罪界の嵐を呼ぶ鳥だな、ワトソン。何だ?」
私は手紙を手渡した。ホームズは目を凝らして読み、私に返しながら言った。
「多くは語っていないな」
「ほとんど何も」
「だが、筆跡が興味深い」
「けれど、これは本人の字じゃない」
「その通り。女性の手だ」
「いや、男性のはずだ」と私は叫んだ。
「違う、女性だ。それも並外れた人物だ。捜査の初めに、依頼人が善かれ悪しかれ、特別な気質を持つ誰かと密接な関係にあると分かることは重要だ。もう興味が湧いた。準備ができているなら、すぐウォッキングへ向かおう。君の友人の外交官と、彼に手紙を口述筆記させる女性に会うために」
幸運にも私たちはウォータールー駅から早い列車に乗ることができ、1時間足らずでウォッキングの松林とヒースの中へ着いた。ブライアーブレーは、駅から数分の敷地内に独立して建つ大きな屋敷だった。名刺を通すと、上品に調度された応接間へと通され、数分後、やや太めの男がにこやかに私たちを迎え入れた。年齢は三十より四十に近いかもしれないが、頬は赤く、瞳はいたずらっぽく輝いていて、ぽっちゃりしたやんちゃ坊主のような印象を与えた。
「来てくださって本当に嬉しい」と彼は私たちの手を熱心に握りながら言った。「パーシーは朝からあなた方のことを尋ねていたよ。ああ、かわいそうに、最後の望みにすがっているんだ。ご両親はあの話題を口にするのも辛いので、代わりに私に会ってくれと頼まれたのです」
「詳しい話はまだ伺っていません」とホームズ。「ご家族の方ではありませんね?」
我々の知人は驚いた様子で、それから自分の胸元を見下ろして笑い出した。
「もちろん、君は私のロケットの“J.H.”のイニシャルに気付いたんだろう」と彼は言った。「一瞬、君が何か見事な推理をしたのかと思ったよ。ジョセフ・ハリソン、それが私の名前です。パーシーは私の妹アニーと結婚することになっているから、少なくとも義理の親族にはなる。妹はずっと彼に付き添って看病してきたんだ。すぐに部屋へ案内しましょう。彼はとても待ちきれない様子なので」
案内された部屋は応接間と同じ階で、居間兼寝室となっており、あちこちに可愛らしく花が飾られていた。青ざめてやつれた若者が、窓際のソファに横たわっていた。開け放たれた窓からは庭の豊かな香りと穏やかな夏の空気が流れ込んでいた。女性が彼のそばに座っており、私たちが入ると立ち上がった。
「出ていた方がいい?」と彼女は尋ねた。
彼はその手を握って引き留めた。「やあワトソン」と親しげに声をかけた。「その口ひげじゃ君だとは思わなかったし、君も僕だとは断言できないだろう。こっちが有名なホームズ氏だね?」
私は簡単に紹介し、二人で腰掛けた。太めの若者は部屋を出て行ったが、妹の方は病人の手を握ったまま残っていた。彼女は印象的な容貌の女性で、やや小柄で体格もよかったが、オリーブ色の美しい肌、大きな暗いイタリア風の瞳、そして豊かな黒髪を持っていた。その鮮やかさが隣の白い顔をいっそうやつれて見せていた。
「時間を無駄にするつもりはない」と彼はソファから身を起こして言った。「前置き抜きで本題に入ろう。私は幸せで成功した男だった。結婚を目前に控え、突然の恐ろしい不幸が僕の将来を全て打ち砕いた。
「ワトソンも知っている通り、私は外務省におり、叔父のホールドハースト卿の引き立てで急速に責任ある地位に就いた。叔父が現政権で外務大臣になると、私は何度も重要な任務を任され、すべてを成功させたことで、彼は私の能力と機転を全面的に信頼するようになった。
「今から十週間近く前――正確には五月二十三日のことだ――彼の執務室に呼ばれ、これまでの働きを褒められた後、新たな重要案件を任せると告げられた。
『これがそうだ』と彼は机から灰色の書類束を取り出して言った。『これは英国とイタリアの秘密条約の原本だ。残念なことに、すでにその存在が一部報道されてしまっている。これ以上の漏洩は絶対に避けねばならない。フランスやロシアの大使館がこの内容を知れば莫大な金を払ってでも手に入れようとするだろう。絶対に手元から出すべきものではないが、どうしても写しを作る必要がある。君の執務机はあるな?』
『はい』
『では、この条約を持ち帰り、しっかり机にしまっておけ。他の職員が帰ったら一人残って、誰にも見られる心配なくゆっくり写すといい。終わったら原本も写しも机に施錠し、明朝、直接私に渡すのだ』
「私は書類を受け取り――」
「ちょっと失礼」とホームズ。「その話のとき、あなたは一人だったのか?」
「完全に」
「広い部屋か?」
「縦横それぞれ三十フィートほど」
「部屋の中央で?」
「そうだ」
「小声で話したか?」
「叔父の声はいつも特別低い。私はほとんどしゃべらなかった」
「ありがとう」ホームズは目を閉じて言った。「続けてくれ」
「指示通り、他の職員が去るのを待った。同室のチャールズ・ゴロが仕事の遅れを取り戻す必要があったので、私は彼を残して食事に出かけた。戻ると彼はいなかった。私は急いで仕事を片付けたかった。というのも、先ほどのハリソン氏――ジョセフ――がロンドンにいて、十一時の列車でウォッキングに来る予定だったからだ。できればその列車に間に合いたかった。
「条約を開いてみると、すぐに叔父の言葉が大げさでなかったと分かった。詳細は省くが、それは英国の三国同盟に対する立場を定めたもので、フランス艦隊が地中海でイタリアに対して優位を完全に握った場合、英国がとるべき政策を示唆していた。内容は純粋に海軍に関するもので、末尾には高官たちの署名があった。ざっと目を通し、写し始めた。
「長文のフランス語文書で、全部で二十六条あった。できる限り急いで写したが、九時の時点で九条しか書けておらず、列車に間に合わせるのは絶望的だった。夕食のせいと長い一日に疲れて、眠気が襲ってきていた。コーヒーを飲めば頭が冴える。建物の階下の詰所には、夜通し詰めている伝令がいて、遅くまで働く職員のために酒精ランプでコーヒーを淹れてくれるのが習慣だ。そこで私はベルを鳴らして呼んだ。
「ところが、驚いたことに現れたのは女性で、年かさで顔立ちの荒い大柄なおばさんだった。伝令の妻で掃除を担当しているとのことで、私はコーヒーを頼んだ。
「さらに二条写したが、ますます眠気が強くなり、立ち上がって部屋の中を歩き回った。コーヒーがまだ来ないので、遅れている理由を確かめるため廊下に出た。私が仕事をしていた部屋から伸びる廊下は、薄暗く直線で、出口はそこだけだった。その先には曲がった階段があり、階下の通路に伝令の詰所がある。階段の途中には小さな踊り場があり、そこから直角に別の廊下が分岐している。その先に小さな階段があり、使用人用の脇玄関に通じている。ここはチャールズ通りから来る職員の近道にも使われている。これがその略図だ」
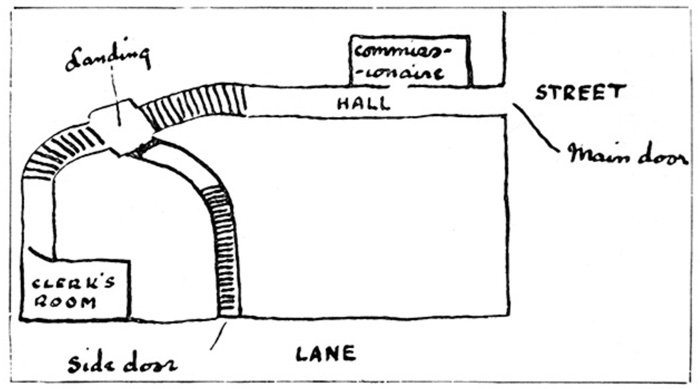
「ありがとう。よく分かった」とシャーロック・ホームズ。
「この点が非常に重要だ。私は階段を下りてホールに出ると、伝令が詰所で深く眠り込んでおり、酒精ランプの上ではやかんが激しく沸騰していた。私はやかんを下ろし、ランプの火を消した。水が床に噴き出していたのだ。そして、彼を揺り起こそうと手を伸ばしたそのとき、頭上のベルが激しく鳴り響き、伝令も驚いて目を覚ました。
『フェルプスさま!』と彼はきょとんとした様子で見上げた。
『コーヒーができたか見に来たんだ』
『やかんを沸かしてるうちにうっかり寝てしまって……』彼は私と、そしてまだ震えているベルを交互に見て、ますます驚いた面持ちだった。
『あなたがここにいるのなら、誰がベルを鳴らしたんでしょう?』
『ベル? どのベルだ?』
『あなたが働いていた部屋のベルですよ』
私は心臓を氷の手で締め付けられるような思いがした。誰かが、机の上に大切な条約があるあの部屋にいるのだ。私は狂ったように階段を駆け上がり通路を走った。しかし、廊下にも部屋にも誰の姿もなかった。机の上だけが違っていた。預けられた書類のうち、写しは残っていたが、原本が消えていたのだ」
ホームズは椅子に座り直し、手をこすり合わせた。彼にとって理想的な難問だったのが分かった。「その後、どうしたのかね?」と彼は静かに言った。
「すぐに、犯人は脇玄関の階段から上がってきたのだと確信した。反対側から来れば、必ず私と行き違うはずだから」
「犯人が部屋や先ほど話した薄暗い廊下にずっと隠れていた可能性は否定できるか?」
「絶対に不可能だ。ネズミ一匹も隠れられない。隠れ場所が全くないんだ」
「ありがとう。続けてくれ」
「伝令も私の蒼白な顔を見て異変を察し、私と共に階上へ駆け戻った。二人で廊下を走り、チャールズ通りに続く急な階段を下りた。下の扉は閉まっていたが、鍵はかかっていなかった。私たちは扉を開けて外へ飛び出した。はっきり覚えているが、そのとき近くの時計が三回鳴った。午後九時四十五分だった」
「それは非常に重要だ」とホームズはシャツの袖口にメモを書きながら言った。
「夜はとても暗く、温かい小雨が降っていた。チャールズ通りには誰もいなかったが、奥のホワイトホール通りではいつも通り賑やかだった。私たちは帽子も被らず歩道を走り抜け、角で警官を見つけた。
『盗難があった!』と私は息を切らして叫んだ。『外務省から極めて重要な書類が盗まれた。誰かここを通ったか?』
『私は十五分ずっとここに立っています』と巡査は言った。『その間に通ったのはたった一人――背の高い年配の女性で、ペイズリーのショールを羽織っていました』
『それは私の妻です』と伝令が叫んだ。『他には誰も?』
『いません』
『なら犯人はもう一方の道を使ったに違いない』と伝令は私の袖を引いた。
『だが私は納得できなかったし、彼が私を引き離そうとする態度も疑念を深めた。
『その女性はどちらへ行った?』
『分かりません。ただ通ったのは見ましたが、特に注意していなかったので。急いでいたようです』
『いつごろ通りましたか?』
『それほど前ではありません』
『ここ五分以内か?』
『ええ、五分も経っていません』
「『お時間の無駄ですよ、旦那。今は一分一秒が大事なんです』と、守衛が叫んだ。『私の家内が関わっているなんてことは絶対にありませんから、通りの反対側まで来てください。まあ、来ないというなら、私だけでも行きますよ』そう言うや否や、彼は反対方向に駆け出した。
だが、私はすぐにその後を追い、彼の袖をつかんだ。
『どこに住んでいる?』と私は尋ねた。
『ブリクストンのアイヴィ・レーン16番地です。でもね、フェルプスさん、間違った手がかりに引きずられないでください。通りの向こう側に行って、何か手がかりがないか探しましょう』
彼の助言に従っても失うものは何もなかった。私たちは警官とともに急いで通りを下ったが、そこは人通りが多く、行き交う人々はみなこの雨の夜に少しでも早く安全な場所にたどり着きたがっている様子だった。誰が通り過ぎたかを教えてくれるような暇な人間はひとりもいなかった。
それから私たちは再び事務所に戻り、階段や通路を調べたが、結果は得られなかった。部屋へと続く廊下には、クリーム色のリノリウムが敷かれていて、足跡がつきやすいのだが、念入りに調べても何の痕跡も見つからなかった。」
「夜のあいだ、ずっと雨が降っていたのか?」
「七時ごろから降り出した。」
「では、なぜ九時ごろ部屋に入った女性が、泥だらけの靴で跡を残していなかったのだ?」
「その点については、あなたが指摘してくれてありがたい。当時も気になっていた。掃除婦たちはいつも守衛の詰め所で靴を脱ぎ、フェルトのスリッパに履き替えているのだ。」
「それなら納得できる。つまり、夜は雨だったが、足跡は残らなかったのだな? 出来事の流れは確かに非常に興味深い。次はどうした?」
「部屋も調べた。隠し扉がある可能性はなく、窓も地面から九メートル以上高い。しかもどちらもしっかり内側から施錠されている。カーペットが敷かれていて、床下扉の仕掛けも不可能だ。天井は普通の漆喰塗りだ。私の書類を盗んだ者が入れたのは、ドアからだけだと断言できる。」
「暖炉は?」
「使われていない。ストーブしかない。ベルの紐は机のすぐ右に垂れている。ベルを鳴らした者は、机のすぐそばまで来なければならない。だが、なぜ犯人がわざわざベルを鳴らす必要があったのか? まったく理解不能だ。」
「確かに異例の事件だ。次に取った行動は? 部屋の中を調べて、侵入者が何か痕跡――たばこの吸い殻や落とした手袋、ヘアピンなど、小物を残していないか探したのだろう?」
「そういったものは一切なかった。」
「臭いは?」
「そこまでは考えが及ばなかった。」
「たばこの匂いでもあれば、調査で大いに役立ったのだが。」
「私はたばこを一切吸わないので、もしあればすぐ気づいたはずだ。匂いも手がかりもまったくなかった。唯一現実的な事実は、守衛の妻――タンジー夫人が急いでその場を出て行ったということだけだ。夫も、彼女がいつも帰る時間だったとしか説明できなかった。警官と私は、もし彼女が書類を持ち出していたのなら、処分される前に確保するのが最善策だと考えた。
この頃には警察本部に警報が伝わり、刑事のフォーブズ氏がすぐ事件を引き継いだ。ハンサム馬車を雇い、三十分ほどで教えられた住所に着いた。ドアを開けたのはタンジー夫人の長女だった。母親はまだ帰っておらず、私たちは居間で待たされた。
十分ほどして、ノックの音がした。そこで私は唯一、自分で自分を責める大きな過ちを犯した。ドアを私たち自身で開ければよかったのだが、娘に任せてしまった。娘の『お母さん、家に男の人が二人待ってるわ』という声が聞こえ、直後に誰かが廊下を駆け抜ける足音がした。フォーブズがドアを開け放つと、私たちは奥の部屋――台所に駆け込んだが、すでにその女性はそこにいた。彼女は挑戦的な目でこちらを見つめ、私の顔に気づくと、驚愕の表情に変わった。
『なんだ、事務所のフェルプスさんじゃないか!』と彼女は叫んだ。
『なあ、君は僕たちを誰だと思って逃げたんだ?』と私の連れが尋ねた。
『差し押さえの業者かと思ったのさ。ちょっと商売のことで揉めててね』
『それは少し都合が良すぎるな』とフォーブズが答えた。『君が外務省の重要書類を持ち出し、ここに処分しに来たと我々は疑っている。スコットランド・ヤードに同行して身体検査してもらうぞ』
彼女は必死に否定し、抵抗したが無駄だった。四輪馬車を呼んで、三人で乗り込んだ。まず台所、とくに火を使った形跡がないか調べたが、灰や紙片など何も見つからなかった。スコットランド・ヤードに着くと、すぐ女性係官に引き渡した。私は結果を固唾を呑んで待ったが、何の手がかりも得られなかった。
そこで初めて、自分の立場に対する恐怖が全身を襲った。それまでは動き回ることで思考が麻痺していたし、書類をすぐ取り戻せると信じていたから、失敗した時の結果までは敢えて考えないようにしていた。だが、もはやなす術はなく、身の上を冷静に自覚する余裕ができてしまった。悪夢のようだった。ホームズさん、ワトソンならお分かりだろうが、私は学校時代から神経質で繊細な性分だ。それが私の本質なのだ。私は叔父や内閣の同僚たち、自分が彼らや家族、関係者全員に与えた恥辱のことを思った。自分は不可抗力の被害者だったとしても、外交問題では事故が考慮されることはない。私は破滅した。恥ずべき、希望のない破滅だった。自分がどうしたのかも覚えていない。騒ぎを起こしたのだろう。ぼんやりと、役人たちが私に群がり、なだめてくれる場面だけが記憶に残っている。一人がウォータールー駅まで付き添い、ウォーキング行きの列車に乗せてくれた。もし家の近くに住んでいるフェリエ医師が同じ列車でなかったら、最後まで付き添ってくれたかもしれない。医師は親切にも私の世話をしてくれ、駅で発作を起こし、家に着く前にはほとんど狂人同然になっていた。
この家の者たちが医師の呼び鈴で起こされ、私の異常な姿を見てどれほど驚愕したか、想像できるだろう。アニーや母は悲嘆にくれた。フェリエ医師は駅で刑事から簡単な事情を聞いていて、全容を話してくれたが、それでますます悲しみが深まった。私は長い療養が必要と判断され、ジョセフはこの明るい寝室から追い出され、そこが病室となった。私はここで九週間以上も意識を失い、脳炎でうわごとを言い続けていた。もしハリソン嬢や医師の看護がなければ、今こうして話すこともなかっただろう。彼女が昼間は私の看病をし、夜は雇い看護婦が交代で見ていてくれた。私は発作中、何をしでかすかわからないような状態だった。やっと正気を取り戻したのは、ここ三日ほどのことだ。時には記憶が戻らなければいいとさえ思った。最初にしたのは、担当のフォーブズ氏に電報を打つことだった。彼はすぐ来て、できる限りのことはしたが、手がかりは全くないと保証してくれた。守衛夫婦も徹底的に調べられたが、何の進展もなかった。警察の疑いは、あの夜遅くまで事務所に残っていた若いゴローに向けられた。彼が残っていたこととフランス系の名前だけが疑わしい点だったのだ。しかし実際には、私が仕事を始めたのは彼が出て行った後だし、彼の家系もユグノーの流れで、同じく英国の伝統に根ざしている。彼を巻き込む証拠は何もなく、そこで話は終わった。ホームズさん、私はあなたに最後の望みを託す。他に道がなければ、私は名誉も地位も永遠に失うのだ。」
長い話を終えて、病人はぐったりとクッションに身を沈めた。看護婦が刺激になる薬をコップに注いでやる。ホームズは頭を背もたれに預け、目を閉じて黙ったまま――他人から見れば無気力にも思える体勢だったが、私にとっては彼特有の深い没頭状態を示していた。
「お話は極めて詳細で、ほとんど質問の余地がありません」と、やがて彼が言った。「ただし、きわめて重要な問いが一つあります。この特別な任務のことを、誰かに話しましたか?」
「誰にも話していません」
「例えば、ここにいるハリソン嬢にも?」
「いいえ。命令を受けてから用事を果たすまで、ウォーキングには一度も戻っていません」
「ご家族の誰かが、たまたまあなたに会いに来ることは?」
「ありません」
「家族の誰かが事務所の勝手を知っていましたか?」
「ああ、全員が案内されたことはある」
「とはいえ、条約の件を誰にも話していなければ、この問いは関係ありませんね」
「ええ、何も話していません」
「守衛について何か知っていますか?」
「軍人上がりということ以外は」
「どこの連隊か?」
「ええ、たしか……コールドストリーム・ガーズと聞いたことがあります」
「ありがとう。詳しいことはフォーブズから聞き出せるでしょう。役所というのは事実を集めるのは得意ですが、それを活かしきれないことがあるものです。バラは美しいですね」
ホームズは寝椅子のそばを通り、開け放たれた窓のところで、しおれかけたモス・ローズの茎を持ち上げ、赤と緑の繊細な色合いを見つめていた。それは私には新しい一面だった。彼がこんなに自然のものに関心を示すのを、これまで見たことがなかったからだ。
「宗教ほど推理が必要とされるものはない」と、彼は窓のシャッターにもたれかかりながら言った。「宗教は、推論する者にとってはまるで厳密な科学のように組み立てることができる。神の摂理の善意を確信できる最大の根拠は、花にあると私は思う。他のもの――能力も欲望も食物も、すべてはまず私たちが生きるために必要不可欠なものだ。だがこのバラは違う。香りも色も、人生を飾るものであって生存の条件じゃない。余計なものを与えてくれるのは善意だけだ。だから私は、花々には大いに希望を託せると言うのだ。」
パーシー・フェルプスと看護婦は、こうしたホームズの話に驚きと、どこか落胆の色を滲ませて見つめていた。彼はモス・ローズを指でひねりながら、物思いに沈み込んでいたが、それは数分続いた。やがて若い女性が沈黙を破った。
「この謎を解決できそうですか、ホームズさん?」と、やや鋭い声で尋ねた。
「おっと、謎でしたね!」と、ホームズは現実に返ってきて答えた。「まあ、この事件は非常に込み入っていて難解なのは間違いないが、できる限り調べて、何か気付いた点があればご報告しましょう」
「何か手がかりは?」
「七つほどいただきました。ただし、それらの価値を見極めるには、これから検証せねばなりません」
「誰かを疑っていますか?」
「私自身を疑っています」
「えっ!」
「結論を急ぎすぎているのではないか、という意味です」
「ではロンドンに行って、仮説を検証してください」
「ごもっともなご助言です、ハリソン嬢」ホームズは立ち上がりながら言った。「ワトソン、ロンドンへ向かおう。フェルプスさん、あまり淡い期待を抱かないでください。この事件は非常に入り組んでいます」
「再びお会いするまで、私は気が気でありません」外交官は叫んだ。
「では、明日同じ列車で戻りましょう。ただし、報告は陰性になる可能性が高いですが」
「約束してくださって本当にありがとうございます」依頼人は叫んだ。「何か進展があると思えるだけで、また生きる力が湧いてきます。ところで、ホールドハースト卿から手紙がありました」
「ほう、内容は?」
「冷ややかではありましたが、厳しくはありませんでした。私の重病に配慮してのことでしょう。事件が極めて重大であることを再度強調し、私の将来――つまり解雇――については健康が回復し、不運を挽回する機会が与えられるまで保留にする、とのことでした」
「それは合理的で思いやりのある対応だ。さあ、ワトソン、今日はロンドンで大いに働かねばならない」
ジョセフ・ハリソンが駅まで送ってくれ、私たちはポーツマス行きの列車でロンドンへ向かった。ホームズは深い考えに沈み、クラッパム・ジャンクションを過ぎるまでほとんど口を開かなかった。
「こういった鉄道でロンドンの高架を通るのは、なかなか気持ちがいいものだ。家々を上から見下ろせるからね」
冗談かと思ったが、彼はすぐ解説を加えた。
「あの、瓦屋根より高くそびえる孤立した大きな建物の塊を見てごらん。まるで鉛色の海に浮かぶ煉瓦の島だろう」
「学校ですか」
「灯台さ! 未来への道標だ。ひとつひとつの建物は何百もの小さな種――賢い未来のイギリスを生み出すだろう。ところで、あのフェルプスは酒を飲まないだろうな?」
「その心配はないと思う」
「僕もそう思うが、あらゆる可能性を考慮しなければならない。彼は本当に窮地に陥っていて、我々が助け出せるかどうかは分からない。ハリソン嬢をどう思った?」
「芯の強い女性だ」
「そうだが、いい人間だと思う。彼女と兄はノーサンバーランドの鉄工場主の子どもだ。去年の冬の旅行で彼と婚約して、兄を伴って家族に紹介しに来た。そこへ事件が起き、彼女は恋人の看病のために残り、兄のジョセフも居心地がいいと長居している。僕なりに独自に調べてみたんだ。だが今日は調査の日にしよう」
「私の診療の方が――」私は言いかけた。
「おや、君は自分の患者の方が僕の事件より面白いと?」とホームズがやや刺々しく言った。
「いえ、一年で一番暇な時期なので、二日やそこらは平気だと言いたかったんだ」
「それは良い。では一緒に調べよう。まずフォーブズに会うべきだ。必要な詳細は彼から聞けるだろう。事件がどこから攻めるべきものかを知るには、それが一番だ」
「手がかりがあると言っていたね?」
「いくつかあるが、その価値はこれからの調査で分かる。最も追いにくい犯罪は、目的のない犯罪だ。しかしこれは目的がある。得をする者は誰か? フランス大使、ロシア大使、そして両者に売ろうとする者、そしてホールドハースト卿」
「ホールドハースト卿が?」
「たとえば、政治家が、ああいった書類が偶発的に紛失することで助かる立場に立つことは、絶対にないとは言い切れない」
「ホールドハースト卿のような立派な経歴の人が?」
「可能性として排除できない。我々は卿に会い、何か知っているか確かめる。すでに調査も手配している」
「もう?」
「ああ、ウォーキング駅からロンドン中の夕刊全紙に電報を打っておいた。この広告が載ることになる」
彼は手帳から切り取った紙を差し出した。鉛筆でこう書いてある。
「【懸賞金十ポンド】 5月23日午後9時45分ごろ、チャールズ・ストリート外務省前で客を降ろしたタクシーの番号を求む。応募先:ベーカー街221B」
「犯人がタクシーで来たと確信しているのか?」
「そうでなくても問題ない。しかし、フェルプス氏の話どおり室内にも廊下にも隠し場所がなければ、犯人は外から来たはずだ。雨の夜、数分以内に調べたリノリウムに濡れ跡が残っていなかったなら、タクシーで乗り付けた可能性が高い。つまり、タクシーだと推定できる」
「もっともらしいな」
「これが一つの手がかりだ。何かにつながるかもしれない。それからもちろん、ベルだ――この事件で最も特徴的な要素だ。なぜベルが鳴った? 犯人の度胸試しか? 共犯者が犯罪を止めるためだったのか? それとも偶然か? あるいは――」彼は再び沈思黙考に入り、やがて新しい可能性に思い至ったように見えた。
終点に着いたのは三時二十分。急いで駅のビュッフェで昼食を済ませると、スコットランド・ヤードへ直行した。ホームズはすでにフォーブズに電報を入れてあり、私たちが着いたときには、彼――小柄で鋭いが、決して好感の持てない面持ちの男――が待ち構えていた。彼は私たちの用件を聞くと、あからさまに冷ややかな態度を取った。
「あなたのやり方については、以前から聞いていますよ、ホームズさん」と彼は辛辣に言った。「警察が集めた情報を利用しておいて、あとは自分で事件を解決して警察の面目をつぶそうとする。」
「いや、逆だ」とホームズは言った。「この五十三件の事件のうち、私の名前が公に出たのはわずか四件で、四十九件はすべて警察の手柄になっている。君がそれを知らないのも無理はない。君はまだ若くて経験が浅いからな。だが、新しい職務で出世したければ、私と対立せず協力したほうがいい。」
「ヒントをもらえるならありがたいですね」と、探偵は態度を軟化させて言った。「今のところ、この事件で何の手柄も挙げていませんから。」
「どんな手を打った?」
「タンジー、守衛ですが、彼の行動はずっと見張っていました。彼はガーズを良い評判で辞めており、何も怪しい点は見つかりません。ですが、彼の妻は評判が悪い。私は、彼女が表に出ている以上のことを知っているのではと思っています。」
「その妻を見張ったのか?」
「うちの女性部員の一人をつけました。タンジー夫人は酒癖が悪く、我々の者が二度ほど酔った時に同席しましたが、何も聞き出せませんでした。」
「家に差し押さえ業者が入ったと聞いているが?」
「はい、でもすでに支払い済みです。」
「その金はどこから出た?」
「それは心配ありません。彼の年金の支給日だったのです。金回りがよくなった様子はありません。」
「フェルプス氏がコーヒーを頼んだとき、なぜベルに応じたのかという説明は?」
「夫がとても疲れていたので、自分が代わってやりたかったそうです。」
「なるほど、後で椅子で寝ていたという話とも辻褄は合う。なら、彼らに疑わしい点があるとすれば妻の素行だけだな。あの夜、なぜ急いで帰ったのか聞いたか? その慌てぶりは警官の注意を引いたそうだ。」
「いつもより遅くなったので、早く帰りたかったと言っています。」
「君やフェルプス氏は、彼女より少なくとも二十分遅れて出たのに先に帰宅したことは指摘したか?」
「バスとハンサム馬車の違いだと説明しています。」
「到着してすぐ裏口の台所へ駆け込んだ理由は?」
「差し押さえ業者に支払うお金が台所にあったからだと。」
「なるほど、すべてに答えが用意されているな。帰り際、誰かと会ったり、チャールズ街でうろついている人を見たかと尋ねたか?」
「警官以外は誰も見ていないとのことです。」
「ずいぶん徹底的に尋問したようだな。他には?」
「事務員のゴローも九週間ずっと見張りましたが、何も怪しい点はありません。」
「ほかに何かあるか?」
「いえ、それ以外に頼りになる証拠は何もありません。」
「そのベルがどうして鳴ったのか、仮説は立てたか?」
「正直、さっぱり見当がつきません。あんなことをするなんて大胆な奴ですよ。」
「確かに妙な行動だ。いろいろ話してくれてありがとう。もし犯人を君の手に渡せることがあれば、連絡する。行こう、ワトソン。」
「さて、これからどこへ?」と私はオフィスを出ながら尋ねた。
「今から、イギリスの内閣大臣であり、将来の首相候補であるホールドハースト卿に面会する。」
幸運なことに、ホールドハースト卿はまだダウニング街の執務室におり、ホームズが名刺を渡すとすぐに案内された。国務大臣は、その名高い古風な礼儀で私たちを迎え、暖炉の両脇にある豪奢な長椅子に座るよう勧めてくれた。彼は、私たちの間の敷物の上に立ち、痩身で背が高く、鋭い顔立ちと思慮深い表情、そして早くも白髪が混じったカールした髪が印象的だった。本当に高貴な人物という、あまり多くはないタイプを体現していた。
「ホームズさん、お名前はよく存じ上げています」と彼は微笑みながら言った。「もちろん、ご訪問の目的を知らぬふりはできません。この執務室で、あなたの関心を呼ぶような出来事は一つだけです。どなたの利益のために行動しておられるのか、お聞きしてもよろしいですか?」
「パーシー・フェルプス氏のためです」とホームズが答えた。
「なるほど、不幸な甥ですね。ご承知のとおり、親類関係にあるがゆえに、なおさら彼をかばうことはできません。この事件が彼の将来に甚だ悪影響を及ぼすことを恐れています。」
「しかし、もし文書が見つかったら?」
「それはもちろん、話がまったく違ってきます。」
「いくつかお伺いしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか、ホールドハースト卿。」
「私に分かる範囲であれば、どんな情報でもお教えしましょう。」
「この文書の写しを作るよう指示したのは、この部屋だったのですか?」
「そうです。」
「では、誰かに聞かれた可能性はほとんどない?」
「ありえません。」
「誰かに、文書を写させるつもりだと話したことは?」
「一度もありません。」
「それは間違いありませんか?」
「絶対にありません。」
「だとすると、あなたもフェルプス氏も誰にも話していなかった以上、あの部屋に盗人がいたのは全くの偶然ということになる。たまたまチャンスを見て盗んだわけです。」
大臣は微笑した。「そこは私の専門外ですね」と言った。
ホームズはしばし考えてから言った。「もう一つ大事な点について伺いたい。ご心配されていたのは、この条約の詳細が明るみに出れば重大な結果を招くかもしれない、ということでしたね。」
大臣の表情に影がさした。「まさに重大な結果となるでしょう。」
「もう何か起きましたか?」
「まだです。」
「もし仮に、その条約がフランスやロシアの外務省に渡っていたとしたら、何か情報が入っているはずですよね?」
「そうです」とホールドハースト卿は苦い顔で答えた。
「十週間近く経っても何も聞こえてこないのは、何らかの理由で条約が相手に渡っていないと考えるのが妥当でしょう。」
ホールドハースト卿は肩をすくめた。
「盗人が条約を額に入れて飾ろうとしたとは、さすがに考えられませんよね、ホームズさん。」
「もっと高値で売れるのを待っているのかもしれません。」
「もう少し待てば、何の値打ちもなくなりますよ。数か月もすれば、条約の機密性は失われる。」
「それは大変重要なことです」とホームズ。「もっとも、盗人が急な病気にでも――」
「例えば、脳熱でも?」と大臣は鋭い視線を送った。
「私はそうは申しません」とホームズはさらりと返した。「さてホールドハースト卿、もうこれ以上貴重なお時間を奪うのも心苦しいので、これで失礼します。」
「どんな犯人であれ、あなたの捜査が成功することを祈っています」と貴族は頭を下げ、私たちを送り出した。
「立派な人物だ」と、私たちがホワイトホールに出たときホームズが言った。「だが、地位を維持するのは苦労している。決して裕福ではなく、多くの出費もある。君も気付いただろうが、靴の底が張り替えられていた。さてワトソン、もう君の本来の仕事の邪魔はしない。今日のところは、もし馬車の広告に返事がなければ、何もしないつもりだ。だが、明日またウーキングまで昨日と同じ列車で同行してくれると、とてもありがたい。」
私は翌朝言われた通り彼と合流し、一緒にウーキングへ向かった。広告には何の返事もなく、事件にも新たな進展はなかったと言う。彼が本気で望んだときは、顔色一つ変えないインディアンのごとき無表情ができるので、現状に満足しているのかどうか、私はまるで読み取れなかった。道中で話したのはベルトゥイヨンの測定法についてで、フランスの学者への熱烈な賛辞を述べていたのを覚えている。
依頼人は、献身的な看護師の世話を受けていたが、前よりずっと元気そうだった。私たちが入ると、彼はソファから難なく立ち上がり、出迎えてくれた。
「何か進展は?」と彼は熱心に尋ねた。
「予想通り、報告は否定的なものだ」とホームズ。「フォーブスとも、君の伯父とも会い、いくつか新たな調査も始めている。」
「まだ諦めてはいないのですね?」
「とんでもない。」
「そう言ってくださって神に感謝します!」とミス・ハリソンが叫んだ。「勇気と忍耐を持ち続ければ、きっと真実は明らかになります!」
「あなた方よりも、私たちの方が報告することがあるのですよ」とフェルプスは再びソファに腰掛けて言った。
「何かあったのか?」
「ああ、昨夜、小さな冒険があったんだ。しかも深刻な事態になる恐れもあった。」彼の顔は語るうちに真剣になり、恐怖に近いものが目に浮かんだ。「昨夜の経験から考えると、私は何か巨大な陰謀の、知らず知らずのうちに中心にされているのだと思えてならない。私の名誉だけでなく、命まで狙われているのではないか。」
「ほう!」とホームズ。
「信じがたい話だが、私には世界に敵などいないはずだ。だが、昨夜の出来事からはそうとしか思えない。」
「ぜひ聞かせてくれ。」
「実は、昨夜は初めて看護師なしで一晩を過ごしたんだ。ずいぶん回復したので必要ないと思ったのさ。ただし、豆電球はつけていた。午前二時ごろ、うとうとしていたとき、かすかな物音で目が覚めた。まるでネズミが板をかじるような音だったので、しばらく気にせず聞いていた。だがやがて音は大きくなり、窓の方から鋭い金属音がした。私は驚いて起き上がった。その音が何かは、もはや疑いなかった。最初の音は、誰かが窓のサッシの隙間に道具を差し込んでいる音で、次は掛け金を外す音だった。
「それから約十分間の間があった。どうやら物音で私が目覚めたかどうか、様子をうかがっていたのだろう。それから、窓がゆっくりと軋む音がした。私はもう耐えられず、ベッドから飛び出して雨戸を開けた。そこに男が窓にもぐり込んでいた。姿はよく見えなかったが、あっという間に逃げ去った。顔の下半分を覆うようなマントを身に着けていた。一つだけ確かに覚えているのは、手に武器を持っていたことだ。私には長いナイフのように見えた。男が振り返ったとき、ナイフがきらっと光ったのがはっきり見えた。」
「非常に興味深い話だ」とホームズ。「それからどうした?」
「体力があれば、窓からすぐ追いかけていたところだ。しかしそれができず、ベルを鳴らして家中を起こした。キッチンにしかベルが鳴らず、召使いたちは皆階上で寝ているので、少し手間取った。だが、私は叫び声も上げ、ジョゼフが駆け下りてきて他の者も起こした。ジョゼフと馬丁が窓の外の花壇に足跡らしきものを見つけたが、最近ずっと雨が降っておらず芝生の跡は追えなかった。ただ、道路沿いの木の柵に、誰かが乗り越えるときに上部を折ったような跡があったと言う。まだ地元警察には何も話していない。まずあなたの意見を聞いた方がいいと思って。」
この話は、シャーロック・ホームズに驚くべき影響を与えた。彼は椅子から立ち上がり、抑えきれない興奮で部屋を歩き回った。
「不運は重なるものだ」とフェルプスは微笑んだが、明らかに動揺していた。
「君は本当に災難続きだな」とホームズ。「少し家の周りを一緒に見て歩けるか?」
「もちろん、ちょっと日光に当たりたいくらいだ。ジョゼフも一緒に行こう。」
「私も行くわ」とミス・ハリソン。
「それはいけません」とホームズは首を振った。「そのまま、ここにいていただきたい。」
若い女性は不満そうに席に戻った。だが彼女の兄が加わり、私たちは四人で外に出た。芝生を回り、若い外交官の窓の外に出た。そこには彼の言う通り、足跡らしきものがあったが、全く不明瞭だった。ホームズはしばしそれを観察したが、肩をすくめて立ち上がった。
「これは何も手がかりにならないな」と彼。「家の周囲を回って、なぜこの部屋が狙われたのか見てみよう。居間や食堂の大きな窓の方がよほど魅力的に思えるが。」
「道路からよく見えるからでしょう」とジョゼフ・ハリソン氏。
「なるほど。ここにドアがあるが、これは?」
「業者用の勝手口です。夜はもちろん施錠しています。」
「これまでにこのような騒ぎは?」
「一度もありません。」
「銀器など、盗人が狙いそうなものは?」
「貴重品はありません。」
ホームズはポケットに手を入れ、珍しく無頓着な様子で家の周りを歩き回った。
「ところで」と彼はジョゼフに言った。「柵を越えた跡があるそうだが、見せてくれ。」
ふくよかな若者が案内したのは、木柵の上部が割れて、小さな木片がぶら下がっている場所だった。ホームズはそれを取り、じっくりと観察した。
「昨夜のものだと思うか? だいぶ古いようにも見えるが。」
「まあ、そうかもしれません。」
「反対側に飛び降りた跡はない。ここからは手がかりは得られないな。部屋に戻って話し合おう。」
パーシー・フェルプスは、未来の義兄に腕を預けて、とてもゆっくり歩いていた。ホームズは芝生をさっさと横切り、私たちより先に寝室の窓に着いた。
「ミス・ハリソン」とホームズは最大限の緊迫感で言った。「今日一日、絶対にここから出てはなりません。どんなことがあってもです。これはきわめて重要です。」
「もちろん、あなたがそうおっしゃるなら」と彼女は驚きながら答えた。
「寝るときは、この部屋の外から鍵をかけ、鍵を持っていてください。約束してください。」
「でもパーシーは?」
「彼は私たちとロンドンへ行きます。」
「私だけ残るのですか?」
「彼のためです。あなたにしかできない役目です。早く、約束してください!」
彼女はうなずき、ちょうど他の二人が戻ってきた。
「どうしてそんなに塞ぎ込んでいるんだ、アニー」と兄が声をかけた。「外で日向ぼっこしよう!」
「結構よ、ジョゼフ。ちょっと頭が痛くて、この部屋はとても涼しくて気持ちいいの。」
「これからどうなさるおつもりですか、ホームズさん?」と依頼人が尋ねた。
「この小事件の調査で、本筋を見失ってはならない。ロンドンにご同行いただければ、とても助かるのですが。」
「今すぐ?」
「いや、ご都合のよい時に。例えば一時間後くらいに。」
「本当にお役に立てるなら、十分強い気分です。」
「これ以上ないほど役立ちます。」
「今夜もロンドンに泊まった方がいいでしょうか?」
「そう提案しようと思っていた。」
「では、昨夜の訪問者がまた来ても、鳥は巣立ったあとということだ。我々はあなたの指示に従います。ジョゼフも一緒に行った方がいいですか?」
「いや、ワトソンは医者だから、君の世話は任せてくれ。昼食をここでいただいてもよければ、三人ですぐにロンドンへ向かおう。」
ホームズの提案通りになり、ミス・ハリソンはホームズの助言に従い寝室から出なかった。友人のこの作戦の目的は私には皆目見当がつかなかったが、もしかすると女性をフェルプスから引き離すためかとも思われた。だがフェルプスは回復への手応えと行動の見通しで活気づき、私たちと食堂で昼食を共にした。だが、ホームズはさらに私たちを驚かせる発表をした。彼は駅まで私たちを見送り、客車に乗せると、ウーキングを離れるつもりはないと平然と言い放った。
「まだ確かめておきたい細かい点がある」と彼は言った。「あなたが不在の方が、ある意味私には好都合です。ワトソン、ロンドンに着いたらすぐベーカー街へフェルプス氏と向かい、私が来るまで一緒にいてくれ。お二人は旧友だから話も尽きないだろう。フェルプス氏は今夜は空いている部屋を使い、私は朝食には間に合うように来る。八時発の列車があるから。」
「ロンドンの捜査は?」とフェルプスはがっかりした様子で尋ねた。
「それは明日やろう。今はここでの用事の方が急を要する。」
「ブライアブレーには明晩戻るつもりだと伝えてほしい」とフェルプスはホームズに駅のホームから声をかけた。
「私はブライアブレーには戻れない気がする」とホームズは返し、私たちが駅を出る際に陽気に手を振った。
フェルプスと私は道中そのことを話し合ったが、この新しい展開の理由を納得できるものは思いつかなかった。
「昨夜の事件、泥棒だとしても何か手がかりを探したいのだろう。だが、私には普通の盗賊とは思えない。」
「それで、君自身はどう考えているんだ?」
「実のところ、神経が弱いせいだと思われても仕方ないが、僕の周囲で何か深い政治的陰謀が動いていて、その陰謀者たちが、僕には理由も分からないが、僕の命を狙っているのだと信じている。こう言うと大げさで馬鹿げているように聞こえるだろうが、事実を考えてみてほしい! なぜ泥棒が、何も盗れるはずのない寝室の窓から侵入しようとしたのか? なぜ、長いナイフを手に持って来たのか?」
「それは本当に泥棒のバールじゃなかったのか?」
「いや、間違いなくナイフだった。刃がきらりと光ったのをはっきり見たんだ。」
「しかし、一体全体、なぜ君がそこまで憎まれて狙われなければならない?」
「ああ、それが問題なんだ。」
「もしホームズも同じ考えなら、彼の行動にも説明がつくのではないか? 君の理論が正しいとすれば、昨夜君を脅した男を捕まえれば、海軍条約を盗んだ犯人に迫ることになる。君が敵を二人も持っていて、一人が盗み、もう一人が命を狙うなんてことは、馬鹿げている。」
「でもホームズはブライアブレイには行かないと言っていたじゃないか。」
「僕は彼と付き合いが長いが、これまで理由もなく何かをしたことは一度もないよ」と私は言った。そして私たちの話題は他のことへ移った。
だが、その日は私にとっても疲れる一日だった。フェルプスは長い病気の後でまだ体が弱っていたし、不運のせいで気難しく、神経質になっていた。私は彼の気を紛らわせようとアフガニスタンやインドの話、社会問題など、何でも話題を変えようと努めたが無駄だった。彼はどうしても失われた条約に話を戻し、あれこれ推測したり、ホームズが今何をしているのか、ホールドハースト卿がどんな手を打っているのか、明朝にはどんな知らせが来るのか、考えずにはいられないようだった。夜が更けるにつれ、彼の興奮は痛々しいほどだった。
「君はホームズを絶対的に信頼しているのか?」
「彼が見事な手腕を見せた場面を何度も見てきたよ。」
「でも、これほど暗闇に包まれた事件を解決したことはないだろう?」
「いや、これよりも手がかりの少ない事件を解いたことも知っている。」
「だが、これほど大きな利害がかかった事件は?」
「それは分からない。だが、私が知る限り、彼はこれまでヨーロッパの三つの王家のために極めて重大な案件に関わったことがある。」
「でも、君は彼をよく知っている、ワトソン。彼は本当に底知れない男だから、いつもどう受け止めていいか分からないんだ。彼は希望を持っていると思うか? 成功するつもりでいるのかな?」
「何も言っていない。」
「それは悪い兆候だ。」
「いや、逆だよ。彼は見当がつかなくなると、たいていそう言う。手がかりを見つけて、まだそれが正しいか確信が持てないときほど、彼は黙っているものだ。さあ、いくら心配しても事態はよくならないのだから、とにかく寝て、明日に備えようじゃないか。」
ようやく私は彼を説得してベッドに入らせることができたが、その興奮ぶりからして安眠は望めないと分かっていた。実際、その気分は私にも伝染し、私自身も夜半まで寝返りを打ちながら、この奇妙な事件についてあれこれ思いめぐらし、百もの理屈を考え出したが、どれもこれも現実味に欠けていた。なぜホームズはウォキングに残ったのか? なぜミス・ハリスンに一日中病室にいるよう頼んだのか? なぜブライアブレイの人々には自分が近くにいることを知らせなかったのか? 私は頭を悩ませ続け、全ての事実を説明できる理屈を探しながら、ようやく眠りに落ちた。
目が覚めると七時で、私はすぐにフェルプスの部屋へ向かった。彼はやつれ果てており、夜通し一睡もできなかった様子だった。最初の問いは、ホームズがもう到着したかというものだった。
「彼は約束通りの時間に来るさ、早くも遅くもなく」と私は答えた。
そしてまさにその通りになった。八時を少し過ぎたころ、馬車が玄関先に駆けつけ、私たちの友人が降り立った。窓から見ると、彼の左手は包帯でぐるぐる巻きにされ、顔は非常に険しく青ざめていた。彼は家に入ったが、二階に上がってくるまで少し時間がかかった。
「彼は打ちひしがれた男のようだ」とフェルプスが叫んだ。
私はその通りだと認めざるを得なかった。「結局、事件の手がかりはこの町にあるのかもしれないな」と私は言った。
フェルプスは呻いた。
「どうしてだか分からないけど、彼の帰りにはすごく期待していたんだ。でも、彼の手は昨日あんなふうに包帯されてはいなかったはずだ。どうしたんだろう?」
「怪我をしたのかい、ホームズ?」と私は部屋に入ってきた友人に尋ねた。
「いや、単なる自分の不注意でできた擦り傷だ」と彼は答え、私たちに挨拶した。「この事件は確かに私が今まで調べた中で最も難解なものの一つだ。」
「君にも手に負えないかと心配していたんだ。」
「実に特異な経験になったよ。」
「その包帯は冒険の証拠だな」と私は言った。「何があったのか話してくれないか?」
「朝食の後にしよう、ワトソン。今朝はサリー州を三十マイルも移動したんだ。私の馬車の運転手への広告には返事はなかったんだろう? まあ、毎回うまくいくとは限らないさ。」
テーブルの準備はできており、私が呼び鈴を押そうとしたとき、ハドソン夫人が紅茶とコーヒーを持って入ってきた。数分後には三人分の料理も運ばれ、私たちはテーブルについた。ホームズは空腹そうに、私は好奇心でいっぱい、フェルプスは暗い絶望の中にいた。
「ハドソン夫人はよくやってくれたな」とホームズはカレー味の鶏肉の蓋を取って言った。「彼女の料理の幅は限られているが、スコットランド婦人のように朝食を分かっている。ワトソン、そちらはなんだ?」
「ハムと卵だよ」と私は答えた。
「よし! フェルプス君、君はカレー味の鶏にするか、それとも卵にするか? 自分で好きなものを取るかい?」
「ありがとう。何も食べられそうにない」とフェルプスは言った。
「まあまあ、目の前の料理をちょっと食べてみなさい。」
「いや、本当に遠慮しておくよ。」
「じゃあ」とホームズはいたずらっぽく目を光らせて言った。「僕を手伝うのは構わないだろう?」
フェルプスが蓋を上げると、彼は叫び声をあげ、皿の上と同じくらい真っ白な顔でそれを見つめた。中央には青灰色の小さな筒状の紙が載っていた。彼はそれをつかみ取り、目でむさぼるように見て、突然胸に抱いて狂ったように部屋中を駆け回り、歓喜のあまり叫び声を上げた。すると力尽きて肘掛け椅子に崩れ落ち、気を失いかけたので、私たちは彼の喉にブランデーを注ぎ込まねばならなかった。
「落ち着いて、落ち着いて」とホームズはあやすように彼の肩をたたいた。「こんなふうに君を驚かすのは酷だったが、ワトソンが証人で私はどうしても劇的な演出に抵抗できない性分なんだ。」
フェルプスは彼の手を握り、口づけした。「神のご加護を!」と彼は叫んだ。「君は私の名誉を救ってくれた!」
「僕自身の名誉も懸かっていたからね」とホームズは言った。「私も事件に失敗するのは、君が任務をしくじるのと同じくらい嫌なんだよ。」
フェルプスは貴重な書類を上着の一番奥のポケットに押し込んだ。
「これ以上朝食の邪魔をしたくないけど、どうやって手に入れて、どこにあったのか知りたくてたまらない。」
シャーロック・ホームズはコーヒーを一杯飲み干し、ハムと卵に手を伸ばした。それから立ち上がってパイプに火を付け、椅子に深く腰を下ろした。
「まず私が何をしたかを話し、その後なぜそうしたのかを説明しよう」と彼は言った。「駅で君たちと別れた後、サリーの美しい風景の中をぶらぶら歩いて、リプリーという小さな村に着き、そこで宿屋でお茶を飲み、念のため水筒に水を入れ、サンドイッチを紙袋に入れてポケットにしまった。夕方までそこにいて、再びウォキングへ向かい、日没直後にブライアブレイの外れの街道に戻った。
「道路の人通りがなくなるまで待ち――まあ、そもそもあまり人が通る道じゃないと思うが――それから塀を乗り越えて敷地に入った。」
「門は開いていたはずじゃ?」とフェルプスが口を挟んだ。
「ああ、だが私はこういう時に変わった趣味があるんだ。三本のもみの木が並んだ場所を選び、その陰に隠れて、誰にも見られずに乗り越えた。向こう側の茂みに身をかがめて、膝が泥だらけになるまで這い進み、君の寝室の窓の正面にあるシャクナゲの茂みにたどり着いた。そこで私はしゃがみ込み、事の成り行きを見守った。
「君の部屋のブラインドは下ろされておらず、ミス・ハリスンがテーブルのそばで本を読んでいるのが見えた。彼女が本を閉じ、雨戸を閉めて寝室に引き上げたのは十時十五分だった。
「彼女がドアを閉め、私は外から鍵をかけたことを確信した。」
「鍵だって?」とフェルプスは叫んだ。
「ああ。私はミス・ハリスンに、外側からドアに鍵をかけ、寝るときは鍵を持っていくよう指示しておいた。彼女は私の指示を一字一句守ってくれた。彼女の協力なくしては、今君のコートのポケットにあの書類はなかっただろう。彼女が部屋を去ると明かりも消え、私はシャクナゲの茂みの中に残された。
「夜は良かったが、それでも非常に長い見張りだった。もちろん猟師が水辺で獲物を待つときのような興奮はあったが、とはいえとても長く感じられた――ワトソン、君と一緒に『まだらの紐事件』であの凶悪な部屋で待ち伏せしたとき並みにね。ウォキングの教会の時計が四分ごとに時を告げていて、何度も止まったのかと思ったほどだ。だが午前二時ごろ、突然、閂(かんぬき)が静かに外される音と、鍵のきしむ音が聞こえた。次の瞬間、使用人用のドアが開き、ジョセフ・ハリスン氏が月明かりの下に現れた。」
「ジョセフだって!」とフェルプスは叫んだ。
「彼は帽子をかぶっていなかったが、黒いコートを肩にかけていて、万一見つかってもすぐ顔を隠せるようにしていた。壁の影に沿ってつま先立ちで歩き、窓に着くと長いナイフで窓のサッシの留め金を外した。それから窓を開け、ナイフを雨戸の隙間に差し込んでバーを持ち上げて雨戸も開けた。
「私が潜んでいた場所からは部屋の中も彼の動きもすべて見渡せた。彼はマントルピースの上にあった二本の蝋燭に火をつけ、それからドアのあたりのカーペットの端をめくり始めた。やがて彼は配管工がガス管の継ぎ目にアクセスするために残すような四角い板を外した。その下にはちょうど台所にガスを送るT字管がある。その隠し場所から、彼はあの小さな筒状の紙を取り出し、板を戻し、カーペットを整え、蝋燭の火を吹き消して、私が窓の外で待ち構えていたところにまっすぐ出てきた。
「さて、ジョセフ君は思ったよりも獰猛だった。彼はナイフで私に襲いかかってきて、私は彼を二度も取り押さえ、挙句指の関節を切られてしまった。仕舞いには彼の唯一見える片目で殺意をにじませていたが、最終的には論理を認め、書類を渡した。書類を手に入れたので、私は彼を放したが、今朝フォーブスにすべてを電報で伝えた。もし彼が間に合って小鳥を捕まえられればよし、だが私の読み通りなら巣は空っぽだろうし、それなら政府にとっても都合がいい。ホールドハースト卿もペルシー・フェルプス君も、この件が警察沙汰にまで発展しない方が好ましいはずだ。
「なんということだ!」と依頼人は息をのんだ。「この十週間、苦しみ続けてきた間、盗まれた書類はずっと同じ部屋の中にあったというのか?」
「その通りだ。」
「それにジョセフが! ジョセフが悪党でしかも泥棒だったなんて!」
「うむ、ジョセフの人物像は外見から受ける印象よりもずっと深く、危険なものだと考えざるを得ない。今朝彼から聞いた話では、株で大損をし、いかなる手段でも財産を増やそうとしていたらしい。まったく利己的な男で、チャンスが来れば、妹の幸せも君の名誉も顧みなかった。」
ペルシー・フェルプスは椅子に沈み込んだ。「頭がくらくらする。君の話は衝撃的だ。」
「この事件の最大の難点は、証拠が多すぎたことにあった」とホームズは教師ぶった口調で言った。「重要なものが、無関係な事実に隠されていた。提示された事実の中から、本当に必要なものだけを選び、それらを順に並べて、この特異な事件の流れを再構成しなければならなかった。私はすでに君がその夜ジョセフと一緒に帰宅するつもりだったことから、彼が途中で君を迎えに行くのが自然だと考え、彼を疑い始めていた。寝室に何かを隠せたのはジョセフしかおらず――君が医者と到着したとき、彼を部屋から追い出したと君自身が語った――しかも看護婦が不在の初めての夜に侵入が試みられたことで、家の事情に通じている者だと確信した。」
「なんと自分は盲目だったのか!」
「私の推理によれば、ジョセフ・ハリスンはチャールズ・ストリート側のドアからオフィスに入り、事情を知っていたので、君が部屋を出た直後にまっすぐ君の部屋へ入った。誰もいないのを見てすぐにベルを鳴らし、その瞬間、テーブルの上の書類に目を留めた。国家機密文書だと一目で気付き、即座にポケットに押し込んで姿を消した。君が眠そうな門衛からベルのことを知らされたのは数分後で、そのわずかな時間が、彼に逃げる十分な隙を与えた。
「ジョセフは最初の列車でウォキングへ向かい、戦利品の価値を確かめてから、数日後にフランス大使館か、最も高く売れるであろう場所に持ち込むつもりで、非常に安全と思われる場所に隠した。ところが君が突然帰宅し、彼は警告もなく部屋から追い出された。それ以降、常に二人以上が部屋にいて、彼は宝を取り戻せなくなった。彼にとっては気が狂いそうな状況だっただろう。しかしついにチャンスが巡ってきたと見て忍び込もうとしたが、君が目を覚ましていたため失敗した。あの夜、君はいつもの睡眠薬を飲まなかっただろう?」
「確かにそうだ。」
「彼はその眠り薬が効くよう細工していたはずで、君が意識を失うと当てにしていたのだろう。当然、また安全にできる時に再び試みると思っていた。君が部屋を離れたことで、彼はついに望んだ機会を得た。私はミス・ハリスンを一日中部屋に居させて、彼に油断させないようにした。そうして彼の警戒心を解いた上で、私が先ほど話したように見張っていた。書類が部屋にあることは既に分かっていたが、床板や幅木を片端から壊して探すのは避けたかった。だから彼に隠し場所から取り出させ、それを捕らえることで余計な手間を省いたわけだ。ほかに知りたいことは?」
「最初のとき、なぜ彼はドアから入らずにわざわざ窓から入ろうとしたんだ?」と私は尋ねた。
「ドアにたどり着くまでに七つの寝室の前を通らなければならない。だが芝生には簡単に出られる。他には?」
「彼に殺意はなかったと思うか?」とフェルプスが尋ねた。「ナイフは道具として持っていただけじゃないのか?」
「そうかもしれない」とホームズは肩をすくめた。「ただ一つ言えるのは、ジョセフ・ハリスン氏という人物に私は絶対に情けを期待したくないということだ。」
XII. 最後の事件
私は重い心で筆を執り、これが友人シャーロック・ホームズ氏の卓越した才能について記す最後の言葉となることをここに書く。まとまりのない、そして心から不十分だと感じるやり方で、私は「緋色の研究」の時代に偶然出会って以来、「海軍条約事件」に彼が関与し、その関与が重大な国際的混乱を未然に防ぐという明白な結果をもたらすまで、彼と共に経験した奇妙な出来事のいくつかを記録しようと努めてきた。当初、私はそこで筆を置き、私の人生に空白を生じさせた、すでに二年が過ぎても埋めがたいあの事件については、何も語るつもりはなかった。しかしながら、最近ロス大佐が兄の名誉を弁護する書簡を公表したことにより、私は事実をありのまま公にするほか選択肢がなくなった。本件の絶対的な真実を知るのは私だけであり、もはやそれを隠しても何の益もない時が来たと確信している。私の知る限り、公の報道は三つだけである。1891年5月6日付『ジュルナル・ド・ジュネーヴ』、5月7日付英字新聞のロイター電、そして私が言及した最近の書簡である。最初の二つは極めて要約されており、最後のものは、今から示す通り、事実を全く歪めている。モリアーティ教授とシャーロック・ホームズ氏の間に実際に何が起こったのか、初めて私が語ることになる。
私が結婚し、それに伴い開業医として独立してから、ホームズとの親密な関係もある程度変化したことを、読者は覚えているかもしれない。彼は調査に同行者を必要とする時、時折私を訪ねてきたが、その機会は次第に減り、1890年には記録に残っているものだけで三件しかなかった。その年の冬から翌1891年の春にかけて、新聞で彼がフランス政府に極めて重要な案件で雇われていることを知り、彼からナーボンヌとニームからの日付入りの手紙を二通受け取った。それによれば、彼のフランス滞在は長引きそうだと察した。だから4月24日の夕方、彼が私の診察室に現れた時には、少なからず驚いた。しかも彼はいつにも増して青白く、やつれて見えた。
「そうだ、少し自分を酷使しすぎていた」と、私の言葉というより視線に応じて彼は言った。「少々忙しすぎてね。シャッターを閉めてもいいか?」
部屋の灯りは、私が読書していた机上のランプだけだった。ホームズは壁際をそっと歩き、シャッターを勢いよく閉じてしっかりと閂をかけた。
「何かを恐れているのか?」私は尋ねた。
「まあ、そうだな」
「何をだ?」
「空気銃だ」
「ホームズ、どういう意味だ?」
「ワトソン、君は私をよく知っているはずだが、私は決して神経質な男ではない。しかし、危険が目前に迫っている時、それを認めないのは勇気ではなく愚かさだ。マッチを貸してくれないか?」彼はタバコの煙を吸い込み、その鎮静作用を喜ぶような様子だった。
「遅くに訪ねて申し訳ない」と彼は言った。「もう一つ頼みがあるが、後ほど君の家を裏庭の塀をよじ登って出させてもらえないだろうか」
「どういうことなんだ?」私は尋ねた。
彼は手を差し出し、ランプの光の下で二つの指関節が裂けて血を流しているのが見えた。
「決して根拠のない不安ではないと分かるだろう」と彼は微笑んだ。「むしろ、手を傷めるほどの現実なんだ。ワトソン夫人は在宅か?」
「彼女は留守だ」
「そうか。君は一人か?」
「完全に」
「それなら、君に大陸へ一週間ほど同行してもらう提案がしやすい」
「どこへ?」
「どこでもいい。私にはどこでも同じだ」
これはとても奇妙なことだった。ホームズが目的もなく休暇を取るような性格でないことは私もよく知っているし、やつれた顔つきには神経が極度に張り詰めている様子が見て取れた。私の疑問を読み取った彼は、指先を合わせ、肘を膝に乗せて説明した。
「モリアーティ教授の名を聞いたことはないだろう?」と彼は言った。
「ない」
「それこそが、その男の天才ぶりであり、驚異なんだ!」と彼は叫んだ。「彼はロンドン中にその影響を及ぼしているのに、誰も彼の存在を知らない。そこが犯罪史における彼の頂点だ。真面目に言うが、ワトソン、もし私があの男を打ち破り、社会から排除することができたなら、私の経歴も絶頂に達したと感じ、もっと穏やかな人生へと移る覚悟もできていたろう。実のところ、最近私が手助けしたスカンジナビア王家やフランス共和国の案件で、私は望むなら静かな生活に移り、化学研究に専念できる立場にある。しかしワトソン、もしモリアーティ教授のような男がロンドンの街を我が物顔で歩いているのを知ったまま、私は安穏と椅子に座ってはいられないのだ」
「彼は何をしたんだ?」
「実に異様な経歴の持ち主だ。良家の生まれで教育も極めて優秀、天性の数学的才能に恵まれていた。21歳で二項定理に関する論文を書き、それが欧州中で評判となった。そのおかげで、ある地方大学の数学講座を任され、将来は輝かしいものと見られていた。しかし、その男には生まれつき極めて邪悪な資質があった。彼の血には犯罪性の傾向が流れており、それは矯正されるどころか、異常な知力によって一層危険なものとなっていた。大学町では彼を巡る黒い噂が絶えず、ついには講座を辞さざるを得ず、ロンドンに下って軍人予備校の講師となった。世間が知るのはここまでだが、今君に話しているのは、私が自ら突き止めたことだ。
「知っての通り、ワトソン、ロンドンの犯罪上層世界を私ほど知る者はいない。ここ数年、私は犯罪者の背後に何らかの力、法の前に立ちはだかり、悪事を庇護する深い組織力の存在を常に感じていた。偽造、強盗、殺人など様々な事件で、この力の存在を感じ、多くの未解決事件でも、その作用を推測してきた。長年、そのベールを破ろうと努め、ついに手がかりをつかみ、千々に入り組んだ道を辿り、ついに数学界で名高い元教授、モリアーティに行き着いた。
「彼は犯罪界のナポレオンだ、ワトソン。この大都市で行われる悪事の半分、未発覚のもののほとんどを組織する天才だ。哲学者であり、抽象思考の持ち主で、一流の頭脳を持つ。蜘蛛の巣の中心にじっと座す蜘蛛のように動かずして、その巣の放射する千の糸の震え一つ一つを知り尽くしている。自分ではほとんど手を下さず、計画を練るだけだが、配下は数多く見事に組織されている。何か悪事が必要なら、たとえば書類の盗取、家の荒らし、人間の排除――教授に伝えれば、手際よく計画され実行される。実行役が捕まっても、保釈金や弁護費用が用意されている。しかし、その背後にいる黒幕には決して手が届かない――疑いすらかけられない。私が推理し、暴こうと全力を注いだのがこの組織だ。
「だが教授は、いかに私が動いても法廷で有罪にできる証拠を得るのが不可能と思えるほど、巧妙に防御策を巡らせている。君も私の能力を知っているだろう、ワトソン。だが三か月の追跡の末、ついに私と互角の知力を持つ敵に出会ったことを認めざるを得なかった。その犯罪に戦慄する一方、技量には感嘆せざるを得なかった。だが、ついに彼は一つ、ほんの小さな、だが私がここまで迫っている時には致命的なミスをした。私はそこを起点に網を張り巡らし、今や完全に包囲した。三日後――つまり来週の月曜には、全ての準備が整い、教授は配下の主要人物ごと警察の手に落ちる。その後には世紀最大の刑事裁判が開かれ、四十件を超える未解決事件が解決し、全員が絞首刑となるだろう。だが少しでも早まれば、最後の瞬間に逃げられる危険もある。
「もしこれがモリアーティ教授に気づかれぬまま進行できたなら、何も問題はなかった。しかし彼はあまりにも狡猾だった。私が包囲網を狭めるあらゆる手を見抜き、その度に脱出を図ったが、私はそれを阻止し続けた。もしこの静かな駆け引きの詳細な記録があれば、推理史上最も輝かしい攻防戦として歴史に残るだろう。それほど私は高みに達し、これほど手強い敵に苦しんだことはなかった。彼の攻撃は鋭く、だが私はさらに一手下を読んだ。今朝、最後の手立てが揃い、あとは三日だけで事が成就するはずだった。私は部屋で状況を考えていた。するとドアが開き、目の前にモリアーティ教授が立っていた。
「私の神経も相当鍛えられているが、あれほど頭の中にあった男が敷居の上に立っているのを見て、さすがにぎょっとした。外見はよく知っていた。背が非常に高くやせて、額は白く丸く盛り上がり、目は奥深くくぼんでいる。無精髭もなく、青白く、禁欲的な印象で、顔立ちには教授らしさが残る。勉学のしすぎで肩は丸まり、顔は突き出し、爬虫類のように常にゆっくり左右に揺れている。彼はしかめ面の目で私をじっと観察した。
「『君は予想より前頭部の発達が少ないな』と彼は言った。『バスローブのポケットで装填済み拳銃をいじるのは危険な癖だ』
「実は、彼が入ってきた瞬間に、私は自分が極めて深刻な個人的危険にあることを悟った。彼にとって唯一の逃げ道は、私の口を封じることだけだった。私は即座に引き出しからリボルバーを抜き取り、ポケット越しに彼を狙っていた。彼の言葉に、私は銃をテーブルの上に出して構えた。彼はなおも微笑み、瞬きを続けていたが、その目には銃を用意していて良かったと思わせる何かがあった。
「『君は私を知らないようだな』と彼は言った。
「『いや、むしろ知っているのは明らかだろう』と私は答えた。『どうぞ座ってくれ。もし何か言うことがあるなら、五分は取れる』
「『言いたいことはすべて君の頭に浮かんでいる』と彼は言った。
「『ならば私の返答も君の頭に浮かんでいるだろう』と私は返した。
「『君は譲らないのか?』
「『断固として』
「彼はポケットへ手をやり、私はテーブル上の拳銃を構えた。しかし、彼が取り出したのは、日付を書き込んだ手帳だった。
「『君が私の邪魔を始めたのは一月四日だ』と彼は言った。『二十三日には迷惑を被り、二月中旬には本格的な支障となり、三月末には私の計画が完全に妨害され、そして今や四月末、君の執拗な追及で自由を失う危機にある。もはやこの状況は許容できない』
「『何か提案はあるか?』と私は尋ねた。
「『手を引くべきだよ、ホームズ君』と彼は顔を揺らしながら言った。『本当に、そうしなさい』
「『月曜以降ならな』と私は答えた。
「『ふむふむ』と彼は言った。『君ほどの知性ある者なら、この件の結末は一つしかないと分かるはずだ。君が仕組んだことで、我々には残された手段が一つしかなくなった。君の手際を見るのは知的な喜びだったが、極端な手段を執るのは本意ではない。君は笑っているが、私としては本当に不本意なのだ』
「『危険は私の職業の一部だ』と私は言った。
「『それは危険などではない。必然的な破滅だ。君は個人だけでなく、君の想像を超えた巨大な組織の道を塞いでいる。身を引かねば、踏み潰されるぞ、ホームズ君』
「『残念だが、この会話に夢中で他の大事な用件を疎かにしているようだ』と私は立ち上がった。
「彼も立ち上がり、無言で私を見つめ、悲しげに首を振った。
「『さて、仕方ない。私はできることはした。君の手の内は全て分かっている。月曜までに君にできることは何もない。これは君と私の一騎打ちだ、ホームズ君。君は私を被告席に立たせようと望んでいるが、私は被告席に立つことは決してないだろう。君は私に勝とうとしているが、決して勝つことはできない。もし君が私を破滅させるほど賢いなら、私も同じだけのことを君にやるだろう』
「『モリアーティ氏、君にはいくつか礼を言われたが、私からも一つ礼を言わせてもらおう。もし私が前者の運命を確信しているなら、公衆の利益のために喜んで後者も受け入れよう』
「『私は一方は約束できるが、もう一方はできない』と彼は唸り、背を向けて、瞬きしながら部屋を出て行った。
「これがモリアーティ教授との異様な面会だった。彼の柔らかく明確な話しぶりは、ただの脅迫者では生まれない真剣さを感じさせ、私の心にも不快な余韻を残した。もちろん君は『警察に保護を求めればよかったのでは?』と言うかもしれないが、私は攻撃が教授自身ではなく彼の手下から来ることを確信している。それを裏付ける証拠も揃っている」
「すでに襲撃されたのか?」
「ワトソン、モリアーティ教授は手をこまねいている男ではない。私は今日正午頃、オックスフォード・ストリートで用事を済ませていた。ベンティンク街からウェルベック街の交差点にさしかかると、馬車が凄い勢いで曲がってきて、あっという間に私に迫ってきた。私は歩道に飛び上がり、もう一瞬遅れていたら命はなかった。馬車はメアリルボーン・レーンを曲がって消えた。その後はずっと歩道を歩いたが、ヴェア・ストリートを下っていると、家の屋根から煉瓦が落ちてきて、私の足元で粉々になった。警察を呼び、現場を調べてもらったが、屋根の上には修理用の瓦や煉瓦が積まれており、風で落ちたと主張された。もちろん私は違うと分かっていたが、証明はできなかった。その後タクシーでパル・マルの兄の部屋へ行き、一日を過ごした。そして今、君の所に来たが、道中、こん棒を持った荒くれ者に襲われた。私はそいつを打ち倒し、警察が身柄を確保したが、私が拳で歯を砕いたあの男と、十マイルも離れた所で黒板に問題を書いている数学の講師の間に、どんな繋がりも見つかることは絶対にないだろう。だから君が、私が君の部屋に入るなりシャッターを閉じ、目立たぬ裏口から出してくれと頼んだのも、当然と思ってくれ」
私はこれまでにも友人の勇気に感心してきたが、悪夢のような一日を冷静に事実として語る彼の姿には、これまで以上に敬服した。
「今夜はここに泊まるのか?」と私は言った。
「いや、ワトソン、私が君の家にいるのは危険かもしれない。すでに計画は整っているから、逮捕そのものは私がいなくても進む。だが有罪にするには私の出席が必要だ。だから、警察が動くまでの残りの日々をどこかで過ごすのが最善ということになる。もし君が一緒に大陸に来てくれれば、私としてもこれ以上ない喜びだ」
「診療所も暇だし、融通の利く隣人もいる。喜んで同行しよう」
「では、明朝出発できるか?」
「必要なら」
「もちろん、絶対に必要だ。では、これが君への指示だ、ワトソン君。どうか一字一句違わず守ってほしい。今、君はヨーロッパで最も狡猾な悪党、そして最も強大な犯罪組織を相手取って、私と二人で駆け引きをしているのだから。よく聞いてくれ。今夜、持っていく荷物は信頼できる使いに託し、宛先を書かずにヴィクトリア駅へ送っておいてくれ。朝になったらハンサム・キャブを呼ぶが、そのときは最初に来たものでも二番目でもないものに乗るよう、使いの者に伝えておくこと。このハンサムに飛び乗ったら、ロウザー・アーケードのストランド側の端まで向かい、住所を書いた紙切れを御者に渡して、捨てないよう頼んでくれ。運賃は用意しておき、キャブが止まった瞬間にアーケードを突っ切って、9時15分ぴったりに反対側へ出るようにする。歩道にぴったり寄せて待っている小さなブロアムが見つかるはずだ。御者は襟に赤い縁取りのある黒い重いマントを羽織っている。そのブロアムに乗り込めば、大陸間急行に間に合うようにヴィクトリア駅に到着できる。」
「どこで君に会えばいい?」
「駅でだ。前から二番目の一等車両が我々用に予約されている。」
「つまり、その車両が待ち合わせ場所だな?」
「ああ、そうだ。」
私はホームズに夜までいてくれるよう頼んだが、無駄だった。彼はこのまま同じ屋根の下にいると迷惑をかけるかもしれないと考えているのが明らかで、それが彼を出発させる動機だったのだろう。翌日の計画を手短に確認し合うと、彼は立ち上がり、私とともに庭に出て、モーティマー通りへ抜ける塀をよじ登った。そしてすぐさまハンサム・キャブを口笛で呼び、私にはそのまま彼が去る音だけが聞こえた。
翌朝、私はホームズの指示通りに行動した。用意されたハンサム・キャブは、事前に仕組まれたものではないことを確かめてから乗り込み、朝食後すぐにロウザー・アーケードへ直行した。アーケード内を全力で駆け抜けると、分厚い黒い外套をまとった大柄な御者のブロアムが待っていた。私は乗り込むや否や、彼は馬を叩き、ヴィクトリア駅まで一気に駆け抜けた。駅で降りると、御者は振り向きもせず、再び馬車を急がせて走り去った。
ここまではすべて順調だった。荷物も届いており、ホームズが示した車両もすぐに見つかった。それは列車で唯一「予約済み」の札がかかっていたからだ。しかし、私を不安にさせたのはホームズの姿が見えないことだった。発車時刻まであと7分しかない。旅人や見送り客の中を探してみたが、友のしなやかな姿はどこにもなかった。しばらくして、英語の拙い年配のイタリア人神父が荷物をパリまで送りたいとポーターに説明しているのを手伝った。もう一度辺りを見回し、車両に戻ると、なぜかポーターがチケットにもかかわらず、私の旅行仲間としてあのイタリア人を同じ車両に乗せていた。彼にここは違うと説明しようにも、私のイタリア語は彼の英語以上に拙く、私は仕方なく肩をすくめて友の到着を待ち続けた。ホームズに何かが起きたのではないかという不安が胸をよぎった。車両のドアはすべて閉まり、汽笛が鳴った、そのとき――
「ワトソン君、挨拶もしてくれないとは寂しいな」と声がした。
私は驚愕して振り向いた。年老いた聖職者がこちらを向いた。すると一瞬で皺が消え、鼻と顎が離れ、突き出た唇も消え、ぼんやりした目に光が戻り、力なげだった体つきが一気に張りを取り戻した。次の瞬間、また元の老人に戻り、ホームズはさっとその姿を消した。
「なんてことだ! 驚かせないでくれ!」
「まだ油断はできない」と彼はささやいた。「やつらが我々のあとを追っているのは間違いない。ほら、あれがモリアーティ教授ご本人だ」
列車が動き出すと同時にホームズは言った。振り返ると、長身の男が人混みをかき分けて必死で駆け寄り、手を振って列車を止めようとしている。しかし、すでに列車は加速し、あっという間に駅を離れてしまった。
「どれだけ用心しても、ぎりぎりだったな」とホームズは笑いながら言い、変装の黒いカソックと帽子を脱いで鞄にしまった。
「朝刊を見たか、ワトソン?」
「いや」
「ベイカー街のことは知らないんだな?」
「ベイカー街?」
「昨夜、我々の部屋に放火された。大した被害はなかったが」
「なんてことだ、ホームズ! そんなの許せない!」
「彼らは棍棒使いが逮捕されてから、私の足取りを完全に見失ったようだ。でなければ、私が部屋に戻ったと勘違いするはずがない。そのかわり、君の動向はしっかり監視していたようで、それがモリアーティをヴィクトリア駅に呼び寄せたのだ。君が途中で何か手違いをしたわけじゃないよな?」
「君の言った通りにした」
「ブロアムは見つかったか?」
「ああ、待っていてくれた」
「御者に見覚えは?」
「いや、なかった」
「それは私の兄、マイクロフトだ。こういう時、金で買われた他人を信用せずに動けるのは有利だ。さて、これからモリアーティをどうするか考えよう」
「この列車は急行だし、船も連絡しているから、やつをうまく振り切れたはずだと思うが」
「ワトソン君、君は私が“同じ知的水準の相手”と言った意味が分かっていないようだ。もし私が追う側なら、これほど些細な障害で諦めると思うか? なぜ彼をそこまで侮る?」
「彼はどうする?」
「私ならどうするかを考えればいい」
「君ならどうする?」
「特別列車を雇うだろう」
「だが遅すぎるんじゃないか?」
「いや、そんなことはない。この列車はカンタベリーで停車するし、船の出発まで最低15分は待たされる。そこで追いつかれる」
「まるで我々が犯罪者みたいだな。彼が到着したら逮捕しよう」
「それでは三ヶ月の苦労が水の泡だ。大物は捕まえられても、小物は一斉に逃げ出す。月曜になれば全員捕まえられるのだ。逮捕は絶対に不可だ」
「それなら?」
「我々はカンタベリーで降りる」
「その後は?」
「陸路でニューヘイヴンへ行き、そこからディエップに渡る。モリアーティも私ならそうすると思うだろう。やつはパリ行きに乗り、我々の荷物をマークし、二日間パリ駅で張り込むはずだ。その間に我々はカーペットバッグを手に入れ、旅先で現地の産業を応援しながら、ルクセンブルク、バーゼル経由で、のんびりスイスへ向かう」
というわけで、我々はカンタベリーで降りた。しかし、ニューヘイヴン行きの列車まで一時間待たねばならなかった。
私は、自分の衣類が詰まった荷物車が遠ざかっていくのを名残惜しそうに見送っていたが、ホームズが袖を引き、線路の先を指さした。
「もう来た、見てごらん」と彼は言った。
遠くケントの森から細い煙が立ち上っていた。さらに一分も経たぬうちに、機関車と車両が駅へ続くカーブを猛スピードで走るのが見えた。荷物の山陰に隠れる間もなく、それは轟音とともに通過し、熱風が我々の顔を打った。
「ほら、あれだ」とホームズは車両が分岐を揺れながら通り過ぎるのを見て言った。「やつの知恵にも限界がある。もし私の考えを先読みして動いていたら、まさにクーデメートルだったろうな」
「もしやつが我々に追いついたら、どうなった?」
「間違いなく、私を殺しにかかったはずだ。しかし、これはどちらが仕掛けてもおかしくない“ゲーム”だ。さて、今ここで早めの昼食にするか、ニューヘイヴンのビュッフェまで空腹を我慢するか、どちらに賭けるかだな」
その晩、我々はブリュッセルに着き、二日間滞在した後、三日目にはストラスブールまで移動した。月曜の朝、ホームズはロンドン警察に電報を打ち、夜にはホテルで返事を受け取った。彼はそれを引き裂いて暖炉に投げ込み、毒づいた。
「やはりそうだったか!」とうめいた。「逃げられた!」
「モリアーティか?」
「手下どもは全員捕まった。だが本人だけは網をくぐった。私が国を離れたのが運の尽き。対応できる者がいなかったのだ。だが、もう一歩で手中に収められたのに……ワトソン、君はイギリスに戻ったほうがいい」
「なぜ?」
「今の私は危ない同伴者だ。やつはやることがなくなった。ロンドンに戻れば終わりだ。だが私の読みが正しければ、やつは復讐に全力を注ぐはずだ。短い面会の時もそう言っていたし、本気だろう。君は診療に戻ることを勧めるよ」
しかし、古い戦友であり親友の私に、この訴えが通じるはずもなかった。我々はストラスブールの食堂で30分ほど議論したが、その夜には旅を再開し、順調にジュネーヴへ向かった。
我々はローヌ渓谷を一週間も気ままに旅し、ローイクで分かれてゲンミ峠を越え、インターラーケン経由でマイリンゲンに到着した。春のやわらかな緑と、山上の純白の雪の対比が美しい旅だったが、ホームズが片時たりとも自分の身に降りかかる影を忘れていないのは明らかだった。素朴なアルプスの村でも、人影まばらな峠道でも、すれ違う一人ひとりの顔を鋭い目で見定める様子から、どこへ逃げても危険がすぐそばにあると彼自身が確信しているのだと分かった。
一度、ゲンミ峠を越えて陰鬱なダウベン湖に沿って歩いているとき、右手の尾根から大きな岩が転げ落ち、轟音とともに湖へと沈んだ。ホームズは瞬時に駆け上がり、高い岩の上から四方を見渡した。案内人は春にはよくある落石だと説明したが、ホームズは黙ったまま、期待通りの現象を目撃した男のように私に微笑みかけた。
それでも、彼はいささかも沈んだ様子を見せなかった。むしろ、かつてないほどに陽気だったように思う。何度も彼は、もしモリアーティ教授が社会から消えるなら、自分の人生も終えて構わない、と繰り返した。
「ワトソン君、こう言ってもいいだろう。私は無駄に生きてきたわけではない。今夜、私の記録が締めくくられたとしても、私はそれを平然と見渡せる。私が居たことでロンドンの空気もいくらか澄んだものになったろう。千件を超える事件で、私は自分の力を間違った側に使ったことはない。最近では、社会的な問題よりも、自然が与える謎に惹かれるようになった。私の最後の偉業が、欧州最凶の犯罪者の捕獲か消滅で飾られるとき、君の回想録も終わりだな」
残る話は、簡潔かつ正確に記す。これ以上は本来書きたくはないが、何も省かず記す責任が私にはある。
5月3日、我々は小さな村マイリンゲンに着き、当時ペーター・シュタイラー老人が経営していたエングリッシャー・ホフに泊まった。主人は聡明で、ロンドンのグロブナー・ホテルで三年間ウェイターをしていたため英語も堪能だった。彼の勧めで、4日午後、我々は丘を越えロゼンラウイの村で一夜を過ごすつもりで出発した。ただし、途中のライヘンバッハの滝を見物するため、必ず道を少し外れて寄るようにと強く言い渡された。
そこはまさに恐ろしい場所だ。雪解け水で膨れ上がった急流が巨大な裂け目に落ち込み、噴き上がる飛沫はまるで燃え盛る家の煙のように立ち上る。川が突入する縦穴は黒光りする岩に囲まれ、まるで底知れぬ泡立つ釜のように狭まっていく。轟々と流れ落ちる緑の水と、絶え間なく上がる厚い飛沫のカーテンが、見る者をめまいに誘う。我々は縁近くまで進み、黒い岩肌に砕ける水の光と、深淵から飛沫とともに響く半ば人間のようなうなり声を聞いた。
滝の周囲には眺望用の道が半分ほど切り開かれているが、行き止まりで引き返さねばならない。我々が戻ろうとしたとき、スイスの少年が手紙を持って駆けてきた。それは我々が出たばかりのホテルの印があり、主人から私宛てだった。数分前に、末期の肺病を患うイギリス婦人が到着したが、ダヴォス・プラッツで冬を越し、今ルツェルンの家族の下へ向かう途中で急な吐血に襲われ、数時間の命と思われる。イギリス人医師の診察が最大の慰めだろうから、ぜひ戻ってほしいとのこと。追伸で、婦人はどうしてもスイス人医師を拒むため、主人自身も私の助力を大変ありがたく思うとあった。
この訴えを無視することはできなかった。異国で死に瀕した同胞の願いを断るわけにいかない。しかし、ホームズを一人残すのは気がかりだった。だが最終的に、ホームズが少年を道案内と連れにして残り、私はマイリンゲンに戻ることに同意した。ホームズは滝でしばらく過ごし、それからゆっくりロゼンラウイまで歩くという。私は戻りがけ、岩に背を預け、腕を組んで水の奔流を見つめるホームズを見た。これがこの世で私が彼を見る最後の姿となった。
坂の下まで来たとき、私は振り返った。滝そのものは見えないが、丘の肩を回る道がはっきり見えた。その道を、黒い服の男が速足で歩いていたのを覚えている。その精悍な歩き方は印象に残ったが、私は急ぎの用に心を奪われ、すぐに忘れてしまった。
マイリンゲンに着くまで、たぶん一時間少々だったろう。ホテルのポーチにはシュタイラー老人が立っていた。
「どうです、あの婦人はご無事ですか?」と私は駆け寄った。
彼の顔に驚きの色が走り、眉が一瞬動いたとき、私の心は鉛のように沈んだ。
「これは、あなたの手紙ではないのですね?」と私はポケットから手紙を取り出した。「ホテルにイギリス婦人はいないのですか?」
「まったくそんなことはない!」と彼は叫んだ。「だが、ホテルの印が押されている! ああ、きっとあなたのあとに来た背の高いイギリス人が書いたのだ。彼は――」
だが、私は主人の説明を待たずに心の底から恐怖に駆られ、村の通りを駆け抜け、さきほど降りてきた道を逆戻りした。下りに一時間かかった道を、全力で登ってなお二時間かかり、ようやく再びライヘンバッハの滝にたどり着いた。そこには、私が残したままのホームズのアルペン・ストックが岩に立てかけられていた。しかし、彼の姿はなく、呼んでもむなしく岩壁にこだまするだけだった。
そのアルペン・ストックを見た瞬間、私は氷のように冷たくなり、吐き気を覚えた。ホームズはロゼンラウイには行かなかったのだ。あの幅三フィートの道――片側は絶壁、反対は断崖――に彼は留まり、敵を待っていた。スイスの少年も姿を消していた。彼はきっとモリアーティの手先だったのだろう。そして、その後何が起きたのか? それを語れる者は誰もいなかった。
私はしばらくの間、呆然としたまま立ち尽くしていた。あまりの恐ろしさに、心を落ち着ける必要があったからだ。それから私はホームズ自身のやり方を思い出し、この悲劇を読み解くためにそれを実践しようと試みた。残念なことに、それはあまりにも容易なことだった。
私たちは会話の最中、道の終わりまで行ってはいなかった。登山杖が、私たちが立っていた場所を示している。黒ずんだ地面は絶え間ない飛沫で常に柔らかく、鳥でさえも足跡を残すだろう。その道の先のほうには、私から遠ざかるように二列の足跡がはっきりと刻まれていた。戻ってくる足跡はなかった。道の終わりから数ヤードのところでは、土が掘り返されて泥になり、谷を縁取る枝やシダも無残に引き裂かれ、しおれていた。私は腹ばいになって身を乗り出し、周囲から吹き上がる水しぶきの中、下を覗き込んだ。私がここを離れた時よりもあたりは暗くなっており、今や私は黒い岩壁に点々と光る水滴と、遥か下の底に砕ける水面のきらめきしか見えなかった。私は声を張り上げて叫んだが、返ってきたのは、滝の半ば人間じみた叫び声がこだまするのみだった。
だが結局のところ、私は友であり同志でもある彼からの最後のあいさつを受け取る運命だった。先に述べた通り、彼の登山杖は、道に突き出た岩に立てかけられていた。その岩の上から、何か光るものが目に留まったので、手を伸ばすと、かつて彼が愛用していた銀のシガレットケースが置かれていた。それを拾い上げると、その下に敷かれていた小さな四角い紙片が地面にひらひらと落ちた。広げてみると、それは彼の手帳から破った三枚のページであり、私宛てに書かれていた。宛名の記載が正確で、筆致も力強く明晰で、まるで書斎で書いたように整っているのが、いかにも彼らしいと感じた。
「親愛なるワトソン
この数行を書くことを許してくれたモリアーティ教授の厚意により、今、私はこれを書いている。彼は、いかにしてイギリス警察の追跡をかわし、我々の動静を把握していたかについて、その手口の一端を語ってくれた。確かに、私はかねてから彼の能力を非常に高く評価していたが、それが裏付けられる内容だった。私は、社会が今後彼の存在からこうむる被害を、これで根絶できると考えているが、それが私の友人たち、特に親愛なるワトソン、君に苦痛を与えることになるのではと心配している。しかし、私の人生はすでに決定的な局面に達しており、どのような結末であろうと、これほど自分にふさわしいものはないと、以前から君には話しておいた通りだ。実を言うと、君にだけは率直に告白しておきたいのだが、マイリンゲンからの手紙は最初から悪戯だと確信していたし、こういった成り行きになるだろうという予感のもと、君には使いに出てもらったのだ。パターソン警部には、あのギャング団を有罪にするための書類が、‘M. ’と記された鳩穴の中に、青い封筒で『モリアーティ』と表書きして保管されている、と伝えてほしい。イギリスを発つ前に全ての財産の処分を済ませ、兄のマイクロフトに託してある。ワトソン夫人によろしく伝えてくれたまえ。そして親愛なる友よ、どうか私を信じてほしい。
心より敬具
シャーロック・ホームズ」
残されたことは、もうわずかだ。専門家による調査の結果、二人の男は互いに組み合ったまま、どうしようもなくそのまま転落したのだと考えられる。遺体の回収はまったく望みがなく、渦巻く水と泡が沸き立つあの恐ろしい大渦の底には、時代を代表する最も危険な犯罪者と、法の最も優れた擁護者が、永遠に横たわることとなった。あのスイスの若者は二度と発見されることはなかったが、彼もモリアーティが雇っていた多数の手先の一人であることは疑いない。ギャング団については、ホームズが収集した証拠が彼らの組織をいかに暴き出したか、そして死した男の手がいかに彼らに重くのしかかったかは、読者の記憶にも新しいだろう。あの恐るべき首領の詳細は、裁判の過程でもほとんど明らかにならなかった。私が今、彼の経歴について明確な記録を残さねばならなかったのは、軽率にも彼の名誉回復を試みる者たちが、私がこの先も最良にして最も賢明な人物と信じてやまない男――ホームズ――を攻撃したことによるものである。

